左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。
|
2025,01,01, Wednesday
    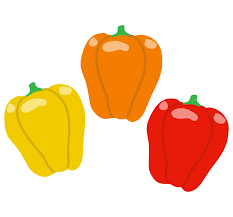  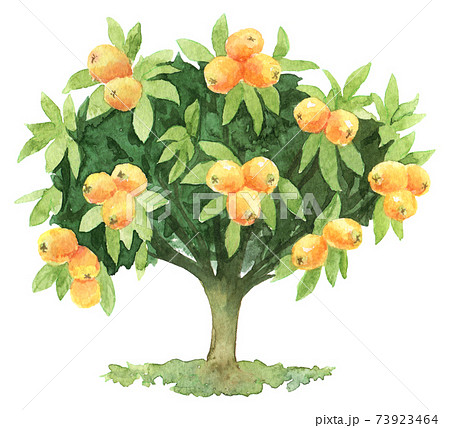 本年も、よろしくお願いします。 原産地は海外だが、現在は日本で普通に作られている作物は、米麦芋類をはじめ野菜・果物・蚕と数が多く、原産地が日本のものを探す方がむしろ難しいくらいだ。そのため、これからも日本産に移行できる作物は多いであろう。 (1)レモンの国産化 ちょっと前まで、レモンは輸入する作物だったが、*1-1のように、最近は国産のレモンもよく見かけるようになった。広島県尾道市瀬戸田町の生口島と高根島は、年平均気温が15・9度という温暖な気候と年間降水量の少なさが柑橘類の栽培に適していて、畑の主、由川光明さんはミカン・ネーブル・不知火・はるか・はるみ・ハッサクなどを作っているそうだ。島の生産者はレモン専業ではなく、収穫時期が異なる複数種類の柑橘類を栽培するそうだが、これができる地域は多いのではないかと思う。 消費者から見ると、農薬や保存料を使っていない国産レモンは、皮まで利用できるため貴重で、私は、国産レモンを皮ごとみじん切り機で粉砕し、それに蜂蜜を加えてレモンジャムにし、長期間、美味しく食べている。また、私は、100%レモンジュースを製氷器で氷にして冷凍することによって鮮度を長持ちさせ、1個あたりの分量が決まっていることを活かして、寿司はじめ色々な料理や菓子作りに使っている。願わくば、20cc毎の氷になった100%レモンジュースが売られていれば、使う時は必要な個数を電子レンジで溶かせば良いので、なお便利であろう。 *1-1は、「葉の商品開発の成功事例はない」としているが、オリーブの葉のように乾燥させれば、レモンの香リの香辛料ができ、オリーブの葉と同様に料理に使えそうだ。 なお、レモンはインド北部原産で柑橘類の中でも寒さに弱いそうだが、私がレモンの中に入っていた種を、(夏は暑くて冬は寒い)埼玉県で植えたところ、芽を出して元気に育っている。ただし、レモンは葉も美味しいらしく、蝶の幼虫が次々と葉を食べてしまうので、防虫剤を撒かざるを得なかった。なお、最近は、埼玉県でもミカンの実がなっているのを見るため、地球温暖化で作物の栽培適地も北上していると思う。 そのような中、*1-2は、京都でレモン栽培の試みが始まり、果実の加工を手掛ける日本果汁・宝酒造・良品計画が「京檸檬」のブランド化に挑んでいるというので期待できる。しかし、冬の冷え込みが厳しいと言われる京都でも、少し工夫すれば、グリーンレモンだけではなく黄色く色づいたレモンも収穫できると思う。 (2)パプリカとアボカドの国産化 *2-1のように、パプリカは約30年前にオランダから輸入されてから輸入品が流通の大半を占めていたが、円安・輸送費の高騰・大手資本の参入、環境制御が可能な大型温室での栽培拡大等によって、生産量が10年で倍増し、国内流通における国産比率は2割に高まり、「日本に着くまで日数を要するため、早取りする輸入品と比べて、色づいてから収穫する国産は味の乗りが良い」のだそうだ。しかし、未だ、価格差があって、契約取引が主体であるため、一般には入手しにくいのが難点だ。 それでは、メキシコからの輸入が主体だったアボカドは国産化できないのかと探してみたところ、*2-2のように、長崎市千々地区のビワ農家ら約10人が2024年11月22日に「長崎地区国産アボカド振興会」を発足し、長崎市産のアボカドとしてブランド化を進めて販売戦略を確立させるそうだ。アボカドは虫による害が少なく、農薬散布の手間が省けるほか、低いところに実がなるため、高齢の生産者も収穫がしやすく、ビワ農家の高齢化や後継者不足を踏まえて、ビワを守っていくためにもアボカドで収益を安定させ、夢のある農業にしたいとのことである。 実は、私は、スーパーで売っている長崎県産の美味しい琵琶を食べた後、その種を埼玉県で植えたところ、冬でも元気に育っている。また、アボカドもメキシコ産のものを使った後、その種を植えたら、埼玉県の場合は、夏は問題なく育ったが、冬になると枯れはしないものの成長が止まったように見える。そのため、場所を選んだり、環境制御が可能な大型温室で栽培したりすれば、どちらも問題なく作れると思う。なお、大温室の暖房は、地中熱やヒートポンプを使ったり、その他の工夫をしたりすれば比較的安価だ。 (3)カカオの国産化 チョコレートの原料となるカカオ豆の約8割は、*3-2のように、西アフリカのガーナの森から日本に届いているそうだが、ガーナの自然保護団体「エコケア・ガーナ」創設者のオウスアダイ氏によると「1万9千haのカカオ農園が金の違法採掘で破壊され」、採掘された金はアラブ首長国連邦やインドで加工されて欧米・日本・中国などにも金製品として輸出されているそうだ。 世界的な金の価格高騰が金の違法採掘の「追い風」となり、それとは対照的にカカオの生産量が落ち込んでいるとのことで、国際ココア機関(ICCO)によると、2020年度に年間104万tあった生産量が2023年度には48万トンと半減し、ニューヨーク市場価格では、2023年の年始以降、価格が上昇傾向で2024年に急騰し、わずか1年半で5倍近くまで跳ね上がり、その影響が日本のチョコレート菓子にも及んでいるのだそうだ。確かに、クリスマスケーキの価格は、2021年の3,862円から2024年には4,561円まで上昇した。 そのような中、*3-1のように、金の出ない日本の東京都小笠原村母島でカカオが栽培され、埼玉県草加市の平塚製菓が東京産カカオを使ったチョコレートを発売していたのは嬉しい。高温多湿地域で育つカカオは、これまで赤道に近いコートジボワールやガーナが主産地だったが、日本でカカオのできる場所は、沖縄や小笠原村母島だけでなく意外に多いのではないかと思う。 (4)真鯛の養殖など 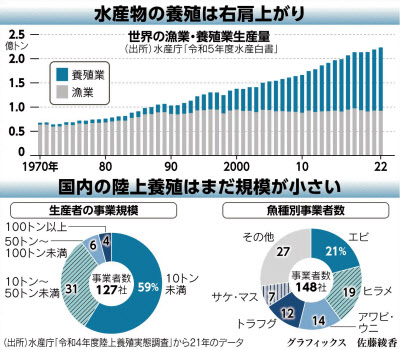 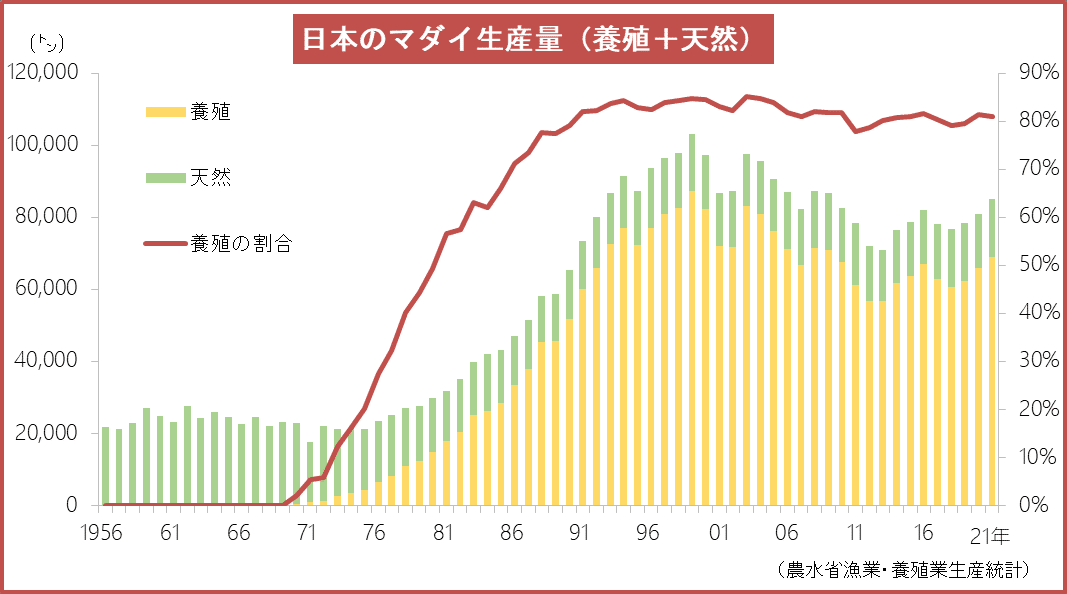  2024.10.24日経新聞 みなと新聞 京都大学 (図の説明:左図のように、世界の漁獲高は1980年代半ばから一定だが、養殖業は伸びている。また、中央の図のように、日本の真鯛生産量も、天然ものの漁獲高は一定だが養殖ものが増え、現在では養殖の割合が80%になっている。そして、右図の右側が、ゲノム編集で筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させて食べられる部分の割合を増やした京大発の真鯛だ) *4は、①リアス海岸の西予市三瓶湾に真鯛の養殖場 ②体長50cm・重量1.8kg程度の真鯛が味が良く人気がある ③日本の全体漁獲量は最盛期の1980年代と比較して約3割まで減少、真鯛は天然はほぼ同水準、8割を占める養殖は約2割増加 ④大豆・白ゴマ等を混合した飼料を2020年に開発し、2022年に魚を全く含まない餌を食べた真鯛を出荷できた ⑤養殖鯛は天然鯛のコリコリ、もちもち感は乏しいが、熟成のうまみは遜色ない ⑥真鯛は人間が卵から孵化させた「人工種苗」がほぼ全てで自然の影響を受けない ⑦養殖の成否は人工種苗の優劣で決まる ⑧近大水産養殖種苗センターの谷口さんは「天然の稚魚を養殖すると1kgまで3年程度かかり、うちのは1年半」と言う ⑨近大の稚魚は、1960年代に兵庫県で漁獲された真鯛から生まれた子のうち、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを繰り返して14世代目 ⑩遺伝的リスク分散のため、別の海域由来の2つの系統の親魚も同様に選別を繰り返している ⑪京大発スタートアップ、リージョナルフィッシュは、筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させることで成長を早め、食べられる部分を増やすことに世界で初めて成功し、ゲノム編集した「22世紀鯛」を陸上養殖できる技術を開発して2021年に厚労省と農水省に食品としての届け出た ⑫人間は1万年以上かけて動植物の有益な突然変異を選んで繁殖を繰り返して品種改良したが、豚はその一例 ⑬ゲノム編集は自然界で起こる突然変異をスピーディーに再現 等としている。 世界の漁獲高は、上の左図のように、1980年代半ばから一定だが養殖漁業は伸び続けており、日本の真鯛生産量も、上の中央の図のように、天然の漁獲高は一定だが養殖が増えて、現在では、養殖の割合が80%にもなっている。 そして、③のように、日本の全体漁獲量は最盛期の1980年代から約3割まで減少しており、真鯛の場合は、海への排水管理や稚魚の放流などで天然ものも何とか同水準を保っているが、養殖ものが供給量全体の8割を占めているそうだ。 なお、日本のリアス式海岸は、①②のように、波が穏やかで海面養殖に向いている。私は玄界灘の天然真鯛と養殖真鯛を比較できるのだが、確かに養殖魚は必要な大きさまで成長させて出荷時の大きさを揃えることができ、かつ安価であるため、料理によっては養殖魚で十分である。しかし、⑤のように、筋肉質ではないため、新鮮な魚のコリコリ感がなく、刺身には向かない。なお、私は、“熟成”は“新鮮さ”とは対極にあり、腐る寸前の状態なので食べない。 しかし、養殖漁業は餌が必要であるため、豊富で安価な餌で養殖できなければ採算が合わない。そのため、④のように、大豆や白ゴマなどを混合した飼料を2020年に開発したわけだが、それでも餌に人間と競合する農産物を使うので、私は、ミドリムシ(https://www.euglena.jp/whatiseuglena/ 微細藻類ユーグレナ)の方が鯛にとっては栄養豊富で良いと思う。また、愛媛県であれば、餌にミカンの皮などを混ぜると、安価に柑橘系の香りがする鯛ができそうだ。 また、真鯛の良いところは、⑥のように、人間が卵から孵化させた「人工種苗」がほぼ全てであるため、稚魚を捕獲しなければならない魚種と違って自然の影響を受けず、⑦⑧のように、養殖の成否は人工種苗の優劣で決まるため、⑧⑨のように、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを繰り返す品種改良をすれば、必要な形質を持つ魚を作れることだ。 そして、近大は、⑩のように、遺伝的リスク分散のため別の海域由来の2つの系統の親魚も同様に選別を繰り返しているそうだが、私は瀬戸内海の鯛よりも玄界灘の鯛の方が流れの速い海で鍛えあげられているため、自然とマッスル鯛の系統になっていると思う。 なお、京大発スターチアップ企業が、⑪及び上の右図の右側のように、ゲノム編集で筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させ、成長を早めて食べられる部分を増やした「22世紀鯛(マッスル鯛)」を作ったそうだが、筋肉質になればコリコリ感も増すだろう。 人間は、⑫のように、1万年以上かけて動植物の有益な突然変異を選んで繁殖を繰り返し、品種改良をして人間にとって優良な農産物を作ってきた。ただし、⑬のように、ゲノム編集は自然界で起こる突然変異をスピーディーに再現しはするが、本当に必要な部分のみが変化して有害な物質は含まないのか否かは、多くの人がそれを食べた後でなければわからない。 (5)難民の受け入れ支援と職業紹介について 現在の日本では、少子高齢化が進んで“生産年齢人口”の割合が減ったため、労働力不足がネックになって、価格で国際競争に勝てなかったり、生産そのものができなくなったりするものが増えた。そして、これらを解決するには、女性や高齢者を“生産年齢人口”に組み込むだけでなく、外国人労働者の受け入れも重要である。 しかし、日本政府は、“生産年齢人口”が多くて困っていた昭和42年の閣議決定以来、「“単純労働者”は原則として受け入れない」との方針をとっており、現在の入管法でも“単純労働者”のためには、期間・業種・家族の帯同を限定した特定技能や技能実習しか認めていない。現在は、農林水産業・中小企業等で労働力不足がネックになっていることを考慮すれば、これらは早急に改められるべきである(https://www.moj.go.jp/isa/content/001407635.pdf、https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999336_po_20080108.pdf?contentNo=8 参照)。 そのような状況であるから、日本政府は、難民の受け入れにも著しく消極的だが、*5-1・*5-2のように、母国で内戦が繰り返されたり、地球温暖化で住む場所をなくしたり、母国では人権侵害を受けたりする難民が多いのだが、これらの外国人が日本人より犯罪率が高いわけでも努力しないわけでもなく、むしろ新しい財やサービスを作るのに役立つのである。 そのため、気候変動・戦争・人権侵害等を理由とした移住ビザの発効を行なって移住を支援し、認定NPO法人「難民支援協会」だけではなく、日本政府や地方自治体が渡航費・日本語学校の学費・教育などの支援や職業紹介を行なえば、日本における労働力不足と難民の福利の両方が解決される。さらに、人間は、困っている時に助けてくれた人の恩は忘れないものである。 ・・参考資料・・ <輸入作物の国産化> *1-1:https://digital.asahi.com/articles/ASS530T99S53UTFL00VM.html (朝日新聞 2024年5月4日) 生産量は全国の4分の1 レモンの島にレモン専業農家がいない不思議 最近は国産のレモンを店頭でよく見かけます。爽やかな酸味で夏のイメージが強いものの、収穫期は秋から春にかけて。日本有数の産地を訪ねると、収穫のラストスパートを迎えていました。瀬戸内海に浮かぶ生口島(いくちじま)と高根島という二つの島からなる広島県尾道市瀬戸田町。年間降水量が少なく、年平均気温は15・9度という温暖な気候が、かんきつ類の栽培に適している。生口島の山あいにあるレモン畑で、畑の主、由川光明さん(69)が待っていた。緑の葉の間から、実ったレモンが見え隠れする。「木の内側に入ると、もっとたくさん見えます」。由川さんの言葉に誘われ、腰をかがめて幹に近づいた。ちょうど傘の中に入ったかのように、広がった枝に囲まれる。枝からはレモンがたわわにぶら下がる。木の外側は風があたって皮が傷つきやすい。なるべく葉の内側に実るよう、剪定(せんてい)などで調整すると由川さん。「葉もレモンの香りがしますよ」とちぎって渡してくれた。青々しい刺激が鼻から頭へ届き、スッキリする。この香りを生かした商品開発をいくつもの企業が試みたが、まだ成功事例はないという。収穫は10月から4月、大きくなった順番にもいでいく。「他のかんきつもあるから、収穫期が長いレモンはつい後回しにしちゃうこともあるけれど」。レモンのほかに、由川さんは、ミカン、ネーブル、不知火(しらぬい)、はるか、はるみ、ハッサクなどを手がけている。「色々つくる中で、レモンは柱の一つ」と話す。島の生産者はレモン専業ではなく、収穫時期が異なる複数種類のかんきつを栽培する。JAひろしまによると、瀬戸田町の収穫量は年間2千トン前後。およそレモン2千万個で、全国の約4分の1を占める。中でも、由川さんら137戸の農家で構成する「せとだエコレモングループ」は、町のレモン畑の約2割にあたる32ヘクタールで特別栽培のレモンをつくっている。レモンは他の果実と違い、「もう1個食べて」と需要拡大を呼びかけるのはなじまない。ならば品質を国産の中でも別格に高めようと考えた。化学合成農薬と化学肥料を通常の栽培の半分に減らして育てたのがエコレモン。「皮まで食べられるレモン」をキャッチコピーに、2021年度は約600トンを販売した。エコレモンは、使用する農薬を抑えている分、病害虫に襲われやすく、外見の悪さなどから加工品の原料に回る割合が通常より高い。同JAは、企業と協力して、レモンケーキなどの菓子や飲料、調味料などを開発し、販売。収穫したレモンはすべて無駄なく利用しているという。レモンは5月中旬に花が咲く。夏を越えて、10月から早摘みの収穫が始まる。まだ皮が青く、グリーンレモンと呼ばれる。爽やかな香りとすっきりとした酸味が楽しめる。そのまま木に実らせておくと、黄色に色づき、香りが落ち着いて、果汁は増える。黄色いレモンは1月から4月までの収穫。熟すと酸味はまろやかになり甘さも出てくる。収穫が途切れる5月からは鮮度保持フィルムに包んで冷蔵していた黄色のレモン、6月中旬からはハウス栽培ものを出荷。年間を通じ瀬戸田のレモンを供給している。JAひろしまの理事でエコレモングループの会長、宮本悟郎さん(61)は「地元の関心も高まり、若者も帰ってきて、島に動きがあります」と話す。一昨年からは、広島特産のカキの殻を原料にした肥料を使い始めた。「さらに一歩進め、環境循環型農業を目指します」 *レモン 原産はインド北部と言われる。かんきつ類の中でも寒さに弱い。日本に流通する大半が輸入品で国産品は輸入品の1割強。広島県産が国産のおよそ半数を占める。ほかに愛媛県や和歌山県などが主な産地。 *1-2:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO84678320Y4A101C2LKB000/ (日経新聞 2024年11月9日) 京都レモン、名産品に育て 農家24軒が国産不足で栽培、宝酒造・無印が商品開発 京都でレモン栽培の試みが始まった。6年前に植えた苗が育ち、収穫が本格化している。旗振り役となるのが果実の加工を手掛ける日本果汁(京都市)だ。宝酒造や良品計画とともに京都産レモンを使った商品を生み出し「京檸檬(れもん)」のブランド化に挑んでいる。京野菜の九条ネギ畑の隣に青々と茂ったレモン畑が広がる。村田農園(京都府久御山町)では10月下旬に収穫イベントが開かれた。夏の日差しでレモンの表面が焼けてしまった部分もあったが豊作だという。レモンは苗木から本格的に収穫できるまで5年ほどかかる。現在は京都府南部を中心に24軒の農家が栽培しており、2024年の収穫量は23年比で6割増の5トン超となる見込みだ。インドが原産とされるレモンは、温暖な気候で夏に乾燥する地域が栽培に適しており、年間の気温差が激しい京都府ではほとんど栽培されてこなかった。レモンが熟すのは12月~3月だが、冬の冷え込みが厳しい京都では実が凍るのを防ぐため黄色く色づく前のグリーンレモンを収穫する。グリーンレモンは酸味よりも苦みが際立つが、すっきりとした味わいが特徴だ。このため加工に適している。宝酒造は23年11月から京都産レモンを使った地域限定チューハイ「宝CRAFT京檸檬」を販売している。「甘すぎず食事に合わせやすいチューハイに仕上がった」(広報担当者)。無印良品では一部店舗で京檸檬を使っためんつゆと肉のたれを販売。さっぱりとした味わいが好評だったという。京都でレモン栽培が広がる背景には、国産レモンの供給不足がある。広島県や愛媛県などが主な産地で19~21年の栽培面積は2割ほど増えたが、収穫量はむしろ2割近く減った。気候変動や農家の高齢化などが主な要因だ。京檸檬を主導する日本果汁の河野聡社長は「国産レモンを思うように仕入れることができないこともあった」と打ち明ける。かんきつ類に詳しい京都大学の北島宣名誉教授は「地域を見極めれば京都でレモンを育てることも可能」と話す。府内の各地で栽培した結果、冬の平均最低気温が数度でも暖かいと、特定の地域ならレモンの木が冬を越せることがわかった。村田農園では成木に育った現在、冬の防寒対策はほとんど必要ないという。冷え込みにくい地域を探して成功例を重ねている。18年に立ち上がった「京檸檬プロジェクト協議会」は宝酒造や伊藤園など飲料・食品メーカーが参画する。農家が育てたレモンは日本果汁が買い取り、果汁などに加工してメーカーに納めている。農家が販路を心配せず、栽培に集中できる仕組み作りを心がけている。今後、京檸檬の生産者を増やすために北島名誉教授は「手をかけすぎない栽培方法の確立が欠かせない」と語る。主要産地と異なり、京都でレモンを栽培する農家は兼業農家が多い。幼木期の防寒やせん定などの手間を減らすことが重要だ。村田農園は現在、レモン畑を第3圃場まで増やして300~400本の木を栽培している。日本果汁は京都府内で30トン以上の収穫量を目指す。河野社長は「いずれは宇治茶や京野菜と並ぶ京檸檬ブランドを築きたい」と意気込んでいる。 *2-1:https://www.agrinews.co.jp/news/index/280445 (日本農業新聞 2025年1月5日) [シェア奪還]国産パプリカ10年で倍増 大手参入 円安追い風、味で優位 輸入品が流通の大半を占めていたパプリカで、国産が存在感を高めている。生産量は10年で倍増し、国内に流通する国産の比率は2割に高まった。輸入品にとって逆風となる円安の中、大手資本が相次ぎ参入し、環境制御が可能な大型温室での栽培が拡大。安定調達したい実需者のニーズを捉え、シェアを着々と伸ばしている。パプリカは約30年前にオランダから輸入されて以来、食卓に定着した。ただ、近年は円安や輸送費の高騰が進行し、財務省の貿易統計によると、2023年の輸入量は2万5027トンと5年で4割減っている。勢いがあるのが国産だ。農水省によると、22年のパプリカ出荷量は7130トンと10年で9割増えた。その結果、10年前に1割だった国産比率は2割まで高まった。輸入への逆風をビジネスチャンスと見て、大手資本による生産への参入が相次いでいる。 ●大型温室整備、高収量法人も 24年5月には富永商事ホールディングス(兵庫県南あわじ市)が、国産の先駆けとして知られる水戸市の農業法人Tedyから企業譲渡を受けた。同法人は22年、高度な環境制御システムを備えた1・8ヘクタールの大型温室を整備。ビニールだと収量は10アール15トンが限界だったが、ガラス温室で太陽光を取り込めるようになり、23年産は同20トン以上を確保した。林俊秀会長は「日本に着くまで日数を要し早取りする輸入品と比べて、色づいてから収穫する国産は味の乗りが良い」と優位性を語る。11月後半から出荷を始め、年末の需要期にピークが来るよう照準を定める。国産の出回りが増えたことで、実需には国産の調達を強化する動きも出ている。総菜店「RF1」などを展開するロック・フィールド(神戸市)は、10年前に重量ベースで8割だった生鮮野菜の国産比率を、前期(23年5月~24年4月)には92・5%まで高めた。近年強化するパプリカは、魚介とあえたマリネやサラダなど、幅広いメニューに使う。調達部は「栽培技術の向上や生産者の増加で、年間を通じて輸入品と併用できるようになった。価格差も縮まってきている」と、調達環境の変化を語る。仕入れは契約取引が主体。自社で扱う総菜用に適しており生産者も取り組みやすい規格を両者で協議し、設定する。24年には国産比率を5割まで高めた。 *2-2:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=0263d5205af4460f8d4d0d301235f3c1 (長崎新聞 2024/11/23) 『長崎産アボカド』ブランド化へ 千々地区ビワ農家ら 振興会設立 新たな収入源としてアボカドを栽培する長崎市千々地区のビワ農家ら約10人が22日、「長崎地区国産アボカド振興会」を発足した。長崎市産のアボカドとしてブランド化を進め、販売戦略を確立させる。安定した収量の確保が見込まれる来冬の初出荷を目指す。市農林振興課によると、アボカドは虫による害が少なく農薬散布の手間が省けるほか、低いところに実がなるため、高齢の生産者も収穫がしやすいという。アボカドの栽培は、同地区のビワ農家で長崎アボカド普及協議会副会長の森常幸さん(78)が収益安定のため約6年前に始めた。周辺のビワ農家にも耐寒性が強いとされる品種「ベーコン」「フェルテ」の種を配り、現在約20人が栽培している。この日は森さんの果樹園に約10軒のビワ農家が集まった。来冬の初出荷に向け、栽培品種の選定や販売戦略などを協議した。森さんはビワ農家の高齢化や後継者不足を踏まえ「ビワだけでは厳しくなっている。ビワを守っていくためにもアボカドで収益を安定させ、夢のある農業にしたい」と呼びかけた。森さんが種から栽培を始めて約6年。この冬は一定の収量を確保できる見通しだ。収穫したアボカドは来年1月に鈴木史朗市長に贈呈しPRするほか、同17日に市役所食堂で提供される。 *3-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51355770U9A021C1L83000/ (日経新聞 2019年10月24日) 東京産カカオのチョコ、小笠原で栽培 平塚製菓 チョコレートなどのOEM(相手先ブランドによる生産)生産を手がける平塚製菓(埼玉県草加市)は24日、東京都小笠原村の母島で栽培したカカオを使ったチョコレートを発売した。2003年から栽培に取り組み、商品化した。国産カカオは沖縄で作られている例はあるものの、東京産の商品化は初めてとなる。「TOKYO CACAO」という商品名で2万個を限定販売する。30日まで東京・渋谷の商業施設「渋谷ヒカリエ」内で販売するほか、11月1日からは同社のオンラインストアで扱う。カカオ分70%の約6センチ×6センチの板状のチョコレートが2枚入って3000円(税別)で、かんきつ類のような酸味と香りが特徴だ。高温多湿の地域で育つカカオは、赤道に近いコートジボワールやガーナが主産地となっている。同社は亜熱帯に属する母島で質の良いカカオを作るため、土壌の改良などに取り組んできた。現在は年間で約1トンのカカオ豆を収穫できるといい、「今後は2トン収穫できるように木を大きくしたい」(平塚正幸社長)としている。 *3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16120047.html (朝日新聞 2025年1月6日) ガーナのカカオ 違法な金採掘、急騰するチョコ 年末年始につい食べ過ぎてしまうスイーツといえば、チョコレートだろう。クリスマスケーキはもちろん、冬に食べるチョコアイスは格別だ。その原料となるカカオ豆の約8割が、西アフリカのガーナの森から日本に届いている。分けいつても分けいつてもカカオ山――。俳人の種田山頭火がガーナを訪れていたら、こう詠んでいたかもしれない。2024年12月、ガーナ東部州のカカオ農園には、そう思わせるような光景が広がっていた。「この山はカカオの木で覆われている」と話すのは、地元のカカオ生産組合のテイノル・フランシス会長(38)。幹にはこぶし大の実がいくつもぶらさがっていた。「でも、多くの山はまるで変わってしまった」。フランシスさんは、そう明かした。 * 異変はすぐに判明した。近くの山でトラクターが地響きをあげている。地面はでこぼこに固まった赤土で覆われ、ため池は濁った緑色だ。カカオ農家のアモア・ジョージさん(52)は「以前はカカオの森だったのに」と悔しそうに話す。親族らで営むカカオ農園は、サッカーコート約4面分の広さだった。しかし、4年前に違法な金の採掘業者に迫られ、約2・5面分を1万9千セディ(約19万円)で売却。すぐに採掘が始まった。違法採掘は、不況で職に就けない若者らの働き口になっていた。地面が数十メートル掘り下げられ、あちこちで地下水が流れ出した。金の精製で使う水銀や重金属がこの水に溶け出した。残ったカカオの農園の土壌が汚染され、生育に影響が出始めた。異常気象も重なった。カカオには週に2度ほどの雨が必要だが、2週間ずっと雨が降らないこともあった。弱った木からさらに病気が広がり、面積あたりの収穫量は4年前の6分の1まで落ち込んだ。今年に入って採掘が終わり、土地は返還された。だが、緑の森は赤土の山と化していた。いま、採掘場に土を埋め戻している。ジョージさんは「再びカカオを植えても、育つかわからない。収入がほとんどなく生きるすべがない」と嘆く。 * ガーナの自然保護団体「エコケア・ガーナ」創設者のオベド・オウスアダイ氏は「1万9千ヘクタールのカカオ農園が、違法採掘で破壊された」と指摘。採掘された金は、アラブ首長国連邦やインドで加工され、欧米や日本、中国などにも金製品として輸出されているとみられる、と説明した。世界的な金の価格高騰が違法採掘の「追い風」にもなっているという。対照的に、カカオの生産は落ち込んでいる。国際ココア機関(ICCO)によると、20年度に年間104万トンあった生産量は、23年度に48万トンと半減したとみられる。ニューヨークの市場価格では、23年の年始以降、価格が上昇傾向となり、24年になると急騰。わずか1年半で5倍近くまで跳ね上がり、「カカオショック」と呼ばれた。この影響は、日本のチョコレート菓子にも及んでいる。明治は24年、「きのこの山」や「たけのこの里」などの価格を2度にわたり値上げ。ロッテも、「コアラのマーチ」や「パイの実」などを2度値上げした。帝国データバンクによると、クリスマスケーキの平均価格は21年の3862円から、24年には4561円まで上昇。主要な原材料が軒並み値上がりする中でも、チョコレートの値上げ幅が最も大きいという。ガーナでの「カカオよりも金」の流れは止まらず、元に戻すのが困難な段階まできている。新たな懸念も浮上している。土壌汚染のカカオ豆への影響だ。カカオにはもともと、土壌由来などの重金属が少量含まれる。農場の汚染が進めば、さらに重金属の含有量が増える恐れがあると、専門家らはいう。オウスアダイ氏は「日本の消費者にとっても、ひとごとではない。(生産者に適正な対価が支払われる)フェアトレード商品を選ぶなど消費行動を変えることで、生産地によい影響を与えられるということも知ってほしい」と呼びかける。 ■金鉱山、数百万人が従事 「カカオ農園を壊す金鉱山で働く人は悪人か」と問われると、返答に困る。数百万人が従事する産業となっており、金の採掘なしに彼らの暮らしは成り立たない。白昼堂々と採掘していたのは「ふつうの若者」たちだ。採掘を取り締まれば数百万人の食いぶちがなくなり、治安悪化にもつながりかねない。生産地で何が起きているのか、自覚したいと思う。 ■農家には「ぜいたく品」 カカオの実は、果肉つきの豆を約1週間発酵させ、1週間乾燥させると、「チョコレート」色の豆が顔を出す。焙煎(ばいせん)し粉末にしてミルクや砂糖を加えれば、チョコレートができあがる。ガーナでも、バレンタイン商戦では多くのチョコが出回るというが、地方ではあまり消費されない。製品は原料の10倍以上の価格で、農家にとっては「ぜいたく品」だ。 <養殖漁業> *4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD062EG0W4A201C2000000/ (日経新聞 2025年1月5日) 真鯛を科学する 養殖やゲノム編集で持続可能な魚へ進化 花は桜木、魚は鯛(たい)――。古来祝いの席に欠かせないのが、色かたちが美しい真鯛だ。新たな年を迎え、さっそく舌鼓を打った人も多いことだろう。そんな和食文化を代表する縁起物が伝統を守りながらも、日々進化していることをご存じだろうか。技術を駆使し、世界へ羽ばたく「百魚の王」を追った。 ●養殖で目指す「大国」 リアス海岸が美しい愛媛県西予市三瓶(みかめ)湾。早朝、漁船に乗り込むと10分ほどで目的地へと到着した。ここは真鯛(まだい)の養殖場だ。10メートル四方の生け簀(す)には、ひとつにつき約5千尾の真鯛がいるという。深さ約10メートルまで沈めた網を少しずつ引き上げると、にわかに海面が魚影で赤く染まり、水しぶきが跳ね上がる。生きのいい鯛をたも網ですくい、船上のカゴに移していく。いずれも体長50センチ、重量1.8キロ程度。真鯛は寿命が15年以上と長く、10キロ以上に成長するのもあるが、最も味が良く人気があるのはこのサイズだという。カゴには6尾入るが、お互い傷つかないように1尾ずつたて板で仕切られていた。この日は70箱以上が岸で待ち構えているトラックに積まれ、午前9時すぎには市場に運ばれた。スズキ目タイ科マダイ属の真鯛だが、日本近海にはチダイ属、キダイ属、クロダイ属などが生息する。そのなかで見た目が赤く、姿が美しい真鯛はおめでたい魚の象徴だ。日本の漁獲量(海面)全体は最盛期だった1980年代から約3割の水準まで減少した。しかし、真鯛はここ10年で見ると天然ものはほぼ同水準、8割を占める養殖ものは約2割増えている。「真鯛はサステナブルな水産資源になり得ます。モデルはノルウェーです」。水揚げ作業を見せてくれた赤坂水産(愛媛県西予市)の赤坂竜太郎さんはこう言って笑った。ノルウェーは養殖サーモン生産量で日本のすべての海面養殖量を上回る「大国」。目指す先がはるか彼方(かなた)にあるのは分かっているが、真鯛こそが可能性を秘めた魚だとの確信がある。 ●餌づくりから改革 まず着手したのが餌だった。養殖真鯛は1キロ太るのに餌としてカタクチイワシ4キロが必要という。水産資源の保護が叫ばれるなか、これでは持続可能とはいえない。そこで赤坂さんは真鯛の雑食性に着目。餌に魚を使わず、大豆や白ゴマなどを混合した飼料を2020年に開発した。配合など試行錯誤しながら22年に魚をまったく含まない餌を食べた真鯛を出荷できるまでになった。養殖ではマグロやブリ、ヒラメなども人気だが、こうはいかない。いずれも肉食の傾向が強く、魚なしの餌では成長しづらいのだ。とはいえ、おいしくなければ消費者には受け入れられない。養殖鯛は天然鯛のようなコリコリ、もちもち感は乏しいが、熟成のうまみは遜色ない。「世界で食べられているノルウェーサーモンも柔らかいでしょう?」。赤坂さんは養殖場の近くに加工施設も完備し、全国どこでも販売先が望む熟成度で配送可能という。 ●人工種苗が支える 日本が「真鯛大国」になり得る理由はもうひとつある。マグロやブリ、カンパチなどの場合、稚魚は漁師から調達する「天然種苗」が大半だ。一方、真鯛はサーモンと同様に人間が卵から孵化(ふか)させた「人工種苗」がほぼすべてを占める。つまり自然の影響を受けにくいのだ。健康で美しく、成長が早いうえにおいしい成魚に育つ稚魚をいかに生み出すか――。養殖の成否は人工種苗の優劣で半ば決まると言っても過言ではない。しかし、養殖業者がそれを手掛けているわけではない。 「天然の稚魚を養殖すると1キロの大きさに成長するまで3年程度かかりますが、うちのは1年半です」。近畿大学水産養殖種苗センター(和歌山県白浜町)で事業副本部長を務める谷口直樹さんはこう言い切る。道のりは長かった。近大で生まれる稚魚は1960年代に兵庫県で漁獲された真鯛に遡る。それらから生まれた子どもたちのうち、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを世代ごとに繰り返した。現在はこの系統の親魚は14世代目だという。遺伝的なリスクを分散するため、別の海域を由来とする2つの系統の親魚も同じように選別を繰り返している。2025年1月に産卵させる予定の親魚を見せてもらった。水槽内で泳ぐ35尾はいわば精鋭中の精鋭だ。オスはすべて兵庫由来の系統でメスは別系統という。真鯛の産卵は白浜海域では通常3〜4月だが、養殖業者のニーズに合わせて、明るさや水温を調整することで産卵時期を調整することができるようになった。産卵すると40〜50時間後に孵化し、それから40〜50日で3センチほどのピンク色の稚魚に成長する。この段階で海の生け簀網に移す「沖だし」を迎え、養殖業者に引き渡すまで50〜60日程度を過ごす。歩留まりも向上し、出荷できるのはこのうち70%程度。その後の養殖業者の段階では9割以上が成魚に育つという。 ●ゲノム編集が「世界を救う」 海を必要としない真鯛も登場した。京都大発のスタートアップ企業、リージョナルフィッシュ(京都市)はゲノム編集した「22世紀鯛」を陸上養殖できる技術を開発した。筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させることで成長を早め、食べられる部分を増やすことに世界で初めて成功。21年に厚生労働省と農林水産省に食品としての届け出を完了した。人間は1万年以上をかけて自然界で起こる動植物の有益な突然変異を選び、繁殖を繰り返して品種改良してきた。家畜化したイノシシが豚になったのはその一例だ。社長の梅川忠典さんは「ゲノム編集は自然界で起きる突然変異をスピーディーに再現するもの」と意義を強調する。商業ベースに乗せるには量産化が不可欠だが、大手企業と組んで施設を建設する計画が進行中という。ゲノム編集した食物に抵抗感のある消費者がまだ多いのも確か。ただ22世紀鯛は商品化にあたり、「ゲノム編集技術を使用」とあえて強調した。「ゲノム編集は世界を救う技術。この魚を生み出したことを誇りに思っています。これからも消費者の理解を得るとともに、科学で社会に貢献するという信念に変わりありません」。梅川さんはこう言い切った。 ●万葉集にも鯛の料理法 日本での真鯛(まだい)の歴史は縄文時代に遡る。各地の貝塚でその骨が出土され、青森県の三内丸山遺跡では、つながったままの真鯛の背骨も見つかった。遺跡には煮たり、焼いたりした痕跡があり、どのように食べていたのかと想像が膨らむ。奈良時代に成立したとされる日本最古の和歌集、万葉集には既に「鯛」の表記と料理法が登場する。「醬酢(ひしほす)に 蒜(ひる)搗(つ)きかてて 鯛願ふ 我れにな見えそ 水葱(なぎ)の羹(あつもの)」。現代訳すれば、醬(ひしお)と酢にすりつぶした蒜(のびる)を混ぜて鯛を食べたいのに、お吸い物など私に見せないで――という内容だ。古代から鯛が人気の食べ物だったことがうかがえる。高貴な食材でもあった。平安時代中期の法典「延喜式」には、真鯛が各地から朝廷に献上されていたことが記載されている。ほとんどが干物や塩漬けだが、和泉(大阪)からは鮮魚も届けられていたようだ。 ●平安時代から伝わる「式包丁」 当時をしのばせる儀式が残っている。藤原道長の時代から伝わるという「式包丁」だ。宮中で節会など重要な行事で行われていたもので、大きな俎(まな)板にのせた真鯛や鯉(こい)など魚や雉(きじ)や鶴といった鳥を直接手で触れることなしに包丁刀と俎箸(まなはし)で切り分け、めでたい形を表現する。殺生した命を食材に移行するための儀式だ。滋賀県甲賀市のミホ・ミュージアムに烏帽子(えぼし)と狩衣(かりぎぬ)姿で登場したのは、京都の和食店、萬亀楼(まんかめろう)の小西将清さん。生間(いかま)流の式包丁を一子相伝で受け継ぐ、30代目家元にあたる。この日はイベントで式包丁を披露した。かつて朝廷で最も高貴な魚とされたのは鯉だった。真鯛が「百魚の王」ともてはやされるようになったのは江戸時代以降。「めでたい」と語呂を意識するようになったのもこのころだ。1785年には「鯛百珍料理秘密箱」という鯛を使った100に及ぶレシピを紹介する本も登場した。 ●締め方でおいしさ長持ち 鯛をいかにおいしく食べるか。そんな欲求は現代も変わらない。2024年10月、北海道函館市で開かれた世界料理学会で画期的な真鯛の締め方が報告され、話題となった。発表したのは兵庫県明石市で天然真鯛などの仲卸業を経営する鶴谷真宜(まさのり)さん。セリで落とされた真鯛の締め方は通常、①脳に傷を入れることで動きを止める「脳殺」、②血を抜くことで腐敗や臭みを抑える「放血」、③脊髄を破壊し死後硬直を遅らせる「神経破壊」――からなる。しかし、鶴谷さんは、脳殺せずに神経破壊だけして動けなくなった真鯛が水の中でエラ呼吸しているのを見つけた。これをもとに16年に研究を開始。神経破壊によるショックで排せつが促されるとともに、動くことができないので体内にあるおいしさのもととなる成分(アデノシン三リン酸=ATP)の消費が抑えられているとの仮説を立てた。「数万尾ほど試して、現在の締め方にたどり着きました。個体や顧客の好みによって締め方は少しずつ変えます」と鶴谷さん。18年に東京の高級日本料理店「龍吟」に認められたのをきっかけに、その鯛は全国にファンが広がっている。地元のすし屋「明石菊水」もそんな店のひとつ。代表の楠大司さんは「最大の特徴はおいしく食べられる状態が長持ちしたことです」という。以前は朝に届いた真鯛はその日のうちに提供していたが、いまは翌日でもおいしく食べられる。翌日になると少し熟成して柔らかくなる一方で、コクは増す。お客の好みによって使い分けることも、同時に食べ比べることもできるようになった。鶴谷さんは「どうしておいしさが長持ちするのかなど自分なりの考えはありますが、科学的に実証できていません。大学など研究機関の協力を得て解明したい」とおいしさへの追求に貪欲だ。 ●「百魚の王」、世界へ 漁師、仲買人、料理人らに共通するのは、おいしい真鯛を多くの人に食べてもらいたいという思いだ。国連食糧農業機関(FAO)によると、世界ではたんぱく質源としての魚介類の需要は拡大の一途をたどり、1人当たりの消費量は過去半世紀で2倍に膨らんだ。ところが、日本からの養殖真鯛の輸出は増加傾向とはいえ、23年で66億円程度。輸出先の大半は韓国だ。その他の国々で鯛を食べる習慣がないからだ。「とにかくおいしさを知ってもらうことが重要」と愛媛の赤坂さんは自社の養殖真鯛を輸出するだけでなく、米国に鯛をメインにした和食レストランを開く準備を始めた。明石の鶴谷さんも24年10月から天然真鯛を冷蔵でシンガポール、タイ、マレーシアの和食料理店に販売し始めた。海外への普及に欠かせないのは料理人だ。世界に和食ブームが定着して久しいが、鯛のさばき方や調理法を本格的に学んだ人はそう多くない。そんななか京都市は京料理を世界へ普及させることを目的に外国人に特例措置を導入した。老舗料亭、菊乃井本店で働くベトナム出身のファム・ドゥック・ユイさん(25)はそのひとり。蒸しものと煮ものが担当のユイさんは明石産の真鯛をさばき、あら炊きを調理していた。味つけは先輩が担当するが「味見もできますし、何でも教えてくれます」。総料理長の辻昌仁さんは「日本料理を世界に広げるのが菊乃井の考え。隠すものはなにもありません」。この日はミャンマーやハンガリーからなど、ほかの制度で滞在する外国人6人も調理場で働いていた。ユイさんは言う。「夢は30代で故郷に近いホーチミンに本格的な日本料理店を開くことです」。本場仕込みの鯛料理が世界中で食べられる日は案外近いのかもしれない。 <難民と外国人労働者> *5-1:https://digital.asahi.com/articles/ASSDT2JCPSDTUHMC00BM.html (朝日新聞 2024年12月26日) 日本めざす難民学生、外国人が必要な日本 つなぐNPO支える米国人 日本に来て6年になる栃木県内の大学4年生、マダネ(24)が13歳の時のことだ。故郷、シリアのホムスは内戦の激戦地帯。マダネの家があった地区は安全とされていたが、ある晩、爆撃が始まった。戦闘機が飛び交い、ミサイル音が耳をつんざく。隣の家が爆撃を受け、家族7人で身を寄せ合った。「死ぬのは仕方ない。でも、もし3歳下の弟と2人だけ残されたら、どうやって生きていこう」。家族は無事だったが、直後に全員でレバノンに出国。その後イエメン、サウジアラビアと移る。マダネは「日本に行きたい」と思い始める。日本のアニメやゲームが好きだった。「日本は安全で平和な国。明日生き延びられるかわからない生活はもう嫌だ」。ネットで「日本」「難民」「行きたい」と検索すると、日本の認定NPO法人「難民支援協会」が実施する、シリア人学生が対象の日本語教育プログラムを見つけた。2年間の日本語学校の学費と渡航費を出してくれるという。選考はトルコで行われていたため、単身トルコに移り、応募。合格した。千葉・松戸にある語学学校、日本国際工科専門学校に通い、生活費はパン工場のバイトで稼いだ。作業はきつかった。でも、日本語が上達すると製品管理の仕事もまかされ、やりがいも出てきた。奨学金で大学の電子情報工学科に進み、IT企業に就職も決まった。「日本はがんばれば認めてくれる国。困難を抱える人に、日本で人生が変えられると希望を与えたい」。教育プログラムは、日本国際工科専門学校が2015年、難民支援協会に「シリアの若者を学生として受け入れられないか」と相談して始まった。アフガニスタンやウクライナに広がり、150人以上受け入れた。21年からはNPOの「パスウェイズ・ジャパン(PJ)」が引き継いだ。学生のコミュニティーを作り、交流や相談の機会を多く設け支援する。 ●日本が変われば影響は大きい」 PJの代表理事、折居徳正(56)は事業の意義を「優秀で日本に来たいと願う学生たちがいる。一方で、日本も外国人の留学生や働き手が必要。その橋渡し」と語る。プログラムの大口寄付者の1人が、米国人のエド・シャピロ(59)だ。シャピロはボストンで27年間、金融業界で活躍。02年に社会に恩返しをしたいと家族で財団を設立した。米国にはこういう「ファミリー財団」が4万以上あるという。15年、米国政府がシリア難民の受け入れ拡大を表明。16年にボストンにも難民の家族がやってきた。シャピロは財団の運営に専念し、難民支援に力を入れるようになる。22年にウクライナ戦争が起こると、米ワシントン・ポスト紙に、日本の避難民受け入れについて記事が載った。日本の難民認定率が非常に低いこと、「ウクライナ避難民の受け入れが日本の難民政策の抜本的改善につながることを期待する」という難民支援協会の代表理事、石川えり(48)のコメントが紹介された。記事を読んで日本の難民政策に関心を持ったシャピロは石川に連絡をとり、PJの事業を知って寄付を決めた。なぜ米国人のシャピロが日本に来る難民の支援にお金を出すのか。「日本は経済大国。そこが変われば世界への影響は大きい。しかも、日本は少子化に悩んでおり、外国人の力を必要としている。社会を開く良い機会だと思う」。シャピロはとりあえず26年までの寄付を決めている。「いずれは、プログラムの卒業生が寄付をして回る仕組みになるといい」と思い描く。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250107&ng=DGKKZO85884200X00C25A1EA2000 (日経新聞 2025.1.7) 〈逆転の世界〉オセアニアから見ると 気候難民、日米受け入れを 私の母国であるオーストラリアは太平洋の島しょ国に対する最大の支援国だ。2023年にはツバルと「ファレピリ連合条約」を結び、世界で初めて気候変動を理由とした移住ビザの発行を決めた。国内ではあまり話題になっていない。豪州の国民は高騰する生活費への対応など政府のインフレ対策に対する関心が最も高い。気候変動は最重要課題ではない。米航空宇宙局(NASA)による人工衛星の観測データを使った分析では、海面上昇の速度は約30年前と比べて2倍に高まった。ソロモン諸島ではすでにいくつかのサンゴ礁の島が海に沈んだ。被害を受ける島しょ国は、化石燃料を大量に消費する先進国に対して温暖化ガスの排出削減を求めてきた。先進国が十分に責任を果たしているかといえば、答えは「ノー」だ。豪州を含む先進国の議論にはスピード感がない。「気候難民」はすでに存在するし、今後も生まれる。彼らが移住を決断しなければいけない時に、先進国は選択肢を少しでも多く提供することが重要になる。受け入れ先が豪州だけでは不十分だ。パラオやマーシャル諸島とつながりが深い米国や日本も役割を果たせるだろう。太平洋の島しょ国では、インフラ整備などを積極支援する中国の存在感が高まっている。24年に取材で訪れたトンガでは街のあちらこちらの建物に「(建設は)中国の支援だ」と示す看板がかけられていた。海洋進出を狙う中国も念頭に、豪州は島しょ国への支援を続けるだろう。
| 農林漁業::2019.8~ | 12:56 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,12,16, Monday
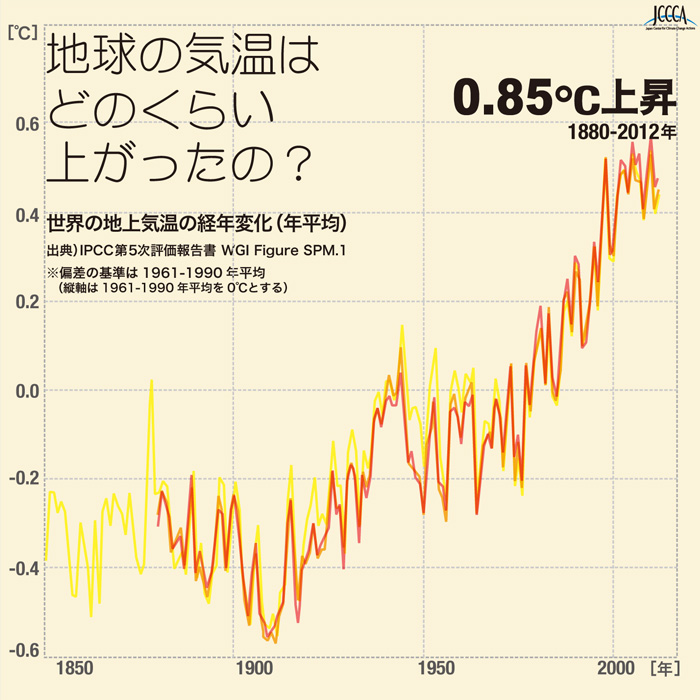 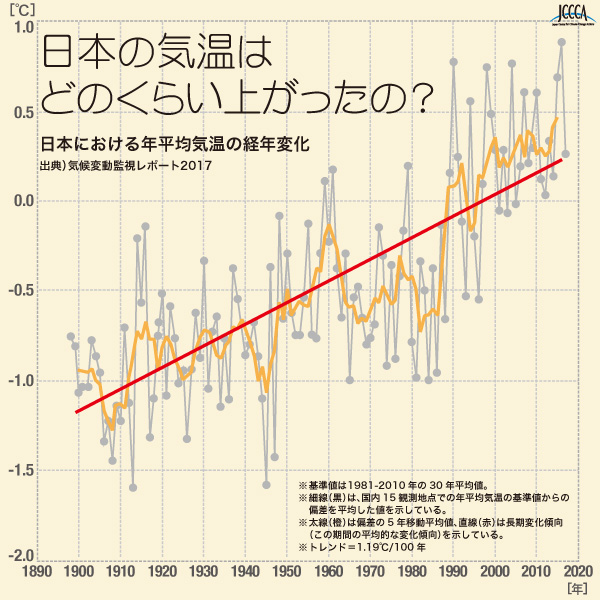 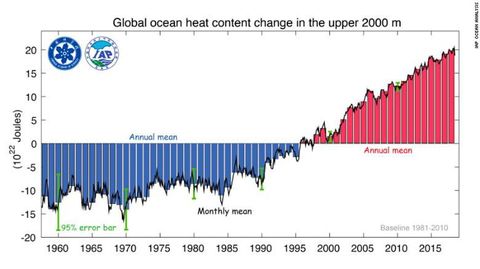 気温の上昇 海水温の上昇 (図の説明:左図のように、地球の気温は1880年~2012年に0.85°C上昇し、中央の図のように、日本の気温は1900年~2017年に1.19°C上昇している。また、右図のように、海水温も上昇しており、これらは農業・漁業に影響を与えている) (1)米国とのFTA交渉における日本の敗北 1)農業は、自動車と引き換えにはできない 経済官庁が農業を差し出して確保しようとしてきた自動車の利益は確保されず、*1-1のように、日米貿易協定における米国の自動車関連の関税撤廃の約束はあることにされているが実際はなく、これは「ある」ことにしないと米国貿易額の92%をカバーしたとしているのが50%台に落ち込んで国際法違反の協定となり、国会批准ができないからだそうだ。 この日米貿易協定は、自動車・部品の関税撤廃が実現しないと800億円程度、農産物は9500億円程度の生産減少が生じる可能性があり、日本のGDPはマイナスになるそうだ。トランプ氏は強力なネゴシエーターで農産物も自動車も「勝ち」、日本は農産物も自動車も「完敗」であり、その上、日本は米国から大量の武器購入や基地負担の増大を要請されて、一部は既に行っているわけである。 こうなった理由は、日本の政治・行政には長期計画やそれに伴う戦略がなく、成り行き任せで国民のために必死の交渉を行わないことや、メディアが外国との交渉中に首相や政治家を批判して貶め、首相をレイムダックのようにさせることが大きいと、私は考える。 2)食料自給率低下と隙だらけの安全保障 TPPや日米貿易協定締結のために、経済官庁が農業を差し出して自動車の利益を確保しようとしたことを受け、日本政府が甘い想定に基づいて農業に厳しい条件を突きつけたため、農業を放棄したり、農業を承継しない人が増えた。 その結果、*1-2のように、耕作放棄や農地転用による農地面積の減少が農水省の想定を大きく上回り、2015~19年(5年間)に、荒廃農地は7万7000ha、農地転用は7万5000ha、合計15万2000haの農地が減少し、再生された農地は3万2000haに留まる。 しかし、*1-3のように、農業の生産基盤や担い手が減れば、1億人の人口を擁する我が国の食料自給率はますます下がり、いくら防衛費を増強しても兵糧攻めだけで結果が出て戦争は終わり、エネルギー自給率も7.4%なので、日本を責めるのに武器はいらないのである。その上、ミサイルに核弾頭など積まなくても、原発を狙えば勝手に自爆する状態だ。 なお、農林水産業は地方の重要な産業であるため、これを大切にせず、たたいて担い手をいためつければ、「地方創生」にも大きなマイナスなのである。 (2)農業の解決例 1)環境税を使う スペインのマドリードで開かれたCOP25は、*2-1のように、徹夜で協議したが対立が解けず、積み残されていたパリ協定の実施ルール作りの合意を断念して次回会合に先送りしたそうだ。私は、化石燃料に世界ベースで環境税をかけて資金を集め、CO₂を吸収する藻場や緑の面積(CO₂吸収力)に応じて公正にそれを配分するのが、どの国からも文句が出ず、エネルギーの転換が進むと考える。 この時は、日本国内の農地・山林・藻場も、その面積(CO₂吸収力)に応じて資金を受け取ることができるので、受け取った資金をその手入れに活かすことができる。 2)温暖化を活かす 地球温暖化が現在のペースで進むと、海面が上昇して陸地が減ったり、野生動植物の生息適地がなくなったりするのだが、日本では、*2-2のように、現在も暖かい地域はさらに暖かくなり、緯度の高い北海道でも米作が容易になり、標高の高い所まで何らかの作物ができるようになるため、自治体毎の影響を環境省のHPで確認できるよう準備を進めているそうだ。 農業分野は、将来のその地域の気候が現在のどの地域と同じになるかをそのHPで判断でき、転換する品目・品種や転換スケジュールの検討で参考になるため、果樹などの栽培や転換に時間がかかるものは、苗木の準備計画に役立ててもらいたいそうだ。 3)生産性を向上させる 農林水産業の全自動化につながる技術開発が進んでいるが、*2-3は、全自動化の技術開発と併せて、農村での雇用創出から定住化につながるような研究をしてもらいたいとしている。 高望みしたり、不可能に挑戦したり、解決の難しい社会の課題に挑んだりすることを「ムーンショット(月を撃つ)」と言うそうだが、そのような人たちのおかげで、現在は、ロケットで月の軌道まで行って実際に月を撃つことができるようになったのである。従って、ムーンショットは実現可能であり、他の技術も同様に進歩しているのだ。 もちろん、全自動化しても、機器を作ったり、使いこなしたり、維持管理したりすることができる人材が必要になるので新しい仕事が生まれるが、若い人が農村に定住したいと思う社会制度にしなければ、国として成り立たなくなることは明らかである。 4)付加価値を上げる ①米粉の例 米粉市場は伸びており、その理由は、*2-4のように、圧倒的な品質力(微細粉にする高い製粉技術、加工技術)の進展でパン・菓子・麺など多彩な商品化が実現し、和菓子やせんべいの原料だった従来の米粉の世界を一新して米粉新時代を開いたからだそうで、消費増で工場の稼働率も向上し、一部メーカーは小麦粉並みの製粉コストを実現して、伸びる需要に生産が追い付いていないとのことである。 実需側の在庫も少なく、このままでは3万トンを超す需要を満たせず、地域によっては原料確保に苦心する企業も出そうで、海外市場も「グルテンフリー市場」が急成長しているとのことだ。私は米粉で作るなら、ラーメンよりフォーだと思うが、今のところ、フォーの即席麺はないため、先入観のない加工品開発や販促活動に期待したい。 ②ゲノム食品の例 消費者庁は、*2-5のように、ゲノム編集技術で品種改良した農水産物の大半について生産者や販売者らにゲノム編集食品であると表示することを義務付けないと発表したが、表示がなければゲノム編集食品かどうか分からないため、消費者が選択できずに悪貨が良貨を駆逐する状況になる。さらに、このような規制は厳しくして対応した方が、付加価値が上がるのである。 (3)その他の地方産業 ①林業 林野庁は、*3-1のように、森林空間を活用した「森林サービス産業」の創出に乗り出し、森林空間そのものを活用して、木材生産・供給だけでなく、健康需要などを見据えて森林体験や商品開発で新たなビジネスを生み出し、山村地域に新たな雇用と収入を生み出すそうだ。 しかし、最も効果があるのは、子育て世代の多くが地方に住み、森林・田畑・海などを見ながら育つ子どもを増やして、自然に対する美意識を育てることだと、私は考える。 ②観光業(クルーズ船の寄港) 2019年の沖縄へのクルーズ船の寄港予定回数は、*3-2のように、過去最多を更新する719回に達するそうだ。経済成長著しいアジアでのクルーズ市場拡大がこの背景にあり、今後も寄港増や船舶の大型化が見込まれるとのことである。 沖縄へのクルーズ船寄港予定回数が過去最多の719回に達する背景には、クルーズ市場が拡大するアジア市場に近接しているという地理的な優位性があり、クルーズ旅行は比較的安価な「カジュアルクルーズ」の増加に伴って市場が拡大しており、沖縄以外の国内でクルーズ船が多く寄港するのはいずれも九州の博多、長崎で、地理的な近さが強みなのは明らかだそうだ。 ③漁業 農水省が、*3-3のように、水産資源保護のために新たな取引規制を作り、魚介類の水揚げ場所や出荷日を示す公的な証明書を作って、国が指定した魚や一部の輸入品を国内で取引するときに添付を求め、違法操業で証明書のない魚介類は事実上、市場で売買できなくするそうだ。 ただ、私は、水産庁の漁業対策は資源管理に偏っており、漁業資源が減少した本当の理由を科学的に追及していない点で不足だと考える。 このような中、*3-4のように、海水温が50年間で表層水温1.23度上昇した結果、朝鮮半島では食卓の魚が変遷し、「イシモチ→スケソウダラ→サバ」と国民魚が変わり、温暖化や乱獲の影響でスケソウダラの「国籍」も変わって、近年はカタクチイワシとサバが豊漁となり、この2~3年の1位はサバだそうだ。 日本でも似たようなことが起こっているため、地球温暖化や海水温上昇の影響は漁業にも大きな影響を与えているわけである。 ・・参考資料・・ <日本の農業と食料自給率> *1-1:https://www.agrinews.co.jp/p49324.html (日本農業新聞 2019年11月26日) 「完敗」 協定の深刻さ 国際法違反 責任重く 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏 このところ、「ある」ものを「ない」と言うのが話題になっているが、「ない」ものを「ある」と言うのもある。日米貿易協定における米国の自動車関連の関税撤廃の約束は、合意文書が示す通り「ない」が、その約束が「ある」ことになっている。それは、「ある」ことにしないと米国側の貿易額の92%をカバーしたとしているのが50%台に落ち込み、前代未聞の国際法違反協定となり、国会批准ができないからである。米国は大統領選対策として成果を急いだので、協定を大統領権限で発効できる(関税が5%以下の品目しか撤廃しない)「つまみ食い」協定と位置付けたから議会承認なしに発効できるが、国会で正式に承認する日本側は国際社会に対する顔向けとしても責任は重い。筆者も役所時代はもちろん、大学に出てから多くの自由貿易協定(FTA)の事前交渉(産官学共同研究会)に参加してきた中で、経済産業省や外務省、財務省が世界貿易機関(WTO)ルールとの整合性を世界的にも最も重視してきたと言っても過言ではない。しかも、経済官庁が農業を差し出して確保しようとしてきた「生命線」たる自動車の利益が確保されなかったのだから、心中は察して余りある。試算例でも明白だ。政府が使用したのと同じモデル(GTAPと呼ばれる)で、自動車関税の撤廃の有無を分けて日米協定の影響の直接効果を改めて試算し直した。「直接効果」とは、政府が用いた「生産性向上効果」(価格下落と同率以上に生産性が向上)、「資本蓄積効果」(国内総生産=GDP=増加と同率で貯蓄・投資が増加)などの、いわゆる「ドーピング剤」を注入する前の効果のことである。表が示す通り、自動車と部品の関税撤廃は日本の生産額を3400億円程度増加させる可能性があるが、関税撤廃が実現しないと800億円程度の生産減少に陥る可能性がある。一方、農産物は9500億円程度の生産減少が生じる可能性も示唆される。全体のGDPで見ても、自動車を含めても0・07%(政府試算の10分の1程度)、自動車が除外された現状ではほぼゼロという状況である。GTAPモデルにおける「労働者は完全流動的に瞬時に職業を変えられる」といった非現実的な仮定を修正すれば、日本のGDPはマイナスになる。日本にとっては農産物も自動車も「負け」、トランプ氏は農産物も自動車も「勝ち」という、日本の完敗の実態が数字からも読み取れる。国際法違反を犯してまで完敗の協定を批准する事態の深刻さを再認識したい。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p49488.html (日本農業新聞 2019年12月14日) 農地減少 政府想定上回る 荒廃、転用2倍ペース 対策見直し必須 耕作放棄や農地の転用による農地面積の減少が農水省の想定を上回って進んでいる。2015~19年の5年間に発生した荒廃農地は7万7000ヘクタール、農地転用は7万5000ヘクタールに上った。それぞれ同省が想定した2・5倍、1・5倍のペースで増えた。農地の再生が一定程度進んだものの、新たな荒廃農地の発生や転用に追い付かない状況だ。農地は1961年をピークに一貫して減少し、2019年は439万7000ヘクタールまで落ち込んだ。政府が15年に策定した食料・農業・農村基本計画に掲げる25年の確保目標440万ヘクタールを既に下回った。19年までの5年間の減少面積は12万1000ヘクタールに及ぶ。同省が変動要因を分析したところ、5年間で新たに発生した荒廃農地と農地以外に転用された面積は、合計で15万2000ヘクタールに上る。一方、再生された農地面積は3万2000ヘクタールにとどまり、減少要因が増加要因を大きく上回った。基本計画では、荒廃農地と農地転用を合計で8万1000ヘクタールにとどめつつ、2万7000ヘクタールの農地を再生することで、農地の減少を5万4000ヘクタールに抑える想定だった。同省は、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度を使って農地保全に取り組んだ地域は耕作放棄が抑制され、農地の再生も想定以上に進み、政策が効果を発揮したとみる。一方、「高齢化の進展や担い手不足などで新たな荒廃農地の発生が大きく見通しを上回った」(農村振興局)と認める。現行の対策だけでは、農地減少が十分に食い止められていないことが明らかになった格好。将来にわたり農地を確保するため、より踏み込んだ対応が求められそうだ。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p48934.html (日本農業新聞 2019年10月8日) 国会論戦に望む 弱る生産基盤「解」導け 安倍晋三首相の所信表明演説に対する各党の代表質問を皮切りに国会論戦が始まった。現憲法下200回目の国会で、令和初の本格的な論戦となる。構造改革路線に偏った農政では農業・農村の未来を切り開けない。生産現場の声に耳を傾け、農家に寄り添う農政に軌道修正する節目の国会とすべきだ。謙虚な政権運営も求められる。首相は所信表明でこれまであまり使わなかった言葉を盛り込んだ。その一つが農業の「生産基盤の強化」だ。日米貿易協定について触れた部分で「それでもなお残る農家の皆さんの不安にもしっかり向き合い、引き続き、生産基盤の強化など十分な対策を講じる」と語った。ところが生産基盤の強化をどう進めるのか、何も語らなかった。一方で「地方創生」の項目で農産物輸出には字数を費やし、「それぞれの地方が誇る農林水産物の輸出をさらに加速」することや「農産品輸出拡大法の制定」を強調した。国内で需要が減る米を海外に輸出できれば、水田を守る手法の一つとはなる。だが、輸出拡大に向けた競争力強化だけでは従来の構造改革路線と何ら変わらない。農家の高齢化や担い手不足は深刻で、中山間地域を中心に集落消滅が起き始めている。規模拡大や競争力強化は必要だが、大規模農家だけでは農村や集落を守れない。中小規模の家族経営を含めて多様な担い手が共存できる農業・農村をどう実現するのか。国会で議論を深め、具体策を示すべきだ。安倍政権が中央集権的な官邸主導の政策決定を進める中で、地方自治体の農業部門は人員、財源とも縮小が進んだ。生産現場と密着した農政は、地方自治体やJAグループなどの農業団体の協力や連携なくして軌道に乗せられない。生産基盤の立て直しに向けは、こうした連携の強化も不可欠だ。首相は所信表明の「一億総活躍社会」の項目で、「多様性」の言葉も使った。農業や農村こそ多様性が重要となる。若い新規就農者から田舎暮らしで移住する定年退職者まで、さまざまな人を呼び込まない限り、生産基盤の強化は絵に描いた餅に終わりかねない。国会は、国民への説明責任を果たす重要な場である。首相は日米貿易協定について「ウィンウィン」と語ったが、それでは納得を得られない。情報開示の在り方も異様だった。日本政府は最終合意するまで公式な情報提供をしなかった。秘密交渉とされた環太平洋連携協定(TPP)でも節目で情報を一定に開示した。「安倍1強」で通商交渉の情報さえ開示されないのであれば、国会は空洞化する。新たな食料・農業・農村基本計画策定や正念場を迎えた米政策2年目、豚コレラ対策など農政を巡る課題は山積みだ。国会で熟議を尽くし、農家に寄り添う施策で国民の財産である農業の生産基盤を後世に引き継ぐのが農政の眼目だろう。 <農業の解決例> *2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019121501001866.html (東京新聞 2019.12.15) COP25、合意断念し先送り パリ協定ルール、対立解けず閉幕 スペイン・マドリードで開かれた国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議(COP25)は15日、一部積み残されていたパリ協定の実施ルール作りの合意を断念し、来年の次回会合に先送りする決議を採択し、閉幕した。会期を2日延長して徹夜で協議したが対立が解けなかった。来年に本格始動するパリ協定では、深刻な地球温暖化を踏まえて史上初めて、全ての参加国が自主的な目標を掲げて温室効果ガス排出削減を進める。ルールの大枠は過去の交渉で決まっており、完成しなくても協定は始動するが、出だしから課題を抱えることになった。来年の会議は11月に英国で開かれる。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p49450.html (日本農業新聞 2019年12月10日) 温暖化で植物適地移動 VoCCで分析 果樹転換参考に 長野県など研究 地球温暖化が現在のペースで進むと、国内の高山帯に生息する野生動植物は、21世紀末に生息適地がなくなる可能性がある──。長野県環境保全研究所などでつくる研究グループが発表した。全国1キロ四方ごとに温暖化の影響を推計したのは初めて。影響は市町村ごとに閲覧できるようにし、農業分野では作物転換の検討に使ってもらう。推計には、気候変動速度(VoCC)という指標を用いた。現在のペースで温暖化が進むと、VoCCの全国平均は1年当たり249メートルとなる。樹木の移動は、最大で同40メートルといわれており、気候変動に追い付けない。これは、身近な自然が将来、緯度の高い所や標高の高い所でしか見られなくなるということを示唆する。都道府県ごとに影響を見ると、沖縄が同2174・3メートルで、最も速度が速かった。次いで千葉、長崎となった。自治体ごとの影響は、環境省のホームページ内で確認できるよう準備を進めている。農業分野では、将来の地域の気候がどの地域と同じになるのか判断でき、転換する品目・品種や転換のスケジュールの検討で参考になる。同研究所の高野宏平研究員は「果樹などの永年作物は栽培や転換に時間がかかる。苗木の準備計画に役立ててもらいたい」と話す。 <ことば> VoCC ある地点で気候が変化した場合、将来同じ気温になる場所の最短距離を、変化した時間で割った速度のこと。例えば、年平均気温15度の場所が100年間で100キロ北上したら、VoCCは1年当たり1キロとなる。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p49317.html (日本農業新聞 2019年11月25日) 農業の完全自動化 農村への定住策視野に 農林水産業の全自動化につながる技術開発が進んでいる。過疎・高齢化で人手不足に悩む農村にとってありがたいが、農村への定住促進や雇用機会の創出など農村人口を増やす策を忘れてもらっては困る。全自動化の技術開発と併せ、農村での雇用創出から定住化につながるような研究が必要だ。 内閣府は昨年度から、解決が難しい社会の課題に挑むような研究開発を促すため「ムーンショット型研究開発」という制度を創設した。従来技術の延長にはない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究を進めるという。研究領域として少子高齢化対策や地球環境問題などを示し、目標例として「2040年までに農林水産業の完全自動化を実現」することを挙げる。ムーンショットとは「月を撃つ」ということ。米国のジャズシンガー、ノラ・ジョーンズさんの歌に、月を撃つという意味の歌詞がある。高望みをする、不可能に挑戦する、というような意味合いで使われた。内閣府では既存技術の組み合わせではない独創的なアイデアを取り入れた技術開発を進めるために、この表現を使ったようだ。「農林水産業の完全自動化」は「35年までに高齢者のQoL(生活の質)を劇的改善」「40年までに建設工事の完全無人化を実現」などとともに、野心的な目標例として掲げた。農業の現場では、ロボットトラクターのような自動化技術、圃場(ほじょう)の作業状況や作物の生育状態を遠隔地から確認できる情報通信技術(ICT)など、最先端の技術が瞬く間に広がっている。内閣府が目指す農業の完全自動化は、月を撃つような荒唐無稽な夢物語では既になくなりつつある。過疎化、高齢化で労働年齢人口が急速に減っている農業にあって自動化技術は魅力的だ。だが、果たしてそれだけでいいのか、あえて疑問を挟みたい。農村が美しいのは、棚田にしろ牧草地にしろ、人が手を入れいているからだ。ロボットが農業をすれば、農地の見た目の美しさは維持されるかもしれないが、生活の匂いは伝わらない。全自動化が求められているのは働き手がいなくなったからだ。しかし、この研究は対症療法でその場しのぎのように見える。完全自動化しても人手は要る。機器を使いこなす人材の教育や故障時の修理要員など、全自動化の普及に伴う新しい仕事が生まれるはずだ。人手不足の根本原因への対処が必要だ。月を撃つような斬新な発想で研究開発に取り組むなら、工学的な機械開発だけではなく、労働や人口などの社会科学と組み合わせ、農村への定住化対策も視野に入れた広い分野の研究として進めてはどうか。若い人が居つく農村像を描いてほしい。ノラ・ジョーンズさんの歌では「あなたは月を撃とうとして、完全に失敗した」と続く。国民の期待を見定め、的を外さない研究を求めたい。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p49361.html (日本農業新聞 2019年11月30日) 伸びる米粉市場 実需と結び付き強化を 米粉の消費が伸びている。品質の向上で品ぞろえが増えたことが大きい。国の後押しで輸出機運も高まる。課題は生産の安定、実需との結び付き、製粉コストの低減、魅力的な商品開発だ。有望な米粉市場を安定軌道に乗せるため、官民一体で取り組みを加速させよう。米粉新時代を開いたのは、圧倒的な品質力だ。微細粉にする高い製粉技術、加工技術の進展で、パンや菓子、麺など多彩な商品化が実現。和菓子やせんべいの原料だった従来の米粉の世界を一新した。2018年からは、日本米粉協会が、健康食材の特性を生かす「ノングルテン米粉認証制度」、消費者が選びやすいよう菓子・パン・麺用の表示をする「米粉の用途別基準」の運用を始め、普及に一役買った。アレルギー対応食材として認知度も高まり、需要量は近年、堅調に推移。農水省などによると17年度2万5000トン、18年度3万1000トン、19年度は3万6000トンを見込む。消費増で工場の稼働率が向上し、一部メーカーは小麦粉並みの製粉コストを実現している。問題は、伸びる需要に生産が追い付いていないことだ。米粉用米は、水田活用の直接支払交付金による転作支援もあり、一定に定着した。過去2年は2万8000トンで推移。19年度も同水準になる見込みだ。主食用価格が堅調で、米粉用米の生産が足踏みしている状況だ。実需側の在庫も少なく、このままでは3万トンを超す需要を満たせず、地域によっては原料確保に苦心する企業も出そうだ。有望な米粉市場に生産現場が対応できないのはもったいない。専用品種や多収品種の導入で、主食用に近い収益性を上げている産地もある。米粉用米生産の政策目標は25年度までに10万トンにすること。伸びしろはある。官民挙げ、水田フル活用による転作誘導、生産と実需の結び付きを強めるべきだ。もう一つの活路は海外市場だ。欧米では、麦に含まれるグルテン由来の疾病が社会問題となっており、「グルテンフリー市場」が急成長している。日本の米粉・関連食品の輸出は過去2年間は、約50トン、約200トン。今年は約700トンを見込む。着実に増加しているが、まだ緒に就いたばかりだ。日本の強みは、グルテン含有量「1ppm以下」という世界最高水準の「ノングルテン表示」で日本産米粉をアピールできること。だがこの表示は民間認証で、これを早急に日本農林規格(JAS)に格上げして、農水省による「お墨付き」として海外市場での有利販売につなげてほしい。併せて、混載による流通コストの低減、米粉ラーメンなど付加価値の高い加工品の開発、現地での地道な販促活動を継続すべきだ。米粉の市場性、可能性を追求することは、日本の水田を生かし、世界の健康に貢献することにつながる。 *2-5:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019091901002102.html (東京新聞 2019年9月19日) ゲノム食品、表示義務なし ルール決定、年内にも流通 消費者庁は19日、ゲノム編集技術で品種改良した農水産物の大半について、生産者や販売者らにゲノム編集食品であると表示することを義務付けないと発表した。ゲノム編集食品は特定の遺伝子を切断してつくられるが、外部から遺伝子を挿入する場合と挿入しない場合があり、現在開発が進む食品の大半は挿入しないタイプという。厚生労働省は同日、同タイプの販売について安全性審査を経ずに届け出制にすると通知。今回の消費者庁の発表で流通ルールの大枠が決まった。早ければ年内にも市場に出回る見通しだが、表示がなければゲノム編集食品かどうか分からず、消費者から不満が出るのは必至だ。 <他の地方産業> *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p49495.html (日本農業新聞 2019年12月15日) 「森林サービス」創出 健康需要で産業化へ 林野庁 林野庁は、森林空間を活用した「森林サービス産業」の創出に乗り出した。森林空間そのものを活用し、これまでの木材生産・供給だけでなく、健康需要などを見据えて森林体験や商品開発で新たなビジネスを生み出し、山村地域に新たな雇用と収入を生み出すのが狙い。どれだけ多くの民間団体・企業の参入を促し、定着させることができるかが鍵となりそうだ。同庁は、健康志向の高まりに加えて、企業が従業員の健康管理を考える「健康経営」の考え方が広まっていることや、インバウンド(訪日外国人)需要が伸びていることに着目。「健康」「観光」「教育」の観点で森林を活用して、新たな需要を取り込むのが「森林サービス産業」の狙いだ。子育て層を対象にした森林体験、企業の研修・保養利用などを想定する。具体策を検討するため、同庁は有識者らでつくる森林サービス産業検討委員会(委員長=宮林茂幸東京農業大学教授)を設置。①エビデンス(効果)②情報共有③香イノベーション──の専門部会で議論に着手。19年度中に報告書を取りまとめ、20年度以降、モデル育成を本格化させる。香イノベーション部会では、スギやヒノキなどを精油の原料として有望視。新たな市場形成を見据え、精油の効用やアロマテラピーでの使用状況などを調査する。エビデンス部会は、森林浴などが健康に与える効果のデータを集積し、事業化を後押しする。今年度は研究成果などの情報を集める。情報共有部会では、森林サービス産業に関心を持つ企業や団体、自治体などを引き合わせるプラットフォームの創設を構想。同庁は「Forest Styleネットワーク」を発足した。12月3日時点で63の企業や団体、地方公共団体などが加入。今後、新たな事業が生まれるきっかけを生み出す交流の場としたい考えだ。同庁は「民間や自治体と協力し、モデル地域の育成を進めていく」(森林利用課)としている。 *3-2:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-851348.html (琉球新報 2019年12月1日) 沖縄へのクルーズ船の寄港、過去最多の719回予定 2019年 アジアのクルーズ市場拡大が背景 2019年の沖縄へのクルーズ船の寄港予定回数が19日現在で、過去最多を更新する719回に達することが主要5港の港湾管理者への取材で分かった。18年は529回の見込みで、来年は1年で190回の大幅増となる。那覇港が67回増、平良港が63回増、石垣港が51回増でけん引している。719回寄港すれば130万人が訪れると試算でき、入域観光客数増加に寄与しそうだ。18年は12月31日までにクルーズ船の寄港数が2回以上あるのは5港で那覇243回、中城28回、本部2回、平良144回、石垣107回。その他が計5回で過去最多の合計529回となる見込み。19年の寄港予定は那覇310回(18年比67回増)、中城43回(同15回増)、本部1回(同1回減)、平良207回(同63回増)、石垣158回(同51回増)となっている。本部を除く4港で軒並み増える予定で、記録を塗り替えることになる。県がまとめたクルーズ船の寄港回数と海路入域観光客数をみると、17年は515回の寄港で94万1900人が訪れている。1回当たり1828人が訪れた計算となる。この数値と19年のクルーズ船寄港回数を単純に掛けた場合、19年の海路入域観光客数は131万5千人になると試算される。沖縄へのクルーズ船寄港数の増加は経済成長著しいアジアでのクルーズ市場拡大が背景にあり、今後も寄港増や船舶の大型化が見込まれる。県内の主要5港では岸壁の新設、整備、改良などが実施、計画されており、受け入れ態勢整備が進んでいる。そのためクルーズ船の寄港回数は今後さらに増加すると予想される。一方、クルーズ船は台風や寄港地変更などによってキャンセルされることもあり、実際の寄港数は予定数から減少することもある。 <解説>巨大市場近接で優位/交通渋滞解消など課題 2019年の沖縄へのクルーズ船寄港予定回数が過去最多の719回に達する背景には、クルーズ市場が拡大するアジア市場に近接しているという地理的な優位性がある。クルーズ旅行は比較的安価な「カジュアルクルーズ」の増加に伴い市場が拡大しており、1週間前後の短期間の旅行商品も増えている。特に中国は市場が伸びており、30年には1千万人市場になると見込まれている。巨大市場の上海、厦門、香港などから近い沖縄への寄港が多くなっているという。実際、沖縄以外の国内でクルーズ船が多く寄港するのはいずれも九州の博多、長崎。地理的な近さが強みなのは明らかだ。県内への寄港数を見ても09年は95回だったが、この10年で7倍に急増する見込みだ。そこで国も受け入れ態勢を強化しようと、民間資金を活用した「官民連携による国際クルーズ拠点」を指定している。現在、県内では本部港と平良港が指定されており岸壁が整備されている。那覇港も同制度への応募を準備。石垣港は国の方針で岸壁を延長している。市場取り込みの準備は着々と進む。一方、大型のクルーズ船寄港は一気に数千人が港から押し寄せることになる。那覇港では3隻が同時に寄港することもある。近隣の商業施設の混雑や交通渋滞などが引き起こされ、オーバーツーリズムだと指摘する声もある。観光客、地元住民の不満も低減し、持続可能な旅行形態として定着できるか。市場拡大に向けた受け入れ態勢整備が急務となっている。 *3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191126&ng=DGKKZO52596760V21C19A1MM8000 (日経新聞 2019年11月26日) 水産資源保護へ新規制 農水省、取引に産地証明、各国と協調、乱獲抑制 水産資源の枯渇を防ぐための新たな取引規制ができる見通しになった。魚介類の水揚げ場所や出荷日を示す公的な証明書を作り、国が指定した魚や一部の輸入品を国内で取引するときに添付を求める。違法操業で証明書のない魚介類は事実上、市場で売買できなくなる。米欧が先行する流通の規制を日本も取り入れ、国際的な水産物の資源管理(総合2面きょうのことば)の実効性を高める。魚介類は新興国を中心に消費が拡大し、乱獲による資源の枯渇が懸念されている。農林水産省によると2015年時点で世界の水産資源のうち約3分の1は、このままでは減少が止められない水準まで数が減った。とれる魚が減り、日本の漁業・養殖業の生産量は18年に439万トンと、ピークだった1984年の3分の1になっている。資源の管理に向け、海を回遊するマグロやサンマなどは各国で漁獲枠の設定が進む。沿岸漁業は地域ごとに禁漁期間がある。ただ、管理をすりぬける違法操業は後を絶たない。日本でも2017年の密漁の検挙数は20年前より3割増えた。違法操業を防がなければ、資源管理の実効性は保てない。このため農水省は漁獲段階だけでなく、流通でも乱獲の防止につながる対策をとる方針だ。具体的には魚介類に採取者や水揚げ港、出荷日を記した証明書をつける。漁業協同組合の組合員や国・地方から許可を受けた事業者による適法な漁による水揚げだけが証明書を得られる。証明書がない魚介類は市場で扱えないようにする。不正を防ぐため、証明書は国の登録を受けた漁協などが出す。ICタグなどデジタル化した形式も認める。証明書を義務化する対象は、密漁のリスクが高いナマコやアワビから始める見通しだ。輸入する水産物でも、一部では相手国の証明書を添付することを義務づける方針だ。対象は今後決めるが、輸入額が大きく密漁のリスクが高いイカやサンマなどが候補となる。日本は水産物では世界3位の輸入国。密漁でとった魚介類は受け入れず、海域全体で資源を守る。農水省は関連法案を早ければ20年の通常国会に提出する。法案の成立後、2年程度かけて対象とする魚介類を定め、制度の運用を始める。先進国では輸入する魚介類に証明書を求める動きが広がっている。農水省によると、09年に始めた欧州連合(EU)は養殖を除くすべての水産品が対象で、米国と韓国も乱獲が懸念される一部の魚で採用した。各国が証明書のある魚介類しか輸出入しなくなれば、乱獲された魚介類の流通を世界的に抑えることができる。日本は米欧と連携して、国際的な資源管理の議論を主導する考えだ。漁獲制限による資源管理はルールを守らない漁が後を絶たず、守る漁業者との間で不公平感が出る。岩手県漁業協同組合連合会の担当者は「流通面での対策が講じられなければ、密漁をなくすことはできない」と話す。 *3-4:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191103-00034824-hankyoreh-kr (Yahoo 2019/11/3) イシモチ→スケソウダラ→サバ…熱い海が「国民魚」変える ●朝鮮半島「食卓の魚」変遷史 50年間で表層水温1.23度上昇 全世界の水温変化の2.5倍超え 1人当たり年間水産物消費量59キロ 7年間で60%以上増加…世界1位 温暖化・乱獲でスケソウダラの「国籍」変わる 最近2~3年間の1位はサバ 「飲み水とおかずが切れて兵士たちが動揺した。林慶業(イム・ギョンオプ)将軍がいばらの木を持ってきて水に刺しておくと、イシモチの群れがかかったのでおかずにして食べた」。西海地域では朝鮮の仁祖(インジョ)の時代の林慶業将軍をイシモチ漁の始祖とする伝説が伝えられている。西海を渡る途中、飢えた兵士たちのために釣りをしたところ、木の枝と枝の間に挟まるほどイシモチが豊富に採れたという話だ。茶山チョン・ヤギョンの兄、チョン・ヤクチョンが全羅南道新安郡黒山島(シナングン・フクサンド)に島流しになっていた時に書いた魚類学書『チャ山魚譜』(1814)を改題した詩人のソン・テクス氏の本『海を抱いた本 チャ山魚譜』(2006)にも「イシモチの鳴き声が漢陽(ハニャン、現在のソウル)まで聞こえた」とある。こうした話は文字通り「伝説」としてのみ残った。1970年代には年間3万~4万トンに達していたイシモチの漁獲量は、40年後には半分に落ちた。イシモチを塩漬けにして干して作る干物「クルビ」も、秋夕(中秋節)のギフトセットでしか見られない状況だ。流通業界では2~3年前からニベやイシモチより大きさが3倍ほどある中国産フウセイでクルビ不足を補っている。かつては「国民魚」として東海を泳ぎ回っていたスケソウダラは国籍を変えた。1970年代には年間漁獲量が最大5万トンに達していたが、2010年代に入ってからは1~9トン程度だ。最近は市場に出回るスケソウダラは90%以上がロシア産だ。学界と業界では定着性魚種ではスケソウダラの幼魚の乱獲が、回遊性魚種では水温の変化が影響しているとみている。5年間にわたりスケソウダラの幼魚の放流などの「スケソウダラ再生プロジェクト」を推進してきた海洋水産部は、今年からスケソウダラの漁獲を年間を通じて禁止した。 ●スケソウダラ沈み、サバ浮上 韓国は年間1人当たりの水産物消費量が2017年現在59.3キロで世界第1位だ。「水産大国」ノルウェー(53.3キロ)や日本(50.2キロ)も抜いた。スピードも速い。2000年には36.8キロに過ぎなかったが、60%以上も増えたことになる。その間に「国民魚」も替わった。1990年の国民1当たり1日平均消費量が最も多い水産物はスケソウダラだったが、スルメイカに交替した。最近2~3年のアンケート調査ではサバが名実共に「好きな魚」第1位だ。韓国人の食卓の魚が替わったのには、何よりも朝鮮半島周辺海域の水揚げ推移が変わった影響が大きい。スケソウダラやイシモチだけでなく、東海岸の「常連」だったサンマやハタハタも滅多に見なくなった。一方、カタクチイワシとサバは豊漁だ。1970年には5万トン程度だったカタクチイワシの漁獲量は2017年には21万トンに、サバは3万トンから21万トンに大幅に増えた。1970~80年代には年間3万~4万トンだったスルメイカも2010年代には15万トンにまで跳ね上がった。まず、地球温暖化などによる水温の変化が原因の一つに挙げられる。国立水産科学院の集計によると、朝鮮半島海域の表層水温は1968年~2018年の間に1.23度高くなった。同期間の全世界の水温変化(0.49度上昇)を上回る数値だ。同院のハン・インソン研究士は、「水温上昇時は栄養塩類の量が減り、水産生物の成長が制限され得る。繁殖と生息地の移動も影響を受ける。ただし生息地と魚種によって影響に違いが出る可能性はある」と指摘する。最近、朝鮮半島海域に暖流性魚種のサバやカタクチイワシが大量に入ってきた一方、寒流性魚種のスケソウダラやハタハタは北上した。イカは南海から東海や西海に生息地を広げており、南海岸では亜熱帯魚種が多く見られるよるになっている。クロマグロが2010年に初めて漁獲量統計の対象になったのに続き、去年の統計によれば済州沿岸に現れた魚類の42%がキンチャクダイ、タカノハダイなどの亜熱帯種であった。 ●「幼魚の乱獲を規制すべき」 急激な魚種変化を異常気象だけで説明することは難しい。中国漁船中心の攻撃的な操業や無分別な乱獲などの方が影響が大きいという指摘もある。産卵もしていない幼魚を安値で売ったり生餌に使ったりして水産資源の枯渇を引き寄せているというのだ。スケソウダラ激減のきっかけも1970年の幼魚漁獲禁止令解除だという見方が支配的だ。1976年には、スケソウダラの漁獲量の実に94%が幼魚だった。イカの漁獲量が2016年の約12万トンから昨年の4万トンあまりに急減したことをめぐっても、同院のカン・スギョン研究士は「産卵場所の低水温現象で産卵資源が減少した上、多くの漁船による乱獲まで重なったため」と分析する。昨年発行された海洋水産開発院の報告書『幼魚乱獲の実態および保護政策の研究』によると、2016年の漁獲量のうち、幼魚の割合はタチウオが69~74%、イシモチが55%、サバが41%に達した。産地価格が1万ウォン(1キロ当たり)以上にもなるほど収益性の良いイシモチなどが未成魚(幼魚)のうちに捕獲され、飼料に使われていると報告書は指摘する。さらに「ノルウェーは1971年に30センチ未満のサバの捕獲を禁止した結果、2014年には北東大西洋のサバのうち成魚の割合は89%となった。タチウオ、イシモチなどの幼魚は販売場所や違法漁獲物の取引を規制すべき」と指摘する。 ●おまえ、どこの海から来たの 所得水準が上がり西欧の水産物に対する需要が拡大することにより、輸入品目が多様になった効果もある。サケ、ズワイガニ、ロブスターなど、かつては高級飲食店でしか扱われなかった輸入水産物は、いまや大手スーパーやコンビニでも簡単に買えるようになった。韓国農水産食品流通公社の統計によると、ズワイガニの輸入額は昨年1億2675万ドルで2年前と比べ3倍ほど増加した。サケの輸入の20%を占めるトンウォン産業の関係者は「2000年代に『ウェルビーイング』の流れに乗って大衆的需要が形成された。原価負担が分散し、価格も下がった」と語る。イーマートの関係者は「エビの産地を2015年の3カ所から昨年は10カ国に増やすなど、価格の合理化を図っている」という。水産物の消費の仕方や購買経路が多様化していることも関心が集まる部分だ。大型スーパーなどからからコンビニエンスストアやオンラインに目を向ける消費者が増えている。コンビニ「GS25」の資料によれば、去年1~9月の水産物の売上げは前年同期比で26.1%増え、ロブスターやサバなどの魚介類の売上比率も2017年の8.0%から今年上半期には10.2%に増加した。同社の関係者は「手軽に料理できる食品を求める流れが続いていているとともに良質の食事を求める20~30代が増えたことで、水産物の需要も増加傾向にある」と語った。 <エネルギーの国産化と地方創成> PS(2019.12.18追加):*4-1のように、「環境保護≒不便を我慢すること」と解している人は多いが、飛行機に乗らずに長時間かけて移動する方法を選べる人は限られている。そのため、航空機燃料を水素に変更したり、航空機を電動化したりするのが合理的で、そうすると「環境保護→進歩→経済発展」にできる。その理由は、①便利さを犠牲にしない ②CO₂はじめ排気ガスを出さない ③国産化可能な燃料であるため輸入する必要がなく、エネルギー自給率も上がる ④水素を作るための電力に再生可能エネルギーを使えば、地方振興に役立つ などが挙げられる。そのため、これまで作っていなかった航空機を日本企業が作る場合に、原油由来のジェット燃料を使う航空機を作る必要はないだろう。既に、IHIとIHIエアロスペースは、*4-2のように、2012年に米ボーイング社と共同で世界初の再生型燃料電池システムを民間航空機に搭載して飛行実証することに成功しており、経産省も電動飛行機を作ろうとしている。    *4-2より 2019.1.24News24 2019.2.17朝日新聞 (図の説明:左図のように、燃料電池航空機が既にできており、中央と右の図のように電動航空機の開発も始まっているので、早く実用化すべきだ) *4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191218&ng=DGKKZO53492300Y9A211C1MM0000 (日経新聞 2019.12.18) 先進国「飛び恥」じわり、環境意識、飛行機手控え 航空会社が陸路提供 欧州など先進国を中心に飛行機の利用を手控える動きが広がり始めた。温暖化ガスの排出増加による環境負荷への関心が高まっているためで、16歳の環境活動家、グレタ・トゥンベリ氏が交通手段として飛行機を回避していることでも注目を集める。短距離の移動に鉄道の利用を勧める航空会社や温暖化ガスの排出量の少ない燃料の使用を促す例も出てきた。グレタ氏は米誌タイムの2019年の「今年の人」に選ばれた。9月にニューヨークで開催された国連気候行動サミット、12月のマドリードでの第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)にそれぞれ参加するため、ヨットや鉄道で移動した。環境負荷が比較的小さいとの判断だ。海をまたぐような長距離の移動にも飛行機の利用を避けた。「気候変動の危機が実際に起きている問題であることを示したい」との考えからだ。グレタ氏の出身国のスウェーデンには、飛行機の利用が恥だと考える「フライトシェイム(飛び恥)」という造語がある。スウェーデンの国営空港運営会社によると、1~9月の国内線の利用者数は前年同期より約8%減少した。同社は景気減速に加え、気候変動を巡る議論を要因にあげた。スイス金融大手UBSが9日発表した欧米やアジアなど8カ国の消費者を対象とした調査によると、回答者の37%が環境への影響を懸念し、過去1年間に飛行機の利用回数を減らした。ほかに25%が「利用減を検討している」と回答した。回答者を欧米4カ国に限れば、利用回数を減らした割合は42%で、5月調査(21%)の2倍になった。国際航空運送協会(IATA)によると、18年の航空業界の二酸化炭素(CO2)排出量は約9億トンで、世界全体の約2%に相当した。米国の非営利団体、国際クリーン交通委員会(ICCT)によると、民間の飛行機のCO2排出量は過去5年で32%増えた。年平均では5.7%増で、国際民間航空機関(ICAO)の予測(約3.3%)よりもペースは速い。先進国発の飛行機のCO2排出量が全体の約6割を占める。一部の航空会社は対策を始めた。KLMオランダ航空は鉄道会社と連携し、20年3月からアムステルダムとブリュッセル間の便数を減らし、代わりに鉄道での移動を提供する。米ユナイテッド航空は10月末、CO2削減技術やバイオ燃料開発に4000万ドル(約43億円)投資すると発表した。フランスは20年、同国発の航空券を対象に環境保全のためのエコ課税を導入する方針だ。新たに得られる税収は鉄道などほかの輸送手段の強化にあてる。ドイツも20年、航空券への課税率を引き上げる。米西部カリフォルニア州は19年、輸送用燃料に適用する排出量取引制度を航空燃料にも広げた。UBSは、飛行機の利用を恥と思う動きが「勢いを増している」と指摘する。気候への影響に対する意識が高まれば、欧州における20年の飛行機の利用者の伸び率は19年の前年比約4.8%から3.4%に低下すると推測する。「飛び恥」の意識が急速に高まった場合は、飛行機の利用者の伸び率が前年より3.5%減る可能性があるとも試算している。英ビジネス・エネルギー・産業戦略省によると、英国における国内便の乗客1人当たりのCO2排出量は1キロメートル当たり133グラムと、長距離便(102グラム)や国内鉄道(41グラム)に比べて多い。 *4-2:https://response.jp/article/2012/10/05/182565.html (Response 2012年10月5日) IHI、世界初となる再生型燃料電池システムの民間航空機飛行実証に成功 IHIとIHIエアロスペースは、米ボーイング社と共同で再生型燃料電池システムを民間航空機に搭載し、飛行実証することに成功した。再生型燃料電池システムの飛行実証は、世界初の試み。再生型燃料電池は、充電可能な燃料電池で、エンジンからは独立して電力を供給することができる。また副産物は水のみであるため、省エネルギー化、二酸化炭素排出削減を可能とし、航空機の環境負荷を低減する。今回の飛行実証は、ボーイング社の環境対応技術実証を目的としたecoDemonstrator計画の一環として、米シアトル近郊においてアメリカン・エアラインのボーイング737型機を用いて実施。フライト試験では、航空機の離陸前から高度上昇中において、燃料電池からの発電による電力供給を行い、巡航飛行時に航空機の電源を用いて充電を実施。その後、再度、発電、充電、発電のサイクルを行うことに成功している。IHIは、今回得られた経験をもとに、再生型燃料電池の小型化、大出力化の改良を進め、航空機の低燃費及び環境負荷低減に寄与する民間航空機用補助電源の製品化に向けた検討を実施していく。 <大学入試共通テストでの国語・数学の記述式問題について> PS(2019.12.19追加):*5-1のように、50万人の受験生の採点をしなければならない大学入試共通テストへの国語・数学の記述式導入はしない方がよいと私も思うが、その理由は、①一人の採点者が採点してもブレが生じる記述式を50万人規模で多様な採点者が行えば、入試の質や公平性が確保できず ②そもそも思考力の育成には、学校だけでなく家庭やメディアなど一般社会の大人が論理的な議論を見せておくことが必要であり ③知識や科学に基づかない議論は無意味であるため、高卒段階では知識や理解力を測る方が重要であること などである。 しかし、国語・数学の記述式問題がないとなると、入試改革が漂流状態に陥ったとする論調も多く、*5-2のように、「情報をつなぎ合わせただけの文章を書く」「他の学生と同じような論点を書く」「検索で集めた情報の中から自分の意見を探す」などとも書かれてもいる。しかし、「ジョークを2つ示して、共通する笑いどころを考えて書かせる」よりも、インターネットで情報を集めて自分の意見をまとめた方がずっと高尚なものができそうであり、思考力・表現力・批評力は内容があって初めて意味があるものだ。従って、知識の活用力は大学入試で測るよりも、大学卒業後に持っておくべきものだと、私は考える。 なお、私がこのブログで記載している文章について、「新聞等の情報をつなぎ合わせただけの文章を書いた」と思う人がいたとすれば、それは甘すぎるし、女性を過小評価している。何故なら、これらの文章は、大学までに学んだ知識、公認会計士・税理士として持っている知識・経験・監査手法、国会議員として社会調査を兼ねて地元を廻りながら集めた問題点などを総合的に考慮して書いたもので、添付した新聞記事等は、情報の比較やup-date・証拠資料などとして使っているにすぎないからだ。このように、記述式の評価は採点者によって異なり、採点者は自分の知識・経験・想像力の範囲内でしか採点できず、最高でも7~8割しかとれないのである。 *5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191208&ng=DGKKZO53091800X01C19A2EA1000 (日経新聞社説 2019.12.8) 記述式入試は抜本的に見直せ 何のための入試改革だったのか。原点に立ち返り、ゼロベースから仕切り直す時だ。政府・与党は、来年度の大学入試共通テストで導入予定の国語と数学の記述式問題を延期する方向で検討を始めた。受験生の混乱を招いた行政の責任は重い。記述式では、50万人規模の採点を民間事業者が担う。採点者には学生バイトも加わる。今国会の審議で文部科学省は、採点の信頼性をいかに確保するかについて説得力ある解決策を示せなかった。実施にこだわる同省は国立大に対し、国語の記述式を2次試験の受験者数を絞る「二段階選抜」に利用しないよう促す。これは、公平な採点が難しいことを認めたに等しい。不信感は募る一方で、政権への批判を恐れる与党が試合中断のタオルを投げ込んだ格好だ。一方、記述式を合否判定に使う予定の国公私立大は全体の半数にとどまった。こうした状況で来年度からの実施を急ぐ意味は実質的に失われた。導入を見送り、各大学が個別試験で受験生の思考力・表現力を測る独自の記述問題を充実するほうが合理的である。新テストでは、英語民間試験でも制度の不備で導入を見送った。入試改革は破綻しつつある。なぜこのような事態に至ったのか。真摯な検証が欠かせない。当初の構想は、一発勝負をやめて、複数回受験が可能な「到達度試験」への転換を目指した。急速な少子化により、大量の受験生を1点刻みでふるい落とす従来型試験の意味が薄れたからだ。共通テストはスリム化する一方、各大学が記述式を含む個別試験を拡充し、学力を丁寧に判定する改革を志向した。しかし、複数回実施は困難と判断。民間の協力で、英語力や思考力を問う方向にカジを切った経緯がある。記述式のみ大まかな到達度で評価し、残りはマーク式の1点刻みで選抜する。矛盾を抱えた新テストの構造自体を抜本的に見直す必要がある。その場しのぎの延期はさらなる混迷と不信を招く。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191219&ng=DGKKZO53509930Y9A211C1CR8000 (日経新聞 2019.12.19) 思考力底上げ 重い課題 共通テスト、記述式見送り、漂流 大学入試改革(上) 2020年度に始まる大学入学共通テストの二本柱だった英語民間試験と国語、数学の記述式問題が消え、足かけ6年にわたった入試改革は先が見えない漂流状態に陥った。混乱の過程で浮かんだ日本の入試制度の課題とその解を探る。情報をつなぎ合わせただけの文章、ほかの多くの学生と同じような論点――。学生にリポートや論文の書き方を教える早稲田大ライティング・センターの佐渡島紗織教授(国語教育)は、学生の文章のそんな箇所に気づくことが少なくない。インターネットで情報が簡単に入手できる現代。「検索で集めた情報の中から自分の意見を探すような傾向もみられる」。このため指導の場面では、ネット上に答えがなさそうな課題を出す。例えばジョークを2つ示して「共通する笑いどころ」を考えて書かせる、といった具合だ。「考える学生を育てることに意識的に取り組む必要がある」と佐渡島教授。ベテランの高校教員からも「この10年間で生徒の思考力が急激に落ちた」「調べて発表するのは得意だが、自分の考えを聞くと答えられない」といった声が上がる。日本の10代の思考力に、黄信号がともっている。文部科学省は共通テストへの記述式問題の導入を、こうした現状を打開する切り札に位置づけた。答えを選択肢から選ぶのではなく、自分の力で書くことで思考力や表現力を測る――。「小中学校は学習指導要領の改訂を経て表現力などを重視する授業に変わっているのに、高校は大学入試に縛られて指導を改善できていない」という同省などの不満もあった。その理念は現実の壁に阻まれた。当初「最大300字程度」だった記述の上限は検討が進むにつれ、「80~120字程度」にしぼんだ。50万人規模の答案を約20日間で採点できるようにするためだが、それでも公平性への疑念を払拭できず、実施まで1年の土壇場で見送りに追い込まれた。「小中学校は指導改善の成果が出ている」という改革の前提も揺らぐ。経済協力開発機構(OECD)の18年の学習到達度調査(PISA)で、日本の15歳の読解力は参加国・地域中15位と過去最低の順位に沈んだ。特に記述式問題の正答率が落ち込み、批評的に考える力の弱さなどが指摘された。思考力の底上げは待ったなしだ。現場は模索する。大分県教育委員会は15年度から「深い学び研究会」と呼ぶ事業を始めた。大きな課題を共同作業で考え、答えを導く「知識構成型ジグソー法」という対話型学習を広め、学びの深化を目指す。6月、同県立大分鶴崎高で開かれた現代文の研究授業では3年生の生徒が哲学者の西谷修さんの評論を題材に「他者との関係があることで、人間が一つの存在として成り立つ理由は何か」をジグソー法で考えた。指導した佐藤秀信教諭は「これからの社会を生きていく力を育むには、本質的な問いに向き合う学習が欠かせない」と強調する。情報化やグローバル化が急速に進み、高校教育も変わる中で、大学入試が旧態依然の暗記中心型であってよいわけがない。知識の活用力や、自分の考えを伝える力を測るうえで記述式問題は有力な手段だが、私立大は実施が難しい大学も多い。次代に必要な学力をどう問うか。今後の制度設計の重い課題だ。 <地方で作れるエネルギー> PS(2019年12月20、23、25、27日、2020年1月5日追加):*6-1のように、COP25は「パリ協定」の実施ルール合意を見送って閉幕したそうだが、国を先進国と途上国に分けて「他国(“途上国”)への“技術支援”で削減できた温室効果ガスの排出量を自国の削減分として計算する」などという小賢しいルールは、“先進国”自体のCO₂排出量を減らすわけではないため、合意しなくてよかったと思う。それより、どの国も実際にCO₂排出量を減らす必要があり、それは可能で、そうした方が日本の地域振興にも役立つ。 例えば、*6-2の福岡県八女市の地域新電力会社「やめエネルギー」のように、地域の再エネを使って発電し、大手電力会社に支払っていた年間約53億円の電気料金の一部を地元で廻したり、もっと積極的にやるとすれば発電した電力を他の地域に売ったり、豊富な水資源を使って水素と酸素を作ったりなど、エネルギーを電力と水素に変えさえすれば、環境と両立させながら地域を潤すことが可能なのだ。 なお、*6-3のように、茨城大学、茨城県農業総合センターなどの研究グループによると、地球温暖化の影響で2040年代には「コシヒカリ」の白未熟粒が全国で2010年代の2倍に増え、その経済損失が351~442億円と見積もられるそうだが、これは佐賀県では既に起こって解決済のことで、高温耐性品種で特A評価のヒノヒカリやサガビヨリなどが開発済である。 「少子高齢化で支え手が不足するから、消費税増税と痛みの分配という難題と向き合うことが社会保障改革である」とする記載は、*6-4はじめ、財務省主導でメディアによってしばしば行われる。しかし、この議論に欠けているのは、①高齢者の生活に対する配慮 ②少子化した理由の正確な分析 ③公会計の導入による国の無駄遣いの排除 ④財源確保の手段に関する工夫 だ。このうち、①については、今回の消費税増税は反対が少なかったが、高齢者は何も言わずに(他に方法がないため)節約するだけであり、それによって財・サービスが売れなくなるのは当然で、実際に生活に困っている人は多いのだ。また、②のように、少子化したことがいけないかのような批判も多いが、日本国憲法で男女平等になった戦後も女性が仕事と子育てを両立できる社会を作らず、憲法施行から65年以上経過した今でも保育所や学童保育が足りず、教育に金がかかるシステムにしておきながら、何でも国民(特に女性)の責任であるかのように言って国民負担を増やそうとするのは不誠実で安易だ。そして、③については、日本は景気対策と称する無駄遣いが多いが、そもそも無駄遣いとそうでないものを区別して、国有財産をしっかり管理できる会計すら採用していないのが大きな問題なのである。さらに、④については、外国に高額の資源代金を払うことが目的のようなエネルギー政策をとって国民を貧しくさせながら、工夫もなくあちこちで金をばら撒いているのを改めればよいのだ。 なお、*6-5のように、唐津市馬渡島と平戸市的山あづち大島周辺の海に、東京都の民間企業が大規模な洋上風力発電を設置する計画があり、最大65基の風力発電機を設置して発電出力61万7500kwを見込むそうだ。私は、遮るものがないので安定した風が吹き、漁業以外の産業がないため地元の人も積極的であることから、離島が風力発電基地になるのはよいが、地元の会社がそれを行えば電力料金が地元で廻るので、さらによいと思う。また、景観や漁業との両立のためには、よくある風力発電機を立てるのではなく、環境影響評価の段階で鳥などの野生動物を巻き込まず、むしろ漁礁となったり養殖と併用させたりできる風力発電機を指定した方がよいため、漁協も出資してお互いに工夫しあう事業主体にしたらどうかと考える。 このような中、*6-6、*6-7のように、政府は、中東海域での情報収集態勢を強化するためとして海上自衛隊を中東に派遣することを閣議決定し、不測の事態(??)に日本船舶の護衛に当たり、武器使用も排除しないそうだ。しかし、エネルギーをいつまでも中東から輸入する高い石油に依存していることも化石の名にふさわしく、「調査・研究」名目なら国会の承認なく自衛隊を海外に派遣できるというのは都合よく拡大解釈しすぎである。さらに、日本の船舶を海賊等から護衛すべきは、日本の自衛隊ではなく、その海域を領有する国の海上保安庁であるため、日本はそのような無駄遣いで負の投資をする金があるのなら、速やかに必要な送電線を敷いたり、レアメタルを採掘したりした方が未来のためにプラスの投資になるのである。 ドイツでは、*6-8のように、太陽光・風力などの再エネ発電シェアが、2019年には前年から5.4ポイント上昇して46%となり、発電量に占める再エネ比率が化石燃料を上回ったそうだ。原子力発電所は海を温める上、事故時は化石燃料よりも深刻な公害をもたらすためお薦めでないが、自動車等の電動化とあいまって、再エネ発電によるクリーンなエネルギー社会を早く作ってもらいたいものである。  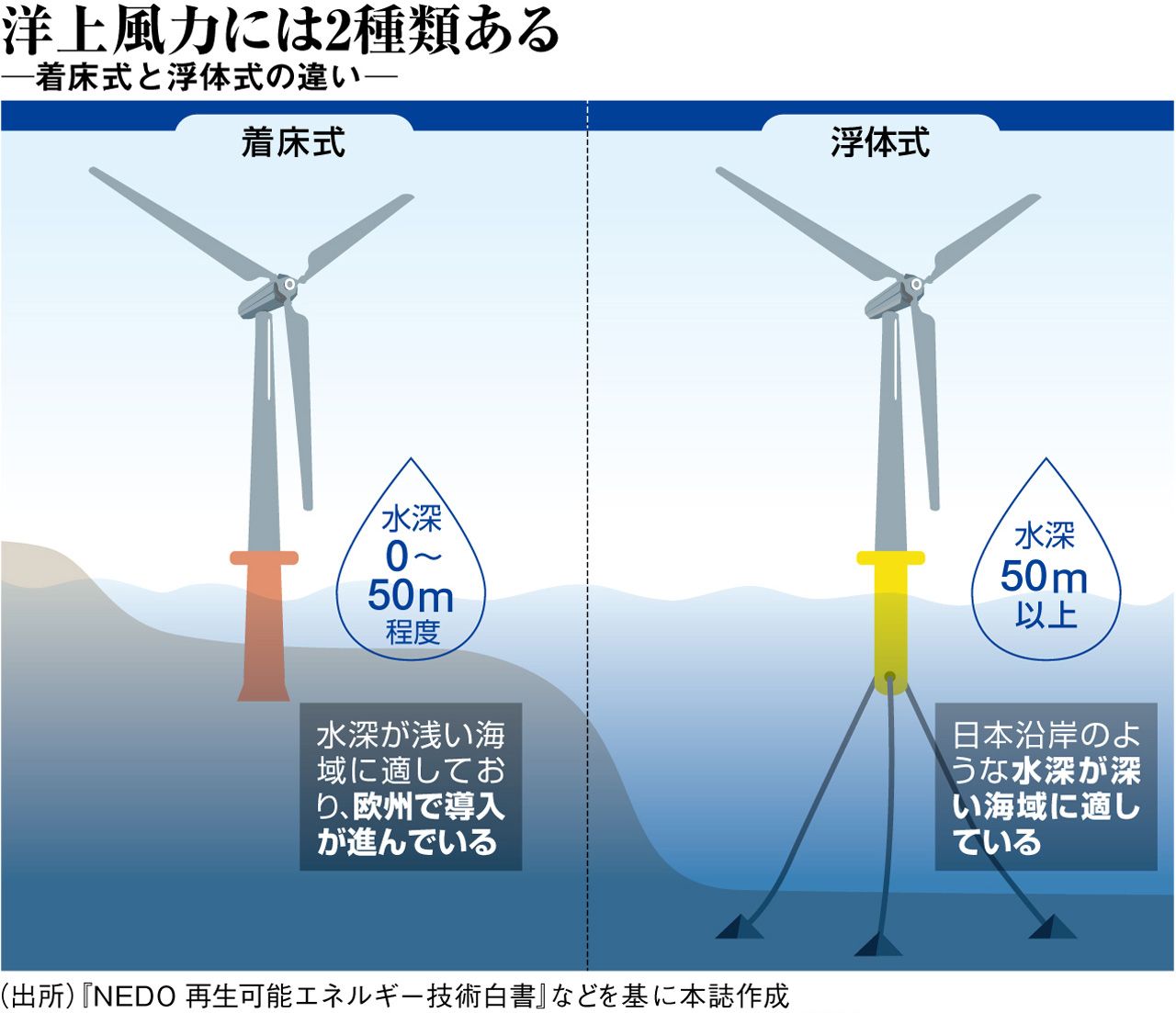 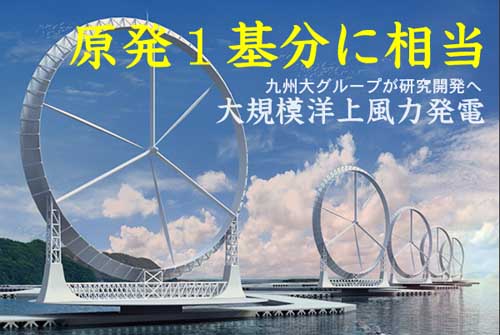  (図の説明:左の2つは、よくある風力発電機。右から2番目は大型の風レンズ風車、1番右は、カーボンファイバーを使った風レンズ風車が養殖施設に併設されている様子だ。右の2つがお薦めで、さらに発電量が増したり、鳥が飛びこまない工夫があったりすればよいと思う) *6-1:https://www.agrinews.co.jp/p49506.html (日本農業新聞 2019年12月17日) 温室ガス削減強化 世界が協調し踏み出せ 地球温暖化の対策を話し合う国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議「COP25」は、「パリ協定」の実施ルールの合意を見送って閉幕した。異常気象による災害が日本を含め世界で頻発している。各国は早期に合意し、二酸化炭素(CO2)をはじめ温室効果ガスの削減強化に協調して踏み出すべきだ。世界の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す「パリ協定」は2015年に採択され、20年に始まる。運用ルールは昨年のCOP24でほとんど決まっており、今回の合意の見送りが与える影響は少ないとの楽観的な見方もある。しかし、完全な形で合意できなかったことは国際協調のきしみをうかがわせた。今回合意を目指したのは、途上国などへの技術支援で削減できた温室効果ガスの排出量を自国の削減分として計算するルール。実効力を高めるものとして期待された。ところが両方の国で二重計上しないルールを巡って難航。自国の実績が減らされることを懸念するブラジルやインドなどが反対し、合意は来年以降に先送りされた。世界最先端水準の削減技術を持つ日本は、東南アジアなどへの技術支援で温室効果ガスの削減に貢献できるはずだ。政府は、早期の合意に向けた合意形成に全力を挙げるべきだ。世界の環境団体でつくる「気候行動ネットワーク」は、地球温暖化対策に後ろ向きな国に贈る「化石賞」に日本を選んだ。石炭火力発電の利用にこだわる政府の方針を批判したものだ。不名誉で遺憾である。政府は、環境に優しいエネルギーに転換する姿勢を示すべきだ。世界の科学者などでつくる、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の特別報告書は、世界の平均気温は17年時点で産業革命前に比べおよそ1度上昇しており、「早ければ2030年には1・5度上昇し、異常気象がさらに増加する」とした。国連環境計画(UNEP)の報告書でも、世界の温室効果ガスの排出が今のペースで進めば、「破壊的な影響」が出ると警告した。削減のスピードを上げなければならない。国連のグテレス事務総長は、9月の温暖化対策サミットでこれまで以上の対策を取るように各国を促した。しかし、来年再提出することになっている削減目標の引き上げを表明した国は、80カ国ほどにとどまる。排出量が多い中国やインド、日本などの主要国の新たな削減への取り組みが鈍い。米国は、「パリ協定」からの離脱を通告したままだ。地球温暖化は世界の食料生産にも甚大な被害を与える。危機感を強めなければならない。今回の会議では、温室効果ガス削減目標の引き上げを各国に促す文言が成果文書に盛り込まれた。義務付けは見送ったとはいえ、各国は足並みをそろえて取り組むべきだ。日本は率先して目標を引き上げ、削減強化の世界的機運を高める必要がある。 *6-2:http://qbiz.jp/article/135441/1/ (西日本新聞 2018年6月10日) 電力料金地元で循環 事業開始から1年 「やめエネルギー」社長 本村勇一郎さん(40) 子育て支援メニュー構想も 福岡県八女市の地域新電力会社「やめエネルギー」が昨年5月に事業を開始してから1年。「電気料金として地域外に流れていた資金を地元で循環させる」ことを目的に、広川町を含む八女地域の73社の出資で設立された。本村勇一郎社長(40)に経営の現状、今後の事業展開について聞いた。 −この1年を振り返って。 「事業所を中心に既存の電力会社から切り替えをお願いして回りましたが、最初は私たちの取り組みを知ってもらう啓発活動のようなものでした。その中で理解をいただいて契約数も少しずつ増えていきました」 −小売り契約数は250件に達した。 「『やめのでんき』のブランド名で販売していますが、茶業、林業、ちょうちんや仏壇といった伝統工芸、酒蔵など八女ならではの事業者の方も契約を結んでくれました。契約容量も約5メガワットまで伸び、近く採算のめどが立ちそうです。当初、みやま市の新電力会社『みやまスマートエネルギー』に担ってもらっていた電力供給も、今年5月からは自社でしています」 −あらためて会社設立の目的は。 「八女市全体で年間約53億円の電気料金を大手電力会社などに支払っていますが、これまでそのお金は地元には残らなかった。電力自由化をきっかけに一部でも地域に残せないか、それを循環させ、八女を潤すことができないかという思いが私たちの原点です」。(以下略) *6-3:https://www.agrinews.co.jp/p49536.html (日本農業新聞 2019年12月20日)温暖化続けば― コシ白未熟粒倍増 年間損失442億円 茨城大学など2040年代予測 茨城大学、茨城県農業総合センターなどの研究グループは19日、地球温暖化の影響で2040年代には、米「コシヒカリ」の白未熟粒が全国で10年代の2倍に増える予測を発表した。これまでのペースで温室効果ガスの排出が増え続けた場合、21世紀末に気温が4度上昇し、40年代に全国の平均白未熟粒発生率は12・6%(10年代は6・2%)。経済損失は1年間で442億円で、10年代の5・15倍と推計した。高温耐性品種の開発など、長期的な戦略が求められる。白未熟粒は登熟期の高温で多発し、米の検査等級が下がるため農家収入が減る。研究グループは、これまで明らかになっていなかった発生率の増え方や経済損失を、主要品種である「コシヒカリ」で日本全国を1キロ四方ごとに区切って予測した。温室効果ガスの排出量は、パリ協定の目標量に抑えられた場合と、これまでのペースで増え続けた場合の二つの想定に基づいて行った。全国の白未熟粒発生率の平均は、パリ協定の目標量に抑えた場合(10年代は7・1%)でも、40年代に10・9%に増えることが分かった。これは10年代の約1・5倍に相当する。発生率が高い地域は、沿岸の平野部から広がり、偏りが予想される。さらに2等米以下の水田面積の割合は、40年代には低くて26・2%、高ければ32・9%と推定した。2等米の発生が増え年間の経済損失は低くて351億円、高ければ442億円と見積もった。同大学農学部の増冨祐司准教授は「温暖化へ長期的な戦略を立てるとともに、高温耐性品種の開発・導入が重要。同時に各地域で実行可能な対策を検討・確立・実施する必要がある」と警鐘を鳴らす。 *6-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019122002000138.html (東京新聞社説 2019年12月20日) 社会保障改革 難題と向き合わぬのか 政府の全世代型社会保障検討会議が中間報告をまとめた。政権主導の改革を担うはずだが、その推進力は心もとない。何より財源確保をはじめ負担の分かち合いという難題に向き合っていない。将来を見据え全世代が安心を得られる制度へのつくり直しができるのか、甚だ疑問だ。「人生百年時代の到来を見据えながら」「社会保障全般にわたる持続可能な改革を検討してきた」。報告書はそううたっている。だが、持続する制度の実現には、必要な財源をどう手当てするのか、その議論が欠かせない。なぜなら、今後直面する大きな課題が、高齢者数がピークを迎え、財源不足と介護などの人材不足が深刻化する二〇四〇年ごろに向けた制度の再構築だからだ。人口減の中で、これまでのように現役世代が保険料で支える力は弱まっている。だから、税財源の根本的な見直しという難題に今から取り組まねば間に合わないのではないか。政権が政治主導で検討会議を設置したのなら、四〇年を見据えた増税など「痛みの分配」こそ果敢に議論すべきだった。安倍晋三首相は消費税率の10%超への引き上げ議論を現政権では封印した。ならば、「将来の安心」を次世代に渡すための財源確保策を具体的に示すべきだろう。今回の改革案は雇用、年金、医療、介護の四分野だが、対策の射程は団塊世代が七十五歳を超え医療や介護ニーズが高まる二五年までだ。しかも、年金では厚生年金の適用拡大の対象となる企業規模の撤廃は盛り込まれなかった。医療の七十五歳以上の自己負担の引き上げもどこまで対象を広げるのか不明だ。業界や与党の反発から踏み込み不足の感は否めない。首相の言う「全世代型」とは、高齢者に偏っている給付を現役世代にも振り向けることのはずだ。だが、肝心の子育て支援策が見当たらない。一九年の出生数は想定より早く九十万人を下回りそうだ。実効性ある支援がなければ少子化を止められまい。気になる点がまだある。制度は「大きなリスク」に備える役割だという。小さいリスクは自己責任でという意味か。リスクの大小を誰が判断するのかも含め丁寧な説明が要る。どれだけの負担を引き受ければ納得できる給付を得られるのか、それを知りたい。政府は、その将来像を早く示すべきだ。 *6-5:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/470024 (佐賀新聞 2019/12/25) 唐津の馬渡島周辺に洋上風力発電計画 東京の企業が県に説明、最大65基設置 佐賀県唐津市の馬渡まだら島と長崎県平戸市の的山あづち大島周辺の海に、大規模な洋上風力発電を設置する計画があることが分かった。東京都の民間企業が計画し、最大65基の風力発電機を設け、総発電出力は61万7500キロワットを見込む。国内では実用例が少ない、海底に固定しない「浮体式」の発電機も導入する見通し。今後は2028年の運転開始を目標に、工事に必要な環境影響評価(アセスメント)への対応を進める。24日に県庁であった県環境影響評価審査会で、実質的な事業主体である再生可能エネルギーの発電事業会社「INFLUX」(インフラックス、東京都)が計画の概要を説明した。洋上風力発電機を設置する想定区域は、馬渡島と的山大島の周辺と中間の海域約1万9546ヘクタール。平均風速が毎秒7・63メートルと状況がよく、水深80メートル以内の比較的浅い区域を抽出した。東松浦郡玄海町の絶景ポイント「浜野浦の棚田」からの景観にも配慮するという。1基当たり9500~1万2千キロワットの風力発電機を最大65基設置する計画で、水深50メートル以内は海底に固定する「着床式」、50メートル以上は「浮体式」を採用する予定。アセスを経て、25年の着工、28年の運転開始を目指す。総事業費は4200~4500億円。今後は地元との調整を進め、渡り鳥など生態系への影響も詳しく調べる。インフラックスの担当者は「事業による環境への影響はあると思われるが、風車の配置などを考慮し、できる限り低減する。地元にも丁寧に説明したい」と話す。県内では同じ会社が唐津市の神集かしわ島近海に、大規模な洋上風力発電設備を設置する計画があり、別の事業者も唐津市肥前町の向島むくしま沿岸に数基の洋上風力発電を設置する計画がある。 *6-6:https://www.sankei.com/politics/news/191027/plt1910270009-n1.html (産経新聞 2019.10.27) 自衛隊中東派遣、ホルムズ海峡排除せず どうなる武器使用 政府は、緊張が高まっている中東海域での情報収集態勢を強化するため、早ければ年明けに自衛隊を独自派遣する方針だ。ただ、派遣の方法や法的整合性の検討、部隊への教育訓練の実施期間を踏まえると来春にずれ込む可能性がある。国家安全保障局を中心に外務省、防衛省などで活動場所や時期の調整を進めている。政府内には「与野党から反対や慎重な意見が相次いでいる。3カ月後(年明け)というのは難しいのではないか」(防衛省幹部)との声もある。自衛隊派遣の検討を具体化したのは、サウジアラビアの石油施設への攻撃、イラン国営会社所有のタンカーの爆発など情勢が緊迫化する中、石油輸入を中東に依存する日本が主体的に情報収集に関わらざるを得なくなったからだ。得た情報は米国主導の有志連合構想に加わる国などに提供する方向で調整している。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は18日の記者会見で、派遣先として「オマーン湾」「アラビア海北部」「バべルマンデブ海峡東側」を中心に検討すると発表。事態が最も緊迫し、情報収集の必要性が高いホルムズ海峡には言及しなかった。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「中東地域のどこかを特筆して排除していない」と述べ、ホルムズ海峡で活動する可能性も排除せずに検討する考えを示した。 ◇ 政府は自衛隊の中東派遣の具体的な方法について、海上自衛隊の護衛艦1隻を新たに派遣する案を軸に検討している。すでに中東近隣で海賊対処の任務についている海自のP3C哨戒機2機のうち1機の任務を今回の情報収集に変更することも選択肢に入る。防衛省の統合幕僚監部の検討チームでは、さまざまな事態を想定しながら必要な装備などについてケーススタディーを進めている。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「新規の船(護衛艦)の派遣と、ジブチを拠点とするP3C哨戒機や護衛艦の活用も検討対象にしている」と説明した。すでにソマリア沖アデン湾での海賊対処のため、護衛艦1隻とP3C哨戒機2機がアフリカ東部のジブチを拠点に他国と連携して活動している。ジブチは情報収集を目的とする今回の派遣候補地に近い。このため、日本から護衛艦1隻を追加派遣して計2隻態勢とすれば、「1隻は既存の海賊対処を継続し、もう1隻は新たな情報収集」という2つの任務の両立が可能となる。海上自衛隊が保有する護衛艦は48隻で、能力や装備が今回の任務に適しているのは20隻余り。中国の海洋進出が強まる中、「東シナ海などに展開する護衛艦を減らして警戒監視を弱めるわけにいかない。現場のやりくりに余裕はない」(自衛隊幹部)と不安視する向きもある。ただ、海賊対処部隊は平成28年、海賊事案の減少に伴い2隻態勢だったのを1隻に減らした。防衛省関係者は「『もともと2隻だろう』といわれれば、その通りだ」と語る。一方、派遣済みのP3C哨戒機2機のうち1機を海賊対処から情報収集に転用する場合、活動場所はバべルマンデブ海峡東側の公海の上空になる公算が大きい。オマーン湾はジブチから2千キロ余り離れており、所要時間や航続距離を考えると往復するだけでほぼ終わってしまうからだ。今回の派遣は、防衛省設置法で定められる省の担当業務「調査・研究」を法的根拠としている。常日頃の日本周辺海域での警戒・監視の根拠規定にもなっている。つまり、中東派遣は通常の任務の延長線上に位置づけられる。正当防衛以外での武器使用はできず、日本関係船舶を武器を使用して護衛することは法的に難しい。 *6-7:https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122700270&g=soc (時事 2019年12月27日) 官邸主導の自衛隊派遣、拡大する恐れ 中東シーレーン安全確保 中東に派遣される海上自衛隊は、不測の事態には日本船舶の護衛に当たり、武器使用も排除されない。本来なら立法措置を講じるべきだが、国会承認の必要がない防衛省設置法の「調査・研究」が派遣根拠になっている。国会のチェック機能が働かず、首相官邸が主導する形の海外派遣が今後、なし崩しに広がっていく恐れがある。調査・研究は学術的なイメージもあるが、「情報収集」と読み替えた方が分かりやすい。防衛相の命令で自衛隊を運用でき、日本近海での日常的な警戒監視活動の根拠になっている。地理的な制約がないとはいえ、中東の緊迫した海域で長期間、実任務に就く活動の根拠に調査・研究を用いるのは、拡大解釈と言わざるを得ない。調査・研究に基づく海外派遣の先例には、2001年の米同時テロ後、米艦などへの後方支援活動に先立ち、インド洋で護衛艦が情報収集に当たったケースがある。ただ、当時の派遣は旧テロ対策特別措置法の成立後で、準備を目的にしたものだった。今回、特措法は制定されず、テロ対策特措法に明記されたような国会承認の手続きは踏まれない。日本船舶を護衛する場合の海上警備行動への任務の切り替えも閣議決定で完結し、国民を代表する国会には結果を報告するにすぎない。首相官邸の裁量で実力部隊の自衛隊を海外で運用することが可能で、シビリアンコントロール(文民統制)や情報開示の面で大きな問題をはらんでいる。 *6-8:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200104&ng=DGKKZO54032220U0A100C2NNE000 (佐賀新聞 2020.1.4) 独、再生エネ発電が逆転、昨年46% 化石燃料上回る ドイツの発電量に占める再生可能エネルギーの比率が2019年に初めて化石燃料を逆転した。太陽光や風力などの再生エネの発電シェアは18年から5.4ポイント上昇し、46%に達した。石炭などの化石燃料は約40%だった。英国でも原子力を含めた二酸化炭素(CO2)排出ゼロの電源が初めて化石燃料を上回り、欧州の脱炭素を裏付ける結果となった。独フラウンホーファー研究機構太陽エネルギー研究所(ISE)が2日、ドイツの19年の純発電量をまとめた。企業の自家発電は含まない。1年間の発電量5155億6千万キロワット時(515.56テラワット時)のうち24.6%を風力が占め、最大の電源となった。発電量は18年比16%増え、シェアは4.2ポイント上昇した。太陽光のシェアは0.6ポイント上がり9.0%だった。バイオマスと水力もそれぞれシェアを伸ばし、再生エネ全体で237テラワット時となり、化石燃料の207テラワット時を上回った。化石燃料では品質の悪い褐炭が4.4ポイント減、石炭が4.5ポイント減とそれぞれ大きくシェアを落とした。発電量でもそれぞれ22.3%、32.8%減った。天然ガスはシェアが3.1ポイント上昇し、10.5%、22年までに運転をすべて停止する原子力は0.5ポイント増の13.8%だった。フラウンホーファーISEは、再生エネの逆転の理由について「発電費用の安い再生エネの拡大で、欧州排出量取引制度(EU-ETS)の排出枠価格が上昇し、CO2排出の多い褐炭などの発電では利益が出なくなっている」と指摘する。英米ナショナル・グリッドによると、英国では19年に風力・太陽光・水力・原子力を合わせたCO2排出ゼロの発電量シェアが48.5%となり、化石燃料の43.0%を初めて上回った。欧州連合(EU)は19年12月、2050年に域内のCO2の純排出をゼロにする目標で合意した。自動車などの電動化が柱のひとつで、動力となる電気を生み出す発電の脱炭素が実現のカギを握っている。 <多様な人が考えれば、地方創生も可能> PS(2019.12.22追加):*7-1に、2018年に関東・関西にある主要6空港以外の地方空港から入国した訪日客は、前年比11.7%増の758万人と入国者数全体の25.2%に達し、客数は2008年の5.5倍になったと書かれている。しかし、福岡の人が欧州に行くには関東・関西の空港まで来て出国するのではなく、福岡空港で出国してソウル空港に行った方が飛距離が短く、乗り換えも便利なのである。つまり、福岡空港・仙台空港・千歳空港などは既にその地域の主要空港であるため、成田、羽田、中部、大阪、関西、神戸の主要6空港を除く57空港を地方空港と位置付けるのは東京目線だと思う。また、佐賀空港は九州佐賀国際空港と名前を変更して海外路線を開拓し、10年間で入国訪日客が70倍以上になったのである。そして、乗客にとっては各地の空港が網の目のように結ばれている方が便利だ。 政府は、*7-2のように、「まち・ひと・しごと創生会議」を開き、2020年度から5年間の第2期地方創生総合戦略を了承したそうだが、その内容は、①地方への移住・定着の促進 ②関係人口の創出 ③2024年度までの東京圏への一極集中是正 ④多様な人材の活躍を目標に据えてJAの参画も強調 などだそうだ。しかし、①には、都市と賃金格差のあまりない仕事の存在が不可欠で、地方の製造業・農林漁業の生産性向上が必要になる。また、③の東京圏への一極集中是正は、過密で狭すぎない住居で暮らせるKeyだが、実行には地方のインフラ・産業・教育・文化の向上が必要で、②④や第1期で行った事業の効果に関する検証が重要だ。 *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191222&ng=DGKKZO53672170R21C19A2MM8000 (日経新聞 2019.12.22) 空からの地方創生(上) 訪日客は地方直行、25%が主要6空港以外へ 西日本の伸び顕著 インバウンド(訪日外国人)の玄関口として地方空港(総合2面きょうのことば)が存在感を増している。2018年に成田や関西など主要6空港以外の地方空港から入国した訪日客は前年比11.7%増の758万人と入国者数全体の25.2%に達した。客数は08年の5.5倍となった。自治体の誘致などで直行便が増え、西日本の空港で伸びが目立つ。韓国や中国など東アジアからが中心だが、欧州便が就航する動きも出ている。16日午前9時すぎ、フィンランド航空の定期便の初便がヘルシンキから新千歳空港に着いた。同国の男性プログラマー(35)は来日17回目だが北海道は初めて。「友人が留学したことがあり来てみたかった」と話す。新千歳には同日、オーストラリアのカンタス航空も就航。タイからは18年に道内の空港を通じ10年前の約220倍の14万人が入国し、観光地は国際色を増す。全国の空港で入国した訪日客は2932万人と10年で3.5倍。地方空港の伸びはそれを上回る。国土交通省「空港管理状況」や法務省「出入国管理統計」などから空港ごとの利用者や入国者を集計。08年以降に訪日客が入国した63空港から成田、羽田、中部、大阪、関西、神戸の主要6空港を除く57空港を「地方空港」として独自に分析した。入国訪日客が最も伸びたのは山形空港。08年の2人が18年に6550人に膨らんだ。台湾からのチャーター便が18年度に123便と4年間で9倍以上増えた。山形県が航空会社の着陸料減免や旅行会社への助成などで支援し、山形を起点に東北の食や温泉を楽しむツアーが人気という。18年の入国訪日客は福岡の241万人を筆頭に17空港が5万人を上回り、うち11空港が西日本だ。東京や京都など「ゴールデンルート」以外を見たいという訪日リピーターを集める。政府も点から線へ訪日客の周遊を誘おうと自治体の広域連携を支援する。佐賀空港は10年間で入国訪日客が70倍以上。18年度のチャーター便は177便と地方空港では4位だった。佐賀県も着陸料などの優遇で訪日客の観光を促し、年間100億円規模の経済効果を見込む。足元での韓国便運休は痛手だが、中国の西安から新路線を招くなど手を打つ。地方発着の国際定期便は19年夏に週1132便と14年冬の1.8倍に増えた。ただ、訪日客は18年に韓国からが全体の4割強で台湾、中国、香港を加えた4カ国・地域が9割を占める。中国などが増え19年1~9月は前年同期を上回ったが、日韓対立の影響で9月にはほぼ全空港で韓国からが前年を下回った。空港経営に詳しい慶応義塾大学商学部の加藤一誠教授は地方空港の東アジア依存について「運航コストや効率面から距離の近い西日本への路線が多くなる」と指摘。「幅広い地域からの路線を誘致するとともに、地元から海外へのアウトバウンド需要の創出にも取り組むべきだ」と語る。19年に日本の12会場で開かれたラグビーワールドカップ(W杯)は訪日客の多様化で可能性を示した。出場17カ国(イングランドなど3チームは英国)からの入国は9月に地方空港で前年比40.6%増と全体の伸びを上回った。20年の東京五輪・パラリンピックでも地方にどう波及効果を呼び込むかが課題となる。 *7-2:https://www.agrinews.co.jp/p49535.html (日本農業新聞 2019年12月20日) 地方創生 第2期総合戦略 人材活用 JA参画を 政府は19日、まち・ひと・しごと創生会議(議長=安倍晋三首相)を開き、2020年度から5年間の第2期地方創生の総合戦略を了承した。関係人口の創出を柱の一つにし、24年度までに東京圏への一極集中の是正を目指す。多様な人材の活躍を目標に据え、JAの参画も強調した。20日に閣議決定する。第2期総合戦略では、最重要課題に東京一極集中の是正を掲げた。18年時点で13万6000人の地方から東京圏への転入超過数を24年度までに解消する。一極集中是正に向けて、地方への移住と定着の促進に加え関係人口創出に力を入れる。兼業や副業で、農山村で働いたり、祭りや草刈りを手伝ったりするなど、多様な形で農山村と関わる関係人口を広げ、地方と都市のつながりを強化する。政府は関係人口の拡大に取り組む自治体数で1000を目安にするが、数値目標(KPI)とはしない。数字ではなく関係づくりを重視したい考えだ。第2期総合戦略の共通目標として、「多様な人材の活躍推進」の他、持続可能な開発目標(SDGs)で持続可能な地域づくりを進める「新しい時代の流れを力にする」を提示した。JAの参画も強調した。具体的には、住民を中心に地域の課題解決に取り組む「地域運営組織」や住民の暮らしを支えるサービス、機能などを集約し、周辺集落と交通網で結ぶ「小さな拠点」の形成などでJAを明記した。国の地方創生総合戦略の決定を踏まえて、各自治体は今年度中にも第1期(15~19年度)の検証と併せ、第2期の地方版総合戦略策定を決定する。 <1カ月ではあてにできないこと> PS(2019年12月28、29日追加):*8-1のように、政府は少子化対策として男性国家公務員に1カ月以上の育児休暇を取得させる取り組みを2020年度から実施するそうだ。男性の育休取得が進まない理由は、①業務面の懸念 ②育休を取得しにくい雰囲気 ③育休中は無給扱いで標準報酬日額の50~67%にあたる手当金が出るが収入減になること などの背景があったからとのことだが、これは女性も全く同じで、男性なら問題にするが女性なら問題にしないという風潮は根強い性別役割分担意識に基づく女性差別だ。また、これを個人の福利を増すためではなく少子化対策としてやろうとしている点は個人を大切にしない全体主義の発想であるし、1カ月休んだくらいでは(何もしないよりはよいが)家事・育児を理解することすらできないと思う。 このような中、*8-2は、スーパーで肉や魚を買った客が、商品のラップを外して中身を包み、トレーは店内のごみ箱にポイとすてることが問題にされており、不便やコストアップを受け入れる意識改革が進んでいるのをよいことのように記載しているが、家事労働を効率化しなければ仕事と家事を両立することはできない。そして、このようなことを、主体として家事労働をした人でなければ想像もつかないのかと不思議に思う。この事例で(1995年頃にリサイクルを提唱した)私が気付くのは、④それから四半世紀経っても不便なままのゴミ収集やリサイクル方法を改善しない自治体や企業の怠慢 ⑤客のニーズに合わせない店舗 である。④については、(指定のごみ袋を買わせるなどして)ごみ収集に手数料をとってもよい時代になったため、分別しやすく、いつでも出せるゴミ収集に改めるべきだ。また、⑤については、私も、トレイに入っている肉が脂身が見えないようにトレイ側に折りたたまれて入っていて「まいったな」と思うことがあるし、確かにトレイはかさばりもするため、トレイに入れたものとビニール袋に入れたものの両方を準備して購入者が選択できるようにした方がよいと思う。 なお、家事の効率化には、*8-3のような加工野菜や調理済惣菜が便利で需要が増えるのは当然だが、これまで加工すると原産地表示が不要になった。そのため、(かなり遅いが)食品表示法改正によって2022年4月から全ての加工食品に原産地表示が義務化されるようになったのは、需要者の手を伸びやすくするだろう。 *8-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191228&ng=DGKKZO53963870X21C19A2EA3000 (日経新聞 2019.12.28) 男性公務員の育休「1カ月超」原則に 少子化対策男女共に手厚く 政府は27日、少子化対策として男性の国家公務員に1カ月以上、育児休暇・休業を取得させる取り組みを発表した。2020年度から実施する。部下の育休は上司の責任と位置づけ、全員取得を目指す。「月100時間残業」といった長時間労働の是正とセットで取り組む必要もあり、職場の意識や働き方を変えられるかが焦点となる。新制度では、既存の育児休業のほか、特別休暇「男の産休」(最長7日間)や年次休暇を活用し、1カ月以上休めるようにする。育休中は無給扱いだが、標準報酬日額の50~67%にあたる手当金が出る。有給の休暇とセットにすることで収入減の懸念を和らげる。このほか男性の育休取得が進まない背景に、業務面の懸念や取得しづらい職場の雰囲気もある。このため、上司が対象職員と相談しながら取得計画を作成し、育休中の職場の体制を事前に整えるとした。部下の取得状況を直属の上司や幹部の人事評価にも直結させて、職場が一丸となって取り組む姿勢を明確にする。今回、対象となる男性国家公務員は約44万人で、長時間労働を抱えるケースの多いキャリア官僚も含む。職場ごとに計画策定や取得状況を公表し、フォローアップすることも検討している。菅義偉官房長官は同日の女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会で、各省庁の幹部に「男性の育児参加、女性活躍、少子化対策の観点から極めて重要だ」と強調した。菅氏の下で8月末から検討を始め、わずか4カ月で制度の発表にこぎつけたのは、少子化への危機感の表れだ。政府は15年に「希望出生率1.8」を目標に掲げたが、18年の合計特殊出生率は1.42と3年連続で下がった。厚生労働省が24日発表した19年の出生数(年間推計)は、予想よりも2年早く86万人まで落ち込んだ。国立社会保障・人口問題研究所によると、夫婦に聞いた「理想」の子どもの数は2.32人。都内の30歳代の女性会社員は「平日の夜は(家事や育児を1人でこなす)ワンオペ。2人目はためらってしまう」と語る。男性が子育てや家事に費やす時間は先進国中、最低の水準だ。一方で、夫の家事・育児時間が長いほど第2子以降の出生割合が高いという調査結果もある。共働き世帯が当たり前になった今、男女ともに仕事と子育てを両立できる職場環境づくりが欠かせない。もちろん育休の取得だけがゴールではない。男性が前向きに取り組めるように、出産前の「両親学級」といったスキルアップの機会を増やすことなども課題だ。政府は民間企業などへの波及も狙う。男性も保育所の送り迎えができるように、子どもと夕食を取れるように、政府と民間が一体となった継続的な取り組みを期待したい。 *8-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/571540/ (西日本新聞 2019/12/27) 食品トレーは必要?“くるりポイ”巡り議論広がる 消費者、店側の声 スーパーで肉や魚を買った客が、商品のラップをくるりと外して中身を包み、トレーは店内のごみ箱にポイ。この「くるりポイ」行為を報じた「あなたの特命取材班」の記事を受け、インターネット上で容器包装のあり方が議論になっている。プラスチックごみ削減が国際的な課題となる中、消費者は何を求めているのか。意見の一部を紹介する。記事をヤフーニュースで公開した11月、コメント欄には約4700件の意見が寄せられた。「私も見た」との目撃情報、マナー面や衛生面で問題視する声に加え、議論は「なぜ『くるりポイ』をする人がいるのか」にも及んだ。理由の一つに挙がったのが、トレーの分別収集の分かりにくさだ。容器包装リサイクル法は市町村に分別収集の「努力義務」を課しており、対応はさまざまだ。福岡市では燃えるごみだが、北九州市では資源ごみ。白色トレーを分別する自治体もあり、「洗浄や乾燥に手間がかかりすぎて、店に捨てる人もいるのだろう」と推測する意見も。来年7月からはレジ袋の有料化が義務付けられる予定だが、「トレーがかさばって持参した買い物袋に入りきらない」との不満も噴出していた。家庭ごみを減らしたい高齢者の事情も垣間見えた。「買った物をカートに積み、バスで家まで運ぶ。少しでも荷物を減らしたい」「有料のごみ袋がすぐ満杯になる。ごみ出しも大変」。商品の見栄えを良くする「上げ底トレー」、野菜や果物を保護する「念のためトレー」、個包装の菓子をさらに包む「おもてなしトレー」などの丁寧すぎる包装についても、店側に簡素化を求める意見が相次いだ。一方で、店側にも言い分があるようだ。「無駄な経費になるトレーなど、本来なら自分たちも使いたくない」。「レジを素早く通して客の待ち時間を短縮し、クレームを最小限にするための店側の気遣いでもある」。「消費者のニーズである衛生的で均一化された品質、安定価格を実現するために、中間センターで食材処理や包装をする仕組みができあがってきた。変えるには、不便やコストアップを容認する消費者の意識の変化も必要」。確かに「野菜が少しでも傷んでいると苦情が出るので、トレーに入れる」というコメントもあり、多様なニーズの板挟みとなっている様子だ。しかし、消費者からは「トレーか袋かを選べるといいのに」「簡易包装でトレーに載せて売り、トレーは店が回収を」などのアイデアも。容器持参で買いたいという声や、トレー価格の上乗せを容認する声も少なくなかった。不便やコストアップを受け入れる意識改革は、少しずつ進んでいる。 *8-3:https://www.agrinews.co.jp/p49580.html (日本農業新聞 2019年12月26日) 加工・業務野菜 需要捉え好機逃がすな 国内で消費する野菜の6割を加工・業務用が占める。高齢・単独世帯や共働き世帯の増加、個食化の進展、消費者の求める利便性・簡便性を背景に需要が伸びる。国内産地は、消費動向を分析し、きめ細かい対応で好機をつかむべきだ。2018年度のカット野菜・冷凍野菜・野菜総菜の小売販売動向調査(農畜産業振興機構)によると、09年から18年までの10年間の全国のスーパー約1000店舗の販売額は、いずれも10年前より増加した。1000人当たりの販売金額は冷凍野菜は5545円と10年前比22%増、野菜菜総菜は7215円と同50%増。カット野菜は7236円と3・3倍になった。伸びが大きいカット野菜を「サラダ」「キット」「カット」「総菜サラダ」に4分類したところ、サラダは同4倍、キットは同3・5倍、カットは同2・6倍、総菜サラダは同3倍だった。品目で見ると、消費動向の変化が分かる。多くの品目が増加する中、ゴボウはカットは減り、総菜サラダが増加。簡便性の高まりで、調理済みの総菜サラダの活用が多い。加工・業務用といったひとくくりの用途ではなく、末端の消費動向を詳しく分析した産地づくりが必要といえる。日本農業新聞は企画「ゆらぐ基~広がる危機」で、人手不足に悩む外食企業が、カット野菜の使用を増やしている事例を紹介。その需要に対し輸入野菜が浸透し、国産が需要を取りこぼしている点を指摘した。国内産地は今まで以上に加工・業務用に目を向けるべきだ。JAグループでは、JA全農が加工・業務用のブロッコリー産地づくりに乗り出した。東北から九州の10県の生産者に、加工時の歩留まりが良い通常の2倍の重さのブロッコリーを生産してもらい、コンビニのセブン―イレブンと取引。11月から国産サラダとして販売が始まった。全農によると、契約取引で農家は安定収益が見込め、調製作業の省力化といった利点もあるという。食品表示法の改正で、22年4月には全ての加工食品に原料原産地の表示が義務化される。国産ニーズが高まることは必至で追い風が吹く。この好機を商機に結び付けたい。農水省も来年度の概算要求で、加工・業務需要に対応した新事業を要求。安定的な生産・供給に向けて、生産事業モデルの育成を支援する計画だ。事業者にとって使い勝手のよい支援策となるよう求める。加工・業務用野菜の取引は「定時・定量・定品質・定価格」の「4定」が重要といわれる。青果物は天候不順に合いやすく「4定」を履行するには、需給調整が大きな鍵を握る。産地だけでなく、卸売会社などの流通業者の協力も不可欠だ。業界一丸で「4定」に挑戦し、加工・業務需要を取り込み、産地の活性化につなげよう。 <「日本産は安全」とも言えないこと> PS(2019年12月31日、2020年1月9日追加):*9-1のように、TPP発効から1年経過した現在、日本産を優遇してきた関税の削減・撤廃で食肉・果実を中心に輸入が増え、今後は日欧EPAや日米貿易協定も発効するので日本の農業は自由化の波に晒されている。しかし、日本産の肉は確かに美味しいが蛋白質を摂りたいのに同時に多量の脂肪を摂らされ、(米国産は安いが品質がイマイチというのと異なり)カナダ産の豚肉は美味しくて脂肪が少ない上に安く、ニュージーランド・オーストラリア産の牛肉は脂肪が少なく価格も安いため、私も普段使いはこちらに変更した。しかし、これらは、飼育方法を変えれば日本でもできることなのだ。また、ニュージーランド産のリンゴは手頃な大きさで一人暮らしや少人数の家族に適している上、価格も安い。一方、日本産は価格が高い上に大きすぎて少人数の家族には向かず、冷蔵庫にも入りにくい。つまり、日本産は、マーケットリサーチしてニーズに合わせた生産をすることが苦手で、その理由は、農業が国に頼りすぎているからなのである。そのため、農協始め農業関係の皆さまは、農業で勝っている国を訪ねて農業の「Best Practice」を実地に調査されるのがよいと考える。 それでは、日本産は安全なのかといえば、牛肉は米国に合わせてBSEの検査基準を引き下げたため米国並みになり、それなら安い方がよいことになった。また、*9-2・*9-3のように、経産省と(疫学の専門家ではない)原発の専門家が「基準値以下に薄めればよい」などという非科学的な理屈で、フクイチの汚染水を海洋放出か大気放出すると決めたような感覚だ。そのため、「日本産」の表示は安全性を保障しないことになり、安全性は地域の取り組みによって変わるものの、地域別の産地表示がなされていなければ選択することができないため、日本産全体を避けた方がよいことになるわけである。 このような状況の下、*9-4のように、立憲民主党と国民民主党が合流協議で焦点の一つとなっている原発政策で、「再稼働を認める条件を厳格化して原発ゼロを目指す方向」という玉虫色の決着をするそうだ。しかし、電力自由化が進んだ今、大手電力会社もグリーンエネルギー・全国展開・海外展開などの新しい選択肢ができたのだから、電力総連の組織内議員を抱える国民民主党がこのような対応をするのは、野党の弱さの原因の一つになるだろう。 *9-1:https://www.agrinews.co.jp/p49626.html (日本農業新聞 2019年12月31日) TPP発効1年 食肉、果実で輸入攻勢 日米控え警戒強まる 環太平洋連携協定(TPP)の発効から30日で1年。関税の削減・撤廃を機に、食肉や果実を中心に輸入攻勢が強まり、国内農業はかつてない自由化の波にさらされている。各国が対日輸出を強化する中、参加国と非参加国でのシェア争いも激化。日欧経済連携協定(EPA)に続き、年明けには日米貿易協定の発効も控える。国内では警戒感が広がっている。 ●豚肉・牛肉 カナダ産対日強化 「カナダにとって日本は最大の輸出相手国に成長した。TPPによってさらに新しいチャンスがきた」。カナダ産豚肉の輸出団体、カナダポーク・インターナショナルは11月、対日輸出増の手応えをこう表現した。財務省の貿易統計によると、1~11月期の豚肉の輸入量は、前年同期比4%増の88万6671トン。同5%増のカナダ産は、4月に単月の輸入量で初めてトップの米国を上回るなど勢いを増す。「品質には定評がある。関税削減で価格面でも優位性が高まった」(大手輸入業者)など、品質・価格の両面で攻勢をかける。国内での人手不足が深刻化する中、カットなど1次加工品を中心としたメキシコ産も同16%増と大幅に増えた。牛肉は、輸入量全体では前年同期並みだが、カナダ産が同95%増の3万9730トン、ニュージーランド産が同32%増の1万7368トンと、参加国からの輸入量は大きく伸びた。「関税削減で高価格帯の価格が下がり、米国産からシフトした」(食肉業者)という。主力のオーストラリア産は現地価格の高騰が影響したため、同5%減となった。輸入と競合するとされる乳用種の小売価格は、年明け以降、下落傾向が続いている。農畜産業振興機構の調べによると、2019年度の11月までの乳用種など「その他」の牛肉の小売価格は、ばら肉が100グラム当たり386円と前年度比9%安となっている。 ●ブドウ・リンゴ 店頭でも存在感大 スーパーなどの店頭で急速に存在感を高める輸入果実も、TPP参加国からの攻勢が鮮明になっている。発効国で関税が撤廃されたブドウは同27%増の4万3556トン。オーストラリア(25%増)やメキシコ(122%増)などからの増加が目立つ。卸売業者は「種なし皮ごとの手軽さが消費者に受けている。関税撤廃で価格が下がったことも大きい」と指摘する。リンゴも、同30%増えた。ニュージーランド産が同35%増と大きく伸ばした。異常気象や高齢化で国内産地が課題を抱える中、「国産リンゴの不足分を補う」(卸売業者)との声もあり、シェアを奪われる可能性がある。 ●ワイン・乳製品 低価格の競争激化 ワインは、同7%増の26万1359キロリットル。日欧EPAで関税が即時撤廃された欧州からの増加が中心だが、メキシコ(15%増)、ニュージーランド(7%増)などからの輸入も増えた。山梨県で「日本ワイン」の醸造に力を入れるワイナリーは「国内では、低価格帯のワインを選ぶ消費者の比率が高い」と、輸入増加による競争の激化を懸念する。乳製品は、ナチュラルチーズが同6%増の27万900トンとなった。もともと関税が低い野菜は、大幅な増加は見られなかった。 ●影響監視継続的に 農畜産物の貿易に詳しい北海道大学農学部の東山寛准教授の話 食肉やブドウといった果実など影響が懸念されていた品目では、確実に輸入量が増えている。国は、品目ごとの輸入量の動向や国内価格への影響を継続的に注視して、必要な国内対策に結び付けることが重要だ。今後、懸念されるのが、国内対策の財源確保になる。これまで安定的な財源となっていた関税やマークアップ(輸入差益)が年々減っていく中で、将来的にどう財源を捻出するのか。国は明確な枠組みを示すべきだ。4月以降、関税の削減率は3年目水準に下がり、輸入攻勢はさらに強まるだろう。産地には、価格ではなく、付加価値を高めるなどの対抗策が求められる。 *9-2:https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=600592&comment_sub_id=0&category_id=142 (中国新聞 2019/12/29) 福島原発の処理水 地元に我慢強いるのか 東京電力福島第1原発の汚染水は、いくら処理しても放射性物質が残る。タンクに保管され、増え続ける「処理水」をどうするか。政府の小委員会の議論が大詰めを迎えている。海洋放出と大気放出を軸にした取りまとめ案を先ごろ、経済産業省が示した。風評被害の懸念は根強く、タンクでの長期保管を望む声もある。技術面や時間的制約から選択肢を絞り込んだのは理解に苦しむ。未曽有の原発事故によって、深手を負った地域経済は今もなお復興の途上にある。追い打ちを掛けるような提案ではないのだろうか。小委員会では、他にも地層注入、放射性物質トリチウムの分離、地下埋設の3案を検討課題としていた。いずれも新たな技術や規制が必要だとして、「現実的な選択肢として課題が多い」と除外。前例が国内外にある、海洋と大気に放出する案だけを残した。廃炉作業では、溶融核燃料(デブリ)の取り出しという未知の技術開発に挑もうとしている政府の姿勢とは、落差があまりに大きい。処理水でも、地元が風評被害に遭わずに済む手だてを見いだすべきである。結論を急ぐのは、2022年夏ごろまでに保管タンクに収めきれなくなることと無関係でないだろう。背に腹は代えられないからと、手っ取り早い策を選んだように映る。取りまとめ案では、保管中の処理水全てを1年間で海洋や大気に捨てたとしても、一般の人が年間に被曝(ひばく)している線量の約1600分の1~約4万分の1にとどまるとしている。だからといって風評被害が起きないとは限るまい。地元にとって死活問題であるのに、風評被害の深刻さや規模は比べられないとして、経産省は各案での被害想定を示さなかった。福島県民からすれば、誠実さを欠く態度に受け取れよう。原発事故によって、県産米は今も、放射性物質濃度について全量全袋検査を続けている。農業や水産業にとどまらず、観光にも影響が及ぶ恐れもある。小委員会の委員から「社会的影響は極めて大きい、とはっきり書くべきだ」といった意見が相次いだのは当然だろう。最終的に処理方法を決めるのは政府である。小委員会からの提言書が、重要な判断材料になる。だからこそ、各案が及ぼす風評被害の程度も明記する必要があるのではないか。原子炉から抜け落ちたデブリは水で冷やし続けている。それに伴って生じる汚染水の量は、事故直後に比べて3分の1ほどに減ったとはいえ、1日当たり170トンに上る。おととい公表された最新の廃炉工程では、25年までに汚染水を100トン以下にするとした。それで目いっぱいというのが、安倍晋三首相の言う「アンダーコントロール(制御できている)」の実態に他ならない。福島県内の漁業は、魚種や海域を限定した試験操業がほそぼそと続き、先行きは見通せていない。畜産業でも、避難指示が解除された地域でさえ牛農家の95%が立ち直れていない。地元から上がっている不安や懸念に丁寧に耳を傾け、支援してこそ「復興」は近づく。これまでの苦境を思えば、新たな我慢を強いるべきではない。 *9-3:https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201912/0012996958.shtml (神戸新聞社説 2019/12/29) 原発処理水処分/「安全神話」に頼りすぎだ 東京電力福島第1原発の敷地内で保管する処理水の処分について、経済産業省が政府小委員会に海洋と大気への放出を軸とする3案を示した。いずれも放射性物質による健康不安や風評被害への懸念が大きい。社会的影響を無視した強引な絞り込み方には地元で反発の声が高まっている。ゼロベースで再考すべきだ。第1原発では、事故で溶け落ちた核燃料を冷やす際に生じる汚染水が増え続けている。多核種除去設備(ALPS)で浄化した後の処理水を、敷地内にタンクを増設して保管している。東電は2022年夏ごろに満杯になるとしており、小委員会で検討を続けてきた。ALPSでは放射性物質のトリチウムを除去できない。しかし海水や空気で基準値以下まで薄めれば健康上の問題はないというのが東電や政府の見解だ。国内外の原子力施設で海洋放出されていることも今回の経産省案の根拠になっている。しかし公聴会などでは人体の内部被ばくや、食物連鎖によって濃縮される問題を研究者らが指摘した。トリチウムの「安全神話」が生まれているとの科学的な批判を受け止め、議論を丁寧にやり直す必要がある。そもそも第1原発内だけで保管するのもおかしな話だ。人が住めなくなった原発の周辺地など、候補はある。それなのに、不明確な根拠で保管継続を選択肢から外したのは乱暴と言わざるを得ない。近畿大学などのチームは、トリチウムの除去技術を開発している。こうした研究の実用化を支援することが、事故を起こした東電や国の責任ではないか。処理水にトリチウム以外の放射性物質が残っていたことを東電は公表しなかった。隠蔽(いんぺい)体質への反省も十分でないまま、放出に地元の理解が得られると考えているなら甘過ぎる。自然界に放出した場合の漁業などへの風評被害についても、経産省案は十分に検討していない。住民の実害への不安にも寄り添う態度が見られない。政府案は、コストが低い海洋放出の優位性を強調する文言が並ぶ。リスクを軽んじれば最大の被害を招くという警鐘を真摯(しんし)に受け止めるべきだ。 *9-4:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/381853?rct=n_politics (北海道新聞 2020/1/9) 立憲と国民、原発再稼働厳格化で調整 立憲民主党と国民民主党が合流協議で焦点の一つとなっている原発政策を巡り、再稼働を認める条件を厳格化し、原発ゼロを目指す方向で最終調整していることが分かった。昨夏の参院選を前に両党など4野党が合意した事実上の共通政策に基づき、避難計画や地元合意を条件付け、再稼働が困難な内容とする。立民の枝野幸男、国民の玉木雄一郎両代表が7日夜の会談で一致。関係者が9日、明らかにした。立民が「一日も早い原発ゼロ実現」を掲げ、再稼働を認めないのに対し、国民は「2030年代」を目指し、再稼働を容認する電力総連などの組織内議員を抱える。このため政策は原発が主な論点となっている。 <風と流れをとらえるグリーン&ブルーインフラ> PS(2020年1月3日追加):*10のように、ノーベル化学賞を受賞された吉野彰さんが言われるまでもなく、今後は環境を護る経済でなければ持続可能ではない。しかし、それを実現する技術革新・地域資源の利用などの脱炭素の要請は、実は日本にも地方にも追い風なのである。そのため、国が無駄遣いをする余裕などない人口減時代の新たな国土計画には、いつまでも直接支払いをあてにする農業ではなく、農林水産業を生業とする場所で同時にエネルギーを創出できるような投資をしてもらいたいわけだ。 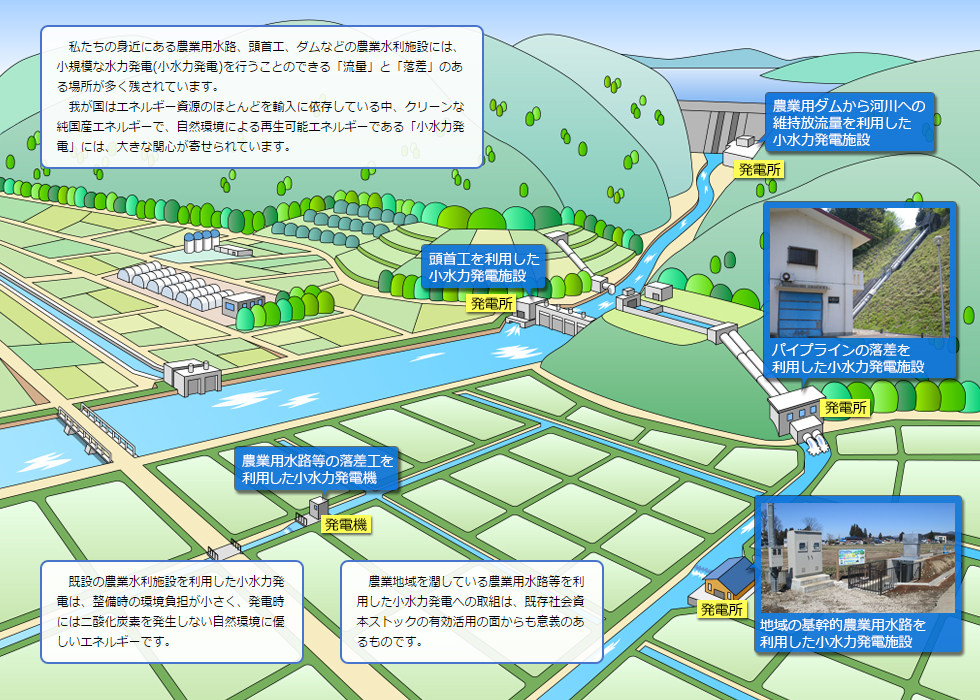     (図の説明:1番左は、農業施設に設置できる発電機例、左から2番目は農業用水路に設置した小水力発電機、右の3つは農業地帯に建てられた風力発電機だが、風力発電機は進歩が望まれる。なお、中央の図のように、田畑が小さく区切られているのをよく見かけるが、もっと大きな区割りにしないと大型機械が入らず、生産性が上がらないだろう) *10:https://www.agrinews.co.jp/p49627.html (日本農業新聞論説 2020年1月3日) [風をとらえる] 緑の資本論 農と自然の力で世直し グリーンパワーが日本を再生へと導く。今年は、農業や自然環境が持つ豊かな恵みを国土や地域づくりに生かす「グリーンインフラ(緑の社会資本)」推進の年。人口減、地方衰退、気象災害などの課題を克服し、持続可能な社会へ踏み出す時だ。成長から成熟へ、競争から共創へ。大転換期を生き抜く「緑の資本論」を提唱する。「グリーン公共事業」「グリーン経済」「グリーン資本主義」。より良い経済や社会のためのキーワードは「グリーン」。総称して「緑の資本論」と名付け、社会課題の「解」を探る。まずグリーンインフラの実例から──。 ●大地潤す命の水 その人は人生を懸けて「命の水」を求めた。昨年12月、アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師。享年73。中村さんは「百の診療所より1本の用水路」を信条に、内戦と干ばつに苦しむ不毛の地で「緑の大地計画」を進めた。生きるための水は、大地を緑の沃野(よくや)に変えた。17年かけて27キロに及ぶ農業用水路を通し、1万6500ヘクタールの土地を潤した。その水は今、65万農民の営農と暮らしを支える。平たんな道ではなかった。資金、機材、技術、労力、どれも乏しい。生態系もこれ以上壊したくない。答えは中村さんの足元、郷里の福岡県にあった。筑後川の中流、朝倉市に江戸時代から伝わる「山田堰(ぜき)」。大小の石を斜めに敷くことで暴れ川の流れを和らげ、用水路に導くせきである。今も現役で、一帯を有数な水田地帯に変えた。この技術を中村さんに橋渡ししたのが「山田堰土地改良区」の前理事長・徳永哲也さん(72)。昨春、中村さんから「ぜひ現地を見てほしい」と誘われ、アフガンに赴いた。「目にしたのは山田堰そのものでした」。胸が詰まった。中村さんも満面の笑み。その笑顔が最後になるとは思いもよらなかった。「山田堰は世界に誇れる技術」と言ってくれた中村さんの思いが今は分かる。「先生の遺志を継ぐのが私たちの務めです」。江戸の知恵が時空と国境を越え、人々の暮らしとなりわいを支える。 ●共生・循環経済を ダムや橋をハードインフラとするなら、今求められているのは「緑の社会資本」。1次産業や自然の持つ多様な力を地域づくりや国土計画、防災・減災に生かすこと。「緑の大地計画」は、その生きたお手本である。国交省は昨年を「グリーンインフラ元年」と位置付け、今年から官民連携のプラットフォームを始動させる。引き金は、深刻化する気候変動と環境破壊、1次産業や地方の衰退だ。食、農、環境など17分野で、2030年までに国連が各国に問題解決を求めた「持続可能な開発目標」(SDGs)。今年から運用が始まる温暖化防止のパリ協定。「持続可能社会」が世界の共通語になった。その有効な解決策となったのがグリーンインフラ。欧米では1990年代後半から、都市緑化による雨水管理、自然環境を利用した減災・防災対策が始まった。特に欧州は生物多様性の保全を重視。水質や大気の浄化で気候変動を和らげる「生態系サービス」の考えを取り入れる。造園家で東京都市大学特別教授の涌井雅之さんは「日本こそが、自然共生と再生循環の歴史を持つ」と指摘。里山などの知恵を引き、日本人は自然を「手入れ」することで、その恩恵を最大化し、災害を最小化してきたという(総合情報誌『地域人』)。 ●農山村は先進地 グリーンインフラは、農業の多面的機能そのものだ。だが生産基盤の弱体化は、災害への抵抗力を弱め、集落機能の喪失は環境破壊の悪循環を招いている。国土管理と防災の視点で、森林・河川、水田、里山・里海、農業水利、都市農地などの役割を再評価し、先端技術と組み合わせ、維持・修復のために直接支払いや公共投資を大胆に行うべきだ。いわば日本版「グリーン・ニューディール」政策である。自然環境の「保全」と併せ、農山村の資源を宝に変える「攻め」でも投資、雇用、人材を呼び込みたい。営農型大型太陽光発電、バイオマス(生物由来資源)や小水力発電によるエネルギーの地産地消、小型電動車の「グリーンスローモビリティ」、人工知能(AI)を活用した「スマートため池」など、農山村は課題解決の先進実験場だ。そこで大事なのは住民の参加。地域内外の多様な人材が、それぞれの持ち場で、課題に関わりを持つことだ。棚田の復活、生き物が集うビオトープや水辺の再生、市民農園参加など、身近なところから一歩踏み出してみよう。ノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんは言う。「環境と経済を調和させる技術革新が持続可能な社会を開く」。地域資源や先端技術を活用し、社会や経済の仕組みを変えるのは脱炭素時代の要請だ。各省庁も発信を強める。国交省のグリーンインフラ戦略のほかに、環境省の「地域循環共生圏」、農水省の「農林水産業×環境・技術×SDGs」構想などがある。新たな国土のグランドデザインに向け、関係省庁を横断的につなぐ国家戦略と体制が必要だ。経済界も変わり始めた。環境や社会課題に配慮した「ESG」投資が広がる。社会貢献が企業価値となる時代だ。「グリーン・キャピタリズム」(緑の資本主義)が企業活動の新潮流になるだろう。国連環境計画(UNEP)は、環境リスクや生態系への影響を減らし、人々の生活の質を向上させて不平等を解消するための「グリーン経済」を提唱する。「緑の資本論」で、環境と調和した持続可能な社会をどうつくるか。国連が求めた「大胆な変革」へ。残された時間は多くない。国家も個人も問われている。 <次の農業基本計画は・・> PS(2020年1月4、9日追加):私は、①食料自給率の向上 ②農業の多面的機能の発揮 ③農業の持続的発展 ④農村の振興 という農業基本計画には賛成だが、「若者が田園回帰し始めても農業者や農地の減少が止まらない」背景には、農業を始めるには「自然や農業が好きであること」以外のさまざまなハードルが存在することがあると思う。そのハードルとは、i)世襲でなければ用地を確保しにくい ii)個人企業なので、資金を要しリスクを伴う iii)機械の値段が高い iv)家族労働を強いるので配偶者に仕事の選択の余地がなく、1人当たりの年収が少ない v)家制度を前提としたムラ社会に溶け込まざるをえない vi)ただ働きが多い などであるため、求められる農業のスタイルは、世襲制度・家制度・家族労働・ムラ社会・共同作業という価値観を共有しなくても安心して農業を選択できる方法を準備すること、農業機械や農業資材の高額すぎる価格付けをやめること、融資やリスク回避の方法を充実することなどだと考える。 上のi) ii)iii)iv)については、*11-2のように、よい承継相手を見つけることができれば世襲でない方法もあるが、譲渡(もしくは賃貸)の範囲や公正な価値について書面で契約しなければ不満が残る。日本では不動産評価に売却価値を用いて収益還元価値を使わないため、立派な果樹等が評価されないことになり易いが、これらは事業承継や企業価値評価に慣れた公認会計士・税理士等に任せればよいと思う。また、引退者が園地を現物出資して承継者と農業生産法人を作り、貢献分の利益を配分してもらえば、引退者は園地と縁が切れる寂しさもなく、承継者にスムーズに技術移転することが可能だ。なお、*11-3のように、若者が推進力となって「田園回帰」が起こっているそうだが、*11-4のように、多様な移住者が活躍できる地域づくり、交通網・病院・学校などのインフラの確保は必要で、全国町村会の食料・農業・農村基本計画の改定に向けての政策提言に期待される。ただし、「交付金」は、既得権益化するのではなく、離陸するための滑走期間の投資として使って欲しい。 *11-1:https://www.agrinews.co.jp/p49633.html (日本農業新聞 2020年1月4日) [風をとらえる] 転換期の基本計画 後世意識し使命果たせ 農家の営農と生活、農村の風景は10年後の2030年にはどうなっているか。国民の食料はしっかり守られているか。目指すべき姿を描く新たな食料・農業・農村基本計画の検討が詰めに入る。時代状況が激変、価値観が多様化しつつある転換期にふさわしい、後世に恥じない基本計画を打ち立てるべきだ。農業者や農地の減少が止まらず、追い打ちを掛けるように国際化を受け入れた。一方で、若者の田園回帰に見られる農業への新たな期待も広がる。その中で迎えた今回の基本計画の改定は、政府の段取りでは3月。審議日程は残りわずかしかない。議論が尽くされているかというと、疑問だ。正式な審議開始は昨年9月で、駆け足の印象を拭えない。だが、基本計画の使命は大きい。原点にさかのぼりたい。初の基本計画は2000年。前年に制定された食料・農業・農村基本法の①食料の安定供給の確保②多面的機能の発揮③農業の持続的な発展④農村の振興──という基本理念に沿った政策を具体化し着実に進めるためだ。当時は、世界貿易機関(WTO)農業交渉が始まるという時期。国際化の荒波から、国民合意の下に農業をどう守るかという切迫した状況認識があった。国民の食料安全保障として食料自給率目標を基本計画で定め、洪水防止をはじめとする多面的機能の維持へ中山間地域等直接支払制度を導入するなど、新たな局面に対応した農政転換を果たしたのもこの時である。今の状況はどうか。環太平洋連携協定(TPP)、日欧経済連携協定(EPA)と日米貿易協定が相次ぎ発効。WTO交渉で想定していた水準をはるかに超える自由化を受け入れた。本来なら経営・所得安定の在り方を抜本的に検討すべきところだったが、基本計画の審議では全く踏み込んでいない。ただ、生産基盤の維持・強化が欠かせないという共通理解は深まった。特に家族経営や中小規模農家に目配りすることを、政府が方向性として示したことは大いに歓迎したい。どう具体化するかが今後の焦点だ。事業の補助要件を緩和するだけで終わらせてはならない。一人一人の力を集め、地域として大きな力を発揮してもらうことが重要だ。その手だてを考えることが、今後の審議に欠かせない。地域の姿が変わりつつあることにも目を向けたい。若者らが農村に移住する動きがある。地域の外から農業を応援する都市住民も増えている。どのようなビジネススタイルや生活のにぎわいが生まれるか、農業・農村の新しいイメージを描く作業も手付かずで残っている。時代の転換期に直面する今回の基本計画は、背負う課題があまりに多い。過去の審議に当たった委員は本紙取材に「いま振り返り、使命を果たしたと言える」(森本一仁氏=農業)と語った。今回も胸を張れるように論議を尽くしてほしい。 *11-2:https://www.agrinews.co.jp/p49678.html (日本農業新聞 2020年1月9日) [新たなバトン 世襲ではない継承へ](2) 果樹園に新規就農 契約巡り食い違い 壁乗り越え信頼感 (山口県周南市) 山口県周南市須金集落。細い1車線の道路を進むと急傾斜のブドウ園が見えてくる。見谷勇さん(86)、朝子さん(83)夫妻が45年前から育ててきた1・2ヘクタールの観光果樹園だ。2年前、見ず知らずの田中友和さん(43)、和歌子さん(42)夫妻が受け継いだ。他人への継承はいくつもの壁があったが、田中夫妻は独立して2年、ほぼ営農計画通りで売り上げも順調だ。友和さんは「消費者に喜んでもらえるブドウを作り、農家の仲間を増やしたい」と見据える。朝子さんは「以前のお客さんが今も喜んで買っている。丁寧な仕事だから、これからも大丈夫」と園を託す。2人とも県外出身の公務員だった田中夫妻。友和さんは働きながら農家への夢を温めてきた。40歳を間近に控えた頃、行楽で見谷夫妻のブドウ園を訪れ、観光農業と果樹に興味を感じた。一方、見谷夫妻の子どもたちは農業を継ぐ気はなく、夫妻も自宅から30分離れた園地に続く細い山道の運転が高齢で難しくなってきたことなどから、離農を考えていた。「あんなに美しい園地は他にない」(県農業会議所)といわれるまでにした園地の荒廃は辛い──。そこで、知人の勧めで県農業会議所の後継者を募集する農家のリストに登録した。2015年、就農先を探していた田中夫妻はリストで三谷夫妻の果樹園を見つけ、会議所に問い合わせた。その後、勇さんと田中夫妻、市など関係機関が集まり、継承に向けた会議を何度も開いた。16年に田中夫妻は退職し、子どもを連れて同集落に移住。2年後の継承に向けて見谷夫妻の元で研修を始め、草刈りや配達などに励んだ。しかし、研修半ばに契約問題が浮上。友和さんは資産の売買額を園地全体のものとして、合意できたと思っていたという。見谷夫妻は金額は農地とブドウの木230本分と捉え、農機や作業所、トイレなどは別途契約すると考えていたため、齟齬(そご)が生じてしまった。当事者同士での話し合いが続いた。ブドウの木が育つまで7年間ほぼ無収入という苦難を乗り越えてきた勇さんは、当初の金額では「納得できなかった」という。他にも、研修内容など意思疎通が難しい局面が何度かあった。勇さんは人に教えた経験がなく、親子以上の年齢差での研修は手探り。特に繁忙期は教える余裕もなかった。肝心の売買金額が合意できず、田中夫妻は研修をやめることも考えたが、未収益期間の長い果樹の新規就農は難しく、最終的には当初の金額から上乗せして契約した。勇さんから過去2回分の青色申告を見せてもらい、経営内容が良好だったことも決断を後押しした。県農業会議所は「契約問題は大きな反省点」とし、教訓とする考えだ。朝子さんは「田中さんたちが折れてくれた」と感じる。見谷夫妻も田中夫妻も「金額面は最初に書面で残すべきだった」と後悔する。だが、継承を果たした今は、互いに感謝する。「懸命に働く姿を間近で学べた」と和歌子さん。友和さんも、棚や農地だけでなく販路も継承できたことは「見谷さんのおかげ」と感じる。勇さんは「山間部で土地は最高。高品質のブドウを作り続けてほしい」と願う。見谷夫妻は継承後、果樹園は見に行かないと決めている。朝子さんは「私たちが行ったら気を使わせてしまう。人柄が優しい2人だから、お客さんとの関係もうまくいく」と見守る。見谷夫妻は心の中で応援し続ける。 *11-3:https://www.agrinews.co.jp/49644?page=2 (日本農業新聞 2020年1月5日) 「田園回帰」着々と 本紙独自調査 28府県移住最多 若者が推進力 都道府県の移住施策担当者に移住者の数や傾向、施策などを聞いた。移住者数の全国調査は政府統計になく、17年度実績から本紙が調べている。17年度は26府県で移住者数が過去最多だった。ただ、各県で移住者の定義が大きく異なり、単純比較はできない。そのため都道府県ごとの過去の調査と比べた。岩手など、調査手法を変えたなどで17年度以前と比較できない県もあった。東京や大阪など都市の都府県は調査しておらず、新潟や熊本は公表していない。長崎県は、移住者を「県と市町村の相談窓口を通じて県外から移住した人」として調べ、06年度からの調査で18年度は初めて1000人を突破した。県によると、16年度に「ながさき移住サポートセンター」を発足させたことなどが奏功し、飛躍的に伸びている。高知県は、「転勤や進学は除き、定住する意志を持って県外から県内に生活拠点を移す」と定義する。県と市町村の相談窓口で把握した数は18年度が934組1325人で、12年度から8倍に増えた。新規就農を希望して移住する若者も目立つ。07年度から調査し、移住者を順調に増やす福井県は、就農相談を定期的に行い、農家希望者向けのバスツアーなど移住と農業部門が連携して進める。専業農家だけでなく、直売所や兼業農家、週末農業など、多様に農との関わりを求める移住者が多いとした県の回答が多かった。一方、移住者数が減り「頭打ち」とする県もあった。島根県は、県外からの転入者に5年以上居住する意志を持っているかを市町村の窓口で調べ、全市町村からの報告から把握する。18年度は3900人で、17年度に比べ200人以上減った。同県は「移住者が減ったことは重く受け止めているが、関係人口の拡大なども力を入れていく」とする。移住者数が減少した他の県も「県の認知度を高めることが重要で、移住者の増減だけで一喜一憂していない」「移住者数の正確な把握は難しく、定住を重視する」などと答えた。 *11-4:https://www.agrinews.co.jp/p49640.html (日本農業新聞 2020年1月5日) [風をとらえる] 農村価値創生 格差解消と両輪で築け 農村に可能性や価値を見いだす移住者らが増えている。この機運を生かし、多様な主体が活躍できる地域づくりを進めたい。それは生産面だけでなく交通網や病院、学校など生活基盤の確保が前提だ。田園回帰を広げ都市との格差解消と向き合い農村価値創生の時代を開こう。移住者に関する日本農業新聞の調査では、以前と比較可能な28府県で2018年度の移住者数が過去最高を記録した。住んでいなくても地域や住民と継続的に関わる「関係人口」や、農村を訪れる訪日外国人(インバウンド)も増えている。人々のつながりや里山の暮らし、食文化、山や田畑といった農村の価値に魅了されている。地元の農家や地域住民だけでなく、世代や仕事、立場などの垣根を越えて連携、融合していくことが農村価値創生の鍵となるだろう。そして価値の土台をつくるには、都市と農村の格差と真剣に向き合わなければならない。農村の価値創生は、効率性や目先の財政にとらわれては実現できない。政府は学校統廃合や病院の再編を進めるなど、地方創生を進めるとしながら矛盾した政策を続けている。また、選果場の閉鎖や、農業施設や水利施設の老朽化、人手不足など生産基盤の弱体化も深刻だ。新しい考えや仲間を受け止める包容力の向上や、多世代が集う場の仕組みづくりなどのソフト面と共に、学校や病院、通信網、農業施設など生活・生産基盤の充実は両輪で考える必要がある。学校や病院がない農村をあえて目指す移住者はいないだろう。全国町村会は食料・農業・農村基本計画の改定に向けて、「新たな価値を創造する舞台としての農村」をつくることを柱とした政策提言を行った。農村の価値を持続的、安定的に高めるための「農村価値創生交付金」の必要性を主張している。地域独自の多様な取り組みが展開できるよう、国が使途の大枠を決め自治体に客観的な基準で配分する仕組みだ。財源は既存の補助金の移行などで確保するとしており現実的な提案だ。交付金は、移住者らの呼び込みや道路や学校、通信など都市と農村の格差解消でも期待される。産業政策や各府省の地域政策と連動させ、政府は総力を挙げて具体化すべきだ。今年は、3月の策定に向けて基本計画の改定論議が大詰めとなる。21年度の施行を目指す新たな過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)も、策定への論議が本格化する。また、20年度から5年間の地方創生の基本方向を示した第2期総合戦略が昨年末に閣議決定され、これを受けて各自治体は地方版総合戦略を策定する。こうした農業・農村振興の中長期的なビジョンづくりとその取り組みに向け、田園回帰を後押しする政策と基盤の格差解消を両輪として考え、農村価値創生を実現させたい。 <ごみ処理と給電・給湯> PS(2020.1.6追加):*12の鳥栖市真木町の広域ごみ処理施設建設予定地は、災害リスクのみならず人口密度から考えても適地ではないだろう。ゴミ処理施設建設は周辺住民に嫌がられるわけだが、少し離れた高い場所にある山林を拓いて作り、ゴミ処理で発生する熱で発電したり湯を作ったりして、迷惑をかける地域の住民に低価格で販売すれば、マイナスとプラスが相殺されるのではないだろうか。発生するCO₂は、それだけなら山林の成長にプラスだ。 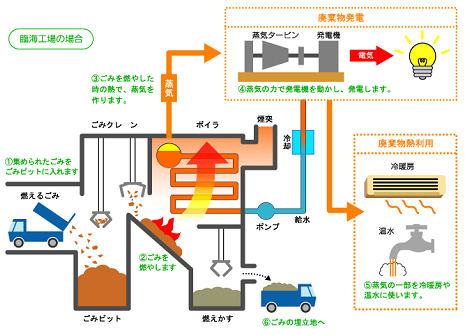 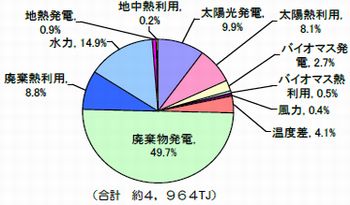 (図の説明:左図のように、ゴミの焼却熱で発電するのは普通になりつつあり、右図のように、再エネ発電に占める割合も高い。また、ゴミ処理時に発生する熱で給湯するシステムもある) *12:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/473078 (佐賀新聞 2019年1月6日) 鳥栖ごみ処理施設予定地「災害の危険」 島谷・九大大学院教授が講演 鳥栖市真木町の次期広域ごみ処理施設建設予定地の災害リスクについて考える講演会が5日、同市内で開かれた。河川工学の専門家で土木学会九州北部豪雨災害調査団長などを務めた島谷幸宏・九州大学大学院教授は「筑後川流域で最も災害の危険性がある地域」と語り、適地ではないとの見解を示した。島谷教授は、国土交通省が2016年に公表したハザードマップで予定地の浸水想定が最大5メートル未満に見直され、地形的にも河川が集中している点に注目。国交省が昨年10月、気候変動で気温が4度上昇した場合、九州北西部は短時間雨量が1・5倍、洪水発生頻度は4倍になると発表したことに触れ、「毎年氾濫が起きる可能性がある。常識的には選ばない場所」と指摘した。福岡県朝倉市などを襲った17年7月の豪雨後に現地調査をした経験などを踏まえ、「仮に大きな水害が発生すれば、1軒当たり2トンの水害ごみが出る。施設をかさ上げして造っても周辺道路が水没し、土砂などが流れてきたら簡単に復旧できないのではないか。ごみが運べず大混乱する恐れがある」などと語った。講演会は予定地周辺の住民らでつくる「ハザードを考える会」(代表=馬場祐次郎・鳥栖市あさひ新町区長)が主催し、同市や久留米市、みやき町などから約100人が参加した。 <これが日本の林野庁のレベルだ> PS(2020/1/10追加):森林の間伐が行われない等の問題点を指摘したら、*13のように、山肌をまるごと伐採する皆伐をしはじめたのが日本の林野庁である。このやり方が、大規模な土砂崩れを発生させると同時に、山の保水力をなくし、流れ出した土で川やダムが浅くなって、水害が起こりやすくなるのは誰でもわかることである。それらを総合的に考えることもできず、単に現在の木材生産量を増やすことだけを目的として、戦後せっかく植えたスギ・ヒノキなどの森林資源を数十ヘクタールにもわたって皆伐するのに補助金を出すなど、専門家のすることとはとても思えず、呆れるわけである。 *13:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/574555/ (西日本新聞 2020/1/10) 「皆伐」から「自伐」減災林業 九州の業者が連絡会結成へ ●小規模作業、土砂崩れ拡大防止に 小規模な林道や作業機械を使って、スギやヒノキなどの人工林を伐採する「自伐型林業」を推進するため九州の自伐型林業者が今月、連絡会を結成してネットワーク化を図る。国は木材生産量を増やすために、山肌まるごと伐採する「皆伐」を推進している。林業研究者は、このやり方が「土砂崩れなどの災害を拡大させる」と問題視しており、山への負荷の小さい自伐型林業の推進により減災を進める狙いだ。自伐型林業は、山林所有者や中山間地の住民が、山の斜面や水の流れを考慮した上で、自らパワーショベルを使って山の中に軽-小型トラックが1台通れる幅2メートル程度の道を高密度に整備し、木材を搬出するやり方。小規模だが、伐採作業を森林組合などに委託する委託料がかからないため利益を出しやすい。一部の木は伐採せずに残して100年超えの優良材に育て、持続可能な林業へつなげる。国内の山林では、戦後の造林政策で植えられたスギやヒノキが利用に適した時期を迎えている。そうした木を数十ヘクタールにわたり高性能林業機械を使って切り出す皆伐が主流となっている。林野庁は2018年度から初めて皆伐(再造林も含む)作業にも補助金を適用する補助事業を始めた。木材生産量を増やし「成長産業化」する狙いだ。自伐型林業を推進するNPO法人、自伐型林業推進協会の中嶋健造代表理事は、17年の九州豪雨で33人が死亡した福岡県朝倉市を調査。その結果、「調査した皆伐地域のすべてで崩落を確認した。地形を考慮せずに林道が築かれ、そこから崩れた場所も目立った」と指摘する。林野庁は九州豪雨の原因調査で「雨量が原因」としたが、中嶋氏は「林業にも大規模災害となった一因がある」と訴える。九州大の佐藤宣子教授(森林政策学)は「皆伐後しばらくたつと広く根を張った木がなくなり、山が最ももろくなる。地形などを踏まえて伐採をしないと災害につながる恐れがある」と話す。連絡会には現段階で、宮崎県、熊本県などで活動する自伐型林業者のグループなど6団体が加入予定。26日に福岡市早良区の九大西新プラザで設立記念講演会を開く。
| 農林漁業::2019.8~ | 04:43 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,08,19, Monday
     (図の説明:日本の農業の代表がワインだとは思わないが、地球温暖化の影響で葡萄の産地が山梨県から長野県の高原にまで広がり、現在、長野県塩尻市では各種の葡萄ワインのほかリンゴ、桃のワインもできている。そのほか、各地でミカンやラフランスのワイン、桃のスパークリングワインなどもできており、私は、輸出するならリンゴ・ミカン・ラフランスのワインや桃のスパークリングワインが、ONLY ONEで有利な競争ができるのではないかと思う) (1)食料自給率の低下と生産力の弱まり 1)食料自給率低下の理由 日本における2018年度のカロリーベースの食料自給率は、*1-1-1・*1-1-2・*1-1-3・のように、37%となり大冷害の1993年度と並ぶ過去最低になった。しかし、今回は、災害による低下ではなく、1965年度には73%あった食料自給率が一貫して下がり続けてきた構造的な問題であり、1993年度よりも深刻である。 一方、日本政府は2025年度に食料自給率を45%に高めるという低い目標を掲げているが、これも達成できそうにない。また、カロリーベースを目標とすることに疑問の声は多いが、価格が高くなると生産量が増えたように見える価格ベースよりは参考になる。そして、人口減少しつつある現在では、食料自給率100%を達成する目標を立てても少しもおかしくないのだ。なお、国内飼育の肉類も輸入飼料で育てると、輸入飼料が入らなくなれば国内飼育もできなくなるため、「自給」に入れないわけである。 長期的な食料自給率低下の原因は、①農業経営体と担い手の減少 ②担い手の高齢化による離農 ③人手不足による新規就農者の減少 ③耕地面積の急減 ④輸入品との競争 などによる国内生産力の弱まりだそうだ。 しかし、*1-1-2のように、今回の食料自給率低下は、北海道の夏の低温と日照不足による小麦・大豆の生産落ち込みが主因で、これに牛肉・乳製品の輸入増加に伴う国内生産の伸び悩みが重なったのだそうで、TPPとEUとのEPAの影響が出てくるのはこれからだが、これに加えてトランプ米大統領が農産物の巨額購入を要求しており、ここにも米国との安全保障条約の見返りに日本の長期的安全保障に関わる農業を犠牲にする構図が見えるのである。 2)日本の農業政策失敗の原因は? 食料自給率が過去最低になったことから、*1-1-3・*1-1-4に、農業の持続可能性を目指すべきことや、食料自給率を上昇に転じる道筋を示すべきことが書かれている。 食料自給率が過去最低になった理由の一つには、地球温暖化を背景とする2018年度の天候不順による影響もあるが、地球温暖化は既に織り込んで対応しなければならない時である。また、農業への若者の参入が少ないため、担い手不足や高齢化が止まらないのは、他産業と比較して①農業所得が低かったり ②所得の不安定性が高かったり ③農業に誇りを持てなかったり ④農業に従事すると仕事以外での制約が増えたりする からだと思われる。 このうち、①②③は、地形や気候を活かした稼げる農業を企画してこなかったことに原因がある。そして、それができなかった理由は、戦後の食料難時代を過ぎてコメ離れが進み、肉を多く食べるような食生活の変化があっても、中央政府が全国一律に米作奨励の補助金を出して他の作物を不利に扱ってきたからだ。これによって、TPPやEUとのEPAの発効で安い農産物が輸入されると、日本の農業は敗退することになってしまったが、“中山間地”という地形が原因でないことは、スイスやコルシカ島の農業が敗退していないことで明らかである。 しかし、それぞれの地形や気候を活かした稼げる農業経営に移行するためには、中央政府が日本全国の農業を一律に企画することに限界があるのだろう。そのため、(個の農家毎では規模が小さすぎるものの)地方自治体くらいが、どういう農業を行って魅力的で稼げる農業を作り、海外と自由貿易しても勝てるようにするかの基本的デザインをすべきだと考える。 なお、④については、*2-5-2に、「家族農業守れる農政を」と書かれているが、「家族農業が基本」とする現在の農村文化は、①配偶者との結婚生活 ②両親を含めた生活形態 ③配偶者の職業 等を制限してしまうため、それでも農業をやりたいという人が等比級数的に減る。それを解決するには、農業経営を法人化して多様な就労形態や生活形態に対応できるようにし、報酬や年金に関する心配を減らすのがよいだろう。 また、現在は、有無を言わせないグローバル競争の時代になっているため、安全保障や外交の代償として農業やその他の産業を使っても日本経済が成立する時代ではなくなり、食料確保のためには食糧自給率アップも不可欠であることを、経産省はじめ中央政府は再認識すべきだ。また、「もうかる農業」を作るツールは、農地集約による大規模化や輸出だけでなく無数に存在するため、国内や諸外国の先進ケースを調査しながら地域全体で企画するのがよいと思われる。 このような中、「小規模農家の切り捨て」に関しては、小規模だからといって甘える時代も早く終わるようにすべきで、農地の「洪水防止」「景観保持」等の機能については、それに見合った適切な金額を環境維持費用として国の予算から支出するのが妥当だ。 なお、担い手不足解消のため、省力化の先端技術を活用したり、農業分野への門戸を外国人労働者に広げたりしたことは重要だ。JA全中は、*1-3のように、政府の2020年度の農業関係予算要請で①食料安全保障の確立に向けた万全な予算の確保 ②新規就農者の育成 ③スマート農業支援の拡充 ④中小経営を含めた青果や畜産の生産基盤強化策 ⑤輸出の拡大 ⑥農泊・農福連携への支援 ⑦鳥獣被害の減少に向けた十分な対策 ⑧災害に強い農業づくりに向けた支援の拡充 などの具体的な要請をしている。また、公認会計士監査への移行に伴ってJAに実質的負担増がないよう支援も求めるそうだが、公認会計士は他産業の経営も多く見てきているため、経営に関するアドバイスを聞けば有益で、単なるコスト増ではなく使いようなのだ。 (2)G20農相宣言について 日本が議長国を務めるG20農相会合で、*1-2のように、世界人口と食料需要増に対応するため、農業の生産性向上や持続可能性をどう確保していくかを議論して「G20農相宣言」を採択するそうだ。 しかし、吉川農相が「(特に中国、韓国とは)フクイチ事故に伴う放射能汚染による日本産食品の輸入規制の緩和・撤廃を中心に話したい」と強調したのは、歓迎レセプションで福島県産などの食材を提供したからといって安全だという証明にはならない上、中国・韓国だけを名指しするのもおかしいため、むしろ日本政府の意識の低さを示すことになりそうだ。 (3)農業経営と人材 1)日本の人材不足 *2-1のように、離農者の農地を引き受けて地域の農地を守りつつ、規模を拡大してきた担い手の労働力が離農者に比べて不足し、今では限界を迎えつつあるそうだ。例えば、両親と3人で農事組合法人を経営して45haを耕作する永須さん(38)は、平場で営農条件は悪くないものの、繁忙期には地域の臨時雇用で人手を賄っていたのに、地域の高齢化でその確保も難しくなり、両親が60代後半となり、マンパワー不足でこれ以上は引き受けられないのだそうだ。 また、JA全青協の副会長を務める杉山さんは、急傾斜地で、両親や弟とミカン2haなどを経営しているが、人手確保や新たな投資に加えて、元の持ち主との仕立て方も違い、老木の改植など果樹特有の課題もあるため、自身は高齢農家に農地の引き受けを求められても、やむなく断ることがあるそうだ。 このように、2018年の農業就業人口は「基幹的農業従事者」「雇用労働力」とも、*2-1のように、175万人と1998年の389万人から55%減少し、全国の農業経営体数も、*2-2のように、120万を割って過去10年で最少規模となり、今後は多様な担い手をどう育成するかが問われているとのことである。 また、*2-3-1のように、若手新規就農者数が2万人を割り込んだのは、他産業との人材獲得競争が激しく雇用就農者が減ったことが影響したからで、このような中、*2-3-2のように、新規就農者を支援する国の「農業次世代人材投資事業」の2019年度予算が、年齢を引き上げて対象が拡大されたにもかかわらず減額されたのは、自治体にとって頭の痛いことである。 しかし、全体としては、既にある農地をどうやって活かすかが問われているのであり、食糧不足で農地も少なかった時代と比べれば、解決が容易な悩みと言える。 2)一般企業の農業参入 一般企業の農業参入条件が緩和された農地法改正から10年を迎え、参入した法人数は全国で3000社を超えて、農家の高齢化や跡継ぎ不足で耕作放棄地が増える中、*2-5-1のように、有力企業も動き出しているそうだ。 イオンは、借地面積約350haと国内最大規模を誇り、有機野菜を栽培する認定農場も運営しており、人間の経験と先端技術を融合した効率的な生産を行って、2025年度までに借地面積を1000haに広げる計画だそうだ。食品小売業者が農業生産法人を作って農業に進出するのは理にかなっており、ブランド化も容易だろう。 ただ、植物工場の収支状況は全体の49%が赤字なのも尤もで、安全で栄養豊富な有機野菜が求められるのに、人工光線と液肥のみで育った植物工場の野菜に価値がつくわけはなさそうだ。 3)外国人材の受け入れ 日本政府は、*2-4-1のように、外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法を成立させ、2019年4月から新たな特定技能制度による受け入れを始めた。新制度の下で働く場合、耕種か畜産の農業技能測定試験と日本語能力の試験を受ける必要はあるが、約3年の技能実習を修了していれば、試験は免除されるそうだ。 農業分野では、受け入れ元の直接雇用に加えて、派遣形態の雇用も認めるため、1)2)の人材不足を補うことができる筈だが、住居の確保やさまざまな支援は必要になる。そのため、*2-4-2のように、福岡県は「福岡県外国人材受入対策協議会」を発足させ、生活・労働情報・課題などを共有して受け入れ環境の向上を図るそうだ。 このような中、*2-4-3のように、日本に入国して強制退去処分を受けたナイジェリア出身の外国人が収容中の施設内で死亡し、大村市の教会を訪れたクルド人の男性(30)は、2カ月間、仮放免の許可を求めて食事を拒むハンガーストライキをして、2年近く収容されていた大村入国管理センターから「仮放免」が認められたのだそうだ。 いずれも、難民や移民の人権を無視し、不法滞在として長期に渡って無為に拘束し、施設で収容中に死亡した外国人が15人(うち自殺者5人)もいるそうで、これは日本国憲法違反であると同時に、もったいないことをしていると思う。 <食料自給率低下と生産力の弱まり> *1-1-1:https://www.iwate-np.co.jp/article/2019/8/12/62220 (岩手日報 2019.8.12) 食料自給率最低 生産力の弱まりを映す 日本の食料自給率が、再び過去最低となった。2018年度のカロリーベースは前年度より1ポイント低い37%で、1993年度と並ぶ。93年度といえば「平成の大冷害」で、米が記録的な凶作に見舞われた。青立ちのまま実らぬ稲が今も語り草になる。その年と同じとは、いかに低い水準かが分かる。自給率低下は、天候不順により小麦や大豆の生産が落ち込んだことが大きい。特に主産地である北海道の生産減が響く。だが、天候だけに原因は求められない。65年度に73%あった食料自給率は、ほぼ一貫して下がり続けている。9年前に40%を割り込んだ後は、30%台後半のままだ。もはや構造的な問題と言えよう。政府は25年度に45%に高める目標を掲げるが、一段と遠のいた。米離れに加えて安価な輸入農産物が増え続ける現状のままでは、達成は極めて困難とみられる。もっとも、食料の重さを熱量換算したカロリーベースを目標とすることには疑問の声が多い。熱量の高い米の比重が大きく、野菜はほとんど評価されないからだ。消費量が増えている肉類は、国内の飼育でも、輸入飼料で育てられると「自給」と見なされない難点もある。このためカロリーベース目標には風当たりが強い。だが、飼料が国産・輸入のいずれかに関係なく計算しても、自給率は46%にとどまる。食料の半分以上を輸入に頼る構図は変わらない。やはり自給率の低下は、国内生産力の弱まりを映すと見るべきだろう。そこから目を背けずに、対策を打たなければならない。生産力が弱まる一因に、農業を担う人の減少が挙げられる。全国の農業経営体数は120万を割り、この10年で50万も少なくなった。耕地面積も急減している。現場では担い手の高齢化が著しい。とりわけ輸入品との競争に直面する畜産・酪農では、やめていく人が増えた。そうなると飼料用の米作りも持続が難しくなる。岩手の17年度の食料自給率は101%で、2ポイント落ちた。100を超えて農業県の面目を保つものの、下落傾向は続く。やはり生産力の弱まりが背景にあるとみられる。現代日本で食料難は想像もできないが、最新の国連推計で30年後、気候変動により穀物価格が最大23%上がると公表された。国家間で食料の争奪が激しくなると見込まれ、輸入頼みは危うい。自給率を上げるには、農地の保全と活用が不可欠だ。中山間地にも農業を営む人がいる必要がある。農業の場合は産業政策とともに、地域を守る政策の拡充を望みたい。 *1-1-2:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/335650 (北海道新聞社説 2019/8/18) 食料自給率最低 政権の危機感が足りぬ 農林水産省が発表した2018年度の食料自給率は、カロリーベースで前年度比1ポイント低下の37%に落ち込んだ。記録的冷夏でコメが凶作となった1993年度と並ぶ過去最低の数値である。自給率が40%を下回るのは、これで9年連続となる。25年度に45%に引き上げるという国家目標は遠のくばかりだ。長期低迷の原因は、農業の生産基盤が弱体化していることに尽きる。高齢化による離農が増え、人手不足のあおりで新規就農者は減少している。これでは国民の食を守ることはできない。政府は農業を安心して続けられる環境整備と、担い手を増やす施策に力を入れるべきだ。今回の自給率低下は、北海道の夏の低温と日照不足により小麦と大豆の生産が大幅に落ち込んだことが主因となった。これに牛肉や乳製品の輸入増加に伴う国内生産の伸び悩みが重なった。ただ、昨年末の環太平洋連携協定(TPP)、今年2月の欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)の発効の影響が出てくるのはこれからである。加えてトランプ米大統領も安倍晋三首相に農産物の巨額購入を直接要求している。輸入農産物の攻勢が本格化する19年度以降、自給率がさらに下落する懸念は拭えない。米国や欧州主要国の自給率は最低でも60%を上回っており、40%未満が常態化している日本の食料事情は極めて深刻である。なのに、安倍政権には全く危機感が感じられない。それどころか、自らの農業政策について、生産農業所得が3年連続で増加しているデータを挙げて「アベノミクスの成果」と自画自賛している。生産農業所得は災害や不作による農作物価格の上昇にも左右される。増えたからといって、農業が強くなった証拠にはならない。昨年までの5年間で国内の耕地面積は約10万ヘクタール、農業経営体は約20万件も減っている。49歳以下の若手就農者数も昨年、5年ぶりに2万人を割り込んだ。政権に都合の良い数値をアピールするのではなく、農地と担い手の減少という現実を直視し、歯止めをかける政策こそが必要だ。国連の気候変動に関する政府間パネルは今月、干ばつの増加などで50年の穀物価格が最大23%上昇する恐れがあると警告した。世界的な食糧難が予測される中で、日本が安易な輸入頼みを続けている場合ではないはずである。 *1-1-3:https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=562805&comment_sub_id=0&category_id=142 (中国新聞 2019/8/18) 食料自給率過去最低 持続可能な「農」目指せ 2018年度の食料自給率はカロリーベースで前年度より1ポイント低い37%だった。コメの記録的な凶作に見舞われた1993年度と並び過去最低となった。地球温暖化を背景とする18年度の天候不順で、北海道などで穀物生産が減ったのが響いた。とはいえ、この10年、自給率は下がり続けており、危機的と言わざるを得ない。今後も上昇は困難だ。というのも農業の担い手不足や高齢化が止まらない上、環太平洋連携協定(TPP)などの発効で安い農産物輸入が増えるからだ。政府が目標とする25年度の45%達成には赤信号がともった。必要な食料を自国内で賄う「食料安全保障」は破綻していると言えよう。農林水産物の増産や担い手づくりにつながる、持続可能な「農」への抜本的対策を政府は打ち出すべきだ。18年度の国内生産量を見ると大豆が16・6%落ち込み、小麦は15・7%減った。悪天候が理由だが、自給率は09年度の40%から徐々に下がり、近年は30%後半を推移している。コメ離れが進み、輸入肉などを多く食べる食生活への変化が主な理由だ。気になるのは、深刻さを増す生産現場の担い手不足だ。農業就業人口は約168万人と10年前に比べ4割減った。うち7割が65歳以上で高齢化も著しい。新規就農も進まない。49歳以下の若手就農者は18年に約1万9千人と5年ぶりに2万人を割った。あおりで耕地面積も約440万ヘクタールと、10年前より約20万ヘクタール少なくなっている。一方、海外からの農産物は増える。TPPに加え、欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)が昨年度相次いで発効した。輸入の肉類や乳製品が国内に大量に流れ込んでいる。来週、米国との貿易交渉が再開される。結果次第では、農産物輸入が増える。自動車など日本の工業製品を守るためとはいえ、これ以上、国内農業を犠牲にすることは許されない。世界では自給率上昇に力を入れる国が多い。13年には米国とフランスが100%を超え、ドイツ95%、英国63%と、日本は大きく水をあけられている。国家間の食料争奪戦は今後、激しさを増す。人口増は止まらず温暖化による干ばつや豪雨が増えれば、農産物の生産量が減りかねない。食料確保のため、自給率アップは不可欠である。政府は4月、担い手不足解消のため、農業分野への門戸を外国人労働者に広げた。だが在留期間は5年と短く応急措置にすぎない。省力化のためロボット技術や人工知能(AI)など先端技術の活用も必要で政府の対応が急がれる。安倍晋三首相は1月の施政方針演説で「強い農業」推進を訴えた。農地集約で大規模農家をつくり農産物輸出を増やす「もうかる農業」の重視である。それは、小規模農家の切り捨てにならないか。中国地方は島や山が多く、農地の大規模化や大型機械の導入は進めにくい。棚田は、食料生産に加え、洪水防止や景観保持など多面的な役割を果たしている。それを維持しているのが中山間地域の農家である。忘れてはなるまい。私たちも消費者として農林水産業への理解を深め、「食」という恵みを生み出す農山漁村の担い手を支援すべきである。 *1-1-4:https://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/20190816489029.html (新潟日報社説 2019年8月16日) 食料自給率 上昇に転じる道筋を示せ このままでは日本の食料安全保障が揺らぐ恐れがある。政府はもっと危機感を持って、食料自給率の上昇へ向けた取り組みを強化しなければならない。2018年度の食料自給率がカロリーベースで前年度より1ポイント減の37%になった。記録的なコメの凶作となった1993年度と並ぶ最低の水準だ。65年度は73%あったが、コメ離れや肉を多く食べる食生活の変化などで漸減し、2010年度以降は40%を切っている。国の「食料・農業・農村基本計画」では、25年度までに自給率を45%にする目標を掲げている。計画ができたのは00年だが、一向に改善できずにきた政府の責任は重い。気掛かりなのは、18年度が過去最低となった要因として、農林水産省が天候不順で小麦や大豆の国内生産量が大きく減ったことを挙げている点だ。地球温暖化により世界各地で干ばつや豪雨などが増えている。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、50年には穀物価格が最大23%上がり、食料不足や飢餓のリスクが高まるとの報告書をまとめた。こうした中で、日本の自給率は小麦が12%、大豆は21%にとどまっている。これらの輸入は米国、カナダ、オーストラリアなどに頼っている。輸出国が異常気象で作物が凶作となった場合、これまで通り安定的に供給できるのか。食料安全保障に不安を覚える。来年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定する国は、目標との乖離(かいり)を検証すると同時に、将来の食料危機も見込んだ対策を示してほしい。農水省は45%の目標達成に向けて主要品目ごとの生産目標も示している。コメは100%達成しているが、小麦は18年度実績より18万トン増の95万トン、大豆も11万トン増の32万トンに引き上げねばならない。国内の生産を強化するには、担い手の減少や耕作放棄地の増加といった課題の解決が不可欠だ。国も対策に取り組んできたが、効果は上がっていない。担い手は10年には全国で約205万人いたが、18年は60万人減の145万人になった。高齢化も急速に進み、集落の維持が困難になっている地域も増えている。本県も同様の傾向だ。集落や地域農業も含めたさまざまな観点から対策を強化することが欠かせない。農作業の負担軽減や生産性の向上につなげるため、ロボットや人工知能(AI)などの最新技術を活用する「スマート農業」の実用化を急ぐことも柱の一つだろう。先の参院選では、野党も高い自給率の目標数値を公約に掲げていた。与野党問わず、実現に向けて知恵を出してほしい。都道府県別の自給率では、本県はコメの不作の影響で前年度より9ポイント減の103%だった。安定した収量と品質の確保に向けて、県や農業団体などは品種の改良やきめ細かな技術指導などに最大限の努力を図ってもらいたい。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p47616.html (日本農業新聞 2019年5月11日) きょうからG20農相会合 持続可能性で議論 日本産輸入規制撤廃も 日本が議長国を務める20カ国・地域(G20)農相会合が11日、新潟市で開幕する。12日までの日程。世界の人口と食料需要の増加に対応するため、農業の生産性向上や持続可能性をどう確保していくかを議論し、「G20農相宣言」を採択する。吉川貴盛農相は10日の閣議後会見で、各国閣僚との会談を通じ、中国や韓国など日本産食品の輸入を規制している国に対して、早期の規制緩和、撤廃を求めていくとした。6月に大阪市で開かれるG20首脳会議(サミット)に向けた一連の閣僚会合の第1弾。吉川農相は閣議後会見で、農業・食品分野の持続可能性の実現に向けて、各国の優良事例を集め、有効策を見いだす考えを示した。 また、東京電力福島第1原子力発電所事故に伴う、日本産食品の輸入規制の緩和、撤廃に向け「特に中国、韓国とは、そのようなこと(規制緩和、撤廃)を中心に話したい」と強調。11日の歓迎レセプションでは新潟県や農相の地元の北海道に加え、岩手、宮城、福島各県の食材も提供。日本産の安全性をアピールする。期間中は、米国のパーデュー農務長官との会談も予定されている。日米貿易協定交渉が本格化する中、パーデュー氏とは「農業全般の諸問題について率直に意見交換したい」と述べた。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p48137.html (日本農業新聞 2019年7月7日) 食料安保を最重視 人材・スマート化拡充 全中 予算要請へ JA全中は、政府の2020年度農業関係予算への要請内容を決めた。食料安全保障の確立に向けた万全な予算の確保を最重視。新規就農者の育成やスマート農業の支援の拡充、中小経営を含めた青果や畜産の生産基盤強化策などを求める。参院選後、8月末の概算要求を前に政府・与党への働き掛けを強める。20年度は新たな食料・農業・農村基本計画の実践初年度のため、全中は同計画とともに予算でも食料安保の重視を訴える。農業者の急速な減少・高齢化による担い手や人手の不足を受け、19年度予算で減額された農業次世代人材投資事業などの充実を要請。生産性向上や労働力不足の解消に向け、スマート農業の導入支援の拡充も求める。多くの割合を占める中小規模・家族経営も含めて生産基盤を強化するため、野菜・果樹対策では産地パワーアップ事業や強い農業・担い手づくり総合支援交付金とともに、省力樹形への改植支援などを求める。畜産・酪農対策では、畜産クラスター事業に加え、キャトルステーションなど外部支援組織や経営継承への総合的な支援を要請。豚コレラ終息に向けた防疫態勢や、水際対策の強化なども求める。19年産米の需給緩和が懸念される中、水田農業対策では、水田活用の直接支払交付金をはじめ、水田フル活用に関する交付体系や予算の恒久的な確保、産地交付金の運用見直しなどを要請する。農地中間管理機構(農地集積バンク)の見直しを受け、地域の話し合いの活性化に向けた支援の拡充なども求める。農業・農村への理解の促進や、国産農畜産物の消費拡大に向けた官民の取り組みの強化も訴える。輸出の拡大や農泊、農福連携への支援の他、鳥獣被害の減少に向けた十分な対策、災害に強い農業づくりに向けた支援の拡充なども要請する。JAグループの自己改革をさらに後押しするため、公認会計士監査への移行に伴うJAの実質的な負担増がないよう、引き続き支援も求める。 <農業経営と人材> *2-1:https://www.agrinews.co.jp/p48103.html (日本農業新聞 2019年7月3日) [ゆらぐ基 持続への危機](3) 担い手 規模拡大 限界 重い負担 経営リスク 「一面の水田を前にこれ以上の規模拡大は難しい」と話す永須さん(秋田県横手市で)。離農者の農地を担い手が引き受け、地域の農地を守りつつ、規模を拡大する。そんなサイクルが今、限界を迎えつつある。離農者に比べて担い手や労働力が不足し、一定以上の規模拡大には経営リスクが付きまとう。 ●平場地域でも 「頼まれても、これ以上は増やせない」。2600ヘクタール超の水田が広がる秋田県横手市平鹿町。高齢農家の離農で「農地を引き受けてほしい」との声が毎年のように上がるが、水稲「あきたこまち」など、地域有数の規模の45ヘクタールを経営する永須巧さん(38)は難色を示す。平場地域で営農条件は悪くないにもかかわらず、なぜか──。最大の要因は「マンパワーが足りない」ことだ。永須さんは両親と3人で農事組合法人を経営。田植えや収穫は、地域内からの臨時雇用で人手を賄う。だが、住民の高齢化でその確保が難しくなり、両親も60代後半となった。その分、負担は永須さんに集中する。今年は田植えに1カ月以上を要し、作業中に「もう限界」と感じた。繁閑の差が大きい水稲は通年で人を雇うのが難しい。冬の作業確保で園芸作物を導入するにも、豪雪地帯の同市ではハウスなどに大きな投資が必要だ。これ以上の水稲の拡大も、現在の農機や施設では対応しきれない。自宅近くに農地を集積しているが、分散して非効率となる恐れもある。米価が不透明な中、「リスクを背負えない」と経営面からも二の足を踏む。地元のJA秋田ふるさと平鹿営農センターによると、農機の更新などを機に離農する2、3ヘクタール規模の高齢農家が多い。20~30ヘクタール規模の担い手や集落営農組織も存在するが、作業者の不足や高齢化などの課題を抱える。農地中間管理機構(農地集積バンク)を使っても受け手がなかなか決まらない場合があるという。一方、農地を集めた担い手の病気やけがで、一度に大量の農地が宙に浮いてしまうリスクもある。同JA管内でも数年前に10ヘクタール程度を耕作していた農家が病気となり、周囲で分担したが、一部は作付けできなかったという。 ●誇りだけでは 水稲より規模拡大が難しい果樹。「新たに引き受けるには、別の農地を返さざるを得ない」と語るのは、静岡市清水区の農家、杉山祥丈さん(40)だ。全国農協青年組織協議会(JA全青協)の副会長を務める杉山さんは、急傾斜地の農地で、両親・弟とミカン2ヘクタールなどを経営。地域内でも基盤整備された農地は引き受け手があるというが、自身は高齢農家に農地の引き受けを求められても、やむなく断る場合があるという。人手の確保や新たな投資に加え、元の持ち主との仕立て方の違い、老木の改植など果樹特有の課題もあり、規模拡大のメリットは期待しにくい。「農地を荒らしたくない気持ちはあるが……」。政府は2023年までに、全農地面積の8割を担い手に集積する目標を掲げる。全青協の飯野芳彦参与は「その分、リスクや負担も集中する」と指摘。「担い手の使命感や誇りで地域の農地を維持していくにも限度がある」と話す。 ●労働力 7万人不足 18年の農業就業人口は175万人で、1998年の389万人から20年間で55%減った。このうち「基幹的農業従事者」は98年が241万人、18年が145万人で40%減った。一方、17年の新規就農者は5万5670人。49歳以下の若手は4年連続で2万人を超えたが、離農者を補うには及ばない。人口減少局面で、雇用労働力も不足。政府は農業での不足が19年度に7万人、24年度に13万人と見込む。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p48314.html (日本農業新聞 2019年7月29日) 農業経営体 120万割れ 大規模でも農地減少 全国の農業経営体数が120万を割り込み、過去10年で最少規模となったことが、農水省の調べで分かった。全体の9割以上を占める家族経営体が前年比2・7%減の115万2800に落ち込んだ。労働力不足、高齢化が深刻で生産基盤が揺らぐ実態が浮かび上がった。小規模の家族経営体の農地の受け皿だった大規模経営体の耕地面積も減少に転じ、多様な担い手をどう育成するかが問われている。農業経営体数の合計数は前年比2・6%減の118万8800。10年前の167万9100と比べると、減り幅は49万を超え、約3割の減少となっている。組織経営体のうち、農産物を生産する法人数は2万3400。前年から3%程度増えた。半面、小規模の家族経営体は減少に歯止めがかかっていない。国内の経営耕地面積353万1600ヘクタールのうち、1ヘクタール未満の経営体が占める割合は9・3%。5年前の14年は12・8%と1割を超えていたが、減少が続く。国内の経営耕地面積の半分以上となる53・3%は、10ヘクタール以上の経営体がカバーする。ただ、大規模経営が手掛けている耕地面積は今回、減少に転じた。10ヘクタール以上の経営体の耕地面積は、前年から8700ヘクタール減り、188万ヘクタールとなった。同省は「担い手への集積はある程度進んだが、新たな集積は停滞している」(経営・構造統計課)とみる。小規模農家の離農が加速し、大規模経営が農地を受け切れず、国内の経営耕地面積そのものも、約6万ヘクタール減の353万ヘクタールに縮小した。労働力の不足と高齢化も、歯止めがかかっていない。販売農家の基幹的農業従事者は140万4100人で、前年から3・2%減った。基幹的農業従事者の年齢構成を見ると、70歳以上が59万100人と全体の42%を占める。49歳以下は14万7800人にとどまり、前年と比べると2・9%減っている。雇用労働も、常雇い数は前年比1・7%減の23万6100人。20代から70歳以上まで、年齢構成に大きな偏りはなく、それぞれ10、20%台だが人数全体では増えていない。 *2-3-1:https://www.agrinews.co.jp/p48420.html (日本農業新聞 2019年8月10日) 若手就農 2万人割れ 他産業と取り合い 18年 49歳以下の若手新規就農者数が2018年は1万9290人となり、前年から7%減り、5年ぶりに2万人を割り込んだことが9日、農水省の調べで分かった。他産業との人材獲得競争が激しさを増し、雇用就農者が減ったことが影響した。新規就農者全体は前年と同水準の5万5810人で、2年連続で5万人台にとどまった。15、16年は6万人台だった。生産基盤の再建に向け、新たな人材をどう確保するかが課題に浮かび上がった。14年以降、49歳以下の若年層は4年連続で2万人を超えていた。だが、16年から減少傾向が続いていた。就農形態別に見て、49歳以下の減少が特に目立ったのは、法人などへの雇用就農者だ。前年比11%減の7060人だった。自営農業就農者は1万人を割り、同2%減の9870人。土地や資金を独自に調達して就農した「新規参入者」は、同13%減の2360人と、軒並み減少している。減少に転じた理由について、同省は「各産業とも人手不足が深刻化し、人材獲得競争が激しさを増している」(就農・女性課)と説明。18年の有効求人倍率は1・61で、14年に1・09と1点台に乗って以降、上昇が続いており、若手が他産業に流れているとみられる。一方、全世代を含む新規就農者5万5810人は、前年から140人増。このうち、自営農業就業者は同3%増の4万2750人だった。60歳以上が2万7000人と同11%増となり、全体を押し上げた。同省は定年帰農者などの増加を要因の一つに挙げる。雇用就農者と新規参入者は、全世代を含めても前年から減少していた。雇用就農者は4年ぶりに1万人を割り込み、同7%減の9820人。15年に、統計を取り始めた06年以来初めて1万人を突破し、3年連続で1万人台を維持していたが、その傾向が途絶えた。新規参入者は3240人と、前年から11%減った。前年は増加傾向に転じていたが、再び減少傾向に戻った格好だ。 [解説] 担い手確保 具体策を 生産基盤を再建する上で、重要な役割を果たす新規就農者が増えていない。将来を担う若年層の49歳以下の新規就農者数は2万人を切った。離農が加速する中、新たな人材をどう確保するか。具体策が求められている。14年以降、4年連続で49歳以下の新規就農者が2万人を超えていたことは、安倍晋三首相が農政改革の成果の一つとして強調してきた。それだけに今回の2万人割れを、安倍政権は重く受け止めるべきだ。他産業でも人材獲得競争が激しくなる中、いかにして農業の魅力を高めるかが問われている。他産業並みの収入確保、省力化などによる労働環境の向上など課題は多い。農政の中長期的な指針を示す食料・農業・農村基本計画の見直し期限が2020年3月に迫る。政府・与党は、新たな基本計画の策定に向けて、現在の政策を徹底的に検証し、実効性のある政策を構築すべきだ。支援策が十分かどうかも検証が必要だ。新規就農者らを資金面でサポートする農水省の「農業次世代人材投資事業」の19年度予算額は、前年度から1割以上減っている。20年度予算での財源確保も大きな焦点となる。 *2-3-2:https://www.agrinews.co.jp/p48454.html (日本農業新聞 2019年8月15日) 就農支援 交付できぬ 予算減額で自治体混乱 新規就農者を支援する国の「農業次世代人材投資事業」の2019年度予算の減額で、地方自治体が対応に苦慮している。経営開始型の新規採択を予定する新規就農者に対し交付をいまだ決定できない自治体や、全額交付の確約がないまま半額分の上期支払いを決定した自治体もある。現場の混乱に、農水省は「必要性が高い人に優先的に配分してほしい」とする。 ●追加配分 要望相次ぐ 同事業は12年度に前身の就農給付金事業から始まり、就農前の研修期間に最大150万円を2年間交付する準備型と、定着に向け最長5年間同額を交付する経営開始型の2本立てで構成する。19年度からは年齢を原則45歳未満から50歳未満に引き上げ、対象を拡大したにもかかわらず、予算は154億7000万円で、18年度の175億3400万円に比べて12%、20億円以上減額した。事業の減額で、要望額を大きく下回る配分額を同省から提示された自治体が続出。支援を営農計画に織り込んで生計を立てている新規就農者もいるだけに、波紋が広がっている。佐賀県では、同省の配布額では現時点で5000万円足りない。市町村に対し、国からの配布額が減額したことを説明した上で、営農意欲など事業の要件を満たした交付希望者全員に上期分(最大75万円)の支払いを決定した。残りの下期分は国から支払われるか不透明だが、同県は「経営開始型の5年間の交付は農家との約束だ」として、影響を最小限にとどめるために上期分は例年通りの時期に決定したという。同県は「万が一、国からの予算がこのまま大きく足りない状況だと、半額しかもらえない若者が出てきてしまう。そうならないよう、農水省に強くお願いする」と強調する。岡山県も交付希望者全員に上期分(最大75万円)の支払いを決定した。残る半額は同省の追加配分を待つという。岐阜県では経営開始型の新規採択予定者の交付はストップしている状況だ。多くの自治体から、予定していたのに交付されない新規就農者が出ることがないよう、追加配分に向けて強い要望が同省に相次ぐ。 ●調整では限界 国は対応検討 同省は、都道府県の要望額や前年度実績などを踏まえ、配分額を決定する。例年、予定していた新規就農者が病気で交付申請をやめるなどして当初の見積もりを下回り、配分額から返却する自治体がある。同省では毎年11月に予算の執行調査を行い、返却分から足りない自治体に追加配分するなどしてきた。19年度はこうした自治体間の調整は小まめに行う方針だという。ただ、19年度は前年度比20億円以上もの減額で、大半の自治体で配布額が要望額に満たず、調整だけでは限界がある。同省は「現場の苦慮する声は聞いている。予算の執行状況を丁寧に調査し、どう対応できるか考えていく」と説明している。 ●就農支援減額に不満の声 頼みの綱…「死活問題」 山間部に30戸が暮らす佐賀市三瀬村の井手野集落。5年前に大阪からUターンした庄島英史さん(44)は、ピーマンを栽培する。あぜ道が多く耕地面積を上回る古里で農業をする厳しさは、稲作農家の両親の経営を見て痛感していた。それでも「会社員生活でいろいろな地を訪れたが、古里以上の場所はない」と就農した。今年は経営開始型交付の最終年に当たる5年目。これまで綿密な営農計画を提出し、給付金はトラクターや運搬車、パソコンの購入費用に活用してきた。規模拡大や効率化に限界がある農地だったが、同事業が大きな支えになった。庄島さんは「支援がないと農業を続けるのは厳しかったかもしれない」と振り返る。来年度から経営を自立できる見通しだが、それも経営が安定しない初期段階に同事業の補助金を受給できたからだという。古里に仲間を呼び込みたいと考え、同事業をPRし、若者に就農を勧めてきた庄島さん。「この事業を頼りにする後輩もいる。打ち切りになればあまりに影響が大きい」と訴える。庄島さんの後輩で、同集落に移住し、無農薬で少量多品目を栽培する佐藤剛さん(35)は、今年度の受給が不透明な現状に困惑する。同事業があるから、無農薬栽培や新たな生産方法などにチャレンジできていたという。「非常に貴重で頼りにしていた支援。農家出身ではなく、基盤がない移住者なので、事業の減額は死活問題だ」と主張する。同市で経営開始型の補助を受けるのは、庄島さん、佐藤さんを含めて48人。これまで1年間まとめて県から市に予算が振り込まれてきたが、今年は予算が足りないとの理由で上期分だけだった。市は「急に『支払えない』とは、現場で頑張る新規就農者に言えない。非常に大きな問題だ」と憤る。JAや県と新規就農者の呼び込みに力を入れてきた同市。同事業も就農を呼び掛ける材料の一つにしてきたが、今後はこの事業についてどう説明すればいいのか途方に暮れているという。 ●自治体も困惑「説明できぬ」「寝耳に水」 「信頼揺らぐ」市が補正予算 現状、経営開始型の新規採択者には給付金を支払っていない岐阜県。同県飛騨市では、トマトで就農を目指す3人への給付が不透明なままだ。このため市は緊急の対応として補正予算を組んだ。全額国費の同事業に、自治体が補正予算で対応するのは異例だ。都竹淳也市長は「制度としての信頼が揺らぐ深刻な問題。新規採択予定者の不安な状況を避けるために、緊急避難的な対応としてやむを得ず補正予算を組んだ」と説明する。都竹市長が事態を知ったのは5月。会議で他の自治体首長から問題提起があったという。現場の混乱が想定される大きな予算の減額に国から説明がなく、「寝耳に水。情報伝達の面でも大きな問題だ」と語気を強める。他の自治体からも「年齢を引き上げ、対象を拡大したのに予算を減らすのはおかしい。追加配分してほしい」「受給できる前提で営農計画を組んでいる若者に説明できない」との声が相次ぐ。「農業の産地ではなく、国の予算が少ないからという理由で補正予算を求めても財政部門や議会が納得してくれない」と話す市の担当者もいる。同事業は17年度までの6年間で準備型8916人、経営開始型1万8235人が受給し、新規就農者の育成に大きく貢献してきた。新規就農者や自治体が同事業の必要性を訴える一方、同事業には2017年秋の行政改革推進会議などでは厳しい指摘があり、財務省からは緊縮財政の中で予算削減を求められている。農水省は新規就農者の苦慮する状況について「どういう対応ができるかを検討している」と説明している。 *2-4-1:https://www.agrinews.co.jp/p48240.html (日本農業新聞 2019年7月20日) 外国人材受け入れ 特区 特定技能に移行 来年度から 円滑な契約 課題 政府は、改正出入国管理法に基づく特定技能制度が始動したことを受け、農業分野での国家戦略特区制度の外国人労働者受け入れは2020年度以降、新制度に移行する方針を決めた。特区制度での契約終了後も外国人が働き続けるには、新制度の資格を得る必要がある。円滑な移行ができるかが焦点となる。国家戦略特区を活用し、農業分野で外国人労働者の受け入れが始まったのは、18年10月。特区の認定を受けた愛知県、京都府、新潟市、沖縄県で、19年6月1日までに52人が派遣元と契約し、入国している。一方、外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が成立。4月からは、新たな特定技能制度による受け入れが始まった。特区制度と新制度が並存する中、政府は今後の運用方針を決定。20年度からは、新制度での受け入れを求める。移行期間を設け、19年度までは特区制度で派遣業者が外国人労働者と雇用契約を結べるようにした。19年度中に特区制度に基づいて契約した外国人は、契約締結時点から通算3年を上限に就労できる。契約後、新制度に移行できれば、新制度の通算5年と合わせて合計8年の就労が可能となる。今後、特区制度での契約が順次切れていく中、外国人労働者が新制度の資格を取得し、引き続き今の現場で働くことができるかが課題となる。新制度の下で働く場合、耕種か畜産の農業技能測定試験と日本語能力の試験を受ける必要がある。だが、約3年の技能実習を修了していれば、試験は免除される。特区制度で働く外国人は、既に技能実習を修了しているため、新制度への移行時は試験が免除となる。農業分野では、受け入れ元の直接雇用に加え、派遣形態の雇用も認める。特区制度での受け入れ実績を持つ派遣業者が新制度でも受け入れ先になるには、住居の確保など生活を支える支援計画を策定する必要がある。同省は「計画策定などは、社会保険労務士や農業団体など登録支援機関が支援する。新制度へ円滑な移行を促したい」(就農・女性課)と話す。 *2-4-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/513963/ (西日本新聞 2019/5/29) 福岡県、外国人材受け入れへ協議会 官民56団体連携 外国人就労を拡大する改正入管難民法の4月施行を受け、福岡県や市町村、業界団体、留学生支援団体などは6月に「県外国人材受入対策協議会」を発足させる。生活、労働情報や課題を共有し、受け入れ環境向上を図る狙いだ。外国人材に関連した官民の横断的な組織の設立は九州で初めて。県は9月にも市町村と連携した広域の外国人相談窓口の設置を予定している。法務省によると、県内の在留外国人は7万3876人(昨年6月現在)。改正法は新たな在留資格「特定技能」を創設。県内でも農業、介護、建設などの分野に従事する外国人数の増加が見込まれる。協議会は県に事務局を置き、福岡市、北九州市、県市長会、県町村会、福岡労働局をはじめ、農業や介護のほか外食、宿泊、建設など13業種の業界団体を含む計56団体で構成。アンケートなどで就労や生活面の不安、事業者が抱く制度の課題点や困り事を把握し、必要な対策につなげる。新設する相談窓口は「県外国人相談センター」(仮称)。政令市を除く58市町村に寄せられる相談をセンターと共有できるネットワーク体制を構築する。(1)外国人と担当の市町村職員(2)センターのスタッフ(3)通訳業者‐の3者が機器で同時通話できるシステムを活用。スタッフが生活、就労、医療など相談内容次第で各専門機関にもつなぐ。県は、関連経費として計約2300万円を2019年度一般会計当初予算案に計上する方針。 *2-4-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/527877/ (西日本新聞 2019/7/18) サニーさんの死なぜ 大村入管のナイジェリア人 収容3年7ヵ月 強制退去処分を受けた外国人を収容する西日本唯一の施設「大村入国管理センター」(長崎県大村市)で6月下旬、収容中の40代のナイジェリア人男性が死亡した。男性は施設内で「サニーさん」と呼ばれ、慕われていた。収容期間は3年7カ月に及び、亡くなる前は隔離された状態で衰弱していたという。センターは死因や状況を明らかにしておらず、支援者からは第三者機関による原因究明を求める声が上がっている。「外に出られたことを神に感謝している」。今月8日午後、大村市の教会を訪れたクルド人男性(30)はキリスト像を前に頭を垂れ、じっと動かなかった。2年近く収容されていた大村入国管理センターから「仮放免」が認められ、その足で向かったのが教会だった。目は落ち込み、頬はこけていた。男性は収容中の3月から2カ月間、仮放免の許可を求めて食事を拒むハンガーストライキをした。一時は他の外国人と隔離され、複数の部屋が並ぶ「3C」と呼ばれる居住区にいた。その隣の部屋に、サニーさんがいた。「彼は食事を取っておらず体力がなかった。『水くらいは飲んで』と伝えたんだが…」。最後に見た時はやせ細り、骨と皮ばかりになっていたという。支援者によると、サニーさんが収容されたのは2015年11月。日本人女性との間に子どもがおり「出国すると子どもに会えなくなる」と帰国を拒んでいたという。「3C」で意識を失っているサニーさんを職員が見つけたのは6月24日午後1時すぎ。搬送先の病院で死亡が確認された。法務省によると、記録が残る07年以降、大村入国管理センターで収容中の外国人が死亡したのは初めてだった。2日後、施設内の一室に献花台が設けられた。同じナイジェリア出身の男性は「助けてあげられなくてごめんね」と涙を浮かべた。「親切」「穏やか」。収容されている外国人はそう口をそろえ、同じ部屋で過ごしたフィリピン人男性は「兄のような存在。食事が足りない時には分けてくれた」と振り返った。支援者や収容者によると、サニーさんはこれまで仮放免の申請を4回却下されていた。ハンストしていたとの情報もあるが明確な証言はない。その最期は覚悟の上だったのか。それとも‐。「3C」にはサニーさんや、後に仮放免されたクルド人男性など、食事を取らなかった複数の外国人が各部屋に隔離されていたという。その理由についてもセンターは「個別事案には答えられない」(総務課)と公表していない。サニーさんの死亡について、出入国在留管理庁は調査チームを設置。福岡難民弁護団は第三者機関による原因究明と調査結果の公表を求める声明を発表している。 ◇ ◇ ●ハンスト後絶たず 強制退去処分を受けた外国人の収容の長期化が指摘される中、全国の入管施設では仮放免の要求や長期収容への抗議のためのハンガーストライキが後を絶たない。大村入国管理センターで外国人との面会活動を続けている牧師の柚之原寛史さん(51)によると、同センターではサニーさんの死後、ハンストがさらに広がっているといい「収容期間が長い人ほど精神的に追い詰められており、このままでは第二、第三の犠牲者が出かねない」と危機感を募らせる。サニーさん死亡を受け、山下貴司法相は2日の閣議後会見で「健康上の問題などで速やかな送還の見込みが立たない場合は、人道上の観点から仮放免制度を弾力的に運用する」と説明。これに対し、全国難民弁護団連絡会世話人で外国人収容問題に詳しい児玉晃一弁護士(東京)は「命を懸けたハンストが広がる背景には、理由の説明もないまま長期間収容する入管側に問題がある」と指摘。「ハンストすれば仮放免の道が開けるという情報が収容者に広がれば危険だ。難民申請中などで早期の出国が見込めないケースなどは原則として仮放免を認めるべきだ」とし、場当たり的な対応ではなく根本的な政策の見直しを訴えている。 【ワードBOX】外国人の収容 不法滞在などで強制退去処分を受けた外国人は、出国まで全国17カ所の入管施設に収容される。うち出国のめどが立たないケースは東日本入国管理センター(茨城県)か、大村入国管理センターに移送される。大村の収容者数は2018年末時点で100人。在留を特別に認める「仮放免」制度などがあるが、ここ数年は収容期間の長期化も指摘され、大村では収容者の94%が半年以上に及ぶ。法務省によると記録がある07年以降、全国の施設で収容中に亡くなった外国人は15人。うち自殺者は5人。 *2-5-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48474260Q9A810C1EA1000/ (日経新聞 2019/8/10) 農業参入3000社、収益確保なお途上 農地法改正10年 ■イオン、借地面積3倍へ 一般企業の農業参入の条件が緩和された農地法改正から10年を迎えた。参入した法人数は全国で3千を超え、農家の高齢化や跡継ぎ不足で耕作放棄地が増えるなか、有力企業も動き出す。イオンは借地面積を2025年度までに3倍に拡大し、他の民間による植物工場の新設も相次ぐ。ただ大規模な農業経営は期待されたほど進んでいない。農業ビジネスの収益性の低さが改めて課題となっている。改正農地法は09年に施行され、農地を借りる形であれば完全に自由となった。家族経営に支えられてきた従来の農業が行き詰まりを見せるなか、新たな担い手として民間企業が名乗りを上げ、株式会社などの参入は順調に増えてきた。代表格がイオンだ。全額出資子会社のイオンアグリ創造(千葉市)を通じ09年に農業に参入し、現在、全国20カ所に直営農場を持つ。借地面積は約350ヘクタールと国内で最大規模を誇る。有機野菜を栽培する認定農場も運営している。特徴は人間の経験と先端技術を融合した効率的な生産だ。収穫など単純作業はロボットに置き換え、20カ所の農場で様々なデータを集める。収集したデータを人工知能(AI)で分析し、地道な栽培技術の向上に役立てている。イオンは生産から販売まで担う製造小売業(SPA)の「農業版」を目指す。イオンアグリ創造の福永庸明社長は「農地を借りてほしいとの引き合いは強い」という。25年度までに借地面積を現在の3倍の1000ヘクタール規模に広げる計画だ。農林水産省によると、株式会社を含む一般法人の参入数は17年12月末で3030法人。改正前の10倍に拡大した。農業や食品関連に加え、建設業や製造業など異業種からの参入も多い。13年に参入した食品スーパーのいなげやは、国内33カ所で約9ヘクタールの農場を運営する。主に長ネギやニンジンなどの野菜を栽培する。自社店舗で販売し、関連会社が手掛ける給食事業でも使う。植物工場を建設する新たな動きもみられる。半導体・電子部品商社のレスターホールディングスは18年12月、秋田県鹿角市に完全閉鎖型の植物工場を稼働した。国内5カ所目でリーフレタスなど1日当たり1万7千株を生産する方針だ。新設した工場では発芽した苗の移植工程を自動化し、肥料や照明、生産実績などをクラウド上で管理する。レタスなどはコンビニエンスストアのサンドイッチやスーパーにも供給する。課題は残る。1法人当たりの経営面積は平均で3ヘクタール弱と一般的な農家とほぼ変わらない。農地法の改正で民間企業が参入し、運営規模の拡大や生産量の増加が期待されたが、現実は農業が長年抱えてきた構造的な問題を引きずっている。 ■「黒字化のメド立たず」 小規模経営は収益性の低さにもつながる。参入した民間が手がける栽培品目の中心は野菜だ。野菜は天候で収穫量や販売価格が変動しやすく、規模が小さいとリスク分散も難しい。企業は機械化を進め効率的な生産を目指したが、人間の勘や経験に頼る面は色濃く残る。企業からは「現時点で黒字化のメドは立っていない」(いなげや)との声が聞かれる。日本施設園芸協会がまとめた18年度の植物工場の収支状況では全体の49%が赤字だった。黒字の工場も増え18年度で全体の31%と3年で6ポイント改善してはいるが、黒字化には数年かかるとされる。企業も手をこまねいているわけではない。システムやサービスの提供といった新たな切り口で農業に携わり効率化を支援する動きが広がる。カゴメは地域の契約農家や自社が出資する農業生産法人を通じ、全国のスーパーで発売するトマトを生産している。屋内の栽培施設ではトマトが育ちやすい温度や二酸化炭素(CO2)の環境を細かく管理する。契約農家には自社が培った栽培技術などを助言する。NTTドコモはビッグデータを使い安定生産できるサービスを提案している。野村総合研究所の佐野啓介上級コンサルタントは企業の参入を促す上で「販路や物流網の整備が重要になる」と指摘する。農作物の売り先確保などで企業のノウハウが生かせる余地はありそうだ。佐野氏は「一部で見られる地域商社などによる生鮮品の共同輸送や、栽培品目などの情報を集め買い手と売り手をつなぐプラットフォームも有効だ」と話す。国内の農業従事者の平均年齢は65歳を超えた。耕作放棄地は今後も増え、農業の未来に向け残された時間は長くない。受け皿となる企業が農業で安定した経営基盤を築くことが急務だ。 *2-5-2:https://www.agrinews.co.jp/p48352.html (日本農業新聞 2019年8月3日) 基本計画 家族農業守れる農政を 官邸主導の農業の構造改革路線を軌道修正できるか。参院選後の焦点はそこにある。生産現場の不満を踏まえ、自民党は参院選公約で家族農業を含む多様な農業を守ると訴えた。それでも1人区では苦戦した。今後の農政のかじ取りで現場の不満や不安を解消すべきだ。選挙戦で与党は農産物輸出の拡大やスマート農業の加速など農業の成長産業化を柱に掲げた。これに対し野党は、戸別所得補償による農業経営の維持を訴えた。過去の国政選挙で繰り返されたなじみの対決構図だが、その中の変化を見過ごせない。変化は与党の側だ。自民党は選挙公約に「家族農業、中山間地農業など多様で多面的な農業を守り、地域振興を図ります」と明記した。安倍政権は当初から「農業の成長産業化」を旗印に農政改革を加速。10年間に農地利用の8割を担い手に集積し、法人経営体を5万法人に増やすなどの構造政策に力を注ぎ、家族農業に配慮する姿勢は弱かった。家族農業の重視は、むしろ野党側が力を入れてきた主張である。そうした与野党対決の構図の中で、自民党公約は従来より中道寄りに歩み出してきたように見える。家族農業を守ることは、農業・農村の実情を踏まえると極めて現実的な対応というべきだ。中小規模農家の経営縮小や離農によって流出する農地を、担い手の規模拡大では受け止め切れなくなっているからだ。2019年の農業経営体数は119万で、09年の175万と比べて56万(32%)も減った。そのほとんどを家族経営体が占める。特にこの5年間はそのスピードが速まり、14年からは28万(19%)の減少となった。深刻なのが、農地の減少である。30ヘクタール以上層がカバーする経営耕地面積は19年、合計119万ヘクタールに及び、全体の3分の1を占める。ただ、これまで一貫して増加基調だったのが、19年は初めて減少に転じた。規模拡大だけでは農地を守り切れなくなっている状況で、構造政策をどう進めるのか、今後の重要な問題となる。農地利用の8割を担い手に集積するという現行の政府目標は現実離れしており、担い手が受け止め切れずに行き場の見つからない荒廃農地を増やす心配すらある。集積目標は現場のスピードに合わせながら、家族農業経営が持続できるような政策を充実させて農地の流出をできるだけ食い止めることこそが、むしろ大事ではないか。今秋に始まる食料・農業・農村基本計画の審議では、こうした人と農地の問題を軸に、生産基盤の立て直しが最大の論点となる。食料自給率向上の大前提となる問題であり、現行計画の延長にとどまらない、踏み込んだ議論が求められる。政権与党である自民党は公約で家族農業を守るとした。これを基本計画に反映させることが、農家との約束を果たす第一歩となる。 <林業について> PS(2019年8月20日追加): 国は、*3-1・*3-2のように、2024年度より全国民から徴収される年1000円の森林環境税を前借りする形で、本年9月より自治体に森林整備資金を配り、資金の一部を人口に応じて割り振るため政令指定都市の平均(全国20市)は全市区町村平均の7倍を超えるそうだ。しかし、森林環境税を財源として配る森林整備資金なら整備する森林の面積に比例して配分すべきであり、基準を人口にすれば、森林整備の目的が達せられない。 また、私有林の3割近くが登記簿で所有者がわからず、境界がはっきりしない森林も多く、市町村が山林所有者から山林を預かって管理する制度はできたが、所有者探しや地籍調査も並行して行わなければならないそうだ。しかし、登記簿で所有者がわからず境界もはっきりしないような山林の所有者探しは、「2年以内に名乗りでなければ公有にする」とアナウンスして、名乗り出ない人はその山林を必要としていないので公有化するというのが、所得のない人まで含めた全国民から年1000円の森林環境税を徴収する以上、公正である。 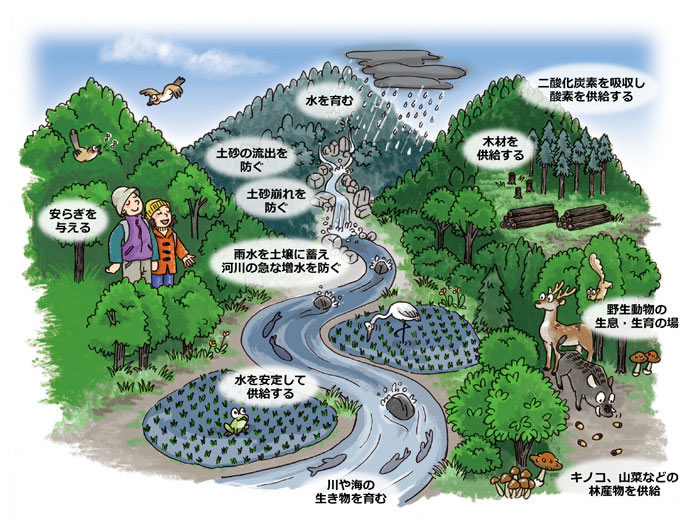  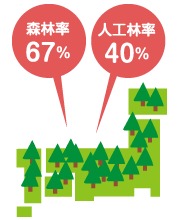  森林の働き 健全な森林サイクル 森林と人工林 所沢ユリ園 *3-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/334835?rct=n_politics (北海道新聞 2019年8月14日)森林整備資金、政令市が7倍超 市区町村に比べ、反発も 国が本年度から自治体に配る森林整備の資金は、全市区町村の平均が年間920万円に対し、政令指定都市(全国20市)は7倍超の平均6880万円に上る見込みであることが14日、分かった。資金の一部を人口に応じて割り振るためだ。総務省は「都市の木材消費を促す事業も重要」と説明しているが、一部自治体は「少額で事業ができない」と反発している。政令市でつくる指定都市市長会が本年度の配分額を試算した。自治体ごとの配分額は、総務省が9月中にも公表する。配分基準は法令で定められているが、大都市が有利な仕組みが妥当かどうか検証が求められそうだ。 *3-2:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48475070Q9A810C1SHF000/ (日経新聞社説 2019/8/11) 森林を預ける制度の活用を お盆は里帰りや行楽で山を間近で感じることが多い。放置された山林が増えるなか、私有の人工林を市町村に預けて管理を任せる制度が4月に始まった。山の日を森林を考える機会にしたい。森林は国土の3分の2を占める。うち57%は民間が所有し、その管理は所有者に任されてきた。しかし私有人工林の3分の2は適切に管理されず、土砂災害の原因になったりしている。新制度では市町村が所有者から山林を預かり管理権を持つ。その山林を使いたい民間の木材業者などがいれば、改めて管理を委ね国産材の活用を促す。いなければ市町村が管理し間伐などを担う。埼玉県秩父市は7月から2カ所の山林を所有者から預かり、管理を始めた。新制度を適用した第1号である。この制度を知った所有者から市に預けたいと申し出があり、スムーズに運んだ。私有林の4割は所有者がその市町村に住んでいない。都市部に住みながら相続で山林を持つことになった人も多いだろう。管理に手が回らないようなら、市町村に預けることを帰省の際に親族で話し合ってはどうだろうか。所有者が預ける意向を持っているか、多くの市町村はこれから調査するところだ。実は私有林のうち3割近くは登記簿では所有者がわからない。境界がはっきりしない森林も残る。所有者探しや地籍調査も並行して行うため、新しい管理制度への移行が終わるには15年ほどかかる、と林野庁はみている。新制度の財源になるのが、年1人1000円を負担する森林環境税だ。徴収は2024年度からだが、それを前借りする形で9月から自治体に配り始める。山村だけでなく都市部にも配分がある。新制度は伐採期を迎えた国産材の活用を促すねらいもあり、都市部では新しい財源の使い道として公共施設に国産材を使うことなどが想定される。木のぬくもりが増えることは好ましいが、無駄な使い方がないか目を光らせたい。 <農林水産業の担い手> PS(2019/8/21、24追加):北海道初山別村では、*4-1のように、業種によって繁忙期が異なることを利用し、労働力不足解消に向けて農業・建設などの異業種が連携した新たな取り組みが進んでいるそうだ。具体的には、建設会社が派遣業の許可を取って社員を農漁業の現場に送り込んで作業しており、建設業と農業などの給与差が課題になるそうだが、それは建設会社が人材派遣業を別会社にして日本人だけでなく外国人も雇用し、仕事の難易度・熟練度・作業量・責任の重さ等に応じて給与を変える方法で解決できるだろう。ただ、外国人を就労させる場合には、*4-2のように、教育はじめ社会インフラの環境整備が必要になるため、同一言語を使用するグループを市町村毎にまとめて住まわせた方が、言語対応にかかるコストが少なくてすむわけだ。 なお、*4-3のように、農林漁業には宝が豊富であるため、それを利用できるか否かがKeyになるが、それにもアイデアと人手を要するわけだ。*4-4の鶏卵価格の低迷による生産調整は「もったいない」の一言につき、生だけでなく惣菜や菓子に加工したものを国内外で販売すれば収益源になるし、*4-5の食品宅配は、高齢化と共働き化によって伸びることが明らかだ。そして、JAらしい新鮮でこだわった食材による地域貢献が期待されるが、これらもアイデアと人手の問題になる。 2019年8月24日、朝日新聞が、*4-6のように、「①新在留資格の『特定技能』を持つ外国人労働者の生活を支援する1800を超える『登録支援機関』が続々誕生」「②質が保てるか懸念」「③外国人支援代行手数料の相場は月数万円」等と記載している。既に国外に製造・販売ネットワークを持つ会社が人材養成校を作って日本に外国人労働者を送り出したり、人材派遣会社が登録支援機関になったりすれば、これまでに蓄積したノウハウとのシナジー効果が発揮できるのでよいが、①②によって支援の質が低下したり、③のような高すぎる手数料をとって外国人労働者から搾取したりすれば、せっかく日本を選んで来た外国人労働者が日本に関する悪いイメージを持って本国に帰ることになり、長期的には国益にならないので注意すべきだ。 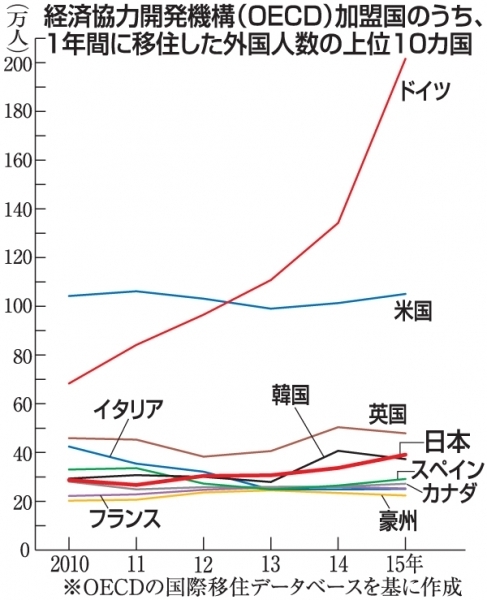 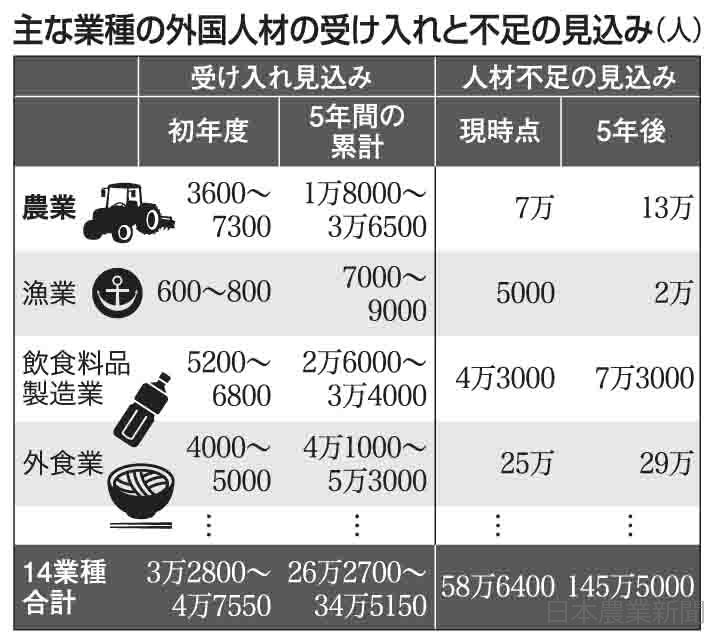  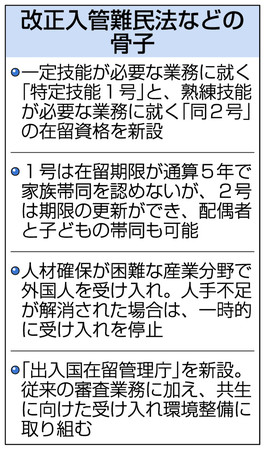 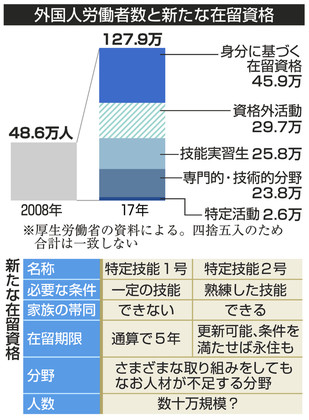 2018.5.30 2018.11.20 2019.1.26 2018.12.8 2018.10.12 西日本新聞 日本農業新聞 西日本新聞 東京新聞 東京新聞 (図の説明:1番左の図のように、OECD諸国のうち移住外国人が多いのはドイツ・アメリカで、日本は少ない方である。しかし、左から2番目の図のように、日本でも農漁業はじめ多くの産業で外国人労働者を必要としている。また、中央の図のように、日本でも外国人労働者は漸増しており、その出身国は中国・ベトナム・フィリピンの順になっているが、人権に配慮した雇用については問題の多いことが指摘されている。そのため、右の2つの図のように、入管難民法が改正されたが、これも改善すべき点が多いわけだ) *4-1:https://www.agrinews.co.jp/p48473.html (日本農業新聞 2019年8月17日) 派遣元は建設会社 農漁現場へ人材融通 新たな連携手応え 北海道初山別村 北海道留萌地方にある人口1200人ほどの初山別村で、労働力不足解消に向け農業、建設など異業種が連携した新たな取り組みが進んでいる。業種間で繁忙期が異なることから、建設会社の社員を農漁業の繁忙期に派遣し、成果を上げている。人口減少が進む中、今ある労働力を地域内で活用する動きは、経済産業省北海道経済産業局なども着目。来年にも同村の手法を他地域に広げる計画で注目が高まっている。同村では高齢化や人口減少が進み、人手不足による廃業などが課題となっていた。村の基幹産業の一つである農業も、これまで親戚などに手伝ってもらっていたが、人手を集めにくくなり、生産者から労働力の確保を求める声が高まっていた。同村の商工会やJAオロロン、漁協などは、連携して2017年に「初山別村労働力調整協議会」を立ち上げ、検討に着手。同村を含め周辺地域も過疎化が進んで人材を呼び込むことが難しい中、18年度から人材融通の仕組みを始めた。具体的には、建設会社が派遣業の許可を取り、社員を農業や漁業の現場に送り込み作業してもらう。実施したのは、4月の養殖ホタテの稚貝を他の網に移す作業や5月の米の田植えなどが集中する、春先だ。18年度は漁業に6人、農業に4人を派遣。19年度は漁業に3人が入った。経験のない人を受け入れることに最初は不安を抱える農家もいたが、簡単な作業を割り振り教えることで対応できたという。受け入れ農家の調整を担った、JA初山別支所は「農家からは助かったという声が多く、希望者も増えている」と話す。農家にとっては、個人ではなく建設会社と契約することで、安心感もある。基幹産業の一つである第1次産業の衰退は、地域の衰退になることから異業種が結束したという。一方、仕組みを持続させるための課題も浮かび上がっている。同商工会によると、建設業の方が農漁業よりも給与が高い傾向にあり、社員を送り出す建設会社に対して村が差額を補填(ほてん)している状況だ。また、人手を求める需要に対し、融通できる人員は限られており、ネットワークの拡大も欠かせない。留萌地方は、他の地域よりも有効求人倍率が高く労働力不足が顕著。北海道経済産業局と北海道留萌振興局は同村の取り組みを処方箋にしようと、来春にも同地方南部でも仕組みを広げる考えだ。留萌振興局は「課題などを含め今後、細部を詰めながら進めたい」(産業振興部)とする。 *4-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/536299/ (西日本新聞 2019/8/20) 日本語できぬ親への対応は? 就労拡大…教育現場、追い付かず 「子どもの同級生の親は日本語ができない。学校が配布するプリントは読めず、配慮が足りないのでは」。福岡県久留米市の女性(53)から、特命取材班にそんな声が寄せられた。改正入管難民法が4月に施行され、外国人の就労拡大が見込まれる。家族を呼び寄せたり、日本で子どもをもうけたりするケースは今後さらに増える見通しだが、教育現場の環境整備は進んでいるのか。女性には小学3年の子どもがおり、昨秋、クラスにフィリピンから男児が転校してきた。今春、クラスのPTA役員決めの際、男児の母親が何も話せず困っているのに気付いた。「大事なことはきちんと伝えないと」と思い、母親と無料通信アプリLINE(ライン)の連絡先を交換した。5月の金曜日。母親からLINEを通じて「子どもが明日学校があると言っている。本当か」と英語で聞かれた。土曜日は授業参観の予定で、プリントで案内されていたが母親は内容を理解していなかった。以後、女性は学校から配られるお知らせをスマートフォンの翻訳アプリで英訳し、LINEで母親に知らせるようになった。女性は「先生たちは忙しく、これ以上負担を増やすのは難しい」と理解を示しつつ、「振り仮名を付けるだけでは配慮になっていない。理解できていないという現状を学校現場は理解してほしい」と願う。 ■ 文部科学省によると、日本語の指導が必要な児童生徒数は2016年5月の調査で4万3947人。前回14年調査から約6800人増えた。うち福岡県は小学生415人、中学生142人、高校生ゼロだった。女性が住む久留米市の教育委員会に聞くと、8月14日現在、28小中学校に149人が在籍。10校に日本語指導担当教員13人を、地域で外国語を話せる人にサポートしてもらう非常勤の外国人児童等授業介助員も28校に配置している。一方、日本語を話せない保護者への対応は追い付いていない。ようやく本年度から日本語指導担当教員がいる学校に翻訳機を導入し、家庭訪問の際に担任が持参している。 ■ 法務省によると、18年末時点の在留外国人数は過去最多の約273万1千人。日本語指導が必要な外国人の数はかなりの規模に上るとみられる。吸収力の高い成長期の子どもに比べ、大人の方が語学習得に苦労しがち。保護者も含め、日本語を話せない人をどう受け入れ、意思疎通をしていくかが教育現場の課題になりつつある。今年6月、外国人への日本語教育の推進を国や自治体などの責務と位置付ける日本語教育推進法が成立した。国は今後、基本方針を取りまとめるが、本格的な検討はこれからという。福岡県内の教育委員会関係者は言う。「都市部に比べ、地方ほど予算がなく、態勢が整わずに困惑している。外国人受け入れを国策として打ち出す以上、国が重点的に予算や人材を確保することが必要だ」。教育現場だけでなく、地域社会にとっても無視できない問題だ。近年、外国人の定住者が増えたという長野市の50代女性会社員は「子どもたちは仲良くしていても、周りの大人が外国人と距離を置く。外国人の保護者と会話をしただけで、白い目で見られた」と特命取材班に憤りの声を寄せ、こう訴えた。「これからもっと外国人は増える。閉鎖的な“ムラ意識”は改めないといけないのでは」 *4-3:https://www.agrinews.co.jp/p48270.html (日本農業新聞 2019年7月24日) 磯荒らす厄介者名産に ミカンの皮、キャベツ残さが餌ウニ養殖 神奈川県小田原市漁協青年部 神奈川県小田原市漁業協同組合青年部17人が、魚介類を育む磯を荒らす厄介者のウニに特産のミカンの皮やキャベツを与える養殖に取り組み、地域の新しい名産にしようと奮闘している。今月、念願の初出荷を迎えた。農業分野の資源を生かし、漁業の課題を解決する取り組みとして地域から期待が高まっている。同手法で養殖されたウニの出荷は神奈川県内では初めて。養殖するのはムラサキウニ。近年、海水温上昇などによりウニは増加傾向にあり、海藻が食い荒らされ減ってしまう「磯焼け」の懸念が高まっていた。一方、ムラサキウニは天然の状態では身が詰まっておらず、売り物にならないため捕獲されずにいた。「このままでは海藻類が食べ尽くされてしまう。深刻になる前に、何かできないか」と部員が立ち上がった。キャベツなどを餌にしたウニの養殖技術を開発していた県水産技術センターを3月、同部員が技術のノウハウを学ぶために視察。3月下旬から約1000個を捕獲し、養殖をスタートさせた。餌は地元農家などから廃棄するミカンの皮などを譲ってもらっている。週2回、スーパーなどから出るキャベツの外皮をもらって、100匹当たり約1・5玉分を与える。色を良くするため、養殖始めや出荷1週間前に冷凍保存していたミカンの皮を与えた。ウニは小田原漁港周辺の食堂で提供される他、スーパーなどで販売する。同青年部の古谷玄明部長は「小田原のウニが有名になり、知名度が上がれば部員の生産意欲にもつながる。手頃な価格でおいしいウニを喜んで食べてもらえたらうれしい」と思いを語った。 *4-4:https://www.agrinews.co.jp/p48264.html (日本農業新聞 2019年7月23日) 鶏卵低迷が長期化 生産調整の効果出ず 鶏卵の価格低迷が長期化している。今月のJA全農たまごの東京地区のM級価格は1キロ150円で推移し、前年同期を1割下回る。成鶏の早期出荷を促す国の生産調整事業が発動してから2カ月を超えたが、価格が上向く気配はない。専門業者の処理が追い付いていないためだ。需要は加工卵中心に鈍い。梅雨明けも、需給緩和状態の解消は見込みにくく、「軟調で推移する」と東京都内の流通業者はみる。東京地区のM級は6月上旬からもちあいで推移する。前年同期(175円)と比べると14%(25円)安だ。2018年度も供給過剰により価格は低迷していたが、7月に入り上向いた。「昨夏は猛暑の影響で生産量が落ちた」(都内の流通業者)ことが影響したためだ。今年は冷涼で、鶏や卵のサイズへの影響は現状ではないという。生産調整を促す成鶏更新・空舎延長事業は5月20日に発動した。価格が上向かず、今回の発動期間は直近2年間で最長となる見込み。成鶏を早期出荷し、ひなを新たに導入せず鶏舎を一定期間空舎にした生産者に対して奨励金を国が支払う。だが、廃鶏処理業者の対応が追い付かない状況が続いている。処理業者の三和食鶏(茨城県古河市)は「年内いっぱいの処理は予約で埋まっている」と話す。成鶏処理後の加工品の販売先がなく、工場の稼働率を高めることができないという。「事業が機能していない」と指摘する流通業者もいる。生産者が自主的に生産調整も行うが「需給を大きく改善するほどではない」という。鶏卵の販売は苦戦している。夏場に需要が増える加工卵の荷動きが悪い。雨天続きで外食からの注文が例年より少なく、「冷やし麺などに使う温泉卵や煮卵などの需要が思うように伸びていない」(流通業者)。梅雨明け後には「外食需要への期待はあるが、家庭消費が落ちる」(同)ため、販売全体では苦戦が続きそう。供給過剰の改善も見込めず「価格低迷が続く」見通しだ。 *4-5:https://www.agrinews.co.jp/p46450.html (日本農業新聞論説 2019年1月17日) 伸びる食品宅配 JAらしい地域貢献を 食品の宅配市場が伸びている。共働きや高齢世帯の増加に伴い、買い物に手軽さを求める消費者が増えているためだ。特に次代の消費を担う若い世代ほど宅配の利用に関心が高い。農家やJAも宅配事業の可能性を探り、参入を考える時だ。調査会社の矢野経済研究所の推計では、2018年度の食品宅配市場は2兆2000億円を超える見込みだ。12年度以降、毎年3%前後の成長が続く。スーパー270社の総売上高10兆円超(17年)には及ばないが、スーパーの売上高が4年ぶりに前年を割り込んだことと比べると勢いの差は明らかだ。生協は「共同購入」から組合員宅に届ける「個配」への転換が進む。日本生活協同組合連合会に所属する地域生協では個配が全体の7割に達する。昨年は有機食材を手掛ける宅配大手3社が合流して「オイシックス・ラ・大地」が発足、物流を効率化して事業を拡大している。異業種の参入も相次ぐ。17年にインターネット通販最大手のアマゾンジャパンが「アマゾンフレッシュ」を立ち上げ、昨年は「楽天西友ネットスーパー」が誕生した。事業伸長の理由は明らかだ。買い物に行くのが難しい高齢者や日中忙しい共働きの世帯が増え、食材調達と調理の簡便化が求められているためだ。中でも、伸びが著しいのが「ミールキット」だ。1食分の献立に必要な下ごしらえが済んだ野菜や肉などの食材と調味料、レシピをセットして家庭に届ける。包丁を使わず簡単に調理でき、材料を余らせることもない。ミールキットは若い世代ほど魅力を感じている。タキイ種苗によると20、30代の4割が「興味がある」と答え、50代(2割以下)とは対照的だった。食品卸大手の19年の消費トレンド予想でもミールキットの需要は今後も拡大し、月額制で多様な料理を楽しむサービスが増えると分析する。「食の簡便化」という消費動向に、産地側も乗り遅れてはならない。地産地消を広げ、地域貢献につなげたい。JA全農とちぎは、昨年からJAふれあい食材の配達員による高齢者の「見守りサービス」を始めた。配達中に独居高齢者宅などを訪問し、会話を交わし安否を確認する。食材宅配サービスと合わせると利用料金が割安になる。地域貢献を兼ねたJAならではの宅配事業だ。JA静岡経済連も昨年から、地元の生協と協業しJA組合員に宅配利用を勧めている。組合員のニーズに応え、生協に県産食材を提供する機会を増やす。阪神・淡路大震災が発生してきょうで24年。大震災以降、防災の備えや被災時の救出活動など、地域住民の「共助」を呼び掛ける声が強まった。住民と触れ合う機会が増える宅配事業は共助の意識を高めるきっかけになるはずだ。地域の連帯を促すJAらしい事業に育てよう。 *4-6:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14150463.html (朝日新聞 2019年8月24日) 特定技能外国人の支援、参入続々 住居確保・生活指南など代行機関 新たな在留資格「特定技能」を持つ外国人労働者の生活を支援する「登録支援機関」が続々と誕生している。政府は今後5年間で最大34万5千人の受け入れを見込む。支援業務が商機になるとみて、企業を中心に各地で1800を超える機関が法務省に登録した。短期間に大量の支援機関が誕生することで、支援の「質」が保てるのか、懸念もある。特定技能の外国人に対し、受け入れ企業は出入国時の送迎や住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約などで支援することが法律で義務づけられている。登録支援機関は、そうしたノウハウがない中小企業に代わって外国人支援を「代行」し、1人当たり月数万円が相場とされる委託費を受け取る。すでに8月22日時点で全国で1808機関が登録した。うち、関東、甲信越の10都県を管轄する東京出入国在留管理局には738機関が登録。同管理局の福山宏局長は「半分弱は株式会社。外国人の受け入れ会社から委託費を受け取れるので外国人支援を『業』として展開できる好機、と踏んで参入している」とみる。登録支援機関になったTSB・ケア・アカデミー(東京都調布市)が6月に都内で開いた説明会には、外国人労働者の受け入れを検討している介護事業者ら約40人が参加した。アカデミーの親会社は電子部品の商社で、中国や東南アジアに製造・販売ネットワークを持つ。すでにベトナムに3校、フィリピンとラオスに1校ずつ人材養成学校をつくっており、早ければ年内にも日本へ送り出しを始めたい考えだ。外国人技能実習生の日本側の受け入れ窓口である「監理団体」が登録支援機関を兼ねる例も目立つ。実習生として3年の経験がある外国人は事実上、特定技能の資格が自動的に得られるからだ。主に造船業の実習生をフィリピンなどから受け入れる監理団体「ワールドスター国際交流事業協同組合」(愛媛県今治市)もその一つだ。代表理事の橋田祥二さんは「企業から『実習終了後も引き続き、特定技能の在留資格で外国人に働き続けてもらいたい』という声があり、手を挙げた」と話す。大手も動き出した。人材派遣のパソナ(東京都千代田区)は8月9日に登録支援機関になった。企業からの支援依頼が見込まれるためだという。個人も名乗りを上げる。なかでも行政書士は、外国人の在留資格の申請手続きなどに必要な書類を作成しており、登録が相次ぐ。神奈川県のある行政書士は「いまの仕事量だけでは生活が厳しい」として、外国人ビジネスへの参入を決めた。 ■申請書の提出「簡単」 支援機関になるためのハードルは高くない。日本語学習支援の取り組みなどを確認する申請書を法務省に提出する。だが、「ほとんどがチェックボックス式の回答なので簡単。拍子抜けだ」と東海地方の人材派遣会社の幹部は言う。申請書類には、外国語で対応できる担当者名を明記する必要があるが、「記した人物がどれだけ外国語会話ができるかなど詳細は聞かれない。架空でも通る」(幹部)。一方、法務省は「必要に応じて警察当局をはじめ関係省庁に照会している。ハードルを低くしていない」(出入国在留管理庁在留管理課)と強調する。「大量生産」に伴って懸念もふくらんでいる。支援機関は、契約先の企業で働く外国人と定期的に面談するが、この場で「残業代をもらっていない」などと訴えられた場合、労働基準監督署などの関係行政機関に通報しなければならない。だが、支援機関にとって受け入れ企業は、委託費をくれる「顧客」でもある。その顧客の不正を自ら明るみに出せるのか。法務省は「まずは通報しないといけない。できる、できないの話ではない」(在留管理課)と言い切る。劣悪な労働環境が批判を浴びている技能実習生の場合、受け入れ企業から集めたお金で運営される監理団体が甘いチェックで不正を見逃す例が数多く指摘されてきた。支援機関の立ち位置もこの監理団体と同じだ。現状では、特定技能の資格を得て在留している外国人は7月末時点で44人と少ないため、トラブルは表に出ていないが、大量にできた支援機関が十分な「質」を伴わず、チェック機能を果たさない事態が相次ぐ可能性がある。外国人の受け入れ制度に詳しい弁護士の杉田昌平氏は、企業は「我が社の外国人従業員の生活をきちんと支援してくれる支援機関を選ぶ」という意識を強く持つべきだ、と指摘。支援機関に関する情報を業界で共有することなどを提言する。 <時代にあった新作物> PS(2019年8月24日追加):*5-1のように、栃木県宇都宮市や東京都立川市がレモンの産地化を進めているだけでなく、福島県も地球温暖化適応策としてレモンの栽培実証を始めたそうだ。私も安心して皮まで食べられる国産レモンは貴重だと思い、毎年、佐賀県太良町のマイヤーレモン(レモンとオレンジをかけ合わせたもので、酸味がまろやかで美味しい)をふるさと納税の返礼品にもらって親戚まで配っているくらいだから、日本産の各種レモンができれば有望だと思う。また、福島県のミカンは、露地ミカンよりハウスミカンやハウスレモンにした方が、栽培しやすい上、他の産地と異なる季節に出荷でき、放射能汚染も少ないと思う。 さらに、*5-2のように、秋田県立大学が多収で難消化性のでんぷんを含む「あきたさらり」を育成したそうで、確かにダイエットに有効そうだ。収穫期が「あきたこまち」より1週間遅くて作業分散できるのもよく、今後は植物の品種改良という高度な技術力にも期待したい。そして、もちろん、種苗には、知的所有権があるわけだ。     (図の説明:1番左はマイヤーレモン、左から2番目は瀬戸内のレモンで、右から2番目はレモンケーキ、1番右は100%レモン果汁だ。日本製のレモンで100%レモン果汁を豊富に作れると、レモン果汁を使うのが容易になって、さらに消費が進むと思われる) *5-1:https://www.agrinews.co.jp/p47680.html (日本農業新聞 2019年5月17日) かんきつ産地 北へ 国産に需要 温暖化対策 関東、東北で試行錯誤 かんきつ産地に北上の兆し──。温暖な地域で栽培されているレモンの産地化が関東で進んでいる。輸入品が約9割を占めているが、防かび剤などを使っているため、安心して皮まで利用できる国産の需要が高まっているためだ。宇都宮市周辺では空いたハウスを活用し結実。東京都立川市では、消費地に近いことを生かし、町おこしの起爆剤に位置付ける。一方、福島県のJAふくしま未来は、地球温暖化への適応策として、栽培実証を始めた。 ●遊休施設 有効に ハウスレモン 宇都宮市 2018年、宇都宮市で「レモン研究会」が設立された。農家8人で、産地化に向けて新規栽培者の確保や栽培技術の確立を進めている。レモンへの可能性を感じて栽培に取り組む、研究会会長の竹原俊夫さん(65)は、18年にハウス3アールで14本の木から約600個のレモンを収穫した。現在は、栃木県内4店の飲食店などに販売している。竹原さんは「酸味がまろやかなので、フルーツ感覚でサラダなどにして提供する店もある。レモンの固定概念を変えたい」と説明。飲食店などからの国産へのニーズを感じ取った竹原さんは今年、需要拡大を見越して規模を拡大し、新たに20本の苗木を植えた。レモン栽培は、高齢化で遊休化する花きやイチゴのハウス活用としての側面もある。同市周辺は、冬に気温が氷点下になるほどで、レモン栽培には向いていないが、研究会はハウスを有効利用すれば栽培できると考えた。イチゴなどに比べ、管理が手軽なのも利点だ。現在「璃の香(りのか)」と「リスボン」の2品種を栽培する竹原さん。「ハウスを加温するとコストが上がるので、耐寒性のテストが必要だ。仲間と試行錯誤して、宇都宮産レモンを根付かせたい」と意気込む。 ●商店街おこし 新しい名物を 東京都立川市 東京では商店街がレモンで町おこしに取り組む。「立川に名産品をつくろう」と考えた立川市商店街連合会のメンバーらが「立川レモンプロジェクト」を始動。「とびしま」と呼ばれ、レモンの島々が浮かぶ広島県呉市から、18年に苗木を取り寄せ、市内の「なかざと農園」に植えた。「とびしま生まれ立川育ちの“立川とびしまレモン”」として、23年の出荷を目指す。現在は、10アールの園地に26本のレモンの木が育っている。同園の中里邦彦さん(47)は「寒さをどのように克服するかが課題だが、頑張りたい」と話す。プロジェクトリーダーの岩下光明さん(61)は「飲食店を経営している人からは、地元の新鮮なレモンがあれば使いたいとの声を聞く。消費地が近いことを生かして、立川といえばレモンと言われるような名物にしたい」と期待する。16年の財務省の貿易統計によると、国内に流通する輸入レモンは約4万9000トン。一方で、農水省の特産果樹生産動態等調査によると、国産は広島県や愛媛県などから約6000トン。国内で流通するレモンの多くは輸入品だ。 ●将来見据え 実証 露地ミカン JAふくしま未来 JAふくしま未来は、露地ミカンの試作を今年度から始めた。地球温暖化の進展により農産物の適地が移動することを見越し、中山間地域や海岸地域など条件の異なる管内4地区で営利生産に向けた栽培観察と検証を行う。収穫は2022年の予定。商業ベースに乗れば、現在の北限とされている茨城県・筑波山西麓に代わる露地ミカン生産の北限となる。試作導入するのは、早生種の「興津早生」100本と晩生種の「青島温州」10本。管内の希望する農家20人に配布した。試作する農家の一人、伊達市霊山町の佐藤孝一さん(64)は、4月中旬に「興津早生」4本を定植した。佐藤さんは「温暖化が進み、作ってみたいと思った。普段はあんぽ柿を作っているが、ミカンを作る選択肢ができるようになればいい。後継者がミカンもできるんだと思えるように栽培技術が確立することを期待している」と話す。今回植えたのは2年生苗。JAは、主産地である静岡県のJAみっかびと連携しながら同JAの栽培指導の資料を基に、技術を指導していく。22年に初収穫したミカンは、試作者全員で試食し、適地の確定と推進策を検討する。JAは「地球温暖化は進んでおり、将来の産地を維持する対策が必要になる。品質、量ともに安定生産できるめどが立てば、露地ミカンを桃、柿に続く果樹品目として普及を検討していきたい」と話している。 *5-2:https://www.agrinews.co.jp/p46461.html (日本農業新聞 2019年1月18日) 米粉用で多収品種 難消化性でんぷん豊富 ダイエット食材に 秋田県立大など 秋田県立大学などが、多収で消化しにくいでんぷん(難消化性でんぷん=RS)を含む新たな米粉向け品種「あきたさらり」を育成した。10アール当たり収量が800キロ程度と多収で、栽培コスト低減が期待できる。RSの含量は3%で、「あきたこまち」の3倍以上と多い。ダイエットなど健康志向の消費者にPRできることから、県内企業と、同品種の米粉を使ったうどんなどの商品開発を進めている。「あきたさらり」は同大と県農業試験場、国際農林水産業研究センター(JIRCAS)などが育成。2018年秋に農水省に品種登録出願を申請し、出願が公表された。米粉は製粉費用がかかるが、多収で栽培コストを下げることでカバーする。熟期は「あきたこまち」より1週間遅く、作業分散が期待できる。同大と企業の共同研究で、米粉を小麦粉に20%ほど混ぜてうどんを作ると、腰が強く、ゆでた後もべたつきにくい麺が作れることが分かった。「あきたさらり」はアミロース含量が高く、大粒で米粉適性が高い。同大生物資源科学部の藤田直子教授は「小麦アレルギーの人向けに、グルテンフリーのうどんなども作れる可能性がある。水田転作にも役立つ」と期待する。現在の栽培面積は約1ヘクタールだが、さらに拡大する見込みだ。 <都会の暑さとCO₂を利用> PS(2019年8月25日追加):*6-1のように、東京都千代田区の住友商事ビルのエアコン室外機近くにつった布袋でサツマイモを栽培し、給水や給肥はチューブを通して自動で行って、猛暑でも順調に育っているそうだ。その狙いは葉や茎から出る水蒸気が周辺の温度を下げる省エネ効果で、室外機の運転効率が1割ほど向上し、ヒートアイランド現象対策にも繋がるとのことだが、都会で豊富なCO₂もプラスに働くので、*6-2のキャッサバもよさそうだ。     2019.8.22日本農業新聞 2019.2.10東京新聞 (図の説明:左の2つは、*6-1のサツマイモ、右の2つはタピオカ原料のキャッサバ芋で、どちらも暑さに強く、炭素を固定化するのが得意なので、都会のビルの屋上にうってつけだ) *6-1:https://www.agrinews.co.jp/p48509.html (日本農業新聞 2019年8月22日) 都会の温暖化 “救世主”は芋 ビルの屋上に緑のしま模様を描くサツマイモの葉──。東京都千代田区にある住友商事美土代ビルの、エアコンの室外機周りにつった布袋で芋を栽培する屋上緑化が注目されている。住友商事と設計事務所の日建設計が2014年に始めた。9階建てビルの屋上に土が入った150の袋が並び、それぞれサツマイモが2株植えてある。給水や給肥はチューブを通して自動で行う。狙いは省エネだ。葉や茎から出る水蒸気が周辺の温度を下げる効果で、夏場は室外機の運転効率が1割ほど向上。ヒートアイランド現象対策にもつながるという。毎年秋に地元高校生と住友商事の社員らで芋を収穫。熊本県の造り酒屋で、屋上にちなんだ「頂(いただき)」と銘打った芋焼酎にしている。同社ビル事業部の高橋俊貴さん(26)は「猛暑でも毎年順調に育つサツマイモの強さは驚きだ」と話す。 *6-2:https://www.agrinews.co.jp/p48511.html (日本農業新聞 2019年8月22日) ブーム続く タピオカミルクティー 牛乳消費 盛り上げ 若者需要けん引期待 若い女性を中心としたタピオカミルクティーの一大ブームで、牛乳特需が起きている。熊本県の人気店では、1日に約100リットルの加工乳を消費。東京のチェーン店では、8店舗で牛乳1000リットルを使う。酪農関係者は「飲食店としては類を見ない消費量」と驚く。若者向けの新需要として、期待を集めている。熊本市にある「熊本ミルクティー」。休日は開店から閉店まで、列が途切れない人気店だ。メイン客である10、20代の女性の心をつかむのがタピオカミルクティー(500ミリリットル、500円)。濃く煮出した台湾茶に冷たい加工乳をたっぷり注いで作る。1日に約900杯を売る。他店との違いは、ミルクへのこだわりだ。ショーケースには、地元の熊本県酪連(らくのうマザーズ)が県産生乳から作る加工乳「らくのう特濃4・3」のパックがずらり。購入した20代のOLは「ミルクが濃厚だ」とほほ笑む。同店で使う加工乳は、1日約100リットル。新原一季店長は「ミルクは味を決める重要なもの。今の原材料を使い続ける」と強調する。東京を中心に8店舗を展開するTAPISTAでは、成分無調整牛乳を使ったタピオカミルクティーが支持を集める。8店舗で使う量は1日1000リットル。同店は「甘さと強いこくがあるものを選んでいる」と説明。他に、25店を展開する人気チェーンの「THE ALLEY」も一部メニューに牛乳を使っている。近年、健康志向の高まりで牛乳消費は堅調に推移。ただ、けん引するのは高齢者で、若者の消費は伸び悩んでいた。若者の牛乳消費を引き上げるタピオカミルクティーに、酪農業界も期待。らくのうマザーズは「一過性に終わらず、販路として広がってほしい」と話す。 <ことば> タピオカミルクティー ミルクティーに、キャッサバ芋のでんぷんで作った粒「タピオカ」を入れた飲み物。2018年にブームに火が付き、19年も新規出店が相次いでいる。1990年代や2000年代にも流行した。台湾発祥。現地では脱脂粉乳を使うのが主流だが、日本では牛乳や加工乳を使う店も出てきている。 <温暖化と豪雨> PS(2019年8月29、30日追加):近年は明らかに豪雨が増え、長崎県・佐賀県・福岡県に大雨を降らせた*7-1-1・*7-1-2の北部九州豪雨は記録的だった。これだけ大きければ激甚災害の指定を受けられるだろうが、被害状況を見ると、少し高い場所にある住宅は浸水を免れており、今後は豪雨も想定した災害に強い街づくりをすべきだ。農業は、保険をかけているものとそうでないもので明暗が分かれるが、稲が水没しても比較的被害が少ないことにはいつも感心する。 しかし、*7-2のように、かんきつ類を除く常緑果樹(オリーブ・マンゴー・アボカドなど)の栽培面積が10年間で5割増加して1000ヘクタールを突破し、国産原料をアピールする食品会社や飲食店などから引き合いが強くて、産地が栽培規模を拡大しているそうだ。マンゴーの伸び悩みの原因は価格を高く設定しすぎて日常使いになれなかったことなので、オリーブオイルも高すぎない価格設定にしなければ同様になると私は思うが、地球温暖化の影響で作物の変更がやりやすくなった。そして、*7-3のバニラも有望で、タコは中国や欧米で需要が急増しているため、日本が農林水産物の自給率アップだけではなく、輸出国にもなれるような基盤整備をすれば、面白いビジネスができると思われる。 また、*7-4のように、人口増・食の洋風化でカカオ豆の消費が世界的に伸び、サイクロン被害も手伝って、カカオ豆やバニラ豆の輸入価格が上昇傾向だそうだ。バニラ豆もカカオ豆も赤道付近が栽培に最適でアフリカ以外に調達先を広げるのは容易ではないと書かれているが、バニラは刀豆とかけ合わせるなどして、健康に良く日本でも大量に栽培できる農産品にできないか? なお、*8のように、豪雨で冠水被害などに見舞われた佐賀県武雄市や大町町などが、災害ボランティアの受け付けを8月31日から始めるそうだが、それに加えて、県か被害のなかった市町村がふるさと納税の募集を代行してはどうだろうか?     2019.8.28天気 2019.8.28毎日新聞     日本のバニラ栽培 鹿児島の刀豆 日本のマンゴー栽培 日本のアーモンド並木 *7-1-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/419657 (佐賀新聞 2019年8月28日) 【佐賀豪雨】濁流一気「まるで川」 武雄市、広範囲に被害 「通りが川になり、瞬く間に水が入ってきた」。28日未明からの記録的大雨は、佐賀県中西部に大きな被害をもたらした。武雄市では市が「数百件に及ぶため把握不能」とするほど広範囲で浸水。飲食店が集まる武雄町の中心部では何店もが「数日は営業は無理」と口をそろえ深刻な被害が広がった。北方町や杵島郡大町町では水が引かずに孤立する人が相次ぎ、夜になってもボートによる救助や物資運びが続いた。「変な音でドアを開けたら一気に水が入ってきた。通りは川みたいで、あわてて隣のビルの2階に逃げた」。武雄市中心部の飲食街中町通りの飲食店主は、28日午前4時ごろに急変した町の様子を語った。スナック経営の女性は「雨がひどくて帰れず、店で寝ていたら冷たい水を感じて起こされた。ひざ上まで水が入り冷蔵庫が水に浮いた。何もできなかった。電気もつかない。しばらく店は開けられない」と途方に暮れた。周辺の店も同様で、疲れた様子で片付けを続けていた。松浦川が氾濫した武内町も広範囲で冠水した。自宅前のビニールハウスがつぶされたアスパラ農家の浦郷敏郎さん(66)は「濁流にのまれるハウスをただ見ているしかなかった。ハウスは保険で建て直せるけど、作物は全部ダメになった」と肩を落とした、勤め人を辞めて就農して7年目。「これからどやんしゅうか。もう(農業を)やめないかんかなあ」と漏らした。車に乗ったまま水に流され男性1人が死亡した現場は武雄町西部の住宅街。道路から10メートルほど離れた田んぼの中に男性が乗っていた軽乗用車があった。近くの人は「道路脇の小川があふれて道に水が流れ込んでうずになり、水が車をさらうように田んぼに流したと聞いた」と話した。車の周囲の稲穂は乱れもなく、屋根付近まで水につかったとみられる。別の車も水田横の店の一角に乗り上げていた。大雨の影響で市役所も1階が浸水して窓口業務を休止。スーパーや飲食店も休店や開店遅れが相次いだ。 *7-1-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/538800/ (西日本新聞 2019/8/29) 九州北部記録的大雨 2人死亡88万人避難指示 3県に特別警報 対馬海峡付近に停滞する秋雨前線の影響で、九州北部地方は28日、観測史上最大を記録する猛烈な雨となり、佐賀県などで冠水被害が相次いだ。気象庁は一時、同県の全20市町、福岡県筑後地方の14市町村、長崎県の7市町に大雨特別警報を発表、3県で最大約37万700世帯、88万2800人に避難指示が出た。福岡県八女市で車から泳いで避難していた浜砂国男さん(84)と、佐賀県武雄市で車ごと流された50代男性が死亡した。特別警報は同日午後に解除されたが、29日も非常に激しい雨と土砂災害に厳重な警戒が必要だ。九州北部に、積乱雲が次々と発達して帯状に連なる「線状降水帯」が発生した影響で、佐賀県では28日明け方に1時間100ミリ超の猛烈な雨が降り、広範囲で冠水した。午前5時15分ごろには、同県武雄市武雄町武雄の武雄川で「軽乗用車が流されている」と通行人から110番があった。約2時間後、田んぼで水没した車が見つかり、運転席にいた50代男性の死亡が確認された。福岡県八女市立花町では午前7時50分ごろ、近くの浜砂さんが運転する車が冠水した道路を走行中に流された。浜砂さんは近くの男性から助け出され、泳いで避難している途中で用水路に流された。約2時間後に近くで心肺停止の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。佐賀市水ケ江では、70代女性の軽乗用車が水路に転落。女性は水没した車の運転席から救助されたが意識不明の重体という。佐賀県警によると、車で仕事に向かった武雄市武内町の50代女性が行方不明。車は武雄川の下流で水没した状態で見つかった。佐賀県大町町では「佐賀鉄工所」が冠水し、タンクから大量の油が流出。近くの住宅地や病院に流れ込んだ。流出した油は最大で8万リットル。近くの六角川や有明海への流出は確認されていないという。気象庁によると、降り始めから28日午後10時までの総降水量は、長崎県平戸市527ミリ▽佐賀市458ミリ▽福岡県久留米市399ミリで、いずれも8月の平年降水量の倍以上を記録。佐賀市では同日明け方の1時間雨量が観測史上最大の110ミリに達した。福岡県久留米市の巨瀬川、佐賀県多久市と小城市の牛津川、同県伊万里市の松浦川が一時、氾濫した。佐賀市では土砂崩れで送水管と配水管が破損、約750世帯で断水している。28日午後10時現在、佐賀、長崎両県の計約17万3700世帯、計41万2200人、福岡県で久留米市など3市村の約11万7800世帯、26万9400人に避難指示が出ている。3県の避難者は計約3200人。前線の停滞は30日にかけて続き、30日午前0時までの24時間降水量は多いところで福岡、佐賀、長崎150ミリ、大分120ミリ、熊本100ミリの見込み。 ◇ ◇ ■病院冠水201人孤立 佐賀・大町 28日の記録的な大雨で佐賀県大町町の順天堂病院が冠水し、患者や職員ら201人が孤立状態となっている。病院には近くの鉄工所から流出した油を含んだ水も流入、患者らは上階に避難している。全身の筋肉が萎縮していく難病の筋ジストロフィー症などで人工呼吸器を付けた重症患者も多く、別の病院への避難は難しいという。県は自衛隊などと連携し、支援策を検討している。県医務課などによると、敷地内には3階建ての病院のほかに、2階建ての老人保健施設がある。入院患者110人、施設利用者は70人。病院職員や介護職員の多くは出勤できておらず、県などは看護師らスタッフの送り込みを検討中。電気やガスに影響はないが、水道が止まっており、予備のタンク(1・5日分)で対応している。同病院の看護師は電話取材に「容態が切迫した患者さんはいません。大丈夫です」とだけ話した。 *7-2:https://www.agrinews.co.jp/p48543.html (日本農業新聞 2019年8月25日) 常緑果樹1000ヘクタール突破 かんきつ除き農水省が調査 06年→16年 5割増加 輸入より国産 オリーブ7倍 オリーブやマンゴーなどの常緑果樹(かんきつ類を除く)の栽培面積が1000ヘクタールを突破したことが農水省の調べで分かった。10年間で5割増えた。常緑果樹は輸入に頼る品目が多いが、国産原料をアピールする食品会社や飲食店などから引き合いが強く、産地が栽培規模を拡大している。同省は2016年、都道府県単位で50アール以上栽培されているなどの要件を満たす常緑果樹について調査。栽培は14品目、1082ヘクタールに上った。10アール以上の栽培がある品目を対象にした06年の調査では16品目、715ヘクタール。10年間で51%増えた。増加が目立ったのはオリーブで、06年の61ヘクタールから7倍の423ヘクタールに拡大した。栽培地域は2県から14県に増えた。同省は「若者を中心にオリーブオイルが注目され、国産原料の需要が増えて各地で栽培が広がった」(園芸作物課)と指摘。収穫後の劣化が早いため、国産需要の確保・拡大には、搾油のための加工場の整備など、6次産業化が必要とみる。マンゴーは421ヘクタール。面積はオリーブに次ぐ2位だが、06年で348ヘクタールと一定の規模が栽培されていた。ブームが落ち着いたことが影響し、11年の454ヘクタールをピークに減少傾向にある。栽培面積はまだ少ないが、生産が本格化しつつあるのがアボカド。14年の調査で3ヘクタールの栽培を初めて確認し、16年は9ヘクタールに増えた。同省によると、国内流通の大半は輸入品。国産需要の獲得に向けて、同省は栽培マニュアルをまとめるなどして導入を推進している。 *7-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14154991.html (朝日新聞 2019年8月27日)(アフリカはいま TICAD7)異変、バニラバブル 5年で10倍、銀より高値 庶民の味として親しまれてきたタコやバニラが高級品になりつつある。異変が起きた理由が、日本から遠く離れたアフリカにあった。アフリカ大陸の東方に浮かぶ島国マダガスカル。世界のバニラ豆の約8割を生産し、日本は9割強をここからの輸入に頼っている。首都アンタナナリボから北東に約500キロ離れたサバ地方は温暖で適度な湿度が保たれ、特に生産に適している。アンタラハという町から小型のボートで1時間揺られた先に、広大なバニラ農園が見えてきた。バニラ農家のファーリン・ジュディさん(26)は「土壌によって手入れの仕方を変えるなどして、品質を保つよう努めている」と語った。この地で異変が起きたのは5年ほど前。天然のバニラ人気が強まった欧米に加え、中国などでケーキやアイスクリームに使うバニラの需要が増え、取り扱う業者が急増。投機的な買い上げの動きもあり、2013年に1キロ当たり約5千円だった取引価格は、急上昇した。さらに追い打ちをかけたのが、自然災害だ。17年にサイクロンの被害を受けて一時、約6万円まで高騰。18年も価格は高止まりし、1キロあたりの取引価格は同じ年の銀の1キロ当たりの輸入価格(約5万5千円)を超えた。30年前からこの地に進出し、バニラ豆を輸入してきたミコヤ香商(東京)の水野年純社長(59)は「バブル状態が続いている」と話す。高騰などを受けて、ハーゲンダッツジャパンは今年6月出荷分から主力のアイスクリーム約20品目を23~85円値上げ。同社広報部は「バニラ味のアイスは一番人気だが、バニラの仕入れ価格はこの数年で10倍になった」と頭を抱える。1人当たりの国民総所得(GNI)が約400ドル(約4万2千円)にとどまるマダガスカル。トタンなどでできた家で暮らす人も多い。だが、サバ地方では、欧州や日本製の高級車を頻繁に見かけた。水野社長は「バニラ高騰でもうけた業者たちだ」と言った。地元で「バニラ御殿」と呼ばれる豪邸も点在していた。一方、価格高騰で農家らを悩ませているのが「バニラ泥棒」の増加だ。英誌エコノミストによると、年間の収穫物の15%以上が盗難にあうため、被害を防ぐために十分に育つ前に収穫する農家も出てきたという。バニラ輸出業者の「アグリ・リソース・マダガスカル」でも今年、バニラ豆の一部が盗まれた。マチュー・ルーガー最高経営責任者(CEO)(39)は「夜にパトロールをしていても、完全に食い止めるのは難しい」とぼやく。 ■タコも高騰、欧米でも需要急増 サハラ砂漠の西側にあるモーリタニア西部の港町ヌアディブ。タコつぼ漁を終えた漁師が12メートルほどの木製ボートで次々に漁港に戻ってきた。近くの水産加工会社のジャミラ・ベルハディール社長は「5年ほど前までは、タコのほとんどは日本向けだった。それが、最近は欧州勢が次々に参入して輸出先の8割が欧州になった」と明かす。タコ輸入業者などによると、日本で流通するタコの約半数が、モーリタニアかモロッコ産。現地はタコの餌となる貝が豊富で、日本は古くから地元でタコつぼ漁などの指導にあたってきた。欧米ではかつて、タコは「デビルフィッシュ(悪魔の魚)」と呼ばれ、競争相手は少なかったという。ところが、両国と距離が近いスペインやイタリアに加え、ヒスパニック系住民が増えた米国などで需要が増加。日本が仕入れる大きさのタコでは、昨年のモーリタニア産の仕入れ価格は一時、5年前の約2倍になり、過去最高水準を記録した。別の水産加工会社のヤクブ・エルナミ社長は「今は世界中でタコを食べるのが一種のファッション。日本の支援には感謝しているが、高く買ってくれるところに売るのがビジネス」と語る一方、「中国漁船が一気に増えて、他の魚と一緒に小さなタコも取ってしまっている」と打ち明けた。現地の邦人企業の担当者は「タコが大衆向けだった時代は終わった。たこ焼き屋でも、タコの粒を小さくしたり、別の国から仕入れたりするところも出ている。質は西アフリカ産が一番だが」と話した。 *7-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190829&ng=DGKKZO49088230Y9A820C1QM8000 (日経新聞 2019年8月29日) カカオ豆、価格引き上げへ 西アフリカ2カ国が「COPEC」 農家の手取り増狙う チョコレート原料のカカオ豆の取引価格を引き上げる動きが出ている。主産地のアフリカのコートジボワールとガーナが今夏、カカオの販売価格の引き上げで協調した。取り組みは原油市場の石油輸出国機構(OPEC)と似ており、カカオの頭文字をとって「COPEC(コペック)」とも呼ばれる。農家の手取りを増やす試みでカカオ豆が値上がりする可能性もある。カカオは年間の平均気温が27度以上の高温多湿な場所で栽培され、西アフリカが主産地。世界では生産量1位のコートジボワールと2位のガーナの両国で約6割のシェアを占める。その両国がカカオ豆の価格底上げを目指して今夏、1トン2600ドル(約2100ポンド)を最低販売価格とすることを国際会議で提案した。指標となるロンドン市場のカカオ豆先物相場は過去2年ほど1400~1900ポンド前後で推移していた。5年ぶりの低水準で生産者の間で不満が募っていた。両国の提案は価格水準を引き上げ、農家への配当拡大や持続可能な生産につなげる狙いがある。両国の提案を巡っては「市場価格と乖離(かいり)し、需要家企業と折り合いがつかなかった」(専門商社)ため流れたもようだ。代わりに両国が2020~21年度産で販売する全契約分に1トン400ドルの価格を上乗せする方針となった。国内のカカオ豆のトレーダーや食品会社には「価格押し上げ要因になる」との懸念が広がる。人口増や食の洋風化でカカオ豆の消費は世界的に伸びている。足元の相場は1700ポンド台に下がったが、7月上旬には産地の降雨不足と高値維持姿勢が材料視され、1年2カ月ぶりの高値をつけた。天候の変動に加え、生産国の価格政策が値動きを荒くさせている。同じくアフリカのシェアが高い農産物でも、高値が長期化しているのがアイスクリームなどの香料に使うバニラ豆だ。インド洋に浮かぶ島国のマダガスカルは日本の輸入元シェアでも約9割を占める。世界的にアイスクリームやケーキ向けの需要が伸びる一方、2年前に産地を襲ったサイクロンで花の受粉がうまくいかず生産が減った。日本の輸入価格も上昇傾向で、貿易統計によると19年1~6月平均で1キロ当たり4万8千円。サイクロン被害前の16年平均と比べると2倍以上だ。香料の原料を扱う輸入会社は「高値が限界点を超えた印象」と話す。日本では原料高でハーゲンダッツジャパンなどがアイス値上げに動いた。バニラもマダガスカルなどの安価な労働力が供給を支えてきたが、同国では18年の全産業の最低賃金が前年比で8%上昇。産地のドル建て価格も上昇している。パティシエなどが使う製菓向けの高級品は1キロ550~600ドル程度と、15~16年度の2倍近い水準だ。高値が新たな供給不安を誘発するケースも起きている。マダガスカル産地では価格が上昇したバニラビーンズを略奪するため、窃盗集団が栽培農家を襲撃するトラブルも相次ぐ。業界では「バニラ戦争」とも呼ばれる。農家は自衛手段を迫られ、生産コストを押し上げる要因になっている。バニラ豆もカカオ豆も赤道付近が栽培に最適とされ、アフリカ以外に調達先を広げるのは容易ではない。需要家企業などは天候や政情、産地の価格政策など苦い供給リスクに対して一段の備えが必要だ。 *8:https://www.nishinippon.co.jp/item/o/539248/ (西日本新聞 2019/8/30) 佐賀でボランティア受け付け開始 猛烈な雨で冠水被害などに見舞われた佐賀県武雄市や大町町などは、災害ボランティアセンターを設置し、31日から受け付けを始める。避難所への救援物資の運搬のほか、浸水した路上の泥のかき出し作業や住宅の清掃などを想定している。避難中で自宅に戻れない住民も多く、ニーズの把握が困難なこともあり、武雄市と大町町は31日のボランティアは、原則的に県民に限定する。大町町社会福祉協議会によると、30日にセンターを設置して以降、県内外から問い合わせの電話が相次いでいるという。
| 農林漁業::2019.8~ | 03:16 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,04,30, Tuesday
    ティラノサウルスの骨格と想像図 羽毛恐竜の化石と想像図 (図の説明:最近は恐竜化石の発見が多く、次第に全貌が見えてきたが、恐竜と鳥の骨格は類似点が多い。また、羽毛恐竜の化石も発見されている。そして、ティラノサウルスの骨格は、下のエミューや鶏のような組み立て方をするのが、重心が足の上にくるので正解だと思われる)     (飛べない鳥)エミューの親子と骨格 (あまり飛べない鳥)鶏の成鳥の骨格と雛 (図の説明:左の2つは、オーストラリアの飛べない鳥エミューの生きている姿・雛・骨格だ。また、右の2つは、鶏の骨格模型と雛である)    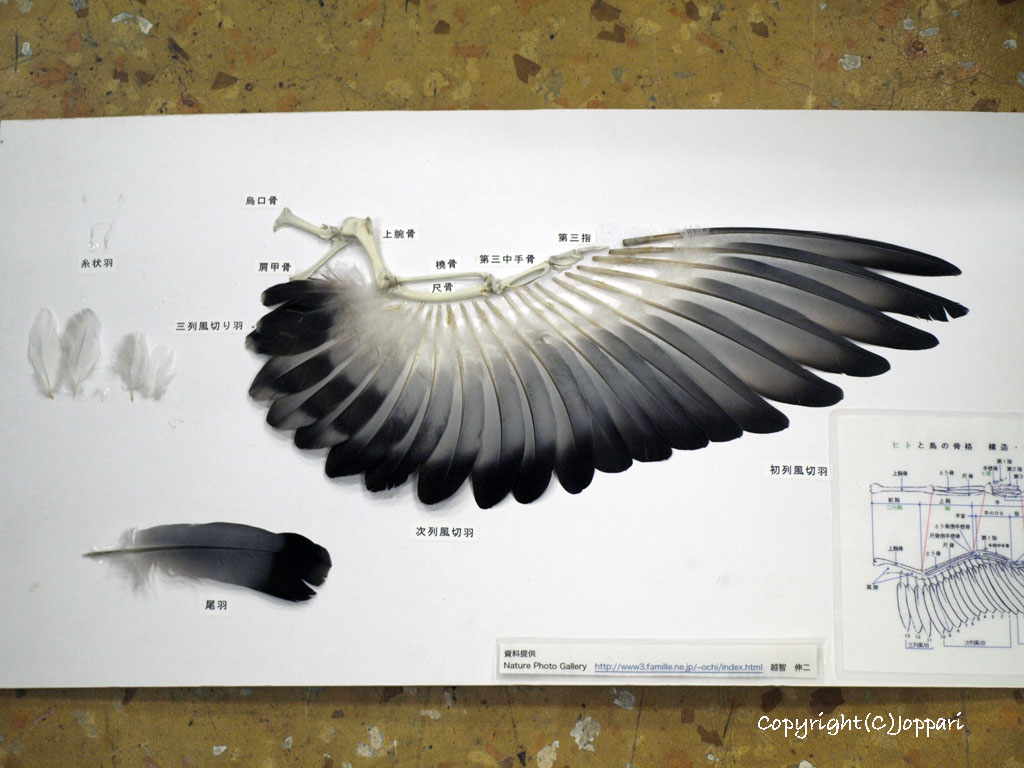  (飛ぶ鳥)鶴と鶴の雛 (飛ぶ鳥)鳩の飛び方、翼の構造、骨格 (図の説明:左の2つは、鶴の成鳥と雛、右の3つは鳩の成鳥・翼の仕組み・骨格だ) (注)生態を調べるためでも、むやみに鳥を傷つけたり、殺したりしないで下さいね。 (1)ティラノサウルスはトカゲではなく、飛べない鳥だったのでは? 1)自然に起こった進化 *1-1のティラノサウルス(学名:genus Tyrannosaurus)は、約6850万~6550万年前の北アメリカ大陸に生息していた肉食恐竜とされ、サウルス(saurus:ギリシア語のラテン語形学名で「トカゲ」を意味する)は恐竜・翼竜・首長竜等の絶滅爬虫類に用いられてきた(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B9_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF) 参照)。 しかし、爬虫類であるトカゲの骨格は、手足の長さが同じで地を這いやすいようになっているのが特徴で、ティラノサウルスの骨格は手が短くて羽でも生えていなければ役に立たなそうに見える。これに近い大きさの手を持っているのは、飛べない鳥エミュー(オーストラリアの非公式な国鳥で、オーストラリア大陸全域の草原や砂地など拓けた土地に分布している)で、エミューは風切羽を持たず糸状羽毛だけが生えており、手は座って卵を抱く際に地面についている。 鳥として最終形に進化している鶴や鳩の骨格を見ると、手(=翼)の骨が長く、羽も自由に動かすことができ、翼を広げれば自在に飛べる仕組みになっている。それでも、「個体発生は系統発生を繰り返す」と言われているとおり、雛の手はエミューやティラノサウルスと同様に短く、羽毛は生えているが羽はない。ティラノサウルスと鳥の違いは、口の構造のように見える。 このような進化が起こった理由は、そうしなければ生きられない環境があり、環境と生殖の両面から迫る淘汰圧によって、より環境に適応した個体が生き残って子孫を増やせたからである。 2)農業などで人が作った進化(or退化?) 鶏は、キジの仲間のセキショクヤケイを、4000~5000年ほど前に、人が飼い馴らして家禽としたもので、現在では、肉や卵を生産する用途別に品種改良が進められ、約120品種以上あるそうだ(http://zookan.lin.gr.jp/kototen/tori/t421_1.htm 参照)。 そのため、セキショクヤケイの間は、得意ではなくても少しは飛べる鳥だったようだが、家禽として人が飼うようになってからは、飛ぶ能力よりも、産卵能力や肉の美味さによって人に選別されて変わってきたわけだ(品種改良)。その鶏の手は鶴や鳩よりもずっと小さいが、エミューと違って風切り羽はあり、幼鳥の時は羽毛だけだが、成長するにつれて風切羽が生えてくる。 3)ティラノサウルスはトカゲではなく、エミューのような鳥だったのでは? 結論として、ティラノサウルスと鳥類の足や首は殆ど同じ形であることもあり、最初に「トカゲ」という名前を付けたのが誤りで、本当はエミューと同じような飛べない鳥だったのではないかと、私は考える。また、陸上の寒冷な場所なら、うろこより羽毛の方が役立つだろう。 (2)農業における品種改良 家畜や稲などの農産物は、味をよくしたり、気候に合わせたり、生産性を上げたりするために、品種改良や技術開発が行われるが、品種改良は生物の方から見ると進化(or退化)である。 最近は、*1-2のように、比較的栽培が容易なことからオリーブの生産が活発化しており、油が取れるだけでなく、健康に良く、植木や枝物としても利用でき、6次産業化すれば国内だけでなく輸出にも耐えられることから、オリーブの産地化には期待が持てる。 しかし、オリーブは、もともと地中海性気候の地域で栽培されていたものであるため、九州や瀬戸内海に浮かぶ広島県江田島市が市を挙げてオリーブの産地化を進めるのはわかるが、耕作放棄地対策や他果樹からの転換品目として東北でも栽培するには、かなりの品種改良が必要なのではないか? このようにして、農業は時間をかけて品種改良をしてきたわけだが、栗・クルミ・アーモンドなど、もっと東北で作り易い作物もあるのではないかと思った。 (3)放射線が、DNAを通して進化に与える影響 1)進化の仕組み それでは、どのようにして生物の進化が起こるのかと言えば、同じ種の生物でも偶然起こるDNAの突然変異によって多様な個体が生まれ、環境に適さないものも多く生まれるが、特に環境に適したものも生まれ、後者が多くの子孫を残すことで、その生物の全体に占める割合を増やしていくことによって起こるのである。 そして、自然では、生殖と環境による淘汰圧のバランスによって選択されて変化の方向とスピードが決まり、家畜や農作物は、人の選択によって変化の方向とスピードが決まる。食品等のゲノム編集は、人がDNAに直接手を加えて変化させるので早いが、個体や環境に予想もしていなかった多くの影響が出る可能性があるため、慎重にも慎重を重ねるべきなのである。 2)自然放射線と人工放射線の違い ショウジョウバエの突然変異を起こすのに放射線を使うことを高校生物で勉強したが、放射線を当てるとDNAが損傷するから突然変異が起こり易くなるのであり、これは、人を含む他の生物でも同じことで、放射線には、①自然に降り注いでいる自然放射線(これが、年間1mSv未満と言われているもの) ②核爆発によって人が起こした人工放射線があるわけだ。 これまで地球上で生き残ってきた生物は、①については、対応できているため問題ない。何故なら、対応できていない生物は子孫を残せないため、現在まで生き残っていないからだ。しかし、②については、そのストレスに曝露され始めてから70年前後であるため、寿命が長くて少産少死の生物は対応できていないわけである。 そして、*2-1に関して、WTOが報告書に「日本産食品は科学的に安全」という記載をしなかったのは、②については、日本産食品が国際機関より厳しい基準で出荷されていても、科学的に安全とは言えないからである。そのため、*2-2に「日本は科学的立証せず、裏目に出た」と書かれているが、正確な統計をとって科学的に調査をすれば、(何度も書いているので長くは書かないが)安全ではないという結果になるだろう。 なお、BSEのケースは、日本が国際ルールより厳しい基準を設けて前頭検査をしていたのだが、吉野屋の強い要望で米国産牛を輸入し、日本産牛の前頭検査もやめて米国基準に合わせた。しかし、米国が米国産牛の安全性を主張しているのは、それを食べてクロイツフェルト・ヤコブ病になった人がいたとしても、どの牛肉が原因だったかを判定することができないので損害賠償請求もできないだろうという考え方である。今では、日本もBSE牛が発生しやすくなっていると思われるため、せっかくやっていた前頭検査をやめて価格だけ高い牛肉になってしまったのは残念なことである。 また、*2-3に、福島県産の野菜・果物・魚などの放射性物質の検査で、昨年度に日本の食品基準(100ベクレル/ kg)を上回ったのはおよそ1万6000点のうち6点で、イワナ・ヤマメ・たらの芽だったそうだが、問題は「100ベクレル/ kgなら無害」という根拠が科学的に示されていないことなのである。 そのため、*2-4のように、「100ベクレル/ kg以下の食品なら、いくら食べ続けても無害だ」という根拠を科学的に示すことなく風評被害と強弁し、農水省・復興庁・経産省が連名で業界団体に対して福島県産農産物を敬遠したり、買いたたいたりすることがないよう求める通知を出したことは、日本は産業のためには人の命を差し出しても何とも思わない国だということで、とても許せるものではない。しかし、このような安全性に対する鈍感さは日本製全体の信頼を損なうため、産業のためにも有害なのである。 ・・参考資料・・ <生物の進化> *1-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201904/CK2019042802000147.html (東京新聞 2019年4月28日) ティラノサウルス勢ぞろい 坂東・県自然博物館 企画展入場10万人突破 坂東市のミュージアムパーク県自然博物館で開催中の企画展「体験!発見!恐竜研究所-ようこそ未来の研究者-」が人気だ。肉食恐竜ティラノサウルスの全身骨格を三体同時に見られる日本初という展示が好評で、ゴールデンウイーク初日の二十七日に企画展の入場者が十万人に達した。十万人目になったのは、神栖市から家族で訪れた宍戸真子さん(4つ)。「恐竜が好きで見に来た。(十万人目になり)びっくりした」と話した。企画展は二月にスタート。恐竜の標本や模型など二百二十三点を展示し、恐竜の復元された姿の変化や、骨から年齢を推定するなどの最新の研究、日本で発見された恐竜などを紹介している。発掘体験コーナーもある。三体のティラノサウルスの全身骨格は、それぞれ二十歳、十一歳、二歳ごろとされる。大人、若者、子どもの年齢で、体格の違いを見比べられる。さいたま市の小学一年生吉田光汰(ひなた)さん(7つ)は「大きくて、歯がすごかった」と驚いていた。六月九日まで。月曜休館(二十九日、五月六日は開館、同七、八日は閉館)。入場料は一般七百四十円、高校・大学生四百五十円、小・中学生百四十円。五月四日と六月五日は無料で入館できる。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p47300.html (日本農業新聞 2019年4月7日) 国産オリーブ 多用途で地域を元気に オリーブの生産が活発だ。比較的栽培が容易なことから、耕作放棄地対策や他果樹からの転換品目として、栽培は東北から九州に及ぶ。魅力は油が取れるだけでなく、植木や枝物としても利用できること。6次産業化で新たな雇用が生まれた事例もあり、地域を元気にする果樹として産地化を進めよう。瀬戸内海に浮かぶ広島県江田島市は、市を挙げてオリーブの産地化を進める。目指すのは「カキに匹敵する産業」。市内はかんきつ栽培が盛んだが、高齢化で耕作放棄が年々拡大。管理の手間がかんきつより少なく、6次化への展開が期待できるとして目を付けた。市は苗木の助成や、荒廃した園地の改良に必要な機器リース料の助成の他、6・6ヘクタールを新たに造成するほどの力の入れようだ。果実はそのままでは利用できないため、脱渋や塩漬け、搾油といった工程が必要になる。その核となるのが、江田島オリーブ(株)だ。同社は自ら生産、販売、加工を手掛けるだけでなく、オリーブ油を使った料理などが楽しめる施設を運営する。これにより、地元に50人の雇用を生んだ。地元農家が作った果実も1キロ850円で買い取るため、農家にも地元住民にも、会社にも利益が得られる好循環が生まれている。ユニークな活用法を目指すのが、群馬県館林市の農業生産・加工を手掛けるジャングルデリバリー。鉢植えにしたオリーブを生産し、街路樹向けとしてレンタルする事業に乗り出した。生産に必要な農地は8戸の農家から借り、現在5000本の苗木を育てる。将来は面積を広げ、地域の雇用創出や農福連携も展望する。この他にも化粧品や枝物としての販売、植木としての需要も見込める。香川県では、茶樹のように仕立てて葉を収穫し、オリーブ茶として販売する。栽培の広がりを受けて2月下旬には、栽培発祥の地・香川県小豆島で初の全国サミットが開かれた。参加したのは12府県24自治体で、北は宮城県石巻市から南は鹿児島県日置市。会合では「日本オリーブ自治体協会」の設立を目指し、産地間の連携や国際オリーブ協議会への加入を目指すことを確認した。栽培に適した環境は、①年平均気温14~16度で一時的には氷点下10度でも耐えられる②年間日照時間は2000時間以上が理想。1700時間程度の産地でも結実する③年間降水量は1000~2000ミリ。地球温暖化の影響で適地は広がっているとみられるが、懸念されるのは近年の異常気象による大量の降雨。香川県小豆オリーブ研究所は「地質条件や気象条件に応じた技術開発が必要」とみる。国内で流通する国産のオリーブ油は1%未満。油にはオレイン酸、果実や葉にはポリフェノールなど機能性成分が含まれ、健康志向にマッチする。産地化に向け情報を共有し、栽培の機運を高めよう。 <自然放射線と人工放射線の違い> *2-1:https://digital.asahi.com/articles/ASM4Q54YDM4QULFA01W.html?ref=mor_mail_topix1 (朝日新聞 2019年4月23日) WTO判決「日本産食品は安全」の記載なし 政府と乖離 韓国による東京電力福島第一原発事故の被災地などからの水産物の全面禁輸を事実上容認した世界貿易機関(WTO)の判断をめぐり、日本政府が第一審の判断を根拠に説明している「日本産食品の科学的安全性は認められた」との記載が第一審の判決文にあたる報告書にないことがわかった。国際法の専門家から「無理のある説明だ」と報告書の内容との乖離(かいり)を指摘する声が出ており、「身内」なはずの経済産業省所管のシンクタンクも問題視するリポートを出した。この紛争は、韓国が2013年、事故を起こした福島第一原発から汚染水が流出しているとして、福島など8県の水産物の禁輸対象を一部から全面に拡大したことに対し、日本がWTO協定に違反しているとして提訴した。紛争を処理する上級委員会が11日、韓国の禁輸を「不当な差別」とした第一審・小委員会の判断を破棄する報告書を出した。日本の事実上の逆転敗訴だが、菅義偉官房長官は12日の記者会見で「敗訴の指摘は当たらない」と強調した。理由として、上級委が日本産食品の安全性に触れていないため「日本産食品は科学的に安全であり、韓国の安全基準を十分クリアするとの一審の事実認定は維持されている」ことを挙げた。河野太郎外相もほぼ同じ発言をした。だが、実際には第一審の報告書には「日本産食品は科学的に安全」との記載はなかった。さらに、第一審は「日本産食品が韓国の安全基準を十分クリアする」と認定していたものの、上級委はこれを取り消していた。「食品に含まれる放射性物質の量だけに着目した第一審の判断は議論が不十分」というのが理由だ。「科学的に安全」と付け加えたことについて、外務省と農林水産省の担当者は「第一審の『日本産食品が国際機関より厳しい基準で出荷されている』との認定をわかりやすく言い換えた」と釈明する。だが、WTOの紛争処理に詳しい中川淳司・中央学院大教授は「日本の基準が国際基準より厳しいことと、科学的に安全かは同義ではない。苦しい説明だ」と指摘する。また、福永有夏(ゆか)・早大教授は「そもそも第一審で安全性の認定は行われていない」と話す。日本が訴えたのは韓国が日本産食品を差別的に扱っていることなどで、安全性自体の認定は求めなかったためという。「韓国の安全基準を十分クリアする」との説明には、川瀬剛志・上智大教授が「明らかに判決の解釈を誤っている」と指摘する。経産省所管の独立行政法人「経済産業研究所」は16日、同研究員でもある川瀬教授がこうした問題点を指摘したリポートを出した。翌17日、外務省の山上信吾経済局長は自民党の会合で、「韓国が定める『安全性の数値基準』を十分クリアできる」と述べ、政府の公式見解を一部修正した。「判決を精査した結果、より適切な表現に改めた」(農水省担当者)という。「科学的に安全」との説明はそのまま続けている。川瀬教授は、「判決は日本の食品の安全性を決して否定していない」と強調した上で、「政府がやるべきことは事実をごまかすことではない。冷静に現実と向き合い、23カ国・地域で残る食品の輸入規制にどう対処するかを考え抜くことだ」としている。 *2-2:https://digital.asahi.com/articles/ASM4L441NM4LULFA00Y.html?iref=pc_extlink (朝日新聞 2019年4月23日) 日本は科学的立証せず「裏目に出た」 WTO判決の敗因 世界貿易機関(WTO)の上級委員会が判決に当たる報告書で、東京電力福島第一原発事故を理由とした韓国による日本産水産物の禁輸を事実上容認し、日本が「敗訴」した。なぜ負けたのか。今後どのような影響があるのか。WTOの紛争処理に詳しい2人の国際経済法の専門家に聞いた。 ●中川淳司教授(中央学院大・現代教養学部) 今回の日韓紛争の本質は、韓国の輸入禁止措置に科学的な根拠があるのかどうかだ。にもかかわらず、日本はこの「本丸」を正攻法で立証せずに脇から攻め、裏目に出た印象だ。衛生植物検疫措置に関するWTOの国際ルール「SPS協定」は、2条の2で、各国の輸入規制は「科学的な原則に基づいてとること」を求めている。日本はこの条文では訴えず、「同一または同様の条件下にある国の恣意(しい)的または不当な差別」(2条の3)と、「必要以上に貿易制限をしてはならない」(5条の6)で韓国を訴えた。2条の3違反には、日本と他国が「同一条件にある」ことが必要だ。だが、普通に考えて、国際社会は福島第一原発の事故があった日本と他国が同一条件とは思わないはずだ。5条の6違反には、韓国の措置が「必要以上」であることを立証しなければならない。だが、食品の安全をどこまで求めるのかは国民性で違いがあるため、SPS協定は各国の裁量の余地を残している。日本も牛海綿状脳症(BSE)では、国際ルールよりも厳しい基準を独自に設けて、米国産牛肉の輸入を制限した。日本が2条の2違反を主張しなかったのは、立証が難しいと考えたからだろう。日本が放射線被曝(ひばく)量に関する国際基準より厳しい出荷規制をしていても、「科学的に安全」と認められるとは限らない。負けた時の風評被害のリスクも意識したのではないか。日本が「王道」の議論を避けた時点で、この裁判は勝ち目が無かったと思う。WTOの紛争処理では、上級委の判決には重みがある。日本が今後韓国以外の国を訴えた場合、今回の判決が重要な参考とされるはずだ。日本にとって今回の敗訴は、非常に厳しい。 ●福永有夏教授(早稲田大・社会科学部) WTOの紛争処理においては、各国の「安全」と考える対応について、その国の裁量をより広く認める傾向は以前からある。今回の上級委の判断の妥当性に、問題はないと思う。ただ、韓国の禁輸措置をSPS協定違反とした一審の判断を破棄したものの、肝心な「違反があったかどうか」について最終的な結論は出さなかった。中途半端で、日韓の紛争が解決されずに残ってしまったと言える。判断は韓国の禁輸を「協定に違反していない」と積極的に認めたわけではないが、「違反している」とも認めなかった。最終結論は出ていないので、法律論としては、今回は「引き分け」との評価が一番妥当だ。ただ、重要な日本の主張が退けられた観点では、日本の事実上の敗訴と言える。今後、東京電力福島第一原発の事故を理由に日本産食品に輸入規制をかけている23カ国・地域と、日本が規制撤廃を交渉していく上で、痛いつまずきとなった。米国が「上級委が必要以上に判断を出しすぎだ」とWTOを批判しており、上級委がこうした批判を意識し、最終的な結論を出すのを控えた可能性もある。懸念するのは、日本国民のWTOへの信頼が損なわれることだ。WTO紛争処理は法に基づく貿易紛争の解決に貢献しており、これまで日本も多くの恩恵を受けてきた。いまのWTO紛争処理には「差し戻し」の制度が無く、今回のように上級委が第一審の判断を破棄すると、最終的な結論を下されないまま判断が確定してしまう恐れがある。差し戻し制度の導入も検討すべきで、日本は今回の判断を契機に、WTO改革を主導していく役割を果たしてほしい。 ◇ 〈韓国による日本産水産物の禁輸をめぐる経緯〉 韓国が2013年9月、福島第一原発から汚染水が流出しているとして、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の8県の水産物の禁輸対象を一部から全面に拡大。日本が15年8月にWTO協定に違反しているとして提訴した。第一審の小委員会は「不当な差別」として韓国に是正を勧告したが、第二審の上級委員会は、小委員会の判断について、検討が不十分だったとして破棄した。WTOの紛争処理は二審制で、この判断が確定することになる。 *2-3:https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20190417/6050005159.html (NHK 2019年4月17日) 放射性物質 基準超の食品は6点 福島県産の野菜や果物、魚などの放射性物質の検査で、昨年度国の食品の基準を上回ったのはおよそ1万6000点のうち6点でした。基準を超えたのはイワナとヤマメ、たらの芽でした。福島県は原発事故のあと県内でとれた野菜や果物、魚などの一部で放射性物質の検査を行っています。昨年度は492品目、1万5941点を検査し、国の食品の基準の1キロあたり100ベクレルを超えたのは0.04%にあたる6点で、10点だった前の年度に比べ、4点減りました。基準を超えたのは、福島市、伊達市、桑折町の阿武隈川水系でとれたイワナ2点とヤマメ3点、北塩原村でとれた野生のたらのめ1点でした。基準超えの食品は原発事故の直後に比べ大幅に減少していて、肉類は平成23年度から、野菜や果物は25年度から、コメなどの穀類は27年度から、国の基準値を上回るものは出ていません。県環境保全農業課は、「安全安心を確保するにはこうしたデータがベースになるので、品目や検体の数も含めてこれまでと変わらず検査を徹底するとともに正確に情報発信していきたい」としています。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p47514.html (日本農業新聞 2019年4月30日) 福島産 敬遠回避を 物流業界に農水省指導 農水省は29日までに、復興庁と経済産業省の連名で、卸売業者や小売業者などの業界団体に対し、福島県産農産物を敬遠したり、買いたたいたりすることがないよう求める通知を出した。東京電力福島第1原子力発電所事故を受けて根強く残る風評被害の払拭(ふっしょく)につなげる。農水省は3月末、同県産農産物の流通実態について、2018年度の調査結果を発表した。主要な農産物である米や桃などの販売価格は全国平均を下回り、震災前水準まで回復していなかった。事業者や消費者へのアンケート結果からは、福島産を敬遠する傾向が浮かんだ。今回の通知はこうした調査結果を踏まえて出した。卸売業者や仲卸業者、小売業者などの業界団体に対しては、①同県産の評価に見合った販売を行うこと②同県産農産物であることだけで取り扱わなかったり買いたたいたりしないこと③同県産と他産地産を対等に比較して取扱商品を選択すること──などを求めた。3省庁は生産者団体に対しても通知を出した。農業生産工程管理(GAP)を着実に行い、県産農産物のイメージアップにつなげることや、積極的な販売促進活動を行うことを呼び掛けている。農水省は今回の通知について、流通業者や同県の生産者を対象に説明会を開くなどし、理解を呼び掛けていく考え。 <恐竜絶滅の中で鳥類だけが生き延びた理由> PS(2019.5.1追加):*3に、「①恐竜絶滅で、なぜ鳥だけが生き延びたか?」「②空飛ぶ恐竜はほかにもいたはず」と書かれているが、小惑星が衝突して気候が寒冷化し、陸上動物が少なくなった地球で生き残る要件は、①食物が水中・地中・木の中などにある ②体毛がある などで、そのため、大型で動物の肉を切り裂く歯を持つ恐竜が絶滅し、嘴と羽毛を持つ鳥類が生き残ったのではないかと思う。      トラ(肉食) ワニ(肉食) イグアナ(草食) 2016.4.11日経BP 現生動物の口と歯の比較 (アメリカの恐竜展より) *3:https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/050100197/(日経BP 2018.5.2)恐竜絶滅、なぜ鳥だけが生き延びた?空飛ぶ恐竜はほかにもいたはず、科学で迫る鳥類進化の秘密 ここ数年、鳥類の進化を解明する手がかりになるような発見が続いている。米国のニューメキシコ州では最近、原始的なネズミドリの化石が断片ながら見つかった。6200万年前のものと推定されるこの化石は現在のところ、大量絶滅後に生息していた鳥類のうち、最も古い部類に属する。このほか、ニュージーランドでは6100万年前の太古のペンギンの化石が最近見つかったが、同時代のほかのペンギンとは異なる外見をしていたと考えられる。こうした化石のすべてが、最新の遺伝子解析で明らかになった進化の道筋と一致しているようだ。「数千万年に及ぶ進化の結果、前肢を羽ばたかせて空を飛ぶ小型の恐竜が誕生しました。その後、小惑星が衝突した際、そうした体の構造が実に好都合だとわかったのです」と、英エディンバラ大学の古生物学者スティーブン・ブルサティは語る。「こうした鳥の一部が大量絶滅を生き延び、ほかの動物がほとんどいなくなった地球で繁栄することになりました」。しかしまだ、より難解な謎が残っている。なぜ、現在の鳥類の祖先だけが生き延びたのかということだ。その理由に関しては、さまざまな説が唱えられている。バース大学のダニエル・フィールドと彼の同僚たちは、森林の大規模な消滅が関係しているのではないかと考えている。白亜紀末の地球は現在よりも温暖で湿潤だった。生い茂った森には、さまざまな種類の初期の鳥たちが生息していて、現生の鳥と似たものも多かったと考えられる。繁殖能力の高さが鍵を握ったとする説もある。2017年、米フロリダ州立大学のグレゴリー・エリクソンが率いる研究チームは、非鳥類型の恐竜は卵を抱いて孵化させるのに数カ月かかっていたとする証拠を示した。一方、現生鳥類の多くは一般に繁殖頻度が高く、数日から数週間という短期間で孵化するので、小惑星衝突後の過酷な状況を生き抜くことができた可能性がある。世界各地で、研究者たちは鳥類の進化の謎に挑んでいる。南米やニュージーランド、南極で進行中の発掘調査から、新たな発見が近々もたらされると期待されている。さらに今後数年のうちに、より詳細で豊富な遺伝情報が得られることになりそうだ。中国広東省の深センにある国家遺伝子バンクでは、従来よりも高速で精度の高い技術を駆使して、2020年までに1万種を超す現生鳥類すべての全遺伝子のドラフト配列(おおよその配列)を解明する取り組みを進めている。このプロジェクトの成果を応用すれば、化石となった太古の鳥の特徴と現生の鳥の特徴を照合できるようになるはずだ。ある種の鳥だけが絶滅を免れたのは、それに適した条件をいくつも備えていたからだと考えるのが、生き残りの謎に対する最も妥当な答えといえそうだ。だからこそ、これからも証拠を積み上げ、新たな説を次々と検証していくことが大切なのだ。「私たちが取り組んでいるのは、6000万年以上も時間をさかのぼり、地球規模で起きた極めて複雑な出来事を解明することなのです」とフィールドは話す。それでも「相互に関連するこうした疑問を詳細に研究することによって、地球史上でも最大規模の深刻な大量絶滅を生き延びた鳥という生き物に対して、少しずつ理解が深まっています」 <皇室が絶滅しないために、求められる「国民統合の象徴」像> PS(2019年5月1日追加):こういう場所に書いて申し訳ないが、*4-1のように、平成天皇が2019年4月30日に退位され、「退位礼正殿の儀」で「象徴としての私を受け入れ、支えてくれた国民に、心から感謝します。令和の時代が平和で実り多くあることを皇后と共に心から願います」とお言葉を述べられた。また、同年5月1日には、*4-2のように、令和天皇が即位され、「即位後朝見の儀」で「憲法に則り、日本国および日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓う」と述べられた。これらはよいが、「剣璽等承継の儀」は皇位継承資格を有する男性皇族しか参列できないというのは、大日本帝国憲法下で女性を一人前の人間と認めていなかった時代ならともかく、現在の日本国憲法下では合憲でなく、国民感情に寄り沿ってもいない。 そのため、昭憲皇后が洋装で積極的に人々の前に姿を見せ、貞明皇后が側室制度を無くし、美智子皇后が恋愛結婚して乳母制度を廃止し、雅子皇后がキャリアウーマンから皇室に嫁ぐなど、一歩先を行く女性像を示してきた皇室なら、次は女性天皇・女系天皇を出し女性宮家も認めて皇室を男女平等にするのが、女性を含む国民統合の象徴の役割だと考える。 側室制度を作ったり、外部から天皇として男系男子を養子に迎えたりすることを、*4-3のように国民は望んでおらず、現在の環境にも合っていないため、天照大御神(皇祖神で女性)は、その改革を進めるために令和天皇御一家に女の子だけを授けたのかもしれない。 なお、*4-4に、新天皇のお言葉全文が記載されているが、雅子皇后について宮内庁が2004年7月に公表した「適応障害」は病名として存在せず、いい加減だ。そのため、雅子皇后には、もともと持っている個性と能力を活かして新しい皇后像を作ってもらいたいが、皇后の能力は、知識や語学だけでなく容姿やファッションセンスも含んでおり、世界に出しても恥ずかしくない皇后であっていただきたいわけだ。そのためには、メディアでよく褒め言葉として使っている日本独特の「やさしさ」と意味なき「笑顔」では不足である。 それにしてもメディアのキャラウーマン叩き(人権侵害と侮辱そのもの)はものすごく、私もこのキャラウーマン叩きの“空気”に大変迷惑したのだが、訴訟して勝っても謝罪もされないし、損害を回復するための補償もなかったので、決して忘れてやることも許すこともない。     2019.1.5産経新聞 2019.5.1産経BZ 2019.5.1朝日新聞 (図の説明:左図の予定に従って退位及び即位の儀式が行われる。左から2番目と3番目は平成天皇退位の儀式で、1番右は令和天皇即位の儀式のうちの「即位後朝見の儀」だ。私は、皇室の儀式を私費で賄うよりも、国費で賄って立派に行いつつ世界に放映した方が、皇室の歴史を感じさせたり、外交でプラスになったりすると同時に、歴史で稼げると考える) *4-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44368970Q9A430C1000000/?n_cid=BMSR3P001_201904301709 (日経新聞 2019年5月1日) 「国民に心から感謝」 天皇陛下の最後のお言葉全文 、退位礼正殿の儀 天皇陛下が退位礼正殿の儀で述べられたお言葉は以下の通り。 今日をもち、天皇としての務めを終えることになりました。ただ今、国民を代表して、安倍内閣総理大臣の述べられた言葉に、深く謝意を表します。即位から30年、これまでの天皇としての務めを、国民への深い信頼と敬愛をもって行い得たことは、幸せなことでした。象徴としての私を受け入れ、支えてくれた国民に、心から感謝します。明日から始まる新しい令和の時代が、平和で実り多くあることを、皇后と共に心から願い、ここに我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります。 *4-2:https://www.nishinippon.co.jp/feature/gougai/article/506992/ (西日本新聞 2019年5月1日) 天皇陛下即位の儀 「憲法にのっとり責務果たす」 天皇陛下は1日、皇后さまと共に皇居・宮殿「松の間」で、国事行為の「即位後朝見(ちょうけん)の儀」に臨み「憲法にのっとり、日本国および日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓う」と、天皇として最初のお言葉を述べられた。即位後朝見の儀には、安倍晋三首相ら三権の長をはじめ都道府県の知事や議長、市町村長の各代表らが参列。皇嗣(こうし)秋篠宮ご夫妻ら女性も含めた成年皇族も同席した。陛下は「自己の研鑽(けんさん)に励むとともに、常に国民を思い、国民に寄り添う」と決意を誓った。朝見の儀に先立ち、陛下は松の間で国事行為の「剣璽(けんじ)等承継の儀」に臨んだ。即位後初めての儀式で、陛下は皇位のしるしとされる「三種の神器」のうち剣と璽(じ)(勾玉(まがたま))を、国の印章の「国璽(こくじ)」と天皇の印の「御璽(ぎょじ)」とともに受け継いだ。皇位継承資格を有する男性皇族のみが参列し、前例に倣って女性皇族は同席しなかった。 *4-3:https://digital.asahi.com/articles/ASM4H42NFM4HUTIL00P.html (朝日新聞 2019年4月18日) 「容認」7割超、女性天皇も女系天皇も 朝日世論調査 新しい天皇陛下には被災地訪問などを期待し、将来の安定した皇位継承のために女性・女系天皇を認めてもよい――平成から令和への代替わりを前に実施した朝日新聞社の全国世論調査では、こんな傾向も浮かび上がった。新天皇に期待する役割を複数回答で選んでもらったところ、「被災地訪問などで国民を励ます」が最も多く66%、「外国訪問や外国要人との面会」が55%、「戦没者への慰霊など平和を願う」が52%――などとなった。被災地訪問や戦没者慰霊は平成の時代に天皇、皇后両陛下が力を入れてきた活動。象徴天皇の活動として、広く浸透したことがうかがえる。一方、安定した皇位継承のために、女性天皇や母方だけに天皇の血をひく女系天皇を認めるのかと尋ねたところ、女性天皇については76%、女系天皇は74%が、それぞれ認めてもよいと回答した。天皇の退位を認める特例法案が国会に提出される直前の2017年3~4月の調査でも、女性天皇は75%、女系天皇は72%が認めてもよいと回答しており、ほぼ同様の結果だった。また、今後の皇室の活動を維持するために、女性皇族が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」の創設については、50%が賛成、37%が反対と答えた。現在の皇室典範では、天皇になれるのは父方に天皇の血をひく「男系」の男性のみ。このため、5月の代替わり後、新天皇となる皇太子さまよりも若い皇位継承者は、5歳違いの秋篠宮さまと今年13歳になる悠仁さまだけになる。今回の天皇退位を実現する特例法ができた際、国会は付帯決議で、安定的な皇位継承を確保するための諸課題などを検討して国会に報告するよう政府に求めた。今回の調査で、安倍内閣を支持すると答えた層の意見をみてみると、女性天皇容認は72%、女系天皇容認は70%で、全体の76%、74%をそれぞれ下回った。逆に「男性に限った方がいい」は25%で、全体の19%を上回った。安倍首相の言葉を「大いに信頼できる」と答えた層でみると、女性・女系を認める意見と男性・男系に限るべきだとする意見が拮抗していた。 新天皇に期待する役割(複数回答) ・被災地訪問などで国民を励ます 66% ・外国訪問や外国要人との面会 55% ・戦没者への慰霊など平和を願う 52% ・宮中祭祀(さいし)など伝統を守る 47% ・国民体育大会など国民的な催し出席 36% ・国会召集など国事行為に専念する 21% *4-4:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019050190135516.html (東京新聞 2019年5月1日) 「常に国民を思い、寄り添う」 天皇陛下即位お言葉 一日に即位した天皇陛下は午前、皇居・宮殿の正殿「松の間」で、皇位継承儀式「剣璽(けんじ)等承継の儀」と、国民の代表と会う「即位後朝見(ちょうけん)の儀」に臨まれた。朝見の儀で陛下は、初のお言葉で「常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国および日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓います」などと述べた。この日午前零時、「平成」から代替わりした「令和」がスタート。陛下は五十九歳で、戦後生まれの初の天皇となった。皇后さまは五十五歳。剣璽等承継の儀と即位後朝見の儀は、憲法に定める天皇の国事行為として行われた。剣璽等承継の儀では、陛下が皇位の証しとされる「三種の神器」のうち、剣と勾玉(まがたま)(璽(じ))、国印の国璽(こくじ)と天皇印の御璽(ぎょじ)を継承した。即位後朝見の儀では陛下のお言葉に続き、安倍晋三首相が国民代表として「天皇陛下を象徴として仰ぎ、平和で希望に満ちあふれ、誇りある日本の輝かしい未来を創り上げていく決意です」などと祝意を述べた。剣璽等承継の儀には、男性の成年皇族である皇嗣(こうし)秋篠宮さまと常陸宮さまのほか、安倍首相、大谷直人最高裁長官、大島理森衆院議長、伊達忠一参院議長の三権の長と閣僚、最高裁判事ら二十六人が参列。皇位継承権のない女性皇族は立ち会わず、片山さつき地方創生担当相が憲政史上初めて女性として参列した。即位後朝見の儀には、剣璽等承継の儀の参列者に加え、皇后さまをはじめ女性の成年皇族、地方自治体の代表ら約三百人が参列した。これに先立ち、陛下は即位後初の国事行為として両儀式を行うとの閣議決定を裁可した。 ◆天皇陛下お言葉全文 日本国憲法および皇室典範特例法の定めるところにより、ここに皇位を継承しました。この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。顧みれば、上皇陛下にはご即位より、三十年以上の長きにわたり、世界の平和と国民の幸せを願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その強い御心をご自身のお姿でお示しになりつつ、一つ一つのお務めに真摯に取り組んでこられました。上皇陛下がお示しになった象徴としてのお姿に心からの敬意と感謝を申し上げます。ここに、皇位を継承するに当たり、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し、また、歴代の天皇のなさりようを心にとどめ、自己の研鑽に励むとともに、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国および日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望いたします。 <天皇陛下> 名前は徳仁(なるひと)。1960年2月23日生まれで、幼少時の称号は浩宮(ひろのみや)。学習院大文学部史学科を卒業後、同大大学院に進学。英オックスフォード大にも留学した。89年1月、昭和天皇の逝去に伴い皇太子となり、93年6月に元外交官の雅子さまと結婚した。学習院女子高等科3年の長女愛子さまと3人家族。ライフワークは水問題に関する考察で、2013年と15年、国連本部で開かれた「水と災害に関する特別会合」で講演した。趣味はビオラ演奏と登山。 <皇后雅子さま> 1963年12月9日、後の外務事務次官小和田恒氏と妻優美子さんの長女として生まれた。85年に米ハーバード大を卒業。学士入学した東京大を中退後、87年4月に外務省に入り、日米の経済外交に携わった。86年10月、東宮御所で開かれたスペインのエレナ王女歓迎会で、天皇陛下と出会い、93年6月に結婚した。2001年12月に長女愛子さまを出産。03年12月から療養生活に入り、宮内庁は04年7月、病名を「適応障害」と公表した。現在も療養が続いている。 PS(2019.5.2追加):雅子妃に対するバッシングは、*5に書かれているとおりで、この内容が当時の週刊誌(私は、そのような週刊誌は買わないので美容院で読んだ)に掲載され、それを人権侵害や侮辱だとすら思わないほど女性蔑視の“空気”が世の中に蔓延していた。私は、世界の中で「適応障害」を起こしたのは、このようなことを言いたてた日本国民の方だと思う。 *5:https://rondan.net/17760 (論壇ネット 2019.3.12) 【雅子さま】別居・離婚・廃太子論……数々の批判を乗り越えて“新”皇后に Contents 1 長期療養中の雅子さま 2 別居 3 離婚 4 小和田家が引き取れ 5 廃太子 6 廃太子した後の皇太子 7 まとめ 1 長期療養中の雅子さま 適応障害になられてから、久しく公務や祭祀を欠席されている雅子さま。元はと言えば「御世継ぎを」のプレッシャーから適応障害になられ、今度はその適応障害を批判されるという負のスパイラルの中にありました。一連の雅子さまバッシングの中核を担った論者としては西尾幹二氏や、橋本明氏、保坂正康氏などが有名です。一方で、雅子さま擁護論を展開した論者としては、竹田恒泰氏や小林よしのり氏が挙げられます。一時はバッシングに次ぐバッシングの嵐だったものの、最近になって落ち着いてきたように思います。これも適応障害など精神疾患に関する国民の理解が進み、小室圭さん問題に端を発する秋篠宮家に注目が集まっていることなどが挙げられるでしょう。またこの5月に控えた御譲位も大きく影響しているように思えます。今回は、そんな雅子さまへのバッシングを振り返ってみたいと思います。特に取り上げるのは、橋本明「「別居」、「離婚」、「廃太子」を国民的議論に」『WiLL』(2009.9号)です。この記事は、「廃太子論」にまで飛び火したことで非常に有名です。またこの記事と関連する書籍や対談も取り上げていきたいと思います。 2 別居 橋下氏の理論は、雅子さまのご病状を回復させることが重要であるとして、①別居、②離婚という二つの方法を挙げ、その二つが適用できずご病状も改善しないのなら③廃太子(秋篠宮殿下を皇太子にして、現・皇太子殿下は親王に格下げ)すべきだという内容です。雅子さまのご病状を心配しているような書きぶりで、実際には東宮家への強い批判が込められた文章です。まず、別居を薦める下り。 [雅子妃がご病気を克服されるということは健康を取り戻すことです。徹底的に治療する環境を作るというのは一つの方策だと思います。つまり、別居して治療に専念するということです。 橋本明「「別居」、「離婚」、「廃太子」を国民的議論に」『WiLL』(2009.9号)] より具体的には次のように。 [この際思い切って雅子妃を皇室から遠ざけ、ストレス因子の存在しない空間に身を移し変えて回復に専念する態勢を創出してはいかがだろうか。そこでは公務や育児の責務を逃れ、治療に専念していただく。公務を抱える殿下、学業がある愛子内親王とは別居となる。女官なども遠ざけ、身の回りの世話は専門の看護師あるいは介護者が当たればよい。橋本明『平成皇室論——次の御代へむけて』朝日新聞出版, 2009.] 具体的な療養として、栃木の御料牧地でのアニマルセラピーが挙げられるなど、おちょくってるのか、大真面目なのか解らない文章が続きます。きっと前者なんでしょうけど。もちろん別居して改善する保証などどこにもないのですから、「別居すればいい」などとは橋本氏の妄想以外の何物でもない選択肢です。 3 離婚 さらに橋本氏の妄想は加速して「離婚」を薦めます。 [もちろん離婚はあり得ますが、離婚は両者の合意に基づくもので一方的には決められません。決められない場合は民間であれば離婚調停を行うわけですが、皇室にはそれを保護する法律の後ろ盾はあるのかということです。いったいどこの裁判所で誰が調停員になるのか。ですから常識的にはないにしても、ご結婚が皇室会議の賛同を得なければ成立しないのと同じように、皇室会議に持ち出せば離婚もあり得ると思います。橋本明「「別居」、「離婚」、「廃太子」を国民的議論に」『WiLL』(2009.9号)] ただし、同氏による書籍では、離婚という選択肢もあるが、現実的には離婚など有り得ないだろうという文脈でこれが語られています。 [雅子妃の静養が長引くにつれ、ご夫妻をめぐる報道に「離婚」という文字が散見されるようになった。雅子妃を皇室という環境から解放して差し上げようといった同情的な論調から、東宮のあり方に疑問を呈するむきまでさまざまだが、皇太子が雅子妃を愛し、守り続ける覚悟に今後も生きるとすれば離婚はもとより問題外となる。仲睦まじいいまのお二人の姿からも、離婚などという事態は想像し難い。橋本明『平成皇室論——次の御代へむけて』朝日新聞出版, 2009.] なお法的に皇族が離婚できるのかどうか議論があるようです。しかしここで重要な点は、橋本氏は、皇太子殿下と雅子さまの「離婚」を現実的な選択肢として語っているのではなく、単に雅子さまが皇室不適格だとなじるために言っているにすぎません。先の「別居」、今回の「離婚」、これに続く「廃皇太子」いずれも実行可能な選択肢として語られているのではなく、極論を持ち出して東宮家(特に雅子さま)を貶めたいだけの言論であるように思えます。 4 小和田家が引き取れ このような橋下氏による雅子さま攻撃の根源的原因は、どうやらその父・小和田恆氏が左派リベラル的活動をしていたことに起因するようです。本筋とは全く関係の無い人格攻撃を持ち出して次のように言っています。 [橋本 常識的に考えて、「私の娘は役に立ちませんから引き取らせて頂きます」と申し出るのが本当の親の役目だと思います。ところが、小和田ご夫妻には、そのような意識はかけらもありませんでした。私は個人攻撃をするつもりはありませんが、国家の問題として言わざるを得ません。ところが、小和田ご夫妻には、そのような意識はかけらもありませんでした。私は個人攻撃をするつもりはありませんが、国家の問題として言わざるを得ません。小和田恆氏は、男女共同参画の産みの親のような方です。小和田氏が国連大使の時代に、国際婦人年があり、その総会で決まったことを日本に持ち帰って法律化しようと、労働省の婦人少年局長と渡り合いました。その時の記録を見ると小和田氏は、日本も男女同格で、女性も権利をもって働く国にならなければ駄目だと明確に言っています。婦人少年局長のほうがまだ尻込みしていて、そこまでまだいきませんと言っているくらいです。そらく今の雅子妃の姿を見ると、小和田氏は「こんな娘で申し訳ない」という気持ちではなく、「こんな娘にしたのは誰彼のせいだ」と思っているでしょう。橋本明×西尾幹二「雅子妃の御病気と小野田王朝」『WiLL』(2009.10号)] 橋下氏の理論からすれば、皇室とは平等や人権とはまったく別個の世界であり、そこに適応できない雅子さまとその両親が悪いということのようです。この様な理論は保守論客の中でまま見られるものです。しかし、これは「開かれた皇室」を目指す現皇室の在り方と相容れていないことを留意すべきです。今上陛下も皇太子殿下も秋篠宮殿下も、結婚に関しては当時としてリベラル的な選択をした恋愛結婚です。また、平等という観念にも皇室は寄り添おうと努力しています。被災者を前にしても昭和天皇は決して膝を折りませんでしたが、今上陛下は膝を折り視線の高さを同じくして声に耳を傾けています。 5 廃太子 このように「別居」して治療してもダメ、「離婚」も有り得ないのであれば、「廃太子」するしかないと言い出します。 [治療をしても雅子妃がよくならない場合について、もう少し考えてみよう。離婚という事態は、お二人のお気持ちの中に一切ないであろう。その場合、仮に皇太子が以下のように考えたとしたらどうだろうか。自分はあくまでも雅子妃と愛子内親王と共に暮らして一家庭という単位で人間として幸福を追求する。ただし、この形態のまま践祚・即位した場合、皇室のあるべき運営に不都合をきたす。よって天皇にはならない──。このように考えた場合は、立太子の儀を経て皇位を継ぎ、次期天皇に即位する既定路線が定まっているこれまでの生き方を否定し、その立場を廃するという道も選択肢のひとつとして考えられる。橋本明『平成皇室論——次の御代へむけて』朝日新聞出版, 2009. ] 過去の歴史で「廃太子」は実際にあったことのようですが、皇太子殿下ご自身が心身健康なのに、廃位を求めるというのは流石に滅茶苦茶でしょう。事実、こっぴどく批判されています。要点は次のように。 [もう一は、廃太子、つまり秋篠宮を皇位継承第一位にするという方策もあります。皇室典範の第三条には、皇太子が心身を病んだりして公務ができない場合、皇位継承順位の変更を皇室会議で認めることが定められているからです。これについても先述の所氏は、「規定の趣旨はあくまで皇太子さま本人に決定的な不都合が生じた場合であって、雅子さまの病気が皇位継承の順番を変える理由になるはずがありません」と言います。さらに、同誌で小田部雄次静岡福祉大教授は、「公務は天皇の単独が基本で、夫婦でやるのは今の両陛下が欧米型を取り入れてから。雅子さまが公務をやらないことを理由に離婚されるとは、おかしな話です。周りが勝手な皇室像を押し付けていると感じます」という。橋本明「「別居」、「離婚」、「廃太子」を国民的議論に」『WiLL』(2009.9号)] つまり、雅子さまのご病状の如何で皇太子殿下が継承権を辞退する必要はないし、雅子さまがご病気で公務や祭祀ができなくても問題ないということです。特に、「両陛下が公務を行なうというのは平成流であって、皇室の伝統ではなかった」ことは、今後の雅子さまのご公務の在り方を考えるうえで重要でしょう。 6 廃太子した後の皇太子 また「廃太子」となった後の皇太子殿下の処遇というのは次のようなもの。 [もし「廃太子」が現実になったと想定しても、徳仁親王の皇族というお立場を定める身位は「親王位」にあり、皇太子を放棄しても基本的身分に変更はない。徳仁親王家が皇族として存在することに何らの変化も生じない。ご家族とて同じである。宮家として公務に専念する立場にも変化はない。皇位継承順位もいままでの一位から三位に下がるだけだ。ただし、その際には新たに立太子礼を他の皇族について挙げ、皇太子として内外に宣明する手続きと宮中行事が必要となる。具体的に言えば、皇次子秋篠宮文仁親王が立太子礼を経て皇太子になるということだ。同時に徳仁親王には新宮家が創設され、宮号が賜れる。皇位継承順位は秋篠宮、悠仁親王、そして徳仁親王となる。東宮家のご身位は、いまの秋篠宮家と同格になる。橋本明『平成皇室論——次の御代へむけて』朝日新聞出版, 2009. ] 具体的なのは結構ですが、秋篠宮殿下が“皇太子”になったら継承順位は二位じゃないの? こういう基本的なところでオカシナところが目につきます。単に東宮家バッシングしたいだけなんでしょうね、きっと。 7 まとめ 以上、雅子さまバッシングの極まり「別居」「離婚」「廃皇太子論」を見てきました。東宮家叩きが収まり、秋篠宮家批判が強まりつつある今となっては、時代遅れの議論である感が否めません。当時、雅子さまや東宮家を叩きに叩いていた評論家たちが、今になって皆黙っているのは奇妙な現象であると言わざるを得ません。手のひらを返して「秋篠宮家廃嫡」すら主張できないほどの惨状です。所詮その程度の信念だったということでしょうか?雅子さまは、 様々なバッシングを浴び抜いて、とうとうこの五月に“新”皇后になられます。果たしてどの様な“象徴”となられるのか、もうすぐ明らかになります。
| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 01:15 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,03,19, Tuesday
     梅の花 桃の花 瀬戸内の桜 アーモンドの花 レモンの花と蜂蜜 (図の説明:春は梅の花に始まり、桃・アーモンド・桜・レモンと続き、花があるからには蜂蜜がとれて実がなる。掲載の写真は、どれも日本国内で、日本産のレモンは美味しい) (1) 日本の食料政策について 1)食料自給率が低い理由は? 我が国の食料自給率は、*1-1-1のように、38%と先進国の中でも最低である上、耕地面積はこの10年で4%減り、農業現場は高齢化が進んで労力不足が深刻となり、生産基盤の弱体化がさらに進みかねないが、そうなった理由は、戦後の農業政策に失敗が多すぎたからだと言わざるを得ない。 失敗の原因は、主に「①主食とされる米麦の価格や供給を政府が管理する制度(食管法)が、太平洋戦争中の食料不足だった1942年に制定され、それが1995年に『主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)』が施行されるまで続いたこと」「②1970年代になると米が余って備蓄米が年間生産相当量まで達したため、政府主導で減反政策を推進して耕作放棄地を増やしたこと」である。これは、時代が変わっても既得権を離さず管理を続けたがる役所の性格によるものだが、政府が管理しすぎると、よい意味での市場原理が働かず産業に競争力がつかないため、成長が遅れる。これは、昔の社会主義・共産主義経済の行き詰まりと同じ現象だ。 また、「③2004年に『主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法を大幅に改正)』を施行して誰でも自由に米を販売・流通させることが出来るようにした」「④輸入も一定額支払えば自由に行うことができるようにした(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6 参照)」などの改正もあったが、これらは1970~1980年代にはやっておかなければならなかった改革で、時代に合わせて変化しなかった結果、農業は所得が低いため次世代が参入しにくく、衰退が続く産業になった。そのほか、「⑤農業は製造業と比較して、大切にされなかった」という経緯もある。 2)貿易自由化は正しい意思決定だった? そのため、TPP11やEUとのEPAの中で日本の農業は生き残れるのか心配だが、世界の人口は確実に増えており、中長期的には食料が逼迫するので、農業はじめ食品産業に追い風が吹くのは間違いない。その時、IT・データ・自動車を食べることはできないため、国民の食料確保(食料自給率)は、まじめに考えておかなければならない重要な課題である。 なお、まじめに取り組んでいる地域JAも多いが、これまでの経緯から、*1-2-1・*1-2-2のように、米の補助金政治・補助金行政に頼りがちな地域も多い。こうなると、*1-2-4のように、国産米が高値となり、安価な米を求める消費者は豪州産米を使わざるを得ない変なことになる。 このような政府の政策に翻弄されない農業を行うには、生産性を向上させ、*1-1-2のように付加価値を上げ、補助金に頼らない農業を作るのが正攻法で、そうなると財政の無駄遣いもなくなる。 3)農家所得を高める方法について 農家所得は、「ア.農業収入 – イ.農業経費[i)機械の減価償却費 ii)エネルギー代金 iii)資材購入費 iv)労務費 v)販促費等)] + ウ.補助金」であるため、農家所得を増やすには、アの農業収入を増やし、イの農業経費を減らして、ウの農業補助金もできれば増やしてもらう方法しかない。 そして、アの農業収入を増やす方法は、付加価値の高いものを多く作ることしかないため、①栽培面積を増やす ②他では作れないものを作る ③品種改良する ④自然エネルギーを使った自家発電電力や副産物を販売する 等々の方法がある。 イのうち、機械の減価償却費を減らす方法は、「(生産国にかかわらず)安い機械を選択する」「農業生産法人や集落営農等の集団で機械を購入して、一人あたりの負担を軽くする」などが考えられるが、日本では製造業のために農業が犠牲にされ続けた。また、エネルギーは、「自然エネルギーを使って自家発電する」「動力は電力にして自家発電で賄う」「エネルギー会社に交渉する」等が考えられる。 さらに、資材購入費は、独占や寡占になると価格をつり上げられるので、JAだけでなく、その他の資材販売会社とも価格を比較し、安くて品質のよいものを選択できるようにすればよい(既にそうなっている)。また、労務費は、今回JAがセッティングした外国人労働者を繁忙期だけ雇えるシステムや農福連携、繁忙期のアルバイト雇用など、栽培面積の増加に労務費が比例しない人の使い方もある。販促費は、これまでは農協による国内販売が殆どだったが、他産業のように商社等を使って輸出する方法もある。 ウの農業補助金を増やしてもらう方法は最も安易だが、国が農業に口や手を出しすぎると統制経済となり、よい意味での市場原理が働かなくなるため、日本の農産物の競争力を弱める。 なお、農水省は、*1-1-3のように、中長期的な農政の方向性を示す食料・農業・農村基本計画の見直しについて、秋から有識者らで構成する審議会での議論を始め、生産現場の声をより反映させようと農業者から意見聴取するそうだが、物は消費者がいて初めて売れ、消費者によって磨かれるため、政府が生産者の意見だけを重視しているのは間違いだ。 もちろん、何も聞かずに「えいやっ」と政策にするよりは農業経営の現状・課題に関して農家や食品事業者の声を聴いた方がよいが、全方位の要望を聞いた上で客観的な市場調査による裏付けをしていなければ、いくら丁寧な言葉で議論しても的外れの政策ができる可能性が高い。 (2)中山間地政策について     (図の説明:中山間地の定義は不明だが、中山間地に合わないのは穀物の大規模生産だけで、高度・気温・傾斜・草地を利用するなどの工夫によって、他ではできない生産方法があるだろう) 農水省は、*1-2-3のように、農地保全協定を集落等で作成すれば①外部からの人材確保 ②住み続けられる地域づくりに向けた生活環境の充実 ③農作業の効率を高めるためのスマート農業推進 に、2019年度の中山間地域等直接支払制度で加算措置を設けるそうだ。もちろん、中山間地の農業も継続が望まれ、そのためには①②③が必要だが、次第に自立して欲しい。 なお、*1-3-1の鶏卵・養鶏は、中山間地でもでき、物価の優等生で輸出競争力もあるのに生産調整を優先するのでは、米と同じ過ちを繰り返す。さらに、*1-3-2の牛乳・乳製品も、日欧経済連携協定(EPA)で輸出関税が即時撤廃されたのに、牛乳や卵の使用割合が合わせて50%以下の加工食品しか輸出可能にならないというのは、かなり情けない。 (3)スマート農業      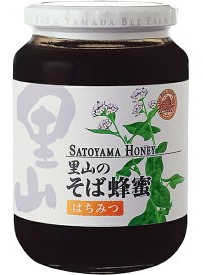 ジャガイモの花 大豆の花 カボチャの花 ナスの花 蕎麦の花と蜂蜜 (図の説明:大豆はマメ科なので、スイートピーのような花が咲いて実がなり、青いうちにとった実が枝豆だ。カボチャやナスの花も意外と美しい。広い畑にジャガイモや蕎麦の花が咲くのは壮観で、蕎麦の花の蜂蜜もある。写真はもちろん日本国内だ)  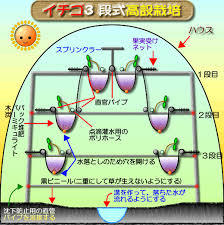 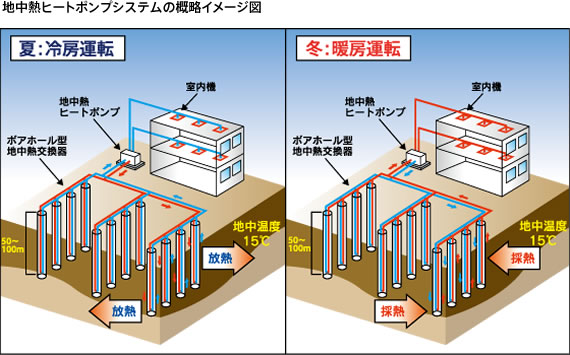  スイカの花 イチゴの温室栽培 ヒートポンプの仕組み 地熱発電所 (図の説明:左はスイカの花で、やはり美しい。また、左から2番目の図のようなハウスでのイチゴ栽培もあり、施設園芸で加温するにも右から2番目の図のようなヒートポンプは有用だ。そして、右図のように、中山間地には地熱発電が可能な地域も多い) 1)CO₂の利用 *2-1のように、地球温暖化に伴う気候変動が起こり、農業は世界の温室効果ガスの1割以上を占めるため、環境保全型農業実践の時だそうだ。そのような中、農研機構は大気中のCO₂濃度が高い中で水稲を栽培することで収量が16%増えたという研究結果を発表し、農家が環境に配慮した農業(減農薬・減化学肥料栽培と堆肥の使用)を行うことで温室効果ガスが削減でき、昆虫や魚類などの生物多様性の保全に繋がるそうだ。 2)ICT・IoTの利用 なお、*2-2のように、総務省がICT・IoTを活用した農業の省力化を、2030~40年頃までに実現を目指すとしたのは、5年後ではなく10~20年後としたところが日本独特の遅さで、これでは使い物にならないのである。 3)衛星の利用 北海道は、*2-3のように、「北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会」を組織し、農業分野ではトラクターの自動走行や農作物の生育、品質把握などで衛星データの利用が進みつつあることを踏まえて、道内に多い大規模経営に役立つ方法を検討するそうだ。 しかし、GPSを使って自動走行する田植え機やトラクター、人工衛星が撮影した農地の画像を使って作物の生育や品質を把握するリモートセンシング技術などは、北海道だけでなく大規模栽培する米・畑・牧草での利用が期待され、現代的でスマートである。 4)品種改良とライセンス(許諾使用料)収入      リンゴの花と蜂蜜 みかんの花と蜂蜜 オリーブの花 (図の説明:リンゴの花は美しく、蜂蜜もとれる。みかんはレモンと同じ柑橘類なので、レモンと似た花が咲いて蜂蜜がとれる。それぞれの蜂蜜は、ほのかにその果物の香りがして美味しい。近年は、日本でもオリーブを作り始めており、写真はすべて日本国内だ) *2-4のように、長野県はイタリアの生産者協同組合2組織と長野県育成のりんご「シナノゴールド」について新たなライセンス契約を結び、既に栽培されている北半球のEU加盟国に加えて、両組合を通じ主に南半球の5カ国での栽培を許諾することで海外での生産・販売を拡大し、通年販売も可能になるそうだ。こうするとライセンス使用料収入が入る上、「yello」の商標と「日本の長野県」が有名になる。 なお、日本のミカンも美味しいのだが、これまで輸出や外国での栽培実績が低いため、あの形のミカンが、すっぱいものも含めてすべて「マンダリン」と呼ばれてユーラシア大陸で流通しているのに驚いたことがある。そのため、ミカンやレモンの産地も、長野県を参考にすべきだ。 そのような中、*2-6のように、佐賀県が開発した新品種のイチゴ苗が県農業試験研究センター元職員によって無断で県内の農家に譲渡されていたそうだが、これは開発にかかったコストを認識しておらず、コストを回収しようという意思もないことを意味している。また、「いちごさん」という名前もブランド確立に資するとは思えず、長野県のように、日本だけでなく世界市場を視野に入れた名称にした方がよいと思う。その点、ユーラシア大陸の国々は、いつも大陸全体を視野に取引を行っている点でスケールが大きいと感じる。 5)ゲノム編集による品種改良 厚生労働省と環境省各審議会の調査会と検討会は、*2-5のように、①動物や植物に新しい特性を持たせるため他の生物の遺伝子を導入するのは、既存の遺伝子組換技術と同じ扱いで安全性審査などの規制対象 ②もともとある特性を消し去るため遺伝子の一部を削るのは、自然界でも起こり得る変化の範囲内として規制の対象外 としたそうだ。 本当は、他の生物の遺伝子を導入するものでも、殺虫効果を持たせてヒトに無害であることが証明できていないものはNOで、無害であることが証明済ならOKなのである。そして、もともとある遺伝子の一部を削るだけでも、それまで発現していなかった毒性を発現し始める生物もいないとはいえず、いずれも安全性が証明されていればOK、証明されていなければ不明も含んでNOというのが正しい。しかし、検証もせずに安全だと言われても障害が出るまではわからないため、いずれも消費者が選択できるよう遺伝子組替表示は明確に行うべきだ。 ・・参考資料・・ <日本の食料政策> *1-1-1:https://www.agrinews.co.jp/p44742.html (日本農業新聞 2018年7月30日) JA食料安保提案 連携広げて国民理解を JAグループは、食料安全保障の確立に向けた基本政策や自らの行動計画の検討を始めた。食料自給率が低迷し、生産基盤の弱体化がさらに進みかねない中、政策への反映や行動の具体化には国民理解が欠かせない。検討段階から消費者や他の団体などと幅広く連携し、国民的な議論を巻き起こしたい。食料安全保障は大きな岐路に立っている。食料自給率は38%と低迷を続け、耕地面積は444万ヘクタールと、ここ10年で4%減った。食料の潜在生産能力を示す「食料自給力指標」も2015年、16年と大きく下がった。農業現場では高齢化が進み、労力不足が深刻だ。一方、米国を除く環太平洋連携協定(TPP11)や欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)の発効が迫る。国際化が進む中、世界の食料需給は、人口増や異常気象の多発などで中長期的に逼迫(ひっぱく)する可能性は高い。食の未来に不安を感じる国民は多い。14年の内閣府世論調査によると、将来の食料供給に「不安がある」としたのは回答者の83%に上った。理由は「農地減少や高齢化で、国内の食料供給能力が低下する恐れがある」(82%)、「異常気象や温暖化の進行で国内外で不作の可能性がある」(62%)などが挙がった。今、行動を起こさなければ将来の食料の安定確保は危うい――。そんな危機感を持って食料安全保障の大切さを共有し、行動を自ら打ち出し、国の政策に反映させようというのがJAグループの取り組みの狙いだ。食料自給率低迷と自給力の低下について、JA全中は国内生産の減少が大きな要因とみる。生産減をもたらしているのは、農業の担い手・労働力不足と分析する。政策提案では品目別の農地面積や農業者数で、政府が数値目標を立てることを提起。「農」だけでなく「食」「地域」「世論形成」の観点から具体的な施策を検討し、19年にも審議が始まる政府の次期食料・農業・農村基本計画への反映を目指す。JAグループも自己改革を実践しながら、食料自給率・自給力向上につながる取り組みを実践する行動計画をつくる。全中は9月に基本的考え方、来年1月にも素案をまとめる。検討過程を含めて地方自治体や他の協同組合、経済団体との意見交換や共同提案も模索する考えで、より開かれた形で議論することが欠かせない。政策提案、行動計画というと堅いイメージになりがちだが、鍵はいかに多くの人の共感を得られるかだ。幅広い連携を生かし、分かりやすい数値目標やキャッチフレーズを打ち出すことが重要となる。さらに目標達成に向けて、国民一人一人がどんな行動をすればいいか、分かりやすく訴求する必要がある。JAグループが中心となって、さまざまな知恵を集めて議論を盛り上げたい。 *1-1-2:https://www.agrinews.co.jp/p47022.html (日本農業新聞論説 2019年3月13日) 食の簡便化 産地発の6次化商品を 日本人の食生活は、平成の30年間で大きく変わった。家庭の食卓は洋風化とともに、準備にかける時間を短縮する「簡便志向」が顕著だ。高齢化が進み、単身世帯や共働き世帯も増加する中、今後も簡便化の流れは加速するだろう。食の動向を把握し、産地ならではの商品を提案していくべきだ。食の簡便化は、総務省発表の家計調査から読み取れる。2018年と1989(平成元)年の1世帯(2人以上)当たりの食品年間支出額を比べると、生鮮品から調理済み食品へのシフトは鮮明だ。特に生鮮品の中で魚介と果実の支出減が著しい。一方で乳製品は倍増し、調理食品は7割増となった。品目別に見ると、支出額の増加率トップとなったのはサラダの3・3倍で、生鮮野菜の2%減と対照的だ。次いで洋食になじみやすいヨーグルトやチーズ、ワインが続いた。逆に減少率でトップとなったのは米の6割減。主食で競合するパンは2割増え、18年の支出金額は3万円超と米を3割近く上回った。米の需要は冷凍チャーハンなど加工米飯に移ってきたとはいえ、主食の座をパンに奪われた格好だ。ご飯を主食とした和食が減り、パンに乳製品、サラダなど洋食の場面が増えた食卓の姿がうかがえる。和食でも米はパック米飯や冷凍米飯で、総菜はコンビニなどの中食を購入するケースが増えている。日本政策金融公庫の調べでは、4割の人が週2日以上は市販の弁当や中食を購入しており、需要はさらに増えると予測する。少子高齢化に伴って高齢者の割合は今後さらに高まり、家計を支えるために夫婦共働きの家庭は増えることが予想される。これは、食材を買って調理し、食事を作る時間的な余裕がさらになくなることを意味する。調理も、生協の宅配で伸びている下ごしらえ済みの「ミールキット食材」の需要が増えそうだ。食品メーカーは、モヤシなどの野菜の上にかけて電子レンジで温めるだけで一品料理ができる時短調味料を相次いで発売している。産地は、こうした動向を捉えて商品を提案する必要がある。需要が伸びている業務用米もその一つだ。家庭用と比べて単価は安いが、多収で一定の収入を見込める。生鮮果実の消費は減っているが、皮ごと食べられるブドウ「シャインマスカット」のように比較的高値でも消費を伸ばしている品目もある。缶詰や乾燥品などの果実加工品は5割増の伸びで、ケーキなどに使われる果実も増えている。産地が6次化商品を開発して売り込むことができれば、高い付加価値が見込め、収入増につながる。加工品のブランド化は生鮮品の知名度アップと販促につながる。手軽さ、健康、安全・安心、国産原料への信頼などのキーワードを手掛かりに、6次化を視野に入れて簡便化の時代を乗り切ろう。 *1-1-3:https://www.agrinews.co.jp/p46474.html (日本農業新聞 2019年1月19日) 基本計画 審議会 秋から議論 現場の声反映へ聴取 農水省 農水省は18日、中長期的な農政の方向性を示す食料・農業・農村基本計画の見直しについて、有識者らで構成する審議会での議論を秋から始めることを明らかにした。生産現場の声をより反映させようと、農業者らの意見聴取をした上で、議論を本格化させることが必要と判断した。1月末に諮問し、1年程度の期間をかけて議論するのが通例だっただけに、安倍政権の農政改革に対する十分な検証が担保できるかが課題となる。同日の食料・農業・農村政策審議会企画部会で同省が説明した。基本計画は食料・農業・農村基本法で「おおむね5年ごと」に見直すと定める。現在の基本計画は同省が2014年1月に同審議会に見直しを諮問後、企画部会で議論し、15年3月末に決定した。同省は、施策の効果や次期基本計画に盛り込む施策などを審議会に説明し、議論を開始するという従来の進め方では、前もって生産現場の意見を聞く機会が乏しいと判断。今回は農業経営の現状や課題について、農家や食品事業者らの声を聴取した上で、審議会には見直し議論を「秋ごろをめどに諮問」すると提案した。意見聴取は、年度内にも始まる見込みだ。諮問後の同部会での議論の期間は半年間程度になる見込みだ。審議会への諮問時期の先送りについて、政府内には、首相官邸主導の農政運営や参院選などの政治日程が影響したとの見方もある。基本計画の見直しの焦点の一つが、食料自給率の目標設定だ。現行はカロリーベースで45%だが、17年度の実績は38%と低迷。農家の減少など生産基盤の弱体化が懸念され、相次ぐ大型の経済連携協定の発効も抱える。食料安全保障確立へ重要局面での基本計画の見直しとなるだけに、農政改革の検証や今後の施策について、丁寧な議論ができるかが問われる。 *1-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41679330T20C19A2EA1000/ (日経新聞 2019/2/24) 備蓄米、高値で買い入れ 政府、TPP11理由に上限拡大 主食のコメを政府が高値で買い入れ、備蓄に回している。需給を引き締めたいJAグループの要望に応え、今年買い入れ上限を拡大。11カ国による環太平洋経済連携協定(TPP11)への対策で国産米を市場から吸い上げる。安いコメがほしい食品業界は反発。4年連続の米価上昇でコメ離れが進むなか、小売店も「店頭価格がさらに上がりかねない」と懸念する。農林水産省は2019年から備蓄米の買い入れ上限を前年より5%多い年間20万9140トンとした。TPP11では日本がオーストラリア産米の輸入枠を設定。豪州産米が増える分、国産米を政府が買えば需給が締まり、民間取引を高値で維持できるとの算段だ。4年連続の米価上昇を映し、代表銘柄の新潟産一般コシヒカリ(魚沼産など除く)の全国平均の店頭価格は上昇前の14年産より2割以上高い水準が続く。19年秋にとれる新米を対象に、農水省はこれまでに2回の買い入れ入札を実施。買い入れ額は1俵(60キロ)1万3800円前後と前年より6%高かった。安い価格帯のコメを作る生産者には卸などに売るのと同水準。「こんなに高くなるとは想定外」(大手コメ卸)と驚きが広がった。現時点での落札量は9万7千トン。上限までの残り約11万トンが今後の焦点となる。高値買い取りの背景には全国農業協同組合中央会(JA全中)の要望がある。農業改革で地方農協への指導権限がなくなり19年秋に一般社団法人になるJA全中にとって、米価上昇は各産地に示せる「存在意義」。「着実に全量を買い入れる」(JA全中幹部)よう政府に申し入れていた。備蓄米は「平成のコメ騒動」と呼ばれた1993年の大凶作がきっかけ。作況指数(100で平年並み)は74まで落ち、民間取引で米価は急騰した。政府は米国、豪州、タイ、中国から計259万トンを緊急輸入した。現在の年間消費の4割近い量だ。95年に始まった食糧法で「コメが不足する事態に備えて」備蓄米を制度化し、約100万トンを常備している。ただ目的とは別に、米価対策の思惑で備蓄を増やすよう政府に圧力がかかる。農水省は各地の農協に政府にコメを売るようビラで呼びかけている。中食・外食業者は「減反が終わったのに国産米を使わせない政策だ」と反発する。安価な銘柄が備蓄に回れば、さらにコメを仕入れづらくなる。 *1-2-2:https://www.agrinews.co.jp/p46925.html (日本農業新聞 2019年3月3日) 備蓄米 主食用より高収入 生産2割増2400トンへ 多収性品種で奨励 宮城・JA栗っこ 宮城県のJA栗っこは今年、政府備蓄米の生産量を前年比2割増の2400トンに拡大する。多収性品種の栽培で10アール当たりの収入は主食用米を上回るとの試算を示し、作付けを促す。JAは、米1俵(60キロ)当たりの価格から、10アール当たりの収入に着目した米作りを農家に推奨。業務用向けの多収性品種の契約栽培も同4割増の1000ヘクタールに拡大する。JAの試算によると、10アール当たり収量が630キロ程度の多収性品種で備蓄米に取り組んだ場合、同13万円程度の収入が見込める。JA管内の栗原市の平均収量は同526キロ。主食用の「ひとめぼれ」を作付けした場合は同11万円程度の収入となり、備蓄米の方が上回る。備蓄米の入札はJA全農みやぎに委託。2400トンは同県への「優先枠」の5分の1に当たる。生産量が2400トンを超えても応じられるよう、調整している。JAの前年の備蓄米生産量は1980トン。栗原市では、2019年産米の生産の目安が前年比554トン(1・2%)減ったため、JAは非主食用米への転換で生産調整を進める。輸出用米や飼料用米についても、水田活用の交付金や産地交付金などで10アール当たりでは主食用米と遜色のない収入が見込めると試算し、集落座談会などを通じて農家に周知する。「各県の生産の目安や備蓄米の落札状況を見ると、19年産米の需給は緩和しかねない」と、JAの大内一也専務は備蓄米などによる生産調整の必要性を強調する。「どれを作るのが得か、1反(10アール)当たりでよく考えてほしい。飯米以外は主食用米を作らない米農家がいても不思議ではない」と、経営面でも非主食用米のメリットは大きいとする。10アール当たりの収入を重視する方針から、JAは業務用向けの多収性品種「萌えみのり」の作付けも増やす。米卸との契約栽培で、平均収量は10アール当たり630キロ程度。管内の水稲作付面積は約9000ヘクタールだが、多収穫米生産部会を中心として、18年産の作付面積は約700ヘクタール、19年産では1000ヘクタールを目指す。同品種としては全国一だという。10アール当たり収入は13万円程度が見込め、主食用「ひとめぼれ」を上回る。栗原市若柳新田地区の農家80戸でつくり、米や大豆を約80ヘクタールで栽培する営農組合「新ファーム田(でん)」は今年、備蓄米を6・5ヘクタール、業務用の「萌えみのり」を14ヘクタール作付けする。組合長の小野寺克己さん(58)は「JAの試算を見て、しっかり収入が確保できると判断した」と話す。 *1-2-3:https://www.agrinews.co.jp/p46910.html (日本農業新聞 2019年3月2日) 19年度中山間直払い 「モデル」加算措置 人材確保住環境向上 次期対策につなぐ 農水省は、2019年度の中山間地域等直接支払制度で、モデル地区を対象にした新たな加算措置を設ける。外部からの人材確保と、住み続けられる地域づくりに向けた生活環境の充実、農作業の効率を高めるためのスマート農業推進の3項目で、加算単価を設定。営農、生活両面の条件を向上させ、地域の活性化につなげる。20年度から始まる同制度の第5期対策に反映させたい考えだ。同制度を受けるには、農地保全といった協定を集落などで作成することが必要となる。同省によると協定を作っている組織数は、17年度時点で2万5868。14年度には2万8078にまで増えたが、第4期対策に入った15年度に2万5635と9%減って以来、微増にとどまる。同省は、協定の廃止、縮小を避け、農地の保全活動を続けていくには、新たな人材の確保や住民の定着、作業の効率化が必要と判断。第5期対策を見据え、19年度は試行的にモデル地区向けの加算措置を設けた。三つの新たな加算措置のうち、「人材活用体制整備型」は、地域おこし協力隊や都市部の若者など新たな人材を確保した場合、200万円を上限に、協定面積に基づき10アール当たり3000円交付する。従来も、活動の中心となる人材確保に対する支援はあった。今回は中心メンバーに限らず、営農や草刈りの手伝い、事務作業など幅広い関わり方を想定し、人材不足を補ってもらう。「集落機能強化型」では、営農以外に高齢者の見守りや買い物支援など、住民の生活を支える活動を後押し。新たに来た人材や住民にとって、より暮らしやすい環境を整え、協定への参加にもつなげる。地域運営組織との連携なども想定。200万円を上限に、同3000円を交付する。「スマート農業推進型」は草刈りロボットやドローン(小型無人飛行機)などの導入を支援。小規模な農地が多く、大型機械を使った省力化が難しい中山間地の地形条件に配慮し、先端技術を生かして作業効率を高め、営農を続けやすくする。400万円を上限に、同6000円を交付する。対象地区には、定期的に活動状況を同省に報告することを求める。18年度中に都道府県からモデル地区の推薦を受け、予算成立を受けて正式決定する。同省は「モデル地区での実践例を分析し、改善点を明らかにした上で第5期対策につなげたい」(地域振興課)と展望する。 *1-2-4:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39913990R10C19A1EA5000/?n_cid=SPTMG002 (日経新聞 2019/1/11) 豪州産米、国産米高値で人気 TPP11も追い風 外食やスーパーなど流通小売りでオーストラリア産のコメの利用が広がっている。国産米の取引価格が4年連続で上がっているためだ。一部の小売店では2~5割安い輸入米が目立っている。豪州産は11カ国による環太平洋経済連携協定(TPP11)で輸入枠ができた。人件費上昇に悩む飲食業を中心にコスト低減策の一環として調達拡大をめざす動きも出てきた。「つゆとの相性も良いので使い始めた」。ロイヤルホールディングス傘下で天丼チェーン「てんや」を展開するテンコーポレーション(東京・台東)は、1年前から店によって豪州産米を5割混ぜて提供している。豪州産米はコシヒカリに似た短粒種が主力。アジアで主流の長粒種と異なり、ご飯としてそのまま食べるのにも適している。豪州産は明治時代に日本人が種を持ち込み、稲作を始めたのがきっかけ。現在はサンライス社(ニューサウスウェールズ州)がコメ輸出を一手に担い、日本の精米技術も採り入れている。日本は1993年のウルグアイ・ラウンド貿易交渉を受け、年間77万トン(うち主食用は約10万トン)のコメ輸入枠を設けた。コメ貿易の規制緩和を当初拒否したことで懲罰的に課されたものだ。ただ低価格な輸入米は次第に定着。国産米が高値になると割安な輸入米が増えるのが一般的になった。国産米が豊作で安かった2014年度は豪州産の輸入量は少なかったが、18年度までに国産米の取引価格は4割上昇。輸入量は55倍の3万トン超に増えた。主食用輸入米でのシェアは1割から3割へ上がり米国産に次ぐ2位となった。実施中の18年度入札でも3割を維持している。ユーザー側はコストに敏感だ。社員食堂を含め約1900店を展開する西洋フード・コンパスグループ(東京・中央)は18年から一部で豪州産米を使い始めた。定食店を営む大戸屋ホールディングスも昨秋、国産米の高騰でご飯大盛りの量を減らす一方、健康志向に応えた「五穀ご飯」に豪州産米も使いコストを抑えた。「小諸そば」の三ッ和(東京・中央)もどんぶりなどで使っている。住友商事は「うららか」という豪州産米を輸入し、18年は西友にも並んだ。都内の業務用スーパーでは豪州産米「オーパス」が5キロ1350円と、青森産「まっしぐら」より20%安い。18年末に発効したTPP11で、日本は豪州産米に特化した輸入枠(最終的に年8400トン)を設けた。この結果、主食用のコメ(各国産の総量)は1割多く輸入できるようになる。増える輸入米対策として、農林水産省は国産米の備蓄を増やす。全国農業協同組合中央会(JA全中)の要望に応え、国内各地からの政府買い入れを今までより5%多い年間約21万トンにする。国産米の需給が締まり、価格の維持につながるという目算だ。ただ「値ごろな国産米が足りないのに、さらに市場から奪うのはコメを使うなということか」(中食企業)と批判的な声も多い。国産米が高値のままなら、外食や流通小売業の目は輸入米に向く。TPP交渉から離脱した米国も日本市場開拓をもくろむ。米国はTPPで7万トンの日本向けコメ輸出枠を得るはずだった。現在は日米の新貿易交渉でコメの輸出増を狙う。18年夏にはUSAライス連合会(バージニア州)のサラ・モラン副会長が来日し、中食・外食企業の責任者にコメ需要を聞いて回っている。日本の食を巡る攻防が激しくなる。 *1-3-1:https://www.agrinews.co.jp/p46535.html?page=1 (日本農業新聞 2019年1月25日) 鶏卵 生産調整を優先 経営安定対策事業 財源枯渇 回避へ 日本養鶏協会が、今年度の財源が枯渇する恐れのあった鶏卵農家向けの国の経営安定対策事業について、対応策を決めたことが24日、分かった。需給調整を進めて低迷する鶏卵価格の回復を優先させるなど、限られた財源を適正に振り分けることで枯渇を回避する。価格下落の補填(ほてん)は1月分に限り引き下げるが、「実質は通常(下落幅の9割)の大半に相当する水準を確保できる」と見通す。同対策事業は鶏卵価格や生産者の経営安定が目的。鶏卵価格が基準価格を下回ったとき差額の9割を補填する価格補填事業と、成鶏の更新で長期の空舎期間を設けた生産者に奨励金を交付する生産調整事業の二段構え。財源は生産者の負担金と国の助成金(2018年度予算は約49億円)で、同協会が事業主体となる。今年度は価格低迷が続き、補填などの判断に使う標準取引価格は、今年の初取引に1キロ96円の異例の安値を付けた。24日現在は133円と持ち直したが、補填基準価格(185円)や生産調整事業発動の基準価格(163円)を下回る。今年度は補填事業が4~8月に、生産調整事業は4月下旬~6月下旬に発動した。このまま相場低迷が続き、手を打たなければ、「事業の財源が枯渇する」との懸念が生産現場に広がっていた。協会は16日の緊急理事会で対応策を決定。対応策では、従来通り生産調整事業を発動し、需給改善により価格回復を優先させる。その場合、10万羽以上の大規模生産者は価格補填事業の対象から外れる仕組みになっている。補填事業は相場動向を見通しながら2、3月分の必要最大額を試算した上で確保した。残りの財源を1月分に充てる。ただ、生産調整に伴って大量の成鶏処理が発生し、作業が追い付かなくなる課題が残る。24日に農水省や日本成鶏処理流通協議会との3者会合を開き、協力して対応することを確認した。 *1-3-2:https://www.agrinews.co.jp/p46982.html (日本農業新聞 2019年3月9日) 牛乳・乳製品 EU輸出26日解禁 吉川貴盛農相は8日の閣議後会見で、欧州連合(EU)向けの牛乳、乳製品の輸出が26日から解禁されると発表した。EUの輸入承認リスト(第三国リスト)に掲載された。ただ、実際に輸出するにはEUが認める基準の施設や農場で生産する必要がある。一部の加工食品については、同日から輸出できる。 2月に発効した日欧経済連携協定(EPA)では、食肉や乳製品などの輸出関税が即時撤廃されたが、主要品目で実際に輸出しているのは牛肉だけ。輸出拡大には品目ごとの解禁の動向が焦点になっている。EUは施設の衛生管理や温度管理、アニマルウェルフェア(快適性に配慮した家畜の飼養管理)への対応など、より高い基準を求めている。日本政府はEU当局と協議し、施設の認定や農場の登録に必要な条件を盛り込んだ「対EU日本産畜産物輸出取扱要綱(仮称)」を決める。事業者は要綱に沿って施設や農場を管理し、認定取得を目指す。牛肉が輸出解禁された際は、第三国リストの掲載から施設認定や輸出開始まで1年以上かかった。牛乳や卵の使用割合が合わせて50%以下の加工食品は、解禁と同時に輸出が可能になる。鶏卵、卵製品は既に第三国リストに掲載された。 <スマート農業> *2-1:https://www.agrinews.co.jp/p45474.html (日本農業新聞 2018年10月14日) 気候変動と農業 環境保全しリスク減を 地球は一体、どうなってしまうのだろう。巨大台風や豪雨など甚大な 災害が世界で相次いで起きている。地球温暖化に伴う気候変動とどう向き合うかが問われている。世界の温室効果ガスの1割以上は農業が占める。環境保全型農業の実践の時だ。温暖化が止まらない。今夏、日本を襲った40度超えの酷暑をはじめ世界で気温が上がり続けている。8日まで韓国で開かれていた国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、早ければ2030年にも気温が1・5度上昇するとの特別報告書をまとめた。20年からの温暖化防止の国際ルールを定めた「パリ協定」では今世紀末までに気温を2度未満、できれば1・5度に抑えるとの目標を掲げる。だが、その達成は、もはや危ういことを今回の報告書は示した。同協定の詳細は、ポーランドで12月に開く国連気候変動枠組条約締約国会議(COP24)で決めるが、その前に各国に対策の一層の加速を促した格好だ。1・5度上昇で地球はどうなるのか。報告書によると、100年までに海水面は26~77センチ上昇し、昆虫の6%、植物の8%、脊椎動物の4%で生息域が半減。海洋生態系に重要な役目を果たすサンゴの生息域は70~90%減る。これが2度になると深刻度は増す。水面はさらに10センチ上昇。昆虫の18%、植物の16%、脊椎動物の8%で生息域は半減。サンゴの生息域は99%以上消失。熱波や極度の干ばつ、洪水のリスクも一段と高まる。農業への影響はどうか。100年には米やトウモロコシなど主要穀物の収量が20~40%減少。米に含まれるタンパク質やミネラル、鉄分などの栄養素も減り、アジアを中心に約6億人に影響が及ぶという。一方、対策を取ることで農業生産を高めることもできる。農研機構は大気中の二酸化炭素(CO2)濃度が高い中で、水稲のもみ数を育種で増やすことで、収量が16%増えたという研究結果を発表した。農家は何をすべきか。鍵となるのは環境に配慮した農業だ。農水省によると減農薬・減化学肥料栽培や堆肥の施用などで15万トンの温室効果ガス削減が見込め、昆虫や魚類など生物多様性の保全につながることが分かった。環境省の地球温暖化対策計画では、農地が炭素を吸収する対策として30年度に696万~890万トン(CO2換算)の土壌吸収を目標にしており、一定の貢献度がうかがえた。国連国際防災戦略によると、ここ20年間の自然災害による経済損失額は約329兆円。このままでは異常気象はさらに頻発し犠牲者は増え、損失額は増える。次世代に“ツケ”を持ち越さないために、持続可能な社会に向けて環境に配慮した農業の実践は欠かせない。異常気象を肌で感じ取る農家だからこそできる取り組みはある。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p44873.html?page=1 (日本農業新聞 2018年8月12日) 農業省力化へIoT 人口減、高齢化に対応 総務省検討委 総務省の情報通信審議会IoT新時代の未来づくり検討委員会は、情報通信技術(ICT)を活用し、2030~40年ごろの実現を目指す「未来をつかむTECH戦略」をまとめた。地方の人口減・高齢化が加速する中、IoT(モノのインターネット)を利用した農業の省力化、人工知能(AI)を生かした住民の健康状態把握などを挙げる。各分野で最新技術を取り入れ、地域の働き手や高齢者を含めた住民の生活を支えることを目指す。同戦略は、将来に日本が直面する問題に対し未来の理想の姿を描き、そこから逆算して長期的に取り組むべき政策を提言することが目的。同省は、働き手となる生産年齢人口の急減や独居高齢者世帯の急増、医療介護の需要増加が一層進むと見込む。30年代までには現在の社会の仕組みが立ち行かなくなると懸念。ICTの活用を進める方針を打ち出し、①人づくり②地域づくり③産業づくり──のテーマに基づき、同検討委で戦略をまとめた。産業づくりでは、時間当たりの労働生産性を現在の1・5倍超にまで高める目標を掲げた。このうち、農業では耕作などでIoTやドローン(小型無人飛行機)、ロボットを導入し、遠隔管理ができるようにするアイデアを挙げた。人づくりでは、高齢者の長寿命化と生活のサポートを重視。100歳まで健康に暮らせるよう、体に装着して自動制御で歩行を助ける補助装置の開発を挙げた。地域づくりでは、高齢者を含む住民の見守り体制の整備を目指す。AIを活用して健康状態を24時間見守り、問診や検査を省力化する健康管理サポートなどを提起した。同省は、同戦略について、審議会での承認を得た後、来年度からの予算編成などに反映させる考えだ。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p44429.html (日本農業新聞 2018年6月23日) 衛星データ 農業活用 官民で協議会 大規模経営支援へ 北海道 北海道は、農業などの産業振興を目的に人工衛星から得たデータの活用に乗り出す。最新技術の活用に向けて官民で「北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会」を組織。農業分野ではトラクターの自動走行や農作物の生育、品質把握などで衛星データの利用が進みつつあることを踏まえ、道内に多い大規模経営に役立つ方法などを検討する。協議会内に農業など分野ごとにプロジェクトチームを設け、来年度にもモデル事業を始める。協議会の幹事会には、道や道立総合研究機構などが参加。アドバイザーとして、情報通信技術(ICT)に詳しい北海道大学の野口伸教授らが就任した。どの分野で衛星データをどのように活用できるか今後、検討する。道は「北海道のように土地の面積が広い地域ほど、多くの衛星データが得られ、農業などさまざまな分野で有効に使える」(科学技術振興室)と有望視する。農業分野では現在、衛星から得たデータの利用が広がっている。衛星利用測位システム(GPS)を使って位置情報を把握し、自動走行する田植え機やトラクターの開発が進む。大規模経営の作業効率の向上につながるとして注目されている。人工衛星が撮影した農地の画像を使い、米の登熟など、栽培している作物の生育や品質を把握するリモートセンシング技術の導入も盛んだ。北海道ならではの大規模で栽培する米や畑作、牧草での利用が期待される。今後、IT企業や自治体、JAや研究者など多方面からの会員参加を呼び掛け、8月にも農業を含め、分野別のプロジェクトチームを発足させる。衛星データを使った新規事業について効果やコストなども含め検討する。来年度にも国の補助事業を活用した上で、モデル事業として着手。将来の普及の足掛かりにする考えだ。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p47024.html (日本農業新聞 2019年3月13日) シナノゴールド 南半球で栽培許諾 長野県が新たに契約 世界的リンゴ銘柄に 長野県は12日、イタリアの生産者協同組合2組織と、県育成のリンゴ「シナノゴールド」について新たなライセンス契約を結んだ。既に栽培されている北半球のEU加盟国に加え、両組合を通じて主に南半球5カ国での栽培を許諾することで海外での生産・販売を拡大。通年販売も可能になる。契約を結んだのは、イタリア南チロル地方の「南チロル果物生産者協同組合(VOG)」と「ヴァルヴェノスタ協同組合(VI・P)」。長野県庁で阿部守一知事とVOGのゲオルグ・ケスラ社長が契約書に署名した。同県は2007年、「シナノゴールド」の栽培を許諾する契約を両組合と締結済み。16年にはEU加盟国での生産、販売などに関するライセンス契約を結んだ。両組合は欧州で主流の黄色系「ゴールデンデリシャス」の後継を視野に、商品名を「yello(イエロ)」として販売してきた。今回両組合と交わした契約により、EU加盟国に加え南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリア、チリ、米国の5カ国の、各国1社が「シナノゴールド」を栽培できる。販売地域も「yello」の商標を取得した全ての国に拡大。これまではEU、北欧、北アフリカの諸国、スイス、ロシアに限られていた。品種名「Sinano Gold」は、販売時の包装容器などに記載される。両組合はパンフレットなどで「日本の長野県が育成」と明示する。県は、各国の生産者から売り上げに応じた許諾使用料を得るとともに、「シナノゴールド」を世界的なブランドへ育て、将来的な輸出増につなげたい考えだ。日本への輸出はしない契約。阿部知事は「販路が飛躍的に拡大した。世界にしっかり発信していきたい」と意欲を示した。ケスラ社長は「栽培地域の拡大で、各国の最高の生産者によって育てられるシナノゴールドを紹介していきたい」と応じた。 *2-5:https://www.agrinews.co.jp/p46490.html (日本農業新聞 2019年1月21日) ゲノム編集 不安に応え議論慎重に 消費者から不安の声が上がっている。ゲノム編集で作り出した作物やそれを使った食品などの規制について、厚生労働省と環境省各審議会の調査会と検討会は、半年にも満たない議論で結論を急ごうとしている。農業への影響も大きい。新しい技術だけに、より慎重に検討すべきである。ゲノム編集は、遺伝子を効率良く改変する技術だ。既存の遺伝子組み換え(GM)技術に比べて簡単で間違えが少なく、汎用(はんよう)性があり、開発期間を短くできる特徴がある。主に①動物や植物に新しい特性を持たせるため、他の生物の遺伝子を導入する②もともとある特性を消し去るため、遺伝子の一部を削る──などの手法がある。これらの技術を活用し農研機構などは、従来の育種なら10年以上かかる小麦で、穂発芽を促進する機能のない品種を1年ほどで開発した。他にも超多収稲や日持ちが良いトマト、毒素を作りにくいジャガイモなどの開発が期待できるという。規制の検討は食品衛生法とカルタヘナ法に基づくもので、政府の「2018年度内に規制の在り方を明確化する」との方針を受けて、昨年夏から始まった。半年間の議論で両省はほとんど同じ結論を導いた。他の生物の遺伝子を導入する①については既存のGM技術と同じ扱いで、安全性審査など規制の対象とした。遺伝子の一部を削る②については「自然界でも起こり得る変化の範囲内」として規制の対象外とした。研究者や企業側からの安全性などの情報提供は「任意」とし、届け出を行わなかった場合も罰則規定はないとした。こうした両省の方針に対する消費者の不安は大きい。厚労省の調査会はこれまで4回しか開かれず、関係団体へのヒアリングは1回にとどまった。消費者団体側は「GMもゲノム編集も、遺伝子を操作するという点で同じ」「アレルギーや毒性など安全性に懸念がある」と問題視する。同省は17日に開いた審議会部会で、無届けのゲノム編集を用いた食品が確認された場合、届け出がないことを含めて情報を公開するとしたが、これで問題は解決されるのだろうか。農業への影響もある。遺伝子の一部を削るゲノム編集で開発した農作物は、規制の対象外となるだけに知らないうちに栽培していたという事態が起こりかねない。多国籍企業による種子の支配が一層強まる恐れもある。欧州司法裁判所は昨年7月、「自然には発生しない方法で生物の遺伝子を改変して得られた生物はGMに該当する」と判断し、ゲノム編集に慎重な姿勢を示した。日本とは対照的だ。両省は今年度中に規制の在り方をまとめる予定だが、残された課題は多い。政府はまず、国民の不安を取り除くべきである。結果を急がず、丁寧に審議を進める必要がある。 *2-6:http://qbiz.jp/article/150570/1/ (西日本新聞 2019年3月20日) 佐賀県新イチゴ、無断で苗を譲渡 元研究センター職員 佐賀県は19日、県農業試験研究センターの60代の元職員が県産イチゴ「いちごさん」の品種登録前に無断で苗を持ち出し、県内の農家に譲渡していたと明らかにした。苗は別の農家にも渡り、5株を販売。県は二つの農家が所有する苗を全て廃棄させたが、5株の流出先は不明という。いちごさんは20年ぶりに県が開発。昨年8月に国が品種登録を認め、県と契約したJAさがが栽培や販売を独占的に担うことになった。県によると、元職員は在任中の2017年春、知人農家に頼まれ、県が試験栽培中の苗6株を譲渡。知人は苗を増やし、別の農家に15株を渡した。今年1月、この農家は近所の直売所で鉢植えの苗5株やパック詰めのいちごさんを販売。苗が販売されていることを不審に思った農業関係者の連絡で発覚した。県によると、元職員は昨年3月に退職、「いずれ新品種が出回るので大丈夫と思った」と謝罪しているという。県は「誠に遺憾。いちごさんのブランド確立に努めたい」と話している。 <農業の6次産業化> PS(2019年3月20、23日追加):私も原発事故後に西日本産のお茶や水を買うことから始めて、①小売店の選別を得ずに広い範囲の品物から選択できる ②価格の比較もできる ③重たいものでも文句を言わずに持ってきてくれる などが理由で、アマゾンなどの宅配をよく使うようになった。また、ふるさと納税でお礼の品として並んでいる商品も、その自治体が自慢の品を選んで掲載しているため、参考にしている。従って、共働きや高齢世帯の増加に伴って食品の宅配市場が伸びている時に、*3-1のように、農家・JA(農協)・FA(漁協)などが宅配事業に参入すれば、採れたての新鮮なうちに調理された食品を最小の仲介手数料で入手できるため重宝だと思う。この時、せっかく商品を間近で見て選ぶスペースがあるのに、イトーヨーカドー等のスーパーが流行らなくなるのは、かさばるもの・重たいものを買っても自宅に届けるのを嫌がったり、消費者が望んでいる商品を置かなかったりなど、現在の消費者ニーズに応えていないことが原因であり、過去の成功に甘えた油断の結果だと考える。 なお、*3-2の多収で難消化性でんぷんを含む「あきたさらり」は、栽培コストが低減できるだけでなく、糖尿病予備軍やダイエット志向の消費者に便利だ。しかし、米粉の使い方については、うどんだけでなくフォー(ベトナムの人気麺料理)など米作地帯の料理を作った方が、本物の美味しさで食べられるのではないかといつも思う次第である。 また、*3-3のように、JA全農が、JR品川駅構内に弁当・総菜店「みのりみのるキッチン」をオープンして国産活用のノウハウを中食でも生かすそうで、これは全国の駅で沿線の農産物を使って展開すると面白い。例えば、地域ブランドのPRは、鉄道なら使った食材の生産現場の写真や生産過程の話を包装紙等に印刷してあると、これから行く地域や今通っている地域のことであるため、より消費者の関心を引いて印象に残ると考える。 *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p46450.html (日本農業新聞論説 2019年1月17日) 伸びる食品宅配 JAらしい地域貢献を 食品の宅配市場が伸びている。共働きや高齢世帯の増加に伴い、買い物に手軽さを求める消費者が増えているためだ。特に次代の消費を担う若い世代ほど宅配の利用に関心が高い。農家やJAも宅配事業の可能性を探り、参入を考える時だ。調査会社の矢野経済研究所の推計では、2018年度の食品宅配市場は2兆2000億円を超える見込みだ。12年度以降、毎年3%前後の成長が続く。スーパー270社の総売上高10兆円超(17年)には及ばないが、スーパーの売上高が4年ぶりに前年を割り込んだことと比べると勢いの差は明らかだ。生協は「共同購入」から組合員宅に届ける「個配」への転換が進む。日本生活協同組合連合会に所属する地域生協では個配が全体の7割に達する。昨年は有機食材を手掛ける宅配大手3社が合流して「オイシックス・ラ・大地」が発足、物流を効率化して事業を拡大している。異業種の参入も相次ぐ。17年にインターネット通販最大手のアマゾンジャパンが「アマゾンフレッシュ」を立ち上げ、昨年は「楽天西友ネットスーパー」が誕生した。事業伸長の理由は明らかだ。買い物に行くのが難しい高齢者や日中忙しい共働きの世帯が増え、食材調達と調理の簡便化が求められているためだ。中でも、伸びが著しいのが「ミールキット」だ。1食分の献立に必要な下ごしらえが済んだ野菜や肉などの食材と調味料、レシピをセットして家庭に届ける。包丁を使わず簡単に調理でき、材料を余らせることもない。ミールキットは若い世代ほど魅力を感じている。タキイ種苗によると20、30代の4割が「興味がある」と答え、50代(2割以下)とは対照的だった。食品卸大手の19年の消費トレンド予想でもミールキットの需要は今後も拡大し、月額制で多様な料理を楽しむサービスが増えると分析する。「食の簡便化」という消費動向に、産地側も乗り遅れてはならない。地産地消を広げ、地域貢献につなげたい。JA全農とちぎは、昨年からJAふれあい食材の配達員による高齢者の「見守りサービス」を始めた。配達中に独居高齢者宅などを訪問し、会話を交わし安否を確認する。食材宅配サービスと合わせると利用料金が割安になる。地域貢献を兼ねたJAならではの宅配事業だ。JA静岡経済連も昨年から、地元の生協と協業しJA組合員に宅配利用を勧めている。組合員のニーズに応え、生協に県産食材を提供する機会を増やす。阪神・淡路大震災が発生してきょうで24年。大震災以降、防災の備えや被災時の救出活動など、地域住民の「共助」を呼び掛ける声が強まった。住民と触れ合う機会が増える宅配事業は共助の意識を高めるきっかけになるはずだ。地域の連帯を促すJAらしい事業に育てよう。 *3-2:https://www.agrinews.co.jp/p46461.html (日本農業新聞 2019年1月18日) 米粉用で多収品種 難消化性でんぷん豊富 ダイエット食材に 秋田県立大など 秋田県立大学などが、多収で消化しにくいでんぷん(難消化性でんぷん=RS)を含む新たな米粉向け品種「あきたさらり」を育成した。10アール当たり収量が800キロ程度と多収で、栽培コスト低減が期待できる。RSの含量は3%で、「あきたこまち」の3倍以上と多い。ダイエットなど健康志向の消費者にPRできることから、県内企業と、同品種の米粉を使ったうどんなどの商品開発を進めている。「あきたさらり」は同大と県農業試験場、国際農林水産業研究センター(JIRCAS)などが育成。2018年秋に農水省に品種登録出願を申請し、出願が公表された。米粉は製粉費用がかかるが、多収で栽培コストを下げることでカバーする。熟期は「あきたこまち」より1週間遅く、作業分散が期待できる。同大と企業の共同研究で、米粉を小麦粉に20%ほど混ぜてうどんを作ると、腰が強く、ゆでた後もべたつきにくい麺が作れることが分かった。「あきたさらり」はアミロース含量が高く、大粒で米粉適性が高い。同大生物資源科学部の藤田直子教授は「小麦アレルギーの人向けに、グルテンフリーのうどんなども作れる可能性がある。水田転作にも役立つ」と期待する。現在の栽培面積は約1ヘクタールだが、さらに拡大する見込みだ。 *3-3:https://www.agrinews.co.jp/p47152.html (日本農業新聞 2019年3月23日) 中食もっと国産活用を 全農が初の弁当店 JA全農は22日、東京都港区にあるJR品川駅構内に初の弁当・総菜店「みのりみのるキッチン」をオープンした。全農は食料自給率向上などを目指す「みのりみのるプロジェクト」の一環で、全国にレストランやカフェを展開。外食で培った国産活用のノウハウを需要が急拡大している中食でも生かす。今後も同様の店舗を広げる考えで、国産農畜産物の消費拡大と、中食での国産100%活用のモデル店舗を目指す。みのりみのるプロジェクトは、原料原産地表示の普及や地域ブランドのPR、国産消費拡大などを狙いに開始。2010年に初のレストランを出店し、現在、カフェを含め全国に15店舗を展開。外食店舗では、旬の野菜を使ったり、直売所と連携したりする工夫を重ねる。他社にも、外食で国産を活用するノウハウを提供している。一方、中食の市場規模は17年に10兆円を超えた。今後も大きな伸びが見込まれるが、中食では輸入食材が多く使われていることから、全農は国産100%の弁当・総菜店の開店に踏み切った。食材は一部の香辛料などを除き全て国産。ご飯に加え、複数から主菜1品、副菜2品を選べる弁当も用意。この弁当の米には開店当初は山形県産「雪若丸」を使うが、定期的に変えていく構想だ。約33平方メートルの店舗では、JAの加工品などを売るスペースも設ける。全農は「外食、中食での取り組みを通じ、日頃食べているものの産地を意識してもらうきっかけにしたい」(リテール事業課)と強調する。営業時間は午前9時から午後10時まで。エキュート品川内にある。 <多様な担い手の活用> PS(2019年3月21日追加):*4-1のように、農業界全体では経営・地域社会・方針決定への女性参画が十分でないが、1974年には「めんどり(発言する女性)のさえずる家は栄えた試しなし」と言われていたが、現在では「農山漁村女性の日、活躍なくして発展なし」と言われるようになったため、かなり変化したと言える。実際に、農業は消費の意思決定の多くを女性が行う食品産業であるにもかかわらず、男性優位で意思決定の場に女性が少ないことが衰退の一因だろう。そのため、性別・年齢・国籍・障害の有無にかかわらず、多様な人のアイデアを活かすことが次の発展の糸口になると思われる。 このような中、*4-2のように、49歳以下の新規就農者が2017年で2万760人となり、4年連続で2万人を超えて、都市から農山村に移住して農業を営む流れが若年層の間に続いているが、政府は農業生産の継続に必要な農業就業者数を約90万人と推計し、これを60代以下で担うため、49歳以下の農業従事者を2023年度までに40万人にする目標を掲げているそうだ。 しかし、*4-3のように、先端技術を活用したスマート農業に脱皮しなければ、一人当たりの生産性が上がらないので、一人当たりの農業所得も上がらない。また、障害者は安すぎる賃金で働かされていることが多いが、働きに見合った労賃とやり甲斐を得られなければ不幸だ。そのため、「スマート農業」や「農福連携」は重要なテーマである。 2019年度の都道府県の予算(案)では、*4-4-1のように、約8割の28都府県が農林水産予算を増やし、中でも外国人労働者受入拡大に向けての環境整備を進める労働力確保対策やスマート農業の導入支援が目立つそうだ。私は、スマート農林水産業の技術開発は、各大学やメーカーの自動運転・ロボットなどの研究チームが研究室から現場に出て、現場のニーズを把握しながら行うのがよいと考える。何故なら、農林水産業は自動運転やロボットを使える局面が多いが、研究室の中だけではそのニーズを把握できないからだ。 また、国は、*4-4-2のように、外国人労働者がすべての金融機関で口座を開設できるようにしたり、日常生活の相談に応じる「多文化共生総合相談ワンストップセンター」を全都道府県に設けたりするそうだ。しかし、*4-4-3のように、「日本で働く外国人が増えると不正に医療保険を利用する」という見方があるのは残念で、外国人労働者も公的社会保険料の支え手であることを忘れてはならず、政府がやるべきは、加入すべきなのに未加入・未徴収の企業への指導や周知の徹底だろう。 *4-1:https://www.agrinews.co.jp/p46992.html (日本農業新聞論説 2019年3月10日) 農山漁村女性の日 活躍なくして発展なし 農業界全体で経営や地域社会、方針決定の場への女性参画が十分とは言えない。業界を挙げた意識改革と環境整備、支援が不可欠だ。きょうは「農山漁村女性の日」。「農山漁村女性の日」は、1987年度に農水省が制定。農林漁業の重要な担い手として、女性の能力発揮を進めるのが狙いだ。関連行事として行われた2018年度の農山漁村女性活躍表彰は、農山漁村男女共同参画推進協議会が主催。17年度に「女性・シニア活動表彰」と「男女共同参画優良活動表彰」を一本化。地域社会や法人への参画、起業・新規事業開拓、若手の参入など6部門を設けた。女性活躍法人部門で農水大臣賞に輝いた岩手県一関市・かさい農産は、役員4人のうち2人、構成員全体の8割近くが女性。それぞれの家庭状況に合わせ、子育て中の女性だけではなく高齢者や障害者にとっても働きやすい職場を実現した。若手女性チャレンジ部門農水大臣賞の福島県二本松市・菅野瑞穂さんは13年に、20代で会社を設立。大手旅行会社と連携し、東日本大震災からの復興を目指す生産現場を自分の目で見てできることを考える「スタディーツアー」を始めた。毎年100人近くが参加している。女性地域社会参画部門で農水大臣賞を受賞した熊本県菊陽町の那須眞理子さんは、74年に結婚を機に就農。当時は「めんどり(発言する女性)がさえずる家は栄えた試しなし」といわれていたが、「ようやく時代が追いついた」と振り返る。40年間、地域や経営で男女共同参画へ活動した努力が実を結んだ。審査委員長を務めた福島大学の岩崎由美子教授は「個人の活動や仕事づくりが地域の課題を解決している」と共通点を指摘、女性が輝く社会は「地域全体の活性化につながっている」と評価した。こうした取り組みを全国に広げていくことが重要だ。今、家庭で、職場で、地域で発言しにくかったり、働きにくかったりする場面はないだろうか。女性の参画は確実に進んではいるものの、男性優位の社会構造は続いている。JA全中によると、「1JA当たり役員2人以上の登用」という目標は2年連続で達成したが、全役員に占める女性の割合は8%。農業委員会に占める女性の割合は12%。市議会は14%、町村議会は10%といずれも1割程度にすぎない。男女が対等に運営に携わる社会は程遠い。旧態依然とした体制を続けていても未来は開けない。時代の変化に対応するには、性差にとらわれない意識改革が必要だ。目指すべきは年齢や性別、障害の有無にかかわらず、多様な人の発言やアイデアを受け止められる社会をつくることだ。労働力不足の中で、人生のどのステージにあっても無理なく自分らしく働ける地域づくりも欠かせない。女性の活躍なくして農業界と地域の発展はない。 *4-2:https://www.agrinews.co.jp/p44887.html (日本農業新聞 2018年8月15日) 49歳以下の新規就農者 4年連続2万人超え 田園回帰流れ続く 後継者育成課題も 49歳以下の新規就農者が2017年で2万760人となり、4年連続で2万人を超えたことが農水省の調査で分かった。農業以外から就農する新規参入者が、49歳以下では調査開始以来、最多となるなど、若年層の田園回帰の動きが続いている。だが、新規就農者全体では5万5670人で前年比7%減。生産力の維持には、農家子弟の経営継承への支援をはじめ、一層の担い手の確保、育成が求められる。49歳以下の新規就農者は14年に2万1860人となって以降、2万人台を保っている。農地などを一から確保し経営を始めた新規参入者は、49歳以下は17年で前年比10%増の2710人で、07年の調査開始以降で最多。同省は「都市から農山村に移住し農業を営む田園回帰の流れが、若年層の間に続いている表れ」(就農・女性課)と指摘する。農業への定着を促すため、就農前後に補助金を交付する農業次世代人材投資資金(旧・青年就農給付金)も下支えしたとみる。新規参入者は50歳以上も含めた全体でも6%増の3640人で、14年の3660人に次ぐ多さとなった。一方、実家の農業を継いだ新規学卒者ら新規自営農業就農者は4万1520人で10%減、うち、49歳以下は1万90人で12%減となった。高齢化を背景に農家全体が減る中で、後継者数も減っている状況だ。農業法人への就職者など新規雇用就農者にもブレーキがかかった。14年以降伸びていたが、17年は1万520人で1%減、うち、49歳以下は7960人で3%減だった。国内全体で労働力不足が進む中、他産業に人材が流れたとみられる。政府は農業生産の継続に必要な農業就業者数を約90万人と推計し、これを60代以下で安定的に担うために、49歳以下の農業従事者を23年度までに40万人にする目標を掲げる。49歳以下の農業従事者数は、17年度は前年比8000人増の32万6000人。目標達成には、さらに新規就農者を増やし、従事者確保のペースを上げる必要がある。また、認定農業者に占める49歳以下の割合を見ると、06年3月には4割近くあったが、15年3月では約2割に低下している。若年層の新規就農者が認定農業者など地域の担い手として定着できるよう、支援を強化する必要性も高まっている。 *4-3:https://www.agrinews.co.jp/p46476.html?page=1 (日本農業新聞 2019年1月19日) 農水省 白書作成へ議論着手 先端技術、農福連携が柱 農水省は18日、食料・農業・農村政策審議会の企画部会(部会長=大橋弘東京大学大学院教授)を開き、2018年度の食料・農業・農村白書の作成に向けて議論を始めた。重点的に取り上げる項目として、先端技術を活用したスマート農業などを提示した。委員からは、全国的な普及が進むよう求める声が出た。白書は3月に骨子案を示し、5月の閣議決定を予定する。同省は、同部会で白書の構成を説明。特集のテーマに「スマート農業」「農福連携」を挙げた。これらとは別に、18年度の特徴的な動きとして取り上げる項目に①多発した自然災害②農産物・食品の輸出拡大に向けて③規格・認証・知的財産の活用④消費が広がるジビエ(野生鳥獣の肉)──を挙げた。スマート農業を巡り、同審議会会長を務める東京大学大学院の中嶋康博教授は「農業団体や集落などの組織をどう変えていくかの議論ができないか」と提起。技術導入に合わせて組織の体制を整えていく必要性を挙げ、議論を呼び掛けた。JA全中の中家徹会長は、スマート農業について「平地や大規模というイメージが先に浮かぶ。中山間地でもやってみようと思える視点が必要だ」と指摘した。家族農業など中小規模の農家も活用できるよう、技術の導入費用に関する議論も進めるよう求めた。全国農業会議所の柚木茂夫専務は、18年度からの米の生産調整見直しに対し「米政策の転換期だった。点検や評価を丁寧に記述するべきだ」と強調した。 *4-4-1:https://www.agrinews.co.jp/p47115.html (日本農業新聞 2019年3月20日) 28都府県が増額 労働力対策を拡充 本紙調べ 19年度農林水産予算 2019年度の都道府県予算(案)が出そろった。日本農業新聞の調べでは、知事選のため骨格・暫定予算を組んだ11道県を除く36都府県のうち、約8割の28都府県の農林水産予算を増やした。国の防災・減災緊急対策に伴い、公共事業費などが増えていることに加え、農政改革に対応し、予算を手厚くした。担い手の高齢化を受け、労働力の確保対策や、省力化に向けたスマート農業の導入支援対策の新規事業が目立っている。農林水産予算が最も伸びたのは広島県の39%。西日本豪雨の復興事業を計上し、大きく増加した。岩手県は、東日本大震災からの復興事業で、沿岸部の防潮堤工事の支払いがピークを迎え22%増。宮城県、福島県も、震災からの復興事業により増減が大きくなっている。奈良県は18年度、国営水利事業の地元負担金を計上したため、大きく減った。農林水産予算の内訳を見ると、労働力確保に向けた事業が目立つ。4月からの外国人労働者の受け入れ拡大に向け、環境整備を進める狙いだ。茨城県は、県内の外国人労働者数が過去最多の3万5062人(18年10月末時点、茨城労働局調べ)に上る。外国人労働者が農業に従事しやすいよう「農業労働力確保総合支援対策事業」(700万円)に新規で取り組む。農業生産法人などが受け入れに向けた住環境整備で融資を受けた場合に、その利子補給を行う。外国人労働者が農耕用の大型特殊免許やフォークリフトなど農作業に必要な資格取得費用も負担し、人材育成につなげる。秋田県は新規で「外国人材の受入体制整備事業」(1050万円)を展開。外国人技能実習生などの活用方法の検討や農業法人などを対象とした研修会を開く。長野県は、JAグループと連携して、外国人材を含めた労働力確保推進の体制整備を支援。「JA長野県農業労働力支援センター」の取り組みを後押しする。農業労働力の安定確保支援事業費を計上した。省力化に向けたスマート農業の導入支援も加速する。作業の省力化と生産性向上につなげる。新潟県は「スマート農業加速化実証プロジェクト」を立ち上げる。4億円を計上し、農機具メーカーなどと連携して実証研究を実施。ロボットや人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)などの先端技術を水田作や園芸分野で導入する。京都府は、AIや情報通信技術(ICT)などを活用する「スマート農林水産業加速事業」を2億1200万円計上。モデルとなる経営体で技術を展示・実証することで、普及を後押し。導入する生産者の費用を一部補助する他、産官学連携でスマート農業技術のメニュー開発に取り組む。高知県は「Next次世代型施設園芸農業の推進」として、8億4900万円を計上し、AIによる作物の生理・生育情報の可視化と利活用などの研究を進める。省力化により担い手の経営高度化につなげる考えだ。 *4-4-2:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38788160R11C18A2MM8000/?n_cid=NMAIL006 (日経新聞 2018/12/11) 外国人労働者 口座開きやすく 生活相談など支援拡充へ 政府は改正出入国管理法に基づき、2019年4月に新設する在留資格「特定技能」を巡り、まずはベトナムやフィリピンなどアジア8カ国から外国人労働者を受け入れる。19年3月までに情報共有などを定める2国間協定を結ぶ。来日した労働者の銀行口座の開設を容易にするなど働き手の不安を緩和し、日本での生活になじむよう最大限の環境整備に取り組む。19年4月の新制度開始時は8カ国のうち、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアの7カ国が決まっており、残り1カ国は調整を続けている。専用の日本語試験を設けて、新たな労働者の受け入れを始める。4月以降、順次拡大する。技能実習制度で日本に在留している外国人は今年6月時点で約28万5千人。ベトナムは最も多い約13万4千人を占め、新制度でも柱となる。中国は約7万4千人、フィリピンも約2万8千人が在留する。現在、技能実習を受けている実習生は8カ国以外でも新資格に移行する場合がある。外国人労働者の受け入れ拡大では、賃金の未払いなど劣悪な労働環境に陥ることもある働き手が安心して暮らせる基盤をつくることが急務となっている。日本と相手国政府の双方が、言語や風土が異なる場所で働くことになる外国人の生活環境に配慮し、公的関与のもとで情報共有する。受け入れ側と送り手側の双方のメリットとなる仕組みづくりをめざす。そのためにまずは受け入れの前提として、8カ国とは労働者の権利保護などを目的とした2国間協定を結ぶ。国会での批准手続きは必要としない形式をとる。ベトナムなどは日本滞在中の労働者としての権利保護を求めていた。受け入れる外国人の身元や生活実態などを把握しながら就労環境を整える。技能実習制度では、就労前に多額の手数料や保証金を支払わせるといった悪質ブローカーが相次ぎ、実習生の失踪などにつながっていた。2国間協定を結ぶと警察当局が捜査情報を互いに共有し、悪質な業者の摘発につなげやすくなる。年内に決める「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策」には生活環境の改善策も明記する。金融庁が金融機関向けの指針をつくる。外国人労働者がすべての金融機関で口座を開設できるようにして、給与を管理しやすくする。これまで技能実習生は銀行口座の開設が難しく、給与を現金で受け取る例が目立っていた。銀行口座があれば、支払額を客観的に把握することも可能になる。政府は新資格での労働者は日本人と同等以上の給与水準を支払うよう求めており、係争時に国が適正に支払われているかチェックすることができるようになる。日常生活の相談に応じる「多文化共生総合相談ワンストップセンター」も全都道府県に設ける。政令指定都市などにも置き、全国で約100カ所程度を想定する。全ての医療機関で外国人が医療行為を受けられるような体制も整える。公共機関の窓口には翻訳システムを導入する。住宅を確保しやすくするため、外国人の入居を拒まない賃貸住宅の情報を提供する仕組みもつくる。複数の言語で賃貸借契約書の書式をつくり、賃貸人や仲介事業者向けには外国人対応の実務マニュアルを配る。生活で使う言葉に重点を置いた日本語教育へ全国に教育施設を展開する。19年度予算案に200億~300億円の関連予算を計上する。不法残留などの問題を減らすため、日本語教育機関への定期的な点検や報告を義務付ける。いまは日本語学校へ留学目的で入国した外国人が就労し、不法残留するケースが目立っている。新資格の就労により門戸を広げる一方で、不適切な就労の根絶を目指す。こうした対策について、安倍晋三首相は法務、外務、厚生労働など関係省庁による外国人受け入れに関する閣僚会議を年内に開き、8カ国の受け入れ方針などを正式決定する見通しだ。 *4-4-3:http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018121402000165.html (東京新聞社説 2018年12月14日) 外国人の医療 不正ありきは差別生む 「日本で働く外国人が増えると不正に医療保険を利用する」-。政府はそんな見方を前提に医療保険制度の改善を考えているようだ。外国人への差別や偏見を助長しかねない議論は慎むべきだ。まるで性悪説に立つような議論は、外国人労働者を隣人として受け入れる姿勢に欠ける。今後、年金制度も含め社会保障の適用ルールの議論が始まるが、監視する相手としか見ないのなら共生はおぼつかない。外国人労働者の受け入れ拡大を目指す改正入管難民法が成立した。その中で出てきた議論が、来日した外国人が公的健康保険を不適切に利用する懸念からの防止策である。日本の企業で働く外国人は主に健康保険(健保)に入る。母国にいる家族も被扶養者と認められれば母国や日本で健保を利用できる。受診のために来日して高額医療を受けることもできる。こうなれば外国に住む家族のために費用がかさみかねないという。また、日本への留学生は国民健康保険(国保)に加入するが、偽りの在留資格で加入したり、複数の人が同じ保険証を使い回す「なりすまし」の懸念がある。本人確認の必要性を政府は言い始めた。こんな点が問題視されている。社会保障は支え合いの制度だ。不適切な利用は許されないし制度の穴はふさがねばならない。日本人との公平性に配慮しながら制度改善を進めることは必要である。だが、外国人という理由でこうした不適切利用が横行するかのような前提で議論がされている。厚生労働省は昨年三月、日本で高額医療を受けた外国人について、医療費の使われ方を調べた。国保加入から半年以内に高額医療を受けた人の中で明確な不適切利用は見つからなかった。政府は一月から、国保へ加入間もない外国人が高額医療を申し込む際、窓口となる自治体が在留資格と実態を確認する調査を試験的に始めた。資格と実態が違う場合は自治体から入管当局に通報する仕組みで違和感を覚える。しかもこの調査も九月に法相が、在留資格を取り消した事案はないと説明した。不正が続出するとの懸念は取り越し苦労だろう。むしろ働く外国人は医療保険の保険料を払う貴重な存在になる。政府がやるべきは、加入すべきなのに未加入の企業への指導や制度の周知ではないのか。外国人を信頼しない姿勢では、前向きな制度議論はできない。 <日本人も感じる銀行の不便> PS(2019年3月22日追加):*5のように、大手3銀行が先端IT技術を導入して新卒採用を抑制し、組織のスリム化を進めて経営効率化を加速するのは、新卒者数も限られ、ITでもできる業務よりは稼げる熟練業務を行う方が担当者も遣り甲斐があると思われるのでよいと思う。しかし、私は佐賀県を地元として衆議院議員になった時、大手銀行の支店が限られた場所にしかなく、あわてて佐賀銀行に口座を作った経緯がある。しかし、佐賀銀行の支店は埼玉県の自宅付近にはなく、自宅付近では通帳記帳ができない。 そのため、この際、銀行通帳の規格を統一し、別の銀行に行っても持っている通帳で引き出し・払込・通帳記帳等ができるようにして欲しい(通帳交換の時には表紙を印刷できるようにしておけばよい)。その点、ゆうちょ銀行は日本中どこにでもあり、通帳のみで引き出し・払込・記帳等ができる点が便利だが、まだ銀行機能をすべてはもっていない欠点がある。 *5:http://qbiz.jp/article/150659/1/ (西日本新聞 2019年3月21日) 大手3銀行が合理化加速 IT導入で業務量削減 三菱UFJ銀行が、2023年度末までに9500人分の業務を削減する計画を大幅に積み増すなど、大手3銀行が先端のIT技術の導入を進め、経営効率化を加速することが21日、分かった。新卒採用数を抑制し、組織のスリム化も進める。20年度の採用数は4年連続で減少し、リーマン・ショック以降で最少になる見通しだ。業務量削減は、手作業で処理していた単純な業務の自動化が柱だ。支店や事務部門の行員数を減らすなどしてコスト削減を図り、稼げる分野に人材を配置転換する狙いもある。三菱UFJ銀は、住宅ローン審査の一部を人工知能(AI)に肩代わりさせたり、複数拠点に分散していた業務を集約したりすることで削減幅を拡大する。必要な人員は減る見込みで、20年度の採用数を19年度の950人から2割以上減らす方針だ。三井住友フィナンシャルグループは19年度末までに4千人分の業務量削減を目指すが、当初計画から上回る見込み。傘下の三井住友銀行の20年度の採用数は19年度の650人から1割程度減らす方向で検討している。みずほフィナンシャルグループは、人員削減を26年度末までに1万9千人行う方針だったが、前倒しを視野に計画を練り直し始めた。19年度は700人だった採用数も減らす予定だ。超低金利の長期化による収益悪化やIT企業など異業種の参入が相次いでいることで、銀行業界を取り巻く環境は厳しさを増している。変化の速度は想定以上で、生き残りに向けてさらなる効率化を徹底する。 <化石燃料由来の水素と原発補助金とは、どこまで馬鹿なのか> PS(2019年3月22、23日追加):*6-1のように、「東電が水素事業に参入して2020年に稼働する」というので「やっとそうなったか」と思ったら、「水素を都市ガスから生産する」と書かれていたので呆れた。何故なら、都市ガスから生産した水素による燃料電池車なら、それは輸入エネルギーである上、CO₂削減もおぼつかず、燃料電池車が増えれば増えるほどその付近の空気中の酸素が薄くなるという新しい公害が起こるため、費用が課題だと言っていることまで含めて、どこまで馬鹿かと思うからだ。一方、自然エネルギー由来の電気で水を電気分解して水素を作れば、同時に酸素もできるため、車内に酸素を吹き出して酸素不足を解決することもできるので、化石燃料由来の水素はボイコットしたい。そのため、東電・中電の株主や投資家は、この投資の意義について、株主総会で追及した方がよいと思う。 さらに、*6-2のように、経産省は、温室効果ガス対策を名目に、原発由来の電気について電力小売事業者と発電事業者間の市場価格に一定価格の上乗せ(原発に対する新しい補助金)を認めようとしているそうだ。そして、その理由を「原発は環境への貢献で付加価値をもたらしているから」としているが、実際には放射線公害という大きな負の付加価値をもたらしているため、それをこそ反映すべきだ。また、経産省が「原発には競争力がある」として原発を「ベースロード電源」と位置づけ、2030年度の電源構成で20~22%に引き上げる目標を掲げたのは、「バランスよくエネルギーミックスを決める」という名目で、市場を無視して盲目的に決めた統制経済そのものであり、このように特別扱いしてまで原発を維持したい理由は原爆の開発以外に考えられない。しかし、ミサイルが主役となる時代に原爆を開発するのは、戦闘機が主役となる時代に戦艦を重視したのと同じくらい時代遅れの発想なのである。 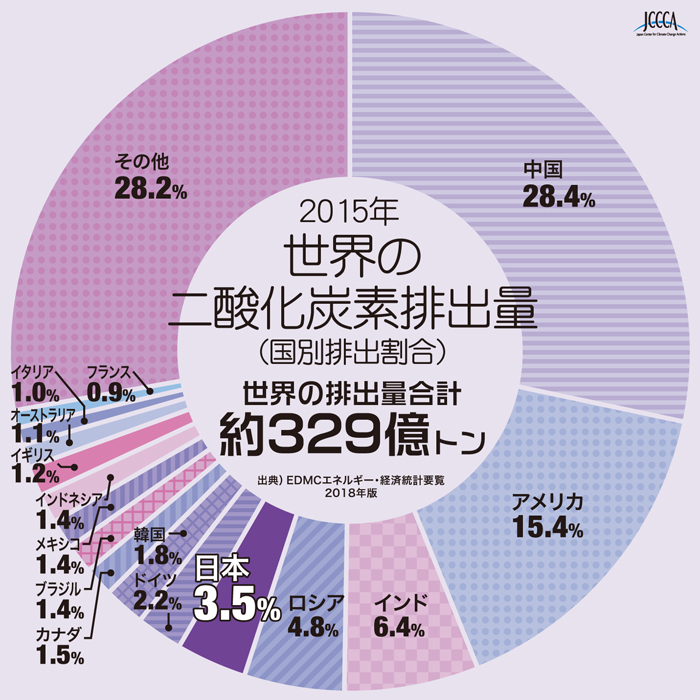 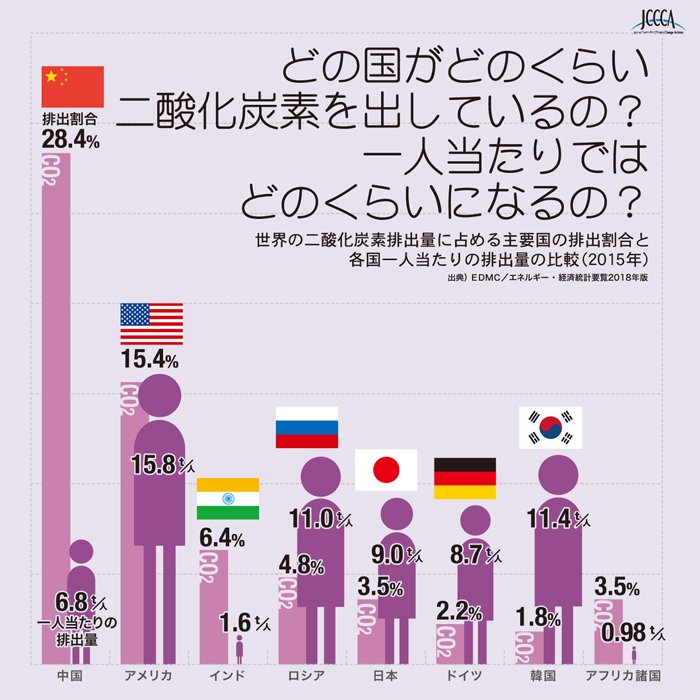   (図の説明:左図のように、2015年の日本全体のCO₂排出量は世界第5位で、左から2番目の図のように、一人当たり排出量は世界第4位だが、右から2番目の図のように、削減目標は低い。そのような中、無公害車と期待している右図の燃料電池車の水素を化石燃料から作ったり、原発に補助金を出したりなど、どこまで環境に無神経なのかと呆れるわけである) *6-1:http://qbiz.jp/article/150686/1/ (西日本新聞 2019年3月22日) 東電が水素事業参入、2020年稼働 中部電力と折半のJERAに継承 東京電力ホールディングス傘下で火力発電を担う東京電力フュエル&パワー(FP)が水素事業に参入することが22日分かった。石油元売りのJXTGエネルギーと共同で水素の製造設備を造り、2020年中に稼働させる。中部電力と折半出資して設立した火力発電会社JERA(ジェラ)に継承する。22日午後に正式発表する。製造設備は、東電FPの東京都品川区にある大井火力発電所の敷地内に新設し、都市ガスから水素を生産する。水素で走る燃料電池車への供給設備も併設する。投資額は数十億円となる見通し。JXTGは既に水素事業に参入しており、水素の製造や供給設備の運用の知見を持つ。東電と協力することで生産費を減らせるとみる。東電FPは今年4月にJERAへの全事業の移管が完了する。水素事業も同時に移す。燃料電池車は水素を酸素と反応させて発電して走行し、二酸化炭素を排出しない。水素は太陽光や風力で発電した電気で水を分解して生産することも可能だ。ためることのできない電気を水素に転換して貯蔵できるという利点もあるが、費用が課題となっている。 *6-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S13945799.html (朝日新聞 2019年3月23日) 原発支援へ補助制度案 売電価格上乗せ 経産省検討 経済産業省が、原発で発電する電力会社に対する補助制度の創設を検討していることが分かった。温室効果ガス対策を名目に、原発でつくった電気を買う電力小売事業者に費用を負担させる仕組みを想定しており、実現すれば消費者や企業が払う電気料金に原発を支える費用が上乗せされることになる。2020年度末までの創設をめざすが、世論の反発を浴びそうだ。経産省の内部資料や複数の関係者によると、省内で検討されている仕組みは、原発については、発電事業者と電力小売事業者との間で取引する際の市場価格に一定の価格を上乗せすることを認めるものだ。原発を温室効果ガスを排出しない「ゼロエミッション電源」と位置づけ、環境への貢献で付加価値をもたらしている、との理屈だ。発電事業者は原発の電気をより高い価格で買ってもらえるため収入が増える。これが事実上の補助金になるという想定だ。モデルにするのは、米国のニューヨーク州が導入する「ゼロ・エミッション・クレジット(ZEC)」という制度で、原発の電気について市場価格への上乗せを認める。経産省が検討を進める背景には、東京電力福島第一原発事故を受けた規制基準の強化で安全対策費用が高騰し、原発でつくった電気の価格競争力が低下していることがある。それでも政府は原発を「ベースロード電源」と位置づけ、30年度の電源構成に占める原発の割合を20~22%に引き上げる目標を掲げており、特別扱いしてでも原発の競争力を維持するねらいがある。政府は30年度から、電力小売事業者に原発や再生可能エネルギーなどの「非化石エネルギー源」の電気を販売量の44%にするよう義務づける。小売事業者は、補助制度で原発の電気が割高になっても、一定程度は買わざるを得なくなる可能性がある。その負担は基本的に消費者や企業に回ることになる。だが、こうした制度は「原発の電気は安い」としてきた政府の従来の説明と矛盾する。原発事故後、再稼働に反対する世論は賛成の倍近い状況が続いており、経産省の思惑通りに実現するかは見通せない。 ■競争力あるなら政府支援いらぬ 元原子力委員会委員長代理で長崎大核兵器廃絶研究センター長の鈴木達治郎さんの話 経済産業省は今でも数値を示して、原発は競争力があると言っている。原発に競争力があるなら政府の支援はいらないはず。2050年までに温室効果ガスを80%削減するために支援の必要性を示すなら、長期目標を達成する明確な道筋を示してからだ。
| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 02:53 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2018,05,23, Wednesday
(1)皇后の養蚕と現代科学の融合はいかが?
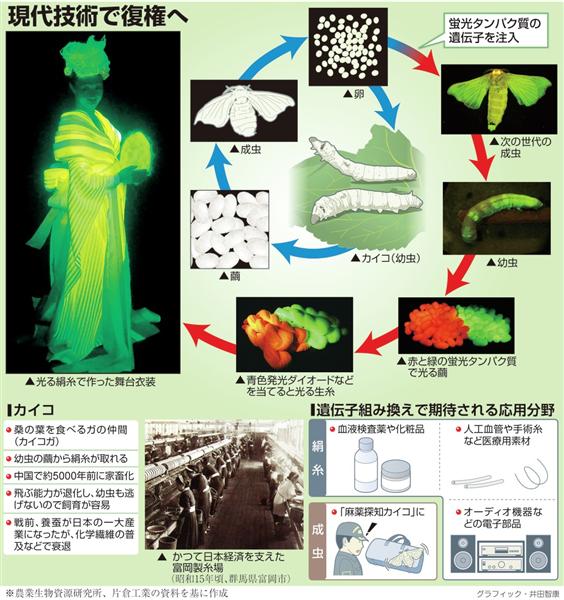 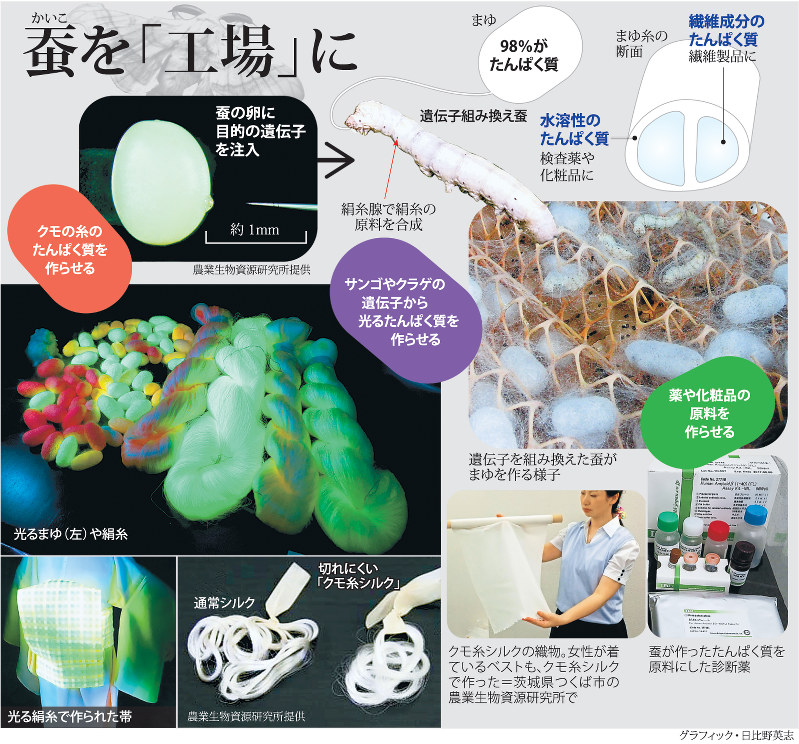  2014.11.3産経新聞 2016.2.25毎日新聞 できた光る繭と絹糸 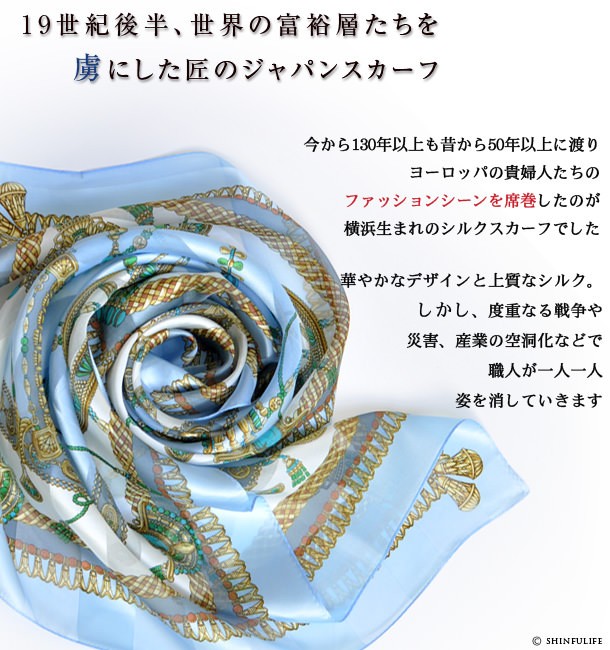     日本の絹のスカーフ 絹シフォン、友禅染のスカーフ 明治時代の養蚕は、良質の生糸を大量に輸出して「外貨獲得産業」となり、日露戦争の軍艦はじめ近代兵器は絹糸の輸出による外貨で購入されたといっても過言ではなく、日本の近代化(=富国強兵)の礎を築いた。そのため、皇居の養蚕は、*1-1のように、明治天皇の后だった昭憲皇太后が産業奨励のために始められ、歴代の皇后に受け継がれて、現在は美智子皇后がやっておられ、来年の天皇陛下の退位後は、雅子妃殿下に引き継がれるそうだ。 しかし、雅子妃殿下に引き継がれるのなら、明治時代と同じやり方を引き継ぐのではなく、この際、*1-2の「遺伝子組み換えの光るカイコ」を、*1-3のような飼育方法で年間を通じて飼育し、品質が高くて色あせしない生糸から、上品でおしゃれなスカーフを作り、「Empress Masako」というブランドで皇居に来た人に差し上げると、記念になってよいと思う。 外国の賓客や日本に赴任して挨拶に来た外交官やその婦人などは、驚いて世界にこの生糸を宣伝してくれることは間違いなく、単に同じことを続けるのではなく日本の産業を振興することが、昭憲皇太后はじめ明治時代の人が意図したことだったと思われる。そして、もちろん紅型・友禅染・江戸小紋・その他の柄で、他の一般業者も暗いところでライトが当たると光るスカーフなどを、高すぎない価格で、オリンピックまでに作れば、売れる大きなチャンスになるだろう。 (2)種子や製造方法の特許権について 上の蚕の品種や育て方に特許権があることには誰も異論がないと思うが、*2-2のように、種子法が廃止されたのには驚いた。何故なら、これまで作られた種子には特許権があり、日本の農業の50%以上は良質な種子で支えられており、良質な種子は国民の財産だからだ。 しかし、品種改良を国主導ではなく民間が行うようになると、地域毎に異なる気候に合わせた種子ができる筈はない。何故なら、佐賀県のコメが高温障害でできにくくなった時に種子を改良して2~3年で特A評価を得られる品種ができたのも、近年のトマトやカボチャやとうもろこしが非常に美味しいのも、地域の地道な品種改良があってのことで、地域ブランドになる少量品種の品種改良を民間企業はやらないからである。 さらに、*2-3のように、種苗の自家増殖を原則禁止するなど、農水省は種苗会社の利益のために農家をやりにくくしているように見える。何故なら、例えば、みかん農家は、より美味しい品種を作ろうと工夫を重ね、農家が作った美味しい品種も多数あるからで、優良品種の海外流出を防ぐことが狙いなら、新品種を作った人が特許権をグローバルにとりやすくすればよいからだ。そのため、農水省は世界特許を容易に取れるシステムを世界で作るべきなのであり、種苗の自家増殖を原則禁止するのは、日本の農家をやりにくくする逆の政策である。 また、*2-1のように、日本の平均気温はこの100年で1.19度上昇したそうで、日本農業新聞は「温暖化への備えに、新技術や資材を生かそう」と呼び掛けている。確かに、新品種の開発やヒートポンプ・ハウス内環境制御装置の利用などの資材の進歩は素晴らしいが、私は気温が高くなることは日本の農業にとってはマイナスばかりではないと考える。何故なら、東北の冷害はなくなり、北海道の米も美味しくなったし、高温でこれまでの作物が作れなくなった地域はより暖かい地域の作物に転作したり品種改良したりすれば、獲れる作物の種類と量が増えるからだ。消費者は、多種の作物が近くで獲れた方が嬉しいのである。 (3)農業と環境 森林を壊してコンクリートの工業地帯を作ると、光合成をしないためCO₂(二酸化炭素)を吸収してO₂(酸素)を作る機能がなくなり、土壌がないため保水力もなくなり、環境に悪いことは明らかだ。それに対し、森林を壊して農業地帯を作った場合は、生物多様性は少なくなるが、光合成をするためCO₂を吸収してO₂を作る機能は残り、土壌があるので保水力も維持される。これが、工業と農業の環境に与える負荷の差である。 さらに、*3-2のエコファーマーのように、田んぼの生き物調査を行い、天敵を活用する農業を普及し、有機肥料を使って、農薬や化学肥料を減らして土づくりを進める農業者は、より生物多様性を保全し、環境を壊さない農業を行うことができ、生産物の味や栄養にも深みがある。そのため、エコファーマーの認定を受けると交付金が支払われる制度になっていたのだが、今回の農薬や化学肥料の削減を求めない「グローバルGAP」への誘導は、この点で後退なのだ。もちろん、輸出するにはグローバルGAPの認証が必要だが、環境保全型で価値ある農産物を作るエコファーマーも優遇すべきだろう。 そして、*3-1のように、持続可能な社会づくりを促すためには、産業における農業の役割は重要で、そのゴールとなる目標は「飢餓と貧困をなくす」「全ての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」「陸と海の豊かさを守る」「クリーンなエネルギーを」「つくる責任・つかう責任」などで、直面する課題への共通認識がある。私も、これらは大切なことだと思うが、日本政府の農協改革は事業弱体化の方向で進められており、改悪政策は問題だと考える。 また、メディアは「新自由主義」を批判の言葉としてよく使うが、「新自由主義」の明確な定義は不明だ。現代では、日本国憲法にも記載されているとおり、「自由」は紛れもなく重要で、不自由や拘束される方が良いと思う人はいない。また、市場原理は、競争に基づく現在の経済現象を説明するツールであり、これを批判すれば共産主義や配給制がよいのかということになるが、これらは頑張って働く動機付けをなくすため歴史的に失敗してきた経済制度である。さらに、「格差」のみを取り上げて問題視する人もいるが、全員が上に合わせることは不可能であるため、全員が下に合わせて貧乏になれば格差はなくなるが、それでよい筈はない。 なお、市場原理の中にあっても、原発などで環境を破壊すれば、*3-3のように、取返しのつかない大きな損失を負って持続可能でなくなり、経済は破綻する。従って、環境は、市場原理と併立して、(“外部不経済《経済学用語》”にしておかず)環境維持コストを経済に組み込んで維持すべきなのである。 <皇后陛下の養蚕と現代科学の融合> *1-1:http://www.yomiuri.co.jp/national/20180521-OYT1T50073.html (読売新聞 2018年5月21日) 皇后さま、最後の「給桑」…雅子さまが引き継ぎ 皇后さまは21日、皇居内の紅葉山御養蚕所で、蚕に桑の葉を与える「給桑きゅうそう」をされた。養蚕所では日本純産種の「小石丸」など3種類の蚕を飼育。皇后さまは小石丸に桑の葉を与え、葉を食べる音に耳を澄まされていた。この日は、蚕が繭を作る場所となる「藁蔟わらまぶし」を編む作業が公開され、皇后さまは「リズムが出ると楽しいですね」と話されていた。皇居の養蚕は明治天皇の后きさきだった昭憲皇太后が始め、歴代の皇后に受け継がれており、来年の天皇陛下の退位後は皇太子妃雅子さまが引き継がれる。 *1-2:https://www.sankei.com/life/news/141103/lif1411030034-n1.html (産経新聞 2014.11.3 16:40) 遺伝子組み換えカイコ 「光るドレス」、医療に応用も 養蚕業の再興へ研究本格化 カイコの遺伝子を組み換えて、従来の絹糸に代わる新たな需要を創出する研究が本格化している。「光るドレス」や医療材料など幅広い分野で応用が期待されており、大量飼育を目指す実験も始まった。衰退の一途をたどってきた養蚕業が、遺伝子組み換え技術で再興する可能性が出てきた。 ◆日本に強み カイコは「カイコガ」というガの仲間。幼虫は桑の葉を食べて体長7センチほどに成長し、口から長さ計1・2キロほどの絹糸を出して繭を作る。野生の「クワコ」が先祖で、約5千年前に中国で家畜化されて分かれた。絹糸は高級品として重用され、明治以降に日本の主要な輸出品となり近代化を支えた。だが戦後は化学繊維の普及や安価な中国製の台頭で養蚕業は衰退を続けている。こうした中、農業生物資源研究所(茨城県つくば市)は2000年、卵に穴を開け、他の生物の遺伝子を注入することでカイコの遺伝子組み換えに初めて成功した。遺伝子が生殖細胞に組み込まれると、次世代の一部は全ての細胞に目的の遺伝子が組み込まれたカイコとなり、その性質が代々、受け継がれる。カイコは餌を探す能力がなく、成虫は飛べないので逃げ出すことはなく、扱いやすい。短期間で成長し、タンパク質でできた絹糸を効率よく作るため、目的の遺伝子を組み込めば、優れた性質の絹糸やタンパク質を大量に得られると期待される。同研究所の瀬筒秀樹ユニット長は「日本は養蚕業が盛んだったので、飼育のノウハウや研究の蓄積があるのが強み」と強調する。 ◆11色の絹糸 同研究所ではクラゲやサンゴなどの蛍光タンパク質の遺伝子をカイコに組み込むことで、緑、赤、オレンジなど11色の光る絹糸を作製。青色発光ダイオード(LED)などの光を当てると美しく光るのが魅力で、婚礼用や舞台用などのドレスが試作された。また、遺伝子組み換えで光沢のよい極細の絹糸を開発。クモの遺伝子を注入することで、切れにくいクモの糸のような強い絹糸を作ることにも成功した。組み換え技術の手法も改良が進んでいる。従来は目的の遺伝子をゲノム(全遺伝情報)のどこに入れるか制御できず、効率が悪かったが、近年は特定の遺伝子を破壊したり、別の遺伝子に置き換えたりする「ゲノム編集」の研究が進展し、多様なカイコを効率良く作れるようになった。遺伝子組み換え動物は生態系に影響を与える恐れがあるため通常、厳重に閉鎖した環境でしか飼育できない。これでは農家への普及は難しく、大量生産できない。このため同研究所は国の承認を得て今年7月、組み換えカイコを養蚕農家と同様の状態で飼育し、問題がないかを確かめる実験を始めた。 ◆麻薬も探知? 組み換えカイコは絹糸から取り出したタンパク質の利用も進んでおり、血液検査薬や化粧品が既に実用化している。細くて血栓ができにくい人工血管や手術糸などの開発や、電子部品のコンデンサーに使ってオーディオ機器の音質を高める構想もある。成虫を生きたまま利用することも考えられる。雌のフェロモンに反応する雄の遺伝子を別の遺伝子に置き換えると、雄は臭いや光、熱に反応して羽をばたつかせる。この性質を利用すれば、例えば麻薬の探知に役立つ可能性がある。麻薬探知犬のような訓練や世話は不要だ。食品のカビや有害物質を検知したり、人間の呼気をかがせて病気を見つけたりするアイデアも。マウスなどに代わる実験動物として、ヒトの遺伝子を入れたカイコを使う研究も進んでいる。養蚕農家は数が減少している上、高齢化で後継者難を抱えている。瀬筒氏は「養蚕業を再興させるには、組み換えカイコの実用化を急ぐ必要がある」と指摘する。米国や中国の研究水準も高く、競争は激化しているという。今年6月には旧富岡製糸場(群馬県富岡市)が世界文化遺産に登録された。日本の絹産業が見直される中、養蚕が最先端の技術で復権できるか注目される。 *1-3:https://www.sankei.com/region/news/160728/rgn1607280005-n1.html (産経新聞 2016.7.28) 山鹿市で無菌の大規模養蚕工場起工式 無菌状態で蚕を育て高品質のシルク原料を生産する養蚕工場の起工式が27日、熊本県山鹿市で開かれた。熊本市の求人広告会社「雇用促進事業会」が養蚕事業に新規参入した。同社は「大手商社を通じてシルク生地にし、欧州の高級ブランドへの売り込みも図りたい」としている。国内最大の産地である群馬県の生産量に匹敵する年間約50トンの繭の出荷を目標とする。雇用促進事業会は参入に当たり新会社「あつまる山鹿シルク」(熊本市)を設立した。23億円をかけて約4200平方メートルの平屋建て工場を建設する。来年3月に完成予定で、飼料に使う桑の畑約25ヘクタールも確保した。蚕は病気に弱いが、この工場では温度と湿度を蚕に最適な状態にした無菌室で飼育する。桑を原料にした人工飼料を成長段階に応じて量を調整しながら与えると、年間を通じて品質の高い繭が生産できるという。あつまる山鹿シルクの島田俊郎社長は記者団に「この工場の繭からは、色あせしない生糸ができる。熊本からのシルクロードを世界につなげていきたい」と述べた。 <種子・製造方法の特許> *2-1:https://www.agrinews.co.jp/p44130.html (日本農業新聞論説 2018年5月21日) 温暖化への備え 新技術や資材生かそう 気象庁によると、日本の平均気温はこの100年で1・19度上昇した。特に1990年代に入り、高温の年が増えた。温暖化の影響をどの産業よりも大きく受ける農業。地球規模で加速する温度上昇を見据え、環境制御など最新の技術や装置、品種などを駆使して対抗できる生産基盤を整えたい。2017年の年平均気温は、1981~2010年の平均に比べ0・26度高かった。わずかな上昇幅に見えるが、温度で栄養成長や生殖成長を切り替える植物にとっては大きな変化だ。また、農作物の収穫時期や収量には積算温度が大きく影響する。わずかな温度上昇でも積もり積もれば収穫の前倒しなど生産計画の狂いを生む。今春の野菜価格の下落も、気温の変動にうまく対応できなかったことが大きな要因だ。夏の暑さが際立つ温暖化だが、最も気候変動が激しいのは冬だという指摘もある。狭い範囲で大雪が降る地域があれば、積雪が減った地域も増えている。厳しい寒波の到来もあるが、長期的には冬の気温が高まりつつあるため、一定の低温が必要な果樹で休眠打破がうまくいかない、施設園芸やトンネル被覆の開閉の見極めが難しく作物の生育不良を招くといった影響が出ている。地球規模で起きる気候変動を抑えることは難しい。一方で、施設園芸を中心に環境制御技術が大きく進化している。重油高騰を受けて、導入が進んだヒートポンプは冷房機能があるため、夏の遮熱対策に有効だ。熱を吸収する被覆フィルムや、保温効果の高いフィルムなども市販化されている。ハウス内の温度、湿度、日射量、かん水量などを総合的に管理する環境制御装置も、スマートフォンの利用で扱いやすくなってきた。露地でも遮熱効果や保湿効果の高い被覆資材が相次いで開発された。耐暑性や耐寒性など機能性を強めた品種も多く育成されている。10年前と比べて、異常気象への対抗策は増えたといえる。篤農家と呼ばれている人に共通しているのは、気象を読み取る力だ。天候の変化を誰よりもいち早く感じ取り、栽培管理に生かしている。気象では、“観測史上最高”という言葉をよく耳にするようになった。温暖化の影響でこれまでの常識を超えた異常気象が頻発する時代である。天候の変化をいち早く察知し対応する力が農業者に求められる。篤農家が経験と技で身に付けた天候の予測は、気象や栽培データの「見える化」で補うことが可能になってきた。気象庁が出した7月までの季節予報では、気温は高く推移するとみられる。目前に迫る夏を乗り切る対策も重要だが、長期的な視野に立って、環境制御技術の深化や品種開発など総合的な対策が望まれる。指導機関やJAも一体となって、最新技術や資材などの活用を進めたい。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p44066.html (日本農業新聞 2018年5月14日) 種子法廃止への懸念 品種改良は危機管理 農林中金総合研究所客員研究員 田家康 米や麦、大豆の優良種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた主用農作物種子法(種子法)が4月1日をもって廃止され、70年近い歴史に幕を下ろした。規制改革の一環で、品種改良を国の主導ではなく、民間活力を利用して官民一体で行う趣旨という。だが、米などの品種改良は農業におけるセーフティーネット(安全網)であり、国家の危機管理からの視点も必要ではないだろうか。米の品種を巡る歴史は長い。『万葉集』編さんに関わった歌人の大伴家持が「早田」という表現で、早稲を歌っている。平安時代中期の『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』には早稲(わせ)・中稲(なかて)・晩稲(おくて)という登熟期による区分けもある。 ●用途別に多様化 天候への耐久性、酒造などの用途別といった品種の多様化は鎌倉時代以降から見ることができる。中国から渡来した「大唐米(たいとうまい)」は干ばつに強いとされ、山陽地方を中心に普及した。国内産では酒造用の早稲や多収性の品種など用途別に多様化が進んだ。良い品種といっても、干ばつや冷害に強い品種、収穫量の多い品種、食味の良い品種などさまざまある。そして、こうした性質は往々にして相いれない。江戸時代に東北地方を中心に天明の飢饉(ききん)、天保の飢饉などの大冷害が起きたが、その背景には品種の選択があった。津軽では味が悪いものの冷害に強い赤米があったが、領主も農民も作況が良ければ豊作が約束される晩稲の「岩山」の栽培にこだわった。明治時代以降も冷害が何度も繰り返され、耐冷性があり、収穫量の多い品種の開発は国家的な課題であった。冷害に強い「陸羽132号」は1921年、秋田県にあった国立農事試験場陸羽支場で育成された日本初の人工交配による優良水稲で、戦後まで長年、作付面積トップの座を占めた。「陸羽132号」をさらに改良して誕生したのが「水稲農林1号」。「水稲農林1号」と「水稲農林22号」を掛け合わせて育成された「コシヒカリ」は、偶然にも良食味品種の代表になり今日に至っている。 ●進行する温暖化 大気中の温室効果ガス増加による温暖化は、今世紀末には一層進行するだろう。登熟期に高温になると背白粒が増え、1等米比率の減少が見込まれるため、新品種開発が課題となっている。農水省は研究プロジェクトを公募しているが、委託先のほとんどが国立大学や県の試験場である。収量が多く食味が優れる品種であれば、すぐにビジネスとして成り立つだろう。だが、年々の気温の上下動は大きく、地球温暖化による気候の変動はいつどのような形で顕在化するかも分からない。品種改良とは、将来の異常気象に備える農業生産におけるセーフティーネットであり、危機管理の視点が必要となる。これは民間の知恵で解決できる問題ではない。種子法の廃止が、品種改良への国や各県などの関与を緩めることがないよう心から願うばかりだ。 <プロフィル> たんげ・やすし 1959年生まれ。農林中央金庫森林担当部長などを経て、農林中金総合研究所客員研究員。2001年気象予報士資格を取得し、日本気象予報士会東京支部長。日本気象学会所属。『気候で読み解く日本の歴史』などの著書。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p44074.html (日本農業新聞 2018年5月15日) 種苗の自家増殖 「原則禁止」へ転換 海外流出食い止め 法改正視野、例外も 農水省 農水省は、農家が購入した種苗から栽培して得た種や苗を次期作に使う「自家増殖」について、原則禁止する方向で検討に入った。これまでの原則容認から規定を改正し、方針を転換する。優良品種の海外流出を防ぐ狙いで、関係する種苗法の改正を視野に入れる。自家増殖の制限を強化するため、農家への影響が懸念される。これまで通り、在来種や慣行的に自家増殖してきた植物は例外的に認める方針だが、農家経営に影響が出ないよう、慎重な検討が必要だ。自家増殖は、植物の新品種に関する国際条約(UPOV条約)や欧米の法律では原則禁じられている。新品種開発を促すために種苗会社などが独占的に種苗を利用できる権利「育成者権」を保護するためだ。一方、日本の種苗法では自家増殖を「原則容認」し、例外的に禁止する対象作物を省令で定めてきた。その上で、同省は育成者権の保護強化に向け、禁止対象を徐々に拡大。現在は花や野菜など約350種類に上る。今後は自家増殖を「原則禁止」し、例外的に容認する方向に転換する。そのため、自家増殖禁止の品目が拡大する見通しだ。同省は、今回自家増殖の原則禁止に踏み込むのは、相次ぐ日本の優良品種の海外流出を食い止めるためと説明。自家増殖による無秩序な種苗の拡散で、開発した種苗業者や研究機関がどこまで種苗が広がっているか把握できないケースも出ているという。中国への流出が問題となったブドウ品種「シャインマスカット」も流出ルートが複数あるとされる。民間企業の品種開発を後押しする狙いもある。2015年の品種登録出願数は10年前と比べると、中国では2・5倍に伸びているが、日本は3割減。日本の民間企業は野菜や花の品種開発を盛んに行うが、1本の苗木で農家が半永久的に増殖できる果樹などへの参入は少ない。このため同省は、育成者権の保護強化で参入を促す。仮に自家増殖を全面禁止にすれば、農業経営に打撃となりかねない。同省はこれまで、農家に自家増殖の慣行がある植物は禁止対象から外し、農業経営への影響も考慮してきた。今回の原則禁止に当たっても、一部品種は例外的に自家増殖を認める方針だ。自家増殖の原則禁止は品種登録した品種が対象。在来種のように農家が自家採種してきたものは対象外で、これまで通り認められる。昨年政府がまとめた知的財産推進計画では、自家増殖について「農業現場の影響に配慮し、育成者権の効力が及ぶ植物範囲を拡大する」と掲げている。 <農業と環境> *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p44040.html (日本農業新聞論説 2018年5月11日) 国連・持続可能目標 協同活動で貢献しよう 地球と人類がこの先も続くように、国連が各国に産業や暮らしの変革を呼び掛けている。食・農・環境・教育・福祉などの分野で17目標を設定し、持続可能な社会づくりを促す。どれも日本の協同組合が取り組む課題だ。国際協同組合同盟(ICA)も目標達成に全面的な貢献を約束する。協同活動の今日的意義と役割を再認識しよう。正式名は「持続可能な開発目標」(SDGs=エスディージーズ)。2015年の国連サミットで採択された。30年を期限とし「2030アジェンダ」とも呼ばれる。ゴールとなる目標は17分野169項目。「飢餓と貧困をなくそう」「全ての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」「陸と海の豊かさを守ろう」「クリーンなエネルギーを」「つくる責任・つかう責任」など直面する課題への共通認識から生まれた。世界を変え、救う処方箋といえる。注目すべきは、協同組合活動との親和性の高さだ。国連教育科学文化機関(ユネスコ)が、協同組合を無形文化遺産に登録した主な理由は、社会的問題への解決能力であった。中でも日本の協同組合、とりわけ総合事業を展開するJAは、その先駆的な役割を果たしてきた。昨年11月のICA総会では、SDGsに積極的に取り組むことを確認し、「協同組合の存在感を高めていく」(グアルコ会長)とした。また、今年の国際協同組合デー(7月7日)のテーマを「持続可能な消費と生産」に設定し、国連目標へのより積極的な貢献を打ち出す。SDGsで日本の推進役を担うのが、JAや生協、労協などの協同組合を横断的につなぐ連携組織として今春生まれた「日本協同組合連携機構」(JCA)だ。先日の公開研究会でもこのテーマを取り上げ、協同組合の果たす役割と意義を再確認した。特に、国連目標をそれぞれの協同組合組織の活動に落とし込み進化させること、協同組合間同士の連携を深めることが再確認された。同研究会でJAふくしま未来の菅野孝志組合長は「農業を基軸とする持続可能な地域づくり」を提起。「JAの活動は国連の定めた17目標に全てつながっている」とし、地域、農業、暮らしを守る運動の重要性を訴えたが、同感である。まさに総合事業だからこそできる地域貢献の姿がそこにある。残念なのは日本政府の取り組み方針だ。協同組合との連携に触れているが位置付けが弱い。しかも一連の農協改革は総合事業を弱体化させる方向で進んでおり、世界の潮流と逆行する。市場原理優先の農政改革、原発依存のエネルギー政策、企業視点の働き方改革にも共通する。そこには今日の貧困や格差、環境破壊が新自由主義に起因していることへの反省や洞察はない。持続可能な社会づくりへの大胆な政策転換、強欲な金融資本主義に代わる新たな経済モデルの構築が求められる。 *3-2:https://www.agrinews.co.jp/44059?page=2 (日本農業新聞 2018年5月13日)エコファーマー 環境支払い除外なぜ? 農家疑問の声 GAPありきか ハードル高まる 「見直しはおかしい」。宮城県大崎市で有機栽培や特別栽培による水稲3ヘクタールを経営する佐々木陽悦さん(71)は、方針転換に納得がいかない。田んぼの生き物調査を行い、天敵を活用する農業を普及してきた。エコファーマーで交付金を受けてきたが、現場の努力が後退しかねないと危ぶむ。環境支払いは、地球温暖化防止や生物多様性保全の営農活動を支援する制度。11年度に創設した。交付額は10アール最大8000円。エコファーマー認定が要件の一つだった。今年度から国際水準GAPの研修を受けた上でGAPを実施し、「理解度・実施内容確認書」を提出しなければならない。国際水準GAPには第三者認証の「グローバルGAP」「ASIAGAP」「JGAP」がある。グローバルGAP認証を取得したエコファーマー、北海道洞爺湖町の佐伯昌彦さん(63)は「GAPは否定しないが要件とするには違和感があり、無理やり誘導している感がある」と断じる。GAPは労働安全、食品安全、環境保全など幅広く規定している。だが、農薬や化学肥料の削減は求めていない。一方、エコファーマーは持続農業法に基づき農薬や化学肥料を減らし、土づくりを進める農業者。直接支払いの趣旨と合致する。全国エコファーマーネットワークの香取政典会長は「GAPに取り組むかどうかは農家の経営判断だ」とし、肝心の環境保全型農業が置き去りになりかねないかと心配する。自治体も悩ましい。宮城県登米市は3月末に生産者を集め、制度変更の説明会を開いた。17年度の環境支払い水田は約1200ヘクタール、37組織に上る。市は「制度のハードルが高くなり、そこまでやるのかと身構えてしまう農家が出そう」と、不安を口にする。 ●農水省「導入へ研修など支援」 農水省は要件からエコファーマーを外した理由について、生産者の高齢化などでエコファーマーの認定期間の5年を終えると更新しないケースが増えてきたためとし、「持続可能で環境保全型農業の拡大のためにはGAP導入の方が有益」(生産局農業環境対策課)と強調する。環境支払いは昨年6月、農水省の行政事業レビューで交付要件の見直しが指摘された。同省は「質の高い経営レベルに誘導していくためにGAPに取り組んでもらいたい」とし、GAP研修の予算措置や無料オンライン研修を用意していく。 *3-3:http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201805/CK2018052102000239.html (東京新聞 2018年5月21日) 【社会】福島農業、遠い再建 避難指示地域 農家4割「再開断念」 東京電力福島第一原発事故から七年が過ぎ、福島県では避難指示解除とともに農業再開の動きも広がる。しかし避難中に田畑は荒れ、人手不足や高齢化といった課題は山積している。国などの調査に被災地の農家の四割以上が「再開するつもりはない」と回答し、今後の見通しは厳しい。「先祖代々の田畑が台無しになった。一からのやり直しは考えられない」。南相馬市小高区の横田芳朝(よしとも)さん(73)は、雑草が生えた荒れ地を前にため息をついた。事故前は約五百本のナシの木が茂っていたが、避難中にほとんどが病気になり、昨年すべて切り倒した。「七十五歳までは農業を続けようと思っていたが、これから除染をして、土を耕さなければならない。風評も厳しいし、再開しても見合わない」。かつてはコメも作っており、田植えや稲刈りは隣近所で手伝い合った。しかし事故はそのようなコミュニティーも破壊した。近所で帰還した農家はまばらで「農業は一軒だけではできない」とこぼす。横田さんも長女が暮らす埼玉県に避難中で、戻るかどうか、決心がつかないでいる。農業を再開しても苦労は絶えない。福島県富岡町で仲間と米作りに取り組む渡辺康男さん(67)は「元の景色を取り戻したい一心でやってきた」と話す。避難先の同県西郷村から片道約二時間かけて通う。今年の作付けは約五ヘクタールで、事故前の四分の一にとどまる。悩みはイノシシなどの鳥獣による被害。避難中に人里に慣れ、人間を恐れることなく田畑を荒らし回る現状は「動物天国」だという。電気柵で囲ってもイノシシは侵入し、平気で田んぼで水浴びをしたり、稲を引っこ抜いたりする。困難続きの日々だが「自分の経験を伝えることで、再開を迷っている人を少しでも後押しできれば」と願う。国や県、地元企業でつくる合同チームの調査によると、事故で避難指示が出た十二市町村の農家約千人のうち、42%が「再開するつもりはない」と回答している。高齢化や地域の労働力不足、古里への帰還を諦めたことが理由に挙がった。チームの担当者は「若い担い手の帰還が見込めず、再開に踏み切れない農家が多い」と分析している。 <農業の近代化とその資金> PS(2018年5月25日追加):農業は、*4のように、集落営農組織の法人化が進んでおり、高齢化してもそれぞれの構成員に役割を与えながら持続可能な経営体でいられる準備ができつつある。法人化のメリットは、①多数決でよいため意思決定が早く ②規模拡大して ③人材や資金の確保がしやすい ことである。法人化のメリットは、水産業についても同じだろう。 *4:https://www.agrinews.co.jp/p44061.html (日本農業新聞論説 2018年5月13日) 集落営農の法人化 総力挙げて経営安定を 集落営農組織の法人化が進んでいる。農水省の調査によると、法人率は34%で10年以上伸び続けている。しかし法人化がゴールではない。経営を軌道に乗せることが重要だ。地域農業を担う持続可能な経営体の育成に向け、JAや行政が継続的に支援すべきだ。2018年2月現在で集落営農数は1万5111。地域別では水田農業の比重が高い東北3344件が最も多く、九州2415件、北陸2383件と続く。数はほぼ前年並みだが、農事組合法人などの法人数は5106件、前年より413件増えた。法人化率は初めて30%台を突破した17年を上回った。法人化が進む背景の一つとして、人材確保の有利性が挙げられる。同省の調査では、30ヘクタール以上を集積する法人は全体の4割を占める。高齢化でリタイアする人たちの農地の受け皿役を果たしている。だが、オペレーターと呼ばれる作業者の高齢化も進む。将来に渡って組織を存続させるには次世代の人材が必要だ。そのためには社会保障などの雇用条件を整えることが必須で法人化を選ぶ。法人化には農地集積への合意形成や登記、定款策定など、やらなければならない事務作業が多い。行政やJAのサポートも法人増加の背景にある。しかし、法人化が済めば地域農業の抱える課題が解決するわけではない。経営内容を充実させ、将来に渡って組織が存続するようにしなければならない。秋田県大仙市の農事組合法人・新興エコファームは、水稲にエダマメなどの園芸品目や野菜加工を組み合わせて収入を確保し、地元農家から引き受けた50ヘクタールを維持する。作業が重複する品目もあるが、農家間で人員を融通するなど工夫を凝らす。農地集積が進み、経営面積は設立当初と比べて20ヘクタール増えた。同法人の役員は「今後も農地は集まる」との考えから、若手の人材育成を重視。20~40代の3人を雇い入れた。法人経営の安定には役員の手腕が大きいが、当事者任せにしてはならない。経営を長持ちさせるためには、高齢の農地提供者も何らかの形で経営に関わり、「自分たちの組織」という意識を持たせることが重要だ。「少数精鋭」では限界がある。野菜作りや直売所、加工品などの多角化を進める上でも女性活用がポイントになる。だからこそ国や県、市町村、JAによる経営支援への期待は大きい。宮城県のJA南三陸は「担い手サポート班」を設け、作物ごとに担当を配置。法人や若手農家らへの支援を充実させ、頻繁に通うことで「あの人に相談すればいい」という関係を築き、経営を下支えしている。技術指導はもとより、労務、税務面の管理や資金調達、実需者とのマッチング、6次産業化の相談・助言など、行政やJAが法人に対し、できることは多い。地域農業の将来像を描く端緒が開けるはずだ。 <農業の6次産業化> PS(2018年5月26、28日追加):*5-1のように、「海外で原材料を安く仕入れて安価な製品を流通させるのではなく、現地が持続的に潤う生産体制を」という考えに基づくファッションブランドがあるそうで、よいことだと思う。そして、これは農林漁業の6次産業化と同様、原料を安く販売するよりもそれに加工を加えて販売(輸出)すれば、そのための雇用が発生し、技術が育ち、特に女性の賃金獲得に貢献する。しかし、これを持続的に行えるためには、善意や倫理だけではない本当の市場ニーズを満たす商品を作る必要があり、それには、①デザイン ②品質 ③コスト で世界と勝負できる製品を作らなければならない。 それには、バッグや小物なら、単に流行にとらわれないだけではなく、本当によいデザイン(エチオピアの製品なら、アフリカの太陽の下での明るい原色を使った製品やアフリカの自然を思い出させる図案など、現地の人がデザインしたものの方がエキゾチックで面白いだろう)と品質を追究すべきだ。そして、これは、鹿・山羊・羊等の皮がある日本も同様である。 また、中米グアテマラの極彩色で緻密な手織りである「コルテ」なら、それを自動織機で生産して、新しくデザインの良いものを高すぎない価格で販売できるようにした方が、現地の人のためにもよいと思われる。これは、日本各地に伝承された優れた織物や染色についても同じだ。 なお、日本では、*5-2のように、これまで保護してきた野生鳥獣が増えて、農林業への鳥獣害が深刻化する状況になったため、狩猟ビジネス学校もでき始め、良質の肉や皮を手に入れることが可能になりつつある。      2018.5.25西日本新聞 スキッとおしゃれなスペイン製 フランス製    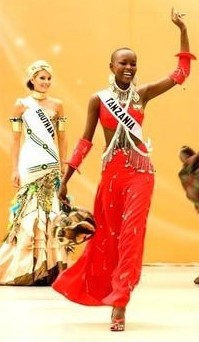  かわいいイタリア製 アフリカの色使いとファッション *5-1:http://qbiz.jp/article/134586/1/ (西日本新聞 2018年5月25日) 「持続可能なファッションを」 2ブランドが福岡市・大名で展示販売会 海外で原材料を安く仕入れて安価な製品を流通させるのではなく、現地が持続的に潤うような生産体制を――。こんな考え方に基づく二つのファッションブランドが、福岡市で26日まで展示販売会を開いている。実用性とデザイン性、そして倫理性(エシカル)を備えた製品が並んでいる。エチオピアで育ったヒツジの皮を使ったバッグや小物を並べているのは「andu amet(アンドゥ・アメット)」(東京)。福岡での展示販売は初めてだ。柔らかくて軽い上に丈夫な「エチオピアシープスキン」は世界有数の高品質な皮革とされる。ただ、現地に加工技術や商品化のノウハウがなく、これまでは欧米の有名ブランドに原皮を提供するのが主だった。青年海外協力隊でエチオピアに赴任した経験を持つ鮫島弘子さんは、「それでは現地に雇用が生まれず、技術も残らない」と2012年、現地で生産体制を整える形でアンドゥ・アメットを立ち上げた。現在、直営の現地工場で働くのは10人。給与はエチオピアの平均的な労働者の3倍程度という。「大量消費の競争に巻き込まれないように、流行にとらわれないデザインを意識している」と鮫島さん。今後も、地方での展示販売会を企画していく方針だ。 ◇ ◇ ◇ もう一つのブランドは、中米グアテマラの民族衣装を再利用した巻きスカートなどを制作している「ilo itoo(イロイト)」。福岡市出身のデザイナー大久保綾さんが12年に設立。今年4月に法人化した。グアテマラの女性が身に着ける巻きスカート「コルテ」は緻密な手織りで、極彩色の模様と丈夫さが特長。大久保さんは服飾を学んだ大学生時代にコルテを知り、グアテマラを訪問。技術力の高さの割に経済的な対価を受け取っていない現地の状況を知った。使われなくなったコルテを現代風に仕立て直して販売すれば、現地が潤う上に技術も継承されると考えたという。「自分たちが織ったコルテが外国で売れることを知ると織り手の女性たちもすごく喜んでくれる」と大久保さん。イロイトが仕立てる巻きスカートは体型を気にせず着られ、妊婦も着やすいという。「一過性ではなく、年月を重ねても着られる。幅広い世代に使ってもらいたい」。目指す姿はアンドゥ・アメットの製品と共通している。 ◇ ◇ ◇ 展示販売の会場は福岡市中央区大名1丁目3−7のサウスステージ1。26日は午前11時〜午後7時。 *5-2:https://www.agrinews.co.jp/p44189.html (日本農業新聞 2018年5月28日) 狩猟ビジネスで学校 捕獲から開業みっちり 千葉県君津市 農林業への鳥獣害が深刻化する千葉県君津市で、次代の捕獲者を育てようと「君津市狩猟ビジネス学校」が始動した。2018年度の1年間、受講者は鹿やイノシシ、キョンの解体、くくりわなの仕掛け方、ジビエ(野生鳥獣の肉)料理店の運営などを総合的に学ぶ。4、5月の入門編を終え、6月から人数を絞り込んで専門編が始まる。同市周南公民館で今月、2回目の講習があった。50人の募集に対し受講者は60人に上り、県外からが3割ほどを占めた。年齢も20~70代と幅広い。市内から参加した春木政人さん(36)は兼業農家で、イノシシの被害に悩まされてきた。「猟や止め刺しをする人が足りない現状で、自分も動かないとまずいと思った。市がいい機会で学校を始めてくれた」と動機を語った。隣接する木更津市でレストランを営む野口利一さん(36)は、一般的な洋食の他に季節のジビエ料理を出す。「店でイノシシや鹿を扱うが、猟師としての視点も欲しい」と、弟の晃平さん(29)と受講した。今回の講習はイノシシの解体。当日朝、公民館近くに仕掛けた箱わなに子どものイノシシがかかり、内臓を取り出す「腹出し」作業から実習した。午後は林業について学んだ。講習を取り仕切る原田祐介さん(45)は「もちろん技術も教えるが、メインではない。いかにお金にするかだ。ビジネスに特化した狩猟学校は初めてではないか」と話す。狩猟に農業や林業を組み合わせ地域で生計を立てられる人材を育てるため、実技だけでなく座学にも時間を割く。原田さんが代表を務める「猟師工房」は、埼玉県飯能市を拠点に狩猟や野生鳥獣の調査研究などを手掛ける。君津市にも解体処理場を置く縁で、市から学校の開校に際して声が掛かった。同市の農作物被害は、16年度で4900万円を超え県内最多。捕獲者の高齢化、担い手不足で駆除が追い付かない。市内には全国的に珍しく獣肉処理施設が3カ所あるが、捕獲物の活用にも限界がある。そこで市は、地方創生交付金を生かし同学校を立ち上げた。来年3月まで全12回を予定する。1、2回目の入門編は50人を募集。6月からの専門編では30人に絞り込む。過去2回の参加者から回収したアンケートなどを基に“本気度”を見定めて人選。プロレベルの解体法や野外活動の知識などを身に付けてもらう。市外からの移住を含めた捕獲従事者をはじめ、多彩な狩猟ビジネスの担い手を育てる構想だ。市農政課鳥獣対策係の岡本忠大係長は「学校で学んだ人がジビエレストランを目指し、市内で取れる肉を使ってもらえれば、有効利用の一つになる」と期待。捕獲増に伴う販路拡大も見据える。 <中食産業について> PS(2018年5月28日追加):共働き世帯・高齢世帯では家事の合理化が必要であるため、全自動洗濯機・乾燥機・食洗機・掃除ロボットなどが役に立っているが、それらをうまく使うには、家・家具・食器・衣類の適応も重要だ。また、コンロも自動調整機能がついて便利になったものの、原材料を買って調理するのは時間と労力を要し、高齢者は火事や怪我のリスクもあるため、中食産業が拡大しているわけである。そのため、*6の中食食品は、単身者・共働き世帯・高齢世帯のいずれの需要も拡大しており、生産者にとっては、加工の雇用が生まれる上、品種改良された穀物・野菜・果物などのタネが出回らないというメリットもある。 *6:https://www.agrinews.co.jp/p44191.html (日本農業新聞 2018年5月28日) 17年中食市場 10兆円突破、過去最高 共働き増え需要拡大 総菜や弁当といった中食市場の拡大が続いている。2017年の市場規模は初めて10兆円を突破。共働き世帯の増加などで、調理済み食品を自宅で手軽に食べるニーズが高い。コンビニエンスストアやスーパーは国産原料などのこだわり商品を投入し、需要を盛り上げる。原料農産物を手掛ける国内産地の仕向け先として、中食が存在感を高めている。 ●共働き増え需要拡大 日本惣菜協会の調査によると、17年の市場規模は前年比2%増の10兆555億円で過去最高を更新。この10年で2割強増えた。業態別に最も伸びが大きいのは「コンビニ」で前年比4%増の3兆2300億円。全体の3割強を占める。店舗数が多く営業時間も長いため、働く女性から高齢者まで、幅広く支持を受けている。「専門店」が1%増の2兆9200億円、「食品スーパー」は3%増の2兆6200億円で、コンビニに比べると伸びは小幅だった。購入品目別では、おにぎりや弁当など「米飯類」が1%増の1兆9800億円で最大。おにぎりはコンビニ各社が新潟「コシヒカリ」を使うなどこだわり商品を投入しながら、値上げに踏み切ったことも背景にある。サラダなど「一般総菜」は2%増の1兆800億円。健康を気遣う人が手軽に野菜を取れるとして、注目している。特に伸びが大きいのは、肉じゃがやハンバーグ、豚のショウガ焼きなどをパックした「袋物総菜」。前年比22%増の4200億円となった。中食市場が伸びる背景に消費者の生活様式の変化がある。厚生労働省によると17年の共働き世帯は1188万世帯で10年で2割近く増え、単身世帯も増加傾向。そのため家庭で調理することが減り、手軽に食べられる総菜需要が広がっている。日本惣菜協会は「国内の人口が減る一方、小売各社は国産素材や機能性を押し出した付加価値商品を売り込んでいる。今後も中食市場の成長は続く」と指摘。国産農畜産物の売り先として、注目度は高まる一方だ。 <運輸業の対応> PS(2018年5月31日追加):「配達が夜に集中すると残業を増やすだろう」と忖度し、なるべく昼の時間帯に荷物が着くように指定すると、受け取り先が留守で再配達になったりする。つまり、女性が普通に働いている時代、「昼間は誰も家にいない」という前提で動かなければ二度手間になるだけであるため、*7のヤマト運輸が、夜間中心の配達要員の確保を急いでいるのは合理的だ。さらに、遠慮なく夜の時間帯を指定できるような「注意書き」が送り状に書かれている方が良いだろう。なお、疲れるため誰もが嫌がる時間帯に勤務する人は、同じ給与でも勤務時間が短いのは当然である。 *7:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180531&ng=DGKKZO31149580Q8A530C1EA1000 (日経新聞 2018年5月31日) 「朝だけ」「夜だけ」勤務OK、JR東が運転士も育児・介護に、ヤマトは再配達に5000人確保 JR東日本は2018年度末をめどに、運転士や車掌が朝のラッシュ時だけ短時間乗務できるよう制度を改める。ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸も12月までに、宅配便の再配達が多い夜だけ働く社員を約5千人確保する。介護などで特定時間帯だけ働きたい社員の希望と、業務が集中する時間帯の人手を確保したい企業のニーズをマッチさせ、人手不足を乗り越えようとする動きが広がってきた。厚生労働省の29日の発表によると、輸送業の4月の有効求人倍率は2.37倍と高く、深刻な人手不足が続く。鉄道乗務員や宅配運転手は資格や経験が必要なためすぐに大量採用するわけにいかず、人手確保のため一歩進んだ働き方の見直しに踏み込む。 ●車掌も対象 JR東は運転士や車掌の勤務体系を見直す一環として、「朝だけ勤務」ができるようにする。親の介護や育児が必要な乗務員を対象とする。今後、労働組合と交渉する。通常、運転士や車掌は平均9~10時間の勤務時間がある。介護や育児などの理由があれば6時間に短縮できるが、電車に乗務できるのは日中だけなどと働き方が限られていた。これを柔軟にする。例えば昼すぎに退社を希望する日は、早朝に出社した上で、ラッシュ時の2~3時間に乗務し、その後、事務作業などをしてから退社できるようにする。夕方だけ、など乗務可能な時間帯も増やす。過去に運転士や車掌を経験した社員も、乗務できるようにする。JR東日本は現在、1日に約1万2千本の列車を走らせており、運転士と車掌が合計で約1万1千人いる。今後、旧国鉄時代に採用した55歳以上の社員約1万4千人の退職が相次ぐが、東京圏への人口流入が続き鉄道利用が増えるため、運行本数は減らしにくい。女性社員の積極採用など、可能な対応策を進める。国会では多様な働き方の実現を目指す働き方改革関連法案の審議が大詰めを迎えているが、深刻な人手不足を背景に企業では先行して取り組みが進む。ヤマト運輸は「アンカーキャスト」と呼ぶ夜間中心の配達要員の確保を急ぐ。19年度までに1万人規模にする計画だ。同社の現在の配達体制は、朝~夕方に配達や集荷、営業を同時にこなす運転手が主力。だが近年はインターネット通販の利用者が不在の場合の再配達が増え、夜間業務に偏り、残業を迫られている。 ●分業で対応 そこで既存のパート・契約社員からの転換や新規採用で夜間配達員を確保し、運転手と分業することで再配達をこなす考え。今春時点では数百人規模だった。12月は歳暮やクリスマス、年末年始の贈答需要で荷物が増える繁忙期となるため、それまでに計画の約半数に上る5千人超まで増やして体制を整える。人手が足りない時間帯を短時間勤務などで乗り切る取り組みは、資格などが必要ない業種や職種で先行している。外食業界では、タリーズコーヒージャパンが17年に2時間から働ける制度を導入。すかいらーくは1日の労働時間を4時間から12時間まで5つのパターンから選べるようにした。4月の全体の有効求人倍率(季節調整値)は前の月と同じ1.59倍で高止まりしている。企業がとくに採用を増やしている正社員は1.09倍と過去最高を更新した。 <欠点を克服せよ> PS(2018年6月3日追加):加賀友禅の色留袖に佐賀錦の帯を締めると、上品で華やかな和装となり、外国で開かれた国際色豊かなパーティーで着たら、ファッションの国フランスの人にも感心された(ただし、私の佐賀錦の帯は母からの借り物)。しかし、現在、これを買うと数百万円などという途方もない金額になり、買うことが困難なほど高価で、手入れも大変な和装は、衰退しつつある。そこで、着物や帯の価値は価格や手間にあるのではなく、ファッションにあるという原点に戻れば、*8のように、①糸を1色しか使わないシンプルな布でも1日に織れるのは7〜8センチで ②使う色の種類が多く、模様が複雑な布になると1日に1センチも織れない というのでは、できあがりがよくても生産性が低すぎて現代の賃金体系では産業として成立しない。が、コンピューター制御の自動織機を使えば、同じパターンを繰り返す織物などは得意中の得意で、模様が「菱」「網代」「亀甲」「鳳凰」などの複雑なものでも、プログラムさえ組んでしまえば色やパターンを変えて迅速かつ正確にいくらでも織れる。私は、佐賀錦や博多帯の糸に光る絹糸などを使って、新しい時代の帯を品質を落とさず安価に作れば売れると思う。  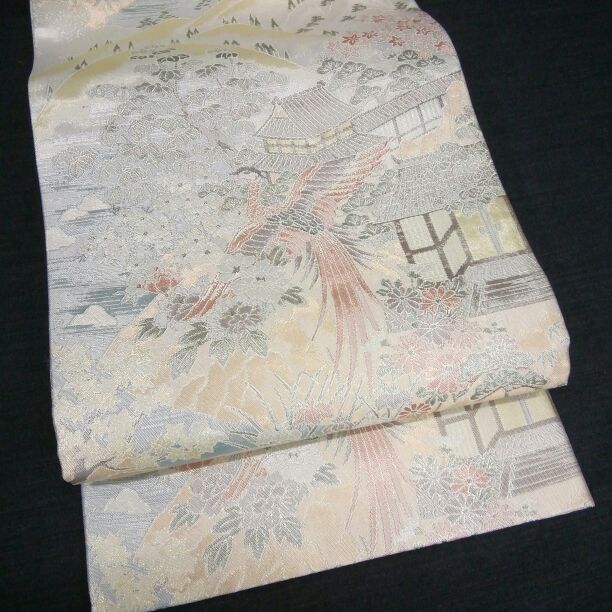    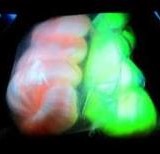 現在の佐賀錦の帯 現在の博多織の帯 光る絹糸 *8:http://qbiz.jp/article/134866/1/ (西日本新聞 2018年6月3日) 繊細 金銀織りなす「佐賀錦」 旧福田家で手織り体験 鮮やかな絹糸と金銀の糸が織りなす模様が、光を反射して滑らかな布に浮かび上がる。佐賀市内の土産物店で、県指定伝統的地場産品の「佐賀錦」を使った小物に目を奪われた。キーホルダー、入れ、ペンダント…。繊細で整然とした模様の全てが、手作業で織られているという。「どのように作るのだろうか。近くで見てみたい」。佐賀市松原4丁目の「旧福田家」で手織り作業の見学や体験ができると知り、訪ねてみた。 ●地道な作業 模様は無限 旧福田家は今年で築100年を迎える和風住宅。近くの「旧古賀銀行」や「旧牛島家」などの歴史的建造物とともに市歴史民俗館として一般公開されている。玄関の引き戸を開けると、畳敷きの部屋に置かれたガラスケースの中に、佐賀錦で作られたバッグや人形がずらり。淡く光沢を放つ作品たちは、家屋の重厚な雰囲気によく映えていた。「佐賀錦はとにかく時間がかかる工芸で、一日に数センチずつしか織り進められない。大きな作品では完成まで1年以上かかるものもあり、大量生産はできません」。この家を拠点に技術の継承や新商品の開発などに取り組む佐賀錦振興協議会の会長、松本美紀子さん(68)が、佐賀錦の歴史や作り方などを教えてくれた。佐賀錦は江戸時代末期、鹿島藩鍋島家の第9代藩主夫人が病床で天井の模様「網代(あじろ)組み」を見て「この模様で日用品を作れないか」と側近へ相談したのを始まりとする説が有力という。城中の女性たちの手習いとして伝承され、明治初期に一度は衰退したが大隈重信の奨励で再興。1910年には英国ロンドンで催された日英大博覧会で「佐賀錦」の名で出品されて有名になった。材料は金銀の箔(はく)や漆などを貼った和紙を1ミリほどの細さに裁断した経(たて)糸と、カラフルに染色した絹の緯(よこ)糸。木製の台に経糸を張り、方眼紙を使った図案通りに経糸を竹のへらで浮かしたり、押さえたりしながら、緯糸を通していく。糸を1色しか使わないシンプルな布でも、1日に織れるのは7〜8センチほど。使う色の種類が多く、模様が複雑な布になると1センチも織れないという。「菱」や「網代」、「亀甲」など伝統の模様はあるが、色やパターンを変えることで模様は無限にできると松本さん。「地道な作業だけど、図案を考えて自分だけの作品ができる。色の組み合わせを変えるだけでも違う趣になるし、変化に富んだ見応えのある作品になります」。手織りを体験させてもらった。会員の女性に教わりながら、細い和紙の経糸をへらで1本ずつ慎重にすくう作業を繰り返す。しかし、へらを通すべき糸と糸の境目すら分からず苦戦。パターン通りになどとても織れない。「そんなに力を入れなくても大丈夫」。アドバイスをもらうが、集中すればするほど手に力が入って糸を切りそうになってしまう。気付けば2〜3段を織るのに40分ほどが経過。やっとのことで数ミリ織った布の目は粗く、模様もばらばらになってしまった。こんなに細かい作業は、相当に器用な人でないとできないのではないか。尋ねると、「手間はかかるが、慣れれば繰り返しの作業。感性や根気があるかどうかの方が大切だと思います」と松本さん。「織り上がれば、作業の苦労が全て報われます」と話す笑顔に、見る人を魅了する佐賀錦のあの輝きは織り手一人一人の情熱と絶え間ない集中のたまものだ、と実感した。月曜日と祝日の翌日、年末年始を除いた日の午前10時〜午後3時に手織り体験を開いている。手織り体験のみは無料、キーホルダーやアクセサリー作りができる有料のコースもある。5人以上での参加は3日前の午後4時までに予約が必要。同協議会=0952(22)4477。 <一般企業の従業員と農作業> PS(2018年6月4日追加):*9のようなボランティアではなくても、一般企業の従業員が農作業を受託すると、食品関係の会社なら原料の製造過程を知る機会になったり、その農家と取引関係ができたり、その他の業種なら普段と異なる体験ができたりするのでよいと思われる。一般企業には余剰人員がいる場合もあるし、人を集める力もあるのではないだろうか?さらに、農水省・経産省・環境省のお役人は、自然や農林水産業の現場を知って改善策を考えるため、農業・林業・水産業の作業を必須の研修科目にすべきだ。 *9:http://qbiz.jp/article/134648/1/ (西日本新聞 2018年6月4日) 「棚田ボランティア」企業が汗 人手不足の農家で従業員が農作業 佐賀県、16年度からの試み広がる 農業の後継者不足が深刻な佐賀県内の棚田で、生産者が地場企業の人手を借りて農作業をする「棚田ボランティア」の試みが広がっている。勾配がある棚田は平地に比べて作業効率が悪く人手が必要なため、企業の従業員に田植えや草刈りを手伝ってもらう。企業側にとっても従業員のリフレッシュや社会貢献につながり、歓迎されているという。7・7ヘクタールの棚田が広がる多久市西多久町の平野地区。19日、多久ケーブルメディア(同市)とIT企業のプライム(佐賀市)の従業員ら約20人が集まり、地元農家から手ほどきを受けて田植えを手伝った。プライムの一番ケ瀬博史総務部長は「屋外で体を動かして気分転換になり楽しかった。社員同士や生産者との親睦が深まった」と話した。棚田ボランティアは、県や市町、生産者でつくる「さが棚田ネットワーク」(事務局・県農山漁村課)が2016年度に始めた。同ネットワークが橋渡し役となり、これまでに25企業・団体と13地域が協定を締結。17年度は延べ426人が計39回活動をした。県農山漁村課によると、05年の調査で、県内の水田に占める棚田の割合は13%。棚田は水田が狭くてあぜが多く、草刈りに手間がかかる。勾配での農作業は「平地に比べて2倍以上の労働力が必要」(同課)という。平野地区の農家でつくる振興協議会の小園敏則会長(71)は「働き手の高齢化が深刻で、棚田での作業は体力の消耗がきつい」と吐露。「若者や子どもがにぎやかな雰囲気で手伝ってくれると元気をもらえるし、棚田米のアピールにもなる」と喜ぶ。さが棚田ネットワークは試みを広げたい考えだが、一部の地域は企業側と連絡や調整をするリーダーがいないなど課題もある。同課の川路勝係長は「市町や生産者の協力を得ながら取り組みを広げていきたい」と話す。 <女性の活躍> PS(2018/6/7追加):政府が、*10-1のように、中小企業に女性が働きやすい環境を整えるため、従業員数101人~300人の企業に女性登用の数値目標を盛り込んだ行動計画を作る義務付けをするのはよいが、食品・織物・保育・介護・家事サービスなどの中小企業で働く女性は多いので、2016年施行の女性活躍推進法が301人以上の企業にのみ行動計画づくりを義務付けたのは変だった。また、役員を含む課長相当職以上の管理職に占める女性比率が2016年度に1割に満たないというのも、人材という資源の無駄遣いであるため、「女性は採用したくない」「女性を男性と同様には昇進させたくない」と答える企業や「働きたくない」と答える女性には、その本当の理由を聞き、そうなった背景を改善することが重要である。 なお、*10-2のように、封建的と思われている農業分野でも前から女性農業者は活躍していたが(10人以下の企業や家族労働が多い)、JA役員や農業委員で女性登用を増やすためには組織リーダーである男性の意識改革をさらに進めなければならないし、女性の能力発揮には、地域をはじめとする社会全体の理解が必要だ。 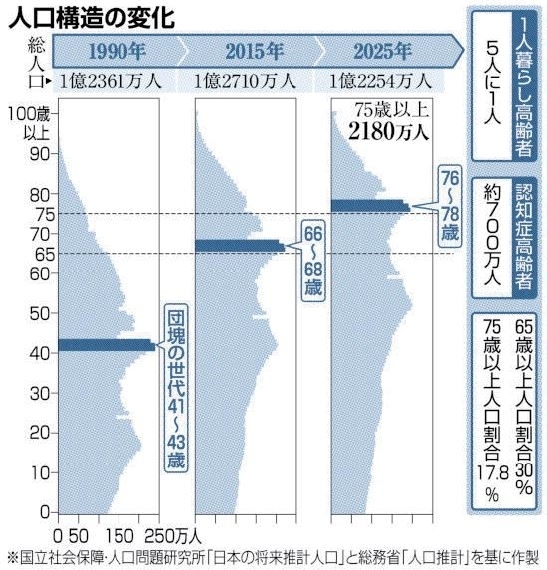    人口ピラミッド 2018.6.8日経新聞 農業女子 大島紬 2018.5.7西日本新聞 (図の説明:人口構成は次第に細長い逆台形になるため、高齢者や女性もできるだけ働く方が健康に良いだけでなく、支える側にいることができる。しかし、女性の場合、左から2番目のグラフのように、努力に比して昇進が遅かったり、職場で不快な思いをしたりすることも多いため、その状況を改善すべきだ。また、農業は機械化すれば女性がカバーできる範囲を増やすことができ、織物も自動化や先端技術の導入で、生産性と付加価値の両方を上げることが可能だろう) *10-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31498220X00C18A6MM8000/?n_cid=NMAIL006 (日経新聞 2018/6/7) 女性の登用計画、中小にも義務付け 政府検討、活躍推進法改正へ 政府は従業員数101人以上300人以下の企業に女性登用の数値目標を盛り込んだ行動計画をつくるよう義務付ける検討に入った。人手不足が深刻な中小企業に女性が働きやすい環境を整えるよう促すのが狙いだ。2019年にも女性活躍推進法を改正し、20年の運用開始をめざす。日本の労働力の見通しは厳しい。15~64歳の生産年齢人口は40年度に18年度比で約1500万人減る見込み。政府は高齢者や外国人が働きやすい環境づくりにも取り組む。女性の15~64歳の就業率は17年に67.4%となり、比較可能な1968年以降で最高となった。将来に向けて女性の労働力はさらに重みを持つ。16年4月に施行した女性活躍推進法は301人以上の企業に行動計画づくりを義務付けた。厚生労働省によると、301人以上の企業のうち届け出た企業は今年3月末時点で1万6千社あまり。全体の99.6%に達した。従業員数30人以上の企業のうち、役員を含む課長相当職以上の管理職に占める女性比率は16年度に1割に満たないが、前年度比で0.9ポイント上がった。上場企業に占める女性役員の比率は17年に3.7%と前年と比べて0.3ポイント上昇し、1500人を上回った。行動計画づくりの義務付けは罰則はないものの、効果は徐々に上がっている。一方、行動計画づくり義務付けの対象外だった300人以下の企業の届け出は約4500社にとどまった。中小企業全体の1%未満だ。日本の企業は中小が99.7%。政府は300人以下の企業にも義務付けの対象を広げ、女性が働きやすい環境づくりを後押しする。行動計画には女性の採用や管理職への起用、育児休業の取得率の向上など数値目標と実現のための取り組みを盛り込む。計画とは別に企業は厚労省が省令で定める14項目のうち1項目以上について、現状の数値を公表しなければならない。女性管理職の比率や、採用者数に占める女性の割合、男女別の育児休業の取得率などだ。みずほ総合研究所の堀江奈保子上席主任研究員は「中小企業にも女性登用の意識は広がりつつあるが、企業によって差がある」と指摘。「一定規模の中小にも義務付ければ、全ての経営者が意識せざるを得なくなり、取り組みが一歩進む可能性がある」と評価する。安倍晋三首相は女性や高齢者など誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の実現を政権の重要課題として掲げる。政府や企業などで20年までに指導的地位に占める女性の割合を30%にする目標を打ち出す。中小が行動計画を作成すれば、女性の働きやすい環境ができるわけではない。政府が達成状況を検証し、その時々で改善を求める作業も必要になる。 *10-2:https://www.agrinews.co.jp/p41934.html (日本農業新聞論説 2017年9月18日) 女性農業者の活躍 能力発揮へ地域の理解 農水省の農業女子プロジェクトのメンバーが9月下旬から、香港でイベントを開く。日本の農産物や加工品をアピールし、輸出の足掛かりになると期待される。こうした女性農業者の活躍が最近、目覚ましい。農業に夢を描き、その実現へ奮闘する彼女たちをもっと支援しよう。家族に加え、地域の理解が欠かせない。思う存分能力を発揮できる環境を整えたい。香港のイベントは27日から10月31日まで。今年1月に続く2回目だ。百貨店やスーパーでの試食PR・店頭販売の他、農業女子が講師となり、自ら生産した農産物を使った料理レッスンを開き、現地レストランで特別メニューを提供する。初回のフェアをきっかけに香港への輸出を始めたメンバーもおり、販路開拓の意気込みは盛んだ。女性農業者の活躍が求められる背景の一つに、農業の6次産業化がある。農業者自身が生産・加工・販売に取り組む形は、これまでの「作れば売れる」から「売れるものを作る」発想への転換が必要となる。女性農業者は、生産者であると同時に家庭を切り盛りする生活者・消費者の視点を持つ。買い物好き、ネットワークづくりに優れた人も多い。そんな彼女たちの感性が、6次産業化を進める上で不可欠だ。生産物の品質はもちろん、消費者ニーズを捉えた加工品開発、見栄えのいい包装、直売やカフェに売り場を広げるなどして顧客の心をつかみ、起業家や経営者としての手腕を発揮する。一方、男性を中心とした農村社会の構図は依然として残る。「夫が経営の収支を教えてくれない」「妻は労働力としか思われていない」といった意見をいまだに聞く。農業女子からさえも「自治体からの通知がないと会合に外出しづらい」との声が出る。活躍する姿の裏に、こうした課題が潜んでいることを見逃してはならない。女性農業者はかつて無報酬労働が当然とされ、子どもの服を買う小遣いすらままならなかった。彼女らは思い切って義父母に要望したり、こっそりと内職をしたりして、わずかでも自由になる小遣いを稼いできた。そんな中で生活改善を進め、家族経営協定を結び、少しずつ地位向上を果たしてきた歩みがある。支えたのは義父母や夫、子どもたちなど家族の理解だ。現在、農業者の高齢・減少化が深刻さを増し、女性農業者の活躍が農村社会の活性化に欠かせなくなっている。これを後押しするには、家族の理解だけでなく、農村社会の中軸であり地域農業に従事する男性の協力が必要だ。JA役員や農業委員で女性登用を増やすため、こうした組織リーダーである男性の意識改革をさらに進めなければならない。政府が女性活躍推進へ積極的に取り組む今こそ、真の意味で女性が輝ける仕組みをつくり上げるべきだ。農業発展の鍵を握る女性たちが、活躍する“芽”を育てていこう。 <補助金頼みは他の国民に迷惑> PS(2018年6月9日追加):*11に、「所有者不明農地が山林化して、現場はお手上げだ」と書かれているが、所有者が死亡して子孫が分からない土地の固定資産税(納税義務者=所有者)は誰が払っているのだろうか?まさか都道府県は、固定資産税が不納になっても放置するような不作為を行っているわけではないだろう。従って、固定資産税が不納になったら督促状を出し、それでも納付されなければ、その土地で物納させれば、その土地は公有財産になる。そのため、九州を上回る推計約410万ヘクタールもの所有者不明の土地を、知事の判断で期限付きなら公益目的で使える特別措置法を作ったというのは、ぬるま湯すぎる。 さらに、方針が決まらなければインフラ整備も進まないので、借り手農家がなければ農業生産法人に貸し、産出物があるのなら道路も作ればよいだろう。つまり、「中山間地の実態とは懸け離れているから・・(補助金を出せ)」というのは他の国民に甘えすぎであり、249ヘクタールもの耕作放棄地をどう利用するかはまず地元が方針を決めるべきなのだ。そして、選択肢は、①放置して林野に戻す(=住民も税収もなくなる) ②放牧する ③みかん・レモン・オリーブ・アーモンドなど適地適作をする など多岐にわたり、規模拡大だけが経営方法ではなく、経営体や労働力の確保にも選択肢は増えたが、経営方針を決めるのは経営者と地元が主体なのだ。 *11:https://www.agrinews.co.jp/p44299.html (日本農業新聞 2018年6月9日) 所有者不明農地が山林化 現場「お手上げ」 所有者不明の農地が増え続け、近隣農家や農業委員会に重い負担となっている。中山間地では山林化した土地が多く調査は難航、所有者が死亡し子孫が分からないケースも多い。農水省は所有者不明の耕作放棄地を知事裁定で農家に貸し出す仕組みを始めた。ただ、開墾が必要な農地も多く「誰が管理するのか」「活用できない農地こそ問題」と切実な声が出る。条件の厳しい中山間地で、所有者不明の農地の問題が深刻さを増す。 ●借り手農家少なく 静岡県東伊豆町 急傾斜地の農地が点在する静岡県東伊豆町。軽トラック1台がやっと通れる細い山道を上り、ミカンを作る楠山節雄さん(69)は「規模拡大や集約化と盛んに言われるが、伊豆の山間地の実態とは懸け離れている」と険しい表情を見せる。同町の耕地面積は249ヘクタール。大半は車が通れない山奥にあり、農家は消毒タンクを背負い山道を何往復も“登山”する。収穫も重労働だ。同町では毎年、農家と役場職員が農地の利用状況を調査する。対象農地は7300筆を超え、地図と照らし合わせる確認作業は時間を要する。登記上は農地でも、山林化した耕作放棄地は相当数ある。その面積は把握できず、多くは所有者も分からない。「現場から言うとお手上げ」(同町農林水産課)の状況だ。同町は2017年、所有者不明の農地889平方メートルを全国で初めて知事裁定し、農地中間管理機構(農地集積バンク)を通じて農家に貸し付けた。同町が戸籍をたどると、所有者は戦後間もなく死亡し、5人の子どもも孫も亡くなっていた。ひ孫まで調べたが、所有者がつかめなかったことから知事裁定に至ったという。雑草どころか雑木が生え、花のハウスの日照を阻害していた耕作放棄地は現在、借りる農家が、かんきつ栽培に向け農地に復元する作業を進める。ただ同町によると、金と手間をかけて耕作放棄地を解消したいとする農家は一握り。農業委員会会長も務める楠山さんは「脚立を真っすぐ立てられないほどの急傾斜の農地ばかりで、高齢で耕作を諦める人が多い。農地を相続するメリットが乏しく、所有者不明の農地は増えるばかり」とみる。政府は6月、登記の義務化や、所有者が土地を放棄する制度を検討する方針を示した。8日に閣議決定した土地白書でも、8割が土地の所有権を「放棄を認めても良い」と回答する。ただ、同町農業委員会の梅原巧事務局長は「放棄後に費用をかけて農地に復旧しても、誰が管理するのか」と不安を募らす。 ●九州超す410万ヘクタール 民間調査によると、16年時点の所有者不明の土地面積は九州を上回る推計約410万ヘクタール。6日の参院本会議では、所有者不明の土地を知事の判断で、期限付きで公益目的で使える特別措置法が成立した。農水省は14年の農地法改正で、所有者が不明の耕作放棄地に知事裁定による利用権を設定し、農地集積バンクを通じて貸し出す仕組みを導入した。同省によると、これまでに4市3町1村で11件4・6ヘクタールの農地を貸し出している。静岡県内では、公示後に所有者が名乗り出た自治体もある。 ●中山間地でより深刻に 中山間地では、活用しにくい所有者不明の農地こそ深刻な課題だ。鹿児島県指宿市の農業委員会会長で、オクラなどを栽培する諏訪園一行さん(78)は「相続未登記農地の追跡調査を重ねてきたが、解決は難しい。法制度を整備しても、解決するのは現場感覚では非常に厳しい」と話す。青森県五戸町農業委員会会長でリンゴ農家の岩井壽美雄さん(67)は「誰も使いたがらない、機械が入らないような狭い農地こそ所有者不明になる。こうした農地を今後どうするのかが問われている」と指摘する。 <ビワ好きからの一言> PS(2018年6月12日追加):私は、高校を卒業するまでは九州に住んでいたため、ビワの季節には毎日のようにビワを食べられたが、大人になって関東に住むようになってからは、高価で年に一度くらいしか食べられなくなった。しかし、果物を食べるのに遠慮しなくてはならない国民は、世界でも少ないだろう。そのため、*12は何とか労働力を確保してビワ作りを続けてもらいたいわけだが、ビワの産地でない地域の人には「ビワは種が大きくて、食べるところが少い」と言われることもある。確かにそうなので、美味しさはそのまま、種なしや種の小さな品種のビワを作れば、さらにビワのファンが増えると考える。 *12:https://www.agrinews.co.jp/p44316.html (日本農業新聞 2018年6月12日) ビワ日本一 でも高齢化進み収量半減 産地どう守る 長崎県 100年の歴史を誇るビワのトップ産地・長崎県で生産基盤の弱体化が深刻だ。生産者の高齢化などで出荷量は10年前の約半分。80歳を超える農家が産地を支えるが、近年は気候変動の影響で1年置きに寒波が襲い、収量減で意欲を削がれた人が徐々にリタイア。瀬戸際にある産地を救おうと県やJA全農ながさきなどが対策に乗り出した。産地復活は、急傾斜地での栽培という課題を克服できるかが鍵を握る。 ●傾斜きつく作業困難 1年置きの寒波追い打ち 県内最大の産地、長崎市茂木地区。急傾斜の園地に高さ3メートル以上のビワの木が並ぶ。農家は脚立を使い、一つずつ幼果に袋を掛けて栽培する。白い袋に包まれた実が出荷を待つ一方、管理されず放置された“裸ビワ園”が増えている。JA長崎せいひ長崎びわ部会の山崎繁好部会長は「放置した木では果実が木の養分を使ってしまい、次期作に影響が出てしまう」と指摘。悪循環に陥る危険性を訴える。同県の出荷量は全国の約3割を占め、全国トップ。しかし急傾斜で作業負担が重く、多い時は700人を超えた部会員は500人まで減った。さらに近年、2年に1度の頻度で低温が襲う。今年1月の寒波では14センチの積雪を観測。直後は大きな被害は確認されなかったが2月以降、幼果の種子が凍死し肥大が進まない果実が多発した。同JAは「肥大せず階級が計画より1、2段階下がった」と肩を落とす。全農ながさきは「今季は豊作だった17年産の8割を予定したが、6割ほどしかない」という。 ●ジュース用に買い取り JAやシェフ活用応援 ビワ産出額の減少を食い止めようと、県は簡易ハウスの導入と優良品種「なつたより」への改植支援、果樹共済の推進を強化。同品種に改植する場合、国が半額助成する改植費に県が1割上乗せする。100年続く産地をどう守るのか。山崎部会長は「寒波の克服には、簡易ハウスの導入が必要。ただ、段々畑でハウスの施工費は高い。共済金の導入や安価な資材を充実してもらわないと産地が消えてしまう」と危機感を募らせる。農家の収入減を食い止めようと、全農ながさきは今季から放任園の果実をジュース用として買い取る考え。腐敗果や未熟果、虫食い以外の果実を1キロ100円で買い取り、系統工場で加工する予定。山﨑部会長は「低木にし果汁専用木を作るなど継続的に出荷できる仕組みを作り産地を守りたい」と力を込める。市内の料理店のシェフらも、産地を支援する。14店舗が協力し、旬に合わせ「びわスイーツフェスタ」を実施した。イタリア料理店「Muggina」のシェフ、鈴木貴之さん(42)が企画。鈴木さんは畑に何度も足を運び、高齢化で荒れた園地を見て心が動いた。「料理人は食材を作る農家あっての仕事。傷物やはねものなどを有効活用していきたい」(同)と意気込む。鈴木さんは、クリームチーズとビワを混ぜたアイスケーキ「茂木びわのカッサータ」を考案した。試作用のビワは同JAなどでつくる「長崎びわ産地活性化推進協議会」が無料で提供した。 ●千葉・鹿児島も2~4割減 農水省によると全国の栽培面積は過去10年で3割減、出荷量は4割減。長崎に次ぐ主産地、千葉や鹿児島でも2~4割減り、各地で荒園や放任園が目立つ。千葉県のJA安房によると急傾斜地で作業する後継者が不足。袋掛けができない荒地にはイノシシが入り、高齢農家を悩ませる。JAは「台風や低温の影響で今季は過去10年で最も少ない」と話しており、情勢は深刻だ。 <外国人労働者とその家族> PS(2018年6月14日):*13-1のように、沖縄県は農業に外国人労働者を受け入れるため国家戦略特区が認定される見通しになったそうだが、*12のビワ農家はじめ、労働力がネックとなって産業の衰退が起こりつつある他の地域や産業にも同じニーズがあると思われる。そして、外国人労働者を受け入れた場合、本人や家族が日本語や日本で必要になる知識を習得するためには、*13-2のような夜間中学・夜間高校などの教育支援が必要であり、このニーズは戦中・戦後の混乱で義務教育を修了できなかった日本人にだけあるのではない。さらに、*13-3の結城紬の「糸取り」など伝統工芸の担い手は、日本人だけでなく外国人労働者の妻もできそうで、この場合、祖国の多様性が魅力的な新製品を生み出すかも知れない。 *13-1:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-728694.html (琉球新報 2018年5月30日) 沖縄県、農業支援に外国人 国家戦略特区 計画認定の見通し 30日に都内で開かれる国家戦略特区会議で、沖縄県が申請する農業支援外国人受け入れ計画が審議される。計画は認められる見通し。特区会議の後、近く開かれる国家戦略特区諮問会議の答申を経て、首相が認定する。特区になれば、外国人の農業就労が認められ、成長基調にある沖縄の農業分野で即戦力人材の確保につながり、関係者は農業基盤の確立や発展に貢献すると期待している。農業支援外国人の受け入れは、即戦力となる技術や語学力を持つ外国人を農業現場に受け入れ、農家経営を支援することを目的とした事業。今年3月に愛知県、京都府、新潟市の3区域が特区に認定された。沖縄県は今年2月に県内で外国人材が必要な品目や時期を調査するなど、準備してきた。県農林水産部の島尻勝広部長は「生産現場の強い要望で申請した。事業を活用して、さらなる農業の成長産業化や競争力の強化が期待できる」とコメントを出した。特区が認定されれば、県は、沖縄総合事務局や入国管理局、労働局を交えた「適正受け入れ管理協議会」を早期に設立。外国人材の受け入れを希望する企業などの「特定機関」を公募する。外国人材は特定機関と雇用契約を結び、特定機関と派遣先の農業経営法人などは労働者派遣契約を結ぶ。外国人は通算3年の期間で、農作業や製造、加工などと付随する作業に従事できる。特区導入を求めてきたJA沖縄中央会の砂川博紀会長は「認定されれば、今後の農業振興・発展に弾みがつくと大いに期待している」と述べた。 *13-2:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-735609.html (琉球新報社説 2018年6月10日) 夜間中学支援再開 教育確保は行政の責務だ 県教育庁は2017年度で打ち切ったNPO法人珊瑚舎スコーレの自主夜間中学校に対する支援について、18年度内に再開する方針を決めた。多くの人々が支援継続を求めており、署名は2万305筆に上った。県がこうした声に耳を傾け、支援再開に踏み切ることを高く評価したい。県教育庁は戦中・戦後期の混乱で義務教育を修了できなかった人の学びを後押しするため、11年度から支援事業を開始した。講師の手当や光熱費、施設の賃借料の一部を補助していた。支援対象者は1932年~41年生まれの今年86歳から77歳になる人たちだ。17年度時点で珊瑚舎スコーレなど3事業所が支援を受けていた。2事業所は17年度までに対象者の受け入れを終えていたが、珊瑚舎スコーレは7人の対象者のうち、5人は18年度も在籍予定となっていた。珊瑚舎スコーレの17年度支援額は395万円だった。ところが県教育庁は事業の当初終了予定が15年度だったことを理由に、この年度に入学した対象者が卒業する17年度で支援を打ち切った。理由について「事業の成果はある程度出た」と説明していたが、5人の在籍者がいる中での打ち切りは拙速な判断だったと言わざるを得ない。珊瑚舎スコーレは現在、義務教育未修了の人は無料、学び直しの人には年額3万円で授業を提供している。その理由を星野人史代表は「貧困のために義務教育を諦めなければならなかった人たちに、お金で再び学問を諦めさせるわけにはいかない」と説明する。運営費は寄付などに頼らざるを得ず、行政の支援は不可欠だ。教育基本法の4条は「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」とうたっている。国と地方公共団体には、経済的理由による修学困難者への支援を講じるよう定めてもいる。教育の機会を等しく確保することは行政の責務だ。夜間中学は戦後の混乱や不登校などを理由に、義務教育を修了できず学齢期を過ぎた人たちが学び直しをしている。全国8都県に市町村立の夜間中学が31校ある。しかし県内には公立の夜間中学は1校もない。珊瑚舎スコーレなどの民間が受け皿となってきた。県は現在、公立中学校夜間学級等設置検討委員会を設置して、課題を洗い出し、需要調査を進めている。15年度に発表した県子どもの貧困対策計画でも夜間中学の設置検討を挙げている。文部科学省も全都道府県での夜間中学の設置方針を掲げている。県は公立設置までは、民間の夜間中学への支援事業を継続すべきだ。現在設けている支援対象の年齢枠も取り払い、支援を拡大してほしい。 *13-3:http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201806/CK2018061402000162.html (東京新聞 2018年6月14日) 結城紬の未来を紡ぐ 「糸取り」養成に本腰 日本を代表する高級絹織物で、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産にも登録されている結城紬(ゆうきつむぎ)の生産の先行きが危ぶまれている。材料の糸を紡ぐ職人「糸取り」が減少し、高齢化も著しいためだ。産地・結城市の関係者が、後継者の養成に乗り出した。「糸がなくなれば、結城紬もなくなる。絶やさないためには、一人でも多くの方の力添えが必要だ」。結城市で二月上旬に開かれた会合で、本場結城紬卸商協同組合の藤貫成一副理事長(56)がそう訴えた。会合は、初めて糸を紡ぐ人向けの道具や糸の見本、解説DVDなど一式を「スターターズキット」として貸し出すための説明会だ。キットを借りた人は、一定期間内に決められた量の糸を納め、対価を受け取る。定期的な講習会でスキルアップを促し、職人として定着してもらう。参加者は二十六人。関東だけでなく、山形県や山梨県の人もいた。結城市の森律子さん(41)は、幼い長女を連れて参加。母親が糸取りで、以前から興味があったという。「糸が足りなくなりそうだとは知らなかった。地元の伝統工芸に少しでも貢献したい」と力を込めた。結城紬には、糸取りが真綿から手で紡いだ撚(よ)りのない無撚糸(ねんし)が使用される。軽い上に暖かく、肌触りも良い特有の風合いは、この工程が鍵を握る。作業を担う職人が「糸取り」。従来は主に農家の女性たちが副業的に担ってきた。本場結城紬原料商共同組合の鈴木孝一理事長(62)によると、昭和五十年代は七千~八千人ほどがいたが、生活を保証するほどの収入にならず働き口が多様化する中、担い手は年々減少。今では三百~四百人程度で平均年齢は七十五歳を超えているとみられる。鈴木理事長は「毎年二十人くらいずつ養成していかないと行き詰まる」と危機感を口にする。結城紬の生産量は、ピークだった昭和五十年代の二十分の一以下ともされるが、二〇一〇年の無形文化遺産の登録などで復活の兆しもあり、約一年前から糸不足が深刻化してきた。そこで原料供給、生産、卸など、結城紬に関わる五つの組合が連携し、糸取りの後継者養成に本腰を入れることになった。説明会で糸紡ぎの実演を披露した国認定の伝統工芸士の植野智恵さん(下妻市)は「地域だけでは担い手が足りなくなる。一人でも多くの後継者をつくりたい」と、産地外からの参加者を歓迎した。 ◇ 卸商協同組合によると、一八年度は筑西、下妻の二市でも新たに糸取り説明会を開く予定という。スターターズキットも四十セットほど貸し出したため、追加で五十セット用意する。 <結城紬> 結城市と栃木県小山市を中心に生産されている絹織物。全工程が手作業で、起源は奈良時代とされる。作業で重要な3工程の糸紡ぎ、絣(かすり)くくり、地機(じばた)織りは1956年に国の重要無形文化財に登録。結城市では、市長や市議らが結城紬の着物で議会に臨む「紬議会」も開催している。 <農林漁業地域の自然は美しくて有益> PS(2018年6月16日追加):*14-1のように、九州北部には雄大な山や美しい海がある。*14-1で紹介されているのは九大の演習林だが、*14-2の水力発電の水源かん養目的で九電が所有している社有林のように、美しさと実益を兼ね備えた森林も多い。また、長崎県五島市にある福江島の本土最西端の灯台付近も美しいようだ。「イルカと海に帰る日」を書いたジャック・マイヨールは、この近くの玄界灘で初めてイルカと出会い、その後、一緒に海に潜っている。そこで、これからの100年を見据えて森林や藻場の設計についてアドバイスするのは、九大はじめ地域の大学の役割だろう。     2018.6.16西日本新聞 玄海灘 2017.10.1朝日新聞 宗像大社の「みあれ祭」での漁船のパレード *14-1:http://qbiz.jp/article/135387/1/ (西日本新聞 2018年6月16日より抜粋) 心ふるえる感動トリップへ!一度は見ておきたい、九州北部の夏絶景5選 雄大な山々や美しい海。九州には、自然が織りなす絶景スポットが多くある。神秘的な水辺の森はじめ、九州本土最西端の灯台で眺める夕日や、自然と融合したデジタルアートなど、今回は6月から夏休みシーズンに楽しめる九州北部の夏絶景を紹介する。 ●神々しい雰囲気に包まれる水辺の森 九州大学が所有する演習林(えんしゅうりん)で、同敷地の西端に位置する「篠栗九大の森」。都市近郊に残存する森の一部を、同大学と篠栗町が共同で整備し、2010年より一般公開を始めた。17ヘクタールの森は、自然の回復力を主体とする最低限の管理に留め、今もなお約90種類の樹木や野生の動物が生息している。森の中心にある池を一周する約2kmの遊歩道は、高低差が少なく、気軽に森林浴を楽しめるコースとなっている。見どころはなんといっても“水辺の森”。樹齢を重ねた落羽松が、その根を水辺にひたしながら立ち並ぶ姿はまさに幻想的だ。 ●“九州本土最西端”で眺めるロマンチックな大瀬崎灯台の夕日 長崎県・五島市の福江島に、九州本土最西端に位置する「大瀬崎灯台」がある。歴史がある灯台自体も見どころだが、なにより素晴らしいのはそこから見える風景。昼は真っ白な灯台、周囲の青い海、崖に打ち付ける荒波と、鮮やかかつ壮大な景色に感動する。日没15分前ごろからは、灯台のバックに沈む美しい夕日が見られる。“九州本土最西端”ということは、九州本土で最後に夕日に出合える場所ということ。そのロマンチックな事実とともに、この夕日はぜひ大切な人と一緒に楽しみたい。昼間は駐車場から遊歩道を進んで灯台まで行けるが、日没後は真っ暗なため、展望台から観賞しよう。 *14-2:http://qbiz.jp/article/135646/1/ (西日本新聞 2018年6月14日) 新国立競技場に九電産のスギ材 大分の社有林から伐採 九州電力は13日、東京都新宿区で建設が進む新国立競技場の屋根材に、大分県の社有林で伐採したスギが使われたと発表した。契約上の問題で使用量や価格は公表していない。九電は水力発電の水源かん養を目的に、同県九重町や由布市で約4447ヘクタールの社有林を管理している。伐採したスギやヒノキは市場に出荷しており、2017年度は15万立方メートルを販売した。新国立競技場は19年11月完成予定。20年東京五輪・パラリンピックの開閉会式や陸上競技の会場となる。「杜(もり)のスタジアム」を掲げ、国内各地の木材を多く使用する。 <シルクの魅力> PS(2018年6月18日追加):*15-1の緑色に光るシルクは、実需者の関心が高く、養蚕農家の飼育頭数が2年目で2.6倍の31万頭に増加したそうだが、これは先端技術による付加価値増加の典型例であり、これが日本だけでなく世界の織物(例えば、ペルシャ絨毯など)に使われるようになると面白いと思われる。そのほか、蛍光だけではなく、太刀魚の銀色やオオゴマダラの金色のシルクができると、銀糸・金糸を使う必要がなくなるので魅力的だ。 また、日本は、エネルギー・賃金・不動産などの高コスト構造により種々の産業を国内では成り立たなくして外国に追い出し、残った伝統産業も存続の危機に瀕しているため、*15-2のように、受け入れ環境を向上させて外国人の就労を促しつつ生産性を高めることによって、本当は必要なのだが成り立たなくなってしまっている産業を復活させるべきだ。 *15-1:https://www.agrinews.co.jp/p44355.html (日本農業新聞 2018年6月16日) 群馬県内新開発蚕の飼育頭数増加 光るシルク世界で輝け 2年目2・6倍、31万頭 実需者からの関心高く 緑色に光るシルクをつくる蚕の飼育頭数が増えている。世界で初めて昨年から群馬県で実用生産が始まった。開発した農研機構が実需者と契約を結び、県内の養蚕農家に蚕の生産を委託しており、今後は衣料やインテリア素材など幅広い分野での利用が想定されている。海外産の安いシルクの流入で押され気味だった養蚕業だが、日本だけの新たな素材で盛り上げたいと産地は意気込む。緑色に光るシルクをつくる蚕は、農研機構が遺伝子組み換えの技術を使って開発、群馬県蚕糸技術センターと共同で実用化に向けた研究を行ってきた。国の承認を受け、昨年から群馬県内の農家の施設で実用生産が始まっていた。2年目の飼養頭数は、昨年の2・6倍に当たる31万5000頭に増えることが明らかになった。外部への逃亡や近縁野生種との交配など、自然界に影響を与えないよう、施設の側面に網を張るなどの対策を取り、細心の注意を払って飼育するため管理に手間がかかる面はあるが、縮小する養蚕業にあって農家の期待は大きい。飼育する農家は生産量が増えたことに「需要が出ている」と受け止めている。昨年は、農研機構が京都市にある西陣織の老舗、細尾と契約した。生産農家で組織する前橋遺伝子組換えカイコ飼育組合が飼育を、長野県の宮坂製糸所が操糸を、それぞれ委託されていた。細尾は、インテリアやアート作品に利用する方向だ。今年産については、農研機構が新たな実需者と契約し、需要の広がりを見せている。契約先は今のところ非公表。飼育は、県技術センターが蚕の卵をかえし、4齢まで育成してから前橋遺伝子組換えカイコ飼育組合に渡し、同組合の農家が飼育して繭を生産する流れ。蚕期は、昨年は10月5日にスタートした初冬蚕だけで、飼育頭数は12万頭だった。これに対し、今年は計4蚕期で31万5000頭になる予定。5月18日から春蚕が7万5000頭で始まり、6月の夏蚕と9月の晩秋蚕が6万頭ずつ、10月の初冬蚕が12万頭の予定だ。蚕を供給する群馬県蚕糸技術センターは「使いたいという業者は多く、需要はある。世界のどこにもない繊維素材で、若い人が憧れる養蚕業をつくれれば」と期待する。 ●高単価に期待農家「夢ある」 緑色に光るシルクを吐き出す蚕は、一般の蚕に比べて繭の収量は低いものの取引価格が高いことから、今の価格で取引されれば経営上はやや有利になる。「なにより夢がある」と養蚕農家は話している。前橋遺伝子組換えカイコ飼育組合によると、1箱(3万頭)当たりの収繭量は一般の蚕が50キロ以上になるのに対し、緑色の蛍光シルクを吐き出す蚕だと40~45キロと1、2割少なかった。一般的な生繭の取引価格は1キロ当たり2200円ほど。これに加え、群馬県の場合、県から最大1キロ900円、さらに市町村から200~1200円の助成金が出る。緑色に光る繭の取引価格は明らかにされていないが「県や市の助成がなくても、一般の繭より高い」と同組合。1キロ6000~7000円程度になるとみられ、コスト分を勘案しても、収益は一般の蚕より高くなる。同組合の松村哲也組合長は「価格だけでなく、(緑色蛍光シルクには)夢がある」と、新しい素材生産に魅力を感じている。 *15-2:https://www.agrinews.co.jp/p44357.html (日本農業新聞 2018年6月16日) 外国人就労の緩和 受け入れ環境向上が鍵 政府は外国人の就労規制を緩和する方針を打ち出した。農業を含めて人材難に苦しむ業界からは“即戦力確保”への期待が高い。一方で、本当に人手不足解消につながるのか、治安の悪化を招かないかといった不安も少なくない。関連法制度の整備に当たり、解決すべき課題は多い。農業界も受け入れ環境の向上へ自己努力が求められる。15日に閣議決定した経済財政運営の基本方針(骨太方針)に、外国人の新たな在留資格を作る方針を盛り込んだ。技能実習制度や国家戦略特区での外国人受け入れに加えて今回、新たな仕組みを設けるのは、産業界が外国人材の受け入れ拡大を強く要望しているためだ。新たな制度は農業、介護、建設、宿泊、造船の5業種を対象にする見込みだ。技能実習制度の修了者や、それと同等の技能・日本語能力を問う試験に合格した外国人に就労を認める。報酬は日本人と同等以上、就労期間は通算5年を上限とする。詳細は政府が今後詰める。今回の規制緩和に農業界の期待は大きい。だが、狙い通り即戦力を確保し、労働力不足を解消できるかは未知数だ。人不足は日本に限った問題ではない。アジア労働人材の争奪戦には、韓国、台湾なども参入する。賃金や待遇面で必ずしも日本に優位性があるわけではない。さらに、就労先に日本が選ばれたとしても、農業で働くとは限らない。国境を越えた人材獲得競争、国内での業種間競争の二つが待ち構える。農業の人手不足は今後、一段と深刻化するのは必至だ。法人経営体の推進や規模拡大が進むほど、雇用労働力への依存度は高くなる。既に多くの産地では、人不足のために潜在生産力をフルに発揮できない問題に直面する。まさに「人の確保こそ最大の成長戦略」である。二つの競争に勝ち抜けるかは、優位性のある賃金水準や労働環境を実現できるかにかかる。「安い労働力」という意識では結局、虎の子を失う事態になる。一方で、農業経営体は他の業態に比べれば中小零細であり、経営体力に限界もある。今月上旬、関連農業団体と農水省が「農業技能実習事業協議会」を設立した。実習生の失踪や受け入れ側の不正行為などの改善策を考え、実習生が安定的に従事できる環境整備に取り組む。こうした自己努力が重要である。例えばファンドをつくって技術研修や初期渡航費に助成するなど踏み込んだ対策も考えられる。国への支援要望をまとめる必要もあろう。スピーディーな検討がポイントだ。政府は今回の規制緩和について、移民政策と一線を画すとの立場だ。ただ、欧米ではこの問題が国家の深刻な分断の震源と化している。安い労働力への過度の依存は、日本人の低賃金化や技術革新を活用した労働生産性向上に水を差すとの指摘もある。国家の将来像と絡めて国民的な議論を深める時である。 <農業の法人化と設備投資> PS(2018年6月19日追加):*16-1のように、農業の規模拡大で資金需要が高まり、農業法人投資育成制度を活用した農業法人への出資件数が5月末時点で累計500件を超えて、出資先の売上高が平均で4割増えたそうだが、返済する資金計画があるのなら大変よいことである。しかし、農産物は付加価値の高いものだけでなく普通のものも作らなければならないため、利益率が高いとは限らない。このような中、*16-2のような地域の新電力会社が、農業地帯で再エネ発電した電力を買い取って地産地消の電力を供給するようにすれば、農業に副収入ができて経営が容易になる。    牧場の風力発電 畑の風力発電 茶畑の風力発電 *16-1:https://www.agrinews.co.jp/p44383.html?page=1 (日本農業新聞 2018年6月19日) 法人出資500件超え JAが窓口機能 所得増大後押し アグリ社 JAグループと日本政策金融公庫(日本公庫)が設立したアグリビジネス投資育成(アグリ社)は18日、農業法人投資育成制度を活用した農業法人への出資件数が5月末時点で累計500件を超えたと発表した。農林中央金庫によると、同社の出資件数は制度全体の約9割を占める。規模拡大で資金需要が高まる中、JAが窓口機能を果たした。出資先の売上高は平均で4割増えており、所得増大に貢献している。アグリ社は2017年度、計74件に10億2000万円を出資。02年度の創設から5月末時点までの累計では出資件数が512件、出資額は83億4000万円となった。累計の品目別では野菜(32%)が最も多く、畜産(23%)、稲作(17%)が続く。農林中金によると、規模拡大に伴う設備投資資金の調達が多い。農業法人は増えているが、自己資本が脆弱(ぜいじゃく)で資金調達が課題。農業法人投資育成制度はこれを支援するもので、民間金融機関が専門の投資組織を立ち上げて出資する。出資は、資金の使い道に制約がなく、対外信用力の向上で融資が受けやすくなるメリットもある。投資組織はアグリ社の他に17組織あるが、農林中金によると、17組織の出資件数は全て合わせても累計80件程度。アグリ社が群を抜くのは「JAが持つ地域のネットワークが強み」(農林中金食農法人営業本部)のためだ。JAが農業者への訪問活動で得た情報を、農林中金を通じて同社につなぎ出資につなげるなど、地域の窓口機能を果たしている。出資は、JAグループが自己改革で目指す農業者の所得増大や農業生産の拡大にも貢献する。アグリ社が10年度から16年度の出資先の343社の売上高を調べたところ、出資前に比べて平均で1億100万円(42%)増えた。利益が増え、配当を支払う出資先も増加傾向にあるという。農林中金は「(同社を通じて)出資に加え、法人の従業員向けのセミナーなど経営支援にも取り組み、農業の成長産業化に貢献したい」(同)としている。 *16-2: http://qbiz.jp/article/135540/1/ (西日本新聞 2018年6月18日) 「くるめエネルギー」始動 新電力「住みよい街へ貢献」 収益の一部 防犯カメラや公園整備へ 福岡県久留米市の久留米商工会議所青年部を母体とする地域新電力会社「くるめエネルギー」(安丸真一社長、同市)の事業開始式典が11日、市内のホテルであった。安価な電力供給とともに、収益の一部を市内の防犯やインフラ整備に充てる地域還元型のビジネスモデルを目指す。同社は、青年部の有志14社が昨年6月に設立した。市内の電気利用者が、市外資本の電力会社に支払う電気料金を「地域資産の流出」と位置付け、電気利用をくるめエネルギーに切り替えてもらうことで流出を食い止め、地域還元や活性化の観点から、収益の一部を街灯や防犯カメラの設置、公園整備に充てる。地元事業者から出資を募ったところ、132社から応募があった。くるめエネルギーの契約者が、出資店舗や事業所を利用した場合には、割引などのサービスを提供する。2月には、大手商社丸紅グループの「丸紅新電力」と業務提携の基本合意を交わしており、丸紅側のノウハウを今後の事業展開に生かすという。この日の式典では、地域新電力の先輩に当たる「やめエネルギー」の本村勇一郎社長が「競合相手ではなく、互いの地域を尊重しながら、共存できる活動ができたら」とあいさつ。安丸社長は「住みよい街づくりに貢献したい。1人でも多くの人が久留米に住みたいと思う環境をつくっていく」と決意を語った。九州電力より2〜5%安い価格で電力を供給する。初年度の契約目標は、工場やオフィス向けの高圧100件、一般家庭や商店向けの低圧2300件。3年後には、高圧350件、低圧7300件、年間売り上げ10億円を目指す。くるめエネルギー=0942(80)5968。
| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 11:12 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2018,03,21, Wednesday
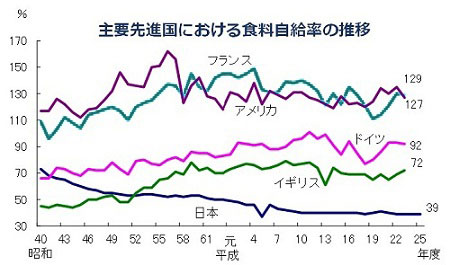 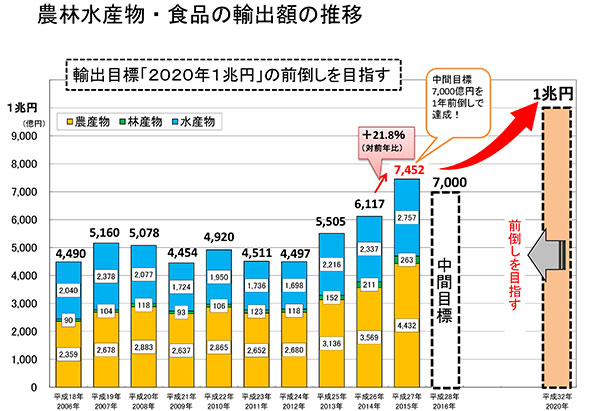 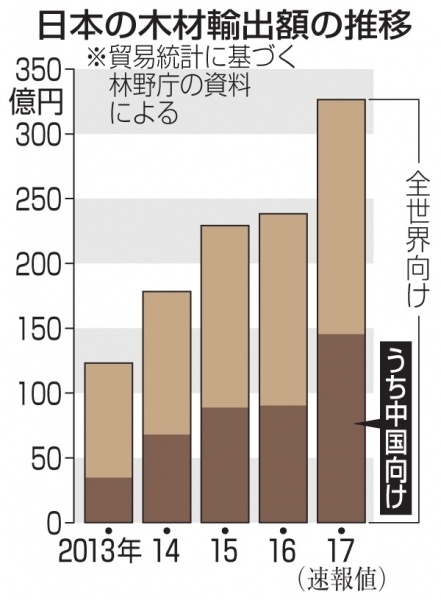 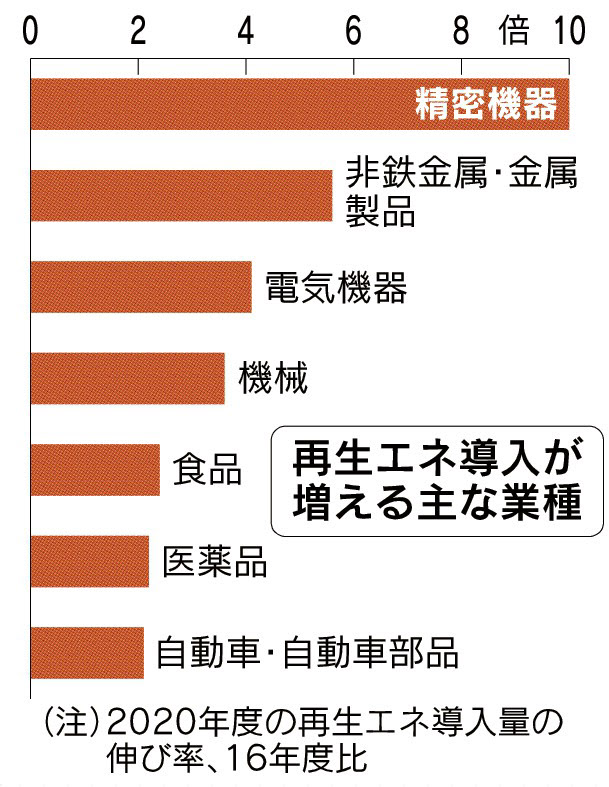 先進主要国の食料自給率 農林水産物輸出額推移 木材輸出額推移 再生エネ導入 2018.2.14 2018.1.21 西日本新聞 日経新聞 (図の説明:フランス・アメリカなどの先進主要国の食料自給率は殆どの時代で100%を超えており、ドイツも2012年で92%だが、日本の食料自給率は1965年の70%程度から一貫して下がり続けて2013年には39%になった。その理由は第2次産業偏重だが、アジア・アフリカ諸国が低賃金を武器に第2次産業に参入している現在、変革にのろい日本の比較優位がいつまでも続くわけではない。従って、第1次・第3次産業もバランスよく大切にすべきで、農林水産物の輸出額が次第に増えているのは望ましいことなのだ。また、再エネ導入量も増えるため、農林水産業地域で再エネ発電をすれば農林水産業に基礎収入を上乗せさせることができて補助金を払う必要がなくなり、また外国に燃料費を支払う必要もなくなって、日本人をより豊かにできる) 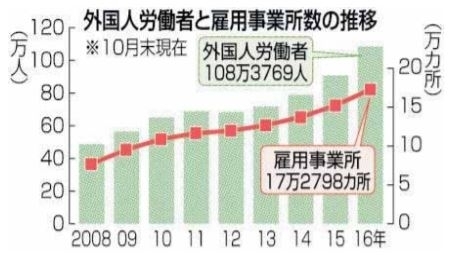  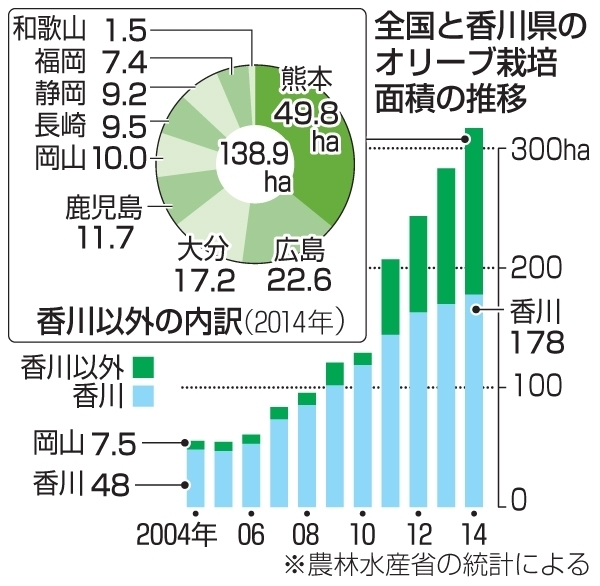  外国人労働者推移 難民申請数・認定数 日本産オリーブ 日本産レモン 2017.12.19 2017.12.21 太良町 日経新聞 西日本新聞 (図の説明:日本で働く外国人労働者や外国人を雇用する事業所は8年で2倍になり、2016年には日本で108万人超の外国人労働者が働いている。しかし、日本の難民認定数は1万人以上の希望者のうち30人程度であり、欧米諸国と比較して冷たい。現在はオリーブやレモンの生産量も増えつつあり、日本には難民が働けそうな場所もあるため、外国人労働者や難民の入国をプラスに働かせることができる局面は多くの産業であるだろう) (1)農林水産業と食料自給率 農林水産大臣が、*1-1のように、衆参両院の農林水産委員会で所信を表明し、農業の成長産業化に向けた改革を続けることに強い意欲を示されたのはよいことだが、自由貿易さえすればよいという発想では農業を衰退産業にしてしまうので、80%くらいの食料自給率と輸出の増加は目標にしてもらいたい。 私も、農業者の高齢化や引退が進む中、農地の集積・集約化が進んで大規模化し、生産性が上がったことはよいと思うが、農業総産出額の増加は物価上昇によるところが大きく、食料自給率は38%に下がっており、農業生産量が増えたわけではないと考える。 なお、*1-1、*1-2に、中山間地域は農地集積が進まないと書かれているが、どこでも同じ穀物を作り、そのために農地を集積することが農業収入を上げる方法ではなく、その地域にあった作物を見つけ、付加価値をつけて売ることが収益を上げる方法である。そのため、国が一律に指導することはできず、地方自治体・地域の農協・農業試験場・地域の大学などが協力して市場調査・品種改良・栽培方法の改善を行うしかない。 また、*1-4のように、この10年間で農業の経営規模が1.5倍に拡大し、規模拡大に伴って従業員の雇用や設備投資の拡大を積極的に進める傾向が出たのはよいことだが、農業は今後、それこそ働き方改革ができるようにならなければ人材が集まりにくいだろう。 しかし、このような生産者の苦労を無視して、*1-3のように、政府は、経産省の政策であるTPPの参加11カ国の新協定に署名することを閣議決定した。茂木担当相は閣議後記者会見で、「早期発効に向けて引き続き主導的な役割を果たしていきたい」と語られたそうだが、やはり主導的にTPP協定を進めていたのは日本だった。ただ、*3-1のように、ISD条項が外されたのは朗報だ。 TPP協定が発効した場合、日本も農林水産物を輸出できなければマイナスが多すぎる。そこで、*1-5を見ると、2011年の日本の水産物輸出は、東電福島第一原発の事故による各国の輸入規制や円高等の影響により数量で前年比25%減少の42万トンとなり、これに対して日本政府は、水産物の放射性物質に係る調査結果や安全確保の措置等を説明するなどの働きかけを行っているそうだが、少しなら有害物質を含んでいても食べたいという人はどの国にもおらず、これは鮮度や味以前の問題である。そのため、有害物質を含まず質の高い日本産水産物を提供しなければ海外市場であっても拡大は難しく、そのための環境整備が必要なのである。 (2)農林業の新技術と新製品 九大大学院農学研究院昆虫ゲノム科学研究室の日下部教授のグループは、*2-1のように、ワクチンの原料となるタンパク質を大量に作るカイコを探し出し、カイコを使って医薬品の原料を作る「昆虫工場」の事業化に乗り出すそうだ。また、*2-5のように、シラカバ樹液・ハーブ類・ヘべス果汁などで体調不良を予防できるシロップを商品化した女性もいる。 さらに、大分大理工学部の衣本助教は、*2-2のように、竹を原料とした次世代素材セルロースナノファイバーの製造法を開発した。これは、広い産業で活用が期待される素材で、放置竹林の解消にも繋がり、この技術の利用のためには竹の安定調達が必要とのことである。 米の食味ランキングで4年連続「特A」を取得した青森県の「青天の霹靂」は、*2-3のように、人工衛星で水田を観測して米の生育や食味を判断する仕組みを取り入れており、埼玉県では梅の害虫被害を宇宙から監視して防除する実証も進んでいるそうで、農業の近代化や効率化が期待される。*2-4のような大規模営農発電を行って、農家の基礎的収入を上げると同時に、耕作放棄地が解消する技術もできた。 農水省が、*2-6のように、ジビエの利用拡大を進めているが、もうそろそろ野生鳥獣も愚痴ばかりではなく、プラスの存在にすべきだろう。 *2-7のように、2017年の丸太輸出額は、中国の旺盛な需要を取り込んで前年比61.7%増の137億円と過去最高を記録し、杉を中心とする九州産が7割超を占めて、「今後は、より良質な木材の輸出にも取り組んでいきたい」と、さらなる意欲を見せているそうだ。しかし、*2-8のように、森林伐採や植樹などを担う「林業従事者」の減少は加速しており、新規就業者の育成が必要な状態である。 (3)長所を伸ばす経営へ *3-2のように、日本は全頭検査していたにもかかわらず、BSEに関する日本の安全基準は、米国産牛の基準に合わせるため、なし崩し的に緩和された。最初は、吉野屋が米国産牛を輸入したくて要望したからだが、国産牛まで変える必要は無かった。何故なら、国産牛まで米国基準に合わせると、国産牛の安全性の長所が失われるからである。その点、畜産が重要な産業であるオーストラリアには原発がなく、その徹底ぶりは感心だ。 しかし、*3-3のように、農産物の輸出額は8073億円となり、5年連続で過去最高を更新した。これは、これまで輸出に積極的でなかったせいもあるが、さらに高い目標を持っているのはよい。ただ、日本で福島第1原発事故が起こったため、輸出先の国・地域が輸入規制を設けたが、これを緩和させたり、撤廃させたりするように動くよりも、徹底して安全な検査済のものを輸出するようにしなければ、日本産全体の評価が下がる。 なお、*3-4のように、沖縄活性化ファンドは、子牛の肥育だけをしていたが、繁殖から肥育までの一貫した経営を進めようとしている「もとぶ牧場」への投資を決定したそうだ。口蹄疫や東日本大震災で国内有数の産地が打撃を受け、畜産農家の後継者不足で子牛相場が上昇しているため、伊藤ハムが自社の繁殖事業のノウハウを「もとぶ牧場」に提供するほか、メインバンクの琉球銀行も発情発見システムなど生産管理を効率化するIT導入の支援を行うそうで面白い。 また、*3-5のように、離島や中山間地域などの“田舎の田舎”ほど若者が集まっており、増加率の上位を占めている離島や山間部には、若者や女性が活躍する場があり、お互いの顔が見えて、小さな自治体は若者の居場所をつくっているからだそうだ。そして、五島列島最北端の離島宇久島に、20~30代の牛飼いが8人となり、この8人が飼う牛は300頭を超えて島の2割を占め、島の大きな推進力になっているそうだ。 (4)農林漁業の担い手 集落営農や農業経営の法人化に官民挙げて取り組んだ理由は、農業の大規模化と世代交代にむけての担い手確保にあった。その集落営農で、*4-1のように、まとめ役や機械作業をする人が見つからず困っているケースが全国的に見られるそうだ。しかし、既に器ができているので、農業は若者にとって魅力的な産業になっており、次世代のリーダーやオペレーターを確保するのは容易になった筈だ。 そのような中、佐賀県白石町の農事組合法人ほくめいが、15の集落営農を合併して2016年に誕生し、経営面積は640ヘクタールに上るそうだが、これならオーストラリアの農業とも競争できそうだ。 なお、このような大規模農業を行うには、*4-3のように、外国人労働者を受け入れたり、*4-4のように、難民に対する冷たい「鎖国」をやめ、協同組合や農林水産業法人で就業させる方法もある。さらに、労働の担い手には、*4-5のようなロボットもいる。 また、*4-2のように、大手スーパーが、異業種と連携して生鮮食品の宅配サービスに相次いで参入しているそうだが、これは共働き夫婦だけではなく、高齢世帯や単身世帯にとっても重要なサービスだ。何故なら、重たい生鮮食品を、(「迷惑そうに」とか「恩着せがましく」ではなく)仕事として爽やかに家まで運んでもらいたいため、私も、水・お茶・液体洗剤などは、既にアマゾンなどのネット販売に変えた状況だからだ。 さらに、生鮮食品なら、産地指定や有機栽培等の選択ができるのもネット販売のメリットだ。そのため、ネット販売は、今や決済の安全性だけが問題なのであり、大手スーパーも産地や有機農産物などの選択肢を増やして一カ所で買い物が終わるようになるとよいと思っている次第だ。 <農林水産業と食料自給率> *1-1:https://www.agrinews.co.jp/p43506.html (日本農業新聞論説 2018年3月12日) 農相所信表明 現場重視で改革着実に 斎藤健農相は衆参両院の農林水産委員会で所信を表明し、農業の成長産業化に向けた改革を続けることに強い意欲を示した。しかし、急進的な改革路線には疑問の声も根強い。生産現場の実態を見据えた着実な改革を目指すべきである。斎藤農相は、これまでの農政改革の成果として、農業総産出額が過去17年で最高の9・2兆円に、生産農業所得も過去18年で最高の3・8兆円になったことなどを強調した。しかし、これらは生産基盤の弱体化による農畜産物価格の上昇が主な要因とみられ、改革関連政策の効果を疑問視する指摘もある。踏み込んだ検証を求めたい。農相が力を入れる施策として第一に取り上げたのは、農地の集積・集約化の一層の加速だ。農業者の高齢化・引退が進む中、大規模経営への構造改革を急ぐ考えだが、現実は容易ではない。2016年度に担い手に集積できた面積は6万2000ヘクタールで、前年度より2万ヘクタール弱減った。目標達成に必要な面積(約15万ヘクタール)の4割水準にとどまる。加速どころか、集積テンポが落ちてきている。農地集積が進まない背景には、中山間地域などの条件不利地や樹園地での集積が難しいことが挙げられる。平場も中山間地域も一律に農地集積を進めようとしても限界がある。23年度までに担い手への集積を8割にする目標自体に無理はないか、慎重に考えるべきだ。農協改革には、「農業者の所得向上に全力投球できる農協の実現に向け、協力していく」として、19年5月までの期間内に具体的な成果を上げるように求めた。現在、JAグループは自己改革の実践に懸命に取り組んでいる。その自主性の尊重が農協改革の出発点である。規制改革推進会議の主張に見られる過度の介入は慎むべきだ。農業現場で今深刻な労働力不足問題には触れなかったのは物足りない。人手不足を理由に規模拡大を断念したり経営縮小したりする農業者が出始めている。改善対策を示す時だ。車の両輪と言いながら、農村政策への言及は、6次産業化の展開や都市農村交流、農泊などを挙げるにとどまり、目新しさに欠ける。安倍政権の地方創生に見劣りしない重厚な農村政策を打ち出すべきだ。米政策は、18年産から生産調整配分への行政関与がなくなる。農相は、情報提供を行うだけにとどめ、主食の安定供給に対する政府の責務には触れずじまいだった。主産地をはじめとして生産調整見直しに対する農家の不安は根強く、今後の論戦でただすべきことは多い。最大の課題は、38%に下がった食料自給率を引き上げることだろう。政府が目指す45%を実現するための具体策が見えない。環太平洋連携協定(TPP)などで農産物貿易の高水準な自由化を進めながら、どのようにして自給率を上げるのか。論戦の中核に据えるべきだ。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p43238.html (日本農業新聞論説 2018年2月10日) 難航する農地集積 中山間地での進展が鍵 農地の利用を「担い手」に集める国の取り組みが難航している。目標の8割集積には、生産条件が悪い中山間地での集積が鍵を握る。地域農業の「担い手」を確保し、実態を踏まえた集積を急ぐ必要がある。農地は食料の生産基盤で、長い年月をかけて整備してきた貴重な社会資本である。食料自給率向上に欠かせない土台でもある。ところが農業者の高齢化が加速し、耕作を続けることが困難な農地が続出している。農水省は2023年度までに担い手への集積を8割に高める目標を掲げ、農地の維持や構造改革に躍起だ。しかし、16年度の集積率は54%。1年間に集積できた面積は6万2000ヘクタールで、前年度より2万ヘクタール弱減った。目標達成に必要な面積(約15万ヘクタール)の4割水準にとどまる。特に食料生産の4割を占める中山間地域の条件不利地や樹園地での集積が進んでいない。耕作を引き受ける担い手が見当たらず、耕作放棄につながる農地も多い。「中山間地域での集積が政府目標を達成する鍵を握る」との指摘がある。政府は、実態調査を急ぐべきだ。農水省は、農地中間管理機構(農地集積バンク)を仲介した集積を目指している。18年度からは、連たん化や20%のコスト低減などの条件が整えば、バンクに貸し出した農地の整備は農家負担なしで行えるようにする。農業委員会制度の見直しで導入した「農地利用最適化推進委員」を動員して、集積を加速したい考えだ。「8割」を押し付けるような「上からの集積」では地域の理解は得られない。自主的な取り組みこそ大切だ。地域で担い手を明確にする「人・農地プラン」をもう一度見直し、「理解と納得」を前提にした集積が重要だ。担い手に位置付けられる認定農業者の経営改善計画の確実な実現や、地元大学との連携、コーディネート育成も欠かせない。「農地利用最適化推進委員」が動きやすいように活動費助成の充実も考えるべきだろう。農地集積バンクに集まった農地を借りるには法人格が必要となる。各地の集落営農組織の法人化を急ぎ、整地された農地の受け皿になれるようにすべきだ。JAが出資法人を立ち上げて引き受けることも考えたい。地域の実情に合った集積方法が最も有効である。JAが主に担ってきた農地利用集積円滑化事業を通した農地集積も活用すべきだ。国の支援が農地集積バンクに偏り過ぎだとの声や、株式会社の農地所有につながるのではないかとの警戒心も根強い。農地集積バンク以外の取り組みへの支援も行うべきだ。相続未登記で集積が困難な農地は、その恐れも含めると90万ヘクタールを超す。水管理を担う土地改良区の維持が困難になるなど、食料生産の屋台骨が揺らいでいる。農地の縮小は国民的な損失である。安倍政権は、中山間地域も含め総合的な生産基盤の立て直しを急ぐ必要がある。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p43465.html (日本農業新聞 2018年3月7日) TPP11 署名を閣議決定 政府は6日、米国を除く環太平洋連携協定(TPP)参加国の新協定「TPP11」に署名することを閣議決定した。参加国は署名式を南米チリのサンティアゴで8日午後(日本時間9日未明)に開き、日本からは茂木敏充TPP担当相が出席する見通し。安倍晋三首相は同日、オーストラリアのターンブル、カナダのトルドー両首相と電話会談し、早期発効に向けた連携を確認した。茂木担当相は同日の閣議後会見で、「早期発効に向け、参加国の進捗状況もにらみながら、引き続き主導的な役割を果たしていきたい」と語った。署名式に先駆け閣僚会合も開き、新規加盟国の扱いなどを議論する。個別の2国間会談も行う。協定に署名後、共同会見を開く。署名後、11カ国は発効に向けて国内手続きを急ぐ。日本政府は3月中に協定承認案と関連法案を国会に提出する。 *1-4:https://www.agrinews.co.jp/p43536.html (日本農業新聞 2018年3月15日) 17年度農業白書骨子案 「若手農家」規模1・5倍 直近10年 従業員雇用割合も増 農水省は14日、2017年度食料・農業・農村白書の骨子案を公表した。49歳以下の担い手や後継者がいる経営体(若手農家)について、直近10年間の動向を分析。稲作や畑作では経営規模が1・5倍に拡大していた。若手農家以外はほぼ横ばいだった。経営規模の拡大に伴い、従業員の雇用や設備投資の拡大を積極的に進める傾向も浮かび、これらの負担軽減策が今後の課題の一つになりそうだ。食料・農業・農村政策審議会企画部会(部会長=大橋弘東京大学大学院教授)で示した。同部会は4月中旬に次回会合を開いて最終案を議論。5月下旬の閣議決定を目指す。今回の骨子案では、今後の日本農業をけん引する若手農家がいる経営体に着目。目玉となる特集面で、農林業センサスなどの調査結果を基に、直近10年間の動向を分析した。若手農家は14万戸(15年)で販売農家全体の1割だった。経営規模を品目別に見ると、稲作単一経営の1戸当たりの経営耕地面積は平均7・1ヘクタール。05年の4・7ヘクタールから1・5倍に増えた。非若手農家はほぼ横ばいだった。稲作以外でも05年に比べ畑作で5割、露地野菜、乳用牛、肉用牛はそれぞれ2割以上経営規模が拡大した。経営規模拡大に伴い、従業員を雇う経営体も増えている。1年のうち7カ月以上働く従業員らを雇う経営体は10年間で約6000戸増えて1万7740戸。全ての若手農家に占める割合は7・3ポイント増え、12・6%になった。省力化や低コスト化に向けて積極的に投資も行っている。機械や設備の投資規模を示す「農業固定資産装備率」は、水田作で2930円で、非若手農家の1・2倍。酪農は6629円で、同1・9倍だった。省力化が進み、水田作10アール当たりの労働時間は4割削減。酪農では搾乳牛1頭当たり4分の3に短縮している。 *1-5:http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23_h/trend/1/t1_2_1_3.html (水産庁) 「水産物の輸出入の動向」より抜粋 (我が国の水産物輸出の動向) 平成23(2011)年における我が国の水産物輸出は、東電福島第一原発の事故による各国の輸入規制や円高等の影響により数量で前年比25%減少の42万トン、金額で前年比11%減少の1,741億円となりました。原発事故の後、輸出先国による規制が強化され、水産物を含む日本産食品の輸出が困難になるという事態が一部の国・地域で発生したことに対応し、政府としては、各国に対し、水産物の放射性物質に係る調査結果や安全確保の措置等を説明するなどの働きかけを行っており、今後ともこのような取組を継続していくこととしています。日本産水産物の品質は、漁獲物の取扱いの丁寧さや発達したコールドチェーンに支えられた鮮度保持の確かさから、世界で高い評価を得ています。さらに日本食の人気が海外で高まっていることも相まって、日本産水産物に対しては世界各国・地域において根強い需要があります。加えて水産物に対する需要は世界的に増大していることから、今後、日本産水産物の海外市場はさらに拡大する可能性があります。水産物は、農産物・畜産物とは異なり、動植物検疫に関する輸入規制の対象となる品目が少ないものの近年、各国の消費者の間で食品衛生問題への関心が高まっていることから、各国の当局が衛生証明書の発行や輸出加工施設の登録を要求するケースが増加しています。このため、政府としては、相手国政府との協議等を通じ、各国の規制や条件に適合するための体制を整備しています。また、海外市場調査に対する支援、展示商談会への出展等の取組を行い、日本産水産物の輸出を促進しています。 <農林業の新技術と新製品> *2-1:http://qbiz.jp/article/125513/1/ (西日本新聞 2018年1月3日) “昆虫工場”カイコで薬 九大・日下部教授ら春に事業化 100年の研究応用、安定供給目指す 九州大大学院農学研究院昆虫ゲノム科学研究室の日下部宜宏教授のグループは、カイコを使い医薬品の原料を作る「昆虫工場」の事業化に乗り出す。九大は約100年前からカイコの研究、保存を続けており、約480種の中から、ワクチンなどの原料となるタンパク質を大量に作るカイコを探し出した。日下部教授らは4月に会社を設立し、第1弾として動物用医薬品の原料製造を目指す。インフルエンザなど感染症予防に使うワクチンは、毒性を弱めるなどしたウイルスを増殖して作る。鶏の受精卵や動物の細胞に感染させて増やすのが一般的。一方、日下部教授らは、病気を引き起こす病原ウイルスの遺伝子の一部を、「遺伝子の運び屋」(ベクター)と呼ばれる物質を使ってカイコに注入。病原ウイルスに形は似ているが感染力はなく、安全なタンパク質(ウイルス様粒子=VLP)を体内で生成させる。VLPは取り出して精製すると、ワクチンの原料になる。日下部教授らは約7年かけ、VLPを効率的に作るカイコを探し出した。カイコは飼育が比較的容易で大型施設なども不要なため、製造コスト低減などが期待できるという。九大が1921(大正10)年から続けている学術用カイコの“コレクション”は世界最大。生物資源を戦略的に収集して活用する国の「ナショナルバイオリソースプロジェクト」の拠点にもなっている。日下部教授は「カイコの活用は、九大が積み上げてきた研究成果を社会に還元するのが目的。安全性が高い次世代型ワクチンは、海外の製薬会社などが特許を持っていることが多く、将来的には安全な国産ワクチンの安定供給につなげたい」としている。日下部教授らが設立する会社は福岡市西区の産学連携交流センターに置く予定。国内の医薬品メーカーとペット用診断薬の原料を製造することで基本合意しており、国の許可が得られれば、製造を始める。ノロウイルスやロタウイルス、子宮頸(けい)がんワクチンに関する研究も進めており、人の医薬品の原料も手掛ける方針。 ■ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP) 日本が生命科学の分野で国際競争力を維持するため、世界最高水準の生物資源を戦略的に収集・保存し、研究機関などに提供する事業。2002年度に始まり、現在、約40の研究機関が連携して30種の動物や植物、微生物などを収集・保存している。九州では九州大がカイコとアサガオ、宮崎大がミヤコグサとダイズの拠点(代表機関)となっている。 *2-2:http://qbiz.jp/article/126245/1/ (西日本新聞 2018年1月17日) 竹で次世代繊維開発 軽量、丈夫、おむつから航空機まで 大分大助教 大分大理工学部(大分市)の衣本(きぬもと)太郎助教(42)が、竹を原料とした次世代素材セルロースナノファイバー(CNF)の製造法を開発した。広い産業で活用が期待されている素材で、パルプなどを原料とする従来の製法よりコストを約10分の1に抑えられるのが特長。放置竹林の拡大が全国的な問題となる中、その解消にもつなげたい考えだ。CNFは、植物由来の天然素材。植物繊維の主成分であるセルロースをナノサイズ(1ナノメートルは10億分の1メートル)まで細かくし、鉄の5分の1の重さで5倍の強度を持つとされる。大手製紙会社がパルプの需要減を補う用途開発として主に研究しており、一部で実用化。表面積の大きさを生かした吸水性の高いおむつシート、インクに混ぜ粘性を増して書きやすくしたボールペンなどが生まれている。将来的には自動車や航空機、住宅部材の他、医療や食品にも活用が期待されており、国は、2030年の市場規模を1兆円と試算している。衣本助教は、放置竹林で多くが伐採、廃棄されるだけの竹を資源として活用できないかと発想。開発した製法は、薄くつぶした竹を圧力釜で煮て、ミキサーで綿状の繊維にした後、薬品処理をして再びミキサーで解きほぐす。できたCNFは直径16ナノメートルの細さ。圧力釜やミキサーなど装置や薬品は市販品で、1キログラム当たり4千〜1万円とされる現在のコストを、数百円に抑えられるという。製法特許を出願中だ。国立研究開発法人・科学技術振興機構(JST)から助成を受け事業化を進めており、当面は竹林がある地域で廃校や空き家などを拠点にしながら地域の雇用にも生かしていく方針。衣本助教は「特別な道具や技術は必要なく、高齢者など誰にでもできる。新産業として地域振興にもつなげたい」と構想を膨らませている。 ◇ ◇ ■竹の安定調達が鍵 放置竹林問題に詳しい北九州市立大のデワンカー・バート教授(都市計画)の話 CNFは最先端の分野で市場は確実に広がっている。事業化が確立されれば竹林対策へ大きな前進だ。ただ、課題は原料を低コストで安定的に調達できるかどうか。竹は山間部に広がっており、伐採する人件費も必要。森林環境税の活用など里山を整備する国や自治体との連携も有効な手段になるだろう。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p43533.html (日本農業新聞 2018年3月14日) 農業変える 宇宙の目 宇宙から得た情報を農業生産に活用する動きが広がっている。人工衛星で水田を観測して、米の生育や食味を判断する仕組みを取り入れている青森県の新品種「青天の霹靂(へきれき)」は、米の食味ランキングで4年連続「特A」を取得。埼玉県では、梅の害虫被害を宇宙から監視し、防除に生かす実証が進む。高齢化や人手不足が深刻化する中、相次ぐ人工衛星打ち上げを利用した農業の省力・効率化が期待される。(猪塚麻紀子) ●青森産米「青天の霹靂」 収穫期・食味 マップに 青森県が10年かけて開発した「青天の霹靂」。デビュー早々の2014年産から連続で「特A」を獲得できた秘訣は、宇宙からの観測データを生かした生産にある。県は16年産から、人工衛星から地球を観測するリモートセンシング技術を導入。津軽地方3000平方キロを撮影した衛星画像を分析して「たんぱくマップ」と「収穫適期マップ」(青森県産業技術センター農林総合研究所提供)を作成、産地の水田約8000枚を1枚ごとに色分けして示すことに成功した。タンパク質は米の食味を左右するため、同品種は厳しい出荷基準を設けている。8月中旬~9月の登熟期の葉色から含有量を判別。これを基に県、JAの営農担当者が指導を行い、次年度以降の施肥設計に活用する仕組みだ。17年産からは、水田ごとの収穫適期をスマートフォンで知らせるアプリを農家も活用し、良食味米の生産につなげた。農水省によると、17年産「青天の霹靂」の1等比率は、10月末時点で98・9%と過去最高の出来。技術を開発した県産業技術センター農林総合研究所の境谷栄二生産環境部長は「人工衛星の情報を活用すれば、産地全体で品質の維持が期待できる」と話す。 ●埼玉の梅農園 虫害ピタリ、適切防除 埼玉県では、宇宙からの“目”が梅の害虫被害を監視する。越生町で梅の生産・加工を手掛ける山口農園は、リモートセンシング技術による適期防除の実証に取り組む。農家の高齢化や人手不足が深刻化する中、同園は1ヘクタールの自作地に加え、地域の農家の防除を請け負っている。山口由美代表が「消毒や収穫の時期をピンポイントで見極めて作業の負担を減らしたい」と、城西大学薬学部の松本明世教授、リモート・センシング技術センター(東京都)と実証試験をスタートした。梅の葉は、アブラムシが付くとしおれて変色する。この色の変化を上空から見極め、被害状況や発生場所を割り出す。近赤外線による観測で、人の目では見分けにくい色の違いを識別でき、高所の様子も分かるため、より効果的な防除につなげられるという。研究を導くのは農家の声だ。山口代表が、梅の陥没症対策や収穫時期の予測など、現場が必要とする技術を提案し、研究員が実証化を探る。「知恵や力を借りることで農業の可能性が広がる」と期待する。同センターは同園での試験を基に、他の果実への応用や海外への普及も視野に入れる。 ●「農家の勘」数値化 人工衛星打ち上げに民間が参入するようになり、安価に活用できる環境が整ってきた。農研機構・農業環境変動研究センターによると、リモートセンシングの利点は「広く見える」「時間による変化が分かる」「人の目で見えないものも見える」ことだ。産地単位のデータを分析して、「農家の勘」を数値化することが期待できる。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p42845.html (日本農業新聞 2017年12月24日) 3.2ヘクタール 最大規模の営農発電 売電収入で雇用創出 耕作放棄地も解消 大豆や小麦生産 千葉県匝瑳市の農家ら合同会社 千葉県匝瑳市の農家が設立した匝瑳メガソーラーシェアリング合同会社が3.2ヘクタールの農地上の高さ約3メートルに、太陽光パネルを整備した。圃場(ほじょう)で農作物の生産と発電を同時にするソーラーシェアリングの取り組みで国内最大規模。パネルの下で大豆と小麦を栽培する。売電収入は年間4700万円を見込み、その収入と農産物販売で収益を上げる新しいビジネスモデルだ。同社は、高さ2・8~3・5メートルの架台を建て、上に横190センチ、縦37センチのパネルを、南向きに約1万枚並べた。2017年3月に通電し、年間の発電量は一般家庭288世帯分の年間消費量に相当する142万キロワットを見込む。パネルを設置する農地は地権者が8人で、半分が耕作放棄地だった。合同会社の椿茂雄代表は「地域では廃棄物の不法投棄も横行し、悩みの種だった」と振り返る。発電所周辺は葉タバコ生産が盛んだったが、徐々に減り、耕作放棄地に替わっていった。その課題解決のため、地元農家や新規就農者に、パネルの下で耕作してもらう仕組みを作った。農地全てをパネルで覆うのではなく、3分の1の面積で発電し、残りの農地は太陽光が当たるようにして大豆と小麦を育てる。人件費は、再生可能エネルギー固定価格買取制度を利用し1キロワット31円(税別)で東京電力に売電した収入から、1人当たり年200万円を支払う。総工費3億円のうち、2億6000万円を信用金庫の融資と社債で調達した。売電収入から、人件費と地代、地域環境を守るための基金、パネルのメンテナンス費用の計約1000万円を差し引いた残り3700万円を、返済に充てる計画だ。既に6月まきの大豆を11月に初収穫した。10アール収量は120キロほどで「この辺りでは上々」と椿代表。まだ売り先は決まっていないが、直売とみそなど加工販売を計画している。後作は、小麦の栽培を計画する。椿代表は「耕作放棄地を農地に戻すため、この仕組みを地域に広げていきたい」と展望する。農水省が農地の一時転用を許可したソーラーシェアリングの件数は、15年度までに全国775件(152・1ヘクタール)。調査を始めた13年度の約8倍で、増加基調という。発電しても、作物の収量が地域平均の8割以上を維持できることが条件の一つで、事業者は毎年、収量や品質の報告義務がある。売電価格は、規模や開始年度で変わる。 *2-5:https://www.agrinews.co.jp/p43504.html (日本農業新聞 2018年3月12日) 子どもの体調不良予防へ シラカバでシロップ 長野の川上さん 長野県川上村のレタス農家、川上知美さん(37)は、村有林で自ら採取したシラカバの樹液をベースにしたシロップを商品化した。小児科医がいない村で子育てをする中で、体調不良を予防できるようなものを作りたいという母心から企画。村のアイデアコンテストで最優秀賞を獲得し、商品開発を村が支援した。商品名は「白樺(しらかば)樹液のハーブコーディアル」。樹液にマロウブルー、ホーリーバジルなどのハーブ類、北海道産のテンサイ糖、宮崎県産のかんきつ「ヘべス」の果汁を材料に作った。優しい甘味と、かんきつの爽やかな香りや酸味があるシロップで、そのままなめたり、お湯や紅茶、炭酸水で割ったりして飲める。村の直売所などで1瓶(100ミリリットル)1200円で販売する。開発のきっかけは、村での子育て中に感じた不便さだ。村には小児科医院がなく、近隣の病院までは車で片道1時間半かかる。そこでハーブ類などの自然の力で、体調不良を予防する方法がないかと考えた。川上さんは「森の手当て屋さん」と題し、2016年に村が地方創生の取り組みで開いたアイデアコンテストで発表。最優秀賞を獲得した。その副賞の事業化の支援を使い、商品を開発した。目を付けたのが村有林に生えるシラカバの木。北欧では、不調を癒す「看護婦さんの木」と呼ばれる。その樹液をベースに、小児科で処方される甘いシロップ剤をイメージした商品に仕上げた。樹液は村の許可を得て川上さんが240リットルを自ら採取。他の材料も国産や有機栽培、無農薬のものにこだわった。味の決め手のヘべス果汁は、川上さんの出身地、宮崎県のJA日向から取り寄せた。樹液の保存などの苦労はあったが、活動に共感してくれた「農業女子」の仲間が協力し、昨年の秋に完成した。川上さんは「商品開発をきっかけに多くの人と出会うことができた。この商品を通じて村や農産物を発信していきたい」と思いを込めている。 *2-6:https://www.agrinews.co.jp/p43489.html (日本農業新聞 2018年3月10日) ジビエ利用へ体制整備 モデル17地区選出 農水省 農水省は9日、鹿やイノシシなど野生鳥獣の肉(ジビエ)の利用拡大を進めるモデル地区に、全国17地域を選出したと発表した。衛生管理された良質なジビエを、安定的に供給できる体制作りを支援する。政府は、年間172億円(2016年度)にも上る農作物被害を減らそうと、ジビエの利用拡大を推進。16年度の利用量(1283トン)を19年度に倍増させる目標を掲げる。同省は18年度予算案などに「ジビエ倍増モデル整備事業」を新たに盛り込んだ。全国にモデル地区を設置し、捕獲や処理加工、衛生管理に関わる人材の育成や、拠点となる処理加工施設の整備、「移動式解体処理車」(ジビエカー)の導入などを支援する。モデル地区は、それぞれが設定した19年度の処理頭数目標に向けたジビエの利用拡大の他、衛生管理の徹底などに取り組む。斎藤健農相は同日の閣議後会見で「有害鳥獣は有効に活用すればプラスの存在になるという意識が変わるようジビエ利用を推進していく」と取り組みに期待を示した。今回選定されたモデル地区は次の通り。 ▽北海道空知地区▽長野市▽石川県南加賀地区▽岐阜県西濃ブランチ▽三重県伊賀市・いなべ市▽京都府・大阪府=京都丹波・大阪北摂地区▽京都府中丹地区▽兵庫県内広域▽和歌山県紀北地区▽同県古座川町▽岡山県美作地区▽鳥取県東部地区▽徳島県内広域▽熊本県内全域▽大分県内全域▽宮崎県延岡地区▽鹿児島県阿久根地区 *2-7:http://qbiz.jp/article/127869/1/ (西日本新聞 2018年2月10日) 九州が「丸太急増」けん引 輸出額の7割超 中国向け杉安定供給 2017年の丸太輸出額は中国の旺盛な需要を取り込み、前年比61・7%増の137億円と過去最高を記録した。このうち、杉を中心とする九州産が7割超を占める。日本木材輸出振興協会によると、丸太の港別輸出額では、九州の港が上位に並ぶ。トップは鹿児島・志布志港の38億円で、87%が中国向けだ。2位は熊本・八代港の13億円。宮崎・細島港が12億円で続く。志布志港の輸出額が多いのは、港を使う鹿児島、宮崎両県の4森林組合が輸出のための協議会を立ち上げ、安定供給できる態勢をつくっているからだ。中国向けの丸太は現在、工業製品の梱包(こんぽう)材用など品質の高くないものが多いが、協議会の堂園司会長は「今後はより良質な木材の輸出にも取り組んでいきたい」と、さらなる輸出増加に意欲を見せている。 *2-8:https://www.agrinews.co.jp/p43582.html (日本農業新聞 2018年3月20日) 林業従事5万人割る 人材獲得競争が激化 15年 森林の伐採や苗木の植樹などの整備を担う「林業従事者」の減少が加速している。林野庁が公表した2015年時点の従事者数は4万5440人で、前回調査(10年)より11%も減少。初めて5万人を割り込んだ。高齢化に加え、他産業との人材獲得競争が激しくなっていることも影響したとみられる。政府は、意欲のある担い手に森林を集約する新たな森林管理制度を19年度から始める方針。林業従事者が減る中、同制度をてこに、必要な森林整備を行う体制を整えたい考えだ。同庁は、総務省が5年ごとに実施する国勢調査を基に、林業従事者数をまとめており、今回は15年時点の結果を公表した。林業従事者は、国産材の価格の低迷による収益性の低下などで、1980年の14万6321人から減少の一途をたどってきた。前回(10年)は5万1200人で、05年比の減少率は2%。新規就業者の育成を支援する「緑の雇用事業」の効果もあって、減少幅も小さくなっていたが、15年は4万5440人と大きく減少した。原因の一つが、林業従事者の高齢化だ。年代別に見ると、65歳以上の従事者が占める割合(高齢化率)は10年から4ポイント増の25%、35歳未満の割合(若年者率)は同1ポイント減の17%となった。働き手が不足し、他業種との人材獲得競争が激しくなっていることも背景にあるとみられる。農業の有効求人倍率は、全産業平均を上回って推移している。政府は25年までに国産材の供給量を4000万立方メートルに増やす目標を掲げる。これに伴い、同庁は、目標の達成に5万3000人程度の林業従事者が必要と試算しているが、15年は大きく下回っている。 <長所を伸ばす経営へ> *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p43522.html (日本農業新聞 2018年3月13日) 米国のISD否定 はしご外された日本 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏 グローバル企業が引き起こす健康・環境被害を規制しようとしても、逆に損害賠償を命じられるISD(投資家・国家訴訟)条項。米国とそれに盲目的に追従する日本が環太平洋連携協定(TPP)で強く推進したが、オーストラリアを筆頭に他国は反対だ。日欧経済連携協定(EPA)で、欧州連合(EU)はISDを「死んだもの」(マルムストローム欧州委員)とさえ言った。北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉で、「震源地」の米国がISDを否定する事態となり、米国に追従してISDを必要不可欠と言い続けた日本だけがはしごを外され、孤立する事態となってきた。「賃金は下がり失業は増える」「国家主権の侵害」「食の安全が脅かされる」との米国民のTPP反対の声は大統領選前の世論調査で78%に達し、トランプ氏に限らず大統領候補全員がTPPを否定せざるを得なくなった。これが米国がTPPを破棄した背景である。この「国家主権の侵害」は、ISD条項を指している。NAFTAにおける訴訟状況を見ると、勝訴または和解(実質的勝訴)しているのは米国企業の12件だけ(2017年3月現在)で、国際法廷の判決が米国企業に有利と言われてきた。だから、グローバル企業と結び付く米国政治家はISDを推進しようとした。しかし、その米国で17年9月、中小企業の社長100人が連名でISD条項削除を求める手紙を出し、最高裁首席判事のジョン・ロバーツ氏も同条項に懸念を表明。ISDを推進したいグローバル企業と結び付く政治家の声を抑えて、トランプ政権はISDを否定する方向にかじを切った。そして、NAFTAで米国は「選択制」を提案した。訴訟に際し、国際法廷に委ねるISDを使うか、国内法廷で裁くかは、各国が選択できることにし、米国は国内法廷で裁く(ISDは使わない)と宣言した。カナダとメキシコはそもそもISD削除を求めていたので、仮に米国提案の選択制を受け入れたとしても、ISDは使わない選択をすることは明白である。つまり、米国提案の選択制はNAFTAにおいて実質的にISDを否定することになる。TPP11では、ISDの投資部分を凍結することで、ISDの懸念をかなり抑制しているが、ISD適用範囲を広く解釈すれば、理不尽な訴訟が起こり得る。米国への「忖度(そんたく)」で、TPP11では中途半端に凍結しているが、そもそも、米国がISDを使わないと宣言した以上、TPP11で残す必要はなくなったと言える。この期に及んで、「死に体」のISDに日本だけがいつまで固執するのだろうか。自身でしっかり考えず、米国に追従してはしごを外される哀れな国から早く卒業すべきである。 *3-2:https://www.agrinews.co.jp/p43151.html (日本農業新聞 2018年1月30日) 戦略的外交は茶番劇 食の安全基準 犠牲に 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏 日本にとっての「戦略的外交」とは、「対日年次改革要望書」や米国在日商工会議所の意見書などに着々と応えていく(その窓口が規制改革推進会議)だけである。全部いっぺんに応えてしまうとやることがなくなってしまうので、必死で交渉しているポーズを取りつつ、一つ一つ順に応えていくのが戦略といえば戦略だ。いずれにせよ、際限なく国益が失われていく「あり地獄」「底なし沼」である。その時、食の安全基準は一層の国益差し出しの格好の材料になる。たくさんの要望がリストアップされているから、それに順次応えていくのにちょうどよい。だから、「日本の安全基準が環太平洋連携協定(TPP)などで影響を受けたことも、今後受けることもない」という政府の国会答弁は「偽証」である。例えば、米国の牛には牛海綿状脳症(BSE)の危険性がある。日本はこれまで、BSEの発症例がほとんどない20カ月齢以下の牛に限定して輸入を認めていた。ところが2010年、米国から「TPPに参加したいなら規制を緩めろ」と言われたため、「入場料」として、「自主的に」(=米国の言う通りに)30カ月齢以下に緩めてしまった。米国はBSEの「清浄国」となっているが、BSE検査率は1%未満でほとんど検査されていないだけだ。と畜段階でのしっかりとした特定危険部位の除去も行われていない。24カ月齢のBSE感染牛も出ている。だから、30カ月齢に緩めることはリスクがある。しかし、食品安全委員会は「科学的根拠に基づいて判断した」と言い張り、本当は、米国へのお土産のための結論ありきだった。さらに、茶番劇が繰り返されようとしている。「清浄国」に対しては30カ月齢以下という月齢制限そのものが問題になる。そこで、15年のTPPの大筋合意後は、日本政府は米国からの「清浄国」に対する月齢制限を撤廃しろとの要求を見越して、「今日言われたら今日にでも撤廃できるように準備万端整えてスタンバイしている」状況が食品安全委員会では1年以上前からできている。そして、ついに、今年の1月13日、米国が月齢制限の撤廃を求めていると日本のメディアが報じ、その要求に対して、「日本は科学的観点から慎重に検討する方針だ」と報じた。本当は、とっくの昔に撤廃の準備はできているのに。またしても見え透いた茶番劇で国民が欺かれるのである。 *3-3:http://qbiz.jp/article/127868/1/ (西日本新聞 2018年2月10日) 農産物輸出8073億円、最高 牛肉41%増、イチゴ56%増 17年速報値 農林水産省は9日、2017年の農林水産物・食品の輸出額(速報値)が前年比7・6%増の8073億円となり、5年連続で過去最高を更新したと発表した。8千億円突破は初めて。和食ブームを受け、牛肉や緑茶などが伸びた。ただ、「19年に1兆円」の政府目標の達成はなお遠い。輸出先は、香港の1877億円がトップ。1115億円の米国、1008億円の中国が続いた。アジアが全体の73・1%を占めた。品目別では、牛肉、緑茶、イチゴ、コメなどが軒並み過去最高になった。鹿児島や宮崎が有力産地の牛肉は41・4%増の192億円。台湾向け輸出が解禁されたことなども後押しした。緑茶は海外の健康志向の高まりを受け、24・3%増の144億円だった。香港や台湾向けが多いイチゴは「あまおう」などが人気で、56・6%増の18億円だった。コメは海外の和食店増加を追い風に18・1%増の32億円。日本酒を含むアルコール飲料も26・8%増だった。みそ、しょうゆなど調味料も伸びた。一方、リンゴは台湾で贈答用に高値が付く大玉が不作で17・7%減だった。農産物全体では8・1%増の4968億円。鹿児島県での養殖が多いブリが好調だった水産物は4・2%増の2750億円。丸太が伸びた林産物は32・3%増の355億円だった。1兆円の目標達成には、新たな市場の開拓のほか、輸出先の各国・地域が福島第1原発事故後に設けた輸入規制の緩和、撤廃などが課題となる。 *3-4:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-677860.html (琉球新報 2018年3月7日) もとぶ牧場、繁殖拡大へ 沖縄ファンドが1.5億投資 政府系ファンドの地域経済活性化支援機構(REVIC、東京)と地元金融機関などが立ち上げた沖縄活性化ファンドは6日、農業生産法人もとぶ牧場(本部町、坂口泰司社長)への投資決定を発表した。優先株と社債を引き受ける形で1億5千万円を拠出する。もとぶ牧場は競り市場で購入した子牛を育てて県産黒毛和牛のブランド「もとぶ牛」として販売展開しているが、近年の子牛価格の高騰を受け、自社牧場での子牛繁殖から肥育まで一貫経営化を進めていく。坂口社長、REVIC地域活性化支援部の小川淳史ディレクター、もとぶ牧場と業務提携する伊藤ハム(兵庫県)の山崎征二国内生産事業部長、琉球銀行の宜保諭常務が那覇市の琉銀本店で会見した。もとぶ牧場は生後9カ月程度で競りに出される子牛を購入し、月齢30カ月まで肥育した上で年間千頭程度を出荷している。3年前から自社で100頭ほどの子牛の繁殖を始めており、沖縄活性化ファンドからの資金調達を基に母牛の導入や牛舎の整備を進め、繁殖頭数を年間500頭と5倍の規模に拡大する。坂口社長は「5~6年前に35万円だった子牛の値段が倍の70万円まで上がり、経営にも影響が出ている」と繁殖事業を本格化させる背景を説明した。口蹄(こうてい)疫や東日本大震災で国内有数の産地が打撃を受けたことや畜産農家の後継者不足で子牛不足が全国的に高まり、子牛相場の上昇につながっている。伊藤ハムは自社の繁殖事業のノウハウをもとぶ牧場に提供するほか、メインバンクの琉球銀行は発情発見システムなど畜産業の生産管理を効率化するIT導入支援を行う。 *3-5:https://www.agrinews.co.jp/p43453.html (日本農業新聞 2018年3月6日) 「縁辺革命」 牛の島にぎわい新た 「縁辺(えんぺん)革命」。今、離島や中山間地域など“田舎の田舎”ほど、若者が集まっている現象を指す。持続可能な地域社会総合研究所の藤山浩所長が名付けた。若い女性の推移を見ると、過疎指定市町村の4割を超える327市町村で流入が超過している。転入者が転出者を上回る人口の「社会増」を実現した過疎市町村も1割を超える。増加率の上位を占めているのは離島や山間部の小さな町村だ。藤山所長は「若者や女性の活躍する場があり、互いの顔が見える範囲の地域に、若者が向かう。小さな自治体こそ、若者の居場所をつくっている」と分析する。 ●8人で300頭超 五島列島最北端の離島、長崎県佐世保市の宇久島。佐世保港からの高速船は1日1便。人口は2000人、15年間で半減した。高校を卒業すれば誰もが島外へ出ていく。人口減の流れが当たり前だった島に「縁辺革命」が起きている。「20年前だったら、想定すらできないことが起きている。仲間ができてうれしい」。畜産農家の西尾光隆さん(31)が笑顔で語る。8年前に就農した西尾さんは当時、20年ぶりの農家と言われ、た。しかし今、20、30代の牛飼いは島に8人。畜産農家90戸1400頭のうち、8人が飼う牛は300頭を超え2割を占めるほどだ。「最終的に、無人島になるんじゃないかと不安だった。だから少しでも手伝えば、高齢農家が牛を飼い続けることができると思って、草刈りや種付け、できることは何でもやった」と振り返る西尾さん。家畜人工授精師として島を周り、父親と増頭を進めた。そんなふうに頑張っていると、同世代が毎年1人ずつのペースで畜産農家としてUターンしてきた。その一人、繁殖雌牛30頭を飼育する辻直哉さん(28)。県外に就職したが、島のコミュニティーと大きく異なる環境になじめず、3年前に島に戻った。実家の畜産を手伝う中で、獣医や西尾さんら仲間と知り合い、少しずつ経営に参画。今では「センスがある」と獣医師から褒められる。1年1産を上回る繁殖成績を残す。「廃れていくだけの島にはしたくない。同世代が多く、牛で島を盛り上げることがきっとできる」。都会の会社員時代は実感できなかった、役割と手応えを感じる。 ●大きな推進力 総務省が2月に発表した田園回帰の調査でも、人口が少ない地域ほど移住者が増えていることが分かった。北海道豊浦町、高知県大川村、鹿児島県十島村など人口5000人に満たない地域が並ぶ。佐世保市と合併した宇久島の潮流は、数字上で成果としては表れにくい。わずか8人。ただ島にとっては、大きな推進力だ。和牛部会会長の西尾政喜さん(58)は若手農家の台頭で、島が活気づいていると感じる。「最近『若者の立場で考えよう』と言う農家が増えたよ。農家以外から声を掛けられる機会も多く、明るい話題が島に広がってきた」と喜ぶ。島の基幹産業だった養蚕、福原オレンジが廃れた今、西尾さんは「島に残るは牛。若者が帰り、牛の島の将来像が描ける」と見据える。地域に、希望が見えている。 ●2015年 実質社会増減率 持続可能な地域社会総合研究所が、死亡者数を除いた転出入による社会増減率を算出すると、都市部より条件の厳しい小さな自治体で人口の社会増を実現していた。熱心な移住促進策で人口を増やしている。発足して3年目。イベントの参加者は小さな子どもから社会人まで広がりました。これからも、幅広い世代に食や農への関心を持ってもらい、面白さや奥深さを知ってもらえるよう活動していきます。(代表・篠崎智子=新潟大学) <農林漁業の担い手> *4-1:https://www.agrinews.co.jp/p43245.html (日本農業新聞 2018年2月11日) 集落営農世代交代 担い手づくり再起動を 集落営農が世代交代期を迎えている。まとめ役や機械作業をする人が見つからず困っているケースが全国的に見られる。集落営農の組織化や法人化に官民挙げて取り組んで10年。世代交代期を乗り切るため、担い手づくり運動の再起動が必要だ。集落営農は2002年の米政策大綱で「集落型経営体」に位置付けられ、国の政策支援の対象になった。07年の品目横断的経営安定対策の導入に合わせ、農水省や県、JAグループなどの農業団体が一体で育成に取り組んだ経緯がある。それから10年。集落営農数は全国に約1万5000(17年2月現在)に増えた。法人化した集落営農は約4700で全体の3割を占める。農水省は23年までに5万の目標を掲げ、法人化を促進する。集落営農もその対象の一つだ。集落営農が抱える主要な課題は2点ある。設立や運営の中核を担ってきたメンバーが引退時期を迎えたときに次の世代の新たなリーダ―を確保できるか。作業委託する高齢組合員が土地持ち非農家化し、地域農業との関係が薄くなることである。後継者のいない地域では、花や野菜を作るJAの青年部員に何度も頭を下げてオペレーターを引き受けてもらうなど、組織の継続に難儀している実態が各地で少なくない。中山間地域ほど人の手当てが深刻だ。新規の法人を増やすのも重要だが、設立して10年以上経過した集落営農の継続対策も怠ってはならない。“要員不足解散”を防がなければならない。そういう中、注目される動きの一つは集落営農の広域化である。佐賀県白石町の農事組合法人ほくめいは15の集落営農組織が合併して16年に誕生。経営面積は640ヘクタールに上る。合併前は集落単位の集落営農組織が後継者不足で役員が交代できない、オペレーターも成り手がないという問題を抱えていた。広域法人化までは一気にいかないが、集落営農法人同士でオペレーターや大型農機をやりくりして、農繁期の人手不足や機械の効率利用を図るという動きも各地に出てきている。愛知県農業振興協会が提案する「地域まるっと中間管理方式」も興味深い。地域の農地を全ていったん、農地中間管理機構に預け、その地域内に設立した一般社団法人が借り受ける。担い手・自作希望農家のすみ分けを柔軟に行う。農地集積率が高く、一社の設立手続きが容易、地域集積協力金の非課税化などのメリットを期待できる。こうした新たな展開を進める上で重要なのは、地域内の合意形成だ。何のための改革か、組合員が果たすべき役割は何か。こうした点が関係者全体に落ちないと、地域の農地を守るという目的の達成は難しくなる。その意味からいま一度、担い手づくり運動を行政、農業団体一体で再起動し、次の一手に踏み出してはどうか。農地集積にも良い効果を生み出すはずだ。 *4-2:https://www.agrinews.co.jp/p43243.html (日本農業新聞 2018年2月11日) 生鮮食品宅配が過熱 スーパー 続々と参入 異業種と連携強化 多様な需要に対応 青果や食肉などの食材や総菜など加工品を自宅に届ける宅配商戦が、過熱している。共働き世帯の増加など、利便性を求めるニーズの高まりを受けたものだ。大手スーパーが、異業種と連携して相次ぎ参入。主に首都圏で展開し、スーパーの常設店舗で伸び悩む売り上げを補う狙いがある。有機農産物を扱う宅配業者も主力3社が経営統合し、配送網の効率化を図り対抗する。食の宅配市場で、熾烈(しれつ)な主導権争いが始まっている。消費者の購買行動が変化している。矢野経済研究所によると、食品宅配市場の事業規模は2016年に2兆782億円となり、17年以降も年3%ずつ成長すると見通す。一方、17年の食品スーパーの売上高は10兆2806億円で、前年より0・4%減。青果物や食肉などの高値で減少幅は小さく映るが、中長期的に見ると減少傾向にある。食の宅配事業は、スーパー業界の将来をかけた、新たな戦略ともいえる。大手スーパーのイトーヨーカ堂を展開するセブン&アイ・ホールディングス(HD、東京都千代田区)は17年11月、通販メ業者のアスクルと連携した生鮮宅配「IY(アイワイ)フレッシュ」をスタートさせた。アスクルの物流機能を活用し、イトーヨーカ堂の宅配拠点から生鮮品を届ける。配送時間は1時間単位で細かく使用でき、利用者は40代の働く世代が中心だという。「まとめ買いではなく、簡便性の高い商品や調理キットなどを少しずつ注文する消費者をターゲットにしている」(同HD)。現在は東京都内の2区だけだが、18年度中に23区全体へ拡大する。 ●ネット事業展開 スーパーの西友(東京都北区)を傘下にする米・ウォルマート・ストアーズは1月、ネット通販大手の楽天と業務提携を結び、9月までにネットスーパー事業を展開すると発表した。イオン(千葉市)も、ソフトバンクやヤフーと、近くインターネット通販事業で提携する方向だ。ソフトバンクとヤフーが持つ顧客基盤と、イオンの食品をはじめとする幅広い商品力や物流網を組み合わせる。17年4月に先行して生鮮宅配に参入したアマゾンジャパンが存在感を高める中で、影響力のある買い物サイトの構築を進めていく。 ●有機は経営統合 これまで食品の宅配事業をけん引してきた有機農産物の宅配メーカーは、経営統合に活路を見いだす。最大手のオイシックスドット大地(東京都品川区)は、オイシックスと「大地を守る会」が17年10月に経営統合して誕生した。今年2月には「らでぃっしゅぼーや」を子会社化し、年間売上額は550億円を超える見通しだ。30、40代の子育て世代に強いオイシックス、シニアをターゲット層にする「大地を守る会」、東北から関西まで19の都市部で自社便の配送網を持つ「らでぃっしゅぼーや」と3社の強みを発揮し、販売拡大を図る。3社は連携後も、農産物にこだわる幅広い年齢層をターゲットに支持層の拡大を進める。有機農産物の登録生産者数を従来の2倍に当たる5100人に増強し調達力を高めたことに加え、物流経路を共有し効率を高める。大手スーパーに、有機農産物という付加価値で対抗する戦略だ。 *4-3:https://www.agrinews.co.jp/p43264.html (日本農業新聞 2018年2月13日) 外国人技能実習制度 受け入れ団体52農協 1月末時点「優良」認定は3 昨年11月に新制度に移行した外国人技能実習制度で、実習生を受け入れる監理団体の許可を受けた農協数は、1月末時点で52に上ることが政府のまとめで分かった。うち、研修生の受け入れ期間や人数を拡大できる「優良」認定を受けたのは3農協。優良認定を得るには、実習生の技能習得の支援や人権保護など、基本的な取り組みの積み重ねが求められる。新制度は実習生の保護などを目的に、実習生の受け入れ農家や監理団体を監督する「外国人技能実習機構」を新設。同機構から農家、監理団体ともに体制や取り組みが「優良」と認定されれば、実習生の受け入れ期間は最長3年から5年に、受け入れ人数の上限は倍にできる。旧制度では農業の監理団体は592団体(2015年度)で、うち、農協は79で、他は事業協同組合など。新制度の開始から1月末までに認定を受けた52農協のうち、優良認定は北海道のJAオホーツクはまなすと熊本県のJA熊本うき、茨城県の茨城中央園芸農協。農協以外の監理団体がどの程度、優良認定を受けたかは示されていない。他産業も含む全体では認定された監理団体は1888で、うち、優良認定は661だった。優良と認定されるには、同機構から120点満点で採点され、6割以上の得点が必要だ。受け入れ農家数に比べ十分な数の常勤役職員がいるかといった業務体制や、実習生が研修修了時に受ける試験の合格率、実習生の日本語学習への支援状況などが評価される他、実習生の失踪など問題が発生すれば減点される。JA熊本うきによると、優良認定を受けるのは決して簡単ではないとし、実習生との丁寧な関係づくりで、失踪を未然に防ぐなどの対応が重要になるとみる。一方、優良認定を得られていない関東のあるJAは、実習生の試験合格率などで得点が伸びなかったという。実習生にはこれまで試験の受験義務はなく、受験率が低かった状況も影響したとみられる。一方、冬場に作業がなく、実習生が1年未満で帰国する形態が定着している産地もあり、「そもそも優良認定を目指さない監理団体があることも想定される」(農水省)状況だ。 ●熟知した職員 確保を 外国人技能実習制度に詳しい日本農業経営大学校の堀口健治校長の話 優良認定を得た監理団体の中に農協系が少ないように見えるが、監理団体の認定は今後も進む見通しであり、数の多少に対する評価は現時点では難しい。実習生が農業現場に円滑に定着するには、農業の実態を十分に理解している監理団体が望ましい。その意味では、農協系の監理団体の役割への期待は大きい。だが、監理団体としての仕事に特化した専門家がいる事業協同組合と比べると、農協の場合、制度を熟知した職員の確保など、工夫が望まれる。(優良認定外の)特定監理団体としてまずは出発して、今後は、優良認定を目指す農協も出てくるのではないか。今後の動向に注目していきたい。 *4-4:http://www.kochinews.co.jp/article/160257/ (高知新聞 2018.2.14) 難民保護】冷たい「鎖国」続けるのか 不法滞在で入国管理施設に収容された外国人が、条件付きで解放された後、再び収容される事例が増えている。過去5年で約4倍に膨らんでいるという。入国管理当局が取り締まりを強化しているためだ。就労禁止違反などが理由になっている。問題は、再収容者には難民認定への申請者が多いことだ。認定審査は長期化する傾向にある。複数年に及ぶケースもある。生活のためにやむなく働く人が少なくない。取り締まり強化の理由も、納得しがたい。政府は2020年東京五輪に向けた治安対策を挙げる。不法滞在が犯罪の温床になる客観的なデータがないにもかかわらずだ。これでは本当に保護が必要な難民を救済できないばかりか、非人道的だと非難されても仕方がない。難民の保護義務を課した難民条約の精神にも反しないだろうか。日本はこれまで、難民の受け入れに消極的な「難民鎖国」と内外から批判されてきた。難民申請数は年々増加している。16年には前年比約44%増の1万901人が申請したが、実際の認定数はわずか28人だった。過去5年間でも30人を超えた年はない。欧米諸国は毎年、数千人、数万人単位で受け入れている。環境が違うとはいえ、桁が違いすぎる。再収容者の増加も、こうした政府の消極姿勢と無関係ではあるまい。日本はこの先も、冷たい「鎖国」のままでいいのだろうか。入国管理施設は原則、在留資格がなく強制送還の対象となる外国人を一時的に収容している。難民申請をしていたり、母国が身柄の引き取りを拒否したりする場合には収容が長期になる。入管当局は病気や人道上の理由から、拘束を解く「仮放免」にすることがある。就労の禁止や保証金の納付などが条件だが、ハードルが高い。精査する必要がありはしないか。仮放免になっても生活費を確保できなければ暮らしていけない。政府によれば、最初から就労を目的にした難民申請者も増えているという。仮にそうだとしても一律に就労を禁じれば、本当の難民を保護できない恐れがある。難民条約が不法入国を理由に処罰することを禁じていることも忘れてはならない。そもそも合法的に入国したり、準備万端で申請できたりする難民は少ないはずだ。移民や難民の受け入れには消極的な一方で、政府は数年間日本で働く外国人技能実習生の受け入れに力を入れている。本来、途上国の若者らに日本の技能を教え、母国の経済発展に生かしてもらう制度だ。ところが、現実には日本の労働力不足を補う手段になっている。実習生が低賃金や長時間労働を強いられる例も後を絶たない。国際社会に理解が得られない政策だ。政府のこうした姿勢の背景には、国民の関心の低さもあろう。抜本的な論議が求められる。 *4-5:https://www.agrinews.co.jp/p43240.html (日本農業新聞 2018年2月10日) ロボットで処理数増 食肉加工技術発表会 日本食肉生産技術開発センターは9日、ロボットなど先端装置を使った食肉加工技術を紹介する研究発表会を東京都内で開いた。食肉加工の機械化を進めることで省力化を図り、業界全体で人手不足に対応する。メーカーは、食肉加工の工程にロボットを導入することで、処理能力が高まったことを報告した。食肉加工メーカーのスターゼンミートプロセッサーは昨年から同社の食肉加工工場に、豚モモ肉の骨を自動で取り除く処理ロボットを導入した。ロボットの導入に伴い脱骨作業に携わっていた人員を5人減らすことに成功。また、1時間当たりの処理頭数が約2割増えたと報告した。機械メーカーのマトヤ技研工業は、豚枝肉の残毛を自動で除去するロボットを紹介した。食肉処理施設でと畜・解体された枝肉は、皮剥ぎ工程で残毛が付着してしまうことがあるという。手作業ではなくロボットで処理することで、正確性と生産性を高めることができる。2018年度中に開発予定だ。同センターの関川和孝理事長は、労働力不足や働き方改革が進む中で、「安全・安心で高品質な食肉生産を消費者に提供する必要がある」と強調した。研究発表会ではモノのインターネット(IoT)の活用についても報告があった。全国の食肉業者ら約150人が参加した。 <水産業> PS(2018年3月24日追加):*5のようなクロマグロはじめマダイ・フグ・コイ・貝類・ノリ・コンブ等々、現在では多くの水産物が養殖されている。このうち魚の場合は、生産コストの半分以上をえさ代が占めるため、安価な飼料を開発すれば輸出可能で、昆虫・ユーグレナ・植物など魚粉以外の飼料を検討するのがよいと考える。 *5:http://qbiz.jp/article/130191/1/ (西日本新聞 2018年3月21日) 鷹島でマグロ「完全養殖」 双日グループ 9月出荷へ、18年は2000尾 長崎県松浦市の鷹島でクロマグロの養殖事業を手掛ける大手総合商社の双日が、人工的に卵からふ化させる「完全養殖」に参入し、9月ごろ出荷を始める。クロマグロは近年資源量が減少し、天然の稚魚を使う通常の養殖に対していけすの上限などの規制がかけられていることから、水産大手や商社が相次いで完全養殖に参入。双日も市場の動向やコストを見極めて生産量を拡大する方針だ。鷹島での通常の養殖は、双日子会社の「双日ツナファーム鷹島」が2008年に始め、現在年間約1万尾(約400トン)を出荷。長崎県の対馬や五島列島などの養殖場と比較して、海水温が低いことから身が締まっているのが特徴で、特に赤身の人気が高いという。18年は完全養殖のクロマグロ約2千尾の出荷を予定している。今後、通常の養殖を含めて年間最大1万3千尾まで増やす計画。双日によると、完全養殖は通常の養殖よりも成育期間が長めで、生産コストの半分以上を占めるえさ代の抑制が課題だという。クロマグロの完全養殖はすでに、マルハニチロ、極洋、日本水産の水産大手3社のほか、商社の豊田通商などが実施。双日の担当者は「資源の安定供給のために完全養殖は必要だが、消費者の認知度はまだまだ。まずは他社とともに完全養殖の市場拡大を図りたい」としている。 <種子の特許権> PS(2018年3月25日追加):*6のように、民間企業の参入促進のため、種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた種子法を3月末に廃止するそうだが、デュポンパイオニアやサカタのタネなど、意欲的に種子の生産に参入して成功してきた企業は多い。一方で、各地域の気候に適応し、日本人のニーズに合った種子を開発して、高すぎない価格で販売するには民間企業では不十分で、何でも民営化さえすればよいというものではない。従って、種子は農業発展の重要な要素であるため、都道府県が現行の体制を維持することは必要で、国民の税金を投入して開発した優秀な種子の特許権(国民の財産)は、世界でとっておくことが必要だと考える。 *6:https://www.agrinews.co.jp/p43590.html (日本農業新聞 2018年3月21日) 「種子法」廃止受け 都道府県 18年度は体制維持 新ルール作り検討 本紙調べ 種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた主要農作物種子法(種子法)が3月末に廃止される中、2018年度は、全都道府県が種子関連事業をおおむね維持し、安定供給の体制を継続する方針であることが20日、日本農業新聞の調べで分かった。地域に適した品種の維持は行政の管理が不可欠との姿勢。種子生産に行政が責任を持つ新たなルール作りに動く県も出始めた。ただ、同法廃止の狙いは民間の参入促進にあるため、種子を企業が握る危うさは残る。19年度以降も、行政の動向に注視が必要だ。全都道府県に、聞き取り調査した。その結果、18年度は種子法に代わる要綱を作成するなどして現行の体制を維持する方針。その上で、新たな制度や仕組みを設ける動きも出ている。全国一の種もみ産地の富山県は18年度、新規事業で種もみ生産技術拠点の整備に着手する。民間や他県の育成品種の原種を病気のない状態で供給するため、隔離圃場(ほじょう)や検定温室を整備する。埼玉県は18年度から、種子産地の強化と若返りを図る新規事業を始める。他産地との連携や共同乾燥施設の設置といった解決策を探る。若い生産者の掘り起こしや技術継承の方策なども検討して「産地強化計画」を作成する方針だ。米産地の新潟県は、同法に代わり稲などの種子の安定生産と供給体制を維持する条例を作成する。2月に条例案を県議会に提出し、4月1日の施行を目指す。兵庫県も新たな条例の制定を進めており、4月1日の施行を目指す。北海道は18年度に現行の体制を維持しつつ、19年度以降に条例制定を含めて検討する方針だ。都道府県から共通して「優良品種の維持と供給に行政の関与は不可欠」との声が上がった。この他、「地域の気候に適した独自の品種が求められ、育成者の県が主体的に関わることが不可欠」(東北の県)などと、行政が一定の役割を果たす意向が多数を占めた。「なぜ種子法を廃止したのか分からない」などとして、廃止理由に疑念を示す声もあった。同法は1952年の公布以来、米、麦類、大豆の優良な種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた。しかし、規制緩和を図る政府は17年、同法が「民間の品種開発意欲を阻害している」として廃止法案を成立させた。農水省は同法廃止について17年11月、都道府県に対して通知を発出。「これまで実施してきた業務を直ちに取りやめることを求めていない」としつつ、種子生産について「民間の参入が進むまでの間、行政の知見を維持し、民間への知見提供を促進すること」とし、民間の参入を促す取り組みを求めている。 <最先端のハウス> PS(2018/3/26追加):JA全農は、*7のように、生産・販売のノウハウを持つJAさが及び全国屈指の収量を誇る地元篤農家と連携して大規模なハウスを建設し、温度・湿度・CO2濃度などの複合制御技術を導入してキュウリの生育に最適な環境を作り、清掃工場で発生する余熱やCO2を活用して、佐賀県内平均の約2倍となる10アール当たり50トンの目標収量を掲げているそうだ。これは、環境にはプラスで安価に生産性を上げようとしている点が頼もしい。 *7:http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196558 (佐賀新聞 2018/3/24) キュウリ実証施設整備へ 全農、佐賀市に全国3例目、JAさが、篤農家と連携 大規模多収モデル確立 JA全農は、キュウリ栽培の高機能実証施設「ゆめファーム全農」を佐賀市に整備する準備を進めている。生産と販売のノウハウを持つJAさがと、全国屈指の収量を誇る地元の篤農家と連携し、施設の設置から栽培管理・収穫販売までのノウハウを蓄積。農業の担い手減少が課題となる中、大規模・多収のモデルとしてパッケージ化し、全国に普及を目指す。「稼げる農業」の確立を目指した取り組み。県内は施設キュウリの栽培レベルが高いことから計画地に選ばれた。正式決定すれば、栃木県の施設トマト、高知県の施設ナスに続いて全国3例目となる。施設は約1ヘクタールと大規模で、高収量が期待できる高軒高ハウスを建設する。温度や湿度、二酸化炭素(CO2)濃度の複合制御技術を導入してキュウリの生育に最適な環境を作り出し、情報通信技術(ICT)で栽培管理データを蓄積、解析するという。建設場所は佐賀市高木瀬の清掃工場西側で、市は新年度当初予算に約4億3千万円を計上、約2・5ヘクタールを取得、整備する。清掃工場で発生するCO2や余熱を活用し、10アール当たりの目標収量は県内平均の約2倍となる50トンを掲げる。全農やJAさがの担当者らは昨年、先進地のオランダを視察。今月13日には、武雄市にある新規就農者の研修施設「トレーニングファーム」を見学し、高い技術や収量を誇る県内の生産者とも意見交換した。JA全農の担当者は「生産者数が減る中、今の国産の生産量を維持するためにも、生産量の最大化と面積の拡大にこだわっている」と説明。「全農としてキュウリ栽培の能力があるわけではなく、地元の生産者に指導していただく立場になる。全農とJA、生産者が三位一体となり、全国展開できる普及の形態を考えていきたい」と話す。 <食品のサイズ> PS(2018年3月28日追加):*8のように、一口サイズのフルーツに注目が集まっているそうだが、私は、前から、長野県のリンゴなど日本の果実は一個のサイズが大きすぎると思っていた。これは、ニュージーランド産のリンゴを見た時に意識したことで、その大きさなら切って食べても一度で完食でき、保存の際に生じる色や味の劣化がなくて便利だと思われた。なお、長野産リンゴの味はよいので、サイズの変更は、品種ではなく栽培の仕方を変え、一枝につく実を多くすれば、利益を増やしながら直ちにできる。また、贈答用でも、日本の果実は大きくすることに力を入れすぎていて、一人暮らしや核家族のニーズを調査していないように見える。 *8:https://www.agrinews.co.jp/p43649.html (日本農業新聞 2018年3月28日) ミニ果実 “歓迎”単身世帯 スイーツに“最適” 「切らずに」「丸かじり」 手軽にフルーツを食べたいという消費者のニーズが高まる中、一口サイズのミニフルーツに注目が集まっている。各産地は、食べやすさや加工のしやすさをアピールし、消費者や製菓店などに売り込む。丸ごとケーキに使えるなど、見た目のインパクトも特徴。食べ切りサイズで無駄がなく、増加する単身世帯や核家族向けの商材としても期待が掛かる。(斯波希) ●有望品種拡大へ 大阪府でイチジク イチジクの生産量全国3位を誇る大阪府は、ミニイチジクの産地化に乗り出している。主力品種「桝井ドーフィン」の3分の1の20~40グラムの大きさで、皮ごと食べられる簡便さや加工のしやすさが売りだ。府産のミニイチジクを「宝石フィコ」の統一ブランドでPRする戦略を描く。府内では約41ヘクタールでイチジクが生産され、全国の収穫量の1割ほどを占める。簡便さを求める消費者や、果実を食べる習慣がない消費者向けの販売戦略として、ほとんど栽培されていないミニイチジクに着目した。品種は海外原産の「イスキア・ブラック」と「ネグローネ」が中心。癖がなく食べやすいのが特徴という。病害虫への抵抗性が強く、栽培しやすいメリットもある。生産者らでつくる大阪府果樹振興会や研究機関が連携し、ブドウに続く特産品の柱に育てたい考えだ。同振興会の講習会で紹介するなど、生産拡大を目指している。本格的な流通は2、3年後を見込む。2017年産では、3個入りパック二つをセットにして1000円で試験販売したところ、24セットが完売したという。丸ごと包んだ「イチジク大福」を府内の和菓子メーカーと共同開発するなど、製菓店向けのアピールにも力を入れる。約40アールでミニイチジクを栽培する、羽曳野市のふじいいちじく園の藤井延康さんは「仲間を増やしてブランド化し、高単価につなげたい」と期待する。ミニイチジクは、富山県でも栽培が広がっている。稲作農家が水稲の育苗ハウスを活用し、新たな園芸品目として導入する動きが盛んだ。ケーキなどの素材として、洋菓子店などから引き合いが強いという。 ●キウイ、リンゴ、柿 香川県では、県と香川大学が育成した一口サイズのキウイフルーツ「さぬきキウイっこ」の生産が広がっている。平均40グラムほどで、爪で割って一口ゼリーのように簡単に食べられるのが特徴だ。平均糖度が高く、キウイ特有のひりひり感もない。県によると、栽培面積は7・5ヘクタール(16年度)。「簡便さと、他にはないかわいらしさが受けている」(県産品振興課)と手応えをつかむ。“丸かじり用”としてミニサイズのリンゴをアピールするのは長野県だ。県果樹試験場が、一般的な品種の半分程度、150~200グラムの「シナノピッコロ」と「シナノプッチ」を育成。切らずにそのまま食べ切れるリンゴとして、直売所などで流通する。「贈答用は大きいサイズが好まれるが、少人数の家族が増え、食べ切りサイズが求められている」(栽培部)。岐阜県や新潟県などで生産されている柿「ベビーパーシモン」も、直径約3センチ、20~30グラムほどの一口サイズで、皮をむかずに食べられる。岐阜県では17年度からスーパーでの取り扱いが始まるなど、出荷量が拡大しているという。 ●希少性生かし まず業務向け 果実の流通に詳しい青果物健康推進協会の近藤卓志事務局長は「まずは、希少性や特異性を生かし業務向けで生産を拡大した上で、簡便さを求める消費者向けにアピールする長期的な視点が必要だ」と話す。 <地方の豊かさ> PS(2018年3月29日追加):*9-1のように、鹿児島県志布志市のJAそお鹿児島ピーマン専門部会は新規就農者育成の先進地として有名だそうだ。しかし、近年は農業法人もできたため、最初は農業法人で給料をもらって働きながら技術を学び資金を貯めて独立する方法もあり、こちらの方が新規就農者にとっては経済的不安がないかもしれない。どちらにしても、稼げる農業を行えることが前提になる。また、*9-2のように、人口減による収入減で小規模な市町村の水道事業の経営が厳しくなるそうだが、こういう地域は、都会のように不潔で不愉快な過度の節水を行う必要はなく、水道の水を飲んだり、新鮮な農水産物を食べたりすることも可能で、暮らしは豊かなのである。さらに、きれいな水が余っている場所なら、ミネラルウオーター・炭酸水・お茶などを作ったり、電気分解して水素燃料を作ったりすれば、水も収入源にできる。 *9-1:https://www.agrinews.co.jp/p43654.html (日本農業新聞 2018年3月28日) [未来へ2]小さな一歩積み重ね 技術も農地もない都会の若者が次々と就農する産地がある。新規就農者育成の先進地として全国でも有名な鹿児島県志布志市のJAそお鹿児島ピーマン専門部会。部会92人のうち7割が農外からの就農者で、平均年齢は40代。就農し子どもを育て家を建てるIターンを見て、「農業では生活できない」と思い込んでいた地元の後継者が就農するケースも目立つようになった。新規就農の実績を残してきた。だが、それでも、地元の農家やJA、農業公社の担当者は口をそろえる。「若者育成に成功した地では、決してない」と。研修生を呼び込み、国に先駆けて就農支援の仕組みを構築したが、当初は夜逃げ同然に都会に戻ったり、地域住民と衝突したりする若者もいた。地元農家の有野喜代一さん(51)は「失敗をいっぱい経験した。ただ、実績が上がらなくても、ばかみたいに長年若者の受け入れを続けてきた」と振り返る。若者と地元農家が価値観やルールの擦り合わせを「一歩ずつ積み重ねただけだ」と言う。その模索は今でも続く。年間300もの視察を受け入れる同部会。恵まれた日照条件やJA、行政の連携体制など、「特殊事例」と見られることも多い。だが、目に見える好条件だけに、若者が引き寄せられるわけではない。鹿児島市から移住し研修中の安田有佑さん(27)は「移住や就農の条件で挑戦の地を決めたわけではなく、紹介してもらった縁が大きい」と明かす。縁が生まれたのも、地域が危機感を持ち、努力を重ねてきた裏返しでもある。新規就農を分析するJC総研の和泉真里客員研究員は、先進地に対し他の産地やJAは、「あの地域だからできた」と別格扱いし、学ぶ姿勢を持たない場合が多いと感じている。「素人の若者を農家に育てる道のりは、ひたすらに地道で時間がかかる。営農指導員や先輩農家が温かく声を掛ける、小さくても具体的な取り組みをまずはまねすることが、若者育成のポイントだ」と指摘する。地方創生の“トップランナー”とされる島根県海士町。若い移住者を多く受け入れ、高校を再生するなど、数々の取り組みを実践する。群馬県出身で、同町に移住した農家、宮崎雅也さん(36)は、地方創生について、自らの体験を基に、こう感じている。「夢を抱いて入ってくる若い世代と地域を長年守ってきた高齢者たちが連携し、息長い取り組みを積み重ねるしかない」。若者と築く農業・農村の未来には、正解も特効薬もない。長い年月を要する。模索する道のりに、若者が育つ可能性が見えてくる。 <現場からの提言> ・世代間連携を密に ・特効薬はない、息長く ・先進地の経験に学ぶ *9-2:http://qbiz.jp/article/130444/1/ (西日本新聞 2018年3月26日) 水道事業の維持策検討 人口減少による料金収入減に備え 総務省は、小規模な市町村を中心に今後、人口減少で料金収入が減り、水道事業の経営が厳しくなるとして対策の検討に乗り出した。有識者研究会が、料金値上げの在り方や広域化推進などサービス維持策を話し合い、10月ごろ報告書をまとめる。水道事業は原則、市町村が経営する。水の需要は、人口減や節水機器の普及で減っており、厚生労働省は、2065年には00年の6割程度になると推計。料金収入は04年度をピークに減少している。一方で高度経済成長期に整備した水道管などが老朽化、改修費用の増加が見込まれる。総務省は、周辺との事業統合といった広域化や民間委託の検討を促してきた。しかし地理的な問題や料金に開きがあることなどが理由で、自治体間の調整が進まないケースがある。研究会は、人口規模に応じて収支を試算し、適正な料金の値上げ幅を検討。事業全体の統合が難しい場合の対策として、情報通信技術(ICT)を活用した一部連携の有効性を探る。民間委託の推進策や国の支援策も検討する。 PS(2018年3月29日追加):*10-1のように、総合商社は優秀な男子大学卒業生を集めながら、他国より高い価格で原油を購入することしかできず(そんなことなら、誰でもできる)、他産業に迷惑をかけてきた。そのため、エネルギー改革に伴い、原油・石炭・ウランなどのエネルギー資源の輸入に携わっていた外国語のできる社員の多くを農林水産物や水素燃料の輸出に回し、しっかりした市場調査の上、高い付加価値で輸出できるようにしたらどうかと考える。なお、*10-2のように、九州7県の工場立地件数が前年比18.8%増で、食料品が最も多く、輸送用機械器具や金属製品も増加したのはよかった。 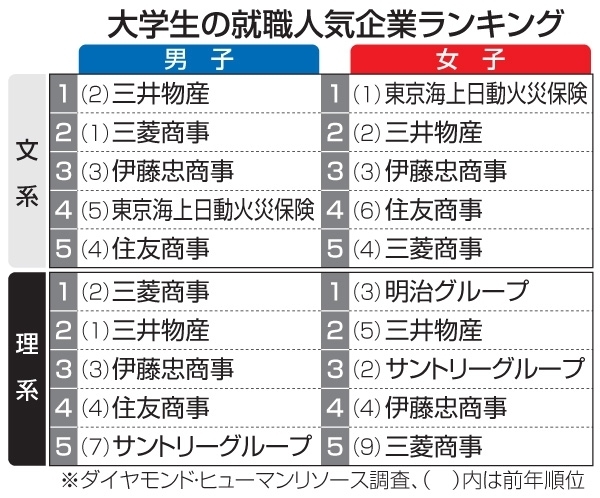 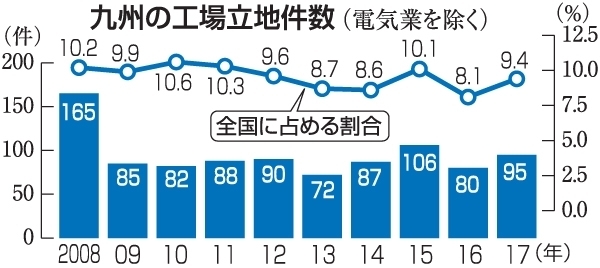 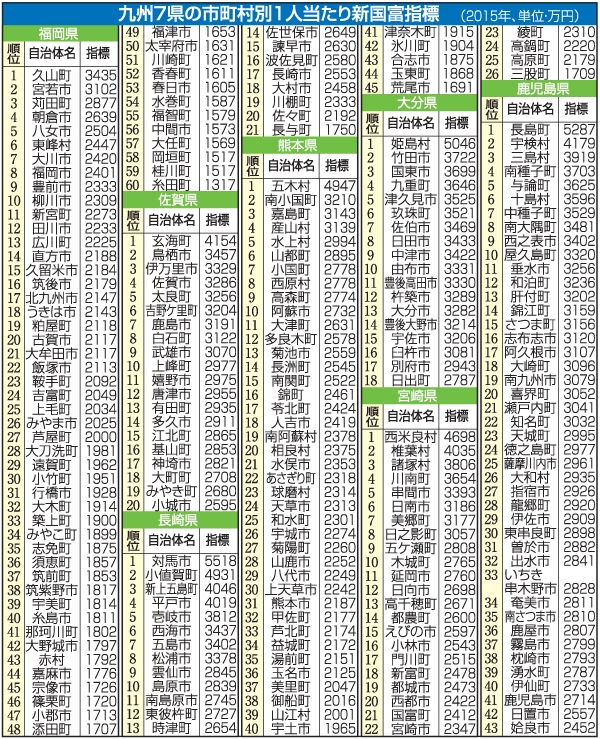 大学生の人気就職口 九州の工場立地件数 新国富指標(豊かさ) *10-1より *10-2より 2018.3.26西日本新聞 *10-1:http://qbiz.jp/article/130722/1/ (西日本新聞 2018年3月29日) 男子は総合商社が上位3社独占 大学生の就職人気企業ランキング 就職情報会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース(東京)が28日発表した2019年卒業予定の大学生らの就職人気企業ランキングによると、男子文系の首位は三井物産で、上位3社を総合商社が独占した。人気を誇ってきた銀行は、26年ぶりに10位以内に一つも入らなかった。女子の首位は文系が3年連続で東京海上日動火災保険。理系は明治グループだった。女性が長く働きやすい環境づくりが評価されたとみられる。銀行の低迷について、ヒューマンリソース社は「マイナス金利政策に伴う事業環境の厳しさや、人工知能(AI)活用による業務量削減などが影響した」と分析している。 *10-2:http://qbiz.jp/article/130695/1/ (西日本新聞 2018年3月29日) 九州の工場立地 18.8%増の95件 リーマン後2番目の高水準、設備投資が活発化 九州経済産業局が28日発表した2017年の九州7県の工場立地件数(電気業を除く、速報)は前年比18・8%増の95件だった。工場立地面積は同2・4倍の139・3ヘクタール。いずれも2年ぶりに前年を上回り、リーマン・ショック後の2009年以降、2番目に高い水準となった。全国に占める工場立地件数の割合は9・4%と前年から1・3ポイント、工場立地面積の割合は11・3%と6・1ポイント上昇した。業種別では、食料品が最も多い25件で、前年を上回った。輸送用機械器具(15件)、金属製品(11件)も増加した。県別では、福岡県(34件)、長崎県(12件)、熊本県(13件)、宮崎県(12件)で増加。佐賀県(7件)と鹿児島県(10件)は横ばいだった。大分県(7件)は前年を下回った。設備投資予定額は1134億円で、6年ぶりに1千億円を超えた。予定従業員数は3395人で前年のほぼ2倍となった。経産局は「投資見込みの伸びに歩調を合わせて、工場立地としての用地取得が伸びたのではないか」とみている。 <ふるさと納税と農林漁業> PS(2018.3.30追加):*11の「ふるさと納税」は、①子どもの教育費や高齢者の医療・介護費を地方が負担しながら、生産年齢人口になると都会に住んで税を支払う人が多いため、地方が財政難に陥る構造を緩和すること ②主権者である納税者が使い道を指定して寄付する文化を育てること などを目的として、私が提案してできたものである。その私は、返礼品の割合を指定するなど、総務省が地方自治体の箸の上げ下ろしにまで口を出すことには反対で、何をどうするかは寄付を受ける地方自治体が決めるのがよいと考える。もちろん、返礼品を地場産品にした方がその地域の産業振興に寄与するが、それには地域の工芸品も含んでよい筈で、それは寄付を受ける自治体と寄付をする納税者が選択することで、総務省が指示すべきことではないように思う。ところで、今年の自治体別「ふるさと納税額」とその順位はどうだったのだろう?      梅 桜と菜の花 桃 梨 みかん (問題:どの順番に、また何月に咲くか、知っていますか?) *11:http://www.sankei.com/economy/news/180328/ecn1803280003-n1.html (産経新聞 2018.3.28) ふるさと納税の返礼品に地場産品を! 総務省が通知へ 総務省が「ふるさと納税」の返礼品について、原則として地場産品とするよう地方自治体に求める通知を近く出すことが27日、分かった。納税額を増やすため、他地域の特産品やカタログギフトなどを返礼品にする自治体も出てきている。通知を通じ、生まれ故郷や被災地に対する貢献や、地場産業の振興といったふるさと納税の本来の趣旨を徹底する狙いがある。総務省は昨年4月の通知で、返礼品の調達額を寄付額の「3割以下」とする目安を示したほか、商品券や家電など換金性や資産性の高いものは送らないよう求めた。今年の通知では、初めて返礼品を地場産品とするよう自治体に適切な対応を求める。ただ、姉妹都市の特産品は可能とするなど例外も認める方向だ。背景には、自治体間の返礼品競争が過熱し、「ふるさと納税の趣旨とかけ離れてきている」(政府関係者)という現状がある。具体的には、佐賀県の自治体が北海道夕張市の「夕張メロン」を、長野県の自治体がフランス産高級シャンパンを返礼品にしたり、岐阜県の自治体が「松阪牛」などが選べるカタログギフトを返礼品にしたりするケースがあった。 <農業の後継者と法人化> PS(2018年3月31日追加):*12-1のように、大分県産の干しシイタケ生産量が高齢化と後継者不足で半数以下に減ったのは、それを使っている私にとっては人事ではないが、農業生産法人にして人を雇用すれば、品質を維持しながら生産を続けられるのではないだろうか。また、*12-2のように、Iターン・脱サラでアスパラを生産して成功している人もいる。なお、佐賀県のアスパラは、このブランドではないが、関東でも販売され、私も使用している。 *12-1:http://qbiz.jp/article/130913/1/ (西日本新聞 2018年3月31日) 干しシイタケ生産者激減に危機感 30年で半数以下、平均73歳 生産量トップの大分県、移住研修者に給付金 干しシイタケの生産量が全国トップの大分県。一方で、高齢化や後継者不足により、生産者がここ30年近くで半数以下に減っている。危機感を強める大分県は2018年度から後継者育成の新事業を実施する。3月下旬、大分県別府市の天間地区。スギ林の下に、長さ約1・2メートルのクヌギの原木がずらりと並ぶ。原木に生えたシイタケを、小川健(たてき)さん(70)が次々と収穫していた。この道30年以上のベテラン。昨年の「第65回全国乾椎茸(ほししいたけ)品評会」(日本椎茸農業協同組合連合会など主催)で最高賞の農林水産大臣賞を受賞した腕前だが「まだ満足していない」と、品質向上に余念がない。作業は妻康子さん(66)と2人。子ども2人は独立し「後継者がいないのが悩み」という。県によると、県内の干しシイタケ生産者数は1989年が9406だったが、2016年は半分以下の4015に減少。高齢化も進み、平均年齢は16年時点で73歳だ。原木を伐採する作業が重労働で、後継者不足を招いているという。生産量も16年は1144トンで、2302トンだった1989年の半分以下。それでも全国の4割以上のシェアを誇る。技術力も高く、第65回全国乾椎茸品評会で、大分県は19年連続51回目の団体優勝を果たした。県は「質、量ともに日本一の全国ブランドを守り続けたい」と、18年度から後継者育成の新事業を導入する。県外から移住して干しシイタケづくりの研修に取り組む55歳未満の人に、年間50万〜75万円を給付する。給付金の半額は受け入れ市町村が負担、研修先は優良生産者が担う。小川さんも「習いたい人がいれば喜んで教える」と意気込む。「50代でも十分若手」と県の担当者。収入については「生産規模が小さいうちは専業で生計を立てるのは難しいが、作業が一段落する夏場に別の仕事をすれば大丈夫」としている。県林産振興室=097(506)3836。 ◇ ◇ ●中国産に押され生産量大幅減少 林野庁によると、全国の生シイタケ生産量はここ約30年、年間6万5千〜8万トン前後で推移。これに対し干しシイタケは1986年の約1万4千トンから、2016年は2734トンと大幅に減少した。干しシイタケは水で戻す手間がかかり、消費が減少していることが背景にある。安い中国産に押されている面もある。シイタケ生産は屋外での原木栽培と屋内での菌床栽培がある。大分県によると、干しシイタケは原木栽培が中心。菌床栽培で育つシイタケは、乾燥させると小ぶりになるためという。大分県に続く干しシイタケの生産地は宮崎県(16年に523トン)で、3位は熊本県(205トン)。大分、宮崎、熊本の3県で全国生産量の7割近くを占める。 *12-2:http://qbiz.jp/article/128119/1/ (西日本新聞 2018年2月18日) Iターン就農の成功モデルに 脱サラ後アスパラ生産 佐賀・太良町の安東さん 佐賀県太良町多良のアスパラガス農家、安東浩太郎さん(38)がIターン就農の成功モデルとして注目されている。“脱サラ”して大阪市から移り住み5年前に栽培を始め、独自の生育方法と販路を確立した。多良岳の清らかな水で育てた商品は「森のアスパラ」としてブランド化し、東京の八百屋や福岡の飲食店に直接出荷している。今春からは研修生を受け入れる予定で培った技術の普及にも力を入れる。 ●独自の栽培、経営確立 林野庁の「水源の森百選」に認定された多良岳のふもと。南向きで日当たりの良い標高約150メートルの山肌にビニールハウス14棟(計約30アール)が並ぶ。「夏は平地より涼しく風通しがいい。高温障害になりにくいこの土地はアスパラ作りに最適です」。1月下旬、安東さんは2月末〜10月末の収穫期に向けてハウス内に堆肥をまいた。北九州市出身。2002年に福岡県内の大学を卒業し、大阪市内で不動産会社などに勤務した。「退職後は地元の九州に戻って、のんびり自給自足の生活をしよう」と考えていた。転機は09年1月だった。同市であった就農支援のイベント「新・農業人フェア」で吉野ケ里町の農業法人に興味を持つ。「農業は担い手の高齢化が進んでいる。若いうちに参入した方がビジネスチャンスがあるはず」。意を決して10年4月に会社を辞めた。 ■ ■ 吉野ケ里町の農業法人で2年間、キャベツやコメの生産と経営を学び、妻の美由紀さん(37)の出身地、太良町で営農しようとしたが農地が見つからなかった。農協の契約社員として同町や鹿島市の農家を手伝い、地元との信頼関係を築くうちに知人から荒れたミカン畑を紹介された。安東さんは同町で盛んなミカン栽培での競争を避け、植え替えが不要など初期投資を抑えられるアスパラに懸けることにした。県と太良町の補助金を活用してハウスの整備を進めて13年に農業に就いた。「ベテラン農家との違いを出すため出荷量より味で勝負する」。液肥、固形、化学、有機など複数の肥料を試し、一番アスパラに合う肥料を選んだ。酸性の土壌を中和するため、カルシウム分を含む竹崎カニやカキの殻を肥料に混ぜた。試行錯誤の末に商品化した森のアスパラは鮮やかなエメラルドグリーン色が特徴で筋が少ない。みずみずしくて軟らかいので生でも食べることができる。料理人からは「うま味が強い」「味が濃い」と好評だ。 ■ ■ 安東さんは農業団体を介さずに直接出荷している。「肥料の種類や出荷先、収量は全て自分で決める。補助金をうまく使って栽培法を研究すれば農業の独立経営やブランド化は可能」と力を込める。小規模事業者の経営相談に無料で応じる「県よろず支援拠点」の協力でホームページを作成し、独自のロゴもデザインした。Iターン就農のモデルとして県から評価され、本年度の佐賀農業賞「若い農業経営者の部」で最優秀賞に輝いた。今春からは、希望者に無償で農業技術や経営について教える。「農地探しやビジネスを確立するまでに苦労した経験を研修生に伝えたい」と意気込む。研修を予定する熊本県出身の元会社員の冨士川聡さん(39)は「友人やお客さんに農作物で喜んでもらい、感謝の声を聞きながら働くのが夢」と目を輝かせる。安東さんは「太良にはカキやカニ、金星佐賀豚、牛肉と『うまかもん』がたくさんある。大好きなこの町にどんどん移住者が来るようにしたい」と話し、町の活性化にも一役買う。
| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 04:21 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2017,08,10, Thursday
   (図の説明:日本では大型の田植機は増えてきたが、その他の作物での自動化は進んでいない。その理由には、大型機械導入を前提とした田畑の区割りになっていないこと、農機の価格が高すぎることなどがあるが、これは農協の努力を超えており、これまでの国の政策の問題が大きい) 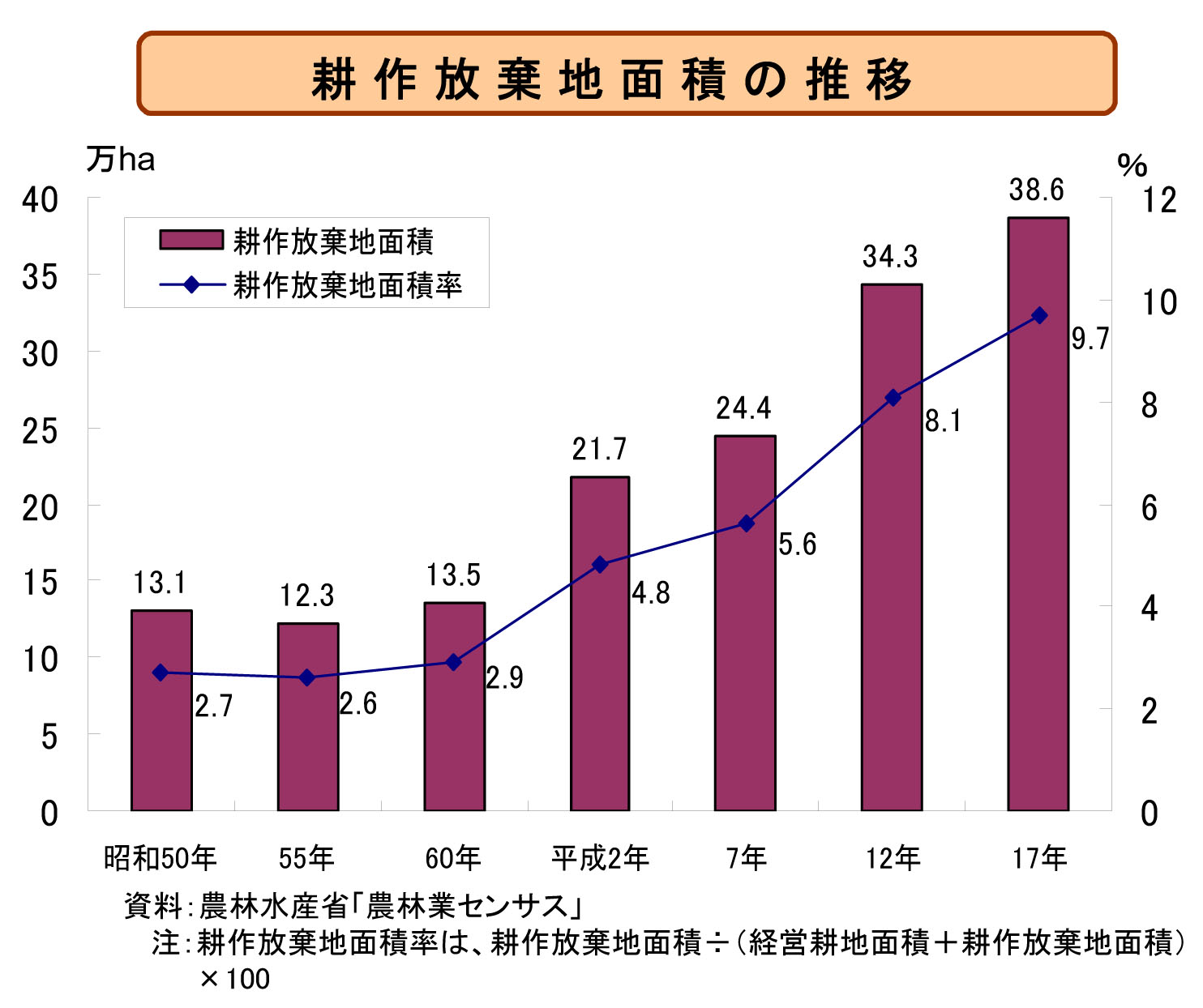   日本の耕作放棄地 オーストラリアの放牧と機械化された搾乳風景 (図の説明:国は、主食米に多額の補助金をつけ耕作面積を制限しながら、他の作物への転作を促さなかったため耕作放棄地が増えた。一方で、豪州の畜産は、右の写真のように大規模な放牧で行われており、日本も飼料用米に多額の補助金をつけるよりも賢い土地の使い方がある筈だ) (1)JAの改革 1)JAさがの持株会社発足 JAさがは、自己改革の目玉として全国の地域農協で初めて、2017年7月21日に、*1-1のように、農産物加工や購買生活関連といったグループ会社9社を傘下に置く持株会社2社を設立し、当面は中期の企画・戦略策定、総務管理部門の集約に注力して、業務の効率化・商品開発等に力を入れるそうだ。私は、農業者の共同体である農協を株式会社化するのではなく、農協の下に持株会社をつけるのがあるべき姿だと考えている。 ちなみに、持株会社制度と連結納税制度は、私がフランスの事例の経験から1995年前後に経産省に提案し、持株会社制度が1997年に解禁され、連結納税制度は2002年度の『税制改正大綱』で100%子会社、孫会社などに限って実施されることになったものだ。 そして、持株会社の下に、①企画部門 ②総務管理会社 ③食品会社 ④人材派遣会社 などをつければ、①は全体を見渡して企画立案でき、②はそのことに熟練した人が関係会社の総務・経理をまとめて面倒見ることによって効率的で質の高い仕事ができるとともに、受託料をもらって農業者の会計・管理を受託することもでき、③は加工・販売を行う食品会社と合弁企業を作れば、お互いのノウハウをつぎ込んで経営する最先端の組織を作って生産性を上げることができ、④は繁忙期に人材派遣を行えば、農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化に繋げることができる。 そのため、JAさがの大島組合長が全国から注目を集める取り組みであることを強調して「絶対に成功させなければならない」と強い決意を語られたのは心強いし、頑張って欲しい。 2)JA全中次期副会長にJA佐賀中央会の金原会長内定 このように、佐賀県のJAは先進的な試みを率先して取り入れたため、*1-2のように、全中副会長にJA佐賀中央会会長金原氏が内定した。次は、持株会社での実績を携えて、JA全中次期会長になれれば嬉しいと考える。 3)JA全農の新執行部 JA全農の新執行部が始動し、*1-3のように、長澤会長は「『全ては組合員のために』の姿勢を貫き、全農の自己改革を完遂する」と強調されたそうだ。私も、産地再生、生産基盤作り、新技術駆使、業務提携などを含む生産力・販売力の強化、生産資材の引き下げなど、農業者の所得向上と地域再生を目的として自己改革すればよいと考える。なお、農家所得増大のためとして特殊な資材の引き下げのみに固執するのは、政府がやるようなことではない。 また、農業は、同じ地域に存在し土地所有者が同じであるという意味で林業と関係が深く、同じ食品であるという意味で水産業とも関係が深い。そのため、漁協や森林組合も持株会社形式で会社を作り、食品会社など協働した方がよいケースでは合弁会社にした方が販売力がより強化できるので、地元の公認会計士・税理士とケースに応じた相談をした上で、具体的な対応を決めるのがよいと考える。 (2)JA全厚連とJAバンクについて 1)JA全厚連について 農家は共働きが一般的で妻の働きも所得に直結するため、JAは、*1-4のように、医療・介護を行う全厚連をもっている。そして、今回、その会長にJA長野厚生連会長の雨宮氏、副会長にJA愛知厚生連会長の前田氏、理事長に中央コンピュータシステム社長の中村純誠氏が選任されたそうだ。 私は、医療・介護を一体としたコンピュータシステムによる管理は、効率化や生産性の向上に役立つと思うが、これまで連続して行われてきた医療費・介護費の削減によって赤字になった病院や介護施設が多いと思われるため、その対応も重要だと考える。 2)JAバンクについて 2008年のリーマンショック時には、みずほ銀行等の一般銀行と並んで農林中央金庫がアメリカのサブプライム住宅ローン(所定基準を満たさない顧客への貸付に対しては、より高い利率をとるローン)に融資し、借り手が破たんして大損していたので、私は本当にショックを受けた。 何故なら、サブプライム層が破たんしても、家は資産としてアメリカに残るが、日本の金融機関は単に損をしただけで、リスクが高い割に還元が少ない外国への融資に農村から集めた資金を出して大損していたからである。ちなみに、この時、地方では、投資すべき案件は多いのに投資が行われないため、生産性が上がらないという悪循環の状況だった。 しかし、JAバンクの貯金額は、*1-5のように、100兆円を超えたため、是非、豊富な資金力を生かして農業への融資拡大や地域重視で必要な投資をしてもらいたい。何故なら、そうすることが、今後の生産性の向上・販売力の強化・地域振興に繋がり、農村の魅力を増して人口回帰に資するからである。 (3)政府が進める農業改革について 中野吉実JA全農前会長が、*2-1に述べられているとおり、政府・与党が主導する農協改革は、「農協=悪い岩盤=農家とは利益相反関係にある」という誤った前提で叫ばれた。そして、提示された改革理由は、農機・化学肥料・農薬などの高価格への対応だったが、それらの高価格は農協よりも生産者の独占や寡占によるところが大きく、安価な有機肥料の利用・減農薬・農協と競争関係にある他の店舗からの購入などで解決できるものが多い。そのため、政府が既定路線にしている全農の株式会社化とは結びつかないものだ。 にもかかわらず、*2-2のように、農水省は8月中旬から農協改革の進捗状況調査に乗り出し、改革の重点を、①農産物の高値販売や生産資材の安値調達に向けた取り組み ②組合員の経営支援 ③改革を進めるための組織体制整備 とし、それが具体的にどの程度進んでいるかを確認して改善を働き掛けるそうだ。農水省は「JAと同じ目線で対話して課題の解決策などを探り、自己改革の実践を後押したい」と言っているそうだが、都会育ちの農水省職員なら、同じ目線どころか現場に同行して教えていただく形で調査すべきで、経営の専門家ではない官の口出しは経営を悪化させる懸念さえある。 その点は、現場をよく知っている知事会も懸念しており、*2-3のように、全国知事会は2017年7月27日に盛岡市で会議を開き、農業振興を柱とした「地域経済の好循環の拡大に向けた提言」を採択した。そして、農業振興を地域社会の基盤と位置付け、政府が定めた「農業競争力強化プログラム」を進めるに当たっては、農業・農村の実情を十分踏まえるよう求めたそうで、これには私も賛成だ。 しかし、安倍改造内閣の斎藤農相(経産省出身)は、*2-4のように、2017年8月7日に、JA全中を訪問し、引き続き安倍政権が進める農業・農協改革への協力を呼び掛けたそうだ。しかし、出向いてちょっと話したくらいで現場の問題点を正しく把握してよい改革案を提示できるわけがないため、結果ありきの話し合いにならないようにしてもらいたい。そして、斎藤農相が本気で農業改革に取り組みたければ、状況が全く異なる北海道・東北・北陸・中部・都市近郊・中国・四国・九州・沖縄・離島などの農業現場を回り、その地域でどういう農業が行われ、何に困っているのかを調査した上で、外国にも負けない生産性や販売力を持ち、土地を有効に利用して農家所得を増大させ、農業の魅力を作って積極的な担い手を増やす方法を考えるべきである。 なお、経産省は、自動農機具やコンピューター制御の温室など優秀な農機を安価に生産して提供するよう知恵を絞って欲しい。そうすれば、その農機はどの国でも重宝され、輸出可能でもある。なお、私は、報酬をもらって仕事でやっているわけではないので、*2-5の農業強化法は見ていないが、議論を聞く限り、良い方向に改革されているようには見えない。 (4)EPAについて 1)EPAとその交渉内容 私は、安全規制等の国家主権を放棄することになるTPPには反対だったが、EPAには賛成だった。何故なら、TPPの参加国は広大な農地を持つ国が多くて太刀打ちできそうもないが、EPAの参加国は広大な農地を持っているわけではないのに知恵と工夫で生産しているので、主権を放棄しない自由貿易が前提なら、日本の農業が学ぶところは大きいと考えたからである。 そのため、*3-2のように、交渉中に情報開示を行うことはその分野の専門家が見て意見を述べるために必要で、日本が相手国並みにも情報開示を行わないのは、交渉官が国民に見せられるような交渉をしておらず、国民には背信行為の結果ありきの交渉をしている証拠だろう。 2)自由度を高めさえすればよいのではないこと 日経新聞の論調は、*3-1のように、いつも経済の一体化を主張し、農業の将来を考えるためにも自由度を高めるべきだとする。しかし、そのEPA交渉では、自動車と酪農製品(特にチーズ)のバーター的な関税削減を巡って、交渉が最後まで難航したのだそうだ。 そのうち自動車については、EUとEPAを結んでいる韓国車が無税で輸出できるのに、日本車は10%の関税が課されてハンディであるため、自動車の関税撤廃は日欧EPAの大きな目的の一つだったそうだが、日本は人件費が高く、全体として高コスト構造になっているため、日本のグローバル企業は、人件費が安くて労働の質の良い東欧で生産することが多い。また、現在では、自動車もEVで遅れ始めているため、環境規制や本体価格の問題を抜きにして、関税だけで売れ行きがよくなるとは思えない。 一方、農業については、TPPを超える乳製品(特にチーズ)の関税削減が問題となり、出荷先にかかわらず加工用生乳はすべて補給金の対象となるそうだが、今まで指定団体に出荷しなければ加工用生乳に対する補給金が支給されなかったというのは、食料不足時代の食糧管理のやり方のようで、TPPやEPAとは関係なく、変えていなければならなかった問題だろう。 私は、欧州産のチーズは美味しく、種類も豊富で、よく工夫されていると思うが、日本産の食品も冷凍ピザのような中食にまで加工したり、健康志向を加えたりすれば、欧州では見られない商品ができると考える。そのため、欧州の人の口に合わせながらも、手間が省けて美味しく、健康に良い新しい食品に進化させれば、日本産チーズは関税0でもやれるのではないだろうか。 また、*3-1には、最先端にいるフロンティア農業者の自由度を高め、フロンティアを広げる政策が必要として、米の減反政策廃止が提言されている。しかし、そもそも主食用米ばかり作っても、その需要は日本国内が殆どであるため、だぶついて価格が低下し、生産したこと自体が無駄になりそうだ。これは、経済学における典型的な市場の失敗の例で、昔から世界中で起こっていることのようである。かといって、多額の補助金を使って飼料米生産に誘導するのも、甚だしい無駄遣いだ。 そのため、私は、足りない産品を作るように転作すればよいと思うのだが、「日本の農家は、どうして米ばかり作りたがり、足りない産品に転作しないのか?」と問うと、「米を作れば機械化でき、何かと楽で兼業農家でもできるから」という答えが、(特に東北の農家から)返ってくる。私は、ここが問題の本質で、他の産品に転作しても損をせず、機械化でき、保険や作業システムを整えて、兼業しなくても生活できる所得を得られるようにすべきだと考える。そうすれば、余剰な米ばかりを作りたがり、耕作放棄地を増やしながら、食料自給率は低いという日本の変なシステムを変えられると思うが、これは決して農協だけの責任ではない。 なお、EPAやTPPについては、*3-3のように、「経済規模が大きく自由化度が高いのが優れているとの論調は経済学的に間違いだ」とする注目すべき意見もある。 3)食料自給率と安全保障 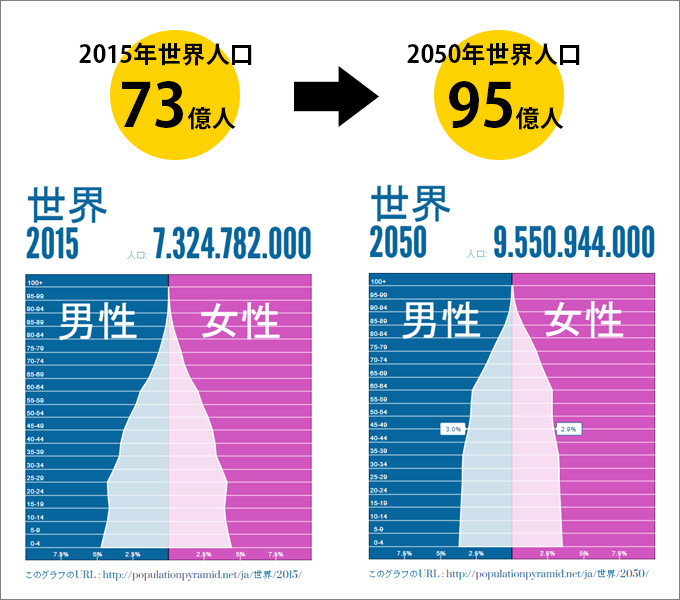  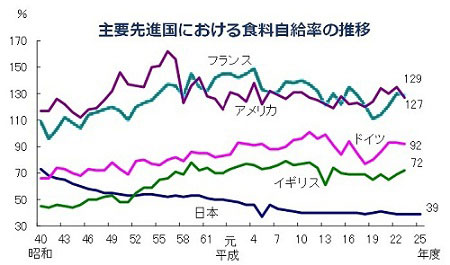 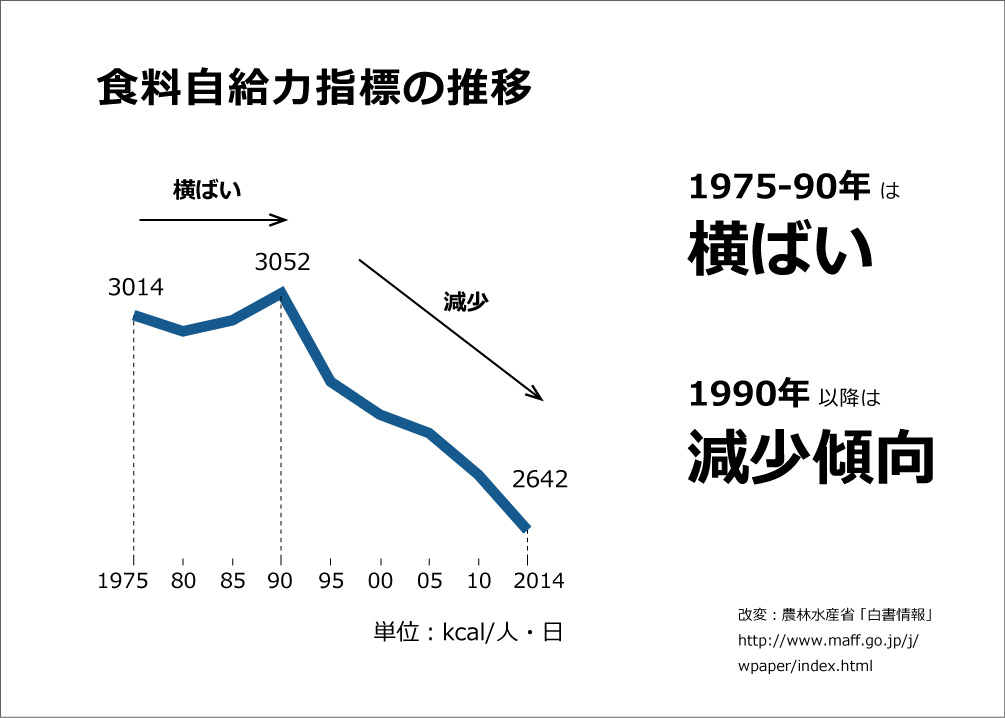 世界の人口増加 食糧不足の発生リスク拡大 主要先進国の食料自給率 日本の食料自給率 (図の説明:一番左と左から2番目の図のように、世界人口は2050年には95億人になることが予想されており、気候変動による生産減も起こる。そのため、右から2番目のグラフのように、どの先進国も農業を疎かにはしておらず食料自給率が高いが、日本だけ著しく低い。その日本の食料自給率は、一番右の図のように、1975~1990年の間はほぼ横ばいだったが、1990年以降は下降の一途を辿っており、政府が「国民の命と健康を守る」と言うのは白々しく聞こえる) *3-1は、「日本農業が活路を見いだすには、市場を世界に求めなければならず、そのためには関税なき貿易が必要で、それを前提に日本の農業の構築を考えなければ、農業の産業としての独り立ちは見えてこない」としている。 しかし、*3-4、*3-5のように、食料自給率は減り、食料の安定供給を果たす「食料安全保障」はさらにおぼつかなくなった。それについての拙い言い訳は不要であり、食料はカロリーだけでは不十分であるとともに、価格だけでは話にならないことは、中等教育以上で栄養学を学んだ人(殆ど女性)なら常識だ。 なお、*3-4の「低自給率を強調するよりも、消費者に選ばれる農産物をつくり、輸入に対抗できる競争力を磨いていけば、おのずと国内農業の供給力が高まるのではないか」という部分は、世界人口の予測と世界の食糧事情を無視し、農業生産を行うには生産基盤や日進月歩する機械・技術・種子が必要であることを無視した、驚くべき楽観論である。 <JAさがの持株会社発足> *1-1:http://www.saga-s.co.jp/column/economy/22901/448475 (佐賀新聞 2017年7月22日) JAさが持ち株会社発足 効率化進め商品開発強化、地域農協初自己改革の目玉 JAさが(大島信之組合長)は21日、農産物加工や購買生活関連といったグループ会社9社を傘下に置く持ち株会社2社を設立した。業務の効率化を進めて商品開発などに力を入れる。8月1日から業務を始め、当面は中期的な企画・戦略の策定と、総務管理部門の集約に注力する。持ち株会社化は、「農協の一員としての自覚とガバナンス(企業統治)の強化」「事業統合によるコストダウン」「会社の枠を越えた商品開発」の3点を主眼に置く。政府・与党が農協改革に力を入れる中、農業者の所得増大、生産の拡大、地域の活性化につなげようと、JAさがが自己改革の目玉として、全国の地域農協で初めて打ち出した。設立したのは、「JAさが食品ホールディングス(HD)」と「JAさがアグリ・ライフホールディングス(HD)」。JAさがグループ15社のうち9社がぶら下がる。食品HDは、JAフーズさがとジェイエイビバレッジ佐賀、JAさが富士町加工食品の3社を傘下に置く。社長には大島組合長が就き、大手からのOEM(相手先ブランドによる生産)のほか、独自ブランドを開発し、地域の農畜産物を全国に発信する。宅配や通販事業などにも取り組む。アグリ・ライフHDの傘下には、JA建設クリエイトさがやJAオート佐賀など6社が入る。タマネギやミカンの収穫など農家の人手が足りない繁忙期に人的支援をしたり、農業経営に参画して農地を活用したりして、担い手育成に努める予定。JAさがの中村直己副組合長が社長を務める。2016年度のグループ15社の総売上高は約680億円。持ち株会社の傘下に入っていない残り6社については引き続き、HD編入に向けた準備、検討を進める。佐賀市の県JA会館で行われた設立総会で、JA佐賀中央会の金原壽秀会長は「それぞれがさらにもう一段パワーアップして、農家、組合員、地域の評価をいただけるように飛躍を遂げてほしい」とあいさつ。大島組合長は、全国から注目を集める取り組みであることを強調し、「絶対に成功させなければならない」と強い決意を語った。 *1-2:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/450623 (佐賀新聞 2017年7月30日) 金原氏、全中副会長に JA佐賀中央会会長、県出身者で初 来月正式決定 全国農業協同組合中央会(JA全中)の次期副会長に、JA佐賀中央会の金原壽秀会長(67)=杵島郡江北町=が内定したことが29日、分かった。JAグループの独立的な総合指導機関であるJA全中の副会長に県出身者が就任するのは初めて。8月10日の全中臨時総会で正式に決定する。 金原氏はJAさがの理事や常務理事を経て、2014年から組合長を1期務めた。6月30日の通常総会でJA佐賀中央会の会長に就任した。中央会の前会長である中野吉實氏(69)は11年から今年7月25日まで2期6年、全国農業協同組合連合会(JA全農)の会長を務めた。佐賀の中央会トップが2代続けてJA全国組織の要職を務めることになる。JA全中の次期会長にはJA和歌山中央会の中家徹会長が内定。もう一人の副会長には、中家氏と会長選で競ったJA東京中央会の須藤正敏会長が就く見込み。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p41464.html (日本農業新聞論説 2017年7月27日) 全農新体制と改革 結集こそ組織の「底力」 JA全農の新執行部が始動した。陣容は「改革加速内閣」とも言えよう。営農経済事業を担う全農は、系統組織のいわば“心臓部”だ。役割発揮はJA自己改革の成否に直結する。事業改革の年次計画に沿った着実な実践と、内外への「見える化」が欠かせない。組織の結集力と求心力こそが大きな鍵を握る。新執行部の使命は、会見で長澤豊会長が強調した「『全ては組合員のために』の姿勢を貫き、全農の自己改革を完遂する」ことに尽きる。最終ゴールは、農業者の所得向上を通じた元気な地域の復活だ。全農はこれまでも多様な事業改革を実施してきた。いま力を入れるべきことは、改革加速化と併せ、農業者の営農と経営にどう結び付くのかの「見える化」である。組織内外への広報強化は、経済事業への組合員の理解と納得にもつながる。理不尽な全農批判の防波堤ともなる。「全ては組合員のために」は、何のための組織なのかを改めて自らに問う原点回帰宣言でもあろう。産地再生、生産基盤づくり、新技術の駆使、新たな業務提携も含む販売力強化、生産資材の引き下げ。農業者の所得向上と地域再生にはトータルコストの引き下げが重要だ。資材下げなど一分野だけをあげつらうのは見当違いだ。その意味では、全農が全国55JAと取り組むモデル事業は、今後の総合的なコスト下げに向けて全国展開の礎となり得る。「ゴーゴー作戦」として、地域農業再生への旗振り役を果たしてもらいたい。意欲的な数値目標を掲げた全農の事業改革年次計画だが、滑り出しはほぼ予定通り。だが、本番はこれからと言っていい。年次計画は年を追うごとに大きな目標値となっているだけに、この1、2年が正念場となる。自己改革完遂へ残された時間は少ない。政府・与党の改革フォローアップや2019年5月とされる改革集中期間の最終期限も2年を切った。代表理事体制も一新した。新理事長の神出元一氏はこれまで専務として全農改革に関わり、政府・与党との調整の陣頭指揮を担ってきた。専務となった岩城晴哉氏は外食大手・スシローと業務提携するなど、米・園芸の販売事業強化を進めた。もう一人の山崎周二氏は改革の本丸となった生産資材引き下げなど、購買事業見直しの具体案を取りまとめた。改革加速化に期待したい。一方で、農政改革では政府の責任こそが問われなければならない。民間組織の全農ばかりに改革努力を迫るのは間違いだ。通常国会冒頭での安倍晋三首相の施政方針演説に大きな違和感を覚える。「農政新時代」の項目で「農家のための全農改革」を挙げた。首相自ら民間組織の具体名を挙げることは極めて異例だ。政権による「全農先行」改革の意図が透けて見える。政府は全農自己改革を後押しする姿勢に徹するべきだ。 *1-4:https://www.agrinews.co.jp/p41476.html (日本農業新聞 2017年7月28日) 全厚連 会長に雨宮氏(長野) JA全厚連は27日、東京都内で通常総会後に経営管理委員会を開き、会長に雨宮勇氏(JA長野厚生連会長)を選任した。空席になっていた副会長には前田隆氏(JA愛知厚生連会長)を選任した。加倉井豊邦会長は同日付で退任した。理事長に、中村純誠氏(中央コンピュータシステム社長)を選任。総会では、経営管理委員16人を選任し、そのうち9人が新任した。任期は2020年度の通常総会終了まで。 *1-5:https://www.agrinews.co.jp/p41520.html (日本農業新聞論説 2017年8月2日) 農協貯金100兆突破 協同組合こそ明日開く JAバンクの貯金額が100兆円の大台を超えた。計画目標よりも1年前倒しの達成は、組織結集力の結果である。大台達成を契機に、いま一度、地域や農業の足元を見直し、協同組合金融の特色を確認したい。根底には、組合員目線に立ち地域重視で利用者第一の考え方がある。JAの総合力の発揮こそが持続可能な社会づくりの「明日」を開くはずだ。金融の根幹は「信用」である。信用事業と言われる理由だ。貯金額が100兆円を突破したのは、JAバンクへの組合員・利用者の「信用」の表れである。健全経営の徹底や万が一の事態へのセーフティーネット(安全網)の整備など、金融機関として安全・安心が評価されてきた結果とも言えよう。農林中央金庫のリテール事業本部長を務める大竹和彦専務は、日本農業新聞のインタビューで「JAの総合事業、地域での人と人とのつながりこそが他金融機関にない強さ」と強調。協同組合金融の特色発揮が、揺るぎない「信用」につながっている。運動体でもあるJAグループは、目標を掲げた組織展開に強みを持つ。100兆円達成も運動の成果の一つだ。歴史をさかのぼれば、協同組合は信用事業の確立と重なる。組合運営の原則を制定した英国のロッチデール公正先駆者組合設立は1844年。日本はその1年前の43年、江戸時代に二宮尊徳が基金をつくり困窮した農民に無利子で貸し出す報徳社をつくった。協同組合の原点の一つである。尊徳は600もの村落で協同の精神で地域復興を果たす。JAバンクを束ねる農林中金は、6年後に創業100周年を迎える。前身の産業組合中央金庫は関東大震災の直後、1923年末から営業を開始した。協同組合金融は地域の復興・再生の歴史と共に歩み発展してきた。こうした歴史的な経過をしっかり踏まえたい。今後の課題は「ポスト100兆円」の戦略だ。少子高齢化、日銀のマイナス金利の影響などで、金融業界は大きな岐路に立つ。地域金融機関を中心に合従連衡の動きが活発化してきた。系統信用事業も、地域単位では次の目標を検討するだろうが、数値で全国一本の“旗”を掲げる時代とは明らかに異なる。時代の変化を踏まえ農林中金は、JA全農や関連企業との連携を強め、食農ビジネスを本格化させている。豊富な資金力を生かした農業融資の拡大、担い手育成は喫緊の課題だ。「食と農、地域の振興のためにできることは何でもやる」と食農法人営業本部長を務める宮園雅敬副理事長。新たな一手として、組合員の資産形成のため投資信託などを推進する「JAバンク資産形成推進部」を新設した。「ポスト100兆円」をどうするのか。模索は続くが、基本路線は営農経済事業をはじめ地域に根付くJAの総合力、相互扶助を歴史的な原点とした協同組合金融の強さのはずだ。 <政府が進める農業改革> *2-1:https://mainichi.jp/articles/20170730/ddm/008/020/116000c (毎日新聞 2017年7月30日) 中野吉実・JA全農前会長:農協への圧力、再燃を懸念 全国農業協同組合連合会(JA全農)会長を今月退任した中野吉実氏(69)が29日までに共同通信のインタビューに応じ、政府、与党が主導した農協改革を「(日本農業が低迷する現状を踏まえ)誰かを悪者にしないと駄目だったのだろう」と振り返り、改革が再燃し農協への圧力が強まりかねないとの懸念を示した。JA全農の株式会社への移行は「絶対すべきでない」と強く否定した。2011年7月から2期6年にわたる在任中、政府の規制改革推進会議などから組織縮小やコメ全量買い取りなどを求められたほか、自民党の小泉進次郎農林部会長から組合員に提供する農機や肥料などが高すぎるとして改革を迫られた。中野氏は、農家の所得向上を目指すとの方向性は政府と一致しているとした上で、「農協が力を付け、組合員に還元できるようにしていく」ことが重要だと指摘した。在任中の成果として17年3月に自己改革をまとめたことや、コメの安定的な出荷先確保のため回転ずしチェーン大手「あきんどスシロー」の持ち株会社に出資したことを挙げた。その上で「農協と農家が一緒に努力し生産性を高めていくことが所得向上につながる」との認識を示した。政府、与党で議論されたJA全農の株式会社化に関しては「海外では農協が株式会社化した後、穀物メジャーに買収された例がある。農家を守る立場の組織がなくなったら元も子もない」と改めて反対を表明した。政府は18年産米から生産調整(減反)を廃止するが、「米価が下がらないようJAグループが各地の収穫量を配分する。それができることが前提だ」とし、コメ農家に大きな影響は出ないとした。 ■ことば:全国農業協同組合連合会(JA全農) JAグループで商社機能を担う全国組織。肥料や農薬といった生産資材を農家に供給するほか、農産物を集めて販売する。事業収益は大手商社に匹敵。政府、与党が改革の方針を昨年11月にまとめたことを受け、今年3月に資材価格引き下げなどに向けた自己改革案を策定した。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p41525.html (日本農業新聞 2017年8月3日) 農協改革 中旬から進捗調査 月内にも進捗調査 各県1JAを行脚 農水省 農水省は全国のJAを対象に、農協改革の進捗状況の調査に乗り出すことが分かった。各地のJAに担当者を派遣。改革の重点となる農産物の高値販売や生産資材の安値調達などが具体的にどの程度進んでいるかを確認し、改善を働き掛ける。今年度は試行的に各都道府県の1JAを対象に調査を実施する方針で、8月中にも始める。2014年6月の農協改革に関する与党取りまとめでは、5年間を「農協改革集中推進期間」として、JAに自己改革の実行を強く求めている。既に同期間の中間年を迎える中、改革の実践を加速させる必要があるとみて、今回の調査に乗り出す。特に重点的に調査するのは、(1)農産物の高値販売や生産資材の安値調達に向けた取り組み(2)組合員の経営支援(3)改革を進めるための組織の体制整備――の3項目。都道府県の担当者と共にJAに出向き、JAが事業計画などに盛り込んだ目標数値など具体的な指標に照らし合わせて、取り組みが進んでいるかどうかを聞き取る。思うように成果が上がっていない取り組みについて、何が課題かをJAとの間で共有、同省から先進事例を紹介するなどで改善策を探る。都道府県は意見聴取後も、特定した課題について、JAの解決に向けた取り組みの進捗を確認し、改革の着実な進展を促す。こうした一連の流れを今年度、試行的に実施、検証し、来年度以降の対応を検討する。同省は「JAと同じ目線で対話して課題の解決策などを探り、自己改革の実践を後押したい」という。16年4月に施行された改正農協法では、農協の事業目的に、農業者の所得増大に最大限配慮することを掲げ、JAに営農経済事業の強化を求めている。こうした中、JAグループは16年度からの3年間を自己改革の集中期間として自己改革の実践を進めている。同省が各都道府県の1JAを試行的に調査することに対し、JA全中は「自己改革に取り組んでいるJAの実態を見て、理解してもらうには良い機会だ」と話している。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p41471.html (日本農業新聞 2017年7月28日) 現場踏まえ対応を 農業競争力プログラム 全国知事会 全国知事会は27日、盛岡市で全国知事会議を開き、農業振興を柱とした「地域経済の好循環の拡大に向けた提言」を採択した。農業振興を地域社会の基盤と位置付け、提言5項目のうち2項目を農業関連とした。政府が昨年決めた「農業競争力強化プログラム」を進めるに当たって、農業・農村の実情を十分踏まえるよう求めた。改革を急進的に進める政府に対し、くぎを刺した格好だ。日欧経済連携協定(EPA)をはじめ、国内農業への影響に懸念を示し、丁寧な情報提供を求めるとした。会議には「地方から日本を変える」をテーマに、全国都道府県の首長が参加した。政府が2016年11月に決めた同プログラムでは、生産資材の引き下げや全農改革、卸売市場法の見直しを提起。政府はこれに沿って農業改革を進めている。提言では、地域間格差の是正や、多様性に満ちあふれた地域の創出に取り組むべきとした。その上で、プログラムに関する制度設計について、地域の農業・農村の実情を十分踏まえるよう求めた。地域の農業者が意欲と希望を持って営農に取り組めるようにすべきとした。国際貿易交渉を巡っては、日欧EPAをはじめ国内農林水産業への影響が懸念されると指摘。全ての貿易交渉で、重要品目に対する必要な国境措置を確保することが必要と提起した。交渉の進捗(しんちょく)や国内の影響についての情報提供を丁寧にするよう求めた。米、大豆など主要農作物種子法(種子法)の廃止に際して、今後も生産者に良質で安価な種子の供給と普及ができるよう、財政措置の確保を要望した。国産種子の海外流出の防止などの措置も求めた。この他、農業分野では担い手らの人材育成、農地集積、ICT(情報通信技術)をはじめとするスマート農業、鳥獣害防止対策について国の支援の充実を提起。資材の価格低減、所得向上への支援策、輸出促進策の強化も必要とした。会議では、国と地方を挙げて「防災庁」の創設に取り組むことや、東京一極集中の是正などについて議論、提言した。災害に強い国土づくりを進める「岩手宣言」も採択した。 *2-4:http://qbiz.jp/article/115975/1/ (西日本新聞 2017年8月7日) 農相、改革継続に協力要請 就任直後異例のJA訪問 斎藤健農相は7日、全国農業協同組合中央会(JA全中)を訪問し、奥野長衛会長や中家徹次期会長らに対して引き続き安倍政権が進める農業・農協改革への協力を呼び掛けた。就任直後の農相がJA首脳を訪ねるのは異例。自民党の農林部会長や農林水産副大臣を歴任して農協改革を主導し、3日に農相に就任した。10日にJA全中の次期会長に選出される中家氏は政権の改革に距離を置く慎重派とみられており、自ら出向くことで話し合いを重ねていく姿勢を示した。面会では、JA全中に加え、全国農業協同組合連合会(JA全農)、農林中央金庫などJAグループ幹部が顔をそろえた。奥野氏は「本来ならこちらが伺うのが筋」と謝意を表明し、斎藤氏は「日本の農業が厳しいという状況認識を共有できれば、農家の皆さんが前向きに取り組める環境づくりに向け、いい関係で前進ができる」と述べた。面会後、報道陣に対して奥野氏は「大臣としての農業に対する強い思いから、自らこちらに足を運ばれた。官僚の経験を生かし、いろいろ課題を提起していただくことになる」と語った。中家氏も「問題があったときには話し合いをして互いに理解し合うのが大事」との認識を示した。 *2-5:https://www.agrinews.co.jp/p41511.html (日本農業新聞 2017年8月1日) 農業強化法が施行 改革推進丁寧に 農業生産資材価格の引き下げや農産物流通の合理化に向けた構造改革を進める農業競争力強化支援法が1日施行される。農水省は、卸売市場法の抜本改革など規制・規格の見直しや資材の開発促進、直販の促進といった改革を実行に移す。同省が、生産性の低さや機能不全を問題視する米卸や飼料メーカーには業界再編をてこ入れする。同時に、JA全農の改革の実行を促す方針だ。いずれも生産現場に密接に関わる課題だけに、具体化には、多様な農家の声を踏まえた丁寧な議論が欠かせない。同法は、5月に成立。資材価格下げや農産物流通の合理化に向けて①国が講じるべき施策②業界再編や事業参入に向けた支援措置――を定めたのが柱。同省は今後の政策展開は一義的に行政の仕事として「与党の了承を取る必要はなく、農水省の権限で粛々と進めればよい」(同省幹部)としている。だが、法律上は国の政策の方向性を示す抽象的な文言にとどまる。施行を受け、同省は、法律が定める国内外の農業資材供給や農産物流通の実態調査に着手。この結果を踏まえて2019年8月までに施策見直しを検討する。同省は昨年、日本の肥料などが韓国に比べて割高とする調査結果をまとめ、全農に改革を迫った経緯がある。だが、殊更に価格差だけを取り上げれば、品質の劣化を招く恐れがある。農業全体の構造や品質格差を踏まえた冷静な分析が必要だ。参院農林水産委員会は、協同組合の本来機能である共同購入や共同販売の機能の強化、民間事業者の自発的な取り組みの尊重を求める付帯決議を採択した。今後の法律運用では、政府による過剰な民間干渉につながらないか国会による監視が求められる。 <EPAについて> *3-1:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170801&ng=DGKKZO19451050R30C17A7KE8000 (日経新聞 2017.8.1) 日欧EPAの課題(下)農業の将来 考える好機に、最先端分野、自由度高めよ 本間正義・西南学院大学教授(1951年生まれ。アイオワ州立大博士。専門は農業経済学。東大名誉教授) ポイント ○チーズの低関税輸入枠設定の影響小さい ○日本農業は関税なき貿易で世界に活路を ○コメの減反政策廃止や農地政策改革急げ 日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)交渉が大枠合意した。米国が環太平洋経済連携協定(TPP)から離脱し、自由貿易の推進に暗雲がたち込めていただけに、この合意の意義は大きい。また貿易だけでなく、グローバル化時代の包括的な経済活動のルールづくりを目指すTPPと目的を一にする。世界の国内総生産(GDP)の28%、世界貿易の37%を占める両地域のEPA実現に向けた大きな一歩を歓迎したい。日欧EPAの交渉でも、またぞろ農産物が焦点の一つとされた。だがTPPでの合意が基礎となっていることや、欧州の関心の低いコメが除外されていること、日本からも日本酒などの食品輸出の拡大が見込めることなどもあり、国内の反応は関係者を除けば比較的冷静だったといえる。とはいえ、自動車と酪農製品、特にチーズの関税削減を巡っては最後まで交渉が難航した。日本にとって自動車の関税撤廃は日欧EPAの大きな目的の一つだった。EUとEPAを結んでいる韓国の自動車が無税で域内に輸出できるのに対し、日本の自動車には10%の関税が課され、大きなハンディとなっていた。一方、EUが求めてきたのはTPPを超える乳製品、特にチーズの関税削減だった。金額でみると、日本からEUへの自動車輸出額は1兆2494億円(2016年)に対し、EUからのチーズ輸入額は378億円(同)にすぎない。従ってこの両者をバーター(交換取引)にしたとみるのは適当ではない。日EUともに包括的なEPA締結に十分大きなメリットを見いだした結果と解釈すべきだろう。EUが今回の交渉でチーズにこだわる理由はあった。EUは15年3月末、30年以上継続してきた生乳クオータ(割り当て)制度を廃止した。加盟各国に生乳供給の上限を課す制度だが、これを自由化し市場志向性を高め、乳製品の需要増大が見込める国際市場で活路を見いだそうとした。しかしEUが輸出増を期待したロシアは、欧米がウクライナ問題で科した経済制裁に対抗し、欧米からの農畜産物の輸入禁止措置を継続している。このためEUは別の市場を求め輸出戦略を練り直しており、途上国への輸出拡大とともにEPAを通じた日本市場の開放が重要課題だった。表は、合意したEUからの主な農産物の関税削減の内容を示したものだ。焦点だったチーズは、TPPでは関税を維持したカマンベールやモッツァレラなどソフト系チーズを一括して新たに低関税輸入枠を設けた。この枠内関税率は徐々に削減し、16年目に撤廃するとしている。輸入枠は初年度2万トンから、16年目に3万1千トンに拡大する。EUからのソフト系チーズ輸入量は2万トン(16年)程度であり、輸入枠は現状に比べ16年で1.5倍に拡大するだけなので、大きな影響はあるまい。またチーズは差別化できる製品であり、国内でも様々な取り組みが展開されている。輸入品に対抗できる日本ブランドのチーズが多く生み出されることを期待したい。さらに生乳の流通制度改革も進行中だ。これまで全国を10地域に分けて、各地域の指定団体に出荷しなければ加工用の生乳に対する補給金は支給されなかったが、出荷先にかかわらず、加工用の生乳はすべて補給金の対象となる。また補給金受給のためには指定団体に原則全量委託することを義務付けていたが、これも部分委託が可能となる。従って個々の農家や農家グループの創意工夫を乳製品の生産に生かせる道が広がる。日欧EPAの合意は、英国のEU離脱決定や米トランプ政権の誕生で挫折しかかった自由貿易の方向を、決して後戻りさせてはならないという両地域の強い政治的意志でもある。今後、他のEPAや新たな交渉を通じ貿易の拡大と経済活動に関するルールの共通化が進展していくと予想される。その際、交渉結果に一喜一憂するのでなく、日本農業も国境措置に依存しない体制を築くことが重要だ。先ごろ日本経済調査協議会は、元農水事務次官の高木勇樹氏を委員長とする食料産業調査研究委員会がまとめた提言「日本農業の20年後を問う」を公表した。筆者はこの委員会で主査を務めた。これから20年後の日本農業をどう考えるか。少子高齢化・人口減少で日本の国内市場は確実に縮小する。一方、浮き沈みはあるにせよ、グローバル化の波は今後も間違いなく押し寄せてくる。これらの条件の下で日本農業が活路を見いだすには、市場を世界に求めなければならない。それには関税なき貿易が必要だ。この関税なき世界を前提に日本農業の構築を考えなければ、農業の産業としての独り立ちは見えてこない。日本の農家数は経営体でみて過去20年間で毎年平均して6万戸減少している。このままいけば20年後には10万戸を切ることになる。それでも各農家(経営体)が年間1億円規模の生産を担えば、日本農業は10兆円の生産額を維持できる。そうした方向に向かうにはどのような政策が望ましいのか。真っ先に必要な政策は最先端にいるフロンティア農業者の自由度を高め、フロンティアを広げる政策である。第1にコメの減反政策の廃止だ。政府は生産割り当てをやめると言うが、多額の補助金で飼料米生産に誘導し、主食米生産を制限し高価格を維持する政策を継続する。小規模兼業農家が維持され、大規模農家の生産拡大が阻害される。第2に農地政策の改革だ。現行農地法は農地を生産資源として活用するというより、農地所有者の権利を守ることを目的としている。農業内での権利移動を前提とするために、リースは認められても、農外の株式会社が農地を保有することは禁じられている。第3に耕作地が何カ所、何十カ所にも分散している非効率な経営の解消だ。農地のリースや所有を自由化しても耕作地が細切れでは生産効率は上がらない。地域で連坦(れんたん)化してひと続きの耕作面積を確保するために、孤島的に別経営をしている農地を周囲と一体化し、耕作を統合する仕組みが必要となる。農地の流動化のためには、農地の利用に応じた税制の整備などが有効だと考えられる。フロンティアは海外での販売戦略でも広げる必要がある。概して日本の農業関係者は海外でのマーティングが不得手だ。農産物の品質の高さのアピールが足りない。それは日本の農業者がいまだにプロダクトアウト(作り手優先)の姿勢から抜けきらず、消費者ニーズを取り込むマーケットインの姿勢に切り替えられずにいることに通じる。和食がユネスコ無形文化遺産になっている今日、世界に日本の農と食を広範にアピールするチャンスだ。今回の日欧EPAで日本酒の関税が撤廃され、欧州への輸出拡大が期待される。日本酒をフランスワイン並みのブランドに育て、それに合う和食とその魅力を伝える好機でもある。一方で、農業はその生産プロセスそのものが付加価値を生む。農作業はそれ自体が面白い。また工夫により様々なアクティビティーに展開可能でもある。農業の魅力を都市住民に伝え、農業体験をより手軽にできるような体制づくりは、これからの農業のあり方の一つとしても重要だ。農業が20年後に自立した産業となるには、国内海外を問わず今何をすべきか、国民全体での活発な議論を期待したい。 *3-2:https://www.agrinews.co.jp/p41351.html (日本農業新聞 2017年7月12日) EPA 情報開示に差 EUは協定文案一部公開 欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)の大枠合意を受け、欧州委員会が日本政府が開示していない協定文案の一部を公開していることが分かった。一方、日本政府は文案が固まっていないとして公表しない方針で、日欧の情報開示の差が露呈した。民進党など野党は、情報開示に後ろ向きな日本政府の姿勢を問題視し、欧州と同水準の開示を求める方針だ。欧州委員会は日欧首脳が大枠合意を発表した6日付けで、ホームページに投資やサービス、電子商取引、紛争解決などに関する協定文案の一部や欧州側の提案を掲載。最終案ではないと断りながら「交渉への公衆の関心の高まりを考慮」して開示したと説明している。一方、日本の外務省は同日開かれた民進党の会合で「テキストが固まっておらず、最終調整する必要があるので、今の時点で公表に至っていない」と開示しない理由を説明した。民進党の会合では、出席議員から「情報公開には(日欧で)互いに同じ対応するのではないのか」(玉木雄一郎氏)など、情報開示に後ろ向きな政府の姿勢を質す意見が相次いだ。協定案を巡り、交渉の経過を含めて国民に積極的に開示しようとする欧州側と、内容が固まるまでは国民に知らせるべきではないとする日本政府の対応の違いが浮き彫りになった。交渉における情報開示の少なさは、農業関係者からも不満の声が相次いで挙がっており、今後の政府の説明に注目が集まっている。 *3-3:https://www.agrinews.co.jp/p41449.html (日本農業新聞 2017年7月25日) EPAの経済学分析 貿易ゆがみ損失も大 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏 日欧経済連携協定(EPA)は国内総生産(GDP)で世界の約3割を占め、全体で95%超の関税撤廃率で、日本の農林水産物の関税撤廃率も82%で環太平洋連携協定(TPP)並みに高いとして、「経済規模が大きく自由化度が高い」のが優れているとの論調は経済学的には間違いである。そもそも自由貿易協定(FTA)は「悪い仲間づくり」のようなもので、A君は好きだから関税なくしてあげるがB君は嫌いだから関税をかけるというものである。仲間だけに差別的な優遇措置を取るのがFTAだから、「経済規模が大きく自由化度が高い」方が貿易が大きくゆがめられ、「仲間外れ」になる域外国の損失は大きくなる。われわれの試算では、日欧EPAによって締め出される域外国の損失は23億1600万ドルで、日欧のメリットの17億6200万ドルより大きい。しかも、自由化度が高いほど、締め出される域外国の損失は大きくなるから、農産物のような高関税品目は除外した方が域外国の損失は緩和できる。われわれの試算では、域外国の損失は23億1600万ドルから16億2300万ドルに減少する。さらに、日本にとっても、農産物を自由化しない方が、日本全体の経済的利益は、11億2600万ドルから21億3200万ドルに増加する。高関税の農産物を欧州連合(EU)だけに関税撤廃すると、例えば、最も安く輸入できる中国からの輸入が差別的な関税撤廃によってEUに取って代わる「貿易転換効果」によって、消費者の利益はあまり増えず、生産者の損失と失う関税収入の合計の方が大きくなってしまうからである。このように、FTAは、仲間外れになった国は損失を被るし、域内国も貿易が歪曲されて損失が生じることなどから、日本では、長年、政府も国際経済学者も世界貿易機関(WTO)を優先し、FTAを否定してきた。ところが、2000年ごろから、日本政府がFTA推進にかじを切り出すと、みるみるうちに、同じ学者がFTAやTPPを礼賛し始めた。しかも、「農産物を例外にしてはいけない」と主張したい人たちにとっては、日本にとっても、域外国にとっても、農産物を除外する方がベターだ、という試算結果は不都合なので、そういう数値は表に出ないように極力隠されてきた。経済学者の良識、経済学の真理とは何なのかが問われている。 *3-4:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170621&ng=DGKKZO17910830Q7A620C1EE8000 (日経新聞 2017.6.21) 経済:骨太診断(6)消えた「食料安全保障」 農家、保護より自立促す 経済財政運営の基本方針(骨太の方針)の「攻めの農林水産業の展開」を見ると、2016年の骨太の方針にあった「食料安全保障の確立」の文言が消えている。農林水産省関係者によると、食糧安保を象徴するものは「食料自給率」。食料の安定供給を果たす責務を国が放棄するわけではないが、食料自給率を重要な指標として位置づけるのを見直しつつある状況の表れだ。食料自給率は、国内で消費する食品がどれだけ国産の材料で賄われているかを表す。供給熱量で換算するカロリーベースで2015年度は39%。主要先進国の中で最低水準にあることが「手厚い農業予算が必要」(農業団体幹部)との主張を支えてきた。ただ、カロリーベースの食料自給率は野菜をつくっても上向きにくいなどの問題が指摘される。生産額ベースになれば66%まで引き上がるのも、「(カロリーベースが)むやみに危機を高める指標になっている」(農水省OB)との見方を強めている。生産額ベースも下落傾向にあり、食料の安定供給を懸念する主張に根拠がないわけではない。ただ、ことさら低自給率を強調するより、消費者に選ばれる農産物をつくり、輸入に対抗できる競争力を磨いていけば、おのずと国内農業の供給力が高まるのではないか。安倍政権が自民党の小泉進次郎農林部会長らの主導で農協改革に乗り出したのも、保護農政から脱却する狙いが強いからだ。日本の農村を守る適度な予算の配分は必要だが、自立できる強い農家を各地にどれだけつくり出せるかという視点が欠かせない。 *3-5:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170810&ng=DGKKASFS09H3O_Z00C17A8EE8000 (日経新聞 2017.8.10) 食料自給率、38%に低下 昨年度、23年ぶり水準 小麦の生産減 農林水産省は9日、2016年度の食料自給率(カロリーベース)が38%だったと発表した。コメが不作だった1993年度の37%に次ぐ低水準。北海道を襲った台風などの影響で、小麦やテンサイの生産量が落ち込んだ。政府は2025年度までに自給率を45%に高めるという目標を掲げている。しかし09年度を最後に40%台には届いておらず、目標達成の道筋は見えない。カロリーベースの自給率は、コメや小麦といった穀物の供給量に左右されやすい。政府は輸入品が多い畜産飼料を国産に置き換えようと、飼料用米の増産に力を注ぐ。しかし草を食べる牛の飼料にコメを配合してもその割合には限界があり、自給率の押し上げ効果は乏しい。単価の高い野菜や畜産物などの動向が影響する生産額ベースの自給率は15年度に比べて2ポイント増の68%だった。野菜や果実で輸入が減り、国内生産が増えた。生産額ベースは2年連続で上昇した。 <農林漁業とエネルギー> PS(2017.8.11、16追加):私も、*4-1の「太陽光などの再生可能エネルギーで作った電気でEVを動かすシステム」が、CO2はじめ排気ガスを0にできるため、最もよいと考える。なお、日経新聞は「フランスは原子力発電の比率が高いので、CO2を出さない」としているが、フランスは、2015年7月22日に制定した「エネルギー転換法」で、①原子力発電所の大幅削減 ②化石燃料消費の廃止 ③再生可能エネルギーへのシフト ④石油由来廃棄物の大幅削減 などを決め、マクロン新大統領も、*4-2のように、エネルギー・環境政策をさらに推し進めるとして、国民議会(下院、定数577)選挙で大勝した。そして、その中には、農業分野の環境改善や輸送分野のエネルギー効率改善なども入っている。 日本でも、*4-3-1、*4-3-2、*4-3-3のように、平成26年5月1日に、農山漁村で自然再生可能エネルギー(太陽光、風力、小水力、地熱、バイオマス等)を積極的に活用する「農山漁村再生可能エネルギー法(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/pdf/re_ene1.pdf)」が施行され、地域の所得向上・農山漁村の活性化・農林漁業の振興などを進め、再生可能エネルギーの地産地消により、地域内での経済循環を構築する方向性が示された。そのため、農林漁業は、機器を電動化して自然エネルギーで自家発電するのが近未来の姿になる。従って、全農は、持ち株会社の下に自然エネルギーによる発電子会社(仮名:全農自然エナジー)をつければよいだろう。 やはり、*4-4のように、日経新聞は経済教室で、慶大卒・東大院博士課程満期退学・災害情報論専門の関谷氏に、「偽ニュースを考える」として「①市場に流通している福島県産の農作物・海産物は徹底した検査をして、99.99%がND(検査機器が設定した検出限界より大きい値の放射性物質が検出されなかったこと)で安全確認されている」「②NDとは生産者・流通業者・消費者の間で流通上の許容量のデファクトスタンダード(事実上の基準)として結果的に合意した値」「③現在、このNDの状態でも風評被害により経済被害が起きている」「④流通業者・農業関係者の中に、まだ福島県産の農産物に多くの消費者が不安を抱いていると思い込んでいる人も多い」「⑤福島県の農林水産物についての情報発信は、検査結果に関する広報が十分ではなく、おいしさをアピールするブランド戦略や広告が中心となっている」と書かせている。 しかし、①②にも書かれているとおり、ND(検査機器が設定した検出限界より大きい値の放射性物質が検出されなかったこと)は、生産者・流通業者・消費者の間で流通上の許容量の事実上の基準として人為的に合意した値にすぎず、長期間食しても健康を害さないことが証明された値ではない。そのため、NDだから安全確認されたとは言えず、④のように、流通業者・農業関係者・消費者に疑念を抱いている人がいる方が尤もであり、③のように、これを風評被害と断じることこそ無知である。また、放射能で汚染されても味は変わらないため、「おいしさをアピールすればよい」と考えている人には、もともとこの問題を論じる資格がない。そして、⑤のように、この検査でNDであったことをアピールしても「だから長期間食しても健康を害さないのか」は依然としてわからず、薬剤と同様、安全性が不明なら摂取しないのが常道だ。さらに、“災害情報論の専門家”というのが何を勉強してきた人かは不明だが、東大の教官でもこのようなことを断じる知識があるとは限らないことをわきまえるべきである。 なお、*4-5のように、東京電力は、市民の反対と福島の不安に応えず、2016年9月にフクイチの1号機建屋カバーを外した。チェルノブイリでは、原発からの放射性物質の飛散を防ぐために、旧ソ連が国家の威信をかけて石棺を突貫工事で完成させ、30年を経て石棺の老朽化により再び飛散の危険があるため、2千億円をかけてさらに石棺を覆うシェルターを完成させたにもかかわらず、フクイチは、青天井で放射性物質が飛散し放題の状態になったのである。そして、これらは、「差別」や「感情論」などという否定のための誹謗中傷にもめげず、「女性自身」はじめ環境意識のある女性によって多く主張されていることを忘れてはならない。 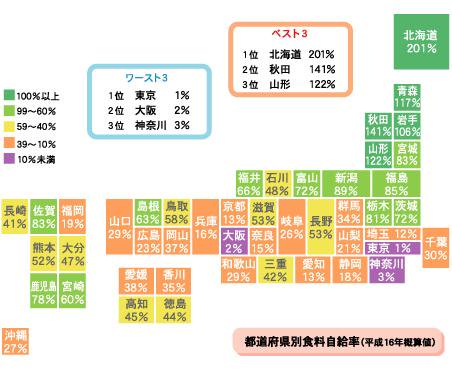   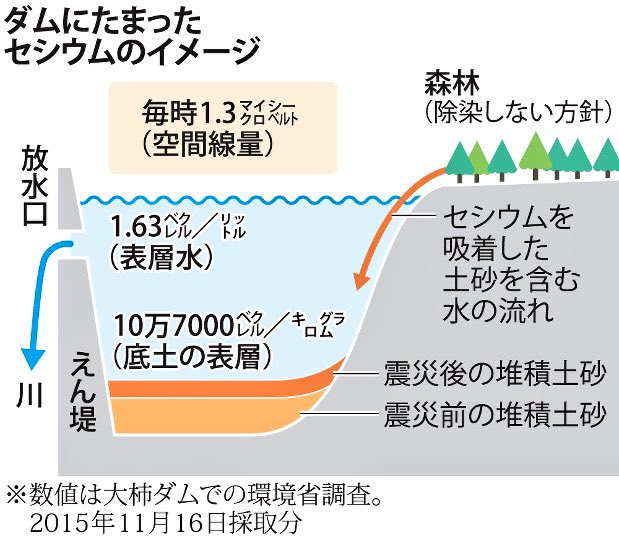 都道府県別食料自給率 フクイチ事故の状況と“除染”後のフレコンバッグ (図の説明:一番左の都道府県別食料自給率で福島県は85%と高い方だったが、原発事故後の福島県の農産物や海産物は0ではない放射性物質を含み、安全でなくなった《まさか、これをフェイク・ニュースとは言わないでしょうね》。その上、他の原発も食料自給率の高い地域(農林漁業地帯)に建設されているため、エネルギーに原発を使うのはコストが高い上、食料自給率にも影響し、亡国へのパスポートである) *4-1:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170811&ng=DGKKZO19918370R10C17A8MM8000 (日経新聞 2017.8.11) EV大転換(下)これが持続可能な未来だ さらば石油、世界も揺れる 7月上旬に横浜で開かれた太陽光発電の見本市。目玉は米テスラだった。「太陽光で作った電気を蓄電池でためて電気自動車(EV)で使う。これが持続可能な未来だ」。テスラのカート・ケルティ・シニアディレクターはこう語った。 ●一気通貫めざす テスラは2月に社名から「モーターズ」を外した。16年に太陽光発電の米ベンチャーを買収。EV用電池に加え据え置き型蓄電池にも事業を広げる。創業者、イーロン・マスク氏の狙いは発電からEVまで一気通貫のエネルギーインフラを作ることにある。なぜそこまでするのか。「発電時の二酸化炭素(CO2)排出量まで考えれば、エンジン車はEVとの差がなくなる」。ある国内自動車メーカー幹部はこう主張する。背景にあるのは「ウェル・トゥー・ホイール」(油井から車輪)という考え方。燃料を作る段階からトータルの環境負荷を見る発想だ。国立環境研究所の調査では、ガソリン車に対するEVのCO2削減率はフランスで90%。一方、中国では15%減にとどまる。フランスは原子力発電の比率が高いのに対し、中国は7割以上をCO2を多く排出する石炭火力発電に依存するためだ。いくらEVを増やしても、エネルギー源から変えなければ根本的な地球温暖化対策につながらない。EVシフトの先には太陽光発電など再生可能エネルギーの拡大が待ち受ける。多くの企業がそのことに気がつき動き始めている。北欧では米IBMや独シーメンスなどが連携し、風力発電による電力をEVに供給するシステムの整備が進む。日本でも一部自治体で同じような実証実験が進むが、「欧州では既に商用段階に入っている」(日本IBMの川井秀之スマートエネルギーソリューション部長)。石油メジャーも「変身」に動く。仏トタルは低炭素の液化天然ガス(LNG)などガスの生産量が発熱量ベースで原油を超えた。仏電池メーカーを買収し再生エネ事業の拡大にも走る。自動車に素材、そしてエネルギーまで産業構造を大きく変えようとしているEVへの大転換。それは世界の秩序にも影響を与える。 ●試される産油国 「40年には1日に800万バレルの石油需要が減る」。米調査会社ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスはEVシフトの影響をこう予測する。800万バレルは石油輸出国機構(OPEC)の1日の生産量の4分の1に相当する。世界の石油消費量の65%は自動車など輸送用が占める。発電用途は全体の4%程度。自動車用の落ち込みを補うのは難しい。各国が協調して需給調整するOPECの戦略が成り立たなくなるかもしれない」。日本エネルギー経済研究所の田中浩一郎中東研究センター長は指摘する。需要減により協調が崩れれば、次世代産業にカジを切れるかどうかで産油国間の格差が広がる。不安定な中東に新たな不協和音を生みかねない。EVへの大転換は地政学に大きな影響を与える可能性もある。 *4-2:https://sustainablejapan.jp/2017/05/12/macrons-energy-policy/26778 (Sustainable Japan 2017/5/12) 【環境】フランスのエマニュエル・マクロン新大統領のエネルギー・環境政策の骨子 5月7日のフランス大統領選挙で勝利を収めたエマニュエル・マクロン元経済・産業・デジタル大臣。5月14日に第25代フランス大統領に就任します。フランスでは、社会党を与党とする現オランド大統領政権時代に、環境・エネルギー政策の大転換がありました。その最たる例が2015年7月22日に制定された「エネルギー転換法」。この法律では、フランスの電力の代名詞であった原子力発電所の大幅削減、化石燃料消費の廃止、再生可能エネルギーへのシフト、石油由来廃棄物の大幅削減、企業及び金融機関に対する気候変動関連情報開示制度など、世界初の政策を大規模に盛り込みました。同時に政府の公的年金でもESG投資が大規模に推進されました。これまで欧州の環境先進国と言えば、ドイツやイギリス、または北欧という印象が強かった近年。フランスは後塵を拝していましたが、このオランド政権時代に、欧州、そして世界の「トップクラス」へと躍進しました。その中、関心が集まるのが、マクロン新大統領のエネルギー・環境政策です。マクロン新大統領は今回、無党派として立候補し、極右と言われる国民戦線のマリーヌ・ル・ペン候補だけでなく、フランス二大政党である社会党のブノワ・アモン候補、共和党のフランソワ・フィヨン候補とも選挙戦を競いました。選挙戦中には、現政権与党の社会党幹部が、自党の候補ではなく、マクロン新大統領を支持するという事態も発生しました。なぜマクロン氏には社会党の支持が集まっているのか。その背景には、マクロン新大統領の経歴が関係しています。マクロン新大統領は、2004年にフランスの名門大学、国立行政学院(ENA)を卒業後、フランス財務省に就職。国家官僚として勤務する一方、政治家を志し、社会党へ入党します。その後、2008年に財務省から、英国老舗資本家であるロスチャイルド家の中核投資銀行であるロチルド&Cie銀行に転職。投資銀行家としてのキャリアを積み、2010年には社会党を離党し、無党派として政治家を目指す姿勢に転向します。マクロン氏が、最初に政権入りするのが、2012年。当時就任したばかりのオランド大統領に招聘され、大統領府副事務総長としてオランド大統領に側近の地位を得ます。そして2014年、オランド政権の経済・産業・デジタル大臣に任命された後、今回の大統領選挙出馬を視野に2016年8月に大臣を辞任。そして、39歳の若さで大統領選挙に勝利。このように、マクロン新大統領は、無党派ながらも現オランド政権を支えてきました。マクロン氏は、2010年に社会党を離党した背景について、「私は社会主義者ではない」とし、右派・左派を超越した政治を目指したい考えを訴えています。さて、このマクロン新大統領の環境・エネルギー政策はどう展開されていくでしょうか。マクロン新大統領は、選挙期間中に、すでに自身の「環境・エネルギー政策」の骨子を表明しています。大きな柱は、現オランド政権のエネルギー・環境政策を「さらに推し進める」というものになっています。 <電力> •2025年までに原子力発電比率を2025年までに現在の67%から50%に削減 •国営電力会社EDFが業績が大幅に低下している原子力発電会社アレヴァを救済合併 •2022年までに石炭火力発電を2022年までに全て廃止 •フランス領内での石油・ガス採掘を全て禁止 •2030年までにエネルギー消費に占める再生可能エネルギー割合を現在の約15%から32%に引き上げ •2030年までに発電量に占める再生可能エネルギー割合を現在の約18%から40%に引き上げ •再生可能エネルギーと環境保全分野に150億ユーロ(約1.8兆円)を投資 •再生可能エネルギー発電の設備容量を26GW分を新たに追加 <交通燃料> •ガソリンとともにディーゼル燃料に対する増税を実施し、石油燃料の消費を抑制 •2040年までに化石燃料自動車を廃止する将来構想を提示 •電気自動車向けの充電スタンド設置に対する政府支援 <エネルギー効率> •不動産分野のエネルギー効率改善のため、低所得家庭に対し40億ユーロ、政府施設に対し40億ユーロを助成 •農業分野の環境改善と地域農業協働促進のため50億ユーロを助成 •輸送分野のエネルギー効率改善のため、50億ユーロを助成 •EUの排出権取引制度に対し、フランス国内では下限価格を設定する意向を表明(2020年までに1t当たり56ユーロ、2023年までに100ユーロ) 再生可能エネルギー推進では、すでにEUからの助成が決定しています。大統領選挙の前の5月10日、EUの行政府である欧州委員会が、再生可能エネルギー発電所建設プロジェクト合計17GW分に対する約13億ユーロ(約1,600億円)の助成金給付を承認しました。そのうち、15GW分は陸上小型風力発電所(最大3MWで6基以内)。残りは、小型太陽光発電所(100kW以内)が2.1GWと、下水発生ガスを用いた廃ガス火力発電所が1ヶ所です。マクロン新大統領はこれらの野心的な政策を実現できるのか。それは今後の国会運営にかかっています。無党派で出馬したマクロン新大統領は、現在国会内に1議席も有していません。マクロン氏は当選後、支持団体をもとに新政党「レピュブリック・アン・マルシェ(共和国前進)」を設立。6月11日から18日に行われる国民議会(下院、定数577)選挙に向け、428人の公認候補を発表しました。社会党の下院議員24人もマクロン新党公認候補として出馬します。一方、半数以上の候補が新人候補であり、選挙戦は容易ではありません。マクロン新大統領は、従来の政党には依存しない政権運営を目指すため既存の政治との訣別を掲げ、有権者に支持を訴えています。マクロン新大統領が打ち上げたエネルギー・環境政策が花開くか。次の下院選挙が帰趨を決します。 *4-3-1:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/ (農林水産省) 再生可能エネルギーの導入促進 私たちの身のまわりには、土地や水、風、熱、生物資源等が豊富に存在しています。有限でいずれは枯渇する化石燃料などと違い、これらは、自然の活動などによって絶えず再生・供給されており、環境にやさしく、地球温暖化防止にも役立つものとして注目を集めています。農山漁村において、これらのエネルギー(太陽光、風力、小水力、地熱、バイオマスなど)を積極的に有効活用することで、地域の所得の向上等を通じ、農山漁村の活性化につなげることが可能となります。農林水産省は、再生可能エネルギーの導入を通じて、農山漁村の活性化と農林漁業の振興を一体的に進めていきます。 *4-3-2:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/sinkou.html (農林水産省) 農山漁村の再生可能エネルギー振興策について 農山漁村における再生可能エネルギー振興策について、固定価格買取制度の活用等による発電の取組と併せて、再生可能エネルギー熱の利用や、電力小売全面自由化を捉えた再生可能エネルギーの地産地消の取組による地域内経済循環の構築等、今後推進すべき方向性の一例を紹介します。 *4-3-3:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/houritu.html (農林水産省) 農山漁村再生可能エネルギー法 平成25年11月15日に農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(農山漁村再生可能エネルギー法)が成立し、11月22日に公布され、平成26年5月1日に施行されました。この法律は、農山漁村における再生可能エネルギー発電設備の整備について、農林漁業上の土地利用等との調整を適正に行うとともに、地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を併せて行うこととすることにより、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電を促進し、農山漁村の活性化を図るものです。この法律の条文や概要等につきましては、以下のリンク(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/pdf/re_ene1.pdf 等)を御参照下さい。 *4-4:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170816&ng=DGKKZO20000960V10C17A8KE8000 (日経新聞 2017.8.16) 経済教室:経済教室偽ニュースを考える(下)周知不足が風評被害拡大、流通や行政にも課題多く 関谷直也・東京大学特任准教授(1975年生まれ。慶大卒、東大院博士課程満期退学。専門は災害情報論) ポイント ○安全確認されても経済的被害が止まらず ○消費者の不安和らぐも供給側に思い込み ○ブランド戦略優先し検査体制のPR不足 風評被害とはもともと原子力分野において、放射性物質による汚染がない状況で食品や土地が忌避されることとして問題となってきた。過去の事例をまとめると、風評被害とは、ある社会問題(事件、事故、環境汚染、災害、不況など)が報道されることによって、本来「安全」とされるもの(食品、商品、土地、企業など)を人々が危険視し、消費、観光、取引をやめることなどによって引き起こされる経済的被害を指す。環境汚染や食中毒などの危険性のあるものや、安全でないものが売れないのは当然である。それとは別に「安全であるにもかかわらず売れない」からこそ問題となる現象が風評被害である。2011年の東京電力福島第1原子力発電所の事故と、その後の福島県産の食品に関する消費者の購買行動を例に、風評被害のメカニズムと解消に向けた対応策を論じたい。原発事故の直後の段階では、公的には政府が定めた放射線量の基準値以下ならば安全であるとして、この基準値以下で人々が商品を買わないことや、福島県を訪れないことで生じる経済被害が「風評被害」とされた。事故直後は出荷制限された農産物も多く存在し、実際に放射性物質が検出されることもあったため、風評被害か実害かは議論が分かれるところであった。だが、放射性物質のセシウム134はすでに半減期(約2年)が過ぎ、空間線量や農作物の放射性物質の含有量は大幅に低下してきている。汚染の状況も把握され、空間線量も明らかにされてきた。カリウムを含んだ肥料をまくなどの吸収抑制策の成果もあり、農作物に含まれる放射性物質の値は下がり、昨年度の放射性物質モニタリング検査結果では野菜2870点、果実923点、肉類3791点、野生・栽培キノコ796点はすべて基準値以下である。しかも市場に流通している福島県産の農作物は徹底した検査がされている。米は毎年、約1000万袋全量が調査されているが、15年と16年は放射性物質が基準値を超えたものはなく、99.99%が不検出を意味する「ND」であった。海産物についても昨年度は8766件が調査され、全て基準値以下だった。現在、10魚種の出荷制限が続いているが、魚種や海域を絞った試験操業は拡大している。NDとは正確には、検査機器の設定した検出限界より大きい値の放射性物質が検出されなかったという意味で、生産者や流通業者、消費者の間で、流通上の許容量のデファクトスタンダード(事実上の基準)として結果的に合意した値である。現在の風評被害は、このNDの状態であっても生じる経済被害のことだといえる。さらに、社会状況や消費者の心理状況も大きく変化している。福島第1原発は廃炉の見通しが立っていないものの、避難指示区域は縮小してきている。筆者らが実施したアンケート調査の結果を比べると、福島県産の購入を拒否する人の割合は減ってきており、とくに福島県内で消費者の意識の変化が大きく、拒否する人の割合は12%にまで減った(図参照)。放射性物質に関して不安が薄らいだ理由としては、「基準値を超えた品目は出荷制限がなされている」「放射性物質が検出されなくなってきている」など、検査体制の充実による信頼感が生まれてきたことが大きいと考えられる。筆者らのこれまでのアンケート調査でも繰り返しこれらの結果が得られている。福島の風評被害の焦点は現在、人々の不安や心理の問題から、流通の問題へと変化している。流通業者や農業関係者の中に、いまだ「福島県産の農産物に多くの消費者が不安を抱いている」と思い込んでいる人も多い。社会心理学で言う、周囲の意見を正確に認識できない「意見分布の無知」という現象である。人々への影響力の大きいソーシャルメディアでも、ユーザーが見たい情報を選択的にみる「フィルターバブル」と称される現象が起きている。一般の関心は低下しているものの、ネット上では強い関心を持つ人が多くの意見を書き込むため、「放射能の問題の有無について、いまだに論争が続いている」という印象を持つ人も少なくない。さらに福島県産の農産物の安全性は確認されてきているにもかかわらず、(1)流通が長期間滞ったことで他産地の商品に置き換わり、販路が途絶えた(2)安全なことが分かっているうえ、安価でおいしいので業務用とされることが多い(3)震災後の混乱を経験した仲卸や小売店が福島県産の回復に消極的――といった問題がある。これらが総じて現在の風評被害の最も大きな課題であるといえよう。福島の風評被害の問題はすでに次のステージに入っている。放射能などに関する「科学」的な理解の問題や、リスクに関する情報を社会で共有する「リスクコミュニケーション」の問題でもなければ、行政に対する不信感の問題でもない。「事実」がきちんと周知されていないというPRの問題である。筆者らの統計的な分析でも、購買行動に大きく影響を与えるのは「検査結果」や「検査体制」である。「福島県内では米に関して全量全袋検査が行われている」ことの周知率は、福島県内では79.0%に達しているのに対し、県外は40.8%にすぎない。「食品への含有放射性物質の検査でもほとんどがNDである」ことの周知率は県内では50.3%にもなるが、県外では17.3%しかない。図で紹介したように、福島県産の食品の購入状況が県内と県外で異なっているのは、全量全袋検査やスクリーニングなどの検査体制や、ほとんどがNDという検査結果について、事実の周知に差があるためと考えられる。福島県外では汚染対策などへの関心の低下により周知度が低く、食品に対する不安感の低減が遅れているとみられる。検査体制や結果について事実が周知されなければ、これ以上の消費の回復は望めない。現在の福島県の農林水産物についての情報発信は、検査結果に関する広報が十分ではない段階にもかかわらず、「おいしさ」をアピールするブランド戦略や広告が中心となっている。だが産地間競争が増すなかで、他地域も栽培技術の開発やマーケティングに熱心に取り組んでおり、おいしさのアピールだけでは風評被害の払拭は望めない。そしりを恐れずにいえば、現代社会では消費の選択の自由がある。福島県産を心情的に拒否する人がいても、それはやむを得ない。だが、少なくとも今の福島県の検査体制や検査結果の事実を知った上で、福島県産を拒否する合理的な根拠はすでにないことは理解される必要がある。福島第1原発事故の事例に限らず、「風評被害」という社会問題は単に消費者の不安感だけが原因なのではない。メディアの報道姿勢、人々の安全認識、安全基準の設定、市場流通、産地間競争、復興時の情報発信などが複雑に絡み合った問題である。多義的であり、時間の経過と共に変化するといえる。それゆえに風評被害は単なるリスクコミュニケーションや広告だけで解決できるものではない。課題から目を背けず、社会問題としての風評被害の事実を正確に把握し、事実をきちんと知ることが解決策につながるのである。 *4-5:http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/24433de21832131caeb66f361abde4fa 木村結、東電株主代表訴訟事務局長 「女性自身 2017年4月4日号」(光文社)引用記事 昨年9月、市民の反対と福島の不安に応えず、東京電力(以下、東電)は福島第一原子力発電所1号機の建屋カバーを外した。東電は放射性物質には飛散防止剤を使うので心配はないと説明していた。しかし、「女性自身」編集部が原子力規制庁のデータを検証したところ、福島県双葉郡では2017年1月の放射性セシウム134が770ベクレル/立方メートル、137が4700で合算5470ベクレル/立方メートル。カバーを外す前の2016年9月と比べると約65倍に急増していた。東京都新宿区では約4.5倍、神奈川県茅ヶ崎市では約9倍、群馬県前橋市では約13倍、千葉県市川市で約5倍となった。これは東電の怠慢であると同時に国民の安全を守らなければならない国の怠慢であり、全国各地で定点観測している規制庁は数値を知りながら警告せず放置していたことになる。1986年に福島原発と同じくレベル7の事故を起こしたチェルノブイリ原発は30年経って石棺にヒビが入り放射能漏れを起こしたため、ドーム型の覆いを施したが、これは100年持つという。チェルノブイリではデブリ(=原子炉から解け落ちて鉄や金属とともに固まった核燃料。非常に高い放射線量を持つ)を取り出すことはまだ不可能と考えているということ。ところが日本は再稼働をしたいばかりに事故を起こした原発から無理にデブリを取り出し、何が何でも廃炉が可能と言いたいようだ。それは取りも直さず作業員に多大なる被ばくを強い、無理やり帰還させた福島の住民をも被ばくさせるだけでなく、全国民も知らないうちに被ばくさせられているということ。このような原発推進ありきの政治を一刻も早く終わりにしないと日本は世界の核のゴミ捨て場になってしまう。 -----(引用ここまで)-------- 政府・原子力ムラはこの記事の否定に躍起ですが、1号機に限らずガレキ撤去のたびに周辺の線量が跳ね上がることは以前から観測されており、何の不思議もありません。しかも溶融燃料が格納容器の底を突き抜けて地下に沈下しており、地下水と接触して大量の放射性蒸気も噴き上げています。今さら騒ぐこともない当たり前の事実です。口汚く「女性自身」を罵っている連中は、何一つ科学的なデータや根拠を示すことはしません。チェルノブイリ原発からの放射性物質の飛散を防ぐために、旧ソ連は国家の威信をかけて石棺を突貫工事で完成させました。30年を経て石棺の老朽化により再び飛散の危険があるため、さらに2千億円もかけてこのたびそれを覆うシェルターを完成させたのです。石棺も何もない青天井の福島第一原発(1F)からは放射性物質は飛散し放題です。風が吹けば大量の放射性微粒子が舞うのです。こんな当たり前のことをデマだと騒いで否定する連中は頭がおかしいとしか言いようがありません。今月1Fを見学したNYタイムズの記者たちが防護服・マスクをしていたのも、きちんとした理由があるのです。被ばくをしたくなければ、1Fから放射性物質が飛んでこない地域に避難移住するしかありません。「女性自身」には、誹謗中傷にめげず今後もぜひ真実を伝え続けてほしいと思います。読んで応援しましょう。 <人材派遣会社> PS(2017年8月12日追加):全農の人材派遣子会社が、*5のように、リレー方式で農繁期の地域を渡り歩いたり、加工に携わったりする人を雇用して派遣すれば、働く人にとっては、①正規社員になれば生活が安定する ②多様な農業を体験できる ③定年後の高齢者・外国人などの雇用の受け皿が増える などのメリットがあり、派遣を受ける農家や加工会社にとっては、④繁忙期のみ人を増やすことができる というメリットがある。 そして、①は被用者にとってプラスであり、②は農業に従事し始めたばかりの人や外国人にとってよい経験となり、③は雇用が増える効果がある。また、私は、この時の賃金の支払い方は、時間給だけでなく成果給を入れるのが効率を上げるポイントだと考える。何故なら、1時間あたりのみで賃金を決めるのではなく、収穫一箱あたりでも賃金を決めると、能率の良い人ほど短時間で多く稼ぐことができるため能率を上げる動機付けができ、賃金の決め方によっては双方にとってプラスになるからである。 *5:https://www.agrinews.co.jp/p40280.html (日本農業新聞 2017年3月3日)北海道-愛媛-沖縄で農作業 3JAがリレー方式 アルバイト周年確保 即戦力、人材情報を共有 愛媛県のJAにしうわと沖縄県のJAおきなわ、北海道のJAふらのは、農繁期の労働力確保へ、アルバイトをリレー方式でつなぐ事業に乗り出した。農繁期がずれる3JAを、アルバイトが1年間渡り歩くイメージで、一定の農作業経験を積んだ即戦力として期待できる。2016年度は各JAが連携先のJAで人材募集をかけた。17年度からは他JAの加入も検討する。産地維持にアルバイトは必須なだけに、人材情報を共有するなど連携を強化し、人材確保につなげる。各JAがアルバイトに聞き取り調査などをしたところ、提携するJAでも農作業をしている事例が多く、リレー方式による連携を決めた。アルバイトの1年間の流れはこうだ。11月10日から12月20日ごろまでJAにしうわでミカンの収穫や選果場での選別作業をする。その後、JAおきなわで12月中旬から翌年3月までサトウキビの収穫や製糖作業に従事。JAふらので4~10月までメロンの品質管理やミニトマト、スイカの定植と管理、収穫を担う。各JAでは年々、アルバイト不足が深刻化している。JAおきなわは15年度、必要な約250人が集まらず一般の派遣会社を利用した。派遣会社を通じた場合は紹介料などもあり、直接募集するアルバイトより2割以上高いという。同JAは「1人でも多くリピーターを増やしたい」と連携による人材確保に期待する。JAふらのは年々、必要な採用人数に達する時期が遅くなっている。これまで4月末までに120人を確保できたが、近年は5月下旬にずれ込む。同JAの子会社で農作業支援サービスを展開するアグリプランによると、今年は2月末までで15、16人の採用しか決まっていない。「前年は同時期に約20人が決まり、状況は悪化している」と嘆く。JAにしうわ管内のアルバイトの採用人数は年々増えている。16年度は前年を2割近く上回る212人を農家が雇用した。「将来的に労働力の確保の要望は高まる」とみる。連携により、農作業経験がある優良なアルバイトの確保につなげる。新規の場合は作業効率が悪いことや働く姿勢に個人差があるため、事前にJA間で情報を共有し、有望な人材を確保する。アグリプランは「農業は他のバイトに比べ、雇用主と向かい合ってやりとりをする機会が多い。事前に参加者の個性を知ることは重要」と強調する。今後は連携JAの拡大も検討する。JAにしうわは「アルバイトにとっても選択肢が増えれば、さまざまな働き方ができるようになる」と強調する。 <脱原発・脱化石燃料と農林漁業の貢献> PS(2017年8月13日追加):地球温暖化対策の推進に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html)の第21条1項には「都道府県・市町村は、温室効果ガスの排出量削減や吸収作用の保全・強化のため措置計画を策定する」と定められており、3項には「その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーの利用、都市機能集約、公共交通機関利用者の利便増進など)を行う」等々が定められている。また、農山漁村の活性化と再生可能エネルギーによる発電推進を目的として、「農山漁村再生可能エネルギー法(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/pdf/re_ene1.pdf)」も制定されているため、農山漁村で発電して市町村の上下水道に併設した送電線で電力を集め、鉄道の敷地に(超電導)電線を敷設して大量消費地に送るシステムにすると、*6の脱原発・脱化石燃料と電線の地中化が比較的安価に実現できる。 これにより、外国に支払う燃料費が不要になるとともに、農林漁業に再生可能エネルギー発電機器を補助して所得を下支えすることにより、農林水産物への永遠の補助金を削減することが可能になり、送電した組織には送電料収入が入る。こうなると、2014年の日本の原油輸入額13.9兆円(GDP比2.9%)のうちの燃料の割合が92%の12.9兆円であるため、この外国への支払いが次第になくなって国内で廻るようになり、こういう構造改革をしていくと消費税増税や子ども保険の徴収を行わなくても必要な社会保障ができるようになる。そして、これまでこういう改革ができなかったのは縦割りの別省庁の管轄だったからで、これこそ政治主導でやるべきなのだ。 なお、日本もEV化を進めるために、東京オリンピックを期限として東京都が東京23区内へのEVや燃料電池車以外の乗り入れを禁止すれば、瞬く間にあらゆる車種の環境車への変換が進み、空港や道路で排気ガスに燻されることがなくなり、世界に驚きを与えるだろう。また、東京だけでなく、奈良・京都・大阪・札幌・福岡やその他の観光地もそうすればよいと考える。 *6:http://digital.asahi.com/articles/DA3S13084985.html (朝日新聞社説 2017年8月13日) エネルギー基本計画 「脱原発」土台に再構築を 電気や熱などのエネルギーをどう使い、まかなっていくか。その大枠を示す国のエネルギー基本計画について、経済産業省が見直し論議を始めた。世耕弘成経産相は「基本的に骨格は変えない」と語った。しかし、小幅な手直しで済む状況ではない。今の計画は、国民の多くが再稼働に反対する原発を基幹電源とするなど、疑問が多い。世界に目を向けると、先進国を中心とした原子力離れに加え、地球温暖化対策のパリ協定発効に伴う脱石炭火力の動き、風力・太陽光など再生可能エネルギーの急速な普及といった変化の大きな波が起きている。日本でも将来像を描き直す必要がある。まず土台に据えるべきは脱原発だ。温暖化防止との両立はたやすくはないが、省エネ・再エネの進化でハードルは下がってきた。経済性や安定供給にも目配りしながら、道筋を探らなくてはならない。 ■偽りの「原発低減」 14年に閣議決定された今の計画にはまやかしがある。福島第一原発の事故を受けて、「原発依存度を可能な限り低減する」との表現を盛り込んだが、一方で原発を「重要なベースロード電源」と位置づけた。新規制基準に沿って再稼働を進める方針も明記し、実際に各地で再稼働が進んでいる。計画をもとに経産省が15年にまとめたエネルギー需給見通しは、原発回帰の姿勢がさらに鮮明だ。30年度に発電量の2割を原発でまかなうと想定する。30基ほどが動く計算で、再稼働だけでなく古い原発の運転延長か建て替えも多く必要になる。だが、原発政策に中立的な専門家からも「現実からかけ離れている」と批判が出ている。事故後、原発に懐疑的な世論や安全対策のコスト増など、内外で逆風が強まっているからだ。原発から出る「核のごみ」の処分も依然、日本を含め大半の国で解決のめどが立たない。先進国を中心に原発の全廃や大幅削減をめざす動きが広がっている。次の基本計画では、原発を基幹電源とするのをやめるべきだ。「依存度低減」を空証文にせず、優先課題に据える。そして、どんな取り組みが必要かを検討し、行程を具体的に示さねばならない。 ■温暖化防止と両立を 脱原発と温暖化対策を同時に進めるには、省エネを徹底し、再エネを大幅に増やすことが解になる。コストの高さなどが課題とされてきたが、最近は可能性が開けつつある。省エネでは、経済成長を追求しつつエネルギー消費を抑えるのが先進国の主流だ。ITを使った機器の効率的な制御や電力の需要調整など、技術革新が起きている。かつて石油危機を克服した時のように、政策支援と規制で民間の対応を強く促す必要がある。再エネについては、現計画も「導入を最大限加速」とうたう。ここ数年で太陽光は急増したが、風力は伸び悩む。発電量に占める再エネの割合は1割台半ばで、欧州諸国に水をあけられている。本格的な普及には障害の解消が急務だ。たとえば、送電線の容量に余裕がない地域でも、再エネで作った電気をもっと流せるように、設備の運用改善や、必要な増強投資を促す費用負担ルールが求められる。世界では風力や太陽光は発電コストが大きく下がり、火力や原子力と対等に競争できる地域が広がっている。日本はまだ割高で、設置から運用まで効率化に知恵を絞らねばならない。再エネは発電費用を電気料金に上乗せする制度によって普及してきたが、今後は国民負担を抑える仕組みづくりも大切になる。一方、福島の事故後に止まった原発の代役として急増した火力発電は、再エネ拡大に合わせて着実に減らしていくべきだ。現計画は、低コストの石炭火力を原発と並ぶ基幹電源と位置づけ、民間の新設計画も目白押しだ。しかし、二酸化炭素の排出が特に多いため、海外では依存度を下げる動きが急だ。火力では環境性に優れる天然ガスを優先する必要がある。 ■世界の潮流見誤るな 今回の計画見直しでは、議論の進め方にも問題がある。経産省は審議会に加え、長期戦略を話し合う有識者会議を設ける。二つの会議の顔ぶれは、今の政策を支持する識者や企業幹部らが並び、脱原発や再エネの徹底を唱える人は一握りだ。これで実のある議論になるだろうか。海外の動向や技術、経済性に詳しい専門家を交え、幅広い観点での検討が欠かせない。資源に乏しい日本では、エネルギーの安定供給を重視してきた。その視点は必要だが、原発を軸に政策を組み立てる硬直的な姿勢につながった面がある。世界の電力投資先は、すでに火力や原子力から再エネに主役が交代した。国際的な潮流に背を向けず、エネルギー政策の転換を急がなくてはならない。 <国政の方針と教育財源> PS(2017年8月18、20日追加):*7-1のように、福島第一原発の廃炉のため国は既に1000億円超の税金を投入し、電力ばかり食って効果の上がらない汚染水対策や調査ロボットの開発費に使ったそうで、経産省が原発事故処理にまでたかって予算を獲得していることがわかる。さらに、東芝の失敗を見てもなお、*7-2のように、日立の英国子会社はスペインのテクナトム社と提携して原発新設に携わる作業員の育成や原発の運営・保守に繋げるそうで、*7-3のように、米政府代表でさえ「パリ協定」の完全履行を求める内容を含む閣僚宣言を採択したにもかかわらず、日本の経産省幹部は、①石炭火力発電所の新増設 ②国外での削減貢献分の算入 ③目標を引き下げるか原発を新設するかの選択 などを主張しているのだ。 しかし、私は、②については、環境省の「国内の努力だけで達成すべき」というのが正しく、①③ではなく、環境に配慮した製品への代替こそが経済成長のKeyになると考える。そのため、韓国でも、*7-4のように、現代自動車が、1回の水素充填で580キロメートル走る新型FCVを2018年に韓国と欧米市場に投入し、1回のフル充電で390キロメートル走るEVも発売する予定とのことであり、この調子では、太陽光発電は中国製か台湾製、EVやFCVは中国製か韓国製が優れたブランドになり、日本は国が大きな補助をして実質マイナス価格で原発か石炭火力発電機器を売るしかなくなりそうだ。 さらに、上のような莫大な無駄遣いを放置しつつ、*7-5のように、高等教育の無償化や福祉については、必ず財源問題が主張される。そして、政府は有力な2案(①全国民を対象に在学中は授業料を取らず、卒業後に所得に応じて拠出金の形で納付する案 ②一定の所得制限をした上で給付型奨学金を拡張する案)に絞って検討を進める方針だそうだが、教育・福祉の財源は、国内にある自然再生エネルギーで発電すれば容易に出てくるため、国立・公立大学の授業料は(無料である必要はない)せいぜい月額1万円を上限とし、奨学金は親の所得とは関係なく必要とする学生には支払うべきである。また、そうすることによって、補助金にぶら下がった仕事をするのではなく、報酬以上の付加価値を自らつけられる教育をすべきだ。 なお、*7-6のように、日経新聞は社説で「①全員入学に近づいて大半の大学が学力による学生の選抜機能を失っている」「②このまま門戸を広げれば大学の質が低下する」「③必要なのは量的拡大より国際競争力の強化と規模の適正化だ」「④そのため外部評価に応じた資金配分が必要だ」としている。私は、大学まで無償化する必要はないと思うが、大学を卒業することにより社会貢献が多くなる学生に少ない費用で教育したり、奨学金を出したりするのは理にかなっていると考える。その際、大学の立場から見れば、①②は、選抜して間口を狭くしさえすれば質が上がるわけではなく、教育のゆとり化やスポーツ重視で高校までに得ている知識が少なく思考力が弱くなっている生徒をいくら選抜しても限界があり、少なくとも高校までの内容を身に着けていなければ大学の授業についていけない。そのため、大学はじめ試験者は、選抜者の顔色や空気を読んで相手が気に入る答えをする能力だけが鍛えられる推薦を廃止し、知識や思考力を測る試験に変えるべきだと考える。また、③の国際化が必要なのは、実は国際競争をしている第一線の人材だけで、職業によっては国際競争は少ないが専門教育を受けることが必要なものもある。そのため、望む人が大学に行けるようになったのはよいことで、今後は、知識を更新したい社会人の再教育や医療・看護・介護、工学、農学などの外国人への門戸拡大が必要だ。そして、日本の大学が勉学に困難を極める開発途上国の若者を受け入れるようになれば、結果は日本にも戻ってくる。④については、外部評価の公正性を担保した上でなら評価に応じた資金配分に異存はないが、日本人は(教育のせいか)将来を見据えた公正な評価ができないのが問題なのである。 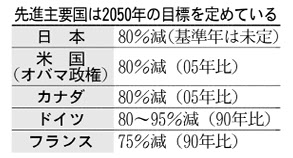 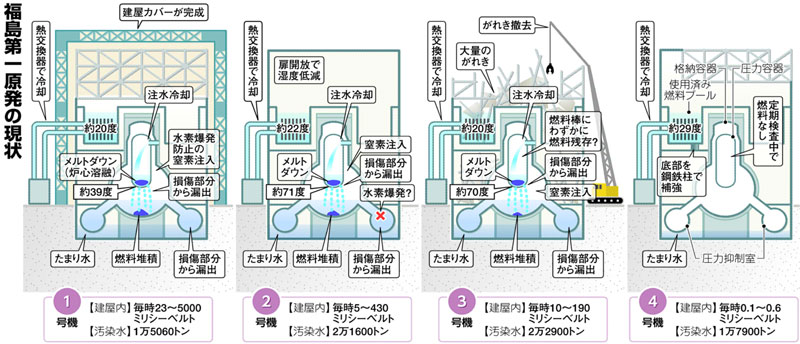 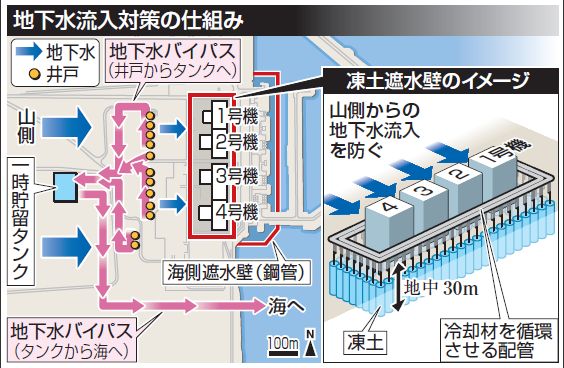 2017.8.18日経新聞 2011.11.13東京新聞 凍土遮水壁 *7-1:http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201708/CK2017081402000112.html (東京新聞 2017年8月14日) 【社会】福島第一 廃炉に税金1000億円超 7月まで本紙集計 東京電力福島第一原発事故の廃炉作業で、国が直接、税金を投入した額が一千億円を超えたことが、本紙の集計で分かった。汚染水対策や調査ロボットの開発費などに使われている。今後も溶け落ちた核燃料の取り出し工法の開発費などが必要になり、金額がさらに大きく膨らむのは必至だ。廃炉費用は東電が負担するのが原則だが、経済産業省資源エネルギー庁によると「技術的に難易度が高い」ことを基準に、税金を投入する事業を選定しているという。担当者は「福島の早い復興のため、国が対策を立てることが必要」と話す。本紙は、エネ庁が公表している廃炉作業に関する入札や補助金などの書類を分析した。廃炉作業への税金投入は二〇一二年度からスタート。今年七月までに支出が確定した業務は百十六件で、金額は発注ベースで計約千百七十二億六千万円に上った。事業別では、建屋周辺の地下を凍らせ、汚染水の増加を防ぐ凍土遮水壁が、設計などを含め約三百五十七億八千万円。全体の三割を占め、大手ゼネコンの鹿島と東電が受注した。ロボット開発など、1~3号機の原子炉格納容器内の調査費は約八十八億四千万円だった。福島第一の原子炉を製造した東芝と日立GEニュークリア・エナジーのほか、三菱重工業と国際廃炉研究開発機構(IRID)が受注した。受注額が最も多いのは、IRIDの約五百十五億九千万円。IRIDは東芝などの原子炉メーカーや電力会社などで構成する。国は、原発事故の処理費用を二十一兆五千億円と試算。このうち、原則東電負担となる廃炉費用は八兆円とされている。除染で出た汚染土を三十年間保管する中間貯蔵施設は国の負担だが、賠償費用は主に東電や電力会社、除染費用も東電の負担が原則だ。 *7-2:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170720&ng=DGKKASDZ19IOJ_Q7A720C1EAF000 (日経新聞 2017.7.20) 日立の英子会社が提携 スペイン原発関連と 日立製作所は英国の原子力発電事業開発子会社ホライズン・ニュークリア・パワーがスペインの原発関連エンジニアリング会社であるテクナトム社と提携したと発表した。英国中部のアングルシー島で進める原発新設に携わる作業員を育成し、確実な原発の運営・保守につなげる。 *7-3:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170818&ng=DGKKZO20106770X10C17A8EE8000 (日経新聞 2017.8.18) 経済:エネルギー再考 論点を探る(下)50年目標、具体化か素通りか 温暖化対策、省庁間で溝 7月半ば、ニューヨークでの「持続可能な開発目標(SDGs)」閣僚級会合。地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の完全履行を求める内容を含む閣僚宣言を採択した直後、米政府代表は言い放った。「米国は協定に関する部分とはかかわりを持たない」 ●米抜きでも歩み ほぼすべての国が参加するパリ協定。温暖化ガスの2割弱を排出する米国の離脱表明が衝撃だったのは確かだが、欧州連合(EU)や中国など主要国が歩みを止める兆しはない。7月、独ハンブルクでの20カ国・地域(G20)首脳会議で、米を除く各国は「パリ協定は撤回できない」と宣言。仏英は2040年からガソリン・ディーゼル車の販売を禁止し電気自動車などを優遇すると発表した。再生可能エネルギーの普及を急ぐドイツやカナダを含め、各国の念頭には「産業革命前からの気温上昇を2度未満にする」との協定に盛られた目標がある。カギになるのが50年をメドとする長期の削減戦略。仏独などは基本対策とともに国連に提出済みだ。各国は対応が経済成長につながるとみる。経済協力開発機構(OECD)によると、G20が温暖化防止に取り組めば50年時点で成長を約5%押し上げる。30年までに年平均6兆9000億ドルの投資が必要になる。 ●石炭火力やり玉 一方の日本。50年に80%減という長期計画を閣議決定したが、国連に出せていない。政府内調整が難しいためで、特に温暖化対策を推進する経済産業、環境両省の足並みがそろわない。「どんどん設置されれば二酸化炭素(CO2)の削減はできない」。中川雅治環境相は約40ある石炭火力発電所の新増設計画をやり玉にあげる。中部電力の計画に待ったをかけるなど影響が出ているが、経済産業省は「電力安定供給に石炭火力は必要」との立場だ。80%減を巡り、環境省は国内の努力だけで達成すべきだと訴えるが、経産省は国外での削減貢献分も算入するよう主張。対策を示す報告書も別々にまとめた。地球環境産業技術研究機構(RITE)の分析によると、国内だけで80%減を実現するには電源構成の4割以上が原子力になる。1割強はガス発電だが、排出されるCO2を回収する装置をつける。残りは再生可能エネルギーだ。このシナリオではCO2を1トン減らすのに60万円以上かかり、原発の新設も必要になる。経産省は30日、50年を見据えた有識者会議の初会合を開く。経産省幹部は「目標を引き下げるか原発を新設するかの選択になるかもしれない」と言う。将来像を詰めて具体化するか素通りするか。温暖化対策への本気度も問われる。 *7-4:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170818&ng=DGKKASDX17H0I_X10C17A8FFE000 (日経新聞 2017.8.18) 現代自が新型燃料電池車 航続距離39%増 欧米でも来年投入 韓国の現代自動車は17日、新型の燃料電池車(FCV)を公開した。2018年の第1四半期(1~3月)に韓国で発売するのを皮切りに、欧米市場などにも投入する。現行モデルと同じ多目的スポーツ車(SUV)型で、航続距離は現行比39%延びるという。18年に航続距離を2倍にした電気自動車(EV)を発売することも公表した。現代自にとって2代目になるFCVは、水素と酸素を化学反応させて電気をつくる燃料電池スタックや水素供給装置などの中核部品を全面的に見直した。化学反応から推力を得るシステムの効率を60%と現行比約5ポイント上げ、1回の水素充填で走る距離を580キロメートルに延ばす。モーターの出力は163馬力でトヨタ自動車のFCV「ミライ」(154馬力)を若干上回る。欧米とオーストラリアで「18年後半の発売を見込み、中国販売も検討する」(現代自幹部)とする。FCV市場で先行するトヨタなどを追撃する。ハイブリッド車(HV)などを含む環境対応車を20年までに現在の14車種から31車種に増やす方針も明らかにした。EVは1回のフル充電で390キロメートル走るSUV型を来年前半に出す。また、現代自は航続距離が500キロメートルのEV開発に着手したことも明かした。 *7-5:http://digital.asahi.com/articles/DA3S13091724.html?_requesturl=articles/DA3S13091724.html&rm=150 (朝日新聞 2017年8月18日) 高等教育無償化2案 卒業後に拠出金納付・給付型奨学金を拡張 安倍政権が掲げる大学などの無償化について、政府は、有力な2案に絞って検討を進める方針を固めた。全国民を対象に在学中は授業料を取らず、卒業後に所得に応じて拠出金の形で納付する案と、一定の所得制限をした上で給付型奨学金を拡張する案の二つ。ただいずれの案でも、数兆円規模で必要ともされる財源の確保策には現時点では踏み込んでおらず、検討が難航する可能性も残る。意欲があれば大学や専修学校に進学できるようにし、高等教育への機会均等の確保を図るのがねらい。政権の目玉政策「人づくり革命」を具体化するため、9月に初会合を予定する「人生100年時代構想会議」で大学改革と合わせて議論を開始。関係法案をまとめ、2020年4月からの新制度の施行を目指す。第1案は、オーストラリアの高等教育拠出金制度「HECS(ヘックス)」を参考にする。在学中の授業料などを全額、公費で負担する代わりに、卒業してから所得に応じて拠出金を納めてもらう。「高等教育費は保護者が負担する」という原則を「社会が共同で支える」考え方に転換するものだ。拠出金は、卒業者がその時点の所得に応じて社会に貢献してもらうという位置づけだが、拠出金のあり方や額などによっては、奨学金の貸与を受けて返済するのと変わらなくなる可能性もあり、慎重な制度設計が不可欠になる。第2案の「給付型奨学金の拡張」は今年度、先行実施された給付型奨学金制度がもとになる。この制度では最終的に、年6万人程度が返済不要の奨学金を受ける見込み。日本学生支援機構が貸与し、返済義務がある奨学生(15年度で約132万人)に比べてまだまだ少ないため、拡張を検討する。しかし、所得制限をかけることで、高等教育をすべての国民に等しく開かれたものにするという考え方からは離れることになる。財源をどうするかも課題だ。新たな借金(国債)で賄うことになれば、将来世代に負担を先送りすることになりかねず、構想会議や政府部内でも激しい議論を招きそうだ。 ■高等教育無償化の二つの案 ◇日本版HECS(高等教育拠出金制度) 【対象】 全国民 【在学中】授業料は無償 【卒業後】所得に応じて拠出金を納付 ◇給付型奨学金の拡張 【対象】 一部(所得制限あり) 【在学中】現行制度では、授業料は減免制度で対応 【卒業後】返還の必要なし *7-6:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170820&ng=DGKKZO20171740Z10C17A8EA1000 (日経新聞社説 2017.8.20) 政府は高等教育の無償化の検討を始めた。だが、私立大学の約40%が定員割れし、大半の大学が学力による学生の選抜機能を失っている。現状のまま無償化で門戸を広げれば、大学の一層の質の低下は避けられない。必要なのは、量的拡大よりも国際競争力の強化だ。人材育成や研究の中核を担う「公共財」としての価値をいかに高めるのか。長期的な視野に立ち、抜本的な大学改革に乗り出す時だ。 ●規模適正化が課題に まず、検討すべきは大学の規模の適正化だ。バブル経済崩壊後の低成長、少子化時代に、大学はその数、入学定員を増やし続けた。その結果、志願者の90%超が進学する「全入」に近づいた。水ぶくれした大学が限られた予算を奪い合い、国全体としての教育・研究の投資効率を低下させてはいないか。18歳人口のピークは1992年度の205万人。直近は120万人で、2040年には88万人と予測される。現在の大学数は780。92年に比べ18歳人口は約40%減ったが、大学数は約50%、入学定員も約25%それぞれ増加した。今の大学進学率、入学定員が維持されると仮定すると、20年後には十数万人規模の供給過剰になる。入学定員1000人の大学が100校以上不要となる計算だ。1980年代に18歳人口が減少した米国では、大学が入学者数を抑制し、選抜機能を維持した。新入生の減少で大学は授業料を引き上げたが、連邦政府は貸与奨学金と寄付制度の拡充という支援策を講じた。少子化が進む韓国では現在、大学を5段階にランク分けし、評価下位大学に定員削減を求める荒療治を始めた。日本でもようやく規模適正化の議論が始まった。少子化による教員採用減が確実な国立大の教員養成大学・学部に対し、文部科学省の有識者会議は定員削減や他大学との機能集約・統合を求める報告書案を示した。妥当な判断だ。20年後には日本の労働人口の約49%が人工知能やロボットなどにより代替可能という民間調査がある。産業別就業者の推計なども参考に今後は、国公私立の設置形態の別を問わず、入学定員の総枠の削減を視野に、時代に適合した学部の重点化を図るべきだ。政府は東京23区内の私立大の定員増を今後認めない方針を決めた。若者の東京一極集中を是正する目的だが「木を見て森を見ず」の感が否めない。問題はむしろ学生の選抜機能を失い教育の質の低下が懸念される地方の小規模大学だ。大学間の単位互換や校地の共有化など、地域教育の中核となるような統合・再編が望まれる。大学の数や入学定員が急増したのは、「事前規制から事後チェックへ」という政府の規制緩和策が大学設置基準にも及び、一定の要件を満たせば新規開設が認められるようになったからだ。規制緩和の本質は、新規参入を促す一方、質の低いサービスは市場から淘汰される仕組みにある。しかし、大学の経営や教育水準をチェックするため2004年度に文科省が導入した「認証評価制度」がうまく機能していない。 ●評価に応じ傾斜配分を 大学基準協会などの機関が評価結果を公表しているが、社会的にほとんど認知されていない。財務省の財政制度等審議会は、主に規模や定員の充足率に応じ交付する私立大の補助金を評価結果に連動させ傾斜配分すべきだと提言。学術論文の数や学生の就職実績なども勘案すべきだと指摘する。どんな評価指標が妥当かは議論の余地があるが、公費の使途や効果の「見える化」は国民的な要請だ。評価機能の拡充も課題だ。その点、気になる動きがある。評価機関によって経営や教育が「不適格」とされた地方の私立大が公立大に衣替えするなど、定員割れの私大を地方交付税で救済する事例が相次いでいる。納税者の観点からは、違和感がある。日本の大学の国際的評価が総じて低調なのは、密度の低い教育を量的に拡大してきたからだ。高等教育無償化の前提は、各大学が入学金や授業料が公費で充当されるにふさわしい公的価値を持つことを、社会に証明することにある。国はまず、定員を戦略的に削減し教育の質を高める大学を支援するなど規模適正化と、外部評価に応じた資金配分に着手すべきだ。 <21世紀の農林漁業へ> PS(2017年8月21、22、24、26日追加):現在の森林環境税は、都道府県が森林整備の目的で徴収する法定外目的税だ。しかし、この仕組では森林面積が広くて人口の少ない地域が二酸化炭素吸収源で水源である森林を整備することになるため、*8-1のように、国が森林環境税を新設しようとしているのは実現すべきだ。問題はどう配分するかで、私は、森林・田園・緑地帯・藻場などの面積に比例して都道府県・市町村の役割に応じて両方に交付すればよく、そのためには都道府県・市町村の役割分担を明確にする必要があると考える。そうすれば、森林・田園・緑地帯・藻場などを護ることが、直接的な地域の収入にもなる。 なお、農業は、*8-2のように、熊本県山鹿市が民間企業と協力して最適な温度と湿度を保った無菌室で蚕を飼育し、桑の葉を人工飼料に加工することによって年24回の繭の生産を可能にして養蚕業の再興に乗り出し、「山鹿シルク」のブランドを確立させて世界のシルク産業の拠点にするそうだ。そのシルクの使用目的は、製糸、医療・医薬品、化粧品開発などだが、日本の技術の粋を尽くしたシルクのブランドイメージを作るためには、「山鹿シルク」よりも「日本シルク」「九州シルク」のようなもっと大きなブランド名の方がよいと考える。 また、*8-3のように、鹿児島県十島村では、輸入品の多い神棚のサカキを栽培する新しい組合が生まれたり、島の特性や気候を活かして野生のヤギを出荷したり、バナナの栽培が始まったりしている。さらに、*8-4のように、佐賀県伊万里市南波多町にブドウや梨の収穫体験ができる観光農園が開園したそうだが、現代の最大の贅沢は自分で選んだ採れたての野菜や果実でジャムを作ったり料理を作ったりすることで、それが贅沢である理由は、大都会ではそれができにくいからだ。 菓子とガムを生産していた「九州グリコ」が、*8-5のように解散し、従業員のうち非正規社員211人が雇用契約を更新されず、跡地の活用も未定だそうだ。跡地(佐賀市鍋島町大字蛎久、3万1520平方メートル)は神野公園の前にあるため、工場よりも付加価値の高い使い方ができるが、私は残った人で土地価格の安い場所に引っ越し、残った機械や技術を活用して、ケーキと洋菓子のメーカーをすればよいと考える。何故なら、この頃、馬鹿の一つ覚えのように生クリームのケーキしかなく、私はアマゾンを通して広島のケーキ屋さんからバタークリームのケーキを購入しているくらいで、ケーキも冷凍して運べば遠くからでも運ぶことができ、解凍すればできたてのようになるからだ。その際、戦後の「菓子でさえあればよい」という発想は捨て、フランスの一流パティシエを招いて作るのがよいだろう。そのケーキ・洋菓子の材料は、小麦粉・米粉・牛乳・果物・野菜など佐賀県に豊富にあり、6次産業化しての輸出も可能である。 なお、最近は、*8-6のように、惣菜が売れている。その理由は、1~2人暮らしの家族では、いろいろな材料を買って手作りするよりも、できあがった中食を買う方が安くつき手間も省けるからだが、「九州グリコ」の元従業員のように、衛生的に食品を作ることに慣れている人は、そちらへの転用も可能だろう。しかし、この際も、惣菜だから味・栄養価・品質が一段落ちたり高くついたりしてもよいというわけではなく、手作り以上の味・栄養価・品質を出して合理的な価格で売るのが、継続的にヒットするコツである。 また、*8-7のように、西日本新聞が「パスタ・菓子 本場の味に対抗できるか」という記事を書いているが、私は「ゆで時間が短い」「束になっている」などの理由で、国産スパゲティを買うことが多いため、国産も十分に太刀打ちできると考える。さらに、カルシウム・鉄・ビタミンなどを配合して付加価値を増し、調理を簡単にするための美味しいトマトピューレや冷凍海産物があると、売り上げがさらに上がると思われる。   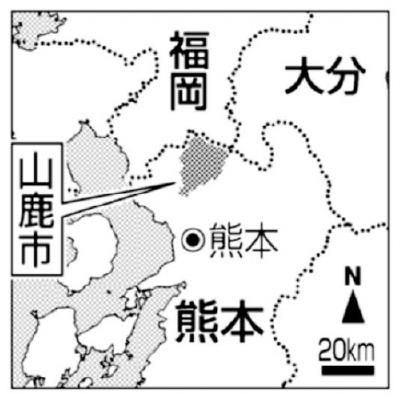  これからの課題 福岡県の森林環境税に関する説明 熊本県山鹿市のシルク 2017.8.16佐賀新聞 (図の説明:2050年の世界人口は95億人となり、今のまま構造改革をしなければ、食料・水・エネルギー・資源が不足する事態となる。そのため、我が国も持続可能な社会を意識して、食料・エネルギーの自給率を上げておくことが必要だ。さらに、持続可能にするためには、国内の自然を壊さず、公害を出さずに、国内資源を十分に活用できるようにしておく必要があるため、環境税の徴収による環境維持は重要である。さらに、農林漁業に生物学・生態学の最先端の知識を導入して、担い手が誇りを持ち、豊かな生活ができる産業にしなければならない) *8-1:http://qbiz.jp/article/116766/1/ (西日本新聞 2017年8月20日) 森林環境税、都道府県にも税収を 知事会「整備に関与不可欠」主張 市町村の森林整備費を賄うため政府、与党が新設を検討している「森林環境税」について、全国知事会が「森林整備は都道府県の関与が不可欠」として、税収の一部を配分するよう働き掛けを強めている。ただ都道府県に配れば、取り分が減る市町村からは反発も予想される。年末の税制改正大綱の取りまとめに向け、議論が過熱しそうだ。森林環境税は、所有者が分からない森林の増加や林業の担い手不足が問題になる中、地域の実情に最も詳しい市町村が私有林の間伐を代行する財源を確保するために検討が始まった。個人住民税に上乗せして徴収し、国が森林面積などに応じて市町村に配分する仕組みが想定されている。これに対し、7月に盛岡市で開かれた全国知事会議では「都道府県が関わらないと森林整備はできない」(佐竹敬久秋田県知事)、「林業の専門職員が少ない市町村だけでは厳しい」(尾崎正直高知県知事)といった声が噴出した。会議では、都道府県が市町村への間伐事業の指導や林業技術者を派遣することなどを念頭に「税収は役割分担に応じて配分すべきだ」との提言を採択した。 *8-2:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/455475 (佐賀新聞 2017年8月16日) シルク産業 世界拠点へ 熊本・山鹿市に巨大養蚕工場 ■耕作放棄地桑畑に転換 製糸、化粧品開発も視野 かつて養蚕が盛んだった熊本県山鹿市は、民間企業と協力して養蚕業の再興に乗り出した。市内の廃校跡には世界最大級の養蚕工場が建設され、耕作放棄地約25ヘクタールは桑畑に生まれ変わった。「山鹿シルク」のブランドを確立させ、世界のシルク産業拠点となることで地域経済の活性化を狙う。今年4月、熊本県北部の山あいの地に延べ床面積約4170平方メートルの養蚕工場が完成し、5月に稼働を始めた。総工費は約23億円。最適な温度と湿度を保った無菌室で蚕を飼育し、病気から守る。桑の葉を人工飼料に加工する設備もあり、通常は葉の収穫に合わせて年3回程度の繭生産が、通年で24回可能となった。取り組みのきっかけは、工場を運営する市内の農業生産法人「あつまる山鹿シルク」側の提案だった。市は2014年12月、同社と新養蚕産業構想に関する協定を締結。同社による養蚕工場建設や桑畑造成の計画が具体化した。土地の有効活用や雇用創出につながると、市は用地選定や桑畑へのアクセス道路の沿道整備といった面から支えた。3年以内に国内最大産地の群馬県に匹敵する年約50トンの繭生産を目指す。現時点で、地元を中心に約20人の雇用が生まれている。あつまる山鹿シルクの島田裕太専務(37)は「徐々に生産量を増やしたい」と意気込む。一方、取り組みはまだスタート地点。市は、製糸工場建設や、繭のタンパク質を活用した医療・医薬品、化粧品開発も展望する。大手商社などと連携し、情報発信や販路開拓を強化。構想名をIT産業の聖地、米カリフォルニア州シリコンバレーになぞらえた「SILK on VALLEY(シルク・オン・バレー)」とし、関連産業の集積を図りたい考えだ。市によると、県内には昭和初期、約7万軒の養蚕農家があった。しかし、安価な輸入品の増加や、高齢化に伴う廃業により衰退し、14年には市内の2軒を含め県内で5軒にまで減った。養蚕業再興の成否はこれからだ。山鹿市は熊本の近代養蚕業の開祖とされる長野濬平(しゅんぺい)の出身地。中嶋憲正市長(67)は「広がりの大きい産業が山鹿の地から生まれれば、市民の誇りや希望につながる」と話している。 *8-3:https://www.agrinews.co.jp/p41655.html (日本農業新聞 2017年8月19日) [にぎわいの地] 島で生きる 鹿児島県十島村(下) なりわい育む“家族” 移住者の夢村民が応援 ●サカキ特産化組合つくる シャツに記された文字は「悪」。フェリーが港に着岸すると、高齢者から若者までそろいの服を着て港で積荷の作業に励む。命綱である生活物資を島に運び入れる作業だ。収入を得るための出荷物も皆で送り出す。家族のような一体感。それが、悪石島(鹿児島県十島村)の特徴だ。36世帯78人が暮らす。昨年、神棚に備えるサカキを栽培する新しい出荷組合が生まれた。名古屋市出身の西澤慶彦さん(20)、東京都出身の太田有哉さん(21)ら都会育ちの“ヨソモノ”と地元農家12人が団結。手間が掛からず台風に強いサカキ。組合長で自治会長の有川和則さん(65)は「ヨソモノじゃなくて家族と思っている。サカキは将来の収入の種。若者を島に残すため金をつくる仕組みを皆でつくる」と知恵を絞る。 ●野生のヤギで新ビジネスを ここ数年、島には夢を抱いて新しい農業に挑戦する若者が移住する。必ずしも全員が夢を持ってやってきたわけでない。中には都会で傷ついた若者たちも。島で生きるため、移住後、夢を見付ける。大人たちが団結し、若者の夢を育み、支える。野生のヤギの生体出荷を始めた太田さん。「牛の草をヤギが食べて島民を困らせている。土砂崩れの原因にもなる。一石二鳥のビジネスでしょ」。少し自慢そうに構想を明かす。ここまで何かに本気になって挑戦したことは、初めてだ。太田さんは農林漁業のイベントで有川さんと知り合い、西澤さんを誘って3年前に移住した。家事が苦手で、売店もない島の生活は苦労の連続。遅刻などでたびたび島民に怒られる。「けんかするのも怒るのも家族だから。本気で僕を育ててくれている」。心の中で島民に、感謝している。病気になってもライフラインが壊れても、助け合って応急処置するしかない離島。西澤さんは「誰かが勝ち残るのではなく皆で生きていく感覚を島で初めて知った」と語る。ゲーム漬けで孤独だった高校生活。皆で支え合う家族的な島の雰囲気に、生きる居場所を見つけた。村で成人式を挙げた西澤さん。将来も島で生きていく術(すべ)を懸命に模索する。サカキ、スナップエンドウ、バナナなど新たな特産品で生計を立てようと必死だ。早朝から夕刻まで、畑へ。 ●団結と温かさ一体感が支え 高知県から移住し、漁業とバナナを栽培する鎌倉秀成さん(38)は「夢を持って生きることができる島。家族のように受け入れてくれる温かさが、生きる励み」と感謝する。若者の夢は、島民の夢でもある。畜産農家の有川俊江さん(59)は「島を選んでくれて心からうれしい。絶対、島に残ってほしい」と願う。手伝えることがないか、いつも考えているという。悪石島の名の由来は諸説ある。農家の有川安美さん(84)は隠し財宝を悪人から守るために先祖が命名したと聞いて育った。終戦も長く知らず島で生きてきた有川さん。「島に来てくれて夢に向かって頑張る若い人は、悪石島の財宝のよう。自分たちが財宝を守っていきたい」と決意する。誰もがわが事として、移住してきた若者の挑戦を応援している。本当に定住できるかは、これからにかかっているからだ。発想力を生かし挑戦する若者たちの移住。人口は増え、悪石島には保育園も近くでき、島は確実に変わった。その変化の道のりは、時に摩擦も生じる。十島村の住民は、新しい風を受け止めながら、島を残す歴史をつむいでいく。 キャンペーン「若者力」への感想、ご意見をお寄せ下さい。ファクス03(3257)7221。メールアドレスはwakamonoryoku@agrinews.co.jp。フェイスブック「日本農業新聞若者力」も開設中。 *8-4:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/456578 (佐賀新聞 2017年8月21日) 伊万里に観光フルーツ園 9月30日まで ■ブドウやナシ収穫体験 「フルーツの里」の伊万里市南波多町で20日、特産のブドウや梨の収穫体験ができる観光農園が開園した。今年はブドウ、ナシともに品質が上々で、家族連れの観光客がもぎたてをかごに入れながら笑みを浮かべていた。9月30日まで。地元農家でつくる観光農業推進協議会(池田徳和会長)が毎年町内5カ所の園地を開放しており、今年で41回目。初日は高瀬ぶどう園で開園式があり、池田会長は「猛暑の影響が危ぶまれたが、ここ数日の涼しさで着色も酸切れもよく、抜群の食味」と太鼓判を押した。ナシも好天で玉太りが良好となり、「近年では一番の出来栄え」という。入園無料で、持ち帰り料金は巨峰1キロ1000円、シャインマスカットは2000円。ナシ(豊水・新高)は1キロ500円。開園時間は午前9時から午後5時。問い合わせは「道の駅伊万里ふるさと村」、電話0955(24)2252へ。 *8-5:http://qbiz.jp/article/116868/1/ (佐賀新聞 2017年8月22日) 九州グリコが解散へ 2018年12月に菓子生産停止 ●江崎グリコ創業の地「特別な思い」 江崎グリコ(大阪市)は21日、菓子とガムの生産子会社「九州グリコ」(佐賀市)の生産を来年12月に停止し、会社を2019年1月に解散すると発表した。工場の老朽化と販売不振が理由。乳製品などの生産子会社「広島グリコ乳業」(広島市)も来年10月に解散し、それぞれ生産は国内17工場に集約する。九州では、グループ工場が乳製品などを製造する「佐賀グリコ乳業」(佐賀市)のみとなり、菓子製造から撤退する。江崎グリコによると、九州グリコの従業員は262人。うち正社員51人は他工場に転籍させるが、パートなど非正規社員211人は雇用契約を更新しない。跡地(3万1520平方メートル)の活用は未定。九州グリコは1953年に九州工場として操業を開始し、01年に現地法人化した。菓子の「チーザ」とガム類を生産し、17年3月期の売上高は11億6900万円とピークの09年3月期から半減したという。佐賀県は江崎グリコの創業者江崎利一の出身地。有明海のカキの煮汁をヒントにキャラメルのグリコを製品化したといい、九州グリコの干貝(ひがい)博彦社長は「(佐賀県には)特別な思いがある」とコメントを出した。 *8-6:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/457446 (佐賀新聞 2017年8月24日) 総菜ポテトサラダ出荷元O157不検出 埼玉 埼玉県熊谷市のスーパーに入る「でりしゃす籠原店」などで7、8日にポテトサラダを買って食べた14人が腹痛などを訴え、県は23日までに10人の検体からO157が検出されたと発表した。群馬県高崎市は23日、出荷元の同市の食品加工工場にあったサンプルを調べた結果、菌は検出されなかったと発表した。立ち入り調査で感染者が食べたのと同じ製造日のものを持ち帰り検査していた。高崎市によると、埼玉県からの依頼で21日と23日に調査し、製造工程を確認。感染者の食べたサラダは5~7日に製造され、6、7日に群馬、埼玉、栃木の34店舗に計約590キロ出荷されていた。5日と7日の製造分は菌が検出されなかったが、調理器具などの検査結果が24日以降に出る見込み。市は「原材料の衛生状態などに問題はなく、管理上明らかに不適切な点は確認できなかった」としている。工場は19日から操業自粛中という。埼玉県によると、総菜店を運営する群馬県太田市の「フレッシュコーポレーション」は、同工場から袋詰めのポテトサラダを仕入れ、ハムやリンゴをまぜて販売していた。 *8-7:http://qbiz.jp/article/115782/1/ (西日本新聞 2017年8月26日) 【よく分かる日欧EPA】その5:パスタ・菓子 本場の味に対抗できるか 「今でも国産は太刀打ちできないのに、先は厳しい」。経済連携協定(EPA)で欧州連合(EU)産スパゲティやマカロニの関税が11年目になくなると決まり、国内メーカーでつくる日本パスタ協会(東京)の担当者は肩を落とす。協会によると、消費者の国産志向は強いが「パスタに限ってはイタリア、ギリシャ産が好まれる」。形や食感の種類が豊富な輸入品には国産と価格が大差ないものもあり、2016年は輸入量が国内生産量を上回った。1キロ当たり30円の関税がゼロになれば、本場のブランドがさらに浸透する。パスタ協会は原料の小麦輸入時に事実上の関税がかかり、高値で調達せざるを得ない仕組みの見直しを求めている。加工食品では、菓子の関税も軒並み撤廃される。チョコレート菓子の関税は現在10%。詰め合わせだと数千円はするベルギーのチョコ「ゴディバ」といった高級品ほど恩恵は大きくなる。国内メーカーには、EU産と日ごろ食べる国産菓子とはすみ分け可能との見方が多い。ただ、乳酸菌入りのチョコを手掛ける不二家は「今後も付加価値のある製品開発に力を注ぐ必要がある」と輸入増加に気を引き締めており、新商品の投入競争が活発になりそうだ。 ◇ ◇ 日欧EPAで貿易や投資のルールがどう変わるのか。暮らしや産業への影響を中心に解説する。 <漁業について> PS(2017年8月24、26、28日追加):一般の人に海は水面しか見えていないため変わっていないように感じるだろうが、実際には水中のいたるところに生物が生息し生態系があって、人間はそれを利用しているわけである。わかりやすい例では、*9-1のように、ウニは食べ物の海藻が少なければ身が入らず商品にならない。また、海藻が減って砂漠のようになった海を「磯焼け」と呼び、「磯焼け」の主な原因は海水温の上昇で生物が増えて海藻が食べ尽くされることと書かれているが、海水温上昇の原因は地球温暖化だけではなく原発の温排水や海底火山の噴火もあり、海藻の生育にも適切な海水温があるため、「磯焼け」する原因は多い。その結果、食べる身のないウニが増えるため海藻は重要なのである。ただし、ウニの場合は身のないウニを捕獲して陸上の植物や藻類のユーグレナなどで安い飼料を作って養殖することが可能だと私は考える。 そのような中、*9-5のように、原子力規制委員会は、2017年8月25日に九電が再稼働を目指している玄海原発3号機(佐賀県玄海町)の「工事計画」を認可したそうだ。原発が稼働すると、温排水により海が暖められて正常な生態系が壊れるとともに、原発を冷やすために大量の海水とともに海の生物の幼生を吸い込んで煮殺して排出する。これも藻場の衰退や漁獲高減少の原因であるにもかかわらず、原発を再稼働させるなど何を考えているのかと言いたい。 しかし、*9-2は、「①三陸沖での漁獲量が減っているのは、中国が公海で大量に獲っているのもあるが、資源の枯渇も原因だ」「②日本の水産業が抱える問題の縮図が、東日本大震災が起きた三陸にある」「③震災により廃業した漁業者が増え、高齢化と後継者不足が顕著に表れている」「④より厳しく確実に水産資源を管理し、地球環境だけでなく漁業者の生活にとっても持続可能な漁業を実現すべき」などとしている。しかし、①の中国が公海で大量に獲って資源が枯渇しそうなのは事実だが、②③の東日本大震災で原発事故が起きた三陸沖はいろいろな意味で漁業に適さない海になっているという特殊事情があるため、他の要因と混同させるのはよくない。また、④については、日本の漁船は既に網目を大きくして幼魚は逃げられるようにし、漁業者の数も減っているため、日本の水産資源管理を厳しくするよりは他国にも同様の規制を促すとともに、海の環境を守ることの方が重要だ。そして、その結果は食料自給率に影響する。 さらに、*9-3のように、「第6あおい丸」が優良な漁場である長崎県壱岐沖で海砂を採取した後、平戸沖を経由して諫早市久山港に向かう途中の平戸沖で沈没した。対馬や壱岐沖ではイカ釣りなどの漁業が盛んだが、海砂を取ると砂の中に産み付けられた魚介類の卵を一緒に吸い込むため、不漁の一因になっていると言われている。そのため、一石二鳥になるよう、海砂ではなく、埋まってしまったダムの底や天井川の川底の砂をとるべきで、日本はこのように漁業を持続可能にするための国を挙げての努力が行われていないのだ。 その上、*9-4のように、ロシアは北方領土を経済特区に指定し、「先行発展地域」に指定するそうで、日本政府の言う「特別な制度」にどういう意味があるのかは不明だが、日本政府は現在最もやるべきことを考えていなかったため、北方領土を返還してもらうこともできず、“共同経済活動”だけを行って北方領土を諦めることになったらしいのは、悲しくも阿保らしい。 そのため、このような漁業上の理由からも、*9-6の高知新聞による「エネルギー計画は、脱原発を明確にすべきだ」という意見及び*9-7の山陽新聞による「エネルギー計画、現実踏まえ抜本見直しを」という意見に全く賛成だ。    *9-1より (図の説明:ウニの漁獲高は、左のグラフのように年々減少している。その原因は、①中央の写真のように、えさとなる海藻がなくなる磯焼けをしていること ②それにより、右の写真のように、餌不足のウニに食用部分の身が入らないこと などである) *9-1:https://abematimes.com/posts/2467906 (Abema Times 2017.6.2) 寿司屋からウニが消える?漁獲量を減少させる「磯焼け」とは 玄界灘に面した新三重漁港をはじめ、長崎県は全国4番目の漁獲量を誇るウニの好漁場だ。しかし近年、ウニの漁獲量は年々減少しているという。中には身の入っていないウニもあった。原因は「磯焼け」だ。海岸に生えているコンブやワカメなどの海藻が減少、不毛の状態となってしまう現象だ。磯焼けの海で獲れるウニは、身入りが悪く、売り物にはならない。長崎県のウニの漁獲量は1970年代後半には4000トン以上を記録していたが、現在はその10分の1程度にまで落ち込んでいる。福岡市中央区にある「うにと海老の専門店 魚魚魚」の島津料理長によると、価格も高騰、1キロ5000円~1万円の幅で変動しているという。30年以上全国各地の海に潜り「磯焼け」を研究、水産庁の「磯焼け対策ガイドライン」策定にも携わった東京海洋大学の藤田大介准教授は、「磯焼け」の主な原因は温暖化による水温上昇が引き金となって生物の活動が活発化し、海藻が食べ尽くされてしまったことだと話す。さらに、気候変動で大型の台風や時化の発生が増え、海藻が引き剥がされ枯れてしまうのだ。 また、ウニそのものも「磯焼け」の原因になってしまっている。飢餓に強く、食料がない場合は生殖せずに生きていこうとするのだという。「磯焼け」の海で取れた、身の入っていないウニは、精巣・卵巣の部分の成長を抑えているウニということだ。「実は東日本大震災の直後、養殖施設が流れてしまったことで潮通しが非常に良くり、海藻にとってプラスに働いた。その後に生まれたウニたちが食べ盛りになっていて、今、大いに暴れている。そこで水温が高くなると、ますます海藻を食べてしまう」(藤田准教授)。長崎の漁師たちも手をこまねいていたわけではない。漁協では、ウニの移植で磯焼けの解消を図っている。ウニを普通の藻場に移し、磯焼けが進行した場所には海藻を移植、繁殖を促している。また、藤田准教授は「北海道では冬のエサがない時期にイタドリの葉っぱを与えるという試みもあった。エサに困るところはそういう努力もしている」と、不要になった野菜を使った養殖の可能性も示唆した。将来、私たちが美味しいウニを食べられなくなる日が来てしまうのだろうか。藤田氏は「磯焼け対策の中でも、一般市民ができることはまだまだあると。ダイバーの方は写真を撮って記録していただくとか、陸上で手伝えることもあると思う。参加していただければと思う」とした。 *9-2:http://www.nikkei.com/article/DGXMZO19950560U7A810C1I00000/?n_cid=MELMG002 (日経新聞 2017/8/16) 市場で買う魚がない 減り続ける水産資源、三陸沖の不都合な真実(上) ノルウェー近海、北米東海岸と並び世界三大漁場のひとつといわれる三陸沖。親潮と黒潮がぶつかる潮目でとれる豊富な種類の魚介類は、長らく日本人の食生活を支えてきた。しかし今、三陸沖での漁獲量が減っている。宮城県北部の気仙沼湾。最も奥まったところにある鹿折地区に、18社の水産加工会社が名を連ねる気仙沼鹿折加工協同組合(気仙沼市)がある。地元の加工業者が事業コストを減らすために設けた7000トンの大型冷蔵庫が低い音を響かせる。 ■細る漁獲量 しかし組合は冷蔵庫の稼働率を高めるのに苦労している。2016年末の時点で稼働率は6割ほど。本来は魚で冷蔵庫の棚を埋めたいところだが、やむなく組合企業から海藻類を集め、やっとのことでフル稼働に近づけた。「サンマやカツオなど、気仙沼で揚がる主要な魚種がとれなくなっている」。当初の計画通りに漁獲量が上がらず、組合の細谷薫事務局長は頭を悩ませる。組合企業で缶詰などを製造するミヤカン(気仙沼市)で原料・直販を担当する三浦謙一氏は、最近魚市場に買い出しに行っても何も買わずに帰ってくることが増えた。「水揚げそのものがない場合が多く、揚がっていても高くて入札で落とせない」。サンマの缶詰は同社の主力商品の一つだ。だが16年の日本のサンマ漁獲量は約11.4万トンと、水産庁が統計を取り始めた1977年以降の最低を記録した。気仙沼魚市場には16年10月時点では5700トンのサンマが揚がり、1キログラムあたり188円の値が付いた。03年10月と比べると量は約半分に、価格はほぼ4倍に跳ね上がっている。ミヤカンの寺田正志社長は「台湾や中国などが公海でたくさんとっているのもあるが、資源そのものの枯渇も原因だ。ここ2年ほどは小さいものしか揚がらない」と嘆く。 ■漁業大国は過去のモノに 「6本目ェ!」「はい7本目ェ!」。午前3時、宮城県東部の石巻湾。東松島市の漁師、大友康弘氏が海からはえ縄を手際よく船上にたぐり寄せる。縄の先の針をくわえた旬のスズキは甲板の上でバタバタと力強い音を立て抵抗する。大友氏は釣ったスズキの水揚げ量を記録し、岩手大学の石村学志准教授に報告する取り組みを2年前から始めた。水産資源学が専門の石村准教授のもとでスズキの資源量を科学的に調べ、どのくらいの漁獲量なら資源の回復と漁業が両立し得るか、その水準をはじき出すのが狙いだ。石巻湾のスズキは長く漸減傾向にあった。ところが11年の東日本大震災から4年間、湾内ではスズキ漁が取りやめになり、資源量が大きく回復したという。「スズキが増えた今がチャンスだ。この資源水準を保てる漁のやり方を探したい」。大友氏は過去に記録していた水揚げ量の資料も含め計7年分のデータを石村准教授に渡している。「日本は漁業大国」。世界各国の水揚げ高と比べれば、そんな言葉が過去のものだということは一目瞭然だ。国連食糧農業機関(FAO)によると、日本はかつて他国を大きく引き離していたが、1984年の1159万トンをピークに右肩下がり。中国、ペルー、米国、インド、インドネシアに抜かれ、現時点では6位まで下がった。特に三陸地方の主要漁港である八戸、宮古、釜石、大船渡、気仙沼、女川、石巻、塩釜の8港の水揚げ高は、03年に55万トンだったのが15年には42万トンにまで減少。東日本大震災が起きる前から減少傾向は続いている。水産庁によると、日本周辺の主要な48魚種79系群(系群は一つの魚種の中で産卵場、産卵期、回遊経路などが同じ集団を指す)のうち、16年9月時点で実に半数の資源量が低位にあり、3割超は資源量が中位にあるという。資源量が低位にある魚種にはマサバやスケトウダラ、ズワイガニやトラフグなどが挙げられている。スズキ以外のこうした日本の食卓になじみ深い魚種についても、大友氏は警鐘を鳴らす。「今の発達した漁業技術をもってすれば、この石巻湾内のあらゆる魚を取り尽くすのはいとも簡単なことだ」 ■漁業者は利益上げにくく 漁獲量の減少により、漁業者や水産加工会社は利益を上げにくくなっている。特に日本の漁業生産額の約6割を占める沿岸漁業では個人経営が多く、原油の高騰なども所得に大きく響いている。15年時点の沿岸漁船漁師の平均漁労所得は年261万円と漁業だけで生活するには困難な水準だ。収入が低いため若い漁業者も集まりにくく、後継者不足と高齢化が深刻化している。 日本の水産業が抱える問題の縮図が、東日本大震災が起きた三陸にある。震災により廃業した漁業者が増え、高齢化と後継者不足がより顕著に表れている。全国の漁業経営体の数は13年に9万4507件と03年から28%減少したが、宮城・岩手の両県では計5676件と、同じ10年間で41%も減っている。 ――より厳しく確実に水産資源を管理し、地球環境だけでなく漁業者の生活にとっても持続可能な漁業を実現する――。国や漁業関係者のあいだで、漁業大国の名を名実ともに取り戻すための挑戦が始まろうとしている。 *9-3:http://qbiz.jp/article/116928/1/ (西日本新聞 2017年8月22日) 長崎・平戸沖で砂運搬船が沈没 2人不明1人心肺停止 ●停泊中、3人は漁船に救助される 22日午前3時40分ごろ、長崎県平戸市沖で長崎市平野町の「葵新建設」所属の台船を押す押し船「第6あおい丸」(98トン)が遭難信号を出した後、沈没した。佐世保海上保安部によると、乗船していた男性6人のうち4人が救助されたが、航海士大浦作美さん(59)=福岡市南区大橋3丁目=の死亡が確認された。2人が行方不明となっている。救助された他の3人はいずれも意識があるという。行方不明になっているのは、船長の竹谷和浩さん(48)=長崎県新上五島町七目郷、航海士丸山勝広さん(46)=同県平戸市生月町山田免。第7管区海上保安本部(北九州)が捜索している。海保などによると、第6あおい丸は台船の「第8あをい丸」と連結して運航。長崎県・壱岐沖で砂を採取した後、平戸沖を経由し、同県諫早市の久山港に向かう途中で、現場付近でいかりを下ろして停泊していたという。台船もともに沈み、救助された4人は台船に乗っていたという。海保によると、現場は平戸島北東約4キロの海上で、当時は晴れており海は穏やかだったという。乗組員の一人は「船が浸水して急に傾き、6人が海に投げ出された」などと説明している。他に救助されたのは、機関長森律雄さん(66)=平戸市、航海士森元徳さん(55)=同、機関士笹山安彦さん(48)=長崎市。笹山さんは近くの漁船に救助され、2人の森さんは海保が救助したという。 ●過去にも転覆・沈没 長崎県沖では、これまでにも船の転覆・沈没事故がたびたび起きている。 五島列島沖では1993年2月、巻き網漁船「第7蛭子(えびす)丸」(80トン)が転覆して沈没、乗組員19人が行方不明になった。同年7月には、佐世保市沖で巻き網漁船「第21金光丸」(14トン)と砂利運搬船「龍玉丸」(683トン)が衝突、金光丸が沈没して9人が死亡した。2009年4月には平戸市沖で、巻き網漁船「第11大栄丸」(135トン)が沈没して船長ら12人が犠牲になった。その10日後には、五島市沖で巻き網漁船「有漁丸」(19トン)が座礁・沈没。10年1月にも同市沖で底引き網漁船「第2山田丸」(113トン)が沈没、10人が死亡した。15年9月には、対馬市沖でイカ釣り漁船「第5住吉丸」(10トン)など5隻が転覆し、5人が死亡している。大きな事故が起こるたび、漁業者や行政は事故防止策の見直しを進めてきた。ただ、後継者不足や魚価低迷で老朽化した船の新造が難しいなど、事故の背景には漁業が直面する厳しい現状を指摘する声もある。 *9-4:http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201708/CK2017082402000123.html (東京新聞 2017年8月24日) 【国際】ロシア、北方領土を特区指定 共同経済活動影響か タス通信によれば、ロシアのメドベージェフ首相は二十三日、訪問先の極東サハリン州で、南クリール諸島(北方領土)を、外国企業の誘致などを目的としたロシアの経済特区「先行発展地域」に指定する決定に署名した。日本政府は、北方領土で双方の法的立場を害さない「特別な制度」での共同経済活動実現を目指してロシア政府と協議中。一方的ともいえる特区指定は、共同経済活動の実現に否定的な影響を及ぼす可能性がある。日ロは現在、観光や養殖など共同経済活動の事業案絞り込みを進めるが、ロシア側は「特別な制度」をめぐる協議には消極的とされる。九月上旬に極東ウラジオストクで予定される日ロ首脳会談を前に、特区指定で日本をけん制する狙いもあるとみられる。先行発展地域には税制優遇措置などがあり極東地域では十八番目。メドベージェフ氏は「漁業やインフラ整備に役立ち、地域の発展を後押しする」と強調した。共同経済活動を巡って、ロシアの経済関係者からは「日本が特区に参加する形で進めるべきだ」との意見がある。一方、ロシアが指定した特区での経済活動は、北方領土でのロシアの主権を認めることになる。日本側が創設を求める「特別な制度」とは矛盾し、日本側としては受け入れ困難。 *9-5:http://qbiz.jp/article/117302/1/ (西日本新聞 2017年8月26日) 九州の原発:玄海原発3号機の工事計画認可 再稼働は越年も 原子力規制委員会は25日、九州電力が再稼働を目指す玄海原発3号機(佐賀県玄海町)について、設備の詳細設計をまとめた「工事計画」を認可した。九電は、設備性能を現地で確認する「使用前検査」を28日にも申請する。工事計画の審査が長引いたため、今秋を想定していた再稼働は12月以降にずれ込む見通しで、越年の可能性が出ている。再稼働には使用前検査に加え、運転管理体制を定めた「保安規定」の認可も必要。一連の手続きに4、5カ月程度を要するとみられる。九電は25日、「引き続き国の審査に真(しん)摯(し)かつ丁寧に対応する」とコメントした。玄海原発3、4号機は1月に新規制基準の適合性審査に合格した。九電は3号機を先行して再稼働する方針。4号機は工事計画の審査が続いており、九電の補正書提出を受け、3号機に続いて認可される見通し。 *9-6:http://www.kochinews.co.jp/article/121389/ (高知新聞 2017.8.28) 【エネルギー計画】脱原発を明確にすべきだ 国の中長期的なエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」の改定に向け、経済産業省が作業に入った。有識者の意見を聞きながら年度内にもまとめる方針だ。最大の焦点はやはり原発の方向性になる。国民が納得のいく、しっかりとした論議を求めたい。現計画は2014年4月に策定された。東京電力福島第1原発事故後初の改定で、事故の反省と教訓を前面に打ち出したが、矛盾が目立つ内容というしかない。序文で「震災前に描いていたエネルギー戦略は白紙から見直し、原発依存度を可能な限り低減する」と強調する一方で、その原発を石炭火力や水力とともに安定供給を図る「ベースロード電源」に位置付けた。事故後に停止した全国の原発の再稼働を進める方針も掲げている。旧民主党政権は事故後、脱原発の声の高まりを受け、「30年代の原発ゼロ」を打ち出していた。政権交代で後を継いだ安倍政権がそれを転換し、「原発回帰」を掲げたといっていいだろう。国民の声を無視し、アベノミクスの実現を優先したとの批判もある。15年には30年度の電源構成比率を決め、原発を「20~22%」とした。世界各国が積極的に導入している再生可能エネルギーの位置付けは「22~24%」にとどまっている。政府の原発依存の姿勢は明らかだ。しかも、原発の電源構成比率2割以上を実現するには、いま停止中の原発の再稼働を進め、老朽化した原発の運転期間延長や建て替えが前提になる。福島第1原発事故後に改正された原子炉等規制法は、原発の運転期間を原則40年としているが、原子力規制委員会が認めれば、特例で1回に限り20年の延長ができる。に2基が延長審査に合格しており、原発事故を教訓に設けられた運転期間制限の形骸化が早くも懸念されている。建て替えとなれば脱原発はさらに遠のく。世耕経産相は、計画改定について「(計画の)骨格を変える段階にない」と述べている。電源構成目標の達成方法を論議したいという。ひとたび原発の過酷事故が起これば、復興がいかに難しいかは被災地が示している。福島第1原発はいまもって廃炉の具体的な見通しが立たず、事故対策費は約22兆円に上るとの試算もある。原発は極めてリスクが高く、他の発電方法と比べコスト競争力に勝るとも言えなくなっている。何より多くの国民が脱原発を望んでいる。一足飛びにはいかないにしても、政府は中長期の戦略である新計画で脱原発を明確に打ち出し、その道筋を探るべきだ。地球温暖化防止も含め、再生可能エネルギーの導入にもっと汗をかく必要がある。福島の事故責任の一端は、「安全神話」に陥り、過酷事故への備えが不十分だった政府にもあると、現計画も記している。まやかしのような計画や政策を続けてはならない。 *9-7:http://www.sanyonews.jp/article/587277/1/ (山陽新聞 2017年8月28日) エネルギー計画 現実踏まえ抜本見直しを 国の中長期的なエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」の見直し議論が経済産業省の有識者会議でスタートした。2014年の現行計画の決定以降、エネルギーや環境を巡る状況は変化している。抜本的な見直しに踏み出すべき点は少なくないはずだ。ところが、世耕弘成経産相は大幅見直しに慎重な姿勢を示している。原発について現計画は「依存度を可能な限り低減する」としつつ、「重要なベースロード電源」とも位置付けている。30年度の「電源構成」目標では、原発が20~22%を担うとした。東京電力福島第1原発の事故を受けて、脱原発を望む多数の国民の思いを反映しておらず、逆に原発回帰路線を鮮明に打ち出したものとなった。原発で約2割をまかなうためには既存の42基の多くで再稼働が必要となる。「例外」とされたはずの運転期間の40年制限を超えた延長もしなければ達成できず、実現性には疑問符が付こう。老朽原発の運転データはまだ少なく、トラブル増加を招く恐れも指摘されている。計画が示された14年以降、再稼働した原発は5基にとどまっている。新潟県の柏崎刈羽原発を巡る地元同意の難航など、再稼働が容易でないことも示されている。目標が現実に即したものになるよう、丁寧な議論が必要だ。もう一つの焦点が再生可能エネルギーである。現行計画は「導入を最大限加速する」とうたい、目標を22~24%(水力含む)としている。再生エネは原発事故後、日本でも育ちつつあるとはいえ、水力を除いた太陽光、風力などは6%にとどまる。26%を占めるスペイン、25%のドイツなどの欧州各国と比べれば立ち遅れは明らかだ。日本が再生エネの課題に挙げる発電コストの高さについて欧州では、市場拡大による設備価格の低下などにより火力、原子力と同等か割安の水準を実現している。昨年秋には、地球温暖化防止のための新たな枠組み・パリ協定が発効した。日本は温室効果ガス排出量を50年に13年比で80%削減する目標を掲げ、先進各国も思い切った目標を設定した。多くの国で再生エネ拡大を目標達成手段の柱に据え、技術革新やインフラへの投資が相次いで、ビジネスチャンスともなっている。経済面からも乗り遅れないようにしたい。現行計画で推進を掲げている核燃料サイクル政策の根本的な見直しも急務だ。政府は昨年末、トラブル続きの高速増殖原型炉もんじゅの廃炉を決めた。政府は後継となる高速炉の開発を進めるというが、サイクル政策の延命にも限界があろう。日本のエネルギー政策が時代に取り残されることのないよう、政府は現実を直視し、計画を練り直していくことが求められる。 <では、次に進もう> PS(2017.8.28追加):10-1のように、準天頂衛星「みちびき」を使えば、既存のGPSと併用して最小6cmの誤差で位置を測ることができ、正確な測位で農機の自動走行ができるようになるというのはすごいが、確かに道路を移動中も安全に自動運転して欲しい。 また、*10-2-1のように、水田の給排水を自動化して水管理時間を8割減少させ、遠隔操作できるのようにしたというのも素晴らしい。このような中、*10-2-2のように、地震や豪雨で多くの溜池が決壊したそうだが、この際、どうしても必要な溜池と地下水や下水浄化水で代替できる溜池を選別したらどうだろうか。このうち下水浄化水は、現在では飲めるほどまで浄化できるそうだが、窒素・リン酸・カリウムを少し残して肥料の節約をすることも可能だ。 さらに、*10-3のように、「農家・漁師をスターにする」として、早稲田・慶應など首都圏8大学の学生編集部が生産者の生の声を月間約2万の読者に届けているのは面白いが、販売はマーケティングで、自動農機はロボットであるため、いろいろな学部の学生が農林漁業の現場を体験して、スマートに問題解決する方法を考えれば有意義だと思われる。 *10-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170828&ng=DGKKZO20441280Y7A820C1PE8000 (日経新聞社説 2017.8.28) 衛星生かし精密農業の推進を 衛星画像やIT(情報技術)を利用し、農業生産の効率向上をめざす「精密農業」が米国で広がっている。日本でも担い手が不足する農業の改革は待ったなしで、準天頂衛星「みちびき」を使う日本版GPS(全地球測位システム)を最大限活用すべきだ。米国では東京ドーム400~500個分もの農地を数人で経営する場合もあり、精密農業による効率化のニーズが高い。GPS受信機、収量計測装置などを搭載し、自動運転も可能なトラクターやコンバインが増えている。日本の農地は規模が小さいが生産性向上などの課題は米国と共通しており、学ぶべき点は多い。米モンサントはGPSの位置情報を使い農地の区画ごとの雨量、収量などをスマートフォン(スマホ)画面の地図上にわかりやすくカラー表示するサービスを始めた。気象情報会社を買収し観測やデータ解析のノウハウを得た。近年は局地的豪雨が増え、隣接地でも雨量が異なる場合がある。同じように育てた同一品種でも、収量が少ないこともある。スマホなどで常に実態を把握できれば、区画ごとに収穫時期をずらしたり品種を替えたりするのに役立つ。日本はみちびき1~3号機の打ち上げに成功し、今年度中に4基目が上がる予定だ。既存のGPS信号と併用して最小6センチメートル程度の誤差で位置を測れるようになる。精密農業の普及につながる新サービスを展開する好機だ。正確な測位で農機の自動走行の安全性は高まる。農林水産省は今年3月、人間が近くで監視しながら、農地でトラクターなどを無人で自動走行させる際の安全指針を出した。今後は遠隔操作での無人走行や、農地に隣接した一般道の走行も検討すべきだろう。測位情報は他の衛星の画像、気象、地形、地質などの多様なデータと組み合わせてこそ使い道が広がる。斬新なアイデアをもつ企業がこれらを素早く入手して事業に生かせるよう、関係省庁が連携して仕組みづくりを進めてほしい。 *10-2-1:https://www.agrinews.co.jp/p41733.html (日本農業新聞 2017年8月28日) 水田給排水を自動化 管理時間8割減 遠隔操作装置+アプリ 農研機構 農研機構農村工学研究部門は、スマートフォン(スマホ)などで水田の給排水を自動設定し、水管理の時間を8割減らすシステムを開発した。給水バルブと排水口に遠隔操作装置を取り付け、圃場(ほじょう)に行かなくても水深が制御できる。給排水の両方を自動化したのは日本初で、今年度中に市販化の予定。水稲の労働時間の3割を占める水管理を軽減し、農地を集積する担い手を支援する。研究は内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の一環。遠隔操作装置はソーラーパネルやアンテナ、モーターなどを組み合わせて作り、給水バルブと排水口の両方に使える。電波で開閉し、各社のバルブに後付けできる。この他、水深を感知するセンサー、電波の基地局などを設置する。制御の仕組みは、センサーが水深の変化を感知すると自動で給排水を調節し、元の水位に戻す。水位の設定は専用のアプリを使いスマホやタブレット、パソコンでできる。アプリでは水位や気温の確認もできる。省力の他、豪雨で急に増水したときも有効だ。20アール区画で実証試験をしたところ、水管理の年間の労働時間は3時間と、慣行水田の15時間に比べて8割減った。無駄なかけ流しが減るため、使う用水量を50%に節約する効果もあった。システムは年度内に国内メーカーから発売される予定だ。価格は基地局が1台20万~30万円、バルブを動かす装置(給水、排水共通)が同10万円。サーバーの利用料が1カ月当たり2000~4000円ほどを見込む。同部門は「農地の集積で分散した水田が増える中、担い手の省力効果は大きい」と説明する。品種などから水管理が自動で分かり、収量や品質が向上できる仕組みも開発中だ。 *10-2-2:https://www.agrinews.co.jp/p41729.html (日本農業新聞論説 2017年8月27日) ため池 総点検 防災強化へ再整備急げ 地震や豪雨で決壊するため池が続発している。釣りなど娯楽中の死亡事故も続く。政府は農業用水の確保に欠かせぬため池の再整備を急ぎ、防災機能と安全性を高める必要がある。ため池は、西日本を中心に全国に約20万カ所ある。主に雨の降水量が少ない地域で農業用水を確保するために人工的に造られた。洪水調節や土砂流出を防止する効果に加え、生物の生息・生育の場所の保全、地域の憩いの場の提供など、多面的な機能もある。2ヘクタール以上の農地をカバーするため池は約6万カ所あり、このうち7割が江戸時代以前に造られた。取水施設などでの老朽化が進んでいる。多くは地元の水利組合や土地改良区、農家などが管理する。農家の減少や高齢化から管理が行き届かず、堤の崩れや排水部の詰まりなどが起きている。農水省の調査によると、下流に住宅や公共施設のあり、決壊すると大きな被害が予想される「防災重点ため池」は、1万カ所を上回った。近年は都市化や混住化が進み、事故の危険性が増している。安全性が確認できない3391カ所に対する詳しい調査を地方公共団体が行うが、整備を急ぐ必要がある。最近10年のため池被災は、7割が豪雨、3割が地震で決壊や流失している。7月の九州北部豪雨災害で大きな被害を受けた福岡県朝倉市では、市内のため池108カ所の1割に当たる11カ所が流出・決壊した。こうしたため池の復旧を急ぐとともに、耐震性を高め、洪水防止策を強めるなど、安全性の強化を急ぐことが肝要だ。ため池を抱える地域では、農家が減る中で受益農家にかかる工事費用の負担が重く、改修工事の合意形成も容易ではない。政府がしっかり支援すべきだ。農水省は農村地域防災減災事業(508億円)に含まれているとするが、心もとない。現場のニーズに応えられるように予算を確保し、改修工事などをしやすくしたい。また、補助率を高めるなど農家負担を減らす方法も改修を後押しするはずだ。ため池での死亡事故は増加傾向にある。2016年度は26件で32人が亡くなった。60歳以上の高齢者が多く、例年水利用が多くなる5月から9月にかけて多発している。ため池を管理する土地改良区や個人は、安全管理に対する意識を高めるとともに、監視を強める必要がある。死亡事故には、釣りなどの娯楽中の事故も多い。夏休み期間の子どもたちが危険な箇所に立ち入らないように注意喚起したり、安全柵を設置したりする対策も進めるべきだ。また、管理作業中の事故も多い。高齢者の作業は特に注意する必要がある。農山村は人口減少と高齢化が進んでいる。ほったらかしにしたままのため池はないか。地域のみんなで点検し、必要な整備を急ぐことが大事だ。政府は、こうした取り組みを全力で支援すべきである。 *10-3:https://www.agrinews.co.jp/p41724.html (日本農業新聞 2017年8月27日) 若者力:[食農応援隊 大学生リポート](9) 長期密着し“スター”育成 首都圏8大学の学生が編集 農家の生の声を発信するWEBサイト 日本食べるタイムス 「タケノコ王」って知っていますか? 目印はピンク色のタンクトップ。全国放送のテレビ番組で準レギュラーとしても活躍するタケノコ農家、風岡直宏さんです。2年前、無名だった風岡さんの情報発信を「日本食べるタイムス」(以下食べタイ)が引き受け、彼が“農家スター”になるまで伴走しました。今では彼の下にファンがサインを求めて訪れ、タケノコの産直販売は大盛況です。食べタイは、農家の生の声を発信するWEBサイトです。コンセプトは「農家・漁師をスターにする」。早稲田、慶應など首都圏8大学の学生編集部20人が、全国約200人の生産者の生の声を、月間約2万の読者に届けています。大量の情報の中に埋もれてしまった農家のブログやSNS(インターネット交流サイト)投稿を掘り起こしたり、学生が現地で取材したりして記事を発信しています。何度も現場に通い、一緒に農作業をすることもあります。このような長期密着・仕事体験型の取材は、学生だからこそできる発信方法です。登録生産者からは「過去最高の売り上げになった」「ここで働かせてほしい、と若者に志願された」などと反響をいただいています。われこそは、という農家、推したい農家さんがいる農業関係者の皆さん、ぜひ食べタイにご連絡ください。登録は無料です。(代表・森山健太=早稲田大学) *キャンペーン「若者力」への感想、ご意見をお寄せ下さい。ファクス03(3257)7221。メールアドレスはwakamonoryoku@agrinews.co.jp。フェイスブック「日本農業新聞若者力」も開設中。 <お粗末な日本の食料政策> PS(2017年8月31日、9月1日追加):*11-1の「①食料自給率が38%にダウンしたから、1ポイント上げるために、ご飯をもう一口食べろ」「②日々の食卓に、ちょっと工夫しろ」という指示を出すような意識の低い人が人がリーダーでは困るのである。何故なら、①は、現在は、*11-2、*11-3のように、健康上の理由で栄養バランスを考えて糖質・炭水化物を控えている時代だからであり、供給者が需要に合わせて生産を調整するのではなく、できたものを食べるように需要者に注文を付けるというのは市場主義にも反するからである。また、斎藤健農相の「消費者が意識を持ってもらうことが重要」「子や孫のことを考えて食料自給率向上に目を向けてほしい」というのも呆れたもので、消費者は十分に意識が高いからこそ栄養バランスを考えて糖質を抑え、放射性物質が混入している可能性のある食品を控えているのであり、政府の方がよほど意識が低いのだ。そんなことも、言われなければわからないのですか? なお、*11-4のように、全ての加工食品に原材料の原産地表示を義務付ける改正食品表示基準が9月1日に施行されるが、5年も猶予期間があり、完全施行は2022年4月からだそうだ。これは、政府はしぶしぶこの法律を施行するという意味で、実質的には2022年3月までは施行されないということだ。それも、国名だけの表示なら、安全基準の緩い日本産は買わないことになるが、まさか国名だけの表示ではないでしょうね。 さらに、*11-5のように、TPP署名11カ国は2017年8月30日にシドニーで首席交渉官会合を行い、日本は議論を主導する立場なので関税分野の見直しを提案しにくく、最終的には米国のTPP復帰を促して12カ国での発効を目指すのだそうだ。しかし、オーストラリアは優秀な農業国で原発はなく、赤身で脂肪の少ない牛肉や乳製品が安いため日本の消費者は嬉しいが、日本の農業には不利である。それでも日本政府は、まともな交渉もせずに議論を「主導」し、このTPP条約が締結されれば食料自給率がさらに下がるが、それでもTPP条約の締結は麻生副総理の言われる「結果を出した」ことになるのですか? *11-1:https://www.agrinews.co.jp/p41748.html (日本農業新聞 2017年8月29日) 食料自給率 38%にダウン +1ポイント作戦始動 ご飯もう一口、国産豆腐は月に2丁… 日々の食卓 ちょっと 工夫を ご飯を1日もう一口、国産豆腐を月に2丁――。食料自給率を1ポイント上げるため に必要な国民の食事量の一例だ。2016年度の食料自給率(カロリーベース)は38%と、先進国の中で最低水準にまで落ち込んだ。半世紀前の73%から半減し、もはや国民の食と命を自国で守れない危機的な状況にある。自給率向上へ国民一人一人がどんなことをすればよいのか? 誰でも簡単にできる「1ポイント上げる」ためのちょっとした工夫を紹介する。農水省が提示する食料自給率を1ポイント向上させる方策によると、全国民が、ご飯を1日にもう一口(17グラム)食べるだけで1ポイント自給率が向上する。「国産米粉パンを月に6枚(400グラム)食べる」「国産大豆100%の豆腐を月に2丁食べる」「国産小麦100%のうどんを月に2玉食べる」などでも向上する。これら全て実現できれば、4ポイント向上する計算だ。日常の食事を増やすわけでなく、国産の農産物を選ぶことで自給率が上がる。国産の比率が高いのが米を使ったメニューだ。おにぎり1個98%、にぎりずし75%、親子丼70%など、米料理の自給率は高い。ただ、和食を多く食べれば自給率の向上に直結するかというと、そう単純ではない。原料の輸入割合が高いそばやうどんでは自給率は下がり、「エビの天ぷらそば」は24%まで低下する。本みりん(98%)、かつおだし(69%)などだしの自給率は高いが、しょうゆ(23%)、エビ(5%)などの低さが自給率を下げる要因だ。しかし、国産のそば粉や小麦粉を使うと自給率は向上する。ソバの自給率22%の中で、国産そば粉を使ったそばを提供する東京・上野の「はなみずき」店主、弘田千秋さん(43)は「国産のそば粉は、海外産と味が違う」と国産にこだわる理由を明かす。そば粉を100%国産にすれば、天ぷらそばの自給率は71%まで上昇する。最近ではラーメン用やちゃんぽん用、パスタ用など小麦の品種開発が進んでおり、こうした品種が広がれば自給率向上に貢献しそうだ。農水省は自給率への意識を高めてもらおうと、インターネット上で、料理の自給率を計算するソフトを公開。ハンバーグ(14%)、ねぎとろ丼(82%)といったメニューや、家庭で作る料理の食材を選んで入力すれば、食料自給率を算出できる。 ●国民が危機感を共有 食料自給率は、国民の平均カロリー摂取量のうち、国産食材で得られるカロリーの割合を示す。16年度は国民1人が1日当たり2429キロカロリーを摂取しており、このうち国産食材からの摂取は913キロカロリーにとどまる。国民の摂取カロリーの割合で最も多いのは米(自給率98%)、次いで畜産物(同16%)、油脂類(同3%)。この3品目だけで摂取カロリーの全体の半分を超える。4番目に多いのは小麦(12%)だ。同省によると、自給率の高い米の消費が減る一方で、飼料を海外に依存している肉類や油脂類、小麦製品の消費量が増え、自給率を下げる要因となっている。食の洋風化や油脂類・小麦の輸入増などが、自給率低下をもたらしている。少子高齢化で国内の食市場そのものが縮小している状況を踏まえ、斎藤健農相は「消費者が意識を持ってもらうことが重要。子や孫のことを考えて食料自給率向上に目を向けてほしい」と危機感を示す。 *11-2:https://mainichi.jp/articles/20170719/ddl/k37/040/330000c (毎日新聞 2017年7月19日) 糖尿病:治療「中断」17.1% 県、491機関の患者を調査 /香川 ●「仕事」理由、重症化の傾向 仕事の忙しさや症状がなかったことなどから糖尿病の治療を中断した経験を持つ人が患者の17・1%いることが、県の調査で分かった。若い患者ほど中断経験があり、40歳以下では24・8%と4人に1人近くに上った。中断経験者は重症化しやすい傾向もあり、県は治療継続のために地域や職場、医療が連携する必要性を指摘している。昨年の人口動態調査(概数)によると、人口10万人あたりの糖尿病死亡率は14・1人で、全国平均(10・8人)を上回り、全都道府県でワースト9位となっている。調査は2008年度に続いて2回目。生活習慣から発症が多いとされる「2型糖尿病」患者を治療する491の内科や専門医療機関を対象に、60歳以下の患者について昨年12月に実施。226機関が1367人(男882人、女482人、性別不明3人)分を回答した。受診のきっかけは、46・1%が健康診断で、35・7%は妊娠や交通事故などの診察や治療だった。糖尿病の症状が出て受診した患者も15・2%いた。だが、すぐに受診したのは78・5%。受診しなかった理由(複数回答)では、▽「特に症状もなく必要はないと思った」59・8%▽「仕事や用事で時間が取れなかった」42・4%▽「生活習慣を変え自分で改善できると思った」30・8%--などだった。17・1%の患者で治療の中断経験があった。男性は18・5%で、女性の14・7%を上回った。中断理由(複数回答)では、男性の47・7%が「仕事が忙しいので通院できなかった」を挙げたが、女性は22・4%だった。女性は「症状がなかった」が29・9%で最多だった。治療継続のために必要なことは、男性は「職場の理解」が31・4%、女性は「家庭の理解」が36・9%だった。治療を中断後に再開した患者は、網膜症や腎症、神経障害といった糖尿病合併症の併発率が中断しなかった患者と比べて3・2~2・6倍に達した。また、40歳以下の患者の86・8%が肥満だったが、41歳以上50歳以下は74・4%、51歳以上は64・4%にとどまった。食事、運動療法を続け、年配者ほど効果が出ているためとみられるという。他の医療機関との連携状況では、歯科医との連携が24・6%と低かった。県健康福祉総務課の担当者は「歯周病と糖尿病には高い相関関係のあることが分かっているが、歯科医との連携が低かった。症状がなくても治療の必要があるといった知識の普及を進めたい」と話している。 *11-3:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/459618 (佐賀新聞 2017年8月31日) くら寿司が糖質制限メニュー ■シャリは大根酢漬け 回転ずしチェーン「くら寿司」を運営するくらコーポレーションは29日、すしの酢飯の代わりに大根の酢漬けを使った「シャリ野菜」など、業界で初めて糖質制限に対応したメニューを発表した。31日から全国の店舗で販売する。ご飯など炭水化物に多い糖質の摂取量を減らす「糖質制限」の人気に着目し、若い女性などの集客増を目指す。一方、「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトが期間、時間帯限定の食べ放題サービスを28日から対象店舗を拡大して実施するなど、回転ずし業界各社は激化する競争での勝ち残りへ知恵を絞っている。シャリ野菜は酢飯を使った通常のすしと比べて糖質を最大88%カットした。すしネタはエビやビントロなど4種類。酢飯の量を半分にした商品も用意し、価格は108円。担当者は「糖質を気にせずに野菜と一緒においしく食べてもらいたい」とアピールする。かっぱ寿司の食べ放題は今後も実施店舗を変えて継続する方針で、担当者は「大学生や家族連れなど幅広い層に利用してもらいたい」と話す。「スシロー」を展開するあきんどスシローは、国内の天然魚の活用や、海外産食材の調達多様化を進めている。 *11-4:http://qbiz.jp/article/117878/1/ (西日本新聞 2017年9月1日) 全加工食品に原産地表示 きょうから義務化 全ての加工食品に原材料の原産地表示を義務付ける改正食品表示基準が1日、施行された。メーカーや販売店が表示を変更する準備ができるよう猶予期間が設けられ、2022年4月から完全施行される。内閣府・消費者委員会が8月、改正案を首相に答申していた。輸入食品の増加が見込まれる中、消費者が購入の際に参考にできるようになるほか、国産品のブランド力向上などの効果を狙う。 22年4月以降、虚偽の原産地表示をした食品を販売した個人に、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、法人には行為者への罰のほか、1億円以下の罰金が科せられる。 *11-5:https://www.agrinews.co.jp/p41765.html (日本農業新聞 2017年8月31日) 日本 見直し提案せず TPP11首席会合終了 環太平洋連携協定(TPP)署名11カ国は30日、オーストラリア・シドニーで3日間の首席交渉官会合の日程を終えた。知的財産分野の見直しでは一致したが、その他の分野で各国から修正要望が続出。日本は農業関係者が要望する農産品関税の見直しを提案しなかったもようだ。次回は9月後半に再び日本で首席交渉官会合を開く。 ●米国要求項目 棚上げ 12カ国で合意した内容のどの部分を見直すか具体的に議論した。米国が要求した項目について、いったん凍結し棚上げすることで米国のTPP復帰を促し、最終的に12カ国での発効を目指す。しかし、米国に復帰の兆しは見えず、先行きは依然不透明だ。交渉関係者によると、焦点の関税分野の見直しについては、各国から要望が出なかった。日本の農業関係者は、乳製品の輸入枠など米国の参加を前提にした合意内容の見直しを求めているが、日本は今回見直し提案をしなかったもようだ。日本は議論を主導する立場のため、「各国が慎重な関税分野の見直しを率先して提案しにくい」(交渉筋)。政府は米国の焦りを引き出すため11カ国での発効を急ぎたい考えだが、米国の2国間交渉で追加の農産品の市場開放を求められるとの警戒感は農業関係者に根強く、日本国内の意見調整も難航しそうだ。今回の会合で、実質8年の医薬品のデータ保護期間については凍結する方向でおおむね一致した。議論を主導する日本とオーストラリア、ニュージーランドはTPPの自由化水準を下げないよう協定の内容の見直しを極力少なくしたい考え。ただ、投資などルール分野の修正要望が続出。国内調整が引き続き必要な国もあり、見直し項目を絞り込みきれなかった。11月のアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議までの合意を目指し、来月の首席交渉官会合で検討を継続する。 PS(2017年9月2、3日追加):*12-1のように、JA全中が「らくらくWeb簿記システム」を本格始動し、経理・税務申告書類や源泉徴収票の作成・経営コンサルなどに役立てるのは、不得意な作業から農業者を解放し、質の高い生産・販売に専念できる基盤になるため、大きな進歩だ。また、*12-2のような直売所での販売、*12-3のような林業、不動産、その他所得を経理や税務申告に正確に反映させ、日報や月報を出して経営管理することも容易になって農家の意欲増大に繋がる。この時、一つだけ懸念があるのは、農協に全サービスを依存する結果、農協が農家を支配することが可能になることだが、この問題は、政府が行っているような農協の弱体化で解決すべきではなく、その他の主体が同様以上のサービスを行って農協と切磋琢磨し、農業者がよりよいサービスを選択できるようにすることが重要なのだ。 なお、*13について、JAグループが、2019年4月に自己改革の評価を把握するために、全国1000万人超の正・准組合員全てを対象にアンケート調査を実施するのは大変よいと思うが、客観的で役立つ情報を得るためには、JAの役職員が訪問するよりも郵送・匿名で、期待・クレーム・要望などを言いやすい状態にして年に一度くらい調査し、継続的に改善していくことが重要だと考える。さらに、調査する際には、国際的なコンサルティング・ファームを利用して海外と比較すれば、これまで考え付かなかったような解決策が提案される可能性が高い。 また、*14のように、事務作業も自動化が進んでいるため、農協自体も人材を組合員に役立つ営農支援や販売、顧客対応などの業務により手厚く配置して生産性を上げることが可能になった。もちろん、RPAをブラックボックス化するのではなく、その仕組を理解している人が業務を把握しておく必要はあるが、組織全体として生産性を上げることができるわけである。 *12-1:https://www.agrinews.co.jp/p41769.html (日本農業新聞 2017年9月1日) 「Web簿記」本格始動 申告支援 経営指導も 全中 JA全中は、担い手への経営コンサル機能を強化するため、税務申告書類を効率的に作成できる「らくらくWeb簿記システム」を本格始動した。中央会・JA向けシステムで、農業者の事務負担を軽減するとともに、税務申告で集約する販売、購買事業データや信用事業の資金情報を活用し、担い手への経営戦略のアドバイスに役立てる。8月にはJA群馬中央会が導入した。今後は、各県の判断を踏まえ、活用を進める方針だ。同システムは、静岡県農協電算センターが開発。2017年度、全中が保守管理を引き受けて全国の情報を管理するシステムを構築した。具体的には、システムで農業所得や不動産所得の情報を管理できる。貯金の入出金や販売精算などの情報を入力すれば自動的に青色申告や白色申告で使う決算書や、収支計算書などの書類の作成も可能。農業法人などの従業員向け源泉徴収票も作れる。それらの情報を、経営分析に活用する。JA管内の農業者の経営状況との比較を踏まえてアドバイスできる他、経済事業で取引の際に使うシステムと連動させ、日頃の実績を帳票などに反映できる。生産や販売、購買、資金対応、労務管理など各分野での個別提案を目指す。将来的には、集約した経営情報を全国規模で分析し、地域、品目別の提案も視野に入れる。全中は「JAの各事業での連携を重視したシステムであり、事業間連携にもつながる」(JA情報システム対策部)と強調する。JA自己改革では、大規模化する担い手経営体との信頼関係の構築の強化を目指しており、システムの活用で、その取り組みを加速する。JAの総合事業の強みを発揮し、担い手経営体を支援する。 *12-2:https://www.agrinews.co.jp/p41753.html (日本農業新聞論説 2017年8月30日) 広がるJA直売所 課題克服し魅力磨こう JA直売所が着実に増えている。地元産の安心感や新鮮さで消費者に受け入れられ、生産者の所得増にもつながった。日本農業新聞の調査によると、2016年度は売上高10億円を超える大規模店が15年前と比べ10倍になった。ただ、直売所の乱立で競争は激しく、出荷者の高齢化で品ぞろえも厳しさを増す。品ぞろえはもちろん魅力ある直売所づくりに向け、JAグループの結集力が求められている。消費者にとって直売所の魅力は、地元産の安心感、収穫後すぐに店頭に並ぶ鮮度の良さ、それに流通ルートの短さによる低価格の三拍子がそろっていること。JA直売所が急増したのは直売所設置が決議された1997年の21回JA全国大会以降だ。この動きは、日本農業新聞の調査でも明らかになった。調査は、本紙掲載記事などを参考に、売上高5億円以上と推定される133店を対象に実施し、110店から回答があった。それによると9割の直売所が、20年前のJA全国大会以降に開設した。特に、7割の店は、21世紀に入ってからの10年間にオープンした。当時、JA合併が急激に進み、広域JAが管内各地に次々に設置したことや、先行JAのノウハウが近隣JAに伝授されたことも急増に拍車を掛けた。その結果、15年前の01年度にわずか4店だった年間売上高10億円を超える直売所は、今回の調査で39店と10倍に増えた。福岡県JA糸島の「伊都菜彩」(41億円)、和歌山県JA紀の里の「めっけもん広場」(28億円)、愛媛県JAおちいまばりの「さいさいきて屋」(22億円)など20億円を超える店が6店もあった。地域別でも5億円以上の店舗は、関東や東海だけでなく、東北から九州まで全国各地に広がっている。直売所によって「生産者の所得向上」に9割、「消費者に好評」に7割が効果あったと回答。農家だけでなく地域住民にも人気だった。同時に、出荷者の高齢化や品ぞろえの確保が課題として浮かび上がった。農水省の調査(15年度)によると、全国2万3600カ所の直売所のうちJA直売所は2000店。ライバル店の増加で、開店から7、8年で売上高は横ばいとなり、各店とも売り上げ維持に懸命となる。最大の課題は、野菜を中心とする地場産品の確保だ。1直売所で500人ほどいる出荷会員は、年々、高齢化が進む。さらにスーパーのインショップなどの増加で、農家の出荷先はJA直売所以外にも広がる。これに対しJAは、直売所出荷者を育てる農業塾、営農指導部署と連携した新作物講習会、遠距離地区向けの集荷便などさまざまな取り組みを進めており、評価したい。地域に密着し豊富な品ぞろえで魅力あるJA直売所を育てるため、出荷者である組合員も含めて、JAグループ一丸となった積極的な取り組みを期待する。 *12-3:https://www.agrinews.co.jp/p41719.html (日本農業新聞論説 2017年8月26日) 稼げる林業経営 担い手への集約対策を わが国の林業政策が2018年度から新段階に進みそうだ。政府が掲げる「林業の成長産業化」の具体策として、林野庁が新たな林業経営の在り方の検討に入っている。年内に結論をまとめ、来年度の政府予算と制度改正で新対策を打ち出す。山持ち林家が林業経営を担い手に任せる代わりに、木材収入の一部をいわば借地料としてもらう。その仕組みをうまく作ることが重要になろう。「林業の成長産業化」は安倍政権が3年前に掲げたが、推進の具体策に欠けていた。政府は本腰を入れ、新対策の方向を6月に公表した未来投資戦略でこう記した。「森林の管理経営を、意欲ある持続的な林業経営者に集積・集約化する」。林業経営を集約型にして、稼げる林業を目指す方向に異論はない。一方で、条件不利地の林業に向かない森林の管理は「市町村等が行う新たな仕組みを検討」として、公的管理を強める。併せて、昨年末に与党が今年度税制改正大綱で示した森林環境税について、将来導入した際に市町村主体の森林整備の財源に充てる手法を検討していく。政府の新対策はつまり二段構えだ。稼げる林業を目指すとともに、それが困難な森林の管理は市町村に責任を持ってもらう。地元の森林を林業向けと保全管理向けに区分けするのは、市町村の役目になろう。市町村は現在、今年4月施行の改正森林法で義務付けられた林地台帳作成へ、森林の所有者・境界の特定を進めている。条件不利地の森林管理だけでなく、林業向けの森林をまとめ、担い手に集積推進する自覚と責任が求められる。林業経営の担い手には、自立林家の他、森林組合と林業事業者がなるのが現実的だろう。だが現在、両者とも再造林から伐採までの施業請負が大半で、経営責任を伴わない。ここから大きく踏み出し、いわば借地の林業経営を積極的にやれる制度作りが、政策的に必要となる。借地型の林業経営では、収益確保の努力を迫られる。施業効率化に向け、高性能機械導入や、主伐とコンテナ苗を使った植林の一貫作業化などが進むはずだ。伐採木の販売努力を含めた生産性向上こそが、稼げる林業実現の道となる。林業での借地料は定期的な支払いが難しく、伐採木収入の一部の充当が妥当だろう。林家と担い手の双方が納得できる仕組みが肝要となる。林家は「林業はもうからない」と嘆き、赤字経営も実際多い。それだけに、森林の所有と経営を分離し、必ず収入が得られる借地型は安心感を持てるのではないか。わが国の人工林の半分が主伐期を迎えており、伐採して活用する推進政策が急がれる。日本と欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)大枠合意による林産物の輸入関税の段階的撤廃の打撃を乗り越え、林業の成長産業化を達成するには、稼げる林業を全力で築くしかない。 *13:https://www.agrinews.co.jp/p41775.html (日本農業新聞 2017年9月2日) JAグループ 19年に全組合員調査 自己改革評価把握 実践加速、全JAも JAグループは、現在進めている自己改革への評価を把握するため、全国1000万人超の正・准組合員全てを対象にしたアンケートを2019年4月に実施する。全組合員調査はJAグループ初の試み。併せて、全JA調査も行い、自己改革の取り組み実績をまとめる。節目を設定し、高評価の獲得を目標にして改革を加速させる。各JAは、評価や実績を基に一層の改革案などを検討し、次期中期計画を策定する。全組合員調査は、全JAの役職員が正・准組合員の全戸を訪問。農産物の販売事業や生産資材の購買事業、営農指導への期待度や満足度などをアンケート形式で調べる。全国のJAの組合員数は正・准合わせて1037万人(15年度)。JA全中によると、全国の組合員全てを対象に調査を行うのは初めてだ。一方、全JA調査はこれまでも毎年実施しているが、調査項目を見直す。例えば、ある事業について「何割のJAが取り組んだか」から「何人の組合員が利用したか」などに変更。組合員目線で、自己改革がどこまで進んだかを定量的に把握できるようにする。全組合員調査に合わせ、19年4月1日を基準日に19年度の調査を実施する。JAグループは15年の第27回JA全国大会の決議を受け、農業者の所得増大などに向けた「創造的自己改革」を進めている。同大会決議の実践期間は18年度までで、各JAがつくる自己改革の工程表も18年度を区切りとする。このため19年4月を自己改革の一定の節目とし、全組合員・全JA調査で評価や実績を把握することにした。政府の規制改革推進会議が、19年5月末を「農協改革集中推進期間」の期限としていることも考慮した。調査で把握した改革の実績や評価を踏まえ、全国のJAは19年度からの一層の取り組みを検討し、次期中期計画を策定する。中期計画には、総合事業を継続するか信用事業の代理店化を選択するかの判断なども盛り込む。信連や農林中央金庫による手数料水準の提示を受け、JAは信用事業の運営体制の在り方を検討し、19年5月までに結論を出すことにしているためだ。ただ全中は、総合事業を展開した方が農業者の所得増大や農業生産の拡大に有利とみて、多くのJAが総合事業の継続を選ぶと見込む。自己改革の実績や評価、それを踏まえた今後の計画は対外的にも発信する。全中は、こうした一連の取り組み方針を理事会で決めた。全中の比嘉政浩専務は「自己改革に終わりはないが、明確な節目をつくることで改革を加速化する」と強調。「全組合員調査で高い評価を得ることを一つの目標にして、JAグループを挙げて取り組む必要がある」と話す。 *14:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20170903&ng=DGKKZO20699380S7A900C1EA5000 (日経新聞 2017.9.3) 事務作業も自動化進む、第一生命やオリックス、「ロボ」ソフトで労働時間削減 オフィスの作業を自動化するソフトウエアが日本で浸透し始めた。データ入力など人手に頼っていた単純作業を自動的に処理することからロボットと呼ばれ、第一生命保険は最大で150人相当の業務を代替する。人手不足の深刻化や働き方改革で労働時間の削減を急ぐ大手企業が次々に導入している。生産性を引き上げて、貴重な人材を顧客対応や企画部門に厚く配置する動きにつながりそうだ。パソコンを使った定型的な繰り返し作業を担うのが「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」と呼ばれるソフト。米オートメーションエニウェアや英ユーアイパスなど欧米企業が先行し、2年ほど前から日本企業で利用が広がり始めた。紙ベースのデータを光学式文字読み取り装置(OCR)で読み取ってデジタル情報として基幹システムに入力したり、ウェブの画面から数値をコピーしてエクセルにペーストしたりするような作業を担う。あらかじめ操作を設定しておけば、検索やデータの取得、入力、確認などの作業を人間と同じ手順で処理する。オリックスグループは10月末からRPAで担う仕事を増やす。これまでレンタカーの予約情報を基幹システムに登録する業務で使用してきた。外部の旅行サイトなどから受け付けると目視で確認して入力し直す必要があり煩雑な作業が伴った。RPAでは時間当たりの処理件数が人手に比べ8倍になり、ミスもなくなったという。この結果を受け、生命保険や不動産などグループ各社が導入を予定する。これまでの子会社1社から全社にRPAの利用を広げる。第一生命は試験的に使っていたRPAを10月から本格稼働する。社内で自動化に切り替える作業を募り2千以上、年間30万時間分の業務が候補に挙がった。従業員150人分に相当する。可能な業務から順次、RPAのソフトで代替していく。例えば保険金請求の処理業務を担当する社員を決める割り振りに使う。疾病や事故の内容によってスキルの程度を含めて対応する社員をあらかじめ分類し、自動的に仕事を振り分ける。人手で年間1000時間かかる作業を代替する見込み。日本RPA協会の調査ではRPA利用企業の97%で適用した業務の処理時間が半分以下になった。KPMGコンサルティングは単純作業に従事する労働力を4~7割減らせるとみている。電通も年末までに300の業務でRPAを導入する。自動化により月間で5万8千時間分の労働時間の削減を目指す。既に各種メディアの視聴率のデータを取得、入力する業務に使用済み。長時間労働問題を受けて進める働き方改革の一環として活用範囲を広げる。日本の時間あたり労働生産性は経済協力開発機構(OECD)加盟35カ国中20位で、かねて単純作業の見直しが必要と指摘されてきた。RPAソフトの機能が上がるのと並行して働き方改革の機運も高まり、関心を示す企業が増えた。単純作業を減らせば生産性は上がり、働く意欲の向上も見込める。第一生命は営業や海外事業などの部門に再配置したい考えだ。米調査会社トラクティカによると、ソフト利用や関連コンサルなど世界のRPA市場は2025年に51億ドル(約5600億円)と16年の30倍以上に増える。仕事が効率よく進み、企業のコストが下がるとの期待が高まる一方、25年までに世界で1億人の知的労働者の仕事がRPAに置き換わるとの試算もある。RPAは作業内容を社内で誰かが把握していないと、データの取得先のフォーマットが変わるなど環境が変化した場合も従来と同じやり方で作業を続け、業務が混乱する恐れがある。ソフトバンクはRPAソフトに操作を設定する人員や使用している業務を一元的に把握して、RPAに仕事を任せきりにしないよう管理している。 PS(2017年9月8日追加):*15-1のように、全農が、農家所得の増大や農業生産の拡大に向け、実需者への直接販売拡大のために営業開発部を設置するそうでよいと思うが、国内外の需要の変化に応じて持続的に新製品を出したり製品の改善を続けたりするのは、他産業ではこれまでもやってきたことなので遅すぎたくらいだ。なお、最近は、インターネット通販の利用で望む産地から直接買う消費者が増えたため、努力する生産者には利益獲得のチャンスが増えた。今後は、例えばデパ地下の惣菜などの業務用食材も相手の仕様に合わせて産地で下ごしらえして販売すれば、①ゴミまで都会に輸送しないため輸送コストを下げ ②人件費の安い産地で新鮮で安価な製品を作ることができ ③需要者の要求が手に取るようにわかるため今後の生産計画に役立ち ④地方で付加価値をつけるので地方の所得を増加させることもでき ⑤ゴミになる部分は地方で養殖魚の餌や肥料に再利用できるので、よりよくなると考える。 なお、日本は農畜産物の輸出額が非常に小さいが、*15-2のように、JA全農は、香港で日本産農畜産物に特化した特設サイトを開設して、ネット通販をはじめとするEC事業を展開するそうだ。私は、合理的な価格で販売すれば売上が増えると思うが、品揃えの充実と量の確保は欠かせないだろう。そのような中、熊本県のJA菊池は、*15-3のように、牛の繁殖拠点を整備して年間500頭の増産を目指し、安く供給することで農家の手取りを増やす考えだそうだ。 ところで近年、日本では野生鳥獣の数が増えたので、*15-4のように、鹿・イノシシなどの野生鳥獣を捕獲した狩猟者に支払う「鳥獣被害防止総合対策交付金」ができた。しかし、捕獲した野生鳥獣は、尻尾を切って写真を添えれば助成金をもらえるため捨てられることが多く、これでは、人間はあまりにも不遜で命を無駄にしていると言わざるを得ない。しかし、野生鳥獣の肉は、脂肪が少なく蛋白質が豊富で健康的であるため、適切に料理すれば家畜より価値の高いごちそうにもなる。そのため、*15-5のように、何とかしてジビエとして活用すべきだ。 さらに、*15-6のように、九州から欧米へ続々と米粉が輸出され始めたのは希望多きことだが、米粉は、*15-7のように、菓子、パン、麺などの様々な用途に使うことができ、米粉のパンは固くならないなどの長所がある上、フォー(ベトナムの麺:爽やかで美味しい)は米粉でしかできない麺であるため、農水省が「戦略作物」として生産拡大を支援したり用途別に支援したりするのはバラマキであるとともに、市場を歪める大きなお世話になるだろう。 <全農の経済事業> *15-1:https://www.agrinews.co.jp/p41785.html (日本農業新聞論説 2017年9月3日) 全農が営業新部署 直販拡大へフル活動を 実践2年目となるJAグループの自己改革が9月で半年を迎える。経済事業を担うJA全農は、農家所得の増大や農業生産の拡大の実現に向け1日、営業開発部を設置、販売力強化の取り組みを加速する。実需者への直接販売拡大を狙う実働部隊に位置付ける。消費や販売形態の変化など市場動向に即応した機能アップが成否の鍵を握る。営業開発部は政府の「農林水産業・地域の活力創造プラン」への対応を実践するため、司令塔としての役割も担う。精米や青果など従来、縦割りに進めてきた営業活動を品目の垣根を取り払って横断的に実施する。新たな取引先の開拓や取扱品目の拡大が使命だ。併せて、実需者ニーズを産地に伝え、生産から加工・流通、販売までをつなぐ全農としてのバリューチェーン構築を目指す。その際に意識しなければならないのは、消費構造や販売形態の変化だ。最近の動向を見ると、生活の多様化に合わせ、市場では業務用需要が伸び、並行してインターネット通販の利用が増えている。さらに、作り手の論理を優先させる「プロダクトアウト」から、消費者ニーズを重要とする「マーケットイン」を意識した事業展開が強まっている。単にモノを売るだけにとどまらず、実需者ニーズを捉えた付加価値のある商品の企画・開発が求められている。こうした時代の流れをくみ、全農は従来の取引先であるスーパーや生協に加え、コンビニエンスストアや外食・中食業者、インターネット通販、ドラッグストアなど幅広い分野の実需者をターゲットにリスト化。取引先ごとに横断的なチームをつくり、新たな品目の売り込みと新規顧客の開拓を進める。直販事業を拡大するには、消費構造の変化への対応が重要だ。その一つが電子商取引(EC)だ。野村総合研究所が昨春公表したインターネット利用者を対象にした調査によると、3000円以下のちょっとした買い物でもネットを使う実態が浮き彫りになった。利用層も若者だけでなく中高年層に広がり、生活に定着している。農産物の販路の拡大・新規開拓には、既存の事業モデルの見直しと併せて、EC戦略を磨き上げることが欠かせない。全農は3月に決めた事業改革の年次計画で、2024年度の直接販売の割合を米で9割、園芸品目で取扱額の過半の5500億円という意欲的な目標を据えた。7月下旬の通常総代会の時点での実行状況はほぼ計画通りとしている。米の買い取りは2017年度計画の30万トンを超えたという。実績の積み上げへ新部署の果たす役割は大きい。有効に機能すれば、産地を巻き込んだ栽培や商品開発という好循環を作り出すことにもつながる。目に見える成果が問われる改革の必達。 <農畜産物の輸出> *15-2:https://www.agrinews.co.jp/41743?page=2 (日本農業新聞 2017年8月29日) 全農、香港で通販事業 最大級サイトと連携 農畜産物輸出拡大 JA全農は、日本の農林水産物・食品の最大の輸出先である香港で、ネット通販をはじめとする電子商取引(EC)事業を展開する。香港最大級の通販サイト「HKTVmall(HKTV)」などと連携し、日本産農畜産物に特化した特設サイトを開設したと、28日に発表した。百貨店など実店舗に加え、ネット通販を積極的に活用することで、消費者に直接売り込める期待がある。ネット通販は利便性が強みで、日本産農畜産物の新たな顧客層を獲得し、輸出拡大を狙う。輸出事業の拡大へ全農は4月、輸出対策部を新設。実務を子会社のJA全農インターナショナルに集約するなどの体制を整備し、産地づくりやCA(大気調整)コンテナなどを活用した試験輸送、国・地域別の輸出戦略の策定などに動く。9月1日に「営業開発部」を設置して取り組みを強化し、新たな販売網としてネット通販戦略の構築を進める。今回の仕組みは、HKTVに加え、国内外で料理教室などを展開する「ABCクッキングスタジオ(ABC)」とも連携する。国内から米や肉、果実など農畜産物を調達する全農と、食材を生かす調理方法などを紹介するABC、販売を担うHKTVがそれぞれの強みを生かし、香港の家庭などに日本産農畜産物を届ける。物流は、全農が既に構築している現地の青果や食肉などの卸をはじめ、取引先との仕組みを生かす。香港は他国に比べて輸入規制が少ないため、日本にとって幅広い品目を輸出しやすい。輸出戦略でも最重点地域で、現地では日系の総合スーパーや高級スーパーなどを中心に日本産農畜産物や加工品の取り扱いが広がり、消費者の購入機会が増えている。ネット通販で利便性が高まり、新たな顧客層の獲得に期待が大きい。取扱品目は、現時点で米、青果、牛肉、豚肉など。今後、販売状況を見ながら、品ぞろえの充実を検討する考えだ。全農は「香港の消費者ニーズを捉え、商品を広げていきたい」(輸出対策部)としている。 *15-3:https://www.agrinews.co.jp/p41799.html (日本農業新聞 2017年9月5日) 繁殖拠点を整備 管内で和子牛安く提供 熊本・JA菊池が新方式 熊本県のJA菊池は、和牛子牛を増やすためキャトルブリーディングステーション(CBS)を整備した。生まれた子牛は市場に出荷せず、管内の生産者に安く譲る全国初の方式を導入する。子牛高騰に苦しむ肥育農家の経営改善につなげる狙いだ。西日本最大の酪農地帯である利点を生かし、管内の酪農家から乳用牛を預かって受精卵移植(ET)で和牛子牛を生ませる。JAが所有する繁殖和牛にも子牛を生ませ、3年後をめどに合計で年間500頭の増産を目指す。4日に菊池市に完成したCBSで竣工式を開いた。和牛と乳用牛を合わせて常時850頭を飼養。効率化のため哺乳ロボットや発情発見器などを完備する。国の畜産クラスター事業を利用し、総額約9億5000万円を投じて整備した。JAが所有する最大200頭の和牛に人工授精(AI)で子牛を年間180頭生ませる他、預かった酪農家の乳用牛最大240頭にETを施し、同140頭生産する。加えて、管内の酪農家組織の乳用牛300頭にもETで同180頭生ませる。受精卵はJAが用意し、代金も負担する。黒毛和種だけでなく褐毛和種(あか牛)も生産する他、生乳の生産基盤を守るため乳用後継牛の確保にも活用する。酪農家から預かる乳用牛は1日700円程度で管理を請け負う。生まれた和牛子牛は生後1週間程度で酪農家から全て買い取る。受精卵や引き取った後の管理にかかるJAの費用を勘案し、価格はスモール牛(3、4カ月齢)の市場相場の半額程度を想定する。生まれた子牛はCBSである程度育成した後、全頭を管内の肥育農家に供給する。市場出荷せず確実に管内にとどまるようにする。価格は県内市場の相場より1頭5万円ほど安くする方針。繁殖農家への影響も考慮して決めるが、一定程度安くし、採算ぎりぎりの状態にある肥育経営の改善につなげる。JAによると生産した子牛を市場出荷せずに安く供給する施設は「全国でも例がない」(畜産企画課)という。JAの正職員3人と嘱託職員3人が主に作業に当たる。獣医師1人と、哺育や育成などを担当するパート16~18人を確保するめどもついた。CBSは宿泊可能で、新規就農者らの研修施設としての役割も果たす。酪農と肉用牛肥育・繁殖の全てに対応する。JAの三角修組合長は「和牛子牛の不足と相場高騰は農家個人では解決できない問題だ。JAが子牛を生産して安く供給することで、農家の手取りを増やす。乳用牛を預かることで、酪農家の負担軽減にもつなげる」と強調する。 *15-4:https://www.agrinews.co.jp/p41783.html (日本農業新聞 2017年9月3日) 鳥獣対策交付金 捕獲確認を厳格化 不正防止へ 来年4月 尻尾と写真 必ず イノシシなどの野生鳥獣を捕獲した狩猟者に支払う国の「鳥獣被害防止総合対策交付金」について、農水省は交付ルールを厳しくする。実際に野生鳥獣を捕獲したかどうか地方自治体が書類で確認する場合、写真に加え、証拠として尻尾の提出を義務付ける。交付金の不正受給防止が狙いで、10月をめどに交付金の実施要領を改正。周知期間を設けた上で、2018年4月から施行する。同交付金は、市町村の認定を受けた狩猟者を対象に、鹿やイノシシなどの捕獲に最大1頭8000円を助成する仕組み。実際に捕獲したかどうかの確認は、市町村職員や都道府県職員が実際に捕獲現場に出向く「現地確認」、狩猟者が市町村や都道府県に証拠を提出する「書類確認」がある。書類確認の証拠は写真だけでもよいルールになっている。だが、3月に兵庫県と鹿児島県で証拠写真で不正が発覚。撮影地点を変えるなどして1頭の個体を使い回し、実績よりも多く捕獲したように見せかけ、交付金を多く受け取っていた。新しい交付ルールでは確認作業について、「現地確認」か、処理加工施設への持ち込み時の「搬入確認」を基本とする。これらが難しいケースだけ書類確認を認める。書類確認の内容も厳しくする。証拠として写真に加え、尻尾の提出も義務付ける。証拠を尻尾に統一することで、耳や牙など複数の証拠部位を使って1頭の個体で複数回申請されることを防ぐ。証拠写真は個体の向きを「右向き」に統一し、向きを変えて複数個体に見せかける不正を防ぐ。現地確認でも、尻尾を回収したりスプレーで着色したりすることを義務付け、個体の使い回しを防ぐ。野生鳥獣による農産物被害(15年度)は176億円。高水準にあり、捕獲は欠かせない。同省は今回の見直しで不正受給の再発を防ぎ、交付金を着実に執行していきたい考えだ。 *15-5:http://qbiz.jp/article/118256/1/ (西日本新聞 2017年9月7日) 夢の「ジビエカー」初導入 捨てる有害獣の肉、活用可能に    捕獲したイノシシやシカなどの有害鳥獣を有効に活用しようと、高知県檮原(ゆすはら)町が、移動式のジビエ(野生鳥獣肉)解体処理車「ジビエカー」を全国で初めて導入した。処理場まで遠く、これまで廃棄せざるを得なかった捕獲獣をその場で解体、冷蔵運搬することが可能。業界内で「夢のような車」との声が上がっている。檮原町では昨年度、ハンターらが農作物に被害を与えるイノシシやシカを約1500頭捕獲。その数は2008年度の約10倍に膨れ上がっており、自家消費されるもの以外の大半が山中に捨てられているという。ジビエカーは箱型の荷台を備えた2トントラック(全長約6・5メートル)で、1台2175万円。日本ジビエ振興協会(長野県) 機械化された日本の田植え 中国の小麦刈り取り 米国の消毒 と長野トヨタ自動車が共同開発し、これまで宮崎県などで実証実験が行われてきた。本格導入は檮原町が初めてだ。最大でイノシシやシカ5頭分の枝肉を冷蔵・冷凍保管できる冷蔵室や、皮や内臓を取り除いて殺菌できる解体室を完備。捕獲現場に出向いてすぐに1次処理できるため鮮度が保たれ、臭みの少ない良質な肉が得られる。解体で出た臓器や汚水を現場に残さないなど、環境にも配慮した。今後は高知県が中山間地域の拠点として設置する同町の集落活動センターが、地元猟友会と協力して運用する。来年3月には町内にジビエ専用の食肉処理施設も完成予定。ジビエカーと連動すれば年間400〜500頭を食肉用に加工、出荷できる見込みだ。同町の矢野富夫町長は「山に捨てていたものが収入に変わり、雇用も生まれる」と期待する。 <米粉> *15-6:http://qbiz.jp/article/118122/1/ (西日本新聞 2017年9月6日) 米粉輸出、九州から欧米へ続々 グルテンフリー人気受け 農業振興へ国も支援 国産のコメを原料にした米粉を欧米に輸出する業者が、九州で相次いで登場している。欧米では小麦粉に含まれるタンパク質「グルテン」が症状を引き起こす「セリアック病」への警戒から、米粉などグルテンフリー(グルテンを含まない)食品人気が広がる。輸出の拡大は国内農業の振興につながることから、農林水産省も注目している。熊本製粉(熊本市)は2015年2月、米国への米粉輸出を始めた。まずは家庭用から手掛け、16年11月には業務用に拡大。米国のグルテンフリー認証機関の認証を15年1月に取得した上での取り組みだ。同社などによると、米国はセリアック病の患者が多い上、グルテンフリー食品を健康にいいと評価する消費者が増加。浦郷弘昭取締役は「米国のグルテンフリー食品市場の規模は約6千億円と大きく、現地の市場調査で自社の米粉が高く評価されたため、参入できると判断した」と話す。輸出する米粉は大半で熊本産のコメを使い、独自の製粉技術で生産。浦郷氏は「当社の米粉で作ったパンは、米国の既存のものよりふっくらと仕上がる」と胸を張る。「輸出は始めたばかりだが手応えは感じている。知名度を上げ、より浸透していきたい」という。和菓子の材料として米粉を長年製造している小城製粉(鹿児島県薩摩川内市)は、14年11月からドイツに輸出。現地の商社を通じ、顧客はフランスにも広がっているという。「これまでに約25トン輸出したがもっと伸ばしたい」と能勢勝哉社長。9月にドイツ・ハンブルクに販売拠点を設け、米粉素材のパンや菓子も製造、販売する計画だ。「製品をパン用やパイ用などに分け、欧州でも『おいしい』と評価を頂いている。課題は価格の高さだが、価値を一層PRし欧州各地に販路を広げたい」という。農林水産省は輸出を後押しするため、NPO法人国内産米粉促進ネットワーク(東京)が今秋に欧州で計画する米粉のPR活動を支援する。 *15-7:https://www.agrinews.co.jp/p41797.html (日本農業新聞 2017年9月5日) 米粉 用途別に支援 農水省18年度 品種実証や設備 農水省は2018年度、今春に示した米粉の用途別基準や米粉の特性を踏まえた生産をする産地とそれを活用する実需の支援に乗り出す。菓子、パン、麺と三つの用途区分はアミロース含有率で決まる。新事業では、それぞれに合った品種の栽培実証や栽培マニュアル作りなどを促す。用途などを意識して販売する製造業者も支援する。多様な商品化を後押しし、米粉用米の需要拡大につなげる。農水省が18年度予算概算要求に盛り込んだ「戦略作物生産拡大支援事業」(1億3000万円)の中で支援する。同省は3月、「米粉の用途別基準」を発表した。米粉のアミロース含量は、菓子・料理用で20%未満、パン用で15%以上・25%未満、麺用で20%以上と三つに分けた。こうしたアミロース含量は品種や栽培管理で変わるため、実需に応じた生産には統一した技術を確立する必要がある。しかし産地にそうしたノウハウはないのが現状だ。そこであまり普及していない高アミロース品種の導入や、栽培のマニュアル化といった産地の取り組みを支援。例えば高アミロース品種には「モミロマン」「越のかおり」などがある。産地と連携する業者に対しても、小麦アレルギー患者から需要の高いノングルテン米粉を製造する設備や小麦粉製品の混入防止対策などを支援する。同省は「高アミロースを必要とする米粉の麺はまだ利用が少なく、事業で需要を広げたい。ノングルテン米粉は小麦アレルギーの多い欧米などへ輸出も見込める」(穀物課)と期待する。同省は米粉用米について、25年度に13年度比で約5倍となる10万トンの生産努力目標を掲げるが、国内需要量は約2万3000トンでここ数年はほぼ横ばい。農水省は米粉用米を戦略作物と位置付け、水田活用の直接支払交付金で飼料用米と並ぶ水準で助成している。 <本当の改革の進め方> PS(2017年9月10日追加):*16-1の農水省の元事務次官で農林中金総合研究所理事長の皆川氏の話の内容は良いと思うが、①日本は人口減少という大きな課題に直面している ②貿易立国として世界のものづくりを担うのは難しい ③農業は2次、3次産業までの付加価値を足すと、GDP(国内総生産)の1割を稼いでいる ④地域社会を支え続ける意味でも、農業やその関連産業には大きな可能性がある ⑤家業としての農業経営の持続可能性がなくなっていることは否定できない とされていることに関して、①②は、一人当たりの国土や財産が増えるのでよい点も多く、女性・高齢者・障害者など、これまで生産年齢人口の健常男性に道をあけるために雇用から外されていた人に雇用の機会を与えるので悪いことばかりではない。さらに、③④については、食料自給率や環境維持を考慮すれば、GDPには載らない農林漁業の重要性もある。また、⑤については、家業としての経営は農業だけでなく製造業にもあり(トヨタ、ホンダ、有田焼、唐津焼など)、オーナー会社やベンチャー企業は、経営者によっては将来性ある意思決定を迅速に行えるので強みになることも多い。 また、生産物の種類を増やせば、これまで輸入品しかなかった産物を国内産に回帰させたり、生産革命で消費者が高すぎて買わなかった産品を買えるようにしたりできるため、日本の市場規模は小さくなるとは限らない。しかし、輸出で他流試合をするのは、外貨を稼ぐだけではなく、日本産の価値を客観的に知って改善を続けるために重要である。 なお、競争に勝つための連携目的で準組合員や非農家理事を作ったり、全農の持株会社が他産業とジョイントベンチャー子会社を作ったりする必要も出てくるため、*16-2に書かれているとおり、実態を知らない人が「上から改革」で准組合員を規制するのはもってのほかだ。そして、農林中金の役割は、農村から集めた資金を、改革・改善のために資金を必要とする地方の農林業に提供できる卓越した視野と金融技術を持つことなのである。 *16-1:http://www.saga-s.co.jp/column/economy/22901/461886 (佐賀新聞 2017年9月9日) 農業の複合化避けられず 多様な連携で地域貢献を、農林中金総合研究所 皆川理事長講演 佐賀県内のJAグループ役員を対象にしたセミナーが佐賀市で開かれた。農水省の元事務次官で農林中金総合研究所理事長の皆川芳嗣氏が、人口減少が進む今後の日本における農業の可能性、JAが果たすべき役割について語った。要旨を紹介する。日本は人口減少という大きな課題に直面し、かつてのように貿易立国として世界のものづくりを担うのは難しい。金融、技術も国を引っ張るだけの産業にはなり得ない。では農業はどうか。数年前にTPP(環太平洋連携協定)の議論で、「農業は日本のGDP(国内総生産)のたかだか1・5%しかない」と言った政治家がいた。だが、フランスやアメリカでもGDPに占める1次産業の割合は1~2%。あんなに農村を抱えている中国でも10%しかない。1・5%はあくまで原料の世界。2次、3次産業まで付加価値を足すと、生産額ベースで国の1割を農業から派生した分野が稼いでいる。地方に行くと、そのウエイトはさらに高い。地域社会を支え続ける意味でも、農業やその関連産業には大きな可能性がある。ただ、家業としての農業経営の持続可能性がなくなっていることは否定できない。後継者が成り立つ事業にするには、規模拡大や複合化はある程度避けて通れない。労働のピークを経営の中でどう分散させられるか、マネジメントをJAも一緒になって取り組まなければならない。農地基盤の条件整備、農地の権利問題といったことも今後、JAがやる必要があるだろう。日本の市場規模は必ず小さくなる。地域にこだわりつつ、“他流試合”に挑むのも大事だ。福岡と東京のJAさが系統の店(季楽)は、他の地域の需要を食って佐賀の農産物が売れている。外に打って出る取り組みを加速させる必要がある。東アジアは必ず成長し、消費社会になる。インバウンドを生かさない手はない。地域全体を良くするためには、いろんな人たちと連携し、包み込むという考えが重要だ。JR九州の「ななつ星in九州」は、九州の風土と皆さんが丹精込めて作った食材がなければ成功しなかった。旅をする理由はその場所でいろんなものを食べたり、体験したりできるから。連携相手としてもっと深くつながれるのではないか。農業と福祉の連携もある。農業分野の一部でも、JAから福祉サイドに手を差し伸べるのは大きな社会的意義がある。障害者雇用は日本の企業の責務だが、企業本体の業務で雇用の場を提供することが難しい場合もある。企業が特例子会社をつくり、その子会社の事業として農業や園芸に取り組めば、法定雇用の人数に組み込める制度がある。農業のノウハウや販路を生かし、地域のためにより積極的に役割を果たすJAにしていただければありがたい。 *16-2:https://www.agrinews.co.jp/p41762.html (日本農業新聞論説 2017年8月31日) JA組織基盤強化 組合員と共に未来開く JA自己改革の要諦は、組合員との結び付きを強め、その成果を「見える化」することに尽きる。多様化する組合員の「姿」をつかみ、理念や課題を共有し、共に農と地域の未来を開いていこう。政府主導の一連の農協改革は、総合事業を弱め、地域のライフライン機能を損ねる方向で進んでいる。対してJAグループが進める創造的自己改革は、「食と農を基軸として地域に根差した協同組合」を目指す。課題克服の「解」は常に現場にある。「上から改革」ではなく、「現場からの改革」でなければ真の自己改革はできない。JAグループの目標は、農業者の所得増大、豊かで暮らしやすい地域社会の実現だ。それには、共に歩む正組合員・准組合員とのつながりが欠かせない。JAを支える土台が揺らいでは改革などなし得ない。組織基盤を強め、JAが組合員、地域住民にとって、なくてはならない存在になることが改革集中期間に問われている。JA全中、JC総研が東西2カ所で開いた「JA組織基盤強化フォーラム」は、そうした問題意識に貫かれ、先進事例報告や識者提言など示唆に富む内容だった。フォーラムで問われたのは、多様な組合員の営農・生活実態、JA組織・事業・経営への関与の度合いを把握できているかだ。徹底した意向調査でJAの「強み」「弱み」を知り、きめ細かく組合員の要望に応えることが求められている。組合員と言っても、JA事業や地域農業を支えた親世代の正組合員、高齢化で販売の一線を退いた正組合員、後継者世代のJAに対する意識も一様ではない。既に数の上では正組合員を上回る准組合員にしても、単なる事業利用者から就農意欲のある人、JA運営参画を目指す自覚的な人までさまざまだ。組織基盤強化とは、多様化する組合員と直接向き合い、信頼を深めることにほかならない。正組合員には、営農・経済改革の果実をスピード感を持って届けることだ。経営者は明確なビジョンを掲げ、全ての職員は渉外であり、広報担当だという自覚と当事者意識を持とう。あらゆる場面で職員は、具体的な目標、手段を自らの言葉で語れるよう「人材力」を磨こう。准組合員への対応も総合事業の将来を左右する。政府が准組合員の事業利用規制問題を調査・検討する2021年3月末までに、「利用者」から「パートナー」「応援団」へと結び付きを強めることだ。准組合員は、総会への議決権などJA経営に直接参加する「共益権」はないが、さまざまな機会を捉え、参加・参画を促そう。支店の協同活動、総合ポイント制の活用、農業祭、食農教育、家庭菜園指導、健康講座など日頃の交流が理解と関係を深める。自己改革の進捗を政府から問われたときに、全ての組合員が「わがJA」と胸を張れるようにしたい。 <合理的な農業交付金> PS(2017年9月15日追加):*17に、①主食用米以外の米作りを進めて水田の生産機能を維持するのは、食料自給率向上と食料安全保障に寄与する ②農水省は2018年度農林水産予算で飼料米助成や産地交付金など水田活用の直接支払交付金として3,304億円を要求した ③財務省や一部マスコミなどからは「財政負担が大きい」と疑問視する意見が出ている ④水田活用交付金は自給率向上の“要石”だ 等が書かれている。 しかし、このうち①④は、転作するのに水田と米以外の選択肢を持たず、本来なら他の付加価値の高い作物を作ることができる場所で水田を維持するために、②のように膨大な予算を要求していることが問題なのである。つまり、別の不足している付加価値の高い作物を作って合理的な経営をすれば、国からの補助金はいらず、他産業はそうやって利益を出しているのだ。そのため、③のように、財務省が財政支出の負担が大きいというのは当たり前で、国民負担を増やさずに教育や福祉を充実させるには、一人前の生産年齢人口の大人には原則としてだらだらと補助金を出さずに自立してもらうしかない。ただ、農林漁業の場合は、環境や食糧安全保障にも寄与しているため、環境税その他から貢献度に見合った補助金を出すのは合理的である。 *17:https://www.agrinews.co.jp/p41901.html (日本農業新聞論説 2017年9月14日) 水田活用交付金 自給率向上の“要石”だ 米価を上げるのに税金を投入するのは問題だという意見をしばしば聞く。それは皮相的な見方だ。主食用米以外への作物転換で需要に見合った米作りを進め、併せて水田の生産機能を維持するのは、食料自給率向上と食料安全保障に寄与する。農水省は2018年度農林水産予算で飼料米助成や産地交付金など水田活用の直接支払交付金として3304億円を要求した。この点に関し財務省や一部マスコミなどから「財政負担が大きい」と疑問視する意見が出ている。米価にようやく上向き傾向が見られるだけに、転作予算を“影の米価維持対策”に見立てて、批判を強める気配が感じられる。年末までの予算編成過程では、総額や助成単価の水準を巡り、財務省と農水省の厳しい綱引きが想定される。水田面積243万ヘクタールは全耕地面積447万ヘクタールの5割強に相当する。農地面積が減少する中、この貴重な生産機能を将来にわたって維持することは、脆弱(ぜいじゃく)化するわが国の食料安全保障上極めて重要である。毎年8万トンに及ぶ米の需要減が今後も見込まれる中、〈生産調整の強化↓需給緩和・米価下落↓耕作放棄地の拡大↓食料供給力の低下〉の悪循環を食い止めなければならない。最終的には国民・消費者の食を脅かす事態となる。15年度からの新しい食料・農業・農村基本計画を決定したのは安倍内閣であり、食料自給率の引き上げ目標を民主党政権が設定した50%(カロリーベース)から45%に下げた。現実的な目標に修正し、向上を目指すというのが理由だった。しかし、自給率は16年に1ポイント下落し38%にまで落ち込んだ。この目標設定に関わった食料・農業・農村政策審議会の中嶋康博会長は本紙のインタビューで「自給率が上がる姿が見えてこない。ほぼ全ての農産物が自給率を下げる要因になっている」と厳しい認識を示した。政府・与党はこの事実を重く受け止めなければならない。産地交付金や飼料米助成は、主食用米以外に作付け転換することで、需要に応じた米作りによる安定供給と水田機能の維持という二つの目標を実現する政策である。財政負担が小さくないのは事実だが、現状ではこれに代わる政策展開は見いだせない。斎藤健農相の肝いりで動きだす米の輸出拡大プロジェクトは、19年で米加工品を含めて10万トンという量である。これさえ実現は簡単なことではない。納税者の理解を得ながら、農家が主食用米以外を選択できる環境を整えるしかない。水田という持続可能性の高い生産装置を守ることは、食料自給率の向上と併せ、国土の保全や災害時の洪水防止といった多面的機能の発揮にもつながる。食料自給率低下を機に、審議会はわが国の食料安全保障の在り方を見詰め直し、危うい現状を発信し、広く国民理解を得る取り組みをしてはどうか。
| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 07:39 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2017,05,01, Monday
 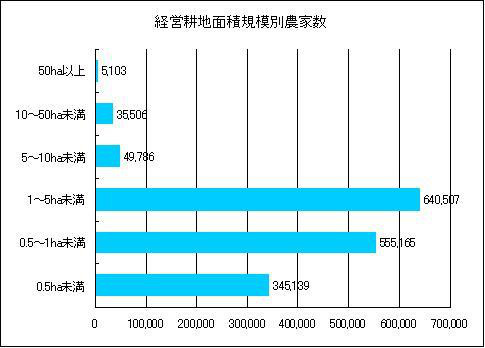 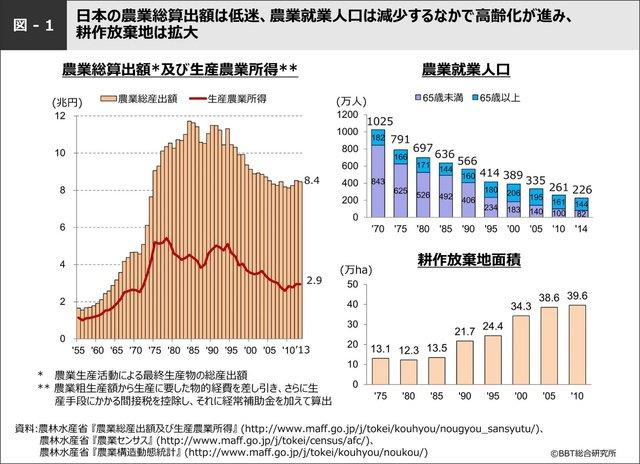  日本における 耕地面積の 日本農業の課題 田畑の区割り 大規模農家の比率 規模別農家数 (図の説明:一番左と左から2番目のグラフのように、日本の農家は一戸当たりの耕地面積が小さくて大型機械が入りにくいため、これが穀倉地帯での生産性や農家所得を下げる原因となっている。そのため、右から2番目の図のように、農業の就業人口が減るのを機会に耕地をまとめ区割りを大きくして大型の農業機械が入りやすいようにすると、すべての問題が解決する。その方法として、①農業生産法人の設立 ②パートナーシップ ③集落営農 等が考えられるわけだ) (1)JAの組織改革について 1)JAさがの分社化戦略 JAさがは、*1-1のように、持株会社2社を年度内に新設し、農産物加工等のグループ会社15社のうち9社を傘下に置くそうで、進んだ組織になる。また、総務・経理などの業務を一元化し、人件費削減や商品開発強化に繋げるのなら、総務・経理を独立した会社にして、公認会計士・税理士・社会保険労務士・ITの専門家などに緊密なアドバイスを受けながら、希望する農家の会計・税務を受託したり、繁忙期に人材を派遣したりすることも可能だ。そうすると、総務・経理部門は単なるコストセンターではなく、収益獲得能力も持つことになる。 また、持株会社の下で子会社として独立させると、*1-1に書かれているとおり、給与体系や規定を違えることも可能だ。本社から子会社に異動させられる職員もいるが、子会社の方が本社より成長した会社もあり、例えばNTTは本体より子会社であるNTTドコモやNTTコミュニケーションの方が成長会社になった。 なお、外部出資者がいる会社は100%子会社ではないので、現在は連結納税の対象にならないが、その外部出資者との間に販売協力や技術協力があるケースもあるため、節税のためだけに必ず100%子会社にしなければならないということはない。 2)農協への国の“経営指導” 私は、*1-2のうち、農協の買い取り販売拡大や生産資材価格の引下げなど、国が民間経営の箸の上げ下ろしまで指導するのはいかがなものかと思う。何故なら、国の“有識者会議”は、地域によって異なる農業の状況を分析し、理解した上で解決策を提示しているわけではないからだ。また、需要と供給に応じて価格は決まるため、①どれだけの分量を ②どういう形で ③誰に ④いくらで販売するか は、生産者や関連事業体の経営意思決定によるものであり、統制社会でなければ自由であるべきだからである。 さらに、生産資材も、農協から化学肥料を買わなくても他から買うこともでき、耕畜連携すれば安い価格で有機肥料を手に入れることも可能であるため、そういう状況の中でどういう意思決定をするかは、農家や地域の工夫次第なのだ。また、事前契約に基づいて確実な出荷を行うなど、国が考えるよりも先を行く工夫も多いため、国は民間の工夫を邪魔しないように気を付けながらサポートすべきである。 なお、近年まで日本の農業は輸出を眼中に入れていなかったが、*4-1のように、輸出し始めるとその成長率は高い。しかし、農産物を輸出するにあたっての品種の保護は、*4-3のように始まったばかりで、特許権を持てるような優良品種も誰でも栽培できる。しかし、穀物や種のある果物を生で輸出すれば、特許権があっても保護には限界があるため、いま出盛りの南米の葡萄が比較的安価で味もよく種のない品種であることに、私は感心している。また、*4-2のように、加工して出荷する方法もあるだろう。 (2)米作を優遇する農業政策はやめるべきであること 1)二毛作農家の不利益 「我が国は、米が主食」と言う人が多いが、米だけで身体を維持する栄養素を賄えるわけではない。そのため、炭水化物・脂肪・糖などの取りすぎに注意しながら栄養バランスのよい食事をするのが近年の常識であり、主食・副食の区別はなくなったと考えるべきだ。そこで、農家は地域の気候にあった多様な作物を作ることが、食料自給率を上げるために必要不可欠であるにもかかわらず、需要が減った米に固執していれば米が余って米価が下がるのは必然である。 しかし政府は、*1-3のように、2017年度から飼料用米などの“戦略作物”への助成を優先し、二毛作の助成金は産地交付金に組み込まれて8割になり、二毛作を行っている農家の所得が減る恐れがあるとして、二毛作が盛んな西南暖地の関係者が心配しているそうだ。日本中で耕作放棄地が増えている中、西南暖地は二毛作により100%を超える耕地利用率を誇って食料自給率や農業に貢献しているのだから、褒められることはあっても飼料用米より不利な扱いを受ける理由はないだろう。 さらに、“戦略作物”とされた飼料用米は、米作用の機械しか持っていない兼業農家の要請で始まったもので、家畜の飼料としては米が最も栄養価が高くて安価なわけではないため、専業農家が作る他の作物への助成を減らしてまで助成すべきものではない。にもかかわらず、自給率の低い麦や大豆への助成を減らして、飼料用米への助成を増やす農政は間違っている。 2)大豆の収量低迷 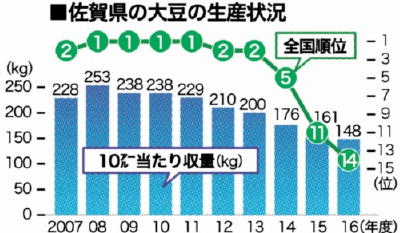     2017.4.22佐賀新聞(*1-4) ブラジルの大豆栽培 北海道の栽培 佐賀県が転作の基幹作物としている大豆の収量は、*1-4のように低迷しているそうで、がっかりだ。何故なら、私が蛋白質が豊富で需要の多い大豆に転作しようと呼びかけて、2005~2010年頃には、日本一の収量を誇っていたからである。 大豆不作の理由は、①播種期の豪雨 ②記録的な猛暑による生育不良 ③生産の大規模化で農地管理が行き届かなくなったこと などが挙げられており、佐賀県農産課は「④高温乾燥による生育不良も響いた」としているが、上の写真の北海道、ブラジルの大豆畑は佐賀県の大豆畑よりずっと大規模で、機械化により生産性も高いため、①~④は解決可能であり、文明国で口にすべき理由ではないだろう。 なお、遺伝子組み換えでない国産大豆は、安全性の観点から需要が多いため、農地管理や機械化、品種改良などで効率的な収量アップに繋げて欲しいが、安全性が高くても収穫に苦労の多い遺伝子組み換えでない国産大豆を生産し続けられるためには、*2-4のように、遺伝子組み換え(GM)食品の混入割合を欧州連合(EU)同様、加工食品まで全て表示を義務付け、少しくらい高くても消費者が選択できるようにすることが必要不可欠であり、何でも規制緩和しさえすればよいわけではない。 (3)生物由来の肥料と病中害の抑制 *2-1のように、熊本県阿蘇地域の野草に病害抑制効果のある拮抗菌が含まれ、病害抑制効果のあることが佐賀大学の研究で分かり、阿蘇地域世界農業遺産推進協会が野草の利用促進を強化しており、農家も活用に意欲的だそうだ。 確かに野草は強いため、このほかにも有効な物質を含んでいたり、有益な微生物が繁殖したりするのは想像に難くなく、生物由来の資源で安価に施肥と病気の抑制ができるのは素晴らしい。 (4)資源として利用されていなかったものを資源化する 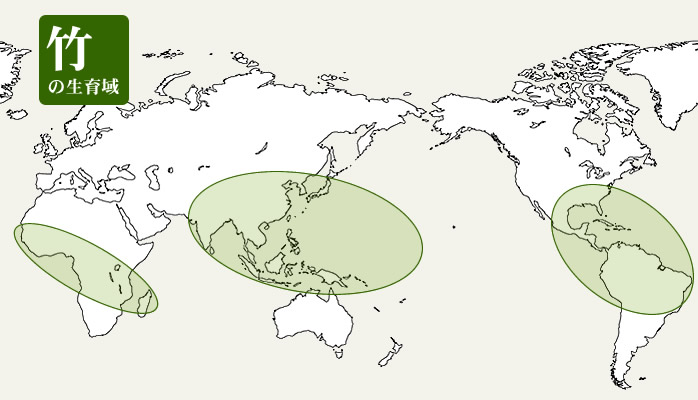 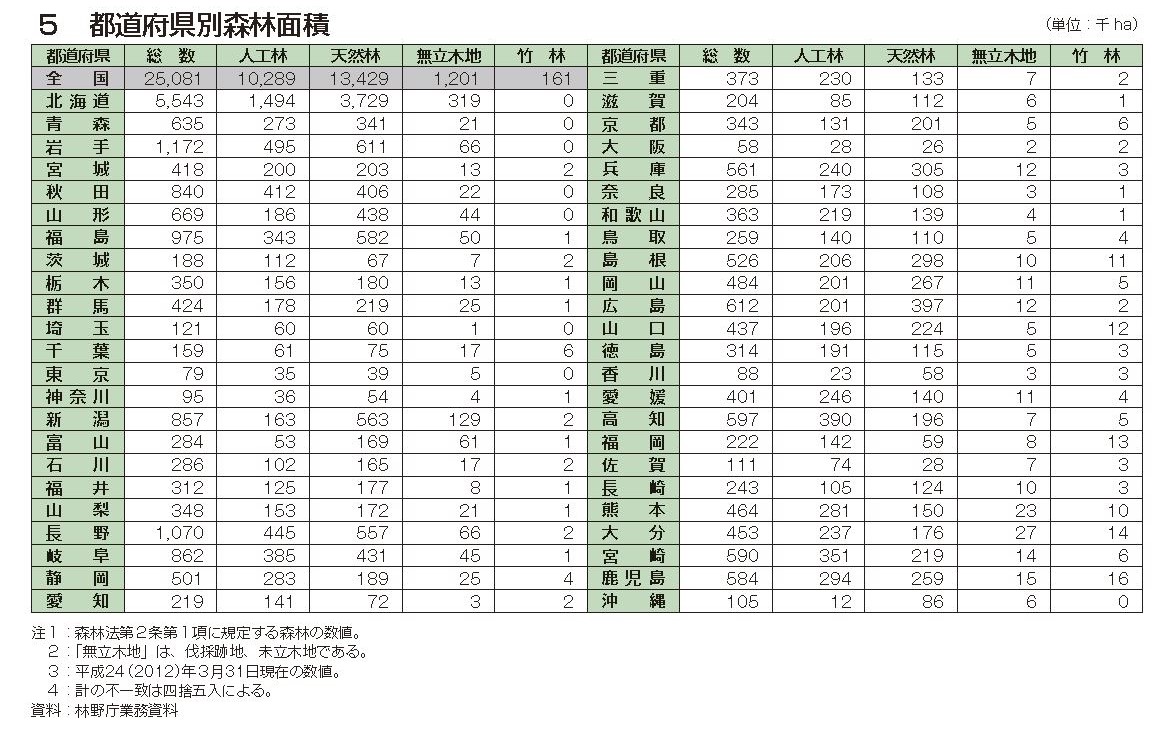   世界の竹生育地 日本の都道府県別森林面積 竹林 スペイン製手袋(山羊皮) 日本で竹が繁茂するのは上のように暖かい地域で、森林を侵食するため邪魔者とされることが多かったが、*2-2のように、放置竹林を資源として活用する方法が開発され、①竹の繊維を使ったプラスチック材料 ②タケノコの観光農園 ③竹蒸気抽出液 等ができるようになった。 また、*2-3のように、鹿は、繁殖しすぎて田畑を荒らすようになったため、害獣として頭数管理をしているが、食肉処理後の鹿皮や角を使い、ブックカバーやキーホルダーなどの雑貨作りが挑戦されているそうだ。しかし、まだ余った鹿皮の活用程度のものなので、スペインやフランスのデザイナーを使えば、牛皮よりも薄くて軽く柔らかい高級鹿皮製品ができると思われる。 (5)他国の生産方法を参照する     スペインのオリーブ畑 同枇杷畑 同イベリコ豚の飼育風景 同施設園芸 1)ハイテク化 九州は、*3-1のように、人口・面積ともオランダと同程度だが、オランダの農作物輸出量は米国に次いで世界2位だそうだ。私は、植物工場で作られたような形だけで栄養価の低い野菜を食べるのは勧めないが、①農業のハイテク化 ②農地の大規模化 は必要だろう。作物の集約化は、連作被害もあるので状況によると考える。 また、*3-2のように、オランダの施設園芸の生産性は日本の6倍もあるそうで、植物生理学からトマト栽培のLEDの青と赤の最適比率を調べており、エペ・フーベリンク准教授は、大分県で稼働しているパプリカのガラスハウスについて、「モダンだったが、収穫量はオランダの半分。オランダのハウスをただ日本に移設するだけでは不十分で、設置する場所の地形、気候などに適合した温室に改良することが必要だ」と指摘したそうだ。通気口からの病害虫の侵入を防ぐためには、通気口に換気扇につけるようなフィルターをつければよいだろう。 さらに、*3-3のように、九重町ではパプリカの栽培に温泉熱も利用しており、地中熱や温泉熱の利用も可能であるため、この辺はエンジニアの出番だ。 なお、スペインもEUでは農産物の輸出が多い国で、スーパーに入るとオリーブオイルは5L単位で売られ、果物も安くて豊富であり、イベリコ豚は美味しく、全体として豊かさを感じた。また、*3-4のように、スペイン国王フェリペ6世が来日され、日本との関係を強化することになったため、日本の農業者もヨーロッパの農業を視察に行き、オランダ・スペインの農業や農産品輸出のやり方を参考にするのがよいと考える。 2)労働力 日本では、農業の話をすると、必ず農業従事者の高齢化と後継者難がネックだと言われるが、*5-1のように、農山漁村に移住してみたいとする都市住民の割合は既に3割を超え、自然環境に恵まれ、子育てに適しているという理由で、田園回帰の意向が広がっている。 ただし、これらの若者は、農村の封建的・保守的な文化が好きなのではなく、豊かな自然や食を評価しているのであるため、農村は、封建性・保守性をなくしながら魅力ある仕事を創れば、若者の転出を減らし、転入を増やして、農業の後継者もできることになる。 さらに、*5-2のように、自動車工場では既に外国人が貴重な戦力になっており、和食居酒屋でも外国人が活躍しているにもかかわらず、日本はまだ外国人の単純労働者を技能実習生としてしか受け入れていない。そのため、日本政府は、アメリカやイギリスを批判する前に、自国の外国人労働者の受入態勢を整え、労働力が足りない分野に配置できるようにすべきだ。 <農業政策とJA組織改革> *1-1:http://qbiz.jp/article/106852/1/ (西日本新聞 2017年4月4日) JAさが、持ち株会社設立 地域農協初 年度内に9社傘下に 佐賀県農業協同組合(JAさが、金原寿秀組合長)は3日、持ち株会社2社を本年度内に新設し、農産物加工などのグループ会社15社のうち9社を傘下に置く再編計画を明らかにした。総務や経理などの業務を一元化して効率化し、人件費削減や商品開発強化につなげる。JAさがによると、地域農協による持ち株会社設立は全国初。再編計画は3月27日の臨時総代会で決定した。当初は合併を検討したが、給与体系や規定が異なり調整に時間がかかるため持ち株会社化を選択した。新設する持ち株会社は「アグリ・生活関連」と「食品加工関連」。それぞれ、自動車販売のJAオート佐賀や葬祭事業のJAセレモニーさがなど6社▽JAさが富士町加工食品やJAフーズさがなど3社−を傘下とする。外部の出資者がいるグループ会社は100%の出資を目指し、持ち株会社への編入を検討する。原寿男常務理事は「重複する業務を見直し、生産拡大や農業者の所得増大につなげたい」と話した。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p40563.html (日本農業新聞 2017年4月7日) 役割明示 販売、購買で工程表 自己改革行動計画 全農・JA JA全中は6日、昨秋決めた自己改革の方針「『魅力増す農業・農村』の実現に向けたJAグループの取り組みと提案」に基づく行動計画をまとめた。JA全農の事業改革方針を反映させ、直接・買い取り販売の拡大や生産資材価格の引き下げなど重点的な取り組みについてJA段階までの具体策や工程表を盛り込んだ。全農だけでなく、JAグループ一体で農業所得の増大に向けた改革を実行していく。「重点事項等具体策」として、6日の理事会で確認した。今後、各JAでも工程表や行動計画に反映させる。奥野長衛会長は同日の会見で「農家の理解がないと前に進まない。(全農の改革方針を)現場にどういう形で下ろし、どう実践していくかが、これから求められる」と述べた。米の買い取り販売は、全農やJAが実需者への販売推進を踏まえて生産者にニーズを伝え、取り扱い条件を提案。全農は、事前契約の実施時期を生産する前年に早める。JAは事前契約に基づく確実な出荷へ、生産者との出荷契約の履行を徹底する。いずれも2017年度に始める。青果は全農とJAが連携し、販売力があり戦略を共有できるパートナー市場を選別。卸売市場を通じた販売を従来の無条件委託販売から、取引先を明確にして数量や価格を事前に決める予約相対販売に転換する。輸出はグループ全体で19年度までに金額で340億円超を目指す。全農とJAが協力しリレー出荷体制を整備。17年度はイチゴや柿で取り組む。肥料の共同購入はグループ全体で、事前予約注文を基に入札などで最も有利な価格や購入先を決める方式に転換、価格を引き下げる。全農とJAは18年の春肥からの転換を生産者に周知する。JAは銘柄集約した集中購買品目の事前予約注文をまとめ、全農に積み上げる。農薬は、品目を集約し価格を引き下げる。全農が水稲除草剤を中心に絞り込んだ重点品目を、JAは18年用の防除暦や注文書に掲載し、推進する。17年度から始める。資材価格の「見える化」も進める。17年度中にJAは資材価格や商品特性などをホームページ(HP)などに掲載し分かりやすい価格体系に見直す。全中はこうしたJAのHPを全中のHPにリンクさせ、グループ全体の環境を整備する。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p40604.html?page=1 (日本農業新聞 2017年4月13日) 二毛作助成目減り 困惑 西南暖地には打撃 補正予算で財源確保を 水田のフル活用を支える二毛作助成の単価が目減りし、所得が減る恐れがあるとして、農家から不安の声が相次いでいる。2017年度から同助成が産地交付金に組み込まれ、配分が8割にとどまる恐れがあるためだ。米・麦の二毛作が最も盛んな福岡県では、農家の手取りが10アール当たり約3000円減るとの試算もある。同県糸島市で裏作麦を30ヘクタール生産する元全国稲作経営者会議会長の井田磯弘さん(79)は「米価が安定せず、ただでさえ利益が薄い。助成が減れば土地利用型農業は維持できない」と困惑する。農水省は16年度まで、水田活用の直接支払交付金で二毛作助成(10アール1万5000円)の枠を確保していた。これに財務省は昨年、同助成について「取り組みはほぼ定着している」として全廃を要求。農水省は17年度、同助成を産地交付金に組み込んだ。産地交付金は、当初分として8割を配分し、残り2割はいったん国が留保し、深掘りへの対応や飼料用米などの戦略作物への助成を優先して10月に配分する方式だ。飼料用米などの生産が全国的に増えれば、追加配分で二毛作助成に充てる額が減ることになる。福岡県の関係者は、二毛作助成に充てる額が県内で最大7.4億円減る恐れがあると試算。単価は従来に比べ10アール3000円ほど減って1万2000円ほどになるとみる。農水省によると、16年度は留保分の全てを戦略作物助成に使っており、追加配分は「全国的な飼料用米の増産傾向を考えると期待できない」(JA福岡中央会)との見方が強い。井田さんの経営では、仮に産地交付金の留保分の追加払いがない場合、所得が100万円近く減る計算で、大規模な担い手ほど打撃も大きい。地域農業全体にも影響が心配され、補正予算で財源を確保するよう求める。産地交付金で留保した2割分について、農水省は「全て戦略作物助成に回るとは限らない」と説明。仮に産地交付金の追加配分がなかった場合も「福岡県も含め深掘りを達成した地域の戦略作物助成に回るため、現場に損はない」(穀物課)と説明する。ただ、福岡中央会や県などは「二毛作が盛んな西南暖地には打撃になる」として、地域特性を踏まえた目配りを求める。 *1-4:http://www.saga-s.co.jp/column/economy/22901/423685 (佐賀新聞 2017年4月22日) 大豆収量低迷 大規模化、管理行き届かず、16年産反収、ピーク時の半分 佐賀県が転作の基幹作物とする大豆の収量が低迷している。2016年産の県産大豆の10アール当たり収量(反収)は148キロで、ピーク時の02年産(293キロ)から半減。かつては日本一を争ってきたものの、減少に歯止めが掛からず、全国14位に落ち込んだ。集中豪雨や記録的な猛暑による生育不良が主な要因だが、生産の大規模化で農地管理が行き届かなくなっていることも影響している。「播種(種まき)は時間との戦いだが、作付面積が広く、雨のたびにさらにずれ込んでいく」。小城市芦刈町の7~11ヘクタールほどの農地で大豆を栽培する平野裕さん(45)は頭を抱える。播種の適期は7月上旬の10日間ほど。梅雨の貴重な晴れ間を生かしての作業となるが、最近はゲリラ豪雨などの天候不順も重なり、「作業は年々難しくなっている」と平野さん。以前よりも収量が落ち込んでいるという。昨年は7月下旬から8月にかけて、最高気温35度以上の猛暑日が続いた。梅雨明け後に終日雨が降ったのは1日だけで、県農産課は「高温乾燥による生育不良も響いた」と分析する。県産大豆の反収は、07年産から13年産まで200キロ台で推移。08年産からは4年連続で全国トップになった。水田を水稲作と麦・大豆の転作作物で交互に利用するブロックローテーション(田畑輪換方式)で連作障害を抑えてきたが、11年産から6年連続で前年実績を割り込み、この2年間は全国平均も下回っている。反収減の背景には、生産者の高齢化や担い手不足による農地の規模拡大もある。「作業効率を優先せざるを得ないため、排水対策などの技術面や農地の管理が行き届かない生産者が増えている」と県農産課。県やJAは昨年から専門職員による巡回指導を強化、土壌の改良や播種作業を容易にする重機の導入も推進している。遺伝子組み換え作物など外国産に対する安全性への不安などから、国産大豆の需要は高い。県産は豆腐の原料として全国トップクラスの評価も受けており、県農産課の永渕和浩課長は「農地管理を徹底することで天候の影響もある程度低減できる。収量アップにつながる体制をつくっていきたい」と話している。 <技術革新と資源化> *2-1:https://www.agrinews.co.jp/p40077.html (日本農業新聞 2017年2月5日) 野草から拮抗菌大量に 病害抑制 利用を促進 世界農業遺産の熊本・阿蘇 世界農業遺産に認定された熊本県阿蘇地域の野草に、病害抑制効果がある大量の拮抗(きっこう)菌が含まれ、病害抑制効果があることが佐賀大学の研究で分かった。野ざらしにした野草に多く、野草をマルチに使ったハウスにも高密度に拮抗菌が生息していた。阿蘇地域世界農業遺産推進協会はその成果を生かし、野草の利用促進活動を強化した。農家も活用に意欲的だ。阿蘇には約2万2000ヘクタールの草原があり、希少植物が生息する生物多様性を維持している。県やJA、関係市町村などで組織した協議会が国連食糧農業機関(FAO)に申請し2013年、「阿蘇の草原の維持と持続的農業」が世界農業遺産に認定された。刈った野草は牛の餌や堆肥に利用する。同協会は、農家の間で「野草堆肥を使うと作物に病気が出ない」と言われていたことを確かめるため、佐賀大学農学部の染谷孝教授に研究を委託した。すると野外に積んだ野草や野草ロールから、病原菌を抑える拮抗菌の放線菌とバチルス属菌が大量に見つかり、野草をマルチし5年以上連作したトマトハウスにも高密度に生息していた。野草ロールは堆肥ではないが、堆肥と同等以上の細菌がおり、優れた微生物資材であることが分かった。染谷教授は「屋内に保管したものは良い菌がいなかった。雨ざらしにするのがいいようだ」と話す。同協会は世界遺産を次世代に継承するアクションプランの柱の一つに、耕種農家による野草利用の新たなシステムづくりを据える。採草と堆肥化に労力がかかる、野草価格が高いといった課題を解決するため、草原再生オペレーター組合を支援し採草面積を2倍以上に増やして、野草のストックヤードの建設や堆肥センターの拡充などで低コスト化と利用促進を目指す。草原再生オペレーター組合で採草に活躍しつつ、トマト栽培に利用する農家の竹辺大作さん(39)は「野草はトマトの病害予防に役立っている手応えがある。草原を守るため、採草活動に力を入れたい」と言う。 *2-2:http://qbiz.jp/article/105433/1/ (西日本新聞 2017年3月19日) 放置竹林を資源に活用する方策とは? 福岡で活動する産学の識者に聞いた 里山を荒らす「厄介もの」となっている福岡県久留米市高良山の放置竹林を、肥料や手入れ不要で多様な用途を持つバイオマス(生物資源)として活用しようと、NPO法人「筑後川流域連携倶楽部」による「竹林と経済の両立塾」が始まった。竹の持つ可能性について、事務局の山村公人さん(50)と、竹繊維を使ったプラスチック材料を開発した九州工業大大学院生命体工学研究科(北九州市)の西田治男教授(61)=高分子化学=に聞いた。 −竹繊維プラスチック材料の開発の経緯は。 西田「私はもともとバイオマスを原料とするバイオプラスチックの研究者。福岡県八女市は竹繊維とトウモロコシを原料にしたバイオプラスチックの食器を小中学校の給食に使用しており、私に『食器の強度を高めてほしい』と要望してきたのがきっかけとなった。普通のプラスチックに竹繊維を混ぜた方が強度が増すのではと調べたところ、竹繊維にはおもしろい性質があることに気付いた。微粉末化した竹繊維をプラスチックに30〜50%配合すると、曲げ強度が倍増するほか、熱による膨張も10分の1程度に抑えられる。静電気を帯びにくい性質もあり、非常に優れた工業素材となる」 −どのような手法で竹を繊維に。 西田「これまで竹は粉砕が難しく、工業利用に適していなかった。そこで、約200度の高温水蒸気を当てるだけで細かく粉砕し、繊維を取り出す方法を新たに開発した。八女市と九州工業大、企業が連携して設立したバンブーテクノ(同市立花町)では、市内の竹林から回収した竹を竹微粉末に加工。竹粉とプラスチック複合材を使ったコンテナや溝ふたなどを製品化し販売している」 −「両立塾」でバンブーテクノを見学したが、どのような可能性を感じたか。 山村「200度程度の水蒸気があれば竹微粉末ができると聞き、町中の小さな工場から水蒸気を買い、処理機を設置して加工できるのではないかと感じた。夢みたいな話だが、近所の竹を運んできて処理する小規模なプラントも可能では」 西田「一から水蒸気を作り出すとなると、かなりのコストになる。現在の竹微粉末の価格も水蒸気のコストがかなりの部分を占める。これが大規模な工場やごみ処理場などの廃熱が利用できるようになると一気に値段を下げることができるようになるだろう」 −竹粉末の工業利用の課題は。 西田「現在の竹微粉末生産量は月約1トン。工業製品を一つ作るには最低でも月100トンの年間1200トンが必要で、まずはこの量を生産できる態勢を目指すこと。製品化には、竹の伐採から粉末化、プラと混ぜ合わせるコンパウンティングという工程が必要。安定した製品供給のためには2社以上の企業での生産が求められる」 山村「バンブーテクノがすでに商品化している竹プラスチックのコンテナを、環境問題に敏感な生活協同組合などの買い物かごや配達用のコンテナに取り入れてもらえることができるのではないか。最初から大きな量を目指すのではなく、小さなことから実績を積み上げていけるのでは」 −手応えをどう感じたか。 山村「タケノコの観光農園ともに竹プラスチックも十分有望な事業になると実感した。東京五輪に向け、環境に優しい商品として売り出していけるのでは。みんなで知恵を出し合い、何が商品化できるのか考えていきたい。そのためのマーケティング会社の設立も必要になってくる」 −今後の取り組みは。 山村「来年度は林野庁の複数の補助事業を申請し、官民挙げての取り組みとしていきたい。放置竹林の問題は久留米だけに限らず九州全体の問題。地元住民と里山が共生する仕組みを考えなければならない。私自身も広川町で観光タケノコ園を経営する夢を持っており、伐採した竹も利用していきたい」 西田「竹微粉末の製造工程の副産物で竹蒸気抽出液ができる。いわゆる竹酢液だが、200度の低温で処理するため有害なタールが含まれておらず、皮膚につけても安全で入浴剤としても利用できる。竹微粉末とともに、魅力ある素材としてアピールしていきたい」 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p40574.html (日本農業新聞 2017年4月9日) 鹿皮や角で雑貨作り 食害 知ってほしい 静岡県伊豆市 猪股学さん 静岡県伊豆市の地域おこし協力隊、猪股学さん(34)は、食肉処理後の鹿の皮や角を使い、ブックカバーやキーホルダーなどの雑貨作りに挑戦している。閉園した幼稚園をアトリエとして、元デザイナーのキャリアを生かしながら商品デザインや縫製をして販売する。猪股さんは「商品を通じて伊豆の鹿被害について考えてほしい」と訴える。猪股さんは山梨県出身で、元々ジュエリーデザイナーとして甲府市で働いていた。その頃に、直営の鹿肉加工施設から出る皮や角の処理に悩んでいた伊豆市が、これらを有効活用するための地域おこし協力隊を募集。デザイナーとしてのキャリアが生かせると考えて応募し、2016年から伊豆市に移住して活動を始めた。使うのは市内で捕獲され、食肉処理をした後に余った鹿の皮や角。業者になめし加工してもらい、裁断や縫製して商品にする。野生の鹿のため、皮にはダニがかんだ傷やけがによる染みもある。猪股さんは「これも鹿が生きた証し。個性として楽しんでもらいたい」と話す。ブックカバーや名刺入れ、ピアスやネックレスなど現在までに10種類ほどの商品を開発。昨秋から「mori―kara」のブランド名で販売を始め、現在は市内のセレクトショップやイベントなどで販売している。今後は首都圏や静岡市内などに販路を広げる計画だ。猪股さんは「伊豆は海のイメージが強いが、鹿による食害で周辺農家は悩んでいる。商品を通して、実情を伝えていく」と意気込む。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p40698.html (日本農業新聞 2017年4月25日) GM表示見直し着手 混入割合引き下げ焦点 消費者庁 消費者庁は、遺伝子組み換え(GM)食品の表示制度の在り方で有識者による検討会を立ち上げ、表示対象の拡大を視野に議論に着手する。現行制度は2001年4月にスタートし、この間の分析技術の精度向上や、GM作物の栽培拡大・流通の変化などを踏まえる。表示義務がない混入割合は、現行は5%未満と他国に比べて緩く、どこまで狭められるかが大きな焦点だ。より詳しい表示ができれば、消費者の商品選びに役立ち、国産農産物に追い風になるとみられる。初会合を26日に開き、17年度内に取りまとめる予定だ。 ●厳格化で国産追い風 現行制度は大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、ナタネ、綿実、アルファルファ、テンサイ、パパイアの8種類の農産物に表示を義務付けている。それらを原材料とする豆腐、納豆、みそ、スナック菓子など33食品も表示の対象。ただ、GM作物の使用重量が小さく、原材料に占める割合が上位4位以下や5%未満であれば、表示する義務はない。5%未満で線引きすることには、当時から消費者団体などから緩いとの指摘があったが、「意図せざる混入」として認められた。一方、欧州連合(EU)ではGM作物を使った加工食品の全てを対象に、表示を原則義務付けている。「意図せざる混入」が許されるのは0.9%未満まで。韓国は3%未満で、日本よりは厳しい。しょうゆ、油、でんぷんから加工される果糖ブドウ糖液糖などは、現在は任意表示にとどまる。加工工程でGM作物のDNAやタンパク質が分解されるなどして検出できないという理由だ。それらの原料の大豆、ナタネ、トウモロコシは、米国やカナダなど主産国でGM比率が9割台に達しており、義務表示を求める声が消費者団体などに強い。消費者庁は「必要とあれば、検討会の中で議論する」との構え。検討を左右するのは、技術的な課題に加え、表示拡大に対する各業界、団体の主張だ。消費者団体の関係者は「消費者が情報を手に入れる幅が広がる」と期待する声が上がる。一方で「分析による設備投資などで加工業者のコストが膨らみ、商品価格に転嫁される恐れもある」と消費者の負担増加を懸念する見方もある。加工業からは冷静な受け止めも聞かれる。関係者は、大きな影響はないと予測し、「多くの業者が既に分析技術を高めている。『意図せざる混入』を引き下げられても対応できるだろう」と指摘する。国内農家からは、消費者がGM食品を改めて考えるきっかけになると期待する声が上がる。北海道恵庭市の大豆生産者は「消費者の食への意識が高まり、厳しい基準で生産された国産大豆に関心を持ってほしい」と話す。世界のGM作物の作付面積は、1996年に170万ヘクタールだったが、現行の表示制度ができた01年には5260万ヘクタール、15年で1億7970万ヘクタールと急増している。26日の検討会では、消費者庁がGM表示に関する海外の状況と消費者アンケートの結果を報告し、今後の検討会の進め方などを議論する予定だ。 <他国の生産方法参照> *3-1:http://qbiz.jp/article/102549/1/ (西日本新聞 2017年1月30日) 【九州農業の生産額は全国の2割】成長のヒントはある国に… 「九州は1割経済」と言われるが、「2割経済」を誇る産業もある。農業だ。 ■生産額は1・6兆円 日本政策投資銀行九州支店のリポートによると、生産額は1・6兆円で、全国8・4兆円の19%を占める(2011年時点)。九州は「豊かな自然と温暖な気候を生かして農業、特に野菜・果物・畜産が盛ん」とした上で、「日本における農産物供給基地としての役割を担っている」と位置づけた。ただ、成長を遂げるには、ある国のノウハウを学ぶ必要があることを提案している。それは、オランダだ。人口、面積ともに九州と同程度のオランダ。それなのに、農作物輸出量が米国に次いで世界第2位となっている。 ■ハイテク化する農業 政投銀のリポートのタイトルは「九州における植物工場などハイテク農業の成長産業化に向けた課題と展望」。「農業先進国からハイテク化による競争力強化の手法を学んではいかがだろうか」と呼びかけ、オランダの事例を紹介している。高い国際競争力の理由について、リポートは「環境制御型施設園芸(太陽光型植物工場)に関する技術が発達していることが主因」と分析する。例えば、トマト。「面積当たりで3〜5倍、労働時間当たりで8倍も日本より生産性が高い」という。さらに「農地の大規模化」や「作物の集約化」もオランダ農業の強みらしい。韓国の成功事例も紹介していたが、背景にはやはりオランダが存在していた。植物工場で栽培したパプリカを日本向けに大量に輸出しているが、技術の後ろ盾はオランダ農業だった。韓国は「技術やノウハウをオランダから丸ごと導入し、農業のハイテク化を推進した」というのだ。 ■オランダ方式に鍵が 九州農業も、着実な成長が読み取れる。農林水産省によると、15年の九州農業の生産額は1兆7541億円。全国(8兆8631億円)の19・8%で、リポートで報告された11年時点から、金額も割合も拡大している。ただ、喜んでばかりはいられない。リポートで生産額が1・6兆円と同規模の「鉄鋼」は、全国(18・2兆円)に占める割合が約9%にとどまっていた。つまり、農業は鉄鋼に比べると、まだまだ「分母」が小さいというわけだ。リポートでは、「国内の他地域と同様、農業従事者の高齢化や後継者難、国際競争力の弱さなど、農業に内在する課題は深刻」との指摘もあった。九州農業が、全国の農業生産額をけん引しながら「2割経済」をさらに突破できるか。オランダ方式にそのヒントがあるのかもしれない。 *3-2:http://qbiz.jp/article/108137/1/ (西日本新聞 2017年4月22日) 施設園芸オランダに学べ 生産性は日本の6倍も 最適な環境創出が鍵 施設園芸先進国のオランダの手法を参考にして、農業の生産性を高めようと、農林水産省が施設園芸の支援に力を入れている。九州でもオランダの技術を導入した施設が稼働しているが、“本家”との違いはどうか。3月にオランダを訪れ、最先端の園芸技術を取材した。施設園芸分野で世界トップレベルの研究を誇るワーヘニンゲン大学。オランダ中部にあり、案内された研究用ガラスハウスに入ると、赤紫色の発光ダイオード(LED)がネオン街のように輝いていた。「トマト栽培にとってLEDの青と赤の比率はどの程度が理想かを調べている」。解説するのはエペ・フーベリンク准教授。植物生理学が専門だ。執筆を一部担当した書籍「トマト オランダの多収技術と理論」は日本語版も出ている。今年1月末から2月上旬にかけて来日し、農研機構の研究者と一緒に、複数の「次世代施設園芸拠点」を視察した。大分県九重町で昨年4月から稼働しているパプリカ生産のガラスハウス(栽培面積2・4ヘクタール)も視察先の一つだった。准教授は大分の施設について「モダンだったが、収穫量はオランダの半分。オランダのハウスをただ日本に移設するだけでは不十分」と指摘した。准教授によると、オランダのハウスは通気口が少ない。大分の施設も同じだったが、日本の気候だと通気口が不足して換気が十分にできていないという。「設置する場所の地形、気候などに適合した温室に改良することが必要」と准教授。大分の施設を運営するタカヒコアグロビジネスの松尾崇史専務は「通気口を増やすと病害虫侵入のリスクも高まる。どう対応するか研究中」と話す。農水省は「日本の環境に合わせる重要性は十分認識している」と受け止める。 ■ ■ 農水省は2013〜16年度、民間が全国10カ所で手掛けた次世代施設園芸拠点の整備に対し、補助金を支出。各拠点はオランダ式の大規模ガラスハウスや、ハイテクによる環境制御の仕組みを導入。補助金総額は111億円に上る。「安倍氏もちょうど、このあたりに立ちました」。オランダ西部にあるバルスター社。3・4ヘクタールの広大なガラスハウス内で経営者のウィボ・バルスターさんは、14年3月に安倍晋三首相の視察を受け入れたことに触れ、中を案内した。肌寒い季節だったが、ハウス内は25度で、バルスターさんは半袖姿。天井までの高さは約6メートルで、見上げると、透明なガラスの向こうの青空が鮮やかだった。パプリカの収穫量は1平方メートル当たり年間で約40キロという。日本の6倍ほどで、バルスターさんは「うちはオランダの中でも生産性が高い」と胸を張る。オランダの園芸施設はビニールハウスでなく、ガラスハウスが一般的。日本より安価な天然ガスで沸かした湯を流すパイプをハウス内に張り巡らせて暖房を得ている。さらに気温、湿度、二酸化炭素濃度などが最適になるように、ハイテク機器などで制御しているのが特徴だ。バルスターさんは生産性が高い理由について「企業秘密」と詳しく説明してくれなかった。「立派なハウスを設けても、それを活用するための知識がなければ、利益は得られない。日本に対し協力したい」と話していた。 *3-3:http://qbiz.jp/article/105837/1/ (西日本新聞 2017年3月18日) 温泉熱でパプリカ栽培 九州最大、オランダの手法導入 九重町で建設業子会社 *写真:パプリカ生産のガラスハウス 温泉熱と高度な環境制御技術を利用して、パプリカを生産する大規模園芸施設が大分県九重町で稼働している。施設の随所に、園芸先進国であるオランダの手法を導入。栽培面積は2・4ヘクタールで年間400トンの出荷を見込み、2億4千万円を売り上げる計画。大分県によると、パプリカ栽培施設としては九州最大。脱燃油とハイテクで、収益性の高い農業を目指しており、今後の成果が注目される。総合建設業「タカフジ」(大分市)の子会社「タカヒコアグロビジネス」(九重町)が経営。2・4ヘクタールの栽培室に加え、育苗室0・3ヘクタール、出荷センター、熱交換システムを備える。昨年4月から稼働を始めた。熱交換システムは、事業地内に湧き出る温泉の熱で、施設内を巡る循環水を加温する装置。タカフジが開発した。栽培室と育苗室には、循環水が流れる直径10センチほどの管が延べ数十キロにわたって血管のように張り巡らされている。管からの放熱で暖房装置の役目を果たし、冬でも室内の気温を20度前後で維持する。 ■ ■ 栽培室と育苗室は、オランダで一般的なガラスハウス(高さ約7メートル)を採用。ビニールハウスよりも耐久性や採光性に優れているという。室内の気温、湿度、二酸化炭素(CO2)濃度、日射量、養液量は、パプリカの生育に最適であるよう、センサーや霧の噴射装置などで自動的に制御している。これもオランダ仕様だ。農林水産省が全国10カ所で整備を支援した次世代施設園芸拠点の一つ。温泉掘削費も含む総整備費約16億円のうち、約5億8千万円を農水省が補助した。 ■ ■ 販売先は市場に頼らず、百貨店や生協、病院食業者などを独自で開拓。収穫は昨年7月末からで、周年安定供給を目指している。今のところ予定通りの生産という。暖房もこれまで、厳しい寒さがそれほどなく、温泉の熱で全て賄えており、重油の使用はゼロ。農水省が要件とする「化石燃料の使用量を5年後までにおおむね3割以上削減する」を楽にクリアしている状況だ。ただタカヒコアグロビジネスの松尾崇史専務は「パプリカの年間生産量はオランダは1平方メートル当たり40キロ以上だが、うちの当面の目標は16キロ。栽培技術向上に努め、オランダに追い付きたい」と話している。 *3-4:http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017040601001699.html (東京新聞 2017年4月6日) 【政治】首相、スペイン国王と懇談 外交150年へ関係強化 安倍晋三首相は6日、国賓として来日中のスペイン国王フェリペ6世夫妻と東京・元赤坂の迎賓館で懇談し、両国の外交関係樹立150周年に当たる来年に向け両国関係を強化する考えで一致した。首相は「世界平和と発展のため貢献していく大切なパートナーだ」と強調。国王は「国民同士の距離を縮めることも非常に重要だ」と応じた。首相と国王は懇談後、若者らが相手国で働きながら勉強できるワーキングホリデーなどに関する協力文書の交換式に立ち会った。その後、国王夫妻は首相夫妻が主催する夕食会にも出席。サッカーのスペイン1部リーグ、エイバルの乾貴士選手も参加した。 <農産品の輸出> *4-1:https://www.agrinews.co.jp/p40078.html (日本農業新聞 2017年2月5日) 和牛輸出 アジア・欧州向け強化 対米は高関税が壁 全農グループ JA全農グループは和牛肉の輸出拡大を強化している。2020年度に500トンの目標を掲げ、5年間で約1.8倍に増やす考えだ。輸出が増えたことで、米国では日本産牛肉に設定している低関税枠(200トン)を超える情勢。枠を上回る輸出には高い関税が適用されるためこれまでの勢いを維持できなくなる可能性があり、アジアや欧州、中東への輸出を強めるなど攻勢をかける。全農は需要拡大が見込めるアジアや欧州への輸出に注力する。香港、シンガポールは現在も主要な輸出先になっているが、国内消費は飽和状態に近く、競合他社とのシェア争いをしているのが現状だ。そこで、タイやフィリピン、ベトナムといった、今後の経済成長が見込まれる新興国の高所得者向けの需要拡大を期待する。欧州では14年に牛肉の輸出が解禁され、和食人気、食の安全・安心志向を背景に潜在需要が高いとみる。和牛の食べ方などを通じた魅力発信を進め、市場開拓を狙う。全農は昨年、農林中央金庫と英国の食品卸を買収。現地の実需ニーズを見極めて直販体制を構築し、輸出を強めていく考えだ。中東も国内消費だけでなく、世界の観光客需要に期待する。一方、米国は現在、日本産の牛肉に200トンを上限とする低関税輸入枠を置く。枠内の関税は1キロ当たり4.4セント(約5円)だが、200トンを超えると26.4%の関税がかかる仕組みだ。日本全体の16年の対米輸出量は244トンで、200トンを超えた。全農グループの米国への輸出割合も高く、年間2割程度伸びていたが「高関税がかかると輸出の伸びは厳しく、様子見の状況」(全農畜産総合対策部)。トランプ米大統領の就任で、先行きも不透明だ。多様な部位の現地加工による商品化を通じた輸出拡大も目指す。輸出する牛肉はブロックのため、使い勝手が悪いケースもある。現地で食肉加工施設を設置し、カットやスライスして提供、多様な販売先を開拓する。全農は「拡大を達成するには、親日で食文化が近い台湾などの輸出解禁は不可欠」と強調する。 *4-2:https://www.agrinews.co.jp/p40037.html (日本農業新聞 2017年1月31日) 加工用需要拡大へ 青森:桃 宮城:リンゴ 果実の加工需要を掘り起こそうという動きが、ジュース以外でも広がっている。青森県のJА津軽みらいは、菓子や料理の材料として桃をピューレやシロップ漬け向けに出荷。2016年産の出荷量は約5トンで、当初の5倍に増えた。宮城県は、加工向けのリンゴ「サワールージュ」の菓子利用を推進。複数店舗の協力を得て1カ月間、同品種を使った菓子を販売し販路を開拓した。実需との連携が重要な鍵を握っている。 ●ピューレ、シロップ漬けに JА津軽みらい管内では79人が約15ヘクタールで桃を栽培する。リンゴ農家に果樹の複合経営を促すため、桃を導入した。規格外品は、ピューレやシロップ漬けの製造を業者に委託し、ケーキやソフトクリームなどの原料として菓子店を中心に販売する。売り先の一つ、青森県土産販売(青森市)は、桃のピューレを年間約200キロ調達する。16年4月には「ピンクカレー」を商品化。11月末まで約2万個売れ、同社の主力商品となった。JAは県外にも販路を広げ、東京のジェラート店からピューレ約800キロ、ホテルからシロップ漬け約500キロの注文が来た。加工向けの農家手取り価格は10キロ約1000円。ピューレやシロップ漬けを始める前の11年の同約290円の3倍以上となった。JАもも生産協議会の会長を務め、平川市でリンゴ2・3ヘクタール、桃70アールを生産する木村俊雄さん(70)は「1次加工品の販売は所得確保につながる」と実感する。 ●菓子利用や料理素材向け 宮城県は、独自に育成したリンゴ「サワールージュ」を加工向け品種と位置付け、菓子のPRに力を入れる。13年度から毎年、10月の1カ月間、仙台市内の洋菓子店やホテルと協力し、同品種を使った菓子を販売する。16年度は9業者が参加。当初の3倍に拡大した。洋菓子店のガトーめぐろは同品種のアップルパイを販売。1カ月の期間中、1日20個を作り、全日完売した。同社の目黒栄治社長は「サワールージュは酸味が強く、果肉が硬いため煮崩れしにくい。今後も調達量を増やしたい」と評価する。県内では現在、同品種を約100人が1・5ヘクタールで生産する。菓子需要の拡大を背景に、栽培が始まった11年度当初の10アールから15倍に拡大し、16年度の出荷量は2トンとなった。県は「菓子需要を拡大していくには実需者との連携が欠かせない。今後も協力店を増やしたい」(農産園芸環境課)と展望する。 ●「国産」「地元産」実需者にPRを *果実のマーケティングに詳しい弘前大学の成田拓未准教授の話 生鮮果実の消費量が減る中、業務用需要は果樹農家の所得を確保する上で重要な販路になる。国産果実は、菓子の付加価値を高めることにつながる。今後も加工向けの国産果実の需要は増えるだろう。産地は、洋菓子店など実需者に対し、国産や地元産をPRすれば新たな商機も出てくる。 *4-3:https://www.agrinews.co.jp/40720?page=2 (日本農業新聞 2017年4月27日) 海外で品種登録支援 無断栽培を防止 知財計画 政府方針 政府は26日、農産物の輸出促進へ、海外での日本の農産物の品種登録への支援を強化する方針を明らかにした。品種登録によって国内の品種の育成者が種苗や収穫物を販売する権利を保護し、海外で無断栽培される事態を防ぐ。来月にも改訂する政府の知的財産推進計画に盛り込む。政府は同日に開いた知的財産戦略本部の会合で、同計画の素案を示した。柱の一つに「攻めの農林水産業・食料産業を支える知財活用・強化」を掲げ、農業分野での知的財産の活用に向けた施策を、従来の計画よりも大幅に拡充する。主にアジア向けに輸出が伸びているブドウ「シャインマスカット」は農研機構が開発したが、中国で品種登録をしなかったことから無断栽培が拡大。アジア各国で日本産と中国産が競合する懸念が指摘されている。イチゴやサクランボ、カーネーションなどでも無断栽培の事例が起きている。こうしたことから政府は、国内の育成者が海外で品種登録を出願する際の支援策を同計画に盛り込む方針だ。品種登録が迅速に進むよう、国内での品種登録の審査結果を海外の登録機関に無償で提供する取り組みや、品種登録後に無断栽培が発覚するなど権利が侵害された場合の支援策などを盛り込む。輸出促進では他に、地理的表示(GI)の海外での保護や、日本発の農業生産工程管理(GAP)認証の普及なども進める。湿度や土壌水分などさまざまな情報をセンサーで読み取り、温室を自動制御するなどICT(情報通信技術)の普及へ、国内でICTの標準的な規格を作るといった取り組みも盛り込む。同日の会合では委員から「農業でこれだけ具体的に明記したのは重要だ」と素案を評価する声や、日本の地名を冠した商品が海外で売られているとして、「現地の商標を取り消す費用の助成制度が必要だ」との声が上がるなどした。 <労働力> *5-1:https://www.agrinews.co.jp/p40119.html (日本農業新聞 2017年2月10日) 都市住民 農村へ移住3割が関心 総務省調査 総務省が9日公表した調査で、農山漁村に移住してみたいとする都市住民の割合が3割を超え、田園回帰の意向が広がっていることが明らかになった。移住したい理由には「気候や自然環境に恵まれている」が47%と最も多い。農山漁村地域が子育てに適しているとした割合は23%で、若い世代ほど高かった。同省の「田園回帰に関する調査研究会」に示した。東京都内や政令指定都市の20~64歳の3116人に1月にインターネット調査した。農山漁村への移住の意向は、「条件が合えば移住してみてもよい」(24%)、「いずれは移住したい」(5%)、「移住する予定がある」(1%)で合わせて3割に上った。20代(38%)、30代(36%)の割合が高く、男性の方が移住希望の割合が高かった。移住希望がある人に移住のタイミングを聞いたところ、「条件が整えばすぐにでも」が20%に上った。「自分または配偶者が退職したら」が23%だった。研究会委員を務める鳥取大学の筒井一伸准教授は「田園回帰の傾向が改めて把握できた。移住したい層が確認できたので、仕事の確保を中心にどういう条件を現場で組み立てていくかヒントが見えてきた」と分析する。 *5-2:http://qbiz.jp/article/106654/1/ (西日本新聞 2017年3月31日) 【新移民時代 変わる仕事場】(1)レクサス生産に外国人が「貴重な戦力」 「世界一有名なトヨタの車を造るのはうれしいね」。自動車部品製造のテクノスマイル(福岡県宮若市)の工場。ミャンマーからの技能実習生テ・アウン・テさん(22)は、大型機械のそばに立ち、一つの部品を作る作業を担当する。ミャンマー中部マグウェイ出身。「家は農民で、お金がなくて車は買えない。けど車は大好き」。作った部品は近くのトヨタ自動車九州の工場で、日本が誇る最高級車「レクサス」の車輪上部に組み付けられる。タイヤがはねた小石の音が車内に響かないようにする高級車向けの部品だ。テクノスマイルは2008年に実習生を受け入れ始めた。当初は技術伝承の「国際貢献」が理由だったが、今は工場で働く42人のうち17人が実習生。幹部は「自動車メーカーが日給1万3千〜1万4千円で求人しても人員確保に苦労する。コスト削減を迫られる下請けの賃金では、日本人は集まらない」と打ち明ける。 ■ ■ 自動車生産設備製造の福設(宮若市)では、ベトナム出身の技術者グエン・トゥアン・ブゥさん(26)が真剣な表情でパソコン画面に向かっていた。3D設計ソフトを使って製図しているのは「レクサス」などを生み出すトヨタ自動車九州の生産設備だ。ベトナムの大学を卒業後に「日本の製造現場を学びたい」と来日。専門技術が評価されて派遣社員として働いていたが、昨年会社に請われて正社員採用。日本人と同等の給料で働く。現在は9人の設計担当者のうち2人がベトナム出身者だ。「国内で技術者が不足する中で貴重な戦力。さらにベトナム出身の人材を増やしたい」。井上貞夫会長(68)の期待は大きい。日本の「ものづくり」をけん引する自動車産業。巨大なピラミッド構造のあらゆる階層を外国人が支え、彼らの携わった「日本車」が九州から世界中に輸出されている。 ■ ■ 「らっしゃいませー」。平日の午後7時すぎ、JR博多駅に近い和食居酒屋。調理場から威勢のいい声が響いた。声の主はアルバイトのベトナムからの男性留学生(22)だ。焼き鳥、刺し身、からしれんこんもお手の物。調理をこなし、別の従業員が仕上げたギョーザ鍋には「違う。たっぷり」と指導。博多万能ねぎを土鍋に盛り付けてみせた。手を抜かない仕事ぶりに「働く姿勢は日本人のお手本で、社員になってほしい」と店長(41)。無形文化遺産の「和食」も、海外人材が中心になりうる。店舗の運営会社は、福岡県中小企業経営者協会連合会が計画する、海外の若者に日本語学校の学費を貸す事業に参画を予定している。昨春、日本人の新卒入社は0人。留学生が将来入社し、幹部として海外展開を手掛ける夢を描く。一方、「労働と留学が一体の契約」として摘発された宮崎県の法人の事例もある。給料面や職業選択の自由への配慮も欠かさないつもりだが…。社長(61)は「海外人材なくして、今後企業はうまく回らなくなる」と危機感を隠さない。 × × 少子高齢化が進み、労働力人口が減少する日本。世界第3位の経済大国・日本の企業は、外国からの労働者、専門技術者、高度人材なくしては成り立たなくなろうとしている。この現実に、私たちは対応できているのだろうか。「新 移民時代」第6部は、外国人との共生を模索する「変わる仕事場」を訪ねた。 PS(2017年5月2日追加): *6-1のように、日本国内の外国人労働者が100万人を超し、外国人労働者は九州でも貴重な戦力となっている様子が、西日本新聞の九州主要企業104社へのアンケートでわかった。つまり、九州主要企業では、社員かパート・アルバイトに外国人を採用している企業が約7割(70社)を占め、うち4割が採用拡大を考えているとのことである。 ここ数年、*6-2のように、日本では30年遅れの“働かない改革”が主張され、若者に「働きすぎてはいけない」という意識を定着させすぎて悪影響を与えているが、現在は1980年代とは異なり、日本人労働者の平均労働時間は既にアメリカよりも短く、労働生産性も低く、問題になっている残業時間制限は季節性のある企業の事情を考慮したものであるため、それ以下にしたければ、残業時間上限の詳細は個々の企業別労働組合で決めればよいことである。ただし、職種や年収によって「脱時間給」「裁量労働制」などとするのは、同じ人間であり、異常な長時間労働やプレッシャーは誰でも同じように健康を害することからおかしい。 そのような中、*6-3のように、徳島県のJA東とくしまが管内の若手農家と共同出資して農業生産法人を設立し、農地を集積して耕作放棄地対策を進めながら、付加価値の高い米作り等を推進するそうだ。若手農家が参画しやすい経営体づくりをして大規模化すれば、資金力・生産性を上昇させ、農業生産法人で労働者を雇うこともできるようになるだろう。 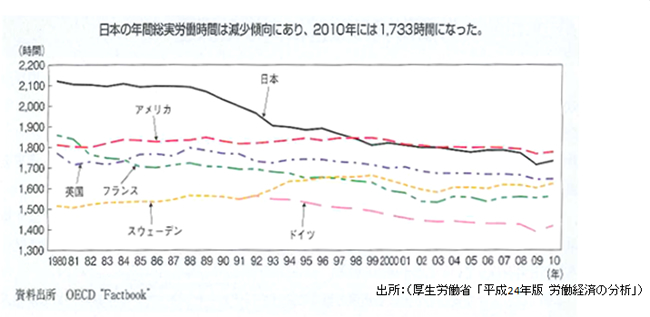  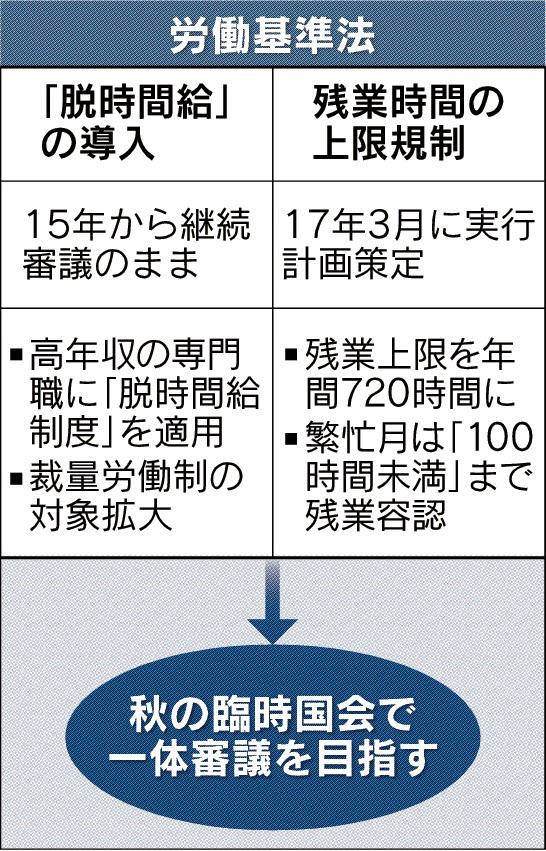 年間労働時間国際比較(厚労省) 日本の年間労働時間の減少 2017.5.2日経新聞 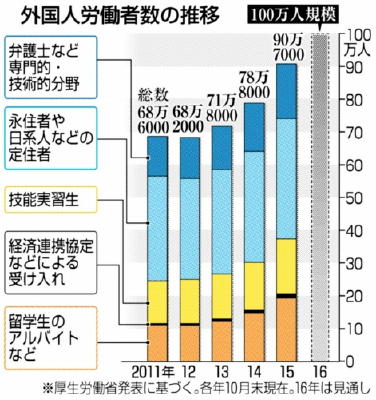 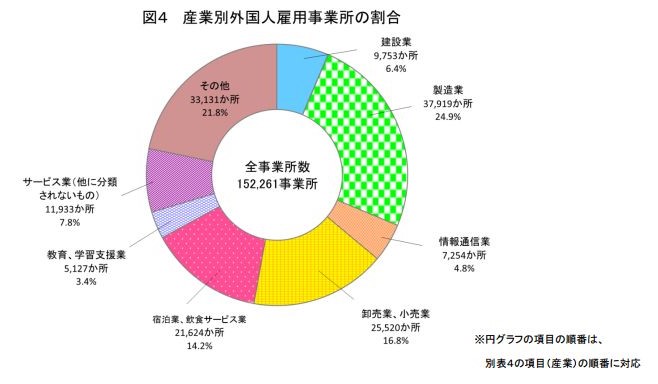 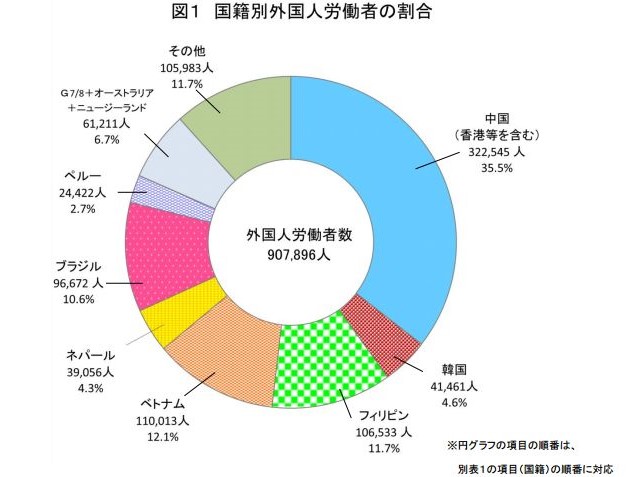 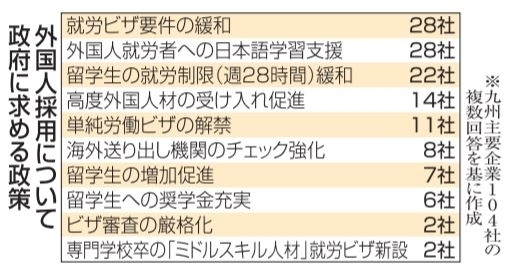 2016.4.3 産業別外国人雇用 国籍別外国人労働者 2017.5.2西日本新聞 佐賀新聞 事業所割合(厚労省) (厚労省) *6-1:http://qbiz.jp/article/108738/1/ (西日本新聞 2017年5月2日) 「外国人」九州企業7割が採用、うち4割は「拡大」方針 104社アンケート 西日本新聞の九州の主要企業104社アンケートで、社員かパート・アルバイトに外国人を採用している企業が約7割(70社)を占め、うち4割が採用拡大を考えていることが分かった。理由として、海外事業展開や訪日外国人対応に加え、2割の企業が「人手不足で日本人が集まらない」と回答。政府に就労ビザ要件の緩和や日本語学習支援を求める声が多かった。国内の外国人労働者が100万人を超す中、九州でも貴重な戦力となっている実態が浮き彫りになった。外国人を採用中の企業のうち、社員としての雇用は59社、パート・アルバイトは33社。今後の方針として外国人の人数減少を検討している企業はゼロだった。採用理由(複数回答)は、多い順に(1)海外での事業展開のため=20社(2)訪日外国人に対応するため=19社(3)海外企業との提携や交渉のため=15社(4)人手不足で日本人が集まらないため=14社(5)高度な技術を持っているため=8社−などだった。外国人の社員やパート・アルバイトがゼロの30社のうち、9社が「採用を検討している」と答えた。外国人の採用について政府や行政機関に求める政策を複数回答で尋ねたところ、「就労ビザ要件の緩和」と「外国人就労者への日本語学習支援」がともに28社で最多。次いで「留学生の就労制限(週28時間以内)の緩和」が22社、「高度外国人材の受け入れ促進」が14社に上った。「単純労働ビザの解禁」を挙げた企業も11社あった。外国人採用拡大への政策を促す声の一方、外国人技能実習生などを受け入れる企業の中には「海外の送り出し機関のチェック体制強化」や「ビザ審査の厳格化」を求める企業もあった。調査は4月に160社を対象に実施し、104社から有効回答があった。 *6-2:http://www.nikkei.com/article/DGXKZO15975270S7A500C1PP8000/ (日経新聞 2017/5/2) 残業規制、脱時間給とセット 働き方改革、連合苦悩 安倍晋三首相が「最大のチャレンジ」と位置付けた働き方改革。労使代表らがメンバーの「働き方改革実現会議」は3月末、約半年間の議論を経て残業時間の上限規制などを盛り込んだ実行計画をまとめた。秋の臨時国会ではいよいよ立法段階に入るが、改革の旗振り役だった連合の顔色がなぜかさえない。月平均60時間、年間では720時間とし、焦点の繁忙月の特例は100時間未満とした残業時間規制の最終案。「100時間はあり得ない」としてきた連合の意向を踏まえた首相要請で決まったもので、労働基準法70年の歴史で初の大改革となる。連合にとっても悲願だったはずだ。しかし、実行計画をとりまとめた3月28日の実現会議の終了後、連合の神津里季生会長は厳しい表情を浮かべて記者団に語った。「今のままで法案が通るのは反対だ」。連合の要求を反映させた残業時間規制案となったにもかかわらず、わざわざ苦言を呈したのには理由があった。神津氏が問題にしたのは実行計画に盛り込まれた一文だ。労働時間ではなく仕事の成果に応じて賃金を支払う「脱時間給制度」の導入を柱とする労基法改正案に触れ「国会での早期成立を図る」と明記した。同法案は野党や連合が「残業代ゼロ法案」と批判。審議されないまま約2年たなざらしになっている。その法案を政府は今国会での成立を見送り、今回の残業時間規制を盛り込んだ労基法改正案と一体で秋の臨時国会で審議する方針だ。残業時間規制とともに、時間にとらわれない働き方も認め、企業側が懸念する労働の生産性の低下を防ぐ狙いだ。批判の多い脱時間給導入だけで労基法を改正するより世論の理解を得やすいとの判断もある。残業時間規制という成果を勝ち取った神津氏だが、脱時間給制度は「長時間労働を助長し、残業時間規制とは矛盾する」との立場。しかし、一体審議となれば残業規制の導入を求めてきた立場から法案審議への明確な反対を唱えにくい。さらに連合を悩ませるのは支持政党である民進党が残業時間規制を巡り、繁忙月の例外を100時間未満とすることにした今回の案に「長すぎる」として反対の立場を示していることだ。脱原発などで関係は既にぎくしゃくしているが、これ以上溝が深まるのは避けたいところだ。脱時間給制度と残業時間規制を別々の法案として審議し、民進党も残業時間規制には賛成に回ってくれるのが連合にとってはベストシナリオ。しかし政府は連合の立場を承知のうえでパッケージ案を突きつける構えだ。民進党が政府案に賛成しないのも連合が一番分かっている。 *6-3:https://www.agrinews.co.jp/p40758.html (日本農業新聞 2017年5月2日) 若手農家と法人設立 特栽米生産を振興 農地集積し放棄地対策も JA東とくしまが共同出資 徳島県のJA東とくしまは管内の若手農家らと共同出資して、農地所有適格法人(農業生産法人)を設立した。共同出資という深いつながりで連携し、付加価値の高い米作りを推進する。法人に農地を集積し、耕作放棄地対策も進める。農家とJAが共同出資して農業生産法人を設立するのは珍しい。新法人は「ほのか株式会社」。地域の農家5人とJAで組織する。年齢構成は30代が2人、60代が1人、70代が2人。代表は、小松島市で米やトマト、小松菜などを生産し、社員20人がいる「樫山農園」専務の樫山直樹さん(38)が務める。若手農家を中心に、地域で栽培面積の広い生産者の元に農地を集積し、農業振興に貢献する。JAは法人に職員1人を派遣する。参加農家の合計面積は70ヘクタール。条件不利地に点在する農地の利活用を進めたいJAと、規模拡大したい農家の思いが合致した。法人は、構成農家が既に取り組む特別栽培米の生産振興の他、酒造好適米や飼料用米を組み合わせ、有利販売に結び付ける。米の乾燥・調製を行うライスセンターを建設することなどで、150ヘクタールまで拡大可能。県の農地中間管理機構を利用し、農地集積を進める。将来的にはトマトの作付け拡大も視野に入れる。JAは、今回の法人設立だけにとどまらず、来年度には野菜の生産法人を立ち上げる予定。直売所と連携して地産地消を進める。収益性の高い野菜と組み合わせた施策で、農家手取りの向上を図り、地域活性化につなげる。JAは今回の法人立ち上げから、地域で勢いのある若手農家との結び付きを一層強めていく。将来的には、若手農家が参画しやすい環境をつくるための経営体づくりを目指す。荒井義之組合長は「自己改革の一歩先を行く事例をつくりたかった。担い手を育てるだけでなく、担い手と共に農業をしていくことが、地域貢献につながる」と強調する。 PS(2017年5月5日追加):アメリカと通商交渉すると、(経産省が発信源かも知れないが)乱暴な規制緩和要求をされる。そのため、「モノを輸出するには相手国の需要にあったモノを作らなければならない」という当たり前の主張ができる国とだけなら、TPPを行っても制度破壊が少なくて済み、それでも、なし崩し的制度破壊が行われないように気を付けることは重要だ。その点、*7-1のオーストラリア・ニュージーランドは、日本とは季節が逆の農業国で農業技術が進んでおり、日本の農業を無作法に侵食する程度は低い。そこで、これらの国と(TPPではなく)FTAを発効し、例えば福島県の帰還困難区域に当たる地域の農業者が移住して農業を行えば、日本の需要にあった農産物を逆の季節に作ることも容易だろう。 なお、*7-2のように、TPP交渉の開始以降、確かに農業政策には理念が見られず、浅薄な通商ゲームの“カード”にされているため、「国内に、何故農業が必要か」について国民的議論を行い、農業を守る政策を行うことが必要だ。 *7-1:http://qbiz.jp/article/108837/1/ (西日本新聞 2017年5月4日) TPP、5カ国先行発効案が浮上 11カ国難航で日豪やNZ 環太平洋連携協定(TPP)を巡り、離脱した米国を除く11カ国のうち、5カ国以上で先行発効させる案が浮上していることが3日分かった。早期発効を主導したい日本やオーストラリア、ニュージーランドなどが検討している。11カ国はカナダのトロントで2日午後(日本時間3日未明)、首席交渉官会合を開き、米国抜きの発効に向けた議論を始めた。日本は最小限の変更による早期発効を主張したが、問題点を指摘する国が相次ぎ、難航は避けられない見通しだ。発効に積極的な国の交渉関係者は取材に対し「5カ国での発効でも構わない」と明言した。5カ国程度の場合、日本などのほか、貿易自由化に積極的なシンガポールやブルネイといった国の参加が想定される。2日の会合では、規模が大きい米国市場への輸出を期待していたベトナムやマレーシアなどが、米国抜きの発効に難色を示したとみられる。日本などは消極的な国に翻意を働き掛ける方針だが、議論が行き詰まると、5カ国以上で先行発効させる案が有力になりそうだ。その場合も、TPPの経済効果は当初の想定より大幅に縮小する可能性が高い。先行発効は、保護主義の動きを強める米トランプ政権に、アジア太平洋地域の貿易や投資ルールの確立を目指すTPPの意義の再認識を促す狙いもあるとみられる。発効させた後、米国を含む残りの国が加われる仕組みも整えたい意向だ。首席会合は2日間の日程で、米国抜きの発効に向けた道筋を模索。3日午前に2日目の議論をし、3日午後に閉幕した。今月20、21日のアジア太平洋経済協力会議(APEC)貿易相会合に合わせて開くTPP閣僚会合の声明案なども協議した。11カ国での発効に消極的なベトナムなどのほか、中南米4カ国の貿易自由化の枠組み「太平洋同盟」に参加しているチリやペルーも積極的な姿勢を示していない。カナダとメキシコは、北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉での米国の出方次第でTPPに集中できなくなる可能性があり、態度を決めかねているとされる。 *7-2:https://www.agrinews.co.jp/p40779.html (日本農業新聞論説 2017年5月4日) 理念薄い通商政策 農業守る国民的議論を 政府が通商政策で農業をどう守ろうとしているのかが見えない。最近では、環太平洋連携協定(TPP)から離脱した米国にあくまで復帰を呼び掛ける従来方針を転換し、米国抜きTPPにかじを切った。米国との2国間交渉を避けたい意向がうかがえるが、戦術論に明け暮れていないか。理念が伝わらない。過去の政権は交渉入り前、農業を守る国民的な合意づくりに注力したが、現政権にはそれがないのだ。理念づくりが急がれる。「多様な農業の共存」。2000年に政府が世界貿易機関(WTO)交渉に際して掲げた日本提案の理念だ。ウルグアイ・ラウンド交渉で農業批判が上がった反省から、国内農業を守る理由を明確に打ち出した。食料安全保障や農業の多面的機能を維持することが消費者にも必要だと説き、公正な貿易ルールを目指す方針を示した。04年に政府がアジア各国との経済連携協定(EPA)交渉に臨んだ際には、「みどりのEPA推進戦略」をまとめた。タイなどは農産物の対日輸出に強い意欲を示していたが、日本は相手国の農村の貧困解消に力を貸すことを提案。アジア地域の農業発展の在り方について、「自由化と協力のバランス」を確保することが重要だとして折り合った。しかしTPPでは、こうした次元の議論がなかった。重要品目の聖域確保を目指した国会決議は、文字通り国会の提案で、政府は決議を自らの理念として語っていない。交渉合意後は、「TPP対策を措置するから国内農業に影響はない」という答弁に終始した。重要品目を一部関税撤廃したにもかかわらずだ。この論法に従えば、今後の交渉でも対策を打てばどう決着しようと問題ない、となる恐れがある。譲れぬ一線をいくら議論したところで、無意味になりかねない。さらに深刻なのは、農業を守る国民合意どころか、農業攻撃が政府内からやまないことだ。国際競争力を高めるべきとの理由で、地域を支えてきたJAに抜本改革を繰り返し迫り、いまだに規制改革論議が続く。農家所得を高める自己改革は必要だが、そうした域を超えた過剰介入と言っていい。産業としての農業論一辺倒で、過去の国民合意で重視した食料安全保障や農業の多面的機能の維持といった視点が軽視されていないか。改めて、WTO日本提案が“農政の憲法”である食料・農業・農村基本法を制定する国民的議論の中から生まれたことを思い出したい。現政権の一面的な農政は、「食料」「農村」という柱を高く評価した“憲法”の理念からもそれているように映る。浅薄な農業観で国内に批判を抱え、通商交渉でどうやって他国とわたり合っていくというのか。これからまた交渉が本格化しようとしている。今こそ政府は、農業を守る理念について懐の深い国民的議論を起こしていくべきだ。 PS(2017年5月7日追加):サラリーマンである士族社会と違って、農漁村では女性も自宅近くでずっと働いており、働けない女性の方がむしろ肩身が狭かったため、*8-1は、これまでの女性の活躍や貢献を過小評価している。そもそも、元祖“道の駅”は、リヤカーで新鮮な野菜や魚を売り歩いていた農家や漁家のおばさんたちだった。しかし、問題は、*8-2のように、重労働していたにもかかわらず女性の地位が低く、女性認定農業者は4.6%、JAの女性役員は7.5%、女性農業委員は7.4%と10%にも届かないことで、これは男性中心・女性蔑視の文化が原因だったのであって女性自身が垣根を作って閉じこもっていたのではないことを、ここで明確にしておく。そして、このように何でも女性のせいにする文化(このため「責任転嫁《責任を嫁に擦り付けること》」という熟語がある)も卒業しなければ、女性の地位は上がらない。 私は、女性が農業や加工に主体的に参入することで、皿の上に盛った料理まで見据え、簡便性や栄養価を考えた無駄のない野菜や惣菜が出てきたと感じている。例えば、大根・小松菜などのつまみ菜は、それらの間引きした苗だが、ミネラル・ビタミン・食物繊維を含み、コラーゲンの生成を促してシミ・そばかすを防ぐビタミンCが豊富で、アリルイソチオシアネートによる血栓防止効果や、グルコシノレートによる解毒作用強化・抗がん効果、食物繊維による整腸作用・生活習慣病予防効果も期待できるそうだ。これから勢いよく成長しようとする植物がこれらを含んでいるのは容易に想像できるが、これまで間引きした野菜を売ることなど考えられていなかったのではないだろうか。買う方は、切る手間が省け、一人前の味をしているつまみ菜を、感心しながら買っている次第だ。 *8-1:https://www.agrinews.co.jp/p40799.html (日本農業新聞論説 2017年5月7日) 若手女性の起業 垣根を越え飛び出そう 個人で起業活動を始める若手女性農業者が増えている。日本農業新聞が4月に始めた企画「の・えるSTAR(スター)」(日曜付「女性のページ」)では、直販、加工はもちろん、子育て女性を雇用する農場の設立、カフェの出店など、多彩に奮闘する女性が登場する。従来の経営スタイルを超え、夢の実現にまい進する彼女たちは常にアンテナを張り、交流を広げる中で一線を越えていく。地域の新たな活力として期待したい。農水省がまとめた2014年度の農村女性による起業数(15年3月現在)は、個別経営が4939件と全体の52%を占め、初めてグループ経営の数を上回った。特に39歳以下の個別経営が165件と2年前の前回調査より21%増えており、若手の躍進が目立つ。女性の社会進出の進展や、インターネット販売、インターネット交流サイト(SNS)の活用により、個人が活動しやすい状況が農村部でも広がっていると言えよう。「の・えるスター」に登場する女性たちを突き動かすのは、「今の状況を変えたい」という率直な思いだ。「もぎ取り体験では1週間しか客を呼べない」「子育てママが働けない」「畑に机を置くだけの直売所では人が呼べない」などである。悩みの解決へアンテナを張り、交流を広げ、時に業種の垣根も越えて連携へ動きだす。伝統野菜の知名度不足に悩む女性は、行きつけのラーメン店主に「レストラン」の夢を語る中から、店舗貸しの提案を受けて弁当販売を始めた。ブドウもぎ取り園の集客を模索する女性は、農水省の「農業女子プロジェクト」に参加、観光サービス会社との提携に乗り出した。県の普及指導員から助成事業の助言を受けた女性は、集客方法から売り上げの見込み額まで示す計画書を作成。審査に通り、直売所出店にこぎ着けた。一歩を踏み出すきっかけとなったのは、自ら動いて得た「つながり」である。もちろん、いいことばかりではない。限定販売に徹したり、投資を抑えたりなどの工夫をしても、経営がうまくいかないこともあるだろう。農村の因習という壁もある。若手女性農業者の発表の場では「農村はまだまだ男社会。女性が営業活動するには制約がある」「家族の理解を得られず家を空けられない女性は少なくない」といった声が出る。それでも、思いがあるならぜひ挑戦してほしい。動けば必ず共感し、支援してくれる人がいるはずだ。今後、経営が発展すれば、新たな課題が出てくるだろう。人手や賃金の確保、多様な消費者ニーズへの対応などである。地域との連携や食育、福祉といった広がりも求められる。柔軟な発想で挑む彼女たちが、地域にどんな活力をもたらすのか楽しみである。思いを実現するチャンスは、いろんなところに転がっているはずだ。 *8-2:https://www.agrinews.co.jp/p40297.html (日本農業新聞 2017年3月5日) 農山漁村女性の日 発展の鍵握る活躍期待 3月10日は「農山漁村女性の日」。この日を前後して、農山漁村女性の社会参画促進や地位向上へ、さまざまな啓発行事が行われる。女性は農業従事者の約半数を占め、農村社会と農業の発展に欠かせない存在だ。農業経営が6次産業化を進める中、生産者であり、かつ生活者と消費者の視点も併せ持つ女性の役割は、ますます重要さを増していくはずだ。その役割の価値を見つめ直すきっかけにしよう。農業経営やJAなどの方針決定の場へ、女性の参画が増えている。農水省の調査によると、女性の認定農業者は2016年3月で1万1241人と前年より429人増えた。12年から毎年400人以上増え続けている。JA女性役員は1305人(16年7月)で、全役員に占める割合は7.5%と前年比0.3ポイント増。女性農業委員も2636人(15年9月)で、全委員に占める割合は7.4%と同0.1ポイント増となった。農水省の「農業女子プロジェクト」も4年目を迎え、農業女子メンバーは、今では500人を超える。企業と提携して商品を開発したり、教育機関と組んで学生に就農を促したりと活動が盛んだ。ことし初めて、農業女子の取り組みを表彰するイベントを開いてPRを強める。ただ、社会参画への進み方は遅い。女性認定農業者が増えているとはいえ、全体の4.6%だ。JA女性役員、女性農業委員も、第4次男女共同参画基本計画で共に早期目標に掲げる10%には届かない。「役員になり外出が増えると、夫が嫌な顔をする」「男性役員ばかりの中で意見が通らない」。JA女性役員からは、そういった不満の声が上がる。一方、組織化せず活動の自由度が高く見える農業女子の集まりの中でさえ「出掛けるには家族の許可がいる」と悩む声を聞く。家族経営が主流で、かつ男性が中心となっている農村社会の閉鎖的な構図が、依然としてうかがえる。女性農業者が真に活躍し、能力を発揮するにはまだ厚い壁があるのだ。家族の後押しはもちろん、活動を受け止める男性らがさらに理解を深める必要がある。日本政策金融公庫が16年に発表した調査では、女性が経営に関与している経営体は、関与していない経営体よりも経常利益の増加率が2倍以上高かった。特に、女性が6次産業化や営業・販売を担当している経営体で、経常利益の増加率が高い傾向にあった。買い物好きでコミュニケーション能力が高い女性だからこそ、的確に消費者ニーズを把握できていることの表れだ。農業収益を増やし、経営発展の鍵を握るのは女性農業者だ。「農山漁村女性の日」が3月10日とされたのは、女性の三つの能力である知恵、技、経験をトータル(10)に発揮してほしい――との願いが込められている。もっと活躍できる社会へ、家族、地域挙げて環境整備を急ぐべきだ。 PS(2017年5月9日追加):*9のように、もちろん小さくたっていい。だから、最初の「図の説明」にも、「耕地面積が小さく大型機械が入りにくいのは、穀倉地帯での生産性や農家所得を下げる原因になっている」としか書いておらず、すべての農業で面積だけが競争力の源泉だとは書いていないのだ。しかし、中山間地などで面積を広げられず、少ない面積で所得をあげなければならない場合は、少量でも利益のあがる付加価値の高い農産物を作ったり、ブランド化や差別化をしたり、他の資源と組み合わせたり、6次産業化したり、環境維持活動をして日当をもらったりなど、さまざまな工夫をする必要がある。その理由は、利益を増やすには、生産コストを下げるか、付加価値を上げるか、その他で稼ぐかしかないからだ。 ただし、日本の財政は苦しく国民の財布は一つであるため、物価を上げ、福祉や教育を減らし、国民負担を増やして、健康な生産年齢人口の人に渡す補助金だけは永久に確保しようなどという甘えはやめて欲しい。つまり、自立できるのなら、違法でない限り何をやってもよいのだ。 *9:http://qbiz.jp/article/108970/1/ (西日本新聞 2017年5月9日) 小さくたっていいじゃないか 雑誌編集部に勤務後、2008年入社。地域報道センター、福岡西支局、佐賀総局を経て経済部。顔つきからか九州出身によく間違われる が、東京出身(八王子ですが)。「成長産業」の候補として国が大規模化や企業化といった「改革」を押し進める農業。そんな農政の方向とは異なる小規模な農業の在り方を考える「小農学会」のシンポジウムが4月下旬に福岡市であった。農家や農業関係者約100人が集まって意見を交わした。この学会、九州の農家や研究者が中心になって呼び掛けて2015年に発足した。シンポジウムは昨年に続いて2回目で、参加者は1回目よりも40人ほど増加。東北や関東からも参加があった。つまり、大規模化を目指す農業に違和感を抱く人が各地に少なからずいるということだと思う。農林水産省の15年度の資料によると、日本の農家1戸当たりの耕地面積は2・5ヘクタール。放牧の畜産などを含む数字とはいえ、EUは16・1ヘクタール、米国は175・6ヘクタール。オーストラリアは2845・9ヘクタールとその差は圧倒的だ。稲作に絞った農水省の14年の資料で比べても、日本のコメ農家の平均は1・4ヘクタール。これに対し、米国の典型的なコメ生産地とされるカリフォルニアでは約320ヘクタールだ。10アール(1反)当たりの生産コストは日本が3・5倍高いという。国は農業の「競争力強化」を掲げるが、世界市場を見据えたとき、どこまでこの差を埋めるというのか。もちろん、ある程度の農地集約や効率化は必要だ。しかし、日本の農地は約4割が中山間地。広大な平地が続く外国とは事情が違う。効率化だけを追求したら、中山間地の農地は不要になってしまう。その先にあるのは、荒れ果てた農地に覆われた農山村の姿だ。「集落を守るためには、小農をつぶさないことだ」。シンポジウムで実践事例を報告した福智町の農家は力を込めた。集落の71軒の農家の中で専業農家は6軒。小規模の兼業農家も、農地を守る立派な担い手だ。特に中山間地の農地は水源かん養や国土保全などの役割も大きい。荒廃すると、その影響は都市部の住民の暮らしにも及ぶということだ。農業は「成長力のある産業」だと思うし、大規模化も一つの方策だ。しかし、進む道はいくつもあっていい。小農学会の活動がこれからどう広がっていくのか注目したい。 PS(2017年5月11日追加): *10-1のように、営農指導の担当者を増員して担い手農家に出向く体制を増強したのは、今後は新規就農者が増え、利益率の高い農業が求められるためよいと考える。また、*10-2のように、①東京農大合格者の女性割合が52.8%と半数を超え、全国大学の農学系学科に在籍する女子学生の割合は2016年度45%で、30年前の1986年度15%と比べて3倍となり ②女性は農村に活気をもたらし、収益性を向上させるとの調査結果もあるため ③農水省女性活躍推進室の久保室長が、「女性が職業の一つとして農業を選べる流れをつくり、農業の成長産業化を図る」 としているのは、やっと与謝野晶子の言う「山動く日ぞ来る」という状態が来たのだと思う。しかし、高等教育を受けても、就職時や就農時に差別されて意思決定できる立場に行けなければ女性が増えた効果は薄くなるため、今後は認定農業者やJA役員等の女性割合を母集団に見合ったものにすべきだろう。 *10-1:https://www.agrinews.co.jp/p40835.html (日本農業新聞 2017年5月11日) 営農指導に人員シフト 資材配送拠点を再編 引き取りは5%引き 大阪・JAいずみの 大阪府のJAいずみのは、購買と営農指導の部門をまたいだ人員配置見直しや資材配送拠点の再編を通じ、農家に出向く体制の強化に乗り出した。資材の予約購買で、従来の配送に加え、引き取り方式を2017年度にスタート。配送にかかっていた購買部門の人員を減らし、営農指導の担当者を増員して担い手に出向く体制を増強した。両部門が連携しながら、農家の所得向上に向けた提案活動に力を入れる。 ●出向く体制を強化 部門連携で提案に力 これまで、資材の配送拠点を岸和田市の営農総合センターの購買店舗に集約していた。ただ管内は4市1町と広域で、配送に往復2時間かかる場所もある。特に繁忙期は配送に労力が割かれ、十分な提案活動ができない課題があった。資材配送の効率化と提案活動の強化に向け、配送拠点を、より組合員に近い各購買店舗に再編。地域ごとの5店舗に引き取りに来てもらう方式を4月に始めた。引き取りの場合、肥料、農薬の価格を5%引きし、農家にとってもメリットがある形にしたことで、7割の組合員が引き取りに転換したという。今後、9割ほどまで高めていきたい考えだ。水稲の資材で引き取りを利用した樋口忠俊さん(69)は「資材価格は収益面にすぐ反映されるので、安くなるのは助かる」と話した。今後は、農家に直接出向いての資材の提案活動や、各購買店舗の品ぞろえの見直し、店内広告(POP)の充実など、配送以外の業務にも注力し、農家のニーズに応えていく考えだ。購買事業の効率化を、営農指導事業の強化にもつなげる。配送などにかかっていた人員を減らし、営農指導担当者を2人増員した。地域農業の担い手に出向くJA担当者(愛称TAC=タック)体制を整え、認定農業者らのサポートを強化する。一連の改革は、地域営農ビジョンに沿った16年度からの第3次総合3カ年計画の営農経済事業改革の柱で、自己改革の一環でもある。JA営農経済部の信貴正憲部長は「農家の所得向上と農業生産の拡大に向けた起爆剤にしたい」と強調する。 *10-2:https://www.agrinews.co.jp/p40828.html (日本農業新聞 2017年5月11日) 農業系女子増加 東京農大の合格者 女性過半に 「現場で活動」「就職の幅」魅力 農村での活躍期待 農業が、今や女子学生憧れの業界に――。大学農学部や農業高校に進学する女性が増え、農学系女子を「ノケジョ」と呼ぶ造語も登場。東京農業大学の今年度の入学試験で初めて、合格者比率で女子が男子を上回った。女性は農村に活気をもたらし、収益性を向上させるとの調査結果もあり、ノケジョ躍進に期待が集まる。神奈川県伊勢原市にある東京農業大学の農場で9日、2年生の農場実習が野菜、果樹、花きの3コースで実施された。女子学生もこの日は、ジャージやつなぎ姿で土や緑と向き合い農作業に汗を流した。実習に参加した田川真子さん(19)は、実家が長崎県の兼業農家。自身が入院した時、祖父が持参した花に感動して農業を継ごうと決意。指導者になる夢を抱き「地元の耕作放棄地を何とかしたい」と笑顔で話す。横浜市の仲田萌夏さん(19)は、農家以外の出身だが、植物の育種に興味を持ち「生花店や花き卸、種苗会社など、植物に関わる仕事に就きたい」と、胸を膨らませる。同大では、2017年度入試で合格者に占める女性の割合が52・8%と男女比が逆転。同大入試センターの藤枝隆センター長は「おそらく開学以来初めて」とみる。これまで農学部は「ダサい」「汚い」とのイメージを持たれていた面もある。しかし近年は「生命科学や環境問題、地方創生など、社会問題の解決手段として認知度が高まってきた」(藤枝センター長)。女性が増える要因について藤枝センター長は「女性は社会のトレンドに対し、男性より敏感で感性がいい」と分析。さらに「座学中心の文系学部より現場で活動する農学部に魅力を感じ、さらに就職面では農業や食品関連、公務員など幅広い選択肢がある」とみる。「ダイコン踊り」に象徴される男性的な同大のイメージは、今や昔話だ。 ●共同参画で成長産業に 女性の力に着目する農水省は、13年度「農業女子プロジェクト」を発足。昨年度からは女性の就農を促そうと、同大と東京都内の女子高校をモデルに新企画に着手した。先輩の女性農業者との交流、農業の魅力発信などを仕掛け、女性の就農意欲と働きやすい環境づくりを進める。同省女性活躍推進室の久保香代子室長は「女性が職業の一つとして農業を選べる流れをつくり、農業の成長産業化を図る」と意欲を示す。もちろん、誰もが就農するわけではない。同大では、多くが食品企業や公務員などへの就職を希望する。同大キャリアセンターは「就農や農業法人への就職意向は増えているが、他の企業と比べ、労働に応じた給与の水準が低いのが課題」とみる。女性が農業経営に参画すると、収益向上につながるとの調査結果もある。日本政策金融公庫によると、女性が経営に関与している経営体と関与しない経営体を比べると、経常利益の増加率が70ポイント高い。女性が営業や販売部門を担当する経営体は関与しない経営体と比べ収益性の伸び率に5倍の差があるとの結果もある。 ●学生割合3倍に 文部科学省によると、全国の大学農学系学科に在籍する女子学生の割合は2016年度が45%で、30年前の1986年度(15%)と比べ3倍になった。農業高校、高校の農学系学科も16年度は49%と、男女比が1対1に。農水省の調査では、学校を卒業して新規就農(雇用含む)した20代以下に占める女性比率も増加。15年は26%と、07年(17%)より大きく増え、若い女性の就農志向は鮮明だ。 PS(2017年5月12日追加):*11は、進歩ではあるもののまだ生産者側の論理で、消費者が購買しなければ販売できないのだということを忘れてはならない。その消費者は、単に「国産か否か」ではなく、①減農薬で有害物質が残っていないか ②有機肥料を使用しているか ③遺伝子組み換えにより害虫も寄り付かなくなった農産物に、人間にとって有害な物質は生成されていないのか ④農産品なら収穫地域 ⑤海産物なら漁獲海域 などを、外食・中食も含めて知りたいと思っている。そして、表示がなく状況がわからなければ、安全性を重視して外国産を選択したり、その産品は使わないという意思決定をしたりする自由もある。そのため、消費者が知りたい情報は表示し、表示されて困るような環境汚染には気を付けるべきなのだ。   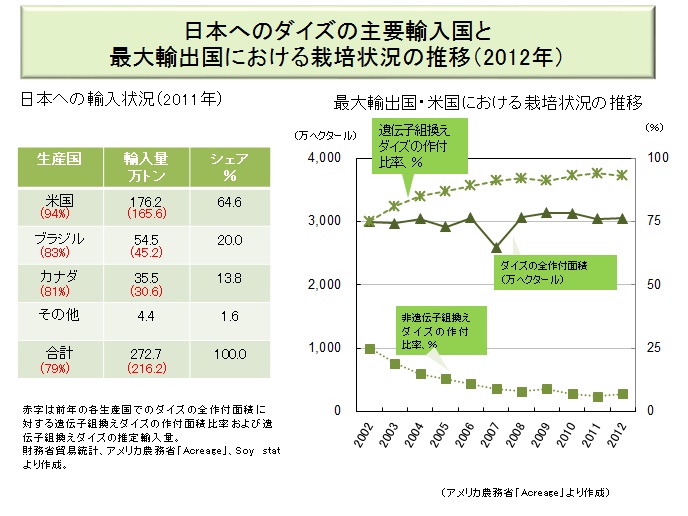  遺伝子組換作物について 農薬について (図の説明:生産コストを下げることができるため遺伝子組換作物の割合は上がっているが、遺伝子組換後の作物が生成する物質を直接食べても人間には無害だという証明はされていないものが多い。そのため、少し高い価格を出しても遺伝子組換でない作物からできた商品を購入するか否かの判断は消費者に任せられるのだが、その判断をするためには遺伝子組換作物混入割合の情報が必要であるにもかかわらず、日本の表示義務はEUと比較して甘い。また、農薬使用量も、日本はヨーロッパ諸国よりもかなり多い) *11:http://qbiz.jp/article/109290/1/ (西日本新聞 2017年5月12日) お総菜や弁当、外食も原産地表示を 九経連が義務化を求める提言 九州経済連合会のワーキンググループ(WG、座長・山尾政博広島大大学院教授)は11日、弁当店などの「中食」と外食について原料原産地表示の義務化を求める提言をまとめた。九経連として30日に承認後、6月にも農林水産省と消費者庁に提出する。提言は、中食・外食が使う食材全てに原料原産地表示の義務化を一律に求めるのではなく「段階的に表示していくことが望ましい」と指摘。義務化の対象食材を牛肉、豚肉、鶏肉、サーモン、ウナギ、マグロ、フグ、ヒラメの八つに絞った。対象事業者については公平を期すため、全ての中食・外食事業者とした。食品の原材料の原産地表示は現在、食品表示法に基づき、生鮮食品と加工食品の一部が義務化の対象となっている。さらに政府は数年後、全ての加工食品で原則的に義務化する方針。ただ、外食と中食の一部は対象外で、消費者の国産選択が難しい状況という。このため九経連は、生産や流通などの関係者を集めてWGをつくり、1月から提言を検討してきた。
| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 12:56 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2016,10,09, Sunday
   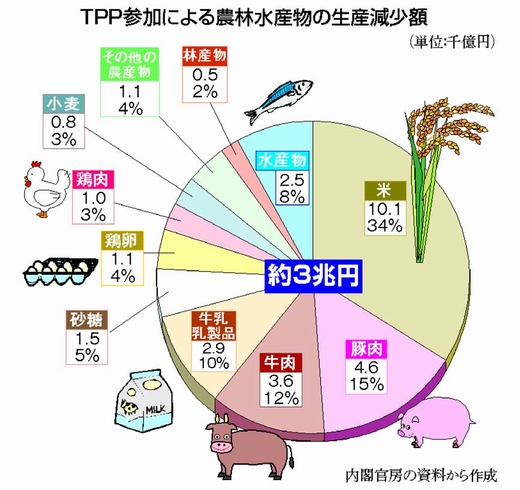 TPPの範囲 TPPに関する 交渉参加に関する TPPによる 政府と野党の主張 決議 生産減少額  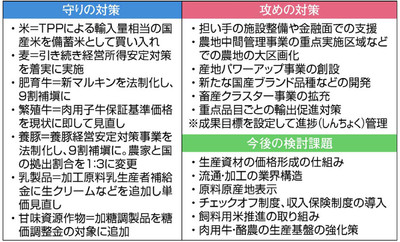 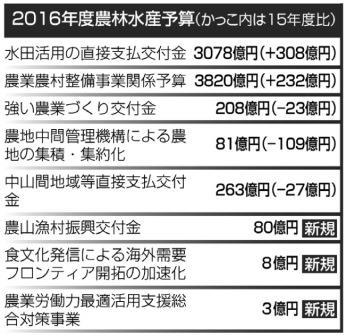 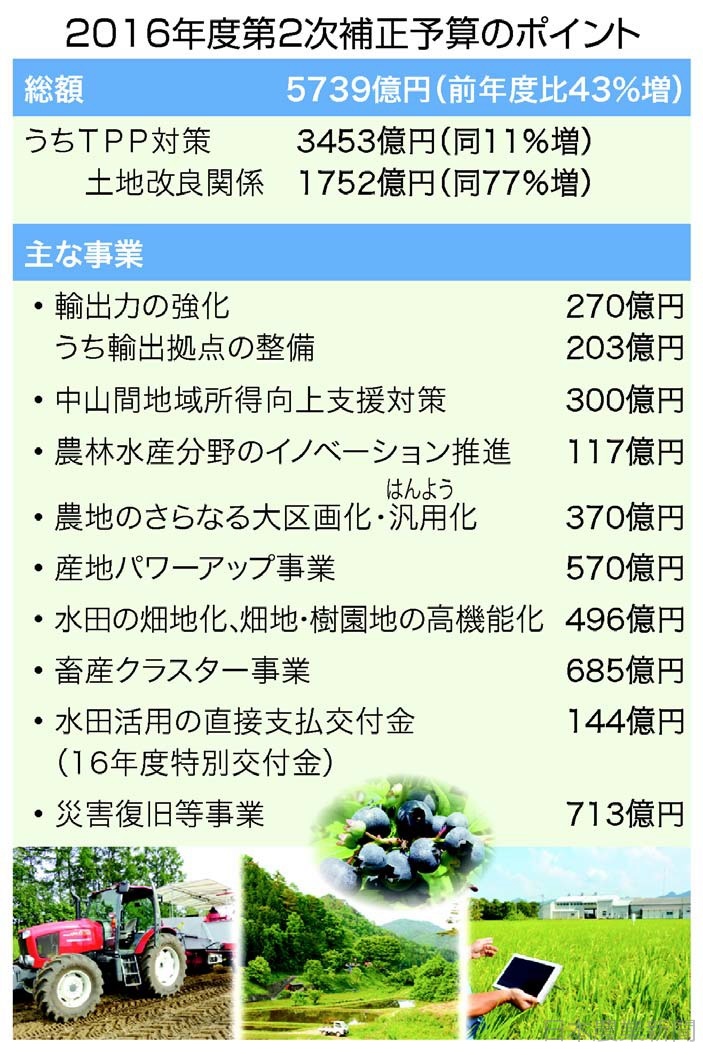 2015.11.26朝日新聞 2015.11.18日本農業新聞 2016/3/30及び10/11日本農業新聞 TPP関連施策 攻めと護りに分けた施策 2016年度の農林水産関係予算 (図表の説明:農業者が海外に販路を広げる方法は多いため、TPPは必要条件ではない。にもかかわらず、国会決議を無視し、農業はじめ日本へのデメリットを過小評価してTPPに驀進するのは問題が大きく、後で後悔しても取り返しがつかない。また、交渉結果とその正確な影響を示して国会で議論されていないため、国民の納得は得られていない。なお、TPP対策として行われる施策は、強い農業を作るためにはTPPとは関係なく必要なものも多く、予算は大きいが無駄遣いになりそうな項目もあるので、全体としてどれだけの予算を農業・TPP対策としてつぎ込み、どれだけの効果があったかの検証が必要だ) (1)「破壊すれば創造に繋がる」というのは甘すぎる *1-1のように、神戸大学の三品教授(専門は経営戦略論)が「破壊を伴う創造行為が産業競争力を左右する」とし、①日本の産業競争力起死回生の鍵は創造的破壊 ②生産現場は強いが大変化には対処できない ③米産業はネットワーク経済で強みを発揮している ④なぜ日本の絶頂期は一瞬で終わってしまったのか ⑤国はもはや産業競争力のけん引役とはなり得ない 等々、書いておられる。 しかし、①については、常日頃から必要な改革・改善はやり続けなければならず(英語は、Continuing improvement)、それを怠って破壊すれば新しいものが創造されると考えるのは甘すぎ、次に創造するものの形が見えていなければ破壊されただけに終わって創造はできない(ピンチをチャンスに変えることはできない)。また、次に創造するものは、当然のことながら実需で裏付けられていなければ成功しない。そして、国が実需を決めることはできないため、⑤のとおり、日本は、国主導で産業競争力の牽引を行う段階ではないのである。 また、②については、製造業は国の重点産業とされ、国民の安い賃金と勤勉さに支えられて国際的にも強かったが、重点産業とされなかった産業や公的資金で支えられてきた産業は生産性が低い。しかし、現在では日本国民の賃金は安くなく、高コスト構造も残ったままで、他に賃金の安い多くの国が製造業に参入してきたため、製造業も比較優位ではなくなったのである。さらに、日本の製造現場は優秀だが、狭い範囲の改善はできても経営意思決定を伴う改革はできないので、国民の人口構成や環境変化に伴う需要の変化に合った製品にシフトする大きな改革は、営業を踏まえた経営からしかできない。 ③は、日本でも経済のネットワーク化は既に進んでおり、そのネットワークは国境を超えているが、ネットワーク化の必要性は個々の経営体で異なり、ネットワーク化を進めさえすればよいわけではない。 また、④の日本の絶頂期が一瞬で終わってしまった理由は、i)日本は共産主義や朝鮮戦争で市場経済において競争相手なき生産者を担うことができたという千載一遇の幸運の下にあったが、その時代が終わり、それらの国々が安い賃金で競争相手として参入してきたこと ii)日本は幸運の下で工業生産において比較優位の輸出国になっていたが、それを他国と異なる技術力・勤勉さを持っている結果と勘違いして傲慢に振舞い、速やかに環境変化に対応せずに蓄えを費やしたこと iii)そのため低賃金で高い生産性を持つ振興国に太刀打ちできなくなったこと iv)それでも産業構造を変えずに同じスキームを続けようとしていること 等であり、政治・行政・経済学者・経営学者・経営者等のリーダーが問題なのである。 このような中、*1-2のように、米国では、次期大統領候補がTPPへの反対姿勢を示して発効への道筋が不透明になっているのに、日本政府は妥協を重ねて交渉をまとめた上、TPPの承認を急いで発効への機運を高め、他国の手続きを後押しするとのことである。もともと、TPPの発案者は日本の経産省で、事実に即してよく考えられたスキームではなく、一体化しさえすればグローバル化して輸出入が増えるという安易な思い付きで締結を進めているため、交渉内容や根拠は、開示して議論するに堪えるシロモノではなく、破壊しさえすれば創造できると考えている恐るべき政策なのである。 そのため、破壊されれば後戻りできない農地を有する農業分野に反対や慎重が多く、与党はTPPで予想されるメリットとデメリット、デメリットに対する対策とその効果を検証して、TPP参加への当否を決めるべきである。なお、*1-2にも、TPPで関税をなくしたり引き下げたりすれば製造業の輸出が活発になるかの如き記載があるが、実際にはTPPにより食品の輸入が増え、食品安全基準における主権を失い、生産コストの高い日本から外国への製造業の製品輸出は増えず、農業で独り負けして食料自給率を減らすだけだと思われる。 それでも、*1-3-1のように、首相が「TPP協定の承認案と関連法案の早期成立を目指し、他国に先駆けて国会で協定を承認して早期発効に弾みをつけるのが、自由貿易で経済発展を遂げたわが国の使命」などとしているのは、古い発想から抜け出せない経産省(経済界はその下部団体)の言いなりになっているためだが、このように役人(官)を使うどころか使われる人が連続して議員に当選して大臣や首相になっていくのが、日本の民主主義の未熟な点である。 また、*1-3-2は、「民進党にも隠れ賛成派がいるため、TPP反対に歯切れが悪い」と書いているが、民進党にも経産省系の議員や農業の育成より低価格の農産物という都市部出身の議員や製造業出身の議員はおり、自民党と同様だろう。しかし、本当に国益を護り、日本の将来に悔いを残さないか否かは、正確に日本語に訳された黒塗りでない資料を基に、影響調査や議論を行ってから判断すべきだ。 (2)農水省がTPP対策に3453億円もの補正予算を計上したが・・ *1-4-1のように、農水省は8月23日、農林水産関係の総額を5739億円とする2016年度第2次補正予算案を自民党の農林関係合同会議に示して了承され、これは、2015年度補正予算を43%上回る大幅増だそうだ。このうちTPP関連対策に2015年度11%増の3453億円、土地改良(農業農村整備)関連事業に同77%増の1752億円を確保したそうだが、TPP対策で総計いくら使って何をし、どういう効果があったのかを、明らかにすべきだ。 また、*1-4-2のように、9月27日、農林水産省は国内外での農産物の販売促進に充てるために、TPP対策の一環として農家から拠出金を集めるという論点を自民党の会合で示したそうだが、原発の販促は首相まで海外訪問して熱心に取り組み、経産省が製造業の販促をするのは無償であるのに、農水省が農産物の販促のためにTPP対策の一環として農家から拠出金を集めるのはおかしい。 (3)TPPは、日本政府(経産省)の主導だが、ぶっ壊すだけであること *2-1のように、TPPの経済効果について、米国は日本への農産物輸出増を約4,000億円と試算し、日本政府は米国以外の影響も含めて日本での生産減少額は1,300億~2,100億円に留まると試算している。品目別では、米国は米の対日輸出額が23%増えるとし、日本は生産減少額は0としており、牛肉も米国は対日輸出が923億円増とし、日本は生産減少額は311億~625億円としているため、日本は影響を過小評価していると言われている。 農水省は、「A.米国の輸出額が増えても他国産と置き換わる場合もあり、米国の輸出増がそのまま日本の生産減には繋がらない」「B.影響を緩和する国内対策を日本の試算に織り込んでTPP対策の効果が発揮されたという前提で生産量は維持できる」「C.米の場合は米国とオーストラリアに合計7万8400トンの国別輸入枠を設けるが、同量の国産米を備蓄で吸収するなどで影響はない」などが差の理由だとしているが、Aは甘すぎ、Bは対策の効果が不明であるうちに試算に織り込むのはおかしく、Cは一時的に備蓄してもそれが出荷される時が必ずあるのでタイムラグにすぎない。 そのため、*2-2のように、JA長野県グループは街宣車でTPPの情報公開等を訴える活動を始め、秋の臨時国会での審議に向けて、「国民への丁寧な説明と十分な審議を求めます」「TPPは農業農村、保険医療、食の安全、雇用など、私たちの生活に大きな影響を及ぼす恐れがあります」などのメッセージを流しているが、これは、TPPによってこれまで作り上げてきた農地や農業を打ちのめされる可能性の高い人たちとして当然のことである。 このような状況の中、*2-3のように、TPPの審議日程が窮屈であるため強行採決の可能性もあるとのことだが、*2-4のように、十分な情報開示もなく、試算は甘く、そのため本当の議論が深まらず、農家も国民も納得していないのである。そのような状況で、TPP発効を見据えた農業“改革”を行うのは、農家にとっても国民にとっても不幸だ。そして、この間、TPPに関わったKey Personは、甘利経済再生担当相(神奈川13区)、斎藤自民党農林部会長(千葉7区、経産省出身)、石原TPP担当相(東京8区)、小泉自民党農林部会長(神奈川11区)など、農業に殆ど関わりのない地域を地元とし、農業に関する知識のない人たちが多いため、この人事で国益を考慮した交渉をしたとは思えない。 なお、小泉自民党農林部会長が強く求めている全農の株式会社化も、そうしなければならない必然性がないため根拠を説明することはできず、農薬や肥料などの生産資材価格を政治が決めるのは市場主義に反している。そのため、自由競争を促すのがあるべき姿だ。 そして、佐賀県の場合は、私が国会議員となった2005年からすぐに、公認会計士として多くの日本系・外資系企業の製造業・サービス業を見てきた目で佐賀県の農業を見て改革案を出し、全農はじめ農協が協力して農業改革にとりかかり、すでに必要な改革は進んでいるのだ。そのため、全農の中野会長(佐賀県の農協出身)が言われる「方向に間違いはない」「改革には既に鋭意取り組んでいる」というのは本当であり、農地の大規模化、機械化、米以外への転作などの改革が遅れているのは東北であって、九州では進んでおり地域差があるため、日本全国を一緒にひっくり返せばよいわけではないのである。 (4)全農“改革”の不合理 全農改革を進捗管理するとして、*3-1のように、資材価格引き下げや農産物の流通構造の改革を議論しているのは、20年以上も時代遅れだ。資材価格は競争の自由度を増せばよく、*3-2、*3-3のように、化学肥料を韓国から買ってコストを下げるだけの発想では、日本の農産物は栄養価も味も悪くなり、農地が荒れることは経験済である。 それよりも、*3-5のように、今まで捨てていたものを有機肥料として活用すれば、農業だけでなく漁業にも役立ち、その地域や作物に合った堆肥をつくることもできる。ちなみに、佐賀県の場合は、肉牛の排泄物を肥料として使い、化学肥料は土壌を計って足りないものを補充するようにしてコスト削減しており、りっぱな作物ができている。そして、これらは、何も知らない人がめくらめっぽうに壊すのではなく、それなりの知識のある人が工夫し、地域を総動員して初めて行い得るものである。 <愚かな“農業改革”> *1-1:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20160920&ng=DGKKZO07382980X10C16A9KE8000 (日経新聞 2016.9.20) 日本の産業競争力(上)創造的破壊、起死回生の鍵、強い経営で攻勢に転じよ 三品和広 神戸大学教授 (1959年生まれ。ハーバード大企業経済学博士。専門は経営戦略論) ポイント ○生産現場は強いが大変化には対処できず ○米産業はネットワークの経済で強み発揮 ○破壊を伴う創造行為が産業競争力を左右 産業競争力という概念が脚光を浴びるようになったのは1980年前後のことだ。日本で製造されたテレビや自動車が欧米諸国の市場を席巻し、貿易摩擦を引き起こし始めた時期にほかならない。ハイテクの最先端に位置する半導体メモリーのDRAMの品質で日本製が米国製を上回るというリポートを米ヒューレット・パッカードが公表、衝撃が走ったのも80年のことだ。予想外の展開に遭遇して、欧米諸国が産業競争力の分析に乗り出したのも無理はない。以下では日本の絶頂期と、それに続く衰退のプロセスに関する一つの解釈を述べる。日本の急伸が世界の意表を突いたのは、日本が保護貿易や為替管理と決別してから15年ほどしか経過していなかったからだ。決別当初は、日本の市場は輸入品に制圧され、企業は買収されるという悲観論が渦巻いていた。それが杞憂(きゆう)だったとわかるころには石油ショックが勃発し企業倒産が相次いだことから、新たな悲観論が日本を覆いつくした。日本製品が貿易摩擦を引き起こすなど、誰も夢想だにしなかったはずだ。競争力という概念が国次元ではなく、また企業次元でもなく、中間の産業次元に設定されたのは、明確な理由による。いくら日本が注目を集めたといっても、農業のように後進性の目立つ産業があった。企業次元に転じてトヨタ自動車を俎上(そじょう)に載せても、やはり住宅のように競争力に劣る事業がある。これに対し日本の競争力が目立った産業では、例外を見つけるのが難しかった。テレビではソニーや松下電器産業(現パナソニック)のみならず下位の三洋電機や日本ビクターですら、自動車ではトヨタのみならず下位のスズキやいすゞ自動車ですら、DRAMでは東芝やNECのみならず下位のシャープや沖電気工業ですら、競争力を発揮した。この事実が世界を驚かせた。しかし日本の絶頂期は長く続かない。いまやテレビとDRAMで産業競争力を誇るのは韓国で、日本企業は事業縮小・撤退を余儀なくされた。自動車でも日産自動車、マツダ、三菱自動車が外資に救済を仰ぐ事態を迎え、もはや産業競争力は死語と化した観がある。なぜ日本の絶頂期は一瞬で終わってしまったのか。そもそも日本の産業競争力は、生産現場や実務組織に根源を置いていた。新卒採用した社員を比較的狭い守備範囲に張り付けることで、真面目に働く人間なら誰でも練度が上がっていく体制を構築し、そこに人事考課と昇進制度を入れて社員の間で息の長い競争を促していく。さらに歩幅の小さな定期異動により社員が思考停止に陥る危険性を排除したうえで、それでも起きかねないミスを稟議(りんぎ)で組織的に潰していく。こうした工夫は、一方で目に見えるモノの設計や製造において大きな威力を発揮するが、他方で目に見えない犠牲を伴った。そこには経営人材の育つ余地がなく、最強の管理人材が経営にあたる結果、大きな変化に対処できなくなってしまったのである。この弱点を米国は鋭く看破して、反攻策を周到に準備した。やれ現地生産、やれ市場開放、やれ内需拡大と高飛車の要求を積み重ね、それに円高誘導やココム(対共産圏輸出統制委員会)規制を絡めて日本の霞が関と産業界を横から揺さぶるというのが、その骨子だ。反攻が一巡すると、仕掛けた米国も驚くほど、日本企業の経営は暴走、または迷走し始めた。その経緯については拙著「戦略暴走」(2010年)で触れている。米国は国際政治力を駆使して、グローバリゼーションの時代を呼び込む策も打っていた。新たに新興国市場の開拓が競争の焦点になると、経営上のボトルネックはモノづくりから販路にシフトする。過去の経験が生きない展開の中で、日本企業は大挙して安易な合弁契約に走り、新興国で悪戦苦闘を強いられた。執拗な波状攻撃を受けて、日本は産業競争力を著しく低下させた。個社次元で耐え抜いたのはトヨタくらいだ。企業経営はモノづくりだけでは成立せず、先行きが不透明になるほど、または多面攻撃を受けるほど、経営が浮沈を分けてしまう。そこに80年代の日本は致命的な弱点を抱えていたことを、われわれは反省材料とすべきであろう。ただし反省材料はもう一つある。反攻に転じた日本を米国が封じ込めるという第二幕が控えているからだ。そこで彼らが武器としたのはインフォメーション・スーパーハイウエー構想だった。これは副大統領になる前のアル・ゴア上院議員が提唱していたもので、最終的にインターネットの一般開放に結実した。米国の起死回生の一手により、世界を支配する原理は「規模の経済」から「ネットワークの経済」に移行した。同じモノを大量につくって安くするより、同じプラットフォームを多くの人々が使うことで生まれる便益が企業間競争の行方を左右し始めると、戦略の要衝は大きくシフトする。チャンスの窓が開いている期間は短く、初動で結果が決まってしまう。プラットフォーム間の短期決戦を制したのはいまのところグーグル、フェイスブック、アップル、アマゾン・ドット・コムなど米国ベンチャー勢に限られる。こうした変化を日本も看過していたわけではない。ハイビジョン映像用のMUSEデコーダー(信号変復調器)、総合デジタル通信網(ISDN)、第5世代コンピューターなど、国が資金を注ぎ込んで技術革新を先導しようとしたが、軒並み失敗に終わった。テレビ産業や自動車産業も日本流の「イノベーション」、すなわち技術革新に再起を懸けたが、薄型テレビやハイブリッドカーは救世主となり得なかった。薄型テレビを主導したシャープは台湾企業の救済を仰ぐに至り、ハイブリッドカーは米国市場で占有率3%台に到達したあたりで頭打ちとなっている。国はもはや産業競争力のけん引役とはなり得ない。社員間の公平な競争を入社後四半世紀も引っ張る日本の大企業も、しかりである。なぜならば、いま世界を席巻するイノベーションは破壊を伴う創造行為で、純然たる技術革新とは一線を画しているからだ。例えばアップルはデジタルカメラ、ビデオ、電子辞書、電卓、携帯電話、携帯情報端末(PDA)など、日本が得意としてきた産業多数を破壊した。破壊の標的となっている産業に身を置く企業が正面から対抗すれば、身の丈が縮むことは避けられない。それどころか過去に雇用した人々を抱え続ける企業は防戦に打って出ざるを得ない。護送船団の先頭に立つ国も同類だ。エレクトロニクスを押し流した創造的破壊の波は、既に自動車や産業機械に矛先を向けている。その次は医療や農業や物流に襲いかかる気配が濃厚だ。守勢をとっても勝ち目は見えない。しからば、破壊の標的を自ら断ち切り、攻勢をとる展開に持ち込むほうが得策であろう。そのためには、まずは実務の強さに経営の強靱(きょうじん)さを併せ持つよう日本企業自体を創造的に破壊する必要がある。一連のガバナンス(統治)改革で、その作業は緒に就いた。水面下では、新たな日本企業を一から興す作業も静かに始まっている。あとはどこに起死回生の一手を求めるかだ。そこで妙手が出れば日本が産業競争力を回復する日は意外と近いのかもしれない。 *1-2:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12589160.html (朝日新聞社説 2016年10月3日) TPPと国会 不安解消へ審議尽くせ 交渉を主導した米国では、民主、共和両党の次期大統領候補がそろってTPPへの反対姿勢を示し、発効への道筋は不透明になっている。そんな中で、日本の国会ではTPP承認案と関連法案の審議が本格化する。政府・与党はTPP承認を急ぐ構えだ。発効への機運を高めて他国の手続きを後押ししつつ、米国で高まる再交渉論を牽制(けんせい)するのが狙いだ。野党側は、農業分野などを懸念する民進党をはじめ反対・慎重論が強い。TPPをめぐっては今春の通常国会で審議入りしたが、議論が深まらないまま継続審議になった。いま、あえて審議を再開するというのなら、今後の暮らしや農業など国内業界に予想される影響について、丁寧にかつ徹底的に議論する必要がある。衆院TPP特別委員会の理事を務める自民党議員が「強行採決という形で実現するよう頑張る」と発言し、辞任する騒動があった。「承認ありき」で数の力を頼むことは許されない。与党は肝に銘じてほしい。そのうえで、野党を含めて望みたいのは、TPPで予想されるデメリットとその対策をしっかりと検証することだ。TPPの対象は幅広い。貿易を活発にするためにモノの関税をなくしたり、引き下げたりする。投資や金融、小売りなどのサービス分野の規制を減らす。著作権や特許、労働に関する規定も各国で歩調を合わせる。通商国家として発展してきた日本にとって、グローバル化への対応は避けられない。ただ、各国が妥協を重ねて交渉をまとめただけに、分野や項目ごとにプラスとマイナスが入り交じるのも確かだ。生活の安全・安心が脅かされないか、国内業界が打撃を受けて雇用が失われないか、といった不安は根強い。代表例が農業だろう。農林水産物の8割にあたる約2千品目の関税が撤廃され、ほかの品目の多くも引き下げられる。海外産の輸入が増えるのは必至で、消費者の食卓への不安のほか、農家の反対も続いている。政府は昨年末にまとめた分析で、コメへの影響について「(直前に決めた)対策の効果で、国内の生産量は減らない」と結論づけた。影響があるから対策を打つのに、順番が逆だ。政府をただし、情報公開を徹底させる。TPPの負の側面と向き合い、政府の対策が必要かつ十分かどうかを考える。そんな国会審議を求める。賛否の結論ありきの論戦は不毛だ。 *1-3-1:http://qbiz.jp/article/95543/1/ (西日本新聞 2016年10月7日) 首相、TPP他国に先駆け承認を 関係閣僚会議で 環太平洋連携協定(TPP)に関する関係閣僚会議が7日、首相官邸で開かれ、協定の承認案と関連法案の早期成立を目指すことを確認した。出席した安倍晋三首相は「他国に先駆けて国会で協定を承認し、早期発効に弾みをつける。自由貿易で経済発展を遂げたわが国の使命と確信している。この国会でやり遂げなくてはいけない」と述べた。承認案と関連法案は衆院特別委員会での審議入りを控えている。閣僚会議ではTPPを担当する石原伸晃経済再生担当相が、会談した各国要人と再協議を行わないことで一致したと報告した。石原氏は会議後の記者会見で、米大統領選で共和、民主両党の候補がTPPに反対していることに関連し「日本が率先して(承認を)行うことで、オバマ大統領による議会承認を後押しする」と述べた。TPPに関する関係閣僚会議は昨年9月以来。政府が機運を高めようとしているほか、経済界からも早期承認の要望が出ている。 *1-3-2:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20161005&ng=DGKKZO08017530V01C16A0PP8000 (日経新聞 2016.10.5)民進、歯切れ悪いTPP反対、党内に隠れ賛成派も 今国会の焦点は、環太平洋経済連携協定(TPP)承認案の行方に移る。野党第1党の民進党は国内の農産物保護が不十分で、自動車産業などへの利点も少ないなどと主張し反対する。党内には推進派もいるが、発言力のある反対派に配慮せざるを得ない党内事情もある。歯切れの悪い印象はぬぐえない。民進党は3月の結党時に「経済連携協定によって自由貿易を推進する」との立場を掲げた。しかし、安倍政権が合意した協定案は「国益が守れたとは評価できない」との考え方に立つ。最大の反対理由は、牛肉・豚肉など農林水産物の重要品目の保護を求めた衆参農水委員会の決議との整合性だ。決議では重要品目を「聖域」と位置づけ、10年を超す段階的な関税撤廃も認めないなどとした。民進党は牛肉・豚肉の大幅な関税引き下げなど「聖域として守れた水準ではない」(大串博志政調会長)との立場だ。自動車分野で得た「成果の乏しさ」も強調する。完成車の対米輸出で関税撤廃まで約30年の期間を設けたことを「関税には触らないと言っているに等しい結果」と批判。政府が輸出増の試算を示せていないことも問題視。大串氏は4日の記者会見で「攻めきったとはいえない」と語った。3つ目は「交渉過程が情報開示されていない」との主張だ。先の通常国会中に示された日米の交渉録は全面的に黒塗りだった。TPP参加判断の根拠となった政府の国内農業への影響試算についても正確性を疑問視している。交渉前に3兆円と見積もった農林水産物の生産額減少が、大筋合意後の農林水産省試算では最大2100億円にまで圧縮された経緯が不透明だとしている。党内事情も大きい。党の見解はTPP推進派と反対派が混在する党内の「最大公約数」で意見を集約しただけとの見方もある。9月末に開いた細野豪志代表代行のグループ会合では「農村ではなく都市部でどう説明するのか」などの意見が相次いだ。自動車関連企業が集積する中部地方選出の議員は「民進党の主張は話にならない」と言い切る。旧民主党政権下では当時の野田佳彦首相(現民進幹事長)が、党内反対派を押し切って関係国との事前協議入りを決めた経緯があり、これも民進党の見解の分かりにくさにつながっている。 *1-4-1:https://www.agrinews.co.jp/p38505.html (日本農業新聞 2016年8月23日) 総額5739億円 4割増 TPP対策に3453億 補正予算農水関係 農水省は23日、農林水産関係の総額を5739億円とする2016年度第2次補正予算案を、自民党の農林関係合同会議に示し、了承された。2015年度補正予算を43%上回る大幅増。このうち環太平洋連携協定(TPP)関連対策には同11%増の3453億円、土地改良(農業農村整備)関連事業は同77%増の1752億円を確保した。24日に閣議決定する。目玉と位置付ける「中山間地域所得向上支援対策」には、300億円を計上した。内訳は、中山間地域で収益性の高い農産物に取り組む際の計画策定に5億円、計画に基づく基盤整備に70億円、施設整備に25億円。また、産地パワーアップ事業と畜産クラスター事業の優先枠各50億円、土地改良事業の優先枠100億円と組み合わせる。輸出力の強化策には270億円。そのうち空港や港に近い卸売市場のコンテナヤード(集積場)など、国内外の輸出拠点の整備が203億円を占める。農林水産分野のイノベーション(技術革新)推進にも117億円を計上する。TPP対策のうち産地パワーアップ事業に570億円、畜産クラスター事業には685億円を計上。いずれも前年度を1割超上回る。また、農地のさらなる大区画や汎用(はんよう)化に370億円、水田の畑地化や畑地・樹園地の高機能化に496億円、草地整備にも94億円を盛り込んだ。この他、飼料用米の拡大に伴い、水田活用の直接支払交付金の財源を144億円積み増す。熊本地震などの災害復旧等事業には713億円を計上した。大幅増額を受け、自民党の西川公也農林水産戦略調査会長は会合で「すばらしい補正予算ができた」と指摘。今月末に概算要求する17年度予算でも、万全な金額を確保したい方針を強調した。. *1-4-2:http://qbiz.jp/article/94797/1/ (西日本新聞 2016年9月27日) TPP対策、農家から拠出金も 強制徴収で販売促進制度を法制化 農林水産省は27日、環太平洋連携協定(TPP)対策の一環として、農家から拠出金を集め、国内外での農産物の販売促進に充てる「チェックオフ制度」の論点を自民党の会合で示した。制度を法制化する場合は、拠出金の強制徴収が避けられないとの考えだ。拠出金の強制徴収は、恩恵へのただ乗りを防止し、制度の公平性を確保するのが狙い。しかし、お金を納付しない場合は、罰則の適用も考えられるため、制度導入には一定の負担を強いられる農家から幅広い理解を得る必要がありそうだ。農水省が会合で示した資料によると、米国などで導入されているチェックオフ制度は、集めたお金の使い道を、国内外での販売促進や、調査研究などに充てると法令で決めている。日本で導入する場合は、強制徴収に見合うお金の使い道や、金額を定める必要があると説明した。お金を強制徴収される農家の同意が不可欠とも指摘した。海外では、法制化の際に品目ごとの業界団体が自ら農家に説明しているほか、業界の任意の仕組みから始め、業界内の合意形成に取り組んでいるとした。会合後、この検討課題を担当する福田達夫衆院議員は記者団に「(日本では)養豚業界が熱心だ。まずは業界がどういうことをやりたいのか提案してほしい。まだ段階として詰まっていないところがある」と述べた。 <TPPは日本政府主導であること> *2-1:http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=37594 (日本農業新聞 2016/5/21) TPP試算 日米で大きな開き 国内対策 効果に疑問も 環太平洋連携協定(TPP)の経済効果をまとめた日米両政府の試算が出そろった。米国は日本への農産物輸出が約4000億円増えるとはじくが、日本は米国以外の影響も含めて生産減少額は1300億~2100億円にとどまると見込む。日本政府の試算には、以前から影響を過小評価しているとの指摘もあり、試算について一層丁寧な説明が不可欠だ。米国の政府機関・国際貿易委員会は18日、TPPが米国経済に与える影響を分析した報告書を出した。品目別に見ると、米国の試算では米の対日輸出額は23%増えるが、日本の試算では生産減少額はゼロ。牛肉も、米国の試算で対日輸出は923億円増えるが、日本の試算では生産減少額が311億~625億円で差がある。米国の輸出額が増えても他国産に置き換わる場合もあるため、輸出増加がそのまま日本の生産額減少につながるわけではない。だが、影響を緩和する国内対策を日本の試算に織り込んでいることが試算の差の大きな理由だ。日本政府がまとめた影響試算では、関税撤廃・引き下げによる国産価格低下の影響だけを見ている。コスト削減などのTPP対策の効果が発揮されたという前提で生産量は維持できるとする。例えば米は、米国とオーストラリアに合計7万8400トンの国別輸入枠を設けるが、同量の国産米を備蓄で吸収することなどを理由に影響はないとする。一方、米国の試算ではこうした対策を織り込んでいない。日米の違いについて農水省は「前提が異なるため、単純に比較できない」とする。TPP対策を行うことが既に決まっているため、対策の効果を入れない状態で再試算する考えはない考えも度々示している。ただ、対策の効果が具体的に見えない段階で試算に織り込むのは適当ではなく「過小評価」との批判が野党から出ている。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p38582.html (日本農業新聞 2016年9月2日) TPP情報開示 十分な審議訴え 街宣車県内リレー JA長野県グループ JA長野県グループは1日、街宣車で環太平洋連携協定(TPP)の情報公開などを訴える活動を始めた。2台の軽トラックが県内JAをリレーして、9日まで各地を巡回。秋の臨時国会での審議に向け、県民にアピールする。街宣車は、荷台に「国民への丁寧な説明と十分な審議を求めます」などと描いた看板を掲示。スピーカーからは「TPPは農業農村、保険医療、食の安全、雇用など、私たちの生活に大きな影響を及ぼす恐れがあります」などのメッセージを繰り返し流す。同日、長野市のJAビルを出発した街宣車は、県東部のJA長野八ケ岳と県南部のJAみなみ信州に引き渡された。今後、各JAが街宣車を引き継ぐ。9日には、同グループと生協など38団体でつくる連絡会が同市内でTPP学習会を開催。街宣車は、この会場をゴールに県内を走る。JA長野中央会は「TPPは農業の問題だけにとどまらない。県民の皆さんに一緒に考えましょう、と伝えたい」(農政対策課)と意気込む。. *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p38540.html (日本農業新聞 2016年8月27日) TPP 審議日程 窮屈に 強行採決の可能性 政府与党 環太平洋連携協定(TPP)承認案の審議が、9月召集の臨時国会で再開する。11月8日の米大統領選までの衆院通過を目指す政府・与党。だが民進党代表選の影響で召集日は26日にずれ込む見通し。審議日程が窮屈になり、強行採決の可能性もある。政府・与党は、臨時国会を9月13日に召集し、TPPの審議時間を確保する構えだった。だが民進党代表選が15日に設定され、26日召集で調整せざるを得なくなった。同党の新執行部が決まらなければ、事実上、審議が進められないためだ。約2週間のずれ込みだが、政府・与党には「かなり痛い」(政府筋)。米大統領選候補がTPP反対を強調する中、「大統領選までに衆院を通過させ、日本が承認する見通しを付ける」(同)ことで、米国の早期批准を促す考えがあるからだ。26日召集になれば、2016年度第2次補正予算案の審議などを優先し、衆院TPP特別委員会の審議再開は、10月中旬にずれ込むとみられる。参院選でTPP反対を掲げた民進、共産などの野党の厳しい追及は必至で、11月8日までに衆院通過が「微妙」(自民党幹部)な情勢だ。円滑な審議に向け、自民党は臨時国会で衆院TPP特別委員長を西川公也氏から塩谷立氏に代える。通常国会では、西川氏の著作とされる「TPP内幕本」が審議停滞の一因となったためだ。審議日程を野党と調整する筆頭理事も森山裕前農相に交代し、万全を期す。与党側は、衆院通過までに、通常国会(約23時間)と合算して40時間程度の審議を想定する。だが野党はゼロからやり直すとの考え。8月に就任した山本有二農相らのTPPへの答弁能力も未知数で、政府・与党内には「与党だけで強行採決もやむを得ない」との指摘もある。 *2-4:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/359145 (佐賀新聞 2016年9月24日) 「TPP議論不十分」 全農・中野会長、国に疑問 環太平洋連携協定(TPP)の承認案・関連法案審議が焦点となる臨時国会(26日召集)を前に、全国農業協同組合連合会(全農)会長を務める中野吉實JA佐賀中央会会長は、佐賀新聞社のインタビューに応じた。早期成立を目指す政府、与党の姿勢に対し、「議論は尽くされておらず、国の主張を農業関係に押し付けようという風潮があるようだ」と疑問を呈した。通常国会で政府がTPP関連文書をほとんど黒塗りで開示したことに触れ、「黒塗り資料では議論は深まらない。農家も納得していない」と批判し、十分に議論するようくぎを刺した。TPP発効を見据えた農業改革の一環で、小泉進次郎自民党農林部会長が強く求めている全農の株式会社化には、海外企業から買収される懸念を示し「株式会社化の強制は断固反対と言わざるを得ない」と明言した。農薬や肥料など生産資材価格を巡る自民党プロジェクトチームとの議論については、「改革に後ろ向きと言われるが、自己改革には鋭意取り組んでいる」と強調した。 <全農“改革”> *3-1:https://www.agrinews.co.jp/39043?page=2 (日本農業新聞 2016年9月30日) 全農改革を進捗管理 来週にも提言 業界再編へ法整備 規制改革推進会議 政府・与党は11月に取りまとめる環太平洋連携協定(TPP)中長期対策の一環で、資材価格引き下げや農産物の流通構造の改革を議論している。29日にはこうした農業改革を集中議論する未来投資会議の「ローカルアベノミクスの深化」会合と規制改革推進会議の農業ワーキンググループ(WG)が合同会議を開き、WG座長の金丸恭文フューチャー社長が検討方向の試案を示した。試案は、両会議による提言のたたき台となる。試案では、資材価格の低減などへ関連企業の競争を促すため、業界再編が必要だと強調。再編を起こす「重要なツール」として、全農の資材の仕入れや農産物販売の改革を位置付けた。改革を促すため、規制改革推進会議による農協改革の進捗管理の一環として、全農の組織体制の見直しや役職員の意識改革、外部人材の活用などを重視して管理していくとした。業界再編に向けては、税制支援などを措置する産業競争力強化法や、公正取引委員会の監視強化など独占禁止法の活用も促した。改革の着実な推進を担保する法制度を、次期通常国会で検討することも求めた。両会議の提言を受け、自民党農林水産業骨太方針策定プロジェクトチームを中心に、具体策の検討が加速する見通しだ。一方でJAグループも、全農が扱う肥料の銘柄数を絞り込むことで工場の集約化につなげるなど、業界再編を目指す方針を既に掲げている。ただ、政府・与党内には、改革の踏み込みを求める声も強い。11月のTPP中長期対策の取りまとめ以降も、規制改革推進会議の進捗管理を通じて、全農を中心とするJAグループの改革の実践に、厳しい目が向けられる構図が続きそうだ。. *3-2:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20160907&ng=DGKKZO06959210X00C16A9MM8000 (日経新聞 2016.9.7) 農業改革、肥料値下げ促す JA全農が高コスト批判に対応 銘柄数半減 全国農業協同組合連合会(JA全農)は、国際的にみて割高との批判が強い肥料や農機の生産コスト削減策を打ち出す。コメ農家が使う肥料の銘柄をいまの約2000種から半分に減らし、1品種あたりの生産量を増やして値下げにつなげる。肥料や農機など農業資材をめぐっては、環太平洋経済連携協定(TPP)への対応策を話し合う自民党のプロジェクトチーム(委員長・小泉進次郎農林部会長)がJA全農に値下げを強く求めている。JAグループが近く公表する改革案は、TPP参加をにらんで農業の高コスト体質の改善を迫る政府・自民党の批判をかわす狙いもある。国内でコメ向けの肥料を製造するメーカーは約3000社にのぼる。JA全農はこうしたメーカーから肥料を買い取り、地域の農協を通じて農家に販売している。JA全農が扱うコメ向け肥料は地域限定品など約2300種に及ぶ。成分や効果が似通った製品が異なる銘柄で売られているケースも目立つ。肥料メーカーは少量多品種の生産体制をとるため、JA全農への卸価格はどうしても高くなる。JA全農はメーカーから買い取る銘柄の数を「半分あるいはそれ以下」(幹部)に抑えて卸価格の引き下げを促す。肥料代が安くなれば、農家の生産コストは下がる。農林水産省も銘柄数の増加に歯止めをかける制度改正を検討する。JA系の肥料メーカーのなかには銘柄の削減でJA全農との取引が減り、経営が苦しくなるところも出てくるとみられる。「業界再編のきっかけになる」(業界関係者)との見方は多い。農水省によると、韓国のある肥料メーカーは生産能力136万トンに対し、銘柄数は52。一方、日本のあるメーカーでは生産能力31万トンに対し、銘柄数は500近い。日本の肥料価格は平均で韓国の2倍に達している。JA全農は生産コストの2割を占める農機でも調達方法を見直す。大規模な農業法人と連携し、安価なコンバインやトラクターを農機メーカーから共同購入する仕組みをつくる。大規模な農業法人はコスト削減を狙って簡素な農機を購入する傾向があるが、JA全農での扱いは不十分だった。また農薬では開発費を抑えたジェネリック農薬の発売を検討する。 *3-3:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20161004&ng=DGKKZO07931020T01C16A0KE8000 (日経新聞 201.10.4) 農業の効率化と地方創生(3)化学肥料で穀物単収6~10倍に 東京大学准教授 川島博之 第2次世界大戦が終わったころから農業の効率が飛躍的に向上しました。効率向上の要因は農薬、農業機械など色々ありますが、最大の功労者は空気中の窒素から作る化学肥料です。農作物の生産量を増やすには、(1)農地面積を広げる(2)単位面積当たりの収穫量(単収)を増やす――の2つの方法があります。人類が農業を始めてから長い間、単収はほぼ一定でした。人類は農地面積を広げることに注力し、それが土地の奪い合いにつながりました。現在でも領土問題は戦争の最大の原因ですが、それは人類に農地が重要だというメッセージが刻み込まれているためでしょう。19世紀に土壌中の窒素含有量を増やすと、穀物単収が増えることが分かりました。欧州では農地に窒素を供給する方法として、チリで採掘された硝石が使われました。しかし、地下資源には限りがあるため、19世紀末の欧州では、硝石を掘り尽くすと食料危機になると心配されていました。その悩みを解決したのが空気中の窒素から化学肥料を作る技術です。20世紀初頭のドイツで開発され、開発者の名前にちなんでハーバー・ボッシュ法といいます。空気が原料なので、いくらでも生産できます。化学肥料は著しい効果を発揮しました。人類が農耕を始めてから長い間、穀物単収は1ヘクタール当たり1トン程度でした。一生懸命に耕し、苦労して堆肥や厩肥(きゅうひ)を投入しても、同2トン程度にしかなりませんでした。それが、化学肥料を投入すると目を見張るような速度で増加し、現在、先進国では穀物単収は同6~10トン程度になっています。あまりにも化学肥料が効いたため、化学肥料に不信感を抱く人々もいます。副作用もあると考え、従来型農法である有機農業に取り組んだりしています。しかし、化学肥料なしでは、現在の世界の73億人もの人口を扶養できません。もし、化学肥料を全く使用しなければ、地球上にはその半分ぐらいの人々しか生きることができないでしょう。一方、アフリカなどの発展途上国でも先進国並みに化学肥料が使われるようになれば、地球は現在の2倍の人口でも楽に扶養できると思います。 *3-4:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B3%B6%E5%8D%9A%E4%B9%8B 川島博之氏の略歴のみ引用:東京都生まれ。1977年東京水産大学卒業、1983年東京大学大学院工学系研究科博士課程単位取得の上退学。東京大学生産技術研究所助手、農林水産省農業環境技術研究所主任研究官、ロンドン大学客員研究員などを経て、現在、東京大学大学院農学生命科学研究科准教授。 *3-5:http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=37949 (日本農業新聞 2016/6/18) 大地と海 連携 ホタテの天敵・ヒトデを堆肥化 北海道・JAつべつ×網走、西網走2漁協 漁師の悩みを農家が解決する試みが、北海道北東部の津別町で始まっている。キーワードは「ヒトデ」。特産のホタテを食い荒らす天敵を、堆肥にして作物を育てようという作戦だ。ヒトデの処分費用、堆肥の原料コスト双方が削減できる。堆肥化に挑むのはJAつべつ。来年から本格的に畑作に利用する。漁協と共に川の水質を守る植樹活動にも取り組み、大地と海をつなぐ活動を展開する。農家と漁師が手を組んだのは、網走湖の汚染問題が背景にある。湖には網走川の淡水が流れ込んでいるが、2001年の台風で農地の土砂が流出し、湖が汚染されて真っ赤になり、漁業を脅かした経緯がある。そこでJAと網走、西網走2漁協が話し合いを重ね、11年に「網走川流域農業・漁業連携推進協議会(だいちとうみの会)」を立ち上げ、流域の環境保全に乗り出した。「農業と漁業がしっかり手を組んで地域を支えていかなければならない。われわれには上流域としての大きな責任がある」と、同協議会副幹事長を務める酪農家、山田照夫さん(69)は意義を強調する。双方の問題解決につながる試みの一つが、ヒトデの堆肥化だ。ヒトデはオホーツク海の特産であるホタテを食べるため、漁協にとっては天敵。年間600トンものヒトデが大発生することもあり、漁師の悩みの種だ。そこでJAは13年から、ヒトデの堆肥化を考え始めた。ホタテと共に水揚げされた20トンほどのヒトデを搬入し、樹皮を発酵させたバーク堆肥を混ぜることで、完熟堆肥を作ることに成功した。試しにテンサイの畑に施用したところ、収量や品質は問題ないことが分かった。漁協は従来、ヒトデの処分を1キロ15~20円で業者に頼んでいた。600トンを処理すれば、費用は最大で1200万円にも上る。堆肥化が軌道に乗れば、この膨大な処分費用の削減につながる。JA側も堆肥の原料コストを削減でき、互いにメリットになる。JA営農部の有岡敏也部長は「ジャガイモなど他の作物にヒトデ堆肥を使っても、収量や品質には問題ないだろう」と手応えをつかんだ。漁師の間では「ヒトデには虫が嫌がる成分がある」と言われており、堆肥にもその効果が表れればさらにメリットが生まれる。今年は秋にヒトデを搬入して堆肥化し、17年産の作付けから本格活用する計画だ。 ●植樹、清掃も 協議会は毎年、植樹活動にも取り組んでいる。「大地と海をつなぐ植樹」と題し、14日には農家と漁師ら130人が参加し、アオダモやハンノキなど300本以上を植えた。こうした活動の結果、網走川流域の網走市、美幌町、大空町の農業関係者も集まる場になり、女性部からも参加する。26日には4市町で流域の一斉清掃事業も開かれる。協議会の新谷哲章幹事長は「土壌環境や水質への視線は今後さらに厳しくなってくる。漁業、農業が経済を支える町が多い道内で、モデルとなる取り組みにしていきたい」と先を見据える。 PS(2016.10.10追加):*4に、「①酪農家が、補助金の関係で原料生乳の販売先を自由に選べない」「②企業による農地の実質所有解禁は国家戦略特区だけの例外にしてはならない」「③生産性の低い農業資材メーカーの再編などを支援する新法の制定を提言した」「④重要なのは公正で自由な競争が安くて優れた商品やサービスを生む環境を整えることだ」と書かれているが、このうち①は、農業者の政治活動を農協が行うのではなく、農業者の政治連盟を作ることで解決するだろう。また、②は農業生産法人を作ることにより既に解決されており、本当に農業をやろうとする企業は、JR九州のように農業生産法人の子会社を作って既に農業に参入している。にもかかわらず株式会社でなければ農業ができないなどとする企業が農業に参入することは(理由を長くは書かないが)むしろ弊害の方が大きい。さらに、農業機械価格が高すぎるのは問題だが、その原因は機械メーカー等の独占・寡占であるため、③のように政府がメーカーの再編などを支援する新法を制定するのは逆効果であり、④のように公正で自由な競争を行って外国からでも自由に機械や資材を購入できるよう、公正取引委員会がしっかり働くのが筋である。 *4:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20161010&ng=DGKKZO08196920Q6A011C1PE8000 (日経新聞社説 2016.10.10) 自由な競争で農業の成長力を高めよう 安倍晋三首相は今国会の所信表明演説で、生産から流通、加工まで農業分野の構造改革を進める決意を表明した。農業の競争力を高めるために肝心なのは、成長を阻む旧弊や横並びの保護策を見直し、企業の新規参入を活発にして創意工夫を引き出すことだ。改革を加速してもらいたい。安倍政権は農業協同組合制度の改革などで一定の成果をあげた。しかし、農業分野には旧態依然とした制度が残る。たとえば酪農家は事実上、原料生乳の販売先を自由に選べない。50年も前に制定された暫定措置法が存続し、生乳を原則すべて地域ごとの「指定団体」に出荷しないと補助金がもらえない仕組みだからだ。政府の規制改革会議は5月にまとめた答申で規制緩和の結論を先送りしている。新たに発足した規制改革推進会議は、今秋まとめる改革策で自由な競争環境の実現を提言してほしい。農林水産省の統計でコメの生産額は2014年で1兆4370億円、生乳は6979億円と農産物の1、2位を占める。しかし、03年と比べるとコメの生産額は38%減り、生乳も2%弱の増加にとどまる。トマト(22%増)やレタス(31%増)に比べ成長力は劣る。競争力の弱い農産物は手厚い保護で守る。そんな競争を排除する横並びの保護政策が成長を阻害してきた結果だ。これでは将来の展望が描けない。企業による農地の実質所有解禁は国家戦略特区だけの例外にしてはならない。成長を後押しする競争には企業の新規参入が不可欠だ。規制改革推進会議と未来投資会議は6日に合同会合を開き、生産性の低い農業資材メーカーの再編などを支援する新法の制定を提言した。農業資機材の価格や農産物の流通コストの高さが農業所得の拡大を阻む要因とみており、再編で効率化を促す狙いがある。非効率な企業の再編は必要だ。ただ、より重要なのは公正で自由な競争が安くて優れた商品やサービスを生む環境を整えることだ。これまで大部分の農家は肥料や農薬、農業機械を地域の農協から購入してきた。一般の消費財のように価格の安さやサービスの内容を農家に訴求し、競う環境が実現すれば再編はおのずと進む。農業分野に自由な競争を阻害する構造問題はないか、公正取引委員会もこれまで以上に目を光らせてほしい。 PS(2016.10.10追加):*5のように、麻生財務相は、「①自由貿易には大いなる意義があると強調し」「②保護主義の広がりに強い懸念を示し」「③過度な悲観論に陥ることなく、潜在成長率の引き上げに正面から取り組むと指摘した」そうだが、グローバル企業は、既に自由貿易ではなく相手国に生産及び販売拠点を作っているので、①は30年ほど古いテーゼだ。しかし、自国の柱になる産業を保護・育成することは必要であるため、②は必ずしもそうとは言えない。さらに、③は、何もないところから出発する開発途上国と異なり、先進国のGDPの成長率が低いのは当然であって、現在の日本は、国民一人一人の豊かさ(購買力平価による一人当たりGDP)を比較して、これを増加させなければならない時期なのである。そのため、財務相がこのような発言をすることこそ、悲観要因だ。 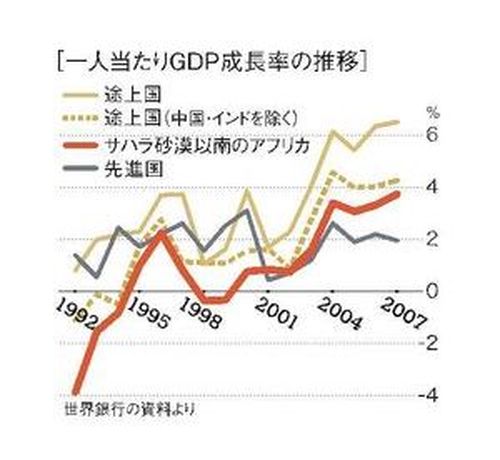 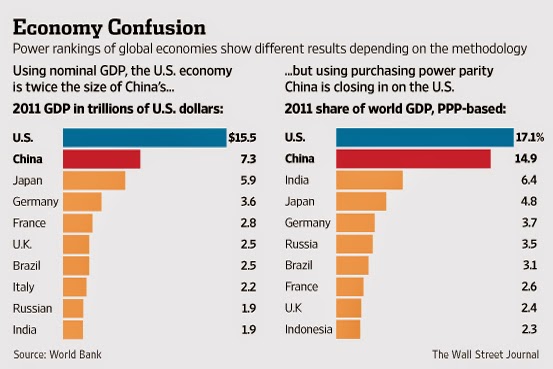 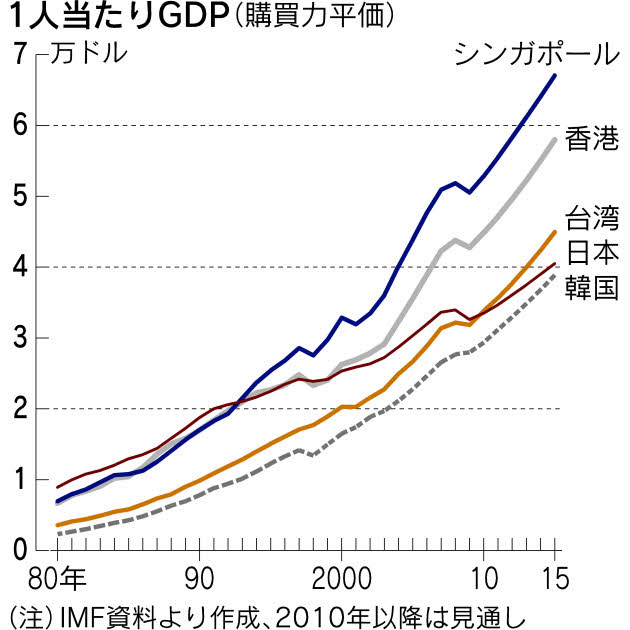 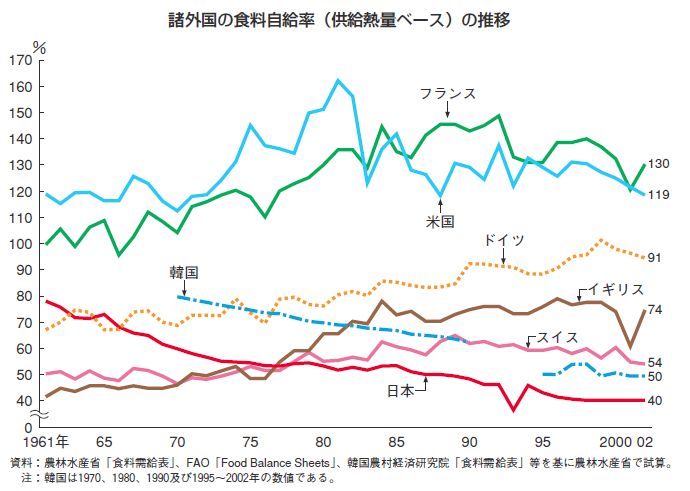 発展段階別 $と購買力平価による アジアの購買力平価による 先進国の 一人当たりGDP成長率 GDP比較 一人当たりGDP 食料自給率推移 (グラフの説明:先進国ほど「一人当たりGDP成長率(「一人当たりGDP」ではない)」は低い。また、物価の高い日本では購買力平価によるGDPの順位が$ベースより低く、アジアの中で比較しても日本の購買力平価による一人当たりGDPは高くない。さらに、先進国の中で、日本の食料自給率は著しく低い) *5:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20161008&ng=DGKKASDF08H02_Y6A001C1MM0000 (日経新聞 2016.10.8) TPP推進を確認 麻生財務相、米長官と会談 麻生太郎財務相は米ワシントンで7日、米国のルー財務長官と会談し、環太平洋経済連携協定(TPP)の実現に向けた取り組みを互いに進めていくことを確認した。麻生財務相は会談後、日銀の黒田東彦総裁と開いた会見で、「自由貿易には大いなる意義がある」と強調し、保護主義の広がりに強い懸念を示した。麻生財務相は会見で、過度な悲観論に陥ることなく「潜在成長率の引き上げに正面から取り組む」とも指摘した。働き方改革などの構造改革や生産性の向上につながるインフラ整備などを進める考えを表明。さらに、デフレ脱却を確実にするためには「継続的に賃金を上昇させることが極めて重要だ」と述べた。20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議では金融緩和が長期化することの副作用が議論された。黒田総裁は会見で「金融政策だけでバランスのとれた成長につながるというのは難しい」と指摘。「財政政策、構造政策といったあらゆる政策手段を用いてバランスのとれた成長を実現していくという考え方が共有された」と説明した。 PS(2016年10月13日追加):*6-1のように、JR九州ファーム(本社:佐賀県鳥栖市)が長崎県松浦市で大規模にアスパラガスの生産を行い、一般主婦・警察官・建築会社出身の人を雇用しているのは面白いが、環境意識の高さを示す洗練されたJR九州のロゴがあった方が世界で周知されやすいと考える。また、雇用された主婦は需要者の要望をキャッチしやすく、建築会社経験者はあちこちの現場で人や機械を廻して仕事を進めるのが得意で、警察官経験者は警備を任せられ、元JR職員は時間に几帳面など、前職による得意技もありそうだ。なお、*6-2で、JR九州の青柳社長が、「今後、鉄道と相乗効果のある事業に進出したい」と言っておられるが、その地域はリアス式海岸の美しい場所であるため、農林漁業の現場自体を鉄道と相乗効果のある観光地にすることもできそうだ。また、「赤字ローカル線を絶対に廃線にしないとは言い切れない」とも言っておられるが、駅ビルや高架下を充実して使うことにより便利な街づくりを進めることができ、そこから膨大な収益を上げることもできるため、JR九州の場合は、まず既に所有している資産をスマートに有効活用するのが最も安全確実な収益獲得方法だと思われる。また、赤字ローカル線は赤字になる理由があるため、その理由を精査して解決するのが資産を壊さない方法だ。 *6-1:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/364999 (佐賀新聞 2016年10月11日) JR九州、長崎・松浦で営農 アスパラ特産に 長崎県松浦市にあるJR九州ファーム(鳥栖市)の農場で今年、アスパラガスが初めて収穫された。同社は九州最大のアスパラガス農場にしたい考えで、担い手不足に悩む地元は企業的な農業経営を通じた生産力アップ、特産品化に期待している。ただ、外部からの参入を不安視する声もあり、同社は地域との連携を密にする姿勢を打ち出している。 ▽自慢 長崎県のアスパラガス生産量は全国4位。北部に位置する松浦市は土壌に豊富なミネラルを含み、ほどよい甘みと苦みが特徴だ。しかし、高齢化で栽培農家が減少。JR九州ファームは昨年5月、市と農業参入に関する協定を結んだ。海に近い地区に土地を借り、アスパラガス用のハウスは現在12棟。この秋から23棟に拡張し、栽培面積は3・3ヘクタールになる。別に露地栽培でブロッコリーも育てる。今年は10月までにアスパラガス25トンの収穫を予定。2019年には約100トンに増やすのが目標だ。農業経験のない主婦、元警察官ら地元の17人を採用。建築会社から転身した松本敏光さん(61)は「農業をしたいと思っていた。自分が手入れしたものを食べてもらえることが幸せ」と話す。同社は地元のJAながさき西海から資材や営農指導の支援を受け、収穫した約7割を出荷。残りは福岡市にある直営店「八百屋の九ちゃん」などで売る。 ▽期待 JR九州は10年4月、大分市でニラ栽培に参入したのを皮切りに、九州各地で営農を開始。長崎県への参入は松浦市が初めてだ。松浦市のアスパラガス農家は減少傾向にあり、市の担当者は「大規模経営で産地強化と雇用拡大が見込める。ブランド化を進め、特産品にしてほしい」と期待する。一方、地元には「国土の保全も担う農業と利益を追求する企業は水と油。企業はもうからないと撤退する」と心配する声もある。今回の参入では第1希望だった土地の関係者に反対され、場所を変更。現在の農場でも地元住民から夏場のホタルを守るよう求められたため、蛍光灯などでガを駆除する「防ガ灯」の使用も諦めた。それでもJR九州ファーム松浦事業所の森崎崇所長(40)は「農業も鉄道も地元との関わりがあって成り立つ」と地元の声を尊重する方針を強調。地権者との交流にも積極的に参加しており「不安を抱く地域の人々に寄り添い、信頼につなげたい」と話している。 *6-2:http://qbiz.jp/article/95799/1/ (西日本新聞 2016年10月13日) 上場後、赤字ローカル線「絶対に廃線にしないとは言い切れない」 JR九州青柳社長に聞く 25日に株式上場するJR九州の青柳俊彦社長が12日、報道各社の共同インタビューに応じ「上場することで、スピーディーで大胆な展開ができるようになる。今まで取り組んでいなかった事業にもチャレンジしていきたい」と述べた。主なやりとりは次の通り。 −上場で何が変わるか。 「100%株主だった独立行政法人の鉄道・運輸機構から解放される。責任は重くなるが、経営判断のスピードは速まる」 −上場後、鉄道事業の収支が改善する見込みは。 「JR九州グループにとって永遠の課題だ。収入の増加とコスト削減を、これまで以上に積極的に展開していきたい」 −赤字ローカル線の運営についての考えは。 「昨年、国会で上場後も路線を維持することを宣言した。効率化に向けて積極的に廃線にする考えはない。ただし、絶対に廃線にしないとは言い切れない。路線の使命が終われば検討せざるを得ない」 −今後、新たにチャレンジしたい事業は。 「イメージはまだないが、鉄道との相乗効果がある事業が望ましい」 −海外での事業展開はどう進めるか。 「アジアでマンションやホテル事業をしたいと考えている。東京に進出してきたように、海外にも出て行きたい」 PS(2016年10月14日追加):JR九州の豪華寝台列車「ななつ星in九州」は、車両が豪華であるだけでなく、食事や列車内の調度もその地域トップの産物を使っているのが人気の秘密だ。また、*7のように、JR西日本のトワイライトエクスプレス瑞風が「美しい日本をホテルが走る」をコンセプトにしているのも魅力的で、乗り換えなどの手間なくポイントとなる地域を周遊できるメリットがある。しかし、ななつ星も、3泊4日コースで1人当たり最高95万円などという超豪華コースだけでなく、同じコースをホテルを使って周遊した場合と同程度の金額のコースも作った方が日本人や外国人の観光客が増えると思われる。 *7:http://mainichi.jp/articles/20161014/k00/00e/020/176000c (毎日新聞 2016年10月14日) JR九州運行開始から3年 予約20倍超の人気 JR九州の豪華寝台列車「ななつ星in九州」が運行開始から15日で3年を迎える。高額な乗車料金にもかかわらず、予約平均倍率は20倍超の人気ぶりを継続。上場を控えるJR九州の知名度向上にも大きく貢献した。一方、来春にはJR東日本や西日本も豪華寝台列車を投入予定で、各社間の競争が激しくなりそうだ。「高い価格でも価値を感じていただけている」。当初から運行に携わるJR九州クルーズトレイン本部の仲義雄次長は手応えを語る。ななつ星には今年9月末までで、延べ7297人が乗車。直近の予約平均倍率は24倍に達し、再乗車を希望する客も2割に上っており、人気は衰えない。支持される理由は豪華さだけでなく、きめ細やかなサービスにある。訓練を重ねたクルー(乗務員)が最高の笑顔で迎え、沿線住民も盛んに手や旗を振って歓迎する。温かいもてなしに乗客は感激し、最終日には多くが涙を流して列車との別れを惜しむ。ななつ星を追いかけるようにJR2社も来春、豪華寝台列車を相次いで投入する。JR西日本のトワイライトエクスプレス瑞風(みずかぜ)は「美しい日本をホテルが走る」がコンセプト。車両には風や香りを体感できる展望デッキを設ける。JR東日本のトランスイート四季島(しきしま)は、高級車フェラーリを手がけた奥山清行氏がデザインを担当した。制作費50億円の車両は、淡い金色の外観やガラス張りの展望車が特徴だ。いずれも富裕層や外国人客の獲得を狙う。両社の動きについて、ななつ星の生みの親であるJR九州の唐池恒二会長は「鉄道業界の刺激につながったことは素直にうれしい」とし、ライバル登場についても「(豪華寝台列車に)乗りたいと思う層が拡大する。私どものお客さんが奪われるという危惧は全くない」と強気だ。ななつ星は来年3月の出発分から体験コース充実を理由に5度目の値上げに踏み切る。3泊4日コースで1人当たり最高95万円となり、高額と話題となった運行当初(同55万円)から7割も跳ね上がった計算だ。顧客の選択肢が広がる中で、価格に見合ったサービスを提供し続けることができるかが、ななつ星4年目のカギになりそうだ。 PS(2016年10月15日追加):どうも官制合併は、①大きくなりさえすればよいと考えている ②寡占や独占状態にしたがる など、経済原則や経営合理性からはずれたものが多いが、*8の九州を中心とする離島を結ぶ地域航空会社の統合なら、JR九州が航空会社を作って統合し、列車との接続をよくして離島の価値を上げつつ、空への進出を計るのがよいと、私は考える。 *8:http://qbiz.jp/article/96017/1/ (西日本新聞 2016年10月15日) 離島結ぶ地域航空会社の統合検討 国交省、大手2社に要請 国土交通省がANAホールディングス(HD)と日本航空に対し、離島などを結ぶ地域航空会社の統合を検討するよう求めたことが15日、分かった。燃料の調達や機体の整備などでコストを削減し、地域の航空網を維持する狙いがある。国交省は地元自治体の意見も聞き来年夏までに統合計画をまとめたい意向だが、ANAHDと日航は慎重に検討するもようだ。統合を検討するのは北海道エアシステム(札幌市)、ANAウイングス(東京都)、オリエンタルエアブリッジ(長崎県大村市)、天草エアライン(熊本県天草市)、日本エアコミューター(鹿児島県霧島市)の5社。各社はそれぞれANAHDや日航と資本や業務の提携関係がある。国交省では、地域航空会社を傘下に収める持ち株会社を設立したり、経営規模のより大きな会社が小さな会社を合併したりする案などが浮上している。5社はいずれも30〜70席程度のプロペラ機を中心に運航し、北海道や九州の離島を結んでいる。各社はともに路線の利用率が低く、経営基盤は弱い。保有する機体が少なく、整備や乗務員の養成にかかるコストも高くなる傾向がある。主に100席以上の大型機を運航するANAHDや日航から機体の融通を受けることも難しい。このため国交省は同じ課題を抱える地域航空会社が連携し、効率化する必要があると判断した。ただ、ANAHDと日航は競合関係にあり、地元の自治体や企業も地域航空会社に出資している。このため国交省は関係者の意見を聞き、統合に関する課題の洗い出しを進める。 PS(2016年10月24日追加):*9-1のように、SBS米を商社が扱う理由は、「安い」「自社のビジネスが増える」にほかならない。そして、輸出国も日本の消費者に合わせた製品を最低コストで生産する工夫をしており、(自民党農林族のベテラン議員が中国に視察に行った時、中国産コシヒカリと日本産コシヒカリを食べ比べて区別がつかなかったように)味だけを比べれば国内産が勝るとは限らない。そのため、産出地・遺伝子組み換えの有無・使用した農薬・食品添加物などに関する表示は、消費者の選択を可能にするため、最低限必要なのである。 なお、*9-2の「都会だから食料自給率が低い」という見解は成立せず、日本の食料自給率は先進国の中でも際立って低く、それもカロリーだけを比較するのは一面的で、本来は主要な栄養素の自給率を示すべきだ。また、「コメの消費拡大が鍵で、需要面の政策が必要」というような見解の人は議員・行政(殆どが栄養学の“え”の字も知らない男性)にも多いが、供給を需要に合わせるのが財・サービスを販売するには当然であり、「供給が余るから重要を増やす政策が必要」などとして糖尿病患者を増やすのは逆である。にもかかわらず、このような発想で農業政策を行い、余っても米に固執しながら減反してきたため、日本の農業政策は失敗したのだ。  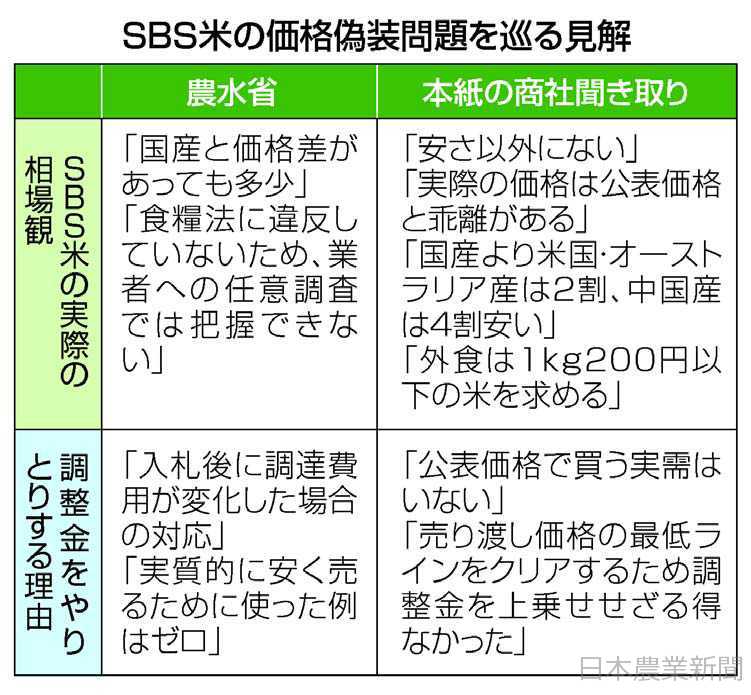 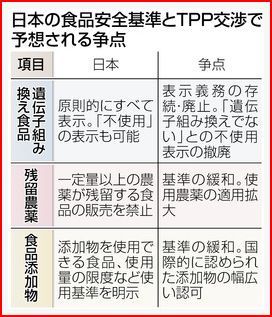 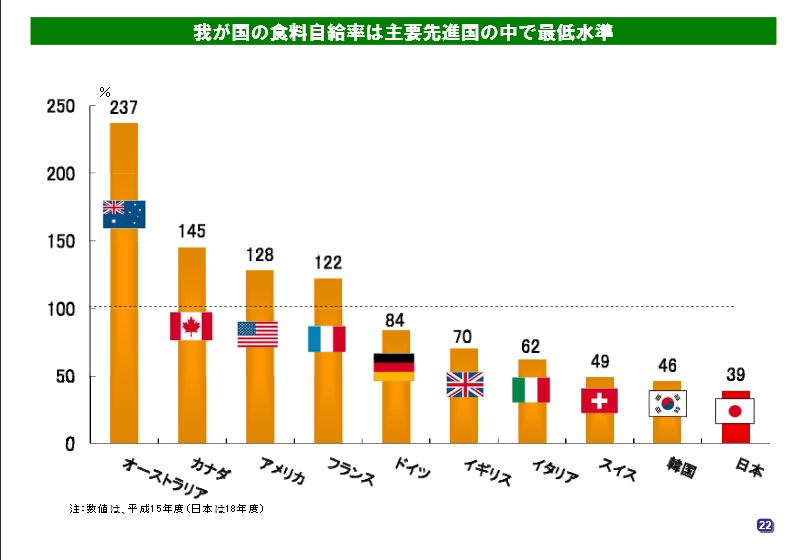 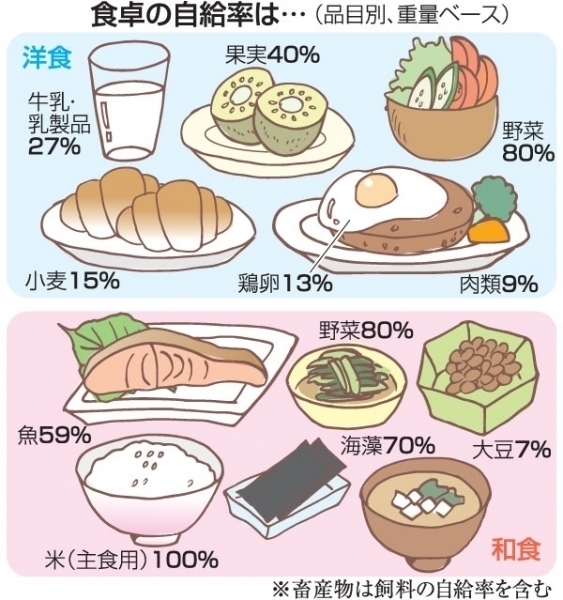 政府と大学教員 SBS米の価格偽装 TPPで争点 先進国の食料自給率 嗜好の変化 の会の試算 201610.23 となりそうな 国際比較 2016.10.24 日本農業新聞 食品安全基準 西日本新聞 *9-1:https://www.agrinews.co.jp/p39269.html (日本農業新聞 2016年10月23日) SBS米扱う理由 商社「安いから」 相場は国産の2割安 本紙聞き取り調査 輸入米の売買同時入札(SBS)取引を巡って日本農業新聞は、商社に聞き取り調査を行い、回答を得た全社が輸入米を扱う理由に「国産米より安いから」を挙げた。取引する米の相場は「国産品より2割安」が最も多かった。SBS米の「調整金」を使った価格偽装問題に対し、今月7日に農水省が公表した調査結果は、実需者への販売価格に十分踏み込まないまま、「国産相場への影響はない」と結論付けた。“安さありき”で取引される実態と、同省見解との間には大きなずれがある。国会での徹底審議が求められる。 ●国の見解と食い違い 調査は、今月13~21日にSBS参加資格を持つ全24の商社を対象に聞き取り、11商社(設問への一部回答も含む)の回答をまとめた。「輸入米を扱う理由」には、11商社全てが「国産米より安いから」と答えた。長い輸送時間で劣化しやすく、炊飯時に割れやすいなど品質面で見劣りする点も織り込んだ回答だ。タイ産の香り米などでは料理適性が調達基準になるが、まれなケースだった。米卸を通じた輸入米の売り先は、外食・中食といった業務筋が中心。企業や福祉施設向けの給食事業者もあった。安さを優先し、原産地表示が目立たない場面で採用されていた。単一銘柄での使用は少なく国産米とのブレンドが中心だった。実際に取引する輸入米の相場観は、国産米より「2割安」が4社と最も多く、「1割安」が2社と続いた。米国産やオーストラリア産より一段安い中国産を想定し、「4割安」とする回答もあった。近年、同省が公表するSBSの売り渡し価格は、国内業務市場で競合する国産B銘柄と接近するケースが目立つ。だが、同価格ではSBS米の魅力はなく、「公表される価格と実際の取引価格は、明らかに乖離(かいり)している」(大手商社)との受け止めが業者に広がっていた。調整金について商社は「農水省が定める売り渡し価格の最低ラインをクリアし、実需が求める安い水準で販売するための手法」(中堅)と受け止める。そうした使途を打ち消すために同省が挙げる「米卸が商社に支払う“逆調整金”もある」という事例は、「取扱量が少ない銘柄を試験輸入する場合など限定的」(大手商社)とみる。SBS売渡価格に米卸の手数料などを加算した実需への販売価格は、複数社が「1キロ当たり200円がボーダーライン」とみている。その水準を下回ると、実需の調達意欲が高まる傾向にあるという。14、15年度のSBS入札の不調は、国産米が大幅に値下がり、B銘柄を輸入米並みの価格で調達できたことが影響していたとみられる。 *9-2:http://qbiz.jp/article/96476/1/ (西日本新聞 2016年10月24日) 【福岡県の食料自給率20%】九州で唯一、全国の39%を下回るワケ 国内で供給される食料のうち、国産で賄われる割合を示す食料自給率(カロリーベース)。日本は39%と先進7カ国(G7)で最も低く、食料の多くを輸入に頼っている実態があらためて分かる。さらに、これを都道府県別にみると、福岡県の“お寒い”状況が浮かぶ。自給率は九州で最低の20%。しかも唯一、全国の39%を下回る。 ■胃袋は多いのに品目は低カロリー? 直近は2014年度(概算値)のデータだ。それによると、九州の他6県は、佐賀90%▽鹿児島84%▽宮崎67%▽熊本59%▽大分48%▽長崎44%−の順で高く、全国の39%を下回っている県は一つもない。なぜ福岡だけ、食料供給が“ぜい弱”なのか。農林水産省のある職員はこう解説する。「福岡はそれなりの農業県だが、それ以上に人口(約510万人)が多いからだ」。つまり、胃袋の数が多く、供給が追いつかない、というわけだ。栽培品目に着目する意見もある。福岡県の農政担当者は「カロリーが低いお茶やイチゴなどの生産に力を入れていることも影響している」と分析する。確かに、野菜や果実に比べカロリーが高いコメの産地は上位に並ぶ。全国では、1位は北海道だ。自給率208%は北海道“二つ分”のカロリー供給力を誇る。全国の農地面積の4分の1超を占め、酪農の生乳や、畑作のばれいしょ、小麦の生産も盛んだ。2位以下は米どころが目立つ。秋田190%▽山形141%▽青森123%▽岩手111%▽新潟105%―が100%を超え、余剰分を他県へ“輸出”できる供給力を持っていることを意味する。逆に、自給率が低いのは、東京と大阪が1%と同率ワースト1位。続いて神奈川の2%がワースト3位で、「一ケタ」はこの3都府県のみ。いずれも大都市で、福岡の20%も、九州で都市化が進んだ表れかもしれない。 ■コメ消費拡大が鍵、需要面の政策も 都道府県別の食料自給率について、農水省は「2025年度末までに全国で45%」とする政府目標達成に向け、「地域ごとの取り組みを推進する参考データにしてほしい」と説明する。とはいえ、コメの生産を増やそうにも、簡単ではない。農水省は米価下落を防ごうと、生産調整(減反)を進めている。各都道府県に、上限となる生産数量を割り振り、過剰生産をしないよう要求。これを守らない生産者には、麦や大豆の転作助成金を支払っていない。食料自給率は1965年は73%だった。それが、経済成長とともに、右肩下がりに下がってきた経緯がある。背景には、日本人の食生活の変化を指摘する声もある。食の「欧米化」が進み、コメ中心の食事はパンやパスタ、卵、肉など、いずれも輸入に頼る食品へシフトした。畜産は、牛や豚、鶏といった家畜を国内で飼育しているものの、その飼料の大半を輸入に頼っているため、自給率は低いままだ。「米離れ」の実態は、1人当たりの年間コメ消費量をみると、明らかだ。1962年度の118キロをピークに、現在(2015年度)は54・6キロと半分以下になっている。コメは日本が唯一自給できる主食。その消費が増えれば、おのずと自給率も上がり、輸入への依存度も下がる。農水省は自給率アップについて「(麦や大豆など)コメ以外の農産物の生産量を増やして対応してほしい」というが、そもそもコメの消費拡大をどう進めるのか。需要面で実効性ある政策を示す必要もありそうだ。 PS(2016年10月26日追加):農業において種子は最も重要で、開発者に特許権があるにもかかわらず、何年もかけて開発した種子を技術提供として簡単に外国に渡しているのが我が国の現状だ。しかし、それを改めなければ外国産との差別化はできず、日本で種子の開発をする民間はなくなるだろう。 *10:https://www.agrinews.co.jp/p39282.html (日本農業新聞 2016年10月25日) 野菜種子を国産化 海外品より発芽率高く 福岡市の種苗メーカー 種苗メーカーの西日本タネセンター(福岡市)が、野菜種子の国産化に乗り出す。流通する種の大半が海外産の中、管理が行き届いた国内施設で育てて品質を高める。価格は海外品より高くなるが、発芽率は高まるため、種を買う農家の採算性はトータルで改善すると同センターは見込む。キュウリ、トウガンなど70~80種を栽培し、年内にもJAや種苗店へ販売する。日本種苗協会は「種子を本格的に国産化する事業は初めてではないか」と指摘する。福岡市内の3ヘクタールの農地に建てた6メートル×20メートルのハウス43棟で採種用の植物を育てる。ハウスでは1種類の採種を完全に終えた後、別の品種の栽培に移る。同センターによると、屋外中心の海外の圃場(ほじょう)は虫害や他品種との交雑、異物混入といったリスクがあり、「正品率の低さが課題だった」(諸岡譲代表)という。ハウス室内の温度やかん水は専門の社員が管理する。収穫した種子は消毒、選別した後、発芽率が高まるように種の外皮を研磨する。生産した種子の8割はグループ会社の中原採種場(同市)が販売を担う。県や農研機構などが育成した品種は同センターが直接JAなどに販売する。山口県と同県のJA下関が共同開発した小ネギ「YSG1号」などは山口県内の複数のJAと契約し、全量販売する予定だ。日本種苗協会によると国内に流通する種(F1種)の9割は海外産とみられる。気温などの栽培適性、農地の確保のしやすさ、人件費の安さが理由だ。ただ、異常気象や人件費アップなど海外の生産条件が今より悪化する恐れが高まっており、同センターは「国産化が安定供給につながる」と事業の将来性を見込む。同センターは今後、耕作放棄地を活用しながら規模拡大を進める計画だ。2020年までに農家委託を含め、県内外20ヘクタールにハウス計300棟まで増やす。扱う品種も段階的に増やす。消えそうな固定種や在来種の保存も進める考えだ。種子の海外輸出も想定する。同センターのハウスを今月、視察した佐賀県の職員は「近場で安定的に種子が供給される環境が整うようであれば、県内で使える品種があるか、検討したい」と期待する。事業化に当たっては、6次産業化などを後押しする農林漁業成長産業化支援機構(A―FIVE)やサブファンドが8000万円を出資した。 PS(2016.10.26追加):木質バイオマス発電は、限られた資源である木材チップを燃やして発電するシステムで、これが21世紀の日本で進められるのには驚かざるを得ない。また、農地を売却して製造業・運送業・倉庫業などの5業種の建屋に用途を変える場合は地主農家が所得控除を受けられるようにするというのは、日本でしかできない農業のための農地を、外国で簡単に肩代わりできる製造業に転用するということで、何の工場かにもよるが50年も前のスキームだ。さらに「食の安全意識の高まりから室内で野菜をつくる植物工場」と書かれているが、確かに農薬は使わないものの、限られた栄養素のみを溶かした水耕栽培で人工光による「形だけ野菜」を、誰が、どこで食べるのか、呆れてモノが言えない。 *11:http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20161026&ng=DGKKASFS24H4L_W6A021C1MM0000 (日経新聞 2016.10.26) 農地転用 税優遇広く、バイオマスや植物工場 製造業中心を転換 農林水産省は農地を売却する農家への税制優遇を拡大する。全国で広がる木質バイオマス発電所や植物工場を運営する企業に売却する際にも所得税を軽くする方針だ。運営企業には固定資産税の軽減も検討する。現行制度で優遇を受けられるのは製造業などに転用した場合に限られる。産業構造の変化を踏まえ、新たな産業を誘致して農村で就労機会を増やす狙いだ。年末の与党の税制調査会の議論を経て実施を目指す。併せて2017年の通常国会に農村地域工業等導入促進法(農工法)の改正案を出す。現在は農地を売却して製造業や運送業、倉庫業など5業種の建屋などに用途を変える場合に限り、地主の農家は800万円を上限に所得控除が受けられる。一般的に農地転用は厳しく制限されるが、農工法のもとで例外が認められている。農水省は既存の5業種に加え、木材チップなどを燃料にするバイオマス発電所や植物工場、農家レストランなど農林業と関わりがある場合も税優遇の対象とする。追加業種を限定せず、広く対象に加える案もある。農家への優遇措置を広げるとともに、農工法が対象とする場所でバイオマス発電所などを運営する企業の進出も支援する。日本政策金融公庫の低利融資を受けられるようにするほか、新たに導入する機械設備の固定資産税を3年間は2分の1にする方向だ。農工法はコメ余りに悩んでいた農家の振興策として1971年に制定された。だが農地転用の有力な受け皿だった製造業は円高などで海外への生産シフトを加速させてきた。2015年の国内の工場立地面積はピークだったバブル期の4分の1まで減少。農工法に基づいて工業団地を整備するケースは1970年代に年間200件を超えることもあったが、2015年にはわずか1件にとどまった。代わって存在感を増しているのが農林業系の産業だ。11年の東京電力福島第1原子力発電所事故後に生じた電力不足の解消を狙ってバイオマス発電所の建設が相次いでおり、全国の認定容量は原発1.5基分に達した。食の安全意識の高まりから室内で野菜をつくる植物工場も全国300カ所を超え、地場産業としての期待が高まりつつある。バイオマス発電所や植物工場などの広がりは農工法制定時には想定されていなかった。農水省は新しい産業の誘致を通じ、農村での雇用機会の拡大につなげたい考えだ。 PS(2016年11月1、2日追加):*12-1に書かれているように、TPPが発効されれば、かつての不平等条約と同様、日本の農業や国民生活に打撃があるにもかかわらず、政府が自分もわかっておらず口当たりが良いだけの答弁を繰り返して採決に進もうとしているのは論外だ。なお、*12-2の鹿児島県鶏卵販売農協の経営の行き詰まりはもったいなく、①フクイチ事故で、放射能汚染の心配がない九州の農産物は付加価値がついているため全国区のスーパーや百貨店に販路を拡大する ②「飼料の高騰、高騰」と騒がなくてもよいように、材料は多いので安くて質の良い飼料を工夫して近くで作る などを行えば、経営が改善した上、飼料も販売できるようになると考える。また、*12-3のように、人口が減少して一人一人が豊かになる社会の休耕田や耕作放棄地の使い方には、佐賀県みやき町で秋咲きのヒマワリが咲いて観光名所になり、近くでこだわりの農産物を販売しているように、風景の美しさと食へのこだわりの両方を満足させる企画もある。 *12-1:http://qbiz.jp/article/97095/1/ (西日本新聞 2016年10月31日) 「TPP反対」650人が気勢 JA福岡など福岡市で集会 環太平洋連携協定(TPP)をめぐる衆院の論戦が大詰めを迎える中、JAグループ福岡などは29日、福岡市・天神のエルガーラホールで「TPP断固反対 農業政策要請 県農業者集会」を開いた。JA組合員(農業者)ら約650人が参加。「TPPが発効されれば、将来のわが国の農業のみならず、国民生活に対して大きな懸念を残す」などとするTPP反対の決議を採択した。JA福岡中央会の倉重博文会長はあいさつで、最近の国会審議に関して「野党の質問は丁寧だが、受け答えする政府側がはっきりしない。TPPは秘密主義だ」と批判。「(TPP承認案と関連法案について)急いで採決に向かっていることが全く分からない」と述べた。また、集会に参加した県選出の自民党国会議員らに対し、「TPPの合意内容が、農林水産分野の重要5項目などの聖域確保を求めた国会決議を満たしているとは考えられない。協定内容を十分に精査し、さらなる情報開示などを行うこと」などを要請。参加者は「TPP断固反対」と書かれた旗を掲げた後、「頑張ろう」と声を上げて集会を締めくくった。 *12-2:http://qbiz.jp/article/97174/1/ (西日本新聞 2016年11月1日) 鹿児島県鶏卵販売農協が2回目の決済も不調 東京商工リサーチ鹿児島支店によると、鹿児島県内の養鶏農家でつくる「鹿児島県鶏卵販売農業協同組合」(鹿児島市)が2回目の決済も不調となり、経営が行き詰まっていることが分かった。事実上の倒産で、負債総額は約8億円の見込みになるという。同支店によると、同農協は1973年に採卵養鶏農家が共同出資して設立した。組合員となる農家が生産した鶏卵をスーパーなどに販売し、最盛期は売上高15億円を超えたという。しかし、卵の価格が低迷した上、飼料が高騰し、事業環境が悪化。資金繰りが悪化し、取引先への支払いを予定していた9月30日と10月20日の決済がそれぞれ不調に終わったという。 *12-3:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/372599 (佐賀新聞 2016年11月2日) 秋の棚田大輪10万本 みやき町の山田ひまわり園 佐賀県みやき町簑原山田地区の「山田ひまわり園」で、秋に咲くヒマワリが見頃を迎えている。中山間地の棚田を活用した会場内には約10万本の黄色い花が咲き誇り、赤く色づいたケイトウとのコントラストが来場者の目を楽しませている。27日まで。地区住民でつくる山田地区中山間地組合が、耕作放棄地対策とにぎわいづくりを目的に2001年から取り組んでいる。昔ながらの石積みの棚田が残る約6千平方メートルの園内に、8月中旬から種をまいて準備を進めた。10月中旬から開花し、約2メートルの高さまで育った茎の先端に太陽に似た大輪の花を咲かせている。家族で訪れた西津博幸さん(47)は「インスタグラムで見て初めて訪れた。迫力があってきれいで、涼しいから子連れでもいいですね」と幼い我が子を抱きかかえながらほほ笑んだ。近年は観光バスのコースに組み込まれることも増え、長年の目標だった「来場者1万人」を2014年に達成。昨年は1万3千人が訪れた。今年は10日前後まで見頃が続くという。組合代表の眞子生次さん(69)は「棚田が荒れないよう守り続けるための活動だったが、ここまでの観光名所になった」と目を細める。場所は県道31号と136号が交わる綾部東交差点から北に約1・7キロ。開園時間は午前10時~午後4時半。大人1人100円の協力金を呼び掛けている。組合員らが手掛けた米などの農産物も販売する。問い合わせはみやき町観光協会、電話0942(96)4208。
| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 08:44 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
PAGE TOP ↑
