左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。
|
2025,07,17, Thursday
(1)運輸業・建設業等の人手不足と人材獲得
 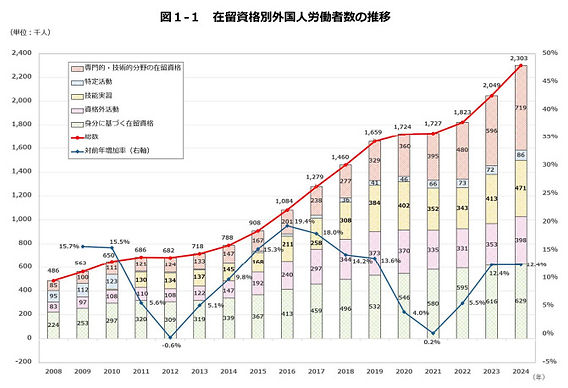  出入国在留管理庁 Connect Job 2025.7.16NHK (図の説明:左図は、就労が認められる在留資格で、*1の特定技能は2018年に閣議決定され、2019年4月から*2の特定産業分野のみで施行されていた。中央の図は、在留資格別外国人労働者数の推移で、2024年には230万人超になっているが、それでも全就業者の3.4%にすぎない。また、右図は、外国人の犯罪率は外国人の数が増えるに従って低下して現在は日本人と変わらず、「外国人はルールを守らず犯罪が多い」と言うのは偏見にすぎないことがわかる。なお、ルールにも憲法違反と思われるものがあるため、ルールもまた時代に合わせて変えるべきである) 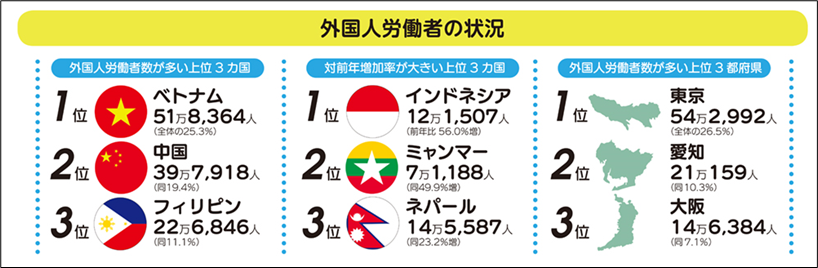 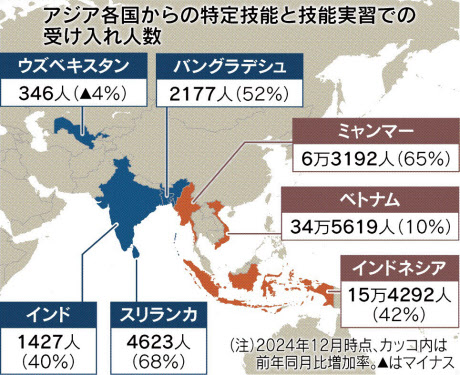 厚労省 2025.7.17日経新聞 (図の説明:左図は、就労目的で日本に来た外国人の状況で、出身国はベトナム・中国・フィリピンの順に多く、現在はインドネシア・ミャンマー・ネパールが増加中である。また、右図のように、これまで少なかった南アジアや中央アジアの国々を開拓する動きも官民で広がっている) 1)運輸業のケース *1-1-1は、①2030年度には運転手の数が2020年度比で27%減り、36%の物流が滞る恐れがあって、物流業界は人手不足が深刻 ②政府は自動車運送業を特定技能に追加して外国人就労枠は上限24,500人 ③SBSホールディングスは、インドネシアに自動車学校を設立して講師を現地派遣し、全寮制で半年間教育して日本の交通ルールや日本語を教え、2026年から年間100人程度のペースで採用して1800人の外国人運転手を採用し、10年で運転手の約3割を外国人にする予定 ③外国人が最長5年間働ける「特定技能」の制度を活用 ④多くがイスラム教徒であると想定して礼拝・食事等に配慮し、働きやすい環境を整備 ⑤賃金は日本人より低い見通し ⑥船井総研ホールディングスも傘下の物流コンサルティング会社、船井総研ロジが外国人運転手を中小企業に仲介するサービスを始め、主にバングラデシュやベトナムからの採用を想定 ⑦ヤマト運輸・佐川急便・福山通運等も外国人採用に乗り出しており、ヤマト運輸・佐川急便は決まったルート配送中心のため日本語が苦手でも働きやすい職種 ⑧特定技能による外国人運転手はバス・タクシー・引っ越し等の運転手も含む ⑨自動運転の実現が見通せない中、地方のバス運行会社等も外国人運転手の確保に動く ⑩物流に限らず、公共交通・介護まで様々なサービスで外国人なしに成り立たない としている。 このうち①⑩は現実であるため、⑧⑨のように、自動運転の実現が見通せなければ外国人運転手は必要である。また、⑦のように、決まったルートを配送するのなら必要な日本語は限られているため、働き易いと思われる。そのため、より簡単な仕事を任せる分だけ、⑤のように賃金が安いのには合理性があるだろう。 しかし、現在、雨が降ったり、暑かったりすればタクシーも来ない状況なので、②のように、政府が自動車運送業を特定技能に追加したのは合理性があるが、外国人就労枠の上限が24,500人で足りるか否かは心配だ。 そのため、③⑥のように、SBSホールディングスがインドネシアに自動車学校を設立して講師を派遣し、教育した上で資質のある人を採用したり、船井総研ロジが外国人運転手を中小企業に仲介するサービスを始めてバングラデシュやベトナムから採用したりしているのは、さすが民間企業の工夫だと思った。 しかし、このように教育費をかけて外国人を採用し、③のように、「特定技能」の制度を使ってもなお外国人の就労機関が最長5年では、採用する企業はロスが多い上に、日本社会は熟練労働者の割合が少なく、結果として働く外国人は意欲を失い、日本人は不便なままになりそうだ。そのため、④の働き易い環境というのは、日本で安心して長く働くことができ、頑張れば昇進して賃金で報われる環境であって、④のようなイスラム教徒向けの礼拝・食事の配慮が第1ではないと思われる。 また、*1-1-2は、運輸業に限らない外国人労働者就労の歴史を述べており、⑪2024年10月時点で外国人就労者数は230万2587人・就業者全体の3.4% ⑫人手不足の深刻化で10年前の2.9倍に増加 ⑬在留資格は、技術・人文知識・国際業務18%、特定技能・技能実習30%、留学生アルバイト14% ⑭1989年に「定住者」資格で中南米の日系人を受け入れ、1993年に表向き技術移転目的として「技能実習制度」を創設したが、低賃金の人手不足対策としての使用が広がった ⑮2019年に「特定技能制度」を導入し、「1号」は最長5年・「2号」は熟練者向けで在留期間の制限はなく、明確に人手不足対策として位置づけた ⑯来日・定住・永住の増加を懸念する声もあり、参院選で与野党が外国人規制強化の是非を議論している としている。 まず、日本国憲法は、前文で「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」とし、第17条で「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」、第18条で「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。 そのような中、⑪⑫⑬のように、人口構造の変化に伴い、2024年10月時点では外国人就労者数は230万2587人となっているが、未だに人手不足の状態が続いているため、⑯のように、来日・定住・永住の増加を懸念したり、公務員である衆議院議員や参議院議員候補者がヘイトスピーチをするなどは、「何を考えているのか!」と思われる。 なお、⑭のように、少しずつ門戸を開いた在留資格のうちの技能実習制度は滞在期間が1号1年、2号2年、3号2年で、3号への移行は実習生の受入れ企業や監理団体が優良だと認めた場合のみ可能だそうだが、このようにいやいや延長していること丸出しの細切れで低賃金の労働条件では、働く意欲を保つ方が困難であろう。 そのため、⑮のように、2019年に「特定技能制度」が導入されたのだが、これも「1号」は最長5年が上限で狭い産業分野に限られる上、在留期間の制限のない特定技能2号を取得するには、i) 特定技能2号評価試験に合格するか、技能検定1級に合格する ii) 監督・指導者として一定の実務経験を積むの2つを満たす必要があって、日本語が母国語であるため比較優位性がある筈の日本人よりも難しく、「2号には進ませたくないぞ」と言わんばかりのハードルなのである。 2)建設業のケース ← 日本人が減った産業を外国人が支えている現実がある *1-2-1・*1-2-2は、働き方改革による残業時間の上限規制(2024年4月から月45時間・年360時間)と高齢化の進行による慢性的な人手不足や生産性の低さが原因で、未完了工事額が約15.4兆円(2025年3月時点、国交省建設総合統計)にも達し、この状況が、i)商業施設や工場建設の遅延 ii)建設費の高騰 iii)設備投資の停滞 などを通じて日本経済に成長力低下をもたらしており、2023年末の建設業における外国人労働者数は約17.8万人(全体の約7.7%)・有効求人倍率は5.22倍(全産業平均の約4倍)となって、建設業界では外国人労働者の受け入れが進んでいる としている。 具体的には、①建設就業者数が2010年比で6%減少し、477万人になった(総務省の労働力調査) ②65歳以上の高齢化率が約2割(80万人)で、10年間で高齢化率が5%上昇した ③加齢で体力が衰えれば若い頃のようには働けない ④かねてから深刻だった人手不足に2024年4月から始まった時間外労働の上限規制で、建設業は月45時間・年360時間までしか残業できなくなり、総労働時間/人が前年比32.3時間減少した(全産業平均14.3時間の2倍以上) ⑤生産性向上を急がなければ民間企業の設備投資や公共投資の制約となり、日本の成長力が一段と下振れする恐れがある ⑥建設作業員が集まらず工事が計画通り進まなかったため、イオンモールは福島県伊達市の店舗オープンを2024年末から2026年下期に延期した ⑦建設業界全体で供給力が縮んでいる ⑧民間の産業用建築物1m²あたり着工単価は2024年に約30万円と前年より18%上昇した ⑨大手建設会社は採算性・工期を重視し、利益率の高い案件を優先している ⑩人材確保で後手に回って採算の良い案件に参入できなかった中小建設会社は廃業が増加している ⑪建設従事者が使える省人化等のソフトウエアの導入量/人は、フランス・英国の1/5である ⑫生産性向上にはデジタル化による効率化が不可欠 としている。 このうち、①②はデータであるため事実だが、老年学会は75歳までは問題なく働けるとしているので、③のように、「65歳以上は加齢で働けない高齢者である」と認識して高齢化率を計算したり、65歳定年制によって退職させたりすることの方に、むしろ人権侵害の問題があるだろう。 また、④の「人手不足の原因には時間外労働の上限規制があるが、これは働かせない改革になっている」「残業しないため、仕事が中途半端にならないよう早めに終わらなければならない」「もっと働いて稼ぎたい」と言う人も少なからずいるため、上限規制ではなく、働いた分だけ支払う規制にしてはどうかと思う。 さらに、⑤⑪⑫のデジタル化による効率化や省人化による生産性向上は必要不可欠で、それがなければ民間企業の設備投資や公共投資の制約となって日本の成長力が一段と下振れする恐れがるが、これらをすべてやったとしても、建設業に進む日本人の若者が著しく減る以上、外国人労働者を積極的に入れなければ、⑥⑦⑧⑨のように、建設作業員が集まらずに工事の遅延が起こったり、建設業界全体で供給力が縮んで着工単価が上がったり、人材確保のできない中小建設会社の廃業が増加したりする。 そのため、「日本人が減った産業を外国人労働者が支えている」というのは事実であり、外国人労働者をまるで邪魔者ででもあるかのように在留資格の交付を小刻みで厳しくするのではなく、家族帯同を容易にしたり、日本人と同様、家族もまた働いたり学んだりできるようにしたりして、日本で働くことのハードルを下げる必要があるのだ。 3)今後、さらに増えるニーズ ← 運輸業は、共働きの増加と高齢化に伴って通販や配達のニーズが増え、建設業は、 インフラの老朽化と適時・適切な維持管理・更新の需要が確実に増えること 2025年1月には、埼玉県八潮市で、下水道管の破損による地盤空洞化で道路が陥没し、トラックの運転手が犠牲になった。また上水道管の破裂事故も頻繁に起きている。 そのような中、*1-2-3は、①財務省所管研究所の調査によると、市町村の公営企業が運営する上水道事業の99%が設備更新に必要な資金を確保できていない ②上水道事業は原則として必要経費を住民が支払う使用料で賄う ③各事業者が現在の設備を維持したまま必要な内部留保を確保するには平均83.2%の料金引き上げが必要で、国交省によると2022年度末の一般家庭の月額水道料金は全国平均3,332円が6,100円程度に上昇する ④将来の収支見通しが甘く、費用を料金に十分に反映できていない自治体が多い ⑤単年度損益は黒字でも、実は手元資金が少なく老朽化した水道管を更新する資金までは準備できていない例も ⑥水道料金を上げると住民の反発が予想され、物価高対策として水道料金を割り引く例も ⑦総務省よると全国の上水道は1975年頃に整備が進み、足元で法定耐用年数の40年を過ぎた水道管が全体の2割超 ⑧手元現金が少なければ、日常的な保守だけでなく緊急時の対応にも支障が出る ⑨京都市は4月に市内の幹線道路地下を走る水道管が破損して広範囲に冠水し、県鎌倉市も6月に水道管が破裂して市内の約1万世帯が断水した ⑩各自治体は必要経費を料金に反映するとともに、近隣自治体との業務の共同化等でコストを削減することが必要 ⑪事業統合・経営一体化も有力な手段 ⑫人口減少をふまえると市街地の集約による水道インフラ縮小も重要な選択肢 等と記載している。 上下水道等の公的インフラは共通した問題を抱えており、それは当然行なわれなければならなかった固定資産の維持管理が適時・適切に行われず、1970年代に整備され老朽化した水道管・下水管を法定耐用年数(約40年)がすぎるまで、減価償却もせず、修繕引当金も積まずに使い続けてきたことである。 そのため、①④のように、収支の見通しが甘くて更新費用を料金に反映しておらず、突然、「上水道事業の99%が設備更新に必要な資金を確保できていない」などという事態が起こるわけだが、本来、設備の更新に必要な資金は、②③⑥のように、現在の使用者が支払うだけではなく、上下水道ができてからこれまでそれを使用してきた使用者も支払うべきだったのであり、民間企業は、皆、そうしているのだ。 その更新や修繕の費用を合理的に見積もって引き当てるのが、会計用語で減価償却引当金・修繕引当金等と呼ばれる負債性引当金なのだが、公的機関は、⑤のように、単年度のキャッシュフローしか見ていないため、耐用年数が過ぎれば当然必要になる「老朽化した水道管を更新する資金」のようなものすら準備できておらず、⑦のように、1975年頃に整備が進み法定耐用年数40年を過ぎた水道管が全体の2割超あり、⑨のように、水道管の破裂事故が多発し始めても、⑧のように、手元現金がないなどと言っているのである。 従って、これは、公的機関の資産管理全般に関する会計の問題であり、財務省は国所有のインフラも含めて、資産・負債に関して必要な引当金を積み立てる普通の会計制度に変えるべきである。しかし、役所には、税務署を除いて会計に詳しい人が著しく少ないため、私は、公認会計士・税理士(含:税務署を退官した人)等の専門家を担当する役所に派遣して、複式簿記の会計制度をきっちり作らせれば良いと考える。 なお、地方自治体側からは、「技術職員の高齢化や人材不足で更新計画の立案・遂行能力が現場に不足している」等の理由が挙げられることもあるが、それは資産・負債に関して必要な引当金を認識せず、耐用年数が過ぎれば更新時期を迎えることすら忘れていたという状態であるため、管理者として不適格と言わざるを得ない。 そのため、*1-2-3は、選択肢として、⑩⑪の近隣自治体との業務共同化や事業統合・経営一体化を挙げているが、上下水道は複数自治体で管理しても住民に支障は無く、むしろ経営の効率化によって安価に使える方が望ましいため、この選択肢は有力な手段である。 しかし、⑫の「人口減少による市街地の集約や水道インフラの縮小」は、都会の人口密集地帯で育った人ばかりがリーダーになっているために出てきた発想で、食料生産・森林管理・エネルギー生産等は、人口密度の低い地域でしか行なわれないため、その人口密度の低い地域で生産に励んでいる人々を不便にすることがあってはならないのである。 さらに、現在なら、分散型で再エネを生産して大量に使う場所に運ぶために、上下水道の更新と合わせて近くに電線を敷設し、送電料収入を得ることも考えられるし、検針や異常検知を自動的に行なってその位置と状況を電波で知らせることも可能である。そのため、更新時には、スマート化やサステナビリティーを含む更新をすれば良いだろう。 4)外国人材のリクルートについて *1-3-1によれば、母国の経済成長で東南アジア諸国からの来日が頭打ちになるのを見据え、また、韓国・台湾との人材獲得競争の激化もあって、日本政府と民間企業は外国人材の供給源を東南アジア中心から南アジアや中央アジアに広げつつあるそうだ。 具体的には、①厚労省が民間団体に委託して南アジア・中央アジアの「送り出し機関」に聞き取りを行い、日本での就労ニーズや制度面の障害を現地調査 ②インド・スリランカ・ウズベキスタン等を想定 ③オノデラグループは、ウズベキスタン移民庁と連携して日本で働きたい若者に半年ほど日本語を教えて特定技能試験合格の上で来日させるプログラム開始 ④同グループは外食・介護など向けに年間200人程度の育成から始めて年間500人に拡大する計画 ⑤日中亜細亜教育医療文化交流機構もウズベキスタンに日本語教育拠点3カ所を設置し、特定技能での日本就労を目指す ⑥ワタミはバングラデシュに研修センターを設立し、年間3,000人の特定技能人材送り出しを目指す ⑦技能実習・特定技能は2024年12月時点で計74万人が働き、国別ではベトナム34万5,619人と半数近くを占めるが、名目GDPが10年で1.8倍になって伸び率が鈍化 ⑧技能実習で10万人超が働いていた中国は、名目GDP/人が7,000ドルを超えた2013年から来日が減って2024年12月は2万5,960人 ⑨厚労省の担当者は東南アジア各国も他国で働く必要が薄れて獲得が難しくなると分析 ⑩韓国は外国人労働者を対象とする「雇用許可制」の年間受け入れ上限を、2021年の5万人程度から3年で3倍に拡大、時給換算最低賃金は既に日本の全国平均並 ⑪台湾も製造業や建設業等で外国人労働者の賃金上昇 ⑫特定技能と技能実習の合計人数はインドが2024年12月時点で1,427人、スリランカ4,623人、ウズベキスタン346人と南・中央アジアからの来日は未だ少なく、人材送り出しの潜在力は高い ⑬インドの2023年の労働力人口は4億9,243万人で毎年1000万人以上増加し、15~24歳の失業率は15.8% ⑭バングラデシュは2024年12月時点で特定技能・技能実習の合計が2,177人で前年同月比1.5倍 ⑮急速な来日拡大には慎重意見や単純労働者受け入れ制限を求める声もあり、20日投開票の参院選で外国人規制が争点に急浮上 としている。 日本では、(1)の1)2)3)はじめ、多くの産業分野で人手不足による限界が明確になっており、⑩⑪のように、韓国や台湾も外国人労働者のさらなる獲得に動いている中、⑦⑧のベトナムや中国のように、自国の名目GDPや賃金が上がって、既に来日が減っている国もある。 そのため、①②⑨⑫⑬⑭のように、厚労省の担当者が東南アジア各国も他国で働く必要が薄れて獲得が難しくなる考えて、民間団体に委託し、人材送り出しの潜在力は高いが未だ来日の少ないインド・バングラデシュド・スリランカ・ウズベキスタンなど南アジア・中央アジアの「送り出し機関」に聞き取りを行い、日本での就労ニーズや制度面の障害を現地調査をするのは当然のことだ。 また、調査を委託された民間団体の方は、③④のオノデラグループのように、ウズベキスタン移民庁と連携して日本で働きたい若者に半年ほど日本語を教え、特定技能試験合格の上で外食・介護向けに年間500人来日させるプログラム開始したり、⑤の日中亜細亜教育医療文化交流機構のように、ウズベキスタンに日本語教育拠点を設置して特定技能での日本就労を目指させたり、⑥のワタミのように、バングラデシュに研修センターを設立して年間3,000人の特定技能人材送り出しを目指したりなど、合理的かつ効率的な外国人材の開発を始めている。 にもかかわらず、⑮のように、i)急速な来日拡大には慎重意見 ii)単純労働者受け入れ制限を求める声 があり、今回の参院選では外国人規制が争点に急浮上した。そして、母国語で働くことができ、偏見がないだけでも優遇されている日本人労働者の職を侵食し、賃金を下げるなどとして、事実ではない言説を流して外国人労働者への偏見を煽る政党や候補者が少なからずあったことについて、私は、「外国人労働者の必要性やグローバリズムをしっかり説明できない国会議員・候補者・メディアの方が資質が低い」と感じた次第だ。 ちなみに、私がEY(Big4の1つ)で勤務していた時、オランダ人のパートナーやフィリピン人の事務員がいたが、オランダ人のパートナーは夕方5時に帰るものの、「電話が少なくて働き易い」と言って朝7時から事務所に来て仕事を始めていて感心した。また、やはり夕方6時には帰りたいフィリピン人の事務員は、弁当を持ってきて、昼食は事務所で食べながら昼休みも仕事を続けるなど、節約しながら効率的に働くことに頭を使う真面目な人だった。 つまり、「外国人は、怠け者で、犯罪率が高く、日本人のお荷物である」と考えている人は、外国人とともに働いたことがなく、「GDPの高い日本に生まれただけで、日本人である自分の方が優れている」などと勘違いしているのではないかと思うわけである。 (2)外国人制度の再設計 ← マイクロソフトの AI 「Copilot」に情報を集めてもらって記載した 1)外国人労働者について     2025.7.17、2024.3.7日経新聞 2022.3.7Global Saponet 2024.6.15読売新聞 (図の説明:1番左の図は、2024年10月末時点の在留資格別外国人労働者の割合で、技能実習が最も多い。また、左から2番目の図は、2019年4月1日に開始された特定技能のうち1号の国籍別の数で、2024年12月末時点では1号283,634人・2号832人である。右から2番目の図は、産業別の外国人労働者の割合である。そして、1番右の図が、外国人労働者のキャリアが途中で途切れることを防ぐために、2024年6月に公布された改正法に基づいて創設された育成就労制度だが、「公布日から3年以内の施行」とされているため、いつから始まるのか不明だ)    技能実習・特定技能Sapport Center Japan Job School 2023.11.25沖縄タイムス (図の説明:左図は、特定技能1号と2号でできる仕事であり、2025年7月現在では、1号で従事できる仕事は16分野にわたって定義され、各分野で外国人が担う業務が具体的に定められている。しかし、在留可能期間に上限がなく家族も滞在できる特定技能2号には、移行不可能な仕事が多い。そのため、中央の図のように、2025年現在、特定技能2号の分野拡大と1号からのスムーズな移行に向けた制度整備が進行中で、2027年までの本格運用開始が予定されている。右図は、技能実習と新制度である育成就労の比較で、技能実習の目的が建前上は発展途上国に技術を伝える国際貢献であったのに対し、育成就労は人材確保と育成を挙げている点が異なる) (1)の1)2)3)のように、多くの産業分野で人手不足による限界が明確になってきたが、東南アジアからの来日は、4)のように母国の経済成長で頭打ちになるため、日本は人材の供給源を東南アジアから南アジアや中央アジアに広げつつある。 一方、日本の外国人就労制度は、上の段の1番左の図が2024年10月末時点の在留資格別外国人労働者の割合で「技能実習」が20%と最も多いが、下の段の1番右の図のように、1993年に導入された「技能実習」の在留資格は、発展途上国に技術を伝えることを建前としているため、i)最長5年での帰国が前提 ii)原則転職禁止 iii) 家族の滞在禁止 iv)就ける仕事は91職種・168作業(2025年時点) 等、熟練度が低くて単純労働に近い初級レベルの作業ばかりで、日本で結婚・出産すると難しい在留資格変更を要求され、人間としての生活を阻害してきた。 このような技能実習制度の課題と日本における深刻な人手不足を受けて、上の段の1番右の図のように、外国人労働者のキャリアが途中で途切れないよう、2019年4月に「特定技能1号・2号」が創設され、2024年6月21日に公布された改正法で育成就労制度も創設されたが、「公布日から3年以内の施行」という非常にゆっくりした構えなのだ。 また、技能実習を修了した外国人が特定技能1号になるためには、技能検定3級(実技)か技能評価試験(専門級)に合格し、実習先企業が作成した「評価調書」によって技能・勤務態度・生活状況良好と認定される必要があるが、そこまで辿り着くのに約3年かかる。 さらに、「特定技能1号」の対象分野は下の段の中央の図のように16分野となり、2027年までに始まるとされる「育成就労」の受入れ分野は、上の段の1番右の図のように「特定技能1号」と揃えられるようだが、どちらも家族の帯同は原則不可であるため、日本に入国して在留期間の制限がなく、家族の帯同もできるようになるためには、下の段の左図のように、「特定技能2号」の在留資格をとらなければならない。 しかし、特定技能1号から2号への移行に関しては、i)特定技能2号評価試験か技能検定1級(分野により2級)合格 ii) 2〜3年以上の実務経験(分野毎に異なる) iii)移行可能なのは11分野(建設・外食・農業などは可能だが、介護は対象外) iv)管理・指導的立場での業務経験 等の複数の要件をクリアした上で、入管へ在留資格変更申請(審査期間:約2〜3ヶ月)を行う必要があり、2025年3月時点でも特定技能2号で働いている外国人は832人しかいないのである。 つまり、日本は、今でも「外国人労働者は、単純労働に近い初級レベルの作業をし、数年したら母国に帰ってもらいたい」というスタンスでいるわけだ。 このような中、*1-3-2は、全国知事会は、外国人の受け入れ拡大を国に求める提言を纏め、①2027年開始の「育成就労制度」の柔軟な運用を求め ②人口減が加速する中で外国人は地域産業や地域社会の重要な担い手 ③参院選で外国人規制が争点となって過剰な規制強化の懸念 ④外国人受け入れと多文化共生社会実現に国が責任を持って取り組むよう強く要請 ⑤「国は育成就労の受け入れ要件を厳格化して一定以上の日本語能力を要求する方針だが、技能実習の作業職種から大きく減少することを危惧する声が多数の自治体から聞かれる」と指摘 ⑥外国人の受け入れ環境を整えるため、国が主体となって制度設計や財源確保に取り組むことも要望 ⑦多文化共生に向けた施策を担う司令塔組織の設置も提案 ⑧全国知事会の村井会長は「排外主義があってはならない」と強調、静岡県の鈴木知事は政府が設けた在留外国人の犯罪などに対処するための組織を取り上げて「排斥・規制だけが取り沙汰されるようなことは正さなければならない」と述べた としている。 私も、②のように、人口減の中で外国人労働者は地域産業及び地域社会の重要な担い手になっており、この傾向は高齢化率の高い地方ほど顕著であるため、全国知事会が外国人の受け入れ拡大を国に求める提言を纏めたのは当然である。 しかし、世界では外国人材の獲得競争が激化している中、我が国の“技能実習”制度は、発展途上国に技術を伝えることを建前としながら単純労働に近い作業ばかりさせた上で、「5年経ったら帰れ」というスタンスであり、人権も無視してきた。その欠点を補うために、国は、2019年4月に「特定技能1号・2号」を創設し、2024年6月21日に改正法で育成就労制度も創設したが、「公布日から3年以内の2027年頃に開始」とのことである上、①⑤のように、育成就労の受け入れ要件を厳格化し、作業職種も大きく減少しそうな消極的態度なのである。 さらに、③のように、今回の参院選で外国人に対して過剰な規制強化の懸念が生じたため、④⑥のように、全国知事会は、外国人受け入れと多文化共生社会実現に国が責任を持って取り組み、外国人の受け入れ環境を整えるため、国が主体となって制度設計や財源確保に取り組むことも要請し、⑦⑧のように、司令塔組織は多文化共生に向けた施策を担うために設置し、「排外主義・排斥・規制だけが取り沙汰されるようなことがあってはならない」と強調したのだが、こちらの方が国会議員やその候補よりもずっとまともな主張だと、私は感じる。 そもそも、犯罪率が高いのは職にあぶれて生活に困った人である。そのため、「育成就労→特定技能1号→特定技能2号」と進む間に、在留資格がなくなったり、キャリアを中断させられたりすれば、“不法滞在”という(軽微な)犯罪になるし、近年の日本では、年金の目減りで生活に困った高齢者の万引きも増えているのだ。 これに加えて、*1-3-3は、外国人労働者について、⑨「選ばれない日本」に陥る可能性と外国人労働者が特定地域に偏る弊害 ⑩まだ日本の賃金・待遇には魅力があるが、地域に根付かず都市に流入することで負の循環に繋がる可能性 ⑪特定技能人材の退職理由調査は、入社から3カ月以内の退職で最も多かった理由が「人間関係の不満」で、時期を追う毎に「家族・友達・パートナーの近くに転居」が高くなる ⑫業務・職場の不満はどの時期も高いが、「業務内容が合わない」が主原因 ⑬入社1年を超えると定着率が高まる ⑭人材会社は業務内容の理解促進やキャリア意識を持った人材育成をし、雇用側は異文化理解を促進し、自治体は長期就労を見据えた生活基盤確保支援に取り組むべき ⑮生活基盤確保は、家族との住居探し・子供の日本語支援・妊娠・出産のサポートが必要だが、多額の費用がかかるわけではない としている。 このうち、⑨⑩については、確かに開発途上国の人にとっては、日本の賃金・待遇はまだ魅力があるが、米国と違って「頑張れば成功する」という“Japan Dream”は描きにくいため、頑張る人にほど「選ばれない日本」に陥る可能性が高い。 しかし、外国人労働者が地域に根付かず都市に流入することについては、都市は賃金が多くても不動産価格や家賃はじめ物価がそれ以上に高いため、⑭⑮については、自治体が県営住宅や市営住宅などの長期就労を見据えた住宅政策を行なえば、i) 育児と就労の両立支援 ii) 妊娠・出産期の支援 iii)乳幼児期の支援 iv)学齢期の支援 v)中等・高等教育の支援 等の子育て支援や医療・介護制度、年金制度等については既に国が整えているため、開発途上国と比較すれば外国人を差別しない限り悪くない筈である。 そして、働いて日本人と同じように税金や社会保険料を支払い、日本社会に貢献もしている外国人を差別する理由は無いため、⑮のように、キャリア形成に資する人材育成をしたり、異文化に対する理解を深めたりすれば、定着率は上がるだろう。なお、⑪の退職理由は、その地域にコミュニティーができ、外国人に対しても公平・公正が守られるようになれば解決するだろうし、⑫⑬の「業務内容が合わない」というのは、リクルートする際に業務内容をしっかり告げ、その後のキャリア形成のルートも示しておけば双方にとって「はずれ」は減る。 2)難民の受け入れについて    すべて2025.6.20難民支援協会 (図の説明:左図は、2024年末時点で世界で移動を強いられた人の数である。また、中央の図は、主な難民受け入れ国で、難民の73%を中低所得国が受け入れている。そして、右図が、難民認定数と申請者に占める認定率の国際比較で、日本は著しく低い) 上の左図のように、2024年末時点で世界で移動を強いられた人の数は1億2,320万人で、中央の図のように、難民の73%をイラン(350万人)・トルコ(290万人)・コロンビア(280万人)・ドイツ(270万人)・ウガンダ(180万人)など、主に中低所得国が受け入れている。 また、右図の日本における難民認定率は2.2%だが、AIの調べでは、2024年の日本に対する難民認定申請者は12,373人(出身国:スリランカ、タイ、トルコ、インド、パキスタン等)、難民認定数は190人(アフガニスタン:102人、ミャンマー:36人、イエメン:18人、パレスチナ:8人、中国:5人)で、難民認定率は約 1.5%(190人/12,373人)であり、この認定率は国際的に見て極めて低いため、先進国としての日本政府の人権侵害に対する意識・日本における難民の定義・難民認定制度の透明性・難民審査の迅速性に疑問が出るわけである。 また、2023年12月に始まった補完的保護制度では、補完的保護対象者認定数1,661人、うちウクライナ出身者1,618人(約97%)であり、難民認定後は、難民認定された本人は「定住者」又は「永住者」として日本に滞在・就労することが可能で就労に制限はないが、その配偶者は「定住者」になれば就労制限はないものの、「家族滞在」のままでは週28時間までのアルバイトしかできない。子どもは、年齢・就学状況により異なり、「家族滞在」又は「定住者」となる。 このように、日本の難民認定制度は、i)審査基準が非公開で、認定・不認定の判断基準が不明確 ii)審査期間が長期で、結論も不確実性が高いため、申請者の生活が不安定になる iii)却下通知に不認定理由の具体的な根拠が示されない iv)独立した第三者による審査制度や監査制度がない など、命を賭けて来日し難民としての認定を申請している外国人に対して、保護よりも排除を優先した不誠実極まりない態度になっているのだ。 しかし、難民政策が「外交・安全保障・国益」と密接に関係して形成されている中、このような島国根性丸出しのスタンスのままでは、日本はODA等で金をいくらばら撒いても尊敬されず、口づてに伝わる日本の評判は決して芳しくならず、外交で負けるのは必然なのである。 なお、日本で難民受け入れ数が少ない理由を、AIに具体的にリストアップしてもらたところ、以下のとおりだった。 1. 認定基準が極めて厳しい ・ 「個別把握論」など日本独自の解釈により、迫害の証明が困難 ・強制労働や集団的迫害が「迫害」と認められないケースが多い 2. 手続きのハードルが高い ・日本語での証拠提出が求められ、翻訳支援が乏しい ・面接の録音・録画がなく、通訳の質が検証できない 3. 政治的意思の不在 ・難民保護より「管理」の視点が強く、積極的な受け入れ政策が打ち出されていない ・難民問題が選挙や政策議論で優先されにくい 4. 国民の理解・関心の不足 ・難民に対する誤解や偏見が根強く、世論調査でも受け入れに慎重な意見が多数 ・難民を「他人事」と捉える傾向がある 5. 制度設計の不備 ・難民認定を入管が担っており、「保護」より「取り締まり」の視点が強い ・独立した審査機関が存在せず、第三者的な判断が困難 6. 支援体制の脆弱さ ・住宅・就業支援が乏しく、自治体やNPOへの依存度が高い ・難民の定住支援(日本語教育・職業訓練など)が限定的 7. 地理的・歴史的要因 ・島国であるため、難民の流入が物理的に少ない ・難民受け入れの歴史が浅く、制度的蓄積が乏しい 8. 偽装申請への懸念 ・就労目的の「偽装難民」申請が増加したため、制度が厳格化された ・その結果、本来の難民保護目的が後退する懸念がある しかし、現生人類であるホモ・サピエンスは、約30万年前にアフリカで発祥し、地球上の世界各地に広がったものである。また、他の土地に移動した目的は、現在と同様、縄張り争いに負けて逃げたり、新天地を求めて積極的に出て行ったりしたものであろう。 そのため、現生人類の殆どがもともとは移民・難民であり、古代や中世の日本でも渡来人・亡命者・難民的存在の人が日本社会に受け入れられ、農業はじめさまざまな新技術を伝えたり、律令体制の成立・仏教文化の発展などに貢献したりしたのだ。つまり、日本人も、もとは単一民族ではなく、難民受け入れの歴史が浅いわけでもないのである。 3)まとめ ← 現在の外国人就労制度は、外国人労働者のキャリア形成と 生活支援サービスの視点が欠落していること イ)外国人は、キャリアが続かず、家族の帯同もできない産業がある 2025年7月現在、特定技能1号から2号への移行が認められている分野は、建設・造船・舶用工業・ビルクリーニング・工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)・自動車整備・ 航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業に限られている。 そして、2024年度に追加された新分野の自動車運送業・鉄道(車両整備と軌道保守)・林業(伐採・育林)・木材産業(製材・合板製造)は、2号が未設定であるため移行できないが、特定技能1号を追加した時点で2号も追加しなければ、キャリア形成のルートを示すことができない。また、介護は、国家資格である「介護福祉士」を取得して在留資格「介護」へ移行すれば、家族を呼び寄せたり、永住したりすることも可能だが、どの分野も2号への移行要件は厳しい。 ロ)家事延長系の産業が疎かにされている 最初から特定技能制度に含まれていない分野もあり、その第1は、家事支援(掃除・洗濯・料理等)サービスである。外国人の家事支援サービスは、高度外国人材が帯同した場合や東京都・神奈川県・大阪府等の特区でのみ限定的に認められているが、高すぎない時給で家事支援サービスを充実すれば、施設に収容しなければならない高齢者や生活支援を必要とする高齢者が減り、それと同時に高齢者の生活の質も上がる。また、共働き世帯の家事労働を減らせば、時間的にゆとりが増えるため、1人で抑えていた子の数を増やすことも可能であり、家事支援は絶対に特定技能1号と2号に加えるべきである。 第2は、保育サービスで、「保育士の資格が必要」というのがその理由にされているが、保育所にも保育士以外でもできる仕事は多いため、介護と同様、特定技能1号で保育助手として受け入れ、保育士の国家資格をとったら在留資格「保育」に移行させ、家族を呼び寄せたり、永住したりすることも可能にすればよいだろう。 なお、医療・看護・介護・教育・保育等の人手不足が深刻な分野は、特定技能1号で受け入れて国家資格を取得させる方法もある一方、国家資格の相互承認(ある国で取得した資格や免許を、お互いの国で同等の効力を持つようにする制度)をする方法もある。 国家資格の相互承認をするためには、教育・訓練の質の同等性が必要だが、それは日本の方が高いとは限らないし、日本の方が高い国に対しては、資格の相互承認が質を揃える作業を通じて国際貢献になる。さらに、国際的な人材移動を促進したり、専門職のグローバルな活躍を支援したりするためには、国家資格の相互承認が日本人にとっても重要なのだ。 (3)参議院議員選挙と外国人政策      2025.7.20日経新聞 2025.7.9佐賀新聞 2025.7.3 2025.7.6 2025.7.8読売新聞 日経新聞 沖縄タイムス (図の説明:1番左の図は、外国人に関するメディアの偏った報道をきっかけとして流れた誤りの多い言説を元に、各党が真偽を確かめずに決めたお粗末な対応で、2025年7月の参議院議員選挙の期間に、演説として頻繁に放送された。また、左から2番目の図は、この参議院議員選挙における外国人政策に関する各党の公約だが、数少ないケースを敷衍して「外国人全体が悪い」としている点が、統計学を理解しておらず非論理的である。そして、中央の図が社会保障に関する各党の公約だが、高齢化率が上がる中、負担を増やさず給付を充実するには外国人の力が不可欠であることもわかっていない。さらに、右から2番目の図が、賃上げ等に関する各党の公約だが、労働生産性に見合った賃金でなければ日本に競争力はなくなるのである。最後に、1番右の図が、大学に関する各党の公約だが、公務員が人を国籍で差別することは許されない) 1)主な党の参院選公約について *2-1-1は、①自民党の小野寺政調会長が参院選公約発表で「『違法外国人ゼロ』に向けた取り組みを加速化する」と宣言した ②国民民主党の玉木代表も参院選公約で、差別解消を掲げつつ「外国人に対する過度な優遇を見直す」「国の財政が厳しい状況にあるなら、税金はまず自国民に使うのが当然」とした ③参政党は参院選公約で、外国人労働者の受け入れ制限や入国管理強化により「望ましくない迷惑外国人などを排除」と謳う ④論戦の名を借りた排外主義の喧伝が危ぶまれる ⑤師岡弁護士は「『外国人が優遇されている』と主張して日本人と外国人を分断し差別を煽る行為は、「税金で公的ヘイトスピーチを行なっているもので、人種差別撤廃条約とヘイトスピーチ解消法に基づいて公的機関は選挙運動におけるヘイトスピーチを批判すべき」 ⑥ジャーナリストの布施氏は、「『日本で優越的な権利を有した外国人住民がいる』という主張は事実ではない」「優遇されているとして挙げるなら米軍人で、『外国人が増えると治安が悪くなる』との言説も根拠はないが、米兵による事件事故は多発している」 と記載している。 また、*2-1-2は、⑦政府は「外国人との秩序ある共生社会推進室」を内閣官房に設置し、発足式を首相官邸で開いた ⑧石破首相は「ルールを守らない人への厳格な対応や外国人を巡る現下の情勢に十分に対応できていない制度の見直しは政府として取り組むべき重要な課題」と指摘 ⑨首相は出入国在留管理の適正化・社会保険料等の未納防止・土地等の取得を含む国土の適切な利用管理に対処するよう指示 ⑩首相は発足式で「外国人の懸念すべき活動の実態把握や国・自治体における情報基盤の整備、各種制度運用の点検、見直しなどに取り組んでもらいたい」と求めた ⑪新組織発足は政府を挙げて施策を推進する姿勢をアピールする狙いで、過度な規制強化や権利制限に繋がりかねない懸念 ⑫参院選では外国人政策を巡って与野党が規制強化や共生の重視を掲げる ⑬参院選では自民、国民民主、参政各党が規制の強化を訴え、立憲民主党は外国人の人権保護を掲げている と記載している。 今回の参議院議員選挙で外国人政策が浮上したのは、メディアが外国の運転免許を持っている外国人が日本で運転して事故をおこしたことを連日放送したためだが、運転免許も相互承認で認めているものであるため、日本人も外国で運転させてもらっているのである。そのため、日本の交通法規を教え、その理解度を確かめる手順が疎かだったにすぎない。 しかし、日本で不動産を取得する外国人の中には、投資目的で不動産を買って空き屋のままにしている人もいるため、不動産の値段が高騰して住みたい人が住めないという問題が生じたそうだが、日本人にもそういう人はおり、不動産を投資目的で所有すれば儲かるようにしたことが問題の本質である。もちろん、「安全保障上、ここに外国人は住んで欲しくない」という場所もあるが、そういう場所はあらかじめルールを決めておかなければ、罪刑法定主義にならない。 そこで、①については、自民党の政調会長が参院選の公約発表で「『違法外国人ゼロ』に向けた取り組みを加速化する」と宣言したのだから、これは首相の決定と言うよりは自民党の政策決定である。また、②③のように、国民民主党や参政党も参院選公約で誤った理解の下、外国人の管理強化や排除を主張し、今回の参院選ではこの2党が議席を伸ばしたわけである。 そのため、1965年に国連総会で採択され、1995年に日本も批准している人種差別撤廃条約に基づいて、人種・皮膚の色・出身民族等による差別を撤廃し、教育・立法・行政等を通じて差別の根絶を図り、人種差別的な扇動はやめさせるべきである。 また、日本には、2016年6月施行のヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)もあり、国・地方公共団体に対して「本邦外出身者」に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消に向けた取組・啓発・教育などの対応を求めているのに、④⑤⑥のように、事実ではないことを基に論戦の名を借りて排外主義を喧伝したり、参議院議員候補者や応援の国会議員が税金を使ってヘイトスピーチを行なったりしており、そうした方が票を集められる日本人のレベルにも呆れるほかなかった。 しかし、不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)は、セクハラ同様、「表現の自由」にはあたらず、国連人種差別撤廃委員会は日本に対して実効性ある法整備を勧告している上、欧州諸国ではヘイトスピーチに対する刑事罰を導入している国も多いため、日本でも罰則を備えた法律にすべきだ。 そのような中、石破首相は、⑧⑨のように、「ルールを守らない人への厳格な対応をすべき」としているが、外国人の運転免許も不動産投資も、ルールを破って行なっていたわけではないし、外国人労働者の社会保険料等の未納が日本人より多いわけでもない。そのため、「出入国在留管理の適正化」「社会保険料等の未納防止」「土地等の取得を含む国土の適切な利用管理に対処」というのは、根拠もなく飛躍しすぎているのだ。 さらに、⑦⑩⑪の政府が内閣官房に設置した「外国人との秩序ある共生社会推進室」は、(架空のルールを守らない)外国人の懸念すべき活動を防止するためとして過度な規制強化や権利制限を行なうのではなく、現存するルールの人種差別撤廃条約やヘイトスピーチ解消法の違反者に対して罰則をつけることによって、日本社会の支え手となっている外国人との秩序ある共生社会を実現するようにすべきだ。 そうすれば、その議論の過程で、国民に物事の善悪が明確になるため、⑫⑬の今回の参院選のように、外国人政策で規制強化を訴えた政党が議席を増やすのではなく、外国人にも日本人と同じ人権保護を訴えたまっとうな政党が議席を伸ばすことになろう。 2)参院選の結果、「トップに結果責任があるため、引責辞任すべき」と言うのは非論理的 ← 「権限無きところに責任なし」なので、責任は公約や候補者を決めた人にある *2-4-1・*2-4-2は、①自民党は大敗した参院選の結果に関する意見を聞くため、党本部で両院議員懇談会を開催 ②党総裁の石破首相は「自らの責任は総合的・適切に判断したい」「国家や国民に対して決して政治空白を生むことがないよう責任を果たす」と続投を表明 ③首相は「米国との関税交渉合意実行」「農業政策」「社会保障と税の改革」を続ける理由に挙げた ④懇談会では首相に選挙敗北の責任を取って退陣するよう求める「石破おろし」の声が多数 ⑤森山幹事長は総括委員会を設け、8月中に結論を得た上で「自らの責任について明らかにしたい」と話した ⑥首相続投に反対する党所属国会議員は両院議員総会開催を求める署名集めをし、既に総会開催を要求できる1/3以上の署名を確保し、旧茂木派の笹川農林水産副大臣は必要な署名を集めたと述べた ⑦小林元経済安全保障相は「組織のトップとしての責任の取り方についてしっかり考えていただきたい」と退陣を求めた ⑧「政治空白を作るべきでない」と続投を支持する声は少数 ⑨報道各社の世論調査では参院選大敗要因は石破氏より自民党そのものにあるとの見方がある ⑩両院総会の署名集めは旧茂木派・旧安倍派・麻生派が主導したが、旧安倍派は自民党離れに繋がった政治資金問題を引き起こしたため、「反省の色がないのはおかしい」との声も としている。 選挙前のメディアは、衆議院解散や参議院議員選挙に関する報道が多く、選挙後は「与党が過半数に達しなかったため、石破首相が引責辞任すべき」ということばかり報道し続けており、メディアは選挙や勢力争いが好きなだけで、政策内容はよく理解していないように見える。これには、自民党の部会でメディアに頭取りだけをさせて、議論しているところは見せないことが影響しているため、時々は議論の全過程を見せることが必要だと思われる。 では、⑦の「選挙に負けたから組織のトップが責任をとるべき」という主張は正しいのかと言えば、世界的には、法的・契約的責任などがある場合に責任をとることは正しいが、そうでない場合はトップが引責辞任をして「けじめ」をつけたとし、原因を曖昧にすることで他の関係者を不問に付すことは、むしろ根本的解決を遠のかせると考えられる。 にもかかわらず、日本ではトップの引責辞任が潔いかのように美化されるが、その理由は、i) 1582年に羽柴秀吉と毛利氏が闘った備中高松城の戦いで水攻めをされた毛利方の清水宗治が自刃して講和した武士道に基づく美談がある ii)第2次世界大戦後の日本でもリーダーが戦犯として裁かれただけで、開戦の空気を作ったメディアやその空気に流された国民は戦争責任を問われず、むしろ責任が曖昧にされたことが美化された などである。しかし、そのため、現在でも、同じ構造が残っているのだ。 そして、「自らを正当化するためには、国民を犠牲にしても良い」と考える官の発想は、今回の参院選でも各党の公約に散見され、そういう政策こそが、①の自民党大敗と立憲民主党の伸び悩みの原因である。そのため、②③のように、石破首相が政治空白を作らず、「米国との関税交渉合意実行」「農業政策」「社会保障と税の改革」を続けたとしても、また、⑩のように首相が旧茂木派・旧安倍派・麻生派出身者に交代したとしても、政策立案を官に依存して国民不在の政策を実行している限り、普通に選挙すれば負けるのが当然なのだ。 従って、④⑥のように、両院議員総会を開催して「石破おろし」をしようと、⑤のように、森山幹事長が総括委員会の後に引責辞任しようと、表紙と目次を変えれば本の中身(=政策の内容)が変わるわけではないため、⑨のように、世論調査では「参院選大敗要因は石破氏より自民党そのものにある」と見抜かれているし、⑧のように、事情がわかっている少数のベテラン議員が「むしろ政治空白を作るべきではない」と石破首相の続投を支持しているのである。 3)外国人との共生が不可欠な理由    2025.7.23日経新聞 2025.7.31日経新聞 (図の説明:左図が、各年の在留外国人数で、中央と右の図が、*2-2-1に書かれている経済学者へのアンケート結果である) *2-2-1は、①経済学者の66%が「外国人増加が財政収支の改善に寄与する」と回答 ②財政改善の理由は、若年層(20代・30代)が在留外国人の55.9%を占め、勤労世代が中心で、税収・社会保険料収入の増加に繋がり、現時点では給付より保険料と税の負担が上回るため ③労働市場では、建設・運輸などで人手不足を補完し、モノ・サービスの供給不足や価格上昇の抑制に寄与しつつ、日本人との雇用競合は限定的・補完的 ④多様な価値観や考え方が生産性の向上に繋がる ⑤経済学者の76%が「在留外国人の増加が平均的な日本人の生活水準向上に寄与する」と回答 ⑥外国人の定住・高齢化を見据えた子弟への教育・高齢期の給付等の十分な対応が必要 ⑦現在、日本の外国生まれの人口は日本では3%とOECD平均の11%を大きく下回る 等としている。 また、*2-2-2は、⑧人口減少下の日本は外国人の力を借りなければ人手不足で社会機能を維持することも困難 ⑨政府が「移民は受け入れない」という建前を維持しつつ、外国人受け入れを拡大してきたことが矛盾 ⑩その建前を排して外国人の社会統合を真剣に考えるべき ⑪参院選の終盤、政府は「外国人との秩序ある共生社会推進室」を内閣官房に設置したが、国はこれまで外国人政策を自治体任せにし、本気で取り組んでこなかった ⑫日本の社会制度の多くが外国人を想定しておらず制度設計が不十分 ⑬定住を前提とした移民と認めず、一時的な滞在者との位置づけでは共生にも力が入らない ⑭制度の透明性と分かりやすさが社会統合の質を高める ⑮留学生支援も知日派育成の戦略として重要 等としている。 このうち①の「経済学者の66%が「外国人増加が財政収支の改善に寄与する」と回答した理由は、②③⑧のように、現在は勤労世代が中心で税収・社会保険料収入が給付より多く、建設・運輸等の人手不足で供給不足を起こして社会機能を維持すら困難になっている財やサービスの供給を増やして価格上昇の抑制に寄与すること、日本人との雇用競合は限定的・補完的であること などである。 また、⑤の経済学者の76%が「在留外国人の増加が平均的な日本人の生活水準向上に寄与する」と回答した理由は、④のように、多様な価値観や考え方が生産性の向上に繋がるからである。これは、*2-3のように、日本に来た渡来人が鉄器や稲作などを伝えて技術革新を起こしたことによって、日本で人口増が起こったことが既に歴史で証明されているわけだが、*2-3の研究のうちキビやアワは少し乾燥した山間部や寒冷地に適しているため北部九州の土器には確認されず、高温多湿で水稲に適していた九州では稲作が普及したのだ。 つまり、現在も起こっていることだが、外国人の増加によって食文化も多様で豊かになり、多様な価値観や文化の流入とよい方向への取捨選択が、生産性を向上させて日本を豊かするのである。そのため、⑥⑨⑩のように、「移民は受け入れない」などという建前は排して外国人の社会統合を目指し、外国人の定住・高齢化を見据えた十分な対応を行うべきだ。 国は、⑬のように、「定住を前提とした移民は受け入れない」という建前から、⑪のように、外国人政策に本気で取り組んでこなかったため、日本の社会制度の多くが、⑫のように、外国人を想定しておらず、制度設計が不十分である。政府は、参院選の終盤、「外国人との秩序ある共生社会推進室」を内閣官房に設置したが、一時的な滞在者との位置づけでは共生に力が入らないため、⑭のように、制度の透明性と分かりやすさで社会統合の質を高める必要がある。 さらに、⑮のように、留学生や母国に帰還する外国人も知日派・親日派予備軍であるため、粗末にせず育成することが重要だ。現在、欧米では、移民・難民の急増、異なる宗教・習慣・言語などによる文化的摩擦、国境管理、選挙戦略として移民排斥などがかまびすしいが、⑦のように、現在の日本では、外国生まれの人口は3%とOECD平均の11%を大きく下回るため、そのような心配は周回遅れである上、日本は国境管理が比較的容易で、懸念事項についても平等の理念の下で対応が可能なのである。 (4)地方創生とそれに不可欠な外国人労働力 *3-1は、①東京圏への人口の過度な集中是正は不十分 ②東京圏は進学・就職を契機に全国から若者を集める ③基本構想は、東京への転入を止めるのは難しいとして地方の魅力を高めて地方に転出する若者の流れを倍にする目標を掲げたが、これで均衡にできる保証はない ④地方は若者、特に若い女性が働きたくなる場所が少ない ⑤東京から地方への転出増には若者らが仕事を通じて自己実現できる魅力的な職場を地方に増やすことが前提 ⑥石破政権が東京一極集中是正を掲げ続けるなら、まず中央省庁の一部や関係機関を地方に移転させるべき ⑦大胆な税制優遇策を導入して企業の本社移転を促す ⑧地方の居住者もリモートワークによって東京の企業でもっと働けるようにする ⑨基本構想の目玉は、仕事や趣味を通じて居住地以外の地域に継続的に関わる人を「ふるさと住民」として登録する制度の創設で、これでは地方の賑わいや人口増には直結しないため、地方創生2・0も石破政権の政治的なアピールの道具に終わる恐れ ⑩地方税収に占める東京都と東京23区の割合は上昇傾向が続き、豊かな財政を生かして手厚い子育て支援・高校授業料実質無償化等を進めて周りの県からの移住も促す ⑪東京都の独り勝ちは、首都直下地震といった災害への脆弱性を高め、地方の持続可能性も損なう ⑫国土の均衡ある発展のため東京都の豊かな税収の一部を他の自治体にさらに回すことなども議論すべき ⑬専門人材不足で道路、上下水道の管理・更新、介護、保険等の行政サービスを1市町村だけでは実施できなくなり、今後は複数の市町村が共同で実施するか、都道府県が市町村を支援する仕組みの整備が不可欠 ⑭地方自治の充実のため、住民に一番近い市町村に権限を移す地方分権が進められてきたが、今後も職員不足が深刻化する状況で、市町村から都道府県に権限を移すことも考えざるを得ない 等と記載している。 また、*3-2は、⑮自民党は、2014年年末の衆院選公約の柱の1つに「地方が主役の『地方創生』」を明示し、「人口減少に歯止めをかける」と訴えた ⑯自民党は選挙の度に「地方創生」を掲げ、地域の活性化を軸に支持を集めたが、成果は全く見えない ⑰2024年に生まれた日本人の子の数は、統計開始以降初の70万人割れで、女性1人が生涯に産む子の推定人数は過去最低を更新した ⑱多死時代に入って、人口は2024年だけで約92万人減 ⑲与党政権が地方創生、人口減に歯止めといくら連呼しても、反転の兆しすらない ⑳地方の人口減少は加速し、ヒト・モノ・カネの東京一極集中が進む ㉑立憲民主党は、少子化、人口減少、東京一極集中の流れを止め、国に人口戦略を総合的に推進する体制を整えると主張 ㉒体制の必要性は理解できるが、止めることは不可能 ㉓この参院選で人口減を前提に行政サービスをどう維持するか、地域社会をどう守るか議論すべき ㉔石破政権は「地方創生2・0」の実現を掲げ、関係人口、交流人口を拡大させ若者・女性にも選ばれる地域づくりを進めるのが目玉だが新味に欠ける ㉕自民党の公約・総合政策集を見ても地方創生失敗の反省はなく、人口減社会への対応策を羅列するに留まるが、政権与党として骨太の地方政策を示す責任がある ㉖国民民主党は大都市圏への人口集中是正策として「移住促進・UIJターン促進税制」創設、リモート勤務者支援等の地方への移住・企業移転を促す税制を提案 ㉗人や企業が地方に移る方が、東京にいるより支払う税金が少なくて済むといった打開策をさらに検討すべき ㉘東京への集中は災害時のリスクも高めるため、石破政権が防災庁設置などで「災害に強い日本」を実現すると言うのなら、一極集中是正に本気で取り組むべき ㉙日本維新の会は、公約で災害発生時に首都中枢機能を代替できる「副首都」を大阪に作り、多極型社会への移行を目指すと提案 ㉚多極的国土構造は社会の維持のため不可欠で、人口や産業、行政サービスの適正な配置について国民的議論を始める時 等と記載している。 さらに、*3-3は、㉛青森市で7月23日開催された全国知事会議は、人口減対策に最優先で取り組むよう国に求める提言を纏め、総合的対策を展開するための民間企業も巻き込んだ国民的運動推進や庁レベルの「司令塔」設置を要望 ㉜外国人政策を巡り、多文化共生の推進も訴え ㉝人口減対策に関する提言では、女性や若者の意見を取り入れ、働き易く子育てし易い環境を整備することや税制改正等を通じて企業・大学の地方分散を推進することも求めた ㉞知事会としても経済界を巻き込む形で結婚支援策を検討する方針を確認 ㉟外国人政策を巡っては「国は労働者としてしか見ていないが、自治体は生活者として受け入れている」といった意見が相次いだ ㊱外国人の受け入れや定着のために、教育などの環境整備に国が責任を持つよう提言 ㊲地方税財政については、参院選で消費税減税を訴える政党が伸長した影響も議論 ㊳徳島県の後藤田知事は「持続可能な社会保障制度の維持が非常に不安定化している」という危機感を表明 ㊴東京一極集中による地方税の偏在の是正を訴える声も多く上がった 等としている。 1)東京一極集中の是正には首都移転しかないこと 東京に一極集中した理由は、i)徳川幕府が江戸に幕府を置き、明治時代に首都が京都から東京に移され、政治・行政機関が東京に集約されて、国家予算・政策決定が東京中心になった歴史があること ii)そのため、次第に東京に大企業の本社や金融機関が東京に集中し、企業間連携や取引も容易になって、雇用や投資も東京に集まったこと iii)有名大学・研究機関も東京に集中したため、東京に進学先・就職先が多くなったこと iv)その結果、交通網・医療・娯楽・文化施設等も充実し、生活の利便性の高い情報・文化の発信地になったこと v)これにより、若者の進学・定住が加速し、高学歴・高スキルの人材が東京に集まって地方は人口減・空洞化が進んだこと 等である。 そのような中、⑥⑧⑨㉔の「中央省庁の一部や関係機関を地方移転」「地方の居住者がリモートワークで東京の企業で働けるようにする」「居住地以外の地域に継続的に関わる関係人口を増やす」等の部分的移転は、不便や非効率が増すだけで、東京を中心として廻っているサイクルを本質的に解決することはできない。 そのため、「政治・行政→インフラ→経済・文化→教育」等の首都機能の全面的移転と一貫した首都の設計が必要なのであり、それがないことが、⑯のように成果が出ない理由なのである。 従って、⑦⑩⑫㉗のような「大胆な優遇策で企業の本社移転を促す」「地方税収に占める東京都と東京23区の割合は上昇傾向が続く」「国土の均衡ある発展のため東京都の税収の一部を他の自治体に回す」「人や企業が地方に移る方が、東京にいるより税金を安くする」等も、既にあるパイの分配を少し変えるだけの弥縫策にすぎず、国民の生活を豊かにするものではないため、効果が乏しく、持続可能でもないだろう。 しかし、⑪㉘のように、首都直下地震という災害への対応を怠っては、国の持続可能性すら危ういため、上のi)~v)のサイクルを変えるためには、㉙のような大阪での副首都建設というコストばかりかかる対策ではなく、首都移転が効果的だと、私は考える。 海外では、近年、タンザニアが1996年にダル・エス・サラームから国の地理的中心地ドドマに首都を移転し、カザフスタンが地震リスクの回避と政治的安定のために1997年にアルマトイからアスタナへ首都移転した。さらに、マレーシアが行政の効率化とIT政府構想のために、1999年に、クアラルンプールからプトラジャヤへ首都移転し、インドネシアは首都の過密化・環境問題・ジャカルタの水没危機等への対応のために、2024年以降にジャカルタからヌサンタラに首都を移転する予定であり、第2次世界大戦後に首都移転を決めた国だけでも、少なくとも15か国以上ある。 このうち、首都の過密化・環境問題・地震リスクの回避・水没危機への対応・行政の効率化・IT政府構想・地理的中心地という要素は、日本にもそのまま当てはまる。そして、東京一極集中是正・災害対応力強化・地域の自立促進・政治行政システムの再構築を目的として、1992年には、「国会等の移転に関する法律」が制定されて既に首都移転が議論され、1999年には、国会等移転審議会が栃木・福島地域、岐阜・愛知地域、三重・畿央地域を候補地として選定していたのだ。 しかし、現在であれば、イ)顕著になった地球温暖化に対応するため、高原の涼しい場所が省エネで住み易い場所になったこと ロ)長野県駅付近の地盤は比較的安定し、津波や火山災害のリスクも低いこと ハ)南アルプスの眺望や自然環境が美しいこと 二)大阪・京都・名古屋等と比較して地価が安いため、コストを抑えて広い面積を再開発できること ホ)山地で地下建造物も作り易いこと へ)日本の中央部に位置すること ト)リニア中央新幹線で東京から長野県駅まで約40分になること チ)データや文書の保管に適していること 等々の理由で、リニア新幹線の「長野県駅」を下伊那郡などの広域を含む呼称である「南信州駅」として、新首都をそこに決めるのが良いと思う。 2)東京圏への人口集中が止まらない理由 1)のi)~v)の理由で、①②③のように、東京圏に進学・就職のため全国から若者が集まるため、東京への若者の転入を止めるのは難しく、このままでは流入と流出を均衡にできないため、東京圏への人口の過度な集中是正もできない。 また、④⑤のように、地方は若者や特に若い女性が働きたくなる場所が少なく、東京から地方への転出が増えるためには、若者らが仕事を通じて自己実現できる魅力的な職場を地方に増やすことが、確かに必要である。しかし、これを主張すメディアや政党の公約でさえ「女は子どもを産む機械」と言わんばかりのジェンダーに満ちた発想を前提にして物を言っているのだ。 その例は、⑮⑰㉕のように、「女性1人が生涯に産む子の推定人数は過去最低を更新したことが問題である」として自民党が2014年年末の衆院選公約の柱の1つに「人口減少に歯止めをかけることを目的として地方が主役の『地方創生』」を示したり、㉑のように、立憲民主党が少子化・人口減少・東京一極集中の流れを止めて国に人口戦略を総合的に推進する体制を整えると主張したり、㉛のように、青森市開催の全国知事会議が人口減対策に最優先で取り組むよう国に求めたりしていることで、これでは、地方に女性が仕事で自己実現できるような働きたくなる場所が増えないのは当然のことなのだ。 つまり、⑮⑰㉕㉛のように、「人口減が問題だから、生涯に産む子の数を増やせ」とか、㉞のように、「知事会が結婚を推奨する」などというのは、「仕事を通して自己実現したい」と考える女性の自由な選択や生き方を否定する暴力的な発言であり、「女性は、結婚(=家庭責任)・育児・介護で十分に働けない」「女性は昇進に消極的」などという前提が制度設計に組み込まれることで、実際には育児・介護をしておらず昇進に積極的な女性でも、「女性は昇進に不適」と看做されて選択肢を狭められるのである。そして、この手の干渉は周囲との関係が密な地方ほど大きく、これが女性が地方に留まらず、周囲からの古くさい干渉の少ない都市に集まりたがる原因でもあるのだ。 このように、男女雇用機会均等法の理念は、地方に行くほど未だ浸透しておらず、地方自治体は女性職員の採用が進んでも管理職登用は低水準で、女性議員の比率も地方ほど低く、女性議員や女性職員は発言権を持ちにくく、意思決定の場で孤立することさえあって、未だに根強く残る性別役割分業による構造的・文化的障壁があることを、女性は知っていて嫌っているのだ。 そのため、女性を地方に残したいのであれば、まず女性を「産む性」としてのみ捉えるのではなく、女性が男性と同様に敬意をもって扱われ、政治や社会の意思決定の場で遠慮無く発言できるジェンダー平等となる文化や意識構造の再構築が必要なのである。 3)人口減は必然であり、解決可能であること 人口減の問題を声高に主張する人は、⑱⑲⑳㉒のように、「多死時代に入って人口が2024年だけで約92万人減少した」「与党政権が人口減に歯止めといくら連呼しても反転の兆しがない」「地方の人口減少が加速してヒト・モノ・カネの東京一極集中が進む」等と、人口減そのものを問題にしているが、戦後のベビーブームで子どもの数が一気に増えて、1990年代までは「子どもの数は2人まで」という家族計画を推奨していたのだから、日本の人口ピラミッドが坪型になるのは60年前からわかっていたことだ。また、そうでなければ雇用の維持もできなかった。 にもかかわらず、「不動産価格が高くて狭い家にしか住めない」「食料・エネルギーの自給率が低い」等の問題を抱えながら、「人口減少が問題」「不景気だから財政出動が必要」などと主張している人は、同一人物の中で矛盾だらけだ。 そのため、㉝のように、人口減対策に関する提言で、「女性や若者の意見を取り入れ、働き易く子育てし易い環境を整備する」としているのは、「子育てし易いように、非正規やリモートワークなどの多様な働き方ができるようにする」ではなく、「やり甲斐を持って、堂々と仕事ができる魅力的な環境を整備する」に変更した方が良い。また、誰でも年をとるのだから、若者しか見ていない国や地域には住めない。 また、地方における人口減の問題として、⑬⑭㉓のように、「人材不足で道路、上下水道の管理・更新、介護、保険等の行政サービスを1市町村だけでは実施できず、複数の市町村が共同で実施するか、都道府県が市町村を支援する仕組みが不可欠」「この参院選で人口減を前提に行政サービスをどう維持するか、地域社会をどう守るか議論すべき」については、複数の市町村が合理的な範囲で連携や合併すれば済むことである。 そして、これは、30年前の1990年代に行なわれた「三位一体の改革」のうち行政体制の再編と効率化で既に議論したことで、職員不足は広域連携・共同処理・民間委託・応援職員派遣等で解決することになっていたため、将来を見据えてこれらの問題に取り組んでいたのかを、むしろ聞きたい。 なお、㉖のように、国民民主党も大都市圏への人口集中是正策として移住促進・UIJターン促進税制創設・リモート勤務者支援など地方への移住や企業移転を促す税制を提案しているが、(4)1)に書いたとおり、東京への集中は、「政治・行政→インフラ→経済・文化→教育・研究」という循環が歴史的背景を持って有機的に成立しているため、補助金や減税くらいではコストの割に効果が限られるのである。 そのため、私は、リニア新幹線の「長野県駅」付近への首都移転を提案したわけだが、もちろん、㉚のように、多極的で分散型の国土構造を作ることは社会の維持のため不可欠である。その時に、ITを駆使して政府の二重ワークをなくし、AIを使って分散型でも高度なサービスを提供できるようにすれば、地方に住むことはメリットの方が多くてディメリットが少なくなるため、特定の地域に集中しすぎるということはなくなるだろう。 4)人口減解決のKeyは、外国人労働者と難民を含む移民である 首都移転を決め、政治や行政を移転するためには、首都の建設が必要になるが、今度こそ、最初から道路を広くとり、緑の多い自然豊かな町並みにして、21世紀型の交通インフラを張り巡らせなければならない。そのため、既に開発が進んだ現在の“都会”はむしろやりにくいのである。 政治や行政を移転すれば、大企業や金融機関の本社(大きい必要は無い)が集まってきて、お互いの情報交換が容易になるため、経済の要になり、投資が行なわれて雇用も生まれる。この時に、自然が素晴らしい新天地に一流の教育施設や研究施設を集めれば、文字通り「Japan Valley(JPN Valley)」もしくは「Shinsyu Valley」と呼ばれる最先端の都市を造れるだろう。 しかし、新首都を建設して必要な施設を作ったり、松本空港を拡張したり、リニア建設を急いだりするには、リーズナブルな賃金の労働力を多く必要とするため、日本人だけでなく、外国人労働者や難民などの移民の力も必要になる。 なお、外国人政策について、全国知事会議は、㉜㉟㊱のように、「国は労働者としてしか見ていないが、自治体は生活者として受け入れている」「外国人の受け入れや定着のために、教育などの環境整備に国が責任を持つよう提言した」「多文化共生の推進も訴えた」としているが、高齢化が進んで労働力不足に悩んでいる地方や産業にとって、解決のKeyは外国人労働者と難民を含む移民であるため、尤もなことである。 徳島県の後藤田知事は、㊳のように、持続可能な社会保障制度の維持が不安定化していることに危機感を持っておられるが、看護・介護・保育・家事支援など労働力不足がネックになっている産業は、リーズナブルな賃金で働いてくれる労働力が必要不可欠だ。また、これらは女性が担うことの多い職種であるため、移民夫妻の場合なら妻の仕事として有望である。 このように、外国人労働力を活用してその地方の産業を進展させれば、㊴の税の偏在はかなり是正される。また、㊲の地方税財政のうち消費税減税については、最初は付加価値税(企業が負担)を導入しようとしたが、経済界の反対で消費税(消費者である個人が負担)になってしまったものである。しかし、その2税の違いを書くと長くなるため、またの機会に譲る。 (5)地方の仕事・日本人のレベル・日本の低成長理由 ← 地方に仕事を通じて自己実現できる魅力的な産業を創るべき 1)自己実現に繋がる仕事の条件 入社した時や事業を開始した時からすべて満たされるというわけにはいかないが、自己実現に繋がる仕事の条件をAIにリストアップさせた後、私が整理したものが下である。 イ)個人の成長と能力発揮が可能 ・継続的教育の機会(教育・研修・キャリアパス) ・創造性・判断力・主体性発揮可能な業務 ロ)社会的意義と貢献の実感 ・社会課題解決や地域・人々への貢献実感 ・利用者・顧客との関係で感謝や評価を獲得 ・公共性・倫理性が高く、誇りを持てる ハ)働きがいと報酬 ・適正な報酬と安定した雇用形態 ・心身の健康を守れる環境 ニ)働くことの文化的・精神的価値 ・伝統・文化の継承と革新に関与可能 ・自己の価値観や人生観と調和 ・「生き方」「表現」として位置づけ可能 ホ)制度的支援 ・職能評価・昇進・異動等が透明・公正 ・業界全体として持続可能性・革新性を追求 2)それでは、地方の産業である農業を魅力的な産業にするには、どうすればよいか 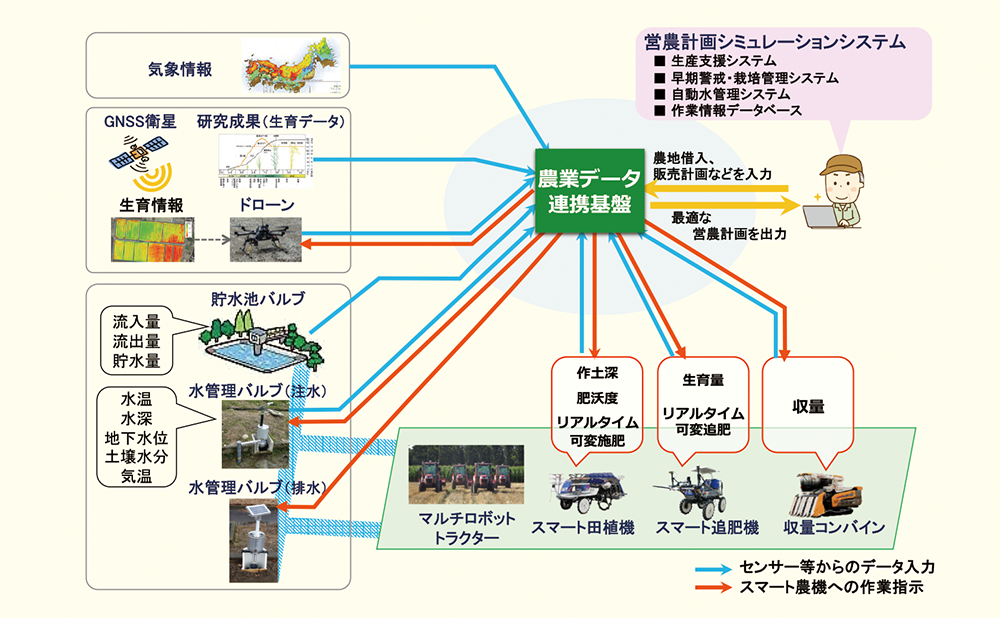  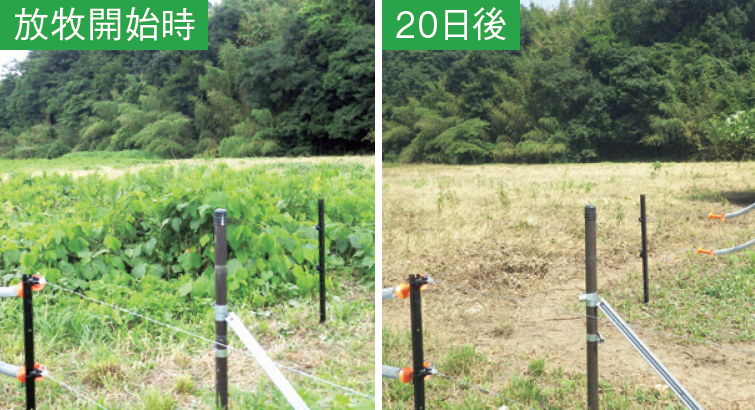 季刊 大林 Agli Food NARO (図の説明:左図は、大林組が作成したスマート農業システムで、中央の図が、実際にスマート農機を使って農作業をしている様子だ。また、右図は、耕作放棄地に肉牛を放牧して20日後には農業を開始できる状態になった状況である) 1)のイ)の「個人の成長と能力発揮」については、ICT・スマート農業の導入による技術革新や多様な職能(経営・販売・観光・教育)を統合した職域設計が挙げられる。 また、ロ)の「社会的意義と貢献の実感」には、国民の暮らしを支えている誇りを実感できることがあるだろう。 さらに、ハ)の「働きがいと報酬」については、6次産業化・直販・ブランド化・再エネ電力の販売等による農業収益の改善や季節労働・繁閑差への対応による収入の安定化がKeyであり、それには地域間連携による人材の循環や研修制度の充実、地域産業とのネットワーク構築が考えられる。 そして、二)の働くことの文化的・精神的価値には、「自然を守りながら自然と共に生き、イノベーションにも携われる」ということが挙げられそうだ。 なお、農業には、女性・外国人・若者・高齢者・障がい者が、その長所を活かして容易に活躍できる素地がある。そのため、国がキャリアを継続して永住可能な特定技能制度を整備し、地方自治体が住居・教育等の生活基盤を整備して、農業を従来の3K「きつい、汚い、危険」で「低賃金・補助金なしでは成り立たない」仕事から、新3K「感動・かっこいい・稼げる」と3Y「やりがい・役立つ・夢がある」仕事に変えられることも重要である。 このような中、*4-4-1は、①コメ不足と価格高騰が消費者に不安を与え、随意契約の政府備蓄米放出で落ち着いたが対症療法 ②農家・消費者の双方が安心できるコメ政策必要 ③転作奨励金等を見直して増産に転換し、農家の所得安定と両立させるべき ④米価高騰で「コメの生産量が足りない」という疑念 ⑤「訪日客による外食産業の需要拡大で消費量は減っていない」との指摘 ⑥卸売業者が何重にも関与する流通過程での価格水準不明確 ⑦生産者の自家消費や知人らに配る縁故米の把握できず ⑧石破首相はコメ輸出の拡大を念頭に「増産にかじを切る」と強調 ⑨これまで農政は生産量を抑えて価格維持する手法で、減反政策終了後も人口減によるコメ消費減を見越して飼料米・加工米への転換を促した ⑩立民は水田2.3千円/a、国民は稲作農家に1.5千円/a支給を唱え ⑪支援が農地集約や大規模化の動きを妨げる ⑫農業の担い手は急ピッチで高齢化、担い手不足の深刻化に歯止めをかける対策も必要 ⑬自民党は土地改良・農地集約、デジタル技術導入のため、思い切った予算を確保すると公約 ⑭立民は就農支援資金を10倍に拡充して都市部からの移住を後押ししようとする ⑮国民は若者の新規参入を促すため直接支払制度に「青年農業者加算」を設け、兼業農家も支援対象に ⑯コメ増産や農家所得を支える財源も課題 ⑰農政改革に伴う農業予算の組み替えや洗い直しを検討すべき ⑱日本維新の会は「ミニマムアクセス」の枠外で輸入するコメの関税を時限的に引き下げると訴え ⑲政府はコメ輸出拡大を目標にするが農産物の海外販路開拓は簡単ではなく、良い品質のコメを決められた時期に契約通り出荷することを輸出先から求められる と記載している。 このうち⑨の生産量を抑えて価格を維持する政策は、国際価格より高い分だけ消費者に負担を強いている上、輸出しようにも国際競争力がないという問題を生んでいる。しかし、⑩の水田や稲作農家に1.5~2.3千円/aを支給するやり方では、⑪のように、農地集約や大規模化の動きを妨げる結果、日本の農業全体が低収益・非効率なまま停滞する上に、⑯のように、コメ増産や農家所得を支える財源が問題である。 また、国から補助金を貰わなければ成り立たないような仕事に、新3K「感動・かっこいい・稼げる」は見いだせないため、⑭⑮のように、就農支援資金を10倍にしても、都市部から移住して農業に新規参入したい若者は限られる。つまり、農協や行政による管理が強くて経営の自由度が低い現在の農業は、自由市場で工夫次第で稼げる産業として成長しにくいため、3Y「やりがい・役立つ・夢がある」の達成も難しいのだ。 そして、これが、⑫のように、若者の農業参入が少なく、農業の担い手の高齢化が進んだ原因であるため、⑬⑰のように、土地改良・農地集約、デジタル技術導入のための予算に農業予算を組み替え、農業改革を進めることが重要なのである。 その農業改革には、⑥のように何重にも卸売業者が関与する人材及びコストの無駄を省くため、規模小売店等が農業法人を作って自らのブランドで米その他の作物を作って加工や販売を行なうのが、資本力・販売戦略があって国際競争力がついて、⑧⑲の問題が解決する。さらに、関係する製造業・サービス業が農業法人を作って従業員を農業に従事させると、実際に農作業をしながら必要な機器を考えたり、疲れた従業員をリフレッシュさせたりもできるので一石二鳥だ。 そのため、⑱のように、日本維新の会が「ミニマムアクセス」の枠外で輸入するコメの関税を時限的に引き下げると訴えたことについて、私もこれが良いと思う。本来なら1993年にGATTウルグアイ・ラウンドの農業合意によって日本はコメの輸入自由化を受け入れ、1995年には食管法が廃止され、それから30年も経過しているため、現在は関税0%でもおかしくないのである。そのため、現在の日本の農業者(基幹的農業従事者)の平均年齢が約69.2歳で65歳以上の割合が70%以上であることを考慮しても、今後10年かけて段階的に0%にすれば十分である。 なお、①のように、コメ不足でコメの価格が2倍以上に高騰すれば、日頃はおとなしい消費者も怒りを覚えてコメの消費を減らすので、随意契約で政府備蓄米を放出したのはひとまず良かったが、コメだけ食べて必要な栄養素がとれるわけでもないのに、②③のように、「農家・消費者の双方が安心できるコメ政策のためコメのみを優遇して農家の所得を安定させよう」と考えるのは、いくら何でも勉強不足すぎる。 また、④⑤⑦のように、農協や行政による管理は、予算や補助金の獲得に専念しており、本当に考えるべき要素が抜けすぎているため、早急に止めて情報提供・生産支援・販売支援へのバックアップに留めるのが良い。 3)地方の有望産業である林業は魅力的な産業にできるか  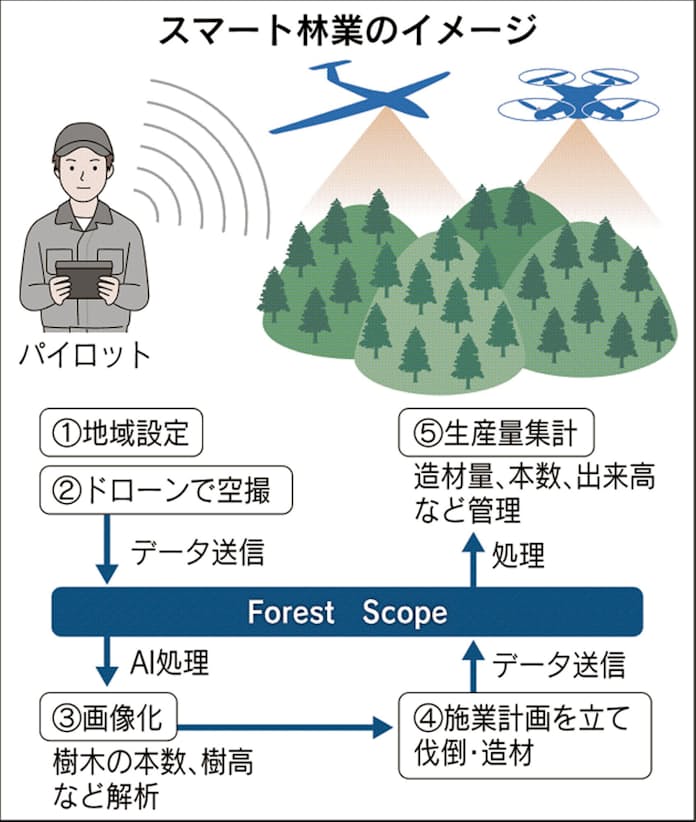  ドローンBiz 2018.8.6日経新聞 Forest Journal (図の説明:左図は、林業を成長産業化させるための森林管理のサイクルを示したもので、中央の図が、航空レーザー・ドローン・衛星画像を使ったスマート林業のイメージだ。そして、右図が、林業用ハーベスターを使用して伐採している様子である) 日本は、国土の約66%(国土面積:約3,780万ha、森林面積:約2,500万ha)が森林で、トドマツ・エゾマツが豊富な北海道約8〜9億m³、スギ・カラマツ中心の岩手県約4〜5億m³、カラマツ・ヒノキ・スギ等の多様な樹種がある長野県約4〜4.5億m³、ヒノキ・スギの人工林が多い岐阜県約3〜3.5億m³、スギ・ヒノキ中心の高知県約3〜3.5億m³、スギの蓄積が多い熊本県約3.5〜4億m³など、北海道・東北・中部山岳地帯・四国・九州は、森林面積も伐採可能な木材の蓄積量も高水準である(林野庁の統計ページ 、 e-Statの都道府県別統計 参照)。 そのため、国産材の活用は地域経済の再生に有効なのだが、現在の日本は、伐採可能な段階に達した人工林の蓄積量が約33億m³(2017年時点)で、年間木材使用量は約7,000万m³程度であるにもかかわらず、木材自給率は約35.8%(2022年)にすぎず、豊富な木材資源があるのに外材依存が続いている状況だ。 これまで国産材が使われてこなかった理由は、i)コストの高さ:伐採に道づくりから始めるため、運搬・加工に多額の費用がかかったこと ii)若者の就業忌避:収益性・安全性・社会的評価の低さが原因で、林業従事者の高齢化と担い手不足が進んだこと iii)外材との価格競争で敗北:円高と輸入自由化によって安価な外国産材に市場を奪われたこと iv)流通の非効率と加工インフラの不足 v)生活者のニーズ(都市型住まい・価格・デザイン)とのずれ 等が原因である。 一方、フィンランドは、国土の約70%が森林で森林資源を国家戦略の柱に位置づけており、バイオ製品・バイオマテリアルへの転換で木材の付加価値を最大化したり、森林のデジタル管理で持続可能な伐採を実現したり、森林所有者を組織化して森林組合による情報提供やマッチング支援を活発に行なったりしている。 また、スウェーデンは、高収益で持続可能な林業をめざして適切な伐採と植林により持続性を確保し、林業を外貨獲得産業として位置付けることによって、年間100億ドル以上の外貨収入を得たり、林業用ハーベスター導入や廃材のバイオマス活用を行なったりしている。 さらに、オーストリアは、効率化と規模の経済を追求し、所有林の集約化によって効率的な森林整備と運搬を実現し、大型製材工場の整備(年間50万㎥以上)で木材供給を安定化し、森林整備と運搬の一体化で作業効率と収益性を向上させたりしている。 そのため、海外の好事例からの日本への示唆は、森林所有者の協力で所有林を集約・大規模化し、航空レーザー・ドローン・衛星画像を使ったスマート管理を行い、林業用ハーベスターを使用して作業を効率化し、工業製品化された安価な木材製品を増やし、流通の無駄をなくして、収穫した木材を高付加価値で使うことである。そうすれば、林業もまた、新3K「感動・かっこいい・稼げる」と3Y「やりがい・役立つ・夢がある」の仕事に変えられるのだ。 なお、私はマンションに住んでいるため、日本家具よりも北欧家具や北欧カーテンの方が部屋にマッチするのだが、北欧では、女性が高い割合で社会の意思決定する立場に進出しているためか、生活者の視点で、住まいの質を高めたり、家具や建材のデザインを決めたりしているように見える。つまり、日本と違って、制度や教育が、デザイン性や創造性を備えた工業製品化を後押ししているわけである。 このような中、*4-4-2は、①長野県林業大学校はドローン操作実習等の新カリキュラムを2026年度から導入 ②林業は人手不足や従事者の高齢化が深刻で、機械化による生産性向上が急務 ③スマート林業や林業経営を習得する新たなカリキュラムで多様な学びのニーズに対応し、即戦力を求める産業界の需要に応える ④新設するのは企業経営と高所作業の2科目で、ほかにスマート林業への対応で林業機械学等の実習を強化 ⑤実習を通じてドローン操作は国家資格の二等無人航空機操縦士を取得できるようにする ⑥進路に応じて2年次でのコースを選択できるよう再編し、マネジメントコースとスペシャリストコースを設ける としている。 林業に使う最新技術は、林野庁・大学・民間企業が連携して開発・実証を進めている下のようなものがあるため、林業大学校は、森林科学・育林技術だけでなく、最新の機器を使いこなせるかっこよくて役に立つ卒業生を輩出しなければならない。 A)センサー測定技術: ・ドローンによるレーザー計測:森林の地形・樹高・蓄積量を高精度で把握 ・地上レーザー(LiDAR):GNSSが届かない急斜面でも3D地形データ取得 ・スマートチェンソー:GPS・加速度・ジャイロセンサー搭載で作業状況を記録 B) 機械・ロボティクス ・ラジコン式伐倒作業車「ラプトル」:急傾斜地での伐倒・搬出を遠隔操作 ・自動走行フォワーダ:搬出作業の自動化で省力化 ・ロボットアームによる伐採:危険作業の代替手段として注目 C) AI・デジタル技術 ・AI地形解析:最適な作業路網を自動設計 ・森林クラウド:森林情報のデジタル管理・共有 ・ブロックチェーン・トレーサビリティ:木材の合法性やCO₂吸収量などの情報を可視化 D) ドローン活用 ・苗木運搬・播種:1時間で500本運搬、10aあたり6分で播種可能 ・Swarm Drone(群制御):峡谷地形でも自律飛行 そのため、①~⑤のように、長野県林業大学校がスマート林業や林業経営を習得する新たなカリキュラムで多様な学びのニーズに対応し、即戦力を求める産業界の需要に応えようとしているのは尤もだと思うが、転職を志す多様な出身の若者にも門戸が開かれるとさらに良い。 しかし、⑥のように、学生時代からマネジメントコースとスペシャリストコースに分けるよりは、最初はすべてを学んで経験し、就職してから自然とマネジメントとスペシャリストに分かれるようにしなければ、技術も現場経験も乏しいためマネジメントとして機能しないマネジメント候補者ができてしまうと思う。 4)地方の産業である水産業を魅力的な産業にするには、どうすればよいか 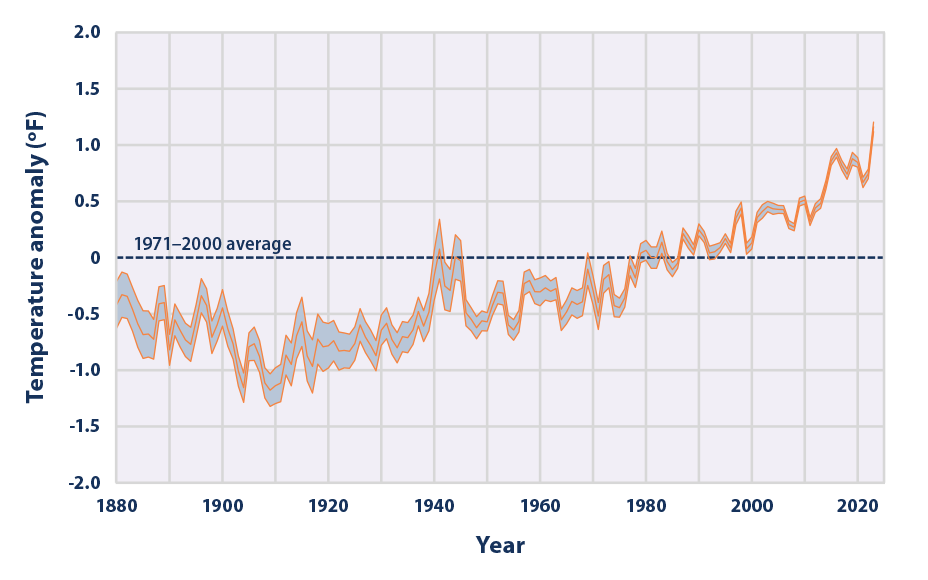 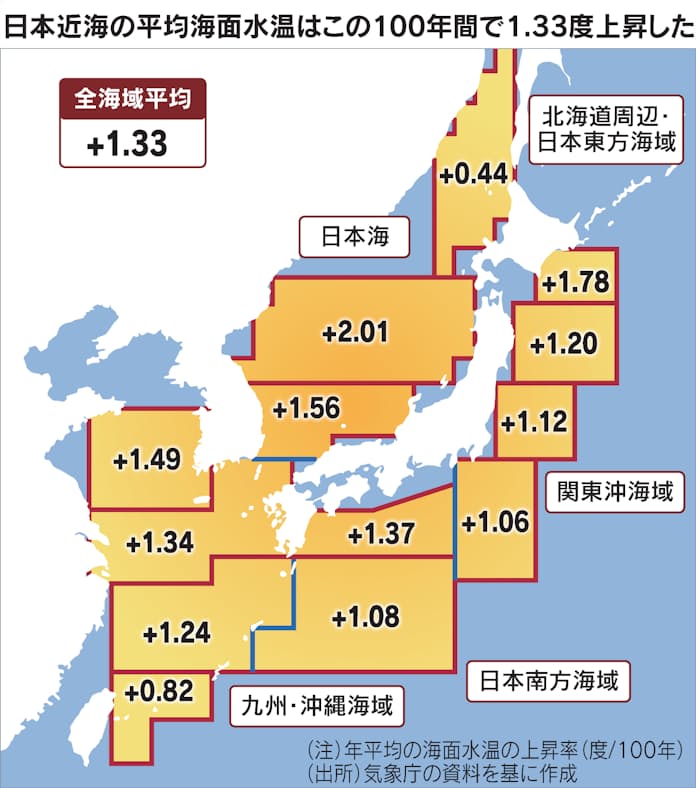 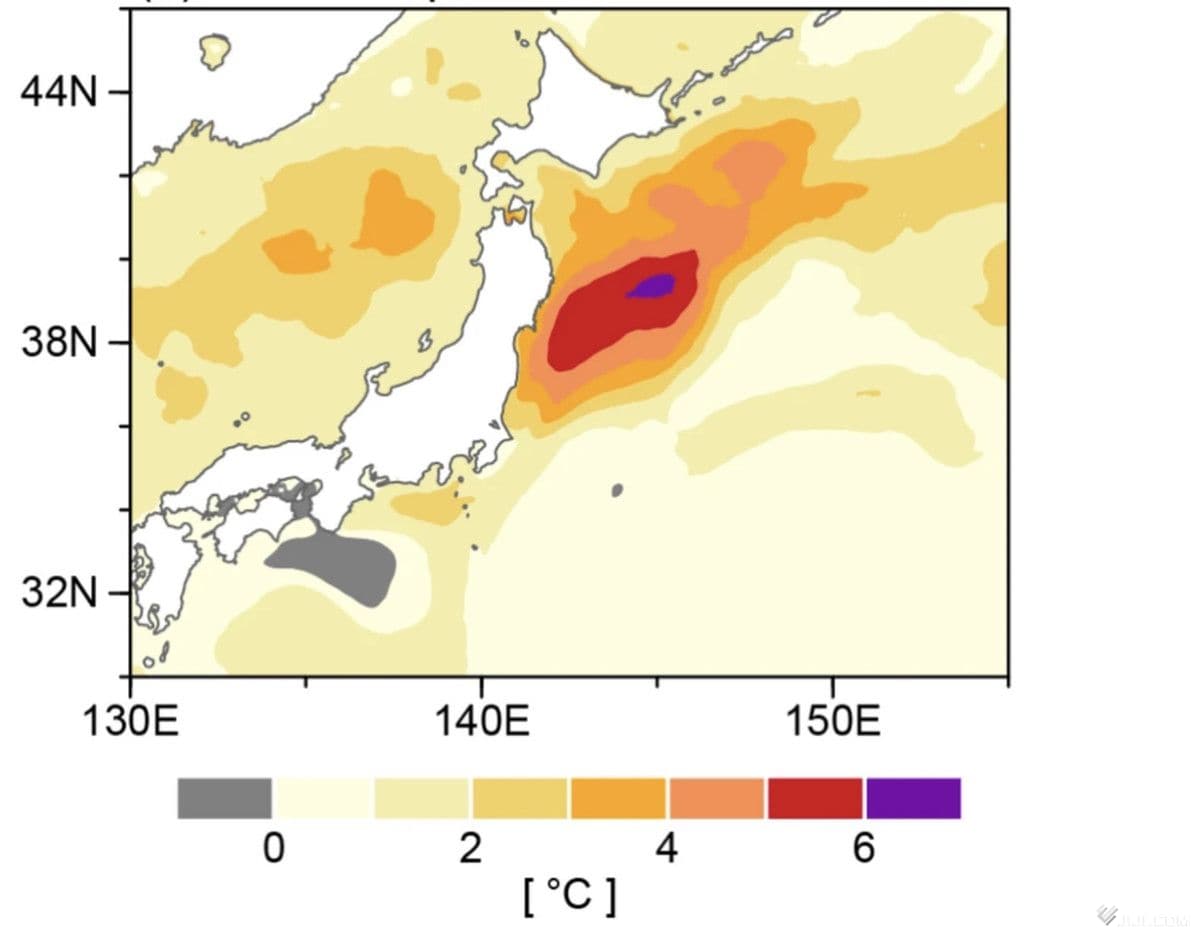 2024EPA 2025.8.5日経新聞 2025.2.14時事 (図の説明:左図のように、世界の平均海水温は1880年以降上昇し続け、1970年以降の上昇が顕著だ。また、中央の図のように、日本近海の海水温は過去100年間で1.33℃上昇し、世界平均《0.62℃上昇》の2倍以上だ。さらに、右図のように、三陸沖の水温が平年より最大6℃も高くなるなど、東北沖や北海道沖での上昇が顕著で、海洋生態系や漁獲高に影響を及ぼしている) 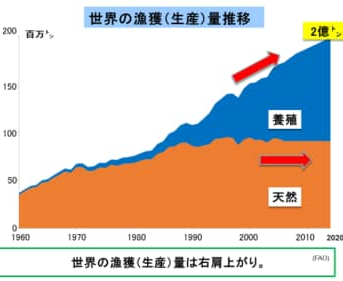 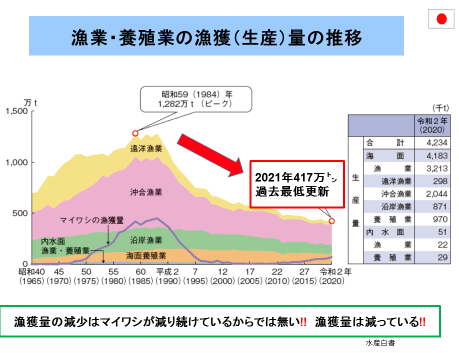 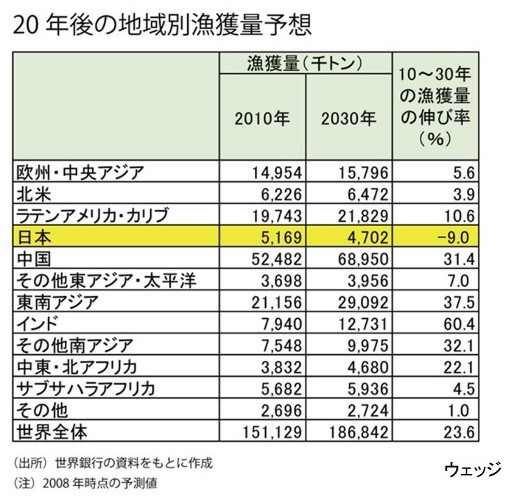 2022.9.13東洋経済 2022.9.13東洋経済 2022.2.17WedgeOnline (図の説明:左図は、世界の漁獲高推移だが、天然ものは資源管理して1990年以降一定、養殖ものが増えて全体として増加している。中央の図は、日本の漁獲高推移だが、1984年の1282万tから2021年には417万tと1/3以下に減少している。右図は、世界銀行資料から作成した2028年の漁獲高だが、世界第6位の排他的経済水域を持っているのに、世界中で日本だけがマイナスになっており、日本の食料戦略は失敗していると言わざるを得ない。何故そうなるのか?) 1.天然漁業について 世界の平均海水温は、1880年以降上昇し続け、特に1970年代以降の上昇が顕著だが、2023年は観測史上最も高温となって平均海水温が20.98℃に達し、台風の強化、サンゴの白化、漁業資源の変化など、海洋生態系に広範な影響を及ぼしている。 その中でも、日本近海の海水温は、上の段の中央の図のように、過去100年間で1.33℃と急激に上昇し、これは世界平均(0.62℃上昇)の2倍以上である。特に、上の段の右図のように、三陸沖の水温が平年より最大6℃も高くなるなど、東北沖や北海道沖での上昇が顕著であり、2023年には記録的な高温が続いて、磯焼けやサンゴの白化など、沿岸の生態系に深刻な影響が出た。また、気温が高くなって豪雨被害が激甚化するなどの影響もあった。 その理由について、*4-4-5は、「『地球温暖化+黒潮流路の変化』によって暖水が東北沿岸まで到達し、「生き物・水産資源・気象にも影響があるはず」とのみ説明しているが、原発からの温排水による海水温上昇もあり、原発の稼働中(温排水により海水温が最大7℃上昇する)には藻場が消失(磯焼け)し、停止中に海藻が回復したという事実もあるため、原発からの温排水の影響も決して見逃せないのである。 そのような中、*4-4-3は、①日本の漁獲量が大幅に減少し、1984年に1,282万tあった漁業・養殖業の生産量は減り続けて、2023年に372万4,300tと最低になった ②減少原因は複数で、i)1982年に「国連海洋法条約」が採択され、200海里内に外国船が勝手に入って漁をしてはいけないことになった ii)その条約により、ピーク時の漁船漁業全体の約4割を占めていた遠洋漁業の生産量が、1990年頃に約1割まで低下した iii)温暖化による海水温上昇が日本近海は世界の海より早く進行し、この100年で1・28度高くなった iv)これにより魚の生息域が変わった v)その結果、日本近海で獲れていた魚が獲れなくなったり、漁獲量が減少したりした など ③海洋環境の異変が進行し続ければ漁獲量減少は今後も進む ④国・自治体・漁業協同組合等は現状の漁獲量減少に歯止めをかけようと、操業期間や漁獲量などの制限を行なったり、養殖業を増やしたりして「持続可能な漁業」の取り組みを行っている ⑤海洋ごみ・海岸に不法投棄されたごみ等による海洋汚染は魚の生態系にも大きな影響を及ぼすため、レジ袋やペットボトルの使用を控えたり、ビーチクリーンや河原の清掃活動に参加したりするなどの海洋環境に貢献できる取り組みで海の資源保全を行うと、魚を食べられる日常を守ることに繋がる 等としている。 このうち①は事実である。しかし、減少原因を、②のi)ii)のように、200海里内に外国船が入って漁ができなくなった「国連海洋法条約」のせいにしているのは、言い訳がすぎる。何故なら、200海里内の面積は日本が世界で6番目に大きく公海で漁をすることもできるからで、世界では下の段の左図のように、資源管理を始める1990年代までは天然ものの漁獲高も増加し、資源管理を始めて以降は養殖ものの漁獲高のみが増加しているからである。 日本では、下の段の中央の図のように、資源管理が始まる1990年代から遠洋漁業も減り始めているが、200海里内で行なう沖合漁業や沿岸漁業はさらに激しく減少しており、海面養殖業もさほど増加していない。その理由は、②のiii) iv) のように、化石燃料の使い過ぎで地球温暖化が進んだと同時に、原発からの温排水の排出もあって、日本近海の海水温上昇が世界の海の2倍の速さで進行して魚の生息域が変わったのに、変化に応じて漁獲する魚種を変えたり、目的の魚がいる場所まで移動したりできなかったため、②のv)の結果になったということなのである。 なお、正しい原因分析をせずに、④のように、資源管理ばかりしてきたため、漁業者は収入減が著しく燃油価格高騰によって出漁コストは増加したため漁業所得が減り、若者が漁業に参入しなくなった。そのため、漁業者の高齢化が進み、多額の資金を要する漁船・漁具のスマート化もできず、現在は悪循環に陥っているのである。 この大きな政策ミスの流れの中で、⑤の海洋ごみや海岸に不法投棄されたごみによる海洋汚染は小さな問題である上、レジ袋やペットボトルは海洋に投棄するより焼却処分やリサイクルにまわされる量の方が大きいため、それらの使用を控えることで漁獲高が上がるとは思えなかった。そして、やはり、それらの使用を規制して控えても、漁獲高は上がっていないのである。つまり、日本政府は、本質的な原因追及と解決を行なわず、国民に不便を強いることのみを行ない、効果が出ない場合は外国のせいにしているわけなのだ。 そのため、日本の水産業を悪循環から好循環に切り替える方策は、イ)国や地方自治体が産学連携して、漁業資源の量や生態系の変化を正確に把握するための科学的調査を実施する ロ)公正中立な科学的調査に基づいて、漁業資源を増やす方法を考え実施する ハ)化石燃料の価格変動に左右されず地方の収入源となる再エネ発電由来のグリーン水素を漁業地帯で量産する 二)漁船をはじめとする船を水素燃料船に変え、漁業者には水素燃料船への買い換え費用を補助する ホ)漁船にスマート機器を積んで漁業の生産性を上げる費用を補助する などが考えられる。 そして、この大きな政策ミスが起こった理由は、a)経産省が原発や化石燃料に固執し、グリーン水素燃料の実装に力を入れてこなかったこと b)既得権益を持つ電力・石油・商社が経産省傘下で、水素燃料への転換に消極的であること c)地方の声・漁業者の声が政策に反映されにくいこと d)政治家や省庁幹部には法学・経済学系の文系男子が多く物理・工学・生物に関する理解が浅いため技術的直感が乏しいこと e)農水省幹部にも法学・経済学系の文系男子が多く、食料安全保証への寄与や栄養学・生物学・生態系に関する知識が乏しいこと 等が挙げられる。つまり、再エネや水素社会は、技術の問題ではなく、政治・行政及び教育の問題なのである。 2.養殖漁業について ウナギが広く国民に食べられてきた理由は、日本の川・湖・田んぼに天然ウナギが広く分布し、筒漁や手づかみで捕獲でき、炭火焼きと甘辛いタレが庶民の人気を博したからである。 では、何故、今では天然ウナギが絶滅危惧種に指定されるほど激減し、養殖ウナギもシラスウナギの乱獲が問題になっているのかと言えば、ニホンウナギはマリアナ諸島付近で産卵すると言われており、黒潮に乗って日本へ来遊し、川を遡上して育った後に、再び海へ戻って産卵する「両側回遊魚」で、海洋環境の変動(海流の変化、水温上昇等)が稚魚の来遊を妨げたり、ダムや堰によって海と川の連続性が失われて遡上・降下が困難になったり、コンクリート護岸によって岩陰や泥底などの隠れ場が消失したりした上に、農薬・生活排水・工業廃水等によって水質が悪化し、川がウナギの生息に適さなくなったことなどが挙げられる。 その上、シラスウナギも養殖用に高値で取引されるため、過剰な捕獲が続いて、特に1970年代以降に漁獲量が激減し、資源の再生産が追いつかなくなったのだそうだ。 そのため、堰に魚道を設置したり、人工産卵場を整備したりするニホンウナギの生息環境改善の取り組みも進行中ではあるが、それだけでは効果が限られるのが現状だ。 そこで、解決策の1つとして、2023年に完全養殖技術が確立され、*4-4-4が、①2024年、国内で流通したウナギは6万941tで、外国産も含めほぼ養殖 ②環境省が2013年に絶滅危惧種に指定したニホンウナギは、マリアナ海溝周辺で産卵し、5~6cmの稚魚に成長し、日本周辺で捕獲されて国内の養殖場で半年~1年半ほど育てられ出荷 ③稚魚は減少傾向で国を挙げて安定供給のための「完全養殖」の研究が進む ④水産研究・教育機構は、2010年に人工稚魚を親魚まで育て、その親の卵を孵化させる完全養殖に世界初の成功 ⑤政府は2050年までに天然稚魚を使わない完全養殖への移行を掲げる ⑥機構とヤンマーホールディングスが稚魚を大量生産できる水槽を開発 ⑦エサもサメの卵から鶏卵や脱脂粉乳等の安価な材料に切り替えて特許取得 ⑧生産コストは2016年に4万円/匹だったが、現在は1,800円/匹に下げたものの天然稚魚の3倍 ⑨水槽の大型化・光熱費削減・エサやり自動化等を進め、将来的には1,000円/匹以下での生産を目指す ⑩ウナギ養殖には、川越市の武州ガスや印章製造販売大手「大谷」など異業種からの参入も相次ぐ と記載している。 このうち①は事実だが、②のうち「ニホンウナギは、マリアナ海溝周辺で産卵する」という点については、生物が地球上の1ヶ所でしか産卵せず、その種が日本内陸の川・湖・田んぼで日常的に見られたというのはむしろ不自然であるため、昔から食べられていたウナギはニホンウナギだけだったのかについても吟味すべきだ。 そもそも、日本の沿岸地域は、新鮮な海水魚を簡単な調理で美味しく食べることができたため、濃い味付けのウナギが好まれるのは新鮮な海水魚を得にくい埼玉県・長野県などの海に面していない地域であり、野生のウナギは泥くささを隠すために、泥抜きをし、炭火で焼くことで香ばしさを加え、濃い味付けにしたのである。そのため、泥底の田んぼや小川で捕獲されたウナギは、ニホンウナギとタウナギが混在していたのではないだろうか。 そして、現在、日本全国で食べられているウナギは、絶滅危惧種に指定されたニホンウナギであるため、③④のように、「完全養殖」のための研究を重ね、⑤⑥⑦⑧⑨⑩のように、日本政府も2050年までに天然稚魚を使わない完全養殖への移行を目指しているのは良いことだ。 しかし、炭火で焼いて香ばしさを加え、タレで濃い味付けにすれば、材料は鶏肉でも太刀魚でもウツボでも、もともと泥臭さはないため、ウナギ同様に美味しい味になりそうである。 3.他産業に犠牲にされてきた漁業 これまで述べてきたように、漁業は、地球温暖化や原発温排水による海水温の上昇、工業廃水・生活排水・農薬・肥料の川や海への流出による水質汚濁、ダムや堰の設置・沿岸部の埋立・港湾の物流拠点化等による開発によって、知らず知らずのうちに犠牲にされてきた。 その理由の第1は、漁業は海上及び海中での活動が中心であるため、都市に住むリーダーや都市住民から見えにくいことである。また、理由の第2は、漁業は生物資源依存型の産業で生態系に影響されるのだが、環境変化が生態系に与える影響や漁業資源の再生産に関わる研究が遅れ、研究結果が出ても製造業や農業が優先されて漁業が無視されてきたことである。 そのため、日本国民に不可欠で食料安全保障のKeyになる産業であるにも関わらず、漁業振興のための制度整備は後回しにされ、獲りすぎを防ぐ資源管理のみが強調されてきた。 そこで、MicrosoftのCopilot君に、「リーダーたちは、何故、生態系を軽視してきたのか」と尋ねたところ、「海は広くて無限という幻想がある」「生態系に関する知識の欠如とその専門家の排除がある」「縦割り行政で環境省や水産庁の知見が経産省や国交省のインフラ・エネルギー政策に反映されにくい」「開発こそが地域振興で漁業は時代遅れという産業ヒエラルキーの固定観念がある」「環境省は、海は食の提供だけではなく気候調整・水質浄化など生活全体を支えると明言している」などの答えが返ってきて、そのとおりだと思った。 2007年公布の海洋基本法(https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033/《私が衆議院議員時代に言い出して作られた》)は、海洋環境の保全と海洋資源の持続的利用の両立を目的とし、「国と地方自治体は、連携して海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を負う」としている。この海洋に関する施策は、海洋汚染を防止し、海洋環境を保全して海洋生態系を保護する施策を推進しているが、海洋の持続可能な利用には、漁業資源だけでなく、鉱物資源の開発及び利用も含む。 すなわち、日本の排他的経済水域内の資源は国有財産であると同時に、国民共有の財産であるため、国主導で資源戦略としてレアメタル等の採掘を行なえば、これまで失政を重ねて積み上げられてきた日本の財政問題は、国民負担を増やして国民を苦しめることなく解決することができると同時に、技術立国としての競争力強化にも繋がるのである。そのため、後は、やろうという意志の問題だけだったのだ。 5)地方に利益をもたらす再エネ電力の普及は、何故、遅いのか *4-1-1の国連事務総長グテレス氏の寄稿は、再エネ普及が単なる環境対策ではなく、経済・社会・安全保障の根幹に関わる「文明の転換」であることを強く訴えておられ、このうち送電網・蓄電池への投資不足は、日本における政策形成にも当てはまる重要な課題である。 内容は、①クリーンエネルギー時代の夜明けだ ②昨年の世界の新設電源のほぼ全てが再エネでクリーンエネルギーへの投資額が2兆ドル(約300兆円) ③今や太陽光・風力が地球上で最も安い電源で、クリーンエネルギーは雇用創出・経済成長の原動力になっている ④化石燃料への補助金はずっと多いが、化石燃料に固執する国は競争力を損なっている ⑤再エネはエネルギー主権と安全保障の確保に繋がる ⑥化石燃料市場は価格変動・供給網の寸断・地政学リスクに左右されるが、太陽光に価格急騰はなく、風力は禁輸対象にならない ⑦エネルギーの自給自足を可能とする再エネ資源は殆どの国に存在する ⑧再エネの力発揮のため、送電網・蓄電池にもっと投資し、エネルギー需要の増加分を再エネで賄うべき ⑨2030年までに世界のデータセンターの電力消費量が日本1カ国の使用量に匹敵する可能性があり、IT企業は再エネで電力を賄うべき ⑩再エネ関連製品の供給網は特定地域に集中しているが、調達先を多様化し、関税を引き下げ、投資協定を見直すべき ⑪人権侵害や環境破壊が横行する重要鉱物の供給網も改革すべき ⑫太陽光発電に適した地域の多いアフリカの昨年の再エネ投資額は世界の2%にすぎず、開発銀行の融資能力を引き上げて途上国に資金を流入させるべき 等である。 また、*4-1-2は、⑫工場・店舗の屋根に置く太陽光パネルの導入目標策定が国内1万以上の事業者に来年度から義務化 ⑬多くの工場は屋根に重いものを置く設計がされておらず、導入拡大は「ペロブスカイト」が有力選択肢 ⑭化石燃料の利用が多い工場・店舗は2026年度から屋根置き太陽光パネルの導入目標を国に報告する必要 ⑮経産省幹部は「太陽光発電の量を増やすことだけが目的ではなく、日本に技術的強みのある次世代型太陽電池の普及を促す目的もある」とする ⑯積水化学が量産に目途をつけて市場に本格導入が始まるペロブスカイト型の普及促進が念頭 ⑰イオングループは2025年2月までに1469カ所の店舗・施設にシリコン製を導入済 ⑱キユーピーも設置可能な既存工場のシリコン製導入をほぼ終了 ⑲キリンホールディングス(HD)はグループ全体の約7割の工場でシリコン製を導入済 ⑳軽量薄型のペロブスカイトは設置場所が広がるため、イオングループも軽量で移設が容易なら施設の壁・窓・屋内への導入を検討 ㉑ユニ・チャームも建物の側面にも設置でき、倉庫等への展開を期待 ㉒1963年にシャープの量産を皮切りに国産品の製造が広がったが、価格に優れた中国製との競争に負け、パナソニックやソーラーフロンティアが国内自社製造から手を引いた ㉓2025年1~3月に国内出荷された太陽光パネルのうち国内生産されたものは約5% ㉔ペロブスカイト型はヨウ素など主要原料を国内調達でき、国内の積水化学やシャープが技術開発を進める ㉕建設業者等は「安価なパネルと比べると投資に対し発電効率が低い」「50年以上運用する工場で耐用年数10~15年程度の採用は難しい」とする ㉖パネルメーカーは「設置条件が定められておらず、軽さを生かした設置が難しいため、ルール整備も必要」「中国勢も一部で量産を始めており、安価な中国勢に流れてしまう懸念も」とする ㉗SOMPOリスクマネジメントの堀内上席コンサルタントは「設置方法でリスクは変わり、分析が必要」とする ㉘供給体制も未熟で、積水化学は現状の生産ペースでは設置目標義務を賄えない恐れ ㉙日本が先行したシリコン製は国内産業としては衰退し、太陽光発電設備の多くが輸入 ㉚ペロブスカイト型も中国勢が勢い 等としている。 このうち①②③は、事実で喜ばしいことだが、日本は㉒㉓㉙のように、シャープが1963年に灯浮標(ブイ)などの海上設備向け向け太陽電池を量産化し、1967年には宇宙用太陽電池の開発に着手し、1976年には太陽電池付電卓を発売して、1992年には量産可能な単結晶太陽電池で世界最高のセル変換効率22%を達成し、1994年には世界初の住宅用太陽光発電システム(系統連系)を商品化して、2000年には生産量が世界一になったにもかかわらず、国内のメディアからくだらない批判の数々を受けて住宅用太陽光発電システムを十分に普及できず、中国製との競争に破れて手を引いたという、あまりにもったいない歴史がある(https://jp.sharp/business/solar/point/history.html 参照)。 その「くだらない批判」とは、i)太陽光発電は原子力発電よりコストが高い ii)メガソーラーは森林を破壊する iii)太陽光発電は、夜間・悪天候時に発電できないため、バックアップ電源が必要である iv)FIT制度による再エネ賦課金で電気料金増加する v)発電効率が悪い vi)大量のパネル廃棄の懸念 等々だ。 しかし、政府補助まで含めた原価総額を比較すれば、i)は真っ赤な嘘で、ii)は設置する場所の選び方と設置方法の工夫で容易に解決できる。また、iii)は蓄電池を設置すれば解決でき、iv)のFIT制度による再エネ賦課金で電気料金が増加しているかのように見えるのは、他の電源と請求書の書き方が違うだけで実際には国の補助金は、④のように化石燃料の方がずっと多い上に、化石燃料に固執する国は競争力を損なっているのだ。さらに、vi)の大量のパネル廃棄の懸念は、使用済核燃料の廃棄や原子炉の廃炉、事故原発の後処理と比較すれば異次元の安さであり、容易さなのである。 また、v)の「発電効率の悪さ」については、㉕でも言われているが、設置単価あたりの発電量や設置可能面積を考慮すれば、数%の発電効率の違いを問題にする必要はない。また、㉕の「50年以上運用する工場で耐用年数10~15年程度の採用は難しい」というのも、鉄筋コンクリート造りの建物の法定耐用年数が50年であったとしても、窓ガラスの耐用年数は10~30年、その建物で使う自動ドアの法定耐用年数は12年など、機材によって耐用年数が異なるのは普通のことであるため、交換しやすい取り付け方をすればよいのである。 このように、原発事故の放射能汚染と違って工夫すれば解決できる問題を挙げ連ねて、反対のための反対をしてきたのが、日本で再エネ発電が遅れた理由なのである。そして、その間、真面目に取り組んできた中国の製品に敗退し、日本国内出荷の約8割が中国製となり、さらに、③のように、世界では太陽光・風力が最も安い電源になっているにもかかわらず、日本だけが普及を遅らせて相変わらず高止まりしているのだ。そのため、何故、こういう行動になるのかが、深く追求すべき問題なのである。 それに加えて、日本でこそ、⑤⑥⑦のように、再エネは化石燃料市場の価格変動・供給網の寸断・地政学リスクに左右されず、エネルギー主権と安全保障の確保に繋がり、エネルギーの自給自足を可能とするのだ。また、⑧のように、「送電網+蓄電池」にもっと投資して充実すれば、集中電源よりエネルギー安全保障に資するし、⑪の重要鉱物は、日本もEEZ内の海底にレアメタルの相当量の埋蔵が確認されているため、むしろ供給側となって国際貢献すべきなのである。 しかし、最近、⑨のデータセンターの電力消費量の多さを理由に原発の必要性を叫ぶ声が大きいが、データセンターを冷やす電力に原発由来の電力を使えば二重に地球を暖めることになるため、データセンター自体を寒冷地に作って節電したり、データセンターの電力消費量を減らしたり、再エネでデータセンターの電力を賄ったりする工夫をすべきである。 なお、*4-1-1は、国連事務総長グテレス氏の寄稿であるため、⑩⑫のように、再エネ関連製品の供給網を開発途上国に作ったり、アフリカには太陽光発電に適した地域が多いのに昨年の再エネ投資額は世界の2%にすぎなかったことから開発銀行の融資能力を引き上げて途上国に資金を流入させて欲しいという主張もあるわけだが、これには開発銀行を通した資金援助や技術移転を通じてさまざまな支援方法が考えられる。 *4-1-2の㉔のように、ペロブスカイト型はヨウ素など主要原料を国内調達でき、国内の積水化学やシャープが技術開発を進めているため、⑫⑬⑭のように、ペロブスカイト型太陽電池を選択肢として義務化するのは良いと思う。しかし、⑮⑯については、主として積水化学のペロブスカイト型太陽電池の普及を促す目的であっても、義務化するのであれば罰則をつけた方が効果が上がる。また、⑰⑱⑲のように、既にシリコン製を導入済の企業も多く、⑳㉑のように、軽量薄型なら設置可能場所が広がるため、壁・窓・屋内・倉庫に設置された建材一体型で良いデザインのペロブスカイト型太陽電池が設置されているのを、早く見たいと思う。 一方で、㉖㉗㉘㉚のように、ルールについて提案しなければならない側の損保会社やパネルメーカーが「設置方法でリスクは変わり、分析が必要」「設置条件が定められておらず、軽さを生かした設置が難しいため、ルール整備も必要」「供給体制が未熟」等と言ってぐずぐずしている間に中国メーカーが量産して安価で気の利いた製品を作り、またまたペロブスカイト型でも中国勢に敗退しそうである。そして、世界はまた、できあがった製品が安価で使い安く、建物の付加価値を上げる方に軍配を上げるだろう。 5)原発再稼働の是非 イ)原発による公害 *4-2-4・*4-2-5は、①東京電力が2030年代初頭に着手を目指していたフクイチ3号機での溶融核燃料(デブリ)の本格取り出しは2037年度以降にずれ込む ②「廃炉の本丸」であるデブリ取り出しは2号機で先行したが、取り出せたのは計1g未満 ③原子力損害賠償・廃炉等支援機構の更田廃炉総括監は「2051年までの廃炉完了目標は実現の目途が立っていない」と強調 ④東電は「(2号機での)採取は性状分析のためで本格取り出しは全く別」「想定通り進捗した場合でも技術的に不透明な部分があり、東電が実現可能性を1~2年かけて精査」 ⑤3号機原子炉建屋北側の廃棄物処理建屋は本格取り出し前に撤去する必要があるが、廃液等が保管されている建屋解体は難工事で、発生するがれきは高線量の廃棄物となるので保管先確保が必要 ⑥デブリ取り出しルートの原子炉建屋1階にも極めて高線量のエリアがあり、制御棒の関連機器が汚染源らしく除染しても線量が下がらない ⑦取り出したデブリの処分先・処分方法は検討さえ始まっていない ⑧東電は2051年までの廃炉完了目標に拘泥するが、見直しは避けられそうにない ⑨廃炉は、政府と東電が2011年12月にまとめた廃炉工程表に基づいて東電が進めており、これまでも使用済核燃料の取り出しなど多くの作業が遅れたが、2051年までの廃炉完了という大枠は維持 ⑩東電は、3号機の燃料デブリの取り出し開始時期は明らかにしたが、作業期間は「不確かさがある」として示さず、1~3号機で推計880tあるデブリのうち1、2号機は工程も工法も決まっていない 等と記載している。 しかし、②は何度も延期してやっと1g取り出せたのであり、③の廃炉完了目標は実現の目途が立たないというのは、チェルノブイリ原発の事例から考えても最初から想定できたことである。そのため、①④は、東電の希望にすぎず、実現可能性はなさそうだ。 そのため、⑤⑥⑦⑩のように、デブリや高線量のがれきの取り出し工程・工法・処分先・処分方法の検討もなく、⑧⑨のように、単に「2051年までの廃炉完了」を目標にしているだけなのだろうが、人間が近づいて制御することが不可能であるため実現可能性のない目標を掲げて、原発に金を使い続けるのは無責任極まりない。 その上、*4-2-6のように、原発は蒸気機関であるため、熱効率は33%(1/3)しかなく、利用したエネルギーの2倍の67%(2/3)のエネルギーを、温廃水として海に捨てており、冷却に使った海水は、膨大な熱とともに放射能や化学物質も伴って海に排出されるのだそうだ。 この無駄に捨てるエネルギーは想像を絶するほど膨大で、1秒間に70tの海水の温度を7℃上昇させるため、逃げることのできない植物や底生生物は死滅し、逃げることができる魚類は温廃水の影響範囲の外に逃げて海の生態系を変えるため、近海の海産資源が打撃を受けるのだそうだ。 つまり、原発は、事故時の放射性物質の広範な拡散で農業や漁業を壊滅させるだけでなく、平時から温廃水を流して海を温めているのである。そのため、日本近海の海水温上昇は世界平均に比べて高く、特に(5)4)に添付した上段の右図のように、福島県沖と日本海の温度上昇は著しく、これで温暖化しなければ、その方がおかしいくらいなのである。なお、温められた海水からは、溶け込んでいたCO₂が大量に放出されるため、その効果も無視できないそうだ。 現在では、熱効率が50%しかなく化石燃料である火力発電を使わなくても、再エネを電力に変える方法が安価になった。そのため、地方を豊かにしながら、数々の公害をなくす再エネを使わない手はないのである。 ロ)既存原発の再稼働と原発新設の論理破綻 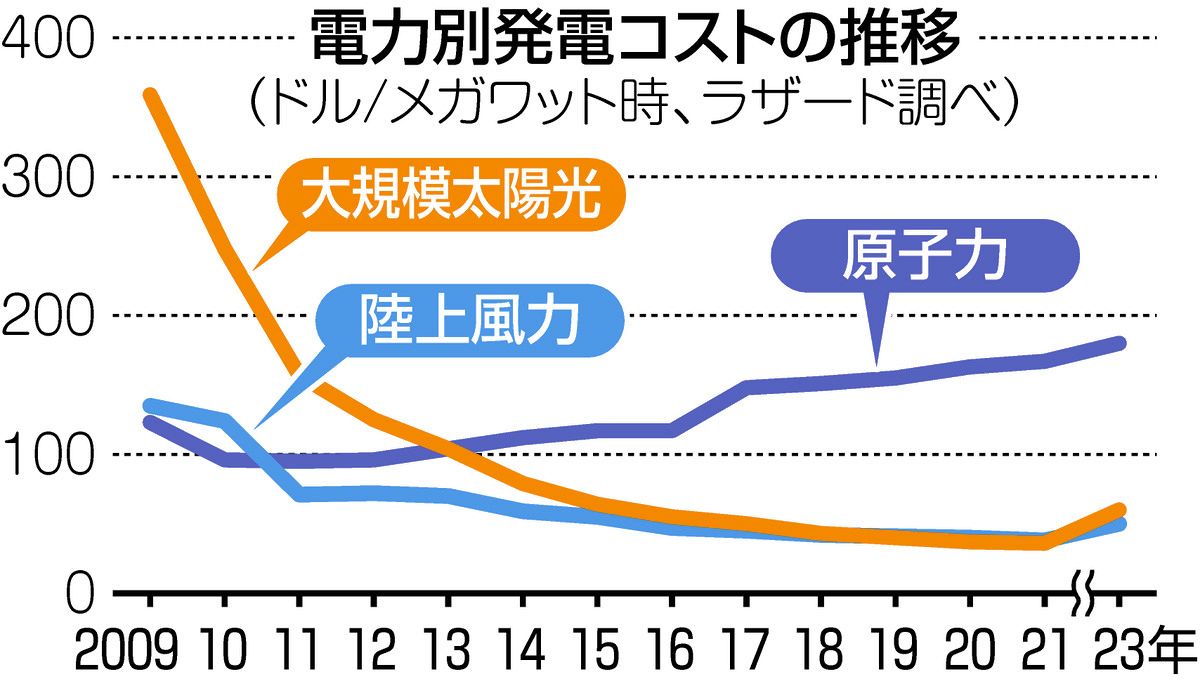 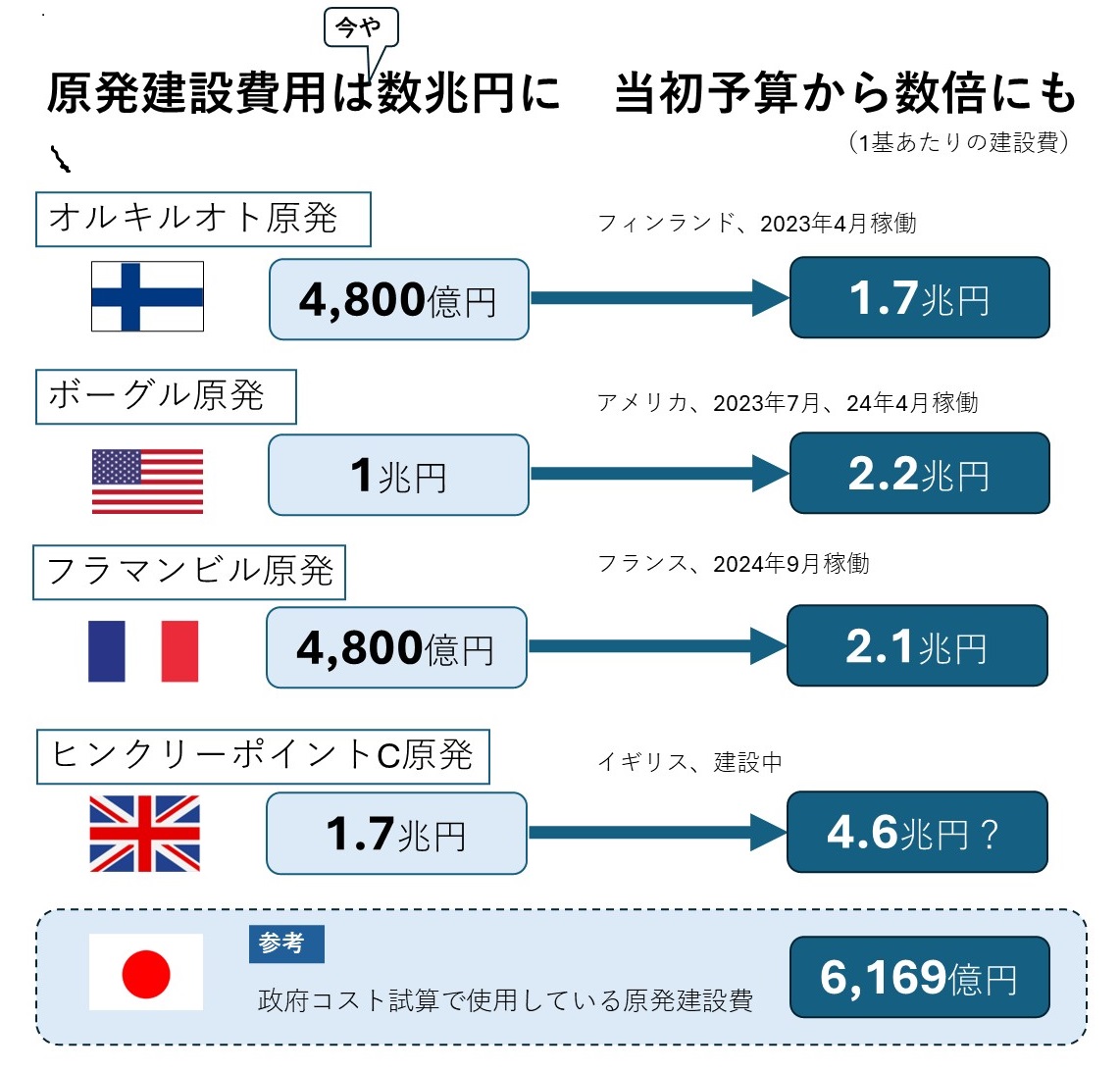 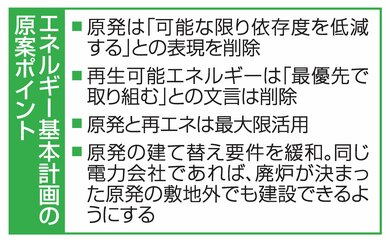 2024.8.21東京新聞 2024.10.10 FoE Japan 2024.12.17新潟日報 (図の説明:左図は、世界の電源別発電コストの推移で、大規模太陽光と陸上風力が最も安く、原発はその3倍近くである。また、中央の図のように、原発の建設費用は世界では兆円単位だが、日本では6千億円程度しか見積もっていない。そのような状況下で、右図のように、日本政府は原発推進に舵をきったのである) 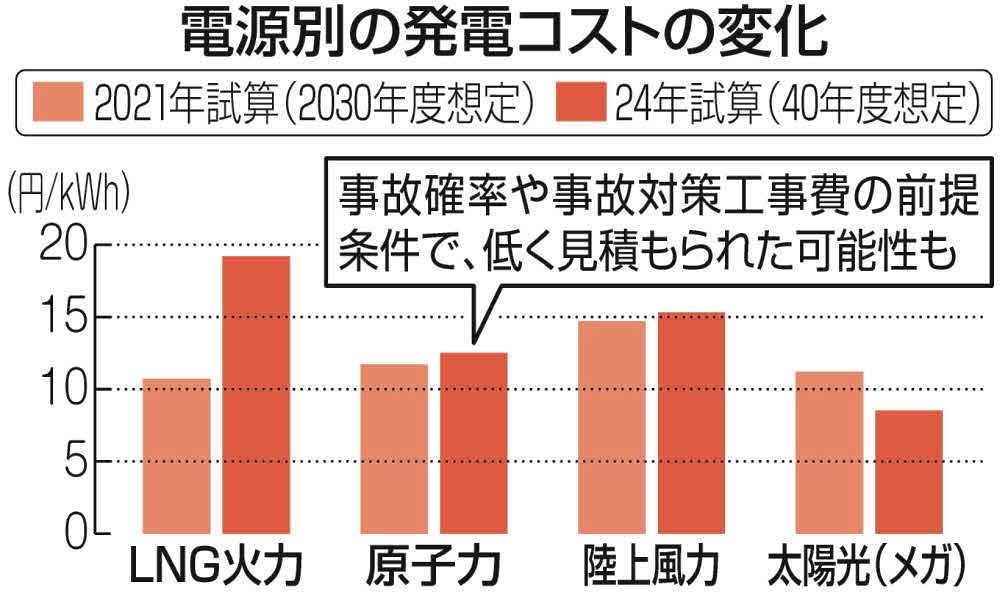 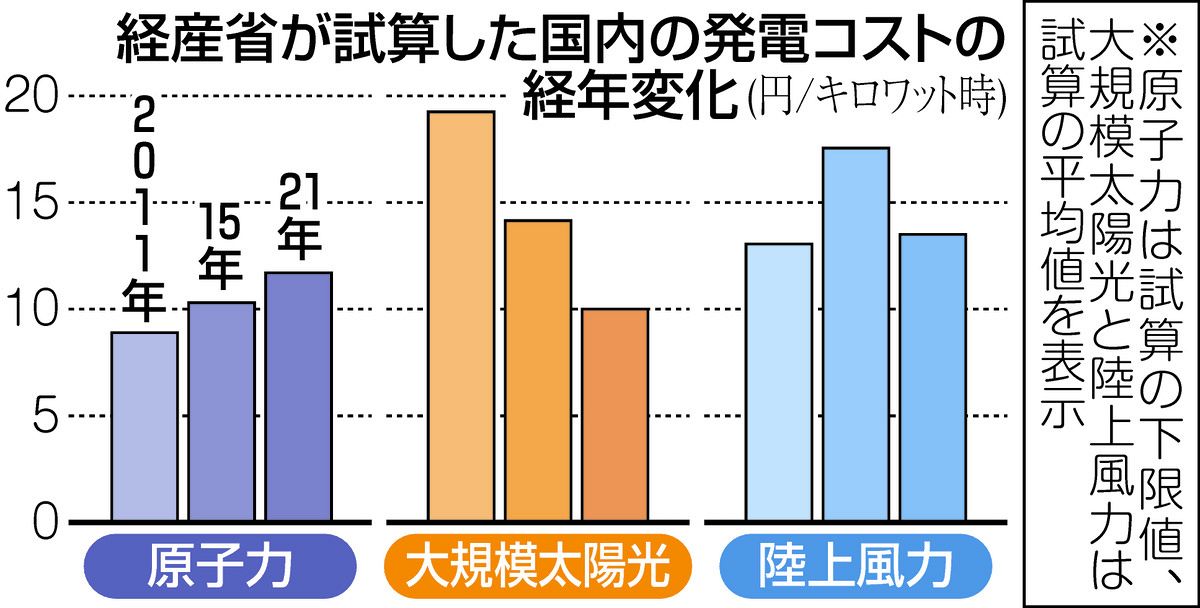 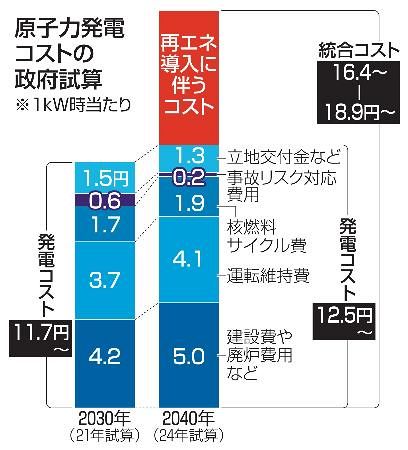 2024.12.27、2024.8.21東京新聞 2024.12.27山陽新聞 (図の説明:左図は、電源別の発電コストの比較だが、原子力は事故確率や事故対策費を低く見積もっている上に、国が負担している費用は全く入っていない。経産省が試算した中央の図も、まるで再エネよりも原子力の方が発電コストが低いかのようだが、原子力は試算の下限値、太陽光と風力は試算の平均値が記載されている。そして、再エネには国が負担するコストはなく、右図のような電力会社の再エネ賦課金だけがあるため、再エネ導入に関するコスト《3.9~6.4円》も、原発のコスト12.5円の1/3~1/2になっているのだ) 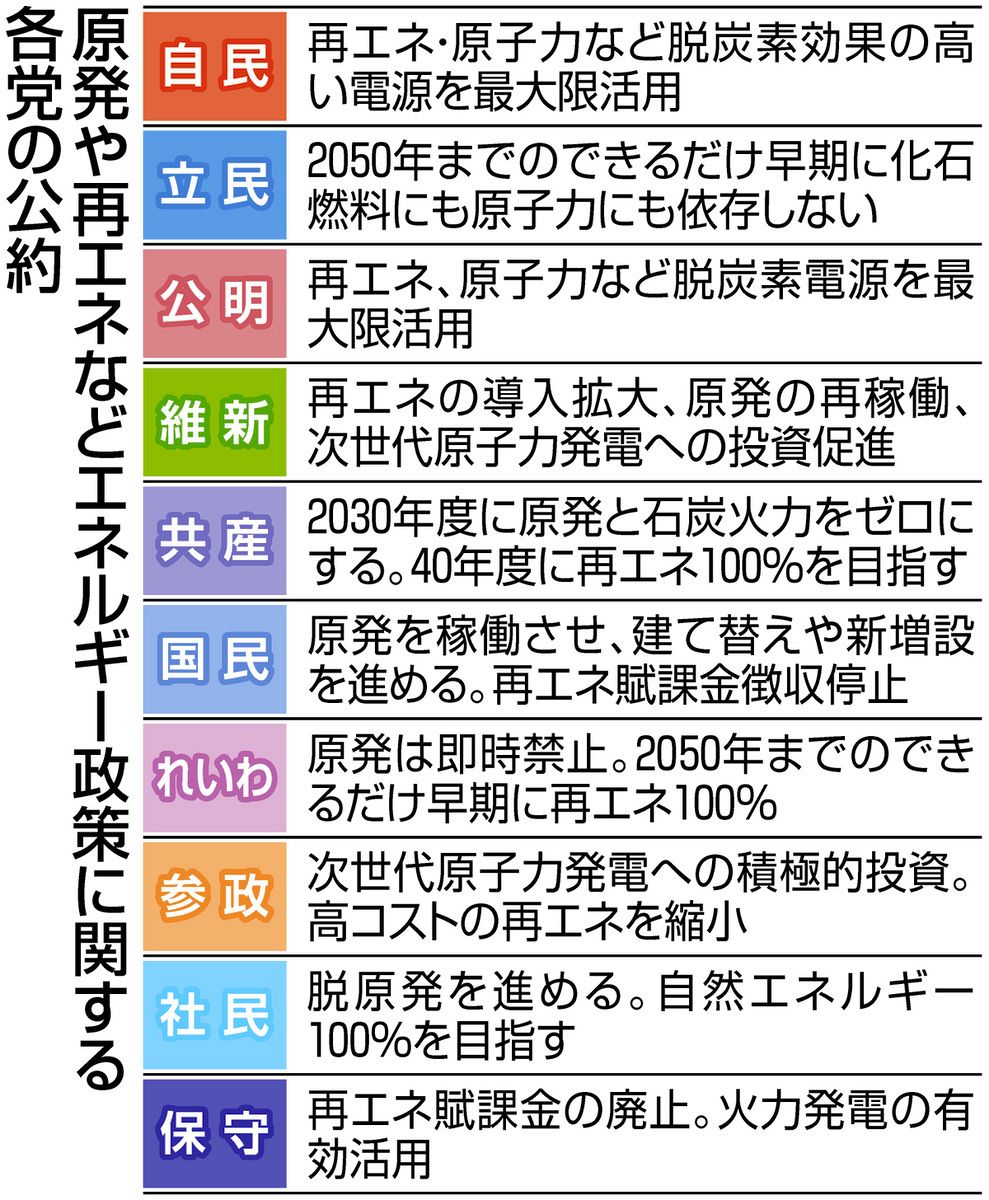 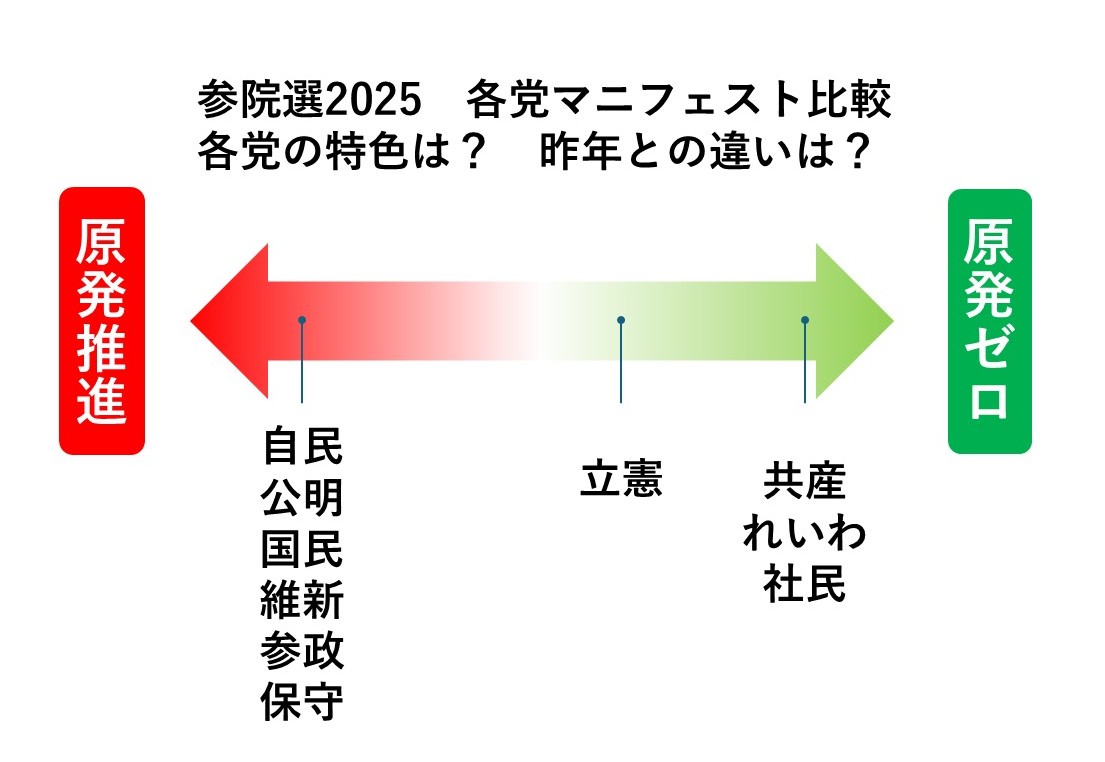 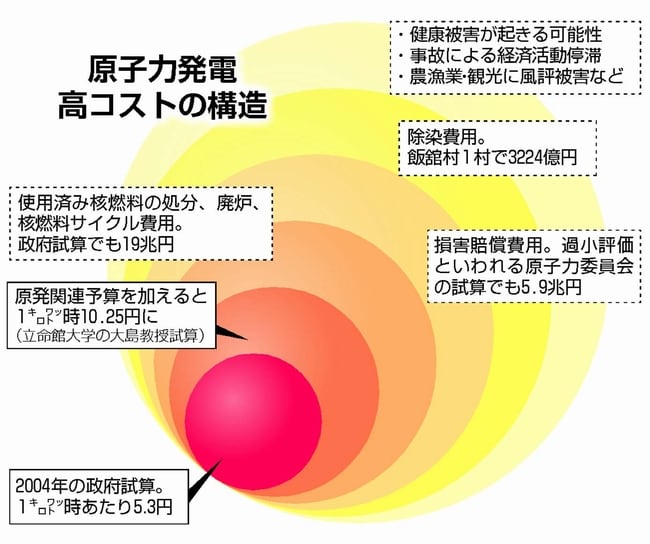 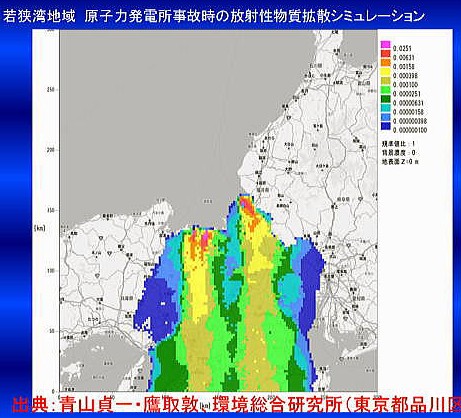 2025.7.13東京新聞 2025.7.2 EoE Japan 2013.7.14日本共産党 環境総合研究所 (図の説明:1番左と左から2番目の図が、2025年参院選における各党の原発政策である。また、右から2番目の図が、2004年時点の政府試算による原発コストで、この時、5.3円/kmhとしていたものが、2024年試算で2040年に12.5円/kmhになるとしているわけだが、どちらも原発関連予算以降は含めていないのだ。そして、1番右の図は、若狭湾岸の原発で事故が起こり、海風の北風が吹いた場合の放射性物質の拡散状況で、日本海側の原発の場合はフクイチと異なり、すべて陸地に落ちるため被害はさらに甚大になる) 上のイ)のような状況の中、*4-2-1は、①参院選では原発と再エネをどこまで活用するかで各党が大きく分かれた ②自民・公明両党は、政府のエネルギー基本計画「原子力など脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」を意識し、安全性確認済み原発の再稼働を「最大限活用」へ方針転換し「可能な限り原発依存度を低減」という文言は削った ③国民民主・日本維新の会・参政党は、再稼働だけでなく、次世代原発の研究・建て替え・新増設に積極的 ④立憲民主は再稼働を容認しつつ、実効性ある避難計画と地元合意が前提で新増設には反対、れいわ・共産は原発ゼロを明確に主張 ⑤立憲・共産・れいわは、将来的に電源構成100%再エネを目指す ⑥自民・公明は、再エネ「最大限導入」とするが数値目標はなし ⑦日本は国土が狭く、平地が少ないため、再エネの適地が限られ、海外に比べて導入コストが高くなりがち ⑧天候に応じて出力が変わる再エネをどう制御し、安定的に電力を供給するかも大きな課題 ⑨国民民主・参政党は再エネ賦課金が国民に大きな負担になっているとして停止・廃止を主張 ⑩AI・データセンターの普及で電力需要は増加し、40年度には発電量が22年度比で1~2割増 等としている。 参院選では、①②③④⑤と上の最下段の1番左及び左から2番目の図のように、原発と再エネをどこまで活用するかで各党の政策が分かれた。しかし、日本のように再エネ資源(地熱・水力・風力・太陽光etc.)の豊富な国で、⑥のように、「再エネでエネルギーの100%を賄う」と言えないのは、著しく高コストである原発を推進して、本気で再エネに取り組んでこなかったからにほかならない。 そして、⑦⑧のように、「日本は国土が狭く、平地が少ないため、再エネの適地が限られ、海外に比べて導入コストが高くなりがち」「天候に応じて出力が変わる再エネは安定的に電力供給できない」などと思考停止状態の言い訳をしているが、自然の恵みである再エネは日本にも豊富で、蓄電池を使えば安定供給も可能になり、原発に依存する必要は殆どなくなるのである。 また、⑨のように、国民民主・参政党は「再エネ賦課金が国民に大きな負担になっている」として、再エネ賦課金の停止・廃止を主張していたが、上の中段の右図のように、電力会社の再エネ購入費が原発コストに上乗せされる形で請求書が書かれているのが誤りなのである。もし、電源別に請求書を作りたいのなら、電源別のコスト明細を作り、コストに応じた単価を記載するべきであるし、電源別には請求しないのであれば、再エネだけ再エネ賦課金として上乗せする記載の仕方をするのは、意図的でおかしいのである。そして、そのくらいのことを、人から言われなければわからないだろうか。 なお、⑩の「AI・データセンターの普及で電力需要は増加し、40年度には発電量が22年度比で1~2割増」については、*4-2-2に関連して詳しく言及する。 *4-2-2は、⑪関西電力の森社長が「美浜原発で原発建て替えに向けた地質等の調査を始める」と発表 ⑫新増設の具体的動きは2011年のフクイチ事故後初 ⑬再始動する新増設を、原発への信頼を取り戻し、AI時代の産業構造に作り替える起点にすべき ⑭森社長は「電力需要はデータセンター(以下“DC”)や半導体産業の急激な成長を背景に伸びる。脱炭素を進めるためにも原子力は必要不可欠」と強調 ⑮安全性を高めた新規制基準の下、電力会社は既存原発の再稼働を進めている ⑯電力需要増大や温暖化ガス削減に向けた脱炭素電源の選択肢として原発に目を向ける時 ⑰再エネを最大限伸ばす努力を諦めてはならないが、太陽光・風力発電の適地の偏りや時間・天候で変化する出力の不安定性から再エネだけでは力不足 ⑱電力需要増大の象徴がAI普及を支えるDCで、日本ではDCの9割が関東・関西に集中 ⑲DCの電力需要増大への対応には、北海道・九州等の電源豊富な地域にDCを集約して光ファイバーで通信する方法と、大都市圏で大量・安価な脱炭素電力を供給する方法がある ⑳米国では巨大IT事業者が自社のDC用に原発から直接電力を買ったり、原発に隣接してDCを置いたりする動きが広がりつつあるので、日本でもDC事業者が新たな原発の建設・運営に参画して一定の電力引き取りを確約するといった選択も可能にしてはどうか 等としている。 ⑪のように、関西電力の森社長は「美浜原発で原発建て替えに向けた地質等の調査を始める」と発表されたそうだが、高浜・大飯・美浜原発(関電、11基)と敦賀原発(日本原電、2基)は、福井県の日本海に面する若狭湾岸に林立しており、この地域は、下の段の1番右の図のように、原発事故時には、近畿地方全域が立ち入り不能や耕作不能に陥る場所である。また、原発は、平時から海に温排水を出していると同時に、事故時には高濃度の放射性物質を含む汚染水が日本海に流出する恐れの高い地域で、それは⑫のフクイチ事故を見れば明らかである。 にもかかわらず、⑭⑯のように、関電の森社長がDCの電力需要と脱炭素を根拠に「原子力は必要不可欠」と強調しておられ、「電力需要増大や温暖化ガス削減に向けた脱炭素電源の選択肢として原発に目を向ける時」などとも書かれているが、イ)で述べたとおり、原発はCO₂より海を暖めて地球温暖化を早めている上に、DC最大の電力消費は冷却なので、高地や寒冷地(北海道・東北・中部地方)にDCをおけば、自然冷却可能で冷却効率が良く、このような場所は再エネの宝庫でもあるのだ。一方、⑱のように、DCを関東・関西に集中させ、福井県の原発から電力を供給するのは、地震のリスクが高い上に、冷却効率が悪く、電力消費も大きい。 また、原発事故時には、「電力遮断→冷却不能」「放射線→避難→立入禁止」等が同時に発生するが、DCは電力・冷却・人的アクセスが不可欠であるため、原発事故はDCを稼働不可の状態にする。さらに、通信は、1秒で地球を何周もできる速度であるため、⑲のように、大都市にDCを作って近くの原発から電力を供給する必要は無いし、電源豊富な地域にDCを集約する必要も無い。それよりは、データをバックアップしたり、分散したりすることによって、セキュリティを高める方がよほど重要なのである。 従って、AIやDCによる電力需要の増加は事実であるが、それを理由に原発新設を正当化するのは論理の飛躍であり、「再エネ+蓄電+地域分散型電源」等の他の選択肢が、電力会社の利益のために排除されている。そのために、嘘のコスト計算を行い、環境を度外視し、AIやDCによる電力需要増を理由に論理を飛躍させて原発新設を正当化するのでは、⑬の「再始動する新増設が原発への信頼を取り戻す」どころか、どういう頭で考えればそういう結論になるのかと思うわけである。 なお、⑮の「安全性を高めた新規制基準」といっても、その基準を守れば原発は決して事故を起こさないと言う人はおらず、もちろん言えもしないため、電力会社が既存原発の再稼働を進めているのを、私たちは再エネで電力を100%賄えるようになるまで容認しているにすぎない。しかし、既に、その時期は来たのだから、⑰のように、再エネを最大限伸ばし、出力の不安定性は蓄電池・水素等でカバーすれば良いだろう。 さらに⑳は、米国では巨大IT事業者が自社のDC用に原発から直接電力を買ったり、原発に隣接してDCを置いたりする動きが広がりつつあると述べているが、日本では原発廃棄物処理の経済性や課題も解決されていないのに、米国では原発の廃棄物はどう処分するのだろうか。「原発はコストが安い」などと言う以上は、建設費・運転費・立地自治体の住民対策費・廃棄物処理費・廃炉費・事故処理費等のすべての費用を加算してコスト計算すべきである。 ハ)それでは、原発立地自治体と既存電力会社はどうすれば良いのか 福井県のような原発立地自治体が原発の再稼働や新設に前のめりになる理由は、交付金依存の財政構造で、自治体予算に占める電源立地交付金の割合が高く、交付金による歳出によって公共事業にも金が落ち、原発関連企業やその下請け企業に依存する雇用が多いことである。 そして、原発立地自治体に税金から交付される交付金には、i)発電所立地自治体に交付される電源三法交付金(原発への財政依存や政策誘導の温床) ii)地域活性化名目の地域振興整備費(効果の乏しい使途が多い) iii)廃炉作業に伴う廃炉支援交付金(廃炉を長期化させて継続的依存に陥る可能性が大きい) 等がある。 しかし、放射線による健康被害や原発温排水による漁業被害があるため、原発立地自治体では、普通の産業を誘致したり、発展させたりすることが難しく、地域の将来像が暗くなって、ますます若者が流出するという悪循環が生まれている。そのため、原発立地自治体でも環境意識の高まりで住民の中に原発に対する懸念や反対の声を持つ人は少なくなく、この「昭和のスキーム」は限界を迎えているのだ。 佐賀県の玄海町を例に挙げれば、原発事故のリスク・廃炉の長期化・温排水による漁場環境の変化等の地域の未来に希望が持てない状況が続き、地域産業の多様性も欠如しているため、原発以外での雇用の選択肢が乏しくなり、若者が「暮らしたい」と思える町づくりがなされず、進学や就職を機に都市部へ流出して戻らないという状況が続いている。 これを、令和型のスキームに転換するには、脱原発依存の地域経済を構築することが必要不可欠で、そのためには、農林漁業・製造業・IT・観光等の多様な産業を育成し、農林漁業地帯の再エネを活かした再エネ電力を創って、その電力を使うモデルが必要なのである。 ちなみに、住民が住みたい町の条件は、i)放射線被害の心配がない安全・安心な生活環境 ii)原発関連以外の産業育成による地域の経済的自立 iii)働く場の多様性 iv)チャレンジ機会の確保 v)充実した教育機関 vi)福祉の充実 vii)自身が町作りに関われる体制 等である。 そのため、下の⑨のように、東電の柏崎刈羽原発6・7号機は技術的に再稼働可能だとしても、事故リスクが0でない以上、地元住民の同意が難しいのは当然なのだ。 そのような中、*4-2-3は玄海原発の地元紙である佐賀新聞の記事であり、内容は、①2025年2月に政府が纏めた新エネルギー基本計画はフクイチ事故の反省から掲げた「可能な限り原発依存度を低減」という文言を削除し原発推進を明確化 ②参院選では原発・エネルギー政策の議論は低調 ③政府は原発の電源構成比を2023年度の8.5%から2040年度に約20%に引き上げ方針 ④現在稼働中の原発は14基で目標達成には30基以上の原発再稼働が必要 ⑤古い原発の建て替え要件も緩和して新設に道を開いた ⑥自民党は既存原発より安全性が高いとする「次世代型」の具体化を掲げ、公明党も「総基数は増えない」として容認 ⑦再エネは最大電源と位置づけ2040年度に40~50% ⑧野党はさまざま ⑨東電の柏崎刈羽原発6・7号機は技術的には再稼働可能だが、地元同意が最大のハードルで、東電に原発を動かす資格があるのかが問われている ⑩廃炉作業は困難を極め、デブリ880tのうち取り出せたのは0.9g ⑪「30~40年で廃炉」という目標達成は厳しい ⑫フクイチ周辺の住民避難も続き、六ケ所村の核燃料サイクル施設や核のごみ最終処分場等の課題も未解決 ⑬柏崎刈羽原発は新潟県や東電だけの問題ではないという意識で注視 ⑭地球温暖化対策やCO₂削減は喫緊の課題 等である。 このうち、①②は、政府が纏めた新エネルギー基本計画は、フクイチ事故の反省から掲げた「可能な限り原発依存度を低減」という文言が削除されて原発推進になり、参院選では原発・エネルギー政策の議論は覆い隠されたことを憂えているが、全くそのとおりだ。 また、③のように、政府は、原発の電源構成比を2040年度にはフクイチ事故前と同じ約20%に引き上げようとし、④⑤⑥のように、目標達成には30基以上の原発再稼働が必要として、古い原発の建て替え要件を緩和して新設に道を開き、自民党は「次世代型原発(革新軽水炉・SMR・高速炉・高温ガス炉・核融合炉)は既存原発より安全性が高い」などとしているが、次世代型原発も基本的には蒸気機関であり、熱エネルギーを電気に変換するものであるため、熱効率(カルノー効率)の限界は避けられず、冷却による環境への熱放出は不可避だ。また、事故時には人間が制御することが困難になり、安全性が向上したとしても事故の確率が0にならないことに変わりはない。 その上、⑧のように、野党の主張はさまざまだが、与党は原発推進をしたため、⑦のように、再エネ比率は2040年度でも40~50%にしかならない。しかし、日本の場合は、再エネ100%も可能であるため、⑭の地球温暖化対策には、原発よりも再エネを使った方が良いのである。 なお、フクイチでは、⑩⑪⑫⑬のように、廃炉作業が困難を極め、デブリ880tのうち取り出せたのは0.9gにすぎず、「30~40年で廃炉」という目標は机上の空論でしかなかった。また、周辺住民の避難生活も続いており、六ケ所村の核燃料サイクル施設も核ごみの最終処分場等の問題も未解決であり、これはフクイチや東電だけの問題ではないのである。 それでは「既存の大手電力会社はどうすれば良いか」については、電気のプロである人材が豊富であるため、日本企業がアフリカ等のインフラ整備が不十分な開発途上国に進出する際に伴走して現地でインフラ整備を支援すれば良い。その際には、再エネ技術を使って地域密着・分散型の電力供給モデルを輸出し、SDGsを中心に据えた事業スキームを展開すれば良いと考える。 そして、アフリカ市場で事業展開をするには、*4-5のように、アフリカからの留学生を奨学金で支援し、卒業後に自社に就職した場合は返済を免除したり、特定技能でアフリカ人を雇用したりして、親日的なアフリカ人を育てるのが効果的だと思う。 6)EVについて ガソリンエンジンの熱効率も非常に低く、日常運転時は約15〜30%(アクセル全開状態が少ないため、効率低下)で、最大熱効率でも約40〜41%(ホンダのハイブリッド車「シビック HEV」で最大41%)だそうだ。そして、エネルギー損失の主な原因は、i)冷却損失(熱として放出) ii) 排気損失(排気ガスに含まれる未利用エネルギー) iii)機械損失(摩擦など) iv)ポンプ損失(吸気・排気のためのエネルギー) v)未燃焼損失(燃料が完全に燃焼しない) 等で、ガソリンの持つエネルギー(熱量)のうちタイヤを回すエネルギーは非常に少ないのだ。 そのうち、特にi) iii)は、ガソリンエンジンが約60〜85%のエネルギーを熱として捨てていることで、都市部の「ヒートアイランド現象」を加速し、交通量の多い地域では局地的な気温上昇も起こって廃熱による都市の局地的温暖化を引き起こしている。 また、ii) v)は、排気ガスによる大気汚染を起こして呼吸器疾患・アレルギー・癌などの原因となり、CO₂は地球を温暖化させて気候変動や海面上昇を引き起こす。また、NOₓやPM(微細な粒子)は、酸性雨・光化学スモッグ等の原因となり、呼吸器疾患のリスクを高める。さらに、不完全燃焼によって発生するCOは人体に有害である上、VOC(揮発性有機化合物)は光化学オキシダントの原因となって特に都市部の大気汚染を悪化させているそうだ。 そのほか、燃料の採掘・精製・輸送時に、環境破壊(原油採掘による生態系破壊・精製過程の化学物質排出・タンカーの座礁など輸送中の事故による海洋汚染)も引き起こしている。 そのため、欧州では2035年以降のガソリン車販売禁止を打ち出す国も多く、EVへの移行が加速しており、日本でも2030年代半ばまでに新車の電動化100%を目指す方針が示されている。 そのような中、*4-3-1は、①日産は東南アジア・中東・中南米を想定し、2026年に中国からEV輸出を始める ②中国で開発・生産され価格・性能の両面で競争力のあるEVセダン「N7」を中心に海外展開を図る ③N7はデザイン・開発・部品の選定まで中国の合弁会社が担った初のEV ④広州工場で生産し価格は約240万円からでBYDの競合製品と比べて同水準 ⑤ソフトウェアに中国企業のAI技術を採用し、国によって利用制限がある ⑥日産は中国のEV開発大手IAT社に出資し、輸出仕様のソフト開発を推進 ⑦東風汽車集団との合弁会社で通関業務 ⑧中国は世界に先駆けてEV化が進み、航続距離・車室の快適性・エンターテインメント機能等の性能が高く、国外でも需要あり としている。 日本は、1995年にドイツのベルリンでCOP1が開かれた時から地球温暖化と温室効果ガス削減を提唱し、それと同時に市場投入できるEVの開発に着手した。そして、1997年に京都で開催されたCOP3では「京都議定書」を採択して先進国にCO₂等の温室効果ガス削減義務を課し、2015年にパリで開かれたCOP21は全加盟国が温室効果ガス削減に参加して気温上昇1.5℃以内を目標とし、2023年にドバイで開かれたCOP28では化石燃料からの脱却に初合意してロス&ダメージ基金の運用を開始した(環境省 https://www.env.go.jp/earth/copcmpcma.html)。 つまり、日本は1995年頃から地球温暖化と排気ガスによる公害を認識してEV開発を進めていたのだが、2010年に日産が世界初のEV普及車「リーフ」を市場投入したにもかかわらず、日本のメディアは屁理屈の数々を重ねてEV普及を阻害し、先鞭をつけて世界のトップランナーになった日産を破綻寸前まで追い込んだのである。馬鹿にも程があるのだ。 そして、この構造は、シャープの太陽光発電など他のイノベーションにも言えることで、その間、科学的根拠に基づいて真面目に取り組んできた国に差をつけられ、①~⑧の事態に陥った。 また、*4-3-2は、⑨日本政府はアフリカ諸国とのFTA締結を検討し、日本車を輸出促進 ⑩第9回アフリカ開発会議で発表 ⑪ケニアなど東部8カ国でつくる「東アフリカ共同体(EAC)」との交渉が候補で、最終目標はアフリカ全体とのFTA締結 ⑫ケニアは港湾が整備されており、日本政府は東アフリカをインド洋を通じた物流の要と位置づけてインド・中東諸国と一体の経済圏を築く ⑬アフリカで人口最大のナイジェリアも候補で原油生産量最大・内需拡大中 ⑭西アフリカの物流・工業のハブとして成長中のガーナも連携相手 ⑮港湾から内陸国へ陸路で運ぶのに複数国を通過し、各国の関税が輸送コストの上昇要因になるのでFTA締結で日本企業のビジネス環境を整備 ⑯日本からの輸出は中古車を含む自動車が多く、輸入は鉱物資源の割合が高い ⑰経団連は韓国・インド・欧州が先行するアフリカとの協定整備の遅れで、世界との競争条件で大きな格差が生じたと指摘 としている。 このうち⑨⑩の「日本政府はアフリカ諸国とFTAを締結する」というのは、⑪⑫⑬⑭及び⑮⑰を考慮した時に重要なことだが、⑨⑯のように、日本車(それも中古車)を輸出して鉱物資源を輸入するのでは、未だに昭和の加工貿易・ガソリン車・アフリカ蔑視から抜け出しておらず、これではアフリカ諸国に感謝されずに中国に完敗することは間違いない。 それより、アフリカにEVの製造拠点を作って、環境に負荷をかけない再エネによる分散発電由来の電力で工場を稼働させ、EVを動かすのが、アフリカの自然保護と工業化を両立させる方法である。なお、日産はじめ日本車は、スタイルにスマートさはないが、悪路でもへこたれない丈夫さを持っているため、アフリカに開発・製造・販売拠点を持つのが合理的だと思う。 また、大手電力会社は、アフリカで再エネによる分散発電を普及させることによって、アフリカに進出する日本企業の伴走をするとともに、地元に電力インフラを普及させれば感謝されるだろう。もちろん、道路や上下水道の専門家も必要であるが、日本でやったのと同じ失敗を繰り返して負の遺産を作らないようにすべきである。 7)地球温暖化と食糧不足 イ)地球温暖化の第一次産業への影響 *4-3-3は、①北極の海氷が急速に減少しており、2027年には9月に殆どなくなる予測も ②冷却源である海氷の減少で地球温暖化が加速 ③1999~2024年までの25年間で9.38cmの海面上昇が確認され、島嶼国の気候難民が気候移住を始めた ④世界各地の陸上に点在する氷床や氷河の減少も深刻で、世界の氷河は2000~2023年に年間平均2,730億トン減少して約1.8cmの海面上昇を引き起こした ⑤海面上昇の6割が氷河や氷床の融解を原因とし、3割は海水温が高くなったことによる海水の膨張 ⑥気候変動に伴う記録的な熱波で山火事が頻発し、専門家は人為的な気候変動による気温・雨量の変化が影響と分析 ⑦2024年の森林焼失面積は1,350万haで前年比13%増で、温暖化を加速させる悪循環 等としている。 上の①②のように、冷却源となる北極の海氷が急速に減少して地球温暖化が加速し、北極海の通行が容易になるのは良いものの、③④⑤のように、海氷融解や氷床・氷河の減少に加え、海水温上昇による海水の膨張で、1999~2024年の25年間に9.38cmの海面上昇が確認されたそうだ。 そのうち、海面上昇の6割は氷河や氷床の融解、3割は海水温上昇による水の膨張が原因であり、島嶼国の気候難民が気候移住を始めたそうだが、日本も沿岸部の海岸線が変化したのは既に知られているところである。しかし、海水温上昇の影響は、海岸線の変化に留まらず、海中の生態系の変化や気象の変化に及んで、水産業や農業に悪影響を与えている。 さらに、人為的な気候変動による気温や雨量の変化で、⑥⑦のように、記録的な熱波による山火事が頻発し、2024年の森林焼失面積は1,350万haで前年比13%増となり、森林資源に悪影響を与えた上、さらに温暖化を加速させるという悪循環に陥っている。 ロ)食料自給率向上の必要性 国連の2024年改訂推計では、2050年の世界人口は96.6億人、世界人口のピークは2084年に102.9億人と予測されており、2050年までの人口増加の大部分は、インド、ナイジェリア、パキスタン等の9カ国で発生すると予測されている。それと同時に、これらの国でも製造業が発展し、食料のニーズが高まるため、日本は、輸入にばかり頼っていると食糧不足に陥るのだ。 *4-3-4は、①農水省は政府の生産拡大意向を反映し、米の生産費の削減のため農地の大区画化を進めてスマート技術の導入を加速する ②労働力不足の対応として、水田に種を直接まく直播を普及する ③高温耐性品種や多収性品種への転換も促す ④主食用米の将来的な需給緩和を懸念する声を踏まえ、産地の自主的な長期計画販売への支援も盛り込んだ ⑤主食用米から麦・大豆、米粉用米などへの転換を促す水活を明記 ⑥「農業構造転換集中対策」は5年間で事業規模2.5兆円、うち国費1.3兆円を見込む としている。 米を例にすると、日本では気温上昇で従来の品種が不作となって米不足に陥ったため、③のように、農水省が高温耐性品種や多収性品種への転換を促しているが、佐賀県では、夏の高温障害に対応して既に佐賀県農業試験研究センターが研究・ 開発を行って2009年には「さがびより」を本格的に栽培し、2010年から特A評価を得ている。そのため、高温耐性の美味しい米は既にあるのである。 また、イネの原種は熱帯植物であるため、ベトナムやタイでは二期作・三期作・直播・乾田栽培は普通に行なわれており、②の直播は、労働力不足対応だけでなく、生産性向上にも効果的なのである。さらに、イネを刈る時に茎を長く残して「ひこばえ」から米を収穫すれば、再度、田植えや直播をする必要が無く二番穂の収穫も早い。そのため、地域の気候条件を加味せず、全国一律で年に1度の田植えを行なって米粒の大きさまで規制するのは食料自給率向上に資さない。 従って、気候が異なる産地の自主的な長期計画が必要なことは言うまでもないが、ニーズがあって売れる製品を作っている農業が、④のように、主食用米の需給緩和を懸念する声を踏まえて税金を使って販売支援を行い、今後も高コスト構造を維持する必要は無いと思う。 さらに、コスト低減には、①のような農地の大区画化とスマート化が必要不可欠だが、これも国際価格までのコスト低減圧力があって初めて、速やかに進むものだ。 なお、⑤のように、米粉のためにわざわざ米粉用米を作らなくても、白濁したり炊飯用に適さなかったりする米を余すところなく使えば資源と労力の無駄が減る上に、生産者の所得も増える。また、“主食”の米だけ食べて生きていける筈がないため、主食用米から麦・大豆等への転換や二毛作の推進は必要不可欠である。 しかし、これまでの農政は、金を使う割に生産性が上がらず、農業は、いつまでも保護を必要とする産業から脱皮することができなかった。そのため、⑥の「農業構造転換集中対策」の「5年間で事業規模2.5兆円、うち国費1.3兆円」は、単なる金のバラマキではなく、生産性向上を通して国際競争に勝てる産業にするための基盤整備に使ってもらいたいのである。 ハ)日本で常識化した食料と資源の無駄使い *4-3-5は、①大手コンビニのミニストップの一部店舗で、店内加工した「手作りおにぎり」や総菜食品の消費期限を偽って販売する不正が見つかった ②原因究明と改善策が実施されるまで、全店で店内加工のおにぎり・総菜・弁当の販売を中止 ③国内全1784店のうち埼玉・東京・愛知・京都・大阪・兵庫・福岡の23店で、店内調理後、ただちに消費期限を計算してラベルを貼るべきところ時間をおいて貼るなどして期限を2~3時間過ぎた商品を販売した ④購入者から健康被害の連絡はない 等としている。 ミニストップの23店舗の行為については、①のように、「消費期限の偽装は食品表示制度の根幹を揺るがす不正で、消費者の信頼を裏切る行為だ」という論調の批判が多いが、消費者である私も「日本は食料自給率が低いのに、消費期限や賞味期限の名の下に、食べられる食品を捨てるのはもったい」と思った。ちなみに、私自身は、雑菌がつかないように気をつけて昼食用に作ったおにぎりが余れば、それを夕食や翌日の朝食に食べることもあり、その際には、冷蔵庫に保管したり、食べる前に殺菌目的で電子レンジをかけたりする。 そのため、消費期限切れや賞味期限切れによる食品ロスについて調べたところ、サプライチェーンに賞味期間の1/3以内で小売店舗に納品する「1/3ルール」があり、賞味期間の1/3以内で納品できなかったものは廃棄されるため、i)賞味期限表示の大括り化(年月日から年月、日時から日など) ii)賞味期限の延長(=納品期限の緩和) iii)フードバンク・子ども食堂への食品提供 などの商慣習の見直しや食品リサイクルを含めた食品ロス削減に取り組んでいるとのことだった(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/syokansyu/torikumi2024.html 農水省 参照)。 また、消費者庁も関係5 府省庁と連携して、事業者と家庭の双方で食品ロス削減を目指して「No Foodloss Project)を展開しているそうだ(https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/265.html 参照)。 従って、②③の国内全1784店のうち埼玉・東京・愛知・京都・大阪・兵庫・福岡の23店舗で、販売時間を2~3時間過ぎた商品を販売したため、全店で店内加工のおにぎり・総菜・弁当の販売を中止するというミニストップの対応は、④のように、健康被害の連絡もないのにヒステリックな対応に思えた。販売時間を2~3時間過ぎたら食べられなくなるほど、雑菌の多い作り方をしたり、保存の仕方をしたりしているのだろうか? つまり、食品ロスは、環境負荷・経済損失・倫理を含む複合的な問題であり、杓子定規な運用は必要以上の社会的コストを生むため、作り方・保存時の温度管理・陳列時の鮮度維持方法に応じて消費期限や賞味期限は変えた方が良いと思われる。 それらの管理を、ミニストップのようなチェーン店が一斉に行なうには、セントラルキッチンで纏めて作って在庫を見ながら少量ずつ配送する方法もあるし、急速冷凍・氷結・真空パックなどと併用すれば冷凍技術の進歩により解凍後も「作りたてのような美味しさ」を保てる食品が増えているため、消費期限や賞味期限を「保存条件別に可変」とすることも可能である。 いや、むしろ浜で水揚げされた魚を即座に加工・急速冷凍して、産地の美味しさを維持した惣菜や弁当を全国に配送するような「産地加工・冷凍・全国配送モデル」の方が、「都市部で原料購入・加工・販売モデル」よりも、安価で新鮮なものを届けられる可能性が高く、そうなれば産地も6次産業化して付加価値を上げることができる。しかし、ここでネックになるのが流通コストなのだ。 現在は何でも物価上昇して運賃も上がったため、人口の多い都市部から遠い場所が損することになっているが、外国人運転手の雇用促進・無人運転制度の整備・EVや燃料電池トラックの普及などを国が誘導し、国産の安価な燃料で安く流通できるようにすべきだし、それは可能である。 (6)日本の規制が促すサービス業の質低下 1)物流について *5-1は、①インターネット通販大手のアマゾンジャパンは1日、指定住所までの「ラストワンマイル」の起点となる配送拠点を岡山・千葉・福岡・石川・北海道・東京の6カ所に新設すると発表 ②入荷から保管、梱包、仕分け、配送までできる当日配送専用の拠点も全国16カ所で展開し、数万点の商品を午後1時までの注文で夜間に配送する ③アマゾンの物流施設では自走式ロボットが商品棚を持ち運び、大量の荷物を効率よく発送する「アマゾンロボティクス」を採用し、ロボットは世界300カ所以上の拠点で計100万台導入されている ④より効率的な動きを実現するため新たな生成AI「ディープフリート」を取り入れ、従来より効率を10%高める ⑤8月に名古屋市に延べ床面積12万5,000m²で西日本最大の拠点を稼働し、壁面にも太陽光発電設備を導入して、発電設備容量5,500kW としている。 このうち①②は、現在でも便利なアマゾン通販の買い物がより便利になるため、消費者として歓迎である。そして、その便利さが、③のように、アマゾン物流施設の自走式ロボットによる「アマゾンロボティクス」による安価で迅速な配達ができているのであれば、顧客第一主義で顧客の便利さを増やしても損なうことなく、さらに効率化しているのでアッパレと言える。 また、④のように、より効率的な動きを実現するため新たな生成AI「ディープフリート」を取り入れて従来より効率を高め、⑤のように、名古屋市で稼働する西日本最大の拠点は、壁面にも太陽光発電設備を導入して発電設備容量5,500kWだそうだが、これが、合理的意志決定を続けて発展していく優良民間企業の経営である。 一方、*5-2は、⑥国交省は、物流業界の人手不足対策として再配達を減らし負担削減に繋げる目的で、宅配便の標準サービスに「置き配(宅配ボックス・玄関前への配送)」を検討(現行ルールは対面受け取り前提で置き配は荷物を受け取る側が選択) ⑦置き配は時間を気にせず受け取れるが、盗難・汚損等のトラブルや不在時に業者が敷地内に立ち入るプライバシーやセキュリティ対策が必要 ⑧トラブル防止のための宅配ボックス設置方法も課題 ⑨国交省幹部は「地域で不可欠な物流サービスを持続可能にするため、今の時代に合った合理的なやり方を生み出したい」と説明 ⑩物流各社は、国交省が作った基本ルールを参考に荷主との契約条件などを盛り込んだ「運送約款」を策定 ⑪物流業界の人手不足が深刻化する中、2024年からトラック運転手の時間外労働規制(年960時間)開始 としている。 国交省は、⑪のように、トラック運転手の時間外労働規制(年960時間)が開始され、物流業界の人手不足が深刻化したため、⑥のように、再配達を減らして運転手の負担削減に繋げるため、対面受け取り前提で置き配は荷物を受け取る側が選択できる宅配便の標準サービスに「置き配(宅配ボックス・玄関前への配送)」を検討するとのことである。 しかし、規制官庁は、生産者を護るための負担を消費者に押しつけることしかできないことがこれでわかる。私がそう言う理由は、2Lのお茶8~9本入りを(重たいから)アマゾンで買って家まで宅配してもらったところ、最近、勝手に遠い場所にあるマンションの宅配ボックスに配達されて、自宅に運べず酷い目にあったことが数回あるからだ。 つまり、宅配を頼む理由は様々であるため、配達員の効率性のみを優先するのではなく、消費者である高齢者・障がい者・育児中の世帯・共働き世帯等のニーズに合った配達をしてもらわなければ困るのだ。そのため、明文化して「宅配ボックス優先」から「利用者選択優先」に転換すべきである。 そうすれば、重い荷物の持ち運びが不要になるため、要支援・要介護サービスも効率化でき、要支援者の自立支援もできて生活の質向上に役立つ。また、自治体の地域包括ケアと連携して、宅配サービスだけでなく、見守りサービスも追加すれば、新たな事業機会になる。 そのような中、⑦は、「置き配は時間を気にせず受け取れる」としているが、留守中に玄関前に置いていかれると留守であることが判明するし、マンションでは⑧の宅配ボックス自体が離れた場所にあったり、玄関前には置くスペースがなかったりする。そのため、⑨⑩の「今の時代に合った合理的なやり方」とは、高齢者・障がい者・育児中の世帯・共働き世帯のそれぞれのニーズに合った配達方法を選択できる「利用者選択優先」の運送約款を作ることである。 そして、「利用者選択優先」を実現するためには、注文時に「重量物は玄関配達希望」「重いものは宅配ボックス不可」などを消費者が明示できるようにしたり、AIで荷物の属性を判定して適切な配達方法を提案(例:「この商品は対面配達推奨」)したりする方法がある。また、地域密着型で顔の見える配達員になれば、柔軟な対応も可能になるだろう。 なお、共働き世帯が増えたことによる再配達増加は、夜間配達(18〜21時)を標準化して、夜間に3時間くらい働きたい人(副業・兼業希望の人、年金が不足する高齢者、学生アルバイト等)を配達員として雇用し、夜間手当を支給すれば解決する。 *5-3は、⑫総務省は、各自治体に「最高AI責任者(Chief AI Officer “CAIO”)」と補佐官の設置を促す ⑬人材確保の観点から複数自治体が共同で専門人材を置くことも可で法的拘束力はなし ⑭自治体は住民情報を扱う部署も多いため、AI学習に個人情報等の機密情報を用いることは禁止する ⑮AIを使って住民の相談を24時間受け付けるサービスなど例示 ⑯AI活用で会議の議事録要約で5割、企画書の作成で3割の業務時間を減らした自治体も ⑰自治体が安全に生成AIを活用できれば、人口減少下で地方行政の効率を高められる としている。 アマゾンが「ロボティクス」を採用して当日配送を可能にしている時代に、総務省は、⑫⑬のように、各自治体に「最高AI責任者」と補佐官の設置を促し、人材確保が困難な自治体は複数自治体が共同で専門人材を置くことも可としているが、この調子では効率化も期待薄である。 しかし、⑭の個人情報保護は重要であるものの、介護認定・要支援認定・母子手帳交付・障害者手帳交付・年齢情報などを自治体内の複数部署から統合すれば、AIが属性を分類して支援が必要になりそうな住民を自動抽出して、「この地域には要介護者7人、要支援高齢者15人、妊娠中3人」などと人数を可視化して、声をかけたり、支援漏れを防いだりすることができ、⑮のように、AIによる住民相談の24時間受け付け(残業代不要、コーヒーブレイクなし)も可能だ。 また、⑯のように、AIを活用すれば、会議の議事録要約で5割、企画書の作成で3割の業務時間を減らすことも可能だそうだが、私は、会議中の声を発言者を区別して拾って文字起こしし、会議の要約までAIができるようになれば、会議の議事録作成とその要約にかかる時間は7~8割削減できると思う。そのため、⑰のように、自治体が本当に生成AIを活用できれば、地方行政の効率は高められるだろう。 2)“法定点呼”について *6-1は、①約75%の郵便局(2391局)で法定点呼がルール通り実施されず、日本郵便が国交省の運送事業許可取り消し処分を受けた ②飲酒運転(4件)・業務中の飲酒・飲酒した配達員の事故も ③取り消しで各地の郵便局にあるトラック・バン約2500台が5年間使用不可に ④虚偽の点呼記録作成・管理者不在時の点呼省略等の不正があり、経営陣・管理職の指示を現場が軽んじる体質 ⑤現場で起きている問題を上層部が把握できていない構造的問題 ⑥郵政民営化後も旧体質が残存する懸念 ⑦企業統治の徹底と取締役会の役割強化が必要 ⑧持ち株会社の日本郵政による監督も必要で、郵便物の減少により日本郵便の2025年3月期決算は42億円赤字だったが、今回の行政処分で収益に打撃が生じるのは確実 ⑨日本郵便は下請け企業からの値上げ要請を拒否して公正取引委員会から行政指導を受け、ゆうちょ銀行の顧客情報の不正利用も発覚して、日本郵政・日本郵便ともトップ交代して、旧郵政官僚が社長に ⑩官業への逆戻りを防ぐためにも改革が急務 としている。 これに加えて、*6-2は、⑪軽自動車約3万2000台にも安全確保命令が出て、国交省の監査が継続中で一定期間の車両使用停止等の行政処分検討中 ⑫総務省が「監督上の命令」を発出 ⑬日本郵便は代替手段として自社の軽自動車活用や外部委託で利用者への影響最小化を目指す ⑭国交省は、行政処分でトラック等の車両が使用できなくなる中でも郵便サービスを維持することや再発防止策の着実な実施・見直しを求めている ⑮日本郵政の株主総会で増田社長が一連の不祥事を陳謝 としている。 さらに、*6-3は、⑯日本郵政の株主総会は株主の質問が点呼問題に集中し、この日で退任する増田社長は「極めて深刻な事態」「再発防止策に取り組み、オペレーション確保に万全を期す」「業績への影響は精査中」とした ⑰株主の怒りは収まらず、(民営化前の)治外法権の意識が残り、法律を守る意識がないのではないか」「管理職の能力の問題ではないか」「危機管理能力が経営陣も現場もないのでは」との指摘も ⑱日本郵便は「郵便やゆうパックのサービスは維持する」と強調 ⑲日本郵便は軽四輪にも一定の処分が出ると身構え、委託範囲の拡大を迫られる可能性 ⑳外部委託拡大や再発防止対策でコストが膨らむ見込み ㉑千田社長は「ゆうパックの値上げは今の時点で一切考えていない」と言い切ったが、大規模な不祥事が業績に影響を及ぼすのは時間の問題 としている。 ここで言われている“法定点呼”とは、国交省令である貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条「貨物自動車運送事業者は、運転者に対して対面等で点呼を行い、酒気帯びの有無や体調等に関する報告を求め、確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者等ごとに点呼を行った旨・報告・確認・指示の内容等を記録し、その記録を一年間保存しなければならない」という規定に基づいて行なわれるものである(貨物自動車運送事業輸送安全規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 参照)。 しかし、法律である貨物自動車運送事業法は第13条・第14条などで「安全確保の義務」を抽象的に規定しているだけで、「点呼」に関する規定はしていないため、「点呼ルール」は、国交省令の貨物自動車運送事業輸送安全規則で具体的に規定されているだけなのだ。そのため、このルールは法律で定められた規定ではなく、省令による指針にすぎないと言える。 従って、①のように、約75%の郵便局(2391局)で点呼がルール通りに実施されなかったからといって、②があったくらいで人身事故等の重大事故を起こしたわけでもないのに、国交省が日本郵便に対し運送事業許可を取り消し、③⑪⑲のように、事業の継続すら危うくする重い処分を下すのはやり過ぎであり、民主主義の罪刑法定主義に反する。そのため、この件に関して行政訴訟をすれば、日本郵便が勝つかも知れない。 また、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条を見ると、小学生の箸の上げ下ろしにまで口を出すような細かい指示だが、霞ヶ関からこのような細かい指示を出しても、現場の実態に合っていないため、④のような“不正”があり、現場が経営陣・管理職の指示を軽んじたのではないかと思う。そのため、私は、権限と責任を現場の管理職に下ろし、現場で状況に応じて適切に対応させた方が良いと思う。 私がこういうことを言う理由は、「最近のゆうパックは、電話をしたらすぐ集荷に来て、ヤマト運輸より早くてサービスが良い」という優れたものだったからで、むしろ競争に負けそうな他の物流会社が足をひっぱったのではないかと思うからである。そのため、⑬⑱のように、日本郵便が代替手段を使って利用者への影響最小化を目指し、郵便やゆうパックのサービスを維持するのは有難いが、⑳㉑のように、競争会社に外部委託すれば競争会社は儲かり、コストがかさんで、消費者の費用負担が増えるのである。 ⑤については、むしろ上層部が消費者のニーズと現場のサービスを理解していない構造的欠陥があり、⑥⑩については、省庁が民間企業の個別の経営に口出しを続ければ、せっかく郵政民営化しても、天下りが復活して実質的に旧来の体質に戻るということなのである。 従って、⑦の企業統治の徹底と取締役会の役割強化は必要だが、天下りの経営者ではアマゾンのような民間企業の合理性は発揮できず、今回のような行きすぎた事業許可取り消しによる⑧のような損失は、結局は、運賃上昇やサービス低下に加え、国民の税金で穴埋めされることによって、国民に皺寄せされる。 なお、⑨によると、日本郵便は下請け企業からの値上げ要請を拒否して公正取引委員会から行政指導を受けたそうだが、⑭の事情もあるため、日本郵便はゆうパックを完全子会社化して下請けを減らし、(ラストワンマイルの運転手が日本語が達者であれば消費者は困らないため)敬虔なイスラム教徒で酒を飲まず、健康な若い男性(外国人労働者)を長距離輸送の運転手として雇用してはどうかと思う。 また、点呼を貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条に従って行なわなかったのは、運送事業者としての規則違反であるため、郵便法や日本郵便株式会社法のユニバーサルサービス義務とは直接関係がない。にもかかわらず、⑫のように、総務省が「監督上の命令」を発出したところを見ると、総務省も国交省と同様、この機に天下りを出したかったのだろうか。 ちなみに、⑮の日本郵政の増田社長は一連の不祥事を陳謝したが、次の日本郵政グループのトップ層は旧郵政省(現在は総務省)出身者で固められているそうだ。そのため、日本郵政の株主総会では、⑯⑰のように、株主の質問が点呼問題に集中したが、民営化前の親方日の丸意識を変えるためには、むしろ新経営陣の構成に着目すべきであった。 (7)日本の教育について 1)初等・中等教育 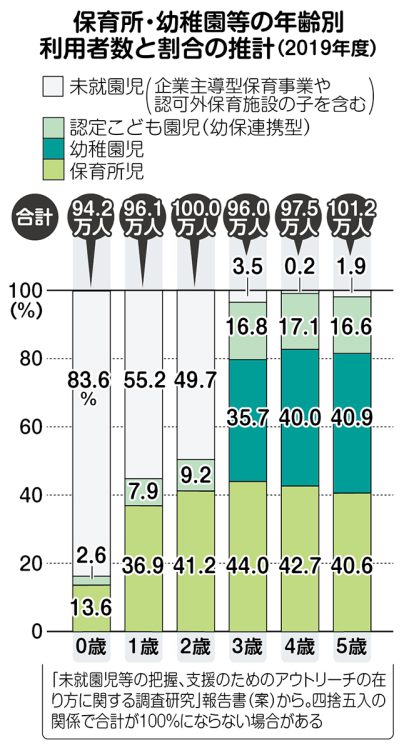 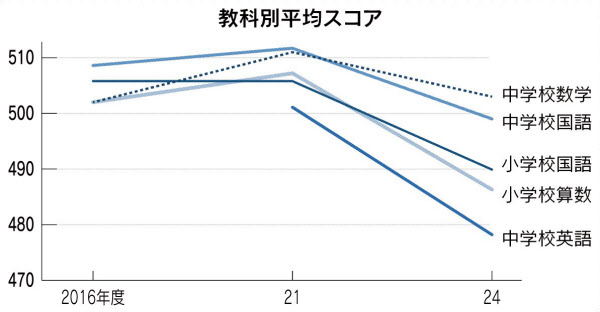 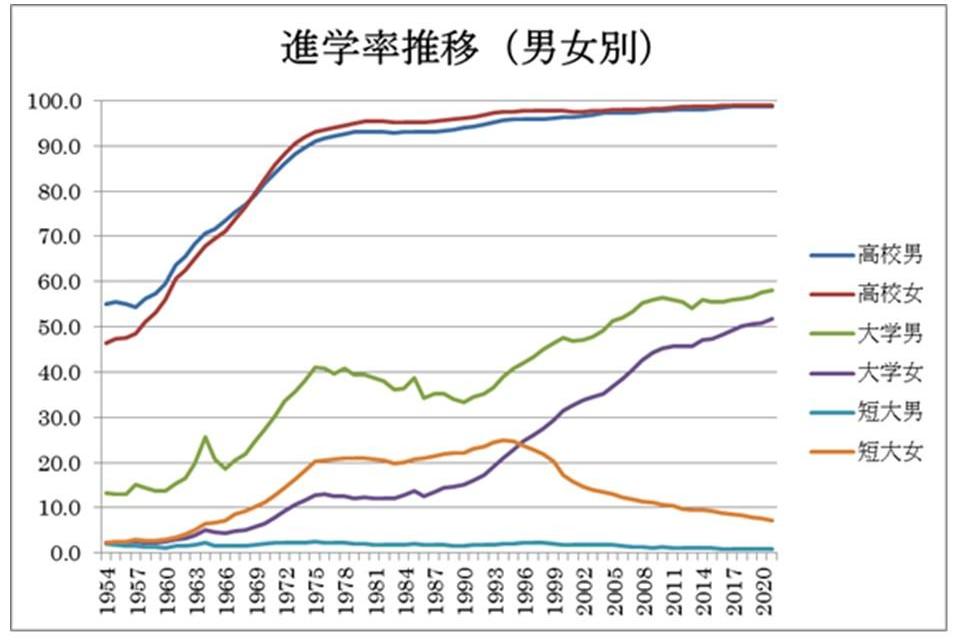 2023.3.29東京新聞 2025.8.18日経新聞 2023.1.10フリステWalker (図の説明:中央の図のように、文科省が3年に1度行なう全国学力テストの平均スコアが低下し、その理由として、「教える時間の不足」と「教員の質低下」が挙げられた。しかし、左図のように、3歳以降に民定子ども園・幼稚園・保育園に通う子どもは100%に近くなり、右図のように、高校に通う生徒も100%に限りなく近づいているため、これらを義務教育化すれば「教える時間の不足」は解決する) 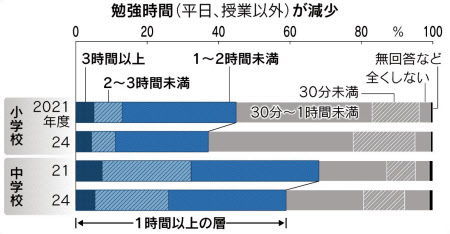 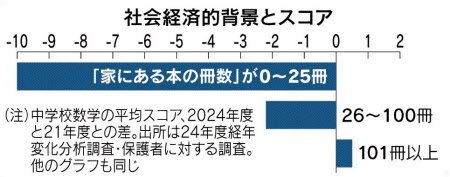 2025.8.18日経新聞 (図の説明:左図は、平日の授業以外の勉強時間で、小学校・中学校とも2021年より2024年の方が減っている。また、右図は、家にある本の冊数《家庭の知性度と正の相関関係》とスコアの関係で、本の冊数が多いほどスコアが高い。確かに、私も勉強時間は左の10%以内に入り、勉強していない時も学校図書館の本や父親の本を読んでいたが、それで読解力がついたと思う) 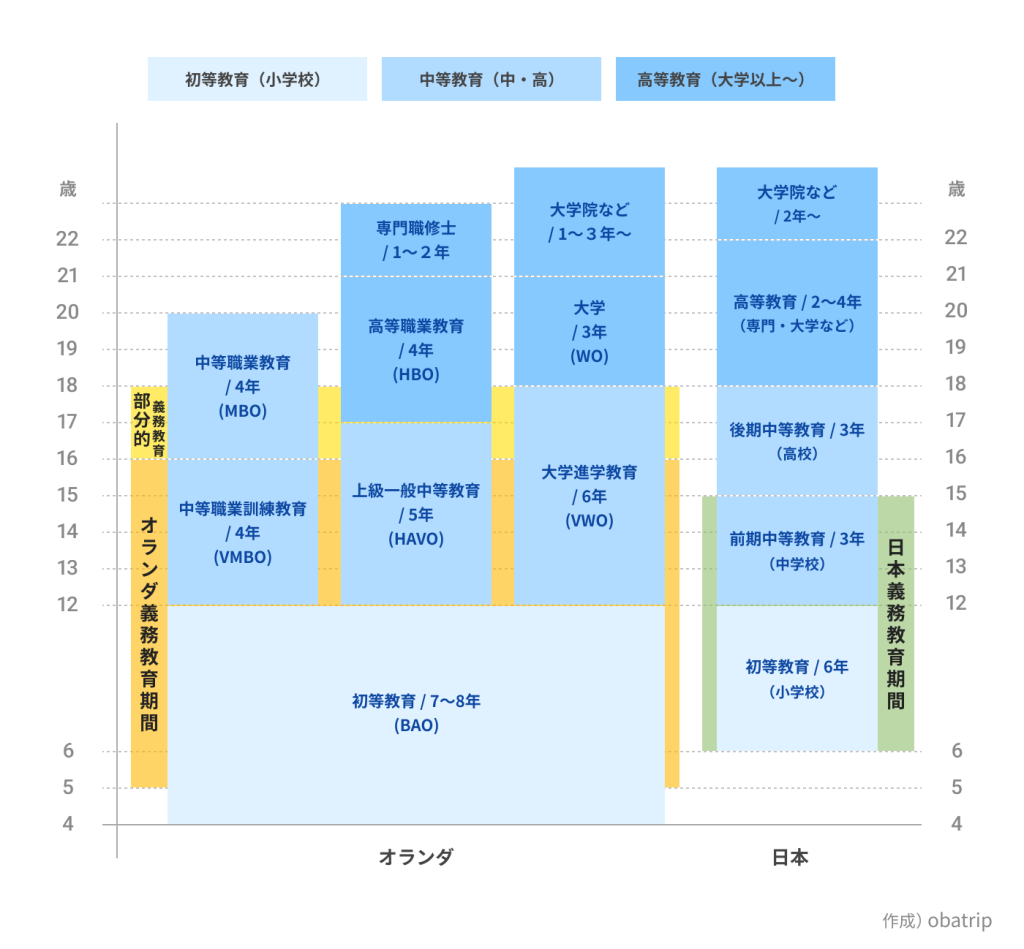 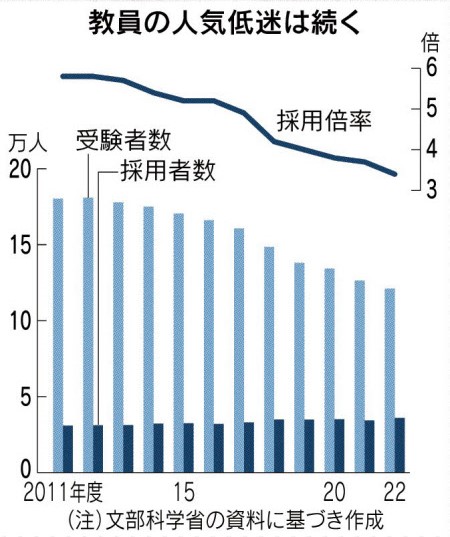 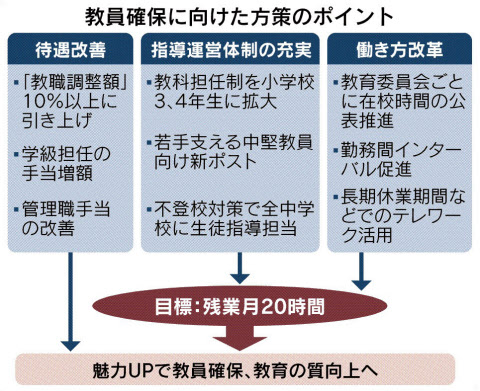 おばとりっくブログ 2024.4.20日経新聞 2024.4.20日経新聞 (図の説明:左図は、オランダのケースで初等教育開始年齢は4歳で8年間教育した後、12歳で終了する。また、中等教育はVMBO《職業教育》コースなら16歳、HAVO《高等一般教育》コースなら17歳、VWO《大学進学準備教育》コースなら18歳で終了し、学力や発達状況に応じて「留年」や「飛び級」が行われることもある。このほか、義務教育の出口で試験をして留年制度があるのは、フランス・ドイツ・アメリカ・フィンランド・スペイン・ブラジルなど多数ある。中央の図は、教員の受験者数と採用倍率の推移だが、次第に下がっており、右図のように、教職の魅力UP策がいろいろと言われているが、最も重要なのは苦労に報いる社会的評価とそれに連動する報酬であろう) *7-1-1は、①文科省が3年に1度程度行う全国学力テストの経年変化分析調査で、小6の国語・算数、中3の国語・英語で平均スコア低下 ②子ども全体の学力低下がこれほど顕著にデータに表れたのは約20年ぶり ③勉強時間が減少し基礎学力も揺らぐ ④テレビゲームやスマホ利用増加、家庭の経済格差、保護者の「良い成績にこだわらない」姿勢等が背景 ⑤成績にこだわらない価値観は一概に悪いとは言えず、情操・道徳心など成長過程で大切にすべき資質は多く、低下した「学力」自体が非認知能力を含む幅広い学力の一部 ⑥デジタル環境への受け身な接し方が言語能力の劣化に繋がる可能性 ⑦教育現場で教える時間不足、教員の時間的余裕の乏しさ ⑧教員の質低下 ⑨「主体的・対話的で深い学び」重視で定着の確認なし ⑩少子化で高校・大学とも難関はごく一部となって受験プレッシャー緩和、入試以外に学ぶ意味を実感させず学ぶ意欲減退 ⑩背景にある知性と学びの危機に目を向ける必要 等としている。 また、*7-1-2は、⑪文科省は、小中高校の成績の基となる学習評価を見直し、「主体的に学習に取り組む態度」の評価比重を軽減する方針で2030年度以降実施予定 ⑫主体的な態度は2020年度以降、小中高校で評価の観点に加えられ主体性の評価は内申点にも影響するが、客観的な判断が難しいとの指摘 ⑬評価の観点は教科毎に「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つを、小学校は3段階・中学校は5段階でつける ⑭導入当初から学校現場では「何を根拠に評価したらよいのか分からない」という声が上がっていた ⑮評価の透明性と妥当性を高めることで、子どもの意欲向上と管理教育の緩和を目指す ⑯早稲田大学の田中教授は「『主体的に学習に取り組む態度』の評価は教員にとって難しく、評価方法を改善するのは良いこと」「主体性評価が高校入試等で活用される内申点に関わるため、生徒は過度に品行方正な振る舞いを求められ管理教育になった」等と指摘した としている。 イ)子どもの基礎学力低下と社会一般の価値観 ①②のように、文科省が3年に1度程度行う全国学力テストで平均スコア低下して子ども全体の学力低下がこれほど顕著にデータに表れたのは、2008年に学習指導要領が改訂され、ゆとり教育が廃止されてから、約20年ぶりだそうだ。 そして、③⑩のように、子どもの勉強時間が減少して基礎学力が揺らぎ、知性と学びの危機に陥った理由の第1は、文科省自身が、全国学力テストの目的を「義務教育の機会均等と水準の維持向上の観点から、全国児童生徒の学力・学習状況を把握・分析して、教育施策の成果と課題を検証し改善を図ることで、児童生徒個人を評価するためのテストではない」として、まるで学力で児童生徒を評価してはならないかのような意見を持っていることである。 このため、小中学校では、スポーツ大会で優勝した生徒は表彰するが、優秀な成績をとった生徒を褒めることはなくなり、生徒に対しては部活重視で勉強する動機付けを与えることがなくなった。そして、このことは、不適切なものも多い人間が作った単純なルールを偏重し、コートの中の目に見える仮想敵を打ち負かすことしか考えられない、AIやロボット以下の視野の狭い大人を大量生産するという結果を生んでいるのだ。 この文科省のスタンスは、小6の国語・算数、中3の国語・数学・英語等の学科の一部についてのみ全国学力テストを行い、経年変化分析調査は3年に1度程度しか行わないことからも明らかである。本当は、毎年、初等・中等教育の出口にあたる小6・中3・高3の全員に対して、英・数・国・社・理などの全国学力テストを行ない、学校別の基礎学力達成度を明らかにして、次年度以降の改善に繋げることが必要なのである。 しかし、「学力で児童生徒を評価してはならない」という主張は、文科省だけではなく、⑤のi)成績にこだわらない価値観は一概に悪いとは言えない ii)情操・道徳心など成長過程で大切にすべき資質は多い iii)低下した『学力』自体が非認知能力を含む幅広い学力の一部 というように、メディアはじめ世間一般でもよく言われていることなのだ。 正しくは、ii)の情操・道徳心は前頭葉に由来するため、学力と負の相関関係ではなく正の相関関係がある。このことは、犯罪を犯した人の学歴(学力と正の相関関係あり)分布を見れば明らかで、iii)については、全国学力テストの科目を増やせば良い。また、全国学力テストの結果とその後の人生における賞罰を結びつけて相関関係を見れば、道徳心や成功と学力に正の相関関係があることも検証できるだろう。 このように、大人が「成績にこだわらない価値観は悪くない」「情操・道徳心と学力は別で学力のある生徒は狡いことをしているからだ」等と言っていれば、子どもは安きに流れて、⑩のように、少子化で受験プレッシャーが緩和すれば、学ぶ意味を無くして学ぶ意欲も減退するのが当然である。 ロ)公教育の重要性と教員の質 親は、親になるための資格試験を受けて親になったわけではないため、子の家庭環境はさまざまで、④⑥のように、子にテレビゲームやスマホを利用させ放題にしたり、デジタル環境に受け身で接して言語能力を劣化させたり、保護者が「良い成績にこだわらない」という態度を示して子のやる気を削いだりなど、家庭間格差は大きい。 そこで、国民の水準を一定以上に保つために公教育の充実が重要なのだが、⑦のように、「教える時間の不足」「教員の時間的余裕の乏しさ」が長く挙げられ続けても、教育現場で教育の質を落とさずに、これらを改善する対策がとられなかったことは明らかだ。しかし、それが、⑧の教員の質の低さそのものなのである。 まず、教える時間の不足については、日本では、6歳で小学校に入学してそこで6年間過ごし、13歳で中学校に入学して3年間過ごす9年間が義務教育であり、義務教育終了時は15歳だ。オランダは、4歳で小学校に入学して8年間を過ごし、義務教育の中等学校で4〜6年(学校種により異なる)を過ごして、最長13年かけて義務教育が終わる。アメリカ・ドイツは州ごとに制度が異なるため省くが、イギリスは、5歳で小学校に入学して6年間過ごし、中等学校で7年間過ごす11年間が義務教育で義務教育終了時の年齢は16歳だが、その後、16〜18歳は教育又は訓練が義務とされている。また、フランスは、3歳で始まる幼児教育から義務教育に含めて、小学校5年間、中等学校7年間の合計13年間が義務教育で、義務教育終了時の年齢は16歳である。 つまり、義務教育開始年齢を6歳に固定する必要は無く、日本でも、上の上段左図のように、3歳以降は認定子ども園・幼稚園・保育所に入る子どもが100%に近いため、オランダを参考にして3歳から初等教育を開始するか、フランスのように3歳から就学前教育を始めるかすれば、「教える時間の不足」は解決し、過度に親に依存することによる家庭間格差も生じずにすむ。そして、その時に必要となるのは、各段階で時間を無駄にせず、効率的に教えるための年齢に適したカリキュラム編成と教員の質・量の充実なのである。 また、上段右図のように、日本の高校進学率も2020年で男女とも100%に限りなく近づいているため、中学・高校は一貫したカリキュラムを作って義務教育化すれば、学習の無駄を省き、さまざまな学習を効率的に行なうことができる。 さらに、「教員の時間的余裕の乏しさ」は、教員に教育以外の仕事をさせず、部活も専門家に任せてレベルの高い指導をしてもらえばよいのに、いつまでも改善せずに同じ事を言い続けているのでは、教員の質が低いと言わざるを得ない。 なお、教員のレベルについては、フィンランドが修士必須、オランダは修士推奨、イギリス・フランスは学士で教員資格取得者、アメリカは学士である。また、教員の職能開発時間・ICT活用授業の頻度・授業設計の自律性は、他国は高いが日本は低い。 しかし、教員のレベルを上げるには、i)社会的地位の高さ(尊敬される職業で、政策形成・教育改革にも関与できること) ii)報酬と待遇(給与・昇給制度・退職金・福利厚生における他の専門職《医師・技術者・政治家など》との競争力) iii)研究や専門性を磨く機会の多さ などの改善が必要であるため、日本は悪循環に陥っているのである。 ハ)基礎学力がなくては、「主体的・対話的で深い学び」もできないこと 主体的な態度は、⑨⑫のように、2020年度以降に小中高校で評価の観点に加えられ、その評価は内申点にも影響するが、学んだことの定着の確認ができず、客観的判断が難しいとの指摘があった。その評価方法は、⑬⑭のように、教科毎に「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つを、小学校は3段階・中学校は5段階でつけたが、導入当初から学校現場で「何を根拠に評価したらよいのか分からない」という声が上がっていた。 また、⑯のように、主体性評価が高校入試等で活用される内申点に関わるため、生徒は過度に品行方正な振る舞いを求められ管理教育になったという指摘もあり、文科省は、⑪⑮のように、「主体的に学習に取り組む態度」の評価比重を軽減し、評価の透明性と妥当性を高めることで、子どもの意欲向上と管理教育の緩和を目指す方針に変更したそうだ。 しかし、思考・判断・表現は、基礎的な知識・技能がなければ有為に成立しないため、「主体的・対話的で深い学びを重視」と言いながら、基礎的知識・技能を習得する時間を減らせば逆効果となる。また、教員自身が、勉強好きで深い知識を持つ実力者でなければ、子どもの思考・判断・表現を正しく評価して良い方向に導くことはできず、単に品行方正な振る舞いを求めるだけの管理教育になって社会に悪影響を与える。 一方、フィンランドの場合は、教員の質の高さを、修士号取得を必須として教育の専門性の高さを担保し、教科横断型の学習で知識を実生活に結びつける力を育成する点が参考になる。また、アメリカの場合は、実社会の課題をテーマにして調査・発表・議論を通じて学力と思考力を同時に育成するプロジェクト型学習が参考になる。 日本の場合は、文科省が「主体的・対話的で深い学び」と言っても、実社会の課題をテーマにして調査・発表・議論を通じて学力と思考力を同時に育成できる教員の質や教育時間が不十分であるため、教育制度や教員の質に関し、時代にあった制度の再構築が必要になるわけだ。 2)男女別学教育の是非について イ)埼玉県には県立の男女別学高校が未だに存在すること *7-2-1は、①埼玉県教委が保護者・県民との意見交換会で共学化推進方針を説明し、賛否両論噴出 ②保護者の部は子が別学高校に通う父母を中心に18人が参加、県民の部は別学校卒業生や県立高校教員経験者など17人が参加 ③共学化反対の意見は、i)女子の目がないので力をフルに発揮でき、人間力が育つ ii)共学の中学校で性被害を受けた人もいる iii)男女の特性に合わせた教育が必要 iv)異性が苦手な人には別学が必要なので、トップ校だけでなく幅広い学力の層に別学校が必要 v)男女共同参画社会と共学化に相関関係があるのか vi)埼玉には名門校のピラミッド構造があり、女子が男子校に入学したら男子の足を引っ張る vii) 女性しかいない中で女性のリーダーシップが育つ 等々 ④共学化賛成の意見は、i)全国的に知名度のある浦和高校に女子が行けないガラスの天井をなくすべき ii)男子校の文化祭の在り方に違和感 iii)共学化しても結果的に男子校や女子校になることがあるから共学化しても良い iv)女子が入ってきても全く問題なく、県立高校は変化を続けなければいけない 等々 ⑤県教委の考え方は、i)共学化で男女共同参画を推進していくものではない ii)男女で教育活動の差を設けることは考えていない iii)一人ひとりの希望と能力に応じた学校の選択肢を用意したい iv)少子化で学校を再編する際は別学校の共学化も検討対象 などと記載している。 1947年に施行された日本国憲法は、「第14条:すべて国民は法の下に平等で、人種・信条・性別・社会的身分・門地により、政治的・経済的・社会的関係において差別されない」「第15条:すべて公務員は全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」「第26条:すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する」と規定しており、女性より男性を優遇してよいとする条文は全くない。そして、その下部の法律として、「男女雇用機会均等法」「男女共同参画基本法」「ストーカー行為等の規制等に関する法律」などがあるのである。 そのような中、埼玉県教委は、今時、①②のように、県立高校の共学化推進のために保護者・県民との意見交換会を行なったそうだが、その保護者の部には、子が別学高校に通う父母を中心に18人を選んで参加させ、県民の部には別学校卒業生や県立高校教員経験者など17人を選んで参加させたそうだ。しかし、埼玉県民で多額の県民税を支払っている我が家に参加意思を聞かれたことはないため、県民税を埼玉県立高校のために支出するのは止めてもらいたいと思う。 そして、県立高校共学化反対意見には、③のi) vi)の「女子の目がないから力をフルに発揮でき、人間力が育つ」とか「埼玉には名門校のピラミッド構造があり、女子が男子校に入学したら男子の足を引っ張る」などという男性中心の視座のものが多い。こういう男性中心の視座を持つ高校を卒業した男性が、職場でも「女性がいない方が働きやすい」とか「女性は昇進に不向き」などと言って、堂々と男女雇用機会均等法違反や男女共同参画基本法違反をするのである。 また、③のii)の「共学の中学校で性被害を受けた」というのは、女性(or男性)に対するセクハラ又は暴力行為であるため、その場で注意して人間の尊厳やそれを護るための道徳を教えるのも学校の仕事であるのに、それもせずに男女別学にすれば、「性加害は悪いことである」ということを教える機会も失って、おかしな大人が卒業してくるのである。 さらに、③のiii)の「男女の特性に合わせた教育が必要」やv)の「男女共同参画社会と共学化に相関関係があるのか」などと言っている人は、男女平等の憲法や男女雇用機会均等法・男女共同参画基本法を持つ日本で、未だに性的役割分担に基づくジェンダーを主張しているわけだが、これに対し、⑤のi)のように、県教委も「共学化で男女共同参画を推進していくものではない」などと言っているのは、憲法14条・15条及び26条違反であり、教師として質が悪い。 なお、県立高校共学化反対意見の中には、iv)の「異性が苦手な人には別学が必要」という意見もあるが、社会に出て「異性が苦手」などと言っていれば、働く場所はなく、結婚もできない。従って、多感な青春時代に、対等な友人として、また手強い競争相手として、異性と同じ校舎で学び、本当の姿の異性を知っておくことが重要なのである。 さらに、③のvii)の「女性しかいない中で、女性のリーダーシップが育つ」という意見も、言い換えれば、「女性しかいない中でしか女性はリーダーシップを発揮できず、その壁を打ち破る気も無い」という情けないものである。そして、こういう事例の積み重ねが、「女性は昇進に不向きである」という固定観念を作って、他のそうでない女性に迷惑をかけているのだ。 共学化賛成の意見のうち、④のi)の「全国的に知名度のある浦和高校に女子が行けないガラスの天井をなくすべき」は、憲法第26条及び男女雇用機会均等法の趣旨から考えて尤もだ。何故なら、しっかり勉強していなければ、いくら機会均等でも、就職も昇進もできず、その結果、リーダーにもなれないからである。 ④のii)については、私は「男子校の文化祭」に行ったことがなく何とも言えないが、④のiii)の「共学化しても結果的に男子校や女子校になることがあるから共学化しても良い」というのも、女性の能力を低く見ている女性蔑視そのものであり、女性に対して失礼千万である。また、iv)の「女子が入ってきても全く問題なく、県立高校は変化を続けなければいけない」というのは、女性がいると何か問題があるかのようで、これも賛成はしているが、男性中心の視座である。 そのため、⑤の県教委は、ii) iii)のような視点をもっているのなら、iv)のような少子化対策に逃げるのではなく、「男女で公教育に差を設けることは、男女平等の日本国憲法に反し、男女雇用機会均等法や男女共同参画基本法にも反するため、県立高校の公務員として、男女差別はしない」ときちんと説明できなければならないのである。 ロ)女子大学は男女を率いるリーダーを育めるのか *7-2-2は、①2000~2025年に、私立女子大学は25校が共学化・2校が廃止・2校が募集停止して存亡の危機 ②日本の女子大は20世紀初め、「良妻賢母」という実践的ジェンダー・ニーズを満たすために設立 ③この使命は多くの女性が共学の大学に進学するようになった1990年代以降に戦略的ジェンダー・ニーズに移行 ④多くの女子大学は家政など伝統的な学科を廃止してグローバルコミュニケーション等のキャリア志向のプログラムを新設したが、女子大が女性のリーダーシップやジェンダー平等に影響を与えたとする研究は乏しい ⑤日本は国際的なジェンダー平等の指標で一貫して低い順位 ⑥女性理事割合が50%を超えるのは津田塾・白百合・聖心女子大の3校のみ ⑦津田塾・日本女子大は理事会の半数を現職教職員が占めるが、他は1/3未満 ⑧多くの私立女子大は、国公立や私立の一流大学の男性教授がキャリアの終盤に移籍して教授・理事のポストを占める ⑨日本企業の取締役や別の大学で運営経験を持つ男性が退職後に女子大理事に就任するケースも ⑩多くの私立女子大理事会は、エリート男性の第二のキャリアの目的地に ⑪日本女性の自由と社会貢献の拡大は、女子大が女性を意思決定プロセスの中核にしない限りは実現が困難 等としている。 また、*7-2-3は、⑫今年に入って、京都ノートルダム女子大が学生募集停止、武庫川女子大が共学化方針発表 ⑬女子大減少は続くが、今も大学全体の1割弱を占め、存在意義や役割を考える必要 ⑭日本は先進国の中でも政治・経済分野で女性リーダーが圧倒的に少ない ⑮お茶の水女子大の室伏前学長は、「性別役割意識や『わきまえる』という無意識の偏見から離れて過ごせる女子大は、女性がリーダーシップを学ぶ上で優れた場所」 ⑯では、女子大は、どれだけリーダーを輩出し、ジェンダー平等に寄与したか ⑰アジアを含めた海外との比較検証と日本社会に横たわる根深い課題を示すことが女子大の役割では 等としている。 このうち②については、戦前の男女差別や性的役割分担意識が激しかった時代、男子の「旧制高等学校」や「大学予科」に相当する教育機関が女子にはなかったため、女子に限った専門教育機関として、「実践的ジェンダー・ニーズを満たすため」と言って「良妻賢母」を目指す文学・家政学・教育学・栄養学・保育・看護などを中心に教える女専(女子専門学校)ができた。そして、その時代としては先進的な家庭の子女で優秀な女性が女専に入学したため、女専は、その時代の重要な役割を果たしたのである。 しかし、戦後、日本国憲法が施行されて男女共学が原則となってからは、③④のように、優秀な女性は旧帝大でもどこでも入れるようになったため、女専の多くは女子短期大学や女子大学として再編され、現在の女子大の基盤となった。そして、男女雇用機会均等法が施行された1990年代以降は、戦略的ジェンダー・ニーズに移行し始めたのである。しかし、私の96歳になる母は、女専を出ているが、私には「せっかく男女平等の世の中になったのだから、共学校に行きなさい」と言っていたので、本当に男性と互角に仕事や研究をしたいと思う優秀な女性は男女共学校に行き、女子大を選択する女性が社会でリーダーシップをとったり、ジェンダー平等に貢献したりすることは少ないと思われる。 従って、役目を終えた女子大が、①⑫のように、共学化・廃止・募集停止となるのは、抗うことのできない時代の流れであろう。そのため、⑬のように、無理に存在意義や役割を考える必要は無く、それでも一定割合の人は家政学・栄養学・保育などを学びたいと思っているだろうから、共学化してもそのニーズを満たせるようにすれば良いのだ。ただし、⑰のように、アジアを含めた海外との比較検証や日本社会に横たわる根深い課題を研究を通して明らかにすることは、東大でもやっていた人はいるが、女子大の方がやりやすいのかもしれない。 なお、⑤⑭の「日本は国際的なジェンダー平等の指標で一貫して低い順位」「日本は先進国の中でも政治・経済分野で女性リーダーが圧倒的に少ない」というのは本当だが、家政学・栄養学・保育などを学んだ女性が活躍しているのは家庭科の先生や保育所の保母であり、女性であっても政治・経済の素養がなければ政治・経済分野のリーダーにはなれない。 さらに、⑮のように、お茶の水女子大の室伏前学長が「女子大は、性別役割意識や『わきまえる』という無意識の偏見から離れて過ごせるため、女性がリーダーシップを学ぶ上で優れた場所」と言っておられるが、女性の中だけでしか性別役割意識や『わきまえる』という無意識の偏見から逃れられない人が、男女混成の社会でリーダーになれるわけがないのである。そして、⑯のように、女子大は、むしろ性的役割分担意識に支えられているため、社会で多くのリーダーを輩出してはおらず、ジェンダー平等にも寄与していないと思われる。 また、⑥⑦のように、女性理事割合が50%を超えるのは津田塾・白百合・聖心女子大の3校のみで、⑧⑨⑩のように、多くの私立女子大は、エリート男性の退職後のセカンドキャリアとなっているそうだが、女子大は卒業生が大きな力やネットワークを持っているわけではないため、⑪のように、日本女性の自由と社会貢献の拡大を女子大が担うのは、女性を意思決定プロセスの中核に据えても難しいと思う。 3)外国人留学生への支援 *7-3は、①現在14億の人口を擁して人口・経済ともに成長中のアフリカ市場に日本が食い込むには日本語や日本文化に精通した人材育成が必要 ②立命館アジア太平洋大学は学生の半数が留学生で、アジア各国で多くの卒業生が日本とのビジネス交流に力を発揮 ③アフリカも留学生を通じた人材育成を図ることが、アフリカ市場進出の足がかりになる ④大学院生と同様、四年制大学のアフリカからの学部留学生を増やすことが重要 ⑤アフリカ留学生はエリート家庭出身も多く、卒業する学生は本国に戻ってすぐ現地エリートとして活躍するので、親日層の獲得効果が高い ⑥学部のアフリカ留学生は、生活・病気・事故時の突発的対応など生活面の不安が課題 ⑦日本国内に同郷人コミュニティーが殆どないので、「アフリカ留学生支援基金」創設を提案する ⑧緊急の資金貸与・在京大使館からの支援・卒業後の就職で便宜が得られるメニューも揃えば、留学生の自主的登録が期待できる ⑨日本の大学を卒業した留学生のデータベースにもなり、日本企業の高度人材採用に活用できる ⑩米トランプ政権や欧州での移民排斥の中、欧米以外への留学志向が高まっているため、日本は安全性と文化的魅力で好機 等としている。 ⑩の米トランプ政権以前のアメリカは、これまで留学生に対する支援が手厚く、⑤⑥のように、生活面の不安を軽減して親米層を獲得する効果を出していた。具体的には、i)給付型奨学金(成績優秀者や経済的困難者向けの返済不要奨学金で、留学生も対象で専攻分野や出身国に応じた特別枠もある) ii)大学による生活支援(留学生向けオリエンテーション・メンタルヘルス支援・医療保険制度案内・ビザ・就労・文化適応など) iii)キャリア支援と就職連携(大学が企業とネットワークを構築してインターンや就職を支援) iv) コミュニティ形成と文化交流(留学生同士のネットワーク形成や地域住民との交流プログラム) などがある。 また、カナダは、v)公立大学の授業料が比較的安価で留学生にも奨学金がある vi)永住権取得に向けた制度(PGWP)との連携で留学が移民戦略と直結 などである。 日本も、①②③④のように、人口・経済ともに成長が見込まれる市場とビジネス交流するためには、その国から大学院生だけでなく四年制大学の学部に優秀な留学生を積極的に入学させて、日本語や日本文化にも精通した人材を育成することが必要である。 それには、i)のアメリカのように、給付型奨学金を日本人だけでなく留学生にも支給し、特に人手が足りず必要な分野を専攻する学生には特別枠を設ける方法があるし、v)のカナダの例のように、公立大学の授業料を比較的安価にした上で留学生にも奨学金を給付する方法もある。 また、⑦の日本国内に同郷人コミュニティーが殆どないことについては、ii)の大学による生活支援、iii)の大学と企業のネットワークによるキャリア支援・就職連携、iv)の留学生同士のネットワーク作りや地域住民との交流などが考えられる。また、在京大使館の支援も重要ではあるが、日本企業も奨学金支給段階から参加して相談相手となり、インターンや採用に繋げるのが、⑧⑨の高度人材採用に効果的だろう。 このように、人道的支援だけでなく、国際関係・新市場開拓・人材確保の観点から見ても、今の日本で外国人差別を行なっている場合ではないのである。 ・・参考資料・・ <運輸業・建設業等の人手不足> *1-1-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC209UK0Q5A520C2000000/ (日経新聞 2025.7.2)物流大手SBS、運転手の3割1800人を外国人に インドネシアで養成 物流大手のSBSホールディングス(HD)は10年以内にトラック運転手の3割を外国人にする。外国人が最長5年働ける「特定技能」の制度を活用し、主にインドネシアから1800人を採用する。ヤマト運輸など業界大手も採用に乗り出しており、人手不足が深刻な物流業界において外国人頼みが強まっている。SBSHDはまず年内にインドネシアに自動車学校を設ける。講師を現地に派遣し、日本の交通ルールや日本語を教える。全寮制で半年間学んだうえで来日してもらう。2026年からは年間100人程度のペースで採用を始める。現在は特定技能の外国人運転手はおらず、10年以内に全体の3割に当たる1800人程度にする。多くがイスラム教徒であると想定し、来日後も礼拝や食事などに配慮して働きやすい環境を整備する。賃金は日本人より低くなる見通しだ。政府は24年に外国人在留資格について最長で5年就労できる特定技能1号に自動車運送業を新たに加えた。上限は2万4500人。物流業界ではこの制度を通じ、外国人運転手を採用する動きが広がる。船井総研ホールディングス(HD)も傘下の物流コンサルティング会社、船井総研ロジが中小企業に仲介するサービスを始めた。主にバングラデシュからの採用を想定する。顧客である中小企業の要望に応じ、現地の送り出し機関と連携して面接による資質の見極めや入社前後の研修、採用後のマニュアル整備などを支援する。25年からの3年間で510人を計画し、その後も年200人ペースで仲介する。既に28人の採用が内定したという。このほか、福山通運も今秋にベトナム人を運転手として初めて約15人採用する予定。センコーグループホールディングスは32年度までに100人を採用する。背景には業界の人手不足がある。野村総合研究所は30年度に運転手の数が20年度比で27%減り、36%分の荷物が運べなくなると試算する。少子高齢化に伴う人口減に加え、24年度からは運転手の残業規制が年間960時間までに制限されたことで人手不足に拍車がかかっている。SBSHDといった主に企業向け配送を担う企業だけではなく、個人向けが中心の宅配大手も外国人の採用に乗り出す。ヤマト運輸を傘下に持つヤマトホールディングスでは今秋にも、長距離の幹線輸送やルート配送といった中長距離の拠点間を担う運転手として勤務が始まる予定。佐川急便も長距離や店舗間の輸送で採用を検討している。決まったルートを行き来するため、日本語が不慣れな外国人でも働きやすいとみる。特定技能による外国人運転手はバスやタクシー、引っ越しなどの運転手も含む。船井総研ロジはこのうち、トラック運転手が8割を占めるとみる。自動運転の実現が見通せないなか、地方のバス運行会社なども外国人運転手の確保に動いている。物流に限らず、公共交通、介護まで、様々なサービスは外国人なしには成り立たないのが現実だ。受け入れる企業は外国人が働きやすい仕組みづくりだけでなく、サービスを利用する消費者に受け入れられる環境整備も求められる。 *1-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250717&ng=DGKKZO90077840W5A710C2EA2000 (2025,7,17) 外国人材 特定技能・技能実習が3割 ▽…厚生労働省によると、日本で働く外国人は2024年10月時点で230万2587人と就業者全体の3.4%を占める。人手不足の深刻化によって10年前の2.9倍に増えた。高度人材向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務」は全体の18%で、製造・建設などの現場で働く特定技能や技能実習が約3割を占める。留学生のアルバイトも14%に上る。 ▽…受け入れが本格化したのは1990年代だ。89年の出入国管理法改正で中南米の日系人を主な対象とする在留資格「定住者」を設けた。93年には、技術移転を通して途上国の経済成長に貢献するとして技能実習を創設した。労働力需給の調整手段ではないとされたが、実際には人手不足の穴埋めとして広がった。 ▽…2019年に導入された特定技能は正面から人手不足対策とうたう。最長5年の「1号」のほか、熟練者向けに在留期間の制限がない「2号」がある。来日や定住・永住の増加を懸念する声もあり、20日投開票の参院選で与野党が外国人規制の強化の是非を議論している。 *1-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA091TP0Z00C25A2000000/ (日経新聞 2025年6月8日) 縮む建設業、工事さばけず 未完了が15兆円超え過去最大 【この記事のポイント】 ・未完了の建設工事が過去最大級15兆円超 ・建設就業者が10年で6%減、高齢化率2割 ・生産性向上課題、IT活用は英仏の5分の1 国内で商業施設や工場などの建設が停滞している。建設会社が手元に抱える工事は金額にして15兆円を超え、過去最大に膨らんだ。かねて深刻な人手不足に2024年からの残業規制が拍車をかけている。生産性の向上を急がなければ、民間企業の設備投資や公共投資の制約となり、日本の成長力が一段と下振れする恐れがある。イオンモールは福島県伊達市の店舗のオープンを当初予定の24年末から26年下期に延期した。建設作業員が集まらず、工事が計画通りに進まなかった。「東北地方は人手がもともと少ないうえに各地に散らばっている。確保が難しい」と説明する。こうしたケースは各地で相次いでいる。国土交通省の建設総合統計によると、建設会社が契約したうち完了できていない工事は25年3月に15兆3792億円(12カ月移動平均)に達した。物価上昇も影響し、業界全体のデータを遡れる11年4月以降で最も高い水準で推移する。1990年代初めごろも今と同じように手持ち工事高が積み上がっていた。当時はバブルの崩壊で経済が長い低迷期に入る前で、建設需要の増加が大きかった。対照的に目下の大きな問題は業界全体で供給力が縮んでいることだ。総務省の労働力調査によると、24年の建設関連の就業者数は10年前に比べて6%減り、477万人となった。このうち65歳以上が80万人と2割近くを占めた。高齢化率は10年間で5ポイント上がった。加齢で体力が衰えれば若いころのようには働けなくなる懸念がある。社会全体での働き方改革の不可逆な流れも、こと労働力の確保という部分では足かせになる。24年4月に始まった時間外労働の上限規制で、建設業は原則として月45時間、年360時間までしか残業できなくなった。結果として24年の一人あたりの総労働時間は前年から32.3時間減った。マイナス幅は全産業平均の14.3時間を上回る。限りある人手の争奪戦は激しくなっている。先端半導体の量産を狙うラピダスの工場建設が進む北海道は、従業員10人以上の企業で働く建設労働者数が23年におよそ13万人と前年比23%増えた。所定内給与は月平均32万6000円程度と3万円以上増えた。伸びは全国平均の約1万4000円を上回る。建設会社が利益率の高い工事を優先する傾向も強まる。民間の産業用建築物の1平方メートルあたりの着工単価は、24年におよそ30万円と前年から18%も上がった。ある大手のトップは「採算や工期を十分に確保できるかによって厳格に選別している」と語る。近年は中小の建設会社の廃業も目立つ。人手の確保で後手に回り、好採算の案件にあぶれて生き残りが難しくなっているとみられる。労働集約型の産業構造の改革という古くからの課題も改めて浮上する。大和総研の末吉孝行氏は「日本の建設業は中小が多くIT(情報技術)の導入が遅れている」と説く。建設従事者が使える省人化などのソフトウエアの一人あたり導入量はフランスや英国の5分の1にとどまるというのが現状の試算だ。業界全体で工事をさばく能力が低下した状態が続く弊害は大きい。働き手の確保が難しいのなら、デジタル化などによって生産性を高めるしか道はない。建設業は日本の国内総生産(GDP)の5%程度を占める。内需の柱である設備投資の3分の1ほどにあたる。たとえば工場の建設が停滞すれば、備え付ける機械の投資の遅れなどにも波及する。ただでさえ低成長が続く日本経済のボトルネックになりかねない。 *1-2-2:https://www.nikkei.com/ask (日経新聞 ASK) 建設業の労働力不足の背景 建設業界では、かねてからの人手不足に加えて、時間外労働の上限規制が導入されたことなどが要因となり、労働力不足が深刻化しています G。 ⚙️ 人手不足と高齢化 就業者数の減少: 2024年の建設関連の就業者数は477万人と、10年前に比べて6%減少しています。高齢化の進行: 建設業の就業者に占める65歳以上の割合は2割近くに達し、高齢化率は10年間で5ポイント上昇しています 。高齢化により、体力の低下から若い頃のように働けなくなる懸念があります。 ⏱️ 労働時間の上限規制 残業規制の導入: 2024年4月から時間外労働の上限規制が建設業にも適用され、原則として月45時間、年360時間までしか残業できなくなりました。労働時間の減少: 結果として、2024年の1人当たりの総労働時間は前年から32.3時間減少し、全産業平均の14.3時間を上回る減少幅となっています。 💰 給与水準と待遇 給与の伸び悩み: 建設業では待遇の低さから若者の就業が進まないことが課題となっています。待遇改善の動き: 一部の企業では、初任給の引き上げやリーダー職の待遇改善など、人材確保に向けた動きも見られます 。積水ハウス建設HDでは、特に評価の高い30〜40歳代のリーダーの年収を前年比40%以上増の約850万円に引き上げました。 🏢 中小企業の状況 廃業の増加: 近年、中小の建設会社の廃業が目立っています 。人手確保が難しく、好採算の案件にあぶれて生き残りが難しくなっているとみられます。IT導入の遅れ: 中小企業ではIT(情報技術)の導入が遅れており、省人化などのソフトウェアの導入量が少ないのが現状です。 🔨 その他の要因 建設需要の増加: 国内各地で再開発事業や工場建設などが行われており、工事需要が高い傾向が続いています。技能者の不足: 技能実習制度に代わる育成就労制度や特定技能制度を通じて外国人の受け入れを進めていますが、韓国やオーストラリアも建設分野の外国人材の受け入れに熱心であり、待遇面での競争も激しくなっています。これらの要因が複合的に影響し、建設業界における労働力不足が深刻化しています。 *1-2-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA01BVM0R00C25A7000000/ (日経新聞 2025年7月2日) 老朽水道管、更新資金足りない 財務省研究所「平均8割値上げ必要」 全国の上水道事業の99%が、水道管など設備の更新に必要な資金を確保できていない恐れがあることが財務省所管の研究所の調査で分かった。更新費用を水道使用料だけで賄おうとする場合、料金を平均で8割引き上げる必要があることも明らかになった。近隣自治体との業務共同化などコスト削減策が急務となる。上水道事業は原則として、必要な経費を住民が支払う使用料で賄う。もっとも、将来の収支見通しが甘く、費用を料金に十分に反映できていない自治体が多いとの見方がある。単年度の損益は黒字を確保できていても、実は手元資金が少なく、老朽化した水道管を更新する資金までは準備できていない例もある。そんな状況でも水道料金を上げると住民の反発が予想される。物価高対策として逆に水道料金を割り引く場合もある。東京都は検針の時期によって今年6月から9月、または7月から10月の4カ月間、都内すべての一般家庭の水道の基本料金を無償にする。 ●月額水道料金は全国平均で3332円 上水道は主に市町村の公営企業が運営している。上水道事業の資金繰りを把握するため、財務総合政策研究所の研究班が全国1241事業者を分析した。財務省が保有する公営企業の2013〜22年度の会計データを活用し、給水人口が5000人を超える事業者を対象とした。年間使用料によって経費を賄えているかどうか、どれだけ現金を手元に残せるかという2つの観点から評価した。全体の99%にあたる1228事業者が事業継続に必要な金額を使用料で賄えておらず、安定的に設備投資に回せるほどの現金を生み出せていなかった。各事業者が現在の設備を維持したまま、必要な内部留保を確保するには、平均で83.2%の料金上げが必要になることも分かった。国土交通省によると、22年度末時点で一般家庭の月額水道料金は全国平均で3332円。単純計算でこれが同6100円程度に上昇することになる。総務省などによると、全国の上水道は1975年ごろに整備が進んだため、足元で法定耐用年数の40年を過ぎた水道管が全体の2割を超える。各事業者は手元の現金が少なければ、日常的な保守だけでなく、漏水など緊急時の対応にも支障が出かねない。実際、老朽化した水道管の漏水事故も全国で起きている。京都市では4月、市内の幹線道路の地下を走る水道管が破損し、広範囲に冠水した。神奈川県鎌倉市でも6月、水道管が破裂して市内の約1万世帯が断水した。各自治体は必要経費を料金に反映するとともに、近隣自治体との業務の共同化などのコスト削減策が必要になる。事業統合や経営一体化も有力な手段で、すでに大阪府内の自治体などが取り組んでいる。人口減少をふまえると、市街地の集約による水道インフラの縮小も重要な選択肢となる。財務省は調査結果を自治体や総務省、国交省などと共有し、毎年の実地監査などに活用する。 *1-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250717&ng=DGKKZO90079440X10C25A7EA1000 (日経新聞 2025/7/17) アジア人材獲得、西へ拡大、東南アの成長織り込む ルート多様化、バングラは1.5倍 外国人材の来日が少なかった南アジアや中央アジアの国々を開拓する動きが官民で広がっている。厚生労働省は年度内に日本での就労ニーズなどを現地調査する。日本語教育プログラムなどを始める企業も相次ぐ。東南アジアの経済成長で来日が頭打ちとなるのを見据え、他地域に獲得ルートを広げる。厚労省は民間団体に委託して、南アジアや中央アジアの「送り出し機関」(人材会社)などに聞き取りをする。日本での就労ニーズや制度面の障害を調査する。インドやスリランカ、ウズベキスタンなどを想定する。高級すし店などを手掛けるオノデラグループで特定技能人材の育成と紹介を担うオノデラユーザーラン(東京・千代田)は6月11日、ウズベキスタン移民庁と連携協定を結んだ。早ければ今秋から、日本で働きたい若者に半年ほど日本語を教え、特定技能の試験に合格したうえで来日させるプログラムを始める。外食や介護など向けに年200人ほどの育成から始め同500人に拡大する計画だ。日本に留学を希望する学生を支援する日中亜細亜教育医療文化交流機構(東京・港)も4月、ウズベキスタンの3カ所に日本語教育の拠点を設けた。特定技能として日本での就労を目指す。ワタミは特定技能人材を育成する研修センターをバングラデシュに設立する。同国政府機関の施設で教育プログラムなどを提供する。年間で約3000人を特定技能人材などとして日本に送り出す目標を掲げる。製造・建設・介護などの現場で外国人を雇用できる技能実習や特定技能は2024年12月時点で計74万人が働く。国別ではベトナムが34万5619人と半数近くを占めるものの伸び率が鈍っている。かつて技能実習で10万人超が働いていた中国は1人あたり名目国内総生産(GDP)が7000ドルを超えた13年から来日が減り、24年12月は2万5960人となった。ベトナムは24年に約4500ドルと10年で1.8倍になった。厚労省の担当者は東南アジア各国も近い将来、他国で働く必要性が薄れ獲得が難しくなる可能性があると分析する。韓国や台湾との人材獲得競争も激しくなっている。韓国は外国人労働者を対象にする「雇用許可制」について、21年に5万人程度だった年間の受け入れ上限を3年で3倍に拡大した。時給換算の最低賃金はすでに日本の全国平均に並ぶ。台湾も製造業や建設業などで外国人労働者の賃金が上昇している。南・中央アジアからの来日はまだ少ない。特定技能と技能実習の合計人数はインドが24年12月時点で1427人、スリランカ4623人、ウズベキスタン346人にとどまる。人材送り出しの潜在力は高そうだ。厚労省によると、インドは23年の労働力人口が4億9243万人に上り、毎年1000万人以上増えている。15~24歳の失業率は15.8%に達する。バングラデシュは24年12月時点で特定技能・技能実習の合計が2177人で前年同月比1.5倍になった。急速な来日拡大には慎重意見もある。単純労働者の受け入れ制限などを求める声があり、20日投開票の参院選で外国人規制が争点に急浮上している。 *1-3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250725&ng=DGKKZO90242720U5A720C2EA1000 (日経新聞 2025.7.25) 「外国人材受け入れ拡大を」 全国知事会、国に要請へ 参院選受け過剰規制懸念 全国知事会は23~24日開催の全国知事会議で、外国人の受け入れ拡大を国に求める提言をまとめた。人材育成や確保を目的として2027年に始まる「育成就労制度」の柔軟な運用などを求める。人口減が加速するなか、外国人は地域産業や地域社会の重要な担い手となる。参院選で外国人規制が争点となったこともあり、過剰な規制強化への懸念は大きい。提言では「外国人の受け入れと多文化共生社会の実現に国が責任を持って取り組むよう、強く要請する」と主張し、技能実習制度の後継となる育成就労制度に関する要望を多く盛り込んだ。技能実習は日本で学んだ技能・技術を出身国の経済発展に生かしてもらうのが目的だが、育成就労は人材の育成と確保を主眼とする。国は受け入れ要件を厳格化し、一定以上の日本語能力を要求する方針だ。知事会は育成就労について「技能実習の作業職種から大きく減少することを危惧する声が多くの自治体から聞かれる」と指摘。受け入れ分野の追加や手続きの簡素化など柔軟な運用を求めた。外国人の受け入れ環境を整えるため、国が主体となり制度設計や財源確保に取り組むことも要望した。多文化共生に向けた施策を担う司令塔組織の設置も提案した。外国人規制は参院選で主要な争点となった。日本で排外主義のような極端な主張が急速に広がっているわけではないが、国民の関心は高まっている。外国人材が地域を支える存在となっている地方自治体の危機感は強く、全国知事会の村井嘉浩会長(宮城県知事)は「排外主義はあってはならない」と強調した。静岡県の鈴木康友知事は政府が設けた在留外国人の犯罪などに対処するための組織を取り上げ「排斥、規制だけが取り沙汰されるようなことは正さなければならない」と述べた。 *1-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250725&ng=DGKKZO90229370U5A720C2KE8000 (日経新聞 2025.7.25) 外国人材、地方での定着が重要 マイナビグローバル代表取締役 杠元樹 外国人労働者の増加に伴い、問題点についても多く議論されるようになった。主な論点は「選ばれない日本」に陥る可能性と外国人労働者が特定地域に偏ることによる弊害である。2つの問題の解決の鍵は「都市部」ではなく「地方」にあり、「入り口」ではなく「定着」にあるのではないか。まず、外国人の採用自体はそれほど大きな課題とはなっていない。外国人留学生の増加もあり、外国人在留数が多い都市部の採用はもちろん、地方においても海外から日本に来る外国人を採用する場合、まだ十分に日本の賃金や待遇に魅力があるからだ。求める給与水準が上昇した中国人やベトナム人の採用は難しくなっているが、日本が選ばれるための対策を優先する状況にはない。多額の費用をかけて採用し、入社までに長い時間を待ったにもかかわらず、すぐに退職して都市部へ移り住んでしまうことが、あらゆる弊害の要因である。早期退職ゆえにその地域に根付かず、都市部へ流入することで一極集中し、地域共生社会を妨げる負の循環につながる可能性があるからだ。定着のために必要なのは外国人労働者特有の退職メカニズムを理解し、雇用主・自治体・人材会社がそれぞれの役割を果たすことだ。マイナビグローバルの特定技能人材の退職理由の調査では、入社から3カ月以内の退職で最も多かった理由は「人間関係の不満」であり、「家族・友達・パートナーの近くに転居」は時期を追うごとに高くなる傾向がある。業務・職場の不満はどの時期も高いが、「業務内容が合わなかった」が主な要因だった。また、入社1年を超えると定着率が一気に高まる。人材会社は責務として業務内容の理解促進やキャリア意識を持った人材を育成し、雇用側は異文化理解のコミュニケーションを促進する教育を行い、自治体は長期就労を見据えた生活基盤確保の支援に取り組むべきだ。生活基盤の確保については、家族との住居探し、子供の日本語支援、妊娠・出産の病院でのサポートが必要だが、必ずしも多額の費用はかからない。地方での定着が進めば、おのずと日本就労の魅力は増加し、過度な都市部への流入を食い止められるはずだ。 <参議院議員選挙と外国人政策> *2-1-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/416128 (東京新聞 2025年7月1日) 「違法外国人問題」の公約ではりあう自民・国民・参政党…見え透いた「狙い」と危ぶまれる「ヘイト演説」 自民党の参院選公約に盛り込まれた「違法外国人ゼロ」を巡って「こちら特報部」は疑問を呈してきたが、外国人に照準を定めた公約を掲げる政党は他にも出てきている。彼らは「優遇の見直しを」「迷惑外国人を排除」と訴える。危ぶまれるのが、論戦の名を借りた排外主義の喧伝。「違法ゼロ」を訴えるなら、むしろあの問題に目を向けるべきでは。 ◆「外国人の規制で生活苦は解決しないのに」 「『違法外国人ゼロ』に向けた取り組みを加速化します」。自民党の小野寺五典政調会長は6月19日、参院選の公約発表で宣言した。外国人による運転免許切り替えや不動産所有の際に起き得る問題への対応を徹底するという。外国人に照準を定めた公約は、最近耳目を集める他党にも広がっている。一例が国民民主党。昨秋の衆院選で「手取りを増やす」と身近な政策を訴えて議席を4倍に増やし、先の東京都議選は議席数をゼロから9に。参院選公約で差別解消を掲げつつ「外国人に対する過度な優遇を見直す」とし、玉木雄一郎代表はX(旧ツイッター)で「国の財政が厳しい状況にあるなら、税金はまず自国民に使うのが当然」と記す。政治ジャーナリストの角谷浩一氏は「外国人に照準」が広まる背景について「ひと言で言えば受け狙いだろう」と語る。「国民は『生活が苦しいのに、自分たちは政治にないがしろにされている』といった不安を持っている。外国人の規制で生活苦は解決しないのに、外国人に問題があるとあおることで、人気を得ようとしているように見える」。 ◆「選挙になれば、選挙運動としてあちこちで主張される可能性」 目を引くのは参政党も。議席ゼロで迎えた都議選で3議席を獲得。共同通信の6月28、29日の世論調査では、参院選比例代表の投票先として同党を選んだのは5.8%。全党のうち4番手で、国民民主の6.4%に迫る勢い。参院選公約では外国人労働者の受け入れ制限や入国管理の強化により「望ましくない迷惑外国人などを排除」とうたう。その参政党は、これまでどう支持を得てきたか。保守派の言論に詳しい作家の古谷経衡氏は「支持者を取材すると、40〜50代の女性が多い。一度も選挙に行ったことがなかったような『無関心層』が目立つのが特徴」と指摘する。参政党は食品添加物などを否定し、有機農法や自然食品の意義を説いてきた。古谷氏は「『自然食品を徹底すれば健康になり、社会も改良される』というオーガニック信仰は、先進国の比較的富裕な層に受け入れられてきた。政治的な知識がなくても理解しやすい。それが無関心層を引きつけた」とみる。「オーガニック信仰は突き詰めると、体に不純物を入れてはならないという発想」で、コロナ禍で同党が訴えた反ワクチンも同じ考えの上にあるという。ただ「コロナ禍が終わり、反ワクチンが受けなくなったのか、代わりに従来主張していた保守的な政策を再び強く訴えるようになった」。強い危惧もある。反人種差別の政策に詳しい師岡康子弁護士は「『外国人が優遇されている』といった主張は日本人と外国人を分断させ、差別をあおる。選挙になれば、選挙運動としてあちこちで主張される可能性がある」と話す。「税金でいわば公的ヘイトスピーチがなされるが、公職選挙法に守られて市民が止めるのは限界がある。人種差別撤廃条約とヘイトスピーチ解消法に基づき、公的機関は選挙運動におけるヘイトスピーチを批判すべきだ」 ◆外国人優遇?「優遇されているとして挙げるなら米軍人だ」 排外主義に陥りかねない参院選公約。「違法外国人ゼロ」「優遇許さず」に反応するのが、ジャーナリストの布施祐仁氏だ。「『日本で優越的な権利を有した外国人住民がいる』という主張は事実ではない」と述べた上で「優遇されているとして挙げるなら米軍人だ」と語る。「『外国人が増えると治安が悪くなる』との言説も根拠はないが、米兵による事件事故は現に多発している」。沖縄県警がまとめた犯罪統計書によると、1972〜2022年の日本復帰後50年間で、県内での米軍関係者(米軍人や軍属ら)の刑法犯の検挙件数は6163件。昨年は73件で、過去20年で最多だった。 *2-1-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1509850 (佐賀新聞 2025/7/15) 外国人「制度見直し重要な課題」、首相、在留管理の適正化を指示 政府は15日、外国人に関連する施策を担う事務局組織「外国人との秩序ある共生社会推進室」の発足式を首相官邸で開いた。石破茂首相は「ルールを守らない人への厳格な対応や外国人を巡る現下の情勢に十分に対応できていない制度の見直しは政府として取り組むべき重要な課題だ」と指摘。出入国在留管理の適正化や社会保険料などの未納防止、土地などの取得を含む国土の適切な利用管理に対処するよう指示した。参院選では外国人政策を巡り、与野党が規制強化や共生の重視を掲げ、争点の一つに浮上している。新組織発足は政府を挙げて施策を推進する姿勢をアピールする狙いがあるが、過度な規制強化や権利制限につながりかねない懸念がある。首相は発足式で「外国人の懸念すべき活動の実態把握や国・自治体における情報基盤の整備、各種制度運用の点検、見直しなどに取り組んでもらいたい」と求めた。林芳正官房長官は記者会見で、新組織発足は参院選対策ではないかと問われ「選挙対策との批判は当たらない」と述べた。新組織は内閣官房に設置。入国や在留資格の審査を担当する出入国在留管理庁、社会保障制度を所管する厚生労働省、納税管理を受け持つ財務省などの担当者で構成する。参院選では自民、国民民主、参政各党が規制の強化を訴え、立憲民主党は外国人の人権保護を掲げている。 *2-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250731&ng=DGKKZO90369360R30C25A7MM8000 (日経新聞 2025.7.31) 外国人増で財政改善66% 学者47人調査、若年層が寄与、共生へ制度設計半ば 日本経済新聞社と日本経済研究センターは経済学者を対象とした「エコノミクスパネル」で外国人政策について聞いた。在留外国人(総合2面きょうのことば)が増えることで財政収支が改善するとの見方が66%に上った。若い外国人労働者が人手不足を補完し、税や社会保険料の支払いも大きいためだ。外国人の定住や高齢化を見据えた制度設計を求める声も多かった。2024年末時点の在留外国人数は約377万人と前年から11%増えた。外国人労働者の受け入れが経済に欠かせないとの見方がある一方、日本人の雇用との競合や、治安への悪影響を懸念する声もある。そこで47人の経済学者に「在留外国人の増加が平均的な日本人の生活水準の向上に寄与するか」を問うた。回答は「強くそう思う」(6%)「そう思う」(70%)の割合が計76%に達した。建設や運輸などの分野では人手不足が目立つ。東京大の田中万理准教授(労働経済学)は「外国人の就業増加によりモノやサービスの供給不足や価格上昇が抑えられる」として受け入れのプラス面を強調した。日本人の雇用との競合も限定的との見方が大勢だった。一橋大の森口千晶教授(比較経済史)は「実証研究によると外国人と日本人労働者は主に補完的関係にあり、日本人の賃金や失業率に負の影響を与えていない」と述べた。多様性のメリットを重視する意見も目立った。東京大の仲田泰祐准教授(マクロ経済学)は「(外国人が)新しい考え方を職場にもたらすことは生産性向上につながり得る」と答えた。在留外国人の増加を巡っては、生活保護など公的支出の増加や社会保険料の未納を不安視する見方もある。調査では「日本の財政収支の改善に寄与するか」も問うと「そう思う」との回答が66%だった。外国人の増加が財政を改善させると経済学者が考えるのは、今の在留外国人が「若い」ためだ。法務省の在留外国人統計によると、24年末時点で20代と30代が在留外国人の55.9%を占める。カナダ・ブリティッシュコロンビア大の笠原博幸教授(国際貿易)は「外国人の受け入れ増は働き盛り世代の割合を高めて税収や社会保険料収入の増加につながる」と答えた。一橋大の佐藤主光教授(財政学)も「現時点で在留外国人は勤労世代が多く、給付による受益以上に保険料や税を負担している」と述べた。外国人の受け入れが長期的に経済や財政の安定に寄与するかは今後の制度設計にかかっている。佐藤氏は「在留外国人の子弟への教育の確保や、高齢期を迎えたときの給付は十分な対応が求められる」と付け加えた。現在、日本の外国生まれの人口は3%と経済協力開発機構(OECD)平均の11%を下回る。先行して移民を受け入れた欧州などでは社会への統合が進まず、外国人受け入れのコストが強調されるようにもなっている。慶応大の小西祥文教授(実証ミクロ経済学)は「多様なバックグラウンドを持つ人々が持続的に共生しうる社会を実現するには、財政支出も含む包括的な多文化共生政策が必要だ」と述べ、長期的な視点を求めた。 *2-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250723&ng=DGKKZO90194050T20C25A7MM8000 (日経新聞 2025.7.23) 検証 日本の針路(2)移民政策の矛盾 外国人共生へ建前を排せ 参院選での参政党の台頭は、在留外国人やインバウンド(訪日外国人)の増加に国民がうすうす感じている不満を顕在化させた。政府が建前では「移民は受け入れない」としつつ、現実には外国人の受け入れを増やしてきた矛盾が露呈したといえよう。人口減少が進む日本では、外国人の力を借りなければ人手不足で社会機能を維持することもままならない。排外主義の芽を摘み、民主主義を守ってゆくためにも、建前を排して外国人の社会統合を真剣に考えるべき時期を迎えている。参院選の終盤、政府は急きょ「外国人との秩序ある共生社会推進室」を内閣官房に設置した。その慌てぶりは、政府がこれまで外国人政策を自治体任せにし、本気で取り組んでこなかったと認めたに等しい。政権の枠組みがいかなる形になろうとも、外国人政策を進めてゆくのが参院選で示された民意である。選挙中の指摘には事実に基づかないものもあるが、日本の社会制度の多くが外国人を想定していないのは確かだ。社会のルールを守ってもらうために規制を強化することは必要だろう。 ●定住前提の施策 より重要なのは社会になじんでもらうための共生の充実だ。政府にも共生社会に向け中長期的な課題を挙げたロードマップはある。だが定住を前提とした移民と認めず、あくまで一時的な滞在者との位置づけでは共生にも力が入らない。ドイツは第2次大戦後から多くの外国人労働者を受け入れてきたが、移民と認めたのは2000年代に入ってからだった。そこから社会になじんでもらう統合プログラムを始めた。外国人がコミュニティーを形成するのは自然の流れだが、それが閉鎖的になるのが問題だ。英国は外とのつながりをどの程度保っているかを統合の指標として見える化し、社会の分断を防ごうとしている。こうした取り組みにもかかわらず、欧州では難民危機などもあって排外主義的な勢力の台頭が著しい。日本の在留外国人は総人口の3%だが、増加ペースは年々高まり、参院選で現れたような反発もくすぶる。 ●知日派育む戦略 一口に外国人といっても、永住者、高度な専門職、特定技能、技能実習、留学生、インバウンドなど立場は異なる。それぞれに応じたきめ細かな対応が社会統合の質を高めよう。社会統合を考える際は、既存の制度をより透明でわかりやすいものにしていく視点も要る。外国人に選ばれる国になるうえで重要であり、それは日本人にとってもよいことだ。外国人政策は対外政策の意味もある。学生支援では自国民を優遇する国も多いが、日本は平等主義が一般的だ。留学生の受け入れは各国の指導層に知日派を育てるソフトパワー戦略であると考えたい。参院選では外国勢力の介入も指摘された。この問題に詳しい小林哲郎・早大教授は「防衛省、外務省、総務省などが外国勢力からの情報を検出しているが、それが世論にどのような影響を与えているかといった検証は十分でない」と指摘する。専門家を含めた体制づくりが急務だ。 *2-3;https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250723&ng=DGKKZO90190010S5A720C2CT0000 (日経新聞 2025.7.23) 食文化、縄文→弥生で継続 農耕伝来後も煮炊き料理 奈文研、土器に残る脂質分析 奈良文化財研究所(奈良市)などの研究チームは22日、土器で魚などを煮炊きする縄文時代の日本列島の食文化が稲作伝来後の弥生時代でも継続していたとする成果を発表した。遺跡から出土した調理用土器に残る脂質を分析した。日本列島には朝鮮半島から稲作や、キビやアワなどの農耕が伝わったとされる。研究では、検出方法が確立されているキビの成分に着目。朝鮮半島南部の遺跡(紀元前17~同8世紀ごろ)で出土した土器からはキビの成分が検出されたが、縄文から弥生にかけての九州北部の遺跡(紀元前18~同4世紀ごろ)の土器には確認できなかった。一方で、海産物などの成分は縄文土器と弥生土器のいずれからも検出された。このことから煮炊き調理に関しては従来の食文化が維持されていると結論付けた。研究は英ケンブリッジ大や英ヨーク大と共同で実施。朝鮮半島や九州の土器計258点を対象に分析した。成果は米科学誌にオンラインで掲載された。 *2-4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250729&ng=DGKKZO90317130Z20C25A7MM8000 (日経新聞 2025.7.29) 首相、続投方針変わらず 森山氏「自身の責任、来月示す」 自民両院懇 自民党は28日、大敗した参院選の結果への意見を聞くため、党本部で両院議員懇談会を開いた。党総裁の石破茂首相は「国家や国民に対して決して政治空白を生むことがないよう責任を果たす」と語り、続投する方針を改めて表明した。懇談会では首相に選挙の敗北の責任を取って退陣するよう求める声が相次いだ。首相は終了後、記者団に続投の考えに変わりないと述べた。懇談会は当初の2時間の予定を超え、4時間半ほど続いた。首相は米国との関税交渉の合意に触れ「実行に万全を期したい」と強調した。コメなどの農業政策、社会保障と税の改革も首相職を続ける理由に挙げた。森山裕幹事長は参院選の結果を総括する委員会を設置する考えを示した。8月中に報告書をとりまとめた段階で、進退も含めた自身の責任を明らかにするとした。森山氏は懇談会後、記者団に「幹事長が責任を取れという意見もあり、真摯に耳を傾けないといけない」と語った。引責辞任に含みを持たせた。首相は懇談会の冒頭で「多くの同志の議席を失うことになった。深く心からおわび申し上げる」と陳謝した。懇談会は意見交換会の意味合いが強い。首相や森山氏は出席者の声を聞き、続投への承諾を得る場と位置づけていた。首相の続投に反対する党所属の国会議員は、重要事項が決められる両院議員総会の開催を求める署名集めをしている。すでに総会の開催を要求できる3分の1以上の署名を確保した。森山氏は記者団に29日の役員会で総会を開く方向で協議する方針を明らかにした。 *2-4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250729&ng=DGKKZO90316860Z20C25A7EA2000 (日経新聞 2025.7.29) 首相に退陣要求噴出 自民幹事長「両院総会開催へ協議」 反・石破勢力、総裁選の前倒し視野 自民党が28日開いた両院議員懇談会は石破茂首相(党総裁)への退陣要求が続出した。「石破おろし」を進める勢力は総裁選の前倒しを視野に両院議員総会の開催を要求する方向だ。首相は日米関税合意の履行や参院選の総括を理由に続投する方針を崩しておらず、党内対立は激しさを増す。両院懇談会では2024年の衆院選と今回の参院選に敗北した責任を問う意見が相次いだ。小林鷹之元経済安全保障相は「組織のトップとしての責任の取り方についてしっかり考えていただきたい」と退陣を求めた。出席者によると発言は退陣を求める声が多数を占めた。「政治空白をつくるべきでない」と続投を支持する声もあったものの、少数にとどまった。続投するなら総裁選を実施して勝利をめざすべきだとの意見もあった。森山裕幹事長は両院懇談会で参院選の大敗を検証する総括委員会を設けると表明した。8月中に結論を得たうえで「自らの責任について明らかにしたい」と話した。首相は終了後、記者団の質問に「幹事長の判断としておっしゃったことについて私は言及をすべきではない」と答えるにとどめた。自らの責任に関しては「総合的に適切に判断したい」と述べつつ、続投方針に変わりはないと改めて表明した。倒閣勢力は委員会の設置を「時間稼ぎだ」と批判する。首相に圧力をかける次の一手は両院総会の招集になる。意見交換にとどまる両院懇談会と違い、重要事項の議決権がある両院総会は総裁選の前倒し実施などを議案に出して採択を迫ることができる。党則35条は党所属議員3分の1以上の要求で両院総会を開くべきだと明記する。旧茂木派の笹川博義農林水産副大臣は必要な署名を集めたと述べており、近く党側へ提出すると明らかにした。こうした動きを受け、森山氏は記者団に29日の党役員会で両院総会を開催する方向で協議したいと説明した。開催するかは不透明な面もある。森山氏は26日時点では「どういう内容の署名かという確認も必要だ」と語っていた。要求から7日以内に「招集すべきものとする」との党則規定は努力義務にすぎないとの解釈もある。党執行部が両院総会の開催要求を受け入れなかった先例もある。09年7月、首相だった麻生太郎氏の衆院解散戦略に反発した勢力が3分の1超の署名を集めた。執行部は有効な署名が足りていないと説明し、両院懇談会しか開かなかった。執行部が開催に応じない場合、倒閣勢力は次の選択肢として党則6条の活用を検討する。国会議員と各都道府県連の代表者1人の総数の過半が賛成すれば総裁選実施を前倒しできるとの規定だ。一方で、倒閣勢力は決め手を欠く。報道各社の世論調査から参院選の大敗要因は石破氏よりも自民党そのものにあるとの見方がある。「ポスト石破」の総裁選に名乗りを上げる動きも28日夕までに出ていない。衆目が一致する次の総裁候補が定まらない以上、少数与党下で必要な野党との協力交渉も後回しになる。政策が停滞するリスクがある。両院総会の署名集めは旧茂木派と旧安倍派、麻生派が主導した。旧安倍派は自民党離れにつながった政治資金問題を引き起こしただけに、党内に「反省の色がないのはおかしい」との声もある。足元の動きは非主流派との党内政局の様相が色濃い。国民民主党や参政党に流れた支持をどう取り戻すかという党再生の道筋を示すには遠い。 <地方創成について> *3-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1486172 (佐賀新聞 2025/6/17) 「地方創生2・0」国は東京問題と向き合え 政府は地方創生の今後10年の指針となる基本構想を閣議決定した。「地方創生2・0」と銘打つ石破政権の看板政策だ。安倍政権が打ち出した地方創生は、文化庁の京都移転など数えるほどの成果しかない。急速な少子高齢化への対応、人口減少への歯止め、東京圏への人口の過度な集中の是正は不十分なままだ。失われた10年とも言われる状況の打破が政府に求められている。東京圏は進学や就職を契機に全国から若者を集める。2014年に始まった地方創生では、東京圏への転入と転出を20年に均衡させる目標を設定。27年度に先延ばししたが達成は不可能だろう。基本構想は東京への転入を止めるのは難しいとして、地方の魅力を高め、地方へ転出する若者の流れを倍にする目標を掲げた。これで均衡にできる保証はない。地方には若者、特に若い女性が働きたくなるような場所が少ない。転出増には、若者らが仕事を通じ自己実現できる魅力的な職場を地方に増やすことが大前提となる。石破政権が東京一極集中の是正を掲げ続けるなら、まず中央省庁の一部や関係機関を地方に移転させるべきだ。次にこれまで以上に大胆な税制優遇策を導入する。これによって企業の本社移転をさらに促す。地方の居住者でも、リモートワークによって東京の企業でもっと働けるようにするのである。基本構想の目玉が、仕事や趣味を通じて居住地以外の地域に継続的に関わる人を「ふるさと住民」として登録する制度の創設という。目標は10年で登録者1千万人。二地域居住者や「ふるさと納税」する人らを登録すれば、数字は膨らみ「やっている感」は出せる。だが、新制度は地方のにぎわいや人口増に直結しないだろう。登録先に住民税を分割して納付できる制度を提案する声もあるが、総務省は検討しておらず実質は伴わない。このままでは、地方創生2・0も石破政権の政治的なアピールの道具に終わる恐れがある。地方税収に占める東京都と東京23区の割合は近年、上昇傾向が続く。豊かな財政を生かし手厚い子育て支援、高校授業料の実質無償化などを進める。これらの施策は周りの県からの移住も促す。東京都の独り勝ちは、首都直下地震といった災害への脆弱(ぜいじゃく)性を高める。同時に地方の持続可能性も損なう。都には首都として地方にも配慮した自治体経営を求めたい。それをしないのなら、国土の均衡ある発展のため、東京都の豊かな税収の一部を他の自治体にさらに回すことなども議論すべきだ。これら東京の問題に国は正面から向き合い調整すべきである。専門人材の不足によって道路や上下水道の管理・更新、介護、保険などの行政サービスを一つの市町村だけで実施できなくなってきた。今後は複数の市町村が共同で実施するか、都道府県が市町村を支援する仕組みの整備が不可欠となる。地方自治の充実のため、住民に一番近い市町村に権限を移す地方分権が進められてきた。今後も職員不足が深刻化する状況では、市町村から都道府県に権限を移すことも考えざるを得ない。人口減少が著しい市町村では、住民の生活維持が最優先である。都道府県、国が一定の責任を負いもっと前面に出なければ地域は守れない。 *3-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1507655 (佐賀新聞 2025/7/12) 参院選・人口減少と地方 地域維持の戦略をつくれ 「地方創生」は安倍政権が2014年に打ち出した。年末に行われた衆院選の自民党の公約は「景気回復、この道しかない」とある。公約の柱の一つに「地方が主役の『地方創生』」を明示し、「人口減少に歯止めをかける」と訴えた。自民は選挙のたびに「地方創生」を掲げ、地域の活性化という夢を軸に支持を集めてきた。政権浮揚には一定の効果があったと言えるだろう。しかし、その成果は全く見えない。2024年に生まれた日本人の子どもの数は、統計開始以降で初めて70万人を割り込み、女性1人が生涯に産む子どもの推定人数は過去最低を更新した。少子化は政府推計より15年も早く進んでいる。多死の時代に入り、24年だけで人口は約92万人も減った。与党政権が地方創生、人口減に歯止めといくら連呼しても、反転の兆しすらないのが現実だ。地方の人口減少は加速し、ヒト・モノ・カネの東京一極集中が進む。これらを止めるのは難しいとされていたにもかかわらず、安倍政権は掲げ続けた。結果から見て、選挙対策だったと疑われても仕方あるまい。立憲民主党が公約で「『地方創生』政策の検証」としたのはうなずける。さらに、少子化や人口減少、東京一極集中の流れを食い止め、国に人口戦略を総合的に推進する体制を整えると主張する。体制の必要性は理解できるが、食い止めることはもはや不可能だと指摘せざるを得ない。この参院選では、人口減を前提に行政サービスをどう維持するか、地域社会をどう守るかをもっと議論すべきだろう。石破政権は「地方創生2・0」の実現を掲げる。関係人口、交流人口を拡大させ若者・女性にも選ばれる地域づくりを進めるのが目玉だ。これまでの創生策で評価が少し高い施策を強調しているだけで、新味に欠ける。自民の公約、総合政策集を見ても、地方創生の失敗への反省はなく、人口減社会への対応策を羅列するにとどまった。政権与党として骨太の地方政策を示す責任があるのではないか。国民民主党が、大都市圏への人口集中の是正策として「移住促進・UIJターン促進税制」の創設、リモート勤務者支援など、地方への移住、企業の移転を促す税制を提案したのは注目したい。東京の独り勝ちは地域社会の存立にも影響する。人や企業が地方に移る方が、東京にいるより支払う税金が少なくて済むといった打開策をさらに検討すべきではないか。東京への集中は災害時のリスクも高める。石破政権は防災庁の設置などで「災害に強い日本」を実現すると言うなら、一極集中の是正に当然、本気で取り組むべきだ。日本維新の会は公約で、災害発生時に首都中枢機能を代替できる「副首都」をつくり、多極型社会への移行を目指すと提案した。維新発祥の地である大阪に副首都を誘致する考えだけに、党勢維持案としての面もあるだろう。それでも多極的な国土構造は社会の維持のためには不可欠だ。もはや自治体間で人口を奪い合うような余裕はない。人口や産業、行政サービスの適正な配置について、国民的な議論を始めるのである。そして、地域の持続可能性を維持する観点から、中小都市を核として地域を守る戦略を急いでつくらねばならない。 *3-3:https://www.agrinews.co.jp/news/index/321212 (日本農業新聞 2025年7月23日) 人口減対策を国民運動に 知事会議が提言 司令塔組織設置も 全国知事会議が23日、青森市で2日間の日程で開幕した。歯止めがかからない人口減少への対策に最優先で取り組むよう国に求める提言をまとめ、総合的な対策を展開するため民間企業も巻き込んだ国民的運動の推進や、取りまとめを担う庁レベルの「司令塔」の設置を要望。外国人政策を巡り、多文化共生の推進も訴えた。会議の冒頭、村井嘉浩会長(宮城県知事)は20日投開票の参院選の結果に触れ、「こうした時だからこそ、なお一層一致団結して、国難とも言える今の状況を克服するために取り組んでいかなければならない」とあいさつした。人口減対策に関する提言では、女性や若者の意見を取り入れた上で、働きやすく子育てしやすい環境を整備することや、税制改正などを通じて企業や大学の地方分散を推進することも求めた。知事会としても今後、経済界を巻き込む形で結婚支援策を検討する方針も確認した。外国人政策を巡っては、「国は労働者としてしか見ていないが、自治体は生活者として受け入れている」(静岡県の鈴木康友知事)といった意見が相次いだ。受け入れや定着のため、教育などの環境整備に国が責任を持つよう提言をまとめた。地方税財政については、参院選で消費税減税を訴える政党が伸長した影響も議論された。徳島県の後藤田正純知事は「持続可能な社会保障制度の維持が非常に不安定化している」との危機感を表明。東京一極集中による地方税の偏在の是正を訴える声も多く上がった。関税措置を巡る日米合意に関する意見も出た。富山県の新田八朗知事は23日午後の会合で、「一定の影響はあると思うが、輸出先の多角化などの課題に、国と地方がスクラムを組んで取り組む必要がある」と指摘した。 <地方の仕事・日本人のレベル・日本の低成長理由> *4-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250723&ng=DGKKZO90190860S5A720C2FF8000 (日経新聞 2025.7.23) 再エネ普及へインフラ強化 送電網・蓄電池へ投資訴え グテレス国連事務総長寄稿 エネルギーは人類の歴史を形作り、火や蒸気機関、原子力を生み出してきたが、現在はクリーンエネルギーの新時代の夜明けを迎えている。昨年、世界の新設電源のほぼ全てが再生エネだった。クリーンエネルギーへの投資額は2兆ドル(約300兆円)に達し、化石燃料への投資を8000億ドル上回った。太陽光や風力は今や地球上で最も安い電源で、クリーンエネルギーは雇用を創出し、経済成長の原動力だ。一方、化石燃料への補助金ははるかに多い。化石燃料に固執する国は経済を守るのではなく、むしろ競争力を損なっている。再生エネはエネルギーの主権と安全保障の確保にもつながる。化石燃料の市場は価格変動や供給網の寸断、地政学リスクに左右される。太陽光は価格の急騰もなく、風力は禁輸の対象にならない。エネルギーの自給自足を可能とするだけの再生エネの資源は、ほとんどの国にある。再生エネは社会の発展も促進する。電気のない生活を送っている数億人に迅速かつ安価、持続可能な形で供給できる。再生エネに移行する流れが止まることはない。だが、移行の速度と公平性は足りない。開発途上国は取り残され、温暖化ガス排出量は増えている。これを改善するには6つの取り組みが必要だ。第一に政府はクリーンエネルギーが普及するよう尽力する必要がある。各国は今後数カ月で新たな排出削減目標を提出すると約束している。世界の気温上昇を1.5度に抑える道筋を示さなければならない。世界の排出量の約8割を占める主要20カ国・地域(G20)がその先頭に立つべきだ。加えて、送電網や蓄電池にもっと投資すべきだ。これがないと再生エネは本来の力を発揮できない。現状は、再生エネに1ドル投じられるごとに、送電網と蓄電設備への投資は60セントにとどまる。この比率を1対1にする必要がある。さらに、エネルギー需要の増加分を再生エネで賄うべきだ。2030年までには世界のデータセンターの電力消費量が日本1カ国の使用量に匹敵する可能性がある。IT企業などは再生エネで賄うと打ち出すべきだ。エネルギー移行での社会的な公正さへの目配りも必要だ。脱炭素に備え、化石燃料に依存するコミュニティーを支援すべきだ。人権侵害や環境破壊が横行する重要鉱物の供給網も改革しなければいけない。再生エネ関連の供給網は特定地域に集中している。調達先を多様化し、再生エネ関連製品の関税を引き下げ、投資協定を見直す必要がある。最後に、途上国に資金を流入させるべきだ。太陽光発電に適した地域が多いアフリカは昨年の世界の再生エネ投資に占める地域別の割合がわずか2%だった。途上国の財政を債務が圧迫するのを防ぎ、開発銀行の融資能力を大幅に引き上げるべきだ。私たちは、この世界的な移行の機会を逃してはならない。 *4-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250705&ng=DGKKZO89832400U5A700C2EA5000 (日経新聞 2025.7.5) 太陽パネル導入に壁、来年度から工場や店設置目標義務 新型、効率・供給に課題 企業の工場や店舗の屋根に置く太陽光パネルの導入目標策定が国内1万以上の事業者に義務化される。多くの工場は重いものを屋根に置く設計はされておらず、導入拡大へは屋根や壁面に設置しやすい軽量薄型の新型太陽電池「ペロブスカイト」が有力な選択肢となる。性能や価格面など企業が導入を急拡大するには課題が山積する。化石燃料の利用の多い工場や店舗は2026年度から屋根置き太陽光パネルの導入目標を国に報告する必要がある。定期的に計画を更新する必要はあるが、3~5年後をめどに掲げる導入目標が達成できなくとも虚偽の目標設定や報告でなければ罰則はない。目標未達でも罰則を設けないのは太陽光発電の量を増やすことだけが目的ではないためだ。経済産業省幹部は「日本に技術的強みのある次世代型太陽電池の普及を促す目的もある」と明かす。積水化学工業が量産にめどをつけるなど、今後市場への本格導入が始まるペロブスカイトの普及促進を念頭に置く。経産省はこれまでも積水化学の研究開発や生産ラインの整備費用やカネカの研究開発費用などを支援してきた。国内に大規模な工場や店舗を持つ企業は脱炭素に向けて太陽光パネルの導入を進めてきた。例えばイオングループは2月までに1469カ所の店舗・施設に導入済みだ。キユーピーも設置可能な既存工場への導入をほぼ終えた。キリンホールディングス(HD)はグループ全体で約7割の工場で導入した。各社が導入を進めるのはシリコン製の太陽電池がほとんど。軽量薄型のペロブスカイトでは設置場所が広がる。イオングループも「軽量かつ移設が容易にできるのであれば施設の壁や窓、屋内への導入を検討する」と関心を示す。ユニ・チャームも「建物の側面にも設置でき、倉庫などへの展開も期待できる」とする。太陽光パネルの国産化再興の一手としての期待もかかる。1963年、シャープの量産などを皮切りに国産品の製造が広がったが、価格に優れた中国製との競争に苦しんだ。パナソニックホールディングスや出光興産子会社のソーラーフロンティア(東京・港)が国内自社製造から手を引いた。太陽光発電協会(東京・港)によると、25年1~3月に国内出荷された太陽光パネルのうち国内で生産されたものは約5%にとどまる。ペロブスカイトはヨウ素など主要な原料を国内調達でき、国内の積水化学やシャープが技術開発を進める。ただ足元ではペロブスカイトの導入拡大へは懐疑的な声もある。建設業者などからは「安価なパネルと比べると投資に対して発電効率が低い」といった声も漏れる。耐久性も課題を残す。耐用年数は10~15年程度とされ、建設大手の関係者は「50年以上運用する工場などでの採用は現状難しい」と話す。設置条件などが定められておらず、「軽さを生かした設置が難しい」(パネルメーカー)といい、ルール整備も必要だ。SOMPOリスクマネジメントの堀内悟上席コンサルタントは「設置方法で(火災や事故の)リスクは変わり、分析が必要だ」とする。供給体制も未熟だ。積水化学は「現状の生産ペースでは設置目標義務を賄えない恐れがある」と懸念を示す。シャープやカネカも製品化を急ぐが、企業が求める量を確保できるか不透明だ。「湿気に弱い点や鉛使用による環境リスクなどの課題がある」(ユニ・チャーム)。「価格面から補助金など資金面での支援の充実が必要だ」(キリンHD)。中国勢も一部で量産を始めている。「安価な中国勢に流れてしまう懸念もある」(パネルメーカー)。ユーザーとメーカー両サイドの不安はつきない。太陽光発電は設備の多くを輸入に頼る。日本が先行したシリコン製は国内産業としては衰退した。ペロブスカイトも中国勢が勢いを増す。技術や環境整備の壁を乗り越えるには官民の目線を合わせた連携が不可欠になる。 *4-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250717&ng=DGKKZO90077710W5A710C2EA2000 (日経新聞 2025.7.17) 〈参院選2025 選択の夏〉原発再稼働の是非は、積極派は電源に「最大限活用」 慎重派、将来は再エネ100%に 参院選では、暮らしや企業活動に欠かせないエネルギーをどうまかなうかも争点になる。原子力発電所と再生可能エネルギーをどこまで活用するかで各党の立場は大きく分かれた。自民党は安全性を確認した原発の再稼働を積極的に認める方針で政策集には「原子力などの電源を最大限活用する」と記した。公明党も「最大限活用」で足並みをそろえ、2024年衆院選の公約にあった「可能な限り原発依存度を低減」との文言も削除した。自公両党は政府が2月にまとめたエネルギー基本計画を意識する。同計画は「原子力など、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」と明記。4年前の前回計画にあった「可能な限り原発依存度を低減する」との文言を削り、原発推進にカジを切った。 ●国民民主は新設 原発活用に最も積極的なのは国民民主党だ。再稼働のみならず、建て替えや新増設も進める。日本維新の会も早期の再稼働や次世代原発への建て替えを認める立場だ。参政党は再稼働を巡るスタンスを明らかにしていないが、次世代原発の研究に積極投資する考えだ。原発に慎重姿勢を取る野党も多い。立憲民主党は再稼働を容認する構えだが、実効性のある避難計画と地元合意を前提にしている。新増設には反対するほか、「すべての原子力発電所の速やかな停止と廃炉決定を目指す」と将来の原発ゼロ方針も維持する。れいわ新選組は「即時使用禁止」、共産党は「速やかに原発ゼロ」をうたう。エネルギーを巡るもう一つの論点が、太陽光や風力など再エネの推進だ。積極的なのは立民、共産、れいわ。いずれも将来の電源構成の100%を再エネでまかなうと主張する。温暖化ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」は再エネ拡大を進めて達成するとの立場だ。自公両党は「最大限の導入」とする表現にとどめ、具体的な数値目標は設けなかった。日本は国土が狭く、平地が少ない。再エネの適地が限られるため、海外に比べて導入コストが高くなりがちだ。また天候に応じて出力が変わる再エネをどう制御し、安定的に電力を供給するかも大きな課題になる。再エネの急速な拡大に慎重な党もある。国民民主は再エネ普及のため電気料金に上乗せされている賦課金の徴収停止を訴える。同党は「手取りを増やす」ことにこだわっており、「賦課金が増大し国民に大きな負担になっている」ことを問題視している。 ●家計負担が増大 太陽光発電などの拡大に伴って、25年度の再エネ賦課金は標準家庭で月1500円余り。年換算では1万9000円ほどに増えており、家計にとって無視できない負担になっている。参政党は再エネ賦課金を廃止するとともに「高コストの再エネを縮小」と明記。温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から離脱し、カーボンニュートラルの是非そのものを検証すると主張する。日本政府は「50年までのカーボンニュートラル達成」を20年に宣言した。実現には温暖化ガスを排出しない再エネ拡大が不可欠で、導入費用を国民が広く薄く負担するのが賦課金だ。その停止・廃止は「日本が脱炭素に背を向けた」と国際社会から批判されかねない。経済産業省は再エネ賦課金を停止・廃止した場合「発電事業者から訴訟を受けるリスクがある」(幹部)とみる。政府は再エネ電力を火力などよりも高く買い取る固定価格買い取り制度(FIT)を12年度に始めた。企業や家庭が再エネで発電した電気を電力会社が10~20年間買い取る仕組みで、電気料金に上乗せする賦課金を原資とする。国は一定額での買い取りを約束しており、財源がなくなって買い取りを中止すれば訴訟問題になりうる。再エネ賦課金の総額は年3兆円規模。消費税で約1%分にあたる規模で、代替財源を見つけるハードルは高い。電力需要は今後、人工知能(AI)普及やデータセンター拡大によって増えると政府は見込む。エネルギー基本計画によると40年度の発電電力量は1.1兆~1.2兆キロワット時と、22年度実績より1~2割増える。安定的で安価なエネルギーの確保は、国民の暮らしと企業の国際競争力にも直結する課題だ。安全性を大前提としたうえで、安定性や経済性、脱炭素といった要素をどう組み合わせていくかについて国民的な議論が求められる。 *4-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250723&ng=DGKKZO90193750T20C25A7MM8000 (日経新聞 2025.7.23) 原発「脱炭素へ不可欠」、関電、美浜に新設調査発表 AI時代の電源整備 関西電力の森望社長は22日、美浜原子力発電所(福井県美浜町)において、原発の建て替えに向けた地質などの調査を始めると発表した。新増設の具体的な動きは2011年の東京電力福島第1原発の事故後、初となる。再始動する新増設を、原発への信頼を取り戻し、人工知能(AI)時代の産業構造へ作り替える起点にしていかねばならない。森社長は記者会見で、「電力需要はデータセンターや半導体産業の急激な成長を背景に伸びていく。脱炭素を進めるためにも原子力は必要不可欠だ」と強調した。未曽有の被害をもたらした福島第1原発事故から14年。安全性を高めた新しい規制基準の下で電力会社は既存原発の再稼働を進めている。一方で電力需要増大や温暖化ガス削減に向けた脱炭素電源として、原発に対する視線は変わりつつある。電力広域的運営推進機関によれば、国内の電力需要は向こう10年で約6%増える。再生可能エネルギーを最大限伸ばす努力をあきらめてはならない。しかし、太陽光や風力発電の適地の偏りや、時間や天候で変化する出力の不安定性を考えると、再生エネだけでは力不足だ。原発には不断の安全への取り組みや、回復途上の国民の信頼という大きな課題が残る。原発の建設や運転に関わる人材が先細りしている問題もある。それでも選択肢として目を向けるときだ。既存原発の再稼働を進めても、いずれ設備としての寿命を迎える。新設に着手しても稼働開始まで20年単位の時間が必要だ。50年のカーボンニュートラル実現を約束する日本には、そんなに時間が残されていない。電力需要増大の象徴がAI普及を支えるデータセンターだ。日本ではデータセンターの9割が関東、関西に集中する。その需要増大に対応するには2つの方法がある。1つは原発や再生エネといった脱炭素電源が豊かな北海道や九州にデータセンターを集め、光ファイバーで必要なデータをやり取りする方法だ。電力の単位である「ワット」と、通信の単位である「ビット」をつなげて「ワット・ビット連携」と呼ぶ。もう1つの道は、データセンター需要が集中する大都市圏で、大量かつ安価な脱炭素電力を供給する力を高めることだ。関電の美浜原発での建て替えはこれにあたる。重要なのはワット・ビット連携や、美浜原発の建て替えを、AI時代の産業構造転換に弾みをつけるために戦略的に活用していくことだ。米国では巨大IT事業者が自社のデータセンター用に原発から直接電力を買ったり、原発に隣接してデータセンターを置いたりする動きが広がりつつある。同様の取り組みは、日本では難しい。発電事業者は電力を需要家に平等に売らねばならないルールがあり、原発立地地域や特定の顧客だけに電気を安く売ることは原則できない。そこでデータセンター事業者が今後、新たな原発の建設・運営に参画し、一定の電力引き取りを確約するといった選択も可能にしてはどうか。より安い地点を求め移り気なデータセンター事業者を、国内につなぎとめる材料になるはずだ。こうした仕組みを整えることが、原発が立地する地域の電気料金を下げるなど恩恵を目に見える形にする早道でもある。 *4-2-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1511189 (佐賀新聞 2025/7/17) 参院選 原発・エネルギー/福島事故の教訓忘れずに 政府が原発推進にかじを切る中、参院選で原発とエネルギーについての議論は低調と言わざるを得ない。だが14年前に東京電力福島第1原発事故を経験した私たちにとっては、常に考えなければならないテーマだ。政府は2月、新しいエネルギー基本計画と地球温暖化対策計画をまとめた。福島事故の反省から掲げてきた「可能な限り原発依存度を低減する」の文言を削除し、原発推進を明確にした。電源構成に占める原発の割合を8・5%(2023年度実績)から40年度に2割程度に上げる。また再生可能エネルギーを最大電源として位置づけ、40年度に4~5割にする目標も掲げた。現在動いている原発は14基。基本計画が示す2割にするためには30基を超える既存原発をほぼ全て動かさなければならない。電力需要を賄うためにはいくつもの方法を組み合わせていく必要がある。これが政府・与党の考えだ。基本計画は古い原発を建て替える要件を緩和し、新たな建設に道を開いた。自民党は既存原発より安全性が高いとする「次世代型」の具体化を掲げ、公明党も「総基数は増えない」として容認した。野党はさまざまだ。立憲民主党は「新増設は認めない」とする。日本維新の会や国民民主党は再稼働を推進する姿勢だ。参政党や日本保守党も前向きだ。一方で共産党やれいわ新選組、社民党は原発反対を訴えている。各党の立場の幅は広い。再稼働を巡る現在の最大の課題は、東電柏崎刈羽原発だ。6号機と7号機は既に原子力規制委員会の審査に合格し、技術的には動かすことが可能になっており、東電は6号機を優先する方針を表明している。だが大きなハードルが残っている。再稼働に必要な地元同意である。新潟県の花角英世知事は県民の意見を聞き是非を判断するとしており、市町村長との懇談会や、県民の公聴会を開いている。県民意識調査も9月末までに結果がまとまる。知事の判断時期は近づいているとみられる。重要なのは、福島で事故を起こした東電にとって初めての再稼働になるということだ。技術的にクリアされても、東電に原発を動かす資格がそもそもあるのか。そのことが問われる。柏崎刈羽原発は新潟県や東電だけの問題ではないという意識で注視したい。福島第1原発では今も過酷な廃炉作業が続いている。取り出した溶融核燃料(デブリ)は昨年11月が0・7グラム、今年4月も0・2グラム。全体で880トンと推定されているのに比べ、ごくわずかだ。東電は今後大規模な取り出しをする考えだが、その方法は決まっていない。「事故から30~40年で廃炉」という目標の達成は厳しい状況に追い込まれている。周辺住民の避難も続いている。福島第1原発だけではない。完成延期を繰り返している青森県六ケ所村の核燃料サイクル施設や、核のごみの最終処分場など重要な課題は解決できていない。地球温暖化対策や、二酸化炭素(CO2)の排出を減らす脱炭素の取り組みは喫緊の課題だ。ウクライナや中東の情勢もあり、資源に乏しい日本にとってエネルギー確保に不安な状況が続く。ただ、まだ終わらない福島事故の教訓を忘れてはならない。 *4-2-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1520936 (佐賀新聞 2025.7.30) 【福島第1原発】「廃炉の本丸」攻略遠、難題山積、見直し不可避 東京電力が2030年代初頭に着手を目指していた福島第1原発3号機での溶融核燃料(デブリ)の本格取り出しが、37年度以降にずれ込む見通しとなった。デブリ取り出しは「廃炉の本丸」とされるが、その前段にも多くの難題が立ちはだかり、なかなか切り込めない。東電は51年までの廃炉完了目標に拘泥するが、見直しは避けられそうにない。 ▽困難 「元々困難だと感じていた。検討を進めれば進めるほど、より深刻に分かってきた」。廃炉の技術支援を担う原子力損害賠償・廃炉等支援機構の更田豊志廃炉総括監は29日の記者会見で、51年までの廃炉完了目標の実現性について、包み隠さず語った。原子力規制委員会前委員長の更田氏は第1原発の廃炉に思い入れが強く、処理水放出などにも率直な見解を示してきた。目標見直しの必要性は「現時点で十分な判断材料はない」と踏み込まなかったものの、現在有力視される取り出し方法も「小さな可能性が見えたというような感じだ」と述べるにとどめ、目標実現のめどが立っていない現状を強調した。 ▽不透明 デブリの取り出しは、建屋の水素爆発を免れて原子炉格納容器内部の把握が進んでいた2号機で先行した。試験的採取との位置付けで、取り出せたのは計1グラム未満。東電は「採取は性状分析のためで、本格取り出しとは全く別」と説明する。3号機での本格取り出し前に12~15年の準備工程が必要との案が示された。「想定通り進捗した場合」との条件付きで、技術的に不透明な部分があるとして、東電が実現可能性を1~2年かけて精査するとしている。3号機原子炉建屋北側にある廃棄物処理建屋は、本格取り出し前に撤去する必要性が指摘された。廃液などが保管されている建屋解体は難工事となるのは必至。発生するがれきなどは高線量の廃棄物となり、保管先を確保する必要がある。デブリの取り出しルートと想定される原子炉建屋1階にも極めて高線量のエリアがある。制御棒の関連機器が汚染源とみられ、除染しても十分に線量が下がっていない。 ▽何年か 3号機での本格取り出しは、原子炉建屋上部に開口部を設けて、細長いポール状の機器を差し込んでデブリを崩す方法と、横から取り出す方法との組み合わせが有力とされたが、その後の工程は今回の検討の対象外だ。さらに1、2号機の取り出しも待ち構える。デブリがある場所や形状、建屋の状況はまちまちで、3号機の進め方が通用するのか予断を許さない。順調にデブリを取り出せたとしても、どこにどのように処分するかは検討さえ始まっていない。東電の小野明廃炉責任者は、51年までの廃炉完了を掲げた国と東電の工程表は「重い」として、見直す時期ではないと強調。一方で「(廃炉が終わるのが)何年とは言えない」と漏らした。 *4-2-5:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16270772.html (朝日新聞 2025年7月30日) 東電、「51年廃炉」は維持 専門家「現実性ない」 福島第一 東京電力福島第一原発の本格的な燃料デブリの取り出し開始時期が、後ろ倒しになった。最難関の作業が遅れることになるが、東電は2051年までとする廃炉完了の目標は維持する考えだ。東電福島第一廃炉推進カンパニーの小野明代表は29日の記者会見で「廃炉完了目標時期を否定する状況ではない」と繰り返した。廃炉は、政府と東電が11年12月にまとめた中長期ロードマップ(廃炉工程表)に基づいて東電が進めている。これまでも、使用済み燃料の取り出しなど多くの作業が遅れた。工程表は改訂を重ねたが、51年までの廃炉完了という大枠は維持されてきた。今回、3号機の燃料デブリの取り出し開始時期は明らかにしたが、作業期間は「不確かさがある」として示していない。さらに1~3号機で推計880トンのデブリがあるが、1、2号機は工程も工法も決まっていない。小野代表は会見で、今後1~2年で1、2号機の準備作業の検討を進めるとして「1~3号機で同時に(デブリを)取り出すのは不可能ではない」と述べ、「どう達成できるかを考えていきたい」と強調した。東電が今回示した工法は、廃炉について助言する原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)が昨年3月に示した提言をもとにしている。NDFは専門家による小委員会をつくり、デブリに水をかけながら取り出す「気中工法」、原子炉を水で満たす「冠水工法」、デブリを充填(じゅうてん)材で固めて削り出す「充填固化工法」の3案を検討。冠水工法は原子炉や建屋の損傷が激しく、建屋を覆う構造物を設置するのも難しいことから、放射線量を抑えられる充填固化工法と気中工法を組み合わせることを提案した。東電は提案された工法を採用したうえで、原子炉建屋の上に設ける装置を小さくすることで負荷を減らし、原子炉の側面から取り出す方法を示した。ただ、今後1~2年で取り出し工法について検証を進め、必要があれば見直すとしている。早稲田大学の松岡俊二教授(環境経済・政策学)は「37~51年の14年間で、推計880トンのデブリがすべて取り出せると思う人はいないのではないか。現実性のない目標が維持され続けるのは、福島の復興を考える上でも良くない」と指摘する。 *4-2-6:https://imidas.jp/jijikaitai/k-40-059-10-03-g112(IMIDAS 2010/3/26) 原発温廃水が海を壊す、原発からは温かい大河が流れている(元京都大学原子炉実験所助教 小出裕章) 原子力発電所の稼働に不可欠な冷却水は、その膨大な熱とともに放射能や化学物質をともなって海に排出される。この温廃水(温排水 hot waste water)の存在、あるいは環境への影響が論じられることは少ない。地球温暖化への貢献を旗印として原子力回帰が叫ばれる中、けっして避けられない温廃水の問題を浮き彫りにする。 ●蒸気機関としての宿命 地球は46億年前に誕生したといわれる。その地球に人類が誕生したのは約400万年前。地球の歴史を1年に縮めて考えれば、人類の誕生は大みそかの夕方になってからにすぎない。その人類も当初は自然に寄り添うように生活していたが、18世紀最後の産業革命を機に、地球環境との関係が激変した。それまでは家畜や奴隷を使ってぜいたくをしてきた一部の人間が、蒸気機関の発明によって機械を動かせるようになった。以降、大量のエネルギーを使うようになり、産業革命以降の200年で人類が使ったエネルギーは、人類が全歴史で使ったエネルギー総量の6割を超える。その結果、地球の生命環境が破壊され、多数の生物が絶滅に追いやられるようになった。その期間を、地球の歴史を1年に縮めた尺度に合わせれば、大みそかの夜11時59分59秒からわずか1秒でのことである。今日利用されている火力発電も原子力発電も、発生させた蒸気でタービンを回す蒸気機関で、基本的に200年前の産業革命のときに誕生した技術である。その理想的な 熱効率は、次の式で表される。 理想的な熱機関の効率=1-(低温熱源の温度÷高温熱源の温度) (※それぞれの温度には「K(ケルビン)」の単位で表す絶対温度を用い、「℃」で表す 摂氏温度の数字に「273」を加え、たとえば0℃=273K、100℃=373Kとなる) だが、現実の装置ではロスも生じるため、この式で示されるような理想的な熱効率を達成することはできない。火力発電や原子力発電の場合、「低温熱源」は冷却水で、日本では海水を使っているので、その温度は地域差や季節差を考慮しても300K(27℃)程度であり、一方の「高温熱源」は炉で熱せられ、タービンに送られる蒸気である。そのため、火力発電と原子力発電の熱効率は、基本的にそれらが発生しうる蒸気の温度で決まり、その温度が高いほど、熱効率も上がることになる。現在稼働している原子力発電では、燃料の健全性を維持するため冷却水の温度を高くすることができず、タービンの入り口での蒸気の温度はせいぜい550K(約280℃)で、実際の熱効率は0.33、すなわち33%しかない。つまり、利用したエネルギーの2倍となる67%のエネルギーを無駄に捨てる以外にない。 ●想像を絶する膨大さ この無駄に捨てるエネルギーは、想像を絶するほど膨大である。たとえば、100万kWと呼ばれる原子力発電所の場合、約200万kW分のエネルギーを海に捨てることになり、このエネルギーは1秒間に70tの海水の温度を7℃上昇させる。日本には、1秒間に70tの流量を超える川は30筋もない。原子力発電所を作るということは、その敷地に忽然として「温かい大河」を出現させることになる。7℃の温度上昇がいかに破滅的かは、入浴時の湯の温度を考えれば分かる。ふだん入っている風呂の温度を7℃上げてしまえば、普通の人なら入れないはずである。しかし、海には海の生態系があって、その場所に適したたくさんの生物が生きている。その生物たちからみれば、海は生活の場であり、その温度が7℃も上がってしまえば、その場では生きられない。逃げることのできない植物や底生生物は死滅し、逃げることができる魚類は温廃水の影響範囲の外に逃げることになる。人間から見れば、近海は海産資源の宝庫であるが、漁業の形態も変える以外にない。 ●途方もない環境破壊源 雨は地球の生態系を持続させるうえで決定的に重要なもので、日本はその恵みを受けている貴重な国の一つである。日本には毎年6500億tの雨が降り、それによって豊かな森林が育ち、長期にわたる稲作も持続的に可能になってきた。雨のうち一部は蒸発し、一部は地下水となるため、日本の河川の総流量は年間約4000億tである。一方、現在日本には54基、電気出力で約4900万kWの原子力発電所があり、それが流す温廃水の総量は年間1000億tに達する。日本近海の海水温の上昇は世界平均に比べて高く、特に日本海の温度上昇は著しい。原発の温廃水は、日本のすべての川の水の温度を約2℃温かくすることに匹敵し、これで温暖化しなければ、その方がおかしい。そのうえ、温められた海水からは、溶け込んでいた二酸化炭素(CO2)が大量に放出される。もし、二酸化炭素が地球温暖化の原因だとするなら、その効果も無視できない。もちろん、日本には原子力発電所を上回る火力発電所が稼働していて、それらも冷却水として海水を使っている。しかし、最近の火力発電所では770K(約500℃)を超える高温の蒸気を利用できるようになり、熱効率は50%を超えている。つまり、100万kWの火力発電所の場合、無駄に捨てるエネルギーは100万kW以下で済む。もし、原子力発電から火力発電に転換することができれば、それだけで海に捨てる熱を半分以下に減らせる。さらに、火力発電所を都会に建ててコージェネレーション(cogeneration)、すなわち無駄に捨てるはずの熱を熱源として活用すれば、総合的なエネルギー効率を80%にすることもできる。しかし、原子力発電所は決して都会には建てられない。 ●熱、化学物質、放射能の三位一体の毒物 温廃水は単に熱いだけではなく、化学物質と放射性物質も混入させられた三位一体の毒物である。まず、海水を敷地内に引き込む入り口で、生物の幼生を殺すための化学物質が投入される。なぜなら海水を施設内に引き込む配管表面にフジツボやイガイなどが張り付き、配管が詰まってしまっては困るからである。さらに、敷地から出る場所では、作業員の汚染した衣服を洗濯したりする場合に発生する洗濯廃水などの放射性廃水も加えられる。日本にあるほぼすべての原子力施設は、原子炉等規制法、放射線障害防止法の規制に基づき、放射性物質を敷地外に捨てる場合に濃度規制を受ける。原子力発電所の場合、温廃水という毎日数百万tの流量をもつ「大河」がある。そのため、いかなる放射性物質も十分な余裕をもって捨てることができる。洗濯廃水も洗剤が含まれているため廃水処理が難しい。原子力発電所から見れば、苦労して処理するよりは薄めて流すほうが得策である。 たとえば、昨今話題となる核燃料サイクルを実現するための核燃料再処理工場は、原子力発電所以上に膨大な放射性物質を環境に捨てる。ところが、再処理工場には原子力発電所のような「大河」はない。そこで、再処理工場は法律の濃度規制から除外されてしまった。逆にいえば、原子力発電所にとっては、温廃水が実に便利な放射能の希釈水となっているのである。 *4-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250705&ng=DGKKZO89837470V00C25A7MM8000 (日経新聞 2025.7.5) 日産、中国をEV拠点に 来年から 東南アや中東に輸出 日産自動車は2026年に中国から電気自動車(EV)の輸出を始める。輸出先は東南アジアや中東、中南米を想定している。日産は業績低迷を受けて世界で生産体制を見直している。価格と性能の両面で競争力のある中国製EVを幅広い地域に出荷し、経営の立て直しを急ぐ。日産は4月に中国で発売し、売れ行きが好調なEVセダン「N7」などを中国から輸出する。N7はデザインや開発、部品の選定まで日本の本社ではなく中国の合弁会社が担った初めてのEVだ。中国での価格は11万9900元(約240万円)から。現地のEV大手、比亜迪(BYD)の競合製品と比べても同水準の安さだ。広東省広州市の工場で生産している。N7のソフトウエア機能には中国企業の人工知能(AI)技術を採用している。国によっては利用が制限されている。日産は4月に中国のEV開発大手、阿爾特汽車技術(IAT)に出資した。同社の協力を得て中国市場向けのソフトなどを輸出仕様車に変える。日産の現地子会社が中国の国有自動車大手、東風汽車集団と通関などの実務を担う合弁会社を設立することでも合意した。新会社には日産子会社が6割を出資する。中国は世界に先駆けて車の電動化が進んだことで、EVの航続距離や車室の快適性、エンターテインメント機能などの性能が高い。日産は中国製の低価格EVの需要は国外でも高いとみる。 *4-3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250817&ng=DGKKZO90720210X10C25A8MM8000 (日経新聞 2025.8.17) 政府、アフリカとFTA検討 日本車輸出を促進 日本政府はアフリカ諸国と自由貿易協定(FTA)の締結に向けた検討を始める。産学官による検討会を設置し、本格的な交渉入りをめざす。まずはケニアなど物流の要衝になる東部や人口が多いナイジェリアを念頭に置く。日本からの自動車輸出の促進などを期待する。20~22日に横浜市で開く第9回アフリカ開発会議(総合2面きょうのことば、TICAD9)で発表する見通しだ。産学官の検討会で経済連携の効果や課題を2年程度かけて検証する。日本企業の進出意欲の高い国との協議を優先する。ケニアなど東部8カ国でつくる地域経済共同体「東アフリカ共同体(EAC)」との交渉が候補になる。アフリカ全体とのFTA締結を最終目標とする。ケニアは港湾が整備されている。日本政府は東アフリカをインド洋を通じた物流の要と位置づけ、インドや中東諸国と一体の経済圏を築く構想を持つ。東部以外ではアフリカで人口最大のナイジェリアが候補になる。原油の生産量も最大で、内需が拡大する。西アフリカの物流や工業のハブとして成長するガーナなども連携相手に挙がる。港湾から内陸国へ陸路で運ぶのに複数の国を通過するため、各国の関税が輸送コストの上昇要因になる。各国の関税を撤廃し、アフリカ進出を図る日本企業のビジネス環境を整える。日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、2024年に日本とアフリカは輸出入ともにそれぞれ1兆3000億円程度にとどまっている。日本からの輸出は中古車を含む自動車が多く、輸入は鉱物資源の割合が高い。日本は50カ国を超すアフリカのいずれの国ともFTAや経済連携協定(EPA)を結んでいない。経団連は6月の提言で、アフリカとの協定整備の遅れを指摘した。韓国やインド、欧州勢が先行し「世界の競合企業と競争条件で大きな格差が生じている」と訴えた。 *4-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250817&ng=DGKKZO90715160W5A810C2TYC000 (日経新聞 2025.8.17) 北極の氷消え、地球過熱、50度超の熱波で山火事も頻発 氷が消え地球に熱がこもる。こんな悪循環が加速している。気温上昇を抑える役割を果たしてきた北極の海氷は2030年には消滅するという予測さえある。氷が溶けて海水面が上昇し、太平洋の島しょ国の住民は故郷を離れ始めた。熱波による山火事と感染症も猛威を振るっている。「地球温暖化の最前線」とも呼ばれる北極域は温暖化の影響が最も表れる地域とされる。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国立極地研究所によると、24年9月に人工衛星で観測した北極の海氷の年間最小面積は407万平方キロメートルと、衛星観測史上で5番目に小さかった。北極の海氷面積の最小値は長期的に減少傾向にある。米コロラド大などの国際研究チームは24年、温暖化がこのまま進むと27年にも北極の海氷が9月にほとんどなくなる可能性があると国際科学誌で報告した。 ●島から気候移住 北極は地球の冷却源として働くが、海氷が減るとその機能が弱まる。海氷は太陽光を反射して温暖化を抑える役割がある。また海面に蓋をして水分の蒸発量も抑えている。海氷がなくなると、北半球での水の循環が強まり、豪雨や干ばつなどが起きやすくなると指摘されている。同様に深刻なのが、世界各地の陸上に点在する氷床や氷河の減少だ。スイスのチューリヒ大学などの研究グループによると、世界の氷河は00~23年に年間で平均2730億トン減少し、約1.8センチメートルの海面上昇を引き起こしたと推計された。25年5月にはスイス南部のアルプス山脈で、氷河の崩壊によって大規模な土石流が発生し、築600年の家屋が並ぶ歴史ある村が土砂に埋め尽くされた。海面上昇は沿岸部の居住地を奪って移住を余儀なくする「気候難民」を生み出す。太平洋諸島のツバルは、2100年までに国土の約9割が水没する恐れがある。 ●氷河解け海面上昇 23年にはオーストラリアとの間で、年間280人のツバル国民がオーストラリアの永住権を取得できる協定を結んだ。25年7月の申請の締め切りまでに全国民の約9割が申し込んだ。欧州連合(EU)の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」によると、1999~2024年までの25年間で9.38センチメートルの海面上昇が確認された。上昇の6割が氷河や氷床の融解を原因とし、3割は海水温が高くなったことによる海水の膨張が影響した。気候変動に伴う記録的な熱波は、世界各地で頻発する山火事にも深く関係する。国内最高気温となる50.5度を記録したトルコでは25年の7月下旬、各地で山火事が相次いで発生した。広範囲が焼失して町や村単位で住民が避難したほか、消火作業にあたった複数人が死亡した。火災によって焼失する森林の面積は近年増えている。米シンクタンクの世界資源研究所(WRI)によると、24年に焼失した森林は1350万ヘクタールで、ギリシャの国土面積に相当する。23年の1190万ヘクタールから13%増加した。25年に入っても、米カリフォルニア州や日本、韓国、カナダなどで大規模な火災が立て続けに発生した。専門家は、いずれも人為的な気候変動によって気温や雨量に変化があったことが影響したとする分析結果を発表している。山火事は被害を出すだけでなく、温暖化を加速させる悪循環も生む。温暖化が進むことで、山火事を引き起こしやすい極端に乾燥した環境をつくる。 ●感染症が拡大 温暖化は蚊が媒介する感染症のまん延を加速する。25年7月から中国南部の広東省仏山市を中心に「チクングニア熱」の感染拡大が続き、7000人以上の感染が確認されている。チクングニア熱は発熱や発疹、関節痛などを引き起こす。世界保健機関(WHO)によると死に至ることはまれだが、ワクチンや治療薬はないという。また15年に1355人だったデング熱の死者数は24年には6991人にまで増えた。高温が日常となったいま、危機への対応は急務となっている。 *4-3-4:https://www.agrinews.co.jp/news/index/326952 (日本農業新聞 2025年8月21日) 農水予算重点事項 生産費減へ大区画化 直播の普及支援 農水省は20日、2026年度農林関係予算概算要求の重点事項を示した。政府が生産拡大意向を示す米が柱。生産費の削減へ、農地の大区画化を進める。労働力不足への対応になるとして、水田に種を直接まく直播(ちょくは)を普及する。主食用米の需要に応じた生産を支える水田活用の直接支払交付金(水活)を明記した。自民党農林合同会議に示した。27日に総額や各事業の額を示す。米の生産性向上へ、農地の大区画化を進める。農地集積・集約化やスマート技術の導入を加速する。共同で利用する機器の導入や、「節水型乾田直播」の検証を支援する。高温に耐える品種や多収性品種への転換を促す。農地の大区画化を巡っては、農家自らの施工による区画拡大などを支える「大区画化等加速化支援事業」も盛り込んだ。同事業では巨大区画化の効果検証や普及も進める。主食用米の将来的な需給緩和を懸念する声を踏まえ、産地の自主的な長期計画販売への支援を盛り込んだ。農家の減収の一部を穴埋めする収入保険制度の普及や、27年度からの新たな環境直接支払交付金の「制度設計」の推進を掲げた。主食用米から麦・大豆、米粉用米などへの転換を促す水活を明記した。議員からは財源確保を念押しする意見が出た。農水省は「水活は需要に応じた生産の核となる部分だと思っている。しっかり対応する」と応じた。共同利用施設の再編など「農業構造転換集中対策」の詳細は要求段階では示さず、年末にかけて詰める。同対策は5年間で事業規模2・5兆円、うち国費1・3兆円を見込む。議員からは既存事業の財源を減らさずに確保するよう求める声が上がった。 *4-3-5:https://digital.asahi.com/articles/AST8L2VVWT8LULFA00DM.html (朝日新聞 2025年8月18日)ミニストップ、おにぎりや弁当の消費期限を偽装 全店で販売を中止 大手コンビニエンスストアのミニストップ(本社・千葉市)は18日、店内で加工した「手作りおにぎり」や総菜食品について、一部の店舗で消費期限を偽って販売する不正が見つかった、と発表した。原因の究明と改善策が実施されるまでの間、全店で店内加工のおにぎりや総菜、弁当の販売を中止する。同社によると、一部店舗で6月下旬、消費期限を記したラベルが二重に貼られたおにぎりが見つかった。同社が調査したところ、国内全1784店のうち、埼玉、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都府県の23店で不正が確認された。店内で調理後、ただちに消費期限を計算してラベルを貼るべきなのに、時間をおいてから貼るなどして、期限を2~3時間過ぎた商品を販売していたという。これまでのところ、購入者から健康被害の連絡はないという。ホームページでも一連の経緯を説明し、謝罪文を掲載した。 *4-4-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1509477 (佐賀新聞 2025/7/15) 参院選・コメと農政 増産と所得安定の両立探れ コメを巡る政策が改革を迫られている。随意契約による政府備蓄米の放出で、コメの流通はようやく落ち着く兆しが見えてきたが、対症療法にとどまっている。コメ政策の見直しは避けて通れず、農家と消費者の双方が安心できる政策が必要だ。転作奨励金などを見直して増産に転換する道筋を描き、農家の所得安定と両立させることが焦点になる。昨年からの米価高騰は「コメの生産量が足りないのではないか」という疑念を生じさせた。インバウンド(訪日客)によって外食産業で需要が拡大し、消費量は思ったほど減っていないとの指摘もある。卸売業者が何重にも関与する複雑な流通の過程で、コメがどんな価格水準で取引されているのか、はっきりしない面もある。生産者の自家消費や、知人らに配る縁故米の把握もできていない。石破茂首相はコメ輸出の拡大を念頭に「増産にかじを切る」と繰り返し強調しているが、生産調整見直しの具体策はまだこれからだ。コメ不足と価格高騰が消費者に大きな不安を与えたことを考えれば、生産や流通の実情把握を急ぐべきだろう。これまでの農政は生産量を抑え、価格を維持する手法を続けてきた。減反政策が終了してからも、人口減によるコメ消費の減少を見越して、主食用から飼料米や加工米への転換を促す政策がとられてきた。増産路線に転じるなら、米価が下落した場合に備え、生産者の支援策が必要だろう。立憲民主党は水田10アール当たり2万3千円を農家に支給する「食農支払」の創設を唱えている。国民民主党は稲作農家に10アール当たり1万5千円を交付する「食料安全保障基礎支払」を提案している。農家への所得補償は丁寧に制度を考えねばならない。営農の規模や形態によって、収入保険と直接支払いを組み合わせる工夫があってもいい。ただ、資金支援が農地の集約や大規模化の動きを妨げるのは避けたい。農業の担い手は急ピッチで高齢化している。担い手不足が深刻化するのに歯止めをかける対策も必要だ。自民党は土地改良や農地集約、デジタル技術導入のため今後5年間、思い切った予算を確保すると公約した。立民は就農支援の資金を10倍に拡充し、都市部からの移住を後押ししようとしている。国民は若者の新規参入を促すため、直接支払制度に「青年農業者加算」を設けるとしている。兼業農家も地域の実態を踏まえて支援対象にするという。コメの増産や農家の所得を支える財源も課題になる。転作奨励金などを振り替えれば足りるのだろうか。農政改革に伴い、農業予算の組み替えや洗い直しを検討しなければならない。コメ不足の対策として、日本維新の会は「ミニマムアクセス(最低輸入量)」の枠外で輸入するコメの関税を時限的に引き下げると訴えている。政府はコメの輸出拡大を目標にしてきた。だが農産物の海外販路の開拓はそう簡単ではない。良い品質のコメを決められた時期に、契約通り出荷することを輸出先から求められるのは当然だ。生産拡大につなげるには、冷凍おにぎりや酒類など加工品の輸出も考える必要がある。コメ政策は国内の農業の行方を左右する。選挙戦の渦中でも深さと広がりのある議論を求めたい。 *4-4-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC1279H0S5A610C2000000/ (日経新聞 2025年6月26日) 長野・林業大学校、即戦力化へ新カリキュラム スマート林業に対応 長野県林業大学校(長野県木曽町)はドローン操作実習などの新カリキュラムを、2026年度から導入する。林業では人手不足や従事者の高齢化が深刻で、機械化による生産性向上が急務となっている。スマート林業や林業経営を習得する新たなカリキュラムで多様な学びのニーズに対応するとともに、即戦力を求める産業界の需要に応える。新設するのは企業経営と高所作業の2科目で、ほかにスマート林業への対応として林業機械学などの実習を強化する。実習を通じて、ドローン操作では国家資格の二等無人航空機操縦士を取得できるようにする。また、進路に応じて2年次でのコースを選択できるよう再編し、マネジメントコースとスペシャリストコースを設ける。募集人員は20人で、修業年限は2年間。県によると林業大学校は全国に28あり、定員を充足しているのは長野県林業大学校を含む3校という。1979年の開校以来、836人が卒業し、民間企業や森林組合などに就職している。 *4-4-3:https://mainichi.jp/articles/20250112/ddm/005/070/040000c (毎日新聞 2025/1/12) 日本の漁獲量=回答・金将来 <気になる> 日本の漁獲量(ぎょかくりょう)が大幅に減少しています。1984年に1282万トンあった漁業・養殖業(ようしょくぎょう)の生産量は、この40年間でどんどん減り続け、2023年に372万4300トンと統計開始以降、最低を更新しました。このままだと、いずれ国産の魚が食べられなくなるのでしょうか。減少している背景を探り、持続可能な漁業について考えます。 ◆どうして減っているの? ○国際的規制や海の温暖化で なるほドリ なぜ日本の漁獲量は減っているの? 記者 減少の原因は複数あります。まず挙げられるのは、およそ40年前に国際的なルールで定められた「200海里水域制限(かいりすいいきせいげん)」です。日本の漁船は70年代ごろまで、はるか遠くの外国の海で漁業を行う「遠洋(えんよう)漁業」を盛んに行っていました。しかし、82年に「国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)」という国際ルールが採択されて、それぞれの国の岸から200カイリ(約370キロ)内に外国の船が勝手に入って漁をしてはいけないことになり、日本の漁獲量は徐々に減り始めました。 Q 日本は遠洋漁業が主流だったの? A 水産庁によると、日本の漁業は戦後、沿岸から沖合へ、沖合から遠洋へと漁場を拡大することで発展しました。ピーク時の遠洋漁業の漁業生産量は、漁船漁業全体の約4割を占めていましたが、90年ごろにその量は約1割まで低下しました。条約の規定によって、打撃を受けたわけです。 Q ほかの原因は何? A 近年、最も深刻な問題となっているのは、気候変動による海水温の上昇や海洋汚染による海洋環境の異変です。特に、温暖化による海水温の上昇は顕著(けんちょ)で、気象庁によると、日本近海の海面水温はこの100年で1・28度高くなりました。特に直近4~5年間の海面水温の上昇は異常なレベルで、日本近海の温暖化は世界の海よりも早く進行しているという分析もあります。 Q 海の温暖化が進むと、なぜ魚がとれなくなるの? A 魚は種(しゅ)によって適した水温の海域に生息します。このため、海水温の変化によって、魚たちは生息域(せいそくいき)を変えているとみられます。例えば、サワラは暖かい海を好み、もともと東シナ海や瀬戸内海に多く生息していました。ですが、海水温の上昇で日本海などでの生息が確認されるようになりました。このほか、サンマは主に北太平洋に生息し、秋になると千島列島(ちしまれっとう)から日本列島の東岸を来遊するのが主流でしたが、現在はより沖合を来遊するようになっています。これらの魚が生息域を変えることで、日本近海でとれていた魚がとれなくなったり、特定の魚の漁獲量が減少したりしています。 Q 漁獲量が増えている魚もあるの? A 日本の全体的な漁獲量は減少していますが、地域によっては、これまでとれなかった魚がとれたりして、漁獲量が増加している魚の種類もあります。特に、北海道のブリの漁獲量は10年ごろから増え、20、21年は全国トップになるほどに増加しました。宮城県のサバやタチウオ、福島県のトラフグなどは10年前と比べて大幅に漁獲量が増加しています。これらの現象は、地域の名産物(めいさんぶつ)であった魚がそうでなくなったり、反対にこれまでとれなかった魚がとれることでその地域の水産物になったりと、我々消費者にも大きな影響を与えています。現場の漁師からは「海の変化に困惑している」との声が聞かれます。 ◆国産が食べられなくなるの? ○生産力維持へ さまざま工夫 Q このまま漁獲量が減り続けたら、国産の魚を食べられなくなる日がくるのかな? A たしかに、海洋環境の異変が進行し続ければ漁獲量の減少は今後も進むことが予想されます。一方、国や自治体、漁業協同組合(ぎょぎょうきょうどうくみあい)などは現状の漁獲量の減少に歯止めをかけようと、魚介類(ぎょかいるい)の多様性や生産力を維持できる「持続可能な漁業」の取り組みを行っています。例えば、青森県五所(ごしょ)川原(がわら)市は、大和(やまと)しじみの操業期間や漁獲量などの制限を持続的に行い、安定的な生産を実現しています。また、北海道のホタテは多くの水産物が生産量を減らしている中、長年、養殖業も合わせて年間約30万~40万トンの生産を維持し続けており、13年に環境への配慮と水産資源の持続可能性を実現した漁業に与えられる国際的なエコラベル認証を取得しています。 Q 私たちにできることはあるの? A 海にやさしい環境への配慮を一人一人が心がけることが大切です。海洋ごみや海岸に不法投棄されたごみなどによる海洋汚染は、魚の生態系にも大きな影響を及ぼすとされています。エコバッグやマイボトルを使用してレジ袋やペットボトルの使用を控えたり、ビーチクリーンや河原の清掃活動(せいそうかつどう)に参加したりするなど海洋環境に貢献できる取り組みは多くあります。小さな取り組みが海の資源保全につながり、魚を食べられる日常を守ることにつながります。 *4-4-4:https://digital.asahi.com/articles/AST7L13S0T7LUTIL018M.html (朝日新聞 2025年7月19日)進むウナギの完全養殖 細長の水槽で生存率アップ、異業種から参入も 稚魚の不漁によって価格が高騰するウナギを安定的に生産するため、「完全養殖」の研究が進んでいる。19日は土用の丑(うし)の日。ウナギの養殖には、ハンコやガス会社など異業種からの参入も相次いでいる。水産庁によると、2024年に国内で流通したウナギは計6万941トンで、外国産も含めほぼ養殖でまかなっている。環境省が13年に絶滅危惧種に指定したニホンウナギは日本から約2千キロ離れたマリアナ海溝周辺で産卵する。孵化(ふか)した赤ちゃんは5~6センチほどの稚魚(シラスウナギ)に成長し、日本周辺で捕獲された後、国内の養殖場で半年~1年半ほど育てられ、出荷される。稚魚は減少傾向で、国を挙げた安定供給のための研究が進んでいる。千葉県成田市の老舗うなぎ屋「駿河屋」の店主で、全国鰻蒲焼(うなぎかばやき)商協会理事の木下塁さん(48)は「新技術で安定供給につながるのはいいこと。一方で、将来的に供給が増えすぎ、価格が大幅下落する不安もある」と話す。水産研究・教育機構は2010年、人工の稚魚を親魚まで育て、その親の卵を孵化させる完全養殖に世界で初めて成功した。政府は25年先の50年までに天然の稚魚を使わない完全養殖への移行を掲げる。実現のため、低コストで卵からシラスウナギを育てる技術が欠かせず、機構は今年7月、農業機械を販売するヤンマーホールディングスなどと稚魚を大量に生産できる新たな水槽を開発したと発表した。従来の1千リットル規模のかまぼこ形の水槽では数百匹の飼育が限度だった。水槽の直径が50センチ以上になると成長速度と生存率が低下することが確認され、直径40センチ、長さ150センチの新たな細型の水槽を作ると、1千匹を飼育できた。機構の担当者は「水槽の直径が大きいと、7ミリほどの赤ちゃんがエサにたどり着けない可能性があった」と指摘する。水槽の素材も従来のアクリル製から、安価な繊維強化プラスチックに変更。エサも希少なサメの卵から、ニワトリの卵や脱脂粉乳など比較的安い材料に切り替え、特許も取得した。2016年に4万円だった稚魚1匹の生産コストは20分の1以下の1800円に下げたが、天然稚魚の取引価格と比べ、依然として3倍ほど高い。水槽の大型化や光熱費の削減、エサやりの自動化などを進め、機構の担当者は「将来的には1千円以下での生産を目指す」と話す。水産庁によると、国内のニホンウナギの養殖事業者は442(昨年11月時点)に上り、異業種からの挑戦も目立っている。 ●ハンコ販売やガス会社も参入 3年前から地下水を利用して陸上養殖を始めた、埼玉県川越市のガス会社「武州ガス」もその一つだ。「武州うなぎ」として、年間3万匹の出荷をめざす。昨年から機構と完全養殖の共同研究を進める。ウナギの赤ちゃんを人工海水を使った専用の水槽で飼育し、稚魚に成長させることができた。今後は1%に満たない成功率のアップが課題で、責任者の大河原宏真さん(52)は「近隣には老舗のウナギ店が多く、地域貢献につなげたい」と話す。デジタル化や少子化で、印章の市場が縮小する中、印章製造販売大手「大谷」(新潟市)は24年からウナギの養殖に参入した。同社はすでにウイスキーの製造に取り組み、蒸留時に発生する温水を活用し、養殖池の温度を27~30度に保ち、ウナギを育てる。「新潟ウイスキーうなぎ」としてネットで販売するほか、地元のホテルでも提供する。堂田尚子社長は「数千万円の初期投資が必要だったが、ウナギは単価が高いので、生産量を増やしつつ、数年で黒字化を目指したい」と話す。 *4-4-5:https://www.jiji.com/jc/article?k=2025021401087&g=soc (時事通信 2025年2月14日) 三陸沖の水温上昇、過去最大 黒潮の異常進路で―東北大 三陸沖の海水温が2023年以降、平年より6度以上高い状態が続いていることが、東北大などの研究チームの解析で分かった。22年末から続く黒潮の異常な北上が原因で、上昇幅は世界の海と比較しても過去最大。水産業への影響や豪雨など異常気象との関連が懸念される。論文は14日までに、日本海洋学会の英文国際誌に掲載された。黒潮は九州の南から太平洋を北上する暖流。本来は房総半島沖で東に向かうが、22年末ごろから三陸沖を北上し、昨年4月には青森県沖に達した。東北大の杉本周作准教授らは、人工衛星や観測航海で得られた水温データを解析。23年4月から昨年8月までの間、三陸沖の海面水温は平年と比べ6度以上高い状態が続いていた。また、塩分濃度の解析から、黒潮の北上でもたらされた南方の暖かい海水が、水温上昇を引き起こしていることも分かった。影響は水深700メートルまで達し、海面からの熱は上空2000メートルの気温も上昇させていた。黒潮の異常進路は、和歌山県沖で南に大きく蛇行する「大蛇行」が17年以降続いていることや、北海道から三陸沖に南下する寒流の親潮が弱まっていることなどが原因の可能性があるという。杉本准教授は「生き物や水産資源、気象にも影響があるはずで、海水温上昇が私たちの暮らしにどういう影響があるかを評価したい」と話した。 *4-5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250818&ng=DGKKZO90722200X10C25A8TL5000 (日経新聞 2025.8.18) がんゲノム検査に財政の壁、制度で対象制限、治療到達は「10万人中7000人」 がんの患者ごとに遺伝子を検査し、最適な治療薬を届ける「がんゲノム医療」を受けた件数が3月末で10万件を超えた。しかし実際に治療薬が見つかった件数は7000件程度に過ぎない。検査条件が末期患者に限られるなど制度設計の問題もあるが、背景には高額な検査費用に対する医療費増への懸念が立ちはだかっているようだ。今年5月、国立がん研究センターは2019年から始まったゲノム医療の中核となる「遺伝子パネル検査」に登録した人が10万例を超えたと発表した。河野隆志・がんゲノム情報管理センター長は「一つの大きな通過点で、より多くのデータを集めて治療の向上に使いたい」と成果を強調する。 ●化学療法後の「最後の手段」 もっとも実際に最適な治療薬が見つかり治療までたどり着いたのは7000件程度と非常に少ない。日本では転移が分かった段階でホルモン療法や化学療法などの「標準治療」を受け、その治療が効かなくなる段階でパネル検査を受ける制度となっている。米カリフォルニア大学の加藤秀明准教授は「転移が分かっても制度上すぐにパネル検査ができない。(日本に闘病中の家族がおり)非常にもどかしい」と打ちあける。足元ではせっかく登場した新薬が、パネル検査を受けないと使えないという「矛盾」も生じている。24年に登場したアストラゼネカの乳がん治療薬「カピバセルチブ」、ファイザーの「タラゾパリブ」の2つは、特定の遺伝子に変異がある患者に使えるが、変異を調べるためにはパネル検査が必要となる。パネル検査は吐き気や脱毛などの副作用を伴う化学療法などが終わった後の体力が落ちた患者が対象となるため、投与できないケースも多い。新薬の承認条件を調べるとこうしたパネル検査が必須となる薬剤は計8種類もあり、今後さらに増える可能性もある。ある大学病院の乳腺外科の専門医は「検査と治療薬の使い方に齟齬(そご)がある」と指摘する。当然のように医療学会や患者団体からは制度改正を求める声があがる。6月にはがんの専門医や研究者でつくる日本臨床腫瘍学会などが「パネル検査の制限撤廃が理想的だ」とする声明を出した。東京科学大学の池田貞勝教授は、患者に適切なタイミングで薬が届かないことについて「規制上の障壁による『隠れドラッグロス』とも呼べる状況だ」と指摘する。 ●高額な検査費用 10万人で560億円 しかし厚生労働省は制度改正に慎重だ。検査対象を制限している点について「患者の生存期間の改善につながるというエビデンス(根拠)が現時点で証明されていない」と説明するが、最大の理由には医療費負担の懸念があるようだ。がん患者の多くは治療薬や検査、入院などを含めて支払いが高額となるため高額療養費制度を活用することが多い。自己負担額の上限が決まっており、仮に年収370万~770万円程度で月額医療費が100万円かかった場合、自己負担額上限は8万7000円程度。残りは公費と保険者の負担となる。もともとパネル検査は高額で、1回あたり約56万円かかる。検査を受ける人が年間で1万人増えると単純計算で56億円。日本で新たにがんと診断される人は年100万人いるとされ、うち1割の患者が検査を受けると560億円の新たな医療費が必要となる。政府関係者は「いまは末期の患者だけだからなんとかなっているが、治療薬も合わせると費用は膨大だ。財源を考えると対象を絞るのは仕方がない」と明かす。米国のパネル検査は転移が分かった段階で速やかに受けられる設計となっており、標準治療後などの条件はない。しかし加入する保険のプランによって受けられる治療・検査の範囲が異なるほか保険料も高額だ。低中所得者にとって金銭的なハードルは高い。英国では費用対効果を厳格にチェックする仕組みがあり受診する病院も自由に選ぶことはできない。高額な治療薬の使用が認められないケースもあり「各国でもある意味で制限されている」(国内専門医)という。日本では画期的な新薬や検査技術が比較的早く承認され、自己負担を抑えながら様々な治療を受けられる。パネル検査の対象が広がればより多くの人が早い段階で、最適ながん治療を受けられるようになる。しかし高齢化が進み、医療費が膨らむなか、高額な検査をいつまでも受け入れていくだけの余力はない。限られた医療財源と画期的なゲノム医療。このバランスをどうとるのか、医療の取捨選択を含めて国民的な議論が必要となる。 *4-5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250818&ng=DGKKZO90722300X10C25A8TL5000 (日経新聞 2025.8.18) 国際競争、社会の理解不可欠 2003年に人類がヒトの全ゲノムを解読して以降、ゲノム情報を医療にいかす取り組みが加速している。特に進展が著しい分野の一つががんだ。一気に数百の遺伝子を調べるパネル検査によって、個々の患者のがんの原因遺伝子を調べられるようになった。そこで始まったのがゲノムデータ集積の国際競争だ。米国は15年からゲノムを活用した個別化医療を目的に2億ドル以上の費用を投じている。18歳以上の成人100万人以上の国民データを集めて、がんを中心に遺伝子情報や血液や腸内細菌などのデータの蓄積を進めている。がんだけでなく希少疾患や遺伝子が原因の先天性の難病といった情報を集めており、世界で先行しているとされる。英国では13年から「ゲノミクス・イングランド」という国家プロジェクトを立ち上げ約10万人分の全ゲノムを解析する取り組みをスタート。すでに解析を終え、その知見から新たな診断技術や治療薬の開発につなげている。現在は追加のプロジェクトを立ち上げ、最大500万人の参加者を集めたゲノム解析事業を進めている。その意味で日本はゲノム解析の後発組といえる。ゲノム医療はがん患者の検査に役立つ新たな選択肢であることは確かだ。ただし患者に質の高いゲノム医療を届けるには、限りある医療財源の課題とその解決、そして日本におけるゲノムデータ構築の目的、意義、利活用方針をこれまで以上に社会に理解してもらうよう周知していくことも大切だ。 *4-5-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250818&ng=DGKKZO90723950X10C25A8CM0000 (日経新聞 2025.8.18) 消化器外科医「5000人不足」 がん診療「病院集約を」 厚労省検討会、40年推計 2040年にがん手術を担う消化器外科医が約5千人不足する――。こうした推計を盛り込んだ報告書を、厚生労働省のがん診療に関する検討会がまとめた。「必要な医師数が確保できず現在提供できている手術を継続できなくなる恐れがある」と指摘。高齢化と現役世代の減少が進む中、長時間労働などを理由に、若手医師が消化器外科を避けがちなことが背景にありそうだ。報告書は、治療の効率性を向上し、医師が経験を蓄積して高度な医療技術を維持できるよう、都道府県が医療機関の集約化などを検討する必要があるとした。40年時点で新たにがんと診断される患者は推計105万5千人で、25年の102万5千人と比べ約3%増加。85歳以上は40年に25万8千人で、25年の17万8千人から約45%増となる。検討会では手術の需要と供給のバランスを予測した。需要は、初回手術を受ける患者数が25年で推計46万5千人なのに対し、40年は約44万人で約5%減る。一方、供給側の医師はこれを大幅に上回る速さで減少する。特に外科医の約7割を占める消化器外科では、日本消化器外科学会の所属医師(65歳以下)が25年の約1万5200人から、40年に約9200人へ約39%減少。需給を単純計算すると、約5200人の不足が見込まれるとした。報告書は手術の他、放射線療法では高額な装置の維持が困難になる場合があり「効率的な配置を計画的に検討することが必要だ」と言及。薬物療法は、患者が定期的に継続して治療を受けられるよう、どの地域でも提供できる体制の構築を訴えた。必要ながん医療の体制は、都市部かどうかなどによっても異なる。報告書は都道府県での検討に当たり、患者の医療機関へのアクセス確保に留意するよう求めた。 <日本の規制が促すサービス業の質低下> *5-1:https://mainichi.jp/articles/20250701/k00/00m/020/251000c (毎日新聞 2025/7/1) アマゾン、配送拠点を6カ所新設 年内に全国翌日配送も可能に インターネット通販大手のアマゾンジャパンは1日、指定住所までの「ラストワンマイル」の起点となる配送拠点を国内6カ所に新設し、当日配送専用の拠点も全国16カ所で展開すると発表した。2025年内に翌日配送を全国で可能にし、当日配送できる地域も順次拡大させるとしている。新たな配送拠点は、岡山、千葉、福岡、石川、北海道、東京の6都道県に設ける。さらに入荷から保管、梱包(こんぽう)、仕分け、配送までできる拠点も年内に16カ所整備し、午後1時までに注文した商品を当日の夜間帯に届ける当日配送を数万点の商品で可能にするという。アマゾンの物流施設では、自走式ロボットが商品棚を持ち運び、大量の荷物を効率よく発送する「アマゾンロボティクス」と呼ぶ仕組みを採用。ロボットは世界300カ所以上の拠点で計100万台導入されている。今回、より効率的な動きを実現するため、新たな生成AI(人工知能)「ディープフリート」を取り入れることで、従来より効率を10%高めるという。東京都内で1日開かれた記者会見で、開発子会社の技術責任者タイ・ブレイディ氏は生成AIの技術について「サービスにかかるコストを削減し、顧客からの信頼性も向上できる。まだ始まり。(生成AIは)多くのデータから学び、さらに賢くなる」と期待した。日本での事業開始から25年。アマゾンジャパンのジャスパー・チャン社長は「最新技術でネットワークを築いてきた。今後もより良い暮らしに貢献できるよう取り組む」と話した。また、名古屋市に8月、新たな物流拠点を稼働させると発表した。三菱地所が設計し、延べ床面積は12万5000平方メートルで、「西日本最大」の拠点となる。温室効果ガスの排出削減にこだわり、壁面にも太陽光発電設備を導入。発電設備容量は5500キロワットで、米国外では最大規模だという。 *5-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1493859 (佐賀新聞 2025/6/27) 「置き配」標準化検討、国交省、物流業者負担軽減、秋にも方向性 国土交通省は26日、宅配ボックスや玄関前に荷物を届ける「置き配」を、宅配便の標準サービスとする検討に入った。業界で人手不足が深刻化する中、再配達を減らし、負担削減につなげるのが目的。物流業界関係者も交えた検討会の初会合を同日開いた。秋までに方向性をまとめる。置き配は、配達時間を気にすることなく、荷物を受け取れるという利点がある一方、盗難や汚損などのトラブルへの懸念から利用をためらう人もいる。トラブル防止など課題の解消が焦点となりそうだ。検討会は有識者や自治体関係者らで構成。会合は非公開で、国交省によると、出席者からは、受取人が不在時、業者が敷地内に立ち入ることを念頭に、セキュリティーやプライバシー面での対策を求める意見が出た。トラブル防止のため宅配ボックス設置をどのように推進するかといった課題を指摘する声もあったという。会合に出席した国交省の幹部は「地域で不可欠な物流サービスを持続可能なものにするため、既成概念にとらわれず、今の時代に合った合理的なやり方を生み出したい」と説明した。物流各社は、国交省が作った基本ルールを参考に、荷主との契約条件などを盛り込んだ「運送約款」を策定している。現行の基本ルールは対面での受け取りを前提としており、置き配は、荷物を受け取る側が選択する追加サービスとなっているケースが多い。国交省は、ルールを改定し、対面での受け取りに加え、置き配も標準と位置付けることを視野に入れている。物流の輸送力低下 低賃金や高齢化などで物流業界の人手不足が深刻化する中、トラック運転手の時間外労働の上限を年960時間とする規制が2024年4月から始まった。労働環境が改善するとの期待の一方、運べる荷物の量が減り、輸送力の衰えがさらに進むとの指摘がある。インターネット通販の浸透で荷物の量が増えていることも背景にある。 *5-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250818&ng=DGKKZO90726060Y5A810C2MM8000 (日経新聞 2025.8.18) 自治体に「最高AI責任者」 総務省が指針 補佐の専門人材も 総務省は地方自治体向けに生成AI(人工知能)の利用手引を作成する。行政事務での活用事例や使用上の注意事項をまとめ、年内にも公表する。生成AIの活用推進や管理を担う最高AI責任者(CAIO)を各自治体に置き、専門知識をもってCAIOの判断を助ける補佐官の設置を求める。 補佐官の設置に関しては、人材の確保が地方では難しいとみられることから、複数の自治体が連携して共同で置くことも想定している。設置に法的拘束力はないものの、自治体側の取り組みを促す。自治体では住民情報を扱う部署が多く、AI学習に個人情報などの機密情報を用いることを禁止するとも明示する。行政事務での活用事例については、自治体での先行事例を示す。AIを使って住民からの相談を24時間受け付けるといったサービスを例示する。AI活用によって会議の議事録の要約で5割、企画書の作成で3割の業務時間を減らした自治体もあるという。利用指針のひな型も用意し、地方行政における生成AIの活用を後押しする。小規模な自治体ほどAIに関する知見をもつ人材の確保に難があり、導入に踏み切れないケースは多い。総務省が6月に公表した調査結果では、政令指定都市以外の1721市区町村で生成AIを導入しているのは全体の3割程度にとどまっていた。導入していないと回答した自治体は半数近くに上り、すでに9割ほどが導入済みの政令指定都市と大きな開きがある。利用指針がない自治体も全国で1000を超える。総務省は自治体が安全に生成AIを活用できるようになれば、人口減少下での地方行政の効率を高められるとみている。 <その規制は意味があるのか> *6-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1498093 (佐賀新聞 2025/7/2) 日本郵便処分 規律不在の原因を究明せよ 安全をないがしろにする法令違反がなぜ放置されてきたのか。日本郵便が国土交通省の行政処分を受けた。集配業務を手がける郵便局の約75%に上る2391局で酒気帯びの有無などを確認する法定点呼がルール通り実施されていなかったためだ。飲酒運転も発覚しており、規律不在としか言いようがない。各地の郵便局にあるトラックやバン約2500台が使えなくなった。異例の重い処分だ。経営陣や管理職の指示を現場が軽んじる体質があるのではないか。現場で起きている問題を上層部が把握できていないこともはっきりした。問題の根は深い。当たり前の規律が社内に浸透していないのは明らかだ。社長だった千田哲也氏は「会社全体の構造問題だ」と述べたことがある。限られた地域や部門だけで起きた不祥事ではないのだ。点呼を法令で決まった通り実施するのは当然だ。しかしそれだけで解決するわけではない。本来あるべき規律が確立していなかったのか、どこかで緩んでしまったのか。17万人の従業員を抱える巨大組織をいつまでも迷走させてはならない。郵便局の法定点呼は配達員を対象に、アルコール検知器を使って確認する。これまでの調査では、繁忙時には手順に沿った点呼が実施されなかったり、管理者がいる時だけ実施したりしていた事例が判明している。「適切に実施した」と虚偽の報告をしていたケースもあったという。日本郵便によると、2024年度に飲酒運転は4件あった。ワインをペットボトルに入れ、配達員が業務中に飲んでいたり、飲酒した配達員が車を塀に衝突させる事故が起きたりした。郵政民営化によって郵便、貯金、簡易保険は日本郵政を持ち株会社とする民間企業に生まれ変わった。民間のガバナンス(企業統治)を受け入れ、誠実に働いてきた従業員が大半だろう。だが民営化以前の古い組織や体質が温存されている面も否定できない。法令順守よりも旧来の慣習が優先されることはなかったか。郵便局の現場でなれ合いのような関係が残っていないだろうか。取締役会を軸に企業統治を徹底することが欠かせない。不祥事隠しを許さず、直ちに取締役に報告し是正する。こうした経験を重ねることが社内に緊張感を生む。持ち株会社の日本郵政による監督も必要だ。郵便物が減少し、日本郵便の25年3月期決算は42億円の赤字だった。今回の行政処分によって、ライバルの物流会社に業務委託せざるを得なくなり、収益に打撃が生じるのは避けられない。安全確認をないがしろにしてきたツケは重く、26年3月期決算にも影響が生じる可能性がある。日本郵便は昨年、下請け企業からの値上げ要請を拒否し公正取引委員会から行政指導を受け、ゆうちょ銀行の顧客情報の不正利用も発覚した。日本郵政、日本郵便ともトップが交代し、旧郵政官僚が社長に就いた。法令順守と企業統治を最優先する布陣だろうが、業務効率化と過疎地を含むサービス維持という基本を忘れてはならない。郵政民営化は国民の選択によって実現した。不祥事によって郵便事業や人事が官業に回帰することはあってはならない。新経営陣の覚悟と知恵が問われている。 *6-2:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250625/k10014844061000.html (NHK 2025年6月25日) 国交省 日本郵便のトラックなど使った運送事業の許可取り消し 日本郵便が配達員の点呼を適切に行っていなかった問題で、国土交通省は25日、トラックなどおよそ2500台の車両を使った運送事業の許可を取り消しました。また3万台余りの軽自動車を使った事業については早急な対策を求める安全確保命令を出しました。日本郵便では、全国の郵便局3188か所のうち75%にあたる2391か所で配達員に対して飲酒の有無などを確認する点呼を適切に行っていなかったことがことし4月、会社の調査で明らかになっています。この問題について国土交通省は監査の結果、虚偽の点呼の記録を作成するなどの違反行為が確認されたとして、25日、日本郵便の千田哲也社長に対し、トラックなどを使った運送事業の許可の取り消しを伝える文書を手渡しました。この処分によって、トラックやバンタイプの車両、およそ2500台が5年間、配送に使用できなくなります。文書を受け取った千田社長は「多大なるご心配、ご不安をおかけしていることを改めておわびします。この処分を厳粛に受け止め、経営陣が先頭にたって再発防止に取り組みます」と述べました。また、国土交通省は、日本郵便が国に届け出て行っている3万台余りの軽自動車を使った事業について、監査の結果が出るまでに時間がかかるとして、早急な安全対策を求める安全確保命令を出しました。国では今後、監査の結果を踏まえて、車両の使用停止などの行政処分を検討する方針です。 ●日本郵便 “代替手段を確保し利用者への影響 最小限に” 国土交通省が、トラックなどおよそ2500台の車両を使う運送事業の許可を取り消したことを受けて、日本郵便は、代替手段を確保して利用者への影響を最小限に抑えようとしています。 日本郵便は、 ▽およそ2500台のトラックやバンタイプの車両で「ゆうパック」の集荷や郵便局の間の輸送を行っているほか ▽およそ3万2000台の軽自動車や、 ▽およそ8万3000台のバイクで郵便物の配送を行っています。 このうち、今回、許可が取り消されたのは、およそ2500台のトラックなどを使った事業です。 会社では、当面、 ▽自社の軽自動車を活用するほか ▽大手宅配会社などに業務を委託する といった代替手段を確保して、利用者への影響を最小限に抑えようとしています。日本郵便が使用できなくなる、およそ2500台の車両と同じタイプのものは、大手宅配会社2社も合わせて6万台使用していることから、国土交通省は、業務委託などを進めることで影響は抑えられるとみています。一方、国土交通省は、郵便物の配送を担う、およそ3万2000台の軽自動車を使う事業についても、点呼が適切に行われていなかった疑いがあるとして、監査を進めています。この事業について国土交通省は一定の期間、車両の使用を停止させるなどの行政処分を検討する方針です。処分の内容によっては、郵便物の配達などに支障が出るおそれもあることから、日本郵便は、利用者への影響が最小限となるよう対応を検討することにしています。国土交通省と総務省は、日本郵便に対して、コンプライアンスの強化や再発防止の徹底に加え、物流に影響が出ないよう十分な対策をとるよう求めています。 ●総務省 日本郵便に最も重い行政処分「監督上の命令」 総務省は25日、日本郵便が全国の郵便局の配達員に対して法令で定める飲酒の有無などを確認する点呼を適切に行っていなかったとして、会社に対して法律に基づく行政処分「監督上の命令」を出しました。これは、日本郵便に対する処分では最も重いもので、総務省は25日、日本郵便の千田哲也社長に対し、処分を伝える文書を手渡しました。命令では、国土交通省の行政処分でトラックなどの車両が使用できなくなる中でも郵便サービスを維持することや、再発防止策の着実な実施や見直しなどを求めています。文書を受け取った千田社長は「心よりおわび申し上げる。処分を厳粛に受け止め再発防止策に取り組みたい。ユニバーサルサービスを担うものとして、お客様にご迷惑をおかけしないようにしたい」と述べました。 ●日本郵政の株主総会 増田社長が一連の不祥事を陳謝 日本郵政は、郵便局の配達員に対して法令で定める点呼を適切に行っていなかった問題などグループで不祥事が相次ぐ中、株主総会を開きました。この中で増田寛也社長は極めて深刻な事態だとして、一連の不祥事を陳謝しました。日本郵政では、郵便局の配達員に飲酒の有無などを確認する点呼を適切に行っていなかったことや、日本郵便が金融商品の勧誘のため、ゆうちょ銀行の顧客情報を不正にリスト化していたことなど、グループ内での不祥事が相次いで明らかになりました。こうした中、会社は都内で株主総会を開き、冒頭、増田寛也社長は、一連の不祥事について、「極めて深刻な事態であり、この場をお借りして多大なご迷惑と心配をおかけしたことを深くおわび申し上げる」と陳謝しました。株主からは、法令順守の意識が不足しているので、再発防止に向けた組織づくりを徹底してほしいとか、現場の管理職が指導を徹底する体制が不十分だといった意見が相次ぎました。会社側は総会で、不適切な点呼の問題により25日、国土交通省からトラックなどおよそ2500台を使った運送事業許可の取り消しの処分を受ける見通しとなっていることを明らかにしました。処分による事業への影響について会社の担当者は、他社への配送の委託に加え、処分の対象となっていない軽トラックを効率的に運用し、配送業務に支障が出ないよう対応すると説明しました。このあと、増田氏の後任の社長に内定している根岸一行常務ら13人を取締役に選任する議案が可決されました。郵便・物流事業の赤字が続き、処分による業績へのさらなる影響も懸念される中、グループ全体のガバナンスや経営の立て直しが今後の課題となります。 *6-3:https://digital.asahi.com/articles/AST6T2SJFT6TULFA01JM.html?iref=comtop_7_01 (朝日新聞 2025年6月25日) 郵便・ゆうパックに影響は 日本郵便、一部運送を佐川などに委託開始 日本郵便で集配時の点呼がまともにされていなかった問題は、25日に国土交通省の処分を受け、大口顧客の集荷などに使うトラックが使えなくなる事態に発展した。物流や業績への影響は、どこにどう出てくるのか。25日に都内であった日本郵政の株主総会は、株主の質問が点呼問題に集中した。この日で退任する増田寛也社長は国交省の処分について「極めて深刻な事態」だとし、「再発防止策に取り組み、オペレーション確保に万全を期す」と述べた。業績への影響は「精査中だ」とした。それでも株主の怒りは収まらない。ある株主は「(民営化前の)治外法権の意識が残り、法律を守る意識がないのではないか」と批判。会社側が公表した原因分析や再発防止策を疑問視し、「管理職の能力の問題ではないか」「危機管理能力が経営陣も現場もないのでは」との指摘も出た。 ●ゆうパック値上げ「今の時点では…」 日本郵便によると、今回の処分を見据え、約2500台ある1トン以上のトラックなどは24日までに使用を停止した。これらはおもに、大口顧客からの集荷や近距離の集配局間の運送に使われ、月に約12万便が行き来していた。そのうち4割強は自社の軽四輪で運び、6割弱は社外に委託する方針で、切り替えは19日から順次進めてきた。佐川急便や西濃運輸など多くの同業者に協力を仰いでおり、一部では代替の集荷や運送がすでに始まっている。日本郵便は「郵便やゆうパックのサービスは維持する」と強調している。個人が差し出す郵便やゆうパックの多くは軽ワゴンや原付きバイクで運ばれており、直接的な影響はなさそうだ。ただ、点呼を省いたり偽ったりする不正は、約3万2千台を保有する軽四輪での集配にも同様に及んでいる。日本郵便は今後、軽四輪にも一定の処分が出ると身構えており、委託範囲の拡大を迫られる可能性がある。外部委託の拡大や再発防止の対策でコストが膨らむ見込みで、それが郵便・物流事業の収益を押し下げるのは必至。千田哲也社長は17日の会見で「ゆうパックの値上げは今の時点で一切考えていない」と言い切ったが、大規模な不祥事が業績に影響を及ぼすのは時間の問題だ。 <教育について> *7-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250818&ng=DGKKZO90722000X10C25A8CK8000 (日経新聞 2025.8.18) 小中「学力低下」の背景 知性と学びの危機に目を 小中学生の「学力低下」が確認された。要因は未解明だが子どもの生活や保護者の意識の変化とも関係がありそうだ。原因究明と指導改善を急ぎつつ、社会全体で対応を考える必要があろう。文部科学省は全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の中で、3年に1回程度「経年変化分析調査」を行っている(2020年度は新型コロナウイルス禍で中止)。小6・中3の全員が対象の「本体調査」と違い、教科ごとに約300校を抽出して調べ、測定対象にした学力の中長期的な変動をつかめる。その24年度調査の結果が出た。小6の国語と算数、中3の国語・数学・英語のうち数学を除く4教科で、基準年度の16年度(英語は21年度)より平均スコアが下がった。子ども全体の学力低下がこれほど顕著にデータに表れたのは、ほぼ20年ぶりだろう。2000年代前半、経済協力開発機構(OECD)の学習到達度調査(PISA)などで日本の成績や国際順位が落ち「ゆとり教育」の見直し路線が不動になった。その後、学力水準は回復。20年代にはコロナ禍で世界の学校教育は大きな制約を受けたが、日本は現場の努力もあって学力への影響が非常に少ないと見られていた。それが今回、覆った。教育界には少なからぬ衝撃が走った。1日、文部科学省が開いた全国学力テストの専門家会議で、塩見みづ枝総合教育政策局長は「結果を重く受け止め、真摯に向き合って改善に取り組む」と述べた。委員の校長や教育学者からも「勉強時間(の減少)はショック」「どうしてこうなった、と言いたくなる状況だ」など厳しい発言が続いた。基礎学力の揺らぎも見られる。25年度本体調査の小6算数で「10%増のハンドソープは増量前の何倍か」という問いに「1.1倍」と正答できた児童は41.3%だった。スコアの低下以外にも気がかりな傾向が浮かんだ。保護者への調査によると、平日に1時間以上勉強する児童生徒の割合は小6で37.1%、中3で58.9%で、それぞれ前回21年度の調査から7.8ポイント、9.2ポイント下がった。平日に2時間以上テレビゲームをする子どもは小6で37.1%、中3で41.5%。いずれも前回より10ポイント強増えた。中3の53.3%が平日、2時間以上スマートフォンや携帯電話を使う。前回は41.4%だった。家庭の経済力による格差が広がった。自宅にある本の数を社会経済的背景(SES)の代替指標として層分けして見ると、数学など複数教科で低SES層の子どもほどスコアが大きく低下している。保護者はというと「学校生活が楽しければ、良い成績をとることにこだわらない」という姿勢がコロナ期を境に強まった。小6の保護者の59.7%、中3で52.4%が「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えている。それぞれ17年度の調査を8.4ポイント、7.6ポイント上回った。成績にこだわらないという価値観は一概に悪いとはいえない。情操や道徳心など成長過程で大切にすべき資質はたくさんあるし、学校が誰もが楽しく通える包摂的な場であることも重要だ。低下した「学力」自体、非認知能力を含む幅広い学力の一部にすぎない。すると今回の結果は、どうとらえればよいのか。興味深いのは「やはり」と感じた向きもあることだ。専門家会議の座長を務める耳塚寛明・お茶の水女子大名誉教授はその一人。耳塚氏はPISAの成績のOECD平均が12年前後で頭打ちになり下降していることに着目する。この間、スマホ・ゲームを含むデジタル環境の生活への浸透が世界的に進んだ。「成績低下との因果関係は断定できないが、デジタル環境に受け身で接してばかりいると言語を操作する能力が劣化しやすい。日本だけ、その影響を免れるとは考えられない」と耳塚氏は言う。そのうえで「デジタル環境に能動的に触れ、広い意味での学習に活用することが非常に重要になるのではないか」と問題提起する。元小学校長で全国連合小学校長会長を務めた喜名朝博・国士舘大教授も今回の結果は「実感に合う」という。理由は3点。まず、学校現場で徹底して教えることが減った。教えることが多い一方、教員に時間的余裕がない。次に「主体的・対話的で深い学び」といった学び方が重視されすぎ、定着の確認ができていない。最後に「学ぶ意欲の減退、勉強しなくても進学できるという意識の広がり」を挙げる。教員の問題も指摘する。採用倍率の低下で小学校高学年を教えるには学力に不安のある教員が増え、理想的な授業ができる教員は減った。本体調査では「授業がよく分かる」と答える子どもの割合が各教科で下がっている。少子化で大学も高校も難関はごく一部となり、受験プレッシャーの緩和は極限に迫りつつある。なのに学校教育は入試以外の「学ぶ意味や意義を実感させてこなかった」(喜名氏)。識者2人の話は学力低下の背後にある課題の大きさを感じさせる。今回の結果が重い理由はそれだ。スマホ・ゲームへの接し方をはじめ大人のあり方も考えざるをえない。日本は成人の学力も高いがリスキリングは低調だ。子どもの自己調整力の育成と大人の学び直しの活性化は地続きであり、生涯学び続ける社会の実現に本気で取り組む時ではないか。教育制度との関連では、下の学年の内容を学び直す機会をよりしっかりと保障する必要があろう。今の学習指導要領では、学習の積み上げが特に大事な中学校数学でも「学び直しの機会の設定に配慮する」と書かれている程度だ。学力低下の性急な犯人捜しは避けたい。政策の失敗はあっても問題の一部だ。背景にある知性と学びの危機にこそ目を向ける必要がある。耳塚氏は「危機の要因は多岐にわたる。腰を据えて取り組むべきだ」と訴える。人工知能(AI)を含むデジタル技術の隆盛の中で人の知性の水準と質をいかに保つか。明確な答えはまだ、どこにもない。それへの挑戦の一環と捉える姿勢を持ちたい。 *7-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250705&ng=DGKKZO89830650U5A700C2CM0000 (日経新聞 2025.7.5) 成績「主体性」の比重小さく 小中高で評価見直し、文科省案、客観的な判断困難指摘で 文部科学省は4日、学習指導要領の改訂を議論する中央教育審議会の特別部会で、小中高校の成績の基となる学習評価を見直す案を示した。「主体性」の評価の比重を小さくする。内申点にも影響するが、客観的な判断が難しいとの指摘があった。2030年度以降に実施する見通し。「主体性の表れ方は子どもによって違うのではないか。先生はきちんと見てくれているのかなと思っていた」。東京都目黒区の小学校に娘を通わせる女性(39)は話す。主体的な態度は20年度以降、小中高校で順次、評価の観点に加えられた。教科ごとに、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点についてA~Cで評価。この観点別評価に基づき、各教科の「評定」を小学校は3段階、中学校は5段階でつけている。評定から「内申点」が算出され、高校入試や大学入試などで活用される。主体的な態度を評価の観点に加えた背景には、社会が激しく変化するなかで、自ら課題を見つけ、学んだ内容を生かして解決を目指す人材を育成したいとの狙いがあった。こども家庭庁の23年度調査によると、「うまくいくかわからないことに取り組める」と答えた日本の若者の割合は米国やフランス、ドイツなどと比べて半分以下だ。一方、導入当初から学校現場では「何を根拠に評価したらよいのか分からない」という声が上がっていた。「知識・技能」はペーパーテストの点数、「思考・判断・表現」は作文や発表などに基づいて判断しやすいが、主体性は定量的にはかることが難しい。入試に関係することも踏まえて、納得性を高めようと挙手やノート提出の回数などを基に評定をつける例も多いが、「勤勉さの評価にとどまっている」などとする批判が出ていた。不登校の子どもについては、実際の学習態度を見る機会が少なく、主体性の評価がより難しいという課題もあった。文科省が示した見直し案によると、成績の基となる評価観点を「知識・技能」「思考・判断・表現」の2つに再編する。そのうえで、主体性は総合所見欄などに記述したり、特に強い主体性をみせた児童生徒に「○」をつけたりする。評定をつける際に「○」の有無を勘案するかは、今後検討されるものの、内申点への主体性の影響は現状より減ることになるという。文科省は「過度な評価材料集めを抑制し、段階別に評価することが難しいという特性を踏まえた評価方法にしたい」と説明する。通知表には児童生徒が自分の学習状況を知り、取り組み方を改善したり意欲を向上させたりする狙いがある。評価に納得感がなければ、こうした効果を期待しにくくなる。早稲田大学の田中博之教授(教育工学)は「教員にとって『主体的に学習に取り組む態度』の評価は難しく、お手上げ状態だった。評価のあり方を改善することは良いことだ」と話す。そのうえで「主体性の評価が高校入試などで活用される内申点に関わるため、生徒は過度に品行方正な振る舞いを求められ、管理教育になっている」と指摘。「通知表の総合所見欄などで主体性が肯定的に評価されることは、子どもの長所を伸ばし、意欲向上につながるだろう」と評価した。 *7-2-1:https://digital.asahi.com/articles/AST8R3W91T8RUTNB00KM.html (朝日新聞 2025年8月24日) 県教委と保護者、県民が意見交換 埼玉県立高校共学化めぐり 埼玉県立の男女別学高校の共学化について、県教育委員会と中高生の保護者や県民との意見交換会が23日、さいたま市浦和区の県県民健康センターで開かれ、参加者からは賛否両論の意見が噴出した。午前に保護者の部、午後に県民の部があり、県教委の事務局を担当する依田英樹・高校改革統括監が「主体的に共学化を推進する」と決定した県教委の考え方を説明した。保護者の部には、別学高校に子どもが通う父母を中心に18人が参加した。共学化に反対する父母からは「女子の目がないので力をフルに発揮できる。人間力が育つ」「共学の中学校で性被害を受けた人もいる」「男女の特性に合わせた教育が必要」といった意見が出た。「男女共同参画社会と共学化の相関関係があるのか」などの疑問も呈され、根拠やデータを示すように求めた父親もいた。一方、共学化に賛成する父母からは「男子校の文化祭の在り方に違和感をもった」「全国的に知名度のある浦和高校に女子が行けないというガラスの天井をなくしてもらいたい」といった意見があり、「共学化しても結果的に男子校や女子校になることがある。共学化してもいいのでは」という提案もあった。「異性が苦手な人には別学が必要」という考え方から、「トップ校だけでなく、幅広い学力の層に別学校が必要」という声も複数あった。県民の部には、別学校の卒業生や県立高校の教員経験者など17人が参加した。別学校の卒業生からは「埼玉には名門校のピラミッド構造がある。女子が男子校に入学したら男子の足を引っ張る」「女性しかいない中で、女性のリーダーシップが育つ」などの反対意見が目立つ中、男子校を卒業した男性から「女子が入ってきても全く問題ない。県立高校は変化し続けなければいけない」という賛成意見もあった。依田統括監は「県教委は、共学化で男女共同参画を推進していくという考え方ではない」としたうえで、「男女で教育活動の差を設けることは考えていない。一人ひとりの希望と能力に応じた学校の選択肢を用意したい」とし、「少子化で学校を再編する際には、別学校の共学化も検討の対象になる」などと説明した。 *7-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250705&ng=DGKKZO89818130U5A700C2TCR000 (日経新聞 2025.7.5) リーダー育む女子大学に 国際基督教大学教養学部教授 西村幹子氏(2005年にコロンビア大博士(教育学)、専門は教育社会学。神戸大准教授などを経て18年から現職) 日本の女子大学は存亡の機にある。2000~25年に私立の女子大は25校が共学化され、2校は廃止、さらに2校が募集を停止している。マンチェスター大のキャロライン・モーザー名誉教授は、女子大について「実践的ジェンダー・ニーズと戦略的ジェンダー・ニーズがある」と語る。実践的ジェンダー・ニーズは、ジェンダー構造の不平等が前提にある。例えば家庭での役割を支援するために家庭科を教えることなどだ。一方、戦略的ジェンダー・ニーズはジェンダー平等を促すことで満たされ、女性のリーダーシップと自己変革を重視する。アジアでは多くの国に強いジェンダー規範が存在するため、女子大が依然として盛んだ。その中でも戦略的ジェンダー・ニーズに対応している女子大も存在する。バングラデシュのチッタゴンにあるアジア女子大学(AUW)はその好例だ。リーダーシップ開発と変革の力を重視し、アジアの貧困層などに全額奨学金で高等教育を受ける機会を提供している。日本の女子大は20世紀初め、国策の下で「良妻賢母」という実践的ジェンダー・ニーズを満たすために設立された。この使命は多くの女性が共学の大学に進学するようになった90年代以降、戦略的ジェンダー・ニーズに移行した。多くの大学は家政など伝統的な学科を廃止する代わりに、グローバルコミュニケーションなどキャリア志向のプログラムを新設した。しかし女子大が女性のリーダーシップやジェンダー平等に影響を与えたとする研究は乏しい。日本は国際的なジェンダー平等の指標で一貫して低い順位に甘んじている。女性の経済・政治参加が進んでいないためだ。日本の女性が高等教育には比較的容易にアクセスしているにもかかわらず、政治や経済への参加で後れをとっているのはなぜなのか。この難問に答えるため、私は女子大の経営構造を分析し、戦略的ジェンダー・ニーズへの取り組み具合を調べた。東京にある20の私立女子大について、意思決定プロセスにおける女性や教職員(男女双方)の割合を比較した。大学の理事会における女性の参加率は9%から71%まで幅がある。女性理事の割合が50%を超えるのは津田塾、白百合、聖心女子大の3校だけだった。津田塾や日本女子大は理事会の半数を現職の教職員が占めているが、他の大学では3分の1未満だった。では日本の女子大の理事会を誰が支配しているのか。多くの私立女子大では、国公立や私立の一流大学の男性教授がキャリアの終盤に移籍して教授や理事のポストを占めるのが一般的だ。同様に日本企業の取締役や別の大学で運営経験を持つ男性が、退職後に女子大の理事に就任するケースも多い。つまり日本の私立女子大は女性や現職の教職員が意思決定に権限を持たないという特徴がある。多くの私立女子大の理事会は単にエリート男性の第二のキャリアの目的地になっているようにみえる。日本の女性はキャリアにおいて引き続き苦闘しており、男性に比べて家事労働に多くの時間を費やしている。女子大は規模が比較的小さく、学生が教職員と交流する機会が多いため、硬直的なジェンダーギャップの克服に一役買うことができる。日本の女性の自由と社会貢献の拡大は、女子大が女性を意思決定プロセスの中核にしない限りは実現が困難だろう。 *7-2-3:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20250705&c=DM1&d=0&nbm=DGKKZO89818130U5A700C2TCR000&ng=DGKKZO89818200U5A700C2TCR000&ue=DTCR000 (日経新聞 2025.7.5) 「平等」への寄与、検証を 今年に入ってからも京都ノートルダム女子大(京都市)が学生募集の停止を、武庫川女子大(兵庫県西宮市)が共学化の方針を発表している。女子大の減少は続きそうだが今も大学全体の1割弱を占めており、その存在意義や役割を改めて考える必要がある。日本は先進国の中でも政治や経済分野で女性リーダーが圧倒的に少ない。お茶の水女子大の室伏きみ子前学長によれば「性別役割意識や『わきまえる』といった無意識の偏見から離れて過ごせる女子大は本来、女性がリーダーシップを学ぶ上で優れた場所」だ。ではどれだけのリーダーを輩出し、ジェンダー平等に寄与したのか。アジアを含めた海外との比較検証と、日本社会に横たわる根深い課題を示すことこそ女子大の役割ではないだろうか。 *7-3: https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250818&ng=DGKKZO90688080V10C25A8KE8000 (日経新聞 2025.8.18) アフリカからの留学生支援を 立命館アジア太平洋大学副学長 岡村善文 14億人の人口を擁し、人口、経済ともにさらに成長するアフリカ市場に、どのように日本が食い込んでいくか。8月20日から横浜市で開催されるアフリカ開発会議(TICAD)の重要なテーマだ。立命館アジア太平洋大学では学生の半数が留学生だ。アジア各国で多くの卒業生が日本とのビジネス交流に力を発揮している。現地に日本語を話し、日本の流儀が分かる人材がいることは、日本企業にとって大いに助けになる。アフリカでも同様に、留学生を通じた人材育成を図ることがアフリカ市場進出の足がかりになるだろう。大学院生レベルでは、2013年のTICADで「ABEイニシアチブ(アフリカビジネス教育)」を始動し、すでに10年以上の実績がある。四年制大学の学部生レベルでも同様に、アフリカ留学生を増やすことが重要である。学部生は院生と比べてはるかに良く日本語を学び、日本の社会文化を吸収するからだ。アフリカの留学生はエリート家庭出身も多く、卒業する学生は本国に戻り、ただちに現地エリートとして活躍するため、親日層の獲得効果が高い。しかし、社会経験や生活力のある院生と違い、学部レベルの留学生には特有の問題がある。学費や渡航費は工面しても、学生の親にとっては、子供の生活、病気や事故の時の突発的な対応などが心配になる。アフリカは遠く、日本国内に同郷人コミュニティーがほとんどないため、学生の不安は一層大きい。この不安を低減するため、アフリカからの学生に対し、生活面で困った時など緊急に必要な支出を融資する「アフリカ留学生支援基金」を設けてはどうか。緊急の資金貸与だけでなく、在京大使館からの支援や、卒業後の就職で便宜が得られるようなメニューもそろえれば、留学生たちが自主的に登録することが期待できよう。日本の大学を卒業した留学生のデータベースになり、日本企業の高度人材採用に活用できる。これまでアフリカの学生の主たる留学先は欧米の大学だった。だが、米トランプ政権の政策や欧州での移民排斥の高まりの中、アフリカの学生は欧米以外に視野を広げている。安全にも定評がある日本はアフリカから留学生を導き入れる良いチャンスを迎えている。
| 経済・雇用::2023.3~ | 01:38 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
PAGE TOP ↑
