左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。
|
2024,03,07, Thursday
   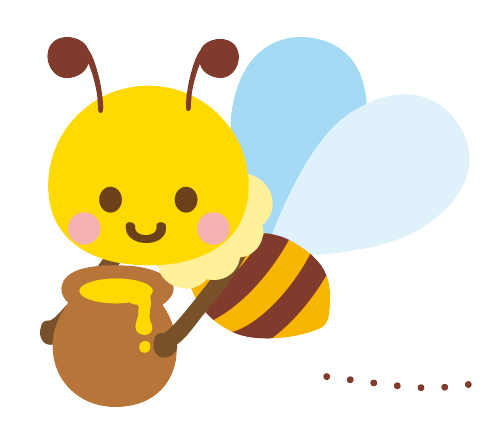 梅林 アーモンドの花 レンゲの花 蜜蜂 (図の説明:この章を書いているうちに、「梅→アーモンド→レンゲ」の花と季節が進みました。蜜蜂を飼っている友人に言わせると、「蜜蜂は、自分で餌を採ってくるし、巣も自分で掃除するので、犬猫より飼うのが簡単で、蜂蜜もくれる」とのことです。また、「蜜蜂の行動範囲は巣から1~2kmなので、花を選んで蜂蜜を採ることも可能」だそうです) (1)地球環境及び食料・エネルギー自給率の理念から見た歳出改革について 1)研究開発・イノベーション力とヒト・モノ・カネの関係 *1-1-1は、イ)「生産性向上のための構造改革が置き去り」として、①「国民経済計算」確報版で示された日本の2022年名目GDP/人はOECD加盟国中21位でG7最低 ②日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」では、2022年の労働生産性/人はOECD加盟国中31位 ③GDP全体でも人口が日本より3割以上少ないドイツに抜かれて4位 ④労働生産性が2022年に31位まで後退した理由は、日本は就業者比率が高く、欧州はユーロの評価以上に生活水準の高い国があるから ⑤労働生産性の順位こそ深刻に受け止めるべき ⑥日本でGDP/人や労働生産性/人の低迷が起きた理由は、財政・金融政策頼みの経済運営で生産性向上のための構造改革が置き去りにされてきたから 等としている。 このうち①③は事実で、1人当たりGDPはOECD加盟国中21位と決して高い方ではなく、G7で見れば離れて最低なので、日本は先進国とは言えない状態だ。また、総GDPも人口が日本より3割以上少ないドイツに抜かれて情けない限りだが、こうなる理由は、規制で既得権益を守ってイノベーションをやりにくくしている政府や“日本文化”の責任が大きいのである。 また、②④⑤の労働生産性はOECD加盟国中31位で、その理由は「就業者比率が高いから」と説明されているが、生産年齢人口の割合が減少すれば就業者比率は高くなるのが当然であるため、日本は、力仕事やルーチンワークの機械化・生産性の高さに報いる給与体系・組織のフラット化などの生産性を上げるシステムへの移行ができていないのが本質的な原因であろう。 このような中、⑥のように、日本政府は、漫然と莫大な予算を使って国債残高を増やしつつ財政・金融政策頼みの経済運営をして経済にカンフル剤を打っただけで、教育・研究開発・実用化に向けた規制改革をしてイノベーションを起こし易くし、生産性を向上させる取り組みが少なかっただけでなく、部分的には後退までさせていたのだ。 また、*1-1-1は、ロ)「良質なヒト、モノ、カネが国外流出の恐れ」として、⑦良質なヒト、モノ、カネが国を見捨てて流出していく ⑧教育水準の高い人や才能のあるスポーツ選手が実力を発揮した場は欧米 ⑨実際に人口減少の中で日本人の海外永住者数は増加中 ⑩イノベーション不足の国はモノへの投資も海外へ向かう ⑪カネに関しても、日本は0金利を維持して資金流出と円安を招いた ⑪良質のヒト・モノ・カネの流出はさらなる貧困化を招き、一層政府への依存度を高める ⑫既得権益や規制の壁も大きい としている。 このように、生産性の高さに報いない給与体系で、規制により既得権益を守ってイノベーションをやりにくくしていれば、日本で研究しても報われないため、⑦⑧⑨⑩⑪⑫のように、良質なヒト・モノ・カネが国を見捨てて流出し、日本人の海外永住者数が増加している。 実際、⑧のように、教育水準の高い人や才能あるスポーツ選手が実力を発揮した場所は、人の能力を小さく規定せずに能力を存分に発揮させる欧米であり、⑪のように、良質のヒト・モノ・カネが流出する結果、政府への依存度の高い人ばかりが残って国内はさらに貧しくなる。これは、数十~百年単位では、次世代への生物的遺伝も加わるため、大きな違いとなるのだ。 さらに、*1-1-1は、ハ)生活の豊かさまで含めたビジョンが必要 として、⑬生活を豊かにするサービスを市場経済から供給されるサービスに限らず、環境を含む市場外サービスまで拡張し ⑭それらを提供する民間資本・社会インフラ・自然資本・人的資本等の組み合わせを政策目標とし ⑮単なる過去への回帰でない「豊かさ」への戦略を練る必要 等と記載している。 しかし、⑬のように、環境は「市場外サービス」と考えること自体、「昭和的」というより「戦後復興期」の日本の開発途上国時代の発想だと、私は思う。 例えば「生活を豊かにする環境」とは、住居の場合なら、i)都市計画の行き届いた自然が多くて文化的な都市 ii)ゆとりある個人住宅や庭 iii)住宅の断熱性能 iv)水だけでなく湯の出る環境 v)職住接近による可処分時間の確保 など、欧米では市場経済で供給されているが、日本では市場に存在しなかったり、存在しても著しく高価で可処分所得を圧迫するため購入できなかったりするものだ。そのため、同じ名目所得を得ても、欧米の方が生活を豊かにする環境で生活でき、日本は今でも開発途上国の住環境にあるのである。 従って、⑭のうちの自然資本と社会インフラは、国や地方自治体がこれまでに整備しておくべきだったもので、それらが整備されて後に、そこで民間資本や人的資本が活躍できるのだ。そのため、⑮の「単なる過去への回帰でない豊かさ」が必要なのは当然だが、それは公的部門も漠然と前例を踏襲したり、多額の予算をつけたりしていればできるものでは決してないのである。 2)生活の豊かさを増す政策(その1) ← 省エネと再エネの導入 日本は再エネが豊富な国で、エネルギー自給率向上にも役だち、国富の海外流出を抑えられるにもかかわらず、様々な屁理屈をつけて再エネ利用に消極的で、化石燃料や原子力等の従来型集中発電方式を優先してきたため、日本初の技術である再エネの実用化や商用化が遅れた。 そのような中、*1-1-2は、①経産省は2025年度にビル壁や窓等でも発電できるペロブスカイト型太陽光発電を再エネ電力固定価格買取制度(以下“FIT”)に加える ②現行太陽光向け水準を上回る10円/kwh以上に優遇する ③それにより、民間投資を促して日本の再エネ拡大に繋げる ④日本発の技術で開発段階では日本勢に優位性があったが、中国企業は量産を始めて商品化で先行 ⑤ペロブスカイト型普及で都市を発電所にできる 等としている。 このうち①②のように、経産省がペロブスカイト型太陽光発電をFITに加え、現行の太陽光発電以上に優遇して、③のように、民間投資を促して日本の再エネ拡大に繋げるのはよいと思う。しかし、2025年度まで待たなくても2024年度からやればよく、④のように、量産を始めて商品化で先行している中国企業と同じ以下のコストにしたり、断熱窓と組み合わせたり、ビルの壁面らしい色に印刷したりなどして、速やかに高付加価値の製品を作るべきである。 そうすることによって、⑤のペロブスカイト型太陽電池を自然な色や形で都市の色調にマッチさせて普及することができ、電力消費量の多い都市自体を発電所にすることができるのである。 このほか、*1-1-3は、⑥高断熱や複層ガラスによる省エネ性能の高い窓への交換が急増 ⑦背景に冷暖房コスト増で断熱性の高い窓に交換して電気代を抑える需要 ⑧立川市のマンションは、2022年に修繕工事の一環として全136戸の窓ガラスを日本板硝子の省エネガラス「スペーシア」に交換 ⑨スペーシアは2枚のガラス間に0.2ミリメートルの真空層を作って熱の伝導や対流を抑えるもので、厚さは1枚ガラスとほぼ同じで4倍の断熱効果 ⑩夏の電気代が2〜3割減少 ⑪AGCの複層ガラスも4〜5月の販売数が前年比5割増で6月は2倍 ⑫政府は2023年度から省エネ性能の高い窓ガラスや窓枠の交換費用のうち1戸あたり上限200万円まで補助する「先進的窓リノベ事業」を展開しており、政府の補助金も追い風 としている。 化石燃料の輸入を減らし、国富が国外流出するのを防いで、エネルギー自給率を高める方法には省エネもあり、断熱性の高い住まいは国民の生活の豊かさも増す。そのため、⑥⑦は実需であり、⑧⑨⑩⑪のように、中古マンションの大規模修繕工事の際に全戸の窓ガラスを「スペーシア」や「複層ガラス」に交換して電気代を抑えるのは良いし、その際に住民に反対が出ないためには、⑫のように、政府が「先進的窓リノベ事業」として補助するのがよいと思う。 そのため、*1-1-4のように、⑬政府は戸建て・集合住宅のリフォーム工事を対象として住居の窓を断熱性の高いものに改修する工事へ支援制度を延長する方針 ⑭工事にかかる費用の半分(1戸最大200万円)を国が負担 ⑮登録した事業者が施工する場合に適用 ⑯環境省は2024年度予算の概算要求で1170億円を求めた というのは、2023~2024年だけでなく2032年までの10年間くらいは続けて良いと思う。 3)生活の豊かさを増す政策(その2) ← 地球環境と藻場、漁業 イ)大阪湾湾奥部の藻場再生について *1-2-1は、①大阪府が2023年8月にBOIと事業連携協定を締結した ②藻場はCO2を吸収して長期貯留してSDGsに寄与する ③藻場はO₂の供給など水質改善効果も期待でき、魚類など生き物のすみかとなる ④大阪湾全体の湾奥部だけがコンクリート等でできた人工護岸のため「ミッシングリンク」だった ⑤大阪府は「大阪湾MOBAリンク構想」を掲げたが、i)船舶等の港湾利用に影響を及ぼさない藻場創出技術 ii)海面下の海藻の生育状況確認 iii)企業の所有地に面した護岸と海藻を育成したい人の少なさ が課題だった ⑥大阪湾奥部は大都市圏から流入する河川等の影響で汚濁物質が溜まりやすく水質改善も課題 ⑦2021年12月に大阪市が管理する「大阪南港野鳥園」の護岸にある消波ブロックにワカメを育てる30センチ四方のパネルを設置し、2022年4月にはワカメの繁茂を確認していた としている。 上の②③のように、藻場は、光合成によって水中のCO2を吸収してSDGsに寄与し、同時に水中にO₂を供給し、水中の養分を吸収して、水質を改善する。そのため、藻場は、貝類や魚類の餌場・すみか・産卵場所となり、「港は魚の保育園」とも言われている。 しかし、大阪湾の湾奥部は、④⑥のように、大都市圏から流入する河川等の影響で汚濁物質が溜まり易い上、コンクリート等でできた人工護岸のため藻場がなかったため、大阪府は、⑤のように、「大阪湾MOBAリンク構想」を掲げたのだそうだ。 そして、2021年12月には、⑦のように、大阪市管理の「大阪南港野鳥園」護岸にある消波ブロックにワカメを育てる30センチ四方のパネルを設置し、2022年4月にはワカメの繁茂を確認していたが、⑤iii)のように、企業の所有地に面した護岸は近づけないため藻場の再生ができていなかったとのことである。本来は、波消ブロックやコンクリート護岸設置で藻場を喪失させた企業は、(それも公害であるため)企業自身が藻場の復元を行なうことを国は義務化すべきだ。 また、⑤i)の船舶等の港湾利用に影響を及ぼさない藻場創出の技術は、海藻の種類を選べば可能であるし、⑤ii)の海面下の海藻生育状況確認は、①のように、大阪府が2023年8月に事業連携協定を締結したBOIのメンバーであるスタートアップが保有する海洋ドローン等で調べるそうだが、近年はカメラも安価になっているため、24時間、毎日、複数のカメラで撮影して画像を送信し続ければ、海藻の生育状況と魚介類の増加状況が時間の経過とともに記録され、有用なデータになると思われる。 ロ)唐津アカウニの資源回復について *1-2-2は、①藻場の磯焼けでアカウニの資源が大きく減少していた ②唐津ブランド・アカウニ資源を回復するため、唐津市内の漁業者とNPO法人「浜-街交流ネット唐津」が長崎県産アカウニの大型種苗を放流した ③これまで佐賀県産の小型アカウニ種苗を放流していたが、小型種苗は生残率が低かった ④今後、収穫までの生残率を定期的に調べて効果的なアカウニ種苗の放流を検証する ⑤NPO代表理事は「アカウニの資源が減り、危機的状況。資源回復の効果を確認していきたい」と語る としている。 しかし、①~⑤については、藻場が減ってアカウニの餌となる海藻が減り、その結果、アカウニが減少しているのであるため、藻場を回復しなければアカウニの種苗を放流しても生残率が低かったり、売り物にならない痩せたウニになったりする。 従って、アカウニの資源回復のためには、餌の海藻を増やす必要があり、餌の海藻は、i)地球温暖化による海水温上昇 ii)原発の温排水による海水温上昇 でこれまでの海藻が育ちにくくなり、残った海藻をウニが食べ尽くして磯焼けになったのであるため、何らかの方法で藻場を再生してウニの餌を増やすか、ウニの種苗を養殖するかしなければ、良質のアカウニを出荷することはできないのである。 このような中、*1-2-3は、⑥唐津市は、唐津市沖に誘致を検討している洋上風力発電事業の有望区域指定を進めるため、副市長をトップとして経済部・漁業・港湾振興部等の横断的体制を立ち上げた ⑦市長は「事業の早期実現は、地域振興・経済波及効果が大いに期待できる」としている ⑧国は、2021年9月に唐津市沖を「一定の準備段階に進んでいる区域」にした ⑨住民からは観光地の景観や沿岸漁業への懸念の声が出ている としている。 洋上風力発電は原発と違って温排水を排出しないため、洋上風力発電機の存在が磯焼けを起こしたり、漁獲物を減らしたりすることはない。むしろ、洋上風力発電機周辺の設計によっては、風力発電機周辺を藻場にして海藻を収穫したり、ウニを放流したりすることも可能である。 しかし、景観(これも重要な環境である)は、洋上風力発電機の設置場所にもよるが、悪くなる可能性が高い。また、洋上風力発電機は洋上に設置するため、建設や維持管理が陸上風力発電機より複雑で高コストになる。そのため、私は、離島・半島はじめ山林・農地等の陸地に設置した方が、低コストで同じ電力を生み出せるのではないかと考えている。 ハ)養殖について *1-2-4は、①ニッスイはサステナブルな食のために養殖技術開発に力を入れ、養殖事業の拡大を長期ビジョンの成長戦略の1つに位置づけている ②任意の時期に産卵させる技術と優れた特性を持つブリを育種で選別し、1年を通して育成スピードが速く高品質なブリの出荷を可能にした ③国内ではギンザケの養殖にも注力し ④環境負荷を低減する研究もして収益安定化に繋げた ⑤2020年には地下海水を利用したマサバの陸上循環養殖の実証実験を開始し、2023年にはバナメイエビの陸上養殖も事業化した ⑥日本は長年天然の水産物の恩恵を受けてきたが、近年縮小する漁業生産を補う養殖の重要度は高まっている 等と記載している。 農業で品種改良や栽培技術の発達があったように、同じ生物である水産物も品種改良や栽培技術の発達ができる筈で、これが軌道に乗れば第五次産業革命と言える(第一次~第四次産業革命については「https://spaceshipearth.jp/fourth-industrial-revolution/」参照)。そして、上の①~⑥は、その重要な過程を示している。 一方、*1-2-5は、⑦有明海の海況悪化で赤潮の発生が長期化し、ノリ養殖の不作が続いている ⑧環境改善のため赤潮発生原因となる植物プランクトンを捕食するスミノエガキの養殖に、佐賀県有明海漁協新有明支所(白石町)の青年部が取り組んだ ⑨スミノエガキは、河口域の低塩分に強く成長も早いため、漁業者の収益向上も期待できる ⑩その取り組みが全国青年・女性漁業者交流大会で資源管理・資源増殖部門最高賞の農林水産大臣賞に選ばれた ⑪スミノエガキは、国内では有明海にのみ生息し、淡水流入による河口域の低塩分化に強く、単年出荷可能(マガキは2年かかる) ⑫カキをかごに入れて海中につるすと、干満に関係なく常時捕食して身入りが良くなった ⑬海況を改善し食べられて収入になるので『一石三鳥』で、マガキと出荷時期が違うため、需要・価格面でも期待できる と記載している。 ⑦~⑬は、確かに頭を使って考えれば、ピンチもチャンスにできる良い例で、有明海の海苔養殖は既に軌道に乗っていたが、有明海の富栄養化も副産物(ここではスミノエガキ)との同時生産で収入増に繋げることができそうだ。 二)農業について i) 政府は基本法改正・食料供給困難事態対策法案・農地法改正案 *1-2-6は、①政府は地球温暖化・国際紛争・物流途絶等を挙げ、食料供給量が大幅に不足するリスクが増大していると指摘 ②国内の食料供給システム強化の新たな農業政策を閣議決定 ③基本理念は「食料安全保障」 ④日本農業は担い手の減少・高齢化の進展・農地の減少等で足腰が弱い ⑤農業を魅力ある産業として若者や都市在住者らの新規就農を促す必要 ⑥IT活用によるスマート農業進展や農地のさらなる集約 ⑦輸出環境整備等による現場の活性化 ⑧生産基盤の一層の強化が不可欠 ⑨日本のカロリーベースの食料自給率は38%で先進国の中で最低 ⑩相対的経済力の低下で、影響世界市場での食料買い付け力も落ちた ⑪政府は基本法改正に併せて食料供給困難事態対策法案と農地法改正案も決定 ⑫困難事態対策法案は、深刻度に合わせて農業者への生産拡大要請など3段階の対応を規定 ⑬国民が最低限必要とする食料が不足する恐れがある場合は、生産転換や割り当て・配給を実施し、罰則も設けた ⑭極端な例は、花卉類を生産している農家にイモ等のカロリーの高い農作物を栽培するように強制するケースも想定 ⑮稲作は国内需要を上回る供給力を持ちながら、減産で価格を下支えしてきた ⑯食料供給の大幅不足が懸念されるというのなら、コメ生産能力のフル活用も考えたい ⑰国内で消費できない分は輸出に回し、いざというときは国内に戻す構想は検討に値するため、日本米のさらなる海外市場開拓に官民の知恵を絞りたい としている。 このうち①⑨⑩は事実であり、③の「食料安全保障」は重要だが、②の食料供給システム強化に関する農業政策は、⑪⑫⑬⑭のように、政府が強制的に花卉類からイモ等への生産転換や割当・配給実施のような第二次世界大戦中や戦後日本に戻ったような政策であるべきではない。 現在、日本の農業は、④⑤のように、高齢化の進展によって担い手が減少し、それに伴って農地も減少して生産力が落ちており、都市在住者・若者だけでなく、女性・外国人労働者・企業の新規就農を促し、農業を(儲かる)魅力ある産業にしていく必要がある。 しかし、日本に耕作放棄地が増えて農業生産力が落ちた理由には、⑮のような減反政策があった。それは、戦後の食糧難時代は米の増産が国全体の問題で、昭和40年代に肥料・農機の導入が進んで技術革新が起こり、米の生産量が大きく伸びたが、食卓の欧米化に伴って米消費量/日本人が減って余剰米が生じるようになり、当時の食管制度による米価調整では農家からの買取価格よりも市場への売渡価格の方が安くなるという逆ザヤが頻繁に起こるようになった。そのため、日本政府は1970年に新規開田を禁止し、耕作面積の配分を行う生産調整を開始したが、この単純な米の減産に補助金を出した政策が失敗だったのだ。 つまり、余剰している米ばかり作らず、ニーズに応じて輸入割合の高い小麦・大豆・野菜・果物・畜産等を行うのは、⑨のようなカロリーベースだけではなく、栄養バランス良く食料自給率を高める方法であるため、私は、水田でも麦や大豆などを作れば、「3万5000円/10アール」の補助金を出したり、加工用米や家畜の飼料米に補助を出したりするのはまあ良いと思うが、⑮のように、単純な米の減産に補助金を出した減反政策は農家のやる気をなくさせ、耕作放棄地を増やしたと思う。 なお、農業の生産力向上には、⑥のIT化によるスマート農業の進展や大規模農機を使うための農地の集約が必要なことは言うまでもなく、⑧の生産基盤の強化も不可欠だ。 従って、⑯⑰の「(i)食料供給の大幅不足が懸念⇒(ii)コメ生産能力フル活用⇒(iii)国内消費できない分は輸出し、いざという時は国内に戻す」という構想は、(i)の食料供給の大幅不足が懸念されるのは米ではないため、(ii)のコメ生産能力フル活用では栄養バランス良く国民の食料自給率を高めることはできない。また、(iii)の輸出は良いが、日本米を食べたい人にしか売れないことを忘れてはならず、輸出できる農産物は米とは限らないため、ニーズのある製品を作って売るために、⑦の輸出環境整備を考える必要がある。 根本的には、「米はじめ穀物を作って腹を満たしさえすればよい」という発想ではなく、栄養学の知識を持って農水産物の本当のニーズを発掘できる人が、農業政策を行う必要があるのだ。 ii) 賢い農業へ     無肥料で作った蓮根 パクチー パクチー使用のラーメン パクチーサラダ (図の説明:左図は、無肥料で作ったレンコンで、富栄養化したクリークならレンコンを作って毎年収穫すれば、次第に通常の状態に戻るだろう。また、左から2番目はパクチーで、1度植えれば折れた茎からでも根が出て繁茂するたくましいハーブであるため、クリークの縁に植えて定期的に収穫すれば他の植物は生えず料理の使い道も多くて便利だ) 肥料や家畜の餌を輸入して日本で生産したものは、国内の食料自給率に加えるべきではないが、38%といわれる日本のカロリーベースの食料自給率には、それが含まれていることが明らかになった。 そこで、*1-2-9は、①化学肥料の原料価格が高騰 ②化学肥料の主な原料となるリンを含むリン鉱石は、中国・モロッコなどからほぼ全量輸入 ③国と東京都は巨大都市から大量に出る「下水汚泥」からリンを採り出す実験を開始 ④東京都は全国普及を目指して国やJA全農と連携 としている。 上の③④は、これまで邪魔者として捨てて海を富栄養化させていた資源を利用して良質の肥料を作る技術を開発し全国に広げる意図であるため、肥料の国産化にも資して賢い。これによって、①②のように、ほぼ全量を海外依存して交際情勢や円安の影響を受け易く、簡単に高騰していた化学肥料の原料価格が抑えられれば、食料自給率とコストの両面から有用である。 *1-2-7は、⑤佐賀市は清掃工場から出るCO₂を活用し、魚の養殖と野菜の水耕栽培を組み合わせた新しい農業「アクアポニックス」の事業化を目指している ⑥アクアポニックスは魚の養殖と植物の栽培を組み合わせた資源循環型型農業 ⑦魚を養殖した水を水耕栽培で再利用して溶け込んだ窒素やリンを植物が養分として吸収する ⑧水は養殖で再利用するため水槽に戻す ⑨化学肥料をやったり、土を耕したりする必要はない ⑩4月下旬からマスを2千匹規模で養殖し、約40平方メートルの水耕ベッドで葉物野菜を育てる ⑪CO₂を利用することで脱炭素社会への取り組みを強化しつつ野菜の生育促進に役立てる としている。 上の⑥~⑩は、農業と漁業を組み合わせて水を循環させ、化学肥料を不要にする方法で、これならどの地域でもできそうである。また、⑤⑪のように、清掃工場から出るCO₂を活用して脱炭素社会への取り組みを強化しつつ、野菜の生育促進に役立てるのは、これまで捨てていた邪魔者を有用なものとして利用し尽くす点が本当に賢い。 このような中、*1-2-8のように、⑫特定外来生物で水生植物の「ナガエツルノゲイトウ」や「ブラジルチドメグサ」が、爆発的な繁殖力で佐賀市内のクリークや河川で繁茂を続ける ⑬茎の切れ端からでも再生・繁殖し、長期間の乾燥にも耐え、一度除去しても残った部分から再生する ⑭農地に侵入すれば農地を覆い、農作物の収量・」品質・作業効率の低下を招く ⑮樋門や排水ポンプなどの機能に支障が出かねず、市は水面や根から除去し続けている ⑯対策費は2022年度に7154万円と、この5年間で倍増 等と記載している。 上の⑫~⑯は、市の予算を使って人力で除去しようとした点で賢いとは言えない。しかし、それだけ水生植物が繁茂するというのは、佐賀市内のクリークや河川が富栄養化している証拠であるため、(i)富栄養化を利用して有益な植物(例:ハス)を育てる (ii)除去した「ナガエツルノゲイトウ」や「ブラジルチドメグサ」を焼却して肥料に使う (iii)「ナガエツルノゲイトウ」や「ブラジルチドメグサ」を食べる有用生物をクリークに放す 等の人手や予算をできるだけ使わず、富栄養化したクリークや河川を利用する方法を考えた方が良いと思われた。 3)膨大すぎる原発のリスクとコスト イ)フクイチの廃炉・汚染水・処理水について 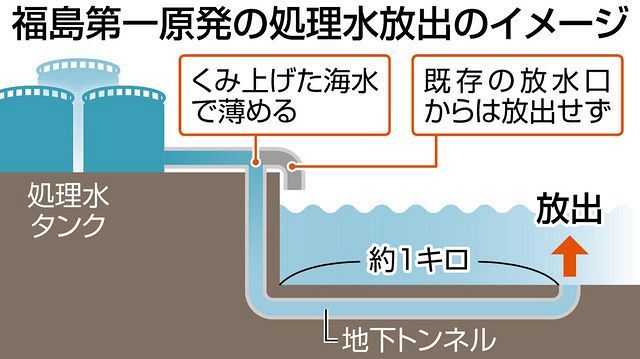 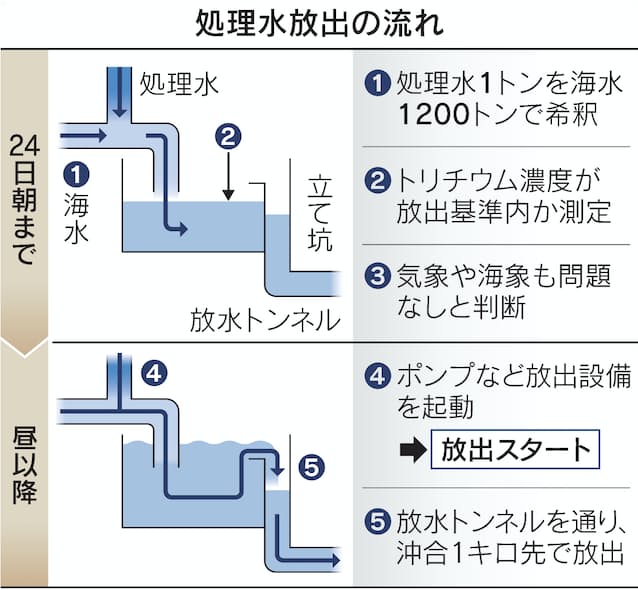  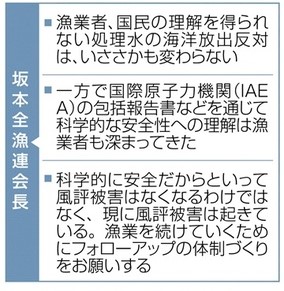 2023.8.21東京新聞 2023.8.24日経新聞 2023.8.21西日本新聞 (図の説明:1番左と左から2番目の図のように、ALPS処理水を汲み上げた海水で薄めてトリチウム濃度を基準値以下にし、海水に放出するのが処理水放出の流れだ。そして、右から2番目の図のように、今後数十年に渡ってこれを続け、予算措置を続けるそうだが、リスクを風評と断じる点や膨大な予算を使っても平気な点が、原発に対する場合の異常性なのである。一方、1番右の図のように、漁業者は、IAEAの包括報告書でALPS処理水の安全性への理解が深まったそうだが、下に記載したとおり、それで科学的安全性が担保されたとは言えないのである) *1-3-1は、①2011年のフクイチ事故で、2号機取水口付近のピットから高濃度汚染水が海へ流出 ②おがくず・新聞紙・吸水性ポリマー等が大量に投入したが止水できず、乳白色の入浴剤で流れる経路を調べるなどの「ローテク」ぶり ③放射能の脅威を前に日本の土木技術やロボット技術は敗北し、この技術レベルでは安全神話なくして地震国での原発推進は難しい ④東電は2024年1月末、2023年度内としていたフクイチのデブリ取り出し開始を三たび延期すると発表 ⑤1~3号機に推計880トンものデブリがあるが、どこにどのような状態で存在するかもわからず ⑥廃炉の「最終形」に関わる議論は進まず、多額の金を投じて「全量取り出す」前提で技術開発 ⑦世界的な核融合フィーバーだが、発電技術は進化したか としている。 また、*1-3-2も、⑧フクイチで“処理水”の海洋放出が始まったが、廃炉作業の終わりが見えない ⑨「処理水」とは汚染水をALPSに通して大半の放射性物質を取り除き、トリチウム濃度を500ベクレル/リットル(国の放出基準の1/40)未満となるように海水で希釈したもの ⑩東電はALPS処理水を分析してトリチウム以外の29の放射性物質濃度が放出基準を下回っているか確認 ⑪さらに海水で希釈してトリチウム濃度を薄めて基準未満かを確認 ⑫この水を蒸留させるなどして測定の邪魔になる不純物を取り除いた後に、放射線を受けると発光する試薬を使って光量から濃度を換算 ⑬東電・国・福島県が周囲の海水をモニタリングし、トリチウム濃度が放水口近くで700ベクレル/リットル、沖合10㎢で30ベクレル/リットルを超えると放出停止 ⑭水産庁が放水口の南北数キロに設置した刺し網で捕獲したヒラメなどのトリチウム濃度を測定し、放出停止する異常値は確認されていない ⑮東電によると処理水放出は30年ほど続く見込みで年間22兆ベクレルを上限に廃炉完了の目標時期である2051年までに終える見込み ⑯廃炉作業の「本丸」である燃料デブリは計約880tあるが事故から13年が経っても1gも取り出せていない 等としている。 このうち、①②③や事故時の説明については、私も意外なほどローテクで知識が乏しいのに驚かされたし、③の安全神話は現在でも形を変えて存在しており、「裏付けのないことでも、信じれば救われる」と考える日本人が多いのにも呆れたが、何故、そうなっているのだろうか? そして、⑤⑯のように、やっと推計約880tあることがわかったというデブリは、どこにどのような状態で存在するのか未だわからず、事故から13年経っても1gも取り出せずに、④のように、東電は2023年度内としていたフクイチのデブリ取り出し開始を三度延期している。 また、燃料デブリを冷やして汚染水となり、⑧⑨⑩⑪のように、ALPSに通して大半の放射性物質を取り除いてトリチウム濃度を500ベクレル/リットル(国の放出基準の1/40)未満となるように海水で希釈した “処理水”の放出は、⑮のように、年間22兆ベクレルを上限に廃炉完了(目標:2051年)まで30年ほど続くとのことだが、事故から13年経ってもデブリ取り出しができない状況で、⑥のように、多額の金を投じて「全量取り出す」前提の廃炉では、膨大な予算の無駄遣いと海の汚染による水産業への打撃がひどくなりすぎるのである。 これに対しては、⑬⑭のように、「東電・国・福島県が周囲の海水をモニタリングして、トリチウム濃度が放水口近くで700ベクレル/リットル、沖合10㎢で30ベクレル/リットルを超えると放出を停止するから大丈夫」「水産庁も放水口の南北数kmに設置した刺し網で捕獲したヒラメ等のトリチウム濃度を測定して異常値は確認されていないから大丈夫」等の主張がされる。 しかし、私は、中国政府の「『基準値を満たすこと』『検出下限値未満であること』と『存在しないこと』は別である」という主張の方が科学的に正しく、希釈した分だけ体積の増えた“処理水”に含まれる核種の総量は変わらないため、「海洋放出によって海洋環境や人体に予期せぬ被害がある」とする方が保守的な安全性評価だと思う。また、原子力の平和利用での協力を進める中心機関であるIAEAは、特別な利害関係があり第三者ではないため、独立性を持ってモニタリングできていない可能性が高いと考えるのが監査の常識である(https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_001548.html、https://www.unic.or.jp/info/un/unsystem/specialized_agencies/iaea/ 参照)。 このような中、廃炉に膨大な無駄遣いをし、水産業に打撃を与え、中国から海洋汚染の賠償金請求までされては、日本国民の暮らしはますます貧しくなるため、廃炉の「最終形」に関わる議論を海洋も含む環境を壊さない形で早急に進めるのが、科学的で現実的である。 なお、⑫の「ALPS処理水を蒸留させるなどして測定の邪魔になる不純物を取り除いた後に、放射線を受けると発光する試薬を使って光量から濃度を換算する」というのは、蒸留した水は核種も含めて何も含まないため、科学的どころか意味がない。 このように、非科学的で核種や放射線に対して無神経な国が、「核融合なら、環境や人の健康を守りながら扱うことができる」と考えるのは甘すぎるため、⑦の世界的な核融合フィーバーに日本が乗るのは、無駄使いが多すぎる上に危険極まりないのである。 ロ)能登半島地震と志賀原発について 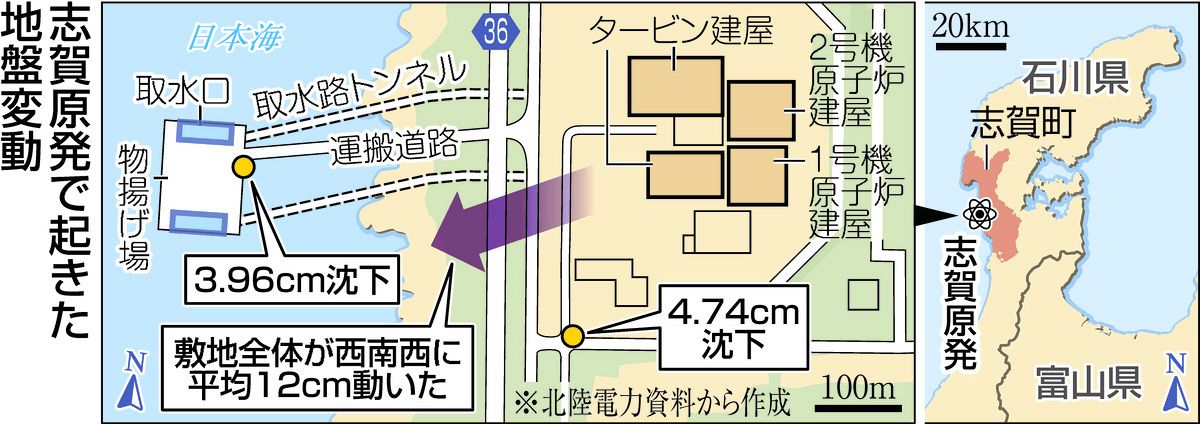 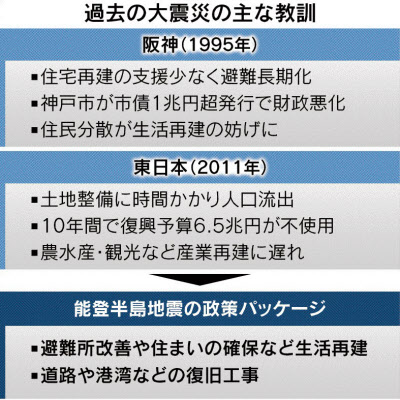 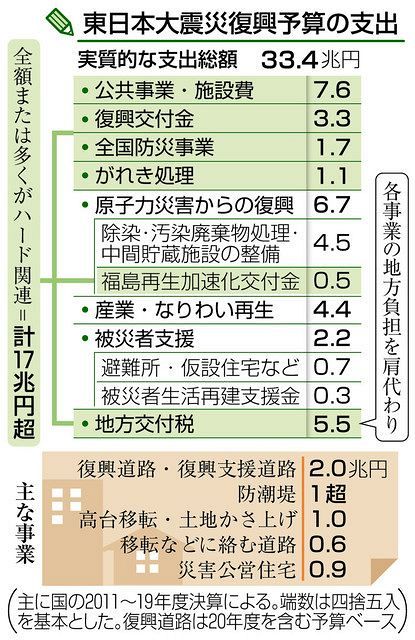 2024.3.25東京新聞 2024.1.25日経新聞 2021.1.21 中日新聞 (図の説明:左図のように、能登半島地震で志賀原発の敷地は12cm動き、3.96~4.74cmの沈下も起こったが、今回は原発事故にはならなかった。しかし、中央の図のように、避難路を含む道路が寸断され、全半壊した住宅も多かった。東日本大震災では、右図のように、原子力災害からの復興に2020年までに既に6~7兆円かかっており、これからも大きな金額がかかる予定だ) *1-3-4は、①北陸電力は、能登半島地震後に志賀原発敷地が地震前と比べて平均4cm沈下と発表 ②測量した11カ所の沈下幅は4.74~3.82cmで隆起した地点はない ③原子炉を冷却する海水の取水口に近い物揚げ場は3.96cm沈下 ④敷地全体が西南西方向に平均12cm移動 ⑤敷地内の地面に段差や割れを約80カ所で確認、担当者は「舗装が変形したためで敷地内の断層が動いた形跡はない」と説明 ⑥能登半島地震で半島北側の沿岸一帯が隆起し、輪島市西部では最大4m隆起 ⑦志賀原発から1km北の岩ノリの漁場が数十cm隆起 ⑧志賀2号機は新規制基準適合性審査中で、北陸電は「地震で原発北側の輪島市付近の断層が動いた場合20cm以下の隆起が起きるが、冷却水の取水に影響はない」と主張 としている。 また、*1-3-5は、⑨志賀原発が立地する半島西側は活断層が存在 ⑩今回動いたエリアの脇にある半島西側の志賀町沖断層で、地震が発生し易くなった ⑪今回の地震で北陸一帯の断層帯に地震を起こしやすくする力がかかり、マグニチュード7クラスの大地震発生リスクが高くなった ⑫次の地震で心配なのが志賀原発だが、北陸電の広報担当者は「原子炉建屋は基準地震動600ガルまで耐えられ、今回の地震による地盤の揺れは600ガルよりも小さく、2号機については1000ガルまで耐えられるので原子力施設の耐震安全性に問題はない」と説明 ⑬現行技術水準では活断層の全容が捉えがたく安心もできない ⑭原発に及ぶ地震の脅威は揺れ以外にもあり、メートル単位で上下・水平方向にズレが生じれば、計算するまでもなく原発はもたない ⑮志賀原発は2012年に直下に断層があると指摘されたが、原子力規制委員会は直下断層の活動性を否定する北陸電の主張を妥当と判断 ⑯原発が止まっていても核燃料がプールで保管されているため、災いの元凶になる核燃料の扱いを早急に議論すべき 等としている。 上の①②③のように、北陸電力の発表では、「能登半島地震後、志賀原発の敷地が地震前と比べて平均4cm(3.82~4.74cm)沈下し、隆起した地点はない」とのことだが、⑥⑦のように、能登半島北側の沿岸一帯は隆起し、志賀原発から1km北の岩ノリの漁場で数十cm、輪島市西部では最大4mの隆起が確認されている。 また、④⑤のように、北陸電力の敷地全体が西南西方向に平均12cm移動し、敷地内の地面に段差や割れを約80カ所で確認されているが、北陸電力の担当者は、「舗装が変形したためで敷地内の断層が動いた形跡はない」と説明しており、影響に関する過小評価が目立つのである。そして、このような小さな安全神話の積み重ねが大きな安全神話となって、⑧のように、「新規制基準に適合」と判断されるのが危ないのだ。 さらに、北陸電力の広報担当者は、⑫のように、「原子炉建屋は基準地震動600ガルまで耐えられ、今回の地震による地盤の揺れは600ガルよりも小さく、2号機については1000ガルまで耐えられるため、原子力施設の耐震安全性に問題はない」と説明し、⑮のように、「直下に断層がある」と指摘されても直下の断層の活動性を否定し、原子力規制委員会も北陸電力の主張を妥当と判断しているのだ。 しかし、⑨⑩⑪のように、志賀原発が立地する能登半島西側に活断層が存在し、今回動いたエリアの脇にある志賀町沖断層で地震が発生し易くなっており、今回の地震で北陸一帯の断層帯に地震を起こしやすくする力がかかってマグニチュード7クラスの大地震発生リスクが高くなっている上に、⑬のように、現行技術水準では活断層の全容が捉えがたいため、活断層に関しても北陸電力は過小評価になっており、これでは、科学的とも安全側に保守的とも言えないのである。 そのため、当然、⑭のように、原発直下でメートル単位の上下・水平方向にズレが生じれば、計算するまでもなく原発はもたず、数十cm単位のズレでも、⑯の核燃料プールが傾いたり、ひびが入ったりして水がこぼれ、保管されている大量の使用済核燃料が爆発する等の災いが起きるため、早急な議論が必要であることは間違いないのだ。 ハ)政策決定手法の転換へ *1-3-3は、①未だ被災者に大きな影響を与え続けているフクイチ事故から13年 ②この間に世界のエネルギー状況は大きく動いた ③化石燃料依存リスクが鮮明になった ④発電コストや建設費の増大で原子力発電は停滞 ④価格低下した太陽光・風力発電は急拡大 ⑤目指すべきは高コスト・高リスクの大規模集中型電源から低コストの再エネを主とする分散型システム ⑥自公政権のエネルギー政策はこの流れに逆行 ⑦日本政府や電力会社は、水素やアンモニアを利用して「CO₂を出さない火力」を目指すことに注力しているが、高コストの手法は気候変動対策にならない ⑧日本は限られた資金や人材の多くを原発や不確実な将来の新技術に投じ、日本国内の再エネ市場は他国に比べて大きく見劣り ⑨今になって大規模な洋上風力発電の開発を進めようにも風車は輸入 ⑩経産省が指名した委員による委員会で、役所のシナリオに沿って政策を決める非民主的な手法を見直して、科学とデータに基づき、多くの市民や専門家の意見を聞いて民主的政策議論を進める「政策決定手法の大転換」も重要 としている。 この記事には、必要な論点がすべて書かれていると、私は思う。例えば、①については、原発事故さえなければ既に回復できていた筈の農林漁業地域に未だに帰還困難区域を作らざるを得ず、超長期避難者も多い。また、②③④⑤は、私が1995年前後に初めて再エネ推進を提言した時から言っていたことだが、それを世界はやっと現実として認識したのだ。 にもかかわらず、⑥のように、自公政権のエネルギー政策は世界の流れに逆行し、⑦のように、日本政府や電力会社は水素やアンモニアを利用して「CO₂を出さない火力」を目指しているが、この方法は化石燃料より高コストになることが避けられない。従って、⑧⑨のように、使えない技術の開発に限られた資金や人材を投入して再エネ技術を疎かにしたのは、日本の経済成長を低め、円安を促進する効果しかなかった日本政府の誤った政策判断なのである。 なお、このような誤った政策が進められた背景には、⑩のように、経産省がやりたいことを先に決め、経産省が指名した委員からなる委員会で、経産省のシナリオに沿って政策を決めてきたことがある。その中で、民主的に選ばれた筈の政治家は、自分の頭では考えられなかったためか、経産省の言いなりになった方が身の安全を守れるためか、ともかく経産省の言いなりになったのだ。そのため、このような手法を見直して、多くの市民や専門家の意見を集め、科学とデータに基づいて政策を決定するという当たり前の手法への大転換が必要なわけである。 二)日本列島の成り立ち・断層・玄海原発   2023.7.23現代ビジネス BS朝日 (図の説明:左図は、ユーラシア大陸の一部だった日本列島が、太平洋プレートの沈み込みに伴って大陸から引き剥がされ、島を形作っていく様子だ。このように、大陸が切り離されて間に海ができる様子は、現在では、右図のアフリカ大陸の大地溝帯に見ることができる。つまり、日本海や瀬戸内海は、地溝帯に海水が流れ込みながら、次第に広がったものだろう) 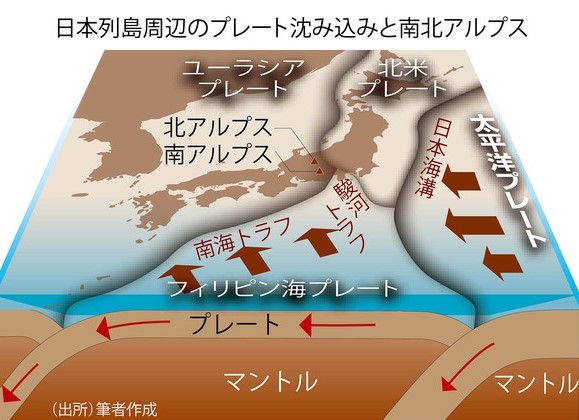 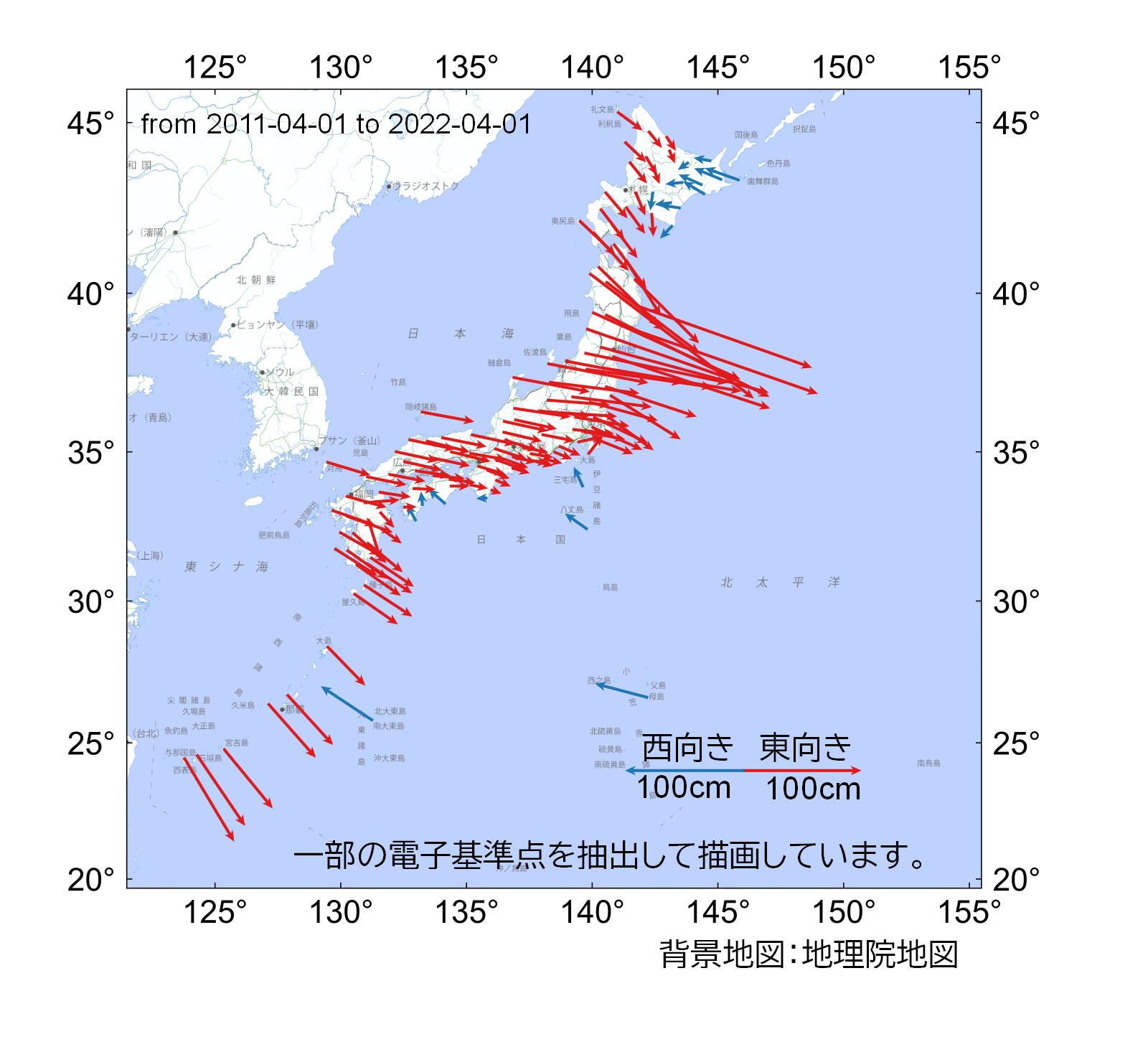 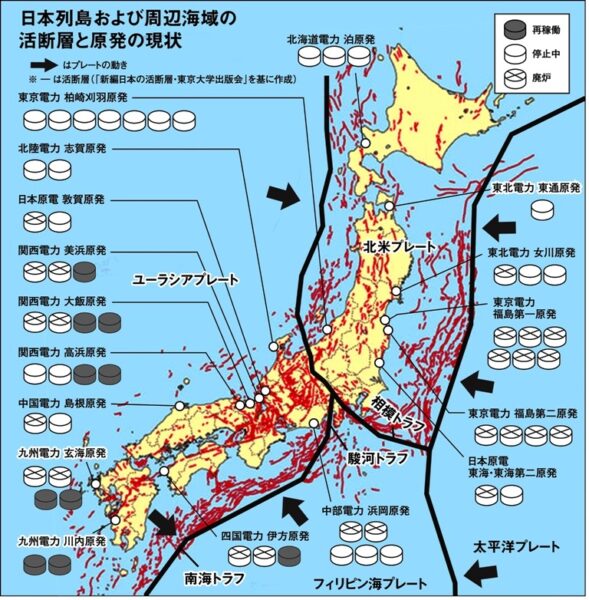  2021.9.6Economist 国土地理院 2024.1.15長州新聞 2024.3.30佐賀新聞 (図の説明:1番左の図は、太平洋プレートがユーラシアプレートに沈み込み、フィリピン海プレートや北米プレートとせめぎ合いながら、日本列島に力をかけている様子だ。この力によって、日本列島の各地点は、左から2番目の図のように、2011~2022年に矢印の方向に移動し、矢印の長さが移動距離・矢印の方向が移動方向を示している。このように、測定地点により移動距離や移動方向が違うため、歪みが蓄積して耐えられなくなった時に地震が起こって地形を変化させる。また、右から2番目の図は、現在わかっているとされる日本列島とその周辺海域の活断層及び原発の位置だが、「海底の活断層はわかっていない」として殆ど表示されていない。なお、1番右の図は、佐賀県と周辺の活断層を示したもので、海底の断層は表示されていないが、名護屋浦・串浦・外津浦・仮屋湾・伊万里湾は、地形から見て断層そのものではないかと思う) *1-3-6は、①九電は3月8日に原子力規制庁との会合で、玄海原発3、4号機の基準津波を修正する方針 ②政府の地震本部が2022年に公表した日本海南西部の海域活断層長期評価を踏まえて検討した結果、想定される津波が既存値を上回ることが分かったから ③日本海南西部海域活断層長期評価では対馬南西沖断層群と第1五島堆断層帯が連動したケースで想定される津波の高さ6.37m、低さマイナス2.65mで、現行基準津波(高さ3.93m、低さマイナス2.6m)を超えるが、基準地震動への影響はない ④玄海原発は高さ約11m、取水位置の低さ(マイナス13.5m)で想定される津波に対して余裕があり、追加工事はない としている。 上の①~④は、津波に関して余裕があってよかったとは思うが、地震については不明だ。 *1-3-7の佐賀県内首長原発アンケートでは、i)玄海原発の運転継続について、玄海原発立地町の脇山玄海町長だけが「賛成」・15市町長が「条件付き賛成」・反対0 ii)原発の今後に在り方については、16市町長が「将来的に廃止」 iii)原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場を受け入れる市町長は0 とのことである。 運転継続について「どちらともいえない」とした深浦伊万里市長は、「事故が発生すれば取り返しがつかないことになるため基本的に反対だが、電力は企業活動や市民生活を支える基礎的なインフラで安定的な供給は不可欠であり、原発を止められない現実がある」とされている。しかし、太陽光発電による電力は既に余剰が出て捨てており、大規模集中型発電より分散型発電の方が大規模停電のリスクも小さいため、電力の安定供給は既に原発稼働の口実にはならなくなっている。それより、原発事故時は、どこにどれだけの期間、避難しなければならないのか、それは可能なのかを検討すべきであろう。 また、「条件付き賛成」を選んだ首長は、条件として「電力事業者・国の責任で安全性を追求し、可能な限り情報公開に努める(村上嬉野市長)」、「使用済核燃料の処理方法について国の責任で対策を講じる(江里口小城市長)」などを挙げられたそうだが、原発には大きなリスクがあり、100%の安全を保証した人は1人もいないし、使用済核燃料の処理は1mmも進んでいないことを思い出すべきである。 さらに、原発の今後で「将来的に廃止」を選択した首長は、「カーボンニュートラルの実現に向けて取り組む(向門鳥栖市長)」「再エネ導入を進めて原子力への依存度を下げていく(松尾有田町長)」「能登半島地震を踏まえ、南海トラフ地震を含めた対策を一から見直すことも重要課題で、代替エネルギーの研究も加速させるべき(岡みやき町長」」などの見解を示されたそうだが、再エネは遠い未来に実現可能な技術ではなく、既に実用化されている原発よりずっと安価な技術であり、街作りと一緒に行なえばモダンで効果的な街ができるのである。 能登半島地震では北電志賀原発周辺で道路の寸断・家屋倒壊等が相次ぎ、避難と屋内退避の実効性が問われたため、*1-3-8では、佐賀県内の首長に原発重大事故時の避難ルートについて質問し、iv)7市町長が現行の避難計画を「見直す必要がある」と回答、他の12首長は「(規制委の)今後の議論を注視したい(坂井英隆佐賀市長)」という意見が多かった v)松尾鹿島市長は「避難が現計画で対応できるかなど再検討の必要がある」とされた とのことである。 日本の“避難”は、我慢しても1週間しかいられないような体育館や公民館等の劣悪な環境であるため、原発事故時の長期間の避難には全く向かない。そのため、「原発事故に遭いたくなければ、原発立地地域やその周辺には住まない方が良い」という悪循環の選択になりそうだ。 (2)人口構成と高齢化社会対応から見た歳出改革→高齢者への給付減・負担増ではない 1)公的年金目減りの原因であるマクロ経済スライドについて 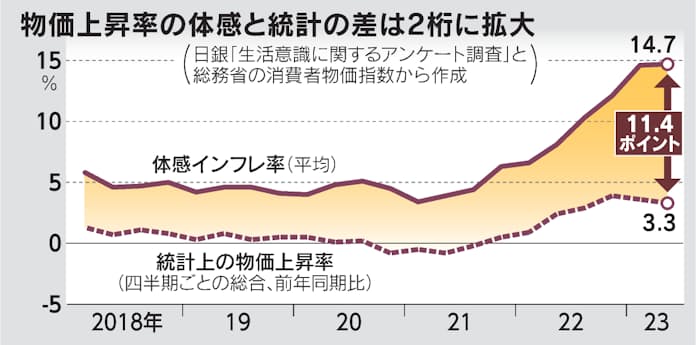 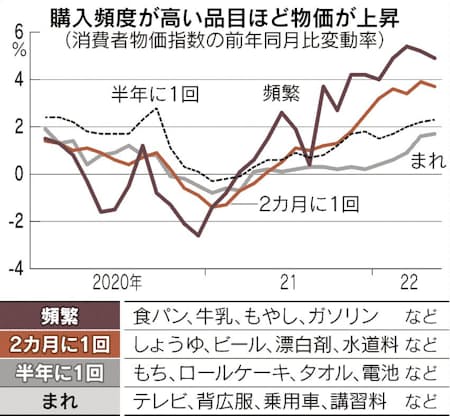 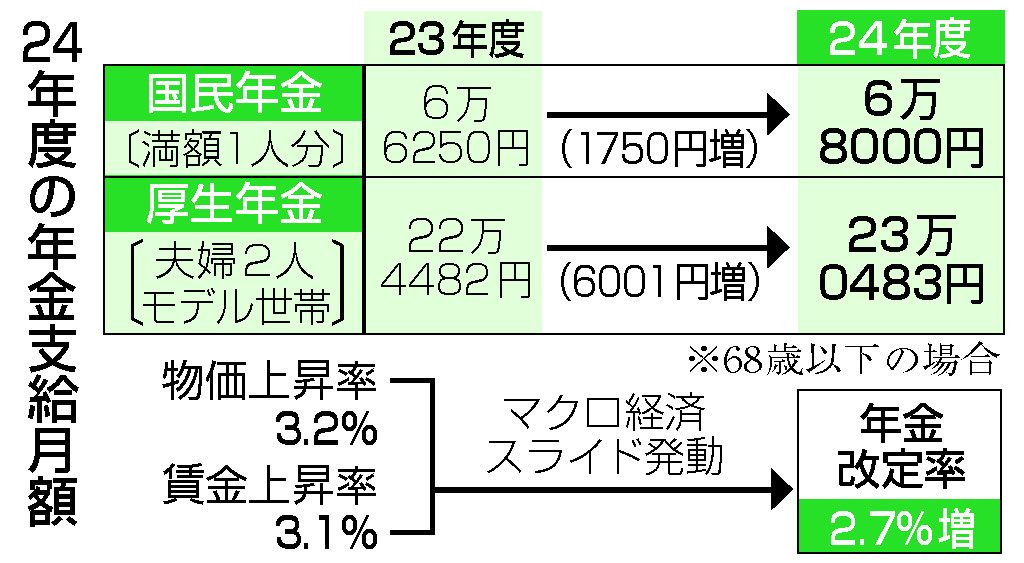 2023.9.30日経新聞 2022.6.25日経新聞 2024.1.19時事わ (図の説明:左図のように、物価上昇率の体感と統計には11.4%の差があるが、これは、中央の図のように、食料品などの単価は安いが頻繁に買わざるを得ない必需品の物価上昇が激しいからである。しかし、「マクロ経済スライド」が適用され、右図のように、年金改定率が2.7%に抑えられたため、所得が低いので食料品等の購入割合が高くなっている年金受給者の体感物価との差は12%以上になるのだ) *2-1-1は、①物価と賃金の上昇で2024年度の公的年金額は前年度比で2.7%増だが、0.4%分目減り ②年金財政の安定のための「マクロ経済スライド(直近1年間の物価変動率と過去3年度分の実質賃金変動率を元に改定し、物価と賃金の伸びよりも年金支給額を抑える)」で物価と賃金の伸びに届かず ③マクロ経済スライドの影響で、国民年金は実質年3600円、厚生年金は同1万1500円ほど目減り ④厚労省の審議会では財政に余裕のある厚生年金が基礎年金に資金支援して給付水準抑制を前倒しで終了する案が出た ⑤就労を促進して高齢者の手取り収入を増やす方向の改正も議論 ⑥一定の所得のある高齢者の年金支給を減額する在職老齢年金制度も見直しを求める声が強い 等としている。 また、*2-1-2も、⑦公的年金の2024年度支給額は、マクロ経済スライドで実質価値減少 ⑧名目賃金上昇率3.1%が、前年の物価上昇率3.2%より低く、労働者数の減少と高齢化の影響により「マクロ経済スライド」が2年連続で発動され、0.4%分を差し引いた2.7%のプラス改定 ⑨本来は物価が上がっても買えるものが減らないように給付(支出)を引き上げる必要があるが、保険料(収入)は賃金が上がれば増え下がれば減るため、物価上昇が賃金上昇を上回ると支出が収入を上回って年金財政が悪化するため、物価上昇率と名目賃金上昇率の低い方を改定率計算に使用 ⑩少子高齢化の日本で将来世代の年金を確保するには、さらなる措置が必要で、その影響を織り込んで給付を抑える仕組みが「マクロ経済スライド」としている。 このうち、①②⑦⑧⑨⑩は、「マクロ経済スライド(尤もらしい名称だが、経済学にこの言葉はない)」によって、年金財政が悪化しないように物価上昇率と名目賃金上昇率の低い方と労働者数の減少を年金改定率の計算に使い、年金のプラス改定分は「物価上昇率3.2%>名目賃金上昇率3.1%」より0.4%低い2.7%となるということである。 その結果、③のように、ただでさえ所得代替率の低い国民年金・厚生年金の実質価値は目減りし、さらに所得代替率(年金を受け取り始める時点《65歳》の年金額が、現役世代男性の平均手取り収入額《ボーナス込み》と比較した時の割合)が下がるのである。 しかし、前年の物価上昇率3.2%は、上の左図の2023年9月30日における3.3%に近いが、この時の体感物価指数は14.7%であり、体感と統計との間に11.4%の差がある。その理由は、上の中央の図のように、食品等の頻繁に買うものの物価上昇が大きいからであり、年金生活者が買うのは耐久消費財ではなく食品等のエンゲル係数に直結する品目の割合が高いため、年金生活者の体感物価指数は14.7%以上で、年金プラス改定分より12%以上高い。そして、これが、「マクロ経済スライド」と呼ぶ、反対運動を起こさせずにこっそり年金を引き下げるやり方なのだ。 それでは、「マクロ経済スライド」を導入しなければ年金財政が悪化して年金制度を維持できないのかと言えば、支払われた保険料を積立方式できちんと積立てて運用し、保険料を支払った人にのみ、支払額に応じて年金を支給すればそのようなことはなかった筈だ。しかし、日本政府はそれをせず、団塊の世代が受給する段になって慌てているというお粗末さなのである。 また、「少子高齢化≠労働力の減少」であるにもかかわらず、少子高齢化を年金支給額引き下げの口実にしているが、女性に対する結婚罰・妊娠罰・子育て罰を1970~80年代に廃止しておけば、著しい少子化は起こらなかった筈で、政府の政策は40~50年遅れているのだ。 そして、④のように、厚生年金に入って高い保険料を支払った人の積立金を基礎年金に流用するなどという議論を厚労省の審議会で行なっているそうだが、保険であれば流用は禁物で、足りなければ税金から支出すべきである。 その税金を原資とする財源は、エンゲル係数が高くて食べるものまで節約している高齢者からむしりとるのではなく、*2-1-5のように、経産省が最先端半導体の量産を目指すとしてラピダスに税金から2024年度までに累計9200億円もの支援をするようなことをやめて作るべきである。何故なら、半導体という30年以上も前から必要性が言われてきた産業に、今頃、国が多額の支援を行なわなければならないような企業に将来性はなく、仮に将来のニーズを満たす企業なら、税金ではなく民間銀行の貸し付けや社債・株式の発行で資金調達すれば良いからだ。 従って、労働者数の減少と年金の所得代替率の低さから、⑤のように、高齢者の就労を促進したり、年金保険料の支払期間を延ばしたりするのは良いが、⑥のように、(著しく低く、いつなくなるかわからないけれども)一定の所得があるからといって高齢者の年金支給額を減らすのは、結局は高齢者層の購買力を無くさせ、次の時代に本当に必要とされる製品の開発を妨げることになるのだ。 2)物価上昇と賃上げについて *2-1-3は、①2023年7月の消費者物価指数は変動の大きな生鮮食品を除く総合指数で前年同月比3.1%上昇、エネルギーも除けば4.3%上昇 ②物価の上昇圧力が続き、食品・日用品の値上がりが家計を圧迫して消費を下押し ③16カ月連続で日銀が掲げる2%の物価目標を上回る ④7月にはハンバーガー前年同月比14.0%上昇、プリン27.5%上昇、宿泊料15.1%上昇、携帯電話通信料10.2%上昇 ⑤外食は1.8%増とプラスを維持したが、5月(6.7%増)から伸びを縮めた ⑥サービス消費は新型コロナ禍からの正常化で回復期待が高かった割に動きが鈍い ⑦値上げが目立つ品目ほど消費が減少し、総務省の家計調査で2人以上世帯の6月の消費支出は実質前年同月比4.2%減で経済成長に水 ⑧2023年4~6月期実質GDPは季節調整済前期比年率6.0%増と高い成長率だが、牽引役は復調した輸出等の外需で、個人消費は物価高で前期比0.5%減 ⑨2023年の賃上率は30年ぶり高水準だったものの物価上昇に追いつかず、2024年以降に賃上げが息切れすれば家計の購買力低下を通じて再びデフレ圧力 ⑩実際、コロナ禍前の2019年10~12月期と足元を比較すると雇用者報酬は実質3.5%減と物価上昇に賃金が追いつかず消費は伸びていない ⑪日米欧では米国だけが賃金と消費を伸ばしている 等としている。 上の①については、変動が大きいからといって生鮮食品を除いたり、エネルギーを除いたりすれば、それらの購入割合が高い世帯(低所得でエンゲル係数が高く、政府が最も注視しなければならない世帯)の体感消費者物価指数が、統計とはかけ離れた数値になる。 また、②⑦のように、総務省の家計調査で2人以上の世帯の2023年6月の消費支出が実質前年同月比4.2%減だったのは、物価が4.3%上昇し、賃金・年金を含む国民全体の所得が増えなかったことを考慮すれば当然の結果である。 私も、④⑤⑥のように、著しく物価上昇した商品やサービスは、どうしても仕方のない場合を除いて購入しないよう工夫したが、そもそも前年度はコロナ禍で経済を止めていたため、前年同月と比べれば少しは伸びる状態だったのである。 にもかかわらず、日銀は、③のように、2%の物価上昇目標を掲げて国民の資産と政府や企業の債務を目減りさせている。そして、これによって、政府や企業の実質借入金額を物価上昇分だけ目減りさせ、それと同時に金利も「名目金利 - 物価上昇」であるためマイナスにしている。つまり、実質預金は物価上昇分だけ目減りすると同時に、実質金利もまたマイナスになっており、これは、通貨の安定を通して国民の財産を護るべき中央銀行として、おかしな行動なのである。 しかし、これらの政策の結果、⑧のように、2023年4~6月期の実質GDPは季節調整済で前期比年率6.0%増と高い成長率になったが、その牽引役は復調した輸出等の外需で、物価高によって実質で貧しくなった国民の個人消費は前期比でも0.5%減となっているのだ。 「物価を上げれば、それ以上の賃上げができるのか?」と言えば、物価上昇分をすべて賃上げに充てても、生産性向上がなければ最大で物価上昇分までの賃上げしかできない。そのため、⑨⑩のように、コロナ禍前の2019年10~12月期と足元を比較すれば、雇用者報酬は実質3.5%減と賃金上昇は物価上昇に全く追いつかず、2023年の賃上率は30年ぶりの高水準でも物価上昇に追いつかず、2024年以降に賃上げが息切れすれば家計の購買力低下を通じて再びデフレ圧力となるのだ。そして、これも、こっそり賃金を引き下げる政策の一環なのである。 なお、⑪によれば、「日米欧では米国だけが賃金と消費を伸ばしている」そうだが、米国は生産性の高い産業に労働移動し易いシステムで、外国人や移民も加わって新技術を作ったり、新技術によるイノベーションを起こしたりするのが早い。これは、政府主導で、外国を模倣しながら、30~50年遅れのイノベーションもどきを起こそうとしている日本とは、気質と土壌が全く違うと言わざるを得ないのだ。 3)医療・介護について 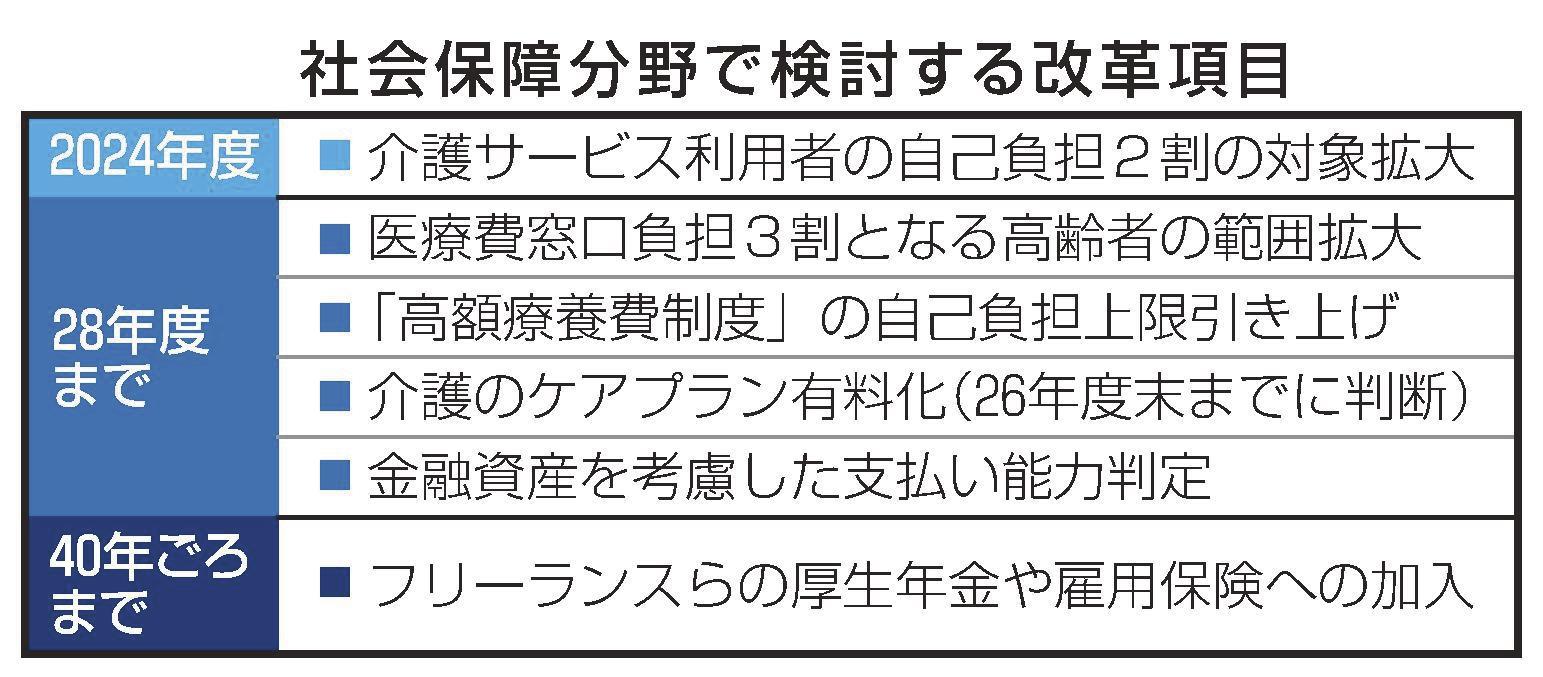 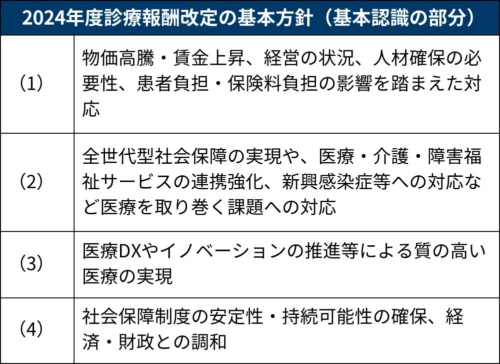 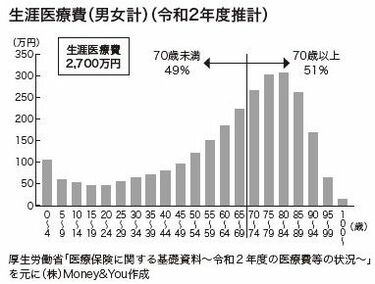 2023.12.6山陰中央新報 2023.12.26日経Xテック 2023.6.9東洋経済 (図の説明:左図は、政府が社会保障分野で検討する“改革”項目だが、「介護のケアプラン作成の有料化」は見積もりを有料化するのと同じく社会常識からかけ離れており、「金融資産を考慮した支払能力判定」が行なわれれば金融資産は日本で所有すべきでなくなる。また、中央の図は、2024年度の診療報酬改定の基本方針だが、時代のニーズが変わっているのだから、持続可能性は厚労省管轄の予算内だけで考えるべきではない。さらに、右図は、令和2年度に支出される医療費の推計で、70歳以上の人が医療費の51%《半分以上》を使い、特に75~85歳の医療費が高くなっている。この図は、世代毎の医療費支出と人口を掛け合わせて産出したものだが、個人についても、75歳以上の退職後高齢者になってから生涯医療・介護費の半分以上を支出するのが普通であるため、在職中に入る医療保険は大幅な黒字の筈である) 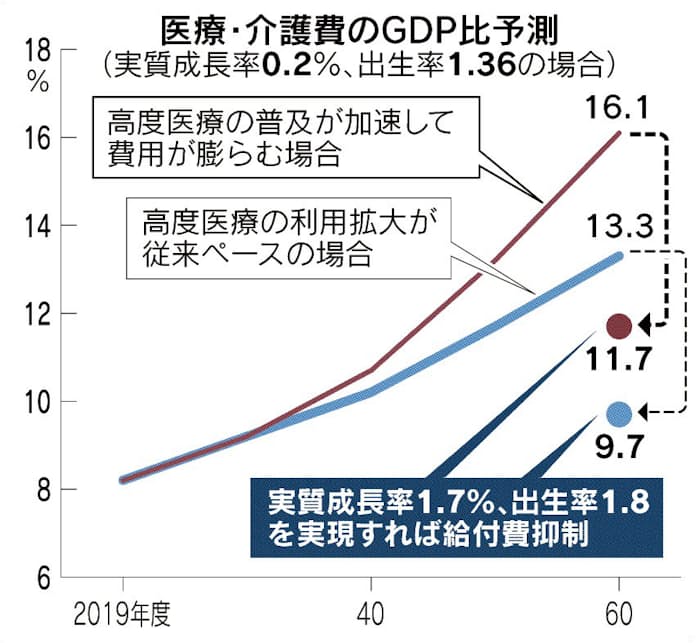 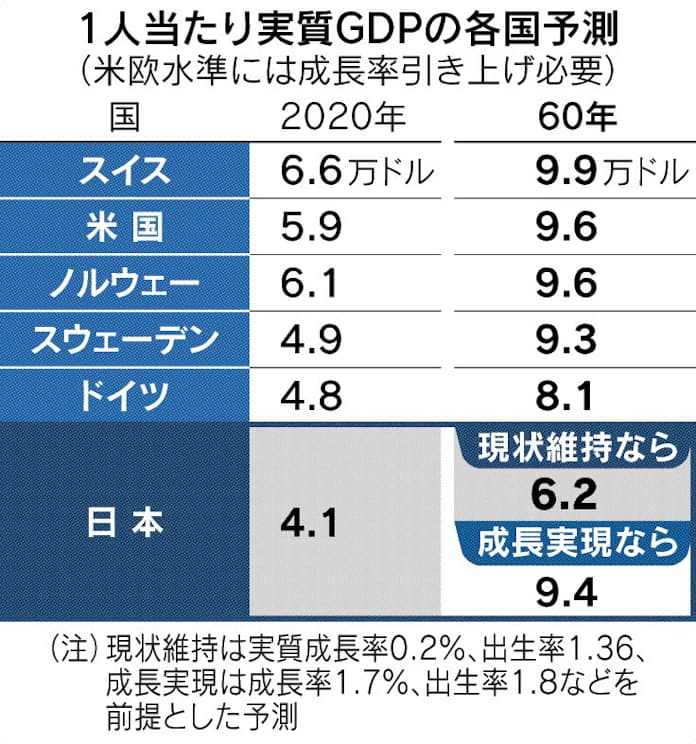 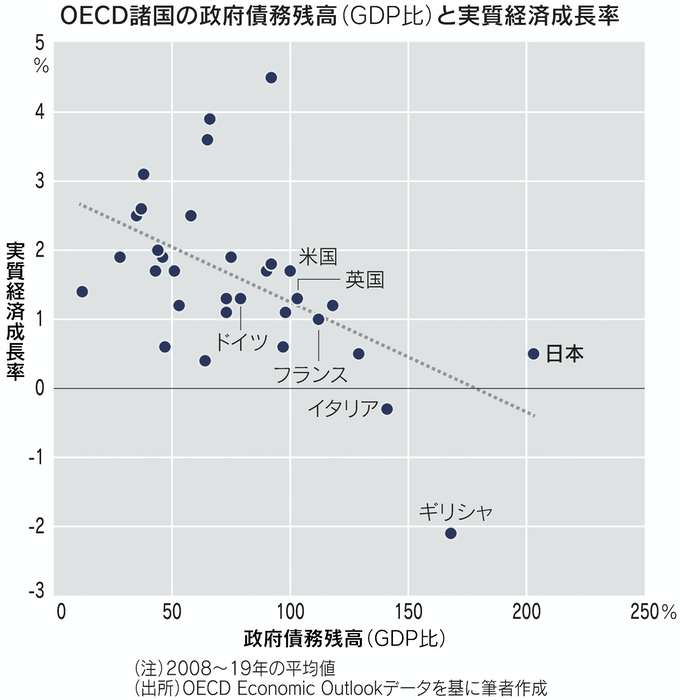 2024.4.3日経新聞 2024.4.3日経新聞 経済産業研究所 (図の説明:左図は、内閣府による医療・介護費のGDP比予測だが、高度医療が医療・介護費を膨らませると仮定している点が誤りであるし、出生率を上げれば実質成長率が上がると仮定している点も、世界を見ればわかるとおり事実ではなく少子化対策への流用を誘導しているにすぎない。中央の図は、2020年と2060年の各国の実質GDP/人の予測だが、日本より人口の少ないスイス・ノルウェー・スウェーデン・ドイツの実質GDP/人《国民1人1人の豊かさを示す》は日本より高く、これらは研究開発に熱心で社会保障も整っている国だ。また、右図は、OECD各国の政府債務残高《GDP比》と実質経済成長率の関係で、単なるバラマキによって政府債務残高を増やした日本は、政府債務残高が多い割に実質経済成長率が低いという当然の結果が出ている) 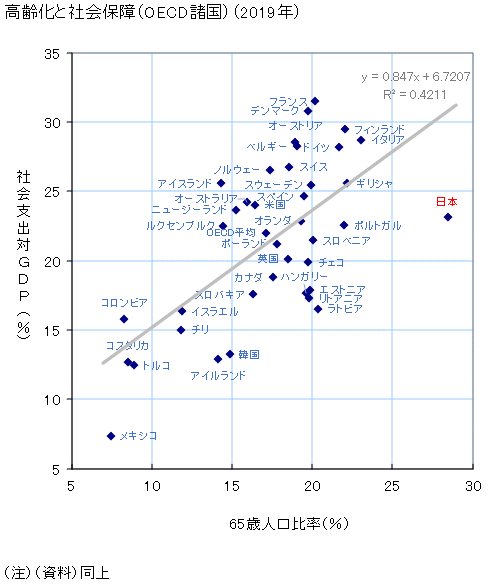 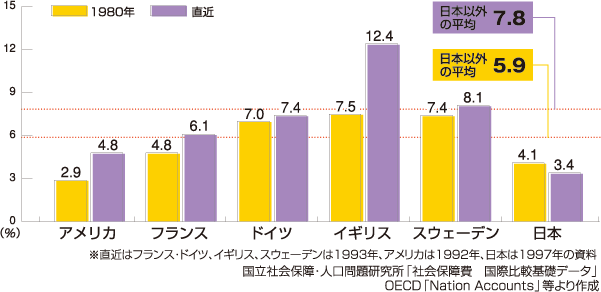 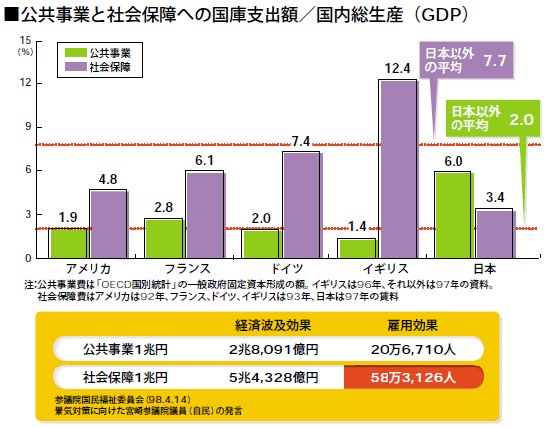 社会実情データ 保団連 ダイアモンド (図の説明:人生の終盤に年金・医療・介護費が増えるため、高齢化すれば社会保障費が増えるのは当然で、左図が、65歳以上の人口割合と社会保障支出/GDPの関係だが、日本は他国と比較して高齢化の割に社会保障支出が少ない国である。また、中央の図のように、1980年と比較して直近の社会保障支出/GDPが減っているのは日本だけであり、先進国中最低になっている。さらに、右図のように、先進国中、日本だけが「社会保障支出/GDP<公共事業支出/GDP」であり、日本の社会保障支出/GDPは現在でも決して大きくない。つまり、「全世代型社会保障」と称して高齢者に負担を押しつける政策は、根本的に間違っているのである) *2-1-4は、①医療・介護給付費は65歳以上人口がピークアウトする2040年度頃から急激に増加 ②医療・介護利用の多い85歳以上人口が継続的に増すため ③2025~60年度の平均実質成長率は、i)0.2%の「現状維持」 ii)1.2%の「長期安定」 iii)1.7%の「成長実現」で試算 ④医療・介護給付費のGDP割合は、「現状維持」で2060年度13.3%と2019年度より6割贈、「成長実現」で9.7%と2割弱増 ⑤社会保障制度維持にはデジタル化による効率化やGDP成長率の引き上げが急務 ⑥医療技術革新が加速すれば給付費は一段と膨らみ、高額医薬品の登場による医療費拡大が従来の2倍ペースだとGDP比は「現状維持」で2060年度に16.1%で 2019年度の2倍 ⑦岸田首相は「実質1%を上回る成長で力強い経済を実現し、医療・介護給付費のGDP比上昇に対する改革に取り組む」と強調 ⑧政府は2023年12月公表の改革工程素案に介護サービスを利用する際の2割負担の対象者を2024年度に拡大すると盛り、与党からの反対等で見送った ⑨政府は社会保障の歳出改革で少子化対策による実質的負担増を回避すると主張するが、介護負担拡大の先送り等が続けば実現は遠のく ⑩実効性ある社会保障改革に繋げるには試算の妥当性検証も必要 等としている。 上の右図のように、普通の人は75歳以降に生涯医療費の半分以上を使い、特に85以上で医療・介護関係の支出が増えるが、これは誰にでも言えることである。 そのため、①②は事実だが、③の成長率の試算については、iii)の1.7%の「成長実現」が合計特殊出生率1.8程度まで回復、「全要素生産性(TFP)」がバブル期並みの1.4%の上昇という条件を設定していることに、私は意図的なものを感じた。 何故なら、女性の教育や能力が向上して職業選択の自由度が高まれば、結婚・出産・子育てのみを人生の最終目標にする女性割合は著しく減るため、いくら児童手当を支給したり、教育を無償化したりしても、外国人を閉め出して日本人だけでやる限り、合計特殊出生率が1.8程度まで回復することはないからである。また、金融緩和をしただけのバブル期に、「全要素生産性(TFP)」が1.4%上昇したというのも疑わしい。 そのような中、④のように、医療・介護給付費の対GDP比を下げようとすれば、⑤⑦のように、GDPを増やすためGDP成長率を上げることは重要だ。しかし、GDP成長率の引き上げ方法は、デジタル化による効率化だけではなく、⑥の先進的な医療・介護機器や医薬品の開発による医療技術の革新を国内で起こし、それを世界市場に投入する方法もある。そうすれば、それを使用することによって、一時的には医療給付費が膨らむが、日本のGDPが増えたり、医療・介護費の合計が減ったりする効果もある。その良い例が、米国のコロナワクチンだ。 にもかかわらず、政府見解にはいつも優れた医療・介護機器や医薬品の開発とその世界市場投入によるGDP成長率向上・国民の福利増進の視点が抜けている。効果が高く副作用の少ない優れた新薬のために医療費給付が一時的に高額になっても、副作用が大きく効果の薄い旧来型の治療法を保険適用から外せば、国民は先端医療を享受しながら、医療・介護費用の節減を正攻法で行なうことができて歳出改革に繋がるのに、である。つまり、現在は、政府(厚労省・財務省)自身がそれを邪魔して、GDP成長率向上を阻害していることになる。 また、⑧のように、政府は2023年12月公表の改革工程素案に介護サービスを利用する際の2割負担の対象者を2024年度に拡大すると盛ったが、確かに高齢になっても働いて現役並みの所得を得ている人もいれば、年金のみで生活しなければならず食費やエネルギー代にも事欠いている人もいる。そのため、「原則は全員3割負担で、所得に応じて医療・介護費の自己負担額合計が一定上限額を超えない範囲」とするのが公平で適切だろう。 しかし、日本政府は、現在は高齢者に関しては生活保護程度の所得でも高所得と看做しているため(ここが大きな問題)、1年間の医療・介護費支払上限額は、医療・介護費が生活費を圧迫しないよう所得の5%以下と低く設定し、いろいろな意味で個人情報保護の怪しい「マイナ保険証」で受診しなくても、窓口で自己負担分だけ支払えば済むようにすることが条件になる。 なお、⑨のように、政府は、高齢者に対する医療・介護給付の削減を社会保障の歳出改革と称しているが、医療保険料・介護保険料として支払った保険料を少子化対策に使うのは目的外の流用である上、日本の医療・介護制度を支えるのは“生産年齢人口”に当たる15~65歳の日本人男性だけでなくても良い。そのため、いくら屁理屈をこねても流用は合理化できないし、現役世代の負担が重いといっても、殆どの人が同じ経過を辿って死ぬため不公平はなく、高齢者はいつまで現役並みの所得を得られるかわからないので貯蓄は必要なのである。 さらに、⑩については、政府がこれまで行なってきた政策を正当化するためか、原因分析や予想が甘すぎる点が散見され、確かに仮定・原因・試算等の妥当性の検証も必要だと思われる。 上のほか、*2-1-6も、⑪バラマキをやめ財政を「平時」に戻す必要 ⑫「賢い支出」を追求して財政健全化と成長の両立をめざすべき ⑬内閣府は2060年度までの社会保障費と財政状況の長期推計を初めてまとめ、社会保障費の急増で財政が持続可能でなくなる危うい未来が浮かんだ ⑭毎年度の社会保障費を高齢化による伸びの範囲内に収め、給付の抜本改革や消費税を含めた負担の議論もすべき ⑮新型コロナウイルス禍の危機対応で膨張した財政の規律を取り戻す必要 ⑯歳出改革で4兆円削り、税収が5.3兆円上振れしても、基金の乱立等で新たな歳出が3年前の試算に比べて7.5兆円増え、効果を薄める ⑰首相は財政健全化の決意を行動で示すべき ⑱成長を実現し、将来の歳出を減らすため、DX等で生産性を高める賢い支出は欠かせない 等としている。 このうち⑪⑫⑮⑰は賛成だが、⑬⑭のように、歳出改革と言えば、「持続可能性のため社会保障費を削減するか、消費税増税が必要」と主張するのは、国民不在・省益優先の行政の代弁であり、日経新聞の悪い点である。しかし、こういうことを言うメディアは、ほかにも多い。 特に、社会保障のうちの医療・介護保険制度は、*2-1-7のように、高齢化社会のニーズに対応して作った優れた制度であり、中身を濃くしながら充実することはあっても、数値だけを見て削減するような数合わせに終始してはならないものだ。 日経新聞は、日頃から、著しい金食い虫である原発は熱心に推進し、⑱のように、ラピダスのようなDX企業への補助金も兆円単位であっても成長を促す「賢い支出」としているが、関連性まで含めた経済の仕組みがわかっていないのではないか? また、生産に資するのではなく、破壊に資する武器を作る兆円単位の支出が「賢い支出」とは、どう考えても言えないと思う。 つまり、首尾一貫した主張をすべきなのは、政治家だけではなく、メディアも同じであり、責任ある大人であれば、誰でも同じなのである。なお、⑯については、複数年での予算の使用を可能にし、毎年、費用対効果を検証しながら翌年の予算を決められるシステムにすれば、基金の乱立は不要であり、国会議員始め国民にとって透明で賢い使い方になる。 4)少子化対策について *2-2-1・*2-2-2は、①政府は、児童手当や育児休業給付など少子化対策の拡充のため、2024年度からの3年間で年3.6兆円の予算を確保する ②「医療保険料からの支援金制度」で初年度6000億円、段階的に金額を増やし2028年度には年1兆円集める ③他は歳出改革で1.1兆円、既定予算の活用で1.5兆円確保する ④首相は「2028年度拠出額は加入者1人当たり月平均500円弱」「社会保障の歳出改革で保険料の伸びを抑え、今春以降の賃上げで負担率の分母が増えるため、実質的な負担増にならない」とする ⑤支援金は、サラリーマンの場合は給料から天引きされる医療保険料に上乗せし、75歳以上の後期高齢者も含む全世代が負担する ⑥実際の1人当たり負担額は個人毎に差が出て所得の高い人ほど負担額が増える としている。 また、*2-2-3は、⑦野党から、「支援金は事実上の子育て増税」と批判 ⑧立憲の山井氏は「所得階層別の負担額を出してほしい」と迫り、加藤こども政策相は「年収別拠出額は数年後の賃金水準等に依るため、現時点では一概に申し上げられない」と繰り返した ⑨少子化対策の最大の争点は財源確保策 ⑩立憲の早稲田氏は「給付と負担の関係が明白な社会保険の考え方に到底見合わない。租税でまかなわれるべき」と指摘し、加藤氏は「(医療保険等の)社会保険制度はともに支え合う仕組み。支援金制度も少子化対策で受益のある全世代・全経済主体で支える仕組み」と答弁 ⑪岸田首相も衆院本会議で「少子化・人口減少に歯止めをかけることで、医療保険制度の持続可能性を高める」と強調 ⑫本会議では国民の田中氏が「こども誰でも通園制度を拡大していく考えはあるのか。保育士等の賃金・労働条件を改善し、質の高い保育の提供に必要な人材を確保すべき」との指摘 としている。 しかし、日本の最高法規で法体系の頂点に立つ日本国憲法は、第25条で「1項:すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する 2項:国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めている。 また、第 26 条で「1項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する 2項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする」と定めている。 そして、それらに使うために、第30条で「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と定め、国民から税を徴収しているのだ。 つまり、子育ての中の保育や義務教育の無償化や(年齢を問わず)すべての国民に対する医療・介護・公衆衛生の増進は、憲法で保障された国民の権利であり、国はそれを実現するために国民から税を徴収しているのだ。そのため、優先順位の低い事に無駄使いした挙げ句、「少子化対策のためだから、国民負担を増やす」とか「財源を探す」などという議論にするべきではなく、③のように、優先順位の低い歳出をカットして必要な財源を確保し、憲法で定められた国民の権利を保障すべきなのである。 従って、子育てのための支援を増やしたり、教育無償化したりするのは良いが、それを①のように、少子化対策と位置づけるのはそもそも問題の本質から外れているし、②のように、その財源の一部を医療保険料から流用すれば、全国民に対する公衆衛生の向上・増進を阻害して憲法違反となるのである。 なお、④⑤⑥のように、首相は「2028年度拠出額は加入者1人当たり月平均500円弱」「社会保障の歳出改革で保険料の伸びを抑え、今春以降の賃上げで負担率の分母が増えるため、実質的な負担増にならない」等とされたそうだが、「500円弱」というのは働いていない人まで含む人口で割って出した金額で実際の負担額は人によって異なるため誤解を生み、社会保障の歳出改革で社会保険料の伸びを抑えれば、医療・介護はさらに疎かになって、国民の健康や公衆衛生の増進に逆行するのである。 そのため、⑦⑧のように、野党が「支援金は事実上の子育て増税」「所得階層別の負担額を出すべき」と反論するのは尤もだが、優先順位が高いにもかかわらず、これまでサボっていたことをするのに追加負担を求めるのは、どの所得階層の国民であっても許し難いのだ。 従って、⑨の財源は、⑩のように、税で賄われるべきであり、加藤氏の説明はこれまで明確だった事をわざと混同させて煙に巻いている。また、⑪の岸田首相の「少子化・人口減少に歯止めをかければ、医療保険制度の持続可能性を高める」というのも、児童手当や育児休業給付で少子化が止まるという証拠はなく、現在いる人材も本当に必要な場所で有効に使っているわけではない上、医療保険等の社会保障を支えるのは日本人の生産年齢人口(15~65歳とされる)の男性でなければならないとも決まっていないため、その場しのぎの言い訳にすぎないのである。 5)外国人労働者について 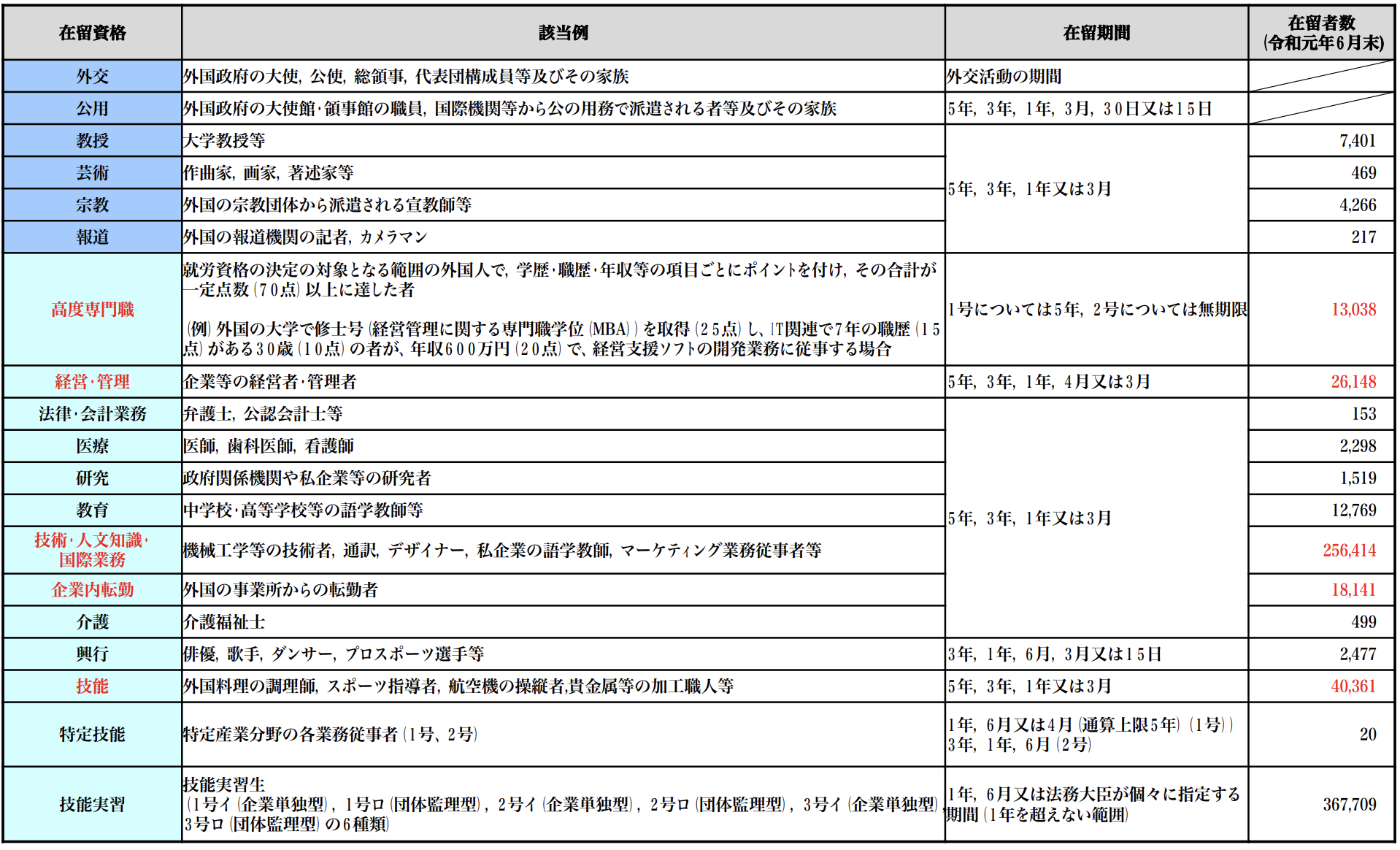 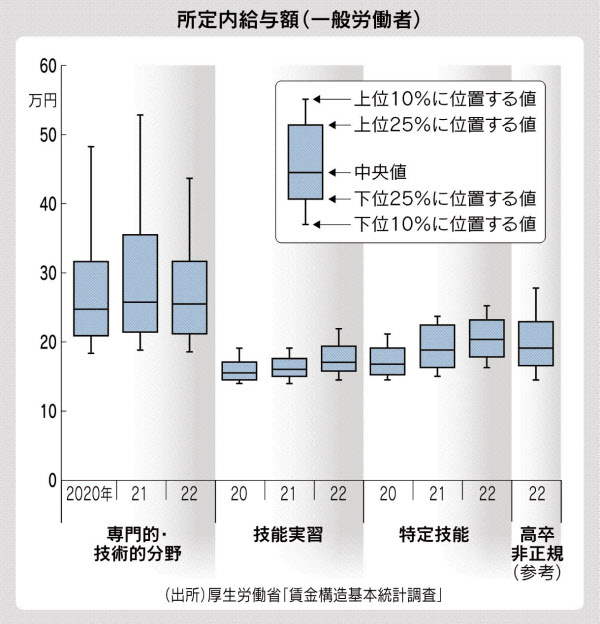 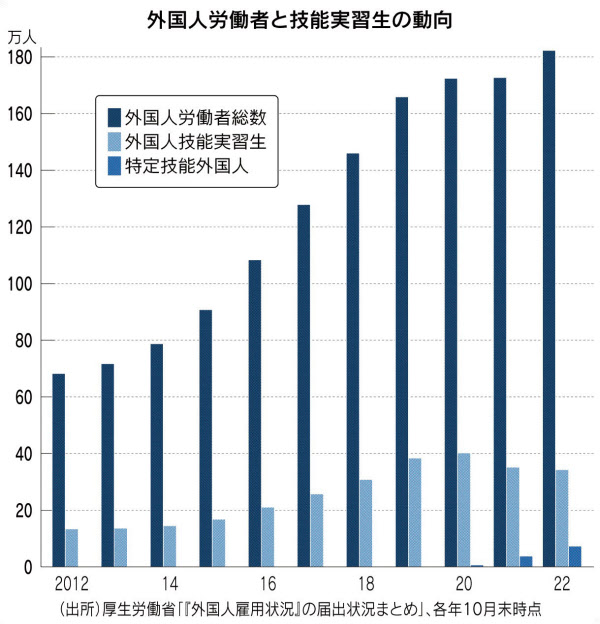 (図の説明:左図は、外国人労働者の在留資格・在留可能期間・在留者数を示したもので、在留期間を短く区切って滞在者数を制限し、医師・看護師・介護福祉士・保育士・美容師等の資格の相互承認はしておらず、生産年齢人口に対して雇用機会が不足している時の体制のままになっている。また、中央の図のように、外国人労働者の給与は技能実習を終えた特定技能でも日本人の高卒非正規程度で外国人差別が存在しており、日本が「選ばれる国」になるのを妨げている。このように、熟練した頃には強制的に母国に返すため、右図のように、特定技能や技能実習の外国人は限られた数になり、人手不足が補えないのだ) 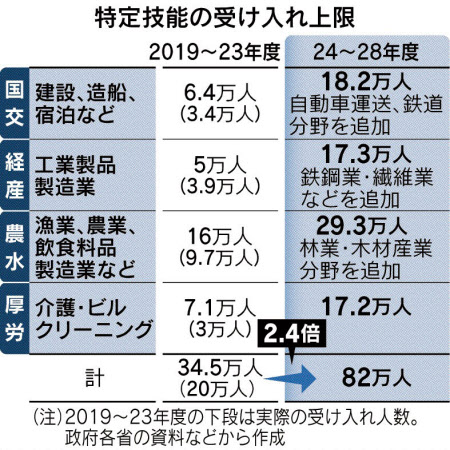 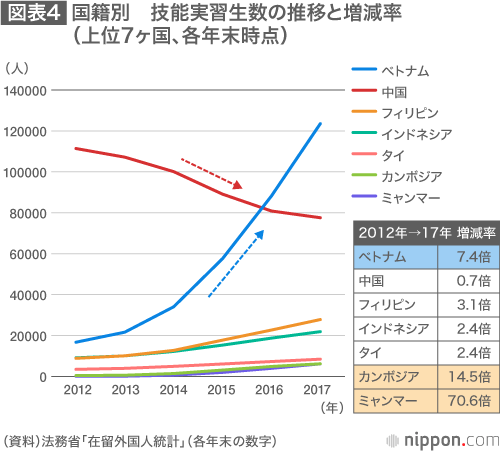 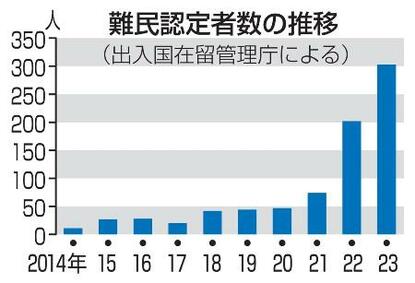 (図の説明:そこで、左図のように、日本政府は特定技能の受入上限を「2024~28年に82万人」と増やしたが、職種は殆ど男性で日本人ばかりの政治家・行政官が思いつく範囲に留まるため不十分だ。このような中、中央の図のように、自国の所得水準との差が縮まれば日本で働く魅力は薄れるため、所得水準の差の大きな国が外国人労働者の供給源として有望なのだが、右図のように、日本の難民受入数は2023年に300人程度と先進国の中で桁違いに低く、他国を批判する割には困っている時に助けない「《大金を払わなければ》好かれない国」となっている) まず、日本国憲法は前文で、「全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する」「いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる」と定めている。 そして、*2-3-1は、①政府は外国人労働者の在留資格「特定技能」の受け入れ枠を提示し、2024年度からの5年間で現行の2倍以上の82万人を受け入れる ②内訳は国交省所管分18.2万人・経産省所管分17.3万人・厚労省所管分17.2万人 ③数字は業界毎に成長率・需要等から不足人数を出し、人材確保や生産性向上の努力で解決できる分を差し引いて算出 ④急速な少子高齢化に見舞われる地方からは悲痛な声が上がっていた ⑤厚労省発表の2023年10月の外国人労働者は約200万人で、JICAは年平均1.24%の成長を2040年に達成するには674万人の外国人労働者が必要と推計 ⑥政府は特定技能だけでなく技能実習に代わる「育成就労」と合わせて受け入れ数を増やす方針 ⑦円安や低下した賃金水準は日本が「選ばれる国」になる足かせ ⑧外国人の職場への順応や生活環境の支援策を整えることが重要 ⑨移民統合政策指数の2020年版の総合評価で日本の順位は56カ国中35位で、韓国に後れをとる 等としている。 このうち③の「業界毎に成長率・需要等から不足人数を出し、人材確保や生産性向上の努力で解決できる分を差し引いて外国人労働者の必要数を算出する」というのは、国内のイノベーションを計りながら、雇用との調和を維持しようとするするもので良いと思う。 しかし、外国人労働者が必要な分野は、②の国交省・経産省・厚労省だけではなく、文科省・農水省・環境省・防衛省等の分野にも及ぶため、人手不足が経済の足をひっぱらないためには、①の82万人ではなく、④⑤を考慮して必要とされる分野は躊躇なく追加すべきである。 また、⑥の2019年に始まった特定技能制度は、人手不足が著しいとされた特定分野に限って一定の専門性と日本語能力を持つ外国人材を受け入れる制度だが、それでも「1号」の在留期間は最長5年で家族は帯同できず、「2号」になって初めて家族を帯同できるが、就労している限り更新の上限がないという条件の悪さである(https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/2685 参照)。 そして、特定技能1号の取得方法には、i)分野毎に用意された技能試験と日本語能力試験に合格 ii)職種と作業内容に関連性のある技能実習を良好に3年間終了する の2つがあるが、技能実習制度には問題が多発しているため、日本政府が2024年2月9月に技能実習制度廃止と育成就労制度(特定技能への移行を目指す制度)創設を決定したものの、改正法施行は2025年~27年と消極性をあらわにするゆっくりした進展なのである。 このように雇用条件が悪ければ、⑦のように、円安や低下した賃金水準で他国との賃金格差が縮まれば日本は「選ばれる国」にならない。また、⑧のように、外国人のみに職場や生活環境への順応を求めれば、外国人の日本での生活しにくさは著しいものになる。これらの結果として、⑨の2020年版移民統合政策指数総合評価で日本の順位は56カ国中35位になり、言葉の特殊性は日本と同レベルの韓国にも後れをとっているのである。 難民については、*2-3-2が、⑩出入国在留管理庁が自国で迫害を受ける恐れがあるとして2023年に303人(申請者数のわずか2.2%)を難民認定したと発表 ⑪内訳は、2021年の政変後に退避したJICA職員が多いアフガ二スタン237人、軍政による弾圧が続くミャンマー27人、エチオピア6人など ⑫難民認定申請者数は1万3823人で、スリランカ3778人、トルコ、パキスタンの順 ⑬難民認定制度とは、難民を「人種・宗教・国籍・政治的意見・特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害される恐れがあって国外に逃れた人」と定義し、出入国在留管理庁の調査官が面接等で審査 ⑭日本の難民認定数は年間1万人超の国がある欧米と比べて著しく少なく、基準が厳しすぎるため「難民鎖国」との批判がある と記載している。 このうち⑩⑪⑫⑬は事実だが、⑭のように、日本の難民認定数は欧米先進国と比較して著しく少なく、基準が厳しすぎて「難民鎖国」そのものである。しかし、気候変動等によって食料や土地の支配権を巡る争いが頻発するようになれば、移住を余儀なくされる人も増えて難民は増加する。その時に、難民を軽蔑して排除するような国が「国際貢献している国」と評価されるわけはなく、大金を払わなければ「好かれる国」にも「選ばれる国」にもならないだろう。 それでは、難民になる人は労働者としてレベルが低いのかと言えばそうではなく、いろいろな点で日本人より優れた人も多い。そのため、私は、難民鎖国は早急に止めた方が良いと考える。 わかり易い例を挙げれば、*2-3-3の日本を代表する指揮者で“世界のオザワ” の小澤征爾氏は、満州国奉天に生まれ、大陸で生まれ育ったことが日本人離れした活躍の源で、戦後は立川に住まいを移して中学3年生の時に齋藤秀雄(桐朋学園で多数の著名指揮者や弦楽器奏者を育てた大功労者)に弟子入りし、23歳でブザンソン国際指揮者コンクールで優勝し、1961 年にニューヨーク・フィルハーモニックの副指揮者に抜擢された。 その後、輝かしい活躍をされたのだが、最初は敗戦後の開発途上国であった日本の一青年が国際指揮者コンクールで優勝できる先進国のFairな審査があり、その結果を受けて機会を与えたボストンフィル、ニューヨーク・フィル、ウィーン・フィル、ベルリン・フィルなどがあって、小澤征爾氏は世界をはじめとして日本でも活躍できたのである。そして、このような人は多い。 そのため、日本もFairな態度で広い母集団から人材を選ぶことが必要不可欠であり、そうすれば、結果として日本だけでなく世界のためにもなるだろう。 そして、*2-4は、⑮職に就いていないが仕事を希望する「働き手予備軍」は2023年に411万人と15歳以上の3.7%に留まり、その割合は20年で半減 ⑯予備軍が減ったのは景気回復で女性・高齢者の働く環境整備が進んだため ⑰一般労働者は1.0%増でパートの伸びが際立ち、女性・高齢者の労働参加が進んで人材プールが細った ⑱国立社会保障・人口問題研究所によれば、生産年齢人口はピークの1995年と比較して2023年に15%減だが、その間に就業者は約400万人増 ⑲「M字カーブ現象」もほぼ解消 ⑳日本は1960年代後半に「ルイスの転換点」を過ぎたが女性・高齢者を含めて新たな転換を迎える可能性 ㉑人手不足で採用できず、非正規の時給引き上げが続けば、低採算の事業は撤退をせざるを得ない 等としている。 このうち⑮⑯⑱⑲は良かったと思うが、⑰⑳については、女性・高齢者が短時間勤務を希望したとしても、短時間の正規雇用として雇用を安定化させつつ、社会を支えることもできるのに、未だパート中心で「ルイスの転換点」にも達していないことには落胆させられる。 しかし、㉑の低採算で人手不足の産業が不要な産業ばかりでは決してないことは、高くて必要なものも買えなかったり、必需品の多くを輸入依存していたり、日本企業でさえ安価な労働力を求めて海外に生産拠点を移し国内の産業が空洞化していたりする状況を見れば明らかだ。 そのため、本格的に外国人労働者を受け入れ、安価に国内生産できる製品を増やし、さまざまな製品やサービスを開発・提供すべき時であることは間違いないだろう。 ・・参考資料・・ <歳出改革の理念1←地球環境と食料・エネルギー自給率> *1-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240221&ng=DGKKZO78623090Q4A220C2KE8000 (2024.2.21 日経新聞) 生産性停滞 要因と対策(上) 「豊かさ」への新たな戦略探れ 宮川努・学習院大学教授(56年生まれ。東京大経卒、一橋大博士(経済学)。専門はマクロ経済学) 木内康裕・日本生産性本部上席研究員(73年生まれ。立教大院修了。専門は生産性に関する統計作成・経済分析) <ポイント> ○生産性向上のための構造改革が置き去り ○良質なヒト、モノ、カネが国外流出の恐れ ○生活の豊かさまで含めたビジョンが必要 2023年末、日本の国内総生産(GDP)や生産性に関する国際的順位が公表された。「国民経済計算」確報版で示された22年の1人当たり名目GDPは、経済協力開発機構(OECD)加盟国中21位と主要7カ国(G7)で最低となった。また日本生産性本部の「労働生産性の国際比較2023」では、22年の1人当たりの労働生産性はOECD加盟国中31位となった。円安が要因とはいえ、GDP全体でも人口が日本より3割以上少ないドイツに抜かれ、4位に転落した。日本の経済的地位の低下を嘆く報道は恒例行事と化した感がある。しかし当面の順位にこだわるだけでは、日本が直面している問題の解決にはならない。本稿では日本経済の国際的地位を念頭に置きながら、労働生産性の向上を含めた日本の選択肢について述べたい。1人当たりGDPや労働生産性などの経済的豊かさに関する指標の国際順位が調査により異なるのはなぜか。1人当たりGDPも労働生産性も分子はGDPだが、それを割る分母の指標が異なる。1人当たりGDPでは人口、労働生産性では労働者数や労働時間数で割っている。さらに影響が大きいのはドルに換算する際の為替相場の違いで、内閣府の順位ではその時々の為替レートを使うため最近の円安が大きく影響する。一方、日本生産性本部の指標ではドル換算時に購買力平価を使う。購買力平価は日米の生活水準を同じくするレートで計算されており、00年は1ドル=155円、22年は同98円とむしろ円高になっている。つまり現在の日本の財・サービスは品質が良く、米国ではより高く売れるということだ。それでも労働生産性が22年に31位まで後退しているのは、日本の就業者比率が高く、欧州でユーロの評価以上に生活水準の高い国があるからだ。従って労働生産性の順位こそ深刻に受け止めるべきだろう。長年にわたる1人当たりGDPや生産性の低迷はなぜ起きたのか。筆者らは21世紀初頭から生産性の国際比較をしてきたが、この間アベノミクスに代表される財政・金融政策頼みの経済運営により、生産性向上のための構造改革が置き去りにされてきたと感じる。かつて政府は「世界最高水準のIT(情報技術)社会の実現」という目標を掲げた。だが依然マイナンバーの普及が十分でなく、ライドシェア一つ実現できていない社会を世界最高水準のIT社会と呼べるだろうか。実際、労働生産性の順位は10年代半ばごろから急落している(図参照)。構造改革を労働強化とする批判も生産性向上が進まない一因だが、新技術の習得に努めなければ経済的な豊かさどころか安全性も維持できなくなりかねない。筆者らが日本経済の課題の一つとして生産性向上を唱え始めたころは、日本経済はいずれリバウンドするという期待があった。だが当初の予想を上回る長さの低迷から考えると、この流れを直線的に延長していけば、予想される未来は「緩やかなアルゼンチン化」だ。地球の反対に位置しながら、経済成長の分野で両国は奇妙な縁がある。産業革命を経て先進国化した欧米諸国の次に先進国入りをするのはどの国かということが議論された際に、候補として挙げられたのが日本とアルゼンチンだ。その後は大方の予想を裏切り日本がアルゼンチンよりも経済的に成功したが、21世紀に入り日本はアルゼンチンの後を追うように坂を転がり続けている。世界銀行のデータでは、1995年から22年の労働生産性順位の変化を見ると、日本は28位から45位、アルゼンチンは44位から55位へとともに順位を落としてきた。アルゼンチン化の特徴の一つは、良質なヒト、モノ、カネが国を見捨てて流出していくことだ。ヒトに関しては、日本の教育水準の高さは先進国でも群を抜いている。スポーツでも、両国とも野球の大谷翔平やサッカーのメッシという百年に一度ともいわれる才能のある選手を輩出している。しかし彼らが実力を発揮した場は欧米だ。日本であれば二刀流というイノベーション(革新)は十分に許容されなかったのではないか。実際、人口が減少するなかでも、日本人の海外永住者数は増え続けている。イノベーション不足の国ではモノへの投資も海外へ向かう。従来型ビジネスで稼ぐには、日本企業は低金利で調達し収益性の高い海外で投資した方が有利だ。最後のカネに関しては、アルゼンチンは何度も資本流出により経済危機に見舞われた。日本でもその兆候は見え始めている。22年から欧米が金利を引き上げたのに対し、日本はゼロ金利を維持しており、資金の流出と円安を招いている。良質のヒト、モノ、カネの流出はさらなる貧困化を招き、皮肉にも人々は一層政府への依存度を高めることになる。だが政府自身に経済を活性化する機能はない。最終的にアルゼンチンのように肥大化して身動きがとれなくなった政府に徹底した「ノー」を突き付けるような状況が日本に訪れる可能性は否定できない。「緩やかなアルゼンチン化」から逃れる方法はあるのか。一つは従来型の成長戦略をより強い形で実行していくことだろうが、実現性が低いかもしれない。既得権益や規制の壁も大きな理由の一つだ。加えて長年の経済低迷の影響で、90年代までに社会人としての経験がない世代には、改革後の成長のイメージが浮かばず説得力に欠けるのだ。いわゆる氷河期世代以降は成長期の体験が乏しく、停滞する日本経済だけを見てきた。彼らにとって、日本は経済活力や科学技術の面で世界的に優れた国ではない。こうした世代には、経済的豊かさを優先した世代のシナリオは魅力的でなく、生活の豊かさまで包含したビジョンが必要だろう。1月18日付本欄で滝澤美帆・学習院大教授が紹介した日本生産性本部の生産性を含む包括的な豊かさの指標を探る試みも昭和的な成長志向の修正を企図している。だがより経済学的、政策的なアプローチは、パーサ・ダスグプタ英ケンブリッジ大名誉教授が「生物多様性の経済学」で示した「資本アプローチ」だ。資本アプローチは、人々の生活を豊かにするサービスを市場経済から供給されるサービスに限らず、環境を含めた市場外のサービスにまで拡張してとらえ、それらを提供する基盤となる民間資本、社会インフラ、自然資本、人的資本などの組み合わせを政策目標として考える。このアプローチが定着するには時間がかかるだろうが、これまで経済的豊かさの指標として君臨してきたGDPも将来はより包括的な豊かさを取り入れたものへと変化していくだろう。GDPや生産性の低迷をきちんと受け止めることは大切だが、単なる過去への回帰ではない「豊かさ」への戦略を練る必要がある。 *1-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240308&ng=DGKKZO79073400Y4A300C2MM8000 (日経新聞 2024.3.8) 曲がる太陽電池を優遇 経産省、電力買い取り額上乗せ 経済産業省は再生可能エネルギーの電力を高く買う固定価格買い取り制度(FIT)で、軽くて曲がる次世代の太陽光発電装置「ペロブスカイト型」を優遇する。2025年度にも同型による発電をFITに加え、通常の太陽光発電より高く買い取る。新技術への民間投資を促し、日本の再生エネの拡大につなげる。経産省はペロブスカイト型の買い取り額を、現行の太陽光向けの水準を上回る1キロワット時あたり10円以上で調整する。ペロブスカイト型の太陽電池はビル壁や窓など今まで設置できなかった場所でも発電できる。日本発の技術で、耐久性といった開発段階の品質では日本勢に優位性がある。一方、中国企業は量産を始めており商品化で先行する。FITでの優遇で、日本勢の関連ビジネスの競争力を高める。国土の狭い日本では太陽光パネルを設置できる余地が狭まっており、各地で林地開発のトラブルも相次ぐ。ペロブスカイト型が普及すれば、都市部のビルの壁面といった新たな発電場所を開拓できる。 *1-1-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC231FM0T20C23A5000000/ (日経新聞 2023年8月17日) 省エネ窓にリノベ、家計守る 高断熱ガラス売り上げ2倍 省エネ性能の高い窓に交換する世帯が急増している。大手メーカーの高断熱や複層ガラスの売り上げは前年比2倍の伸びで、冬場に向けて増産の動きもある。背景には冷暖房コストが増すなか、断熱性に優れた窓に交換して電気代を抑えたい需要の高まりがある。修繕工事の一環で全136戸の窓ガラスを日本板硝子の省エネガラス「スペーシア」に、2022年に交換した東京都立川市のマンション。住民の後藤和夫さんは「夏の電気代が2〜3割減った」と語る。スペーシアの3月以降の売り上げは、前年同期比約2倍と好調だ。スペーシアは2枚のガラスの間に0.2ミリメートルの真空層をつくることで、熱の伝導や対流を抑える。厚さは1枚ガラスとほぼ同じだが、4倍の断熱効果がある。施工費用などを除いたガラスのみで、1平方メートルあたり約5万円で注文できる。スペーシアは1997年の開発以来、通常のガラスと比べて価格が数倍高いこともあり、販売は思うように伸びなかった。電気代の上昇が家計を圧迫するなか、断熱性能の高い窓ガラスへの交換需要が増えている。東京電力ホールディングスや中国電力など大手7社は6月、火力発電所に使う液化天然ガス(LNG)価格の上昇などを理由に家庭向け電気料金を1〜4割程度値上げした。7月から電気料金は下がっているが、依然として高水準のままだ。AGCの複層ガラスも4〜5月の販売数が前年比で5割増え、6月は2倍に伸びている。工場の稼働はフル生産しているが、納期は1カ月以上先になる場合もあるという。秋以降に設備投資して、最大15%程度の増産を検討する。建築ガラスアジアカンパニー日本事業本部の古賀潔氏は「節電のために窓を交換する世帯が増えている」と指摘する。政府の補助金も追い風となっている。政府は23年度から省エネ性能の高い窓ガラスや窓枠の交換費用のうち、1戸あたり上限200万円まで補助する「先進的窓リノベ事業」を展開している。予算枠は約1000億円で、3月31日から交付申請を受け付けている。8月16日時点で申請額は予算の5割を超える。22年度の補助制度と比べて補助額の上限が大きいため、高額でも断熱性に優れた窓ガラスへの交換を後押ししているとみられる。「補助金の枠を使い切ってしまう可能性は十分ある」。LIXILの瀬戸欣哉社長は指摘する。同社では想定の6〜8倍の注文があり、4月の取替窓の販売は10倍に伸びた。瀬戸社長は「断熱性のある窓に交換する需要はこれからも大きくなるだろう」とみる。記録的な猛暑が続く中、より手軽に窓回りの断熱性能を高めるグッズを購入する消費者も増えている。ホームセンター大手のカインズでは、「断熱カーテンライナー」の販売が好調だ。ニトリでも通販サイト内の節電グッズ特集で遮熱性能のあるレースカーテンや遮熱窓シートなどを紹介している。 *1-1-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0641G0W3A001C2000000/ (日経新聞 2023年10月8日) 断熱窓への改修補助金、経済対策で延長へ 政府 政府は住居の窓を断熱性の高いものに改修する工事への支援制度を延長する方針だ。工事にかかる費用の半分ほどを国が負担する仕組みで、エネルギー消費が増える冬場を見越して対応を促す。10月中にまとめる経済対策に盛り込む。制度は2023年度から始まった。戸建て・集合住宅のリフォーム工事が対象で、登録した事業者が施工する場合に適用する。事業者を通じて手続きする。断熱窓は窓枠を二重にしたりガラスに熱を通しにくく加工したりしたものを指す。補助額は1戸あたり最大で200万円で、窓の性能やサイズなどで変わる。10月上旬時点での申請額は予算規模のおよそ7割に達した。この秋に取りまとめる経済対策で国内投資の促進策として制度延長を打ち出す。環境省は24年度予算の概算要求で1170億円を求めた。予算が足りなくなる可能性があると判断し前倒しで23年度補正予算案に計上する見通しだ。住宅内の熱の出入りは7割が窓を通じているとされる。断熱にすれば冬場で3割ほどの電力を抑えられる効果があるという。 *1-2-1:https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM113VK011092023000000 (日経新聞 2024/1/31) NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム:SDGs 海洋保全 脱炭素:大阪湾護岸に「藻場」創出 大阪府、海洋保全で官民連携、ブルーオーシャン・イニシアチブと事業連携 兵庫県とアライアンス設立 大阪府が大阪湾の護岸に海藻などの「藻場(もば)」を創出するため、民間企業との連携を強めている。一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブ(BOI)と2023年8月に事業連携協定を締結。2024年1月には兵庫県と「大阪湾ブルーカーボン生態系アライアンス(MOBA)」を設立した。2025年の大阪・関西万博で藻場創出の取り組みを国内外に発信する。藻場は海の生物多様性を増すほか、二酸化炭素(CO2)を吸収して長期で貯留できるため、持続可能な開発目標(SDGs)達成に寄与するとして注目を集めている。官民連携を通じて藻場を生み出すための様々な課題を解決する。 ●「ミッシングリンク」解消目指す 海藻類が育つ藻場はCO2の吸収源となるほか、魚類など生き物のすみかとなる。酸素の供給など水質改善の効果も期待できる。しかし、大阪湾のうち北は大阪市から南は貝塚市までの「湾奥部」(海岸線延長約180㎞)は大半がコンクリートなどでできた人工護岸で藻場はほぼ存在しない。一方、泉佐野市以南の湾南部や西部には海藻が自生しており、淡路島や兵庫県南部を含めた大阪湾全体で見ると「湾奥部だけが藻場がない『ミッシングリンク(連続性が欠けた部分)』になっている」(大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課の田渕敬一課長補佐)という。大阪府は湾奥部に藻場を創出することで、大阪湾全体を藻場や干潟などの回廊でつなぐ「大阪湾MOBAリンク構想」を掲げ、その実現には主に3つの課題があるとみている。第1の課題は船舶などの港湾利用に影響を及ぼさず藻場を創出する技術だ。第2の課題は海藻が海面下にあるため生育状況を確認するための費用がかかる点だ。第3の課題は護岸の多くは企業の所有地に面していて近づけないうえ、海藻を育成したい人が限られること。大阪府はこれらの課題を解決するための事業に着手した。 ●湾奥部でワカメを育成 大阪湾奥部は大都市圏から流入する河川などの影響で汚濁物質がたまりやすく、水質改善が課題となっている。そこで傾斜型の護岸に海藻が定着しやすい技術を確立して藻場を創出し、そこから周辺の護岸に広げていくことを目指している。2021年12月には大阪市が管理する「大阪南港野鳥園」の護岸にある消波ブロックにワカメを育てる30センチ四方のパネルを設置した。徳島県鳴門市産のワカメの胞子がパネルについて大きくなる仕組みで、漁礁工事の日本リーフ(兵庫県南あわじ市)が公募で事業者に選ばれた。府はこの事業にかかった経費の半額を補助金として支給。ワカメは順調に育ち、2022年4月にはワカメが繁茂していることを確認できた。護岸に面した事業所を所有する企業とも連携する。2022年にENEOS堺製油所(堺市)の護岸で環境省のモデル事業として海底にブロックを設置してワカメを育てた。波が想定より小さく、ワカメは育たなかったが、府は知見を生かして他の方法で藻場創出を支援する。 ●スタートアップなどの技術に期待 大阪府は2023年8月に一般社団法人のBOIと事業連携協定を締結した。2022年12月に設立されたBOIは海のサステナビリティ(持続可能性)実現に向け、産官学民の関係者が協力して活動している。具体的には、①長崎県対馬市と連携した海洋プラスチックごみ削減②魚類などの海洋資源保全と関連事業の活性化③ブルーカーボンクレジットの推進など海洋に関する気候変動対応――の3分野を中心に、「海の万博」といわれる2025大阪・関西万博を経て、SDGsの期限である2030年を目指し活動を推進する。大阪府は連携を通じてBOIに「MOBAリンク構想」に参画してもらい、海藻などの生態系に関する技術やノウハウを有する企業とのネットワークを構築し、湾奥部における藻場創出を加速する。例えば、BOIのメンバーであるスタートアップが保有する海洋ドローンなどの技術を活用して海中を「見える化」し、海藻の生育状況を調べることなどを想定。国内の他の地域で実績がある海藻の育成技術などの提供にも期待する。BOIのメンバーであるNPO法人ゼリ・ジャパンが2025大阪・関西万博で設けるパビリオンやイベントでMOBAリンク構想を国内外に発信する。例えば、来場者が大阪湾の海藻の周りに魚などが生育している様子を水中ドローンの映像で体感するイベントなどを想定する。 ●兵庫県とのアライアンスで会員募集 大阪府は2024年1月、兵庫県と「大阪湾ブルーカーボン生態系アライアンス(MOBA)」を設立した。具体的な活動内容として①取り組み状況の情報発信や普及啓発②ブルーカーボン生態系創出の取り組みを活性化③会員の連携による新たな事業の創出④藻場の創出が生物多様性などに与える影響の把握――などを予定。大阪湾MOBAリンク構想の実現に向けて、MOBAの活動に賛同する企業や団体、研究機関、行政機関などの会員を募る。2025年の大阪・関西万博で事業の認知度を高め、2026年度からSDGsの達成期限である2030年にかけて藻場の創出を加速させる。 *1-2-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1195380 (佐賀新聞 2024/2/17) アカウニの資源回復へ大型種苗放流 唐津市の漁業者とNPO法人、収穫までの生存率を検証 唐津ブランド・アカウニの資源を回復しようと、唐津市内の漁業者とNPO法人「浜-街交流ネット唐津」が6日、アカウニの大型種苗を放流した。生残率を検証するため、今回は種苗を小型から大型に変えた。魚やウニのすみかとなる藻場の磯焼けで、近年はアカウニの資源が大きく減少している。これまでは佐賀県内で生産されている小型アカウニの種苗を放流してきたが、小型種苗は魚の食害を受けやすく、生残率が低いという。山口県の報告書によると、放流して1年後の平均生残率は殻径1センチ以下で9・5%、1・6センチ~2センチで52・4%、2センチ以上で80・5%。今回は長崎県の種苗センターから3センチサイズを調達し、市内の沿岸に放流した。今後は収穫までの生残率を定期的に調べ、効果的なアカウニ種苗の放流を検証していくという。NPOの千々波行典代表理事は「唐津を代表するアカウニの資源が減り、危機的な状況が続いている。資源回復の効果を確認していきたい」と語る。 *1-2-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1205735 (佐賀新聞 2024/3/7) 洋上風力発電推進へ庁内組織立ち上げへ 唐津市 唐津市は7日、佐賀県が唐津市沖に誘致を検討している洋上風力発電事業を巡って、有望な区域への指定を進めるため副市長をトップとした庁内組織を立ち上げる方針を示した。経済部、漁業や港湾振興の部署など横断的な体制を立ち上げていくという。同日の市議会一般質問で伊藤泰彦議員(清風会)が質問した。峰達郎市長は「事業を早期に実現することは地域振興、経済波及効果が大いに期待できる」とし、「『一定の準備段階に進んでいる区域』から『有望な区域』へ整備されるよう推進体制を構築し、地元の理解を賜り、早期に次のステップに進めるよう尽力したい」と答弁した。国は2021年9月、唐津市沖を第1段階の「一定の準備段階に進んでいる区域」に整理した。次の段階として、利害関係者を特定した上で、法定協議会の設置について了解を得る必要がある。県と市は候補海域と隣接した五つの離島や相賀、湊地区などで説明会を開く一方、住民からは観光地の景観や沿岸漁業への懸念の声が出ている。峰市長は取材に対し、「待ったなしの状況で、集中的にアクションを起こしていきたい。地元住民の不安に対し、一歩踏み込んで説明していかないといけない」と語った。 *1-2-4:https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM21AEA021122023000000 (日経新聞 2024/1/9) NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム:ニッスイ、積み重ねた養殖技術への誇り、水産資源を守り未来につなげる ニッスイは、2022年4月に長期ビジョンを発表し、中期経営計画に着手、同年12月には社名を変え、新たな成長に向けてスタートを切った。ミッションに掲げる「新しい"食"の創造」の実現のひとつとして、養殖技術開発に力を入れる。ニッスイが目指す持続的な水産業の未来とは。中央研究所大分海洋研究センターの取り組みを追った。 ●天然資源への負荷を低減する サステナブルな養殖技術 ニッスイは、2022年4月にミッション(存在意義)を「海で培ったモノづくりの心と未知を切り拓く力で、健やかな生活とサステナブルな未来を実現する新しい"食"(Innovative Food Solutions)を創造していく」と定義した。時代や環境の変化に応じて"食"の新たな可能性を追求し、社会課題を解決していくことがグループの使命であると宣言した。環境負荷を抑えて高品質な養殖魚を持続的かつ安定して出荷するには、養殖技術を高めることが欠かせない。ニッスイが養殖事業の研究開発を担う中央研究所大分海洋研究センターを設置したのは、1993年のことだ。大分県佐伯市にあるこの研究所では、現在、養殖に関する基礎研究から事業化に向けた応用研究まで、約30人の研究員と支援員がそれぞれの研究分野に取り組んでいる。 ●人工種苗・育種技術の高度化により 年間を通じて高品質ブリを提供 大分海洋研究センター研究員の山下量平氏は、現在ブリ養殖の中心メンバーとして基礎研究から事業化に向けた応用研究までを担っている。ニッスイのブリ養殖の歴史は、04年にブリの養殖会社を事業譲受して黒瀬水産を設立したことから始まった。翌05年には、大分海洋研究センターで親魚から採卵し、受精卵から一貫して人の手で管理するブリの人工種苗の開発に着手した。一般的なブリの養殖では、「モジャコ」と呼ばれる天然の稚魚を取り、大きく育ててから出荷しているが、産卵後成熟後期の夏以降にブリがやせてしまい、周年にわたって品質の良いブリを生産するのは困難だった。そこで、ブリの産卵時期は年1回だが、任意の時期に産卵させることができれば、周年を通して安定したサイズ・品質のブリができると考え、成熟誘導技術の開発を進めた。この任意の時期に産卵をさせる成熟誘導技術と、育種による優れた特性を持つブリを選別し次世代につなげることの組み合わせで、1年を通して育成のスピードが速く高品質のブリの出荷が可能となった。22年度には、黒瀬水産が出荷する「黒瀬ぶり」の全量が人工種苗によるものとなり、23年には年間200万尾の出荷を目指している。山下氏は「長年蓄積してきた高度な養殖の知見・技術によって、高度な養殖が実現するとともに、成熟誘導や種苗生産技術の開発により時期をずらしながら種苗を生産することで、完全養殖ブリの周年出荷が実現しました。世界を見てもこの養殖技術はニッスイの強みだといえます」と話す。ただ、生き物が相手なだけに、研究は困難の連続だ。現在は完全養殖を始めてから5世代目の育成を進めているが、養殖環境下で遺伝的な多様性を確保しながら改良を続けているという。「人工種苗100%の完全養殖を実現したことで、現在では年5回、時期をずらしながら種苗を生産できるようになりました。今後は成長性や安定した品質はもちろん、環境負荷の軽減も考えていかなくてはなりません」と山下氏は話す。その解決のために、飼料や魚の性質の改良を進め、環境負荷を低減する研究にも取り組んでいる。選抜育種と人工種苗の技術を磨いたことで、高品質なブリを夏場でも出荷できる強みにもなった。差別化した安定供給できる商品を増やしていくことは、水産市況の変動の影響を低減して、収益の安定化にもつながっている。 ●養殖技術を拡大し 新しい"食"の創造に貢献 ニッスイは養殖事業の拡大を長期ビジョン・中計の成長戦略のひとつに位置づけており、国内ではブリ以外にはギンザケの養殖にも注力している。ギンザケの場合は、淡水で約1年稚魚を育成してから、生育に適した海水温になった時期に海上のいけすに収容し、半年間飼育してから出荷される。大分海洋研究センターでは、ギンザケの稚魚が早く海水に適応できるようにする研究などにも取り組んでいる。また、ニッスイでは近年注目度が高まっている陸上養殖にも着手しており、20年に地下海水を利用したマサバの陸上循環養殖の実証実験を開始している。23年4月には「閉鎖式バイオフロック法」を用いたバナメイエビの陸上養殖を事業化した。世界的には人口増加や健康志向の高まりなどを受け、水産物の需要は右肩上がりに増加しているが、漁獲量自体は増えておらず、その増加分を補っているのが養殖だ。日本はかつて水産大国といわれ、長年天然の水産物の恩恵を受けてきたが、近年縮小する漁業生産を補う養殖の重要度は高まっている。水産資源の枯渇や持続可能性への懸念が指摘されるなか、効果的な漁業管理など適切な処置による漁業資源の維持や再生が重要になっている。食の安全や環境負荷の低減などの観点からも、ニッスイが養殖の研究開発を続ける意義は大きい。「ニッスイが取り組む以上、高いレベルの品質を維持して安全・安心を提供しないといけない。新しい"食"を創造するために研究開発を重視する方針を会社として守り続けているからこそ、今の養殖事業があります。養殖の研究は私にとってライフワークであり、人生を懸けて取り組むことにやりがいを感じています」と山下氏は語った。 *1-2-5:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1210627(佐賀新聞 2024/3/16)スミノエガキ養殖、海況改善へ 基幹のノリ漁不作で取り組み 佐賀県有明海漁協新有明支所青年部 有明海の海況が悪化して赤潮の発生が長期化するなどし、基幹漁業のノリ養殖の不作が続いている。環境改善へ、赤潮の発生原因となる植物プランクトンを捕食するスミノエガキの養殖に、佐賀県有明海漁協新有明支所(白石町)の青年部が取り組んでいる。河口域の低塩分に強く成長も早いため、漁業者の収益向上も期待できるという。取り組みが評価され、3月上旬の全国青年・女性漁業者交流大会で資源管理・資源増殖部門最高賞の農林水産大臣賞に選ばれた。スミノエガキは国内では有明海にのみ生息し、夏に大雨が降った後に産卵するなど淡水の流入による河口域の低塩分化にも強いとされる。成長が早く、マガキの養殖が一般的に出荷まで2年かかるのに対し、単年出荷が可能という。昭和30年代ごろまで養殖が盛んだったが、ノリ養殖の発展とともに衰退していた。有明海のノリ養殖は海況の悪化で生産が不安定になっており、新有明支所では色落ち被害が起き、2021、22年度の生産量は例年の半分以下に落ち込んでいる。同支所青年部(15人)はサルボウなど二枚貝の減少が要因の一つと考え、県有明水産振興センターからの提案を受け、スミノエガキの養殖に着手した。22年度は天然のスミノエガキを10~12月の2カ月半、はえ縄式の養殖施設でかごに入れて海中にカキを垂下したところ、むき身の肥満度が5%向上し、グリコーゲン量も1・3倍に増加した。海底では干潮時にプランクトンを捕食するが、海中につるすと潮の干満に関係なく常時捕食でき、身入りが良くなった。年明けにも再度養殖し販売した。23年度は単年養殖に取り組み、塩田川河口域で天然採苗にも成功して、間もなく収穫期を迎える。24年度は作業を軽減する機器を導入して、さらに養殖に取り組む予定という。取り組み開始時に部長を務めた木下祐輔副部長(35)は「海況を改善し、食べられて、収入にもなり『一石三鳥』。3、4月が旬で、3月中旬に終わるマガキと出荷時期が違うため、需要や価格面でも今後期待できるのでは」と話している。 *1-2-6:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1208602 (佐賀新聞 2024/3/13) 農業基本法改正 有事対応と活性化同時に 国際紛争の激化や気候変動などに対応する新たな農業政策を展開するため、政府は農政の在り方を示す食料・農業・農村基本法の改正案を閣議決定した。今国会で成立させ、食料供給システムの強化を図りたい考えだ。1999年の同法施行から実に25年になり、この間、国内外の情勢は大きく変化した。時代にふさわしい内容にするのは当然だ。打ち出した基本理念は「食料安全保障」。具体的には「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義した。有事に対応した備えは重要だ。だが足元を見ると、担い手の減少や高齢化の進展、農地の減少などによって日本農業の足腰が弱っていることは明白だ。ここを修復しない限り、どんな理念を掲げても内容を伴うことは難しいのではないか。農業が魅力ある産業となり、若者や都市在住者らの新規就農が促されなければならない。ITの活用によるスマート農業の進展や農地のさらなる集約、輸出環境の整備などによって現場を活性化させ、生産基盤の一層の強化に取り組むことが不可欠だ。これまでも取り組んできたが、今回の改正を機に改めてその重要性を認識し、取り組みを加速させたい。政府は今回の農政転換の背景として、地球温暖化の進行や、物流の途絶などを挙げ、食料供給量が大幅に不足するリスクが増大していると指摘した。確かにウクライナ危機による穀物相場の高騰や中東情勢の緊迫化による海運の混乱は、海外依存度が高い日本のアキレス腱(けん)をまざまざと見せつけた。日本のカロリーベースの食料自給率は38%で先進国の中で最低だ。専門家の間では相対的な経済力の低下などが影響し、世界市場での食料買い付け力が落ちてきたとの指摘もある。政府は基本法改正に併せて、食料安保政策を具体的に進める食料供給困難事態対策法案と農地法改正案も決定。困難事態対策法案は、気候変動に伴う穀物類などの主要産地の生産不安定化などを想定し、深刻度に合わせ、農業者への生産拡大要請など3段階の対応を規定した。国民が最低限必要とする食料が不足する恐れがある場合は、生産転換や割り当て・配給を実施し、実効性を担保するために違反や拒否には罰則も設けた。極端な例としては、花卉(かき)類を生産している農家に、イモなどカロリーの高い農作物を栽培するように強制するケースも想定できる。こうした対応を取らざるを得ないような状況は緊急事態だろうが、私権を制限することになるだけに、必要性や具体的な内容を丁寧に説明しなければならない。なぜここまでの想定をしなければならないのか、国会で十分に議論を尽くしてほしい。日本農業は潜在力を十分に発揮できているだろうか。稲作は国内需要を上回る供給力を持ちながら、減産で価格を下支えしてきた。食料供給の大幅不足が懸念されるというのなら、コメ生産能力のフル活用も考えたい。国内市場は縮小しているが、国内で消費できない分は輸出に回し、いざというときは国内に戻す構想は検討に値するのではないか。まずは日本米のさらなる海外市場開拓に官民の知恵を絞りたい。 *1-2-7:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1210513 (佐賀新聞 2024/3/16) 魚の養殖×野菜栽培、新たな農業模索 水を循環、CO2も活用 熊谷組が佐賀市で実証事業 佐賀市は、市清掃工場(高木瀬町)周辺で、ゼネコンの熊谷組(本社・東京)が実証事業を始めると明らかにした。清掃工場から出る二酸化炭素(CO2)を活用しながら、魚の養殖と野菜の水耕栽培を組み合わせた新しい農業「アクアポニックス」の事業化を目指す。アクアポニックスは、魚の養殖と植物の栽培を組み合わせた循環型農業。魚を養殖した水を、水耕栽培で再利用し、溶け込んでいる窒素やリンを植物が養分として吸収する。水は再び、養殖で使用するため水槽に戻す。化学肥料をやったり、土を耕したりする必要もなく、資源循環型のシステムとして注目を集めている。市バイオマス産業推進課によると、同社は既に佐賀市などから2人を雇用。4月下旬からマスを2千匹規模で養殖し、約40平方メートルの水耕ベッドで葉物野菜を育てる。CO2を活用することで脱炭素社会への取り組みを強化しながら、野菜の生育促進に役立てる。実証事業は6人体制で、少なくとも3年間実施する。量や質の確保、他社との差別化、販売ルートの確保などの観点で検証する。市は「資源循環の取り組みとして互いに共感することが多く、佐賀市のフィールドを選んでいただいたと感じている」と話す。 *1-2-8:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1205171 (佐賀新聞 2024/3/7) 爆発的繁殖力の外来水生生物 佐賀市、除去作業に苦慮 5年間で対策費倍増、農業被害も 爆発的な繁殖力で農業被害などをもたらす特定外来生物で水生植物の「ナガエツルノゲイトウ」や「ブラジルチドメグサ」が、佐賀市内のクリークや河川で繁茂を続けている。水位を調整する樋門や排水ポンプなどの機能に支障が出かねず、市は水面や根から除去し続けているが抜本的な解決策はない。対策費は2022年度に7154万円と、この5年間で倍増。一度除去しても残った部分から再生する力があり、堂々巡りの状況に市は苦慮している。ナガエツルノゲイトウは南米原産の多年生の浮遊植物で、長く折れやすい茎を持っている。河川やクリークに群生し、茎の切れ端からでも再生、繁殖するほか、長期間の乾燥にも耐える。一度農地に侵入すれば、農地を覆い、農作物の収量や品質、作業効率の低下を招く恐れもある。市内では2010年に初めて確認された。ブラジルチドメグサは15年に初確認。南米産の多年生の浮遊植物で扁平(へんぺい)な葉が特徴で、ナガエツルノゲイトウ以上に生育が速い。生育面積は把握できる農業用水路だけでも約10万平方メートルに拡大。ブラジルチドメグサが本年度初めて高木瀬地区で確認されるなど、まちなかにも広がっている。市農村環境課には農家から「ポンプの周りに繁茂し、支障が出ている」との相談が寄せられている。市は重機や人力で除去を行ったり、繁茂の激しい地区では、水路ののり面にコンクリートを張り付けたりと対策を行っている。一見、きれいに片付いたと思っていても、翌年にはびっしり繁茂したケースも。繁殖力の強さが、担当者を悩ませる。対策費も膨らんでいる。事業費(決算額)は、18年度の3540万円が22年度は7154万円と倍以上になった。市幹部の一人は「小中学校の給食費値上げ分を補助する費用を上回る額」とし、厳しい財政状況の中で対策事業が大きな負担となっていると指摘する。除去の相談が増えるのは例年、春先から。市は地元の協力も広げていこうと、「切れ端を回収する」「根から取り除く」といった市民への周知も始めた。市環境政策課は「繁茂が小規模な段階で、効果的に除去できるよう考えていきたい」とする。 *1-2-9:https://www.asahi.com/articles/ASS316T7WS29OXIE058.html (朝日新聞 2024年3月3日) 首都の「下水」が化学肥料に 東京都、全国普及へ国やJA全農と連携 化学肥料の原料価格が高騰し、国内農業に影を落としている。ほぼ全量を輸入に頼っている現状から抜け出そうと動き出した実験の現場は、農業に縁遠そうな東京。国と東京都は、巨大都市から大量に出る「下水」に目を付けた。農林水産省によると、化学肥料の主な原料となるリンを含むリン鉱石が国内では産出されないため、中国やモロッコなどからリン酸アンモニウムなどの形で必要量のほぼ全てを輸入している。しかし、ウクライナ危機や世界的な穀物需要の増加を受け、2022年に国際価格が急騰した。財務省貿易統計によると、リン酸アンモニウムの輸入価格は、同年7月には前年同時期の2・4倍に。23年以降、いったん下落したが、なお不安定な状況が続く。安定確保策として国が目を付けたのが、東京の「下水汚泥」だった。 *国と東京都は、下水汚泥から化学肥料の原料を取り出す実証実験を始めました。記事では、東京都が民間と共同開発した独自技術や、JAと組んで目指す全国普及について紹介します。 *1-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240225&ng=DGKKZO78735540U4A220C2TYC000 (日経新聞 2024.2.25) <サイエンスNextViews>危ういテクノロジー頼み 廃炉・温暖化、現実直視を 編集委員 矢野寿彦 原子炉3基が立て続けに炉心溶融(メルトダウン)した2011年の東京電力福島第1原子力発電所の事故。今も脳裏に焼き付く1枚の画がある。2号機取水口付近のピット(作業用の穴)から高濃度汚染水がじゃばじゃばと海へ流れ出る様子を伝えていた。おがくずや新聞紙、おむつに使われる吸水性ポリマーなどが大量に投入されるが、なかなか止水できない。流れる経路を調べるために使ったのは乳白色の入浴剤。あまりの「ローテク」な対応にあぜんとした。放射能の脅威を前に日本が誇ってきたはずの土木技術やロボット技術は敗北した。有事にはまったく使い物にならなかった。原子力ムラが築いた「安全神話」はもってのほかだが、この技術レベルでは安全神話なくして地震国での原発推進は難しかったともいえる。あれからまもなく13年。東電は24年1月末、23年度内に予定していた福島第1原発のデブリ(溶け落ちた核燃料)取り出し開始を三たび延期すると発表した。原子炉への貫通部が堆積物で埋め尽くされており、現状では英社と開発中のロボットアームが使えないことが判明したという。解せないのは3度目の延期ではない。釣りざお式という別の方法で24年10月ごろに数グラムの試験採取を目指すとしたことだ。過去に炉内調査で実績があるとはいえ、この方式は本格的な採取に移行できた場合に使うことを想定していないという。工程表にある「デブリ採取に着手」ありきと批判されても仕方ないだろう。1~3号機には推計880トンものデブリがあるという。どこにどのような状態で存在するかもわかっていない。すべてを取り出すことが技術的に可能なのか。無理だとしたら廃炉の「最終形」をどうするか。根幹に関わる議論が一向に進まないまま、多額のお金を投じて「全量取り出す」を前提に技術開発が進む。「地球沸騰」なる言葉がしっくりくるほど深刻化する気候変動の対策において、テクノロジーの進化で困難は乗り越えられると楽観するのも危うい。ここ数年、世界的な核融合フィーバーだが、発電に向けて技術は進化したのだろうか。それほどのブレークスルーは見当たらない。20年ほど前、日本とフランスが繰り広げた国際熱核融合実験炉(ITER)の誘致合戦を取材した。その際、核融合の世界にはこんなジョークがあることを知った。「あと50年、あと50年と言われ続けて50年」。太陽が膨大なエネルギーを生み出す核融合反応を地上で再現し安定的に発電するのは、永遠に「夢の技術」というわけだ。テクノロジーには原罪のように未知なる災禍の種子が蓄積されており、不可避的に突如はじける。仏思想家のポール・ヴィリリオ氏は著書「アクシデント 事故と文明」で技術文明が事故を発明する、と説いた。技術がもたらした危機は技術の力によって克服できる。こうしたテクノロジーの万能性への信仰は、廃炉にしろ温暖化対策にしろ、リスク回避の本質から目を背けていることになる。 *1-3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15880553.html (朝日新聞 2024年3月7日) (東日本大震災13年)原発 処理水、安全どう保つ 東京電力福島第一原発では処理水の海洋放出が始まり、敷地内のタンクが増え続ける状況が変化した。だが廃炉作業は足踏みが続き、終わりは見えないままだ。 ■放出作業、完了まで約30年 専門家「外部のクロスチェック必要」 処理水の海洋放出は、昨年8月24日に始まった。初年度の2023年度は、敷地内で保管しているタンクの水3万1200トンを4回に分けて放出する計画。24年度は、7回にわけて約5万4600トン分を流す。処理水は、汚染水を多核種除去設備(ALPS〈アルプス〉)に通し、大半の放射性物質を取り除いた後、トリチウムの濃度を1リットルあたり1500ベクレル(国の放出基準の40分の1)未満となるよう海水で希釈したもの。海底トンネルを介して沖合約1キロにある放水口から海に流す。処理水として放出するには、含まれる放射性物質が基準未満であることを確認する必要がある。ALPSではトリチウムを除去できないため、東電はまず、ALPSに通した後の水を分析し、トリチウム以外の29の放射性物質の濃度が放出基準を下回っているか確認する。さらに海水で希釈してトリチウムの濃度を薄める。放出直前の分析では、トリチウム濃度が基準未満かを確認。この水を蒸留させるなどして測定の邪魔になる不純物を取り除いた後、放射線を受けると発光する試薬を使い、光量から濃度を換算するという。第三者による分析は、日本原子力研究開発機構(JAEA)が担う。放出後も、東電や国、福島県が周囲の海水のモニタリングをする。東電は、トリチウム濃度が放水口近くで1リットルあたり700ベクレル、沖合10キロ四方で同30ベクレルを超えると放出を止めることにしている。これまでの分析結果は同22ベクレルが最大値で、すべて下回っている。海産物については、水産庁が放水口の南北数キロに設置した刺し網で捕獲したヒラメなどのトリチウム濃度を測定している。これまで、放出を停止するような異常な値は確認されていない。福島第一原発周辺の放射線測定を続けている小豆川勝見・東京大助教(環境分析化学)は、放出開始後の昨年10月に沿岸の海水や魚について、トリチウムを含む複数の核種の測定をして、異常値は検出されなかったという。「処理水の放出は1、2年で終わることではなく、これから何十年と続く。いつまで緊張感を維持して作業を続けていけるかが課題。外部の専門家などによるクロスチェックが必要ではないか」と話す。東電によると、処理水の放出は30年ほど続く見込み。年間22兆ベクレルを上限に、廃炉完了の目標時期とする51年までに終えるよう放出のシミュレーションを示している。今も福島第一原発には、汚染水をALPSに通した後の水を保管するタンクが1千基以上ある。処理水の放出によって保管する水の量が減り始めたとはいえ、溶け落ちた核燃料(燃料デブリ)を冷やす水に地下水や雨水が加わることで汚染水は発生し続けている。汚染水対策はこれからも続く。 ■停滞する廃炉、見通し立たず 燃料デブリ取り出し、3回延期 今年度の廃炉作業では、汚染配管の撤去などは進んだものの、原子炉建屋の内部について大きな進展はなかった。作業の延期もあり、先行きはまだまだ見通せない。最も難航しているのは、廃炉作業の「本丸」といわれる溶け落ちた核燃料(燃料デブリ)の取り出しだ。1~3号機で計約880トンあると推計されているが、事故から13年が経とうとしている今も、1グラムも取り出せていない。まず2号機で数グラム程度の試験的な取り出しを始める予定だが、東電は今年1月、今年度中の着手を断念すると発表した。デブリを取り出すロボットアームの動作精度不足などが理由で、延期は3回目。当初は2021年の予定だった。改良に時間がかかることから、今年10月までに「釣りざお式装置」を使って取り出しをはじめる方針に切り替えた。ただ、釣りざお式で採取できるのは限られた範囲だけで、大規模な取り出しには役に立たない。ロボットアームを使った取り出しも24年度末までに着手するとしているが、不透明だ。本格的なデブリの取り出しについては、使用済み燃料の移動が済んでいる3号機から始める計画。廃炉のための研究や技術開発、助言をする原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)が工法を検討している。NDFはこれまで、現状のままデブリ取り出し作業を進める「気中工法」と、原子炉建屋全体を鋼鉄の構造物で囲って建屋ごと水没させてから取り出す「冠水工法」を検討していたが、コンクリートなどの「充填(じゅうてん)材」を流し込み、固めてから掘削装置を使って削り出す「充填固化工法」を新たに検討するという。専門家でつくる小委員会が、三つの案の実現可能性などを整理した提言を近くまとめる予定だ。1号機については、使用済み燃料の取り出しに向け、建屋全体を覆う大型カバー設置の準備を進めているが、設置完了目標は23年度中から25年夏ごろに延期された。1号機では、原子炉圧力容器を支える台座の下部が全周にわたってコンクリートが失われ、鉄筋がむき出しになっていることが判明している。東電は、耐震性は保たれており、仮に原子炉圧力容器が沈み、格納容器に穴が開いたとしても敷地境界での被曝(ひばく)線量は「極めて軽微」と評価する。ただ、時間とともに老朽化が進むため、楽観はできない。 *1-3-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1205783 (佐賀新聞 2024/3/8) 福島原発事故13年 原発のリスク再認識を いまだに被災者に大きな影響を与え続けている東京電力第1原発事故から13年になる。この間に大きく動いた世界のエネルギーを取り巻く状況を見つめ、原発が抱えるリスクを改めて心に刻む日としたい。目指すべきは、高コスト、高リスクの大規模集中型電源から、しなやかで低コストの再生可能エネルギーを主とする分散型システムへの転換だ。この間のエネルギーを巡る動きを特徴付けるものの一つは化石燃料依存のリスクが鮮明になったことだ。石炭などからの二酸化炭素(CO2)がもたらす気候危機は「地球沸騰時代」と言われるまでに深刻化した。ロシアのウクライナ侵攻の影響で化石燃料価格は急騰、エネルギー関連の輸入額は三十数兆円に上り、多くの企業や市民が高騰の影響を受けている。一刻も早い脱炭素電源の実現が求められる。もう一つの特徴は急速に価格が低下している太陽光や風力発電の急拡大と発電コストや建設費の増大が招いた原子力発電の停滞だ。国際シンクタンクの調査によれば、原発の電力が世界の総発電量に占める比率は1996年の17・5%をピークに減少傾向が続き、2022年には9・2%で過去40年間で最低だった。多くの国が低コスト、低リスクで、導入までの時間が短い再生可能エネルギーを増やし、変動する電源を安定的に利用する技術や政策の実現を急いでいるのは当然だ。だが、自公政権のエネルギー政策はこの流れに逆行してきた。岸田文雄首相は気候変動対策としての原発推進を打ち出した。だが、気候危機対策では短期間に大幅なCO2排出削減が求められ、「今後10年が気候危機の将来を左右する」といわれる。新設はもちろん再稼働にも長期間を要する原発を重視する気候危機対策は非合理的だ。1基で100万キロワットを超える大規模な電源が自然災害によって一瞬にして失われることの影響の大きさを原発事故は教えた。能登半島地震で北陸電力志賀原発の再稼働の見通しがまったく立たなくなったことからも、原発が電力の安定供給に貢献するとの言説も疑わしい。日本政府や電力会社は、水素やアンモニアを利用して「CO2を出さない火力」を目指すことに注力している。だが、高コストで技術的課題が山積するこの手法が有効な気候変動対策となり得ないと指摘されている。限られた資金や人材の多くを原発や不確実な将来の新技術に投じたため、日本国内の再エネ市場は、他国に比べて大きく見劣りする結果となった。今になって大規模な洋上風力発電の開発を進めようにも、風車は輸入に頼るほかない状況で、小さな日本の市場が海外の投資家や企業から見向きもされなくなる懸念が示されている。政府は間もなく、エネルギー基本計画の見直しに着手する。世界の主流から後れを取った日本のエネルギー政策を根本から見直し、大転換を実現する最後のチャンスと言えるかもしれない。そのためには、経済産業省が指名した委員による委員会で、役所のシナリオに沿って政策を決めるという非民主的な手法を見直し、科学とデータに基づき、多くの市民や専門家の意見を聞きながら民主的な政策議論を進める「政策決定手法の大転換」も重要だ。 *1-3-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/317278 (東京新聞 2024年3月25日) 志賀原発の敷地が平均4センチ沈んでいた 能登半島地震で 北陸電力は「影響はない」と説明 北陸電力は25日、能登半島地震後に志賀原発(石川県志賀町)の敷地内を測量した結果、地震前と比べ平均4センチの沈下を確認したと発表した。北陸電はオンラインの記者会見で「変動は小さく(安全確保に)影響はない」と説明した。 ◆隆起した地点はなかった 北陸電によると、測量した11カ所の沈下幅は4.74センチ~3.82センチで、隆起した地点はなかった。原子炉を冷却する海水の取水口に近い物揚げ場は3.96センチの沈下だった。また、敷地全体が西南西方向に平均12センチ動いていた。敷地内の地面に生じた段差や割れを約80カ所で確認。ほとんどが土を盛ったり埋め戻したりした場所で発生していた。担当者は「舗装が変形したためで、敷地内の断層が動いた形跡はない」と話した。能登半島地震では半島北側の沿岸一帯が隆起し、輪島市西部では最大4メートルに上った。地元住民によると、志賀原発から1キロほど北の岩ノリの漁場が数十センチ隆起したという。志賀2号機は新規制基準への適合性の審査中。北陸電の申請内容では、地震で原発北側の輪島市付近の断層が動いた場合、20センチ以下の隆起が起きると想定し、その場合でも冷却水の取水に影響は出ないと主張している。 *1-3-5:https://www.tokyo-np.co.jp/article/307026 (東京新聞 2024年2月3日) 断層上にある志賀原発は「次の地震」に耐えられるか 能登半島地震で高まった巨大地震発生リスク マグニチュード(M)7.6を記録し、200人余が犠牲となった能登半島地震。発生から1カ月たつ中、拭い去れない危惧がある。次なる地震だ。先月、半島北側の断層が大きく動いた影響で、周辺の断層も動く可能性があると指摘されている。懸念が強まるのが北陸電力志賀原発(石川県志賀町)。立地する半島西側は活断層が少なからず存在する。現状にどう向き合うべきか。 ◆震度5強以上の発生確率「平常時の60倍」 「いずれ志賀原発の近くでも大きな地震が来るんじゃないか」。能登半島の東端に位置し、先月の地震で甚大な被害が生じた珠洲市の元市議、北野進氏はそう語る。この3年ほど、能登半島は群発地震が活発化した。地震の規模が少しずつ大きくなっていたところに今回の大地震に見舞われた。そんな経緯がある中、志賀原発差し止め訴訟の原告団長も務める北野氏は「次の地震」に気をもむ。先の地震から1カ月を過ぎ、余震の数は減った。ただ気象庁は1月末に「今後2〜3週間程度、最大震度5強程度以上の地震に注意を」と呼びかけ、その発生確率は「平常時の60倍程度」と付け加えた。 ◆周囲100キロ以内で「地震活動は活発に」 研究者らも懸念を示す。先の地震は能登半島の北側で東西約150キロにわたって断層が活動したとされる。東北大の遠田晋次教授(地震地質学)が周辺の断層に与えた影響を計算したところ、今回動いたエリアの両脇、具体的には能登半島東側の新潟・佐渡沖、半島西側の志賀町沖の断層で今後、地震が発生しやすくなったという結果が出た。遠田氏は「佐渡島周辺や志賀町沖などで体に感じないほどの小さな地震が増えている。何らかのひずみが加わったサインだ」と解説する。「今後の地震の発生時期や規模は分からないが、陸地を含めて周囲100キロ以内の地震活動は活発になっており、しばらく警戒が必要だ」と説く。 ◆「流体」今回の地震のトリガーに? 「流体」の存在も気にかかるところだ。能登半島で起きた近年の群発地震は、地下深くから上昇した水などの流体が原因とされる。断層帯にある岩盤の隙間に流体が入り込み、潤滑油のように作用することで断層がずれやすくなったと考えられてきた。「流体が今回の地震のトリガーとなった可能性がある」と話すのは金沢大の平松良浩教授(地震学)。 今後も流体が断層活動を引き起こすのか。 ◆「地震を起こしやすくする力がかかった」 平松氏は「現時点では分からない」との見方を示す一方でこう続ける。「今回の地震によって、能登半島の西側を含め、北陸一帯の多くの断層帯に地震を起こしやすくする力がかかったことが分かっている。マグニチュードで7クラスの大地震発生のリスクは相対的に高くなった」。次なる地震で心配なのが志賀原発だ。立地するのは能登半島の西側。地震が起きやすくなったとも。原発の周辺は、活動性が否定できない断層が少なくない。北陸電の資料を見ると、原発の10キロ圏に限っても陸に福浦断層、沿岸地域に富来(とぎ)川南岸断層、海に兜岩沖断層や碁盤島沖断層がある。次なる地震に原発は耐えられるか。北陸電の広報担当者は、地震の揺れの強さを示す加速度(ガル)を持ち出し「原子炉建屋は基準地震動600ガルまで耐えられ、今回の地震による地盤の揺れは600ガルよりも小さかった。さらに2号機については1000ガルまで耐えられると新規制基準の審査に申請している。原子力施設の耐震安全性に問題はない」と話す。 ◆「想定を超えた」北陸電の言い分 北陸電の言い分はうのみにしづらい。そう思わせる過去があるからだ。同社が能登半島北側の沿岸部で想定してきた断層活動は96キロの区間。だが先の地震では、政府の地震調査委員会が震源の断層について「長さ150キロ程度と考えられる」と評価した。なぜ想定を超えるのか。「海底の断層を調査する音波探査は、大型の船が必要。海底が浅い沿岸部は、調査の精度が落ちる。近年は機器が改良され、小型化されたが、特に日本海側は調査が行き届いていない」 ◆現行の技術水準では全容捉えがたく こう指摘するのは新潟大の立石雅昭名誉教授(地質学)。陸の断層も「地表に見える断層が数キロ離れていても、地下で一つにつながっているかもしれない」。現行の技術水準では捉えがたい活断層の全容。それだけに安心もできない。志賀原発周辺で注目すべき一つは、北に約10キロの距離にある富来川南岸断層。この断層の全容は見方が割れる。北陸電の資料では陸域を中心に長さ9キロと書かれる一方、研究者からは、海まで延びる可能性を指摘する声が上がってきた。脅威の程度が捉えづらいこの断層。再評価を求めるのが名古屋大の鈴木康弘教授(変動地形学)だ。 ◆地表のずれとたわみ、志賀町内に点在 先の地震後に志賀町内を調べ、富来川南岸断層とみられる地表のずれやたわみが点在しているのを確認した。「1970年代から推定されていたが、今回の痕跡でより確度が高まった」。鈴木氏は「今後の活動が必ずしも迫っているとは思わない」と慎重な見方を示しつつ、「先の地震では、能登半島北西部の沿岸の断層がどのような動きをしたのかは分かっていない。今までの知見に頼らず、断層の評価を検討し直す必要がある」と語る。志賀原発の近くにあり、多大な影響を及ぼしかねない富来川南岸断層。同様に再検証が必要なのが、原発の西4キロの海域で南北に延びる兜岩沖断層という。北陸電の資料によれば、「活動性が否定できない」とされ、長さは4キロとある。 ◆「計算するまでもなく原発はもたない」地盤がズレたら… 鈴木氏は「本当にこの長さか。今回の地震で、沖合に長い断層があることで隆起が起きることが改めてわかった。原発付近も海岸に同様の隆起地形があることから、長い断層がないと説明できない」と訴える。原発に及ぶ地震の脅威でいえば、揺れ以外にも思いを巡らせる必要がある。地盤のズレもだ。元東芝原発設計技術者の後藤政志氏は「メートル単位で上下や水平方向にズレが生じたら、計算するまでもなく原発はもたない」と指摘する。原発は、揺れの大きさに対して耐震設計基準が示されている一方、地盤のズレなどにより「原子炉建屋が傾いたり、損壊したりすれば壊滅的な被害となる」。配管にズレが生じると取水できず、核燃料を冷却できなくなる可能性もある。 ◆手放しで安心できぬ規制委の判断 志賀原発は2012年、直下に断層があり、これが動いて地盤のズレが生じうると指摘された。原子力規制委員会は昨年、直下断層の活動性を否定する北陸電の主張を妥当と判断した。ただ、手放しで安心できるかといえば、そうではないと後藤氏は説く。「周囲の断層が起こす地震によって、直下断層の動きが誘発される恐れもある」。地震リスクの懸念が拭い去れない志賀原発。いま、何をすべきか。龍谷大の大島堅一教授(環境経済学)は「原発が止まっているとはいえ、核燃料がプールで保管されている。金属製のキャスクに移すなどの対策が必要ではないか」と述べ、災いの元凶になりうる核燃料の扱い方について早急に議論するよう求める。地震リスクは他の原発にも潜むとし「現状で動いている原発も止めた上で断層の再評価など規制基準の見直しが必要だ」と訴える。 ◆デスクメモ 被災した方々を考えると、次の地震が起こらないよう願うばかり。ただ核燃料は、まだ志賀原発に。プールは揺れやズレに耐えられるか。搬出すべきか。それは可能か。事が起きた時、被災地に残る方々が避難できるのか。願うばかりでは心もとない。どう備えるかの議論も必要では。 *1-3-6:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1206413 (佐賀新聞 2024/3/8) 玄海原発3、4号機 基準津波を修正へ 九州電力が政府の調査結果を反映 九州電力は8日、原子力規制庁との会合で、玄海原発3、4号機(東松浦郡玄海町)の基準津波を修正する方針を明らかにした。政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が2022年に公表した日本海南西部の海域活断層長期評価を踏まえて検討した結果、想定される津波が既存値を上回ることが分かったという。7月をめどに原子炉設置変更許可を申請する見通し。地震本部が公表した日本海南西部の海域活断層長期評価では、九電が玄海原発3、4号機の再稼働に当たって検討したものとは異なる断層の評価が指摘されている。このうち、対馬南西沖断層群と第1五島堆断層帯が連動したケースでは、想定される津波の高さが6・37メートル、低さはマイナス2・65メートルとなり、現行の基準津波(高さ3・93メートル、低さマイナス2・6メートル)をいずれも超える値となった。一方、基準地震動への影響はないという。今後は、基準津波の修正に関する原子炉設置変更許可を申請するが、玄海原発の敷地の高さは約11メートルであることや、取水位置などの低さ(マイナス13・5メートル)も想定される津波に対して余裕があることから、現時点で設備面での変更や追加工事は発生しない見通しだという。 *1-3-7:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1206983 (佐賀新聞 2024/3/10) <佐賀県内首長原発アンケート>玄海原発運転継続、15市町長「条件付き賛成」 最終処分場は全員「受け入れず」 佐賀新聞社が佐賀県内の知事と市町の首長を対象に実施した原子力政策に関するアンケートで、玄海原発(玄海町)の運転継続について15市町長が「条件付きで賛成」と回答した。反対はゼロだった。原発の今後に在り方に関し、「将来的に廃止」としたのは16市町長だった。原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場は全員が受け入れない考えを示した。玄海原発の立地町の脇山伸太郎玄海町長は、運転継続に唯一「賛成」と回答した。「国のエネルギー基本計画にのっとって、エネルギーミックスによる原発の割合を維持していくべき」という認識を示した。山口祥義知事は賛否の選択肢は選ばなかった。「原発への依存度を可能な限り低減し、再生可能エネルギーの導入を進める取り組みを積極的に行うべき」としつつ「一定程度、原発に頼らざるを得ない現時点においては、県民の安全を何よりも大切に、玄海原発と真摯(しんし)に向き合い続けていく」と回答した。「条件付き賛成」を選んだ首長は、その条件として「電力事業者、国の責任で安全性を追求し、可能な限り情報公開に努めてもらうこと」(村上大祐嬉野市長)、「使用済み核燃料の処理方法について国の責任で対策を講じること」(江里口秀次小城市長)などを挙げた。「どちらともいえない」とした深浦弘信伊万里市長は「事故が発生すれば取り返しがつかないことになるため基本的に反対の立場だが、電力は企業活動や市民生活を支える基礎的なインフラで安定的な供給は不可欠であり、原発を止められない現実がある」との認識を示した。原発の今後で「将来的に廃止」を選択した首長からは、「カーボンニュートラルの実現に向けて取り組む」(向門慶人鳥栖市長)、「再生可能エネルギーの導入を進めて原子力への依存度を下げていく」(松尾佳昭有田町長)などの見解が示された。原子力政策全般の課題に関し、岡毅みやき町長は能登半島地震を踏まえて「南海トラフ地震を含めた対策を一から見直すことも重要課題。代替エネルギーの研究も加速させるべき」と回答した。「住民の不安払拭(ふっしょく)のためにより一層の情報公開」(松田一也基山町長)「住民や近隣市町に課題を丁寧に説明し、安心して生活を送れるように努めてほしい」(永淵孝幸太良町長)といった注文もあった。アンケートは、官製談合事件で内川修治市長が逮捕、起訴されて不在の神埼市を除く20首長が回答した。 *1-3-8:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1206979 (佐賀新聞 2024/3/10) <佐賀県内首長原発アンケート>7市町長、玄海原発の避難計画見直し「必要」 能登半島地震で課題浮上 東京電力福島第1原発事故から13年になるのに合わせ、佐賀新聞社は佐賀県の山口祥義知事と各市町の首長に、九州電力玄海原発(玄海町)の在り方や原子力政策に関するアンケートを実施した。元日の能登半島地震を受けて原発の重大事故時の避難ルートなどが課題に挙がる中、7市町長が現行の避難計画を「見直す必要がある」と回答した。他の自治体の首長も、見直しの動きを注視している姿勢がうかがえた。アンケートには首長20人が回答した。官製談合事件で内川修治市長が逮捕、起訴された神埼市は、市長不在として無回答だった。能登半島地震では北陸電力志賀原発(石川県志賀町)の周辺で道路の寸断や家屋倒壊などが相次ぎ、避難と屋内退避の実効性が改めて問われた。原子力規制委員会は、住民避難などをまとめた原子力災害対策指針の見直しに着手している。アンケートで避難計画の見直しを「必要」としたのは、多久、武雄、鹿島の3市長と吉野ヶ里、みやき、有田、江北の4町長。横尾俊彦多久市長は「あらゆるリスクや課題を想定し、万全を期した対策を充実することが最重要」、松尾勝利鹿島市長は「避難が現計画で対応できるかなど再検討の必要がある」とした。他の12首長は「その他」を選び、原子力災害対策指針の見直しの動向を踏まえて「(規制委の)今後の議論を注視したい」(坂井英隆佐賀市長)といった意見が多かった。「現行の計画のままでよい」はゼロだった。武広勇平上峰町長は選択しなかった。玄海原発が立地する玄海町の脇山伸太郎町長は「新たな指針などが示された後、検討を加え計画の見直しが必要な場合は修正する」との考えを示した。隣接自治体の峰達郎唐津市長は「必要性に応じ、市民の生命と財産を守るために速やかに対応する」と答えた。山口知事は「(規制委の)議論の結果など、能登半島地震から得られた意見や気付きを検証し、避難計画の実効性を高めていく」と回答した。 <歳出改革の理念2←人口構造と高齢化社会≠高齢者への給付減・負担増> *2-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240120&ng=DGKKZO77825980Z10C24A1EA1000 (日経新聞 2024.1.20) 公的年金、来年度2.7%増 0.4%分目減り 物価伸びより抑制 物価や賃金の上昇を受けた2024年度の公的年金額は前年度比で2.7%増額となり、1992年度以来32年ぶりの伸びとなった。年金財政の安定のために支給額を抑える「マクロ経済スライド」により、物価の伸びには届かなかった。同スライドはデフレ下で何度も発動が見送られており、抑制の長期化で将来の給付額が想定より減る懸念が高まっている。厚生労働省が19日、24年度の支給額を発表した。4、5月分をまとめて支給する6月の受け取り分から適用する。自営業者らが入る国民年金は40年間保険料を納めた場合、68歳以下の人は1人当たり1750円増の月6万8000円になる。厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯は、6001円増の月23万483円になる。モデル世帯は平均的な収入(賞与を含む月額換算で43万9千円)で40年間働いた夫と専業主婦のケースを指す。年金額は直近1年間の物価変動率と過去3年度分の実質賃金の変動率をもとに、毎年4月に改定する。23年度は厚生年金で月22万4482円、同年度に67歳以下の人の国民年金で月6万6250円だった。支給額は2年連続で増えたが物価や賃金の上昇分に届いていない。物価や賃金の伸びよりも支給額を抑えるマクロスライドの影響で、国民年金は実質年3600円ほど、厚生年金では同1万1500円ほど目減りする。24年度の物価や賃金を反映した改定率は3.1%だった。23年の物価上昇率(3.2%)と20~22年度の名目賃金変動率(3.1%)を考慮し賃金が物価を下回ったため賃金の変動率を採用。そこからマクロスライドによる0.4%分の抑制分を差し引き、最終的な改定率は2.7%となった。公的年金は現役世代から集めた保険料を高齢者に給付する仕組みのため、少子高齢化が進むと年金財政の維持が難しくなる。このためマクロスライドで支給額を抑えている。だが物価や賃金が下落するデフレ下では発動しないルールのため、2004年に導入されてからの20年間で4回しか発動されていない。支給額の抑制が想定より遅れると、マクロスライドを発動させる期間が長期化し、将来の給付水準が過度に低下する。特に基礎年金の抑制は現行のままなら、46年度まで続く見通しだ。この結果、現役男性の平均手取り収入に対する年金額の比率を示す基礎年金の「所得代替率」は、19年度の36.4%から46年度には26.5%と約3割も低下する見通しだ。25年は5年に1回の年金制度改正の年にあたり、24年中に具体的な改革案が示される。厚労省の審議会では財政に余裕のある厚生年金が基礎年金に資金支援して、給付水準の抑制を前倒しで終了する案が出た。就労を促進して高齢者の手取り収入を増やす方向の改正も議論されている。一定の所得のある高齢者の年金支給を減額する在職老齢年金制度も見直しを求める声が強い。老後の収入を充実させるために、個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)など私的年金の活用促進も重要になる。ニッセイ基礎研究所の中嶋邦夫上席研究員はマクロスライドについて「抑制期間の長期化を防ぐために、賃金や物価の下落局面でも毎年スライドを発動させるための議論が必要だ」と指摘する。 *2-1-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15842823.html (朝日新聞 2024年1月20日) 公的年金、実質目減り 物価上昇率下回る2.7%増 来年度 公的年金の2024年度の支給額は、物価や賃金の上昇を反映して23年度より2・7%増えることが19日、決まった。増額は2年連続。ただし、物価上昇率よりは低く、将来世代に向けて今の年金を抑制する措置も2年連続で発動され、実質的な価値は下がる。年金額は毎年度、物価や賃金の変動を反映して、改定される。今回は、名目賃金の上昇率3・1%が、前年の物価上昇率3・2%より低く、賃金の変動幅に応じて改定される。さらに労働者数の減少や高齢化の影響による「マクロ経済スライド」も2年連続で発動されるため、0・4%分を差し引いた2・7%のプラス改定となる。上昇率は1992年度の3・3%に次ぐ高さとなった。支給額は人によって異なるが、自営業者やパート・アルバイトの人らが入る国民年金の月額(40年加入の1人分)だと、前年度より1750円増えて6万8千円。24年度中に69歳以上になる人なら、1758円増えて6万7808円。年額で初めて80万円を超えた。会社員や公務員などの厚生年金では、「平均的な給与で40年間働いた夫と専業主婦の妻の2人分」のモデル世帯で計算すると、前年度より6001円増えて、23万483円になる。本来、年金はインフレで物価が上がっても、買えるものが減らないように給付(支出)を引き上げる必要がある。ただし、年金の「お財布」に入る保険料(収入)は、賃金が上がれば増え、下がれば減る。もし物価上昇が賃金上昇を上回ると、支出が収入を上回り、財政が悪化してしまう。今回の改定では、物価の上昇率(3・2%)と、名目賃金の上昇率(3・1%)を比べ、低い方の賃金を改定率計算に用いた。少子高齢化の日本で、将来世代の年金を確保するには、さらなる措置が必要になる。保険料を払う現役世代は減り続ける一方、年金を受け取る人たちの高齢化が進む。その影響を織り込んで給付を抑える仕組みが「マクロ経済スライド」だ。今回の改定では、この分で0・4%マイナスになる。この仕組みは04年の年金改正で導入されたが、デフレ下では十分に機能せず、今回がようやく5回目の発動となった。 *2-1-3:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?R_FLG=1&b=20240120&be=・・=DEA2000 (日経新聞 2023/8/19) 続く物価高、消費に影 生鮮・エネ除く指数4.3%上昇、食品高止まり、宿泊料伸び拡大 賃上げは追いつかず 物価の上昇圧力が続いている。7月の消費者物価指数は生鮮食品とエネルギーを除く総合指数が前年同月比4.3%上昇し、伸び率は再拡大した。食品や日用品の値上がりは家計を圧迫し、消費は伸び悩む。物価上昇と賃上げの好循環はなお遠く、景気回復の勢いも弱まりかねない。総務省が18日発表した7月の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.1%上昇した。伸び率は6月の3.3%から縮んだものの、日銀が掲げる2%の物価目標を16カ月連続で上回る。価格が変動しやすい品目をさらに除いた指数をみると、物価上昇はむしろ勢いを増す。生鮮食品とエネルギーを除く総合指数は前年同月比4.3%プラスで、2カ月ぶりに伸びを拡大した。消費者物価は2023年度の後半にかけて鈍化するとの見方もあるが、現時点ではまだピークアウトしたとは言えない状況にある。最大の要因は、全体の6割を占める食料の高止まりだ。7月はハンバーガーが前年同月比で14.0%上昇した。10%超えは13カ月連続。プリンは27.5%プラスで、6月の12.6%から伸び率が拡大した。米欧に遅れた価格転嫁の波が続いている。宿泊料は15.1%プラスと、6月から10ポイントほど伸び率を拡大した。インバウンド(訪日外国人)の回復などによる需要の高まりに、政府の観光支援策「全国旅行支援」が今夏以降に各都道府県で順次終了したことが重なった。ほかのサービスも上昇に弾みがついた。携帯電話通信料は10.2%プラスと統計上さかのぼれる01年以降で過去最高の伸び率となった。NTTドコモが7月から新料金プランを投入したことが背景にある。日銀は7月、23年度の生鮮食品を除く物価上昇率の見通しを2.5%に引き上げた。4月の段階では1.8%とみていた。物価上昇率が11カ月連続で3%を超えて推移するなど、物価高が想定を超えて続いている。SMBC日興証券の宮前耕也氏は「日銀も市場関係者もウクライナ侵攻による輸入物価上昇のインパクトを読み違えた」とみる。過去の物価高局面と異なり「一度ではコストを転嫁しきれず、複数回値上げする動きを読み切れなかった」と説明する。長引く物価高で消費への下押し圧力は強まっている。総務省の家計調査によると、2人以上の世帯の6月の消費支出は実質で前年同月比4.2%減った。マイナスは4カ月連続だ。品目別に見ると、物価上昇の大きな要因となっている食料が3.9%減で、9カ月連続のマイナスとなった。プリンやハンバーガーといった値上げが目立つ品目ほど消費は細っている。6月の実質消費支出はそれぞれ15.4%、13.5%減った。逆に、電気代は燃料価格の低下や政策効果による価格下押しで支出が5.9%増えている。外食は1.8%増とプラスを維持するものの、5月(6.7%増)から伸びを縮めた。サービス消費は新型コロナウイルス禍からの正常化で回復期待が高かったわりには動きが鈍い。勢いを欠く消費は経済成長に水を差す。23年4~6月期の実質国内総生産(GDP)は季節調整済みの前期比年率6.0%増と高い成長率となったものの、けん引役は復調した輸出などの外需だった。個人消費は物価高を受けて前期比0.5%減に沈んだ。23年の春季労使交渉の賃上げ率は30年ぶりの高水準だったとはいえ、物価の伸びには追いついていない。24年以降に賃上げが息切れすれば、家計の購買力の低下を通じて再びデフレ圧力が強まるとの懸念がにじむ。実際、コロナ禍前の19年10~12月期と足元を比較すると、雇用者報酬は実質で3.5%減っている。高止まりする物価に賃金が追いつかず、消費はほとんど伸びていない。日米欧では米国だけが賃金と消費を伸ばす。秋以降は物価上昇が加速する恐れもある。政府が実施しているガソリンや電気・都市ガスの価格抑制策は延長措置がなければ、ともに9月分で終了する予定だ。第一生命経済研究所の新家義貴氏はガソリン価格抑制の補助金事業が終われば、10月以降の生鮮食品を除く消費者物価指数を0.5ポイント押し上げるとみる。総務省は電気・都市ガスの価格抑制策が7月の物価の伸びを1ポイントほど押し下げたと推計する。対策が終われば、単純計算で1.5ポイントの上昇圧力となるリスクがある。高い物価上昇率は金融政策の議論にも影響を与える。日銀は物価の安定には「まだまだ距離がある」(植田和男総裁)とみて、金融緩和を続けている。ただ、物価上昇の勢いがこのまま衰えなければ、現状の金融緩和策の見直しが焦点となる。 *2-1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240403&ng=DGKKZO79748190S4A400C2EA2000 (日経新聞 2024.4.3) 医療・介護費、40年以降急増 60年度にGDP比6割増、政府が初試算、DXで効率化急務 内閣府は2日、2060年度までの社会保障費と財政状況の試算を公表した。医療と介護の給付費の国内総生産(GDP)に対する割合は40年度以降に上昇ペースが速まる。社会保障制度を維持するにはデジタル化による効率改善や成長率引き上げなどが急務となる。内閣府によると社会保障と財政に関する60年度までの長期推計をまとめたのは初めて。同日の政府の経済財政諮問会議に資料を提示した。岸田文雄首相は会議で「実質1%を上回る成長により力強い経済を実現するとともに、医療・介護給付費のGDP比の上昇基調に対する改革に取り組む」と強調した。試算結果をみると医療・介護の給付費は65歳以上人口がピークアウトする40年度ごろから増加の勢いが増す。高齢者人口の全体数が減少に転じても、医療や介護の利用が多い85歳以上の人口は継続的に増えるためだ。国立社会保障・人口問題研究所による最も実現性が高いケースの推計では40年の1006万人が60年には2割弱多い1170万人になる。試算は25~60年度までの平均実質成長率について(1)0.2%ほどの現状維持ケース(2)1.2%ほどの長期安定ケース(3)1.7%ほどの成長実現ケース――の3シナリオに分けてまとめた。給付費は現状維持ケースで最も高くなる。医療と介護を合わせた名目GDPに対する割合は60年度に13.3%と19年度より6割上がる。成長実現ケースでも60年度に9.7%と2割弱の増加が避けられない。医療の技術革新が加速すれば給付費は一段と膨らむ。試算では高額医薬品などの登場による医療費の拡大が従来の2倍ペースにあたる年率2%で進む場合、GDP比は現状維持ケースで60年度に16.1%まで高まり、19年度の2倍近くなる。経団連の十倉雅和会長ら諮問会議の民間議員は試算を基に成長率などの数値目標を定め、実現に必要なこの先3年程度の政策パッケージをまとめるよう求めている。社会保障制度の健全性を保つには歳出改革が必須条件となる。内閣府は毎年度の社会保障費を高齢化による伸びの範囲に収め、医療の高度化による増加をカットする改革を実施した場合の姿も示した。この改革を徹底する前提で成長実現ケースにあてはめると、60年度の給付費はGDP比8.2%と19年度と同水準には抑えられる。歳出改革は足元でもおぼつかない状況で、将来も続けられるかは見通せない。政府は23年12月公表の改革工程素案に介護保険サービスを利用する際の2割負担の対象者を24年度に拡大すると盛ったものの、与党からの反対などを受けて見送った。政府は社会保障の歳出改革を通じて少子化対策による実質的な負担増は回避すると主張する。介護負担拡大の先送りのような事例が続けば実現は遠のく。現役世代の負担が重いままでは結婚や出産をためらわせる要因にもなりえる。歳出抑制につながる施策の一つはデジタルトランスフォーメーション(DX)による医療・介護サービスの効率化だ。マイナンバー保険証での受診を促して投薬情報を共有しやすい体制をつくることなどが挙げられる。社会保障費の削減につながる民間投資の後押しも欠かせない。介助ロボットや認知症予防策などが普及すれば長期的な介護費抑制につながる。内閣府は成長実現ケースを達成すれば1人当たりの実質GDPは60年に9.4万ドルと米国や北欧に肩を並べられるとの試算も示した。逆に現状維持ケースでは6.2万ドルと先進国で最低水準に落ち込む。社会保障改革は日本の豊かさを左右する。試算の前提には甘さも見える。成長実現ケースは合計特殊出生率が1.8程度まで回復し、企業の技術進歩や労働者の能力向上などを示す「全要素生産性(TFP)」がバブル期並みの1.4%の上昇を続けるという条件ではじき出した。出生率が1.8を上回っていたのは1984年が最後だ。2022年は1.26と17年ぶりの低水準まで落ち込んだ。TFPは内閣府の推計で13年度以降、一度も1%に達していない。11月の米大統領選でトランプ前大統領が再選すれば対中関税の引き上げなど保護主義的な政策が広がって目先の成長率も落ち込みかねない。実効性のある社会保障改革につなげるには試算の妥当性を点検する作業も必要になる。 *2-1-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240403&ng=DGKKZO79743040S4A400C2TB1000 (日経新聞 2024.4.3) 〈TODAY〉ラピダス、AI半導体注力、「後工程」に補助金535億円 素材・装置と連携 最先端半導体の量産を目指すラピダスは、人工知能(AI)半導体向けに次世代の「後工程」技術を開発する。複数の異なる機能を持つチップを集約し、性能を高める。経済産業省がラピダスの後工程の技術開発に535億円を補助する。国内の装置メーカーや素材メーカーとも連携し、官民で半導体の技術開発を進める。組み立て作業である後工程の技術開発では、日本が競争力を持つ素材や製造装置の技術が不可欠だ。台湾積体電路製造(TSMC)などに回路の微細化では先行されるが、後工程の分野でリードできれば国内半導体産業の底上げにつながる。小池淳義社長は2日に開いた記者会見で「日本には優れた装置や素材メーカーがあるが、(研究開発の)出口となる半導体メーカーがなかった。力を合わせて日本から世界に貢献できる半導体をつくりたい」と語った。経産省は同日、2024年度にラピダスに対し最大5900億円を支援すると発表した。ラピダスは25年4月に試作ラインを稼働させ、27年から線幅2ナノ(ナノは10億分の1)メートルの最先端半導体を量産する計画だ。国の支援は回路をつくるための「前工程」向けが中心だったが、今回、後工程を初めて支援する。半導体はこれまで回路線幅を微細化して性能を高めてきたが、コストや物理的な課題から限界に近づいている。ラピダスは機能の異なる複数のチップを1つの基板に集積する「チップレット」などの技術開発を進める。小池社長は「コスト低減と性能向上の2つを実現できる」と話す。ラピダスが後工程に注力する背景には、AI向けの半導体の需要拡大がある。AI向け半導体には演算や記憶といった機能が求められる。複数の半導体を1つの基板に収めることができれば、効率よく相互に連動させられる。必要な機能を担うチップを入れ替えるだけで性能を高められる。同社はドイツの研究機関、フラウンホーファー研究機構と連携し、ウエハーの研磨技術やチップの接合、素材開発などの要素技術を取り込む。省電力素材に優れる国内の素材メーカーや装置メーカーとも連携する。試作品開発ではラピダス工場に隣接するセイコーエプソンの小型液晶パネルの製造拠点を活用する。後工程分野は台湾や韓国メーカーも注力している。TSMCは独自技術を使って、米エヌビディアのAI半導体の製造を受託。世界の素材メーカーと技術を開発し、性能改善を図る。韓国サムスン電子も24年度に横浜市に先進後工程の研究拠点を設置する予定だ。経産省はラピダスへの支援を経済安全保障上、重視している。半導体はサプライチェーン(供給網)が途絶するリスクがあり、日本で最先端品を生産できれば国内産業の安定につながる。斎藤健経産相は2日の記者会見で「日本産業全体の競争力の鍵を握る。経産省としても成功に向けて全力で取り組む」と話した。ラピダスは27年の量産開始までに5兆円の資金が必要だとしている。国からは24年度までに累計で最大9200億円を受けるが、追加の資金調達が必要となる。同社幹部は「中長期的には民間の金融機関からの資金調達や、新規株式公開(IPO)を検討する」と話す。 *2-1-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240404&ng=DGKKZO79769220T00C24A4EA1000 (日経新聞社説 2024.4.4) 「賢い支出」で財政健全化と成長の両立を ばらまきの発想をやめ、一刻も早く財政を「平時」に戻す必要がある。一方で、将来に向けた投資まで絞り込めば成長の芽を摘んでしまう。「賢い支出」を追求し、財政の健全化と成長の両立をめざすべきだ。内閣府は2日、2060年度までの社会保障費と財政状況の長期推計を初めてまとめた。そこから浮かび上がるのは、社会保障費の急増で財政が持続可能でなくなる危うい未来だ。実質でみた25~60年度の成長率が現状と同じ平均0.2%ほどで推移した場合、名目の国内総生産(GDP)に対する医療と介護を合わせた給付費の割合は13.3%に達する。19年度の8.2%を6割も上回る水準だ。医療の技術革新が給付費をさらに膨らませる可能性がある。内閣府は高額医薬品などの登場で、GDP比が60年度に16%超まで上昇するケースも想定する。このままでは社会保障制度を維持できなくなる。いまから手を打たねば間に合わない。毎年度の社会保障費を高齢化による伸びの範囲内に収めるだけでなく、給付の抜本改革や消費税を含めた負担の議論からも逃げるべきでない。なによりまず、新型コロナウイルス禍の危機対応で膨張した財政の規律を取り戻す必要がある。政府の有識者会議が3月末に示した25年度の国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)に関する見通しでは、基金の乱立などで新たな歳出が3年前の試算に比べ7.5兆円増える。せっかく歳出の改革で4兆円削ったり、税収が5.3兆円上振れしたりする見込みなのに、その効果を薄めてしまう。25年度にPBを黒字化する目標を達成できるかどうかはなお微妙だ。岸田文雄政権の危機感は乏しい。コロナ後の23年度も大型の補正予算を組み、6月には効果がはっきりしない所得税減税に踏み切る。首相は財政健全化への決意を行動で示すべきだ。もちろん、支出を抑えるだけでは経済全体が縮む。成長を実現し、将来の歳出を減らすためにも、デジタルトランスフォーメーション(DX)などで生産性を高める賢い支出は欠かせない。その際に必要なのが、根拠に基づく政策立案(EBPM)の視点である。しっかりとしたデータで効果を検証する仕組みを日本にも根づかせなければならない。 *2-1-7:https://toyokeizai.net/articles/-/677510?display=b (東洋経済 2023/6/9) 医療・介護費が減る「公的制度」意外に知らぬ活用術、せっかくの制度をきちんと利用しない手はない 定年後に必要となる生活費の中で、人によって大きく異なるのが医療費と介護費です。そのため、将来設計を考えるときに心配になりがちですが「公的制度を優先して、足りない分は貯金で補う」方針をすすめるのが、経済ジャーナリストの頼藤太希氏です。頼藤氏が医療費と介護費の公的制度について解説します。 ●70歳未満は生涯の医療費の半分も支払っていない これまで何度となく、病院や薬局のお世話になってきたことでしょう。しかしもし今70歳未満ならば、まだ生涯の医療費の半分も支払っていないといったら、驚く方もいるかもしれません。厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」(2020年度)によると、1人あたりの生涯医療費はおよそ2700万円。そして、そのうち約半分は70歳未満、もう半分は70歳以上でかかっています。つまり、70 歳以上の医療費は1350万円くらいかかるのです。高齢になると、病気やケガをしやすくなるものです。入院・退院を繰り返したり、治療に時間がかかったりするのは、仕方のないことかもしれません。もっとも、1350万円をすべて自費で負担する必要はありません。健康保険があるため、70歳以上の医療費は原則2割負担、75歳以上の医療費は1割負担となるからです(所得によっては2割・3割負担もあり)。そのうえ、毎月の医療費が自己負担の上限を超えた場合は、高額療養費制度を利用することで超えた分が戻ってきます。また、医療費だけでなく介護費用がかかる場合もあります。自分の介護より前に、親の介護にお金がかかる人もいるでしょう。生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(2021年度)によると、介護費用の平均は、一時費用が74万円、毎月の費用が8.3万円。また、平均的な介護期間は5年1カ月ですので、すべて合計すると約580万円かかる計算です。しかし、介護費用も公的介護保険によって1~3割の負担で済みます。さらに、介護費用が高額になった場合は「高額介護(予防)サービス費」や「高額医療・高額介護合算療養費制度」といった制度を利用することで抑えることができます。そして何より、親の介護の費用であれば親の収入・資産から出すこともできるでしょう。病気になったり、介護が必要になったりした際に保険金が受け取れる民間の医療保険や介護保険もありますが、公的な医療保険や介護保険は意外と充実しています。医療費や介護費はもちろんかかるのですが、一度に支払うお金はそれほど高額ではありません。普段から貯蓄をきちんとしていれば、十分まかなえる金額です。それに、民間の介護保険では、所定の要介護状態になっても保険会社独自の基準を満たさない場合には保険金が受け取れないケースもあるのです。いざ介護が始まったというときに介護保険が利用できないのでは、保険料の無駄です。まずは公的な制度を活用することを優先しましょう。 ●「高額療養費制度」で自己負担を減らす 日本では「国民皆保険」といって、原則すべての国民が健康保険制度に加入します。病気やケガで医療機関にかかるとき、保険証を提示すると医療費の自己負担額は最大でも3割で済みます。しかし、3割負担であっても、入院や通院が長引けば医療費の負担が大きくなってしまいます。この負担を減らせる制度が高額療養費制度です。高額療養費制度は、毎月1日から末日までの1カ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、その超えた分を払い戻してもらえる制度です。自己負担額の上限は、年齢が70歳未満か70歳以上か、所得の水準がいくらかによって変わります。例えば、年収180万円の70歳未満の方が入院・手術などをして、1カ月の医療費が100万円かかり、3割負担で30万円を支払ったとします。こんな場合でも、高額療養費制度の申請をすればこの方の自己負担限度額は5万7600円で済みます。残りの約24万円は、後日払い戻されます。さらに、過去12か月以内に3回以上自己負担額の上限に達した場合は「多数回該当」となり、4回目から自己負担限度額の上限が下がります。先の年収180万円の方なら、自己負担限度額は4万4400円になるのです。先に医療費を立て替えるのが厳しい場合は「限度額適用認定証」を申請することで、自己負担分だけの支払いだけで済ませることもできます。なお、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」で受診すれば、限度額適用認定証の申請手続きをしなくても自己負担分だけの支払いですみます。 ●対象外の費用もあるので要注意 ただし、高額療養費制度には対象外の費用もあります。例えば、入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などです。入院中の食事代は「標準負担額」といって、基本的に1食あたり460円です。もしも1カ月入院したら約4万円かかります。差額ベッド代とは、希望して個室や4人までの少人数部屋に入院した場合にかかる費用です。金額は人数や病院によっても異なりますが、中央社会保険医療協議会の「主な選定療養に係る報告状況」(令和3年7月)によると、差額ベッド代の1日あたり平均徴収額は6613円。個室は8315円と高いのですが、2人部屋は3151円、3人部屋は2938円、4人部屋は2639円と、金額に開きがあります。先進医療とは、厚生労働大臣が認める高度な技術を伴う医療のことです。先進医療の治療費は健康保険の対象外なので、全額自己負担です。もっとも食事代や差額ベッド代は確かにかかりますが、そこまで高い金額ではありません。貯蓄をしっかりしておけば、十分まかなえる金額です。また、先進医療の費用は、がんの陽子線治療や重粒子線治療などは数百万円しますが、数万円から数十万円で済む治療もあります。そして厚生労働省「令和4年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」によると、先進医療を受けた患者数は2万6556人ですから、日本の人口(1億2500万人)で割ると先進医療が必要になる確率はわずかに0.02%です。この費用をあえて医療保険やがん保険で用意する必要はないと考えます。介護サービスを利用し、1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた部分が戻ってくる「高額介護(予防)サービス費」という制度があります。高額介護サービス費の上限額は住民税の課税される世帯(現役並み所得者がいる世帯)で14万100円、住民税非課税世帯で2万4600円となっています。高額療養費制度の医療費と同様に、介護費用の負担も一定の上限額までにできる、ありがたい制度です。 ●高額医療・高額介護合算療養費制度も活用 とはいえ、長期間にわたって医療費と介護費がかかり続けると、家計の負担が大きくなってしまいます。そんなときに利用したいのが高額医療・高額介護合算療養費制度です。高額医療・高額介護合算療養費制度は、同一世帯で毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間にかかった医療費・介護費の自己負担額の合計額(自己負担限度額)が上限を超えた場合、その超えた金額を受け取れる制度です。高額療養費制度や高額介護サービス費制度を利用すれば自己負担は減りますが、ゼロになるわけではありません。高額医療・高額介護合算療養費制度を利用することで、その自己負担をさらに軽減できます。高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は、世帯の年齢や所得によって異なります。年間の医療費・介護費を計算して、制度が利用できるか確認しましょう。高額医療・高額介護合算療養費制度の申請は、公的保険の窓口で行います。国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合はお住まいの市区町村、協会けんぽや健康保険組合などの場合は勤務先を通じて申請を行います。ただし、高額療養費制度・高額介護サービス費制度の対象外となっている費用は、高額医療・高額介護合算療養費制度でも対象外です。例えば、高額療養費制度では入院時の食事代や差額ベッド代、高額介護サービス費制度では要介護度別の利用限度額を超えた費用などは自己負担になります。高額介護サービス費の自己負担の上限額は、本人の所得で決まる場合と世帯の所得で決まる場合の2つのパターンがあります。そこで、同居している家族が住民票の世帯を分ける「世帯分離」をすることで、介護費用を削減できる場合があります。なお、世帯分離をしても、同居を続けてかまいません。世帯分離とは、同居している家族が住民票の世帯を分けることです。世帯分離をすることで、介護費用を削減できる場合があります。例えば、介護サービスを受ける親を世帯分離して、親単独の世帯にすれば、世帯としての所得が大きく減るため、高額介護サービス費の自己負担を大きく減らせる、というわけです。 ●世帯分離をしても、別居する必要はない 介護サービスを受けている親(住民税非課税)が、住民税の課税される世帯と同世帯にしていた場合、高額介護サービス費の負担限度額は月額4万4400円になります。しかし、世帯分離をして親だけの世帯になった場合、高額介護サービス費の負担の上限額は「世帯全員が住民税非課税」にあてはまるので、月額2万4600円となります。さらに、仮にこの親の前年の年金年収とその他の所得金額合計が80 万円以下だったとしたら、負担の上限額は月額1万5000円になります。同じ介護サービスを受けていても、負担が月約2万~3万円、年間で約24万~35万円ほど減らせることになります。高額介護サービス費は、最も負担の重い世帯で月額14万100円の負担になっています。ですから、高所得者の方こそ、世帯分離を検討するといいでしょう。なお世帯分離をしたからといって、別居する必要はありません。世帯分離は介護費用の削減にとても役立つ方法なのですが、高額療養費制度や高額介護サービス費の「世帯合算」はできなくなります。高額療養費制度や高額介護サービス費は、世帯ごとにかかった費用を合算して申請できます。しかし、たとえ同居していても、世帯分離をすれば親と子で別の世帯になりますので、合算できなくなります。とくに、2人以上介護している場合には、世帯分離がかえって損になる可能性があります。損得をトータルで考える必要がありますので、詳しくはお住まいの自治体にご相談ください。 *2-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240207&ng=DGKKZO78285980W4A200C2PD0000 (日経新聞 2024.2.7) 少子化支援金、首相「1人あたり月500円弱負担」、医療保険料に上乗せ 歳出改革・賃上げ推進 岸田文雄首相は6日、少子化財源確保のために医療保険料に上乗せする新たな「支援金制度」の負担額が平均で1人当たり月500円弱になるとの見通しを表明した。実質的な負担増にならないとも強調した。個人ごとにみると負担は首相の説明通りにならない場合もある。政府は2024年度からの3年間で年3.6兆円の予算を確保して、児童手当の増額など少子化対策の充実に充当する。その財源のうち1兆円を「支援金制度」で賄う。首相は6日の衆院予算委員会で「粗い試算」として「支援金の総額を1兆円と想定すると、28年度の拠出額は加入者1人当たり月平均500円弱となると見込まれている」と語った。これまで1人当たりの負担水準を明らかにしていなかった。立憲民主党の早稲田夕季氏に答弁した。実際の1人当たりの負担額は個人ごとに差が出る。会社員らが加入する健康保険組合では定率で保険料を上乗せして支援金を集める見通し。加入する健康保険組合や年収によって個人の負担額は変わる公算が大きい。たとえば、22年度の医療保険料率は中小企業が主な対象となる全国健康保険協会(協会けんぽ)は平均で10%。大企業が中心の健康保険組合連合会(健保連)は9.26%と異なる。被保険者の平均年収も21年度時点で協会けんぽ272万円、健保連は408万円と差がある。日本総研の西沢和彦理事の試算によると、医療保険の加入者(家族を含む)1人あたりの支援金の平均額は協会けんぽでは月638円となる。健保組合は月851円、後期高齢者医療制度で月253円になるという。所得が高い人はこの負担額がさらに増える。予算委では野党から「組合の種類や所得によって、(支援金の負担額が)上がっていくということを言わないと不誠実だ」との批判が出た。首相は支援金を導入しても、社会保障分野の国民負担率を上げない方針を示す。社会保障の歳出改革で保険料の伸びを抑え、今春以降の賃上げにより負担率の分母が増えるとの訴えだ。6日の予算委でも「実質的な負担は全体として生じない」と語った。その実現は見通せない。歳出改革では政府が23年12月にまとめた28年度までの工程表で早くもほころびが見えている。介護保険サービスを利用した際の自己負担について、政府は24年度から2割負担の対象者を広げる方針だった。現行は原則1割となっている。対象拡大は自民党などの反発を受けて、27年度以降に先延ばしとなった。賃上げ頼みの仕組みも課題だ。国民民主党の玉木雄一郎代表は6日の予算委で「賃上げはどれくらいを見越しているのか」と首相に問いただした。仮に歳出改革が計画通りに進んでも、賃上げが実施されない企業で働く人は支援金の実質負担が発生するケースがあり得る。日本総研の西沢氏は「実質的な負担は生じないという説明は誤解を生む。『500円弱』の数字が独り歩きする説明では国民の理解が得にくいのでは」と指摘する。 *2-2-2:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20240207&c・・=DPD0000 (日経新聞 2024.2.7) 少子化支援金、首相「1人あたり月500円弱負担」 医療保険料に上乗せ 歳出改革・賃上げ推進、財源1兆円「支援金」で捻出 26年4月から徴収 政府は24年度からの3年間で年3.6兆円の予算を確保し、児童手当や育児休業給付など少子化対策の拡充に充てる。その財源のうち1兆円を「支援金制度」で捻出する。そのほかは歳出改革で1.1兆円、既定予算の活用で1.5兆円を確保する。支援金はサラリーマンの場合は給料から天引きされる医療保険料に上乗せして集める。75歳以上の後期高齢者も含む全世代で負担する。低所得者には負担軽減策を設ける。26年4月から徴収が始まる。初年度は6000億円を集め、段階的に金額を増やし28年度に年1兆円の確保をめざす。使い道や政策への充当割合などを明記した関連法案を今の通常国会に提出する。 *2-2-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15903977.html (朝日新聞 2024年4月4日) 少子化対策、財源巡り攻防 徴収の「支援金」野党批判 政権、負担明示せず 政権の少子化対策「子ども・子育て支援法等改正案」の国会審議が本格化している。3日の衆院特別委員会では、財源の一つで医療保険料とあわせて徴収する「支援金」について、「ごまかしで事実上の子育て増税」などと野党の追及が相次いだ。「(支援金の)所得階層別の負担額を出してほしい」。立憲民主党の山井和則氏がそう迫ったが、加藤鮎子こども政策相は「年収別の拠出額は数年後の賃金水準などによるため、現時点で一概に申し上げられない」と繰り返すばかりだった。2日に衆院で審議入りした法案。最大の争点は財源確保策だ。法案には児童手当の大幅な拡充などを盛り込んだ。少子化対策全体では年3・6兆円規模で、うち1兆円を支援金で賄う想定。ただ、政府は医療保険ごとの加入者1人あたりの平均額の試算を出した一方、所得に応じた負担は提示せず「2021年度の医療保険料月額の4~5%程度」という月額の「目安」を示すのみで、野党の批判が強まっていた。少子化対策の財源を、税ではなく医療保険とあわせた形で徴収することにも批判が殺到。立憲の早稲田夕季氏は「給付と負担の関係が明白である社会保険の考え方には到底見合わない。租税でまかなわれるべきものだ」と指摘した。加藤氏は「(医療保険などの)社会保険制度はともに支え合う仕組み。支援金制度も、少子化対策で受益がある全世代・全経済主体で支える仕組みだ」と答弁。岸田文雄首相も2日の衆院本会議で「少子化、人口減少に歯止めをかけることで医療保険制度の持続可能性を高める」と強調していた。論点には充実策の実効性も挙がる。保護者の就労要件を問わずに保育所などを利用できる「こども誰でも通園制度」については現在、子ども1人あたり月10時間までで試行的に運用中だ。2日の本会議では「今後拡大していく考えはあるのか。保育士などの賃金や労働条件を改善し、質の高い保育を提供するための必要な人材を確保すべきだ」(国民・田中健氏)といった指摘があった。首相は「試行的事業の状況等も踏まえながら、今後検討していく。引き続き、処遇改善も行っていく」と応じた。政府は今国会での法案成立を目指すが、「現段階ではこの法案にもろ手を挙げて賛成するということは極めて難しい」(維新・音喜多駿氏)などと意見が出ている。野党との対立がさらに激化する可能性もある。 *2-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240307&ng=DGKKZO79039740X00C24A3EA2000 (日経新聞 2024.3.7) 特定技能、窮余の拡大 人手不足で上限枠2.4倍82万人に 煩雑な申請など足かせ、待遇改善急務 政府は外国人労働者の在留資格「特定技能」の受け入れ枠を自民党に提示した。2024年度からの5年間で現行の2倍以上の82万人を受け入れる。同じく人手不足に直面する他国との人材争奪はますます激しくなる。日本が「選ばれる国」となるための支援策を整えることが急務となる。政府が6日までに自民党の部会に受け入れ枠を広げる方針を示し、了承された。内訳は建設業など国土交通省の所管分で18.2万人となる。製造業など経済産業省の所管では17.3万人、介護を含む厚生労働省の所管を17.2万人とした。それぞれの数字は業界ごとに成長率や需要などから不足人数をはじき、人材確保や生産性向上の努力で解決できる分を差し引いて算出した。急速な少子高齢化に見舞われる地方からは悲痛な声が上がる。福岡県鉄構工業会は4日、特定技能に関する要望書を小泉龍司法相に提出した。「最先端技術の導入などの取り組みをしても必要な人材確保が困難な状況だ」と訴えた。厚労省が発表した23年10月の外国人労働者はおよそ200万人だった。国際協力機構(JICA)などは年平均1.24%の成長を2040年に達成するには、674万人の外国人労働者が必要だと推計する。政府は特定技能だけでなく、技能実習に代わる非熟練労働者の新制度「育成就労」などと合わせて受け入れ数を増やしていく方針だ。それでも日本社会の機能を維持するのには足りない。政府は特定技能制度が始まった19年に34.5万人の受け入れ枠を設定した。実際の在留者数は23年11月時点でおよそ20万人にとどまった。伸び悩んだのは新型コロナウイルス禍の影響が大きかった。介護や農業など海外で試験を受けて入国する労働者の受け入れが滞った。外国人雇用に詳しい杉田昌平弁護士は「コロナ禍で送り出し国での試験実施が遅れ、運用の確立や制度の浸透が不十分だった」と指摘する。コロナ禍のせいだけにもできない。行政側の対応や、受け入れ企業の負担が大きい現状にも課題がある。宿泊分野で外国人材紹介を手掛けるダイブ(東京・新宿)の菅沼基氏は入管への申請数の増加を要因に挙げる。「申請結果が出るまでの時間が長く入国待ちや変更待ちの人が多数いる」と話す。特定技能の場合、技能実習とは異なり受け入れ窓口である監理団体が存在しない。受け入れ企業が実習や日本語教育の支援を自社で賄うケースもある。日本は諸外国と外国人材の獲得を競わなければならない。オーストラリアや韓国は外国人労働者を獲得する政策を積極展開する。円安や相対的に低下した賃金水準は、日本が「選ばれる国」になるための足かせとなりつつある。賃金面で魅力を高める努力とともに、外国人の職場への順応や生活環境の支援策を整えることが重要だ。特定技能で来日した労働者を国籍別に見るとベトナムが最も多く、インドネシアやフィリピンなどが続く。文化や慣習の異なる東南アジアが中心になっている。勤務上のトラブルが発生した場合の支援体制や、日本語の学習環境の整備は欠かせない。日本人との共生には、自治体と地域の企業が一体となってバックアップに取り組む体制が求められる。各国の共生政策を比較する移民統合政策指数(MIPEX)の2020年版の総合評価で見た日本の順位は56カ国中35位にとどまった。スウェーデンが1位で、アジアでは18位の韓国に後れをとっている。 特定技能の受け入れ枠拡大を巡り、自民党の部会で目立った異論は出なかった。外国人材に頼らなければ地方経済が回らなくなりつつある現状を映している。 ▼特定技能制度 一定の専門性と日本語能力を持つ外国人材を受け入れる制度で19年に始まった。海外から入国する場合は、技能と日本語の試験に合格すれば最長5年在留できる「1号」の資格を得られる。さらに条件を満たせば在留資格の更新に制限がない「2号」になれる。家族を帯同でき将来は永住権も申請できる。現在は人手不足が著しい12の分野が対象。政府は新たにタクシーやバスの運転手である「自動車運送」や列車乗務員の「鉄道」など4分野を追加し16分野とする計画だ。 *2-3-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1215816 (佐賀新聞 2024/3/26) 入管庁の難民認定、最多303人、23年、アフガンが大半 出入国在留管理庁は26日、自国で迫害を受ける恐れがあるとして、2023年に303人を難民認定したと発表した。22年から101人増え、最多を更新。うち237人がアフガニスタン国籍で、関係者によると、21年の政変後に退避した国際協力機構(JICA)の職員らが多くを占める。難民認定申請者数は1万3823人で、22年の3倍超と大幅に増えた。入管庁によると、難民認定者303人の内訳は、アフガンが最多で、軍政による弾圧が続くミャンマーが27人、エチオピアが6人など。アフガンでは22年も日本大使館の元職員や家族らが多く認定されている。申請者数は、17年の1万9629人に次いで2番目に多い。スリランカが3778人で最も多く、トルコ、パキスタンが続いた。入管庁は「新型コロナウイルスの水際対策が終了し、来日者数の回復に伴い申請者も増えた」と分析している。23年に成立した改正入管難民法で新設され、紛争避難民らを難民に準じる形で在留を認める「補完的保護」は、申請を受け付けた23年12月から今年2月末までに1110人が申請。647人が認められ、ウクライナ避難民が644人、23年4月に軍事衝突があったスーダンが3人だった。「定住者」の在留資格を付与する。難民と認めなかったものの、23年に人道的配慮から在留を認めたのは1005人。ミャンマーなど本国の情勢を踏まえた許可が大半を占めた。難民認定を巡っては、年間1万人を超える国がある欧米と比べ、日本は認定数が少なく、基準が厳しいとの指摘がある。難民認定制度 外国人から申請を受け、難民条約が定義する難民に該当するかどうかを判断する。条約は人種や宗教、国籍、政治的意見、特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害の恐れがあり、国外に逃れた人を難民と定義し、出入国在留管理庁の調査官が面接などで審査する。認定されると「定住者」の在留資格を付与。不認定の場合は審査請求ができる。日本では、制度が開始した1982年から2023年までに1420人を条約上の難民と認定。欧米と比べ少なく「難民鎖国」とも批判される。 *2-3-3:https://www.nippon.com/ja/features/c03707/ (Nippon.com 2024.2.9) 小澤征爾:“人間力”で「世界のオザワ」に上り詰めたカリスマ指揮 柴田 克彦 《日本を代表する指揮者・小澤征爾さんが2月6日死去した。“世界のオザワ” の冥福を祈るとともに、敬意を込めて2018年に公開した記事を改めてお届けする》世界のクラシック音楽界で頂点に立つ指揮者の1人、小澤征爾。“音楽エリート” ではなく、苦労しながら努力と行動力、そして人間的魅力で世界に嘱望されるまでに至ったマエストロの軌跡を振り返る。 (2018年6月12日に公開した記事を再掲致します) 2002年1月1日、小澤征爾はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の「ニューイヤー・コンサート」に登場した。60年もの歴史を誇り、約60カ国にテレビ中継されるこの世界的風物詩を指揮する初めての日本人だった。彼は、米国ビッグ5の名門、ボストン交響楽団の音楽監督を約30年にわたって務め、この年の秋からオペラ界の頂点、ウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任することになっていた。さらには、世界最高峰の2強、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とウィーン・フィルの定期演奏会にレギュラーで登場する数少ない指揮者の1人だった。これらは全て、西洋の文化であるクラシック音楽の分野で日本人が達成するには、あまりにハードルが高い、正真正銘の偉業である。無論、小澤以外に成し遂げた日本人指揮者はおらず、裾野に近づいた者さえごく限られる。 ●日本人離れの行動力の原点 小澤征爾は、1935年9月1日、満州国の奉天(現・中華人民共和国の瀋陽)に生まれた。山梨の貧しい農家の出で、苦学の末に歯医者となった父・開作は23歳の時に満州へ渡り、長春で歯科医を開業。その地で征爾の母となる若松さくらと結婚した。だが開作は、アジア民族の一体化を理念とする政治活動に没頭し、政治団体「満州国協和会」の創立委員として奉天に移り住んだ。そこで生まれた三男は、開作が知遇を得た陸軍大将・板垣征四郎から「征」、関東軍参謀・石原莞爾から「爾」を取って「征爾」と命名され、6歳の年まで満州で過ごした。大陸で生まれ育ったこと、さらには父譲りの行動力が、小澤の日本人離れした活躍の源にあるのではないか…そう思えてならない。小澤はいわゆる “音楽エリート” ではなかった。音楽との出会いは5歳のクリスマスに母が買ってくれたアコーディオンで、ピアノを始めたのが10歳の時。一家は41年に帰国して立川に住まいを移していた。もちろん当時、家にはピアノがなく、後に親戚から譲り受けた際も、兄たちが横浜から立川まで3日かけてリヤカーで運んだ。ピアニストになる夢はあっても、スタートがあまりに遅い。そんな折の49年12月、日比谷公会堂における日本交響楽団(現・NHK交響楽団)のコンサートで、ロシア出身のピアニスト、レオニード・クロイツァーがピアノを弾きながら指揮をする演奏を聴いて、初めて指揮に強い魅力を感じた。そして母さくらの遠縁に音楽教育者・チェロ奏者の齋藤秀雄(1902~74年)がいることが分かり、弟子入りを志願する。中学3年生の時だった。 ●生涯の師、友との出会いを経て2大巨匠の下へ 人生とは巡り会い。小澤の道のりをたどるとそれを痛感させられる。齋藤秀雄は、桐朋学園で多数の著名指揮者や弦楽器奏者を育てた大功労者だ。彼は小澤の生涯の師となった。もう1人、齋藤の指揮教室で巡り会ったのが山本直純(1932~2002年)。後にコマーシャルの「大きいことはいいことだ」のフレーズで名をはせた指揮者にして、映画『男はつらいよ』のテーマ音楽を手がけた作曲家である。小澤は最初、兄弟子にあたる山本に指揮を教わった。1952年小澤は斎藤が開設に関わった桐朋女子高等学校音楽科に入学、55年桐朋学園短期大学に進学した。やがて、「音楽をやるなら外国へ行って勉強するしかない」と強く思うようになった小澤に向かって、山本は「音楽のピラミッドがあるとしたら、オレはその底辺を広げる仕事をするから、お前はヨーロッパへ行って頂点を目指せ」と言って後押しした。そしてそれは実現した。59年2月、持ち前の行動力を発揮し、スクーターと共に貨物船で単身渡仏した23歳の小澤は、同年ブザンソン国際指揮者コンクールに挑んだ。実は応募の締め切りを過ぎていたのだが、つてを頼って紹介してもらった米国大使館の職員の口利きで参加がかない、見事優勝。これが飛躍の第1歩となった。まずは審査員だった巨匠シャルル・ミュンシュの一言でボストン交響楽団が毎夏米国マサチューセッツ州で主宰するタングルウッド音楽祭に参加し(60年)、それを機に、61 年レナード・バーンスタイン率いるニューヨーク・フィルハーモニックの副指揮者に抜てきされた。またヘルベルト・フォン・カラヤンの弟子を選出するコンクールにも合格。そこで小澤は、20世紀後半の指揮界を二分するカラヤン、バーンスタイン両雄の薫陶を受けることができた。このような経験を持つ指揮者は、世界でも恐らく小澤しかいない。 ●「N響事件」を経て新日本フィル結成へ 小澤征爾は天才ではなく、努力の人である。「勉強、勉強、また勉強」が彼の生き方。そして小澤を知る者は、「彼ほど人懐っこく、人間に対する愛情が深く、義理固い人はいない」と言う。日々の努力にそうした人柄が加わったからこそ、良き巡り会いが生まれたに違いない。ただ日本では順風満帆ではなかった。1962年には、契約を結んだNHK交響楽団からボイコットされる「N響事件」が起きた。同年6月から半年間の指揮契約を結んでいたが、楽員から27歳の小澤に対し「生意気だ」「態度が悪い」などの感情的反発が生まれていたのだ。そこで翌年「小澤征爾の音楽を聴く会」が開催され、発起人に、浅利慶太、石原慎太郎、井上靖、大江健三郎、曽野綾子、武満徹、谷川俊太郎、團伊玖磨、中島健蔵、黛敏郎、三島由紀夫ら、驚きのビッグネームが並んだ。これも小澤の吸引力のなせる業だろう。しかし彼は事件を機に日本に見切りをつけ、世界にのみ目を向けた。事件は結果的に “世界のオザワ” 誕生を導いたといえる。72年には、縁あって首席指揮者を務めていた日本フィルハーモニー交響楽団が、フジサンケイグループからの支援を打ち切られる。急きょ米国から帰国した小澤は何とか存続を図ろうと奔走し、天皇陛下へ直訴までする。同年日本芸術院賞を受賞していたが、その授与式で「自分だけ賞をもらいましたが、今一緒にやっているオーケストラは大変な状況なんです」と思わず言ってしまったのだ。結局当時の “財団法人日本フィル” は解散(注:裁判闘争を続けながら自主運営団体として継続し、現在は公益財団法人として活動中)、小澤は山本直純と共に新日本フィルハーモニー交響楽団を結成する。その後長い間、日本では基本的に新日本フィルしか指揮せず、同楽団を起用した山本の公開テレビ番組「オーケストラがやって来た」に再三出演するなど、義理堅さを発揮した。 ●クラシック界の頂点に駆け上がる 世界における快進撃の始まりは、「N響事件」の翌年、1963年にシカゴ交響楽団が主宰する「ラヴィニア音楽祭」に急きょ代役で出演し、成功を収めたことだった。64年には同音楽祭の音楽監督に就任(68年まで)。65年にはトロント交響楽団の音楽監督に就任した(69年まで)。66年には「ザルツブルク音楽祭」ならびにウィーン・フィル、さらにはベルリン・フィルの定期演奏会にデビュー。70年には「タングルウッド音楽祭」の芸術監督(2002年まで)、サンフランシスコ交響楽団の音楽監督(76年まで)に就任した。そして73年、ボストン交響楽団の音楽監督に就任し、2002年まで約30年間に及ぶ米国では異例の長期体制を築いた。79年パリ・オペラ座、80年ミラノ・スカラ座、88年ウィーン国立歌劇場にデビューし、オペラでも世界最高峰の舞台で活躍。2002年のウィーン国立歌劇場の音楽監督就任(2010年まで)に至る。膨大なディスクも録音し、中でも冒頭で言及した「ニューイヤー・コンサート2002」のライブCDは、日本で80万枚(世界で約100万枚)というクラシック界では空前絶後のセールスを記録した。94年にはタングルウッドにその名を冠した「セイジ・オザワ・ホール」が建てられた。日本での活動も徐々に活発化した。87年に齋藤秀雄の門下生を主体とする「サイトウ・キネン・オーケストラ」の活動を開始。同楽団は世界から一流と目される存在となった。90年には水戸室内管弦楽団の芸術顧問に就任。92年には「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」(2014年から「セイジ・オザワ松本フェスティバル」)の総監督に就任し、同音楽祭は垂涎の内容で人気を集めた。98年には長野冬季オリンピックの開会式で、世界5大陸を結ぶベートーヴェン「第九」を指揮。2000年には若手音楽家を育成する「小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクト」を始めた。 ●“人間力”で最高の音楽を引き出す 指揮者は、自ら音を出さない不思議な音楽家だ。実際に音を出すのは、おのおのが一家言持つ100名ものプロフェッショナル演奏家集団である。彼らに意を伝え、持てる能力を発揮させ、1つの音楽を形作るには、技術や知識以上に人間的な魅力やカリスマ性を必要とする。指揮法を体系化した齋藤秀雄譲りのバトン・テクニックは素晴らしい。しかし彼の本領は、人柄に努力と経験が加わった “人間力” に尽きる。小澤のカリスマ性を示すエピソードがある。2015年、新日本フィルの創設期を共にしたティンパニ奏者の山口浩一が亡くなる直前、小澤は彼を見舞いに訪れた。山口はほとんど意識がなく、周りで見守る人たちが「分かったら手を握って」と言うと、辛うじて握り返す程度だった。ところが小澤が声をかけると、パッと目を開け、会話までしたという。1986年2月13日、東京文化会館における小澤指揮/ボストン交響楽団によるマーラーの交響曲第3番は、筆者にとってこれまで経験した最高のコンサートだった。終始引き付けられた末の深い感銘を、30年以上たった今でもありありと思い出す。この体験は生涯まれな “ギフト” だった。小澤の音楽は熱い。彼はきっと同様の感銘を皆に与えてきたであろう。ここ数年は健康状態を鑑みながら活動している。今秋には83歳を迎える小澤。だがまだまだギフトを与え続けてほしいと願わずにはおれない。 *2-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240407&ng=DGKKZO79852220W4A400C2EA2000 (日経新聞 2024.4.7) 働き手「予備軍」、20年前から半減 昨年411万人に、女性・高齢者の就業進む 人手不足、事業再編迫る 日本の働き手が枯渇してきた。今は職に就かず仕事を希望する働き手の「予備軍」は2023年に411万人で15歳以上のうち3.7%にとどまり、割合は20年で半減した。女性や高齢者の就業が進み、人手の確保は限界に近い。企業を支えた労働余力は細り、非効率な事業の見直しを迫られている。現場の人手不足を敏感に映すのが時給の動きだ。労働政策研究・研修機構が毎月勤労統計をもとに集計したパートタイムの時間あたり給与は、23年10~12月期に前年同期比3.8%増だった。新型コロナウイルスの影響があった時期を除くと15年以降で最も高い。一般労働者は1.0%増で、パートの伸びが際立つ。コロナの影響が薄れたことによる景気要因だけではない。より大きいのは、女性や高齢者の労働参加が進み、人材のプールが細ったという構造要因にある。総務省がまとめた労働力調査によると、15歳以上で職に就かず仕事を探していないが、就業を希望する人は23年に233万人と20年前に比べて297万人減った。職探しをしている完全失業者の178万人と合わせた「予備軍」は411万人で15歳以上の人口の3.7%にあたる。03年の8.0%に比べて半分以下の水準だ。予備軍が減ったのは景気回復とともに、女性や高齢者が働く環境整備が進んだためだ。国立社会保障・人口問題研究所によると、15~64歳の生産年齢人口はピークだった1995年に比べ23年は15%減ったが、就業者は20年間で約400万人増えた。足元では結婚や子育てで女性が職を離れ、30代の就業率が下がる「M字カーブ現象」もほぼ解消した。大和総研の田村統久氏は「働き手の減少を女性や高齢者で補うのは限界に近い」と指摘する。英国の経済学者、アーサー・ルイス氏は農村で余った労働力が工業部門に吸収されて成長する中で、ある時点で余剰労働力がなくなる「ルイスの転換点」の考え方を示した。転換点を過ぎれば賃上げの圧力が強まる。日本は1960年代後半に過ぎたと見られているが、女性や高齢者という観点で新たな転換を迎える可能性がある。企業も戦略の転換を迫られる。低金利による借り入れ負担の軽減と、非正規で働く女性や高齢者の活用はコスト低減の柱だった。低収益の事業でも存続しやすくなり、景気回復下でも賃金が上がらないデフレの色合いを強めた。日銀のマイナス金利解除に伴い、金利には上昇圧力がかかる。人手不足で採用ができず、非正規の時給引き上げが続けば、低採算の事業は選別し撤退をせざるを得なくなる。 <男女別学と教育について> PS(2024年4月15日追加): 国連の女子差別撤廃条約を持ち出すまでもなく、日本国憲法が第3条で「すべて国民は、等しく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と教育の機会均等を定めている。そして、西日本では、男女別学だった公立校は日本国憲法施行と同時に男女共学に変更され、その恩恵によって私の今がある。 しかし、*3-1・*3-2のように、未だに男女別学の公立高校が存在する埼玉県で、市民グループ「共学ネット・さいたま」が、①公立校としての公共性 ②ジェンダー平等 ③性の多様性 の三つの観点から県立高校の共学化を求め ④埼玉県男女共同参画苦情処理委員が2023年8月に埼玉県教育長に対して共学化を勧告したところ、埼玉県教育委員会は「名門2校(浦高と浦和第一女子)」の卒業生に対し聞き取りを実施し ⑤i)伝統維持 ii)選択肢の確保 を強調する反対意見が多数を占め、男女の機会均等などを訴える賛成派はわずかだった とのことである。 具体的な反対意見には、⑥男子校の埼玉県立浦和高校同窓会は「浦高」は埼玉唯一の全国ブランドで別学を維持しないと文化が壊れる」と別学維持を求めて大野元裕知事に意見書を渡した ⑦女子側“トップ校”の浦和第一女子高同窓会は事前に集めた卒業生アンケートで「500件のうち483件が共学化に反対」「女子校出身者の方が理系選択が多い」「女子校は男女の性差にとらわれることなく能力や個性を発揮できる」などの意見があった ⑧勧告後に始まった共学化反対のインターネット署名は2万件を超えた としている。 しかし、④のように、卒業生に聞き取りを行えば、男女共学高校で教育を受けた経験がなく、自らの過去を肯定したいという動機も重なって、反対意見が出るのは当然だが、卒業生(過去の在学生)の意見を根拠に男女別学を維持するのは、日本国憲法に反して意図的であり、本末転倒だ。また、⑤の伝統維持についても、その長い伝統は男女の性別役割分担や女性差別・女性蔑視に基づく伝統であるため、女子差別撤廃条約・日本国憲法及び①②に反しており、「伝統維持=女性差別・女性蔑視の維持」になっている。そのため、このような教育制度・社会意識の下では埼玉県に赴任する子育て家庭は父親だけの単身赴任になり、埼玉県の人口10万人あたり医師数は全国最下位で、人口の割に高校のレベルも上がらない。ちなみに、私は、子供を作らないと決めてから埼玉県にマンションを買ったが、その理由は東京・神奈川と比較してかなり安かったからで、住民(男性だけでなく女性も)にも女性蔑視があるのは不愉快に感じている次第だ。 なお、⑥については、その“全国ブランド”の恩恵に預かるのは男子生徒だけであり、このようにして男女別学かつ男性優遇の中で育った男性が女性の能力を過小評価して職場や社会でも女性を差別し、社会進出を阻んでいることを忘れてはならない。また、簡便のために東大で比較すると、浦和高校は、文I:4人(浪人3)・文II:9人(浪人6)・文III:5人(浪人3)・理I:13人(浪人6)・理II:13人(浪人7)・理III:0・合計:44人(浪人25)など、理系や職業に結びつく学部への合格者が多い(https://www.inter-edu.com/univ/2024/schools/336/jisseki/ 参照)が、女子側“トップ校”の浦和第一女子高校は、文I:1人(浪人1)・文II:2人(浪人2)・文III:3人(浪人2)で、文系でも現役で法律・経済学部に合格した女子生徒はおらず、理系学部に合格した女子生徒は現役・浪人合わせて全くいないため、⑦は根拠なき主張だ(https://www.inter-edu.com/univ/2024/schools/374/jisseki/ 参照)。さらに、浪人割合が高いのは、高校までの勉強では東大に入れず、予備校での浪人生活があって初めて東大に合格したということである。これに加えて、卒業生が“全国ブランド”と考えている浦和高校も理IIIの合格者は0で、これは高校だけで頑張っても中高一貫校で勉強した人には追いつけないことを意味する。その中高一貫校は男女別学の私立が多く、学費も高いため、東大合格者は所得や出身校で偏り、地方出身者が減って、多様な視点の源であるリーダーの多様性もなくなった。国・埼玉県及び他の地方自治体は、これでよいのだろうか? *3-1:https://digital.asahi.com/articles/ASS4B420XS4BUTNB004M.html (朝日新聞 2024年4月11日) 男女別学県立高の共学化を 市民団体が改めて早期実現訴え 男女別学になっている県立高校の共学化を求める市民グループ「共学ネット・さいたま」が10日、県庁で会見し、改めて共学化の早期実現を訴えた。共学ネットは、「公立学校としての公共性」「ジェンダー平等」「性の多様性」の三つの観点から、県立別学校の問題点を指摘。「別学は選択肢の一つ」という代表的な反対意見に対し、「別学と共学の選択肢がある生徒は事実上学力の高い一部の生徒だけで、大半の生徒は選択していない」と反論した。県立の別学校をめぐっては、県男女共同参画推進条例に基づく苦情の申し出を受け、苦情処理委員が2023年8月、県教育長に対し、共学化を勧告。男子校の県立浦和高校の同窓会は別学維持を求め、大野元裕知事に意見書を渡している。 *3-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1209922 (佐賀新聞 2024/3/15) 県立高、共学化勧告に波紋、伝統か機会均等か、埼玉 「名門」卒業生が反対 男女別学の県立高校は早期に共学化すべきだ―。昨年夏、埼玉県教育委員会が県の男女共同参画苦情処理委員から受けた勧告が波紋を呼んでいる。県教委は「名門」2校の卒業生への聞き取りを実施。伝統維持や選択肢の確保を強調する反対意見が多数を占め、男女の機会均等などを訴える賛成派はわずかだった。8月までの報告を求められた県教委の対応に注目が集まっている。「『浦高』は埼玉唯一の全国ブランド」「別学を維持しないと文化が壊れる」。今年1月、県内屈指の「名門男子高」とされる浦和高(さいたま市)での聞き取りには、大学生から80代までの約110人が参加した。議論は3時間に及び、反対意見が噴出。「選択肢を残すべきだ」と声が上がる中「優れた教育を受ける権利を否定するべきではない」といった賛成意見は少数だった。女子高側の「トップ校」浦和第一女子高(同市)では、同窓会の栗原美恵子会長ら約10人が出席し、事前に集めた卒業生のアンケートを紹介。500件のうち483件が共学化に反対した。集まった意見は「女子校出身者の方が(進路での)理系選択が多い」「女子校は男女の性差にとらわれることなく能力や個性を発揮できる」など。栗原会長は「伝統や愛着ではなく、女子校が男女共同参画に成果を上げている点を見てほしい」と訴えた。県教委によると、県立高137校のうち男女別学は男子校5校、女子校7校の計12校ある。勧告は別学があった宮城、秋田、福島3県で2016年度までに全校が共学になったことなどに言及し、対応を求めた。勧告した男女共同参画苦情処理委員は、知事が委嘱した弁護士らで構成。発端は22年4月に寄せられた「男子校が女子の入学を拒むのは、国連の女子差別撤廃条約に反する」との申し出だった。条約は女子に男子と平等の権利を確保することを目的に、女子に対する差別を撤廃するための適当な措置を取るよう求めている。日本も1985年に批准した。同様の勧告は2002年にもあった。県教委は報告書に「各校が特色ある学校づくりに向けて主体的に取り組む中で、共学化を検討する可能性もある。その場合は支援したい」と記載。ただ共学化は大きくは進まなかった。今回の勧告後に始まった共学化反対のインターネット署名は2万件を超えた。県内の共学校の関係者も賛同し、議論は広がりを見せている。県教委は全別学校で聞き取りを実施。日吉亨教育長は1月の記者会見で「意向に応じて場を設定した。中学生や在校生へのアンケートを交えながら、多角的に意見を聞きたい」と話した。 <政治資金の寄付とその恩恵は・・> PS(2024年4月21、22《図》日):*4-1-1・*4-1-2は、①自民・公明両党は自民派閥の政治資金問題を受けた再発防止策として、政治資金収支報告書のデジタル化と外部監査導入を打ち出す方針 ②公明党は、i)国会議員関係政治団体収支報告書のオンライン提出義務化 ii)政治資金の透明性向上のため外部監査・第三者機関活用 iii)収支報告書虚偽記入は政治団体代表者が会計責任者の選任や監督に関して「相当の注意」を怠れば50万円以下の罰金 iv)罰金刑を受けた議員は公民権停止 とした ③首相と与党は、i)議員本人を含め罰則強化 ii)収入を含めた外部監査充実 iii)デジタル化による透明性向上を打ち出す見通し ④公明党は今回の問題のきっかけとなった政治資金パーティーを巡り、パーティー券購入者の情報開示基準を現行の20万円超から5万円超に引き下げるよう求め、自民党内は「特定政党との繋がりを明かしたくない人もいる」との慎重論が根強く、野党はパーティーの廃止を主張 ⑤政党から政党幹部ら政治家に支出する政策活動費については、公明党は使途公開義務付けを主張し、自民党は使途公開を含めて反対論があがる ⑥公明党は国会議員の関係政治団体から寄付を受けた「その他の政治団体」の資金に関する透明性の確保策も盛り込んだ ⑦国会議員関係政治団体は1件1万円超の経常経費と政治活動費を政治資金収支報告書に明細まで記載しなければならず、資金管理団体等の「その他の政治団体」は経常経費の記載は不要で政治活動費も1件5万円以上と基準が緩い ⑧公明党案は批判に配慮して国会議員関係政治団体から年間で一定以上の寄付を受けた政治団体は、国会議員関係政治団体と同等の公開基準とするように要求 ⑨自民党の渡海政調会長は20日、政治資金規正法の今国会中改正の実現を巡って「会期を延ばしてもいいから徹底的にやるべき」と話し、自民党独自案は23日にも方向性を示すことになると言明したが、「公職選挙法の連座制と同じものは作れない」と述べた としている。 国会議員の「事務所費問題」がクローズアップされた2007年に政治資金規正法改正法が成立し、その時は自民党衆議院議員として改正案の議論に私も参加していたため、政治資金を寄付した寄付者が裏切られたり、寄付を受けた議員が本当は他の意図があるのに政治資金規正法違反で叩かれたりしないように、「議員関係の政治資金収支報告書を複式簿記に変更して網羅性・検証可能性を確保し、適正性の意見表明ができる公認会計士監査(独立性のあるプロによる外部監査)を導入すること」を提案した。しかし、成立した改正法は、イ)国会議員関係の政治団体は「国会議員関係政治団体」と法律上明確に定義する ロ)この範囲の政治団体の収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため一定の義務を課す という非常に限定されたものであったため、外部監査も政治資金規正法への準拠性の表明に留まった(https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/pdf/35246.pdf 参照)。 そして、イ)のように、国会議員関係の政治団体のみに限ったため、代表者が政党・派閥・地方議員・後援会長等の「その他の政治団体」は、⑦のように緩い基準になり、今回の不記載が合法的に起こったのである。これに対し、①②③⑤⑥⑧のように、自民・公明両党は、自民派閥の政治資金問題を受けた再発防止策として、i)国会議員関係政治団体収支報告書のオンライン提出義務化 ii外部監査・第三者機関活用 iii)収支報告書虚偽記入に対する代表者の罰金 iv)罰金刑を受けた議員の公民権停止等を検討しているそうだが、i)ii)iii)は、国会議員関係の政治団体収支報告書に限定している点で不足であるし、iv)は標的にした議員叩きのツールとして使われることもあるため注意すべきである。 また、国会議員関係の政治団体収支報告書限定では不足である理由は、例えば*4-2-1・*4-2-2・*4-2-3・*4-2-4のように、政権与党に寄付して政策を歪めることにより恩恵を受けたい企業や個人は、国会議員関係の政治団体に寄付しなくても、政党・県連・首長・地方議員等に寄付することも可能で、それが政策を歪めていないことを証明できるためには、取引の全てを網羅性・検証可能性のある複式簿記で記帳し、外部監査人の適正意見をつけて速やかに開示し、少なくとも7年間は保存する必要があるからだ。 なお、④のように、公明党は今回の問題のきっかけとなった政治資金パーティー券購入者の情報開示基準を現行の20万円超から5万円超に引き下げるよう求め、自民党内は「特定政党との繋がりを明かしたくない人もいる」との慎重論が根強く、野党はパーティーの廃止を主張しているそうだが、金額を細かくしても従業員の名前を使って小分けすれば匿名で寄付することができるため、私は政治資金パーティーを廃止し、かわりに民主主義のコストとして国が議員秘書の数を増やし、議員個人にも相当の交付金を出すのが良いと考える。何故なら、その方が歪んだ政策に何兆円も歳出してイノベーションを止められるより、国民にとって2~3桁安上がりだからだ。 さらに、政権与党である自民党は情報も人材も豊富な筈なのに、自民党の機関誌は共産党の赤旗のように資金源になれていない。そのため、自民党は機関誌の内容を充実して販売代金を党の収入に充てればよいと思うし、有権者や後援会員などに集まりたい人がいる場合は、飲み食いや権力の誇示が主目的のパーティーではなく、報告会や研修会を開いて集まった人の意見を吸い上げつつ、それなりの会費を徴収すれば良いと思う。そして、それは、有能な人が議員になっていれば可能であるため、議員の資質の評価にも役立つだろう。 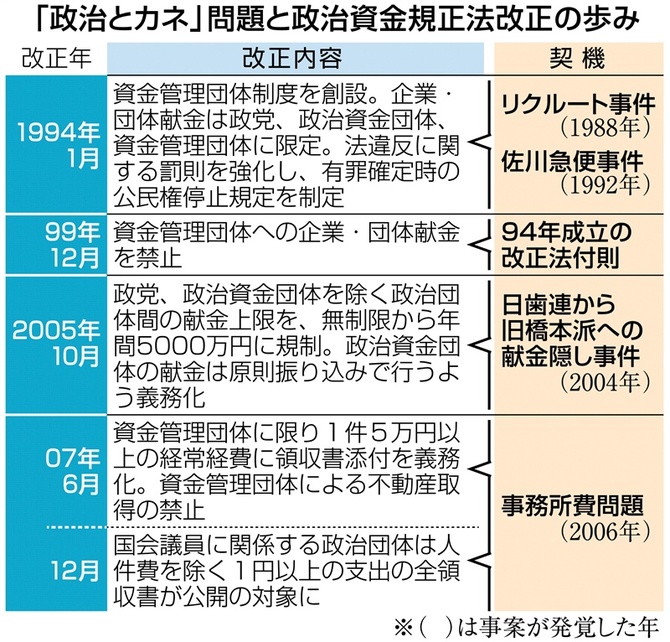 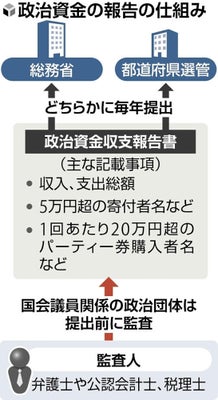 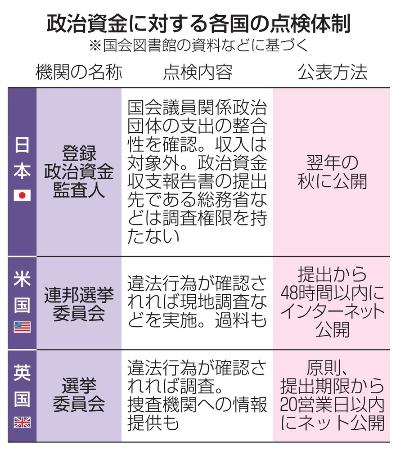 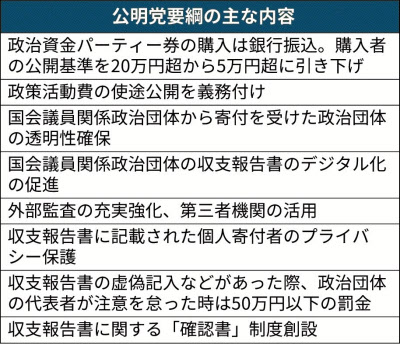 2023.12.25西日本新聞 2023.12.18 2024.1.15静岡新聞 2024.4.20日経新聞 読売新聞 (図の説明:1番左の図のように、「政治とカネ」問題が起こる度に政治資金規正法が限定的に改正されてきたが、正確な情報を国民に開示するという積極的姿勢はなく、この姿勢は国の予算の使い方でも同じだ。現在の政治資金の報告の仕組みは、左から2番目の図のとおり、抜け穴が多い。また、右から2番目の図のように、日本以外の先進国の公表時期は提出から「48時間以内」「20営業日以内」のインターネット公開と迅速だが、日本は翌年の秋という桁外れに遅い時期であり、これも国の決算と同じで問題である。そして、1番右の図のように、公明党が政治資金規正法改正案を出しているが、①対象を国会議員関係団体に限定した点 ②政治資金パーティーを温存した点 ③プライバシー保護として寄付者の氏名を出さない点 等が不十分である) *4-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240420&ng=DGKKZO80164480Z10C24A4EA3000 (日経新聞 2024年4月20日) 政治資金報告、デジタルに、規正法改正、与党で調整 外部監査を導入 自民、公明両党は自民党派閥の政治資金問題を受けた再発防止策として政治資金収支報告書のデジタル化や外部監査の導入を打ち出す方針だ。政治資金規正法の改正案に盛り込むことをめざし調整する。与党で案をまとめたうえで野党と内容を詰める。公明党は19日の政治改革本部で規正法改正案の要綱を決めた。自民党幹部は来週初めにも規正法改正に向けた独自案をまとめる方針を示した。同党は当初取りまとめに慎重な見方もあった。公明党の要綱は国会議員が関係する政治団体の収支報告書のオンライン提出を義務付けると定めた。政治資金の透明性向上へ外部監査や第三者機関の活用を明記した。収支報告書の虚偽記入があった場合の対応も記した。政治団体の代表者が会計責任者の選任や監督に関して「相当の注意」を怠ったときは50万円以下の罰金を科す内容も加えた。罰金刑を受けた議員は公民権が停止され、選挙に立候補できなくなる。いずれの措置も岸田文雄首相(自民党総裁)が主張する方向性と一致する。首相は規正法の改正に関して(1)議員本人を含めた罰則強化(2)収入を含めた外部監査の充実(3)デジタル化による透明性の向上――を軸に議論を進めるよう党内に指示している。自民党幹部は首相が示す方針は与党案でも打ち出すとの見通しを示す。公明党の案のうち首相が立場を明らかにしていない項目は擦り合わせが必要になる。公明党は今回の問題のきっかけとなった政治資金パーティーを巡り、パーティー券購入者の情報開示基準を現行の20万円超から5万円超に引き下げるよう求めた。自民党内は「特定政党とのつながりを明かしたくない人もいる」などと慎重論が根強い。政党から政党幹部ら政治家に支出する政策活動費について公明党は使途公開の義務付けを主張する。自民党は使途公開を含めて反対論があがっている。立憲民主党など野党は廃止を主張する。公明党は国会議員の関係政治団体から寄付を受けた「その他の政治団体」の資金に関する透明性の確保策も盛り込んだ。国会議員関係政治団体は原則、1件1万円超の経常経費と政治活動費を政治資金収支報告書に明細まで記載しなければならない。一方で資金管理団体など「その他の政治団体」は経常経費の記載は不要で、政治活動費も1件5万円以上と基準が緩い。立民は自民党の茂木敏充幹事長の国会議員関係政治団体から別の政治団体に2022年までの10年間でおよそ3億2000万円が寄付されたと国会で追及した。新藤義孝経済財政・再生相についても同様の資金移動があり、使途の大半がわからないとただした。公明党案はこうした批判に配慮し、国会議員関係政治団体から年間で一定以上の寄付を受けた政治団体は、国会議員関係政治団体と同等の公開基準とするように要求した。次期衆院選をにらみ、透明性のハードルをあげる実績づくりを狙う。自民党はいまだ独自案をつくっていない。公明案をどこまで受け入れるかが与党案のとりまとめに向けた調整のポイントとなる。公明党の山口那津男代表は16日の記者会見で、衆院3補欠選挙の投開票日の28日までに与党の基本的な考え方をまとめるのが望ましいとの認識を示した。与党内の調整が終われば野党との協議に入る見込みだ。立民などは政策活動費の廃止や企業・団体献金の禁止など自民党にとってさらに受け入れにくい案を取り入れるよう主張する可能性が高い。与党協議に時間がかかると、それだけ野党との話し合いに残された時間が少なくなる。与党の調整のスピードは首相が掲げる今国会中の規正法改正を左右する。 *4-1-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2028W0Q4A420C2000000/ (日経新聞 2024年4月20日) 政治資金規正法改正、23日にも自民案 渡海政調会長 自民党の渡海紀三朗政調会長は20日、政治資金規正法の今国会中の改正の実現を巡り「会期を延ばしてもいいと思う。徹底的にやるべきだ」と話した。党の兵庫県連との会合後に記者団に話した。規正法の自民党独自案については23日にも方向性を示すことになると言明した。自民案について「原則は透明性と説明責任をどう担保していくかだと思う」と言及した。会計責任者だけでなく政治家自身も処分可能にする「連座制」を例に挙げて、「公職選挙法の連座制と同じものは作れない」と述べた。「議論し国民に理解してもらい、現実の政治活動に支障がないようにやっていかないとならない」と説明した。28日投開票の衆院補欠選挙の情勢は「たいへん厳しいと聞いている」と語った。「今回の政治資金にまつわる一連の不祥事が選挙に反映されている」と分析した。 *4-2-1: https://digital.asahi.com/articles/ASS4L3GMGS4LULFA012M.html?iref=comtop_7_01 (朝日新聞 2024年4月18日) 減税の恩恵受けた企業はどこ? 政府は非開示、法人コードは毎年変更 政策減税で毎年8兆円超の税収が減っているにもかかわらず、減収に見合った効果が得られているか検証する仕組みは整っていない。総務省は毎年秋、所管省庁が新設や期限の延長を求めている租税特別措置(租特)の効果を点検する。昨年は36項目のうち、19項目でこれまでの効果について、32項目で将来の効果について、それぞれ説明や分析が不十分だと指摘した。とりわけ昨年末に「延長」と「拡充」が決まった賃上げ減税は、過去の減税効果が示されていないなどとして、「分析・説明の内容が著しく不十分」だと厳しい評価がくだった。財務省も昨秋、有識者を交えて賃上げ減税の政策効果を検証したが、減税が賃上げに寄与しているかどうか、はっきりとは確認できなかった。こうした事態に、上村敏之・関西学院大教授(財政学)は、「減税の政策効果を検証するために必要なデータが開示されていないことが一番の問題だ」と指摘する。賃上げ減税の効果を検証するには、減税が適用されなかった企業よりも、適用された企業の方が賃上げをしていることを示さなければならない。だが、どの企業が減税の恩恵を受けているかの情報は非開示となっている。財務省が法律に基づき、租特の適用状況を毎年まとめている報告書には、項目ごとに上位10社の適用額だけは示されているが、アルファベットと6桁の数字で作る「法人コード」で表されるだけで、具体的な企業名はわからない。しかも法人コードは、守秘義務を理由に過去の実績から企業名が推測できないよう、毎年変えられている。ほかに開示されているのは、業種ごとや資本金の規模ごとにまとめた減税の適用件数や合計額にとどまる。22年度の自民党税制改正大綱では透明性を高めようと、減税を受ける大企業に対して賃上げ方針の公表を義務づけたが、具体的な賃上げ額や減税額の公表までは求めなかった。かつては、抜本的な見直しを検討した時期もあった。10年に法人税関連の租特について定めた透明化法を策定した民主党の鳩山政権は、報告書に企業の実名を記す方向で検討を進めていた。当時、財務副大臣を務めた峰崎直樹元参院議員によると、経済界や経済産業省からの強い反発にあい、党内の意見集約もできず断念したという。峰崎氏は「どの企業が減税の恩恵を受けているかわからなければ、成果が出ているかもわからず、国会の審議などで追及もできない」と話す。そこで朝日新聞が、研究開発減税の適用額上位10社について、有価証券報告書などの公表資料と照らし合わせて分析した。22年度の適用額トップ企業は、トヨタ自動車とみられることがわかった。その額は914億9925万円で、研究開発減税全体の1割強を占める。トヨタの法人コード「DI07300」は、賃上げ減税も80億5209万円で、2番目に多く優遇を受けていた。研究開発費に毎年1兆円規模を投じるトヨタは減税規模も他企業を大きく上回り、22年度までの10年間で連結ベースの減税額は累計9千億円を超える。トヨタは朝日新聞の取材に「研究開発税制は日本企業のイノベーションを加速し、競争力強化を後押しする、一つの有効な制度だ」とコメントした。しかし、トヨタ以外の上位10社を公表資料から特定することはできなかった。 *4-2-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1228542 (佐賀新聞 2024/4/18) ガソリン補助金 「賢い支援」に転換急げ ガソリン補助金の出口が見えない。4月末に期限を迎えるが、政府は7度目の延長を決めた。 だがガソリン、灯油の価格を抑えるために投じた補助金は6兆円を超えている。持続可能性や効率の面から疑問が生じるのは当然だろう。所得、地域、業種にかかわらず一律に支援する方式から早く転換すべきだ。原油高は続いているが、財政資金は無尽蔵ではない。低所得世帯や過疎地に支援対象を絞り込んでほしい。生活を支える補助金だからこそ、効率的で長続きする「賢い支援」に切り替えねばならない。ガソリンなどの燃油価格を抑えるため、補助金が導入されたのが2022年1月のことだ。原油の国際市況が値上がりしたためで3月末までの時限措置のはずだった。しかし2月にロシアのウクライナ侵攻が始まり、資源価格は一層高騰した。ロシアのエネルギー資源を利用できなくなり、原油や天然ガスは中東、米国、オーストラリアなどからの調達に変更してきたが、円安や中東情勢の悪化の影響もあり、原油価格は依然高い。補助金は石油元売りに渡し、店頭の値段を一定水準に抑える仕組みだ。最近のガソリンの小売価格は175円程度だが、補助金がなければ200円近くになるという。生活に直結する補助金は導入よりも打ち切るタイミングが難しい。消費者にとっては負担増になってしまうからだ。縮小や廃止のタイミングをあらかじめ検討しておくべきだという意見は、導入前から政府内にもくすぶっていた。だが政府はいたずらに期限延長を繰り返してきた。ガソリン補助金は特定の業種や所得層に対象を限らない支援だけに影響も大きい。内閣支持率や選挙をめぐる思惑が働いたのだろうか。運送業の大半は中小企業であり、公共交通機関が少ない地域では家庭も車に頼らざるを得ない。ガソリン補助金は暮らしを支えてきた面がある。政府は5月の使用分を最後に、電気・ガス代への補助金を打ち切る。液化天然ガス(LNG)などの価格が落ち着いたためだという。ガソリン補助金も縮小や廃止の方向をできるだけ早く決め、車のユーザーや家庭に周知してほしい。見直しの基本は補助金の支援対象を農漁業や物流・運輸などに限定することだ。車に頼らざるを得ない地域と、交通網が張り巡らされた都市部で差があるのも当然だろう。灯油は寒冷地への支援に絞ったらどうか。零細企業や低所得層への配慮は欠かせないが、高級車に乗る富裕層には不要だ。業種の選定や所得による絞り込みの仕組みをつくるのに時間がかかるなら、一律支援の目安となるガソリン価格の水準を引き上げる移行措置を考えてほしい。補助金の規模を圧縮できるはずだ。補助金を漫然と続ければ、省エネやエコカーへの乗り換えに弾みがつかず、結果的に化石燃料への依存が続く負の効果を生みかねない。直接の恩恵が車のユーザーに限られる補助金を見直し、省エネや脱炭素を加速させる政策に財源を振り向けるべきではないか。エネルギー分野以外にも子育て、教育、奨学金など政府の手助けが必要な分野は多い。ガソリンの巨額補助金の見直しは、財政資金の公平で有効な使い道を考えることにほかならない。 *4-2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240416&ng=DGKKZO80041660V10C24A4EP0000 (日経新聞 2024.4.16) 佐賀・玄海町の核ごみ調査、地元団体が受け入れ請願 原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場選定に向けた文献調査を巡り、佐賀県玄海町の飲食・宿泊などの3団体が調査の受け入れを求める請願を町議会に提出した。町によると、原発立地自治体で文献調査に関する請願が出されたのは初めてという。 町議会は今後、原子力対策特別委員会で請願を審議する予定で17日に同特別委を開く。請願を提出したのは玄海町の旅館組合と飲食業組合、防災対策協議会の3団体で、4日付で受け付けた。脇山伸太郎町長は「重く受け止めている。まずは議会での議論を見守りたい」とのコメントを発表した。 *4-2-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1229932 (佐賀新聞 2024/4/20) 核のごみ最終処分場選定調査 原発立地自治体の責務か 九州電力玄海原子力発電所が立地する東松浦郡玄海町で、地元3団体が高レベル放射性廃棄物(核のごみ)最終処分場選定に関する文献調査の受け入れを求める請願書を町議会に提出した。難問である核のごみ処分について議論をする上で「一石を投じた」意義は否定しないが、一部の請願書の「原発立地自治体の責務」という表現には強い違和感を覚える。過疎地がさらなる核のリスクを自ら背負う義務があるとは言い難い。核のごみは強い放射線を出し続けるため、国は地下300メートルより深い岩盤に埋める地層処分の最終処分場を国内1カ所に造る計画で、場所の選定を進めている。現在、北海道の寿都町(すっつちょう)と神恵内村(かもえないむら)の2町村が第1段階の文献調査に応じて作業が進み、今年2月、次の段階となる概要調査に進むことが可能とする報告書案が公表された。長崎県の対馬市議会は昨年9月、調査受け入れ促進の請願を採択したが、市長は反対し、応募しなかった。今回、玄海町議会で文献調査受け入れを求めた請願の審議は、原発立地自治体では初めてとなる。町議10人のうち過半数が賛同する見通しで、全議員で構成する25日の特別委員会、26日の本会議で採択される公算が大きい。これを受けて脇山伸太郎町長がどう判断するかが焦点となる。請願書は町の旅館組合、飲食業組合、建設業者でつくる防災対策協議会が個別に提出した。東日本大震災を経て、老朽化した玄海原発4基のうち1、2号機が廃炉となり、原発関連の作業員が減って需要が大幅に減り、コロナ禍も重なって経済的打撃を受けている現状を訴えている。長年、原発産業に依存してきた町は福島第1原発事故後、「脱原発依存」に官民さまざまに取り組んできた。原発関連施設の固定資産税収入などもあり、県内で唯一、国から地方交付税の配分を受けていない不交付団体で、町の財政は比較的安定している。文献調査を受け入れた場合、国から最大20億円が交付される。再び「原発マネー」による経済活性化の方策へと進むのが、長期的に見て地域のためになるのか。原発によらないまちづくりの障壁が何であるかはいま一度検証し、深い議論を望みたい。玄海町をはじめ、隣接する唐津市も日常的にリスクに向き合っている。原発による電力を生み出し、使用済み核燃料からの「核のごみ」を排出する責任を問われるなら、電力の大消費地である都市部にも受益者として責任の一端はあろう。立地自治体が原発の全てのリスクを背負う義務はなく、これ以上の負担を負わせるべきではないと考える。最終処分場の選定に関し、山口祥義知事は従来、玄海原発などエネルギー政策で「佐賀県は相当の役割を果たしている」と指摘し、「新たな負担を受け入れるつもりはない」と主張、県内での建設に反対の立場を示してきた。今回も同様の考えを表明している。原発に対する賛否を超えて、知事の考え方は一定支持を得られるのではないか。核のごみの放射能レベルは時間とともに減少するものの、数万年から10万年は生活環境から隔離する必要があるといわれている。当該世代はもちろん、人類として予測が難しい時間軸である。文献調査受け入れが最終処分場候補地決定とすぐになるわけではない。地震が頻発する日本列島でもある。今回の一石を重く受け止め、長期的に向き合わざるを得ない原発のありようをあらためて考える機会にもしたい。 <賢くない支出から賢い支出へ> PS(2024年4月24、25、26、27《図》日追加):*5-1-1は、①民間事業者から大型投資に向け、政府側により長期の計画策定を求める声があり、経産省は2035年脱炭素目標の先の電源構成の議論を始めて2024年度中に2040年度の構成を定める ②太陽光・風力といった再エネと原子力の活用が主要な論点 ③「エネルギーへの投資の難しさは将来どの技術が伸びてくるかが分からないところ」と水素事業に携わる国内大手商社幹部が指摘 ④国内では再エネが急速に普及する一方、石炭等の火力発電が主力電源として残る ⑤太陽光・風力発電の出力制御で都内の再エネ事業者から「原発再稼働を見通せず、出力制御される再エネは投資判断が難しくなった」という声も ⑥日本の電源構成は2022年度実績で脱炭素電源は再エネ21.7%、原子力5.5% ⑦政府の現行エネルギー基本計画は2030年度に再エネ36~38%、原子力20~22%に増やす目標 ⑧菅政権時に日本は2050年までにCO₂等の温暖化ガス排出を実質ゼロにする目標を表明 ⑨政府は再エネ・原発への投資や新技術開発が進むよう制度を整えて支援に乗り出してきた ⑩電力投資は大規模で投資回収は数十年単位で考える必要があるが、2050年の脱炭素社会に向けた具体的な数値目標や電源構成が不透明な現状では将来の利益を見通せず、再エネ事業者も原発事業者も新たな投資を決断しづらい ⑪天然資源に乏しい日本でこのまま脱炭素が進まない状態を放置すれば、エネルギー安全保障の観点でも問題が生じる ⑫現在、電源の7割を頼る火力発電に使う石炭などの化石燃料は多くを輸入に依存 ⑬太陽光や風力の発電に用いる中核部品も中国や欧米企業の製品に頼らざるを得ない ⑭再生エネの新技術に関する国内産業を育成し、供給網を強化して、輸入に過度に依存しない体制を整える必要 ⑮原発の再稼働や新増設に道筋をつけることも欠かせない ⑯再エネ新技術では日本発のペロブスカイト型太陽電池や浮体式洋上風力発電があり、政府は明確な目標設定を年度内に検討 ⑰原発の再稼働や新増設を促す追加策も不可欠 ⑱政府はこうした背景を踏まえて2040年度電源構成を含めた長期見通しを示して民間投資を後押しする狙い 等としている。 しかし、②⑨⑮⑰⑱は、CO₂という温暖化ガスを排出しないという1点のみで再エネ発電と原子力発電を同一視し、「地球温暖化対策に貢献する」として意図的に読者をミスリードしている点が、大きな間違いである。何故なら、地球温暖化対策なら、もともとはなかったところに膨大な熱エネルギーを発生させ、余った熱エネルギーを海に捨てている原発は、地球温暖化防止に貢献するどころか温暖化を促進しているからである。一方、太陽光・風力等の再エネ発電は、地球にもともと存在するエネルギーを熱エネルギーに変換させずに電力に換えているため、本当に地球温暖化防止に貢献しているのである。また、⑩については、投資が膨大で数十年どころか数万年かかっても政府補助がなければ廻らないのは原発だけであり、太陽光・風力等の再エネは、⑤のように、原発再稼働で出力制御されなければとっくに採算がとれ、規模拡大すれば安価にもなるからだ。さらに、⑪のように、馬鹿の一つ覚えのように「日本は天然資源に乏しい」と主張する人が多いが、日本には太陽も当たらず、風も吹かず、水流もないとでも言うのだろうか? そして、エネルギー安全保障は、③④⑫のように、化石燃料を他国より高い値段で輸入し続け、水素でさえ輸入しようとし、その負担は国民に押しつければよいと考えてきた大手商社や政府(特に経産省)に問題があるのであり、安全保障全体から見ても武力行使されれば無防備な原発を北西の風が多い日本海側に並べておくなどもってのほかなのだ。 そのため、政府が、⑥⑦のように、現在は5.5%しかない原子力発電を2030年度に東日本大震災前と同じ20~22%に増やす目標をたて、⑧の「2050年までのCO₂等の温暖化ガス排出を実質ゼロ」に関して故意に目的をすり替え、①⑱のように、民間事業者からの原発への大型投資を促すなどというのは国民不在の無責任な態度でしかない。もともと太陽光発電は日本発の技術で日本がトップランナーだったのに、政府やメディアが逆風を吹かせた結果、⑬のように、中核部品を中国や欧米企業の製品に頼らざるを得ない羽目になったのである。その上で、⑭のように、再エネの新技術に関する国内産業を税金を使って育成し、供給網を強化し、輸入に過度に依存しない体制を整えるのでは、国債残高ばかりが膨らんで経済は停滞するのが当然だ。なお、⑯の日本発ペロブスカイト型太陽電池は、ビルや住宅に自然な形で組み込まれるように、最初は補助金をつけてでも普及させるべきで、決してシリコン型太陽光発電機器の二の前にするべきではない。また、浮体式洋上風力発電も風レンズ風車や養殖施設併設型等の工夫された付加価値の高い日本発の機器があり、電気は創って使う時代になりつつあるため、政府は「省庁や大企業の既得権維持」という狭い視野ではなく、省庁の枠を越えたイノベーティブな判断をすべきである。 つまり、分散発電を推進しつつ、発電された電力を特定の場所に集めるには、*5-1-3の耐用年数40年を過ぎた水道管更新時に、耐震化しながら、電線を地中化し、各建物で発電された電力を集めれば良いし、ここに国費を投入すれば賢い支出になる(ただし、この頃、“節水”と称して水の勢いを弱くする蛇口が多いが、これは、掃除や食器洗いに必要な水の分量が同じである以上、タイパ(タイムパフォーマンス)を悪くして、人を疲れさせるだけである)。このようにして各地で集めた電力を遠くへ送電するには、*5-1-2のように、いつまでも「開かずの踏切」のままにして国民の生産性を下げている鉄道を高架化し、そこに送電線も通して、運賃と同時に送電料も取れるよう投資すればよい。つまり、既にある連続した土地を、管轄する省庁を問わずに共用できれば、それぞれを安価に改良することができ、賢い支出になるのである。 なお、原発は、*5-2-1・*5-2-2のように、地震の多い日本では危険な施設であり、原発が事故を起こせば取り返しのつかないことになるのは明らかだ。そのため、いつまでも国の膨大な補助金がなければ廻らない危険施設は、早急に廃止するのが国民のためであり、何度も同じ事故が起きなければそれを理解できないということは、まさかないだろう。 原発については、電源立地地域対策交付金・広報・調査等交付金・核燃料サイクル交付・原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金・原子力発電施設等立地地域特別交付金・福島特定原子力施設地域振興交付金・エネルギー構造転換理解促進事業を活用した事業・原子力発電施設立地地域共生交付金(運転年数30年超の原子力発電施設が所在す道県へ)・原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業等、多くの補助金が支払われている上、原発の維持管理のために多数の人を雇っており、これが立地地域・周辺地域や経産省にとって既得権となっているが、これらの財源は、国民が支払った税金と電気料金である(https://www.enecho.meti.go.jp/committee/disclosure/dengenkoufukin2/ 参照)。 そのような中、*5-3-1のように、佐賀県玄海町の町内3団体は、それだけで国から20億円の文献調査交付金が交付される「文献調査」を求める請願書を町議会に提出したが、この交付金も税金で国民が負担していることを忘れてはならない(https://digital.asahi.com/articles/ASP1H6V6ZNDTIIPE01R.html 参照)。そこで、*5-3-2は、⑲佐賀県玄海町議会は原発から出る高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査受け入れを求める地元3団体の請願をスピード採択する ⑳人口約4900人の玄海町は今年度当初予算約100億円の6割を原発関連収入が占め、佐賀県内唯一の「不交付団体」で財政に窮してはいない ㉑賛同町議は「原発立地自治体として責任を果たさなければいけない」「原発自治体で真っ先に手を挙げたかった」と語り、全国の原発立地自治体の手挙げに繋がることを期待 ㉒町旅館組合・町飲食業組合・町内の建設業者で作る町防災対策協議会は、請願理由を「原発立地自治体の責務」「文献調査での地質の把握」とした ㉓反対派町議は「文献調査は原発立地自治体の責務ではない」と反発 ㉔町民には反発の声が広がらず、町議会前で「危険原発と永久処分場」等ののぼりを掲げたのは、佐賀県唐津市や福岡市など町外の4人だった と記載している。 このうち、⑳については、現在の佐賀県玄海町は原発関連収入で「不交付団体」となっており、財政に窮してはいないものの、原発が廃止され、原発から出る高レベル放射性廃棄物が他の自治体の最終処分場に移されれば、原発の雇用・旅館宿泊・飲食・建設ニーズをはじめ原発関連の交付金もなくなるため、⑲㉑㉒のように、町旅館組合・町飲食業組合・町内建設業者などの地元3団体が「原発立地自治体の責務」「文献調査での地質の把握」等として請願を行ない、スピード採択に至るのだと思われる。それで、㉓のような町内の声が広がらない理由は、「原発は危険で、自分にはメリットがない」と感じる人は既に町外に引っ越しており、玄海町に住んでいる殆どの人は原発によるメリットを受けているためで、㉔のように、町議会前で「危険原発と永久処分場」等ののぼりを掲げたのは、危険性と負担を押しつけられる割にはメリットの少ない唐津市・福岡市など町外の人だ。が、事故時の汚染地域の広さや原発の維持管理・最終処分の負担を考えれば、狭い立地地域の判断のみで原発の立地・維持管理・最終処分場の誘致を決めるのはむしろ問題なのである。 しかし、既に大量に存在する使用済核燃料や廃炉時に出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場は速やかに決めるべきであり、最終処分場は人間の生活環境から遠く離れ、酸素が少なく物質が変化しにくいという理由で、地表から300m以上深い地層に処分することに、現在は、なっている。が、地表から300m以上深い地層に処分すれば全く管理不要というわけでもなく、施設の建設費やその維持管理費はかかるため、有人島も含めて合計14,121の離島がある日本の場合は、人間の生活環境から300m以上離れ、漁業等に支障の無い無人島を使った方が施設の建設費や維持管理費がずっと安価ですむと、私は思う。そして、都道府県別の離島数は、1位長崎県1,479(うち無人島1,407)、2位北海道1,472(うち無人島1,466)、3位鹿児島県1,256(うち無人島1,225)等であり、このうち長崎県対馬市は昨年4月に調査受け入れを求める地元の動きがあり、市議会が同9月に請願を採択したが、対馬市は国境離島であるとともに漁業も盛んな地域であるため、私も対馬市長と同様、もったいないし不向きだと思っていた。しかし、漁業等に利用されておらず、本土に近い無人島なら適地は多く、建設コストを最小にするには、(石炭はもう使わないため)軍艦島のような既に放棄された地下施設のある場所が良いと思われる。 そして、原発はこれだけ多くの問題を抱えているのに、*5-4は、㉕政府は2035年頃までの最大10年間の計画のうち前半の2024年度からの5年間で200億円を核融合研究に投じる ㉖従来はトカマク型という大型炉に特化してきたが、今後はレーザー方式など複数方式の支援も手厚くする ㉗2035年までに原理実証して2050年頃の実用化を目指す ㉘文科省は「発電に限らず、ロケットエンジン向けや熱利用等の様々な用途への応用を視野にチームを作る」とする ㉙核融合はCO2が発生せず、1gの燃料から石油8t分のエネルギーを生み出す ㉚実用化できれば脱炭素を進めながら生成AIやEV普及に伴う電力消費の急増に対応しやすくなる ㉛核融合により放出エネルギーが投入エネルギーを上回る「エネルギー純増」が2022年に世界で初めて達成された ㉞半世紀以上の研究の歴史があるが未だ実用化できていない 等としている。 核融合・核融合と言う人は多いが、㉞のように、半世紀以上研究しても未だ実用化できない技術が、㉗のように、2050年頃には実用化でき、㉚のように、生成AIやEV普及に伴う電力消費の急増に間に合って役立つとは思えない。アメリカは、広い砂漠があり、リスクをとって実験することもでき、科学的論理性に長けた国であるため、原爆・原発・ロケット・コンピューター・インターネット・AI・バイオ医薬品等も世界で最初に開発した国だ。そのため、㉖のように、核融合原発も開発・実用化することが可能かも知れないが、アメリカで開発された核分裂型の原発を猿マネして地震・津波の多い日本でそのまま使い、大変な事故を起こしたのがフクイチ原発事故である。さらに、核分裂を使う現在の原発でさえ、暴走し始めると人間の手には終えずに広い範囲に迷惑をかけまわっているのに、㉛のように、放出エネルギーが投入エネルギーを上回る核融合原発が暴走したらどうなると思っているのか。また、㉘のようにロケットエンジンに核融合を使って、打ち上げに失敗したら地球の広い範囲が汚染されるが、これらもまた、安全神話と“風評被害”で乗り切るつもりだろうか。さらに、㉙は、核融合はCO₂が発生せず、1グラムの燃料から石油8トン分のエネルギーを生み出すとしているが、発生する莫大な熱エネルギーを冷やした熱は地球を暖めないとでも言うのか。つまり、ここまで非科学的・非論理的な日本という国が、㉕のように、核融合研究に数百億円投じても無駄使いになるだけなのである。そして、その数百億円は、ただでさえ足りない高齢者の医療・介護保険制度から流用する金額より大きいのだ。 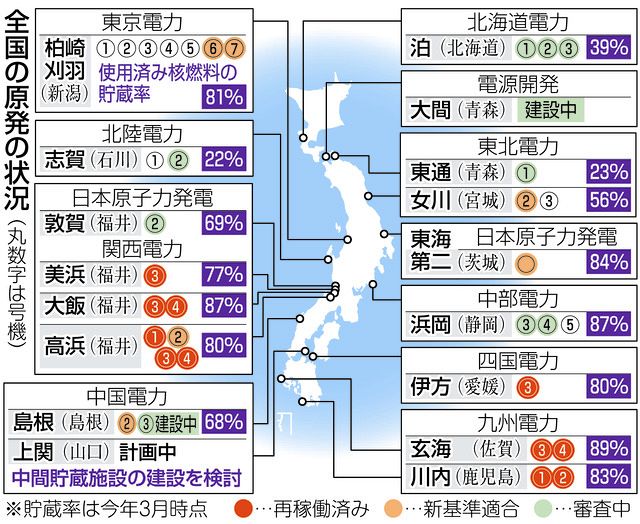 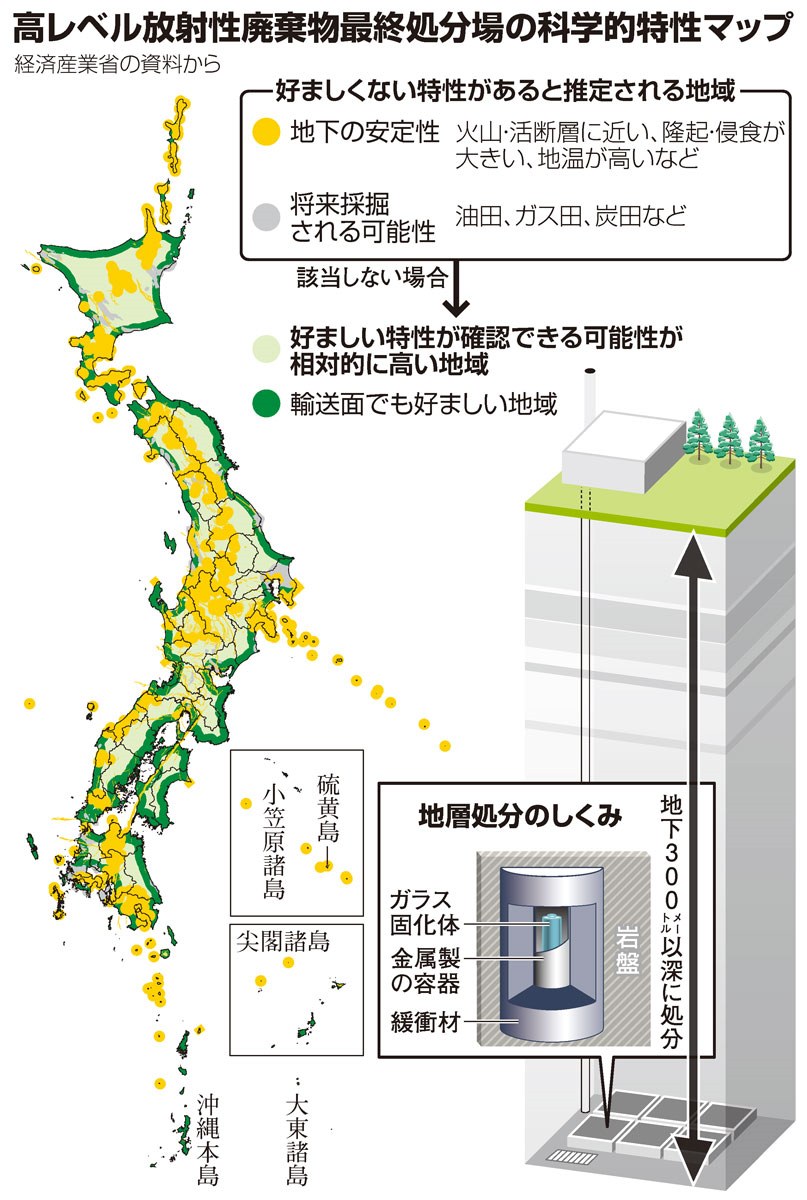 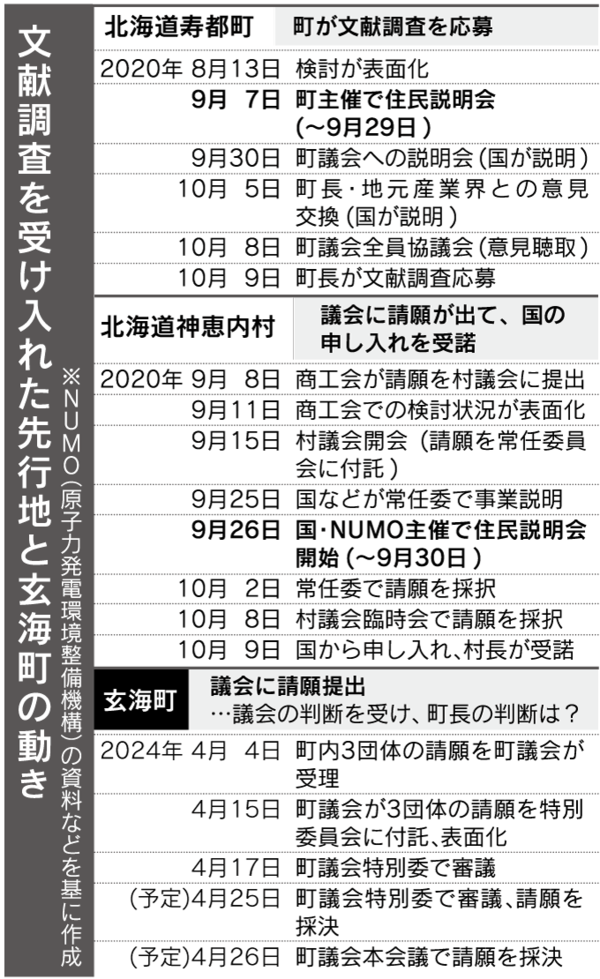 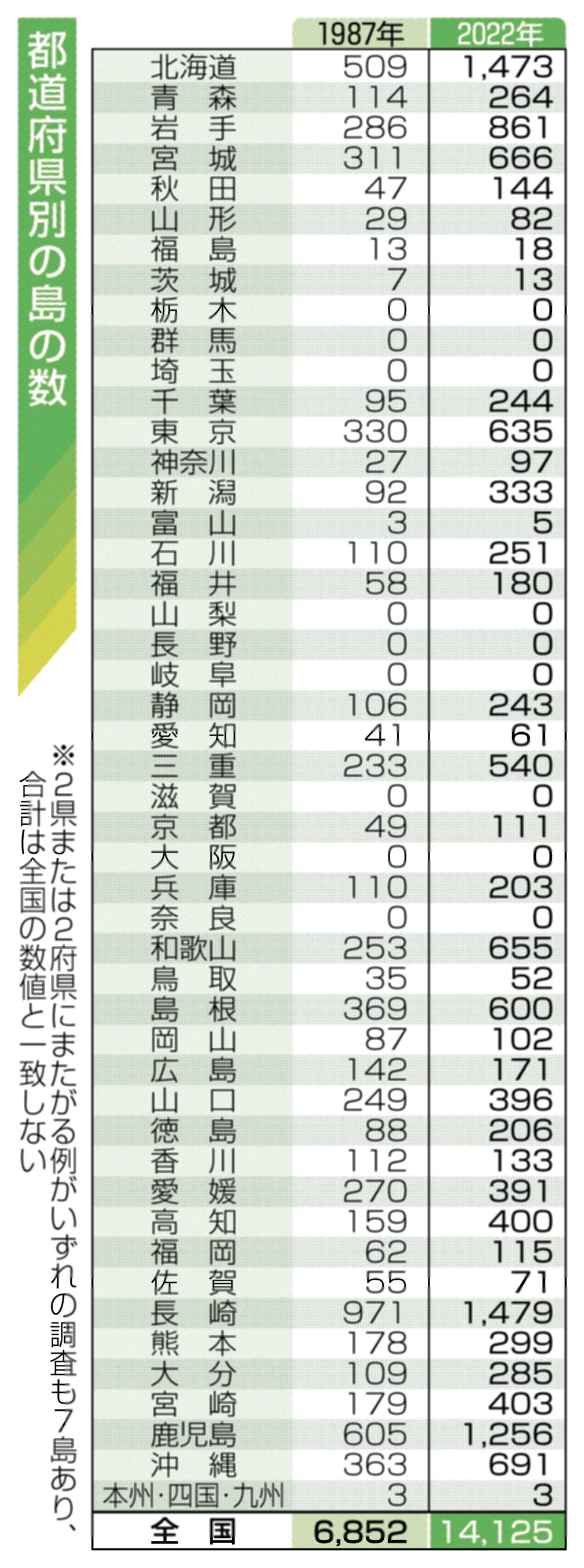 2023.8.1東京新聞 2018.4.19朝日新聞 2024.4.22佐賀新聞 2023.2.14福井新聞 (図の説明:1番左の図のように、既に使用済核燃料貯蔵率の高い原発が多い上、それを水中で貯蔵して冷却する使用済燃料貯蔵プールは原発に近い高い位置にあるため、地震によるひび割れや倒壊の危険性が高い。また、左から2番目の図のように、現在、高レベル放射性廃棄物の最終処分場は、ガラス固化体にして金属容器に入れ、人が近づかない地下300m以深に保管する形が好ましいとされており、右から2番目の図のように、北海道寿都町・神恵内村と佐賀県玄海町が国から20億円の交付金が得られる文献調査を受入れているが、1番右の図のように、日本には本土から300m以上離れた離島(無人島も)は多く、無人島から入る形で海底の地下に最終処分場を建設すれば300m以深である必要は無いため、安価で維持管理もしやすいと思われる) *5-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240416&ng=DGKKZO80041590V10C24A4EP0000 (日経新聞 2024.4.16) 再エネ・原発 拡大どこまで、30年度目標、達成なお遠く 電源構成で道筋示す 経済産業省は国際公約となる2035年の脱炭素目標のさらに先を見すえた電源構成の議論を始める。24年度中に40年度の構成を定める。民間事業者からは大型投資に向け、政府側により長期の計画策定を求める声があった。太陽光や風力といった再生可能エネルギーと原子力の活用が主要な論点となる。「エネルギーへの投資の難しさは将来どの技術が伸びてくるかが分からないところにある」。水素事業に携わる国内の大手商社幹部は現状の課題を指摘する。日本国内で再生エネが急速に普及する一方で、石炭などの火力発電は主力電源として残る。太陽光や風力による発電を止める出力制御が問題となり、都内の再生エネ事業者からは「原発の再稼働を見通せず、その調整弁として出力制御される再生エネは投資判断が難しくなっている」といった声も聞かれる。日本の電源構成は22年度の実績で、脱炭素につながる電源は再生エネが21.7%、原子力が5.5%にとどまる。現行の政府のエネルギー基本計画では30年度に再生エネを36~38%、原子力を20~22%に増やす目標をかかげる。達成までの道のりは遠い。前の菅義偉政権時代に日本は50年までに二酸化炭素(CO2)など温暖化ガスの排出を実質ゼロにする目標を表明した。政府は再生エネや原発への投資、新技術の開発が進むよう制度を整え、支援に乗り出してきた。それでも、現場には脱炭素への機動的な投資に踏み出しにくい構図が残る。電力への投資は大規模で、投資回収は数十年単位で考える必要がある。50年の脱炭素社会に向けた具体的な数値目標や電源構成が不透明な現状では、将来の利益を見通せず、再生エネ事業者も原発事業者も新たな投資を決断しづらい。天然資源に乏しい日本でこのまま脱炭素が進まない状態を放置すれば、エネルギー安全保障の観点でも問題が生じると指摘される。足元で電源の7割を頼る火力発電に使う石炭などの化石燃料は多くを輸入に依存する。太陽光や風力の発電に用いる中核部品も中国や欧米企業の製品に頼らざるを得ない。再生エネの新技術に関する国内産業を育成し、供給網を強化して、輸入に過度に依存しない体制を整える必要がある。原発の再稼働や新増設に道筋をつけることも欠かせない。再生エネの新技術では、日本発の曲がるほど薄い新型太陽電池「ペロブスカイト」や、深い海域にも設置できる浮体式の洋上風力発電などがあげられる。国土が狭いため、既存の太陽光や風力の平地での適地が限られる日本において、再生エネ拡大の切り札とされる。政府はペロブスカイトや浮体式洋上風力といった新技術に関しても、明確な目標設定を年度内に検討する。原発の再稼働や新増設を促す追加策も不可欠となる。政府はこうした背景をふまえ、40年度の電源構成を含めた長期見通しを示して民間投資を後押しする狙いだ。 *5-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240416&ng=DGKKZO80024680V10C24A4TLH000 (日経新聞 2024.4.16) 開かずの踏切 解決の道険し、立体交差に費用と時間 遮断機が下りた時間が長い「開かずの踏切」が、なかなか解消されない。都市部では過密ダイヤでラッシュ時にほとんど開かない状態が続く。遮断時間が長いと通勤通学や物流など交通の障害となるうえ、事故にもつながる。開かずの踏切の現状と解決策をグラフィックスで探る。開かずの踏切とは、朝晩など混み合う時間帯に1時間のうち40分以上閉まっている踏切を指す。国土交通省によると全国に539カ所あり、東京都に288カ所、大阪府に81カ所、神奈川県に76カ所など大都市圏に集中している。最も遮断時間が長いのは、京急線品川駅近くの踏切(東京・品川)で58分。京王線明大前駅(同・世田谷)でも57分と、1時間で3分しか開かない。関西ではJR阪和線鳳(おおとり)駅(堺市)や近鉄大阪線長瀬駅(大阪府東大阪市)が52分。愛知県では近鉄名古屋線蟹江駅(蟹江町)で51分だ。愛知では踏切による渋滞が激しい場所が多い。開かずの踏切は、通勤通学や物流に大きく響く。緊急車両の通行にも支障をきたす。渋滞が続けば二酸化炭素(CO2)排出量も増える。踏切待ちによって発生するトータルの経済損失は年間1兆5000億円との試算もある。世界の主要都市と比べ、東京の踏切の多さは突出している。東京23区の踏切は米ニューヨークの約13倍、パリの約90倍だ。全国には3万2000超あり、踏切大国で知られるインドと同水準だ。欧米では早くから馬車が発達したため、鉄道は建設当初から高架上を走り、踏切は少ない。解決策は限られる。鉄道か道路を高架化・地下化して立体交差にするのが抜本策だが、莫大な費用と時間がかかる。3月には東京都が開かずの踏切が最も多い西武鉄道の一部区間での立体交差事業に着手したが、完成は13年後。事業費は2660億円を見込む。解消への道のりは遠い。 *5-1-3:https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20240314-OYT1T50009/ (読売新聞社説 2024/3/14) 災害時の断水 水道管の耐震化なぜ進まない 大きな地震が起きるたびに、老朽化した水道管が損傷し、断水が繰り返されている。各地で遅れが目立つ水道管の耐震化を急がねばならない。能登半島地震で大きな被害が出た石川県の奥能登地方では、今も断水が続いている。住民は食事や衛生面で不便を強いられ、病院などの運営にも支障が出ている。石川県の水道管の耐震化率は36%で、全国平均の41%よりも低い。街の中心部だけでなく、山あいに点在する集落につながる水道管も至る所で破損し、復旧に時間がかかる要因となっている。道路の寸断で、復旧にあたる作業員も現場到着に困難を極めた。今回の断水は、ひとたび水道網が破壊されたら、容易には立て直せないことを浮き彫りにした。日本の水道網は、高度経済成長期に集中的に整備され、現在では耐用年数の40年を過ぎた水道管も多い。国は、地震が起きても壊れにくく、つなぎ目が外れにくい水道管への更新を推奨しているが、切り替えが進んでいない。水道事業は主に市町村が担っている。人口減や節水技術の向上で料金収入が減る一方、住民の負担になる大幅な値上げは難しく、各地で苦境にある。水道管の更新費用も捻出できない状況だ。道路や 橋梁きょうりょう なども老朽化が深刻だが、水の確保は人の命にかかわる。地震は今後も、いつどこで起きるかわからない。水の安定供給を維持するためには、各自治体がいかに水道事業の効率化を図り、財政基盤を強化できるかがカギを握る。香川県は2018年、県内ほぼ全域の水道事業を統合した。業務の一元化で経費を削減し、設備の更新費用などに充てている。組織の規模を生かし、災害時には早急な人員派遣も可能になる。宮城県は水道事業の運営を民間に委託している。各地域で実情に見合う方法を検討してほしい。限られた予算を有効に活用するためには、どのエリアから水道管の耐震化を進めていくのかという判断も重要になる。大阪府堺市は、災害時に避難所となる学校や、被災者を受け入れる病院に水を送る水道管を優先的に耐震化している。福島県会津若松市は、AI(人工知能)で水道管の劣化度を調査し、その結果を基に更新の順番を決めている。水道行政は4月、厚生労働省から、道路を担当する国土交通省に移管される。道路工事の際、水道管の耐震化も併せて行うなど、一体的な整備につなげるべきだ。 *5-2-1:https://digital.asahi.com/articles/ASS4K7RSNS4KULBH00ZM.html (朝日新聞 2024年4月18日) 地震後に伊方原発3号機の出力2%低下、規制庁「安全には影響ない」 四国電力は18日、前日夜に発生した豊後水道を震源とする最大震度6弱の地震後、運転中の伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の発電機出力が約2%低下したと発表した。地震の影響とみられる。原子力規制庁によると、安全への影響はないという。四国電によると、3号機では水平方向に33ガル(ガルは揺れの勢いを示す加速度の単位)を観測したが、自動停止する設定値190ガルを下回ったため、運転を継続している。17日夜の地震後、タービンに送る蒸気の加熱装置のタンクの水位計に不具合があり、発電効率が落ちたことで発電機出力が下がったという。四国電が原因を調べている。廃炉作業中の1、2号機に異常はないという。 *5-2-2:https://mainichi.jp/articles/20230110/k00/00m/040/069000c (毎日新聞 2023/1/10) 南海トラフ地震後 1週間以内のM8級、発生率は100~3600倍 近い将来起きる可能性の高い「南海トラフ地震」が発生すると、さらに続けて巨大地震が起きる確率は平常時より大きく高まり、1週間以内の場合は100~3600倍になるなどとする試算結果を、東北大と京都大、東京大の研究チームが10日付の国際学術誌「サイエンティフィック・リポーツ」に発表した。チームによると、これまで連続発生する確率の具体的な試算はなかったといい、連続発生を想定した備えが重要だと指摘している。太平洋側の駿河湾から日向灘にかけて延びる海底地形の南海トラフ沿いでは、100~150年間隔で巨大地震が繰り返し発生している。近代では、1944年の昭和東南海地震の2年後に南海地震が起きた。また、1854年には安政東海地震の約32時間後に南海地震が発生したことを示す記録が古文書に残る。このように、トラフ沿いの異なる場所を震源域とする巨大地震が連続する傾向がある。一方、1707年の宝永地震のように、震源域が分かれずトラフ一帯が震源域となった事例もある。福島洋・東北大災害科学国際研究所准教授(地震学)らは、地震の国際的な統計にある巨大地震の連続発生事例と、過去の南海トラフ地震のうち確度が高い1361年以降の履歴を基に、南海トラフ地震が連続発生する確率を最初の地震からの経過時間別に試算した。その結果、地震の規模を示すマグニチュード(M)8級の巨大地震が連続発生する確率は、最初の地震から6時間以内=1~53%(平常時の1300~7万7000倍)▽1週間以内=2・1~77%(同100~3600倍)▽3年以内=4・3~96%(同1・3~29倍)――となった。数値の幅が広いのは、地震の履歴が多くないためという。気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域でM6・8以上の地震が発生し、それに連続して「後発」の巨大地震発生の可能性が高まったと評価した場合、「南海トラフ地震臨時情報」を発表して警戒を促すことにしている。研究結果について福島さんは「連続して発生する確率は時間を変えてもさほど上昇しておらず、地震直後に起きる可能性が高いことが示された。臨時情報への対応の必要性を裏付けるもので、迅速な対応ができるよう日ごろからの備えや訓練が重要だ」と話している。 *5-3-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1230734 (佐賀新聞 2024/4/22) <玄海町核ごみ請願>住民説明会なくスピード採決へ 町議ら「原発政策、町民は理解」 原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場選定を巡り、玄海町の町内3団体が町議会に提出した「文献調査」を求める請願書は、25日に議会特別委員会で採決される。調査を受け入れた北海道の2町村では、町や議会の判断前に住民説明会を開催している。玄海町では今のところ予定はなく、「原発政策を町民は理解していて、説明会をやる必要はない」との意見もある。原発立地自治体ならではのスピード感で判断へ進もうとしている。原発が立地する自治体で調査に向けた具体的な動きが出たのは今回が初めて。先行する北海道の寿都(すっつ)町と神恵内(かもえない)村も、原発とは無縁ではなく、共に北海道電力の泊原発の30キロ圏にある。町に応募の意思があった寿都町は町主催で説明会を開催。神恵内村は商工会が請願を村議会に提出し、議会側の求めで、国や原子力発電環境整備機構(NUMO)が説明会を開いた。神恵内村の担当者は「原発との長い付き合いから安全性もリスクも浸透しているが、地層処分はあまり知られていなかった」と振り返る。2020年当時、村の人口は800人弱で、4地区で計5回の説明会に267人が参加。ほとんど反対意見はなく、それも参考に議会で採決されたという。議会での審議は、委員会への付託から2週間強の期間で行われた。それに対し玄海町では、委員会付託から10日間で採決される見通し。説明会の予定はなく、17日の特別委員会でも早期開催を求める意見は出なかった。特別委の岩下孝嗣委員長は17日の審議終了後、「私たちは町民から付託を受けており、大多数の理解は得ていると思う」と話した。前副町長で区長会会長を務める鬼木茂信さん(73)は、1980年代から延べ数千人の町民が使用済み核燃料の再処理工場の建設が進む青森県六ケ所村などを視察していることを引き合いに「(事業の)中身は分かっていて、町民からあえて説明会を、という声は上がらないかもしれない」と推測する。採決前に説明会を開く必要性について脇山伸太郎町長は「委員会が判断することで、コメントできない」と述べるにとどめた。市長が文献調査を受け入れなかった長崎県対馬市では、推進派、反対派それぞれから請願が出された経緯がある。文献調査に反対している宮﨑吉輝町議は「関心があれば反対請願も出るはず。町民は『もう言っても一緒』と思っているのかもしない」と厳しい表情を見せる。町内の男性(86)は、国が2017年に公表した処分場の適性を示す科学的特性マップで町周辺が「好ましくない地域」に分類されていることを挙げ「(議会は)町民から選ばれているとはいえ、対応が早すぎる」と批判。「せめて町長には多くの町民の声を聞いてほしい」と訴える。 *5-3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15918448.html (朝日新聞 2024年4月23日) 「20億円ほしいわけでは」「原発立地自治体の責任」 核ごみ文献調査、賛同の佐賀・玄海町議は 原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場選定をめぐり、佐賀県玄海町議会は25日、文献調査受け入れを求める地元3団体の請願を特別委員会で採決する。九州電力玄海原発が立地する町での議論は、請願の背景、採決までのスピード、少ない町内の反発など、これまで文献調査を議論したどの自治体とも違う異質の展開となっている。現在、国内で文献調査に応じたのは、北海道の寿都(すっつ)町と神恵内(かもえない)村だけ。長崎県対馬市では昨年4月に調査受け入れを求める地元の動きが表面化し、市議会は同9月に請願を採択したが、市長が同月拒否して頓挫した。これら3市町村に共通するのは、財政難に悩む自治体事情だ。文献調査を受け入れて国から20億円の交付金を得られることの是非も問われた。一方、人口約4900人の玄海町は今年度の当初予算約100億円のうち6割を原発関連収入が占め、貯金に当たる基金は187億円(2022年度末)ある。佐賀県内で唯一、財政が豊かとされる「不交付団体」だ。「20億円がほしくて手を挙げたわけじゃない。冗談で、資源エネルギー庁に20億円いらんと言ったら(先方は)なんと言うやろ、と同僚議員とも話した」。町議の1人はこう明かす。「原発立地自治体として、責任は果たさないといけない。全然、関係なかところに処分場つくるわけなかやん。だから原発自治体で真っ先に手を挙げたかった」とも語り、全国の原発立地自治体の手挙げにつながることを期待した。実際に、請願文の内容もこの町議の考えと重なる。請願は、町旅館組合と町飲食業組合、町内の建設業者11社でつくる町防災対策協議会が1~3月に提出。請願の理由を「原発立地自治体の責務」「能登半島地震があり、九州でも地震が偶発的に発生している。玄海原発の立地の安全を再確認するためにも、文献調査で地質を把握することが必要」などとした。 ■「反対活動、町で数人だけ」 反対派の町議は「文献調査は原発立地自治体の責務じゃない」と反発。請願の根拠のおかしさを指摘した。「文献調査で原発の安全を再確認する」との請願については、推進派の町議からも「これでいいのかと思う部分はあるが、思いは伝わるのでは」との声が漏れる。国が17年に公表した「科学的特性マップ」でも、玄海町は、地下に石炭があり、ほぼ全域が「好ましくない」地域に分類されている。ほぼ全域が「好ましい」地域だった対馬市や寿都町とは対照的だ。それでも町民の間では反発の声が広がっていない。17日、町議会前で「危険原発と永久処分場」などののぼりを掲げたのは、佐賀県唐津市や福岡市など町外の4人だった。玄海町は、プルトニウムとウランをまぜた核燃料を使うプルサーマル発電を国内で初めて認めたほか、福島第一原発事故後に原発の運転再開を全国で初めて認めた自治体だ。原発反対派の80代の町民男性は「今、町内で表だって原発反対の活動に参加できるのは2、3人だけ」と明かす。朝日新聞の取材では、町議全10人のうち7人は文献調査に賛成している。特別委のメンバーは議員全員で、25日の特別委、翌26日の本会議ともに、請願は採択される見込みだ。町議会で請願が付託され、一連の動きが表面化した15日からわずか10日での採決となる。町議会が請願を採択すれば、脇山伸太郎町長の受け入れ判断が問われることになる。脇山町長はこれまで「町のほうから調査に応募する考えはない」と文献調査に慎重だったが、賛成派の町議は「『議会の意見を聞いて判断する』と言っている。変わってきた」と自信をにじませる。 *5-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240423&ng=DGKKZO80188840S4A420C2TJK000 (日経新聞 2024.4.23) 核融合 複数方式を支援へ、政府、まず5年で200億円 発電への道進む後押し 政府は核融合の研究に2024年度からの5年間で約200億円を投じる。従来はトカマク型という大型の炉に特化してきたが、今後は米国で研究が進むレーザー方式などほかの炉型の支援も手厚くする。35年までに原理実証し、50年ごろの実用化を目指す。日本発の破壊的イノベーション創出を目指す大型研究開発プロジェクト「ムーンショット型研究開発制度」に核融合発電が加わり、3月から研究テーマの募集を始めた。6月に締め切り、支援対象を決める。今回の研究支援は35年ごろまでの最大10年間の計画で、前半5年間で200億円を投じる。文部科学省の担当者は「発電に限らず、ロケットエンジン向けや熱利用など様々な用途への応用を視野にチームをつくる」と話す。核融合発電は太陽の中で起きている反応を再現する。燃料をセ氏約1億度のプラズマ状態にして、原子核をくっつけたときに発生するエネルギーを発電に利用する。二酸化炭素(CO2)が発生せず、1グラムの燃料から石油8トン分のエネルギーを生み出す。実用化できれば、脱炭素を進めながら、生成AI(人工知能)や電気自動車(EV)の普及に伴う電力消費の急増に対応しやすくなる。半世紀以上の研究の歴史があり、日米欧など主要国の多くは核融合を実現している。ただ、小規模かつ一瞬にすぎない。発電に結びつけるには、高温のプラズマを長時間にわたって安定して維持するために、高温や放射線に耐える材料の開発などが必要になる。従来、日本では磁力を使って核融合を制御する「磁場閉じ込め方式」のトカマク型を中心に支援してきたが、最近注目が高まっているレーザー方式などの研究も募る。トカマク型はドーナツ状の炉の周囲に強力な磁力を流してプラズマを制御する。装置は大型になるが安定して電気を送れる。トカマク型の国際熱核融合実験炉(ITER)は日米欧中などが協力し、フランスで07年に建設が始まった。投入量の約10倍のエネルギーの取り出しを目指すが、発電しない。日本はITERの成果を生かした原型炉の開発を目指してきた。核融合実験装置「JT-60SA」の運転を23年に始めたが、発電する原型炉の完成は50年ごろだ。欧州も同時期の発電目標を掲げるが、より早期の実用化を目指した動きが海外で活発になっている。英国は40年までに発電できる原型炉を建設する計画で、中国は発電能力を備えた試験炉「CFETR」の建設に着手しており、40年代に発電実証する。民間では米国などのスタートアップが多額の資金を投資家から集めて、30年代の発電を目指す。米コモンウェルス・フュージョン・システムズは、ITERに比べて体積が40分の1ほどのトカマク型発電炉を計画している。ビル・ゲイツ氏などが出資し、調達額は20億ドル(約3000億円)超と最大だ。民間企業で初めてセ氏1億度のプラズマを達成した英トカマク・エナジーなどもある。有力な技術として急浮上したのが、レーザー方式だ。燃料の液滴を四方八方からレーザーで一気に圧縮・加熱し、核融合を起こす。出力の調整や小型化がトカマク型よりも容易だ。世界をリードするのは米エネルギー省傘下のローレンス・リバモア国立研究所だ。放出されるエネルギーが投入エネルギーを上回る「エネルギー純増」を22年に世界で初めて達成した。レーザーを的確に液滴に当てて核融合を起こす技術に優れている。同研究所のジョン・エドワーズ研究顧問は「企業などと協力して30年代には発電も含めた要素技術を実験するプラントを造りたい」と話す。エクスフュージョン(大阪府吹田市)はレーザーに強い大阪大学の技術をもとに、30年代の発電の実証を目指す。一方、安定した発電には高出力のレーザーを1秒間に10回程度照射する必要があり、開発は道半ばだ。もう一つ注目されているのは、磁場閉じ込め方式の一種である「磁場反転配位型」と呼ばれる手法だ。中性子が出ず、安全性がより高いという。この手法で世界をリードするのが米ティーエーイー・テクノロジーズで、グーグルや住友商事などが出資し、累計調達額は12億ドルを超える。日本では日本大学と筑波大学発スタートアップであるリニアイノベーション(東京・港)が開発に取り組む。いずれの方式も一長一短があり、これから開発競争が本格化する。 <高齢者・障害者を差別するのが解決策である筈がない> PS(2024年5月31日追加):*6-1は、①2019年4月に池袋で高齢ドライバーの車が暴走して11人が死傷した事故で妻子を亡くした松永さんら遺族が5月29日に運転していた飯塚受刑者(92歳)と面会した ②飯塚受刑者は「早く免許を返すように伝えて下さい」とした ③松永さんは、「こうならない未来はなかったのか」と改めて悲しみを覚えた ④高齢者の免許返納後の移動支援等、再発防止体制を社会全体で考えてほしいと語った としている。 結論から言って、私は、高齢ドライバーの車が起こした事故で妻子を亡くしたからといって、すべての高齢者の運転を禁止する権利はないと思っている。理由は、i)生物年齢と老化の進捗は人によって異なる ii)自動車免許は遊びで持っているのではなく、運転禁止は仕事からのリタイアや外出禁止と同じ効果になる人が多い iii)仕事からのリタイアや外出禁止は、高齢者の生活権を奪い、社交を封じて健康を害させ、認知症を増やす などである。そのため、池袋での事故から現在まで、裁判を通して、①②③のように、高齢者の運転が悪いことででもあるかのような世論形成がなされたのには大きな違和感を感じた。そのような中、高齢者・障害者の運転を禁止せず生活権や移動権を守りながら交通安全を保つ方法は、*6-2のような自動運転技術であるため、その方向に頭を使って欲しい。自動運転技術を進化させた中国は、*6-3のように、自動車だけでなく道路や社会も一体化した自動運転に取り組んでおり、自動運転技術を高めるためには誰が考えてもそうなるのに、日本は高齢者・障害者に運転を禁止することが解決策ででもあるかのように言っている点が、時代のニーズに合わず、将来性に乏しいのである。 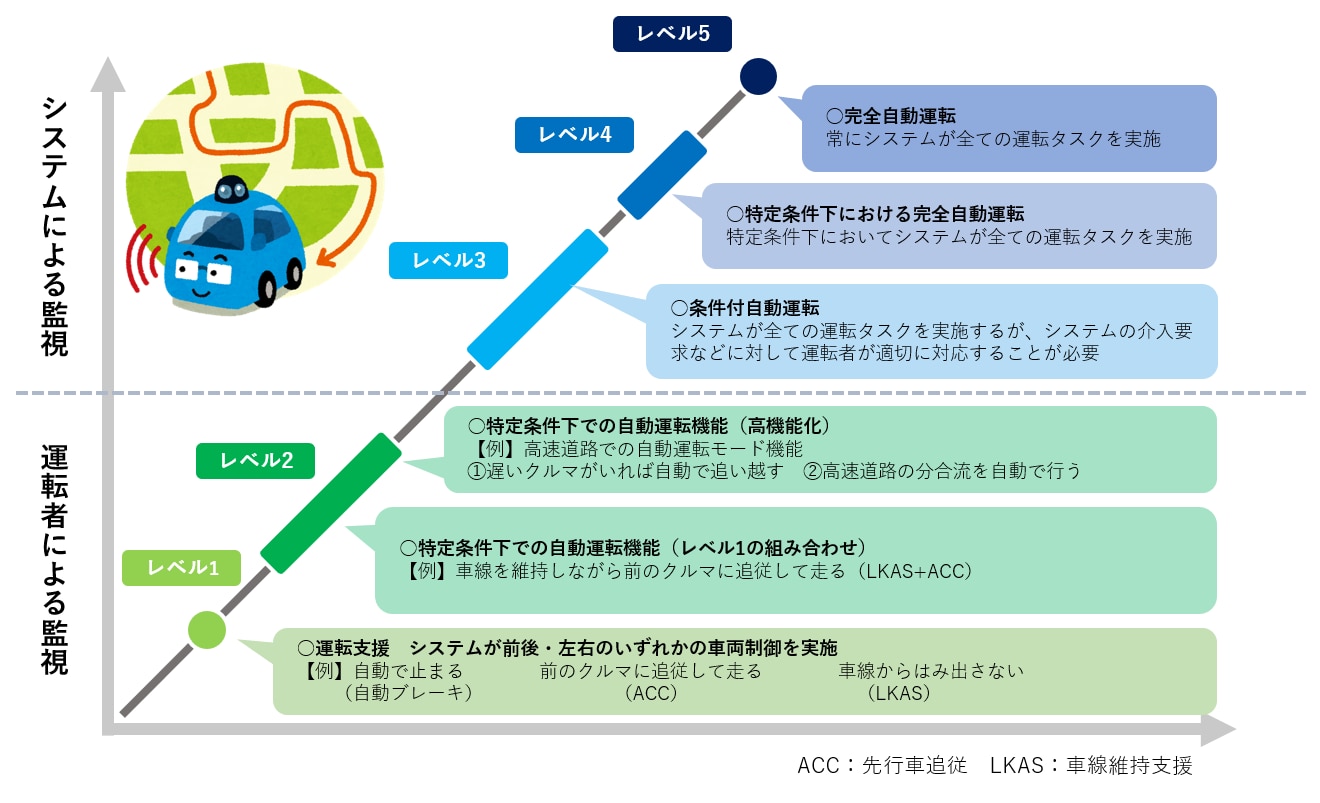 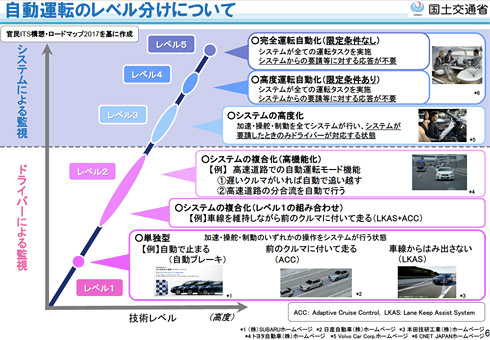 ZMP ITmedia (図の説明:左図のうち、レベル1・2の自動運転は既に実用化されているが、問題は、その機能を搭載している車種が、極めて少なく、高価で、かつ農機具・建機・商用車等には搭載されていないことだ。しかし、日本は課題先進国であるため、レベル3・4・5も速やかに市場投入する政策にすれば、将来のニーズを先んじて実用化できるのに、何に関しても時間と金ばかり使って進捗の遅いのが欠点なのである) *6-1:https://www.sankei.com/article/20240529-LHZIJVG7CRPOFAOTLCG54NVGSY/ (産経新聞 2024/5/29) 池袋暴走事故の松永拓也さんら遺族、飯塚受刑者と面会 「面会受けた勇気無駄にしないで」 平成31年4月に東京・池袋で高齢ドライバーの車が暴走し、11人が死傷した事故で、妻子を亡くした松永拓也さん(37)ら遺族が29日、車を運転していた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三受刑者(92)=禁錮5年の実刑確定=と初めて面会した。刑務官に連れられ、車いすで面会室に入った飯塚受刑者は、うまく言葉が出ない状態だったというが、松永さんらの目を見て問いかけに応じていたという。松永さんは妻の真菜さん=当時(31)=の父、上原義教さん(66)とともに飯塚受刑者が収監されている刑務所の面会所に入り、約50分間にわたり面会。飯塚受刑者は「世の中の高齢者や家族に伝えたいことは」との問いかけには、「早く免許を返すように伝えてください」と答え、最後には2人が面会に訪れたことに対し「ありがとうございました」と絞り出すように話したという。松永さんは今年、遺族の心情を刑務所職員が聞き取って受刑者に伝える「被害者等心情聴取・伝達制度」を利用。飯塚受刑者に再発防止への思いや面会の希望を伝え、4月に面会に応じる旨の返答を受け取った。飯塚受刑者と顔を合わせたのは令和3年の刑事裁判以来。当時、法廷で飯塚受刑者の姿を見て、誰も被害者や遺族、加害者にならない世界はなかったのかと感じたという松永さん。面会後の記者会見では、「今までで一番近い距離で会話をすることができた」と振り返り、月日を経て面会室でアクリル板を挟んで向き合い、「こうならない未来はなかったのか」と改めて悲しみを覚えたという。また、高齢者の免許返納後の移動支援など、再発防止のための体制を社会全体で考えてほしいと語り、「彼が面会を受けたという勇気を無駄にしないで」と訴えた。 *6-2:https://toyokeizai.net/articles/-/742707 (東洋経済 2024/3/24) カギは「LLM」、完全自動運転を目指す大実験の中身、半導体チップも自前で開発するTuringの挑戦 2022年11月にOpenAIが公開したAIチャットボット「ChatGPT」は、多くの企業の業務プロセスで利用されるほど、一気に身近な存在となった。この技術の基となるLLM(大規模言語モデル)は、AIの能力を大幅に向上させ、まるでAIが「脳」を持っているかのごとくふるまうことを可能にした。そんなLLMを、自動運転に応用させようとしている日本企業がある。2021年に創業したTuring(チューリング)だ。Turingは「We Overtake Tesla(テスラを追い越す)」をミッションに掲げ、完全自動運転のEV開発を進める。山本一成CEOは、過去にコンピュータ将棋プログラム「Ponanza」を開発。山本氏と共同で創業した青木俊介CTO(最高技術責任者)は、アメリカのカーネギーメロン大学で博士号を取得し、自動運転システムの開発・研究に従事してきた。2024年2月には、生成AIの基盤モデルを開発する事業者向けに経済産業省などが行う支援事業に、唯一「製造業」の企業として採択された。今回の助成を受け、約7.4億円相当のGPU(画像処理半導体)の計算資源も活用し、開発を進める。 ●レベル5の完全自動運転を目指す 自動運転はその段階に応じてレベル1~5に分けられる。現状、多くの市販車はレベル2などが中心で、アクセルやブレーキ、ハンドルの機能が部分的に自動化されている段階だ。Turingが目指しているのはレベル5。あらゆる条件下ですべての運転操作を自動化する、完全自動運転だ。その実現に向けて、なぜLLMに目を付けたのか。これまで自動運転の手法は大きく2つあった。1つは、レーザー光を車体に取り付け、その周囲に反射させる「LiDAR(ライダー)」という技術で、周りにある物体を3次元で認識する手法だ。センサーベースの高精度な3次元の地図をあらかじめ作成しておき、車のセンサー情報と合わせて、今どの辺にいるかを観測する。この手法は、ロボット掃除機などにも使われている。2つ目は、2010年後半に普及した、カメラと深層学習のAIモデルを組み合わせた手法だ。複雑なセンサーや事前の地図情報の取得を必要とせず、画像認識ベースで周囲の障害物の有無や位置情報などを全部調べることができる。ただ、これらの手法では完全自動運転を目指すうえで限界があった。TuringでAI開発全般のマネジメントを行う山口祐氏は「従来の手法でも9割程度は実現できるが、道路では子供の飛び出しや、見たことないような標識などが当然のようにいろんなところで出てくる」と話す。完全自動運転では、このような稀なケースにも完璧に対応しないといけない。視覚情報だけでの対処には限界があり、人間が普段運転しているときに頭で考えるような、幅の広い認知・思考能力などが必要になるという。そこでTuringが考えたのが、LLMの活用だった。Turingでは、まず言語を理解するLLMから画像や音声なども認識するマルチモーダルへ、そして空間把握や身体性を認識するAIを経て、完全自動運転AIへの発展を目指す。 ●難しい場面でも人間に近い選択が可能 Turingは昨年、OpenAIのLLM「GPT-3.5 Turbo」を使って車を制御する実験に取り組んだ。例えば車のカメラが前方の状況を撮影し、ドライバーが「○○してください」などと話すと、それを音声認識技術でテキストに起こしてGPT-3.5 Turboに渡す。GPT-3.5 Turboは、撮影された画像やテキストの情報に基づいて、目的地までの経路などに関するパスを出し、計算する。TuringのLLMを活用した自動運転の実験の様子この実験では赤色、青色、黄色のカラーコーンを設置して、「バナナと同じ色のコーンに行って」と抽象的な命令を出しても、正解を選ぶことができた。また、トロッコ問題のようにどの進行方向を選んでも犠牲者が出てしまうような場面では「どっちに行ってもけがをするので、一旦停止します」と動かない状態になった。複雑な状況を解釈できるマルチモーダル生成AIや高速な半導体、車体制御まで行える自動運転AIシステムなどがそろえば、将来的にはこのような倫理的な判断もできるようになる。「われわれ人間は、運転中に稀なシチュエーションに遭遇しても、運転していないときに学習した経験などを応用して対応できる。それと同じ対応を目指すには、非常に広範な知識や常識のようなもの、さらに思考能力が必要になってくる」。ただ、英語圏で学習したGPTなどは、日本の交通環境に関する情報や交通常識が欠落している。自動運転で活用する以上、国ごとの交通常識などを身に付ける必要がある。Turingでは、マルチモーダル開発ツール「Heron」で学習を行う同社独自のLLMの開発を続ける。LLMで完全自動運転を達成するためには、それ専用の半導体チップも必要となってくる。そこでTuringは2023年12月、半導体チップと車載用LLMアクセラレーターを開発するチームを発足させた。 ●TuringのLLMを活用した自動運転の実験の様子 半導体の自社製造を決めた背景には、車ならではの制約があることが大きい。例えばスマホでChatGPTを使う場合、基本的にはネットワークを介して通信を行う仕組みになっており、応答までに数秒のラグがある状態だ。チャットボットの応答なら数秒のラグがあっても問題ないが、時速100km(1秒間で約30メートル)で進むような車では、そのラグは致命的となる。また、車は夏場に70℃を超えたり、冬には氷点下になったりすることもある。このような環境下では、普通のサーバー用の半導体チップはまるで動かない。さらにGPUに使われるメモリーは振動や電磁波に弱く、通常のGPUでは運転中の振動により壊れてしまう。エヌビディアも車載向けGPUなどを出しているが、サーバー向けのハイエンドなGPUに比べると性能が10分の1になってしまうという。これでは自動運転で1秒間に10回など推論させるとなると、スピードが追いつかない。そうした欠点を埋めるためにも、自分たちで専用の半導体を作るしかないという決定に至った。 ●世間に受け入れられるためのハードル Turingが開発している半導体は、同社が作るAIモデルでしか動けないが、推論が速いという。既存技術の積み重ねで開発を進めており、具体的な性能の検証段階に入っている。技術的な達成度合いを高めていったところで、完全自動運転が世間に受け入れられるためには、乗り越えなければならないハードルがある。倫理観の問題だ。この先AIの精度がさらに向上しても、数学的に「100%」の正解を実現するのは難しく、自動運転での事故も0にできるとは言えない。「例えば、人間による運転よりもAIだと事故率が10分の1になったらどうかなど、社会的に許容されるラインはどこになるのかを常に考えている。技術の積み重ねや法整備などに関する議論を進めつつ、世間の人に丁寧に説明していく必要がある」(山口氏)。Turingは、完全自動運転EVの量産開始の目標時期を2030年と定める。山口氏はこれを「スマホみたいな車」と表現する。かつてAppleは、iPhoneをハードウェアだけじゃなく、ユーザー体験を考えたようなソフトウェアまで一貫して作ったことで、世界的な普及に成功した。Turingも、EVとAIモデルを垂直的に統合したかたちで開発を進め、自動車業界での革命を見据えている。 *6-3:https://wisdom.nec.com/ja/series/tanaka/2022072201/index.html (次世代中国 2022.7.20) 方向転換する中国の自動運転、「クルマ単体」から道路、社会と一体化した「車路協同」へ 自動運転技術の進化にともない、中国の政府や企業が自動運転に取り組む方向性の変化が明確になってきた。一言でいえば、クルマ単体での自立した自動運転の実現を目指す姿勢から、「道路の智能化」を加速し、クルマと道路が一体となった「車路協同」路線への転換である。その背景には、米国を中心に広がってきた「クルマ単体」での完全な自動運転の実現を目指す動きが、なかなか商業化のメドが見えないという状況がある。その点、道路を中心とした社会インフラの整備は、中国の政治体制、メーカーと政府の協力関係など、自国の強みを活かしやすい。早期の社会実装による効果が大きく、営利化が見込めるとの読みがある。さらに言えば、IoT(Internet of Things、モノのインターネット)ですべてのモノが情報ネットワークでつながる時代を見据え、信号機との連動や渋滞情報、駐車スペースの利用状況共有など都市の「交通管理」と自動運転を結びつけ、インテリジェント化した移動のシステムを実現し、政府の総合的な統治能力を高めたいとの思惑がある。 <教育について> PS(2024年6月24日追加):*7-1のように、「優れた人材を育てなければ国が衰える」として、中央教育審議会特別部会委員の伊藤慶応義塾塾長が国立大値上げの提案をされたのは、問題意識と解決策が逆であるため驚いた。伊藤氏は、①18歳人口が2040年に82万人まで減少する ②高等教育の質向上が必須 ③内容は、教養・判断力・議論力・人間性・語学力・設備更新・少人数教育等々で高水準の教育には最低でも学生1人当たり300万円必要 ④質向上のためには同じ条件で競い合わせ、研究・教育の質が低い大学が淘汰される必要がある とされている。 このうち、①については、18歳人口が2040年に82万人まで減少したとしても、下の左図のように、大学入学者が18~19歳に著しく集中しているのは日本だけで、他国は幅のある状況から見れば、社会に出て問題意識を持った後に大学で学び直したり、留学生を受け入れたりすることも盛んなのだと思う。また、②③については、高等教育の質向上が重要であることには賛成だが、国公私立の別を問わずに、その半分を学生が負担しなければならない理由はなく、国公立は設置主体の負担割合が大きくても問題はない筈だ。そもそも、「格差是正」と称して、私立の授業料に国公立の授業料を揃えたことによって、中央の図のように日本の大学進学率が低くなり、大学院進学率はさらに低くなったのだ。そして、これにより、まともな経済成長が抑えられてきたことは、右図の中国や米国と比較すれば明らかである。 それでは、④の質向上のために競い合わせる「同じ条件とは何か」について考えると、入試科目に理系・文系の重要科目を含み、入試時点で受験生にとっての負担は重いがバランス良く知識を持たせる国公立大学は、授業料が安くても同じ条件と言える。何故なら、政治・経済・法律を論じるにも、生物・物理・化学・生態系等の基礎知識は必要不可欠だからで、その例は、*7-2のように、日本の排他的経済水域内にある南鳥島近海に希少金属資源を発見しても、経済成長や安全保障に繋げる発想のわかない政治・経済・法律学者を作らないためである。また、*7-3のように、発癌性の指摘される有機フッ素化合物(PFAS)が各地の浄水場や河川で検出されたり、フライパンのコーティングや食品包装に幅広く使われていても、人体への影響がピンとこない政治・法律・経済学者を作らないためでもある。つまり、環境と経済は対立するものではなく相互作用しながら発展していくものだが、その相互作用の仕方は入試科目に理系・文系科目をバランス良く含めて大学入試までに勉強させておかないと、考えることができないのだ。 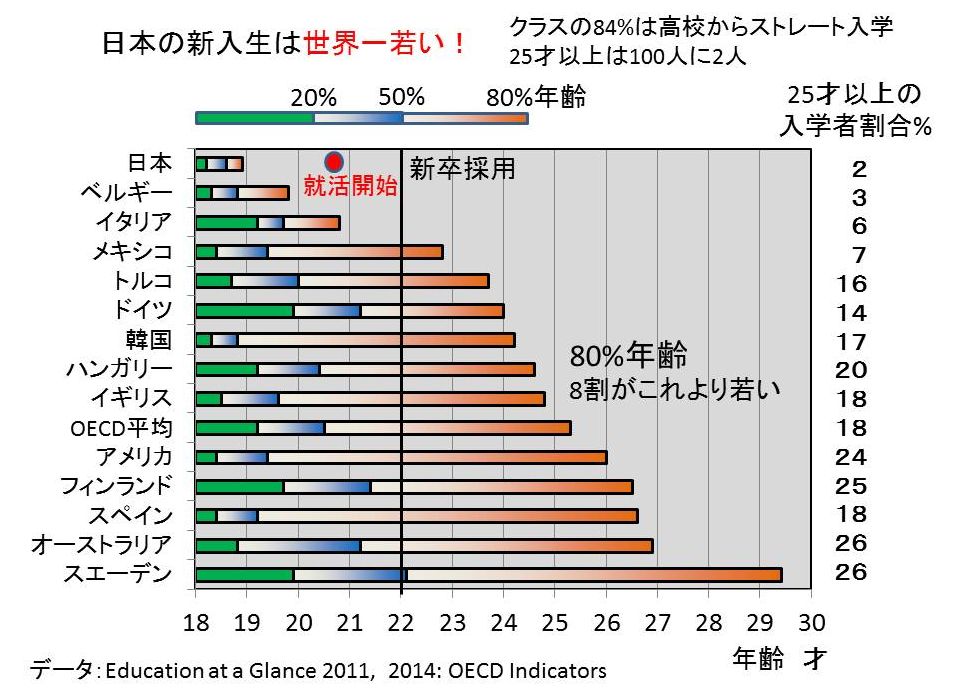 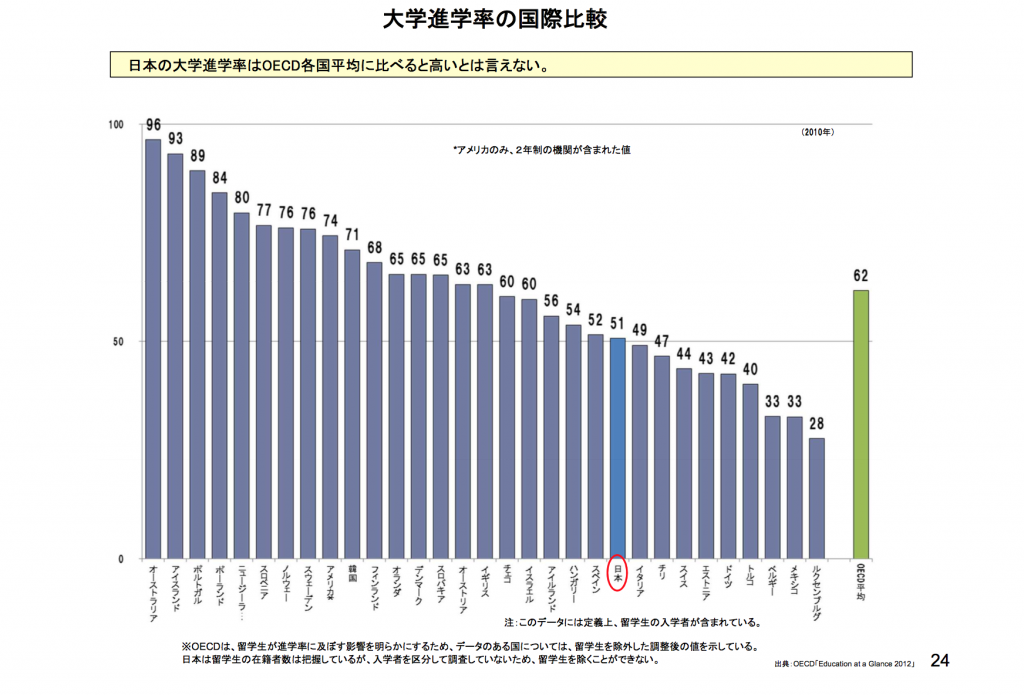  大学入学年齢国際比較 大学進学率国際比較 高等教育学生数国際比較 (図の説明:左図は各国の大学入学年齢で、日本はとりわけ18~19歳に集中している。また、中央の図は大学進学率の国際比較で、日本はOECD諸国だけでなく他の先進国と比較しても高くない。さらに、右図のように、研究開発を進めて経済成長の盛んな米国や中国と比較して日本の高等教育学生数は著しく少なく、これは、今後の経済成長に大きく影響すると思われる) *7-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15965480.html (朝日新聞 2024年6月24日) 東大、値上げ案の波紋 授業料「2割増」、物価高で財務悪化 国立大の授業料をめぐる動きが活発化している。東京大学が2割増額する案を検討していることが表面化し、賛否両論がぶつかり合うなか、議論は他の国立大にも広がっている。なぜ今こうした動きが起きているのか。値上げは他の国立大にも波及するのか。 ■世帯年収450万円未満の学生も14% 「教育・研究環境の国際化やデジタル化を進めるため、2割値上げする案を検討している」。21日夜にオンラインで開かれた、藤井輝夫総長が東大生と意見を交わす「総長対話」。学生からは、値上げとセットで示された授業料減免の内容などについて質問が相次いだ。また、「値上げせずに済むように国に予算増を求めるべきだ」などと反対する意見が続いた。国立大の授業料は、文部科学省令に基づき各大学の判断で「標準額」から20%まで増額できる。東大は標準額と同じ53万5800円。2005年度から据え置いてきた。東大は今回、学部も大学院も20%増額し、64万2960円にする案を検討している。対象は来年度の入学者からで、在学生は対象外だ。値上げとセットで、授業料全額免除の対象を現在の「世帯年収400万円以下の学部生」から「同600万円以下の学部生・院生」まで拡大し、「同600万~900万円の学部・大学院生」も状況を勘案して一部免除することも検討している。7月中旬にも値上げを正式発表する考えだ。全国86国立大のうち、学部の授業料を標準額から引き上げているのは、東京工業、東京芸術、千葉、東京医科歯科、東京農工、一橋の6大学。東大が値上げすると7大学目となる。東大は世界の研究機関と競うために、研究施設・設備の整備などに巨額の資金を必要としている。一方、教職員の人件費や研究費に充てる国からの運営費交付金は、法人化した04年度の926億円から減少し、22年度は830億円。収入源を増やそうと産学連携や寄付金獲得などに力を入れ、この間に収入額は2067億円から2937億円に増えた。だが、最近の光熱費や物価の高騰で、支出が一気に年数十億円も増加。財務状況が悪化するなかで、「聖域」としてきた授業料の値上げに踏み切ろうとしている。東大の収入全体からみれば、22年度の「授業料、入学料、検定料収入」は5%(149億円)にとどまる。値上げでの増収は約29億円と見込まれ、財務上の効果は限定的だ。しかし同大幹部は「使途に制約がある寄付金や共同研究の資金などと違って何の『ヒモ』もついていない。授業料収入は、大学にとって一番使いやすいお金だ」と明かす。値上げを検討する背景には、東大生には裕福な家庭の出身者が多いという事情がある。東大が21年度に実施した調査によると、世帯年収が950万円以上の学生は54%と半数を超える。学内には「値上げの影響は限定的」との見方がある。一方で、世帯年収450万円未満の学生も14%いる。5月にあった東大の学園祭で値上げ反対を訴えた学生の中には、授業料免除を受けている女性もいた。「東大生が全員、恵まれているわけではない」。免除には成績要件があり、「審査でいつ免除が打ち切られるかわからない不安がある」。東大が値上げとセットで検討している授業料減免の対象拡大案に、同様の要件が付けられることを心配している。日本学生支援機構の有利子奨学金を借りる文系学部4年の男子学生も、厳しい生活を送る。入学後にアルバイトを始めたが、体調を崩すなどして収入が減少。物価高騰もあって食費を削った結果、入学時から4キロも体重が減った。妹も一人暮らしで私立大に通う。実家の母が夕飯をレトルトカレーにしていると知り、家族に食費を削らせていると申し訳なく感じたという。大学院進学をめざしているため、値上げされれば自分も対象になる。大学院入試に向けて勉強中で、就職活動はしていない。「この時期に値上げを決められても、進路変更は難しい」(増谷文生、山本知佳) ■電気代や人件費、他大学も苦境 値上げの動きは他の国立大に波及するのか。 旧帝大に取材したところ、7大学のうち東大を除く北海道、東北、名古屋、京都、大阪、九州の6大学の総長がそろって「具体的な検討をしていない」と答えた。このうち九州大の石橋達朗総長は5月下旬の会見で、現時点での値上げの検討を否定したうえで「大学はいま非常に苦しい状況。電気代や実験道具の値上げ、人件費上昇などがあり、授業料値上げも考慮に入れなければならない」とも述べた。広島大の越智光夫学長は5月下旬の会見で「2年以上前から授業料をどうするか検討している。上げる、上げないも含めて調整している」。西日本のある国立大の学長は「値上げはしたいが、周辺の国立大が上げない限り踏み切れない」と明かす。こうしたなか、国立大学協会の永田恭介会長(筑波大学長)は6月7日に緊急記者会見を開き、国立大の財務状況について「もう限界」とする声明を発表。運営費交付金の増額を訴えた。永田会長は「中長期的に、学生と国が授業料をどのような割合で負担するのか、しっかりと国全体で議論しなくてはならない」と強調した。(伊藤隆太郎、副島英樹) ■優れた人材育てなければ国衰える 国立大の値上げ提案 慶応塾長・伊藤公平氏 少子化が一段と進む2040年以降の大学のあり方を検討している中央教育審議会の特別部会でも値上げの議論がある。委員の伊藤公平・慶応義塾塾長は、国立大授業料を現標準額の約3倍にあたる150万円程度に引き上げるべきだとの資料を出し、議論を呼んだ。真意を聞いた。 ◇ 特別部会は今年度中に提言をまとめる。高等教育の質向上のための改革案を示し、必要な費用に対する自己負担額を150万円と示したのだが、後半の数字だけが独り歩きした感がある。東大の値上げの議論とは関連性は全くない。 ――なぜ値上げが必要なのか いま18歳人口は約106万人。40年には82万人まで減るという推計もある。科学技術の発展や人工知能(AI)の浸透などの中で社会水準を向上させ続けるためには、高等教育の質向上が必須。優れた人材を育てなければ国力は衰える。教養や判断力、議論する力、AIを使いこなす人間性や語学力。留学や設備更新も必要だし、論文添削や少人数教育には人件費がかかる。40年以降、高水準の教育には最低でも学生1人当たり300万円は必要と考え、受益者負担という視点から半額負担を提案した。一方、国立なのだから公費補助の充実は不可欠だ。 ――経済的理由で国立大を目指す人もいる 給付型奨学金制度を拡充するなどの「アクセス保障」が欠かせない。払える人は払う。少しでも苦しい人には家計の状況に応じた制度を用意する。学費の個人負担が減るバウチャー(クーポン)制度の導入も一考すべきだ。こうした政策の実現のため、公財政支出を増やさねばならない。 ――教育費無償化を求める声も 二つの意味で反対だ。財政に余裕がある自治体のみが実施すれば、他の地域の空洞化が進む。もう一つは、研究・教育の質が低い大学が淘汰(とうた)されず健全な競争にならない。日本の大学は約800校。国公立・私立ともに緩やかに淘汰が進むだろう。8割近くの大学生が通う私立は私立で頑張る。ただ、質の向上のためには同じ条件で競い合わせる必要がある。(聞き手・大内悟史) ■使途、学生や社会に丁寧な説明を 小林雅之・桜美林大特任教授(高等教育政策)の話 大規模大は収入が多い一方で設備費や光熱費、人件費など支出も多い。東大が値上げで収入を増やしたいと考えるのは、支持はできないがやむを得ない判断だ。他にも内々に検討している大学は多いだろう。各国立大が一斉に値上げへと動く可能性もある。だが、国立大の大きな使命は、住む地域や家計状況に関わらず、高等教育の機会を提供することだ。やむを得ず値上げをする場合でも返済不要の奨学金や授業料減免の拡充をセットで行うよう強く求めたい。米国には授業料が年1千万円と高額な有力大もあるが、そうした大学でも9割の学生が経済的支援を受けている。値上げするのであれば、何に使うのか、学生や社会に丁寧に説明することも重要だ。 ■値上げ難しい地方、軽視しないで 石原俊・明治学院大教授(社会学)の話 国は本来、国立大への運営費交付金の減額分を元に戻すべきだ。今の減額や物価上昇が続くなら東大の授業料値上げは選択肢の一つだが、日本を代表する大学の動きは影響が大きい。地方国立大にも影響が及び、授業料を値上げできない大学との差が広がりかねない。大学の将来像をめぐる慶応の伊藤塾長の提言も頭ごなしに否定はできない。ただ、授業料値上げが難しい中小規模の地方国公立大も、公務員や教員などの確保に不可欠だ。国公立大は、東大のような国際競争にさらされる有力大学だけでなく、地域を代表する中堅の大学、規模が小さい大学を軽視してはならない。私立大も、首都圏などの大規模私学だけでなく地方の中小私学を見捨ててはならない。 *7-2:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81574570R20C24A6EA5000/ (日経新聞 2024年6月22日) 南鳥島近海に希少金属 コバルトなど2.3億トン、日本財団・東大 日本財団と東京大学は21日、日本の排他的経済水域(EEZ)内にある南鳥島(東京都)周辺の深海にコバルトやニッケルなどのレアメタル(希少金属)を含む鉱物資源があるという調査結果を発表した。資源量は約2億3000万トン以上と推計され、コバルトは国内消費量の約75年分、ニッケルは約11年分に相当するとみる。2026年以降に企業を集めて商業化を目指す。東京大学の加藤泰浩教授らは16年、南鳥島沖の海底でマンガンやコバルト、ニッケルを含む「マンガンノジュール」という球状の鉱物を大量に見つけていた。日本財団と共同で24年4~6月に岩石などを採取する装置や遠隔操作型の無人潜水機を使い、水深5200~5700メートルの海底を100カ所以上探査した。すると約1万平方キロメートルの範囲にマンガンノジュールが約2億3000万トンあるのが確認できた。採取したマンガンノジュールを詳しく調べ、コバルトの資源量を約61万トン、ニッケルは約74万トンと試算した。加藤教授は「マンガンノジュールの密度が高く、相当にいい物がある。産業育成のために開発につなげたい」と話す。マンガンノジュールは鉄やマンガンの酸化物でできている。人のこぶしくらいの大きさで、マンガンを約20%、コバルトやニッケルを1%以下含む。大昔に海に沈んだ魚の骨の周りに数百万~数千万年かけて金属がくっついてできたとされる。日本財団などは1日あたり数千トン規模のマンガンノジュールを採取する実証試験を25年に始める計画だ。採取したマンガンノジュールは金属の精錬を担う国内企業に提供する予定だ。26年以降に日本財団が中心となって企業を集めて共同事業体を作り、商業化を目指す。 *7-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1266923 (佐賀新聞 2024/6/22) 政府、水道水のPFAS全国調査、汚染の実態確認へ 発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)が各地の浄水場や河川で検出されている事態を受け、政府が水道水の全国調査に乗り出したことが22日、分かった。汚染の実態把握が急務と判断した。PFASに特化し、小規模事業者にも対象を拡大した大規模調査は初めて。政府関係者が明らかにした。今後進める水質目標の見直しに生かす。政府が5月下旬、47都道府県の担当部署や国認可の水道事業者などに文書で要請した。PFASの健康影響については確定的な知見がなく、政府は水道水や河川の暫定目標値について、代表的な物質PFOSとPFOAの合計で1リットル当たり50ナノグラム(ナノは10億分の1)としている。PFASは水や油をはじき、熱に強い特徴があり、フライパンのコーティングや食品包装など幅広く使われてきた。自然環境では分解されにくく「永遠の化学物質」とも呼ばれる。米軍や自衛隊基地、化学工場周辺で検出される事例が多い。環境省が38都道府県の河川や地下水を対象にした2022年度の調査では、16都府県で目標値を超えた事例があった。今回の調査対象は、水道の蛇口から出る水などで20~24年度に検出された最大濃度や、関連する浄水場の名前など。目標値を超えた場合の対応や、検査していない場合は理由や今後の実施予定についても回答を求める。期限は9月末。岡山県吉備中央町の浄水場では、目標値の28倍となる1リットル当たり1400ナノグラムのPFASが検出。取水源の上流近くに野ざらしで保管された使用済み活性炭から流出した可能性が高い。政府関係者は「工場などが上流になくても、下流で高濃度になる可能性が否定できない状況だ」と危機感を強めている。PFASは近年、日本水道協会の水道統計でも検査項目の一つとして調べられているが、対象は給水人口が5千人超と規模の大きい水道事業などに限定。今回は小規模な簡易、専用水道にも対象を広げた。国土交通省によると、給水人口5千人超の水道事業の数は23年3月末時点で約1300。5千人以下の簡易水道は約2380、社宅などの専用水道は約8170ある。PFAS 有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物とポリフルオロアルキル化合物の総称。1万種類以上の物質があるとされる。耐熱や水、油をはじく特性から布製品や食品容器、フライパンのコーティングのほか、航空機用の泡消火剤に使われてきた。有害な化学物質を規制する「ストックホルム条約」でいくつかの物質が対象となっており、国内ではPFOSが2010年、PFOAが21年に輸入や製造が原則禁止され、その後PFHxSも追加された。 <厚生年金の企業規模要件撤廃> PS(2024年6月27日追加):私は、*8のように、厚生年金加入の「企業規模要件」を撤廃するのに賛成だ。その理由は、短時間労働者の厚生年金加入を拡大して年金財政に資するというよりは、多くの人が保険料を労使折半することの恩恵を受け、退職後の生活不安をなくすことが必要だからだ。しかし、その期待が裏切られないためには、厚労省はじめ日本年金機構は集めた年金資金を適切に運用し、年金保険料を払えばそれだけ給付額が増えて払い損にならないという仕組にすべきである。そうすれば、年金保険料を支払うことに抵抗感はなくなるし、中小企業も、保険料支払いの支援を受けるよりは、人手不足時代でAI使用・デジタル化を進めれば省力化可能な時代であるため、労使折半で保険料を負担できる雇用者数にして事業を進めれば良いと思う。 *8:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1269144 (佐賀新聞 2024/6/26) 厚生年金、企業規模要件を撤廃へ、パートら130万人加入 厚生労働省は、パートら短時間労働者の厚生年金加入を拡大するため、勤務先の従業員数が101人以上(10月からは51人以上)と定めている「企業規模要件」を撤廃する方針を固めた。職場の従業員数にかかわらず厚生年金に加入できるようにし、将来受け取る年金額を手厚くする狙い。対象は約130万人に上るとみられる。関係者が26日、明らかにした。厚労省の有識者懇談会が、企業規模要件に関し「撤廃の方向で検討を進めるべきである」と明記した報告書を7月1日に取りまとめる。これを踏まえ、厚労省が施行時期を検討し、2025年通常国会に関連法改正案の提出を目指す。現在、短時間労働者が厚生年金に加入するには、企業規模に加え(1)週の労働時間が20時間以上(2)月給8万8千円以上―といった要件を全て満たす必要がある。これらのうち企業規模の撤廃を優先する。撤廃により保険料を労使で折半することになり、新たな費用や事務負担が増えるため、中小企業への支援策も検討する。個人事業所で働く人の厚生年金加入も推進する方針。現在は従業員5人以上の「金融・保険」など17業種に限り加入義務が生じる。これを宿泊業や飲食業にも拡大する方向で調整する。対象人数は約30万人を見込む。厚労省は、将来の年金給付水準を点検する財政検証の結果を7月3日に公表。企業規模要件の撤廃による給付底上げ効果についても試算する。厚生年金 会社員らが対象の公的年金。加入者は2022年度末時点で約4618万人。保険料は労使が折半して支払う。納めた保険料に応じ、将来受け取れる額が変わる。厚生労働省によると、平均的な給与で40年間働いた夫と専業主婦のモデル世帯で、現在の受給額は月23万483円。自営業者や無職の人らは国民年金に加入する。
| 財政 | 02:37 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2023,08,17, Thursday
(1)日本の財政 ← インフレ政策だけで経済成長し、再建できるわけはないこと
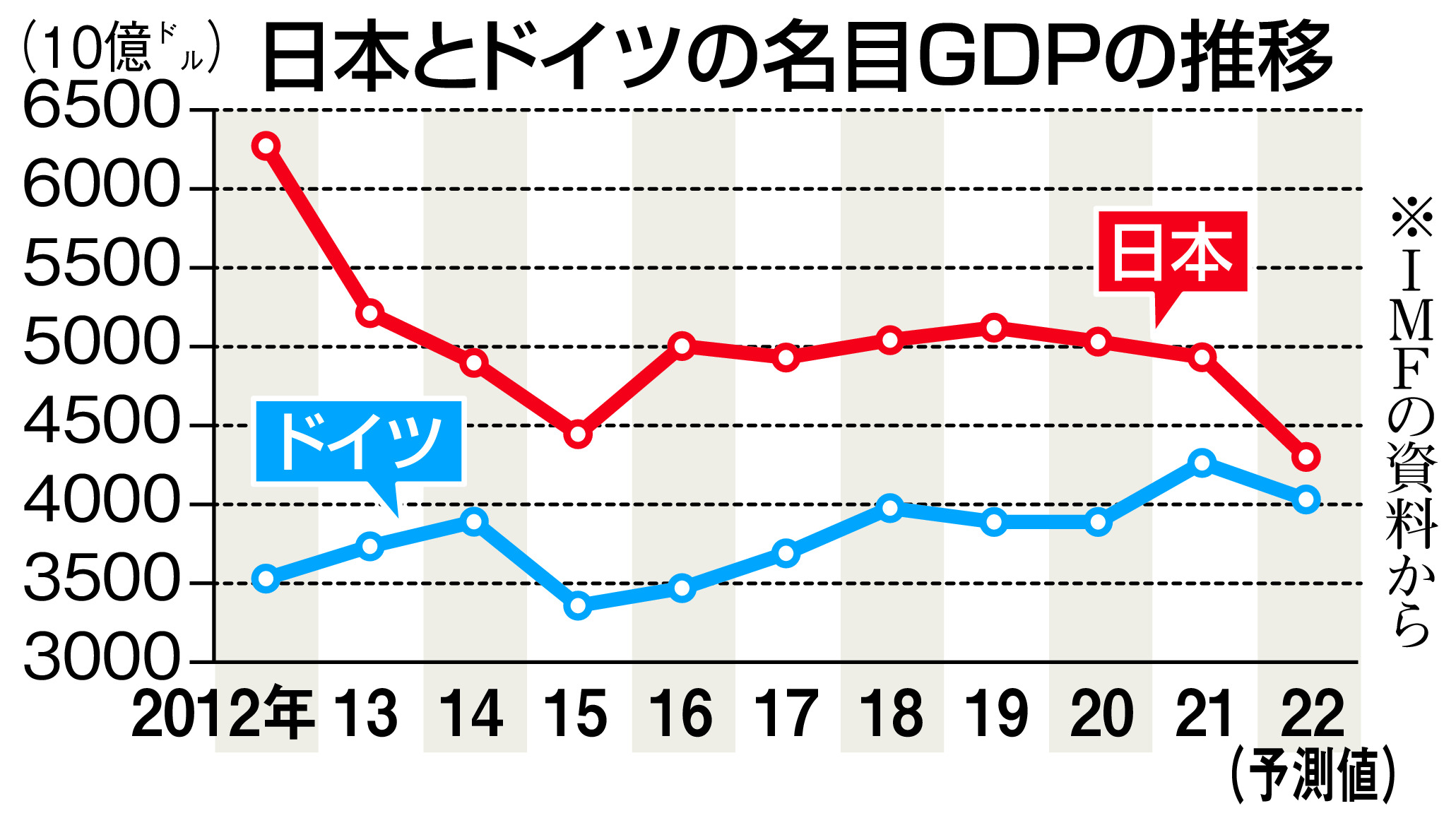 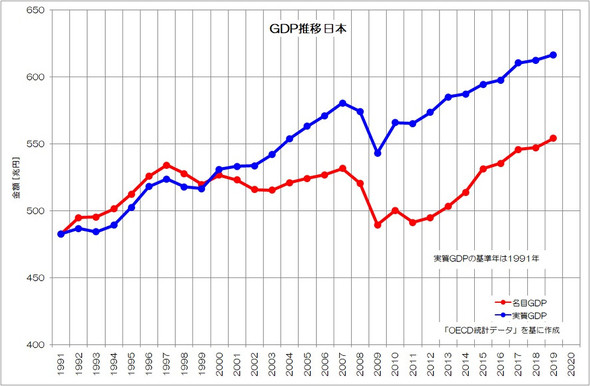 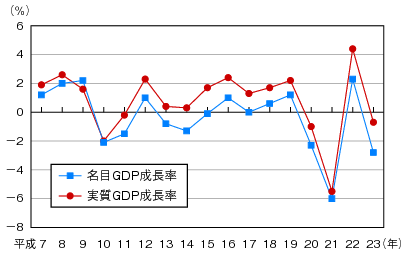 3023.1.22産経新聞 2021.7.21Monoist 総務省 (図の説明;左図のように、日本の名目GDPは、日本よりも人口の少ないドイツの名目GDPと比較して、2012年には大きな差があったが、2022年には殆ど差がない。この間、日本では金融緩和が続けられ、イノベーションがつぶされたが、ドイツでは逆に脱原発やEV化を計画的に行った。また、中央の図のように、日本における実質GDPは、1991年から1999年までは名目GDPより小さかったが、2000年以降は名目GDPより実質GDPの方が大きい。これは、1991年に崩壊したバブルの後始末が1999年頃までかかり、2000年以降にやっと正常軌道に乗ったからである。さらに、右図は、1995年~2021年の名目GDP成長率と実質GDP成長率の推移であり、殆ど同じ動きをしているが、少しはイノベーションが進んだ1999年以降2009年までは実質GDP成長率の方が大きかったのである) 1)名目600兆円経済だから何か? *1-1-1は、「内閣府が発表した4~6月期のGDP速報値で、物価変動の影響を除いた実質季節調整値が3四半期連続プラス成長・前期比1.5%増・年率換算6.0%増だった」と大喜びで書いているが、2022年は上の左図のように、コロナによる経済停止で日本は著しくGDPが下がっていたため、2022年と比較すればもとに戻りつつある現在、GDPが増えるのは当然である。 さらに悪いのは、個人消費が弱くなっているため、前期比年率で内需はマイナス1.2ポイント、外需はプラス7.2ポイントと輸出に頼って全体を上げており、これは、国民は貧しくなり、先進国に輸出することで稼いでいる開発途上国型経済に戻りつつあるということなのである。 そして、これは、インフレで実質賃金を下げた上に、65歳以上には100%公的年金生活世帯が24.9%、80~100%公的年金生活世帯が33.3%もいるのに、年金給付額を下げ社会保険料を上げて可処分所得を減らし、インフレ政策で物価を上げたことが原因である。 そのため、実質GDPが560.7兆円とコロナ前のピーク2019年7~9月期の557.4兆円を超えても国民が貧しくなったことに間違いはなく、需要の大半を占める消費が物価高で落ちて、耐久消費財の白物家電も下押し要因となり、その結果、設備投資も伸びなかったのだ。 そのような中、*1-1-2は、①日銀は長期金利が0.5%の上限を一定程度超えるのを容認すると決めた ②日本経済は長期にわたるデフレ不況を克服してインフレの下で新たな成長に向かいつつある ③政府と日銀が慎重な経済運営を続けるなら、名目国内総生産(GDP)600兆円超の思ってもみなかった視界が開ける ④物価が上がりだして名目GDPが押し上げられた ⑤GDPだけでなく、企業の売り上げ・利益・働く人の給与明細・株価・政府の税収などの目に見える経済活動は「名目」で表示される ⑥デフレ脱却が大きな影響を及ぼすのは企業行動 ⑦大企業は、1990年度から2021年度にかけ、売上高が5%増に留まる中で、リストラによって利益を捻出し経常利益を164%伸ばした ⑧企業による設備と人件費の抑制は、経済のエンジンである投資と消費を失速させた ⑨インフレ到来で2022年度の大企業の売上高は前年度比10.6%増えてバブルの頂点だった1989年以来の高い伸び、中堅・中小企業も合わせた全規模でも売上高は8.7%増えた ⑩売り上げ増の手応えをつかんで、企業は国内で設備投資のアクセルを踏み出し、2023年度の設備投資は名目ベース100兆円台に乗せて過去最高となる勢い ⑪今回の物価上昇のきっかけはロシアのウクライナ侵攻に伴う世界的インフレでコロナ禍からの回復や人手不足も手伝って国内にも価格転嫁や賃上げの波が及んだ ⑫賃金の伸びは物価の上昇に追いつかず、実質賃金は14カ月連続の減少 ⑬消費者物価上昇率は民間エコノミストの予想を平均すると、2023年7~9月期が前年比2.76%で賃金の伸びが物価を上回れば2023年度下期に実質賃金は増加に転じる ⑭家計の所得が消費を後押しする好循環に入るチャンスが巡ってきた ⑮バブル崩壊後、30年あまり続いた光景が変わるにつれ、財政・金融政策も正常化を探る動き ⑯その際に政府・日銀が心すべきは、経済の好循環に水を差さぬこと ⑰政府はインフレの受益者で、税収の自然増が財政を下支えしている 等と記載している。 このうち、①②は、「日銀の金融緩和(長期金利0.5%の上限)のおかげで、日本経済は長期にわたるデフレ不況を克服し、インフレ下で新たな成長に向かいつつある」と主張しているが、上の中央の図のように、この記事が“デフレ”と呼んでいる2000年以降の実質GDPは名目GDPより高い。つまり、「インフレになれば経済成長する」という説自体が正しくないのだ。 また、③の「政府と日銀がこのまま低金利政策を続ければ名目GDP600兆円超の視界が開ける」というのは、単に尺度となる貨幣価値下がったから同じ実体経済が大きく表されただけである。わかりやすく言えば、1mの長さを現在の半分と決めれば、地球の赤道は(約4万kmではなく)約8万kmになるのと同じだ。そのため、貨幣価値が下がって物価が上がれば、④のように名目GDPが上がるのは当然のことなのである。 また⑤⑥は、低金利で金利より高い物価上昇が続けば実質金利はマイナスになるため、金を借りた方が得をして金を貸した方が損をする。そのため、預金を持っているよりも、何でもいいから利益を生むものに投資した方がよいということになるが、これが日本企業の投資利益率が低い理由だと再認識した。そのため、私は、日本企業にはなるべく投資しないことにする。 さらに、⑦の「大企業は1990年度から2021年度にかけ、リストラで利益を捻出し経常利益を164%伸ばした」というのは、リストラのやり方には問題が多かったと記憶しているが、利益が出ずいらない部門を整理すればリストラは必要になる。そのため、そういうことが多い時期には、国が財政支出をしてインフラ整備を進め、失業者を吸収するのが定石なのである。 従って、⑧の「企業による設備と人件費の抑制は、経済のエンジンである投資と消費を失速させた」というのは、時と場合とやり方に依るのだ。 なお、⑨の「インフレ到来で2022年度の大企業の売上高は前年度比10.6%増えてバブルの頂点だった1989年以来の高い伸び、中堅・中小企業も合わせた全規模でも売上高は8.7%増えた」というのは、今もバブルになりかかっているため、そのうち整理が必要になると思う。 そのため、⑩の「企業が売り上げ増の手応えを掴んで、国内で設備投資のアクセルを踏み出し、2023年度の設備投資は名目ベース100兆円台に乗せて過去最高となる勢い」というのは、一部はイノベーションのための本物の設備投資かもしれないが、物価上昇による売上増部分は、近いうちに数量で調整されるため、喜びすぎない方がよいだろう。 なお、⑪のように、今回の物価上昇のきっかけはロシアのウクライナ侵攻に伴う世界的インフレが主であるため、コストプッシュインフレで、かつ物価上昇分は輸入代金として海外に流出している。そのため、企業に残っているのは、低金利による借り得の部分だけであり、⑫のように、賃金の伸びが物価の上昇に追いつかず実質賃金が14カ月連続減少するのは必然なのだ。 また、⑬の「消費者物価上昇率は民間エコノミストの予想を平均した」というのも、あまりに意図的で正確ではなく、2023年7~9月期の消費者物価上昇率が前年比2.76%というのは低すぎる。そのため、賃金の伸びが物価を上回って実質賃金が増加に転じ、⑭のように、家計所得が消費を後押しする好循環に入ることはないと思われる。 従って、⑮⑯⑰については、財政・金融政策が正常化を探るのは当然のことだが、⑰のように、政府はインフレの受益者で、税収自然増が財政を下支えしているだけでなく、インフレで国債実質残高も目減りするメリットがあるため、今となっては、政府は、国民を犠牲にしてもこの状況を変えるのは期待し難いわけである。 2)名目と実質の差が意味すること 日経新聞は、*1-1-3で、①内閣府発表4~6月期GDP速報値は、名目成長率が前期比年率プラス12.0%でインフレが日本経済の名目値を押し上げた ②デフレで長らく低迷していた名目GDPが世界的な物価上昇を契機に動き出した ③コロナ禍の時期を除けば1990年4~6月期(プラス13.1%)以来の伸び ④企業の売上高・賃金・株価等は名目値なので、インフレによる経済規模拡大で経済指標も上昇する ⑤名目成長率を項目別にみると、個人消費は名目前期比0.2%減だが、インフレの影響で実質は0.5%減 ⑥設備投資は実質横ばい、名目0.8%増 ⑦GDPデフレーターからみた物価上昇率は前年同期比3.4%と3四半期連続プラスで現行基準で遡れる1995年以降最高 ⑧過去の基準も含めて1981年1~3月期以来 ⑨GDPデフレーターの上昇要因は、輸入物価上昇の一巡による押し上げ効果と価格転嫁による国内物価上昇 ⑩賃金も安定的に上昇すれば、日本経済の脱デフレに向けた道筋が本格化する と記載している。 日経新聞は、④のように、「企業の売上高・賃金・株価等は名目値でインフレによる経済規模の拡大で経済指標も上昇する」として名目値を重視しているが、それは指標となる数字上のことにすぎない。実際には、消費(=実需)は実質でしか行えないため、必ず実質による修正が入るのである。その結果、②とは違って“デフレ”と経済低迷は無関係だったり、⑤の個人消費は実質0.5%減だったり、その結果、⑥の設備投資は実質横ばいだったりという事実があるのだ。 従って、⑩の賃金の安定的上昇も、企業が実質利益を安定的に上昇させることができなければ起こらず、金融緩和によるインフレ政策だけでは無理なのだ。 佐賀新聞は、*1-1-4で、⑪内閣府が発表した2023年4~6月期のGDP(季節調整済)速報値は、物価変動を除く実質で前期比1.5%増、年率換算6.0%増 ⑫半導体の供給制約の緩和で自動車などの輸出が伸びた ⑬輸入の減少が統計上プラスに寄与した ⑭物価高の影響でGDPの約6割を占める個人消費は低調 ⑮景気実感に近いとされる名目GDPは前期比2.9%増で、年率換算は12.0%増 ⑯物価高を反映して20年7~9月期(年率22.8%増)以来の高い伸びで、金額も過去最高の590兆7千億円に達した ⑰4~6月期の実質を項目別に見ると、個人消費は前期比0.5%減で、外食・宿泊は伸びたが食料品や白物家電が相次ぐ値上がりの影響で落ち込んだ ⑱設備投資は0.0%増 ⑲輸出は3.2%増 ⑳輸入は4.3%減で、輸入の減少はGDPを押し上げる要因 等と記載している。 ⑪の2023年4~6月期のGDP(季節調整済)速報値が実質で前期比1.5%増、年率換算6.0%増だったというのも、コロナ禍からの回復途上であることを考えれば当然である。 また、⑬のように輸入減が統計上プラスに寄与したり、⑰のように個人消費は前期比0.5%減で外食・宿泊は伸びたが食料品・白物家電が値上げの影響で落ち込んだりした結果、⑱の設備投資は0・0%増でしかないのだから、経済の拡大は数字上のトリックにすぎない部分が多い。 3)物価上昇率以上の賃金上昇はない 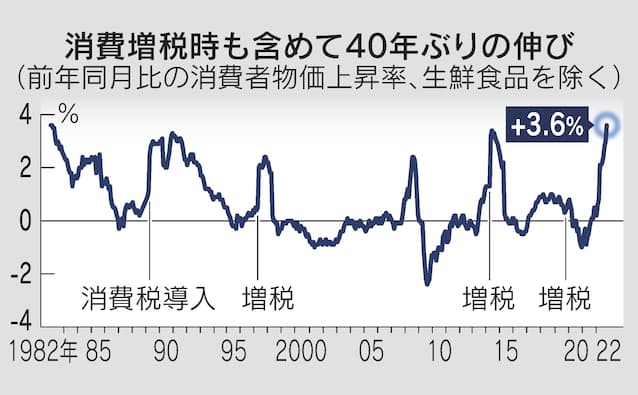 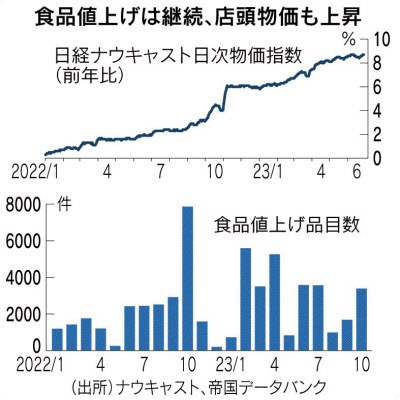 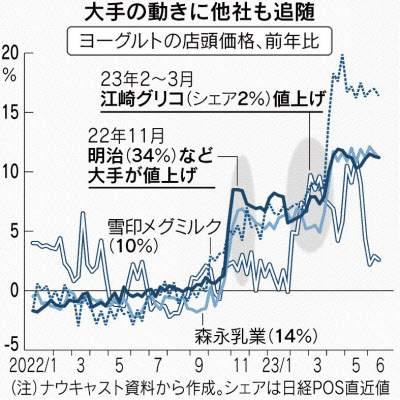 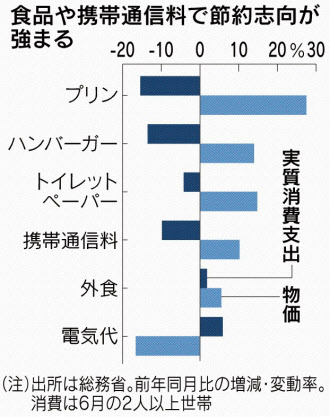 2022.11.18日経新聞 2023.7.3日経新聞 2023.8.19日経新聞 (図の説明:1番左の図は、前年同月と比較した場合の物価上昇率で、消費税増税によって物価上昇し、国民の節約によって《国民が貧しくなって》元に戻ることを繰り返してきたが、それでも日経新聞は、2020年に3.6%物価上昇したのを「物価の伸び」などと表現している。そして、中央の2つの図のように、必需品でエンゲル係数の高い食品の値上げが8%以上、牛乳の値上げは10~20%に達し、貧しい人ほど物価上昇による負担が大きい結果となった。そして、今回も1番右の図のように、収入以上の支出はできないため、国民は節約して不便になりながら、物価だけは元の水準近くに戻るだろう) 内閣府発表の2023年4~6月期GDP速報値は、*1-1-5のように、年率換算6.0%増加、GDP成長率は名目年率12%、実質年率3.7%になったが、外需に一時的に支えられ、個人消費・設備投資の内需が弱かった。 そのため、メディアは、賃上げや投資の実行へ官民で策を練るべきとしているが、日本は、イノベーションや構造改革で生産性を上げない限り、物価上昇率以上に賃金を上げて実質所得をプラスにすることはできないというのが私の結論であるため、以下に、その理由を記載する.。 i) サービス輸出で訪日外国人のインバウンド消費が堅調だったのはよいが、サービス輸出には観光だけではなく、高度な医療・介護サービスを外国人に提供する付加価値の高いサービスもある。しかし、この10年以上、政府は医療・介護費用を削減することしか思いつかず、日本社会の成熟化を活かした高度な医療・介護サービスを作ることができなかったため、日本は既にこの分野で高度とは言えなくなっていること ii) モノを輸出するには良いものを安価に作る必要がある。しかし、新興国はイノベーション等で品質も磨いているが、日本はイノベーションを嫌い、高コスト構造を変えず、わずかな改良しかしなかったため、日本製は品質より数倍高価になり、競争力が落ちていること iii) 年率6%成長のうち輸入減の貢献は4.4%分で輸入は4.3%減だったそうだが、輸入の数量減は内需の弱さを映しており、これは、実質所得が目減りして個人消費がマイナスになるからだが、(リーダーが余程の馬鹿でない限り)やってから失敗し、時間と金を無駄遣いしなくても容易に想像できたこと iv) 高コスト構造を変えないため、企業は名目利益増加の多くを人件費以外のコスト増に費やさざるを得ず、実質所得がプラスになるほどの賃上げはできないが、これは、*1-1-6や*1-1-7のように、結果として表れていること v) 実質所得がマイナスで、預金や債券も目減りし、国民の財産や所得が政府や企業に移転して消費は以前より少なくなるため、内需を当てにした民間設備投資は減ること vi) *1-1-6に「日銀が掲げる2%の物価目標」と書かれているが、日銀の2%物価目標自体が国民の目を欺きながら国民の財産や所得を政府や企業に移転する目的であるため、日銀は中央銀行の役割を果たしていないこと 4)年金世帯は物価上昇で必ずマイナスになる 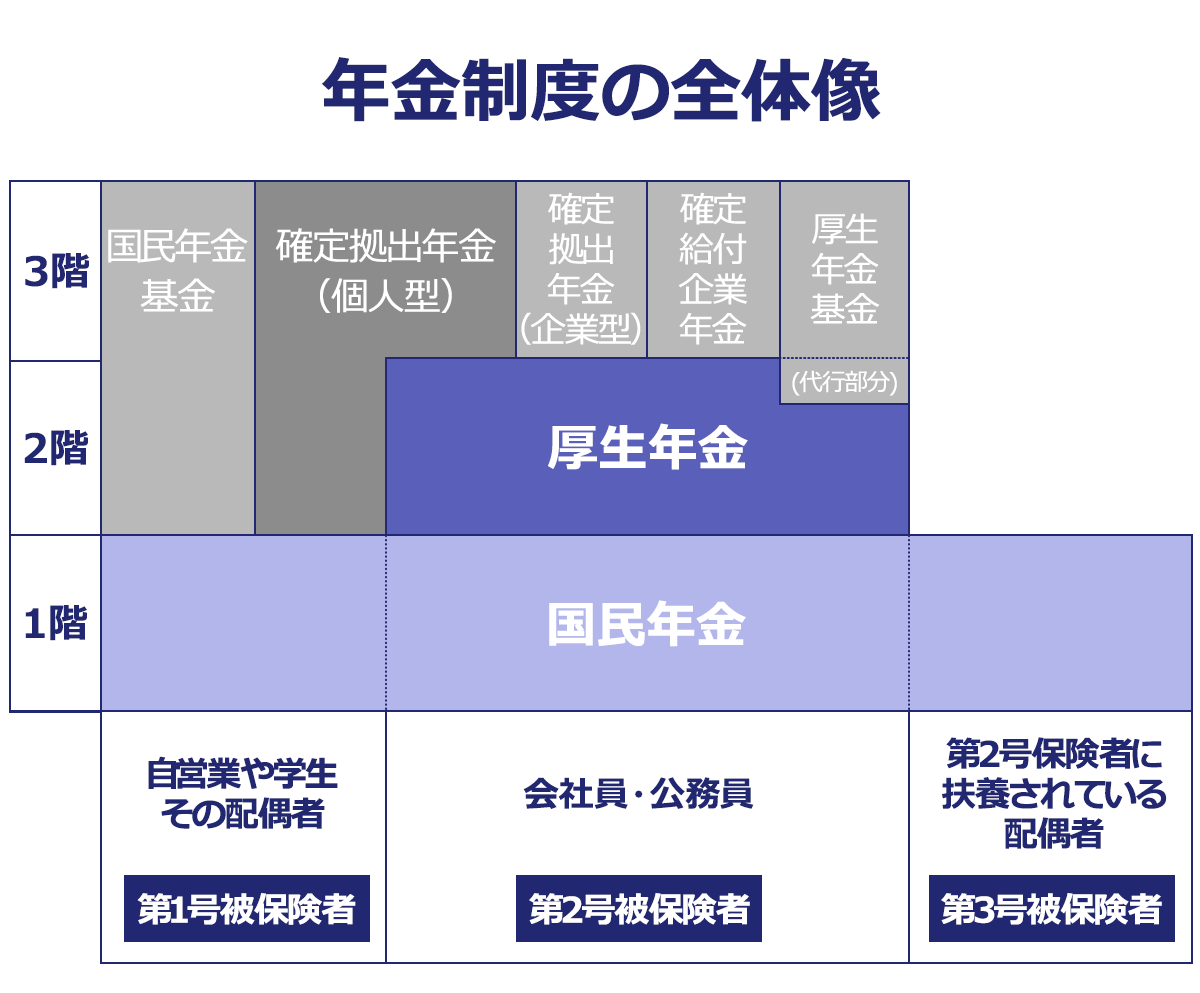 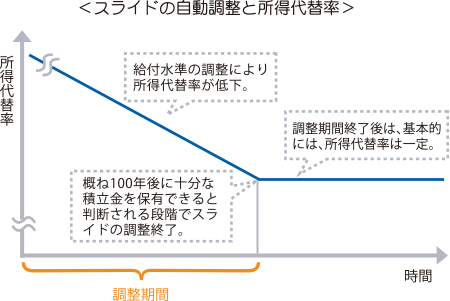 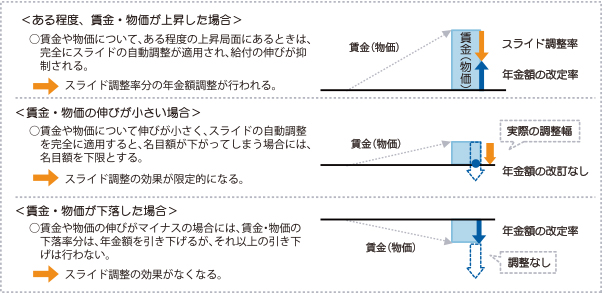 Hacs 厚労省 厚労省 (図の説明:左図が年金制度の概要で、国民年金は65歳以上になれば全員もらえるが、サラリーマンの専業主婦だけはその原資を支払っておらず、制度導入時からその不公平は指摘されていた。しかし、それでも、団塊の世代が支える側にいた時は年金原資が豊富だったので、厚労省は年金原資を使って無駄遣いの限りを尽くし、団塊の世代が支えられる側になる時に『制度が維持できない』として、中央の図の物価スライド制を導入する制度改正をしたのである。物価スライド制のKeyは、右図のように、賃金や物価の上昇時にそれより低い年金支給額上昇にすることによって、年金受給者が気付かぬように年金の所得代替率を下げていくもので、この改正は『高齢者は豊かだ』というデマをメディアを通じて大々的に流すことによって行われた。本当は、年金原資を発生主義で積み立てておくべきだったのだが、現在もそれは行われていない) 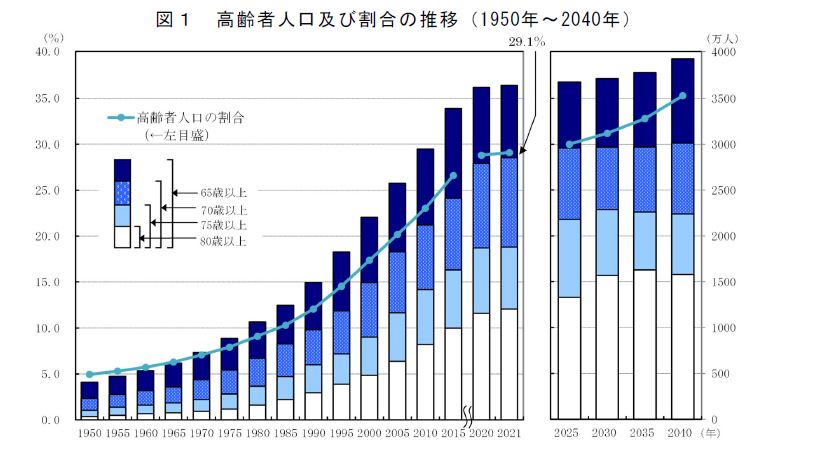 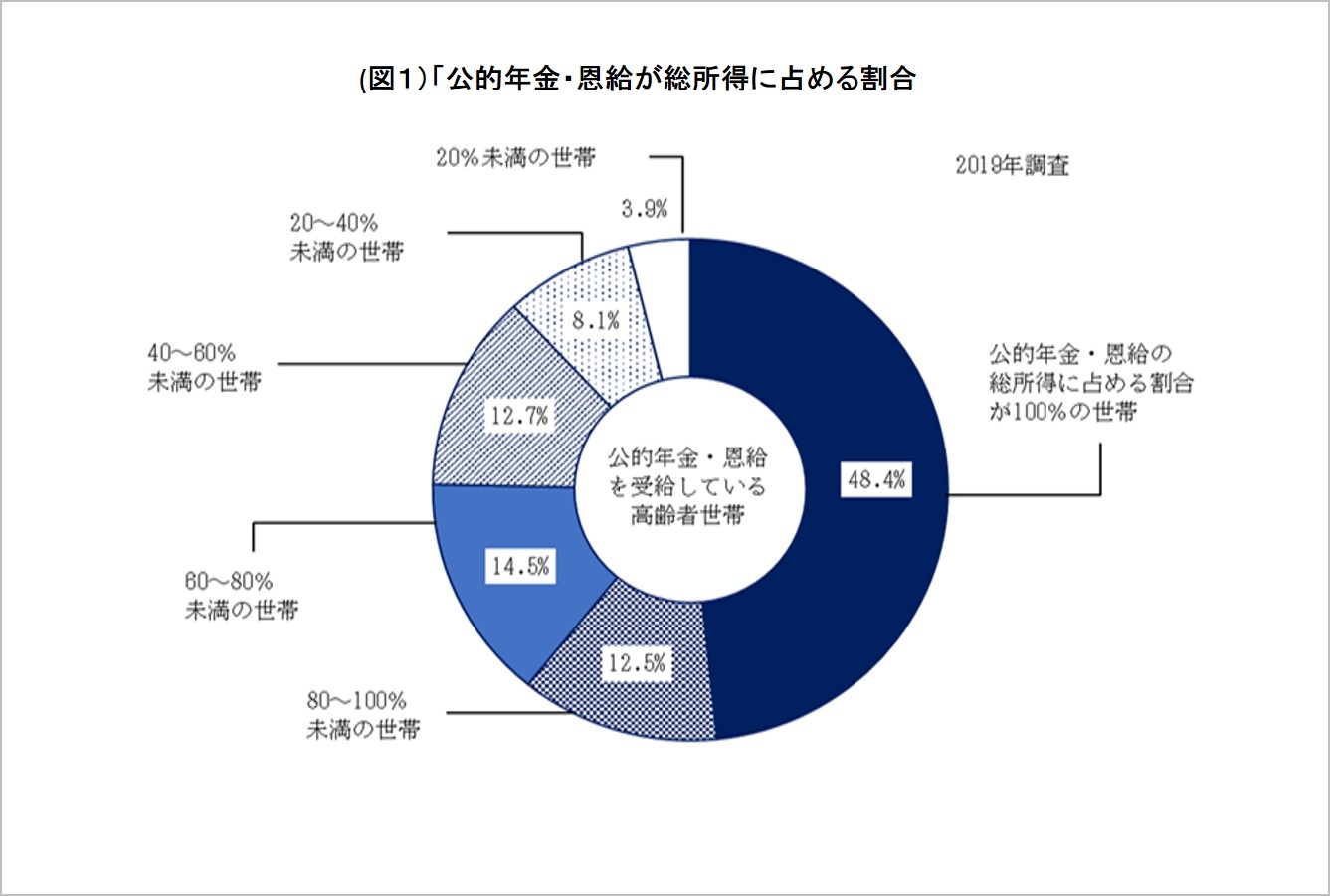 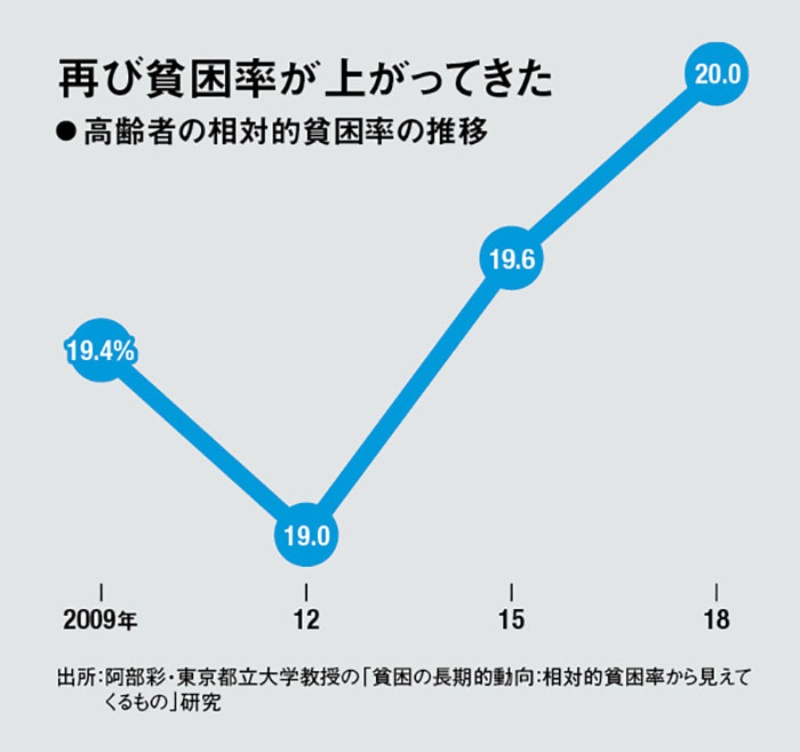 総務省 2020.7.21時事 2022.1.31ビジネス日経 (図の説明:65歳以上を“高齢者”と定義して退職させれば、左図の折れ線グラフのように2021年には29.1%が高齢者であり、その後も高齢者の割合は増えていく。そして、中央の図のように、2019年は高齢者の48.4%で公的年金か恩給が総所得の100%を占め、同じく12.5%で公的年金か恩給が総所得の80~100%を占めるのである。従って、右図のように、高齢者の貧困率はうなぎ上りに上がっているのだ) 年金世帯は、下の段の左図のように、2021年の数字で全世帯の約30%であり、そのうち総所得の100%を公的年金・恩給で賄っている世帯が(2019年の調査だが)48.4%、80~100%を公的年金・恩給で賄っている世帯が12.5%、60~80%を公的年金・恩給で賄っている世帯が14.5%であるため、年金支給額は年金世帯の所得を通して、個人消費に占める割合が大きい。 *1-3-1も、①世帯主が65歳以上世帯の2022年の1ヶ月平均支出は21万1,780円で全体の39% ②年金暮らし世帯がGDPの15%に影響 ③賃上げの恩恵を受けにくい高齢者の消費活性化がデフレ脱却を左右 ④日本の2022年名目GDPは556兆円で5割は個人消費 ⑤GDP全体の15%程度を年金世帯の消費が担っている 等と記載している。 このうち①について、平均で21万1,780円/月支出するのは、生活保護の基準となる最低生活費(神奈川県横浜市の場合:185,490円、https://seikatsuhogo.biz/blogs/140 参照)に近く、都市部ではぎりぎりの生活水準で、年金生活者にはこれ以下の人が半分はいるのである。 また、③の「高齢者は賃上げの恩恵を受けにくい」のは、上の段の中央及び右図のように、「マクロ経済スライド」が導入されたことで、物価上昇と賃上げの恩恵は年金世帯には一部しか及ばないため、物価上昇率を加味すると実質年金支給額はマイナスになるということである。 つまり、物価上昇は実質年金支給額をマイナスにすることで、②④⑤のように、高齢者に消費を減らさせ、GDPには悪影響を与え、下の段の右図のように、高齢者の貧困を増やすのである。 しかし、日経新聞は、これがGDPを押し下げることしか問題にせず、新世代の高齢者が自由に所得を使えれば高齢化した国で必ず必要になる高齢者向けのサービス(医療・介護・生活支援を含む)が磨かれることについて全く触れていない。これらのサービスを磨くことは、政府が生産性の低い金の使い方をするよりずっと将来のためになるのに、である。 なお、*1-3-1は、「65歳以上の無職世帯夫婦の金融資産は1,915万円で、全世帯平均より636万円も金融資産が多い」とも記載しているが、長期間溜めればそれだけ金融資産が多くなるのは当然だが、少ない年金の足しにしたり、夫婦に医療・介護が必要になった時の備えとすべき流動資産なのである。そのため、1,915万円の金融資産というのは、足りなくなる確率の方が高い金額だ。 *1-3-2は、2023年1月20日、⑥来年度の公的年金額は3年ぶりの増額改定だが、「マクロ経済スライド」の適用で物価高騰に追いつかず実質0・6%の目減り ⑦長期的に年金財政を維持して将来世代の支給水準を確保するための対応 ⑧食料品・光熱費等の値上がりが続く中で年金頼みの高齢者にさらなる痛手 ⑨公的年金制度は現役世代が払う保険料等で高齢者への給付を賄う「仕送り方式」 ⑩高齢者は消費期限が近い「見切り品」の食料品購入が中心で、冬はエアコンなどの電源をオフにして凌ぐ 等と記載している。 つまり、⑨のように、「仕送り方式(賦課課税方式)」を前提として、⑦のように、「長期的に年金財政を維持して将来世代への支給水準を確保する」として「マクロ経済スライド」を肯定しているが、仕送り方式だから世代間で人口が変動すると年金原資が余ったり、足りなくなったりするのだ。これが、企業会計の年金給付会計のように発生主義で年金原資を積み立てておけば問題は生じず、その考え方はFASB83により1985年には既に世界で認知されていたのである。 そのため、⑥のように、「マクロ経済スライド」の適用で年金額を実質目減りさせたり、⑧や⑩のように、物価高騰の皺寄せを高齢者に押し付けたりするのは、仕方がないのではなく悪意であると言える。 なお、*1-3-3は、⑪政府は2023年3月に物価高対策等として予備費から2兆2,226億円を支出すると閣議決定 ⑫「地方創生臨時交付金」に1兆2,000億円 ⑬自治体を通じたLPガス利用者等の負担軽減や低所得世帯へ一律3万円の給付 ⑭低所得世帯の子ども1人につき5万円の給付を実施 ⑮家畜の餌となる配合飼料の価格高騰対策965億円 ⑯輸入小麦の政府売渡価格激変緩和策310億円 ⑰農業用水利施設の電気料金対策34億円 ⑱飼料対策は価格安定制度とは別に8,500円/t支給 ⑲新型コロナ対策として病床確保する医療機関への交付金向けに7,365億円 等としている。 しかし、⑪~⑲は、賢い歳出を続けていれば防ぎ得た事象についてその一部を補填しているにすぎず、高齢者に恩恵があるのはそのうちのごく一部であり、本来はこういう事態が起こらないようにすべきであり、また、(1つづつ詳細には書かないが)それはできた筈なのである。 佐賀県統計分析課がまとめた2023年7月の佐賀市消費者物価指数(2020年を100)は、*1-3-4のように、全体では104.9と4.9%上昇し、うち家事・家具用品は114.7と14.7%上昇、食料は111.9と11.9%上昇など、必需品の物価上昇率が著しく高い。そのため、家計が感じた佐賀市民の消費者物価上昇率は10~15%程度となるが、私が住む埼玉県の場合は体感消費者物価上昇率が20%以上になるため、家計は全体ではなく必需品の消費者物価上昇率を感じていることになる。これは、必需品でなければ高すぎるものは買わないため、当然と言える。 5)“異次元金融緩和”の本当の目的は何だったのか *1-2は、①日銀は、2013年1~6月の金融政策決定会合の全議事録を公表 ②この議事録はデフレ脱却のため大規模な金融緩和を掲げて2012年12月に誕生した第2次安倍政権の意向で変わる日銀の姿を示す ③日銀出身の白川総裁時代は「物価目標を『2%』と定めて大規模緩和する」という政権の方針に日銀は抵抗 ④白川総裁は、総選挙の大勝という「民意」を背にした安倍政権の圧力に屈して2013年1月の会合で物価上昇率2%の目標を決定 ⑤投票権を持つ政策委員たちから「目標達成は難しい」とする意見が相次いだ ⑥同年3月、白川氏の後任として安倍政権に起用された財務官僚出身の黒田総裁は着任後すぐ大規模緩和に着手 ⑦黒田総裁は「人々の『期待』に働きかけてデフレを脱却するため、市場に流す金の量を2倍に増やし、2年程度を念頭に2%の物価目標を目指す」と決定 ⑧佐藤審議委員は、大規模緩和の考え方が根本的に誤っている可能性を指摘 ⑨「2%の物価目標」は今も達成されていない 等としている。 このうち、①②は良いが、⑥⑦の「大規模緩和して市場に流す金の量を2倍に増やせば、人々の期待によってデフレを脱却できる」という考え方は、あまりにも国民や経済を甘く見ているし、根本的に誤りである。 しかし、④については仕方がないとしても、③⑤⑧の「物価目標を『2%』と定めて大規模緩和する」という安倍政権の方針に、日銀が抵抗したり、委員が反対したりした言葉は、「○○は難しい」とか成功する可能性も一部は残したような曖昧な言い方であるため、経済や金融の専門家にしては、経済の素人に対して、誤解させずに理由を説明する義務を果たせていない。 そして、私の予想通り、散々な迷惑を国民にかけても、⑨のように「2%の物価目標」は今も達成されていないが、そもそも「コストプッシュインフレでもいいから、ともかく物価上昇させて政府の実質債務を減らそう」という考え方自体が、日本国憲法前文に書かれている国民の福利を完全に無視しているのだ(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm 参照)。 6)歳出の正常化について *1-4は、①政府は来年度予算編成の基本方針をコロナ禍以降に膨張した歳出について平時に戻していくと決め ②各省庁の予算要求に制限をかける概算要求基準も閣議了解し、配分にメリハリをつけつつ全体の規模を抑える方針だが、例外や抜け穴が目立つ ③最たるものは政権が2倍近くへの拡大を打ち出した防衛費で、防衛費大幅増は今年度予算から始まって他の重要分野や財政健全化にしわ寄せを及ぼしつつある ④子ども政策財源も防衛費増と同様に別枠で、政府は幅広い「歳出改革」による捻出を当て込む ⑤各省庁の裁量性が高い経費の一律1割減を求めた上で、削減額の3倍分までの要求を「重要政策」として約4兆円の特別枠で認める ⑥歳出の「正常化」への試金石は、高騰したガソリンや電気・ガス料金の補助金の扱い ⑦社会保障など他の分野も物価高や賃金上昇に応じた増額を求める声は強まっている ⑧身の丈に合わない予算増を無理に続ければ政策資源の配分を歪めるため、減らせる予算の徹底的な洗い出しが必須の筈 ⑨先進国で最悪水準の借金が積み上がっている ⑩この状況を漫然と続けるのは将来世代への背信 等と記載している。 ①については、日本はコロナでそこまで経済を止める必要はなく、感染症が流行すればワクチンや医薬品を製造・輸出する科学技術力があって当然の先進国なのだが、厚労省は適切な指導ができなかったため、歳出が膨張しただけで歳入は増えなかった。 また、日本は膨らんだ予算を縮小するのに、②⑤のように、各省庁の予算要求を一律10%減らすなどめくらめっぽうの乱暴なやり方しかできず、それを補うため削減額の3倍までを「重要政策」として特別枠を認めるなど、かえって無駄遣いを含む歳出を増やす状況である。 これについては、国際公会計基準(IPSAS)に従い、複式簿記を使用して、速やかに財務書類を公表して各年度の財政政策の影響を国民に報告するとともに、予算委員会では、前年度の財務書類を基にして次年度予算を審議することが解決策になる。 この際は、当然、省庁毎ではなく事業毎の行政コスト(国民にとっての受益と負担)も計算し、政策について反省しながら、効果の高かった政策を残し、無駄遣いの多かった政策は止める等の作業を繰り返せば、国の歳出生産性は次第に上がるのである。ただし、国や地方自治体で「『効果が高い』とは何か」については、民間企業と全く同じではないため、事前に十分な議論をして定義を決めておく必要がある。 これらを念頭に考えれば、③④については、より良い代替案のある無駄遣いが多額で、それを、⑦のように、ただでさえ生活が苦しい高齢者予算から一部でも引き出すのは論外である。 また、⑥の高騰したガソリンや電気・ガス料金への補助金のうち、ガソリンはハイブリッド車の使用で消費が1/2程度に減っているため、価格が2倍になってもあわてる必要はない筈だ。また、電気・ガス料金も、輸入化石燃料に頼り続けてきたから上昇しているのであるため、1995年頃から言っている環境対応をさっさと行っていれば問題はなかった筈である。 そのため、⑧のように、時代に合わない補助金はかえって資源配分を歪めるので、地球温暖化対策に逆行する予算は真っ先に減らすべきだ。そして、日本政府が内容の検証もせず不適切な政策を採り続けたことにより、日本は、⑨のように、先進国最悪の借金を抱えたが、これは、⑩のように将来世代への背信であるだけではなく、現在及び過去の国民に対する背信でもあり、大変迷惑な行為なのである。 (2)気候変動について 今年の夏は7月からものすごく暑かったため、私は電気料金度外視で夜もエアコンをつけっぱなしにしていたが、エアコンをつけることさえ節約している年金生活者も決して少なくないため、この電気料金高騰の中でどう過ごされていただろうか。 そのような中、WMOとEUの気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」は、*2-1のように、2023年7月の世界平均気温が観測史上最高となる見通しと発表し、太古の気候を探る研究者は「地球の平均気温は約12万年ぶりの最高気温を記録した」と警鐘を鳴らしたのだそうだ。 12万5000年前の「エエム紀」の平均気温は現在の工業化前(1850~1900年)と比較してセ氏0.5~2.0度ほど高かったが、今年6月の世界平均気温は工業化前を1.5度以上上回り、国連のグテレス事務総長は「地球の沸騰が始まった」と警告した。 ただ、12万5000年ぶりの暑さが「エエム紀」と異なるのは、*2-2のように、人間の活動が地球環境に多大な影響を及ぼして起こったことで、そのため現代を「人新世」とする議論が国際地質科学連合で大詰めを迎えているのだそうだ。確かに、現在は人口が多く、影響の大きな公害を出す技術も使うため、注意を怠れば地球に不可逆的な変化をもたらす。 従って、*2-3のように、IPCCは第6次統合報告書を纏め、温暖化対策の緊急性を強く訴えたが、今年は日本がG7の議長国だったため、G20と連携して積極的な対策を加速すればよかったのに、原発も禁止した「パリ協定」以下の成果しか出さず、意識の高さに違いが見られた。 さらに、アジア等の途上国で石炭火力への依存度が高ければ、日本は再エネ・蓄電池・省エネ投資等で手伝えばよいのに、*2-5のように、自国でもそれを十分に行わず、石炭火力にアンモニアを混ぜたり、石炭火力から出るCO₂ を貯留したりなど、コストが上がって量にも限りがある提案をし、原発回帰に走ったのは情けない。 このような結果、*2-4のように、台風の豪雨や線状降水帯が頻繁に発生し、過去最多の雨量を記録するケースも目立っているが、この原因も地球温暖化である。そのため、その原因をなくすか、災害時には短期間の避難ではすまないため安全対策として移転するかしかないだろう。 (3)原発と予算 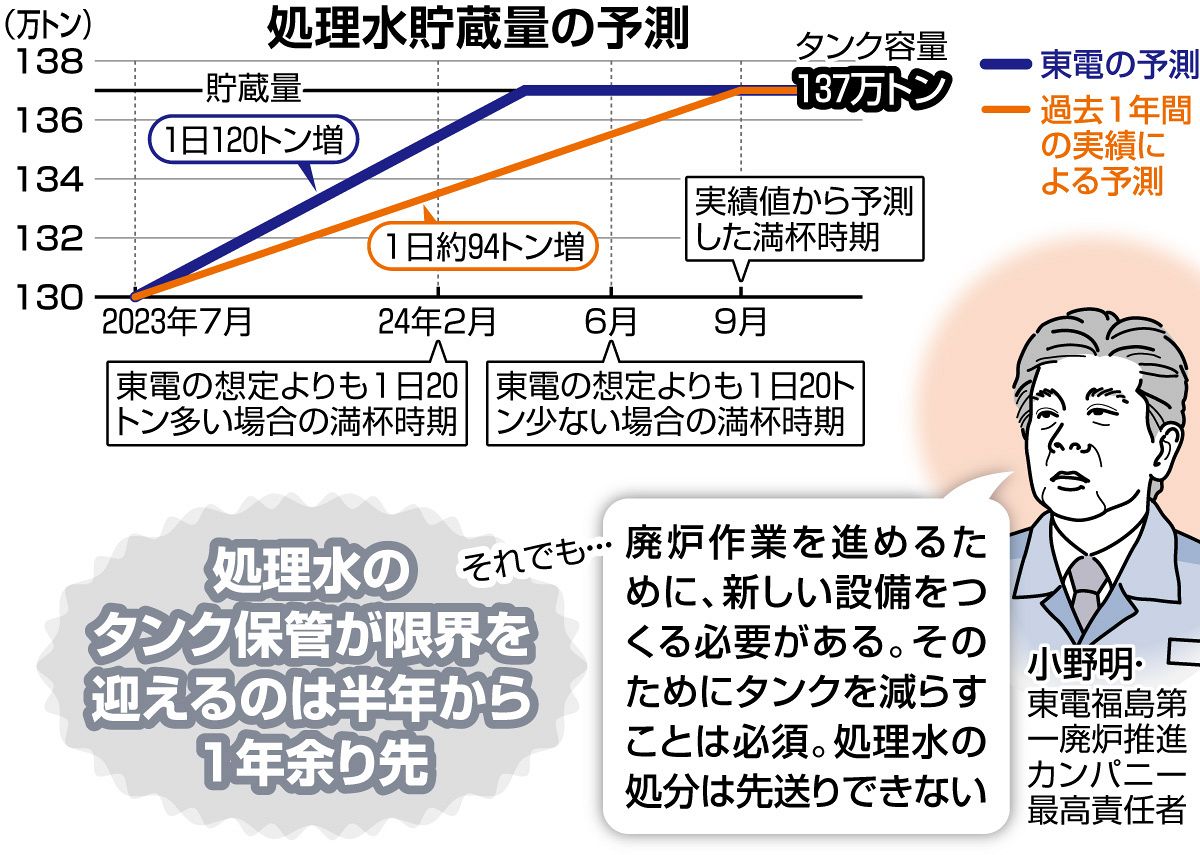 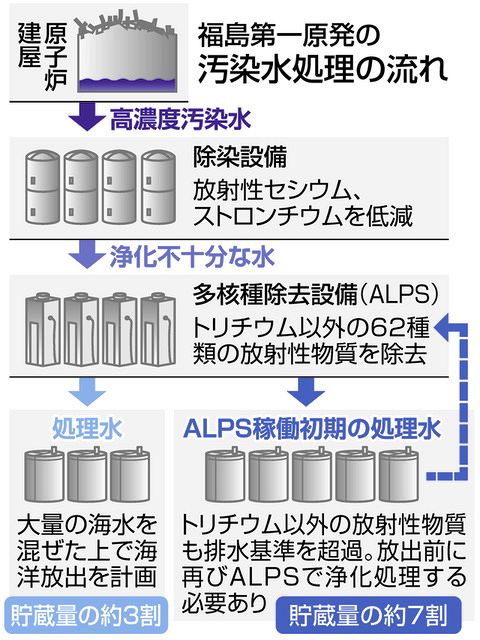 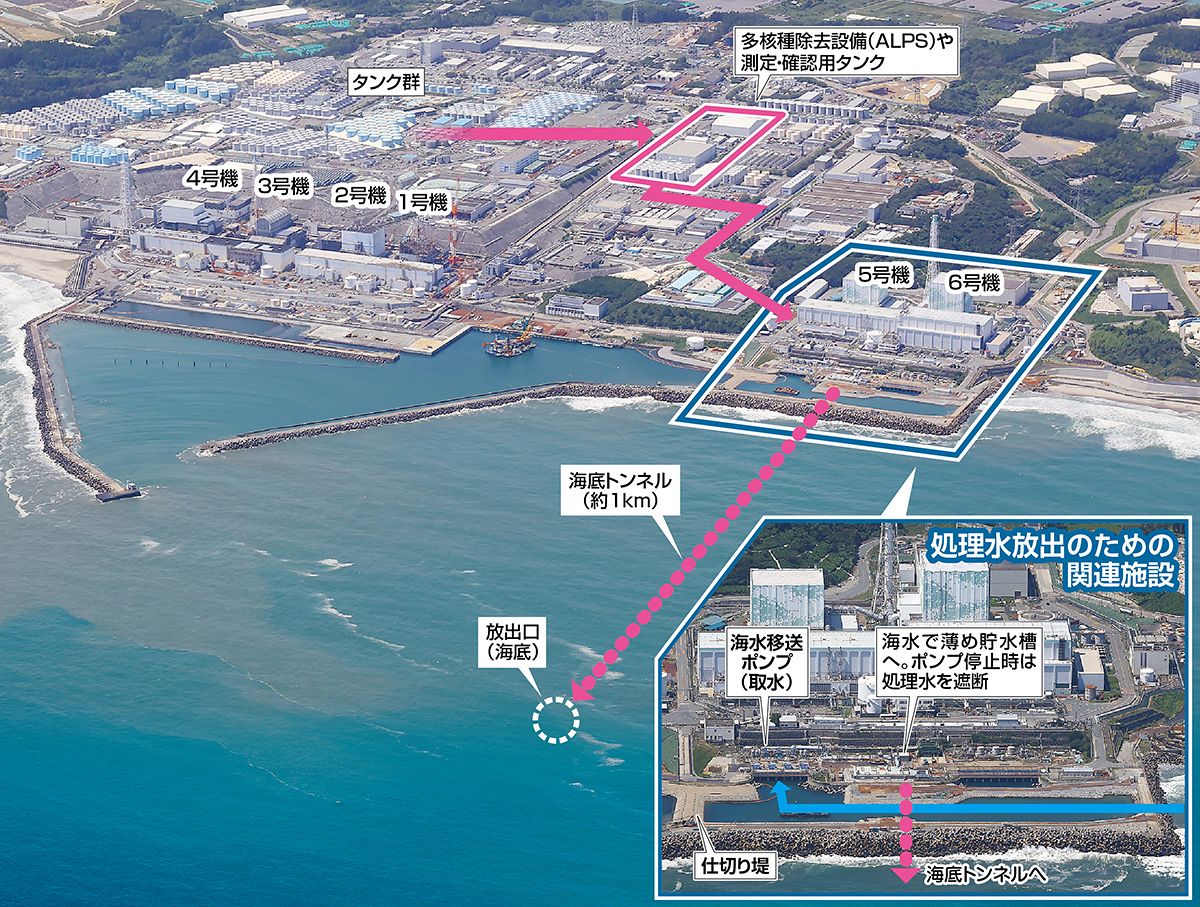 2023.8.7東京新聞 2023.8.8東京新聞 2024.8.24東京新聞 (図の説明:左図のように、「廃炉作業を行うために、タンクを減らして新しい設備を作る必要がある(科学的根拠ではない)」として、中央の図の仕組みで処理水の海洋放出が始まった。処理水の放出口は、右図のように、陸から1kmしか離れていない水深12mの場所にあるため、汚染物質の濃度は放出口付近及び潮流に乗って東北の太平洋沿岸で高くなると思われる) 1)アルプス処理水の放出について *3-2-1は、フクイチの原発処理水は、2023年8月24日午後1時頃放出開始で、①タンクの水を約1200倍の海水で希釈した処理水を22日夜に採取してトリチウム濃度を調べ ②トリチウム濃度は計画の基準1500ベクレル/リットル(国の放出基準の40分の1)を下回り ③トリチウム以外の放射性物質濃度が基準未満であることは確認済 ④原発内のタンクには大半の放射性物質を除去する「多核種除去設備(ALPS(アルプス))」を通した水が約134万トン溜まっており ⑤今年度はこのうち約3万1200トンを放出する計画 ⑥1回目の放出は約17日間かけて約7800トンを流し ⑦放出開始から1カ月程度は、沖合約1キロ先の放水口の周辺で海水を毎日採取し、トリチウム濃度を調べる としている。 このうち①②より、希釈する前の処理水は180万ベクレル/リットル(=1500ベクレル/リットルX1200=国の放出基準の30 倍)で、⑤⑥⑦より、1回目の放出で約17日間で14兆400ベクレル(=180万ベクレル/リットルX7800X1000 )のトリチウムを海岸から1kmしか離れていない放水口より放出し、⑤より、今年度内に56兆1,600億ベクレル(180万ベクレル/リットルX 31,200X1000)のトリチウムを同じ放水口から放出することがわかる。 ここでおかしいのは、i) 希釈して薄めれば何でも濃度基準以下にはなるが、それでよいわけがなく、総量で議論すべきこと ii) (理由を長くは書かないが)“国の濃度基準”を満たせば健康被害を起こさないという科学的根拠もないこと iii)海岸から1kmしか離れていない水深12mの浅い放水口から放出すると、(海流の影響があるので詳しい調査が必要だが)汚染物質の濃度は放水口付近や東北の太平洋沿岸で濃くなると思われること である。 また、そもそも④の「多核種除去設備(ALPS(アルプス))を通した水が約134万トンも溜まっている理由は、事故で溶け落ちた核燃料に地下水が流れ込むのを防ぐために凍土壁を作り、冷却液を循環させて年間十数億円もかけているのに地下水の流入を防ぐことができず、陸側に遮水壁も作ったがそれでも原発建屋に雨水・地下水が流入するのを防げていないからである。 そのため、③は当然であって欲しいが、それも危うく、「国の濃度基準さえ満たせば、科学的で安全である」と考えていること自体が非科学的であるため、安全にも疑問があるわけだ。 しかし、*3-2-2も、⑧岸田首相は、「漁業が継続できるよう、政府が全責任を持って対応する」と「風評被害」を恐れる漁業者に強調した ⑨順調に進んでも30年に及ぶのに誰が・どう責任を取り続けるのか ⑩フクイチでは、事故で溶け落ちた核燃料を冷やすため大量の冷却水をかけている ⑪そこへ地下水や雨水が加わって「汚染水」が毎日約90トンずつ出続ける ⑫その「汚染水」から多核種除去設備(ALPS)で大半の放射性物質を取り除いたものが「処理水」である ⑬政府は、一昨年、濃度を国の基準値未満に薄めた上で海底トンネルで沖合一キロの海に流す方針を決めた ⑭原発構内には1000基を超える「処理水」タンクが林立し、廃炉作業の妨げになるとしている ⑮ALPSを用いても放射性物質はわずかに残り、30年間放出し続ければ膨大な量になる ⑯全国漁業協同組合連合会の坂本会長は「科学的な安全と社会的な安心は異なり、科学的に安全だからと言って風評被害がなくなるものではない」と強い懸念を表明した 等と記載している。 このうち、⑧⑯の「風評被害」という言葉は、「根拠のない間違った情報や意図的なデマで生じる経済的損害」という意味だが、⑮のように、国の濃度基準を満たしていても30年間放出し続ければ膨大な量になる。そのため、「濃度が基準以下であれば安全」と考えていること自体が科学的でないため、言葉の使い方も間違っているのだ。 また、⑨のように、「誰が・どう責任を取り続けるのか」も不明で、放出の意思決定をしていない国民の税金や電力料金で責任をとるのなら論外である。さらに、⑩のように、未だに事故で溶け落ちた核燃料を冷やすために大量の冷却水をかけなければならないのであれば、「冷却水をかけて冷やせばよい」と判断したこと自体に問題があったわけだし、⑪のように、未だに地下水や雨水が流れ込んでいるのなら東電や経産省の工事に問題がある。 そのため、⑫の「汚染水」から多核種除去設備(ALPS)で大半の放射性物質を取り除いたという「処理水」がどこまで安全かも疑問になるし、⑬のように、「濃度を国の基準値未満に薄めれば沖合一キロの海に流し続けても安全だ」ということこそ、科学的根拠がない。 さらに、⑭の「原発構内にある1000基を超える“処理水”タンクが廃炉作業の妨げになる」というのは単なる場所不足による時間切れにすぎず、科学的根拠にはならない。そして、廃炉作業も、いつから始めていつ終わるつもりだろうか? 2)国の責任のとり方について イ)国内の状況 *3-3-1は、西村経産相がフクイチの処理水放出が始まるのを前に小売業界団体の幹部と面会し、①福島県産水産物等の風評被害が懸念されるので積極的に販売に取り組むよう求め ②都内で開かれた風評対策・流通対策連絡会で小売関連6団体の幹部に処理水の海洋放出後も福島県産の販売継続を要請 ③日本チェーンストア協会の三枝会長は「放出後も三陸常磐でとれた水産物をこれまで通り取り扱う」と応じ ④小売業界は消費者が安心して買い物できる環境を整備するよう政府に要望し ⑤具体的には、国際機関等の第三者による安全性の厳格な確認・処理水が基準を満たしているかの監視結果の迅速な公表・水産物の検査体制の徹底を求めた ⑥地元漁業者らは処理水の放出により風評被害で売れ行きが落ち込むのではとの懸念を訴え ⑦全漁連の坂本会長らが自民党水産部会に参加して処理水放出に伴う中国・香港の輸入規制を巡り、販路拡大への支援を求めた ⑧中国は処理水放出に反発して日本産水産物の規制を強め ⑨岸田首相は放出と風評被害に「国が全責任を持つ」と強調 ⑩復興庁は処理水処分に伴う対策として水産物・水産加工品の販売支援事業41億円、漁業人材の確保で21億円を24年度概算要求で要求する と記載している。 また、*3-3-2は、⑪イトーヨーカ堂が、真っ先に処理水放出後も「東日本大震災で被災した生産者を応援していく」とし ⑫イオンも国際基準より厳しい放射性物質の自主検査を実施しながら、関東圏などの総合スーパーで継続販売する方針 ⑬ヤオコーも「商品の見直しはせず販売を継続する」 としている。 ⑨の岸田首相の「国が全責任を持つ」との発言を受けてか、西村経産相がフクイチ処理水放出が始まる前に、①②のように、都内で開かれた“風評”対策・流通対策連絡会で小売関連6団体幹部に処理水の海洋放出後も福島県産の販売継続を要請し、③④のように、日本チェーンストア協会の三枝会長が放出後も三陸常磐でとれた水産物をこれまで通り取り扱うので消費者が安心して買い物できる環境を整備するよう政府に要望されたそうだ。ただ、首相・経産相はじめ小売業界幹部は全員男性で、産業振興には熱心でも食品の安全性にはあまり興味がなく、科学に疎い人たちであることを忘れてはならない。 また、⑤の「国際機関等の第三者による安全性の厳格な確認・処理水が基準を満たしているか」については、政府の言う「食品中の放射性物質の基準値」は、厚労省薬事・食品衛生審議会等の議論を踏まえて設定されたもので、食品の国際規格を策定しているコーデックス委員会(FAO《国連食糧農業機関》とWHO《世界保健機関》の合同委員会)が指標としている年間許容線量1ミリシーベルトを基にしている。しかし、これは、外部被曝を前提とした一般人の許容範囲であり、食品として体内に入る場合は至近距離から被曝するため影響がずっと大きいのだ。 さらに、フクイチの近くは、基準値以下であっても単一の食品のみに放射性物質が含まれているのではなく、多くの食品に基準値以下の放射性物質が含まれ、その上いろいろな場所で外部被曝もするため、それらを総合するとかなりの被曝量になる筈だが、政府は総合値を表示していないのである。(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/risk_commu_2021_002/assets/comsumer_safety_cms203_220311_02.pdf 、http://shiteihaiki.env.go.jp/radiological_contaminated_waste/basic_knowledge/additional_exposure_dose.html 参照)、 また、IAEAも「日本政府及び東京電力が公表したデータの裏付けを行うために、処理水及び環境中の放射性物質のモニタリングをIAEAと第三者の研究所が独立した立場で実施する」としているが、IAEAには、日本政府が多額の金を出して多くの職員を送っており、また原子力推進機関でもあるため、公正な第三者機関にはなり得ないのである(https://www.iaea.org/ja/topics/response/fu-dao-di-yi-yuan-fa-niokeruchu-li-shui-nofang-chu、https://www.tokyo-np.co.jp/article/261656 参照)。 このような中、⑪⑫⑬のように、イトーヨーカ堂は真っ先に「生産者を応援する」としたが、東日本大震災後も被災地近くの食品を置き続けたのが消費者を敬遠させた理由なのだ。また、イオンが国際基準よりも厳しい放射性物質の自主検査を実施するのはよいが、私は関東圏にいてもフクイチ事故後は日本海側の水産物しか買っていない。ヤオコーは「商品の見直しをしない」 とのことだが、西部地域や外国製の食品も多いので、それらを選ぶことになるだろう。 このように頼りない政府に対する消費者の自己防衛策を、政府はじめ生産・販売関係者は、①②⑥⑨のように、「風評被害:根拠のない間違った情報や意図的なデマで生じる経済的損害」と呼ぶが、意図的・組織的に間違った情報やデマを流しているのはどちらだろうか。 なお、⑥のように、地元漁業者も「処理水放出による風評被害」と表現しているが、本当に、「売れ行きが落ち込む理由は、風評だ」と思っているのだろうか。 また、⑦⑧のように、全漁連の坂本会長らが自民党水産部会で処理水放出に伴う中国・香港の日本産水産物に対する輸入規制強化を巡って販路拡大への支援を求められたそうだが、それならIAEAやFAO・WHOの地元である米国で販売すればよい。何故なら、米国は肉食が中心で他の食品から内部被曝を受ける機会が少なく外部被曝もしない場所であるため、水産物を口に合うように美味しく加工済・調理済にした製品を輸出すれば売れると思うからである。 そのため、⑩の復興庁の水産物・水産加工品販売支援事業41億円は、米国や米軍などに販売する水産物加工品製造設備の設置に使ったらどうか。 ロ)中国の禁輸 *3-3-3は、①8月24日にフクイチ処理水の海への放出が始まり、少なくとも今後30年続く ②中国政府は日本産水産物輸入を同日から全面的停止と発表 ③香港も同日から10都県(福島・東京・千葉・栃木・茨城・群馬・宮城・新潟・長野・埼玉)の水産物禁輸を開始 ④対象は「食用の水生動物を含む水産品」で冷蔵・冷凍とも魚類・貝類・海藻に適用 ⑤2022年の水産物輸出額は中国871億円が1位、香港755億円が2位 ⑥東電は24日午前、海水で希釈した処理水のトリチウム濃度の測定結果を発表したが、国の放出基準の1/40を大きく下回った ⑦東電の小早川社長は「国内の事業者で輸出に係る被害が発生した場合は適切に賠償する」とコメント ⑦岸田首相は首相官邸で「科学的根拠に基づいて専門家同士がしっかりと議論を行っていくよう中国政府に強く働きかける」と語った としている。 このうち①は、(3)1)に書いたとおり、放出される放射性物質は全体ではかなりの量にのぼるため、どこからでも輸入でき、自前で漁獲もしている中国が、②④のように、日本産水産物輸入を全面的に停止しても不思議ではないが、放出口の位置と海流によって計測ポイント毎の放射性物質濃度は日々変化し、漁獲海域毎に水産物汚染の度合いは異なる筈である。 また、③のように、香港も、同日から10都県(福島・東京・千葉・栃木・茨城・群馬・宮城・新潟・長野・埼玉)の水産物禁輸を開始したそうだが、福島・東京・千葉・宮城はわかるが、栃木・茨城・群馬・長野・埼玉は海のない県なので、フクイチ処理水が水産物に与える影響は殆どないと思う。また、新潟は日本海側であるため、海流から考えてかなり後にならなければフクイチ処理水の影響は出ないだろう。なお、海流は逆向きだが神奈川の方がフクイチに近く、水産業の盛んな県である。 そこで、⑦のように、日本政府は「希釈して薄めて濃度が基準以下になれば科学的根拠に基づいている」という態度を崩さないため、中国が必要な計測ポイントに計測機器を設置し、ポイント毎の放射性物質の濃度を測って報告して欲しい。現在は、計測機器さえ設置すれば自動的に計測して通信することが可能であるため、簡単だと思う。そして、専門家(原子力の専門家だけでなく公衆衛生の専門家も含む)が、データに基づいて議論できる環境を整えるべきである。 2022年の水産物輸出額は、⑤のように、中国871億円が1位、香港755億円が2位であるため、⑥⑦のように、東電が海水で希釈した処理水のトリチウム濃度測定結果を発表し、「国内の事業者で輸出に係る被害が発生した場合は適切に賠償する」とコメントしている。しかし、これが電気料金や税金で賄われるのでは、日本国民は二重三重のパンチを受けるのである。 3)廃炉について 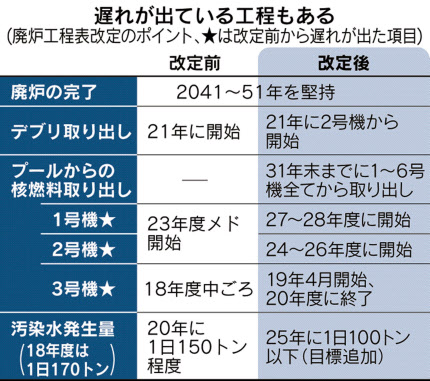 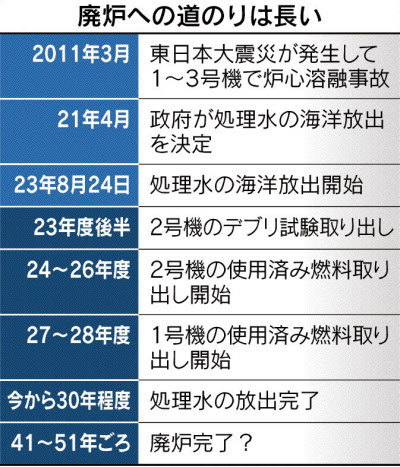 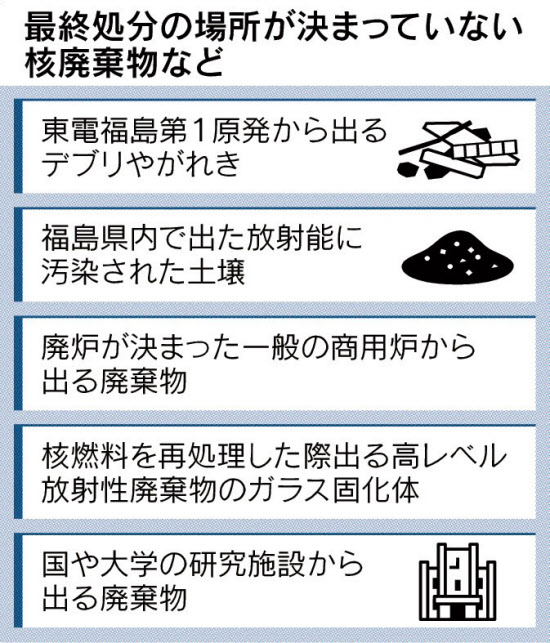 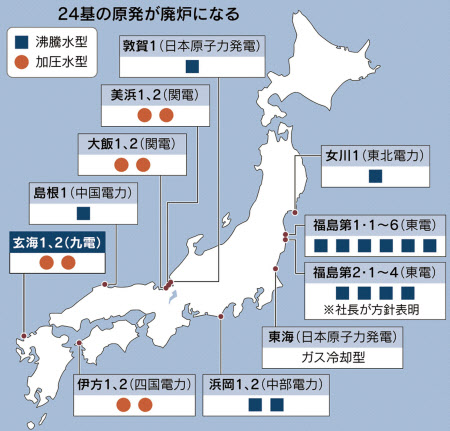 2019.12.27、2023.8.25日経新聞 2022.9.11日経新聞 2022.9.1Goo (図の説明:1番左の図のように、2019年の廃炉工程表改定でプールからの使用済核燃料の取り出し時期が遅れた。そして、左から2番目の図のように、2023年8月現在でも、デブリ取り出し・使用済核燃料取り出しの両方が始まっていない。さらに、右から2番目の図のように、核廃棄物の最終処分場も決まっていないが、1番右の図のように、24基の原発は既に廃炉が予定されているため、仕事は同時に進めればよい筈だ) *3-4-1は、①原発処理水海洋放出は廃炉に向けた第一歩 ②処理水を放出しなければ取り出したデブリを保管する場所が確保できない ③今後はデブリ取り出しが難事業 ④放射線量が非常に高く人が近づけないデブリは1~3号機全体で推計880tあるため作業は遠隔操作 ⑤ロボットアームを使い2号機から着手する ⑥東電等によれば1回目で取り出すのは数グラム程度だが、それすら実際に出来るか不明 ⑦日本原子力学会フクイチ廃炉検討委員会の宮野委員長は「政府が示す廃炉計画は具体的な見通しがあるわけではなく、最も難しいデブリ取り出しの手法が描けなければ廃炉の見通しも立たない」と指摘 ⑧原発内部からの溶融燃料取り出しは、政府目標の30年後廃炉完了も見通せていない ⑨国は廃炉について最終的な形を明らかにしていない ⑩政府はデブリ回収に6兆円・廃炉全体で8兆円の費用試算を2016年に公表したが、さらに増えそう ⑪事故賠償や除染も含めると事故後12兆円を既に支出 ⑫費用総額は廃炉の最終的な形も大きく左右し、負担は国民に跳ね返る 等と記載している。 また、*3-4-2は、⑬東電は8兆円もの廃炉費用を捻出できる力が弱く、経営再建の道筋が描けない ⑭2023年度内に最難関とされるデブリの取り出し作業が始まるが、炉内の正確な状況が分からず、取り出す工法も手探りで費用が想定より膨らむ可能性 ⑮廃炉総額約8兆円のうち約6兆円がデブリへの対処 ⑯東電は廃炉だけでなく除染にかかる費用も全額負担し、賠償も半分払う ⑰東電は新電力への顧客流出で収益基盤が揺らいだまま ⑱原発再稼働が進まなければ、国主導でグループの経営体制の見直しを迫られる可能性 ⑲東電の小早川社長は「財務基盤が安定しなければ、廃炉や賠償などの責任を果たせない」と厳しい表情で語った ⑳廃炉作業を進めるためにも、早期に稼ぐ力を示すことが不可欠 等と記載している。 このうち、①②は、原発処理水を海洋放出する科学的根拠には全くならず、処理水の貯留に限界があるのも最初からわかっていたため、貯留のために膨大な予算を使った挙句に見切り発車して処理水を海洋放出する方法を採用した理由を、まず明らかにすべきである。 その上で、③のように、「推計880tあるデブリは取り出しが難事業だ」と言ったり、④⑤⑥⑦⑧⑨のように、「デブリは放射線量が高くて人が近づけないためロボットアームで取り出すが、それも実際に出来るかどうか不明だ」「デブリ取り出し手法が描けなければ廃炉の見通しも立たない」等と言っているのはあまりにも遅すぎ、人間は核燃料を扱うことはできないという事実を意味している。そのため、「原発を維持する」「新しい核融合原発を作って地球上に太陽を作る」などと言うのは、後始末もできない危険物を作って稼働させるという無責任な行為だ。 また、⑩⑪⑫のように、事故の賠償や除染も含めると事故後12兆円を既に支出しており、政府は2016年にデブリ回収に6兆円、廃炉全体では8兆円の費用試算を公表したが、それらが多様な形ですべて国民負担になる。しかし、他に重要な予算は多いのに、それは削られるため、何を考えてどう予算を決めてきたのかを聞きたい。 なお、⑬⑭⑮⑯は、「デブリの取り出し作業が最難関で取り出す工法も手探り」「東電は8兆円もの廃炉費用を捻出できる力が弱く、経営再建の道筋が描けない」「東電は廃炉だけでなく除染にかかる費用も全額負担し、賠償も半分払う」等としているが、それらは原発稼働を決めた時点で覚悟しておくべきことだったため、今さら泣き言を言ったり国民に追加負担を求めたりはして欲しくない。 私は、東電社員にはレベルの高い人や、良い仕事をする人も多いと思うが、⑱のように、未だに原発にしがみつき、⑳のように、廃炉作業の目途も立たないようなら、既に経営体の体はなしておらず、人材の有効活用もできていないと思われる。 従って、東電の経営体制は見直した方が良いが、経産省を中心とした国主導では、⑲のように、「財務基盤を安定させ廃炉や賠償などの責任を果たすために国民負担を追加する」という解決策しか思いつかないため、今後の生産性向上に役に立つ電力会社の改革はできず、新たに匙を投げた顧客が、⑰のように、東電から他の電力会社に流出すると思う。 4)非科学的で不合理な原発回帰論 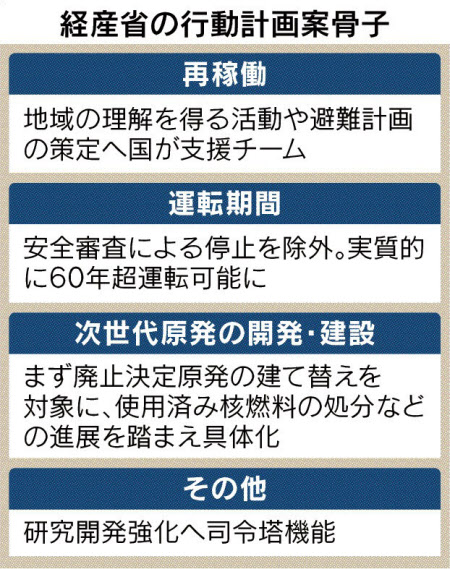 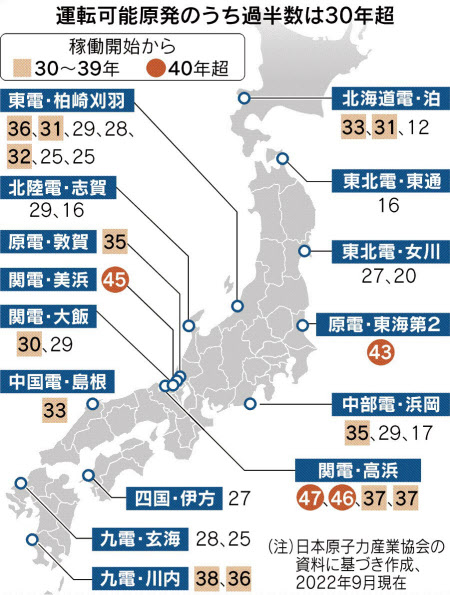 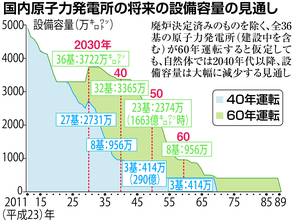 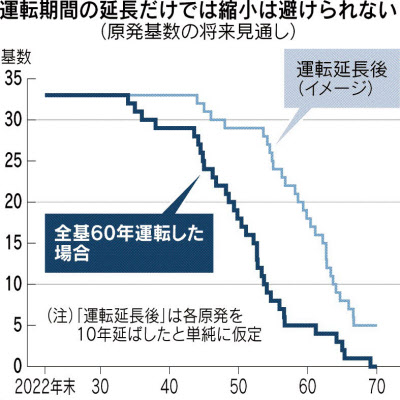 2022.11.29、2022.9.30日経新聞 2022.10.2産経新聞 2022.11.29日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、経産省は既存原発の再稼働と60年超の運転期間延長、次世代原発の開発と建設を計画しており、その理由を、左から2番目の図のように、運転可能原発の過半数が既に30年超を経過しており、右から2番目の図のように、原発の40年運転を厳守すると2060年代には稼働できる原発がなくなり、60年まで運転期間を延長しても2080年代に稼働できる原発はなくなり、1番右の図のように、運転期間延長だけでは原発の縮小が避けられないからとしている。しかし、これは原発運転時の高コストの負担や事故時の膨大なリスクと後処理費用の負担、膨大な核廃棄物の処理費負担、技術の不確実性・不安定性など、原発のあらゆる短所に目をつぶった不合理で強引な行動計画である) 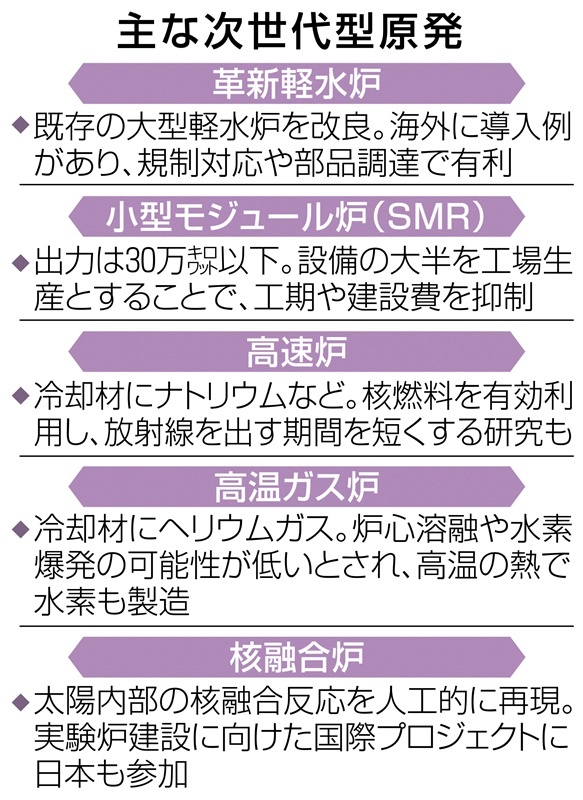 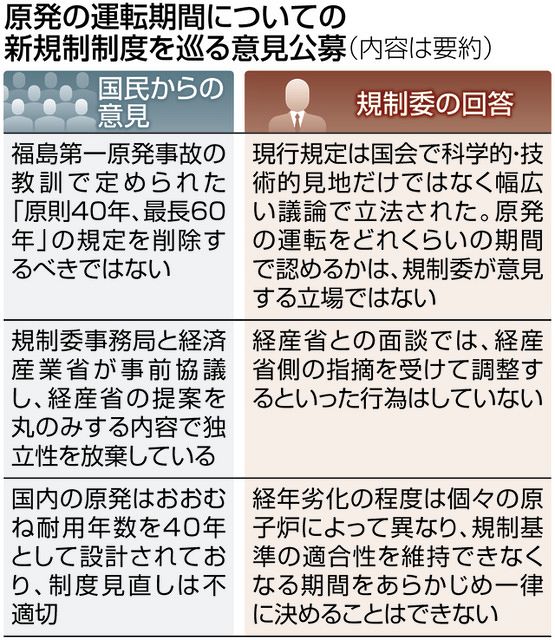 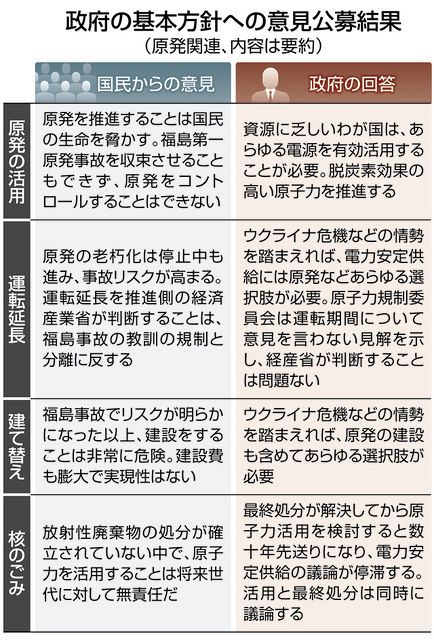 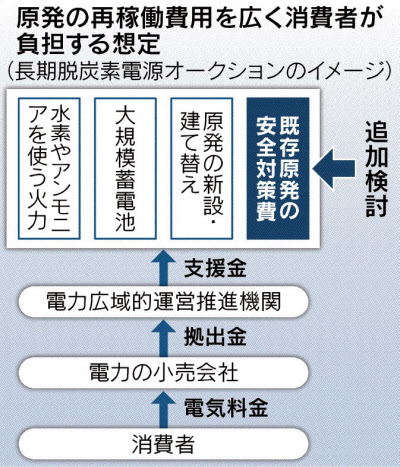 2022.9.5西日本新聞 2023.2.9、2023.2.11東京新聞 2023.7.27日経新聞 (図の説明:1番左の図が経産省の言う次世代型原発だが、既存原発の改良型なら既存原発と同じ問題が残り、冷却材にNaを使うもんじゅは何年経っても成功しなかった。また、高温ガス炉や核融合炉も爆発のリスクがある上、超高温を発生してタービンを回すシステムはエネルギーロスが多く、冷却時に多量の熱を外部に出すのである。そのため、原発は経済合理性《リスクも金額に換算する》によって自然淘汰されるべき電源だが、左から2番目と右から2番目の図のように、政府は、原発の運転期間を伸ばし、建て替えまで選択肢に入れている。その上、1番右の図のように、原発由来の電力を使わない消費者からまで強制的に原発のコストを徴収すると、政府が介入することで市場を歪めて筋の悪い発電方法を残すことになり、目的不明である) これまで書いてきたように、原発は、1966年に日本で最初の商業運転を始めてから57年が経過してなお、平時でも立地地域に税金を投入してやっと運営しており、使用済核燃料の処分先が決まらないばかりか、災害でコントロールを失えば大きな事故となり、莫大な税金を投入しなければ事故処理すらできないシロモノであることが明るみに出て、「原発はコストが安い」という主張は真っ赤な嘘であったことが判明した。 そうすると、次は「電力の安定供給」「脱炭素社会の実現」「ウクライナ危機によるエネルギー情勢の変化」など、その場限りの思いつきの説明をしているが、災害時にも安定的に電源を供給できるのはむしろ再エネによる自家発電の方なのだ。再エネは燃料電池や蓄電池で電力を溜めれば過不足なく電力を供給でき、戦争や災害時も原発のようにコントロール不能の状態に陥ることなく、国内の資源からクリーンな電力が得られる。そのため、化石燃料はもとより、原発も、既に再エネに完敗しており、原発回帰は筋の悪い政策なのである。 イ)原発回帰ありきのパブリックコメントと有識者会議 *3-1-1・*3-1-2は、①政府は、原子力基本法に原発活用による電力安定供給や脱炭素社会実現を「国の責務」と明記 ②原子力の安定的な利用を図る観点から60年を超える運転を可能にして、原発回帰を鮮明にした ③電気事業法や原子炉等規制法など5本をまとめた「束ね法案」で通常国会に提出 ④「原則40年、最長60年」としていた運転期間を原子炉等規制法から電気事業法に移管し、上限維持の上で行政処分や裁判所の仮処分命令などで停止した期間を運転期間の計算から除外できるとした ⑤原発建替・60年超運転等の原発推進策を盛り込んだ政府基本方針はパブリックコメントに4000件近くの意見が寄せられ、多くが原発に反対する声だった ⑥政府が公表した意見公募結果には「フクイチ事故は人間が原発をコントロールできない証明」「将来世代に重大な危険を呼び込む」など政府に再考を求める意見が並んだ ⑦しかし、政府は大筋を変えず閣議決定した ⑧原発に否定的意見に対する政府の回答は、ウクライナ危機によるエネルギー情勢の変化で電力安定供給が危機的状況と強調するのみで ⑨脱炭素効果のある再エネとともに原子力の活用を図るとの説明を繰り返し ⑩原発建替は「廃炉が決まった原発敷地内」とした ⑪原発に否定的な委員からも国民的議論を求める意見が相次いだが、方針決定まで国民の声は聞かなかった ⑫西村経産相は「原子力利用政策の観点でまとめ、安全規制の内容は含まれないため問題ない」と説明 ⑬経産省有識者会議委員も務めたNPO法人原子力資料情報室の松久保事務局長は「反対意見に聞く耳を持たず、原発推進の結論ありきで強引に進めた。政策決定の手法として許されない」と批判 ⑭政府が原発推進策を盛り込んだ基本方針を閣議決定した日、市民団体「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」が主催して、永田町の首相官邸前で約100人が抗議行動を展開し、冷たい雨の中で「原発の新増設は許さない」「福島を忘れるな」と声を合わせた ⑮国際環境NGO「FoE Japan」事務局長の満田夏花さんは「原子力産業の生き残りのため将来世代に大きな負担と事故リスクを背負わせる民意を無視した閣議決定に断固反対」と強調した と記載している。 このうち、①は、電力の安定供給には、再エネと蓄電池を組み合わせて普及させれていれば原発は不要であったため、原子力基本法に「国の責務」などと記載して、民間会社の特定の発電方法である原発にいつまでも税金をつぎ込むと、市場を歪めて最善の発電方法が選択されなくなる。そして、脱炭素社会には、原発ではなく再エネ利用のためのインフラを速やかに整備した方が、エネルギーの変動費を0にして産業に役立ち、エネルギー自給率も上げ、温室効果ガスを発生させず、冷却熱を環境に放出しないため温暖化対策としてもBetterなのである。 そして、これは、原子力村の住民とそこから金を得ているメディアや政治家以外なら誰でもわかることであるため、⑤のように、パブリックコメントに多くの反対意見が寄せられ、⑥のように、「人間は原発をコントロールできない」「将来世代に重大な危険」などの政府に再考を求める意見が並んだのだ。 また、⑪のように、原発に否定的な委員からも国民的議論を求める意見が相次いだのに、政府は方針決定まで国民の声を聞かず、⑦のように、大筋を変えずに閣議決定したのだそうだ。そのため、⑮の「原子力産業の生き残りのために、将来世代に大きな負担と事故リスクを背負わせる民意を無視した閣議決定」というのは、正しいだろう。 そして、政府は、⑧のように、ウクライナ情勢を言い訳にし、⑨のように、脱炭素効果を主張するが、それらは再エネや省エネ設備の導入というよりよい選択肢があったため、説得力のある説明にならないのである。さらに、③のように、電気事業法や原子炉等規制法など5本をまとめた「束ね法案」にして通常国会に提出すると、野党の追及が十分にできず、国民の理解も進まないため、国民の反対を無視して突破するには都合が良いものの、民主主義の原理から大きく外れるのだ。 つまり、⑫で西村経産相が「原子力利用政策の観点でまとめた」と説明しておられるとおり、原子力利用政策が先にあり、そのために形だけ、有識者会議を開いたり、パブリックコメントを集めたりしたが、その結果を反映する意図はなかったのだと思われる。 また、②の「60年を超える運転を可能にした」というのは、前にも書いた理由で、科学的根拠がない上に過去よりもリスクが増す方向への政策転換であり、フクイチ事故後の政策転換として不適切である。また、④の「原則40年、最長60年の運転期間から行政処分・裁判所の仮処分命令等で停止した期間を除外できる」としたのも、科学的根拠がなく、過去よりもリスクが増す方向への政策転換なのである。 これに加えて、⑩の「原発建替は廃炉が決まった原発敷地内」としたのも、武力攻撃に抵抗力のない原発を日本海側に林立させている状態を継続させる決定であり、災害からのセキュリティーも考えていなければ、防衛費増との整合性も全くない。そのため、⑬の「反対意見に聞く耳を持たず、原発推進の結論ありきで強引に進めた。政策決定の手法として許されない」との批判は正しく、「多面的な意見を吸い上げて纏めていれば、矛盾だらけではないスマートな結論を出せたのに」と思われる。 最後に、⑭の政府の閣議決定の日、市民団体「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」主催で永田町首相官邸前で約100人が抗議行動をし、冷たい雨の中、「原発の新増設は許さない」「福島を忘れるな」と声を合わせられたのは、感心すると同時に敬意を表する。 ロ)根拠薄弱な原発政策の転換 *3-1-3は、①巨大地震・津波で世界最悪の原発事故を起こして12年経過しても、事故収束の見通しは立たない ②当時の民主党政権は「2030年代に原発稼働0を可能とするよう、あらゆる政策資源を投入する」とし ③自民党政権下でも「原発依存度は可能な限り低減」としていた原発政策を、岸田首相は大した議論もせずに大転換して原発最大限の活用を掲げた ④世界のエネルギー情勢を無視した「先祖返り」のエネルギー政策は、根拠薄弱で将来に禍根を残す ⑤「ロシアのウクライナ侵攻が一因のエネルギー危機や化石燃料使用による気候危機に対処するため原発の活用が重要」というのが転換の根拠だが、フクイチ事故は大規模集中型の巨大電源が一瞬で失われるリスクの大きさを示した ⑥小規模分散型の再エネを活用する方がこの種のリスクは小さく気候危機に対して強靱 ⑦フランスでは熱波で冷却できずに多くの原発が運転停止を迫られ、原発が気候危機対策に貢献するという主張も根拠薄弱 ⑧気候危機対策には2025年頃に世界の温室効果ガス排出を減少に向かわせ、2030年までに大幅な削減を実現することが求められるが、原発の新増設も再稼働もこれに貢献せず、再エネ急拡大が答えであることは世界の常識 ⑨岸田首相の新方針は時代遅れの原発に多大な政策資源を投入し、気候危機対策の主役である再エネ拡大のための投資や制度改革には見るべきものがない ⑩この12年間で安全対策等のため原発コストは上昇し再エネコストは急激に低下 ⑪原発の運転期間を延ばせばさらなる老朽化対策が必要になるから、原発の運転期間延長も発電コスト削減効果は限定的 ⑫米ローレンスバークリー国立研究所等の研究グループは、蓄電池導入や送電網整備、政策の後押しなどにより日本で2035年に再エネの発電比率を70~77%まで増やせると分析 ⑬日本のエネルギー政策に求められるのは、この種の科学的成果や世界の現実に関するデータを基礎に熟議の上で合理的で説得力のある政策を決めること ⑭いくらそれらしい理屈と言葉を並べても、科学的根拠が薄く決定過程に正当性のないエネルギー政策は机上の空論に終わる 等としている。 このうち①⑥⑦⑧⑩⑪は事実で、地震・津波のリスクを無視して世界最悪の原発事故を起こした上、エネルギー自給率が著しく低く、化石燃料高騰で国民も産業も苦しんでいる日本こそ、②のように、あらゆる政策資源を投入して2030年代に原発稼働0を可能にしなければならなかったし、できた筈なのである。 しかし、③のように、自民党政権下で「原発依存度は可能な限り低減」として後退し、岸田首相はさしたる議論もないまま原発の最大限の活用に大転換したが、まさに④⑨のとおり、世界のエネルギー情勢を無視して時代遅れの原発に後ろ向きの多大な政策資源を投入し、気候危機対策の主役である再エネ投資や制度改革には見るべきものがないという将来に禍根を残すエネルギー政策なのである。 なお、⑤の「ロシアのウクライナ侵攻で化石燃料価格が高騰し、原発の活用が不可欠になった」という政策転換根拠もよく聞くが、化石燃料価格の高騰は、中東産油国が原油価格を70%引き上げた1973年(今から50年前)のオイルショック以来続いているのだ。また、ロシアのウクライナ侵攻による化石燃料価格高騰は、ロシアに対する日本の金融制裁に対する制裁返しであるため、これは、自給率が低いくせに制裁ばかりした国の末路と言える。 そのような事情の中でも、エネルギー変換を拒み、大量の化石燃料を輸入して国富を流出させ続け、地球温暖化まで招き、化石燃料価格が高騰したからと言っては化石燃料に補助金をつけてエネルギー変更を拒んできた“政策”は、製造業を国内で成り立たなくし、国内にあった産業を外国に追いやってしまった原因の1つであることを忘れてはならない。 また、⑤の「フクイチ事故は大規模集中型の巨大電源が一瞬で失われるリスクの大きさを示した」というのも事実であるため、原発は安定電源というのも合理性も説得力もない。 つまり、⑫の米ローレンスバークリー国立研究所等のグループが言うとおり、現在ある技術を最大限に活用しない技術は開発して、蓄電池導入・送電網整備を政策の後押しで行えば、日本は2035年には再エネ発電比率(≒エネルギー自給率)を70~77%まで増やせると、私も思う。 そして、⑬⑭のように、日本のエネルギー政策に求められるのは、科学的成果や世界の現実に関するデータを基礎に、熟議の上で合理的で説得力のある政策を決めることで、いくら尤もらしい理屈や言葉を並べても、科学的根拠が薄く決定過程に正当性のないエネルギー政策は机上の空論に終わるだろう。 5)政府の水産事業者向け支援策について 2)イ)に、私が「復興庁の水産物・水産加工品販売支援事業41億円は、米国等に販売する水産物加工品製造設備の設置に使ったらどうか」と書いてから、日本政府は、*3-5-1のように、中国への輸出依存から転換するための販路開拓等で、①国内消費拡大・生産持続対策 ②風評影響への内外での対応 ③輸出先の転換対策 ④国内加工体制強化対策 ⑤迅速で丁寧な賠償 など合計1007億円の水産事業者向け支援策にをまとめたそうだ。 このうち、②の“風評”という言葉使いは賛成しかねるし、①の国内消費拡大は、どの海域で獲れた汚染されていない水産物かどうかによって良し悪しが異なる。また、③の輸出先転換でホタテ等の一時買い取り・保管・新規販路開拓支援も、とりあえず買い取って長期間保管し、他の場所に販路を求めるというのでは、汚染されていない水産物かどうかによって評価が全く異なるのである。しかし、⑤については、未だに汚染水が増えている現状では、処理して海に放出しているとしても、東電や政府はそうするしかないだろう。 しかし、④の「中国に依存している水産物の加工を国内に呼び戻す」として、*3-5-2のように、「加工も中国頼みで、輸出したホタテを中国でむき身に“加工”した後、米国に3万~4万トン輸出していた」というのは、ホタテの殻をとってむき身にするのは加工と呼ぶほどのことではないし、殻つきのホタテを中国の加工場まで運び、そこでむき身にして米国に輸出すれば余分なエネルギーがどれだけかかったかと思われ、呆れた。 私が書いた「水産物を美味しく加工済・調理済にした製品を輸出すれば売れる」というのは、「日本食キャンペーン」をして日本食として売るのではなく、例えばホタテ(牛肉でも豚肉でもないため、ヒンズー教徒もイスラム教徒も食べられる)であれば、ホワイトシチュー・カレー・ハンバーグ・ギョウザ・シュウマイ・燻製等の相手が好む料理に加工して輸出することを意味していた。ここで注意すべきは、水産物は、日本だけで食べられている食材ではないことである。 また、中国向けナマコは、干して輸出し、中華料理に使うのが主だったと思うが、中華料理も世界で食べられている料理であるため、その原料として販売したり、調理済にして販売したりすることを意味していた。そのため、商社や食品加工会社の出番なのであり、栄養士の監修の下、美味しくて健康的な料理にして販売すれば、日本らしい付加価値の高い食材になるわけだ。 ここで、「建設資材が高騰し機械も電気代も値上がりする中、加工は現実的な対策か」「仮に加工施設を国内に設けても、働き手の確保は簡単でない」という声があるが、こういう問題に対する環境整備こそ政府が行うべきであり、現在は、この高コスト構造に負けない付加価値をつけなければ海外販売はできないわけである。 (4)化石燃料と予算 1)日本が遅れる理由は何か 1990年頃から気候変動に関する指摘があり(発端が私だから詳しいのだが)、1992年に気候変動枠組条約が採択されたが、発効は2年後の1994年だった。また、1997年のCOP3では、日本が主導して京都議定書を採択したが、抵抗も多く、その発効は8年後の2005年であり、気候変動に関する歩みは遅々としていた。しかし、2015年にCOP21でパリ協定が採択され、これは翌年の2016年に発効した。 京都議定書とパリ協定の大きな違いは、i) 京都議定書が2020年までの枠組みであるのに対し、パリ協定は2020年以降の枠組みであること ii) 京都議定書は先進国(日本、米国、EU、カナダ等)のみに温室効果ガス削減目標を示していたが、パリ協定ではすべての締約国が対象になったこと である。 しかし、iii) 京都議定書は「目標達成」を義務としていたが、パリ協定は「温室効果ガスの削減・抑制目標を策定・提出すること」を求めているだけで目標達成を義務とはしていないこと 及び、iv) 2020年以降は、温室効果ガスの削減に関しては世界共通の「2度目標(努力目標1.5度以内)」のみが掲げられていること である(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page22_003283.html、https://www.asahi.com/sdgs/article/14767158 参照)。 このような中、*4-1は、「IPCCが2023年20日に公表した統合報告書でこれまで以上に危機感を打ち出し、その一方で、人類は温室効果ガスを大幅に削減する手段をすでに手にしていると指摘し、この10年間の行動が人類と地球の未来を決めるとした」と記載している。しかし、これは30年前からわかっていたことで、そのために、建材一体型の再エネ機器やEV等の温室効果ガス削減手段を開発してきたのである。 *4-1は、具体的に、①温室効果ガス排出量が増えるほど温暖化が進むと強調 ②世界で稼働・計画中の化石燃料インフラを使い続けると気温上昇が2度を超える ③「パリ協定」で各国が提出する温暖化対策目標を達成しても2.8度上昇する可能性 ④温暖化が進むほど損失・被害拡大 ⑤水害や海面上昇は堤防などの治水対策で一定のリスクは減らせる ⑥国連のグテーレス事務総長はCOP28までに、G20リーダーのすべてが野心的な新目標を約束することを期待し、温暖化に大きな責任を負う先進国は、2040年までに実質排出0を前倒しするよう求めた ⑦G7の米英独加は2035年に電源の脱炭素化目標を掲げ、仏は2021年に91%を脱炭素化済 ⑧日本は2021年に2030年度の46%削減、2050年の実質排出0を掲げ、2040年の目標はなし ⑨IEAは「世界で導入された再エネは昨年最大4億400万kwで2019年から倍増の見通し」とする ⑩EUは昨年5月に再エネ強化目標「リパワーEU」を決め、2030年時点の再エネ比率を40%から45%に引き上げた ⑪米国はエネルギー安保と気候変動対策の約3700億ドルを含む「インフレ抑制法」が成立し、2030年までに40%前後排出減 ⑪日本の再エネの導入ペースは鈍い ⑫COP28ではパリ協定の下で初めて各国の削減目標の進み具合の評価が行われ、2025年までに新たな目標を提出することになるが、環境省幹部は「まだ何も手が付いていない」と言う ⑬2月閣議決定の「GX実現に向けた基本方針」は、今後10年間で150兆円以上の脱炭素投資を見込み、うち20兆円を国が支出するが、発電量に占める再エネ比率を2030年度36~38%と変更なし ⑭大排出源の石炭火力発電燃料にアンモニアや水素を混ぜる技術の推進に7兆円を投じるが、技術的に未確立でコストも高く、石炭火力の延命との批判 ⑮日本のGX基本方針には真剣さや迫力がない ⑯「脱炭素経済」移行に遅れれば日本の産業競争力は引き続き低下 ⑰水素・アンモニアの混焼は「見せかけの脱炭素化」と見られ、世界の投資家から理解を得られない と記載している。 このうちの①④は、科学的に考えれば当然のことである。また、②③のように、気温が上昇すれば、⑤についても、大きく海面上昇すれば、海抜の低い地域は堤防等でリスク軽減するのに費用対効果が著しく悪くなり、ちょっとした豪雨で内水反乱や水害を起こすようになるため移転を余儀なくされ、日本も居住可能地域が狭くなるということだ。 そのため、⑥のグテーレス事務総長の要請は尤もであり、⑦⑩⑪のように、日本を除くG7各国は早めの電源脱炭素化目標を掲げて実行し、⑨のように、IEAも「世界で導入された再エネは2019年から倍増」としているが、日本は、⑧⑪⑬のように、2040年の目標はなく、2023年2月の閣議決定「GX実現に向けた基本方針」で150兆円以上の脱炭素投資を見込み、うち20兆円を国が支出してもなお、再エネ発電比率は2030年度36~38%と変更せず、再エネ導入ペースを意図的に遅くしているのである。 また、⑭の石炭火力発電燃料にアンモニアや水素を混ぜる技術の推進に7兆円も投じるなど寄り道のための無駄遣いも多く、目標を定めて資源を集中しないため、日本のGX基本方針には⑮のように真剣さや迫力がなく、⑰のように「見せかけだけの脱炭素化」になるのだ。 そして、この調子では、⑯のように、「脱炭素経済」への移行に大きく遅れ、国民に無用の負担を押し付けて生活を圧迫しつつ、エネルギー自給率は相変わらず上がらず、日本の産業競争力は他国と比べてさらに低下し続けて、リーダーシップどころではなくなるわけである。 何故、我が国の政府はこのような対応しかできないのか? 私が最初に気候変動に関する指摘をしてから30年以上経過するため、その間に見てきて感じたことを書けば、日本政府は必要な情報を総合して纏めることによって合理的な目標を定めることができず(当然、重要性によって順位をつけ、不要なものは除くべき)、何でも混沌とさせたまま、後戻りしたがったり、「ミックス」にしたがったりするからである。 つまり、日本政府(縦割りに固執した省庁まで含む)は、科学を基礎にしてはじき出した目的に資源を集中させることができず、何でも「ミックス」にして認めることによって政敵を作らないことを重視し、その結果、最も重要な本来の目的を見失うとともに、本来の目的を達成するための国民負担を無視するからである。 そして、この最も根本的な原因は、初等・中等・高等教育における理系科目の軽視と、空気を読んで狭い範囲の周囲にのみ同調することを教える文化にあるだろう。 2)化石燃料価格引き下げ目的の有害補助金について *4-2-1は、①世界銀行は「各国政府が自国産業に出す補助金のうち、環境に有害なものが世界で年間計7兆ドル(約1千兆円)を超える」と公表し ②使い方を見直して環境保護に活用するよう訴え ③補助金のマイナス面に警鐘を鳴らした ④これには不十分な規制で産業を利する「暗黙の補助金」も含む ⑤通常の補助金にも国民生活に不可欠なものがあり、全てを環境保護に振り向けるのは難しい ⑥エネルギー分野では化石燃料価格引き下げにつながる補助金を問題視 としている。 このうち①②③は全くその通りで、世界銀行は良いことを言うと思う。しかし、④の「暗黙の補助金」については具体例が書かれていないためよくわからないが、例えば、原発に関る種々の補助金、放射性物質や排ガスを出す機器への規制の緩さ等が挙げられるだろう。 また、⑤の「環境保護に振り向けるのが難しい国民生活に不可欠な補助金」の具体例も書かれていないのでわからないが、例えば農林漁業関係の補助金の一部はそれに当たると思う。 何故なら、いつまでも農業機械・漁船・トラック・航空機等に化石燃料を使い、「燃油価格が高騰したから補助が欲しい」「コストが合わないから漁に行けない」等々は、私が聞いただけでも20年くらい同じことを言い続けているため、とっくに電動農機・電動船・電動トラック・電動航空機に変更して国内産の再エネ電力でそれを動かしていていい時期だからである。そのため、この20年間、日本政府は膨大な無駄遣いをしながら、何をしていたのかと思う。 つまり、⑥については、最初は仕方がないため燃料に補助するものの、化石燃料価格の引き下げに繋がる補助金は早々に新機器買い替えのための補助金に変え、とっくの昔に新機器への移行を終えていなければいけない時期であり、化石燃料への補助金ではなく、むしろ炭素税を課して移行を促すべきだったのである。 また、*4-2-2は、⑦政府は「9月末まで」としていたガソリン補助金を年末まで延長する方針 ⑧補助の長期化は国民負担を増やし脱炭素に逆行 ⑨8月28日時点の価格(全国平均)は185.6円/lと統計開始以降の最高値 ⑩店頭価格上昇の背景は原油価格の高止まり ⑪産油国は減産によって原油相場を維持 ⑫ロシアも原油輸出を減らす方針 ⑬円安・ドル高の進行もガソリン価格を押し上げ ⑭政府が原油高によるガソリン・軽油・灯油等の価格高騰を抑えるため始めた石油元売りへの補助金は、2022年夏は40円/l前後で、現在は10円/l程度 ⑮ガソリン高は家計の負担増に繋がり、特に地方の家計に響く ⑯補助金の長期化は自然な市場メカニズムの働きを抑える副作用もあるため ⑰「補助金の一部を再エネ・省エネ関連の建設費に投じて将来的な光熱費低減に繋げるべき」との指摘もある 等と記載している。 このうち⑦は、⑪⑫の産油国の減産と⑬の円安で、⑨⑩のように原油価格が高止まりしていれば、それがこれまでの日本政治のツケであっても、今となっては仕方がない。しかし、⑧のように、出口はなく長期化して脱炭素に逆行すると同時に、現在及び将来の国民負担が増えるのだ。 なお、⑭のように、政府が石油元売りに補助金を出すのは変であり、むしろ⑮のように負担増になった家計がガソリンなどの燃油を購入する際に補助すべきだ。そして、早急に燃油依存を止めるため、ドイツのようにガソリンスタンドに充電設備設置を義務付けたり、充電設備設置に補助したりすべきである。 そのため、私は、⑰の「補助金の一部を再エネ・省エネ関連の建設費に投じて将来的な光熱費低減に繋げるべき」との指摘に賛成である。そして、1997年のCOP3で京都議定書の採択を主導した日本なら、2000年になったらすぐにそれを開始していなければならなかったし、集中してやれば今のように借金を増やすことなくできた筈なのだ。 (5)再エネと予算 1)ペロブスカイト型太陽電池への期待  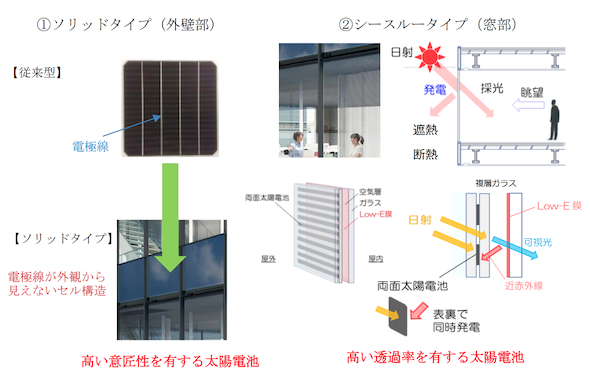 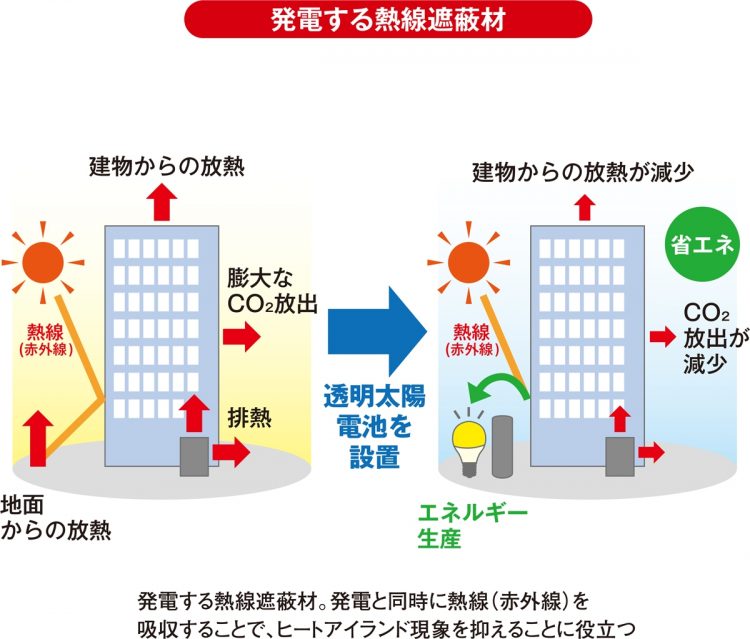 2023.9.7Yahoo 2019.12.20Smart Japan 2022.1.13Money Post (図の説明:左図が、積水化学工業が開発したペロブスカイト型太陽電池ガラスだが、完全に透明にできていない点で改良の余地がある。中央の図は、外壁タイプとシースルータイプの太陽電池の説明だが、外壁なら煉瓦のような模様を印刷できたり、ガラスなら透明ガラスや色ガラスにできたりしなければ、建材としての実用化には遠い。しかし、右図のように、赤外線や紫外線を使って発電し、可視光線は完全透過して、遮熱と発電を同時に行えるガラスも既にできている) *5-1-3は、①「ペロブスカイト型」太陽電池が注目を集めており ②太陽光の吸収にペロブスカイトと呼ぶ結晶構造の薄膜材料を使うため、重さがシリコン型の10分の1 ③薄いフィルム状で折り曲げられ、建物の壁・EVの屋根など場所を問わず自由に設置可能 ④日本で原料を確保しやすいため、国内でサプライチェーン構築可能 ⑤政府は2030年までに普及させる方針で、国内企業を支援 ⑥積水化学工業や東芝が2025年以降の事業化に向け開発を急ぐ ⑦ペロブスカイト型太陽電池は水分に弱いが、積水化学は封止材の技術を使って保護し、耐久性を10年相当に高めた ⑧事業化に欠かせない変換効率も高めた ⑨JR西日本がJR大阪駅北側に2025年の開業を目指す「うめきた駅」に設置する予定 ⑩室内光や曇り・雨天時等の弱い光でも発電可能なため、屋内向け電子商品などにも使われる可能性 ⑪経済波及効果は2030年までに約125億円、2050年までに約1兆2500億円 等と記載している。 このうち、②③④の性質によって、「ペロブスカイト型」太陽電池は、①のように、注目に値すると私も思う。そのため、⑤のように、政府が2030年までに普及させる方針で国内企業を支援するのは、脱炭素化・エネルギー自給率の向上・脱公害という意味で、大変良いと思う。 しかし、⑥⑦のように、積水化学工業や東芝などの民間企業が、2025年以降の事業化に向けて、得意技を使って開発を急いでいるのはさらに期待でき、⑨のように、JR西日本が「うめきた駅」に設置することを既に決めているのも頼もしい。なお、⑧の変換効率については、設置可能面積が著しく広いため、シリコン型ほど高める必要はないのではないか?また、⑩のように、室内光や弱い光でも発電でき、電子商品が充電不要になると便利であるため、⑪の経済波及効果は、もっと大きいと思う。 *5-1-1によると、積水化学工業は、量産で先行している中国勢を追い上げる形ではあるが、強みの耐久性を生かして屋外での需要を開拓しているそうで、量産時期が「2030年まで」というのは少し遅いものの、期待はできる。 なお、積水化学工業が液晶向け封止材等の技術を応用して液体や気体が内部に入り込まないようにできるのなら、真空複層ガラスの内部を透明なペロブスカイト型太陽電池にし、省エネと発電の両方を行う複層ガラスを作って、公共施設だけでなく、民間のビル・マンション・住宅も標準仕様にして欲しい。中古のマンションやビルの場合は、大規模修繕工事の時に一斉に採用すればよいと思うが、耐久性が10年程度では短すぎるため、もっと長く持つ太陽光発電複層ガラスができれば、ニーズは著しく高くなるだろう。 また、パナソニックは、*5-1-2のように、2023年8月に、透明なガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池を開発し、それはインクジェット塗布製法でガラス基板上に発電層を直接形成するものだそうだ。そして、それを、レーザー加工技術と組み合わせれば、サイズ・透過度・デザイン等の自由度を高めることが可能なのだそうで、大いに期待する。しかし、これなら複層ガラスのペロブスカイト型太陽電池でステンドグラスさえできそうであるため、ウクライナの教会の改修等に利用すれば面白いし、宣伝効果もあると思う。 2)省エネ・創エネ・脱炭素住宅へ *5-1-4は、東京都が、①大規模マンションについては断熱性等の環境性能開示制度を既に設けており ②2025年度から、新築の戸建て・中小規模のマンションやビルも事業者が買い手に建物の断熱性や省エネ効果を説明することを義務付け、都の評価基準を満たしているか契約前に説明し、買い手が環境に配慮した物件を選び易くする ③2025年度に始める新築戸建てへの太陽光パネル設置義務化と合わせて省エネ住宅普及に繋げる ④説明義務を負うのは都内で年間2万平方メートル以上の物件を供給する事業者で、大手住宅メーカー等の50社程度を想定し、都内の年間供給棟数の半数程度が対象 ⑤建物自体の環境性能のほか、EV用充電設備の設置状況が都の基準を満たしているかも説明させる ⑥パネルの設置義務も供給棟数の多い50社程度が対象で、新築物件の半数程度が対象になる見通し ⑦都内全体で毎年4万キロワット程度の発電能力を生み出せる と記載している。 東京都は全国で唯一、都立高校入試に男女別定員があり、同じ高校の入試でも男女の合格ラインが違って女性の合格ラインの方が高くなっており、2024年春の入試からこれを全面廃止するという教育面では著しくジェンダー平等から遅れた地域だが、環境については、*5-1-4のように、先進的な規制をした。 具体的には、②⑤⑥のように、事業者が買い手に建物の断熱性や省エネ効果を説明することを義務付けたり、EV用充電設備の設置を推進したり、太陽光パネルの設置を義務づけたりしており、良いと思う。 しかし、①②④のように、対象物件や事業者を規模で分けると、③の省エネ・⑦の創エネ・⑤の脱炭素効果が中途半端になる上、買い手が環境に配慮した物件を選ぶ時には、建物の規模や事業者の規模、新築か中古かが重要な要素になる。そのため、分けるより、全新築物件・全中古物件に説明義務を課し、中古物件のリノベーションも進めた方が良いと、私は思う。 なお、この規制は、東京都だけでなく、国が徹底した省エネ・創エネ・脱炭素を国内の全建築物の建築基準に入れるのが良い。何故なら、そうすれば、電力コストが下がり、エネルギー自給率は上がり、災害に強い電力システムができて、脱炭素も進むからである。 3)EVについて イ)EVバスはBYDから(!?) *5-2-1は、①2023年3月に、西東京バスや神奈川中央交通などがEVバスを採用 ②「EVバスはディーゼルバスより音や揺れが少なく乗客に好評」と西東京バスの担当者は語る ③EVバスは、中国のBYDから購入している ④ディーゼルバスは大型2300万円程度、EVバスは4000万円台 ⑤政府は2023年度のEVバス補助率を導入費用の最大1/2に高め ⑥政府や自治体の補助金で一般バスよりも安く導入できるケースもあって、燃料費は少ない ⑦日本バス協会は2023年を「EVバス普及の年」と位置づけ、2030年までに累計1万台を導入する目標 ⑧バス充電に使う電力を発電する際まで含めるとEVバスもCO₂を排出するが、ディーゼルバスの半分で済み、脱炭素効果が大きい ⑨1回の充電に5時間かかるが、EVバスの電気代は「ディーゼル燃料の2/3程度 と記載している。 このうち②は当然だが、最初は、「EVは音がしないから危ない」「EVは振動しないから自動車らしくない」等々、長所を短所として批判する驚くべき(呆れる)記事が日本のメディアには氾濫していた。そのため、日本国内ではEV化が進まず、③のように、日本のバス会社も中国のBYDからEVバスを購入しなければならない事態になっているのだ。 また、⑧のように、「発電時にCO₂を排出する」という批判も散見されてきたが、それは、発電を化石燃料か原発に限定するから起こることで、再エネ発電に変えれば完全に脱CO₂・脱排気ガス・脱公害にできるのである。そのため、「何故、そういう前向きな代替案が出ないのか」が、日本の論調の問題点なのだ。 さらに、④のように、ディーゼルバスは大型2300万円程度、EVバスは4000万円台と、構造は簡単であるのにEVバスの価格をより高く設定し、「環境志向すれば高くなる」という論理にしているが、構造が簡単な自動車を大量生産すればより安くできる筈である。ただし、国内だけでなく世界での販売を視野に入れて生産しなければ大量生産しても需要がないため、価格を高く設定すれば他国に敗退するしかないという循環になっているわけである。 そのような中、⑤⑥のように、政府はEVバスの補助率を高め、政府と自治体の補助金で一般バスよりも安く導入できるケースもあり、燃料費はEVバスの方が少ないため、①⑦のように、西東京バスや神奈川中央交通などがEVバスを採用し、日本バス協会は2030年までに累計1万台を導入する目標を立てたそうだ。 しかし、⑨のように、EVバスの電気代はディーゼルバスの燃料より安く、CO₂を排出しない発電方法も多いため、早急に大量生産して「補助金不要」の状態にしてもらいたい。何故なら、日本では、EVもまた、本格的に推進し始めてから既に25~30年も経過しているからである。 ロ)新EVも外国製(!?) *5-2-2のように、①スウェーデンのボルボは日本に投入する3車種目のEVの「ボルボEX30」を11月中旬に日本で発売する ②値段は税込み559万円から ③最大の特徴は機械式立体駐車場でも使えるよう小型化したこと ④EX30は全長4235mm、全幅1835mm、全高1550mmと最も小さい ⑤最大航続距離は480kmで急速充電器を使えば約26分で充電残量を10%から80%にできる ⑥日本法人の不動社長は「日本から要望し続けてようやく実現したサイズで、日本の道路・車庫事情に最もフィットする一台」と話した ⑦大型車が好まれる欧米では苦戦が見込まれていたが、予想に反して売れ行きは好調 ⑧小型化で部品数が減り、従来のEVより100万円以上安く、国や自治体の補助金を使えば400万円台で買える と記載している。 このうち⑥の「日本の道路・車庫事情に最もフィットする」のが、③④の「立体駐車場対応」の「小型サイズ」であることは事実だが、道路を狭いままにして小型サイズでなければ運転しにくくしているのは、都市計画のない街づくりの結果であるため、日本の街づくりや道路づくりは再考すべきだ。 しかし、「日本からの要望で実現したサイズ」が、⑦のように、欧米でも売れ行きが好調なのは、どの国にも小路はあるため、小型車の方が運転しやすく、燃費も良いからであろう。 また、②⑧のように、「部品数が減って安くなり、国や自治体の補助金を使えば400万円台で買える」というのは、庶民の自動車の買い替えには必要条件であり、この値段ならボルボ車でも買える。ただし、私自身は、①のようなSUV(Sport Utility Vehicle、スポーツ用多目的車)ではなく、流線形のスマートなEVの方が好みだ。 なお、⑤のように、「最大航続距離480km」では少し不安が残り、5分で900km走れる充電ができるようになれば十分なのだが、「急速充電器約26分で充電残量10%から80%」というのは、現在なら良い方だろう。 4)車の畜電池について イ)リチウム電池 *5-3-1は、①リチウムの精製・分離は環境負荷が高いため、環境規制が緩くて労働コストの安い中国に依存し、豪州のリチウム輸出先は9割が中国だった ②豪州には完成車メーカーはなく ③現政権は脱炭素に意欲的で、EV国家戦略を公表し、EV関連産業育成やリチウム等の重要鉱物資源国内加工を後押し ④米フォード・モーターが自動車を製造していたジーロングはEV向け電池工場の建設予定地に変貌し、米企業傘下の電池スタートアップ、リチャージ・インダストリーズが工場の立ち上げを計画 ⑤年間生産能力は最大30GWH、EV約30万台分の電池を供給予定 ⑥2025年に生産開始して2550人の雇用創出予定 ⑦豪州は近年、山火事等の自然災害が深刻化し、気候変動対策を求める声が強まる ⑧アルバニージー首相は化石燃料に依存する経済から「再エネ超大国」への転換を目指す 等と記載している。 つまり、①のように、リチウム精製・分離の環境負荷が高いため、豪州は輸出の9割を中国に依存していたが、②のように、完成車メーカーがないため、③のように、現政権は、EV関連産業育成やリチウム等重要鉱物資源の国内加工を後押しし、④⑤⑥のように、ジーロングの米フォード・モーター自動車製造跡地に米企業傘下の電池スタートアップが年間生産能力最大30GWHの電池工場と2550人の雇用創出を予定しているとのことである。 これには、⑦のように、豪州で山火事等の自然災害が深刻化して気候変動対策を求める声が強まり、⑧のように、アルバニージー首相が「化石燃料依存型」から「再エネ超大国」への転換を目指している背景があるそうだ。 一方、*5-3-2は、⑨日本の官民は、カナダでEV向け重要鉱物の探鉱・加工・蓄電池生産を含む供給網を構築する ⑩カナダ政府も補助金等で支援し、両国が協力して供給力を高める ⑪これにより、北米での日本企業のEV販売増に繋げ、経済安全保障を強化する ⑫西村経産相が9月21日にカナダを訪問し、ウィルキンソン天然資源相らと蓄電池供給網に関する協力覚書を結ぶ ⑬協力内容はJOGMEC等によるカナダでのニッケル・リチウム等の探鉱 ⑭カナダ政府は現地に進出する日本企業を補助金等で支援する ⑮米国の税額控除対象になるには、車載電池に使う重要鉱物の4割を米国や米国のFTA締結国から調達し、電池部品の5割を北米で製造・組み立てする等が要件 ⑯日本にとっては供給網の強化も見込める 等と記載している。 このうち、⑮の米国における税額控除対象要件のために、⑨⑫⑬のように、カナダでEV向け重要鉱物の探鉱・加工・蓄電池生産を含む供給網を構築し、これを⑩のように、カナダ政府も補助金等で支援して、⑪のように、北米での日本企業のEV販売増に繋げ、経済安全保障を強化するのはわかる。 しかし、*5-3-3のように、2020年8月には、日本のEEZでコバルト・ニッケル等のリチウム電池に不可欠なレアメタルの採掘成功が報告されているのに、未だにほぼ全てを輸入に頼って量産化の目途も立てないのはどうしたことか。採掘・精製・分離の環境負荷や労働コストが高すぎると言うのなら、先進国である豪やカナダのように課題解決して、積極的に国内(EEZも含む)で探鉱・加工・蓄電池生産をすべきである。 なお、カナダ政府は、⑭のように、現地に進出する日本企業を補助金等で支援し、米国政府は、⑮のように、車載電池に使う重要鉱物の4割を米国や米国のFTA締結国から調達し、電池部品の5割を北米で製造・組み立てすること等を税額控除対象の要件としているが、日本政府はこういうことは何も行わずに、⑯のように、輸入先の多角化を喜んでいるだけなのだ。この調子では、国民負担が増えるばかりで国民が豊かになれないのは当然と言わざるを得ない。 ロ)全固体電池 *5-3-4は、パナソニックホールディングス(HD)が、①ドローン等向けの小型の全固体電池を2020年代後半に量産する方針を明らかにし ②3分程度でドローン用電池容量の8割を充電でき、同じ充電に1時間を要するリチウムイオン電池と比べ利便性が高い ③数万回充放電ができ、一般的リチウムイオン電池の約3000回を大きく上回る ④全固体電池はEVの次世代車載電池としてトヨタ自動車も2027〜28年に実用化する方針 とのことである。 ②③のように、3分程度で電池容量の8割を充電でき、数万回充放電ができるのはよいが、家電でも家庭用蓄電池・コードレス掃除機・ガーデンライトソーラー等々、電気の残量を気にせず使いたい蓄電池はいくらでもあるため、開発し始めてから数年経つのに、①のように「2020年代後半(2025年以降)の量産」などと言っているのは遅すぎる。そのため、これでは他国に抜かれても文句は言えまい。 トヨタも「次世代EV車載電池としての全固体電池は2027〜28年に実用化」などとしているが、これも遅すぎて、EVはリチウム電池の世界になりそうなのである。 (6)組織再編について イ)M&Aの使い方 *5-4-1は、①日本企業同士(イン・イン型)のM&Aが全体の63%を占めた ②相乗効果が見込みやすい国内の事業再編が活発になった ③円安で海外企業を買うハードルが上がって潮目が変わる可能性 ④日本企業同士のM&Aで目立ったのは大手企業が国内投資ファンドと組んで株式を非公開化する動き ⑤東芝はJIPや日本企業20社超の支援を受けて株式非公開化を決めた ⑥半導体材料大手のJSRは政府系ファンドJICによる約1兆円買収を受け入れ ⑦半導体材料の国際競争力を高めるため、国の関与の下で積極投資しやすい環境を整える ⑧経営者の高齢化が進み事業承継目的のM&Aも広がった ⑨2010年代の日本企業のM&Aはイン・アウト型が中心だった ⑩脱炭素社会をにらみ再エネ開発会社の再編も増えた ⑪経産省の「企業買収における行動指針(案)」は企業価値向上に繋がる真摯な買収提案を合理的な理由なく拒まないよう求める ⑫日本は主要先進国の中でも、経済規模に比べてM&Aが少ない 等と記載している。 日本では、組織再編の1つであるM&Aに他社やファンドへの「身売り」イメージが強いため、⑫のように、日本の経済規模と比較してM&Aが少ない。そのため、⑪のように、経産省が「企業価値向上に繋がる真摯な買収提案を合理的な理由なく拒まないよう求める」という行動指針(案)を出すほどなのだが、本当は、i)企業の成長のため、他社の買収や合併を行って自社にない技術や販売網を獲得する ii)新規事業への出資や事業拡大のため、ベンチャー企業を作る iii)後継者のいない企業が事業承継する 等の前向きな目的を持つM&Aも多く、M&Aは企業価値向上の一つの手段となる。 そこで、i)の自社にない技術や販売網を獲得するには、①の「イン・イン型」でも⑨の「イン・アウト型」でもよく、ii)のように、お互いの長所を出しあってベンチャー企業を作ってもよいが、⑤の東芝の場合は、⑨の「イン・アウト型」で高すぎる買い物をして大損を出し、公開情報によって不必要なところまで叩かれたため、自らがJIPや日本企業20社超の支援を受けて株式を非公開化することになったという経緯がある。 そのため、②のような国内企業同士の事業再編の方が、お互いをよく知っているため相乗効果の予測がし易いという長所があるが、国内企業同士では大胆な改革が進みにくいという短所もある。また、⑥⑦のように、国の関与の下で積極投資するという政府系ファンドによる買収が、本当に半導体材料の国際競争力を高めるかどうかについては疑問が多い。 なお、⑩のように、脱炭素社会を睨んでの再編も増えたそうだが、その例としては、ソニーと本田の折半出資で設立されたソニー・ホンダモビリティ(株)のように、高付加価値のEVを共同で開発・販売し、モビリティ向けのサービスも提供することを目的として作ったジョイントベンチャーがあり、発電や送電についても、お互いの得意技を活かした提携やジョイントベンチャーがあり得るわけである。 最後に、iii)のように後継者がおらず、⑧のような経営者の高齢化が進んだ企業で事業承継にM&Aを使うのも良い解決策だが、このほかにマネージング・バイアウトという方法もある。 ロ)そごう・西武買収のケース *5-4-2は、①ヨドバシは米ファンドと組んでそごう・西武を買収 ②西武池袋本店・そごう千葉店・西武渋谷店等に出店方針 ③ヨドバシは百貨店中心部に家電売場を設けて集客力を高め、経営再建に繋げる計画 ④西武池袋本店は低層階の一部と中層階以上に家電売り場を設ける ⑤ヨドバシは人口減の中で効率良く集客でき、インバウンドを見込める都市部での競争力強化が課題 ⑥JR池袋駅や千葉駅近くに店舗があるそごう・西武の資産は魅力 ⑦ストライキ決行に追い込まれたそごう・西武労組の不満は根強く、労使の信頼関係にはしこり ⑧豊島区や地元の商工会議所もヨドバシの西武池袋本店出店に納得せず ⑨一部の高級ブランドはヨドバシの出店計画に難色、ヨドバシの出店形態によっては百貨店の主要テナントである高級ブランドの離反を招く可能性 としている。 私は池袋駅まで40分くらいの場所に住んでいるため、池袋駅に直結した西武池袋本店(以下“西武デパート”)と東武百貨店池袋店(以下“東武デパート”)の両方の顧客だが、東武東上線を利用するので東武デパートの方が改札口に近く便利である。また、食品については、東武デパートの方が安くて品質も良いように思う。 しかし、衣類は西武デパートの方が良いので、衣類を東武デパートで買ったことはない。ただし、東武東上線は有楽町線や副都心線と直通運転しているため、本当に良い衣類を探したい場合は、有楽町線で銀座に出たり、副都心線で新宿三丁目や渋谷に出たりすれば、選択肢が増える。そのため、西武デパートは、Young向けの細身サイズ(これが“標準”か)の衣類ばかり置いて特色を出さなければ、競争に負けると思われる。 このような中、2022年度のそごう・西武の業績は、営業利益は25億円と3期ぶりの黒字、純利益はマイナス131億円の赤字で、経営の足を引っ張っているのは3000億円を超える有利子負債だとされている。しかし、①②③のように、ヨドバシカメラが米ファンドと組んでそごう・西武を買収し、百貨店の中心部に家電売場を設ける」という話が飛び込んできた時、私は顧客としてショックだった。 ショックだった理由は、ヨドバシカメラは量販店で高級イメージがなく、百貨店のイメージとは逆だからである。そのため、⑨のように、一部の高級ブランドがヨドバシの出店計画に難色を示したり、百貨店の主要テナントである高級ブランドの離反を招く可能性があったりするわけだ。また、池袋駅や街のイメージも変わるため、⑧のように、豊島区や地元商工会議所もヨドバシの西武池袋本店出店に納得しないことが起きるのだろう。 しかし、当面の解決策としては、④⑥のように、一階にヨドバシ専用の狭い入口をつけ、低層階の一部と中層階以上に家電売り場を設けるのなら、百貨店の高級イメージを壊すことなく、駅に直結した家電量販店ができて便利だと、私は思う。そのため、⑤のようなインバウンド客だけでなく、住民も取り込めるのではないだろうか。 もちろん、⑦のように、ストライキの決行に追い込まれたそごう・西武労組の不満・不信が根強いのはわかるし、西武デパートの専有面積が狭くなるのも残念だが、それは一等地にある西武デパートを、容積率が増すように建てなおせば解決するのではないか? ただし、根本的には、豊島区が、全体として雑然とした池袋駅周辺の街を、緑が多くて整然とした品のある街づくりに変貌させることが重要だ。また、池袋駅も、昔の渋谷駅に負けず劣らず迷路のような長い通路を歩かせて疲れさせる駅であるため、駅ビルを建てなおしてどちら側にも簡単に行けるようにすれば、客足は伸びると思われる。 ・・参考資料・・ <日本の財政と人口減> *1-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230815&ng=DGKKZO73596380V10C23A8MM0000 (日経新聞 2023.8.15) GDP年率6.0%増 4~6月実質、3期連続プラス 輸出復調、消費は弱含み 内閣府が15日発表した4~6月期の国内総生産(GDP)速報値は、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前期比1.5%増、年率換算で6.0%増だった。プラス成長は3四半期連続となる。個人消費が弱含む一方で、輸出の復調が全体を押し上げた。QUICKが事前にまとめた民間予測の中心値は年率3.1%増で、大幅に上回った。前期比年率で内需がマイナス1.2ポイント、外需がプラス7.2ポイントの寄与度だった。年率の成長率が6.0%を超えるのは、新型コロナウイルス禍の落ち込みから一時的に回復していた20年10~12月期(7.9%増)以来となる。GDPの実額は実質年換算で560.7兆円と、過去最高となった。コロナ前のピークの19年7~9月期の557.4兆円を超えた。輸出は前期比3.2%増で2四半期ぶりのプラスとなった。半導体の供給制約が緩和された自動車の増加がけん引した。インバウンド(訪日外国人)の回復もプラスに寄与した。インバウンド消費は計算上、輸出に分類される。輸入は4.3%減で3四半期連続のマイナスだった。マイナス幅は1~3月期の2.3%減から拡大した。原油など鉱物性燃料やコロナワクチンなどの医薬品、携帯電話の減少が全体を下押しした。輸入の減少はGDPの押し上げ要因となる。内需に関連する項目は落ち込みや鈍りが目立つ。GDPの過半を占める個人消費は前期比0.5%減と、3四半期ぶりのマイナスとなった。コロナ禍からの正常化で外食や宿泊が伸び、自動車やゲームソフトの販売も増加した。一方で長引く物価高で食品や飲料が落ち込み、コロナ禍での巣ごもり需要が一巡した白物家電も下押し要因となった。設備投資は0.0%増と、2四半期連続プラスを維持したものの、横ばいだった。ソフトウエアがプラスに寄与したが、企業の研究開発費などが落ち込んだ。住宅投資は1.9%増で3四半期連続のプラスだった。公共投資は1.2%増で、5四半期連続のプラスだった。ワクチン接種などコロナ対策が落ち着き、政府消費は0.1%増と横ばいだった。民間在庫変動の寄与度は0.2ポイントのマイナスだった。名目GDPは前期比2.9%増、年率換算で12.0%増だった。年換算の実額は590.7兆円と前期(574.2兆円)を上回り、過去最高を更新した。国内の総合的な物価動向を示すGDPデフレーターは前年同期比3.4%上昇し、3四半期連続のプラスとなった。輸入物価の上昇が一服し、食品や生活用品など国内での価格転嫁が広がっている。 *1-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230731&ng=DGKKZO73135260Y3A720C2TCS000 (日経新聞 2023.7.31) 600兆円経済がやって来る、特任編集委員 滝田洋一 日銀は7月28日、イールドカーブ・コントロール(長短金利操作)を柔軟にし、長期金利が0.5%の上限を一定程度超えるのを容認すると決めた。日銀は高まるインフレ圧力に負けたのだろうか。いや、逆だろう。日本経済は長期にわたるデフレ不況を克服し、インフレの下で新たな成長に向かいつつある。政府と日銀が慎重な経済運営を続けるなら、思ってもみなかった視界が開けるはずだ。601.3兆円。内閣府は7月20日、2024年度の名目国内総生産(GDP)の見通しを発表した。600兆円といえば、15年に当時の安倍晋三首相が打ち出した新3本の矢の第1目標である。15年度の名目GDPは540.7兆円。22年度も561.9兆円と21兆円あまりの増加にとどまる。それが23年度には586.4兆円と前年度比24兆円あまり増え、24年度には600兆円に乗せる。物価が上がりだしたことで、名目GDPが押し上げられるのだ。GDPばかりでない。企業の売り上げ、利益、働く人の給与明細、株価、政府の税収。目に見える経済活動は物価を含む「名目」だ。デフレ脱却が大きな影響を及ぼすのは企業行動である。1990年度から2021年度にかけて、大企業は売上高が5%増にとどまるなか、経常利益を164%伸ばした。リストラで利益を捻出したのである。企業による設備と人件費の抑制は、経済のエンジンである投資と消費を失速させてきた。インフレの到来でその舞台は一変した。22年度の大企業の売上高は前年度比10.6%増えた。日銀全国企業短期経済観測調査(短観)によれば、バブルの頂点だった1989年以来の高い伸びである。中堅、中小企業も合わせた全規模でも、売上高は8.7%増えた。売り上げ増の手応えをつかんだことで、企業は国内で設備投資のアクセルを踏み出した。23年度の設備投資は名目ベースで100兆円台に乗せ、過去最高となる勢いだ。日本経済団体連合会は4月、27年度に115兆円という設備投資目標を掲げたが、前倒しとなってもおかしくない。今回の物価上昇のきっかけは、ロシアのウクライナ侵攻に伴う世界的なインフレ。コロナ禍からの回復や人手不足も手伝い、国内にも価格転嫁や賃上げの波が及んだ。もちろん、いいことずくめではない。賃金の伸びは物価の上昇に追いついていない。家計のインフレへの不満はここに根差す。5月には物価上昇を差し引いた実質賃金が前年同月比0.9%減少した。実質賃金は14カ月連続の減少。でも減少幅は1月の4.1%減よりぐっと縮まった。春の賃上げ幅が拡大したからだ。連合の集計によると、23年の春闘の平均賃上げ率は3.58%。1993年以来、30年ぶりの高水準になった。7月20日の経済財政諮問会議。有識者である民間議員は「プラスの実質賃金となるよう、賃上げの流れを拡大すべきだ」と提案した。資料に記されたグラフが目を引く。名目賃金の前年比の増加率は22年度上期の1.6%強が、下期には2.0%強に。名目賃金の伸びがこの調子で高まれば、23年度下期にかけ2.5%を上回る姿が描ける。一方、消費者物価上昇率は、民間エコノミストの予想を平均すると、23年7~9月期が前年比2.76%。10~12月期は2.29%と日本経済研究センターは集計する。予想通り賃金の伸びが物価を上回るようなら、23年度下期にも実質賃金は増加に転じる。民間議員がクギを刺すように物価の不確実性は高い。政府によるきめ細かな物価対策は欠かせない。それにしても、家計の所得が消費を後押しする好循環に入るチャンスが巡ってきたのは確かだろう。バブル崩壊後、30年あまり続いた光景が変わるにつれて、財政、金融政策についても正常化を探る動きが出てきている。その際に政府・日銀が心すべきは、経済の好循環に水を差さぬことである。防衛費や少子化対策予算と絡み増税が議論されるが、足元の税収は出世魚のように増加中だ。22年度は当初見積もりの65.2兆円に対し、決算では71.1兆円と6兆円近く上振れした。経済が名目で拡大しだしたからだ。23年度税収の当初見積もりは69.4兆円。前年度の71.1兆円より少ない予想は、政府の名目成長率見通しと整合的ではない。名目成長率見通しの4.4%と同率で税収が増えるなら、23年度の税収は74.2兆円になる勘定。5兆円近い上振れが見込まれる。政府はインフレの受益者であり、税収の自然増が財政を下支えしているのである。デフレ脱却と経済の好循環実現は、岸田文雄内閣の看板政策である少子化対策との関係でも欠かせない。経済停滞のしわ寄せを、特に低所得世帯が被ってきたからだ。35~39歳で配偶者のいる男性の比率を07年と17年で比べると、年収100万~249万円の所得層で低下が目立つ。年収200万~249万円の層を例にとるなら、有配偶者の比率は45.3%から36.2%に低下している。経済産業省はそんなデータを示す。少子化に歯止めをかけるには、真っ先に経済を軌道に乗せ働く人の所得を引き上げる必要がある。バブル崩壊後の日本は経済が軌道に乗りかけると、財政政策か金融政策かでブレーキを踏み、経済を失速させてきた。その轍(てつ)を踏まぬよう細心の注意が必要だ。 *1-1-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230815&ng=DGKKZO73595470V10C23A8EAF000 (日経新聞 2023.8.15) 名目成長、12%に加速、4~6月、物価高で押し上げ インフレが日本経済の名目値を押し上げている。内閣府が15日発表した4~6月期の国内総生産(GDP)速報値は、名目成長率が前期比年率でプラス12.0%となった。デフレで長らく低迷していた名目GDPが、世界的な物価上昇を契機に動き出しつつある。新型コロナウイルス禍の経済低迷の反動が出た2020年7~9月期(プラス22.8%)以来の高い伸び率となった。コロナ禍の時期を除くと、1990年4~6月期(プラス13.1%)以来の伸びとなる。年換算の実額は590.7兆円となり、コロナ流行前である19年度の水準に比べ33.9兆円多い。企業の売上高や賃金、株価などは名目値であるため、インフレによる経済規模の拡大が進めば、こういった経済指標も上昇しやすくなる。名目成長率を項目別にみると、個人消費は前期比0.2%減だった。インフレの影響で実質は0.5%減と名目より深く落ち込んだ。設備投資は実質でみると横ばいだったが、名目は0.8%増だった。設備投資のコストが高まっている可能性がある。GDPデフレーターからみた物価上昇率は前年同期比3.4%と、3四半期連続でプラスとなった。伸び率は前の期から加速した。伸び率は現行基準で遡れる1995年以降で最も高い。過去の基準も含めて比較すると1981年1~3月期以来の伸び率になる。前期比では1.4%の上昇だった。GDPは輸入を控除項目として全体から差し引く。物価動向を示すGDPデフレーターも同様に輸入物価の影響を全体から差し引いて計算する。資源高で急激に輸入物価が上昇した場合、輸入デフレーターが全体にマイナス寄与するため、GDPデフレーターも落ち込みやすい。実際にロシアのウクライナ侵攻による資源高で22年4~6月期、7~9月期は2四半期連続でデフレーターがマイナスになった。ここに来てデフレーターが上昇しているのは、輸入物価の上昇が一巡したことによる押し上げ効果のほか、価格転嫁が進み国内物価も上昇していることを示す。賃金も安定的に上昇してくれば、日本経済の脱デフレに向けた道筋が本格化する。後藤茂之経済財政・再生相は同日の記者会見で、今後の景気については所得の改善や企業の高い設備投資意欲を背景に「緩やかな回復が続くことが期待される」との見方を示した。一方で「物価上昇の影響や海外景気の下振れリスクには引き続き十分注意が必要だ」と指摘した。 *1-1-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1090961 (佐賀新聞 2023/8/15) 実質GDP、年率6・0%増、4~6月、3期連続プラス 内閣府が15日発表した2023年4~6月期の国内総生産(GDP、季節調整済み)速報値は、物価変動を除く実質で前期比1・5%増、年率換算は6・0%増だった。市場予想(年率プラス3%程度)を大きく上回り、3四半期連続のプラス成長となった。半導体の供給制約の緩和で自動車などの輸出が伸びた。ただ輸入の減少が統計上プラスに寄与した面も大きく、物価高の影響でGDPの約6割を占める個人消費も低調だった。実質GDPの伸び率は、20年10~12月期(年率7・9%増)以来の大きさだった。景気実感に近いとされる名目GDPは前期比2・9%増で、年率換算は12・0%増となった。物価高を反映して20年7~9月期(年率22・8%増)以来の高い伸びとなり、金額も過去最高の590兆7千億円に達した。4~6月期の実質を項目別に見ると、個人消費は前期比0・5%減。外食や宿泊は伸びたが、食料品や白物家電が相次ぐ値上がりの影響などで落ち込んだのが響いた。設備投資は0・0%増にとどまった。住宅投資は1・9%増、公共投資は1・2%増だった。輸出は3・2%増だった。自動車の伸びに加え、統計上は輸出に区分されるインバウンド(訪日客)消費の伸びが寄与した。一方、輸入は4・3%減だった。原油や医薬品などが減った。輸入の減少はGDPを押し上げる要因になる。こうした結果、GDP全体への影響度合いを示す寄与度は、個人消費や設備投資などの「内需」がマイナス0・3ポイント、輸出から輸入を差し引いた「外需」がプラス1・8ポイントとなり、外需がGDPを大きく押し上げた。国内総生産(GDP) 国内で一定期間に生み出されたモノやサービスの付加価値の合計額。内閣府が四半期ごとに公表し、景気や国の経済力を表す代表的な指標とされる。個人消費や企業の設備投資といった「内需」と、輸出から輸入を差し引いた「外需」で構成する。実際の価格で計算した名目GDPと、物価変動の影響を除いた実質GDPがある。前年や前四半期と比べた増減率を「経済成長率」と呼ぶ。 *1-1-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230816&ng=DGKKZO73624790V10C23A8EA1000 (日経新聞社説 2023.8.16) 内需の弱さ直視し賃金・投資増の歯車回せ 内閣府が15日発表した2023年4~6月期の国内総生産(GDP)速報値は季節調整済みの前期比の年率換算で6.0%増加した。3%程度だった市場の事前予想を大きく上回り、3四半期連続のプラス成長となった。日本経済は回復の歩みを続けている。名目値は物価高もあって年率12%と2ケタ成長を記録した。実質値は1~3月期の成長率も従来の年率2.7%から3.7%に改定され、GDPの水準は今回、年換算で560兆円台と新型コロナウイルス禍前を上回った。だが「高成長」を額面どおりに受け止められない面もある。外需の一時的な押し上げに支えられ、個人消費や設備投資は力強さに欠けた。内需に弱さが残る現実を直視し、賃上げ継続や投資の着実な実行へ官民で策を練るべきだ。外需のうち輸出は前期比3.2%増とプラスに転換した。統計上、サービス輸出に含まれる訪日外国人のインバウンド消費が堅調だったのは心強い。半面、モノの輸出増には半導体の供給制約の解消といった要因も効いており、海外経済の盤石ぶりを示すわけではない。中国向けの輸出減速には警戒が必要だ。輸入は4.3%減だった。GDP統計では海外から買った分を取り除くので輸入減は成長を押し上げる。年率6%成長のうち輸入減の貢献は4.4%分に及ぶ。輸入の数量減は内需の弱さを映す面もある。個人消費は前期比で0.5%減と3期ぶりにマイナスとなった。事前には小幅増の市場予想が目立った。所得が物価ほどには伸びず、実質でみた所得が目減りしていることが大きい。積極的な賃上げが24年以降も続くかは予断を許さない。構造的な賃上げの機運を絶やさぬよう、官民は一致して取り組むべきだ。設備投資は1~3月期の前期比1.8%増から減速し、0.03%増と横ばい圏にとどまった。日本政策投資銀行の調査では、大企業の23年度の国内設備投資計画は前年度比21%増と、計画値としては1980年代以降で3番目に高い伸びとなった。企業が強気の投資計画を着実に実行に移すには、安定した経済や市場環境の維持が欠かせない。日銀は7月に長短金利操作の運用を柔軟にしたが、債券や外国為替市場は不安定さを抱える。日銀は市場安定へ市場との綿密な対話や情報発信に一層努めてほしい。 *1-1-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230819&ng=DGKKZO73729570Z10C23A8EA2000 (日経新聞 2023.8.19) 続く物価高、消費に影 生鮮・エネ除く指数4.3%上昇、食品高止まり、宿泊料伸び拡大 賃上げは追いつか 物価の上昇圧力が続いている。7月の消費者物価指数は生鮮食品とエネルギーを除く総合指数が前年同月比4.3%上昇し、伸び率は再拡大した。食品や日用品の値上がりは家計を圧迫し、消費は伸び悩む。物価上昇と賃上げの好循環はなお遠く、景気回復の勢いも弱まりかねない。総務省が18日発表した7月の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.1%上昇した。伸び率は6月の3.3%から縮んだものの、日銀が掲げる2%の物価目標を16カ月連続で上回る。価格が変動しやすい品目をさらに除いた指数をみると、物価上昇はむしろ勢いを増す。生鮮食品とエネルギーを除く総合指数は前年同月比4.3%プラスで、2カ月ぶりに伸びを拡大した。消費者物価は2023年度の後半にかけて鈍化するとの見方もあるが、現時点ではまだピークアウトしたとは言えない状況にある。最大の要因は、全体の6割を占める食料の高止まりだ。7月はハンバーガーが前年同月比で14.0%上昇した。10%超えは13カ月連続。プリンは27.5%プラスで、6月の12.6%から伸び率が拡大した。米欧に遅れた価格転嫁の波が続いている。宿泊料は15.1%プラスと、6月から10ポイントほど伸び率を拡大した。インバウンド(訪日外国人)の回復などによる需要の高まりに、政府の観光支援策「全国旅行支援」が今夏以降に各都道府県で順次終了したことが重なった。ほかのサービスも上昇に弾みがついた。携帯電話通信料は10.2%プラスと統計上さかのぼれる01年以降で過去最高の伸び率となった。NTTドコモが7月から新料金プランを投入したことが背景にある。日銀は7月、23年度の生鮮食品を除く物価上昇率の見通しを2.5%に引き上げた。4月の段階では1.8%とみていた。物価上昇率が11カ月連続で3%を超えて推移するなど、物価高が想定を超えて続いている。SMBC日興証券の宮前耕也氏は「日銀も市場関係者もウクライナ侵攻による輸入物価上昇のインパクトを読み違えた」とみる。過去の物価高局面と異なり「一度ではコストを転嫁しきれず、複数回値上げする動きを読み切れなかった」と説明する。長引く物価高で消費への下押し圧力は強まっている。総務省の家計調査によると、2人以上の世帯の6月の消費支出は実質で前年同月比4.2%減った。マイナスは4カ月連続だ。品目別に見ると、物価上昇の大きな要因となっている食料が3.9%減で、9カ月連続のマイナスとなった。プリンやハンバーガーといった値上げが目立つ品目ほど消費は細っている。6月の実質消費支出はそれぞれ15.4%、13.5%減った。逆に、電気代は燃料価格の低下や政策効果による価格下押しで支出が5.9%増えている。外食は1.8%増とプラスを維持するものの、5月(6.7%増)から伸びを縮めた。サービス消費は新型コロナウイルス禍からの正常化で回復期待が高かったわりには動きが鈍い。勢いを欠く消費は経済成長に水を差す。23年4~6月期の実質国内総生産(GDP)は季節調整済みの前期比年率6.0%増と高い成長率となったものの、けん引役は復調した輸出などの外需だった。個人消費は物価高を受けて前期比0.5%減に沈んだ。23年の春季労使交渉の賃上げ率は30年ぶりの高水準だったとはいえ、物価の伸びには追いついていない。24年以降に賃上げが息切れすれば、家計の購買力の低下を通じて再びデフレ圧力が強まるとの懸念がにじむ。実際、コロナ禍前の19年10~12月期と足元を比較すると、雇用者報酬は実質で3.5%減っている。高止まりする物価に賃金が追いつかず、消費はほとんど伸びていない。日米欧では米国だけが賃金と消費を伸ばす。秋以降は物価上昇が加速する恐れもある。政府が実施しているガソリンや電気・都市ガスの価格抑制策は延長措置がなければ、ともに9月分で終了する予定だ。第一生命経済研究所の新家義貴氏はガソリン価格抑制の補助金事業が終われば、10月以降の生鮮食品を除く消費者物価指数を0.5ポイント押し上げるとみる。総務省は電気・都市ガスの価格抑制策が7月の物価の伸びを1ポイントほど押し下げたと推計する。対策が終われば、単純計算で1.5ポイントの上昇圧力となるリスクがある。高い物価上昇率は金融政策の議論にも影響を与える。日銀は物価の安定には「まだまだ距離がある」(植田和男総裁)とみて、金融緩和を続けている。ただ、物価上昇の勢いがこのまま衰えなければ、現状の金融緩和策の見直しが焦点となる。 *1-1-7:https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2023/fis/kiuchi/0808_2 (NRI 2023/8/8) 春闘の妥結と比べて見劣りする実際の賃上げ率:実質賃金の安定的上昇は2025年半ば以降か:長期インフレ期待の安定回復は日銀の責務(6月毎月勤労統計)、木内 登英 ●期待外れの賃金上昇率 労働省が8月8日に公表した6月分毎月勤労統計で、賃金上昇率は期待されたほどには上昇しなかった。現金給与総額は前年同月比+2.3%と、前月の同+2.9%から低下した。残業代やボーナスなどを除く、より変動の小さい所定内賃金も、前年同月比+1.4%と前月の同+1.7%から低下した。この結果、実質賃金は前年同月比-1.6%と前月の-0.9%から下落幅が拡大し、15か月連続での下落となった。賃金上昇率が物価上昇率に追いつかない状況がなお続いており、潜在的な個人消費への逆風が収まっていない。厚生労働省の発表では、今年の春闘で、主要企業の賃上げ率(定期昇給分を含む)は+3.6%と30年ぶりの高水準となった。6月の毎月勤労統計には、春闘での妥結がほぼ反映されているとみられるが、実際の賃上げ率はそれをかなり下回っている。平均賃金上昇率と概ね一致するのは、定期昇給分を含む賃上げ率全体ではなく、ベースアップ部分である。定期昇給分は個人ベースで見れば賃金増加につながるが、企業の人件費全体の増加率を決めるのはベースアップ部分である。退職者と新規雇用者が同数であれば、定期昇給分は人件費全体には影響しない。ベースアップは連合の発表では+2.3%であった。この水準は6月の現金給与総額の前年比上昇率と一致するが、通常は、ベアと近い動きを示すのは、残業代やボーナスなどを除く、より変動の小さい所定内賃金であり、それは6月に+1.4%に過ぎなかった。ベアを公表する企業が必ずしも多くないことから、その集計には誤差が大きいこと、厚生労働省の数字がカバーするのは、従業員5名以上と、零細企業も含むことが両者の差を生んでいるのだろう。零細企業の賃上げ率は主要企業よりも低かったことが考えられる。 ●実質賃金が安定的に上昇に転じるのは2025年半ば以降か 企業の人件費全体や個人所得全体の増加率を決めるのが、定期昇給分を含まないベアであり、それを幅を持って1%台半ばから2%程度とした場合、消費者物価上昇率がその水準まで低下するにはなお時間がかかる。さらに、物価上昇率の低下を反映して、来年の春闘のベアは比較的高水準ながらも、1%台半ばなど、今年の水準を下回ると予想される。物価上昇率が緩やかに低下していっても、賃金上昇率も低下していくため、なかなか両者の逆転は起きないのである。物価上昇率が安定的にベアを下回り、実質賃金が上昇に転じるのは、消費者物価上昇率が0%台半ば程度まで低下する局面であり、それは2025年半ば以降になると予想される。 ●日本では長期インフレ率が上振れ 米国などと比べて日本では、個人の長期のインフレ期待が大幅に上振れていることが注目される。国際決済銀行(BIS)の計算では、2020年末から3%ポイントも上振れ、足元で+5%に達している(図表1・2)。欧米の中央銀行とは異なり、2%の物価目標にこだわる日本銀行が、物価上昇率が上振れる中でも金融政策を修正せず、長期のインフレ期待の上振れを容認してきたことが、大きく影響しているのではないか。この点から、今後、欧米での物価上昇率は比較的迅速に低下する可能性がある一方、日本では、物価上昇率の低下が遅れるリスクがあるだろう。2%の物価目標達成のために、長期のインフレ期待の大幅上昇は望ましい、との意見もあるが、その考えは危険ではないかと思われる。日本経済の実力から乖離した、足元の物価上昇率の大幅上振れや長期のインフレ期待の大幅上振れは、日本経済の安定を損ねかねない。例えば、企業の長期のインフレ期待は個人ほど上昇していないと考えられる中、企業が賃金の大幅な引き上げに慎重な姿勢を崩さず、その結果、この先の賃金上昇率が個人の高い長期インフレ期待に追いつかないことが考えられる。それが明らかになれば、個人は消費を一気に控えるようになるリスクがある。 ●YCC柔軟化に留まらず本格的な政策修正を 賃金上昇を伴う持続的、安定的な2%の物価目標達成にはなお距離がある、と日本銀行は繰り返し述べている。こうした判断は正しく、足元の物価上昇率が一時的に上振れていると言っても、短期的に2%の物価目標を達成することは確かに難しいと思われる。しかし、政治的圧力のもとで日本銀行が10年前に導入を余儀なくされたこの2%の物価目標には、そもそも妥当性はなかった。日本経済の実力を踏まえれば高過ぎることは今も変わらない。日本銀行は2%の物価目標にこだわらずに、日本経済と国民生活の安定のために中長期の物価安定を確保する姿勢をより強く打ち出すべきだろう。その一環として、先般決めたイールドカーブ・コントロール(YCC)の運用柔軟化に留まらずに、マイナス金利解除など、より本格的な政策修正に早期に乗り出すべきではないか。 *1-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15705085.html?iref=pc_ss_date_article (朝日新聞 2023年7月31日) 異次元緩和への道、不安と高揚 10年前の日銀政策決定、議事録公表 日本銀行は31日、2013年1~6月の金融政策決定会合の全議事録を公表した。今に続く大規模金融緩和を始めた時期にあたる。過去に例のない規模の緩和に踏み出す高揚感があった一方、失敗のリスクを指摘する意見も出ていたことが明らかになった。当時、日銀が掲げた2%の物価上昇目標は今も達成されず、様々な懸念は現実になっている。(山本恭介、土居新平)。日銀は年2回、10年が経った会合の議事録を半年分ごとに公表している。今回の議事録が描き出すのは、物価が下がり続けるデフレから脱するため、大規模な金融緩和を掲げて12年12月に誕生した第2次安倍晋三政権の意向に沿って変わっていく日銀の姿だ。日銀出身の白川方明(まさあき)総裁(当時、以下同)は13年1月の会合で、政権の求めに応じ物価上昇率2%の目標を決めた。同年3月、白川氏の後任として安倍政権に起用された財務官僚出身の黒田東彦(はるひこ)総裁は、着任後すぐ大規模緩和に着手した。日銀の金融政策の大転換期にあたり、極めて重要な議事録となる。白川総裁時代、物価目標を「2%」と明確に定めて大規模な緩和をするという政権の方針に、日銀はあらがっていた。しかし総選挙での大勝という「民意」を背にした政権の圧力に最後は屈する。 日銀は13年1月21、22日の会合で、2%の物価目標を盛り込んだ政府との共同声明を受け入れることを7対2の賛成多数で決めた。 ■委員から異論 だが、議事録によると、投票権を持つ政策委員たちからは、目標達成は難しいとする意見が相次いでいた。反対票を投じたエコノミスト出身の佐藤健裕審議委員は「実現の難しい目標値を設定して中央銀行の信認が失われることを懸念する」と指摘。やはり反対したエコノミスト出身の木内登英審議委員は「当面1%の物価上昇率ですら、なお達成の目途が立っておらず、2%はあまりにも高い」と述べた。賛成した委員からも、「非常に難しいのは事実であることは認める。だから時間がかかるだろう」(経済学者出身の白井さゆり審議委員)といった声があった。出席者は、政権への注文も忘れなかった。電力業界出身の森本宜久審議委員は「構造改革の着実な実行と財政規律への取り組みを推進されることを期待する」と語った。政府代表として出席していた山口俊一財務副大臣は「機動的な財政政策や成長戦略の実施に取り組む」とは約束した。ただ、「2%の物価安定目標をできるだけ早期に実現すべく、不退転の決意を持って、積極・果断な金融政策運営をお願いしたいと考えている」と日銀に改めてクギを刺した。 ■目立った賛同 黒田総裁初となる13年4月3、4日の会合。黒田氏は「量・質ともにこれまでと次元の違う金融緩和をおこなう必要がある」と宣言した。人々の「期待」に働きかけてデフレを脱却するため、市場に流すお金の量(マネタリーベース)を2倍に増やし、2年程度を念頭に2%の物価目標を目指すと決めた。「黒田バズーカ」第1弾だ。会合では、黒田氏への賛同が目立った。「安倍自民党総裁の、日銀に2~3%のインフレ目標の達成をめざす大胆な金融緩和を求めるという趣旨の発言によって、デフレ脱却と日本経済回復の期待が生まれた」(経済学者出身の岩田規久男副総裁)。「次を期待させぬよう十分(市場と)コミュニケーションをとっていくことが特に必要」(金融機関出身の石田浩二審議委員)。緩和の効果になお疑問を呈する声もあった。「量を調節することで、インフレ期待や現実のインフレ率を中央銀行があたかも自在にコントロールできるかのような考え方があるとすれば、政策効果のあり方について重大な誤解があると言わざるを得ない」。佐藤審議委員は、大規模緩和の考え方が根本的に誤っている可能性を指摘した。木内審議委員も「非常に大きな不確実性があり、達成までの道筋に関して納得性の高い説明をすることが難しい。政策に対する信認の低下を招き政策効果が減じられるリスクがある」と強い懸念を示していた。あれから10年経って明らかになったのは、物価目標や大規模緩和に対する当時の懸念は杞憂(きゆう)ではなかったということだ。物価目標を達成できないまま、日銀は異例の追加緩和策を相次ぎ導入し、国債や株の保有額は異例の規模に膨らんだ。確かに企業業績は回復し、株価は上がった。ただ、円安の加速は物価高につながり、人々の暮らしを直撃している。大規模緩和を主導した黒田氏は今年4月に退任し、金融政策の手綱は経済学者の植田和男氏が握ることになった。植田氏は就任後3回目となる7月28日の会合で、債券市場がゆがむなどの緩和の副作用を減じる政策修正に初めて動いた。植田氏は会見で、賃金上昇を伴った2%の物価上昇には「まだまだ距離感がある」と語った。異例の緩和をいつまで続けるのか、「出口」はまだ見えていない。 *1-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230813&ng=DGKKZO73562150T10C23A8MM8000 (日経新聞 2023.8.13) 年金世帯、脱デフレ左右 消費シェア4割 不安払拭なら資産循環 賃上げが30年ぶりの高水準となり、消費の押し上げ効果への期待が高まるなか、高齢化社会ならではの課題が浮かび上がってきた。国内の消費支出は65歳以上世帯が4割を占め、年金暮らしの世帯が国内総生産(GDP)の15%に影響する。賃上げの恩恵を受けにくい高齢者の消費活性化がデフレ脱却を左右する。「将来を考えるとなかなか思い切ってお金を使えない」。横浜市の70代の男性はこう話す。孫へのプレゼントなどには財布のひもは緩むが、大きな買い物は控えがちだ。消費支出に占める高齢者の存在感は高まっている。世帯主が65歳以上の世帯の2022年の1カ月平均の支出は21万1780円だった。全体に占める割合は約39%になる。少子高齢化に伴い、20年前のおよそ23%からほぼ倍になった。団塊世代の65歳到達が一巡したことなどから10年代後半から頭打ち傾向にあるものの、団塊ジュニア世代が高齢者になる30年代からは伸びが再加速する可能性がある。持ち家を借家とみなした場合に想定される家賃を除いた消費額をもとに第一生命経済研究所の星野卓也氏が試算したところ、年金暮らしと考えられる平均年齢74.5歳の無職世帯の消費額は22年に33%を占めた。日本の22年の名目GDPの実額は556兆円で、5割を個人消費が占める。GDP全体の15%程度を年金世帯の消費が担っていることになる。消費者物価指数は生鮮食品を除く総合の上昇率が6月まで10カ月連続で3%を超えた。今年の春季労使交渉の賃上げ率は連合の最終集計で3.58%と30年ぶりの水準だ。ただ賃上げの恩恵は年金世帯には及ばず、物価高で年金支給額は実質的に減る。22年の物価上昇などを受け、既に年金を受け取っている68歳以上の人は23年度の支給額が前年度比1.9%増と、3年ぶりに増える。物価の伸び以上に年金額が増えない仕組みになっており2.5%の物価上昇率を加味すると実質的にマイナス圏に沈む。日本総合研究所の西岡慎一氏は物価が今後2%伸びても給付を抑制する「マクロ経済スライド」の発動で受給済みの人の年金の伸びは1%程度にとどまると試算する。この場合、60歳以上で無職の世帯の消費は0.2ポイント押し下げられるという。一方で高齢世帯は金融資産が多い。日銀の資金循環統計によると23年3月末の家計の金融資産は2043兆円と、過去最高だった。19年の全国家計構造調査では、65歳以上の無職世帯の夫婦の金融資産は1915万円で、全世帯平均より636万円も多い。65歳以上世帯の金融資産の7割弱は現預金だ。物価高では現預金の価値が目減りする。今年は日経平均株価がバブル崩壊後最高値となるなど株高で「貯蓄から投資」の機運がある。多くの人が一定の知識を持って適切に資産形成できれば支えになりうる。問題は将来の不安からお金を使おうとする意欲がそがれていることだ。生きている間に必要になる生活費や医療費が見通しにくいと手元の資産を使って積極的に消費しようという気持ちになりにくい。人口に占める65歳以上の比率は20年時点で日本が28.6%と突出する。ドイツが21.7%、米国16.6%、韓国15.8%だ。そもそも米国に比べ日本は消費意欲が弱い。適切に資産形成したり、ライフスタイルにあわせながら可能な範囲で働き続けたりと解はいくつもある。高齢者が過度に不安にならずに消費できる前向きな社会観をつくれるか。需要不足を脱しきれない日本がデフレに後戻りしないためのポイントの一つになる。 *1-3-2:https://mainichi.jp/articles/20230120/k00/00m/040/283000c (毎日新聞 2023/1/20) 年金増、物価高騰追いつかず 「キャリーオーバー」、高齢者負担増も 来年度の公的年金額は3年ぶりの増額改定となった一方、物価高騰などには追いつかず、実質的には0・6%の目減りとなる。長期的に年金財政を維持し、将来世代の支給水準を確保するための対応だが、食料品や光熱費などの値上がりが続く中、年金頼みの高齢者にとってはさらなる痛手になりそうだ。急激な物価高騰の一方で、年金額が実質的に0・6%目減りするのは、年金額を抑制する「マクロ経済スライド」が適用されるためだ。公的年金制度は、現役世代が払う保険料などで高齢者への給付をまかなう世代間の「仕送り方式」で運営されている。 ●来年度から年金額はこう変わる 現役世代(20~64歳)は2020年の約6900万人から、40年には約1400万人減の計約5500万人になる見通し。一方、高齢者は約3600万人から約3900万人に増え、ピークを迎える。少子高齢化で現役世代が減り、高齢者が増えれば年金財政が悪化の一途をたどる。年金財政を長期的に維持するため、04年の年金改正で導入されたのがマクロ経済スライドだった。しかし、想定外のデフレ長期化で、実際には適用されない事態が続いていた。マクロ経済スライドは賃金や物価の伸びが下がった場合は適用されない。過去約20年で適用がわずか3回にとどまった結果、現在の高齢者の給付水準が想定よりも高止まりし、国民年金の給付水準は47年度には現在より3割減るなど、将来世代へのしわ寄せが懸念される。こうしたマクロ経済スライドの機能不全を補うため、18年に導入されたのが「キャリーオーバー(繰り越し)制度」だ。デフレなどで適用できなかった場合でも、翌年度以降にカット分を繰り越して、物価や賃金が上昇したタイミングで一気に差し引く仕組みだ。 ●年金額改定のイメージ(67歳以下の場合) 今回の賃金上昇分は2・8%。本来なら年金額も同程度の引き上げになるところだが、繰り越し制度が実施され、21、22年度にカットされなかった分を含むマイナス0・6%分が一気に差し引かれることになった。「今の高齢者にとっては厳しい措置だが、将来の現役世代の年金水準を保つためには必要不可欠の対応」。厚生労働省幹部は理解を求めるが、繰り越し分が積み重なった結果、一度に差し引かれる年金額が大きくなれば、高齢者の負担感が増す恐れもある。年金問題に詳しいニッセイ基礎研究所の中嶋邦夫上席研究員は「『雪だるま式』に繰り越した分を次々積み重ね、一気に差し引くキャリーオーバーの仕組みは生活への影響が大きい。物価や賃金の変動に関わらず、マクロ経済スライドを部分的にでも常に適用するなどの方法を模索すべきだ」と指摘する。 ●エアコンオフ、風呂や食事減らしても… 高齢者は年金の実質目減りをどう受け止めるのか。「年金の目減りで、さらに生活は苦しくなりそう」。千葉県八千代市で1人暮らしをする高橋芙蓉子さん(80)はため息をつく。現在の厚生年金額は月10万円ほど。家賃が4万円弱かかり、以前から切り詰めた生活を送っていた。そこに物価高とともに、来年度からは年金の目減りも追い打ちをかける。食料品は消費期限が近い「見切り品」の購入が中心で、冬はエアコンなどの電源をオフにしてしのいでいる。東京都世田谷区の斉藤美恵子さん(76)は、介護保険料などを差し引くと月6万円ほどしか手元に残らない。34歳で離婚後、体の弱い母親や子どもの面倒を見ながら、パートなどで働いてきた。「お風呂の回数や食事を減らして何とかやっている。病気になったらどうすればいいのか」。公的年金制度を巡っては、「財政検証」に向けた議論が今後進む。2004年に導入された仕組みで、「年金の健康診断」として、5年ごとに実施される。24年にとりまとめ、25年通常国会で年金関連改正法案の提出を目指す方針だ。少子高齢化で年金制度の「支え手不足」が懸念される中、次期改正に向けては国民年金(基礎年金)の保険料納付期間の延長が焦点になる見通し。現行は20歳以上60歳未満の「40年間」となっている納付期間を、65歳までの「45年間」に延ばすことなどが検討される。将来世代の年金をどうやって確保するのか。模索が続く。 ●公的年金改定率の推移 ニッセイ基礎研究所の中嶋邦夫上席研究員は「少子化や平均寿命が延びた影響を考えると、年金水準を下げないと財政バランスが取れない」と話す。厚生年金の保険料率は04年から段階的に引き上げられ、17年に現在の18・3%に固定された。中嶋氏は「今の年金受給者は現役時代に、今より低い料率で保険料を納めていた。その分を年金水準の抑制で補っているとも考えられる」と指摘。マクロ経済スライドを適切に実施することで、世代間の不公平感の解消を進めるよう求める。一方で、低年金者への手当ても課題になる。中嶋氏は「賃金変動率より年金額が低ければ、相対的に貧困に陥る高齢者は増える。低年金で、かつ資産もない高齢者には、公的年金制度ではなく、福祉的な制度でサポートすべきだ」と話す。 ●マクロ経済スライド 長期的に年金財政を維持し、将来世代の一定の給付水準を確保するための仕組み。現役世代の減少と平均余命の延びに応じ、毎年4月の改定時に物価や賃金の上昇幅よりも年金額を抑制する。少子高齢化で保険料を支払う現役の人口が減る一方、高齢者への支給は膨らむことから、2004年の制度改革で導入された。 *1-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230328&ng=DGKKZO69647960Y3A320C2MM0000 (日経新聞 2023.3.28) 物価高対策2.2兆円 政府、予備費から支出決定 政府は28日、2022年度予算に計上した新型コロナウイルス・物価高対策の予備費から2兆2226億円を支出すると閣議決定した。22日に決めた追加の物価高対策などの原資とする。国が地方に配る「地方創生臨時交付金」に1兆2000億円を充てる。自治体を通じ、LPガス利用者などの負担軽減や低所得世帯への一律3万円の給付を実施する。自治体の対応とは別に、政府も低所得世帯の子ども1人につき5万円の給付を実施する。この経費に1550億円を支出する。家畜のえさとなる配合飼料の価格高騰対策に965億円、輸入小麦の政府売り渡し価格の激変緩和策に310億円、農業用水利施設の電気料金対策に34億円を充てる。飼料対策は、1~3月期のコスト上昇分の一部を補填する。畜産農家が生産コスト削減などに取り組むことが前提となる。既存の価格安定制度とは別に1トンあたり8500円を支給する。小麦価格の激変緩和は特別会計の事業として実施している。特会の経費が不足しており、一般会計から繰り入れる。新型コロナ対策として、病床を確保する医療機関への交付金向けに7365億円も支出する。年度末の申請増加に備えて積み増す。22年度予算の一般予備費から655億円の支出も決めた。ロシアの侵攻を受けるウクライナの復旧・復興支援や物資提供の経費などとする。コロナ・物価高予備費は22年度に当初と補正で計9兆8600億円を計上した。一般予備費は計9000億円とした。今回の支出後の残額はそれぞれ2兆7785億円、3742億円となる。ほかに第2次補正予算で計上したウクライナ予備費が1兆円残っている。 *1-3-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1096241 (佐賀新聞 2023/8/24) 佐賀市消費者物価 17カ月連続100超え 7月物価高騰続く 佐賀県統計分析課がまとめた7月の佐賀市消費者物価指数(2020年を100)は104・9と、前月比で0・6%上昇、前年同月比で3・3%の上昇となった。昨年3月以降、17カ月連続の100超えとなっており、物価高騰が続いている。項目別にみると、光熱・水道、被服および履物が前月からわずかに下落し、教育は前月と同じだった。ほとんどの項目でわずかに上昇し、家事・家具用品114・7、食料111・9、教養娯楽108・1だった。野菜や海藻、通信などの値上げ幅が目立っている。 *1-4:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15704189.html (朝日新聞社説 2023年7月31日) 概算要求基準 歳出「正常化」できるか 政府が、来年度の予算編成に向けた基本方針を決めた。コロナ禍以降、膨張した歳出について「経済が正常化する中で、平時に戻していく」という。当然であり、かけ声倒れに終われば財政の持続性が問われる。具体的な道筋を示すべきだ。各省庁の予算要求に制限をかける概算要求基準も閣議了解した。配分にメリハリをつけつつ全体の規模を抑える役割があるはずだが、相変わらず例外や抜け穴が目立つ。歳出の肥大化が続く懸念が強い。最たるものは、政権が2倍近くへの拡大を打ち出した防衛費を、別枠扱いにした点だ。安定財源を確保しないまま「見切り発車」したのを、予算要求のルールでも追認した。防衛費の大幅増はすでに今年度予算から始まり、他の重要分野や財政健全化にしわ寄せを及ぼしつつある。身の丈に合わない予算増を無理に続ければ、政策資源の配分をゆがめる。弊害を直視し、再考すべきだ。防衛費増と、同様に別枠にした子ども政策の財源について、政府は幅広い「歳出改革」による捻出を当て込んでいる。であれば、減らせる予算の徹底的な洗い出しが必須のはずだ。ところがこの点で、概算要求基準は従来の方式から踏み込まなかった。各省庁に裁量性が高い経費の一律1割減を求めたうえで、削減額の3倍分までの要求を「重要政策」の特別枠で認める。枠は計約4兆円で「新しい資本主義」関連など対象が広い。これで大きな財源をひねり出せるのか、疑問が大きい。歳出の「正常化」への試金石は、高騰したガソリンや電気・ガス料金の補助金の扱いだ。兆円単位の巨費を投じてきたが、秋に期限を迎える。政府は、物価高の激変緩和措置を段階的に縮小・廃止し、影響が大きい層への支援に絞る方針を示した。物価動向が見通しにくい中で、低所得者層への支えは必要だが、一律の補助金をいつまでも続けるわけにはいかない。与党の反発も予想される中、方針を貫けるのか。社会保障など他の分野でも、物価高や賃金上昇に応じた増額を求める声は強まっている。合理的な範囲にとどめられるか。首相の指導力が問われる。20年度以降、コロナ禍や物価高への対応で、政府の歳出は数十兆円規模で膨らんだ。先進国で最悪水準の借金が、さらに積み上がっている。この状況を漫然と続けるのは、将来世代への背信にほかならない。政策の必要性や優先度を厳しく見極め、真に大切な政策を始めるときは安定財源を確保する。そうした当たり前の財政運営に、立ち戻る時である。 <気候変動について> *2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230731&ng=DGKKZO73196930R30C23A7MM0000 (日経新聞 2023.7.31) 地球「12万年ぶり暑さ」 7月平均気温、古気候学者、温暖化に警鐘 米1.5億人に高温警報 世界気象機関(WMO)と欧州連合(EU)の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」は、2023年7月の世界の平均気温が観測史上で最高となる見通しだと発表した。観測記録のない太古の気候を探る研究者は「地球の平均気温はおよそ12万年ぶりの最高気温を記録した」と温暖化の進行に警鐘を鳴らす。数十万年前の地球の気候を研究するのが古気候学だ。米地質調査所(USGS)によると、地層や岩、年輪、サンゴ、アイスコア(氷床のサンプル)に保存される地質学的、生物学的な情報を分析し、過去の気候を推察する。例えばアイスコアの場合、古気候学者は数千年以上かけて何層にも積み重なった氷や雪の層を採取し、中に含まれる気泡やちりを解析する。気泡にははるか昔の大気サンプルが保存されており、地球の平均気温と比例する二酸化炭素(CO2)など温暖化ガスの濃度や当時の雨量までわかる。こうしたデータに基づいた気候モデルを作成し、遠い過去の地球の気候を再現する。米シラキュース大学で古気候学と古生態学を研究するリンダ・アイバニ教授は「地球は過去80万年間、およそ10万年の周期で温暖化と寒冷化を繰り返してきた」と話す。12万5000年前、地球は2つの氷河期の間に位置する間氷期と呼ばれる状態にあり、「直近で地球が最も温暖となった時期だ」という。局所的な異常気象や猛暑日を古気候のモデルと一概に比較することは難しい。ただ、観測を続ければ長期的な傾向がわかる。アイバニ氏は「過去10年間の年間平均気温は毎年のように最高記録を更新した」と指摘。「間違いなく12万5000年ぶりの暑さだ」と断言する。間氷期は「エエム紀」とも呼ばれる。南極の氷床サンプルに基づいた気候モデルを見ると、エエム紀の平均気温は工業化前(1850~1900年)と比べ、セ氏0.5~2.0度ほど高かったことがわかる。気候モデルによると、今年6月に世界の平均気温が工業化前の平均気温を1.5度以上、上回った。米西部アリゾナ州フェニックスでは7月に入り、セ氏42度以上の猛暑日が10日以上続いた。フェニックスではあまりの暑さでサボテンも枯れ始めている。7月28日には米国全体で1億5000万人以上が高温警報の対象となった。バイデン米大統領は27日の演説で「(連日の猛暑もあり)気候変動の影響を否定できる人はもういないだろう」と述べた。熱波は欧州やアフリカでも広がっており、国連のグテレス事務総長も同日、「地球の沸騰が始まった」と警告した。事態はさらに悪化する恐れもある。アイバニ氏は大気中のCO2濃度がここまで高いのは350万年ぶりだと説明し、「大気中の温暖化ガスを見る限り、まだまだ温暖化は続くだろう」と強調した。 *2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230815&ng=DGKKZO73569050U3A810C2TLH000 (日経新聞 2023.8.15) 地球史に人の時代現る、「人新世」、環境に大きく影響 人間活動が地球環境に多大な影響を及ぼすようになった現代を「人新世(じんしんせい)」とする議論が大詰めを迎えている。2024年にも専門家がつくる国際地質科学連合が、地球史に新たな年代を加えるかを決める。地球史と人間の関係を3つのグラフィックとともに考える。地球の歴史は海の誕生や生物の盛衰、気候変動などが節目になってきた。歴史を塗り替えた事件の1つに小惑星の地球衝突がある。白亜紀に栄えた恐竜が絶滅し、新たな章を刻んだ。こうした過去の出来事を地層に残る痕跡からひもとき、地質年代と呼ぶ時代区分に整理してきたのが地球史だ。現代は直近の氷期が終わった1万1700年前から続く新生代第四紀完新世の真っただ中にあった。だが2000年代から始まった人新世の議論は「もはや現代は完新世とは別の時代だ」とする考えに基づく。地球の環境にとって、今の人間の営みは決定的な変化をもたらしているというわけだ。人間の力は大きくなりすぎたのだろうか。19世紀までの産業革命以降、地球は温暖化している。工業社会の進展は豊かな社会を築いたが、深刻な環境問題も招いた。各地の地層からは、人間が地球環境を変えてきた証拠が見つかっている。1950年ごろを境に、化石燃料を燃やした煤(すす)や化学物質、核実験から生じた放射性物質のプルトニウムなどが増えていた。こうした痕跡は地層に残るいわば「科学技術の化石」だ。人間の振るまいが目立つ1950年以降を新たな地質年代と地質学者らが考えるのも自然な流れなのかもしれない。国際地質科学連合の作業部会は7月、人新世の始まりを象徴する場所に、カナダのクロフォード湖を選んだ。湖底の堆積物は地球の変化を克明に記録しているという。 *2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230326&ng=DGKKZO69601710V20C23A (日経新聞社説 2023.3.26) IPCC報告が示す温暖化対策の緊急性 温暖化による気象災害や食料危機、紛争などの悪化を防ぐための時間は、わずかしか残されていない。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がまとめた第6次統合報告書は、温暖化対策の緊急性を強く訴えた。報告書は気候変動をめぐる今後の国際交渉の土台となる。日本は主要7カ国(G7)議長国として真剣に受け止め、中国を含む20カ国・地域(G20)とも連携して対策を加速する必要がある。温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」は、産業革命前に比べた地球の平均気温の上昇を1.5度以内にとどめる目標を掲げる。だが、報告書によると気温は既に1.1度上がっており、2030年代前半にも1.5度に達する可能性がある。気温が目標を超える期間を短くとどめ、下降に向かわせることが重要だ。それには世界の温暖化ガス排出を25年までに減少に転じさせ、35年の世界の排出量を19年比で約60%減らさねばならないという。パリ協定のもと、各国は25年までに35年の新たな削減目標を提示することになっている。報告書の数値は重要な指標となろう。日本の現行目標は30年度の排出量を13年度比で46%減らし、50%減をめざすというものだ。国際社会から一層の上乗せを求められる可能性がある。見直しの検討を怠ってはならない。報告書は21年10月までのデータに基づいており、ロシアのウクライナ侵攻の影響は含まない。現実にはエネルギーの安定供給を確保するため、化石燃料の利用減を先延ばしする動きもある。石炭火力発電への依存度が高いアジアの途上国などでは、再生可能エネルギーへの転換や省エネの投資が不足している。パリ協定の目標達成は困難を伴う。だが、諦めるわけにはいかない。IPCCのホーセン・リー議長は対策の遅れがもたらす熱波や洪水などの被害拡大に警鐘を鳴らすとともに「報告書は希望へのメッセージでもある」と強調した。再生エネルギーや蓄電池のコストは劇的に下がった。水素製造・利用技術や、火力発電所から出る二酸化炭素(CO2)を吸収・貯留する技術の開発も進む。日本は化石燃料依存を減らしつつ、こうした技術の普及へ積極的な役割を果たすべきだ。実績を積み上げ、被害や損害の軽減につなげることが大切だ。 *2-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1093420 (佐賀新聞 2023/8/19) 豪雨被害 内水氾濫対策の強化急げ 近畿を縦断するように北上した台風7号のように今年も各地で豪雨による災害が相次いでいる。線状降水帯が頻繁に発生し、過去最多の雨量を記録するケースも目立つ。これらの要因に挙げられるのが、地球温暖化だと言えるだろう。国連のグテレス事務総長は7月末に「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」と警告した。その証拠に7月の世界の平均気温は過去最高だった。気温上昇による台風の大型化、一度に降る雨の量が増える傾向が続くことを前提に、水害防止対策を強化しなければならない。台風7号の対応では、台風が来る2日ぐらい前から、対応を時系列で定めている「タイムライン」の運用を始めた自治体もある。早め早めに避難所を開設し、高齢者らの避難を呼びかけるという予防的な対応を普及させることが不可欠だ。東海道・山陽新幹線や在来線の一部区間では15日、事前に運休を知らせる「計画運休」を実施した。この結果、突然の運転取りやめによる混乱は回避できたと評価できる。一方、東海道・山陽新幹線は16日、静岡県内の豪雨のため半日程度の運転見合わせを余儀なくされた。土砂崩れや、盛り土区間での路盤の崩壊などを警戒してのことであり、安全確保のためやむを得ない措置だろう。ただ、今後は温暖化に伴って豪雨の増加も想定される。突然の運休を増やさないためにも、さらなる土砂崩れの防止対策や路盤強化策の検討も必要ではないか。秋田県で7月に記録的な大雨があり、秋田市では「内水氾濫」が発生して床上浸水する住宅が相次いだ。内水氾濫とは、下水道や水路の排水能力を超える豪雨のため低い場所に雨がたまることを意味する。河川の堤防が切れて浸水する「外水氾濫」とは対策が異なる。国土交通省によると、2020年までの10年間の水害被害額は約4兆2千億円あり、内水氾濫はうち3割を占める。東京都では被害総額の8割超が内水氾濫だ。都市部では、農地のように雨水を地下に浸透させる土地が少ないため、氾濫の被害が増える傾向があると分析できる。対策としては、下水道を更新して排水能力を高めることや、雨水を地下に一時的にためる施設を造るハード対策が中心となる。公園や緑地を整備して地下に浸透させる量を増やす方法もある。ただ、これらの対策には多くの時間や予算がかかることが難点だ。このため自衛策も重要となる。まずは内水氾濫によって浸水する地域を示す自治体のハザードマップを見て、自分が住んだり働いたりする地域が浸水しやすい場所かどうかを把握することから始める。未策定の自治体に対しては、早期の作成を要望する。次に水に漬かっては困る非常時用の発電機やコンピューターなどは、地下や1階に置かないようにする。地下街や地下室に水が浸入しないように止水板や土のうを備え、緊急時に備えた訓練も必須である。車を運転する場合に備えて、アンダーパスのように水がたまりやすい場所の情報を集めておくことも必要だ。内水氾濫の対策に時間がかかる場所については、土地をかさ上げして安全度を高めて住むようにする。それも難しい場所は、居住を避けることも選択肢としたい。 *2-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230820&ng=DGKKZO73739880Q3A820C2MM8000 (日経新聞 2023.8.20) 石炭火力、依存断てぬ世界 廃炉超す新設、猛暑も影 迫るCO2許容量 世界の石炭依存に歯止めがかからない。最大の消費国の中国は足元の石炭火力発電(3面きょうのことば)の量が過去5年を大きく上回る。コロナ禍からの経済の回復に猛暑が重なり、電力需要が膨らむ。欧州もウクライナ危機で天然ガスの供給不安に直面し、なりふり構わず石炭に回帰する動きが出た。総じて石炭火力は新設ペースが廃炉に勝り、脱炭素の目標はかすんでいる。二酸化炭素(CO2)排出量で世界の3割を占める中国は電源の過半を石炭に頼る。フランスの衛星データ会社ケイロスによると、7月の1日あたりの石炭火力発電量は1年前と比べ14.2%増えた。宇宙からのCO2観測に基づく推計だ。1年前の6月に上海のロックダウン(都市封鎖)を解除した。年明けには厳しい移動制限を強いるゼロコロナ政策を撤廃した。段階的な経済の正常化で電力需要が増加傾向にある。さらに今夏は熱波が襲う。北京の気温が6月として観測史上最高のセ氏41.1度に達するなど記録的な暑さで、冷房が欠かせなくなっている。脱炭素で足踏みするのは中国だけではない。国際エネルギー機関(IEA)の7月の報告書によると、石炭需要は22年に世界2位のインドで8%増えた。インドネシアは36%増えて世界5位の消費国になった。世界全体も23年に過去最高を更新する見込みだ。石炭は低コストで安定調達しやすい。新興国はもちろん、先進国も有事には頼みの綱とする。脱炭素の旗振り役だったドイツも例外ではない。ウクライナ危機でロシアからのガス供給が滞り、ハベック経済・気候相は「状況は深刻」と石炭火力の稼働を増やした。フランスも再稼働に動いた。日本は電源の30%前後を占める状態が続く。11年に原子力発電所の事故が起き、依存度が5ポイントほど高まった。削減の道筋は見えていない。米調査団体グローバル・エナジー・モニターによると、世界の石炭火力は出力ベースで新設分が廃止分を上回る。新設は日本を含むアジアで多いほか欧州のポーランドやトルコでもある。新設の5割を占める中国は廃止ペースの鈍化も目立つ。新設による効率化を考慮しても温暖化ガスの排出量が相対的に多いことは変わらない。依存を断てなければツケは早々に回ってきかねない。温暖化対策の国際枠組みであるパリ協定は産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑える目標を掲げる。この一線を超えると熱波や豪雨などのリスクが劇的に高まる。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は3月の報告書で、1.5度目標の達成に許容できる温暖化ガス排出量は残り4000億トンとの試算を改めて示した。現状の年400億トンの排出ペースが続くと10年ほどで限界に達する。国連のグテレス事務総長は「気候の時限爆弾が針を進めている」と危機感をあらわにした。各国・地域が無策なわけではない。英シンクタンクのエンバーによると、世界の再生可能エネルギー発電量は00年から22年にかけて3倍になった。直近10年だけでも1.8倍に拡大した。中国も太陽光や風力の出力増が著しい。立命館大学の林大祐教授は「00年代以降に大気汚染対策、新興産業として国家的に育成してきた」と指摘する。問題は成長する経済を再生エネだけでは支えきれていないことだ。世界全体で石炭による発電量も10年で15%増え、ほぼ右肩上がりが続く。温暖化のもたらす熱波が、温暖化を招く化石燃料への依存を深める。そんな悪循環の構図も足元で浮かぶ。残り10年の猶予がさらに短くなる懸念さえちらつく。 <原発と予算> *3-1-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/230118 (東京新聞 2023年2月9日) 原発回帰の姿勢、より鮮明に 政府の法改正案判明「国の責務」 原発活用に向けて政府が通常国会に提出する関連法の改正案が8日、分かった。原子力利用の原則を定めた原子力基本法には、原発活用による電力の安定供給の確保や脱炭素社会の実現を「国の責務」と明記。これまで上限としてきた60年を超える運転を可能にする運転期間の規制は「原子力の安定的な利用を図る観点から措置する」とし、原発回帰の姿勢を鮮明にした。電気事業法や原子炉等規制法など5本をまとめた「束ね法案」で、政府が自民党会合で示した。今月下旬にも閣議決定した上で、通常国会に提出する。「原則40年、最長60年」としてきた運転期間は、原子炉等規制法から電気事業法に移管。上限を維持した上で、2011年3月の東京電力福島第1原発事故以降、安全規制への対応や行政指導、後に取り消された行政処分や裁判所の仮処分命令などで停止した期間を、運転期間の計算から除外できるとした。原子力基本法に、国や事業者が安全神話に陥り、福島第1原発事故を防げなかったことを真摯に反省することを基本原則として盛り込んだ。 *3-1-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/230548 (東京新聞 2023年2月11日) パブコメでは多くが反対、各地の説明会は途中…でも原発推進を閣議決定 「将来世代に重大な危険」声を無視 原発の建て替えや60年超運転などの原発推進策を盛り込んだ政府の基本方針は、意見公募(パブリックコメント)に4000件近くの意見が寄せられ、その多くが原発に反対する声だった。しかし、大筋は変わらないまま、10日に閣議決定された。岸田文雄首相の検討指示から半年足らずでの原子力政策の大転換は、一貫して国民の声に向き合っていない。 ◆与党内の声には配慮 「敷地内」の1点修正 「東京電力福島第一原発事故は、人間が原発をコントロールできないことの証明だ」「将来世代に重大な危険を呼び込む」。閣議決定後に政府が公表した意見公募の結果には、政府に再考を求める意見が並んだ。政府の会議で基本方針を決定した後の昨年12月末から約1カ月間実施した意見公募に寄せられたのは計3966件。政府は、類似の意見をまとめて356件の意見内容と回答を明らかにした。原発に否定的な意見に対する政府の回答は、ウクライナ危機によるエネルギー情勢の変化によって電力の安定供給が危機的な状況だと強調。脱炭素効果のある再生可能エネルギーなどとともに、原子力の活用を図るとの説明を繰り返した。意見公募終了後、基本方針の大きな修正は、原発関連では1点のみ。福島事故後に政府が想定してこなかった原発の建て替えについて、対象となる場所を「廃炉が決まった原発」から「廃炉が決まった原発の敷地内」と詳しくした。これは、与党内の原発慎重派の意見に配慮した側面が強い。 ◆国民の声聞かず 「被災者をばかにしている」 基本方針は経産省の複数の有識者会議で内容を検討。原発に否定的な委員からは国民的な議論を求める意見が相次いだが、方針の決定までに国民の声を聞くことはなかった。昨年末に基本方針を決めた後、経産省は1月中旬から経済産業局などがある全国10都市で説明会をスタート。これまでに名古屋市、さいたま市、大阪市、仙台市の4カ所で開き、3月上旬まで続く。説明会が終わらない中での閣議決定に対し、原発事故被害者団体連絡会の武藤類子共同代表=福島県三春町=は10日の記者会見で「何のための意見交換会なのか理解できない。被災地の福島県では開催せず、被災者をばかにしている」とあきれて見せた。 ◆「結論ありきで強引。政策決定の手法として許されない」 規制当局にも反対意見がくすぶる。基本方針は原発を活用する前提として、原子力規制委員会による厳格な審査や規制を掲げる。今月8日の規制委定例会で、原子炉等規制法(炉規法)に規定された「原則40年、最長60年」とする運転期間の定めを経産省所管の法律に移すことに対し、石渡明委員が「必要性がない」と反対。新たな規制制度が決定できるかは不透明になった。西村康稔経産相は閣議決定後の会見で「(基本方針は)原子力利用政策の観点でまとめており、安全規制の内容は含まれていないので問題ない」と説明し、今後も関連法の改正など手続きを進める意向を示した。経産省の有識者会議の委員も務めたNPO法人・原子力資料情報室の松久保肇事務局長は「反対意見に聞く耳を持たず、原発推進の結論ありきで強引に進めている。政策決定の手法として許されない」と批判する。 ◆首相官邸前では反対の声こだま 政府が原発推進策を盛り込んだ基本方針を閣議決定した10日、東京・永田町の首相官邸前で約100人が抗議行動を展開した。冷たい雨の中、「原発の新増設は許さない」「福島を忘れるな」と声を合わせた。市民団体「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」が主催。環境団体や労組など6団体のメンバーらがマイクを握った。国際環境NGO「FoE Japan」事務局長の満田夏花さん(55)は「原子力産業の生き残りのために、将来世代に大きな負担と事故リスクを背負わせることになる。民意を無視した閣議決定に断固反対」と強調。全国労働組合連絡協議会副議長の藤村妙子さん(68)は「福島第一原発の事故から何も学んでいない。老朽原発の稼働は絶対に許されない」と憤った。 *3-1-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1002105 (佐賀新聞 2023/3/10) 事故後12年の原発政策 根拠薄弱な方針転換だ 巨大地震と津波が世界最悪クラスの原発事故を引き起こした日から12年。われわれは今年、この日をこれまでとは全く違った状況の中で迎えることになった。「2030年代に原発稼働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入する」とした民主党政権の政策は、自民党政権下で後退したものの、原発依存度は「可能な限り低減する」とされていた。岸田文雄首相はさしたる議論もないままこの政策を大転換し、原発の最大限の活用を掲げた。今なお、収束の見通しが立っていない悲惨な事故の経験と、この12年間で大きく変わった世界のエネルギーを取り巻く情勢とを無視した「先祖返り」ともいえるエネルギー政策の根拠は薄弱で、将来に大きな禍根を残す。今年の3月11日を、事故の教訓やエネルギーを取り巻く現実に改めて目を向け、政策の軌道修正を進める契機とするべきだ。ロシアのウクライナ侵攻が一因となったエネルギー危機や化石燃料使用がもたらした気候危機に対処するため、原発の活用が重要だというのが政策転換の根拠だ。だが、東京電力福島第1原発事故は、大規模集中型の巨大な電源が一瞬にして失われることのリスクがいかに大きいかを示した。小規模分散型の再生可能エネルギーを活用する方がこの種のリスクは小さいし、深刻化する気候危機に対しても強靱(きょうじん)だ。昨年、フランスでは熱波の影響で冷却ができなくなり、多くの原発が運転停止を迫られたことは記憶に新しい。原発が気候危機対策に貢献するという主張の根拠も薄弱だ。気候危機に立ち向かうためには、25年ごろには世界の温室効果ガス排出を減少に向かわせ、30年までに大幅な削減を実現することが求められている。原発の新増設はもちろん、再稼働も、これにはほとんど貢献しない。計画から発電開始までの時間が短い再エネの急拡大が答えであることは世界の常識となりつつある。岸田首相の新方針は、時代遅れとなりつつある原発の活用に多大な政策資源を投入する一方で、気候危機対策の主役である再エネ拡大のための投資や制度改革には見るべきものがほとんどない。この12年の間、安全対策などのために原発のコストは上昇傾向にある一方で、再エネのコストは急激に低下した。原発の運転期間を延ばせば、さらなる老朽化対策が必要になる可能性もあるのだから、原発の運転期間延長も発電コスト削減への効果は極めて限定的だろう。透明性を欠く短時間の検討で、重大な政策転換を決めた手法も受け入れがたい。米ローレンスバークリー国立研究所などの研究グループは最近、蓄電池導入や送電網整備、政策の後押しなどにより日本で35年に再エネの発電比率を70~77%まで増やせるとの分析を発表した。これは一つの研究成果に過ぎないとしても、今、日本のエネルギー政策に求められているものは、この種の科学的な成果や世界の現実に関するデータを基礎に、熟議の上で合理的で説得力のある政策を決めることだ。いくらそれらしい理屈と言葉を並べ立てたとしても、科学的な根拠が薄く、決定過程に正当性のないエネルギー政策は、机上の空論に終わるだろう。 *3-1-4:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15726692.html (朝日新聞社説 2023年8月28日) 原発支援強化 経済性あったはずでは 政府が原発の新たな支援策の検討を始めた。再稼働を資金面で後押しする内容で、採算性が低い原発の温存や国民負担の増大につながる懸念がある。既存原発は経済的だというこれまでの説明とも矛盾する。導入ありきで進めるようなことは、あってはならない。経済産業省が審議会に案を示した。脱炭素電源への新規投資を支援する「長期脱炭素電源オークション」の対象に、再稼働前の既存原発を加える。従来は再生可能エネルギーや原発などの新設と建て替えが主な対象で、既設は火力発電の低炭素型への改修に限っていた。オークションは来年初めに始まる。入札で選ばれると、事業者は建設費や人件費など固定費分の収入を原則20年間得られる仕組みだ。元手は小売会社が払うが、電気料金を通じて国民全体の負担となる。福島第一原発の事故以降、原発の安全対策が強化され、大手各社が再稼働に向けて投じた工事費は計約6兆円にのぼる。今回の案は、安全対策投資の回収を保証し、電力会社側の事業リスクを軽くする狙いだ。電力の脱炭素化や長期的な供給力を確保するための仕組みは必要だろう。ただし、手厚く支援する以上、対象は相応の効果が見込めるものに絞るべきだ。この点で、既存原発を加える案には疑問が多い。経産省はこの制度の検討時、「既存電源の最大限活用のみでは不十分」と審議会で訴えていた。新規電源とは言えない既存原発の再稼働も対象にすれば、制度の趣旨から大きく外れる。原発依存を長引かせ、新技術導入を妨げることにならないか。そもそも政府と電力大手はこれまで、「安全対策工事をしても(既存の)原発には経済性が十分ある」として再稼働を進めてきたはずだ。多額の工事費を投じる方針も各社が経営判断で決めており、そのコストは通常の事業の中でまかなうのが筋だろう。後になって公的な支援を入れるのは理解に苦しむ。経産省が7月末に案を示したのも唐突だ。5月末に成立した原発推進の法改正で「安全投資などの事業環境整備」が盛り込まれたのが根拠だという。だが、法改正の検討段階や国会審議では、具体的な手法は説明しなかった。「原発復権」に向けた政権の政策転換に関心が高まった時には議論を避け、法改正を押し通した後に「次の一手」を繰り出すのでは、不信感を持たれて当然だ。審議会では、市場制度のあり方をはじめ、広い視点で徹底的に議論してほしい。疑問を置き去りにした「見切り発車」を繰り返すことは許されない。 *3-2-1:https://digital.asahi.com/articles/ASR8S3DMKR8RULBH00J.html?iref=comtop_7_01 (朝日新聞 2023年8月24日)福島第一原発の処理水問題、原発処理水のトリチウム濃度、基準を下回る 午後1時ごろに放出開始 東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出計画で、東電は24日午前、海水で薄めた処理水を分析した結果、トリチウムの濃度は、計画の基準1リットルあたり1500ベクレル(国の放出基準の40分の1)を下回ったと発表した。 ●「理解」得られた?東電の説明は 処理水放出始まっても廃炉見通せず トリチウム以外の放射性物質の濃度が基準未満であることは確認済みで、東電は24日午後1時ごろに放出を始める。会見した東電福島第一廃炉推進カンパニーの処理水対策責任者、松本純一氏は「一段と緊張感を持って対処したい。直接操作にあたる運転員のほか、情報は速やかに発信できるよう準備を整えている。遺漏なきよう実施したい」と述べた。東電によると原発内のタンクには、大半の放射性物質を除去する「多核種除去設備」(ALPS(アルプス))などを通した水が約134万トンたまっている。今年度は、このうち約3万1200トンを放出する計画。1回目の放出では約17日間かけて約7800トンを流す。放出開始から1カ月程度は、沖合約1キロ先の放水口の周辺で海水を毎日採取し、トリチウム濃度を調べる。東電は、22日午前の政府の関係閣僚会議での正式決定を受けて放出の準備を開始。タンクの水を約1200倍の海水で希釈した処理水を22日夜に採取し、トリチウム濃度を調べていた。海水で希釈した処理水は「上流水槽」にたまる。処理水を入れ続けると、あふれて隣の「下流水槽」に流れ込む。下流水槽の底部には、放水口に続く海底トンネルの入り口があり、処理水は自然に放水口から海へ出ていく仕組みという。 *3-2-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/271966?rct=editorial (東京新聞社説 2023年8月23日) 処理水放出 「全責任」を持てるのか 東京電力福島第一原発にたまり続ける「処理水」が、海に流される。「風評被害」を恐れる漁業者に対し、岸田文雄首相は「漁業が継続できるよう、政府が全責任を持って対応する」と強調するが、順調に進んでも三十年に及ぶ大事業。誰が、どう責任を取り続けるというのだろうか。福島第一原発では、事故で溶け落ちた核燃料を冷やすため、大量の冷却水をかけている。そこへ地下水や雨水が加わって、「汚染水」が毎日約九十トンずつ出続けている。その「汚染水」から多核種除去設備(ALPS)で大半の放射性物質を取り除いたものが「処理水」だ。原発構内には千基を超える「処理水」のタンクが林立し、廃炉作業の妨げになるとして、政府はおととし、濃度を国の基準値未満に薄めた上で、海底トンネルで沖合一キロの海に流す方針を決めた。ALPSを用いても、放射性物質はわずかに残り、三十年間放出し続ければ膨大な量になる。風評被害を恐れる漁業者の不安はぬぐえていない。政府と東電は八年前、福島県漁業協同組合連合会との間で「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わない」との約束を交わした。全国漁業協同組合連合会の坂本雅信会長=写真右端=は二十一日、首相=同左端=と面談し、「海洋放出に反対であることには、いささかも変わりない」とした上で「科学的な安全と社会的な安心は異なるもので、科学的に安全だからと言って風評被害がなくなるものではない」と強い懸念を表明した。約束を反故(ほご)にしての放出開始。いくら首相が「責任を持つ」と繰り返しても、にわかに信じられるものではないだろう。海洋放出の実施については、まだまだ説明と検討が必要だということだ。これほどの難題を抱えつつ、あたかも別問題であるかのように、政府が「原発復権」に舵(かじ)を切るのも全く筋が通らない。日本の水産物輸出先一位の中国は先月から税関検査を強化。七月の輸入量は前の月に比べ、三割以上減少した。拙速な放出開始は将来にさらなる禍根を残す。 *3-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230824&ng=DGKKZO73837360U3A820C2EA2000 (日経新聞 2023.8.24) 経産相、福島産の積極販売を要請 小売6団体幹部に 西村康稔経済産業相は23日、東京電力福島第1原子力発電所の処理水の放出が24日にも始まるのを前に小売業界団体の幹部と面会した。福島県産の水産物などの風評被害が懸念される中、積極的に販売に取り組むよう求めた。政府の支援策と合わせ、漁業者が事業を継続できる環境を整える。「これからも変わらず三陸常磐ものの取り扱いをしてもらえるようにお願いする」。都内で開かれた風評対策・流通対策連絡会。西村経産相は小売り関連の6団体の幹部に、処理水の海洋放出後も福島県産などの産品の販売継続を要請した。西村氏は「消費者の不安などの声も届くと思うので課題があれば言ってほしい」と連携を呼びかけた。日本チェーンストア協会の三枝富博会長は「放出後も三陸常磐でとれた水産物をこれまで通り取り扱う」と応じた。小売業界は消費者が安心して買い物できる環境を整備するよう政府に要望した。具体的には国際機関など第三者による安全性の厳格な確認、処理水が基準を満たしているかの監視結果の迅速な公表、水産物の検査体制――の徹底を求めた。政府は22日の関係閣僚会議で気象などの条件が整えば24日に放出すると決めた。東京電力ホールディングス(HD)は同日朝に放出の可否を判断し、問題なければ午後1時にも開始する。処理水の放出で地元の漁業者らは風評被害で売れ行きが落ち込むのではとの懸念を訴えている。23日の自民党水産部会には全国漁業協同組合連合会(全漁連)の坂本雅信会長ら漁業関係者が参加した。処理水放出に伴う中国や香港の輸入規制を巡り、販路拡大への支援を求める声が出た。中国は処理水放出に反発し、日本からの水産物の輸入規制を強めている。足元では日本でとれたホタテなど一部の水産物は人件費の安さからいったん中国にわたって殻をとるといった加工後に米国などに輸出されている。輸出維持のため、加工地を日本に戻す支援が必要との主張もあった。岸田文雄首相は放出と風評被害に「国が全責任を持つ」と強調する。政府は不安の払拭のため小売事業者に協力を求めたのに加え、首都圏や福島など東北地方でイベントを開いて水産物などの魅力向上にも努める。23日には復興庁が24年度の概算要求で水産業などへの支援事業を拡充する方針が明らかになった。処理水の処分に伴う対策として水産物や水産加工品の販売支援事業では41億円、漁業人材の確保では23年度当初予算比で14億円増の21億円をそれぞれ要求する。 *3-3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230824&ng=DGKKZO73838100U3A820C2MM8000 (日経新聞 2023.8.24) 小売り大手、福島産の販売方針変えず ヨーカ堂「生産者を応援」 原発処理水きょう放出 セブン&アイ・ホールディングスなど小売り大手は、24日以降に東京電力福島第1原子力発電所の処理水が海洋放出された後も福島県産水産物の販売を続ける。イオンは放射性物質の自主検査をしながら、関東圏などの総合スーパーで継続販売する方針だ。販売継続で風評被害を防ぎつつ、フェアを通じて需要を喚起する動きもある。セブン&アイ傘下のイトーヨーカ堂は23日、処理水の放出決定を受けて「東日本大震災で被災した生産者を応援していく」とし、福島県産の販売を続ける考えを示した。食品スーパーのライフコーポレーションやヤオコーなども販売を継続する。ヤオコーは「(福島産を減らすなど)商品の見直しはしない」という。イオンは22日、関東圏などの総合スーパーで福島県産を継続販売すると発表。同時に放射性物質トリチウムの含有量について、国際基準より厳しい自主検査を実施し、サイトで結果を公開する方針を明らかにした。 *3-3-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15724835.html?iref=pc_shimenDigest_top01 (朝日新聞 2023年8月25日) 福島第一、処理水放出 国産全水産物、中国が禁輸 日本政府抗議、撤廃求める 東京電力は24日、福島第一原発の処理水の海への放出を始めた。増え続ける汚染水対策の一環で、少なくとも約30年は放出が続く。これを受けて中国政府は24日、日本産の水産物輸入を同日から全面的に停止すると発表した。香港も同日から10都県の水産物禁輸を始めた。東電は24日午前、海水で希釈した処理水のトリチウム濃度の測定結果を発表した。計画で定める1リットルあたり1500ベクレル(国の放出基準の40分の1)を大きく下回った。ほかの放射性物質の濃度も希釈前に基準未満と確認しており、午後1時過ぎから放出を始めた。放出から約2時間後、沖合1キロ先の放水口周辺の海水を採取する船が原発から出港。1カ月程度は毎日、10カ所で海水のトリチウム濃度を測り、翌日公表する。東電の計画では、今年度はタンク約30基分にあたる計3万1200トンを4回に分けて放出する。トリチウムの総量は約5兆ベクレルで、年間の放出上限22兆ベクレルの4分の1以下。1回目は7800トン分で約17日間かけて流す。これに対し、中国外務省は24日、「断固たる反対と強烈な批判」を示す報道官談話を発表した。その後、中国税関総署が日本を原産とする水産物の輸入を暫定的に全面停止すると公表。対象は「食用の水生動物を含む水産品」。魚類や貝類のほか海藻なども幅広く適用され、冷蔵・冷凍ともに禁輸になるとみられる。中国は原発事故後、福島など10都県からの食品輸入を禁止してきた。さらに、7月から放射性物質の検査を厳格化し、日本産の鮮魚などは実質的に輸入が止まっていた。農林水産省によると、2022年の中国への水産物の輸出額は871億円。全体の約2割を占める最大の輸出先だ。香港も同年の輸出額は755億円で中国に次ぐ2位だった。岸田文雄首相は24日、首相官邸で「科学的根拠に基づいて専門家同士がしっかりと議論を行っていくよう、中国政府に強く働きかける」と語り、中国側に冷静な対応を求めた。外務省の岡野正敬事務次官は同日、中国の呉江浩大使に電話で抗議し、全面禁輸措置の早期撤廃を強く要求した。首相は「水産事業者が損害を受けることがないよう、万全の態勢をとっていく」とも強調した。東電の小早川智明社長は「国内の事業者で輸出に係る被害が発生した場合は適切に賠償する」とのコメントを出した。 *3-4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230825&ng=DGKKZO73874580V20C23A8MM8000原発処理水放出を開始 (日経新聞 2023.8.25) 「廃炉」目標まで30年、デブリなど難題 東京電力福島第1原子力発電所の事故から12年を経て、原発処理水の放出が24日始まった。廃炉に向けて一歩踏み出したものの、原発内部からの溶融燃料(デブリ、総合2面きょうのことば)の取り出しという最難関作業が待ち受ける。政府が目標とする30年後の廃炉完了は見通せない。東京電力ホールディングス(HD)は24日午後1時すぎ、原発敷地内にたまる処理水の海洋放出を始めた。23年度は全体の2.3%に当たる3万1200トンを4回に分けて放出する。24日に始めた初回分は7800トン程度を17日間程度かけて流す。51年までの廃炉期間内に放出を終える計画だ。処理水は放出前に海水と混ぜて、薄めた処理水に含まれる放射性物質トリチウムの1リットルあたりの濃度が国の安全基準の40分の1(1500ベクレル)未満であることを確認した。国際原子力機関(IAEA)のグロッシ事務局長は24日の声明で、IAEA職員の現場での分析で、トリチウム濃度が「1リットルあたり1500ベクレルの上限濃度をはるかに下回っていることが確認された」と指摘した。政府と東電は漁業への風評被害を防ぐため、監視データを定期的に公表して安全性を国内外に示す。基準を上回る濃度のトリチウムが検出されれば、すぐに放出を止める。東電は25日、環境省は27日にデータを公表する。西村康稔経済産業相は放出開始後に都内で記者会見し「データを透明性高く公表して安全安心を確保し、漁業者の生業継続支援に取り組みたい」と述べた。処理水の放出は長い道のりの一歩にすぎない。今後はデブリの取り出しという難事業が控える。処理水を放出できなければ、取り出したデブリを保管する場所が確保できない。放出が進めばタンクが減るため、廃炉計画の具体化に欠かせない過程だ。デブリはメルトダウンで原子炉から溶けた核燃料が金属やコンクリートと一体化したものだ。1~3号機全体でデブリは推計880トンあるとされる。放射線量が非常に高く、人が近づけない。それゆえ取り出し作業は遠隔操作になる。英企業や三菱重工業などが開発したロボットアームを使い2号機から着手する。東電などによると、1回目で取り出すのはわずか数グラム程度にとどまる。それすら実際に出来るのかどうかは分からない。日本原子力学会・福島第1原子力発電所廃炉検討委員会の宮野広委員長は「政府が示す廃炉計画は具体的な見通しがあるわけではない。一番難しいデブリの取り出しの手法が描けないと廃炉の見通しも見えない」と指摘する。国などは福島第1原発の廃炉作業には事故の発生後30~40年かかるとしている。事故後12年を経て残りは30年程度だ。国は廃炉について最終的な形を明らかにしていない。更地となるのか、ある程度の廃棄物が残るのかによって地元の受け止めも大きく変わる。費用も課題だ。政府はデブリ回収に6兆円、廃炉全体で8兆円との費用試算を16年に公表したが、さらに増える可能性が高い。事故賠償や除染も含めると既に事故後12兆円を支出している。費用総額は廃炉の最終的な形も大きく左右する。負担は国民に跳ね返るだけに国は丁寧な説明が求められている。 *3-4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230826&ng=DGKKZO73914760V20C23A8TB0000 (日経新聞 2023.8.26) 東電、廃炉費用8兆円 処理水放出も収益低迷、再建遠く 東京電力ホールディングス(HD)は福島第1原子力発電所の処理水の海洋放出を始め、2051年までの完了を掲げる廃炉作業はようやく前進した。8兆円に上る廃炉費用を捻出するだけの稼ぐ力はまだ弱く、経営再建への道筋を描けないでいる。政府が海洋放出を24日に決め、東電幹部は安堵した。「今夏での決着は廃炉を進める上で大きな意義がある」。敷地内の保管タンクは利用率が98%に達し、限界に近づいていたためだ。19年度の福島第2の廃炉決定に続き、約10年間議論してきた懸案がようやく解消したが、社内には楽観的な空気はない。23年度内には最難関とされるデブリの取り出し作業が始まる。廃炉総額約8兆円のうち約6兆円がデブリへの対処につぎ込まれる。炉内の正確な状況は分からず、取り出す工法も手探りで費用は想定より膨らむ可能性が高い。東電は廃炉だけでなく除染にかかる費用は全額負担し、賠償も半分程度を支払う。まずは20年代半ばに年3000億円の経常利益を稼ぐ目標を達成しなければ支払いは難しくなってくるが、この10年間で達成したのは16年3月期の1度のみ。23年3月期は資源高で2853億円の赤字となり、道のりは険しい。東電は域外への電力販売や再生可能エネルギー事業の強化などを行ってきたが収益を底上げするほどには至っていない。首都圏中心に約2100万件もの顧客を抱えるが、新電力への顧客流出で収益基盤が揺らいだままだ。東電の火力比率は21年度で77%と沖縄電力に次いで高く、今後も資源高で利益が左右されやすい。過去5年で東電HDの純現金収支は1.2兆円の赤字と大手電力で最も悪い。東電にとって、「経営再建には柏崎刈羽しかない」(幹部)。原発1基で1400億円の収支改善につながるだけに経営の最優先事項として取り組んできたが、いまだ先行きは不透明だ。東電は10月に柏崎刈羽7号機の再稼働を目指したが、テロ対策の不備で原子力規制委員会から運転を禁じられたままだ。原発関連の重要書類の紛失などの不祥事も止まらず、立地自治体も不信感をあらわにし、地元同意も遠のいた。金融機関の姿勢も厳しくなってきている。収益力低下に対応するため、東電は財務基盤の強化を進めてきた。4月にも金融機関から4000億円を新規に借り入れたが、「柏崎刈羽が動かない状況では新規融資は難しい」との声もある。中部電力や日立製作所、東芝との原子力事業の提携や、東電の小売りや再生エネ子会社の外部資本の受け入れ論……。単独では経営再建が難しく、中部電と火力事業を統合したように原発や小売事業でも再編案が度々浮上してきた。原発再稼働が進まない状況が続けば、国主導でグループの経営体制の見直しを迫られる可能性がある。「財務の基盤が安定しなければ、(廃炉や賠償など)福島への責任を果たせない。(計画から)大きく外れている状況は改善しなければならない」。23年3月期に大幅赤字になったことを受けて、東電の小早川智明社長は厳しい表情でこう語っていた。廃炉作業を進めるためにも、早期に稼ぐ力を示すことが不可欠だ。 *3-5-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15733888.html (朝日新聞 2023年9月5日) 水産業支援策、5本柱 消費喚起や販路開拓など公表 東京電力福島第一原発の処理水の海への放出で中国が日本の水産物を全面禁輸したことを受け、政府は4日、水産事業者向けの支援策をまとめた。中国への輸出依存から転換するための販路開拓など5本柱からなり、従来の計800億円の基金に加え予備費から新たに207億円を充てる。岸田文雄首相は同日夜、記者団に「水産業を守り抜くということで、政府、東電がしっかりとそれぞれの責任を果たしていきたい」と述べた。支援策は「『水産業を守る』政策パッケージ」と題して、(1)国内消費拡大・生産持続対策(2)風評影響に対する内外での対応(3)輸出先の転換対策(4)国内加工体制の強化対策(5)迅速かつ丁寧な賠償――の5本柱としている。(1)では、国内消費を促すための「『国民運動』の展開」を掲げた。岸田首相は「国民の皆様にも理解と支援をお願いしたい」として、水産物の消費などを呼びかけた。(3)では、輸出が急減しているホタテなどの一時買い取り・保管や海外を含めた新規の販路開拓を支援する。飲食店でのフェアなどを通じて海外市場を開拓していく考えだ。(4)では中国に依存している水産物の加工を国内に呼び戻すため、加工用機器の導入や人材活用などを後押し。海外輸出を進めるため、国際的な衛生管理の手法であるHACCP(ハサップ)の認定手続きも支援する。 *3-5-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15733855.html (朝日新聞 2023年9月5日) 「脱・中国依存」高い壁 国内に加工施設案「現実的なのか」 水産業支援 中国が日本の水産物を全面禁輸としたことを受け、政府が4日に発表した水産事業者支援策では「輸出先の転換」「国内加工体制の強化」などを柱に「脱・中国依存」をめざす。新たな輸出先として欧米や東南アジアを念頭に置くが、実現のハードルは高い。農林水産省によると、中国への水産物の輸出額は871億円(2022年)で、全体の2割を占め、国・地域別では1位だった。22年のホタテの生産量は51・2万トンで、このうち中国に14・3万トンを輸出。ナマコは5100トンのうち中国向けに1900トンを輸出した。香港向けを含むと、この数字はさらに増える。加工も中国頼みだ。同省は輸出したホタテを中国でむき身に加工した後、米国に3万~4万トンが輸出されていると推定。今回の支援策では、日本国内で加工するための施策も含めた。現場の受け止めは複雑だ。北海道網走市で水産物加工会社を営む根田俊昭さんは「建設資材が高騰し、機械も電気代も値上がりする中、現実的な対策なのか」と疑問を投げかける。仮に加工施設を国内に設けても、働き手の確保は簡単ではないという。「人手がないのに、『カネを出すからすぐ作れ』と言われて、できるのか」と話す。政府は欧米の飲食店などで「日本食キャンペーン」も開く方針だ。岸田文雄首相は、輸出先の開拓を対策とした理由に「世界の和食ブーム」を挙げる。しかし、実際に需要の掘り起こしにつながるかは未知数だ。日本産食品の輸出先は中国を始めとするアジア諸国が中心だ。欧米は市場規模は大きいが、食文化の違いが足かせになっていた。一般的に欧米の衛生規制はアジア向けよりも厳しく、対応に時間がかかる可能性がある。長崎県の養殖・加工業者「橋口水産」の橋口直正社長は、中国の全面禁輸によって「億単位の損失が見込まれている」と話す。ブリの約95%を海外に輸出しており、うち約2割が中国だった。現地でのイベントに出店したり、SNSでPRしたりしてきた。「これから伸ばしていこうとしていた矢先だった」と橋口社長。11月から本格的な出荷シーズンが始まり、さらに影響を受けることが予想される。 <化石燃料と予算> *4-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15587145.html (朝日新聞 2023年3月21日) 1.5度目標、ここが正念場 国連パネル報告「水害・海面上昇、適応に限界」 国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が20日公表した統合報告書でこれまで以上に危機感を打ち出した。一方で、温室効果ガスを大幅に削減する手段をすでに手にしているとも指摘。この10年間の行動が、人類と地球の未来を決めるという。 ■再エネ活用「まだ達成の道ある」 報告書は、改めて温室効果ガス排出量が増えるほど温暖化が進むことを強調。世界で稼働または計画中の化石燃料インフラを使い続けると、気温上昇が2度を超える恐れがあるという。2度は温暖化対策の国際ルール「パリ協定」で掲げる目標だが、各国が提出している温暖化対策目標を達成しても2・8度上昇に達する可能性が大きいとする。IPCCはこれまでも警告を発してきた。しかし現実と落差がある。新型コロナからの回復で景気が復調。ウクライナ侵攻などによるエネルギー危機で欧州を中心に各地で一時的に石炭火力を稼働させる動きがある。国際エネルギー機関(IEA)によると、昨年の二酸化炭素(CO2)排出量は過去最多になった。米環境NGO「世界資源研究所」は「今後数年間で化石燃料からの抜本的なシフトがなければ、世界は1・5度の目標を吹き飛ばす」と危機感をあらわにする。報告は温暖化が進むほど、「損失と被害が拡大する」と危機感を示す。食糧や水不足が増えるが、感染症の世界的流行や紛争などと重なるとより事態は難しくなる。水害や海面上昇は堤防などの治水対策で一定のリスクを減らせるが、「適応」には限界がある。すでに熱波や豪雨などの極端現象が増え、陸や海の生態系に相当な被害をもたらした。世界の食糧生産に悪影響を及ぼし、酷暑の増加で死亡率が増えているという。一方で、報告書は「まだ達成の道はある」と希望を残す。再生可能エネルギーや省エネ対策など100ドル以下の対策を活用するだけで、2030年までに排出量を半減できるという。対策は「政治の関与、制度、法律、政策、資金や技術によって可能になる」としている。規制・経済的手段として、二酸化炭素排出への価格付け(カーボンプライシング)や、化石燃料への補助金の撤廃などに言及した。 ■「先進国は目標前倒しを」 遅れる日本 国連のグテーレス事務総長は主要国に対し、温室効果ガスの排出削減目標を年内に更新するよう呼び掛けた。「年末の国連の気候変動会議(COP28)までに、すべての主要20カ国・地域(G20)のリーダーが野心的な新しい目標を約束することを期待する」。温暖化に大きな責任を負っている先進国には、2040年までに実質排出ゼロを前倒しするよう求めた。先進7カ国(G7)のうち、米英独加は35年に電源の脱炭素化の目標を掲げ、仏は21年に91%を脱炭素化した。日本は21年に30年度の46%削減、50年の実質排出ゼロを掲げるが、40年に向けた目標はない。IEAによると世界で導入された再エネは昨年、最大4億400万キロワットで19年から倍増する見通し。EUはロシアのウクライナ侵攻後の昨年5月に再エネを強化する目標「リパワーEU」を決め、30年時点でのエネルギー消費に占める再エネ比率を40%から45%に引き上げた。米国では昨年8月、エネルギー安全保障と気候変動対策の約3700億ドルを含む「インフレ抑制法」が成立。30年までに40%前後の排出減を試算している。一方、日本での再エネの導入ペースは鈍い。IEAの試算では19年に810万キロワットで、22年は最大でも980万キロワット。27年時点も同710万キロワット。COP28では、パリ協定のもとで初めて各国の削減目標の進み具合の評価が行われ、25年までに新たな目標を提出することになる。環境省幹部は「正直、まだ何も手が付いていない」と頭を抱える。国立環境研究所の増井利彦氏は「35、40年の目標を出さないと日本の地位、信頼性が失われる」と指摘する。2月に閣議決定した「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」では、今後10年間で150兆円以上の脱炭素投資を見込み、うち20兆円を国が支出する。だが、再エネについては発電量に占める比率を30年度に36~38%にする目標を変えていない。大排出源である石炭火力発電の燃料にアンモニアや水素を混ぜる技術の推進に7兆円を投じる方針だが、技術的に未確立でコストも高く、「石炭火力の延命」(NGO)との批判が根強い。諸富徹・京都大大学院教授(環境経済学)は「欧州や米国は、IPCCが言う1・5度などの実現に沿った政策づくりを進めており、それによって経済成長も実現しようとしている。だが、日本のGX基本方針からは、そのような真剣さや迫力がまったく感じられない。『脱炭素経済』への移行に遅れれば、日本の産業競争力は引き続き低下していく恐れがある」と指摘する。また環境や社会問題に配慮するESG投資に詳しい夫馬賢治・ニューラル社長は「水素やアンモニアの混焼はグリーンウォッシュ(見せかけの脱炭素化)とみられ、世界の投資家から理解を得られない」と指摘する。(関根慎一、編集委員・石井徹) ◇ 国連広報センターは今年も、メディアと共同で、気候変動への行動を呼びかけるキャンペーン「1・5度の約束――いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」を行う。現時点で、朝日新聞を含む日本メディア127社が参加表明している。20日、発表した。期間は年内いっぱいで、国連総会が開かれる9月18~25日を集中推進期間とし、参加各社が記事や番組、イベントなどで気候変動の現状や対策を発信する。 *4-2-1:https://www.saitama-np.co.jp/articles/33695/postDetail (埼玉新聞 2023/6/29) 環境に有害補助金、年1千兆円超、世界銀行「保護に活用を」 世界銀行は29日までに、各国政府が自国産業に出す補助金のうち、エネルギーや農業、漁業の分野で環境に有害なものが世界で年間計7兆ドル(約1千兆円)を超えるとの試算を公表した。使い方を見直して環境保護に活用するよう訴えている。補助金のマイナス面に警鐘を鳴らす狙い。ただ、不十分な規制で産業を利している「暗黙の補助金」も試算に含めているほか、通常の補助金にも国民生活に不可欠なものがあり、全てを環境保護に振り向けるのは難しい面もある。エネルギー分野では、化石燃料の価格引き下げにつながる補助金を問題視する。 *4-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230903&ng=DGKKZO74127350S3A900C2EA4000 (日経新聞 2023.9.3) 6日 エネ庁、ガソリン価格調査公表、高止まり、補助金は副作用も 資源エネルギー庁は6日、レギュラーガソリンの店頭価格調査の結果を発表する。円安の進行などで最高値を更新するとの見方が多い。政府は9月末までとしていたガソリン補助金を、年末まで延長する方針だ。補助の長期化は最終的に国民負担を長引かせ、脱炭素にも逆行するとの見方がある。エネ庁は原則、毎週月曜に全国の給油所の店頭価格を調べ、水曜に発表する。8月28日時点の価格(全国平均)は1リットル185.6円と、統計開始以降の最高値を15年ぶりに更新した。6日発表の価格(4日時点)は、円安による原油の仕入れ価格上昇を映して「小幅に上がる」との見方が強い。店頭価格上昇の背景には、ガソリンの原料となる原油価格の高止まりがある。アジア市場で指標となる中東産ドバイ原油の価格は、8月28日時点で1バレル86ドル台半ばと6月初めに比べて21%高い。産油国は減産によって原油相場を維持している。サウジアラビアは7月から続けている日量100万バレルの自主減産を、9月も実施すると決めた。ロシアも9月の原油輸出を減らす方針を示した。供給懸念が意識され、原油相場の先高観は強い。円安・ドル高の進行もガソリン価格を押し上げている。8月28日時点の円相場は1ドル=146円台半ばと、約9カ月半ぶりの円安水準だ。原油は主にドル建てで取引する。円安によって輸入価格が上がれば、ガソリンの価格にも反映されやすい。政府が石油元売りに支給している補助金が、6月から段階的に減っているのも大きい。補助金は22年1月、原油高によるガソリンや軽油、灯油などの価格高騰を抑えるために始まった。同年夏には1リットルあたり40円前後を支給していたが、高騰が収まった現在の補助額は10円程度だ。ガソリン高は家計の負担増加につながる。ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査部長は、仮にガソリンの価格が1リットル168円から195円まで上がり、そのまま1年間推移した場合、家計の年間負担増は総額で8780億円に達すると試算する。ガソリン価格の高止まりは特に地方の家計に響く。「自家用車を使う人が多い地方では、都市圏に比べて負担が大きくなる」(斎藤氏)。製油所からの輸送距離が長い長野県や山形県、鹿児島県などでは、平均価格がすでに1リットル190円を超えている。急激なガソリン高に対する批判を受け、政府は9月末に終了を予定していた補助金を年末まで延長する方針を示した。10月中に全国平均のガソリン価格が1リットル175円程度になるよう、段階的に拡充する。13日発表分以降の店頭価格は緩やかに下がるとみられる。ただ、補助金によるガソリン価格の引き下げが経済活動に及ぼす効果は限られるとの見方も強い。石油製品市場に詳しい伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリーの伊藤敏憲代表は、仮にガソリン価格が10円程度抑えられたとしても「一般消費者の負担額は月間で300~400円の減少にとどまり、消費を喚起する効果はほとんどない」と語る。補助金の長期化には副作用もある。ガソリン価格の高騰が需要を抑えたり、よりガソリン消費が少ない車への買い替えを促したりする、自然な市場メカニズムの働きを抑える可能性があるためだ。エネルギー経済社会研究所の松尾豪代表は「足元の高騰を考えると補助金の拡充はやむをえないものの、補助金政策が長引けば最終的に国民自身の負担になる」とした上で「補助金の一部を再生可能エネルギー・省エネ関連の建設費に投じることで、将来的な光熱費低減につなげるべきだ」と指摘する。 <再エネと予算> *5-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230818&ng=DGKKZO73688770Y3A810C2EA2000 (日経新聞 2023.8.18) 積水化学、曲がる太陽電池量産 30年までに 100億円投資 積水化学工業は2030年までに次世代の太陽電池「ペロブスカイト型」の量産に乗り出す。軽くて折り曲げられる同電池では中国勢が量産で先行するが、積水化学は強みとされる耐久性を生かして屋外での需要を開拓し、中国勢を追い上げる。ペロブスカイト電池は太陽光パネルで主流のシリコン製と比べ、重さは10分の1程度と軽く、折り曲げやすい。ただ、水分に弱く耐久性に課題があり、現在ではスマートフォン向けなど用途の広がりに欠ける。積水化学は液晶向け封止材などの技術を応用し、液体や気体が内部に入り込まないよう工夫。10年程度の耐久性を実現している。100億円以上を投じて製造設備を新設し、30年時点で年数十万平方メートルのペロブスカイト型太陽電池を生産する。発電量は数十メガワット。フィルムに結晶の膜を塗布しロール状に巻いて連続生産する。すでに30センチメートル幅のフィルムでエネルギー変換効率15%を達成した。シリコン型の20%以上に及ばないが、技術開発を進めて変換効率をさらに高めていく。より効率の良い1メートル幅での生産の準備を進めており、コスト競争力も高める。太陽光パネルの分野では、かつてシリコン型の開発・実用化でも日本勢が先行していたが、中国勢の攻勢で多くが撤退に追い込まれた。同様の事態を避けるため、日本政府は4月、ペロブスカイト型太陽電池の普及支援を打ち出し、公共施設で積極的に設置するなど需要を創出したり、量産技術の開発や生産体制の整備を支援したりする。ペロブスカイト型の技術支援はエネルギーの安定供給も背景にある。主な原料のヨウ素の世界シェアは日本が2位で国内で調達しやすく、供給網が寸断された場合に備えることもできる。積水化学は政府の支援策によっては生産量を増やす可能性もある。日本は山間部が多いなど、従来型太陽電池に適した立地が少なくペロブスカイト型の市場性は大きいと言われている。富士経済(東京・中央)によると、世界のペロブスカイト型の市場規模は35年に1兆円になる見通しだ。 *5-1-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/0df32a5bc122ac8c2934cd8234646f0255df848d (Yahoo、スマートジャパン 2023/9/7) 「発電する窓」をペロブスカイト太陽電池で実現、パナソニックが実証へ パナソニックは2023年8月、ガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池のプロトタイプを開発したと発表した。今後、技術検証を含めた1年以上にわたる長期実証実験を、神奈川県藤沢市のFujisawaサスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST)内のモデルハウスで実施する。ペロブスカイト太陽電池は、軽量かつ柔軟に製造可能という特徴を持ち、ビルの壁面や耐荷重の小さい屋根、あるいは車体などの曲面といった、さまざまな場所に設置できる次世代太陽電池として期待されている。また、塗布などによる連続生産が可能であること、レアメタルを必要としないなどのメリットも持つ。パナソニックではこれまでに、従来の結晶シリコン系の太陽電池と同等の発電効率を有し、実用サイズ(800平方センチメートル四方)のモジュールとして世界最高レベルという17.9%の発電効率を持つペロブスカイト太陽電池を開発している。今回開発したガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池は、これらの成果を生かし、ガラス基板上に発電層を直接形成したもの。同社独自のインクジェット塗布製法と、レーザー加工技術を組み合わせることで、サイズ、透過度、デザインなどの自由度を高め、カスタマイズにも対応可能だという。 パナソニックでは今後の実証の結果などをふまえ、ガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池をさまざまな建築物そのもののデザインと調和する「発電するガラス」として展開していく方針だ。 *5-1-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC14BIZ0U3A410C2000000/?n_cid=SPTMG002 (日経新聞 2023年5月12日) 曲がる次世代太陽電池、ビル壁面で発電 25年事業化へ 次世代の「ペロブスカイト型」太陽電池が注目を集めている。薄いフィルム状で折り曲げられるため、場所を問わず自由に設置しやすい。原料を確保しやすく、国内でサプライチェーン(供給網)を構築しやすい利点もある。政府は2030年までに普及させる方針を打ち出し、国内企業を支援する。35年には1兆円市場に育つとの試算もある。積水化学工業や東芝が25年以降の事業化に向け開発を急ぐ。ペロブスカイト型太陽電池は太陽光の吸収にペロブスカイトと呼ぶ結晶構造の薄膜材料を使う。重さが従来のシリコン型の10分の1。折り曲げられるため、建物の壁や電気自動車(EV)の屋根などにも設置できる。一方で水分に弱いため、実用化には高い発電効率を維持しながら、耐久性が課題となる。「実用化できる基準には達した」。積水化学はこれまで1日ももたずに壊れてしまったペロブスカイト型の耐久性を10年相当に高めた。液晶向けで培った液体や気体などが部品の内部に入り込まないようにする封止材の技術を使い、太陽電池を保護した。シリコン型の耐久性は約20年であり、R&Dセンターのペロブスカイト太陽電池グループ長の森田健晴氏は「耐久性を高められなければ、事業化には致命的だ」と話す。事業化に欠かせない発電の変換効率も高めた。30センチメートル幅で変換効率15%(シリコン型は20%以上)を達成した。薄いペロブスカイト型はシリコン型よりも熱を逃がしやすく、変換効率の低下につながる電池の温度上昇を抑えられる。今後は実用に近い1メートル幅での開発を目指す。積水化学は東京都下水道局森ヶ崎水再生センターなど複数の拠点で実証実験を実施しており、設置方法を含む実用化を検討している。現状では発電する薄膜に欠陥が生じやすいほか、歩留まりも悪く、製造コストはシリコン型に劣るという。今後は軽さを生かして物流コストなどを抑えることで、設置までの全体のコストでシリコン型に対抗する。25年度に事業化する方針であり、JR西日本がJR大阪駅北側に25年の開業を目指す「うめきた(大阪)駅」に設置予定だ。ペロブスカイト型は敷地を確保しにくい都心での発電が可能となる。室内光や曇りや雨天時など弱い光でも発電可能なため、屋内向けの電子商品などに使われる可能性がある。実験レベルでは高い変換効率を達成しており、耐久性やコスト面で改善が進めば、中国勢が優位に立つシリコン型に対抗しうる太陽電池として期待が高まっている。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は21年から「グリーンイノベーション基金」で次世代太陽電池の開発に約500億円の予算を確保している。30年度までに一定の条件下での発電コストをシリコン型と同等の1キロワット時14円以下の達成を目指す。経済波及効果は30年までに約125億円、50年までには約1兆2500億円を見込む。東芝もグリーンイノベーション基金に採択された企業の1つだ。26年度ごろの事業化を目標に掲げる。広い面積にペロブスカイト層を均一に塗布する独自技術を開発し、703平方センチメートルの大面積で変換効率16.6%を達成した。現在の耐久性能を明らかにしていないが、耐久性の向上と低コストな製品の開発を進めているという。カネカはNEDOが補助するペロブスカイト型だけでなく、シリコン型と2層で重ねる「タンデム型」の開発も進めている。設置済みのシリコン型をタンデム型に置き換えることで、発電効率を高める狙いだ。同社が開発した結晶シリコン太陽電池はトヨタ自動車の新型プリウスのプラグインハイブリッド車(PHEV)などで採用された実績がある。素材開発から量産まで一気通貫で自社で担える強みを生かす。ペロブスカイト型は09年に桐蔭横浜大学(横浜市)の宮坂力特任教授が発明した。だが海外で特許取得をしていなかったことや、各国政府の研究開発支援の充実で、海外との開発競争は激化している。21年にポーランドのサウレ・テクノロジーズが工場を開設した。中国でも大型パネルの量産が始まっている。ただ海外勢の生産規模はまだ小さく、一般向けの製品はほぼない。価格もシリコン型に比べ高額だ。日本企業がコストや性能で優れた製品を量産できれば勝機はある。富士経済(東京・中央)によると、世界のペロブスカイト型の市場規模は35年に1兆円になる見通しだ。 ●国内で供給網、エネルギー安保でも注目 政府がペロブスカイト型太陽電池の開発を後押しする背景にエネルギー安全保障がある。現在主流のシリコン型は原料であるシリコンの供給を中国に依存しており、有事の際に生産が止まるリスクがある。ペロブスカイト型は太陽光の吸収材料に日本が世界2位の生産量を誇るヨウ素を使う。他の原材料も国内で確保しやすいため、国内でサプライチェーンを完結できる可能性がある。株式市場では関連銘柄としてヨウ素メーカーにも注目が集まっている。ガラス最大手AGC子会社の伊勢化学工業が国内シェアの30%を、K&Oエナジーグループが15%を占める。ペロブスカイト型が普及した場合、国内のヨウ素使用量はどれくらい増えるのか試算してみた。ペロブスカイト層の厚さを1マイクロメートルとし、ペロブスカイト結晶の密度から単位面積当たりのヨウ素量を計算すると、1平方メートルあたり数グラムとなる。国内の0.5メガワット以上の太陽光発電施設が占める面積と同程度、ペロブスカイト型が設置されると仮定すると、ヨウ素の必要量は数十トン程度と、国内の年間生産量の1%に満たない。日本発のペロブスカイト型太陽電池は市場規模の成長力とエネルギー安保の両面から実用化への期待が高い。一方で関連企業の業績への影響は未知数であり、銘柄選びには冷静な見極めが必要だ。 *5-1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230825&ng=DGKKZO73877020V20C23A8MM0000 (日経新聞 2023.8.25) 東京都、住宅メーカーに省エネ効果の説明義務、購入時の判断基準に 東京都は住宅の省エネ化を加速する。新築の戸建てや中小規模のマンションについて、2025年度から事業者が買い手に建物の断熱性や省エネ効果を説明するよう義務付ける。都の評価基準を満たしているか契約前に説明し、買い手が環境に配慮した物件を選びやすくする。大規模なマンションについては断熱性などの環境性能の開示制度を既に設けており、より小さな物件に網を広げる。25年度に始める新築戸建てへの太陽光パネル設置義務化と合わせ、省エネ住宅の普及につなげる。延べ床面積2000平方メートル未満の中小規模のマンション、戸建ての注文住宅や分譲住宅について事業者に説明義務を課す。同じ規模のビルも対象とする。説明義務を負うのは都内で年間2万平方メートル以上の物件を供給する事業者で、大手住宅メーカーなど50社程度を想定する。都内の年間供給棟数の半数程度が対象となる見通しだ。事業者に幅広く説明義務を課すのは「自治体初とみられる」という。23年度中に制度の詳細を固め、都民や事業者への周知を始める。25年4月1日以降に建築確認が完了する物件が対象となる。建物自体の環境性能のほか、電気自動車(EV)用の充電設備の設置状況が都の基準を満たしているかも説明させる。都は事業者への訪問調査などを通じ、説明義務を果たしているかどうか確認する。年度ごとの履行状況も事業者に報告を求める。履行状況は都のホームページで公表する。対応が不十分な事業者には都が指導、助言して改善を促す。都内の新築着工棟数のうち2000平方メートル未満の物件は全体の98%にのぼり、その9割を住宅用途が占める。都内で排出される二酸化炭素(CO2)の3割は家庭由来だが、事業所など産業分野に比べて削減の取り組みは遅れ気味だ。東京都によると、家庭からのCO2排出量は21年度の速報値で1729万トンで2000年度に比べて34.8%増加した。都内全体では00年度比で9.2%減っており、家庭部門の排出削減は脱炭素の大きなカギを握っている。パネルの設置義務も供給棟数の多い50社程度が対象で、新築物件の半数程度が対象になる見通しだ。都内全体で毎年4万キロワット程度の発電能力を生み出せるという。 *5-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230815&ng=DGKKZO73587900U3A810C2TEB000 (日経新聞 2023.8.15) EVバス、導入相次ぐ 補助金・燃料費減が後押し、30年までに1万台目標 全国で電気自動車(EV)バスの導入が相次いでいる。3月には京王グループの西東京バス(東京都八王子市)や神奈川中央交通などが採用した。業界団体は2030年までに累計1万台の導入目標を掲げる。「ディーゼルバスよりも音や揺れが少ないと乗客に好評だ」。EVバス3台を運行している西東京バスの担当者はこう語る。バスは中国のEV大手の比亜迪(BYD)から購入した。 自動車検査登録情報協会によると、国内で稼働するEVバスは22年3月末に約150台だったが、さらに23年4月末までの直近1年超で100台以上が納車されたようだ。3月だけで少なくとも10社が運行を開始した。背景には脱炭素の動きを受けた政府や自治体の補助金がある。政府は22年度までEVバスの導入費用の最大3分の1を補助してきた。一般的なディーゼルバスの価格は大型で2300万円程度なのに対し、EVバスは4000万円台。自治体の補助金も併用すると、一般のバスよりも安く導入できるケースも想定される。補助金でコストを抑えられるほか、従来型のバスに比べてエネルギー費(燃料費)を減らせることも普及を後押ししている。新型コロナウイルス禍からの経済再開も影響している。「人流の回復を受けてEVバスの導入を本格化した」(富士急行)など、これまで控えてきた車両更新をきっかけにする会社も目立つ。EVバスは脱炭素の効果が大きい。2台を運行する神奈川中央交通によると、一般的にEVバスは走行時に二酸化炭素(CO2)を排出しない。EVバスの充電に使う電力を発電する際まで含めるとCO2を排出することになるが、ディーゼルバスが走行時に排出する量の半分で済む。バスを走らせる費用も安い。1回の充電に5時間ほどかかるが、EVバスの電気代は「ディーゼル燃料を使う場合の3分の2ほど」(導入した事業者)だという。追い風も吹く。政府は23年度の補助率を導入費用の最大2分の1に高めた。補助予算も前年度の約10倍にあたる100億円規模に引き上げた。日本バス協会は23年を「EVバス普及の年」と位置づけ、30年までに累計1万台の導入を目指すとしている。国内のバス台数の5%程度だが、導入が加速する可能性もある。今後の課題は補助金依存からの脱却だ。現在、日本向けにEVバスを大量供給できるのはBYDとEV商用車開発のEVモーターズ・ジャパン(北九州市)の2社程度だ。乗用車のように国内外のメーカー間での価格競争はまだ起きていない。トルコの商用車メーカーのカルサンやジェイ・バス(石川県小松市)が23~24年度に販売を開始する計画などもある。補助金が減額された場合でも、競争力のある価格を実現できるかが導入のスピードを左右する。 *5-2-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15725527.html (朝日新聞 2023年8月26日) ボルボ新EV、日本好みに 小型化実現 スウェーデンのボルボ・カーズは24日、電気自動車(EV)の新型SUV(スポーツ用多目的車)「ボルボEX30」を11月中旬に日本で発売すると発表した。税込み559万円から。最大の特徴は、日本法人の要望に応えて、機械式立体駐車場でも使えるよう小型化したことだ。EX30は日本に投入する3車種目のEVで、全長が4235ミリ、全幅が1835ミリ、全高が1550ミリと最も小さい。日本は国別の売り上げで上位10位以内に入る重要市場のため、日本で利用者が多い機械式立体駐車場に収まるサイズにした。日本法人の不動奈緒美社長は朝日新聞の取材に「日本から要望し続けてようやく実現したサイズ。日本の道路・車庫事情に最もフィットする一台だ」と話した。サイズを日本に合わせたため、大型車が好まれる欧米では苦戦が見込まれていたが、予想に反して売れ行きは好調だという。米国では6月に販売を始め、すでに想定を上回る9千台の受注があった。不動氏は「米国でも欧州でも、大都市では日本と同じニーズがあったのではないか」とみる。最大航続距離は480キロで、急速充電器を使えば約26分で充電残量を10%から80%にできる。小型化で部品数が減ったため、従来のEVより100万円以上安く、国や自治体の補助金を使えば400万円台で買えるという。 *5-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230826&ng=DGKKZO73915390V20C23A8TEZ000 (日経新聞 2023.8.26) 豪州、車電池で産業育成 EV国家戦略公表、リチウム加工促進、再エネ投資に1.4兆円基金 オーストラリアが電気自動車(EV)関連産業の育成に取り組んでいる。現政権は脱炭素に意欲的で、今年、EV国家戦略を初めて公表したほか、リチウムなど重要鉱物資源の国内加工も後押しする。国内産業を化石燃料や鉱物資源の産出から、付加価値の高い産業へ多様化する狙いがある。「この豪州初の電池工場は、産業界が長らく求めてきた聖杯だ」。5月、豪州南東部ジーロングを訪れたマールズ副首相兼国防相は強調した。かつて米フォード・モーターが約900人を雇用し自動車を製造していた同地は、EV向け電池工場の建設予定地へと変貌をとげようとしている。米企業傘下の電池スタートアップ企業、リチャージ・インダストリーズが工場の立ち上げを計画する。年間の生産能力は最大で30ギガ(ギガは10億)ワット時で、EV約30万台分の電池を供給できる。2024年5月ごろまでに着工し、25年から生産を始める予定だ。2550人の雇用創出を見込む。豪州は自動車産業の「空白地帯」だ。17年にトヨタ自動車などが工場を閉鎖し、豪州で生産する完成車メーカーはない。高い賃金や年100万台程度の小さな市場規模、市場の大きな国から遠いといった背景により、完成車メーカーが戻るのは容易ではない。だがEVシフトを呼び水に、電池製造やリサイクルなど関連産業を育成する機運が高まっている。転機となったのが22年5月の労働党政権の誕生だ。国として30年までの温暖化ガス排出削減目標を05年比43%減と定めたほか、エネルギーや鉱業など排出量の多い企業の削減義務を強化するなど脱炭素を推し進めた。豪州では近年、山火事など自然災害が深刻化し、より踏み込んだ気候変動対策を求める声が強まっている。国は150億豪ドル(約1.4兆円)規模の基金を立ち上げ、EV技術などへの投資を後押しする。豪州は天然ガスや石炭を産出しているが、アルバニージー首相は国内電源や輸出で化石燃料に依存する経済から「再生可能エネルギー超大国」への転換を目指す。4月に公表した初のEV国家戦略では「豪州には部品や電池などEV供給を支える製造業を育成する能力がある」と関連産業の発展に自信をにじませた。伊藤忠総研の深尾三四郎上席主任研究員は「豪州にはEVシフトでも傷む雇用がなく、むしろ新たな雇用を創出する」と指摘する。豪州は脱炭素に欠かせない資源も豊富だ。米地質調査所(USGS)によると、豪州は電池材料に使うリチウム鉱石生産の47%を占め、埋蔵量も24%とチリに次いで2番目に多い。EV普及に伴って、リチウムの世界需要は40年に20年から40倍に増える見通しだ。チリは4月にリチウム生産を国有化する方針を打ち出しており、カントリーリスクが相対的に低い豪州への関心が高まっている。既に米テスラやフォードが豪州の鉱山会社、ライオンタウン・リソーシズとリチウムの供給契約を締結している。だが実現には課題も多い。リチウムを電池材料として使うための不純物を除く精製・分離の工程は環境負荷が高い。そのため、環境規制が緩く労働コストも安い中国に依存してきた。豪州のリチウム輸出の9割は中国へ向かう。米ホワイトハウスによると、中国は世界のリチウムの6割の精製を担う。政府は6月に公表した重要鉱物資源戦略で海外からの投資の誘致方針を示した。国内での精製・分離を目的とした設備投資などへの助成金枠として5億豪ドルを充てる。テスラなど完成車メーカーも豪州に加工能力の増強を求めている。豪州にとっても国内で資源の付加価値を高められれば、より高く売れるメリットがある。世界で脱炭素の流れが強まる中、豊富な埋蔵資源をもつ豪州の強みを国内産業への発展につなげられるか。EVシフトは大きな転機となりそうだ。 *5-3-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA131IQ0T10C23A9000000/ (日経新聞 2023年9月14日) 日本、カナダでEV電池供給網 北米販売を後押し、両政府合意へ 日本の官民がカナダで電気自動車(EV)向けの重要鉱物の探鉱、加工、蓄電池の生産を含むサプライチェーン(供給網)を構築する。カナダ政府も補助金などで支援し、両国が協力して供給力を高める。北米での日本企業のEV販売増につなげるほか、経済安全保障を強化する。西村康稔経済産業相が21日にもカナダを訪問し、ウィルキンソン天然資源相らと蓄電池のサプライチェーンに関する協力覚書を結ぶ。想定する協力内容はまず、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)などによるカナダでのニッケルやリチウムなどの探鉱だ。カナダは重要鉱物の埋蔵は多いものの、技術力や人材面など生産能力に課題を抱える。米地質調査所(USGS)によると、カナダのリチウムの埋蔵量は中国の半分程度で世界有数の規模だ。その半面、生産量でみると中国の2%ほどにとどまる。日本と協力することで生産量を増やす。日本の素材・電池メーカーが、カナダで採掘した重要鉱物の加工や、その鉱物を材料に使う蓄電池の生産工場を建てることを視野に入れる。西村氏の訪問にはパナソニックホールディングスやトヨタ系のプライムプラネットエナジー&ソリューションズ(PPES)といった電池メーカーや、商社などが同行する。カナダ政府は現地に進出する日本企業を補助金などで支援する構えだ。産業育成や雇用創出に期待する。カナダでの電池生産は米国での日本メーカーのEVの販売促進につながる。米国はインフレ抑制法(IRA)で、EVの新車などを購入する消費者に最大で7500ドル(約110万円)を税額控除している。日本車は現在、対象に選ばれていない。対象になるには、車載電池に使う重要鉱物の4割を米国や米国の自由貿易協定(FTA)締結国から調達するほか、電池部品の5割を北米で製造・組み立てするなどの要件がある。カナダで調達や加工をすることで、条件が満たしやすくなる。日本にとっては供給網の強化も見込める。日本は現在、中国やチリなどからリチウムを輸入している。一部の国に依存するのは供給途絶のリスクが大きい。とりわけ蓄電池の生産はエネルギーや気候変動政策の観点で競争力に直結する。西村氏はシャンパーニュ革新・科学・産業相とエング国際貿易相と、人工知能(AI)やクリーンエネルギー、量子といった産業技術に関する覚書にも署名する。量子コンピューターの研究開発では経産省所管の産業技術総合研究所と、カナダ国立研究機構(NRC)の協力を盛り込む。日本は冷却に必要な冷凍機など素材分野で強みを持つ。 *5-3-3:https://www.yomiuri.co.jp/economy/20200821-OYT1T50273/ (読売新聞 2020/8/21) 日本EEZでコバルトやニッケル採掘に成功…リチウム電池に不可欠なレアメタル 石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は21日、日本の排他的経済水域(EEZ)でコバルトやニッケルを含む鉱物の採掘に成功したと発表した。リチウムイオン電池に不可欠なレアメタル(希少金属)で、中国依存度が高く、国産化が課題となってきた。採掘場所は、南鳥島南方沖の海底約900メートル。7月に経済産業省の委託事業として、レアメタルを含む鉱物「コバルトリッチクラスト」を約650キロ・グラム掘削した。JOGMECの調査では、同海域には、年間の国内消費量でコバルトは約88年分、ニッケルは約12年分あるという。コバルトやニッケルは、電気自動車などに使うリチウムイオン電池に不可欠な材料だ。希少性が高く、日本は国内消費量のほぼ全てを輸入に頼っている。超高速の通信規格「5G」時代を迎えて、通信機器への活用も急増し、世界的に取引価格が上昇している。国産化は国内産業の競争力強化にもつながる。経産省は「掘削成功は、レアメタルの国産化に向けた大きな一歩」とし、量産に向けて掘削技術の検証などを進める方針だ。 *5-3-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF127F90S3A910C2000000/ (日経新聞 2023年9月12日) パナHD、全固体電池を20年代後半量産 ドローン用など パナソニックホールディングス(HD)は12日、ドローン(小型無人機)など向けに開発中の小型の全固体電池を2020年代後半に量産する方針を明らかにした。実用化できれば、3分程度でドローン用の電池容量の8割を充電できる見込み。同様の充電に1時間程度を要する現状のリチウムイオン電池に比べ、利便性が大幅に高まるとした。パナソニックHDがこれまで社内向けに開催していた技術展示会を報道陣や取引先企業に初めて公開し、全固体電池について説明した。金属材料の組成など詳細は明らかにしなかったが、想定する充放電回数は数万回とした。一般的なリチウムイオン電池の回数とされる約3000回を大きく上回る。全固体電池は電気自動車(EV)の次世代車載電池として期待されている。トヨタ自動車は27〜28年にも実用化する方針。パナソニックHDの小川立夫グループ最高技術責任者(CTO)は全固体電池の車載向けへの転用は、自動車メーカーと緊密に連携する必要があるとし「自社単独でできるものではないため、コメントできない」と述べた。展示会では木質繊維を使い強度を高めたプラスチック素材や、太陽光を電気に変換せずにそのままエネルギーとして使い水素を製造する装置なども披露された。 *5-4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230815&ng=DGKKZO73591180U3A810C2EA2000 (日経新聞 2023.8.15) M&A、日本企業間で8割増 上期6.8兆円、株価底上げへ国内事業再編が活発 円安、海外買収難しく 日本企業同士のM&A(合併・買収)が増えている。今年上期の買収額は約6兆8000億円で前年同期比8割増えた。株価の底上げに向けて、より相乗効果が見込みやすい国内での事業再編が活発になってきたためだ。円安で海外企業を買うハードルも上がっており、海外に成長を求めてきたM&Aの潮目が変わる可能性がある。金融情報会社リフィニティブによると1~6月の日本関連のM&A全体は約10兆8000億円と2割弱増えた。このうち「イン・イン型」と呼ぶ日本企業同士のM&Aは日本関連のM&A全体の63%を占めた。通年で75%だった2009年以来の高水準だった。件数でもイン・イン型は前年同期比3%増の1828件で、件数全体に占める割合は76%だった。09年当時はリーマン・ショック後の不透明感から「イン・アウト型」と呼ぶ日本企業による海外M&Aが急減した。半面、国内企業の再編が増えたことでイン・イン型の比率が上がった。損害保険ジャパンと旧日本興亜損害保険が経営統合を決めたのも同年だ。23年1~6月はイン・アウト型も約3兆2000億円と3割増えたが、イン・イン型の伸びが上回った。日本企業同士のM&Aで目立ったのは大手企業が国内投資ファンドと組んで株式を非公開化する動きだ。東芝は日本産業パートナーズ(JIP)や日本企業20社超の支援を受けて株式非公開化を決めた。買収額は約2兆1000億円。物言う株主(アクティビスト)を含む複雑な株主構成を整理し、出資企業と連携して再成長を目指す。半導体材料大手のJSRは政府系ファンドの産業革新投資機構(JIC)による約1兆円買収を受け入れた。半導体材料の国際競争力を高めるため、国の関与のもと、積極投資しやすい環境を整える。経営者の高齢化が進むなか、事業承継目的のM&Aも広がった。オリックスによる通販化粧品大手ディーエイチシー(DHC、東京・港)の買収は約3000億円で、承継目的のM&Aでは過去最大級だった。10年代の日本企業のM&Aはイン・アウト型が中心だった。人口減少による国内市場の縮小をにらみ、海外に成長を求める傾向が強かった。日銀の大規模緩和のもと、国内金融機関から買収資金を低コストで調達できたことも大きい。もっとも、海外子会社をうまく経営できない企業も多く、巨額の減損損失を計上する企業も相次いだ。日本企業はこうした経験をふまえ「より相乗効果を発揮しやすい国内再編に注力するようになった」(JPモルガン証券の土居浩一郎M&Aグループ責任者)。東芝やJSRのように、生き残りに向けて戦略的に買収を受け入れる企業も出てきた。脱炭素社会をにらみ再生可能エネルギー開発会社の再編も増えている。NTTのエネルギー子会社は国内火力発電最大手JERAと組み、カナダの年金基金傘下にあったグリーンパワーインベストメント(GPI、東京・港)を約3000億円で買収した。豊田通商はソフトバンクグループ(SBG)からSBエナジー株式の85%を1200億円で取得した。1ドル=140円台まで進んだ円安がイン・アウト型のM&Aのハードルを高めている面もあるが、国内企業同士のM&Aは今後、一段と活発になる可能性がある。要因の一つが株式市場からの圧力だ。東京証券取引所が今年3月末、上場企業に資本コストや株価を意識した経営を要請した。1倍割れの低PBR(株価純資産倍率)に沈む企業に対する市場の目は厳しくなっており対応を迫られている。「M&Aによる業界再編は収益性向上のための有力な手段となる」。政策面の追い風も吹く。経済産業省が策定中の「企業買収における行動指針(案)」は企業価値向上につながる真摯な買収提案を、合理的な理由なく拒まないよう求めている。7月にはニデック(旧日本電産)が工作機械メーカーのTAKISAWAへ買収提案し、同意が得られなくてもTOB(株式公開買い付け)を実施すると明らかにした。日本は主要先進国のなかでも、経済規模に比べてM&Aが少ないとされる。国内再編を軸にM&Aが身近になれば、結果的に国際競争力の強化にもつながりそうだ。 *5-4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230901&ng=DGKKZO74073420R30C23A8EA2000 (日経新聞 2023.9.1) ヨドバシ、そごう・西武主要3店に出店 都心需要に的、労使しこり、再建に影 高級ブランドが難色 そごう・西武を買収する米ファンドと連携する家電量販大手のヨドバシホールディングス(HD)は西武池袋本店(東京・豊島)やそごう千葉店(千葉市)などそごう・西武の主要3店舗に出店する方針だ。百貨店内の中心部に家電売り場を設けて集客力を高め、経営再建につなげる。1日付でそごう・西武を買収するフォートレス・インベストメント・グループと組み、ヨドバシは西武池袋本店とそごう千葉店の別館にあたる「ジュンヌ館」へ出店する計画だ。西武渋谷店(東京・渋谷)への出店も検討する。出店時期や規模は今後詰めるが、西武池袋本店では低層階の一部と中層階以上に家電売り場を設ける考えだ。ヨドバシはそごう・西武の主要な売り場に入り、経営再建と自らの成長の両立を狙う。ヨドバシは都市部の駅前立地を軸に全国で24店舗を展開する。売上高規模でヤマダデンキやビックカメラに次ぐ3位に入る。人口が減るなか、効率良く集客でき、インバウンド(訪日外国人客)を見込める都市部での競争力強化が課題だった。特にビックカメラは千葉市や東京・豊島などの主要都市に店舗を構える。シェア向上にはJR池袋駅や千葉駅近くに店舗があるそごう・西武の資産は、収益力向上に直結する魅力があった。交渉過程でヨドバシは当初は西武池袋本店内の大部分に家電量販を出店する考えだったが、そごう・西武の労働組合や豊島区などの反発を考慮して計画を修正した。「1階と地下1階の売り場はほしかったが、メインは百貨店に譲った」(ヨドバシ首脳)。譲歩してまでもそごう・西武の買収にこだわったのは、都市部の家電量販店競争で勝ち残りに欠かせないピースだったためだ。ヨドバシは百貨店内に家電量販の売り場を設けることで従来は百貨店を利用していない若年層などの来店を促し、そごう・西武の収益力を高める。ヨドバシ首脳は「百貨店に負けないくらい品ぞろえには自信がある。地域の方々に喜んでもらえる店にしたい」と話す。ヨドバシが一筋縄に戦略を実行できるかどうかは不透明だ。売却に関してセブン&アイ・ホールディングスはステークホルダー(利害関係者)の理解を十分に得られなかった。ストライキ決行に追い込まれたそごう・西武労組の不満は特に根強い。寺岡泰博中央執行委員長は8月31日、今後はフォートレスに対して「引き続き雇用維持と事業継続を求めていく」と述べた。労使の信頼関係にしこりが残ったままだ。豊島区や地元の商工会議所もヨドバシの西武池袋本店への出店に対して依然として納得していない。ヨドバシHDの出店形態によっては百貨店の主要テナントである高級ブランドの離反を招く可能性もある。すでに一部の高級ブランドはヨドバシの出店計画に難色を示しているとされる。高級ブランドとの調整は難航が予想される。 <中国不動産不況の突破口は・・> PS(2023年9月23日):*6-1のように、中国政府が2020年夏に不動産会社に対する融資規制を強化し、金融機関の貸し渋りに直面した恒大集団は、2023年6月末で債務超過額約13兆円(=6442億元X20.32円/元)・販売できない開発用不動産(住宅開発用の土地使用権と建設途中のマンション)約22兆円(=1兆860億元 X20.32円/元)となり、住宅価格下落が本格化すればさらなる評価減で債務超過拡大が避けられず、*6-2のように、マンション建設など3千個のプロジェクトで約28兆円(=1兆4千億元 X20.32円/元)の負債がある中国最大の不動産開発会社碧桂園も社債利子を払えない状態で、*6-3のように、中国主要不動産11社で開発用不動産は約130兆円(=約6兆3500億元X20.32円/元)あり、評価額が3割下落すれば資本が枯渇して債務超過に転落するそうだ。また、11社合計で203兆円(=10兆元X20.32円/元)超の負債(建設・資材会社等への買掛金25%、住宅購入者への契約負債33%)があり、中国政府は、建設業者や建材メーカー等の幅広い取引先に悪影響を与え、社会不安に繋がる法的整理には慎重で、政策金利引き下げ・住宅購入規制緩和等で住宅市場の活性化を狙うが、未完成のまま放置されているビル群も多く、消費者は引き渡し不能を恐れて未完成物件の購入をためらい、効果は限られるそうだ。 庶民が買える価格まで住宅価格を下げなければならなかったのは理解できるが、「不動産不況も規模が違う」というのが私の印象で、未完成のまま放置されている建設中のマンションが多く、代金支払済の消費者に引き渡しもできず、建設・資材会社の買掛金も払えないというのでは問題が大きすぎる。しかし、現在の中国では、土地は国有で私的所有はできず、開発に土地使用権を購入する仕組みなので、政府が特定の場所を選んで土地の所有権を売却し、その金で建設中マンションの一部を購入して庶民向けの賃貸住宅を建設すれば問題は解決するのではないか?私が上海旅行をした時には、中国の人が「あそこはフランス租界、ここは日本疎開だったんだ」とむしろ誇らしげに日本語で語っているのを聞いたことがあり、中国にとって「租界」は悪い思い出の方が多いかもしれないが、その国の自由を認めたことによって多様で先進的な文化が育まれたメリットもあった。そのため、土地を売った特定の場所は特区にして租界のようにし、例えば、フランス疎開・ロシア租界・ドイツ疎開などができればフランス風・ロシア風・ドイツ風の街づくりをするし、日本疎開ができれば日本風の先進的な街づくりをして、それぞれの国から移り住む人がいれば、いろいろなノウハウが集まって面白いと思うわけである。   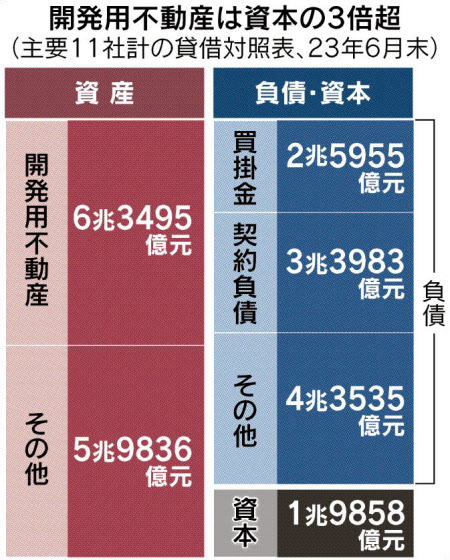 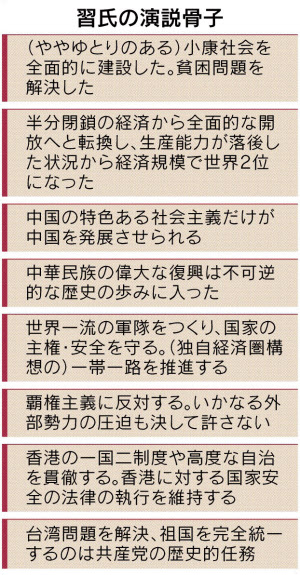 2023.8.27ZakuZaku 2022.10.12日経ビジネス 2023.9.1日経新聞 2021.7.2日経新聞 (図の説明:左の2つの写真は工事が途中で止まった開発用不動産、右から2番目の図は、2023年6月末で中国の主要11社の開発用不動産が11社の資本合計の3倍超あることを示す貸借対照表である。また、1番右の図は、習近平国家主席が2021年7月1日に天安門広場で開催された中国共産党創立100周年祝賀記念式典で行った演説の骨子で、これまでの100年で貧困問題を解決してややゆとりのある小康社会を建設したことには賛成だが、これからの100年で豊かな中国社会を築くには、政府が力づくで経済《社会現象である》を変えようとすると、きしみが生じてむしろ逆効果になることを述べておきたい) *6-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM280K60Y3A820C2000000/ (日経新聞 2023年8月28日) 中国恒大、22兆円の開発用地が重荷 債務超過拡大も 経営再建中の中国恒大集団の債務超過額が6月末時点で6442億元(約13兆円)に膨らんだ。負債総額は2兆3882億元(約48兆円)にのぼり、販売のめどがつかないまま抱える1兆860億元(約22兆円)の開発用不動産が重くのしかかる。住宅価格の下落が本格化すればさらなる評価減につながり、債務超過の拡大は避けられない。恒大が27日発表した2023年1〜6月期連結決算は最終損益が330億元の赤字だった。中国の不動産規制(きょうのことば)が導入された2020年夏以降、業績が急激に悪化した。中国上場企業として過去最大の4760億元の最終赤字となった21年12月期と比べて赤字額が1割以下に縮小したのは、住宅用地など開発用不動産の評価減を21億元にとどめたためだ。21年12月期には3736億元の評価減を計上した。6月末の資産総額1兆7440億元のうち6割を占めるのが、将来の住宅開発のために中国各地で仕入れた土地(使用権)や建設途中のマンションなどの開発用不動産だ。評価額は合計で1兆860億元にのぼる。仮に中国の住宅価格が1割下がれば、単純計算で1000億元を超える評価減となる。在庫負担を軽減するために住宅を安売りすれば、保有資産の評価損がさらに膨らむ悪循環を招く。恒大は開発用不動産の評価減を主因とした度重なる赤字計上で債務超過が拡大した。理論上の株式価値は実質ゼロとなっており、28日に香港取引所で約1年5カ月ぶりに再開した恒大株の取引は前回終値に比べ87%安で始まり、79%安で取引を終えた。恒大は28日に予定していた外貨建て債務の再編協議を9月下旬に延期した。債権者への提案には最長12年の債券や関連会社の株式への転換を盛り込む。同社の有利子負債(6247億元)のうち外貨建ての割合は26%に限られ、仮に債権者と合意できても抜本的な経営再建には力不足だ。膨大な開発用不動産は業界共通の課題だ。中国不動産最大手の碧桂園控股(カントリー・ガーデン・ホールディングス)は22年末で8838億元にのぼる。住宅上昇局面では虎の子だった開発用不動産が、住宅不況で一転して経営再建の最大のお荷物となっている。さらなる評価減のリスクがぬぐえず、不動産各社の債務超過額が膨らみ続ける懸念がある。中国政府は20年夏、不動産会社に対する融資規制を強化した。負債比率などによって資金調達の規模を制限する「3つのレッドライン」を設定し、金融機関の貸し渋りに直面した恒大などが経営難に陥った。中国政府は建設業者や建材メーカーなど幅広い取引先に悪影響を与え、社会不安につながりかねない法的整理には慎重姿勢を崩していない。中国は人口減社会に入り、長期的にも住宅需要の急回復は見込めない。抜本的な解決を先送りすれば中国景気のさらなる減速を招き、世界経済に影響を及ぼしかねない。 *6-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/20c44aaeec00fc89aeadee41547c4ff91f3646ae (Yahoo 2023/8/11) 中国不動産最大手に債務不履行の兆候…「恒大集団以上の衝撃」 中国最大の不動産開発会社が社債の利子を払えない事件が起き、中国の不動産危機が再び高まっている。デフレの兆しを見せている中国経済を揺るがす雷管になりかねないとの懸念が出ている。売上高基準で中国最大の不動産開発会社である碧桂園(カントリーガーデン)の不渡りへの懸念により、中国の不動産市場が急速に冷え込んでいる。ロイター通信などが10日報道した。これに先立つ7日、同社は2社に対する社債の2250万ドルの利払いを履行できなかった。会社の規模に比べて少ない金額を定められた時期に返済できないほど資金難が深刻であり、会社側は今後の償還計画も明らかにしていない。碧桂園が今後30日間の猶予期間内に利払いができなければ不渡りとなる。2021年、大型不動産開発会社である恒大集団(エバーグランデ)が債務の元利金を償還できず不渡りになり、中国の不動産市場はバブルがはじけ急速に沈滞した。碧桂園は昨年末基準でマンション建設など3千個のプロジェクトと関連して1兆4千億元(1990億ドル)の負債がある。来月には58億元の債務満期が到来し、利子4800万元を払わなければならない。また、34億元相当の債務について返済か延長を決定しなければならないオプションもかかっている。2024年末までに中国国内で24億ドル、海外で20億ドルの債務を返済しなければならない。市場では碧桂園の不渡りへの懸念が急速に広がり、同社の社債価格は暴落している。香港証券市場に上場された株式も、8日に前取引日に対し14.4%暴落するなど、昨年末と比較すれば株価が70%も下落した。ドル建ての中国ハイイールド債券(信用格付けの低い会社が発行した債券)は、今年に入って最低の1ドル当たり平均67セント前後で取引され、碧桂園問題が伝染する様相を呈している。ブルームバーグ・インテリジェンスは9日「碧桂園には恒大集団よりも4倍も多いプロジェクトがあり、支払い不能事態も恒大集団の崩壊よりもさらに大きな衝撃を中国住宅市場に加えるだろう」と見通した。特に、碧桂園は恒大問題の際に当局が不動産市場の崩壊を防ぐために取った資金支援などの最大受恵者となり、これまで市場を支えてきたが、資金難に陥り市場の崩壊が憂慮される。碧桂園は今年上半期の6カ月間、売上1280億元(約2.4兆円)で30%の減少を記録した。碧桂園は中国のすべての省でマンションなどの工事を進行中だが、特に60%がいわゆる3・4等級の中小都市で進行中だ。大都市とは異なり、中小都市では需要の不足で不動産低迷がさらに深刻だ。政府が保証する中央中国不動産有限会社も最近、債務の利払いを定時ではなく猶予期間中に履行した。7月には大連ワンダグループの子会社と政府が保証する遠洋(シノオーシャン)グループも猶予期間の最後に利払いを行なった。 *6-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230901&ng=DGKKZO74074560R00C23A9MM8000 (日経新聞 2023.9.1) 中国主要不動産11社、開発用地3割評価減なら債務超過 政策効果は限定的 中国の不動産開発会社に債務超過リスクが浮上している。主要11社の6月末の開発用不動産(開発用地)は約6兆3500億元(約130兆円)にのぼる。単純計算ではこの評価額がおよそ3割下落すれば現在の資本は枯渇し、債務超過に転落する。開発用不動産は住宅開発のために仕入れた土地使用権や建設途中のマンションを指す。日本経済新聞が2022年の販売上位10社に中国恒大集団を加えた11社の6月末の開発用不動産を集計したところ、合計約6兆3500億元だった。不動産開発会社は入札や相対で開発用地を仕入れ建設会社に建設を発注する。引き渡しまで物件を自社のバランスシート(貸借対照表)上に保有するため、住宅価格の下落局面では評価減のリスクにさらされる。主要11社の6月末のバランスシートは資産総額約12兆3300億元に対し、負債総額が約10兆3400億元。差し引き約1兆9900億元が資本となっている。資産のおよそ半分を占める開発用不動産の評価が32%下がれば資本不足で債務超過に転落する計算だ。主要11社が保有する開発用不動産は経営再建中の恒大が最多で1兆859億元にのぼる。恒大は2021年12月期に3736億元、22年12月期に16億元、23年1~6月期に21億元の評価損を計上した。これが巨額の最終赤字の主因となり、6月末に6442億元の債務超過となった。不動産最大手、碧桂園控股(カントリー・ガーデン・ホールディングス)は6月末時点で2544億元の資産超過だった。ただ8436億元と資本の3倍を超える開発用不動産を抱え、リスクをはらむ。1~6月期決算は恒大と碧桂園の2社が最終赤字、4社が減益、5社が増益と分かれた。資産をどう評価するかは経営陣と監査法人の裁量が大きい。恒大以外は目立った評価減を計上しなかった。11社で計10兆元を超える負債は建設・資材会社などへの買掛金が25%、住宅購入者を対象にした契約負債が33%を占める。中国政府は政策金利引き下げや住宅購入規制の緩和などで住宅市場の活性化を狙う。ただ消費者は引き渡し不能を恐れて未完成物件の購入をためらうようになっており政策効果は限られている。 <ジャニーズ問題と日本のタレント> PS(2023年10月1、3日追加):旧ジャニーズ事務所は、*7-2のような故ジャニー喜多川元社長の性加害問題があったため、*7-1のように、現在のジャニーズ事務所は被害者への補償に専念し、所属タレントのマネジメント等の業務は新会社に移管する方向で検討しているそうだ。これには、9月7日の会見後、ジャニーズ所属レントを用いるスポンサー企業の間で事務所の人権尊重やガバナンスの不十分さに対する批判が相次ぎ、所属タレントとの契約見直しの動きが止まらず、経団連の十倉会長が9月19日の定例記者会見で「日々研鑽しているタレントの活躍の機会を奪うのは違う」と述べたことがある。しかし、*7-2のように、ジャニー氏個人の問題や隠蔽した組織の問題のみならず、知りながら沈黙していたマスメディアや芸能界の問題は大きいという指摘もある。 私が、ここでこの問題に触れる理由は、日本の歌謡界や芸能界のレベルの低さは開発途上国より劣ると思うからで、その年にどういう歌が流行ったのか知るため年に一度見る紅白歌合戦では、音楽や歌と言うより数でごまかして運動しているチームばかりが多くて心に響くものがなく、歌謡曲は何十年も女性蔑視丸出しだからである。そのため、*7-2の内容を読むと、こういうのを「枕芸者(芸がないため、性で売っている芸者)というのかな」「他の事務所はどうなのか」と思われたからである。現在のファンは、それしか知らないから、それで満足しているのではないか?そのため、ジャニーズ事務所の所属タレントのマネジメント等の業務を新会社に移管するのなら、例えば、ソニーやヤマハなどの会社が出資して本物の芸術を売れるタレントを本気になって発掘したり、育てたりして欲しいと思うわけである。 10月2日、*7-3のように、ジャニーズ事務所は、①所属タレントのマネジメント業務を手掛ける新会社を設立し ②新会社(資本構成未定)がタレント業務に必要な知的財産を引き継いで創業家一族は経営に関与せず ③新会社は「エージェント会社」としてタレントと契約を結び仕事獲得等を請け負う ④旧ジャニーズ事務所は10月17日に社名を「SMILE-UP」に変更して被害者への補償手続きを順次進め、被害者救済終了後に廃業する ⑤チーフコンプライアンスオフィサーに企業のリスク管理に詳しい山田弁護士を就任させる 等の立て直し策を発表した。 このうち①は良いし、②は、1~2日で決まる筈がないため未定で当然だ。また、⑤ように、チーフコンプライアンスオフィサーに企業のリスク管理に詳しい弁護士が就任すれば、ガバナンスについても弁護士と相談しながらやれば間違いない。ただ、④のジャニーズ事務所の被害者への補償額は見積もりでもいいから算定され、新会社へは負担が生じないことが明らかにならなければ、新会社に出資する人や会社は困るわけである。そのため、被害者を早く確定して(例えば10月末で締切など)、各人の機会費用まで含めた損害額を計算し、それを合計して全体の見積額を出す必要があるが、組織再編におけるリスク管理は公認会計士の方が得意である。なお、⑥のように、「新会社の経営陣に喜多川氏が築いたシステムで育ったタレントが就くのは問題があり、スポンサー離れが続く可能性がある」という指摘もあるが、それでは被害者に責任を負わせることによって被害を受けても沈黙を強いるということになるため、人権侵害の上塗りになる。その上、経営陣にタレントもいなければ、具体的な新会社の今後の発展はおぼつかないと思われた。 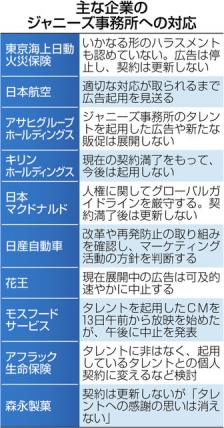 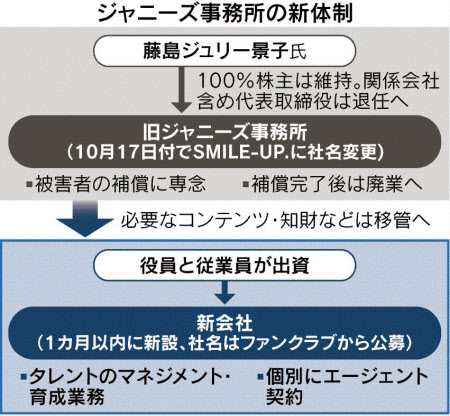 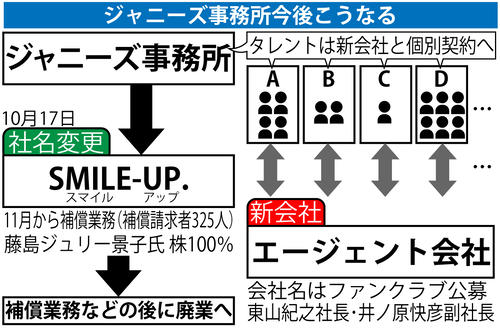 2023.9.15中日新聞 2023.10.3日経新聞 2023.10.2日刊スポーツ (図の説明:9月7日の会見の後、左図のように、ジャニーズ事務所のタレントを起用した広告停止や契約非更新が相次いだが、タレントに非があるわけではないため、タレントとの個人契約に切り替えた会社もあった。そして、10月2日の会見で、中央と右図のように、役員と従業員が出資してタレントとエージェント契約を結び、タレントのマネジメントや育成を行う新会社を立ち上げ、旧ジャニーズ事務所は10月17日付けで社名変更して被害者の補償に専念し、補償完了後は廃業することになった。これは、マネージド・バイアウト方式の組織再編だが、タレントの今後の世界進出のためには、資本力があって文化に関わる事業を行ってきた世界企業の出資や協力もあった方がいいと、私は思う) *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20231001&ng=DGKKZO74912850R01C23A0EA2000 (日経新聞 2023.10.1) ジャニーズ、補償と経営分離 マネジメント新会社、社名を公募へ 藤島氏は出資せず ジャニーズ事務所が会社を再編する方針を固めたことが30日、わかった。新会社を立ち上げ、所属タレントのマネジメントなどの業務を移管する。現在のジャニーズ事務所は故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償に専念する。新会社の社名はファンから公募で決める方向で検討しているもようだ。新会社にはジャニーズ事務所前社長の藤島ジュリー景子氏は出資せず、業務にも携わらないとみられる。現在のジャニーズ事務所の社名の変更も検討している。民放各社から「補償とマネジメントを行う組織の分離を検討すべきだ」との声が上がっていた。芸能事務所としての業務と補償を明確に分離する。ジャニーズ事務所は9月7日に会見を開き、喜多川氏による元所属タレントらへの性加害を事務所として初めて認めた。被害者には法的な枠組みにとらわれず補償する意向も示した。引責辞任した藤島氏は代表取締役にとどまり、藤島氏が全株式を保有する株主構成やジャニーズという社名も当面維持するとした。これらの対応について、所属するタレントを広告などに用いるスポンサー企業の間では人権尊重の視点やガバナンス(企業統治)が不十分だとして批判が相次いだ。CM放映の中止など起用を見直す動きが広がった。事態を打開しようと、同事務所は今後1年間、所属タレントの広告や番組出演で得た出演料について受け取らず、タレント本人に支払う方針を示した。ただ、契約見直しの動きは止まらなかった。帝国データバンクによると、テレビCMなどにジャニーズの所属タレントを起用した上場企業65社のうち、半数にあたる32社が起用方針を見直した。経団連の十倉雅和会長は9月19日の定例記者会見で「日々研さんしているタレントの活躍の機会を奪うのは少し違うのではないか」と述べ、所属タレントの救済策を検討すべきだと指摘した。日本商工会議所の小林健会頭も社名について「継続しないほうがいい」と述べた。ジャニーズ事務所は2日、今後の経営方針について会見を開く。被害者への補償の具体策とあわせて再編案についても説明する見通し。 *7-2:https://diamond.jp/articles/-/328852 (Diamond 2023.9.8) 「ジャニー氏は1万円を渡して…」ジャニーズ性加害問題、もし今の法律で裁かれていたら? ジャニーズ事務所の性加害問題について「外部専門家による再発防止特別チーム」が「調査報告書」を発表したのは2023年8月末。この中で、故・ジャニー喜多川氏による長年にわたる性虐待の実態が、被害者からの証言の形で記されていた。しかし、いわゆる「男性も性被害者」として認める法改正がなされたのは17年になってからのことだ。法改正が遅れたことによる影響を改めて振り返ってみたい。 ●衝撃的な「ヒアリング結果」 「調査報告書」では、ジャニー氏による性加害は1950年代から2010年代半ばまで続いていたものであり、被害に遭った少年が多数いることが認定された。また、その原因は4つ「ジャニー氏の性嗜好異常」「メリー氏による放置と隠蔽」「ジャニーズ事務所の不作為」「被害の潜在化を招いた関係性における権力構造」と指摘されている。ジャニー氏の個人による問題と、隠蔽した組織の問題の両方があり、さらにその背景には「マスメディアの沈黙」「業界の問題」があったという指摘を、マスコミや業界関係者は重く受け止めなければならないだろう。被害の一端を知りながら、あるいは薄々勘づいていながら、ほぼ全ての人が何も行動を起こさなかったのだ。調査報告書の中で、特に読む人に衝撃を与えたのが、性加害についての「ヒアリング結果」だろう。この中では具体的にどのような被害があったのかについて、匿名の証言が列挙されている。「ジャニー氏は1万円を渡してきたので、これは売春のようだと思った」「私が被害を受けている間、周囲のジャニーズJr.たちは見て見ぬふりをしていた」といった証言が悲痛である。性犯罪については、近年大きな変化があった。23年7月、性犯罪に関する刑法が改正され「不同意性交等罪」や「性交同意年齢の引き上げ」があったことが大きく報道されている。ただ、今回のポイントは「男性が性被害にあった場合」への対処の遅れに注目したい。 ●「強姦罪」から名称変更された意味 男性の性被害に関して言えば、6年前の17年の時点で大きな改正があった。それは、従来の「強姦罪・凖強姦罪」が「強制性交等罪・凖強制性交等罪」に名称変更されたという点だ。ネット上で「罪名を変更しても厳罰化しなければ意味がない」というコメントを見かけたことがあるが、これは単なる名称変更ではない。それまでの刑法では、暴行や脅迫を用いて膣性交(女性器への男性器の挿入)を行うことを「強姦罪」としていたが、改正後は膣性交だけではなく、口腔性交と肛門性交の強要が同等に裁かれることとなったからだ。この改正が「男性も被害者に」と報道されたのは、このためである。また、「強姦」は「女性を姦淫する」という意味であるため、名称が変更され、やや違和感のある罪名となったのである(23年の改正で、不同意性交等罪に改められた)。2017年以前は、口腔性交や肛門性交の強要は「強制わいせつ罪」であり、懲役6月~10年の罪だったため、男性に対する性犯罪は女性に対する性犯罪よりも「軽く」捉えられていたと言える。そんな状況だったのが、17年の改正で「強制性交等罪(旧強姦罪)」の量刑が、懲役3年以上から懲役5年以上に引き上げられることで、厳罰化が進んだのである。 ●男児複数人への性加害、懲役20年のケースも 「調査報告書」を見ると、口腔性交をされたという証言は多く、中には肛門性交をされたという証言もある。これらは、現在の基準であれば懲役5年以上の「不同意性交等罪(17年7月~23年7月12日までは強制性交等罪)」となる。22年の裁判で、男児に対する性的暴行で逮捕された元ベビーシッターの男に対して懲役20年が言い渡された。この事件の被害児童は20人、強制性交等罪での立件が22件、強制わいせつ罪が14件と報道されている。仮定の話に意味はないが、現在の基準で故・ジャニー喜多川氏が裁かれていたとすれば、相当重い懲役となったはずである。しかし、ジャニー氏の存命中にこの問題が発覚していてもどうであったか……。故・ジャニー喜多川氏の加害行為は、わかっている範囲で1950年代から2010年代半ばという。17年の法改正より前の被害については、口腔性交・肛門性交の強要は「強制わいせつ罪」だった。もちろん、そもそも被害申告できなかった人が多いので刑事事件になった可能性は低いが、それでも法改正がもっと早く行われていれば、「男性の性被害」に関する意識の変化はそれだけ早かったかもしれない。 ●13~15歳の被害が多いのはなぜか また、もう一つのポイントは性交同意年齢だろう。調査報告書を見ると、被害に遭った年齢は10代前半に集中している。「13~14歳時」「14~15歳時」「中学1年頃」「中学2年頃」といった証言が多い。23年の刑法改正まで、日本の性交同意年齢は男女関係なく13歳だった(法改正後は16歳に引き上げ)。13歳未満の者に対しては、性的行為をした時点でアウトだが、13歳に達していた場合、「暴行・脅迫」が用いられたどうかが問われていた(23年の改正前刑法)。「調査報告書」の中では、ジャニー氏が性的行為に及んだ際に明確な暴行や脅迫があったとは記されていない。だからといって、彼の行為が「同意のある性行為」だったと考える人は、今やほぼいないだろうが、これらについて「被害」を立証することは、当時の法律や認識では難易度が高かっただろう。「嫌ならなぜ抵抗しなかったのか」「男の子なのだから逃げようと思えば逃げられたはずだ」と言われてしまったであろうことは容易に想像できる。23年の法改正では性的同意年齢が16歳に引き上げられ、「経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって不利益を憂慮させること」も、「不同意性交等罪」を成り立たせる事由の一つとされた。この条件が当時もあったのであれば、ジャニー氏による加害行為は訴えやすかったはずだ。 ●時効の問題 23年の改正では、性犯罪の時効についても変更があった。不同意性交等罪(改正前は強制性交等罪・凖強制性交等罪)は10年から15年、不同意わいせつ罪(改正前は強制わいせつ罪)は7年から12年に時効が引き上げられた。ただし改正以前に行われた行為については、時効はそれぞれ10年、7年のままである。※ただし改正以前の事件でも改正までに時効を迎えていなければ、改正後の時効が適用される。口腔性交と肛門性交の強要が強制性交にあたるようになったのが2017年だが、強制性交等罪にあたる被害については、そもそも2017年の法改正以降しか問うことができないということだ(それ以前の口腔性交、肛門性交の強要は強制わいせつ罪なので、さかのぼれるのは2016年までだ)。ジャニー喜多川氏は19年に亡くなっているが、死去の直前まで加害行為があったとすれば、被疑者死亡ながら時効を迎えていない被害もあるのだろう。「ジャニーズ性加害問題当事者の会」は9月4日の会見で刑事告発を行う考えを明らかにしているが、告発を行う人がいるのであれば、この期間(時効が過ぎていない期間)での被害なのではないか。性被害は被害申告までに時間がかかる場合が多く、特に子どもの頃の被害は被害に気づくまでにも時間がかかるといわれる。23年の法改正では、未成年の被害は、成人を迎えるまで時効がストップされることになったが、それでも、最大で33歳までに被害を申告しなければ時効となる。今回、被害を打ち明けた当事者の人々の中には、40~50代以上も多い。これをどう考えるかは、今後社会に向けても問われることとなりそうだ。 【追記】27段落目:※ただし改正以前の事件でも改正までに時効を迎えていなければ、改正後の時効が適用される (2023年9月27日9:50 ダイヤモンド編集部) *7-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20231003&ng=DGKKZO74950020S3A001C2EA1000 (日経新聞 2023.10.3) ジャニーズ、補償後に廃業。新会社に知財移管へ ガバナンスなお不透明 ジャニーズ事務所は2日、性加害問題からの立て直し策を発表した。所属タレントのマネジメント業務を手掛ける新会社を設立、同事務所は被害者救済に専念し終了後に廃業する。新会社はタレント業務に必要な知的財産を引き継ぎ、創業家一族は経営に関与しない。新会社の資本構成は明らかになっておらず、ガバナンス(企業統治)が機能するかなお不透明だ。ジャニーズ事務所は17日付で社名を「SMILE-UP.(スマイルアップ)」に変更し、被害者への補償手続きを順次進める。法令順守に向けて、チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)に企業のリスク管理などに詳しい弁護士の山田将之氏が就任。全ての事業活動で子どもの保護と安全を確保するグループの人権方針も策定した。創業者の故ジャニー喜多川氏から性加害を受け、補償を要求した人は9月30日時点で325人いる。2日に記者会見した東山紀之社長は「自分たちでジャニーズ事務所を解体する」と述べた。同事務所は9月の会見で、引責辞任した創業家出身で前社長の藤島ジュリー景子氏が代表権を持ったまま、全株式を持つ株主構成を見直さず、「ジャニーズ」という社名も当面維持するとしていた。所属タレントを広告に起用するスポンサー企業から人権尊重の視点やガバナンスが不十分との指摘が相次いでいた。前回の会見から1カ月足らずでの方針転換となった経緯について、東山社長は「内向きだったと批判されても当然。喜多川氏と完全に決別する」と述べた。ジャニーズの名称を使ったグループについても変更する。藤島氏は関連会社を含めて代表取締役を退任する。新会社は1カ月以内に立ち上げる。藤島氏は出資せず、取締役にも就任しない。資本金は検討中で役員や従業員が出資する。社長は東山氏が兼任し、社名はファンクラブの公募で決める。社外取締役の起用も検討する。新会社は所属する個人のタレントやグループが会社と個別に契約を結ぶ「エージェント会社」とする。エージェント会社はタレントと契約を結び、仕事獲得などを請け負う形をとる。ハリウッドなどでは一般的な契約方法で、国内では吉本興業ホールディングスが、所属タレントが反社会的勢力の会合に参加した「闇営業」問題などを受けて19年に導入した。同事務所が再建に向けて選んだのは「第二会社方式」と呼ばれる手法だ。水俣病の原因企業のチッソは水俣病特別措置法に基づき、11年に事業部門を100%子会社のJNC(東京・千代田)に分社し、チッソは補償業務に特化した。同事務所は広告起用の見直しが相次ぐ所属タレントの活動継続と、被害者の救済を両立する狙いがある。外部の専門家チームは8月末に公表した報告書で、喜多川氏による性加害は半世紀以上に及び、被害者は数百人に及ぶとした。今後は補償額がどの程度まで膨らむか、その原資が焦点となる。非上場企業のジャニーズ事務所は、主要な経営指標を公表していないが、民間調査会社によると売上高は800億円程度。稼ぎ頭はファンクラブ収入だ。「嵐」や「Snow Man」など15グループだけで会員数は累計1100万人超になる。年会費は4000円で、総額500億円前後に上る計算だ。このほか東京都内の所有ビルなどの資産価値は計1000億円程度とみられる。企業の人権侵害を巡る視線の厳しさが増す中、「ジャニーズ離れ」に歯止めがかかるかは不透明だ。帝国データバンクによると、テレビCMなどにジャニーズ所属のタレントを起用した上場企業65社のうち、半数にあたる33社が起用方針を見直した(9月30日時点)。所属タレントを起用した広告や販促物の展開を停止している日産自動車は2日、「事務所が発表した改革や再発防止の取り組みを注視しながら、適切な対応を取っていく」と述べるにとどめた。スポンサー企業は過去との決別の是非について資本構成で判断するとされるが、新会社の構成は明らかになっていない。企業のガバナンス問題に詳しい青山学院大学の八田進二名誉教授は「現状ではスポンサー離れを食い止めることはできない」との見方を示す。日本リスクマネジメント学会理事長で関西大学の亀井克之教授(リスクマネジメント論)は「新会社の経営陣に喜多川氏が築いたシステムで育ったタレントが就くのは問題がある。スポンサー離れが続く可能性がある」と指摘する。
| 財政 | 02:48 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2023,07,06, Thursday
(1)日本経済の現状 ← 経常黒字半減・物価上昇・実質賃金減少
1)家計苦境の実態 *1-1-1は、①国の2022年度一般会計税収が71兆1,373億円と過去最高を記録 ②理由は円安の重なった物価上昇による消費税増収と所得税・法人税の増収 ③多額の防衛費や少子化対策費を歳出する岸田首相にとっては好材料 ④税収増は家計苦境の裏返しでさらなる負担は受け入れ難い ⑤2022年度消費者物価指数は前年度比3.2%増で食品・電気・ガス、サービス関連まで値上げが及んだ ⑥それと連動して2022年度の消費税収は過去最高の23兆792億円に達した ⑦景気に左右されにくく物価の影響を受けやすい消費税の特徴が表れ、税収の確かさから社会保障を支える消費税の役割を再認識できた ⑧家計から見れば物価上昇に消費課税増のダブルパンチ ⑨消費税は逆進性があり、家計の重荷は深刻 ⑩多くの人は収入増がインフレに追い付かず、実質賃金は13ヶ月連続で減少 ⑪2022年度は円安による輸出企業の業績上振れで法人税も14兆9,397億円と増収 ⑫岸田政権による血税の使途と財政運営が厳しく問われるのは当然 等と記載している。 このうち①②④⑤⑥⑧⑩は、日銀が「2%の物価目標」を達成しようと低金利政策を続ける理由だが、「物価目標」とは、(欧米先進国を見ればわかるとおり)過熱したインフレを抑制して国民の生活を護るために上限として設定するものであるため、日銀の物価目標は本来の使い方とは逆なのである。 にもかかわらず、日銀が「2%の物価目標」を継続する真の目的は、③のような際限のない政府歳出によって積みあがった多額の国債(国債の所有者から見れば財産)を目減りさせ、⑪のように、輸出企業の業績を上振れさせ、実質賃金を減少させることなのだ。少し考えればわかるとおり、金融緩和を続けて名目賃金が上がっても、構造改革して生産性を上げなければ実質賃金を上げることはできず、次第に円の価値が下がって円安になるのは明白である。 また、⑦は「消費税は、景気に左右されにくく、物価の影響を受けやすいから、税収が確かで社会保障を支える役割を再認識できる」とするが、所得税・法人税等の所得に応じて増減する税は、ビルト・イン・スタビライザー(財政自体に備わっている景気を自動的に安定させる装置)の役割を備えているが、景気に左右されない消費税は、その逆だ。また、⑨のように、逆進性があることで、所得が低くて消費性向の高い層ほど重い税となるため、家計の重荷がより深刻になる税である。 従って、所得の低い層に恩恵の多い社会保障を支える税として消費税を挙げること自体が目的と矛盾しており、⑫のように、既得権を振りかざした無駄の多い税の使途こそ厳しく検証すべきだが、これはずっと前からそうだったのであり、岸田政権に限った話ではない。 2)社会保障・消費税・医療費など イ)社会保障と消費税について *1-1-2は、①岸田首相が消費税等の議論を封印し、政府税調も「中期答申」で増減税等の具体的改革の方向性を示さなかった ②終身雇用や専業主婦世帯が主体と考えられた旧態から働き方や人生設計が多様になった ③デジタル化やグローバル化が進んだ ④税制も経済成長を促す発想で組み直す必要がある ⑤社会保障や財政の持続可能性にも配慮して負担や歳出を見直すことは妥当 ⑥「消費税は社会保障給付を安定的に支えるため、果たす役割は今後とも重要」とだけ記した ⑦税調では現行10%からの引き上げが必要とする議論も出たが、答申は税率や時期等の具体論を避けた ⑧所得税は働き方の違いで不公平が生じないよう給与・退職金・年金への税負担のバランスをとるよう促したが、具体的手法の言及がない ⑨問題は政治が与野党とも次の選挙に影響するとして税や社会保険料など安定財源の確保で真剣な議論から逃げていること ⑩財源を曖昧にして給付だけを増やすのは将来世代に対して無責任 等と記載している。 ①⑤⑥⑦⑨のように、(新聞には消費税がかからないためか)新聞は消費税増税を進める論調が多いが、本当は記者も生活者で社会保障の受給者でもあるため、社会保障の不適切な見直しや消費税増税は自らにも負担になる筈なのである。 また、②の終身雇用が保障されたのは、ずっと前から大企業に勤めている男性正社員だけだった。さらに、専業主婦世帯が主体だったわけでもなく、正社員として働いている女性の割合が少なかったとしても、少ないからと言って不公正・不公平を無視してよいわけではなく、その少人数の女性が苦労して切り開いたからこそ現在があるため、言葉には気を付けるべきである。 デジタル化やグローバル化は、③のとおり、確かに進んで生産性向上がやりやすくなったが、「税法」や「出入国管理及び難民認定法」が、デジタル化・グローバル化・少子高齢化に合い、④の経済成長を促すものになっているとは言い難い。 なお、⑧の所得税等は働き方の違いで不公平が生じないようにすべきだが、現在はまだ過渡期で、女性に専業主婦を強要する社会システムや終身雇用を前提とした賃金体系が残っているため、具体的手法の言及は難しかっただろうとお察しする。 しかし、⑩の「財源を曖昧にして給付だけを増やすのは将来世代に対して無責任」というのは、日本国憲法第25条「第1項:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第2項:国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」や同第26条「第1項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。第2項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」等の憲法に記載されていることについては、他を削り優先順位を高くして行うべきであるため、負担増という話にはならない筈である。 ロ)医療費と消費税について 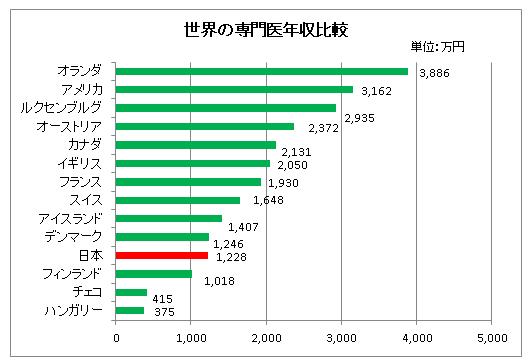 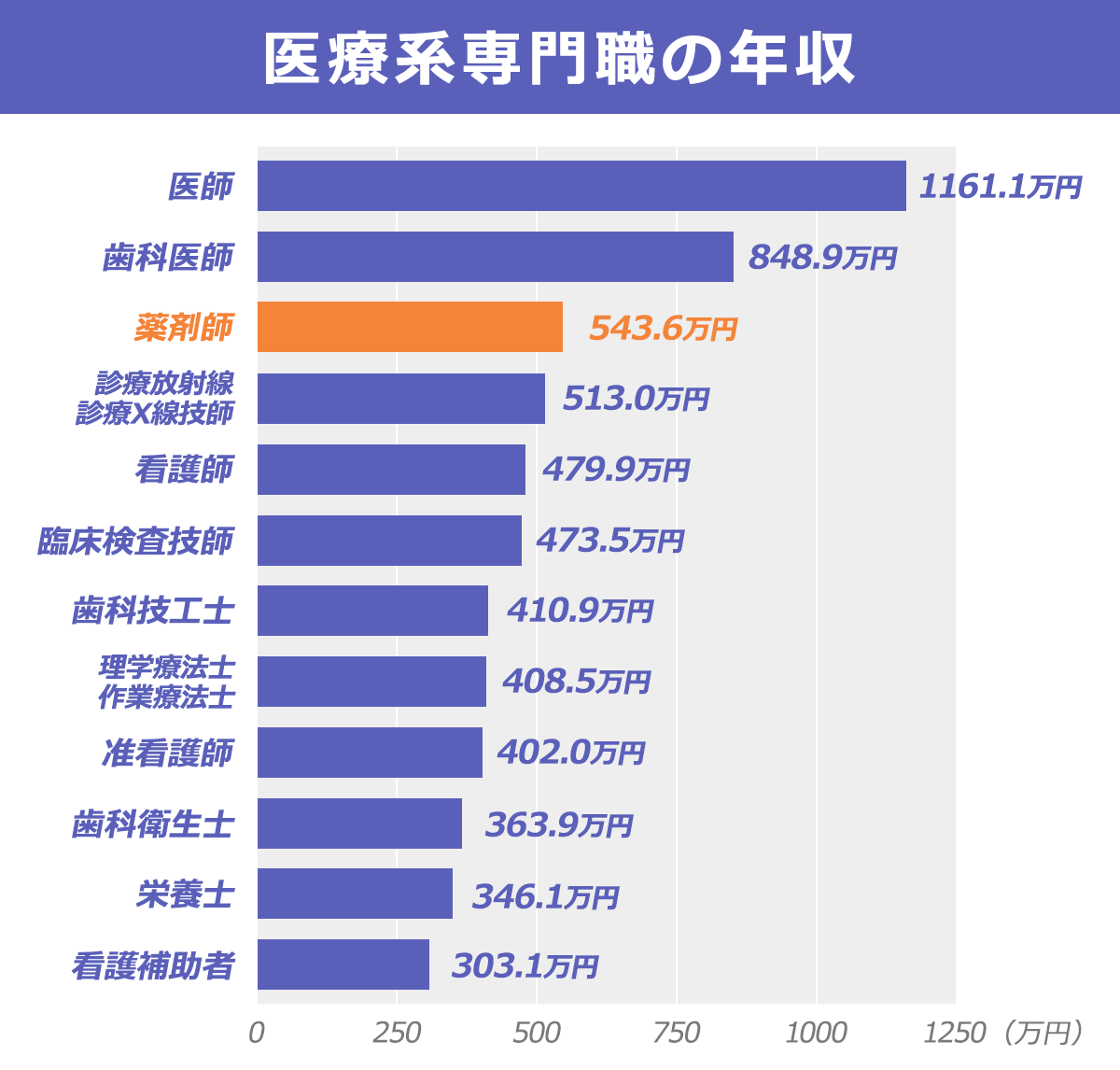 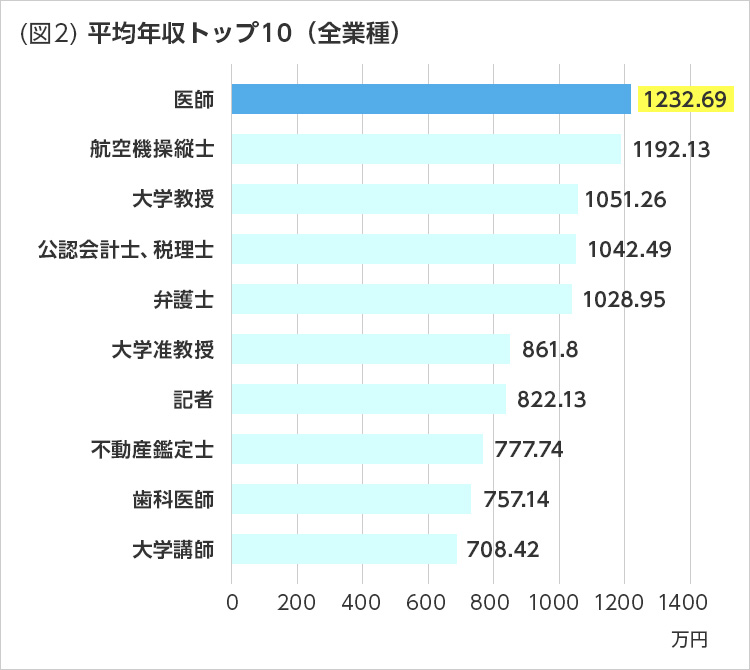 世界の専門医年収比較 日本の医療系専門職年収 日本の平均年収トップ10 (図の説明:左図は世界の専門医年収比較だが、日本は決して高い方ではない。また、中央の図は医療系専門職の年収で、《どうやってこの数値を出したのかは不明だが》さほど高くない。そして、右図の記者と比べて医師は間違ったことをすると取り返しのつかないことになるリスクを常に引き受けている割には高くない。そのため、医療系の人は、職種や業態別の平均年収を把握し、それを他の職種の同等の人材と比較したデータを自分たちで作って公表した方がむしろ有利だと思われる) *1-1-3は、①年間45兆円に上る医療費が物価高を反映させる形で一段と膨らむ可能性 ②物価高で医療機関の経費が増えているのは確かだが、医療費を増やせば患者負担や国民の保険料負担が重くなる ③政府は医療の持続性確保から、丁寧かつ慎重に検討して欲しい ④保険医療は診療報酬という公定価格のため、光熱費・設備費・委託費等の経費増加分を医療費に転嫁できない ⑤2022年4月改定の診療報酬はその後の物価上昇分を勘案しておらず、日本医師会等は2023年度中に補助金で緊急措置を実施した上、2024年4月の次期改定で物価水準を反映するよう求めた ⑥産業界の労使交渉では賃上げと生産性向上をセットで議論するのが一般的で医療従事者の賃上げを考える際も業務効率化の方策を同時に検討すべき ⑦岸田政権は社会保障等の改革で国民負担を抑制して新たな少子化対策に要する負担増分を相殺する方針を閣議決定 ⑧この施策との整合性から国民負担を増やす診療報酬増額は安易に行うべきでない ⑨医療従事者の賃上げはデータに基づく議論も必要 ⑩医師や看護師、事務員等の職種別給与データ提出を医療法人に求め、処遇実態を把握した上で賃金水準のあり方を検討して欲しい 等と記載している。 このうち①②③は、産業界には「物価上昇に見合った賃上げを」と言いつつ、医療費については「患者負担や国民の保険料負担が重くなる」等として反対するのは変である。何故なら、物価を上げれば、それ以上の賃上げをしなければ実質賃金が下がるのは、誰でも同じだからだ。 また、医療は消費税について非課税取引であるため、支払消費税をすべて事業者がかぶっており、それも苦しくなった原因の1つだ。その上、④のように、保険医療は公定価格であるため、光熱費・設備費・委託費等の著しい経費増加分を医療費に転嫁することができないわけである。 そのため、⑤の日本医師会の要望は尤もと思われるし、⑥の医療界の生産性向上は、マイナンバーカードにひもづけてセカンド・オピニオンもとれなくすればよいというものではない。そのため、これらは第三者が勝手に決めるのではなく、その専門家が検討すべきことなのである。 ⑦⑧の「社会保障等の改革で国民負担を抑制」「国民負担を増やす診療報酬増額は行うべきでない」ということについては、高齢者の割合が増えて今までどおりの治療をすれば医療・介護費が増えるのは当然であるため、治療方法や職務分担を合理化したり、薬価を下げる仕組みを入れたりするしか方法はないだろう。 なお、⑨⑩は、「医師・看護師・事務員等の職種別給与データ提出を見て医療従事者の賃金水準のあり方を検討したい」ということだろうが、上の左図の通り、日本の医師の賃金水準は世界の中で高い方ではないため、賃金水準をこれ以上低くすると優秀な人が日本で働かなくなり、その結果、日本の医療の質が落ちて国民が困る事態になるのである。 3)企業物価と消費者物価の上昇 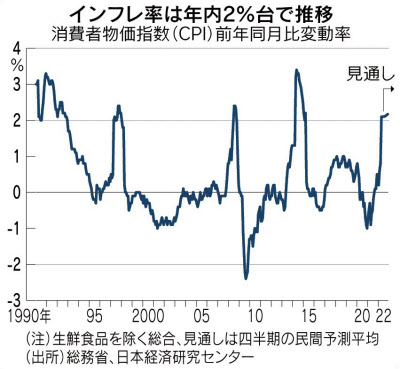  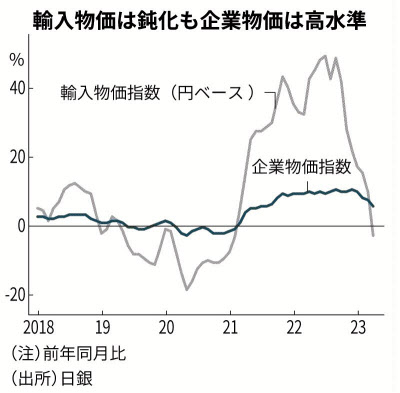 2022.6.24日経新聞 2023.6.23日経新聞 2023.5.16日経新聞 (図の説明:左図は、1990~2022年の消費者物価指数前年同月比変動率、中央の図は、2022年5月~2023年5月の生鮮食品を除く消費者物価指数の前年同月比変動率で、どちらも前年同月比で2~3%の物価上昇になっている。そのため、1990~2023年の累積消費者物価上昇率は著しく大きい。また、右図は、2018~2023年の輸入物価指数と企業物価指数の前年同月比であるため、累積物価上昇率はこれよりずっと大きい) イ)企業物価の上昇 *1-2-1は、①日銀が発表した2023年4月の企業物価指数は前年同月比5.8%の上昇で公表された品目の8割超で価格が上昇し、②食品等の川下品目での価格転嫁が当面続き ③円相場は136円/ドル程度で円安による直接的押し上げ圧力は一服して、輸入物価指数のうち石油・石炭・天然ガスはマイナス9.0%、金属・同製品もマイナス7.5%だが ④電力・都市ガス・水道の前年同月比上昇率は25.8%で(それでも、電力・ガス料金は2月以降は政府の価格抑制策が効いて、0.7%程度全体の上昇率を押し下げた) ⑤これまでのコスト高で複数回に分けて値上げに踏み切る企業もあり価格転嫁による押し上げ圧力は継続しており ⑥消費者物価指数(生鮮食品を除く)も前年同月比3.1%上昇と高水準で推移している ⑦日銀は物価上昇率が23年度半ばに2%を下回るとの見方を示し ⑧植田総裁は「(2%の物価目標を達成すると)安心して言えるところまで到達していない」として大規模緩和を維持する方針 等としている。 このうち①③④に示される数字は、2022年4月との比較であるため、2020年4月と比較すればかなりの上昇率になる。そして、②⑤のように、生活必需品である食品等の価格転嫁や複数回に分けた値上げで価格上昇は当面続き、⑥のように、最も上昇率の高い生鮮食品を除いても消費者物価指数は前年同月比3.1%上昇と高水準で推移しているのだ。 にもかかわらず、⑦⑧のように、物価上昇率が2023年度半ばに2%を下回るとの見方から「2%の物価目標を達成すると安心して言えるところまで到達していない」として、植田日銀総裁は大規模緩和を維持する方針だそうだが、実質所得を下げ、実質資産を目減りさせて国民を貧しくしながら、日銀は「2%の物価目標」を何のために設定しているのか、それと日銀の役割との整合性はどうなのかについて明確に説明すべきだ。 ロ)消費者物価の上昇 *1-2-2・*1-2-3は、①2023年5月の消費者物価指数は生鮮食品を除き104.8(2020年を100とする)で1981年の第2次石油危機4.5%以来の高い上昇率 ②生鮮食品を除く食料は9.2%プラスで1975年の9.9%以来の上昇幅 ③食品・日用品の店頭価格の上昇が続いてPOSデータによる日次物価の前年比上昇率は6月28日時点で8.7% ④大手が価格改定して中堅企業が続く追随型値上げの傾向 ⑤原材料価格・物流コスト上昇で、アイスクリーム10.1%・ヨーグルト11.3%・洗濯用洗剤が19.9%・宿泊料9.2%上昇 ⑥日銀の物価目標2%を上回る状況が続いている ⑦原材料高を商品価格に反映する動きはウクライナ危機をきっかけに広がり ⑧値上げしてもPOSでみた売上高は大きく落ちないメーカーもある ⑨インフレが定着しつつあり、値上げによる客離れは深刻化していない可能性 ⑩2023年6月は28日までの平均で生鮮卵42%・ベビー食事用品26%・水産缶詰21%上昇など幅広い商品で2桁の値上げ ⑪日本は米欧に比べて価格転嫁が遅れ気味だと指摘されてきた 等と記載している。 まず、⑪のように、日本は米欧に比べて価格転嫁が遅れ気味だと指摘したり、値上げを「物価の伸び」と表現したりして、コストプッシュインフレであっても良い物価上昇であるかのような表現が目につくが、日本は食料・資源・エネルギー等の自給率が低いため、輸入物価の上昇は富の海外流出増にほかならないことを忘れてはならない。 その中で、①②の原油の輸入単価が上がって他の財・サービスに波及した「第二次石油危機以来の高い物価上昇率」は、政府にとっては名目税収増と実質債務減という大きなメリットがあるが、国民にとっては実質収入減と債権や預金の目減りに加え、物価上昇というマイナスの効果しかない。さらに、物価上昇は消費性向の高い低所得層にほど重いステルス課税になるのである。 例を挙げれば、③⑩の食品・日用品等の生活必需品は、値上がりしても買わないわけにはいかない。そのため、裕福でも貧乏でもさほど購入金額の差が出ないが、収入以上の支出はできないため、⑧のように、値上げしても売上高は落ちないが、それは節約によって販売数量が減り、売上金額全体はさほど変動がない状態なのである。そして、「節約せざるを得ない状態になった」というのは、「国民を前より貧しくした」ということなのである。 にもかかわらず、④⑤⑨のように、物価上昇がまるで良いことであるかのような書き方が散見されるが、この物価上昇は、⑦のように、ウクライナ危機と円安により輸入物価が上がったことによって起こったコストプッシュ・インフレである。そのため、値上げ分の富は海外に支払ってしまって国内で廻すことができなくなるのであり、欧米のディマンド・プル・インフレのように景気が過熱して起こったものではないのだ。 従って、⑥の日銀の「物価目標2%」を上回ったからといって全くめでたいわけではないのに、(故意か過失か)メディアはこれを完全に無視している。そもそも「物価目標2%」というのは、ディマンド・プル・インフレが過熱して困る場合に、金融を引き締めて(=公定歩合を上げて)物価上昇を2%以内に抑制するためのものである。 4)実質賃金の減少と実質消費支出の減少 イ)実質賃金の減少 *1-3-1は、①厚労省の2023年4月の毎月勤労統計調査(従業員5人以上の事業所)によると、名目賃金(現金給与総額)は1.0%増、物価変動を考慮した実質賃金/人は前年同月比3.0%減少 ②実質賃金の減少は13カ月連続で、物価の伸びに賃金上昇が追いつかない ③物価上昇率が4.1%に達し実質賃金のマイナス幅は3月より広がった ④厚労省は「まだ交渉中の労使があるから結果が十分に反映されていない」と言う ⑤就業形態別現金給与総額は正社員等の一般労働者1.1%増で36万9468円、パートタイム労働者1.9%増で10万3140円 等としている。 日本政府は、「国民は名目賃金しか意識しないため、物価が上昇しても名目賃金が上がれば喜んでいるだろう」と思ったようだが、国民は激しいインフレを第二次世界大戦後とバブル期の2度経験し、賃金が上がってもそれ以上に物価が上がれば生活が苦しくなることがわかっているため、そうはいかない。 また、金融緩和による円安とウクライナ危機をきっかけとした輸入物価上昇によるインフレであれば、それはコストプッシュ・インフレにほかならず、日本の場合は海外に支払う金が増えるため、物価上昇分の全てが賃金に回るわけがない。従って、①②③は、日本の経済構造から見て必然で、④のように厚労省がいくら待っても物価上昇以上の名目賃金上昇はないのである。 従って、名目賃金上昇も、⑤のように物価上昇と比較すれば小さいが、第二次世界大戦後やバブル期よりも深刻なのは、2022年10月1日現在の65歳以上の人口割合は29.0%、75歳以上の人口割合は15.5%になっており、年金支給額が“物価スライド”で減らされた上に医療・介護関係費用が負担増で可処分所得が減っているため、人口の3割近い人がさらなる節約を強いられ、景気がよくなるどころではないことなのである。 ロ)実質消費支出の減少 このようにして、*1-3-2のように、①総務省の4月の家計調査で2人以上の世帯の消費支出は30万3076円と実質で前年同月比4.4%減少し ②マイナスは2カ月連続で ③食料、通信など生活関連の品目や教育への支出が減って消費を押し下げた そうだ。 しかし、①②③の数字は、より生活の苦しい1人暮らしの高齢者世帯を除いているため、まだ甘く出ている方なのである。 (2)G7とジェンダー平等 1)G7男女共同参画・女性活躍担当相会合について G7の男女共同参画・女性活躍担当相会合が2023年6月24、25日に日光市で開かれ、*2-1のように、①企業の女性役員登用や成長分野への就業を進めて賃金格差を解消することで女性の経済的自立を進める方向で一致した そうだ。 その共同声明では、②女性役員登用 ③成長分野や報酬の高い分野への女性の労働移動促進 ④女性の起業支援 等を具体策で示し、⑤家事・育児・介護等の女性に偏る無償労働は「女性がフルタイムで働く能力や指導的地位に就く能力を損なう」と指摘し ⑥家族への公的支援を強化し ⑦男性の無償労働への参加を増やすための施策を求め ⑧女性や性的少数者(LGBTQIA+LGBTを含めた多様な性)の人々の人権と尊厳が完全に尊重・促進・保護される社会の実現に向けた努力を継続する」 とのことである。 しかし、ジェンダー平等や賃金・男女格差の解消をテーマに取り上げた時、日本では⑧のように、必ず“性的少数者の尊重”を持ち出すが、これは間違っている。何故なら、②③④の女性が高い地位に就いたり、報酬の高い分野で働いたりするのは、働く以上は当然のことだが、これと生物学的性と性自認間に相違のある障害者としての性的少数者とは次元が異なるからである。 もちろん障害者の人権も無視してはならないが、男女差別と性自認の問題を混同するような文化自体が、日本のジェンダーギャップ指数が146ヶ国中125位と下から数えた方が早く、男女間賃金格差は22.1%と大きく、企業の女性役員比率は11.4%と小さく、無償労働が女性に偏っている状況を作った理由だからでもある。 また①については、「まだそんなことを言っているのかな」と思うくらい当たり前のことだが、⑤⑦は、(男性がやろうと女性がやろうと)体力を決して簡単ではない無償労働にとられ、フルタイムで働いて指導的地位に就いていく能力を損なうのは同じである。そのため、⑥の保育所・学童保育・学校教育の充実・介護の社会化・家事労働の担い手確保等の公的支援が最も重要なのだ。 なお、会合に参加した他国の担当相や団体の代表者9人はすべて女性で、日本だけが男性だったことについては私も変な感じがしたが、女性なら誰でもいいわけではなく、男女平等の強い信念とリーダーシップを持つ女性の方が指摘が的確になってよいと思われた。 2)日本の「ジェンダー・ギャップ指数」について *2-2・*2-3は、①日本は世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ指数で146ヶ国中125位で過去最低 ②政治分野138位・経済分野123位と長年指摘されている両分野で指数が悪化 ③「教育」は47位、「健康」は59位 ④政治分野における男女平等はサウジアラビア(131位)を以下で世界で最も低い圏内 ⑤経済分野も女性管理職比率(133位)が低く、男女の所得格差・昇進を阻む「ガラスの天井」が存在 ⑥リーダー層になるにつれ働く女性が減る構造 ⑦政府は東証プライム上場企業の女性役員比率を2030年までに30%以上にする目標を掲げた ⑧教育は大学以上の進学率が加わって前年の1位から47位に大きく下がり、全体の順位を下げた ⑨多様性がイノベーションを生むのは世界の共通認識で、投資家は組織の意思決定者に多様性を求め、取締役会が男性ばかりの日本企業にノーを突きつける と記載している。 このうち⑨の「多様性がイノベーションを生む」は、需要の主役抜きで議論しても多角的な意見が出ないため正しい結論に至らないことは日本の政策を見れば明らかだ。また、日本企業は国内に洗練された消費者を持ちながら、(既に存在する製品の製造過程を細かく改善するのは得意だが)需要に合わせて最終製品を企画し製造するのは不得意であることからも実証済である。 そして、これは、発言権や意思決定権のある女性(製品によっては高齢者)が組織内にいることでしか解決できないため、世界の投資家が組織の意思決定者に多様性を求めるのは尤もだ。 ③⑧の「教育は大学以上の進学率が加わって前年の1位から47位に大きく下がった」というのは、今まで大学以上の進学率を加えていなかったのかと残念に思うが、同じ大学でも学部によって男女の割合が偏っており、製造・経済・経営等のビジネスに必要な学部に女性が少ないことは、⑤⑥の女性管理職比率の低さやリーダー層になるにつれて女性割合が減る構造を変えるべき母集団に女性が少ないことを意味するため、初等・中等教育の進路指導から変える必要がある。 そのため、⑦の「政府が東証プライム上場企業の女性役員比率を2030年までに30%以上にする目標を掲げた」は悪くないが、女性の多くは中小企業で働くため、東証プライム上場企業の女性役員比率だけでは不足で、会社法にも女性役員比率に関する規制を入れた方がよいと思う。 また、②④の「政治分野は138位でサウジアラビア(131位)以下の世界で最も低い圏内」というのは、日本の政策が生活や環境を軽視しており、エネルギー・食糧の自給率は低く、社会保障は必要なものも作らず、既にある有用なものも削ることしか考えつかない一方で、無駄なバラマキが多いため世界最高水準の債務残高を抱えたという結果を出したわけである。 ④については、サウジアラビア等の資源国は、これまでは資源の輸出により、女性を活用しなくても財政が潤っていたが、今後、最終製品の製造によって世界市場で勝つためには、やはり女性を教育して意思決定権のある場所につけていく必要があると思われる。 このように、①の世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ指数で日本は146ヶ国中125位と過去最低になったが、その理由は、他国はまともに女性活躍の素地づくりに取り組んできたが、日本はやっているふりが多かったからだと言える。 3)女性役員比率について *2-4は、①政府は東証プライム市場へ上場する企業に2025年をめどに女性役員を最低1人選任するよう促す女性活躍・男女共同参画の重点方針を決定し ②女性役員比率を2030年までに30%以上とする目標も盛り込んだが ③いずれも努力義務で罰則は設けない ④岸田首相は女性活躍と男女共同参画に関する会議で「全ての人が生きがいを感じられ、多様性が尊重される持続的な社会の実現のため取り組みを進める」と述べ ⑤年内に東証の上場規則に数値目標に関する規定を設けることを想定している と記載している。 このうち①②は悪くないが、もともとは「202030」と言って、2003年に政府が「2020年までに社会のあらゆる分野で指導的地位に女性が占める割合が30%になるようにする」と女性管理職比率の数値目標を定めたが達成できず、断念したものだ。 202030を達成できなかった理由は、「社会構造等の阻害要因」「現行女性活躍推進法は努力目標で罰則がないこと」「強制力がなく実効性のない法律で企業が目標を達成することは難しいこと」などが挙げられている(https://www.qualia.vc/glossary/203030.html 参照)。 しかし、①は「東証プライム市場に上場する企業」という狭い範囲のみの規制であり、②③は、女性役員比率を2030年までに30%以上にするという先延ばしした目標を盛り込んではみたものの、やはり努力義務で罰則を設けないため達成は期待できそうにない。 そのため、④の「全ての人が生きがいを感じられ、多様性が尊重される持続的な社会の実現のため取り組み」を進めるためには、私は、⑤の東証の上場規則に数値目標を設けるだけでなく、会社法の役員構成にも女性役員比率に関する規制を設ける必要があると思う。 4)年収の壁について 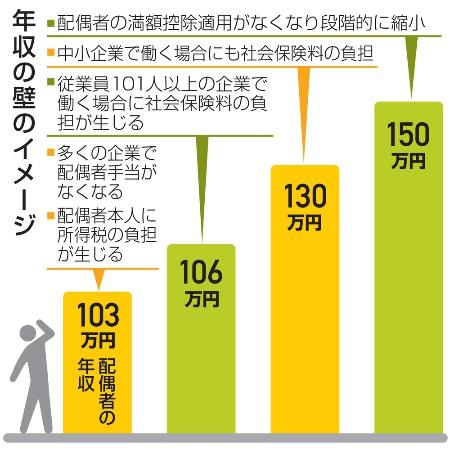 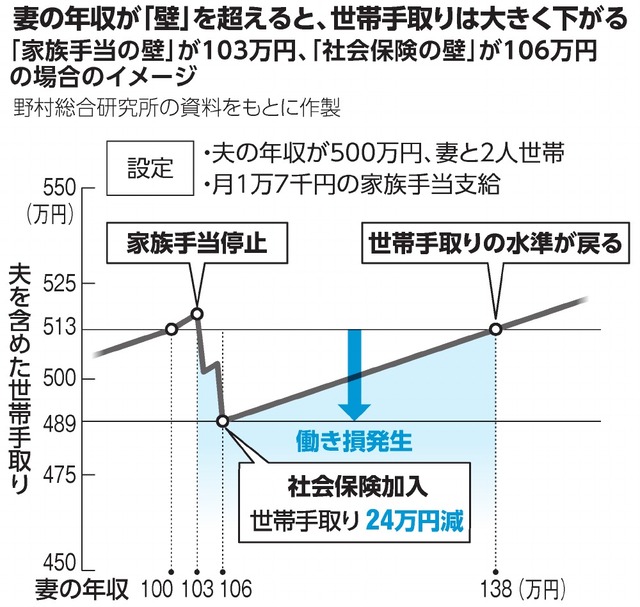 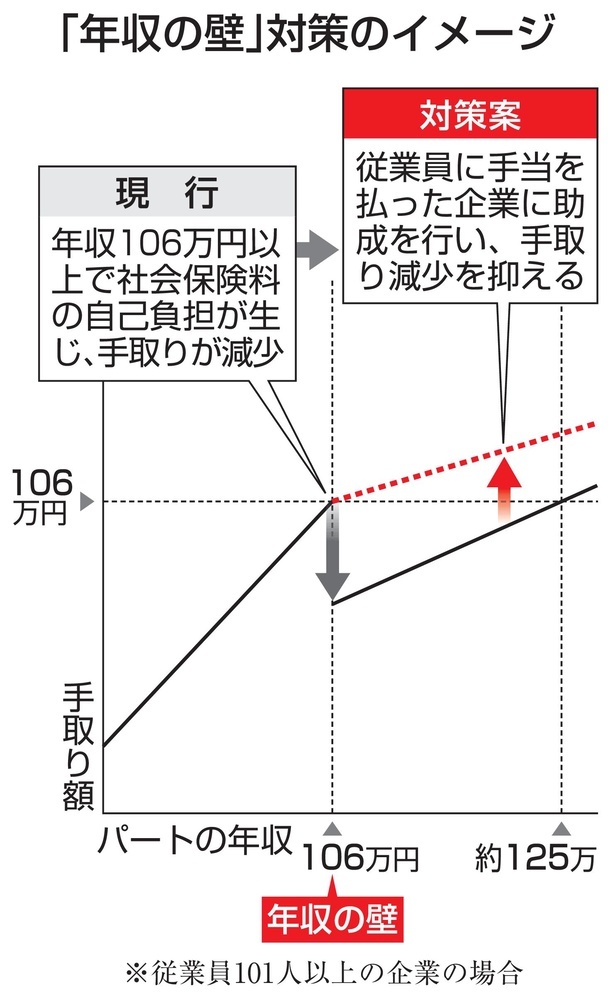 2023.3.16静岡新聞 2023.2.21朝日新聞 2023.6.28Yahoo (図の説明:左図の103万円・106万円・130万円・150万円が年収の壁である。実は、住民税が発生する100万円の壁もあるが、住民税は税率が低いため世帯の手取りは下がらないそうだ。中央の図は、年収500万円で妻が所得税非課税の103万円まで1.7万円/月の配偶者手当をもらえる夫と2人暮らしの妻の年収が変化した時の世帯の手取りの変化を示したグラフだが、扶養手当の停止や社会保険料負担の開始で妻の年収が138万円になるまで世帯の手取りはむしろ減少している。そのため、右図のように、政府が従業員に手当を払った企業に助成して手取りの減少を抑えようとしているが、これは不公平に不公平を重ねるバラマキであろう) 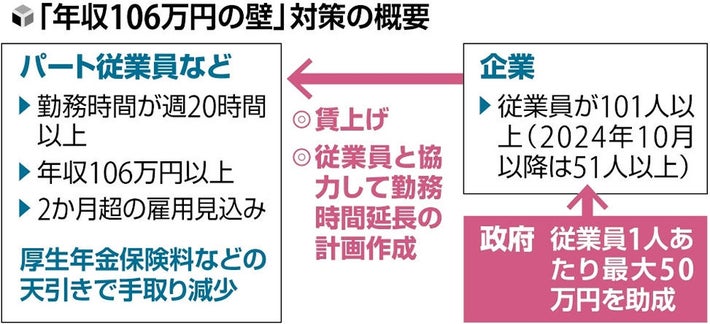 2023.6.29読売新聞 (図の説明:上図のように、政府が意図しているのは社会保険料の発生によって起こる106万円の壁の緩和だが、社会保険料の支払いは将来の年金受給額増加や労災保険・失業保険の受給権発生など見返りのある支払いであるため、手取りの減少がすべて払い損になるわけではない。また、他の労働者は女性も含めて応能負担しているため、その人たちが支払った税金から助成金を出すのは不公平の上塗りにしかならない) *2-5は、①配偶者に扶養されるパート従業員が社会保険料負担の発生を避けるため働く時間を抑える「年収の壁」に関する政府の対策案が分かった ②保険料穴埋めの手当を払った企業に対し最大50万円/人助成する ③従業員の負担を解消し労働時間を延長しやすくして、人手不足緩和を狙うため ④飲食業・観光業を中心にコロナ禍後も働き手が戻らず、営業に支障が出ている所もあるので、個人の収入確保と経済を円滑に回す環境整備である ⑤「年収の壁」見直しは人手不足に悩む企業側が求めた ⑥抜本対策は、先送りして2025年の法案提出を目指す年金制度改革で議論する ⑦現在、従業員101人以上の企業で働くパートは年収106万円以上になると配偶者の扶養を外れ、厚生年金等の保険料を負担して手取りが減るが、扶養されている間は国民年金の「第3号被保険者」として保険料を払わずに将来の年金が受け取れる ⑧対策案では所定労働時間の延長などで生じた保険料の全部または一部を、企業が手当として従業員に払うことができる仕組みを作り、手当は賃金に含めない特別扱いとするため、手当による保険料増は生じない ⑨手当の仕組みを後押しするため、政府は既存の助成金を拡充して企業に支給する ⑩それを、手当・賃上げ原資・企業が負担する社会保険料に充ててもらう ⑪扶養に入っている従業員だけでなく単身者も対象とする ⑫企業が3年以内に労働時間を延長する計画を策定し、実際に延長した従業員も助成対象に加える 等としている。 このうち①②③⑧⑨⑩⑪は、上の図の説明に書いたとおり、社会保険料の支払いは将来の年金受給額増加や労災保険・失業保険受給権の発生など見返りのある支払いであるため、手取りの減少がすべて払い損になるわけではなく、他の労働者は女性も含めて応能負担しているため、その人たちが支払った税金から助成金を出すと、不公平を上塗りしてバラマキすることになる。 第1の不公平は、男女雇用機会均等法が施行され、男女共同参画・女性活躍を推進している時代に、女性が働かないことを奨励する配偶者手当を出す企業があることだが、これは従来からの慣習を変えていないだけだろうから、配偶者手当を廃止して個人の基本給を上げればよい。 第2の不公平は、女性が働こうと思えば働ける現在でも、⑥⑦の国民年金3号被保険者が存在することである。何故なら、日本年金機構は「配偶者である2号被保険者が加入している被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合等)の保険料・掛金等の一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているから、3号被保険者は自分で保険料を納付する必要はない(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/sango.html 参照)」と記載しているが、共働きの2号被保険者は2人とも保険料や掛金を支払っており、家事労働は共働きの2号被保険者も同様に行っているからである。 第3の不公平は、社会保険料の負担が生じる年収が企業規模によって異なる点で、これでは国民の安全を支える保険の役割を果たさない。そのため、社会保険料は所得税が発生する年収からすべての人が負担するように所得税と一致させ、所得税が発生する年収を基礎控除を物価上昇に伴って引き上げることによって変えればよいと考える。 しかし、現在でも、女性であることによって働こうと思ってもうまく働けなかったり、賃金を低く抑えられたりするという第4の不公平が確かに存在する。しかし、それこそ、1947年施行の日本国憲法「第27条1項:すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」や1986年施行の男女雇用機会均等法に従って変えるべきなのである。 なお、④⑤⑫のように、この施策は、飲食業・観光業を中心にコロナ後も働き手が戻らず営業に支障が出ているため、人手不足に悩む企業が求めて労働時間を延長しやすくするために行うそうだが、人手不足に悩んでいるのなら、思い切って賃金を上げたり、正規雇用に変更したりするまたとない機会だ。そのための生産性向上のツールは出揃ってきており、日本人労働者が足りなければ外国人労働者を雇用すれば、誰にも迷惑をかけないばかりか、むしろ感謝される。 (3)気候変動と国土利用計画 1)気候変動について 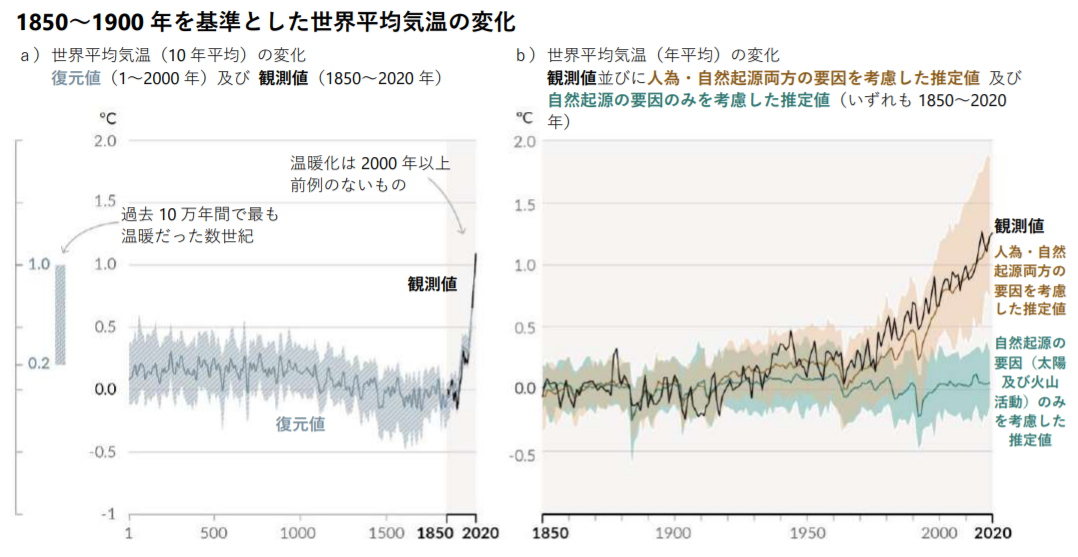 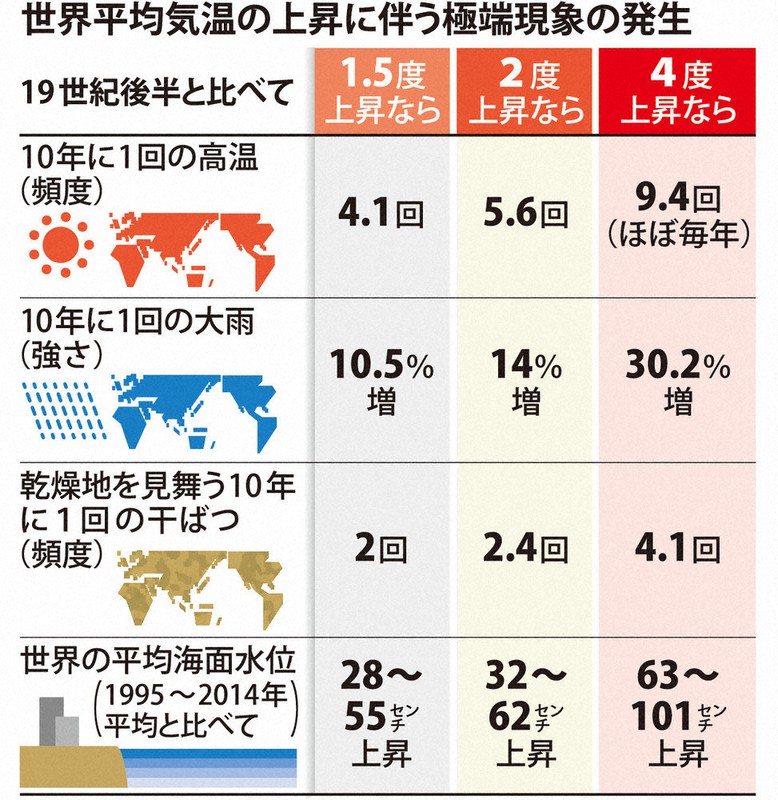 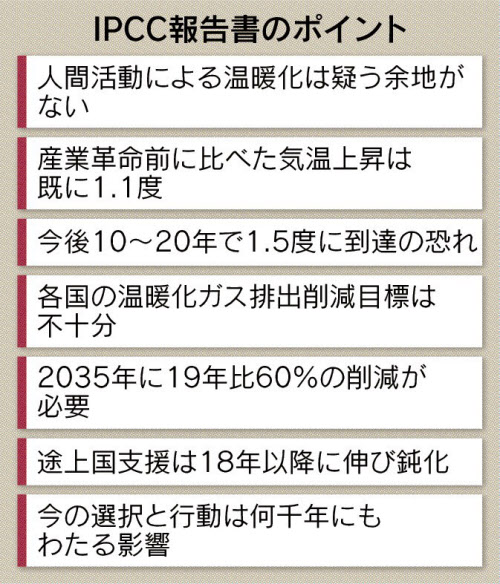 2021.10.27Amita 2023.3.21毎日新聞 2023.3.21日経新聞 (図の説明:左図のように、世界の平均気温は1850年以降に急速に上がり始め、特に高度経済成長期の1970~1980年以降の上昇が著しい。そのため、右図のように、IPCC報告書は「人間活動による温暖化は疑う余地がない」としている。そして、中央の図は、「世界平均気温上昇による極端な気象現象の発生回数が多くなる」としているが、まさにそのとおりになっている。しかし、今は極地の氷が残っているため、海水温の上昇はまだ緩やかに抑えられているのだ) 国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が、2023年3月、*3-1のように、第6次統合報告書をまとめ、温暖化対策の緊急性を強く訴えたそうだ。 内容は、①温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」は産業革命前に比べた地球の平均気温の上昇を1.5度以内に留める目標を掲げたが ②気温は既に1.1度上がって2030年代前半にも1.5度に達する ③そのため気温が目標を超える期間を短く留めて下降に向かわせることが重要 ④それには世界の温暖化ガス排出を2025年までに減少に転じさせ、2035年の世界の排出量を2019年比で約60%減らす必要 ⑤IPCCのホーセン・リー議長は対策の遅れがもたらす熱波や洪水などの被害拡大に警鐘を鳴らした 等である。 確かに、⑤のように、近年は世界で熱波・干ばつ・洪水などの異常気象による被害が拡大しているが、日本では、*3-2-1・*3-2-2に書かれているとおり、梅雨前線に暖かく湿った空気が大量に送り込まれて線状降水帯が発生し、それが停滞して集中豪雨となったり、観測史上最大の降水量となったりする頻度が増した。 これによって、川の氾濫・がけ崩れ・ダムの緊急放流が起こったり、それが終わったら観測史上最高の気温になったりもしているため、①②③④は喫緊の課題なのだが、日本政府は、目標なき妥協が多く、気候変動への対応を急いでいるようには見えないし、被害を最小にするための土地利用計画の見直しも行っていない。 2)国土利用計画について 1)サウジアラビアの未来都市 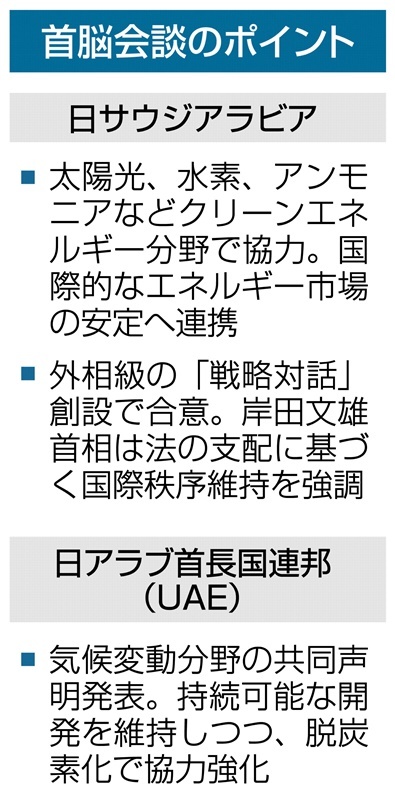   2023.7.19西日本新聞 「ザ・ライン」 2029年冬季アジア大会誘致地域 (図の説明:左図が、日本・サウジアラビアと日本・アラブ首長国連邦首脳会談のポイントだが、アンモニアをクリーンエネルギーの中に入れたことで、日本の意識の遅れがわかる。中央と右の図は、サウジアラビアが構想している未来都市だ) 岸田首相が訪問されたサウジアラビアは、*3-3-1のように、①世界最大の石油輸出国でも脱炭素時代を見据えた大改革を進め ②サウジ北西部砂漠地帯にスマートシティー(長さ170km、幅200m、高さ500m)「ザ・ライン」を建設中で ③これが一つの街になって将来は900万人が住み ④このスマートシティーは道路も車もなく高速鉄道で移動し ⑤石油ではなく再エネですべて賄い ⑥未開発の山岳地帯を会場に2029年冬季アジア大会を招致し ⑦岸田首相はサウジのムハンマド皇太子との会談で2016年合意の「日・サウジ・ビジョン2030」へのさらなる支援を表明し ⑧日本はクリーンエネルギー・脱炭素技術で協力し ⑨日本企業の投資への関心も高く、1ヵ月前に同行の呼びかけをしたが約30社集まった のだそうだ。 このうち①⑤は、未来を考えれば当然と言えるが、②③④の長さ170km・幅200m・高さ500mの砂漠地帯に一直線に建設されているスマートシティーは私の想像を超えるもので、i)人間の自然な欲求を満たさないと思うが、どうして一直線にするのか ii)どうして500mの高さが必要なのか iii) どうして道路も車もなく、高速鉄道で移動するのか iv) 2022年のサウジアラビアの人口は3,218万人だが、そのうち900万人をこのスマートシティーに住まわせるのか など疑問が尽きない。しかし、仮に海水面が60~100cm上がるとすれば、現在の平野部は海に沈む地域が多いため、都市の移転か建物による対応が必要になることは確かである。従って、⑥のように、未開発の山岳地帯を有効活用することも重要だろう。 また、⑦の日本がサウジアラビアに支援を表明するのは良いし、⑨の日本企業のサウジアラビアへの投資の関心が高いのも良いと思うが、その内容が、⑧の脱炭素技術協力と称してアンモニアの利用を推奨したり、中国の影響力を意識して負けずに接近するだけというのであれば、サウジアラビアとは桁違いに日本の構想は小さいと言わざるを得ない。 2)中国、深圳の未来都市 *3-3-2は、①中国広東省深圳西部の宝安を走る高速道路「G107」周辺の再開発に向けてドローン専用高速道路が提案され ②プロジェクトは「サステナビリティ」「テクノロジー」「グリーン建築」等をテーマに、ドローン・自動運転等の最先端テクノロジーと自然を融合させた近未来の都市を提示し ③排気ガスを出した12車線の高速道路は4車線ずつの2つの道路として筒状の空中トンネルに格納して大気汚染を解決し ④人々はその空中トンネルの上の緑の歩道を歩いて都市と自然が一体化した暮らしを実現し ⑤こうした環境に配慮したスマートシティ構想は深圳以外の世界中で進んでおり ⑥ドローンを活用した新たな空中物流インフラを構築できれば地上のトラック輸送・物流を大幅に削減でき、オフィスビルを貫くドローン専用高速道路が人々の目を引く ⑦ドローンが安全・効率的に飛び回って輸送インフラとしての機能を果たすには、ドローン輸送を前提とする都市計画が必要 等と記載している。 私も、⑥⑦のように、ドローンを安全・効率的に使用して物流改革を行うには、ドローンの通り道となる高速道路とドローン輸送を前提とする都市計画が必要だと考えていた。つまり、誤って落下しても、間違っても下を通る人や物の上に落下しない仕組みにすべきなのである。 また、①②③④⑤の排気ガスを出していた道路は、筒状の空中トンネルに格納しなくても、EVかFCVに置き変えれば排気ガスは出ない。それを筒状の空中トンネルに入れてしまえば、移動中に周囲の景色を見ることができなくなって、精神的にむしろマイナスだろう。また、道路を高架にして建物の中も通し、その高速道路の上をドローンが飛んで、人・車椅子・自転車などは緑豊かに都市計画された地上を歩いた方が良いと、私は思う。 しかし、ダイナミックにドローン専用高速道路等を提案し、そこから改良を重ねていくのも、長期的には無駄遣いにしかならない対症療法ばかりしているよりはずっと良い。 3)日本の未来都市は? ← みんなで考えよう 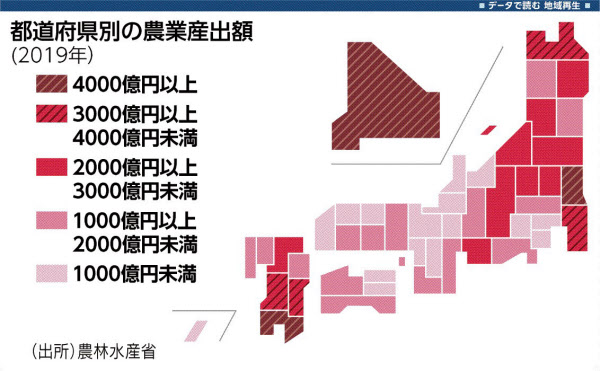 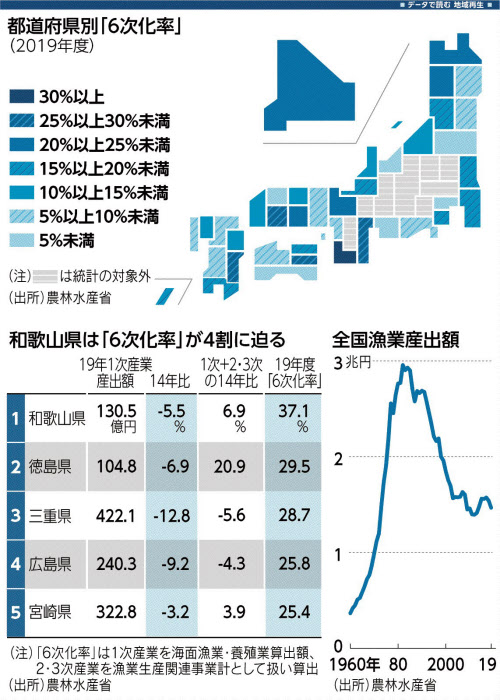 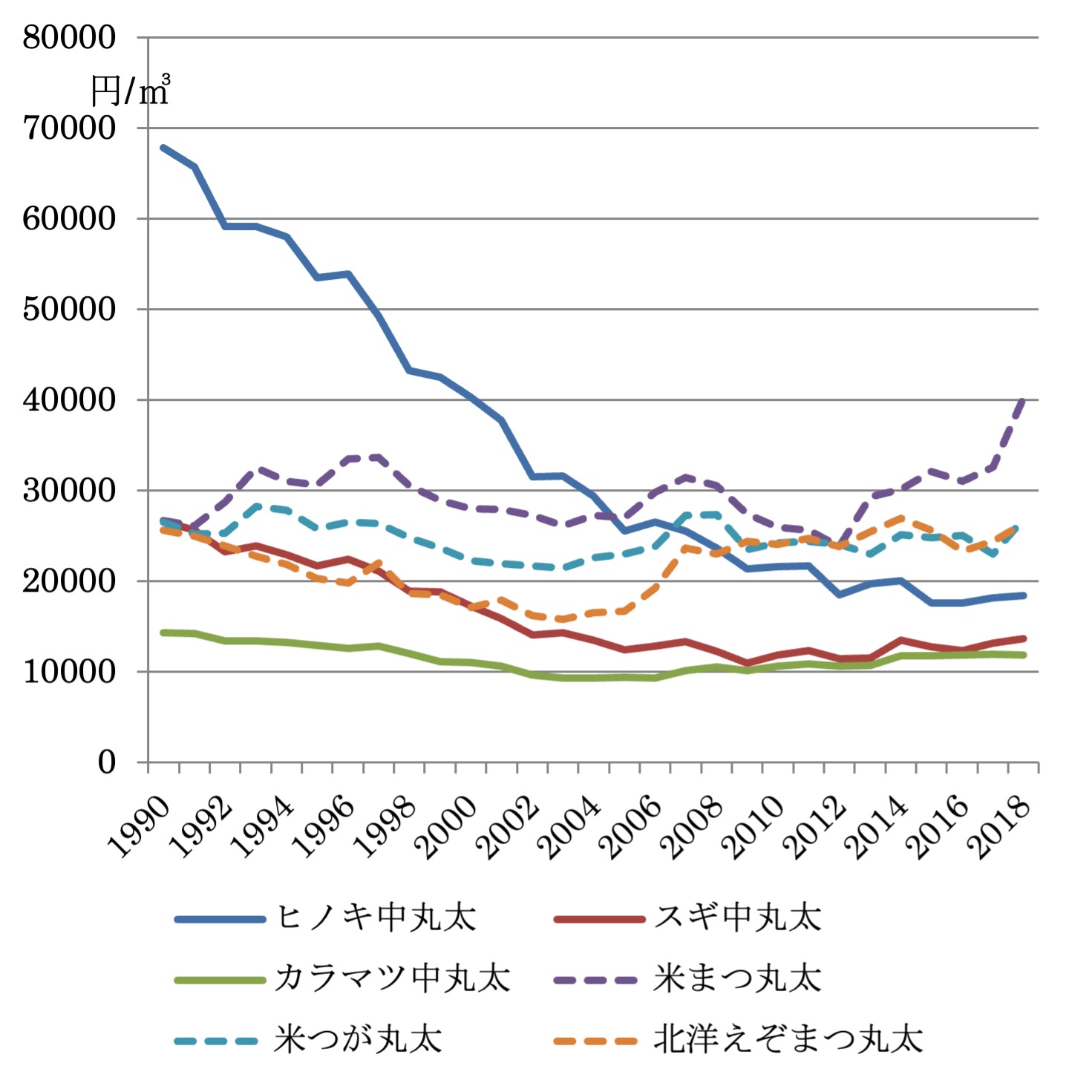 2021.8.14日経新聞 2021.11.6日経新聞 2021.9.7論座 (図の説明:左図のように、都道府県別農業産出額は北海道・栃木県・鹿児島県・青森県・千葉県・熊本県・宮崎県が頑張っている。また、中央の図のように、漁業産出額は1980年前後をピークに低下の一途を辿り、右図のように、林業も低迷しているが、これらは、日本政府が第1次産業を軽視してきた結果である。これによって、日本の食料自給率やエネルギー自給率は著しく低くなり、恵まれた国土を十分に活かすことなく、地方自治体の税収や自立力が低下している)   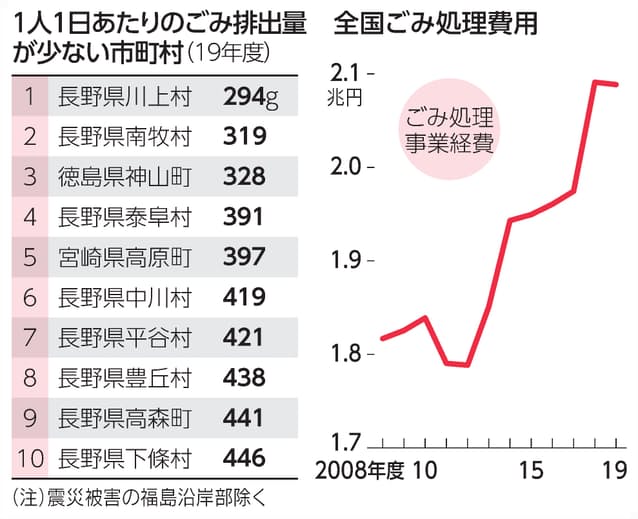 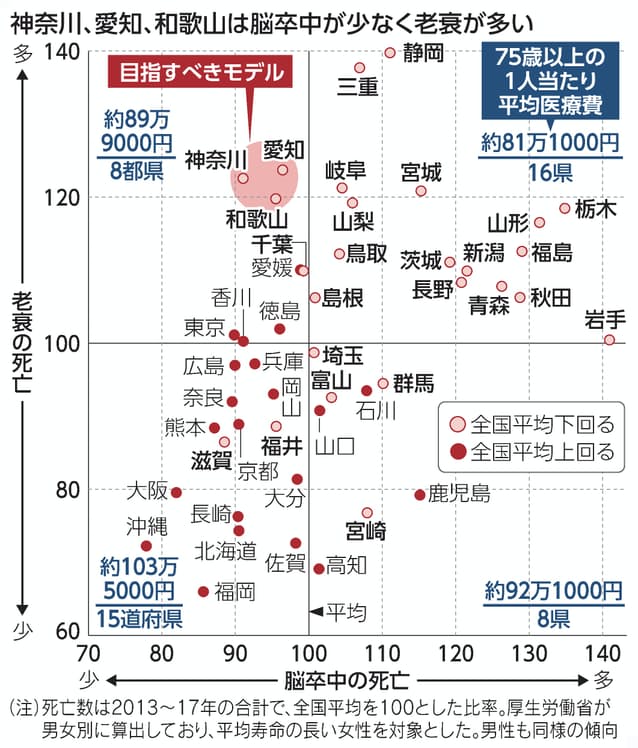 2021.7.2日経新聞 2021.7.10日経新聞 2021.5.21日経新聞 (図の説明:左図は、2009年と2019年を比較した場合の個人住民税の増減比較で、20%以上増加している県に沖縄県・宮城県・熊本県・北海道などの大都会以外も入っているが、正確に比べるには、法人住民税・事業税・地方消費税を加えた住民1人当たりの地方税収額の比較が必要だ。住民1人当たりの地方税収額を比較すると、法人の本社・工場がある地域の法人住民税・事業税が多く、そこで働く従業員等の個人住民税も多いため、その地域の地方税収が大きくなる。従って、既に国家資本を集中投下し、法人の本社・工場が多数存在する地域が潤沢な税収を得ることになるが、そういう地域は食料やエネルギーを殆ど生産していないと言っても過言ではない。また、中央の2つの図は、全国のごみ処理費用がうなぎ上りであるのに対し、1人あたりのごみ排出量が少ない市町村があるという話だが、そうなる理由が大切である。右図は、脳卒中が少なく老衰による死亡が多い都道府県で医療費が少ないという表だが、これに介護費を加えるとさらに著しい差が出る。しかし、「老衰」とされるものには、病気の見逃しや放置も含まれるため、少なくさえあればよいという見方は禁物だ) このような中、*3-3-3は、①戦後から今日まで東京圏へ人口・企業の集中 ②2022年都道府県別転入超過率は埼玉県0.35%・神奈川県(0.30%)・東京都(0.27%)・千葉県(0.14%)で、東京圏全体では10万人弱転入超 ③東京都の所得/人は575.7万円(19年度)で全国平均の約1.7倍で2位の愛知県366.1万円を引き離しており ④東京都の上場企業本社数(22年7月)は2122社で全国の約54% と記載している。 このうち①④については、上の図の下の段に書いたとおり、国家資本を集中的に投下した首都圏に企業の本社・工場が多数存在しており、その結果、②のように、生産年齢人口の勤労者が多く流入するため、③のように、東京都の所得/人は全国平均の約1.7倍と高くなり、この地域が潤沢な税収を得ることになるのである。 しかし、2019年の県庁所在地公示地価は、東京23区601,300円/㎡、名古屋183,100円/㎡、福岡150,100円/㎡、佐賀39,200円/㎡と著しく異なり、これは住居費のみならず、すべてのコストに反映されるため、東京都の生活コストは全国平均の約1.7倍どころではない筈だ。 また、*3-3-3は、⑤小中学生時点で東京圏以外に居住し調査時点で東京圏に居住する回答者は他のタイプと比べて所得水準が高く、人的資本水準の高い人材が経済合理的判断から都市に移動 ⑥近年、先進国で人口や産業の集中度と経済成長がマイナスないし非有意の関係となる研究が目立つ ⑦「労働年齢人口」の伸び率の低さは「1人当たり県内総生産」の伸び率の低さと関連 ⑧日本の地域及び全国の経済成長には社会移動だけでなく人口構造変化への対策が重要 とも記載している。 このうち⑤については、地域内で比較的人的資本水準の高い人材が都市に移動する傾向は確かにあるが、所得水準は同一勤務先の同一職階であれば同じ筈であるものの、女性にはガラスの天井(もしくは、コンクリートの天井)が用意されている上、高校の同窓生を優遇する習慣があるため、地方出身者は職階を上がるのも大変になるのだ。 また⑥については、先進国で人口や産業の集中度と経済成長がマイナスないし非有意の関係となるのは、既に人口や産業が集中しすぎているため、土地をはじめとするすべてのコストが上がっていて高コスト構造になり、中国はじめ新興国における生産コストにかなわないからである。 さらに、既存の都市にはまとまった空地が少ないため、サウジアラビアのように、未利用の砂漠や山岳地帯に未来都市を作るようなダイナミックな構造改革はできず、日本ではちょっと変えるのに数十年もかかることになる。そのため、首都移転したり、新しい産業都市を作ったりする先進国や新興国が多いのだ。 しかし、⑦の「『労働年齢人口』の伸び率の低さは『1人当たり県内総生産』の伸び率の低さと関連するから」といって、「高齢者は早く逝くことを推奨する」というのは、文明の進歩に逆行しており、先進国や福祉国家の名にも値しない。もし生産年齢人口が足りなければ、女性・高齢者の使用に加えて、生産年齢人口の外国人労働者も招けばよい。つまり、⑧の社会移動に、国内移動だけではなく、国際間移動を加えればよいのである。 *3-3-3は、⑨「まち・ひと・しごと創生法」は「地方創生」を国の重要な政策として位置づけ、自治体に様々な取り組みを求め、自治体が計画を立案して、国がその計画を支援する形だが ⑩自治体の自主財源比率が低く ⑪財政面での国と地方の関係も人口の東京一極集中を助長した ⑫地方版総合戦略策定にあたって多くの自治体が国からの地方創生関連交付金を基に東京都に本社がある業者に外部委託した ⑬税収の地域間格差が比較的少ない地方消費税率引き上げなどでの自主財源強化が検討に値する とも記載している。 このうち⑨⑫の地方版総合戦略策定に多くの自治体が、国からの地方創生関連交付金を基に、東京都に本社がある業者に外部委託したというのは、東京に本社のあるコンサルティング・ファームなら国内の他地域だけでなく海外の事例も容易に参照できるという点で優れているが、その地域の事情に詳しいわけではないため、地方自治体が主体となってコンサルティング・ファームや地域の大学を使うのがよいと思う。そして、それもできないのであれば、地域主体の地域創生などとてもできないため、⑪は仕方がないということになろう。 地方財政についても、⑩のように、自主財源比率が低すぎることはよくわかるが、⑬のように、地方消費税率を引き上げただけでは、大きな財源にはならない。そのため、農林漁業・再エネ発電・企業誘致など、地域の特色を活かして法人住民税・事業税及びそれにかかわる個人住民税を確保する必要がある。 なお、*3-3-3は、⑭町村などの過疎地域では既に高齢化が進み、実際の人口分布以上に地方議員の年齢階層が高齢者に集中し ⑮地域の現場で長期的展望に立って政策を進める若手政治家が不足 ⑯日本の地方議員は大企業で働く会社員や常勤公務員と比較して経済的に恵まれず、人口減少が進む町村で成り手不足が一層深刻化 ⑰勤め人が地方選挙に出る選択は、家族を養うこととの両立が難しく就労世代が政治に関わりにくい ⑱議員定数に年齢枠や女性枠を設ける「クオータ制」導入や地方議員の報酬増を検討すべき ⑲中長期的には東京以外にも様々な人材・産業が集積する拠点を整備する方向性が望ましい としている。 確かに、地方創生をこなし、教育・保育・医療・介護などの諸制度を的確に運用するには、地方議員の質と量が重要である。そのため、⑮ほど「若手でなければ、長期的展望に立てない」とは思わないが、⑭のように、人口分布に比例した男女比・年齢層になるのが多面的なニーズをくみ取るためには必要だと思う。 そのためには、⑯⑰は事実であるため、⑱のように、地方議員定数に年齢枠や女性枠を設けたり、議員の報酬増を検討したりすることは不可欠である。しかし、それにもまして重要なのは、くだらないことで誹謗中傷したり、足を引っ張って喜んだりするのも止めることで、そうでなければ有用な人材を議員にして住民のために継続的に働いてもらうことはできない。 最後に、⑲については、過密で高コスト構造で不便になった東京以外の地域にも、中長期的視点で産業や人材が集積する場所を作ることは重要である。それには、自然条件・災害・気候変動・海面上昇なども考慮して、これまでは人口の少なかった地域に首都機能を移転したり、スマートシティーを作ったりするのが、恵まれた国土を無駄なく使う方法であると、私は考える。 ・・参考資料・・ <日本経済の現状 ← 経常黒字半減・物価上昇・実質賃金減少> *1-1-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1065635 (佐賀新聞 2023/7/4) 税収過去最高 家計の苦境に目を向けよ 国の2022年度の一般会計税収が、71兆1373億円と過去最高を記録した。円安の重なった物価高で消費税が増え、所得税、法人税も伸びたためだ。防衛費や少子化対策に多額の追加歳出を計画する岸田文雄首相にとっては、政権運営の好材料かもしれない。しかし税収増は家計の苦境の裏返しであり、さらなる負担は受け入れ難い点に目を向けねばならない。政府の当初予算時点の税収見積もりは65兆2350億円だった。70兆円台は初めてで、3年続けて過去最高を更新した。税収を押し上げた大きな要因は物価上昇だ。22年度の消費者物価指数は、石油や輸入原材料の高騰に円安が拍車をかけ、前年度比3・2%と約30年ぶりの伸びとなった。値上がりは食品から電気・ガス、サービス関連にまで及び、連動して消費税額も膨らんだ結果、22年度の消費税収は過去最高の23兆792億円に達した。19年10月に税率を10%へ引き上げた効果などが続き最高だった前年度に比べ、約1兆2千億円も多かった。景気に左右されにくい一方で、物価の影響を受けやすい消費税の特徴が表れた形だ。税収の確かさから、社会保障を支える消費税の役割を再認識することができよう。だが消費税収の好調を喜んではいられない。家計にしてみれば、物価上昇に課税増のダブルパンチとなったからだ。新型コロナウイルス禍からの経済回復があり単純比較はできないものの、前年度からの増収分は0・5%程度の税率引き上げに匹敵する。消費税は所得の低い世帯ほど負担感の重い「逆進性」がある点を考えれば、家計の重荷は深刻ととらえるべきだろう。基幹税では所得税も22年度は伸び、前年度より1兆円超多い22兆5216億円だった。物価高に伴う賃上げや、企業から株主への配当増が税収につながったとみられる。ここで留意すべきは十分な賃上げが大企業などに限られ多くの人は収入増がインフレに追い付かない状況である。物価動向を反映した実質賃金は、4月まで13カ月連続で減少している。22年度はコロナ禍からの立ち直りや円安による輸出企業の業績上振れで、法人税も14兆9397億円と増収だった。物価高が収まらない中で、配当など株主還元に比べて見劣りする賃上げの充実が引き続き課題である。岸田政権による血税の使途と財政運営が厳しく問われるのは当然だ。税収増の結果、22年度は2兆6294億円の決算剰余金が生じた。政府は防衛力強化の財源の一つに年7千億円の剰余金を想定しているが、多額の剰余金の発生は、もう一つの財源であり与党に抵抗感の強い増税の先送り論につながる可能性があろう。しかし議論すべきは「先送り」でなく、今以上の家計負担が困難な点である。防衛増税を実施するにしても課税余地のある企業向けを軸にすべきだし、財源に不安のない規模へ防衛費を縮減するのが理にかなっている。税収増を受け政府、与党で歳出拡大の声が高まることも戒めたい。今年の「骨太方針」はコロナ沈静化を受けて歳出を「平時に戻していく」と明記。国と地方を合わせた基礎的財政収支を25年度に黒字化する財政健全化の目標を維持した。歳出増はその方針を揺るがしかねない。 *1-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230701&ng=DGKKZO72407730R00C23A7EA1000 (日経新聞社説 2023.7.1) 政府税調まで消費税論議から逃げるのか 中長期を見据えた税制の提言というには、看板倒れの内容だ。政府税制調査会(首相の諮問機関)が4年ぶりにまとめ、岸田文雄首相に提出した「中期答申」のことだ。前回の10倍の約260ページの分量ながら、増減税など具体的な改革の方向性を何ら示さなかった。答申を受け取る立場の岸田首相が少子化対策の財源を巡り、消費税などの議論を封印している。だが、各界の有識者から税制の将来について率直な意見を集める政府税調は、政治への忖度(そんたく)と一線を画すべきだ。逃げ腰と言わざるを得ない。中期答申は昭和・平成時代の税制改革を回顧し、最近の経済と社会の構造変化を総括した。終身雇用や専業主婦世帯が主体と考えられた旧態から働き方や人生設計が多様となり、デジタル化やグローバル化が進む。税制も経済成長を促す発想で組み直す必要がある。新型コロナウイルス対策などで悪化した財政の立て直しにも目配りが欠かせない。政府税調は「公平・中立・簡素」の原則に加えて、税の「十分性」の重視を掲げた。社会保障や財政の持続可能性にも配慮し、負担や歳出を見直すことは妥当といえる。だが、個別の税制をどう変えるかの記述はない。消費税に関しては社会保障給付を安定的に支える観点で「果たす役割は今後とも重要」とだけ記した。税調では現行10%からの引き上げが必要とする議論も出ていたが、答申は税率や時期などの具体論を避けている。所得税を巡っては働き方の違いで不公平が生じないよう、給与や退職金、年金への税負担のバランスをとるよう促した。そこは適切な指摘としても、具体的な手法への言及はない。「基幹税としての財源調達機能を適切に発揮する」と、原則論の確認にとどまる。税制改正の具体像を決めるのは政治家であり、中期答申は議論の下地となる考え方を提示するというのが政府税調の認識という。問題は、政治が与野党そろって、次の選挙に影響するとして税や社会保険料など安定財源の確保で真剣な議論から逃げていることだ。財源を曖昧に給付だけを増やすのは将来世代に対して無責任だ。専門家の立場から将来の負担のあり方で見識を示し、踏み込んだ議論を喚起する。それが政府税調に求められる役割ではないか。問題先送りを続ける政治に、あえて歩調を合わせる必要は全くない。 *1-1-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230702&ng=DGKKZO72416970R00C23A7EA1000 (日経新聞社説 2023.7.2) 医療費の物価反映は慎重に 年間45兆円に上っている医療費が物価高を反映させる形で一段と膨らむ可能性が出てきた。政府が6月に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に「次期診療報酬改定で必要な対応を行う」と明記された。物価高で医療機関の経費が増えているのは確かだが、医療費を増やせば、患者負担や国民の保険料負担が重くなることを軽く見るべきではない。政府は医療の持続性を確保する観点から、丁寧かつ慎重に対策を検討してほしい。保険医療は診療報酬という政府が定める公定価格で提供されるので、医療機関や薬局は光熱費や設備費、委託費など経費の増加分を患者の医療費に転嫁できない。2022年4月に改定された今の診療報酬にはその後の物価上昇分が勘案されていないため、日本医師会などは23年度中に補助金で緊急措置を実施した上で、24年4月の次期改定で物価水準を反映するよう求めている。賃上げが重要なのは医療従事者も例外ではない。ただその原資や経費の増加分すべてを診療報酬の増額で賄う考え方で国民の理解を得られるだろうか。産業界の労使交渉では賃上げと生産性向上をセットで議論するのが一般的だ。医療従事者の賃上げを考える際も、業務効率化の方策を同時に検討すべきだ。岸田文雄政権は社会保障などの改革で国民負担を抑制し、新たな少子化対策に要する負担増分を相殺する方針を閣議決定している。この施策との整合性を考えても、国民負担を増やす診療報酬の増額は安易に行うべきではない。医療従事者の賃上げにはデータに基づく議論も必要だ。医師や看護師、事務員など職種別給与データの提出を医療法人に求め、処遇実態を把握した上で賃金水準のあり方を検討してほしい。新型コロナウイルス対策の病床確保料などで医療機関の収支が改善した点にも留意が要る。物価反映が国民の理解を得るにはプロセスを踏んだ議論が欠かせない。 *1-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230516&ng=DGKKZO71023830V10C23A5EP0000 (日経新聞 2023.5.16) 企業物価上昇、なお5%台、4月、食品などで価格転嫁続く 資源高・円安の影響は一服 日銀が15日発表した4月の企業物価指数は前年同月比5.8%の上昇だった。伸び率は4カ月連続で鈍化し、1年8カ月ぶりに5%台まで低下した。資源高や円安の影響が和らいだことで、市場には「今夏には5%を割る」との見方もある。ただ食品などの川下の品目での価格転嫁は当面続きそうだ。輸入物価指数(円ベース)は2年2カ月ぶりに前年同月比でマイナスになった。足元で円相場は1ドル=136円程度で推移しており、円安の直接的な押し上げ圧力には一服感が出ている。輸入物価指数の石油・石炭・天然ガスはマイナス9.0%、金属・同製品もマイナス7.5%になった。電力やガス料金には2月以降、政府の価格抑制策が効いている。企業物価指数の電力・都市ガス・水道の前年同月比上昇率は、25.8%と3月の26.8%から鈍化した。日銀によれば抑制策で0.7%程度、企業物価指数全体の前年同月比上昇率を押し下げている。SMBC日興証券の宮前耕也シニアエコノミストは「早ければ(企業物価指数の前年同月比上昇率が)6月に5%台を割り込む可能性がある」と話す。ただこれまでのコスト高を受け、「複数回に分けて値上げに踏み切る企業もあり価格転嫁による押し上げ圧力は継続している」と指摘する。輸送用機器や生産用機器では、部品などの材料価格や物流費の上昇を価格に反映する動きが目立った。飲食料品は小麦などの原材料高を価格転嫁する動きが続いている。鉄鋼もこれまでのエネルギーコスト高が影響し前年同月比で上昇した。政府の抑制策で価格が抑えられている一方、事業用電力では燃料価格の上昇や託送料金の引き上げなどを価格に反映する動きもみられた。日銀は「コスト上昇分も含めた川下への価格転嫁の動きなどを注視していく」としている。4月分は公表されている品目のうち8割超で価格が上昇した。足元では消費者物価指数(CPI、生鮮食品を除く)でも前年同月比3.1%上昇と高水準での推移が続く。企業物価指数はCPIの先行指標ともされる。高止まりが続けば、CPIにも上振れの要因として波及しやすくなる。日銀は物価上昇率が23年度半ばには2%を下回るとの見方を示している。植田和男総裁は「(2%の物価目標を達成すると)安心して言えるところまで到達していない」として大規模緩和を維持する方針だ。価格転嫁が継続してCPIを押し上げれば、先行きの物価動向や政策運営にも影響を与える可能性がある。 *1-2-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2274H0S3A620C2000000/ (日経新聞 2023年6月23日) 消費者物価、5月3.2%上昇 食品や宿泊が伸び高止まり 総務省が23日発表した5月の消費者物価指数(CPI、2020年=100)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が104.8となり、前年同月比で3.2%上昇した。プラスは21カ月連続で、高水準での推移が続く。食品といった生活必需品や宿泊料の値上がりが全体を押し上げ、物価上昇の品目も増えた。QUICKが事前にまとめた市場予測の中央値の3.1%を上回った。再生可能エネルギー発電促進賦課金の引き下げや燃料価格の下落があった電気代が押し下げ、4月の3.4%からは伸び幅が縮小した。日銀の物価目標である2%を上回る状況が続く。生鮮食品を含む総合指数は3.2%上昇した。生鮮食品とエネルギーを除く総合指数は4.3%上昇し、プラス幅が前月から0.2ポイント拡大した。伸びの拡大は12カ月連続となる。第2次石油危機の影響で物価が上昇した1981年6月の4.5%以来41年11カ月ぶりの高い上昇率となった。品目別では生鮮食品を除く食料が9.2%プラスだった。75年10月の9.9%以来47年7カ月ぶりの上昇幅となる。原材料価格や物流コストの上昇で、アイスクリームが10.1%上昇した。4月に価格改定のあったヨーグルトも11.3%伸びた。日用品も値上げが続き洗濯用洗剤が19.9%上がった。宿泊料は9.2%伸びた。政府の観光支援促進策「全国旅行支援」の効果が続く一方で、新型コロナウイルス禍からの経済社会活動の正常化で観光需要が増えて価格が上昇した。17.1%マイナスだった電気代を中心にエネルギーは8.2%低下した。都市ガス代も1.4%上昇と4月の5.0%プラスから伸びが縮小した。総務省の試算では、電気・都市ガス料金の抑制策と全国旅行支援をあわせた政策効果は、生鮮食品を除く総合の前年同月比伸び率を1.0ポイント押し下げた。単純計算すると、政策効果がなければ前年同月比で4.2%の上昇だったことになる。生鮮食品を除く総合を構成する522品目のうち前年同月より上がったのは438品目、変化なしは43品目、下がったのは41品目だった。4月は433品目が上昇しており、物価上昇の裾野が広がっている。日本経済研究センターがまとめた民間エコノミスト36人の予測平均では4〜6月期の生鮮食品を除く総合の前年同期比が3.24%プラスで、前回調査から0.31ポイント引き上げた。2024年4〜6月期も同2.01%伸びると予測する。足元では再び進行する円安が輸入価格の上昇圧力にもつながり、物価は高止まりが続く可能性がある。 *1-2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230703&ng=DGKKZO72422720T00C23A7NN1000 (日経新聞 2023.7.3) 食品・日用品の大手値上げ、中堅に波及 店頭価格8.7%上昇、原材料高の転嫁広がる 食品や日用品の店頭価格の上昇が続いている。POS(販売時点情報管理)データに基づく日次物価の前年比伸び率は6月28日時点で8.7%となった。昨年秋以降、業界大手を中心に価格改定に踏み切り、中堅企業などが追いかける「追随型値上げ」が多くの商品で広がっている。デフレが長く続く日本では値上げで売り上げが落ち込むリスクが強く意識され、価格転嫁を避ける傾向があった。ウクライナ危機をきっかけに原材料高を商品価格に反映する動きが広がり、潮目が変わりつつある。日経ナウキャスト日次物価指数から分析した。この指数はスーパーなどのPOSデータをもとにナウキャスト(東京・千代田)が毎日算出している。食品や日用品の最新のインフレ動向をリアルタイムに把握できる特徴がある。217品目のうち価格が上昇したのは199品目、低下は16品目だった。ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年2月に価格が上昇していたのは130品目にとどまっていた。全体の前年比伸び率も当時は0.7%だった。足元ではヨーグルトや冷凍総菜などの値上げ幅が拡大している。ヨーグルトの値段は22年夏までほぼ横ばいだったが、11月に6%上昇し、今年4月以降はその幅が10%となった。この2回のタイミングでは業界最大手の明治がまず値上げを発表し、森永乳業や雪印メグミルクなどが続いた。その結果、江崎グリコなどシェアが高くないメーカーも値上げしやすい環境になり、業界に波及した。冷凍総菜も昨年6月は4%程度の上昇率だったが、11月に9%まで加速し、23年6月は15%まで上がった。味の素冷凍食品が2月に出荷価格を上げたことが影響する。ナウキャストの中山公汰氏は「値上げが大手だけでなく中堅メーカーに広がっている」と話す。ナウキャストによると、値上げをしてもPOSでみた売上高は大きく落ちていないメーカーもみられる。インフレが定着しつつあり、値上げによる客離れがそこまで深刻化していない可能性がある。品目の広がりも鮮明だ。ウクライナ侵攻が始まった直後は食用油が15%、マヨネーズが11%と、資源価格の影響を受けやすい商品が大きく上昇する傾向にあった。23年6月は28日までの平均で生鮮卵が42%、ベビー食事用品が26%、水産缶詰が21%の上昇になるなど幅広い商品で2ケタの値上げがみられる。日本は米欧に比べて価格転嫁が遅れ気味だと指摘されてきた。食品価格の上昇率を日米欧で比べると米国は昨年夏に10%強まで加速したが、足元は6%台に鈍化した。ユーロ圏は今年3月に17%台半ばまで高まり、5月は13%台に鈍った。日本は昨夏が4%台半ば、昨年末は7%、今年5月に8%台半ばと上げ幅が徐々に高まってきた。直近では瞬間的に米国を上回る伸び率になった。帝国データバンクが主要食品企業を対象に調査したところ7月は3566品目で値上げが予定されている。昨年10月が7864件と多かったが、その後も幅広く価格改定の表明が続く。昨年、一時的に10%を超えた企業物価指数は足元で5%台まで伸びが鈍化しており、資源高による川上価格の上昇は一服しつつある。それでも昨年からの仕入れ価格上昇や足元の人件費増を十分に価格転嫁ができているとは限らず、値上げに踏み切るメーカーは今後も出てくると予想される。日本のインフレも長引く様相が強まっている。 *1-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230606&ng=DGKKZO71652180W3A600C2MM0000 (日経新聞 2023.6.6) 4月実質賃金、3%減 13カ月連続マイナス 物価高続く 厚生労働省が6日発表した4月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所)によると、1人当たりの賃金は物価変動を考慮した実質で前年同月比3.0%減った。減少は13カ月連続となる。名目にあたる現金給与総額は1.0%増の28万5176円だった。物価の伸びに賃金上昇が追いつかない状態が続いている。実質賃金のマイナス幅は3月の2.3%減から広がった。実質賃金の算出で用いる物価(持ち家の家賃換算分を除く総合指数)の上昇率が4.1%に達しており、3月の3.8%から拡大した影響が出た。現金給与総額の増加は22年1月から続いており、16カ月連続となる。新型コロナウイルス禍からの経済活動の正常化に伴う動きだ。現金給与総額のうち、基本給にあたる所定内給与は1.1%増、残業代などの所定外給与は0.3%減だった。今年の春季労使交渉では物価高を背景に賃上げ率は30年ぶりの高水準となっている。4月の速報段階では「まだ交渉中の労使があることなどから結果が十分に反映されていない」(厚労省)という。就業形態別に現金給与総額を見ると、正社員など一般労働者は1.1%増の36万9468円、パートタイム労働者は1.9%増の10万3140円だった。1人当たりの総実労働時間は0.3%減の141.0時間だった。業種別では不動産・物品賃貸業が14.3%増となったほか、飲食サービス業も6%を超える伸びだった。 *1-3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230606&ng=DGKKZO71652190W3A600C2MM0000 (日経新聞 2023.6.6) 消費支出、4月4.4%減 2カ月連続マイナス 総務省が6日発表した4月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万3076円と、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比4.4%減少した。マイナスは2カ月連続。食料、通信など生活関連の品目や教育への支出が減り、消費を押し下げた。下落幅は21年2月の6.5%減以来2年2カ月ぶりの大きさとなった。 <G7とジェンダー平等> *2-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15670995.html (朝日新聞 2023年6月26日) 賃金、男女格差「解消を」 性的少数者尊重も言及 G7担当相声明 主要7カ国(G7)男女共同参画・女性活躍担当相会合が24、25日に栃木県日光市で開かれ、企業の女性役員登用や成長分野への就業を進め、賃金格差を解消することで女性の経済的自立を進める方向で一致した。ジェンダー平等で遅れる日本にとって、議論を踏まえた取り組みが急がれる。男女間の賃金格差はG7共通の課題で、共同声明は「是正には包括的アプローチが必要」と強調。女性役員の登用▽成長分野や報酬の高い分野への女性の労働移動の促進▽女性の起業支援――などを具体策で示した。また、家事や育児、介護など女性に偏る無償労働は「女性がフルタイムで働く能力や指導的地位に就く能力を損なう」と指摘。家族への公的支援を強化するほか、男性の無償労働への参加を増やすための施策を求めた。今月公表された各国の男女格差を数値化した「ジェンダーギャップ報告書」で、日本は146カ国中125位。男女間の賃金格差は22・1%、企業(東証プライム上場)の女性役員の比率は11・4%でともにG7各国では最下位。無償労働時間は女性が男性の5・5倍長く、男女差はG7で最大との統計もある。会合の議長を務めた小倉将信・男女共同参画相は今後の対応について、会見で「女性起業家の支援などを着実に進める。男性の家事育児への参画促進のための施策に取り組みたい」と述べた。会合に参加した他国の担当相や団体の代表者9人はすべて女性。日本だけが男性だったことについて、小倉氏は「女性だけが主張しても実現しえない。非常に強い熱意を持つ男性リーダーが一緒に行動を起こさないと実現しない、というのが共通認識だった」とした。また、共同声明では性的少数者に関して、女性や「LGBTQIA+(LGBTを含めた多様な性)の人々の人権と尊厳が完全に尊重され、促進され、保護される社会の実現に向けた努力を継続する」とした。LGBT法連合会の神谷悠一事務局長は「LGBTQIA+の問題がジェンダーの課題であると強力に示された。政府は今後、国内での平等に向けた取り組みを具体的に進めていくべきだ」と話した。 *2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230621&ng=DGKKZO72075270R20C23A6MM0000 (日経新聞 2023.6.21) 男女平等、日本125位 過去最低 政治や経済分野悪化 世界経済フォーラム(WEF)は21日、男女平等がどれだけ実現できているかを数値にした「ジェンダー・ギャップ指数」を発表した。調査した146カ国のうち、日本は過去最低の125位だった。政治や経済分野での指数が悪化し、前年調査(116位)より順位を落とした。主要7カ国(G7)では最低水準となった。調査は「経済」「教育」「健康」「政治」の4分野で男女平等の現状を指数化している。完全に実現できている場合は1、まったくできていない場合をゼロとして各分野ごとに指数化し、総合評価のランキングを毎年発表している。日本の順位を分野別にみると「政治」が138位、「経済」が123位となった。改善の必要性が長年指摘されている両分野で指数が悪化した。国内での教育格差が相対的に小さいことや、男女の健康に大きな差がないと判断されたことから「教育」は47位、「健康」は59位となった。日本の評価が特に低いのは政治における男女平等だ。女性の議員数や閣僚数が他の国・地域と比べて大幅に少ないことに加え、これまでに女性の首相が誕生していないことなどが指数や順位に織り込まれた。女性の権利を制限していると指摘されるサウジアラビア(131位)を下回り、世界で最も低い圏内にある。経済の項目でも低い評価が目立つ。女性管理職の比率が低いことや、男女の所得に依然として差があることなどが響いた。政府は東証プライム市場に上場する企業の女性役員の比率を2030年までに30%以上にする目標を新たに掲げ、多様性の確保を急ぐ。WEFは教育における日本の男女平等は99%以上達成できていると分析した。ただ、今回は大学以上の進学率が加わったことで、順位は47位と前年(1位)から大きく下がった。全体の順位が下がった一因にもなったと考えられる。総合評価が高かったのはアイスランドやノルウェー、フィンランドなどだ。アイスランドでは男女平等の達成率が90%を超えた。最下位はアフガニスタンだった。WEFは世界で男女平等が実現されるのは131年後の2154年だと試算する。男女平等の度合いは新型コロナウイルス感染拡大前の水準までには回復した一方で、「進展のペースは鈍化している」としている。 *2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230622&ng=DGKKZO72100240S3A620C2EA1000 (日経新聞 2023.6.22) 男女平等、達成率68% 政治・経済の壁なお 世界の格差指数 日本、過去最低の125位 世界経済フォーラム(WEF)が21日発表した2023年の男女平等の度合いを示すジェンダー・ギャップ指数で、日本は146カ国中125位と過去最低になった。政治分野の低さが変わらず、経済分野は女性管理職比率の低さが足を引っ張る。世界全体でも格差はなお残り、WEFはこの差を埋めるにはあと131年必要だと指摘する。調査は経済、教育、健康、政治の4分野に関する統計データから算出する。男女が平等な状態を100%とした場合、世界の達成率は68.4%。WEFは現状では世界での男女平等実現は2154年になると指摘する。格差が目立つのは経済、政治の両分野。差を埋めるには経済で169年、政治で162年かかるという。国別にみると、首位は14年連続のアイスランドで91.2%。日本は64.7%、最も低い146位のアフガニスタンは40.5%だ。地域別では欧州や北米が高く、WEFは東アジア・太平洋地域の歩みが10年以上停滞しているとみる。ニュージーランドなどは上位だが、韓国(105位)や中国(107位)などは課題を抱える。リポートでは労働人口に占める女性の割合が4割を超す一方、上級指導職の女性割合が10ポイント近く低い点も指摘。昇進を阻む「ガラスの天井」が依然存在するとした。日本も政治(138位)や経済(123位)の低さが目立つ。経済は女性管理職の比率が133位にとどまるのが大きく影響している。働く女性がリーダー層になるにつれ減る構造がある。23年版男女共同参画白書によれば、日本の就業者に占める女性の割合は45%で米国(46.8%)と大差なく、韓国(43.2%)より高い。だが管理職に占める女性比率は12.9%で米国(41.0%)を下回り、韓国(16.3%)より低い。民間企業の場合、係長級で24.1%いる女性が課長級で13.9%、部長級は8.2%に減る。キャリアの階段が細くなる背景に何があるか。ロールモデルが身近にいないことや硬直的な働き方、家事・育児負担の偏りなどが指摘されるが、そのままでは企業の成長は期待できない。政府は女性活躍・男女共同参画の重点方針(女性版骨太の方針)で、東証プライム上場企業は25年をめどに女性役員を最低1人起用、女性役員比率は30年までに30%以上の目標を掲げる。ヒントはある。キリンホールディングスは入社後10年ほどまでに多くの業務を担当し、プロジェクトリーダーなどに挑戦する「早回しキャリア」で女性管理職育成を急ぐ。各段階で切れ目なく支援をし、「管理職手前」の層を厚くする。結果的に改善への早道になる。経済で多様性がイノベーションを生むのはすでに世界の共通認識だ。投資家は組織の意思決定者に多様性を求め、取締役会が男性ばかりの日本企業にノーを突きつける。ジャパン・インターカルチュラル・コンサルティングのロッシェル・カップ社長は「欧米に比べて日本は政策や慣行、法律などを変えるのに消極的だ。リーダーは具体的な行動を起こす必要がある。現状維持優先の態度はますます遅れにつながる」と強調する。 *2-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA128CD0S3A610C2000000/ (日経新聞 2023年6月13日) 女性役員比率30%目標に 政府「女性版骨太の方針」決定 政府は13日、女性活躍・男女共同参画の重点方針(女性版骨太の方針)を決定した。東証プライム市場へ上場する企業に2025年をめどに女性役員を最低1人選任するよう促す。女性役員比率を30年までに30%以上とする目標も盛り込んだ。いずれも努力義務で罰則は設けない。岸田文雄首相は同日の女性活躍と男女共同参画に関する会議で「全ての人が生きがいを感じられ、多様性が尊重される持続的な社会の実現のため取り組みを進める」と述べた。近くまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に反映する。目標達成のためプライム上場企業に行動計画をつくるよう推奨する。年内に東証の上場規則に数値目標に関する規定を設けることを想定している。東証プライム上場で女性役員比率が30%を超える企業は22年7月末時点で2.2%にとどまる。女性役員が1人もいない企業の比率は18.7%だった。優良なスタートアップ企業に占める女性起業家の比率を33年までに20%以上とする目標も掲げた。「Jスタートアップ」と呼ばれる新興企業が対象で、経済産業省を中心に23年5月時点で選定した238社の女性起業家比率は8.8%だった。 *2-5:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1062235 (佐賀新聞 2023/6/28) 年収の壁、企業助成50万円、従業員の保険料穴埋め、年内にも 配偶者に扶養されるパート従業員が、社会保険料負担の発生を避けるため働く時間を抑える「年収の壁」に関する政府の対策案が分かった。保険料を穴埋めする手当を払った企業に対し、従業員1人当たり最大50万円を助成。従業員の負担解消につなげ、労働時間を延長しやすくすることで人手不足緩和を狙う。関係者が28日明らかにした。飲食業や観光業を中心に、新型コロナウイルス禍後も働き手が戻らず、営業に支障が出ている所もある。個人の収入確保とともに、経済を円滑に回す環境整備を進める。政府内の調整を経て最終決定し、年内にも対策を開始。時限措置とする。「年収の壁」見直しは人手不足に悩む企業側が求め、岸田文雄首相が2月に「対応策を検討する」と踏み込んだ。抜本的な対策は先送りし、2025年の法案提出を目指す年金制度改革の中で議論する。現在は、従業員101人以上の企業で働くパートの場合、年収106万円以上になると配偶者の扶養を外れる。厚生年金などの保険料を自ら負担し、手取りが減る。扶養されている間は国民年金の「第3号被保険者」として、保険料を払わず、将来の年金が受け取れる。対策案では、所定労働時間の延長などで生じた保険料の全部または一部を、企業が手当として従業員に払うことができる仕組みをつくる。手当は賃金に含めない特別扱いとし、手当による保険料増は生じない。手当の仕組みを後押しするため、政府は既存の助成金を拡充し、1人当たり最大50万円を企業に支給。手当や賃上げ原資、企業が負担する社会保険料に充ててもらう。基本給を増やしたかどうかで助成額が変動する。扶養に入っている従業員だけでなく、単身者も対象とする。企業が3年以内に労働時間を延長する計画を策定し、実際に延長した従業員も助成対象に加える。年収の壁 会社員や公務員の扶養に入る配偶者がパートなどで働くと、一定以上の年収で社会保険料が発生したり税の優遇が小さくなったりする。この額の境目が「壁」と呼ばれる。保険料の場合、勤め先の従業員数規模などに応じて106万円や130万円が境となり、手取りが減る。106万円の壁では、年収が約125万円になると手取りが106万円に戻る。税は、年収が150万円を超えると所得税の配偶者特別控除の満額を受けることができない。 <気候変動と国土利用計画> *3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230326&ng=DGKKZO69601710V20C23A (日経新聞社説 2023.3.26) IPCC報告が示す温暖化対策の緊急性 温暖化による気象災害や食料危機、紛争などの悪化を防ぐための時間は、わずかしか残されていない。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がまとめた第6次統合報告書は、温暖化対策の緊急性を強く訴えた。報告書は気候変動をめぐる今後の国際交渉の土台となる。日本は主要7カ国(G7)議長国として真剣に受け止め、中国を含む20カ国・地域(G20)とも連携して対策を加速する必要がある。温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」は、産業革命前に比べた地球の平均気温の上昇を1.5度以内にとどめる目標を掲げる。だが、報告書によると気温は既に1.1度上がっており、2030年代前半にも1.5度に達する可能性がある。気温が目標を超える期間を短くとどめ、下降に向かわせることが重要だ。それには世界の温暖化ガス排出を25年までに減少に転じさせ、35年の世界の排出量を19年比で約60%減らさねばならないという。パリ協定のもと、各国は25年までに35年の新たな削減目標を提示することになっている。報告書の数値は重要な指標となろう。日本の現行目標は30年度の排出量を13年度比で46%減らし、50%減をめざすというものだ。国際社会から一層の上乗せを求められる可能性がある。見直しの検討を怠ってはならない。報告書は21年10月までのデータに基づいており、ロシアのウクライナ侵攻の影響は含まない。現実にはエネルギーの安定供給を確保するため、化石燃料の利用減を先延ばしする動きもある。石炭火力発電への依存度が高いアジアの途上国などでは、再生可能エネルギーへの転換や省エネの投資が不足している。パリ協定の目標達成は困難を伴う。だが、諦めるわけにはいかない。IPCCのホーセン・リー議長は対策の遅れがもたらす熱波や洪水などの被害拡大に警鐘を鳴らすとともに「報告書は希望へのメッセージでもある」と強調した。再生エネルギーや蓄電池のコストは劇的に下がった。水素製造・利用技術や、火力発電所から出る二酸化炭素(CO2)を吸収・貯留する技術の開発も進む。日本は化石燃料依存を減らしつつ、こうした技術の普及へ積極的な役割を果たすべきだ。実績を積み上げ、被害や損害の軽減につなげることが大切だ。 *3-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE102J80Q3A710C2000000/ (日経新聞 2023年7月10日) 停滞した梅雨前線に水蒸気が流入、九州の大雨の要因に 九州北部では7月に入ってから断続的に線状降水帯が発生し、10日は土砂崩れによる家屋被害や河川の氾濫が相次いだ。梅雨前線が九州付近に長くとどまり、太平洋高気圧の縁を回るように大量の水蒸気が流れ込んでいることが要因とされる。この時期は同様のメカニズムで豪雨が起こりやすく、気象庁は注意を求めている。気象庁気象研究所によると、7月に「3時間降水量が130ミリ以上」の豪雨が起きた頻度は、2020年までの45年間で約3.8倍に増えた。梅雨の時期に起きた集中豪雨の多くは、積乱雲が発達して連なる線状降水帯を伴うものだという。6月下旬〜7月上旬の梅雨時期は、日本の南側から張り出した太平洋高気圧の縁を回るようにして暖かく湿った空気が大量に梅雨前線に送り込まれやすくなる。とくに今年は上空の偏西風が弱いことなどから梅雨前線が九州付近に停滞。7日午後からは九州北側の対馬海峡の周辺にとどまり、雨雲のもととなる大量の水蒸気が流入し続けた。17年の九州北部豪雨でも九州の北側に梅雨前線が停滞し、線状降水帯が発生した。 *3-2-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE151YT0V10C23A7000000/ (日経新聞 2023年7月15日) 秋田大雨で河川氾濫 秋田駅前が冠水、16日新幹線運休 発達した梅雨前線の影響により秋田県で15日、記録的な大雨となった。秋田市ではJR秋田駅前など市街地が冠水した。夜時点で14市町村に避難指示が出され、最高の警戒レベル5に当たる「緊急安全確保」も6市町村で発令された。秋田市添川地区の住宅が土砂崩れに巻き込まれ、4人が軽傷を負った。同市には避難所が開設された。秋田県は同日、15市町村への災害救助法の適用を決定した。秋田新幹線は運休が相次ぎ、16日は盛岡-秋田間で始発から終日運転を見合わせる。17日も見合わせる見通しだ。大雨で川の水位が上昇し、同県五城目町の内川川や秋田市内の太平川などで氾濫が発生した。八峰町の水沢ダムと秋田市の旭川ダムでは午後、大雨により貯水しきれなくなった水を下流に流す「緊急放流」が始まった。同県内での午後5時時点までの24時間降水量は秋田市で最大287.5㍉、男鹿市で244.0㍉、藤里町で237.0㍉、八峰町で219.0㍉など7カ所で観測史上最大となった。八峰町では既に7月の平年1カ月分を超えた。朝鮮半島から東北を通って日本の東に延びる前線に暖かく湿った空気が流れ込み、前線は16日にかけて東北に停滞し、活発な状態が続くとみられる。16日午後6時までの24時間予想雨量は多いところで東北北部で120ミリ、東北南部で100ミリの見込み。 *3-3-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15690019.html (朝日新聞 2023年7月17日) 脱・石油、サウジが見る夢 首相中東歴訪 岸田文雄首相の中東3カ国歴訪が始まった。いずれも日本が石油やガスの供給元として依存するペルシャ湾岸諸国だが、「脱石油」時代に向けて、国の姿を変え始めている。湾岸諸国は、日本に何を期待しているのか。日本は、この地域にどう関与するのか。 ■全長170キロスマートシティー・外交で存在感 岸田首相がまず訪れたサウジアラビア。世界最大の石油輸出国ながら、脱炭素時代を見据えた大改革を進めている。サウジ北西部の赤茶けた砂漠地帯に、うっすらと浮かぶ1本の直線。衛星写真がとらえた線は長さ170キロ。幅200メートル。道路ではない。これ自体が一つの街になるという。サウジの国政を取り仕切るムハンマド皇太子が2021年に発表したスマートシティー「ザ・ライン」の建設現場だ。将来的に900万人が住み、道路も車もなく、高速鉄道などで移動。石油ではなく、すべてを再生可能エネルギーでまかなう計画だ。ムハンマド氏は「自然を守り、人類の生存可能性を高めるモデルを作る」と語った。サウジでは、石油依存からの脱却を図る社会改革が進行中だ。その指針が、ムハンマド氏が副皇太子時代の16年に発表した「ビジョン2030」。産業の多角化や教育・医療改革、女性の社会参加などを含む野心的な内容だ。世界が脱炭素へ向かう中、良くも悪くも原油価格次第という産業構造の転換は、サウジにとっての喫緊の課題だ。振興を目指す新産業は再生可能エネルギーや観光、文化、スポーツなど多岐にわたる。すでに観光ビザの発給を始め、自動車ラリー、eスポーツなどの国際イベントを誘致。未開発の山岳地帯を会場に29年冬季アジア大会も招致した。サウジは中東地域で唯一のG20(主要20カ国)メンバーで、アラブ圏、イスラム圏の盟主的な存在だ。近年はその枠を超えて、外交面での影響力も高まっている。ウクライナ侵攻では、昨年3月の国連総会でロシア非難決議に賛成しつつ、ロシア制裁を強める欧米とは距離を置く。主要産油国でつくる「石油輸出国機構(OPEC)プラス」のメンバーであるロシアとの関係を重視し、親米国家ながら、米バイデン政権の原油増産要請をはねつけた。一方、ロシアとウクライナの間で捕虜交換も仲介するなど、バランスをとる姿勢が目立つ。3月には、中国の仲介で、敵対関係にあったイランと7年ぶりに外交関係の正常化で合意。敵対から和解へ、中東各地で進む流れを主導する。安全保障面で後ろ盾となってきた米国は、中東での存在感を低下させている。サウジは外交攻勢によって独自に安保環境を整え、脱炭素時代に向けた国造りに資源を集中させたい考えとみられる。新構想には、すでに中国や韓国が投資や技術面での協力を表明しているが、日本への期待も高そうだ。 ■日本、支援に前のめり 中国の影響力警戒 日本の首相のサウジ訪問は、20年1月の安倍晋三元首相以来で約3年半ぶり。岸田首相は昨夏に中東訪問を模索したが、新型コロナ感染で見送った。外務省幹部は「突出した国力を持つサウジを含む中東への訪問は、これ以上遅らせることはできなかった」と話す。背景には、中東での中国のプレゼンスの高まりがある。岸田氏はサウジのムハンマド皇太子との会談で、16年に合意した両国の協力に関する「日・サウジ・ビジョン2030」へのさらなる支援を表明する。その柱に掲げるのが、クリーンエネルギーや脱炭素技術の協力だ。首相周辺によると、日本企業の投資への関心も高く、同行の呼びかけが1カ月前だったにもかかわらず、約30社が集まったという。岸田氏は16日、日本を発つ前に「グローバルなエネルギー安全保障と現実的なグリーン・トランスフォーメーション(脱炭素化)の実現に向け、緊密な連携を確認したい」と記者団に語った。会談では、アニメなどの日本文化、観光、教育などでの交流の推進で一致する見通し。岸田氏は両国間の幅広い分野での連携強化により、サウジの中国への接近に歯止めをかけたい考えだ。ただ、中東情勢の専門家のなかには「サウジとの連携を強める国際社会の中で日本は周回遅れだ」と指摘する人もいる。中国の影響力がさらに高まれば、日本のエネルギー政策にも影響しかねないと懸念する。岸田氏はまた、法の支配に基づく「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力を呼びかける。日本は今年、主要7カ国(G7)の議長国を務めており、首相周辺は「日本は中東やグローバルサウスと西側をつなぐポジションにあり、それを生かすことが重要だ」と話す。ムハンマド氏との信頼関係の構築も重視する。サウジは「中東全体を動かすパワーを持つ」(外務省幹部)ため、現在37歳の同氏との関係は、将来にわたる日本の国益につながると踏む。ただ、18年にトルコで起きたサウジ人記者殺害事件をめぐっては、ムハンマド氏の関与が疑われ、米国が問題視している。 ■<考論>存在感低下、技術や投資で関与を 日本エネルギー経済研究所理事・保坂修司氏 日本の石油輸入量の9割以上を占める中東の安定は、日本の経済安全保障という観点から重要だ。ウクライナ戦争を引き金にしたエネルギー危機で、世界的に中東の重要性は高まっているが、近年、中東での日本の存在感は低下している。湾岸諸国は、石油依存からの脱却をめざす。石油を売ったお金を石油以外の分野に投資し、経済を多角化すべく、急速に改革を進めている。首相が訪れる3カ国が日本に期待するのも、「脱炭素」に向けた協力や投資だろう。注目されている水素技術は、日本にも先端技術がある。こうした分野で協力関係を構築していくべきだ。安く安定的に石油やガスを供給できる地域は、今後も中東以外は考えにくい。首脳レベルでの関係強化は欠かせない。中東の人口は増加が見込まれ、経済的にも潜在力を秘めている。紛争が多く、政情不安に陥りやすい地域であるため、(企業が進出に)二の足を踏むのもわかる。ただ他国や他国企業も、一定のリスクをとって関与し続けている。日本側にもそうした姿勢が必要だ。 *3-3-2:https://ideasforgood.jp/2016/09/14/drone_baoan/ (Ideas For Good 2016年9月14日) 世界初、ドローン専用の高速道路?深圳が描く未来都市 約1,500万人の人口を抱え、今や中国はおろか世界を代表する経済都市として「中国のシリコンバレー」と呼ばれるまでになった中国広東省の深圳で、また新たな一大プロジェクトが始まろうとしている。深圳の西部にある宝安(Bao’an)を走る高速道路、「G107」周辺地域の再開発プロジェクトにおいて、その全容は明らかにされた。宝安地区の再開発に向けてAvoid Obvious Architectsらが提案したのは、世界で初めてとなるドローン専用の高速道路だ。ニューヨークのマンハッタンよりも長く、30kmに渡って宝安地区を横切るG107は、同地域を都市化が進むウォーターフロントエリアと自然が残されたままの内陸エリアに分断し、都市の持続可能な発展を妨げる要因となっている。都市における高速道路の役割を再定義するところから始まった同プロジェクトは、「サステナビリティ」「つながり」「テクノロジー」「シェアリングエコノミー」「社会創造」「グリーン建築」の6つをテーマに置き、ドローンや自動運転といった最先端のテクノロジーと自然を融合させた近未来の都市の在り方を提示するものとなっている。大量の排気ガスを排出していた12車線の高速道路は、4車線ずつに分かれた2つの道路として筒状の空中トンネルの中に格納され、大気汚染の問題が解決される。そしてその空中トンネルの上に敷き詰められた緑の歩道を人々は歩き、都市と自然が一体化された暮らしを実現する。こうした環境に配慮されたスマートシティ構想は深圳以外にも世界中で進んでいるが、今回提示された都市ビジョンの中でひと際人々の目を引いたのは、何といってもオフィスビルを貫くドローン専用の高速道路の存在だ。現在、ドローンは産業分野での活用が期待されているテクノロジーの一つだが、その中でも特に関心が寄せられているのが、輸送・物流分野における革命だ。ドローンを活用した新たな空中の物流インフラを構築することができれば、地上のトラック輸送・物流を大幅に削減することができ、利便性はもちろん環境面におけるプラス効果も期待できる。しかし、ドローンが空中を安全かつ効率的に飛び回り、輸送インフラとしての機能を果たすためには、ドローン輸送を前提とする都市計画が必要となる。そこで今回提案されたのが、ドローン専用の高速道路なのだ。ドローンの輸送導線を考慮したビル設計を行うことで、効率的な輸送インフラが実現し、テクノロジーと利便性、環境へ配慮が一体化した都市が実現するというわけだ。今回プロジェクトを提案した香港とニューヨークに拠点を置く建築デザイン会社のAvoid Obvious Architectsは、今回のプランを段階的に実現し、2045年までにこの自然とテクノロジーが融合した未来都市を完成させる計画だ。今から約30年後の2045年、世界の都市はテクノロジーと共にどのような進化を遂げているのか。そして、そこで私たちはどのような暮らしをしているのか。想像するだけで夢は膨らむが、その未来を現実にするための最初の一歩は、既に始まろうとしている。 *3-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230628&ng=DGKKZO72254030X20C23A6KE8000 (日経新聞 2023.6.28) 地方経済をどうするか(下) 自治体財源・議会の改革カギ、浦川邦夫・九州大学教授(うらかわ・くにお 77年生まれ。京都大学博士(経済学)。専門は応用経済学、福祉政策) <ポイント> ○過度な都市集積は成長にプラスと限らず ○地方消費税率上げなどで自主財源強化を ○地方議会での年齢枠・女性枠導入も一案 戦後から今日に至るまで程度の差はあるが、日本の地域格差のほぼ一貫した特徴として、東京圏、とりわけ東京都への人口・企業の集中の傾向が挙げられる。総務省の「住民基本台帳人口移動報告」を基に、2022年の人口移動の状況を確認すると、都道府県別の転入超過率は埼玉県が0.35%と最も高く、神奈川県(0.30%)、東京都(0.27%)、千葉県(0.14%)が続く。東京圏全体で10万人弱の転入超過だった。東京都の転入超過率は前年に比べて最も大きく上昇(0.23ポイント)しており、コロナ禍でやや沈静化していた東京一極集中の傾向が再び鮮明になりつつある。政府統計によると、東京都の1人当たり所得は575.7万円(19年度)と全国平均の約1.7倍で、2位の愛知県の366.1万円を大きく引き離す。東京都の上場企業本社数(22年7月)は2122社で、全国の約54%を占める。東京都の高い所得水準や多様な企業の存在は地方から多くの人材を引きつける。筆者は10年代前半に9千人規模の調査を用いた共同研究で、回答者の幼少期以降の地域移動のパターンと現在の所得水準の関係を検証した。小中学生時点で東京圏以外の地域に居住し、調査時点で東京圏に居住する回答者(地方から都市への移動経験を持つ回答者)は、他の移動タイプ(移動経験なしを含む)の回答者と比べ、一般に所得水準が高い傾向が確認された。これは、もともと人的資本の水準が高い優秀な人材が自己の選択により経済合理的な判断から都市に移動するとしたトルコ・コチ大学のインサン・ツナリ氏らの分析を支持する結果だ。都市の最適な人口規模を考えるうえで「ヘンリー・ジョージの定理」が知られる。住民の効用を最大化させるような最適な人口規模がどのような条件下で達成されるかについて、都市集積のベネフィットとコストの差に注目した定理だ。東京圏など特定地域に労働や資本が集まることは、規模の経済や集積の経済を通じて日本全体の平均的な生産性を高める効果が期待される。一方で、過度の集積は混雑や騒音などによる地域住民の生活環境の悪化をもたらし、出生率の低迷や福祉水準の低下につながりうる。大規模災害や環境汚染に対する脆弱性への対応も重要な論点だ。立正大学の西崎文平氏は、20世紀後半以降のデータを基に大都市集中と経済成長の関係に関する各国の先行研究を調べた。その結果、近年は主に先進国で人口や産業の集中度と経済成長がマイナスないし非有意の関係となる研究が目立つと指摘した。すなわち経済規模が一定水準を超えて成熟した国については、大都市への集中が成長にポジティブな影響を与え続けるとは一概にはいえない。「県民経済計算」を用いたアジア成長研究所の戴二彪氏の分析は、「労働年齢人口」の伸び率の低さが「1人当たり県内総生産」の伸び率の低さと関連している点を指摘する。このことは、日本の地域経済成長および全国の経済成長に対し、社会移動に加え、出生数の減少や高齢化など人口構造変化への対策が本質的に重要なことを示唆する。14年制定の「まち・ひと・しごと創生法」は、人口減少・高齢化・労働力不足などの地域的課題を解決すべく「地方創生」を国の重要な政策として位置づけ、自治体に様々な取り組みを求める。具体的には、各自治体が地方創生に関する計画を立案し、国がその計画を支援する形が採られた。だが現状の社会経済指標(人口移動、経済成長など)を踏まえると、全体としての取り組みには課題が残る。ここでは、必要とされる視点やとるべき方策について主に2点指摘したい。第1に地域のあり方を決める主役はその地域の住民であることから、地方創生に向けた取り組みは自治体ができる限り自主財源(地方税など)を駆使して実施する形が望ましい。しかし現行の自主財源比率は7割を超える自治体もある一方で、過疎地では2割を割り込む自治体もある。財源の多くが国の判断に左右されやすい状況下で、毎年の歳入・歳出規模が決定される構造が自治体には定着している。財政面での国と地方の関係性も、人口の東京一極集中を助長した一因だ。宮崎雅人・埼玉大教授は地方版総合戦略の策定にあたり、多くの自治体が国からの地方創生関連交付金を基に、東京都に本社がある業者に外部委託した点を指摘する。地域政策の経済効果が地元の経済にどの程度還元されているかを検証する手法として産業連関分析があるが、使用財源を明確にした形での経済効果の検証が求められる。自主財源を高める措置としては、税収の地域間格差が比較的少ない地方消費税の税率引き上げなどが検討に値する。第2に町村など人口が少ない地域では既に高齢化が相当進んでいるが、実際の人口分布以上に政治家(地方議員)の年齢階層が高齢者に集中しているという問題への対応が必要だ。総務省の「地方選挙結果調」によると、19年4月実施の統一地方選で当選した全国約1万5千人の地方議員のうち、39歳以下は7%で、町村議に限れば3%を下回る(表参照)。地域の現場で長期的な展望に立って政策を進める若手政治家が非常に不足しているといえる。他方、無投票で当選・再選を果たす地方議員は増加傾向にある。19年統一地方選の無投票当選率は市議選では2.7%にとどまるが、町村議選では23.4%にのぼる。人口減少が進む町村では成り手不足が一層深刻化しており、立候補者が定数に至らないこともある。日本の地方議員は、大企業で働く会社員や常勤の公務員に比べて必ずしも経済的に恵まれているとはいえない。会社員の立候補者が選挙運動のための休暇をとることや、議員に就任した一定期間後に従前の職または同等の給与が得られる地位に復職できる制度は海外諸国と比べて不十分だ。企業の勤め人が地方選挙に出るという選択は、家族を養うこととの両立が難しく、結果として就労世代の住民が政治の現場に関わりにくい状況にある。地方創生にかかる政策の推進を正面から支援するには、議員定数の中に年齢枠や女性枠などを設ける「クオータ制」の導入や地方議員の報酬増を検討すべきだ。東京圏への人口・産業集中をさらに進めるべきか、あるいは地方分権を進めて自立した経済圏を持つ複数の都市を中心とした多極化を目指すべきか、国と地域の望ましい将来像に対して様々な議論がある。短期的には人口が集中する東京圏の生活環境(子育て、教育など)の改善が重要な課題だが、中長期的には東京以外にも様々な人材・産業が集積する拠点を整備する方向性が望ましい。特にコンテンツ、ソフトウエア・システム開発、研究開発、デザイン、芸術などの創造的な産業は、IT(情報技術)を駆使して空間的な距離を克服しやすいことから、地方での立地のさらなる増加を目指すべきだ。 <原発は温暖化対策にならないこと> PS(2023年8月7日追加):*4-1のように、東京・埼玉・千葉・横浜・水戸・静岡等で危険な暑さが続き、宇都宮・前橋も厳重警戒だが、内陸である埼玉県の暑さは東京・千葉・横浜を上回る。この極端な高温増加の背景にはCO₂の排出など人間活動による地球温暖化の影響が大きいが、コンクリートとアスファルトで覆った街やエアコンが吹き出す熱も影響が大きいだろう。 CO₂排出による地球温暖化を阻止するには再エネが一番だが、政府は脱炭素化に向けた基本方針として原子力基本法で「原発事業者が安全投資と安定的な事業ができる環境を整備する施策を国が講じる」と決め、*4-2-1・*4-2-2のように、電力会社が既存原発の再稼働に投じた巨額の安全対策費を再エネ由来の新電力と契約している消費者にまで負担させる制度導入を検討するとのことである。しかし、原発のコストは、原発にかかる全ての支出を合計して出すべきであるため、いつまでも政府や再エネ事業者から拠出を受けなければならないような原発のコストはとんでもなく高いのである。また、大手電力会社を護るために再エネ事業者に犠牲を強いているため、イノベーションも進まない。さらに、原発は大量の温排水を出して海水温を上げているため、地球温暖化阻止に役立っているかどうかも、本当は疑わしいのである。 このような中、*4-3のように、1974年に運転を始めた関西電力高浜原発1号機が、「原則40年」の運転期間を延長して12年ぶりに再稼働し、事故時の避難計画の実効性や使用済核燃料の扱いなど課題は残ったまま、設計は古く、コンクリートやケーブルの劣化も懸念されるのだそうだ。関電の大飯・美浜原発、日本原電の敦賀原発が林立する福井県の若狭湾沿いは、もともとは好漁場だったのだが、事故が起こればフクイチどころではない日本海沿岸の汚染になるにもかかわらず、そこで40年ルールを形骸化させたことは住民の安全と食糧自給率を無視した対応だ。仮に避難路が使えたとしても、どこにどれだけの期間避難し続けたらよいと思っているのか。それに加えて、使用済核燃料の中間貯蔵施設や最終処分場確保も見通せないのである。 なお、*4-4-1のように、フクイチのアルプス処理水を海洋放出するにあたり、“風評対策”として300億円が2021年度補正予算に計上されたそうだが、これも国民の税金から支出する原発のコストだ。そして、これは水産物の販路拡大支援のために使われるぞうだが、サバ・イワシ等の冷凍しても市場価格が落ちにくい水産物は買い取って冷凍保管し市況が回復してから販売、マダイ・ヒラメ等の冷凍に向かない水産物はネット販売経費助成や企業の食堂で提供する補助金に使うそうだ。しかし、この政策は、「国民が忘れるのを待つ」という意味で国民に対して不誠実であることこの上ない。仮に「基準値以下なら蓄積することなく、全く無害である」と主張するのなら、国の補助金など使わず、無害だと主張する東電はじめ原発関連企業や経産省の食堂で毎日提供すればよいだろう。処理水排出期間中、それを続けても他の国民と比較して癌や心疾患の発生率に有為の差がなければ無害だったと言える。なお、魚介類は、人間と違って超多産多死で生存期間が短いため、抵抗力のある個体だけが生き残り、蓄積も少ない。そのため、処理水を流しても平気な魚介類がいるからといって、人間もそうとは限らない。 このような中、中国電力と関西電力は、*4-4-2のように、山口県上関町に「中間貯蔵施設」建設を検討し始め、2011年のフクイチ事故後に原発建設が中断して財政逼迫している上関町と6基が稼働して使用済核燃料貯蔵プールが5~7年でいっぱいになる関電との思惑が一致し、経産省も政府の方針に沿ったものであることを示唆しているそうだ。つまり、原発を立地すれば国の交付金などの原発マネーが入り、使用済核燃料の中間貯蔵や最終処分にも税金を使うのだ。しかし、四国沖の広い領域で南海トラフ地震が予想されているのに、活断層そのものである瀬戸内海の入り口にあたる上関町に原発関連施設を作るというのは安全性に疑問があり、町が10年持たないのなら周辺市町村と合併して地域振興を考えるのが町民や国民に迷惑をかけない方法だ。なお、空冷式であれば温排水は出ないが、その熱は空気中に発散するのである。 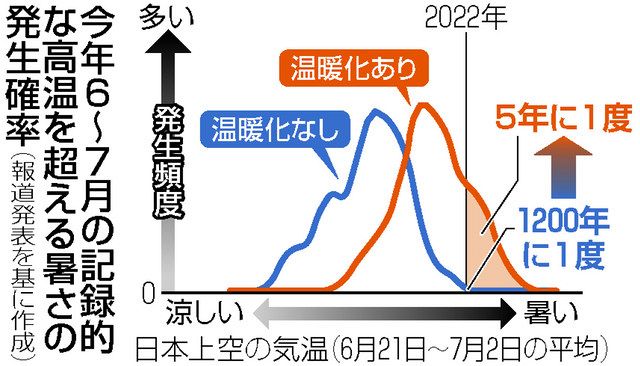 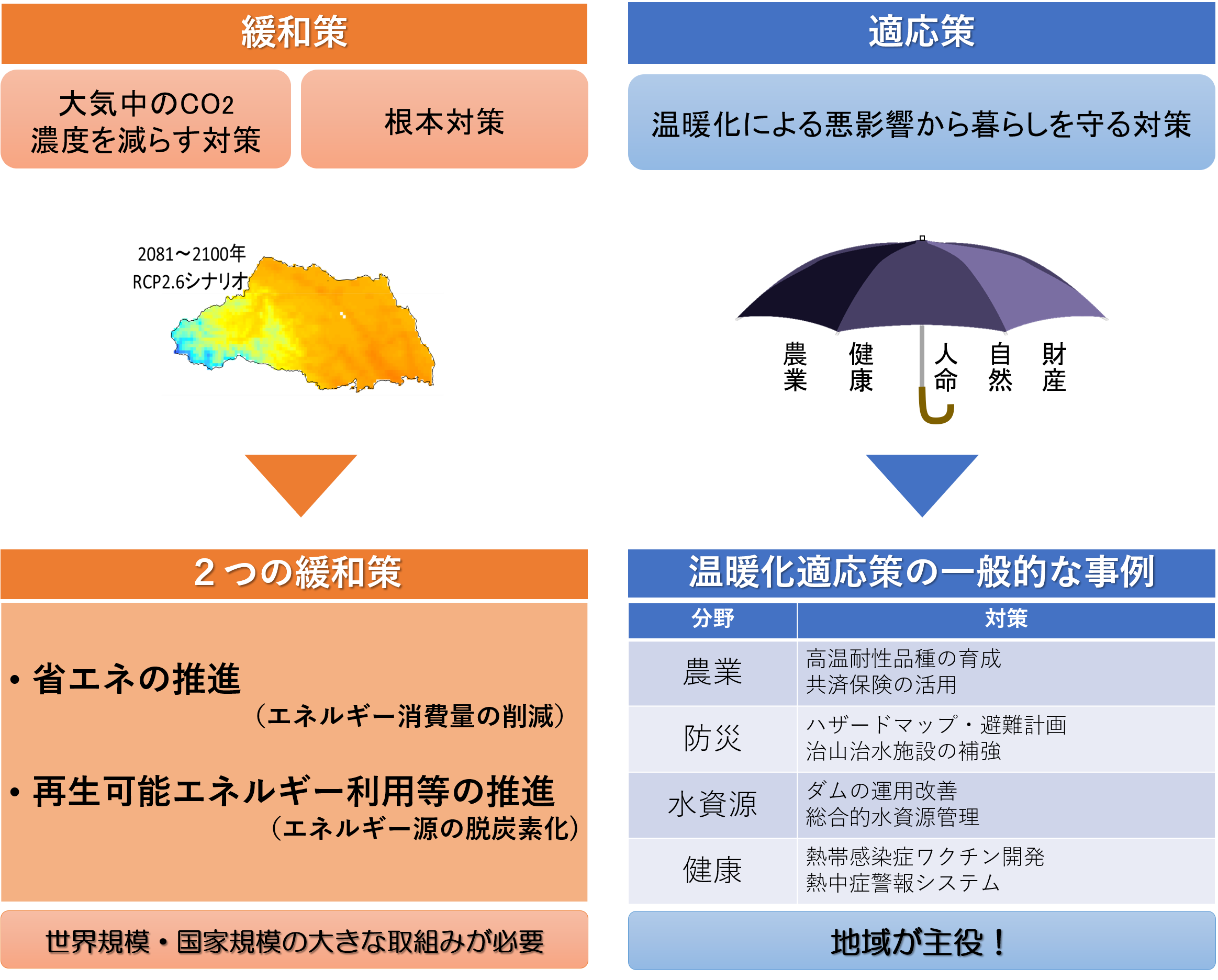  2023.8.7毎日新聞 埼玉県 (図の説明:左図のように、地球温暖化によって猛暑や豪雨の頻度が上がり、中央の図のような対応策が考えられている。そのような中、原発は地球温暖化対策の解にはならず、右図の山口県上関町は原発の立地だけでなく、中間貯蔵施設の立地でさえ危ない場所である) *4-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/268361 (東京新聞 2023年8月7日) <熱中症予報・7日>「危険」は東京都心、さいたま、千葉、横浜、水戸、静岡 「厳重警戒」は宇都宮と前橋 首都圏では7日、熱中症について、東京都心とさいたま、千葉、横浜、水戸、静岡の各市で「危険」、宇都宮、前橋の両市で「厳重警戒」と予測されている。「危険」は「外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。運動は原則中止」とされ、高齢者の熱中症は「安静状態でも発生する危険性が大きい」と警告されている。各地の熱中症予報は、本紙が前日夜に環境省熱中症予防情報サイトを確認し、時間帯別の暑さ指数のうちで最も高い水準を選んだ。予測は定期的に修正され、情報サイトで公開されている。 ◆予防には冷房、水分・塩分補給、休憩を 熱中症は、汗をかくなどの体温の調整機能のバランスが崩れ、どんどん身体に熱が溜まってしまう状態で、最悪の場合、死に至る。気温や湿度が高いときや、脱水、二日酔いや寝不足、激しい運動などによって引き起こされる恐れがある。予防には、暑い場所を避け、水分・塩分をこまめに補給し、積極的に休憩をすることが大切だ。屋内で熱中症になるケースも多いため、エアコンで十分に室内を涼しくすることが重要。省エネとの両立では設定温度は28度が目安になるが、状況次第では実際の室温が28度まで下がらないこともある。室温を測りながら、体調に合わせて快適な温度まで下げることが望ましい。 ◆極端な高温、背景に地球温暖化 熱中症の発症リスクは35度以上の猛暑で特に高まる。地球温暖化によって極端な高温の起きやすさや深刻さは増している。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2021年に公表した最新の評価報告書では、人間の活動によって起きた気候変動で、極端な高温の頻度や強度が増加してきたとの見方が示されている。発電所や車、工場などあらゆる分野で温室効果ガスを出し続けてきたことの影響が既に現れているという。日本では、熱中症による死亡が1000人を超えた2018年7月の記録的な猛暑について、気象庁気象研究所などの研究チームは、温暖化の影響がなかった場合に発生した確率は「ほぼ0%」と推定。世界の気温上昇を1.5度に抑える国際的な目標を達成しても、日本の猛暑日の観測は今の約1.4倍になると予測した。 *4-2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/265526 (東京新聞 2023年7月26日) 原発再稼働費を消費者が負担 電気料金で新電力と契約でも 経済産業省は26日、電力会社が既存原発の再稼働のために投じた巨額の安全対策費を、電気料金を通じて消費者から回収できるようにする制度の導入を検討すると明らかにした。脱炭素に貢献する発電所の新設を支援する制度の対象に、既存原発を加える。導入されれば、再生可能エネルギー由来を売りにする新電力と契約している消費者も、再稼働費用を負担することになる。政府は2月、原発の「最大限活用」を盛り込んだ、脱炭素化に向けた基本方針を決定。5月に改正した原子力基本法は、原発事業者が安全投資と安定的な事業ができる環境を整備する施策を、国が講じるとした。制度は「長期脱炭素電源オークション」で、脱炭素化と電力安定供給の両立を目指し、来年1月に導入する。電力小売事業者から拠出金として集めたお金を発電事業者に分配し、運転開始から20年間の収入を保証することで、投資を促す。再生可能エネルギーや、CO2の排出を新技術でゼロにする火力発電所のほか、原発の新設や建て替えなどを対象としている。 *4-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230727&ng=DGKKZO73083220W3A720C2EP0000 (日経新聞 2023.7.27) 経産省、原発安全対策費を支援 再稼働後押し 原資は電気代 経済産業省は26日の有識者会議で、原子力発電所の再稼働に欠かせない安全対策費の支援策を検討する方針を示した。温暖化ガスの排出削減につながる新規の発電所への支援制度の対象に追加する方向だ。電力会社の巨額負担を減らし、政府が目指す原発の活用促進につなげる。政府は2024年1月に、原則20年にわたって電力会社などに固定収入を保証する「長期脱炭素電源オークション」という新制度を始める。これまで支援対象を水素やアンモニアを燃料に使う火力発電所や大規模蓄電池、新設・建て替えの原発などと定めていた。経産省は26日に開いた会合で、この対象に既存の原発を含めることを検討する方針を示した。実現すれば、大手電力が進める原発の再稼働に向けた安全対策費用の負担が減る。原発の安全対策費は電力11社の総額で5兆円超が必要とされる。例えば関西電力は安全対策に1兆円程度かかるとみており事業者にとって巨額の費用負担がのしかかる。こうした支援の原資は電力の小売会社から集める。国の認可法人の電力広域的運営推進機関がオークションを開いて小売りから資金を集め、発電企業に配る仕組みだ。電力会社が消費者の電気料金を通じて捻出する仕組みが想定される。結果として、幅広い利用者が再稼働の費用を負担することになる。6月には東電など大手電力7社が家庭向け電気料金を値上げしたが、さらなる負担増につながる可能性がある。再生可能エネルギーの導入が進むなか、火力発電所は再エネのバックアップとしての役割が強まっている。ただ火力の採算性は悪化しており、将来供給力が不足する恐れがあった。経産省は必要な電源投資が不足しかねないとの問題意識から、支援対象の拡大を目指す。岸田政権は原発再稼働を掲げているが、現在までの再稼働実績は10基にとどまる。資源エネルギー庁によると30年度に原発で電源の2割程度をまかなう目標の達成には少なくともさらに15基の再稼働が欠かせず、ペースを加速する必要がある。 *4-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15704188.html (朝日新聞社説 2023年7月31日) 高浜原発稼働 不安と疑問、抱えたまま 1974年に運転を始めた関西電力高浜原発1号機(福井県高浜町)が、12年ぶりに動き出した。「原則40年」の運転期間を延長しての再稼働であり、事故時の避難計画の実効性や、使用済み核燃料の扱いなど、重い課題は残ったままだ。不安と疑問を禁じ得ない。高浜1号機は、定期検査中に東日本大震災が起き、運転停止が続いた。東京電力福島第一原発事故を踏まえて原発の運転は原則40年とされ、「1回だけ最長20年延長可」の例外規定が設けられた。高浜1号機にもこれが適用され、原子力規制委員会の審査を経て、16年に延長が認可されていた。だが、半世紀前につくられた原発は設計自体が古い。原子炉の停止期間を含め、コンクリートやケーブルの劣化も懸念される。40年ルールには、原発依存度を低下させることに加え、そうした老朽化に伴うリスクを減らす意味もあったはずだ。しかし、政府は20年延長の例外規定を次々と適用してきたうえに、前国会の法改正では60年を超える運転を可能にし、ルール自体を形骸化させている。事故の教訓を投げ捨てる姿勢と言わざるをえない。「原発復権」の中での再稼働は、老朽化以外にも様々な未解決の難題を突きつける。高浜原発がある福井県の若狭湾沿いは、関電の大飯、美浜両原発、日本原電の敦賀原発も立地する「原発銀座」だ。事故の想定と対応は複雑になる。地形上も避難路が限られるなかで、計画通りに退避できるのか。住民の不安は根強い。「発電後」の問題もある。関電は福井県に対し、県内3原発にたまり続ける使用済み核燃料について、県外に中間貯蔵施設を確保すると約束してきた。最終的に今年末を期限としたが、候補地のメドが立っていなかった。ところが関電は先月、高浜原発分の一部を再処理工場があるフランスに搬出すると公表し、それをもって「約束はひとまず果たされた」と説明した。だが、この搬出分は3原発にある総量の5%に過ぎず、関電の詭弁(きべん)に驚く。県民から反発がでるのも当然だ。しかも、関電は9月にも高浜2号機を再稼働する。さらに同3・4号機の20年間の運転延長も申請中だ。無責任と言うしかない。問題の構図は、すべての原発に共通する。背景には、使用済み燃料を再処理する核燃料サイクル政策の行き詰まりがある。さらに、最後に残る高レベル放射性廃棄物などの最終処分場の確保も見通せていない。電力業界と政府は、高浜原発が示す現状を直視すべきだ。 *4-4-1:https://mainichi.jp/articles/20211126/k00/00m/040/252000c (毎日新聞 2021/11/26) 福島第1原発処理水 海洋放出の風評対策に300億円 補正予算案 東京電力福島第1原発でたまり続ける処理水の海洋放出を巡り、経済産業省は26日、水産物の風評被害に対応する基金のために、2021年度補正予算案に300億円を計上すると発表した。水産物の販路の拡大などを支援する。原発事故による風評被害への対策に国費が投入されることになる。政府と東電は23年春から処理水を海に流す方針を示している。経産省は、補正予算案が成立すれば、基金の管理や運営を担う団体を公募し、22年3月までに基金を創設したい考えだ。基金の事業では処理水の海洋放出に伴う風評被害が起きた場合、漁協などがサバやイワシなど冷凍しても市場価格が落ちにくい水産物を買い取って冷凍保管し、市況が回復してから販売することを想定している。その際、冷凍保管にかかる費用や買い取り資金を借りた場合の利子を補助する。一方、マダイやヒラメといった冷凍に向かない水産物では、ネット販売にかかる経費を助成したり、企業の食堂で提供するのに補助金を出したりすることなどを検討している。基金の対象は福島県産だけでなく、全国の水産物になる。経産省は、基金の費用を22年度の当初予算に計上する方針だったが、放出前から風評被害が生じる可能性があることから、前倒しした。風評被害による損害そのものへの賠償は、東電が別の制度で実施する。経産省の担当者は「基金の運用益だけで事業が回るとは想定していない。政府には風評の影響に対応する責務があり、国費を投入することになる」と説明する。処理水の放出には30~40年かかるとみられており、経産省は基金の残高が不足すれば追加の拠出も検討する。一方、漁業関係者らは、海洋放出に反対している。 *4-4-2:https://digital.asahi.com/articles/ASR826R2LR82PLFA00G.html?iref=pc_extlink (朝日新聞 2023年8月2日) 背水の関西電力、「原発マネー」に頼る町 両者を結んだ中国電力 中国電力と関西電力が共同で山口県上関(かみのせき)町で検討をはじめた「中間貯蔵施設」の建設。施設確保に苦戦する関電、財政が逼迫(ひっぱく)する町など、それぞれの思惑がうずまく。一方、国が描く核燃料サイクルにとっては、急場しのぎの面も垣間見える。中国電が関電と中間貯蔵施設の共同開発に踏み切ったのはなぜか。「事業者間でしっかり連携してほしいということは、国もずっと言い続けていることだ」。原発政策を担う経済産業省の幹部は、今回の動きが政府の方針に沿ったものであることを示唆する。原発を保有する大手電力はそれぞれ使用済み燃料の保管場所を確保する必要がある。だが、中間貯蔵施設をつくるには地元との調整や費用など課題が多い。用地確保は特にハードルが高い。「全国にそう何個もつくれるわけがない」(同幹部)ため、政府は共同利用するなど融通策をとるよう促してきた。大手電力でつくる電気事業連合会も「事業者間の連携・協力をより一層強化する」との方針を掲げている。複数の関係者は、こうした背景に加えて、中国電と関電の利害が一致したとも指摘する。中国電は大手電力の中でも経営規模は中位。中間貯蔵施設を単独で建設し、運営するのは「財務面で難しい」(大手電力関係者)ともされる。隣接地域の九州電力や四国電力と組もうにも、両社は自前で原発敷地内に貯蔵場所を確保している。一方の関電は、経営規模が売上高ベースで中国電の倍以上。福島第一原発事故で事実上国有化されている東京電力に代わって、電力業界の盟主となったが、中間貯蔵施設の確保に苦戦していた。施設の規模は未定だが、中国電は、関電の使用済み核燃料の貯蔵量の方が多くなることも「可能性としてはある」とする。6基が稼働している関電の原発では、使用済み核燃料を貯蔵する原発内のプールがあと5~7年でいっぱいになる見通しだ。関電は2030年ごろに2千トン規模の中間貯蔵施設の確保を目指すが、実現の糸口はつかめていなかった。「確保できていないとあふれる。貯蔵しきれない、というわけにいかない」。ある関電幹部は、差し迫った状況をこう語る。関電は自社の3原発が立地する福井県に対して、県外に中間貯蔵の施設を確保すると約束してきたが、先送りを繰り返してきた。21年には約束の「最終期限」を23年末とし、守れなければ、稼働中の美浜3号機と高浜1号機、9月にも再稼働予定の同2号機の計3基を運転しないとする方針を示した。背水の関電は6月、高浜原発で出た使用済み核燃料のごく一部をフランスへ搬出すると表明。関電側は「約束はひとまず果たされた」との認識を示した。しかし、約束が果たされたかどうかの「ボール」は福井県側の手中にある。県議会では「詭弁(きべん)だ」「小ばかにしている」と反発が広がった。杉本達治知事は「総合的に判断したい」と態度を留保している。知事の判断次第では、ようやく再稼働にめどをつけた原発3基を止めざるを得なくなる。関電は上関町の中間貯蔵施設について、調査前であることなどから「まだ正式に中間貯蔵の計画地といえるものではない」とする。保守系のベテラン県議は「候補地に手を挙げてくれればありがたい」と取材に述べた。一方、杉本知事はこの日、記者団の取材は受けないと回答した。(岩沢志気、小田健司、吉田貴司) ●原発マネーに期待した上関町の財政逼迫 中間貯蔵施設を町内に建設する計画を提案された山口県上関町。報道陣の取材に応じた西哲夫町長は、「町議会の判断を仰ぎたい」と受け入れの是非の明言は避けたが、前向きな姿勢は随所ににじんだ。「このまま何もせずに町が10年もつかと言ったら相当厳しい」「交付金や固定資産税が入れば、町の財政が安定するのは間違いない」「安心できる施設だと思う」。そもそも、この日の中国電幹部の町訪問のきっかけを作ったのは、町側だ。町では、1982年に上関原発の計画が浮上し、2009年に中国電が敷地造成などの準備工事に着手。だが、11年の東京電力福島第一原発事故後、建設は中断した。町税収入が2億円に満たず、国の交付金や関連税収など「原発マネー」に期待していた町の財政は逼迫(ひっぱく)した。昨年12月、西町長は中国電力幹部に着工の見通しを尋ねたが、今年2月の返答は「現時点で着工の見通しは立っていない」だった。「原子力が1ミリも前に進まず、町を生かさず殺さずの状態でええんか」。こう考えていた西町長は今年2月、西村康稔経済産業相と面会。上関原発の建設について「早く目鼻をつけてほしい」と求め、交付金の増額を要望した。西村経産相は「上関町には長年ご迷惑をおかけしている。重く受けとめている」と語ったが、原発建設が進む確約は得られなかった。そうした中で、西町長が頼ったのが中国電だった。今年2月、中国電に新たな地域振興策を要請。この日がその「回答」だった。地域振興策として、中間貯蔵施設を提案されたことに、西町長に驚きはなかった。実は、かつて町側にも誘致案があったからだ。「中間貯蔵施設を選択肢の一つとして考えたい。議員も勉強しておいてもらえんか」。19年、当時の柏原重海町長が町議らに伝えた。当時、町議長だった西町長らは使用済み核燃料が乾式貯蔵される日本原子力発電の東海第二原発(茨城県)を視察した。「よその核燃料を受け入れるなんてとんでもない」。視察前、原発推進の議員らの間にも否定的な見方があったが、貯蔵施設を見て「なんだ、倉庫じゃないか」と懸念が消えたという。中間貯蔵施設の核燃料は空冷式のため温排水も出ない、との説明も受けた。「まさしく百聞は一見にしかず」と、西氏は当時の柏原町長に報告していた。この40年で人口が3分の1ほどの2310人に減り、高齢化率が6割に迫る町は、中国電に何度も頼ってきた。中国電は07~10年度に24億円、震災後の18年に8億円、19年に4億円を町に寄付している。一方、中国電の経営は急速に悪化している。同社は火力発電に大きく依存しており、ウクライナ危機や円安による燃料費高騰などで赤字を計上。カルテル問題も重なり、町への寄付金や支援は見こめない状況だ。中間貯蔵施設を建設する自治体には、建設に向けた調査段階から交付金が出る。調査から知事の同意まで最大で年1・4億円、知事の同意後の2年間は最大で年9・8億円だ。建設や運転段階では貯蔵量などに応じて交付金が出る。ある町議は言う。「中間貯蔵施設なら、まだ原発をあきらめていないという理屈も成り立つし、国の交付金や核燃料税による財源も確保できる。中国電も町も、良い落としどころを見つけたということではないか」。ただ、原発計画の賛否を巡る対立は40年超に及び、中間貯蔵施設への激しい反対運動も予想される。2日朝、町役場前で中国電幹部の進入を阻止しようと住民らが集まり、「町の分断を続けるのか」と訴えた。 <高レベル放射性廃棄物の最終処分場について> PS(2023年8月16日追加):原発の使用済核燃料から出る高レベル放射性廃棄物は、最終処分場で地層処分(人間の管理に委ねなくて済むよう地下深くの安定した岩盤に閉じ込めて人間の生活環境から隔離して処分すること)になっており、日本では「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」で地表から300メートル以上深い地層に処分すると定められている(https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/hlw/hlw01.html 参照)。 そして、現在、最終処分場はなく、文献調査の候補地になるだけで最大20億円の交付金が国から入るため、*5の長崎県対馬市などのように、①土建業等の4団体が文献調査の推進を求める請願を市議会に提出し ②市民団体・漁協が出した反対の請願は不採択になり ③市議会特別委員会が国の「文献調査」を推進する請願を賛成多数で採択して市長に国に応募するよう迫ったりしている。市長は、これまで文献調査について慎重な姿勢を崩さず、「手をあげて『20億円もらったからもうやめる』という考えはない」と定例議会で述べていたが、④政府やNUMOは歓迎し ⑤岸田政権は「核のごみ」最終処分場の選定に全面関与する方針を打ち出し ⑥改正原子力基本法は「国が地方公共団体その他の関係者に対する主体的な働き掛けをする」と明記し ⑦経産省幹部は「北海道の寿都町と神恵内村に加えて対馬でも一歩進んだのは大きく、この動きが他の自治体にも広がってくれればいい」とし ⑧NUMO関係者は「これで市長が反対したら、請願で示された『民意』はどうなるのか。国家のエネルギー政策は重い。『入り口』である文献調査は受け入れるべきではないか」と言っているそうだ。 しかし、①の文献調査候補地になっただけで最大20億円の交付金をもらえるというのは、原発がいかに高コストかを示しており、②の土建業の積極性も国からの文献調査費や最終処分場建設費の流れが明らかだ。しかし、対馬市は対馬海峡の流れの速さに鍛えられた魚が美味しく、養殖マグロも肉質がよくて美味しいと高評価を得ている地域であり(https://nagasaki-keizai.jp/report/report-report/1270 参照)、国境離島でもある。そのため、ここに高レベル放射性廃棄物の最終処分場を作ることは、地域の長所を打ち消すと同時に、セキュリティー上も問題が多いのである。従って、④⑤⑥⑦は税金を無駄遣いしながら地域資源を台無しにする行為であり、予算も人材も不足している食料自給率の小さな国で税金を使うのなら、このような無駄遣いではなく活きた使い方をすべきなのである。活きた使い方とは、例えば再エネ開発や送電線の敷設、漁業・観光の振興であって、間違ってもそれを邪魔する行為ではない。 なお、最終処分場は、国境離島ではない無人島で既に施設のある場所(例えば「軍艦島」など)もしくは排他的経済水域内の数千m以上の深海などが安価でかつ必要な条件を満たしているが、それを可能にするためには、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」で地表から300メートル以上深い地層に処分するという規定を、まず変更する必要があるだろう。 *5:https://digital.asahi.com/articles/ASR8J5645R8JTIPE00L.html?iref=comtop_7_04 (朝日新聞 2023年8月16日) 核のごみを問う、長崎・対馬市議会、「核のごみ」最終処分場の調査「推進」請願を採択 原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)最終処分場をめぐり、長崎県の対馬市議会特別委員会は16日、国の選定プロセスの第1段階「文献調査」を推進する請願を賛成多数で採択した。市議会が比田勝尚喜市長に対し、国に応募するよう迫った形だ。北海道2町村に続く応募自治体となるか、注目される。特別委では、土建業などの4団体が6月に議会に提出した、文献調査の推進を求める請願について採決し、9票対7票の賛成多数で採択した。風評被害などを懸念する漁協などが出した、反対の請願は不採択となった。最終処分場の選定プロセスは3段階あり、文献調査は過去の論文などから処分場の候補地にふさわしいかを調べる。応募した自治体には、約2年間で最大20億円の交付金が国から入る。対馬市は人口減が進み、基幹産業の漁業や土建業は衰退が続く。このため、地元経済界などから、交付金がもらえる文献調査への応募を求める声が上がった。これに対し、市民団体や漁協が反対の請願を6件出して対抗するなど、島を二分する事態に陥っていた。今後の焦点は、比田勝市長の判断に移る。文献調査は、市長が応募を決めなければ始まらないからだ。市議会は9月12日に開会予定の定例会で、正式に推進の請願を採択する見通し。市長は16日、「特別委での議論・採決を踏まえて、さらに熟慮する」とコメントするにとどまった。早ければ9月議会で判断を示すとみられる。市長はこれまで文献調査について慎重な姿勢を崩していない。5月の定例会見で「手をあげて『20億円もらったからもうやめる』という考えはない」と述べていた。一方で、6月の市議会一般質問では「市議会での議論や市民の意見を参考にして判断する」と語った。 ●NUMOは歓迎 一方、今回の結果について、政府や処分場計画を進める原子力発電環境整備機構(NUMO)は歓迎する。岸田政権は「核のごみ」最終処分場の選定に全面関与する方針を打ち出している。5月末に成立した改正原子力基本法では、国が「地方公共団体その他の関係者に対する主体的な働き掛け」をすると明記された。経済産業省幹部は「(すでに文献調査を受け入れている)北海道の寿都(すっつ)町と神恵内(かもえない)村に加えて、対馬でも一歩進んだのは大きい。この動きが他の自治体にも広がってくれればいい」と話す。ただ、対馬市については世論が二分していることから、「まずは地域で丁寧に議論を深めていただくのが重要」(西村康稔経産相)との姿勢を保ってきた。NUMO関係者は、市議会特別委の結論を強調し、「これで市長が反対したら、請願で示された『民意』はどうなるのか。国家のエネルギー政策は重い。『入り口』である文献調査は受け入れるべきではないか」と話す。
| 財政 | 03:49 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
PAGE TOP ↑
