左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。
|
2025,02,03, Monday
(1)農家への所得補償(直接支払い)は最終解でないこと
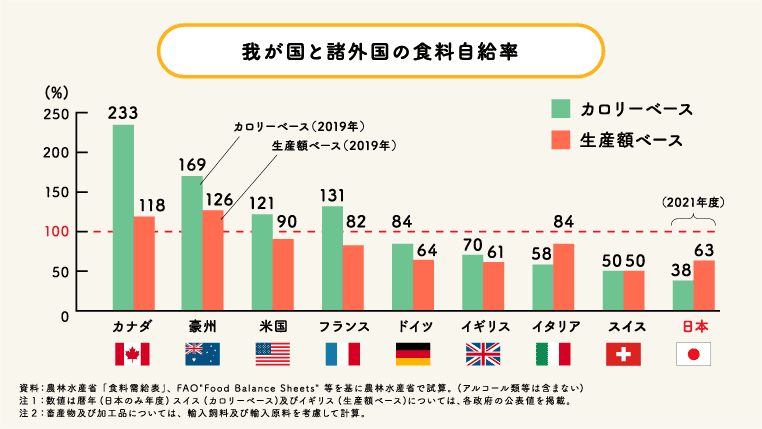 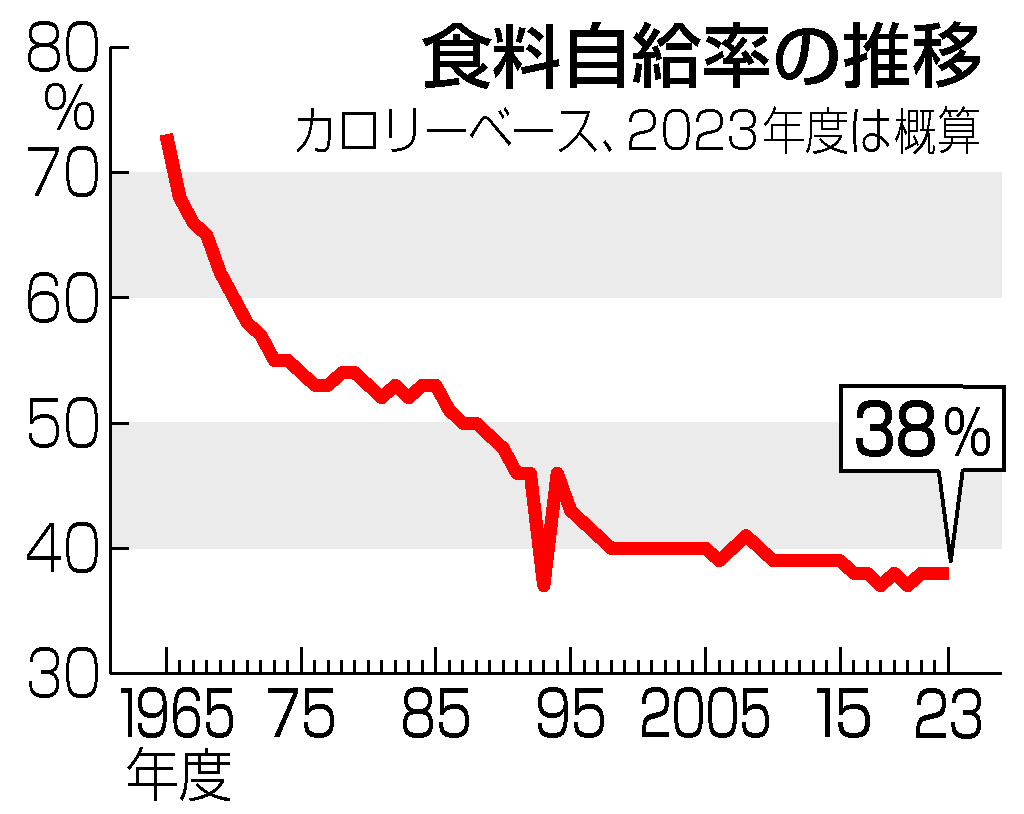 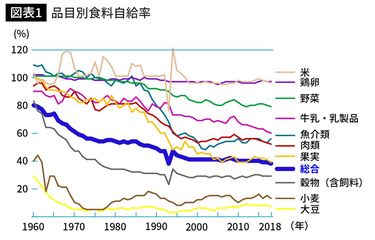 (図の説明:左図は、我が国と諸外国のカロリーベースと生産額ベースの食糧自給率の比較だが、カロリーでは必要な需要を満たした割合はわからず、生産額では単に高いだけかも知れないため、品目別の国内生産重量が需要重量に占める割合《重量ベース》が最も現状を表しているだろう。また、中央の図は、我が国のカロリーベースの食料自給率の推移だが、これは一貫して下がって2023年度は38%にすぎないため、農業政策の是非が問われるわけである。なお、右図は、品目別食料自給率で、米や鶏卵の最終製品は100%に近いが、途中で海外産の資材や餌を投入している製品は、厳密には国産に入れるべきでない) *1-1-1・*1-1-2・*1-1-3は、①日本の食料自給率の長期低迷と農家戸数・耕作面積減少に歯止めがかからず、原因を突き詰めるべき ②持続可能な食料安全保障を確立するため、これまでの農政の効果を検証する必要 ③立憲民主党・国民民主党は戸別所得補償制度(直接支払制度)という観点から提起を始め、石破首相・森山幹事長も「直接支払いの議論を深める」と語った ④農水省は通常国会に農産物の価格転嫁を後押しする法案を提出予定だが、納税者負担による直接支払いの是非が論点として浮上するのは間違いない ⑤「農家の手取り増を実現させる」という石破首相の強いリーダーシップを期待したい ⑥石破政権の「令和の日本列島改造」「地方創生2.0」に「農家の直接支払い」は含まれない ⑦農家数激減から農家への直接支払いは不可欠 ⑧農林業センサスを見ると、高齢化・中小零細農家淘汰で、2005年に208万5000あった農業経営体数は2020年は109万2000まで半減、10haを境に中小零細農家の淘汰が急速に進んだ ⑨2024年5月の食料・農業・農村基本法の見直しは、従来の大規模化による農業の生産性向上政策が前提で、農家数がさらに減少し、農村コミュニティー維持困難 ⑩工場誘致で零細農家も兼業で生き残っていたが、その条件も失われて大規模化が進んだ ⑪円安インフレで農薬・肥料・飼料・燃料の輸入価格が上昇して農業経営を圧迫 ⑫農家の経営困難を救う所得政策が不可欠 ⑬改正基本法はITを使ったスマート農業技術で規模拡大を図ろうとするが、人口減少が進めば地域で学校・病院を維持できず、ますます人が住めなくなる ⑭農業と農家の衰退状況から、欧米並みの農家への直接支払いを導入することが急務 ⑮農水省が2025年度から始まる中山間地域等直接支払制度の次期対策で「集落機能強化加算は継続しない」という方針を示した ⑯加算を終了する理由の1つに「地域運営組織の設立・連携を行うという趣旨が十分に伝わっていなかった」と都道府県・市町村への説明不足を挙げた ⑰集落機能強化加算は「高齢者の見回りや送迎など、生活支援・集落機能強化・ボランティア確保・インターン受け入れといった人材確保を支援している」 ⑱効果を評価していたのに一転、2025年度予算概算要求で加算の廃止が判明 と記載している。 ここで述べられているポイントの第1は、①②から、食料安全保障を確立するために、食料自給率が長期にわたって低迷し、農家戸数・耕作面積が減少している原因を突き詰めて、農政の効果を検証すべき ということだ。 「腹が減っては戦は出来ぬ」と言うように、いざと言う時に国民が飢えたり、栄養失調になったりするようでは、武器ばかりあっても戦が出来ないのは昔から常識であり、そのため「兵糧攻め」や「水攻め」は味方の兵力を損なわずに相手を屈服させる常套手段となっているのである。 その点、日本の農政は、食料自給率が長期にわたって下がり続け、耕作面積も減少しているため、私は「農業政策を検証しなければならない」という主張に賛成だ。しかし、戸別所得補償制度(直接支払制度)による農業振興では、本物の農業振興にならないため、ポイントの第2~第4に、その理由を記載する。 ただし、*1-5のように、日本の食料自給率はカロリーベースで測られているが、人間はカロリーだけで、まして米や芋だけで健康に生きられるわけではない。そのため、栄養バランスを加味した自給率は、現在、需要のある食品毎の重量に対して国内産(海外産の資材で育てられたものは、当然、除外すべき)の割合を出すのが適切であり、主食と副菜の区別も不要である。 また、ポイントの第2として、③④⑤⑥⑦⑫⑭のように、地方創生には、農家の手取り増を実現させるため、農水省の農産物への価格転嫁後押し法案ではなく、農家の経営困難を救う欧米並みの戸別所得補償制度(直接支払制度)を行なって農家数の激減を防ぐべき であり、事実、⑧のように、農林業センサスでは、高齢化や中小零細農家淘汰により、2005年に208万5000あった農業経営体数が2020年は109万2000まで半減し、特に10ha以下の中小零細農家の淘汰が急速に進んだ という主張がある。 しかし、農業の生産性向上による農業所得拡大には機械化や装置化が必要不可欠であり、それができるためには、経営体の規模拡大が必須である。にもかかわらず、これまで中小零細農家が多く、それを温存してきた理由は、戦後の農地改革で小作農が耕作してきた農地を得て自作農になり、家業として農業を引き継いできたからで、細切れの農地が望ましいからではない。 そのため、高齢化による離農をチャンスとして農地を大規模経営体に集約しつつあり、戸別所得補償制度(直接支払制度)がなければ離農したいような中小零細農家は離農しても良く、その農地は大規模経営農家や農業法人に集約すれば良い仕組にしているのである。 なお、ポイントの第3として、⑨⑩⑪⑫のように、円安インフレで農業資材の輸入価格が上昇して農業経営を圧迫し、工場誘致による兼業で支えていた零細農家もさらに減少して、農村コミュニティーが維持困難になっているが、2024年5月の食料・農業・農村基本法見直しは、従来の大規模化による農業の生産性向上政策が前提で大規模化がさらに進んだ とされている。 しかし、円安インフレによる農業資材の高騰は優に想定を超えていたものの、「2024年5月の食料・農業・農村基本法見直しは、従来の大規模化による農業の生産性向上政策が前提で大規模化がさらに進んだ」というのは、本来の意図通りなのである。そして、今回の円安インフレによる輸入価格上昇が経営を圧迫しているのは零細農家だけではなく、輸出企業でない経営体全体の話であり、それでも零細兼業農家を皆が払った税金で支えなければならないかについては、国民全員が支払っている税金であるだけに疑問である。 さらに、ポイントの第4は、⑬⑮⑯⑰⑱のように、改正基本法はITを使ったスマート農業技術で規模拡大を図ろうとしているが、人口減少が進めば地域で学校・病院を維持できず、ますます人が住めなくなる上に、集落機能強化加算は高齢者の見回りや送迎などの生活支援・集落機能強化・ボランティア確保・インターン受け入れといった人材確保を支援しているにもかかわらず、農水省が廃止を表明した としている。 確かに、中小零細農家の離農が進んで住民が減れば、農村コミュニティーが維持困難になり、人口減少が進めば地域で学校・病院を維持できず、ますます人が住めなくなりそうなのはわかるが、スマート農業を行なう大規模経営農家や農業法人の経営者・従業員が住んだり、別の場所に住んで農地に通ってきたりもできるため、住民の暮らし方を変えれば良いのではないだろうか。何故なら、現状維持ばかり主張しても、むしろ現状維持はできないからである。 なお、集落機能強化加算は、「高齢者の見回りや送迎などの生活支援・集落機能強化・ボランティア確保・インターン受け入れといった人材確保を支援している」のだそうだが、若者の農業離れは農業が面白くない産業だから起こっているのではなく、ムラのために無償労働をしなければならないことが多く、ムラの“文化”による縛りが強いからだと言われている。そのため、高齢者の見回りや送迎などの生活支援や環境の維持は、介護制度やシルバー人材などを使って、ボランティアではなく、正当な費用を払って行なわれるべきであろう。 (2)米作の温暖化への適応と令和の「コメ騒動」 *1-2-1は、①温暖化で水稲の生育可能な期間が延び、再生二期作が広がってきた ②島根県の農事組合法人ふくどみは、2024年4月下旬、1haに早生品種を移植し、8月下旬に1度目の収穫を行って追肥し、11月下旬に2番穂を収穫して、10aあたり762kg確保 ③茨城県のJA北つくばは2024年産で「にじのきらめき」など約1haで実証し、10a収量は2度の収穫で計712kg ④2番穂を収穫しても、収穫せずにすき込んでも「労力は大差ない」 ⑤農研機構の2023年研究成果では、福岡県内の試験で「にじのきらめき」の10a収量は2回合計で950kgで、1番穂を地際から40cmと高く刈ることで地上部に栄養を多く残し、2番穂の収量を確保できるとする としている。 野生の稲は、もともと熱帯~亜熱帯地域に広く自生し、多年生型(結実後も親株が枯れず株が生き続ける)・1年生型(種子により毎年繁殖して枯れる)とその中間型がある。そして、日本でも弥生時代は稲穂だけを刈り取る多年生型栽培法がとられ、現在のように田植えをして1年生型栽培の方法が常識となったのは、比較的新しいのだ。 そのため、①のように、日本が温暖化して亜熱帯に近くなれば、穂の近くだけを刈り取って二期作できるようになるのは自然なことである。そして、その二期作では、②③は1度目の収穫時に地際から刈り取ったため、2回の合計で10aあたり700kg代の収穫しかなかったが、④は地際から40cmと高く刈ることで地上部に栄養を多く残したため、2回の合計が10aあたり900kg代になっている。 1回目の収穫では穂を刈り取りさえすればよいので、残りの茎はできるだけ長く残した方が、2回目の収穫が多くなるのは必然で、④の「労力」は、二期作することを前提とした収穫機ができれば、全く大差なくなるだろう。 そのような中、*1-2-2は、⑥昨夏、店頭からコメが消え、昨年末から1月中旬までに3割価格上昇したコメに、政府は備蓄米放出体制をようやく整えた ⑦遅れた背景は米価維持のため生産抑制に重点を置き、消費者への意識を欠いていること ⑧備蓄米放出での値下がりを睨んで、1月24日以降値上がりが止まった ⑨流通を急に増やして米価が値崩れすることを過度に警戒するのは長年の減反政策のため ⑩政府は2018年に農家や生産者の自主性を重んじるため、主食米の生産量を都道府県に指示するのをやめたが、農家にコメから麦・大豆・飼料用米への転作を促す補助金は残した ⑪水田活用「直接支払交付金」は、2015~2023年は年平均3200億円程度の横ばいで、2018年の減反廃止後も減らず ⑫政府が産地毎の農家やJAなどに需給見通しに基づく生産量の「目安」を示す仕組みも残した ⑬需給見通しには訪日外国人の急増による需要の広がりが織り込まれていない ⑭生産調整と引き換えに受け取る補助金収入に依存する零細農家が多い ⑮コメの生産コストは0.5~1haでは2万円/60kg超だが、15~20haでは1万円強/60kgと半分になる としている。 ⑦のように、政府が、米価維持目的の生産抑制に重点を置いて、消費者への意識を欠いているのは、何もコメに限ったことではないが、その結果として、*1-2-3のように、2024年の2人以上世帯の消費支出は月平均で30万243円と名目では増えたが、実質では前年比1.1%減という結果になった。これは、物価上昇によって国民が貧しくなり、食料品等の必需品にも節約志向が及んで、「エンゲル係数」は28.3%と1981年以来43年ぶりの高水準になったという統計数値にも出ている。 ちなみに、「インフレになれば、将来の物価上昇を見込んで現在の需要が高まる」と言う人がいるが、「将来、食料品が値上がりする」と考えて、現在、10~20年分の食料品を買い溜めする人などおらず、むしろ将来の物価上昇に備え、現在は節約して貯蓄を増やすものである。 しかし、日本政府は「(本来の意味とは逆の)2%のインフレ目標」を掲げて、「インフレになれば賃金が上がる(実際は、そうはならない)」と言って物価を上昇させ続け、⑥⑧⑨のように、米価も高止まりさせた結果、米価は2024年12月に2023年12月の1.7倍となり、コメは必需品であるため、「令和のコメ騒動」となったわけである(https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250128.html 参照)。 そして、所得の低い層や年金生活者の中には、食事の回数や量を減らしている人もいるのだが、農水省は、*1-2-4のように、大凶作などに限っていた(⁇)方針から転換して政府備蓄米を放出し、1年以内に同量を買い戻すそうだが、米不足の時に備蓄米を放出するのは備蓄の目的の範囲内だと考える。 なお、政府は、⑩⑪のように、農家や生産者の自主性を重んじるために、2018年に主食米の生産量を都道府県に指示するのをやめたそうで、私は、それは良いと思う。また、農家に自給率の高いコメから自給率の著しく低い麦・大豆への転作を促す補助金を残したのも妥当だと思うが、家畜飼料に米が最も適しているかどうかについては異論がある。 さらに、⑫⑬のように、「政府が産地毎の農家やJAなどに需給見通しに基づく生産量の目安を示す仕組みを残したが、その需給見通しに訪日外国人の急増による需要の広がりは織り込まれていなかった」そうだが、中央政府が日本全国の生産量の目安を示したり、需要の変動を加味して在庫管理したりするのは無理であるため、生産計画は民間に任せ、許容できない価格変動をした場合に備蓄米というシステムを使って価格調整するのが適切ではないかと思う。 そして、⑭の生産調整と呼ぶ減反政策と減反の見返りに配る補助金は止め、⑮のように、大規模生産が著しく生産コスを下げる米・麦・大豆のような作物は、大規模生産し、生産方法も改善して、国際競争力を持つ生産コストにするのが本当の改革だと考える。 (3)中山間地と畑作物について 「中山間地は、耕地面積が狭いので農業に不利」という主張もよく聞くが、*1-3-1は、①広島県の農業法人は、冷涼な標高800mの山間部から瀬戸内海に面する低地までの県内5市で気温差を生かした栽培をしてリレー出荷し、約130haの全国有数規模でキャベツを周年出荷している ②ドローン・営農支援アプリでの作業記録管理と確認・自動収穫機・QRコードでの苗管理・自動操舵システム搭載トラクターなどのスマート技術を組み合わせて効率を高め、中山間地に適した作業体系を確立している ③農地は農地バンクを通じて借りるなどし、1カ所当たり10~20ha規模に集約した ④大規模生産を支えるのは、スマート技術による作業の効率化 ⑤ドローンを約20台所有し、農薬散布ではトマト・ネギ・サツマイモ・飼料作物も含めて計500ha規模で活用 ⑥搭載カメラで撮影した畑の画像を解析して収量を予測したり、鹿対策として赤外線カメラで畑周りの生息域を特定し、効率的な捕獲に繋げたりしている ⑦20人ほどの従業員が移植・収穫・次作に向けた農地準備の3班に分かれて作業 ⑧生鮮用やカットサラダ等の加工・業務用としても出荷 としている。 「米か芋さえあれば、人間は生きられる」わけではなく、肉・魚・野菜・果物もバランス良く摂取しなければ健康を保つことはできない。そのため、①のように、中山間地の高低差を利用したり、南北に長い日本の国土を利用したりしてリレー出荷するのは良いアイデアだと思う。 この時、生産効率を上げるには、②のように、スマート技術を組み合わせて使う必要があるが、現在は、米の生産と比較して中山間地でのスマート化は遅れていると言わざるを得ない。しかし、中山間地であっても、③のように、10~20ha規模に集約して、④⑤⑥のように、スマート技術で大規模生産を支えなければ、コスト競争に負けそうだ。 そのため、*1-3-2のように、全国のプロ農業経営者14人が発起人となり、新組織を立ち上げて、「中山間地の狭い農地でも効率的に作業できる農機」「コストを抑えた環境に優しい肥料」「生産現場が使い易い農業技術の開発・普及」のため、農家の視点を取り入れた技術で、農機メーカーはじめ農業関係の企業・団体と作業負担の軽減や生産コストの低減等の経営課題解決を目指しているのは重要なことである。 さらに、⑧のように、生鮮用やカットサラダ等の加工・業務用としても出荷し、さまざまなニーズに対応することは、無駄をなくし、付加価値を増やすことに繋がる。 従って、必要な農機具を迅速に開発して(海外も含む)必要な場所に速やかに提供できるようにしたり、生産物の適格なマーケティングをしたりするために、(農業自体や農業機器の生産も産業なので)農水省と経産省が合併し、双方が長所として持っている知恵を共有するのがBestだと、私は考える。 なお、⑦のように、20人ほどの従業員が移植・収穫・次作に向けた農地準備の3班に分かれて作業しているとのことだが、有能な従業員を集め、待遇を良くすることができるためには、後で書くとおり、さまざまな方法があるため、政府は規制でそれを妨げないようにすべきだ。 (4)農業に関するその他の意見 1)キャノングローバル総合研究所の「農業に関する6つの提言」 キャノングローバル総合研究所は、*1-4のように、「現在の農政は、基本原則だけでなく、政策手法についても大きな間違いを犯している」として、食料・農業・農村基本法見直しに関して、国民全体の利益という視点から、食料安全保障・多面的機能という利益を確保・向上させる方法を記述している。 確かに、「OECDが開発したPSEという農業保護の指標は、財政負担によって農家の所得を維持している「納税者負担」と、国内価格と国際価格との差(内外価格差)に国内生産量をかけた「消費者負担」(消費者が安い国際価格ではなく高い国内価格を農家に払うことで農家に所得移転している額)の合計である」というのは、尤もであり、正しい。 そのため、「農家受取額に占める農業保護PSEの割合は、2020年時点でアメリカ11.0%、EU19.3%に対し、日本は40.9%(約4兆円)と高く、日本の農業保護は消費者負担の割合が圧倒的に高い」「日本は直接支払いが少ないことで、欧米の方が手厚い農業保護を行っていると主張する農業経済学者がいるが、事実ではない」というのも、そのとおりだろう。 そして、GDPが大きい筈の日本より、外国の市場の方が豊かさを感じることから、これらは体感とも一致している。旅行や出張で海外に行った時には、その国の市場・スーパー・デパートなどに寄って売られているものの種類・分量・価格を日本と比較すれば、その国の人の暮らし・物価水準・日本における高関税の状況がわかるので、お薦めする。 「日本における高関税の理由は、欧米は直接支払いであるのに対し、日本の農業保護は価格支持中心で国内価格が国際価格を大きく上回るため、輸入品にも高関税をかけなければならず、その関税で農家を守り、それを負担しているのは消費者である」というのも、そのとおりである。 つまり、消費者は国産農産物の高い価格を維持するために、輸入農産物に対する高い関税も負担し、農業保護のため国内消費者が負担する額は「内外価格差に国内生産量をかけたPSE+輸入農産物にかかる高い関税」の両方なのである。これに対し、輸出国であるアメリカやEUは輸入が少ない上に関税も低いので、輸入農産物による消費者負担は殆どなく、PSEを国民負担と考えてよいのだそうだ。 アメリカもEUも、価格は市場に任せ、財政からの直接支払いによって農家所得を確保しており、直接支払いの方が価格支持より優れた政策であることは、世界中の経済学者のコンセンサスだそうだ。何故なら、価格支持は、市場で実現する価格よりも高い価格を農家に保証するため、需要は減少するが供給は増え、需給が均衡する市場では起きない過剰が生じるからだ。 そもそも、日本では1995年まで戦後の食糧管理制度が残っていたこと自体が不作為だが、それを廃止した際、高い米価を維持するために減反で供給を減少させることを選択し、日本政府は過剰米を防ぐために補助金を出して減反し、その結果、農家のやる気を削いで食料自給率低下と耕作放棄地の増大を招き、金を使った上に食料安全保障からはかけ離れた状況になったのだ。 そこで、*1-4は、提言として「①消費者に負担を強いる農政を転換しよう」「②減反を廃止するだけでよい」「③私的経済の活用で国民負担を減らせ」「④市場を歪ませ不正を生んだ政策の是正を」「⑤食料自給のためにも米の増産と輸出を」「⑥肥大化した農政をスリムにしよう」を主張している。そして、米価高騰時に物価対策とは逆のことを行っている自民党農林族・JA(農協)・農水省の農政トライアングルを挙げているが、JAは自民党の得票源であり、得票を増やすにはJA傘下に多くの農家がいた方が良いことから、この構造改革は大変だろう。 しかし、日本国民の炭水化物摂取の多くは既に米からパンに移り、小麦は消費量の14%しか自給していないのだから、麦や大豆(蛋白質を多く含む)の生産拡大を推進する補助金は必要である。そして、この補助金は私が衆議院議員時代に増やしたもので、1970年からの減反(単に米の生産を止めて休耕田にすること)とは、意図が全く異なる。 さらに、*1-4は、「財務省は減反の補助金を払いたくないため、水田を畑に転換するための補助金を支出しようとしているが、日本に適した農産物は米だ」としている。しかし、必要な栄養をバランス良く摂取するための食糧生産は、米か小麦かの2択ではないし、日本に最も適した農産物が米とも限らない。それに加えて、数年前の国産小麦はパンを作っても膨らみが悪い上に高かったが、品種改良のおかげか現在は膨らみがよくなり、円安で輸入小麦との価格差も小さくなっている。そのため、製粉業界も小麦の品種改良・イースト菌の改良・小麦生産の低コスト化などに協力したらどうかと思う。 なお、*1-4は長いので逐一コメントはしないが、農地の集約が進めば生産コストが下がって国際競争力のある農産物価格になり、消費者負担が減ると同時に、農家所得は増えて農業が魅力的な職業になる。また、産出国や品種による違いを除けば、一物一価でなければおかしい。さらに、最近の米は低温保存で新米と古米の味が違わなくなったので、牛乳等ももっと日持ちして無駄のない保存方法がある筈だ。そのため、それらの進歩を活かすシステムが必要なのである。 2)Presidentの「卵の自給率」など なお、*1-5-1は、最近値段の上がった養鶏農家の集約化と大規模化が進み、10万羽以上を飼う大規模養鶏場も珍しくなく、大規模養鶏場だけで全国の飼養羽数の75%を占め、卵も鶏肉も同様の傾向だが、飼料の大半は主に米国からからの輸入とうもろこしで、これを考慮すると自給率は10%程度だそうだが、それでは食糧安全保障に資さない。 また、卵も最近値段が上がったが、*1-5-2のように、2025年1月31日時点で、今シーズン(2024年秋~2025年春)の鳥インフルエンザは14道県48件発生し、約911万羽が殺処分になり、それと同時に卵の価格が上がって、東京地区ではMサイズで305円/kgとなり、1月上旬から80円上昇したのだそうだ。 しかし、2022年に過去最大の鳥インフルエンザが発生し、26道県84件、約1771万羽が処分されて、東京地区の卸売価格は350円/kgとなり「エッグショック」と呼ばれたが、その後も、鶏舎を改良して一部で鳥インフルエンザが発生しても全体には感染せず、ヒステリックに何万羽も殺処分しないですむようにするとか、外部から鳥インフルエンザウイルスが入り込まない鶏舎の造りにするなどをしなかったのは、むしろ不思議である。 そのため、卵の価格を上げる目的で、鳥インフルエンザと称して鶏を殺処分しているのではないかと思われ、このような後ろ向きのことを改善もなく何年も何年も国費で行ない、養鶏農家を集約したり、卵の価格上昇で消費者負担を増やしたりするのは、論外だと考える。 (5)森林と林業の重要性 1)縄文時代は、本当に農業がなかったのか? *2-3は、①弥生時代に稲作が広がるまでは、クリやドングリを主体とした採集・狩猟・漁労で食料を得ていた ②イネとともにアワやキビが伝わった頃、中国北部では雑穀を中心とした農業社会が起きていた ③縄文時代晩期末の七五三掛遺跡(長野県小諸市)から出土した縄文人の骨のコラーゲン炭素同位体から、アワやキビを食べていた ④縄文時代の畑は確認されておらず、農業社会には至っていない ⑤縄文人は食料生産のために自然を改変する発想がなく、存在するものを管理して収穫増を計るが、植物を育てる田畑を作る発想はなかった ⑥縄文人は周囲をある程度管理して、ヒエやマメ科のダイズ・アズキの栽培化が進んだ ⑦栽培化と農業は同時期に起きたと考えられていたが、急に農業が確立したのではなく、徐々に進んで農耕という程ではないが、管理した土地の周辺のものを採集していた時期があった 等としている。 しかし、我が国の縄文文化を代表する三内丸山遺跡は、縄文前期中葉から中期末葉の約1,700年間の生活の痕跡が継続して発見されるが、遺跡の広がりは約42haと広大で、各時期のゴミ捨て場や盛土は大量の遺物を含み、約1,000年間に廃棄物が堆積した厚さは約2mに達し、その中には土偶・北海道産/長野県産黒曜石・新潟県産ヒスイ・岩手県久慈産琥珀・アスファルトなど特定の産地でしか採れないものもみつかり、交流・交易の範囲の広いことがわかっている。 これは、住民全員が狩猟・採集・漁労などの食糧獲得活動をしなくても、別の生産活動をするプロを養えるだけの生産性の高さが農業にあったということだ。事実、三内丸山遺跡ではクリやクルミをはじめ木の実が多く出土し、土壌中から大量のクリ花粉が検出され、その量的な比率から集落周辺にはクリの純林が広がっていたと推定されるが、クリは人が下草を刈るなどして成長を助けなければ純林にならないため、各種自然科学分析の結果を総合すれば、縄文人は集落の周囲の林に手を加えて有用な植物が育ちやすい環境を作り出し、持続性の高い生活を営んでいたことがわかるそうだ(https://www.bunka.go.jp/prmagazine/rensai/news/news_002・・・ 2021年8月3日文化庁文化財第二課埋蔵文化財部門 参照)。そのため、①は、農業を「稲作」「畑作」と定義し、クリやクルミの栽培を「採集」に分類している点が誤りであろう。 また、②③のように、七五三掛遺跡出土の縄文人がアワやキビを食べていたことから、縄文晩期に長野県に農業社会があったことは確実で、④の「縄文時代の畑は確認されていない」というのは、田畑は数年放置すれば草地や森に戻るため、「畑が確認されていない」ことをもって「農業社会には至っていない」とは言えず、⑤のように、縄文人は「食料生産のために自然を改変する発想がなかった」とも言えない。そして、人が下草を刈ってクリの木を増やし木の成長を助けたり、アワやキビを栽培したりして、作物の生産性を上げるのは、農業そのものである。 そのため、⑥については、縄文人は、ヒエやマメ科のダイズ・アズキの栽培化を進め、⑦については、人が手を加えて栽培し、生産性を上げ始めた時点が農業の始まりというのが正しいだろう。そして、農業に限らず、技術は生産性の向上を目指して良い物を取り入れながら徐々に進むが、持続可能であるためには、どの時代であっても環境を維持管理することが必要不可欠で、食糧の生産量に応じて養える人口には上限があるわけである。 2)現在の森と林業 イ)鳥獣被害対策 (5)1)で述べたとおり、縄文時代から近年までは、集落の周辺にクリやクルミの林を作ったり、森の動物を狩猟したり、森の恵みを採集したり、森の木を伐採して建物を建てたりして、森林をフル活用していた。 しかし、最近は、*2-2のように、「クマによる人身被害が急増している」と何年も騒ぎ続けながら、警察署の横にある建物の中に入った熊でさえ警察官が見守るだけで手を出せなかったり、「シカやイノシシ等の野生動物による農業や林業への被害が深刻だ」と何年にも渡って言い続けながら、有効な手を打たなかったりすることが頻発している。 また、「野生鳥獣による農作物被害額が2022年度に156億円に及び、その約6割がシカ・イノシシによるため個体数の管理は必要だ」と言いながら、せっかく猟友会がシカやイノシシを狩猟しても「駆除して減らす」だけで利用しないことが多いため、現代人の個人的能力は縄文人以下のように思われる。 なお、「ハンターは趣味の愛好家で、地域のためにボランティアで活動しているため、ハンターの高齢化や数の減少が止まらない」という話も、私が衆議院議員時代から聞いているのに、未だに解決されていないため、大学で森林管理・生態系・狩猟学を一体で教えて森林と野生生物を管理することは重要である。 そして、それは、人口減の時代であっても、*4-1のように、若くして退官する自衛官の希望者に森林管理・生態系・狩猟学などを教えて「森林レンジャー」として雇用したり、国有林で自衛隊の演習をかねて狩りを行い、多すぎる野生鳥獣を減らせば、森林の問題点把握・保護活動・自衛隊の演習が同時にできる。また、民有林であっても、クマが出て危険な場所は、地方自治体などが「森林レンジャー」を雇用して有効に管理するのが良いと思う。 なお、一般住民のゴミの出し方にまで注文が多いと、一般住民も住みにくい上に、ゴミを出せないゴミ屋敷が著しく増えるため、地方自治体が工夫してゴミを出しやすいシステムにすべきである。そして、これらについて、人手不足は言い訳にならない。 ロ)水を育む森林(水源林) *2-1は、①東京都は、水源林として主に山梨県の多摩川上流にある森を買い続け、25,000ha所有する ②1960年代に利根川・荒川水系が上水道に本格利用されるまで、多摩川は都民の「命の川」であり、水源地の荒廃を憂えた東京府(当時)が自ら管理を始めた ③植林を進め、土砂の流出や災害を予防し、きれいな水を確保することが目的だった ④山梨県小菅村の森の中で源流域保全のために間伐や枝打ちをする担い手はボランティアの「森林隊」 ⑤世界では各国政府主導の緑化の取り組みは遅々として進まず、地球温暖化もあいまって森林面積は減り続け、それに伴う水不足も深刻化している としている。 水もまた食糧と同様、人口の上限を決める上、農業用水や工業用水も必要であるため、水源林の保全は重要だ。そのため、①②③の東京都の事例のように、大量の水を利用する豊かな自治体が、植林を進め、土砂の流出や災害を予防し、きれいな水を確保する目的で森を買って自ら管理するのは望ましいことだと思う。 しかし、⑤のように、各国政府主導の緑化の取り組みは遅々として進まず、森林面積が減り続けて水不足も深刻化するのは論外であるとしても、④のように、日本も「源流域保全のために間伐や枝打ちをする人が意識の高い無償ボランティアで、水を当然のように利用している人は利益を得る」というのも理屈に合わない。そのため、水源林の保全のためにも、労働に見合った適切な報酬を支払って「森林レンジャー」を雇用することが必要不可欠である。 (6)その他の人手不足業種 1)埼玉県八潮市の道路陥没事故と上下水道の更新    2025.1.28防災危機管理News 2025.2.3毎日新聞 2025.2.3日経新聞 (図の説明:左図のように、重機が入っているだけで、命をかけて人を救助する筈の多くの消防隊員は突っ立っている。また、中央の図のように、何日もかけてスロープを作ると決定した段階で、被害者である運転手は見捨てられたのだ。そして、右図は、スロープができたら、スロープの強度を高めたり、土嚢を入れたりしているのであり、被害運転手の救助という最大の課題はとっくに忘れ去られている) *3-1-1・*3-1-2・*3-1-3・*3-1-4によると、①28日午前に埼玉県八潮市で県道が陥没してトラック転落 ②「穴の内部に水が溜まり周囲の地盤が不安定で崩落による二次被害の可能性を否定できない」として、2月2日夜になっても消防の救援隊が穴の中に入って運転手を捜索する活動に入らない ③県は穴に繋がる緩やかなスロープ2本を造成し周辺で土壌改良を実施する大規模な工事を続け、現場はショベルカー等の重機やトラックが行き来し、2月1日朝に完成したスロープの強度を強めたり、土囊を入れたりする作業をした ④県等はスロープの完成を受けて本格的な救助活動を進める予定だったが、穴内部の水位が上昇し、消防隊員らの安全確保のため救助活動を中断 ⑤県は破損した下水道管の水の流れが悪くなっているため、管内になんらかの異物があるとみて、ドローン等を使って調査する方針 ⑥運転手の70代男性が閉じ込められた運転席は土砂等に埋もれて確認できない ⑦2月5日に行われた県のドローン調査で、陥没地点の100~200m下流の下水道管(直径4.75m)内にトラックの運転席部分とみられるものが確認 ⑧運転席部分とみられるものが見つかった下水道管内は、水流や硫化水素の影響で人が近づけない ⑨一部が流水につかり、男性の姿は確認できなかったが、県や消防は男性がこの周辺にいる可能性があるとみている ⑩消防は2月9日朝、安否不明となっている70歳代の男性運転手の重機での捜索を再開、手がかりが見つからず、崩落による二次被害の懸念が高まり、約30分で打ち切り ⑪運転席部分とみられるものが見つかった下水道管内の捜索を検討したが、同日、トラックの男性運転手の穴の中での捜索を終了した ⑫県は2月10日、管内を常時監視する機材を投入するため、地表に細い穴を開けた としている。 上下水道インフラが適時に更新されず老朽化が進んでいることは前から言われていたが、①の1月28日午前に埼玉県八潮市で県道が陥没してトラックが転落した事故は、想像以上だった。 しかし、事故対応は、②③④⑥⑩のように、「運転手の70代男性が閉じ込められた運転席は土砂等に埋もれている」と考え、県等は「穴の内部に水が溜まり、周囲の地盤が不安定で崩落による二次被害の可能性を否定できないため、スロープが完成すれば本格的な救助活動を進める」として、重機でスロープ2本を造成し、土壌改良を実施する大規模工事を続け、2月1日朝に完成したスロープは強度を強めたり、土囊を入れたりする作業をしたりしていたが、2月2日夜になっても消防の救援隊は穴の中に入って運転手を捜索する活動に入らず、「穴内部の水位が上昇して消防隊員らの安全が確保できない」などとして救助活動を中断した。 そして、丸12日後の2月9日朝、消防は、安否不明となっている70歳代の男性運転手の重機での捜索を再開したが、手がかりが見つからず、崩落による二次被害の懸念が高まったとして、約30分で打ち切ったのだ。そして、この間、メディアも、下水道の更新不足・危険性・更新にかかる費用・人手不足ばかりを強調して報道し、不慮の事故で下水道の中に閉じ込められ、最初は生きて消防士と話をしていた哀れな運転手の救助には滅多に触れず、重機で穴を掘ったり、スロープを作ったり、穴の周囲にぼさっと立っている人の写真ばかりで、「あらゆる知恵を出して、生きているうちに(短時間で)人を助け出す」という発想と努力に欠けていた。 そのため、事故に遭った70歳代の哀れな運転手は、下水道の危険性を世の中に広めるための生け贄のようになり、人命の尊さや人命救助のためにいる筈の埼玉県内の消防の無気力・無能を露呈したのである。 しかし、⑤⑦⑧⑨⑪のように、破損した下水道管の水の流れが悪くなっているため、管内に異物があるとみて、埼玉県が2月5日にドローンで調査したところ、陥没地点の100~200m下流の下水道管(直径4.75m)内にトラックの運転席部分とみられるものを確認したそうだ。 そして、トラックの運転席が下水道管の上流側に流れていくわけはなく、流されるとすれば必ず下流側であり、重たいため遠くには行かないので、重機で捜索すると同時に、速やかに下流側からドローンや既にある内視鏡型の排水管検査機器を使って、あらゆる角度からまず被害者である運転手を見つけて助け出すべきだったのだ。 また、県や消防は男性がこの周辺にいる可能性があるとみているが、下水道管内は、水流や硫化水素の影響で人が近づけないとして、同日、トラックの男性運転手の穴の中での捜索を終了したそうで、事故から1週間以上経過すれば被害運転手は亡くなっているだろうが、ここでも被害運転手は見捨てられたのである。つまり、これらは、人手不足の問題と言うよりは、人命尊重意識と教育・応用力・課題解決力・やる気の問題である。 なお、県は、⑫のように、2月10日、管内を常時監視する機材を投入するため、地表に細い穴を開けたそうだが、これは事故の被害者救出とは関係がない。しかし、今後の下水道管は、管内の様子を自動的に撮影して、位置と画像を無線で報告し、AIでリスク分析するシステムを備えた方が良いと思われる。 2)退職自衛官の再就職について *3-2は、①退職予定自衛官にバス・トラック・タクシーの運転手を紹介する「運輸業合同説明・運転体験会」が陸上自衛隊北熊本駐屯地で開かれ、119人が参加した ②部隊の強さ維持のため、自衛官の定年は一般公務員よりも早い54~57歳の「若年定年制」で、20~30代半ばで退職する任期制もあり、自衛隊は再就職支援に力を入れてきた ③大型車両の運転免許を持っている自衛官は多く、ドライバー不足に悩む運輸業界にとっては「即戦力」となる ④運輸業界から再就職した自衛官OBが説明役で、「健康なら定年なく長く続けられ、(乗客に)挨拶すれば特に会話しなくても構わない(タクシー)」「安定した生活を送れ、地域社会への貢献という点で自衛隊と通じる(路線バス)」等とPRした ⑤来年5月で退官する男性自衛官(55)は「人と接する仕事も楽しそうだし、仕事で運転しているので、路線バスかトラックの運転手を考えている」と話す ⑥熊本運輸支局の岩本輝彦支局長は「2024年問題で運輸業界は慢性的な人手不足で、自衛官は何事も自分で判断できるスキルもあり、どの会社も大いに期待している」と語った としている。 このうち②の「部隊の強さ維持のため、自衛官の定年は一般公務員よりも早い54~57歳」「20~30代半ばで退職する任期制もある」というのは、平均寿命や健康寿命が延びていることを考慮すれば、定年を延長しても良いし、平時は他の職業に従事しながら有事や災害時に招集される予備役として確保しておく方法もある。 しかし、自衛隊を若くして退職した人なら、①③④⑤⑥のように、体力と同時に経験や技量も持っているため、陸自出身なら大型車両の運転免許を活かして人手不足の運輸業界の即戦力として期待できる。そのため、経験や技量を活かした再就職支援をすれば、再就職後も地域社会に貢献でき、その職種は多少の研修をすれば、運輸業界だけではなく、機械化の進んだ建設業はじめ農業・林業でも活かせると思う。 また、空自出身で航空機やヘリコプターのパイロット資格を持っている人であれば、航空・運輸業界だけでなく農業・林業・救急でも即戦力になれそうだし、海自出身で航海士の資格を持っている人なら、運輸・漁業等で活躍できそうだ。つまり、現在は、人手不足で機械化の進む時代であるため、それに合わせた技量を身につけさせれば、人財を無駄なく活用できるのである。 (7)人手不足を言い訳にすべきではないこと 1)退職自衛官の活用 *4-1は、①岸田首相(当時)は、2022年11月28日、防衛費を2027年度にGDP比2%に増額するよう関係閣僚に指示 ②政府与党の「防衛族」は新たな装備品(長射程のミサイル・艦艇・戦闘機等)に予算を誘導しようとする ③現場が欲しているのは人と安心できるキャリアプラン ④安全保障を担う自衛隊・海上保安庁の現場は人集めに苦労 ⑤自衛官採用には定年と再就職先がネック ⑥地方自治体の防災監として採用されるケースも増えたが、正規職員のポストを用意できない ⑦恩給の支払いができなければ、若年定年退職者は社会保険料の企業負担分を国で面倒見るぐらいのサポートがあって良い ⑧制服組でも将・将補クラスは、天下り規制に引っかかって自衛隊独自の再就職斡旋システムを利用できない ⑨採用難と退職後のキャリアプランの難しさがある 等と記載している。 このうち①②は、多くが米国から長射程ミサイル・艦艇・戦闘機等の装備を購入する前提のようだが、i)どういう事態を想定し ii)どのような作戦の中で iii)どのようにその装備を使うのか iv)その有事の時に、(自給率の低い)食糧・エネルギーや武力攻撃に対応していない原発のリスクはどうするのか を全く考えておらず、プラモデルを集めるかのように、国民の血税を源泉とした大きな予算をつけているため、無用の長物を買っている無駄遣いと言わざるを得ない。 また、③④⑤⑨は「自衛官の採用には定年と再就職先がネックで、自衛隊は人集めに苦労し現場は人と安心できるキャリアプランを必要としている」とするが、退職自衛官は体力があり、独特の技量を持っているため、持っている長所をブラッシュアップして再就職すれば、(6)2)に記載したとおり即戦力になれる。そのため、再教育の仕組みと再就職の選択肢を示し、現役の頃からキャリアプランを意識して仕事をし、資格等もとっておくのが良いと思われる。 なお、⑥は「地方自治体で採用されるケースでは、正規職員のポストを用意できない」としているが、地方自治体は、女性や中途採用者を非正規職員にする場合が多く、これは能力や事情による待遇差ではなく、弱者からの搾取であるため、正規職員にすべきである。従って、⑦のように、「社会保険料の地方自治体や企業負担分について、サービスを受けているわけではない一般国民の税金で面倒見る」というのは、全く筋違いなのである。 さらに、⑧は、「制服組でも将・将補クラスは、天下り規制に引っかかって自衛隊独自の再就職斡旋システムを利用できない」としているが、天下りの問題が起こるのは自衛隊が装備品を購入する等の影響力を持つ企業に再就職する場合に限るため、「恩給+自らの能力で得た再就職で得る収入」で何とかすべきであり、これは50代で民間企業を転職した人も同じ条件なのだ。 2)就業者数は最多になっているが・・ 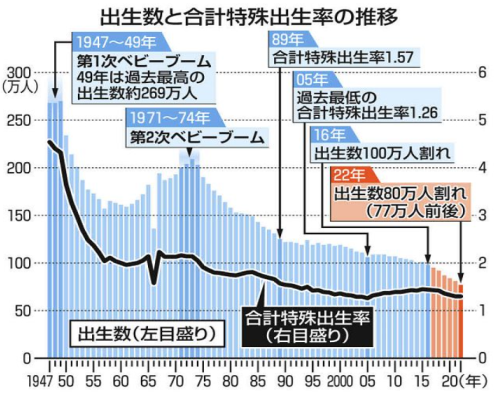 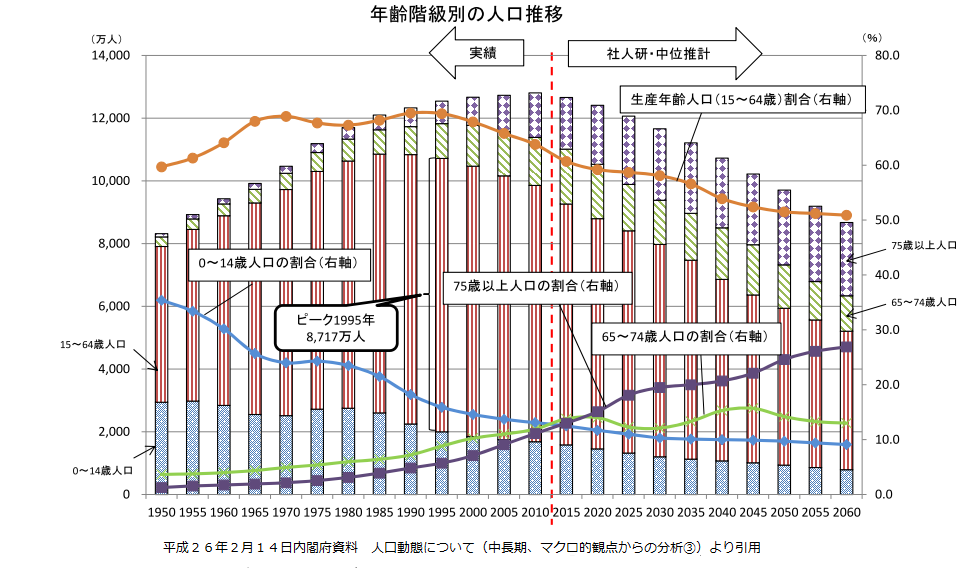 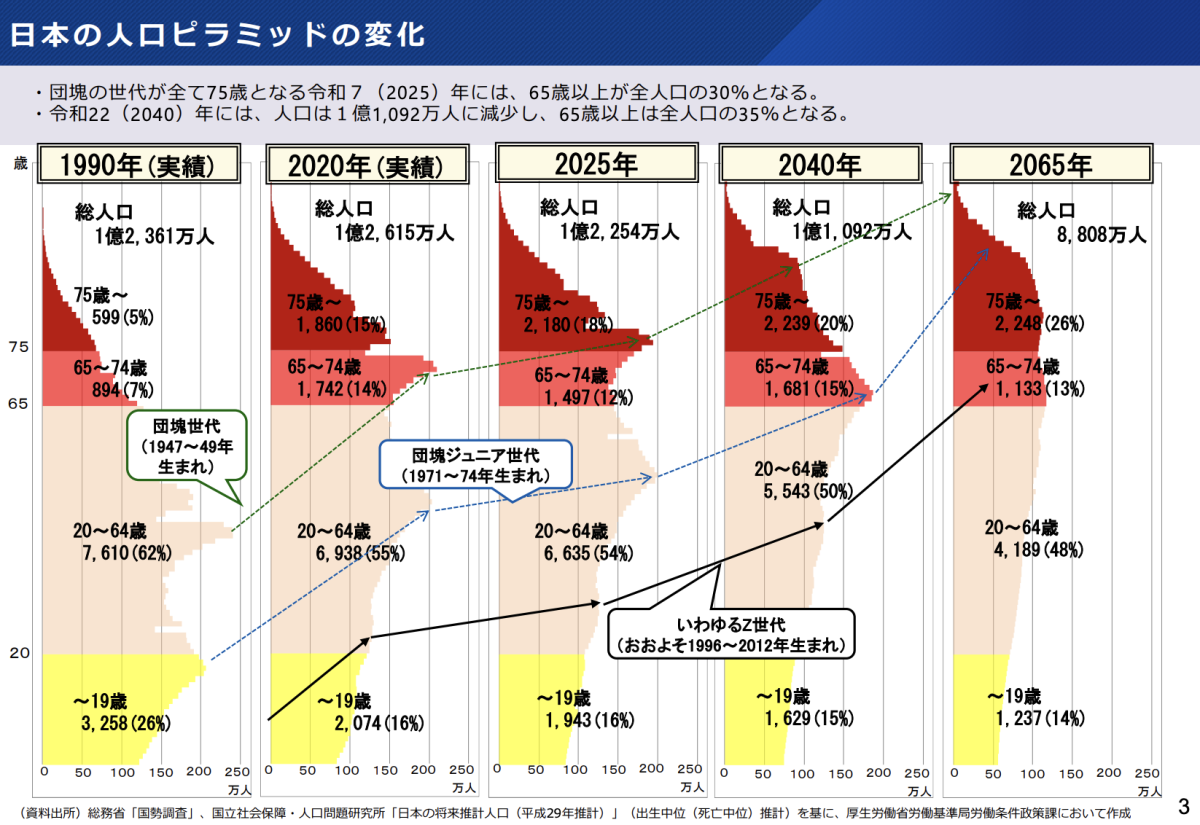 CenturyMaruyoshi Airinku 2023.10.9NewsPicks (図の説明:左図は、出生数と合計特殊出生率の推移で両方とも減少傾向にあるが、理由は、死亡率の減少・寿命の伸び・教育の普及・結婚願望の低下等だろう。中央の図は、結果として現れた年齢階級別の人口推移で、0~14歳と15~64歳の人口割合が減少し、65~74歳と75歳以上の人口割合が増えている。そのため、“生産年齢人口”の定義を18~75歳と定義しなおすのが、全体から見て適切だと思う。なお、右図のように、明らかに人口構成の変化があるため、商品やサービスのニーズも1990年、2025年、2040年では異なるわけである) *4-2は、①2024年の就業者数は6,781万人と前年から34万人増えて1953年以降最多 ②女性・高齢者の就労が広がったが、女性・高齢者は働く時間が短いため想定より労働力の確保に繋がっていない ③女性・高齢者による就業者増は限界があり、2040年時点の就業者数は最も低いシナリオで5,768万人 ④日本経済は生産性を高めながら人手不足に対応する課題に直面しており、今からAI等を活用した生産性向上で働き手減少に備える必要 ⑤就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は2024年は61.7%と前年から0.5%拡大 ⑥女性就業者は前年比31万人増の3,082万人で最多、高齢者就業率も65歳以上が前年比0.5%増で25.7% ⑦雇用形態別では正規雇用39万人増、パート・アルバイト・契約社員等の非正規雇用2万人増 ⑧非正規雇用の待遇を同等の業務をする正社員と揃えたり、勤務地を絞る限定社員を廃止して正社員と同じ待遇に揃えたりする企業も ⑨若手人材確保のため、30万円以上の初任給を提示する企業も ⑩介護・建設分野で有効求人倍率4倍超の職種もあるが、事務系は1倍未満 等としている。 2023年度の高校進学率が男女とも99%に近く、大学進学率(短大を含む)が61%である中、⑤のように、就業率を「15歳以上人口に占める就業者の割合」と定義していることは、1950年代の発想であり古すぎる(https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Data/Popular2024/T11-03.htm 参照)。そのため、生産年齢人口を「18~75歳」と定義し、就業率を「18歳以上の人口に占める就業者の割合」と定義するのが、現在の状況にあっていると、私は考える。 また、大学に進学すれば22歳が最低卒業年齢で、大学院の修士課程まで進学すれば24歳、博士課程まで進学すれば27歳が最低修了年齢であるため、この期間は正規雇用で働くことができず、これらの世代で正規雇用率が低いのは当然ということになる。 そして、“生産年齢人口”の定義で65歳を最高齢としたままでは、最高38年(65-27)の正規雇用期間で、男性の場合なら65歳男性の平均余命20年(65~85歳)分・女性の場合なら平均余命24年(65~89歳)分の生活費(公的年金、公的医療・介護保険を含む)も稼いでいなければ困窮することになり、“生産年齢人口”の期間には子育て費用も払わなければならないため、65歳時点で老後生活資金が十分な人はむしろ少ないのである(https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=60984?site=nli#:~:text=・・・ 参照)。 そのため、上の左図のように、合計特殊出生率の減少で我が国の出生数が減り、上の中央の図のように、2012年以降は人口が減り始めると同時に65歳以上の割合が増えているにもかかわらず、①⑥のように、2024年の就業者数が1953年以降最多になったのは、女性及び高齢者(65歳以上)の就業率が増えているからであり、これは自然なことである。 にもかかわらず、②③⑦のように、女性・高齢者でパート・アルバイト・契約社員等の非正規雇用が多く、「女性・高齢者は働く時間が短いため想定より労働力の確保に繋がっていない」「女性・高齢者による就業者増は限界がある」などと言われているが、女性が働く時間を短くせず、キャリアも中断せずにすむためには、充実した保育・教育・学童保育・介護制度が必要なのだ。そして、これらのサービスはブルーオーシャンでもあったのに重視されず、女性に無償労働を押しつけてきたことが合計特殊出生率を必要以上に低下させたのだということを、日本政府はまだわかっていないようで、それが、⑩のように、介護分野で有効求人倍率が4倍超もあり、サービスする人が集まらない原因になっているのだ。 なお、⑧の非正規雇用については、アルバイトでなければ、勤務地を限定しようと勤務時間が短かろうと、(報酬金額は変わるだろうが)働いている以上は正規雇用にすべきで、非正規雇用にして社会保険料(医療保険・介護保険・年金保険・雇用保険・労災保険)を払わないのは、企業の大小を問わず、社会保険料を払って支えている人や企業に対して狡いのである。 また、④のように、「日本経済はAI等を活用して生産性を高めながら、人手不足に対応する必要がある」というのは事実で、失業率上昇の心配なく生産性を高められるのは良いことである。 ただ、⑨のように、若手だけを人材確保のために初任給30万円にしてボーナスを入れ年間500万円支払うとすれば、扶養家族のないその新人は、所得税約30万円、住民税約26万円、社会保険料約71万円(厚生年金保険料46万円、健康保険料25万円)の合計約127万円(年収の約25%)を国と地方自治体に払うことになる。給与の高い人は、さらに多くの金額を支払い、40歳以上になると介護保険料も支払うが、これだけの金額を支払っても、無駄使いなく国や地方自治体からのサービスで報われているか否かは、最も疑わしくて重要な問題なのである。 3)外国人労働者、留学生、移民・難民 イ)日本で働く外国人労働者の状況 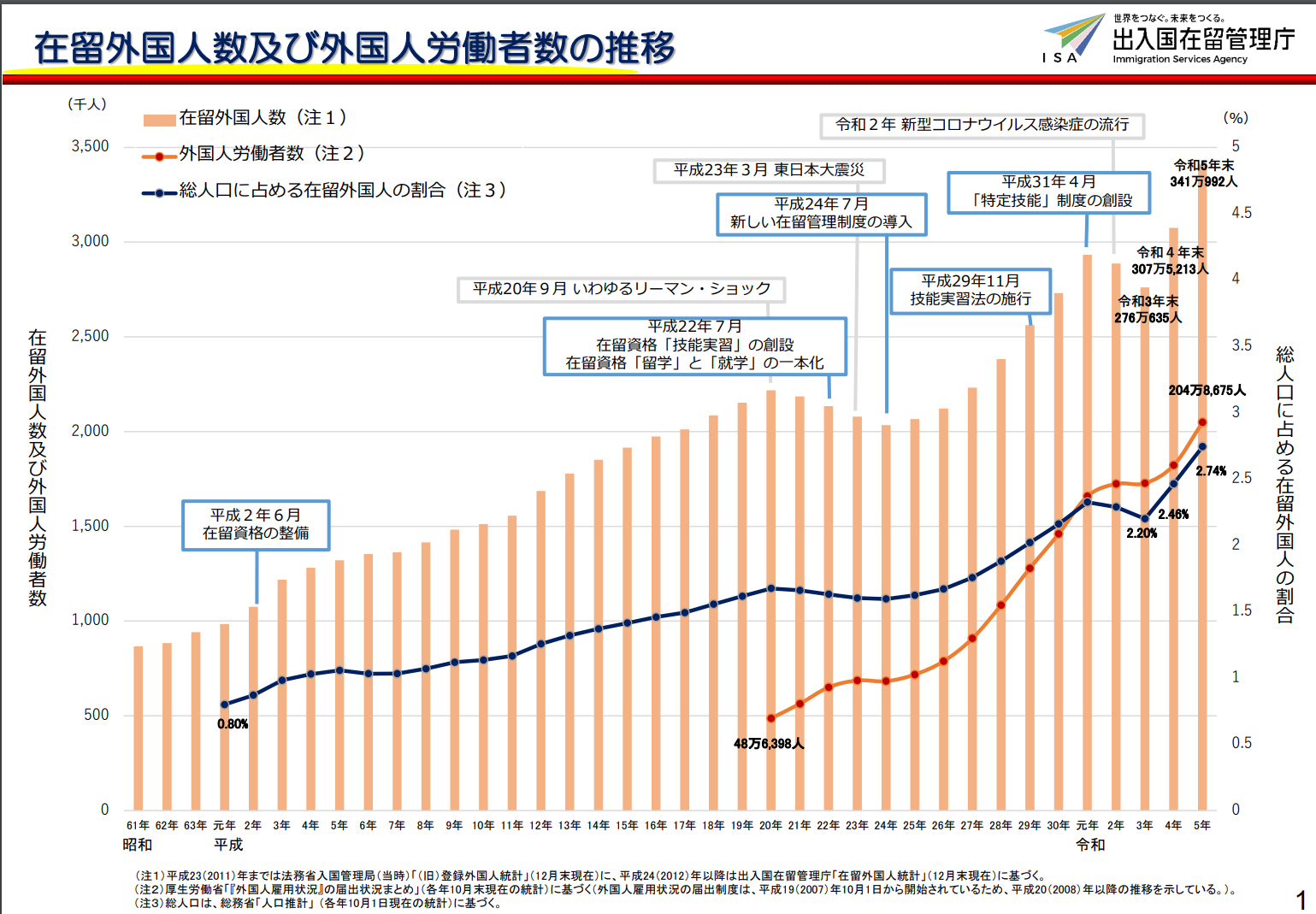 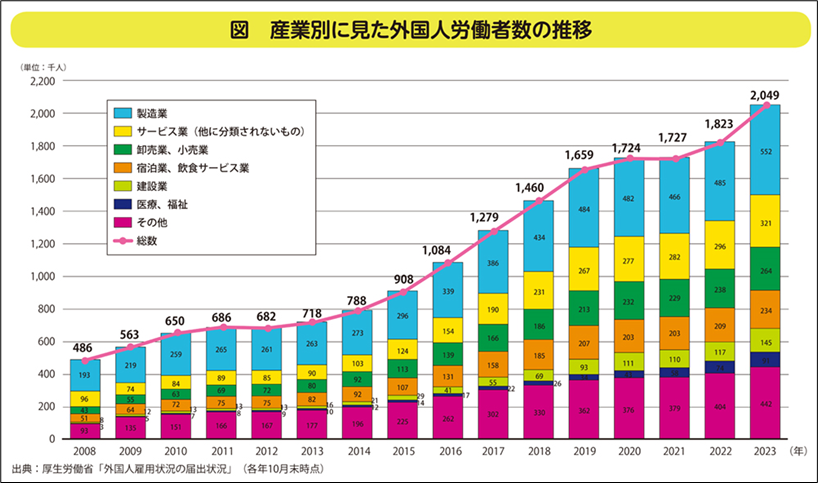 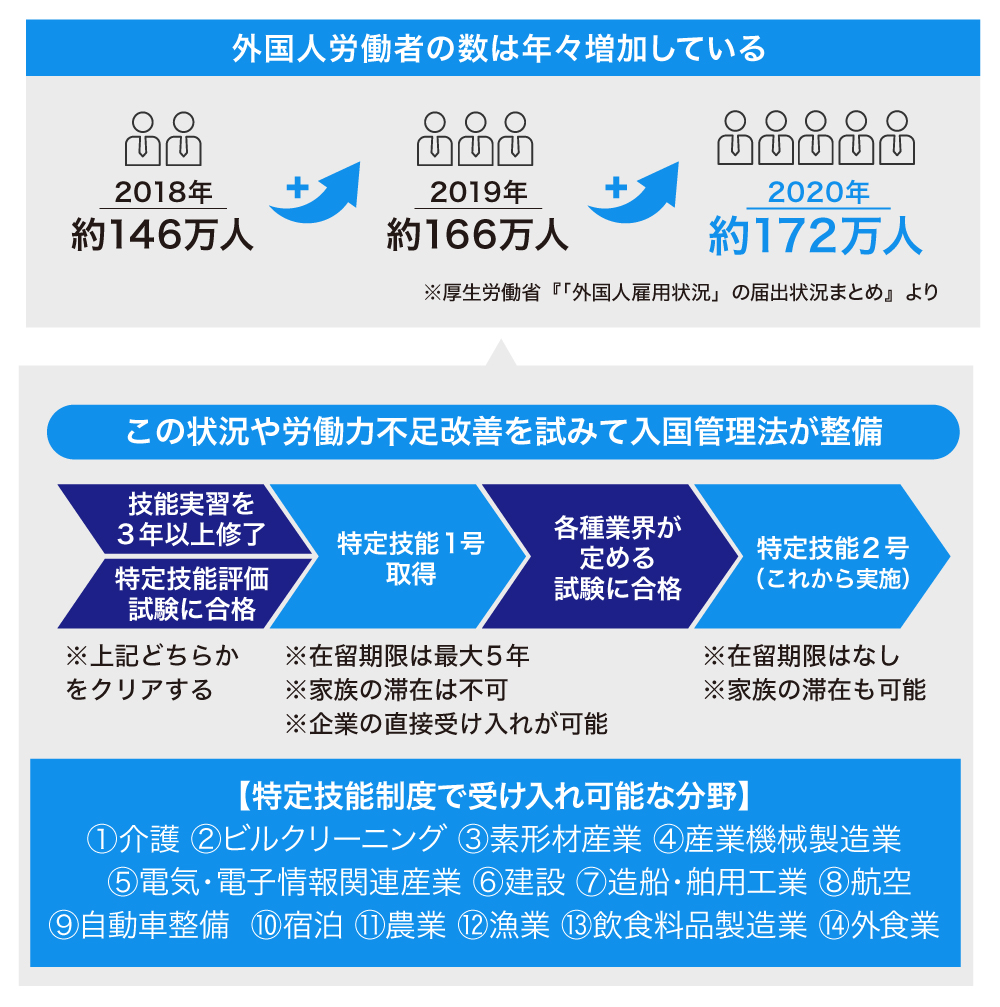 Rise For Business 厚生労働省 FUND INNO (図の説明:左図は、在留外国人数と外国人労働者数の推移で、中央の図は、産業別外国人労働者数の推移だが、人手が足りない介護分野や建設業で未だ少ない。右図は、2019年度に始まった在留資格「特定技能」の内容だが、受入可能分野を狭くしている上、家族の帯同を許さない等の制限を多くしている点で、使う人の立場を考えた制度になっていない) *4-3-1は、①日本で働く外国人労働者が2024年10月末は230万2,587人 ②外国人労働者の職場環境改善のため、国は2007年から外国人を雇用した企業・個人事業主にハローワークへの届け出を義務づけ ③国籍別は、ベトナム57万708人・中国40万8,805人・フィリピン24万5,565人 ④増加率は、ミャンマー61%・インドネシア39.5%・スリランカ33.7% ⑤人手不足解消のため2019年度に始まった在留資格で、建設業・介護など16分野の「特定技能」で働く人が20万6,995人 ⑥厚労省は「人手不足等を背景に外国人労働者が増加し、医療・福祉、建設業の増加率が高い」とコメント としている。 “生産年齢人口”割合が低下して日本人の若者が減少すると同時に、日本人の若者の職業選択と求人が合わずに有効求人倍率の高くなる産業が出たり、日本人の生産性と比較して人件費が高すぎ、国内の産業が空洞化してしまうような場合には、外国人労働者の採用が必要不可欠である。 そのような中、①②のように、日本で働く外国人労働者が2024年10月末に230万2,587人となったため、外国人労働者の職場環境改善が必要であるのはよくわかるが、職場環境改善はハローワークに届け出を義務づけたらできるかは疑問だ。 なお、③のように、現在の国籍別外国人労働者数は、ベトナム57万708人・中国40万8,805人・フィリピン24万5,565人だが、増加率は、④のように、ミャンマー61%・インドネシア39.5%・スリランカ33.7%と、(すべてアジアではあるが)より開発途上国の方にシフトしており、これも国別年間所得の差から必然であろう。 政府は、人手不足解消のため、⑤⑥のように、2019年度に「特定技能」という建設・介護はじめ上の右図の産業を加えた在留資格を開始し、現在は「特定技能」で働く人が20万6,995人いるそうだが、これからは日本人の失業率が高くなるわけではなく、人手不足や人件費高騰で既に成り立たなくなっている産業もあるため、政府が(狭い視野で)外国人労働者を受入れられる業種を決めるのではなく、民間のニーズに応じて外国人労働者を受け入れられるようにすべきだ。 また、*4-3-2は、⑦深刻な人手不足で四国は外国人材増加 ⑧多文化共生は日常 ⑨愛媛県は製造業を中心に外国人労働者が増加、地域別では造船業が盛んな今治地域が全体の3割 ⑩独立系造船会社新来島どっくは、491人の外国人労働者が働き、日本人の人材確保が厳しい中で鉄加工全般や塗装等の重要な戦力として活躍 ⑪高知県は四国銀行が人材紹介6社と提携して取引先に外国人材採用を提案 ⑫高知銀行は技能実習生受け入れをサポートする監理団体4団体と業務提携 ⑬香川県は人材紹介8社と連携協定を結び、企業と外国人材のマッチングに乗り出した ⑭香川銀行もノンバンクのJトラストと提携して取引先にインドネシア人材の紹介開始 ⑮徳島県は2024年9月から半年の予定で、外国人のための無料職場体験プログラムを実施して、徳島県内での就職に関心ある留学生と採用に前向きな県内企業との出会いの場を設定 ⑯異なる人種・文化・価値観を尊重する多様性の推進は四国の活性化に不可欠 としている。 上の⑦⑧⑨⑩⑯は、外国人労働者が実際に必要とされており、(日本にいる限り、日本の法律を守ることは当然だが)外国人労働者を受け入れた地域は異なる人種・文化・価値観を尊重して多文化共生しており、⑪⑫⑬⑭⑮のように、県や信用できる企業が地域のため外国人材の採用を提案したり、企業と外国人材のマッチングをしたり、外国人留学生のための無料職場体験プログラムを実施して県内での就職に関心ある留学生と採用に前向きな企業の出会いの場を設定したりしているということで、このやり方であれば前向きで安心できる。 さらに、外国人を雇った企業から「問題なく働けている」「文化や考え方の違いが刺激になる」「海外の知見を取り入れることで、会社全体の活性化に繋がった」等のポジティブな声が聞こえており、外国人材は実際に各地で活躍しているそうだ(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202406_001.html 参照)。 なお、外国人と協働するには言語がネックになる場合が多かったが、*4-6のように、スタートアップがIT(情報技術)を活用して外国人と協働しやすい環境づくりを急いでおり、「カミナシ」が13言語対応の従業員教育サービスを開発したり、「DXHUB」が企業が採用した外国人に日本語教育ソフトを提供して日本語学習の履歴を管理し、その学習履歴を昇給や賞与の判断材料にできるようにしたりしており、言語の壁は低くなりつつある。 ロ)外国人留学生と日本人学生の動向 *4-4-1は、①AI等先端分野人材の確保のため、文科省・東大等がインドからの留学生獲得を強化 ②インドの大学院生300人弱の留学費用を支援し、2028年度迄に留学生を倍増 ③理工系に強いインドから人材を受け入れ、日本の研究力や産業競争力向上に繋げる ④2025年度から文科省はAI等を学ぶインド工科大などトップ大の大学院生270人程度を対象に日本での生活費や大学での活動費として1人300万円支援 ⑤インドで働くITエンジニアの平均年収は約127万円で、支援額は約2.3倍 ⑥留学生支援は1年間で、日本への定着を視野に企業のインターンシップへの参加も促す ⑦受け入れ大学は2025年度に公募し科学技術振興機構(JST)が審査 ⑧東大・立命館アジア太平洋大(APU)等の国内大学、大使館、民間事業者など50を超える機関が2024年度にインド人留学生を増やす連携組織を立ち上げ ⑨人口14億人のインドは伝統的に理工系人材の育成に強く引用数が上位10%に入る「注目論文」数が世界4位(日本は13位) ⑩インド人学生は英語が得意で日本より英語カリキュラムが充実している欧米の大学を目指す傾向 ⑪インドのほか国際的な存在力を増しているアフリカの大学も対象に 等としている。 私はPWCで監査していた時に,インドステイト銀行日本支店(https://jp.statebank/ja/about-sbi-japan 参照)を監査する機会があったが、そこの行員は本当に優秀な人たちだった。また、インドは公用語が英語であるため、EY東京で私が英語で書いた「Tax Opinion」を日本時間の夕方5時くらいまでにEYのインドオフィスにFaxしておくと、翌朝にはネイティブイングリッシュになり、疑問があればそれも記されて送り返してきていた。そのため、時差を有効活用して、速やかに、ネイティブイングリッシュで、外国人にもわかり易い「Tax Opinion」を作成することができたのである。 そのため、①②のように、インドの大学院生の留学費用を支援し、AI等先端分野人材の確保のために文科省・東大等がインドからの留学生獲得を強化し、日本の研究力や産業競争力向上に繋げようとしているのは良いと思う(ただし、先端分野はAIだけではない)。 特にインドは、「0」の概念を発見した国で、⑨のように、伝統的に理工系人材の育成に強く、人口14億人という母集団がおり、引用数が上位10%に入る「注目論文」数が世界4位であるため、③のように、理工系に強いインドから人材を受け入れて日本の研究力や産業競争力向上に繋げるのは経済合理性もある。逆に、日本の「注目論文」数13位という結果は、日本の教育と社会の仕組みが理系に進む人数を制限し、「個性を伸ばし、誰もやっていないことをする」のを嫌う国民性によって、もともと持っている能力を抑えつけた結果であると、私は考えている。 従って、④のように、文科省がAI等を学ぶインド工科大などトップ大の大学院生270人程度を対象に2025年度から日本での生活費や大学での活動費として1人300万円支援することにし、⑥のように、企業のインターンシップへの参加を促して日本への定着進めれば、眠ったような日本にとって良い刺激になると思われる。そのため、⑦⑧のように、東大はじめ、多くの関係機関がインド人留学生を増やす連携組織を立ち上げたのには、期待が持てる。 確かに、⑩のように、インド人学生は英語が得意であり、日本より英語カリキュラムが充実し、かつ就職等で差別されることの少ない欧米の大学を目指す傾向があるため、⑤のように、インドで働くITエンジニアの平均年収の2.3倍の支援額がなければ、日本は選ばれにくいだろう。なお、より開発途上国の方が、日本との平均年収の差が大きいため、⑪のように、アフリカ等の大学も対象とするのが良いと思われる。 また、*4-4-2は、⑫東京一極集中を是正し、地方との人口流出入を均衡させる地方創生の1つとして、国は2018~23年度に徳島県に計29億円を投じたが、県内からの進学者は増えなかった ⑬政府は大学進学・就職で地元を離れる若者が多いことに目をつけ、2018年から10年間、東京23区内の大学が定員を増やすのを禁じ、地方大学への交付金を創設 ⑭地方の教育・研究の一定の底上げに繋がったが、若年層の人口動態を変えるには至っていない ⑮島根大学は人材の質が高まるほど県外の大企業から求人が殺到するジレンマに直面した ⑯日本の成長力を高める地方創生の狙いにそぐわない規制自体が不合理 ⑰企業誘致・賃上げ等の総合的取り組みが必要 ⑱経済合理性に反する改革は持続可能ではなく、むしろ国力をそぐ 等としている。 東京一極集中の原因を「進学時に東京に出るから」と考えた点が誤っているため、⑫⑬⑮のように、東京23区内の大学が定員を増やすのを禁じ、地方大学への交付金を創設しても、県内からの進学者が増えなかったのだと、私は思う。 そのため、この政策は、i)確かな原因分析の後に行なわれたのか(多分、そうではない) ii)交付金創設の効果はどのくらいあったのか iii)東京23区内の大学の定員増禁止は、学生に不便を与えなかったのか 等について、結果から分析して評価されるべきだ。 なお、⑭で若年層の人口動態を変えられなかった理由は、世界を視野に活躍できる魅力的な就職先が都会に多かったり、教授や学友と相互に能力を磨きあえたり、就職に有利だったりする大学が東京はじめ都会に多いからであるため、そのようなメリットがないのに小手先の交付金創設で若者の進路や人口動態を変えることができないのは当たり前だと、私は思う。 従って、⑯⑰⑱ように、規制自体が不合理で日本の成長力を高める地方創生の狙いに合わないため、本当に地方創生をしたいのであれば、地元企業を大きく育てたり、企業誘致をしたりして、地方に魅力的な就職先を作ることが必要であり、不合理な改革はむしろ国力をそぐだろう。 それでは、「地方大学はどうすれば良いのか」については、大学のレベルを上げ、日本と所得格差はあるが優秀な学生の多い国々からの留学生を増やし、独自の魅力を作って、日本人学生にとっても魅力のある大学になるしかない。そのため、留学生や日本人学生のための奨学金・教授陣の強化・大学設備の充実・地元企業との有効な連携などが有効なツールになると思われる。 ハ)難民の移住と日本の難民受け入れについて  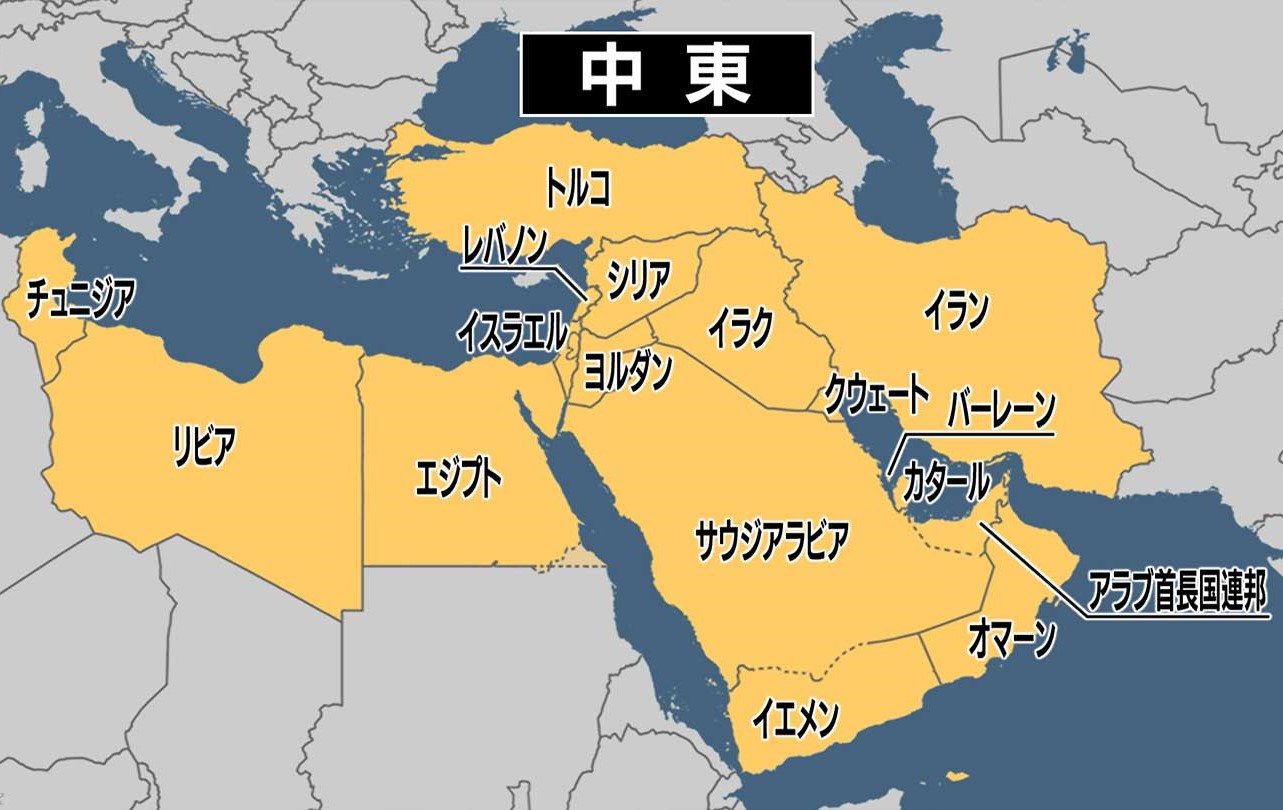 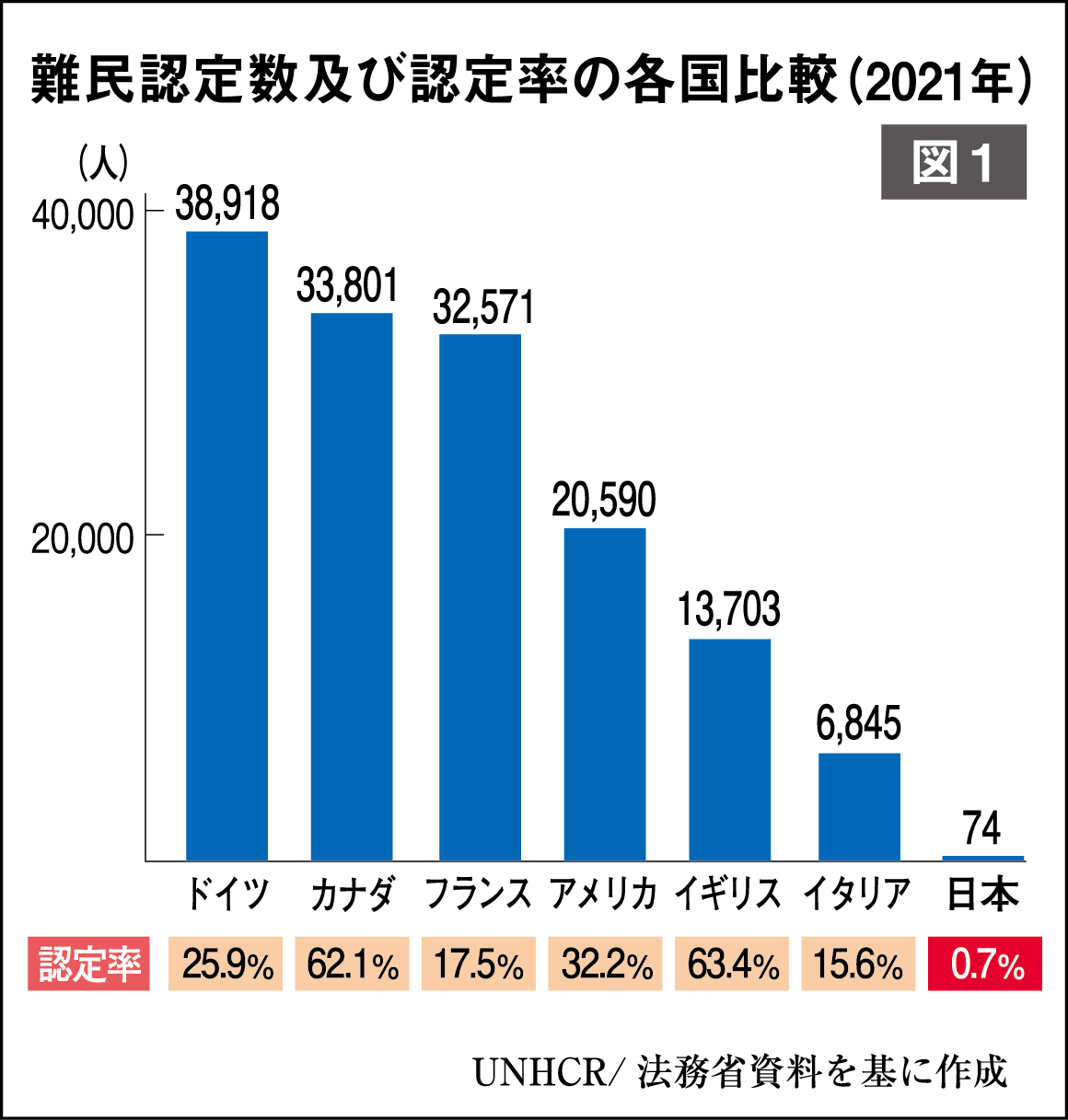 2023.10.9日経新聞 NHK 2023.5.8長周新聞 (図の説明:左図は、ガザ地区とヨルダン川西岸地区のパレスチナ自治区の地図である。また、中央の図の黄色の部分が中東諸国だが、世界4大文明のうちエジプト文明とメソポタミア文明発祥の地を含み、大陸の中で揉まれてきた地域でもあるため、ここに住む人たちは、日本人にはない物品・文明・商魂のたくましさを持っている。なお、右図のように、これまでの日本は、世界でも著しく低い難民認定数・難民認定率であるため、他国の移民・難民締めだし政策に文句の言える立場では到底ない) *4-5-1は、①ガザはイスラエル軍の攻撃で建物が破壊され、多くの女性・子どもが戦闘の巻き添えとなって死者4万7千人超 ②トランプ米大統領は、パレスチナ自治区ガザから約200万人にのぼる住民を出して米国が所有・再建する復興案を出した ③トランプ氏は「(地中海のリゾート地リビエラのように)復興したガザに住むのは、帰還したパレスチナ人ではなく、世界の人々」と語った ④「居住地として別の選択肢があれば、ガザの人々はそちらを選ぶだろう」「米国がガザを長期的に所有して開発を進めれば、中東に安定をもたらすことができる」とも主張した ⑤ウォルツ大統領補佐官(国家安全保障担当)は「アブラハム合意を次の段階に進めることが目標だ」と語り、イスラエルとサウジアラビアの歴史的な関係正常化仲介への意気込みを見せた ⑥サウジアラビアは、パレスチナ国家樹立を正常化の条件としている としている。 また、*4-5-2は、⑦サウジアラビアは、パレスチナ自治区ガザの住民を移住させるというイスラエルのネタニヤフ首相の提案を「断固拒否」と発表 ⑧サウジは「パレスチナの人々はその土地に権利があり、彼らは追放されるべき侵入者や移民ではない」と強い言葉でネタニヤフ発言を非難 ⑨ネタニヤフ首相は、サウジ領内にパレスチナ国家を創設する構想を示唆しつつ、「イスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃後、パレスチナ国家は存在すべきではない」との立場を繰り返した ⑩トランプ米大統領は他の中東諸国に対し、ガザからパレスチナ人を受け入れるよう求めたが、エジプト・ヨルダンは拒否 ⑪イスラエルは戦争で荒廃したガザから港や陸路経由で、ガザ住民を移す計画を策定しつつあるが、i)パレスチナ人が移住を望んでいるか ii)どこに移り住みたいか iii)実際に移住が可能か は不明 としている。 さらに、*4-5-3は、⑫農水省は2025年度から外国人が国内の農地を取得する際の要件を厳格化し、農地取得を目指す外国人が農業委員会に残りの在留期間を報告するよう義務化 ⑬短期間で在留期間が切れる場合は、農地を取得できなくする ⑭取得後、農地が適切に耕作されるか判断する上で、残りの在留期間を把握する必要がある ⑮短期間で遠方に転居する場合も農地取得を認めない ⑯外国人やその関係法人が2023年に取得した国内農地は90.6ha、外国人個人による取得は60ha(2199人)・残り(30.6ha)が法人による取得(農水省) ⑰日本は外国人による土地取得を規制していない としている。 ポイント1:パレスチナ人は、ガザに住み続けて生活していけるのか? ガザ地区は、地中海沿岸に細長く横たわり、長さ約40km、幅6~12km、面積365km²(奄美大島712km²、淡路島593km²、種子島444km²、福江島326km²、小豆島153km²)のエリアに約220万人が暮らしている世界で最も人口密度(6018人/km²、ちなみに東京都全体が6425人/km²)の高い場所で、燃料・食料・日用品・医療品等が慢性的に欠乏し、経済や生産活動も停滞して、国連や支援団体からの援助物資で命を繋いでいる場所である。 また、ガザは人口の約45%が14歳以下の子どもで、7割は難民となった人々だが、「パレスチナの人々はその土地に権利がある」「パレスチナ人は移住を望んでいない」と言っても、「パレスチナ人が、これからもガザで子孫を増やしつつ、住み続けていけるのか?」と言えば、「それは無理だろう」というのが、私の結論だ。 従って、①は非常に気の毒なことだったが、イスラエル人かパレスチナ人のどちらかが移住しなければ、いずれ住む場所もなくなって戦争が再発するし、いつまでも国連や支援団体からの援助物資で命を繋いでいるのは誰のためにもならない。 そのため、②③のトランプ大統領の「パレスチナ自治区ガザから約200万人の住民を出して米国が所有して再建する」「復興したガザに住むのは、帰還したパレスチナ人ではなく、世界の人々」という復興案は米国本位すぎて驚いたものの、よく考えれば、④⑤のように、居住地としてより良い選択肢があれば、ガザの人々はそちらを選んだ方が賢い。また、イスラエルではなく米国がガザを所有するのであれば、パレスチナ人がイスラエルに土地を譲ることなく、中東(イスラエル・イラク・シリア・トルコ・パレスチナ・ヨルダン・レバノン・アラブ首長国連邦・イエメン・イラン・エジプト・オマーン・カタール・クウェート・サウジアラビア・バーレーン)に安定がもたらされ、次の段階に進めるだろう。 ポイント2:パレスチナ国家樹立はどこにするのか? サウジアラビアは、⑥⑦のように、パレスチナ国家樹立をイスラエルとの国交正常化の条件としているが、パレスチナ自治区ガザの住民を移住させることは拒否している。しかし、⑧⑨のように、国土が広く文化も似ている筈のエジプトやサウジアラビアにパレスチナ国家を創設するのは合理的だと思うが、サウジはじめ他の中東諸国(エジプト・ヨルダン)は、⑩のように、ガザからパレスチナ人を受け入れることを拒否したのだ。 また、⑪のように、i)パレスチナ人が移住を望んでいるか ii)どこに移り住みたいか iii)実際に移住が可能かは不明 とされているが、イスラエルが港や陸路経由でガザ住民を移す計画を策定しつつあるのなら、(他にも良い移住候補地はあると思うが)日本も、淡路島(593km²)・小豆島(153km²)はじめ瀬戸内海地域は地中海沿岸と似ており、国境離島でもなく、近年はオリーブやレモンも作り始めており、人手不足の産業が多く、まとまって住むことも可能であるため、(パレスチナ国家樹立候補地にはならないが)移住候補地になり得る。 そして、⑫⑬⑭⑮⑯⑰のように、農地が適切に耕作されるようにするため、農地取得を目指す外国人は農業委員会に残りの在留期間を報告し、短期間で遠方に転居する場合は農地取得が認められないが、難民として在留資格を得て腰を据えて農業をやる場合には、日本は外国人による土地取得を規制していないため、外国人やその関係法人も農地を取得することができ、2023年には外国人やその関係法人が取得した農地が90.6haあるのである。 ・・参考資料・・ <農家への所得補償は最終解ではない> *1-1-1:https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/277523 (日本農業新聞 2024年12月17日) 与野党伯仲国会の審議 農家所得増へ合意探れ 臨時国会は21日の会期末に向けて終盤を迎えた。石破茂首相は所信表明演説で、党派を超えた「幅広い合意形成」を掲げた。国民の命と国土を守る農業、農村政策は試金石となる。農家の所得が増え、展望を描ける農政の在り方について議論を尽くし、合意点を探るべきだ。日本の食料自給率の長期低迷や農家戸数、耕作面積の減少に歯止めがかからなくなっている原因を突き詰め、持続可能な食料安全保障を確立できるのか。臨時国会では、これまでの農政の効果を検証する必要があるとの指摘が相次いだ。石破首相も4日の衆院予算委員会で、「日本が世界の中で食料自給力、自給率、それが突出して低いというのはやはり相当な問題なのだろうと思っている」などと述べ、危機感を示した。だが、議論が深まったとは言えない。現行施策の検証や諸外国の事例の研究を含めて、対応は待ったなしだ。食料・農業・農村基本計画見直しの時期でもあり、与野党は農家手取りを増やす具体的な道筋についてもっと踏み込んだ論争を展開してほしい。とりわけ、違いが目立つのが、直接支払いを巡る議論だ。立憲民主党や国民民主党などは、戸別所得補償制度の名称をあえて使わず、直接支払制度の見直しという観点から提起を始めている。石破首相や自民党の森山裕幹事長が、水田政策などの検討の中で「直接支払いについて議論を深める」と語ったことに呼応したものとみられ、与野党双方が一致点を見いだす努力が求められている。一方、石破首相は戸別所得補償制度を念頭に「(農家の)意欲にブレーキをかけるとか創意工夫に水を差すとか、そういうご意見があることは事実」とも述べ、与野党の主張には依然として差がある。農水省は来年の通常国会に農産物の価格転嫁を後押しする法案を提出する予定だが、同法案を巡っては、納税者負担による直接支払いの是非について再度、論点として浮上するのは間違いないだろう。政府・与党が、従来の立場を繰り返すだけでは法案は宙に浮きかねない。各党の主張の隔たりを超えて、農家の手取り増を実現させるという石破首相の強いリーダーシップを期待したい。与野党は、直接支払いを含めて手取りを増やすために必要な農林水産関係予算を確保した上で、山積する農政課題に正面から向き合うべきだ。自民、公明、国民民主の3党は、いわゆる「103万円の壁」の見直しで合意した。どのように実施するか不透明な部分は残るが、石破首相が唱える熟議の成果だろう。農業の直接支払いについても、熟議の合意を求めたい。 *1-1-2:https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/285622 (日本農業新聞 2025年2月2日) 集落機能強化加算廃止に思う 疑いの目を持ち続ける 集落機能強化加算は継続しないこととする――。2025年度から始まる中山間地域等直接支払制度の次期対策について、農水省が示した方針だ。加算を終了する理由の一つに「地域運営組織(RMO)の設立・連携を行うという趣旨が十分に伝わっていなかった」と都道府県や市町村への説明不足を挙げている。しかし、落ち度を認めるのであれば、加算を継続したり、あるいは次期対策から加算を使おうとしていた集落協定も含めて救済措置を講じたり、現場が混乱しないよう対応すべきではないかと思う。集落機能強化加算は、高齢者の見回りや送迎など、生活支援をはじめとする集落機能の強化や、ボランティアの確保やインターンの受け入れといった人材確保を支援している。同省によると、23年度は555の集落協定が取り組み、加算が始まった20年度から年々増えている。制度の効果を検証する第三者委員会での議論を踏まえ、同省が昨年の8月に公表した最終評価では、集落機能強化加算を使う協定は「さまざまな組織と連携して活動している割合が高い」と効果を評価していたが一転、同月末の25年度予算概算要求で加算の廃止が判明した。これを受け、議論してきた内容と合わないとして、委員の求めで11月に臨時で第三者委員会を開催。同省は、既に加算に取り組んでいる協定を対象に、新設するネットワーク化加算で経過措置として支援を続ける方針を示したものの、次期対策から加算を使おうとしていた協定への対応など、課題は残っている。11月の第三者委員会で同省が示した資料は加算の廃止を前提としており、加算のマイナス面を強調していると感じた。今回のように同省が進めたい政策の方向性に沿うデータが提示されているケースは他にもあるのではないか――。本当の意味でEBPM(客観的な証拠に基づく政策立案)となっているのか、常に疑問を持ちながら取材に臨みたい。 *1-1-3:https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/285872 (日本農業新聞 2025年2月3日) 農家数激減の現状 直接支払い議論、今こそ 慶応義塾大学名誉教授・金子勝(1952年東京都生まれ。東京大学大学院博士課程修了。2000年から慶応義塾大学教授、2023年4月から淑徳大学大学院客員教授。著書に「金子勝の食から立て直す旅」など。近著に、「高校生からわかる日本経済」(かもがわ出版)、「裏金国家」(朝日新書)) 石破茂政権は「令和の日本列島改造」で「地方創生2.0」を打ち出した。食品加工業の育成などを打ち出したものの、農家の直接支払いは含まれていなかった。しかし、農家数が激減する状況を考えるならば、農家の直接支払いは不可欠である。足元を見てみよう。5年ごとの農林業センサスを見ると、農家数は急減し、高齢化とともに中小零細農家の淘汰(とうた)が進んでいる。2005年に208万5000あった農業経営体数は、2020年には109万2000まで半減している。この間、10ヘクタールを境にして中小零細農家の淘汰が急速に進んでいる。 ●農村維持難しく こうした状況の下、2024年5月に食料・農業・農村基本法の見直しが行われた。だが、この改正基本法は矛盾だらけだ。同法は、従来の大規模化による農業の生産性向上政策を前提としており、それでは農家数がますます減少し、農村コミュニティーの維持は困難になっていくからだ。リーマンショックに伴う円高によって、工場が次々に海外移転した。加えてアベノミクスが先端産業化を失敗させた。これまで工場誘致政策に伴って零細農家も兼業化で生き残っていけたが、その条件が失われると、皮肉なことに、かねてから農水省が意図していた大規模化が急速に進んでいる。だからといって、農家経営が楽になったわけではない。アベノミクスは実質賃金低下とデフレに伴って農産物価格の低迷をもたらす一方で、円安インフレによって、農薬・肥料・飼料・燃料の輸入価格が上昇して、農業経営を圧迫しているからだ。農家の経営困難を救う所得政策が不可欠だ。改正基本法は、ITを使ったスマート農業技術を使って規模拡大を図ろうとするが、人口減少が進めば、地域で学校、病院などが維持できず、ますます人が住めなくなるだろう。ところが、定住政策もない。 ●与野党で協議を 農業と農家の衰退状況を考えれば、欧米並みの農家への直接支払いを導入することが緊急に必要である。立憲民主党を中心に、民主党時代の農家への戸別所得補償を引き継ぎ、そのバージョンアップを目指している。だが、農家への直接支払いは、もともとは石破首相が農相時代に行っていた主張であったはずだ。一方、かつての民主党政権は戸別所得補償制度から農協を排除するように動いた。農協に独占させるのは間違いだが、排除することも誤りだった。与野党伯仲時代なのだ。政党の狭い利害を超えて、農村の危機的状況を踏まえて農業者の利益本位に考えて、真剣に与野党で協議すべき時ではないのか。 *1-2-1:https://www.agrinews.co.jp/news/index/282099 (日本農業新聞 2025年1月15日) 水稲再生二期作広がる 温暖化、米価上昇で脚光 温暖化で水稲の生育可能な期間が延びる中、生産現場で再生二期作が広がってきた。温暖な西日本で取り組みが先行してきたが、東日本の主産地でも米を安定調達したい卸業者も参画した試みが動き出している。産地からは「米価の回復もあり、機運が高まっている」との声も上がる。「二番穂の再生が旺盛で関心を持った」と、2024年産で1ヘクタールで再生二期作を行ったのが島根県の農事組合法人ふくどみだ。早生品種を4月下旬に移植。8月下旬に1度目の収穫を行った後に追肥、11月下旬に二番穂を収穫した。10アール収量は二番穂が192キロで、全体で762キロを確保した。「水はけが悪く転作が難しい田で、水稲で2回収入を得られるのは有望」とみる。東海地方のある農家は24年産で「コシヒカリ」約100ヘクタールで取り組んだ。二番穂の10アール収量は、一番穂を早く刈り、水を入れた田で約60キロ。「特に24年産は米価が良かったからか、周りでも取り組む農家が多かった」。二番穂を収穫しても、収穫せずにすき込んでも「労力は大差ない」と話す。関東でも取り組みが始まった。茨城県のJA北つくばは24年産で、「にじのきらめき」など約1ヘクタールで実証に乗り出した。同品種の10アール収量は2度の収穫で計712キロ。25年産は4ヘクタールに広げる。実証には大手米卸の木徳神糧も参画。農家の減少が進む中、同社は再生二期作を「米の安定調達に向けた一策」とみる。他産地での展開も検討する。現場で実践が広がる中、農研機構は23年に研究成果を発表。福岡県内の試験では、「にじのきらめき」の10アール収量は2回の合計で950キロ。一番穂を地際から40センチと高く刈ることで地上部に栄養を多く残し、二番穂の収量を確保できるとする。一方、「長い目で見れば地力が落ちて機械代もかさむ。一番穂をより多く取る方が生産コストでは優れる」(別の東海地方の農家)と、慎重な声もある。農水省によると、二番穂から収穫した米であることを理由にした流通上の規制はなく、通常の米と同様に販売できる。イネカメムシの栄養源を田に残さないよう、通常の作型も再生二期作も収穫後は速やかに耕し、すき込むことも重要になる。 *1-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250201&ng=DGKKZO86463210R00C25A2EA2000 (日経新聞 2025.2.1) 「コメ騒動」消費者置き去り 値崩れ対策に偏重、備蓄放出「口先介入」でようやく流通増 価格上昇一服 政府が緊急時用に備蓄しているコメを柔軟に放出する体制をようやく整えた。店頭からコメが消えた昨夏の「令和のコメ騒動」から半年、価格高騰に背中を押されてのことだった。後手に回った背景には米価が下がりすぎないよう生産抑制に重点を置き、消費者への意識を欠いてきた長年の農業政策のツケがある。政府が24日に放出準備を表明すると上昇傾向が続いていたコメ相場に変化が表れた。堂島取引所(大阪市)に上場するコメの値動きに連動した指数先物「堂島コメ平均」の31日の終値は、発表前の23日終値から1.6%安だった。日本経済新聞が集計する卸間取引価格は31日時点で、新潟コシヒカリが1月中旬比3%高の4万8500円前後(60キログラム)。昨年末から1月中旬まで3割上昇していた勢いが鈍化した。コメ卸の取引担当者は「24日以降、売り物がかなり増え値上がりが止まった」と話す。備蓄米の放出で値下がりするのをにらんだ対応とみられる。足元の値上がりがこのまま落ち着く可能性はあるものの、備蓄米の放出は対症療法でしかない。そんな手法に踏み切るのにさえ時間がかかるのは、流通を急に増やして米価が値崩れすることを過度に警戒してきた長年の政策があるためだ。象徴的なのは国が主導して生産量を抑える生産調整(減反)だ。1960年代半ばから起きたコメ余りを受けて導入して以降、コメの供給が多すぎて価格が下落するのを防いできた。93年の冷夏による大凶作で供給量が足りなくなる「平成のコメ騒動」が発生しても大きな変化はなかった。政府は2018年、農家や生産者の自主性を重んじるべきだとの判断に転じ、主食米の生産量を都道府県に指示するのをやめた。減反の廃止と呼ばれるが、現実には農林水産省内でも「事実上の減反は今なお残っている」といわれる。理由の一つは農家にコメから麦や大豆、飼料用米へ転作を促す補助金があるためだ。「水田活用の直接支払交付金」と呼ばれる制度の予算は2015~23年の間、年平均3200億円ほどの横ばいで推移する。18年の減反廃止後も減っていない。もう一つは政府が産地ごとの農家やJAなどに需給見通しに基づく生産量の「目安」を示す仕組みが残ったことだ。かつての国が都道府県に生産量の上限を提示する制度はなくなっても、この目安が一定の生産調整につながりやすい。需給見通しは将来の推計人口や1人あたりの消費量といった統計から算出する。昨年のようなインバウンド(訪日外国人)の急増による需要の広がりは織り込まれておらず、需給バランスが崩れたときの対応は難しい。減反による副作用の影響も響いている。減反には農家の収入を安定させる目的があったが、生産調整と引き換えに受け取る補助金収入に依存する零細農家が多くなった。担い手不足や収益の悪化を理由にコメ農家は減っている。農水省によるとコメ農家は20年時点で69万9000戸と10年前から39.7%減った。農家の81.7%は兼業農家が占め、2ヘクタール未満の小規模な経営体が多い。農地全体も減少が続く。田の面積はピークだった1960年代に比べ3割減った。耕作放棄地も広がっており、国内の食料生産能力は弱体化が止まらない。生産効率化に向けては大規模化が必要になる。コメの生産コストは0.5~1ヘクタールで60キログラムあたり2万円を超える一方、15~20ヘクタールは1万円強と半分になる。15ヘクタール以上のコメ生産者は10年間で8割増えたものの、経営体全体の1.7%ほどに過ぎない。効率的な生産体制をつくるための予算は多くない。たとえば「農地バンク」と呼ばれる農地中間管理機構を活用して農地集積・集約などに取り組む予算は過去10年の累計で755億円。転作を促す「水田活用の直接支払交付金」の単年の4分の1に満たない。三菱総合研究所は23年の提言でコメは40年に「自給は維持すら難しくなる」と警鐘を鳴らした。コメや小麦といった主食穀物の輸入依存度を現状のまま維持するには113万ヘクタールの耕地が「死守すべきライン」だと試算し、大規模や中規模の農家を増やすよう主張する。米国農務省が1月に発表した需給見通しでは世界のコメ生産量は24~25年度で年間5億3287万トンの見込みだ。このうち輸出に回るのは1割ほど。日本国内で供給不足に陥ったときに輸入で補うのは簡単ではない。食料安全保障の観点からも国内生産基盤を強化していくことが欠かせない。昨夏からの「コメ騒動」について政府は当初、秋に新米が流通すれば品不足は解消されると説明していた。新米が出ても卸などは予定の数量をなかなか確保できなかった。流通量の不足感から買い姿勢を強める悪循環が起き、コメ価格は高止まりの状態が続いた。繰り返さないためには生産抑制にとらわれすぎる政策からの脱却が重要となる。 ▼備蓄米 政府は不作に備えて一定量のコメを買い上げ、備蓄米として保管している。10年に1度の不作や、不作が2年連続して発生しても対処できる水準として100万トン程度を目安に保存している。毎年20万~21万トン程度を買い入れ、最大5年間保管する。期間を過ぎたら飼料用などとして売却する。低温倉庫で保管し、大部分を玄米で蓄える。備蓄米の入れ替えに伴う売買差損も含めると、2023年度決算で備蓄米制度の運営には478億円の国費がかかった。災害時でも迅速に食料を供給できるように一部は精米状態で保管している。農林水産省は精米備蓄について「15度以下で保管した場合、精米後12カ月経過しても食味は大幅に低下しない」との分析結果を示している。 *1-2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250207&ng=DGKKZO86589020X00C25A2MM0000 (日経新聞 2025.2.7) 消費支出、昨年1.1%減 2年連続マイナス 12月は2.7%増 総務省が7日発表した2024年の家計調査によると、2人以上世帯の消費支出は月平均で30万243円と物価変動の影響を除いた実質で前年比1.1%減少した。食料品などの物価上昇が消費の重荷となった。認証不正問題による出荷停止の影響で自動車購入が減り、2年連続で減少した。同日発表した24年12月単月の消費支出(2人以上世帯)は35万2633円と実質2.7%増加した。自動車の購入が増えたことなどから5カ月ぶりに増加に転じた。3カ月移動平均でみた支出も0.5%のプラスに転じたことから「食料品の節約志向が続くものの、足元では消費に回復傾向がみられる」(総務省)としている。2024年通年は支出の内訳に占める比率が高い食料が0.4%減と5年連続で減少した。天候不良の影響で値上がりした野菜や果物の購入が減った。2人以上世帯の消費支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」は28.3%と、1981年以来43年ぶりの高水準となった。交通・通信も4.1%減だった。品質不正問題による一部自動車メーカーの生産や出荷の停止の影響で新車販売が落ち込んだほか、通信では低価格帯プランへ切り替える人が増えたことなどから支出が減った。暖冬で冬場の暖房利用が減ったことなどから光熱・水道も6.8%減少した。24年の勤労者世帯の実収入は実質1.4%増の63万6155円だった。 *1-2-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1400829 (佐賀新聞 2025/1/31) 農水省、備蓄米放出へ転換、1年以内の買い戻し条件 農林水産省は31日、政府備蓄米の放出に向けた新制度の概要を発表した。価格高騰が続く中、大凶作などに限っていた方針から転換する。1年以内に同量を買い戻すことを条件とし、全国農業協同組合連合会(JA全農)などの集荷業者へ売り渡す運用を想定。民間在庫を正確に把握するため、調査対象を農家や小規模な卸売業者などにも広げる考えだ。農水省が備蓄米運用を定めた基本指針の変更案を同省関連部会に示した。著しい不作といった従来の基準に加え「円滑な流通に支障が生じる場合」にも放出を認める。売り渡し価格や数量などの詳細は今後検討する。実施されれば、供給量が増え価格低下につながる可能性がある。方針転換の背景には、昨夏以降に激化した集荷競争がある。2024年産米の収穫量は前年から18万トン増えたが、主要な集荷業者の昨年11月末時点の集荷量は17万トン減った。コメの先高観を見越した小規模業者や農家が、在庫を抱え込んでいるためとみられる。新制度では、政府が申し出のあった集荷業者に備蓄米を売り渡し、不足している卸売業者向けの販売に充ててもらう。卸売業者を通じ、コメを扱うスーパーなどの小売店に供給される見通しだ。関連部会に先立ち、江藤拓農相は31日の閣議後記者会見で「生産量は増えたのに市場に出てこない」と指摘。店頭価格の高騰を踏まえ、昨年末から備蓄米放出の議論を始めていたことを明らかにした。農水省は併せて、最新のコメの需給見通しを31日に発表した。25年6月末の民間在庫量を、昨年10月に示した見通しから4万トン少ない158万トンに下方修正した。過去最低だった昨年の153万トンからは微増するものの、2番目に低い水準。需要が増えれば、品薄が再発する懸念もある。備蓄米 著しい不作など緊急時に備えて国が保有しているコメ。1993年の大凶作「平成の米騒動」をきっかけに95年から制度化した。適正な備蓄量は100万トン程度が目安で、近年は91万トンで推移している。約5年間、全国にある民間倉庫で保有した後、飼料用などとして販売しており、毎年20万トン程度を入れ替える。備蓄運営は政府の「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」に規定されている。 *1-3-1:https://www.agrinews.co.jp/farming/index/282293 (日本農業新聞 2025年1月16日) キャベツ周年供給確立 スマート技術組み合わせ 中山間地でも効率化 広島の法人 広島県庄原市の農業法人・vegeta(ベジタ)は、約130ヘクタールと全国有数規模でキャベツを周年出荷する。冷涼な県北部から温暖な県南部まで、約10カ所に農地を集約。ドローンや作業支援アプリ、自動収穫機などスマート技術を組み合わせて効率を高め、中山間地にも適した作業体系を確立している。同社は2016年度に15ヘクタールでキャベツ栽培を開始した。現在、栽培地は標高800メートルの山間部から瀬戸内海に面する低地まで県内5市に広がり、気温差を生かした栽培でリレー出荷を展開する。農地は農地中間管理機構(農地バンク)を通じて借りるなどし、1カ所当たり多少の分散はあるが10~20ヘクタール規模に集約している。大規模生産を支えるのが、スマート技術による作業の効率化だ。➀ドローン➁営農支援アプリによる作業記録の管理・確認➂自動収穫機➃QRコードを使った苗管理➄自動操舵システム搭載のトラクター――を活用。これらは、19、20年度の農水省のスマート農業実証プロジェクトで検証した上で導入した。ドローンは約20台を所有する。農薬散布ではトマトやネギ、サツマイモ、飼料作物も含め計500ヘクタール規模で活用する。搭載したカメラで撮影した畑の画像を解析して収量を予測したり、鹿対策として、赤外線カメラを搭載して飛ばして畑周りの生息域を特定し、効率的な捕獲につなげたりしている。同社では20人ほどの従業員が移植、収穫、次作に向けた農地準備の3班に分かれて作業する。円滑に作業を進めるため、作業内容の記録や確認などができるアプリ「アグリノート」を使い、各班で仕事の進み具合を共有。自動収穫機は、収穫したキャベツを機械上で数人がかりで調製・選別できる。販売先は、生協ひろしま、県内お好み焼きチェーン店約50店舗、食品スーパーと幅広く確保。生鮮用の他、カットサラダに向く加工・業務用としても出荷する。同社の谷口浩一代表は「次世代型の経営モデルを作り上げたい」と話す。 *1-3-2:https://www.agrinews.co.jp/news/index/285846 (日本農業新聞 2025年2月2日) 「農家の視点×企業の技術」で新組織 現場が第一、技術発展へ 中山間地の狭い農地でも効率的に作業できる農機、コストを抑えつつ環境に優しい肥料――。そんな生産現場が使いやすい農業技術の開発・普及を進めようと、全国のプロ農業経営者14人が発起人となり、新組織を立ち上げる。農機メーカーなど農業関係の企業・団体なども参加。農家の視点を取り入れた技術で、作業負担軽減や生産コスト低減など経営課題の解決を目指す。新組織は、日本農業技術経営会議(通称プラチナファーミングの会)で、3日に設立総会を開く。設立時の会員数は、農家や企業など50を見込む。設立発起人の一人、ぶった農産(石川県野々市市)の佛田利弘会長は「現場起点のかゆい所に手が届く技術を広めたい」と話す。新組織では、3年間の新規プロジェクトを毎年最大5件立ち上げ、新たな農業技術の開発に取り組む。セミナー開催などを通した技術の普及、新技術の開発に向けた課題掘り起こし、企業や研究機関と農家の契約の調整なども行う。研究機関や企業が開発した農業技術には、高い効果が期待できる一方、農家が使うにはハードルが高いものも少なくない。例えば水稲の2段施肥。環境汚染が懸念されるプラスチック被膜肥料の代替技術として登場したが、専用のペースト肥料でしか取り組めず、導入コストも高いという課題があった。新組織では、発起人が開発した通常の粒状肥料でも2段施肥ができる機械の実証を進め、普及に取り組む。場所ごとに肥料の散布量を変える「可変施肥」でも、小規模農地や中山間地でも導入しやすい農機の開発・普及に取り組む。発起人代表の尾藤農産(北海道芽室町)の尾藤光一社長は「農家が受け身ではなく、主体的に技術革新に踏み出せる風土を農業界につくりたい」と意気込んでいる。 *1-4:https://cigs.canon/article/20230118_7220.html (キャノングローバル総合研究所 2023.1.18) 農業を国民に取り戻すための6個の提言、食料・農業・農村基本法見直しを機に農政を抜本的に正せ 前回は、国民全体の利益に立って食料安全保障や多面的機能という利益を確保し向上させるためには、どのような基本原則に立つべきかについて議論した(2022年12月1日付「戦後農政を総決算せよ」)。ここでは、食料・農業・農村基本法見直しに関する論考の最後として、どのような方法で、それを実現すべきかについて、議論したい。今の農政は、基本原則だけでなく、政策手法についても、大きな間違いを犯しているからである。 ●世界標準から周回遅れの日本農政 OECD(経済協力開発機構)が開発したPSE(Producer Support Estimate:生産者支持推定量)という農業保護の指標は、財政負担によって農家の所得を維持している「納税者負担」と、国内価格と国際価格との差(内外価格差)に国内生産量をかけた「消費者負担」(消費者が安い国際価格ではなく高い国内価格を農家に払うことで農家に所得移転している額)の合計である(PSE=財政負担+内外価格差×生産量)。農家受取額に占める農業保護PSEの割合(%PSEという)は、2020年時点でアメリカ11.0%、EU19.3%に対し、日本は40.9%と高くなっている。日本では、農家収入の4割は農業保護だということである。しかも、日本の農業保護は、消費者負担の割合が圧倒的に高いという特徴がある。各国のPSEの内訳をみると、農業保護のうち消費者負担の部分の割合は、2020年ではアメリカ6%、EU16%、日本76%(約4兆円)となっている。欧米が価格支持から直接支払いへ政策を変更しているのに、日本の農業保護は依然価格支持中心だ。国内価格が国際価格を大きく上回るため、輸入品にも高関税をかけなければならなくなる。農政トライアングルの政治家はTPP(環太平洋パートナーシップ)交渉を「国益をかけた戦い」と表現した。その国益とは農産物関税を守ることだった。その関税で守っているのは、国内の高い農産物=食料品価格だ。これで保護しているのは農家であり、負担しているのは消費者である。日本の場合は、小麦や牛肉などのように、消費者は国産農産物の高い価格を維持するために、輸入農産物に対しても高い関税を負担しているので、農業保護のために国民消費者が負担している額は、内外価格差に国内生産量をかけただけのPSEを上回る。これに対し、輸出国であるアメリカやEUについては、輸入が少ないうえ関税も低いので、輸入農産物についての消費者負担はほとんどなく、PSEを国民負担と考えてよい。 ●市場の歪みを財政で処理する日本 農家の所得を保証するのは価格だけではない。アメリカもEUも、価格は市場に任せ、財政からの直接支払いによって、農家所得を確保している。直接支払いの方が価格支持より優れた政策であることは、(食料・農業・農村政策審議会の委員をしている経済学者についてはわからないが)世界中の経済学者のコンセンサスである。価格支持は、本来市場で実現している価格より高い価格を農家に保証しようとする。需要が減少し供給が増えるので、需給が均衡する市場では起きない過剰が生じる。日本では、政府が高価格で米を買い入れていた食糧管理制度の下で、大きな過剰が生じた。EUも同じだった。その過剰を処理するため、日本では補助金を出して減反をし、EUでは補助金を出して国際市場で処理した。つまり、価格支持では、過剰という市場での歪みが生じ、それを処理するために、財政負担が必要となるのだ。直接支払いなら過剰は起きない。アメリカなどから攻められたこともあるが、この問題に気付いたEUは1993年、価格支持から直接支払いに移行した。ただし、同じく補助金を出しても、日本は減産、EUは生産拡大という違いがあった。食料安全保障の観点からは、EUの補助金の方がはるかに優れていた。日本も1995年に食糧管理制度を廃止した際、直接支払いに移行すればよかった。しかし、減反で供給を減少させ、高い米価を維持することを選択してしまった。今は、減反によって事前に過剰米処理をしていることになる。日本の政策当局者にとって不幸だったのは、EUと異なり、日本には、高米価で発展してきたJA農協という圧力団体があったことである。なお、日本の「納税者負担」(直接支払い)が少ないことをもって、欧米の方が手厚い保護を行っていると主張する農業経済学者がいる。日本の農業保護が少ないなどと主張するなら、OECDだけでなく、世界の農業経済学者から相手にされないだろうと思うのであるが、不思議なことに、日本の農業経済学会の中には同調者がいるようである。間違いだと思っている農業経済学者もいると思うのだが、あえて波風を立てないというのが学会の良い所のようだ。日本の農業の場合、専門家の言うことも信じてはいけないのである。 ●提言①消費者に負担を強いる農政を転換しよう 基本法第2条第1項は次のように規定する。「食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない」。さらに、同条第3項は、「食料の供給は、農業の生産性の向上を促進し」と規定する。つまり、基本法は、できる限り安い価格で供給すべきだとし、貧しい消費者にも配慮しているのである。しかし、自民党農林族、JA農協、農林水産省の農政トライアングルは、減反政策を強化してさらに米生産を減少させ、米価を上げようとしている。小麦よりも基礎的な食料だと思われる主食の米について、この価格高騰時にも、物価対策とは逆のことを行っているのである。 ●生活困窮者の声は審議会に届かない 食料・農業・農村政策審議会にも消費者の代表はいるが、豊かな主婦の人たちの代表者であって、貧しい人たちの代表ではない。最近の食料品価格の上昇で、生活困窮者の人たちのためのフードバンクに食料が集まらなくなっている。審議会の消費者代表委員は「多少高くても国産の方がよい」とJA農協の国産国消に同調する人だ。しかし、多少高いどころか、今の食料品価格では満足に食料を買えない人たちがいるのである。生活困窮者の声は審議会には届かない。これまで、消費量の14%しかない国産小麦の高い価格を守るために、86%の外国産小麦についても関税(正確には農林水産省が徴収する課徴金)を課して、消費者に高いパンやうどんを買わせてきた。国内農産物価格と国際価格との差を財政からの直接支払いで補てんするという政策変更を行えば、消費者にとっては、国内産だけでなく外国産農産物の消費者負担までなくなるという大きなメリットが生じる。農業に対する保護は同じで国民消費者の負担を減ずることができるのだ。 ●提言②減反を廃止するだけでよいのだ 農林水産省が努力しなくてもできる政策がある。医療のように、本来財政負担が行われれば、国民は安く財やサービスの提供を受けられるはずなのに、米の減反は補助金(納税者負担)を出して米価を上げる(消費者負担増加)という異常な政策である。国民消費者は納税者として消費者として二重の負担をしている。主食の米の価格を上げることは、消費税以上に逆進的だ。「経世済民」とは対極にある減反は、経済学的には最悪の政策である。減反を廃止するだけでよい。財政的にも3500億円の減反補助金を廃止できる。米価が下がって困る主業農家への補てん(直接支払い)は1500億円くらいで済む。サラリーマン収入に依存している兼業農家には、所得補償となる直接支払いは不要である。米価は下がる。零細な兼業農家は耕作を止めて主業農家に農地を貸しだすようになる。主業農家に直接支払いを交付すれば、これは地代補助となり、農地は円滑に主業農家に集積する。規模拡大で主業農家のコストが下がると、その収益は増加し、元兼業農家である地主に払う地代も上昇する。 ●農地の集約が進めば農村はよみがえる 都府県の平均的な農家である1ヘクタール未満の農家が農業から得ている所得は、トントンかマイナスである。こうした農家のゼロの米作所得に、20戸をかけようが40戸をかけようが、ゼロはゼロである。しかし、20ヘクタールの農地がある集落なら、1人の農業者に全ての農地を任せて耕作してもらうと、1500万円の所得を稼いでくれる。これを地代として、みんなの農家に配分した方が、集落全体のためになる。ビルの大家への家賃が、ビルの補修や修繕の対価であるのと同様、農地に払われる地代は、地主が農地や水路等の維持管理を行うことへの対価である。地代を受けた人は、その対価として、農業のインフラ整備にあたる農地や水路の維持管理の作業を行う。地主には地主の役割がある。健全な店子(担い手農家)がいるから、家賃によってビルの大家(地主)も補修や修繕ができる。このような関係を築かなければ、農村集落は衰退するしかない。農村振興のためにも、農業の構造改革が必要なのだ。国内の米産業を助けるばかりでなく、米価低下は貧しい消費者も助けることになる。食料分野では、減反廃止に勝る物価対策はない。 ●提言③私的経済の活用で国民負担を減らせ 農政は、米価が下がると市場から米を買い上げて米価を維持したり、農家に価格低下分を補てんしてきたりしている。また、2019年から、農家の所得を補償するため、価格低下や災害などで収入が減少した場合に補てんする保険制度を導入している。先物取引は、生産者にとって、将来の価格変動へのリスク回避の行為を行い、経営を安定させるための手段である。具体的に言うと、作付け前に、1俵1万5000円で売る先物契約をすれば、豊作や消費の減少で出来秋(収穫時)の価格が1万円となっても、1万5000円の収入を得ることができる。JA農協は、米が投機の対象となり、価格が乱高下することは望ましくないと主張する。しかし、投機資金で先物価格が2万円に上昇するなら、それは、農家にとっては良いことである。先物価格が上がり、農家が減反に参加しないで米を作り、出来秋に実現した米価が下がっても、農家が受け取る米価は先物価格であって、出来秋の米価ではない。先物価格が上昇すれば、生産者は生産を増やそうとするので、将来の現物価格は低下する。これは市場を安定させる。流通業者も不作で出来秋の価格が高騰しそうなときには、低い先物価格で契約をすれば、リスクを回避できる。先物市場で生産者や実需者の代わりにリスクを負担しているのは、投機家である。JA農協が先物取引に反対するのは、価格が市場で決定されるので、現在の卸売業者との相対取引と異なり、価格を操作できなくなるからである。これまで価格が低下するたびに、政府は財政負担をしてきた。そのような施策があるから、農家は試験的に導入された先物取引にメリットを感じなくなり、これを利用しようとしなかった。利用量が少ないことを主張して、農政トライアングルは先物取引の本格導入を認めてこなかった。しかし、先物のリスクヘッジ(価格安定)機能を利用すれば、価格補てんや保険制度などを行う必要はなくなる。国民負担は軽減される。 ●提言④市場を歪ませ不正を生んだ政策の是正を 2008年に汚染米による不正流通事件が発覚した。カビが生じたミニマム・アクセス米を農林水産省は糊用に売却した。安く政府から買い入れた業者が、主食用などに高く転売して、利益を得た。汚染米8368トンのほとんどが横流しされた。工業用の糊に売却するとトンあたり1万円程度だが、焼酎、あられ、せんべいなどの加工用途だと15万円、食用なら25万円で売却できる。横流しするとかならず儲かるのだ。この問題の本質は、減反政策により主食用の価格を意図的に高く維持する一方、本来主食用と同一の価格では取引されない他の用途向けの価格を安くして需要を作り出し、主食用との価格差を転作(減反)補助金として補てんしていることにある。同じ品質の米に用途別に多くの価格がつけられている「一物多価」の状況が発生するので、これに乗じた不正が発生する。不正をなくすためには、市場の歪みを生じている政策を是正すべきなのだ。 ●政府の介入がなければ一物一価は実現する しかし、農林水産省は、食糧管理制度が廃止され、米の流通規制がなくなったから、米の不正流通をチェックできなくなったとして、2009年米のトレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録および産地情報の伝達に関する法律」)を作った。汚染米事件を農林水産省の組織維持に利用したのだ。しかし、2013年に中国産米や加工用米を主食用に横流しした三瀧商事事件が起きている。米のトレーサビリティ法は役に立たなかった。経済政策の基本は、その問題を生じさせている源にダイレクトに対処すべきということだ。ここでは高米価と一物多価が問題なのだ。米の需要を拡大したいなら、減反を廃止して価格を下げ、輸出用の需要を拡大すべきだ。政府の介入が無くなれば、一物一価は実現する。一物多価が生じているのは、生乳でも同じである。生乳も政府の介入を止めて一物一価を実現すれば、アジアの飲用牛乳の需要拡大に向けた生乳の輸出が可能になる。 ●提言⑤食料自給のためにも米の増産と輸出を 食料自給率が低下した大きな原因は、国産の米の価格を大幅に引き上げてその消費を減少させ、輸入麦(小麦、大・はだか麦)の価格を長期間据え置いてその消費を増加させたことだ。1960年頃は米の消費量は小麦の3倍以上もあったのに、今では両者の消費量はほぼ同じ程度になってしまった。大・はだか麦を入れると、米麦の消費量は逆転した。今では、日本人の主食は米ではなく輸入麦なのかもしれない。国産の米をイジメて外国産の麦を優遇したのだ。今では500万トンの米を減産して800万トンの麦を輸入している。高米価で米の需要が減少したので、米価を維持するために減反政策を実施している。2000年から20年以上も食料自給率を45%に引き上げる目標を掲げているにもかかわらず、2000年の40%から逆に減り続け、2021年の食料自給率は38%である。ところが、1960年の食料自給率79%も、今の38%も、その過半は米である。つまり、食料自給率の低下は、米生産を減少させてきたことが原因なのである。 ●減反廃止で自給率は目標を超える 最も効果的な食料安全保障政策は、減反廃止による米の増産とこれによる輸出である。平時には米を輸出し、危機時には輸出に回していた米を食べるのである。日本政府は、財政負担を行って米や輸入麦などの備蓄を行っている。しかし、輸出は財政負担の要らない無償の備蓄の役割を果たす。輸出とは国内の消費以上に生産することなので、食料自給率は向上する。現在の水田面積全てにカリフォルニア米程度の単収の米を生産すれば、1700万トンの生産は難しくはない。国内生産が1700万トンで、国内消費分700万トン、輸出1000万トンとする。米の自給率は243%となる。現在、食料自給率のうち米は20%、残りが18%であるので、米の作付け拡大で他作物が減少する分を3%とすると、この場合の食料自給率は64%(20%×243%+18%-3%)となり、目標としてきた45%を大きく超える。農政トライアングルは、食料自給率の低さを農業の保護や予算の獲得の方便として利用してきた。彼らにとって、食料自給率は低いままの方がよい。 ●日本に最も適した農産物は米だ 今回も麦や大豆の生産拡大を推進するとしている。しかし、これは1970年からの減反=麦等への転作を行ってほとんど効果がなかった政策である。また、財務省は減反の補助金を払いたくないため、水田を畑に転換するための補助金を支出しようとしている。しかし、日本に適した農産物は米である。米はグルテンフリーであるばかりか、体内で合成できない必須アミノ酸を小麦より多く含む。しかも、国産大豆には納豆などの需要があるが、国産小麦は品質が悪く生産も安定しないので、製粉業界から敬遠されている。小麦を輸入している中にあって、国産小麦は長年過剰なのである。製粉業界は農林水産省からさらに国産小麦を押し付けられるのを心配しているだろう。とるべき政策は、減反廃止=米の増産である。財政負担を大幅に削減しようとすれば、減反を廃止すべきだ。しかし、それだと財務省は自民党と正面対決となる。水田の一部を畑にすれば、その面積だけ減反補助金を払わなくて済む。財政負担軽減からすれば次善の策だが、やらないよりはましだ。このように財務省は考えたのだろう。しかし、姑息である。日本で最も優れている農産物は米なのに、それを生産できないようにしようとしている。多面的機能でも、水田の効果は畑を大きく上回る。経済学的にも正当化できない。そろそろ、国民のために真剣に食料安全保障を議論しようではないか。 ●提言⑥肥大化した農政をスリムにしよう 欧米と異なり、農林水産省は、行政が課題を細かく設定し、手取り足取り指導・支援するといったパターナリスティックな対応を行っている。このため、日本の農業施策は細かく複雑なものとなっている。農林水産省には100程度の課があり、一つの課でも多くの事業がある。ほとんどが零細な補助金による事業である。欧米の農業政策は、法律を読めばおおむね理解できる。しかし、日本の場合、法律やそれに基づく政省令には、具体的な事業や仕組みが書かれていないことが多い。その代わり、様々な補助事業ごとに、趣旨や複雑な交付条件、申請書類の様式、申請手続きや事業実施報告の方法などに関する要綱・要領という長く難解な行政文書(都道府県や団体等への通達)が作られる。農林水産省の下請け機関となっている自治体職員は、これを読み込んだうえで、農業団体や農家に事業の趣旨や仕組みを周知徹底し、補助金の申請を手助けしなければならない。これに自治体職員の膨大なエネルギーが投入されてきた。農林水産省は、自治体の職員が地域の農業振興に必要な政策を考案する時間を奪っている。農林水産省が多種多様な補助事業を作る大きな理由は、自分たちの仕事作りである。例えば、2012年から、新しく農業を始めようとする人に対し、研修期間中は毎年150万円を2年間、経営を開始すると毎年150万円を3年間、合計750万円補助する事業を実施している。さらに、新規就農支援資金(借入限度額3700万円:特認1億円、償還期間17年(据置期間5年)の無利子資金)が用意されている。 至れり尽くせりである。 ●整合性のある政策が推進できない ところが、成果はほとんど上がっていない。多額の補助をもらうことで、努力を怠たったり、農業経営に対する厳しさがなくなったりするからである。しかし、農林水産省は金を出しっぱなしで効果を検証しようともしない。この事業を廃止するつもりはない。また、様々な事業が多くの課ごとに作られるため、整合性のある食料・農業政策は推進できない。農家個人所有の田畑の整備のため、毎年1兆円規模の農業土木(基盤整備)事業が、公共事業として農家の負担わずか15%程度で実施されてきた。農家が投資してコストダウンを図っても、農産物価格が低下すると消費者はメリットを受けるが、農家は投資額を回収できなくなると考えて投資しなくなる、これが、農地整備という私的な投資を公共事業で行う根拠だった。その一方で、農産物価格を下げないことを目的とする減反に50年間で9兆円、過剰米処理に3兆円以上を投入した。しかし、農業土木の関係者としては、予算を獲得して事業を行いさえすれば、天下り先が確保できるので、農政の他の部門には全く関心を持たない。畜産についても、価格競争力向上を実現するとして巨額の財政資金を投下しながら、畜産物価格は逆に上がっている。2000万円の所得がある畜産農家を保護するため、貧しい消費者に負担を強いながら、畜産物価格を上げている。そもそも環境に著しい負荷を与えている畜産は、補助するのではなく課税すべきである。野菜、果樹、花については、関税保護もわずかで、その関税もTPP交渉の結果撤廃される。外国からの飼料に依存する畜産のように手厚い補助金もない。しかし、農地資源は、畜産以上に守っている。農政が論理破綻し複雑かつ矛盾の体系となっている今日、我々は食料安全保障や多面的機能という農政の目的に立ち返り、論理整合的でシンプルな農業政策を検討すべきではないだろうか?食料安全保障も多面的機能も、農地資源を維持してこそ達成できる。そうであれば、品目ごとの農業政策や就農補助などこまごました補助事業は全て廃止して、農地面積確保のため、農地面積当たりいくらという単一の直接支払いを行えばよい。このような単一の直接支払いは、EUが長年の改革の末到達した農業保護の姿である。 ●「何ぞ彼等をして自ら済わしめざると」 雑多な補助事業は、農家の創意工夫を削いできた。困ると農政が助けてくれるという他力本願的な経営になってしまった。前回紹介した、柳田國男、石黒忠篤、石橋湛山には、共通の尊敬する人物がいる。二宮尊徳である。また、かれらが共通して主張したのは、「自助」である。柳田國男は主張する。「世に小慈善家なる者ありて、しばしば叫びて曰く、小民救済せざるべからずと。予を以て見れば是れ甚だしく彼等を侮蔑するの語なり。予は乃ち答えて曰わんとす。何ぞ彼等をして自ら済わしめざると。自力、進歩協同相助是、実に産業組合の大主眼なり」(『最新産業組合通解』定本第28巻130ページ参照))。農地の上に、米、野菜、牧草など、何を植えるかは、農家の創意工夫に任せるべきであって、農政が口を出すべきではない。農地を利用しない輸入飼料依存の畜産には直接支払いは交付されない。農家が基盤整備などの土地改良を行いたければ、直接支払いから支出すればよい。農業土木技官がゼネコンに天下るための公共事業予算獲得運動などなくなる。農水省の組織・定員は大幅にスリム化できる。自治体職員は、こまごました零細な補助事業に悩まされなくなる。今の農政はあまりにもわかりにくく、農林水産省の職員のためのものとなっている。国民のための農政とは遠く離れている。 食料・農業・農村基本法見直しに関する筆者の論考は次のとおりです。 ・「食料・農業・農村基本法見直しの背景はなにか 政治に翻弄された農政の軌跡から見えてくる揺り戻しの正体とは」(2022年10月11日付) ・「『改悪』の結末が透ける食料・農業・農村基本法見直し 保護農政への揺り戻し図る農政トライアングルと『お墨付き』のためだけの審議会」(2022年10月21日付) ・「食料・農業・農村基本法見直しのウソとまやかし だまされないために知っておきたい本当のこと」(2022年11月02日付) ・「戦後農政を総決算せよ 食料・農業・農村基本法見直しのあるべき基本原則とは?」(2022年12月1日付) *1-5-1:https://president.jp/articles/-/47124?page=1 (President 2021/6/23) 96%は国内生産なのに「卵の自給率は10%」と農水省が主張するカラクリ、エサが輸入品なら「外国産」扱い 鶏卵の96%は国内で生産されている。しかし農林水産省の統計では「鶏卵の自給率は10%」とされている。なぜそうなるのか。東進ハイスクール地理講師の山岡信幸さんは「諸外国と異なり、日本だけがカロリーベースという計算式を使っている。だから実態と数字が異なっている」という――。 ●品目別で見れば自給率の高い農産物も多い 日本は主食であるお米の一部をアメリカ合衆国などから輸入しています。ただし、輸入分は加工用などに回しており、食用米の自給率は100%です。では、副食、つまり肉や野菜など米以外の農畜産物の自給率はどうなっているのでしょうか。過去の推移も含めて確認しておきましょう。図表1を見てください。太線で示した総合食料自給率は、1960年の79%から、2018年の37%まで、半分以下に低下しています。もし食料輸入が全面的にストップすれば、1日1食になってしまう(?)という数値ですね。しかし、先述の主食の米に加え、鶏卵・肉類・牛乳などの畜産品、野菜、魚介類など多くの食料の自給率はその数値を上回っています。足を引っ張っているのは小麦などの穀物や大豆などに限られます。なぜ「総合」になった途端に数字が低くなるのでしょう? ●品目別と総合で異なる自給率の計算基準 これには「からくり」があります。品目別の自給率は重量によって計算していますが、総合食料自給率は熱量(カロリー)をベースにした計算なのです。重量当たりの熱量が小さい野菜や果実をたくさん国内で作っていても、熱量の大きい小麦や大豆の輸入が多いため、総合の自給率は低くなっているのです。そのうえ、鶏卵・肉類・牛乳など、飼料(餌)で育てたものは自給分に含まれないことになっています(飼料作物の代表格とうもろこしの自給率がグラフには出てきませんが、ほぼ全量を輸入しており、事実上0%です)。国内の畜産農家が牛や豚や鶏を育てる手間ひまは自給率の分子にカウントされないのです。さらに、この総合食料自給率で分母となるのは、私たちの摂取熱量ではなく供給熱量なのです。つまり国産と輸入の合計から輸出分を差し引いたもの、国内市場に出回った農産物の熱量全体ということです。ということは、莫大な食品ロスも分母に含まれています。日本では、ごくわずかに販売期限を過ぎただけで、推定で140万食分以上のコンビニ弁当が毎日廃棄されているそうです(ジャーナリスト井出留美氏のYahoo!ニュース個人の記事「『24時間営業』だけが問題?全国推定143万個分の弁当を毎日捨てるコンビニはなぜ見切り販売しないのか」による)。先進国では、このような「フードロス」が問題になっており、各地のフードバンク活動でその有効利用が図られるほどです。 ●分母は大きく、分子は小さく 日本人1人1日当たり供給熱量は約2400キロカロリーですが、摂取熱量は約1900キロカロリーですから、2割くらいが廃棄されています。1970年代以降、産業構造の変化によって肉体労働は減少し、日常生活でも自動車利用の増加など利便性の向上で運動量は低下しています。健康志向から「カロリーひかえめ」が好まれる現代では、もう私たちはそれほど多くのカロリーを摂取しないのです。もし、実際に摂取している熱量を分母に計算すれば、自給率は約50%にアップします。このように、分母はなるべく大きく、分子はなるべく小さくなるように計算されたのが「総合食料自給率」なのです。供給熱量ベースで自給率を計算している国は世界的に見てごくわずかであり、一般的には生産額ベースで計算されています。日本の生産額ベースによる食料自給率は66%(2019年)となり、供給熱量ベースの2倍近くに跳ね上がります。保護政策で価格を維持している米や、品質が高く消費者の嗜好に合わせて生産される野菜・果実など、単価の高い農産物の自給率が高いからですね。 ●「自給率の低さ」を強調したい 農林水産省が供給熱量ベースの自給率を公表し始めた1983年といえば、日米貿易摩擦を背景に米国から農産物輸入の自由化が強く求められていた時期です。「外国の安い農産物が大量に輸入されれば、日本の農業は崩壊、食料自給率はさらに低下、国際情勢によって飢餓が訪れる!」と国民の不安感に訴えるには、「今でも自給率はこんなに低い」というアナウンスが必要だったのでしょう。考えてみると、もし海外からの輸入が完全にストップすると、自給率の分子(国内生産)と分母(総供給)は同じになって、食料自給率は100%です。もちろんそれは望ましい状態ではありません。「食の安全保障」という観点から考えるならば、むしろ安定的な食料輸入を可能にする国際関係の確立を図るべきだし、日本農業の振興という観点からは高品質で競争力の高い野菜や果実などの輸出を拡大すべきでしょう。国産農産物にこだわって「食料自給率をできるだけ高めなければならない」という政策目標は、必ずしも正しいとはいえないのではないでしょうか。 ●外国産の卵をスーパーで見ない理由 ところで、先ほどのグラフで品目別に自給率の推移を見ると、さまざまな背景が読み取れます。たとえば、今も自給率96%を維持する鶏卵。新鮮さを求められるが卵自体の冷凍はできず、割れないように長距離輸送するのも困難です。そのような品目の特性上、あまり貿易には向いていませんね。だからほとんどが国産なのですが、それでも4%は輸入です。「価格の優等生」である卵は、スーパーの特売品になることが多いのですが、外国産の卵が売り場に並んでいるのは見たことがありません。実は、殻を除いて冷凍した「液卵」、乾燥させた「粉卵」などの加工品として、菓子の原料、外食産業などの業務用に輸入されているのです(図表2)。 ●進む養鶏農家の集約化と大規模化 ちなみに、卵を産む鶏(採卵鶏)の飼養をする国内の養鶏農家の戸数は年々減っており、全国で2000戸程度にすぎませんが、残った農家は飼養羽数の大規模化が著しく、10万羽以上を飼う大規模養鶏場も珍しくありません。そのような大規模養鶏場だけで、全国の飼養羽数の75%を占めています。肉用のブロイラーでも同様の傾向になっています。いずれにせよ、飼料の大半はおもに米国から輸入するとうもろこしなどです。これを考慮に入れると、卵の自給率は10%程度になってしまいます。 ●「国産野菜」にこだわる意味 鮮度を要求される点では、野菜も鶏卵と同じです。それでも、ほぼ100%だった野菜類の自給率は1980年代から徐々に低下して、現在は77%。多くは冷凍野菜などの加工品ですが、輸送機関・流通の整備によって輸入が可能になってきたことをうかがわせます。中国では、国内の大都市圏にも日本にも近い沿海部の山東シャントン省などで野菜の生産・輸出に力を入れています。ところが2002年には、中国産ほうれんそうの残留農薬が問題となり、その安全性に疑問が投げかけられました。ほうれんそうの中国からの輸入量は激減し、その後も回復できていません。その頃から、外食産業や加工食品に「国産野菜を使用しています」というフレーズを頻繁ひんぱんに見かけるようになりました。しかし、ほうれんそうはともかく、今も中国産を中心に野菜全体の輸入は増加しています。この間の飛躍的な経済成長を背景に、中国みずからの国内において都市住民を中心に安全な食品を求める要請が高まりました。法規制の強化などによって、中国農業の安全管理体制の確立は一定程度進んでいるようです。たまにスーパーで見かける中国産野菜は、大規模生産と安い人件費のおかげで国産野菜に比べてたしかに激安です。とはいえ、あの農薬騒動の記憶が残る日本の消費者としては、値段の魅力だけではなかなか手に取れません。そのため、加工用などに回される割合が高いようですから、結局どこかで口にしているのでしょう。国産にこだわる人も知っておきたいのは、日本も耕地面積当たり農薬使用量が世界トップクラスの農薬大国だということ。最近では、発がん性が疑われる除草剤グリホサートや、生態系への影響が指摘されるネオニコチノイド系農薬などについて、使用禁止に向かう欧州連合(EU)などの潮流に逆行して日本では規制が緩和されています。国産=安全は本当でしょうか。 *1-5-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16139800.html (朝日新聞 2025年2月1日) 卵1キロ卸価格、東京で300円超 23年7月以来 鳥インフルエンザの急増の影響で、卵価格が上昇している。卵の卸売価格の目安となるJA全農たまごが31日に発表した東京地区のMサイズ1キロあたりの値段は305円で、1月上旬から80円上昇した。300円超えは、過去最悪の被害の影響が続いていた2023年7月以来の水準。大阪地区は同290円、名古屋地区は同320円だった。31日時点で、今シーズン(24年秋~25年春)の鳥インフルエンザは14道県で48件発生、約911万羽が殺処分の方針となっている。特に年明けから急増し、1月は過去最大だった22年のシーズン(22年秋~23年春)の発生件数、処分数を上回り、特に千葉県、愛知県に集中している。22年のシーズンは過去最大の鳥インフルエンザが発生し、26道県で84件、約1771万羽が処分された。この影響で、東京地区の卸売価格が350円となり、「エッグショック」とも呼ばれた。江藤拓農林水産相は31日の閣議後の会見で、「特に1月に入ってからは異常な事態。いよいよ価格の面で顕著になってきた。22年のシーズンは(卸売価格が)350円まで値上がりしたが、そういう事態は何としても避けたい」と述べた。 <森林と林業の重要性> *2-1:https://digital.asahi.com/articles/ASS573F9BS57OXIE02LM.html (朝日新聞 2024年5月16日) 東京都が買い続ける森 世界的探検家は言う「都民は恵まれている」 始まりは1901年、譲り受けた8460ヘクタールの森だった。最近では2022年度までの10年間で3500ヘクタール以上を購入。東京都はいまも森林を買い続けており、計2万5千ヘクタールを所有する。その面積は都の10分の1以上にあたる。いったいどこに。そして、なぜ。実はその6割が隣接する山梨県にある多摩川上流域の森。そう、この水源林こそ、都が120年以上にわたって守ってきた東京の水のふるさとだ。蛇口をひねれば、すぐに水が飲める――。1960年代に利根川・荒川水系が上水道に本格利用されるようになるまで、多摩川は都民にとって「命の川」だった。そんな水源地の荒廃を憂えた東京府(当時)が自ら管理を始める。植林を進め、土砂の流出や災害を予防し、きれいな水を確保することが目的だった。「森が守られてこそ水の量と質が保たれる。多摩川は世界のモデルといえる存在です」。世界に名だたる川の源流地域を訪ね歩き、2023年の「植村直己冒険賞」を受けた探検家、山田高司さん(66)はそう断言する。 ●守り続けて120年 ボランティアも 今年3月、筒井和行さん(80)=東京都東村山市=は高さ約20メートルのヒノキの上にいた。山梨県小菅村の森の中で、慣れた手つきで不要な枝を切り払った。ここは都が管理する森林ではない。ただ、地権者の同意が得られれば、源流域の保全のため、間伐や枝打ちをしている。担い手は筒井さんのようなボランティア「森林隊」だ。せっせと植林した昔と違って、いまは切られないまま放置された山林も多い。日が差し込まないことで木や草が育たず、土がむき出しになれば、大雨の際に大量の土砂が貯水池に流出し、水を汚しかねない。「水に関心があるし、山をきれいにしたい。若いとき、趣味の登山で自然によくないことをした罪滅ぼしでもあるんです」。そんな思いから筒井さんはこれまでに300回以上、「森林隊」の活動に参加してきた。 ●多摩川の「最初の一滴」を訪ねて 東京湾から西へ138キロ。山梨県甲州市にある笠取山(1953メートル)の山頂付近の岩場が、多摩川の源流とされている場所だ。「水干(みずひ)」と呼ばれ、最初の一滴がしたたる。4月末、その水干を目指して山を登った。先人たちが苗を植えたカラマツ人工林やミズナラといった天然林に覆われ、静けさと美しさを保っている。残念なことに滴は見られなかったものの、水干から下ってすぐのところで、大河に注ぐ最初のせせらぎに出会えた。清らかな流れに手を浸すと、かじかむぐらいに冷たかった。ここを訪れたことがある山田さんの目に焼き付いている光景があるという。1981年に訪ねたアマゾン川源流域のすさまじい森林破壊だ。燃料の薪にするため切り尽くしたり焼き畑にしたりして、一帯が丸裸になっていた。いま世界を見渡せば、各国政府主導の緑化の取り組みは遅々として進まず、地球温暖化もあいまって森林面積は減り続けている。それに伴う水不足も深刻だ。そんななか、都やボランティア、さまざまな人たちの努力もあって、多摩川源流域は1世紀以上にわたって守られてきた。いまも東京における上水道の約2割は多摩川水系が担う。「都民は恵まれている」と山田さん。だからこそ、訴えたいことがある。「もっと水に、もっと森に、もっと環境に関心をもってほしい」 *2-2:https://digital.asahi.com/articles/ASS6L2R5MS6LUJUB001M.html (朝日新聞 2024年6月19日) クマ被害多発で保護から管理へ 野生動物と人間が共生するには ●2030 SDGsで変える 近年、日本でクマによる人身被害が急増しています。昨年度は被害者が219人(うち死者6人)と過去最多に。一方で、シカやイノシシといった他の野生動物による農業や林業などへの被害も深刻です。SDGsでは生物多様性を保ちながら「陸の豊かさも守る」ことを目指しています。野生動物と人間がどう共生すべきか。被害が多い北東北で、現状と課題を探ります。 ●木の芽やドングリ食い尽くすシカ・イノシシ 5月上旬、岩手県花巻市の山林に、花巻市猟友会の猟師約10人が集まった。猟期は終了しているが、市から有害駆除の委託を受けて、シカを捕獲するためだ。シカを追いあげる「勢子(せこ)」と、猟銃で仕留める「立ち」に分かれて、山中に分け入る。「ここが獣道。踏み固められて、足跡もついているでしょう」。猟友会会長の藤沼弘文さん(78)が斜面を指さした。素人目には見極めが難しい。藤沼さんは獣道の近くで、すぐシカを撃てる態勢に入った。例年、この時期はまだ山に雪が残っていた。だが、暖冬の影響で雪解けが早く、すでに草木が生い茂っている。猟師たちは「シカを探すのが難しい」と顔をしかめた。藤沼さんの携帯電話が鳴った。「温泉街でクマが出た」という市からの連絡だった。山に来ていないメンバーに連絡して、現地に向かってもらった。クマの出没が多発した昨秋には、1日に何件も出動要請があったという。昨年度、岩手県ではクマによる人身被害が49件発生。秋田県に次いで多く、過去最悪の数字となった。今年度も、秋田や岩手ではすでに人身被害が発生している。クマを徹底的に排除してほしい――。被害が多発する地域を中心に、そんな声が高まっている。国は今年、捕獲や調査に国の交付金が出る「指定管理鳥獣」にヒグマとツキノワグマを追加し、これまでの保護政策から管理の方向へかじをきった。だが、半世紀以上山を歩いてきた藤沼さんは危機感を抱く。急増するシカなどへの対策が進まないまま、クマの駆除ばかりが注目されていると感じるからだ。「イノシシやシカが木々の芽やドングリなどを食い尽くした影響で、クマは人里に出るようになったのでは」と藤沼さんは語る。同猟友会では「クマとの共存を考える手帳」を独自で発行し、クマによる被害にあわないために人間がすべきことや、猟友会が近年、シカやイノシシの駆除に追われている現状などを伝える活動もしている。県によると、県内のクマの生息数は、2020年度末で推定3700頭。一方、22年度のシカの生息数は推定約10万2千頭だ。シカは江戸時代に県北部まで広く分布していたが、明治以後の乱獲で姿をほぼ消し、長らく保護される対象だった。それが1970年代から爆発的に増え、20年度以降、県内では狩猟と猟期以外の有害鳥獣捕獲分と合わせて年2万頭以上のシカが捕獲されているが、一向に減らない。 ●個体数把握し対策講じる専門家の育成を 大型野生動物の専門家である岩手大の山内貴義准教授は「シカは植林した苗木や希少な高山植物までも食べ尽くし、林業や自然生態系への深刻な影響が懸念されている」と話す。イノシシは県内では明治末期に一度絶滅したとみられるが、10年代から生息域が広まり、22年度の捕獲数は979頭にのぼった。山内准教授は「シカやイノシシは、クマと食べ物が重複し、冬の間も活動するため、冬眠明けのクマの食べ物が減ったのでは。ここ数年、春先の町中にクマが出没することと無関係ではない」と指摘する。日本の野生動物管理の指導的役割を担ってきた、兵庫県森林動物研究センターの梶光一所長(71)は「人口減少の時代だからこそ、生態学、森林管理、被害防除など多様な分野を学んだ野生動物管理の専門家の育成が必要だ」と強調する。野生動物の個体数を把握・管理して、被害を未然に防ぐため、電気柵の設置といった方策を講じる――。既にその必要性は共有され、被害を防ぐための技術はほぼ実用化されているという。問題は誰が担うかだ。「国の制度や法の改正があるたびに、専門家の育成や配置が重要だとはずっと指摘されてきたのですが……」。環境省によると、昨年度、各都道府県で鳥獣対策にあたる行政職員3603人のうち、専門的な知識を有する人はわずか4.7%。加えて異動があるため、継続的な対応が難しいことも課題だ。昨年、全国で最もクマによる人身被害が多かった秋田県のように、鳥獣管理の専門職員を配置する自治体も出始めたが、まだ少数派だ。国は20年度から、東京農工大を核とした6大学と2団体で検討した野生動物管理学の教育プログラムを支援するなどして、人材育成と配置に着手したところだ。 ●絶滅させない数と地域に許容できる数 国によると、野生鳥獣による農作物被害額は156億円(22年度)で、その約6割がシカ、イノシシによるものだ。国は23年度までの10年間で、シカとイノシシの個体数を半減させる計画をたてたが、シカの目標値を達成できず、計画を5年延長した。捕獲を担うハンターの高齢化や減少が止まらないからだ。ハンターはあくまで趣味の愛好家で、地域のためにボランティアで活動している。各地でクマによる人身被害や目撃情報が急増する中で、現場で対応にあたる人材が圧倒的に不足している。北海道では、自治体からのヒグマ駆除の要請を辞退する猟友会もでている。梶さんは「日本は明治時代にドイツから森林学や狩猟学を導入した。そのドイツでは、教育機関が森林管理と狩猟学を一体で教え、国が森林と狩猟を一体で管理する。趣味の狩猟とは別に、専門的な捕獲者がいる。人口減の時代だからこそ、日本でもそういった専門家が必要だ」。そのうえで梶さんは「地域社会での合意形成」が大事だという。クマの場合、地域ぐるみでゴミを外に放置しないといった対策をしたうえで、人里に居ついた個体は排除する必要がある。「専門家と地元の人が『クマを絶滅させないための生息数』と、『地域にどのくらいの数のクマだったら許容できるか』を十分に話し合い、納得することが大事。正解は一つではない。要は私たちが自然とどう向き合うか、その地域をどう持続させるかを自身で決める必要があるのです」 *2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250202&ng=DGKKZO86466890R00C25A2TYC000 (日経新聞 2025.2.2) <科学で迫る日本人> なぜ縄文に農業始まらず?管理もとに共生植物が食料に 日本列島には食料になる植物がいくつも持ち込まれた。弥生時代に稲作が普及する前にも農耕とまではいかないが、人の管理をもとに「共生関係」が生まれ、食料につながっていた。歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏の著書「サピエンス全史」にある「小麦が人を操った」といったとらえ方とは差があるようだ。日本列島に最初に持ち込まれたイネはどんな品種なのか――。神戸大学の石川亮准教授は弥生時代初期の青谷上寺地遺跡(鳥取市)で出土したイネの籾のゲノム(全遺伝情報)を解析した結果を心待ちにする。この遺跡の籾は水につかっていたためDNAの保存状態がよく、解読できる可能性があるという。イネの研究は進み、もち米かうるち米か、赤色か白色かを決める遺伝子などゲノムの特徴が分かってきた。石川氏は「出土した籾のゲノムをもとに今のイネを品種改良して当時のイネを再現したい」と意気込む。現在のイネは品種改良が進んだもので、当時の社会をはかるにも当時の収量の把握などは重要になる。注目するイネの特徴の一つが、稲穂からの籾の落ちやすさ「脱粒性」だ。時代とともに遺伝子が変異して脱粒性が変わり、今の姿になったのかもしれない。現代の稲作では籾が落ちにくいことで栽培しやすいが、昔は落ちる方が都合がよかった可能性もある。人が栽培することによる遺伝子や形質の変化を「栽培化」という。西アジアの麦、東アジアのイネなどが代表例だ。様々な植物のゲノム解読が進み、栽培化の実像が明らかになりつつある。栽培植物を利用する「農耕」が中心的な役割を果たす農業社会へと進んだ経緯に迫ろうとしている。弥生時代に稲作が広がるまではクリやドングリを主体とした採集や狩猟、漁労で食料を得ていたといわれる。イネとともにアワやキビが伝わったころ、中国北部では雑穀を中心とした農業社会が起きている。日本ではどうなのか。東京大学の米田穣教授らは縄文時代晩期末の七五三掛遺跡(長野県小諸市)から出土した縄文人の骨のコラーゲンの炭素同位体などを解析し、アワやキビを食べていたことを明らかにした。ただ主食のレベルではなかった。縄文時代の畑は確認されておらず、農業社会には至っていないと考えられている。米田氏は「縄文人は食料生産のために自然を改変する発想がなかったように見える。存在するものを管理して収穫増をはかるが、植物を育てるために田畑を作るという発想はなかったのではないか」と指摘する。縄文人の遺跡やその周囲からはクリの花粉が集中して見つかっている。つまり縄文人は周囲をある程度管理していたと考えられている。そこでヒエやマメ科のダイズやアズキの栽培化が進んだ可能性がある。当時を確かめようと、岡山理科大学の那須浩郎准教授らは真脇遺跡公園(石川県能登町)で再現実験を進めている。那須氏は「畑を作らなくても、草刈りをして火入れをするだけで、アズキを増やすことができたのではないか」と話す。実験ではこの方法でアズキの原種のヤブツルアズキを収穫する。こうした簡単な行為だけで、耕起を伴う栽培に負けない収量を得られるとみている。「縄文人は有用な植物の生息環境を構築するという農耕民とは全く別の方法で野生のアズキを維持・管理していたのかもしれない」(那須氏)。従来、栽培化と農業は同時期に起きたと考えられていた。だが、遺跡から出土する植物の栽培化の証拠を年代ごとに調べることで、ずれがあることが分かってきた。栽培化は数千年かけて起きていた。急に農業が確立されたわけではなく、徐々に進んでいたわけだ。農耕というほどではなく、食料の獲得手段の一つとして、管理した土地の周辺のものを採集していた時期があったと考えられている。そこでは人と植物のどちらか一方ではなく、双方が利益を得る「相利共生」の関係があり、人が意図しない形で「共進化」が起きていた可能性がある。例えば、マメ科は縄文時代中期以降に大型化が進んだことが分かっている。「ごみ捨て場で自然に育ったマメのうち、日光にあたりやすい大きな苗が生き残って増え、大型化が進んだのかもしれない」(米田氏)。従来の考古学では、地球の寒冷化や人口増加といった圧力をもとに人類の活動の変化を説明する「ストレスモデル」で考える傾向が強かった。そこから離れ、もっと違う理由を考えるのが今の流れだ。植物にも遺伝的な特徴から、栽培化が起きやすい種類があったかもしれない。例えば、染色体のセット数が少ないタイプは多いものに比べ、1つの遺伝子変異による形質の変化が起きやすい。縄文時代に農耕が起きなかった要因は食糧資源の多様さや堆肥作りに適した家畜の不在など多面的な検証がいるが、共生関係に迫ることで当時の社会が見えてくるだろう。 <その他の人手不足業種について> *3-1-1:https://digital.asahi.com/articles/AST220466T22UTNB00HM.html?iref=comtop_7_05 (朝日新聞 2025年2月2日) 道路陥没事故、本格的な救助至らず 「時間要する可能性高い」と知事 埼玉県八潮市で県道が陥没してトラックが転落した事故は2日夜になっても、本格的な救助活動には至っていない。穴の内部に水がたまり、周囲の地盤も不安定で、崩落による二次被害の可能性を否定できないためで、消防は救援隊が穴の中に入り、運転手を捜索する活動には当面移れないとみている。関東地方は2日、気温が下がり、雨天になった。八潮市内でも雨が断続的に降るなか、現場ではショベルカーなどの重機やトラックが行き来していた。1日朝に完成した救助活動を進めるためのスロープ(傾斜路)の強度を強めたり、土囊(どのう)を入れたりする作業を続けた。県などはスロープの完成を受けて、本格的な救助活動を進める予定だった。だが、穴の内部の水位が上昇したことから、消防は隊員らの安全を確保するため、1日夕からスロープの先にある穴に下りての救助活動を中断している。県などは今後、穴の内部の水位を低下させるため、ポンプ車での排水を進める方針。水のない方向にスロープを延長することも検討するという。陥没した箇所には土砂や岩のほか、コンクリート製の箱形の構造物があるという。県によると、破損したとみられる下水道管の水の流れが悪くなっていることから、管内になんらかの異物があるとみて、ドローンなどを使って調査する方針だ。県によると、事故発生から6日目を迎え、穴の大きさは直径31メートル、深さ16メートルにまで広がっている模様だ。運転手の70代の男性が閉じ込められた運転席は土砂などに埋もれて確認できていない。大野元裕知事は2日の県危機対策会議で、「救出や復旧までさらなる時間を要する可能性が高い」と説明。その上で「12市町120万人や事業者の協力のおかげで、下水の流入は下がっているものの根本的な解決には至っていない」と述べた。県は引き続き、洗濯や風呂の使用をできる限り控えるよう呼びかける。 *3-1-2:https://www.yomiuri.co.jp/national/20250209-OYT1T50061/?utm_source=webpush&utm_medium=pushone (読売新聞 2025/2/9) 転落した運転手の捜索活動、30分で打ち切り…手掛かり見つからず今後の予定なし 埼玉県八潮市の県道が陥没し、トラックが転落した事故で、消防は9日朝、安否不明となっている70歳代の男性運転手の重機での捜索を再開したが、約30分で打ち切った。手がかりが見つからなかった上、さらなる崩落による二次被害の懸念が高まったため。消防によると、作業は午前7時半頃に始まり、消防隊員約20人が重機でがれきや土砂をすくう捜索作業に参加した。ただ、運転手の居場所などに関する手がかりが見つからなかった上、捜索範囲を広げるとさらなる崩落を招く恐れがあり、約30分で終えた。消防は今後の穴内部での捜索は予定しておらず、運転席部分とみられるものが見つかった下水道管内の捜索などを検討するとみられる。事故は1月28日午前9時50分頃に発生。交差点の中央付近が陥没し、トラックが転落した。運転手とは同日午後1時頃に消防隊員と会話して以降、連絡が取れない状況が続いている。消防による捜索は今月1日夜、穴内部で水が湧き出ていたことなどから中断していた。事故現場は土壌がもろく、断続的に下水とみられる水が流れ込んでいることなどから、陥没の穴が拡大。県は穴につながる緩やかなスロープ2本を造成し、周辺で土壌改良を実施するなど、捜索活動に向けて大規模な工事を続けてきた。 *3-1-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/385007 (東京新聞 2025年2月10日) 埼玉・八潮の道路陥没、穴の中での捜索は断念 不明男性の手がかり求め地表から細い穴、下水管の中を捜索へ 埼玉県八潮市の道路陥没事故で、消防は9日、行方が分かっていないトラックの男性運転手について、穴の中での捜索を終了したと明らかにした。今後は下水管内の捜索に軸足を移す。県は10日、管内を常時監視する機材を投入するため、地表に細い穴を開けた。消防や県によると、崩落の恐れがあった地表近くのコンクリート管を8日までに撤去。9日朝、重機で土砂をすくって男性を捜したが、手掛かりは得られなかった。さらなる土砂崩落の恐れもあるため、捜索は30分ほどで中止した。下水管は地下約10メートルにあり、直径は約4.7メートル。ドローンによる管内の調査で、現場の下流100~200メートルの地点でトラックの運転席部分とみられる金属塊が見つかっている。地表から開けた細い穴は直径約13センチ。9~10日に地表から掘り下げ、下水管の表面を破り、金属塊近くの2カ所に通した。距離を測定できる機材や小型カメラなどを投入し、管内の状況把握を試みる。NTT東日本によると、近隣で不通になっていた固定電話400回線は9日までに全て復旧した。 *3-1-4:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16146604.html (朝日新聞 2025年2月11日) 陥没、救助見通し立たず 穴側からの活動断念 埼玉県八潮市で県道が陥没してトラックが転落した事故で、安否不明となっているトラックの男性運転手の救助が難航している。運転席部分とみられるものが見つかった下水道管内は、水流や硫化水素の影響で人が近づけない状況だからだ。県や消防は陥没した穴側からの救助は断念。新たな方法を模索するが、発生から10日以上過ぎても見通しは立っていない。5日に行われた県のドローンによる調査で、陥没地点の100~200メートル下流の下水道管(直径4・75メートル)内に、トラックの運転席部分とみられるものが確認された。一部が流水につかり、男性の姿は確認できなかったが、県や消防は男性がこの周辺にいる可能性があるとみている。さらに上流側ではがれきなどの堆積(たいせき)物が管を塞いでおり、陥没地点側は汚水であふれていた。陥没が起きたのは1月28日。当初、消防は穴の内部に隊員を入れたり、クレーンでトラックごと救助しようとしたりしたが、失敗。荷台部分は引き上げたものの現場周辺で崩落が相次いで穴が拡大し、運転席部分はがれきや土砂で見えなくなった。二次災害の恐れもあり、穴の内部での救助活動が難しくなった。その後は、下水道管の破損箇所から穴の中に汚水があふれ出してきた。県は12市町120万人に下水の利用自粛を要請したが、状況は改善しなかった。穴の中のがれきはほぼ撤去されたものの、引き続き土砂崩れの危険があるとして消防は9日、穴からの救助活動を打ち切った。現在検討しているのが、陥没地点から約600メートル離れた下流側のマンホールなどから下水道管内に下りての救助だ。ただ、管内は汚水の流れが速く、高濃度の硫化水素が発生するなど、八潮消防署の担当者によると「通常では人が入れない厳しい環境」。大野元裕知事は「消防庁、自衛隊とレスキュー方法を検討している」とするが、県からも具体的な方策はあがっていない。救助活動に詳しい元東京消防庁警防部長の佐藤康雄さんは、マンホールからの救助について、距離や水流、硫化水素などの課題を挙げ、「不測の事態が起きたときにすぐに脱出できない。安全を担保しながらの作業は至難の業だ」と指摘。運転席部分があるとみられる場所の上部を重機で掘削し、地上から直接救助する方法も考えられるというが、「土砂が崩れないように掘り進めることは難しく、下水道管に穴を開ければ、管全体が壊れてしまう可能性もある」との見方を示した。 *3-2:https://digital.asahi.com/articles/ASS8J3VNVS8JTLVB001M.html (朝日新聞 2024年8月17日) 自衛隊員は「即戦力」 運輸業界が退職予定の自衛官に再就職説明会 退職予定の自衛官に、次の活躍の場としてバスやトラック、タクシーの運転手を紹介する「運輸業合同説明・運転体験会」がこの夏、陸上自衛隊北熊本駐屯地(熊本市北区)で開かれた。自衛官の定年は一般の公務員よりも早く、多くは54~57歳で退官する「若年定年制」をとっている。加えて、20代から30代半ばで退職する任期制もある。いずれも、部隊の卓越した強さを維持するためだ。そのため、自衛隊は再就職の支援に力を入れてきた。今回は九州運輸局熊本運輸支局が自衛隊側に声をかけ、初開催した。大型車両の運転免許を持っている自衛官は多く、ドライバー不足に悩む運輸業界にとっては「即戦力」になるからだ。7月18日にあった体験会には、北熊本に加え健軍駐屯地(熊本市東区)や高遊原分屯地(熊本県益城町)などからも計119人が参加した。運輸業界からは、再就職した自衛官OBが説明役として登場。「健康であれば定年はなく長く続けられる。(乗客に)あいさつさえすれば、特に会話をしなくても構わない」(タクシー)、「安定した生活が送れる。地域社会への貢献という点で自衛隊と相通じる」(路線バス)などとPRした。希望者は駐屯地の構内で運転を体験した。来年5月の誕生日で退官する予定の男性自衛官(55)は「仕事でも運転をしているので、路線バスかトラックの運転手を考えている。人と接する仕事も楽しそうだし」と話す。熊本運輸支局の岩本輝彦支局長は「2024年問題で、運輸業界は慢性的な人手不足。自衛官には何事も自分で判断できるスキルもあり、どの会社も大いに期待している」と語った。 <何事も人手不足を言い訳にすべきではないこと> *4-1:https://president.jp/articles/-/87177?page=1 (President 2024/10/26) 「退職したらハローワークに直行ですよ」現役自衛官が明かす"50代の中年自衛隊員"を待ち受ける厳しい現実、いくら国のために尽くしても恩給も、再就職先もない 自衛官の定年は一般企業によりも早い。2・3曹は54歳、1曹から曹長・准尉・1~3尉は55歳、2・3佐は56歳、1佐は57歳。幹部クラスの将・将補は60歳だ。定年を迎えた自衛官はどうなるのか。ニッポン放送アナウンサーの飯田浩司さんが書いた『「わかりやすさ」を疑え』(SBクリエイティブ)から紹介する――。 ●「安心できるキャリアプラン」がない 一方に極端に勇ましい言動があり、もう一方には何が何でも話し合いをすればいいというこれまた極端な平和主義論が横行する言論空間。防衛費の増額に関しても、2つの極論がぶつかり合って、現場で真に必要なものが行き届かないことが危惧されています。岸田首相(当時)は2022年11月28日、防衛費を2027年度に国内総生産(GDP)比2%に増額するよう関係閣僚に指示しました。安保3文書の改定と並んで、岸田政権の安全保障政策の大転換といわれました。立憲民主党などの野党やリベラル系といわれるメディアは、この防衛費の増額により「戦争する国になる!」といったステレオタイプの批判を繰り広げました。一方で、政府与党の中でも「防衛族(防衛省と強い繫がりを持ち、安全保障政策・防衛予算などへの影響力を持つ政治家)」と呼ばれるような人たちは新たな装備品、とりわけ長射程のミサイルや艦艇、戦闘機といった大物をそろえる方に予算を誘導しようとします。しかし、現場は予算の増額によって戦争をしようとしているわけではなく、また、大きな装備品をそろえることを急ぐのでもありません。現場が欲しているのは「人」であり、安心できるキャリアプランの「仕組み」でした。安全保障の現場を担う自衛隊や海上保安庁といった現場は、人を集めるのにも苦労する状況が続いています。自衛隊、海保は「公安系」といった具合に括られて、地元の警察や消防とともに就職説明会を開いたりするようですが、そこで言われるのが、転勤について。士や曹といわれる現場の自衛官たちは地元の部隊に所属すれば地元近辺にいることが多いのですが、それでも部隊改変などのために遠くの任地に配属されるケースもあります。 ●早い人だと「54歳で定年」を迎える 海保も現場の海上保安官は管区内での異動が中心とのことですが、たとえば第一管区海上保安本部は小樽に本部を置き北海道内はすべて管区となりますので、東は根室、北は稚内、南は函館と1日がかりで移動する距離。地元の市町村単位の消防や都道府県単位の警察と比べると、特に地元にいたいという人にとっては一つハードルが高くなります。加えて、採用の際には本人よりも親御さんがそのあたりを気にされると言っていました。一方、幹部となれば話はまったく違ってきます。海保も自衛隊も全国転勤が当たり前という世界。警察もキャリア官僚となれば全国転勤となりますが、それは一握りです。そして、これは自衛官の採用の最前線、地方協力本部を取材した時に特に言われたのですが、採用の際に自衛官の定年と再就職先がネックになってきているという話を聞きました。現場の自衛官は精強さを保つという理由で早期退職制が敷かれています。士といういわゆる兵隊さんはそもそも任期制自衛官と言われる若者たちで、1期2~3年を数期務めて巣立っていきます。そこから任用試験等を経て曹というクラスに昇任すると、定年制となり、2・3曹は54歳で定年。その上の1曹から曹長・准尉・1~3尉(大尉~少尉)で55歳、2・3佐(中佐・少佐)で56歳、1佐(大佐)で57歳定年となります。その上の将・将補(中将・少将)となると最長で60歳定年となります。 それぞれに問題を孕みながらも現状なんとか回している状態とのことですが、まず一般企業や他の公安系公務員と比べても定年が早いだけに、現場で若年層をリクルートしようとする時にライバルから「自衛隊は定年が早いから、ウチの方が先々安定するよ」と口説かれるのだそうです。 ●“何か異質のようなもの”として扱われてしまう もちろん、精強さを保つのは安全保障上も重要なことですから制度自体は致し方ない部分があります。実際、陸・海・空三幕の幕僚監部の中にある募集・援護課や現場の地方協力本部も手をこまねいているわけではなく、「援護」と称される再就職支援を積極的に行うことでそれぞれの退職後のキャリアをサポートしていますし、募集の際にもその手厚さをアピールしたりもするそうですが、この少子化の折、子どもの就職にも親が積極的にかかわる時代。となると、より安定を求めて他の選択肢を検討するケースも多いそうです。曹という現場を取りまとめる重要なポストから、幹部自衛官に至るまで、早期退職制度とはいえ最後まで勤め上げ国に貢献したということに変わりはありません。諸外国であれば、賞賛こそすれ再就職先にも困るということはないでしょう。アメリカなどはここまで勤めれば、いわゆる軍人恩給でハッピーリタイアメントという方も少なくないそうです。もちろん、部隊や職種によっては任務の過酷さも米軍は世界一かもしれませんが。海外に出張したり、あるいは研修で海外に赴任したりした現職自衛官が口々に訴えるのが、その扱いの違いです。海外で制服を着て飛行機に乗ろうとすると、「Thanks for your service!」と声をかけられ、搭乗が優先されたり座席に空きがあればアップグレードされたりするなどの優遇を受けられたそうです。社会全体に国家への貢献を評価するという気風があるようなんですね。一方で、日本に帰れば何か異質なもののように扱われ、かつては蛇蝎だかつの如く嫌われた時期もありました。いまだに憲法学者の大多数は自衛隊を違憲の存在としています。 ●「せめて尊敬の気持ちを…」と本音を語った自衛官 そんな肩身の狭さは一体何なのだろうか? 海外に出て、そんな思いにとらわれる人もいます。自衛官は任官の際に、次のように職務宣誓しています。〈私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います〉〈事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め〉ることを誓っているわけです。アメリカのような手厚さがなくてもいいけれど、その心意気にはせめて尊敬の気持ちを持って接してもらいたい。打ち解け、こちらを信用してくれた一部の自衛官の口からこんな本音が漏れてくるのは、夜もだいぶ深まった頃でした。東日本大震災以降特に顕著になりましたが、自衛官に対する世間の見方がそれまでと180度変わって、今では政府内のどの職種よりも国民の信頼が厚くなっています。たとえば、2022年に読売新聞社と米ギャラップ社が実施した日米共同世論調査で、信頼している国内の組織や公共機関を15項目の中からいくつでも選んでもらうと、日本では「病院」が78%(前回2020年調査74%)、「自衛隊」が72%(同70%)、「裁判所」が64%(同57%)でした。 ●退職後も「正規」にはなりにくい それでも、彼ら・彼女らは普段から言動に非常に気を遣っていることが見えてきます。 制度上の理由で早期退職となりますから、その分本来であれば退職金が少なくなってしまいます。勤続20年以上の場合はそれを補う若年定年退職者給付金がありますが、本来は恩給制度等で報いる方法が検討されてしかるべきでしょう。もちろん、援護サイドも頑張っていて、地方自治体の防災監として採用されるケースも増えてきています。平時には現役時の経験を活かして防災や有事への備えを提言し、非常時には古巣の自衛隊との連携をスムーズに行う潤滑油として働く。理想的にも見える再就職で、実際ウィン・ウィンの関係なので防衛省・自衛隊サイドも推している施策なのですが、先方の自治体側もない袖は振れぬでなかなか正規職員のポストを用意できないのが難しいところ。キャリアプランは人それぞれなので、非正規職員となると尻込みするケースもどうしても出てくるようです。また、民間への再就職となると、そもそも50歳を超えてからの再就職は民間から民間でも難しいもの。採用となると、給料の他に社会保険料の企業負担分も面倒を見なくてはなりません。恩給の支払いが現実的でないのならば、せめて若年定年退職者には社会保険料の企業負担分は国で面倒を見るぐらいのサポートがあってもいいと思います。 ●“偉くなった人”ほど再就職先が見つからない 一方、制服組の中でも一握りのトップが将・将補クラス。このクラスになると、自衛隊独自の再就職あっせんシステムである「援護」を利用することができなくなります。「いやいや、でも将や将補まで偉くなった人だったら企業が放っておかないでしょう」「それぞれの専門を活かして退職後も活躍してくれるでしょう」。普通だったらそう思いますが、将・将補クラスとなると一般の公務員とまったく同じで、国家公務員法に基づく再就職に関する行為規制の対象となります。すなわち、それまでの経験を活かすとなると往々にして当該将官と企業との間で利害関係が生ずることになり、それは現職職員による利害関係企業等への求職活動に関する天下り規制に引っかかることになるのです。その上、一般の公務員でしたらこのポジションは次がある、このポジションは上がりだといったようなだいたいの退職時期の相場観があります。自衛隊にもなんとなくはあったりしますが、しかし政治情勢や内外の情勢によって、適材適所で突然の辞令ということも少なくありません。その上、ここまでのクラスになればどの職種にいようとも基本的には激務です。退職ギリギリまで職務に専念しており、再就職活動に時間を割ける人がどれだけいるか、見ている限りはほとんど思い浮かびません。ある同年代の将補など、「もし私が退職となったら、辞令をもらったその足でハローワークに直行ですよ」と赤裸々に話していました。 ●自衛隊を支えているのは「生身の人間」 入口の採用の難しさと、出口の退職後のキャリアプランの難しさ。安全保障の安定なくして繁栄する経済も安定した社会もありません。かつて日本社会においては「水と安全はタダ」といったことが言われていました。しかしそれは、今まで現場の心意気でなんとか保ってきただけだったのではないでしょうか? 今後の少子化も相まって曲がり角に来ています。防衛省・自衛隊に関するニュースというと、防衛費の増額や装備品の購入といったものばかりが並びますが、支えているのは生身の人間です。なんとなく、防衛費増額のニュースを見聞きしていると予算が増えて自衛隊は潤っているような印象になるかもしれません。しかし、内実はこの章で紹介した通りお寒いものでした。飯田浩司『「わかりやすさ」を疑え』(SBクリエイティブ)飯田浩司『「わかりやすさ」を疑え』(SBクリエイティブ)。見出しから受けるイメージだけに引っ張られず、内実まで伝えることがメディアの仕事だと思いますが、今は記者個人や組織のOBが積極的に発信している例も見られます。「この人のこの分野の情報は信頼できる」といった自分自身の情報源のストックも合わせて見ることで、より深くニュースを理解できるのでしょう。かつては自衛隊員が「戦争をする集団だ」と蔑まれ、制服を着て街を歩けないような風潮までありました。今は表立ってそうしたことはなくなりましたが、社会全体としてリスペクトの醸成やキャリアプランを明確に示せるような仕組み作りこそが、結果としてこの国を支える底力になるのだと思います。 *4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250201&ng=DGKKZO86463520R00C25A2MM8000 (日経新聞 2025.2.1) 就業者最多6781万人 昨年34万人増、正社員に転換進む ミスマッチ、人手不足解消せず 働く人が過去最多となった。総務省が31日公表した2024年の就業者数は6781万人と前年から34万人増え、比較可能な1953年以降で最も多い。女性やシニア層の就労が広がり、正規雇用が増加した。余剰労働力(総合2面きょうのことば)は乏しい。日本経済は生産性を高めながら、どう人手不足に対応するかという課題に直面する。就業者とは15歳以上の人のうち、仕事を持って働いている人や一時的に休職している人を指す。就業者数は景気回復などを反映し、2013年以降、女性やシニアを中心に増加してきたが、新型コロナウイルスの影響で20年、前年比で40万人減少した。その後は緩やかに回復が続き、24年は過去最高だった19年の水準を上回った。15歳以上の人口に占める就業者の割合を示す就業率も24年は61.7%と、前年から0.5ポイント拡大した。女性の就業者は前年比で31万人多い3082万人と最多だった。就業率でみると男性は直近10年間で1.9ポイントの上昇にとどまったが、女性は6.6ポイント上昇した。高齢者の就業率も上昇傾向にあり、65歳以上は前年比で0.5ポイント高い25.7%だった。雇用形態別にみると就業者のうち正規雇用は39万人増と大きく増えたが、パートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用は2万人増だった。より良い雇用条件を示さなければ、人材が集められない状況が広がっている可能性がある。リクルートの高田悠矢・特任研究員は「企業側の人材ニーズが高まるなか、これまではパートなどで働いていた女性が正社員となっている」と指摘する。小売り大手のイオンはグループで働くパートなど非正規雇用の待遇について、同等の業務を手掛ける正社員とそろえる制度を広げている。食品スーパーのライフコーポレーションは勤務地を絞った社員種別の「限定社員」を廃止し、正社員と同じ待遇にそろえた。若手人材を確保するため、30万円以上の初任給を提示する企業が増えている。アシックスは25年4月入社の大卒新入社員の初任給を24年から2万5000円引き上げ、30万円とする。大和ハウス工業やファーストリテイリングなども30万円以上の初任給を示している。企業側の人手不足感は強い。日銀がまとめた24年12月の全国企業短期経済観測調査(短観)によると、雇用が「過剰」と答えた企業の割合から「不足」を引いた雇用人員判断指数(DI)は全規模・全産業でマイナス36、先行きはマイナス41だった。厚生労働省によると介護や建設分野では有効求人倍率が4倍を超える職種もある一方、事務系は1倍を下回る。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの藤田隼平・副主任研究員は「求人と求職者のミスマッチが起きている。女性や高齢者は働く時間が短く、想定よりも労働力の確保につながっていないという側面もある」と語る。働く人の増加は経済成長にプラスだ。企業の生産やサービスの供給が増える上、収入増が消費拡大につながり需要が伸びる。社会保険への加入者が増えることで、年金や健康保険の財政的な安定性が高まる。少子高齢化の進展で15歳以上人口は10年代に減少が始まった。女性や高齢者の拡大による就業者の増加には限界がある。労働政策研究・研修機構の推計によると、40年時点の就業者数は最も低いシナリオで5768万人まで落ち込む。今のうちから人工知能(AI)などを活用した生産性の向上などで働き手の減少に備える必要がある。 *4-3-1:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250131/k10014708111000.html (NHK 2025年1月31日) 日本で働く外国人労働者 去年230万人超で過去最多 日本で働く外国人労働者は去年230万人を超え、12年連続で過去最多を更新したことが厚生労働省のまとめでわかりました。外国人労働者の職場環境の改善などにつなげようと、国は2007年から外国人を雇い入れた企業や個人事業主に対して、ハローワークへの届け出を義務づけています。厚生労働省によりますと、去年10月末時点で日本で働く外国人労働者は230万2587人でした。前の年の同じ時期に比べて25万3912人増え、率にして12.4%の増加で2013年から12年連続で過去最多を更新しました。 国籍別にみると、 ▽ベトナムが57万708人と最も多く全体のおよそ4分の1を占め、 次いで ▽中国が40万8805人 ▽フィリピンが24万5565人でした。 一方、前の年からの増加率では、多い順に ▽ミャンマーが61% ▽インドネシアが39.5% ▽スリランカが33.7%などとなりました。 人手不足の解消につなげようと2019年度に始まった制度で、建設業や介護など16の分野で専門の技能があると認められる「特定技能」の在留資格で働く人は20万6995人でした。厚生労働省は「人手不足などを背景に外国人労働者が増加しているとみられる。特に医療・福祉や建設業の増加率が高くなっている」とコメントしています。 *4-3-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC014DT0R01C24A1000000/ (日経新聞 2024年11月4日) 四国の外国人材最多、共生が日常に 今治の造船などで 深刻な人手不足を背景に四国で外国人材が増えている。2023年10月時点の外国人労働者数は届け出が義務化された07年以降で過去最多となった。多文化共生はいまや日常だ。四国の製造品出荷額の約4割を占める愛媛県では、製造業を中心に外国人労働者が増加している。地域別では造船業が盛んな今治地域が全体の3割を占める。独立系造船会社の新来島どっく(愛媛県今治市)では491人の外国人労働者が働く。新型コロナウイルス禍で一時減少したが、入国制限の解除以降はコロナ禍前を上回っている。日本人の人材確保が厳しさを増すなか「溶接作業など鉄加工全般や塗装など重要な戦力として活躍している」と担当者は語る。今後も現状以上の人員を確保する考えだ。高知県では四国銀行が人材紹介の6社と提携し、取引先に外国人材の採用を提案する。高知銀行は9月、技能実習生の受け入れをサポートする監理団体4団体と業務提携した。関心はあるが「どこに相談したらいいか分からない」という企業の声に応える。香川県では香川銀行がノンバンクのJトラストと提携し、取引先にインドネシア人材の紹介を始めた。県も人材紹介の8社と連携協定を結び、企業と外国人材のマッチングに乗り出した。徳島県は9月から半年間の予定で、外国人のための無料職場体験プログラムを実施している。県内での就職に関心のある留学生らと、採用に前向きな県内企業との出会いの場を設ける。夏の阿波踊りには、日本ハムファクトリー(静岡県吉田町)の徳島工場(徳島県石井町)の従業員らでつくる「日本ハム連」が参加。ミャンマーやネパールなど約20人の外国人従業員が日本人と共に生き生きと踊った。高松市中心部の商店街にはインドネシア食材専門店がオープンし、故郷の味を求める人びとが訪れる。異なる人種や文化、価値観を尊重する多様性の推進は四国の活性化に欠かせない。 *4-4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250215&ng=DGKKZO86746440U5A210C2CT0000 (日経新聞 2025.2.15) インド人留学生に300万円 文科省 人工知能(AI)など先端分野での人材を確保するため、文部科学省や東京大学などがインドからの留学生獲得を強化する。インドの大学院生300人弱の留学費用を支援するほか、現地でリクルート活動を行い、2028年度までに留学生を倍増させる。理工系に強いインドから人材を受け入れ、日本の研究力や産業競争力の向上につなげる。文科省は25年度から、AIなどを学ぶインド工科大などトップ大の大学院生270人程度を対象に、日本での生活費や受け入れ大学での活動費として1人300万円を支援する。文科省によると、300万円は渡航費も含めて日本で1年間生活する上で支障のない金額だという。インド通貨ルピーは対ドルで下落基調にあり、日本の大学の方が欧米の大学より金銭的に留学しやすいという環境もある。人材サービスのヒューマンリソシア(東京・新宿)によると、インドで働くITエンジニアの平均年収は約127万円。支援額は約2.3倍と手厚い。留学生への支援は1年間で、日本への定着を視野に入れて、企業のインターンシップへの参加も促す。受け入れる大学は同年度に公募し、科学技術振興機構(JST)が審査する。東大や立命館アジア太平洋大(APU)などの国内大学、大使館、民間事業者など50を超える機関が24年度、インド人留学生を増やすための連携組織を立ち上げた。SNSで日本の大学や奨学金に関する情報を発信するほか、インド人の留学エージェントが現地の大学を回り、日本の大学の魅力を伝える。人口14億人のインドは伝統的に理工系人材の育成に強い。引用数が上位10%に入る「注目論文」数で日本は13位と低迷するが、インドは4位につける。IT分野をはじめとしたインド人材の獲得競争は世界で激しさを増している。一方、インドの学生は日本に目を向けていない。インド外務省によると、日本への留学生数は22年は1300人。米国(46万5000人)やカナダ(18万3000人)、英国(5万5000人)などと比較して圧倒的に少ない。背景について、東大の北村友人教授(教育学)は「インド人学生は英語が得意で、日本より英語でのカリキュラムが充実している欧米の大学を目指す傾向が強い」と説明する。インドでは日本の大学の知名度が低く、進学先の選択肢に入っていないケースがほとんどだという。そのうえで「日本の大学は教育・研究の質が一定程度高い上、海外に比べて授業料が安いというメリットがある」と指摘。「インドではトップ層の大学以外にも優秀な学生は多く、裾野を広げていきたい」と話す。東大などは日本全体のインド人留学生を28年度までに2倍以上の3000人に増やしたい考えだ。文科省は日印の大学による学生の相互派遣も拡大する。25年度から、共同で留学プログラムを設ける国内大学の資金援助を始める。大学間の単位相互認定を皮切りに、将来的には双方で学位を得られる「ダブルディグリー」といった制度を設けることを目指す。インドのほか、国際的な存在力を増しているアフリカの大学も対象とする。同年度に国公私立大を対象に公募し、12件程度を認定したい考えだ。選ばれれば年間2000万~3200万円の助成を受けられ、29年度までの5年間が対象となる。政府は33年までに日本人留学生を50万人に増やし、外国人留学生を40万人受け入れる目標を掲げている。インドをはじめとした新興国「グローバルサウス」との人的交流の強化で目標達成を後押ししたい考えだ。 *4-4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250215&ng=DGKKZO86754130V10C25A2MM8000 (日経新聞 2025.2.15) 〈エビデンス不全〉地方創生の虚実(4)12道県、大学進学で転出拡大 「23区定員規制」効果薄く 「将来は博士号をとりたい」。徳島大学で学ぶ藤井優花さん(20)は地元の徳島県の出身。祖父をがんで亡くしたことなどから内視鏡や顕微鏡を使った研究に興味を持つ。徳島大は青色発光ダイオード(LED)の研究成果でノーベル賞を受賞した中村修二氏の母校。現在、地域の産学官が結集して光技術の専門人材を育成する計画の拠点になっている。国は2018~23年度、県に計29億円を投じた。誤算は藤井さんのような県内からの進学者が思うほど増えていないことだ。23年度も48人と、目標の53人に届かなかった。東京一極集中を是正し、地方との間の人口流出入を均衡させる。地方創生の大きな目標のひとつだった。政府は大学進学や就職で地元を離れる若者が多いことに目をつけた。18年から10年間の時限措置として、東京23区内の大学が定員を増やすのを禁じた。同時に地方大学向けの交付金を創設した。地方の教育や研究の一定の底上げにはつながった。肝心の若年層の人口動態を変えるには至っていない。 ●育てるほど流出 強みの金属素材の分野に磨きをかけた島根大学は学生の地元就職者数が目標に届かない。三浦英生・副学長は「育てた学生を都会に取られてしまう」とこぼす。人材の質が高まるほど県外の大企業から求人が殺到するジレンマに直面する。文部科学省の学校基本調査のデータで19~23年度の大学進学による人口移動を分析すると、37道県は流出超過が続いていた。茨城や香川など12道県は交付金ができる以前の14~18年度と比べて流出が拡大した。東京の流入超過は加速した。大学の定員規制の効果ははっきりしない。23区内の学部入学定員は21年度までの3年間に約2800人増えた。もともと決まっていた学部新設は例外扱いだったことなどが響いている。文科省は「膨大な行政コスト」を理由に、その後は集計していない。日本経済新聞が国の公表資料をもとに数えたところ、21~23年度でさらに約3000人増えていた。そもそも規制自体が不合理との指摘もある。日本の成長力を高めるという地方創生の本来の狙いにそぐわないからだ。東京都の小池百合子知事は「学生の学びと成長の機会を奪うのみならず、大学の教育・研究体制の改革を滞らせ、我が国の国際競争力を低下させることにつながりかねない」と撤廃を求めている。 ●若者の視点欠く 法政大学キャリアデザイン学部の田沢実教授も「当事者である若者の視点が欠けている」と批判する。国による一方的な人口移動の抑制は無理があるとの見方だ。教育や研究が本分の大学に政策的な役割を押しつけるのも限界がある。内閣府の地方創生推進事務局も「企業誘致や賃上げなど総合的な取り組みが必要」と認める。経済合理性に反した改革は持続可能でなく国力をそぎさえしかねない。地方創生という錦の御旗の下、野放図な政策がまかり通っていないか目をこらす必要がある。 *4-5-1:https://digital.asahi.com/articles/AST252P8ZT25UHBI016M.html?comment_id=31653&iref=comtop_Appeal6#expertsComments (朝日新聞 2025年2月5日) トランプ氏の奇策、歴史的成果へ野心 パレスチナの人々置き去りに トランプ米大統領が、パレスチナ自治区ガザから約200万人にのぼる住民を追い出して米国が「所有」し、再建させる復興案を打ち出した。前代未聞の構想は、長年悲劇に見舞われてきたパレスチナの人々を置き去りにしたままぶち上げられた。「ガザを中東のリビエラにする」。トランプ氏はイスラエルのネタニヤフ首相との会談後、共同記者会見でこう述べた。イスラエル軍の攻撃で建物は破壊され、多くの女性や子どもが戦闘の巻き添えとなったガザ。死者は4万7千人を超えた。トランプ氏は、荒廃したガザの将来像を地中海のリゾート地リビエラに重ね、そこに住むのは帰還したパレスチナ人ではなく「世界の人々」だと言った。こうした復興案は、不動産開発業出身のトランプ氏らしい「ディール(取引)」とも言えるが、本人は単なる思いつきではないと主張している。トランプ氏は会談の冒頭、「人々は地獄のような生活を送ってきた。ガザは人々が住むべき場所ではない」と語り、居住地として別の選択肢があれば人々はそちらを選ぶだろうと主張。米国がガザを長期的に所有して開発を進めれば中東に安定をもたらすことができるとし、「軽率に決めたことではない。誰もがこのアイデアを気に入っている。何カ月も検討を重ねてきた」と語った。第1次トランプ政権は、米軍の派遣を伴う対外関与は嫌う一方で、宗教的な理由でイスラエル国家の存立に強く共鳴する国内支持層に応え、イスラエルの主張をそのまま実行したような政策を連発した。最大の成果は、イスラエルと一部の周辺アラブ諸国との関係を正常化させた、2020年の「アブラハム合意」の仲介だ。これにはトランプ氏の外交政策に批判的な専門家らの間でも評価する声があり、トランプ氏自身、「ノーベル平和賞に値する」功績としてアピールしてきた。2期目の今回も、大統領選中から「中東に平和をもたらす」と繰り返しており、歴史的成果へ野心を見せてきた。不動産業に携わってきたユダヤ系富豪のウィトコフ中東特使を政権発足前からガザの停戦交渉に参加させるなど、中東外交に力を入れる姿勢を鮮明にし、停戦合意が成立すると自らの成果として誇示。今回の復興案も、こうした流れで準備してきた可能性がある。米国内では、民間人の犠牲と甚大な人道危機を止められなかったバイデン前政権の中東政策への失望が色濃く残る。歴代政権も周辺のアラブ諸国も、前向きで具体的なガザの将来像を示せてこなかったという背景が、これまでの「常識」から逸脱した提案を打ち出す余地を生んでいる。ウォルツ大統領補佐官(国家安全保障担当)はこの日、記者団にアブラハム合意を「次の段階」に進めることが目標だと語り、イスラエルと地域大国サウジアラビアとの歴史的な関係正常化の仲介へ意気込みを見せた。ただ、サウジはパレスチナ国家の樹立を正常化の条件だとしており、今回のような復興案を打ち出すトランプ政権の思惑通りに進むかはまったく見通せない状況だ。 *4-5-2:https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-10/SRF6VBT0AFB400 (Bloomberg 2025年2月10日) サウジ、ガザ住民移住構想を非難-イスラエル首相やトランプ氏が示唆 サウジアラビアは9日、パレスチナ自治区ガザの住民を移住させるというイスラエルのネタニヤフ首相の提案を「断固拒否」するとの声明を国営サウジ通信(SPA)を通じ発表した。サウジは声明で、「パレスチナの人々にはその土地に対する権利があり、彼らが追放されるべき侵入者や移民ではないことを確認する」と極めて強い言葉で同首相の発言を非難した。イスラエルのチャンネル14との先週のインタビューで、ネタニヤフ首相はサウジ領内にパレスチナ国家を創設する構想を示唆。一方で、2023年10月7日のイスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃後、パレスチナ国家は存在すべきではないとの自身の立場を繰り返した。トランプ米大統領は4日夜、ホワイトハウスでネタニヤフ首相と会談後に共同記者会見し、米国がガザ地区を所有し、ガザを「中東のリビエラ」と呼ばれるような場所に変えたいと述べていた。同大統領は他の中東諸国に対しガザからパレスチナ人を受け入れるよう求めたが、エジプトやヨルダンはこれを拒否している。トランプ大統領の考えはとっぴなものと思われたが、イスラエルはすでに、戦争で荒廃したガザから港や陸路を経由して住民を移す計画を策定しつつある。ただし、パレスチナ人が移住を望んでいるのか、またどこに移り住みたいのか、そして、実際に移住が可能かどうかは不明だ。 *4-5-3:https://www.agrinews.co.jp/news/index/288655 (日本農業新聞 2025年2月16日) 外国人農地取得を厳格化 農水省省令見直し 短期在留は認めず 農水省は2025年度から、外国人が国内の農地を取得する際の要件を厳格化する。取得を目指す外国人に対して、取得の可否を判断する農業委員会に残りの在留期間を報告するよう義務化。短期間で在留期間が切れる場合は、農地を取得できなくする。農地取得に関するルールを定める農地法の省令を見直す。農地が取得後も適切に耕作されるか判断する上で、残りの在留期間を把握する必要があると判断した。短期間で在留期間が切れる場合の他、短期間で遠方に転居する場合も農地の取得を認めない。同省は「(どのくらいの期間が短期間なのかは)事例ごとに農業委員会が判断することになる。収穫まで数年かかる果樹など、作物によっても変わる」(農地政策課)とする。外国人の農地取得を巡っては、同省は2023年9月、取得を目指す外国人に対し、農業委員会に国籍や在留資格の種類を報告するよう義務付けている。同省によると、外国人やその関係法人が23年に取得した国内の農地は90・6ヘクタール。うち、外国人個人による取得は60ヘクタール(219人)で、残りは法人による取得だった。日本では、外国人による土地取得を規制できない。世界貿易機関(WTO)協定の一部である「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)で、外国人が不利になる規制が禁止されているからだ。ただ、韓国やロシアは、外国人の土地取得について適用を留保しており、取得を規制できるという。日本は締結時に留保しなかった。 *4-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250211&ng=DGKKZO86654250Q5A210C2TB1000 (日経新聞 2025.2.11) 外国人と協働にIT駆使 新興「育成就労」導入にらみ商機、カミナシ、13言語のマニュアル DXHUBはスマホで日本語教育 スタートアップがIT(情報技術)を活用して外国人と協働しやすい環境づくりを急いでいる。カミナシ(東京・千代田)は13言語対応の従業員教育サービスを開発し、2025年度に10万人の登録を目指す。外国人労働者は200万人を超え、27年にも新制度「育成就労」の適用が始まる。言葉の壁などの問題解決にスタートアップが商機を見いだしている。現場の帳票入力を電子化するSaaS(サース)を手掛けるカミナシは1月、新サービス「カミナシ教育」を始めた。動画コンテンツ事業を手掛けるVideoStep(東京・港)と業務提携し、同社から動画マニュアル作成機能のOEM(相手先ブランドによる生産)供給を受ける。管理者が現場作業の様子を撮影した映像をクラウドにアップロードして編集すると、人工知能(AI)が音声を文字起こしして字幕をつけ、マニュアルを作成する。 ●AIが字幕音読 従業員がパソコンやスマートフォンで動画を閲覧する際に、マニュアルをベトナム語など13言語に翻訳。字幕を日本語と併記して表示したり、AIが母国語で読み上げたりする。従業員は作業の手順を自分のペースで学ぶことができる。現場作業では、教育を担当する管理者によって指導レベルに差があり、研修を終えたかどうかを管理するプラットフォームが存在しないことも多い。従業員の業務の理解度に差があると、企業が提供する製品やサービスの品質にばらつきが出る懸念がある。カミナシは2月中にも個別の従業員がマニュアルの理解度を確認するアンケートに答えたかを一覧で管理できる機能の提供も始める。食品や機械などの製造業を中心に26年6月までに10万人のユーザー登録を目指す。厚生労働省によると、日本で働く外国人の数は23年10月時点で204万人。前の年から12%増え、初めて200万人を超えた。今後もベトナムや中国、フィリピンなどからの人材流入が見込まれている。問題となっているのが言葉だ。仕事の仕方に不明点があっても理解してもらえないと考えて外国人が対話を避けるケースが多発している。在留外国人を対象にした法務省の23年度の調査では、企業など所属先に困りごとを相談しない理由として、最多の15%が「言語の問題で正確な意思疎通が難しいため」とした。企業の方も、指導や監督で苦労している。厚労省が24年12月に公表した雇用実態調査で「外国人労働者の雇用に関する課題」を聞いたところ、最も多かったのは「日本語能力などのためにコミュニケーションが取りにくい」で45%だった。こうした事態に対応しようと、在留外国人向けの通信サービスを手掛けるDXHUB(京都市)は、オンライン日本語教育ソフト「BondLingo」の事業をボンド(東京・新宿)から取得し、福利厚生型のSIMカードの販売を始めた。企業が採用した外国人にスマホ用SIMカードを配布する際に日本語教育ソフトも提供し、学習への取り組みを管理できる仕組みだ。学習履歴は昇給や賞与の判断材料とするなど、外国人労働者向けのインセンティブとして活用できる。 ●定着率向上に力 企業には外国人や家族の日本語学習に関し、機会の提供や支援に務める義務がある。DXHUBの沢田賢二社長は「日本人や他の外国人社員とのコミュニケーションが取れれば職場は働きやすくなり、企業にとっても外国人の定着率向上が期待できる」と話す。翻訳や教育で業務上の情報格差を緩和し、面談などを通じて働きがいや困りごとの有無を確認しても、実態を把握しきれないケースもある。ミツカリ(東京・渋谷)は24年12月、従業員エンゲージメント調査のサービスを、中国語やベトナム語など合計9カ国語に対応させた。同社のサービスは1分程度のアンケート調査を継続的に実施し、満足度やモチベーションを計測する。企業はデータから外国人労働者の労働意欲低下の兆候を早い段階で捉え、離職防止の対策を取ることができる。住居など生活面での支援でも動きがある。家賃保証審査支援のリース(東京・新宿)は24年12月、外国人が不動産会社に賃貸物件の入居申し込みをする際、家賃保証会社の審査担当者が自身では理解できない外国語の支援を受けられるサービスを始めた。リースは、多言語の相談窓口を運営するインバウンドテックと提携し、書類に不備がないかなどの確認作業を支援する。これまでは審査が後手に回り、契約が成立しないケースもあったが、借り手は入居しやすくなる。外国人労働者を巡っては、18年に成立した改正出入国管理法で在留資格「特定技能」が創設され、19年4月から人材の確保が困難な業界への受け入れが解禁された。27年には、過酷な労働環境下で失跡者が増えるなど問題点が指摘されている技能実習制度に代わり、育成就労が導入される見込み。具体的な運用は有識者会議などで詰めるが、1~2年の就労期間などの条件を満たし本人の意向があれば転職も可能になる方向だ。少子高齢化が定着し、人手不足が本格化するなか、優秀な外国人労働者の存在は企業の競争力を左右するようになっている。ルール順守の上で、外国人側の目線にも立ち、課題に対処していく必要がある。 <日本のブルーオーシャンが、日本政府にいじめ抜かれるのは何故か> PS(2025年3月5~8日追加):*5-1-1は、①家族介護を社会的介護に転換するためにできた介護保険スタートからの25年は改悪につぐ改悪の歴史 ②負担増と給付源(=サービス切り下げ)の繰り返し ③一律1割だった利用者負担は所得に応じて一部の人が2割・3割となり、保険料を支払ったのに必要な時にサービスを受けられず介護保険制度の意味減少 ④事業者に支払う介護報酬抑制と訪問介護の生活援助利用を制限する見直し ⑤今年度から訪問介護基本報酬の引き下げ ⑥ホームヘルパーは極めて高い専門性が求められる職種だが、国は「訪問介護は誰にでもできる仕事」とみなし専門性を評価しないのが問題の根底にある ⑦ヘルパーがいなくなれば要介護高齢者が自宅生活することは困難で、介護報酬の大幅引き上げが必要 ⑧介護保険はいじめ抜かれた ⑨さらに国はi)2割負担対象者の拡大 ii)ケアマネジメントの自己負担導入 iii)要介護1・2の介護保険本体からの切り離し 等の改悪を進めようとしている ⑩国は「制度を持続させるため」として介護費用増加を負担増・給付源で調整しようとしている ⑪財源は公費投入の割合を増やすことも選択肢として国が検討すべき ⑫「3世代世帯」の割合低下、独居と夫婦のみ世帯半数超という家族構成の変化で介護費用抑制の環境にはない としている。 家族介護を社会的介護に転換していなければ、家族が癌や脳出血等で長期療養を強いられた時には、介護の専門家でない他の家族が、仕事を辞めたり、進学を諦めたりして、介護しなければならないが、介護は、⑥のように、知識と経験に基づく専門性が求められる仕事であり、愛さえあればできるものではないため、無知や介護疲れによる虐待・ネグレクト・差別が頻発して家族全員が不幸になる。にもかかわらず、国は、確かに、介護の専門性を評価しておらず、介護は妻や子(特に嫁や娘)・孫など家族の誰かがやるものだと考え続けている点が問題なのである。 私は、家族介護を社会的介護に転換する目的で介護保険制度を作った1人だが、①②③⑧⑨のように、負担増・給付源が繰り返され、1律1割だった利用者負担を(高くもない)所得の人に2割・3割負担させるなどする改悪につぐ改悪が続けられて、介護保険制度は確かに25年間いじめ抜かれたと思うが、何故だろうか。また、著しく物価上昇しているのに、④⑤⑦のように、訪問介護の基本報酬を下げて住み慣れた自宅で療養することを不可能にしたり、介護事業者に支払う介護報酬の抑制や訪問介護の生活援助利用の制限等の見直しをしたりして、高い介護保険料を支払ったのに必要なサービスを受けられないという介護保険詐欺になっている。そして、その理由を、国は、⑩のように、「制度を持続させるため(底の浅い決まり文句)」としているが、日本国憲法25条で定められ、優先的に行なわなければならない福祉を加える度に、他の膨大な無駄使いを放置したまま、国民負担を増加させる財源探しを行うこと自体がおかしい上に、保険料を取るだけで必要なサービスも受けられない骨抜きの制度なら持続させても意味が無いのだ。そのため、⑪⑫については、個別の産業に対する時代遅れで効率の悪い補助金や租税特別措置を止めて公費投入割合を増やしたり、介護の社会化で助かる子や孫の世代からも介護保険料を所得に応じて広く徴収し、介護保険料の負担者を所得のある人全員に広げて高齢者の負担を減らしたりすべきなのである。なお、政府が減らそうとしている介護サービスは、高齢化だけではなく、都市への人口集中・家族構成の変化・共働きの増加等で生じた新たなニーズであり、日本のブルーオーシャンの1つでもあるのだ。 また、*5-1-2・*5-1-3は、⑫福岡厚働相は「高額療養費制度」限度額引き上げ案を修正し、長期治療患者は負担額を変更しないと表明 ⑬長期治療とは直近12ヶ月以内に3回限度額に達した場合の4回目からの「多数回該当」で、その限度額引き上げを見送る ⑭現在は平均的所得区分(年収約370~770万円/年、約31~64万円/月)で多数回該当を利用した場合、限度額は4.4万円/月、2024年末決定の当初案では2027年8月に最大7.6万円/月の予定だった ⑮多数回該当の負担増は見送るが、1ヶ月あたりの限度額引き上げは当初案通り実施し、所得区分を細分化して年収約650万〜約770万円/年(約54~64万円/月)は2027年8月から約13.8万円/月に引き上げる ⑯近年は高齢化や革新的治療の広がりで適用件数が増えて医療保険財政を圧迫、厚労省は2024年末に「制度持続のため」として患者負担限度額の段階的引き上げ案を纏めた ⑰患者団体は福岡厚労相との面会後記者会見で、多数回該当以外の限度額引き上げも凍結を求める方針とした ⑱「高額療養費制度」見直しの背景には、「子ども関連政策」の財源確保に向けた医療費抑制がある ⑲2023年末閣議決定「こども未来戦略」は児童手当の大幅拡充など年3.6兆円規模の対策を盛り込み、うち1.1兆円は2028年度までに社会保障の歳出削減で賄うとする ⑳法改正を経ず閣議決定で制度改正できるので「高額療養費制度」に白羽の矢があたった ㉑高齢化や高額薬剤登場で医療費が増え、現役世代の保険料負担が重荷 ㉒財務省は「個人や企業などの収入をあわせた国民所得に対する社会保険負担割合は2000年度13.0%で2024年度18.4%になる」とする ㉓政府試算では、高額療養費制度見直しで保険料は年3700億円規模の軽減、加入者1人あたり保険料軽減効果は1,100円~5千円程度/年 としている。 「高額療養費制度」も癌や脳出血等で長期療養を強いられた時、収入が著しく減る上、医療費が高いままで生活費の多くを占めるようになると、「貯金が底を突く時が、生きることを諦める時」になってしまうため、衆議院議員時代(2005~2007年)に、私が作った制度だ。 しかし、瑕疵のある「高額療養費制度」限度額引き上げ案に反対が起こると、⑫⑬⑭⑮のように、福岡厚労相は修正案を出したのだが、その内容は、イ)直近12ヶ月以内に3回限度額に達した場合の4回目からの「多数回該当」にあたる長期治療患者の限度額引き上げは見送る ロ)平均的所得区分(年収約370~770万円、約31~64万円/月)で多数回該当を利用した場合、限度額は4.4万円/月に据え置く(当初案では2027年8月に最大7.6万円/月) ハ)多数回該当の負担増は見送るが、1ヶ月あたりの限度額引き上げは当初案通り実施する 二)所得区分を細分化して年収約650万〜約770万円(約54~64万円/月)は2027年8月から約13.8万円/月に引き上げる というものだった。ただし、ここで示している所得区分は総収入であるため、ここから所得税・住民税・社会保険料を引かれ、水光熱費や家賃の支払いをすると、生活費にできる可処分所得はずっと少なくなる。その状況で、月収31万円から医療費4.4万円/月を支払うのは既に負担が大きく、やはり「貯金が底を突く時が、治療を諦める時」になるだろう。それでは、月収54万円の人は医療費上限13.8万円/月を支払えるのかと言えば、所得税・住民税・社会保険料・水光熱費・家賃等を支払った残額から、医療費を支払った後で、生活費を支払わなければならないため、物価上昇による生活費高騰で家族もいればやはり無理だろう。さらに、単身の新人給与でさえ500万円/年になろうとする時に年収約650万〜約770万円/年の収入が高いとは言えず、私は、耐えられる医療費は月収(年収/12)の10%が上限だと思う。また、リスクは誰にでもあるが発生するか否かは人によって異なる事態に備えるために保険があるのであり、保険ならリスクに備えるための1人あたりの負担額は小さいため、㉓のように、加入者1人あたり保険料軽減効果も1,100円~5千円程度/年にしかならないのである。従って、⑰のように、患者団体が「多数回該当以外の限度額引き上げも凍結を求める方針」としたのは、当然のことである。 にもかかわらず、⑯⑰のように、「高齢化や革新的治療の広がり」を理由とし、またまた「制度持続のため」として、厚労省は2024年末に患者負担限度額段階的引き上げ案を纏めたそうだが、⑱⑲⑳のように、「子ども関連政策」の財源確保のため医療保健から支出するのは、目的外の流用であり、医療保険詐欺であるため、決して許されない。その上、㉑の「高齢化や高額薬剤登場で医療費が増えた」という点については、これらの革新的治療は、大量生産できるようになって普及すれば治療費や介護費を安くする効果があり、それが日本発の薬や治療法であればブルーオーシャンそのものなのである。また、㉒のように、財務省は「個人や企業などの収入をあわせた国民所得に対する社会保険負担割合は2000年度には13.0%で2024年度に18.4%になる」としているが、2000年4月に介護制度が始まったのであるため、まじめにサービスを充実していれば今では企業も個人も介護に人手をとられなくてすむようになっていた筈で、そうであれば負担増は当然なのだ。そのため、そういう状況でも「保険料負担が重荷」などと言うような現役世代が育てた子なら、増やしたところでどうせろくな価値観は持っていないだろう。 なお、石破首相が、2025年3月7日、首相官邸で患者団体の代表と面会後、高額療養費の上限引き上げ実施見送りを表明されたのは、誤った政策で突き進むよりはずっとよかった(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA071PL0X00C25A3000000/ 参照)。 それでは、「財源はどこから持ってくるのか」と言えば、常日頃から歳出を見直して、時代遅れになったり、効果がなかったりする歳出は減額や削除し、新たに必要になった歳出やより効果的な歳出に充てるのが当たり前なのである。そして、それを省単位ではなく、政府全体で行なうためには、皆が納得できる主観的ではない客観的な数値が必要であり、その数値を出すためには、網羅性・検証可能性のある複式簿記による会計制度とそれに基づく行政評価が必要なのだ。また、「新たに必要になった」と言っても、義務教育の無償化(日本国憲法4条)や社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上・増進(日本国憲法25条2項)のように、1947年5月3日に施行された日本国憲法に既に明記されているのに、未だに行なわれていない政策は、他の歳出に優先して行なうのが当然である。 そのような中、大きく歳出削減できる例を挙げると、*5-2-1の、㉔政府が2月18日に閣議決定した新エネルギー基本計画は、再エネの活用を掲げつつ「脱炭素」を旗印に原発の建て替えも促す ㉕新エネ基は東日本大震災後に掲げた「原発依存度を可能な限り低減」の文言を削った ㉖原発回帰は大手電力が切望していたが、政府の支援策がなければ投資できない ㉗九電は玄海原発(佐賀県)の2基を廃炉中で、経産省はその分を川内原発(鹿児島県)の「増設」に充てたい考え ㉘関電のある幹部は「エネ基を旗印に、すぐにリプレースできるわけではない」「重要なのは、本当に採算がとれる支援制度が出てくるかだ」 ㉙エネ基は原発建設費の上ぶれ分を電気料金から回収できるようにする制度づくりを進めるとした ㉚「核のごみ」をめぐる課題は解決に遠い である。 何故なら、1966年に日本原電の東海原発が建設され日本で初めて原発が商業運転を開始してから、既に59年も経過しているのに、未だに㉖㉘のように、「政府の支援策がなければ採算がとれない」のであれば、「原発のコストが安い」というのは真っ赤な嘘だからである。その上、㉚のように、膨大な費用を要する「核のごみ」問題は全く解決せず後世に先送りし、フクイチ事故の莫大な事故処理費用もすべて国民負担にし、その上、原発立地自治体への交付金まで国民に支払わせながら、これらを「原発のコスト」に入れていないのだから、原発に競争力がないのはとっくの昔に明らかになっているのだ。また、㉙の原発建設費の上ぶれ分も原発コストにほかならず、㉕㉗のように原発の新増設をするのならそれを電気料金から回収するのは当然だが、電力のユーザーは、このようにして馬鹿高くなった電力は使いたくないからこそ、自家発電するよう努力しているのである。そのような状況で、㉔のように、その場限りの思いつきの理由を並べて、政府が「脱炭素」を旗印に原発の建て替えを促すなどというのは、膨大な無駄使いであり、真っ先に止めなければならないことである。そして、田園・放牧地・山林等に風力発電機を設置して売電料金を農家・林家の所得保証に代え、建物にペロブスカイト型太陽光発電を取り付ければ、2040年度の再エネ割合は「4~5割」どころか100%にでき、同時に農林業の補助金も節約できる上に、国富の海外流出も防げるのだ。 しかも、原発は、*5-2-2・*5-2-3・*5-2-4のように、原発を優位に導く「逆転」のトリックやこれまで無視されていた活断層・大津波・事故による甚大な住民や農林水産業への被害等の問題も多いため、本当に安全を最優先にして国民の命を守りたいのなら、できるだけ早く原発を手仕舞うのが賢明である。 最後に、*5-3のように、日本政府は、2017年に採択され、2021年に発効した核兵器禁止条約の第3回締約国会議に「米国の『核の傘』の下にいる」としてオブザーバー参加もしなかった。しかし、今回は、長年、核廃絶を訴える活動をしてきた日本被団協がノーベル平和賞を受賞して初の締約国会議で、アメリカの「核の傘」の下にいるNATOの加盟国からは1か国も参加せず、ロシアによるウクライナ侵攻が続く中で核抑止力が叫ばれているが、日本は唯一の被爆国であるため、特使を送って核廃絶を訴えるメッセージを出すくらいはすればよかったのである。その上、核による脅迫で保たれる“平和”は、それを脅迫と感じない国が現れれば容易に壊れる危うい均衡であり、戦争が起これば、核兵器を使わなくても原発は自爆し、住民や食糧生産に甚大な被害をもたらすのである。 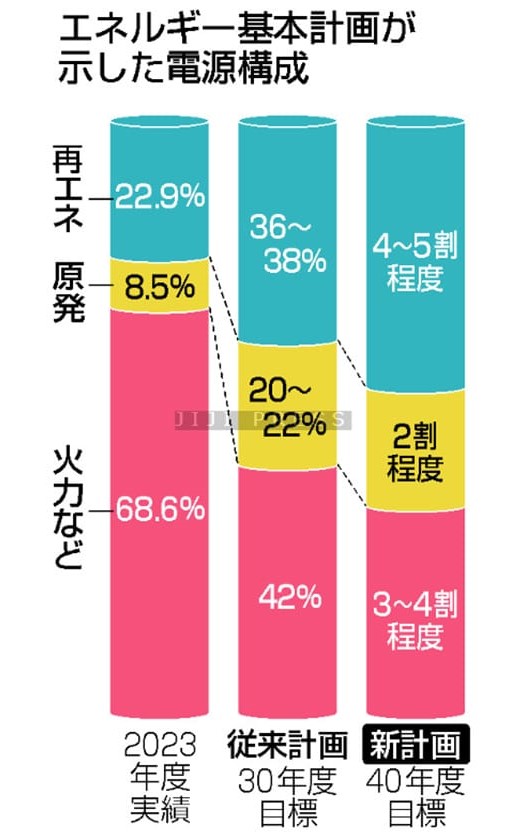 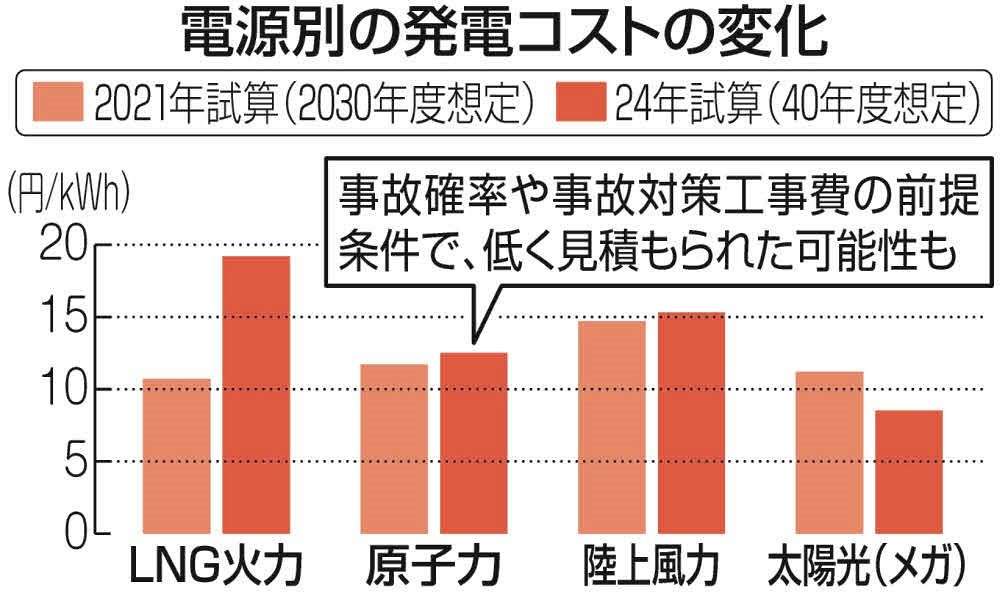 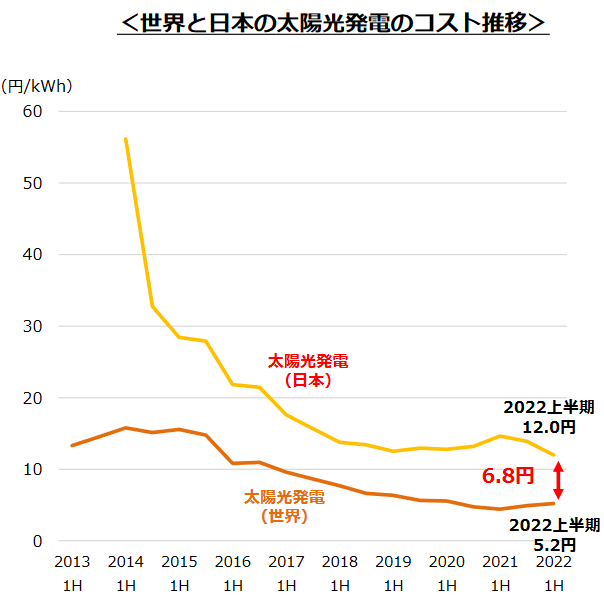 2024.12.27Business Journal 2024.12.17東京新聞 2023.5.9Enetech (図の説明:左図の1番右の棒グラフが「新エネルギー基本計画」による2040年のエネルギー構成で、エネルギーミックスと称して相変わらず原発2割、化石燃料3~4割としており、単価が安くなっても再エネは4~5割と見積もられているにすぎない。また、中央の図は、電源別発電コストの変化とされているが、原子力は、使用済核燃料の最終処分コスト・廃炉コスト・災害発生時の後始末のコストを入れていない超甘の想定でも太陽光発電より高く、今後、ペロブスカイト型太陽光発電が普及すれば、さらに差が開くだろう。右図は、世界と日本の太陽光発電コストの推移で、2022年時点で日本は世界より6.8円高いが、この結果は、できない理由を考えることに専念せず、普及に努力したか否かの差である) 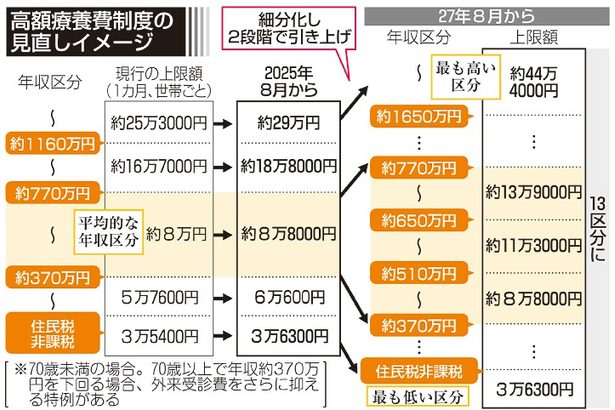 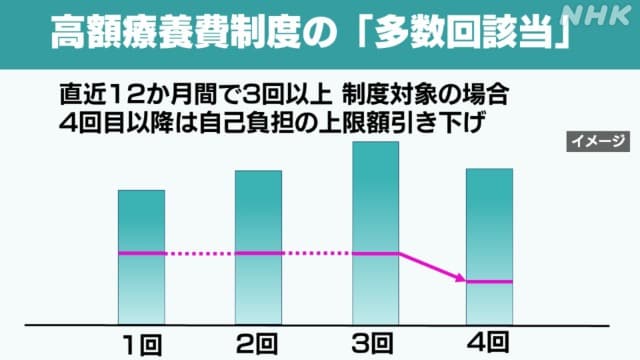 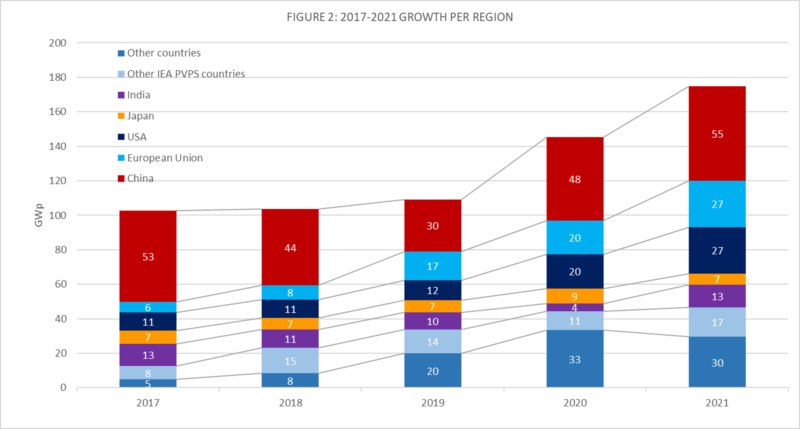 2024.12.24琉球新報 2025.2.17NHK 2022.6.21SustainableSwitch (図の説明:左図が「高額療養費制度見直し」のイメージで、実質賃金や実質年金は下がっているのに、2025年8月に上限を引き上げ、2027年8月にはさらなる引き上げが予定されている。そして、年収1,650万円で扶養家族なし・40歳未満の例で見ると、所得税《約259万円》・住民税《約125万円》・社会保険料《約158万円》を支払うため、残高は約1,108万円/年《約92万円/月》になり、ここから44.4万円の医療費を支払うと生活費に充てられる金額は約48万円になるが、確定申告時に医療費控除はできるが、深刻な病気になってもこの年収が続く人は少なく、扶養家族がいればさらに苦しいだろう。また、年収1,650万円以上は上限が同じ点もおかしい。中央の図は、「多数回該当」に当たる場合の自己負担上限額を据え置いたイメージだが、長期療養を要する深刻な状況の人から巻き上げる構図は変わらない。右図は、上段右図の太陽光発電コストが下がった理由は、普及して設置コストが下がったからだということを示している) 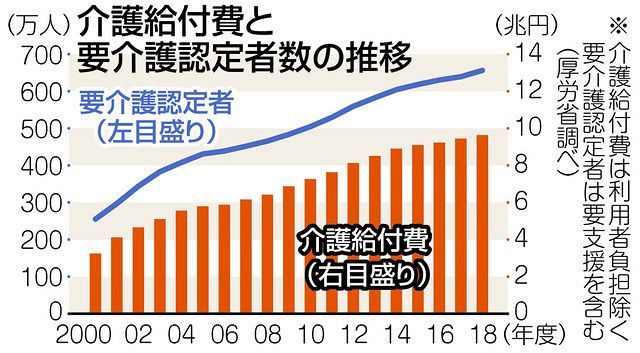 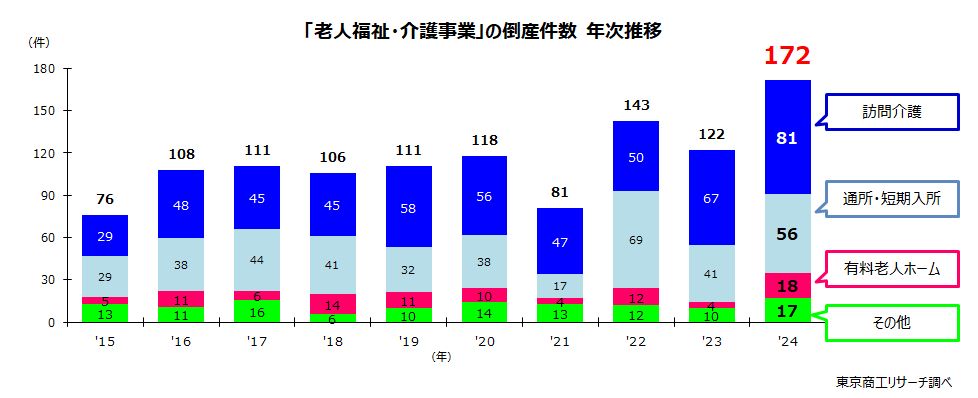 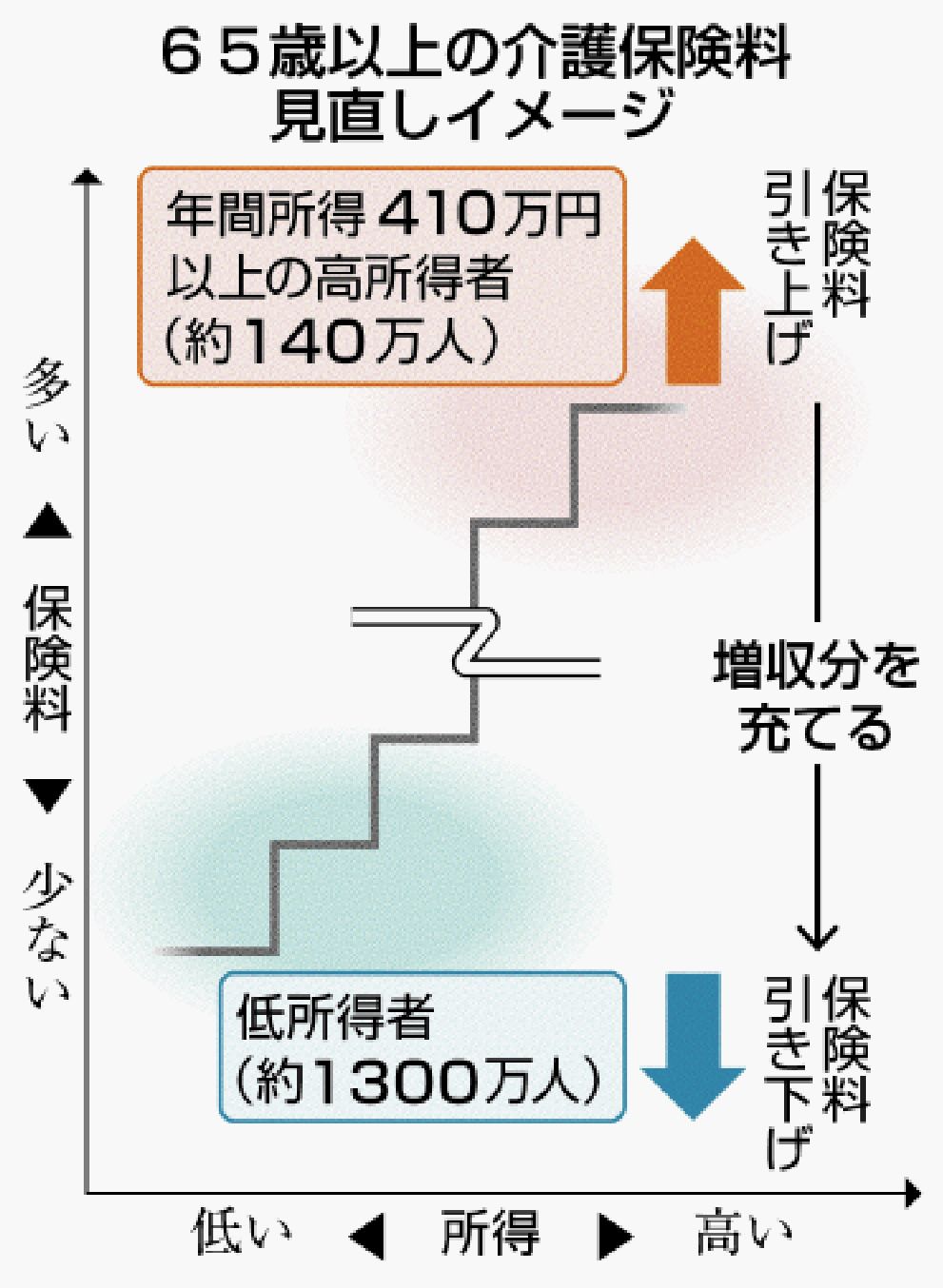 2022.2.22東京新聞 2025.1.9東京商工リサーチ 2023.11.1沖縄タイムス (図の説明:左図は、2000年に始まった介護保険制度の介護給付費と要介護認定者数の推移で、2024年3月現在690万人の方が要介護や要支援の認定を受けているそうだが、これは(7)2)の右図のように、高齢者数が増えれば自然なことであるため、意図的に給付費の伸びを抑えればサービス低下に繋がるのだ。そのような中で、政府は、介護事業者に支払う介護報酬の抑制や訪問介護の生活援助の利用制限をしたため、ただでさえ報酬の低かった介護福祉士が減り、2024年は人手不足による事業所の倒産が著しく増えて、やっとできた資産を減らしたのである。その上、政府は、右図のように、年間所得410万円/年《34万円/月》以上を“高所得者”として保険料を引き上げるそうだが、新人社員でも500万円/年の収入がある物価高騰時代に、高齢者は410万円/年が高所得とはどういうことか!) *5-1-1:https://digital.asahi.com/articles/AST2D05J2T2DUTFL00TM.html?iref=comtop_Opinion_02 (朝日新聞 2025年2月14日) 「いじめ抜かれた」介護保険の25年 利用者への負担転嫁は限界に 「介護の社会化」を掲げた介護保険スタートから間もなく25年。「改悪につぐ改悪の歴史だった」と振り返るのはNPO渋谷介護サポートセンターの服部万里子さんです。制度見直しのどこに課題があるのか、聞きました。 ◇ いま一番問題だと考えているのは、訪問介護の基本報酬が今年度から引き下げられたことです。ホームヘルパーは本来、極めて高い専門性が求められる職種です。しかし、国は訪問介護を「誰にでもできる仕事」とみなし、専門性を評価していない。それが問題の根底にあります。ヘルパーとして働く人がいなくなれば、要介護の高齢者が自宅で生活することは困難になります。介護報酬は大幅に引き上げなければいけない。その財源はどうするか。介護費用の増加を利用者負担に転嫁するのは、もう限界です。公費投入の割合を増やすことも選択肢として、国が検討すべきだと思います。介護保険は、家族介護を社会的介護に転換するためにできました。高く評価しているし、なくしてはいけない制度です。しかし、施行後の25年を振り返れば、負担増とサービス切り下げの繰り返しでした。一律1割だった利用者負担は、所得に応じて一部は2割、3割に。事業者に支払う介護報酬は抑制され、訪問介護の生活援助の利用を制限するような見直しもありました。「いじめ抜かれた介護保険」と私は言っています。さらに国は、2割負担対象者の拡大、ケアマネジメントの自己負担導入、要介護1・2の介護保険本体からの切り離し、といった改悪を進めようとしています。制度を持続させるため、というのが国の言い分です。介護費用の増加を、負担増とサービス利用制限で調整しようとしています。しかし、考えてほしいのです。自宅で暮らす要介護高齢者の世帯構成をみれば、「3世代世帯」の割合は低下し、独居と夫婦のみの世帯で半数を超します。家族のあり方の変化をふまえれば、とても介護費用を抑制できる環境にありません。無理に抑制すれば影響ははかりしれません。利用者負担を1割から2割に上げるというのは、単純に言えば負担額が倍になるということです。各家庭には様々な経済的事情があり、サービス利用をあきらめたり、減らしたりする高齢者が必ず出ます。結果的には要介護度が悪化します。保険料を払ってきたのに必要なときサービスを受けられないなら、なんのための介護保険か。制度の空洞化と言うほかありません。要介護状態になったら人生終わりではなく、その人らしい生き方を保障するのが介護保険であるはずです。未来も維持しなければいけないし、これ以上の改悪は許されません。 *5-1-2:https://digital.asahi.com/articles/AST253GJHT25UTFL00CM.html (朝日新聞 2025年2月6日) 背景に子ども財源の捻出、保険料高騰も 高額療養費制度の見直し 「高額療養費制度」の見直しをめぐる政府案について、修正が検討されていることがわかった。この制度は、公的医療保険の「セーフティーネット」として機能しており、見直しに対して患者らから反発の声が上がった。政府は少数与党での国会運営を余儀なくされる中、野党の批判にもさらされ、再考を迫られた形だ。ただ、今回の見直しの背景には、子ども関連政策の財源確保に向け、医療費の抑制が求められている状況がある。 ●修正案の決着は…… 2023年末に閣議決定した「こども未来戦略」は、児童手当の大幅拡充など年3.6兆円規模の対策を盛り込んだが、うち1.1兆円は28年度までに社会保障の歳出削減で賄う予定だ。そこで政府が同時に示した歳出削減候補の一つが、高額療養費制度の見直しだった。厚生労働省内にも「できるなら見直しは避けたい」との声があったが、法改正を経ずに閣議決定で制度改正できることなどから白羽の矢が立った。現役世代を中心とした保険料負担の軽減も課題だ。医療費の多くは保険料と税金で賄う。高齢化や高額薬剤の登場で医療費が増える一方、現役世代の保険料負担が重荷になっている。財務省によると、個人や企業などの収入をあわせた国民所得に対する社会保険の負担割合は、00年度に13.0%。それが24年度には18.4%になる見通しだ。政府の試算では、高額療養費制度の見直しで保険料は年3700億円規模で軽減される。加入者1人あたりの保険料軽減効果は、年額で1100円~5千円程度とみられる。こうしたことから、厚労省内には、政府案全体の凍結には否定的な見方がある。長期的に治療が必要な人の負担増を軽くすることで、修正案の決着を図りたい考えだ。 *5-1-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA146YW0U5A210C2000000/ (日経新聞 2025年2月14日) 高額療養費上げ、長期治療の負担据え置き 厚労相表明 福岡資麿厚生労働相は14日、医療費が高くなった場合の1カ月あたりの患者負担を抑える「高額療養費制度」の限度額引き上げ案を修正し、長期の治療を受けた患者については負担額を変更しないと表明した。がんなどの患者団体との面会で明らかにした。直近12カ月以内に3回限度額に達した場合、4回目から限度額を下げる「多数回該当」の限度額引き上げを見送る。自己負担が増えれば治療を続けられなくなるといった患者からの声に配慮する。現在は平均的な所得区分である年収約370万〜約770万円で、多数回該当を利用した場合の限度額は4.4万円だ。2024年末に決定した当初案では、25年8月から3回に分けて引き上げ、27年8月には最大7.6万円とする予定だった。修正案では引き上げず、現在の4.4万円のままとする。多数回該当の負担増を見送ることで、25年度予算案は修正を迫られる可能性がある。福岡厚労相は患者団体との面会後、報道陣に対し「予算修正は必要だと思う」と話した。1カ月あたりの限度額引き上げは当初案通り実施する。所得区分を細分化し、年収約650万〜約770万円では27年8月から約13.8万円に引き上げる。現在の約8万円から7割高くする。高額療養費制度はがんなどの重い病気にかかって医療費が高額になった場合に、年齢や所得水準に応じて1カ月あたりの自己負担を一定額に抑える仕組みだ。近年では高齢化や革新的な治療の広がりで適用件数が増え、医療保険の財政を圧迫している。制度の持続性を高めるため、厚労省は24年末に患者負担の限度額を段階的に引き上げる改革案をまとめた。その後、患者団体などから経済的負担の増加を懸念する声が強まったことから、改革案の修正を検討していた。患者団体は福岡厚労相との面会後に開いた記者会見で、多数回該当以外の限度額引き上げについても引き続き凍結を求める方針を示した。 *5-2-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16152512.html (朝日新聞 2025年2月19日) 課題山積、原発建設に道 「採算とれる支援」待つ関電 エネ基に建て替え促す制度 政府が18日に閣議決定した新しいエネルギー基本計画(エネ基)は、再生可能エネルギーの活用を掲げつつ、同じ「脱炭素」を旗印に、原発の建て替え(リプレース)も促す内容だ。原発回帰は大手電力が切望していたとはいえ、政府の支援策がなければ投資に踏み込めない事情も浮かぶ。「今後、原子力が重要になるのは間違いない」。九州電力の池辺和弘社長は1月の会見で、こう強調した。新しいエネ基は、東日本大震災後に掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」との文言を削り、原発の建設を縛っていた「くびき」を外した。池辺氏は「新設も含めて進めていくべきだ」とも語った。新しいエネ基では、老朽原発を廃炉にした分だけ、別の原発でも原子炉を増やせるとした。九電は玄海原発(佐賀県)の2基を廃炉中だ。経産省は、その分を川内原発(鹿児島県)の「増設」に充てたい考えだ。関連業界も動き始めた。原発メーカーの三菱重工業は、2026年度までに本体の原子力事業の人員を昨年4月比で1割増やす方針だ。今後3年間の生産設備と研究開発への投資額も、前の3年間に比べて3割増やす。泉沢清次社長は「関心を持つ学生が多く、新卒採用はほぼ計画通り」と話す。東芝も原発の設計などにあたる専門人材の採用を増やす。ただ、事態はすぐに動きそうにない。原発の建設について、九電のある幹部は「うちがやるのは、あちら(関西電力)がやったあとだ」とし、当面は様子見の構えだ。関電は美浜原発の2基が廃炉中で、「建て替えの着手に最も近い」(経産省幹部)とされる。森望社長も、リプレースや新増設について、「検討を始めなければならない時期に来ている」との考えを繰り返し口にする。だが、関電のある幹部は「エネ基を旗印に、すぐにリプレースできるわけではない」とも語る。「重要なのは、本当に採算がとれる支援制度が出てくるかだ」。エネ基では、原発の建設費の上ぶれ分を電気料金から回収できるようにする制度づくりを進めるとした。だが、具体策はこれから。関電の幹部は「投資の予見性など、具体的な話が見えてきてからだ」と釘を刺す。一方、「核のごみ」をめぐる課題は解決に遠く、核燃料サイクルも順調には進んでいない。今回実施したパブリックコメントでも、原発の安全性や「核のごみ」についての意見が寄せられ、新しいエネ基でも「懸念の声があることを真摯(しんし)に受け止める」と加えた。関電の関係者は「リプレースの検討に向けた次のステップに踏み出すと、すぐに表明するのは難しいだろう」と話す。 ■洋上風力・太陽光、拡大急ぐ 再エネ2040年度に「4~5割」 新しいエネ基では、再エネも「最大限活用する」と強調した。電源構成に占める割合を、いまの2割から40年度に4~5割にする。政府は50年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると約束しており、達成には再エネの普及が欠かせない。とくに期待するのが洋上風力発電だ。政府は40年までに出力3千万~4500万キロワットの事業化をめざす。いまは領海内に限っている設置場所を、排他的経済水域(EEZ)にも広げるため、関連法の改正案を今国会に提出する予定だ。ただ、コスト面では厳しい。国の公募に応じて秋田県沖と千葉県沖で計画を進めていた三菱商事は、建設コストの高騰などで採算の見通しが悪化。24年4~12月期決算で522億円の減損処理をした。経産省は次回の公募から、コストの上昇分を電力の買い取り価格に上乗せできるようにするなどの対応を急ぐ。自然エネルギー財団の大林ミカ氏は「成長途上の洋上風力産業で日本がリーダーシップをとるためには、半導体産業と同じくらい比重をかけるべきだ」と指摘する。もう一つの柱が、太陽光発電のいっそうの普及だ。日本はすでに平地面積あたりの発電量が世界トップクラスにある。東日本大震災後に始まった再エネの固定価格買い取り制度(FIT)で各地にメガソーラーがつくられた効果が大きいが、建設の余地が少なくなっている。近年では、景観への悪影響などから「迷惑施設」とされつつある。そのため今回のエネ基では、軽くて曲げられる次世代の「ペロブスカイト太陽電池」に注目。40年に約2千万キロワットを導入すると打ち出した。いま普及している「シリコン系」と比べて耐久性が劣り、コストも高いが、政府は日本の将来の産業の核になると期待し、導入拡大やコスト削減を後押しする方針だ。再エネの導入に関する経産省の審議会で委員長を務める山内弘隆・武蔵野大学特任教授は、シリコン系についても「空港などの公共施設を活用すれば、拡大余地はまだある」と指摘。今後の再エネの普及には「自治体との調整など、公的な介入が重要になる」と話す。(多鹿ちなみ) ■LNG、陰の主役 火力45%想定も、確保探る 今回の計画で「陰の主役」とささやかれるのが、液化天然ガス(LNG)だ。石炭や石油よりも温室効果ガスの排出が少なく、足元の電源構成の30%超をLNG火力が占める。出力の変動が大きい再エネを補助し、水素の原料にもなるため、「重要なエネルギー源」と位置づけた。エネ基では電源構成に占める火力の割合を、いまの約70%から40年度は3~4割に減らすとしている。だが、経産省は脱炭素化がうまくいかなければ、火力が45%を占めると想定する。経産省内では「現実的にはこちら(45%)」との見方が強く、LNGへの依存は続きそうだ。ただ、LNGはほとんどを輸入に頼り、国際情勢によって価格が跳ね上がるリスクもある。日本エネルギー経済研究所のまとめでは、長期契約によるLNGの確保量は減少していく見通しだ。新しいエネ基でも、LNGを安定して確保することの重要性を書き込んだ。そんななか、トランプ米大統領は前政権が制限していたLNGの輸出の再開にかじを切った。7日の日米首脳会談では、日本が米国からLNGの輸入を拡大することで合意。トランプ氏はアラスカ州のLNG事業について、日米共同開発を検討するとも言及した。米国はロシアや中東に比べて地政学リスクが低い。ただ、アラスカ州の事業は巨費がかかると見込まれる。資源開発大手INPEXの上田隆之社長は「何十年間も計画は実現しなかった。寒い場所でのパイプラインの建設費など解決しなければならない課題がある」と語るなど、警戒感も広がる。さらに、日本が大量のLNGを受け入れることになれば、脱炭素化の遅れにもつながる。 ■<考論>リスクどこまで甘受、議論を 寿楽浩太・東京電機大教授(科学技術社会学) 化石資源が乏しいなかでエネルギーを確保する方法を追求してきた日本には、頼りになるのは原発だ、という考えは古くからある。脱炭素化の流れで、再びそうした考えが出てきても不思議ではない。しかし、原子力の利用に今後どのぐらいのお金がかかるか、積極的に国民に開示すべきだ。そのうえで他の利点やリスクも踏まえて、複数の選択肢を提示してほしい。また、これまでは原発か、再生可能エネルギーかといった「技術の選択」に、やや議論が偏ってきた。その技術によって何を優先して実現しようとするのか、どういうリスクや不都合を甘受するのかが本当の論点だ。原発には重大事故のリスクが伴う。どこまで許容するのか、正面からの議論が必要だ。限られた専門家だけで決定し、「政府の政策を受け入れてください」というやり方は限界にきている。 ■<考論>「電源2割が原発」実現困難 橘川武郎・国際大学長(エネルギー政策) エネルギー基本計画を議論する政府の審議会は、「電気が足りない=原発が必要」とする考えが支配的で、一時は2040年の電源構成に占める原発の割合を25~30%とする数字が打ち出されそうになった。最終的に2割に収まったが、それも実現は困難だろう。前回21年に定めた30年時点の電源構成は、原発を20~22%とした。いま動いている原発に加え、原子力規制委員会が再稼働を不許可とした日本原子力発電敦賀原発2号機や、審査中の9基を含めた27基が稼働することが前提になる。ただ、どう甘く見ても20基前後。原発は頼りにならない。政府は今後、原発の新増設や建て替えを進めるため投資環境を整えようとしている。だが、簡単に進まないだろう。電気が足りないなら再生可能エネルギーでまかなうべきだ。ペロブスカイト太陽電池の実用化、洋上風力の支援拡充といった議論をするのが筋だ。 *5-2-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/374011 (東京新聞 2024年12月17日) 政府、発電コスト「原子力12.5円、太陽光8.5円」と試算…それでも原発を優位に導く「逆転」のトリック 経済産業省は16日、2040年度時点の電源別の発電コストを公表した。発電にかかるコストは、原子力が事業用太陽光(メガソーラー)を上回った。専門家が「計算の前提条件が、原子力など既存の大型電源に有利」と疑問を呈する甘い想定の中でも、原子力が安いとは言えなくなっている。 ◆エネルギー基本計画の基礎となる試算 経産省が有識者会議に示した発電コストは「均等化発電原価(LCOE)」と呼ばれ、3年ごとに見直される。経産省は17日にエネルギー基本計画の政府素案を公表する予定で、今回の試算を基に計画の決定に向けて素案を議論していく。エネルギー基本計画の改定に伴い、2021年の試算では、2030年度にすべての発電所を新設する想定で建設や運転の費用を計算していたが、今回は2040年度に新設する想定へ変更した。主な電源の1キロワット時当たりの費用は、原子力が2021年の11.7円以上から12.5円以上に増加。事業用太陽光は11.2円から8.5円に減少した。陸上風力は14.7円から15.3円に、液化天然ガス(LNG)火力は10.7円から19.2円に上がった。2021年の数値と比べ、原子力は事故発生確率を引き下げたものの、事故防止の追加的対策費や燃料代が増加したことが影響。太陽光や着床式洋上風力は量産による効果で安くなった。火力は二酸化炭素排出対策や円安による燃料代の高騰で大幅に上がった。電力システムに接続したときに追加で発生する「統合コスト」を加味すると、原子力が太陽光を下回る可能性が高いとした。 ◆「再エネへの政策経費が高すぎる」 今回の試算について、龍谷大の大島堅一教授は「原子力は安く見積もられている」と指摘。理由として、 ▽事故対策工事費が新規制基準の審査申請時の価格を基準にしており、許可時までに実際に上昇した分が反映されていない ▽事故発生確率を引き下げる根拠が不十分 ▽福島第1原発の放射性廃棄物処分費が入っていない ーを挙げた。 大阪産業大の木村啓二准教授は再生可能エネルギーの試算について「太陽光や風力にかかる2040年度の政策経費が高すぎる」と指摘。再エネに不利な統合コストについても「電力システムの前提次第で大きく値が変わり、LCOEに単純加算する議論はナンセンス」(大島教授)との批判がある。試算では蓄電池の活用や需給の細かな調整で、統合コストを抑えられる可能性も示された。 *均等化発電原価 実際にある発電所のデータを参考に、建設費、維持費、燃料費を含めた総経費を、運転期間中の総発電量で割って算出する。経済協力開発機構(OECD)や国際エネルギー機関(IEA)などの国際的な指標となっている。原子力は事故対応費用が膨らむ恐れがあるため、下限値のみを示している。 *5-2-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1412731 (佐賀新聞 2025.3.2) 【福島事故の教訓】「厳しい要求ためらわず」石渡明・元原子力規制委員に聞く 2011年3月の東京電力福島第1原発事故を招いた古い体質は、14年後の今も完全には解消されていない。「原子力ムラ」とは無縁の地質学者から原子力規制委員会の委員となり、自然災害の審査を担った石渡明さんは、安全を追求するには電力会社に厳しい要求をすることをためらってはいけないと訴える。(共同通信編集委員・鎮目宰司) ▽大津波 ―事故の教訓は何だと考えていますか。 約千年前の平安時代に東北地方の太平洋岸を大津波が襲ったことは、1990年代に東北大の地質学者が論文で公表していました。2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)でも同様に大津波が生じ、複数の原発を襲いました。福島第1では可能性を考えた対策をしなかったため、大事故が起きたのです。 ―規制委の前身である経済産業省原子力安全・保安院や東電は公表済みの情報をすくい上げて生かせませんでした。知り得た重要な情報は議論をした上で、必要な点を原発の安全対策にすぐ反映することが大切だと考えています。当時の内情を詳しく知らないので一般論ですが。 ▽活断層 ―2014年、事故後に発足した規制委入りを引き受けたのはなぜですか。 震災直後に岩手県や宮城県で津波の調査をして、悲惨な状況を目の当たりにしました。自然災害への備えをしないと原発が危ないのは明らかでした。委員への就任を打診されて「やらざるを得ない」と。国難ですから。 ―規制委では、日本原子力発電敦賀原発2号機(福井県)の断層問題を担当しました。危険性を直視しない体質が見えたと思いますが。 原子炉から約250mの位置に活断層があり、これとは別の断層が原子炉の真下を走っている。真下の断層もずれるのではないかという問題です。ずれる可能性があると分かれば運転は認められません。原電としては「ずれる可能性はない」と、そういうデータを次々と出してくる。一方で不利なデータは無視する。規制委の初期の会合ではかなり戦闘的な態度でした。現地を見て、データを点検すると、原子炉に向かって伸びている断層は何度もずれた結果、岩が幅広くぐちゃぐちゃに壊れていました。壊れた岩の厚さは平均で70cmもある。原電は、この断層は原子炉のかなり手前で消えて直下の断層にはつながらないと説明するのです。驚きました。 ▽重い判断 ―結局、敦賀2号機は規制委の基準に適合しないとの結論でした。 もちろん他にも多くの問題がありました。しかし、原発内を走る活断層は1990年代には専門書で存在が示されていた。原電がこれを認めたのは2008年です。対応が非常に遅いと思います。 ―分かったらすぐ対応するという教訓とは正反対ですね。 いったん運転を許可した後でも、重要な発見や情報が得られれば、対応するまで運転を認めない運用が規制委では新たに可能となりました。重い判断ですが、必要なら積極的に行うべきです。自然災害は本当に予測が難しく、特に原発では安全性を確保するために十分な余裕を持った対策をしておかなければなりません。大地震はもちろん、大津波や火山噴火はめったに起きないので、国内外での情報収集を怠らないことが必要です。 *いしわたり・あきら 1953年神奈川県生まれ。東京都立高教諭などを経て金沢大教授、東北大教授。岩石学、地質学。2014~2024年原子力規制委員。 ▽「言葉解説」東京電力福島第1原発事故 2011年3月11日の東日本大震災で大津波が発生し、浸水した福島第1原発(福島県)では原子炉などを冷却する機器の多くが動かなくなり、一部の原子炉では核燃料が溶け落ち、建物が爆発した。東北地方の太平洋岸では貞観(じょうがん)地震(869年)の大津波などが知られており、福島第1の津波対策を懸念する声があった。東電も経済産業省原子力安全・保安院(2012年に原子力規制委員会に改組)も情報に接していたが、有効な手を打たなかった。 *5-2-4:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16162119.html (朝日新聞 2025年3月4日) (東日本大震災14年)福島の農業 米作り、福島ブランドを再び 東京電力福島第一原発事故は田畑だけでなく、福島県の農産物のブランドも傷つけた。事故から14年が経ち、県産品離れは解消の方向に向かっているが、試行錯誤は今も続いている。 ■全袋検査を経て、徐々に価格復調 原発事故の前、福島県は主食用の作付面積が北海道、新潟県、秋田県に次ぐ全国4位の米どころだった。県によると、避難指示が出た12市町村には県内全体の農家の15%にあたる1万4600戸がいた。放射性物質による汚染などでの作付け制限は約6800戸の8500ヘクタールの農地に及び、2011年産のコメ生産量は前年比2割減の35万トンに落ち込んだ。特に原発がある沿岸部のコシヒカリの出荷量は、震災前の3万トン前後から3分の1に減った。原発事故は米価の下落も招いた。周囲を山に囲まれ、寒暖差が大きな会津盆地で栽培された会津産コシヒカリは、ブランド米として知られていた。しかし、12年以降に全国平均に近づき、震災前に上回っていた北陸産にも逆転された。福島市や郡山市がある県中央部や沿岸部のコシヒカリの価格は、事故前の全国平均並みから、さらに低い水準になった。JA福島中央会の今泉仁寿常務理事は「売り場の『棚』を他の産地に取られた。その分は業務用米に回った」と振り返る。県産米のうち、約7割は弁当や外食用の業務用米で、比率の高さは毎年全国1~3位を推移している。原発事故後、初めての収穫となった11年秋、佐藤雄平知事(当時)はサンプル調査を元に「安全宣言」を出した。しかし、その後、基準値超のセシウムが検出されるコメが相次ぎ、消費者の不安を招いた。その反省から、県とJAなどは翌12年、約1千万袋(1袋30キロ)の玄米を全て検査する世界初の「全量全袋検査」に取り組んだ。科学的には、地区ごとなどにコメを抽出する「サンプル調査」で十分との指摘もあったが、県内での米の生産額の1割弱にあたる年間60億円をかけ、全て検査するという「消費者向けの分かりやすさ」を重視した。15年産で基準値超のコメがゼロになっても、19年産まで続け、その後も避難指示が出た地域に限って全量全袋検査を続けた。今泉さんは「流通では風評被害が残っているが、消費者の忌避感はかなりなくなった」とみる。県は21年、震災前から開発してきたブランド米「福、笑い」をデビューさせた。栽培の条件を満たした農家に生産を限り、粒が大きく、強い甘みと香りが特徴で、高価格帯での販売をめざす。県産米の輸出も復調している。 ■沿岸部、営農再開一歩ずつ 一方、沿岸部では、原発事故の影響で営農再開ができない地域が残っている。避難指示が出た12市町村全体の営農再開率は、24年3月時点で49・7%だが、26年3月に6割にする目標を掲げる。22年に中心部の避難指示が復興拠点として解除された大熊町では今年、解除されたエリアで稲作の再開をめざす。町農業委員会などが、実証栽培を続けてきたが、収穫された米のセシウムは基準値を下回っている。同会長の根本友子さん(77)は「一歩一歩ですが、一人でも多くの人に大熊のお米のおいしさを思い出してもらいたい」と営農再開の広がりに期待する。 ■急落乗り越え、完全回復めざす 「フルーツ王国」と言われる福島県を代表する果物、モモ。ふるさと納税の返礼品としても人気だが、原発事故では大きな打撃を受けた。2011年度の東京都中央卸売市場における、福島産モモの1キロ平均単価は222円と、全国平均より4割安だった。樹木に付着した放射性物質を除染するため、生産者やJAは次の冬、1本ずつ洗浄した。約460本あるモモの木をすべて高圧洗浄機で洗い流した福島市のモモ農家、大宮篤司さん(67)は「極寒期の作業で身体的にも精神的にも大変だったが、前に進むためには頑張るしかなかった」と振り返る。それでも需要は回復せず、市場には行き場を失った県産のモモが山積みになり、安く買いたたかれた。「売れば売るほど赤字が膨らみ、地獄だった」(JA全農福島幹部)。安全性や味の良さのPRなど地道な活動で、県産モモの平均単価は18年度、原発事故前の10年度(438円)を上回る491円に回復。23年度は627円に上がったが、依然として全国平均よりも1割ほど安い。「一度ついた風評は根深く、完全払拭は容易ではない」と県の担当者は話す。(以下略) *5-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1411306 (佐賀新聞 2025/2/19) 核兵器禁止条約 参加こそ「橋渡し」になる 核廃絶の流れに日本政府が背を向けている。3月に米ニューヨークで開かれる核兵器禁止条約の第3回締約国会議について、これまで通りオブザーバー参加も見送ると表明した。核兵器禁止条約は2017年に採択され、21年に発効した。核兵器の開発や実験、保有、使用や威嚇を禁止する。核を巡る国際的枠組みの歴史上、最も踏み込んだ内容で、核を持たない国々や非政府組織(NGO)の取り組みで実現した。だが核拡散防止条約(NPT)で核保有を認められている米ロ英仏中の5カ国を含む核保有国や、米国の核に依存する北大西洋条約機構(NATO)加盟国は参加していない。米国の「核の傘」の下にいる日本も加わっておらず、条約の履行状況を話し合う過去2回の締約国会議にも出席していない。日本政府に参加を訴えてきた被爆者の取り組みは、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)のノーベル平和賞受賞で勢いがついた。被団協は1月、石破茂首相と会い、発言もできるオブザーバー参加を要請した。だがこの時、石破首相は明確な考えを示さなかった。政府側からは、あらかじめ「平和賞の祝意を伝えるもので、意見交換の場ではない」として条約には触れないとの意向が示されたという。石破首相は政府の代わりに与党議員を派遣することを検討したが、自民党の森山裕幹事長は「考えていない」と否定。公明党は議員を派遣するが、政府代表ではなく曖昧さは拭えない。日本政府は参加しない理由として(1)核保有国が参加しておらず、実効性がない(2)米国による核抑止力の正当性を損ない、国民を危険にさらす―ことを挙げている。米国に安全保障の根幹を委ねる日本にとって、条約のハードルは確かに高い。しかし今年は被爆80年。被団協のノーベル平和賞受賞という追い風の中、被爆国が今動かなければ一体いつ動くというのか。一番の問題は、政府として参加するにはどんな方法があるか、模索した形跡がうかがえないことだ。日本が米国に協議を持ちかけたような動きも見えず、今回の石破首相とトランプ米大統領の首脳会談でも、議題にすら上らなかった。こうした状況は、条約発効時の菅義偉元首相、さらに広島選出をアピールした岸田文雄前首相の時から変わらない。それだけ難しい問題だとも言えるが「なんとか参加したいが、できない」ではなく、最初から行かない理由を探しているようにしか見えない。NATO加盟国でもドイツやノルウェー、ベルギーなど、これまで締約国会議にオブザーバー参加し、意見表明した国がある。そのことで、条約に加わるかどうか、すぐに決断を迫られるようなことにはなっていない。「核保有国と非保有国の橋渡しをするのが日本の役割」というのが政府の立場だ。そうであれば、オブザーバー参加して被爆当時の状況や被爆者の現状を説明し、核による惨禍を訴えるべきだ。条約に参加できないのであれば、その理由を明確に伝えることも必要だ。核保有国がその場にいないとしても、メッセージは伝わる。そのことがまさに「橋渡し」になるのではないか。 <トランプ関税と日本> PS(2025年4月6、7日追加):*6-1-1・*6-1-2は、①トランプ米政権は全世界に対する一律10%の関税・国毎の関税率「相互関税」を発表 ②米国外製造の全輸入車は、自動車メーカーの生産拠点を米国に移設させるため、現行に上乗せして25%の関税を発動し、乗用車は2・5%から27・5%・一部トラックは25%から50%に ③2029年1月まで続く第2次トランプ政権の適用除外なき恒久措置 ④日本の自動車産業に大打撃 ⑤米国外生産の主要自動車部品にも25%の関税発動 ⑥原則無課税で輸出入できる「米国・メキシコ・カナダ協定」に適合した自動車は米国製部品使用割合に応じて関税率引き下げ ⑦日産自動車は今夏にも米国向け主力車の国内生産を一部現地生産に切り替え ⑧生産移管は中小の部品サプライヤーに打撃 ⑨トヨタ自動車の北米法人は、メキシコ・カナダからの輸入分を対象として現地の部品メーカーに関税に伴うコスト上昇対応を支援すると伝え、米国での販売価格は当面維持する方針 ⑩自動車は日本の基幹産業で、製品出荷額は国内総生産(GDP)の約1割に相当 ⑪生産移管はGDPの押し下げに繋がるため、政府は国内の空洞化対策を急ぐ必要 としている。 日本のメディアは、①②③④のように、トランプ関税とそれが日本の基幹産業と言われる自動車の輸出に与える影響について多くを語っているが、下の段の左図及び⑦⑨のように、自動車メーカーは米国販売の高い割合を既に現地生産しているため、その割合を高めれば問題解決できる。また、⑤⑧の自動車部品メーカーは、現地生産について行くか、これを機会に日本国内で他産業の部品や完成品も作る等の前向きなことを考えた方が良い。他国は進歩しているため、日本だけがいつまでも⑩⑪のように、自動車のみを日本の基幹産業とし、加工貿易の比較優位幻想にとらわれて、アメリカが関税を上げればGDPが下がるなどと言いながら現状維持に汲々としていると、世界では経済的地位も生活水準も現状維持すらできずに次第に落ちていくものだ。なお、⑥のように、原則無課税で輸出入できたためメキシコに作ってしまった自動車工場は、最初に自動車の大量生産を行い、従業員の賃金を上げて従業員が「T型車」を買えるようにして、従業員を広告塔としてT型車を大量販売することに成功し、資本主義のうねりを生んで20世紀の社会まで変えた米国フォードのマーケティング方式を使えば良いと思う(https://www.webcg.net/articles/-/44857 参照)。それでは、「日本国内に残る部品メーカーが入るべき他産業は、どれが有望か」と言えば、これから国内で大量のインフラ更新が必要で、新しい街作りや最新技術を取り入れた住居への更新もしなければならないことを考えれば、自らの得意技をさらに磨いてそれらの分野に進出するのが良いと思う。また、今後、ブルーオーシャンになりそうな有望分野の例を示すと、*6-3-1のようなAI搭載ロボット(1台ですべてをこなす必要はない)や、*6-3-2のような幹細胞(iPS細胞に限らない)による再生医療に使う細胞増殖そのものや増殖装置の生産もあり、新しいアイデアを製品にして市場投入できるためには、これまで培ってきた精緻な技術が必要であるため、有望分野は多い。また、私は、日本で販売する米国製品や中国製品(BYD等)も日本で作るよう促してもらいたい。 また、*6-2-2は、⑫トランプ米大統領が「我々の友人(日本)が、私たちに米やその他を売らせたくないから(米国産の米に)700%の関税を課している」と語った ⑬日本政府は米・農家を守るため、米の輸入を原則認めてこなかったが、1995年に方針転換した ⑭無関税で米を輸入するミニマム・アクセス米以外は、341円/kg関税をかけている ⑮日本政府は2000年代のWTO交渉で米の国際的な平均価格を約44円/kgとして参考値で「778%」との高めの関税率を示したことがある ⑯直近の米国産うるち精米中粒種(23年度)は約150円/kgであるため、341円/kgの関税を率にすると227% としている。 令和6年産の日本産米は、Amazonで調べると、北海道産ゆめぴりか1,080円/kg、佐賀県産さがびより1,420円/kg、熊本県産ヒノヒカリ1,449円/kg、新潟県産コシヒカリ1,118円/kg、岡山県産あきたこまち976円/kgであるため、*6-2-3のように、関税を払っても米国産米491円/kgの方が安いが、⑯の227%の関税も十分に高関税であり、日本人はこれを払っているのだ。そのため、⑫~⑮のように、トランプ米大統領の古い思い込みを批判する前に、この外圧を利用して米はじめ農産物も自由貿易化し、日本国民や他産業に迷惑をかけないようにすべきだ。その時、食糧安全保障を堅持して農家を護る方法は、下の段の図の説明に書いたとおり、農家の農業法人化・大規模化を促し、スマート農業を普及させてコストダウンさせながら、直接支払に替えて農家に再エネ発電設備設置補助を十分に行なって電力収入を農家の副収入に加え、同時にエネルギー安全保障と環境維持を達成することである。そして、これは、私は10年以上前から言っていることで、その間、真面目に進めていればとっくに実現できており、無駄なバラマキをせずにすんだのである。 なお、日本農業新聞論説は、*6-2-1のように、⑰米国は貿易赤字が膨らみ、2024年は約1兆2000億ドル(約185兆円)で過去最大 ⑱トランプ大統領は「国家非常事態に当たる」「米国経済を復活する」と強調する ⑲米国の貿易赤字の大半は自動車・その部品・半導体など工業製品によるもので、農林水産物は米国が圧倒的な貿易黒字であるため、米の関税を持ち出すのは筋違い ⑳「相互関税」の公表に先立ち米通商代表部(USTR)は、日本の牛肉やジャガイモなどの検疫体制も問題視した 等としている。 このうち⑰⑱については、米国も双子の赤字が大きく、GDP2位の中国に迫られ、輸入ばかりしているわけにはいかない状況なのだから、日本の農業もあちこちに甘えてばかりでは困る。また、⑲の工業製品は自助努力で世界競争に勝っている部分が大きく、「農林水産物は米国が圧倒的な貿易黒字」というのも、あらゆる方法で改善すべきだ。しかし、下の段の中央の図のように、農業は誤った保護の仕方をして本来ある活力を抑え続けたため、改革してもそれが成長に繋がらず、農業人口も食料自給率も減り続けているという実績なのである。そして、日本の財政赤字/GDPは、250%を超え、米国の120%程度の2倍以上であることも忘れてはならない(https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/900009877.html 参照)。  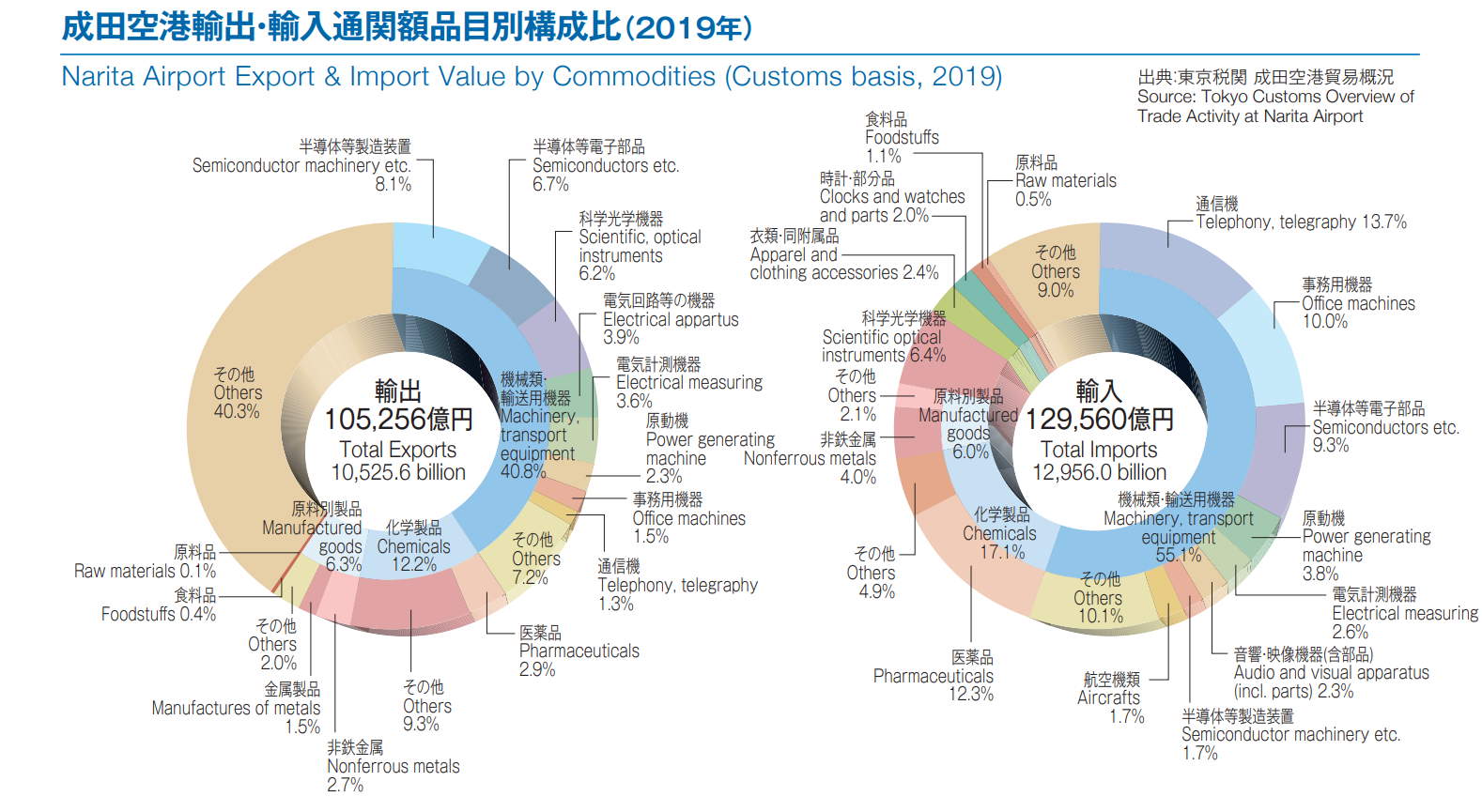 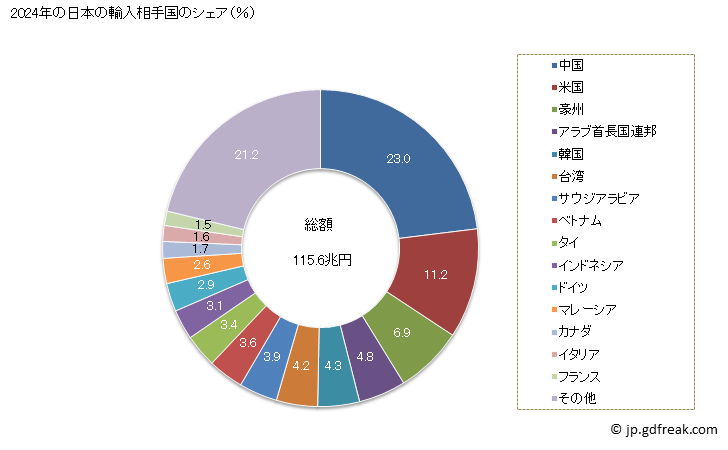 2025.1.25日経新聞 2023.1011世界コネクト GDFreak (図の説明:左図は、日本の最近20年の貿易収支の推移で、2011年以降は赤字続きであるため、トランプ関税を馬鹿にできるような状態ではない。また、中央の図は、2019年の輸出《約11兆円》輸入《13兆円》の内訳で機械類・輸送用機器の輸入も多く、実際に日本製の電気製品を探すのは難しいくらいであるため、「日本が加工貿易に比較優位性を持つ」などという状態はとっくに失われており、右図のように、中国はじめアジア各国が、安い物価水準と安価な労働力を背景に、日本に輸出しているのだ) 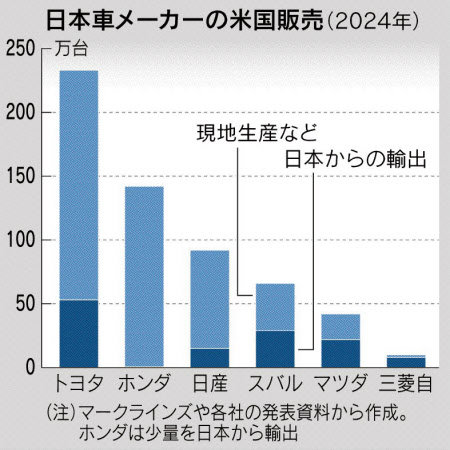 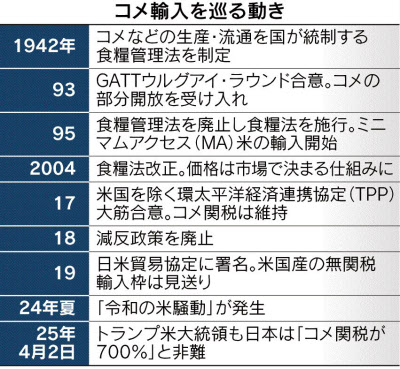 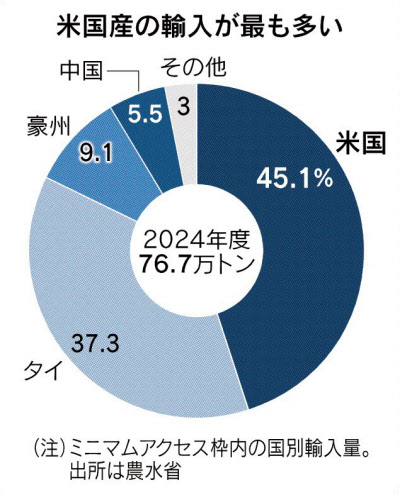 すべて、2025.4.6日経新聞 (図の説明:左図は、日本の基幹産業と言われている自動車メーカーの米国販売額を現地生産と日本からの輸出に色分けして示したもので、既に現地生産の割合が高いので、それをさらに増やせば問題解決できる。中央の図は、日本のコメ輸入を巡る動きで、1995年までも食管法があったが、1995年にこれを廃止して食糧法を施行したものの、2004年までは価格が市場で決まらなかった上、未だに著しい高関税で国内産のコメを護っている。そして、右図のように、輸入米は米国産が最も多いため、そろそろ関税をなくして農家の農業法人化・大規模化を促すと同時に、直接支払に替わる農家への再エネ発電設備設置補助を十分に行なえば良いと思う) *6-1-1:https://mainichi.jp/articles/20250403/k00/00m/020/077000c (毎日新聞 2025/4/3) トランプ政権、25%の自動車関税を発動 日本の自動車産業に大打撃 トランプ米政権は3日、米国外で製造された全ての輸入車に対する25%の関税を発動した。現行の関税に上乗せする形で、乗用車が2・5%から27・5%、一部トラックは25%から50%に引き上げられる。適用除外は設けず、2029年1月まで続く第2次トランプ政権の恒久的措置としている。日本の自動車産業に大打撃となる。海外にある自動車メーカーの生産拠点を米国に移設させる狙い。3日午前0時1分に発動すると明記した布告に、トランプ大統領が署名していた。米国外で生産された主要自動車部品に対しても、5月3日までに25%の関税を発動する。原則無課税で輸出入できる「米国・メキシコ・カナダ協定」(USMCA)に適合した自動車については、米国製部品の使用割合に応じて関税率を引き下げる。USMCAに適合した部品に関しては、非米国産部分のみに課税できるプロセスを確立するまで適用されない。トランプ氏は2日に全世界に対する一律10%の関税や、国ごとに関税率を分けた「相互関税」を発表したが、自動車や主要自動車部品には適用されない。 *6-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250406&ng=DGKKZO87855040W5A400C2MM8000 (日経新聞 2025.4.6) 日産、米に生産一部移管 輸出回避、国内で減産 中小供給業者に影響恐れ 日産自動車が今夏にも、米国向け主力車の国内生産を一部現地生産に切り替える検討に入った。生産を担う福岡県の工場で減産し、輸出を回避してトランプ米政権が発動した追加関税の影響を抑える。生産移管は中小の部品サプライヤーに打撃となる。政府は国内の空洞化対策を急ぐ必要がある。日産は多目的スポーツ車(SUV)「ローグ」の国内生産の一部を米国に移管する方向で検討している。ローグは米国の主力車で、福岡県にある工場と米国の工場で生産している。追加関税の発動後に国内からの生産移管の動きが明らかになるのは初めて。日産の2024年の米国販売は約92万台で、そのうち16%の約15万台を日本から輸出している。主力拠点である福岡の工場は年50万台の生産能力があり、ローグを年12万台程度生産している。減産は一定規模になるもようで、中小のサプライヤーを中心に地域経済に影響が出る恐れもある。過去には海外への生産移管により、国内工場の縮小につながったことがある。日産は国内のサプライチェーン(供給網)を維持するために100万台必要だった。生産台数は24年に約66万台まで減っており、日産の国内生産の再編にも追加関税が影響を与える可能性がある。業績不振の日産は構造改革の一環で、4月以降に米国工場の生産ラインの一部でシフトを半減し、ローグなどを減産する計画だった。追加関税の発動を受けて減産計画を撤回し、一転増産する方針を決めた。トランプ政権が発動した関税政策では、日本などから輸入する自動車に対して25%の追加関税がかかる。福岡県で生産した車両は米国への輸出コストがかさむことになる。日産は日米で車両生産を調整し、関税の影響を抑える。今後、他の自動車メーカーでも国内から米国への生産移管が広がる可能性がある。自動車は日本の基幹産業で、製品出荷額は国内総生産(GDP)の約1割に相当する。生産移管はGDPの押し下げにつながるため、国内の空洞化対策は大きな課題となる。政府は中堅、中小の自動車部品メーカーの事業強化に向けた支援にも取り組む。副大臣や政務官などを自動車産業が集積している地域、関連工場に派遣する。他の日本の自動車メーカーも対応策を急いでいる。トヨタ自動車の北米法人は現地の部品メーカーに、関税に伴うコスト上昇への対応を支援すると伝えた。メキシコ・カナダからの輸入分を対象とし、米国での販売価格は当面維持する方針だ。トヨタは日本のメーカーで最も多く自動車を日本から米国に輸出している。日本の取引先については「当面のオペレーションを維持する」と伝えており、日本から輸出する分については今後、対応を検討するようだ。 *6-2-1:https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/298480 (日本農業新聞論説 2025年4月4日) 米国の相互関税と日本 農業への悪影響許すな 米国が貿易相手国に同じ水準の関税をかける「相互関税」を導入し、日本からの輸入品に24%の関税を課す。トランプ大統領は、日本が米にかけている関税にも言及した。一方的な措置は、世界貿易機関(WTO)協定に反するだけに、関係国と協調し、見直しを強く求めるべきだ。米国は貿易赤字が膨らみ、2024年は約1兆2000億ドル(約185兆円)と過去最大に膨らんだ。トランプ大統領は「われわれの生活を脅かす国家非常事態に当たる」とし、関税措置で「(米国経済を)復活する」と強調した。相互関税は、安全保障上の脅威に対する国際緊急経済権限法に基づくもので、中国には34%、韓国には25%、欧州連合(EU)には20%をかける。これとは別に、輸入車には25%の追加関税を導入した。各国の反発は必至であり、「貿易戦争」につながる恐れがある。日本に24%の関税をかける根拠については、日本が米国からの輸入品にかけている関税が平均で46%になっていることを挙げた。その一例としてトランプ大統領は、日本の米を引き合いに出し、「700%の関税を課している」と言及した。高関税を印象づけようとするもので到底、容認できない。米国の貿易赤字の大半は自動車とその部分品、半導体など工業製品によるものだ。農林水産物は、米国が圧倒的な貿易黒字であり、米の関税を持ち出すのは筋違いである。日本が外国から米を輸入する場合、WTO協定に基づき、年間77万トンものミニマムアクセス(最低輸入機会=MA)と1キロ当たり341円の関税をかけている。第1次トランプ政権時に締結した日米貿易協定でも認められ、共同声明で「協定が誠実に履行されている間、協定と共同声明に反する行動を取らない」としていた。米国の姿勢は、約束を反故(ほご)にするものだ。「相互関税」の公表に先立ち米通商代表部(USTR)は、日本の牛肉やジャガイモなどの検疫体制も問題視した。今後、非関税障壁として圧力も強まるとみられる。日本の農業は、幾多の貿易自由化の結果、生産基盤は弱体化し、食料自給率(カロリーベース)は38%に低迷している。政府・与党は、農林水産物・食品の輸出に力を入れ、30年までに5兆円を目指す。茨城大学の西川邦夫教授は「日本の米輸入制度がターゲットになっていることは明らか。輸出戦略の見直しが迫られる」と指摘する。自動車産業を守るために、日本の農林水産物、農業・農村を犠牲にするようなことがあってはならない。 *6-2-2:https://digital.asahi.com/articles/AST443FLPT44UTIL004M.html (朝日新聞 2025年4月5日) トランプ大統領「日本は輸入米に関税700%」 発言は「誤り」 【トランプ米大統領の発言】「日本では、我々の友人(日本)が(米国産の米に)700%の関税を課しているが、それは私たちに米やその他のものを売らせたくないからだ」(4月2日、米ワシントンのホワイトハウスでの「相互関税」に関する発表で)。トランプ米大統領が2日にホワイトハウスでの「相互関税」に関する発表で語った。江藤拓農林水産相はその後、報道各社の取材に「論理的に私も計算しても、そういう数字が出てこない。なかなか理解不能だ」と述べた。 ●一定枠超えた輸入米、1キロ341円の関税 政府は主食である米や農家を守るため、米の輸入を原則認めてこなかったが、1995年に方針転換した。無関税で米を受け入れる最低枠「ミニマム・アクセス(MA)」を設け、現在は年間約77万トンを輸入し、米国が最も多く半分近くを占める。一方、この枠外で輸入した米には価格に関わらず、1キロあたり341円の関税をかけ、2024年度は今年1月末時点で991トン(暫定値)を輸入する。ランプ氏が示す「700%」の根拠は不明だ。しかし、日本政府は2000年代の世界貿易機関(WTO)の交渉で、米の国際的な平均価格を1キロあたり約44円とし、参考値で「778%」との高めの関税率を示したことがある。最初の設定が高ければ、交渉で関税率を引き下げても、一定の税率を維持し、輸入量を抑える狙いだったとみられるが、現在はこの数字は当てはまらない。 ●「トランプ氏にうまく使われている」 元農水官僚で、国際貿易交渉に詳しい明治大の作山巧専任教授に関税率の試算を依頼した。農水省によると、直近の米国産うるち精米中粒種(23年度)の価格は1キロ当たり約150円で、関税率に換算すると227%と、トランプ氏が主張する「700%」には遠く及ばなかった。作山氏は「かつての交渉では日本が米を守るために高い関税率を示した。それをトランプ氏にうまく使われているのでは」と指摘する。 ●結果判定=「誤り」 政府は無関税で米を輸入する一定量の枠を設け、この枠外で輸入する米には1キロあたり341円の関税を課す。専門家が直近の米国からの輸入米の価格(2023年度、1キロ当たり150円)を元に、341円で関税率を試算すると、227%だった。 *6-2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250406&ng=DGKKZO87854770V00C25A4EA2000 (日経新聞 2025.4.6) コメ政策、内外から圧力 米騒動や関税で強まる 「閉鎖的」批判、改革促す 日本の閉鎖的なコメ政策に内外から圧力が強まっている。「令和の米騒動」を受けて小売りや外食業界はコメ輸入のニーズを高め、米国も日本の高関税の象徴としてやり玉に挙げる。農家保護を優先した守りの農政を脱し、増産や農地集約といった改革路線への転換が欠かせない。農林水産省の農林水産物輸出入情報によると1~2月の米国産コメの輸入量は7万423トンで前年同期比19%増だった。貿易統計を基に分析すると政府経由の輸入が全体の99%以上を占める。民間輸入も58トンと少量ながら3倍になった。小売りや外食で外国産コメを使う動きが広がっている。24年夏にスーパーなどの店頭からコメが消えた「令和の米騒動」が引き金となった。イオンは10日ごろから米国産と国産のコメをブレンドした新商品「二穂の匠」を発売する。米国産と国産を8対2の比率でブレンドし、4キロ2780円(税抜き)と割安感を出す。兼松は12月までに1万トンを輸入する見込みだ。吉野家ホールディングスは牛丼チェーン「吉野家」で2024年春から国産米と外国産米のブレンド米に変更した。輸入米を扱う大手卸の担当者は「外食産業はコメを使ったメニューをなくせない危機感がある。調達の選択肢として輸入米を求めている」と明かす。国産米の価格高騰によって、足元では輸入米の方が割安になっていることも一因という。農水省は25年1月に備蓄米放出にかじを切った。計21万トンの備蓄米を入札2回に分けて市場に順次供給しているものの価格抑制の効果はなお限定的だ。農水省によると、スーパーのコメ5キログラムの平均価格(3月17~23日)は4197円だった。前年同期比で2倍超の高値が続く。この状況が米国には好機と映る。「強い輸入需要を反映している」。米通商代表部(USTR)が3月末に公表した25年の貿易障壁報告書はあるデータに着目し、こう強調した。日本政府が無関税で輸入したミニマムアクセス米を国内の卸業者などが落札する際、国に事実上の関税として支払うマークアップ(輸入差益)だ。制度を導入した1995年度以降、輸入差益が24年末に初めて上限の1キログラム292円に達したことをUSTRは見逃さなかった。トランプ米大統領も2日の相互関税の発表時、日本が「コメに700%の関税をかけている」と非難した。通商問題に詳しいオウルズコンサルティンググループの菅原淳一シニアフェローは米政権にとって700%という数字が「不公正さを強調するのに都合がよく、関税の正当性を示す上でインパクトがある」と指摘する。米国産コメの主産地はカリフォルニア州など民主党の地盤が多い。従来は共和党政権にとって日本のコメ市場の開放の関心は薄いとされてきた。その状況に変化が生じつつある。米国の高関税政策への対抗として農産品に報復関税を設ける国が相次ぎ「米国内で農業者の不満を抑える必要が出てきた」(菅原氏)ためだ。トランプ氏らが日本のコメ関税に重ねて言及する一因とみられる。江藤拓農相は700%という主張は「理解不能だ」と反発する。関税はキロあたりの従量制で、輸入価格に定率の税をかけていない。700%という税率はそもそも存在しないという立場だ。米国側の主張に不正確さがあったとしても、日本のコメ政策が閉鎖的だとの指摘は否めない面がある。国内外で同時に高まる圧力は日本の農政転換の契機になる。コメ価格を下げすぎないことが農水省にとって長年の最重要課題だった。国内の主食用米の需要は人口減を背景に年10万トンほどのペースで減っている。国が産地ごとに生産量を割り振る減反政策は18年に終了したものの補助金を通じた実質的な調整は続く。そのひずみが米騒動であらわになった。JAや大手卸以外の小規模業者の参入が相次ぎ、在庫の全体像を正確につかめない政府の不備も混乱に拍車をかけた。米価高騰が常態化すれば個人消費の重荷になりかねない。 農水省によると、農業を主な職業とする基幹的農業従事者(概数値)は24年に前年比4%減の111万人で、05年の半数ほどに減った。65歳以上の担い手が7割を占め、後継者不在を理由とした耕作放棄が一気に進む可能性がある。東京大の鈴木宣弘特任教授(農業経済学)は「農産物が関税を巡る交渉カードになる可能性はある。コメ輸入によって価格が下がりすぎれば日本の農家は立ちゆかない。もし輸入が途絶した場合、食料危機に直結することにも注意が要る」と指摘する。国土の維持や食料安全保障の観点から農家を支援する仕組みは欧州などで例がある。「国内の増産を支援しつつ、コメ農家の収入を補填するような仕組みの構築が必要だ」と話す。水田集約などを通じて生産性を高める取り組みも不可欠になる。農業全般に意欲ある働き手の新規参入をしやすくし、人工知能(AI)など最新のデジタル技術を活用したスマート農業を普及させることも急務だ。従来型のばらまき補助金では実現は難しい。規模や立地の観点で高い生産性を実現できる農業従事者を重点的に育てる仕組みも検討が必要だ。用水路などのインフラを維持するためにも一定の集約は避けられない。米国の高関税政策は世界の自由貿易体制を揺るがした。食料の多くを輸入に頼る日本にとって国内農業を強くする政策が求められる。 *6-3-1:https://www.yomiuri.co.jp/national/20250103-OYT1T50003/ (読売新聞 2025/1/8) スマホのように、1人1台のロボット…AI進歩で「夢物語ではない」近未来 ●[AI近未来]第1部<1> 「今から持ち上げますね。どこか不快感はありますか」。ベッドに寝かせたマネキンに、人型ロボットが話しかける。左手を背中に差し伸べ、起き上がらせようとするロボット。キッチンを模したスペースでは、容器に入ったお茶を一滴もこぼさずコップに注いでみせた。東京都新宿区にある早稲田大の次世代ロボット研究機構。産学の開発チームを率いる同大の菅野重樹教授(66)が、我が子を見守るようにその様子を見つめる。1人に1台、一生寄り添う――。4月に開幕する大阪・関西万博では、そんなコンセプトの人型スマートロボット「AIREC(アイレック)」が披露される。アイレックの頭脳にはAI(人工知能)が搭載されている。人間がロボットの手や腕を遠隔操作することで、AIが人の動作を学習。体を起き上がらせたり、トイレを掃除したり、様々なスキルを習得した。料理にも挑戦中。スクランブルエッグなら、フライパンで卵の固まり具合に合わせた混ぜ方をマスターした。菅野教授は、アイレックが人の暮らしを支え、人と共生する社会を思い描く。10年先には、人の指示を受けて洗濯物を畳んだり、火加減が難しいオムレツを作ったり、人を手助けする動作が増える。家事だけではなく、健康も管理。人の体に機器を当てて超音波検査を行い、病気やけががないか調べる能力も身につける。そして2040年、アイレックは研究室を飛び出す。50年には社会に溶け込んで、人の意図をくみ取って動き回る。家の中では、住人の指示がなくても率先して好みの料理を作ったり、掃除をしたりする。住人の体調が悪く、歩くのも難しければ、車いすに乗せて病院に付き添う。「スマートフォンのように、生まれた時からロボットが家庭にいて人を支える未来が待っている」と語る菅野教授。1970年の大阪万博では、携帯電話の原型「ワイヤレステレホン」や「動く歩道」が注目され、今や社会に広く普及した。スマートロボットの構想も決して夢物語ではない。人とロボットが一緒に暮らすうちに、人は、家族のように愛情を抱き、ロボットも人の感情や価値観を理解して動く日が来る――。菅野教授は、開発の延長線上にそんな未来を予想する。AIの進歩によって、人の暮らしや社会のありようは、さらに変容する可能性を秘める。野村総合研究所によると、世界のAI研究者約2800人への調査を基にした論文(2024年)では、今後10年以内に、〈ロボットが洗濯物を畳む〉〈小売店の従業員がロボットに置き換わる〉といった変革が50%の確率で実現する可能性があるとされた。野村総研の森健デジタル社会・経済研究室長は「2030年代にはAIの搭載されたロボットが、一部の肉体労働も担い始めるとの見方が多い」と話す。研究者の間では、AIの近未来に楽観と悲観が交錯している。同論文では、68%の回答者が「良い結果の方が悪い結果よりも起こりやすい」とした。一方、「人類滅亡のような極端に悪い結果が起こる可能性がゼロではない」とする回答者も58%に達した。AIによって暮らしの豊かさや経済成長、医療の進歩などが期待される一方、雇用の喪失や、偽情報の拡散による社会の分断、軍事への悪用といった懸念は根強い。 ◇ 人間と会話しているかのような文章を生み出す生成AIが急速に広まってから2年余り。さらに進化を続けるAIは「ドラえもん」のように人を手助けしてくれるパートナーになるのか。それとも、人の知能を超え、人類の命運を左右する脅威になるのか。AI社会の近未来を展望する。 *6-3-2:https://www.yomiuri.co.jp/medical/20250321-OYT1T50142/ (読売新聞 2025.3.21) iPS細胞移植後に2人の運動機能が改善、脊髄損傷患者が自分で食事をとれるように…世界初 慶応大などの研究チームは21日、脊髄損傷で体がまひした患者4人にiPS細胞(人工多能性幹細胞)から作製した細胞を移植した世界初の臨床研究で、2人の運動機能が改善したと発表した。2人は食事を自分でとれるようになり、うち1人は立つことができたという。チームは「移植した細胞が損傷を修復した可能性がある」とみている。臨床研究を行ったのは慶大の中村雅也教授(整形外科)、岡野 栄之ひでゆき 教授(生理学)らのチーム。横浜市で開かれている日本再生医療学会で結果を報告した。発表によると、患者は受傷後2~4週間の18歳以上の4人で、受傷した首や胸から下の運動機能や感覚が完全にまひした。チームは健康な人のiPS細胞から神経のもとになる細胞を作り、2021~23年、患者1人あたり約200万個の細胞を傷ついた脊髄に移植。患者は機能回復を促す通常のリハビリなどを続けた。移植の約1年後に有効性を検証した結果、運動機能の5段階のスコアが1人は3段階、1人は2段階改善した。残る2人は治療前と同じスコアだったが、改善はみられたという。今回の臨床研究は安全性を確認するのが主な目的で、重い健康被害は確認されなかった。有効性はさらに精査する。チームはまひが固定した慢性期患者を対象にした治験を27年に行う方針を明らかにした。脊髄損傷は交通事故などが原因で、国内の新規患者は年間約6000人。慢性期の患者は10万人以上とされる。
| 経済・雇用::2023.3~ | 01:27 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
PAGE TOP ↑
