左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。
|
2022,12,19, Monday
2023年の新年、明けましておめでとうございます。 師走や年初は忙しかったため長引いてしまいましたが、1ヵ月以上かかってやっと完成しました。
(1)防衛費増額のための増税を含む財源について  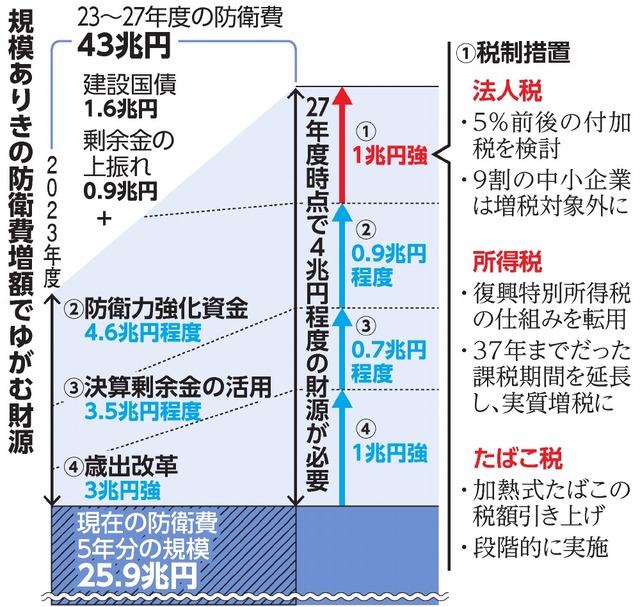  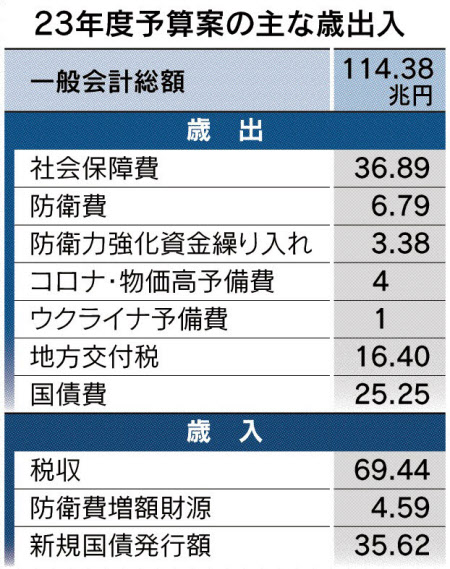 東京新聞 2022.12.15朝日新聞 2022.12.15毎日新聞 2022.12.23日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、日本はNATO諸国の標準に合わせて防衛費をGDPの2%にしようとしている。そして、増額分の今後5年間の財源を、左から2番目の図のように、歳出改革で3兆円・決算剰余金の活用で3.5兆円、防衛力強化資金で4.6兆円、増税で3.5兆円賄い、そのほかに建設国債1.6兆円と剰余金の上振れ0.9兆円を見込んでいる。単年度では、2027年のケースで右から2番目の図のようになっており、この12月23日に閣議決定された2023年度予算は、1番右の図のように、コロナが落ち着いたにもかかわらず、114.38兆円と過去最高になっている) 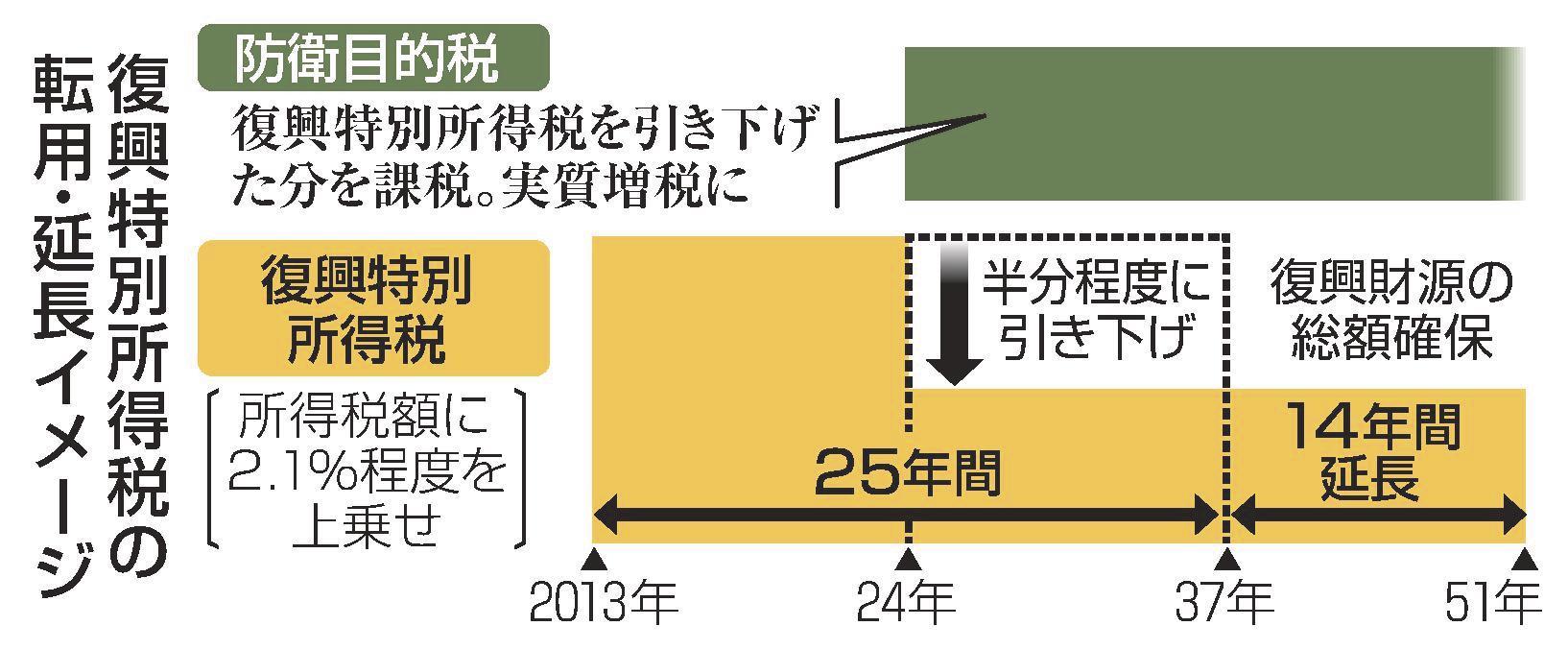 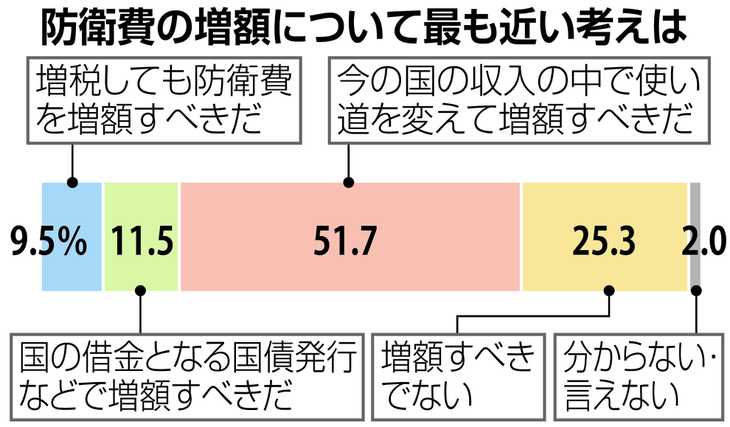 2022.12.15山陰中央新聞 2022.6.20産経新聞 (図の説明:左図は、復興特別所得税を1%下げて防衛税を1%付加するやり方で、そのかわりに復興特別所得税が14年間延長されるというものだ。また、右図は、「防衛費増額の財源をどうすべきか」についてアンケートをとった結果、「今の国の収入の中で使い道を変えて増額すべき」と「増額すべきでない」が多数を占めたことを表している) 1)防衛費増額の財源に法人・所得・たばこ税増税は妥当か 政府は、*1-1-1・*1-1-2・*1-1-3のように、①2023年度から5年間の防衛費を43兆円程度とする方針で ②そうすると、2022年度当初5.2兆円の5年分(25.9兆円)より14.6兆円程度の上積みとなる そうだ。 そして、14.6兆円の財源を、③歳出改革・決算剰余金活用・税外収入等で11.1兆円確保し ④残り3.5兆円を法人税・東日本大震災復興特別所得税・たばこ税増税で確保し ⑤その内訳は法人税7000億~8000億円・たばこ税約2000億円・復興所得税(所得税額に2.1%をかけていた)のうち1%程度を防衛目的税に廻して約2000億円調達し ⑥かわりに復興所得税の期限を当初の2037年から14年間延長し ⑦たばこ税は1本あたり3円上乗せして 調達するそうだ。 しかし、防衛費の財源のために増税しなくても、③の中の歳出改革で賄うべきであり、原発補助金・時代錯誤の農業補助金・エネルギー代金の補助など、適切な対応をとればいらない筈の無駄な歳出がいくらでもあるため、それは可能なのである。 また、⑤の所得税に税率1%の新たな付加税を設けて、現在は2.1%の東日本大震災の復興特別所得税を1%引き下げて合計の税率を2.1%に保ちつつ復興所得税の期間を延長するというのも、2011年に起こった震災の復興は10年程度で速やかにやって欲しいところ、2037年から14年間延長して2051年までもやるのでは、震災復興が復興目的ではなく既得権益となるだろう。 さらに、たばこ税は1本あたり(たった)3円相当増税して防衛財源にするそうだが、喫煙者は肺癌になる確率が有為に高いため、それに見合った金額を増税して医療保険制度の補助にすべきであるし、決算剰余金活用・税外収入は、該当する世代の人口が増えれば増えるのが当然であるのに発生主義でその準備をしてこなかった年金・医療・介護制度の原資にすべきなのである。 なお、政府は増税とは別に、⑧防衛費のうち自衛隊の施設整備や船の建造費など計4343億円を建設国債で賄うそうだが、建設国債は鉄道・道路・送電線の敷設などのように、生産性を上げることによってその後の経済活動に寄与して法人税・所得税などとして戻ってくる固定資産への投資に対して使うものであるため、自衛隊施設や船の建造費のように経済活動で生産性を上げるわけではない消耗品費を建設国債で賄うのは適切でないと、私も考える。 しかし、政府が2022年12月23日に閣議決定した2023年度予算案では、防衛関係費はGDP比1%の目安を超えて1.19%となり、金額で26%増加して過去最大の6兆8219億円となり、これは、ほぼ横ばいの6兆600億円だった公共事業関係費を初めて上回り、一般歳出で社会保障関係費に次いで多かったのだそうだ。 この防衛関係費には、米軍再編経費やデジタル庁が所管する防衛省のシステム経費を含むそうだが、米軍再編経費の中には明らかに無駄遣いに当たるものが多い。また、継戦能力を高めるために、長射程ミサイルや艦艇などの新たな装備品の購入費が1兆3622億円で7割弱増え、装備品の維持整備費も1兆8731億円と5割近く増額したそうだが、これまで機材を共食いさせながら整備してきたような自衛隊に、無駄遣いせずに継戦能力を高めたり、機材の維持管理をしたりする合理的思考があるとは思えないわけである。 2)破壊的活動である防衛費の財源に建設国債の発行は許されないこと *1-2-1のように、政府が戦後初めて、防衛力整備を国債で賄う方針を固めたが、借金頼みで軍拡して国民の財産を灰燼に帰させたのは、ほんの77年前のことである。もう忘れたのだろうか。そして、その時も、強烈なインフレを起こして国民の預金を著しく目減りさせ、それと同時に国債の実価価値を落として返済した。このように国民の生活を無視した同じ失敗の歴史を、何度繰り返したら気が済むのか。 私は、公共事業などの投資的経費には建設国債を充ててよいと思うが、海上保安庁の予算も建設国債ではなく通常の国債を充てるべきだと考える。財政規律は、ここまで失われているのか。老朽化した自衛隊の隊舎であっても、鉄道・道路・送電線のように、その後に生産性を高めて経済を活性化させ、それによって徴収された税で返済することができないのが、建設国債を充てるべきではないと考える理由である。 私は、プロセスが乱暴ではなく整っていたり、説明する言葉が丁寧だったりすれば、妥当性のない内容の政策でも通してよいとは全く思わないが、*1-2-2のように、物価を高騰させ、国民負担を増やし、給付は減らしながら、防衛費を増額して、その財源として新たに増税を打ち出す内容は、まさに国民の生命・財産を大切にしていないと考える。 だからといって、「内閣不信任案」を通して首相を後退させても、さらに強硬な人が首相になればむしろマイナスなので、本当に必要なことは、何故こうなるのかを考えて、それを防ぐことである。なお、沖縄県のあちこちに必要以上に軍事基地を建設するのも、観光を通して金にもなる大切な自然を壊しながら膨大な無駄遣いをしているのに他ならない。 3)2023年度与党税制改正大綱について 上の1)2)の増税は、先見の明ある質の良いものとは決して思わないが、*1-3-1は、それに加えて、12月16日に固まった2023年度与党税制改正大綱は、①NISAが、恒久化・非課税期間の無期限化で拡充された ②欧米は環境問題などを睨んで税制改革を進めているのに、炭素税が先送りされ次の成長策を描けていない ③EV税制は走行距離に応じた課税案があった ④「1億円の壁」という税の不公平是正も踏み込み不足だった ⑤自民党税調は1959年に発足し、11~12月だけ開くのが慣例で、場当たり的な議論に追われている と記載している。 しかし、①は、「分散投資をやりやすくする」という意味ではよいが、分散投資の対象は利益率の低い日本国債や日本企業でなく、利益率が高くて不安定性の低い海外の国債や企業になると思われる。 また、②③については、日本は環境を汚さなければ経済発展しないと考えている人が未だに少なくなく、そのような先見の明なき人がオピニオン・リーダーに多いのが特徴でもあり、復興特別所得税を密かに防衛に流用してもよいとは思うが、環境税・炭素税には拒否感があるのである。東京財団政策研究所の森信さんが、「場当たり的な対応に追われて税体系全体をどうしたいかの議論が置き去りになっている」と言うのは、そういう意味であろう。 ④⑤については、(たとえ東大法学部卒・財務省出身であったとしても)税法は詳しくない国会議員が、支援者から言われた要望をそのまま発言するため、たばこ税は高くできなかったり、企業への現在の負担をできるだけ軽くするため環境税を見送ったりして、先見の明ある税体系の構築ができないのである。そのため、単純な期間の問題ではないのだ。 なお、*1-3-2のように、⑥経済への影響を考慮してカーボンプライシングを2028年度から導入し、小さな負担からスタートする というのは、CO2の削減効果に乏しく、やっている振りにすぎない。また、⑦経産省が化石燃料の輸入業者に「賦課金」を2028年度から始め ⑧電力会社に有償の排出枠を買い取らせる「排出量取引」を2033年度を目途に始める というのも、CO2の排出量に応じた負担になっていないため、不公平感を増すだけであろう。 そして、⑨日本の再エネ利用は遅れているため、欧州等で取り組みが進む中、国内外の投資家から日本企業に向けられる視線が厳しくなって、「対策は待ったなし」という認識が広がったが ⑩EUは、排出量の規制が緩い国からの輸入品に事実上課税する国境炭素税を2026年以降に導入する そうだが、2033年度に新たな賦課金と排出量取引の一部有償化をそろって導入するのでは遅すぎる。その上、負担額も低すぎ、本当は日本が最初に言い出したことであるのに、海外からの圧力で初めて実行に移すところが、リーダーの意識が低く、先見の明がない証である。 (2)戦後安全保障の転換とその内容  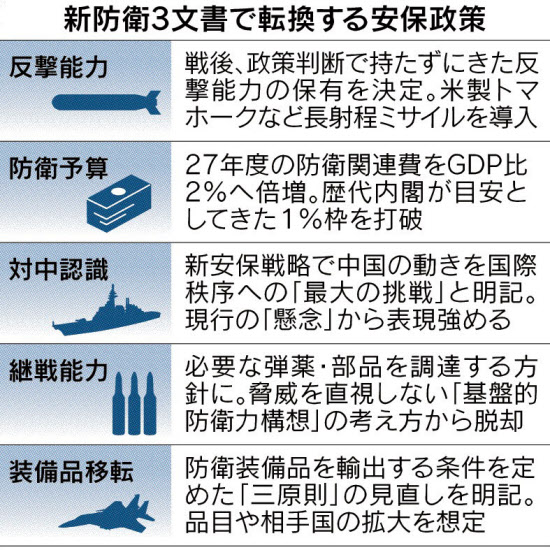 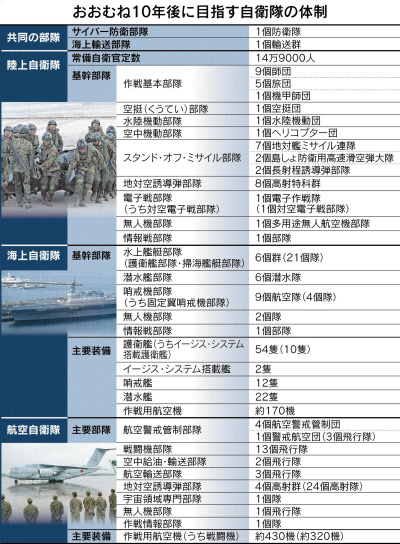 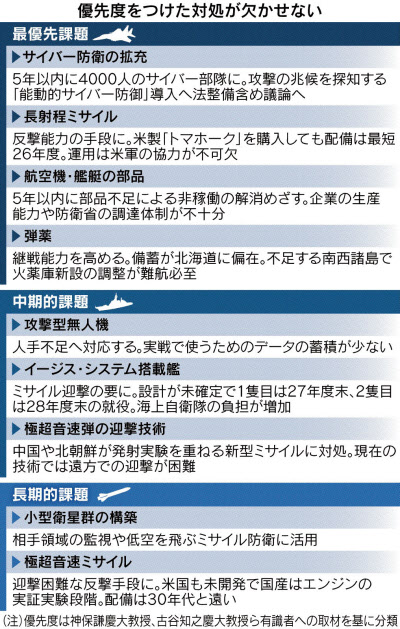 すべて2022.12.17日経新聞 (図の説明:新防衛3文書の枠組みは、1番左の図のように、国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画の3つだが、どれも国家を防衛する発想だけで国民を護る視点のないのが根本的問題である。また、新防衛3文書で転換する安保政策は、左から2番目の図のように、中国を意識しての反撃能力・継戦能力強化のためのGDP比2%への防衛予算増額で、防衛装備品を内生産して輸出する準備もしている。そして、右から2番目が10年後に目指す自衛隊の大勢だそうだが、10年後にしては宇宙・サイバー・ミサイル・無人機が手薄で、多くを人手に頼っており、戦闘機の時代に戦艦に頼っていたのと同じ印象だ。本当は、1番右の図のような優先度をつけた最小コストで最大効果を発揮する防衛予算が望まれるが、コストには国民の犠牲も含めるべきだ)  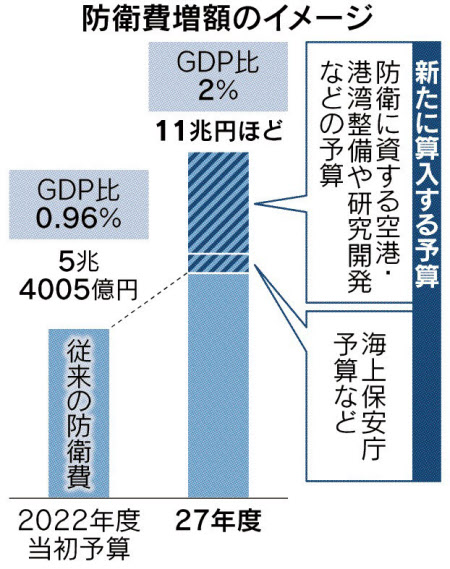  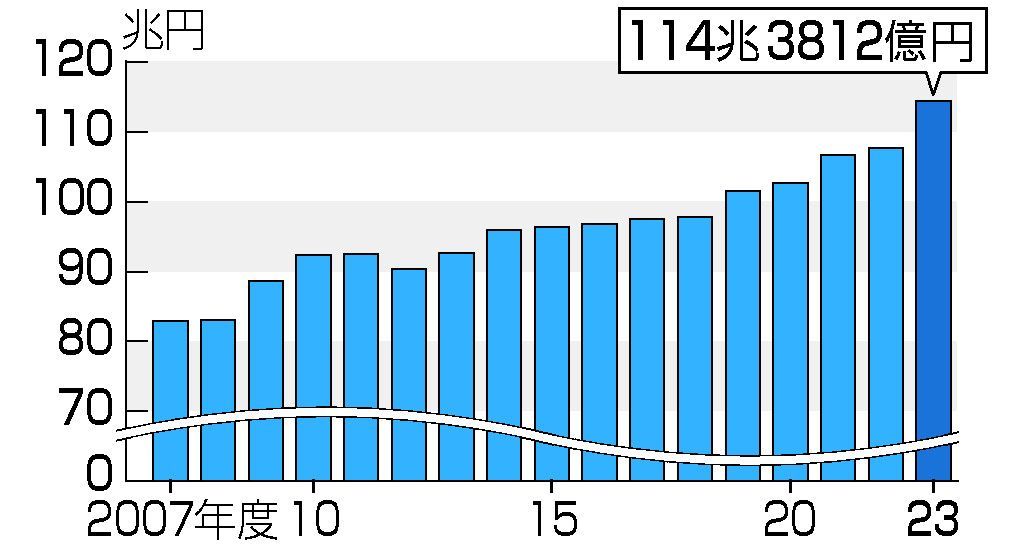 2021.10.23JCP 2022.11.29、2022.12.9日経新聞 2022.12.24Yahoo (図の説明:日本のGDPは世界第3位であるため、他国と同じGDP比2%の防衛予算なら、1番左の図のように、世界第3位の防衛予算になるが、その内容は上の図のとおりだ。そして、防衛費増額のイメージは、左から2番目の図の通りで、その財源は、右から2番目の図のように、歳出改革・決算剰余金の活用・防衛力強化資金・増税とされているが、これらは防衛費以外にも使い道はいくらでもある資金だ。そして、これらの放漫財政を反映して閣議決定された2023年度予算は、1番右の図のとおり、過去最高の114兆3812億円となっているが、これでよいのか?) 1)安全保障の転換内容について 防衛費増額の根拠について、政府は、*2-3-1のように、安保3文書(①国家安全保障戦略 ②国家防衛戦略 ③防衛力整備計画)を定めたが、書かれている内容は、同じことを繰り返している割には曖昧な点が多く、全体としては総花的でまとまっておらず、相互に矛盾する内容も散見される。 そのため、*2-3-2のように、目的意識を明確にした上での優先度が問われる。例えば、無人機やミサイルを配備し、宇宙からの防衛力を強めれば、従来型の有人戦闘機は著しく減らすことができる筈だ。しかし、戦争を前提として準備する以上は、インフラ防護やサイバー防衛は必要不可欠であるのに、原発や送電線はじめセキュリティーに甘い施設の新設も予定され、食料やエネルギーの自給率は著しく低いのである。 これでは、何があっても敵基地を攻撃したり、戦争を始めたりすることなどはできないため、防衛費を増額したからといって国を護ることはできず、防衛費増額は無駄遣いにすぎなくなる。「反撃能力があれば、抑止力になる」という論者も多いが、それは相手国の動機に依存するため希望的観測にすぎず、例えば、ウクライナのように、自国を侵略されれば相手がロシアであっても全力を尽くして闘うのが普通であるため、“抑止力論”は再検討を要するわけである。 そのような中、*2-3-3は、2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻はその40日前にサイバー攻撃で「開戦」しており、ウクライナの官民のインフラ全般が攻撃を受けていたと記載している。戦争における非軍事的手段と軍事的手段の割合は4対1だそうだが、日本はサイバー攻撃には本当に無防備なのである。 2)反撃能力保有の意義について *2-1-1は、①政府は国際情勢がウクライナ侵攻や台湾有事のリスクで急変したため ②2022年12月16日、国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画の新たな防衛3文書を閣議決定し ③相手のミサイル発射拠点をたたく「反撃能力」を保有し ④防衛費をGDP比2%に倍増し ⑤戦後の安保政策を転換して自立した防衛体制を構築し ⑥米国との統合抑止で東アジアの脅威への対処力を高める方針を打ち出し ⑦反撃能力の保有は3文書改定の柱だ と記載している。 つまり、「反撃能力の保有が抑止力となるため、反撃能力は今後不可欠」というのが防衛3文書の柱だそうだが、重要インフラは隙だらけ、エネルギーは殆ど海外依存、食料自給率も極端に低い中で、武器だけ増やしても国民は惨憺たる状態になるというのも、ロシアのウクライナ侵略で明るみに出たことである。 そのため、③④⑦を実行するために、前から存在していた①⑤⑥を理由として、②を閣議決定したようにしか思えない。 3)平和国家の名は、返上したのか? 岸田政権が閣議決定した国家安全保障戦略は、*2-1-2のように、日本周辺の情勢について「戦後最も厳しく複雑な安保環境」だと強調し、反撃能力の保有はじめ防衛力を抜本的に強化して、防衛関連予算を2027年度にGDP比2%に大幅増額するのが柱だそうだ。つまり、「GDP比2%に増額」というのが先にあって、その他の理屈は後から無理矢理つけたため、首尾一貫性や整合性がないのだろう。 また、戦後日本は憲法9条に基づき、「平和国家」として専守防衛に徹してきたことと、他国の領域を攻撃できる反撃能力を保有することは、日米安保条約下で「打撃力」を米国に委ねてきた安保政策を根幹から転換するものであるため、こうした重大な政策転換は国民的議論を行ってから決めるべきだった。ただし、防衛関連は特定秘密が多すぎて充実した議論ができず、議論が空回りしそうなので、これでよいのかとも思う。 そのため、メディアはこの年末年始には、馬鹿笑いするしかないような底の浅い番組ばかりではなく、この点をクローズアップした特集を報道すべきだ。戦争になれば主たる戦力にならざるを得ない若者こそ、防衛費増額・国債発行・増税・戦争の可能性を前に、「政治には関心がない」「選挙に行くのは面倒だ」「政治の話をするのは意識高い系だろう」などと言っている場合ではない筈である。 4)防衛予算における規模先行の弊害 *2-2-1は、①財政力の現実を直視して規模ありきの防衛予算増額を改めるべき ②このまま進めば借金で賄ったり防衛以外の予算を過度に制約したりする ③恒久的支出を増やす以上、安定財源確保が必須 ④国債頼みは財政上の問題に加え、防衛力拡大の歯止めも失わせる ⑤歳出改革で2027年度までに1兆円分を積み上げるとのことだが、「毎年度毎年度いろいろな面で工夫をしていかなければいけない」 とあやふや ⑥政府が実効性ある財源を示せないのは、防衛費の増額が身の丈を超えた規模のGDP2%という「総額ありき」で予算を決めた弊害 ⑦中身を精査して過大な部分を見直すのが先決 ⑧日本が直面する課題は安全保障だけではないため、幅広い視野で適正な資源配分を考えることが政治の役割 等と記載している。 上の①④は全くその通りで、②⑧については、国民の命を護るのに重要な社会保障予算が削られており、本末転倒だ。しかし、③のように、何かと言うと増税すれば国民の可処分所得を減らして、国民の命を護れない。そのため、⑤の歳出改革こそ重要なのであり、時代遅れの補助金が既得権益化しているものをなくしていかなければならないが、これを毎年合理的に判別するには、国に公会計制度を導入して事業毎の費用対効果を適時に見える化する必要があるのである。 これに加えて、*2-2-2は、⑨科学技術費等の国防に有益な費用を合算して省庁横断の防衛費と位置づけ ⑩防衛省予算を増額した上で防衛に有益な他の経費(公共インフラ・科学技術研究・サイバー・海上保安庁等の他省庁予算)を含め ⑪防衛省だけの縦割り体質から脱却して安全保障を政府全体で担う体制に移行 ⑫日本の防衛費は1976年の三木武夫内閣以来GDP比1%以内を目安としてきたが、ウクライナ侵攻を踏まえてNATO加盟国が相次ぎ国防費をGDP比2%にすると表明し、自民党が2%への増額論を唱えていた ⑬2022年度当初で5兆4000億円程度の防衛省予算は、GDP比2%なら約11兆円に達する ⑭柱となるのは「反撃能力」の保有で、ミサイルの長射程化や米国製巡航ミサイル「トマホーク」を導入 ⑮不足している弾薬の購入量を増やすなどして継戦能力も強化 ⑯首相は両閣僚に歳出改革なども含め財源捻出を工夫するよう求めた と記載している ⑥⑫⑬のように、NATO加盟国が相次ぎ国防費をGDP比2%にすると表明したからといって、日本もGDP比2%という「総額ありき」で、⑦のように、中身も詰まらないのに予算を決めるのは意味がない。そのため、⑨⑩⑪のように、防衛に関するものは他省庁の予算でもカウントするのは賛成できるが、⑭⑮のように、柱となるのが「継戦能力」と「反撃能力」の保有、それによる抑止力の期待ではお粗末すぎるのである。 (3)エネルギーの安全保障 エネルギーの安全保障については、a)自然災害や戦争の発生時に被害を最小に食い止められること b)自給率を高くできること c)貿易や経済を通して国民経済に負担をかけず、むしろ活性化させること の3点から見た優位性を検討する。これらは、当然のことなのだが、日本では逆の意思決定がなされることが多いのは何故かを、正確に突き止めて解決しなければならない。 1)再エネについて 国際エネルギー機関(IEA)は、*3-1-1ように、2022年12月6日に公表した報告書で、太陽光・風力などの再エネが2025年には石炭を抜いて最大の電源になるとの見通しを示した。 その理由は、再エネは、各国が自給でき、装置産業であり変動費が無料に近いため、普及すればするほど発電コストが安くなるからで、今では化石燃料や原発の方が安価だなどと言っているのは日本くらいである。しかし、どうして、いつもこういうことになるのか、そこが、日本経済停滞の原因なのである。 また、再エネの普及には、送電網や蓄電池が必要だが、*3-1-2のように、政府は官民で150兆円超の脱炭素投資を見込み、再エネの大量導入に約31兆円を想定しているそうだが、金額が大きい割には、達成目標が2030年度に36~38%と著しく低い。 こうなる理由の1つは、再エネに対して仮想発電所ではなく原発や火力と同じような大型案件を予定するからであり、それでは景観や安全性への懸念から地元自治体が反対するのは当然である。また、送電網の強化も、鉄道網や道路網を利用して陸上でネットワーク上にすれば、敷設・維持・管理を最小コストで行うことができ、安全保障上も優れているのに、広域送電網の整備を海中にするそうなのだ。 また、EUは2026年から炭素価格の低い国からの輸入品に対して国境炭素調整措置の導入を決めたが、日本の炭素税は欧州などよりずっと軽く、開発では日本が先行したペロブスカイト型次世代太陽電池も、早く実用化しなければ普及で世界で置いて行かれるのは必然である。 そして、脱炭素社会の実現には、化石燃料を再エネに転換させる経済改革が必要であるにもかかわらず、政府のGX実行会議は、*3-1-3のように、2022年7月から5回開いて脱炭素化に向けた基本方針を決め、その内容は、①フクイチ事故後「依存度低減」としてきた原発政策を「最大限活用」に変更し ②原発の新規建設や長期運転に踏み込んだが ③原発は、2030年までのCO2排出量半減にも、ウクライナ戦争に伴うエネルギー危機への対応にも間に合わず ④再エネ普及策を徹底的に議論して打ち出すことはしていない とのことである。 つまり、①~④は、CO2排出量削減とウクライナ戦争に伴うエネルギー危機を、大きな予算を使っての原発再稼働・運転延長・新増設の名目として使っただけであり、このようなことの積み重ねが、新技術の普及と日本の経済成長を阻害した上に、世界に類を見ない借金大国にした真の原因なのである。 2)送電網について 政府は、*3-2-1のように、過去10年の8倍以上のペースで、今後10年間に約1000万キロワット分の広域送電網を整備し、太陽光や風力などの再エネによる電気を無駄にせず地域間で効率よく融通できする体制を整えるそうで、これはよいことだ。 ただし、送電の事業主体を電力会社にすれば、現在と同様、送電事業の発電事業からの独立性がなく公正競争も行われないため、再エネ発電事業者にとって不利な送電網利用料金が設定されることは明らかだ。日本は、大手電力会社が地域毎に事業を独占して競争原理を働かせない状態を続けてきたが、送電事業でも同じことが起こっているのである。 そのため、鉄道網を利用すれば発送電事業が分離独立すると同時に、赤字路線に送電収入が追加されるため、損益をプラスにしやすくなる。これについては、送電事業を既得権益とする経産省と大手電力会社が大反対するだろうが、国民に負担をかけない少ない補助金でエネルギー安全保障を確立するためには必要不可欠なことなのである。 そのような中、東京電力パワーグリッドなど大手電力の送配電会社10社は、*3-2-2のように、さっそく電力小売会社から受け取る送電網利用料を2023年度から引き上げて送電網増強やデジタル化といった投資に充てる計画を提出し、経産省の電力・ガス取引監視等委員会の検証が終わったそうだが、このような形で経産省のお墨付きを得て地域独占させてきたことが、工夫もなく日本の電力コストをいつまでも高止まりさせてきた原因そのものなのである。 3)ガス火力について 経産省は、*3-4-1のように、今後の“電力不足”に対応するためLNG火力を緊急建設する方針で、2030年度までの運転開始を念頭に7~8基を作り、建設費を投資回収しやすくする支援策を講じるそうだが、2030年度までの運転開始では緊急時の対応にはならない上、最新ガス火力はCO2排出量が相対的に少ないといっても再エネと違ってCO2を排出するため、地球温暖化対策にならず「長期脱炭素電源」とは言えない。 その上、電力小売りから集めた金を原資にして、新しい技術ではないLNG火力の運転開始から20年間も発電事業者が毎年一定の収入を得ることができるようにするなど論外だ。さらに、経産省のこのような非科学的かつ恣意的対応が、再エネの普及を阻害してコストをいつまでも高止まりさせ、国民に節電を呼びかけなければならないような事態を招いたことを忘れてはならない。 なお、日本は、技術が進んでも馬鹿の1つ覚えのように「資源のない国」だと言う人が多く、石油危機以降もエネルギーの殆どを輸入し続けて、自国の資源は眠らせたままにしている。しかし、これが、*3-4-2のように、貿易収支を赤字にする大きな原因であり、経産省がこのような態度を続けていることが、国内産業を海外に流出させて円安を招いたのでもあって、このように負担増ばかりでは国民の消費が伸びるわけもないのである。 4)原発について(運転延長・廃炉・使用済核燃料・建て替えなど)   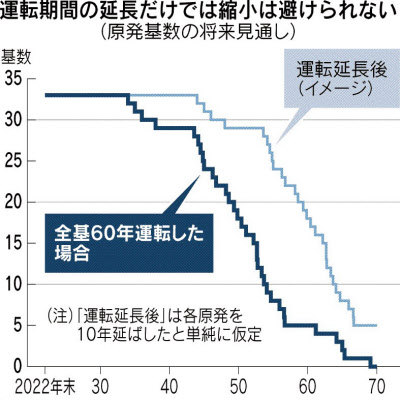 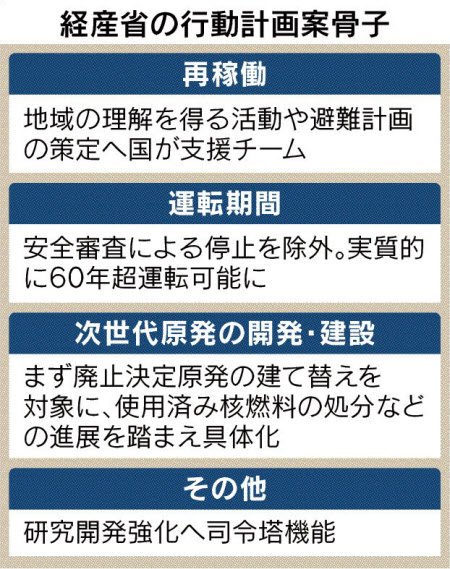 左から2022.11.29、2022.12.7、2022.11.29、2022.11.29日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、フクイチ事故後、原発の再稼働は進んでいないが、これは原発がなくても電力を賄えたということだ。しかし、日経新聞は、左から2番目の図のように、日本の既設原子炉は運転開始から年数の経っているものが多く、右から2番目の図のように、運転期間の延長だけでは原子力発電の縮小は避けられないとしている。しかし、それこそ原発の自然消滅であり、待たれていることなのだ。それにもかかわらず、経産省はロシアのウクライナ侵攻や地球温暖化対策を緊急の理由として、1番右の図のように、原発の再稼働・運転期間の延長・《少し改良しただけと言われる》次世代原発の開発や建設を計画しているわけである) *3-3-1・*3-3-2・*3-3-3・*3-3-6・*3-3-7のように、日本政府は、2022年12月22日、GX実行会議を開いて脱炭素社会の実現に向けた基本方針を纏め、原発については、①再エネと原発は安全保障に寄与して脱炭素効果が高いとし ②「将来にわたって持続的に活用する」と明記し ③廃止が決まった原発を建て替え ④運転期間も現在の最長60年から延長し ⑤2050年の温暖化ガス排出量を実質ゼロにする目標と電力の安定供給の両立に繋げる としたそうだ。 この方針は、パブリックコメントを経て2023年2月までに閣議決定し、政府の正式な方針にした上で法案提出をめざすそうなので、まずは反対意見をパブリックコメントに書く必要がある。 上のうちの①②については、原発は戦争になれば近くに置いてある使用済核燃料まで含めて巨大な自爆装置になるため、安全保障に寄与するどころか、安全保障を妨害するものだ。まさか、実際に起こるまで、それが理解できないわけではないだろうが・・。 また、③の廃止決定した原発建替を具体的に進め、次世代革新炉の開発・建設に取り組んで建設費用が1兆円規模ともされる原発建替を行うというのは、この電力危機には間に合わず、それに乗じた原発回帰にしても気が長すぎる。その上、コスト感覚が全くなく、無駄遣いが甚だしいにもかかわらず、ここまで非科学的・恣意的な意思決定をする政府(特に経産省)のすることが、信用できる筈はないのだ。 なお、④の原発の運転期間延長についても、「原則40年・最長60年とする制限を維持した上で、震災後の審査で停止していた期間などの分を延長する」そうだが、人が住まなくなった家や使わない機械が朽ちるのと同様、機械は停止していても(停止していればむしろ早く)劣化する。その上、原子炉以外の、例えば使用済核燃料プール・配管・建屋などは原子炉を止めていても使い続けていたのだ。 さらに、*3-3-4のように、海外では運転期間の上限がない国が多いが、国際原子力機関(IAEA)によると、現在60年を超えて運転を続けている原発はなく、地震・津波・火山噴火・台風などのリスクが大きい日本で、「中性子照射脆化」、コンクリートの遮蔽能力や強度がおちる経年劣化などを起こした原発を使うのは、さらに危険なのである。 それでも、原子力規制委員会が安全審査を通過させ、60年超の運転が可能になるようなら、*3-3-5のように、もはや原子力規制委員会は独立した公正な組織とは言えないだろう。 なお、原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場も決まらず、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会廃炉等円滑化ワーキンググループは、2022 年 10 月 17 日、⑥原子力事業者は毎年度、将来の不確実性も踏まえて認可法人が算定した拠出金を当該認可法人に対して納付する責任がある ⑦認可法人は廃止措置に要する費用の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負う ⑧原子力事業者は毎年度拠出金を納付することにより、各原子力事業者が保有する個別の原子炉に係る廃止措置費用を確保・負担する責任は負わない という中間報告をしたそうだ。 これについて、日本公認会計士協会は、「廃止措置に係る経済的責任は認可法人に移転するのか」「ここでの廃止措置に要する費用の範囲は、『原子力発電施設解体引当金に関する省令』における制度移行時点の総見積額を網羅しているのか」「個別の原子炉に関する廃止措置費用と拠出金間に相関関係がないが、原子力事業者の責任は毎年度の拠出金納付に限定され、各事業者は保有する個別の原子炉に係る廃止措置費用を確保・負担する責任は負わないのか」「新制度下で各原子力事業者が将来にわたって支払う拠出金累計額は事業者が保有する全ての原子炉の廃止措置に実際に要する費用と一致しないことを前提にしているのか」「規制料金によって回収された現行の解体引当金は、新制度下での認可法人への毎年度の拠出金納付義務とは別個で、制度移行時における各原子炉に係る資産除去債務残高は引き継がないのか」等について、会計処理の根拠を明らかにするため確認している(https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-9-0-2-20221110.pdf 参照)。 つまり、新制度の下では原発の廃止措置に係る経済的責任は認可法人に移転するが、認可法人への拠出金総額は個別の原子炉に関する廃止措置費用との間に相関関係がなく、廃止措置費用が足りなくなれば、それは国民負担になるということなのである。しかし、いかなる産業も汚染物質はクリーンにしてから放出するのがルールであるため、コストが安いと言いながら原発だけをここまで特別扱いにするのなら、費用を負担する国民に対してその理由を明らかにすべきだ。 5)EVについて 日本経済新聞社が予測する2023年のアジアにおける消費の主役は、*3-5-1のようにEVだそうだが、日本勢は未だにガソリン車のミニバンを主軸としているため、長く日本の自動車ブランドが支配的だった市場において、他国車の新規参入余地が大きくなっているそうだ。 しかし、EVの開発を始めて既に30年近く経つため、未だにガソリン車から離れられず、EVに不当に高い値段をつけているようでは、それも当然のことと言わざるを得ない。 また、*3-5-2のように東海道新幹線の豊橋―名古屋間で停電が起き、下り線では列車に電力を供給するトロリ線をつり下げる吊架線が切れていたため、東京―新大阪間のその復旧作業のために上下線で、最大4時間、運転を見合わせたそうだ。 東海道新幹線では、2010年1月にも車両の集電装置「パンタグラフ」の部品が外れて吊架線とトロリ線の間にある「補助吊架線」を切断し、約3時間20分にわたって停電する事故があったそうだが、パンタグラフを使って集電するから吊架線・トロリ線・補助吊架線などが必要で、これらの敷設費や維持管理費は高いのである。 そのため、新幹線はじめ電車もグリーン水素を使った燃料電池で走るシステムにしたらどうかと思う。そうすれば、電線がなくなって景色がよくなる上に、別途、送電線を敷設して送電料を副収入とすることも可能だからである。 6)ものづくりの「国内回帰」時代は来るか? 製造業の生産拠点が海外移転し、エネルギー・食糧の多くを輸入に頼っていては、日本からの輸出は少ないのに輸入が多く、貿易収支が赤字になって円安になる。また、ものづくりが廃れれば、製品の開発や維持管理のための技術も失われ、経済は成長するどころか縮小してしまう。 そのため、製造業の生産拠点を国内回帰させたいわけだが、*3-5-3のように、一時的な円安で海外から国内への輸送コストが相対的に上がり、国内の人件費が相対的に下がっても、工場の海外から国内への移転は時間とコストがかかるため、生産拠点の国内回帰は「限定的」だろうと、私も思う。 その理由の1つは、国内の人件費が円安で相対的に下がっても、原材料を輸入しながら加工だけ行って採算がとれるほど日本は安い人件費ではなく、生産コストだけを考えれば、原材料の産出地近くや人件費の安い開発途上国で生産を行った方が安価に生産できるからである。 また、人件費が高くても我が国で生産した方がよい場合もあるが、それは、技術が飛びぬけてよいため人件費に見合った高い価格をつけても売れる場合であり、既に生産拠点が海外移転して生産しなくなってしまった現在、我が国の技術がそこまでよいとは言えなくなっている。 それでも、国内に購買力があり、国内生産した方がマーケティング上有利であれば、国内生産する選択もあり得るが、定年退職、物価上昇、負担増・給付減による可処分所得の減少などで購買力が落ちているため、国内生産するマーケティング上のメリットも少なくなっているわけだ。 そのため、これらを根本的に解決するには、単なる加工貿易ではなく原材料やエネルギーもなるべく国内生産すること、国内生産した原材料やエネルギーに国際標準よりも高い価格をつけないこと、よい製品を作るために必要な教育・研究を進めること、何かと言えば政府が国民からぶんどって国民の可処分所得を減らさないようにすること などが、あらゆる努力をしてやるべきことなのである。 (4)食糧安全保障 1)食料自給率について 「腹が減っては戦ができぬ」という言葉の由来はわからないが、それが真実であることは確かだ。しかし、日本政府は武器だけあれば戦えると思っているのか、エネルギー自給率は12%程度、食料自給率は38%程度しかないにもかかわらず、本気で改善しようとしていない。これでは、他国同士が戦争しても、いや単に世界人口が増えただけでも、国民は健康で文化的な生活を諦めざるを得ないのである。 その例が、*4-1-1・*4-1-3のロシアのウクライナ侵攻と円安による飼料や燃料費高騰で農家が厳しい経営状況に直面し、廃業の危機にあることだ。しかし、家畜を飼うのに飼料や燃料費を輸入していたのも無防備すぎ、これでは酪農製品は自給率の中に入れられない。率直に言って、家畜の餌くらいは国内で安価に生産できるべきだと思う。 また、自給飼料づくりを目指して粗飼料を自前で収穫していた人もいたのはよかったが、畑で使う肥料も原料の大半が輸入品だったというのは、家畜の排泄物等を加工して使えば肥料を輸入する必要はなかったのに、と呆れられる。 さらに、トラクターを動かす軽油の価格が上がったそうだが、農機具を電動にすれば牧場や農地での自家発電は容易なのに、毎年同じことを言いつつ、いつまで輸入化石燃料を使うつもりだろう? そのため、 “値上がり分の補塡”や“製品の値上げ”をするよりも、政府と一緒になって自給飼料・自給肥料・自家発電システムの設置等を推進した方がよほど賢いと、私は思う。 このような中、*4-1-2のように、JA全農は、2022年10~12月期の配合飼料供給価格を7~9月期価格で据え置くと発表したそうだが、そもそも全農が輸入依存を進めてトウモロコシのシカゴ相場で飼料価格を変えるような体質にならず、むしろ政府に言って自給飼料・自給肥料・自家発電システムの設置を推進すればよかったのである。そのため、この辺は全体として同情の余地がないのだ。 なお、*4-2は、肥料価格が高騰している理由を、「日本は化学肥料の原料である尿素、りん酸アンモニウム、塩化カリウムの殆どを海外輸入に頼っているため国際情勢の影響を受けやすく、今回の高騰はロシアのウクライナ侵攻でアンモニア・塩化カリウムの生産国上位であるロシアへの経済制裁によって供給が停滞し、中国の輸出規制、肥料の運搬に利用される船舶燃料の高騰、円安などが複合的に関係したから」としている。しかし、この実態を見れば、日本とロシア・中国のどちらが偉いかは明らかだと言わざるを得ない。 そして、農林水産省・都道府県・市町村が国民の血税から肥料価格高騰対策事業を実施して対象期間に購入した肥料購入費の一部を助成するそうだが、種子や肥料等の資材も国内生産できず、無駄なことばかりしながら、何かあれば必ず予算措置による助成を求めるのは情けない限りだ。そのため、このように戦争が起これば生産できなくなる製品は食料自給率に入れず、本当の食料自給率を出した上で、根本的解決を行うべきである。 2)経済安全保障について このように、安全保障の視点からエネルギー政策や食糧政策を見ると、「日本は資源がないから」「加工貿易が適しているから」などと戦後すぐの頃の状態を語って世界の変化に全くついて行っていない理屈をつけ、太平洋戦争前後のように大量に国債を発行して、膨大な無駄遣いを続けている姿が見えてくる。 そのような中、*4-4は、①政府は経済安全保障推進法の「特定重要物資」に半導体・蓄電池・永久磁石・重要鉱物・工作機械・産業用ロボット・航空機部品・クラウドプログラム・天然ガス・船舶の部品・抗菌性物質製剤(抗菌薬)・肥料等の11分野を対象とすることを閣議決定した ②対象分野では国内生産体制を強化し備蓄も拡充する ③そのための企業の取り組みに国が財政支援する ④これにより有事に海外からの供給が途絶えても安定して物資を確保できる体制を整える ⑤いずれも供給が切れると経済活動や日常生活に支障を来すものだ としている。 しかし、⑤の供給が切れると日常生活に支障を来す物資の第一は食糧だが、これには言及していない。また、①の中の重要鉱物は、特定国に依存しすぎないための海外での権益取得の後押しと数か月分の備蓄しか考えておらず、国内や排他的水域内で生産することは考慮外である。そして、ここがロシア・中国・アラビアはじめ現在の資源国との違いなのである。そのため、④のように海外からの供給が途絶えるような有事には、数か月分の備蓄の範囲でしか物資を確保することができず、それでは太平洋戦争時のようになるため、紛争も戦争も決してできないのである。 つまり、②の対象分野は重要なところを逃している反面、資源については相変わらず輸入に頼るシナリオで、そのために、③のように、民間企業の取り組みに国が財政支援するというのだ。これでは、予算をばら撒きたいところにばら撒くため安全保障を口実に使っただけであり、政府が市場を歪めてかえって未来を暗くする。 このように、輸出するものは著しく少なくなったのに輸入することばかり考えてきた誤った政策の連続により、*4-3のように、日本は貿易や投資などの海外との取引状況を表す経常収支の低迷が続いて、ついに経常赤字となった。その主な原因は資源高と円安だそうだが、資源高の方は1973年に起こった第一次オイルショック以降の50年間ずっと続いているのであり、それまでの好景気を一変させた最大の理由でもあるのだ。 それでも高い価格で原油を買うことに心血を注いで他の手を打たなかった国が日本であり、政治も縦割りの組織で現状維持重視の行政に従って国民に迷惑をかけ続けているのが、困ったことなのである。 (5)命の安全保障(≒社会保障)について 1)最近の社会保障に関する論調について *5-1-1は、2022年12月19日、①社会保障財源は防衛費の次でいいのか と題し、②国内で生まれる子ども数が80万人を割り込む少子化の危機感があるのか ③どんな判断で政策の優先順位を決めているのか ④首相がトップの全世代型社会保障構築本部と有識者会議が、最も緊急を要する取り組みに「子育て・若者世代への支援」挙げたが ⑤必要となる費用や財源の具体論には言及せず ⑥介護分野の給付と負担の見直しを先送りし ⑦同じ日に政府は今後5年間の防衛予算を現行の1.5倍に増やすことを決めたが ⑧国民や企業の財布には限りがあるため、防衛予算の負担増が先行すれば子育て支援の負担を求めることは難しくなる と記載している。 また、*5-1-1は、⑨国民の暮らしの安心は、安全保障に勝るとも劣らない喫緊の課題で ⑩有識者会議の報告には雇用保険の対象外になっている非正規雇用の働き手支援や、自営業・フリーランス向けの育児期間中の給付金創設など既存の枠を超えた提案もある ⑪巨額の予算を要する児童手当の拡充も「恒久的な財源とあわせて検討」とされたが ⑫かつて「社会保障と税の一体改革」は給付と負担を一体で議論し、全体像を示しながら合意形成を図った ⑬介護保険は要介護度の軽い人向けの給付見直しや利用者負担の引き上げなどの案があるが反対も根強い ⑭それらが無理なら保険料や税による負担増が検討対象になる ⑮結局、財源の議論抜きに改革の前進はない とも記載している。 このうち①③⑤⑦⑧⑨については、太平洋戦争後に政治の指針となっている日本国憲法は、生存権(25 条)、教育を受ける権利(26 条)、勤労の権利(27 条)、労働基本権(28 条)などの国民の権利を明確に保障し、防衛については、前文と9条で平和主義と専守防衛を定めている。その上、経済発展や⑨のような安定した生活が防衛も支えることを考えれば、教育を含む社会保障の優先度の方が高いだろう(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf 、https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi033.pdf/$File/shukenshi033.pdf 衆議院憲法調査会事務局 参照)。 しかし、②④については、最初に少子化問題を取り上げたのは私で、その意図は、働く女性は子育てを両立できないため、実質的に出産できない矛盾を突くものであったため、その結果として起こった少子化のみを問題視して危機感を煽るのは、男性リーダーが大多数を占める政治・経済分野の古臭くてセンスの悪い発想だと、私は思っている。 また、日本国憲法が25 条で定める「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」というのは、当然、高齢者・障害者を除外していないため、経済の成熟に伴って医療・介護制度は充実することこそあれ、後退することは許されない。 従って、⑥⑫の「社会保障と税の一体改革」と称する年金・医療・介護分野の給付と負担の見直しは、高齢者の生活を予定外に圧迫して生存権が危ぶまれる状態に陥らせているという意味で適切でないため、ゼロサムゲームではなく、効用を高めながらコスト削減する方法を考えるべきだし、それは可能なのである。 なお、⑩の非正規雇用・フリーランス・一部の自営業は、労働法で護られない雇用を意図的に作っているものであるため、その存在そのものを検証すべきだ。にもかかわらず、雇用保険料を支払っていない人に育児期間中の給付金を雇用保険制度から支払うのは不公平を増す上、「子育ての便益は社会全体が享受する」として育児休業給付の費用を社会全体で負担すべきとの意見もあるが、それなら他の数々の無駄遣いを削って現在の税収から堂々と充てるべきだろう。 また、⑪の児童手当は、現在は0歳~15歳の子に支払われ、その間は所得税の扶養控除を行わない。仮に、これを拡充して16歳~18歳までの子にも支払うようにすれば、その間の所得税扶養控除を行わなければ整合性がとれる。ただし、所得が一定以上の人は、児童手当をもらえず、扶養控除もできないという前より悪い状態になっているため、所得制限は止めるべきだろう。 ⑬の介護保険制度は、要介護度が高い人はもちろん要介護度が低くても自力では暮らせない人のために給付しているもので、未完成の制度であって給付は足りないくらいであるため、これ以上の給付減は人命に関わる。また、要介護状態になっても稼げる人は殆どいないため、利用者負担増も人命に関わる。そのため、このようなことしか言えないような世代を作るのなら、子育ての便益を社会全体が享受するとは言えないため、一昔前と同様、自分の子は自分で育てる方式にし、稚拙であっても自分の子や孫に介護してもらえばよい。何故なら、そうすれば、「育て方が悪かったのは自分の責任だ」として諦めがつくからである。 そのようなわけで、⑭⑮の介護保険料負担については、65歳以上の第1号被保険者と40歳~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)に分けていたずらに複雑化させるのではなく、乳児まで含めた全世代を介護保険制度に加入させ、同じような基準で給付すると同時に、負担は所得に応じて行わせるべきだと、私は考えている(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf 参照)。 2)子育て政策に本当に必要な予算とバラマキ予算について 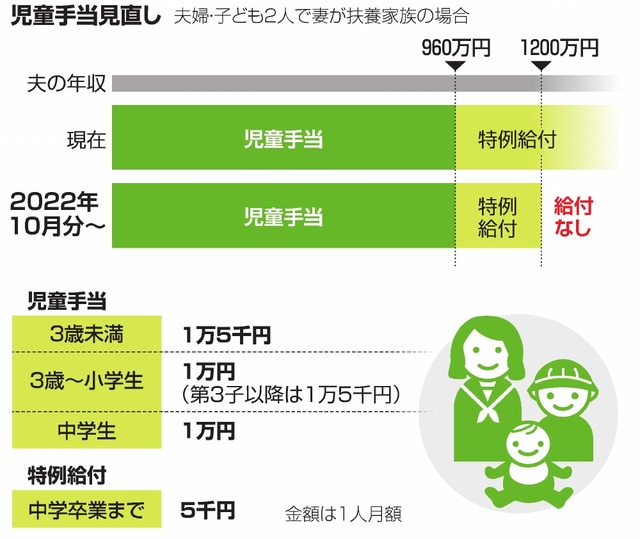 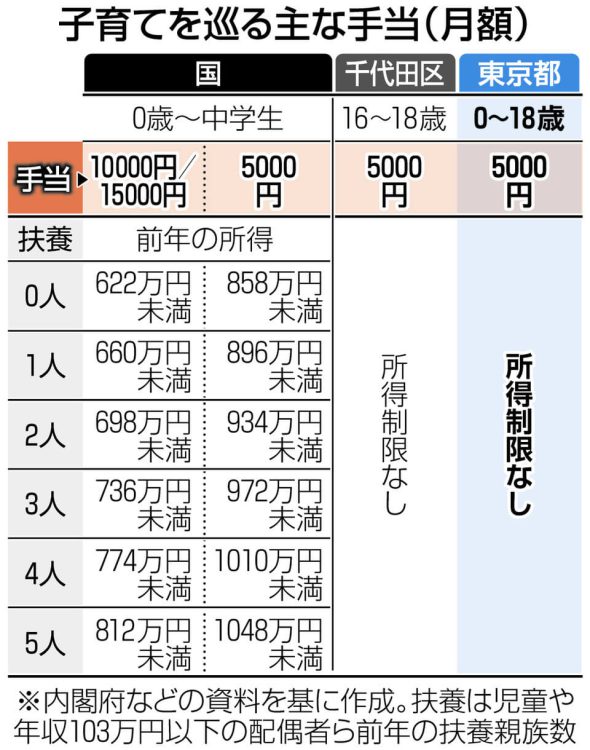 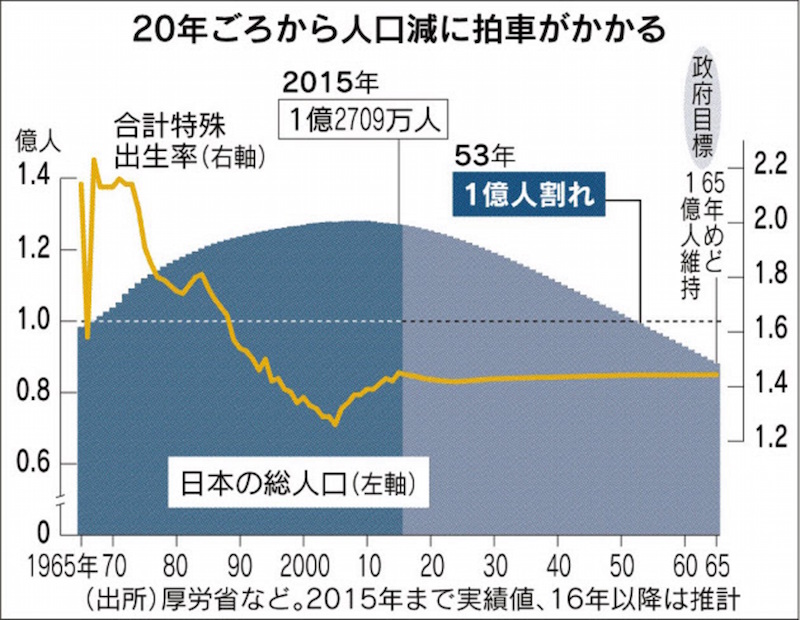 2021.5.21朝日新聞 2023.1.5東京新聞 2017.4.11Agora (図の説明:左図は、2022年10月から施行された児童手当で、3歳未満1.5万円・3~15歳1万円《3子以降1.5万円》を原則として支給し、年間所得960~1200万円の人には中学卒業まで5千円の特例給付を支給するが、年収がそれ以上の人には全く支給しないというものだ。これに対し、中央の図のように、千代田区は所得制限なく16~18歳の子に5千円支給しており、東京都は0~18歳の子に5千円支給しようとしている。が、合計特殊出生率が2以上でなければ人口を維持できないとする説は、右図のように、1980年代全般に合計特殊出生率が2以下になっても2010年代半ばまでの30年間は人口が増え続けており、科学的根拠がない。これは、寿命の延びにより、3世代以上が同時に生きられるようになったことによるものだ)  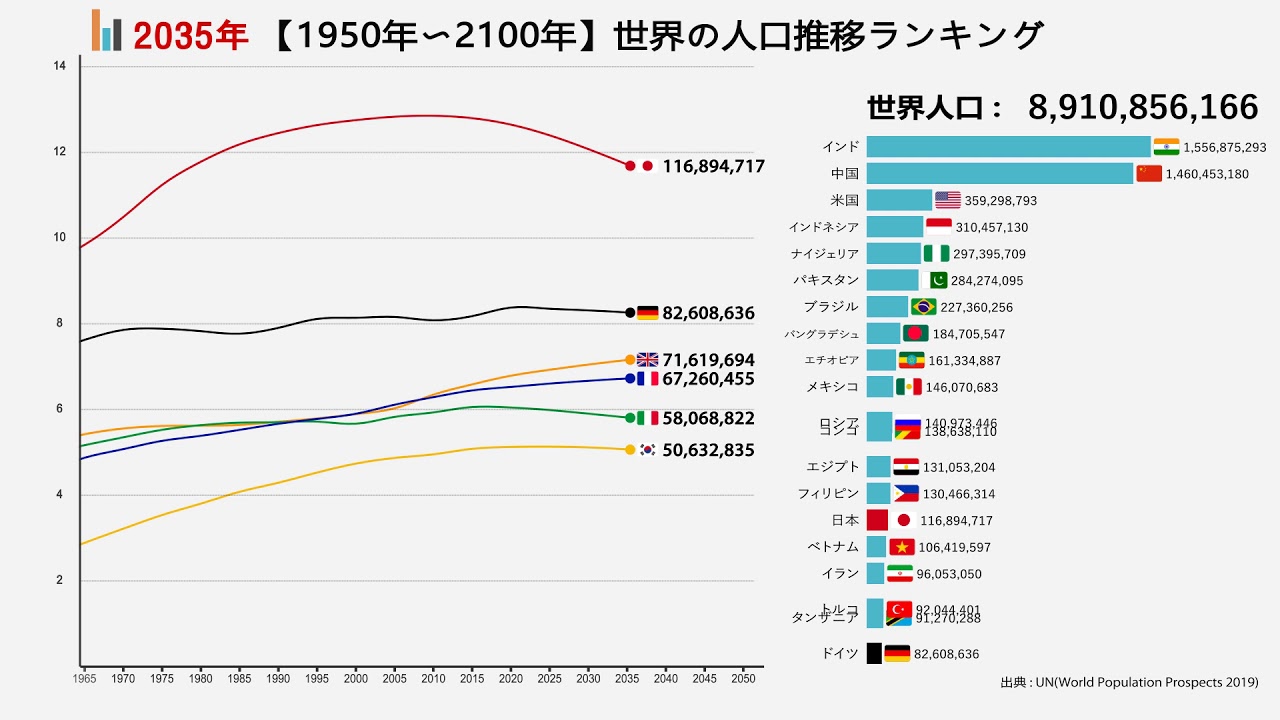 厚労省 UN (図の説明:「少子化で人口が減るから経済成長しない」という説もよく聞くが、右図のように、先進国で日本より人口が多いのは米国だけで、先進国で最も経済成長していないのが日本であるため、この説は間違っている。そして、このような非科学的な論理がまかり通って政策決定に影響を及ぼしていることが、むしろ経済の足を引っ張っているのである。また、左図のように、人口が次第に高齢化することは1980年代からわかっていたため、世界では1980年代から退職金は要支給額を正確に計算して積立方式に変更していたが、日本は未だに賦課課税方式をとって「支える人が減るから云々」などと言っているのであり、これは政治・行政の失敗にほかならない。さらに、人口が増える世代もあるため、その世代のマーケットは増えるに決まっている) イ)出産費用について 政府は、*5-1-2のように、子育て世帯の負担を軽減して少子化対策を強化するため、出産時の保険給付として子ども1人につき原則42万円が支払われる出産育児一時金を、2023年度から50万円程度に引き上げる方向で検討に入り、2023年度の増額分は、これまで一時金を支払ってきた健康保険組合などの保険者が負担するが、2024年度以降は75歳以上が加入する後期高齢者医療制度からも財源の7%程度を拠出してもらう方向だそうだ。 しかし、近年の出産は医師が関与して行うため、正常分娩も健康保険の対象にすればすむことであり、場合によっては介護も必要になる。そのため、育児休業給付などなく、育休中は無給なのに社会保険料だけは支払いながら、出産費用は満額自己負担してきた75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度から財源の7%程度を拠出してもらうというのは筋違いも甚だしい。こういうのを“異次元(≒これまで認められてこなかった不合理なことを” 何でもあり“で解禁すること)”と言うから、“異次元”と言う言葉は「やってはいけないこと」の代名詞になるのである。 ロ)児童手当について *5-1-6は、「岸田首相は、“異次元”の少子化対策」を進めるため、子ども家庭庁の小倉氏をトップに、厚労相、文科相、財務相、経産省らの閣僚と有識者が参加する省庁横断の会議を設置し、児童手当の拡充を中心に必要な対策を6月までに纏めるそうで、相変わらず財源確保には負担増の議論が避けられないと記載している。 しかし、①何故、少子化そのものに対する対策が必要なのか ②仮に必要だったとしても、それは児童手当を中心とした経済的支援なのか ③既に税金を払っているのに、子育て支援や教育支出もために、何故、新たな財源確保を要するのか ④これまでの政策を強化しただけの児童手当と消費税増税が、何故、骨太の方針と言えるのか は大いに疑問だ。 児童手当は、現在、上の段の左図のように、原則として0歳~中学生が対象で所得制限があるが、成年に達する18歳(高校卒業時)まで対象年齢を拡大することには、私は賛成だ。しかし、第2子・第3子だから第1子よりも金がかかるわけではないため、第2子以降に差をつけて増額するというのは「生めよ、増やせよ」論に繋がるため、不適切だと思う。なお、0.5~1.5万円/月で子を育てられるわけではないため、所得税にフランスのようなN分N乗方式も取り入れて選択可能にするというのなら、それは骨太の案と言えるだろう。 東京都は、*5-1-3のように、所得制限を設けず、18歳以下の子に月5千円給付し、第2子の保育料無償化も検討するそうだが、国の児童手当を補完はするものの、月5千円給付されたからといって、母の罰を受けて数千万円~数億円単位の生涯所得をふいにしてまで子を産みたいと思う人はあまりいないと思われる。 しかし、人間も遺伝する生物であるため、出産費用を50万円補助してもらったり、1.5万円/月の児童手当をもらったりするから子を産むという人の子よりも、所得制限によって児童手当をもらえない人や子を産んで母の罰を受ければ数千万円~数億円単位の生涯所得をふいにする人の子の方が次世代として有用であろう。そのため、少子化対策は子を産んでも母の罰を受けずにすむ体制にすることが最も重要で、児童手当等も恣意性がすぎるとバラマキや逆向きの出産奨励になるのである。 ハ)保育と学童保育について *5-1-6のように、岸田首相が省庁横断で設置する会議では、幼児教育や保育サービスの量と質の強化、子育てサービスの拡充、育児休業制度の強化なども検討する予定だそうだ。 子ども・子育て支援に関する日本の公的支出割合は1.79%で、OECD平均の2.34%を下回り、フランス3.6%の半分だそうだが、だからといって新たな財源を確保するというのは少子化対策を名目にした負担増である。何故なら、国民は既に多額の税金を支払っており、国は事業毎の費用対効果も不明のままにして無駄遣いの限りを尽くしており、最も重要な教育資金は他の大きな無駄遣いの数々を削って最初に予算にいれるべきだからである。 しかし、子育てする側から見れば、GDPが世界第2位の日本でGDPに対する公的支出割合を問題にして支出金額を増やす必要はなく、教育や保育の質の方がよほど重要なのだ。 そのような中、*5-1-4のように、共働き世帯の増加に伴うニーズの高まりに整備が追いつかず、学童保育の待機が未だ1.5万人おり、東京都の3,465人で最多で、質より前に量が足りていないなどというのは、少子化の最も大きな原因だろう。 なお、東京などの都市部では狭い家で家族がひしめき合って暮らしているが、これも子を産めない原因であるため、通勤時間30分以内の場所に、ゆとりのある住まいを持てる街づくりをすることも、子育ての重要な要件になる。 3)介護保険制度について  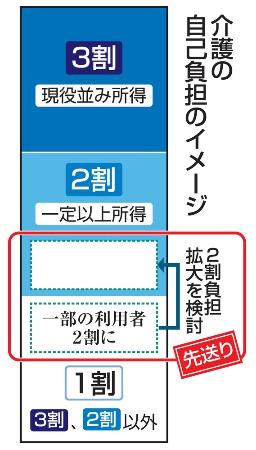   2022.12.15佐賀新聞 Homes 2022.12.14Diamond (図の説明:1番左の図のように、全世代型社会保障構築会議は、“全世代型社会保障”と称して高齢者の医療・介護保険料を増やし、左から2番目の図のように、一定の所得以上の利用者の負担を2割にするという報告をしたが、その“一定の所得”とは、生活保護並みの所得なのである。一方、右から2番目の図のように、介護は65歳以上の人と40~64歳の特定疾病患者のうち介護が必要になった人が受けられるが、介護保険料を支払っているのもこの世代だけであり、これこそ全世代型とは言えない。このような状況の中で、1番右の図のように、物価上昇と人手不足により、老人福祉・介護事業者の倒産が増えているのだ) イ)全世代型社会保障構築会議の報告について *5-2-1は、①現在の全世代型社会保障構築会議は社会保障の充実を議論している段階で財源論が後回し ②自営業者も現金給付のある育児休業があったほうがよく、フリーランスも報酬比例部分のある公的年金に加入できるようにすべき ③経済対策に盛り込まれた妊娠女性に10万円相当を配る出産準備金は恒久化が必要な給付充実策なのに恒久財源がないため、消費増税など税財源の議論も避けるべきでない ④財源論と同時に重要なのは高齢者の増加で給付が膨張する医療・介護の効率化 などと記載している。 確かに財源は考えておくべきなので、①②は事実だが、まず他のバラマキと同時に“少子化対策”と銘打ったバラマキもやめるべきであり、各省庁が既得権益を温存したまま国民負担の増加ばかりを考えているようなら、国民は誰も納得しないだろう。 なお、出産準備金を(小遣い程度の)10万円もらえるから妊娠するという女性は滅多にいないため、「医者にかかったら保険適用」とすればよいので、③は不要であり、このようなバラマキのために消費税を増税するなどとんでもない話だ。そして、④のように、高齢者と言えば「医療・介護給付が膨張するから効率化せよ」などと言うのは、高齢者を邪魔者扱いにしており、憲法違反だ。ただし、寿命の延びによって“高齢者”の健康状態も変わっているため、定年退職年齢も含めて高齢者の定義を75歳以上にする必要はあるだろう。 このような中、*5-2-2は、介護業界で倒産が急増し、その理由を、⑤人手不足とコロナ関連の資金繰り支援効果が薄れてきた ⑥物価上昇をサービス料金に転嫁しにくい ⑦将来有望とされた介護市場に事業者が相次いで進出して過当競争が起こった ⑧2009年度の介護報酬大幅プラス改定で倒産は減少に転じたが ⑨2015年以降のコスト上昇の中、介護報酬改定は低調だったので倒産が増えた ⑩2015年以降は介護補助者の高齢化と人手不足で人件費上昇が収益を圧迫 ⑪2020年は新型コロナ感染拡大が介護業界を直撃 ⑫2022年は円安・物価高で光熱費・燃料費・介護用品値上がり ⑬経済活動再開で人手不足が顕在化 ⑭介護業界では物価・人件費上昇・人手不足が同時に表面化 ⑮一般的介護サービスは介護保険で金額が決められており、仕入価格上昇分を販売価格に転嫁できない 等と記載している。 しかし、⑤⑦⑩⑬等に記載されている人手不足については、2001年に介護制度が始まって既に20年も経過しているので、未だに熟練者を中心とした組織的介護ができていないのであれば、淘汰され倒産しても仕方がないと思われる。そして、日本は、せっかく来てくれた(母国では看護師資格を持つような)若い外国人労働者でも、日本語の介護福祉士試験に合格しないという理由で帰国させているのだから、同情の余地がない。 また、⑥⑧⑨⑫⑭⑮の物価上昇や人件費高騰も政府の責任だが、確かにこれに連動して介護報酬が上がるわけではないため、物価上昇や人件費高騰によるコスト増を介護事業者が負担せざるを得ず、経営が厳しくなって倒産に至るのは理解できる。そのため、介護サービス料も物価スライドにしなければ、介護事業者はたまったものではないだろう。 さらに、ここで述べられていないことは、介護は保険内と保険外のサービスの併用が認められており、併用される自費部分を含めてサービス全体の消費税が非課税であるため、仕入れ税額控除もできず、支払った消費税を全て介護事業者がかぶることになり、消費税率が上がれば上がるほど介護事業者の負担が大きくなる点だ。これは、医療サービスも同じであり、これらを解決するには、医療・介護サービスを、非課税ではなく0税率にする必要があるのだ。 しかし、⑪のコロナ対応では、医療・介護システムのレベルの低さが表に出たようで、状況に応じて速やかに入院・訪問看護・訪問介護などに切り替えることができたり、周囲に感染させなかったり、死亡に至らせなかったりする仕組みになっていないことが露呈した。しかし、本当は医療との緊密な連携が必要であるため、(介護施設数が十分になった後に質の低い施設が淘汰されるのは仕方がないものの)国の不作為によって質を上げられないのでは、努力している医療・介護従事者に気の毒な上、高い保険料を支払っている国民も迷惑する。 このような中、*5-2-3・*5-2-4のように、政府は、「全世代型社会保障構築会議」で、介護保険で高齢者の負担を増やす案は結論を来夏に先送りし、報告書には75歳以上の中高所得者の医療保険料引き上げ・将来的な児童手当拡充だけを盛り込むそうだ。しかし、全世代型社会保障を構築するのであれば、介護保険料はすべての働く人が負担するのが当然であるにもかかわらず、75歳以上の大して所得が多いわけでもなく、要介護の状態に直面して生活が破綻しそうな75歳以上の“中高所得者”をターゲットにして保険料や負担率を引き上げようとしているところが、憲法違反なのである。 なお、企業が従業員をどこにでも転勤させ、親や祖父母の介護などできない状態にしておきながら、「現役世代の負担は限界に来ている」などと言っているのは、医療・介護制度の有難味がわかっておらず、勝手すぎる。 ロ)75歳以上の医療保険負担増について 政府の全世代型社会保障構築会議が報告書に、*5-3-1・*5-3-2のように、①給付が高齢者・負担が現役世代に偏る現状を是正するため、75歳以上の後期高齢者の保険料引き上げを明記して全体の約4割の後期高齢者を対象に所得比例部分の負担を増やす ②さらに75歳以上の高齢者に出産育児一時金財源の7%程度を新たに負担させる ③現役世代が負担する高齢者医療への支援金を減らす ④年金収入が153万円超(12.75万円超/月)の中所得者(!?)以上の保険料を増やす ⑤年収1千万円超の高所得者の保険料負担の年間上限額を66万円から80万円に引き上げる ⑥厚労省は少子化の克服や社会保障制度の持続性向上を掲げて、「全ての世代で負担しあうべきだ」とする ⑦高齢者人口は団塊の世代が25年までに全員75歳以上となった後に2040年頃から減少し始めるが、現役世代の減少で人口に占める割合は現在の30%程度から上昇が続く ⑧膨張する社会保障給付には負担能力に応じて全ての世代で公平に支え合う仕組みが必要になる と記載するそうだ。 生活保護でもらえる金額は、憲法25条の生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」によって定められた最低生活費で、現在、単身者なら10万円〜13万円/月、夫婦2人なら15万円〜18万円/月であり(https://efu-kei.co.jp/contents/public-assistance/ 参照)、受給が決まると「国民健康保険」を抜けて医療費全額が生活保護の「医療扶助」で現物支給されて無料になる。しかし、生活保護支給額や最低賃金も、物価スライドして上げなければ生きていけなくなるだろう。 そして、④の年金収入153万円超(12.75万円超/月)というのは、単身者の生活保護費程度であるにもかかわらず、高齢者の場合は中所得者として健康保険料を増やすというのだから、高齢者には憲法25条に基づく生存権を認めないということだ。 つまり、憲法25条は、⑥のように、これまでの政府の失政によって少子化が進んでいようと、社会保障制度の持続可能性が危うかろうと、制度が役割を果たせなければ生存できなくなるため、歳出改革を行い、他の無駄を削って、優先的に護るべき条文なのである。 また、⑦のように、高齢者人口が増えるのは、寿命の延びに従って定年年齢を伸ばさなかったからで、これは下の世代に地位を譲るために高齢者が退いているのにほかならない。そのため、定年年齢の廃止か75歳以上への延長をすれば、現役世代減少の問題は解決し、⑤⑧のように、負担能力に応じて公平に支え合うこともできるのである。 なお、①の「医療費の給付は高齢者に負担は現役世代に偏る」というのは、誰でも退職し高齢者になれば病気がちになるため不公平はない。それより、②の財源の7%程度を75歳以上の高齢者に負担させて出産育児一時金を支払う方が、世代間の不公平が大きい上に少子化防止効果は殆どない。従って、妊娠出産にかかる医療費を保険適用にする方が、よほど合理的なのである。 さらに③のように、現役世代が負担する高齢者医療への支援金を減らすなどと言うのなら、病気のリスクが低い時代に多額の保険料を支払う現役世代の医療保険は必ず黒字になるため、自分が支払ってきた医療保険に生涯加入し続ける仕組みにする方が、筋が通っている上に公平だ。 このような中、*5-3-3は、⑨政府が2022年12月23日に閣議決定した2023年度予算案で社会保障費は過去最大の36.9兆円 ⑩新型コロナ禍で手厚くした有事対応から抜けきれない ⑪コロナの医療提供体制のために17兆円の国費による支援が行われた ⑫最大40万円/日を上回る病床確保料は平時の診療収益の2倍から12倍 ⑬およそ13兆円を計上する年金は、23年度の支給額改定で給付を物価の伸びより抑制する「マクロ経済スライド」を3年ぶりに発動する 等を記載している。 このうち⑨は事実だろうが、⑩⑪については、治療薬やワクチン接種料を無料にする必要はなかったし、そもそも水際対策に不完全さが多く見受けられた。その上、コロナの流行により経済停止期間を長くし過ぎたため、大きな補助が必要となり、何十兆円にも上る無駄遣いがあった。それに加えて、流行期に間に合うように、国内で検査機器・治療薬・ワクチンの製造するなどの役に立つことは何もできなかったのが、大きな問題なのである。 しかし、⑫については、普段からゆとりを持って診療できる体制になっておらず、急に病床を作ってもそのケアをする人材はプレミアムを載せて募集しなければ集まらないため、普段からいざという時の受入体制の整備をしていなかったことが問題なのだ。 また、⑬については、上にも述べたとおり、ただでさえ生存権行使に届かない年金額なのに、「マクロ経済スライド」というもっともらしい名前をつけて、給付を物価の伸びより抑制しつつ、物価を上げる政策を採用し続けており、これは高齢者の生存権を無視した悪知恵である。 4)「マクロ経済スライド」と称する年金抑制策について 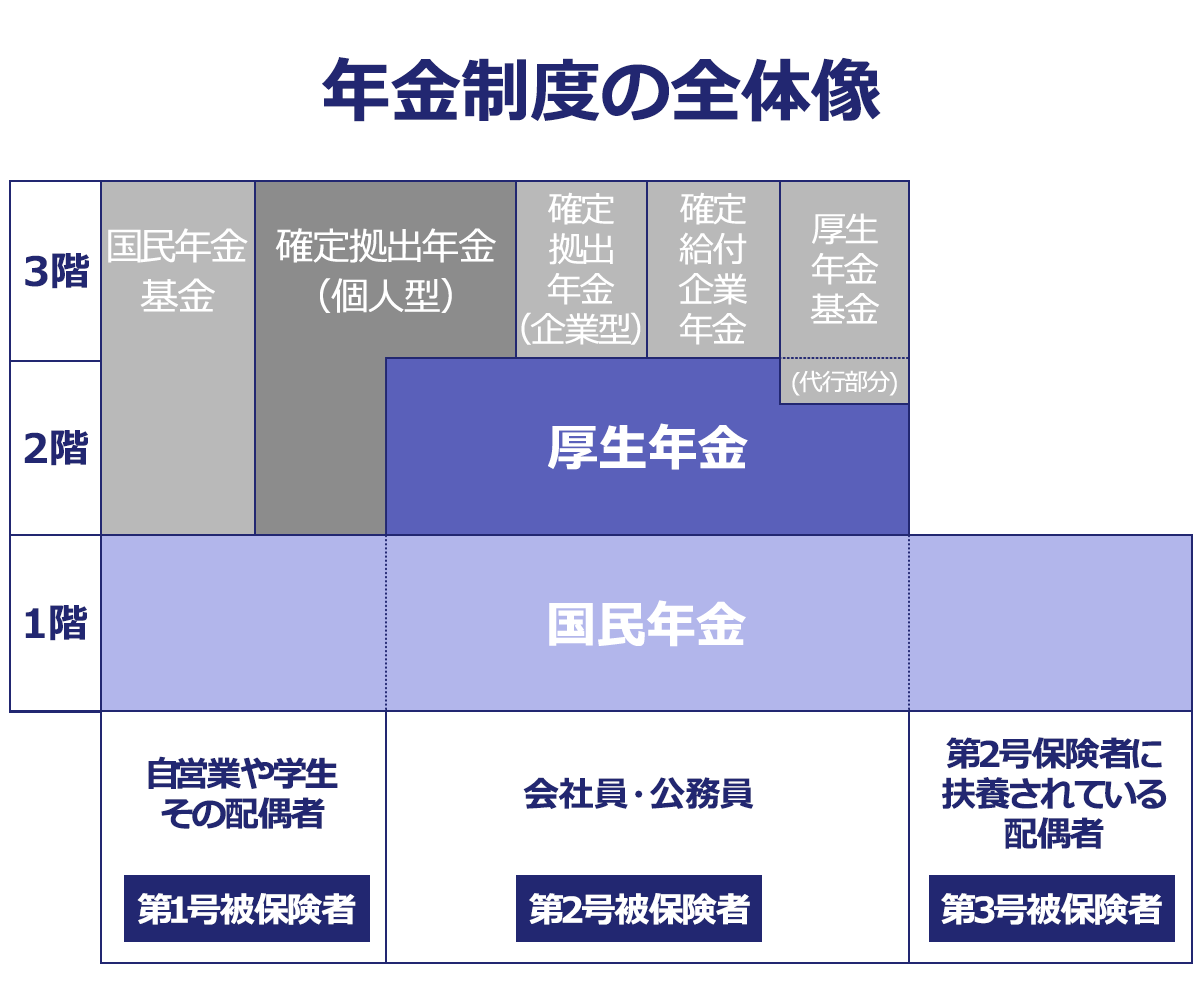 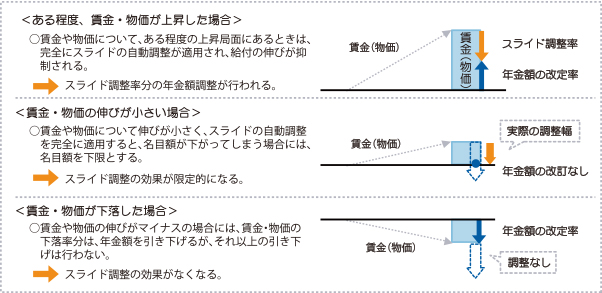  Hacks 厚労省 厚労省 (図の説明:日本の年金制度の全体像は、左図のように、自営業・学生・その配偶者が入る1号、従業員が入る2号、2号被保険者に扶養される配偶者が入る3号に分かれる。1階の国民年金は、1号被保険者は自分で保険料を毎月納付し、給付は全員が受ける。2階の厚生年金は、事業主が毎月の給与・賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて事業主負担分の保険料とあわせて毎月納付し、その従業員だった人が給付を受ける。3階の納付は任意で、納付した人だけが給付を受ける。中央と右の図は、「マクロ経済スライド」の仕組みとその効果で、賃金・物価の上昇よりも年金支給額の上昇を抑え、国民に気付かれないように実質年金額を下げる仕組みなのである。しかし、もともと低い所得代替率をさらに下げるため、高齢者の生活を成り立たなくさせるもので、これがあるため、年金は早くからもらって自分で運用した方がよいわけだ) イ)「マクロ経済スライド」による年金抑制のからくり 政府は、*5-4-1のように、2023年度の公的年金の支給額改定で、「マクロ経済スライド」を3年ぶりに発動する検討に入ったそうだ。 「マクロ経済スライド」とは、賃金・物価に応じた年金改定率から、現役被保険者の減少と平均余命の伸びに応じて算出した“スライド調整率”を差し引いて年金給付水準を下げる仕組みで、具体的には、将来の現役世代の最終的保険料の負担水準を定めて、その範囲内で年金給付支出を決めるというものだ。「マクロ経済スライド」は2014年の年金制度改正で導入され、それ以前は「物価スライド」といって年金額の実質価値を維持するために消費者物価指数の変動に応じて翌年4月から自動的に年金額が改定されていたため、恣意性の入る余地はなかった。 そして、このカラクリによって、2023年度の年金支給額は2022年度より僅かに増えるものの、“マクロ経済スライド”によって物価上昇より低く抑えられているため、年金支給額は実質的に目減りする。にもかかわらず、「給付抑制は年金財政の安定に欠かせない」などとして、少子高齢化等に正しく対応して来なかった失政のツケを国民に押し付け、上のように無駄遣いの限りを尽くしながら、年金制度は維持するが生活を維持できない制度にしてしまったことは、決して許すべきでない。 また、*5-4-2は、①年金、医療、介護等をあわせた社会保障関係費は36兆8,889億円で、2022年度当初予算と比べて6,000億円以上増加 ②2025年に団塊の世代が全員75歳以上となり、介護が必要な人の急増等による社会保障費の膨張は避けられず ③「マクロ経済スライド」により年金額は実質的に目減り ④高齢者の負担感が強まって景気回復に水を差す恐れ ⑤コロナ禍の雇用調整助成金支給で雇用保険財政が悪化し、雇用保険料率も2023年度から上がる と記載している。 しかし、①②③④⑤の年金、医療、介護等をあわせた社会保障関係費の増加は、人口構成を見ればずっと前からわかっていたことで、その世代の人口が増えるからニーズも増えるのである。そのため、そのニーズに応えるサービスや技術を開発していれば、それは世界で通用したのに、政治・行政にはこの発想が乏しく、国民を犠牲にしながら景気対策等々と称して無駄遣いをすることしか思いつかなかったために、こういう羽目に陥ったのである。 ロ)物価上昇政策について *5-4-3は、①総務省が2022年12月23日発表した11月の消費者物価指数が103.8となり、前年同月比で3.7%上昇(生鮮食品を除く)して政府・日銀が定める2%の物価目標を上回る物価高が続く ②生鮮を除く食料は6.8%、食料全体は6.9%上昇し ③エネルギー関連は13.3%上昇して ④物価は第2次石油危機の1981年12月の4.0%以来40年11カ月ぶりの伸び率で消費税導入時や増税時を上回る ⑤円安・資源高の影響で食料品・エネルギーなどの生活に欠かせない品目が値上がりした などと記載している。 物価上昇は、購買力平価を落として国民を貧しくさせるものであるため、①のように、政府・日銀が2%の物価目標を定めるなどということ自体が、日銀の役割を放棄して密かに国民生活の質を落としているものである。そのため、それを上回る物価高が続くのを「物価が伸びた」などと褒めるような表現をするのは、経済の知識がないだけでなく国語力や常識もない。もちろん、中央銀行の役割もわかっていない。 さらに、②③⑤のように、食料6.9%、エネルギー関連13.3%上昇というのは、そもそも食料・エネルギーは生活必需品であるため、生活の苦しい人ほど購入割合が高く、耐久消費財は最初に節約できるものであるため、生鮮食品を除いた物価上昇が3.7%というのは、生活実感からはかけ離れており、意味がない。それでも④のように、第2次石油危機の1981年12月の4.0%以来40年11カ月ぶりの“伸び率”などと言っている点が、何も考えられないのか神経がおかしいかのどちらかなのである。 5)外国人の活用について このように、少子化による生産年齢人口の減少を理由に、高齢者への給付減・負担増を行いながら、失業防止を目的とした景気対策は巨大で、女性や高齢者を十分に活用しない制度を採用している矛盾だらけの国が、日本である。 さらに、多様性と活力の源である外国人労働者についても、*5-6-1のように、技能実習制度を温存したままで、「開発途上国の人材育成が目的」と称しながらも、実際には人権侵害に当たるような労働環境で安価に人手を確保する手段として技能実習生を使っているため、労働条件の悪い技能実習制度の存廃を含めて有識者会議による検討が始まったのはよいことだ。 そもそも日本人は、自分もアジア人で有色人種なのに、有色人種を差別したがる人が多い。そのため、日本と開発途上国の賃金格差が小さくなり、外国人労働者への処遇改善が行われなければ、*5-6-2のように、政府が入管難民法を改正して「特定技能」という新たな在留資格を設け、移民受け入れにかじを切っても、外国人労働者に「選ばれる国」にはならないだろう。 しかし、*5-6-5の草加商議所のように、ミャンマー出身者を中心とする「第三国定住難民」の就労を支援し、難民12人を草加市を中心とする事業所で雇用することを決め、社会貢献と同時に地域の中小事業者の人材不足の緩和にも繋げたのは、双方にとってよいことである。地方自治体も、日本語・日本文化・社会制度等に関する講習の手配、住居の確保、安定した収入による生活基盤の構築などを支援する必要はあるが、それ以上の効果があると思う。 *5-6-3は、①高校で外国人受け入れ枠の導入が進まず ②2023年の入試で全国の公立高の73%が特別枠を設けず ③日本語が得意でない生徒にとって一般入試は容易でないため、中学卒業後10%が進学せず、これは全中学生の10倍である ④文科省は自立には「高校教育が重要」と指摘している ⑤外国人労働者の受け入れが拡大しており、子どもが進学しやすい環境を整える必要があり ⑥特別枠設定や試験教科の軽減などを各地の教育委員会に求めたが、必要性が認識されず指導体制の不安もあって対応しない教委や学校が多い と記載している。 ④のように、文科省も自立には「高校教育が重要」と指摘しているのだから、米国と同じように日本も高校まで義務教育とし、入試をしても最終的にはどこかの高校に入学できるようにした方がよいと考える。その上、外国人労働者の子どもは、母国との懸け橋になったり、グローバル人材に育ったりする可能性が高いため、日本語が苦手でも進学できる公立高が近くに一つでもあればよいと思われる。 このような中、*5-6-4のように、外国人の収容ルールを見直す入管難民法改正案が、1月23日召集の通常国会に提出される見通しとなったが、その内容は、⑥難民申請中の送還を可能にし ⑦収容期間の上限は現行通り設定せず ⑧収容に関する司法審査がなく ⑨21年に国会で審議入りした入管難民法改正案の骨格が維持される そうだ。 しかし、日本は難民認定割合が著しく少なく、収容されている外国人を人間扱いせず、入管難民法改正案では、難民申請を原則2回までに制限して、送還を拒否して暴れると懲役1年以下の罰則を課すなど、日本人の私から見ても難民になった人の立場を考えておらず、開発途上国出身者や有色人種への差別が甚だしく、外国人に対して著しい人権侵害を行っているのである。 6)日本の一人当たりGDPと雇用システムについて 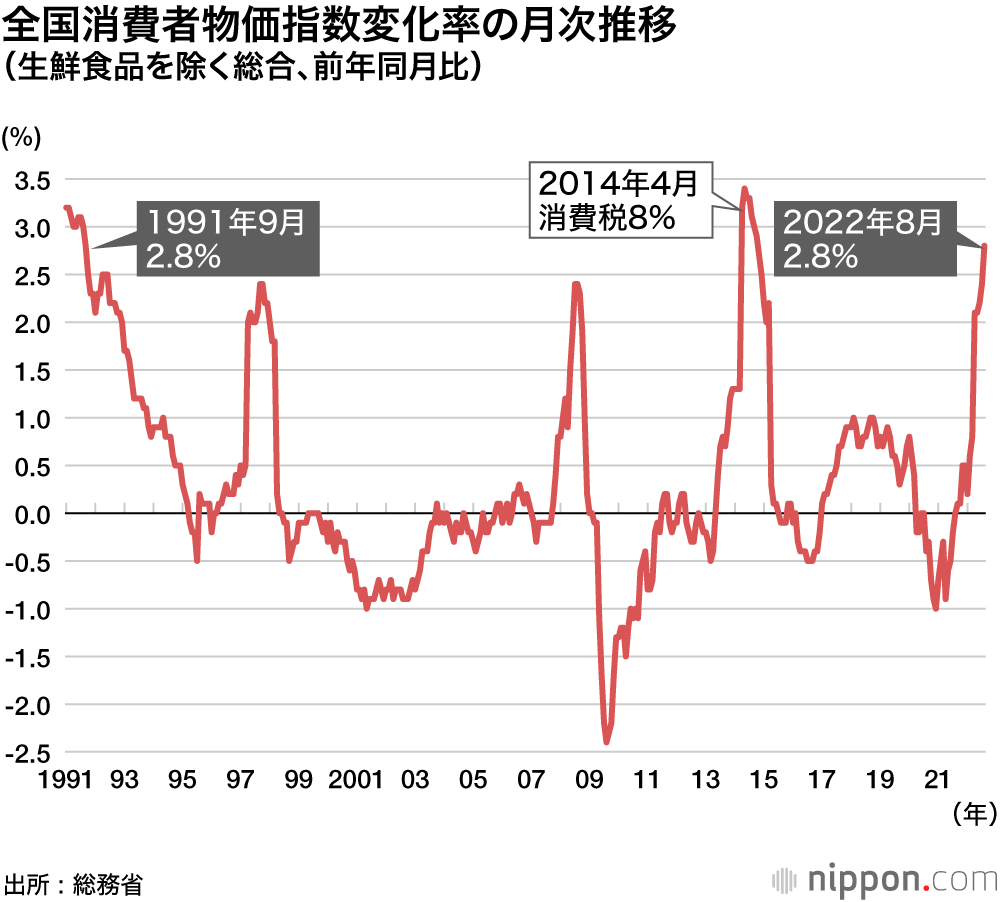 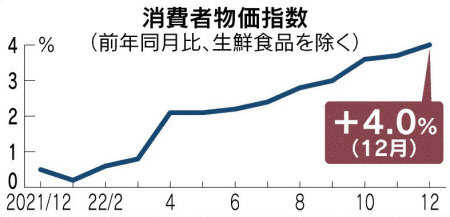 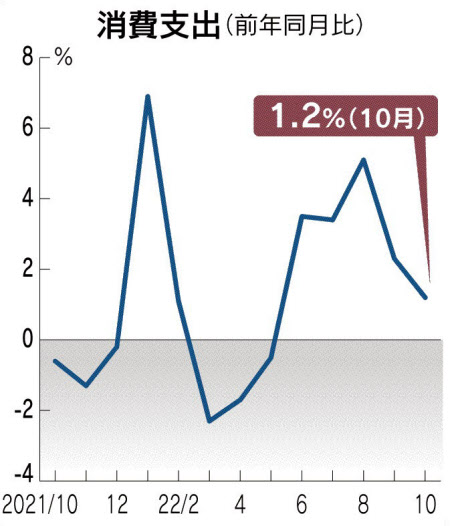 2022.9.20JapanData 2023.1.21日経新聞 2022.12日経新聞 (図の説明:左と中央の図のように、消費者物価指数は、ロシアのウクライナ侵攻後の制裁に対する逆制裁によって急激に上がり始め、右図のように、消費支出は、コロナで一旦は下がっていたものの、物価上昇による豊かさなき値上がりによって、また上がらざるを得ないだろう)  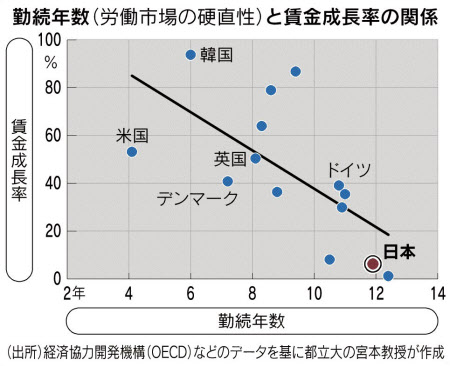 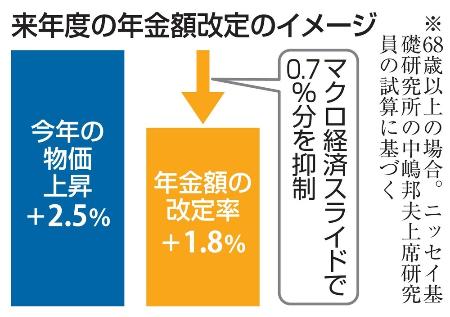 2022.12.6日経新聞 2023.1.18日経新聞 2023.1.21佐賀新聞 (図の説明:左図のように、賃金上昇が物価上昇に追いつかないため、賃金は実質マイナスが続いている。また、中央の図のように、平均勤続年数が長い日本は、生産性の高い部門へのスムーズな労働移動が起こらないため、平均賃金の伸びが小さいという結果が出ている。年金も少子高齢化を理由とした「マクロ経済スライド」と称する抑制システムにより物価上昇よりも低く抑えられるので、国民の可処分所得《≒購買力》は下がる一方なのだ) 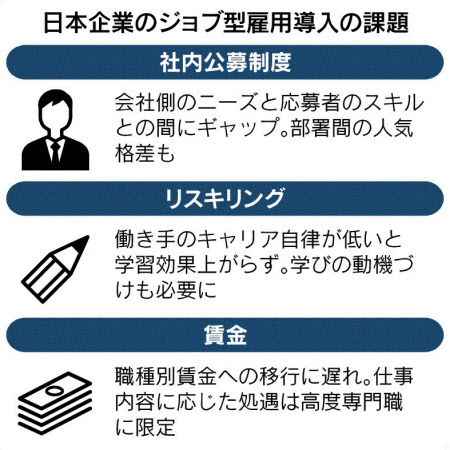 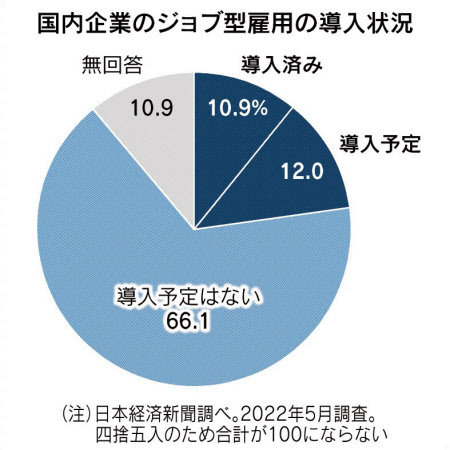 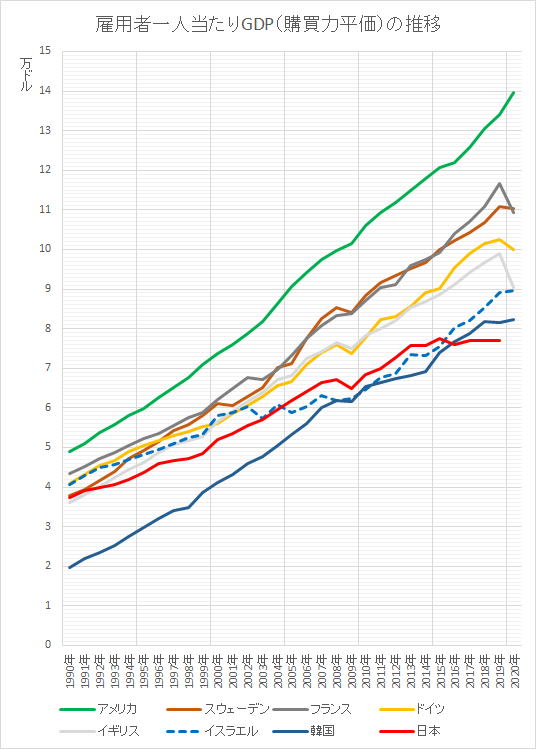 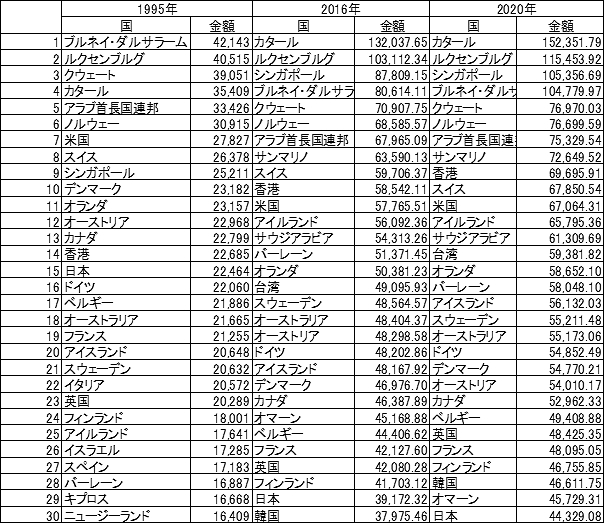 2023.1.5日経新聞 2023.1.5日経新聞 2021.7.4小野研究室 2016.5.25ITI (図の説明:賃金が上がるには被用者個人も生産性を上げて賃金に見合った働きをする必要があるが、それができるためには、社内のあちこちを移動して永遠に素人でいるのではなく、あるジョブに関しては精通していかなければならない。そのためには、左図のように、ジョブを定義し、それをこなすためのリスキリングを行い、雇用者はジョブの熟練度に見合った賃金を支払う必要があるのだが、終身雇用や年功序列型賃金を採用している場合はこれが難しい。そのため、左から2番目の図のように、日本はジョブ型雇用を導入する企業が少なく、その結果、生産性の高い部門への労働移動も行われにくく、右から2番目の図のように、労働者1人当たりGDP《購買力平価による》が低くなっている。また、1番右の図のように、購買力平価による労働者1人当たりのGDPは、1995年は世界で15位だったが、現在では30位まで落ちている) イ)1人あたりGDPについて まず説明しておかなければならないのは、名目・実質・購買力平価換算のGDPと国全体・国民1人当たりのGDPの違いである。 名目GDPとは貨幣価値とは関係なく単純に貨幣で表したGDPで、現在の日本のように、貨幣価値を下げれば物の値段が上がるため、それを総合計した名目GDPは上がる。また、実質GDPとは、一定の基準日を設けて物価水準を測定し、名目を物価水準で割ったものであるため、国内の物価水準の変動には影響されないGDPである。購買力平価換算は、どのくらいのものが買えるかを考慮したもので、物価の安い国は同じ金額で多くのものを買えるため、購買力平価換算のGDPは高くなる。 また、そもそもGDPとは「Gross Domestic Product (国内総生産)」のことで、1年間等の一定期間内に国内で産出された付加価値の総額である。また、国民1人当たりGDPとは、GDP総額をその国の人口で割った数字であるため、購買力平価換算の国民1人当たりGDPが、その国の国民がどのくらい豊かに暮らしているかを最もよく表している。名目GDP総額は、1人1人は貧しい暮らしをしていても、人口が多かったり物価が高かったりすれば高くなるため、国民は名目GDPの高さと1人1人の生活の豊かさを混同してはならないのだ。 このような中、*5-5-1のように、内閣府は12月23日に発表した国民経済計算年次推計で、日本は1人あたり名目国内総生産(GDP)が2021年に3万9803ドルで、OECD加盟国38カ国中20位だったとしたそうだが、本当の豊かさの指標は、1人あたり名目国内総生産(GDP)ではなく、国民がどれだけのものを買えるかを示す購買力平価による1人あたりGDPで、これは上の図の3段目の一番右のように30位である。つまり、日本は、物価が高くて1人1人の国民は豊かでない国なのだ。 *5-5-1によると、名目GDP総額は2021年に5兆37億ドルと米中に次いで世界3位を維持しているそうだが、GDP総額は人口が多ければ多くなるため、1人1人の国民の豊かさの指標にはならない。 それでも、1人あたり名目GDPが2005年には13位だったが、2021年は20位と中長期で下落傾向にあり、世界のGDPに占める比率も2005年には10.1%だったが16年間で半分の5.2%まで下がった。これは、他国は普通に努力していたが、日本は逆のことを多くやってきたからだ。 このような中、*5-5-5のように、2022年12月の消費者物価上昇率は生鮮食品を除く総合で前年同月比4.0%と41年ぶりの上昇、食料全体では7.0%・生鮮を除くと7.4%と46年4カ月ぶりの物価上昇で、その原因は、資源高と円安でエネルギー価格が上がって身近な商品に値上げが広がったからだそうだ。しかし、これは前年同月比であるため、5年前と比べれば体感で消費者物価は20%以上上がっている。 にもかかわらず、リーダーと称するおじさんたちは、「価格転嫁せよ」「脱デフレして物価が上がれば賃金も上がる」などと馬鹿なことを並べているが、賃金や年金は物価上昇に追いつかないため、実質や購買力平価で比べればデフレ時代の方が国民は豊かだったのである。 そして、ここでも「電気代などエネルギー関連が15.2%伸びた」などとコストプッシュインフレがまるでよいことであるかのように記載しているが、これは再エネを全力で伸ばしてエネルギーの自給率を上げることをせず、ロシアから逆制裁を受けて海外への化石燃料代金の支払いが増えたからにほかならない。そのため、国民を豊かにするどころか貧しくしたに過ぎず、威張るようなシロモノではないのだ。 その上、*5-5-6のように、東電等が3~4割の一般家庭向け規制料金値上げを経産省に申請し、今夏までの料金引き上げを目指すそうだが、経産省の審議会で妥当性が議論されたとしても、地域独占に近い状態で経産省が中に入れば、公正競争とは程遠い結果になることは明らかだ。むしろ、燃料費調整制度による燃料調達コストの上乗せより前に、再エネを負担扱いしてその普及を阻害してきた再エネ賦課金をやめるべきである。 なお、金融緩和して物価が上がれば(これをデフレ脱却と呼んだ)、賃金が上がると今でも言っている人が多いが、物価が上がれば仕入れ価格が上がり、売上価格は可処分所得の減少でむしろ減るため、企業の利益は減る。そのため、賃金を上げる余裕などない会社が殆どであろう。 さらに、国民の可処分所得減少分は、賃金の停滞だけでなく、*5-5-7のような少子高齢化を名目とした「マクロ経済スライド」と称する年金の実質減額によっても起こっている。そのため、国民の殆どが可処分所得減額になっており、その上、物価上昇は、貸付金・預金と同時に借入金・国債の実質価値も減額させるため、国会を通さず国民から企業や国に所得移転を行っているのと同じ効果があるのだ。 そして、行政は無謬性を堅持するため故意にこれを行っており、ずる賢いのだが、そのカラクリを暴いて批判することもできず、空気を読んでみんなで同じことを言っている経済学者やメディアは、故意であれ過失であれ、国民から見れば知性のない役立たずである。 ロ)日本の雇用システム 日本の雇用システムの特徴は、終身雇用(正規雇用従業員を定年まで雇用する制度)と年功序列型賃金(年齢・勤続年数を考慮して賃金や役職を決定)で、その目的は、長期的に人材を育成し、熟練した従業員を囲い込むことである。これは、1つの企業が右肩上がりで成長しながら規模を拡大する時代に合った制度で、正規雇用従業員は、終身雇用と年功序列型賃金によって定年まで安定した雇用と収入を得られるメリットがあった。 しかし、これまでも、一部の正規雇用従業員の終身雇用と年功序列型賃金を護るために、非正規雇用という雇用の調整弁を作ったり、大多数の女性に終身雇用や年功序列型賃金を与えない仕組みを取り入れたりしていたのである。 そして、現在は、1つの事業が右肩上がりで成長しながら規模拡大し続ける時代ではないため、*5-5-4のように、経団連が成長産業への労働力の移動を加速することを新たな柱の一つに据え、優秀な人材の獲得競争によって中長期的な賃上水準の向上に繋げようとしている。 東京都立大の宮本教授の分析では、上の2段目中央の図のように、雇用の流動性が高いほど賃金の伸びが大きく、主要国の賃金の1990年~2021年の上昇率を比較すると、平均勤続年数約4年の米国は日本の9倍、8年の英国は8倍、12年の日本は約6%であり、「日本の労働市場は硬直的であるため、成長産業に人材が移りやすくすることで労働生産性を高めて賃金が増えるという流れを作らなければならない」とされている。 ただ、私は、労働者にとっては、平均勤続年数が短ければ雇用が不安定でリスクの高い状態であるため、働いている期間に多い賃金をもらわなければ合わない、つまり、変動(ボラティリティー)が多ければ儲けは大きくなければ選ばれないというハイリスク・ハイリターンの論理も加わっていると考える。 なお、経済界も構造的賃上げを重視し、経団連は「働き手がスキルを身につけて転職することを肯定的に捉える意識改革が必要だ」と提起して、学び直しの時間を確保しやすい時短勤務や選択的週休3日制、長期休暇「サバティカル制度」の整備といった選択肢を挙げているそうだ。 しかし、他社に転職して不利益なく勤務できるためには、終身雇用と年功序列型賃金ではない雇用システムが必要不可欠である。そして、それは、*5-5-3のように、あらかじめ仕事の内容を定めたジョブ型雇用とジョブの職責に対応した賃金制度であり、これならそのジョブに関する専門性を高める意欲を持つこともできる。欧米ではこちらが普通であり、その円滑な運用のためにジョブ遂行能力を公正に評価する制度もあるため、先入観によって転職した人や女性・外国人・高齢者などを冷遇することも減るのだ。さらに、育児期に休職や退職した女性が、必要以上の不利益を蒙らずに仕事に戻ることも容易になる。 ハ)あるべき社会保障改革は・・ 小塩一橋大学教授は、*5-5-2のように、①改革が必要な最大の要因は経済社会の支え手減少で生産・消費のバランスが国全体で崩れる高齢化圧力だが、実際には65歳以上の高齢層の貢献で支え手は増えている ②社会保障改革は支え手を増やせば問題解決する ③しかし、主役は正規雇用者ではなく非正規雇用者やフリーランス・個人事業主で、支え手が増えても質は割り引く必要 ④社会保険料を通じた社会保障財源への還元も限定的 ⑤被用者保険の適用範囲拡大だけでは問題解決せず、国民健康保険や国民年金といった被用者以外の社会保険の仕組みも改める必要 ⑥在職老齢年金制度のように年金が就業の抑制要因にならない改革も必要 ⑦限られた財源をできるだけ公平で効率的に使うには、年齢とは関係なく負担能力に応じて負担を求め、給付も発生したリスクへの必要性に応じたものにする方針が基本 と述べておられる。 女性・外国人労働者・65歳以上でも働ける人など、これまで働けても支え手としてカウントせず、働いても正規雇用にしなかった人は多く、“生産年齢人口”にあたる日本人男性にも景気対策と称して雇用維持対策を図らなければならなかったのが日本の状態であるため、私も①②③④⑤に賛成だ。 つまり、“生産年齢人口”にあたる日本人男性でなくても、日本で正規雇用として働き、収入を得て社会保険料を納めれば、何の遜色もなく支え手になる。しかし、それには⑥の在職老齢年金制度のように年金抑制が就業抑制の原因にならない改革も必要で、さらに、⑦については、負担の公平性だけでなく、待遇の公平性・公正性によって気持ちよく働ける環境づくりも重要だ。 しかし、「将来世代に迷惑をかけない」などと称して、暮らせないほど少ない年金に「マクロ経済スライド」を適用したり、収入の割に高すぎる介護保険料をさらに引き上げたりするのは、廃墟だった日本を建て直してここまでにしたにもかかわらず、感謝されることもなく食うや食わずの生活を強いられている働けない高齢者にさらなる犠牲を強いるものである。そのため、これは憲法25条違反であることはもちろん、人間としての思いやりのなさを感じるものだ。 そのため、私は、高齢者をATMくらいにしか考えていない自分中心の日本人将来世代よりも、苦労して頑張っているため思いやりとファイトのある外国人難民を支援した方が、よほど役に立つと思うわけである。 (6)子育て予算の「倍増」について ← 予算は規模より内容が重要 政府の全世代型社会保障構築会議が、*5-1-5のように、子育て予算を倍増させる道筋も来夏に示すと記した論点整理案を示し、その内容は、①時短勤務で賃金が減る状況の経済的支援のため、賃金の一定割合を雇用保険から拠出して現金給付 ②フリーランス・ギグワーカー・自営業者向けの子育て支援 などだそうだ。 しかし、年金・医療など他の社会保険から拠出して、育児期の時短勤務で賃金が減るのを補填するなどというのは保険料支払者に対する詐欺行為であるため、日本の保険制度の信頼は失墜するだろう。そのため、雇用に関することは、雇用保険料の徴収範囲を広げるか、料率を上げるか、時短勤務すれば賃金が減るのは必然なので補填を止めるかすべきだ。何故なら、世界の人口は爆発寸前で、日本のエネルギー・食糧自給率は低迷しているのに、そこまでして日本人の出生率を上げる必要はないからだ。 また、*5-1-5は、③医療改革を優先する影響で介護保険の議論は停滞気味 ④負担増を想起させる項目は軒並み削られた ⑤介護費は40兆円台半ばの医療費に比べて今は4分の1程度だが伸びが大きい ⑥早期に給付と負担の見直しに着手すべきだが改革機運が乏しい ⑦年金制度の持続性を高めるため避けて通れないマクロ経済スライドの物価下落時での発動など負担増につながるテーマに触れなかった ⑧社会保障給付費財源は6割弱を保険料、4割を消費税などの公費で賄っているが、その一部は国債を充てている ⑨消費税率の引き上げ時に使い道を拡大して子育て支援にも使えるようにしたが、消費税収は地方分を除く全額を社会保障に充てても賄いきれない状況 などと記載している。 ③⑤⑥ように、介護費の伸びが大きいのは、介護サービスが実需で、介護サービスを要する世代が増加しているため当然であるにもかかわらず、新しいサービスはまるで無駄遣いであるかのように言いたて、その成長を阻むところが日本の経済成長を阻む理由なのである。これは、EV・太陽光発電・癌の免疫療法等も同じであり、無知にも程があるのだ。 また、④のように負担増を言うのなら、全世代型社会保障であるため、働く人全員で収入に応じて介護保険料を支払い、サービスも受けられるようにするのが当然である。祖父母や親を社会的介護に任せられるのは、若い世代も利益を享受しているため、それが嫌なら介護保険制度を止めるしかなかろう。 このような中、⑦の「マクロ経済スライド」は速やかに廃止すべきだ。何故なら、高齢者に有り余る年金給付をしているのではなく、年金保険料を支払ってきた契約に基づいて、生活するのにぎりぎりの金額を支給しているにすぎないからだ。そして、年金保険料を支払わなくてよかった人や目的外支出が多かったため、積立金が不足しているのであるから、政策ミスについては政府が責任をとるしかあるまい。 ⑧⑨の消費税については、貧しい者ほど負担の重い逆進税であるため、私はもともと反対だ。それよりも、歳出の無駄をなくす組み換えをしたり、税外収入を増やしたりして必要な費用を捻出するのが当然であり、(鬼と言われるかもしれないが)私ならできるから言っているのだ。 *5-3-5は、⑩政府は、「『こどもファースト』の経済社会を作り上げ、出生率を反転させなければならない」と少子化への危機感を強調した ⑪子供政策は「最も有効な未来への投資」 ⑫「新しい資本主義」の柱の「成長と分配の好循環」実現へカギを握るのが賃上げ と記載している。 しかし、⑩のように、「子どもファースト」「子どもファースト」と言っていると、自分中心の子どもに育って、⑪のような「未来への投資」にならない。また、家庭は皆が大切にされるべき場所であるにもかかわらず、「子のためには他の人(特に母親)を犠牲にしてもよい」などという発想を続けていれば、それこそ少子化の重要な原因になる。何故なら、子のために本当に犠牲になりたい人はいないからである。 また、⑫の「成長と分配の好循環実現へのカギを握るのが賃上げ」というのも、“生産年齢人口”に対して稼ぎ以上の賃金を支払っていれば、企業始め国の借金も増えるため、教育に徹底して力を入れ、稼げる人材を輩出して、イノベーションを支援するのが、「未来への投資」になるのだ。 ・・参考資料・・ <防衛費の財源> *1-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221215&ng=DGKKZO66844270V11C22A2MM8000 (日経新聞 2022.12.15) 防衛費増額、3税財源に、法人・所得・たばこ税 自民税調幹部会が素案 自民党税制調査会の幹部会は14日、防衛費増額の財源として法人税、所得税の一部の東日本大震災の復興特別所得税、たばこ税の3つを軸とする素案を示した。政府は復興所得税の期限を2037年から14年間延長する案をまとめた。この一部を防衛にあてる目的税にする案が出ている。党内には反発もあり、週内にまとめる与党税制改正大綱に具体的な税率や実施時期を明記できるかが焦点となる。政府は今後5年間の防衛費を43兆円程度とする方針だ。うち40.5兆円を毎年度の当初予算で手当てする。22年度当初の5.2兆円の5年分(25.9兆円)から14.6兆円程度の上積みとなる。歳出改革や決算剰余金の活用、税外収入などをためておく「防衛力強化資金(仮称)」で計11.1兆円を確保する。残り3.5兆円程度は増税で確保する必要がある。27年度単年でみると防衛費は現状から4兆円ほど増える。このうち1兆円強を増税でまかなう。幹部会が14日に示した素案で法人税、復興特別所得税、たばこ税で1兆円強を確保すると盛り込んだ。24年度以降に段階的に増税する方針。法人税で7000億~8000億円、復興所得税とたばこ税で約2000億円ずつ集める案がある。宮沢洋一税調会長は会合後、記者団に「役員から賛成を得た」と話した。具体的な税率や実施時期は決まっていない。法人税は本来の税率を変えず特例措置を上乗せする「付加税」方式をとる。湾岸戦争の多国籍軍支援や震災復興の財源確保でこの手法を使った。素案には「所得1000万円相当の税額控除を設ける」と明記した。中小企業の9割は増税の対象から外れる見通しだ。復興所得税は37年までの25年間の期限を延長しつつ歳入の一部を防衛財源に振り向ける。宮沢氏は振り向け分について「当分の間、防衛費のための特別な目的税にする」と説明した。復興所得税は所得税額に2.1%をかけている。22年度に4624億円の税収を見込んでおり2000億円なら1%程度に相当する。政府がまとめた14年間の延長案を今後議論する。税率は据え置き、個人の負担感が増えないようにする。1年当たりの負担は変わらないが、実施期間の長期化で実質的には増税となる。素案はたばこ税の活用で「国産葉たばこ農家への影響に十分配慮する」と言及した。党内にはたばこ増税に反対する声があり、段階的に増税する。1本あたり3円上乗せする案がある。政府はこうした増税案とは別に、自衛隊の施設整備に向けて建設国債の発行も検討する。財務省は自衛隊施設は有事に損壊する恐れがある「消耗品」とみて建設国債の適用を認めてこなかった。与党内で発行を認めるべきだとの声が出ていた。政府や自民党内では増税を掲げる岸田文雄首相に対する反発が続く。閣内では高市早苗経済安全保障相や西村康稔経済産業相が賃上げへの影響などを念頭に慎重論を唱える。自民党内でも安倍派を中心に増税自体に反対する声が相次いでいる。 *1-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221217&ng=DGKKZO66931760X11C22A2MM8000 (日経新聞 2022.12.17) 防衛増税「24年以降」 税制大綱、規模も明示できず 自民、公明両党は16日に決めた2023年度与党税制改正大綱に、防衛費増額に向けた増税方針を盛り込んだ。法人、所得、たばこの3税で27年度に「1兆円強を確保する」と明記した。導入時期などの具体的な議論は23年に持ち越した。法人税は本来の税率を変えず、納税額に特例分を足す「付加税」方式をとる。税額から500万円を引いた金額の4~4.5%を上乗せする。財務省によると、現在29.74%の実効税率が30.64~30.75%に上がる。中小企業の場合、税額500万円(課税所得2400万円相当)以下は増税にならず、大半が対象外となる。岸田文雄首相は同日の記者会見で「対象となるのは全法人の6%弱だ」と述べた。所得税は税率1%の新たな付加税を設ける。いま2.1%の東日本大震災の復興特別所得税を1%引き下げ、合計の税率を2.1%に保つ。新たな付加税の期間は「当分の間」、復興所得税の延長幅は「復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さ」とした。たばこ税は1本あたり3円相当の増税とし、段階的に引き上げる。3税とも増税のタイミングは「24年以降の適切な時期」との表現にとどめた。税目ごとの税収規模も示さなかった。23年の与党の議論は通常は11~12月の税制調査会より早まる可能性がある。自民党税調の宮沢洋一会長は記者会見で「途中段階で(24年度改正とは)切り離すという考え方もある」と述べた。政府は23年度から5年間の防衛費を43兆円とする方針だ。27年度は現状から4兆円弱の上積みが必要となる。2.6兆円強は歳出改革や税外収入などで捻出する。残り1兆円強は増税で確保する必要がある。 *1-1-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221224&ng=DGKKZO67127460U2A221C2MM8000 (日経新聞 2022.12.24) 防衛費26%増の6.8兆円 公共事業費を初めて超す 政府が23日に決定した2023年度予算案で、防衛関係費は過去最大の6兆8219億円となった。22年度当初予算と比べ26%増えた。ほぼ横ばいの6兆600億円だった公共事業関係費を初めて上回り、一般歳出で社会保障関係費に次いで多かった。防衛関係費は米軍再編経費やデジタル庁が所管する防衛省のシステム経費を含む。政府は予算案に先立ち国家安全保障戦略など安保関連3文書を決めた。5年間で43兆円程度をあてる計画で実行への初年度になる。増加は11年連続でこれまでの国内総生産(GDP)比1%の目安をなくした。政府の23年度の経済見通しに基づけば今回の防衛関係費はGDP比で1.19%になる。長射程ミサイルや艦艇など新たな装備品の購入費は1兆3622億円で7割弱増えた。装備品の維持整備費といった「維持費など」も1兆8731億円と5割近く増額し、継戦能力を高める。装備品の調達には歳出が複数年度にわたるものが多い。早期に部隊に配備するため計画で示した施策は可能な限り23年度に契約を予定する。防衛費のうち自衛隊の施設整備や船の建造費など計4343億円は建設国債で財源をまかなう。これまで自衛隊施設などは有事に損壊する恐れがあるとして建設国債の対象経費ではなかった。24年度以降に歳出を持ち越す新たな負担は米軍再編経費などを含め7兆6049億円になった。22年度の2.6倍で23年度予算案の単年での歳出額を超えた。 *1-2-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15502265.html (朝日新聞社説 2022年12月15日) 防衛費の財源 国債発行は許されない 政府が戦後初めて、防衛力整備を国債でまかなう方針を固めた。借金頼みの「禁じ手」を認めれば、歯止めない軍拡に道を開く。即座に撤回するよう首相に強く求める。首相は先日、27年度までの5年間の防衛費を43兆円に大幅増額する方針を示した。このうち約1・6兆円を国債でまかなう方向で検討していることが明らかになった。公共事業など投資的な経費に認められている建設国債を充てるという。戦後日本は、巨額の財政赤字を借金でまかないつつも、防衛費への充当は控えてきた。国債発行による軍事費膨張が悲惨な戦禍を招いた反省からだ。1965年に戦後初の国債発行に踏み切った際も、当時の福田赳夫蔵相は「公債を軍事目的で活用することは絶対に致しません」と明確に答弁している。以来、維持されてきた不文律を、首相は今回の方針転換で破ろうとしている。重大な約束違反であり、言語道断だ。自民党の一部は、海上保安庁予算に建設国債を充てていることを挙げて、自衛隊も同様に認めるべきだと主張してきた。だが、海保は法律で軍事機能が否定されている。自衛隊を同列に扱う理屈にはならない。財政規律は、ひとたび失われると回復が極めて困難になる。巨額の国債を発行し続ける戦後の財政の歩み自体がそのことを示しているはずだ。今回の国債は、老朽化した隊舎など自衛隊の施設整備に充てるという。だが、いったん国債を財源と認めれば、将来、戦車や戦闘機、隊員の人件費へと使途が止めどなく広がるおそれが強い。敵基地攻撃能力の保持に加え、財政上の制約までなくせば、防衛力の際限なき拡大への歯止めがなくなるだろう。戦前の日本は1936年の2・26事件以降、国債発行による野放図な軍拡にかじを切った。それを担った馬場えい一(えいいち)蔵相は、「私は国防費に対して不生産的経費という言葉は使わない」と言い放っている。投資を名分に防衛費を国債でまかなうのは、これと相似形ではないか。防衛費増額の財源では、歳出改革などによる確保策の実効性も疑わしい。復興特別所得税の仕組みを転用する案も浮上したが、復興のための一時的な負担という趣旨を踏まえれば、国民の納得は難しいだろう。国債発行を含めて無理な財源しか示せないのは、首相がGDP比2%という「規模ありき」で防衛費増額を決めたからだ。戦後の抑制的な安全保障政策の大転換を、拙速に進めることは許されない。国民的な議論を重ね、身の丈にあった防衛力のあり方に描き直す必要がある。 *1-2-2:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1073594 (沖縄タイムス社説 2022年12月15日) [安保大変容:「防衛増税」迷走]議論の進め方が乱暴だ 何ともお粗末な話だ。岸田文雄首相は、13日の自民党役員会で、防衛費増額の財源の一部を増税で賄う方針を示した際、「今を生きる国民が自らの責任として、しっかりその重みを背負って対応すべきだ」と語った。自民幹部が役員会の後に会見し、首相発言をそのように紹介した。発言を巡ってはツイッターで批判的な意見が相次いだ。14日になって自民党はホームページで「国民の責任」とあるのは「われわれの責任」だったと発言の一部を修正した。自民党の参院選公約には、増税で対応するとの記載はない。発言の事実関係ははっきりしないが、物価高騰のこのご時世に、防衛費増税を打ち出すこと自体、国民不在と言われても仕方がない。岸田政権は、2023年度から27年度までの5年間の防衛費総額を約43兆円とする方針で、27年度以降は年1兆円強を増税で賄う考えだ。具体的な中身もはっきりしないうちに総額の数字だけが先行し、増税を既成事実化するのは、手順があべこべだ。案の定、自民党内からも「内閣不信任に値する」「増税のプロセスがあまりに乱暴だ」などの異論が続出したという。高市早苗経済安全保障担当相は、現職の閣僚でありながら「総理の真意が理解できない」と疑問を呈した。閣内不一致を指摘されると「罷免されるということであれば仕方がない」と居直る始末。首相の指導力に疑問符が付く事態である。 ■ ■ 自民党税制調査会は、たたき台として法人税、たばこ税、復興特別所得税の3税目の増税案を示している。だが、この案も問題が多い。驚きを禁じ得ないのは、東日本大震災からの復興費を賄うための復興特別所得税の一部を防衛力強化に転用するという案だ。年2千億円程度を捻出するというのである。防衛費と復興費用とでは性格が全く異なる。所得税への上乗せを国民が認めているのは、それが復興に使われるからだった。防衛費への転用は、被災地に対する背信行為であり、承服することはできない。政府はこれまで、耐用年数の短さなどを理由に自衛隊施設については建設国債の活用を認めてこなかった。岸田首相も10日の記者会見で国債の活用を否定した。この従来方針も、明確な説明がないまま転換するというのである。 ■ ■ 建設国債が発行できるのは、道路や橋など将来世代に資産として残る公共事業に限られていた。背景には、戦前に国債を大量発行し、軍拡と戦争につながったとの反省があったからだといわれる。主権者である国民は、ないがしろにされていないか。スピード違反というしかないような、このところの猛烈な防衛力強化策は、尋常ではない。沖縄の軍事要塞(ようさい)化を進め、基地の過重負担を固定化させるような増税には強く反対したい。 *1-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221217&ng=DGKKZO66929830W2A211C2EA3000 (日経新聞 2022.12.17) 税制改正、成長描ききれず、EVや炭素税先送り 改革、世界から遅れ 2023年度与党税制改正大綱が16日、固まった。少額投資非課税制度(NISA)の恒久化といった成果の陰で、脱炭素のカギを握る炭素税などの議論は先送りとなった。世界の変化に対応する防衛増税や電気自動車(EV)税制も詳細は詰められなかった。欧米が長期的視点で環境問題などをにらんだ税制改革を進めるのと対照的に次の成長策を描ききれていない。大綱の目玉といえるのがNISAの抜本的な拡充だ。制度の恒久化や非課税期間の無期限化に踏み切った。「貯蓄から投資を加速させる」(全国銀行協会の半沢淳一会長)と関係者からも歓迎の声が上がる。手本である英国の個人貯蓄口座(ISA)は恒久化した後も、効果を検証して改良を重ねている。日本もより実効的な投資促進策となるよう制度をさらに磨き上げていく必要がある。グローバル企業の法人税負担の最低税率を15%とする国際合意を踏まえた措置も明記できた。23年に法整備を進め、24年4月以降の導入を目指す。国際合意には企業誘致に支障が出かねないと一部の新興国から反発が出ている。いち早く制度化にこぎ着けられれば国際協調の先導役になれる可能性もある。一方で先送りとなった課題は多い。二酸化炭素(CO2)の排出量に応じて企業に負担を求める炭素税は22年度改正に続いて棚上げにした。EV税制は走行距離に応じた課税案などに警戒が強く、3年後に枠組みを示すことで折り合った。グリーン対応で成長する制度設計はなお見通せていない。税の不公平の是正という大きな課題にも踏み込みきれなかった。たとえば所得1億円を境に富裕層の所得税の負担率が下がる「1億円の壁」だ。新しい資本主義を掲げる岸田文雄首相が就任当初からこだわり、NISAの大幅拡充とセットで見直すはずだった。与党が中小企業経営者らを含む富裕層への影響を懸念し、機運が後退した。追加の税負担を求める対象は所得が30億円を上回る200~300人程度とごくわずかになった。国の将来を左右する防衛増税は議論が深まらなかった。自民党税制調査会での実質的な協議は約1週間。大綱は法人税や所得税などの活用を明記しながら導入時期など肝心の部分は持ち越した。東京財団政策研究所の森信茂樹氏は「場当たり的な対応に追われ、税体系全体をどうしたいかの議論が置き去りになっている」と疑問視する。「防衛財源捻出のための復興特別所得税の期間延長など全体の受益と負担の関係が一段と見えにくくなり、複雑化した面がある」。米欧は新型コロナウイルス危機後に抜本的な税改革に着手した。欧州連合(EU)は国境炭素税やプラスチック税など新分野の制度設計を率先し、米バイデン政権も企業の自社株買いや法人への課税強化による増収分を格差是正策や次世代インフラ整備に充て、歳出入の中長期の枠組みを国民に示した。(1)デジタル(2)高齢化(3)グローバル課税(4)環境―。国際通貨基金(IMF)のビトール・ガスパール財政局長は2050年に向けて重要になる税の分野を明示している。デジタル化などの急速な変化に加え、環境などの長期的な視点が必要な問題に、各国・地域が向き合うことを迫られている。日本の税制改正を差配する自民党税調は1959年に発足した。以来、年末に大綱をまとめるため基本的に11~12月だけ開くのが慣例になってきた。「日が高い」うちは結論を出さないのが自民党と霞が関と業界団体の長年の習わしだ。そのつど場当たりの議論に追われる体制では世界の政策競争についていけなくなる懸念がある。 *1-3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15502393.html (朝日新聞 2022年12月15日) 炭素課金、企業側に配慮 まずは軽い負担 排出削減効果は不透明 二酸化炭素(CO2)の排出に課金して削減を促す「カーボンプライシング(炭素課金)」が2028年度から導入される見通しとなった。経済への影響を考慮し、導入まで一定の期間を置いたうえで、小さな負担からスタートする。脱炭素社会の実現に向けた一歩だが、排出削減の効果は不透明だ。経済産業省が14日の審議会で示した制度案は、化石燃料の輸入業者への「賦課金」を28年度、電力会社に有償の排出枠を買い取らせる「排出量取引」は33年度をめどに始めるとした。排出量を減らすほど得をする仕組みにして企業に削減を促す。今でもガソリンや石炭などの化石燃料に課税しているが、一部を除いてCO2の排出量に応じた負担になっていない。当初、経済界からは反対の声が大きかった。欧州に比べて再生可能エネルギーの利用は遅れている。産業の中心は排出量の大きい製造業で、脱炭素のための対策コストが増えることを嫌ったためだ。だが、欧州などで取り組みが進むなかで、国内外の投資家から日本企業に向けられる視線も厳しくなり、対策は「待ったなし」という認識が広がった。炭素課金の導入は、50年の脱炭素社会の実現を20年10月に宣言した菅義偉前首相が検討を指示した。経産省主導でつくった制度案は「成長志向型」と名付けられ、経済界への配慮がにじむ。炭素課金で得られる収入は企業への支援に回すなど、規制と支援をセットにしている。政府は、脱炭素の実現には今後10年間で官民合わせて150兆円超の投資が必要としている。このうち20兆円ほどは23年度以降に発行する「GX経済移行債」(仮称)で調達し、企業に投資を促す支援策に使う。炭素課金で得られる収入はその財源とする計画だ。ただ、経済成長との両立を重視しているため、負担額や導入時期が不十分との見方がある。具体的な課金額は決まっていないが、軽い負担から始め、徐々に引き上げる方針だ。「エネルギーにかかる公的負担の総額が中長期的に増えない」(岸田文雄首相)という。エネルギー関連の賦課金には、再生可能エネルギーの普及費用を電気料金に上乗せする制度があり、これが減少に転じるのは32年度の見通し。このため、新たな賦課金と排出量取引の一部有償化をそろって導入するのは33年度に設定した。気候変動の取り組みは世界的に加速している。欧州連合(EU)は、排出量の規制が緩い国からの輸入品に事実上課税する「炭素国境調整措置(国境炭素税)」を26年以降に導入する見通しだ。EUと同等の規制がないと見なした国・地域からの輸入品の一部に課税する。この日の審議会でも、委員の一人が、今回の制度案ではCO2排出1トンあたりの価格は「多くても3千円程度」と指摘。1万円前後のEUと比べて低く、日本の規制が「十分と見なされるかはわからない」(環境省幹部)という。京都大大学院の諸富徹教授は「温暖化対策に必要な『勝負の10年』を考えると、本格導入の時期は遅すぎるし、負担額も低すぎる」と指摘する。 <戦後安全保障の転換> *2-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221217&ng=DGKKZO66931730X11C22A2MM8000 (日経新聞 2022.12.17) 反撃能力保有を閣議決定 防衛3文書、日米で統合抑止、戦後安保を転換 政府は16日、国家安全保障戦略など新たな防衛3文書を閣議決定した。相手のミサイル発射拠点をたたく「反撃能力」を保有し、防衛費を国内総生産(GDP)比で2%に倍増する方針を打ち出した。国際情勢はウクライナ侵攻や台湾有事のリスクで急変した。戦後の安保政策を転換し自立した防衛体制を構築する。米国との統合抑止で東アジアの脅威への対処力を高める。外交・防衛の基本方針となる安保戦略を2013年の策定以来初めて改定した。新たな国家防衛戦略と防衛力整備計画も決定した。岸田文雄首相は16日の記者会見で「現在の自衛隊の能力で日本に対する脅威を抑止し国を守り抜けるのか。十分ではない」と語った。安保戦略は日本の環境を「戦後最も厳しい」と位置づけた。ミサイル発射を繰り返す北朝鮮や中国の軍事的な脅威にさらされており「最悪の事態も見据えた備えを盤石にする」と明記した。米国は国際秩序を乱す動きに同盟国と一丸で対処する「統合抑止」を掲げる。自衛隊は今まで以上に米軍との一体運用が求められ、安保戦略で実現の道筋を示した。反撃能力の保有は3文書改定の柱だ。「敵基地への攻撃手段を保持しない」と説明してきた政府方針を転換した。首相は16日「抑止力となる反撃能力は今後不可欠となる」と訴えた。反撃能力の行使は「必要最小限度の自衛措置」と定め、対象はミサイル基地など「軍事目標」に限定する。国産ミサイルの射程をのばすほか、米国製巡航ミサイル「トマホーク」も購入する。日米同盟のもと日本は「盾」、米国は「矛」の役割分担で反撃能力を米軍に頼ってきた。自衛隊のこれからの戦略は、迎撃中心のミサイル防衛体制から米軍と協力し反撃も可能な「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」に移行する。サイバー防衛は兆候段階でも攻撃元に監視・侵入などで対処する「能動的サイバー防御」に言及し、法整備の必要性に触れた。日本のサイバー防衛は攻撃を受けた後の対応に重点を置く。米欧のような反撃の仕組みも整っていない。3文書は陸海空の自衛隊と米軍との調整を担う「常設統合司令部」の創設を初めて盛り込んだ。中国を意識し自衛隊の「継戦能力」の強化も提起した。防衛装備品の部品や弾薬などの調達費を現行予算から2倍に増やす。自衛隊の組織は沖縄方面の旅団を格上げする。台湾有事で重要となる空と海の自衛隊員を増やすため、陸上自衛隊から人員を2000人振り替える。宇宙防衛を強化する目的で航空自衛隊は「航空宇宙自衛隊」に組織改編する。中国の現状認識を巡っては安保戦略に「これまでにない最大の戦略的な挑戦」と記した。沖縄県・尖閣諸島周辺での領海侵入などを踏まえ、現行戦略の「国際社会の懸念」から書きぶりを強めた。米欧の戦略と表現をそろえた。防衛費は23~27年度の5年間の総額で43兆円に増やす。現行計画の1.5倍に相当する。27年度には公共インフラや科学技術研究費など国防に資する予算を含めて現在のGDP比で2%に近づける。日本の防衛費は1976年に当時の三木武夫政権で国民総生産(GNP)比で1%の上限を設けた。それ以降はほとんど1%を超えてこなかった。米欧と同水準まで規模を広げて防衛力強化を対外的に示す。日本政府は冷戦期の緊張緩和(デタント)を背景に76年に初めて「防衛計画の大綱」をつくった。当時掲げた均衡の取れた最小限の防衛力整備をめざす「基盤的防衛力構想」からの脱却をはかる。 *2-1-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/963713 (佐賀新聞論説 2022/12/17) 安保戦略の転換 信問うべき平和国家の針路 岸田政権は外交・安全保障政策の基本指針となる「国家安全保障戦略」など安保関連3文書の改定を閣議決定した。国家安保戦略は日本周辺の情勢について「戦後最も厳しく複雑な安保環境」だと強調し、防衛力の抜本的な強化を表明。他国のミサイル発射拠点を攻撃できる反撃能力(敵基地攻撃能力)を保有し、防衛関連予算を2027年度に国内総生産(GDP)比2%に大幅増額すると打ち出した。戦後日本は憲法9条に基づき、「平和国家」として専守防衛に徹してきた。他国の領域を攻撃できる反撃能力の保有は、日米安保条約の下で「打撃力」を米国に委ねてきた安保政策を根幹から転換するものだ。こうした重大な政策転換が今回、国民的な議論抜きに決められた。岸田文雄首相は先の臨時国会では反撃能力に関して明確な方針を示さず、政府の有識者会議や与党協議など非公開の議論だけで決定。首相は5年間の防衛関連予算を約43兆円とし、財源確保のために増税することも一方的に表明した。極めて不透明で、独善的な決め方だ。新たな安保戦略は「国家の力の発揮は国民の決意から始まる」と記述。防衛増税に関して首相は「今を生きるわれわれの責任」と発言した。だが、国民への丁寧な説明や十分な議論は行われていない。平和国家の基軸を堅持するのか、力に力で対抗する国になるのか。国家の針路を国会で徹底的に審議し、総選挙で国民に信を問うべきだ。安保戦略は、中国を国際秩序への「最大の戦略的な挑戦」と位置付け、台湾有事の可能性にも言及。北朝鮮は「重大かつ差し迫った脅威」、ロシアは「安全保障上の強い懸念」との認識を示し、日本周辺で「力による一方的な現状変更の圧力が高まっている」と安保環境の悪化を強調する。その上で、サイバーや宇宙空間での防衛態勢、防衛装備品の研究開発や積極的な輸出などさまざまな分野での防衛力強化を打ち出した。確かにロシアのウクライナ侵攻を機に、国民の不安は高まっている。だが、不安に乗じ、増税まで行う防衛力増強が日本の選択すべき道なのか。GDP比2%の防衛予算は約11兆円で、米中両国に次ぎ、世界で3番目の水準となる。戦力不保持を定めた9条2項との整合性が問われよう。反撃能力は「武力攻撃の抑止」を理由に、長射程のミサイルを導入。安全保障関連法に基づき米国への攻撃も反撃の対象とする。だが、大量のミサイルを持つ国に対して本当に抑止力となるのか。他国の領域への攻撃は、国際法違反の先制攻撃となる恐れも拭えない。安保戦略は、他国が日本を攻撃する「意思を正確に予測することは困難」だとし、相手の能力に応じて「万全を期す防衛力」整備の必要性を主張する。だが、これは軍拡競争で逆に緊張が高まる「安全保障のジレンマ」に陥る論理だ。戦後日本が平和国家の道を歩んだ基礎には甚大な被害をもたらした先の大戦の反省がある。さらに、エネルギー資源の多くを輸入に頼り、食料自給率が低い日本は周辺国との協調が不可欠だ。専守防衛は周辺国との信頼構築の基盤だったと言える。冷静な情勢分析に基づき、地域の緊張緩和に粘り強く取り組む。それ以外に日本が進む道はないことを再確認すべきだ。 *2-2-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15498361.html (朝日新聞社説 2022年12月10日) 防衛予算増額 「規模先行」の弊害正せ 岸田首相が防衛力強化の財源案を示したが、中身を見ると実現性に乏しいものが多い。このまま進めれば、実質的に借金でまかなったり、防衛以外の予算を過度に制約したりすることになりかねない。財政力の現実を直視し、規模ありきの防衛予算増額を改めるべきだ。首相はおととい、防衛力強化のためには27年度には今より4兆円多い防衛予算が必要になると説明し、そのための財源確保策を示した。過半を歳出改革や特別会計などの余剰資金から捻出し、残る1兆円強を増税でまかなうという。自民党内には国債でまかなえとの声も強いが、恒久的支出を増やす以上、安定財源確保は必須だ。国債頼みは、財政上の問題に加え、防衛力拡大のための歯止めも失わせる。首相の方針は、表向きは国債以外でまかなう姿勢にみえる。だが、内実は極めて危うい。たとえば、活用を見込む決算剰余金は、補正予算の主要財源にされてきた。毎年のように巨額の補正を編成する慣行を改めなければ、防衛費増の分だけ国債が追加発行されることになる。実質的に防衛費を借金でまかなうことに等しい。特別会計やコロナ対策予算の不用分の返納も進めるとしているが、本来目的とする事業に支障をきたす恐れが拭えない。歳出改革も27年度までに1兆円分を積み上げるという。だが、中身は「毎年度毎年度いろいろな面で工夫をしていかなければいけない」(鈴木俊一財務相)とあやふやだ。増税は、実現すれば安定財源になりうるだろう。法人税を軸に検討を進めるという。安倍政権下での法人税率引き下げは、多くが企業の貯蓄や配当に回っており、主に企業に負担を求めるのは理解できる。実施時期などを適切に決めるべきだ。この増税をのぞき、政府が実効性ある財源を示せないのは、前提となる防衛費の増額が身の丈を超えた規模であることを示している。GDP比2%という「総額ありき」で予算を先行して決めた弊害だ。水ぶくれした予算のもとで、専守防衛を空洞化させる「敵基地攻撃能力」のための長距離ミサイルや、費用対効果が疑問視される「イージス・システム搭載艦」の費用が次々に盛り込まれた。中身を精査し、過大な部分を見直すのが先決だ。日本が直面する課題は安全保障だけではない。自民党が「国民共通の重大な危機」と位置づける少子化対策も、財源不足で遅れている。巨大地震などへの備えも必要だ。幅広い視野で適正な資源配分を考えることこそ、政治の役割である。 *2-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221129&ng=DGKKZO66365540Z21C22A1MM8000 (日経新聞 2022.11.29) 首相「防衛費2%、27年度」 財源・装備、年内に同時決着、科技費など合算 岸田文雄首相は28日、防衛費を2027年度に国内総生産(GDP)比2%に増額するよう関係閣僚に指示した。科学技術費などの国防に有益な費用を合算し、省庁横断の防衛費と位置づける。装備品を含む向こう5年間の予算規模と財源確保を年内に同時決着させ、戦後の安全保障政策の転換に道筋をつける。首相が防衛費の具体的水準を明言するのは初めて。東アジアの険しい安保環境を踏まえ先送りすべきでないと判断した。自民党内には安倍派を中心に防衛費を賄うための増税に慎重な意見もある。長期にわたる防衛費増を可能にするための安定財源確保にメドをつけられるかが問われる。首相が28日、首相官邸に浜田靖一防衛相と鈴木俊一財務相を呼び防衛費増額に関する方針を指示した。GDP比で2%との基準を示したうえで、年末に(1)23~27年度の中期防衛力整備計画(中期防)の規模(2)27年度に向けての歳出・歳入両面での財源確保――を一体的に決定すると伝えた。浜田氏が面会後に記者団に明らかにした。日本の防衛費は1976年の三木武夫内閣以来、おおむね1%以内を目安としてきた。ウクライナ侵攻を踏まえ北大西洋条約機構(NATO)の加盟国が相次ぎ国防費を2%にすると表明し、自民党が2%への増額論を唱えていた。防衛省の予算は2022年度当初で5兆4000億円ほどだ。GDPで2%とするのは防衛省の予算を増額した上で、防衛に有益な他の経費を含める。公共インフラや科学技術研究、サイバー、海上保安庁といった他省庁予算も加える。防衛省だけの縦割り体質から脱却し、安全保障を政府全体で担う体制に移行する。現在のGDPを前提とすると新たな防衛費はおよそ11兆円に達する。柱となるのは相手のミサイル発射拠点などをたたく「反撃能力」の保有だ。ミサイルの長射程化や米国製巡航ミサイル「トマホーク」を導入する。不足している弾薬の購入量を増やすなどして継戦能力も強化する。財源に関する年内決着も指示した。「まずは歳出改革」と指摘したうえで、歳入面で「安定的に支えるためのしっかりした財源措置は不可欠だ」と伝達した。政府の防衛費増額に関する有識者会議は財源を「幅広い税目による国民負担が必要」とする提言をまとめていた。政府内では法人税に加えて所得税、たばこ税などの増税で賄うべきだとの意見がある。一方で政府関係者によると26年度までは財源確保のための一時的な赤字国債発行を容認するという。自民党側の意見に配慮した措置とみられる。首相は両閣僚に歳出改革なども含め財源捻出を工夫するよう求めた。28日の衆院予算委員会では防衛費の財源に関して余った新型コロナウイルス対策予算の活用を検討すると明らかにした。 *2-3-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15504420.html (朝日新聞 2022年12月17日) 安保3文書要旨 ■国家安全保障戦略 《1 策定の趣旨》 パワーバランスの歴史的変化と地政学的競争の激化で、国際秩序は重大な挑戦にさらされており、対立と協力の様相が複雑に絡み合う時代になっている。我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している。ロシアによるウクライナ侵略で、国際秩序を形作るルールの根幹が簡単に破られた。同様の事態が、将来インド太平洋地域、東アジアで発生する可能性は排除されない。我が国周辺では、核・ミサイル戦力を含む軍備増強が急速に進展し、力による一方的な現状変更の圧力が高まっている。サイバー攻撃、偽情報の拡散を通じた情報戦が恒常的に生起し、有事と平時、軍事と非軍事の境目もあいまいに。防衛力の抜本的強化を始め、備えを盤石なものとし、我が国の平和と安全、国益を守っていかなければならない。この戦略は国家安全保障の最上位の政策文書で、指針と施策は戦後の安全保障政策を実践面から大きく転換するものだ。国家としての力の発揮は国民の決意から始まる。本戦略を着実に実施していくためには、国民が我が国の安全保障政策に自発的かつ主体的に参画できる環境を整えることが不可欠だ。 《2 我が国の国益》 主権と独立を維持し、領域を保全し、国民の生命・身体・財産の安全を確保。経済成長を通じた繁栄、他国と共存共栄できる国際的な環境を実現する。普遍的価値や国際法に基づく国際秩序を擁護し、自由で開かれた国際秩序を維持・発展させる。 《3 安全保障に関する基本的な原則》 積極的平和主義を維持。我が国を守る一義的な責任は我が国にあり、安全保障上の能力と役割を強化する。平和国家としての専守防衛、非核三原則の堅持などの基本方針は不変。日米同盟は我が国の安全保障政策の基軸であり続ける。他国との共存共栄、同志国との連携、多国間の協力を重視する。 《4 安全保障環境と安全保障上の課題》 1 グローバルな安全保障環境と課題 パワーの重心がインド太平洋地域に移り、国際社会は急速に変化。国際秩序に挑戦する動きが加速し、力による一方的な現状変更、サイバー空間・海洋・宇宙空間・電磁波領域におけるリスクが深刻化。他国に経済的な威圧を加える動きもある。 2 インド太平洋地域における安全保障環境と課題 (1)インド太平洋地域における安全保障の概観 「自由で開かれたインド太平洋」というビジョンの下、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の実現、地域の平和と安定の確保は、我が国の安全保障にとって死活的に重要だ。 (2)中国の動向 中国の対外的な姿勢や軍事動向は我が国と国際社会の深刻な懸念事項で、これまでにない最大の戦略的挑戦。我が国の総合的な国力と同盟国・同志国との連携により対応すべきものだ。 (3)北朝鮮の動向 北朝鮮の軍事動向は我が国の安全保障にとり、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威に。 (4)ロシアの動向 ウクライナ侵略によって国際秩序の根幹を揺るがし、欧州方面では安全保障上の最も重大かつ直接の脅威に。中国との戦略的な連携と相まって、安全保障上の強い懸念だ。 《5 安全保障上の目標》 主権と独立、国内・外交に関する政策を自主的に決定できる国であり続ける。領域、国民の生命・身体・財産を守る。有事を抑止し、脅威が及ぶ場合でもこれを排除し、被害を最小化させ、有利な形で終結させる。 《6 優先する戦略的なアプローチ》 1 安全保障に関わる総合的な国力の主な要素 総合的な国力(外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力)を用いて、戦略的なアプローチを実施する。 2 戦略的なアプローチと主な方策 (1)危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境を能動的に創出し、自由で開かれた国際秩序を強化するための外交を中心とした取り組みの展開 ア 日米同盟の強化 イ 自由で開かれた国際秩序の維持・発展と同盟国・同志国との連携の強化 ウ 我が国周辺国・地域との外交、領土問題を含む諸懸案の解決に向けた取り組みの強化 エ 軍備管理・軍縮・不拡散 オ 国際テロ対策 カ 気候変動対策 キ ODAを始めとする国際協力の戦略的な活用 ク 人的交流等の促進 (2)防衛体制の強化 ア 国家安全保障の最終的な担保である防衛力の抜本的強化(〈1〉領域横断作戦能力、スタンドオフ・防衛能力、無人アセット防衛能力を強化〈2〉反撃能力の保有〈3〉2027年度に防衛関連予算水準が現在のGDPの2%に達するよう所要の措置〈4〉自衛隊と海上保安庁との連携強化) イ 総合的な防衛体制の強化との連携(研究開発、公共インフラ、サイバー安全保障、同志国との国際協力) ウ 防衛生産・技術基盤の強化 エ 防衛装備移転の推進(防衛装備移転三原則・運用指針をはじめとする制度の見直し) オ 自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化(ハラスメントを許容しない組織環境) (3)米国との安全保障面における協力の深化 米国による拡大抑止の提供を含む日米同盟の抑止力と対処力を一層強化する。 (4)我が国を全方位でシームレスに守る取り組み強化 ア サイバー安全保障 イ 海洋安全保障・海上保安能力(海上保安能力を大幅に強化・体制を拡充) ウ 宇宙安全保障(宇宙の安全保障に関する政府構想をとりまとめ、宇宙基本計画に反映) エ 安全保障関連の技術力向上と積極的な活用(防衛省の意見を踏まえた研究開発ニーズと関係省庁の技術シーズを合致。政府横断的な仕組みを創設) オ 情報に関する能力(人的情報収集など情報収集能力を大幅強化。統合的な情報集約体制を整備、偽情報対策も) カ 有事も念頭に置いた国内での対応能力(自衛隊、海保のニーズにより、公共インフラ整備・機能を拡大。原発など重要施設の安全確保対策も) キ 国民保護の体制 ク 在外邦人等の保護のための体制と施策 ケ エネルギーや食料など安全保障に不可欠な資源の確保 (5)経済安全保障の促進 自律性、優位性、不可欠性を確保し、サプライチェーンを強靱(きょうじん)化。セキュリティークリアランスを含む情報保全を強化。 (6)自由、公正、公平なルールに基づく国際経済秩序の維持・強化 (7)国際社会が共存共栄するためのグローバルな取り組み ア 多国間協力の推進、国際機関や国際的な枠組みとの連携の強化 イ 地球規模課題への取り組み 《7 我が国の安全保障を支えるために強化すべき国内基盤》 1 経済財政基盤の強化(安全保障と経済成長の好循環を実現) 2 社会的基盤の強化(国民の安全保障に関する理解と協力) 3 知的基盤の強化(政府と企業・学術界との実践的な連携強化) 《8 本戦略の期間・評価・修正》 おおむね10年の期間を念頭に置き、安全保障環境に重要な変化が見込まれる場合、必要な修正を行う。 《9 結語》 我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の下に置かれ、将来の国際社会の行方を楽観視することは決してできない。我々は今、希望の世界か、困難と不信の世界のいずれかに進む分岐点にあり、どちらを選び取るかは、今後の我が国を含む国際社会の行動にかかっている。国際社会が対立する分野では、総合的な国力で安全保障を確保する。国際社会が協力すべき分野では、課題解決に向けて主導的かつ建設的な役割を果たし続けていく。普遍的価値に基づく政策を掲げ、国際秩序の強化に向けた取り組みを確固たる覚悟を持って主導していく。 ■国家防衛戦略 《1 策定の趣旨》 政府の最も重大な責務は国民の命と平和な暮らし、そして我が国の領土・領海・領空を断固として守り抜くことにある。ただ、国際社会は深刻な挑戦を受け、新たな危機の時代に突入している。そこで、自衛隊を中核とした防衛力の整備、維持及び運用の基本的指針である「防衛計画の大綱」に代わり、我が国の防衛目標、達成するためのアプローチとその手段を包括的に示す「国家防衛戦略」を策定する。 《2 戦略環境の変化と防衛上の課題》 1 普遍的価値やそれに基づく政治・経済体制を共有しない国家が勢力を拡大している。力による一方的な現状変更やその試みは、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序に対する深刻な挑戦で、国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、新たな危機の時代に突入しつつある。グローバルなパワーバランスが大きく変化。国家間競争が顕在化し、インド太平洋地域において顕著となっている。さらに、科学技術の急速な進展が安全保障の在り方を根本的に変化させ、各国は将来の戦闘様相を一変させる。いわゆるゲーム・チェンジャーとなり得る先端技術の開発を行っている。 2 我が国周辺国等の軍事動向では、中国は、今後5年が目指す「社会主義現代化国家」の建設をスタートさせる肝心な時期と位置づけ、台湾周辺における威圧的な軍事活動を活発化させるなどしている。その軍事動向は我が国と国際社会の深刻な懸念事項である。北朝鮮は、大量破壊兵器や弾道ミサイル等の増強に集中的に取り組む。関連技術・運用能力を急速に向上させており、従前よりもいっそう重大かつ差し迫った脅威となっている。ロシアによるウクライナ侵略は欧州方面における防衛上の最も重大かつ直接の脅威と受け止められている。また、北方領土を含む極東地域で軍事活動を活発化させている。こうした軍事動向は我が国を含むインド太平洋地域において中国との戦略的な連携と相まって防衛上の強い懸念である。 3 防衛上の課題としては、ロシアによるウクライナ侵略は、高い軍事力を持つ国が、侵略意思を持ったことにも注目するべき。脅威は能力と意思の組み合わせで顕在化する。意思を外部から正確に把握することは困難で、国家の意思決定過程が不透明であれば脅威が顕在化する素地が常に存在する。新しい戦い方が顕在化する中で、それに対応できるかどうかが今後の大きな課題となっている。 《3 我が国の防衛の基本方針》 力による一方的な現状変更やその試みは決して許さないとの意思を明確にしていく必要がある。 1 我が国自体への侵攻を我が国が主たる責任をもって阻止・排除し得るよう防衛力を抜本的に強化する。侵攻を抑止する上で鍵となるのはスタンド・オフ防衛能力等を活用した反撃能力である。我が国周辺では質・量ともにミサイル戦力が著しく増強され、ミサイル攻撃が現実の脅威となっている。これに既存のミサイル防衛網だけで完全に対応することは難しくなりつつある。反撃能力とは我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の3要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として相手の領域において我が国が有効な反撃を加えることを可能とする自衛隊の能力をいう。有効な反撃を加える能力を持つことにより、武力攻撃そのものを抑止する。その上で、万一、相手からミサイルが発射される際にも、ミサイル防衛網により飛来するミサイルを防ぎつつ、反撃能力により相手からの更なる武力攻撃を防ぎ、国民の命と平和な暮らしを守っていく。 2 米国との同盟関係は我が国の安全保障の基軸である。日米共同の意思と能力を顕示し、力による一方的な現状変更やその試みを抑止する。侵攻が起きた場合には、日米共同対処により阻止する。 3 1カ国でも多くの国々との連携強化が極めて重要で、地域の特性や各国の事情を考慮した多角的・多層的な防衛協力・交流を積極的に推進する。 《4 防衛力の抜本的強化に当たって重視する能力》 (1)スタンド・オフ防衛能力 (2)統合防空ミサイル防衛能力 (3)無人アセット防衛能力 (4)領域横断作戦能力 (5)指揮統制・情報関連機能 (6)機動展開能力・国民保護 (7)持続性・強靱(きょうじん)性 《5将来の自衛隊の在り方》 1 重視する能力の7分野では、各自衛隊がスタンド・オフ・ミサイル発射能力を必要十分な数量整備するなど自衛隊が役割を果たす。 2 統合運用の実効性を強化するため既存組織を見直し、陸自・海自・空自の一元的な指揮を行い得る常設の統合司令部を創設する。統合運用に資する装備体系の検討を進める。 3 戦略的・機動的な防衛政策の企画立案が必要とされており、機能を抜本的に強化していく。防衛研究所を中心とする防衛省・自衛隊の研究体制を見直し、知的基盤としての機能を強化する。 《6 国民の生命・身体・財産の保護・国際的な安全保障協力への取り組み》 1 侵略のみならず、大規模テロや原発を始めとする重要インフラに対する攻撃、大規模災害、感染症危機等は深刻な脅威であり、総力を挙げて対応する必要がある。 2 我が国の平和と安全のため、積極的平和主義の立場から、国際的な課題への対応に積極的に取り組む。 《7 いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤》 1 我が国の防衛産業は国防を担うパートナーというべき重要な存在。適正な利益確保のための新たな利益率算定方式を導入する。サプライチェーン全体を含む基盤の強化、新規参入促進、国が製造施設等を保有する形態を検討する。 2 防衛産業や非防衛産業の技術を早期装備化につなげる取り組みを積極的に推進する。我が国主導の国際共同開発、民生先端技術を積極活用するための枠組みを構築する。 3 防衛装備移転三原則や運用指針を始めとする制度の見直しについて検討し、官民一体となった防衛装備移転の推進のため、基金を創設して企業支援をおこなう。 《8 防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化》 1 防衛力の中核である自衛隊員について、必要な人員を確保し、全ての隊員が能力を発揮できる環境を整備する。 2 これまで重視してきた自衛隊員の壮健性の維持から、有事において隊員の生命・身体を救うように衛生機能を変革する。 《9 留意事項》 おおむね10年間の期間を念頭に置いているが、国際情勢や技術的水準の動向等について重要な変化が見込まれる場合には必要な修正を行う。 ■防衛力整備計画 《1 計画の方針》 平時から有事まで、活動の常時継続的な実施を可能とする多次元統合防衛力を抜本的に強化し、5年後の2027年度までに、我が国への侵攻が生起する場合には、我が国が主たる責任をもって、同盟国等の支援を受けつつ、阻止・排除できるように防衛力を強化する。おおむね10年後までに、より早期かつ遠方で侵攻を阻止・排除できるように防衛力を強化する。まず、侵攻そのものを抑止するため、遠距離から侵攻戦力を阻止・排除できるよう、「スタンド・オフ防衛能力」と「統合防空ミサイル防衛能力」を強化する。また、万が一抑止が破れ、我が国への侵攻が生起した場合に優勢を確保するため、「無人アセット防衛能力」、「領域横断作戦能力」、「指揮統制・情報関連機能」を強化する。さらに、迅速かつ粘り強く活動し続けて、相手方の侵攻意図を断念させるため、「機動展開能力・国民保護」、「持続性・強靱性」を強化する。いわば防衛力そのものである防衛生産・技術基盤に加え、防衛力を支える人的基盤等も重視する。 《2 自衛隊の能力等に関する主要事業》 1 スタンド・オフ防衛能力 侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対して、脅威圏外から対処する能力を強化する。スタンド・オフ・ミサイルの量産弾を取得するほか、米国製のトマホークを始めとする外国製スタンド・オフ・ミサイルの着実な導入を実施・継続する。 2 統合防空ミサイル防衛能力 極超音速滑空兵器等の探知・追尾能力を強化するため、固定式警戒管制レーダー等の整備及び能力向上、次期警戒管制レーダーの換装・整備を図る。我が国の防空能力強化のため、主に弾道ミサイル防衛に従事するイージス・システム搭載艦を整備する。 3 無人アセット防衛能力 用途に応じた様々な情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティング用無人アセットを整備する。輸送用無人機の導入について検討の上、必要な措置を講じる。各種攻撃機能を効果的に保持した多用途/攻撃用無人機及び小型攻撃用無人機を整備する。 4 頷域横断作戦能力 (1)宇宙領域における能力 米国との連携強化、民間衛星の利用等により、目標の探知・追尾能力の獲得を目的とした衛星コンステレーションを構築する。 (2)サイバー領域における能力 27年度を目途に、自衛隊サイバー防衛隊等のサイバー関連部隊を約4千人に拡充する。将来的には更なる体制拡充を目指す。 5 指揮統制・情報関連機能 (3)認知領域を含む情報戦等への対処 情報戦に確実に対処できる体制・態勢を構築する。人工知能(AI)を活用した公開情報の自動収集・分析機能の整備、各国等による情報発信の真偽を見極めるためのSNS上の情報等を自動収集する機能の整備、情勢見積もりに関する将来予測機能の整備を行う。 《3 自衛隊の体制等》 1 統合運用体制 常設の統合司令部を創設する。 4 航空自衛隊 宇宙作戦能力を強化するため、将官を指揮官とする宇宙領域専門部隊を新編するとともに、航空自衛隊を航空宇宙自衛隊とする。 《13 所要経費等》 1 23年度から27年度の5年間における本計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金額は、43兆円程度とする。 2 本計画期間の下で実施される各年度の予算の編成に伴う防衛関係費は、以下の措置を別途とることを前提として、40兆5千億円程度(27年度は8兆9千億円程度)とする。 (1)自衛隊施設等の整備の更なる加速化を機動的・弾力的に行うこと(1兆6千億円程度)。 (2)一般会計の決算剰余金が想定よりも増加した場合にこれを活用すること(9千億円程度)。 3 この計画を実施するために新たに必要となる事業に係る契約額(物件費)は、43兆5千億円程度とする。 6 27年度以降、防衛力を安定的に維持するための財源、及び、23年度から27年度の本計画を賄う財源の確保については、歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金の創設、税制措置等、歳出・歳入両面において所要の措置を講ずることとする。 ■防衛力整備計画の別表 【今後5年間で導入】 ◆スタンド・オフ防衛能力 12式地対艦誘導弾能力向上型(地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型) 地上発射型11個中隊、島嶼(とうしょ)防衛用高速滑空弾、極超音速誘導弾、トマホーク ◆統合防空ミサイル防衛能力 03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上型 14個中隊、イージス・システム搭載艦 2隻、早期警戒機(E-2D) 5機、弾道ミサイル防衛用迎撃ミサイル(SM-3ブロック2A)、能力向上型迎撃ミサイル(PAC-3MSE)、長距離艦対空ミサイルSM-6 ◆無人アセット防衛能力 各種UAV、USV、UGV、UUV ◆領域横断作戦能力 護衛艦 12隻、潜水艦 5隻、哨戒艦 10隻、固定翼哨戒機(P-1) 19機、戦闘機(F-35A) 40機、戦闘機(F-35B) 25機、戦闘機(F-15)の能力向上 54機、スタンド・オフ電子戦機 1機、ネットワーク電子戦システム(NEWS) 2式 ◆指揮統制・情報関連機能 電波情報収集機(RC-2) 3機 ◆機動展開能力・国民保護 輸送船舶 8隻、輸送機(C-2) 6機、空中給油・輸送機(KC-46A等) 13機 【おおむね10年後に整備】 ◆共同の部隊 サイバー防衛部隊 1個防衛隊、海上輸送部隊 1個輸送群 ◆陸上自衛隊 ・常備自衛官定数 14万9千人 ・基幹部隊(作戦基本部隊《9個師団、5個旅団、1個機甲師団》、空挺部隊 1個空挺団、水陸機動部隊 1個水陸機動団、空中機動部隊 1個ヘリコプター団) ・スタンド・オフ・ミサイル部隊(7個地対艦ミサイル連隊、2個島嶼防衛用高速滑空弾大隊、2個長射程誘導弾部隊)、地対空誘導弾部隊 8個高射特科群、電子戦部隊(うち対空電子戦部隊) 1個電子作戦隊(1個対空電子戦部隊)、無人機部隊 1個多用途無人航空機部隊、情報戦部隊 1個部隊 ◆海上自衛隊 ・基幹部隊(水上艦艇部隊《護衛艦部隊・掃海艦艇部隊》、6個群《21個隊》、潜水艦部隊 6個潜水隊、哨戒機部隊《うち固定翼哨戒機部隊》、 9個航空隊《4個隊》)、無人機部隊 2個隊、情報戦部隊 1個部隊 ・主要装備(護衛艦 54隻《イージス・システム搭載護衛艦10隻》、イージス・システム搭載艦 2隻、哨戒艦 12隻、潜水艦 22隻、作戦用航空機 約170機) ◆航空自衛隊 ・主要部隊(航空警戒管制部隊、4個航空警戒管制団、1個警戒航空団《3個飛行隊》、戦闘機部隊 13個飛行隊、空中給油・輸送部隊 2個飛行隊、航空輸送部隊 3個飛行隊、地対空誘導弾部隊 4個高射群《24個高射隊》、宇宙領域専門部隊 1個隊、無人機部隊 1個飛行隊、作戦情報部隊 1個隊 ・主要装備(作戦用航空機約430機《戦闘機約320機》注1:上記、陸上自衛隊の15個師・旅団のうち、14個師・旅団は機動運用を基本とする。注2:戦闘機部隊及び戦闘機数については、航空戦力の量的強化を更に進めるため、2027年度までに必要な検討を実施し、必要な措置を講じる。この際、無人機(UAV)の活用可能性について調査を行う) *2-3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221217&ng=DGKKZO66931250W2A211C2EA2000 (日経新聞 2022.12.17) 防衛支出、問われる優先度、増す脅威、首相「量・質両面で強化」 政府は防衛3文書に新装備の導入や自衛隊の体制拡充を盛り込んだ。サイバー防衛の具体策を詰めるのは2023年以降で、反撃能力の手段である長射程ミサイルの配備は最短で26年度になる。北朝鮮など現実的な危機が迫るなかで、政策の優先度と実行力が問われる。岸田文雄首相は16日の記者会見で3文書改定の重要項目として反撃能力やサイバーなど新領域への対応を挙げた。「日本の能力を量・質両面で強化する」と説明した。3文書はサイバー空間で攻撃兆候の探知や発信元の特定をして事前対処する「能動的サイバー防御」に初めて触れ、導入を明記した。政府はこれから(1)攻撃を受けた民間企業による政府への情報共有(2)通信事業者が持つ情報の活用(3)相手システムに侵入する権限の付与―の3点を検討する。実現には憲法21条の「通信の秘密」との整理や法改正が不可欠だ。事業者が保有する通信網の情報を使えば攻撃元が探知しやすくなる。相手システムへの攻撃も可能になれば重大な被害を未然に防げる。米欧の主要国はサイバー防衛で先行する。重要インフラの停止など脅威度が増すサイバー攻撃への対応は優先度が高いと考えるためだ。政府は23年にも内閣官房にサイバー防衛の司令塔を新設し、どこまで情報の活用が可能か議論に入る。慶大の神保謙教授は「能動的サイバー防御の導入方針は画期的だが、法整備に数年はかかるだろう」と語った。人員の確保も課題だ。自衛隊は27年度までに専門人材を現在の4倍以上の4000人規模に増員する。民間からの登用には情報の保秘体制や報酬の面で壁がある。優秀な人材は民間企業との奪い合いになる。新防衛3文書が「最優先課題」に掲げたのは戦闘機や艦艇の修理などに使う部品と弾薬の備蓄拡大だ。自衛隊は部品不足が常態化し、装備の稼働率は5割強しかない。他の機体向けに部品を流用する「共食い」整備は航空自衛隊だけで年3400件もある。防衛省は23~27年度に投じる単体予算43兆円のうち9兆円をかけて5年以内にこうした状況を解消する。弾薬は中長期の戦闘に十分な量に足りていない。備蓄の7割は北海道に偏在し、台湾有事で影響が避けられない南西諸島の防衛に不安が残る。「有事になれば戦えずに負ける」との声さえあがる状況の是正が急務だが、火薬庫を新設するための地元自治体との調整は難航しがちだ。能力強化を巡っても課題は山積する。代表例は相手の脅威圏外から撃つ長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」。相手のミサイル発射拠点などをたたく反撃能力の手段にもなる。中国やロシア、北朝鮮が力を入れる極超音速ミサイルを遠方で迎え撃つ技術は現時点でない。地上に落下する局面では最新鋭の地対空誘導弾パトリオットミサイル(PAC3)や迎撃ミサイル「SM6」などで撃ち落とせるが、防御範囲は限られている。大気圏外を放物線を描いて飛ぶ弾道ミサイルと異なり、高度100キロメートル以下を方向を変えながら飛ぶ極超音速弾に対処する迎撃弾がなければ、抑止力は十分といえない。通常の弾道ミサイルも同時に多数を撃ち込まれればすべてを撃ち落とすのは難しい。迎撃一辺倒では守り切れなくなった現実を踏まえ、日本へ撃てば反撃を受けると認識させて攻撃をためらわせる抑止力を早期に備える必要がある。反撃能力の保有は「時間との戦い」ともいわれる。戦闘で使われた実績がある米国製巡航ミサイル「トマホーク」を購入しても護衛艦への配備は早くて26年度だ。しばらくは抑止力に穴がある状態が続く。台湾有事のリスクが高まるとされる24年の台湾総統選後には間に合わない。中長期の抑止力は極超音速ミサイルの開発が左右する。米国も未開発の段階で、日本が国産の「極超音速誘導弾」を完成させるのは30年代になる想定だ。ロシアはすでに極超音速滑空兵器(HGV)を配備し、中国もHGV搭載可能な弾道ミサイル「東風(DF)17」の運用を始めたとされる。北朝鮮も極超音速ミサイルと称し発射を繰り返す。新型ミサイルに限れば東アジアの軍事バランスはすでに崩れた。限られた予算の中で抑止力強化に効果的な装備や分野を厳選する「賢い支出」という視点は欠かせない。防衛力に完全はなく、体制拡充を求めればキリがない。現実の脅威に対処する方策を見定めつつ、費用対効果を同時に検証する作業が求められている。 *2-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221220&ng=DGKKZO66979290Q2A221C2MM8000 (日経新聞 2022.12.20) サイバー戦争 日本の危機(1)戦争「武力以外が8割」、ウクライナ、40日前に「開戦」 日本は法整備なく脆弱 銃弾やミサイルが飛び交うウクライナ侵攻の裏で、世界はサイバー戦争の脅威に震撼(しんかん)した。日本政府は16日に防衛3文書を改定し、ようやくサイバー防衛を強化する方針を示した。実際に国民を守るには法制度や人材、装備を急いで用意しなければならない。2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻はその40日ほど前に「開戦」していた。3波に及ぶ大規模なサイバー攻撃だ。まず1月13~14日。「最悪の事態を覚悟せよ」とウクライナの70の政府機関でサイトが書き換えられた。2月15日は国防省や民間銀行が標的になる。大量のデータを送りつけてサーバーを止める「DDoS攻撃」だった。第3波は侵攻前日の2月23日。政府機関や軍、金融や航空、防衛、通信など官民のインフラ全般が攻撃を受けた。ロシアには成功体験がある。2014年のクリミア併合だ。侵攻前にウクライナへのサイバー攻撃で通信網を遮断し、官民の重要機関も軍の指揮系統も機能不全にした。ウクライナ軍は実際の侵攻時に対抗できず、短期間でクリミア半島の占拠を許した。 ●戦力差を補完 「非軍事的手段と軍事的手段の割合は4対1だ」。いまもロシア軍を指揮するゲラシモフ参謀総長はクリミア併合前の13年に予告した。現代戦はサイバーや外交、経済などの非軍事面が8割を占めるという意味だ。14年の例を踏まえれば今回もすぐに首都キーウ(キエフ)が陥落しかねなかった。国防費は10倍、陸軍兵力も倍以上とリアルの戦力も大差がある。にもかかわらず泥沼は10カ月も続く。米欧の武器支援は大きいが、主に春以降だ。序盤にウクライナが持ちこたえたのはゲラシモフ論の「5分の4」に入るサイバーの力が大きい。ロシアは14年以降もサイバー攻撃を続けていた。15、16年は電力インフラを攻撃し大規模停電を引き起こした。17年は強力なマルウエア「NotPetya」の攻撃がウクライナを通じて米欧にも被害を与えた。もともとウクライナの通信機器はロシア製が多く「バックドア」と呼ばれる侵入路があった。侵入路から米国に打撃が及ぶと、米政府や米マイクロソフトがウクライナの支援に乗り出した。防衛策をとる過程でロシア製機器は排除し、米国の盾を獲得した。世界最先端ともいわれたロシアの攻撃に対処し続けた結果、防衛の経験と技術も向上した。今回の3波攻撃が致命傷にならず、ウクライナ軍も機能したのはそのためだ。「発覚から3時間以内で対処した」。米マイクロソフトは2月末、今回のロシアによるサイバー攻撃について発表した。攻撃前からロシア内の動向を監視しなければ無理な対応といわれる。同社はロシアが侵攻後に日本を含む40カ国以上のネットワークに侵入を試みた、と6月に公表した。「まず検出能力を養うことだ」と強調した。日本に力はない。「日米同盟の最大の弱点はサイバー防衛。日本の実力はマイナーリーグ、その中で最低の1Aだ」。デニス・ブレア元米国家情報長官は提唱する。元海将の吉田正紀氏は「サイバーは日米で最も格差がある。日本も能力を急速に上げるべきだ」と語る。9月には日本政府の「e-Gov」や東京地下鉄(東京メトロ)、JCBなどがDDoS攻撃を受けた。親ロシアのハッカー集団「キルネット」が犯行声明を出した。折しもロシアは極東で中国などと大規模軍事演習をしていた。仮想敵「東方」から土地を奪還する想定で、サイバーとリアルを連動させたと映る。 ●「逆侵入」できず 中曽根康弘世界平和研究所の大沢淳主任研究員は「日本政府は『ロシアの軍事演習の一環』と分析していなかった」と指摘する。「日本は攻撃者や背景を特定できない」とも話す。サイバーも「専守防衛」で攻撃を感知してから対処する。サイバー防衛は「国の責務」とも規定していない。世界的には異例だ。各国は海外からの通信を監視して攻撃者を特定し対抗措置をとる。「アクティブ・サイバー・ディフェンス(積極的サイバー防衛)」という。12月16日に日本政府が決めた国家安全保障戦略には「能動的サイバー防御」が記されたが具体化は23年以降になる。憲法21条は「通信の秘密」を規定する。外国との通信を監視するなら電気通信事業法の改正が要る。攻撃元の特定には経由したサーバーをさかのぼる「逆侵入」や「探知」が必要だが、不正アクセス禁止法や刑法の改正が前提になる。いまウクライナのような攻撃を受けても盾はない。無防備で国民の安全は守れない。 <エネルギー安全保障> *3-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221207&ng=DGKKZO66612400X01C22A2EA2000 (日経新聞 2022.12.7) 再生エネ「25年に最大電源」 IEA予測、石炭抜く ウクライナ危機で急拡大 国際エネルギー機関(IEA)は6日公表した報告書で、太陽光や風力など再生可能エネルギーが2025年に石炭を抜いて最大の電源になるとの見通しを示した。ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー安全保障への危機感が強まり、各国は「国産エネルギー」の再生エネを急拡大する。侵攻で高騰した化石燃料と比べ、再生エネの発電コストが割安なことも追い風だ。IEAによると、再生エネの発電量は27年までに21年から約6割増えて1万2400テラワット時以上になる見込み。IEAは報告書で「25年初めには再生エネが石炭を抜いて最大の発電源になる」と指摘した。電源別のシェアは21年から10ポイント増えて27年に38%になる。一方、石炭は7ポイント弱減って30%に、天然ガスは2ポイント減の21%になる。再生エネの発電容量は21年に約3300ギガワットで、27年までに2400ギガワット増加する見通し。過去20年に世界が整備してきた規模に匹敵し、現在の中国の容量に相当する。ウクライナ侵攻は、化石燃料の高騰と供給不安を世界で引き起こした。エネルギーを他国に過度に依存するのは大きなリスクになるとの教訓を得た多くの国は、再生エネの拡大をめざしている。輸入に依存する化石燃料と異なり、再生エネは自国領に吹く風や降り注ぐ太陽光で発電できる。最も伸びるのが太陽光で、容量ベースで26年に天然ガスを、27年に石炭を抜く見通しだ。原材料の高騰で発電コストは増えるものの、大半の国では「最も低コストの電源」(IEA)になる。建物の屋根に設置する小規模発電も成長し、消費者の電力料金の負担軽減につながるとみる。風力は27年には水力を抜き、太陽光、石炭、ガスに続く4番目の電源になる。許認可の手続きや電力系統インフラの問題があり、太陽光よりも伸びは緩やかだ。27年までに増える再生エネのうち、太陽光と風力で計9割以上を占める。IEAのビロル事務局長は声明で「現在のエネルギー危機が、よりクリーンで安全な世界のエネルギーシステムに向けた歴史的な転換点になりうるという事例だ」と述べた。けん引するのは米国、欧州、中国、インドで規制改革や導入支援策を拡充している。ウクライナ侵攻の影響を大きく受ける欧州連合(EU)はエネルギーの脱ロシア戦略「リパワーEU」を打ち出し、再生エネの導入目標を引き上げようとしている。米国は今夏成立したインフレ抑制法で再生エネのほか、電気自動車(EV)の普及や水素技術の開発など脱炭素化に重点を置いた。中印は火力発電も温存しながら、再生エネの拡大にも力を入れている。中国は27年までの世界の再生エネの新規容量のほぼ半分を占める勢いだ。各国は太陽光パネルの製造などサプライチェーン(供給網)の多様化にも力を入れている。米国とインドが投資を増やすため、足元では9割の生産能力を持つ中国のシェアが27年には75%に低下する可能性がある。 *3-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221223&ng=DGKKZO67083440T21C22A2EA2000 (日経新聞 2022年12月23日) 150兆円投資 見えぬ具体策、GX基本方針、再エネ拡大難路 脱炭素へ勝負の10年 政府は22日に取りまとめたGX(グリーントランスフォーメーション)に関する基本方針をもとに脱炭素投資を加速する。今後10年で官民で150兆円超を見込む。ただ再生可能エネルギーの大型案件は乏しく、民間資金が集まるかも見通しにくい。50年の脱炭素化と足元の電力供給の安定に向けた勝負の10年となるが、大きな金額になるだけに日本の産業競争力を高める実のある投資にする必要がある。 ●大型案件乏しく 政府は150兆円超の投資のうち再生エネの大量導入に約31兆円を想定している。日本の発電量に占める再生エネは2021年にやっと20%を超えた。30年度に36~38%にする目標の達成には太陽光や風力発電を大幅に増やす必要がある。ただ、具体的な再生エネの大型案件は見えていない。景観や安全性への懸念から地元自治体が反対する事例が増えた。開発案件から撤退する大手電力も相次ぐ。再生エネも原発や火力と同じように地元の協力が欠かせないが、国のサポート体制に課題が多い。世界で再生エネの主流となった洋上風力は国土交通省、総務省、自治体などに所管が細かく分かれ、一体的な調整ができていない。基本方針では「再生エネを最大限活用」と明記した。ただ橘川武郎国際大学副学長は16日の経済産業省の有識者会議で「電力が足りないという危機になれば、主力電源の再生エネをどうするかとの話から入るのが普通だが、その話はわずかだった」と疑問を呈した。11年の東日本大震災の直後から課題を指摘されながら、ようやく着手するのが送電網の強化だ。政府は今後10年間で原発10基の発電能力にあたる約1000万キロワット分の広域送電網を整備する。官民の投資による脱炭素産業の育成も欠かせない。再生エネ技術は太陽光パネルなど日本がリードしていたものが多い。ただ開発や実用化の段階で先行しても、量産・普及段階で中国や欧州のグリーン投資で一気に追い抜かれた事例が続く。天候に発電量が左右される再生エネを生かすには蓄電池の大型化やコスト低減が欠かせない。政府は蓄電池産業の確立に官民で7兆円規模を投じる戦略を描く。政府目標では「国内マザー工場の基盤確立」といった項目が並ぶが、競争力が高まるかは見通せない。足元では蓄電池もパナソニックホールディングスより中韓メーカーの方が勢いがある。日本が開発で先行するペロブスカイト型といった次世代太陽電池も今回の投資対象だが、対応を誤れば中国メーカーなどに普及期に抜かれかねない。水素技術も脱炭素の達成には必要で、再生エネから効率よく水素を製造し、貯蔵する技術が今後のカギとなる。水素燃料を得やすくなれば航空機や船舶、製鉄など排出量の比較的多い産業の脱炭素化につながる。 ●排出負担軽く ただ、企業に脱炭素を促す仕組みは遅れている。炭素を値付けして排出に負担を求めるカーボンプライシングの本格導入時期は30年代と遅く、負担も欧州などより軽い。炭素価格は高いほど排出時に負担がかかり企業の抑制意識が高まる。今回の議論では企業の負担が大きく増えないようにガソリンなどにかかる税負担が今後減る範囲内での導入にとどめた。どういったカーボンプライシングなら気候変動対策に効果的かといった本質的な議論でなく、GX債の償還財源の確保目的に終始した面もある。世界では再生エネが急速に普及する。国際エネルギー機関(IEA)によると22年の新規導入容量は319ギガワット。年間の新規導入容量として過去最大だった21年を超える。欧州連合(EU)は26年から炭素価格が低い国からの輸入品に対して事実上の関税をかける国境炭素調整措置の導入を決めた。日本の対策が遅れれば、欧州などで再生エネの電気を使って生産する製品との差が出て競争力に響きかねない。今回の基本方針は、中長期のエネルギー政策を数年ごとに改定するエネルギー基本計画に匹敵するほどの大きな政策転換といえる。議論が拙速で不十分な点も多いが、それらを早期に補強しながら政府や企業が対策に取り組まないと世界との差は開くばかりだ。 *3-1-3:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2022122500078 (信濃毎日新聞社説 2022/12/25) GX実行会議 議論の方向間違っている 脱炭素社会の実現には、化石燃料を再生可能エネルギーに転換させる社会や経済の改革が必要だ。その議論が尽くされていない。政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」である。7月から5回開き、脱炭素化に向けた基本方針を決めた。東京電力福島第1原発事故後に「依存度低減」としてきた原発政策を「最大限活用」に変え、新規建設や長期運転に踏み込んだ。一方で、主力電源と位置づける太陽光や風力といった再エネをどう拡大させていくのか。先行きは見通せていない。優先すべき課題は、2030年までに二酸化炭素(CO2)排出量をほぼ半減させることだ。政府は、ウクライナ戦争に伴うエネルギー危機への対応も強調する。いずれも原発は間に合わず、主力になり得ない。なぜ再生エネのさらなる普及策を徹底的に議論し、打ち出さないのか。脱炭素やエネルギー危機を名目に、原発回帰にお墨付きを与えるための会議だったとしか思えない。GX実行会議は、省庁横断で政策を検討するために設置された。ところが、岸田文雄首相は、経済産業相を担当に任命。たたき台も含めて議論は、原発推進の旗を振る経産省のペースで進んだ。首相自身も初会合で、原発に触れて「政治決断が求められる項目の明示を」と仕向けている。議論は非公開で、外部委員は財界や電力会社の関係者らだ。原発に慎重な考えを持つ人たちを避けて、短期間で政策を転換させた。太陽光の方が安い発電コスト、巨額に上る建設費や維持費、災害や戦争のリスクといった問題が詳細に検討されたとは言い難い。あまりに拙速だ。自然エネルギー財団は、原発に頼らず再生エネの大幅導入と水素の利用で脱炭素化できると分析している。こうした専門家や次代を担う若者も交えて、国民の見える場で議論するべきだ。政府は新たな国債「GX経済移行債」で調達する資金を、次世代型原発の研究開発にも充てる方針を示している。実用化が不確かで、放射性廃棄物の処理問題を抱える原発への投資は誤りだ。部品を外国製に頼る太陽光や風力にこそ投資を向けねばならない。脱炭素社会の構築は、人類にとって持続可能な地球を残すことに意味がある。廃棄物を次世代に先送りする原発は本来、脱炭素社会と相いれない。政策の転換を撤回し、議論し直すよう求める。 *3-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221219&ng=DGKKZO66947400Z11C22A2MM8000 (日経新聞 2022.12.19) 送電網、10年で1000万キロワット増 政府計画、再生エネを広域融通 北海道―本州で海底線新設、九州―本州は2倍 政府は今後10年間で原子力発電所10基の容量にあたる約1000万キロワット分の広域送電網(総合・経済面きょうのことば)を整備する。過去10年の8倍以上のペースに高める。太陽光や風力など再生可能エネルギーによる電気を無駄にせず、地域間で効率よく融通する体制を整える。脱炭素社会の重要インフラとなるため、事業主体の電力会社の資金調達を支援する法整備も急ぐ。岸田文雄首相が近くGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議で整備計画を表明する。日本は大手電力会社が地域ブロックごとに事業をほぼ独占し、競争原理が働きにくい状態が続いてきた。2011年の東日本大震災では広域で電力をやりとりする送電網の脆弱さがあらわになった。大都市圏が夏冬の電力不足に直面する一方、九州では春に太陽光発電の出力を抑えるといった事態が続いている。50年の脱炭素には再生エネの発電に適した北海道や九州の電気を、東京や大阪に送って消費する体制が欠かせない。ウクライナ危機でエネルギーの供給不安も高まった。地域間の連系線の抜本的な強化を急ぐ。新たに日本海ルートで北海道と本州を結ぶ200万キロワットの海底送電線を設ける。30年度の利用開始をめざす。30年度の発電量のうち、再生エネの割合を36~38%にする政府目標の達成に必要とみている。九州―本州間の送電容量は278万キロワット増やして、556万キロワットにする。27年度までに東日本と西日本を結ぶ東西連系線は90万キロワット増の300万キロワットに、北海道―東北間は30万キロワット増の120万キロワットに、東北―東京エリア間は455万キロワット増の1028万キロワットに拡大する。東西連系線については28年度以降、さらに増強する案もある。過去10年の整備量は東西連系線と北海道―東北間であわせて120万キロワットにとどまっていた。今後10年間は8倍以上に加速させる。巨額の費用の捻出は課題となる。北海道―本州間の海底送電線は1兆円規模の巨大プロジェクトで、九州―本州間の連系線は約4200億円を要するとみている。電力会社を後押しするため、資金調達を支援する枠組みを整える。いまの制度では送電線の整備費用を電気料金から回収できるのは、完成して利用が始まってからとなる。それまでは持ち出しが続くため投資に及び腰になりかねなかった。必要に応じて着工時点から回収できるように改める。23年の通常国会への関連法案の提出をめざす。例えば、海底送電線の建設期間中に計数百億円規模の収入を想定する。初期費用の借り入れが少なくて済み、総事業費の圧縮にもつながると期待する。50年までの長期整備計画「マスタープラン」も22年度内にまとめる。原案では北海道―本州間の海底送電線を3兆円前後で計800万キロワットに、東西連系線は4000億円規模で570万キロワットに増強する。50年までの全国の整備費用はトータルで6兆~7兆円に上ると見込む。 3-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221221&ng=DGKKZO67012450Q2A221C2EP0000 (日経新聞 2022.12.21) 送電網利用料引き上げ 10社、来年度から最大16% 東京電力パワーグリッド(PG)など送配電会社10社は電力小売会社から受け取る送電網の利用料「託送料金」を2023年度から引き上げる。送電網の増強やデジタル化といった投資に充てる。1キロワット時あたりの単価は会社によって異なり、4.4~16.0%の範囲での値上げとなる見通しだ。経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会が20日、各社が提出した収入見通しの検証を終えた。10社の27年度までの5年間の年平均の収入を合算すると4兆6836億円になる。現行コストの場合と比べて4.5%増える。もともと6.5%増の計画を出していたが、監視委の査定で圧縮された。10社は今後、23年4月1日からの新しい託送料金を申請する。各社の計画によると1キロワット時あたりの料金単価は企業や家庭向けを合計した場合、東電PGで4.4%増の5.49円。関西電力送配電は7.3%増の5.30円、中部電力PGは7.6%増の4.98円となる。 *3-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221223&ng=DGKKZO67083690T21C22A2MM8000 (日経新聞 2022年12月23日) 原発建て替え具体化を明記 GX基本方針、震災後のエネ政策転換 政府は22日、GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議を開き、脱炭素社会の実現に向けた基本方針をまとめた。原子力について「将来にわたって持続的に活用する」と明記した。廃止が決まった原子力発電所を建て替え、運転期間も現在の最長60年から延長する。東日本大震災以来、原発の新増設・建て替えを「想定しない」としてきた政策を転換するが、実現には課題が多く実行力が問われる。岸田文雄首相は会合で「法案を次期通常国会に提出すべく、幅広く意見を聞くプロセスを進めていく」と述べた。パブリックコメントを経て2023年2月までに閣議決定し、政府の正式な方針にしたうえで法案提出をめざす。方針では再生可能エネルギーと原子力について「安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」と記載した。50年の温暖化ガス排出量を実質ゼロにする目標と電力の安定供給の両立につなげる。原発については「次世代革新炉の開発・建設に取り組む」と掲げ、「まずは廃止を決定した原発の建て替えを対象に具体化を進めていく」と記した。建て替え以外の開発・建設については「今後の状況を踏まえて検討していく」とした。運転期間の延長については原則40年、最長60年とする制限を維持したうえで「一定の停止期間に限り、追加の延長を認める」と盛った。原子力規制委員会による安全審査を前提に震災後の審査で停止していた期間などの分を延長する。認められれば60年超の運転が可能になる。政府は11年の東京電力福島第1原発事故を受け、原発の新増設や建て替えは「想定していない」との見解を示してきた。原則40年、最長60年とする運転期間も導入した。今回の基本方針で見直すことになる。原子力政策を巡っては進展していない課題が多い。例えば原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)は最終処分場が決まっていない。「バックエンド」と呼ばれる問題で解決できなければ原発を長期に使っていくのは難しい。首相は22日の会議で「最終処分につながるよう関係閣僚会議を拡充する。政府をあげバックエンドの問題に取り組んでいく」と述べた。基本方針に沿って進展するかは見通せない。関西電力美浜原発などが建て替えの候補地とみられているが、政府は具体的な候補地は示していない。建設費用は1兆円規模ともされ、多額の投資費用を回収する見込みがなければ電力会社は建設を決めにくい。33基ある原発のうち14基は再稼働済みか再稼働のメドが立った。一方、安全審査に合格したものの地元の同意が得られていない原発3基を含む19基は再稼働の見込みが立っていない。政府は前面に立ち再稼働を目指すとするが具体策は乏しい。 *3-3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15509882.html (朝日新聞 2022年12月23日) 原発建設へ転換 60年超す運転も可、政府方針 脱炭素、GX会議 政府は22日、原発の新規建設や60年を超える運転を認めることを盛り込んだ「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実現に向けた基本方針案」をとりまとめた。来年に閣議決定し、関連法の改正案を通常国会に提出する。岸田文雄首相の検討指示からわずか4カ月で、2011年の東京電力福島第一原発事故後に堅持してきた政府の方針が大きく転換する。50年の脱炭素社会の実現に向けた取り組みを議論するGX実行会議(議長・岸田首相)が官邸で開かれ、基本方針案が了承された。基本方針案では、原発を「最大限活用する」として二つの政策転換を打ち出した。一つは原発の新規建設だ。政府はこれまで「現時点では想定していない」としてきたが、「将来にわたって原子力を活用するため、建設に取り組む」と明記した。まずは廃炉を決めた原発の建て替えを具体化する。政府が「次世代革新炉」と呼ぶ、改良型の原発を想定している。原発のない地域に建てる新設や増設についても「検討していく」とした。もう一つは、原発の運転期間の延長だ。原発事故の教訓をもとに原則40年、最長20年延長できると定めたルールを変える。この骨格は維持しつつ、再稼働に必要な審査などで停止した期間を運転期間から除く。仮に10年間停止した場合、運転開始から70年まで運転できるようになる。事故後の原子力規制の柱としてきたルールが形骸化するおそれがある。 ■<視点>電力危機に乗じた「回帰」 岸田政権が、原発政策を転換する道を選んだ。ウクライナ危機に伴う燃料高騰や電力不足、脱炭素への対応を強調し、再稼働の推進だけでなく、原発の新規建設や運転期間の延長に踏み込んだ。これは原発依存を続けることを意味する。だが、建設は早くても30年代。いま直面する問題の解決策にはならない。原発事故後に安全対策が強化され、建設には1兆円規模の費用がかかる。「核のごみ」を捨てる場所もない。重大事故が起きれば取り返しのつかない被害をもたらすことも経験した。それでも原発に頼り続けるのであれば、国民的な議論が必要だ。岸田政権はこれらの課題は残したまま、目の前の電気料金上昇や電力不足を強調し、原発推進の旗を振る経済産業省を中心にわずか4カ月で結論を出した。原発政策について、国が国民の声を聴いたことがある。原発事故の翌12年、当時の民主党政権は30年の原発比率を決めるために11都市で意見聴取会を開き、討論を通して意見がどう変わるかをみる「討論型世論調査」をした。導き出したのが「30年代に原発ゼロ」という目標だった。私たちの暮らしや企業活動の根幹に関わるエネルギー政策はどうあるべきか。再生可能エネルギーをもっと増やす選択肢は検討したのか。参院選後、解散がない限り国政選挙は3年間ない。時間をかけて丁寧に議論する好機でもあったはずだ。その機会を放棄し、「電力危機」に乗じた「原発回帰」は疑問だ。 *3-3-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15504298.html (朝日新聞 2022年12月17日) 原発回帰「結論ありき」 「新規建設・60年超運転」審議会が了承 経済産業省の審議会「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」は16日、原発の新規建設や運転期間の延長などを盛り込んだエネルギー安定供給の対策案をとりまとめた。月内に開かれる官邸のGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議で報告する。会議の冒頭、西村康稔経済産業相は「将来にわたって持続的に原子力を活用するため、まずは廃止決定した炉の次世代革新炉への建て替えを対象として具体化を進めていきたい」と話した。さらに、原則40年最長60年の運転期間については、一定の停止期間を除外することで延ばす方針も示し、了承された。原発政策の転換は、岸田文雄首相が8月のGX実行会議で検討を指示していた。経産省の複数の審議会で進めてきた具体策の議論はこの日で終えた。与党も同様の意見をとりまとめている。GX実行会議でも追認されるとみられ、事故以来の原発政策が大きく変わる見通しだ。 ■首相指示を追認・パブコメ後回し 岸田文雄首相の検討指示から3カ月あまり。経済産業省の審議会は、原発政策の転換について議論を終えた。政府は今後、国民から広く意見を募るパブリックコメントをする方針も示している。一方で、審議会の委員からは議論の進め方に「拙速」との声があがる。16日にあった基本政策分科会で示された方針の原案は、8日に開かれた別の審議会「原子力小委員会」でまとめられた。その日の会議の終盤、山口彰委員長がとりまとめにかかろうとしていた中、一人の委員から声があがった。日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の理事を務める村上千里氏だ。村上氏は「パブコメで聴いた意見を踏まえてもう一度議論をするのであれば、国民的な議論が一部なされたと言える。しかし、パブコメが後だと、スケジュール的に議論されないのではないか。納得できない」と主張した。さらに、「運転期間に関しては、この3カ月で出てきた案で議論が国民にも浸透しておらず拙速だ」と注文を付けた。原子力資料情報室事務局長の松久保肇氏も「(基本政策分科会に)報告する前にパブコメにかける必要がある。強引な進め方は政策に対する国民の信頼を損ねる」と続いた。原発に慎重な立場をとる専門家らからは、審議会などの進め方について「結論ありきだ」との批判がある。これに対し、西村康稔経産相は会見で「非常に慎重な方々のご意見のヒアリングなども行ってきている」などとかわすが、審議会は、首相が指示した検討内容に沿った経産省案を事実上、追認してきた。約20人いる原子力小委員会も、明確に「脱原発」の立場から発言するのは2人だけだ。松久保氏は「政策議論が非常に多様性を欠いている」と指摘。パブコメについて西村経産相は9日の会見で「適切なタイミングで実施する」と繰り返すだけだった。原発政策の転換について引き合いに出される事例がある。2011年の東京電力福島第一原発事故後に行われた「国民的議論」だ。当時の民主党政権は30年の原発比率の選択肢を複数示し、討論を通して意見がどう変わるかをみる「討論型世論調査」を取り入れた。さらに、全国11都市で開いた意見聴取会には約1300人が参加したという。こうしたやりとりを踏まえて、当時の民主党政権は「30年代に原発ゼロ」という方針を打ち出した。南山大の榊原秀訓教授は「今回は『討論型世論調査』など熟議型と呼ばれる議論の方法がとられていない。専門技術であったとしても素人の意見を反映するべきだというのが、熟議型とか討議型と呼ばれるものの理念だ。重要政策の決定手段が後戻りしてしまっている」と話す。 *3-3-4:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15513376.html (朝日新聞 2022年12月27日) 60年超原発「未知の領域」 世界に例なし、安全性どう審査 原発の60年超の運転期間を可能にする方針に伴い、安全審査を運転開始30年を起点にして10年を超えない期間ごとに実施する新ルールの骨子案を、原子力規制委員会がまとめた。国民から意見を募るパブリックコメントを実施中。ただ、海外でも60年超の原発はなく、規制委の審査は不透明な部分がある。海外では運転期間の上限がない国が多いものの、国際原子力機関(IAEA)によると現在、60年を超えて運転を続けている原発はない。60年超の安全規制は「未知の領域」(規制委の山中伸介委員長)だ。経済産業省の資料では、米国の運転期間は40年だが、安全審査をクリアすれば20年以内の延長が何度でも可能。1回目の運転延長が認められて40年超の運転に入った原発が2回目の延長を申請し、80年の運転延長が認められた例もある。英国やフランスは、運転期間の制限がない。10年ごとに安全審査があり、運転が認可される仕組みだ。長期の運転をするということは、老朽化対策を含めたコストの増大や、自然災害のリスクにさらされ続けるという側面がある。国の政策転換によって運転ができなくなったケースもある。経済的な理由によって運転をやめた原発もある。フランスでは原子力への依存を段階的に減らす計画の一環として、1977年に稼働を開始した同国内最古の原発が2020年に停止された。ドイツでは東京電力福島第一原発事故後の脱原発政策で8基が停止を命じられた。米国では17~18年ごろ、電力価格低迷などの影響を理由に運転期間が残っていても廃炉を決める原発が相次いだ。日本では地震や津波、火山の噴火、台風などのリスクが比較的大きい。原発事故後、規制委は自然災害への備えの強化や過酷事故対策を義務づけた新規制基準をつくったが、規制委は基準に適合しているかどうかを審査しているに過ぎない。審査をクリアした原発でもリスクは残る。 ■配管など劣化、40年未満でも事故 老朽化のリスクはさまざまだ。原子炉の金属が中性子を浴び続けるともろくなる現象「中性子照射脆化(ぜいか)」のほか、コンクリートの遮蔽(しゃへい)能力や強度は原発が停止していても経年劣化する。東京大の井野博満名誉教授(金属材料工学)は「中性子照射脆化は防ぐ手立てがなく、運転期間が延びれば延びるほど脆化が進むため、その分、リスクも高まる。原発は30年ないし40年運転を前提として設計されており、長期間運転すると原子炉に入れてある監視試験片(原子炉の劣化を予測するための金属片)も足りなくなる。これが運転上の深刻なネックになり、安全性に不安が生じる」と話す。配管やケーブルといった部品の劣化もある。40年未満でも事故は起こる。東京電力柏崎刈羽原発では10月、運転開始25年の7号機タービン関連設備の配管に直径約6センチの穴が開いたと発表。足場を組んだ際に傷がつき、周辺へ腐食が進行。11年ぶりにポンプを稼働させたところ、内側に引っ張られる形で穴が開いたとみられるという。2004年には関西電力美浜原発3号機でタービン建屋の配管が破裂して放射性物質を含まない蒸気が噴出する事故が起き、作業員5人が死亡、6人が重傷を負った。配管の厚みが減っていたという。規制委の山中委員長は21日の会見で、60年目以降についての審査について「50年目の検査に加えて新しい項目を、それぞれのプラント(原発)について特異なものを加えていく必要がある」と述べた。だが、具体的にどうやって安全性を確認するのか示されないままだ。 ■経過措置は「1~3年」 規制委 原子力規制委員会は26日、新たな安全審査のルールの骨子案について、原子力事業者の担当者らとの意見交換会を開いた。規制委側は、新ルールへの経過措置の期間を「1~3年程度」と説明。事業者側からは今後の具体的なスケジュールなどについて質問が相次ぎ、年明けに2度目の会合を開くことになった。事業者などでつくる「原子力エネルギー協議会」の担当者がオンラインで参加した。事業者側は骨子案について「特段の意見はない。事業者として適切に対応していく」と述べた。一方で、具体的な内容が示されていない新ルールで提出が求められる書類の記載内容や、具体的なスケジュールについて質問が相次いだ。規制委の事務局・原子力規制庁の担当者は、30~50年の審査は現行の手法を踏襲するとして「現制度でやっていることを基本的に変えずに移行しようと考えている。現行制度下でやらないといけない安全対策をやっていただければ対応できる」と説明した。 ◆キーワード <原子力規制委員会の新ルールの骨子案> 運転開始30年を起点に、以後10年を超えない期間ごとに事業者による原子炉の劣化評価や長期施設管理の計画を規制委が審査する。30~50年の審査は現行の手法を踏襲する。60年超の原発の審査については、議論が先送りされた。現在のルールでは、新規制基準への適合性が認められていない原発(未適合炉)は運転開始40年の時点で運転できなくなるが、新ルールでは、未適合の状態で40年を超えても再稼働できる可能性が開かれる。 *3-3-5:https://www.kochinews.co.jp/article/detail/618170 (高知新聞社説 2022.12.25) 【原発60年超運転】規制委の独立性はどこへ 原子力行政の変質はもはや明らかだろう。原子力規制委員会が、原発の60年を超える長期運転を認める安全規制の見直し案を了承した。現行の規制で「原則40年、最長60年」とされる運転期間は制度上、上限がなくなる。原発を最大限活用する政府方針を追認したと言え、法改正に向けて着々と手続きを進める政府と、完全に歩調を合わせた格好だ。国民の目に規制組織の独立性がゆらいだと映れば、原発そのものへの不信につながりかねない。新たな制度案は、運転開始から30年を迎える原発について、10年以内ごとに設備の劣化状況を繰り返し確認することが柱となる。電力会社には長期の管理計画を策定し、規制委の認可を得るよう義務付ける。規制委は意見公募や電力会社との意見交換を経て、原子炉等規制法の改正案を来年の通常国会に提出する見通しだ。現行の規制で運転期間を40年、60年とする根拠を問う声もあるが、どんな機器も経年劣化は免れまい。安全性への信頼度も低下しよう。明確な基準を設けること自体が、原発依存度の低減という民意を象徴していたといってよい。これまで山中伸介委員長も「経年劣化が進めば進むほど、規制基準に適合するかの立証は困難になる」と説明していた。しかし規制委は今回、運転が60年を超えた原発の安全性をどう確認するか具体的な方法を示すことなく、詳細の検討を先送りにした。こうした対応では、国民が抱える安全性への不安を置き去りにしたと非難されても仕方があるまい。技術的な問題に加え、見直し案の了承に至る経緯は看過できない問題をはらんでいる。東京電力の福島第1原発事故まで規制行政は、電力業界を所管する経済産業省の枠組みの中に位置付けられていた。推進側と規制側が同居する構造で生じたゆがみは、国会の事故調査委員会に事故の背景として指摘され、「(電力業界の)虜(とりこ)」と断罪された。その反省から設置された規制委にとって、独立性と中立性の担保は組織の出発点であり、根幹にほかならない。それにもかかわらず、推進側の経産省との協議は山中委員長の就任から実質3カ月ほどでスピード決着した。事故の最大の教訓だった規制と推進の分離は形骸化し、いつの間にか原発回帰の「両輪」に変質してしまったのではないか。政府は、脱炭素社会の実現に向けた基本方針を決定し、原発の60年を超える運転期間延長や、次世代型原発への建て替えなど原発推進策を盛り込んだ。この姿勢にも疑問を禁じ得ない。事故後掲げてきた原発依存度の低減から方針を転換するのであれば、国民的な議論で合意を得るべきだ。その手順を踏むことなく、法改正を先行させようとする手法は乱暴で拙速に過ぎる。事故の教訓をないがしろにすることは許されない。 *3-3-6:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/969244 (佐賀新聞 2022/12/29) 「原発政策転換」根拠も正当性も薄弱だ 岸田文雄首相は、新増設や運転期間延長など原発政策の大転換を決めた。エネルギーの安定供給と気候変動対策への貢献が理由だが、その根拠は極めて薄弱だ。国の将来を左右するエネルギーに関する重要な政策転換を、非民主的な形で決めるというプロセスには正当性もない。拙速かつ稚拙な政策は棚上げし、エネルギー政策についての熟議の場をつくるべきだ。首相は「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」で「将来にわたって持続的に原子力を活用する」とし、次世代型原発の開発と建設を明記。再生可能エネルギーと原発を「最大限活用する」とした。2011年の東京電力福島第1原発事故後、続けてきた「可能な限り原発依存度を低減する」との方針からの大転換だ。世界はロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー危機と気候危機という二つの危機に直面している。これにどう立ち向かうかという問いへの答えの一つとして、首相が持ち出したのが原子力の拡大だった。だが、日本のような先進国にとって最も重要なのは、30年までの温室効果ガス排出量を大幅に削減することだ。新増設は言うまでもなく、既設炉の再稼働でさえ、短期的な排出削減への貢献は少ない。重要なのは計画から発電開始までの時間が短い再生エネの大幅拡大だ。長期的にも、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)や国際エネルギー機関(IEA)などの国際組織が気候危機対策として重要視しているのは省エネと再生エネで、原子力はコスト面でも削減可能性でも劣る。エネルギー危機への対応は、低コストの電力を長期的に供給することが重要だが、この点への原子力の貢献も疑わしい。国際的な研究機関の分析では新設原発の1キロワット時当たりのコストは約13~20セント(17~26円)。商業的な太陽光の同3セント前後とは比べものにならない。海外に比べてまだ高い日本の再生エネのコストも低下傾向にある。逆に福島事故後の新たな安全対策などによって原発の発電コストは上昇傾向にある。原発による価格低減効果は限定的だ。福島の事故は、原発のような大規模集中電源に過度に依存することが安定供給上の大きなリスクになることを示したはずだ。安価な再生エネによる小規模分散型の発電設備への投資を拡大するのが本筋だ。今回の決定は、内容にも問題があるが、それ以上に大きな過ちは政策決定に至るプロセスだ。政策を決めた官邸のGX実行会議で首相が原発政策転換の意思を示したのは8月末だった。以来、経済産業省が傘下の委員会などで急ごしらえの報告書を作成、4カ月後のGX会議で方針が決まった。同会議は電力会社や既存の大企業の代表が中心で、議論はすべて非公開と不透明極まりない。自由化された電力市場で競争にさらされる日本の電力会社自身は、新増設に必要な資金を調達することが難しいことを認めている。欧米では巨額の建設費が障害となり、政府が推進方針を示しても、原発建設が進まないという状況が続いている。日本でも同様だろう。内容面でも手続き面でも多くの問題を含む今回の政策を見直す時間は十分にある。 *3-3-7:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15509791.html (朝日新聞社説 2022年12月23日) 原発政策の転換 熟議なき「復権」認められぬ 根本にある難題から目を背け、数々の疑問を置き去りにする。議論はわずか4カ月。広く社会の理解を得ようとする姿勢も乏しい。安全保障に続き、エネルギーでも政策の軸をなし崩しにするのか。岸田政権が、原発を積極的に活用する新方針をまとめた。再稼働の加速、古い原発の運転延長、新型炉への建て替えが柱だ。福島第一原発事故後の抑制的な姿勢を捨て、「復権」に踏み出そうとしている。到底認められない。撤回し再検討することを求める。 ■拙速とすり替え 首相が原発推進策の検討を指示したのは8月下旬だ。重大な政策転換にもかかわらず、直前の参院選では建て替えなどの考えは明示しなかった。そして選挙後に一転、急ピッチで検討を進めた。民主的なやり方とはとても言えない。新方針は、原発依存の長期化を意味する。原発事故後に掲げられてきた「可能な限り依存度を低減」という政府方針の空文化にもつながる。問題設定の仕方にも、すり替えや飛躍が目立つ。8月の指示で首相は「電力需給逼迫という足元の危機克服」と「GX」(脱炭素化)への対応を原発活用の理由に挙げた。だが、足元の危機と原発推進は時間軸がかみ合わない。再稼働には必要な手順があり、供給力が急に大きく増えるわけではない。運転延長や建て替えは、効果がでても10年以上先の話だ。実現性も不確かで、急いで決める根拠に乏しい。政策の優先順位も転倒している。原発推進に熱をあげるが、安定供給と脱炭素化の主軸は国産の再生可能エネルギーのはずだ。政府も主力電源化を掲げている。まず再エネ拡大を徹底的に追求し、それでも不十分なら他の電源でどう補うかを考えるのが筋だ。 ■数々の疑問置き去り 新方針の内容そのものにも、多くの疑問がある。原発は古くなるほど、安全面での不確実性が高まる。「原則40年、最長60年」の運転期間ルールは、福島第一原発の事故後に与野党の合意で導入され、原子力規制委員会が所管する法律にも組み込まれた。ところが、新方針ではこのルールを経済産業省の所管に移し、規制委の審査期間などの除外を認めて、60年を超える運転に道を開く。議論を避けて長期運転を既成事実化するやり方であり、「推進と規制の分離」をも骨抜きにしかねない。建て替えは、経済性への不安が強い。新型炉の建設費は膨張が見込まれ、政府は業界の求めに応じて政策的支援を打ち出した。国民負担がいたずらに膨らむことになりかねない。新方針がうたう「次世代革新炉の開発・建設」も、当面の現実性があるのは、海外では実用化済みの安全装置を従来型に加えた「改良版」だ。安全面の「革新性」は疑わしい。安全性に関しては、日本には激甚な自然災害が多いことに加え、ウクライナで起きたような軍事攻撃の危険に対処できるかといった懸念もある。何より根源的なのは、使用済み核燃料や放射性廃棄物の扱いだ。原発に頼る限り、生み出され続ける。しかし、核燃料サイクルや最終処分への道筋は、何十年かけても実現が見えていないのが現状だ。これらの問いに、新方針は答えていない。不安に乗じて推進の利点ばかり強調し、見切り発車する構図は、先般の安保政策転換とうり二つである。この4カ月を振り返れば、結論と日程ありきのごり押しだったと言うしかない。 ■事故の教訓を土台に 経産省の審議会では、目的のはずのエネルギーの安定供給に原発が具体的にどの程度役立つかすら、精査されなかった。多く時間を費やしたのは、推進を前提にした運転延長や新型炉建設のやり方についてだ。委員は原発の推進論者が大半で、一部の慎重派が1年ほどかけて国民的な議論を進めるよう求めたが、一蹴された。原発は、国論を二分してきたテーマである。政策の安定には社会の広い理解が不可欠だ。さまざまな意見に耳を傾けて方策を練る手順を軽んじれば、事故で失った信頼は戻らない。政府は今後、国民から意見を募り、対話型の説明会も検討するという。だが、ただの「ガス抜き」なら意味がない。そもそも実のある議論には、原発に利害関係がない人や慎重な人も含め、幅広い分野の識者にもっと参加してもらうことが欠かせない。脱炭素の実現に向けて原発の活用は必須なのかなど、おおもとの位置づけからの多角的な熟議が必要だ。国会の役割もきわめて大きい。各政党が、主体的に議論を起こしてほしい。拙速な政策転換は許されない。事故の惨禍から学んだ教訓を思い起こし、将来への責任を果たす道を真剣に考えるべきときである。 *3-4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221204&ng=DGKKZO66533040U2A201C2MM8000 (日経新聞 2022年12月4日) ガス火力の建設支援 7~8基、電力逼迫に対応 経産省、事業者募集へ 経済産業省は今後の電力不足に対応するため液化天然ガス(LNG)を燃料に使う火力発電所を緊急で建設する方針だ。2030年度までの運転開始を念頭に7~8基相当の600万キロワットをつくる。建設費を投資回収しやすくする支援策を講じ、建設・運転する企業を募る。LNGの価格高騰でコストの見極めが難しく、企業が脱炭素の観点で慎重になる可能性もある。23年度から25年度までの3年間に企業を募り、計600万キロワット分のガス火力の建設をめざす。国内の冬や夏の最大需要の3%余りにあたる。大手電力会社が持つ火力発電所は運転開始から20~29年を経過しているものが3分の1程度と老朽化が進む。経産省は30年ごろまでに900万キロワット減少する恐れがあるとみている。最新のガス火力は二酸化炭素(CO2)の排出量が相対的に少ない。石炭火力からガス火力に建て替えれば排出量は半分程度になる。日本は再生可能エネルギーの導入や原発の再稼働が遅れている。ガス火力は主力電源で年間発電量に占める割合が最も大きく、21年度に34%ある。ガス火力発電所の建設には数年かかる。30年度に間に合うよう新規案件だけでなく既に設計や建設に着手した案件も支援対象にする。23年度に導入予定の「長期脱炭素電源オークション」の仕組みを使い、事業者を支援する。電力小売りから集めたお金を原資に、運転開始から20年間は発電事業者が毎年一定の収入を得ることができ、投資回収のメドが立ちやすくなる。燃やしてもCO2が出ない水素などを火力発電所で混焼するといったケースが本来は対象だが今回は例外として排出削減対策を当面、猶予する。水素を燃料に混ぜるといった対策を運転開始から10年以内に導入し、50年時点で排出実質ゼロにすることを求める。国内では3月の福島県沖の地震で複数の火力が停止し、電力需給逼迫警報を出す事態となった。経産省は今夏に続き12月から全国で節電を呼びかけている。建設が実現するかは、コストとの見合いを電力会社などがどうみるかが焦点となる。火力発電の稼働は再生エネの普及拡大を受けて収益性が悪化する傾向にある。火力発電所の建設には1000億円前後の投資が必要で、政府が支援策を講じても電力会社などが応募するかは見通せない面もある。今回の対策は中長期の脱炭素化を条件とするものの、短期的には脱炭素の動きと逆行すると海外では受け取られかねない。その点も企業や金融機関の判断に影響する可能性がある。 *3-4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221117&ng=DGKKZO66056060X11C22A1MM0000 (日経新聞 2022.11.17) 日本の貿易赤字2.1兆円 10月で最大 円安・資源高で 財務省が17日発表した10月の貿易統計速報によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は2兆1622億円の赤字だった。10月としては、比較可能な1979年以降で最大の赤字となった。円安と資源高により、輸入額が前年同月比で大幅に増えた。貿易赤字は15カ月連続で、3カ月続けて2兆円を超える赤字となった。10月以外を含めると、過去5番目に大きい赤字だった。輸入は11兆1637億円で、前年同月比で53.5%増えた。原油や液化天然ガス(LNG)、石炭などの値上がりが響いた。原油の輸入価格は1キロリットル当たり9万6684円と79.4%上昇した。ドル建て価格の上昇率は37.7%だった。円安が輸入価格の上昇に拍車をかけている。輸出は25.3%増の9兆15億円だった。米国向けの自動車や韓国向けのIC(集積回路)などが増えた。輸入は8カ月連続で、輸出は2カ月連続でそれぞれ過去最大を更新した。輸入の増加ペースが輸出を大きく上回り、赤字が拡大している。荷動きを示す数量指数(2015年=100)は、輸入が前年同月比で5.6%上がったのに対し、輸出は0.3%下がった。中国向けの輸出は16.0%の急激な落ち込みとなった。消費不振や住宅不況による中国経済の減速が響いたとみられる。10月の貿易統計を季節調整値でみると、輸入は前月比4.2%増の11兆2054億円、輸出は2.2%増の8兆9063億円、貿易収支は2兆2991億円の赤字だった。 *3-5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221223&ng=DGKKZO67078350S2A221C2FFE000 (日経新聞 2022年12月23日) アジアこれがヒット(下)2023年予想 EV普及元年、低価格競う、タタ自は135万円、予約殺到 先行中国は東南アで攻勢 観光業の復活など新型コロナウイルス後を見据えた動きが出てきた2022年。日本経済新聞社が予測する23年のアジアにおける消費の主役は、電気自動車(EV)だ。インドのタタ自動車が低価格を武器に販売を伸ばし、比亜迪(BYD)など中国勢も東南アジアで攻勢をかける。アジア全域でEVが普及し始め、シェア争いが激しくなる。アジアで強力な低価格EVが現れた。タタ自が23年1月以降に納車を予定する「ティアゴ」だ。最初の1万台限定で84万9000ルピー(約135万円)からと、100万ルピー台の同社の既存EVに比べて大幅に安くした。価格の衝撃は大きく、同社によると、10月の予約開始の初日だけで1万台を超える注文が殺到した。「インドで最も待ち望まれ、最も価格が手ごろなEVだ」。地元メディアはそう評する。タタ自が限定価格の対象台数を増やしたところ、11月下旬までに累計2万台を超え、21年のインドのEV乗用車販売台数をも上回った。かつて20万円台という超低価格のガソリン車「ナノ」を投入したが、品質面で敬遠され販売が伸び悩んだ。低価格のEVに再挑戦する背景には、急速に拡大するEV市場で次こそ失敗は許されないとの危機感もある。インドネシアでは中国勢と韓国勢が低価格で競っている。上海汽車集団のグループ会社で格安EVを手掛ける上汽通用五菱汽車が、8月に世界市場向け小型車「エアev」を発売した。価格は約200万円からと、現代自動車の主力モデル「アイオニック5」の3割程度に抑えた。日本勢が主軸とするガソリン車のミニバンよりも安い。エアevの販売シェアが7割以上と市場をけん引する。11月にバリ島で開かれた20カ国・地域首脳会議(G20サミット)では、公用車として300台が使われ、存在感を一段と高めた。中国自動車大手の奇瑞汽車も攻勢を強める。7月にはインドネシアで約約1300億円を投資し、生産能力20万台規模の工場を現地に建設する方針を明らかにした。現地メディアによると、23年後半にもEVを発売する予定という。ベトナムのビングループも大胆なEV転換を掲げた。「年内にガソリン車の生産を中止する」。傘下で自動車の製造・販売を手掛けるビンファストは、EV専業メーカーになると宣言した。11月末からは米国に輸出を始めた。価格は米テスラの約半分に設定した。ベトナム国内でも高価な電池をリース方式にしてEVの価格を抑え、政府も様々な優遇策で支援して拡大を進める。 ●テスラも対抗 EVを強化する現地企業に対し、テスラも対抗に乗り出した。タイ市場への正式参入を決めた。東南アジアではシンガポールに次いで2カ国目だ。23年1~3月期中に納車を開始し、サービスセンターや充電設備も開設する。主力の「モデル3」の価格はこれまで並行輸入で約1100万円かかったが、約700万円からと大幅に下がる。EVは中国が先行してきた。BYDは主力の「王朝シリーズ」と「海洋シリーズ」を軸に約200万~400万円の中価格帯の需要を開拓しており、22年通年の新車販売台数は200万台に迫る勢いだ。その中国勢も需要が見込める東南アジアに目を向け始めた。22年からEVの海外展開を本格的に始め、すでにシンガポールで高い人気だ。 ●対応急ぐ日本勢 韓国では現代自のアイオニックシリーズが国内や欧州などで好調で、インドネシアでも若年層を狙った販売促進に力を入れる。台風の目となりそうなのが、台湾の自動車大手、裕隆汽車製造(ユーロン)だ。同社が開発・生産を手掛ける初の個人向けEV「LUXGEN(ラクスジェン)n7」の納車を23年後半から始める予定だ。ユーロンとEV合弁を組む電機大手の鴻海(ホンハイ)精密工業は、米国でも別のEVを生産するほか、タイでは国営のタイ石油公社(PTT)と合弁で工場を立ち上げる。英調査会社LMCオートモーティブは「タイとインドネシアを中心に東南アジア各国で、EVは予想より早く普及する」と予測。その上で、「長らく日本の自動車ブランドが支配的だった市場において、新規参入余地が大きくなっている」と指摘する。負けられない日本勢も、トヨタ自動車がタイでEV「bZ4X」を投入。高級車ブランド「レクサス」以外では初のEV投入となる。タイ政府が導入したEV振興策を活用して普及の拡大を急ぐ。これまでEVは日本など一部で普及してきたが、23年はアジア全域で拡大する。各社の戦いは、自動車業界の行方に大きな影響を与える。 *3-5-2:https://digital.asahi.com/articles/ASQDL72C2QDLUTIL00X.html (朝日新聞 2022年12月18日) 東海道新幹線、停電区間で架線切断 13年前も同様事故 18日午後1時ごろ、東海道新幹線の豊橋―名古屋間で停電が起き、東京―新大阪間の上下線で最大約4時間、運転を見合わせた。愛知県安城市の下り線で架線が切れたことが関係しているとみられる。JR東海は、同日午後11時時点で74本が運休、114本が最大4時間28分遅れるなどして約11万人に影響したとしている。JR東海によると、停電は豊橋―名古屋間の上下線で午後1時ごろに発生。上り線は同18分に送電して同22分に運転を再開したが、下り線は安城市内で列車に電力を供給するトロリ線をつり下げるための「吊架(ちょうか)線」が切れているのが見つかり、復旧作業のため、同41分に再び上下線で運転を見合わせた。運転見合わせは当初、豊橋―名古屋間だけだったが、最終的に東京―新大阪間の全線に拡大した。復旧作業は午後3時半から始まり、約1時間半後に終了。午後5時に順次運転を再開した。切断の理由や、切断と停電の因果関係は不明で、原因を調査中という。東海道新幹線では2010年1月にも、横浜市神奈川区で架線が切れ、約3時間20分にわたって停電する事故があった。JR東海の事故後の発表によると、停電直前に現場を通過した車両の集電装置「パンタグラフ」の部品が外れ、吊架線とトロリ線の間にある「補助吊架線」を切断。2日前にパンタグラフの部品を交換した際、4個のボルトをすべて付け忘れたのが原因だった。 *3-5-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/209491 (東京新聞 2022年10月21日) ものづくり「国内回帰」の時代は来るのか? 円安は追い風だが、識者は不安要素を指摘 急速な円安の進行で海外から国内への輸送コストなどが膨らむ中で、期待されるのは製造業の生産拠点の国内回帰だ。海外から国内に生産を戻す動きは一部で出始め、政府も後押しする方針で、岸田文雄首相は「円安メリットを生かした経済構造の強靱きょうじん化を進める」と強調する。だが、日本の経済成長は見込みづらく、円安という追い風があっても移転に踏み切る企業は現時点では限られそうだ。 ◆海外からの輸送費や人件費が割高に 生活用品大手のアイリスオーヤマは9月、国内販売向けの一部の生産設備を中国から日本に移した。判断の背景にあるのは円安に伴う輸送費の上昇だ。プラスチック製の衣装ケースをつくるための金型を、埼玉県深谷市の工場など国内3カ所に運び込んだ。輸送費のかかる一部製品の生産販売を国内での「地産地消」に切り替えることで、約2割のコスト削減を見込む。 カーナビを製造販売するJVCケンウッドも1月から、国内販売向けの生産をインドネシアから長野県の工場に移している。同社の担当者は、海外工場からの輸送費や現地での人件費上昇を理由に「国内での生産・販売の方がメリットが大きくなった」と説明する。 ◆日本市場の成長力や購買力が不安 ただ、エコノミストの間では、海外工場の国内への移転は時間や巨額の費用がかかるため、国内回帰は「限定的」との見方が多い。帝国データバンクの調査では、原材料の仕入れ確保や価格高騰に直面する企業のうち、生産拠点を国内に戻すと答えたのは1割未満にとどまる。第一生命経済研究所の熊野英生氏は「成長力のない日本市場は魅力がないため」と指摘。「賃上げで日本国内の購買力が上がらない限り、高成長が見込める国で生産・販売する方がもうかるとみる企業が多い」と話した。 <食糧安全保障> *4-1-1:https://digital.asahi.com/articles/ASQ966SM6Q89ULUC001.html (朝日新聞 2022年9月7日) ウクライナ危機や円安、飼料高騰で苦境の酪農家 廃業が増える恐れも 飼料や燃料費などの高騰が酪農家を直撃している。行政による支援や乳価の値上げで経営を支える動きが強まっているが、急激な値上がりに対応しきれていない。廃業する酪農家が増える恐れも指摘されている。岩手県滝沢市の武村東(あずま)さん(64)は、3代にわたって牧場を経営してきた。祖父が旧満州から引き揚げて入植し、土地を切りひらいた。しかし、現在は厳しい経営状況に直面している。生産資材の価格高騰が背景にある。特に厳しいのが、トウモロコシを主原料とする配合飼料の値上がりだ。ウクライナ危機や円安などの影響を受けている。農林水産省の飼料月報によると、乳牛用配合飼料の価格(工場渡し価格)は、昨年6月は1トンあたり7万4038円だったが、今年6月には1万円以上(約14%)値上がりし、8万4393円になった。さらに7月からは1トンあたり1万円超の上げ幅となった。武村さんの牧場では配合飼料の費用が経営コストの5割弱を占めるため、打撃が大きい。経営を圧迫する要素はこれだけではない。牛のエサは、配合飼料のほかに、牧草やデントコーン(青刈りのトウモロコシ)などの粗飼料(そしりょう)を混ぜたものだ。武村さんは、円高・円安の影響を受けにくい自給飼料づくりを目指し、粗飼料を47ヘクタールの畑で自前で収穫している。だが、その畑で使う肥料も、原料の大半が輸入品であるため値上がりした。さらに、トラクターなどを動かすための軽油も価格が上がっている。「酪農は輸入産業なんです。円安の影響が厳しい」。酪農家への支援として、国の配合飼料価格安定制度がある。輸入される飼料品目の上昇に応じて値上がり分を補塡(ほてん)する。4~6月は飼料1トンあたり9800円が補塡された。だが、農家にとって十分とは言えず、岩手県は国の制度でまかないきれない分について、配合飼料1トンあたり1千円以内で助成する方向で準備し、市町村でも支援の動きが広がる。さらに、乳業メーカーが酪農家から買い取る際の飲用乳価が、11月から1キロあたり10円引き上げられる。値上げは19年4月以来、3年半ぶり。配合飼料などの高騰に対応したもので、酪農家から生乳販売を受託している指定団体・東北生乳販連は「危機的な状態で、このままでは離農が進むため値上げをお願いした」とする。ただ、乳価の値上げは、難しい問題もはらむ。コロナの影響で消費が落ち込んだ牛乳は供給過剰が続く。保存用に加工された脱脂粉乳の在庫も、全国で10万トンを超えて過去最高水準となっている(5月末時点)。こうした中で小売価格も上がれば、消費低迷を加速させる懸念がある。仕入れ価格が上がる乳業メーカーにとっては、スーパー側との交渉で小売価格に転嫁できなければ、経営状況の厳しさが増す。農業生産資材の急激な価格高騰が、業界全体に大きく影響を与えている。 *4-1-2:https://www.jacom.or.jp/noukyo/news/2022/09/220921-61692.php (JAcom 2022年9月21日) 配合飼料供給価格 据え置き 10~12月期 JA全農 JA全農は9月21日、10~12月期の配合飼料供給価格は7~9月期価格を据え置くと発表した。配合飼料価格は7~9月に1t当たり1万1400円と過去最高の引き上げ額となり1t当たり10万円程度と高騰した。全農によるとトウモロコシのシカゴ相場はロシアのウクライナ侵攻などの影響で高騰し、6月には1ブッシェル(25.4㎏)7.6ドル前後で推移していたが、米国産地で生育に適した天候になったことから7月には同6ドル前後まで下落した。その後、米国産地の高温乾燥などによる作柄悪化懸念から堅調に推移し、現在は同6.8ドル前後となっている。今後は世界的な需給の引き締まりが継続していることに加え、米国産新穀の生産量の減少懸念などから相場は堅調に推移すると見込まれている。また、大麦価格は昨年度からのカナダの干ばつに加え、主要産地のウクライナからの輸出量が減少し世界的に需給がひっ迫していることから、今後は値上がりが見込まれるという。大豆粕のシカゴ相場は、6月には1t470ドル前後だったが、米国産地の高温乾燥による作柄悪化の懸念から8月には同500ドル前後まで上昇した。その後、降雨による作柄改善の期待から下落し、現在は同470ドル前後となっている。国内大豆粕価格は、シカゴ相場の上昇と円安で値上がりが見込まれるという。海上運賃(米国ガルフ・日本間のパナマックス型運賃)は、5月には1トン85ドル前後で推移していたが、原油相場の下落や中国向け鉄鉱石、石炭の輸送需要の減少などで現在は同60ドル前後となっている。外国為替は米国は利上げを実施している一方、日本は金融緩和政策を継続していることから円安は進み、現在は1ドル143円前後となっている。今後は日米金利差の拡大は続くものの、利上げによる米国経済の景気悪化も懸念されるから「一進一退の相場展開が見込まれる」とする。JA全農によると麦類や大豆粕の値上げや円安の進行など値上げ要因はあるものの、トウモロコシ相場や海上運賃など「値下げ要因もあり、原料費の上昇は小幅のため価格を据え置きとした」と話す。全農によると価格が据え置きとなったのは2015年10-12月期以来、7年ぶり。畜産農家にとっては飼料価格が高止まりすることになるが、農林水産省は「配合飼料価格高騰緊急特別対策」を決め、実質的な飼料コストを第2四半期と同水準とするための補てん金を交付する。生産コスト低減や国産粗飼料の利用拡大に取り組む生産者が対象で1トン当たり6750円を補てんする。 *4-1-3:https://news.yahoo.co.jp/articles/d7e922c94d1e0aed4e1627bb7e1288001a8315c0 (Yahoo、日本農業新聞 2022/12/5) 飼料高騰で酪農家の離農加速 半年で400戸減、指定団体に調査 資材高騰を受け、酪農家の離農が加速していることが分かった。日本農業新聞が全国10の指定生乳生産者団体(指定団体)に生乳の出荷戸数を聞き取った結果、10月末は約1万1400戸と半年前の4月末に比べ、約400戸(3・4%)減。2021年の同期間の約280戸(2・3%)減に比べてペースが加速している。各指定団体は、飼料高による経営悪化を理由に挙げる。11月下旬に、酪農家から生乳を受け入れ販売する全国10指定団体に取材した。出荷戸数減にはごく一部に系統外への離脱も含まれるが、ほとんどが離農とみられる。農水省の農業物価指数によると、飼料は7月以降急激に高騰。飼料価格は2020年を100とした指数で、昨年後半から120台と上昇していたが、今年7月からは140を超える水準が続く。配合飼料だけでなく、「粗飼料高騰の影響が一番大きい」(近畿生乳販連)とみる地域もある。北海道では、副産物となる初生牛などの市場価格急落も要因となったとみられる。 ●若手・中堅でも 今年10月末までの半年間の出荷戸数減少率は、四国を除く全地域で前年同時期を上回った。減少率が4%を超えたのは東北、関東、東海、近畿。昨年の同期間の減少率は、全地域とも1~2%台だった。関東生乳販連は「減少ペースが去年の4割増し」、九州生乳販連は「この1年は去年の倍のペースで離農者が出ている」という。若手・中堅での離農も出始め「後継者不在の高齢農家だけでなく、中堅農家が経営中止している」(東北生乳販連)、「中堅農家がこれだけ離農・離農検討をする状況は過去になかったのではないか」(近畿生乳販連)とする地域もある。離農の加速により、生産基盤が損なわれる懸念も強まる。生乳の需給緩和を受け各地域で生産抑制に取り組んでいるが、一部では「生産調整の割り当て以上に乳量が減ってしまっている」(九州生乳販連)とする。北陸酪連も「数年後の不足感に懸念がある」としている。 *4-2:https://smartagri-jp.com/agriculture/5144 (SMART AGRI 2022.9.5) 肥料高騰はいつまで続く? 国や自治体による肥料高騰対策支援事業まとめ JA全農は2022年6月から10月の秋肥について、前期と比べて最大94%価格を引き上げることを発表しました。これまでに経験したことがないとも言われる肥料の高騰はなぜ起こってしまったのでしょうか。この記事では、肥料の価格が上昇している原因をお伝えしつつ、支援対策として国や自治体で行われている補助事業を紹介します。 ●肥料価格が高騰している理由 日本では、化学肥料の原料である尿素、りん酸アンモニウム、塩化カリウムのほとんどを海外輸入に頼っているため、国際情勢の影響を受けやすい状況にあります。2008年にも肥料の需要増加などを理由に肥料価格の高騰が起こり、一度は落ち着いたものの、2021年頃から再び肥料の原料価格が値上がりし始めました。そのような中で、ロシアによるウクライナへの侵攻が始まり、さらに深刻化しているのが現状です。ただし、今回の高騰の理由については、アンモニアや塩化カリウムの生産国上位であるロシアへの経済制裁による供給の停滞や中国の輸出規制、肥料の運搬に利用される船舶燃料の高騰、円安などが、複合的に関係していると見られています。 ●肥料価格高騰に対する支援事業とは? 肥料価格高騰対策事業は農林水産省、都道府県、市町村などが各自実施していて、対象期間に購入した肥料の購入費の一部を助成するものです。「化学肥料の低減に向けて取り組む農業者」や「その自治体に住所を有している農業者」などが対象になります。農産物を生産するためには、生産者の人件費だけでなく、種子や肥料などの資材が必要です。これらの価格が上がった分、農産物の価格に転化できればいいのですが、農産物は人間が生活する上で必要なカロリーや栄養素を賄うために必要な共有資源でもあり、JAなどを中心として一定量を常に平均的な価格で供給できる体制が作られてきました。そのため、肥料高騰の分の損失金額を簡単に解消できるようなものではありません。今回のような国や自治体としての助成を行うことは、生産者を守るだけでなく、国内の食料事情を解決するためにも必要不可欠になっています。だからこそ、必要な助成をしっかり受けることも大切です。申請方法は基本的に事後申請式になっているので、肥料を購入したことがわかる領収書や前年分の確定申告書の控えなどの書類を用意しておきましょう。自治体によっては対象作物を限定していたり、補助対象の期間や申請方法などが異なることもあり、すべての生産者が助成を受けられるとは限りません。詳細は住んでいる自治体のホームページで確認してください。 ●2022年度に実施中の肥料価格高騰対策事業 ここでは、農林水産省が行っている支援事業をはじめ、都道府県や市町村が行う事業のひとつをピックアップして、詳しい支援内容や申請方法を紹介します。 □農林水産省「肥料価格高騰対策事業」 ○支援対象 2022年6月から2023年5月に購入した肥料(本年秋肥・来年春肥として使用するもの) ○支援内容 15事項ある化学肥料低減に向けた取り組みメニューを2つ以上行った上で、前年度から増加した肥料費の7割を支援金として交付 ○助成額の算出方法 助成額=(当年の肥料費-(当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率(0.9))×0.7 価格上昇率は、農水省が発表している「農業物価統計」を基に算出。本年度秋肥については6月から9月までの価格上昇率が考慮されます。 ○申請書類 ・肥料の購入価格がわかる注文票のほか、領収書または請求書 ・化学肥料低減計画書のチェックシートに、実施または実施予定の取り組みを申告(2つ以上にチェックが付けばOK) ○申請方法 5戸以上の農業者グループで農協や肥料販売店などにまとめて申請(申請に関する不明点は都道府県や市町村、農協などに問い合わせ) ○問い合わせ先 北海道農政事務所 生産経営産業部 生産支援課 https://www.maff.go.jp/hokkaido/annai/toiawase/index.html 東北農政局 生産部 生産技術環境課 https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/toiawase.html 関東農政局 生産部 生産技術環境課 https://www.maff.go.jp/kanto/seisan/nousan/kankyou/index.html 北陸農政局 生産部 生産技術環境課 https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/soudan/index.html 東海農政局 生産部 生産技術環境課 https://www.maff.go.jp/tokai/seisan/kankyo/hozen/190624.html 近畿農政局 生産部 生産技術環境課 https://www.maff.go.jp/kinki/org/outline/index.html 中国四国農政局 生産部 生産技術環境課 https://www.maff.go.jp/chushi/kikouzu/gaiyou.html 九州農政局 生産部 生産技術環境課 https://www.maff.go.jp/kyusyu/soumu/soumu/soudanmado/soudanmado.html 沖縄総合事務所 農林水産部 生産振興課 http://www.ogb.go.jp/nousui (以下略) *4-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221209&ng=DGKKZO66679320Y2A201C2EP0000 (日経新聞 2022.12.9) 尾を引く資源高・円安 経常赤字、10月641億円、旅行収支は回復兆し 貿易や投資などの海外との取引状況を表す経常収支の低迷が続いている。財務省が8日発表した10月の国際収支統計(速報)によると641億円の赤字で、長期の傾向がわかりやすい季節調整値では6093億円の赤字となった。原数値で単月の赤字は1月以来、9カ月ぶりだが、季節調整値では2014年3月以来、8年7カ月ぶりとなる。資源高と円安の影響が尾を引いている。経常収支は輸出から輸入を差し引いた貿易収支や、外国との投資のやり取りを示す第1次所得収支、旅行収支を含むサービス収支などで構成する。特定の月に集中する配当の支払いなどの変動をならした季節調整値は6093億円の赤字だった。10月は日本から海外への配当支払い額が原数値より季節調整値の方が大きく、赤字額も大きくなったとみられる。経常収支の季節調整値は従来は1兆円を超える黒字の月が多かったが7月以降は下回っている。10月は6707億円の黒字だった9月からマイナス方向に1兆2800億円変化した。貿易収支の赤字は比較可能な1996年以降で最も大きい2兆2202億円の赤字(原数値では1兆8754億円の赤字)だった。輸入額が前月比5.4%増の11兆991億円となった。原油や液化天然ガス(LNG)、石炭といったエネルギー関係の輸入額が多かった。原油の輸入価格は円建てで1キロリットルあたり9万6684円と前年同月比79.4%上がった。ドル建ては1バレルあたり105ドル96セントと37.8%の上昇だった。一時1ドル=150円台となった記録的な円安・ドル高が輸入物価の上昇に拍車をかけた。輸出額は前月比3.0%増の8兆8790億円。輸出入ともに過去最高だったが、輸入の増加ペースのほうが上回った。第1次所得収支の黒字が2兆3968億円と前月比25.3%減ったことも響いた。商社や小売りなどで海外から受け取る配当が9月に増えた反動が出た。プラスの変化が出始めたのは旅行収支だ。訪日外国人の消費額から日本人が海外で使った金額を差し引いたもので、10月は前月の3.6倍の381億円となった。水際対策の緩和で訪日外国人が49万8600人と前月の2.4倍に増えたことが影響した。新型コロナウイルスの感染拡大直前の20年1月は黒字が2735億円に達しており、まだその1割台の水準にとどまる。経常収支の押し上げ効果は限定的だが、拡大の兆しはみられる。SMBC日興証券の宮前耕也氏は今後の見通しについて「原油高と円安の一服や訪日客の増加により経常収支の赤字は拡大しないだろう」とする一方、「海外経済の減速で輸出が伸び悩めば黒字と赤字を行ったり来たりする可能性はある」と予想する。 *4-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221220&ng=DGKKZO66981260Q2A221C2MM0000 (日経新聞 2022.12.20) 経済安保、「重要物資」11分野を閣議決定 半導体や蓄電池 政府は20日、経済安全保障推進法の「特定重要物資」に関し半導体や蓄電池など11分野の指定を閣議決定した。対象分野で国内の生産体制を強化し備蓄も拡充する。そのための企業の取り組みには国が財政支援する。有事に海外から供給が途絶えても安定して物資を確保できる体制を整える。半導体や蓄電池のほか、永久磁石、重要鉱物、工作機械・産業用ロボット、航空機部品、クラウドプログラム、天然ガス、船舶の部品、抗菌性物質製剤(抗菌薬)、肥料の各分野を対象とした。いずれも供給が切れると経済活動や日常生活に支障を来す。重要鉱物では特定の国に依存しすぎないよう企業による海外での権益取得なども後押しする。台湾有事をはじめとする中国リスクが念頭にある。11分野のうちレアアースなど中国を供給元とする物資は多い。企業にも中国依存から脱却できる生産体制やサプライチェーン(供給網)づくりを促し調達先の多角化につなげる。各物資の安定供給のための目標や体制づくりなどの具体的な施策は、それぞれの所管省庁が公表する「安定供給確保取組方針」で定める。早いものでは年内から順次公表し、そのなかで企業への支援内容も示す。企業は同方針を踏まえ設備投資や備蓄、代替物資の研究開発など安定的に供給するための計画を申請する。承認されれば補助金や低利融資などを受けられる。政府は22年度第2次補正予算で経済安保推進法に基づく支援に充てる費用として合計1兆358億円を計上した。特定重要物資の指定は5月に成立した経済安保推進法の4本柱のうちの1つだ。サプライチェーンを巡り、米中対立やロシアによるウクライナ侵攻、新型コロナウイルスの感染拡大などで寸断のリスクが浮き彫りになっている。 <社会保障←命の安全保障> *5-1-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15505526.html (朝日新聞社説 2022年12月19日) 社会保障財源 防衛費の次でいいのか 想定を上回る少子化への危機感があるのか。どんな判断で政策の優先順位を決めているのか。岸田首相に問いたい。先週末、首相がトップの全世代型社会保障構築本部と有識者会議が、めざす改革の方向性や今後取り組むべき課題をまとめた報告書を公表した。最も緊急を要する取り組みに挙げたのは「子育て・若者世代への支援」だ。だが、必要になる費用やそのまかない方の具体論は、言及がなかった。介護分野の給付と負担の見直しも、来年の「骨太の方針」に向けて検討するとして、先送りした。同じ日、政府は今後5年間の防衛予算を現行の1・5倍に増やすことを決めた。防衛費が最優先、負担増につながる社会保障の議論は後回し。そんな政府・与党の姿勢が議論に影響したことは、想像に難くない。だが、国民や企業の財布にも限りがある。防衛予算の負担増が先行すれば、さらに子育て支援での負担を求めることが難しくなるのは明らかだ。それで、首相が掲げる「子ども予算倍増」はいつ実現できるのか。国内で生まれる子どもの数が今年にも80万人を割り込むと言われているなかで、あまりに悠長ではないか。少子高齢化が加速するなか、子育て以外の分野でも制度を維持できるのかという不安は根強い。国民の暮らしの安心は、安全保障に勝るとも劣らない喫緊の課題であり、目を背け続けることは許されない。有識者会議の報告には、雇用保険の対象外になっている非正規雇用の働き手への支援や、自営業・フリーランスの人向けの育児期間中の給付金創設など、既存の枠を超えた提案もある。巨額の予算を要する児童手当の拡充も「恒久的な財源とあわせて検討」とされた。こうした提起は、省庁の縦割りを超えた検討が生み出した貴重な成果だ。報告書を土台にさらに議論を深め、具体化を急がなければならない。かつての「社会保障と税の一体改革」では、給付と負担を一体で議論し、全体像を示しながら合意形成を図った。今回もそうした工夫が必要だ。既存の制度も、持続性・安定性が揺らぐ。報告書は負担能力に応じた支え合いを強調したが、それだけで解決できない。介護保険では、要介護度の軽い人向けの給付見直しや、利用者負担の引き上げなどの案があるが、反対も根強い。それらが無理なら、保険料や税による負担増が検討対象になる。結局、財源の議論抜きに改革の前進はない。先送りを続ければ国民生活の土台が崩れていくことを、首相は自覚すべきだ。 *5-1-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/484e6366eb63414d656397f74694c8f8a0e5f4f3 (読売新聞 2022/12/7) 政府、出産育児一時金50万円程度に増額の方向で調整…来年度から少子化対策強化狙い 政府は、出産時の保険給付として子ども1人につき原則42万円が支払われる出産育児一時金について、2023年度から50万円程度に引き上げる方向で検討に入った。子育て世帯の負担を軽減し、少子化対策を強化する狙いがある。近く岸田首相が最終判断し、引き上げ額を表明する。加藤厚生労働相は6日、首相に増額案を提示し、政府内で最終調整が行われている。厚労省によると、21年度の平均出産費用(帝王切開などを除く正常分娩(ぶんべん))は約47万円で、一時金の額を上回った。出産時に脳性まひとなった子どもに補償金を支給する産科医療補償制度の掛け金1万2000円を含めると、約49万円となる。厚労省は、少なくともこの水準まで一時金を引き上げる必要があると判断した。岸田首相はかねて「少子化は危機的な状況にある」として、一時金の「大幅な増額」を表明していた。23年度の増額分は、これまで一時金を支払ってきた健康保険組合などの保険者が負担する。24年度以降は、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度からも財源の7%程度を拠出してもらう方向だ。 *5-1-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/223507 (東京新聞 2023年1月4日) 東京都、18歳以下に月5000円給付へ 所得制限設けず 第2子の保育料無償化も検討 東京都の小池百合子知事は4日、都庁での新年のあいさつで、少子化対策として新年度から、都内に住む0〜18歳の子ども1人に月5000円を給付する方針を明らかにした。養育する人の所得制限は設けず、関連経費約1200億円を2023年度当初予算案に計上する見通し。(三宅千智) ◆小池知事「国の予算では少子化脱却できない」 小池知事は、22年の全国の出生数が統計開始以来初めて80万人を下回る可能性となったことに触れ「社会の存立基盤を揺るがす衝撃的な事態だ」と指摘。少子化対策は国策として取り組むべき課題としながらも「国の来年度予算案では、ただちに少子化から脱却して反転攻勢に出るぞという勢いになっていない」と批判し、都が先駆けて着手すると強調した。 ◆年間約1200億円、市区町村との調整必要 ただ、実際に給付するには区市町村との調整が必要で、新年度初めからの実施は難しい。都幹部は「新年度のできるだけ早い時期から始めたい」としている。住民基本台帳によると、都内の0〜18歳の人口は22年1月時点で約193万7000人。全員に月5000円を給付すると、年間約1200億円が必要となる。来年度の一般会計当初予算は、過去最高だった22年度の7兆8010億円を上回る見込み。都の合計特殊出生率は21年に1.08で、全国の1.30を下回っている。国立社会保障・人口問題研究所の調査(同年)によると、夫婦が望む理想の子ども数の平均は2.25人となっており、子どもを持たない理由は「子育てや教育にお金がかかりすぎる」が最多だった。また、都は都内の世帯における「第2子」を対象にした保育料無償化の検討も始めた。都内の保育料は認可保育所や認定こども園の平均で月額3万円以上で、第3子以降は無料となっている。都は国の補助制度と合わせて第2子の保育料も無料になる仕組みを検討している。 ◆子育て支援の明確なメッセージ 出生率念頭なら未婚率も考慮を 東京都が打ち出した新たな子育て支援策は、国の児童手当が適用されない16歳以上や高所得世帯をカバーする。全国に類を見ない独自策で少子化に歯止めをかける狙いだが、一律の手当には「ばらまき」の懸念もある。国の児童手当は0〜2歳は1万5000円、3歳から小学校卒業までは1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1万円。扶養親族が3人の場合、保護者のうち、高い方の所得が736万円未満なら受給対象となる。児童手当の対象外の世帯に向けた特例給付では、扶養親族3人で所得972万円未満なら5000円を受け取れる。東京都千代田区は、児童手当の対象とならない中学卒業後から18歳までの子どもや、高所得世帯の中学生以下の子どもにも月5000円を給付している。小池百合子知事は4日、報道陣に「子どもは生まれ育つ家庭に関わらず等しく教育の機会、育ちの支援を受けるべきだ」と、所得制限を設けない理由を説明した。約1200億円の財源は他の事業の見直しで捻出できるとして「(これは)未来への投資。ばらまきという批判にはまったく当たらない」と述べた。愛知大の後うしろ房雄教授(行政学)は「対象を選別する手間や経費を考えると、所得制限を設けないことは妥当で、子育て支援という明確なメッセージとして評価できる」と話す。その一方で「出生率を念頭に置くなら、子どもが生まれた後だけでなく未婚率も考える必要がある。また、若い世代の所得を引き上げる取り組みなどもないと、ただのばらまきで『東京は金があるからできる』となってしまう」と指摘した。 *5-1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221224&ng=DGKKZO67126250U2A221C2EA4000 (日経新聞 2022.12.24) 学童保育待機1.5万人 5月時点 政府、ゼロ目標達成できず 厚生労働省は23日、共働き家庭などの小学生を預かる放課後児童クラブ(学童保育)に希望しても入れなかった児童が2022年5月時点で1万5180人だったと発表した。前年同月から1764人増え、3年ぶりに増加に転じた。21年度末までに学童の待機をゼロにする政府目標は達成できなかった。21年は新型コロナウイルスの感染拡大期の預け控えがあった。22年は再び利用の希望が増え、入れない児童が増えたようだ。都道府県別では東京都が3465人で最多となった。学年別では4年生の待機が最も多く、4556人と全体の30%を占めた。前年からの増加幅も最も大きく、770人増えた。共働き世帯増加に伴うニーズの高まりに受け皿整備が追いついていない。学童保育に登録している児童数は139万2158人で過去最高を更新。前年から4万3883人増加した。施設数は前年比242カ所減り2万6683カ所だった。子どもの小学校入学後、夕方以降に子どもを預ける場所がないことを理由に親が就労を諦める現象を「小1の壁」と呼ぶ。親の仕事と子育ての両立を支援するため、学童保育の待機をなくすことが課題の1つになっている。厚労省は「現在実施している施設整備などの施策を着実に進め、なるべく早期の解消をめざす」としている。 *5-1-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221125&ng=DGKKZO66266160V21C22A1EA2000 (日経新聞 2022.11.25) 子育て予算、人口減にらみ「倍増」、全世代会議の論点整理案、育休支援へ給付新設 政府の全世代型社会保障構築会議は24日、今後の改革に向けた論点整理案を示した。子育て支援ではフルタイム勤務に比べて支援が手薄な時短勤務者やフリーランス向けに新しい給付の創設を検討する。子育て予算を倍増させる道筋も来夏に示すと記した。具体的な財源の確保策は見えておらず、実効性ある支援につなげられるかが問われる。岸田文雄首相は24日の会議で「必要な子ども政策を体系的にとりまとめる」と強調。「来年度の骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)には子ども予算の倍増を目指していくための道筋を示していく」と述べた。会議ではこれまで、少子化対策や、社会保障制度の持続性を高めるための負担と給付の見直しについて議論してきた。今回の論点整理案では主に子育て支援、医療・介護保険、勤労者皆保険についての方向性を示した。子育ての分野では具体策を打ち出した。2つの給付措置を創設する。1つ目は育児休業明けで勤務時間を短くして働く人向けの新たな現金給付だ。賃金の一定割合を雇用保険から拠出し、上乗せすることを検討する。時短勤務で賃金が減る状況を経済的に支援する。もう1つがフリーランスやギグワーカー、自営業者向けの子育て支援策だ。こうした働き方では、現在、育児休業の給付を受けられない。代わりの現金給付を通じて育児をサポートする。 ●現状打開に壁も ただ2つの給付はそれぞれ財源や実効性に課題がある。時短給付は雇用保険からの拠出が想定されるが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて雇用調整助成金の給付が拡大し、同保険の財政事情は厳しい。積立金はほぼ枯渇し、新たな財源を捻出する余地は乏しい。実効性への懸念もある。支援を通じて経済的な負担は和らぐが、家事・育児の負担が女性に偏る現状の打開にはつながらない。男性の家事・育児参加を積極的に後押しする施策が欠かせない。フリーランスや自営業者向けの給付も新たな財源が必要になる。自ら選んでその形態で働く人もおり、必ずしも経済的に困窮していない場合もある。線引きが難しい。論点整理案では、2023年の骨太の方針で子ども予算の倍増に向けた当面の道筋を示すことが必要だと明記した。23年度に創設されるこども家庭庁の概算要求は約4.7兆円で、倍増するためには少なくとも同程度の予算が必要になり、ハードルは高い。社会保障給付に施設整備費などを加えた家族向けの社会支出は日本は欧州に比べて見劣りしている。国内総生産(GDP)比で日本は2%だが、フランスや英国、スウェーデンなどは2%台後半から3%台半ばに達し、日本より比率が高い。政府内には企業負担の積み増しや、年金・医療といった他の社会保険からの拠出を求める意見もあるが、どれも一筋縄ではいかない。医療・介護保険制度改革についても言及した。医療では幅広い世代で所得に応じた負担を強化し、膨らむ医療費を賄っていく方針だ。ただ医療の効率化や窓口負担の一層の引き上げといった議論は深まっていない。 ●「介護改革は停滞 足元では医療改革を優先する影響で、介護保険の議論は停滞気味だ。論点整理案をまとめる過程では負担増を想起させる項目が軒並み削られた。介護費は40兆円台半ばの医療費に比べて今は4分の1程度だが、伸びは大きい。早期に給付と負担の見直しに着手すべきだが改革の機運は乏しい。勤労者皆保険では厚生年金の適用拡大などが盛り込まれた。年金制度の持続性を高めるために避けて通れないマクロ経済スライドの物価下落時での発動など、負担増につながるテーマには触れなかった。社会保障給付費の財源は6割弱を保険料、4割を消費税などの公費で賄っているが、その一部は国債を充てている。消費税率の引き上げ時に使い道を拡大し、子育て支援などにも使えるようにした。ただ、主力財源の一つである消費税収は地方分を除く全額を社会保障に充てても賄いきれていない状況になっている。 *5-1-6:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15520005.html (朝日新聞 2023年1月6日) 「異次元」少子化対策、財源が焦点 省庁横断の会議設置へ 岸田文雄首相が4日の年頭会見で打ち出した「異次元の少子化対策」を進めるため、政府は省庁横断の会議を設置する。6日、首相が小倉将信こども政策担当相に検討を指示し、児童手当の拡充を中心に必要な対策を6月までにまとめる。財源確保には負担増の議論が避けられず、首相周辺は「今年前半の最大の課題となる」と話す。首相は4日の会見で、「児童手当を中心に経済的支援を強化する」と表明。6月にとりまとめる骨太の方針に盛り込む考えを示した。官邸幹部らによると、会議は小倉氏をトップに、厚生労働相、文部科学相、財務相らの閣僚や有識者の参加を想定。企業の協力を得るため、経済産業省を加えることも検討する。児童手当は現在、0歳~中学生が対象で、月5千~1万5千円が支給されているが、所得制限もある。自民党などは対象年齢の拡大や、第2子以降の増額などを求めている。新設する会議ではほかに、幼児教育や保育サービスの量と質の強化、子育てサービスの拡充、育児休業制度の強化なども検討する予定だ。経済協力開発機構(OECD)の調査では、2017年の国内総生産に対する子ども・子育て支援に関わる日本の公的支出の割合は1・79%で、OECD平均の2・34%を下回る。最高のフランスの3・60%の半分だ。議論の最大の焦点は、「異次元」と称する対策の裏付けとなる財源の確保だ。児童手当の拡充だけでも数兆円の財源が必要とみられる。政府内では企業から集める「事業主拠出金」を増やす案や、医療や介護の公的保険から「協力金」を得る案が浮上している。増税を期待する声もある。どれも企業や個人の負担増を伴う。官邸幹部は「検討すべきテーマが多く、防衛費の財源の議論より困難だ」と漏らす。 *5-2-1:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20221125&c=DM1&d=0&nbm=DGKKZO66266160V21C22A1E ・・ (日経新聞 2022.11.25) 負担と効率化、議論急げ 財源論後回し、裏付け欠く 社会保障が充実されると聞いて反対する人は少ない。だが、そのために保険料や税による国民負担がどのくらい必要なのかが分かると、給付拡充への反対論や慎重論も出てきて、議論が現実的かつ深くなる。今の全世代型社会保障構築会議の議論は前者の段階だ。日本社会の課題に鑑みて必要な社会保障のあり方をまず考える。その後で財源について議論する。こんなアプローチを採り、財源論が後回しになっている。全世代型会議が掲げた改革案は早期に実現すべきテーマが多い。自営業者にも現金給付のある育児休業があったほうがいいし、フリーランスで働く人も報酬比例部分のある公的年金に加入できるようにすべきだ。だが、財源・負担の姿がみえないうちは「総論賛成」の域を出ない。給付の裏付けとなる負担をどうするのか。今後は各論の議論と調整に力を注ぐべきだろう。経済対策に盛り込まれた、妊娠した女性に10万円相当を配る出産準備金は、恒久化が必要な給付充実策なのにそれに見合う財源がない。「給付先行」が議論だけでなく現実になってしまう政権だとすればなおさら負担の検討を急ぐ必要がある。その際、保険料や企業の拠出だけで財源を賄う前提では制度設計に限界がある。消費増税など税財源の議論も避けるべきではない。財源論と同時に重要なのは、高齢者の増加で給付が膨張する医療・介護を効率化する改革だ。診療データの共有などデジタルトランスフォーメーション(DX)によってサービスを効率化し、ムダを排除できれば現役世代の負担軽減に直結し、子育て支援に必要な追加財源も小さくできる。かかりつけ医の制度整備は患者の医療アクセスを確保するだけでなく、医療を効率化する点でも極めて重要な改革だ。診療報酬体系の見直しと一体的に導入すれば、重複診療や重複検査、薬の多剤投与を減らしうる。大改革なので今回の論点整理が示すように、医師と患者の手あげ方式によって「小さく産む」手法を採るのはやむを得ないが、高齢者数がピークになる2040年に向けて、しっかり育てる道筋は立てておくべきだ。 *5-2-2:https://diamond.jp/articles/-/314390 (Diamond 2022.12.14) 「介護事業者の倒産」が過去最多、過酷な業界実態を東京商工リサーチが解説 65歳以上の高齢者が人口の約3割を占め、少子高齢化が進む日本。有望なビジネス市場と目された介護業界でいま、倒産が急増している。すでに1~11月の倒産は135件に達し、過去最多を記録した2020年の118件を上回っている。倒産の急増は、人手不足とコロナ関連の資金繰り支援効果が薄れてきたことに加え、物価上昇をサービス料金に転嫁しにくい業界特有の構造もある。高齢化社会を前に介護業界で倒産が急増している状況を東京商工リサーチが解説する。(東京商工リサーチ情報部 後藤賢治) ●コロナ禍・物価高・人手不足の三重苦で倒産件数が過去最高に 公的要素が強かった介護事業者の倒産は、2000年代初期は年間数件にとどまっていた。だが、将来有望と見込まれた市場に介護事業者が相次いで進出し、一気に過当競争が巻き起こり、倒産は増勢基調をたどった。2002年以降の介護事業者の倒産件数および負債総額は、グラフの通りだ。2009年度の介護報酬の大幅なプラス改定で、いったん減少に転じたが、コスト上昇の中で2015年以降は介護報酬の改定は低水準だったため、再び増勢に転じた。この頃からヘルパーなど介護補助者の人手不足が深刻になり、人件費の上昇が収益を圧迫するようになった。さらにヘルパーなどの高齢化も重なり、2016年以降の倒産は100件超で高止まりした。2020年は新型コロナ感染拡大が介護業界を直撃した。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などで外出自粛を要請され、高齢者や家族もまた感染を恐れて介護事業者の利用を控えるようになった。こうした感染防止策への出費と収入ダウンがダブルパンチとなって経営を圧迫。実際、施設内のクラスターやヘルパーのコロナ感染で通常運営が難しくなったケースもあり、倒産は過去最多の118件に達した。2021年は政府や自治体のコロナ関連支援や介護報酬のプラス改定が下支えし、倒産は前年比31.3%減の81件と大幅に減少。2015年以来、6年ぶりに100件を下回った。ところが、2022年は長引くコロナ禍で資金繰り支援効果も薄れたところに、円安や物価高で光熱費や燃料費、介護用品が急激に値上がりした。さらに、コロナ禍で隠れていた人手不足が経済活動の再開で顕在化し、介護業界は物価と人件費上昇、そして人手不足が同時に表面化した。一般的な介護サービスは、介護保険で金額が決められている。そのため他業界のように仕入価格の上昇分を販売価格に転嫁することは難しい。こうした幾重もの経営リスクの荒波にもまれ、2022年の倒産は1~11月までに135件発生し、倒産の最多記録を塗り替えた。 ●コロナ禍前の利用者が戻らず、売り上げ不振の事業者が急増 2022年に倒産した135件の介護事業者を分析した。詳細は下記の表の通りだ。業種別では、最多はデイサービスなど「通所・短期入所介護事業」が65件(前年同期比282.3%増)と急増した。デイサービスグループ32社の連鎖倒産や運営コストのアップに加え、大手事業者の進出も影響した。「訪問介護事業」も46件(同9.5%増)と増加した。ヘルパー不足や、感染防止の意識が高い高齢者の利用控えなどが響いた。有料老人ホームも12件(同200.0%増)と3倍に増えた。先行投資が過大で、コロナ禍で想定外の環境変化に見舞われて業績が悪化した介護事業者の淘汰が目立つ。形態別では、破産が125件(構成比92.5%)と9割強を占め、特別清算を合わせた消滅型は97.7%に達する。事業継続を目指す民事再生法はわずか3件(同2.2%)にすぎず、介護事業者の倒産はスポンサーが出現しない限り、事業継続が難しいことを示している。原因別では、販売不振(売り上げ不振)が73件(前年比48.9%増)と、大幅に増えた。コロナ前の水準に利用者が戻らず、感染防止対策で利用者数を抑えたことも売り上げ低迷につながった。次いで、連鎖倒産の発生で「他社倒産の余波」が38件(前年同月2件)と急増した。ただ、赤字累積が含まれる「既往のシワ寄せ」は7件(同±0件)と増えていない。これは支援策効果が今も一部では残っているとみられるが、業績回復の遅れた介護事業者では資金繰り難から倒産や廃業が増える可能性を残している。 ●今年11月までに発生した大規模な連鎖倒産 11月末までにグループ全体で38社(うち、6社は負債1000万円未満)が破産した(株)ステップぱーとなー(台東区)の連鎖倒産は、売り上げ至上主義が介護業界になじまないことを印象付けた。同社は、機能訓練特化型デイサービスの「ステップぱーとなー」を主体に、FC事業などを手掛けていた。代表者は介護保険が適用され、初期投資も少額で済むデイサービスに目を付け、積極的に介護事業者を買収した。グループが運営するデイサービスは、北海道から島根県まで全国約150カ所まで拡大していた。グループは独立行政法人福祉医療機構(WAM)から融資を受けていた。WAMは厚生労働省が主管する福祉・医療支援の専門機関で、営利法人でも老人デイサービスセンターを対象に融資を受けることができる。この融資を活かして事業拡大を進めていった。代表が役員を務める企業は50社を超えたが、新型コロナ感染拡大でデイサービス事業の業績は急激に悪化した。それまでも事業の急拡大を金融機関からの新規融資だけでなく、グループ間の資金融通で窮状をしのいでおり、グループの経営を維持するためM&Aを加速して資金を捻出していたが、ついに限界に達してグループ38社が連鎖的に破産に追い込まれた。 ●業界の再編・淘汰は、これから本格化へ コロナ禍前から介護市場への新規参入が相次ぎ、競合から経営不振に陥る介護事業者が増えていた。さらにコロナ禍に見舞われ、施設の利用控えが進む一方で、運営コストは上昇し人手不足も重なった。こうした経営環境が急に変わるわけもなく、2022年の倒産は140件を超える可能性も出てきた。今後、本格的な高齢化社会に入るが、国の財政事情を考慮すると、介護報酬が大幅なプラス改定となる可能性は低い。そんな事情を背景に、小規模事業者は自立を求められているが、介護報酬の単位加算は容易でなく、大手事業者との格差は広がる一方だ。コスト削減が最重要課題と言うのはたやすいが、小資本の事業者が多い介護業界で、IT化や介護ロボットの導入など、多額の先行投資は難しいのが実情だ。さらに、人と人の触れ合いも必要な介護現場では、人手に頼らざるを得ない業務も多い。それだけに介護職員の採用や教育、引き止めなど人材面での負担はますます重要になっている。2022年の介護業界の倒産は、業績不振に起因するケースが多い。今後は運営コスト増大や資金繰り悪化などの本質的な要因に加え、過剰債務による新たな資金調達が難しい事業者の倒産も増えるだろう。また、倒産抑制に大きな効果をみせた「実質無利子・無担保融資(ゼロ・ゼロ融資)」は、2023年春から返済がピークを迎えるが、そこには最長3年間猶予された利払いもサイレントキラーのように隠れている。さまざまな経営リスクが重なり、有望市場だったはずの介護業界で倒産が急増しているが、業界再編や淘汰はこれから本番を迎えることになる。 *5-2-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/962192 (佐賀新聞 2022/12/14) 介護負担、来夏に結論先送り、政府、16日に報告書決定 政府は14日、有識者でつくる「全世代型社会保障構築会議」(座長・清家篤元慶応義塾長)を開き、急速な少子高齢化と人口減少に対応する制度改革案を議論した。介護保険で高齢者の負担を増やす案は、結論を来夏に先送りすることで大筋一致。既に75歳以上の医療で保険料増の方針が決まっているため、影響を見極めて慎重に検討する。16日にも報告書を決定する。報告書には、75歳以上の中高所得者の医療保険料引き上げや、将来的な児童手当拡充などを盛り込む方向。岸田文雄首相がトップを務める「全世代型社会保障構築本部」に提出する。 *5-2-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/962558 (佐賀新聞 2022/12/15) 「大型サイド」介護負担、結論先送り 生活不安、懸念相次ぐ、企業側と対立、今後も難航 3年に1度の介護保険制度改正を巡り、「給付と負担」見直しの結論が来年夏に先送りになった。年末までに厚生労働省の部会が取りまとめることが通例で、延期は異例だ。利用者の負担増の提案に、当事者らから「生活が破綻する」と懸念の声が相次いだことが背景にある。一方、介護財政を支える企業側は制度維持に向けて現役世代の負担を抑えるよう求める。意見は激しく対立し、今後の取りまとめも難航しそうだ。「認知症の母にちゃんとしたケアができなくなるかもと思うとつらい」。「認知症の人と家族の会」(京都市)が9月からオンラインや郵送で集めた、サービスの自己負担増に反対する署名は10万筆を超えた。母親が「要介護2」と認定され、デイサービスに通っているという人は「利用できなくなったらどうしたらいいのか。介護休暇制度を使える企業はまれだ」とコメントを寄せた。認知症の人と家族の会の花俣ふみ代常任理事は「高齢者は年金暮らしの人が多い上、物価高が生活を直撃している。負担が増えたら生きていけない、という切実な声が出ている」と訴える。現役世代の保険料の一部を負担する企業側は、高齢者にも「能力に応じた負担」を求めている。11月下旬、厚労省の社会保障審議会の部会。1割負担の人のうち一部を2割に引き上げる案について、経団連の担当者は「現役世代はどんどん減っていく。一定所得以上の高齢者の負担を検討すべきだ」と支持。大企業の会社員らが入る健康保険組合連合会の担当者も「現役世代の負担は限界に来ており、制度が危うい」と口をそろえた。「最も改革が必要な介護分野において制度改正の議論を出さないことは、この会議が果たすべき使命から逃げていると言われかねない」。負担増への賛否が噴出し、政府の全世代型社会保障構築会議でも方針を打ち出せない状況に、メンバーの土居丈朗慶応大教授は12月初旬の会合で意見書を出し、早急な決着を促した。だが政府は結論を先送りした。政府関係者は、世論を意識する官邸や与党の意向があると背景を解説する。「介護費はものすごく伸びる。何とかしないといけないが、与党や官邸が慎重だ」 *5-3-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15498486.html (朝日新聞 2022年12月10日)75歳以上、平均年5300円負担増 医療保険見直し案、厚労省が試算公表 75歳以上の中高所得者の負担増を盛り込んだ医療保険制度の見直し案について、厚生労働省は9日、保険料への影響額の試算を公表した。75歳以上は、高齢者の負担割合拡大に加え、出産育児一時金の新たな負担(年1300円)で平均年5300円の負担増になる見込み。同省は来年の通常国会で法改正し、2024年度からの実施を目指す。制度見直し案では、後期高齢者が現在は負担していない出産育児一時金の財源の7%程度を賄うほか、現役世代が負担する高齢者医療への支援金を減らす。そのため、後期高齢者の4割にあたる年金収入が153万円超の中所得者以上の保険料を増やしたり、年収1千万円を超えるような高所得者の保険料負担の年間上限額を66万円から80万円へ大幅に引き上げたりする。これらの見直しを踏まえた試算によると、現在42万円の出産育児一時金を47万円に上げると仮定した場合、75歳以上の保険料は24年度には平均で年5300円(月440円程度)上がる。内訳は出産育児一時金の引き上げ分が1300円、そのほかの見直しによるものが4千円。所得が高い人ほど多く負担する仕組みを強化するため、年収200万円の人で年3900円、年収400万円で1万4200円、年収1100万円では13万円の負担増。一方、6割にあたる比較的所得が低い人(年金収入のみで153万円以下)は、負担は増えないとしている。出産育児一時金は、岸田政権が大幅増額を表明。来年度から現在の42万円を50万円程度にする方向だ。今は75歳以上の負担はないが、同省は「全ての世代で負担しあうべきだ」として制度を見直す考えだ。一時金の負担による75歳以上の保険料への影響額試算では、一時金が47万円なら平均で年1300円増。50万円なら年1390円程度増える見込みだ。 *5-3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221207&ng=DGKKZO66607170W2A201C2EP0000 (日経新聞 2022.12.7) 医療、高齢者にも負担増 全世代会議の報告書案、目立つ踏み込み不足 政府の全世代型社会保障構築会議が近くまとめる報告書案の全容が6日、判明した。給付が高齢者、負担が現役世代に偏る現状を是正するため、医療分野では高齢者にも所得に応じた負担を求める方向性を明確にする。子育てや年金でも現役世代の安全網を広げ、少子化の克服や社会保障制度の持続性向上を掲げる。踏み込み不足が目立つほか、安定財源の確保も難題で、実現に向けた道筋を示せるかは見通せない。政府は月内に報告書を正式に決定する。報告書案では少子化が国の存続にかかわる問題であるとし、子育て・若者世代への支援を「急速かつ強力に整備」する必要性を強調した。育児休業給付の対象外となっている非正規労働者や自営業者、フリーランスへの支援を提起した。医療保険制度改革では、75歳以上の後期高齢者の保険料引き上げなどを明記した。全体の約4割の後期高齢者を対象に所得比例部分の負担を増やす。65~74歳の前期高齢者への現役世代からの医療費支援も所得に応じた拠出に見直す。厚生労働省が具体的な検討を進め、来年の通常国会に関連法改正案の提出を目指している。かかりつけ医の制度整備に向けて「必要な措置」を講じることも求めた。厚労省はかかりつけ医の役割を法律に明記するなどの検討を進めており、来年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す。医療機関の質を担保する認定制や、責任を持って担当する患者を明確にするための登録制に言及するのは避けた。医療費の窓口負担の一段の見直しや効率化についても踏み込んでいない。介護保険制度については負担増の具体的な記載を見送っている。子育て給付の財源も見えておらず、具体化が急務だ。年金制度の見直しでは、厚生年金や健康保険の企業規模要件の撤廃を「早急に実現」するよう求めた。中小企業などで働くパートら短時間労働者への適用拡大の理解促進に向けて、関係省庁をメンバーとした政府横断的な体制を構築することを要請した。超高齢社会に備え、給付と負担を見直す必要性にも触れた。高齢者人口は団塊の世代が25年までに全員75歳以上となった後、40年ごろから減少し始めるが、現役世代の減少で人口に占める割合は足元の30%程度から上昇が続くと見込まれる。膨張する社会保障給付について、負担能力に応じて全ての世代で公平に支え合う仕組みが必要になるとの問題意識を強調した。 *5-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221224&ng=DGKKZO67126060U2A221C2EA4000 (日経新聞 2022.12.24) 医療体制、遠いコロナ後 来年度予算案、社会保障費、最高の36.9兆円 効率化は薬価頼み 政府が23日に閣議決定した2023年度予算案で、社会保障費は過去最大の36.9兆円となった。3割強を占める医療関係の支出は22年度当初予算と比べて0.5%の増加に抑えたが、薬価の引き下げ頼みの側面は否定できない。新型コロナウイルス禍で手厚くした診療報酬など有事対応からも抜けきれていない。高齢化で膨張圧力が増す中で効率化が欠かせない。「(コロナの)医療提供体制のために主なものだけで17兆円程度の国費による支援が行われた」。財政制度等審議会(財務相の諮問機関)で財務省が11月に示した資料にはこんな記述が盛り込まれた。病床確保やワクチンなどこれまでにかかったコロナ関連費用をざっとまとめ上げたものだ。こうした対策への財源は補正予算を中心に計上してきており、当初予算案では目立ちにくい。ようやく国内でもコロナ対策は平時への移行を探る局面になった一方で、医療体制の有事対応の手じまいは遠い。21年度に2兆円を支出した病床確保料は今年10月に要件を厳格化した。しかし財制審の資料によると1日当たり最大40万円を上回る病床確保料は、平時の診療収益の2倍から12倍の水準だ。コロナ向けの病床確保が通常の医療を圧迫しているという指摘もある。一段の見直しを視野に入れるべき時期に来ている。23年度当初予算案で社会保障は一般会計総額の3割を占める。22年度当初予算と比べて6154億円(1.7%)増えた。医療関係の支出は22年度比で587億円(0.5%)増えて12.2兆円となった。新たな制度改正によって効率化できた分は少ない。厚生労働省は23年の通常国会で、75歳以上の保険料を24年度から引き上げることなどを盛り込んだ関連法改正案の提出を目指している。ただ、現役世代の負担軽減を主な目的としていることもあり、国費の減少分は50億円にとどまる。保険料や公費で賄う前段の患者本人の窓口負担のさらなる拡大といった課題は先送りのままだ。1人当たりの医療費が75歳未満の約4倍に達する後期高齢者は21年から25年にかけて16%増え、2180万人になる見込みだ。負担と給付のバランスを見直さなければ、医療保険財政の持続性が危うくなりかねない。年金の改定分を除いた社会保障費の自然増は4100億円で夏時点の見込みから1500億円圧縮した。半分弱は薬価引き下げによるものだ。社会保障費の抑制は薬価頼みの構図が続いている。その薬価も23年度予算は様相がかわった。今回の改定は対象範囲がもともと決まっていない。前回の改定と同じように7割の品目を対象にすれば厚労省の試算で4900億円の医療費の削減につながるはずだった。ただ、原材料費の高騰で採算が取れない薬への配慮や、新薬の価格を改定前と遜色ない水準に増額する措置が相次いだ。結局、3100億円にとどまり、削減幅は前回から3割弱減った。およそ13兆円を計上する年金は、23年度の支給額改定で給付を物価の伸びより抑制する「マクロ経済スライド」を3年ぶりに発動する。ただ、物価上昇を反映し、年金額は22年度の水準より増える。制度の安定性を高めるにはマクロ経済スライドを物価の下落時でも発動し、給付の抑制を進める抜本的な見直しが必要だが、機運は乏しい。医療や年金に比べて膨張ペースが際立つのが介護だ。2.7%増の約3.7兆円を計上した。年内に示すはずだった給付と負担の見直し案は23年に持ち越した。00年度の社会保障費は約17兆円と、今の半分以下だった。給付は膨らむ一方、22年の出生数は80万人を初めて割り込む見通しで、将来の支え手も減る。団塊の世代が全員75歳以上になり、膨張圧力が一段と増す25年まで残された時間は少ない。 *5-4-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA19AWU0Z11C22A2000000/ (日経新聞 2022年12月20日) 年金抑制「マクロ経済スライド」3年ぶり発動へ 政府 政府は2023年度の公的年金の支給額改定で、給付を抑制する「マクロ経済スライド」を3年ぶりに発動する検討に入った。年金額は22年度の水準より増えるが、物価上昇率には追いつかず実質的に目減りする見込み。給付抑制は年金財政の安定に欠かせないが、過去の繰り越し分も合わせ、大幅な抑制になる見込みだ。23年度予算案に、マクロ経済スライド発動を前提に社会保障関係費として36兆円台後半を計上する。厚生労働省は23年1月に23年度の改定額を公表する。支給額は前年度を上回るものの、物価上昇を補うほどには増えないとみられる。年金額は毎年物価や賃金の増減に応じて改定する。22年度の厚生年金のモデルケース(夫婦2人の場合)は月あたりの支給額が21万9593円だった。今回は足元の物価や賃金の伸びを踏まえて支給水準が3年ぶりに増える見通しだ。専門家は改定のベースになる22年の物価上昇率を2.5%と試算する。公的年金は少子高齢化にあわせて年金額を徐々に減らす仕組みだ。21年度から2年連続で発動を見送り、0.3%分がツケとしてたまっている。23年度の改定では21~23年度分が一気に差し引かれる可能性が高い。 *5-4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221224&ng=DGKKZO67117500T21C22A2M10800 (日経新聞 2022.12.24) 年金、財政安定へ給付抑制 医療、年金、介護などをあわせた社会保障関係費は36兆8889億円で、2022年度当初予算比で6000億円以上増える。25年に団塊の世代が全員75歳以上となり、介護が必要な人の急増などによる社会保障費の膨張が避けられない。23年度の公的年金の支給額改定で3年ぶりに給付を抑制する「マクロ経済スライド」と呼ぶ措置が発動する前提で予算編成した。年金額自体は上がるものの、物価上昇の伸びに追いつかないため実質的に目減りする見通し。マクロ経済スライドは物価・賃金の下落局面では発動せず、翌年度以降に持ち越す「キャリーオーバー制度」がある。21、22年度に先送りした0.3%分の「ツケ」がたまっている。23年度は0.3%の減額を見込む。合わせて0.6%となる。22年の物価上昇が2.5%との予測などを踏まえ、支給額は68歳以上は前年度比1.9%、67歳以下は同2.2%の引き上げを想定する。正式な改定率は厚生労働省が23年1月に公表する。高齢者の負担感が強まり、景気回復に水を差す恐れもある。新型コロナウイルス禍で雇用調整助成金(雇調金)の支給が膨らみ、雇用保険財政の悪化が著しい。そのため保険料率が23年度から上がる。4月から労使折半の「失業等給付」の料率が0.6%から0.8%になる。月給30万円の労働者の保険料は現在の月1500円から300円増える見通し。雇調金は企業が従業員向けに休業手当を支払う費用を国が助成する。コロナ特例が長期化し、支給決定額は6兆円を突破した。雇用保険のうち、本来の財源である「雇用保険2事業」だけでは補えず、失業等給付の積立金からも拠出して急場をしのいでいたが、資金が枯渇しつつある。 *5-4-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221223&ng=DGKKZO67087830T21C22A2MM0000 (日経新聞 2022.12.23) 消費者物価、11月3.7%上昇 40年11カ月ぶり水準、食品・エネルギー目立つ 総務省が23日発表した11月の消費者物価指数(CPI、2020年=100)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が103.8となり、前年同月比で3.7%上昇した。第2次石油危機の影響で物価高が続いていた1981年12月の4.0%以来、40年11カ月ぶりの伸び率となった。円安や資源高の影響で、食料品やエネルギーといった生活に欠かせない品目が値上がりしている。15カ月連続で上昇した。政府・日銀が定める2%の物価目標を上回る物価高が続く。QUICKが事前にまとめた市場予想の中央値(3.7%)と同じだった。消費税の導入時や増税時も上回っている。調査対象の522品目のうち、前年同月より上がったのは412、変化なしは42、下がったのは68だった。上昇した品目は10月の406から増加した。生鮮食品を含む総合指数は3.8%上がった。91年1月(4.0%)以来、31年10カ月ぶりの上昇率だった。生鮮食品とエネルギーを除いた総合指数は2.8%上がり、消費増税の影響を除くと92年4月(2.8%)以来、30年7カ月ぶりの水準となった。品目別に上昇率を見ると、生鮮を除く食料は6.8%、食料全体は6.9%だった。食品メーカーが相次ぎ値上げを表明した食用油は35.0%、牛乳は9.5%、弁当や冷凍品といった調理食品は6.8%伸びた。外食も5.3%と高い伸び率だった。エネルギー関連は13.3%だった。10月の15.2%を下回ったものの、14カ月連続で2桁の伸びとなった。都市ガス代は28.9%、電気代は20.1%上がった。ガソリンは価格抑制の補助金効果もあって1.0%のマイナスと1年9カ月ぶりに下落した。家庭用耐久財は10.7%上がった。原材料や輸送価格の高騰でルームエアコン(12.7%)などが値上がりしている。日本経済研究センターが15日にまとめた民間エコノミスト36人の予測平均は、生鮮食品を除く消費者物価上昇率が2022年10~12月期に前年同期比で3.61%となっている。23年1~3月期は2.57%になり、1%台になるのは同7~9月期(1.63%)と予想する。主要国の生鮮食品を含む総合指数は、11月の前年同月比の伸び率で日本より高い。米国は7.1%、ユーロ圏は10.1%、英国は10.7%だった。 *5-5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221224&ng=DGKKZO67126340U2A221C2EA4000 (日経新聞 2022.12.24) 日本の1人あたり名目GDP、20位に後退 昨年 内閣府が23日発表した国民経済計算年次推計によると、豊かさの目安となる1人あたりの名目国内総生産(GDP)が日本は2021年に3万9803ドルとなった。経済協力開発機構(OECD)加盟国38カ国中20位と、20年の19位から低下した。日本では1人あたりの所得が伸び悩み、個人消費の低迷が経済全体を下押ししている。日本が20位となるのは18年以来で、3年ぶり。前年の20年は日本が19位、フランスが20位だったが逆転した。フランスは新型コロナウイルス禍からの景気回復が進み、個人消費が伸びた。1人あたりGDPは20年の3万8807ドルから21年は4万3360ドルと増えた。日本は20年(3万9984ドル)から減った。20年と比べて円安・ドル高だったこともドル建ての1人あたりGDPを押し下げた。後藤茂之経済財政・再生相は同日の記者会見で「長引くデフレで企業は投資や賃金を抑制し、個人は消費を減らさざるを得なかった」と指摘した。05年に13位だった日本の順位は、中長期で見て下落傾向にある。名目GDPの総額をみると、21年の日本は5兆37億ドルとなり、世界のGDPに占める比率は5.2%となった。米中に次いで3位は維持したが、比率としては19年の5.8%を下回り過去最低となった。日本のドル建てでみた名目GDPは10年に中国に逆転され、3位に低下した。世界のGDPに占める比率も05年には10.1%だったが、16年間で半分まで下がった。 *5-5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20221221&ng=DGKKZO66987830Q2A221C2KE8000 (日経新聞 2022年12月21日) あるべき社会保障改革(上) 支え手増加の勢い 後押しを (小塩隆士・一橋大学教授:1960年生まれ。東京大教養卒、大阪大博士(国際公共政策)。専門は公共経済学 <ポイント> ○高齢化進む中でも支え手の就業者は増加 ○被用者保険の適用範囲拡大で雇用抑制も ○「全世代」想定する際は将来世代も含めよ 社会保障に関しては、年金・医療・介護各分野で制度改正に向けた日程が具体化し、改革論議が加速している。改革を求める最大の要因は、高齢化がもたらす圧力だ。高齢化は、社会保障を含む経済社会の「支え手」が減少し、生産と消費のバランスが国全体で崩れることを意味する。改革はそのバランスを取り戻すものでなければならない。高齢者向け給付の削減は制度の持続可能性を高める効果があるが、本質的な問題解決にならない。社会保障を経由した公的な扶養を圧縮すれば、家族による私的な扶養もしくは一層の自助努力が必要になるだけだ。高齢化の圧力は財政健全化だけでは消せない。では、社会保障改革はどうあるべきか。話は簡単だ。支え手の増加を目指せばよい。支え手が増えたら、かなりの問題は解決する。ただし私たちの事実認識を改めておく必要がある。意外なことに支え手は減っていない。むしろ増えている。支え手の社会全体における割合をみる場合、生産年齢人口(15~64歳)が総人口に占める比率をみるのが定番だ。だが本来は働いている人、つまり就業者の比率をみるべきだろう。図は1990年を基準として生産年齢人口や就業者数の増減をみたものだ。生産年齢人口の総人口比は、2021年までに約10ポイント低下している。だが就業者数は00年から15年ごろまでは低迷したものの、その後大きく回復し、21年の総人口比は約3ポイント上昇している。支え手は結構踏ん張っているわけだ。貢献しているのは65歳以上の高齢層だ。しかも主役は正規雇用者ではなく、非正規雇用者やフリーランス・個人事業主など被用者以外の就業者だ。出生率の長期低迷が示すように、私たちは人口の再生産から既に手を引いている。少子化対策により産み育てやすい環境は整備できても、出生率の回復までは期待しにくい。一方で、このままでは支え手が足りなくなるから、世の中を回すために働ける者は働こうという調節作用が社会全体で働いているようにみえる。社会保障改革が目指すべき最重要の方針は、支え手回復の勢いをより確実なものにし、人々が支え手として無理なく社会に貢献できる仕組みを構築することだ。そこで気になるのは、高齢層の支え手増加のかなりの部分が正規雇用以外で進んでいる点だ。支え手が増えても、その質は相当割り引く必要がある。社会保険料を通じた社会保障財源への還元も限定的となる。高齢の支え手増加が非正規雇用者や被用者以外の就業者の形をとりがちなのは、保険料負担を回避したい企業の意向を反映している。欧州諸国でも事情は似ており、高齢者就業の回復は被用者保険の対象外となるフリーランスや個人事業主がけん引している。全世代型社会保障構築会議の発想は、被用者保険の適用範囲を正規雇用者以外に拡大し、「勤労者皆保険」の実現を目指すというものだ。その方針は正しい。しかし負担軽減のために非正規雇用を進めてきた企業にとっては、これまでとは逆方向に進めということだから、歓迎できる話ではない。適用拡大の結果、かえって賃金削減・雇用抑制が進み、保険料負担が労働者側にのしかかるだけに終わるリスクもある。経済学の教科書が描く保険料負担の「帰着」の典型例だ。被用者保険の適用範囲拡大だけでは、問題は解決しない。取り残される層が必ず出てくる。国民健康保険や国民年金といった被用者以外の社会保険の仕組みも併せて改める必要がある。国保や国民年金の保険料には減免措置はあるが、定額部分があるため、低所得層ほど負担が相対的に重くなる逆進性の問題がある。給付付き税額控除と組み合わせて低所得層の保険料負担を軽減すると同時に、保険料の拠出実績を残すといった工夫があり得る。最終的には社会保障の財源調達は働き方や所得の源泉とは関係なく、所得に連動した仕組みにすべきだろう。支え手を増やすには、年金が就業の抑制要因にならないようにする改革も必要だ。例えば前回の全世代型社会保障改革では、一定以上の賃金を得ると年金が削減される在職老齢年金制度が、65歳以上については見直されなかった。今後、高齢者のフルタイム正規雇用が一般化して賃金が高まると、この仕組みが就業に対するブレーキとなり得る。少なくなった支え手が負担した財源をできるだけ公平で効率的に活用することも、改革が目指すべき重要な方針だ。日本の社会保障給付は20年度には総額132兆円にのぼる。国内総生産(GDP)の約4分の1に相当する。にもかかわらずひとり親世帯や単身高齢者の貧困率は先進国の中でも高いグループに属する。日本の社会保障は年齢を軸に組み立てられており、かなりの部分が若い層から高齢層へという年齢階層間のお金の流れにとどまる。高齢層でも支援が必要な人がいれば、そうでない人もいる。若い層でも同じだ。限られた財源をできるだけ公平で効率的に使うには、年齢とは関係なく、負担能力に応じて負担を求め、給付も発生したリスクへの必要性に応じたものにするという方針が基本となる。所得が低くない高齢者を対象とした医療の自己負担増はこの方針に沿ったものだ。困っていない人を支援するだけの余裕はなくなりつつある。得られた財源の増分を、支援をより必要とする人たちに重点配分すべきだ。そうでないと将来世代に迷惑がかかる。今を生きる全世代にとって、現行の社会保障の恩恵を維持するための最もてっとり早く、そして政治的に最も受け入れやすい改革は「何もしないこと」だ。医療・介護の自己負担や保険料、給付の対象範囲は据え置くべきであり、年金の支給開始年齢や保険料の納付期間も変更してはならない。社会保障のための消費税率の引き上げなど、もってのほかだ――。こうした選択は、将来世代に負担を先送りすることにほかならないが、人口が順調に拡大すれば問題はない。負担を人口1人当たりでみれば、分母の人口が膨らむので、無限の将来まで転がしていけば分数の値はゼロに近づいていく。それならば、将来世代のことを心配する必要はなく、財政赤字も無視して構わない。しかし状況は変わっている。人口は減少局面に既に入っている。1人当たり負担は、分母が減るので膨らんでいく。私たちが私たちの幸せを追求すると、将来世代に迷惑がかかる。民主主義はあくまでも今を生きる全世代の幸せ追求の仕組みだが、人口増加を暗黙裏に想定している。その限界が顔を出しつつある。全世代型社会保障という場合の「全世代」として、私たちは今を生きる全世代を考える。しかし人口減少の下では将来世代もそこに含める必要がある。将来世代に不要な負担をかけないためには、世の中の支え手を増やし限られた財源を大事に活用するという、よく考えれば当たり前のことを意識的に進めるしかない。 *5-5-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230105&ng=DGKKZO67326060V00C23A1EA2000 (日経新聞 2023.1.5) ジョブ型、試行錯誤、三菱ケミ、ポスト公募の応募半分/KDDI、学び直しの動機づけ腐心 デジタルトランスフォーメーション(DX)など経済環境の変化が加速するなか、あらかじめ仕事の内容を定めた「ジョブ型雇用」が普及してきた。働き手の専門性や意欲を高めやすく、経団連の提言から2年ほどで導入企業は予定も含めると大手企業の約2割となった。もっとも、仕事とスキルのミスマッチや賃金連動の遅れなど課題もみえてきた。仕事の内容や賃金を「職務記述書(ジョブディスクリプション)」などで定義するジョブ型雇用は、欧米で広く普及する。企業は人材の専門性や意欲を高めやすくなり、働く側は転職しやすくなる。日本では職務を限定せず年功序列の色彩が強い終身雇用が標準だったが、2020年1月に経団連が春季労使交渉の指針でジョブ型を提言して以降、高度人材を求める大手企業で導入が加速している。日本経済新聞が22年5月に実施した調査では、有効回答を得た上場企業と有力非上場企業の計813社のうちジョブ型雇用を導入済みの企業は10.9%、今後導入予定の企業は12%に達した。ジョブ型に欠かせないのが、働き手が主体的に自らのキャリアプランを考え、実現に向けた能力開発に取り組む「キャリア自律」だ。企業側では各部署がそれぞれのポストに必要なスキルを明示して希望者を募る社内公募制をとることが多い。20年秋以降、ジョブ型を段階的に導入した三菱ケミカルは、主要ポストを社内公募に切り替えた。これまでに約2700のポストを公募したが、応募があったのは半分で実際ポストに就いたのは3分の1だ。部署間の人気の格差もあるとみられ、応募がない部署は従来の会社主導の人事などで埋めている。公募手法のノウハウ蓄積を急いでいる。24年度までに全グループ会社にジョブ型雇用を広げる日立製作所は、21年度に社内外で同時に約480件のポストを公募した。グループの人材が就いたのは3割で、残りは経験者採用だった。専門性の高いポストと社内人材のスキルのミスマッチもあるようだ。優秀な経験者の獲得とともに「社内労働市場のさらなる活性化を目指す」(同社)として、24年度にグループ内外で公募し、うち社内人材が異動する件数を、21年度比3倍の500件以上に増やす計画。異動希望の社員と受け入れ部署を仲介する制度も導入予定だ。こうしたジョブとスキルのミスマッチ解消にはリスキリング(学び直し)も重要となる。KDDIは20年のジョブ型雇用の導入に合わせ、高度デジタル人材の育成講座「KDDI DX ユニバーシティー」を始めた。希望者がデータサイエンティストなど5つの職種に必要な知識を学べる。22年7月から段階的に全社員にDXの基礎知識を教える研修も始めた。1人当たりの研修時間は21年度に10.4時間で19年度比で倍増した。学ぶ内容や時間は働き手の自主性に委ねられている面もあり、本人のキャリア自律が不足すると学習効果が上がらないリスクもある。KDDIは社員と直属の上司が定期的な対話を通じて「能力開発計画」を策定し、希望キャリアに就くため必要なスキルを助言するなど、リスキリングの効率を高める工夫もする。木村理恵子人財開発部長は「会社の重点領域への人材配置と社員のキャリア選択のバランスは課題」と話す。職種別賃金が一般的な欧米と異なり、日本のジョブ型では仕事内容と賃金の連動が大きな課題だ。日本の標準的な職能給制度は依然として年功色が強い。これでは、仕事の市場価値に応じた高い賃金を提示し、優秀な専門人材を採用しやすくするジョブ型の利点を発揮しにくい。富士通はジョブ型雇用導入に合わせ、20年以降、段階的に働き手を職責で評価する人事制度を導入したが、基本的に職種別の賃金体系になっていない。「日本は欧米に比べ人材の流動性が低く、職種別賃金市場が成熟していない」(同社)ためだ。人工知能(AI)人材など一部の専門職について高い賃金で処遇したり、コンサル人材を集めた専門子会社に独自の賃金体系を導入したりしている。日立やKDDIも職種別賃金体系は導入せず、一部の高度人材やスキル重視の職種別採用などについて賃金を上積みしている。日本の職種間の賃金格差は10%程度だが、ジョブ型が標準の欧米は40%程度に開くという調査もある。職種別賃金の導入で働き手の一部の待遇が悪化する可能性があるのも、各社が制度刷新に踏み切れない理由のひとつだ。米人材コンサル、マーサーの日本法人の白井正人取締役は「職種別賃金への転換には、転職の増加などの労働市場の構造変化も必要で、移行には10~20年かかる可能性もある」とみる。DXの加速など急激な事業環境の変化に、既存の日本型雇用が対応できないことは明らかだ。ジョブ型導入企業で浮き彫りになった課題に向き合い、組織構造の変化に伴う摩擦を抑えながら働き方改革を継続できるかが問われている。 *5-5-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230118&ng=DGKKZO67668430Y3A110C2EA2000 (日経新聞 2023.1.18) 労働移動の加速、賃金の伸び高く 過去30年の上昇率、米英は日本の8~9倍 経団連の報告書は成長産業への労働力の移動を加速することを新たな柱の一つに据えた。優秀な人材の獲得競争によって中長期的な賃上水準の向上につなげる狙いがある。東京都立大の宮本弘曉教授の分析によると、雇用の流動性が高いほど賃金の伸びは大きい。主要国の賃金の1990年から2021年の上昇率を比較すると、平均勤続年数が約4年の米国は日本の9倍、8年の英国は8倍に上る。日本の平均勤続年数は12年で、賃金成長率は過去30年間で約6%と低迷し、海外に比べて大幅に見劣りする。宮本氏は「日本の労働市場は硬直的だ。成長産業に人材が移りやすくすることで労働生産性を高め、賃金も増えるという流れをつくらないといけない」と話す。経済界は「構造的な賃上げ」を重視している。そのため経団連は働き手がスキルを身につけて転職することを肯定的にとらえる意識改革が必要だと提起した。学び直しの時間を確保しやすいよう時短勤務や選択的週休3日制、長期休暇「サバティカル制度」の整備といった選択肢を挙げる。十倉雅和会長は「労働者が主体的にスキルを身につけて自分たちの価値を高めることが本人のキャリアパスや働きがいに資する。社会全体にも貢献する」と働き方改革の重要性を主張する。 *5-5-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230121&ng=DGKKZO67781200R20C23A1MM8000 (日経新聞 2023.1.21) 日本の物価、4.0%上昇 12月 41年ぶり高水準に 総務省が20日公表した2022年12月の消費者物価上昇率は生鮮食品を除く総合で前年同月比4.0%と、41年ぶりに4%台となった。資源高や円安でエネルギー価格が上がり、食品など身近な商品に値上げが広がった。食料の伸び率は7.4%と、46年4カ月ぶりの水準に達した。新型コロナウイルス禍後に回復してきた消費の先行きは、今春の賃上げ水準が左右する。22年を通じた上昇率は生鮮食品を除くベースで2.3%だった。消費増税で物価が上がった時期を除くと、31年ぶりの伸びだった。12月の生鮮食品を除いた指数の上昇率は11月の3.7%から拡大した。4%台は1981年12月(4.0%)以来だ。電気代などエネルギー関連が15.2%伸びた。食料全体は7.0%で、生鮮を除くと7.4%の上昇だった。1976年8月(7.6%)以来の水準となった。原材料の値上がりを受けてメーカー各社が値上げを進めており、食用油(33.6%)やポテトチップス(18.0%)、炭酸飲料(15.9%)などが伸びた。米国や欧州の物価は22年中にピークアウトの兆候をみせている。日本は12月まで伸びが加速した。23年は政府による電気代抑制策が物価の押し下げ要因となる一方、値上げは幅広い商品に広がっている。政府は22年12月に22年度の物価上昇率の予測を総合で3.0%とし、7月の予測(2.6%)から引き上げた。日銀は23年度の生鮮食品を除いた上昇率を1.6%、24年度を1.8%とする。専門家による消費者物価の予測は上振れが続いている。 *5-5-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230121&ng=DGKKZO67781170R20C23A1MM8000 (日経新聞 2023.1.21) 東電、3割値上げ申請へ 家庭向け 今夏までの実施目指す 東京電力ホールディングス(HD)は来週はじめにも一般家庭向け電気料金の値上げを経済産業省に申請する。経産省が認可する規制料金とよばれるプランで、家庭向け契約の過半を占める。申請する値上げ幅は3割前後となる見通し。国の審査を経て今夏までの料金引き上げを目指す。東電が規制料金を上げるのは東日本大震災後に収支が悪化した2012年以来、11年ぶりとなる。実際の値上げ幅は、東電の申請後に経産省の審議会で妥当性が議論された上で最終的に決まる。審査には数カ月程度がかかる見通しで、東電は電力需要が高まる夏までに値上げを実現させたい考えだ。電気料金には「燃料費調整制度(燃調)」に基づいて3~5カ月前の石炭や液化天然ガス(LNG)の輸入価格を自動で反映している。規制料金には転嫁の上限が設けられており超過分については各社が負担する仕組みだ。ウクライナ危機以降の資源高や円安で発電に使う燃料の調達コストが上昇し、東電では22年9月に上限に到達した。電気を売れば売るほど赤字が積み上がる状況だ。足元のLNGの価格はウクライナ危機後のピーク時より2割低くなったが、新型コロナウイルスの感染拡大前の19年12月と比べると2.5倍の水準にある。石炭の価格も5倍になっている。値上げで採算の改善を急ぐ。経営が厳しいのは他の電力会社も同じだ。東北電力や中国電力などの5社も22年11月以降、燃料高などを理由に3~4割前後の値上げを経産省に申請した。北海道電力も検討中だ。経産省の審査では値上げ幅の圧縮に向け、燃料の調達費の抑制や経営の合理化を促す。原発の稼働が進む関西電力と九州電力、中部電力は現時点では値上げを検討していない。 *5-5-7:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/951031 (佐賀新聞 2022/11/21) 来年度の年金、実質減額へ、最大0・7%目減り試算 来年度の公的年金額は実質的に減る公算が大きいことが21日、分かった。4月の改定に伴い、金額自体は3年ぶりに増える見通しだが、物価上昇分に追い付かないため。ニッセイ基礎研究所の試算によると、今年の物価は年間で2・5%上昇するが、少子高齢化に応じて年金額を抑制する仕組みが適用され、68歳以上の場合、支給額は1・8%の増加にとどまる。差し引き0・7%分、目減りすることになる。同研究所の中嶋邦夫上席研究員が9月までの統計を基に、物価上昇率を仮定して計算した。67歳までの人は、賃金の変動率を基に計算する仕組みのため、2・1%増となる見通しで、0・4%の目減り。 *5-6-1:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221214/k10013922771000.html (NHK 2022年12月14日) 技能実習制度見直しへ 有識者会議 制度の存廃や再編含め論点に 外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度を見直すため、14日から政府の有識者による検討が始まり、制度の存廃や再編も含めて論点とすることが了承されました。外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習制度は、発展途上国の人材育成を主な目的とする一方、実際は労働環境が厳しい業種を中心に人手を確保する手段になっていて、目的と実態がかけ離れているといった指摘も少なくありません。制度の見直しに向けて政府の有識者による検討が始まり、14日の初会合には有識者会議の座長を務めるJICA=国際協力機構の田中明彦理事長らが出席しました。冒頭で田中座長は「外国人との共生社会としてありうるべきは、安全・安心で、多様性に富んで活力があり、個人の尊厳と人権を尊重した社会だ。この3つが実現する制度を検討したい」とあいさつしました。今後の論点として、 ▽技能実習制度を存続するか、廃止するか、 ▽人手不足の12分野で外国人が働く「特定技能制度」に一本化して再編するのか等のほか、 ▽技能実習生の受け入れを仲介する監理団体の在り方などを含めて検討することを 了承しました。 委員からは「制度の目的と実態が乖離していることは明らかで、人権侵害と結び付く構造的な原因だ」等の意見が出された一方で、実習生に日本の技術を学んでもらうことで国際貢献を担っているという意義もあるという意見も出たということです。有識者会議は、関係団体から聞き取りを行うなどして来年春に中間報告をまとめ、秋ごろをめどに最終報告書を提出する予定です。 *5-6-2:https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/202301/0015940804.shtml (神戸新聞社説 2023/1/5) 外国人労働者/「選ばれる国」でいられるのか 少子高齢化が進み、地方を中心に働き手不足が深刻になっている。それらを補うために、政府が事実上の移民の受け入れにかじを切ったのは、2018年12月のことだ。「外国人労働者が引きも切らず来日する」との前提で、政策は作られた。主にアジア諸国から来る若者に介護や農漁業、建設業などの仕事を担ってもらおうと、入管難民法を改正して「特定技能」という新たな在留資格を設けた。改正法は19年4月に施行された。4年近くが経過した今、当初の前提に揺らぎが見える。果たして、日本は働く場として魅力的なのだろうか。まずは、兵庫県内で働くアジア出身者を訪ねることにした。 ◇ 神戸市兵庫区の企業「GOLD(ゴールド) LAN(ランド)D」は、外国人向けに通訳や翻訳、不動産仲介などを手がける。チュ・ディエウ・リン社長(30)をはじめ、従業員25人のうち日本人1人を除く全員がベトナム出身だ。リンさんは母国で大学を卒業後、銀行に職を得た。起業を夢見て日本の専門学校に留学し、18年に同社を設立した。2歳の長男を育てる母親でもある。最近、日本行きを希望するベトナム人が減ったと実感する。同胞が中心だった顧客は、ネパールやバングラデシュからの労働者が目立つようになった。「ベトナムは経済成長で賃金が上がっている。しんどい出稼ぎをするより、自国で働きたいと若者が思うのは自然なこと。国が発展して都会育ちが増え、日本の田舎で働くのに抵抗を感じる人もいる」と話す。 ●縮まった経済格差 円安の影響も無視できない。円はベトナムの通貨ドンに対しても値を下げた。リンさんの部下で営業を担当するルオン・バン・トゥアンさん(26)は「故郷の親への仕送りは、円安でやめた。子どもが生まれ、日本の物価が上がったので、逆にお金を送ってもらうほど」と肩をすくめる。円安を理由に帰国を考える同郷人は多いという。日本の外国人労働者は21年10月時点で約173万人に上る。10年間で2・5倍に増えた。外国人抜きでは回らない職場は多い。さまざま分野で重要な担い手となっている。だが、取り巻く状況は変わった。長期の停滞から抜け出せない日本に対し、アジア諸国は持続的に成長している。経済格差は確実に縮まりつつある。門戸を開けさえすれば日本に来る-との姿勢では、いずれ見向きもされなくなる。今後、日本が外国人労働者をさらに必要とするのなら、どうすれば「選ばれる国」でいられるかを考えるべきだ。それは、ご近所や同僚としての外国人とどう共生するかという個々人への問いかけでもある。 ●進まない処遇改善 丹波篠山市の南部に位置する「篠山学園」は、2年制の介護福祉士養成校だ。同市の全面協力を得て、西宮市の社会福祉法人が17年に開校した。当初は女子学生限定でベトナム人が多かったが、21年秋から男女共学に変更し、インドネシアやミャンマーなどにも募集先を広げた。山村信哉学園長は「アジアの優秀な若い人の獲得競争が年々激しくなっている」と危機感を募らせる。根底には、介護職の処遇改善が叫ばれながらも、それがなかなか進まない日本の現状が横たわる。昨年、政府は技能実習制度の見直しを始めた。途上国の人材育成を目的にした制度でありながら、実習生への賃金未払いや虐待などが絶えない。今春に有識者会議が中間報告をまとめるが、人権を守ることを最優先に、制度廃止も視野に入れて議論を進めなければならない。賃金が長らく低迷する中、経済成長する他国へ向かう日本の若者が増えてもおかしくはない。兵庫県内でも、中東などからの求人を紹介できないか検討する企業が出てきた。外国人の労働を考えることは、この国の労働を考えることだ。次世代にそっぽを向かれないようにするには、待遇面はもちろん、やりがいや将来への希望を示すしかない。 *5-6-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230107&ng=DGKKZO67405840X00C23A1MM8000 (日経新聞 2023.1.7) 公立高「外国人枠」なし73% 進学せぬ子、日本人の10倍、本社調査、将来の就労に影響 高校で外国人受け入れ枠の導入が進んでいない。2023年の入試で全国の公立高の73%が特別枠を設けないことが日本経済新聞の調査で分かった。日本語が得意でない生徒にとって一般入試は容易でない。中学卒業後に10%が進学しておらず、全中学生の10倍の水準だ。新型コロナウイルス下の入国制限緩和で外国人労働者受け入れが再び拡大しており、子どもが進学しやすい環境を整える必要がある。高度・専門人材の家族として来日した子どもが制約なく働くには、高卒資格が求められる。文部科学省は指針で自立には「高校教育が重要」と指摘。特別枠の設定や試験教科の軽減などを各地の教育委員会に求めたが、必要性が認識されず、指導体制の不安もあって対応しない教委や学校が多い。4月から高校で日本語を教える授業が単位として認められる。指導の充実を目指す一方で、"入り口"は狭いままだ。22年11月中旬、大阪府立東淀川高校(大阪市)で外国出身の生徒8人が分かりやすい日本語を使った特別授業を受けていた。府内では同校など8校が外国人向け特別選抜を実施し、22年は定員の8割にあたる計約90人が合格した。フィリピン出身のカリーノ・カートさん(18)は「漢字がほとんど分からず一般入試では入れないと思い、この高校を選んだ」と話す。こうした枠がない地域は多い。日経新聞が22年12月、各都道府県教委に23年入試について聞いたところ、一般入試と別に外国人生徒の定員枠や特別選抜を設けるのは27都道府県だった。茨城は県内の全公立高に特別枠を設けるが、北海道は札幌市立高1校のみ。全国では導入は約920校で、全体の約3400校のうち27%にとどまった。枠があっても、受験資格を東京や埼玉などのように「来日3年以内」に限定する例が目立つ。中学に入る前に来日した子どもは対象外となる。外国語の表現を十分理解するようになるには5年ほど必要とされる。NPO法人「多文化共生教育ネットワークかながわ」(横浜市)の高橋清樹事務局長は「3年たっても日本語力が十分でなく、一般入試は困難な生徒が珍しくない」と話す。文科省によると、20年度卒業の中学生で高校や専修学校に進まなかったのは1%未満。一方で「日本語指導が必要」と認定された生徒は10%に上る。授業についていけず中退するケースもあり、21年度の中退率は5.5%と全体(1.0%)との開きは大きい。高卒資格は将来を左右する。外国人材の配偶者や子らが対象の在留資格「家族滞在」で働けるのは原則、週28時間以内。高卒なら就労制限がない在留資格に切り替えられ、生活基盤を築きやすい。米国は高校まで義務教育で英語力にかかわらず進学できる。カナダやオーストラリアは中学校の成績証明書などでの選考が一般的で英語力が不十分でも公立高に進める。東京外国語大の小島祥美准教授は「小中学校段階の日本語教育は自治体間の格差が大きく、高校入試で思考力を評価するには工夫が必要。グローバル人材に育つ可能性を秘めた子どもが高校教育からこぼれ落ちるのは日本社会にとっても損失だ」と話す。 *5-6-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/224937 (東京新聞 2023年1月12日) 「姉のように命落とす人また出る」 収容期限ない入管法改正案の国会提出にウィシュマさんの遺族らが反対会見 外国人の収容ルールを見直す入管難民法改正案が、23日召集の通常国会に提出される見通しとなった。これを受け、2021年3月に名古屋出入国在留管理局で収容中に亡くなったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん=当時(33)=の遺族らは12日、東京都内で記者会見し「収容について上限設定や司法審査もない法案ならば、外国人の人権がないがしろにされる」と訴えた。入管難民法改正案は21年に国会で審議入りしたが、ウィシュマさんの死亡などを受けて衆院法務委員会で採決が見送られ、同年10月の衆院解散で廃案となった。今回の改正案は旧案を一部修正するものの、難民申請中の送還を可能にし、収容期間の上限は現行通り設定せず、収容に関する司法審査がないなど、骨格は維持されるとみられる。会見でウィシュマさんの妹・ポールニマさん(28)は収容期間の上限設定がなければ「入管が都合のいいよう収容してしまうのではないか」と懸念を示した。その上で「姉は無期限で収容されて健康が悪化し、命を落とした。無期限収容を変えないと、姉のように命を落とす人が出るのが当たり前になる」と訴えた。旧案で、原則として難民申請を2回までに制限し、暴れるなどして送還を拒否した場合に懲役1年以下の罰則を設けるとした点は維持される見込み。もう1人の妹・ワヨミさん(30)は「送還拒否で懲役刑というのは、外国人への人権の侵害で、正しいルールではない」と厳しく指摘した。遺族を支援する弁護団からも批判が相次いだ。高橋済弁護士は「(旧案を巡る)与野党での修正協議やウィシュマさんの事件の反省を全く踏まえてない。収容期間の上限設定がないというのは、国際水準からほど遠い状況だ」と非難。駒井知会弁護士も「現状でも難民条約が守られていないのに、さらに状況が悪化する」と怒りをあらわにした。指宿昭一弁護士は「2年前の法案の骨格を維持する内容なら、法案を出すべきではない。ウィシュマさんの死の真相は解明されてなく、入管施設の改善が進んだとも思えない」と話した。 *5-6-5:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC134QG0T10C23A1000000/ (日経新聞 2023年1月13日) 草加商議所、難民の就労支援 地域事業所で12人雇用 草加商工会議所(埼玉県草加市)は、政府が国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の要請を受け、他国の難民キャンプなどから受け入れる「第三国定住難民」の就労を支援し、難民12人を同市を中心とする事業所で雇用することが決まったと明らかにした。社会貢献活動の一環として難民の雇用を支援するとともに、地域の中小事業者の人材不足の緩和にもつなげる。同商議所は、政府の委託を受けて難民の定住支援に取り組む公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(RHQ)と連携。2022年9月に来日した第三国定住難民第12陣29人のうち、単身者12人について地域での就労支援を決めた。会員事業所とのマッチングや職場見学、面接などを経て草加市内で同商議所を含む5事業所、同県八潮市内1事業所での雇用が決まった。難民はミャンマー出身者が中心。現在、難民はRHQ支援センターの6カ月間の定住支援プログラムを受講中で毎日、日本語や日本の文化、社会制度を学んでいるという。受け入れる6事業所は同プログラム修了後、4月から開始する半年間の職場適応訓練に向け、難民の住居確保や職場での指導体制の準備を進めている。同商議所は訓練終了後、各事業所が正式に雇用契約を締結し、難民が安定した収入を得て生活基盤が整うように協力する。商議所が窓口になった第三国定住難民の就労支援としては、これまでにない規模とみている。野崎友義会頭は「ウクライナ避難民のほか、日本を頼ってきた多くの難民の存在を知り、自分たちにもできる貢献が何かないかを模索してきた。今回の結果を通じて地域の中小企業1社1社が力を合わせれば、大きな国際貢献ができることを証明していきたい」と話している。今後も「難民の就労支援に継続的に取り組むことを検討する」(山崎修専務理事)という。 <街づくりと住宅> PS(2023.1.27追加):*6-1は、①東ドイツ時代に建設された団地の約半数は市営住宅になり ②老朽化が進んで富裕層や若い世代が離れて移民・貧困層の割合が増えていたが ③大規模省エネ改修で ④くすんだ色の外壁や窓枠のデザインが一新 ⑤外壁や屋根の外断熱強化 ⑥窓や扉のトリプルガラス樹脂サッシ化で ⑦エネルギー消費が半分になり ⑧太陽光・風力など豊富な再エネ電力で湯を作って地域暖房や給湯に生かす創エネ設備も整備され ⑨子育て世代が多く引っ越してくるようになって ⑩緑化や公共交通の整備も進み ⑪住宅の省エネ化は化石燃料の使用と光熱費減少だけでなく、健康にもいい「一石三鳥」の効果がある ⑫日本でも建物の省エネ基準強化や太陽光パネル設置義務化などの対策が急務 と記載している。 ベルリンを旅行した時、テレビ塔から街を見下ろし、「ブロックに一つ大きな建物があり、中庭があって、どの部屋にも太陽光が入るようになっていて、緑が多く、わかりやすくて、いい街づくりだ」と私は思った。そのベルリンで、①~⑩のように、市営住宅を徹底して省エネ改修し、デザインを明るくして、再エネ電力で湯を作って地域暖房や給湯に生かす創エネ設備を整備したところ、住民の質が向上して緑化や公共交通の整備が進んだというのは、さすがにドイツの合理性だと思う。 日本にないのは、住みよい街を創るための計画性とその方針に従った個々の誘導だが、ドイツのケースを参考にできる地域は多いし、そうすることによって住民や企業の誘致も進むだろう。さらに、再エネ電力で湯を作って地域暖房や給湯に活かすにあたっては、「日本には適地がない」などとできない理由を並べたがる妨害屋は多いが、日本は地熱が豊富であるため、再エネ電力だけでなく地域暖房や給湯もドイツよりやりやすい筈である。 このような中、*6-2のように、先進的な小城市は「ゼロカーボンシティ」を宣言し、市本庁舎の電力を太陽光発電で自給している。これは、電気料金の高騰の中、自らを救うことになっており、新年度から市民や事業所に向けた啓発にも本格的に乗り出すそうだ。また、市の担当者は「採算性や費用対効果に対する関心が高いが、防災面での活用が第一」「啓発を進めつつ、具体的な脱炭素の取り組みを進める」としているとのことである。 日本にも老朽化した団地や住宅は多いため、街づくり計画を立て、それらを改修したり、建て替えたりすれば、住みやすくなると同時に、資産価値も大きくなる。そして、*6-3は、「日本の社会保障制度は大きく6つあり、それは年金・医療・介護・障害者福祉・生活保護・子育て支援だが、欧州はそれに加えて住宅がある」と記載している。 だが、日本にも都道府県営住宅・市町村営住宅など、戦後の住宅難を解消するために建てられた公営住宅は多く存在し、当初は周辺の一般住宅より近代的な設備を備えていたのだが、時代を経て旧式となり、省エネ創エネ・バリアフリー・デジタル化・電子レンジ/食洗機内蔵型システムキッチン・EV向け駐車場など現代の生活に必要な設備を備えていないため、価値の低いものになっているのだ。そのため、これに対しては、*6-1のドイツ方式が参考になるだろう。 こう言うと必ず、「財政力が乏しい」などと言う人がいるが、高齢者ばかりの積雪地帯に毎年出している雪かき費用は消えてなくなる費用なので、設備が整い、賃料の安い公営住宅に高齢者を移動させ、持家だった場所を買い取って有効活用するとか、ふるさと納税を使って返礼品に賃料の割引をするとか、方法はいくらでも考えられ、要するに工夫次第なのである。    2021.4.22日経新聞 (図の説明:左図は、テレビ塔から見えるのと同じベルリン市街で、ブロック毎の建物と中庭に光と緑のある街づくりが美しい。中央の図は、壁に太陽光発電システムを取り付けたビルだが、右図のような薄くて透明な太陽光発電システムを取り付けた建物もあった方がよいと思う) *6-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15519929.html (朝日新聞 2023年1月6日) (気候危機と住まい 適温で暮らしたい)街を再生、ドイツの公営住宅改修 ドイツ北東部、ポツダム。ベルリンに暮らす建築家で起業家の金田真聡さん(41)は、「ポツダムのスラム街」と呼ばれた巨大団地群が、省エネ改修で変化する様子を2016年から見続けてきた。きっかけは、改修プロジェクトを伝える新聞記事を読んだことだった。「社会問題の解決」も目的だという。省エネ改修が、どう社会問題の解決につながるのか。興味を抱いた金田さんはプロジェクトの関係者に連絡を取り、すぐにポツダム市のドレビッツ地区に向かった。約3千世帯、5500人ほどが暮らす団地は東ドイツ時代に建設され、約半数は市営住宅になっていた。老朽化が進み、富裕層や若い世代が離れ、移民や貧困層の割合が増えていた。金田さんが訪れる数年前、団地を含む地区全体40ヘクタールほどの省エネ改修を市職員や地元の建築家らが提案し、コンペを通過。国や自治体の助成を受け、市営住宅を中心に大規模な改修が始まっていた。くすんだ色の外壁や窓枠のデザインが一新され、明るさを取り戻していく。外壁や屋根は外断熱が強化され、窓や扉はトリプルガラスの樹脂サッシに換えられていった。街の変化が楽しみで、金田さんも地区に通うようになった。家の性能が増すと、エネルギー消費は激減して以前の半分になり、住民の光熱費負担は大幅に軽減された。太陽光や風力などドイツ北部の豊富な再エネの電気で湯をつくり、地域の暖房や給湯に生かす創エネ設備も整備された。地区には、若い子育て世代が多く引っ越してくるようになり、緑化や乗り入れの公共交通の整備も進んだ。プロジェクトの担当者の言葉が印象に残っている。「貧しい人が貧しい環境で暮らさないといけないということはない。あたたかい家に住むことは基本的人権です」。金田さんは2020年、東京・目黒駅近くに、6階建て9戸のマンション「MEGUROHAUS」を建てた。「寒いドイツだから高性能な建築が必要だとみられますが、日本の夏も冬も、広くみれば世界有数の厳しい環境。省エネで快適に暮らせる建築を当たり前にする必要があります」。ドイツ式の外断熱と設備を備えた超省エネ集合住宅で、外気温が2度でも室温は無暖房で14度を下回らない。ただ、計画から完成まで5年かかった。「いい家を広めたいと建てた家でしたが、このペースだと60歳までに4棟しかつくれないとわかり、がくぜんとしました」。地球環境にも住む人にもやさしい建築を一棟でも多くつくりたい。金田さんは、建築設計の現場をデジタル化で刷新し、誰もが省エネ建築を設計できる仕組みをつくることを考えた。現実と同じ建物の状況を3Dで再現する設計手法(BIM)を使い、完成時の光熱費や二酸化炭素(CO2)排出量を算出できるウェブシステムを、エンジニアと2年かけて開発。これで、業務効率を高めながら性能と建設コストを最適化する道が開けるという。日本のゼネコンを退職し、ドイツで働き始めて10年余り。「気候危機対策に取り組むこと自体が、企業にとっても個人にとっても有益で、経済発展につながるという意識を、ドイツにいると強く感じます」。誰もが快適に住める環境をつくり、社会課題の解決につなげる。「自ら行動し、結果で示したい」 ■省エネ化は「一石三鳥」、政策進める欧州 ドイツ政府は1990年代後半には新築を制限し、既存建物の省エネ改修推進にかじを切った。国内に約4千万戸ある建物を取り壊して性能のいい新築を建てるより、社会全体の消費エネルギー削減と経済発展につながるという考えだ。また、ポツダム市があるブランデンブルク州は含まれないが、ベルリン市や、全16州のうち7州で、省エネ性能の強化と再エネ設備の導入があわせて義務化されている。建築物関連からの温室効果ガス排出は、世界全体でみれば排出量全体の2割を占める。欧州には、気候変動と住宅政策、まちづくりを一体化して進めている自治体も多い。住宅の省エネは、化石燃料の使用と光熱費を減らすだけでなく、健康にもいいという「一石三鳥」の効果がある。公営住宅では省エネ化が進めやすく、福祉政策にもなる上に、雇用拡大や地域経済振興などの効果も期待できる。若者が入居しやすくなれば、地域の若返りにも役立つ。住宅政策の専門家によると、日本の公営住宅の性能は一般的に、平均的な住宅より低い。「公的支援によって安く提供する住宅には、高い性能を施すべきではない」とする考えが根強いからという。日本でも、東京都が25年度から、新築建物に太陽光パネルの設置を原則として義務づけることになった。都内では、温室効果ガス排出量は建物関連からが約7割を占める。50年までに住宅の7割が建て替えられるとみられ、義務化の意味は大きい。国土交通省と経済産業省、環境省が住宅の省エネリフォームを支援する制度で連携を始めるなど、ようやく住宅性能の向上に本腰を入れつつある。建物の省エネ基準の強化や太陽光パネルの設置義務化、それに伴う費用の補助など総合的な対策が急務だ。 *6-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/981099 (佐賀新聞 2023.1.25) 脱炭素のまちに熱視線 全国から視察相次ぐ 庁舎の電力自給、年間361トンのCO2削減、地域のチカラ移動編集局 小城編 小城市は「ゼロカーボンシティ」を宣言し、2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出量を実質ゼロにすることを目指している。市本庁舎の電力を自給する太陽光発電設備は、電気料金の高騰の中で全国の自治体から熱い視線が注がれる。新年度から市民や事業所に向けた啓発に本格的に乗り出す。自治体庁舎の非常用電源に関する国の指針を受け、太陽光設備の導入に踏み切った。職員と来庁者用の駐車場の屋根に1200枚、総出力500キロワットの太陽光パネルを載せて発電し、庁舎の全電力をまかなう。余った電力は大型蓄電池にため、不測の事態に備える。国の補助などを受けても約2億4千万円の自己負担が生じたが、成果として年間361トンのCO2排出量の削減につながった。新電力と契約していた年間の電気料金は約1千万円からゼロになった。電気料金の価格が上昇する中で、自治体や議会、民間企業など全国から約40件の視察があった。市の担当者は「採算性や費用対効果に対する関心が高い。ただ、あくまでも防災面での活用が第一と説明している」と話す。市は脱炭素をさらに進める。電力会社から買う電力を非化石燃料に固定する「RE100」の事業に賛同し、市内の低圧受電の市管理施設264カ所で昨年12月からRE100の契約に切り替えた。年間約530トンのCO2削減を見込む。昨年11月に開いた市エコフェスタでは、地球温暖化防止対策をアピール。専門家を招いた無料省エネ診断を開催し、多くの事業所が診断に臨んだ。市は「啓発を進めながら、具体的な脱炭素の取り組みを進めていく」と話す。 *6-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD304AK0Q2A830C2000000/ (日経新聞論説 2022年9月6日) 「住宅」が社会保障になる日 低年金でも生活可能に 日本の社会保障制度には大きく6つのメニューがある。年金、医療、介護、障害者福祉、生活保護、そして子育て支援。だが欧州の主要国では7つあるのが普通だ。欧州にあって日本にないもの。それは「住宅」である。正確に言えば、日本にも住まいを確保するための公的支援はある。生活保護の一部である住宅扶助と、離職などで住まいに困った人向けの住居確保給付金の2つだ。だが、生活保護は厳しい資力調査を経なければ受給できない。住居確保給付金は求職活動中の人だけを対象とし、支援は最長9カ月で終わる。対象者は一部の困窮者に限定され、広く一般の人が使える制度にはなっていない。欧州の多くの国では公的な住宅手当があり、所得・世帯要件を満たせば必ず得られる権利とされている。日本の児童手当のようなイメージだ。フランスでは約2割の人が住宅手当を受給している。公営住宅も日本は見劣りしている。住宅政策の柱と位置づける欧州に比べて供給量が限られ、低所得者が希望しても入居できないことも多い。特に1980年代以降、日本の住宅政策は景気対策としての色合いを強めた。持ち家建設を中心に推進され、公営住宅の比率は低下してきた。高度成長期であれば大きな問題はなかった。多くの会社員が正社員として終身雇用で守られ、福利厚生で企業独自の住宅手当を支給された。だが経済の先行きが見えない時代に入り、不安定な非正規雇用が増加。正社員の住宅手当も、仕事と報酬の関係を明確にするジョブ型雇用の導入で廃止される動きが出ている。もっと大きなうねりは、高齢化と世帯の変化だ。就職氷河期世代で不安定な雇用が続き、結婚もしていない人が、2030年には60歳に到達し始める。家族の支えがなく低年金の単身高齢者が急増すれば、住まいの確保が社会問題になりかねない。ひとり親世帯の割合も9%と1980年の5.7%から上昇した。こうした社会の変化を背景に、17年には住宅セーフティネット法が施行された。高齢者、子育て世帯、障害者らの入居を拒否しないことを条件に、賃貸住宅の家主に耐震化やバリアフリー化の改修費用を補助する制度だ。だがこれで救われる人は限られる。65歳以上の人口が最多になる「40年問題」に備え、住宅政策の刷新を求める有識者は少なくない。「日本の社会保障で整備が遅れてきたのが住まいの支援だ」「より普遍的な家賃補助ないし住宅手当の仕組みに発展させることが重要だ」。今年3月の政府の全世代型社会保障構築会議でもこんな意見が相次いだ。全国で800万戸を超す空き家を活用して高齢者の見守り機能がある公営住宅を確保し、月数万円の住宅手当と2本柱とする。生活保護世帯だけでなく、賃貸住宅に住む低所得世帯や、親元から離れて暮らす大学生らも給付対象とし、社会保障制度の7つめのメニューとして確立する。専門家らの意見からはこんな制度の理想像が浮かぶ。とはいえ実現するには巨額の財源が要るため、政府内の議論は低調だ。仮に生活保護から住宅扶助を切り離し、財源とともに新制度に統合したとしても、兆円単位の追加財源が必要になるはずだ。ウルトラCになりうるのは住宅ローン減税の廃止だ。数千億円規模の財源になる。家賃負担に苦しむ人が増えるのに、持ち家取得者に巨額の支援を続けるのはバランスを欠くとの声もある。ただし各方面の猛反発は必至だ。住宅業界はもちろん、これから家を持とうとしている若い世代も「なぜ自分たちは減税の恩恵を受けられないのか」と憤るだろう。世代間の対立を喚起しかねない。「住まい」を社会保障制度にすると、その影響は広範囲に及ぶ。低年金でも何とか生活できる人が増えるかもしれない。介護のあり方にも一石を投じる。景気や家賃相場への影響も慎重に見極める必要があるだろう。簡単に結論を出せるテーマではない。だからこそ、政府は早く本格的な議論を始めるべきだ。改革の難しさを考えると、残された時間はあまりない。 <政府の誤った対応> PS(2023.1.28追加): 政府は、*7-1のように、今頃になってEVを数分で充電できる高出力充電器の普及に乗り出すそうだが、日本は充電インフラの乏しさがEV導入の壁となり、日産リーフの販売開始(2010年)から13年も経過した後で遅すぎ、最初にEVを開発した国でありながら「EV途上国」となって、十分な創業者利得を得られなかった。これではリスクをとって最初にやった人が損をするため、イノベーションによる経済成長など起こるわけがないのである。 また、EVは再エネ電力を使えば温暖化ガス排出抑制や大気汚染防止の効果が高いにもかかわらず、メディアも、「EVはエンジン音がしないから危ない」「発電に化石燃料を使っているからCO2削減にならない」等々、課題解決を行う方向ではなく、できない理由を並べたてて妨害することに専念していた。このような事例は、太陽光発電はじめ他の技術にも事欠かないため、こうなる原因を究明してなくさなければ、漫然と予算をばら撒いてもイノベーションを起こすことなどできずに、同じことが繰り返されるのだ。 しかし、*7-2-1のように、海藻や湿地が吸収するCO2が世界的に注目され始めており、政府は藻場の分布を調査して吸収量を算定して温室効果ガス排出量を2030年度で2013年度比46%削減する目標に反映させたいそうだ。そして、藻場の生育状況を映した衛星写真画像が不鮮明だったため、専用ドローンで海面に近づいて藻場の生育状況を調査するそうだが、それなら海中ドローンも使って立体画像を撮影し、海水温・透明度・光の強さ・海藻の生育状況・そこで生育する魚介類の量などを自動的に記録した方が、今後のデータの使い道が多いと思う。 このような中、*7-2-2のように、2022年度に唐津市鎮西町串浦の海士が減っていた藻場の再生に取り組んで藻場を11haまで取り戻した成果が評価され、「Jブルークレジット(藻場が吸収するCO2を企業に売買する認証制度)」が認証されたのは良かった。しかし、藻場の減少原因は海水温の上昇であり、その理由はCO2排出だけではなく原発温排水にもあるため、鎮西町では近くにある玄海原発の稼働開始後、串浦付近だけでなく離島でも海藻が減った。そして、東日本大震災後の原発停止期間中に、減った筈の海藻が復活した実績があるのである。そのため、人力で藻場復活の成果が出たのは、上昇した海水温に適応できた海藻を増やしたか、稼働している原発数が減ったためと思われるが、代替可能な発電方法があるのに「安定電源」「安価な電源」などと称して原発を推進し、水産業を落ち込ませて日本の食料自給率を低くしているのは、考えが足りないと言わざるを得ない。 なお、*7-3-1のように、近年の有明海は赤潮による貧酸素化により海苔が不作だった上、先日の寒気による暴風雨で海苔養殖場の支柱が折れ網も壊れて、養殖施設には保険がないため新しい設備投資も難しく、今後の海苔の供給減に繋がりそうだ。そこで、海苔養殖の適温を調べると、*7-3-2のように、12~23℃程度であるため、新のり養殖は北から始まり、九州有明地区等を除いて9月末までに全国でほぼ終わるのだそうだ。そして、他の地域は「陸上採苗」だが、有明海だけは「野外採苗(のり種のかき殻を海苔網に取り付け、海中でのり種を放出させてのり網に種付けする)」で、海水温が23℃以下になっていることが必要であるため、10月中旬から野外採苗を始めるのだそうだ。 話を有明海に限れば、支柱が貧弱すぎたため、しっかりしたものに変えることが必要だ。しかし、有明海は広い遠浅の海であるため、洋上風力発電の適地でもあり、支柱のいくつかを埋め込み式の洋上風力発電機にして土台をしっかり埋めて再エネ電力も同時に販売すればよいだろう。また、海苔の野外採苗はよいが、高い海水温でも育つ苗を選んでいく品種改良をすると同時に、赤潮による貧酸素化を防ぐために、下の段には牡蠣殻だけでなく牡蠣の稚貝も置いて養殖すればさらなる副収入が得られると思う。そのため、副収入で設備設置の借金も返せそうだが、自信がなければ洋上風力発電機部分を他の専門事業者に任せる方法も考えられ、どちらにしても国や地方自治体の協力と支援がなければできないだろう。 なお、宮城県沿岸の海苔漁家は、東日本大震災による大津波ですべてを失い、1漁家8,000万円~1億円以上の被害を出して現在は復興しているそうだが、ここに東電のフクイチ原発処理水が海洋放出されれば、またまた海流と場所によっては気を付けた方がよい場所が出るのである。    宗像市(ふるさと納税の使い道より) 有明海苔、色落ち被害と暴風被害 (図の説明:左図は、近年の磯焼けに歯止めをかけるための作業の様子、中央の図は、赤潮で色落ちした有明海苔、右図は、寒波による強風で支柱が倒れた有明海苔の養殖場。ちなみに、海苔は紅藻・緑藻・シアノバクテリア(藍藻)などを含む食用とする胞子で増える藻類だが、アマモは海中に生える種子植物である。コンブ(昆布)は、生物学上の分類がある前からある名前で、オクロ植物褐藻綱コンブ目コンブ科に属する数種の海藻の一般的名称とのことである) *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230104&ng=DGKKZO67293670U3A100C2MM8000 (日経新聞 2023.1.4) EV急速充電器、規制緩和、設置容易に、年内めど 数分で長距離走行も 政府は小型の電気自動車(EV)を数分で充電できる高出力充電器の普及に乗り出す。出力が高い機器の設置や取り扱いに関して適用している規制を2023年をめどに大きく緩め、低い出力と同じ扱いにして利用しやすくする。日本は充電インフラの乏しさがEV導入の壁となっている。自動車産業の競争力を高めるためにも、国内の環境整備を進める。日本は世界的に見て「EV途上国」の状況にある。調査会社マークラインズによると、11月の新車販売に占めるEVの比率は日本では2%にとどまる。中国は25%、ドイツは20%、韓国は9%と日本よりはるかに高い。日本でもEVは他のエコカーより税優遇が手厚く、購入補助もある。それでも消費者が購入をためらう大きな理由の一つが、街角の充電設備が少ないことだ。国際エネルギー機関(IEA)によると、日本の公共のEV充電器(総合・経済面きょうのことば)は21年で約2万9000基。日本より狭い韓国には10万7000基ある。IEAが高速と定義する22キロワット超で見ると日本は8000基で、1万5000基の韓国や47万基の中国に及ばない。家庭用では完全に充電するまでに数時間から10時間超かかってしまう。素早く充電できるインフラの整備を進めるため、政府は23年にも規制を緩和する。ポイントは出力が200キロワット超の充電器も一定の安全性は確保できると判断し、扱いを50キロワット超と同じにすることだ。日本では現在、20キロワット以下には特段の規制はなく、20キロワット超になると安全のための絶縁性の確保など一定の要件を満たす必要がある。50キロワット超はさらに建築物からの距離などで制約がかかる。200キロワット超の充電器は「変電設備」となり、高電圧の電流を変圧する設備との想定で厳しい規制がかかる。屋内に設ける場合は壁や天井を不燃材料で区画する必要があり、設備の形式によっては運営者など特定の人しか扱えない。規制を所管する消防庁が23年中の関係省令の改正を目指す。改正後は200キロワット超の充電器も急速充電設備となり、出力50キロワット超~200キロワットの充電器と同等の扱いで設置しやすくなる。代表的なEVメーカーであるテスラの「モデル3」は、同社が整備を進める出力250キロワットの急速充電器を使うと5分の充電で120キロの走行が可能だ。高出力の機器は小型車であれば数分でかなりの充電をできる。大型の電池を積むEVトラックやEVバスの普及にも欠かせない。現状の規制で200キロワット級の充電器を設置するには、数千万円の設置費や年数百万円の運営費がかかるとみられる。国内で急速充電器を整備する東京電力ホールディングス系のイーモビリティパワーは「規制緩和で設置や運営のコストが下がれば、普及しやすくなる」と歓迎する。日本政府は30年までにEV充電器を15万基とし、このうち3万基を急速充電とする目標を持つ。充電インフラは自動車の開発も左右する。現状のEVは電池やモーターが400ボルトの電圧に対応しているが、200キロワット超に対応するには800ボルトに応じた設計に変更する必要があるとされる。短時間で充電が終わる車種の開発は、商品の魅力向上につながる。EVは再生可能エネルギーを使えば温暖化ガスの排出を抑制する効果が高い。 *7-2-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/972253 (佐賀新聞 2023/1/6) 海藻のCO2吸収量を本格調査へ、政府、温暖化対策に反映 政府は、全国の沿岸で見られる海藻が吸収する二酸化炭素(CO2)の量について、ドローンを用いた本格調査に乗り出す。海藻が吸収する炭素は「ブルーカーボン」と呼ばれ、新たなCO2削減対策として世界的に注目されている。藻場の分布を調査し、詳細な吸収量を算定した上で、2030年度の温室効果ガス排出量を13年度比で46%削減する政府目標に反映させたい考えだ。政府は21年度に全国125の主要港湾で衛星写真による藻場の調査を実施したが、画像が不鮮明で十分把握できなかった。そこで22年度から専用ドローンの開発に着手。海面に近づいて藻場の生育状況を詳しく調査できるほか、レーザーを照射すればコンクリートブロックに隠れた海藻も分かるといい、25年度以降の調査開始を目指す。算定方法に関しては、藻場をデータベース化して継続的にデータ更新することや、算定方法に対する科学的裏付けが課題となっており、環境省や国土交通省などが検討を急いでいる。海外では米国とオーストラリアがCO2吸収量算定の仕組みを確立させている。港湾空港技術研究所(神奈川県)などが19年に出した試算によると、全国の藻場のCO2吸収量は年間132万~404万トン。藻場の保全に取り組めば30年には最大518万トンまで増えるという。森林の吸収量は5166万トンだが、今後樹齢が進むと30年には2780万トンまで減るとされ、政府関係者は「藻場の吸収量を増やすことは政府の目標達成にとって重要だ」と指摘する。 *7-2-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/981061 (佐賀新聞 2023/1/26) 藻場のCO2吸収量、企業に販売 唐津市串浦、脱炭素事業で認証 地元海士らの環境再生評価 海の藻場などが吸収する大気中の二酸化炭素を企業と売買する認証制度「Jブルークレジット」で2022年度、唐津市鎮西町串浦のプロジェクトが佐賀県で初めて認証された。地元の海士(あま)たちが減っていた藻場の再生に長年取り組み、11ヘクタールまで取り戻した成果が評価された。認証に取り組む組合は、同プロジェクトの二酸化炭素吸収量を購入する法人を、27日まで募っている。海中の海藻や湿地が吸収する二酸化炭素「ブルーカーボン」は、脱炭素化の取り組みとして国際的に注目されている。民間のジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)は20年度からクレジット認証を進め、本年度は全国の18事業を選定した。企業は吸収量を購入することで企業活動の発生量を打ち消し、プロジェクト側は売った額を活動資金に充て、さらなる環境改善につなげる仕組み。プロジェクトを行うのは、地元漁師らでつくる任意団体「串浦の藻場を未来へ繋げる会」(11人)。代表で海士の袈裟丸彰蔵さん(45)は、ボランティアなどで20年ほど食害生物の駆除に取り組み、22年5月に団体を立ち上げた。串浦の地先にはガラモやアカモクなどの海藻が茂り、年間に二酸化炭素41・1トンを吸収すると組合から認証された。同組合の桑江朝比呂理事長は「人力で藻場復活の成果が出ているケースは珍しい。地元の素潜り漁師が少ない中で、本気で地道に取り組まれた成果」と評価した。藻場再生は、魚やウニなどの生育環境にもつながる。袈裟丸さんは「自然環境を変える難しさは長年感じてきたが、普段の海の手入れが大切だと思っている。漁師が減って水産業が落ち込む中で、次世代が希望を持てるように活動を続けたい」と話した。吸収量は法人だけが購入でき、1口11万円(税込み)。口数の上限はない。締め切りは27日午後5時まで。問い合わせや申し込みは同組合のメール、jbcredit@jbe.blueeconomy.jp。 *7-3-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/6563243fc0c7c6a75874675b6b626571783a2607 (Yahoo 2022/1/27) 「助けてくださいよ…」不作ノリ養殖場に“追い打ち寒波″壊滅状態に 業者からは「仕入れができない」と悲鳴が上がっています。不作に悩む海苔(のり)養殖場を最強寒波が直撃。暴風雨や波の影響で柱が倒れ、網が絡まる被害を受けました。日本有数の海苔の産地・有明海を進む船。寒気の影響で被害を受けたという現場の視察に向かいます。熊本県漁連関係者:「見てごらん…網がないじゃないですか…」。そこにあったのは、見るも無残な現実でした。海苔の養殖場は、網を支える支柱は折れ曲がり、網も壊れている状態。漁連関係者から出るのは落胆の声ばかり。熊本県漁連関係者:「きのう、おとといぐらいから、ここは出荷する予定だったんですよ。たった一晩です、一晩でやられました」「もう再起不能ですね。修理もできないし…」。今回の災害は、日本の海苔の供給に今後、大きく影響する可能性があります。日本有数の海苔の産地・有明海の養殖場が今、危機を迎えています。寒気による暴風雨で一夜にして、養殖場が無残に壊れた状態に。熊本県漁連関係者:「今まで経験したことのない暴風雨ですね。この冬場に初めてですね。『生産』については、保険があるんです。こういう『施設関係』については全然、保険はないんです。だから困っているんですよ。だから、来年また同じように仕事ができるか?というのは、なかなか大変ですね」。新しい養殖場を作るには、設備投資に莫大な費用がかかることになります。熊本県漁連関係者:「もう収穫はできないし、施設はバラバラだし…。なんとか助けて下さいよ…」。全国的な海苔の不作が続くなかで、収穫シーズンに有明海を襲った悲劇。小売店も不安を抱えています。横浜市にある明治27年創業の海苔屋さん。今、歴史的な品不足に苦労しているそうです。商品のパッケージには、タレントの出川哲朗さんの実家の海苔店です。蔦金商店・出川雄一郎社長:「今季は本当に大変。海苔の凶作。産地によっては2割から3割、良くても5割とれているかな?という状況。それに伴って、値段ばっかりドンドン跳ね上がって、本当に今、大変なことになっています」。蔦金では海苔の乾燥から加工、商品化まで行っています。原料の海苔は、まず入札で仕入れるわけですが。蔦金商店・出川雄一郎社長:「わずかながらの海苔を集中して買い付けが行われる。ほとんど大手さんに買い付けられてしまって、正直に言って、我々みたいな所は買うこともできない、買えないっていう状況です」。起こっているのは入札での海苔の争奪戦。この先の不安を隠せません。蔦金商店・出川雄一郎社長:「今年がね、この先、有明をはじめ、とんでもないことになっているので、果たして『うまく仕入れができるかな?』というのが、かなり心配です」 *7-3-2:https://nori.or.jp/information/report/report_002-001.html (海苔養殖振興会 平成23年10月20日) 産地を追って no.2 新のり養殖始まる 1 新のり養殖は北方から 全国の産地で新のり養殖の季節を迎えました。のりが育ち易い海水温度は、23℃から12℃程度と言われています。のり種をのり網に付着させる作業を採苗(さいびょう)と言います。その作業が野外採苗主体の九州有明地区等を除き、9月末までに全国でほぼ終わったところです。その作業方法は前回紹介しましたが、幅約2メートル、直径約2~3メートルの大きな鉄輪(通称:水車と言います)にのり網(約1.8メートル、長さ18メートル)を巻きつけ、水槽(横約3メートル、長さ約4メートル、深さ約50センチ)の底にのりの種(糸状体)が被いつくして黒くなったかき殻を敷き詰め、海水を入れてのり種が海水中に飛び出したところを、のり網に付着させてのり養殖の種網を作る「陸上採苗」作業です。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海地区でもほとんど「陸上採苗」が行われていますが、「陸上採苗」でのり種を付着させたのり網を一時冷蔵庫に入れて保管しておき、海水温度がのり養殖に適した温度(23℃以下)になる10月上旬過ぎ頃からのり網を海上に張り込む作業が行われます。そのため、海水温度の下がり具合が早い東日本地区が先に始まります。もう一つの採苗方法である、海中に直接のり網を張り込み、のり種のかき殻を海苔網に取り付けて、海中でのり種を放出させてのり網に種付けをする「野外採苗」も海水温度が23℃以下になっていることが必要ですから、ほとんどを野外採苗で種網作りをしている九州の主力産地の有明海では、10月中旬から野外採苗を始めています。また、採苗の時期は気象、海況の地域差によって多少異なりますが、10月下旬までには全国ののり産地の海域にはのり網が広がり、その様子は冬の風物詩としてニュースになることがあります。ところで、今年度の生産状況を見ますと、いままでとは違ったことが気になります。それは、東日本大震災により壊滅的な被害を受けた、宮城県の今漁期(平成23年10月から平成24年4月頃まで)の生産状態です。 2 “めげない”宮城県のり漁家 今年3月11日に東北地区等を襲った大地震と大津波は、宮城県沿岸ののり漁家に未曾有の被害を与えました。宮城県は、全国のり生産県の第5位を占め、特にコンビニエンス・ストアで販売されているおにぎりに使われているのり質に適した産地として5~6年前から注目され始めていた産地だけに、今後の復興が注目されています。私は、被災から6ヵ月目を迎えた9月1日から3日に掛けて、駆け足ではありましたが、被災地の漁家の方々、また、産地ののり問屋の方々にお会いして来ました。被災された方々の厳しい現実を拝聴し、被災現状を見た時に、地震の大きさと共に、津波の力が想像をはるかに超える強さであることを見せ付けられました。その実状を撮影していますが、それをご覧頂きながら、今後の宮城県のり産業の復興をどのように支援すれば良いのかを考えてみたいと思います。平成23年3月11日は宮城県漁協の第14回のり入札会が、県漁協塩釜総合支所で開かれた日です。入札会が終わったのが午後1時ごろでした。当日午後2時11分頃、私は塩釜総合支所次長に電話を掛け入札の結果を取材し「宮城もようやく生産状態が良くなり、これからが生産の追い込みだ!」と言う声を聞いて、電話を切った直後の出来事でした。遅くなった昼食を食べながらテレビを点けたところ、宮城県に大津波が押し寄せている場面が映し出され、慌てて受話器を取り上げ、つい今しがた話を聞いた塩釜総合支所に電話を掛けたのですが、すでに通話出来ない状態になっていました。 3 その時、のり産地でどのような事が起きていたのか! その時、のり産地でどのような事が起きていたのか! その現状が下の写真(写真1)です。およそ20トンもあるのり製造機械が潰され、鉄くずのようになっています。津波の力の恐ろしさにア然とするばかりです。3月11日午後2時過ぎと言えば、「これまで海水中ののりに必要な栄養である窒素などの不足で品質が今ひとつ良くなかったが、ようやく色がよくなり、品質の良いのりの生産状態が良くなってきたから、これから4月まで生産が進むぞ!」と気合が高まりのり製造に力が入っていた時期でもありました。それを象徴する災害現場の様子が残っています(写真2)。のりを製造中の大型機械(のり製造機械)が、津波に押し流されて潰れ、その機械の中の製造中ののりが無残に放り出されています。この日に製造されていたのりは、次の入札日3月18日に出品されるものだったのでしょう。800万円から1,000万円以上もするのり製造機械だけでなく、その機械の中で製造されていた1万5千枚相当ののりも失われてしまいました。その他に、のり摘み船、海上に張込んでいたのり網、のり製造に必要なのり原藻洗い機など付属機械類などを含むのり製造工場自体の流出など、1漁家あたり総額8,000万円から1億円以上の被害額になるようです。今後これをどのようにして取り戻すことが出来るのか、考えただけで眠れなくなりそうです。被害を受けたあるのり漁家は「ここまで完璧にやられると、泣きたくなるのを通り越して、笑ってしまうより他にないべ・・・」と話してくれました。(以下略) <伝統工芸における新しい付加価値> PS(2023.1.29追加):*8-1-1のように、日本にも五月のぼりや大漁旗などの極彩色の染め物があり、伝統文様を組み合わせたり、身近な風景をモチーフにしたりして、芸術の域に達するような作品もある。また、8-1-2のような絹織物の「銘仙」もあり、裏表なく鮮やかな模様を出せるため、それを活かして現在的な製品を作ることも可能だ。そのため、下の図のように、美術館や博物館に収められているよいデザインを絹のスカーフやカップなどに映すと、新しくて面白い付加価値を持った製品ができる。 また、*8-2-2のように、ホンダの人型ロボットASIMOは残念ながらリタイアしてしまったが、機械丸出しの男性好みのロボットではなく、*8-2-1の岩槻のような、人形作りで一流の産業と組んでロボットを発展させてはどうか?この場合は、人形が昔ながらの手作りだから価値があるわけではなく、人間の特徴を捉えることに長けた産業と組むことによって、人間にとって違和感がなく、傍にいて楽しいロボットが作れると思うからである。 しかし、何をするにも興味を持ってそれをやる人材が必要なので、私は、*8-3のように、外国出身の希望する労働者に技術を教え、人間として適切な待遇を与えて、日本で働いてもらえばよいと思う。特に、被服・人形作りなどは、日本女性が最初に開拓した分野であるとおり、教育で差別された女性であっても熟練できる分野だ。従って、アフガニスタンはじめアフリカなどのイスラム圏の女性でも素晴らしいものを作ることができるし、色彩や文様の文化が混合すれば、むしろ新しくて魅力的なものができると思われるのだ。 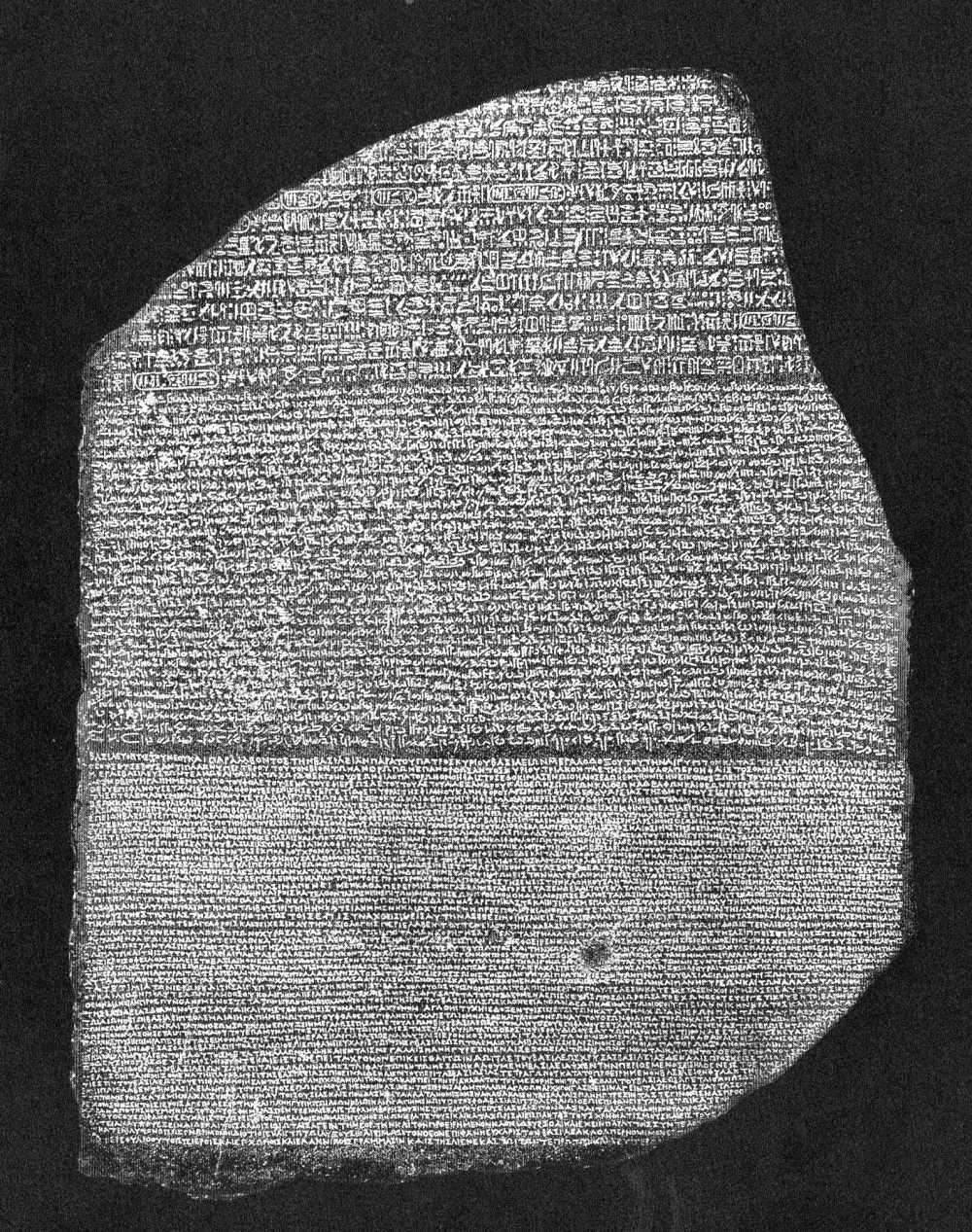    大英博物館のロゼッタ石とそのスカーフ 有田焼で作ったピカソの絵 源氏物語絵巻の一場面 (図の説明:1番左は大英博物館所蔵のロゼッタストーンで、左から2番目は大英博物館の土産物店に売っているロゼッタストーン柄で絹シフォンのスカーフだ。私は、そのアイデアが気に入り、記念になるし、使い勝手もよいので、これの紺色を買って使っている。右から2番目は有田焼で作ったピカソの絵で、これも気に入ったため、2種類も買って部屋に飾っている。1番右は源氏物語絵巻の一場面だが、日本でも絹のスカーフやカップに美術館・博物館の展示品を映し、空港、その美術館・博物館の土産物店、デパート等で売ると新しい付加価値が生まれるだろう) *8-1-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/974782 (佐賀新聞 2023/1/12) 極彩色の染め物12点 「城島旗染工」の城島守洋さん(小城市)、東京・銀座で個展 「城島旗染工」の4代目・城島守洋さん(68)=小城市=の個展が、東京・銀座のノエビア銀座ギャラリーで開かれている。伝統文様を組み合わせた極彩色の染め物が、見る人を楽しませている。3月17日まで。「和の染―現代に息づく伝統文様」と題し、新作12点を展示している。有明海や虹の松原など身近な風景をモチーフにした。「玄界灘」と題した作品は、波の図柄と家紋で使われる雷紋を組み合わせた。緑、黄、赤などの強い色彩と伝統文様が力強い印象を与える。五月のぼりや大漁旗など伝統的な染め物を手がけてきた技法をベースにしながら、伝統文様を大胆に切り取り、組み合わせることで独自の色彩感覚を表現している。2018年には、ニューヨークで個展を開いた。城島さんは「これからの方向性という意味で手応えを感じている。このような染め物があるのを知ってもらい、日常の生活空間の中に取り入れてほしい」と話す。 *8-1-2:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67346140V00C23A1L60000/ (日経新聞 2023年1月6日) 絹織物「銘仙」の魅力発信 大正時代から昭和にかけて北関東で生産され、女性の普段着として親しまれた絹織物「銘仙」。これを若い世代向けによみがえらせているのが、アパレルブランドのAy(アイ、前橋市)だ。慶応義塾大学に在学しながら会社を立ち上げた社長の村上采さん(24)は今春、大学を卒業し、地元の群馬県で事業を本格化させる。ブランドを立ち上げた当初は、大学の活動で訪れたコンゴ民主共和国の衣服を扱っていた。しかし2020年に入ると、新型コロナウイルス禍で渡航が難しくなってしまう。大学の講義もオンラインになり、生まれ育った群馬県伊勢崎市に一時的に戻った。同市はかつての銘仙の一大産地。「郷里の文化を継承したい」と、年代物の銘仙を仕入れ、現在的な衣料品によみがえらせる「アップサイクル」という手法で事業を展開することにした。20年9月から大学を休学してビジネスに取り組んできたが、22年に復学。今年3月にいよいよ大学を卒業する。前橋市に拠点を構えて事業に専念する予定だ。銘仙は今ではほとんど生産されておらず、使う生地はいずれなくなってしまう。村上さんの目標は銘仙の要素を備えた織物を工業的に量産し、次世代に残していくこと。「北欧ブランド『マリメッコ』のようなテキスタイルブランドへと会社を成長させ、銘仙の魅力を世界に発信したい」と意気込む。 *むらかみ・あや 1998年、群馬県伊勢崎市生まれ。中学校の授業で地元の銘仙について学んだ。慶応義塾大学・総合政策学部に進学後の2019年にアパレルブランド「Ay」を立ち上げ、20年に法人化した。 *8-2-1:https://mainichi.jp/articles/20221015/ddl/k11/040/070000c (毎日新聞 2022/10/15) 岩槻の人形作り、後世に 伝統技法に焦点 さいたまで特別展 /埼玉 日本有数の人形産地として知られる岩槻の人形作りを紹介する特別展「人形作り いろはの“い”~後世に伝えたい桐塑(とうそ)の技~」が、さいたま市岩槻人形博物館(さいたま市岩槻区本町6)で開催されている。岩槻で受け継がれてきた人形の製作技法に、同館として初めて焦点を当てた展覧会。12月4日まで。桐塑とは、桐の木片を砕いた粉と生麩糊(しょうふのり)を練って粘土状にした素材。桐塑を型で抜いて作った人形の頭部は「桐塑頭(がしら)」と呼ばれ、ほとんどの工程が手作業で施される。頭、手足、胴、小道具、組み立て――と多段階に及ぶ人形製作の工程のうち、特別展は桐塑頭を特集。製作工程と、凹凸のない桐塑生地を自在に操り面相を生み出す緻密な職人技を、実際の道具や素材、模型などで再現した。1~2畳ほどの狭い作業空間で、特殊な道具は使わず小刀や刷毛(はけ)などの技術のみで人形を作った江戸時代からの伝統技法に迫る。人形博物館によると、岩槻には関東大震災(1923年)以降、東京の人形師が疎開して技術が移入されたことなどで人形作りが隆盛したと考えられている。岩槻人形は2007年に経済産業省の「伝統工芸品」に指定され、熟練の職人は伝統工芸士に認定される。一方、生活様式の変化や工程の合理化で、桐塑頭の製造数は減少し、人形の頭部は石膏(せっこう)による製作が主流となった。田中裕子館長は「(桐塑生地や材料などに)実際に手で触れて体感できる展示もある。普段なかなか見られない人形製作の舞台裏に親しめるよう工夫した。見て楽しんでほしい」と話した。午前9時~午後5時、月曜休館。入館料は、一般400円、高校大学生と65歳以上200円、小中学生150円。期間中、特別展を記念して「武州岩槻町屋のれん会」が桐塑頭を模した和菓子を販売している。 *8-2-2:https://response.jp/article/2022/02/07/353971.html (Response 2022年2月7日) ホンダの人型ロボットASIMO、“定年延長”認められず退職へ[新聞ウォッチ] 北京冬季五輪のノルディックスキーのジャンプ男子個人ノーマルヒルで、小林陵侑選手が今大会で、日本勢の初めての金メダルを獲得。きょうの読売、朝日、毎日、産経が1面トップで報じるなど、各紙もスポーツ面などで北京五輪のニュースが目白押し。北京五輪でのアスリートの輝かしい健闘ぶりの話題はともかく、2月5日付けの読売朝刊が「さよならアシモ」というタイトルで、「ホンダの人型ロボット『ASIMO(アシモ)』が、3月末をめどに表舞台を退く見通しとなった」との残念なニュースを取り上げていた。記事によると、アシモは現在、東京・青山のホンダ本社と江東区の日本科学未来館でほぼ毎日パフォーマンスを行っているが、未来館では3月末に終了することが決まったという。ホンダ本社でも同時期に終える方向で調整しており、定期的な実演はなくなるとも伝えている。初代アシモは2000年の発表だったが、10年後の11年にはより人間らしい自然な動作で進化した現行モデルが登場。プロ顔負けでサッカーボールを蹴ったりジャンプをしたり、料理をトレイに載せ上手に運ぶ姿など、愛くるしいパフォーマンスが子供たちにも人気を集めていた。アシモは14年4月に当時のオバマ米大統領が訪日し、日本科学未来館を訪問した際に出迎えて、英語で「お会いできて光栄です」などと歓迎の意を表したほか、日本ばかりでなく、ニューヨーク証券取引所の鐘を鳴らすイベントなどにも招待されるなど、“海外出張”も数多く、地球規模で活躍したホンダを代表する “スーパー人気アイドル”でもあったようだ。読売によると「ホンダは、数年前にアシモの開発は終了しているが、今後も展示やグッズ販売などキャラクターとしては残す方向で検討している。ロボットの開発現場など舞台裏での活用も続ける」という。新年早々、自動運転などを視野に入れた電気自動車(EV)の本格参入を検討すると宣言したソニーは、中止していたロボット事業を復活しており、“戦後最大のベンチャー企業”などと言われていたホンダとソニーの経営方針を巡る意気込みの違いが読み取れる。 *8-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15540965.html?iref=pc_shimenDigest_top01 (朝日新聞 2023年1月29日) (多民社会)技能実習、変革迫られる現場 人件費、日本人の1.5倍「即戦力」 業務用ミシンが勢いよく動くと、裁断された布が服に仕立てられ積み上がっていく。岐阜県羽島市の縫製会社ヴェルデュール。ミシンを踏む、ほぼ全員が技能実習生だ。ベトナム出身のデイン・リック・タックさん(39)は「最初は不安だったけど、ここに来られてよかった」と笑った。近藤知之社長(49)は「外国人実習生は、安価な単純労働者ではない」と話す。同社で働く実習生の賃金は岐阜県の最低賃金時給910円を上回り、長時間残業は認めない。宿舎は工場近くの、日本人も暮らすアパート。エアコンなど家電付きの2LDKに4人一組で暮らす。「適正な賃金を払い、宿舎費などを含めれば、人件費は日本人の1・5倍」。それでも、実習生を頼るのは「即戦力の彼女たちがいなければ仕事が回らないから」。求人しても日本人労働者は集まらない。 ■賃金不払い横行 岐阜は日本有数の縫製業が盛んな地域だが、1980年代半ばから中国など人件費の安い国との競争にさらされた。そこで利用されたのが、93年創設の技能実習制度だ。制度の目的は途上国への「技能移転」だが、悪用された。外国人を「研修生」として受け入れた前身の制度では最低賃金制度が適用されなかった。実習制度でも、賃金不払いなどが横行した。月200時間に迫る長時間残業や粗末な宿舎での過酷な生活……。各地で技能実習生への人権侵害がくり返された。米国務省からは、制度が「人身取引」と批判された。「岐阜の縫製業は、不正件数ばかりでなく、悪質な事案が多かった」。取り締まる岐阜労働基準監督署の監督官は話す。だが、近年、変化を感じるという。「いまも不正はあるが、法を守り、状況を変えようという経営者や監理団体が現れ、二極化している」。実は、デインさんも賃金不払いの被害者だ。最初の実習先だった愛媛県の縫製工場では給料が支払われなかった。支援団体とともに転籍の仲介をしたのが、近藤さんが加入する監理団体「MSI協同組合」だ。監理団体は、技能実習生の募集や受け入れ手続きなどを行い、受け入れ企業が適正かを監査し、指導する立場だ。しかし、不正の手口を企業に指南したり、企業の不正を黙認したりする監理団体も存在している。MSIは違う。加入できるのは、不正のないクリーンな企業だけ。事前に加入希望社の「身体検査」を徹底する。加入後の監査は、実習生に待遇や労働環境を直接聞き取る。企業に給与明細発行を義務づける。実習生を支援してきた労働組合出身者が監査する。 ■選ばれる土地へ 縫製会社2社も経営する井川貴裕代表理事(49)は「法律や決まりを守るのは当たり前。会社を、岐阜の縫製を存続させるには、実習生に選ばれる土地にしなければならない」。産業界では、原料調達から製造、販売までのサプライチェーン全体で人権侵害を防ぐ「人権デューデリジェンス」が求められるようになった。国際的潮流だ。政府の有識者会議は、多くの問題が指摘される技能実習制度の見直しにも言及。井川さんは言う。「実習制度には矛盾と問題があり、正すべきところはある。でも、このまま廃止されれば、日本から縫製業はなくなるでしょう」 ◇技能実習制度が創設されて拡大が進んだ30年間は、日本経済が長く低迷した「失われた30年」とも重なります。人権侵害など多くの問題を指摘されながら、低賃金の実習生に頼り、人手不足で依存を深めました。産業や地域はどう変わったのか。制度見直しに向けて政府が議論を始めた今、考えます。 <エネルギーへの無駄遣い> PS(2023.1.30追加):*9-1のように、世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)で「ESG(環境・社会・企業統治)」投資が注目を集め、中でも再エネからつくる「グリーン水素」が特に注目を集めたそうだ。ドイツのショルツ首相は「再エネを使って水素を製造する水電解ブームを起こすことが目標」と語り、インド最大級の再エネ会社会長も「あらゆる企業が水素に関連した新しい計画を持っている」と語られたそうだが、私も再エネからつくる「グリーン水素」が最も安価にでき、あらゆる面で効用が高いと思う。 このような中、*9-2-3のように、「燃料高の影響で原発稼働状況が家庭電気代を左右する」などと言って、なし崩し的に原発稼働を進めるのは大きな問題である。何故なら、再エネ発電やグリーン水素利用は東日本大震災によってフクイチ事故が起こった2011年から言っており、電力自由化も既に行った筈なのに、その効果が出ないようにするための論調・行動が多く、未だに輸入化石燃料による発電に依存しているのが根本的問題だからである。 さらに、*9-2-1のように、フクイチ事故の除染作業で集めた「除染土」を再利用するなど、よほど放射性物質が好きな人の考えることであろうが、とんでもないことだ。住民の合意形成も重要だが、それ以前に、環境省が除染土の再利用基準として8000ベクレル以下などとしているのは異常としか言いようがなく、環境省でさえこのような発想をしていることが、日本人に大腸癌が多く、その他の癌も増えた理由であり、決して高齢化だけが癌増加の原因ではない。その上、*9-2-2のように、フクイチ原発処理水の海洋放出開始は設備工事完了に伴って「今年春から夏ごろ」に始めるそうだが、分量が多いため濃度についてのみ国際機関による安全性検証を受けても、放出が終わるまではその辺の魚介類は食べられない。そのため、漁業者に500億円の基金を渡せば問題解決するわけではないだろう。 また、*9-3-1のように、「化石燃料による火力発電の脱炭素化を探るため」として、いつまでも移行期と称しCO2貯留やアンモニア混合を奨励するのは、コストが上がる割に効果が薄いため反対だ。にもかかわらず、高い電気料金と大手電力会社へのバラマキを国民に押し付けながら、電力自由化による電力会社の選択肢増加を邪魔している組織(経産省・大手電力会社)は、まさに独占禁止法違反であろう。 なお、JR西日本も、*9-3-2のように、ローカル線を走るディーゼル車両すべてでバイオ燃料を2030年頃に導入する方針だそうだが、バイオ燃料を作るのもコストが高い上に、今から7~8年後の2030年頃ならディーゼル車をグリーン水素で走る燃料電池電車か再エネ電力で走る電車に変える時間も十分にある。乗客は燃料代も含めて乗車賃を払っているのだから、寄り道して無駄遣いするのではなく、目的を明確にして最小コストで最大効果をあげるべきである。 *9-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230127&ng=DGKKZO67924720W3A120C2EE9000 (日経新聞 2023.1.27) グリーン水素、注目の的に ダボス会議 投資、次の好機探る 英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)のニューズレター「モラル・マネー」は世界経済フォーラム(WEF)の年次総会(ダボス会議)で注目を集めた「ESG(環境・社会・企業統治)」投資について取り上げた。主な内容は以下の通り。20日まで開かれたダボス会議では、脱炭素に役立つ様々な技術やイノベーションが紹介され、参加者の多くが「次の投資の好機」を探ろうと真剣に耳を傾けていた。会議のプログラムには、新しいタイプの生分解性プラスチックや環境負荷の少ない航空機のジェット燃料、核融合エネルギーなど、ありとあらゆる分野のグリーンテクノロジーを扱う討論会が並んだ。そのなかで特に注目を集めたのが、再生可能エネルギーからつくる「グリーン水素」だ。商用化はまだ初期段階であるにもかかわらず、ほかの技術を突き放した存在感を示した。例えば、ドイツのショルツ首相は「再生可能エネルギーを使って水素を製造する水電解ブームを起こすことが目標だ」と語った。肥料大手企業の幹部は欧州連合(EU)の政治家に対して、水素業界の支援をより迅速に行うことを求めた。インド最大級の再生可能エネルギー会社、リニューパワーのスマント・シンハ会長は「あらゆる企業が水素に関連した新しい計画を持っている」とモラル・マネーに語った。シンハ氏は「エネルギー企業がどのようにグリーン水素を生産しようかと考えているだけでなく、利用する側の企業もどのように調達しようか策を練っている」と説明した。ダボス会議の現地でグリーン水素以外に目立ったのは、米国製の商品を優遇する内容を含んだ米国の歳出・歳入法(通称インフレ抑制法)への不満の声と欧州政府に対応を求める企業幹部の意見だ。輸送や販売、サプライチェーン(供給網)などで発生する間接的な温暖化ガス排出「スコープ3」を正確に計測し、公表することの難しさに直面した企業の不満も関心を集めた。11月に産油国アラブ首長国連邦(UAE)で開催される第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP28)も話題になった。 *9-2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/224939 (東京新聞 2023年1月13日) 原発事故の除染土再利用は「人ごとじゃない」 東電と意外な縁のある新宿の住民らが立ち上がった 東京電力福島第一原発事故後の除染作業で集めた汚染土、いわゆる「除染土」を首都圏で再利用する実証事業が公表されてから1カ月。予定地の一つ、新宿御苑(東京都新宿区)近くで生活を営む人らが腰を上げ、再利用に異を唱える団体を設けた。東電と意外な縁がある新宿。地元の人びとは何を思うか。ほかの地域は人ごとで済ませていいのか。改めて探ってみた。 ◆区民の合意形成図っていない 「地元住民の多くが知らないうちに、話が進められようとしている」。こう憤るのは、文筆家の平井玄さん(70)。実証事業に関する説明が足りないとして12日、新宿区に申し入れをした「新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに反対する会」の世話人だ。環境省は先月9日、新宿御苑を候補地にした実証事業を発表。一般入園者が通常入らない事務所棟裏側の花壇を使い、除染土に覆土して植物を植えるという。21日には御苑に面した新宿1、2丁目の住民を対象に説明会を実施。だが参加者はわずか28人。1丁目に住む平井さんも開催に気づかず、報道で知った。「区民の合意形成を図っているとはとても言えない」。平井さんは危機感を募らせ、28日に除染土問題を考える勉強会を開催。今月7日には区民有志らと反対する会を設立した。 ◆大学教授や弁護士、演劇人、ゴールデン街の飲食店主も 12日に区役所を訪れた際には、区民に実証事業を周知し、安全が保証されない限り除染土の持ち込みを中止するよう、区幹部に申し入れ書を提出した。同行した約20人の顔触れは多彩で、地元住民のみならず、大学教授や弁護士、演劇人、御苑近くにあるゴールデン街の飲食店主も。「除染土の再利用は法律できちんと決まっていない」「福島の負担軽減どころか、汚染の拡散につながるのでは」と疑問を呈し、「区は主体性を持ち、環境省に安全性について問いただしてほしい」と訴えた。新宿は歌舞伎町など歓楽街の印象が強いが、新宿御苑周辺にはマンションも多く、3世代にわたって暮らしてきた人もいるという。平井さんも小学生の頃には新宿御苑でよく遊び、今も3日に1度は散歩する。「幼稚園児も多く訪れ、多くの人が行き交う遊歩道もある。そんな園内でなぜ実証事業をやろうとするのか」 ◆歴代の東電幹部輩出した都立新宿高校 東電と浅からぬ縁があるのも新宿の特徴だ。 御苑そばの都立新宿高校の卒業生からは、歴代の東電幹部も輩出。卒業生でつくる「朝陽同窓会」によると、福島原発事故当時は会長だった勝俣恒久氏、事故後に社長を務めた広瀬直己氏らも名を連ねる。さらに御苑近くの信濃町には2014年2月まで東京電力病院もあった。「母校の近くに(除染土を)持ってこようとしていることについて勝俣氏らはどう思っているのか、問いたい」。何より際立つのが、環境省の前のめりぶりだ。新宿の説明会で紹介された動画「福島、その先の環境へ。」からもうかがえる。除染土を「復興を続ける福島の地に、今も残された課題」と説明。除染土を詰めたフレコンバックが並ぶ福島県内の仮置き場の映像を流しつつ、「果たしてこれは、福島だけの問題でしょうか?」と問いかける。除染土を福島県外で受け入れるため実証事業が必要と言いたいようだが、住民の疑問に真剣に応えようとしているかは心もとない。説明会の資料に記されたコールセンターの受け付けは平日のみで「いただいた『ご意見』については、今後の検討の参考とさせていただきます」と素っ気ない。 ◆「国の言い分を新宿区もうのみに」 平井さんは、国の姿勢が住民を置き去りにしているように見えると言う。「(除染土は)科学的に安全とは言い切れないのに、安全とする国の言い分を、新宿区もうのみにしている」と指摘する。反対する会は24日に発足集会を開くなどし、今後も広く問題を訴えていく。実証事業は現在、新宿区と埼玉県所沢市での実施が公表され、茨城県つくば市でも取り沙汰されるが、除染土の後始末はこれらの地域に限った話ではない。環境省によると、福島県内の除染土は、第一原発近くの中間貯蔵施設に集めた後、2045年までに県外へ運んで最終処分する。集めた除染土は昨年末時点で約1338万立方メートル。最終処分する量を減らし、県外に搬出しやすくするために再利用を唱える。 ◆知らぬ間に除染土が身近に… 問題は、再利用する除染土の放射性濃度だ。農林水産省によると、原発事故前の約50年間、全国の農地の放射性濃度は平均で1キログラム当たり約20ベクレル。一方、環境省が除染土の再利用基準として示すのは同8000ベクレル以下で、およそ400倍だ。廃炉にした原発から出る資材の再利用基準の同100ベクレル以下と比べても80倍と緩い。東京経済大の礒野弥生名誉教授(環境法)は「この基準だと相当な量が再利用される。それに、放射性物質濃度の低い土を混ぜれば、基準値まで薄められる」と危ぶむ。再利用に回る量が増えれば、再利用の対象地域も多くなりうる。「知らぬ間に除染土が身近に」ともなりかねない。厄介な問題は他にもある。福島第一原発からは放射性物質が広範に放出された結果、東北や首都圏で広く除染が実施された。除染土は福島県以外でも岩手や茨城、群馬、千葉など7県の計約2万9000カ所で保管されている。環境省は、袋や容器に入れて密閉し、防水シートをかぶせて遮水したり、盛り土で覆ったりなどの対策を促している。しかし保管後の対応は福島県とそれ以外で異なる。政府が11年11月に閣議決定した基本方針では、汚染土などが「相当量発生している都道府県」では国の責任で中間貯蔵施設を確保すると定めた。該当するのは福島県で、それ以外は現地処理となる。 ◆再利用ありきで実証事業に乗り出す環境省 しかし除染土を抱える福島県外の自治体は複雑だ。学校など44カ所で保管している宮城県丸森町は「国と東電の責任で町外に運び出して処理を」と環境省にかけ合ってきた。町総務課の担当者は「町内には『ごみを捨てた人が片付けず、捨てられた場所の人が処分するのはおかしい』という声もある。国は町外搬出に応じていないが、法改正してでも町外でと国に求めている」と語る。人ごとで済ませられない除染土の後始末。ただ、後始末の方法は根拠が心もとなかったり、不透明なところがあったりする。福島県内の除染土の再利用、福島県外の除染土の現地処理は、時の内閣が閣議決定した方針にすぎない。合意形成が十分なのかという問題をはらんでいる。福島県内の除染土の最終処分に関しては、「現在、有識者会議で協議中」(同省担当者)という。こんな状況なのに、再利用ありきで実証事業に乗りだしているのが環境省だ。ジャーナリストの政野淳子氏は「再利用は法的根拠が薄く、ごり押しはおかしい」と批判した上、「実証事業は既成事実を積み上げるための試みだ。実際に道路工事などで再利用するなら、防護策の検証も必要になる」と指摘する。前出の礒野氏も「福島の事故対応は、今後の土台になる。そもそも再利用をしていいのか、するならどう進めるか、丁寧な議論を重ねるべきだ」と訴える。 ◆デスクメモ 東電の原発による放射能汚染。後始末を担うべきは東電のはずだが、各地に汚染土の受け入れを迫る構図になっている。自然災害のように「誰かのせいで起きたわけじゃない」「復興に向けてみんなで協力を」と言わんばかりに。違和感を抱かせる前提部分。ここから問い直すべきだ。 *9-2-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/225016 (東京新聞 2023年1月13日) 政府、海洋放出「春から夏ごろ」 原発処理水で関係閣僚会議 政府は13日、東京電力福島第1原発の処理水処分に関する関係閣僚会議を首相官邸で開いた。海洋放出の開始は、設備工事の完了や原子力規制委員会による工事後の検査を経て「今年春から夏ごろ」との見込みを確認した上で、政府の行動計画を改定し、新たに設けた500億円の基金で、放出の影響を受ける全国の漁業者の支援に取り組むことを盛り込んだ。計画には、風評被害が発生した場合に東電が支払う賠償額の算定方法の具体化を進めることや、海洋放出の必要性について国内外への情報発信を拡充することも盛り込んだ。放出前には、国際機関による安全性の検証を受けたことを周知するとした。 *9-2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230128&ng=DGKKZO67988190X20C23A1EA2000 (日経新聞 2023.1.28) 家庭電気代、広がる地域差 東電値上げ、関西より7割高 原発稼働状況が左右 大手電力会社の家庭向け電気料金で地域差が拡大する。東京電力ホールディングスなど7社は26日までに3~4割程度の値上げを経済産業省に申請した。申請通りになれば政府による負担軽減策の効果を打ち消し家計の負担は増す。関西電力などは現状、値上げをしない方針だ。燃料高の影響が大きい火力発電への依存度で判断が分かれる。東電の値上げで今夏には首都圏の電気代は関西より7割も高くなる。各社が値上げを申請したのは一般家庭の過半が契約する「規制料金」。各社が任意に料金設定できる自由料金と異なり、値上げには経産省の審議会での審査が必要となる。26日に北海道電力が平均で約3割の値上げを経産省に申請し、値上げの意向を示していた7社全てが申請を終えた。今後は各社がそれぞれ妥当性などを審査され、最終的な値上げ幅や時期が決まる。東電は6月の値上げを目指しており、家庭向け契約全体の3分の2程度にあたる約1000万世帯が対象となる。申請内容をもとに足元の燃料価格から値上げ後の料金を計算すると、代表的なプラン「従量電灯B」の料金は標準家庭で1万1737円と29%上がる。料金を据え置く関電(7497円)よりも約6割高い水準だ。電気代高騰を受けて政府が2月に始める負担軽減策では、1キロワット時あたり7円が割り引かれる。電力会社によってベースの料金に差はあるが、補助額は全国一律だ。割引分を組み入れると、6月の東電の料金は9917円、関電は5677円となる。1月に約2割だった東電と関電の料金差は、7割超にまで広がる計算だ。なぜここまでの料金差が生じるのか。値上げ判断に大きく影響しているのが電源構成に占める火力発電の比率だ。東電は21年実績で77%と、沖縄電力に次いで高かった。一方で、値上げを申請していない関電は43%、九州電力は36%と他社と比べても低水準で推移する。火力発電への依存度が高い電力会社が一様に抱える課題が、原発の再稼働の遅れ。東電は主力の柏崎刈羽原発(新潟県)が安全対策の不備で再稼働できず現状で稼働している原発は1基もない。一方、関電は大飯原発3.4号機(福井県おおい町)など全国で最多の5基が稼働中だ。電源構成に占める原発の割合は21年度実績で約28%だったが、足元ではさらに高まっているもよう。23年には高浜1.2号機(福井県高浜町)の運転も始める。関電の原発稼働率は22年度に5割程度だが、23年度には7割台後半にまで高まる見通しだ。関電の22年度の最終損益は1450億円の赤字となる見通しで、東電ほどではないが今期の業績は厳しい。だが関電は原発の稼働率が1ポイント高まると経常費用を95億円減らせると試算する。原発稼働率が高まれば来期以降、採算改善が見込めるとみて、値上げを見送る判断をしたようだ。火力依存度が大手10社の中で最も低い九州電力も現状では値上げの意向は示していない。玄海・川内の2原発が稼働する同社では電源構成に占める原発の比率が21年度に36%と、全国の大手電力のなかで最も高かった。また九電は固定価格買い取り制度(FIT)で調達した電気も含めた再生可能エネルギーの比率も約2割と東電などより高い。燃料高に左右されず電力を安定供給していくためには、安全に配慮しながら原発を活用しつつ、再生エネの比率を高めていくことが不可欠となる。大手電力の値上げへの姿勢の違いは法人料金にも表れている。東電は4月から法人向けの標準料金も12~14%引き上げる。一方で関電は法人向けでも料金を据え置く方針だ。工場などの立地によって電気代負担に大きな差が生じることになり、拠点間の競争力を左右することになりそうだ。 *9-3-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05A8V0V01C22A0000000/ (日経新聞 2022年12月25日) 火力発電、脱炭素化探る CO2貯留やアンモニア混合 大手電力などが石炭火力発電所で脱炭素に向けて、燃料の転換などを進めている。発電から出る二酸化炭素(CO2)は国内の4割程度を占める。長期的に温暖化ガスを実質ゼロにするには再生可能エネルギーの活用拡大が求められるが、移行期は電力の安定供給との両立も必要だ。既存の火力発電所で排出量を抑えることが急務となっている。政府は温暖化ガスを2030年度に13年度比46%減、50年までに実質ゼロにする目標を掲げる。この目標に沿い、経済産業省はエネルギー基本計画で30年度の電源構成を示している。発電量に占める再生エネや原子力を増やし、石炭や液化天然ガス(LNG)、石油の化石燃料を使う既存火力の割合を減らす。火力は19年度の76%程度から30年度には41%に抑える計画だ。一定の割合で残る火力で、電力を安定供給しながら、温暖化ガス削減に向けた技術開発が求められることになる。特に石炭はCO2排出量がLNGの約2倍に上る。電力各社は石炭火力の次世代化や効率化を進める。CO2を地下に貯留する「CCS」やコンクリートなどに使う「CCU」と組み合わせることも有望視されている。Jパワーと中国電力は広島県で次世代火力「石炭ガス化複合発電(IGCC)」の実証実験を続ける。石炭から取り出した水素を燃やすことで発電する。発電効率は高効率石炭火力でも40%前後だが、IGCCは46%程度でより効率的に電気を生み出せる。Jパワーは松島火力発電所(長崎県西海市)で従来型をIGCCに転換する計画も進める。26年度の稼働予定で出力は50万キロワット。石炭の消費量を現状比1割減らせる。脱炭素燃料への転換の取り組みもある。東京電力ホールディングスと中部電力が出資するJERAは石炭の碧南火力発電所(愛知県碧南市)で、アンモニアを混ぜて発電する実証実験を始めた。アンモニアは燃やしてもCO2を発生しない。JERAは新技術の開発に実証データを活用し、アンモニアを混ぜる割合を2割まで高める。仮に国内の石炭火力すべてでアンモニアを2割混ぜればCO2排出量は4000万トン減る計算だ。発電からの排出量の約1割にあたる。技術的な課題もある。水素やアンモニアの混ぜる割合を高めるために燃料を燃やす装置の技術向上が欠かせない。三菱重工業やIHIが新技術の開発に乗り出しており、20年代には一部で5割以上を混ぜたい考え。ただ、化石燃料をアンモニアや水素に置き換えられるようになるのは早くても40年代とされる。脱炭素の切り札と目されているCCSも課題はある。経産省は50年時点の目安として年間最大2億4000万トンのCO2の貯留量を想定する。発電からの排出量の半分程度に相当する量だ。ただ、北海道苫小牧市で実施したCCSの政府の実証試験の累計貯留量は30万トンとごくわずかだ。ENEOSホールディングスやJパワーも30年の事業開始を目指して貯留場所を選定しているものの、まだ具体的な場所は決まっていない。アンモニアや水素の活用推進を火力の脱炭素移行戦略の柱の1つに据えるのは今のところ日本勢が中心だ。石炭火力の延命にもつながるという批判が海外の一部の投資家や非政府組織(NGO)から上がっており、国際社会の理解を得られるかも課題となっている。政府は脱炭素による経済成長を目指す「GX(グリーントランスフォーメーション)」を掲げ、10年間で官民で150兆円超の投資が必要とする。みずほ証券によると国内で公募されたトランジションボンド(移行債)の起債額は22年1~11月で3864億円と、21年の200億円から急増する。民間で高まり始めた脱炭素投資の機運を生かせるか問われている。 *9-3-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF158CQ0V11C22A2000000/ (日経新聞 2023年1月12日) JR西日本、全ディーゼル車にバイオ燃料 脱炭素へ加速 JR西日本は主にローカル線を走るディーゼル車両すべてでバイオ燃料を2030年ごろに導入する方針だ。同社の在来線の4割近くを占める非電化区間の二酸化炭素(CO2)排出を減らす。JR東日本も水素燃料車の実用化を目指すなど、JR各社で脱炭素の取り組みが進む。ローカル線の採算が悪化するなか、軽油より高いコストをどう負担するかが課題となる。日本の鉄道路線(私鉄含む)の非電化区間は全体の3割を占めるとされる。国土交通省によると鉄道事業者(同)のCO2排出量は全体で年993万トン(19年度)。うちディーゼル車両からは5%で比率は大きくない。ただ、車両当たりの排出量ではディーゼル車両は電車の数倍ともいわれる。JR西日本は23年度に山陰線の下関駅(山口県下関市)と長門市駅(同長門市)の区間で走行試験を実施する。軽油をバイオ燃料にすべて置き換える。微生物などから製造し、環境負荷の小さい燃料を使う。ユーグレナや大手商社などから調達する。燃費や走行性能を検証する。バイオ燃料はCO2を吸収した植物などを原料にするため、燃焼しても大気中のCO2総量が増えない。車両を大きく改造しなくても使え、脱炭素対策の初期投資を抑えられる利点がある。ただ、JR西日本によると、現在のバイオ燃料価格は軽油の数倍で、運行コストは増える。JR西日本の全車両のうちディーゼル車両は7%あり、年間2万1000キロリットル(21年度)の軽油を使用している。25年度以降、バイオ燃料の調達量に合わせて車両ごとに転換し、軽油の使用量をゼロにする。30年ごろに全ディーゼル車両へ導入する目標を掲げる。JR東日本は、発電時にCO2を出さない水素を燃料とする燃料電池と蓄電池を組み合わせた新型車両「HYBARI」(ひばり)の走行試験を22年から始めた。30年の実用化を目指し、非電化区間でディーゼル車両との置き換えを視野に入れる。運輸総合研究所(東京・港)の山内弘隆所長は、航空業界ではバイオ燃料などを使う際のコスト増分を利用者に負担させる議論があることに触れて「ローカル線では(利用者負担の増加は)難しい。バイオ燃料を使う場合には国が補助して支援すべきだ」と指摘する。政府が50年のカーボンニュートラル(温暖化ガス排出実質ゼロ)達成を目標に掲げるなか、JR各社には赤字区間の多いローカル線で環境負荷を低減するという難しい取り組みが求められている。
| 外交・防衛::2019.9~ | 04:34 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
PAGE TOP ↑
