左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。
|
2022,03,06, Sunday
  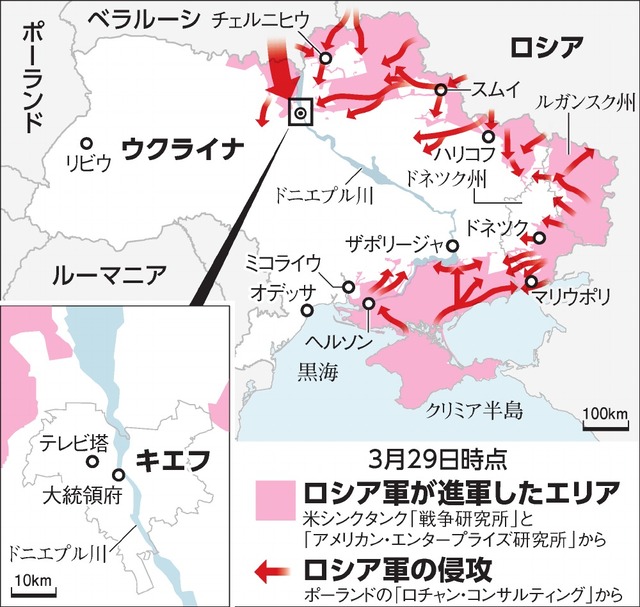 2022.2.25スポニチ 2022.3.4西日本新聞 2022.3.30朝日新聞 私も、戦争の最中に自分の祖国やその同盟国の批判をしたくはないが、これは、言わなければならないから、損得勘定抜きで言っているのである。そして、「言論の自由」というのは、こういう時に必要なものなのだ。 (1)誹謗中傷の嵐は攻撃である フィギュアスケート金メダル候補のワリエワ(15歳)から採取された検体から、2021年12月25日にトリメタジジン(心臓病の狭心症・心筋梗塞等の治療で使われる薬で、血管を広げて血流をよくし、アスリートの心肺機能を上げる効果があるとされる)が検出されたと、*1-1のように、2022年2月11日、ドーピング検査を管轄する国際検査機関(ITA)が明らかにした。 トリメタジジンは“ドーピング薬”に入っているが、筋肉増強効果があるのではなく、リカバリー促進効果を狙う薬で、健康な成人に経口投与した場合は血中からの消失半減期が11.5時間なので、46時間(11.5X4)で6.25%(0.5⁴)まで減少する。そのため、2021年12月25日にワリエワの尿からトリメタジジンが検出されたとしても、オリンピックの時には効果は続いていない筈だ(https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2171007F1210_1_02/2171007F1210_1_02?view=body&lang=ja参照)。 にもかかわらず、ITAが、2022年2月11日に明らかにしたのは、世界中に「ロシアは闇が深く汚い」というイメージを刷り込むためではなかったかと、私は推測せざるを得ない。 なお、トリメタジジンだけではワリエワの意図的な接種を断定できなかったためか、ニューヨーク・タイムズが、*1-2のように、「ワリエワからトリメタジジンのほかに、2つの薬物が検出された」と付け加えた。しかし、他の2つの薬物はドーピング防止当局によって禁止されているものではなかった。つまり、“ドーピング”の定義やルールにも問題があるのに、ルールを振りかざしてケチをつけた感があるのだ。 また、朝日新聞は社説で、*1-3のように、「①スポーツの土台である公正・公平を揺るがす」「②他の選手も巻きこんで混乱を招いた罪は大きい」「③ロシア薬物問題を速やかに真相解明すべき」「④スポーツ仲裁裁判所は、ワリエワが引き続き試合に出ることを認める裁定をした」「⑤選手の健康を守ることが何より大切だ」「⑥2014年のソチ冬季五輪後、ロシアの大規模な薬物使用が発覚し、国家ぐるみの関与と隠蔽が認定された」「⑦ワリエワ問題を機に浮上した疑念と批判は、IOCに対する不信の表明でもある」等と批判し、日本のメディアは、一斉に同じような批判の嵐を吹き荒れさせた。 しかし、⑤については、拍手喝采を浴びるために万難を排して練習してきた選手に対し、競技の最中に②③⑦を述べ立てて混乱させることこそ、精神の健康にとって最悪である上、危険でもある。そのため、④のように、スポーツ仲裁裁判所がワリエワの出場を認める裁定をしたのはよかったのだが、このような環境の下でのワリエワのフリーの出来は散々で、私は、このようにして金メダル候補を貶めた競技の結果が、①の公正・公平にあたるとは思えない。 さらに、⑥のように、「2014年のソチ冬季五輪後、ロシアの大規模な薬物使用が発覚し、国家ぐるみの関与と隠蔽が認定された」として、ロシアの選手はROCとしてしか出場させず、金メダルをとっても国歌は演奏しないというロシア差別をしていた上、*1-4のように、ロシアは「全く悔い改めない」「五輪を複数大会欠場する必要がある」等と、IOCのパウンド氏(カナダ)やWADAのクレイグ・リーディ元会長(スコットランド)が語ったのは、明らかにロシアの選手に対する差別である。そのため、このような状況の下で、ロシアのプーチン大統領が怒りを覚えたとしても、全く不思議でも不自然でもない。 なお、*2-3のように、アメリカのマルコ・ルビオ上院議員などが、「ウクライナに軍事侵攻したロシアのプーチン大統領の精神状態を疑問視する」としたそうだが、五輪の件だけでなく、何でもここまで悪く言われれば、怒るのが当たり前で正常だと思う。 その証拠に、日本語が上手で普段は温厚かつ論理的でもあるガルージン駐日ロシア大使も、プライムニュース(BSフジ)でしつこく追及された時に、やはり顔を赤らめて怒っていた。日本のメディアは、コメンテーターを日本人に偏らせ、予定調和の結論ありきの見解ばかりを披露させる傾向があるが、相手国の専門家もバランスよく出演させて率直な意見を聞くべきである。 (2)戦争はいつ始まったのか? 1)反ロシアキャンペーンとロシアへの経済制裁が戦争の始まりであろう フランスのルメール経済相は、*2-1のように、「制裁は恐ろしいほど効果的で、ヨーロッパの決意を曖昧にしたくない。われわれはロシアとの経済、金融上の戦争に入る」と述べ、侵攻を続けるロシアに対する断固とした姿勢を示されたそうだが、私も、“経済制裁”は武力を使わない戦争開始だと思う。 そのため、*2-2のように、中国が日米欧の対ロ制裁について「①あらゆる違法な制裁に断固反対する」「②制裁は問題を解決せず、争いをエスカレートさせるだけだ」「③中国とロシアは引き続き正常な貿易協力を進めたい」「④正常な金融取引を保つ」としているのはわかる。 2)ロシアのウクライナへの軍事侵攻 ロシアがウクライナに対する軍事侵攻に踏み切って1週間経った現在も、*2-4のように、ロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続き、多くの死者・負傷者・難民が出ていることには、私も心を痛めている。 ロシアは停戦条件としてウクライナの「中立化」「非軍事化」を要求しており、その理由は理解できる。一方、ウクライナはEUやNATOへの加入を望んでおり、両者には隔たりがある。アメリカのブリンケン国務長官は、「われわれはウクライナ支援の用意がある」「ロシアの要求は度を越しており、交渉の対象にもならない」「われわれはロシアが見せかけの外交を行ってきたことを繰り返し見てきた」とし、アメリカはロシアとベラルーシに対して経済制裁を発表した。 しかし、武力であれ、制裁であれ、ウクライナもロシアも脅されたから引き下がるような国ではない。そして、これは、どの国も基本的には同じだ。そのような中、松野官房長官が「ウクライナから避難した人の日本への受け入れに人道的観点から対応する」という考えを示されたのはよかったが、日本がロヒンギャなどのアジア人に冷たくし続けていることに対して、私は日本にも人種差別があると感じる。 なお、「ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって開かれていた国連総会の緊急特別会合では、ロシア軍の即時撤退等を求める決議案が欧米・日本等の141か国の賛成多数で採択され、ロシアの孤立がいっそう際立つ形となった」とも書かれているが、ロシア・ベラルーシ・北朝鮮など5か国は反対し、中国・インドなど35か国は棄権したそうだ。欧米や日本から見ていてもわからないが、インド・中国は、ユーラシア大陸の視野でロシアと普通に商取引してきた長い歴史があるからだろう。 3)原発への武力攻撃が想定外とは・・ ロシア軍が、ウクライナで事故を起こしたチェルノブイリ原発に続いて、欧州最大規模のザポロジエ原発を制圧したそうだ。これについて、*2-5-1は「①稼働中原発への軍事侵攻は前例がない」「②国際社会に大きな衝撃」「③原発への軍事攻撃は、ジュネーブ条約で禁止」「④システム故障や電源喪失が起きれば破滅的な過酷事故にも繋がる」「⑤世界中の原発を攻撃でき、原子力安全の根本が揺らぐ」「⑥原発占拠で脅しや交渉材料になることが分かってしまった」「⑦ウクライナの電源構成の5割近くが原子力」「⑧核燃料は原子炉内に入ったままで使用済核燃料プールもある」「⑨日本の原発は軍事攻撃想定外」と記載している。 しかし、③については、戦争になれば負けないためには何が起こるかわからず、④⑥は当たり前であるため、①②⑤⑦⑧⑨が、想定外と安全神話を繰り返す原発に関する甘い予想である。 日本国内の原発に関しては、フクイチ事故後、テロ対策施設設置を義務化して安全対策を強化したとしているが、原子力規制庁幹部が「テロ対策はしたが、他国の軍隊による武力攻撃は想定していない」としている。これは、想定を最小限にして対応した形だけを作ったことの証明だが、これで「敵基地攻撃能力」などと言っているのだから、考えが甘いにも程があるのだ。 つまり、日本の原発は、*2-5-2のように、テロ対策で義務付けられた設備も再稼働した原発の一部でしか完成しておらず、ミサイル攻撃等で原子炉建屋が全壊するような事態は想定さえしていないのだ。これについては、国会で何度も取り上げられたが、政府は「武力攻撃は手段、規模、パターンが異なり、一概に答えることは難しい」と逃げ、原子力規制委員会は「(電力会社に)弾道ミサイルが直撃した場合の対策は求めていない」と説明した。原発が事故を起こした場合は、人が短期間避難すればすむわけではなく、避難などできない田畑で食料生産をしているため、無責任も甚だしいのである。 4)中華人民共和国が中華民国を併合できる理由はない 1721年に成立したロシア帝国は、ロシア革命で1917年にソビエト連邦となり、1991年のゴルバチョフ大統領によるペレストロイカでソビエト連邦が崩壊して、東欧の脱共産化・東西ドイツの統一などが一気に進んで、東西冷戦は終わった。 それと前後して、ソビエト連邦からリトアニア共和国・ラトビア共和国・グルジア共和国・ウズベキスタン共和国・モルドバ共和国・ウクライナ共和国・ベラルーシ共和国・トルクメニスタン・アルメニア共和国・タジキスタン共和国・カザフスタン共和国が独立し、ロシア連邦がソ連邦の後継となったのは多くの人が知っているとおりだ。 つまり、国は「現状維持して安定」どころか、時代に合わせて変化しているのであり、革命を起こした人は、既存の政府からは、テロリストとして追跡され、処罰されてきたのだということを忘れてはならない。 一方、中華人民共和国の李克強首相は、*2-6のように、2022年3月5日に開幕した全人代の政府活動報告で、「武器や装備の現代的な管理システムをうちたて、国防科学技術のイノベーションを強化し、新時代の人材強化戦略を実施して、軍の質の高い発展を推進する」と述べた。 具体的には、「経済成長率目標5.5%」とし、「2035年に人民解放軍の現代化をほぼ実現し、今世紀半ばに世界一流の軍隊にする目標で国防費予算の伸び率を7.1%とする」「『祖国統一を後押ししなければならない』と述べて台湾統一に意欲を示した」とのことだが、台湾は中華民国という中華人民共和国とは別の独立国であるため、武力で併合することが許される筈はない。 これは、1991年前後に上記の地域を独立させたソ連邦とは全く逆の動きであるため、ロシアのウクライナ侵攻と台湾問題を似たものとして関係付けることは本末転倒である。しかし、日本政府は、「力による一方的な現状変更の試みを非難する」としているだけで、①力によらなければ変更してもよい(←制裁ならよい?) ②一方的でなければよい(←合意を強いることも可?) ③現状変更が悪く、現状がBestである(←よりよい方向なら変革すべき) というおかしなメッセージを発しているだけで、論理性ややる気のある準備を見せていないのである。 (3)日本のエネルギー政策について 日経新聞は、2022年3月1日の時点で、*3-1のように、「①ロシアのウクライナ侵攻が、エネルギー供給でのロシアの存在感とロシア依存へのリスクをあらわにした」「②ロシアの天然ガス生産量は世界2位、石油は3位で、国際決済網からのロシア排除で、さらに高騰しそう」「③ロシアにエネルギーを頼る欧州は強く出られず、その自信がプーチン大統領を侵攻へと動かした」「④脱原子力発電を掲げたドイツは天然ガスのロシア依存を深めていた」「⑤消費国は脱炭素とエネルギー安全保障の両立を探らなければならない」「⑥フランスは原発への回帰に踏み出し、EUも原発を環境に貢献するエネルギーと位置付けた」「⑦日本は再エネの導入が遅れ、原発の再稼働は進んでいない」と記載している。 しかし、①②は事実だが、③は誤りだ。何故なら、欧米諸国は論理的に重要性の順位を考え、ロシアのプーチン大統領もウクライナ侵攻にあたっては諸般の事情を総合的に考慮したに違いないからだ。 また、日本政府の広報版と言われる日経新聞は、3月1日時点で、ロシアのウクライナ侵攻を基に、④⑤⑥⑦のように、「(EUが天然ガスと原発を環境に貢献するエネルギーと位置付けたのだから)原発回帰や原発再稼働を早く進めるべきだ」としているが、原発が原爆と同じかそれ以上に危険であることは、プーチン大統領によって示してもらった筈である。それでも、安全保障のためとして原発を推進するつもりか? こういうことを、事前に、総合的に考慮することもできないから、馬鹿としか言えないのである。 また、ロシアのウクライナ侵攻による原油価格高騰への対応として、*3-2のように、政府はガソリン価格抑制のため石油元売りに配る補助金上限を25円/リットルに引き上げる方針としたが、これは地元からの要請に基づいた与野党国会議員の圧力によるものだろう。しかし、私が現職時代の2006年頃から同じことを言っていたため、15~16年間も同じことを言っているという生産性の低さなのだ。しかし、その間に省エネやエネルギー変換をする時間は十分あったため、補助金とトリガー条項の凍結解除はともに不要である。 なお、地球人口の増加や1人当たりエネルギー消費量の増加は確実に起こるため、(環境や気候危機を考慮しなかったとしても)化石燃料価格の高騰は確実で、再エネへのエネルギー変換とエネルギーの国産化は急務だったのである。 そのような中、*3-3のように、「時限的・緊急避難的激変緩和措置」とされたガソリン補助金を何かと理由を付けて延長し、トリガー条項の凍結まで解除するというのは、金を使って再エネへのエネルギーの変換と国産化を遅らせるものである。そのため、このようなバラマキをする金があったらさっさとエネルギーの変換と国産化のためのインフラ投資をすべきであり、これは、物流についても同じなのである。高い物流コストを上乗せして高価になりすぎた製品(それが市場価格)なら、消費者は買えないから買わない選択をするだけだ。 (4)気候危機とシベリア 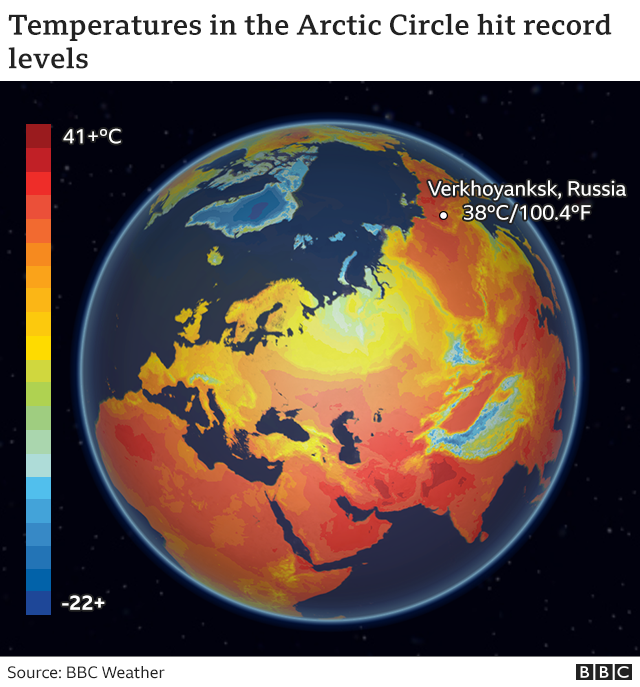   2020.6.23bbc 2020.6.23bbc IEuras(シベリア鉄道:北京⇔モスクワ) (図の説明:左と中央の図は、シベリアで38°Cという最高気温を記録し、森林が火災を起こしたというBBCのニュースだ。また、右図は、北京・モスクワ間を往復しているシベリア鉄道で、その車窓からは広大な草原が見えている) 国連の専門機関である世界気象機関(WMO)が、2021年12月15日、*4-1のように、「①ロシアのシベリアで2021年6月に記録された気温38度が、北極圏の観測史上最高気温だったと認定し」「②当時はシベリア一帯から北極圏まで広がる熱波が到来中で、シベリアの北極圏の平均気温は通常よりも10度上がり、地球規模での気温上昇や山火事・海氷喪失に繋がった」「③この新たな記録は私たちの抱える気候変化問題について警鐘を鳴らしている」とした。 北極圏は世界平均の2倍のペースで温暖化が進み、シベリアの永久凍土は凍土層が解けていると言われている。そして、私が、近年、航空機でヨーロッパに行った時、シベリアの上空を飛ぶと北極圏とは思えないような広大な草原が広がっていた。 もちろん凍土が解けると困ったことが多いのだが、温暖化でできた草原は農地や再エネの宝庫として使える上、氷の解けた北極海は不凍港として使える。従って、ロシアは新たに広大な利用可能地域を得たことになるため、ウクライナとは中国を仲介役として早期に和解し、大人口を抱えて食料・エネルギーが不足しがちな中国と協力してシベリア開拓を行えばよいと思う。 なお、IPCCの報告書には「①人為起源の気候変動は異常気象の頻度・強度を増し、広範囲にわたる悪影響と損失・損害を引き起こしている」「②生態系と33億~36億人の人間が気候変動に対し非常に脆弱な状況」「③短期的には、地球温暖化のレベルは1.5度に達して複数の気候災害が増加し、生態系と人間に複数のリスクをもたらして完全になくすことはできない」「④中長期的にも、気候変動は自然と人間のシステムに大きなリスクをもたらし、食糧不安はより深刻になる」「⑤一時的に1.5度を超える場合でも、(メタンなど)さらなる温室効果ガスの排出を引き起こし、温暖化を低減しても元に戻すことはできない」「⑥氷床・氷河の融解、加速する海面上昇で特定の生態系・インフラ・低地の沿岸集落等に回復不可能な影響」等が書かれていると、*4-2は記載しており、そのとおりだろう。 (5)日本国憲法で国民に約束された生存権と社会保障   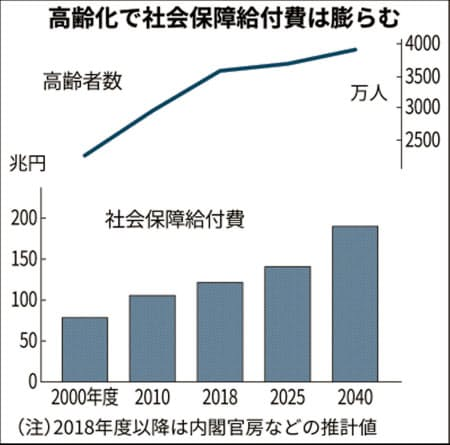 2020.1.6介護ワーカー 事業構想2020.12月号 2020.9.3日経新聞 (図の説明:左図は、自助・共助・互助・公助の考え方であり、家族間扶養は自助に入るとする。中央の図は、「全国47都道府県議会議事録横断検索」からの議会質問と答弁に出た「自助・共助・公助」という言葉の数で、1989年以前にはなく1990年から登場しており、2011・2012年の増加は東日本大震災が背景だそうだ。右図は、メディアが大合唱している「高齢化で社会保障費が膨らむ」というグラフだが、それは当然のことなので予算全体として「入るを計って出ずるを制す」べきであり、無理に社会保障費を減らせば生存権の侵害で憲法25条違反になる) 日本国憲法は25条で、「①すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。②国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障,公衆衛生の向上と増進に努めなければならない」と定め、国民の生存権とそれを護るために国が保障することを規定している。 1)医療・介護について イ)日本の新型コロナ対応 「感染症は何よりもまず検査が重要であるのに、検査・隔離・診断・治療の4層体制が最初から繋がっていなかったことが日本の新型コロナウイルス対応の最大の失敗だ」と阿部知子衆院議員(東大医学部卒、小児科医)が、*5-1のように述べておられ、おおむね賛成だ。 具体的には、「①ダイヤモンド・プリンセス号で陽性でも無症状の人がいることが明らかになったのに、無症状者の存在をふまえた検査体制が全く取られず」「②無症状者も含めた広範な社会的検査で対策の基礎データが得られるのに、政府のコロナ対策は基礎となるデータが全く不十分で」「③緊急事態宣言などで人の行動を縛ることばかりに意識が向いて感染症を扱う基礎が作られず」「④緊急事態宣言からワクチン接種まで現状を把握する検査データが無いまま政策を組み立てるので、感染が拡大するまで方針を決められなかった」「⑤従って、対策を取っても、国民に理由を説明できない」ということだ。 このうち、①②については、新たな感染症を防ぐために経験を科学的に活かすことをせず、③のように、人の行動を縛ることばかりに専念し、新型コロナを口実に日本国憲法に緊急事態条項を入れる必要性にまで言及する人が出たのは、日本が医療を軽んじて人権侵害を行う方向に進んでいる証拠だと思った。 また、④⑤については、日本の政策は何事もそうで、為政者が殆ど丸暗記型の文系で「科学的根拠を基に、理由を国民に説明しなければならない」という発想がなく、「他国と足並みを揃えて孤立さえしなければよい」と考えている面があるからだ。しかし、足並みを揃えることが重要なのは馬車馬のように決まった単純な仕事をやり続ける場合で、自分でモノを考え判断する人間のやるべきことではないため、根本的にはやはり教育の問題である。 さらに、日本の公衆衛生は、「⑥明治時代の結核隔離政策から始まり」「⑦戦後はハンセン病のように医学上は不要なのに社会的に排除するために隔離した負の歴史があり」「⑧1980年代末ごろから『感染症はもう来ない』という前提の下に感染症病床が削減され」「⑨日本で検査数が少ないのは、感染症に対しては検査が基本であるという基礎が忘れられてしまったから」というのも、⑥はその頃の科学技術の水準から考えて仕方がなかったとしても、⑦⑧⑨は、科学的根拠もなく医療やそれを享受する人の人権を疎かにしてきた歴史そのものなのである。 なお、「⑩水際の検疫も検査で陰性になれば市中に入るが、検査は完璧でないため変異株の侵入を防ぐには陰性でも一定期間は留め置くべき」「⑪PCR検査の利点は遺伝子解析ができることで、変異株対策はPCR検査で遺伝子的な特性を把握することが重要」「⑫その上で抗体検査も進めて遺伝子タイプによるワクチン効果の違いが把握できる」「⑬下水のコロナ検査も進んでおり、変異株も含めて地域的対応も可能となった」とも言われており、⑪⑫⑬はそのとおりだが、こうなった理由は、日本の厚労省と同専門家会議は一流の専門家を集めていないからだろう。 そして、⑩の水際の検疫については、無駄に厳しいところがあった反面、ザルになっているところも多く、本当はしっかり防疫して国民を護る気がないのではないかと疑われた。 「⑭ワクチン接種は、東京オリンピック・パラリンピックのため、集団免疫のため、国家のために接種しなければならないなどと言われたが、自分のためにするものだ」「⑮健康はその人にとって、最大、最高の主権だ」については全くそのとおりだと思うが、⑭には、政府・メディアの全体主義的発想があった。⑮は現行憲法で国民に保障された権利なのだが、国の理想を綴った日本国憲法さえ読んだことのない国民が多いのも教育の問題であろう。 ロ)日本が医療産業で二流三流なのは、今だけか? 吉田統彦衆院議員(名大院卒、眼科医、ジョンズ・ホプキンス大学研究員)は、*5-2のように、「①コロナで日本の医療体制には余裕がないことがわかった」「②人材面では日本の頭脳が海外流出する流れを変え、優秀な研究者は巨額の資金をかけてでも国籍を問わず海外から集める必要があるが、報酬が低すぎて招聘できない」「③日本の大学教授は一人で医療と基礎研究の両方やるので、限界がきている」「④日本の医療が基礎研究で海外の後塵を拝している理由はここにある」としておられ、私も①②③④には賛成だ。 しかし、「⑤国立感染研は、(疫学調査や検査だけでなく)ワクチンの開発や治療法の確立をする力が必要で、国民の危機を守ることができるナショナルセンターに生まれ変わらせるべき」「⑥それができる人材が必要」という点については、疫学調査や検査も十分にできなかった上、それを大学や民間の検査センターと手分けして行うこともせず、2年半も不十分な検査で済ませてきた国立感染研には厚労省管轄施設の限界を見た思いがしたため、国立感染研を大きくするよりは、大学・製薬会社等が研究・開発を行い、厚労省は治験に協力して承認を遅らせないための改革が必要だと思った。 さらに、「⑦コロナの国産ワクチンが遅れた根本的問題は、医薬品・医療機器産業における日本のプレゼンスの低下」「⑧治療用の医療機器は世界から遅れている」については、日本の医薬品・医療機器産業は他の産業と比較して前から遅れており粗末でもあった。そして、「⑨生体吸収性ステントは京都医療設計が開発したが、日本より先にドイツで承認・販売された」というのも、最初に欧米で認められなければ日本で認められないという点で全く例外ではなく、そうなる理由は承認する側の人材の問題なのである。 なお、「⑩日本の医療は、技術は一流だが、医薬品・医療機器産業はもう二流三流」「⑪遺伝子医療でも遅れるリスクが大きい」とも言われているが、日本の医薬品・医療機器産業が一流になったことはなく、遺伝子治療でもかなり遅れているが、そうなる理由も、その方面に進む人材・報酬・労働条件やその背景の問題であろう。 2)生活保護について 毎日新聞は、2022年2月14日、*5-3のように、「①失職して生活に困窮した50代の男性が、住まいのある東京都杉並区で生活保護を申請したところ、区は『地方に暮らす80代の両親に扶養照会しなければ生活保護申請の手続きは進められない』と言った」「②路上生活者支援で80代以上の高齢者に出会うことは珍しくないが、親族に連絡が行くのを怖れて生活保護申請をしない人は少なくない」「③扶養照会が生活保護利用にあたっての最大のハードルとなっている」と記載している。 この①②③は、上の中央の図のように、バブルがはじけ、人口の高齢化が言われ始めた1990年頃から議会で質問に登場した「自助・共助・公助」のうち、「自分や家族で対応する」自助を優先して公助を節約するという発想から来ているものである。 しかし、「“扶養を頼める家族の範囲”はどこまでか」「高齢で扶養能力のない“家族”でも扶養義務を負うのか」等の問題から逃げて、公助を減らしたい一心であることがまる見えだ。そのため、これでは、「健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な社会保障」を行わずに、国民の生存権を危うくする。 また、*5-3は、「④厚労省は各地方自治体に照会の範囲を限定した上で、申請者本人の意思を尊重することを求める通知を出した」「⑤生活保護法は親族の扶養は保護に優先すると規定している」「⑥そもそも扶養照会という法律に基づかない仕組み自体が必要なのか」とも記載している。 ④は、何もしないよりはよいが、⑤については、“親族”がいても頼れない事情がある人は多い。そのため、親族の扶養が生活保護に優先するのはどういう親族の場合かを議論し、扶養義務のある“親族”の範囲を狭めるべきである。そのため、⑥については、本人が「“親族”には頼れない」と判断して扶養照会を拒んでいるのなら、その希望を優先すべきだろう。 ・・参考資料・・ <誹謗中傷の嵐は攻撃そのものである> *1-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/1b2e8fd2ee8b9538b604e3a634cda0d2740971a3 (Yohoo 2022/2/14) ワリエワから検出されたトリメタジジン「リカバリー促進効果狙ったのでは」専門家 フィギュア女子のカミラ・ワリエワ(15=ROC)から検出された、トリメタジジンとは、一体どんな物質なのか-。11日にドーピング検査を管轄する国際検査機関(ITA)が陽性反応を明らかにして表面化。北京オリンピック(五輪)代表選考試合の1つだったロシア選手権(サンクトペテルブルク)で12月25日に採取された検体から、持久力向上の効果があるとされる禁止薬物トリメタジジンが検出されたと発表した。トリメタジジンは、心臓の病気である狭心症、心筋梗塞などの治療などで使われる薬だという。血管を広げ、血流をよくしたり、血管の中で、液が固まることを防ぐ作用がある。アスリートが使用すると、心肺機能を上げる効果があるとされ、18年平昌五輪ではボブスレー女子のナジェジダ・セルゲエワ(OAR=ロシアからの五輪選手)が失格処分になった例がある。高島平中央総合病院スポーツメディカルセンター長の元島清香氏は「ドーピングというと、筋肉増強のイメージがありますが、今回のケースはリカバリーを促進する効果を狙ったのでは」と話す。「完璧な演技をするためには、いかに充実したトレーニングを持続するかが大事。たとえばハードトレーニングを3日に1回から2日に1回できるようになれば、当然、アスリートとしてはプラス。肉体疲労からの回復を促す効果を得た可能性もある」と推測した。 *1-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/beca1669dd072a2935d8b1506e36082864c73d67 (Yohoo 2022/2/16) ワリエワの体内からトリメタジジンのほかに2つの薬物検出 NYT紙「非常に珍しい」 北京五輪フィギュアスケート女子に出場しているロシアオリンピック委員会(ROC)のカミラ・ワリエワ(15)を巡るドーピング違反問題で、陽性判定を受けたトリメタジジンのほかに心臓機能を向上させる2つの〝薬物〟が検出されたことが判明した。米紙「ニューヨーク・タイムズ」は「北京冬季五輪のドーピングスキャンダルの中心にいる15歳のロシアのフィギュアスケート選手のワリエワは昨年12月に行われたドーピング検査で心臓の状態を良くするために使用される3つの薬物について陽性だった」と報道。すでにトリメタジジンの陽性判定が明らかになっているが、さらに2つの薬物も検出されていたのだ。ただ「彼女のサンプルで見つかった3つの薬のうち、トリメタジジンだけがドーピング防止当局によって禁止されている」と説明。その上で「他に検出された2つの薬はハイポキセンとL―カルニチンで禁止はされていないが、ドーピング防止当局の関係者は若いエリートアスリートに3つの薬すべてが体内に存在することは非常に珍しいと語った」と指摘している。他の2つの成分は〝シロ〟ではあるものの、トリメタジジンと同様に心臓の機能を向上させ、それが持久力の強化や血液循環の改善を促す効果があるという。そして、すべての成分が同時に体内にあることは不自然だと同紙は追及。「いずれの効果も、高いレベルのフィギュアスケート選手に大きな競争上の優位性をもたらす可能性がある」と分析している。禁止薬物に加えて〝グレー〟の成分を摂取していたことも判明したワリエワ。ドーピング問題の闇は深そうだ。 *1-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15205616.html?iref=comtop_Opinion_03 (朝日新聞社説 2022年2月16日) ロシア薬物問題 速やかに真相の解明を スポーツを成立させる土台である公正・公平を揺るがし、他の選手も巻きこんで混乱を招いた罪は大きい。北京冬季五輪にロシアから参加したフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ選手をめぐるドーピング問題だ。昨年末に採取された検体から禁止薬物が見つかった。資格の停止か解除か、判断が二転三転した後、スポーツ仲裁裁判所は引き続き試合に出ることを認める裁定をした。16歳未満を法的能力が十分でない「要保護者」とする規定があり、15歳の同選手はこれに当たることなどが考慮されたという。選手の権利を尊重した判断といえるが、いくつもの疑問が重なり、納得には遠い。まず薬物陽性の事実が、五輪が開幕し団体種目を終えた段階で公表されたことだ。通常は採取から10日ほどで結果が出る。検体がロシア国外の検査機関に運ばれたことや、コロナ禍で様々な動きが滞っていることを考えても、なぜ1カ月以上を要したか、理由は不明だ。万が一にも金メダルの最有力候補と目される同選手の参加を優先させるような思惑が働いたとしたら、とんでもない話だ。問題の薬物は狭心症や心筋梗塞(こうそく)の治療薬で、選手が使えば血流が増え、持久力を上げたり運動後の回復を早めたりする効果がある。食物などから誤って摂取する可能性は低いという。自分で飲んだのか、誰かが飲ませたのか。目的は何か。その解明もこれからだ。近年、一部の競技で低年齢の選手の参加・活躍が目立つようになった。裁定理由が悪用され、薬物使用の抜け道になることを恐れる。競技の公平性はもちろんだが、選手の健康を守ることが何より大切だ。世界反ドーピング機関を中心に徹底した調査を行い、事態の全容を速やかに明らかにすべきだ。国際オリンピック委員会(IOC)はワリエワ選手が絡むメダル授与などを実施しないことを決めた。すっきりしないまま試合が行われ、成績が定まらない可能性も高い。選手たちの動揺・落胆はいかばかりか。こうした状況を招いた大きな責任はIOCにもある。14年のソチ冬季五輪後、ロシアにおける大規模な薬物使用が発覚し、国家ぐるみの関与と隠蔽(いんぺい)が認定された。だがIOCは毅然(きぜん)とした対応をとらず、むしろロシア五輪委員会に対する資格停止処分を先んじて解除するなどした。薬物根絶を迫る機会を自ら放棄したに等しい。ワリエワ問題を機に浮上した疑念と批判は、この間のIOCに対する不信の表明でもある。五輪はまたも大きく傷ついた。 *1-4:https://hochi.news/articles/20220213-OHT1T51080.html?page=1 (スポーツ報知 2022年2月13日) IOCの最古参委員・パウンド氏、ロシアのドーピング問題に「全く悔い改めない。1、2、3大会五輪を欠場するべき」 フィギュアスケート女子でロシア五輪委員会(ROC)のカミラ・ワリエワ(15)のドーピング違反報道を巡り、国際オリンピック委員会(IOC)の最古参委員であるディック・パウンド氏(79)=カナダ=が、「ロシアはオリンピックから“タイムアウト”する時かもしれない」と語った。12日にカナダの放送局「CBC」が報じた。CBCの電話インタビューに応じたパウンド氏は、ロシアの組織的ドーピング発覚後も「全く悔い改めない」と断じ、「ロシアは問題を抱えている。この問題を収拾できるまで、1、2、3大会五輪を欠場するべき」と語った。また、世界アンチドーピング機構(WADA)のクレイグ・リーディ元会長も、五輪を複数大会欠場する必要があると語ったと、露メディアが報じた。ワリエワは、昨年12月に採取された検体が陽性と判明。ロシア・アンチドーピング機構(RUSADA)は8日に選手資格を暫定的に停止し、ワリエワからの異議申し立てを受けて9日に処分を解除した。この決定を国際オリンピック委員会(IOC)とWADAが不服としてスポーツ仲裁裁判所に提訴。CASは12日、13日に公聴会を開き、14日午後に裁定を下すと発表した。露メディアによると、ワリエワのコーチのエテリ・トゥトベリゼ氏は12日、取材に応じ、「カミラは潔白だと確信している。それを証明する必要はない」と答えた。女子のショートプログラムは15日に行われる。 <経済制裁も攻撃である> *2-1:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220302/k10013508931000.html (NHK 2022年3月2日) ロシアへの経済制裁 フランス経済相「経済 金融の戦争」 フランスのルメール経済相は1日、ニュース専門チャンネルの番組に出演し、ロシアに対する欧米各国の経済制裁について「制裁は恐ろしいほど効果的で、ヨーロッパの決意をあいまいにしたくない。われわれはロシアとの経済、金融上の戦争に入る」と述べました。ルメール経済相は、「戦争」という表現はふさわしくなかったとしてその後撤回しましたが、侵攻を続けるロシアに対する断固とした姿勢を示しました。また、ウクライナ情勢をめぐる経済的な影響について「経済、金融上の力関係は完全にEU=ヨーロッパ連合が上回っている。崩壊するのはロシアの金融システムであり、ヨーロッパへの影響は、物価のわずかな上昇だ」と述べ、必要であれば制裁をさらに強化する考えを示しました。 *2-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/d380e39ed2a1b8c35378582a93026e92df63036e (Yahoo、ANN 2021/3/3) 中国が日米欧の対ロ制裁に“違法”と反発「ロシアと貿易進める」 ウクライナへの軍事侵攻を受けて各国がロシアへの経済制裁に乗り出す中、中国政府は「ロシアと正常な貿易協力を進める」と制裁に反対する姿勢を表明しました。中国外務省は2日の会見で、欧米や日本などによる経済制裁について「あらゆる違法な制裁に断固反対する」とし、「制裁は問題を解決せず、争いをエスカレートさせるだけだ」と主張しました。そのうえで「中国とロシアは引き続き正常な貿易協力を進めたい」と述べ、天然ガスなどの購入を続ける考えを強調しました。また、金融監督当局のトップも2日の会見で、「金融制裁に賛成しない」と明言しました。国際的な制裁の動きには参加せず「正常な金融取引を保つ」としています。 *2-3:https://www.fnn.jp/articles/-/322893 (FNN 2022年3月1日) プーチン大統領の精神状態に疑問論 アメリカの有力議員らから ウクライナに軍事侵攻したロシアのプーチン大統領について、アメリカの有力議員らから精神状態を疑問視する声が上がっています。アメリカの情報機関と近い関係にある、マルコ・ルビオ上院議員は、ツイッターに詳細を明かすことはできないと断った上で、「今言えるのはプーチン氏は何かがおかしいということだ」と書き込みました。また別の書き込みでは、「昔のプーチン氏は冷血で緻密な殺人犯だったが、むしろ今のプーチン氏の方が危険」と警鐘を鳴らしています。アメリカメディアによりますと、ルビオ氏はプーチン氏の精神状態について政府報告を受けているということです。一方、ホワイトハウスのサキ報道官は2月27日、テレビのインタビューで「(プーチン氏は)コロナ禍で明らかに孤立している」としたうえで、「プーチン氏の言動を深く懸念している」と話しました。ただ、専門家の中には「冷静で抑制的な対応をしている」として、精神不安を前提にプーチン氏に対処すべきではないとも出ています。 *2-4:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220303/k10013510551000.html (NHK 2022年3月3日) ロシア ウクライナに軍事侵攻(3日の動き) ロシアがウクライナに対する軍事侵攻に踏み切って1週間。現地では、今もロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いています。戦闘の状況や、関係各国の外交など、ウクライナ情勢をめぐる3日(日本時間)の動きを随時更新でお伝えします。(日本とウクライナとは7時間、ロシアのモスクワとは6時間の時差があります) ●IPC ロシアパラリンピック委員会とベラルーシの選手出場認めない 国際パラリンピック委員会はロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて、4日開幕する北京パラリンピックにRPC=ロシアパラリンピック委員会と、ロシアと同盟関係にあるベラルーシの選手の出場を一転して認めないことを決めました。 ●ロシアとウクライナ きょうにも交渉か ロシアとウクライナは先月28日に続いて停戦に向けた2回目の交渉の実施を調整してきました。これについてロシアの代表団のトップ、メジンスキー大統領補佐官はウクライナ側との交渉が3日にベラルーシ西部のポーランドとの国境付近で行われると明らかにしました。一方、ウクライナ大統領府の高官も2回目の交渉がまもなく行われるという見通しを示しています。ただロシア側は停戦の条件としてウクライナの「中立化」や「非軍事化」を要求していて、ウクライナ側の立場とは隔たりがあります。ロシアは各地で攻撃を激化させるなど軍事的な圧力を強めながらウクライナとの交渉でも強硬な姿勢を貫くとみられ、停戦につながるかは依然、見通せない情勢です。 ●アメリカ ブリンケン国務長官 ロシア側の交渉姿勢に否定的な見方 3日にも行われる見通しのロシアとウクライナの停戦に向けた2回目の交渉について、アメリカのブリンケン国務長官は2日の記者会見で「問題は、ウクライナが自国の利益を保護し、戦争を終わらせるのに役立つと考えるかどうかであり、われわれは支援の用意がある」と述べました。そのうえで、ロシア側が停戦の条件としてウクライナの「中立化」や「非軍事化」を要求していることを踏まえ、「ロシアの要求は度を越しており、交渉の対象にもならない。われわれはロシアが見せかけの外交を行ってきたことを繰り返し見てきた」と述べ、ロシア側の交渉姿勢に否定的な見方を示しました。 ●アメリカ ロシアとベラルーシに対する経済制裁を発表 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐりアメリカのホワイトハウスは2日、ロシアとベラルーシに対する経済制裁を発表しました。ロシアで軍用機や軍用車両、ミサイルなどを製造している合わせて22の軍事企業を対象にしたほか、石油や天然ガスの生産に使う設備のロシアへの輸出を規制し、主要産業に打撃を与えるとしています。 またロシア軍の侵攻拠点の1つベラルーシに対しては、ハイテク製品の輸出規制を実施し、こうした製品や技術がベラルーシを経由してロシアに流出するのを防ぐとしています。 ●松野官房長官 日本受け入れ 人道的観点で対応も ウクライナから避難した人の日本への受け入れについて、松野官房長官は記者会見で、日本の在留資格を持つおよそ1900人のウクライナ人の親族や知人を想定していると明らかにしたうえで、そのほかの人も人道的観点から対応する考えを示しました。また、松野官房長官は、記者会見で「1日の時点で確認されている在留邦人はおよそ110人であり、現時点までに邦人の生命・身体に被害が及んだとの情報には接していない。松田大使ら大使館員は陸路を使い、一時的にウクライナを出国しモルドバに到着しているが、松田大使は近く、リビウの連絡事務所に戻る予定だ」と説明しました。 ●アメリカ国防総省 ICBMの発射実験延期を発表 ロシアのプーチン大統領が核戦力を念頭に抑止力を特別警戒態勢に引き上げるよう命じたのを受け、アメリカ国防総省は2日、今週予定していたICBM=大陸間弾道ミサイルの発射実験を延期すると発表しました。国防総省のカービー報道官は記者会見で「アメリカとロシアは核兵器の使用が壊滅的な結果をもたらすと長い間、合意してきた。アメリカとして誤解を招くような行動をする意図がないことを示す」と述べ、ロシアとの間で緊張を高めないよう冷静に対応する考えを示しました。一方で「われわれは自国や同盟国などを守る能力は損なわれず、準備ができていることに変わりはない」と述べて、発射実験の延期の影響はないと強調しました。 ●アメリカ国防総省 首都キエフ侵攻のロシア軍 依然停滞の認識 アメリカ国防総省のカービー報道官は2日、記者会見で、ウクライナの首都キエフに向けて南下しているロシア軍の部隊について、「依然として動きは停滞している」と述べ、この一日で大きな進展は見られなかったとの認識を示しました。理由についてカービー報道官は、ロシア軍がウクライナ側からの抵抗に加えて燃料などの物資の不足に直面していると指摘する一方、侵攻の遅れを取り戻すため部隊の再編成を行っている可能性があるとの認識を重ねて示しました。一方で、「ロシア軍は燃料だけでなく、食料の補給にも問題が出るなど複数の過ちを犯してきたが、今は克服しようと取り組んでいる」と述べて、ロシア軍は態勢が整いしだい、キエフへの攻勢を強めるという見方を示しました。またカービー報道官は、ロシア軍は人口の多い主要な都市はいずれも奪えていないとの認識を示しました。このうちロシア国防省が完全に掌握したと発表している南部の都市ヘルソンについては「激しい戦いがまだ続いていると見ている」としたうえで、南部の戦闘の状況について「北部と比べてウクライナ軍の抵抗が少ないようだ」と指摘しました。 ●アメリカ ブリンケン国務長官 ヨーロッパ訪問へ ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続く中、アメリカ国務省は2日、ブリンケン国務長官が3日から8日までの日程で、ヨーロッパなどを訪問すると発表しました。ブリンケン長官は、ベルギーの首都ブリュッセルでNATO=北大西洋条約機構やG7=主要7か国の外相会合などに出席し、ロシアへの追加の経済制裁を含む今後の対応について意見を交わすとしています。5日には、ウクライナの隣国ポーランドでラウ外相と会談し、安全保障面での支援やウクライナから避難してきた人たちへの人道支援などをめぐって協議するということです。その後、同じくウクライナの隣国、旧ソビエトのモルドバでサンドゥ大統領などと会談し、避難民の受け入れなどについて意見を交わすとしています。さらにブリンケン長官はロシアの軍事侵攻に対し懸念を強めるバルト3国のリトアニアとラトビア、エストニアを訪問し、NATOの抑止力の強化やウクライナへの支援などをめぐって協議する予定です。 ●国際刑事裁判所 戦争犯罪や人道に対する罪について捜査始める オランダのハーグにある国際刑事裁判所は2日、ウクライナで行われた疑いのある戦争犯罪や人道に対する罪について、捜査を始めると発表しました。国際刑事裁判所のカーン主任検察官の声明によりますと、フランスやドイツ、イギリスなど裁判所の39の加盟国からウクライナでの状況について捜査するよう要請があり、ウクライナも加盟国ではないもののすでに捜査に同意しているとしています。捜査の対象となるのは、2014年にロシアが一方的にウクライナのクリミア半島を併合した前後の時期から今回の軍事侵攻までの期間で、カーン主任検察官は先に発表した声明の中で「予備的な調査の結果、ウクライナで戦争犯罪や人道に対する罪が行われたと考える合理的な根拠がある」としていました。 ●仏マクロン大統領 停戦に向けた仲介続ける考え フランスのマクロン大統領は2日夜、テレビ演説を行い、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐり、改めてプーチン大統領を非難したうえで「プーチン大統領に武器を捨てるよう説得するため連絡を取り続ける」と述べ、停戦に向けた仲介のためプーチン大統領との連絡を続ける考えを示しました。また「ヨーロッパは平和のために代償を支払うことを受け入れなければならない」と述べ、ヨーロッパ各国がロシアからの天然ガスへの依存度を下げエネルギー自給率を上げていくべきだという考えを示しました。そのうえでマクロン大統領は、今回の事態を受け浮き彫りになったヨーロッパのエネルギー面での課題や安全保障の在り方をめぐり、今月10日からパリ近郊で開かれるEU=ヨーロッパ連合の非公式の首脳会議で議論する考えを示しました。 ●バイデン大統領 国連総会決議棄権の中国とインドを批判 アメリカのバイデン大統領は2日、国連総会の緊急特別会合でロシアを非難し、軍の即時撤退などを求める決議案が賛成多数で採択されたことについて中西部ウィスコンシン州で行った演説の中で、「141か国がロシアを非難した。いくつかの国は棄権した。中国は棄権した。インドも棄権した。彼らは孤立している」と述べ棄権した35か国のうち中国とインドを名指しで批判しました。そのうえで「彼らはNATO=北大西洋条約機構やヨーロッパ、そしてアメリカを分断することができると考えているのだろう。そんなことは誰にもできないと世界全体に示そう」と訴えました。 ●プーチン大統領 インド モディ首相と電話会談 ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアのプーチン大統領は2日、関係強化を進めるインドのモディ首相と電話会談を行いました。ロシアとインドは伝統的な友好国で、軍事的な結び付きも強いことから先月25日に国連安全保障理事会でロシア軍の即時撤退などを求める決議案が採決にかけられた時にはインドは棄権し、ロシアに対する制裁にも慎重な姿勢を示しています。ロシア大統領府によりますと、会談ではウクライナ東部のハリコフで退避できずにいるインド人の留学生たちをロシアを経由して退避させる方策について話し合ったということです。ハリコフで1日、現地の大学に通っていたインド人の医学生が戦闘に巻き込まれて死亡し、インド国内でロシアの軍事侵攻への批判の声が強まることも予想されていたことから、プーチン大統領としては、インドへの配慮を示すことで良好な関係を維持するねらいがあるものとみられます。 ●ロシア報道官 “ロシア軍兵士498人死亡”と発表 ロシア国防省のコナシェンコフ報道官は2日、これまでの軍事作戦でロシア軍の兵士498人が死亡し、1597人が負傷したと発表しました。今回の戦闘でロシア側が自国の兵士の具体的な被害状況を明らかにしたのは初めてです。一方、コナシェンコフ報道官はロシア軍による攻撃でこれまでに2870人以上のウクライナ軍の兵士を殺害したほか、ウクライナ国内の1533の軍事施設などを破壊したとしています。 ●ウクライナ東部ドネツク州 住宅などに大きな被害 ロイター通信は2日、ウクライナ東部ドネツク州の親ロシア派が事実上支配している地域で、双方の戦闘で住宅などに大きな被害が出ていると伝えました。現地の映像では、砲撃で激しく壊れたアパートで地元の人たちが部屋の中に散乱するがれきを撤去する作業などに追われていました。地元に住む男性は「私のことばが責任ある人たちに届くのなら自分の親や子どもが戦火にさらされることがどれだけつらいものか分かってほしいです」と涙ぐみながら話していました。 ●キエフでは多くの市民が地下での避難生活続ける 首都キエフでは、多くの市民が安全を確保しようと地下での避難生活を続けています。2日の現地からの映像ではシェルターとなっている地下鉄の駅構内に多くの人が集まり、毛布にくるまったり、家族で肩を寄せ合ったりしながら不安な様子で過ごしていました。市内に住む女性は「地下には子どももたくさんいてひどい状況です。暴力と残酷な行為が早く終わることを願っています」と話していました。またウクライナ軍の兵士として戦う婚約者がいるという女性は「21世紀にこんなことが起きるなんて誰も想像できませんでした。彼としばらく連絡が取れない時はとても不安ですが、正しいことをしている彼を誇りに思います」と話していました。 ●国連総会の緊急特別会合 ロシア非難決議 賛成多数で採択 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって開かれていた国連総会の緊急特別会合で、ロシアを非難し、軍の即時撤退などを求める決議案が賛成多数で採択されました。決議案には、欧米や日本など合わせて141か国が賛成し、ウクライナ情勢をめぐるロシアの国際的な孤立がいっそう際立つ形となりました。採決は日本時間の3日午前2時前に行われ、賛成が欧米や日本など合わせて141か国、反対がロシアのほかベラルーシや北朝鮮など合わせて5か国で、3分の2以上の賛成を得て採択されました。中国やインドなど合わせて35か国は棄権しました。 ●ウクライナ ゼレンスキー大統領「ロシア軍兵士 約6000人死亡」 ウクライナのゼレンスキー大統領は2日、新たな声明を発表し「ロシアによる軍事侵攻が始まってから6日間で、およそ6000人のロシア軍の兵士が死亡した」と明らかにしました。そのうえで「ロシアはその代償に何を得たというのか。ロケットや爆弾、戦車、いかなる攻撃もウクライナを奪うことはできない」と述べました。また1日に首都キエフの中心部にあるテレビ塔がロシア軍の攻撃を受けたことについて、現場付近は第2次世界大戦中、ナチス・ドイツによって殺害されたユダヤ人を追悼する場所だとしたうえで「ロシア軍は私たちの歴史について何も知らない。ホロコーストの犠牲者を再び殺したのだ」と述べ、非難しました。 *2-5-1:https://mainichi.jp/articles/20220304/k00/00m/030/450000c (毎日新聞 2022/3/4) 原発が戦場 史上初、稼働中に攻撃 世界激震 「安全の根本揺らぐ」 ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナで、今度は原発を舞台にした交戦という前代未聞の出来事があった。一体何が起きているのか。 ●明確な国際法違反、常軌を逸した攻撃 暗闇の中を激しい閃光(せんこう)が飛び交い、煙が立ち上ったーー。攻撃を受けたウクライナ南東部のザポロジエ原発。敷地内の監視カメラが捉えた映像は、インターネットなどを通して世界に広まった。稼働中の原発への軍事侵攻は過去に例がない。国際社会に大きな衝撃を与えた。AFP通信は、ウクライナ軍関係者の話として、火災が起きたのは敷地内の研修施設と研究所だと報じた。ウクライナ政府は国際原子力機関(IAEA)に対し、攻撃を受ける前後の放射線量に大きな変化は見られず、火災による「重要な設備」への影響はないと報告した。ウクライナの原子力規制当局は、同原発がロシア軍に制圧されたことを認めた。出力100万キロワットの原子炉を6基抱えるザポロジエ原発は、総出力で欧州最大規模の原発だ。このうち1~5号機は旧ソ連時代の1985年から89年にかけて営業運転を開始した。攻撃時には、検査などのため1基のみが運転中だった。ウクライナ政府は、クリミア半島から進撃する南部戦線のロシア軍が、同原発の制圧を目指しているとして危機感を強めていた。2日には原発の職員や周辺住民ら数百人が、原発に通じる道路を封鎖するバリケードを築いて侵攻に備えた。しかし、ロシア軍はこれを破って敷地に侵攻したとされる。原発への軍事攻撃は、ロシアも批准するジュネーブ条約で禁じられている。原子力の平和利用を目的にしたIAEA憲章にも反する。核問題に詳しい長崎大の鈴木達治郎教授は、「明確な国際法違反であり、ロシア軍は直ちに攻撃をやめるべきだ。システムの故障や電源喪失が起きれば、破滅的な過酷事故につながりかねない。これが許されるならば、世界中の原発が攻撃されることになり、原子力安全を巡る根本が揺らぐ」と危惧する。ウクライナのクレバ外相は4日、ツイッターで「もし爆発すれば、チェルノブイリ(原発事故)の10倍以上になる」と危機感をあらわにした。福島大環境放射能研究所の難波謙二所長は、この見方を「決して的外れではない」と指摘する。「(事故が起きれば)放射性物質による汚染はウクライナの国境を軽く越えて欧州全土や中東にまで広がる恐れがある。原発を占拠してしまえば、脅しや交渉の材料として使えるということが分かってしまった」。ロシア軍は2月24日には、86年に史上最悪の爆発事故を起こしたウクライナ北部のチェルノブイリ原発を占拠した。米ホワイトハウスなどによると、露軍は同原発で事故処理を続けていた職員らを人質に取っているとされる。IAEAはウクライナ政府の報告として、原発にとどまる職員らが「心理的重圧と精神的疲労」に直面しているとし、ロシア側に「重要業務を安全かつ確実に遂行できるよう休養と交代を認める必要がある」と警告した。IAEAによると、2020年時点でウクライナの電源構成の5割近くを原子力が占める。国内ではザポロジエを含む4カ所に15基の原子炉がある。ロシア軍の侵攻に備えて原子炉を停止すれば、全土の電力供給に支障が出る懸念もある。また停止した原子炉でも、外部電源を失って核燃料を冷やせなくなれば、東京電力福島第1原発事故のような炉心溶融(メルトダウン)が起きる。今後の判断は容易ではない。鈴木さんは、「ロシアのやっていることは常軌を逸している。今後何が起きるか分からない。今すぐできることは少ないが、ロシアに対して原発への攻撃をやめさせ、せめて施設の安全性確保に全力を尽くすことを保証させるしかない」と話した。 ●私兵組織、露軍の統制利かず? 砲撃のあったザポロジエ原発1号機は数日前から定期点検に入っていたが、同原発の広報担当者はウクライナのウニアン通信に対し、「核燃料はまだ原子炉内に入ったままで、取り出されていない。使用済み核燃料などを入れるプールもある」と話した。同原発の職員は、攻撃をしているのは「カディロフツィ」と呼ばれるロシア南部チェチェン共和国のカディロフ首長の私兵組織との認識を示し、「彼らは地雷を敷設しようとしている。全欧州を脅すつもりだ」と話したという。カディロフ氏の私兵組織はウクライナの首都キエフへの攻撃にも加わっているとみられ、ロシア軍の統制が十分に利いていない可能性もある。ロシア国防省のコナシェンコフ報道官は4日、「ウクライナの破壊工作グループ」が原発構内に侵入し、「恐ろしい挑発行為を試みた」と主張。警戒に当たっていたロシアの治安部隊と銃撃戦となった後、原発の訓練施設に潜んでいたこのグループが「撤収する際に放火した」と述べ、原発の火災はウクライナ側に責任があると訴えた。ロシアとウクライナの間では3日に2回目の停戦協議も開かれたが、ウクライナの非武装化や事実上の政権交代などを求めるプーチン露大統領は3日のマクロン仏大統領との電話協議で、「特別軍事作戦の任務は何があろうと達成する」と強硬姿勢を崩さなかった。停戦協議を長引かせるようなら「ウクライナにさらに追加の要求をする」と迫っている。2日にウクライナ南部の要衝ヘルソンを制圧したと発表したロシア軍は、黒海沿岸のオデッサ方面に向かうほか、ザポロジエ原発のあるドニエプル川沿いを北上し、ウクライナ中心部へも兵を進めている。ウクライナ国内の主要都市や重要インフラの制圧を進めることで、徹底抗戦を呼びかけるウクライナのゼレンスキー政権との停戦協議を有利に進める狙いもあるとみられる。 ●日本の原発 「軍事攻撃は想定外」 国内の原発は、東京電力福島第1原発事故を踏まえて安全対策が強化された。その一つが、テロ対策施設の設置の義務化だ。航空機の衝突などによるテロで原子炉建屋などが損傷した場合でも、放射性物質の周囲への拡散を防ぐ。しかし、原子力規制委員会の事務局を担う原子力規制庁の幹部は「軍隊による武力攻撃は想定していない」と話す。テロ対策施設は、原子炉を遠隔で制御するための「緊急時制御室」や、炉心を冷やすための「注水設備」、それらを動かすための「電源設備」などを備える。原子炉から十分に離れた所に設置できない場合、航空機を衝突させるテロ攻撃にも耐えられる頑丈さが必要になる。テロにより原子炉建屋などが損傷した場合、テロ対策施設からの遠隔操作や敷地内に配備した送水車による注水などで、原子炉格納容器を冷やして炉心溶融(メルトダウン)させないようにする。各原発のこうした施設はテロ対策の観点から、具体的な位置や設備の内容などは明らかにされていない。規制委の安全審査も非公開で実施されている。ただ、テロと軍事攻撃では被害の状況などが大きく異なる。「テロ対策施設にミサイルが撃ち込まれたら、多分だめだと思う。他国の軍隊が攻めてくるのは想定外だ」。規制庁の幹部はそう明かした。規制庁によると、テロ対策施設は現在、九州電力川内(せんだい)原発(鹿児島県)と関西電力高浜原発(3、4号機、福井県)、四国電力伊方原発(愛媛県)の計3カ所に設置されている。高浜原発(1、2号機)など4カ所では建設中だ。安全対策などの工事計画が認可されてから5年以内の設置が義務付けられており、期限内の完成が間に合わなければ、再稼働後でも運転を停止しなければならない。関西電力美浜原発3号機(福井県)などでは期限に間に合わず、運転を止めた。 *2-5-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/163720 (東京新聞 2022年3月4日) 原発に攻撃、日本の備えは…「ミサイルで全壊、想定していない」 テロ対策施設の未完成、再稼働した5基も ロシア軍によるウクライナ最大のザポロジエ原発への攻撃。日本の原発は2011年3月の東京電力福島第一原発事故以降、地震津波対策は厳しくなったが、大規模な武力攻撃を受けることは想定外だ。航空機衝突などテロ対策で義務付けられた設備は、再稼働した原発の一部でしか完成しておらず、外部からの脅威に弱い。「武力攻撃に対する規制要求はしていない」。政府が次の原子力規制委員長の候補とした山中伸介規制委員は4日、参院の議院運営委員会で原発が戦争に巻き込まれた際の対策を問われ、答えた。規制委事務局で原発の事故対策を審査する担当者も取材に、「ミサイル攻撃などで原子炉建屋が全壊するような事態は想定していない」と説明した。原子炉は分厚い鉄筋コンクリートの建屋にあり、炉も厚さ20センチの鋼鉄製だ。どの程度の攻撃に耐えられるかは、規制委も電力各社も非公表。しかし炉が難を逃れても外部電源を失えば、原発停止後に核燃料を冷やせず、福島第一原発のようにメルトダウン(炉心溶融)に至るリスクを抱える。航空機衝突などで中央制御室が使えなくなった場合は、テロ対策として秘匿された構内の別の場所に設置する「特定重大事故等対処施設(特重)」で炉内の冷却などを続ける。ただ再稼働済みの10基のうち、特重があるのは5基。5基は特重が未完成のまま稼働している。廃炉中を含め全国18原発57基の警備は電力会社、警備会社、機関銃などで武装した警察、海上保安庁が担う。自衛隊が配備されるのは「有事」となってからだ。 ◆国会で何度も質問も、政府「一概に答えられない」 日本国内の原発への「軍事攻撃」に対する危険性は過去の国会で何度も取り上げられたが、政府側は言葉を濁してきた。2015年の参院特別委員会で、参院議員だった山本太郎氏(現れいわ新選組代表)は、原発がミサイル攻撃に備えているか質問。原子力規制委員会は「(電力会社に)弾道ミサイルが直撃した場合の対策は求めていない」と説明。当時の安倍晋三首相は「武力攻撃は手段、規模、パターンが異なり、一概に答えることは難しい」とかわした。民進党(当時)の長妻昭氏は17年の衆院予算委で、原発がミサイル攻撃を受ければ事故以上に被害が大きくなり「核ミサイルが着弾したような効果を狙える」と指摘し、対応を質問。規制委は「そもそもミサイル攻撃は国家間の武力紛争に伴って行われるもので、原子力規制による対応は想定していない」と答えた。同年の参院審議でも、自民党の青山繁晴氏がミサイル攻撃があった場合の避難想定の不十分さを指摘。「地域住民の不安、社会的混乱もすさまじいと思われる」と対策を求めたが、政府側は「武力攻撃による被害は一概に答えられない」としていた。 *2-6:https://mainichi.jp/articles/20220305/k00/00m/030/257000c (毎日新聞 2022/3/5) 中国の国防費3年ぶり伸び率 李克強首相「祖国統一を後押し」 中国政府が5日に公表した2022年の国防費予算(中央政府分)は、前年比7・1%増の1兆4504億5000万元(約26兆3500億円)で、伸び率は21年予算(前年比6・8%)を上回った。国防費の伸び率が前年比で7%を超えたのは19年以来、3年ぶり。国防費予算の伸び率7・1%は、経済の成長率目標の5・5%よりも高かった。中国は35年に人民解放軍の現代化をほぼ実現し、今世紀半ばに「世界一流の軍隊」にするとの目標を掲げている。ここ数年は、成長率目標より国防費予算の伸び率を高く設定する傾向が続いている。李克強首相は5日に開幕した全国人民代表大会(全人代)の政府活動報告で「武器や装備の現代的な管理システムをうちたて、国防科学技術のイノベーションを強化し、新時代の人材強化戦略を実施して、軍の質の高い発展を推進する」と強調。先進的な兵器・システムの研究開発などにより一層、力を入れる姿勢を示した。中国は極超音速滑空体(HGV)を搭載できる新型弾道ミサイル「東風17」などの先端兵器の配備を進めている。李氏はまた「祖国統一を後押ししなければならない」と述べ、改めて台湾統一に意欲を示した。中国は近年、台湾の防空識別圏(ADIZ)に戦闘機を繰り返し進入させるなど、台湾海峡周辺での軍事的な活動を強化している。ロシアによるウクライナ侵攻を受け、台湾では一部で中国による軍事的な圧力がさらに強まることへの懸念が出ている。ただ、国際社会がロシアへの非難を強める中で、中国政府はウクライナ侵攻と台湾問題を関連付けられることには一貫して反発している。今秋に共産党大会を控え、中国は国内外の安定を重視する。このため多くの専門家は、中国が台湾問題で極端な行動に出る可能性は低いとみている。 <日本のエネルギー> *3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220301&ng=DGKKZO58649540R00C22A3MM8000 (日経新聞 2022.3.1) ウクライナ侵攻 危機の世界秩序(4)エネ安保、不作為に警告 原油価格が米市場で7年7カ月ぶりに1バレル100ドルを超えた。未曽有の高値圏にある欧州の天然ガス価格も急騰した。 ●力そがれる不安 ウクライナ侵攻があらわにしたのは、エネルギー供給におけるロシアの存在感と同国に依存するリスクだった。天然ガス生産量は世界2位、石油は3位。国際決済網からのロシアの排除により、さらに高騰するのではないかと世界は身構えている。ロシアは脱炭素が進み、歳入の4~5割を占める石油・ガス収入を失えば、軍事強国の地位も危うくなる。一方、今なら石油とガスの需給は逼迫している。世界の開発投資が急減したからだ。ロシアにエネルギーを頼る欧州は強く出られないのではないか。そうした自信がプーチン大統領を侵攻へと動かした。世界はエネルギー過渡期の弱さを露呈した。2日に開かれる産油国の「石油輸出国機構(OPEC)プラス」閣僚協議。消費国は増産加速を期待するが、主導権を握るロシアが同意するとは考えにくい。原油価格は1バレル130ドルを超えるとの見方も出てきた。今回の行動が、欧州に「ならず者国家に頼って大丈夫か」との恐怖を想起させるのは当然だ。ジョンソン英首相は「石油やガスのロシア依存を集団的にやめなければならない」と語った。プーチン体制と欧州の関係が侵攻前に戻ることはあるまい。脱炭素に傾斜する市場や投資家がロシアの石油・ガス排除を求める圧力は強まり、ロシアは自らの首を絞めることになるだろう。消費国は脱炭素とエネルギー安全保障の両立を探らなければならない。脱原子力発電を掲げたドイツは、天然ガスのロシア依存を深めていた。2014年にロシアのクリミア併合という国際秩序を無視した行為を見ながら、同年から20年までにロシアからの輸入量を46%も増やしていた。フランスは原発への回帰に踏み出した。欧州連合(EU)も原発を環境に貢献するエネルギーと位置付けた。アジアも例外ではいられない。この冬、米国からアジアに向かった液化天然ガス(LNG)船が相次いで欧州に進路を変えた。需給の逼迫した欧州での価格がアジアを上回るという、前例のない事態が出現したからだ。 ●東アジアも火種 「米欧アジアのガス市場は一体化した」。JERAグローバルマーケッツの葛西和範最高経営責任者(CEO)は指摘する。欧州の危機は瞬時にアジアに波及する。日本は再生可能エネルギーの導入が遅れ、原発の再稼働は進んでいない。ロシアの侵攻によって、石油やLNGに頼る脆弱さを改めてつきつけられた。東アジアも台湾などを巡って紛争の火種を抱えている。エネルギーのほとんどを海上輸送で輸入する日本に思考停止は許されない。危機が起きてからでは遅い。ロシアの暴挙はエネルギー安保の不作為に対する警告だ。 *3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220226&ng=DGKKZO80495320V20C22A2EA3000 (日経新聞 2022.2.26) ガソリン補助、5倍の25円に、ロシアの軍事侵攻で高騰警戒、措置長引く可能性 政府は3月からガソリン価格抑制のため石油元売りに配る補助金の上限を1リットルあたり25円に引き上げる方針だ。現行の5円の5倍になる。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けた原油価格の高騰に対応する。来週に詳細を発表する見通し。原油高が続けば措置が長引く可能性がある。岸田文雄首相は25日の参院予算委員会で「まず当面は今の激変緩和措置の拡充で対応したい」と述べた。ガソリン税を引き下げる「トリガー条項」の凍結解除については引き続き検討する考えを示した。「将来的にはさらなる原油高騰もありうるので、あらゆる選択肢を排除せず準備を進めたい」と語った。国民民主党の玉木雄一郎代表は2022年度予算案に賛成した理由として、トリガー条項を排除しない方針を示した首相答弁をあげている。補助金は毎週公表するガソリンの全国平均価格が基準に達したら元売りに支給して卸値の抑制に充てる仕組みをとる。ガソリン、軽油、灯油、重油の4種類が対象になる。支給額は発動開始から3週間目で現行の上限の5円に達した。2月21日時点のガソリン価格は172円。当初想定した170円に抑えられなくなった。野党が主張するトリガー条項を発動した場合の減税額は25.1円で、補助金の支給上限を25円に引き上げればほぼ同水準になる。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は24日に始まった。同日のニューヨーク市場のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物は一時、1バレル100ドル台に上昇した。1バレル100ドルは日本でのガソリン価格で1リットル180円台前半の水準に当たる。補助金の上限が25円になれば170円程度にまで抑えられる。現在は基準額を4週ごとに1円ずつ切り上げている。24日から基準額は170円から171円に改めた。今回の補助金の拡充にあわせ、切り上げを倍のペースに早める。3月に拡充すれば夏には180円を超える。3月中はエネルギー対策特別会計の剰余金を使うほか、一般会計の予備費から数千億円を支出する。5円の補助を1カ月続けると500億円程度、25円の補助を1カ月続けると2500億円ほどが必要になる。 *3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220226&ng=DGKKZO80495350V20C22A2EA3000 (日経新聞 2022.2.26) ばらまき色、一段と濃く ガソリン補助金はもともと2022年3月までの「時限的・緊急避難的な激変緩和措置」だった。日本政府にとってウクライナ情勢の悪化は想定外だったとはいえ、大幅な拡充で当初目的が揺らぐ。所管する経済産業省には「延長後、いつ終えるか明確に示すのは難しい」との声が目立つ。ばらまき色が一段と濃くなってきた。ガソリンや軽油の価格が上がれば物流コストはかさみ、寒冷地で灯油は生活必需品だ。ウクライナの動向次第ではさらなる急騰も懸念されるが、それでもレジャー目的の乗用車のガソリン代まで税金で補助する意義は乏しい。「ガソリンに補助金を出す先進国なんて日本ぐらいだ」。制度設計にあたった経産省の内部からもこんな声が漏れる。21年秋の第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)の成果文書は「化石燃料に対する非効率な補助金の段階廃止に向け努力する」と盛り込んだ。日本も同意した経緯があり、国際社会からの視線は一層厳しくなる。どのように制度を終えるかという道筋を巡っては、仮に3月末で終了すると4月から各地で一斉に5円値上げする事態が想定されてきた。駆け込みで購入する人が押し寄せれば給油所の混乱につながる。政府は延長にあたり、補助を出す基準額を引き上げるペースを速める方針だ。支給額が徐々に減れば給油所の混乱を避けられるというのが経産省の見立てだが、想定より原油が高ければ補助は続く。期限が不明確という粗い制度で価格への公的介入を続けても「賢い支出」にはならない。 <気候危機とシベリア> *4-1:https://digital.asahi.com/articles/ASPDH2R7RPDHUHBI00H.html (朝日新聞 2021年12月15日) シベリアで気温38度を記録 北極圏の観測史上、最高と認定 国連 国連の専門機関、世界気象機関(WMO)は14日、昨年6月にロシアのシベリアで記録された気温38度が北極圏での観測史上最高の気温だったと認定し、気候変動について改めて警鐘を鳴らす記録と位置づけた。AP通信が同日伝えた。WMOが「北極圏よりも地中海にふさわしい」とする気温は昨年6月20日、ロシア東部の町ベルホヤンスクで観測された。WMOによると、当時はシベリア一帯から北極圏まで広がる熱波が到来中だった。これにより、シベリアの北極圏の平均気温は通常よりも10度上がり、地球規模での気温上昇や山火事、海氷の喪失につながったという。WMOのペッテリ・ターラス事務局長は声明で「この新たな記録は私たちの抱える気候の変化(の問題)について警鐘を鳴らしている」と述べた。 *4-2::https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220301&ng=DGKKZO58648050Y2A220C2EP0000 (日経新聞 2022.3.1) 温暖化、元に戻らぬ恐れ IPCC報告書の要旨 湿地や山岳、適応限界に A.イントロダクション 本報告書は気候、生物の多様性を含む生態系、人間社会の相互作用に着目している。これまでのIPCC評価よりも、自然科学や生態学、社会科学、経済学の知識を統合した。 生物多様性の損失や天然資源の持続的でない消費、急速な都市化などが世界で同時に進行していることを前提に、気候変動に適応するための対策や気候変動の影響・リスクを分析した。 B.観測された影響および予測されるリスク 気候変動による影響とリスクは損害、被害、経済的・非経済的損失の観点から示されている。リスクは短期(2021-40年)、中期(41-60年)、長期(81-2100年)で各温暖化の水準などを予測している。 (1)気候変動による影響の観測 人為起源の気候変動は異常気象の頻度と強度を増し、自然と人間に対し広範囲にわたる悪影響と損失や損害を自然の気候変動の範囲を超えて引き起こしている。最も脆弱な地域とシステムが不均衡に影響を受けている。小さな島国では避難を余儀なくされ、アフリカと中南米では洪水や干ばつに関連して食糧不安と栄養不良が増加している。自然と人間のシステムはその適応能力を超えた圧力を受け、不可逆的な影響をもたらしている。 (2)生態系と人間の脆弱性 気候変動に対する生態系、人間の脆弱性は地域などにより大幅に異なる。社会経済の発展の形態、持続可能でない海洋や土地の利用、ガバナンスなどによって引き起こされる。およそ33億~36億人が気候変動に対して非常に脆弱な状況で生活している。生物種の大部分は気候変動に対して脆弱だ。人間と生態系の脆弱性は相互に依存しており、人間による生態系の劣化や破壊は人間の脆弱性を高める。現在の持続可能でない開発のあり方によって生態系と人々はますます気候災害の危険性にさらされている。 (3)短期的なリスク 近い将来、地球温暖化のレベルは1.5度に達する。複数の気候災害は不可避的に増加し、生態系と人間に複数のリスクをもたらす。リスクの度合いは脆弱性、暴露、社会経済の発展水準などの同時期の短期的傾向に依存する。地球温暖化を1.5度付近に抑えるような短期的な対策は、より高い水準の温暖化に比べて人間と生態系に対する損失と損害を大幅に低減できるが、完全になくすことはできない。 (4)中長期的なリスク 40年より先、地球温暖化の水準に応じて気候変動は自然と人間のシステムにおびただしいリスクをもたらす。特定した127の主要なリスクの中長期的な影響は、現在観測されている影響に比べて最大で数倍になる。気候変動の規模と速度、それによるリスクは短期的な緩和策や適応策に強く依存する。気候変動の悪影響やそれに関連する損失、損害は温暖化が進展するにつれて拡大する。地球温暖化の進展は生物多様性損失のリスクを高める。雪解け水や地下水の利用可能性も脅かす。食糧不安はより深刻になり、サハラ以南のアフリカ、アジア、中南米、小さな島に集中して栄養失調などを引き起こす。 (5)複合、混合、連鎖的リスク 気候変動の影響とリスクはますます複雑化し、管理が難しくなっている。複数の気候災害の同時発生、リスクが相互作用して全体のリスクが結びつき、部門や地域を横断して連鎖的にリスクが生じる。気候変動への対応の中には新たな影響やリスクをもたらすものもある。 (6)一時的なオーバーシュートの影響 地球温暖化が今後数十年以内、あるいはそれ以降に一時的に1.5度を超える場合(オーバーシュート)、多くの人間と自然のシステムはさらなる深刻なリスクに直面する。その規模と期間に応じ、さらなる温室効果ガスの排出を引き起こし、温暖化を低減したとしても元に戻すことができなくなる。今世紀中に1.5度を超える温暖化が起きた場合、氷床や氷河の融解、加速する海面上昇によって特定の生態系、インフラ、低地の沿岸集落などに回復不可能な影響をもたらす。 C.適応策と可能にする条件 現在の気候変動に対する適応は主に既存システムの調整によってリスクと脆弱性を減らすというもの。多くの適応策が存在し利用されているが、実行はガバナンスと意思決定プロセスの能力と有効性に依存している。 (1)現在の適応とその効果 適応策の計画と実施はすべての部門と地域にわたって見られ、複数の便益を生み出している。少なくとも170の国と地域が適応策を気候政策と計画のプロセスに盛り込んだ。 しかし適応の進展は不均衡でギャップがある。多くの取り組みでは即時、短期的な気候リスクの低減を優先しており、そのため変革的な適応の機会を減らしている。今後10年間での長期的な計画と迅速な実施が必要だ。 (2)今後の適応策と実現可能性 人と自然に対するリスクを低減できる、実現可能で効果的な適応の選択肢がある。適応策の短期的な実行可能性は部門や地域によって差がある。気候リスクに対する適応策の有効性は特定の状況、部門、地域について文献に記載されており、温暖化が進むと効果が低下する。 (3)適応の限界 人間の適応にはソフトな限界に達しているものもあるが、財政面、ガバナンス、制度面、政策面などの様々な制約に対処することで克服できる。沿岸湿地、熱帯雨林、極域と山岳の生態系など、一部の生態系はハードな適応限界に達している。地球温暖化が進展すれば損失と損害は増加し、さらに多くの人間と自然のシステムが限界に達する。 (4)適応の失敗の回避 第5次評価報告書以降、多くの部門、地域で適応に失敗した証拠が増加している。気候変動への適応の失敗は脆弱性やリスクの固定化を引き起こす。その変更は困難で費用がかかり、既存の不平等を悪化させる可能性がある。多くの部門やシステムに便益がある適応策を柔軟、部門横断的に長期に計画し、実施することで適応の失敗は回避できる。 (5)可能にする条件 人間システムと生態系において適応の実施、加速、維持を可能とするには重要な条件がある。政治的コミットメントとその遂行、制度的枠組み、影響と解決策に関する知識、財源の確保、モニタリングと評価、ガバナンスなどがそれにあたる。 (注)適応とは、被害の低減や有効活用のために、気候変動やその影響に適応するプロセスと定義。人間の介入で促進できる。その限界とは行動をとっても防げなくなることを指す。 D.気候変動に強いレジリエントな開発 (1)条件 第5次評価報告書での以前の評価に比べてさらに緊急性が高まっている。 (2) 気候変動にレジリエントな開発は、国際協力や、すべてのレベルの行政機関が教育機関や投資家、企業と協業することで促進される。それを可能にするには政治的な指導力、制度、ファイナンスを含む資源などによって支援されると最も効果的だ。 (3) 世界的な都市化の傾向は、短期的に気候にレジリエントな開発を進めるうえで重要な機会となる。都市での開発は、都市周辺の地域の製品やサービスなどのサプライチェーン(供給網)や資金の流れを維持し、都市化がそれほど進んでいない地域の適応能力も支える。 (4) 生物多様性や生態系の保護は、気候にレジリエントな開発に必須だ。最近の分析だと、地球規模での生物多様性などの維持は現在の地球の陸域、淡水、海洋の約30~50%の保全に依存すると示唆している。 (5) 気候変動が人間や自然のシステムを破壊していることは明白だ。過去から現在に至るまで、世界的な気候変動にレジリエントな開発は進まなかった。今後10年間の社会の選択と行動で将来の開発がどの程度レジリエントになるか決まる。現在の温室効果ガス排出量が急速に減少しない場合、特に地球温暖化が1.5度を超えた場合、実現の見込みはより低くなる。 <日本の非人道性> *5-1:https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20210719/pol/00m/010/002000c (毎日新聞 2021年7月20日) 感染症対策の基礎「検査」を忘れたデータなきコロナ対策、阿部知子・衆院議員 感染症はなによりもまず検査が重要だ。検査、隔離、診断、治療、この4層体制が最初からつながっていないことが日本の新型コロナウイルス対応の最大の失敗だ。 ●無症状者をふまえた検査体制がない ダイヤモンド・プリンセス号の問題で、陽性になっても全く症状が出ない人が一定程度いることが明らかになった。インフルエンザなどで経験してきたこれまでの常識を変えるものだった。ところが、無症状者の存在をふまえた検査体制はその後も全く取られなかった。医療には「エビデンス・ベースド・メディスン」という言葉がある。証拠(データ)に基づいた医療という意味だ。ところが現在の政府のコロナ対策には、基礎となるデータが全く不十分だ。無症状者の把握も含めた広範な社会的検査をすることではじめて、対策の基礎となるデータが得られる。緊急事態宣言などで人の行動を縛ることにばかり意識が向き、感染症を扱う基礎が作られなかった。緊急事態宣言からワクチン接種にいたるまで、現状を把握する検査、つまりデータが無いままに政策を組み立てているため、感染が拡大するまで方針を決められない。対策を取っても、国民に理由を説明できず、国民と対話ができない。だからすべて後手後手になり、混乱する。 ●感染症の研究体制がない なぜこうなっているのか。日本の公衆衛生は、明治時代の結核に対する隔離政策から始まった。戦後になって結核が減り、一方でハンセン病のように、医学上は不要なのに社会的に排除するために隔離した負の歴史があり、感染症の政策が空白になっていた部分がある。感染症はもう来ない、という前提のもとに1980年代末ごろから、感染症の病床は急激に削減された。そしてほとんどの大学で感染症が研究の中心から外れていく。日本で検査数が少ないのは、感染症に対しては検査が基本であるという基礎が忘れられてしまったからだ。感染症対策を立案するためには、もろもろの検査のデータを研究と結びつけなければならない。しかし、今の大学は必ずしもその役割を果たせていない。感染症は一般診療の問題とされ、研究のなかに占める割合が非常に小さくなっている。大学が新興・再興感染症の問題を研究する体制を再構築しなければならない。 ●水際の検疫に問題 水際の検疫にも問題がある。検査で陰性になれば隔離もされずそのまま市中に入る。しかし検査は完璧ではない。変異株の侵入を防ぐためには、陰性であっても一定期間、留め置くべきだ。また、現在、水際の検疫は抗原定量検査によって行っているが、変異株かどうかが迅速に分からない欠陥がある。PCR検査の利点は、遺伝子解析ができることであって、変異株が早く判明する。変異株対策についてはPCR検査で遺伝子的な特性を把握することが重要だ。そのうえで抗体検査も進め、遺伝子タイプによってワクチンの効果にどのような違いがあるかなども把握していく。これらによってはじめて、変異株を含めた感染の先行きを見通すことができる。また、最近は下水のコロナ検査も進んでおり、変異株も含めて地域的対応も可能となっている。 ●伴走しない政治 私は小児科医なので、特に強く感じるが、医師と患者の情報格差は非常に大きい。さらに政治が関わると裏付けになる情報はすべて政府が持っているにもかかわらず、国民に説明をしないことが起きる。 日本のコロナ対策の最大の問題点は、リテラシー(情報を入手、理解、評価して適切に意思決定できる力)が欠けていることだ。上から命令するばかりで「何が起きているから、どうしなければならず、だからどのように協力してほしい、行動してほしい」ということがない。以前は医療も、「医者の言うことを聞け」だった。しかし今は、医師は専門家であると同時に、患者と一緒に伴走することが大事だと変わってきている。しかし、政治はいまだに相変わらず、情報の差を利用して国民に言うことを聞かせようとしている。 ●自分で判断を 背後に命に関わる恐怖感があるだけに、このことには特に注意しなければならない。自分の健康に関わるため、かえって、しっかり考える前に流されてしまう。ワクチン接種について言えば、東京オリンピック・パラリンピックが開催されるから、あるいは集団免疫を作るため、みんなのため、さらに言えば国家のために接種しなければならないと思いがちだ。しかし、接種の判断は自分のために、自分でしてほしい。健康はその人にとって、最大、最高の主権だ。自分の命、自分の体のことは、可能な限り自分で理解したうえで決めてほしい。 *5-2:https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20220222/pol/00m/010/010000c (毎日新聞 2022年2月24日) 医療産業で二流三流になりつつある日本、吉田統彦・衆院議員 コロナ禍で日本の医療体制に余裕がないことが国民にもよく理解されたと思う。私も提案したコロナ診療の診療報酬の引き上げは重要なことだ。しかし診療報酬の引き上げは患者負担につながる。それだけでは日本の医療を守ることはできない。 ●ネックになるのは人材 大切なのは人材面だ。日本の頭脳が海外に流出する流れを変えていかなければならない。一度海外に出た日本人がまた戻ってくる「ブレーンサーキュレーション」(頭脳循環)が大切だ。先日、世界のがん治療でトップに立つテキサス大学MDアンダーソンがんセンターの日本人教授と話をした。日本に帰って働きたい気持ちはある、収入は減ってもいいと言う。しかしあまりにも減るようでは日本には行けない、年収5000万円なら、と言う。しかし、今の仕組みでは日本の政府や公的研究機関では5000万円の報酬で彼を招聘(しょうへい)することはできない。優秀な研究者を巨額の資金をかけてでも国籍を問わず海外から集め、短期間ではなく一定期間、日本で研究してもらう必要がある。これは国が真剣に取り組まないとできることではない。もう一つは日本の大学の構造的な問題がある。私が在籍していた米ジョンズ・ホプキンズ大学では、内科や外科など臨床系の教室でも、主任教授の下に複数の教授が存在し、もちろん医師の教授もいるが、医師免許を持たない研究者の教授もいる。ところが日本の大学教授は医療もやりながら基礎研究もする。スーパーマンだけれども、限界がきている。日本の医療が基礎研究で海外の後塵(こうじん)を拝している理由はここにある。 ●国立感染研は抜本的改革が必要 国立感染症研究所は、疫学調査や検査をやることも大事だ。しかし国立の研究機関に国民が期待している役割は、やはりワクチン開発や治療方法の確立ではないか。今回のコロナ禍ではそこまでの力は全然なかった。国民の危機を守ることができるナショナルセンターに生まれ変わらせるべきだ。これは国の安全保障の問題だ。ここでも人材の問題がある。定員を増やすだけではだめだ。ワクチンの開発ができるような技術があり、さらに開発チームの指揮をとって完成させることができる人材が必要だ。感染研はそうした人材を雇える態勢にない。発想の転換が必要だ。よく例にあげられる米国の疾病対策センター(CDC)には、政府の委託委員会で、CDCにワクチンに関する意見具申をするACIP(ワクチン接種に関する諮問委員会)がある。民主党政権時代に構想があったが、このような組織も必要だ。 ●日本の医療産業のプレゼンス 国民はなぜコロナの国産ワクチンがこれほど遅れたのかと疑問に思っている。根本的な問題は、医薬品、医療機器産業における日本のプレゼンスの低下にある。たとえばペースメーカーの国産品はない。診断用の機器は、胃カメラで使う内視鏡など分野によっては日本のシェアが高いものがある。しかし、治療用の医療機器は本当に世界から遅れている。なぜこんなことになるのか。金属製ではない画期的な「溶ける」(生体吸収性)ステント(血管などを内側から広げる器具)を京都医療設計という京都の会社が開発した。これが日本より先にドイツで承認され、販売された。象徴的だが、技術はあるのに、日本では生産できない、販売できないという状況がずっとあった。これが日本の医薬品、医療機器の開発能力が落ちた理由だ。ワクチン開発についても「もうすでに時遅し」になりつつあるのかもしれないが、そうは言いたくない。産官学が一体になって医薬品、医療機器産業を盛り上げていかないと本当に手遅れになる。日本の医療は技術としては一流だ。しかし、医薬品や医療機器の産業としてはもう二流三流になっている。 ●遺伝子医療で「遅れる」リスク 自公政権は患者の窓口負担割合を増やして医療費を浮かそうとしている。しかし、遺伝子医療にかんしては非常に高額な薬が出てきている。脊髄(せきずい)性筋萎縮症(SMA)の遺伝子治療薬「ゾルゲンスマ」の薬価は1患者あたり1億円を超えた。しかし遺伝子治療は大学や公的研究機関で完結することが可能な分野でもある。自分たちで作って、自分たちの医療機関で使えば、高品質なものが相当、安価で使える可能性がある。そうしたことを認めなければ、どんどん遅れていく。これからの遺伝子医療については、遅れると結局、国民負担がますます増えていく。そしてそれを保険で見ていくと医療財政が破綻する。これは非常に大きなリスクだ。 *5-3:https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20220210/pol/00m/010/003000c (毎日新聞 2022年2月14日) 「問答無用」で扶養照会を強行した杉並区 誤った制度の運用はいつになれば根絶されるのか、稲葉剛・立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授 ●「どうしてもやる」 「扶養照会はどうしてもやらなくてはならない。やるのは違法じゃない。ただでお金もらっているわけじゃないんだから」。昨年7月、失職して生活に困窮したAさん(50代男性)は、住まいのある東京都杉並区で生活保護を申請した。地方に暮らす80代の両親に心配をかけたくないと考えたAさんは、区に扶養照会(福祉事務所が親族に援助の可否を問い合わせること)を実施しないことを書面で求める申出書を事前に用意して、申請時に提出しようとしたが、対応した複数の職員は書面の受け取りをかたくなに拒否したという。「申出書をひっこめないと保護申請の手続きは進められない」とまで言われたAさんは、書面の提出を諦めざるをえなかった。生活保護が決定した後も、Aさんは担当となったケースワーカーに、親族に連絡をしないでほしいと口頭で伝えたが、それに対しての返答は冒頭に書いた言葉であった。Aさんが抗議すると、担当者は「ただでお金もらっているわけじゃない」という部分については謝罪したが、後日、親族への照会はAさんの意向を押し切る形で強行されてしまった。 ●親族への連絡を恐れ申請をためらう 生活困窮者支援の現場では、扶養照会が生活保護利用にあたっての最大のハードルとなっていることが問題視されてきた。路上生活者支援の夜回りの活動では、80代以上の高齢者に出会うことも珍しくないが、その中には親族に連絡が行くことを怖れて生活保護の申請をためらっている人が少なくない。 せめて、本人の意向を無視して「問答無用」で役所が親族に連絡をしてしまうことを止められないか。そう考えた私たち支援関係者は、昨年、扶養照会の運用改善を求めるネット署名に取り組み、厚生労働省に対して2度にわたる申し入れをおこなった。 ●申請者の意思を尊重する厚労省の通知 その結果、昨年3月末、厚労省から各地方自治体に対して、照会の範囲を限定した上で、申請者本人の意思を尊重することを求める通知が発出された。通知には、照会の対象は「扶養義務の履行が期待できる」と判断される者に限ること、生活保護の申請者が親族への照会を拒んだ場合、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い、照会をしなくてもよい場合にあたるかどうかを検討するように、という内容が盛り込まれている。以前から厚労省は、「概(おおむ)ね70歳以上の高齢者」は「扶養義務履行が期待できない者」として扱ってよいとの解釈を示してきた。Aさんは申請時に、80代の両親が老老介護の状態にあることを職員に伝えており、区も彼の両親が援助を見込める状況にないことを承知していたはずである。本人の意向を尊重することなく、80代の両親に照会文書を送りつけることは、厚生労働省が示している方針に二重の意味で背くことになる。それなのに、なぜ杉並区は「問答無用」の照会を強行したのだろうか。区の姿勢の背後にある構造的問題には、ぜひ第三者による検証のメスを入れてほしいと願っているが、私はそもそも杉並区の担当者が法律や制度を正確に理解できていないのではないかと疑っている。 ●扶養は保護の「要件」ではない 生活保護法によると、親族の扶養は保護に「優先」するとされている。「優先」とはわかりにくい言葉だが、実際に親族からの仕送りが行われた場合にその金額の分だけ保護費が減額される、という意味であり、扶養は保護の「要件」や「前提」となっているわけではない。なお、法律には親族への照会に関する規定はなく、扶養照会は厚労省の局長通知に基づいて実施されているに過ぎない。だが、杉並区など一部の自治体のホームページでは、扶養が生活保護の「要件」や「前提」であるかのような記載が散見される。杉並区の場合、わざわざ生活保護に関するQ&A方式のページを作り、「保護を受けるための要件はありますか」という質問に対して、「保護を受ける前提」として「親・きょうだい・子どもなど扶養義務者からできる限りの援助を受けるようにしてください」と回答している。親族による扶養が保護の「要件」や「前提」であるという誤った解釈を披露するQ&Aは、杉並区が法律に反した制度運用を続けていることの証左となっている。「要件」や「前提」であるから、扶養照会は本人の意思を無視してでも実施されるべきだと区は考えているのだろう。 ●区によって異なる対応 ちなみに同じ東京都の特別区でも、足立区のホームページでは「親・子・兄弟姉妹等(民法に定める扶養義務者)から援助が受けられる場合には、可能な限り援助を受けてください」との文言はあるが、その下には「扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護を受けられないということはありません。『扶養義務の履行が期待できない』と判断される扶養義務者には、基本的には扶養照会を行わない取扱いとしています」との説明も併記されている。また、「扶養義務の履行が期待できない者」の例も列挙しており、その中には「概ね70歳以上の高齢者など」という記載もある。どちらの自治体が、法律や厚労省の通知に沿って制度を運用しようとしているかは明白だろう。 ●一方的な扶養照会に歯止めをかける都の通知 本人の意向を無視して扶養照会を強行した杉並区に対して、私たち支援団体は2月4日、申し入れを行った。私たちはAさんご本人を交えて話し合いの場を設定することを求めたが、区はコロナの感染拡大の影響で多忙であることを口実にして、話し合いに応じなかったため、「抗議・要請書」を書面で提出できただけであった。だが、その後、私たちが申し入れをしたのと同じ日に、区を指導する立場にある東京都が、都内の各自治体の福祉事務所に対して「生活保護に係る扶養能力調査における留意事項について」という保護課長名の事務連絡を発出していたことが判明した。都の保護課長はその通知の中で、「要保護者が扶養照会を拒否する書面を提出するケースが見受けられます」と「申出書」に言及した上で、「扶養が保護適用の前提条件であるといった誤解を与えないよう」にとくぎを刺し、「要保護者が扶養照会を拒否する場合は、理由を確認し、照会を一旦保留し理解を得るよう努めてください」と、従来の都の方針を再確認している。東京都の通知が私たちの申し入れに反応したものであるかどうかは不明だが、このタイミングでの通知発出は事実上、杉並区のように「問答無用」で扶養照会を強行する自治体に対して歯止めをかける効果をもたらすものだ。 ●「本当に屈辱的」 Aさんは扶養照会を拒否したいという意向を示すために「申出書」を作成して役所に持参したが、生活保護の申請手続きを進めてもらうために「背に腹は代えられない」との思いで、書面の提出をあきらめざるをえなかった。生活保護の申請に恣意(しい)的な条件を課す区の対応は申請権を侵害するものだが、その時の心境をAさんは「本当に屈辱的でした」と語っている。杉並区のAさんに対する対応は、厚労省や東京都の方針に幾重にも背くものであり、何よりAさんの尊厳を著しく傷つけるものであった。残念ながら同様の対応は他自治体でも散見されており、職員から「親族への照会はさせてもらう」と言われて、制度の利用を断念させられた人も少なくない。国や都も表向きは否定する「問答無用」の扶養照会は、いつになったら根絶されるのだろうか。そもそも扶養照会という法律に基づかない仕組み自体が必要なのか、という点も含め、国会や地方議会での活発な議論を期待したい。 <核と戦争> PS(2022年3月10日追加):琉球新報が、*6-1-1のように、「①プーチン大統領は、ウクライナ侵攻を始めた2月24日の演説で『ロシアは世界で最も強力な核保有国の一つで、わが国を攻撃すれば悲惨な結果を招く』とした」「②核兵器を使用すれば核による報復の応酬で世界は破滅に向かう」「③ロシアは、1994年にソ連崩壊後のウクライナに残った約1800の核兵器放棄と引き換えにウクライナの安全を保障するとする『ブダペスト覚書』に米国や英国と共に署名し、それを反故にした」「④核兵器は、使えば互いの破滅を招くので実際には使えない兵器」「⑤核兵器禁止条約で世界の核軍縮に道筋を付けることが大国の役割」等と記載している。 このうち①については、「核戦力を持っているぞ、持っているぞ」と言わなければ抑止力にもならないため言うのだろうが、②の理由で、④のように核兵器は使えない兵器だ。NATOが経済制裁で留めているのも、ロシアを相手に第三次世界大戦を引き起こしたくないからである。そのため、③のような『覚書』をもう一度締結し、同時に⑤の核兵器禁止条約を世界で強化して、使えない核兵器を世界から無くすべきである。しかし、核兵器を積まないミサイルでも同じ効果が出ることは、*6-1-2のように、ロシア軍がチェルノブイリ原発・ザポロジエ原発を占拠したことで、誰の目にも明らかになった。原発の中には使用済核燃料や未使用核燃料として大量の核物質が存在し、戦闘で冷却システムが破壊されたり、管理せずに放置されたりすれば自然に爆発する。従って、原発を使いながら核兵器禁止条約を強化しても意味がないのだ。 そのような中、*6-2-1のように、中国の王毅外相は、2022年3月7日、ウクライナ情勢に関して「⑥必要な時に国際社会とともに必要な仲裁をしたい」「⑦我々は公正な態度で問題を判断する」「⑧問題解決に必要なのは冷静さと理性で、火に油を注いで食い違いを激化させることではない」「⑨矛盾が大きいほど腰を据えて話さなければならず、中国は建設的な役割を果たしたい」「⑩ロシアとは互いに最も重要な隣国で戦略的パートナーだ」「⑪国際情勢が危うくなっても、中ロ双方は戦略的なコントロールを維持し、新時代の全面的戦略パートナーシップを前進させていく」と述べておられる。ウクライナ・ロシア双方と戦争状態にない国しか仲裁はできないため、中国のスタンスは重要だ。また、*6-2-2のように、2022年3月10日、G20の議長国を務めるインドネシアのジョコ大統領は、「⑫途上国の再エネ転換を支援する方策を主要議題にする考えを示し」「⑬ロシアのウクライナ侵攻に深い懸念を示して『主権と領土の一体性はすべての当事者に守られるべきだ』と強調し」「⑭制裁は最善の解決策にならず市民が犠牲になる」「⑮すべての国が緊張を緩和し事態のエスカレートを避けて交渉に集中するよう努めることが重要」「⑯ウクライナとロシアはインドネシアの友人」「⑰互いの利益、価値観、国際法を尊重すれば、良い関係が維持される」「⑱ウクライナ侵攻したロシアに停戦を呼びかけ、交渉による解決を促した」等としている。 ウクライナのゼレンスキー大統領の与党は、2022年3月8日、*6-2-3のように「⑲北大西洋条約機構(NATO)への加盟を当面棚上げし、ロシアを含む周辺国と新たな安全保障の取り決めを結ぶ構想を明らかにした」ということであるため、これで十分かどうかはわからないが、G20やNATO諸国の支持があれば交渉による解決が近づきそうだ。  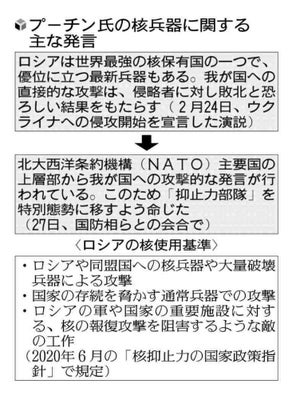 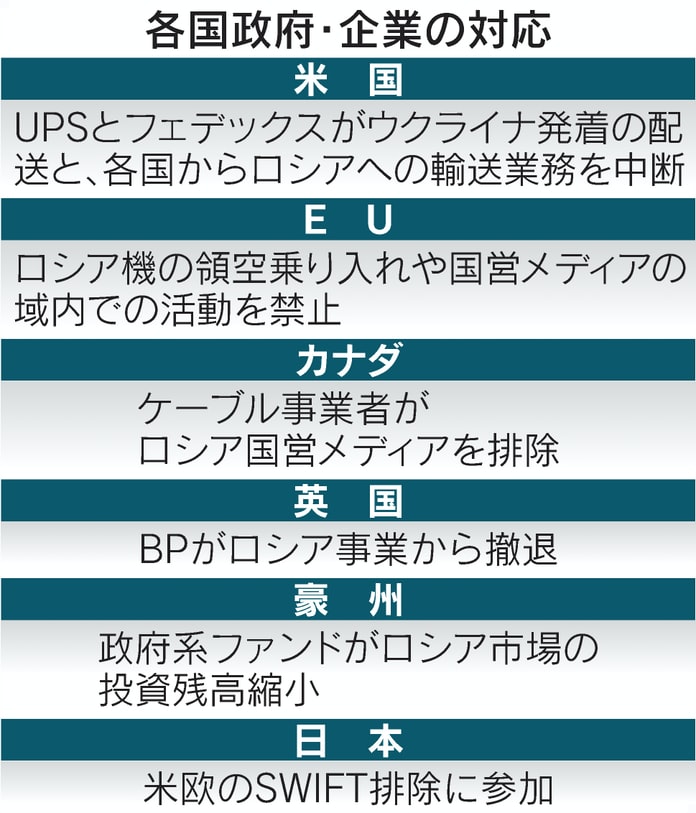 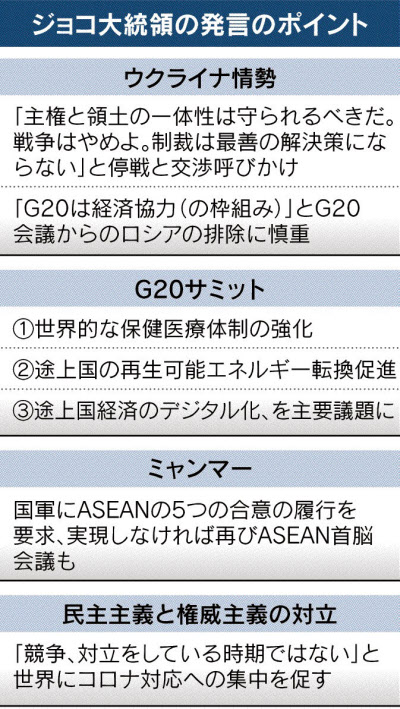 2022.2.19毎日新聞 2022.3.1読売新聞 2022.3.1日経新聞 2022.3.10日経新聞 (図の説明:ウクライナを巡るロシアと米国の立場の違いは、1番左の図のとおりだ。また、核兵器に関するプーチン大統領の発言は左から2番目の図のとおりで、ロシアのウクライナ侵攻後、各国政府や企業は右から2番目の図のような対応をしている。そして、ウクライナ・ロシア間の戦闘が激しくなり、G20議長国インドネシアのジョコ大統領が、仲裁しようと、1番右の図の発言をしている) *6-1-1:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1479619.html (琉球新報社説 2022年3月4日) ロシア核使用威嚇 国際社会は暴走阻止を ウクライナに侵攻したロシアのプーチン大統領が「核の脅し」を続けている。ひとたび核兵器を使用すれば核による報復の応酬となり、破局に向かう。国際社会が結束してプーチン氏の暴走を止めなければならない。交渉戦術であろうと核使用をちらつかせることは断じて認められない。北朝鮮の非核化が遠のくなど、核不拡散体制を機能不全に陥らせかねない。核廃絶の意志を世界が一致して示すことが必要だ。プーチン大統領はウクライナに侵攻を始めた2月24日の演説で「ロシアは世界で最も強力な核保有国の一つだ。わが国を攻撃すれば壊滅し、悲惨な結果になることに間違いない」と強調し、核戦力行使の可能性を示唆した。同27日には核兵器を運用する部隊を高い警戒態勢に置くよう軍部に命令した。ウクライナの隣国ベラルーシでも同27日に国民投票が行われ、核兵器を持たず中立を保つという条項を削除する憲法改正が賛成多数で承認された。これによってベラルーシにロシアの核兵器が配備される恐れが出ている。ロシアは1994年、ソ連崩壊後のウクライナに残った約1800の核兵器を同国が放棄するのと引き換えに、ウクライナの安全を保障するとした「ブダペスト覚書」に米国や英国と共に署名した。覚書は冷戦後の一連の核軍縮に大きく貢献する歴史的な意義があった。プーチン大統領によるウクライナへの侵攻と核による威嚇は国際合意の違反だ。非核化を受け入れたウクライナの決断を反故(ほご)にするものであり、断じて許されない。ストックホルム国際平和研究所によると、ロシアの核弾頭保有数は6255発で、米国の5550発を上回って世界最大だ。その核大国のトップが核戦力の行使を持ち出すことは、核保有国が核軍縮に取り組む義務を規定した核拡散防止条約(NPT)に逆行する暴挙である。核兵器は使われれば互いの破滅を招くため、実際には「使えない兵器」と言われる。米中ロ英仏の核保有五大国は1月に、「核戦争に勝者はおらず、決して戦ってはならない」とうたう画期的な共同声明を発表したばかりだ。昨年1月には核兵器禁止条約が発効している。世界の核軍縮に道筋を付けることこそが大国の果たすべき役割だ。国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチは、ロシア軍が非人道的な兵器として知られるクラスター(集束)弾を使用したと発表している。殺傷能力の高い燃料気化爆弾を使用した可能性も指摘されている。一刻の猶予もない。ロシアは直ちに軍を撤退させるべきだ。日本でも右派の政治家が米国との「核共有」の議論を持ち出すなど、危機に便乗したような言動が出ている。被爆国の日本は核廃絶の流れを絶対に後退させてはならない。 *6-1-2:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6420515 (Yahoo、ロイター 2022/3/10) ロシア占拠のザポロジエ原発、核監視データ停止=IAEA 国際原子力機関(IAEA)は9日、ロシア軍が占拠したウクライナ南東部のザポロジエ原子力発電所について、核物質監視システムからの通信が途絶えていると発表した。IAEAは前日、ウクライナ北部のチェルノブイリ原発についても、放射性廃棄物施設からのデータ送信が途絶えたと明らかにしている。IAEAは声明で「(グロッシ事務局長は)使用済み、もしくは未使用核燃料などの形で大量の核物質がある両原発からIAEA本部へのデータ送信が突然途絶えたことを懸念している」と述べた。原因は定かでなく、データ送信が止まった機器の状態は不明とした。ウクライナの他の原発からのデータ送信は続いているという。IAEAによると、ザポロジエ原発からの報告では、外部の高圧電線4本のうち2本が損傷し、現在使用できるのは2本になっている。必要なのは1本で、5本目が待機しているほか、バックアップのディーゼル発電機もあるという。また、原子炉1基の変圧器について、同原発一帯で戦闘が起きた今月4日以降に冷却システムに損傷が見つかり、緊急修理が行われているとした。 *6-2-1:https://digital.asahi.com/articles/ASQ376H8VQ37UHBI02V.html?iref=pc_rellink_01 (朝日新聞 2022年3月7日) 中国の王毅外相「必要な時に必要な仲裁したい」 ウクライナ情勢巡り 中国の王毅(ワンイー)国務委員兼外相は7日、北京で開催中の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)にあわせて記者会見し、ウクライナ情勢に関して「必要な時に国際社会とともに必要な仲裁をしたい」と述べた。ロシアに近い中国の貢献を求める国際社会の声に押された形だが、具体的にどう導くかは言及しなかった。中国はロシアともウクライナとも良好な関係にあり、ロシアのウクライナ侵攻後、王氏は双方の外相と電話で協議している。中国は、現在もロシアの行動を「侵攻」とは認めていない。これに関して、王氏は「中国の立場は何度も明らかにしている。我々は公正な態度で問題を判断する」と従来の説明を繰り返した。そのうえで、「問題解決に必要なのは冷静さと理性であり、火に油を注いで食い違いを激化させることではない」と訴えた。ロシアとウクライナの和平交渉には期待を表明しつつ、「情勢が緊迫するほど和平交渉は必要で、矛盾が大きいほど腰を据えて話さなければならない。中国は建設的な役割を果たしたい」と語った。市民を避難させる「人道回廊」などの動きについては「人道主義の行動は必ず中立の原則を守り、政治問題にしてはならない。国連が人道支援で役割を果たすことを支持する」とした。ウクライナからの自国民の退避遅れが指摘されていた問題については、「習近平(シーチンピン)総書記自ら関心を寄せ、安全確保を何度も指示している。現地の大使館などが火中に入り、中国人が避難する道を開いた」と十分な対応をアピールした。一方、ロシアとの二国間関係については、「互いに最も重要な隣国であり、戦略的パートナーだ。我々の協力は世界の平和と安定にも有益だ」と強調。「国際情勢がいかに危うくなろうとも、中ロ双方は戦略的なコントロールを維持し、新時代の全面的戦略パートナーシップを前進させていく」と述べ、ウクライナ問題は中ロ関係に影響しないとの見方を示した。 *6-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220310&ng=DGKKZO58946800Q2A310C2MM8000 (日経新聞 2022.3.10) 侵攻のロシアに停戦要求 インドネシア大統領インタビュー、G20議長 エネ転換支援を議論 インドネシアのジョコ大統領は日本経済新聞の単独インタビューに応じた。ウクライナを侵攻したロシアに停戦を呼びかけ、交渉による解決を促した。2022年の20カ国・地域(G20、総合2面きょうのことば)の議長国として途上国の再生可能エネルギーへの転換を支援する方策を主要議題にする考えを示した。インドネシアは東南アジアで唯一、日米欧の先進国に加え、ロシア、中国、インドなどの新興国を含むG20に名を連ね、22年に初の議長国を務める。ジョコ氏がG20の議長として外国メディアのインタビューに応じるのは初めて。ジョコ氏はロシアのウクライナ侵攻について深い懸念を示し「主権と領土の一体性はすべての当事者に守られるべきだ」と強調した。「すべての国が緊張を緩和し事態のエスカレートを避け、交渉に集中するよう努めることが重要だ」と指摘。「戦争はやめよ」と訴えた。インドネシアが国際社会の対ロシア制裁網に加わるかに関し「制裁は最善の解決策にならず、市民が犠牲になる」と否定的な考えを表明した。同国は22年を通じてG20議長国として秋にバリ島で予定する首脳会議(サミット)など首脳や閣僚レベルの関連会議を開く。ジョコ氏は「G20は経済協力(の枠組み)だ」とし、ウクライナ侵攻を踏まえ会議からロシアを締め出すことには現時点で慎重な姿勢を示した。ジョコ氏がロシアに厳しい制裁を科す米国や欧州などと一線を画す根底には「非同盟」を軸にする同国の外交方針がある。「ウクライナとロシアはインドネシアの友人だ」と強調した。G20サミットでは資金面での支援を中心に途上国に再生可能エネルギーへの転換を促す方策を議論したい考えを示した。「革新的な財政支援のメカニズムと技術移転の促進が極めて重要だ」と語った。インドネシアは60年に温暖化ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の目標を掲げる。ジョコ氏は同国を含め多くの途上国が発電を石炭に依存している現状に言及し「もし国際社会の財政支援があれば60年より前に目標を達成できる」と述べた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた世界的な保健医療体制の強化もG20サミットの主要議題に据える。医療機器や医薬品、ワクチンの製造など保健のサプライチェーン(供給網)の構築をめざす。このほか途上国経済のデジタル化の支援を議論する方針だ。ジョコ氏はクーデターにより国軍が権力を掌握するミャンマーの情勢に関し、自身が主導した21年4月の東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳特別会議の5つの合意を履行するよう、国軍に促した。合意を実現しない状況が続けば、改めて首脳会議を開く可能性に言及した。米国を中心とする民主主義の国々と、中国やロシアなどの権威主義の国々による対立が激化する国際情勢に関し「競争や対立をしている時期ではない」と世界はコロナ対応に集中すべきだとの考えを示した。「互いの利益、価値観、国際法を尊重すれば、良い関係が維持される」と指摘した。中国が実効支配を進める南シナ海の情勢については「インドネシアは平和で安定した海であることしか望まない」と強調。当事者が国際法を守るよう求めた。インドネシア領ナトゥナ諸島周辺の排他的経済水域(EEZ)では中国公船が動きを活発化させ対立が強まっている。インタビューは日本経済新聞の井口哲也編集局長が西ジャワ州のパティンバン港近郊で実施した。同港は日本が約1200億円の円借款を供与し整備が進んでいる。 *6-2-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15228898.html (朝日新聞 2022年3月10日) NATO加盟、棚上げ案 ウクライナ与党が構想 地元報道 ウクライナのゼレンスキー大統領の与党「国民のしもべ」は8日、声明を出し、北大西洋条約機構(NATO)への加盟を当面棚上げし、ロシアを含む周辺国と新たな安全保障の取り決めを結ぶ構想を明らかにした。地元メディア「ウクライナ・プラウダ」などが報じた。声明は「(NATOが)ウクライナを最低15年は受け入れる用意がないことは明白だ」と指摘し、NATO加盟までは「ウクライナの安全を完全に保障するしっかりとした取り決め」を、ロシアを含む周辺国や米国、トルコと結ぶ必要があると主張した。声明に先立ち、ゼレンスキー氏は米ABCのインタビューで「ずいぶん前にNATOがウクライナを受け入れる用意がないと理解し、この問題に冷静になっていた」と加盟を求めないことを示唆。「(NATOは)ロシアとのもめ事や対立を恐れている」とも述べた。 <日本外交の不手際> PS(2022年3月11日追加): ロシアによるウクライナ侵攻について、*7-1のように、衆議院は2022年3月1日、参議院は同年3月2日、「①ロシア軍の行動は、明らかにウクライナの主権および領土の一体性を侵害している」「②欧州にとどまらず、アジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない」「③最も強い言葉で非難する」という決議案を採択した。 そこまではかっこよかったかもしれないが、ロシアのプーチン大統領は、2022年3月9日、*7-2のように、北方領土と千島列島に進出する企業に、20年間税金を減免する等の優遇措置を与える法律に署名し、日本政府は「④ロシア側がこのような制度の導入に踏み切ったことは遺憾だ」「⑤北方四島に関する日本の立場や首脳間の合意に基づき日ロ間で議論をしてきた北方四島における共同経済活動の趣旨と相いれない」という日本側の立場をロシア側に申し入れただけである。しかし、④⑤の「遺憾」は「期待どおりにならず残念だ」という意味でしかなく、「①②③を行った日本は、ロシア側の期待どおりにならなかったので報復したまでだ」とロシアに言われれば返す言葉がない。また、「日本側の立場をロシア側に申し入れた」と言うのも、「日本はそういう立場だが、私自身はそう思っていない」と解釈できるため、本当に北方領土返還を求めている言葉とは言えない。このように、日本は自国の領土問題に関して曖昧な言い方に終始し、「そこは、日本の領土だ」という明確な証拠を示すために必要な手続きも行わず、形式的な抗議や非難を繰り返しているだけなのだ。そのため、「日本の男性は甘やかされて育ち過ぎて、考えの甘い人が多い」と言わざるを得ない。 なお、*7-3は、「⑥ロシア軍は、2022年2月1日~15日、北海道に面する日本海とオホーツク海南部で、潜水艦やミサイル観測支援艦を含む24隻のロシア艦艇が連動するように航行し、軍事演習した」「⑦昨年10月には、中ロ艦艇が計10隻で隊列を組み、津軽海峡を太平洋側へ抜けて鹿児島県の大隅海峡を通り東シナ海へ向かう日本列島を周回する航行をした」「⑧中ロ機が編隊を組んで尖閣諸島に向け南下し、ロシア国防省が国営メディアで中ロで東シナ海と日本海上空で共同警戒監視活動を行ったとした」としている。しかし、そもそも、⑥⑦のように、外国の艦艇が津軽海峡を抜けて日本列島の近くを周回できるままにしておくのが、不作為で無防備である。また、⑧の尖閣諸島も、日本政府は「領土問題はない」「力による現状変更に抗議する」「航行の自由作戦」としか言っておらず、日本の領土であるか否かは曖昧にしているため、世界が中ロの行為を妥当だと理解しても不思議ではない状態なのである。 *7-1:https://www.sankei.com/article/20220301-K653CGDIIJOK7E36VTI6FC3TFQ/ (産経新聞 2022/3/1) 衆院、ロシア非難決議を採択「最も強い言葉で非難」 衆院は1日の本会議で、ロシアによるウクライナ侵攻について「最も強い言葉で非難する」との決議案を採択した。力による一方的な現状変更は認められないと強調し、ロシアに「即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう」強く求めた。参院も2日の本会議で採択する。決議では、ロシア軍の行動を「明らかにウクライナの主権および領土の一体性を侵害している」と指摘。「欧州にとどまらず、アジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない」と懸念を示した。政府には、制裁を含む迅速で厳格な対応によりウクライナの平和を取り戻すよう要請した。衆院でウクライナ情勢をめぐる決議を採択したのは2度目。2月8日の前回は、ロシアがウクライナ国境周辺に大規模な部隊を結集させた段階で採択したため、ロシアを名指しで非難していなかった。 *7-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15230124.html (朝日新聞 2022年3月11日) 北方領土進出企業を優遇 ロシアが新法、日本政府反発 ロシアのプーチン大統領は9日、極東のクリル諸島(北方領土と千島列島のロシア側呼称)に進出する企業などに、税金を20年間減免するなどの優遇措置を与える法律に署名した。ウクライナ侵攻をめぐり米欧や日本が厳しい経済制裁を科すなか、極東に国内外の投資を呼び込む狙いだ。ただ、日本政府は「遺憾だ」と反発している。対象は2022年1月以降、同諸島に進出した企業など。法人税や固定資産税の免除などが含まれる。プーチン氏が昨年9月、ウラジオストクで開かれた「東方経済フォーラム」で発表していた。当初、優遇措置は10年間としていたが、その後、20年間に延ばした。これに対し、松野博一官房長官は10日の記者会見で、ロシアの北方領土での税制優遇措置について「ロシア側がこのような制度の導入に踏み切ったことは遺憾だ」と批判した。松野氏は「北方四島に関する日本の立場や首脳間の合意に基づき日ロ間で議論をしてきた北方四島における共同経済活動の趣旨と相いれない」と主張。こうした日本側の立場について、あらためてロシア側に申し入れたと明らかにした。 *7-3:https://digital.asahi.com/articles/ASQ385VTNQ31UTIL05N.html?iref=pc_extlink (朝日新聞 2022年3月9日) ロシア軍が日本周辺でも 中国と歩調合わせ、防衛省内「不気味」 ウクライナに侵攻したロシア軍は近年、日本周辺でも活動の活発化が確認されている。海洋進出を強める中国と歩調を合わせるような動きも目立ち、自衛隊が警戒している。今月1日。ウクライナ侵攻について、岸信夫防衛相は会見で「アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為であって、明白な国際法違反」と非難し、こう述べた。「我が国の安全保障の観点からも決して看過できない」。日本周辺でのロシア軍の異例の動きは、ウクライナ侵攻開始の直前にも確認された。2月1日~15日、北海道に面する日本海とオホーツク海南部で、24隻ものロシア艦艇が連動するように航行。軍事演習の一環とみられ、潜水艦やミサイル観測支援艦も含まれていた。ミサイル発射訓練が行われた可能性もある。岸防衛相は「異例」「ウクライナ周辺における動きと呼応する形で、東西で活動しうる能力を誇示するため活動を活発化させている」と指摘。自衛隊の哨戒機などが警戒に当たった。近年、日本周辺での動きが活発化しており、目立つのは、東シナ海や南シナ海で海洋進出を強める中国と歩調を合わせた動きだ。昨年10月には、中ロ艦艇が計10隻で隊列を組み、日本列島をぐるりと周回するような「異様」(政府関係者)な航行が確認された。津軽海峡を太平洋側へ抜け、鹿児島県の大隅海峡を通り東シナ海へ向かうルートだった。東シナ海には中国の公船が領海侵入を繰り返す尖閣諸島もある。岸防衛相は「我が国に対する示威活動を意図したもの」と非難。防衛省内では「不気味」「挑発だ」との声が漏れた。2019年夏には上空で緊張が走った。7月23日、島根県の竹島上空付近でロシア機と中国機が合流し、ロシア機が日本領空を侵犯。竹島を実効支配する韓国の戦闘機が、約360発の警告射撃を行った。中ロ機はそのまま編隊を組み尖閣諸島に向け南下。自衛隊機が緊急発進し警戒する中、尖閣の領空直前で二手に分かれ、去っていった。ロシア国防省はすぐに国営メディアを通じ、中ロで東シナ海と日本海の上空で初の共同警戒監視活動を行ったと明かした。同様の飛行は20年12月、21年11月にも確認されている。 ●ロシア軍、規模感は? 軍事大国とも言われるロシアの軍とはどんなものなのか。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所の推計では、2020年度のロシアの軍事費の推計額は約617億ドル(約7兆円)で米中インドに次ぐ世界4位。核弾頭の保有数は米国(約5800発)を上回る世界最多の6375発に上る。日本の防衛白書によると、軍の総兵力は約90万人。国全体を四分割して管轄しており、日本に面する極東地域を管轄する「東部軍管区」の司令部は、札幌市の北西約800キロのハバロフスクにある。同管区の核戦力には、オホーツク海を中心に配置されている潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)を搭載した潜水艦3隻や、約30機の爆撃機(TU95)がある。陸海空の戦力ごとに見ると、陸上戦力は約8万人で、変則的な軌道で飛翔(ひしょう)し迎撃が難しいとされる地上発射の短距離弾道ミサイル「イスカンデル」などの新型装備を保有。海上戦力はウラジオストクなどを拠点に主要艦艇約20隻、潜水艦約20隻を含む計約260隻が、航空戦力は戦闘機など約320機が配備されている。部隊は返還交渉中の北方領土にもあり、防衛省の資料によると、択捉、国後両島に約3500人を配置。ミサイル、戦車、戦闘機などが置かれ、地上から艦艇を狙うミサイル「バスチオン(要塞〈ようさい〉)」には、オホーツク海での原潜の活動を担保する役割があるとされる。ロシア軍の動向に詳しい小川和久・静岡県立大特任教授(安全保障)は、オホーツク海に連日、ロシアの原潜の情報をつかもうと米軍機が飛行し、ロシア軍が緊急発進を繰り返していると指摘し、「日本は米軍の戦略的な拠点で、当事国の一つと認識せざるを得ない」と話した。 <経済制裁はやはり戦争である> PS(2022年3月12日追加):「①衣服は生活必需品」「②ロシアは日本のすぐそばなのに、ロシアの人が日本に悪感情を持つのはよいことか」として、3月4日時点で事業を継続する方針だったファーストリテイリングは、*8-1のように、50店を展開するロシア事業の一時停止を決めた。しかし、私は、①②とともに、「独立自尊の商人」とする柳井社長の見解は正しいと思うし、ファーストリテイリングの大損害に同情する。また、これに先立って、ファーストリテイリングは、*8-4のように、中国がウイグル族に対して強制労働や強制避妊させた「人道に対する罪」の隠匿の疑いでフランス当局の捜査も受け、「取引先の縫製・紡績工場では強制労働がなく人権が守られていると確認した綿のみを使っている」と説明していた。そのため、捜査の結果がどうだったかを是非知りたい。何故なら、これは、アフガニスタンと同様、女性には大した教育もせず、保護すると称して家に閉じ込め、多くの子どもを産ませるイスラム教に対する中国の過渡期の政策であり、日本における優性保護法による強制避妊とは異質だと思うからである。 なお、このジェノサイド(集団殺害)や人権侵害という言葉は、*8-3のように、ロシアのウクライナ侵攻の理由としても使われたが、そう主張する根拠については、国際司法裁判所に提訴するのが筋であり、制裁や戦争という圧力で決めることではない。しかし、国際司法裁判所の使い勝手の悪さや公平性・公正性・強制力への疑問は残る。また、国の独立宣言は、独立される側の国が認めることは滅多にないため、独立する国が一方的に行うのが普通だが、ウクライナもそうやってロシアから独立したのではないだろうか? このようにして、制裁と武力行使が行われた結果、ロシア政府は、*8-2のように、「①ロシアから撤退する外資系企業の資産を差し押さえ」「②非友好国の資本が25%超などの企業を対象として外部から管理し」「③接収後、ロシア寄りの経営者に事業を委ねる」ことも想定して検討中だそうだ。しかし、ロシアのデフォルトを目的として行っている制裁もまた戦争の一つであるため、平時の国際法が通用しそうにはない。そのため、「非友好国」の民間企業は、資本が25%以下になるよう対応を迫られるわけだが、例えば、ファーストリテイリングの場合なら、i)ロシア国内の従業員に75%以上の株式を売却してロシア事業の独立性を高める ii)「友好国(例えば中国)」の子会社に75%以上の株式を持たせる などの選択肢があり、臨時株主総会を開いて対応を決定すればよい。グローバル企業は、現地でローカライズしてその国の優秀な人を雇用すれば、さらに多様な製品を作り出すことができ、出てきたアイデアを逆輸入することによって日本の製品も豊かにすることができるので、ローカライズした方がプラスになる場合が多い。 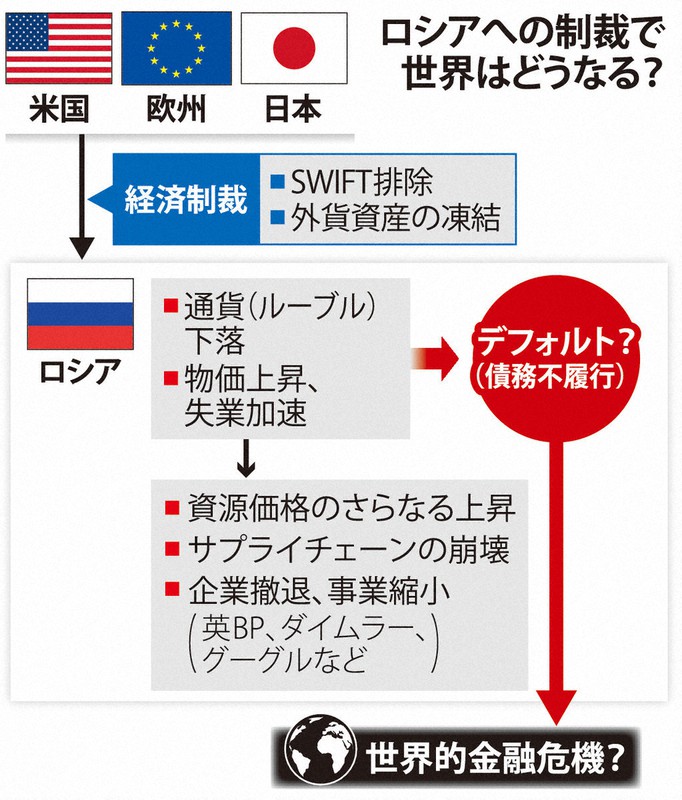 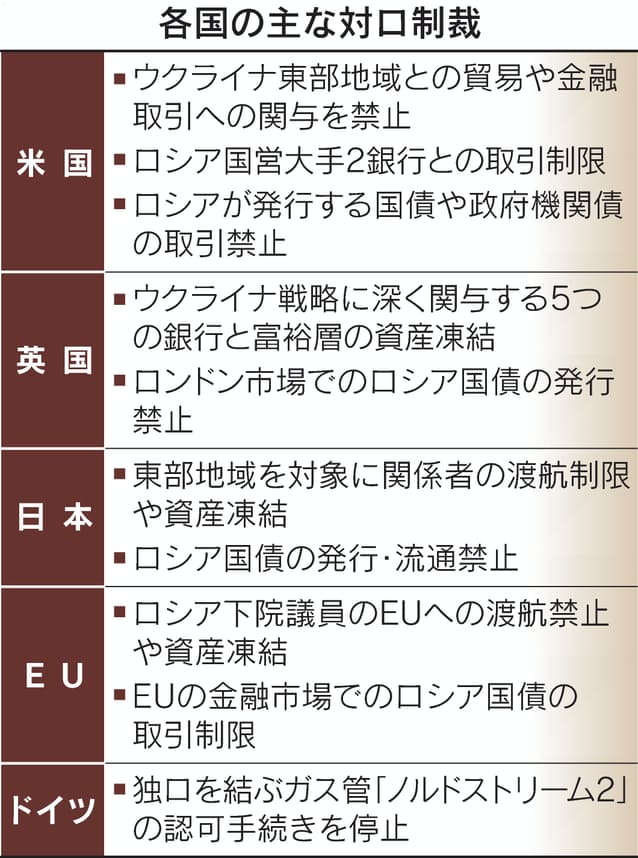   2022.3.1毎日新聞 2022.2.24日経新聞 2022.3.4西日本新聞 2022.3.12日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、ロシアへの経済制裁はロシアのデフォルトを目的として行われており、左から2番目の図が、ロシアの「非友好国」が行っている対ロ制裁だ。そして、右から2番目の図のように、日本企業はロシアの「非友好国」として対応しており、「営業を継続する」としていたファーストリテイリングも変更を余儀なくされた。そのため、ロシアは1番右の図のような対抗措置を行いそうである) *8-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220312&ng=DGKKZO59020360R10C22A3EA5000 (日経新聞 2022.3.12) ユニクロ、世界の目厳しく ロシア事業一時停止へ転換、政治・ビジネス不可分に ファーストリテイリングは「ユニクロ」50店を展開するロシア事業の一時停止を決めた。「衣服は生活必需品」(柳井正会長兼社長)との考えのもと、当初はロシア事業を継続する方針だった。しかしウクライナ情勢が混迷を深め、国際社会でロシアへの批判が強まるなか、修正を余儀なくされた形だ。「企業はそれぞれだと思う。そこに消費者がいる以上はサービスを提供する。当社がアップルのように米国企業ならすぐ止めるかもしれない。でもロシアは日本のすぐそば。ロシアの人々が日本に悪感情を持つことがいいことなのか」。柳井氏は2日に日本経済新聞の取材に応じ、ロシア事業を続ける意義についてこう語っていた。だが方針は一転し、21日から全50店と電子商取引(EC)サイトを休止することを決めた。ウクライナに侵攻したロシアに対して国際社会の批判は強まっている。ファストリの事業継続を巡る反応も、柳井氏の想像以上に厳しかった。駐日ウクライナ大使はユニクロのロシア営業継続方針について「残念だ」と名指しで批判していた。海外でも批判的な受け止めが多く、不買運動の動きも出ていた。休止決定後、米国のラーム・エマニュエル駐日大使はツイッターに「さすがファーストリテイリングとユニクロ、ロシアに英断を下しました。また一つの大企業が私たちとともに立ち向かっています。次に続くのは誰でしょう?」と投稿した。ファストリの2021年8月期の欧州事業の売上高は約1100億円。欧州の全117店のうちロシアは4割超を占め、欧州最大の店舗もモスクワにある。期待の成長市場だったことも、ファストリの事業継続の判断の背景にはあったようだ。しかし、侵攻開始から2週間以上がたち、ロシア軍は病院といった民間施設にまで攻撃を強めている。「一般のロシア国民の生活を助けるということが理解を得られなくなっている」(ファストリ関係者)。社内でも事業継続のリスクやレピュテーション(評判)リスクについて急速に議論が進み、社外取締役などから方針転換を求める声が出ていた。「独立自尊の商人」。柳井氏は自らをこう表現する。21年秋の会見では「自らの信念と現実が違っていたら、勇気を持ってそれは違うと言わないといけない」と強調した。「安易に政治的立場に便乗することはビジネスの死を意味する。これが商人としての私の信念」と語っていた。柳井氏は衣服は生活必需品との考えのもと、周囲の批判にも屈せず店を開け続けることを重視している。11年の東日本大震災では電力不足からの節電要請があっても、売り場の照明は落とさずに営業を継続した。また、20年春の新型コロナウイルスの緊急事態宣言下では多くの企業が営業自粛する中、商業施設に入るテナント店以外の自前店舗を開け続け、コロナ禍中に旗艦店も新規開業した。当時、多くの消費者はこうしたユニクロの行動を支持した。今回、「ロシアの人々にも生活する権利がある」(柳井氏)としたことは、これまでの姿勢とも一貫するものだ。ただ、政治とビジネスは不可分の関係になっている。欧米では企業やスポーツ選手も政治的なスタンスを示すことが当たり前だ。中立の立場を示しても、曖昧な姿勢ととられかねず逆に批判も受けやすい。ファストリは海外での売り上げが国内を上回る日本の小売業ではまれな存在だ。ファストリもウクライナに対しては、約11億5000万円と衣料品約20万点の寄付という日本企業で最大規模の支援を打ち出している。だが、ロシアでの事業継続ばかりが目立ち、評価する声は少ない。柳井氏の信念が世界には通じなかった格好だ。今回のユニクロの動きには、多くの日本企業にとって教訓が含まれている。 *8-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220312&ng=DGKKZO59029290S2A310C2EA2000 (日経新聞 2022.3.12) 対ロ経済封鎖、企業に試練、ロシア政府「撤退なら資産接収」 協定違反、法廷闘争も ロシア政府は、同国から撤退する外資系企業などの資産を差し押さえる検討を始めた。企業の撤退の動きを抑え、日米欧による経済制裁の影響を緩和する狙いだ。国際的な投資協定(きょうのことば)違反とみられる強硬策で、法廷闘争に発展する可能性もある。ロシアに進出する世界の企業は試練に直面する。ロシア政府は、ロシアでの事業停止や撤退を判断した外資系企業の資産を差し押さえるなどの草案を作成。プーチン大統領は政府幹部とのテレビ会議で「(事業を閉じる企業を)外部から管理」と発言した。現地報道によると「非友好国」の資本が25%超などの企業を対象とすることを検討中という。接収後にロシア寄りの経営者に事業を委ねることも想定される。ロシアは外資系企業の締め付けを急速に進める。3月に入り大統領令で1万米ドル超の外貨の国外持ち出しを禁じ、国内の保有資産の売却も制限。いずれも同国からの撤退を防ぐ狙いとみられる。資産接収策の検討は、その決定打ともいえる。既に英BPやシェル、米エクソンモービルなど多くの欧米企業がいち早くロシア事業からの撤退などを表明している。日本企業も事業見直しの検討を進めており、ソニーグループは映画やゲームなどロシアの全事業を停止した。ソニーは、ロシア政府が資産接収策を検討していることについて「コメントを控える」とした。事業の停止や撤退は難路が予想される。まず直面するのは合弁の解消などを巡って起こりうるロシア企業との訴訟リスクだ。こうしたビジネス紛争に備え、国際的な企業契約では公正を期すために第三国での国際仲裁で解決すると定めることが多い。だがロシアは2020年に民事訴訟法を改正。「制裁対象になっている場合などでは、契約の内容にかかわらずロシアの裁判所で紛争を解決しなければならなくなった」(小原淳見弁護士)。ロシア裁判所の判事は国家公務員で、外国企業に不利な判断が出る懸念がある。撤退に関する企業間の交渉が円滑に進んだとしても、ロシア政府が資産を接収する恐れがある。資産接収は、日ロ両国が相互の企業や投資財産を保護するために締結している「投資協定」に違反する可能性が高い。同協定の5条は投資家(企業)の財産に関し「補償を伴う場合を除き収用もしくは国有化の対象としてはならない」などと定めている。藤井康次郎弁護士は「協定違反の場合、日本企業はロシア政府を訴えることができる」と指摘する。この場合は米国など第三国での「投資仲裁」の手続きで争うことになるが、ロシア側の反論などで決着まで難航する可能性もある。企業は難しい判断を迫られる。政府と対立したまま撤退すれば、大きな損失を被るだけでなく将来の事業機会まで失う恐れもある。他方で事業を続ければ投資家や消費者の反発などを受け、企業の評判が落ちることも懸念される。ロシアの強硬姿勢は同国のカントリーリスクを高め、日米欧の企業を遠ざけることにつながりそうだ。ある大手商社は「民間企業の資産接収が進めば中長期的にロシア事業の大きなリスクとなる」と警戒している。対ロ投資が激減することも予想される。 *8-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220312&ng=DGKKZO59028000R10C22A3EA3000 (日経新聞 2022.3.12) 「住民保護のため」ロシアの常套句、08年ジョージア、14年クリミアでも 周辺国、危機感強める ロシアがウクライナ侵攻の口実に「住民保護」を掲げたことへの批判が国際社会で高まってきた。ロシア系住民を守るという理屈は2008年のジョージア(グルジア)紛争や14年のクリミア併合でも用いたが、その根拠は乏しい。ロシア系を多く抱える周辺国は懸念を強める。「特別作戦の目的は8年以上にわたりキエフ政権から大量虐殺を受けている人々を守ることだ」。ウクライナへの侵攻を始めた2月24日、ロシアのネベンジャ国連大使は国連安全保障理事会の会合でこう訴えた。人々とはロシアが一方的に独立を承認した「ルガンスク人民共和国」と「ドネツク人民共和国」に住むロシア系住民を指す。ウクライナ東部にあるルガンスク、ドネツク両州の親ロシア派が事実上支配してきた地域だ。慶大の広瀬陽子教授によると、両地域の住民の2割程度はロシアのパスポートを保有しているという。ロシアは19年、住民がロシアのパスポートを簡単に取得できるようにする措置を導入して地ならしを進めた。ブリンケン米国務長官は3月1日の国連人権理事会で「攻撃を無理やり正当化しようとするロシアの試みを拒否しなければならない」と述べた。神戸大の坂元茂樹名誉教授は「ロシアが主張する虐殺の事実は確認されておらず、武力行使は国際法違反だ」と断じる。ジェノサイド(集団殺害)があったとするロシアの主張にウクライナは全面的に反論しており、国際司法裁判所(ICJ)に提訴した。3月7日に始まった審理をロシアは欠席した。周辺国への軍事介入の際に住民保護を名目にするのはロシアの常套(じょうとう)手段だ。08年のジョージア紛争は同国領内の南オセチア、アブハジアの分離独立を主張する親ロシア勢力とジョージア政府が対立した。ロシアは「自国民保護」を打ち出して軍事介入し、南オセチアなど2地域を支援して独立を一方的に承認した。広瀬氏によるとロシアは南オセチアとアブハジアの住民にパスポートを付与し、08年時点で90%近くの住民が保有していたという。ロシアは14年、ロシア系住民が過半数を占めるウクライナ領クリミア半島に軍事介入した際も住民保護を掲げた。ロシアの圧力のもとで実施された住民投票を経て一方的に併合した。国際法上、自国民を保護するための自衛権に基づく武力行使は場合によっては容認される余地がある。日本政府も「ほかの救済手段がないような極めて例外的な場合」などを条件に認められる可能性はあるとの見解を示す。14年5月の参院外交防衛委員会で当時の外務省国際法局長が「保護、救出するために必要最小限度の実力を行使することが自衛権の行使として国際法上は認められることがあり得る」と答えた。ロシアは根拠に乏しいにもかかわらず国際法の論理を歪曲(わいきょく)して用い、正当な行為であるかのように強弁してきた。ロシアが住民保護を名目に武力によって国境変更を試みようとするのを周辺国は警戒する。旧ソ連の支配下にあった東欧や中央アジア諸国には主にロシア語を話したり、自らをロシア人と認識したりするロシア系住民が多く住む。バルト3国のエストニア、ラトビアはいずれもロシア系住民が2割強に上る。中央アジアに位置するカザフスタンは19%を占める。広瀬氏は「こういった国々ではロシアからの侵攻に対する恐怖が潜在的にある」と指摘する。バルト3国が携行型のミサイルを供与するなどウクライナ支援に乗り出しているのはこうした認識が背景にある。ロシアは住民保護に加え、ウクライナ侵攻は「ルガンスク人民共和国」と「ドネツク人民共和国」への集団的自衛権の発動との主張も展開している。ネベンジャ大使は国連安保理会合で両共和国から軍事支援の要請を受けたと説明し「(個別的・集団的自衛権を容認する)国連憲章51条に基づき決定した」と強調した。 *8-4:https://news.yahoo.co.jp/articles/986cf5be8d6a5ef5098604b7e1e180e56d068480 (Yahoo 2021/7/1) 仏当局、ユニクロなど捜査 新疆強制労働で利益と告発 中国新疆ウイグル自治区での人権問題を巡り、フランス当局は、人道に対する罪の隠匿の疑いで、衣料品店「ユニクロ」のフランス法人を含む衣料・スポーツ靴大手の4社の捜査を始めた。フランスメディアが1日報じた。ニュースサイト、メディアパルトによると、中国の少数民族ウイグル族に対する強制労働など人権抑圧に関するフランス当局の捜査は初めて。捜査は6月末に始まった。ユニクロを展開するファーストリテイリングは、取引先の縫製・紡績工場では強制労働がなく人権が守られていると確認した綿のみを使っていると説明している。 <原発に対する地元の意識> PS(2022年3月13、19、30日追加):佐賀新聞は、*9-1のように、「①ロシア軍のチェルノブイリ原発占拠やザポロジエ原発・核関連施設への攻撃により」「②フクイチ事故から11年後の3月11日に、原発の巨大リスクを再認識し、脱原発への歩みを速める機会としたい」「③大量の冷却水が必要な原発が直面する災害リスクも外部電源喪失の危険度が大きくなる一方だ」「④戦争や災害で原発が止まれば、膨大な量の電力が一挙に失われ、原発依存は電力の安定供給上も大きなリスクがある」「⑤これが戦時に原発が標的となる理由の一つで」「日本の場合は燃料のウラン資源が海外依存」としており、完全に賛成だ。 また、「⑥再エネや蓄電池の価格は急激に低下しているため」「⑦今ある技術を最大限駆使して、国産資源である太陽光や風力、地熱などの再生可能エネルギーを増やして省エネを進めることが答えで」「⑧政策決定者は、今こそ勇気を持って政策の大転換に取り組まねばならない」としているのもそのとおりであり、これが玄海原発地元の新聞に記載されているのだということを、岸田首相は認識して欲しい。なお、これに先立ち、佐賀新聞は、佐賀県内21市町の首長にアンケート調査を行って下の左図のような回答を得ており、福井県・新潟県・福島県の首長がどう考えているかは興味深い。 *9-2は、「①日本政府は、ロシア軍のウクライナ原発攻撃で、原発の安全を確保するため自衛隊の迎撃ミサイル配備や平時からの警護を検討する」と記載している。しかし、「②原発がミサイルなどで武力攻撃を受けた場合はどうするのか」という質問は、衆議院議員時代の2006年に、私が、九電・経産省・防衛省を招いて行った自民党の部会で既に行い、その時、九電は「③民間企業は対応できません」と言い、防衛省は「④すべてのミサイルを撃ち落とすことはできない」と言ったのである。そのため、それから16年経過した今でも「⑤日本の原発の安全対策は地震・津波などの自然災害とテロ対策に軸足を置いてきた」「⑥2国間の紛争による武力攻撃は想定していないので対策を要求していない」などと言い、「⑦原油・LNGの価格高騰で原発は火力発電を補完する選択肢の一つになる」としてリスクに目をつぶり、屁理屈を付けて原発を再稼働させ、当時より進歩したミサイル(敵は馬鹿ではない)を「自衛隊で護れる」などと言っているのは許せない。これでは「歴史は繰り返す」という言葉が真実になってしまうだろう。 さらに、*9-3のように、「自衛隊が原発を守るには、原発周辺に陸自の駐屯地を作ることも検討課題だ」等と言っている人もいるが、そうすると「軍事施設を狙う」と言って遠慮なく原発周辺を攻撃できるため、リスクが高まる。つまり、原発や核の出る幕はもうないのだ。 2022年3月30日、全国知事会の平井会長が、*9-4のように、首相官邸で磯崎官房副長官に原発へのミサイル攻撃対策強化を要請し、磯崎官房副長官は「自衛隊以外にも警察・海上保安庁とも連携して対策をとる」と説明されたそうだが、日本の自衛隊はミサイルを100%撃ち落とすことはできず、サイバー攻撃にも対応しておらず、ましてや警察や海上保安庁がミサイル攻撃に対応できるわけがないため、日本が原発にこれ以上の資金を投入するのは、自己満足のための無駄遣いの上積みにすぎない。  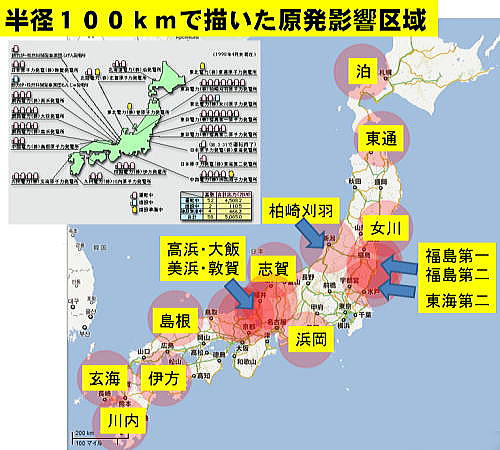 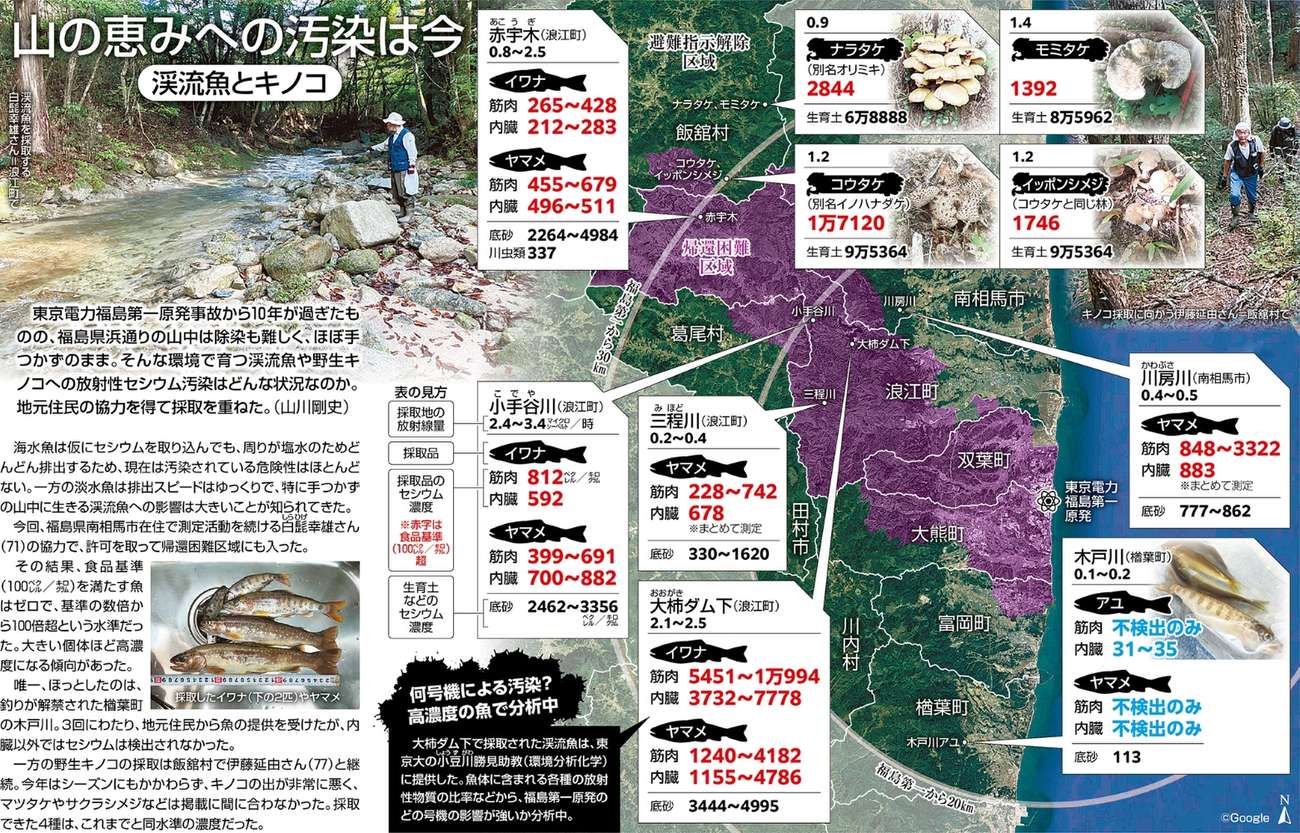 2022.3.12佐賀新聞 EwaveTokyo 2021.11.8東京新聞 (図の説明:左図のように、佐賀県21市町の首長で原発の運転継続に賛成なのは玄海町長のみで、「条件付で賛成しながらも、将来的には廃止」を望む人が最も多く、最終処分場を受け入れる考えのある人はいない。中央の図は、半径100kmで描いた原発影響区域で、日本の多くの地域をカバーしているが、原発の多い福井県・福島県は特に色が濃くなっている。仮に原発を攻撃するとすれば、風向きや地形を考えながら効果的に行うだろうが、日本には甚大な被害を及ぼす。右図は、フクイチ事故後10年半が経過した2021年11月における山の恵みの汚染状況だ) *9-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/823421 (佐賀新聞 2022.3.12) 原発事故から11年、リスクを再認識しよう ロシア軍によるウクライナの原発や核関連施設への攻撃、チェルノブイリ原発の占拠という異常事態が伝えられる中、東京電力福島第1原発事故から11年の3月11日を迎えた。人類史上初めて、多数の原発が稼働する国が本格的な戦場となり、原発が標的となった。原発が広範囲かつ長期間の放射性物質の汚染を引き起こすリスクは津波以外にも多い。11年後のこの日を、原発の巨大なリスクを再認識し、脱原発への歩みを速める機会としたい。事故後、原発が抱えるリスクは果たして小さくなっただろうか。答えは否だ。政情が不安定な中東で原発建設が進んでいる。ロシアの所業は原発が容易に戦闘の標的となることを明確にした。制圧されたザポロジエ原発は欧州最大級で大事故への懸念は大きい。建設コストの高騰で先進国の原発産業が衰退する中、新規の建設はロシアと中国が中心だ。いずれも平和利用に重要な「民主・公開」の原則とはほど遠い国だ。深刻な事故の際に、国際社会に迅速かつ十分な情報が提供されるとは思えない。ここ数年、気候危機が深刻化し、高潮や暴風雨、干ばつといった自然災害の規模が拡大している。沿岸や川沿いに立地することが多く、大量の冷却水の安定的な確保が必要な原発が直面する災害リスクも、外部電源喪失の危険度も大きくなる一方だ。戦争や災害で原発が止まれば、膨大な量の電力が一挙に失われるので、原発依存は電力の安定供給上も大きなリスクだ。11年前、多くの人が突然の計画停電で大きな影響を受けたことを忘れてはいけない。そして、これが戦時に敵国の原発が標的となる理由の一つだ。ウクライナ危機の中、天然ガスなど海外からの化石燃料の高騰が日本経済に大きな影響を与えている。エネルギー安全保障の観点からも、気候危機への対応からも、輸入化石燃料への依存度を下げることも急務だ。ここで聞こえてくるのが「脱炭素、脱化石燃料には原発が不可欠だ」という議論だ。だが、この間、気候危機対策としての原発の重要度は小さくなるばかりだ。福島事故の影響もあって、原発の建設コストは膨れあがり、工期も延びている。一方で、再生可能エネルギーや蓄電池の価格は急激に低下した。産業革命以降の気温上昇を1・5度に抑え、気候危機の影響を可能な限り小さくするためには2030年までに温室効果ガスの排出を大幅に減らすことが必要なのだが、この点への原発の貢献度は小さい。しかも日本の場合、燃料のウラン資源は海外依存だ。不安定化する世界と深刻化する気候危機の中、日本は多くのエネルギー問題に直面している。対応は急務だが、それは高価で高リスクの原発の再稼働や、化石燃料関連産業への補助金などといった安直な対策でも、アンモニアや水素といった未知の新技術への投資によっても解決できない。今ある技術を最大限駆使して、国産資源である太陽光や風力、地熱などの再生可能エネルギーを増やし、省エネを進めることが答えだ。日本ではこの11年間、既得権益に配慮する旧態依然としたエネルギー政策が続いてきた。政策決定者は今こそ、勇気を持って政策の大転換に取り組まねばならない。 *9-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA116HC0R10C22A3000000/ (日経新聞 2022年3月18日) 原発防衛に軍事攻撃も想定 政府、自衛隊活用を検討 政府は原子力発電所の安全を確保するため、自衛隊を活用した迎撃ミサイルの配備や平時からの警護といった対策を検討する。ロシア軍によるウクライナ侵攻で、原発への国家による軍事攻撃が現実の脅威となったためだ。国家安全保障戦略など年内に改定する文書に反映する。日本の原発の安全対策は地震や津波などの自然災害とテロ対策に軸足を置いてきた。2013年に決定した現行の国家安保戦略は原発が他国軍から攻撃される場合の記述がない。「国際テロ対策の強化」に関する項目で「原子力関連施設の安全確保」に言及しているだけだ。原子力規制委員会の更田豊志委員長は原発の安全審査について「2国間の紛争による武力攻撃は想定していないので対策を要求していない」と説明する。国際人道法の一つであるジュネーブ条約第1追加議定書が原発への攻撃を禁止していたことが背景にある。ロシアによるウクライナ侵攻では国際法に反する原発攻撃が起こり得ると明らかになった。ウクライナ政府はロシア軍が4日に欧州最大級のザポロジエ原発を砲撃したと公表した。原子炉への被害はなかったが、原発は周辺の送電網や配管が損傷しただけでも重大事故が生じる恐れがある。原発が立地する福井県の杉本達治知事は8日、防衛省で岸信夫防衛相に会い、原発防衛に関する要望書を渡した。ミサイルの迎撃態勢に万全を期すことを求め、原発が集中立地する同県嶺南地域への自衛隊配備も要請した。岸田文雄首相は16日の記者会見で原発の防衛策について問われ「防衛力の強化が十分なのかを検討していく。国家安保戦略をはじめとする文書の見直しの中で具体的に考えていく」と言明した。国家安保戦略と同時に改定する防衛計画の大綱や中期防衛力整備計画に外国軍からの原発攻撃を想定した自衛隊の防衛体制を盛り込む方向だ。ウクライナ侵攻による原油や液化天然ガス(LNG)の価格高騰で、原発は火力発電を補完する選択肢の一つになる。絶対条件となる安全確保を強化する。懸念する事態の一つは弾道ミサイルや巡航ミサイルによる攻撃だ。飛来するミサイルを撃ち落とす地対空誘導弾パトリオットミサイル(PAC3)部隊を原発周辺に配備するなどの案が選択肢になる。相手のミサイル発射拠点をたたく「敵基地攻撃能力」の保有に関する議論も原発防衛につながる。中国や北朝鮮が開発を進める極超音速ミサイルは迎撃が難しく、反撃する能力を備えることが抑止になりえる。政府・自民党内には武力攻撃を受ける前段階の平時から自衛隊が警護する案もある。外国軍が原発施設に侵攻してから離れた場所で待機する陸上自衛隊が出動したのでは時間を要し、その前に制圧されかねない。現在も警察と自衛隊の共同訓練はあるものの、警察が対処しきれない重武装のテロリストが攻撃してきた場合などに限った出動を念頭に置く。こうした「治安出動」は政府内や都道府県との間で手続きも必要になる。自民党は13年、国会承認なしで自衛隊が動ける「警護出動」の対象に原子力関連施設を加える法改正を検討したことがある。現在の規定では自衛隊や在日米軍の施設などに限定されている。自民党の高市早苗政調会長は「ウクライナの問題で世の中の危機感が変わった。政府が原発警護に自衛隊を活用する方針なら賛同する」と話す。原発の防護に詳しい元陸上自衛隊陸将補の矢野義昭氏によると、米国は米原子力規制委員会(NRC)が一元的な警備基準をつくり、州兵や民間警備会社の従軍経験者が守る場合が多い。「どの国でも軍隊か準軍隊の組織が警備するのが常識だ」と指摘する。ミサイルだけでなく外国軍の特殊部隊やサイバー攻撃への対応も不可欠だと主張する。 *9-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA186NH0Y2A310C2000000/ (日経新聞 2022年3月18日) 平時から原発警護へ自衛隊法改正を 自民党外交部会長 政府は原子力発電所の安全を守るために自衛隊の活用の検討に入った。陸上自衛隊出身の自民党の佐藤正久外交部会長に受け止めを聞いた。外交・防衛の基本方針である「国家安全保障戦略」など3文書に自衛隊による原発の警護を明記すべきだ。自衛隊が原発を守るには平時から警察や発電所と擦り合わせる必要がある。自衛隊法を改正し自衛隊の警護出動の対象に原発を加えたほうがいい。自衛隊の駐屯地と原発との距離が離れている地域は多い。部隊の常駐は難しいとしても、原発への攻撃の緊張が高まった時点で警備できるようにしなければいけない。有事になってから動くのでは手遅れだ。特殊部隊が原発に侵入したり、外部電源を狙われたりしたら極めて危険だ。警察では特殊部隊に太刀打ちできない。原発周辺に陸自の駐屯地をつくることも検討課題になる。 *9-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA3039K0Q2A330C2000000/ (日経新聞 2022年3月30日) 原発へのミサイル攻撃、対策強化を 全国知事会 全国知事会の平井伸治会長(鳥取県知事)は30日、首相官邸で磯崎仁彦官房副長官と面会し原子力発電所へのミサイル攻撃の対策の強化を要請した。ロシアのウクライナへの侵攻で原発の安全を巡る懸念が高まる。平井氏は自衛隊による迎撃態勢や部隊の配備に万全を期すよう求めた。「政府として緊急事態、武力攻撃になった場合は原発と住民の安全を守ることを明確にしてほしい」と語った。磯崎氏は自衛隊以外にも警察、海上保安庁とも連携し対策をとると説明した。 <サハリン2と天然ガス> PS(2022年3月14日追加):対ロシア制裁が強まる中で極東ロシアのガス開発事業「サハリン2」については、*10-1のように、英シェルは撤退を表明したが、日本の三井物産・三菱商事は追随しない方針を維持している。そして、「拙速な撤退は危険で、撤退はロシアや中国を利する」としているが、日本の国益から考えても「短期的には安定供給、中長期的には脱ロシア・脱海外依存」として次第に他国の天然ガスから手を引くチャンスでもある。 何故なら、*10-2のように、新潟県上越沖等の日本海側で表層型の資源量が多いメタンハイドレートの採取が容易なガスチムニーが1742カ所あることが確認され、「ロシアなどの海外から天然ガスを購入したほうがコストが安い」という課題は、回収だけでなく地域経済の活性化や安全保障等の総コストを考慮すればクリアできるからだ。なお、エネルギー自体は再エネや水素に変換すべきであるため、メタンガスの使い道は化学工業における石油の代替になり、そうなるとメタンガスのパイプラインや輸送は不要で、必要最小限の貯蔵基地を作って採掘地付近で加工すれば地域でつける付加価値が増すわけである。 なお、短期的(10年程度)な安定供給には、中立の立場をとっている国又はタックスヘイブン国(リベリア等)に特定目的会社を作り、そこからの投資に切り替える方法がある。 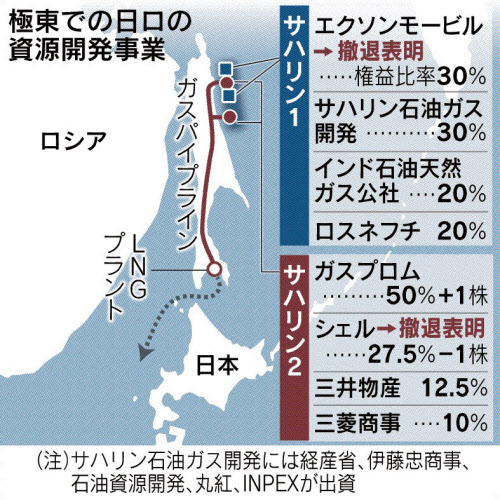 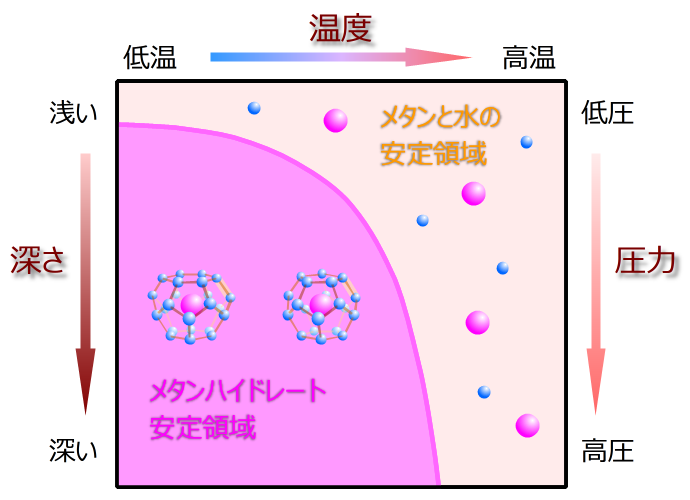 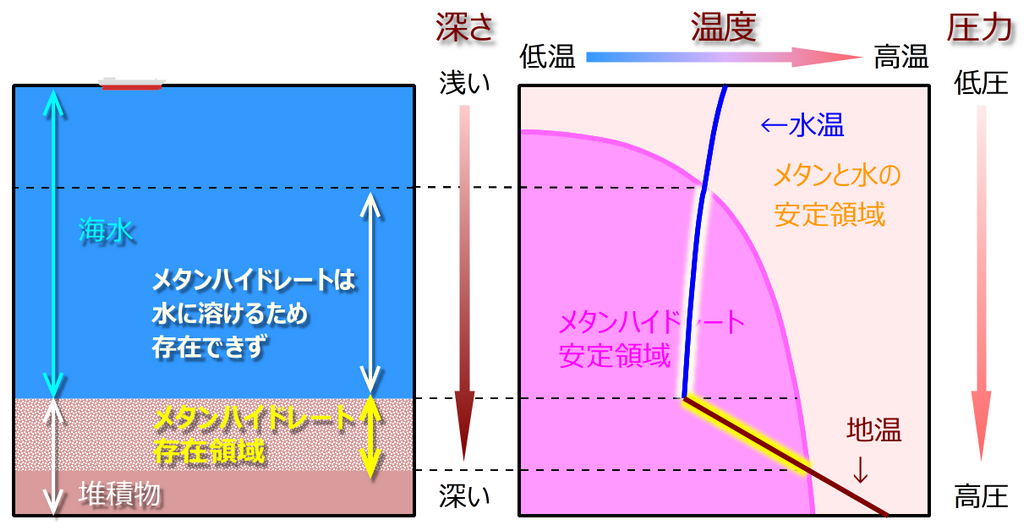 2022.3.13日経新聞 https://finding-geo.info/basic/methane_hydrate.htmlより (図の説明:左図のように、サハリンで進めている天然ガスの開発が、対ロシア制裁が強まる中で暗礁に乗り上げそうだが、中央と右図のように、日本近海にはメタンハイドレートが多量に存在する。そのため、その採掘と加工による地域活性化と安全保障を両立できる日は近い) *10-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220313&ng=DGKKZO59034860S2A310C2EA5000 (日経新聞 2022.3.13) サハリン2進退、2商社苦悩 「安定供給に支障」 極東ロシアのガス開発事業「サハリン2」。2月28日に英シェルが撤退を表明したが、権益を持つ三井物産と三菱商事は追随しない方針を維持する。日本の液化天然ガス(LNG)輸入量の1割近くを占めるサハリン2を手放せば、安定供給やエネルギー安全保障への影響が避けられない。米欧の対ロシア制裁が強まる中、日本勢は板挟みの状態が続く。「サハリンの権益を巡る立ち位置は日本と欧米で大きく異なります」。3月初旬、商社のエネルギー担当は経済産業省の幹部に迫った。資料では「拙速な撤退は危険」「撤退はロシアや中国を利する」との文言が並ぶ。経産省幹部も「非常に重要な権益」と応じた。サハリン2はロシア初のLNGプロジェクトだ。ロシア国営ガスプロムが約50%、シェルが約27.5%、三井物産が12.5%、三菱商事が10%を出資する。2009年に出荷を始めた。年1000万トンの生産量のうち約6割は日本向けだ。ロシアからのLNG輸入量のほぼ全量に相当する。サハリン2のLNGは日本の電力やガス会社に供給される。長期契約で量やコストは安定。航路は3日程度で2週間の中東より短い。日本勢は自国の供給網として組み込んでおり、大半を極東やアジアで売るシェルとは重要性が異なる。政府と商社らは撤退時のリスクを分析した。撤退なら代替分の多くをスポット(随時契約)市場で調達する必要があり、現状で「2兆円近い追加コストが出る」(商社)。ただでさえ上昇基調の電気やガス料金への上昇圧力は一段と強まる。撤退なら「中国に権益を取られる」(政府関係者)懸念もある。日本が撤退してもサハリン2の操業は続くため、政府や商社は「権益を手放してもロシアへの制裁にならない」とみる。日本勢が抜け、中ロが極東の資源権益を独占すれば外交やエネルギーの安全保障上の急所になりかねない。経産省や伊藤忠商事、丸紅などが参画する原油開発事業「サハリン1」も事情は同じだ。原油輸入量の3.6%を占めるロシア産のうち約4割がサハリン1だ。一度権益を手放せば再び得るのは容易ではない。今のところ政府や商社では、サハリン撤退は選択肢にない。日本が注視するのが欧州連合(EU)の動向だ。EUは原油の3割弱、天然ガスの45%をロシアに頼り、エネルギー分野を制裁の例外にしたままだ。ただ仮にEUがロシア産の原油やガスの調達を止めれば日本も現状維持ではいられない。対ロの国際協調から外れてまで権益を優先すれば、台湾有事など東アジアの地政学リスクが表面化した際、友好国間の関係に影響しかねない。投資家の批判が強まり国際社会の信頼を落とす懸念もある。サハリン事業について、経産省幹部は「短期的には安定供給、長期的には脱ロシア戦略にかじを切らざるを得ない」と話す。撤退の損失と継続のリスク、どちらがより国益に響くか。てんびんにかける日々はしばらく続く。 *10-2:https://www.sankei.com/article/20210707-X4I36HCGAFNTZMG5AG4VK42L2Y/ (産経新聞 2021/7/7) メタンハイドレートで地域活性化 新潟県などで高まる期待と課題 資源小国の日本で、自前のエネルギー資源の一つとして注目されているメタンハイドレート。日本海では新潟・上越沖が最も資源量が多いとみられ、新潟県は日本海沿岸の府県とともに開発推進への活動を展開している。ただ、低コストな生産技術の確立や、国が打ち出した2050年カーボンニュートラルとの整合性など、越えなくてはいけないハードルもある。 ●有望な上越沖 国の海洋基本計画では、メタンハイドレートの商業化に向けた民間企業主導のプロジェクトを令和5~9年度ごろに開始することになっている。国はこの計画に基づき、平成25~27年度にかけて日本海側の資源量調査を実施。メタンハイドレートの〝通り道〟とみられる箇所(ガスチムニー)が1742カ所あることが確認された。これらの中で資源量的に有望視されているのが新潟・上越沖である。長年メタンハイドレートの調査研究に携わっている東大名誉教授、松本良氏は「この調査により、上越沖のガスチムニーに400万立方メートルのメタンハイドレートが存在することがわかった。これはメタン量にして6億立方メートルに相当し、かなり高い濃集になっている」と指摘する。 ●新潟県も活性化に期待 地域経済の活性化が重要課題の新潟県もメタンハイドレートに期待を寄せる。「県内の企業とともにメタンハイドレートの回収技術で貢献したい。また、新潟県は国内の天然ガス生産の8割を占めており、メタンハイドレートを商業化できれば、エネルギー安定供給にも寄与できる」(県新エネルギー資源開発室)。県は29年、県内の企業に事業参入を促すため、県メタンハイドレート活用構想を策定。商業化が実現した場合、貯蔵基地やパイプライン、陸上輸送などの分野で、ガスや建設業など約50業種に参入可能性があるとみている。また、県内39の大学、企業、自治体からなる県表層型メタンハイドレート研究会では、最新情報の収集と共有を行い、参入に向けた環境整備を進めている。5月下旬には、新潟県など日本海沿岸の12府県からなる「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」が、経済産業省の江島潔副大臣とテレビ会議方式で会談し、生産技術開発や海洋調査などで地元の大学、中小企業を積極的に活用することや、来年度予算での調査費拡充などを要望。新潟県からは佐久間豊副知事が参加した。 ●商業化への課題 地域から大きな期待が寄せられる一方、商業化には課題も多い。最大のハードルは、海底からメタンハイドレートを回収し、メタンを生産する技術をどれだけ低コスト化できるかだ。海外から天然ガスを購入したほうがコスト的に安いとなれば、開発のメリットは薄れる。さらに政府が掲げる2050年カーボンニュートラルとの整合性も出てくる。50年に向けて脱化石燃料が進むとみられる中、化石燃料のメタンハイドレートに開発コストを投下することに、国民のコンセンサスが得られるのかという問題が頭をもたげる。壁を乗り越え開発を進めることになった場合、地元の新潟県は何をすべきか。松本氏は「沖合での資源探査と回収を進めるには漁業者との調整が必須。自治体として協力を取り付ける環境づくりが必要になる」と指摘する。 *【メタンハイドレート】 天然ガスの主成分メタンが水とともに氷状になったもので、〝燃える氷〟とも呼ばれる。海底の表層に存在する「表層型」と、海底下で砂とまじり合って存在する「砂層型」がある。前者は日本海側、後者は太平洋側を中心に存在する。 <ロシア・ウクライナはじめ欧米の食べ物について> PS(2022年3月17日追加):*11-1のように、ロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシアに850以上の店舗があり、関係企業を含めて約10万人の従業員がいるマクドナルドが、ロシア国内の全店舗の一時閉鎖を決め、最後の営業日には多くの人が惜しんだとのことだ。私も英語圏でない国に旅行した時は、メニューに何が書いてあるかわからないため、何が出てくるか予想できるマクドナルドや中華料理店を利用することが多いが、マクドナルドのメニューは健康によくない。 ちょうど、*11-2に、WHOの統計で、平均寿命はウクライナ(男性68.0歳、女性77.8歳)・ロシア(男性68.2歳、女性78.0歳)はヨーロッパで4番目と3番目に短く、健康寿命はウクライナ(男性60.6歳、女性67.8歳)・ロシア(男性60.7歳、女性67.5歳)がヨーロッパで2番目と3番目の短さだと書かれていたが、(死亡原因をよく見なければわからないものの)癌や白血病が多ければ原子力の多用、心臓病が多ければ肥満などの生活習慣病が考えられる。一方、フィギュアスケートや体操でアジア系の人やワリエワのような大人の身体になる前の女性が有利な理由は、小さい方が激しい動きをしやすいからであり、大人になって体重の増加が著しすぎるのは食ベ物の影響だろう。そのため、マクドナルドの店舗を使わないのなら、従業員が独立してロシア国内で採れる作物から蕎麦・海鮮料理・中華料理などの動物性脂質が少なくて美味しい物を作って出したらどうかと思う。そもそも、血管を広げて血流をよくしたければ、トリメタジジンを飲まなくても、①風呂に浸かる(温泉ならなおよい) ②血流をよくする食べ物を食べる(ショウガ、玉ねぎ等)などの方法があり、これなら「ドーピング」などと言われることはない。つまり、現代栄養学だけでなく、*11-6のような東洋の「薬膳料理」も参考にできる。 しかし、*11-3のように、ウクライナから戦火を逃れて国外脱出した避難民が、2022年3月15日までに300万人を超え、バランスのよい食事どころか食事を摂れるかどうかも危うい状況となり、大半の避難民をポーランド・スロバキア・ハンガリー・ルーマニア・モルドバが引き受け、国連は400万人に達するとの想定に基づいた人道支援を計画しているのだそうだ。避難後のことも考えれば文化や言語の近い近隣諸国にいた方が安心だろうが、夫はウクライナに残って母子家庭になりそうな困難は察するに余りある。しかし、*11-4のように、NATOは3月15日・24日に臨時の首脳会議をブリュッセルの本部で開き、バイデン大統領は同日のEU首脳会議にも出席して、ウクライナに侵攻したロシアの脅威が高まる東欧諸国などの防衛に関与する姿勢を明確にし、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの対応や欧州の防衛について話し合うそうだ。ゼレンスキー大統領は、昨日、米議会でオンライン演説し(それは日本でも同時通訳で放送された)、「ロシアのミサイルと飛行機から我々の領空を守ることがどれだけ重要か理解してほしい」とし、米国は制裁等を通じたロシアへの圧力強化や武器供与等の支援を行うそうだ。 日経新聞は、2022年3月17日、*11-5のように、「①ロシアのウクライナ侵攻は多くの人を不確実な状況に陥れたが、一つだけ確かなことはロシアと西側諸国は戦争状態にあることだ」「②欧米の当局者は、『NATOとロシアの戦闘機が直接衝突する事態は避けたい』と言っているが、史上最も厳しい経済制裁を科し、殺傷能力の高い武器をウクライナに供与し、ロシアを孤立させようする欧米は宣戦布告したに等しい」「③国連総会が3月2日に採択したロシアへの非難決議で、ロシアとともに反対票を投じたのはベラルーシと北朝鮮、シリア、エリトリアに留まる」「④中国の将来は経済成長できるかどうかにかかっているため、中国政府はロシアのウクライナ侵攻を非難はしないが、西側の制裁にある程度は従う可能性が高い」と記載している。私は、事実上の宣戦布告をどちらが先に行ったかは疑問である上、国連非難決議での「棄権」は「賛成できない」という意味であるため、棄権と反対を合わせると地球人口の半分が宣戦布告に賛成していなかったと思うのである。    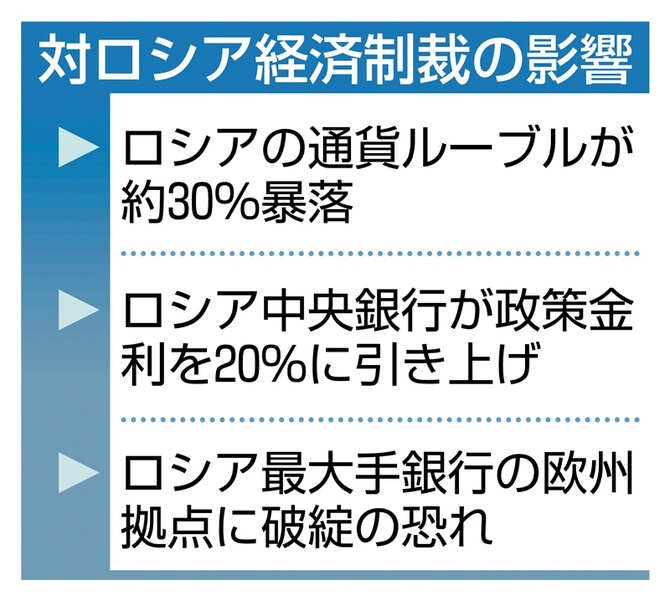 キエフの街 破壊されたオデッサの街 モスクワの街 2022.3.12西日本新聞 (図の説明:1番左がウクライナのキエフの街で、左から2番目が破壊されたウクライナのオデッサの街だ。右から2番目は、ロシアのモスクワの街で、1番右がロシアへの経済制裁の影響だ) *11-1:https://www.fnn.jp/articles/-/330923 (FNN 2022年3月14日) ロシア マック最終日に大勢の客 ユニクロも混雑続く ロシアのウクライナ侵攻を受けて、ロシア国内の全店舗の一時閉鎖を決めたマクドナルドが、13日、最後の営業日を迎えた。1990年から営業を続けてきたマクドナルド1号店には、朝から多くの人が訪れた。「食べ納め」を惜しんで、テーブルクロスや花を用意し、ハンバーガーと一緒にワインを楽しむ客の姿も見られた。マクドナルドは、ロシアに850以上の店舗があり、関係企業を含めると、およそ10万人の従業員がいるが、給与などの支払いは継続するとしている。マクドナルドの客「時代が終わったと感じている」。ロシアで50店舗を展開するユニクロでも、事業の一時停止を発表した日から、大勢の利用客が訪れ、混雑が続いている。一方、モスクワ市内では13日、抗議デモで、これまでに1,000人近くが拘束されている。 *11-2:https://mainichi.jp/premier/business/articles/20220310/biz/00m/020/015000c?cx_fm=mailbiz&cx_ml=article&cx_mdate=20220315 (毎日新聞 2022年3月13日) 平均寿命が短い「ウクライナ」人口減が加速する危機 ロシア軍によるウクライナ侵攻で、民間人に多数の死傷者が出ていると発表されている。ポーランドをはじめとする東欧のウクライナ隣接国は避難民を受け入れており、避難民の国外への動きは当分収まらないだろう。実はウクライナは1990年代以降、人口が大きく減少してきた。今回は、同国の人口減少に関するデータを見ていく。 ●世界で最も人口減少の激しい国の一つ まず、ウクライナの近年の人口推移をおさえる。同国は、91年にソビエト連邦(ソ連)の崩壊で独立国となった。国連の統計(World Population Prospects 2019)によると、独立時の人口は約5146万人だったが、2020年には約4373万人に減少している。人口の年平均増減率は90~00年にマイナス0.5%、00~10年にマイナス0.6%、10~20年にマイナス0.5%で推移し、世界で最も人口減少の激しい国の一つとなっている。背景には、移民となって国外に人口が流出している問題もあるが、基本的には低い出生率と高い死亡率による自然減が強く影響している。国連や世界銀行などの分析によると、飲酒、喫煙、肥満、高血圧、エイズのまん延などが高い死亡率の原因とされている。 ●平均寿命と健康寿命が短い 世界保健機関(WHO)の統計(Global Health Observatory data)をもとにヨーロッパの平均寿命(19年)について見てみる。ウクライナは男性が68.0歳、女性が77.8歳だ。男性は、ヨーロッパでトルクメニスタンとタジキスタンにつぐ短さとなっている。同国を侵攻しているロシアの平均寿命は男性が68.2歳、女性が78.0歳で、いずれもウクライナにつぐ短さだ。今回の侵攻は、平均寿命の観点で見ると「ヨーロッパで4番目に男性平均寿命が短いロシアが、3番目に短いウクライナを攻めている」となる。また、健康寿命(健康上の理由で日常生活が制限されることなく過ごせる年齢寿命、19年)を見ると、ウクライナは男性が60.6歳、女性が67.8歳となる。ロシアは男性が60.7歳、女性が67.5歳だ。男性は、トルクメニスタンについでそれぞれ2位と3位の短さだ。ウクライナもロシアも平均寿命と健康寿命が短い。一方的な侵攻による激しい戦闘が起きていることは不幸としかいいようがない。 ●ウクライナは男性の割合が低い もう一つ注目すべき点として、ウクライナは人口性比(女性100人に対する男性の数)が86.3(国連の統計、20年)で、ヨーロッパではラトビアとリトアニアについで低いことがあげられる。ロシアは86.4で、この点でもウクライナにつぐ水準だ。これは、両国で、飲酒などを原因とした男性の平均寿命の短さが、人口に占める男性の割合の低さとなってあらわれているものとみることができる。今回の侵攻を受けて、ウクライナ政府は18~60歳の男性の出国を禁じた。18~60歳の予備役を最大1年にわたって招集するとしている。今後、戦闘で多くの兵士の生命が失われれば、男性の割合はさらに低下する恐れがある。 ●人口は50年までに19%以上減少の予測 国連の人口予測(中位推計、19年)によると、ウクライナの人口は20年の約4373万人から、50年には約3522万人へと19%以上減少する。この予測は侵攻が起こる前のものだ。 今回の侵攻で多くの兵士や市民が犠牲となったり、国外への避難民が増え続けたりすれば、ウクライナの人口減少は加速する可能性がある。何より、戦闘によるこれ以上の人道上の悲劇をくいとめなければならない。即時停戦でロシア軍の侵攻が止まることを切望する。 *11-3:https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-border-300-idJPKCN2LC22G (Reuters 2022年3月16日) ウクライナ難民300万人超、ポーランドが6割受け入れ=国連 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の集計によると、ウクライナから戦火を逃れて国外に脱出した避難民が、15日までに300万人を超えた。ウクライナ西部リビウ近郊の軍事施設にも攻撃が行われた13日以降、これまで比較的安全とみられていた西部からも避難する人々が出始めたという。難民は300万0381人に上った。大半がウクライナと国境を接するポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、モルドバに滞在しており、中でもポーランドは6割の180万人を受け入れている。またUNHCRによると、これまでに30万人がさらに西の西欧諸国に移動したという。北東部ハリコフから逃れてきたジャンナさん(40)はポーランドのウクライナ国境近くのプシェミシル駅で「ロシア軍がリビウへの攻撃を始めるまでは、ウクライナ西部は安全だと誰もが思っていた」と話した。国内で避難するつもりだったがリビウなどへの攻撃が始まり、小さな子どもがいるため、国外への避難を余儀なくされたと語った。夫はウクライナに残ったという。国連はウクライナからの避難民が400万人に達するという想定に基づいた人道支援を計画しているが、近いうちに拡大する必要もあるとの見解を示している。欧州連合(EU)のヨハンソン欧州委員(内務担当)はウクライナからの難民受け入れについて「われわれがベストを尽くして団結すれば、(この難題にも)対処できる」と強調した。 *11-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220316&ng=DGKKZO59120000W2A310C2MM0000 (日経新聞 2022.3.16) 米大統領が訪欧 NATO臨時首脳会議に出席へ、24日、東欧防衛関与を明確に 北大西洋条約機構(NATO)は15日、24日に臨時の首脳会議をブリュッセルの本部で開くと発表した。バイデン米大統領らが参加する。バイデン氏は同日の欧州連合(EU)首脳会議にも出席し、ウクライナに侵攻したロシアの脅威が高まる東欧諸国などの防衛に関与する姿勢を明確にする。両会議ではウクライナへの侵攻を続けるロシアへの対応や欧州の防衛について話し合う見通しだ。NATOのストルテンベルグ事務総長は声明で「この重要な時期に北米と欧州はNATOのもとでともに立ち向かわねばならない」と訴えた。米ホワイトハウスのサキ大統領報道官は15日の記者会見で、バイデン氏がNATO首脳会議に参加し「欧州の首脳と直接会い、ウクライナの現状を評価する」と説明。「ロシアによる不当なウクライナ攻撃に対する抑止力と防衛努力について議論し、NATOの同盟国への鉄壁の関与を再確認する」と述べた。NATOの根幹は集団安全保障を定めた北大西洋条約の第5条で、締約国への武力攻撃を「全締約国への攻撃とみなすことに同意する」と定める。非加盟のウクライナと異なり、防衛義務が生じる。米国防総省はポーランドやルーマニアなどNATO加盟国に米軍を増派しており、バイデン氏は「NATO諸国の領土を隅々まで守る」と繰り返す。ロシアの脅威に対峙する東欧などの抑止力を強化する狙いがある。EUは24~25日にブリュッセルで首脳会議を開く。バイデン氏は24日の討議に対面形式で参加する。EU首脳会議には、ミシェルEU大統領らEU首脳に加え、マクロン仏大統領やショルツ独首相ら27カ国の加盟国首脳が参加する予定だ。サキ氏は「ロシアに代償を科すための努力、影響を受けた人々への人道支援など共通の懸念を話し合う」と強調した。訪欧に合わせてウクライナのゼレンスキー大統領と会談するかを問われ、現時点で決まっていないとも話した。米メディアによると、バイデン氏がウクライナ西隣のポーランドを訪れる案も検討している。ゼレンスキー氏は15日、カナダ議会下院でオンライン演説し「ロシアのミサイルと飛行機から我々の領空を守ることがどれだけ重要か理解してほしい」と語り、NATO諸国にウクライナ上空に飛行禁止区域を設定するよう求めた。16日には米議会向けにオンラインで演説する。制裁などを通じたロシアへの圧力の強化や、武器供与などの支援を米国に求めるとみられる。 *11-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220317&ng=DGKKZO59124770W2A310C2TCR000 (日経新聞 2022.3.17) 後戻りできないロシアと世界 米ユーラシア・グループ社長 イアン・ブレマー氏 ロシアのウクライナ侵攻は多くの人を不確実な状況に陥れたが、一つだけ確かなことがある。ロシアと西側諸国はいまや戦争状態にあるという点だ。欧米の当局者は、北大西洋条約機構(NATO)とロシアの戦闘機が直接衝突する事態は避けたいと言い続けている。しかしいままでで最も厳しい経済制裁を科し、殺傷能力の高い武器をウクライナに供与し、ロシアを孤立させようとする欧米の取り組みは宣戦布告に等しい。世界はいままさに転換点にある。NATOとロシア軍が直接の武力衝突を避けられたとしても、プーチン大統領の譲歩という、いまや想像しがたい事態が起きない限りロシアと西側は「新冷戦」に直面する。だが、こうした対立は多くの点で20世紀の冷戦ほど危険ではないだろう。ロシアの国内総生産(GDP)は米ニューヨーク州よりも小さく、低迷するロシア経済は制裁により今後1年間で10%以上縮小する可能性が高い。かつロシアの金融システムは崩壊の危機にひんしている。かつてソ連と東欧の衛星国の経済システムは西側と切り離されていたため、西側の経済的圧力の影響は(経済圏には)及びにくかった。いまや欧州は米国と結束し、足並みをそろえているのに対し、旧ソ連圏はプーチン氏の引力に逆らおうと抵抗もしている。ソ連には、世界の民衆や政治家を引き付けるイデオロギーの魅力もあった。いまのロシアには特にイデオロギーはなく、政治的価値観を共有する同盟国にも乏しい。国連総会が2日に採択したロシアへの非難決議で、ロシアとともに反対票を投じたのはベラルーシと北朝鮮、シリア、エリトリアにとどまった。キューバですらプーチン氏の軍事行動を支持せず、棄権に回った。ロシアとの関係強化が懸念されている中国はどうか。ロシアに理想的な選択肢があるとはいえない。中ロは米国の国際的な影響力をそぎ、欧州の強硬姿勢を抑えるという点では同じ考えを持つ。だが、中ロ関係ではロシアの立場が弱い。ロシアの10倍の経済規模である中国は、ロシアが西側に売れなくなった石油・ガス、鉱物などを買い、ロシア経済を支えるとみられる。一方で中国は、資源を買いたたこうともするだろう。中国の将来は経済成長できるかどうかにかかっており、欧米とつながり続けられるかがポイントになる。中国政府はロシアのウクライナ侵攻を非難しないだろうが、西側の制裁にある程度は従う可能性が高い。1980年代に中距離核戦力(INF)廃棄条約が発効するなど、欧米とソ連の首脳はアジアやアフリカ、中南米の紛争がエスカレートし、欧州に壊滅的な打撃が及ぶのを防ぐ壁を設置できていた。西側とロシアが新たな外交基盤と信頼回復を築くには、長い年月がかかるだろう。当事国と世界経済にとってはるかに危険な点もある。新冷戦下の武器はさらに強力になっている。両陣営の本当のサイバー能力はわからないが、いずれも金融システムや送電線など社会インフラを標的にし、壊滅的打撃を与えられるとみられる。サイバー兵器は20世紀後半の重火器よりもコストが低く、計画が容易で広範囲に使えるだろう。例えば、4月のフランス大統領選は新たな戦略を試すチャンスになる。11月の米中間選挙なども同様だ。ロシアは、ウクライナをプーチン氏の支配下に置くために攻撃を続けるだろう。だがロシア軍が全土を制圧したとしても、ウクライナ国民は戦いを止めず、西側の首脳はウクライナを支援し続けるだろう。史上最も厳しい制裁はさらに強化されることになる。新冷戦への道はもはや後戻りできない。 *11-6:https://www.yomeishu.co.jp/health/3371/ (Yomeishu) 薬膳とは? いつもの食材でできる薬膳の基本 ●食の知識 薬膳は手間がかかる、高そうな食材を使いそう...と思われがちですが、いつもの食材で簡単に作ることができます。昔から食材には薬と同じような効能があると考えられてきました。薬膳の知恵を使って、季節や自分の体質、体調に合った食材を組み合わせ、毎日を健やかに過ごしましょう。(中略) ●自然界を5つに分類する考え方「五行」 薬膳で基本となるもう1つの考え方に「五行」があります。五行とは、自然界に存在する物質を「木・火・土・金・水」の5つの性質に分けたものです。 ●自分の体と向き合うために「五味」を知る、5つの味でバランスよく 「五味」とは「酸味・苦味・甘味・鹹味([かんみ]塩からい味)」のことです。それぞれに対応する五臓があり、その臓器に吸収されやすいといわれています。例えば「肝」の動きが過剰になってイライラしたり、頭痛があったりするときは、「肝」の働きを抑える「辛味」のものをとるとよいとされています。 ●五味の作用と働き 健康な人であれば、普段の生活のなかで、五味をバランスよく食べるようにすればよいでしょう。 食材の温める力・冷やす力を活かして ●体を「平性」に保ちましょう 食材には体を温めたり冷やしたりする性質(五性)があり、5つのグループに分類されます。体を温める「温性」、体を極端に温める「熱性」、体を冷やす「涼性」、体を極端に冷やす「寒性」、体を温めも冷やしもしない「平性」です。うるち米など毎日食べている食材には平性の物が多くあります。とうがらしやトマトのように、熱性・寒性の物は合わせる食材を工夫してバランスを崩さないように調理し、それだけとることは避けましょう。また、旬の食材にはその季節にふさわしい性質をもつ物が多いのが特徴です。食は毎日のこと。そこに薬膳の考え方をプラスして、賢く料理をしませんか。毎日3回、美味しいと思う食事が365日続いたら、それは幸せな時間を積み重ねていることになります。そこに薬膳の知恵があれば、健康も積み重ねていくことができるのです。 <現在の“経済制裁”は効果より副作用の方が大きい> PS(2022年3月21、22日追加):*12-1のように、日本メディアの多くは、「制裁の抜け穴にならないよう対ロ制裁でアジアの結束に一層の努力が必要」とし、岸田首相も率先して対ロシア政策で制裁に共同歩調をとるようインド・カンボジアに呼びかけられた。また、バイデン米大統領は、「中国がロシアを軍事・経済面で支援すれば、制裁を科す」と示唆されたが、“経済制裁”ではロシア・中国は参らないと思う。その理由は、ロシア・中国は冷戦後の30年間に西側企業を誘致して必要な技術や経営ノウハウを吸収し、既に自国生産が可能になっているからだ。そのため、原料・エネルギー・労働力を持つ国は自国生産に切り替えれば経済制裁に対抗できるが、それらを海外依存している国は物資不足になる。そのため、現在では、日本が“経済制裁”をすると、自国の経済への悪影響の方が大きいと思われるのだ。 また、*12-2のように、バイデン米大統領が中国への制裁も念頭に、中国が対ロ支援した場合の影響と結果について警告すると、中国の習国家主席は「①制裁がエスカレートすれば、世界経済や貿易、金融、エネルギー、食糧、産業、供給網に深刻な危機をもたらす」「②既に低迷している世界経済をさらに麻痺させ、取り返しのつかない損失を引き起こす」と言われたそうで、私は①②が本当だと思った。また、「③制裁の切り札と見定めるのが、世界の基軸通貨としての米ドルが強い影響力を持つSWIFTからのロシアの締め出し」とも書かれているが、経済・金融を武器として使い続ければ、“制裁”される側もそれに対応して準備するため、基軸通貨としての米ドルへの信用が下がるのも否めないわけである。 なお、*12-3についても、“経済制裁(=戦争)”しながら「平和条約交渉」はないため打ち切られるのが当然で、政府がメディアと一緒になって「日本には日本の国益がある」ということを考えず、適時に必要な手も打ってこなかったことに原因があるため、どうしようもない。 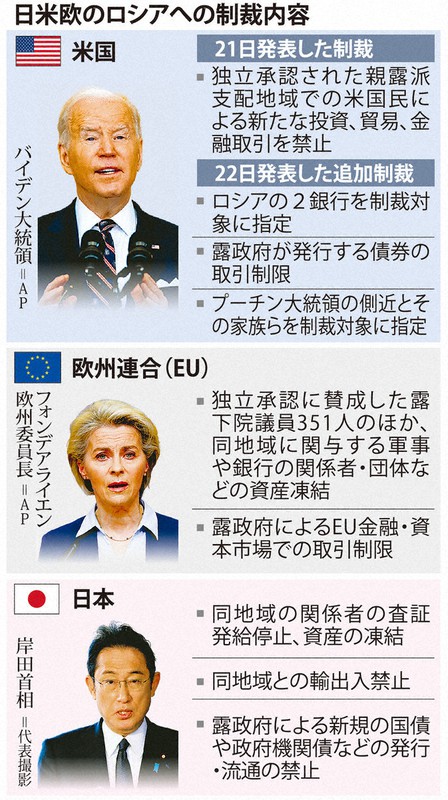   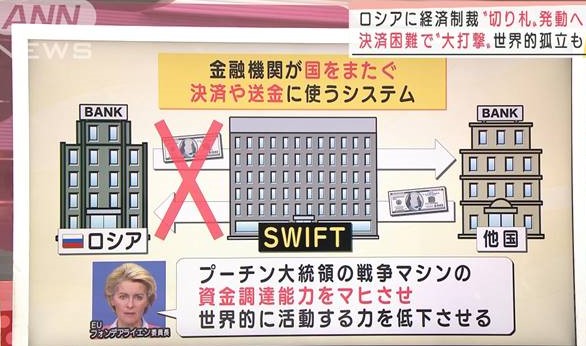 2022.2.23 2022.3.20 2022.3.20 2022.2.27TV朝日 毎日新聞 福井新聞 毎日新聞 (図の説明:1番左の図のように、2月21、22日には欧米と日本が相次いでロシアへの制裁を行い、左から2番目の図のように、3月19日に岸田首相はインドに対ロ非難を促した。また、右から2番目の図のように、バイデン米大統領は、3月19日に習近平中国国家主席と会談して対ロ支援した場合の対抗措置を警告している。さらに、1番右の図のように、ロシアをSWIFTから排除して決済困難にし、世界的に孤立させる制裁も早々に決定されている) *12-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220321&ng=DGKKZO59262820R20C22A3PE8000 (日経新聞社説 2022.3.21) 対ロ外交でアジアの結束に一層の努力を 岸田文雄首相とインドのモディ首相が会談し、ロシアのウクライナ侵攻を念頭に「力による一方的な現状変更はいかなる地域においても許してはならない」と確認した。国際社会で外交努力が加速しており、日本もアジア諸国などの結束に指導力を発揮すべきだ。日印両国と米国、オーストラリアは5月にも日本で「Quad(クアッド)」の首脳会談の開催を予定する。岸田首相がロシアと伝統的な友好関係にあるインドを今年初めての外国訪問先に選び、首脳間の信頼関係づくりに努めたのは評価できる。ロシアへの制裁措置をめぐり日米欧と一線を画すインドとの溝もあらためて浮き彫りになった。岸田首相が対ロシア政策での共同歩調を呼びかけたのに対し、モディ首相はロシアを名指しはせず、両首脳の共同声明にもロシアという言葉が入らなかった。国連総会のロシア非難決議でインドが棄権したのは極めて残念だ。印ロ首脳は昨年末に会談し、武器調達など軍事協力も進める。対ロ政策でインドと完全に足並みをそろえるのは難しくとも、制裁の抜け穴にならないよう民主主義陣営に引き付けておくのが肝要だ。岸田首相が次に訪れたカンボジアは、東南アジア諸国連合(ASEAN)の今年の議長国だ。日米が主導する「自由で開かれたインド太平洋」の実現に欠かせない地域であり、カンボジアなど中ロとの関係が深い国々にも粘り強く協調を働きかける必要がある。林芳正外相は同時期にトルコ、アラブ首長国連邦(UAE)を訪問した。トルコはロシア、ウクライナ両国と緊密な関係を保ち、今回も積極的な仲介外交を重ねる。原油市場の安定に向け、日本の原油輸入先で第2位のUAEとの協力強化も意義がある。こうしたなか米中首脳がテレビ会議形式で協議した。バイデン米大統領は、中国がロシアを軍事、経済面で支援すれば制裁を科すと示唆した。中国はロシアへ影響力が大きく、その対応次第では世界秩序を大きく左右しかねない。大事な局面を迎えている。権威主義国家の暴挙を許さず、東アジアへの波及を阻止しなければならない。民主主義や法の支配を守るのは日本の責任でもある。中国と歴史的、人的関係の深い日本が米国と連携し、中国を完全にロシア側に付かせないための巧みなアプローチが求められている。 *12-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15239690.html?iref=pc_shimenDigest_top01 (朝日新聞 2022年3月21日) (経済安保 米中のはざまで)米ドル覇権、制裁の効果左右 SWIFT、中国・ロシアは対策 「制裁がエスカレートすれば、世界経済や貿易、金融、エネルギー、食糧、産業、供給網に深刻な危機をもたらす」。18日のテレビ電話による米中首脳会談。中国の習近平(シーチンピン)国家主席は、バイデン米大統領が中国への制裁も念頭に、中国が対ロ支援をした場合の「影響と結果」について警告すると、逆にこう切り返した。習氏はさらに「すでに低迷している世界経済をさらにまひさせ、取り返しのつかない損失を引き起こす」とも強調。あえて「世界経済」を持ち出し、米国が対ロ支援を理由に中国に制裁を科すことがないよう牽制(けんせい)した。一方、米国は中ロの接近を警戒。軍事介入を見送りつつ、経済・金融を「武器化」してロシア封じ込めを狙う。とりわけ、制裁の切り札と見定めるのが、世界の基軸通貨としての米ドルが強い影響力を持つ「国際銀行間通信協会(SWIFT)」からのロシアの締め出しだ。締め出しをくらえば、お金のやりとりが難しくなる。この制裁の厳しさを、ロシア側は「宣戦布告にあたる」(メドベージェフ元首相)とかねて牽制してきたほどだ。だが、中国がロシアを支援すれば、その制裁の効果は薄まる。米国の懸念の伏線は、2月の北京冬季五輪での中ロ首脳会談にあった。開会式出席のため、北京を訪問したロシアのプーチン大統領は、中国国営メディアに「一方的な制裁のマイナスの影響を取り除こうと、我々は自国通貨での決済を拡大し、システムを構築してきた」と寄稿。米ドル覇権が及ばない仕組みを構築してきたことを自負した。実際、外交筋によると、同月4日の習氏との会談で、SWIFTから排除された場合の対応策について協議したという。ドルは国際決済額の4割、各国政府が対外支払いのために持つ外貨準備の比率で6割を占める。米国が関わらない二国間の貿易でも、多くの取引で米ドルが使われる。仲介するのも米金融機関だ。制裁でドル取引が禁じられれば、貿易や投資は著しく滞る。米ドルの威力を最小限にとどめられないか――。ロシアはこれまでも外貨準備から米ドルの比率を減らし、2014年のクリミア併合による対ロ制裁を機に、ロシアの通貨ルーブル版SWIFTとして「SPFS」と呼ばれる組織を設立。外国からはカザフスタンなどの数十行しか参加せず、代替にはほど遠いのが現状だ。SWIFTからの締め出しでロシアの国内総生産(GDP)の5%が吹き飛ぶともいわれる。「備え」を着々と進めているのが中国だ。15年には、SWIFTを使わず、人民元で決済できるシステム「CIPS」を設立。参加国・地域は100を超える。世界的な金融産業の業界団体・国際金融協会(IIF)はウクライナ侵攻を受けた2月28日の報告書で、中ロの決済システムの連携を「運用可能なのかは不透明」としつつ、制裁が「ロシアを中国との関係強化へと押しやる無視できないリスクがある」と警告した。通貨は国家の安全保障の根幹を担い、経済安全保障の核心を握る。米ドルと人民元の力の差は、米国と中国の軍事力の差よりもはるかに大きい。だが将来、「米ドル覇権」が崩れるのか、通貨秩序は国際秩序にも影響する。 *12-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB2149G0R20C22A3000000/?n_cid=NMAIL006_20220322_A (日経新聞 2022年3月22日) ロシア、平和条約交渉打ち切り 日本の制裁に反発 ロシア外務省は21日、日本が米欧と歩調を合わせて発動した対ロ経済制裁を巡り「日本との平和条約締結に関する交渉を継続するつもりはない」との声明を発表した。ロシアとの間で領土問題を解決して平和条約を締結するとの日本の一貫した立場が拒否された。ロシアはウクライナへの軍事侵攻を巡り、欧米諸国だけでなく日本からも厳しい制裁を受けた。ロシア外務省は「明らかに非友好的な立場を取り、我が国の利益に損害を与えようとしている」と反発した。ロシア外務省は21日の声明で、平和条約締結交渉を拒否するとともに、ロシアが実効支配する北方領土にビザなしで訪れることができる「ビザなし交流」の廃止も発表した。旧島民の簡素化された北方領土訪問もなくすとした。さらに日本との間で進めていた北方領土での共同経済活動の実現に向けた話し合いも放棄する考えを示した。黒海の周辺国でつくる黒海経済協力機構のパートナー国としての日本の資格延長にも応じないと明記した。声明では、こうした対抗措置を発表したうえ、日ロ関係悪化の責任は「反ロシアの方針を選択した」日本政府にあると一方的に非難した。日本とロシアの前身であるソ連は1956年、日ソ共同宣言に調印し、第2次世界大戦後の2国間関係の再建に着手した。同宣言では平和条約締結後に北方領土のうち歯舞群島と色丹島を日本に引き渡すと明記した。安倍晋三首相(当時)は2018年、プーチン大統領との会談で、同宣言を基礎に平和条約交渉を加速させることで合意していた。ロシアが日ロ平和条約の締結交渉を一方的に拒否したことは、戦後、両国が取り組んできた関係改善の道筋を閉ざすことを意味する。 <日本は化石燃料資源もないのに、外国の化石燃料にしがみつく国である> PS(2022年4月1日追加):*13-1のように、ニューヨーク・マーカンタイル取引所では、米政府が大規模な戦略石油備蓄の追加放出を発表して、原油先物相場は1バレル100.28ドルと反落したが、日本では、*13-2-1のように、自民、公明、国民民主の3党が原油価格高騰対策として石油元売りへの補助金と、ガソリン税の「トリガー条項」凍結解除を政府に迫っているそうだ。また、*13-2-2のように、米欧と一緒になってOPECプラスに大幅な追加増産を要請し、今後も強い増産圧力を続けるそうだが、原油備蓄は日本も行っており、現在の相場は戦時の一時的なものでもあるため、備蓄を放出すればよい。また、1年前より7割高い程度なら、ガソリン車からHV・EVに変え、再エネや省エネ設備を導入すれば吸収できる筈で、そういう根本的な解決をしないから製造業の輸出競争力もなくなり、エネルギー・食糧を大きく輸入に依存しつつ補助金をばら撒いて現状維持に汲々とすることになるのであり、判断ミスも甚だしいのだ。 さらに、*13-3のように、①電力会社の発送電分離は既に終え ②都市ガス会社のパイプラインを製造部門と小売部門とに分ける「導管分離」が4月1日に実施されるそうだ。しかし、①は、安定供給への責任という論理を振りかざして地域独占による無競争状態に胡坐をかいていた大手電力だけでなく、新電力にも電力市場を開放するのに必要不可欠だったが、②のパイプラインの製造・小売部門の分離は、2社以上のガスを1導管で運搬できるわけではないため、あまり意味がありそうに見えない。さらに、100%近くを外国に依存している化石燃料の価格上昇を原因として、何かといえば「安定供給への責任」を言い立てて何十年も状況を改善しないのは、日本独特の不合理な現状維持である。 *13-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220401&ng=DGKKZO59605800R00C22A4MM0000 (日経新聞 2022.4.1) NY原油反落、一時100ドル割れ 米の備蓄追加放出で 3月31日のニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)で原油先物相場は反落した。WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)で期近の5月物は前日比7.54ドル(7.0%)安の1バレル100.28ドルで取引を終えた。一時は1バレル100ドルを割り込んだ。米政府が大規模な戦略石油備蓄の追加放出を発表し、原油需給の逼迫が和らぐとの見方から売りが出た。 *13-2-1https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220331&ng=DGKKZO59555460Q2A330C2PD0000 (日経新聞 2022.3.31) ガソリン補助金「必要」 自公国が実務者協議 自民、公明、国民民主の3党は30日、国会内で原油価格高騰の対策について実務者の協議を開いた。ガソリン税を一時的に下げる「トリガー条項」の凍結を解除するかどうかにかかわらず、石油元売りへの補助金が必要との認識で一致した。 *13-2-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR31CD60R30C22A3000000/ (日経新聞 2022年3月31日) OPECプラス、原油増産ペースを実質維持 対ロ協調重視 石油輸出国機構(OPEC)とロシアなど非加盟の主要産油国でつくる「OPECプラス」は31日、現行の段階的な原油増産を実質的に据え置いた。ウクライナに侵攻し米欧と対立するロシアとの協調の枠組みを重視し、米欧が期待した大幅な追加増産を見送った。OPECプラスは同日オンラインで開いた閣僚協議で、5月は増産幅を日量43万2千バレルにすることで一致した。毎月日量40万バレルずつ増産してきた従来の合意を「再確認する」としたうえで、基準となる生産量を微修正した。次回は5月5日に協議する。協議後の声明で、原油相場の激しい値動きは「ファンダメンタルズでなく、進行中の地政学的な展開によるものだ」と表明。ロシアのウクライナ侵攻で生じた供給懸念の責任を負わない姿勢をにじませた。国際エネルギー機関(IEA)はロシアからの石油輸出が日量250万バレル減ると予測し、穴埋めの余力を持つサウジアラビアなど中東産油国に対し、米欧日が相次いで増産を働きかけていた。他の産油国が代わりに大幅増産すればロシアにとっては敵に塩を送る行為になり、OPECプラスの結束を揺るがす。どの産油国にとっても原油高は追い風で、高値を維持したいのが本音だ。サウジとバイデン米政権との間に吹く隙間風も、増産要請に応じない一因との見方がある。サウジはイエメンの親イラン武装勢力との戦いで米国の支援が弱いと感じ、イラン核合意の再建にも不満を抱く。対照的に中国との関係強化の動きを強めている。ニューヨーク市場のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物は31日、一時1バレル100ドル前後と前日比7%下落した。バイデン米政権が日量100万バレルの石油備蓄を最大180日間にわたり放出することを検討していると報じられ、売りが広がった。IEAも4月1日に石油の協調放出を協議すると伝わった。中国での新型コロナウイルスの感染拡大もあり、相場は上昇一服感があるが、なお1年前より7割高い。OPECプラスの増産が進まず、ロシア産原油も調達しにくくなるなかで、有力な代替先が米国だ。米エネルギー情報局(EIA)は2022年の生産量を日量1200万バレルと、前年より85万バレル増えると予測。23年はさらに同100万バレル近く増える見通しだ。それでもロシア産原油の供給減少分をすべて補えるわけではない。サウジなどOPECプラス構成国が需給の鍵を握る状況は変わらないため、今後も消費国からの強い増産圧力が続きそうだ。 *13-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220331&ng=DGKKZO59558010Q2A330C2EA1000 (日経新聞社説 2022.3.31) 電力・ガス改革は不断の改善を 都市ガス会社のパイプライン部門を、製造・小売部門と法的に分ける「導管分離」が4月1日に実施される。東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの3社が対象となる。電力会社の発送電分離はすでに終えた。今回の導管分離によって、1990年代から段階的に進めてきた電力・ガス市場改革はひとまず完成する。ただ、足元で電力・ガス供給は改革のひずみともいえる様々な問題が表面化している。安定供給を確保し、競争を促す制度への不断の見直しを続ける必要がある。導管分離はガス事業への企業参入を促すのが狙いだ。都市ガスを需要家に届けるパイプラインの運用を中立化し、新規事業者がより公平な条件で使えるようにして競争環境を整える。20年に実施した発送電分離では、沖縄電力を除く全ての大手電力会社が分離の対象になった。190社以上ある都市ガス会社では一定規模以上のパイプラインを持つ大手3社が対象となる。全額出資の子会社を設立し、3社以外は企業内で会計上の分離を求める。電力・ガスの小売り全面自由化以降、電力は700以上、ガスは90以上の事業者が新たに参入した。全販売電力量に占める新電力のシェアは2割を超え、家庭用ガスは15%超が契約先を変えた。電力会社がガスを売り、ガス会社が電力を売る相互参入も進んだ。地域独占を転換し、消費者が事業者を選べるようにしてサービスや料金の競争を促す狙いは、一定の成果があったといえる。一方、足元では燃料価格の上昇により、新電力が販売用電力を調達する卸電力市場の価格が急騰している。増大する費用を転嫁できずに業績が悪化し、撤退も相次いでいる。都市ガス原料の液化天然ガス(LNG)も高値が続く。3月22日には関東・東北で危機的な需給逼迫が起きた。電力もガスも、誰が安定供給に責任を持つのかを明確にしたうえで、そのための仕組みの改善を続けていかなければならない。 <“民主主義国”と言いながら、人(=人材)を人間として大切にしない国、日本> PS(2022年4月2、3日追加): 日経新聞は、2022年3月19日、*14-1-2のように、①ロシアが侵攻したウクライナで人道危機が深まり ②ウクライナ国内で避難生活をしている住民が推計650万人にのぼり ③国外への避難民とあわせて総人口の1/5以上の1000万人に迫り ④さらに1200万人以上が攻撃で退避を阻まれており ⑤南東部マリウポリを包囲していたロシア軍が中心部に入って市街戦になった と報じ、読売新聞は、2022年3月30日、*14-1-1のように、⑥国外に逃れたウクライナ難民が400万人超えた と報じている。 そして、日経新聞は、*14-1-3のように、2022年4月2日、⑦ロシア軍が包囲するマリウポリでICRCの支援チームが50台以上のバスで市民を退避させる筈だった住民退避が難航し ⑧人道支援物資の搬入が拒否され ⑨マリウポリ市内にはなお約17万人が残され ⑩市内は長引く包囲と無差別攻撃で水・食料・医療品が欠乏して人道危機が深刻になり ⑪米戦争研究所はマリウポリが数日以内に陥落すると分析している と報じており、平穏な生活をしていたウクライナの人々には地獄の日々が続いているようだ。しかし、*14-1-2のように、ゼレンスキー大統領はじめ西側諸国は、⑬ロシア軍による当初の計画は失敗した ⑭対話はロシアが過ちによる被害を減らす唯一の手段だ と豪語しており、こういうことを言っている限り、ロシアは後に引けず攻撃が続くだろう。そして、交渉が続いている間、生き地獄は続くのである。 そのような中、*14-2-1のように、林外相が、4月1日の夜、現地ニーズや避難民受け入れの課題を把握して今後の支援に繋げるため、ポーランドに向けて羽田空港から政府専用機で出発され、帰国の際に受け入れを希望する避難民を政府専用機に同乗させるそうだが、そもそも日本には、3月2日~30日に337人のウクライナ避難民しか入国していない。また、政府は4月1日、UNHCRを通じてウクライナ避難民に毛布とビニールシート、スリーピングマットを配布することを決めたそうだが、いずれも一時的な避難を前提としており、長期滞在するための支援に欠けている。そのため、私は、*14-2-3の米ハーバード大のティーンエージャー2人が立ち上げた避難民に受け入れ先を紹介するサイト「ウクライナ・テイク・シェルター」は本当にクールだと思った。これは、ウクライナ政府も太鼓判を押すサイトで、避難民が所在地を入力すると世界中の受け入れ候補が表示され、受け入れ先・利用可能な部屋数・ペットの可否・使える言語・滞在可能期間が一覧で表示され、開設から約3週間で数千人以上が利用したそうだ。日本政府は、この「ウクライナ・テイク・シェルター」に表示された受け入れ先と日本国内の受け入れ先との条件を比較すれば、現地ニーズや避難民受け入れの課題を容易に把握できそうだ。 *14-2-2は、⑮日本政府はウクライナ避難民の受け入れに積極姿勢を示し、支援に手を挙げる地方自治体も相次ぐ ⑯岸田首相は『ウクライナの人々との連帯を示し、人道的な観点から対応する』として避難民受け入れを表明した ⑰避難民らの入国時の在留資格は基本的に旅行者と同様の90日間の「短期滞在」の在留資格になった ⑱古川法相は3月15日、短期滞在から就労可能な1年間の「特定活動」への変更を認めると追加支援を発表し ⑲首都圏では神奈川や茨城が県営住宅、横浜が市営住宅を提供する方針を表明し ⑳人道支援の募金も始めた と記載しているが、いずれも「可哀想だから」という理由で一時的滞在を認めているにすぎず、難民になった人の生活や人生の再建を考えていない。 また、*14-2-2は、㉑海外で紛争や弾圧がある度に、国や自治体が今回のウクライナ侵攻と同じ素早さと手厚さで対応しているわけではなく ㉒ミャンマー人の在留期間は6カ月が基本で就労時間に週28時間の上限が設けられる人もおり ㉓人道的配慮をアピールしても腹の底ではミャンマー人に疑いの目を向けるいやらしさが漂い ㉔日本には50万人超が国内避難民となり約5万人が隣国に逃げているクーデター後のミャンマー避難民を受け入れる特別な仕組みはなく ㉕緊急避難措置でも8割が難民認定されておらず ㉖差別的意識は変わっていないし、日本がトルコ出身のクルド人を難民認定した例はない とも記載している。つまり、ウクライナの避難民の受け入れは積極的な方で、ミャンマー人・クルド人等の難民については、受け入れる仕組みさえないが、本当は難民は多様な人材の宝庫でもある。そのため、このように差別と排除の論理を駆使している日本が世界のリーダーになれるわけがなく、(私にとっては残念ながら)そういう国が世界のリーダーになっては困ると言わざるを得ないのだ。 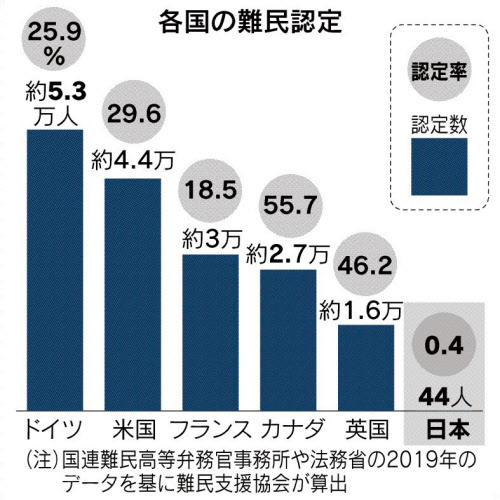 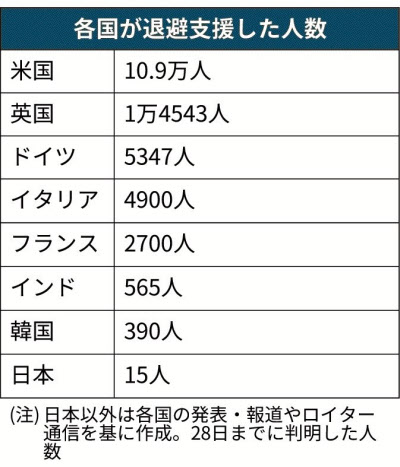  2021.6.3、2021.8.29日経新聞 2021.6.17Goo (図の説明:左図は、2019年の難民認定率で、日本は0.4%と極めて低く、少子高齢化で生産年齢人口の割合が減り、やるべき仕事もできずに産業が衰退しているにもかかわらず、人材鎖国している状態だ。また、中央の図は、アフガニスタンから退避支援した人数で、日本のために働いていたアフガニスタン人すら退避させるという発想がなかった。右図は、2019年のミャンマー出身者の難民認定数と認定率で、これも極めて低い) *14-1-1:https://www.yomiuri.co.jp/world/20220330-OYT1T50261/ (読売新聞 2022/3/30) ウクライナ難民が400万人超える…UNHCRの最大想定人数、5週間で上回る 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は30日、ロシアのウクライナ侵攻に伴い国外に逃れた難民が400万人を超えたと発表した。当初のUNHCRによる最大想定人数を約5週間で上回った。 *14-1-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB191QM0Z10C22A3000000/ (日経新聞 2022年3月19日) 避難民1000万人迫る ウクライナ国民5人に1人、大統領、ロシアに和平協議促す ロシアが侵攻したウクライナで人道危機が深まっている。国連機関は18日、ウクライナ国内で避難生活をしている住民が推計650万人にのぼると発表した。国外への避難民とあわせると1000万人に迫る。総人口の5人に1人以上にあたり、さらに1200万人以上が攻撃で退避を阻まれているという。BBCは18日、南東部マリウポリを包囲していたロシア軍が中心部に入り、市街戦になっていると報じた。首都キエフ市は同日までに民間人60人を含む222人が死亡したと発表した。英国防省はロシアが戦略転換を迫られ「消耗戦」に移ったと分析する。ウクライナのゼレンスキー大統領は19日のビデオ声明で「対話はロシアが過ちによる被害を減らす唯一の手段だ」と述べ、即時の和平協議を促した。英BBCはトルコ高官の話として、ロシアのプーチン大統領がゼレンスキー氏との会談に意欲を示したと伝えた。停戦条件を巡る双方の主張は隔たり、攻撃による被害は拡大している。ゼレンスキー氏は「ロシア軍による当初の占領計画は失敗した」と述べた。いま対話を始めなければロシアの損失が膨らみ、数世代にわたり悪影響が及ぶと訴えた。同氏は侵攻前からプーチン氏に直接協議を求めていたが、ロシアは応じてこなかった。ロシアは駆け引きを続けている。BBCによると、プーチン氏は17日のトルコ大統領との電話協議で、侵攻を止める条件にウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟断念や中立化の確約、ロシアに脅威を与えない形での「非武装化」などを挙げた。直接会談での決着に前向きな構えも示したという。交渉の長期化も懸念される。ウクライナ政府高官は18日、和平協議は数週間以上かかる可能性があるとの見解を示した。米ブルームバーグ通信が報じた。ロシアの対話姿勢が時間稼ぎにすぎないとの見方もある。ロシア通信は19日、国営宇宙開発企業ロスコスモスのロゴジン総裁が「米国が全地球測位システム(GPS)からロシアを切り離すことを検討している」と述べたと報じた。ロシア独自の測位衛星「グロナス」があるため、問題は生じないと主張した。 *14-1-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR01EWZ0R00C22A4000000/ (日経新聞 2022年4月2日) マリウポリに赤十字入れず 住民退避の支援難航 ロシア軍が包囲するウクライナ南東部の港湾都市マリウポリで1日に計画された住民の退避で、支援に向かっていた赤十字国際委員会(ICRC)が同日の現地入りを断念した。2日に再度試みるとしたが、焦点の住民の脱出が難航しているもようだ。一方でウクライナのゼレンスキー大統領は1日、3000人強がマリウポリを脱出したと明らかにした。ICRCの支援チームは50台以上のバスを先導しマリウポリから市民を退避させる運びと伝えられていた。ICRCは1日「民間人の安全な退避促進のためマリウポリに向かったチームが、引き返さざるを得なくなった」との声明を出し、前進が「不可能」とした。これに先立ち、人道支援物資の搬入が拒否されたと報じられ、ロシア側の妨害との見方が出ていた。ロシアは一時停戦して住民を逃す「人道回廊」を1日に設けるとしていた。マリウポリ市内にはなお約17万人が残されているとの見方がある。ロシアは要衝マリウポリの掌握を目指しており、住民を退避させたとして近く総攻撃をかける恐れがある。米戦争研究所はマリウポリが数日以内に陥落すると分析している。市内では長引く包囲と無差別攻撃で、既に水や食料、医療品が欠乏し、人道危機が深刻になっている。一方、トルコのエルドアン大統領は1日、ロシアのプーチン大統領とウクライナ情勢を巡って電話で協議し、トルコでプーチン氏とゼレンスキー氏との首脳会談を開きたいとの意向を伝えた。両国の声明でプーチン氏の反応には言及がなく、前向きな回答はなかったとみられる。 *14-2-1:https://mainichi.jp/articles/20220401/k00/00m/030/237000c (毎日新聞 2022/4/1) 林外相ポーランドに出発 ウクライナ避難民、政府専用機同乗も調整 林芳正外相は1日夜、ウクライナ避難民の受け入れ状況などを把握するため、ポーランドに向けて羽田空港から政府専用機で出発した。帰国の際、受け入れを希望する避難民を政府専用機に同乗させ、日本に渡航してもらう準備も進めている。日本には5日に戻る予定で、林氏は1日の記者会見で「現地のニーズや避難民受け入れの課題を把握し、今後の支援につなげていく」と述べた。政府は当初、古川禎久法相を首相特使として派遣する予定だったが、古川氏が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者になったため林氏の派遣が決まった。中谷元・首相補佐官(人権問題担当)と津島淳副法お相も同行し、ポーランド政府要人との会談や避難民を支援する国際機関との意見交換、支援現場の視察などを実施する。松野博一官房長官は1日の記者会見で、3月2日から同30日までに337人のウクライナ避難民が日本に入国したと明らかにした。また、政府は1日、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を通じてウクライナ避難民に毛布とビニールシート、スリーピングマットを配布することも決めた。UNHCRの要請を踏まえた措置。 *14-2-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/166673 (東京新聞 2022年3月20日) ウクライナとミャンマー、避難民受け入れ、なぜ差があるの? 入管、政治や経済に目配せ「同じように助けて」 ロシアの侵攻を受けたウクライナからの避難民について、日本政府が受け入れに積極姿勢を示している。支援に手を挙げる地方自治体も相次ぐ。難民認定者数が極めて少なく、「冷たい」と言われてきた日本。人道主義に覚醒し、困窮する外国人に分け隔てなく門戸を広げる国に変身した? いや、ウクライナ以外の国への対応に目をやると、答えは「イエス」ではなさそうだ。 ◆就労可能な1年間の「特定活動」認める ロシアのウクライナ侵攻から6日後の2日、岸田文雄首相は記者団に「ウクライナの人々との連帯を示す」と強調し、避難民の受け入れを表明した。1日5000人というコロナ禍対応の入国者数制限からも除外。「日本に親族や知人がいる人の受け入れを想定しているが、それにとどまらず人道的な観点から対応する」と語った。この方針のもと、出入国在留管理庁(入管庁)によると、2日以降15日までにウクライナの避難民57人が入国した。避難民らの入国時の在留資格は基本的に、旅行者と同様、90日間の「短期滞在」の在留資格になる。古川禎久法相は15日の記者会見で、短期滞在から就労可能な1年間の「特定活動」への変更を認めると、追加のサポートを発表した。国の動きを受け、全国の自治体が次々、協力姿勢を見せた。首都圏では神奈川や茨城が県営住宅、横浜が市営住宅を提供する方針を表した。水戸市は市長自ら庁舎にウクライナ国旗を掲揚。人道支援の募金も始めた。神奈川や横浜はウクライナの州や市と友好関係を持つが、同国と特段の縁がない自治体も名を連ねた。 ◆ミャンマー人には制約も ただ、海外で紛争や弾圧がある度に、国や自治体が今回のウクライナ侵攻と同じ素早さと手厚さで対応しているわけではない。例えば、昨年2月1日に軍事クーデターが起きたミャンマー。政府は約4カ月たった5月末、母国の情勢不安のため日本に残りたい在日ミャンマー人に「特定活動」の在留資格を与える緊急避難措置を導入した。入管庁によると、今年2月末までに約4500件の申請があり、約4300件が措置の対象になった。表面上の数字は、ミャンマー人の滞在に寛容にも見えるが「1年間でフルタイムの就労可」のウクライナ人と比べ、制約が多い。まず、在留期間は、特例的に1年のケースもあるが、6カ月が基本だ。就労時間に週28時間の上限が設けられる人もいる。入管庁の担当者は「両国を比較して検討したわけではない」としつつも、ミャンマー人の中に、技能実習や留学の資格で入国後、就労制限なく長期滞在できる「難民」の認定を受けようとする人たちがいる点を制約の理由に挙げる。つまり、在留の根拠が微妙な人たちが、緊急措置に乗っかり、格段に条件のよい在留資格を得ないようにする対策というわけだ。人道的配慮をアピールしつつ、腹の底ではミャンマー人に疑いの目を向けるいやらしさが漂う。 ◆ウクライナ支援は一種の「ブーム」か クーデター後、自治体レベルでミャンマー人支援の広がりはない。先述のウクライナ支援をする首都圏の自治体も、ミャンマー人向けの施策は講じていない。水戸市の担当者はウクライナ支援について「市長が音頭を取り、市を挙げて活動すべきだという方向性になった」と「トップダウン」をにおわせる。 確固たる人道上の信念に基づく支援というより、全体の流れに合わせた一種のブームなのではないか。 ◆「ミャンマーの国民も苦しんでいる」 ミャンマー現地の人権団体「政治犯支援協会」によると、クーデターから18日までに1700人近くが国軍に殺害された。国連難民高等弁務官事務所によると、1日現在で50万人超が国内避難民となり、約5万人が隣国に逃げている。国連人権理事会が設置した独立調査機関は2月1日、国軍の市民への弾圧が「人道に対する罪や戦争犯罪に相当する可能性がある」とする声明を発表した。隣国に侵攻されたウクライナと違いはあるが、深刻な人権侵害が起きている。だが、クーデター後の避難民を受け入れる特別な仕組みは日本にない。「ミャンマーの国民も苦しんでいる。ウクライナの人と同じように受け入れてほしい」。関東地方の40代のミャンマー人女性は、切実な胸中を吐露する。ミャンマーには高齢の親を含む家族がいる。家族はクーデターへの抗議活動に加わったため、転居しながら、国軍の弾圧を避けている。安全な日本に来たがっているが、在留資格を得られないため、叶わない。女性は在日ミャンマー人の仲間と日本で抗議活動をしている。「自分の活動で母国の家族が逮捕や拷問をされないか、私たちはぎりぎりの思いで闘っている」。緊急避難措置では、在日ミャンマー人の難民認定申請者について、迅速に審査し、難民と認められなくても、特定活動の在留資格を与えるとの規定もある。 ◆「緊急避難措置」でも8割が難民認定されず 入管庁によるとクーデター後、11月末までにミャンマー人16人が難民認定された。だが、措置導入後約10カ月たっても、中ぶらりんの人が多くいる。「緊急とは名ばかりで、遅々としている」。全国難民弁護団連絡会議代表の渡辺彰悟弁護士は批判する。渡辺氏が関わるミャンマー人の難民認定申請者165人のうち、約8割の129人に結論が出ていない。結果が出た36人も、難民認定は1家族5人のみ。残りは特定活動だった。結論が出ていない東京都内の女性(38)は14年間にわたり、入管施設収容を一時的に免れる「仮放免」の扱いだ。就労はできず、生活費は友人らに頼る。女性は国軍との内戦が続く少数民族カチン人。2006年以降、4回の難民認定申請をしている。認定を求めて提訴し、20年に地裁で勝ったが、高裁で覆り、不安定な立場のままだ。「緊急避難措置で在留資格を得られると思ったが、入管から連絡がなく、がっかりする毎日」と漏らす。 ◆背景に入管の政治的思惑が 渡辺氏は「入管が政治や経済に目を向けている」と根本的な問題を指摘する。冷戦時代の仮想敵で、北方領土を争うロシアに対しては、日本はウクライナ人保護を含め、欧米と共同歩調で対峙しやすい。一方、ミャンマーには日本は累計117億ドル(約1兆4000億円)の政府開発援助(ODA)を支出。11年の民政移管後は「アジア最後のフロンティア」と官民こぞって進出を図った。関係が悪化し、権益をライバル中国に譲りたくないという思惑が政財界にある。さらに日本はクーデター後、ミャンマーには、対ロシアのような制裁を科していない。軍政にも配慮する姿勢がミャンマー人の処遇に跳ね返るという構図だ。1990年代まで使われた入管職員の教材には、非友好国と比べ、友好国出身者の難民認定は、相手国との関係から慎重になり得るとの記述があった。差別的な意識は「変わっていない」と渡辺氏は厳しくみる。実際、日本国内の難民支援団体によると、日本が「友好国」のトルコ出身のクルド人を難民認定した例はない。2020年の認定総数は47人。年1万人以上の欧米の国々と格段の開きがある。助けを求める人々に対して、格差のある扱い。渡辺氏は「ミャンマーやウクライナの問題を機に見直すべきだ」と訴える。 *14-2-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/167926 (日経新聞 2022年3月26日) ウクライナ避難民の懸け橋に 世界中の受け入れ先検索サイトを米名門大生2人が開設 ロシアによるウクライナ侵攻を受け、避難民に受け入れ先を紹介するサイト「ウクライナ・テイク・シェルター」が話題を呼んでいる。避難民が所在地を入力するだけで世界中の受け入れ候補が表示され、開設から約3週間で数千人以上が利用している。ウクライナ政府も太鼓判を押すサイトを立ち上げたのは、米ハーバード大のティーンエージャー2人だ。「ウクライナ・テイク・シェルター」で、東京都で検索した画面。受け入れ先と、利用可能な部屋数やペットの可否、使える言語や滞在可能期間が一覧で表示される。「ウクライナ・テイク・シェルター」で、東京都で検索した画面。受け入れ先と、利用可能な部屋数やペットの可否、使える言語や滞在可能期間が一覧で表示される。 ◆所在地入力すれば近くの受け入れ先がずらり 「サイトに登録したら、数分後に避難民から連絡が来た」—。サイトをつくった米南部フロリダ州のアビ・シフマンさん(19)のもとには1日に何通も連絡が入る。17歳で新型コロナウイルスの感染状況を分析する世界的に有名なサイト「nCoV2019.live」を立ち上げ、米医療顧問トップのファウチ国立アレルギー感染症研究所長から表彰された経歴を持つ。シフマンさんは2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻に「初めて戦争というものを見て、正気の沙汰とは思えなかった」と、4日後にロシアへの抗議集会に参加。「公園で声を上げるのも大事だけど、自分にはもっと多くの人に役立つグローバルなものをつくることができるはずだ」と感じたという。デモ参加当日に「難民と近隣諸国の受け入れ先を結び付けるサイトを立ち上げたら、クールだろうな」とツイッターに書き込み、大学の友人マルコ・バースタインさん(19)に声をかけて3月3日にサイトを開設した。所在地さえ入力すれば近くの受け入れ先がずらりと並び、使える言語や部屋数など必要情報を一覧してすぐに申し込める。サイトは現在16カ国語に対応しており、極限状態にある避難民のことを考え操作を簡単にした。 ◆3週間で数千人を受け入れ 今後は求人情報も 利用した避難民の数は把握できないが、埋まった受け入れ先の数から「少なくとも数千人」と推測する。避難民の受け入れもこれまで2万5000人が手を挙げており、「近いうちに数10万人になるだろう」。日本からも「片言の英語だけど」「ロシア語を話せる」と支援を申し出る人が後を絶たないという。ウクライナ政府もシフマンさんのツイッターに「重要な仕事をありがとう」と書き込んだほか、メンデル大統領報道官が15日に「若い2人がサイトを立ち上げた」と紹介。シフマンさんは「今後は難民向けの求人情報も載せるとか、シリアやアフガニスタンなど世界中の難民も使えるようにするとか、いろいろ考えていきたい」と、サイトを進化させ続ける考えだ。
| 外交・防衛::2019.9~ | 12:00 AM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2022,01,26, Wednesday
(1)火山の噴火と噴火予知
1)明日は我が身のトンガ海底火山大規模噴火 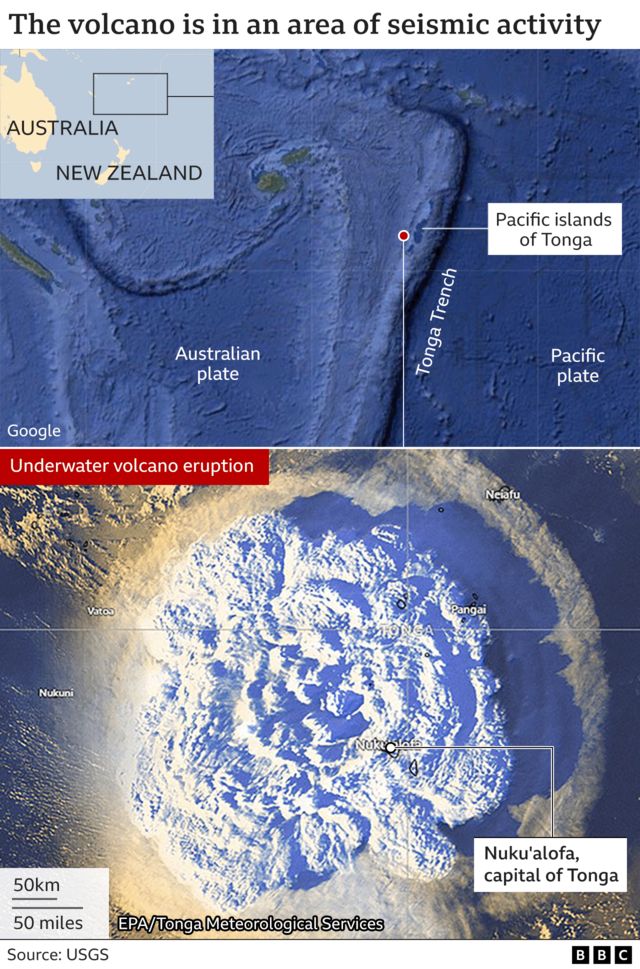  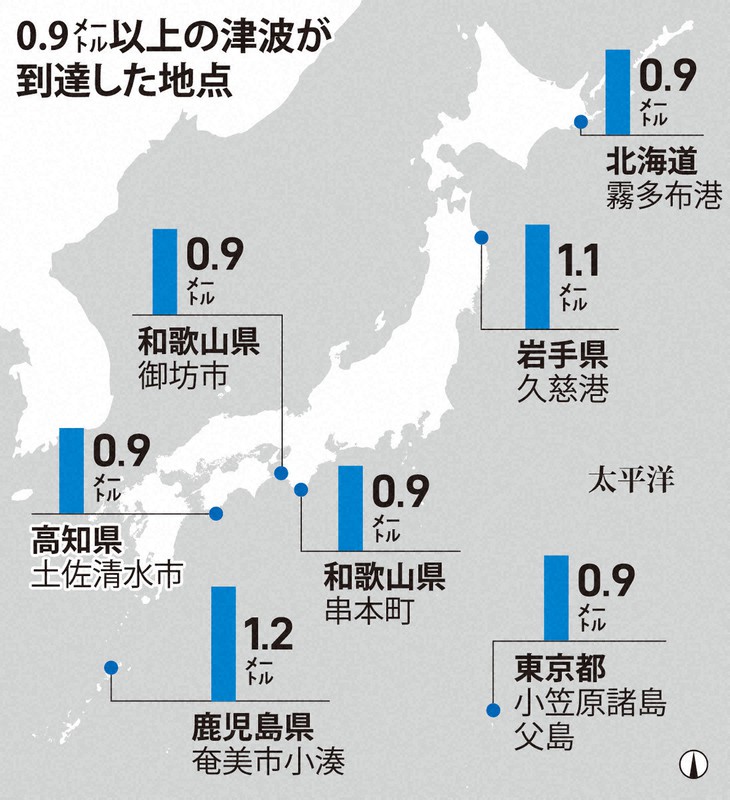 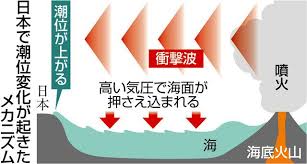 2022.1.16BBC 2022.1.17時事 2022.1.16毎日新聞 2022.1.17中日新聞 (図の説明:1番左と左から2番目の図のように、太平洋プレートがオーストラリア・プレートに潜りこんでいる場所にあるトンガで、2022年1月15日、海底火山が大規模噴火した。日本では、気象庁の予測に反し、右から2番目の図のように、太平洋側を中心に0.9m以上の津波が到達した地点が多かった。気象庁は、「このメカニズムは、これまで経験のない事象だった」とし、1番右の図のように、「噴火によって起こされた気圧変化が空気中を伝わりながら潮位変動を起こし、早く伝わる気圧変化の波と遅れて伝わる潮位変動の波が共振した」と説明している) 日本時間2022年1月15日に、*1-1-1のように、南太平洋の島しょ国であるトンガの沖で海底火山が大規模噴火し、現地では火山灰による農業被害で一部の島で食糧が不足し始め、物流の停滞で石油の備蓄も底をつきつつあり、1週間経ってもインターネットも殆ど復旧していないそうだ。 その爆発時にラジオから避難の呼びかけがあって、沿岸地域の人はいち早く高台に避難したため、津波の被害は小さかったが、雨水を飲料水にしているので水不足が懸念され、灰の付着で作物が枯れて食糧難も発生しつつあり、長期の支援が欠かせないとのことである。 ニュージーランド政府は、1月21日、ヘリコプターを積んだ軍艦、飲料水・淡水化装置を運ぶ軍艦がトンガに到着したと発表し、1月20日には、NZと豪州が支援物資を軍の輸送機で運んだ。日本の自衛隊輸送機も、1月20日、飲料水を運ぶため日本を出発し、中国も水・食糧の輸送を表明済だが、日本から派遣された自衛隊員3人が、*1-1-2のように、新型コロナウイルスに感染していることが確認され、オーストラリアからトンガへの支援物資の輸送ができない状態になっているのは残念なことだ。 新型コロナ禍でトンガは厳しい出入国管理をしているが、損傷した施設の復旧だけでなく将来の災害に備えた強靱な社会を作ることにも支援が必要であるため、支援しながら経験も積むために、自衛隊だけでなく、活火山のある自治体の職員は援助に参加すればよいと思う。この際、災害復興に慣れた日本の自治体が「ふるさと納税」を集め、日本国民からの寄付として一部の救援物資購入費に充てると、日本国民からの誠意ある支援になると思われる。 2)日本における巨大噴火のリスク 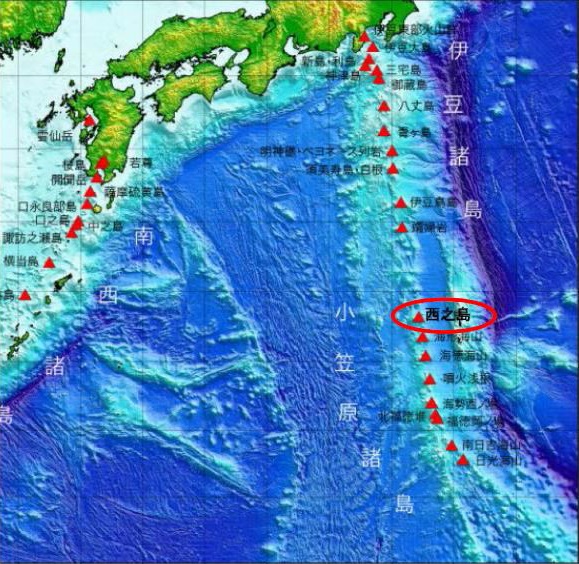  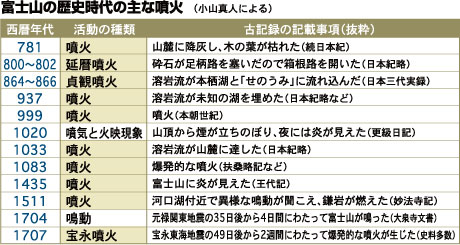 2022.1.21朝日新聞 静岡大学防災センター (図の説明:左図のように、日本も太平洋プレートがフィリピン海プレートに潜りこむ少し先に火山由来の海底山脈があり、海上に現れた陸地が小笠原諸島だ。また、中央の図のように、日本列島付近やその陸地にも、続きと見られる火山が多く、VEI4以上の噴火もしばしば起こる。さらに、小笠原諸島の終わりにある富士山も、右図のように、しばしば噴火しているのである)  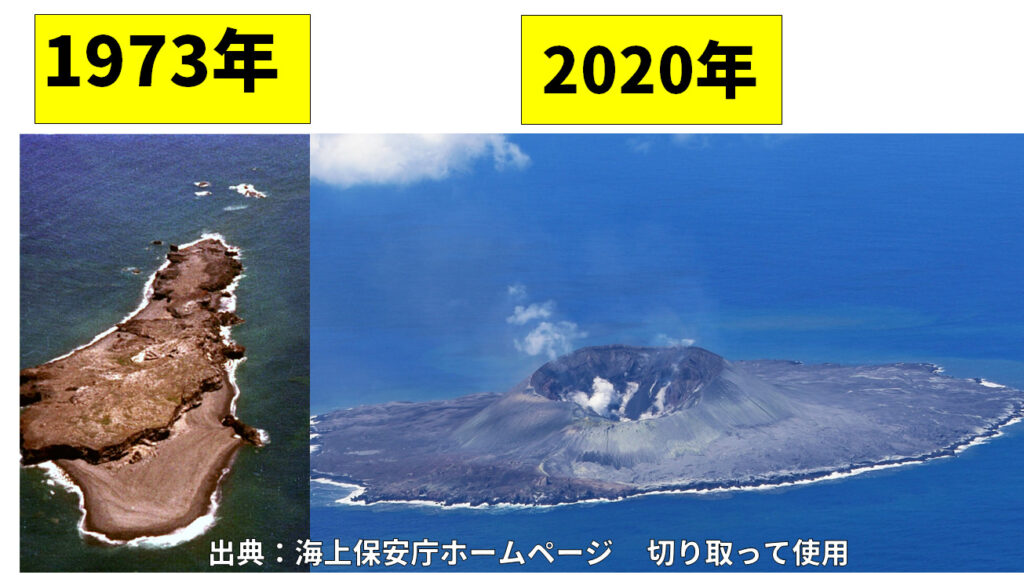 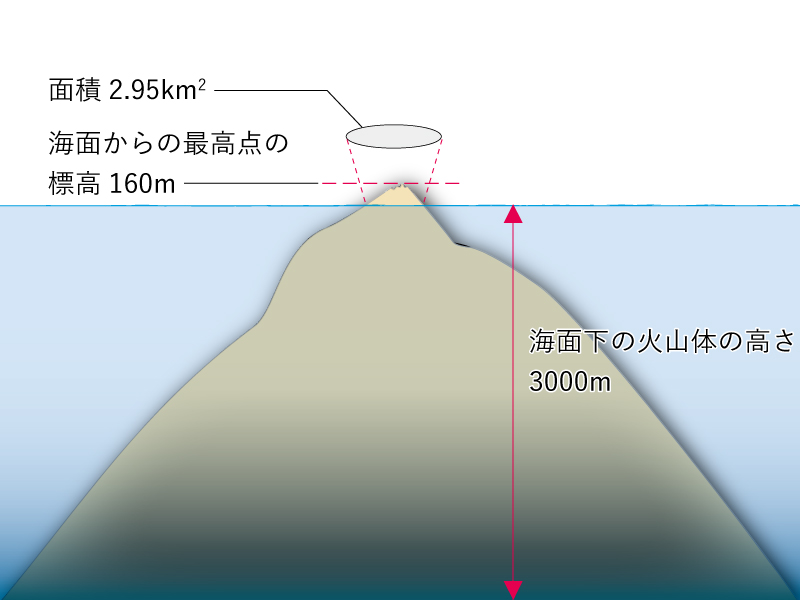 2021.10.23毎日新聞 海上保安庁HPより (図の説明:左図の小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」で2021年8月に起こった大噴火は、噴煙の高さが海上16~19kmに達し、かつては島だった鹿児島県桜島が大隅半島と地続きになった1914年の「大正噴火」に次ぐ戦後国内最大級の大噴火だったそうだ。また、同じ小笠原諸島の西之島は、1973年に有史以来初めて海上で噴火して陸地面積が0.07km²だったが、1999年には陸地面積が0.29km²となり、2013年11月20日に再度噴火し始めて現在は陸地面積が2.95 km²になっている。そして、右図のように、西ノ島の陸上の標高は160mしかないが、海底から見ると3000m以上の火山だ。つまり、地球の地図から海の水を抜いた地図を作ると、小笠原諸島は日本列島と同じく火山によってできた山脈であり、ほかにも海底火山は多いことがわかる) トンガ諸島で発生した海底火山の噴火は、*1-2のように、噴火の規模を示す火山爆発指数(VEI)が6か5だったとみられており、トンガと同じく太平洋プレートが沈み込む場所にある日本も世界有数の火山国でこの規模の噴火を繰り返しており、小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」はVEI4、1914年に鹿児島県の桜島で起きた大正噴火もVEI 4だ。 時代を逆のぼれば、江戸時代1707年の富士山宝永噴火はVEI 5であり、1783年の浅間山噴火はVEI4で天明の大飢饉を起こした。気象庁は、111の活火山のうち、火山噴火予知連絡会が「過去100年程度以内に火山活動の高まりが認められている火山」等の基準で選んだ50の火山を24時間体制で監視しているが、噴火予知は難しいとのことである。 VEIは0~8の段階があって7・8は破局噴火と言われ、日本では600km³もの火山灰が放出され火砕流が九州の広範囲に広がった約9万年前の熊本・阿蘇カルデラ噴火、3万年前の鹿児島・姶良カルデラ噴火、南九州の縄文文化を火砕流で壊滅させた7300年前の鹿児島・鬼界カルデラの噴火がVEI7だったそうで、火山の噴火は原発の審査でも議論になった。 また、政府の中央防災会議作業部会は、2020年、VEI5の富士山宝永噴火と同程度の噴火が再び富士山で発生した場合に想定される首都圏への影響をまとめ、①除去が必要になる火山灰は最大約4.9億m³(東日本大震災の災害廃棄物の約10倍) ②東向きの強い風があれば、灰は3時間で都心に届き、噴火から15日目の累積降灰量は東京都新宿区約10cm・横浜市約2cm・相模原市約30cmで ③微量の降灰でも、地上の鉄道はストップ、視界不良で道路は渋滞、降雨時には0.3cmの降灰で停電、通信アンテナに火山灰がつけば携帯電話等の通信網も寸断 ④木造家屋は降雨時に30cm以上の灰が積もっていれば重みで倒壊する可能性があり ⑤目、鼻、喉への健康被害も生じて喘息等の疾患がある人は症状が悪化する可能性が高い そうだ。 そのほか、大量の溶岩を噴出した864年の貞観噴火クラスの噴火で13億m³の溶岩流が3県27市町村に到達して主要な交通網にも達し、火砕流も1千万m³流れ出て、静岡・山梨両県の10市町村に及ぶそうだ。現在は、日本の人口が首都圏に極端な一極集中をしているため、富士山が噴火した場合の被害は想像を絶するものになりそうである。 (2)火星と月の現在と近未来 1)火星について   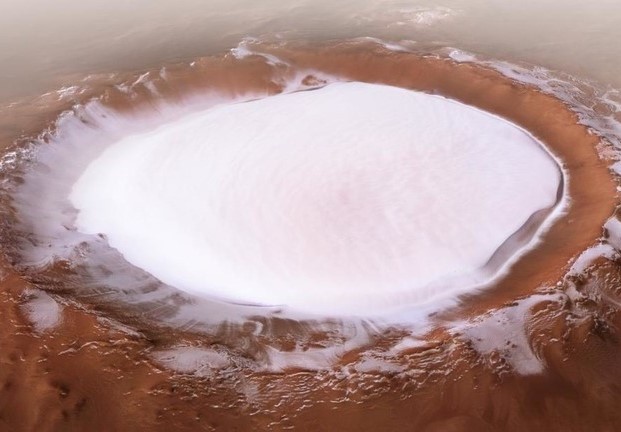 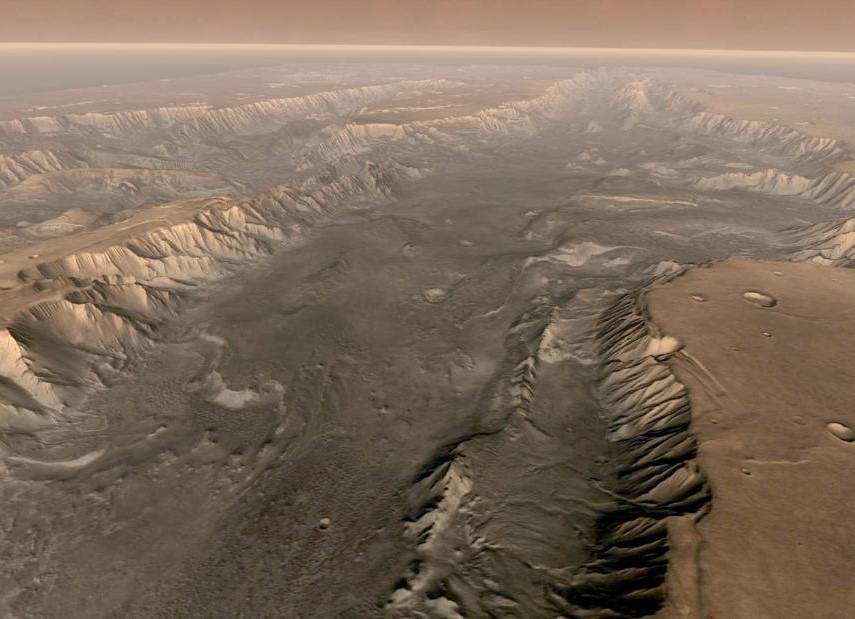 2018.10.23 2013.1.14 2018.1.28 2021.12.17 カラパイア カラパイア CNN CNN (図の説明:1番左の写真は、火星で火山が噴火している様子で、左から2番目の写真は、太陽系最大と言われている火星のオリンポス山《火山で標高25,000m》だが、地球の山も海底から測れば、かなり高い。右から2番目の写真は、火星の極地にある氷だが、1番右の写真のように、マリネリス峡谷を流れている液体の水も発見されている) 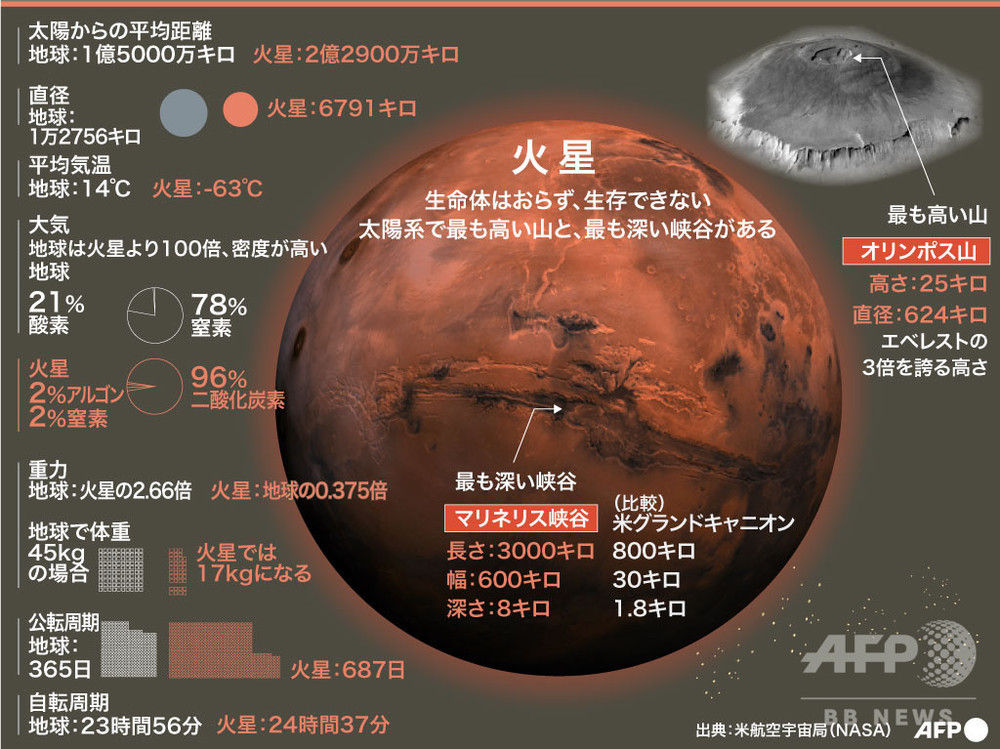 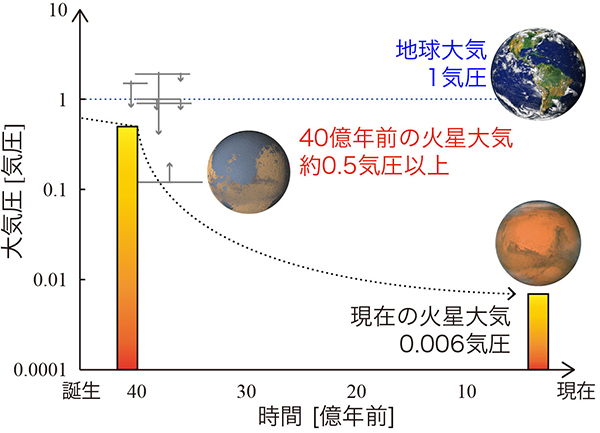 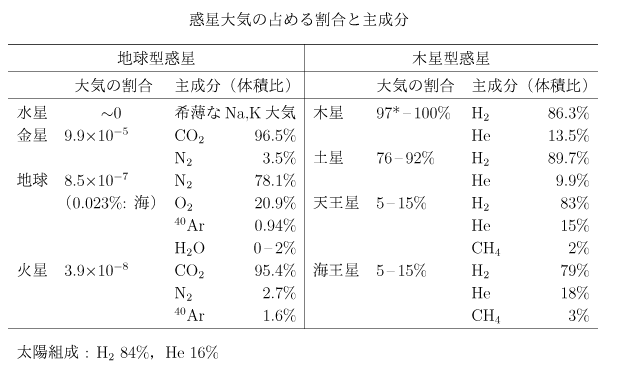 2020.7.20 2017.9.20 2018.4.10 AFPBB News Academist Journal 天文学辞典 (図の説明:左と右の図のように、火星の大気は、地球の1%弱しかなく、大気の成分は、地球がN₂78%、O₂21%、Ar1%であるのに対し、火星はCO₂95%、N₂3%、Ar2%であるため、そのままでは地球の生物は住めないが、一瞬もいられないというわけではない。なお、地球にO₂があるのは、植物の光合成のおかげだ。また、中央の図のように、40億年前の火星には海と陸があり、大気は0.5気圧以上あったが、次第に気圧が下がり、水も減ったのだそうである) 現在の火星の地表の平均気温は約-60°Cで、薄い大気(CO₂95%、N₂3%、Ar2%でO₂はない)と少量の水(極地の氷とマリネリス峡谷を流れる液体の水)があることがわかり、火星に居住することが可能かもしれないという希望になった。しかし、これは日本では全く報道されず、このようなことの連続が日本で理系に親しむ機会が少ない原因なのである。 しかし、40億年前の火星は、*2-1-1のように、0.5気圧以上の大気と液体の水が安定的に存在できる温暖な気候だったのだそうで、それでは何故、火星の環境が大変動したのかが大きな疑問であると同時に、地球の今後に関して考察する上での参考にもなる。 まず、①火星には多くの流水地形や液体の水が存在した鉱物証拠が発見されていた。そして、②火星を液体の水が存在する温暖な気候に保つには、厚い大気と温室効果ガスが必要で ③厚い大気を失ったことが温暖だった火星を極寒の惑星に変貌させた ④厚い大気を失った原因の1つは、火星が地球の10分の1の質量しかないため重力が小さいこと ⑤現在の火星は磁場を持たないため、太陽風が直接吹きつけて大気を宇宙空間へ流出させたこと などが考えられている。 では、「火星の厚い大気が『いつ』『なぜ』失われたのか」については、40億年前に火星で形成されて南極で発見されたアランヒルズ84001という隕石で調査した結果、⑥40億年前の火星は、地表大気圧が約0.5気圧以上という厚い大気に覆われていたが ⑦約40億年前には磁場を持っていた火星が磁場を失ったことで、太陽風が火星の大気の大規模な宇宙空間への流出を引き起こした可能性がある とのことである。しかし、地球の磁場は失われなかったのに、火星の磁場が失われて非常に弱いものになった理由は不明だ。 また、厚い大気に覆われ、地表には液体の水が存在していた40億年前の火星で、生命が誕生しなかったのかについては、将来の火星探査で「火星にはかつて生命が存在した証拠が発見される可能性が十分にある」とのことだ。そして、ここ数年の大きな発見は、「火星はかつて想像されていたような『死の惑星』ではなく、春や夏の比較的温暖な時期に地下から水が湧き出している地域がある」ということがわかってきたため、JAXAが2024年に火星衛星サンプルリターン機MMXを打ち上げる予定で、日本初の火星着陸探査の検討も始まっているそうだ。 なお、「地球の歩き方」という本は私も読んだが、*2-1-2のように、研究者が人類の移住の可能性を探る火星を案内する「火星の歩き方」と言う本を出したのは面白く、開発には環境保全が課題と見据えているのにも感心させられた。 2)月について 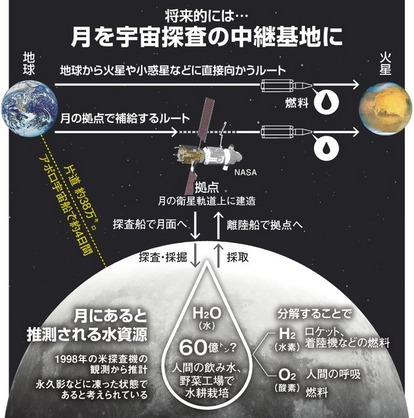 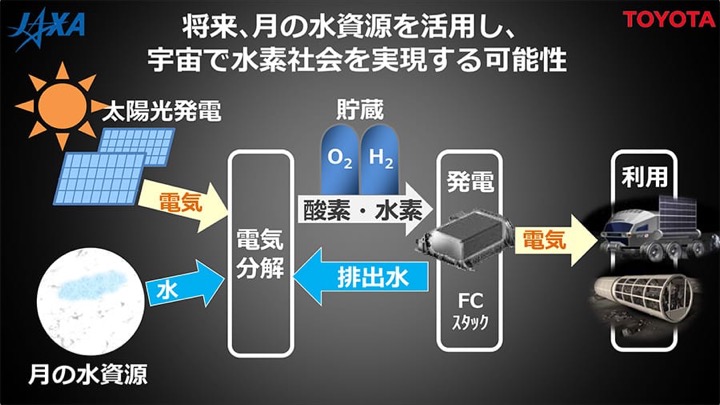 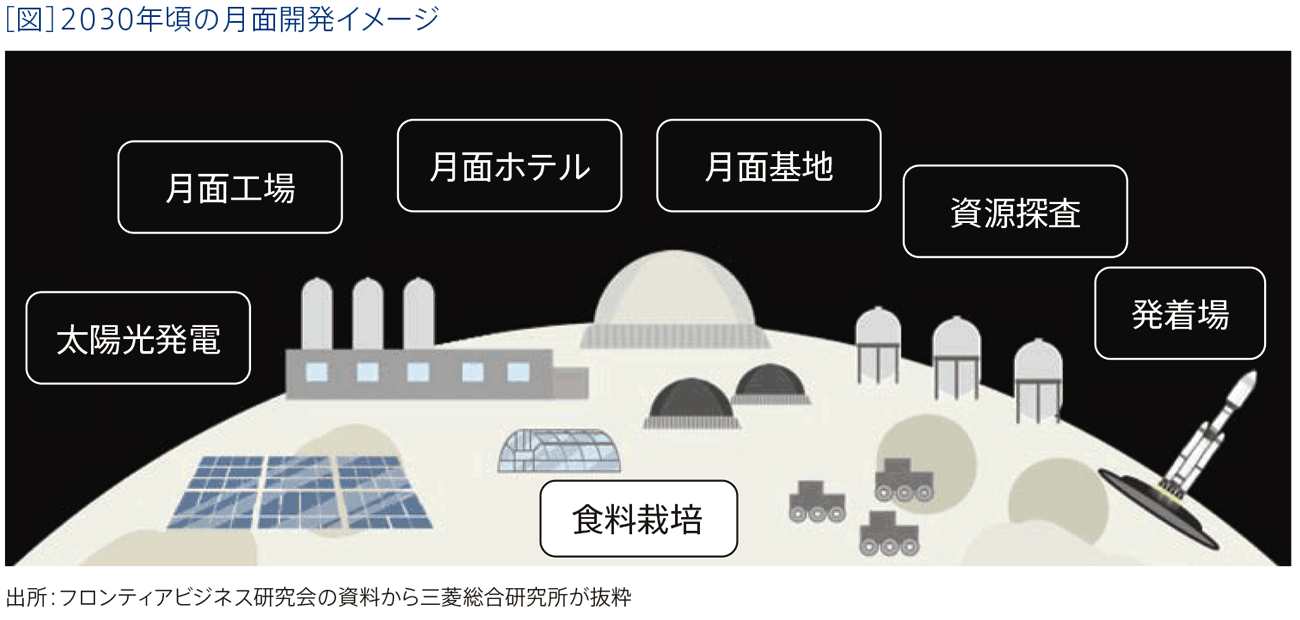 2018.1.9朝日新聞 2019.3.19ToyoTimes 2018.2.1MRI (図の説明:左図のように、月には太陽が当たっている面も含めて60億t程度の大量の水が存在することがわかり、中央と右図のような月面開発が予定されている。しかし、月面に住むには、食料やエネルギーを地球から持って行き続けることはできないので地産地消が必要になる) NASAの探査機LADEEが、*2-2-3のように、隕石が衝突する際に月面から放出される水を検出し、微小な隕石が衝突する際の衝撃によって、年間最大220tもの水が放出されているという論文を発表し、月面付近に大量の水が存在することがわかった。 *2-2-3は、月に水がある理由について、①太陽風に含まれる水素が月面にある酸素と反応 ②月面に衝突する彗星や小惑星に水が含まれる ③月には太古の昔から蓄えられてきた水があり、それが長い時間をかけて徐々に枯渇してきた の3つを記載している。 私は、月・火星・地球の水は、外気圏に移動した後に重力で元の惑星(月や地球)に戻るものもあり、宇宙に出た水(水蒸気)も消えるのではなく、H₂よりH₂Oの方が重いので重力で近くの惑星に吸い寄せられるものが多いと思う。そうすると、地球は質量が大きく空気の層も厚いため戻る水が多く、月や火星は戻る水が少ないことを説明できる。また、温暖化や火山噴火で水が外気圏に移動した後、近くの他の惑星に重力で落下することや、火星表面の水がなくなったこと、近年になって火星や月で多くの水が発見されたことなどを説明できるのだ。 このようにして、地球の水が減ることは由々しきことだが、*2-2-1のように、JAXAを中心とした日本の月探査は、2022年2月以降に初の月面着陸を目指す無人機を米国のロケットで送り込み、2022、2023年度も無人機を計2機打ち上げるそうだ。月を巡る国際競争が激化しており、日本は、宇宙ステーションへの輸送船開発も進んでいて、国際協力で存在感を示し、産業育成に繋げたいのだそうだ。 一方、中国国家宇宙局は、2022年1月28日、*2-2-2のように、宇宙白書の発表にあわせて記者会見し、2030年迄にロシアと共同で月面基地建設を始め、2035年を目途に地球と行き来して月面で活動するためのエネルギー設備や通信システムを基地に整備し、人類が短期滞在する場合には生命維持環境を備えた「小さな村」をつくる構想を披露し、「嫦娥7号では月面の水の分布を調べ、月面基地建設に向けた最初の一歩を踏み出す」と述べたそうだ。 私も、O₂が豊富にない月や火星でH₂を燃料に使うことはできないため、太陽光発電がエネルギー供給の主役になると思う。また、月面で装置を動かしたり、物資を運搬したりするにも、太陽光発電由来の電力が主役になると思われる。 3)現地生産への技術開発 農水省は、*2-3のように、月や火星に人類が進出する未来を見据え、地球上とは全く異なる環境でも農作物を生産し、現地で食料を確保する技術開発に乗り出し、大学や民間企業が参画する産官学プロジェクトを始動したそうだ。 具体的には、①月産、火星産の農産物を現地で食べることを目指し ②人間の健康維持に必要な栄養の大部分を満たせる品目を八つ選定する そうだ。そして、③限られた面積で収量を確保し、美味しい農作物を生産することを基本テーマとし ④大気や日照条件の異なる月・火星で生産するには植物工場のような閉鎖型施設を造り ⑤収量を確保できる環境や設備の研究・実証を進める とのことである。 また、⑥月の砂「レゴリス」でジャガイモ等を栽培する技術の開発を目指し ⑦研究成果は砂漠など地球上の過酷な条件での食料生産に生かすことも念頭に置く そうで、動物性蛋白質を接種できる食品が選抜されていないのは気になるが、全体としては素晴らしい計画だと思う。 (3)エネルギー自給率の向上と気候変動問題への対応 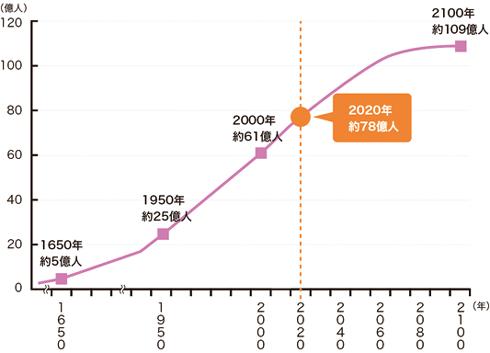  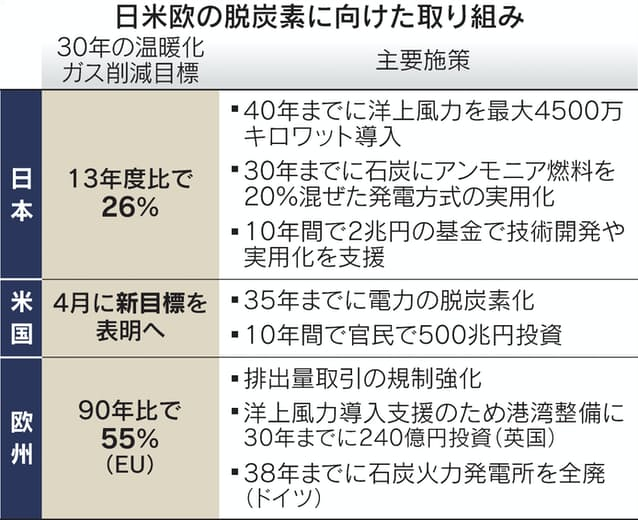 Energia Enechange 2021.3.31日経新聞 (図の説明:左図のように、2020年に78億人だった地球人口は、2100年には109億人になりそうで、1人当たりの平均エネルギー使用量も増えていく。そのため、このままでは、世界のエネルギー需給が逼迫するのは確実で、中央の図のように、エネルギー自給率が著しく低い日本は安全保障以前であるため、再エネによるエネルギー自給率の向上が急務だ。そのため、右図の脱炭素に向けた取組が示されているが、せっかくエネルギーを転換するのに、日本に欠けているのは、「できるだけ地球環境に負荷をかけずに、エネルギー自給率を上げる」という発想だ) 岸田首相は、*3-1のように、「過度の効率性重視による市場の失敗、持続可能性の欠如、富める国と富まざる国の環境格差など、資本主義の負の側面が凝縮しているのが気候変動問題であり、新しい資本主義の実現によって克服すべき最大の課題」と言われたが、この主張は原因と結果が理論的に繋がっていない。 しかし、2020年に衆参両院で気候非常事態宣言決議が可決されたのはよいことで、2050年のカーボンニュートラル実現は必須であるため、日本でも官民が炭素中立型の経済社会に向けた変革をやろうとしているのには賛成だ。しかし、気候変動問題を予算獲得のための枕詞にしている余裕は既になく、資金を効率よく使って最小のコストで最大の効果を挙げなければ、今度は日本の持続可能性がなくなることを忘れてはならない。 そのため、2030年度のCO₂46%削減、2050年のCO₂排出実質0という目標実現に向け、エネルギー供給構造の変革だけでなく産業構造・暮らし・地域全般にわたる大変革に取り組むのは必要不可欠だ。しかし、①送配電インフラ ②蓄電池 ③再エネ ④水素 はよいものの、⑤アンモニア ⑥革新原子力 ⑦核融合は、非炭素というだけで他にはメリットがなく、具体的には、⑤はコスト高で無駄な投資になりそうだし、⑥⑦は日本には適地がないため、遠くの太陽に任せて太陽光発電した方が賢いわけである。 また、発電だけでなく移動手段も、*3-2のように、EVにシフトしなければ化石燃料の使用をやめることができないが、ガソリンスタンドの廃業を受け、人口当たりのEV普及台数は、首位:岐阜県34.8台/人口1万人、2位:愛知県31.3台/人口1万人、3位:福島県30.7台/人口1万人、4位:佐賀県28.2台/人口1万人と、35府県が東京都15.4台/人口1万人を上回るそうだ。 そして、岐阜県の場合は、「道の駅」の7割以上に急速充電器の設置を進め、高山市で環境保護の観点から乗鞍スカイラインでEVレンタカーによる乗り入れを試行し、多治見市で地元の電力小売会社エネファントが小型EVレンタカーを開始したそうだ。 マッターホルンはじめ4000m級の山や氷河に通じる山岳鉄道の基地であるスイスのツェルマットは、環境保護のために、市街地では20年以上前から条例でEVしか走れなくなっており、市街地を走るのはEVと観光用の馬車だけだ。私は、1998年にツェルマットを訪れた時に、それを見て徹底ぶりに感心したもので、日本でも環境を大切にしたい自治体は、EVしか走らせないという条例を作って充電設備を増やせば、それも付加価値になると思う。 また、公共交通機関や商用車もEVシフトを進めて、再エネ発電で電力を賄えば、エネルギー自給率が上がると同時に、安価でクリーンなエネルギーの普及に繋がる。なお、月や火星では、化石燃料はもちろん、O₂を消費するH₂も移動手段の燃料にまでは使えないため、再エネ由来の電力で動くEVを使うしかないだろう。 (4)食料自給率の向上と先進農業 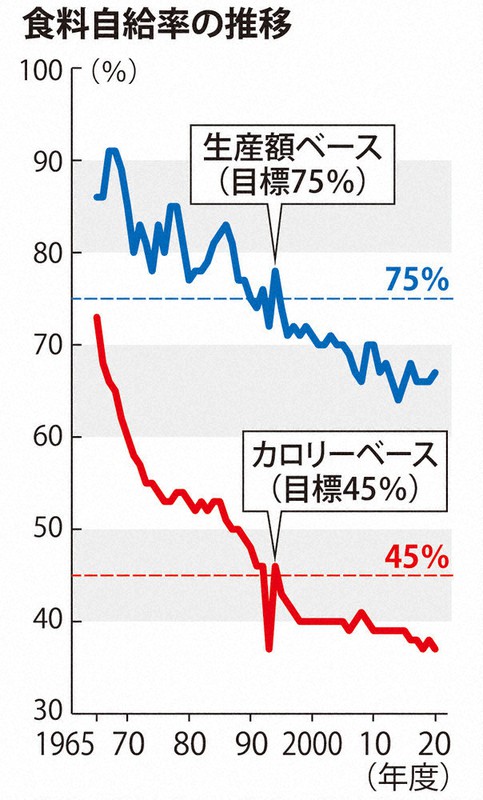  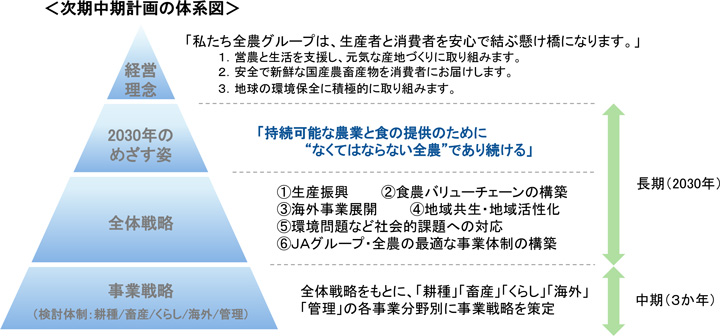 2021.8.26 農水省 2021.11.17JAcom 毎日新聞 (図の説明:左図のように、日本の食料自給率は下降の一途を辿って、2020年度は、中央の図のように、カロリーベース:37%・生産額ベース:67%と諸外国と比較して著しく低い状態になった。カロリーベースよりも生産額ベースが2倍近く高い原因は、カロリーの低い野菜の自給率が高いこともあるが、全体としては価格が高いことが大きな要因であり、これらの農業不振と食料自給率の低迷も、防衛以前の問題である。その解決策の一部を、右図のように、JAが中期計画として掲げており、地域と共生し環境問題を解決しながら農業の発展を目指す重要な視点を含んでいる)     (図の説明:1番左の図は、日本の田園に風力発電機が設置されている様子で、地域と協力して農業地帯に農家が再エネ発電機を設置して電力を副産物にすれば、エネルギー自給率を向上させ、農業補助金は削減することが可能だ。左から2番目の図はオランダのハウス栽培で、オランダはハウス栽培を主にしたそうだが、ハウスを太陽光発電ガラスで作れば電力を供給でき、中に適切な量のCO₂を放出すれば、作物の生育が早くなる。右から2番目の図は、「基盤技術研究本部」が行っているスマート農業の研究で、1番右の図のように、農業における担い手の割合は増えているものの、これらのスマート機器を導入するには一定以上の規模が必要だろう) 1)食料自給率の低迷と経済安全保障 *4-2に、①岸田政権は経済安全保障政策としてエネルギー、情報通信、交通・海上物流、金融、医療の5分野を重点として取り上げた ②食料自給率の低さは国民の命を直接左右するのに経済安全保障政策に入らなかった ③農水省が発表した2020年度のカロリーベースの食料自給率は、輸入が増えて37.17%となり、1965年度以降過去最低 ④農水省は2030年度までにはカロリーベースの食料自給率を45%に高める目標を掲げているが、年々、減少している ⑤カロリーベースの食料自給率は、1965年には73%あったが、今や37%まで下がり、日本人の食料の6割以上を海外からの輸入に頼っているのが現実 と記載されている。 世界人口は、2020年に78億人で2100には109億人まで増えようとしており、工業化が進んで外貨を獲得した国は食料輸入国になるのに、③④⑤の状況で危機感も感じず、①②のように、いつまでも「日本の工業化の方が上位にあり、食料などは工業製品を売った金で他国から買えばよい」と思っているとすれば、それは傲慢か鈍感、もしくはその両方だ。 また、戦争の場合は、兵糧攻めは「兵力を損せずに、相手を負かす」ための原則的手段であり、食料やエネルギーを自給できなければ強気で交渉することもできないため、「食料安全保障」は重要である。従って、新型コロナ禍・天候不順など言い訳はいくらでもできるが、一貫した食料自給率低下と食料価格上昇は、政策による敗戦だ。 2)農林水産輸出「1兆円」達成は功績か? そのような中、*4-1は、①2020年の農林水産物輸出額が、政府が目標に掲げる1兆円を初めて超えた ②国内は人口減少が避けられず、政府は輸出拡大を農林水産業基盤維持の有力な選択肢と位置づけて支援を続けてきた ③食料自給率など農水省の掲げる目標の多くが未達であることを考えれば、農林水産物輸出額1兆円を達成したのは一定の評価ができる としている。 しかし、①③のように、1兆円でも輸出できないよりはできた方がよいが、②は食料自給率が100%ならともかく、37%の国が考えることではないだろう。そのため、私も、政府の支援は、品種改良・物流の効率化・加工施設の整備・再エネとの両立によるコストダウンなど、中長期的な競争力強化につながる政策に絞るべきだと思う。 また、*4-1は、④1兆円を超えても国内生産額に占める割合はまだ2%に留まる ⑤海外の富裕層で日本産の需要が飽和状態に達しつつあり、中間層にも販売を広げることが次の目標達成に欠かせない ⑥日本の農業生産者は、品質のよい商品を高価格で販売しようとする ⑦輸出拡大には生産者が市場のニーズを見極めて、何をどういうコストで生産するか決めることが必要 ⑧米のように輸出向け生産を助成金で優遇する政策は、生産コストを高止まりさせる結果を招く とも記載している。 確かに、④のとおり、農林水産物全体を考えれば少ない輸出額だが、その理由は、⑤⑥のように、“品質の高い”商品を高価格で販売しようとしたことによる。しかし、外国産も日本人のニーズに合わせて“品質”を上げてきているため、決してまずくはなく、肉類はむしろ脂身が少なくて健康志向である上、全体として安価だ。 そのため、私も、⑦のように、生産者は輸出する市場のニーズをつかんで、的確な製品を適切な価格で生産・販売する必要があると思う。そのような中、米だけを優遇して輸出向け生産に政府の助成金で優遇するのは、⑧のように、市場のニーズに合わせる努力を妨げ、米以外の生産者に対して不公平になる。 なお、⑨中国・韓国・台湾など主要輸出先の多くがフクイチ事故後に導入した日本産の輸入規制を続けている そうだが、2011年の原発事故後は55の国・地域が輸入規制を導入し、米国も日本産の輸入規制を2021年9月22日に撤廃したばかりで、まだ15か国・地域が規制を維持している。そのため、日本政府が、大した根拠もなく安全性を主張するのは、むしろ信用をなくす行為だ(https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/210921.html 参照)。 (5)組織再編へのいちゃもんはよくないこと 1)東芝の組織再編 東芝が、*5-1のように、グループ全体を、①発電機器やインフラの「インフラサービス」 ②半導体等の「デバイス」 ③保有株式管理等の会社 に3分割し、中核事業を2つの新会社として分離・独立させ、①②の事業会社を2023年10月~2024年3月に新規上場させる計画の実現を目指すとした時、まるで東芝いじめのような反対論が紛糾したのには呆れた。 その理由は、私も綱川社長の「④今般の再編により新会社はスピード感をもってそれぞれのビジネス特性に応じた事業を展開することが可能になる」「⑤この経営変革がグループの企業価値向上に向けた最善策である」という意見に賛成で、「⑥坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」といういじめ方には反対だからだ。そして、大人が行っているこのような「いじめ」は、子どもにもしっかり真似されていることを忘れてはならない。 私が、この会社分割に賛成する理由は、ビジネスの特性が異なり、異なるタイプの人材を集めて、異なる論理で動かなければならない事業部を、一つの会社のまま、同一の経営陣や人事制度の下に置いておけば、お互いの環境や行動原理を理解しくいため意思決定に時間がかかり、両方とも足を引っぱられるからだ。従って、この会社分割を、「⑦2つの事業グループが新しいリーディングカンパニーとして進化するための準備」とするのも理解できる。 そのため、*5-2のように、臨時株主総会を開いて議決権のある株主が賛否を表明するのはよいが、大株主といっても、会社のおかれた環境とその中で決められた中長期の経営計画を理解して意思決定できるわけではないため、注意すべきだ。 2)労働流動化の必要性とジョブ型雇用 日本は労働の流動化ができていない国で、労働法もそれを前提に定められている。この労働市場のディメリットは、労働者に転職で不利益が生じ、企業も正規労働者を解雇しにくいことである。そして、それを回避するために、企業は非正規労働者という解雇しやすい労働者群を作って労働法を逃れ、労働者の中に犠牲になる集団があって不合理な格差が生じるのである。 また、正規労働者は解雇しにくいため、企業は終身雇用・年功序列の前提の下、専門性の異なる人材を会社内で使い廻すことになり、生産性が低くなる。これを解決して、環境変化に対応できるためには、*5-3のように、ジョブ型雇用を行い、職務を明確化して、人材の専門性を高めることが必要だ。 このジョブ型雇用(働き手の職務内容を明確に規定して、仕事中心に雇用する雇用方法)は、事業展開に合わせて最適な人材を配置したり、外部の労働市場からも機動的に人材を採用したりしなければならない時に、中途採用された労働者が不利益を被らないためにも必要で、欧米企業には前から当然のこととして普及しているものだ。 そして、その特定の業務がなくなれば、担当していた人材は解雇されることも多いが、ジョブ型雇用で専門性を活かせる仕事に配置され続けていれば、他の企業に転職してもその専門性は生きるわけで、もちろん、その場合の賃金は仕事の中身と達成度で公正に評価して決められなればならず、それが労働者がさらに専門性を磨く動機づけになるのである。 日本でも、*5-4のように、年功制や順送り人事を排すジョブ型雇用を導入する企業が広がっており、KDDI、富士通、日立製作所がジョブ型「御三家」だそうだ。そして、*5-4に書かれているとおり、職務内容や求められる能力を明記する職務記述書を柔軟にして、あらかじめ能力発揮を制限しすぎないのがよいと思われる。 ここで気がつくことは、年功序列では機能しにくい部門を持つ企業でジョブ型雇用が進んでいることで、東芝の会社分割は、①発電機器やインフラの「インフラサービス」 ②半導体等の「デバイス」 ③保有株式等の管理会社 を別会社にし、異なる環境の下で、異なる人事制度を持ち、階層を減らして、意思決定を早めるという意図が感じられる。 なお、*5-5のように、やっと「イノベーションの創出には、女性エンジニアが不可欠」と言われるようになったが、「『ジェンダード・イノベーション』には、優れた女性エンジニアの活躍が不可欠」というだけではなく、一般の電気製品も、発言権のある女性の混じった組織で作られたものは、よく工夫されていて、使い勝手がよく、デザインも洗練されている。 つまり、人材の多様性の欠如が日本のイノベーションを妨げ、製品の付加価値も下げているわけで、女性や高齢者にとって、仕事を中断してもまた専門性を評価されて就職できる体制であれば、必要な時に休職や転職をしても、不利益なく仕事を再開できるのである。 ・・参考資料・・ <火山噴火と噴火予知> *1-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220122&ng=DGKKZO79462730S2A120C2EA1000 (日経新聞 2022.1.22) トンガ被害把握難航 噴火1週間、火山灰被害で食糧難、ネット通信復旧遅れ WHO現地職員に聞く 南太平洋の島しょ国、トンガ沖で海底火山が大規模噴火してから22日で1週間がたつ。現地の住民らに取材すると、火山灰による農業被害で一部の島では食糧が不足し始めた。物流の停滞で石油の備蓄も底をつきつつある。インターネットはほとんど復旧しておらず、被害の全容把握にはなお時間がかかりそうだ。海底火山から約65キロの首都ヌクアロファにある世界保健機関(WHO)事務所で働く瀬戸屋雄太郎氏が日本経済新聞の取材に応じた。瀬戸屋氏は噴火の瞬間を「大砲のような音がドーンとした。窓が震えて耳がキーンとなった。圧のようなものを感じた」と振り返る。瀬戸屋氏は「しばらくして避難した。ラジオから『避難をしてください』と呼びかけがあった。沿岸地域にいた人々はいち早く高台に避難したと聞いた」とも語った。瀬戸屋氏は降灰による深刻な被害を指摘した。「作物が枯れたり、葉に灰が付着したりする被害が出ている。小さな島々では食糧難が発生しつつある」という。水不足も懸念される。雨水をタンクにためて飲料水とするが、タンクに火山灰が入った。重金属汚染が懸念され、WHOは飲まないよう呼びかけてきた。瀬戸屋氏は「調査で浄化すれば飲めるとわかった。いまは市販のペットボトルの水を飲む人が多い」と話す。トンガ出身でオーストラリア国立大学のジェンマ・マルンガフ特別研究員は「農産物に付着した火山灰を洗い流す水が不足しているうえ、(火山灰の土壌への影響など)安全性に不安を抱える人が多い」と指摘する。通信の復旧も遅れている。瀬戸屋氏は「一般的にはインターネットは復旧していない。国際電話はオーストラリアとの間でつながり始めた」と語った。ネットが全面復旧していないため、被害の全容把握が難航する。国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、首都のあるトンガタプ島だけで最大100棟の家屋が深刻な被害を受けた。すべての家屋が破壊された島もある。瀬戸屋氏は「長期支援が欠かせない。テントやマスクが必要だ」と話す。トンガは生活必需品の多くを輸入に頼り、物流途絶が長引けば影響は大きい。国際貿易センターによると2020年、トンガの最大の輸入品は石油や石炭といった燃料でモノの輸入の14%を占め、次が肉類(9%)。瀬戸屋氏は「物流が止まっている状況は非常に深刻で、石油の備蓄も不足しつつある」と話した。ニュージーランド(NZ)政府は21日、ヘリコプターなどを積んだ軍艦がトンガに到着したと発表した。飲料水や淡水化装置を運ぶ別のNZ軍艦も同日到着した。20日にはNZや豪州が支援物資を軍の輸送機で運んだ。自衛隊の輸送機も同日、飲料水を運ぶため日本を出発した。中国も水や食糧の輸送を表明ずみだ。新型コロナウイルス禍で人的支援には難しい面もある。トンガは厳しい出入国管理を敷いており、人口約10万人の同国で感染者はわずか1人にとどまる。外国人が入国して新型コロナの感染が広がれば、医療崩壊が起きかねず、トンガ政府は海外からの支援人員の受け入れに慎重姿勢とされる。感染防止と復興支援の両立が課題になる。地域に詳しい笹川平和財団の塩沢英之主任研究員は「今後の支援は損傷した施設の復旧だけでなく、将来の災害に対して強靱(きょうじん)な社会を作るという視点が必要になる」と指摘している。 *1-1-2:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220125/k10013449821000.html (NHK 2022年1月25日) トンガ派遣の自衛隊員 複数がコロナ感染 支援物資の輸送できず 海底火山の大規模噴火で被害を受けたトンガを支援するために派遣された自衛隊員3人が、新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。派遣部隊の感染者は4人となり、防衛省によりますと、この影響でオーストラリアからトンガへの支援物資の輸送ができない状態になっているということです。トンガを支援するため、防衛省は、航空自衛隊のC130輸送機2機を、活動拠点を置くオーストラリアに派遣し、今月22日に初めてトンガに飲料水を届け、支援活動を本格化させています。ところが24日、隊員1人の感染が確認されたほか、25日になって新たに20代から40代合わせて3人がのどの痛みなどの症状を訴え、抗原検査の結果、陽性反応が出たということです。この4人に加え、濃厚接触した疑いのある36人の隊員を隔離する必要があることから、輸送機によるオーストラリアからトンガへの支援物資の輸送ができない状態になっているということです。防衛省は、代わりとなる隊員を新たにオーストラリアの活動拠点に派遣することを含め、対応策を検討していて、感染防止策を徹底し、任務を再開する予定だとしています。トンガの支援活動をめぐって防衛省は、C130輸送機のほか輸送艦「おおすみ」を25日現地に向けて出発させていて、火山灰を取り除くための高圧洗浄機や飲料水を届ける予定です。 *1-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15178929.html (朝日新聞 2022年1月21日) (時時刻刻)巨大噴火リスク、日本にも 火山大国、予知に限界 南太平洋のトンガ諸島で日本時間15日に発生した海底火山の噴火は、噴火の規模を示す火山爆発指数(VEI)で、上から3番目の6かその下の5だったとみられる。日本でもこの規模の噴火は歴史的に繰り返し発生してきた。巨大噴火は予知できるのか。発生への備えはどうあるべきか。トンガと同じく海洋プレートが沈み込む日本は、世界有数の火山大国だ。世界の7%にあたる111の活火山が集まっている。噴火も多く、沖縄などに大量の軽石をもたらした小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」の噴火がVEI4。1914年に鹿児島県の桜島で起きた大正噴火も4で、明治以降はこの二つが最大級だった。時代をさかのぼれば、さらに大規模な噴火も起きている。江戸にも火山灰が降った1707年の富士山宝永噴火は5。そこまでの規模ではなくても、天明の大飢饉(ききん)を起こした1783年の浅間山の噴火(VEI4)や、山が崩壊して村をのみ込んだ1888年の福島・磐梯山の噴火(同2)など大きな被害が出た例も多い。気象庁は、111の活火山のうち、火山噴火予知連絡会が「過去100年程度以内に火山活動の高まりが認められている火山」などの基準で選んだ50の火山を24時間体制で監視している。2000年に北海道の有珠山で噴火の2日前に緊急火山情報を出し、住民の避難が成功した例があるものの、予知は難しい。京都大防災研究所の井口正人・火山活動研究センター長は「日本はトンガと比較すれば監視体制が整っており、地震や地殻変動などから噴火の予兆をつかむことはできる。ただ、それが噴火警報・予報に結びつくかは別問題だ。噴火の規模や噴出形態を予測することは多くの火山ではまだできないのが現状」と話す。VEIは0~8の段階があり、7と8は破局噴火とも言われる。めったに起きないが、日本では1万年に1度のペースで起きているとされる。600立方キロメートルもの火山灰が放出され、火砕流が九州の広範囲に広がったとされる約9万年前の熊本・阿蘇カルデラ、3万年前の鹿児島・姶良(あいら)カルデラ、南九州の縄文文化を火砕流で壊滅させたとされる7300年前の鹿児島・鬼界(きかい)カルデラの噴火はいずれもVEI7だった。巨大噴火は、原子力発電所の審査でも議論になってきた。160キロ圏に五つのカルデラがある九州電力川内原発(鹿児島)の審査では、九電が、運用期間中に破局噴火が起こる可能性は「十分低い」と主張した。九電は同原発が再稼働した2015年度から、破局噴火の兆候をとらえようと、カルデラのモニタリングを本格的に始めた。もし地殻変動などが観測されれば、「噴火の可能性を評価し、燃料の搬出などを実施する」という。ただ、巨大噴火自体の記録やデータに乏しく、兆候を本当につかめるのか、疑問視する研究者は少なくない。 ■首都圏、微量の降灰でも交通混乱 富士山噴火、政府部会の被害想定は… 国内で大規模噴火が起きたら、どんな被害が想定されるのか。日本に破局噴火レベルの被害想定はないが、政府の中央防災会議の作業部会は2020年、VEI5の富士山宝永噴火と同程度の噴火が再び富士山で発生した際に想定される首都圏への影響をまとめた。除去が必要になる火山灰は最大約4・9億立方メートルで、東日本大震災での災害廃棄物の量の約10倍。東向きの風が強く吹けば、灰は3時間のうちに都心に届き、噴火から15日目の累積降灰量は、東京都新宿区約10センチ▽横浜市約2センチ▽相模原市約30センチなどとされる。微量の降灰でも地上の鉄道はストップし、視界不良で道路は渋滞する。降雨時には0・3センチの降灰で停電するほか、通信アンテナに火山灰がつけば携帯電話などの通信網も寸断されるおそれがあるという。木造家屋は降雨時に30センチ以上の灰が積もっていると、重みで倒壊する可能性がある。目、鼻、のどへの健康被害も生じ、ぜんそくなどの疾患がある人は症状が悪化する可能性が高いとしている。噴火による被害は、火山灰だけにとどまらない。山梨、静岡、神奈川の3県などでつくる「富士山火山防災対策協議会」が昨年まとめたハザードマップでは、大量の溶岩を噴出した「貞観噴火」(864年)級の噴火で13億立方メートルの溶岩流が、3県27市町村に到達するおそれがあるとした。東名高速や東海道新幹線といった主要な交通網にも達する可能性がある。噴出物と火山ガスなどが混ざって地表沿いを流れる火砕流も1千万立方メートル流れ出て、静岡、山梨両県の10市町村に及ぶという。人的被害は算出されていない。では、どんな備えが必要なのか。気象庁は、同庁が発表する「噴火警戒レベル」に基づき、自治体から発表される避難情報に従ってほしいとしている。健康被害を避けるため、1ミリ以上の降灰時には外出は控えるのが望ましい。1ミリ未満でも外出時にはマスクやゴーグルをつけて体を守ることが必要で、窓を閉めるのが望ましいとする。予想される降灰量は同庁が発表する「降灰予報」が参考になる。自宅や職場にとどまることも想定し、食料や水を普段から確保しておくことも大切だ。中央防災会議も「基本的な考え方」を示しており、木造住宅に住む人は降灰が30センチに達する前に逃げるなど、早期避難が必要だと指摘する。 <先進技術 ー(その1)火星と月> *2-1-1:https://academist-cf.com/journal/?p=5937 (AcademistJournal 黒川宏之 2017年9月20日) 40億年前の火星は厚い大気に覆われていた – 隕石を手がかりに火星環境大変動の謎に迫る ●火星環境大変動の謎 火星は希薄な大気しか持たない惑星です。その地表は平均気温約-60℃と極めて寒冷で、荒涼とした大地が広がっています。1965年に火星探査機マリナー4号がはじめて火星地表の写真を送ってきたとき、しばしば水の惑星と形容される地球と対比して、火星は“死の惑星”と表現されました。ところが、その後アメリカを中心に行われてきた探査研究の成果として、数多くの流水地形や液体の水が存在した鉱物証拠が発見されてきました。これが意味することは、火星はかつて液体の水が安定に存在できるほど温暖な時代があった、ということです。火星をそれほど温暖に保つためには、厚い大気と温室効果ガスが必要です。厚い大気を失ったことが、かつて温暖であった火星が極寒の惑星へと変貌した原因ではないかと考えられてきました。では火星はいつ、なぜ厚い大気を失ったのでしょうか? 原因のひとつの可能性は、火星が地球の10分の1の質量しか持たず、低重力であることです。重力が小さいことは、大気が宇宙空間に流出しやすいことに繋がります。原因のもうひとつの可能性は、火星が磁場を持たない惑星であることです。磁場を持たない惑星の大気には太陽風が直接吹きつけるため、大気の宇宙空間への流出を引き起こします。私たちの研究グループでは、まず火星の厚い大気が“いつ”失われたかを解明することを目的とし、さらにはその結果から“なぜ”失われたかを推測することを試みました。 ●手がかりは“火星隕石” 失われた太古の火星大気への手がかりとして私たちが着目したものは、火星隕石と呼ばれる、天体衝突によって火星から飛び出し地球まで飛来した隕石です。これらの隕石は、含有ガスの化学組成や岩石の酸素同位体組成をもとに、火星からやってきたことがわかっています。探査研究と比較して、火星隕石を利用した研究は、その隕石が火星地表のどこからやってきたのかわからないという欠点があります。その一方で、実験室で詳細な化学分析ができるため、リモートの探査では知り得ない多くの情報を得ることができます。大気の組成は惑星全域でよく均質化されており地域性がないため、私たちの研究では火星隕石研究の利点のみを活かすことができます。南極で発見された、アランヒルズ84001と名付けられた火星隕石は、詳細な化学分析により40億年前という非常に古い時代に形成されたことがわかっていました。さらに、当時の火星大気を岩石中にガスとして含有していることが過去の研究で報告されていました。今回の研究では、この含有ガスの同位体組成が40億年前の大気量を知る手がかりとなりました。火星大気が宇宙空間に流出する時には、軽い同位体が優先的に流出することで、残る火星大気には重い同位体が濃集します。私たちは、さまざまな火星大気の時間変化シナリオに対してこの同位体組成の時間変化をシミュレートすることで、火星隕石アランヒルズ84001に記録された40億年前の大気の同位体組成を再現する条件を探りました。宇宙空間へ流出する火星大気の模式図。軽い同位体(14Nなど)が優先的に流出することで、火星大気には重い同位体(15Nなど)が濃集する ●厚い大気に覆われていた火星 その結果、40億年前の火星は、地表大気圧が約0.5気圧以上の厚い大気に覆われていたということがわかりました。現在の地球大気が1気圧なので、当時の火星は地球程度の厚い大気に覆われていたことになります。この0.5気圧という値はあくまで下限値であり、実際の火星大気はさらに分厚かった可能性があります。大気が分厚いほど、地表はより温暖になります。一方で、現在の火星は僅か0.006気圧の希薄な大気しか持っていません。すなわち、40億年前以降に火星大気の大部分が失われたことになります。なぜ火星はかつて存在した厚い大気を失ったのでしょうか? 現在の火星に残されている古い地殻が磁化していることから、火星は約40億年前に磁場を持っていたと推定されています。現時点では厚い大気を失った原因を特定することは難しいですが、磁場を失ったことが太陽風による大規模な大気の宇宙空間への流出を引き起こした可能性があります。現在、火星大気の流出過程を観測しているNASAの火星探査機MAVENによる最新の観測結果からも、これを支持する成果が得られつつあります。 ●日本独自の火星探査に向けて 厚い大気に覆われ、地表には液体の水が存在した40億年前の火星では生命は誕生しなかったのでしょうか? 地球では約40億年前にすでに生命が誕生していたことが地質学的な証拠からわかっています。将来の火星探査で、火星にかつて生命が存在した証拠が発見される可能性は十分にあります。さらに、ここ数年の大きな発見として、火星はかつて想像されていたような完全なる“死の惑星”ではなく、春や夏の比較的温暖な時期に地下から水が湧き出している地域があることがわかってきました。火星の極寒で乾いた地表の下には、現在でも生命が存在可能な環境が広がっているのかもしれません。JAXAは2024年に火星衛星サンプルリターン機MMXを打ち上げる予定です。成功すれば日本で初めて人工衛星を火星軌道に投入して探査活動を行うことになると同時に、世界初の火星圏からのサンプルリターンとなります。そして、これに続くミッションとして、日本初の火星着陸探査の検討も始まっています。これらの日本独自の火星探査によって、火星環境の大変動の歴史や、生命誕生の有無を解明できると期待しています。 *参考文献 Hiroyuki Kurokawa, Kosuke Kurosawa, Tomohiro Usui. A Lower Limit of Atmospheric Pressure on Early Mars Inferred from Nitrogen and Argon Isotopic Compositions, Icarus, Vol.299, 443-459, (2018). *2-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220129&ng=DGKKZO79638130Y2A120C2MY6000 (日経新聞 2022.1.29) 『火星の歩き方』臼井寛裕ほか著 ■『火星の歩き方』臼井寛裕ほか著 見知らぬ土地の旅行にはガイドブックが欠かせない。宇宙航空研究開発機構などの研究者が、人類が移住の可能性を探る火星を案内する。月に似た衛星フォボスに始まる気球を用いた旅や、標高2万メートルのオリンポス山登山コースなどの紹介を通して、地形の成り立ちや特徴を概説する。一方、開発には環境保全が課題と見据え「人類に火星を旅行する権利はあるのか」との問いも投げかける。 *2-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220103&ng=DGKKZO78896410S2A100C2PE8000 (日経新聞 2022.1.3) 日本の月探査始動 無人機初着陸へ、補給船も開発急ぐ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)を中心とした日本の月探査が2022年に本格化する。2月以降に初の月面着陸を目指す無人機を米国のロケットで送り込むほか、22、23年度にも無人機を計2機打ち上げる。宇宙ステーションへの輸送船開発も進む。国際協力で存在感を示し、産業育成につなげる。月探査に向けた第1弾は2機の探査機で、「エクレウス」と「オモテナシ」。後者は月への着陸も予定する。JAXAと東京大学が開発した。40センチメートル角に満たない大きさで、少ない燃料で月面に向かう飛行技術や着陸技術をそれぞれ検証する。打ち上げには米国の新たな大型ロケット「SLS」を使う。米国は25年以降の有人月面着陸を目指す「アルテミス計画」の第1弾として、22年初頭に打ち上げる予定。同計画で月の近くに人を運ぶ計画の宇宙船「オリオン」の無人飛行試験と合わせ、2機の探査機を放出してもらう。JAXAがより本格的な月探査の技術実証と位置づけているのが、22年度に打ち上げる探査機「SLIM(スリム)」だ。目的地から誤差100メートル以内での月面着陸を狙う。この経験で技術を磨き、23年度にインドと共同で新たな探査機を打ち上げる。月面で氷や水が存在する可能性が指摘される「極域」を狙う。水は宇宙開発では重要な資源で将来、国際的な争奪戦が予想されている。アルテミス計画を巡っては、日本は4項目で米国と合意している。(1)月周回に建設する新たな宇宙ステーション「ゲートウエー」の居住棟への機器の提供(2)同基地への物資の補給(3)月面データ共有(4)有人探査車の開発――だ。基地への補給には、開発中の補給船「HTV-X」を使う方針だ。国際宇宙ステーション(ISS)向けに9回物資補給を担った「こうのとり」の後継機で、22年度中に初の打ち上げを目指す。まずはISSへ1年に1回のペースで3回打ち上げる。26年以降に、ゲートウエーへの物資や燃料の補給に使うことを想定する。月を巡る国際競争は激化している。20年代前半には日本やインドだけでなく、中国やロシアなども月の極域などを狙った新たな探査を計画する。民間の取り組みも始まっている。国内ではスタートアップのispace(東京・中央)が22年中に着陸機を、ダイモン(同・大田)が探査車を月面に送り込む計画だ。JAXAは月での活動も視野に宇宙飛行士の募集も始めた。政府は21年末に改定した国の宇宙開発の基本方針を示す「宇宙基本計画」の工程表で「20年代後半をメドに日本人による月面着陸の実現を図る」と明記した。月探査に向けた技術や物資、人材をそろえて国際貢献し、宇宙産業の育成に向けた技術やノウハウの取得を目指す。 *2-2-2:https://digital.asahi.com/articles/ASQ1X63R0Q1XUHBI01J.html (朝日新聞 2022年1月28日) 「2030年までに月面基地」 中国、ロシアと共同で建設を計画 中国国家宇宙局は28日、宇宙白書の発表にあわせて記者会見し、2030年までにロシアと共同で月面基地建設を始める計画を明らかにした。35年をめどに、地球と行き来して月面で活動するためのエネルギー設備や通信システムを基地に整備し、人類が短期滞在する場合には生命維持環境を備えた「小さな村」をつくる構想も披露した。会見した宇宙局の劉継忠・宇宙工程センター主任は、無人月探査機「嫦娥(じょうが)6号」で月の南極か北極の土を持ち帰り、7号では高精度な着陸とクレーターの探査を実施。「特に7号では月面の水の分布を調べ、月面基地建設に向けた最初の一歩を踏み出す」と述べた。8号で、ロシアと協力して「月面基地をつくる基本的な目標は達する」とした。6、7号は25年前後までに、8号は30年までに任務を終えるという。28日に公表した「2021中国の宇宙」と題した白書でも、「8号で国際科学研究ステーション(月面基地)を建設するという技術的な任務を完了させる」と明記した。中ロは昨年3月、月面基地建設の協力を進めることで基本合意しているが、呉艶華・宇宙局副局長は「調整は順調に進んでおり、早ければ年内にも両国で署名し、世界に向けて月面基地の建設を正式に宣言できる」と述べた。呉艶華・宇宙局副局長は基地は南極に作るとの見通しを示したうえで、「基地は小さな村を作るようなもので、エネルギーや通信、運搬システムなどが必要になる」と指摘。ソーラー発電や、地球と通信して月面での装置を動かす機能、物資運搬システムなどを指すとみられる。また宇宙飛行士の短期滞在のための生活環境も必要だという見通しを示し、これらは「35年までの重点的な任務だ」と述べた。中国はこれまで、19年に「嫦娥4号」を世界で初めて月の裏側に着陸させることに成功。20年には「嫦娥5号」が米国、旧ソ連に続いて44年ぶりに月の土を持ち帰る「サンプルリターン」を実現するなど、「宇宙強国」を目指して急ピッチで宇宙探査技術を蓄積している。米国にも将来的に月面基地を建設する計画がある。アポロ計画以来の有人月探査となる「アルテミス計画」で、日本も参加を決めている。計画では、2025年以降に男女の飛行士を着陸させ、将来的には月を回る軌道に宇宙ステーション「ゲートウェー」や、月面基地を建設することにしている。日本は宇宙ステーションに物資を運ぶ新型の無人補給船や、有人の月面車の開発を進めている。 *2-2-3:https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44158040U9A420C1000000/ (ナショジオニュース 2019/5/11) 月の地表7センチ下に大量の水 NASA探査機が発見 月のちりと大気を調査するために送り込まれたNASAの探査機LADEE(ラディ―)が、隕石が衝突する際に月面から放出される水を検出した。2019年4月15日付けの学術誌「Nature Geoscience」に掲載された論文によると、微小な隕石が衝突する際の衝撃によって、年間最大220トンもの水が放出されているという。月面付近には、これまで考えられてきたよりもはるかに大量の水が存在することになる。「あまりに大量の水だったため、探査機に搭載されていた機器が、大気中の水をスポンジみたいに吸収したのです」。研究を主導したNASAゴダード宇宙飛行センターの惑星科学者、メディ・ベンナ氏はそう語る。この発見は、月がそもそもどのように形成されたかを理解する新たな手がかりになるだろう。また、今後の有人ミッションにも影響を与えるに違いない。その際には、月面の水分を水分補給や推進力の確保に活用できるかもしれない。「これまでずっと、月は非常に静かで寂しい場所だと考えられてきました」とベンナ氏。「今回のデータによって、実際の月は非常にアクティブで刺激に敏感であることがわかりました」 ●月に降り注ぐ流星群 ある程度の水が月に存在することは以前から知られていた。その大半は、ずっと日が当たらないクレーターの日陰部分にある氷に閉じ込められているか、あるいは表面からずっと深いところに隠されていると考えられてきた。月に水がもたらされる経路には2種類ある。太陽風に含まれる水素が月面にある酸素と反応し、さらに月の岩石と作用して含水鉱物となる、というのが一つ。もう一つは、月面に衝突する彗星や小惑星に水が含まれるケースだ。しかし、NASAの探査機LADEEが収集した新たなデータによって示されたのは、意外な事実だった。LADEEが軌道をめぐる間、地球と同じように流星群が月に降り注ぐのを観測していた。毎年決まった時期に、地球と月は、彗星の軌道と交差する。彗星の中にはたくさんの岩屑をまき散らすものがある。そうした置き土産の大半は、地球の大気圏では燃え尽きる。この現象はふたご座流星群、ペルセウス座流星群、しし座流星群などの名称で呼ばれる。一方、空気のない月では、それらの隕石は月面に衝突する。「何百万という数の細かい岩石が、雨のように降り注ぎます」と、ベンナ氏は言う。「われわれは29回の隕石群を確認しました。そのすべてが彗星と関連していました」。こうした小さな粒子が月面に衝突する際、いちばん上にある細かい表土の層(レゴリス)を舞い上げる。そのおかげで、地表からわずか7.5センチメートルほど下の層に、予想よりもはるかに多くの水があることが判明した。「こうして放出され、失われる水の量は、太陽風によって運ばれてくる水素や、微小隕石自体によってもたらされる水では埋め合わせることができません」と、ベンナ氏は言う。「つまり、月の土壌にはこれら2つでは補充し切れないほどの水が存在することになります。これを説明するには、月には太古の昔から蓄えられてきた水があり、それが長い時間をかけて徐々に枯渇してきたと考えるしかありません」 ●なぜ地球よりも水が少ないのか ベンナ氏のチームは、月面の数センチメートル下には、水がほぼ均等に存在していると推測している。これは、月には太陽風や彗星から運ばれてきたものよりもたくさんの水があることを意味する。太陽系ができたての頃、巨大な若い惑星同士が衝突し、宇宙空間に放たれた岩屑が2つのまとまりになり、互いの周りをバレエのようにグルグルと回り始めた。これが月と地球ができた経緯だ。結果として、月と地球は歴史の一部を共有することになったが、地球にある量と比べてなぜ月にあれほど水が少ないのかについては、これまで明確な理由はわかっていなかった。「これは重要な論文です。なぜなら、今起きている水の放出を測定しているからです」と、米ブラウン大学の惑星科学者、カーリー・ピーターズ氏は言う。衝突によって明るい色の物質が周囲に撒き散らされた様子がわかる(PHOTOGRAPH BY NASA)。研究チームのデータは、月の起源や、それほど大量の水をどのように獲得したかを解明しようとしている科学者たちの役に立つだろう。「とてもワクワクしています。研究チームはすべての経緯をとらえています。水が外気圏に移動し、それが月面に戻るか、あるいは宇宙へ消えていくまでを観測しているのです。これは本当に重要な発見です」。(文 SHANNON STIRONE、訳 北村京子、日経ナショナル ジオグラフィック社)[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2019年4月17日付] *2-3:https://news.yahoo.co.jp/articles/094be2f9738830f0bb2e06f4b084dde847e20203 (Yahoo 日本農業新聞 2022/1/5) 月でジャガイモ、火星でトマト…“現地生産”へ技術開発 産官学プロジェクト始動 月面でジャガイモ、火星でトマト――。農水省は、月や火星に人類が進出する未来を見据え、地球上とは全く異なる環境でも農作物を生産し、現地で食料を確保する技術開発に乗り出した。大学や民間企業が参画する産官学プロジェクトを始動。植物工場などの技術を生かし、5年間で月面や火星を再現した環境下での生産実証を目指す。 ●植物工場を応用 プロジェクトが目指す将来像として、同省は「月面産、火星産の農産物を現地で食べる」(食品企業行動室)ことを想定する。人間の健康維持に必要な栄養の大部分を満たせる品目として水稲や大豆、トマト、ジャガイモなど八つを選定。大気や日照条件が大きく異なる月面、火星で生産するには、植物工場のような閉鎖型施設が必要になる。「限られた面積で収量を確保し、おいしい農作物を生産する」という基本テーマの下、2021年度から5年間の研究プロジェクトが始動。21年12月に千葉大学や農研機構、植物工場の開発企業などの参加が決まった。21年度は3億円の予算を計上。現地の環境を地上で再現し、米やトマト、イチゴを栽培する閉鎖型設備の開発を進める。植物工場の開発で蓄積された技術を生かし、収量を確保できる環境や設備の研究・実証を進める。現地資源の活用も念頭に置く。月の砂「レゴリス」を改良し、ジャガイモなどを栽培する技術の開発を目指す。政府は「宇宙基本計画」に基づき、月面や火星への進出を中長期的な目標に掲げる。現地に長期滞在する場合、食料を確保する必要が出てくる。ただ、地球から食料を輸送すれば膨大なコストがかかる。月面や火星の拠点に滞在する人が長期間、栄養をきちんと摂取できるようにすることも考慮し、同省は現地での農業生産を可能にする必要があると判断した。研究成果は、砂漠など地球上の過酷な条件での食料生産に生かすことも念頭に置く。 <先進技術 ー(その2)気候変動問題への対応> *3-1:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20220118&c=DM1&d=0&nbm=DGKKZO79294570X10C22A1M10600&ng=DGKKZO79294700X10C22A1M10600&ue=DM10600 (日経新聞 2022/1/18) 四 気候変動問題への対応 【成長のエンジンに】 過度の効率性重視による市場の失敗、持続可能性の欠如、富める国と富まざる国の環境格差など、資本主義の負の側面が凝縮しているのが気候変動問題であり、新しい資本主義の実現によって克服すべき最大の課題でもあります。20年、衆参両院において、党派を超えた賛成を得て、気候非常事態宣言決議が可決されました。皆さん、子や孫の世代のためにも、共にこの困難な課題に取り組もうではありませんか。同時に、この分野は、世界が注目する成長分野でもあります。50年カーボンニュートラル実現には、世界全体で、年間1兆ドルの投資を、30年までに4兆ドルに増やすことが必要との試算があります。我が国においても、官民が、炭素中立型の経済社会に向けた変革の全体像を共有し、この分野への投資を早急に、少なくとも倍増させ、脱炭素の実現と、新しい時代の成長を生み出すエンジンとしていきます。30年度46%削減、50年カーボンニュートラルの目標実現に向け、単に、エネルギー供給構造の変革だけでなく、産業構造、国民の暮らし、そして地域の在り方全般にわたる、経済社会全体の大変革に取り組みます。どのような分野で、いつまでに、どういう仕掛けで、どれくらいの投資を引き出すのか。経済社会変革の道筋を、クリーンエネルギー戦略として取りまとめ、お示しします。送配電インフラ、蓄電池、再生可能エネルギーはじめ水素・アンモニア、革新原子力、核融合など非炭素電源。需要側や、地域における脱炭素化、ライフスタイルの転換。資金調達の在り方。カーボンプライシング。多くの論点に方向性を見いだしていきます。もう一つ重要なことは、我が国が、水素やアンモニアなど日本の技術、制度、ノウハウを活かし、世界、特にアジアの脱炭素化に貢献し、技術標準や国際的なインフラ整備をアジア各国と共に主導していくことです。いわば、「アジア・ゼロエミッション共同体」と呼びうるものを、アジア有志国と力を合わせて作ることを目指します。 *3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220122&ng=DGKKZO79465320S2A120C2MM8000 (日経新聞 2022.1.22) EVシフト、地方が先行 岐阜・愛知は東京の2倍普及 給油所廃業後の光明に 電気自動車(EV)など次世代車シフトの「芽」が地方で育ち始めた。人口当たりの普及台数で35府県が東京都を上回った。ガソリンスタンドの相次ぐ廃業を受け「給油所過疎地」(総合2面きょうのことば)が深刻な問題となる中、各家庭で充電・走行が可能となるEVやプラグインハイブリッド車(PHV)は、光明となる可能性を秘める。環境意識の高まりも踏まえ、各自治体はハード、ソフト両面で普及を促す。2009~19年度の都道府県別の普及状況(補助金交付台数、次世代自動車振興センター調べ)を人口1万人あたりで算出した。首位は34.8台の岐阜県。以下、愛知県(31.3台)、福島県(30.7台)、佐賀県(28.2台)が続いた。東京都は15.4台だった。岐阜県は環境への取り組み強化に加え、中山間地を中心とする給油所過疎地の課題解決につなげようと普及を推進する。航続距離への不安を解消しようと県内56カ所ある「道の駅」の7割以上に急速充電器の設置を進め、全域をほぼカバーした。域内自治体も連携して取り組みを進め、高山市では環境保護の観点からマイカー規制中の乗鞍スカイラインでEVレンタカーによる乗り入れを試行。多治見市では地元の電力小売会社、エネファントが11日から小型EVレンタカーを開始した。道路の起伏や気候の状況、利用者ニーズなどの情報を市と共有し、普及への課題を洗い出す。愛知県は21年に「あいち自動車ゼロエミッション化加速プラン」を策定。EV、PHV、燃料電池車の新車販売割合を30年度に30%まで引き上げる目標を掲げ、普及に取り組む。事業者に対しては、上限40万円とした補助制度を創設。走行距離の多い事業者に手厚く配分した。個人向けには、12年から自動車税の課税免除制度を導入。新車新規登録を受けた年度の月割り分および翌年度から5年度分の全額が免除される。地域の足として欠かせない存在のガソリン・ディーゼルエンジン車は、給油網の維持自体が課題となっている。少子高齢化を背景とした後継者難に加え、人口減による需要減で採算性が悪化。全国の給油所数はピークに比べ半減した。20年度末時点でスタンドが3カ所以下の給油所過疎地は全国の2割を占める343市町村。スタンドがない町村も10を数える。維持コストの上昇に耐えきれず安定供給に支障をきたせば、地域は衰退の危機に直面する。一方、EVやPHVは設備さえ整えれば自宅でも充電が可能となる。それだけに熱視線を注ぐ地域も多い。福島県三島町では唯一のスタンドが20年5月に閉店。12月に公設民営として再開にこぎ着けたものの不安は尽きない。EVシフトを見据えた対応も検討する。鹿児島県薩摩川内市の甑島では、実証実験として17年度に島内に40台のEVが導入された。終了後、「給油レス」など利便性の高さを認識した宿泊施設などが計7台を買い上げ、現在も利用を続ける。公共交通機関もシフトを進める。甲府市がEVバスを導入したほか、那覇市などでも導入予定。北九州市を拠点とする第一交通産業は23年3月までにバスやタクシー115台を導入する。さらに災害時の「非常電源」としての期待も高まる。一般的な国産EVは電気を外部に供給できる機能があり、台風や地震などによって大規模停電が発生した際に、電力源として活用できる。現在、多くの自治体がトヨタ自動車、日産自動車などとEV派遣協定締結を進め、21年7月末時点で国内自動車メーカーと自治体が結んだ協定は少なくとも420件。2年で10倍に拡大した。 <先進技術 ー(その3)農業> *4-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15171104.html (朝日新聞社説 2022年1月14日) 農林水産輸出 「1兆円」達成の次は 農林水産物の昨年の輸出額が、政府が目標に掲げる1兆円を初めて超えた。農林水産省によると、昨年1~11月の輸出額は前年同期比26・8%増の1兆779億円。ホタテ貝(前年同期比103・2%増)、日本酒(73・5%増)、イチゴ(73・2%増)などが大きく増えた。日米貿易協定で米国向けの低関税枠が広がった牛肉も87・7%伸びた。コロナ禍の巣ごもり消費に対応するため、ネット販売を強化したことなどが功を奏したという。日本では今後、人口減少が避けられない。政府は輸出拡大を、国内の農林水産業の基盤を維持する有力な選択肢と位置づけて支援を続けてきた。「輸出1兆円」は、最初に政府が目標を掲げた06年当時は13年に達成するはずだった。予定より8年遅れたとはいえ、食料自給率など農水省の掲げる目標の多くが未達であることを考えれば、達成できたことは一定の評価ができよう。政府は輸出を今後も拡大し、25年に2兆円、30年に5兆円をめざす。1兆円を超えても、国内生産額に占める割合はまだ2%にとどまる。米国(12%)、英国(18%)などほかの主要国を下回っており、輸出の拡大余地はまだ大きいというのが農水省の見解だ。ただ、世界の日本食ブームを追い風に拡大してきた輸出の伸びは、19年以降鈍化していた。原因として指摘されるのは、主な販売先だった海外の富裕層で日本産の需要が飽和状態に達しつつあることだ。中間層にも販売を広げることが、次の目標達成には欠かせない。日本の農業生産者は、減反政策で政府が生産量を調整してきたコメを中心に、品質のよい商品を高価格で販売しようとする傾向が強い。輸出をさらに拡大するには、生産者が自ら市場のニーズを見極め、何をどれだけのコストで生産するかを決めることが求められる。重要なのは、輸出で生産者が利益をあげられる構造をつくることだ。コメのように輸出向けの生産を助成金で優遇する政策は、生産コストを高止まりさせる結果を招きかねない。政府の支援は、品種改良や物流の効率化、加工施設の整備など、中長期的な競争力強化につながる政策に絞るべきだ。中国や韓国、台湾など主要輸出先の多くが福島第一原発事故後に導入した日本産の輸入規制を続けている。政府は、環太平洋経済連携協定(TPP)の新規加盟協議などを通じ、規制解除を粘り強く働きかけてほしい。福島第一の処理水を海洋放出するのであれば、安全性を丁寧に説明する必要がある。 *4-2:https://toyokeizai.net/articles/-/464342 (東洋経済 2021/10/30) 日本人は低い食料自給率のヤバさをわかってない、6割以上を海外に頼る状況を放置していいのか 10月31日に投開票を控える衆院選を前に、選挙戦では、どの政党からも「経済安全保障」というフレーズが飛び交っている。岸田政権は、経済安全保障政策として今年5月に閣議決定された「中間取りまとめ」であげられたエネルギー、情報通信、交通・海上物流、金融、医療の5分野を重点分野として取り上げている。しかし、実は日本には古くから高いリスクとして懸念されている安全保障分野がある。それは「食料自給率」の低さだ。食料自給率とは、自国の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標。日本は先進国でかなり低いレベルにある。食料の自給は、国民の命を直接左右するものであり、ある意味では防衛やエネルギー資源以上に意識しなければならない。ただ、今回の総選挙では大きなテーマにもなっていない。日本の食料自給率は、本当に大丈夫なのか……。農林水産省の資料などをもとに、いま一度考え直してみたい。 ●日本の食料自給率、過去最低の37%! 農林水産省が最近になって発表した、2020年度のカロリーベースの日本の食料自給率は、前年度から0.38ポイント減少して37.17%になった。統計データが存在している1965年度以降、小数点レベルで見れば過去最低の数字だ。新型コロナウイルスによる影響で、畜産品の家庭用需要が拡大し、牛肉や豚肉などの国内生産量が増えたにもかかわらず、昨年度は輸入が増えた影響だとされている。農水省は、現在2030年度までにはカロリーベースの食料自給率を45%に高める目標を掲げている。ところが、日本の食料自給率は年々ズルズルと減少しているのが現実だ。食料自給率の考え方には、熱量で換算する「カロリーベース」と金額で換算する「生産額ベース」の2種類がある。カロリーベースでは1965年には73%あったが、前述したように今や37%まで下がっている。生産額ベースの自給率も1965年には86%あったが、2020年には67.42%にまで減少している。日本人の食料の6割以上を海外からの輸入に頼っているというのが現実だ。いわゆる「食料安全保障」と呼ばれる分野である。長い間、そのリスクが指摘されているものの、効果的な政策は出てきていない。最近になって、新型コロナウイルスによる混乱などに伴って、牛肉や小麦、チーズなどが値上げされた。さらには天候不順などが原因で、10月1日以降輸入小麦の政府売渡価格が前期比19%引上げられ、家庭用レギュラーコーヒーが20%程度、そしてマーガリンも12%程度値上げしている。食料品の価格上昇は、日本に限ったことではないものの、世界的に需要と供給のバランスが崩れてきていることは間違いないだろう。 <組織再編へのいちゃもんはよくないこと> *5-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC054YT0V00C22A1000000/ (日経新聞 2022年1月5日) 東芝社長が年頭あいさつ、会社分割は「最善策と確信」 東芝は5日、綱川智社長兼最高経営責任者(CEO)による年頭あいさつを公表した。東芝は2021年11月、グループ全体を3つに分割し、中核事業を2つの新会社として分離・独立させる計画を発表している。綱川社長はあいさつで計画について触れ、「私はこの経営変革がグループの企業価値向上に向けた最善策であると確信している」などと改めて強調した。綱川社長はあいさつで「今般の再編により新会社はスピード感をもってそれぞれのビジネス特性に応じた事業を展開することが可能になる」と分割計画の狙いを説明した。その上で、「22年はビジネス特性が大きく異なる2つの事業グループが新しいリーディングカンパニーとして進化するための準備が本格化する年になる」とした。東芝が21年11月に公表した計画では、グループ全体を、発電機器やインフラの「インフラサービス」、半導体などの「デバイス」、保有株式管理などの会社の計3つに分割する。2つの事業会社は新規上場させる計画で、23年10月~24年3月の実現を目指すとしている。まずは22年3月までに株主の意向を確認する臨時株主総会を開くという。綱川社長はこの他、「(温暖化ガス排出量を実質ゼロにする)カーボンニュートラル社会の実現、レジリエント(強靱、きょうじん)なインフラの実現、社会・情報インフラの進化に向けたグループの使命を果たす」などとした。 *5-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC072SM0X00C22A1000000/ (日経新聞 2022年1月7日) 東芝、臨時株主総会の基準日は31日 3分割計画など審議 東芝は7日、臨時株主総会に向け、議決権を行使できる株主を確定する基準日を31日に設定したと発表した。グループ全体を3つに分割する計画について株主の意向を確認するための総会で、3月中の開催を予定している。日時や議案の詳細はまだ明らかにしておらず、「招集を決定次第開示する」としている。東芝は2021年11月に分割計画を公表し、22年1~3月の間に臨時総会を開催して株主の意向を確認するとしていた。会社側として準備を進めていたところ、6日には株主から臨時株主総会の招集請求が出された。大株主でシンガポール拠点の資産運用会社、3Dインベストメント・パートナーズは臨時総会を招集請求した上で、分割計画の実施を定款に追加するよう求める議案など2つを株主提案するとしている。東芝は3Dからの招集請求については「対応は慎重に検討中」としており、今後、会社側の議案も含め、臨時総会で諮る議案の詳細などを決めるとみられる。 *5-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC07CB90X00C22A1000000/ (日経新聞 2022年1月10日) ジョブ型雇用とは 職務を明確化、専門性を高める ▼ジョブ型雇用 働き手の職務内容をあらかじめ明確に規定して雇用する形態のこと。事業展開に合わせて外部労働市場から機動的に人材を採用する欧米企業に広く普及している。会社の業務に最適な人材を配置する「仕事主体」の仕組みといえる。特定の業務がなくなれば、担当していた人材は解雇されることも多い。日本で一般的な「メンバーシップ型雇用」は、社員にふさわしい仕事を割り当てる「人主体」の仕組みだ。新卒一括採用と終身雇用が標準で、社員を転勤も伴うジョブローテーションを通じて時間をかけて育成する。事業環境の変化が激しくなれば、企業のニーズと人材のミスマッチも生じやすくなる。ジョブ型では賃金は仕事の中身で決まる。人工知能(AI)の専門家など需要が高い職種では、年齢に関係なく賃金は高くなる。一方、人主体のメンバーシップ型では働き手の社内経歴や勤続年数が水準を左右する。技術革新が加速しグローバルな人材獲得競争が激しくなるなか、ジョブ型のメリットが増している。 *5-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK1452M0U1A710C2000000/ (日経新聞 2021年7月19日) ジョブ型「御三家」の知恵 企業が磨く変化対応力 年功制や順送り人事を排すジョブ型雇用を導入する企業が広がっている。この制度の眼目は激しさを増す環境変化への適応力をつける点にある。日本でいち早くこの制度の導入に動き、ジョブ型「御三家」といえるKDDI、富士通、日立製作所。3社の取り組みからは、変化への対応力を高める工夫が随所にみえる。ジョブ型の人事制度は社内の各ポストの職務を明確にし、こなす能力を備えた人材を社内外から起用する。高い専門性が求められ、それに見合った報酬をもらえる職務に就くには自らの能力を向上させなければならない。ポストの獲得競争を活発にすることで、個々の社員のレベルを引き上げる効果が期待できる。KDDIなど3社は、こうしたジョブ型の本質的な利点に着目し、自社の制度を設計してきた代表的な企業だ。組織・人事コンサルティング大手マーサージャパンは5月末~7月中旬、白井正人取締役と3社の人事担当役員・幹部との公開対談をそれぞれ開いた。そこでの3社からの発言をもとに、ジョブ型制度の設計や運用をめぐる知恵を掘り下げてみたい。 ●職務記述書(JD)は柔軟に まず注目したいのは、職務内容や求められる能力を明記する「ジョブディスクリプション(職務記述書、JD)」のつくり方だ。個々人が担当する仕事の中身を明確にしようとするあまり、JDを精緻につくる必要があると考える企業は少なくない。だが、KDDIの白岩徹・執行役員人事本部長によれば、「JDは細かくつくり過ぎると機能しない」。経営環境が刻々と変わるなかで、やるべきことが新たに生じているにもかかわらず、JDの記載内容に縛られて手を打たずにいるリスクがあるからだ。KDDIはジョブ型の人事制度を2021年度から管理職に導入した。JDに相当する仕組みとして、「コンシューマ営業」「法人営業」「研究開発」「データサイエンティスト」など30の領域を設定し、職務内容や要求されるスキル(技能)を記している。この区分はマーサージャパンの白井氏によると、「極めて大ぐくり」だ。白岩氏は「1on1(ワン・オン・ワン)」と呼ばれる上司と部下との個別面談を、少なくとも2週間に1回開くよう求めている。対話のなかで、「設定した目標を柔軟に入れ替えてほしい」。環境変化に後れを取らないためだ。20年度に管理職へジョブ型制度を導入した富士通も、「JDを精緻につくることに労力はかけたくない」と平松浩樹・執行役員常務は話す。外部のJDの事例を参考に、これに追加や修正をする形で管理職約1万5千人分のJDを迅速につくった。「社員本人と上司は、JDに書いてある以上のことを共有している」(平松氏)。社員と上司がどれだけコミュニケーションを深められるかが一段と問われる。欧米企業では、JDに「同僚と協力しながら」といった文言を入れているケースも多い。記載された以外の業務をこなす場合もしばしばある。JDの弾力的な作成・運用はひとつのポイントだ。 ●「戦略に従う」組織に 事業環境の変化に俊敏に対応するため、権限委譲が進む点も目を引く。富士通は社内の各本部に、どんな人材をどれだけの数、確保するかという要員計画づくりをゆだねた。この権限はこれまで人事部門が握っていたが、現場に委譲して機動力を上げる狙いだ。各本部には人材採用の権限も移し、それぞれの戦略をもとに、新卒・中途とも通年で採用する仕組みにした。ジョブ型雇用が浸透した欧米では、組織のリーダーの最も重要な仕事は経営トップの方針に沿って目標を立て、その達成に貢献できる人材を社内外から集めることだ。「組織は戦略に従う」とは米国の経営史家アルフレッド・チャンドラーの言葉。富士通の取り組みは「戦略に従う」組織への改革といえる。そのためには人事部門も変わらなければならない。人材を一括して採用し、各部署に割り振るという日本特有の人事の仕事は、ジョブ型制度の導入に伴い、なくなる方向にある。「人事は事業部門のビジネスパートナー。各本部のリーダーとともに(人材の獲得などでの)課題と向き合い、解決策を提案する」と平松氏。「この本部のビジネスは私が一番わかっている」と言える人事マンを増やしていくという。21年秋までにすべてのポジションについてJDをつくり、ジョブ型マネジメントを本格導入する日立製作所。同社も「ジョブ型ではラインの管理者が主役になり、これに伴い人財部門の役割改革に取り組んでいる」(山本夏樹・人財統括本部人事勤労本部長)という。これからの人事部門の主な役割は、各職場の課題を把握し、人と組織に関する課題の解決策を管理者に提供したり、事業方針の浸透を手助けしたりすることだ。問い合わせに幅広く対応するためデータやノウハウの蓄積も進めている。 ●意識改革へ対話を重視 ジョブ型制度の導入は従来の人事や組織運営の考え方の抜本的な見直しになるだけに、社内の意識改革がカギを握る。日立は人事担当役員・幹部らがジョブ型制度の必要性や運用をめぐって、事業部長や労働組合などとのコミュニケーションを深めている。たとえば山本氏は事業部長クラスとこれまでに計24回、対話の機会を持ち、ジョブ型の人材マネジメントへの理解を促した。「求められるスキルと現在のスキルのギャップが大きい人材はどう活用していけばいいのか」「ジョブ型制度を広げるなかで、日立の強みをどのように発揮していくのか」――。答えがすぐに出るとは限らないが、議論を積み重ねることがジョブ型マネジメントの土台をつくる早道と考えている。管理職以外にもジョブ型を浸透・定着させるうえで、労働組合との問題意識の共有は欠かせない。日立は労組と、ジョブ型制度をめぐって通年で随時、話し合う場を設けている。「長い職業人生のなかではキャリア構築にポジティブ(積極的)なときもあれば、そうでないときもある。従業員が悩んだときに、どう支援すべきか、引き続き議論を深めたい」(労組)。21年の春季労使交渉で日立は、労組の本部や事業所ごとにある支部との間で、ジョブ型制度に関する議論を28回重ねた。 ●社員の再教育を推進 社員のやる気を引き出す取り組みも重要になる。人材の活性化を抜きに、企業が変化への対応力を高めることは難しいからだ。社内公募制を設けるだけでなく、努力すれば希望するポストへの異動がかないやすい環境を整える必要がある。KDDIは事業モデル変革の担い手を育てる「DX(デジタルトランスフォーメーション)人財育成プログラム」の内容を進化させている。基礎的な研修では受講者は事前テストを受け、理解度に合わせてeラーニングやワークショップ形式で無理なくスキル(技能)を習得してもらう。終了後は「コアスキル研修」「専門スキル研修」と、段階的にレベルを上げていく。人材養成拠点として181の宿泊室を備えた研修施設も20年春、東京都多摩市に開設した。3社と対談したマーサージャパンの白井氏は、「従来の日本型雇用と比べたジョブ型雇用の長所は、社員に対してリスキリング(再教育)へのインセンティブ(動機づけ)をはたらかせることができる点にある」と解説する。「デジタル分野など環境変化のスピードが速い分野の企業は、能力の高い外部人材を採用して事業の担い手の入れ替えを進めたり、いまいる社員のスキルの底上げをしたりする必要がある」(白井氏)。技術革新が活発な分野やグローバルに事業展開する企業は、時間をかけて技能に習熟することが求められる企業よりも、ジョブ型雇用を導入する必要性が高いという。 ●ジョブ型導入は効果的手段 「ジョブ型雇用の導入は単に人事制度を変えることではなく、個を重視した人材マネジメントや企業運営への転換といえる。企業にいま必要なのはジョブ型のエッセンスを取り入れた総合的な人事・組織の改革だ」。人的資源管理に詳しい守島基博・学習院大教授はそう指摘する。ジョブ型制度には課題もある。「(専門能力がまだ十分に身についていない)入社後3~5年の若手の場合、ジョブ型は本当に機能するのか。これは悩ましい問題」(日立の山本氏)。製造現場の社員は多能工化が進み、技能の多さに応じて給与が決まる面があるため、ジョブ型導入が賃下げにつながりかねないという。社内公募が浸透したとき、どのポストにも受け入れてもらえない社員は配置をどうするのかという問題もある。欧米などと異なり日本では解雇が厳しく制限され、「戦力外」の人材でも雇用を保障せざるを得ない。戦力外であることを明確に伝え、身の振り方を真剣に考えるよう促すのか。リスキリングによって「戦力内」に戻ってもらう道を探るのか。いずれにしても、企業にとって労力がかかる。だが、それでもジョブ型の導入はメリットの方が上回る。年功制や順送り人事といった日本的な慣行を断ち切って企業の競争力を立て直すうえで、効果的な手段であることに変わりはない。日本型雇用を続けていては株式市場から成長力を疑問視され、海外からの投資も呼び込めない。ジョブ型マネジメントの定着に向け、先行する企業の例も参考に、各企業の創意工夫が求められる。 *5-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220202&ng=DGKKZO79743030R00C22A2TCN000 (日経新聞 2022.2.2) 女性エンジニア、イノベーション創出には不可欠 企業などの研究開発現場に女性リーダーが少ないことの弊害は多い。例えば、男性を前提に設計された自動車のシートベルトでは女性を十分に守れず、交通事故で女性が重傷を負う比率が高かった。性差を分析したうえで技術を革新させる「ジェンダード・イノベーション」には、優れた女性エンジニアの活躍が不可欠という問題意識が各大学の工学教育の現場を突き動かす。お茶の水女子大は22年度にジェンダード・イノベーション研究所を発足させる。「研究所と共創工学部が両輪となり、日本のジェンダード・イノベーションのハブになる」(森田育男理事・副学長)体制を築く狙いだ。いでよ、工学女子。明治期の女子高等師範学校が源流で、100年以上の歴史を持つ2つの女子大に今から工学部が誕生する現象は、人材の多様性の欠如が日本発のイノベーションを妨げている危機感を映し出している。 <“慎重”なのではなく、反対で妨害したトヨタ> PS(2022年2月7日追加):*6-1-1に、①世間はトヨタのFCVを含んだ目標を評価しなかった ②世間とトヨタのズレはHVを主軸に置く戦略から生じている ③豊田は過去にEVを造っていたので「EVはいつでもできる」と考え、充電インフラが盤石でないことから、HVを含む全方位で電動化に臨む姿勢を崩さずEVは選択肢の一つにすぎないと認識し ④石炭を燃やした電気で走っても脱炭素にならない」と日本政府が進めるEVシフトを痛烈に批判していた ⑤この間、世界が急転回してEUはHVを含む内燃機関車を2035年に実質的販売禁止とする方針を表明し ⑥その後、ミュンヘン国際自動車ショーはEV一色になり、トヨタが世界から取り残された ⑦ソニーグループが参入検討を表明した 等が記載されている。 ①は明らかな間違いで、水素燃料電池を使った航空機や電車は既にできており、現在は船舶への応用が待たれている状況だ。しかし、そもそも最初に水素燃料電池を使ったのは、2009年に発売された三菱のi-Mievである。また、②は正しいが、プリウスはよい車だったものの、トヨタは「HVは、EV・FCVとガソリン車との繋ぎ」と理解して、速やかに燃料を電力に変えることを考えるべきだったのだ。 そのような環境下であるため、トヨタは、④のような言い訳を考えてEVを否定している間に、安価で便利なEVや充電設備を造って普及させれば、世界標準をとることができた筈だ。また、③のように、EVはガソリンエンジンよりも格下と位置づけ、資金を分散している間に、⑤⑥のように、環境を重視する他国に静かに置いて行かれたわけである。 一方、*6-1-2のように、日産・ルノー・三菱自動車の3社連合が、2030年に向け新たな計画を発表したそうだが、そもそも日産の電動車を始めて市場投入して世界を牽引したのはカルロス・ゴーン社長(当時)だった。そのため、ゴーン氏の経営判断は正しかったし、功績もとびぬけて大きいが、そのゴーン氏の高額報酬を日本メディアは著しく批判した。さらに、役員報酬の未払い分を隠しで金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)・会社法違反(特別背任)で起訴し、日産を後退させたのは、経産省や警察と組んだ日産の西川広人社長だった。これらが、トップを走って先進技術を応用した人への日本社会の恥ずべき妨害方法なのである。 なお、*6-2のように、⑦新興企業MIRAI-LABOが太陽光パネルを装備した道路舗装を開発し、2022年の実用化を目指し ⑧電気は地中の電線を通じて蓄電池に溜め ⑨中日本高速道路は道路に埋め込んだセンサーを使って自動運転で必要なデータを発信するシステムを開発し ⑩総延長約128万キロメートルに及ぶ道路の価値の掘り起こしが本格化する そうだ。 高速道路と国道の半分を発電型舗装に切り替えれば、日本の消費電力の16.5%を賄えるそうで、電力料金は道路の所有者に入るため、道路の所有者は収入を増やすことができる。又は、道路の所有者が専門の発電業者に道路使用権を貸すことによって収入を得る方法もある。また、地面に電極を敷設して受電装置を備えたEVが上を走ると電気が送られる装置なども魅力的だ。  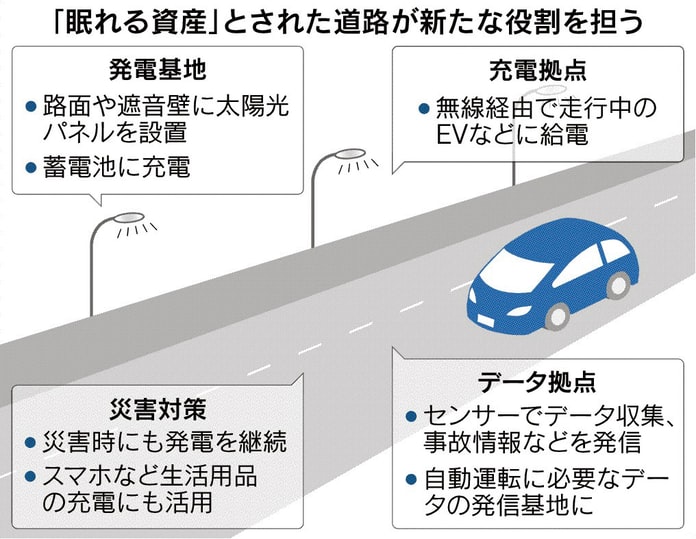  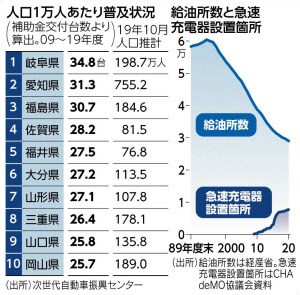 2019.7.20日経新聞 2019.11.13日経新聞 2022.1.22日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、道路を使って太陽光発電する機器もできているため、これを改良しつつ道路を選んで設置すれば、広い面積で太陽光発電可能で、国や地方自治体の財源にもなり得る。また、左から2番目や右から2番目の図のように、道路で無線やタイヤを通して充電するシステムも開発中だ。さらに、1番右の図のように、給油所の減少に伴い、より手軽に充電できる施設が、自動車が必需品の地方で普及し始めている。このように、需要は、より快適で、安価で、手軽に使え、環境にも良い製品にシフトするものだ)     2020.9.22BBC ドイツ 2020.9.17中央日報 燃料電池都バス 燃料電池航空機 燃料電池電車 韓国燃料電池トラック (図の説明:1番左は、エアバスの燃料電池航空機、左から2番目は、ドイツの燃料電池列車だ。また、右から2番目は、現代自動車の燃料電池トラックで、1番右が、トヨタの都バスだ。いずれも、早く普及すればよいと思う) *6-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220207&ng=DGKKZO79911800W2A200C2PE8000 (日経新聞 2022.2.7) EV急加速1 「慎重すぎた」トヨタ 「私たちの思いがまったく通じない世界があることも思い知らされました」。1月7日の年初のあいさつで、愛知県豊田市の本社に集う従業員約500人を前に、トヨタ自動車社長の豊田章男はこう語り始めた。豊田が「通じない世界」を痛感したきっかけは2021年5月12日。30年に電気自動車(EV)200万台を販売する方針を発表したが、燃料電池車(FCV)を含んだ目標を、世間は評価しなかった。「トヨタ社長はEV反対派だとイメージ操作されている」。それ以降、豊田は不満を口にするようになった。 □ □ トヨタと世間とのズレは、ハイブリッド車(HV)を主軸に置く戦略から生じている。1997年に「プリウス」が道を開いたHVの世界販売は1500万台を突破。新型「ヤリス」の燃費性能は現状、世界一に立つ。豊田は過去にEVを造っていたことに触れつつ「HVはEVにもつながる。核となる技術は同じ」と説明してきた。EVの充電インフラが盤石ではないことから、HVを含む全方位で電動化に臨む姿勢を崩さないでいた。「EVはいつでもできる」選択肢のひとつにすぎないとの認識だった。だがこの間、世界が急転回する。欧州連合(EU)は21年7月、HVを含む内燃機関車を35年に実質的な販売禁止とする方針を表明。その後開かれたミュンヘン国際自動車ショーはEV一色に。30年の「EV専業」を宣言した独メルセデス・ベンツ社長のオラ・ケレニウスは「(EVシフトは)もはや意思決定ではない。実行と加速の時だ」と述べた。「脱炭素をどう達成するかが重要なのに『EVをやる』と言ったもの勝ちになっている」と冷ややかにみていたトヨタだったが、気付けば世界から取り残されていた。EUによるHV排除が決まった直後の7月24日、東京・南麻布の在日フランス大使館で豊田は仏大統領のマクロンと向き合っていた。「HVをもう少し使えるよう働きかけてもらえないか」。関係者によると選択肢を残す必要性を訴えたようだが、うなずき返したマクロンは帰国後、規制緩和には動かなかった。思うように状況を打開できないせいか、豊田は政権にも迫った。「けんか別れしたと思われないように取材には応じましょうか」。12月2日、首相の岸田文雄と面会した豊田はこう岸田に話し、「有意義な意見交換ができた」と報道陣に笑顔を見せた。その姿は以前とは大きく異なった。「石炭を燃やした電気で走っても脱炭素にならない」。豊田は政府が進めるEVシフトを痛烈に批判しており、2月に首相(当時)の菅義偉のもとを訪れた際には、取材に応じず無言で官邸を後にした。 □ □ 世界で広がるEVシフトの波に突き動かされるように、豊田が説明会の仕切り直しを決めたのは10月下旬のことだった。12月14日、東京・お台場で開いた説明会で豊田は「30年にEV350万台販売」の新方針を示した。「これでも前向きじゃないと言われるならどうすれば前向きな会社と評価いただけるのか」。準備期間は2カ月弱。披露したEV16台のうち11台は粘土製(クレイモデル)だった。新方針の実現のため、EVに4兆円を投じると説明。ライバルの独フォルクスワーゲン(VW)、ヘルベルト・ディース社長はツイッターで「トヨタもEV。競争は歓迎だ」とつぶやいた。30年までに4兆円の投資は電動化戦略を転換したかのように映る。だが、株式市場によるトヨタの20年度から5年間の営業キャッシュフロー予測は16.7兆円。現金化しやすい流動資産で平均24兆円に上る。資金余力からみると決して高い金額ではない。EV350万台も新車販売全体の3~4割にとどまる。「社内では350万台は目標というよりあくまで基準。私たちは今まで慎重すぎた。ただEVだけにかじを切ったとは思われたくない」。トヨタ幹部は率直な思いをこう語った。12月の説明会後、トヨタの株価はじりじりと値を上げ、22年1月18日には時価総額が初めて大台の40兆円を突破した。 (敬称略) ◇ ソニーグループが参入検討を表明するなど、業界を超え過熱するEVシフトの最前線を追った。 *6-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220204&ng=DGKKZO79849450U2A200C2EA1000 (日経新聞社説 2022.2.4) 日産連合は着実な再出発を 日産自動車と仏ルノー、三菱自動車の日仏3社連合が2030年に向けた新たな計画を発表した。電気自動車(EV)を中心に電池やソフトウエア分野など次世代技術に関して、3社が一体となって取り組むという。着実な実行を期待したい。日産ルノーは会長だったカルロス・ゴーン被告が18年に逮捕されて以来、ガバナンスの問題が指摘されてきた。ルノー会長で3社アライアンスを仕切るジャンドミニク・スナール氏も1月末の記者会見で「3年前には最悪の危機にあり信頼が欠けていた」と認めた。そのうえでの再出発である。良くも悪くもゴーン被告の絶対的な権限のもとに運営されてきた日仏連合を、どう導くのか。スナール氏や日産の内田誠社長ら経営陣は提携の実効性を示して信頼の回復に努めることが不可欠だ。さらに3社の強みを持ち寄ることで、次世代技術で世界をリードできる国際連合にしてほしい。3社が発表した計画では、26年までに車の骨格にあたるプラットホーム(車台)を8割共通化させ、30年までには投入する35車種のEVの車台を9割まで共有するという。アライアンスを深化させる意志は伝わってくる。ゴーン被告が去った際には結束が問われた3社だが、自動車メーカーとして後戻りのできない工程表を示したと言えるだろう。EVの時代に中核技術となる電池やソフトの共有化も含めた具体的な計画には、一定の説得力がある。業界全体を見渡せば、これまでの車づくりの常識が通用しない100年に1度の大変革が起きつつある。ライバルは従来の自動車メーカーだけではあるまい。ソニーグループがEVの新会社設立を表明し、米アップルの参入も取り沙汰される。これらが実現すれば水平分業的な生産体制が広がる可能性がある。ソフトウエアが果たす役割も高まるだろう。3社には外部の知識も積極的に採り入れ、大変革期を主導する戦略も問われる。 *6-2:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO52098720S9A111C1TJ1000/ (日経新聞 2019年11月13日) 道路舗装で太陽光発電、ミライラボ、EV給電も 中日本高速など、CASE対応 「眠れる資産」とされた道路に、最新テクノロジーを実装する動きが広がっている。新興企業のMIRAI-LABO(ミライラボ、東京都八王子市)は太陽光パネルを装備した道路舗装を開発した。中日本高速道路は道路に埋め込んだセンサーを使い、自動運転で必要なデータを発信するシステムを開発している。車の電動化など「CASE」の普及をにらみ、総延長約128万キロメートルに及ぶ道路の価値の掘り起こしが本格化する。2006年設立のミライラボは非常用電源など省エネ機器を手がけ、全国の警察や自治体に販売する新興企業。今回、太陽光で発電する道路舗装「ソーラーモビウェイ」を開発した。太陽光パネルを特殊な樹脂で覆い道路の舗装材の代わりに使う。現在、道路舗装大手NIPPOと性能試験を進めており、2022年の実用化を目指す。通常の太陽光パネルは衝撃に弱く割れやすい。今回、ミライラボは柔軟性のある素材を使い衝撃に強いパネルを採用した。舗装面にパネルが露出していると車がスリップしたり路面が摩耗したりする。これを防ぐためセラミック片を混ぜた透明な樹脂でパネルを覆う。ビル屋上などの太陽光パネルは光の角度が浅いと発電効率が落ちる。開発した舗装材はセラミックが太陽光の角度を変え、1日を通した発電量を高める効果が期待できるという。電気は地中の電線を通じ蓄電池にためる。電気自動車(EV)などで使ったバッテリーの再利用も想定する。国内には総延長約128万キロメートルの道路が走っているが、車や人の移動用途が中心の「眠れる資産」だ。ミライラボの平塚利男社長は「高速道路と国道の半分を発電型の舗装にすれば日本の消費電力の16.5%を賄える」と試算する。ミライラボがにらむのは、車の電動化や自動運転など「CASE」の本格到来だ。発電した電力は街灯や道路表示板に加え、将来は走行中のEVへの無線給電や、自動運転に必要な道路状況に関するデータ通信の電力源としての活用を想定している。停電で自動運転車に情報が送れなくなると事故につながる恐れもあり、電源を道路で賄えるメリットは大きい。道路を発電基地にする利点はほかにもある。平地の少ない日本では森林を伐採してパネルを設置するケースが多く、道路を活用すれば環境破壊を防げる。災害で停電が起きてもパネルで発電すれば信号や街灯を維持できる。再生エネルギーの送電網不足が問題となるなか、道路での発電は「地産地消」につながる。国内の道路は老朽化が進み、今後大規模な改修時期を迎える。国土交通省の試算では今後30年間、高速道路や一般道で年2兆円超の工事が必要になる。老朽化対策の時期がCASEの大波と重なることから、道路に最新テックを埋め込む技術開発が広がる。中日本高速道路(NEXCO中日本)は高速道路にセンサーやカメラを整備する。すでに東名高速など主要道に地磁気センサーを埋め込み、渋滞情報などのデータを集めている。今後、高精度カメラを短い間隔で設置し、道路の運行状況を絶え間なく監視できるようにする。同社は管轄する道路の約6割が建設から30年たち、「来年度から首都圏の主要道路が改修時期を迎える」(担当者)。次世代通信規格「5G」が実用化すれば大容量の映像データをスムーズに送受信でき、自動運転車へのデータ送信など道路の付加価値を高める。大成建設は豊橋技術科学大学と共同でEVのワイヤレス給電システムを開発している。地面に電極を敷設し、受電装置を備えたEVが上を走ると電気が送られる。ブリヂストンも東京大学などと共同でタイヤを通じて道路から充電する技術開発を進めている。道路から給電できれば搭載するバッテリー量を減らし車体の軽量化にもつながる。普及に向けた課題はコストだ。ミライラボとNIPPOが試験を進める発電型の舗装材は「まだ価格を設定する段階ではない」(NIPPO)というが、大幅なコスト増は避けられない。生産規模の拡大によるコスト低減や、道路の付加価値向上による新しい収益モデルの構築が必要になる。海外でも政府や企業がCASE対応を急いでおり、今後は国際競争も激しくなる。例えば道路での太陽光発電は米国やフランスなどで開発が進むが、現時点で明確な成功例は出ていないという。 <インフラの更新と財政健全化の両立> PS(2022年2月8日追加):*7-1-1は、①全国で道路や橋などのインフラの老朽化が止まらず ②2012年の中央自動車道トンネル崩落事故から9年経過しても、予算や人手不足で対応が後手に回っており ③トンネルの約4割は早急に手当てしないと危険な状態だ と記載している。 しかし、ここで重要なのは、①②③が起こった理由であり、それは、国や地方自治体が所有する固定資産(インフラを含む)の数量・価格を正確に把握して、維持管理や更新を続けてこなかったからである。これは、複式簿記で貸借対照表を作り、固定資産を正確に把握して維持修繕や更新を続けている民間企業では起こらないことで、国や地方自治体は単式簿記で貸借対照表項目の管理を全くしていないと言っても過言でないくらいだから起こるのである。 また、*7-1-1は、④人口減も見据えて優先順位をつけ ⑤ばらまきを排した投資を急ぐ必要があり ⑥センサーやドローンなど新技術を活用した保守点検の効率化もカギになる とも記載しているが、⑤⑥はよいものの、④の人口減している地方をますます過疎化させて人口集中を促したり、複式簿記による公会計制度を導入して不断に維持管理を行う根本的な改革はせずに同じ失敗を繰り返したりするのは、あまりにも“賢く”ない。 さらに、⑦施設が劣化するスピードに修繕が追いつかず、インフラメンテナンスが崩壊する可能性がある ⑧予防保全を徹底すれば費用を3割ほどは削れるものの、近年の公共投資は国際的には見劣りする とも書かれているが、⑦⑧を徹底し、合理的な意思決定ができるためには、正確な固定資産の数量・金額の把握が不可欠なのである。 その上、国(財務省・国土交通省)は、④のように、人口減を理由として地方を切り捨てることしか思いついていないが、*7-1-2のように、太陽光発電舗装をして路面で太陽光発電を行い税外収入を得るなど、所有する資産を利用して収入を得る方法もある。そのため、国民の自由を制限したり、予算を使ったりすることしか考えつかないのは、全く“賢い”とは言えない。 このような中、*7-2のように、⑨政治指導者には時に「聞き入れない力」が必要だ として、⑩自民党総裁選に立候補した4人のうち年金改革に関連づけて消費税増税をにおわせたのは河野太郎氏1人だった ⑪河野氏が増税を考えているのがわかった途端、党内の仲間が離れた ⑫自民党の衆参議員の多数派が消費税嫌いという事実ははっきりしたが、「消費税増税が年金の充実をもたらす」と結論付けている。 しかし、平成の間に行われた消費税増税によってもたらされたものは、下の図のように、家計消費支出の縮小、それに伴う民間投資の縮小、需給ギャップを補充するための景気対策と称する生産性の低い政府支出の増加と中央政府の債務増加であり、この間、経済成長率は低下の一途を辿った。政府支出が民間投資より生産性が低い理由は、「正確なデータに基づいて、最低のコストで最大の効果を挙げる」という発想がなく、「○○兆円規模の支出」というように、支出することのみを目的とするからだ。そして、経済成長率を推し上げる技術革新については、それを支える教育・研究を疎かにし、産業を育成する洗練された消費を抑え、現状維持に汲々として先端を抑えたのだから、この結果はやってみる前からわかっていた。 年金・医療・介護の充実については、目的外の無駄遣いをせず、それでも足りなければ赤字国債を発行して、団塊の世代にも対応できる適正な積立金を積むことにより、国民負担を増やしたり給付を削減したりすることなく、保険契約を遂行することによって行うべきだったのである。  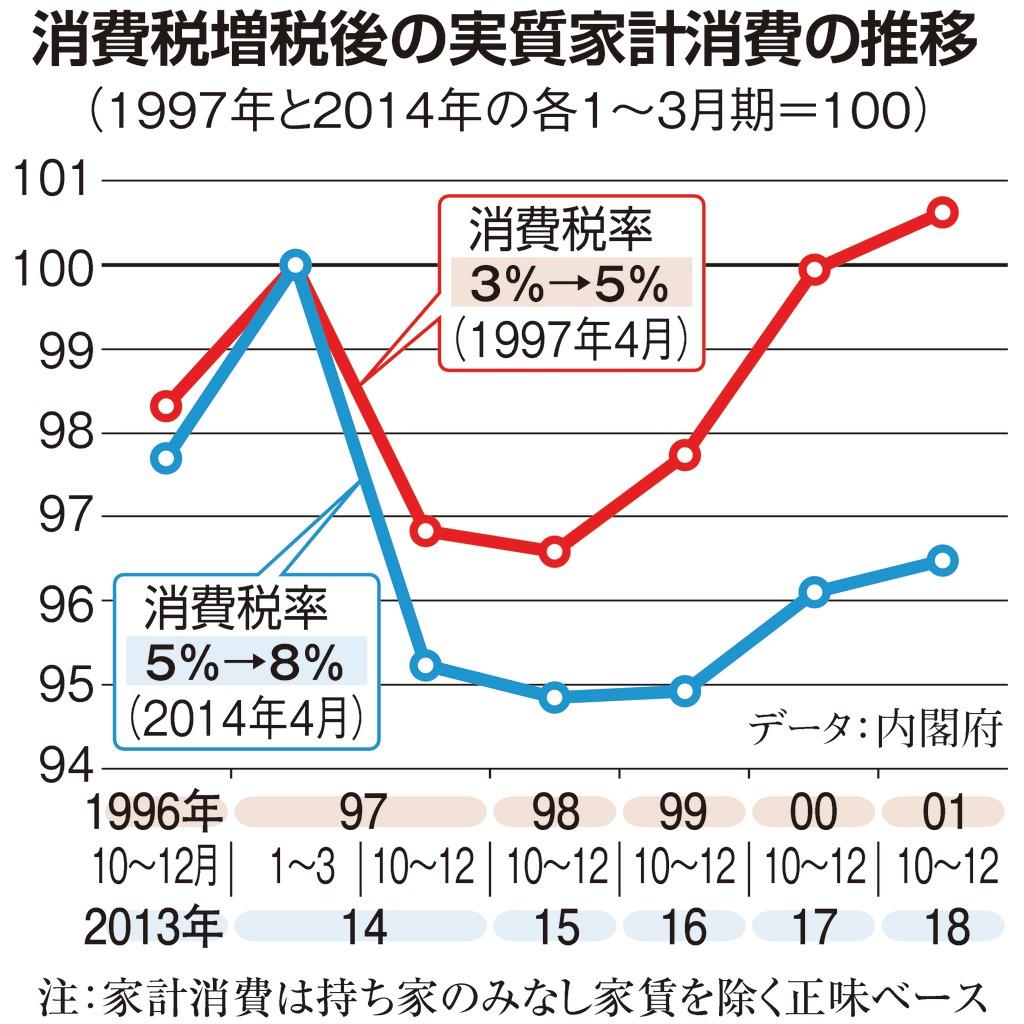 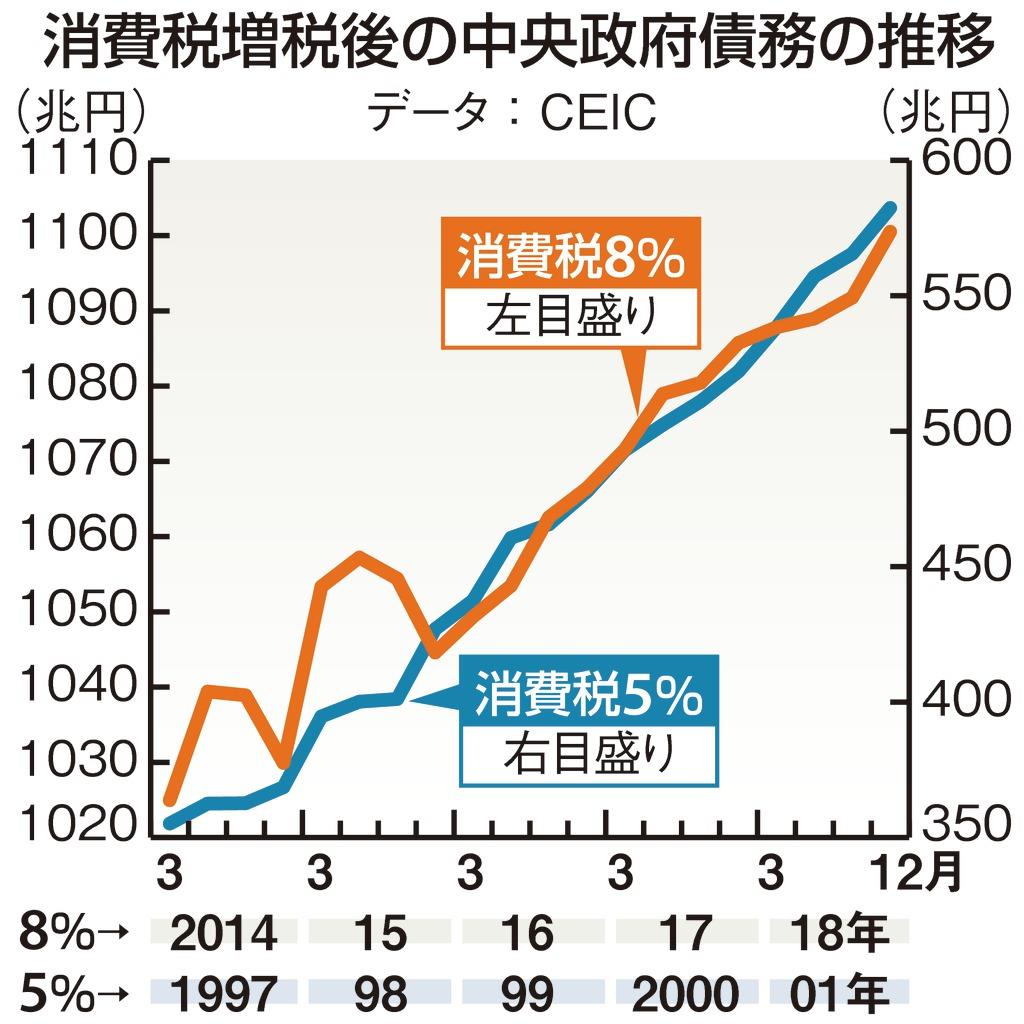 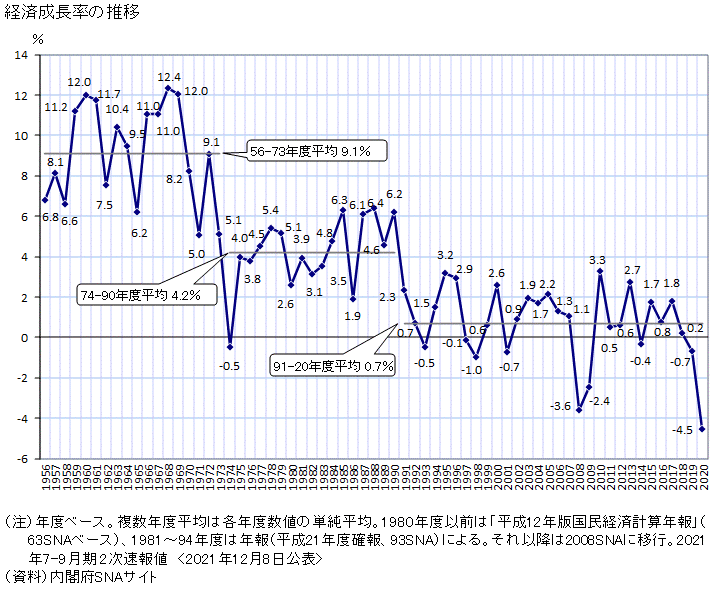 2022.2.7日経新聞 2019.3.30産経新聞 2019.4.13産経新聞 内閣府 (図の説明:1番左の図のように、平成の間に行われた消費税増税で、左から2番目の図のように、実質家計消費が落ち込み、右から2番目の図のように、その補充や景気対策と称して中央政府の支出が増え、債務は減らなかった。そして、1番右の図のように、実質経済成長率は、0近傍からマイナスまで下がり続けており、その理由は経済学で説明できるため、本文に記載する) *7-1-1: https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220206&ng=DGKKZO79905550W2A200C2MM8000 (日経新聞 2022.2.6) インフラ、とまらぬ高齢化、トンネル4割寿命 修繕費膨張、年12兆円も 全国で道路や橋などのインフラの老朽化がとまらない。9人が亡くなった2012年の中央自動車道のトンネル崩落事故から9年。総点検して修繕・更新を進めるはずが、予算や人手の不足で対応は後手に回る。トンネルの約4割は早急に手当てしないと危険な状態のままだ。人口減も見据えて優先順位をつけ、ばらまきを排した投資を急ぐ必要がある。センサーやドローンなど新技術を活用した保守点検の効率化もカギになる。1月中旬、羽田空港と都心を結ぶ首都高速道路の1号羽田線。作業員が寒風に吹かれながら橋桁にボルトを打ち込んでいた。1964年の東京五輪にあわせて整備されてから半世紀以上たち、海水による腐食も進む。首都高会社は1627億円を投じ、品川区内の約1.9キロの区間を2028年度までにつくり直す。首都高は開通から50年以上の路線の割合が40年に65%と20年の約3倍に増える。1日100万台の交通量を支える東京の屋台骨がきしむ。21年末に設置した対策会議で前田信弘社長は「道路機能を維持するには適切な管理と大規模更新・修繕を繰り返す必要がある」と強調した。インフラは建設後50年が寿命とされる。国土交通省によると、全国の道路橋は33年に全体の63%、水門など河川管理施設は62%、トンネルは42%がその目安に達する。実際に損傷も目立つ。16~20年度の目視点検では早期に修繕などが必要との判定がトンネル全体の36%に上った。橋梁は9%、標識や照明など道路付属物は14%だった。東洋大の根本祐二教授は「施設が劣化するスピードに修繕が追いついていない。インフラメンテナンスが崩壊する可能性がある」と警鐘を鳴らす。とりわけ心配なのが自治体だ。総点検で対応が必要とされた橋梁のうち国の管理分は20年度末までに6割が修繕に着手した。市区町村分は3割どまり。中国地方の自治体の担当者は「次々に補修が必要な施設が出てくるのに予算も人手も足りない」と嘆く。国交省によると20年度の橋梁点検でドローンなどを使った自治体は20%のみ。劣化を自動検知する無線センサーなど作業を効率化できる新技術の普及は今後の課題だ。後手に回ればツケは膨らむ。不具合が生じてから手当てする従来型の対応だと国・地方の費用は30年後に年約12.3兆円と18年度(約5.2兆円)の倍以上になる。30年間の総額は約280兆円と国内総生産(GDP)の半分に匹敵する。損傷が深刻になる前に修繕する「予防保全」を徹底すれば費用を3割ほどは削れる見込みだ。岸田文雄首相は1月20日の衆院本会議で「予防保全型の投資が中長期的に費用負担を抑制する効果も踏まえ、効率的な防災・減災のあり方を検討する」と述べた。政府が20年末にまとめた対策は5年間で約15兆円を投じる。より長期の視点で財源をどう確保し、やりくりするかも問われる。近年の公共投資は国際的には見劣りする。19年の投資額を1996年比でみると約4割減と主要7カ国(G7)で唯一落ち込んでいる。この間に英国は4倍、米国は2.3倍に伸びた。超高齢化で社会保障費が膨らむ日本は公共事業費をいたずらに積み増す余裕はない。まず予算の配分や執行の無駄をなくす必要がある。財務省によると公共事業の契約率は14~18年度に87%、予算の支出率は70%。20年度の繰越額は4.7兆円に上る。財源を適切に使い切れていない。東洋大の根本教授は「すべてのインフラを同じように更新するのは限界がある」と指摘する。地域の実情に応じてコンパクトシティーの取り組みで必要なインフラを絞り込むなど「賢く縮む」戦略も試される。 *7-1-2:https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/00088/?ST=msb&P=4 (日経BP 2019/7/20) 「路面で太陽光発電」、NIPPOが2022年までに実用化 ●道路法上の壁も 世界的に見ると、こうした「太陽光発電舗装」の研究開発では、欧州が先行している。フランスでは一般公道の車道、オランダでは、自転車道に試験的に施工したケースがある(図6)(図7)。国内でも、こうした海外製品をコンビニ店舗に採用した例がある (関連記事:太陽光で発電する道路「ワットウェイ」がフランスで稼働)(関連記事:オランダの「太陽光発電する道路」、発電は好調、累計3000kWh以上に)(関連記事:セブン-イレブン、再エネで半分の電気を賄う実験店、路面と屋根に太陽光)。NIPPOでは、今後、「スマートシティ」など脱炭素を目指した街づくりが活発化していくなかで、道路に「再生可能エネルギーによる電源機能」を持たせるニーズは高まるとみている。その際、蓄電池を組み合わせることで、道路に分散配置された「独立電源」として機能したり、区画線や横断歩道などの白線部分をLEDで路面発光させる際の電源、将来的には自動運転に向けた電気機器などの電源としても期待できると見ている。ただ、現状では、道路法上、発電設備を公道の路面に敷設できないため、当面は、商業施設の駐車場や、工場の敷地内など民間所有地での利用を想定している。同社は、電気自動車や自動運転の普及も睨んで、舗装と電気設備を統合した次世代の舗装システムを「e-Smart ROAD」とのブランド名で展開しており、「太陽光発電舗装」もその1つと位置づけている。 *7-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220207&ng=DGKKZO79866250U2A200C2TCT000 (日経新聞 2022.2.7) 消費税、参院選で信を問え 政治指導者には時に「聞き入れない力」が必要だ。違反者に罰金を科す厳しいロックダウン(都市封鎖)のさなか、ロンドン・ダウニング街(英首相官邸)の中庭や執務室で開いた飲み会に、自らも加わっていたジョンソン首相の支持率が急落した。自分がつくったルールを率先して破ったのだから当然である。長らく我慢を強いられていた英国民の堪忍袋の緒は切れ、ついにロンドン警視庁が捜査を始めた。野党労働党が首相の座を即座に降りるよう求めたのは当然として、身内の保守党からもジョンソン辞めろの声が聞こえる。ここは国民受けする迎合策を繰り出し失地回復したいところだ。ところが、である。日曜紙「サンデー・タイムズ」1月30日付への寄稿で、ジョンソン氏は4月からの増税は予定どおりと表明した。自らが辞めた場合、後継候補の最右翼に擬せられているスナク財務相との連名でいわく「カネのなる木はない」。コロナ禍で滞った同国の医療体制を修復するために、増税不可欠の立場を鮮明にした。針のむしろに座らされているなかでの増税宣言である。周りが何と言おうと聞き入れない力を備えているようだ。日本はどうか。昨年9月の自民党総裁選に名乗りを上げた4人のうち、年金改革に関連づけて消費税増税をにおわせたのは河野太郎氏1人だった。政策ブレーンによると、河野氏が増税を考えているのがわかった途端、党内の仲間がサーッと離れていった。序盤優勢だった同氏が中盤で失速したのと符合する。敗因は消費税だけではなかろうが、自民党の衆参議員の多数派が消費税嫌いという事実ははっきりした。ほかの3候補が増税を否定したこともそれを裏づける。納税者は同じ考えだろうか。河野氏は長期にわたって年々小刻みに年金の実質価値を下げてゆくマクロ経済スライドによって、基礎年金の最低保障機能が果たせなくなると訴え、補強のために消費税財源を充てる改革を主張した。増税が年金の充実をもたらすという帰結がみえれば納税者もむげには反対しまい。一方で、政治家が帰結を説明し理解してもらう難しさは残る。総裁選中は「消費税増税に賛成か反対か」を4候補に○×形式で答えさせたりするテレビ番組がたびたび流れる。これだけをみた人が、○を出した候補には首相になってほしくないと思うのは致し方なかろう。日本記者クラブ主催の討論会で、岸田文雄氏が今後10年程度は消費税増税が不要と明言したのも、この文脈でとらえればわかりやすい。消費税問題はメディアのあり方も問うている。岸田氏は外相時代の2017年夏、香川県にある大平正芳の墓に詣でた。間をおかず党政調会長になり「消費税率引き上げを可能にする経済環境をつくる」と語っている。大平は宏池会の先達だ。第1次石油危機後、1975年度の補正予算編成で蔵相として赤字国債の発行に追い込まれた。当時の大蔵省官房長は長岡實氏。同氏は生前「赤字国債に頼らずにすむ強い財務体質を取り戻したいと大臣は繰り返していた」と筆者に話した。79年の総選挙で大平首相は一般消費税の導入を公約し敗北した。墓前で岸田氏が胸に刻んだものは何か。岸田氏が増税不要期間を10年と区切ったのは、安倍晋三氏、菅義偉氏という2人の首相経験者の言を踏襲したものだ。これは意味深かもしれない。5%の消費税率を8%に上げたのは14年だ。この増税の起点は与党が強行採決して成立させた04年の年金改革法だった。100年安心の名の下に基礎年金の国庫負担引き上げを法定した。それまで財務省は年金への一般財源の投入拡大に慎重だったが、04年改革を機に方針を転換した。国庫負担引き上げは消費税増税あってこそだと与党幹部らに働きかけ、歳出・歳入一体改革と名づけた増税構想を緒に就かせた。民主党政権はこれを社会保障・税一体改革と呼び変えたが、中身は不変だった。標準税率を2段階で10%にもってゆく一体改革法が成立したのは野田政権のときだ。野党だった自公両党は採決に賛成した。構想から増税実現までまる10年。岸田首相が官邸に設けた全世代型社会保障構築会議が夏にかけて方向性を示す。それはポスト一体改革の号砲たり得るのか。政治家は消費税が嫌いだ。増税分は巨額の政府債務返済にも充てねばならず、年金や医療・介護、教育サービスなど納税者の受益に直結しにくい宿命を知っているからだろう。それもあって現役世代から健康保険料の一部を召し上げ、高齢者医療費に回す「ステルス増税」は続行中だ。私たちは70兆円を超すコロナ対策費にも借金をつぎ込んだ。病院補助金の制度設計が粗雑だったために、病床を無駄に空けておく幽霊病床の存在が明らかになった。しかし使い方が賢明だったかどうかにかかわらず、その分もいずれ増税が必要になる。財政規律を重くみる英首相のように、医療充実のための増税と、大手をふれないのだ。ただしカネのなる木はないという真実は万国共通である。賢明な歳出を徹底させるかたわらで増税構想への着手は早いに越したことはない。インフレの足音が迫ってきた。金利上昇は政府の利払い負担を重くし、社会保障に回す歳出をさらに圧迫する。夏には参院選がある。聞き入れない力が試される。 <新型コロナ対応の非科学性> PS(2022年2月9、10日追加):*8-1は、東京都発表で、①直近1週間平均の新規感染者は18,575人で前週の120.6%だった ②重症者は51人 ③累計死者数は3,258人 ④新指標の重症病床使用率は22.4% ⑤年代別新規感染者は、30代2,874人、40代2,862人、20代2,780人で、65歳以上1,649人 ⑥ワクチン2回接種済み8,121人、接種なし4,450人だったとしている。 そもそもワクチンを接種していても、ウイルスに暴露されれば一時的には“感染”し、身体の免疫機構(自衛軍、兵隊)がウイルス(敵)に勝って撃退するのであるため、①⑥は、あまり意味のない数字だ。必要なのは、②③の重傷者・死者に占めるワクチン2回接種済と未接種の人の割合で、報道を聞く限り、オミクロン株そのもので亡くなられた方は少ないようだ。また、⑤の年代別新規感染者に、30代、40代、20代と子どもが多いことから、この年代のワクチン未接種者が発症して検査で陽性になる確率が高いのだろう。なお、ワクチンは免疫機構(自衛軍、兵隊)に敵の特徴を覚えさせる手段であるため、抗体が減ってもその特徴は覚えていて必要になれば増やすし、少しくらい変異しても敵として判別できる。また、治療薬は身体が敵と闘う時の援軍になるが、もともと自分の免疫機構が弱い人は、ウイルスに負けて重症になりやすいわけである。 しかし、*8-2の厚労省は、⑥ワクチン2回接種によるオミクロン株に対する発症予防効果はデルタ株と比較して著しく低下するが、追加接種により回復することが示唆された ⑦入院予防効果もデルタ株と比較して一定の低下があるが、追加接種で回復する ⑧英国健康安全保障庁の報告によると、ファイザー、モデルナ製ワクチンのオミクロン株に対する発症予防効果はデルタ株より低く、2回目接種から2-4週後に65~70%、20週後は10%程度に低下 ⑨効果の持続期間は引き続き情報収集する必要がある ⑩オミクロン株に対する入院予防効果はワクチン種類毎には解析されていない としている。が、⑥⑦を日本で本当に調べたようなデータは示されておらず、⑧の英国は、アストラゼネカのワクチンを接種し、マスクもせずに普通通りにしていたため、日本の状況とはかなり異なる。そのため、日本の厚労省が、⑨⑩のように、日本で使用したワクチンと種々の予防策や治療薬の効果を検証することもなく、欧米が言うから何となく⑥⑦を主張し、3回目接種を呼びかけているのは、あまりに非科学的だ。 さらに、*8-3の山梨県の濃厚接触者の待機期間は厚労省の方針を踏襲しているのだろうが、⑪新型コロナ感染症患者に対する(疫学の名に値しない)“積極的疫学調査”をまだ行っており(!) ⑫濃厚接触者とは「患者」(「無症状病原体保有者」を含む)と同居又は長時間接触があった者 ⑬適切な感染防護なしに患者を診察・看護・介護した者 ⑭患者の気道分泌液・体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 ⑮必要な感染予防策なく、1m以内で「患者」と 15 分以上の接触があった者 として、“濃厚接触者”は陽性者と最終接触した日を0日目として7日目までを待機期間とし、不要不急の外出を控えるよう指示している。しかし、この定義の“濃厚接触者”でも、ワクチンを2~3回接種し、症状がなく、検査をして陰性なら、このように“危険な患者”扱いする理由はないだろう。その上、“社会機能維持者”についての待機期間は短縮するそうだが、社会機能を有さない成人は少ないし、症状がなく検査をして陰性なら、一般の人も同様に“危険な患者”扱いする理由はなく、これらの対応がすべて非科学的なのである。 なお、*8-4は、⑯新型コロナ禍が始まって2年経過したが、(留学生を含む)外国人の日本入国を原則禁止する措置が続く ⑰海外との交流遮断は経済・文化・学術など多方面に弊害が及び、日本の魅力と国力を毀損する ⑱合理性に欠ける「鎖国政策」を見直す時 ⑲今は市中感染が広がり、水際対策の意味は薄れた ⑳WHOも新型コロナに関する渡航制限は経済的・社会的な負担が大きいだけとして緩和・撤廃を求め、米国・英国・オーストラリアもワクチン接種証明と陰性証明があれば隔離なしで外国人の入国を認めつつある ㉑日本のように自国民と外国人を区別して外国人の入国を一律に差し止める国は極めて例外的 としている。 このうち、⑯⑰は全くそのとおりだが、⑱は江戸時代ではあるまいし、今時、何をやっているのかと思う。また、⑳も当然で、「ワクチン接種証明と陰性証明があれば隔離なしで外国人の入国も認める」のが差別で、㉑のように「日本人と外国人を区別して外国人の入国を一律に差し止める」のが差別でないと考える人は科学的合理性がない。その上、⑲の水際対策は、どの国から来たか、外国人か日本人かは関係なく全員に同じ検査をし、検査結果に基づいた合理的な待機期間を設けなければ、漏れが起こって市中感染が広がるのは必然なので、何が目的でこういうことをしたのか疑問である。  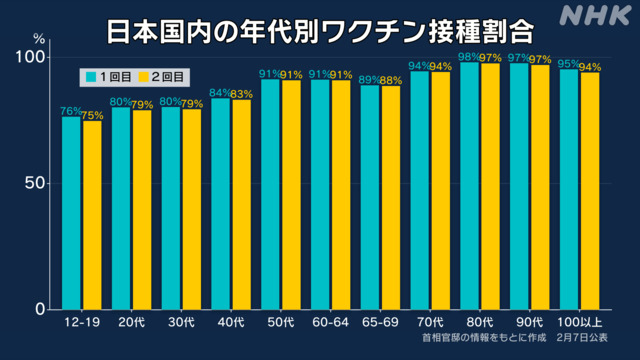  2022.2.7NHK 2022.1.31群馬県 (図の説明:左図のように、日本国内でワクチンを2回接種した人の割合は78.82%で、中央の図のように、高齢世代は90%以上が多い。にもかかわらず、全体の接種割合が78.82%なのは、0~11歳で接種割合が0%である要因が大きい。また、右図のように、群馬県の事例では接種割合が高くなるほど感染者割合は低くなっており、新型コロナのワクチン2回接種と重傷者・死者の割合はもっと強い相関関係があると思う) *8-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC080EX0Y2A200C2000000/ (日経新聞 2022年2月8日) 東京都、新たに1万7113人感染 7日平均で前週の120.6% 東京都は8日、新型コロナウイルスの感染者が新たに1万7113人確認されたと発表した。直近1週間平均の新規感染者は1万8575人で、前週(1万5397人)の120.6%だった。累計の感染者は72万2253人となった。重症者は前日から3人増えて51人だった。新たに11人の死亡が確認され、累計の死者数は3258人となっている。オミクロン型の特性を踏まえた新指標の重症病床使用率は22.4%だった。新規感染者を年代別にみると、30代が2874人と最も多く、40代が2862人、20代が2780人で続いた。65歳以上の高齢者は1649人だった。ワクチンの接種状況別では2回接種済みが8121人、接種なしが4450人だった。 *8-2:https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0111.html (厚労省) 厚生労働省厚生労働省新型コロナワクチンQ&A Q.オミクロン株にも追加(3回目)接種の効果はありますか。 A.オミクロン株に対する初回(1回目・2回目)接種による発症予防効果は、デルタ株と比較して著しく低下するものの、追加接種により回復することが示唆されています。入院予防効果も、デルタ株と比較すると一定程度の低下はありますが、発症予防効果よりも保たれており、追加接種で回復することが報告されています。2021年11月末以降、日本を含む世界各地において、新型コロナウイルスのB.1.1.529系統の変異株(オミクロン株)の感染が報告されています。英国健康安全保障庁(UKHSA)の報告によると、ファイザー社及び武田/モデルナ社のワクチンのオミクロン株に対する発症予防効果はデルタ株より低く、2回目接種から2-4週後は65~70%であったところ、20週後には10%程度に低下することが示されています。ここで、追加接種することにより、その2~4週間後には発症予防効果が65~75%程度に高まり、一時的に効果が回復することが示唆されています。ただし、10週以降はその効果が45~50%程度になるというデータもあり、効果の持続期間については、引き続き情報を収集していく必要があります。また、オミクロン株に対する入院予防効果については、ワクチンの種類毎に解析はなされていないものの、UKHSAの報告によると、2回目接種後25週目以降では44%であったところ、追加接種後2週目以降では89%に回復していることが確認されています(※1)。また、65歳以上の人における、オミクロン株に対する入院予防効果は、追加接種後2~9週で94%、10週以降で89%であったことが報告されており、発症予防効果に比べると、その効果は比較的保たれていると考えられます。 *8-3:https://www.pref.yamanashi.jp/kansensho/corona_taikikikan.html (山梨県) 濃厚接触者の待機期間について ●濃厚接触者とは 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領では、濃厚接触者を次のように定めています。「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。 ・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者 ・ 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者 ・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 ・ その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者 ●新型コロナウイルス(オミクロン株)の陽性者の濃厚接触者の待機期間について 新型コロナウイルス(オミクロン株)の陽性者の濃厚接触者については、陽性者と最終接触した日を0日目として7日目までを待機期間とし、8日目に待機期間を解除します。待機期間中は、濃厚接触者の方は不要不急の外出を控えてください。 ○留意事項 濃厚接触者の方は、待機期間が解除された後も、10日目までは検温などご自身による健康状態の確認を続けていただき、リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用など感染対策を徹底してください。 ●社会機能維持者についての待機期間短縮について 社会機能維持者が次の全てに該当する場合、待機期間を5日目に解除します。 ①待機期間中、無症状であること ②陽性者と最終接触した日から4日目と5日目の両日に当該濃厚接触者の所属する事業者(以下「事業者」という。)において実施した抗原定性検査(簡易検査キット)の結果が2回とも陰性であること ※山梨県においては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」の他、すべての事業に従事する方を社会機能維持者とします。(事業に従事していない方は対象外です。) ○留意事項 濃厚接触者の方は、待機期間が解除された後も、10日目までは検温などご自身による健康状態の確認を続けていただき、リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用など感染対策を徹底してください。また、不要不急の外出をできる限り控えるとともに、通勤時は公共交通機関の利用をできる限り避けてください。事業者は職場等での感染対策を徹底するとともに、社会機能維持者に対して、上記の留意事項を説明してください。本基準を適用する方の範囲は、各事業者が御判断ください。事業者から保健所への報告や協議は必要ありません。(濃厚接触者へは、定期的の保健所から健康観察等の連絡があります。) ○4日目、5日目の検査について 検査は、事業者の費用負担(自費検査)により、薬事承認された検査キットを用いて実施してください。適切な医療を提供するため、医療機関での検査の実施はお控えください。また、薬局等で実施している新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の協力要請に基づく無料検査は利用できません。検査の実施にあたり、事業者は別紙2「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」の①から⑤に対応する必要があります。 ○検査キットの購入について 事業者は、検査キットを医薬品卸売販売業者、メーカー、薬局から購入することができます。購入の際には、別紙1「抗原定性検査キット優先供給に係る説明書」と別紙2「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」を購入元に提出してください。(薬局の在庫量には限りがあります。薬局での購入を希望される場合には、あらかじめ薬局へお問い合わせください。)また、適正な流通を確保する観点から、必要な量の購入にとどめていただきますようお願いします。(以下略) *8-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220210&ng=DGKKZO80028270Q2A210C2EA1000 (日経新聞社説 2022.2.10) 水際措置を緩和し「鎖国」に終止符を 新型コロナ禍が始まって2年たったが、外国人に対してごく一部の例外を除き、日本への入国を原則禁止する措置が続いている。海外との人の往来の制約は、日本の魅力と国力を大きく毀損する。コロナ対策としても合理性に欠ける「鎖国政策」を見直すときだ。政府は2021年11月に入国規制を緩和し、留学生の受け入れ再開などを打ち出したが、その後のオミクロン型の発生を受けて原則禁止に戻した。オミクロン型の特性が不明で、国内への流入がまだなかった時点では、「時間稼ぎ」を目的にした入国規制の強化は理解できる措置だった。だが結局はそれもたいした効果はなく、今では市中感染が広がり、水際対策の意味は薄れた。世界保健機関(WHO)も新型コロナに関する渡航制限は経済的・社会的な負担が大きいだけとして、緩和や撤廃を各国に求めている。世界を見渡しても米国や英国、さらに検疫に厳しいオーストラリアでもワクチン接種証明と陰性証明があれば隔離なしで外国人の入国を認めつつある。そもそも日本のように自国民と外国人を区別し、後者の入国を一律に差し止める国は極めて例外的だ。海外との交流を遮断する弊害は経済や文化、学術など多方面に及ぶ。日本留学を希望する外国人学生はすでに2年弱にわたり来日に「待った」がかかり、他国への留学に切り替えるケースもある。留学経験の喪失は日本と世界を結ぶ人材の喪失でもあり、将来にわたる機会損失は計り知れない。経済の面でも外国人幹部が来日できず、日本での事業拡大を見合わせる外資企業の動きが伝えられた。日本人の再入国についてもホテルなどでの7日間の隔離は大きな負担だ。海外出張がままならず、ビジネスが滞る恐れがある。入国時の隔離はそもそも必要か、必要な場合でも7日間は長すぎないか、についても科学的エビデンスに基づいた再検証が必要だ。国内感染については検査の省略などを矢継ぎ早に打ちだしているのに、水際対策は厳しいまま、というのは整合性に欠ける。島国の日本はともすれば「内向き志向」に陥りがちだが、それでは停滞が長引くだけだ。防疫に細心の注意を払いつつも、状況に応じて適切に国を開き、外部の人材や「知」を受け入れる必要がある。関係省庁が動かないなら、岸田文雄首相の決断が問われる。 <科学技術を軽視する国の将来は暗いこと> PS(2022年2月14、15《図》日追加):*9-1-1のように、世界で新型コロナ治療薬の争奪が強まり、需給が逼迫する恐れがあるそうで、米国や欧州は新型コロナ禍でもワクチンや治療薬を実用化し、利益の機会を得ているのは感心だ。一方、日本は、金もないのに製品の争奪戦に参加しているだけであるため、そうなる理由とその解決が重要である。私は、東大医学部保健学科を卒業して公認会計士になったため、PWCで世界の有名薬剤会社の監査担当になることが多かったのだが、世界の有名薬剤会社の人たちが声を揃えて言っていたことは、「日本は治験がやりにくく、世界で使用している薬でも国内で承認されにくい」ということだった。新型コロナのワクチン・治療薬の治験については、緊急時の「条件付き早期承認」という形で解決しているが、普段から治験が必要以上に煩雑で長期間かかる割に開発者の成功報酬が少ないことは、開発者の困難を増し、国内での開発意欲を削いでいる。そのため、薬剤や医療機器については、厚労省だけでなく、経産省・文科省も参加して本気で開発していく必要がある。 また、*9-1-3のように、①東京都の新型コロナモニタリング会議で専門家は強い警戒感を示し ②小池知事は「他国は行動規制を緩和するとぶり返す例も見られ、東京で同じことはできない」と記者団に語り ③首都圏・中部等の13都県で新型コロナ「まん延防止等重点措置」の適用延長が決まった そうだ。しかし、新型コロナ騒動から2年経過し、*9-1-2のように、浮遊ウイルスを吸着する集塵フィルターを備えた空気清浄機ができていても、寒いのに窓を開けさせ(かえって、こじらせそう)、治療薬は限定的な人にしか使わせず、日本だからできることや日本だから稼げることを無視しているのである。そのため、これらは穏やかに言っても馬鹿としか言えず、こういうリーダーが「憲法に緊急事態条項を入れるべき」などと言っているのは、「何をやるつもりなのか、恐ろしい」というほかない。 癌治療においても、*9-2-3のように、本人の免疫細胞を培養し増やして使う免疫療法は、本人の免疫細胞なので癌細胞のみを攻撃して死滅させる。その点で、盛んに増殖する細胞すべてを攻撃して死滅させる抗ガン剤(化学療法)と異なり、副作用が著しく少ない。また、理論上、癌の種類や臓器を選ばず、同時多発性の癌も治療できる。にもかかかわらず、厚労省は外科手術(癌でない場所まで切除する)、抗ガン剤(盛んに増殖する細胞のすべてを攻撃し死滅させるため副作用が激しい)、放射線(放射線自体が身体に害)を標準癌治療とし、免疫療法はその補完としてしか認めていないため、保険適用のものが著しく限られる。一方で、*9-2-1のように、癌の9割超を占める固形がん向けに、中国のスタートアップが、免疫療法を改良した癌治療薬の製造販売の承認を、2023年に米食品医薬品局に申請する計画で、米国企業や武田薬品も治験を急いでいるそうだ。しかし、免疫療法も、基礎研究では日本が発祥だったのに、保険適用すべく国内で積極的に治験をすることなく、実用化が遅れたものなのだ。 なお、*9-2-2の本庶佑特別教授もオプジーボを開発し、保険適用にし、特許料を認定させるのに大変な苦労をされ、現在は「基礎研究に投資を」と訴えておられるが、基礎研究も重要だが、よい研究に対し速やかに治験を行って実用化することに対し、国が下らない制限を設けず協力することも、開発者利得を増やして民間企業を投資に向かわせ、癌患者を助けるものだ。 このように、日本では知的財産の開発や実用化への評価が低く、その結果が*9-3-1で、④日本国内の野菜・果実・花等の新品種登録の出願数がピークだった2007年の1406件に比べて2020年は713件と半減し、日本国内からの出願だけなら457件とさらに低水準 ⑤日本の18倍に達した中国に大きく水をあけられ ⑥輸出拡大のためにも付加価値の高い新品種の研究開発を支援する環境整備が急務 ⑦都道府県が保有する研究所からの出願数はピーク時と比較して6割減少 ⑧1998~2020年度の登録者別で最も多いのは種苗会社(56%)で、個人(25%)、都道府県(9%)が続いていた ⑨公的機関の人員不足や予算削減などが背景にある である。 しかし、*9-3-2のように、「農産物の優良品種が海外に不正に持ち出されるのを防ぐ」という名目で改正種苗法が成立し、農家が収穫物から種をとって自家増殖することを制限した上、自家増殖している農家は一部だとタカをくくっていたのが、⑧のように25%もあった個人の新種開発を衰えさせた原因だ。また、地方の公的研究機関は地域に適した種苗を競争で開発していたが、これらに開発をやりにくくする変更をしたのも、④⑤⑦⑨の原因だ。従って、⑥の輸出拡大だけでなく、国民も喜んで受け入れる農産物を作るためには、初めから選抜せずに多くの人に開発の機会を与え、知的財産を高く評価して開発者に利益を与える仕組みにする以外にはないのである。 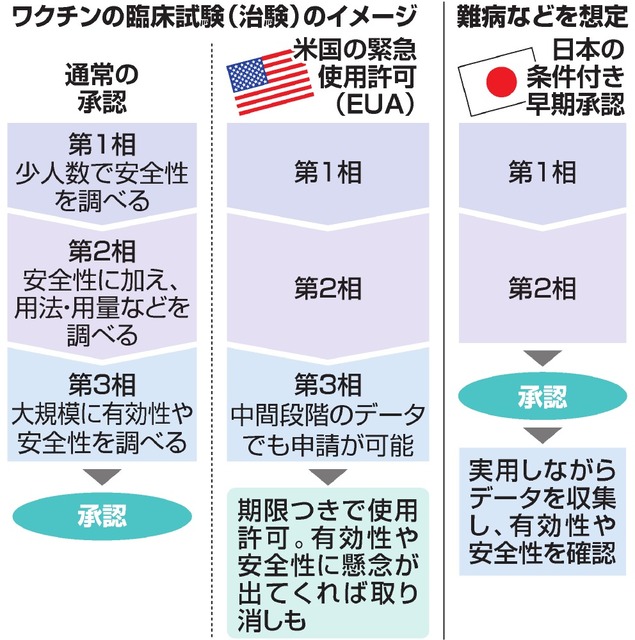  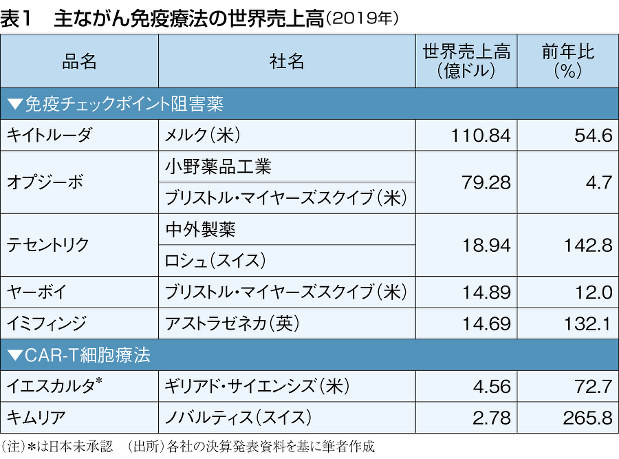  2021.5.13朝日新聞 2022.2.11日経新聞 2020.3.9Economist 2022.2.11日経新聞 (図の説明:新型コロナワクチンの臨床試験は1番左の図のようになっており、一般の薬剤は通常の承認が多い。しかし、患者数が多くない疾患は大規模な治験を行うことができないため、難病と同様の条件付き早期承認を行い、それなりの病院で第3相試験と治療を兼ねて行う必要がある。これらの便宜が図られた結果、左から2番目の図のように、新型コロナのワクチンや飲み薬は海外で開発・実用化され、日本で開発・実用化されたものはなかった。これは、癌の免疫療法も同じで、右から2番目の図のように、海外で開発・実用化され、日本では標準治療にも入らないため、使えないものが多い。1番右の図は、本人の免疫細胞に固形癌の細胞を選択的に攻撃させる方法で、これなら癌治療に副作用がなくなるのである) *9-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220211&ng=DGKKZO80080260R10C22A2EA2000 (日経新聞 2022.2.11) コロナ飲み薬、世界で争奪、ファイザー製、需給逼迫の恐れ 国内薬の承認期待 新型コロナウイルス治療薬を巡り、世界で争奪が強まっている。厚生労働省が10日に特例承認した米ファイザーの飲み薬は、米国が日本の10倍の量の調達契約を結ぶなど需要が旺盛で、当面需給が逼迫する恐れがある。感染者急増で治療薬の需要は今後も増える見通しだ。政府は一段の調達増に取り組む必要がある。厚労省が特例承認したファイザーの飲み薬「パキロビッドパック(海外名パクスロビド)」は2021年12月以降、米国や欧州で実用化された。感染初期に投与して重症化を防ぐ飲み薬は、医療逼迫を抑制する切り札となる。変異型「オミクロン型」の感染拡大を背景に、各国は飲み薬を大量入手しようとしている。米政府はファイザーと2000万人分の調達契約を結び、22年6月までに1000万人分、9月までに残りを調達する。英国政府も同社と275万人分の調達契約を結んだ。 ●下旬に追加供給 日本も飲み薬の確保を急いでいる。政府はファイザーの飲み薬について200万人分を調達することで最終合意。後藤茂之厚労相は10日、第1弾の4万人分に続き、2月下旬に追加分の供給を受けると明らかにした。量については「確定中だ」と述べるにとどめた。すでに国内で実用化された米メルク社の飲み薬については160万人分の供給を受ける。厚労省によると、10日までの納入量は累計34万人分で、このうち4万人分以上が投与された。3月末までに計60万人分の供給を受ける予定だったのが、計80万人分に増えることも明らかにした。だが、当面は需給が逼迫する懸念がある。ファイザーは22年末までに1億2000万人分を生産する計画だが、上期は3000万人分にとどまる。有効成分の原薬の合成に時間がかかるためだ。アルバート・ブーラ最高経営責任者(CEO)は1月、年後半にかけて供給量が増える見通しだとしたものの「1~3月は入手がより制約されるだろう」と述べた。日本への供給スケジュールなど詳細についても、ファイザーも政府も明らかにしていない。足元の患者数の増加に飲み薬の供給が間に合うかは不透明だ。厚労省によると、感染力が強いオミクロン型の拡大で、国内の累計感染者数は約360万人と昨年末から倍増した。直近では2月1日までの1週間で、重症化リスクが高い60歳以上の新規感染者が約6万人に上った。 ●投与患者は限定 ファイザーやメルクの飲み薬は高齢や持病など重症化リスクのある患者に投与される。重症化を防ぎ医療の逼迫を防ぐには、飲み薬を必要な患者に適切に投与できる体制を整える必要がある。ファイザーの飲み薬に需要が集中していることも需給逼迫の解消を難しくしている。ファイザー製は臨床試験(治験)で有効性が高く、需要が大きい。重症化リスクがある感染者に発症から5日以内に投与したところ、入院・死亡のリスクが88%減った。米メルクの飲み薬「ラゲブリオ」は治験で同30%低下だった。安定調達のためにはさらに多くの治療薬が実用化される必要がある。塩野義製薬が最終段階の治験を進める「S-217622(開発番号)」は約50人を対象にした治験データでウイルス量を減らすなどの効果が確認できた。さらに多くの人で有効性や安全性が実証できれば、月内にも厚労省に「条件付き早期承認制度」を活用して製造販売承認を申請する。手代木功社長は7日の記者会見で、「2月末には40万~50万人分の製造を積み上げる」と話した。3月末までに100万人分を生産し、4月以降に年1000万人分以上の供給体制を整える。政府は有効性が明らかになれば迅速に承認審査を進めるとしている。順調に審査が進めば供給安定につながる可能性もある。 *9-1-2:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00120/00361/ (日経XTECH 2020.12.2) 浮遊するウイルスを吸着する集塵フィルターを備えた空気清浄機、飛沫対策空気清浄機 トルネックス トルネックスは、ウイルスとほぼ同じ大きさの粒子(0.08μm)を効率よく捕集する「飛沫対策空気清浄機」を2020年11月に発売した。空気中の浮遊ウイルスを吸着する性能が高い電子式集塵フィルターを備えた空気清浄機だ。北里環境科学センターで行った性能評価試験では、自然減衰の場合、15分経過してもほとんど減少しない浮遊ウイルス数が、5分で99%以下まで減った。処理風量が15m3/分と大きく、フィルターの捕集効率も高いので、相当換気量(空気清浄機で清浄した空気の量)が多い。空気中に浮遊する粉塵や微生物、たばこの煙などを除去する。新型コロナウイルスの検証は行っていない。会議室などに向く「ミーティング用ロータイプ」と、キャスター付きで移動が簡単な「室内循環用ハイタイプ」を用意している。 ○価格は、要問い合わせ。問い合わせ先:トルネックス 電話:03-5643-5800、URL:https://www.tornex.co.jp/ *9-1-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220211&ng=DGKKZO80080310R10C22A2EA2000 (日経新聞 2022.2.11) 東京の自宅療養3倍 まん延防止、見えぬ出口 首都圏や中部など13都県で新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」適用延長が決まった。10日も全国で10万人近くの新規感染が確認され、自宅療養者は各地で増加傾向が続く。「第6波」の長期化に備え、感染対策と社会活動を両立する対策の充実が急務となっている。「経験したことのない危機的な感染状況が続いている」。東京都が10日開いた新型コロナのモニタリング会議で、専門家は強い警戒感を示した。小池百合子知事は行動規制について「他国ではいったん緩和するとぶり返す例も見られる。東京で同じことはできない」と記者団に語った。都内の新規感染者の7日間平均は10日時点で1万7849人と、重点措置が適用された1月21日の3倍近くにのぼる。9日には1日あたりの感染者が今年初めて前週を下回ったが、適用開始から3週間近く右肩上がりだった。自宅療養者もおよそ9万人と開始時の3倍以上に膨らんだ。10日は千葉県や兵庫県、北海道で新規感染者が過去最多を更新した。第6波で重点措置が最初に適用された沖縄県や広島県は減少基調に転じた半面、三大都市圏は拡大傾向が続く。厚生労働省の専門家組織座長を務める国立感染症研究所の脇田隆字所長は9日、感染拡大がピークアウトする時期について「もうしばらく推移を見ていく必要がある」と述べた。大阪や兵庫、北海道など21道府県は20日に適用期限を迎える。兵庫県の斎藤元彦知事は10日の記者会見で「今すぐ解除するのは難しい」との認識を示した。政府の基本的対処方針分科会の尾身茂会長は10日、新型コロナ対策について「出口戦略を含めて議論していくべきだ」と述べた。変異型「オミクロン型」の特性を踏まえて検査や医療の体制を検討すべきだとの考えも示したが、収束のメドが立たないなかで出口を探りにくいのが実情だ。 *9-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220211&ng=DGKKZO80053590Q2A210C2TEC000 (日経新聞 2022.2.11) 免疫細胞で「臓器がん」治療 中国新興や武田が治験、血液がん向け改良で効果 がんの9割超を占める固形がん向けに、手術や放射線、抗がん剤、免疫薬に続く新たな治療法が現れた。遺伝子を改変した免疫細胞を使い、血液がん治療で実用化されている免疫療法を改良。中国のスタートアップが2023年に米食品医薬品局(FDA)へ製造販売の承認を申請する計画で、米国企業や武田薬品工業も臨床試験(治験)を急ぐ。世界で毎年約2千万人が新たにがんを患い、約半数が亡くなる。全死亡者年間5千万人超のうち約6分の1を占める。今後も人口増加と寿命が伸びたことによる高齢層の拡大で、患者数は増えると予想されている。米調査会社のBCCリサーチによると、がん治療薬の世界市場規模は26年に3137億ドル(約36兆円)と、21年比で77%拡大する。そのほとんどが患者数が多い肺がんや大腸がんなどの固形がん向けだ。がんの主な治療法は手術、放射線、抗がん剤や免疫薬。だが、手術で切除できない転移がんなどは放射線や抗がん剤で完治するのが難しい。2010年代に使えるようになった免疫薬も膵臓(すいぞう)がんなどの難治性のがんや進行したがんの治療は難しい。白血病などの血液がんで治療効果が出ているCAR-T療法を改良した治験が相次ぐ。中国の医薬スタートアップ、カースジェン・セラピューティクスは、患者の血液からとった免疫細胞に、CARと呼ぶがんを攻撃するたんぱく質を作る遺伝子を組み込んだCAR-T細胞を作製。さらにその効果を増強させる手法を開発した。CAR-T細胞に、胃がんや膵臓がんなどにくっつくたんぱく質を作る遺伝子を追加で組み込み、転移しやすいがんを追いかけて攻撃しやすいタイプにした。中国で胃がんの第1相治験を終え、第2相を計画中だ。同社は米国でも第1相の治験を進めており、23年に製造販売の承認を申請する予定。FDAと欧州医薬品庁(EMA)から希少疾病用医薬品の指定を受けているため、治験で効果が確認できれば23年以降市場に出てくる可能性がある。同社は、21年秋の欧州臨床腫瘍学会で37人に投与した結果を発表。2種類以上の抗がん剤が効かない胃がんや食道がんの18人のうち、11人(61%)でがんが縮小するか消えた。がんの増殖を抑えた人を含めて15人(83%)で効果があった。担当者は「独自の技術を活用し、世界をリードする地位を固める」と話す。CAR-T細胞で固形がんを追う技術はほかにもある。米製薬のポセイダ・セラピューティクスは、投与したCAR-T細胞が体内で増えやすい技術を開発した。遺伝子を入れる方法を工夫した。体外で投与前にCAR-T細胞を増やす必要がない。体内でがんを攻撃する効果が持続しやすいという。転移した前立腺がんで第1相の治験を実施中で、9人に投与して3人でがんが血液中に出す「PSA」たんぱく質が半分以下に減り、画像診断でも結果が一致したと8月に発表した。1人はがんが見えなくなった。米メモリアル・スローン・ケタリングがんセンターのスーザン・スロビン博士は「患者の(治療効果の)反応は予想をはるかに超えた」と話す。同社は23年に治験を終える予定だ。ほかの固形がん向け治験も計画しているという。国内勢も開発を急ぐ。武田薬品工業は18人の固形がん患者で第1相の治験を始めている。23年に治験を終える予定だ。信州大学は22年春に、がん治療薬開発のブライトパス・バイオの協力で骨軟部肉腫や固形がんで第1相の医師主導治験を始める。その後、同社が第2相の治験を実施し、25~26年に条件付きの早期承認を厚生労働省へ申請する計画だ。山口大学発のスタートアップ、ノイルイミューン・バイオテック(東京・港)は、体内にもともといる免疫細胞を集めて、作ったCAR-T細胞と一緒にがんをたたく技術を開発した。情報伝達を担うたんぱく質を出して免疫細胞を呼び寄せるCAR-T細胞を作った。抗がん剤などの治療を終えた約40人の肺がん患者らを対象に第1相治験をこのほど始めた。肺がんや中皮腫、膵臓がんを狙う。23年中に治験に参加する患者の登録を終える予定だ。 ▼CAR-T療法 患者の血液から採取した免疫細胞にCAR遺伝子を入れて、がんを攻撃する分子(たんぱく質)を作るようにして体内へ戻す治療法。スイス製薬大手ノバルティスが17年に米国で実用化した「キムリア」は、血液がんの白血病の1種で高い効果が出た。これまで固形がん向けでは、CAR-T細胞が患部へ届かなかったり、多数のがん細胞を攻撃しきれず、効果が出ていなかった。 *9-2-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC131U80T10C22A2000000/ (日経新聞 2022年2月13日) 本庶氏「基礎研究に投資を」、京都賞シンポジウムで訴え 京都大学と公益財団法人の稲盛財団(京都市)は13日、「京都賞シンポジウム」をオンラインで開いた。2018年のノーベル生理学・医学賞を受賞した京大の本庶佑特別教授が講演し、がん免疫療法で多数の臨床試験(治験)が進んでいることを紹介し、国や民間が生命科学の基礎研究に投資すべきだと訴えた。本庶氏は免疫細胞の表面にあるたんぱく質「PD-1」を見つけた。がん細胞がPD-1に結合し、免疫細胞から逃れる仕組みが分かった。本庶氏はこれを阻害する治療法により「がん治療のパラダイムシフトが起きた」と強調。既に多くの種類のがんに対して承認されており、さらに「何千という治験が進行中だ」と話した。患者ごとにがん免疫療法が有効かどうかを見分ける方法は研究途上であると指摘し、有効な患者の割合を高めていく必要があるとした。研究者の参入を促すには研究資金を充実させることが重要だと指摘し、国や民間が応用研究だけでなく生命科学の基礎研究に注力すべきだと訴えた。講演者によるディスカッションで本庶氏は「新型コロナウイルスの世界的な流行を通じて、生命科学への理解が不足していると認識した。一朝一夕に答えが出るわけではない。基礎的な研究力を育成することが国の大きな役目だ。研究者も長期的な視点が必要だ」と指摘した。京都賞は優れた科学や芸術の功績をたたえる国際賞。本庶氏はPD-1の発見などの功績で16年に基礎科学部門で受賞した。 *9-2-3:http://www.hu-clinic.net/clinic/promise.html (日比谷内幸町クリニック) 免疫細胞療法による癌治療 1.心と体にやさしい癌治療 当クリニックが行っている免疫療法(免疫細胞療法)は、患者様ご自身の免疫細胞を最新の培養技術で増殖・活性化して患者様のお体へお戻ししますので、肉体的にも精神的にも患者様のからだにやさしい治療です。 ※副作用としては、稀に投与後、発熱することがあります。免疫力が高まっている過程での発熱ですので心配はありません。発熱は個人差にもよりますが、1日程度で治まります。 2.がんの種類を選ばない免疫療法(免疫細胞療法) 高度活性化NK細胞療法は、血液が通う限りどこに出来た癌でも必ずNK細胞が到達して働くので、癌の種類を選びません。そのため胃癌、肺癌、肺腺癌、膵臓癌、肝臓癌、大腸癌、直腸癌、乳癌、食道癌、卵巣癌など個別の癌はもとより、標準の癌治療では困難な同時多発性の癌にも治療を行えます。 3.標準の癌治療との併用も可能な免疫療法(免疫細胞療法) 高度活性化NK細胞療法は、手術、抗ガン剤、放射線など標準の癌治療と併用でき、更にそれらとの組合せで治療全体の効果を上げることができます。例えば、外科療法との組合せが術後の再発・転移を防ぎ、回復を助けます。 4.十分なカウンセリングに基づく癌治療 免疫療法(免疫細胞療法)を開始する際は患者様にとって最適な治療の選択と組合せの判断が重要となりますので、初診相談時に患者様やご家族の方と十分な時間をかけて話し合い、インフォームドコンセント(事前に医師が患者様に十分な説明をし、同意を求めること)を行います。また、免疫療法(免疫細胞療法)の実施中や実施後も、患者様やご家族の方と経過や今後の進め方について話し合います。 5.リラックスして受けられる癌治療 採血や点滴を行う治療ルームは完全個室の落ち着いた空間で、リクライニングシートやテレビなどを備えており、ご家族・ご同伴の方と一緒にリラックスして癌治療を受けられます。また、完全予約制なので待合室でお待たせする事はありません。 *9-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220213&ng=DGKKZO80097900T10C22A2EA1000 (日経新聞 2022.2.13) 農産物新品種、出願数が半減、日本、中国との差18倍に 輸出増へ支援急務 日本国内の野菜や果実、花などの新品種登録の出願数がピークだった2007年に比べて半減した。20年は457件にとどまり、日本の18倍に達した中国に大きく水をあけられた。21年の食品輸出額が1兆円の大台を初めて超えた日本は30年までに5兆円という次の目標へ動き出す。さらなる輸出拡大へ海外にもアピールできる付加価値の高い新品種の研究開発を支援する環境整備が急務となっている。植物などの新品種を保護する国際機関「植物新品種保護国際同盟(UPOV)」によると、日本で20年に新たな品種として出願されたのは713件だった。2007年の1406件をピークに約10年間で半減した。3割は海外からの出願で、日本国内からの出願だけでみると457件とさらに低水準にとどまった。特に都道府県が保有する研究所からの出願数はピーク時と比較して6割減少した。公的機関での人員不足や予算削減などが背景にある。1998~2020年度の登録者別で最も多いのは種苗会社(56%)で、個人(25%)、都道府県(9%)が続く。中国は20年の国内出願数が8329件で日本の18倍に及ぶ。10年の約7.6倍に急増した。トウモロコシや水稲の新品種が多い。登録料を無料にするなど国をあげて新品種の登録や開発を進めたのが奏功した。日本は先進国と比較しても大幅な後れをとっている。20年は欧州連合(EU)の域内での出願件数が2785件、米国は732件、韓国は632件だった。政府は農林水産物・食品の年間輸出額を2025年までに2兆円、30年までに5兆円に増やす目標を掲げる。高級ブドウの「シャインマスカット」やリンゴの「フジ」などブランド力の高い品種の農産物は海外でも人気を集める。輸出のさらなる拡大にはこうした魅力ある新品種の開発が急務だ。ただ品種の新規開発には時間を要し、開発に着手しても理想的な品種が生まれるかどうか不透明だ。育種家や企業からは「コストに見合わない」と指摘する声もあがる。シャインマスカットは国が保有する農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が06年に品種登録した。試験の開始から登録まで18年かかり、13人の研究者が携わった。農産物などの品種登録は開発した人の権利を保護するための仕組みだ。新品種の開発には専門的な知識や時間、費用などを要する一方、いったん開発すると第三者が簡単に増殖できる。品種登録で開発者が登録料を政府に支払う代わりに、栽培を25~30年独占できるようにして開発を促す。輸出しやすい品種の開発や海外での品種登録を促進するため、農水省は21年度の補正予算で国の研究開発を担う農研機構の機能強化で計約9億9000万円を確保した。農研機構は過去の品種開発の研究成果や技術に関する情報が蓄積されたデータベースを持つ。研究所と施設などとをつなぐネットワーク回線を強化し、都道府県の研究機関や企業とのリアルタイムの連携を促す。ビッグデータや人工知能(AI)などで高度な技術を使えるような環境整備も進め、輸出相手国のニーズにあわせた国際競争力のある新品種の開発や、農作物の高品質化のための栽培管理手法の確立につながるような共同開発を加速する狙いだ。農研機構はほかにも大学や都道府県などと共同で、輸送時に傷がつきにくいモモや、日持ちのいいカキなどを開発する7つほどのプロジェクトを21年4月から進めている。3年後に成果を出すのを目標として掲げる。農業分野の知的財産権に詳しい早稲田大大学院の野津喬准教授は「人気品種は海外持ち出しのリスクも高く、育成者の権利を保護するため適切な登録が重要。今後は輸出促進に向け、海外のニーズを踏まえた品種開発も求められる」と話した。 *9-3-2:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66683570W0A121C2SHF000/ (日経新聞社説 2020年11月26日) 農業振興に資する種苗法改正 果物などの優良品種が海外に不正に持ち出されるのを防ぐ種苗法改正案が、臨時国会で成立する見通しとなった。農産物の知的財産を守り、輸出を含めて農業を振興する契機としてほしい。改正案の目玉は、種苗の利用を制限できるようにする点にある。種苗メーカーや研究機関は開発した品種を農林水産省に登録する際、種苗の輸出を認めないと定めることが可能になる。違反すれば損害賠償などの対象になる。すでに衆院を通過した。これまでイチゴなど様々な品種が流出してきた。開発者の権利を侵害するだけでなく、日本の農産品の輸出戦略にも支障が出る。安い値段で作物が逆輸入されれば、国内生産を脅かす恐れもあった。農水省はこうした事態に歯止めをかけるため、種苗メーカーなどが海外で品種を登録するための経費を補助してきた。法改正はこれを補完するのが狙いであり、妥当な措置と言えるだろう。一方、制度改正には一部から懸念も出ていた。農家が収穫物から種をとり、次の栽培に使う自家増殖にも制限がかかるようになるからだ。登録品種を自家増殖しようとすると、今後は開発者の許諾を得ることが必要になる。ただ影響は限定的だろう。各地で昔から作られている作物など、流通している品種の大半は登録外だ。公的な研究機関が開発した登録品種に関しては、自家増殖への許諾料が高額になるとは想定しにくい。しかも重要なのは実際に自家増殖をしている農家は一部で、多くは今も種を買っている点だ。手間のかかる自家増殖と比べて効率的だからで、種の購入代で経営が圧迫されてもいない。彼らが求めるのはむしろ優れた品種の開発だ。頻発する大規模な自然災害に対応し、新たな病害虫を防ぐためにも絶え間ない品種改良が不可欠になっている。開発者の権利をきちんと守り、研究にいっそう力を入れることのできる環境を整えることが求められている。 <教育力について> PS(2022年2月14日追加):*10-1は、①北京冬季五輪フィギュア女子団体で2月7日に素晴らしい演技でROCの金メダルに貢献したカミラ・ワリエワが、2021昨年12月のドーピング違反について団体戦後の2月8日に検査結果が判明したとしてIOC・WADA・ISUから提訴され ②CASが2月14日に提訴を却下し ③4回転ジャンプとトリプルアクセルが武器のワリエワは2月15日にショート、17日のフリー女子個人戦でも金メダル最有力候補とみられている としている。 しかし、ワリエワは、4回転ジャンプで1度失敗したものの、フィギュアの演技のみならず顔・姿勢・音楽・芸術性・衣装まで含めて総合的に文句なしだったので、私にとって①は祝福したい出来事だった。そのため、大会中に陽性反応の出ていない選手に対し、12月のドーピング違反を持ちだして、団体戦後の2月8日に「検査結果が判明した」として提訴したのは、ライバルを利することが目的のように思われた。そのため、私は、②は妥当で、③の理由でワリエワの演技をまた見たいと思っている。 (私もされた経験があるのでわかるのだが)トップになると「ズルいことをしたから成績がいいのだ」と言いがかりをつけて、下だった人が自分を正当化することが少なくない。ワリエワの2021年12月のドーピング違反が2月7日の団体戦後の2月8日に指摘されたのは、不自然な時期だったためこれではないかと思われ、私はCASの提訴却下が公正・公平だと感じた。 そのような中、*10-2には、④文科省が公立小中高校などの教員不足の実態を初めて全国調査し、2021年4月時点で2,558人が計画通り配置されていなかった ⑤管理職も含めて他の教員の負担が増え、しわ寄せは子どもに及んでいる ⑥忙しすぎて「ブラック職場」とまで言われる教職の志願者が減った ⑦学校を魅力的な職場にするには、非正規依存の構造を転換して正規教員を増やすべき ⑧教員を確保しやすい年度初めに調査したので、実態より甘い調査結果が出た ⑨学力低下が騒がれて授業時間が増えた 等が書かれている。が、④⑤⑥⑧で触れているのは、教員の量の充実だけで、質の充実はない。そのため、⑦⑨は、正規職員を増やすだけでなく、正規職員の報酬も上げて教員の質を充実することが必要であり、そうしなければ、知識や具体的データに基づいて自分の頭でモノを考え、正しい判断のできる生徒は育たないのである。  .jpg) .jpg)  北京冬季オリンピックでボレロを踊ったワリエワ ロシア大会のワリエワ (図の説明:バレエの基礎があるらしく、氷の上で凛とした姿勢を保ち、柔らかく、正確で、手先まで絵になる演技をしたワリエワ。しかし、ここに来るまでには、人生をかけたものすごい競争と努力があっただろう) *10-1:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6418177 (Yahoo 2022/2/14) ワリエワ 五輪個人種目の出場認める CASが発表 15日に女子SP 昨年12月のドーピング違反が判明した北京冬季五輪フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ(15、ロシア・オリンピック委員会=ROC)の個人戦出場が認められた。スポーツ仲裁裁判所(CAS)が14日、ロシア反ドーピング機関(RUSADA)によるワリエワの暫定資格停止処分解除を不服とした国際オリンピック委員会(IOC)、世界反ドーピング機関(WADA)、国際スケート連盟(ISU)からの提訴を却下した。4回転ジャンプとトリプルアクセルが武器のワリエワは7日に行われた同五輪団体戦でROCの金メダルに貢献し、15日にショートプログラム(SP)、17日にフリーが行われる女子個人戦でも金メダル最有力候補とみられている。CASは13日午後8時34分(北京時間)から北京市内のホテルに設けた臨時事務所で聴聞会を実施。オンライン形式で14日午前2時10分(同)までIOC、WADA、ISU、RUSADA、ワリエワ本人、ROCを事情聴取した。ワリエワは昨年12月25日のロシア選手権の検査で、持久力向上が期待できる禁止薬物トリメタジジンに陽性反応を示し、今月8日に検査結果が判明。RUSADAが暫定資格停止処分を科したが、異議申し立てを受けてRUSADAの規律委員会が9日に処分を解除していた。WADAは裁定の理由として、16歳未満のワリエワが処分が軽減される保護対象であること、五輪期間中に陽性反応を示していない選手への考慮、今回出場を認めなければワリエワに取り返しのつかない損害を与えること、などを挙げた。団体戦の扱いに関しては裁定を要求されていないため、決定は別になるとも記した。一方でIOCからの要請を受け、WADAはワリエワらROC女子選手を指導するエテリ・トゥトゥベリゼ・コーチや医師ら周辺スタッフの調査を独立委員会に依頼すると明かしている。 *10-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/809895 (佐賀新聞 2022年2月12日) 教員不足調査 学校の悲鳴に政治決断を 文部科学省が公立小中高校などの教員不足の実態を初めて全国調査した。昨年4月時点で2558人が計画通り配置されていなかった。管理職も含めて他の教員の負担が増え、しわ寄せは子どもに及ぶ。過去には一部の授業ができず、自習が続いた自治体もある。団塊世代の大量退職で採用が増える一方、忙しすぎて「ブラック職場」とまで言われる教職の志願者が減ったことが背景にある。穴埋めに非正規教員が担任を務めることも珍しくないが、こちらも重い負担と低賃金で人気がない。学校を魅力的な職場にするには、非正規依存の構造を転換し、正規教員を増やすべきだ。それには教育予算を増額する必要がある。調査結果は実態の一端を切り取っただけだという指摘もある。都道府県や政令市など68カ所のうち、18の自治体が、小学校と中学校のどちらかで不足数を「ゼロ」と答えたからだ。現場の実感にそぐわない結果になった最大の理由は、教員を確保しやすい年度初めに調査したためだ。産休育休や精神疾患による休職や退職は年度途中で出やすい。「年度途中では2倍ぐらいの欠員があるかもしれない」と話す専門家もいる。文科省は今後、年度の途中でも調査してほしい。財務省は増員要求をなかなか認めないが、教員不足の実態を示して「もっと教育予算を」と粘り強く迫るべきだ。国会でも地方議会でも、政治家は後押ししてほしい。これほど学校が厳しい状況になった原因は明らかだ。さまざまな「教育改革」で仕事が大幅に増えたのに、行財政改革で正規教員は減り、身分の不安定な非正規教員が増えて給与水準も下がったからだ。世代交代や社会の変化も重なった。その結果、教職が不人気になって志願者が減る悪循環が起きている。この20年で教員の仕事は急増した。学力低下が騒がれ、授業時間が増えた。小学校では英語が教科になった。思考力や判断力、表現力を求める「主体的、対話的で深い学び」の導入で評価内容や方法も変わった。いじめや不登校の指導も大変だ。だが、地方財政などの改革で小中学校の教員給与の国庫負担は2分の1から3分の1に減り、自治体の財政力の差で正規教員の比率が左右されやすくなった。現場で無理を重ねた結果、2016年度の文科省調査では中学校で6割近く、小学校で3割強の教員が過労死ラインとされる月80時間超の残業をしていた。週の平均勤務時間は06年度の調査より増えたが、この間の主な対策は業務の効率化や教員の意識改善ぐらいだ。働き方改革は必須だが、状況を改善し、教員がゆとりを持って子どもと向き合うには人手が要る。教育費の公的支出を国内総生産(GDP)比でみると、日本は経済協力開発機構(OECD)加盟国で最低水準にある。教育予算を拡大し、子ども1人当たりの正規教員数や事務職員らスタッフを充実させたい。「少子化で将来教員が余ると困るから、今は非正規に頼る」という政策のままでは、事態は深刻化するだけだ。法定の教員数を正規教員で確保し、教員と子どもたちの環境を改善するべきだ。そのためには政治家の決断が必要だ。「聞く力」があるという岸田文雄首相はぜひ、学校現場の悲鳴を聞いてほしい。 <太陽光発電で市庁舎の電力自給も可能> PS(2022年2月25日追加):*11-1のように、佐賀県小城市は本庁舎に太陽光発電設備を整備して、72時間以上の非常用電源を確保するとともに、年間約1千万円かかっていた電気料金を太陽光発電で賄い、脱炭素化の取り組みを促す国の補助金や返済の5~7割を国が負担する地方債を活用してエネルギー消費量が少ない空調やLED照明への切り替えも進めたそうだ。なお、駐車場に急速充電器を設置してEVに有料で充電したり、建物の壁面や舗装でも太陽光発電を行ったりすれば、電力料金を節約できるだけでなく、電力料金で税外収入を得ることも可能だ。 そのような中、*11-2のように、ウクライナ情勢等も受け、「①原油価格が値上がりしたから補助金を拡充せよ」「②ガソリン税の上乗せ部分を停止せよ」等の圧力が与野党から強いが、国産再エネとEVを2000年代から速やかに普及させていれば、このようなことで「緊急事態だ」「緊急事態だ」と言って大騒ぎする必要はなかった。そのため、今でも原油高に対応して補助金をばら撒くべきなのか、再エネやEVの補助金を増して普及を促すべきかは、将来のことも考えて原油高上昇を根本的に解決する方向で予算を使うべきである。 さらに、CO₂排出を0にすることを名目に原発を推進する動きがあるが、*11-3のとおり、「③事故に伴うコスト上昇や最終処分費用のため原発は安価でない上、将来に負担を残すこと」「④原発の生涯で考えれば気候危機対策としても限定的であること」等のため、「⑤依存度低減→脱原発」に舵を切るべきことは明らかだ。また、ウクライナを見ればわかるとおり、原発の存在は安全保障上の脅威でもあるため、「頭隠して尻隠さず」にならないようにすべきだ。 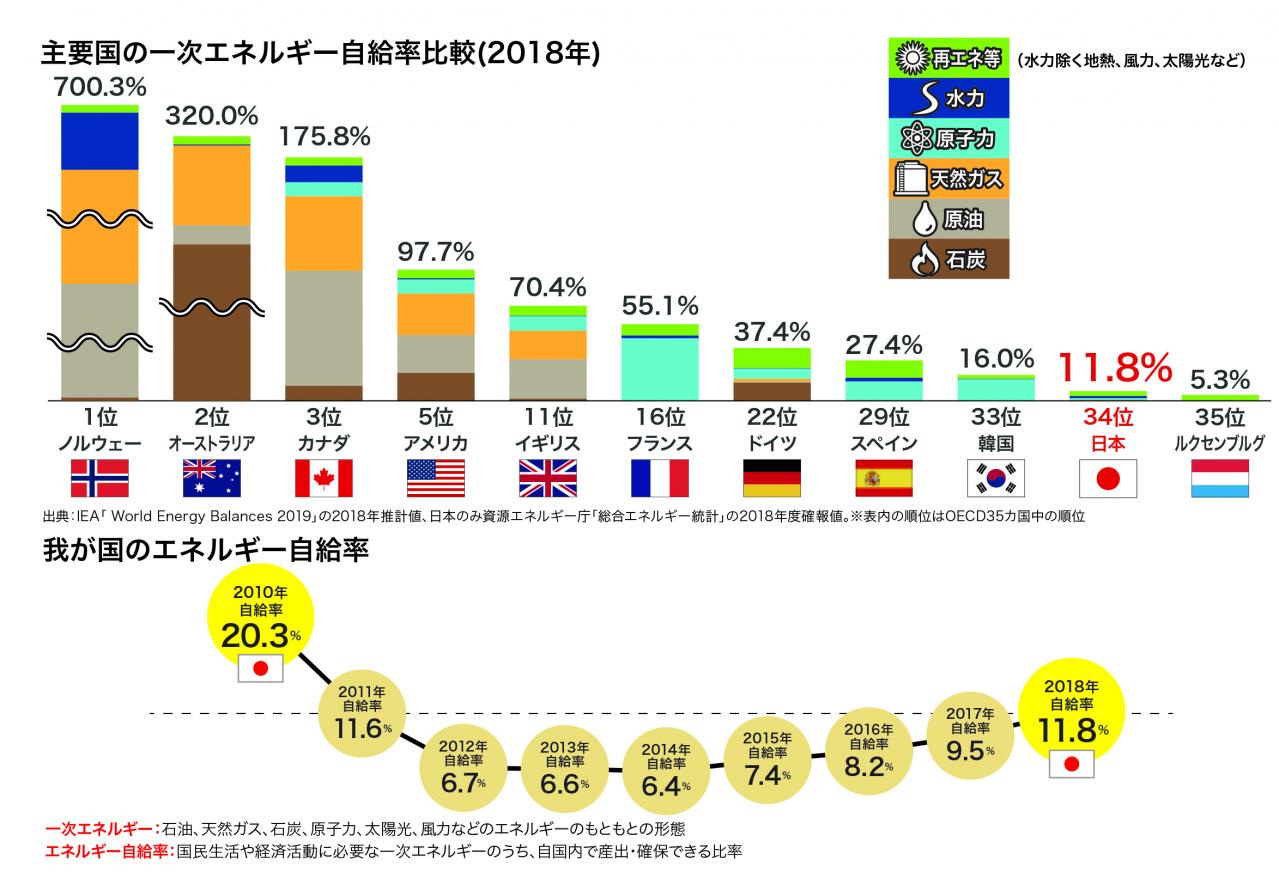 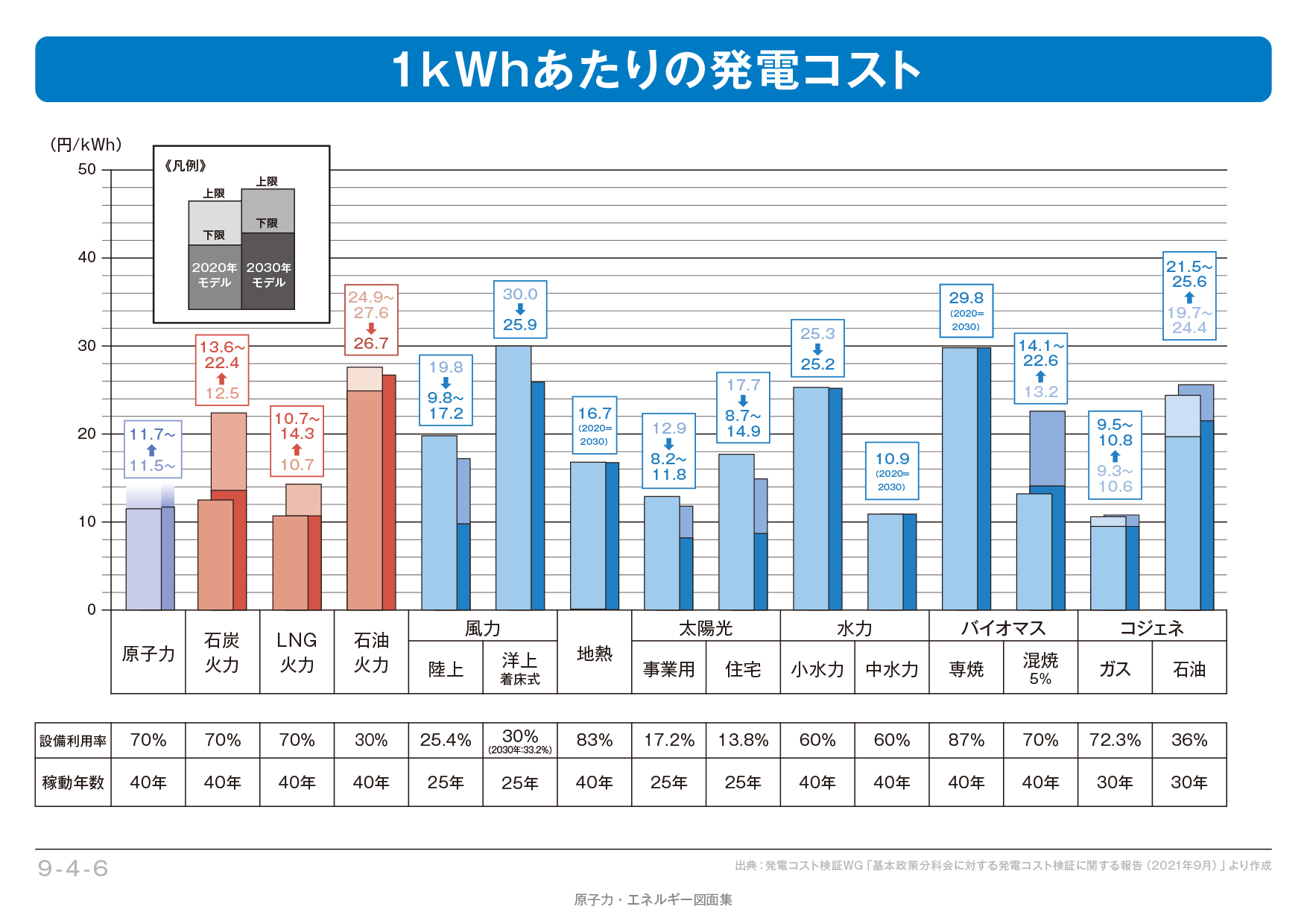 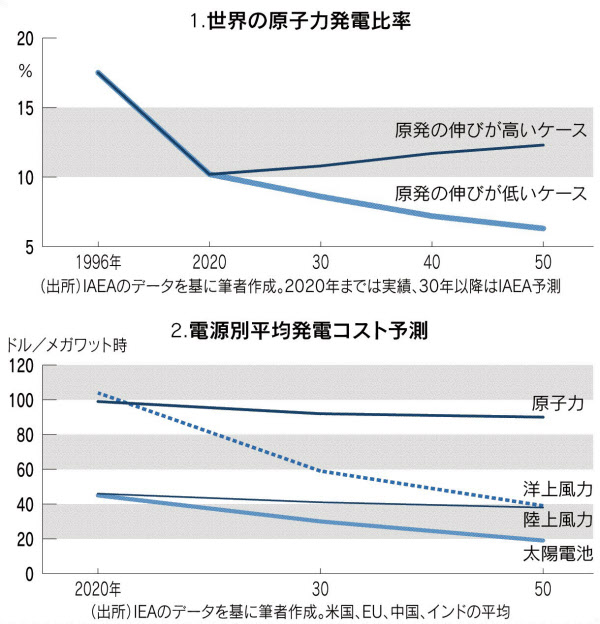 2021.6.21MotorFan 2022.2.16エネ百貨 2022.2.24日経新聞 (図の説明:左図のように、2021年6月の段階で、原発がエネルギー自給率に貢献するという論調は少なくなかった。しかし、中央及び右図のように、再エネのコストはその普及とともに下がるため、2030年にはコスト競争でも太陽光発電が最も安くなる。さらに、日本では、再エネが自給率100%以上を視野に自国で完結できる唯一のエネルギー自給率向上策なのだ) *11-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/815522 (佐賀新聞 2022年2月24日) 小城市庁舎、太陽光で電力自給 全国初、24日から本格運用 小城市が三日月町の本庁舎に整備していた太陽光発電設備が完成した。24日から本格運用し、庁舎内の全ての電力を太陽光発電で賄う。市によると、再生可能エネルギーで自治体庁舎の全電力を自給する取り組みは全国で初めて。市は23日、2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出量を実質ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言した。職員と来庁者用の駐車場に設けた屋根の上に1200枚、総出力500キロワットの太陽光パネルを載せた。余った電力をためる大型の蓄電池も整備し、災害や天候不順で発電できなくても、人命救助の目安になる72時間分の電力を供給する。電力会社から電気を購入せずに自給することで年間約360トンのCO2排出量を削減でき、約1千万円かかっていた年間の電気料金もゼロになるという。総事業費は8億6240万円。脱炭素化の取り組みを促す国の補助金や、返済の5~7割を国が負担する地方債を活用し、エネルギー消費量が少ない空調やLED照明への切り替えを進めた。庁舎の東に位置し、災害時の避難所になる三日月保健福祉センターにも照明や空調の稼働に最低限必要な電力を供給する。江里口秀次市長は23日の完成式でゼロカーボンシティ宣言を行い、「脱炭素化の先進施設で、防災拠点としての機能もこれまで以上に発揮できる」と述べた。太陽光設備の導入は、自治体庁舎の非常用電源について72時間以上の稼働を促す国の指針を受けて実施した。従来は自家発電機1台を設置し、燃料を補給できなければ14時間しか稼働しなかった。 *11-2:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220222/k10013496671000.html (NHK 2022年2月22日) ガソリン高騰対策 石油元売り会社への補助金 拡充検討へ 政府 政府はガソリン価格のさらなる上昇を抑えるため、現在、1リットル当たり5円が上限となっている石油元売り会社への補助金について、大幅に拡充する方向で検討に入りました。さらに中小企業や農業、漁業など幅広い分野向けの支援パッケージをまとめる方向です。ウクライナ情勢などを受けて原油価格は値上がり傾向で、レギュラーガソリンや灯油の価格はおよそ13年ぶりの高値水準となっています。政府は価格上昇を抑えるため、石油元売り会社に補助金を出す対策を1月下旬から行っていますが、早くも1リットル当たり5円の上限に達しています。政府はさらなる価格上昇を抑えるため、補助金について大幅に拡充する方向で検討に入りました。自民党は、緊急提言でガソリン税の上乗せ部分の課税を停止する、いわゆる「トリガー条項」で示されている、1リットル当たり25円を上回る支援を求めています。政府は自民党の緊急提言を踏まえたうえで、今年度予算の予備費から手当てする方向で、5円からどれぐらい補助金を引き上げられるか、調整を進めています。また、原油価格の上昇分を中小企業が適切に価格転嫁できるような対策や農業や漁業など業種別の対策など、幅広い分野向けの支援パッケージをまとめる方向です。 *11-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220224&ng=DGKKZO80366500S2A220C2KE8000 (日経新聞 2022.2.24) 原発政策を考える(下) 依存度低減へ国民的議論を、鈴木達治郎・長崎大学教授(1951年生まれ。東京大博士(工学)。元内閣府原子力委員会委員長代理) <ポイント> ○原発の脱炭素電源としての役割は限定的 ○日本では事故に伴うコスト上昇も重荷に ○政府から独立した機関で客観的な評価を 欧州連合(EU)は2月2日、どんな事業や製品が持続可能かを示す「タクソノミー」法案で、天然ガスとともに原子力発電が「脱炭素に貢献する電源」の基準を満たすとの位置づけを示した。これに対し、EU内や一部投資家から反対の意見が表明されており、脱炭素電源としての原発を巡る議論が続いている。だが原子力発電の世界の現状を見る限り、脱炭素への貢献は限られたものになりそうだ。日本は福島第1原子力発電所事故の教訓を踏まえ、原発の現状を客観的に評価する仕組みを立ち上げ、国民的議論を経て現実的な「依存度低減」政策へかじを切るべきだ。「世界原子力産業現状報告2021年版(WNISR2021)」によると、世界の総発電量に占める原子力発電のシェアは、1996年のピーク(17.5%)から徐々に低下し、最近は10%前後で推移する。発電量も2020年は12年以来の減少(前年比3.9%減)となり、中国を除けば減少率は5.1%に達し95年以来の低水準となった。原発比率低減の傾向は国際原子力機関(IAEA)の50年までの予測でも明らかだ。原発の伸びが高いケースでは総発電量の比率は12.3%と現状の10.2%からやや上昇するが、原発の伸びが低いケースでは6.3%と大きく低下する(21年予測、図1参照)。世界の電力供給における役割が現状程度か低下するのは明らかだ。であれば脱炭素電源としての役割も限定的なものと考えざるを得ない。停滞傾向の最大の要因として考えられるのが、原子力発電の競争力低下だ。図2は、国際エネルギー機関(IEA)による50年までの電源別発電コスト予測を示したものだ。脱炭素電源としての原子力発電コストは、再生可能エネルギーの発電コストの急速な低下に追いつかないとみられる。炭素価格が入っても、脱炭素電源としての競争力を見る限り、原子力ではなく再生エネが主役になることはほぼ間違いないだろう。IAEAの統計では21年末現在、日本で33基運用中となっているが、実際に稼働している原発は10基であり、20年の原子力発電比率は4%にすぎない。日本の電源構成で原発は「主役の座」を既に降りている。さらに原発の今後を占ううえで、重要な経済性について大きな転換点を迎えるデータが21年に経済産業省から公表された。30年時点での新設原発の平均発電コスト比較で、原発は最も低コストの電源ではなくなった。政府による発電コスト比較が公表され始めてから初めてのことであり、原子力の将来を占ううえでも重要な転換期といえる。経済性悪化の背景には、当然のことながら原発事故の影響がある。経産省の発電コスト検証ワーキンググループの推定によると、事故後の追加的安全対策費は発電コスト換算で1キロワット時あたり1.3円(15年には同0.6円)にのぼる。事故リスク対応費用も同0.6円(15年には同0.3円)に上昇している。さらに核燃料サイクルコストも上昇している。青森県六ケ所村に建設中の再処理工場の総事業費は、今や14.4兆円(15年には12.6兆円)にのぼるとされ、発電コストに換算すると同0.6円(15年には同0.5円)となっている。これらのコストは今後も上昇する可能性が高く、原発の競争力は改善する見通しが立たないのが現状だ。政府は21年6月に発表した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」で、原子力産業も成長戦略を担う産業として位置づけた。その中で、小型炉や高速炉などの開発が改めて打ち出された。一方、政府は21年10月、新しいエネルギー基本計画を閣議決定した。この中で原子力発電については前回(18年)と同様、原発事故の反省を踏まえ「依存度をできる限り低減する」ことを再確認した。この一見矛盾する政策が現在の原子力を巡る議論の迷走を生んでいる。依存度をできる限り低減するための具体的な政策は一切示されていない。さらに高速増殖炉「もんじゅ」の廃止が決定した後も、核燃料サイクルについては議論もされていない。現実は「消極的な現状維持」政策とも呼べる。政府は30年度の原発比率を20~22%とする目標を掲げるが、とても実現できそうにない。原子力発電を主要電源と位置づける大前提だった経済性も揺らいでおり、もはや原発はいわば「肩を壊したエース」になったことを認識すべきだ。NHK世論調査(20年11~12月)によると、7割近い国民が原発依存低減を望んでおり、再稼働についても賛成が16%に対し反対は39%にのぼる。国民の信頼は全く回復していない。そうした状況で「脱炭素電源」を担う成長産業と言われても、国民は戸惑うだけだ。この状況を考えれば、70年代の石油危機以降とってきた「原発拡大」政策から、原子力依存度を低減する方向に明確にかじを切るべき時期が来たのではないか。具体的には、原発拡大政策の柱だった電源三法、特に立地自治体への交付金制度を見直す必要がある。高速炉と核燃料サイクルの推進を大きな目標としてきた原子力研究開発も、廃炉や廃棄物処理・処分を最大の柱とする方向に転換すべきだろう。使用済み燃料の最終処分の見通しもない現状を考えれば、50年代から維持してきた「全量再処理路線」の見直しも不可避だ。原発事故から間もなく11年を迎える。原発事故が残した負の遺産はいまだに重く、国民の負担となっている。何よりも事故炉の廃止措置は、技術的に最も困難な課題であるとともに、経済的にも社会的にも今後40年以上にわたり取り組んでいかなければならない問題だ。福島の復興と避難した被災者の健康、生活、環境回復なども、負の遺産として東京電力のみならず政府が責任を持って取り組まなければいけない課題だ。こうした負の遺産への取り組みが、本来は原子力政策の最優先課題であるべきだ。事故原因の全貌もまだ明らかになってはいない。これら負の遺産が解消されないまま、原子力を成長産業として位置づけるのは、事故の反省を踏まえた原子力政策とは言い難い。負の遺産の再評価も含めて原子力発電の現状を客観的かつ総合的に評価し、国民的議論を経て原子力政策を見直す時期が来ている。これまでの評価では、原子力推進を前提とする省庁・機関が中心となっていた。推進・反対のどちらの立場にも偏らず、政府から独立した機関(例えば国会に設置した東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)で客観的な評価をすべきだ。さらに原子力の将来にかかわらず最優先で取り組まなければいけない課題(福島第1原発の廃炉、福島の復興、放射性廃棄物問題、人材確保など)が山積みだ。これらの課題については推進・反対の対立を超えた国民的議論が早急に必要である。このままでは原子力政策は迷走を続けるばかりで、国民の信頼回復も重要な問題の解決も困難だ。 <最新技術と鉄道> PS(2022年3月4日追加):*12が、「①JR九州が利用者数の減来で、来年春、佐賀県内5市町の7駅から駅員を引き揚げる方向で検討している」「②合理化する駅は筑肥線の浜崎・東唐津、唐津線・筑肥線が乗り入れる西唐津、長崎線の牛津・多良、鍋島、鹿児島線のけやき台」と記載している。私は、居住地の埼玉県では「Pasmo」を使い、自動改札を通って電車に乗るため駅員と話すことは滅多にないが、唐津線の無人駅「山本」からディーゼルカーに乗った時は、どこで切符を買ったらよいかわからず、不安な気持ちになった。つまり、切符の自販機や自動改札機があれば無人でも問題ないのだが、稀に助けが必要な人もいるため、無人駅にはコンビニやスーパーを近接させ、店員に世話係をしてもらえばよいと思う。駅に近い店は、乗客にとっても便利なので繁盛し、関係者全員にメリットがあるだろう。 なお、JRも人員削減によるコストカットだけを考えるのではなく、ディーゼルカーをEVや燃料電池車に変更したり、列車を自動運転化したりしてコストダウンすると同時に、高架にして路線に超電導電線を引き、高架下の土地は貸し出して、運賃以外にも送電収入や土地の賃貸料を得る方法を考えた方が、持っている資産をフルに活用して収入に繋げることができると思う。    (図の説明:左図は、オシャレだが小さな志津川駅で、窓ガラスにシースルーの太陽電池がついている。中央の図は、現在、日本で使われている蓄電池電車で、右図は、線路もないのに自動運転で走っている中国の電車だ。現在は、このように、多様なコストダウンの方法ができている) *12:https://news.yahoo.co.jp/articles/ad5f88602126236cc8db8f828f5bb18fb8ec2f05 (佐賀新聞 2021/12/22) 佐賀県内7駅「合理化」検討 JR九州 来春、駅員引き揚げも 営業体制、沿線市町と調整 JR九州が来年春、唐津市など佐賀県内5市町の7駅から駅員を引き揚げる方向で検討していることが21日、分かった。人口減少や新型コロナウイルスの影響で利用者数が減り、大幅な減収になっている経営状況を踏まえ、異例の規模で合理化を図るとみられ、近く発表する。駅の営業体制を沿線市町と調整しており、無人化の回避を検討している駅もある。複数の関係者によると、JRが体制を合理化する駅は筑肥線の浜崎、東唐津▽唐津線で筑肥線も乗り入れる西唐津(いずれも唐津市)▽長崎線の牛津(小城市)、多良(藤津郡太良町)、鍋島(佐賀市)▽鹿児島線のけやき台(三養基郡基山町)。12月中旬に無人化の方針が明るみに出た鍋島、けやき台以外にも5駅が合理化の対象になっている。JR側が、佐賀県や7駅の沿線市町に駅員引き揚げなど営業体制の合理化を説明した。昨年4月に窓口の駅員を配置しない形になった多良駅では一部の時間帯に駅員が巡回していたが、これも合理化する方針とみられる。JR側と沿線市町は、それぞれ対応を調整している。8月に新駅舎が完成したばかりの浜崎駅など、各駅の個別の事情も踏まえ、人員の費用負担などの調整次第では有人駅が維持される可能性もあるという。JR九州管内の計568駅のうち、無人駅は304駅ある。県内では59駅のうち、6割近い33駅が無人になっている。新型コロナの流行やテレワークの普及などで鉄道需要は減少し、2020年度の鉄道運輸収入は会社設立以来、最低だった。
| 経済・雇用::2021.4~2023.2 | 11:47 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2022,01,02, Sunday
(1)2022年度予算案について
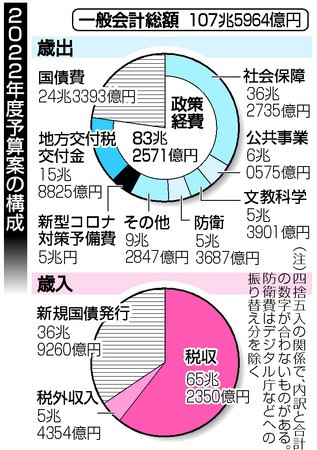  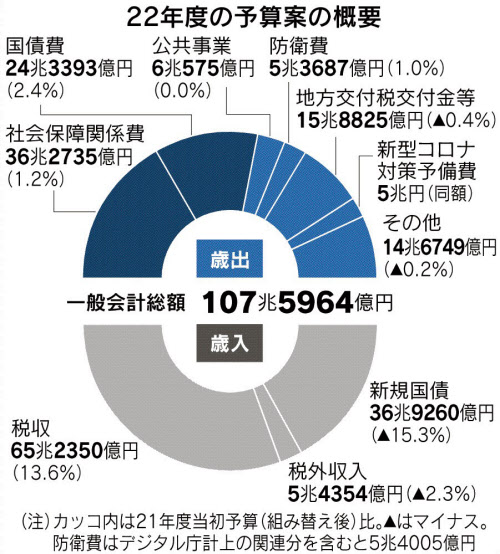  2021.12.24時事 2021.12.24中日新聞 2021.12.25日経新聞 2020.12.21時事 (図の説明:左3つの図のように、2022年度予算案107兆5,964億円の34.3%は国債発行で賄われており、税収で賄われているのは60.6%で、税外収入も5.1%しかない。しかし、1番右の図のように、2021年度予算案も106兆6,097億もある) 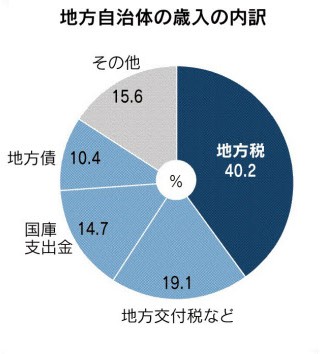 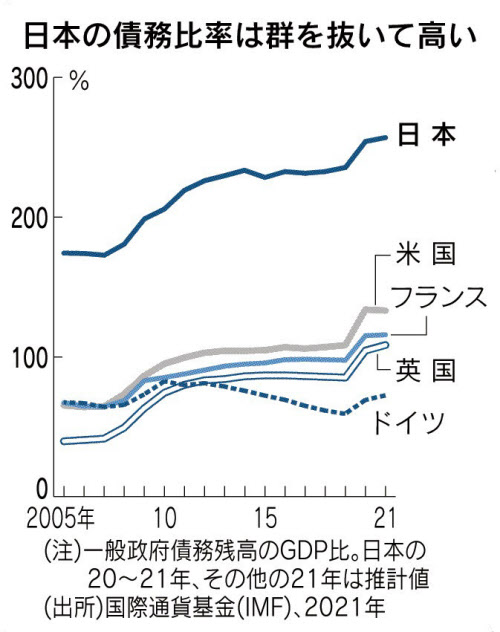 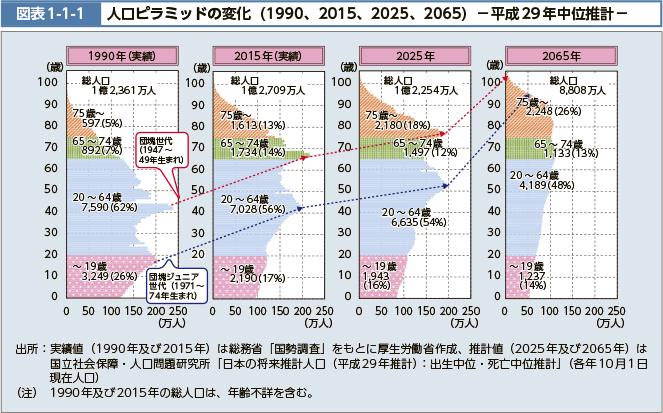 2020.6.10日経新聞 2021.12.26日経新聞 人口動態の推移 (図の説明:1番左の図のように、地方自治体の歳入も、地方税で賄われているのは40.2%で、地方交付税《19.1%》、国庫補助金《14.7%》などとして33.8%を国に依存しており、税外収入は少ない。その結果、中央の図のように、日本の債務比率は世界でも群を抜いて高くなっているため、このようなことが起こる原因究明と解決が最も重要なのである。なお、右図のように、ある年の出生数はその年の年末にはわかるものなので、少子高齢化は突然の出来事ではなく、人口動態はずっと前からわかっていたことだ) 政府は、2021年12月24日、一般会計総額が過去最大の107兆5964億円となる2022年度予算案を決定した。 このうち社会保障費は、36兆2735億円で最大ではあるが、契約に基づいて国民から社会保険料を徴収し、サービスの提供時に国が支払うものであるため、*1-1のように、社会保障費を国債の「元本返済分+支払利子」である国債費と合計し、「固定費」と考えること自体が会計の基礎的な考え方を全く理解していない。 社会保障費は、人口の多い団塊の世代の医療費が膨らむ頃に支出が自然増しても、契約に従って支払っている限り予測可能だったのであり、支出規模が大きいからといって勝手に減らすことは契約違反であると同時に、それを生活の糧としている人々の生活を脅かす。ただ、社会保障費も細かく見れば、子ども医療費の無償化(無償はよくない)などの無駄遣いもあるが、生産年齢人口へのバラマキ的な補助金こそ、かえって産業を衰退させ無駄遣いにもなるのである。 なお、「新型コロナ禍対策で積み上がった債務の返済」と記載されているものも、私がこれまで指摘してきたとおり、必要なことはせずに不必要なことばかりして無駄遣いが多すぎ、全体として全く納得できないものになっている。 それらの結果として、2022年度末の建設国債と赤字国債などの残高合計は1026.5兆円、償還と利払いに充てる国債費は24兆3393億円になる見通しで、*1-2に書かれているように、日本の政府債務は2021年にGDP比256.9%と比較可能な187カ国で最大となり、続く2位以下には209.9%のスーダンなどの発展途上国が並び、現在の日本の状況は、戦費の調達などで財政が悪化した第2次世界大戦当時並みなのだそうだ。 なお、消費税の価格転嫁やインフレ目標は、実質賃金(2025年、20~64歳の生産年齢人口は全体の54%)や実質年金(2025年、65歳以上の高齢者は全体の30%)を密かに下げる手段になっているため、消費は喚起されるわけがなく、このようなことを30年以上も続けてきた結果、「経済成長」とは程遠い環境になった。そのため、この失政の責任を誰がとるのかは、最も重要なポイントである。 そのような地域で、異次元の金融緩和をしたり、分配政策として賃上げ税制を盛り込んだりしても、消費(企業から見れば「売上」)は乏しく、地代・賃金・光熱費などのコスト(企業から見れば「原価」)は高いため、投資後に回収可能な企業は少なくなり、余剰資金があっても国内で投資せずに海外で投資することになる。そして、これが、日本における産業空洞化の原因だ。 なお、先端技術開発や国際競争力の強化など成長戦略に充てる予算は必要だが、日本で最初に始めたため補助金などとっくにいらなくなっている筈の再エネやEV技術も、未だに「世界に周回遅れ」などと言っている始末だ。そのため、こういうことが起こった理由を徹底的に追及し、それを無くさなければ、同じことを何度も繰り返すことになる。 私は、日本政府が賢い支出の割合を増やし、財政健全化を達成するためには、世界で導入されている公会計制度を導入し、資産・負債・純資産・収支を正確に把握して、お手盛りにならないように外部監査人の監査を受け、国会議員や国民に速やかに開示して議論する「Plan Do Check Action」のシステムを作る必要があると考えている。 (2)2022年度税制改正大綱について 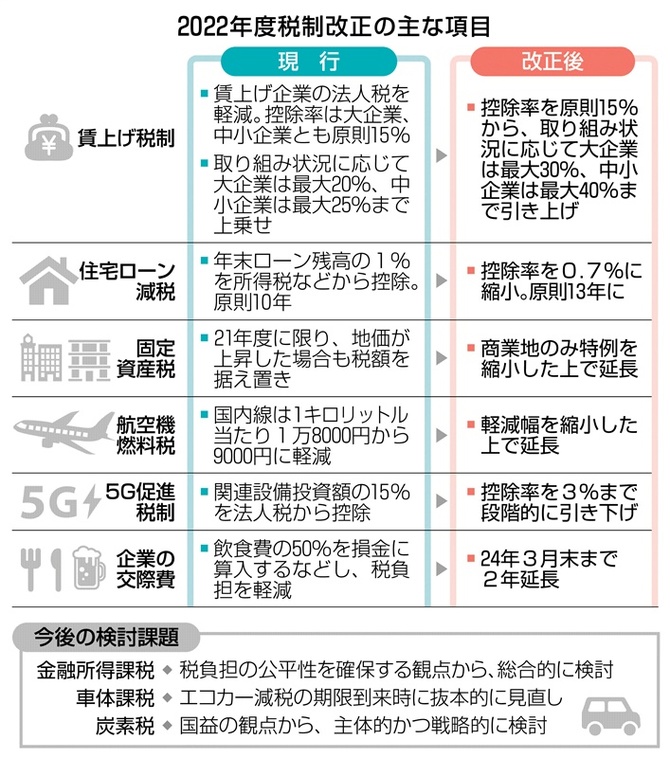 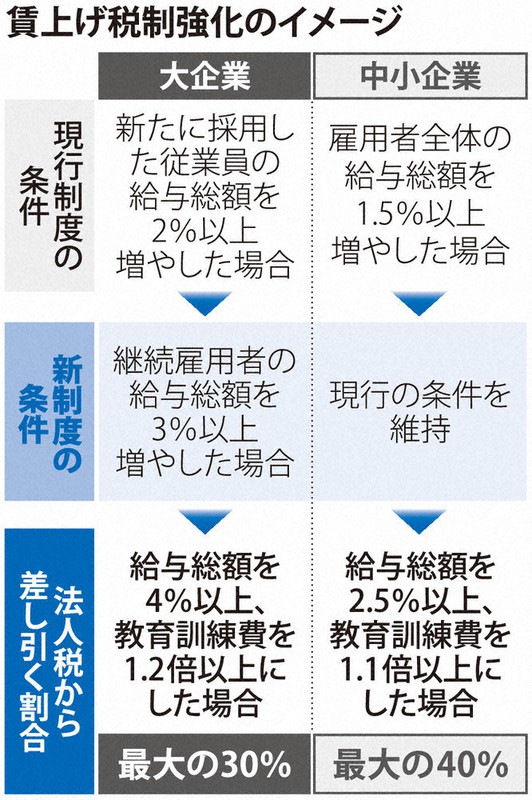  2021.12.11 2021.12.11 財務省 西日本新聞 毎日新聞 (図の説明:左図は、2022年度税制改正の主な項目で、中央の図は、賃上げ税制強化のイメージだ。しかし、右図のように、国の歳出は歳入を大きく上まわり、差額が国債残高純増となっているのである)   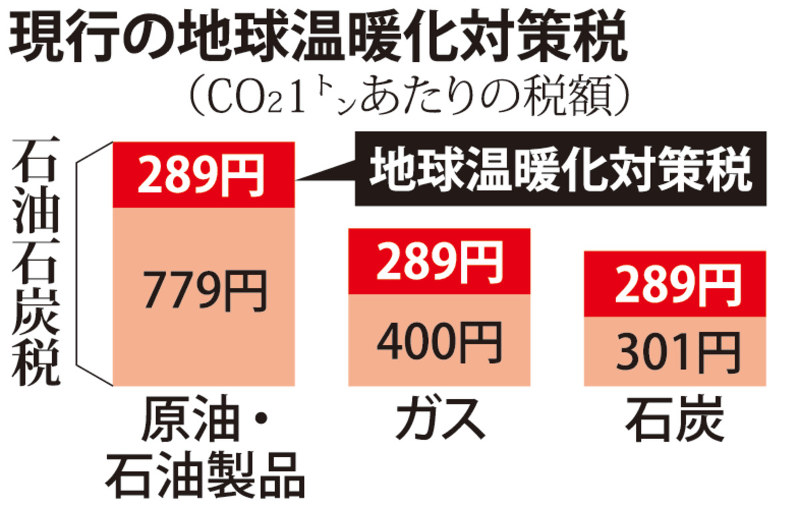 E plan 2019.11.2Eco Jornal 2019.7.26毎日新聞 (図の説明:左図は、主な炭素税導入国の制度概要で日本も2012年に導入されているが、税率が低い。中央の図は、主要国の実効炭素価格《炭素排出費用》で日本は低い方だ。右図は、現行の地球温暖化対策税で、CO₂排出1tあたり289円が原油・ガス・石炭にかかっている) 1)賃上げ企業への優遇税制について 自民・公明両党は、2021年12月10日、*2-1のように、岸田首相が掲げる分配政策として賃上げ企業への優遇税制の拡充を柱とする2022年度の与党税制改正大綱を決めた。 その内容は、①2022年度から大企業は4%以上の賃上げ等の実施で最大30%、中小は2.5%以上の賃上げ等で最大40%まで控除率を引き上げる ②給与総額の計算方法も大企業は前年度から継続して雇う人の給与総額から判断し、中小は新規雇用者の分も含める とのことである。 民間税調は、*2-2のように、③赤字法人が6割あるため賃上げ税制だけでは不十分 ④産業別労組が団体交渉してその産業で働く労働者の最低労働価格を決めるのが解決への道 ⑤その賃金を払えない企業が低価格で商品・サービスを販売することを不可能にし、それなりの高価格での商品・サービスを消費者に受け入れさせるべき ⑥企業の内部留保が増えるのは賃下げも一因 ⑦日本は企業の内部留保に課税しない 等としている。 しかし、①②については、賃金を上げればその分は損金算入(無税)できるので、それ以上に税額控除するのは至れり尽くせりすぎると思う。また、③の赤字法人は、賃上げすれば倒産するような企業であるため、雇用を失うか、低賃金で働くかの選択になっているのである。 さらに、④⑤については、そういう産業があってもよいが、原価と販売単価が上がれば、当然のことながら、それだけ消費が減ることを考慮しておくべきである。なお、⑥⑦のように、内部留保を目の敵にする記述が多いが、どういう意味の内部留保かによって企業にとっての必要性が異なるため、「内部留保は吐き出すことがよいことだ」という論調に、私は与しない。 それより重要なことは、日本の賃金上昇を妨げている一番の要因である終身雇用の原則をやめることである。日本で中途退社した人は、あたかも、イ)同僚より能力がなかった ロ)同僚より忍耐が足りなかった 等々として、同じ会社に勤め続けた人よりも不利な給与体系に置かれたり、負け組のような言われ方をしたりするから、転職できないのである。そのため、労働市場でそのようなことを徹底してなくすことが、労働移動を容易にするKeyになるのだ。 2)金融所得への課税強化について 株式の配当・売買益にかかる金融所得課税について、与党税制改正大綱は、*2-1のように、現行の金融所得の税率20%を引き上げることを念頭に「税負担の公平性を確保する観点から、課税のあり方について検討する必要がある」と記載しつつ見送り、将来の実施時期も明示しなかったそうだ。 私も、金融所得は総合課税されず税率も低いため、国民間では不公平・不公正だと思うが、外国もそうである以上、国際間で揃えておかなければ日本国内への投資が減るため、「一般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう配慮する」としたのは理解できる。 その理由は、これから著しく経済成長する国で投資の回収率が高ければ、税率が高くても投資が行われるが、そうではない国の税率が高ければ、最も他国へ逃げ易いのが投資(=金融資産)だからである。 3)住宅ローン減税について 住宅ローン減税は2025年まで4年間延長する一方、*2-1のように、ローン残高に応じて所得税・住民税を差し引く割合を1%から0.7%に縮小し、ローンの借入限度額は新築・省エネ性能に優れた住宅を優遇するそうだ。 しかし、省エネ性能に優れた住宅を優遇するのはよいが、人口が減少し始めて空き家が目立つ時代に、新築住宅を優遇し続けて優良農地を際限なく住宅地にしていくのは時代錯誤だと考える。それよりも、街の再生をしたり、空き家を改築したりした人に税制優遇した方がよいのではないか? 4)環境税について 上の下の段の図のように、日本も2012年に地球温暖化対策税として、CO₂排出1tあたり289円の炭素税が原油・ガス・石炭にかかっているが、主要国の実効炭素価格《炭素を排出する費用》と比べると、税率が低い。 私は、これを世界でヨーロッパに合わせて環境税として徴収し、世界の森林・田園・藻場の維持・管理費用に充てるのがよいと考える。その理由は、そうすることによって国間の不公平をなくし、同時に、地球温暖化対策の財源にすることができるからである。 (3)日本の所得格差について 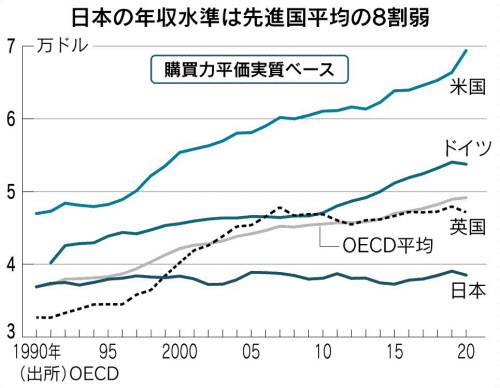 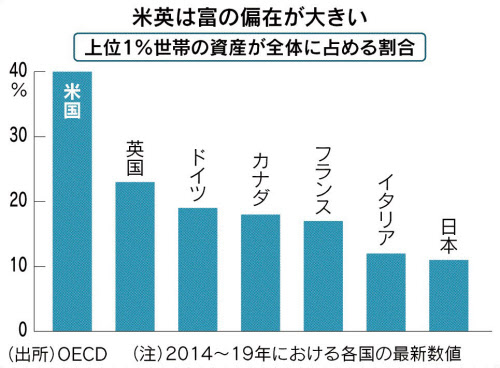 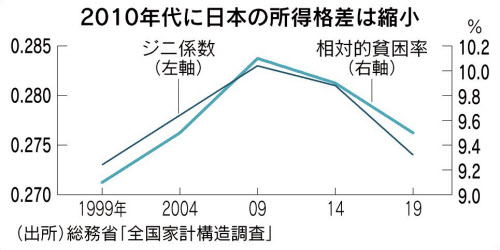 2021.10.16日経新聞 (図の説明:左図のように、日本の年収水準だけが上がっていない。また、中央の図のように、米英は所得の偏在が大きく、日本は小さい。さらに、2010年代に日本の所得格差は縮小しており、みんなで貧しくなって平等に近づいた感があるが、これでいいのだろうか? そのため、何故、こうなったのかについての正確な原因分析が必要である) 自民党総裁選で、*3-1のように、金融所得への課税強化が焦点の一つになり、推進派は格差是正の狙いを訴え、慎重派は株式市場への影響を懸念したそうだ。(2)の2)に書いたとおり、不平等の解消効果はあっても、金融資金の海外逃避による株価の下落は明らかである。 また、「貯蓄から投資へ」という声もよく聞くが、金融資産は高収益と安全性が対立するため、安全性を保ちつつ収益性を高めるには、分散投資するのが普通だ。また、為替差損益を含めた安全性が高く、利率も高い国の金融資産を選ぶことにもなるため、国内の安定性や公平性だけを見て政策を決めていると、日本経済に金融面からも打撃を与えることになる。 なお、社会における収入格差の程度を計測するための指標であるジニ係数は、*3-2のように、日本は2010年に0.336で、社会が不安定化する恐れがあると言われる0.4以下だが、2020~2021年に新型コロナで経済を停止したため、2021年末時点では0.4を超えているかもしれない。しかし、日本のデータは2010年が最新だそうで、このように、日本はデータの迅速性・正確性が乏しく、データに基づく政策形成ができていないことも重要な問題なのである。 (4)補助金を減らして税収・税外収入を増やす方法 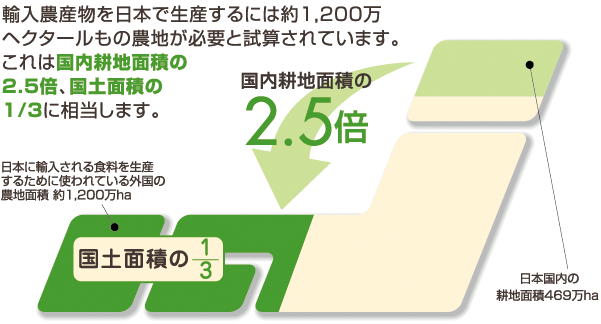 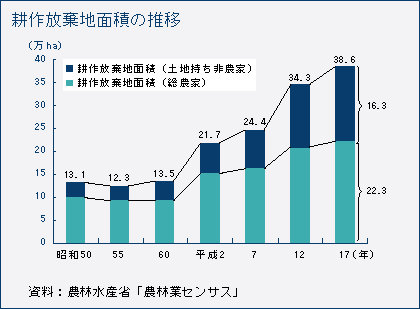 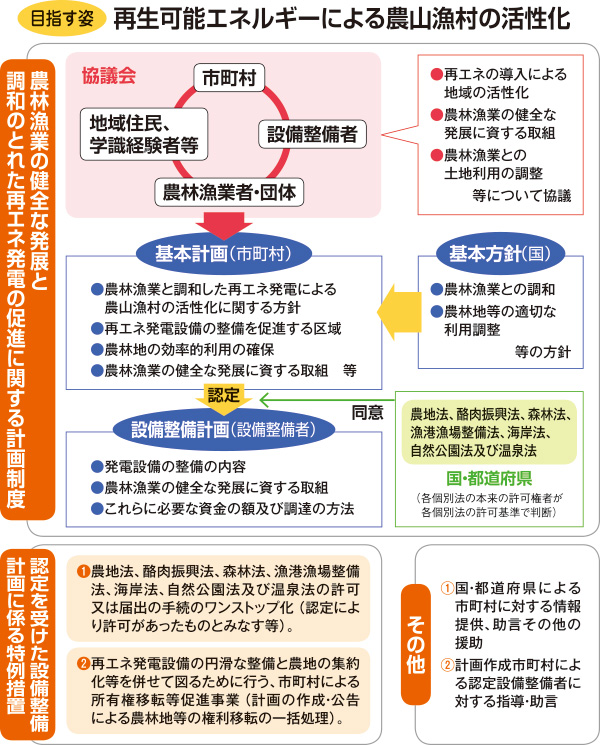 農水省 農水省 (図の説明:1番左の図のように、輸入農産物を国内生産するには、現在の2.5倍の耕地面積が必要と言われているが、左から2番目の図のように、耕作放棄地が耕作地と同じくらいの面積に達している。耕作放棄されるのは、その土地で農業を続けても収入が低いからであるため、農業を続けていれば再エネ発電で電力収入も得られるよう、右図のように、農林漁業地帯で計画的に発電機設置に補助すれば、再エネ発電が増えて耕作放棄地は減るだろう) 1)再エネの普及と送電網の整備 (電気事業者の関連機関の試算では投資は総額2兆円超になるため)日本政府が、*4-1のように、再エネ普及のため2兆円超を投資し、都市部の大消費地に再エネ由来の電力を送る大容量次世代送電網をつくることを決定し、岸田首相が2022年6月に策定するクリーンエネルギー戦略で示すよう指示して、政権をあげて取り組むことを明示されたのはよかった。 これに先立ち、安倍首相時代に(私の提案で)電力自由化が行われ、2016年4月1日以降は電力小売への参入が全面的に自由化されたため、全ての電力消費者が電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになっている。そのため、地域間の電力を融通する「連系線」が充実すれば、大手電力を含むすべての電力会社が再エネ由来の電力を販売しあうことができるようになるだろうし、そうならければならない。 しかし、①2030年度を目標に北海道と本州を数百キロメートルの海底送電線で繋ぐ ②北海道から東京までを4倍の同400万キロワットにする ③九州から中国は倍増の同560万キロワットにする ④送電網を火力発電が優先的に使う規制を見直し、再エネへの割り当てを増やす ⑤「交流」より遠くまで無駄なく送電できるため、送電方式は欧州が採用する「直流」を検討する ⑥岸田首相は夏の参院選前に看板政策として発表し政権公約にする ⑦主に送配電網の利用業者が負担し、必要額は維持・運用の費用に利益分を加えて算定する とされているのは、無駄が多くて大手電力会社優遇にもなっている。 具体的には、①②③については、既存の鉄道・道路の敷地を使って送電線を敷設すれば、網の目のように送電線を敷設することが可能で、これなら、*4-7の粘菌の輸送ネットワークの合理性が道路・鉄道・インターネットだけでなく送電線にも応用できるため、経済合理性がある上にセキュリティーでも優れている。 また、鉄道会社が遠距離送電網を所有すれば送電料が鉄道会社に入るため、送電会社は電力会社間では中立になると同時に、過疎地の鉄道維持がしやすくなる。さらに、④⑦のように、送電網を火力発電や原子力発電に優先的に使わせて大手電力に利益を落とすような経産省による非科学的で意図的な規制を排除することができるのである。 その上、⑤についても、直流で動く機器が多いため、送電も直流で行うのは合理的であるし、⑥のように、夏の参院選の看板政策にしようとすれば、そこまで徹底して行うべきだ。 環境省は、*4-2のように、2022年1月25日から脱炭素に集中的に取り組む自治体を募集し、電力消費に伴うCO₂排出量を実質0にする先行地域を2030年度までに20~30カ所選んで国が再エネ設備の導入等を支援し、環境配慮の街づくりの成功モデルを育てるそうだ。自治体は、上下水道・ダム・市道・県道などを所有しているため、地域内で発電したり、電線を地中化したりするのに役立ちそうで、複数の自治体による応募や企業・大学との共同提案も認めれば、面白いモデルが出てきそうである。 さらに、*4-3のように、農水省は、環境に配慮する農家や食品事業者への支援策を拡充して化学農薬を低減できる農業機械を導入する生産者の所得税・法人税を軽減したり、食品事業者等の中小企業が建物を整備する場合も対象としたりするそうだ。 しかし、農林漁業地帯に生産に支障のない形で再エネ設備を置いて機器を電動化すれば、光熱費無料で、エネルギーを販売しながら食品生産を行うことができるため、農業の利益率が上がり、農業補助金が不要になるため、まず、それを可能にすることが重要である。 2)原発は必要か EUの欧州委員会が、2022年1月1日、*4-5のように、「原子力と天然ガスは、一定の条件下なら持続可能」とし、脱炭素に貢献するエネルギーと位置づける方針を発表したそうだ。しかし、EUの炭素税や個人情報保護規制には賛成だが、原発依存度の高いフランスや石炭に頼る東欧諸国が「原発やガスは脱炭素に資する」と認めるよう訴えても、CO₂は排出しないが有害な放射性物質や放射性廃棄物を出す原発やCO₂を出す天然ガスをいつまでも持続可能とするのは無理がある。 そのため、脱原発を決めたドイツが科学的かつ先進的であり、とりわけ地震・火山国である日本に原発という選択肢はない。それよりも、農林漁業地帯で再エネ発電をした方が、よほどクリーンで国や地方自治体の財政に資するのである。 3)EVについて 再エネで電力を自給することによって光熱費を下げ、国富の海外流出を防ぎ、日本が資源大国になって財政を健全化するには、EVやFCVを積極的に導入する必要がある。そのためには、*4-4のように、日本通運・ヤマト運輸・日本郵便・佐川急便などの商用車を迅速にEV・FCVにする必要があり、米カリフォルニア州の「州内で販売する全てのトラックを2045年までにEV・FCVにする規制」が参考になる。 また、EVの発展と普及に伴って、*4-6のように、より高いエネルギー密度と安全性・長寿命を期待できる全固体電池の研究開発が活発化し、現在では、商用化に近づいているそうだ。そのため、次は、他の機械への幅広い応用が望まれるわけである。 ・・参考資料・・ <2022年度予算案> *1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211225&ng=DGKKZO78786120V21C21A2MM8000 (日経新聞 2021.12.25) 107兆円予算案、減らせぬ費用多く 社会保障・国債費60兆円超、新規事業1%未満、成長に回らず 政府は24日、一般会計総額が過去最大の107兆5964億円となる2022年度予算案を決定した。高齢化で膨らむ社会保障費と、巨額借金の返済でかさむ国債費の合計は初めて60兆円を超えた。なかなか減らせない「固定費」ともいえる社保・国債費が予算全体に占める比率は6割に迫り、予算の硬直化が進む。新規事業は全予算の1%に満たず、成長分野に予算が回っていない。項目別にみて最も支出規模が大きいのが歳出総額の3割を占める社会保障費だ。36兆2735億円と21年度当初予算に比べて4393億円(1.2%)増えた。22年からは人口の多い団塊の世代が医療費が膨らむ75歳以上になり始め、高齢化で支出が自然に増えていく圧力が強まっている。薬の公定価格(薬価)の引き下げや繰り返し利用できる処方箋による通院抑制で自然増を2000億円程度抑えたが、膨張は止まらない。新型コロナウイルス禍対策で積み上がった債務の返済が歳出規模を押し上げる構図も鮮明だ。22年度末の建設国債と赤字国債などの残高は計1026.5兆円と過去最高になる見通し。償還や利払いに充てる国債費は24兆3393億円と5808億円(2.4%)増え、2年連続で過去最高を更新した。社会保障費と国債費の合計は60.6兆円に達する。20年で7割増え、総額の56%を占める。ほかの政策に予算を振り向ける余力が狭まっている。国の政策に使う一般歳出のうち社会保障費以外は計26兆1011億円。この10年の伸びは1割に満たず、伸びた要因も防衛費の影響が大きい。岸田文雄政権は22年度予算案を「成長と分配の好循環」に向けた予算案と位置づける。ただ目玉政策には新味に欠けるメニューが並ぶ。例えば分配政策として盛り込んだ経済産業省の「下請けGメン」。企業の下請け取引の適正化に向けたヒアリング調査員を248人に倍増する。実態は消費増税の価格転嫁が大企業などに向けて適切に実行されているかを調べる「転嫁Gメン」の減員(約240人減)とワンセット。目新しさは乏しく、予算額も全体でみれば減額だ。成長戦略への配分の余地も限られている。主要省庁の予算資料で「新規事業」として計上された主な事業を集計すると、全体で4300億円程度。歳出総額に占める割合は1%に満たない。ただ菅義偉前首相が決めた不妊治療の保険適用拡大(計174億円)など社会保障費もこの中に含まれる。先端技術の開発や国際競争力の強化など成長戦略に充てる予算は、約4300億円の積み上げベースの数値よりも小さい可能性がある。政府は22年1月召集の通常国会に予算案を提出する。22年度予算案は20日に成立した21年度補正予算と一体で編成した。双方を合わせて「16カ月予算」と位置づける。予算編成では本予算の膨張を抑えるため、本来は緊急性の高い支出に絞る補正予算で、各省庁の予算要求に応える手法が常態になっている。財務省も本丸の本予算を守るために容認してきた。今回は21年度の補正予算が最大に膨らんだのに22年度の当初予算案も最大を更新。本予算も伸びを抑えられなかった。本予算には構造的な支出で歳出に足かせがはまる一方、補正予算は甘い査定でバラマキともとれる政策が積み上がる。「賢い支出」につなげるには、使い道の精査やメリハリある配分への取り組みが欠かせない。 *1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211226&ng=DGKKZO78790520V21C21A2EA3000 (日経新聞 2021.12.26) 107兆円予算、財政膨張どこまで 市場の警戒感は薄く 政府が24日に閣議決定した2022年度予算案は一般会計が過去最大の107兆円に膨らんだ。政府債務は国内総生産(GDP)比で世界最大。異次元の金融緩和による低金利の環境が財政拡張を支える構図がある。財政の信認は円の信認にもかかわる。微妙な均衡はどこまで保てるのか。今回の予算案で新規国債の発行は減った。市場での発行額は198.6兆円と21年度から13.6兆円減る。税収増による財源確保を見込むためだ。それでも国債残高は1000兆円に達し、財政の悪化に歯止めはかからない。国際通貨基金(IMF)の試算で、日本の政府債務は21年にGDP比256.9%と比較可能な187カ国で最大だ。続く2位以下には209.9%のスーダンなど途上国が主に並ぶ。現状は戦費の調達などで財政が悪化した第2次世界大戦当時並みともいえる。この数字だけみれば「円離れ」が起きてもおかしくない。実際には、急な金利上昇(債券価格の下落)が起きるとの見方は少ない。債券市場の落ち着きは複雑なバランスで成り立っている。ひとつは10%以下で推移する外国人保有比率の低さだ。世界銀行の20年リポートによると、国債は海外民間投資家の保有比率が20%を超えると価格急落(金利急上昇)の懸念が高まる。この水準はまだ遠い。債務国ではない余裕もある。対外純債権は20年末時点で356.9兆円と30年連続で世界最大だった。さらに日銀が長期金利をゼロ%に誘導する長短金利操作を続けている。日銀が買い支える安心感から、金融機関などがゼロ金利でも国債を保有する。国債が安定的に消化され、利払い費も増えないので、財政拡大の抵抗感が薄まる。財政支出はどこまで拡大できるのか。近年注目された現代貨幣理論(MMT)によれば、自国通貨建てで資金調達できる政府は過度なインフレが起きない限り、債務の増大を懸念する必要はない。インフレを制御できるかは誰も証明できていない。足元では米欧の高インフレの波が日本に及ぶ兆しがある。11月に企業物価は原油高などで41年ぶりの伸びとなった。水面下に沈んでいた消費者物価上昇率も3カ月連続のプラスだ。この流れが加速するようだと金融政策も緩和一辺倒ではいられなくなる。賃上げが鈍いのに物価だけが上がる難しい状況で利上げを迫られる可能性もある。予算案を決めた24日、鈴木俊一財務相は25年度の財政健全化目標を維持したいとの考えを表明した。政策経費を新たな起債に頼らずまかなえる目安となる基礎的財政収支黒字化の旗を降ろさない構えだ。今後の目標見直し論議にクギを刺したともいえる。政府は「国を実験場にする考え方は持っていない」(麻生太郎前財務相)との立場だ。BNPパリバ証券の河野龍太郎氏は「危機のマグマがたまっている」とみる。通貨が大量に発行されている今の均衡が崩れれば金利の急騰や円安の加速を招きかねない。新型コロナウイルス対応で財政の役割が重くなったとはいえ、野放図な拡張には危うさがつきまとう。カナダやスイスなどが21年に新しい財政健全化方針を打ち出した。日本でも財政規律を保つ透明な仕組みを求める声がある。東短リサーチの加藤出社長は、政府から中立の立場で財政を監視する「独立財政機関」を持つべきだと説く。独立機関を持たない国は先進国ではもはや少数派なのが現実だ。 <2022年度税制改正大綱> *2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/148141 (東京新聞 2021年12月10日) 賃上げ促進税制の一方で金融所得課税強化は見送り 22年度税制改正大綱 自民、公明両党は10日、2022年度の税制の見直し内容を示す与党税制改正大綱を決めた。岸田文雄首相が掲げる分配政策の一環として、賃上げ企業への優遇税制の拡充を柱とした。株式の配当や売買益にかかる金融所得への課税強化は「検討が必要」と記載しながら今回も見送られ、将来の実施時期を明示しなかった。現行の賃上げ優遇税制は、大企業が前年度より給与総額を増やした分の最大20%、中小企業で最大25%を控除率として法人税額から差し引く。22年度からは、大企業は4%以上の賃上げなどの実施で最大30%、中小は2・5%以上の賃上げなどで最大40%まで控除率を引き上げる。賃上げ率以外に、給与総額の計算方法も企業規模で異なる。大企業では前年度から継続して雇う人の給与総額から判断するが、中小では新規雇用者の分も含める。住宅ローン減税は25年まで4年間延長する一方で、ローン残高に応じて所得税と住民税を差し引く割合を1%から0・7%に縮小する。その上で、ローンの借入限度額は、新築で省エネ性能に優れた住宅を優遇する。新型コロナウイルス対策として設けた固定資産税の負担軽減措置は、住宅地は予定通り本年度で終了。商業地は22年度も続け、コロナ禍で売り上げが落ち込む企業に配慮する。一方、首相が自民党総裁選時に目玉政策に挙げた金融所得課税の強化は見送られ、次年度の検討事項となった。与党は大綱で、現行の金融所得の税率20%を引き上げることを念頭に「税負担の公平性を確保する観点から、課税のあり方について検討する必要がある」と記載。ただ、実施時期を明記せず、「一般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮する」として慎重姿勢もにじませた。自民党税制調査会の宮沢洋一会長は10日の会見で、賃上げ優遇税制の導入で「1000億円台半ば」の国税減収を、固定資産税の負担軽減措置の一部継続で「450億円程度」の地方税減収を見込んでいると明らかにした。 *2-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/26ccec473ee40e52b2c89f5f1475c7622289ccf7 (Yahoo 税理士ドットコム 2021/12/29) 「安い日本」を変えるのに賃上げ税制では不十分 民間税調、税制改正大綱を斬る 税法や経済学の専門家などでつくる民間税制調査会(民間税調)は12月下旬、2022年度の税制改正大綱を総点検するシンポジウムを開いた。毎年恒例のシンポジウムで、今年は大綱の柱の賃上げ税制にクローズアップし、なぜ日本の賃金が上がらないのか専門家が意見を交わした。(ライター・国分瑠衣子) ●「業界別の最低賃金設定」が話題に 民間税調は租税法の第一人者で、前青山学院大学長の三木義一氏や経済学を専門にする大学教授などでつくる。「日本の税制にもの申す組織」として税制のおかしな点や話題になったニュースについてYouTubeやサイトで発信している。難しい上にあまり知られていない税について興味を持ってほしいという狙いだ。今回のシンポジウムでクローズアップされたのが、2022年度の税制改正大綱の柱である賃上げ税制だ。従業員の賃上げに積極的な企業は法人税の控除率を優遇する。大企業では現行の15%を最大30%、中小企業では最大40%に引き上げるのでかなり大きい優遇策だ。しかし、民間税調は賃上げ税制で恩恵を受ける企業は限定的とみる。「そもそも前提として税金を払っていないと控除は受けられない。日本はコロナ前でも赤字法人が6割もあるのに、税金というインセンティブでいいのだろうか」(青木丈・香川大学教授)。実際に賃上げが実現する策として、民間税調のメンバーで元参議院議員の峰崎直樹氏は独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の濱口桂一郎研究所長による 「情報労連リポート」の寄稿記事を紹介した。濱口氏の寄稿によると、「安い日本」から転換するには個別企業の枠を越えて、産業別に労働組合が団体交渉をして、ある産業の中で働く労働者の労働の価格の最低額を決めることが解決の筋道になると提言している。産業別に労働の価格の最低額を決めることで、その賃金が払えないような企業が低価格で商品やサービスを販売することを不可能にする。それなりの高価格での商品やサービスを消費者に受け入れてもらうという筋道だ。日本以外の先進国では産業別労働組合や産業別団体交渉は一般的だという。事業者が協定して価格を決めるのはカルテルで独禁法違反になるが、濱口氏は寄稿の中で「労働組合が『合法的なカルテル』だからこそできる」と説明する。そして政府の賃上げ要求と産業別の最低賃金制度を組み合わせて、バーチャルな産業別賃金交渉の場をつくることが方法の一つとしている。賃上げを要求する土俵を個別企業から業界全体に変え、政労使で話し合うことが求められていると結論づけている。峰崎氏は「個別企業の枠を超えて産業別の賃金闘争に引き上げないと賃上げは実現しない。安倍、菅政権で実現しなかったことを岸田政権で本気で進める必要がある」と話した。 ●「企業の内部留保が増えるのは賃下げも影響している」 なぜ日本の賃金が上がらないのか。法政大学の水野和夫教授(経済学)は、1997年から24年間にわたり賃金が下がり続けている実態を紹介した。「戦後2番目に長い景気回復のアベノミクスでも賃金や生活水準が下がり続けている。景気が回復すれば賃金が上がるという期待はとっくになくなっている」と話した。水野教授の論考では、1980年代から不動産など実物に投資する「リアルエコノミー」が伸びず、資本家が重視する企業の内部留保など「シンボルエコノミー」が拡大している。「企業の内部留保が増えるのは賃下げで労働生産性基準を無視していることも一因だ」と分析する。また、日本はリアルエコノミーである法人税や個人所得税、消費税には課税しているが、企業の内部留保や相続などシンボルエコノミーにほとんど課税せず、実態とかけ離れている税制の問題点も挙げた。明治大学公共政策大学院の田中秀明教授は「日本は、北欧のように失業しても面倒を見てくれない。だから賃金が下がってもいいから職は守ってほしいという思考になるのでは」と指摘する。その上で「アメリカやイギリスの企業も日本と同じでROE(自己資本利益率)が下がっているが、一方で賃金は上がっている。この違いは何か、日本の賃金上昇を妨げている一番の要因は何かを診断しなければいけないのでは」と問題提起した。この問いに対し水野教授は「日本は労働人口が減り、潜在成長率が低いがアメリカは人口が増えている。また、日本はROEの構成要素の1つである売上高純利益率が極端に低い。売上高純利益率が低いのは日本が製造業中心の供給の国だから。アメリカやイギリスは消費の国なのでこの差はいかんともしがたい」と説明し、潜在的な成長率が低くなっていることが主な要因とした。経済産業省が2014年にまとめた「伊藤レポート」は、日本企業のROEの目標水準を8%としたがコロナ禍で今は5%に落ちている。国際標準まではとても実現できないとして、伊藤レポートは廃止すべきと指摘した。シンポジウムでは賃上げ税制以外にも、固定資産税や金融所得課税についても意見が交わされた。また今後、民間税調が政治家との意見交換会なども視野に、政治的影響力を強めることを確認した。 <日本の格差> *3-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15054798.html (朝日新聞 2021年9月25日) 格差是正、「1億円の壁」破るか 所得税負担率カーブの頂点、総裁選で注目 株式配当などの金融所得への課税強化が自民党総裁選で焦点の一つになっている。推進派は格差を是正するという狙いを訴えるが、慎重派は株式市場への影響を懸念する。ただ、制度の詳細に関する言及はほとんどなく、株価への影響や格差の解消に向けた効果は見えにくい。 ■金融所得への課税強化訴え 総裁選で明確に課税強化を掲げているのは、岸田文雄前政調会長だ。中間層への分配を手厚くすることを経済政策の根幹に据える岸田氏は、政策集に「金融所得課税の見直しなど『1億円の壁』の打破」と明記している。 「1億円の壁」とは、所得税の負担率が、所得が1億円の人を境に下がっていく現状のことだ。給与所得は所得が増えるほど税率が上がる累進制で、最大45%まで税率が上がるが、株の売却益や配当にかかる税率は一律20%(所得税15%、住民税5%)。このため、所得に占める金融所得の割合が比較的高い富裕層ほど、実質的な税率が下がり、格差拡大につながっていると批判されてきた。河野太郎行政改革相は総裁選では、金融所得課税について具体的に触れていないが、政策や政治理念をまとめた自著で「税率を一定程度引き上げるといった対応を検討するべきではないか」としている。また、野党でも、消費税の減税を訴える立憲民主党は、その穴埋め財源の例として、金融所得課税の強化を挙げている。 ■「貯蓄から投資、逆行」 負担率を公平にするための金融所得課税の見直しについては、与党の税制改正大綱でも、「総合的に検討する」とされてきた。財務省が一時、安倍政権下の首相官邸に提案したが、株式市場への悪影響を懸念し、政府・与党での議論は深まらなかった。最も慎重な姿勢だったのは、当時官房長官だった菅義偉首相だったとされる。しかし、新型コロナ対策の大規模な金融緩和で世界的な株高となり、金融資産を持つ富裕層がますます豊かになるなか、米国など、海外でも金融所得課税の強化を検討する動きが出ている。財務省幹部は「コロナ禍で不公平感の問題が出ている。以前ダメだったからといって、今回も絶対ダメではないのでは」と話す。ただ、増税となれば、株式市場への影響は避けられないとの見方が強い。ある金融庁幹部は、金融所得課税の税率が10%から20%に上がった13年、個人投資家が大量の日本株を売り越したとして、「貯蓄から投資への資産形成を進めてきたのに逆行する。富裕層の国外流出にもつながりかねない」と懸念する。実際、高市早苗前総務相は著書などで、税率を30%に引き上げる案を示していたが、その後、物価上昇率2%の目標が達成されるまでは「現実的には増税は難しい」と語り、事実上、撤回している。また、税率を一律で引き上げた場合、所得が1億円未満の人にも増税になるため、格差是正の効果を疑問視する指摘もある。一定以上の金融所得がある人だけを増税対象とする場合、線引きについて議論を深める必要がある。増税の是非を判断するには、こうした制度の詳細に関する情報が欠かせないだけに、総裁選や衆院選では、より踏み込んだ議論が求められる。 *3-2:http://tmaita77.blogspot.com/2012/05/blog-post_08.html (データエッセイ 2012年5月8日) ジニ係数の国際比較 このブログで何回か言及しているジニ係数ですが,この係数は,社会における収入格差の程度を計測するための指標です。イタリアの統計学者ジニ(Gini)が考案したことにちなんで,ジニ係数と呼ばれます。昨年の7月11日の記事で明らかにしたところによると,2010年のわが国のジニ係数は0.336でした。一般に,ジニ係数が0.4を超えると社会が不安定化する恐れがあり,特段の事情がない限り格差の是正を要する,という危険信号と読めるそうです。現在の日本はそこまでは至っていませんが,5年後,10年後あたりはどうなっていることやら・・・。ところで,世界を見渡してみるとどうでしょう。私は,世界の旅行体験記の類を読むのが好きですが,アフリカや南米の発展途上国では,富の格差がべらぼうに大きいのだそうです。世界各国のジニ係数を出せたら面白いのになと,前から思っていました。そのためには,各国の収入分布の統計が必要になります。暇をみては,そうした統計がないものかといろいろ探査してきたのですが,ようやく見つけました。ILO(国際労働機関)が,国別の収入分布の統計を作成していることを知りました。下記サイトにて,"Distribution of household Income by Source"という統計表を国別に閲覧することができます。世帯単位の収入分布の統計です。私はこれを使って,43か国のジニ係数を明らかにしました。しかるに,結果の一覧を提示するだけというのは芸がないので,ある国を事例として計算の過程をお見せしましょう。ご覧いただくのは,南米のブラジルのケースです。旅行作家の嵐よういちさんによると,この国では,人々の貧富の差がとてつもなく大きいのだそうです。毎晩高級クラブで豪遊するごく一部の富裕層と,ファベイラと呼ばれるスラムに居住する大多数の貧困層。この国の格差の様相を,統計でもって眺めてみましょう。上表の左欄には,収入に依拠して調査対象の世帯をほぼ10等分し,それぞれの階級(class)の平均月収を出した結果が示されています。単位はレアルです。一番下の階級は182レアル,一番上の階級は6,862レアル。その差は37.7倍。すさまじい差ですね。ちなみに,わが国の『家計調査』の十分位階級でみた場合,最低の階級と最高の階級の収入差はせいぜい10倍程度です。表によると,全世帯の平均月収は1,817レアルですが,この水準を超えるのは,階級9と階級10だけです。この2階級が,全体の平均値を釣り上げています。富量の分布という点ではどうでしょう。全世帯数を100とすると,階級1が受け取った富量は182レアル×7世帯=1,274レアル,階級2は320×8=2,560レアル,・・・階級10は6,862×13=89,206レアル,と考えられます。10階級の総計値は181,689レアルなり。この富が各階級にどう配分されたかをみると,何と何と,一番上の階級がその半分をせしめています。全体の1割を占めるに過ぎない富裕層が,社会全体の富の半分を占有しているわけです。その分のしわ寄せは下にいっており,量の上では半分を占める階級1~6の世帯には,全富量のたった15%しか行き届いていません(右欄の累積相対度数を参照)。さて,ジニ係数を出すには,ローレンツ曲線を描くのでしたよね。横軸に世帯数,縦軸に富量の累積相対度数をとった座標上に,10の階級をプロットし,それらを結んでできる曲線です。この曲線の底が深いほど,世帯数と富量の分布のズレが大きいこと,すなわち収入格差が大きいことになります。上図は,ブラジルのローレンツ曲線です。比較の対象として,北欧のフィンランドのものも描いてみました。ブラジルでは,曲線の底が深くなっています。フィンランドでは,曲線に深みがほとんどなく,対角線と近接する形になっています。このことの意味はお分かりですね。ジニ係数は,対角線とローレンツ曲線で囲まれた面積を2倍した値です。上図の色つき部分を2倍することになります。計算方法の仔細は,昨年の7月11日の記事をご覧ください。算出されたジニ係数は,ブラジルは0.532,フィンランドは0.189なり。0.532といったら明らかに危険水準です。いつ暴動が起きてもおかしくない状態です。現にブラジルでは,凶悪犯罪が日常的に起きています。一方のフィンランドは,平等度がかなり高い社会です。それでは,上記のILOサイトから計算した43か国のジニ係数をご覧に入れましょう。統計の年次は国によって違いますが,ほとんどが2002~2003年近辺のものです。なお,日本のデータは使用不可となっていたので,日本は,冒頭で紹介した0.336(2010年)を用いることとします。わが国を含めた44か国のジニ係数を高い順に並べると,下図のようです。最も高いのはブラジルかと思いきや,上がいました。アフリカ南部のボツワナです。殺人や強姦の発生率が世界でトップレベルの南アフリカに隣接する国です。この国の治安も悪そうだなあ。ほか,ジニ係数が0.4(危険水準)を超える社会には,フィリピンやメキシコなどの途上国が含まれる一方で,アメリカやシンガポールといった先進国も顔をのぞかせています。ジニ係数が低いのは,旧ソ連の国(ベラルーシ,アゼルバイジャン)のほか,東欧や北欧の国であるようです。社会主義の伝統が濃い国も多く名を連ねています。わが国は,44か国中23位でちょうど真ん中です。社会内部の格差の規模は,国際的にみたら中くらいです。お隣の韓国がすぐ上に位置しています。かつてのK首相がよく口にしていたように,格差がない社会というのは考えられませんが,格差があまりに大きくなるのは,決して好ましいことではありません。ジニ係数があまりに高くなると社会が不安定化するといいますが,それを傍証するデータもあります。昨年の6月28日の記事では,世界40か国の殺人率を計算したのですが,このうち,今回ジニ係数を算出できたのは20か国です。この20か国のデータを使って,ジニ係数と殺人率の相関係数を出したら,0.622となりました。ジニ係数が高いほど,つまり社会的な格差が大きい国ほど,殺人のような凶悪犯罪の発生率が高い傾向です。日本社会のジニ係数の現在値(0.336)は,そう高いものとは判断されません。しかし,今後どうなっていくのか。前回みた大学教員社会のように,ジニ係数が高騰している小社会も見受けられます。わが国の前途に不安を抱かせる統計は,結構あるのです。 <補助金を減らして税収と税外収入を増やす方法> *4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220103&ng=DGKKZO78896630S2A100C2MM8000 (日経新聞 2022.1.3) 再生エネ普及へ送電網 2兆円超投資へ、新戦略明記 首相、脱炭素を柱に 政府は再生可能エネルギーの普及のために次世代送電網を整備すると打ち出す。都市部の大消費地に再生エネを送る大容量の送電網をつくる。岸田文雄首相は2022年6月に初めて策定する「クリーンエネルギー戦略で示すよう指示した。総額2兆円超の投資計画を想定する。政権をあげて取り組むと明示して民間の参入を促す。日本は大手電力会社が各地域で独占的に事業を手掛けてきた。送配電網も地域単位で地域間の電力を融通する「連系線」と呼ぶ送電網が弱い。再生エネの主力となる洋上風力は拠点が地方に多く、発電量の変動も大きい。発電能力を増強するだけでなく消費地に大容量で送るインフラが必要だ。国境を越えた送電網を整備した欧州と比べて日本が出遅れる一因との指摘がある。(1)北海道と東北・東京を結ぶ送電網の新設(2)九州と中国の増強(3)北陸と関西・中部の増強――を優先して整備する。(1)は30年度を目標に北海道と本州を数百キロメートルの海底送電線でつなぐ。平日昼間に北海道から東北に送れる電力量はいま最大90万キロワット。北海道から東京までを4倍の同400万キロワットにする。30年時点の北海道の洋上風力発電の目標(124万~205万キロワット)の2~3倍にあたる。九州から中国は倍増の同560万キロワットにする。10~15年で整備する。送電網を火力発電が優先的に使う規制を見直し、再生エネへの割り当てを増やす。送電方式では欧州が採用する「直流」を検討する。現行の「交流」より遠くまで無駄なく送電できる。新規の技術や設備が必要になり、巨大市場が生まれる可能性がある。一方で国が本気で推進するか不透明なら企業は参入に二の足を踏む。菅義偉前首相は温暖化ガス排出量の実質ゼロ目標などを表明し、再生エネをけん引した。岸田氏も夏の参院選前に「自身が指示した看板政策」として発表し、政権の公約にする。国の後押しを約束すれば企業も投資を決断しやすい。電気事業者の関連機関の試算では投資は総額2兆円超になる。主に送配電網の利用業者が負担する。必要額は維持・運用の費用に利益分を加えて算定する。欧州と同様、コスト削減分を利益にできる制度も導入して経営努力を求めながら送電網を整える。英独やスペインは再生エネの割合が日本の倍の4割前後に上る。欧州連合(EU)は復興基金を使って送電網に投資し、米国は電力に650億ドル(7.4兆円)を投じる。 *4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220105&ng=DGKKZO78941430U2A100C2EP0000 (日経新聞 2022.1.5) 排出ゼロへモデル地域 環境省募集、再生エネ導入支援 環境省は25日から、脱炭素に集中的に取り組む自治体を募集する。2030年度までに電力消費に伴う二酸化炭素(CO2)排出量を実質ゼロにする先行地域としてまず20~30カ所選ぶ。国が再生可能エネルギー設備の導入などを支援し、環境配慮の街づくりの成功モデルを育てる。22年度に新設する交付金を活用する。都道府県や市区町村に再生エネの導入や省エネの計画を申請してもらう。複数の自治体による応募、企業や大学との共同提案も認める。住宅街、オフィス街、農村、離島など多様な地域を想定する。それぞれの特性によって脱炭素の効果的な手法は変わる可能性がある。再生エネ事業による雇用増や住民サービスの向上といった様々な成功事例を示し、地域発の脱炭素の取り組みを全国に広げる。 *4-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220105&ng=DGKKZO78941450U2A100C2EP0000 (日経新聞 2022.1.5) 農家の環境配慮後押し 農機・建物で税負担軽減 農水省 農林水産省は環境に配慮する農家や食品事業者への支援策を拡充する。化学農薬を低減できる農業機械を導入する生産者らの所得税や法人税の負担を軽くする。食品事業者などの中小企業が建物を整備する場合も対象とする。1月召集の通常国会に新制度の裏づけとなる新法案の提出をめざす。農水省がまとめた農業分野の環境保全指針「みどりの食料システム戦略」に基づく取り組みとなる。税の優遇を受ける生産者は都道府県から、新技術を提供する機械・資材メーカーや食品事業者は国からそれぞれ認定を受ける。環境負荷を軽減できる機械や建物について整備初年度の損金算入を増やせるようにして、所得税や法人税を軽くする。機械は32%、建物は16%の特別償却を認める。化学農薬や化学肥料を使うかわりに、たい肥を散布する機械や除草機を導入する生産者などを対象にする。化学農薬に代わる資材を生産するメーカーや、残飯をたい肥にする機械を導入する食品メーカーなども支援先として想定する。 *4-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220105&ng=DGKKZO78939130U2A100C2TB1000 (日経新聞 2022.1.5)日通が中型EVトラック 引っ越し業務で導入 日本通運は2022年度から中型の電気トラックを導入する。三菱ふそうトラック・バス製で最大積載量は4トン以上。まず関東や関西エリアの引っ越し業務で取り入れ、供給網全体の環境負荷を減らす。脱炭素化には小型車だけでなく、積載量が多い中型車以上の電動化が世界で課題となっている。三菱ふそう製の商用電気自動車(EV)「eキャンター」をまず10台導入する。最大積載量は4125キログラムで1回充電あたりの航続距離は100キロメートル。契約価格は明らかにしていないが、1000万円前後とみられる。現在、各社が導入している電気トラックは積載量が1~3トンの小型だ。積載量が大きい中型での導入は国内物流大手では珍しい。ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸も17年からeキャンターを25台導入しているが、3トンタイプの小型にとどまる。まず関東や関西などの支店に導入する。航続距離は小型電気トラック(300キロメートル)よりも短いため、貨物輸送ではなく引っ越し業務で運用する。導入拠点には充電設備を設ける。物流業界ではSBSホールディングスが21年10月、協力会社と合わせて中国企業などから小型EV1万台を調達すると発表。佐川急便も保有する軽自動車7200台を30年までにEVに切り替える。日本郵便も導入を急ぐ。各社が導入するEVは最大積載量1~3トンの小型トラックの中でも1~2トン以下が中心だ。4トン以上の中型は量産できる企業が限られる。バッテリーの小型軽量化が進んでいないためだ。日通は企業向けの物流が主力で、保有するトラックの7割近くが中型のトラックや大型トレーラーのため電動化が遅れていた。eキャンターを導入し、運用コストなどを確認した上で運用台数を拡大する考え。日通は二酸化炭素(CO2)の排出量について23年度までに13年度比30%削減する目標を掲げているが、同社幹部は「EVだけではなく、あらゆる方法を検討する」と話しており、燃料電池車(FCV)の開発状況も注視する。物流業界に脱炭素を求める動きは世界で強まっている。欧州連合(EU)は30年までに商用車のCO2排出量を19年比で3割削減するよう求めている。米カリフォルニア州も州内で販売する全てのトラックを45年までにEVやFCVにする規制を導入した。国内でも政府は企業の温暖化ガス排出量の報告内容を見直す考え。従来は企業単位での公表が原則だったが、今後は企業が持つ事業所ごとや企業グループの供給網全体の排出量も任意で報告を求める意向を示している。 *4-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220103&ng=DGKKZO78896670S2A100C2MM8000 (日経新聞 2022.1.3) 原発は「脱炭素に貢献」 欧州委が認定方針 関連投資促す 欧州連合(EU)の欧州委員会は1日、原子力と天然ガスを脱炭素に貢献するエネルギーと位置づける方針を発表した。一定の条件下なら両エネルギーを「持続可能」と分類し、マネーを呼び込みやすくする。世界の原子力政策にも影響を与える可能性がある。欧州委は環境面から持続可能性のある事業かどうか仕分ける制度「EUタクソノミー(分類法)」を設けており、これに原子力やガスを追加する。「2050年までに域内の温暖化ガスの排出を実質ゼロにする」とのEU目標に貢献する経済活動と認めることで、資金調達をしやすくする。原子力依存度の高いフランスや石炭に頼る東欧諸国が、原子力やガスは脱炭素に資すると認めるよう訴えていた。欧州委は1月中にも案を公表する考え。加盟各国の議論や欧州議会の審議を経て成立する流れだが、脱原発を決めたドイツなどが反対する可能性もある。原子力発電は稼働中に二酸化炭素(CO2)を排出しないが、有害な放射性廃棄物が出る。天然ガスは石炭に比べクリーンだがCO2を出す。ただ欧州委は1日の発表文で未来へのエネルギー移行を促進する手段に「天然ガスと原子力の役割がある」とし、両エネルギーを持続可能と位置づける考えをにじませた。日本経済新聞が入手した原案によると、原子力は生物多様性や水資源など環境に重大な害を及ぼさないのを条件に、2045年までに建設許可が出た発電所を持続可能と分類する方針を示した。 *4-6:https://wired.jp/2021/12/31/5-most-read-stories-membership-2021/ (Wired 2021/12/31) 高まる宇宙開発への関心と、激化する全固体電池の開発競争:SZ MEMBERSHIPで最も読まれた5記事(2021年) 『WIRED』日本版の会員サーヴィス「SZ MEMBERSHIP」では、2021年もインサイト(洞察)が詰まった選りすぐりのロングリード(長編記事)を週替わりのテーマに合わせてお届けしてきた。そのなかから、国際宇宙ステーションで発見された新種のバクテリアの正体や、全固体電池の実用化を見据えたブレイクスルーなど、21年に最も読まれた5本のストーリーを紹介する。2021年は宇宙への世間の関心が一段と高まった1年だった。なかでも国際宇宙ステーション(ISS)の内部で採取された新種のバクテリアは、「未知の生命体」として取り沙汰された。しかし、新種といっても遺伝的にはメチロバクテリウムという地球にありふれた属に由来するバクテリアで、貨物や宇宙飛行士の身体に付着して入ってきたものが宇宙ステーションの環境に適応するために変異したものとみられている。それでも今後、宇宙空間や地球外の惑星で進化する契機となる可能性は十分に考えられる。こうした微生物叢は、ISSでの生活で一部の免疫反応が抑制されたクルーにとって予期せぬ体調不良の要因になりうる一方で、火星のような地球外の環境に存在するかもしれない生命体との接触を検知するために有効な手段にもなりうるという。また、メチロバクテリウムは土壌の窒素分子をアンモニアや硝酸塩、二酸化窒素といった窒素化合物に変換してくれることから、宇宙環境に適応した今回のような微生物叢は、将来的に月面や火星での食料栽培に役立つ可能性も期待できる。 ●全固体電池の商用化に王手 電気自動車(EV)の発展と普及に伴い、より高いエネルギー密度と安全性、長寿命が期待できる全固体電池の研究開発が活発化している。リチウムイオン電池を搭載したEVの共通の課題は、500kmに満たない航続距離と1時間以上を要する充電時間、そして可燃性の液体電解質がもたらす安全面のリスクだ。こうした問題に対する解決策として、電極間に固体の電解質を用いた固体電池技術の研究が進められてきたが、いまだ実用化にはいたっていない。そうしたなか、20年12月に米国のスタートアップのクアンタムスケープが公開したテスト結果は、長きにわたって実用化を阻んできた障壁を一気に打ち砕くような内容だった。ブレイクスルーの鍵を握るのが、正極と負極を隔離するセパレーターの素材である。これまでは主にポリマーかセラミックが使われてきたが、ポリマーではデンドライトの形成を防ぐことができず、セラミックでは充電サイクルにおける耐久性に難があった。クアンタムスケープが新たに開発した柔軟性に優れたセラミック素材のセパレーターは、その両方をクリアしている。一方、同社が公表したのはあくまでセル単位の性能データであり、それらを大量に積み重ねた最終的なバッテリーの性能には疑問が残るという指摘もある。いずれにせよ、クアンタムスケープが全固体電池の商用化に大きく近づいた事実が、開発競争の新たな起爆剤になったことは間違いない。(以下略) *4-7:https://www.jst.go.jp/pr/info/info708/index.html(科学技術振興機構報第708号 平成22年1月22日)粘菌の輸送ネットワークから都市構造の設計理論を構築―都市間を結ぶ最適な道路・鉄道網の法則確立に期待― <東京都千代田区四番町5番地3 科学技術振興機構(JST) Tel:03-5214-8404(広報ポータル部) URL https://www.jst.go.jp> JST目的基礎研究事業の一環として、JSTさきがけ研究者の手老 篤史 研究員らは、単細胞生物注1)の真正粘菌注2)が形成する餌の輸送ネットワークを理論的に解明し、都市を結ぶ実際の鉄道網よりも経済性の高いネットワークを形成する理論モデルの構築に成功しました。本研究の成果であるネットワーク形成に関する理論は、近年ますます複雑化するネットワーク社会において、経済性および災害リスクなどの観点から最適な都市間ネットワークを設計する手法の確立につながるものです。真正粘菌は、何億年もの長きにわたって厳しい自然淘汰を乗り越えて生存し続けています。このため、さまざまな機能をバランスよく保ち、変化する環境にも柔軟に対応することが知られています。すなわち、頻繁に使用される器官は増強され、使用されていない器官は退化しています。これは、人間が作る都市間ネットワークの思想と共通する部分が多いといえます。粘菌のこのような知的な挙動に関しては、すでに手老研究員らから発表され、2008年度のイグ・ノーベル賞を受賞しています。しかし、脳も神経もない粘菌が知的なネットワークを形成するメカニズムについては理論的な解明がなされておらず、生物学上の謎の1つとなっていました。今回、真正粘菌変形体が作る輸送ネットワークを実験・理論の両面から解析し、数理科学的にネットワークを再現する理論モデルを構築しました。これにより、粘菌の作るネットワークによる物質輸送は、実際の鉄道ネットワークより輸送効率が良いことや、アクシデントに強いことが分かりました。今後、都市間を結ぶ道路・鉄道・インターネットなどによる物流・情報ネットワークの整備にあたり、建設・維持コストや災害リスク管理など、さまざまな要件を目的に応じて重視した際に、本研究により構築した理論モデルの適応により最適なネットワークを提示する設計法則の確立が期待されます。本研究は、北海道大学電子科学研究所の中垣 俊之 准教授、広島大学 大学院理学研究科の小林 亮 教授らと共同で行われ、本研究成果は、2010年1月22日(米国東部時間)発行の米国科学雑誌「Science」に掲載されます。(以下略) <男女平等が生む創造性> PS(2022年1月10日追加):アイスランドは、*5-1のように、①2008年のリーマン・ショックで財政破綻の危機に陥り ②「男性中心の経営が法令順守の意識を欠如させた」と分析して ③女性を積極登用する社会に転換し ④2009年に初の女性首相が誕生し ⑤企業などにも女性役員比率を4割以上にするように求め ⑥2011年以降、新型コロナ禍前までGDP成長率は平均3.5%に高まり ⑦2009年の「ジェンダーギャップ指数」でトップになって ⑧それ以後12年連続でその地位を維持し ⑨女性の労働参加率(15~64歳)は2020年時点80.7%と高く ⑩2017年に、世界で初めて企業に男女同一賃金を証明するよう義務付け、違反には罰金を科したそうで、まさに見本となる男女平等の実現を実行している。 私には、①②が男性特有の性格かどうかは不明だが、③のように女性を積極登用する社会に転換してすぐ、④のように「女性首相が誕生」し、⑥のように「GDP成長率が高まった」のは、もともと女性が教育や雇用の場において、日本ほど差別されずに知識や経験を積んでいたからだと思う。その結果、④⑤⑨⑩により、⑦⑧の結果が出ているのだろう。 私も、イケアのような最終消費者と相対する企業に女性が増えると、より多くのアイデアやデザインが生まれると実感している。反対に日本のような男性中心の国の産業は、素材・部品のように、どこかで規格された中間財を生産するには支障がないが、最終財を作るにはアイデアとデザイン力が乏しく、これは他国の製品と比較すればすぐわかることである。その理由は、日本政策投資銀行の指摘のとおり、⑪女性が加わることで多様性が高まって発想が豊かになり ⑫男性も刺激を受けてより成果を出そうとし ⑬特許資産の経済効果が男女混合チームは男性だけのチームと比較いて1.54倍に上る からだろう。そして、この最終消費者向けの発想力の源となる多様性は、女性だけでなく高齢者や外国人も含む。 それでは、「何故、最終消費者と相対する企業に女性が増えると、より多くのアイデアやデザインが生まれ、特許資産の経済効果が混合チームは男性チームの1.54倍に上るのか?」と言えば、*5-2のように、女性は男性の1.9倍の家事・育児をし、最終消費者として購買し、家族のために加工を担当しているからである(これは、同じ仕事を繰り返すよりもずっと難しく、一つ一つを計画的に解決することが必要で、やった振りをしても無意味な仕事なのだ 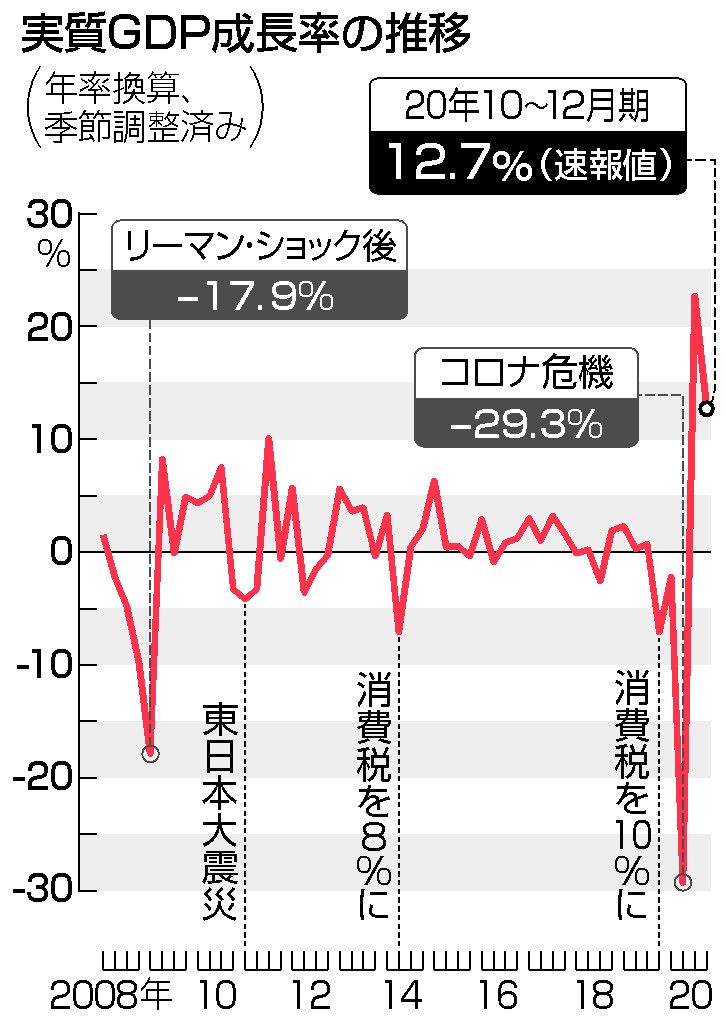 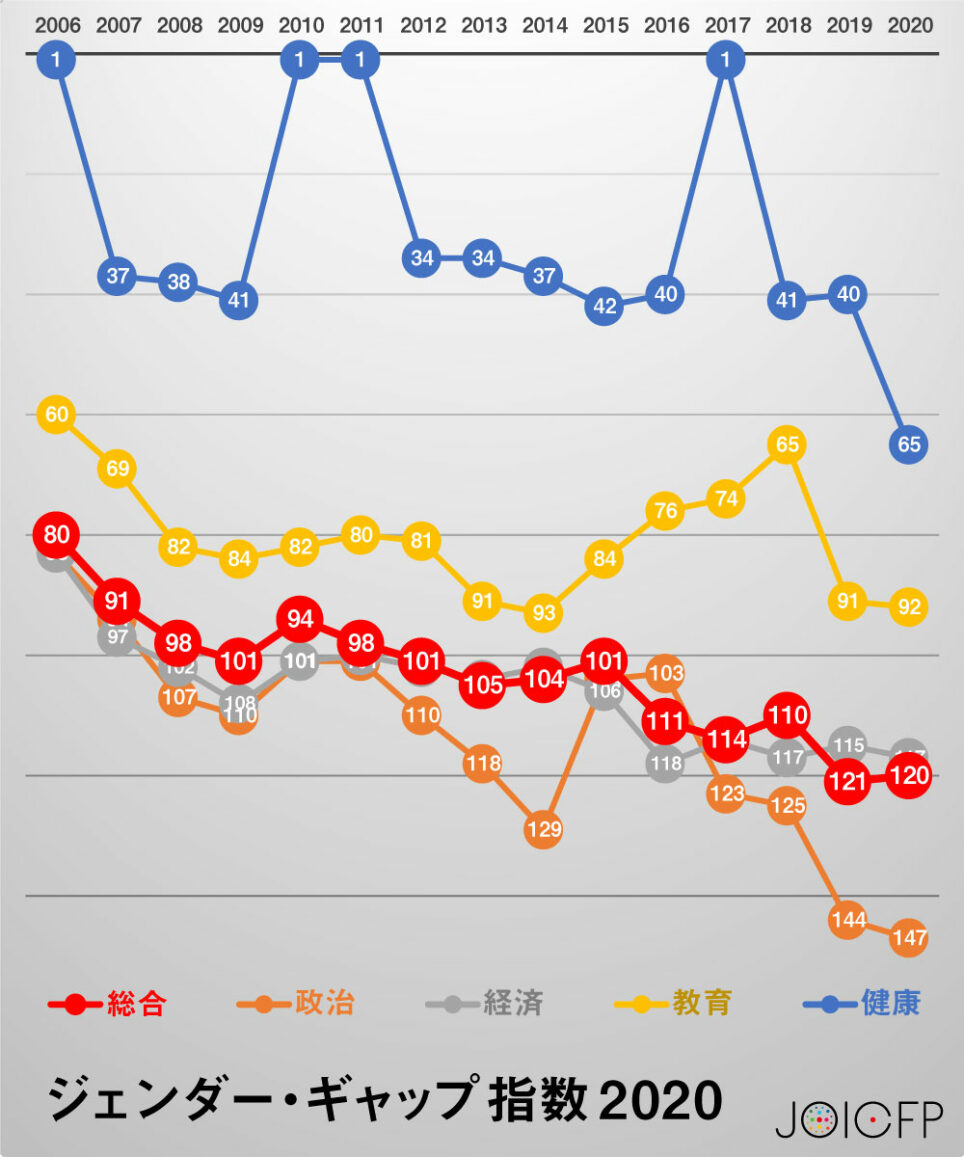   2021.2.15時事 COICFP 2021.3.31Yahoo 2021.5.28日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、日本の実質GDP成長率は、ものすごい歳出超過とインフレ政策にもかかわらず、長期間にわたって0近傍だ。また、左から2番目の図のように、ジェンダーギャップ指数も健康以外は超低空飛行が続いており、右から2番目の図のように、2020年時点で総合が156ヶ国中120位だ。さらに、最終需要者に高齢者の割合が増加しても高齢者を雇用から排除したがる傾向があり、1番右の図のように、外国人難民や移民にも極めて冷たい。しかし、これら多様性のなさが、経済の低迷に繋がっていることは明らかなのである) *5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220109&ng=DGKKZO79079580Z00C22A1MM8000 (日経新聞 2022.1.9) 成長の未来図(8)アイスランド、09年の大転換 男女平等が生む活力 北欧の島国アイスランドは2008年、リーマン・ショックの際、危険な投資にのめり込んだツケが回り、財政が破綻する危機に陥った。なぜ危機を招いたのか。男性中心の経営がコンプライアンス(法令順守)の意識を欠如させた――。政府はこう分析し、女性を積極的に登用する社会へと転換を図った。09年に初の女性首相が誕生。企業などに女性役員比率を4割以上にするよう求めた。11年以降、新型コロナウイルス禍前までの実質国内総生産(GDP)の成長率は平均で3.5%に高まった。 ●労働参加8割超 アイスランドは09年、男女平等の度合いをランキングにした「ジェンダーギャップ指数」でトップに躍り出る。以来、12年連続でその地位を維持し、女性の労働参加率(15~64歳)も80.7%(20年時点)と高い。人口約36万人の小国は手を緩めていない。男女の賃金格差の解消だ。17年に41歳で就任したカトリン・ヤコブスドッティル首相は18年、賃金に性別で差が出ることを禁止する法律を定めた。世界で初めて企業に男女の同一賃金を証明するよう義務付け、違反があれば罰金を科す。女性活躍を後押しするビジネスも沸き立つ。「男女の賃金差をリアルタイムで把握する」。同国のスタートアップ「PayAnalytics」にイケアやボーダフォン・グループなど世界の有力企業から注文が相次ぐ。学歴や評価、役割などの項目を入力すれば人工知能(AI)が適正賃金や男女差を導き出すソフトウエアで、各企業は瞬時に「解」を得られるようになった。創業者のマーグレット・ビャルナドッティル氏は「意識だけでは変わらず、データの分析が必要だ。格差を解消できれば、優秀な人材が集まる」と強調する。顧客の電力会社は約10年前に8.4%あった男女の賃金差を0.03%に縮小させ、能力のある女性技術者の採用が増えた。日本は21年のジェンダーギャップ指数が156カ国中120位と先進国で最下位だ。賃金格差は22.5%に及び、経済協力開発機構(OECD)平均(12.5%)より大きい。児童手当や保育サービスなど家族関係の公的支出も見劣りする。女性活躍を掲げながら17年のGDP比は1.6%とOECD平均(2.1%)より低い。アイスランドは3.3%と高い。時間あたりの労働生産性とジェンダーギャップ指数を交差させると、日本は韓国とともに低さが際立つ。女性が能力を発揮できる環境が整っておらず、非正規雇用が5割以上と高いこともあってなかなか上がらない。スウェーデンのウプサラ大、奥山陽子助教授(労働経済学)は「北欧のように女性の視点をビジネスの現場に取り入れなければ、日本は再浮上できない」と訴える。特に創造性の高い研究開発分野での活躍を見込む。その見立てを裏付けるデータもある。 ●発明価値1.54倍 日本政策投資銀行は18年、国内の製造業約400社が過去25年間に得た約100万件の特許を調査。企業の時価総額や論文の引用件数などから算出した特許資産の経済効果は男女混合チームの方が男性だけの場合と比べ1.54倍に上った。同行は「女性が加わることで多様性が高まり発想力が豊かになる。男性も刺激を受けてより成果を出そうとする」と指摘する。男女平等を成長の原動力にする国が目立つ中、日本は女性を生かす社会を描けていない。賃金格差、子育て、積極的な登用などの課題に本気で向き合わなければ成長へのきっかけはつかめない。国や企業は変わる勇気を示せるか。覚悟が問われる。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?R_FLG=1&b=20220109&be=NDSKDBDGKKZO・・ (日経新聞 2021.5.17) 男女格差解消のために 男性を家庭に返そう 東京大学教授 山口慎太郎 世界経済フォーラムが3月に発表した「ジェンダーギャップ指数」によると、経済分野における日本の男女格差はきわめて大きい。世界156カ国中の117位である。しかし、それ以上に大きいのは家庭内における男女格差だろう。経済協力開発機構(OECD)平均では、女性は男性の1.9倍の家事・育児などの無償労働をしている。日本ではこの格差が5.5倍にも上り、先進国では最大だ。これは日本において性別役割分業が非常に強いことを示している。経済・労働市場での男女格差と、家庭での男女格差は表裏一体なのだ。ワークライフバランスの問題を解決するために、育児休業や短時間勤務などが法制化されてきた。こうした制度は確かに有効だ。2019年における25~54歳の女性労働力参加率をみると日本は80%と高い。米国の76%やOECD平均の74%を上回っている。しかしこうした施策には限界もある。「子育ては母親がするもの」との固定観念がある中では、結局のところ女性が負う子育てと家事の責任や負担が減るわけではない。そのため、女性が職場で大きな責任を担うことは難しいままだ。実際、日本では管理職に占める女性の割合は15%にすぎず、米国の41%やOECD平均の33%を大きく下回る。限界を打ち破る上で有効なもののひとつは、男性を対象とした仕事と子育ての両立支援策だ。男性を家庭に返すことが、女性の労働市場での活躍につながる。その第一歩は男性の育休取得促進である。日本の育休制度は国際的な基準に照らしても充実しているが、強化の余地はある。たとえば最初の1~2カ月限定で育児休業給付金の額を引き上げ、育休中の手取りが減らないようにすべきだ。1カ月程度の育休で何が変わるのかと思うかもしれない。しかし、カナダのケベック州の育休改革を分析した研究によると、男性が5週間ほど育休を取ると、3年後の家事時間と子育て時間がいずれも2割程度増えた。育休取得をきっかけとして家族と仕事に対する価値観が変化し、そのライフスタイルの変化はその後も長く続いた。たかが1カ月。だが男性の育休は、人生を変える1カ月になりうるのだ。 <日本における再エネ出遅れの理由は、リーダーの非科学性・非合理性である> PS(2022年1月14、15日追加): *6-1-1のように、脱炭素社会実現に向け、地熱発電所が2022年以降に続々と稼働するのはよいことだ。日本は火山国で地熱資源は世界第3位と豊富なのに、「日本は資源のない国」という“空気”や“潮流”の下、これまでは地熱開発があまり行われなかった。しかし、地球温暖化対策としての脱炭素は1990年代から指摘されており、排気ガスを出さず、安全で、変動費無料(=コストが安い)であり、日本のエネルギー自給率向上にも資するのが、再エネ発電と電動の組み合わせであることは、ずっと前から明らかだった。にもかかわらず、化石燃料と原子力にかじりついて構造改革を進めなかったのは、日本の“リーダー”の非科学性・非合理性によるものである。 しかし、この非科学性が理系人材の能力不足ではなく、意思決定する立場に多い文系人材の能力不足であることは、*6-1-2のように、その気になれば送電損失0の超電導送電をすぐ実用化できるのに、例の如く「課題はコスト(コストは普及すれば下がる)」などとして使用しない意思決定をしてきたことで明らかだ。この優先順位に関する意思決定の誤りが、日本で多くの有用な技術を産業化できずに他国に譲ってきた理由なのである。 また、太陽光発電も年々進歩し、現在では、*6-1-3・*6-1-4のように、無色透明な「発電ガラス」の販売が、NTTアドバンステクノロジ・日本板硝子・旭硝子などから開始されている。そのため、都会のビルやマンションも改修して無色透明や一定の色の「発電ガラス」を取り付けるように補助すれば、再エネでエネルギー自給率を高めつつ、同時に日本のこれから有望な高付加価値産業を伸ばすことができるのだ さらに、*6-2-1のように、全農も2030年には「持続可能な農業と食の提供のため、なくてはならない全農であり続ける」としているので、効率的に太陽光発電して作物の生育には影響を与えないか、むしろプラスになる「発電ガラス」「発電シート」「建物一体型太陽光発電」などを使うハウス・倉庫・畜舎や地域エネルギーで動く電動車・電動機械に補助して普及を促せば効果が大きいだろう。イオンモールも、*6-2-2のように、国内約160カ所全ての大型商業施設で、「非化石証書」を使わず自前の太陽光パネルとメガソーラーからの全量買い取りを組み合わせて、2040年度までに使用電力の全量を再エネに切り替えるそうなので、これも、なるべく2030年までに前倒しするとよい。そして、イオンモールの駐車場に速やかに充電できる充電施設を設ければ、販売する商品に電力を加えることも可能なのである。 なお、VWの日本法人は、2022年1月13日、*6-4のように、2022年末時点で国内の販売店約250店舗にEVの急速充電器を設置する方針を明らかにしている。この時、①150kwの場合、販売店の設置費用は1基2千万円ほどかかる ②高いから充電器は置けない ③環境と経済は対立するものである などとしてきたのが文系意思決定権者の誤りであり、この発想がすべてを遅らせてきたのである。 このように、民間企業の意識は高まっているのに、日本の経産省は、*6-3のように、またもや東南アジア脱炭素支援と称してアンモニア(NH₃)や水素(H₂)を活用する技術協力を進めるそうだ。再エネ電力で水を電気分解すればできるので水素はよいが、アンモニアは原料の天然ガスから製造する過程でCO₂を排出し、そのCO₂を回収・処理しなければ温暖化対策にならないため、コストが高くなる。従って最適解にならないことは明らかで、インドネシア・シンガポール・タイはしぶしぶ同意したにすぎないだろう。そのため、その国に適した再エネ技術で協力した方が喜ばれ、日本の評判を下げずにすむのだ。 再エネ発電による電力をためる大型蓄電池の開発も(本気でやらなかったため)日本は遅れ、*6-5のように、中国ファーウェイや米国テスラの日本への参入が相次いでおり、日本勢は日本ガイシや住友電工等が大型蓄電池を製造しているが、販売価格で競争力がないそうだ。蓄電池も日本が最初に開発を始めたのにこうなってしまったのであるため、何故そうなるのかが改善すべき最も重要な問題である。    2021.12.24 2021.5.21Optronics 2021.9.2家電 2021.3.23Karapaia 日経新聞 (図の説明:1番左と左から2番目の図のように、地熱発電は天候に左右されないという意味で安定的な電源と言えるが、他の再エネも蓄電池に貯めたり、水素にして貯めたりすることによって、安定電源にできる。また、中央と右から2番目の図のように、透明な太陽光発電機ができたことにより、ビルや住宅の窓・壁面でも発電することができるようになった。さらに、1番右の図のように、農業用ハウスに使うことによって、作物の生育に影響を与えず、むしろ生育を促しながら発電し、発電した電力を利用することも可能である) *6-1-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC158360V11C21A2000000/ (日経新聞、日経産業新聞 2021年12月24日) 生かせるか「地熱」の潜在力 出光など22年に続々稼働 地熱発電所が2022年以降、続々と稼働する。脱炭素社会の実現に向け、地熱が持つ潜在力が必要とされているためだ。太陽光や風力のように発電量が天候に左右されない安定性が魅力で、出光興産やINPEX、オリックスといった大手企業が大型発電所を開業する。資源量が世界3位の日本だが、現状の導入量は火力発電所1基分とわずかだ。脱炭素の潮流が、企業の地熱開発を駆り立てている。 ●脱炭素で熱帯びる 12月上旬、JR盛岡駅から高速道路を経由して1時間。細くうねる山道を抜けると、高さ46メートルの巨大な冷却塔から蒸気がもくもくと噴き出していた。雪景色と共に温泉街特有の硫黄の香りが漂う。東北電力グループが運用する松川地熱発電所(岩手県八幡平市)は最大出力2万3500キロワット。1966年に国内では初めて、世界でも4番目に稼働した今も現役の地熱発電所だ。松川発電所は8本の蒸気井と呼ぶ地下に掘った井戸から300度近い蒸気を取り出し、タービンを回して発電する。最も深い井戸は深度1600メートル。もともとは1950年代に自治体が温泉開業を狙って始めた地熱開発を、発電向けに転換したのが始まりだ。発電に使った後の蒸気は自然の風を使って冷却塔内で冷やされ、冷水は発電所内で再利用される仕組みだ。運営を担う東北自然エネルギーの加藤修所長は「昼夜ほぼ一定の出力で発電するのが地熱発電の最大の強み」と話す。世界的な脱炭素の潮流が、地熱開発を再び呼び起こした。政府の50年カーボンニュートラル宣言以降、地熱発電の開発を本格化しようとする動きが目立つ。政府は6月に改定した「グリーン成長戦略」で、地熱産業を成長分野として育成する方針を公表した。国が地熱を成長分野として位置づけたのはこれが初めてだ。国内に60カ所弱ある地熱発電施設を30年までに倍増する方針も示された。地熱発電の適地は北海道、東北、九州に分布するが、このうち国立公園が多い北海道では今まで開発が十分に進んでこなかった経緯がある。だが国の委員会で21年9月、自然公園法の行政向け通知を変更し、国立・国定公園の第2種・第3種特別地域での地熱開発を「原則認めない」とする記載を削除する方針を決定した。この規制緩和により自然への配慮は前提となるが、開発に着手しやすくなった。さらに従来は熱水を取り出す井戸ごとに申請が必要だった地熱開発のガイドラインも改定し、熱水・蒸気がある地熱貯留層を1つの事業者が管理できるようになった。石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の安川香澄・特命審議役は「複数の事業者が同じ貯留層を奪い合い、開発が進まなくなる事態を防げるようになった」と語る。 ●「塩漬け」に転機 相次ぐ規制緩和の流れを受けて企業の開発意欲も高まっている。オリックスは22年、出力6500キロワットの南茅部地熱発電所(仮称)を北海道函館市で稼働させる。水より低い沸点の媒体を蒸気化してタービンを回す「バイナリー方式」と呼ばれる地熱発電方式では国内最大規模だ。出光興産とINPEX、三井石油開発も22年に秋田県湯沢市で地熱発電所を着工する。出力は1万4900キロワットで、25年にも運転を始める。INPEXはインドネシアで地熱事業に参画しており、資源開発で培った掘削のノウハウも生かして国内での開発に備える。レノバも熊本県や北海道函館市で地熱発電の開発を進めている。地熱発電の設備稼働率は7割以上を誇る。同じ再エネでも太陽光発電や風力発電の1~3割程度と比べて安定性は抜群だ。松川地熱発電所では一般家庭5万世帯分もの電気をまかなえる規模だ。それでも国内で地熱開発がなかなか進んでこなかったのは、油田と同じで掘ってみないと正確な資源量が分からないことがあった。日本の場合、掘削の成功率は3割程度とされ、1本掘削するのに5億円以上かかる井戸を何本も掘る必要がある。環境影響評価から稼働までにかかる時間も15年程度と長く、資本力がない企業では手が出ない。地熱資源量は火山地帯と重なる。日本の資源量は2340万キロワット分と見積もられ、首位の米国やインドネシアに次いで世界で3番目。ただ実際の導入量は計55万キロワット程度と10年前からほぼ横ばいだ。国際エネルギー機関(IEA)によると地熱導入量は世界で10番目にとどまる。一度は機運が高まった地熱発電は、原子力発電所の推進政策に押され、「塩漬けの20年」と呼ばれるほど勢いを失った。脱炭素の潮流が呼び水となり、再び脚光を浴びる今が普及のラストチャンスだ。 ●潮目変わり再び熱帯びる 一度は勢いを失った地熱発電だが、潮目が変わったのは11年の東京電力福島第1原発事故だ。原発の安全神話が崩れ、全基の稼働が止まった。12年の固定価格買い取り制度(FIT)の導入もあって地熱開発に向けた調査が再び増えた。19年1月にはJFEエンジニアリングなどが松尾八幡平地熱発電所(岩手県八幡平市、出力7499キロワット)を稼働した。同年5月にはJパワーなどが山葵沢(わさびざわ)地熱発電所(秋田県湯沢市、4万6199キロワット)の運転を始めて、再び地熱発電が注目された。山葵沢発電所は15年に着工し、現在の設備稼働率は9割程度と稼働状態も良好だ。Jパワー再生可能エネルギー事業戦略部の井川太・企画管理室長は「周辺は既に地熱発電所がある地域だったため、地元との調整もスムーズだった」と振り返る。地熱発電の開発には必ずと言っていいほど、観光事業者や温泉事業者からの反発が出る。これまで地熱発電によって実際に温泉の湯量や泉質に影響した事例はほぼないものの、地域の理解がなかなか得られなかった。地域の理解を醸成するため、近年は地熱発電を通じた地域貢献を進める動きも活発だ。北海道森町では北海道電力の森地熱発電所で発電に使った熱水をパイプラインで市街地に運び、野菜ハウスの暖房に使う取り組みが進む。ハウスではキュウリやトマトなどの野菜を栽培している。 ●新技術で発電効率向上も 地熱発電の拡大には技術開発も欠かせない。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などが実用化を目指すのは「超臨界地熱発電」と呼ばれる技術だ。従来より地下深く、マグマに近いところに存在する「超臨界水」を用いる。超臨界水は高い圧力によって沸点が上昇。温度は500度と通常の地熱発電で使う蒸気より高く、発電効率の向上が見込める。ただ、超臨界水は強い酸性の可能性があり、普通の鋼鉄はすぐ腐食してしまう。これに耐えうる素材開発が欠かせない。通常の地熱発電の井戸が深さ1~2キロ程度なのに対し、超臨界水は地下5キロ程度の深さに存在すると考えられるため、どうやってそこまで井戸を掘削し熱水を取り出すかも課題だ。地熱発電に詳しい京都大学の松岡俊文・名誉教授は「現状の地熱開発のスピードでは国が考える地熱開発目標の達成は厳しい」と指摘する。松岡氏は海底の地熱資源に注目する。海底には多くの火山が存在する。松岡氏が長崎県沖から台湾沖にかけての「沖縄トラフ」周辺の地熱貯留層を調査したところ、約70万キロワットの発電能力があることが分かった。国内地熱導入量を上回る規模だ。海底下を掘削して熱を取り出し発電するのは従来の地熱発電と共通するが、陸上と比べて立地制約が少ないのが利点だ。また海底地熱発電は井戸1本で得られる資源量が陸上より多いとみられ、松岡氏によると海底の圧力に耐えられる設備の検証などは必要となるものの、掘削コストは陸上より安く抑えられる可能性があるという。 *6-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220113&ng=DGKKZO79164000T10C22A1MM8000 (日経新聞 2022.1.13) 送電損失ゼロ 実用へ、JR系、超電導低コストで 脱炭素後押し 送電時の損失がほぼゼロの技術「超電導送電」が実用段階に入った。JR系の研究機関がコストを大幅に減らした世界最長級の送電線を開発し、鉄道会社が採用の検討を始めた。欧州や中国でも開発が進む。送電ロスを減らしエネルギーの利用効率を高められれば地球温暖化対策につながる。送電ロスは主に電線の電気抵抗により電気が熱に変わることで起こる。送電線を冷やして超電導(総合2面きょうのことば)状態にすると、電気抵抗がゼロになるため損失をほぼなくせる。課題はコストだ。かつてはセ氏マイナス269度に冷やす必要があったが、マイナス196度でも超電導の状態にできる素材の開発が進み、冷却剤を高価な液体ヘリウムから、1キログラム数百円と1割以下の液体窒素に切り替えられるようになった。超電導送電線の費用の相当部分を占める冷却コストが大きく減ったため実用化が近づいた。JR系の鉄道総合技術研究所(東京都国分寺市)は送電線を覆う形で液体窒素を流し、効率よく送電線を冷やす技術を開発。世界最長級で実用レベルの1.5キロメートルの送電線を宮崎県に設置して実証試験を始めた。鉄道に必要な電圧1500ボルト、電流数百アンペアを流せる。送電線の製造は一部を三井金属エンジニアリングに委託した。通常の送電に比べて冷却コストはかさむが「送電線1本の距離を1キロメートル以上にできれば既存設備を活用でき、送電ロスが減るメリットが費用を上回る」(鉄道総研)。複数の鉄道会社が採用に関心を示しているという。採用されれば、鉄道で超電導送電が実用化されるのは世界初となる。超電導送電はこのほか風力発電など再生可能エネルギー発電分野でも利用が期待されている。電力会社や通信会社などに広がる可能性がある。超電導送電は電圧が下がりにくいため、電圧維持のための変電所を減らせるメリットもある。変電所は都市部では3キロメートルおきに設置し、維持費は1カ所で年2000万円程度とされる。鉄道総研はより長い超電導送電線の開発にも取り組んでおり、実現すればコスト競争力がより高まる。日本エネルギー経済研究所によると国内では約4%の送電ロスが発生している。全国の鉄道会社が電車の運行に使う電力は年間約170億キロワット時。送電ロス4%は、単純計算で一般家庭約16万世帯分に相当する7億キロワット時程度になる。送電ロス削減は海外でも課題だ。鉄道以外も含む全体でインドでは17%に達する。中国では2021年11月、国有の送電会社の国家電網が上海市に1.2キロメートルの超電導送電線を設置した。ドイツでは経済・気候保護省主導で、ミュンヘン市の地下に12キロメートルの超電導送電線を敷設する「スーパーリンク」プロジェクトが20年秋に始まった。日本は超電導送電に使う送電線を昭和電線ホールディングスが手がけるなど素材に強みがある。JR東海のリニア中央新幹線も超電導を使っており、鉄道総研の技術基盤が生かされている。 *6-1-3:https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1347759.html (家電 2021年9月2日) 無色透明なのに太陽光で発電できる「発電ガラス」販売開始 NTTアドバンステクノロジは、inQsが開発した無色透明形光発電素子技術(SQPV:Solar Quartz Photovoltaic)を活用した「無色透明発電ガラス(以下:発電ガラス)」の販売を開始。東京都新宿区の学校法人海城学園に、初めて導入した。発電ガラスは無色透明で、両面からの日射に対して発電できるという。このため、既存温室の内側に設置しても採光や開放感への影響を与えることなく発電が可能。また天窓を含め、さまざまな角度からの日射でも発電できるとする。今回の発電ガラスで採用されたSQPVは、可視光を最大限透過しつつ発電する技術。一般のガラスが使える全ての用途に発電と遮熱という機能をつけて利用できるとする。SQPVを活用した発電ガラスの主な特長は以下のとおり。表面・裏面および斜めの面から入射する太陽光からも発電が可能。天井がガラス張りのガラスハウスなどでは、北面でも天井からの日射があれば発電が可能。このため、どんな場所でも、デザイン性の高い、省エネルギー発電・遮熱ガラス材料としての用途開拓が可能。レアアースなどの希少かつ高価な材料を用いない。海城学園では、新たに建築されたサイエンスセンター(理科館)屋上の温室に、室内側から取り付ける内窓として導入された。今回は、まず約28cm角の発電ガラスを9枚配置した展示学習用教材を導入。この後、11月頃までに温室の壁面に120枚の発電ガラスが、内窓として取り付けられる予定だという。なお、新たな発電ガラスの内窓取り付けに際しては、しっかりとしたガラス固定・ガラス間配線・メンテナンス性の確保などが必要となる。これらサッシ収容技術についてはYKK APが協力している。 *6-1-4:https://optronics-media.com/news/20190521/57351/ (OPTRONICS 2019年5月21日) 日板,米企業と太陽光発電窓ガラスを開発へ 日本板硝子は,子会社を通じて透明な太陽光発電技術を扱う米ユビキタスエナジーと,同社の透明な太陽光コーティングである「ClearView PoweTM」技術による太陽光発電が可能な建築用窓ガラスの共同開発に合意した(ニュースリリース)。ClearView Powerは,可視光を透過しながら,非可視光(紫外線と赤外線)を選択的に吸収し,視界を遮らずに周囲の光を電気に変換する。標準的なガラス製造過程で建築用窓にそのまま使用することができ,建物一体型太陽光発電(BIPV)による再生可能エネルギーの創出を可能とする。さらに,この製品は赤外線太陽熱を遮断し,建物のエネルギー効率を上げることで,ゼロエネルギー建物の実現に寄与するという。同社は,進行中の研究開発と技術サポートにより共同開発に参画している。 *6-2-1:https://www.jacom.or.jp/noukyo/news/2021/11/211117-55149.php (JAcom 2021年11月17日) 「なくてはならない全農」めざし次期中期計画-JA全農 *JA全農は11月16日の経営管理委員会で「次期中期計画策定の考え方」を了承した。2030年に向け中長期の視点に立った「全農グループのめざす姿」を描き、持続可能な農業と地域社会の実現に向けた戦略を策定する。 ●環境変化を見据える 次期中期計画は、生産と消費、JAグループを取り巻く環境変化をふまえて、2030年の姿を描き、そこからどのような取り組みを展開するか戦略を策定するというバックキャスティングという手法で策定する。 環境変化のうち、農業者人口はその減少が予想以上に進む。2020年の基幹的農業従事者数は136万人だが、2030年には57万人へと42%も減少する見込みだ。この間の日本の人口は5%減との見込みであり、農業者は大きく減少し、同時に農地の集約・大規模化が進む。消費は約10兆円となった中食市場のさらなる増加や、共働き世帯の増加にともなう簡便・即食化などの大きな変化が続くと見込まれる。共働き世帯は1219万世帯で1980年の約2倍となっている。こうした環境変化のなか全農は2030年のめざす姿として「持続可能な農業と食の提供のため"なくてはならない全農"であり続ける」を掲げる。その実現のために長期・重点的に取り組む全体戦略を策定し、それに基づき来年度から3年間の分野別事業戦略を策定する、というのが今回の考え方だ。 ●JAと一体で生産振興 全体戦略は6つの柱を設定する。1番目は生産振興。少数大規模化する生産者と、一方で家族経営で地域を支える小規模生産者への営農指導、組織体制などの課題がある。これらの課題に対して、担い手の育成、多様な労働力支援、JA出資型農業法人への出資なども実施する。また、スマート農業や新たな栽培技術、集出荷の産地インフラの整備も行う。物流機能の強化も課題であり、国内外の最適な物流の構築による安定的な資材・飼料の供給を図る。2番目は食農バリューチェーンの構築。生産、集荷から販売までの全農にしかできない一貫した体制づくりに取り組む。ターゲットを明確にした商品開発、JAタウンの事業拡大とJAファーマーズの支援強化、他企業との連携による加工、販売機能などの最適化などを進める。3番目の柱は海外事業展開。成長が期待される海外市場の開拓と、国内の農業生産基盤とのマッチングを進める。一方、世界的な穀物や資材原料の需要増への対応も課題で安定的な輸入に向けた競争力の強化も図る。 ●地域循環型社会をめざす 4番目の柱は地域共生・地域活性化。人口減少など地域の実情に応じた宅配、eコマースなど利便性の拡充や、地域のエネルギーを活用したEV(電気自動車)・シニアカーシェアリング事業の実践や、営農用への供給、遊休施設や耕作放棄地を活用した太陽光発電や農泊事業などの展開などを進める。また、「食と農の地産地消」に向けた耕畜連携の促進、ファマーズマーケットなどの事業強化も図る。5番目の柱が環境問題など社会的課題への対応。農業分野や地域のくらしにおける温室効果ガスの削減や、みどり戦略を実現するためのイノベーションの実現と普及が課題となる。そのために持続可能な農業に向け適正施肥の推進、有機農業を含む環境保全型農業の実践、環境負荷軽減に資する技術や資材、飼料の開発・普及、再生可能エネルギーに活用による電力供給の拡大などに取り組む。6番目の柱はJAグループ・全農グループの最適な事業体制の構築。全農の機能再編とJAとの機能分担が課題となる。JAも今後は営農経済担当の職員が減少するという見込みのもとで、より全農とJAが連携した事業展開を図る。県域の実態に合わせたJAとの最適な機能分担や、JAへの支援、営農指導・販売機能の強化に向けた人材育成などに取り組む。また、全農グループの機能強化に向けた子会社との新たな事業展開も図る。こうした全体戦略のもと、事業戦略は「耕種」、「畜産」、「くらし」、「海外」、「管理」の5つの事業分野で検討を進める。今後、検討を本格化させ、年明けからの総代巡回などを経て3月の臨時総代会で決める。JA全農はこれまでにない事業と取り込み事業拡大をめざす。 *6-2-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC074WJ0X00C22A1000000/ (日経新聞 2022年1月10日) イオンモール、全電力を再生エネに転換 国内160カ所 イオンモールは国内約160カ所全ての大型商業施設で、2040年度までに使用電力の全量を再生可能エネルギーに切り替える。再生エネの環境価値を取引する「非化石証書」を使わず、自ら太陽光パネルを設置したり、メガソーラーからの全量買い取りなどを組み合わて実現する。年内にも太陽光発電の余剰電力を提供する消費者にポイントで還元する手法も導入し、脱炭素を加速する。小売業の脱炭素で施設の再生エネ導入は重要な課題だが、現状では非化石証書の活用が主流だ。イオンモールの年間電力消費量は約20億キロワット時で国内の電力消費全体の0.2%を占める。国内屈指の大口需要家が使用電力を再生エネに切り替えることで、企業の脱炭素のあり方が変わる可能性がある。運営する大型商業施設「イオンモール」で、22年から本格的に太陽光発電を導入する。自らパネルを設置するほか、メガソーラーなど発電事業者と長期契約を結び、発電した再生エネを全量買い取る「コーポレートPPA」と呼ばれる手法も使う。各施設には大型蓄電池も整備し、集めた再生エネを効率的に運用できる仕組みを整える。再生エネの地産地消を進めるため、一般家庭の太陽光発電の余剰電力を消費者が電気自動車(EV)を使ってイオンモールに提供すれば、ポイントで還元するサービスも始める予定だ。太陽光発電のほか風力発電やバイオマス発電、水素発電などからも電力を調達し、発電事業用の用地取得など関連投資も検討する。親会社のイオンはグループ全体で国内の年間消費電力量が71億キロワット時と、日本の総電力消費量の1%弱を占める。同社は国内外で電力を全て再生エネで賄うことを目指す国際的な企業連合「RE100」に加盟し、40年度に事業活動で排出する温暖化ガスを実質ゼロにする目標を掲げる。大型商業施設の使用電力の再生エネへの全量転換と平行し、ほかのグループ会社の運営スーパーでも順次再生エネに切り替えていく。大手企業の再生エネ導入は広がりつつある。小売り大手では21年からセブン&アイ・ホールディングスがNTTの太陽光発電事業から電力供給を受けているほか、ローソンは22年に親会社の三菱商事から太陽光発電による再生エネ調達を始める計画だ。ただ、現状では日本企業が脱炭素化を進めるための施策は非化石証書が主流だ。化石燃料を使わず発電された電気が持つ「非化石価値」を証書にして売買する仕組みだが、制度が複雑でコスト負担が大きいとの指摘もある。海外では大規模なコーポレートPPAを活用した調達が主流。調査会社ブルームバーグNEFによると、世界の新規コーポレートPPAは20年に発電能力ベースで約2300万キロワットと原子力発電所23基分に達する。旺盛な需要が再生エネの投資拡大やコスト低減につながっており、日本でも今後、同様の影響が期待できる。 *6-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220114&ng=DGKKZO79204810T10C22A1EP0000 (日経新聞 2022.1.14) 東南ア脱炭素支援 高い壁、アンモニア混ぜ発電、日本が推進 「石炭の延命策」批判強く 萩生田光一経済産業相は13日、インドネシアなど東南アジア3カ国の訪問を終えた。脱炭素に向けてアンモニアや水素を活用する技術協力を進める。再生可能エネルギーの支援を進める中国や欧米の動きをにらみ独自色を打ち出したが、「石炭火力の延命につながる」との批判は根強い。供給網を構築して日本の強みをいかせるか、前途は見通しにくい。 ●3カ国と覚書 「2030年までにアンモニアのみを燃焼させる技術の実現をめざす」。萩生田氏は10日、インドネシアとのオンラインイベントでこう表明した。アンモニアは燃やしても二酸化炭素(CO2)が出ない。今回、東南アジア3カ国と覚書を交わした。石炭火力発電所に発電量の過半を頼るインドネシアとは、アンモニア活用での技術協力で合意。シンガポールとは水素やアンモニアの供給網の構築で連携し、タイとは脱炭素工程表策定に知見を提供することになった。東南アジア各国には稼働年数の浅い石炭火力発電所が多い。発電所の廃止にまで踏み切らなくても、設備改修でアンモニアを混ぜられるようにすればCO2排出量を減らせる。その先でアンモニアのみを燃料にすれば、CO2ゼロの火力発電所の実現も見えてくる。「エネルギー転換には国際的なパートナーによる支援が必要だ」(インドネシアのアリフィン・エネルギー・鉱物資源相)。前向きな発言も目立ったことから、経産省は新技術の確立と需要創出への布石を打つことができたとみる。もっとも、実際に燃料としてのアンモニアの需要はまだほとんどない。萩生田氏が言及した「アンモニアの専焼」も本格導入は30年以降だ。それまでは石炭とまぜて燃料にする「混焼」で、どれだけ排出削減できるかが問われる。東南アジア各国を含め新興国の脱炭素化は経済成長との両立が難しく、欧米先進国と比べて取り組みは遅れたままだ。3カ国の発電量のうち、化石燃料への依存度は現状で8割から9割に達する。段階的な脱炭素への移行を前面に出す日本とは異なり、欧米や中国が太陽光や風力など再生可能エネルギーの導入で攻勢を強めている。 ●実質ゼロに課題 支援の主導権を握れるか見通せない。昨秋の第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)で、岸田文雄首相がアンモニアや水素の活用を打ち出したが、国際的な非政府組織から気候変動対策に後ろ向きだと批判された。アンモニアは原料の天然ガスから製造する過程でCO2を排出。このCO2を回収し、地下に埋めるなどして実質ゼロにしなければクリーンとは言い切れない。だからこそ欧州を中心に「石炭火力の延命策」との批判があり、逆風が強まる恐れは拭えない。中国はアジアで広域経済圏構想「一帯一路」を推し進めてきた。米国はアジア各国を巻き込む形で、デジタル貿易や供給網といった分野での協力強化を目指す「インド太平洋経済枠組み」を打ち出している。米中の綱引きがアジアでも激しくなる中、日本の存在感にも陰りが見えてきた。新型コロナウイルスの感染拡大の局面でも萩生田氏が出張したのは、日本政府の危機意識のあらわれであり、巻き返せなければ成長市場を取り込む機会を失いかねない。 *6-4:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15171067.html (朝日新聞 2022年1月14日) VW、販売店に充電器 日本国内の250店舗 VWの日本法人「フォルクスワーゲングループジャパン」は13日、2022年末時点で国内の販売店約250店舗にEVの急速充電器を設置する方針を明らかにした。普及に向け充電環境を整える。日本市場には年内にVWブランドのEV「ID.」を投入予定だ。充電器はVWとアウディの販売店に置く。両ブランドの車はどちらの店でも充電可能。250店舗で充電網ができれば現時点では国内最大級という。充電性能は90キロワット~150キロワット。150キロワットの場合、販売店の設置費用は1基2千万円ほどかかる。充電器はEV普及のカギを握る。まずは店に置くことで環境を整える。充電の料金収益を得ることもめざす。マティアス・シェーパース社長はこの日の会見で「今後生き残るために必要だ」と述べた。シェーパース社長は日本のEV市場について「軽EVの話も出てきている。もう一部のお金持ちが買うものではない。みんなが乗るようになる。全世界で似たような動きがあるので、日本もそうなってくると信じている」と期待する。VWはトヨタ自動車と世界販売台数を競うライバルだ。2年連続でトヨタに軍配が上がりそうで、シェーパース社長は取材に、「明確な理由は半導体不足。トヨタは半導体のストックマネジメントがあって車がつくれた。我々にはそれがなかった」と語った。 *6-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220115&ng=DGKKZO79249610U2A110C2EA5000 (日経新聞 2022.1.15) 大型蓄電池、米中から日本参入、ファーウェイやテスラ、低価格で国内産業の脅威 再生可能エネルギー発電施設の電力をためる大型蓄電池で、大手外資企業の日本への参入が相次いでいる。中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)は3月から出荷を始める。米テスラも2021年から販売している。再生エネの拡大には需給を安定させる蓄電池が欠かせない。米中勢の参入は日本の電池産業にとって脅威となる。ファーウェイは中国・寧徳時代新能源科技(CATL)など複数の蓄電池メーカーから小型の蓄電池パックを購入する。120個程度を束ね、一般的な家庭用蓄電池の約200倍の電力量をためられる2000キロワット時のコンテナサイズの蓄電池を生産する。顧客企業の需要に合わせてコンテナを組み合わせ、容量を変えられる。違うメーカーが製造したものや劣化状況が異なるものをデジタル技術で管理する。蓄電池はパソコンなどの「民生用」、電気自動車(EV)などの「車載用」、施設などに据え置く「定置用」に分かれる。ファーウェイの大型蓄電池は定置用で、再生エネ発電施設に併設する電力貯蔵の用途を狙う。日本法人のファーウェイ・ジャパン(東京・千代田)は、再生エネの適地でありながら送電網の空きが少ない北海道などを主な導入先として検討中だ。陳浩社長は日本市場の先行きを「太陽光発電技術の発展とコスト削減で急速に発展する」と見込む。定置用にはこのほか、家庭用や、商業施設などに使う業務・産業用も含まれる。ファーウェイやテスラはすでに家庭用などで日本市場に参入しており、市場拡大が見込める、より大型の定置用開拓を進める。テスラの日本法人、テスラモーターズジャパン(東京・港)は21年4月、高砂熱学工業がもつ茨城県の研究施設に大型蓄電池を納入した。研究施設内にある太陽光発電所や木質バイオマスガス化発電設備などの電力を制御する。22年夏には、送電線に直接つなぐ大型蓄電池を北海道千歳市内に納入・稼働する。新電力のグローバルエンジニアリング(福岡市)が導入する。再生エネに接続する電池の導入も検討している。ENEOSホールディングス(HD)が買収した再生エネ開発会社、ジャパン・リニューアブル・エナジー(JRE、東京・港)もテスラ製の蓄電池を実証実験で使うと発表した。大手電力ではJパワーが21年11月、広島県のグループ会社の施設内にテスラ製を導入した。中国の太陽光パネルメーカー大手、ジンコソーラーは21年9月に日本で大型蓄電池の受注が決まった。受注先は非公開。同社はまず小型の家庭用で知名度を上げ、その後大型蓄電池の販売を強化していく考えだ。銭晶副社長は「22年には1万台以上の家庭用蓄電池を売りたい」と話す。日本では再生エネ発電施設の電力をそのまま送電線に送ることが多く、大型蓄電池の併設は導入が十分に進んでいない。国内勢では日本ガイシや住友電工などが大型蓄電池を製造している。住友電工は国内外で数十台を納入した実績をもつ。また、車載用を束ねた大型蓄電池の実用化を目指す企業もあり、東京電力HDなどの電力会社や住友商事や丸紅といった商社などが取り組んでいる。米中勢の強みは販売価格の安さだ。三菱総合研究所の資料によると、定置用のうち業務・産業用の国内販売価格は、19年度時点で建設費を含めて1キロワット時24万円程度だ。21年10月に閣議決定された30年度時点での目標価格は同6万円とされる。テスラモーターズジャパンの再生エネ併設用は同5万円以下で販売しているとみられる。ファーウェイもテスラ製と競う価格水準を目指している。再生エネの開発などを手掛ける新電力幹部は「蓄電池を導入する場合、コストが安い企業を選ぶ」と話しており、国内勢が対抗するためにはコスト競争力が課題となる。 <日本におけるEV出遅れの理由も、リーダーの非科学性・不合理性である> PS(2022年1月15日追加):地球温暖化対応で開発競争が激しいEVは、*7-1のように、中間層が台頭する東南アジアでも導入機運が高まっており、中国・韓国のメーカーが参入に積極的だが、新車市場で8割のシェアを握る日本メーカーの動きは目立たないそうだ。例えば、現在はインドネシアとタイで日本車のシェアは9割に達しているが、EVで話題を提供しているのは中韓勢ばかりで、日本もできない理由を並べていては東南アジアの市場を失いそうだ。 そのような中、*7-2のように、日本の自動車メーカーもEVへの巨額投資に乗り出し、トヨタは4兆円、日産は2兆円を投じて、先行する米国・欧州・中国のメーカーに対抗するそうだ。しかし、EVも日本が最初に開発を始めたのに、米国・欧州・中国のメーカーに後れを取ったから、それに対抗する形で後追いするというのは開発途上国のメーカーの発想である。 そのため、*7-3のように、異業種のソニーグループが、2022年春にソニーモビリティという新会社を設立してEV市場への参入を検討すると発表したのは期待が持てるが、車の価値を「移動」から「エンタメ」に変えるのをソニーに期待している人は少なく、①操作が家電並みに簡単で ②デザインがよく ③総合的に信頼できる車 をソニーには求めていると思う。 *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220114&ng=DGKKZO79205530U2A110C2EA1000 (日経新聞社説 2022.1.14) 日本はアジアのEV化に乗り遅れるな 地球温暖化対応で開発競争が激しい電気自動車(EV)は、東南アジアでも導入機運が高まっている。中国や韓国のメーカーが参入に積極的な一方、いまの新車市場でシェア8割を握る日本メーカーの動きは目立たない。新型コロナウイルス禍で足踏みしているものの、人口6億6千万人を抱え、中間層が台頭する東南アジアは、今後も有望な成長市場だ。現在の市場優位を守るため前向きなEV化戦略が求められる。域内の二大市場であるインドネシアとタイに限れば、日本車のシェアは9割に達する。ところがEVに関して話題を提供しているのは中韓勢ばかりだ。インドネシアでは韓国の現代自動車がこのほど稼働させた完成車工場で、3月からEVの生産を始める。基幹部品は当面輸入に頼るが、同じ韓国の電機大手LGグループと共同で、車載用電池の量産工場の建設を進めている。タイでも中国の上海汽車集団や長城汽車がすでにEVの販売を開始した。後者は米ゼネラル・モーターズ(GM)から取得した工場で、2023年からEVの量産に乗り出す計画だ。輸出も視野に入れて生産規模を確保しようとしている中韓に比べて、日本はトヨタ自動車と三菱自動車が23年からタイでEVの現地生産を検討しているくらいで、総じて慎重姿勢が目立つ。及び腰には理由がある。東南アジアは石炭や天然ガスを使う火力発電が中心で、再生可能エネルギーの裏付けなしにEVだけを増やしても、温暖化ガスの排出は減らせないと主張する。充電設備の整備の遅れもあり、ハイブリッド車を軸とする普及戦略を描く。環境規制がより厳しく、購買力も高い欧米や中国でのEV生産を優先し、東南アジアは他の新興国向けもにらんだガソリン車やディーゼル車の生産拠点として残したいという狙いもあるようだ。だが各国政府のEV導入の要請は、環境対策だけでなく、次世代の産業創出の意味合いも大きい。中国車メーカーはタイで自ら充電設備の整備に乗り出した。できない理由を並べていては、既存事業の勝者が新しい事業への参入で後れをとる「イノベーションのジレンマ」に陥り、虎の子の市場を中韓に切り崩される恐れが拭えない。各国政府との対話を重ねつつ、EV化への協力姿勢をもっと積極的に示すべきだ。 *7-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/794952 (佐賀新聞論説 2022年1月11日) 構造転換の未来図描け 電気自動車に巨額投資 日本の自動車メーカーが電気自動車(EV)への巨額投資に乗り出す。トヨタ自動車は4兆円、日産自動車も2兆円を投じ、先行する米国、欧州、中国のメーカーに対抗する。異業種も強い関心を示しており、国内ではソニーグループが市場参入を検討し始めた。だが、EVの開発や普及はメーカーの力だけではできない。日本メーカーがEVシフトへ走りだす2022年は、自動車社会の未来図を描く1年にしなければならない。トヨタ自動車は30年を目標に、EVの販売台数を350万台に拡大する。トヨタの世界販売台数の35%をEVにすることを計画している。日産は10年12月、量産型の「リーフ」をいち早く発売した。その後、米テスラや欧州企業に追い抜かれてきたが、再びEVを経営戦略の中心に据えた。海外勢では新興の米テスラが100万台近くを量産し、先頭を走る。米アップルなどIT企業の参入もうわさされている。EVに及び腰とされてきた日本メーカーの姿勢もはっきり変化してきている。ハイブリッド車(HV)、燃料電池車も選択肢として残るが、世界の潮流を考えればEVに軸足を置くことは避けられそうにない。長距離走行の壁を破り市場で主導権を握るため、新型電池の開発にメーカー各社はしのぎを削っている。トヨタは4兆円の投資額のうち、半分は電池の開発につぎ込む。日産は走行距離を延ばす鍵になる「全固体電池」を搭載した新型車を28年度までに実用化するという。だが、技術開発の競争だけではEVの時代は見えてこない。市街地や高速道路の充電拠点が広がらなければ、安心して遠出はできない。自動車各社の販売店、ガソリンスタンド、商業施設などを利用することが想定されているが、エネルギー業界、政府、自治体などとの協調が欠かせない。電力需要も変化するだろう。国内で大量のEVが走るようになるなら、電力各社の発電能力の増強が必要になる。二酸化炭素を排出するガソリン車は減っても、化石燃料に依存した発電が増えるという見方もある。EV市場の拡大と電力需要に関する信頼できる予測と、それを前提にした電源構成の議論を求めたい。EVが自動車産業に与える影響は大きい。ガソリンなどを燃焼させるエンジンに比べると、EVのモーターは構造は単純で、部品点数も大きく減る。エンジンの部品や素材を生産してきたメーカーは、培ってきた技術を転換する必要に迫られるのではないか。国内の自動車メーカーは、EVへの転換によって部品メーカーの経営が悪化し、技術力を失うのを避けようとしている。日本勢は完成車メーカーを中心に部品や素材の会社が一体で開発に取り組むのが強みだった。しかし、いまはそれが海外のライバルほど素早く動けない要因になっている。技術転換が起きれば、雇用にも変化が生じる。自動車関連の就業者数は約550万人に上る。雇用を維持しながら、事業や技術を転換するのは簡単なことではない。脱炭素の流れを後押しするため、公的資金を使った大規模なEV支援も考える余地がある。充電拠点の整備、雇用維持など社会的に必要な対策を、官民で多面的に検討しておくべきだろう。 *7-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK07AYC0X00C22A1000000/ (日経新聞社説 2022年1月10日) ソニーのEV参入が示す自動車の変貌 ソニーグループが2022年春にソニーモビリティという新会社を設立し、電気自動車(EV)市場への参入を検討すると発表した。米ラスベガスの見本市「CES」では多目的スポーツ車(SUV)型の試作車を披露し、新市場にかける意気込みを示した。「SONYカー」の登場は100年に1度といわれる自動車市場の地殻変動を映すものだ。強い自動車産業は日本経済のけん引役であり、新旧のプレーヤーが競い合うことで、市場の活性化と産業基盤の強化につなげたい。ソニーグループの吉田憲一郎最高経営責任者(CEO)は「車の価値を『移動』から『エンタメ』に変える」と宣言する。車をただの走る機械ではなく、音楽や映像などを楽しむ空間と再定義し、自動運転のための画像センサーや映像・音響など自社の得意技術を詰め込む考えだろう。かつて「ウォークマン」などを世に出したソニーがどんな車をつくるのか、楽しみだ。一方で車は人の命を預かる商品であり、安全が最も重要なのは言うまでもない。電池の発火事故の防止を含め、安全性能の確保に万全を期す必要がある。EV専業の新興企業、米テスラが株式時価総額でトヨタ自動車など業界の巨人を圧倒する現状が示すように、自動車産業は変革のさなかにある。米アップルのEV参入も取り沙汰される中で、日本を代表するイノベーション企業であるソニーの挑戦に期待したい。モーター大手の日本電産も中国にEV用基幹部品の量産工場を設立し、地場メーカーへの供給を拡大しようとしている。これまで車とは縁の薄かった企業が自動車の変革をチャンスととらえ、成長のテコにする動きがさらに広がるかどうか注目される。他方でトヨタはじめ既存企業の底力も侮れない。トヨタは21年の米国市場で米ゼネラル・モーターズなどを抜いて、シェア1位になった。コロナ禍という特殊要因があったとはいえ、強靱(きょうじん)なサプライチェーンや販売店網、ブランドへの信頼など長年の経営努力が実った結果でもある。半導体はじめエレクトロニクス産業が失速し、ネットビジネスやバイオなども振るわない中で、自動車は日本に残された、強い国際競争力を持つ、数少ない産業のひとつだ。新旧企業の競争と協業でその強みを今後とも堅持したい。 <早すぎた選択と集中による再生医療を使った脊髄損傷治療の遅れ> PS(2022年1月16日追加):医学は「神経細胞は再生しない」と教えるが、その理由を説明できる人はいない。そのため、私は「できない理由はないのだろう」と思っていたところ、20年以上前、夫に同伴して行った世界の学会で「脊髄を切断して半身不随にしたマウスが、その後、回復して歩けるようになった」という発表を聞いた。そのため、「マウスにできるのなら、人間にもできないわけはない」と思い、衆議院議員在職中(2005~2009年)に再生医療を提案した。その結果、*8-3のように、患者の骨髄液に含まれる幹細胞「間葉系幹細胞」を5000万~2億個に培養した後、静脈に点滴で戻して脊髄損傷患者の運動・知覚機能回復を狙うニプロの自己骨髄間葉系幹細胞ステミラック注が既に承認されているが、未だ条件・期限付のようだ(https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=66832 参照)。しかし、自己の骨髄間葉系幹細胞から作れば免疫反応も起こらないため、患者に無為な時間を過ごさせず、迅速に治療して、要介護状態から解放するには、早く条件・期限付を解除することが必要である。 日本は、「再生医療=iPS細胞」と早く限定しすぎたため、他のより有効な治療を疎かにした面があるが、*8-1・*8-2のように、岡野教授をはじめとする慶大チームが、2021年12月、①iPS細胞から作った神経の元となる細胞をに脊髄損傷患者1人に移植し ②拒絶反応を抑えるため免疫抑制剤を使い ③経過は順調で ④転院して通常の患者と同じリハビリをしており ⑤今後は、1年間の経過を追ってリハビリのみを行った患者と比較して安全性・効果を確認するそうだ。①③④は、自己骨髄間葉系幹細胞を使用した場合と同じだが、②は他人の細胞を使うから必要なもので、⑤のうち安全性の検証はiPS細胞化しているため癌化のリスクがあるから必要なものである。ただ、自己の骨髄間葉系幹細胞が分裂しにくく5000万~2億個まで培養できない人は、他人の細胞を使わざるを得ない。そのため、若い人から入手した分裂しやすい標準細胞があれば、自己の細胞を培養する必要がなかったりはするだろう。 しかし、神経が再生しても神経回路は学習によって形成されるものが多いため、リハビリは不可欠だ。また、損傷後の早い段階で入れることが望ましいが、損傷後の時間が長い人にも適用できるようにすべきである。なお、夫の外国の学会では、「脊髄損傷は予防できる!浅いプールに飛び込んだり、事故を起こしたりしないことだ!」という声も聞かれたことを付け加えたい。 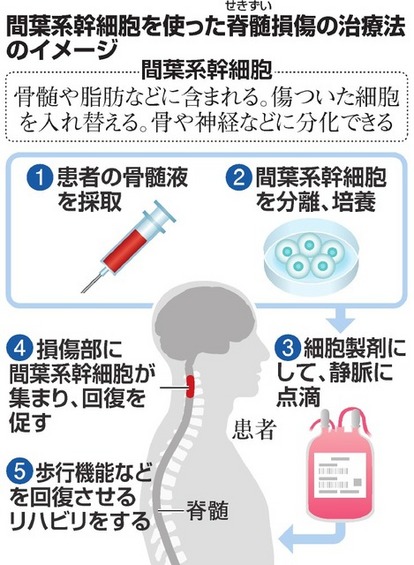   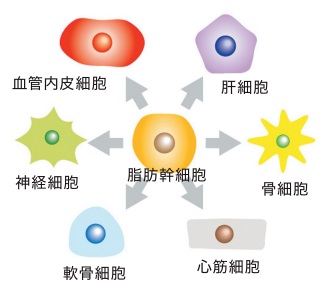 2018.11.21 2022.1.14 2018.11.21 川越中央クリニック 朝日新聞 日経新聞 毎日新聞 (図の説明:1番左の図のように、自分の骨髄や脂肪に含まれる間葉系幹細胞を使った脊髄損傷の治療法もあるが、左から2番目の図のように、他人のiPS細胞を使った脊髄損傷の治療法も開発されようとしており、違いは、右から2番目の図のとおりだ。なお、1番右の図の脂肪幹細胞は、倫理的問題や発癌リスクがなく、採取の負担が小さく、コントロールもしやすいメリットがあるそうだが、いずれも素早い製品化と普及が望まれる) *8-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15172330.html (朝日新聞 2022年1月15日) 脊髄損傷にiPS移植 世界初、実用化には課題 慶大 慶応大は14日、iPS細胞からつくった神経のもとになる細胞を、脊髄(せきずい)損傷の患者1人に移植したと発表した。iPS細胞を使った脊髄損傷の治療は世界で初めて。脊髄損傷を完全に回復する治療法はなく期待は大きいが、実用化に向けては課題も多い。「ヒトのiPS細胞の樹立から15年が経ち、さまざまな困難を乗り越えて1例目の手術ができて、うれしく思う」。会見でチームの岡野栄之・慶応大教授はそう話した。チームによると、移植は昨年12月。移植後の拒絶反応を抑えるため、免疫抑制剤を使っている。経過は順調で、転院して通常の患者と同じリハビリをしている。今後は1年間の経過を追い、リハビリのみの患者のデータと比較し、安全性や効果を確認する。今回の患者を含め、計4人の患者に移植する計画という。今回の臨床研究の対象は、事故などで運動や感覚の機能が失われた「完全まひ」の患者で、程度は重い。脊髄が損傷してから2~4週間後の「亜急性期」に移植する。脊髄損傷はけがや事故などが原因となり、毎年5千人が新たに診断され、国内には10万人以上の患者がいるとされる。リハビリ以外に確立した治療はないのが実情だ。脊髄損傷にくわしい、総合せき損センター(福岡県飯塚市)の前田健院長は、「私たちのからだはずっと再生していて、皮膚や骨などは入れ替わるが、神経細胞は再生しない。神経細胞となる候補を体に入れることで、細胞を再生させることができるかもしれないという点で、iPS細胞には期待できる」と話す。ただし、現時点ではチームは「主な目的は安全性の確認だ」と強調。移植する細胞の数も多くはない。効果をどう判定するのかには難しさも残る。研究に参加する患者は、通常の治療と同じように、移植後に保険診療の範囲でリハビリを続ける。チームの中村雅也・慶応大教授は、「実際に脊髄の再生が起こったとしても、リハビリをしっかり行うことによってのみ、機能的な意味を持つだろう」とリハビリの重要性を指摘する。それ故に、機能の改善がみられたときに、それがiPS細胞の効果なのか、リハビリの効果なのか、わかりにくい面はある。脊髄損傷の患者は、損傷から時間がたち、治療が難しくなった「慢性期」の人が多くを占めるが、今回の研究では対象とならない。岡野さんは、「慢性期の運動機能が残る患者に対する治験の準備も進めている」としている。iPS細胞の作製にはまだ数千万円かかるとされ、実用化に向けては、コストを下げる取り組みも必要となりそうだ。iPS細胞を使う再生医療は目の難病やパーキンソン病、軟骨などでも臨床研究が進む。昨年11月には、卵巣がんでの治験も始まった。ただ、まだ製品化されているものはなく、全体的に当初の目標からは遅れている。今回の研究も2019年2月に厚生労働省の部会で了承されたが、細胞の安全性を慎重に確かめたり、新型コロナの流行で延期になったりしたため、移植までに時間がかかった。再生医療に10年間で1100億円を投資する政府の大型予算が、22年度で終わる。世界は遺伝子治療に注目し、iPS細胞では「創薬」の分野も盛り上がりを見せている。臓器を置き換える、失った細胞を補うといった再生医療の分野がどこまで成果を出せるのか、正念場を迎えている。 *8-2:https://digital.asahi.com/articles/ASLCM5FJGLCMULBJ011.html (朝日新聞 2018年11月21日) 脊髄損傷を患者の細胞で回復、承認へ 「一定の有効性」 厚生労働省の再生医療製品を審議する部会は21日、脊髄(せきずい)損傷の患者自身から採取した幹細胞を使い、神経の働きを回復させる治療法を了承した。早ければ年内にも厚労相に承認され、リハビリ以外に有効な治療法がない脊髄損傷で、幹細胞を使った初の細胞製剤(再生医療製品)となる。公的医療保険が適用される見通し。この製剤は札幌医科大の本望修教授らが医療機器大手ニプロと共同開発した「ステミラック注」。患者から骨髄液を採取し、骨や血管などになる能力を持つ「間葉系幹細胞(かんようけいかんさいぼう)」を取り出す。培養して細胞製剤にした5千万~2億個の間葉系幹細胞を、負傷から1~2カ月以内に、静脈から点滴で体に入れる。間葉系幹細胞が脊髄の損傷部に自然に集まり、炎症を抑えて神経の再生を促したり神経細胞に分化したりして、修復すると説明している。安全性や有効性を確認するため、本望教授らは2013年から医師主導の治験を実施。負傷から3~8週間目に細胞を注射し、リハビリをした患者13人中12人で、脊髄損傷の機能障害を示す尺度(ASIA分類)が1段階以上、改善した。運動や感覚が失われた完全まひから足が動かせるようになった人もいたという。国は根本的な治療法がない病気への画期的な新薬などを対象に本来より短期間で審査する先駆け審査指定制度を適用、安全性と一定の有効性が期待されると判断した。ただ、間葉系幹細胞の作用の詳しい仕組みはわかっていない。今回は条件付き承認で、製品化された後、全患者を対象に7年ほど、安全性や有効性などを評価する。再生医療に詳しい藤田医科大の松山晃文教授は「損傷後の早い段階で入れることで、神経の機能回復の効果を強めているのではないか。有効性を確認しながら治療を進めて欲しい」と話す。脊髄損傷は国内で毎年約5千人が新たになり、患者は10万人以上とされる。慶応大のグループはiPS細胞を使って治療する臨床研究を予定。学内の委員会で近く承認される。 *8-3:https://mainichi.jp/articles/20181122/k00/00m/040/135000c (毎日新聞 2018/11/21) 脊髄損傷治療に幹細胞 製造販売承認へ 厚生労働省の専門部会は21日、脊髄(せきずい)損傷患者の運動や知覚の機能回復を狙う再生医療製品について、条件付きで製造販売を承認するよう厚労相に答申することを決めた。製品は患者の骨髄液から採取した幹細胞を培養し点滴で戻すもので、年内にも正式承認される。厚労省によると、脊髄損傷への再生医療製品の販売承認は世界初とみられる。製品はニプロが6月に申請した「ステミラック注」で、脊髄損傷から約2週間までの、運動や知覚の機能が全くないか一部残る患者が対象。最大50ミリリットルの骨髄液や血液を採取し、骨髄液に含まれる幹細胞「間葉系幹細胞」を約2~3週間で5000万~2億個に培養した後、静脈に点滴で戻す。(以下略) <必要なのは受注統計か?> PS(2022年1月24日):*9-1のように、①建設業の受注実態を表す国の基幹統計で、国交省が全国約1万2千社の建設業を抽出して受注実績の報告を毎月受け、集計・公表する受注実績データを国交省が書き換えた ②受注実績データの回収を担う都道府県に書き換えさせた ③その結果、建設業受注状況が8年前から一部「二重計上」となり過大表示された ④具体的には、業者が提出期限に間に合わず数カ月分をまとめて提出した場合に、その数カ月分合計を最新1カ月の受注実績のように書き直させていたが、毎月の集計では未提出の業者も受注実績を0にせず、同月に提出してきた業者の平均を受注したと推定して計上するルールがあり、それに加えて計上していた とのことである。 統計はデータに手を加えると実態を示さなくなるため、①②③の根本的問題の土壌は、「事実を正確に全数調査せず、サンプル調査を用いた統計でよい」と考え、次第に「推定を含んでもよい」「二重計上してもよい」と考えるようになっていったいい加減さにある。また、経済分析に必要なデータは工事完了分に対応する支払実績であるため、業者が「工事完成基準」を採用している場合はそれに基づいて工事完成時に認識し、「工事進行基準」を採用している場合は工事の進行に基づいて報告してもらう方が正確で簡単だ。そして、大工事を「工事完成基準」でまとめて報告されると変動が大きくなりすぎて不都合であれば、業者に「工事進行基準」で毎月の実績を正確に出すよう要請すべきだったのだ。さらに、現在では、ITを使えば全数調査も容易であるため、全数調査した方が正確な上に簡単なのだ。また、受注実績が重要なのではなく、完成した工事分の支払いが行われることが経済状況の予測上重要なのであるため、④の「業者が提出期限に間に合わず数カ月分をまとめて受注実績を提出した場合、業者の平均を受注したと推定して計上した」というのでは、意味のある数値が出ない。そのため、大規模な工事を請け負う業者には、工事進行基準による実績を毎月出すよう要請すべきだったし、それは可能だった筈である。 そもそも、大きな予算を使っているのに、驚くべきことに、国は「複式簿記を使って固定資産の数量と金額を正確に把握をする」という発想がなく、固定資産はじめ貸借対照表項目の把握が統計になっているのだ。つまり、正確なデータに基づいた維持管理や新設を行っていないということで、これが予算編成の根本的な問題なのである。そのため、「正確なデータを迅速に出す」という発想に変えれば、*9-2の「徹底解明」や*9-3の「自浄作用働く改革」も容易にできるのだ。従って、ここで充実が必要なのは、*9-4のような統計の専門家ではなく、会計の専門家とそれをITやデジタルで実現できる専門家である。 *9-1:https://digital.asahi.com/articles/ASPDG64YYPDGUTIL03X.html (朝日新聞 2021年12月15日) 国交省、基幹統計を無断書き換え 建設受注を二重計上、法違反の恐れ 建設業の受注実態を表す国の基幹統計の調査で、国土交通省が建設業者から提出された受注実績のデータを無断で書き換えていたことがわかった。回収を担う都道府県に書き換えさせるなどし、公表した統計には同じ業者の受注実績を「二重計上」したものが含まれていた。建設業の受注状況が8年前から実態より過大になっており、統計法違反に当たる恐れがある。この統計は「建設工事受注動態統計」で、建設業者が公的機関や民間から受注した工事実績を集計したもの。2020年度は総額79兆5988億円。国内総生産(GDP)の算出に使われ、国交省の担当者は「理論上、上ぶれしていた可能性がある」としている。さらに、月例経済報告や中小企業支援などの基礎資料にもなっている。調査は、全国の業者から約1万2千社を抽出し、受注実績の報告を国交省が毎月受けて集計、公表する。国交省によると、書き換えていたのは、業者が受注実績を毎月記し、提出する調査票。都道府県が回収して同省に届ける。同省は、回収を担う都道府県の担当者に指示して書き換え作業をさせていた。具体的には、業者が提出期限に間に合わず、数カ月分をまとめて提出した場合に、この数カ月分の合計を最新1カ月の受注実績のように書き直させていた。一方、国交省による毎月の集計では、未提出の業者でも受注実績をゼロにはせず、同月に提出してきた業者の平均を受注したと推定して計上するルールがある。それに加えて計上する形になっていたため、二重計上が生じていた。複数の国交省関係者によると、書き換えは年間1万件ほど行われ、今年3月まで続いていた。二重計上は13年度から始まり、統計が過大になっていたという。同省建設経済統計調査室は取材に、書き換えの事実や二重計上により統計が過大になっていたことを認めた上で、他の経済指標への影響の度合いは「わからない」とした。4月以降にやめた理由については「適切ではなかったので」と説明。書き換えを始めた理由や正確な時期については「かなり以前からなので追えていない」と答えた。同省は、書き換えの事実や、過去の統計が過大だったことを公表していない。国の基幹統計をめぐっては、18年末に厚生労働省所管の「毎月勤労統計」が、決められた調査手法で集計されていなかったことが発覚。この問題を受けて全ての基幹統計を対象とした一斉点検が行われたが、今回の書き換え行為は明らかになっていなかった。 *基幹統計とは 政府の統計のうち特に重要とされるもので、統計法に基づいて指定されている。政策立案や民間の経営判断、研究活動などに幅広く使われる。国の人口実態などを明らかにする「国勢統計」や経済状況を示す「国民経済計算」など53ある。正確な集計が特に求められるため、同法は調査方法を設定、変更するには総務相の承認が必要と定めている。調査対象となった個人や企業は回答する義務がある。作成従事者が真実に反する内容にすることを禁じ、罰則もある。 【視点】生データを加工 真相究明が急務 統計は二つの工程で作られる。生データの取得と、集計作業だ。一昨年に発覚した毎月勤労統計の問題では、取得方法にルール違反があった。全数調査をせず、サンプル調査に勝手に変えていた。それでも、生データに手を加えるような行為はなかった。その意味で今回の問題はより深刻といえる。統計は政策立案の基礎となる。言い換えれば、税金の使い方を決める材料だ。だから国は予算と権限を使い調べている。その生データに手が加えられていたならば、統計は社会を映す鏡といえなくなる。書き換えは遅くとも10年ほど前から続いていたという。国交省はなぜ書き換えを始めたのか。誰も問題だと思わなかったのか。なぜ公表しなかったのか。真相究明が急務だ。 *9-2:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/898504 (沖縄タイムス社説 2022年1月22日) [建設統計書き換え] 幕引きせず徹底解明を 政府の基幹統計の一つ「建設工事受注動態統計調査」の書き換え問題で、国土交通省幹部ら10人が処分された。長年にわたるデータの不適切な扱いには不明な点が残る。再発防止に向けた課題もある。処分で幕引きせず、問題の検証を続けてもらいたい。国交省は、毎月の提出期限を過ぎて過去の調査票が出された場合、最新月分として合算するよう、都道府県に書き換えさせていた。指示は遅くとも2000年には始まっていた。その後、国交省側が推計値を計上する処理に変更し、同一業者の受注に二重計上が生じた。国交省の第三者委員会が先週公表した報告書で浮かび上がったのは、事態を正す機会は幾度かあったにもかかわらず、事なかれ主義や問題の矮(わい)小(しょう)化によって隠(いん)蔽(ぺい)とも見える対応を重ねた組織の姿だ。報告書によると、厚生労働省の毎月勤労統計の不正を受けた19年の一斉調査では、統計室の担当係長が書き換え問題を総務省に報告するよう進言したが上司が取り合わなかった。同年6月にも課長補佐が書き換え中止を訴えたものの室長らは是正に動かなかった。11月に問題を指摘した会計検査院に対しては、合算はやむを得ない措置などと取り繕った。総務省統計委員会には別統計の推計方法見直しに便乗して報告するとした。報告書は「幹部職員に責任追及を回避したい意識があった」ことが原因だとした。ガバナンス不全は明らかだ。 ■ ■ 政府の基幹統計は、行政の政策立案や学術研究などに利用される基礎資料で国民の財産だ。正確さが肝心なのは指摘するまでもない。統計を巡っては18年に厚労省の毎月勤労統計で不正が発覚し厳しい批判を浴びた。その時に再発防止対策の柱となったのが、統計担当から独立した「統計分析審査官」の新設だ。各省庁へ派遣されたが、機能していないことが今回の件で露呈した。政府の統計データへの信頼は大きく揺らいでいる。総務省は53の基幹統計を改めて点検する意向だ。今度こそうみを出し切らなければ信頼回復は遠い。第三者委の調査は約3週間と期間が短く限界がある。「大きな数字を公表する作為的な意図は認められない」と報告したが、書き換えが国内総生産(GDP)の算出に影響した可能性がある。実際はどうだったのか国会で解明すべきだ。 ■ ■ デジタル化が進み客観的データの重要性は増す一方だ。だが、統計行政は人員や予算削減の対象になりやすく重視されているとは言えない。報告書は、統計室の慢性的な業務過多や、職員が統計について十分な知識を持っていない点が問題の背景にあるとも指摘した。改善策として統計の専門家をアドバイザーに任命し、定期的に打ち合わせし相談する体制の構築を提案している。チェック機能の強化も欠かせない。抜本的な改革へ向けた議論を求めたい。 *9-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/800316 (佐賀新聞 2022年1月22日) 建設統計書き換え、自浄作用働く改革を 建設受注統計の書き換え問題で国土交通省幹部ら10人が処分された。政府統計のまとめ役である総務省も事務次官ら7人が厳重注意などを受けた。これまでの調査で、国交省は問題に気付きながら、それを隠すような対応をしてきたことが判明している。政府が作成する統計全体の信頼を傷つけた両省の責任は重く、処分は当然だ。政府、日銀などの公的な統計は経済情勢を判断する大きな材料になり、投資家や金融市場への影響も大きい。多くの企業や個人の協力で作られる統計は国民全体の財産でもある。2018年には厚労省でも統計の不正が発覚した。間違いがあれば訂正し、公表するという当たり前のことがなぜできないのか。おざなりな反省や対策ではすまない。政府には、よく利用される基幹統計だけでも53あり、全てにミスがないとは言い切れない。今後検討される再発防止策は、間違いが見つかるのを前提とし、各省庁の統計部門や政府全体で自浄作用が働くように改革することが肝心だ。国交省の調査報告書などによると、企業が提出した調査票の書き換えは遅くとも00年には始まっており、受注推計値と合算する二重計上が13年から始まった。書き換え問題が会議で持ち出され、「触れてはならない雰囲気」になったこともあったようだ。厚労省の毎月勤労統計の不正を受けて実施された19年1月の一斉点検では、係長が総務省に問題を報告するよう進言したが、上司は取り合わなかった。同6月にも課長補佐が指摘したが、室長らは是正に動かなかった。同11月には会計検査院が受注統計の問題点を指摘し、総務省に相談するよう促したが、担当室は時間稼ぎに終始した。総務省の統計委員会には、別の統計の資料に書き換えの説明を紛れ込ませて提出し、承認を受けたように装ったという。現場に近い係長や課長補佐の意見を無視し、外部からの指摘には耳をふさぐ幹部職員の姿勢は、あきれるばかりだ。「事なかれ主義」と責任回避ばかりが際立ち、正しい数字に直していく姿勢はみじんも感じられない。統計は専門知識に基づいて設計し、正確な集計作業を日々続けねばならず、本来厳しい仕事だ。統計要員の削減や政策立案に偏った人員配置が、問題の背景にあったとも指摘されている。日常業務に追われる中で、重要統計を修正するのは重い負担になる。過去の担当者を含め、処分される可能性を感じたのかもしれない。担当幹部が正面から問題に向き合わなかった理由をはっきりさせ、再発防止策に生かす必要がある。各省庁の統計部門の強化も欠かせない。調査方法や分析の専門家が政府に十分いるわけではない。大学、シンクタンク、民間企業の人材に一時的に出向してもらい、政府統計の質を高める必要がある。統計部門の風通しをよくし、担当する公務員の士気を高めることにもつながるだろう。各省庁の統計を定期的に点検するのはもちろん、現場からの指摘を受け入れ、問題点を審査する部署を統計部門の外に設けることを考えるべきだ。各種の統計は経済動向の分析や政策立案の基礎になる。与野党は国会で統計問題の集中審議を実施し、再発を防ぐ対策を徹底的に検討してほしい。 *9-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220122&ng=DGKKZO79462930S2A120C2EA1000 (日経新聞社説 2022.1.22) 統計専門家の充実が急務だ 国土交通省は21日、建設統計を不正に書き換えていた問題で関係する幹部を処分した。政策立案の根幹である統計への信頼を揺るがした責任は重く、処分は当然だ。今回の問題は統計を軽視する風潮が霞が関にはびこっていることを浮き彫りにした。組織の風土を改めるとともに、統計の専門家を充実させることが急務である。第三者の検証委員会によると、担当者は書き換えを問題視して見直しを進言していた。しかし、上司は見て見ぬふりで放置したり、表ざたにしないよう蓋をしたりしていた。コンプライアンスやガバナンスを欠いた組織的な隠蔽であり、言語道断だ。修正をためらう無謬(むびゅう)主義が霞が関に根強いことがうかがえる。誤りを正せば前任者らの責任を問うことになり、組織として支払うコストが大きくなるという意識が働くのだろう。物事を変える労力が大きくなりがちな組織風土は見直さねばならない。統計を重んじる組織にするには専門家を充実させ、その仕事を尊重することが必要だ。専門家の仕事ぶりを通じて幹部と一般職員も常に統計やデータを重視して政策立案にあたる姿勢を身につける。そのように職員の意識が変われば組織風土として定着しよう。官庁統計をつかさどる総務省も不正を見抜けなかったとして幹部を処分した。統計の司令塔であるべき組織にもかかわらず、専門家でない職員も配置され、役割を果たせていなかった。ここでも専門家の充実が求められる。専門家の充実と職員の意識改革が大事なのは、デジタル化も同じだ。デジタル庁を伴走役にし、全省庁でだれもがデジタルを意識するようになることが、質の高いデジタル政府への近道になる。統計とデジタル化は、データを生かした効率的で機能的な政府の両輪であり、実現には政治の役割が大きい。慢性的に業務が多く、デジタル化が進んでいない状況の改善も含め、霞が関改革に政治は指導力を発揮すべきである。 <オミクロン株とワクチンの効果、集団免疫の獲得など> PS(2022年1月25日追加):*10-1に、オミクロン株の特徴は、①感染力はデルタ株の3~5倍 ②米国のデータで潜伏期間が約3日で、デルタ株の約4日より短く、感染者が増えやすい ③沖縄で「症状はこれまでの新型コロナよりインフルエンザに近い」と話す医師もいる ④香港大の実験で「気管支で24時間で増える速さはデルタ株などの70倍だが、肺では10分の1以下 ⑤英国で、12月下旬の段階で入院リスクがデルタ株に比べて50~70%低いとのデータも出ている ⑥重症者が少ないのは病原性が弱いためか、ワクチンや過去の流行で免疫があるためかは不明 ⑦感染者が増えれば、重症者は増える と書かれている。 ワクチン接種済や感染・回復済などでヒトの免疫が強い場合、「ある人に感染したら、その人の免疫で死滅させられないうちに素早く増殖して次の人に感染する」という変異がウイルスが生き残る確率を上げるため、①②③④⑤の特色を持つ変異株が流行するのは尤もで、⑥は、ワクチン接種や過去の流行による免疫獲得がある集団内で生き延びるためのウイルスの変異だと思う。また、⑦も事実だろうが、*10-2の濃厚接触者となった介護職員だけでなく、*10-3のような濃厚接触者とされる一般人も、ワクチンを2回接種し、無症状で、検査を受けて陰性なら開放してよく、潜伏期間が約3日のウイルスに対して、検査もせずに10日間待機させるのは、科学的でないし、長すぎるだろう。 WHOのハンス・クルーゲ欧州地域事務局長は、*10-4のように、「ワクチンと多くの人が感染するという理由で、欧州での新型コロナのパンデミックは終わりが近いかもしれない」と語られ、英国・スペインなどはオミクロン型の重症化率が従来より下がったこと等を理由に、感染者の全件把握や隔離をやめられるか分析しているそうで、私は、こちらの方が科学に基づいた迅速な検討だと思う。なお、日本は、マスク・ワクチン・治療薬などの医療用機材を外国産に頼り、支払ばかりかさませながら利益チャンスを逃しているが、何で稼いで食べていくつもりか? これらの結果になる理由も、改善すべき重要なポイントなのである。 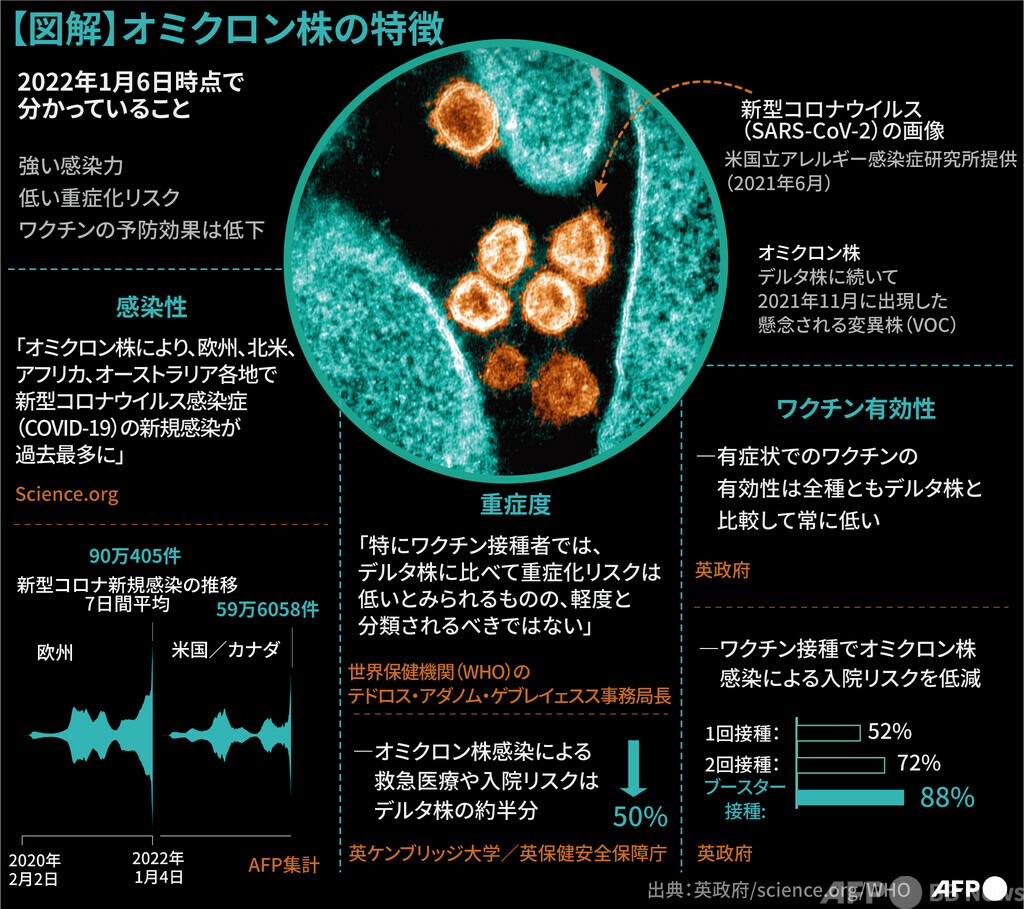 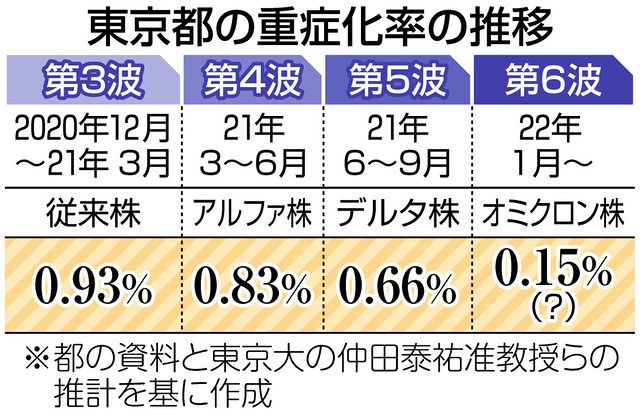  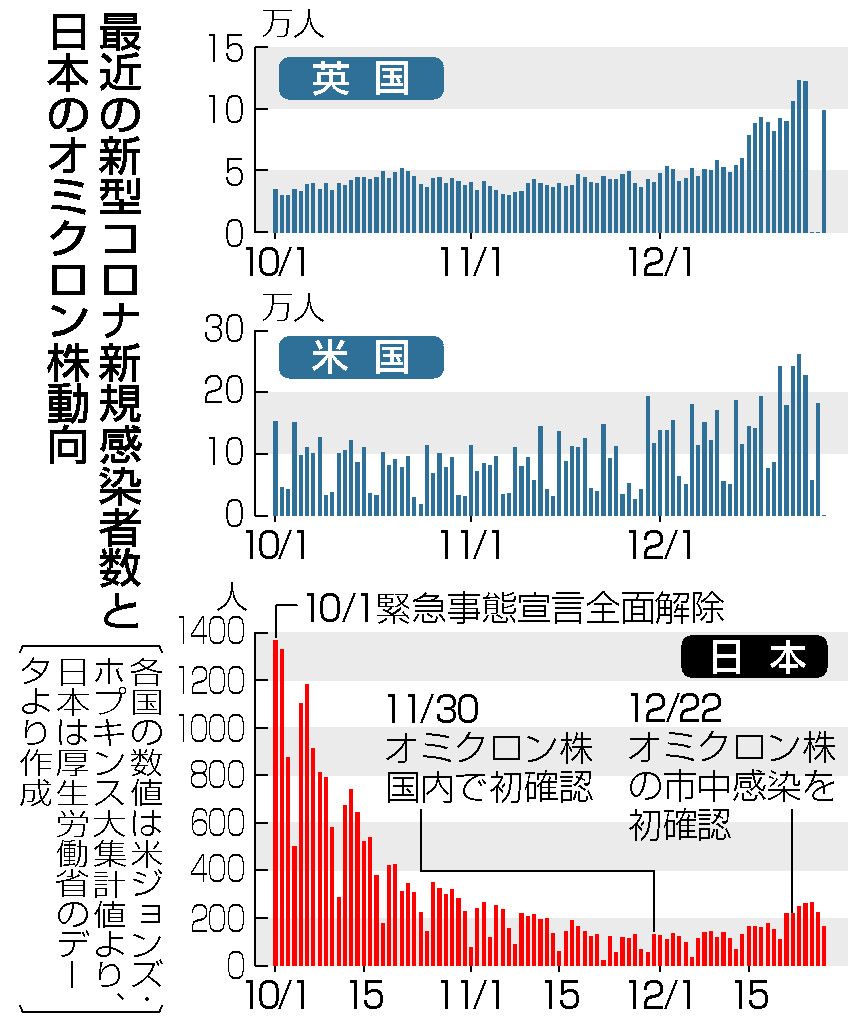 2022.1.12Afpobb 2022.1.14東京新聞 2022.1.23日経新聞 2021.12.30時事 (図の説明:1番左の図のように、新型コロナのオミクロン株は、2022年1月6日時点で、「デルタ株と比較して、感染力は強いが、重症度は低く、ワクチンを2回接種した人の感染による入院リスクは72%とされていた。そして、左から2番目の図のように、東京都の重症化率は、確かに第3波と比較して約1/6、第5波と比較して約1/4になっており、この差は、オミクロン株の特性もあるだろうが、ワクチン接種が進んでヒト側の抵抗力が高まっていることにもよると思われる。なお、右から2番目の図には、感染者が倍増した日数を示して「東京の感染ピークはこれから」と書かれているが、1番右の図のように、英国・米国の感染者数が10万人単位であるのに対して、日本の感染者数は2桁小さい1000人単位であり、感染者にはワクチンを接種していない子どもが多いため、一般の人が大騒ぎして行動制限し過ぎる必要はないと思われる) *10-1:https://www.yomiuri.co.jp/medical/20220113-OYT1T50051/ (読売新聞 2022/1/13) オミクロン株特徴は?…変異30か所、感染力5倍に Q オミクロン株の特徴は。 A 東京大など国内の研究チームの分析によると、英国や南アフリカでの感染力は、日本で昨夏流行したデルタ株の3~5倍に上る。米国のデータでは潜伏期間が約3日で、デルタ株の約4日より短く、感染者が増えやすい。ウイルス表面にある突起のたんぱく質が約30か所変異し、うち半数が人間の細胞につく部位の変異だ。デルタ株より細胞に侵入しやすくなった可能性がある。 Q 症状は。 A 沖縄県で1月1日までに診断された50人の分析(複数選択あり)では、37・5度以上の熱75%、せき60%、 倦怠けんたい 感52%、のどの痛み46%、鼻水や鼻づまり38%、頭痛33%、呼吸困難8%、味覚・嗅覚障害2%などだ。沖縄では「症状はこれまでの新型コロナよりインフルエンザに近い」と話す医師もいる。 Q 重症化しにくいのか。 A 香港大の実験で、気管支で24時間で増える速さはデルタ株などの70倍だが、肺では10分の1以下だった。動物実験でも肺炎が起きにくいようだ。英国では12月下旬の段階で入院リスクがデルタ株に比べ50~70%低いとのデータも出ている。 Q 安心できるのか。 A 重症者が少ないのは病原性が弱いためか、ワクチンや過去の流行で免疫があるためかは不明で、警戒は怠れない。新型コロナは軽症でも倦怠感や息苦しさなどの後遺症が多いが、オミクロン株の後遺症は、ほとんどわかっていない。感染者が増えれば、重症者は自然に増える。3密回避、手洗い、マスクなどの基本対策を徹底する必要がある。 *10-2:https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220125-OYT1T50183/ (読売新聞 2022/1/25) 濃厚接触者の介護職、「陰性」なら待機期間中も勤務へ…沖縄の特例を全国に拡大 政府は25日、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった介護職員について、毎日の陰性確認などを条件に待機期間中の勤務を特例的に認める方針を固めた。変異株「オミクロン株」の感染急拡大で、介護施設の運営が困難となる可能性があるためだ。厚生労働省は既に、感染が深刻な沖縄県でそうした特例を認めている。後藤厚労相は同日の記者会見で、「高齢者施設全体への対応を検討する必要もある」と述べ、全国への拡大を検討する必要性を強調した。沖縄では毎日の検査での陰性確認に加え、ワクチンを2回接種したことや無症状であることなどが勤務の条件となっている。待機の解除は最短で6日目。医療従事者は同様の特例が全国で認められている。 *10-3:https://digital.asahi.com/articles/ASQ1T6VDDQ1TUTFK00P.html?iref=pc_special_coronavirus_top (朝日新聞 2022年1月25日) 首相、机たたき「放置はしない」 濃厚接触者めぐる追及に反論 新型コロナウイルス対応の「まん延防止等重点措置」の対象に18道府県が加わった25日、衆院予算委員会では政府対応をめぐり、激しい論戦がかわされた。普段は淡々と答える岸田文雄首相が、机をたたきながら反論する場面もあった。立憲民主党の山井和則氏が取り上げたのが、子育て家庭で子どもが新型コロナに感染した場合だった。感染者である子どもが原則10日間隔離され、さらに濃厚接触者となった親は、感染者である子どもと最終接触日を起算日に10日間の待機期間を求められる。そのため山井氏は「親は20日間働けない。非常に深刻な問題だ」とし、濃厚接触者の待機期間短縮を求めた。首相は「科学的な見地に基づいて確定している」と政府対応への理解を求め、期間短縮を「検討していく」と応じた。だがこの「検討」という言葉を境に論戦は過熱。山井氏は「首相の答弁は検討するが多い。検討すると言っている間に事態は逼迫(ひっぱく)する」と決断を求めると、首相は「検討する検討するばかりではないか、と言ったが、問題意識をもって努力を続けてきた」「大事なのは国民の納得、安心だ」と応戦した。山井氏が「20日間仕事をできない現状を放置するのか」とさらに追及すると、首相は右拳で机をたたきながら「放置はいたしません」と色をなして否定。山井氏は今週中の決断を促したが、首相は「国民の生命安全がかかった問題だ。期限を区切って申し上げることは控えなければいけない」と応じなかった。3回目のワクチン接種も遅れているとやり玉に挙がった。菅政権下で最も接種回数が多かった時期に比べ、岸田政権で回数が極端に減っていることを挙げ、山井氏は「1日100万回接種」を掲げた菅義偉前首相のように接種目標を定めないのか、と尋ねた。首相は「接種が本格化するのは1月、2月にかけての時期だ」と説明したが、目標については「最初から1日何人というのではなく、できるだけ多くの方に接種をしてもらう体制を作っていきたい」とし、明確にはしなかった。共産党の宮本徹氏は、不足する抗原定性検査キットについて「昨年の夏以降、確保についてどういう努力をしてきたのか」とただした。首相は「昨年までの使用は今の状況と比べるとかなり低調だった」と振り返りつつ、政府として増産の要請を行った年明けの状況を説明した。 *10-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220124&ng=DGKKZO79483730U2A120C2MM0000 (日経新聞 2022.1.24) 「欧州、感染流行終わり近い」 WHO幹部、集団免疫に言及 世界保健機関(WHO)のハンス・クルーゲ欧州地域事務局長は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)について「欧州での終わりは近いかもしれない」と語った。仏AFP通信の取材に答えた。今後多くの人が免疫を獲得して「集団免疫」を達成し、危機の度合いが下がる可能性に言及した。 WHO幹部がパンデミックの終わりに言及するのは異例だ。欧州では急速に変異型「オミクロン型」が感染を広げており、3月1日までに人口の6割が感染するとの試算がある。クルーゲ氏は「オミクロン型が落ち着いたら、数週間か数カ月、集団免疫の状態になるだろう。ワクチンのおかげでもあり、多くの人が感染するからでもある」と説明した。クルーゲ氏は「年末にかけてコロナ流行が再開するかもしれないが、必ずしもパンデミック(と言うほど)ではない」と続けた。ただコロナを危機の水準が下がった状態である「エンデミック」と今すぐ呼ぶことには反対した。「エンデミックというのは我々が次に何が起こるか予想できる状態だ。だが新型コロナウイルスは予想外の変化をみせてきた。警戒を続けなければいけない」と表明した。英国やスペインなどはオミクロン型の重症化率が従来より下がっていることなどを理由に、コロナをエンデミックと定義する検討を始めている。感染者の全件把握や隔離をやめられるか分析している。医療関係者の負担を下げ、隔離者の増加で社会がまひするのを防ぐ狙いがある。
| 経済・雇用::2021.4~2023.2 | 01:24 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2021,12,29, Wednesday
    椿(つばき) シクラメン 梅 水仙 蠟(ろう)梅 (図の説明:冬の花を並べました。現在は、椿とシクラメンが咲き、次第に水仙・梅・蠟梅が咲き始めます。私も忙しくて、いろいろ書いている時間がありませんでしたが、よいお年を!)     (図の説明:森も冬から春へ。日本列島は、雪景色から緑までの森が広がり、潜在力は豊か)     (図の説明:冬の海。左から、北海道、下田、沖縄。沖縄) 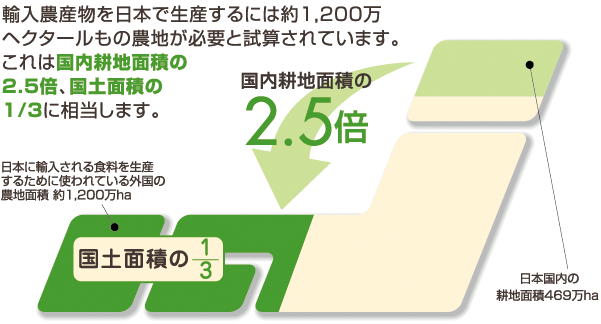 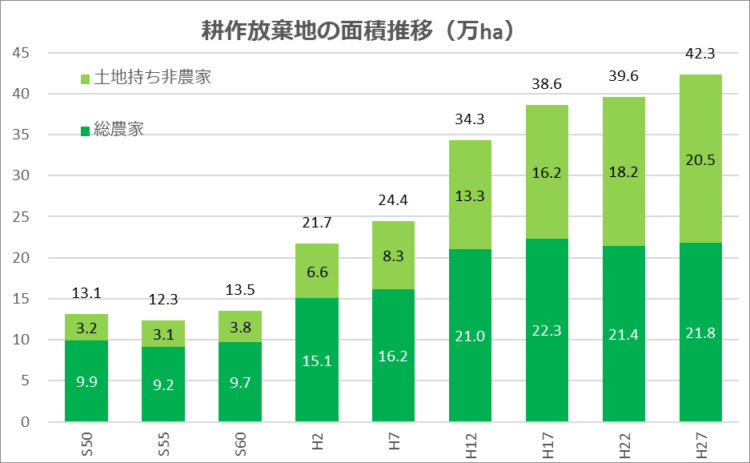   (図の説明:1番左の図のように、輸入農産物を国内生産するには、現在の2.5倍の耕地面積が必要と言われていますが、左から2番目の図のように、耕作放棄地は耕作地と変わらないくらいの面積に達しています。右から2番目と1番右の図が、耕作地の様子です)
| 環境::2015.5~ | 08:34 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2021,11,28, Sunday
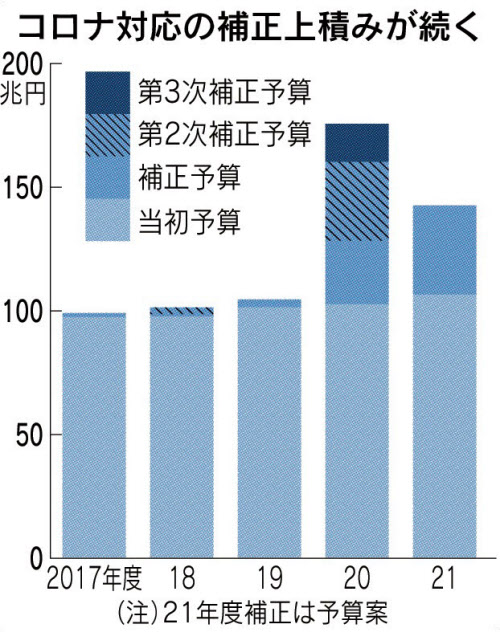  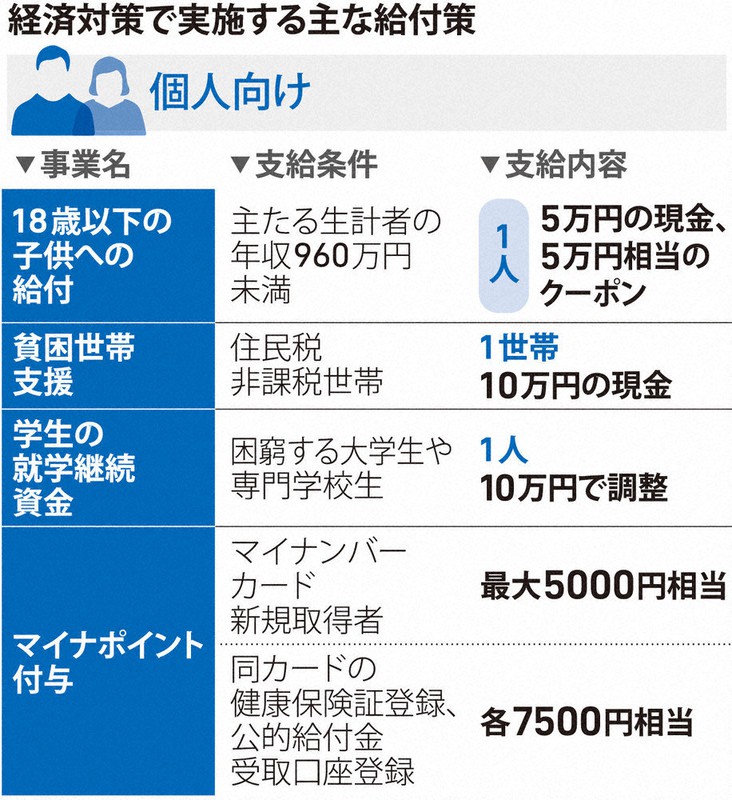 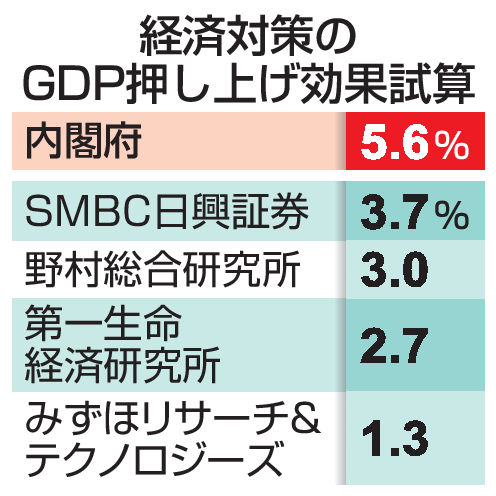 2021.11.27日経新聞 2021.11.27毎日新聞 2021.11.27京都新聞 (図の説明:1番左の図のように、2020年からコロナ対応を理由として通常予算と補正予算の上積みが続いた。そして、衆議院議員選挙後の2021年度補正予算は、左から2番目と3番目の図のように閣議決定されたが、これは本当に必要な予算なのか、賢い支出なのか、積み上がった国債残高は誰がどう支払うことになるのかについて、下に記述したい。なお、右から2番目の図が、補正予算による経済対策で実施される個人給付で、1番右の図は、各組織が試算した経済対策によるGDP押し上げ効果である)  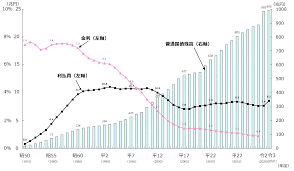 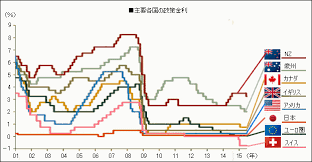 財務省 財務省 Kabuzen (図の説明:左図が、一般会計における歳出と税収の推移で、平成2年《1990年》以降、次第に乖離が大きくなっており、歳出と税収の差は借金である国債発行で埋めている。現在、日本は、右図のように、0%近傍という世界でも非常に低い利子率を続けている国であるため、中央の図のように、国債費のうちの利払費が比較的少なくて済んでいる。が、利子率が高くなれば歳出に占める国債の利払費が格段に大きくなるため、国であっても返済計画のない借金は成立しない) (1)2021年11月の補正予算について 1)使途の点検・監視が不可欠な国の予算 政府が閣議決定した2021年度補正予算案に関して、*1-1は、「①財政法で補正予算編成は当初予算作成後に生じた事由に基づいて特に緊要となった経費に限って認められるが、査定が甘くなる補正で予算を大幅に上積みする手法が常態化した」「②成長に繋がるか否か不透明な事業や緊急性のない事業も補正に盛り込まれた」「③予算の使い道の点検・監視が欠かせない」「④補正予算案は12月6日召集の臨時国会で審議される」等を記載している。 このうち①は確かにそうだが、夏の豪雨被害やCOP26で「待ったなし」になったこともあるため、補正予算に織り込みながら、次期以降の通常予算で長期的視点から計画的に歳出していく必要のある事業もあるだろう。しかし、それには具体的事象とそれを解決するためのビジョンを示し、最低コストで最大効果を挙げる必要がある。また、予算全体がそうなっているか否かについては、③の点検・監視を網羅性・正確性を持って行う必要があり、④の国会はそのために開かれるべきだ。ただ、賢い支出か否かの判断は、②の成長に繋がるか否かも重要な視点ではあるが、それだけではないだろう。 なお、健全な財政状態であっても、具体的な事象と解決のための道筋を示して、最低コストで最大効果を挙げる予算編成をするのが、納税者で社会保険料の支払者でもある国民への受託責任(説明責任ではない)である。しかし、日本は、*1-2のように、経済成長もせず、景気は悪い状態が続き、賃金も上がらず、社会保障は心もとなく、税金と社会保険料ばかりが上がって、経済は停滞したまま、21年度末時点の国債残高は1004.5兆円となる見通しだ。これは、長期ビジョンに乏しく、経済活性化に繋がらない莫大な支出を繰り返してきたからにほかならないが、これに屋上屋を重ねるのが新しい資本主義や分配を重視した政策とは、まさか言わないだろう? 国際通貨基金(IMF)によると、日本の国内総生産(GDP)に対する政府債務残高は、2021年は米国の約2倍の257%でG7最悪である。そうなった理由は、日本は物価上昇やインフレ目標といった誤った経済政策を行ったため、実質2%の経済成長をしたのは2013年度だけで、大規模な財政出動と異例の金融緩和で何とか景気を下支えしたにすぎないからだ。しかし、生産年齢人口にあたる人を財政出動で下支えなければならないのなら、誰がこの国を支えるのか情けないにも程があり、いい加減にしてもらいたいのである。 2)賢い支出とはどういう支出か *1-1は、「⑤病床確保支援金に2兆円を盛り込んだ」「⑥成長戦略向け支出比率は約2割で、半導体の国内生産拠点の確保に6170億円、経済安全保障で先端技術を支援する基金に2500億円等を積んだ」「⑦低所得世帯向け10万円給付1.4兆円」「⑧18歳以下への10万円相当の給付に21年度予備費からの拠出も含めて1.9兆円」「⑨最大250万円の中堅・中小事業者向けの支援金2.8兆円、資金繰り支援1400億円等」とも記載している。 また、*1-4によると、政府は財政支出が過去最大の55.7兆円で民間資金も入れた事業規模が78.9兆円になる補正予算を決め、岸田首相は赤字国債発行も含めて財源を確保するそうだ。 しかし、これらの中には、私にも未来の成長を促す「賢い支出」とは思えない項目が多く、「成長」は達成できないと思う。例えば、⑧の1.9兆円は、義務教育の給食費を継続的に無料にしたり、希望者には無償で朝食も出したり、教材費を無料にしたり、公立高校・公立大学の授業料負担額が年間12万円を超えないようにしたり、奨学金を充実したりなど、子育てを教育で支援すれば将来の成長が見込めるが、中途半端な金額を経済対策としてばら撒いて子育て世帯の親に消費を促しても、成長には結び付かず、少子化対策にもならない。 また、⑦は、困っている人には足りない金額で、そもそも継続的に失業保険か生活保護費を支払うべきだった。そして、失業保険すらもらえないような非正規社員を作るのはやめるべきであり、正規社員の中に「時間限定勤務社員」を作ることは全く可能である。 さらに、⑨や飲食店への時短協力金6.5兆円の支払いも中規模以上の事業者には焼け石に水であり、それより飲食店に営業停止や時間短縮を強制したことによる感染拡大防止効果を検証すべきだ。何故なら、新型コロナの予防は、水際対策・PCR検査・感染者隔離の徹底を行えば、やみくもに全飲食店に営業停止や時間短縮を行わせる必要はなく、費用もずっと安くすんだ筈だからである。0.26兆円のGoToトラベル事業も、しっかり感染症対策をしていれば不要だった。 そして、未だにワクチン接種体制の整備・接種の実施に1.3兆円も充当されており、オミクロン株という新しい変異株が発見されたと大騒ぎしているが、少し変異すれば効かなくなるワクチンは良いワクチンではない。短時間で量産するにはmRNAワクチンが良かったのかもしれないが、もし3度目の接種をするのなら、私は少しの変異では効果を失わない不活化ワクチンの方を選びたい。そもそも、「抗体価が減る=抵抗力が下がる」ではない上、治療薬もできているため騒ぎ過ぎはやめるべきで、⑤のように、今から病床確保に2兆円充当するのも不要だと思う。それよりも、日頃から基幹病院を中心とした病院ネットワークを整備しておくべきである。 なお、マイナンバーカード新規取得者5,000円、健康保険証・給付金受取口座登録者7,500円のマイナポイントを付与するのに1.81兆円もかけるそうだが、マイナンバーカードに多くの情報を紐づけると後で政府にどう使われるかわからないこと、情報を集約し過ぎると個人情報の盗用にも便利であることから、セキュリティー対策として紐づけないのであるため、そういう根拠ある心配を無くすべきなのである。 つまり、上の約18兆円は、より効果的で賢い使い方があったり、既に不要になっていたり、過大であったりするもので、この金額は(別の場所で詳しく述べる)国会議員1カ月分の文書交通費を465人の衆議院議員全員が返還したとしても4億6,500万円(100万円X465人)にしかならないため、数桁異なる大きさなのである。 ⑥の科学技術立国、デジタル化、経済安全保障は成長戦略になると思うが、これまで政府が足を引っ張るなどという失敗が多すぎたため、どうも期待が持てないのが実情で、最も変えるべきはここだろう。 (2)今回の補正予算を具体的に論評すると・・ 1)18歳未満への一律10万円給付について *2-3は、「①18歳以下の子に一律10万円相当を配る必要はあるのか、景気浮揚だけでなく困窮者支援の点でも経済の専門家から効果を疑問視する声がある」「②困窮者支援が目的なら、コロナで収入が減少した世帯に絞るべきで、子どもを基準にするのはコロナ対策としては意味不明」「③子育て世代の富裕層が対象となり、生活が苦しい子のいない世帯が外れる」「④一時的な所得の増加は貯蓄に回る傾向が明確」としている。 私は、②③には賛成だが、そもそも④のように、貯蓄することが悪いことででもあるかのような論調がまかり通っているのが間違いだと思う。何故なら、ミクロ経済学的には、コロナで経済を停止させても、すぐには破綻しない企業や個人が多かったのは、平時からいざという時のために貯蓄をしていたからで、マクロ経済学的には貯蓄が投資の原資だからである。また、(1)でも述べたように、子育て費用を高止まりさせておきながら、10万円相当をばら撒いても少子化対策にはならず、経済成長を後押しすることもないと思う。 2)ポイントを付与してのマイナンバーカード取得促進について *2-4も、「①マイナンバーカード取得等で最大2万円分のポイントを付与する事業費として、1.8兆円が計上された」「②政府の狙いは普及率の向上だが、個人情報漏洩等の懸念に向き合わず、『アメ』で取得を促す手法に、識者から本末転倒との疑問の声が出ている」「③予算はカードの利便性・セキュリティーの向上に使うべきで、ポイントに充てるのは本来のあり方ではない」と記載している。 (1)にも書いたとおり、、マイナンバーカードに多くの情報を紐づけると政府に悪用されかねないこと(後で詳しく記載する)、情報を集約し過ぎると個人情報の盗用にも便利であることから、セキュリティー対策としては情報を集約しすぎないことが重要であるため、②③は正しい。また、①は商店街がやることであって、政府がやることではない。 3)防衛費について 政府は、*2-1-1のように、2021年度補正予算案に防衛関係費7,738億円を計上し、当初予算と合わせて6.1兆円、GDPの1.09%にしたそうだ。 その内容は、日本周辺で軍事活動を続ける中国への対応として哨戒機(3機で658億円)・輸送機(1機で243億円)等の装備取得、北朝鮮によるミサイル発射対策として能力向上型地対空誘導弾PAC3の取得441億円、沖縄県米軍普天間基地の辺野古移設801億円で、戦闘機に搭載する空対空ミサイルや魚雷などの弾薬の確保にも予算を投じるとのことである。 その野古移設801億円は、*2-1-2のように、沖縄県は名護市辺野古の新基地建設に関する変更承認申請を不承認としたが、国は工事継続の方針を示し、岸防衛相も「日米同盟の抑止力維持と普天間飛行場の危険性除去を考え合わせた場合、辺野古移設が唯一の解決策」と述べられたものである。 しかし、*2-1-3・*2-1-4のように、奄美大島・宮古島・与那国島等の空港のある国境離島では既に陸自駐屯地が開設され、石垣島が南西諸島では最後になる状況であるため、陸上自衛隊だけでなく必要に応じて他の自衛隊や米軍とも共用すれば、日米同盟の抑止力維持と普天間飛行場の危険性除去は両立できる。そうなると、「辺野古移設が唯一の解決策」などという合理性のない繰り言はできなくなり、自衛隊駐屯地を景気対策や経済効果だけで作りまくる防衛予算の無駄遣いも減り、日米地位協定は自然消滅するのだ。 沖縄県の玉城知事は、岸防衛相と面会して「宮古島市・石垣市で進む自衛隊基地の建設工事について「地域の理解を得るため折々に工事を止めて、住民の皆さんに丁寧に説明をして頂きたい」と述べ、岸氏は「いろいろ地元のご意見があることはよく承知している」「必要があれば住民の皆さんに説明していけるよう努力する」「これからも対話の場を作っていけるよう努力する」と述べるにとどめられたそうだ。 が、合理的かつ首尾一貫性のある外交・防衛政策がなく、理由は後付けで無制限に新基地建設を行い、同じ説明ばかりされても対話する時間の方がもったいないため、国は早急に最小のコストで最大の効果をあげ得る防衛方針を決めるべきである。 なお、離島の住民で基地のリスクや騒音を嫌う人には、いざという時に避難できる別宅を希望する場所に提供する補償をした方が、辺野古の埋め立てを強行するよりずっと安上りである。 4)省エネ住宅購入への補助等、気候変動危機対策について 国交省は、*2-2のように、2021年度補正予算案に関連費用で542億円を盛り込み、18歳未満の子を持つ世帯か、夫婦いずれかが39歳以下の世帯を対象に、断熱性能に優れた戸建てやマンションを買う際に最大100万円を補助し、省エネ性能を高める改修工事に対しても最大45万円を補助するそうだ。 この対象は、不公正・不公平で年齢による差別も含んでいるが、ないよりはあった方がよい制度だろう。しかし、この対象に入らない人には、省エネを奨励しないようだ(皮肉)。 一方、*3は、「①アメリカのバイデン大統領が、1兆2000億ドル(約140兆円)規模のインフラ投資法案に署名し」「②インフラ投資法は、一世一代の大型財政支出と位置づけられ」「③このうち約5500億ドル(約642兆円)を今後8年間で、高速道路や道路、橋、都市の公共交通、旅客鉄道などの整備にあて、清潔な飲料水の提供、高速インターネット回線、電気自動車充電スポットの全国的なネットワーク整備に取り組み」「④財源に新型コロナ対策で使い残した予算や暗号資産に対する新規課税の税収等の様々な収入を充て」「⑤育児・介護、気候変動対策、医療保険、住宅支援等の充実を図る大規模な社会福祉法案も検討しているが、これは成立の見通しがまだ立っていない」としている。 私は、①②③は、自動車革命が起きており、インフラの更新時期でもある現在は必要なことであり、同時に整備することによって一貫性のある整備を行うことができ、整備することによって生産性が向上し、景気対策・雇用対策にもなるという意味で無駄遣いではないと思う。さらに、④は、困っている人から消費税を巻き上げて調達する財源ではないことも理に適っている。 また、⑤については、米国がどのような育児・介護、医療保険、住宅支援等の充実を図る大規模な社会福祉法案を作るか関心を持って見ているが、気候変動対策は社会福祉というよりは地球環境維持のための経済構造改革だと考える。 (3)国家ビジョン不在の予算編成はどうして起こるのか ← Plan Do Check Action(PDCA)の循環がができていないからである 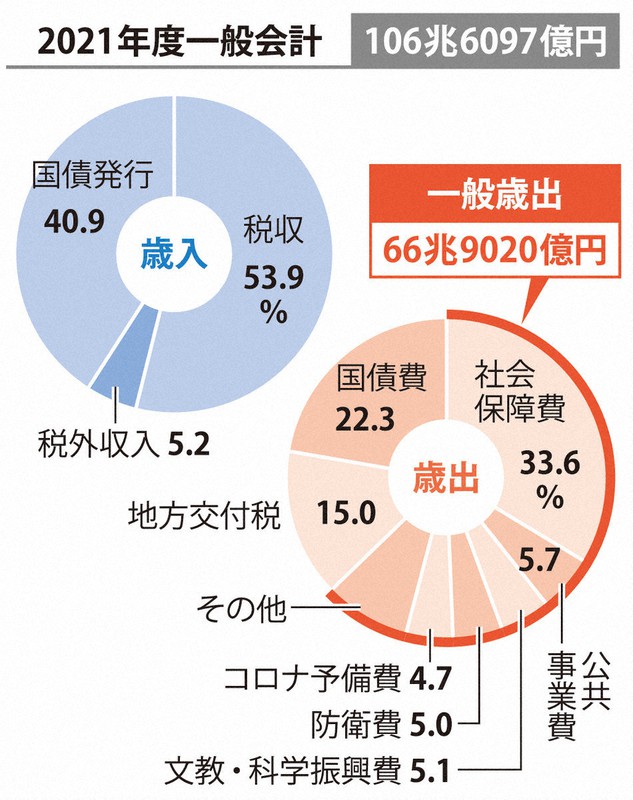  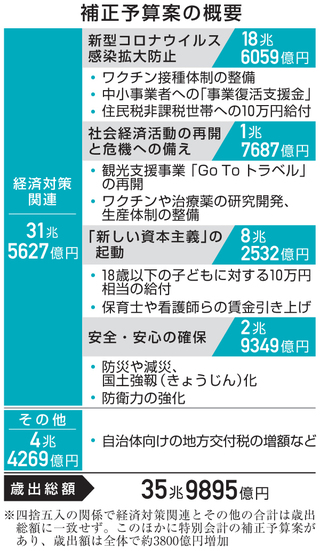 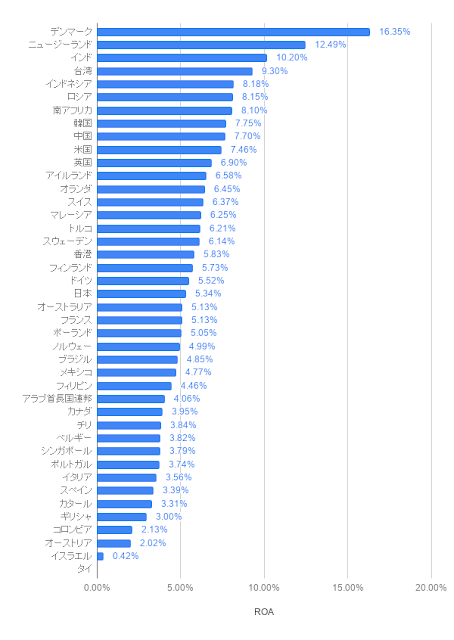 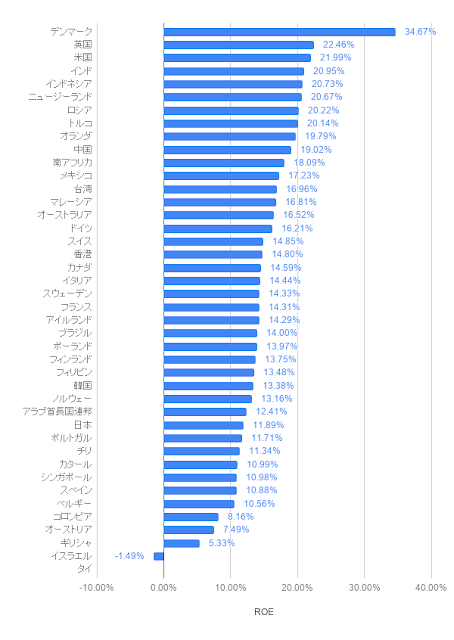 2020.12.21 2021.11.27 2021.11.27 ROA国際比較 ROE国際比較 毎日新聞 毎日新聞 西日本新聞 Ronaldread (図の説明:1番左の図は、2021年度一般会計予算106.6兆円の内訳で、国債発行が40.9%を占め、税外収入は5.2%しかない。また、左から2番目の図が、2021年度補正予算36.0兆円の内訳で、国債発行が62.7%を占め、税外収入は3.8%しかない。そして、中央の図の新型コロナ感染拡大防止18.6兆円とGotoトラベル事業0.3兆円は、不合理なコロナ対応のつけであり、その気になれば防げたものである。また、日本は利子率が低いため、右から2番目と1番右の図のように、民間企業のROA・ROEも国際的に見て低いが、日本政府の省庁は分捕り合戦をして使うことしか考えない風潮があるため、資本生産性が低いだけでなくマイナスのことも多い。そのため、民間から資金を取り上げて国が使う大きな政府(新しい資本主義?)にすれば、国家財政は破綻への道しかなく、これは、共産主義で既に実証済である。従って、修正資本主義ならよいが、これは戦後ずっとやってきたことであり、特に新しいことではない) 佐賀新聞が、*1-3のように、「①岸田首相が、新型コロナ禍を受けて分配政策を柱に据えた経済対策を決定」「②子育て世帯や所得が低い家庭などを幅広く支援する」「③『Go To トラベル』の再開も明記した」「④3回目のワクチン接種も無料にする」「⑤財源の不足分は新たな借金に頼る」「⑥売り上げが急減した中小事業者には最大250万円の事業復活支援金を配り」「⑦住民税非課税世帯に1世帯10万円を給付し」「⑧雇用調整助成金の特例措置を延長し」「⑨ガソリン価格を抑える原油高対策も盛り込み」「⑩『新しい資本主義の起動』に18歳以下の子どもを対象とした10万円相当の給付し」「⑪マイナンバーカードの新規取得者や保有者に対する最大2万円分のポイント付与し」等と記載している。 しかし、その論調は、⑤のように財源不足分は国債に頼ることを認識していながら、③⑨を喜び、①の実現可能性については不問にし、②④⑥⑦⑧⑩⑪の妥当性は評価していない。 また、*1-3は「⑫保育士、介護職、看護師の賃上げを明記し」「⑬経済安全保障の一環で先端半導体工場の国内立地を後押しし」「⑭国内の温室効果ガス排出を実質0にする2050年の脱炭素社会実現に向けて『政策を総動員する』とした」「⑮安全・安心の確保では、大規模災害に備えるため防災・減災を強化し、防衛力を増強する方針を示した」「⑯来年夏の参院選をにらみ30兆円超の補正を求める与党の声に配慮した」「⑰2022年度当初予算案では前年度と同じ5兆円の新型コロナ対策予備費を手当てし、2023年3月までの『16カ月予算』として切れ目なく景気をてこ入れする」とも書いている。 私は、⑫⑬⑭⑮は必要な歳出だが、補正予算より通常予算で対応すべきものが多い上、⑯は衆議院議員選挙支援の代償で、⑰は状況の変化を無視した無駄遣いだと思う。 そのため、*1-5の「⑱これで日本は変わるのか」「⑲未来を切り開くのか、過去に戻るのか、どちらを向いているのか分からない経済対策だ」というのに、私は賛成だ。これは何度も見てきた光景で、これによって日本は借金だけが膨らみ、経済成長はせず、世界から置いていかれたのである。そして、今回も世界は既に新型コロナ後を見据えた成長競争に入っているのに、日本は新型コロナ対策を名目に無駄遣いの大宴会を楽しんでいるようなのだ。 なお、*1-6は、「⑳来夏の参院選を意識するあまり、大盤振る舞いが過ぎる」「㉑国民が期待する経済対策とはいえ、規模を追うのではなく質を高めることにもっと注力すべきだ」「㉒与野党ともに『ばらまき合戦』の様相を呈した衆院選で勝利した与党の要請で規模優先になったとみられる」等と記載している。 私も、⑳㉒に賛成であり、㉑については、国に国際基準による公会計制度を導入し、予算全体を見てその合理性を国民や国会がチェックできるようにし、最小コストで最大成果を上げるよう、継続的に行政をチェックできるシステムにすべきだと考えている。 (4)年金・医療・介護制度と“高齢者”の軽視 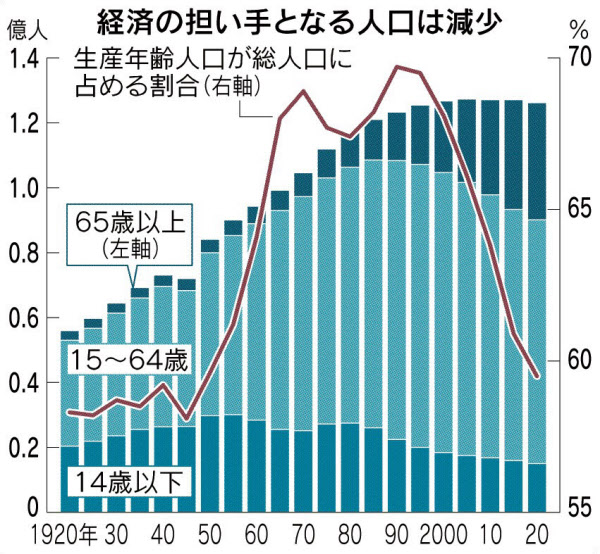   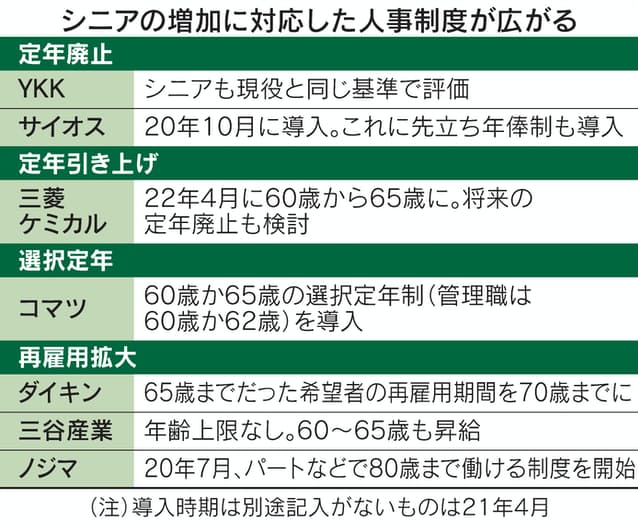 2021.12.1日経新聞 2021.4.19日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、2020年には(定義がこれでよいとは思わないが)15~64歳の生産年齢人口が総人口に占める割合が60%以下となり、そのうち女性の正規労働者は割合が低いため、少ない人数で多くの人を養わなければならなくなった。また、左から2番目の図のように、移動・職業選択・恋愛の自由によって核家族が増えた結果、単身高齢者が一貫して増え、老いたら子に養ってもらうという人は著しく少なくなっている。しかし、右から2番目の図のように、賃金は50代をピークとして大きく減少し、1番右の図のように、定年を廃止したり、80歳まで雇用したりする会社はまだ少ないため、年金は重要な生活原資になっている) 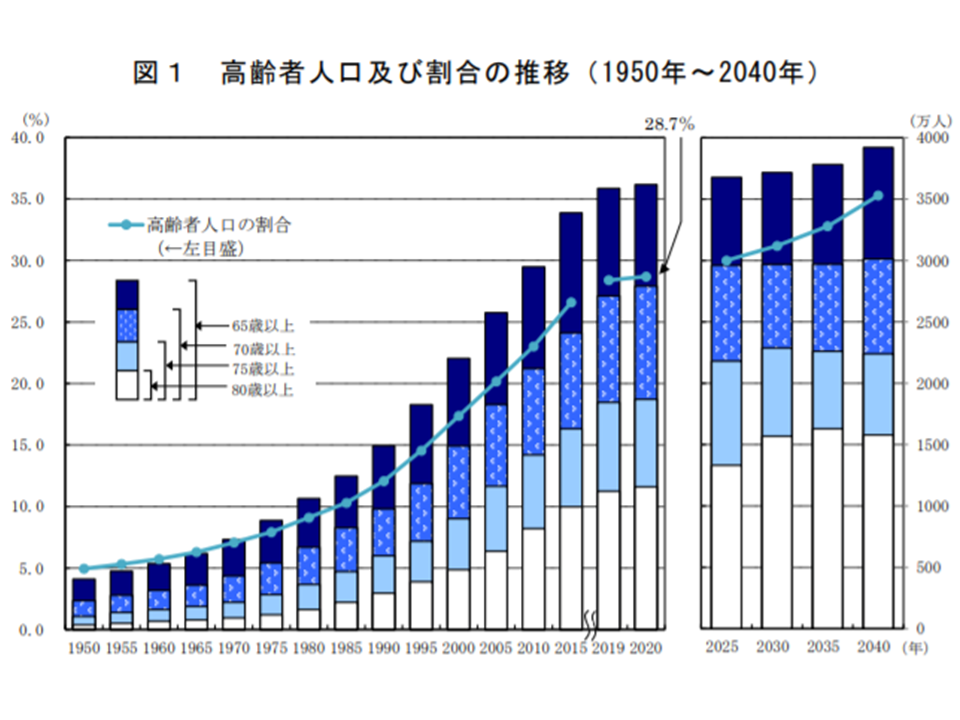 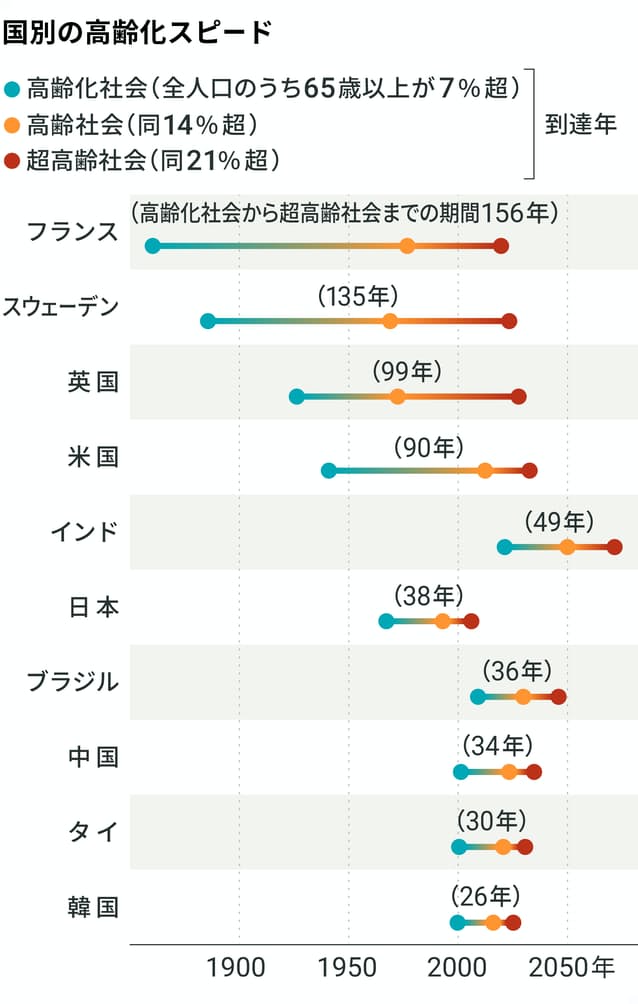  Gen Med 2021.8.23日経新聞 (図の説明:左図のように、“高齢者”人口の割合は、2015年までは指数関数的に伸びているが、ベビーブームの次の世代が65歳以上になり始めた2018年くらいから伸びが鈍化し、2020年時点では28.7%である。ただし、「支える側にいる人」とは、働いて付加価値を作り出し社会保険料を支払っている人のことであるため、この数字がそのまま「支えられる側の人」を現すわけではない。なお、中央の図のように、日本は超高齢社会となっているが、右図のように、米欧に続きアジアでも少子高齢化で生産年齢人口が減り、しばらく生産年齢人口が増加し続けるのはアフリカだけだそうである) 1)あの手この手を使った“高齢者”の可処分所得減額 身体的要因であれ、社会的要因であれ、働くことができない“高齢者”の収入は、①預金利息 ②有価証券の配当 ③公的年金 ④私的年金 ⑤預金の取崩し ⑥その他(不動産所得etc) しかない。 イ)低金利政策が高齢者に与えた影響 このうち、①②は、2000年代以降、低金利政策によって著しく小さくなり、それと同時に、物価上昇やインフレも収まっている。 また、④も、生産年齢人口の時から積み立てていた金額を金融市場で運用して増やすことが前提であるため、低金利政策によって運用益が減っている。つまり、景気対策とされてきた低金利政策は、“高齢者”の金融資産運用益を奪ってきたと言える。 ロ)公的年金制度の歪みと年金給付水準の減額 さらに、③も、金融市場で運用して増やすことを前提として年金定期便に書かれていた金額の受け取りを約束していた筈だが、*4-1のように、少子高齢化を理由として、2014年の年金制度改正で「マクロ経済スライド(現役人口の減少と平均余命の伸びに対応して年金給付水準を減らす仕組み)」なるものを導入し、その範囲内でしか給付しないことにしたため、年金の所得代替率が低下して年金受給者の生活を直撃している。 が、公的年金は、もともとは自分のために積み立てる積立方式だったのに、1985年に最初の男女雇用機会均等法が制定された時、同時にサラリーマンの専業主婦だけを“3号被保険者”とし、他の女性から見れば不公平な制度を作って賦課課税方式に変更したものだ。さらに、この年に、米国ではFASB83が定められ、正味現在価値を計算することによって退職金要支給額を理論的に計算する会計処理方法が確立していたのである。 つまり、日本は20~50年も遅れているのに、年金保険料を支払っていた人にまで“仕送り方式”などという恩着せがましい呼び方をしているのだ。仮に、積立方式のまま自分のために運用する方式を採ってまともな運用をしていれば、このように不公正な減らし方をされる必要はなかった筈である。 なお、所得の再分配は所得税や相続税で行っているため、医療保険料・介護保険料はじめ医療費・介護費・保育費等の負担割合にまで所得で差をつけると、所得に対する負担割合が不自然でおかしなカーブを描き、かえって不公平になる。そのため、保険は契約として負担やサービスの利用費に所得で差をつけないのが、正しいやり方なのである。 しかし、2021年度には年金の改定ルールがさらに見直され、実質賃金が下落した場合は賃金下落に合わせて年金額を改定することが徹底され、2021年度は年金額がマイナス改定になったのだそうだ。その上、*4-2は、「将来の年金のため、マクロ経済スライドの名目下限措置は撤廃を」などと述べているが、現役世代の人が「働き方改革」と称する「働かない改革」ばかりを主張し、政府は景気対策のバラマキばかりで生産性向上に必要な変革のための投資を怠ってきたのだから、実質賃金下落の責任は現役世代にあり、精一杯働いて日本を復興し経済成長させてきて引退した高齢者には全くない。 ハ)金融緩和による物価上昇(=実質所得の下落) 現在、*4-3のように、金融緩和で円安になったことが主な原因で、原油価格や輸入原材料が高騰してコストプッシュ・インフレーションになっており、このコスト高は企業間取引の段階で販売価格に転嫁することは可能でも、最終消費財にまで転嫁することは不可能だ。 何故なら、イ)ロ)に記載したように、著しく所得の低い65歳以上の“高齢者”が、下の段の左図のように、30%近くを占めていて高くなったものは買えないからである。また、生産年齢人口の実質賃金も下がり、全体としてさらに落ちていくという悪循環になっているのだ。 これを解決するには、経済学的視点・国際価格・将来性を見通す目を持って国の実態を分析し、的確な産業政策を決めていくことが必要なのだが、「少子化だから産めよ増やせよ」「最終財に価格転嫁してさらに物価上昇させ、年金や賃金の実質価値を減らして個人消費を弱めよ」という政策を採っているのは、馬鹿としか言いようがない。 また、中央銀行の役割は通貨価値の安定(お金の量や金利は物価の安定を図る目的でコントロールするもの)であり、そのツールが金融政策なのである。そのため、「2%の物価上昇目標」をかざして異次元緩和と呼ぶ大胆な金融緩和で物価を上げ、国民が知らないうちに実質賃金や実質年金の金額を減らそうとするのは、日銀の本来の役割とは逆のことをやっているわけである。 さらに、物価が上がれば預金の実質価値も減るため、上の⑤の“高齢者”の実質可処分所得も密かに減らしているのである。そのため、何故、こういうことをするのかについて正しく原因分析して解決しなければ、今後も、この(政府にとって便利で無責任な)方法は続けられるだろう。 なお、金融緩和して物価を上げるとお金の価値が下がるため、預金の多い人から借金の多い人への密かな所得移転となる。借金の多い国や企業には、この効果も嬉しいのだろうが、このようにして資本生産性の低いところに密かに所得を移転して本物の最終需要を抑えれば、公正性がなく国民を豊かにできないだけでなく、課題先進国の長所を活かした本物の製品開発ができずに他国への追随を繰り返さざるを得ないのである。 2)働くシニアと女性 1)に、「身体的要因であれ、社会的要因であれ、働くことができない“高齢者”の収入は、公的年金に大きく依存する」と記載したが、これまでは社会的要因で働けない人を作りすぎていたと思う。例えば、「少子化で支える人が足りない」と言いながら、働くことを希望しても労働力にカウントされない人を作っているのは矛盾している。 そのため、イ)“高齢者”の定義を「65歳以上」とせず、個人差はあるが人生100年時代の身体的能力を考えて“高齢者”の定義を「75歳以上」とする ロ)身体的には働ける人を社会的に働けなくする定年制を廃止して引退時期を自分で決められる社会保障制度にする などの方法が考えられる。また、生産年齢人口の定義を「15~64歳」とするのも、高卒が99%を超えている日本社会では実態に合わないため、高校卒業後の「18~75歳」に変更すべきだろう。 そのため、*4-4にも、「女性や高齢者の就業が進んでいることに合わせて、年金制度を変更する」として、2022年4月から年金制度改正法が施行されると記載されている。今回の改正では、「①パートなどの短時間労働者への年金適用拡大」「②繰り下げ受給の上限引き上げ」「③確定拠出年金の要件緩和」などが含まれ、①は短時間労働者の働き方に影響を与え、②③はシニアの退職時期に影響を与えそうだ。 しかし、①については、そもそも女性を正規雇用ではない悪い労働条件で働かせてきたのは、非正規労働者にして男女雇用機会均等法の1997年改正をすり抜けるためで、女性の労働市場での活躍を社会的要因で制限してきた女性差別そのものなのである。そして、その社会的要因は、男女の十分な雇用を作れないという理由で女性に道を譲らせたものであるため、少子化で支える人が足りないのであれば、まず女性にも100%近い正規雇用を準備すべきなのだ。短時間勤務の正規雇用労働者を作るのは契約の自由であり、全く問題ないのだから。 また、②については、繰り下げ受給の上限を引き上げて年金受給開始時期の選択肢を拡大することによって、希望により60~70歳の間で受給開始時期を自由に決められるようになるが、私は65~75歳の間で受給開始時期を自由に決められるようにして、役所や企業に定年制度を設けるなら65歳以上を義務付けるのがよいと思う。しかし、65歳をすぎると年収が減るという事実がある以上、在職中の年金支給停止の基準額を47万円(十分?)に緩和することは必要だ。 なお、「女性や高齢者の労働者が増加しているので、多様な働き方に対応しなければならない」として、「短時間労働→非正規労働者→不安定な労働者」という雇用形態を強制される場合が多い。そのため、建前と本音の異なる雇用形態を許さない労働規制も必要である。 3)高齢者の介護保険料負担増加と介護サービスの削減  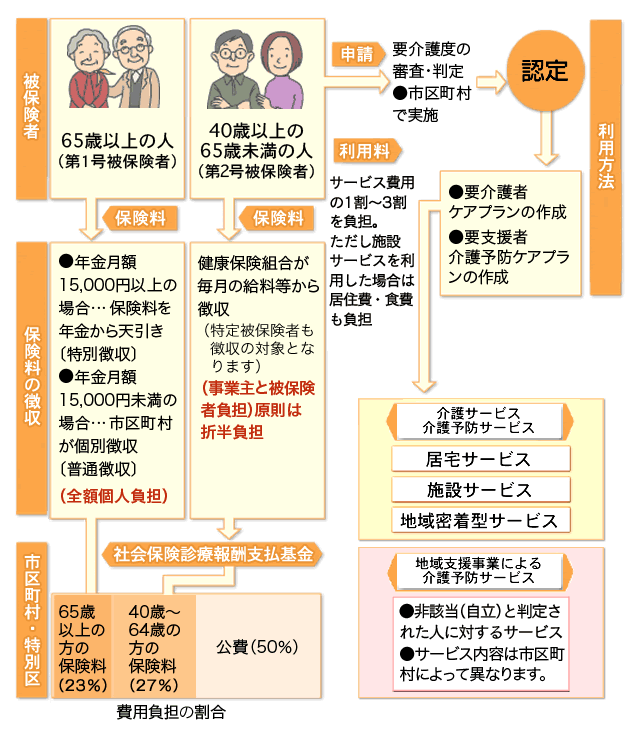  2021.11.15東京新聞 (図の説明:介護保険の財源は、左図のように、40~64歳の人が支払う保険料27%、65歳以上の人が支払う保険料23%で、残りの50%は公費《国25%、県12.5%、市12.5%》だ。この配分でおかしいのは、40~64歳と65歳以上の人口割合は毎年変わるのに負担割合を事前に決めていること、若い人口は都市に多いのに年齢構成を加味せず県・市などにも負担させているため、地方の高齢者は介護保険料は高く介護サービスは受けにくい状態になることである。また、中央の図のように、40歳以下の人は被保険者になっていないため介護保険料を支払わなくてよいが、訪問介護サービスも受けられない。しかし、若い人や子どもでも介護サービスのニーズはあるため、不便なのである。なお、収入の高い人は高い介護保険料を支払い、同じ介護サービスの利用料負担割合が収入によって異なるというのは、保険として根本的におかしい。このように歪んだ制度の中で、所得の少ない高齢者が介護保険料を滞納したからといって差し押さえするのは、共助・公助のどこから考えてもおかしいのである) イ)介護保険制度の目的は何だったか? 介護保険の財源は、上の左図のように、40~64歳が支払う保険料27%、65歳以上が支払う保険料23%、残りの50%は公費《国25%、県12.5%、市12.5%》で賄われている。この配分は、40~64歳と65歳以上の人口割合は毎年変わるのに負担割合を事前に決めていること、生産年齢人口の割合は都市で高いのに年齢構成を考えずに県・市などにも負担させているため、地方の高齢者は介護保険料は高いのに介護サービスを受けにくくなっている点で不合理だ。つまり、潜在を含む要介護者・要支援者のニーズを第1に考えた制度になっていないのである。 また、上の中央の図のように、40歳以下は被保険者になっていないため介護保険料を支払わなくてよいが、介護サービスも受けられない。しかし、新型コロナ等の感染症で浮き彫りになったように、若い人や子どもにも介護サービスのニーズはあるのに除外されており、不便なのだ。 なお、所得の多い人は介護保険料が高く、同じ介護サービスの利用料負担割合も所得によって異なるのは保険制度としておかしい。そのため、訪問看護・訪問介護は、サービスの利用料負担割合を所得によって大雑把に変えるのではなく、負担割合は同じにして医療費負担額と合計し、1カ月の合計支払額に対して所得で上限を設けるのが合理的である。 このように歪んだ制度の下、*5-3のように、介護保険制度が始まった約20年前と比べて保険料が倍以上となり、高齢世帯の家計への負担が増加して2万人超もの所得の少ない高齢者が介護保険料を滞納したからといって差し押さえするのは、共助・公助の精神から考えて変である。 さらに、*5-4のように、1人暮らしの世帯が増加しているが、高齢者は生涯単身の人より核家族化して子とは別の街に住み、配偶者を亡くした人が多い。そのため、2020年の国勢調査で単身高齢者は5年前と比較して13.3%増の671万6806人に増えたのだ。特に女性の場合は、働いたら生涯単身を強いられたという人もいれば、夫を亡くして1人残ったという人も多いため、要介護・要支援になった場合は介護制度が不可欠であり、介護を社会化した費用は働いている国民全体で負担すべきである。 ロ)看護・介護・保育の場で働く人の賃金について 政府の経済対策で、*5-1・*5-2のように、看護・介護・保育の場で働く人たちの賃金を来年2月から引き上げることが決まったそうだ。「女性が主として働く職場の平均賃金は安く、男性が主として働いていた職場に女性が入っていくと、ガラスの天井がある」というのは、1980年代に米国で言われたことだが、日本は40年遅れの2020年代でもそうなのである。 従って、労働量と責任に見合った賃金にしなければ人材が集まらないのは当然のことだが、「さらなる高齢者の負担増・サービス減になるのなら本末転倒なので、どういう財源を使って賃上げするのか」と、私は思っている次第だ。介護保険制度に基づく介護や支援については、働く人全員が支払うようにする形で薄く広く国民負担増を行うのが、歪みを是正しながら労働量と責任に合った賃金を支払い、高齢者の負担増・サービス減に陥らない唯一の方法だと、私は思う。また、介護は、介護保険制度に基づくサービスと全額自己負担によるサービスの両方を提供できるようにする方法もある。 しかし、*5-5のように、日本は、労働力確保の有力な選択肢であり、人口対策でもある外国人労働者の割合が、諸外国に比べて著しく少ない。そのため、私もせっかく日本で技術を覚えた外国人材を冷遇するのは、人権侵害であるのみならず、日本の国益にも反していると思う。 ハ)日本の設備投資が停滞した理由は何か *5-6は、①この20年間で米・英の設備投資は5~6割伸びたが、日本は1割弱しか増えなかった ②日本企業は海外で積極的にお金を使い、利益を国内投資に振り向けない ③設備の更新が進まなければ労働生産性が高まらず、人口減の制約も補えない ④成長の壁としてよく指摘されるのは人口減少や少子高齢化だが、設備投資の停滞も低成長の構造要因として直視する必要がある ⑤就業者は10年間で378万人増え、特に女性や65歳以上の働き手が多くなった 等と記載している。 しかし、どの国の企業であっても、ROAやROEの高い場所で投資しなければ継続できず、日本は、(3)の図にある通り、ROAやROEが高くないのが①②の原因である。そうなる理由の1つは、人件費・不動産コスト・水光熱費等のコストが高いため、製造しても利益率が低いからだ。それなら、優れた新製品を開発して付加価値を上げればよさそうだが、再エネやEVを開発しても政府は火力や原発に固執して後押しするどころか妨害する始末だったし、ワクチンや治療薬の開発もやりにくいのである。そのため、日本で新技術に投資するのはリターンよりもリスクの方が大きく、これらは政府や省庁のセンスの悪さに起因するものではあるが、メディアもその一部を担っていることは否めないだろう。 また、③の設備更新は、今後、何をどういう方法で製造するのか、それを日本でやると稼げる仕事になるのかが明確になって初めて行えるものであるため、その環境が整っていなかったということだ。さらに、④の「人口減少や少子高齢化が成長の壁」などと指摘する人は、1人1人が豊かになることは目指しておらす、1人1人は貧しいまま国民の数を増やして需要を増やそうと考えているのであるため、やはりセンスが悪い。 なお、⑤については、女性や高齢者の働き手が多くなることは、その人たちの人権や職業選択の自由のために必要なことであるため、それを無視してよいかのような言動はおかしい。また、機械の設備更新は少なかったかもしれないが、介護・保育・学童保育など必要性が明確な施設への設備投資は行われてきたため、従来型の設備投資の定義が狭すぎるのではないかと思う。 (5)合理性のある家族の所得合算と世帯人数での分割 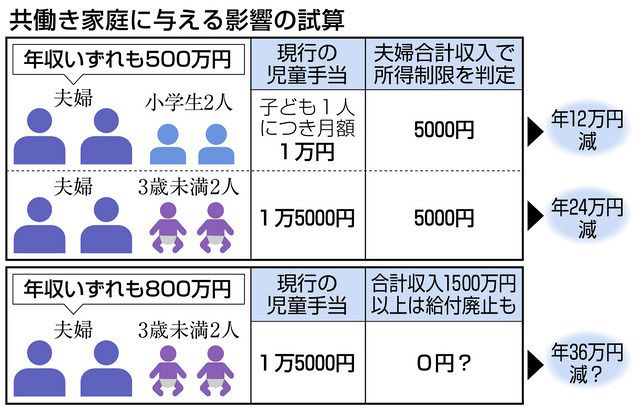 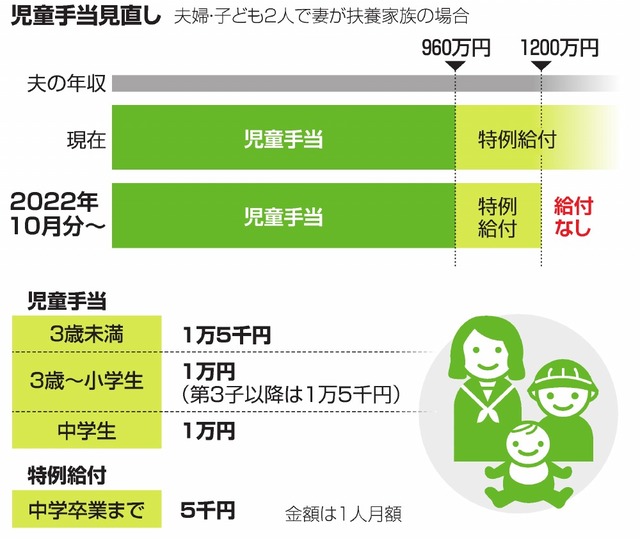 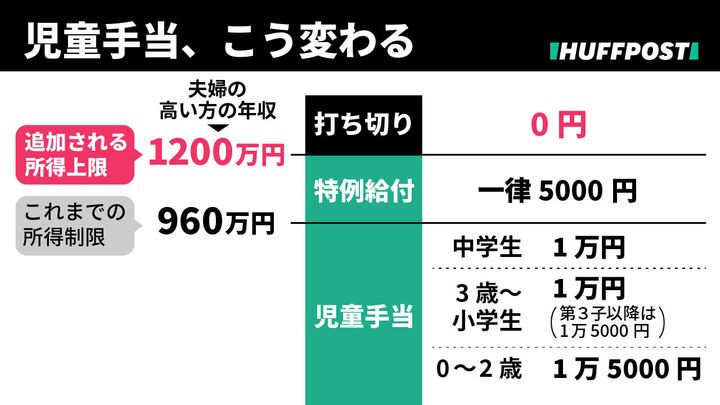 2020.11.14中日新聞 2021.5.21朝日新聞 2020.12.16Huffingtonpost (図の説明:左図のように、児童手当の支給基準は「夫婦のうち年収の高い方が960万円以下」であるため、共働きのケースが有利だと指摘された。また、現在の児童手当は、中央と右図のように、年収の高い方が960万円超の家庭に特例給付が支給されているが、2022年10月以降は特例給付も1200万円以下までとなり、1200万円超の家庭にはなくなるそうだ) 18歳以下の子を対象にした10万円相当給付の所得制限に、夫婦の年収の高い方が960万円以下か否かで支給対象を判定する児童手当の仕組みを利用するため(https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/kaidai/14.html 参照)、*6-1・*6-2のように、「高収入の共稼ぎ夫婦にも支給されることが起こりうる」と与党内からも指摘があるそうだ。 2020年には共働き世帯数が専業主婦世帯の2倍を超え、世帯合算を導入している制度には、低所得世帯向け大学授業料の負担減・返済不要の奨学金支給・私立高校の授業料支援・0~2歳児の保育所利用料等があり、児童手当への世帯合算導入も話題になっているとのことである。 しかし、世帯合算を導入するのなら、配る時だけでなく所得税等を徴収する時にも世帯合算を選択できるようにしなければ、政府は都合がよすぎる。ちなみに、米国は1948年に所得税の徴収に2分2乗方式の世帯合算選択制を導入し、フランスは1946年にn分n乗方式の世帯合算制を導入している。 金額を入れ単純化して世帯単位課税を説明すると、A)夫1人だけで1,000万円の収入があり、子が2人の世帯は、米国の2分2乗方式では、500万円(1,000/2)を1人あたり世帯所得基準として累進課税を行う世帯単位課税を選択できる。一方、フランスのn分n乗方式では、333万円(1,000/《1+1+2/2》)を1人あたり世帯所得基準として累進課税を行う。何故なら、n分n乗方式では、子も1/2人としてカウントするからで、私は、フランス方式の方が所得のない配偶者や子に対して低額の配偶者控除や扶養控除を認めるよりも生活実態にあっていると思う。 一方、B)夫600万円、妻400万円、合計1,000万円の収入があり、子が2人の世帯は、米国の2分2乗方式では500万円(《600+400》/2)を1人あたり世帯所得基準とし、フランスのn分n乗方式では、333万円(《600+400》/《1+1+2/2》)を1人あたり世帯所得基準として累進課税を行うので、A)と変わらず公平である。しかし、合算した方が実態にあっている夫婦ばかりではないため、個人課税と合算課税を選択できることとし、合算した場合の累進税率を有利にすることで、結婚や子育てを支援した方がよいと思う。 この税制を採用すると、A)のケースでは、今まで1,000万円を基準として所得税の累進税率を決めていたのに、米国方式なら500万円・フランス方式なら333万円を基準として累進税率を決めることになるため、税率が低くなって国の歳入が減るという反対論が必ず出る。しかし、これが真の生活実態であり、原因は女性を働きにくくさせている社会制度にあるため、税収を増やすには女性も働いて同一労働・同一賃金で所得を得られる仕組みに変更することが必要なのである。そして、これは時代の要請でもある。 さらに、女性が働く時、家事をすべて家族内でこなすことを前提とするのは、職場での責任と家事の労働量・責任負担の両方を過小評価しすぎており、これらを両立させたことのない人の発想だと、前から思っていた。私は、家事を外部委託した場合のコストは、収入から差し引かれる経費として控除できるようにすべきだと思うし、収入に応じて高い保育料を徴収するというのは論外だと思っている。 従って、*6-3のように、改正児童手当法が、高い方の年収が1200万円以上の世帯に支給している月5千円の「特例給付」も廃止するというのは、やはり世帯の生活実態を反映しておらず、小手先の小さな財源確保策にしかなっていないので考え直すべきである。 (6)こども庁は必要か 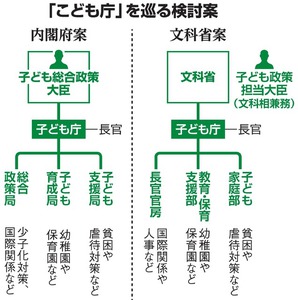 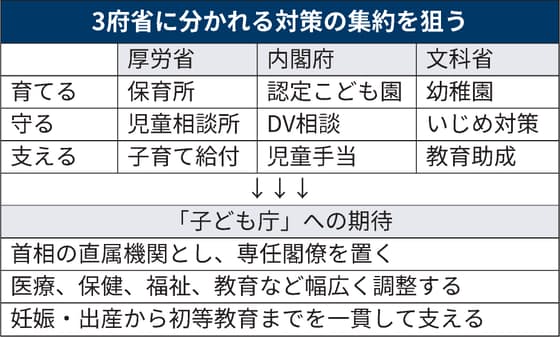  2021.4.10朝日新聞 2021.4.13日経新聞 2021.9.23Yahoo (図の説明:中央の図の上に書かれているように、3府省にわかれている縦割りを廃し、子どものためになる施策を行うべきではあるが、左図のように、新しい庁を作って慣れない人が担当すると、サービスの内容はむしろ後退する。そのため、幼保一元化をすればよく、そのモデルが認定こども園なのだ。なお、右図のように、新しい庁を作っても予算と人員が増えて縦割りと根回しすべき相手が増えるだけでは生産性や効率がさらに落ちるので、これまで子ども政策の何が不十分だったのかを徹底的にチェックし、正確に原因分析してそれを解決する方が重要である) 1)子ども庁は2元制を3元制にしそうであること 2001年1月施行の中央省庁再編の目的は、①縦割り行政による弊害をなくし ②内閣機能を強化し ③事務・事業を減量・効率化することで、1府22省庁から1府12省庁に再編された。 このうち、②の内閣機能の強化は少しは進んだが、①は全くできていない。また、③は、「小さな政府」にして政府の無駄遣いを排除し、国民負担を軽減することを意図していたのだが、「『小さな政府』とは夜警国家のことで、社会保障が無駄遣いである」と意図的に間違った解釈をし、次に「『小さな政府』や『新自由主義』がいけない」と言い始め、その結果、改革努力もむなしく大きな政府に戻す流れになっているのだ。従って、Planはよかったが、Doの段階で元に戻す力が働いたため、「何故、こうなるのか」についてCheckしながら考察する。 なお、私は、「産業側に立つ省ではなく、消費者側に立つ省が必要だ」という理由で消費者庁の創設は進めたが、「こども庁」の創設意義については不明だと思う。そのため、庁と人員を増やして予算を無駄遣いするだけで、2001年1月施行の中央省庁再編の意義が問われるのではないかと考えているのだ。 そのような中、*6-5は、④政府は子ども政策の縦割りを排し、政策立案や強力な総合調整機能を持たせる『子ども庁』を内閣府の外局として新設して担当閣僚を置く ⑤これによって、少子化・貧困・虐待などの問題を解決する ⑥幼保一元化は進んでおらず、厚労省所管の保育所と内閣府所管の認定こども園は子ども庁に移すが、幼稚園は文科省に残す ⑦原案は文科省と子ども庁が相互に内容に関与しながら「教育は文科省」を強調しており、現場の分断を深める恐れがある ⑧子どもの問題は組織をつくれば解決するものではなく、大切なのは具体的施策と裏付けとなる財源 ⑨それには高齢者に偏る社会保障の財源を子どもに振り向けるなど、痛みをともなう改革も必要 というようなことを記載している。 しかし、⑤のうちの虐待は、情報収集力や強制力のある組織(学校・病院・児童相談所・警察等)が連携してしっかり見守り、危機を察知したら行動に繋げられる仕組みでなければ機能しないため、これらの組織の機能不全が何故起こったのかについての原因分析をして改善しないまま、民間人等の強制力のない人が子の意見を聞いてもたいしたことはできない。 また、⑤のうちの貧困は、親の教育や雇用環境などの政府がこれまで行ってきた政策の付けであって、親子の心の問題ではないため、カウンセラーが話を聞けば解決できるようなものではない。さらに、⑤のうちの少子化は、上で示したような時代に合わない政策の結果であるため、解決するには原因を取り除かなければならず、新しい組織や器を作って二重・三重に予算をつければ解決するものではないのである。 さらに、⑥の認定こども園は、幼保一元化するために作った制度なので、認定こども園ができると同時に保育所と幼稚園は認定こども園に衣替えして幼保一元化が進んで縦割りはなくなるのかと思っていたら、両者とも併存したため二元制度が三元制度になったのだ。これは、各省が既得権を守ったものであるため、④のように、「子ども庁」設置して担当閣僚を置けば、子ども政策の縦割りが排され、強力な総合調整機能が持てるかについても、大いに疑問なのである。 つまり、*6-4の「『器』より中身が重要だ」というのに私は賛成だ。ただ、「こども庁」を内閣府の下部に創設して保育所に関する部署は厚労省から内閣府に移し、保育所はすべて認定子ども園としたり、幼稚園は文科省に残して小学校の義務教育期間を3歳からにし、幼稚園を小学校と合併するのなら時代のニーズにあっているため、⑦も含めて賛成である。 なお、「子ども庁」を“少子化対策”のために創設するというのもセンスが悪いと思うが、これまでの政策が少子化を促進してきたのなら、その原因の一つ一つを取り除かなければならないのであり、えいやっと「子ども庁」を創って予算をつけたら改善するわけではない。 そして、財源論となると、⑨のように、「高齢者に偏る社会保障を子どもに振り向けるなど、痛みをともなう改革も必要」とし、社会保障は高齢者に偏っているという誤った前提の下、生産年齢人口に対する膨大な無駄遣いは無視したまま、本物の産業振興はせずに、厚労省内の予算の奪い合いに帰着させ、高齢者に痛みを押し付ければよい改革であるかのように言っている点で稚拙で勉強不足なのである。 また、「子どもまん中」というのは、「子ども以外は従である」という意味であるため、日本国憲法「第11条:基本的人権の尊重」「第14条:法の下の平等」「第25五条:生存権(*参照)」等に違反している。そのため、そういうことを言うのは情けない限りで(https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji003833/3_833_3_up_i1gdnvnk.pdf 参照)、子に対してこういう教育をしていれば、日本国憲法を無視し、他人を軽視する人を再生産することになる。 *日本国憲法 第25五条 ①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上 及び増進に努めなければならない。 2)中国の産業高度化と成長戦略について 日本は、比較的技術力の低い製造業は新興国に移され、技術力の高い製造業に変換することにも失敗している(https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190611002/20190611002_07.pdf 参照)。しかし、経済成長や産業高度化のためには、そうなってしまった原因を分析して変革することが重要で、前だけ見ていては原因分析もできない。 そのような中、*6-6によれば、①中国の地方都市は競い合うように人材誘致を進めて世界中の研究者を引き込もうとしており ②72歳以下の引退した教授なら、国籍や学科を問わず、A級ランクで給料120万元(約2,100万円)以上、住居購入費350万元(約6,200万円)、赴任手当110万元(約2千万円)、研究費等毎年200万~1,000万元(約3,600万~1億8千万円)、合計780万~1,580万元(約1億4千万~2億8千万円)以上で ③医療保険・交通費を準備され配偶者も同伴可で ④勤務先は中国の大学・研究機構・大企業の研究所等で ④日本の専門家への期待は、日本が競争力を持つ素材・自動車・産業機械分野で日本語で募集している そうであるため、該当する人なら行きたくなるのも無理はない。 また、⑤帰国する中国人留学生も過去10年で約5倍に膨らんで年間58万人(2019年)となり ⑥研究開発費は過去20年で約27倍(人民元建て)にもなって米国に次ぎ ⑦米国の大学で理系博士号を取得した中国人は5,700人(2020年)で、10年で7割近く増え ⑧引用回数が上位10%に入る「注目度の高い論文」(2017~2019年平均)で、中国は米国を抜いて初めて世界首位になった そうで、これらは、産業の高度化と成長戦略として正攻法である。 一方、日本は、早めの定年制で熟練技術者を新興国に供給して新興国の技術力を高めたが、自国の競争力は弱めたし、教育・研究も環境整備を疎かにしてきたため人材が多くは育たず経済停滞の原因になっている。そのため、情報管理の強化は必要だろうが、「技術流出の懸念」と言える時代は既に過ぎてしまったことの方が大きな問題なのである。 ・・参考資料・・ *1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211127&ng=DGKKZO77947650X21C21A1EA4000 (日経新聞 2021.11.27) 補正で膨らむ予算、常態化、緊急性低い事業も相次ぎ計上、使途の点検・監視不可欠 政府が26日決めた2021年度補正予算案では、査定が甘くなりがちな補正で予算を大幅に上積みする手法の常態化が鮮明となった。成長につながるかどうか不透明な事業や補正で緊急に手当てする必要性が乏しい公共事業なども盛り込まれている。予算の使い道の点検・監視が欠かせない。補正予算案は12月6日に召集される見通しの臨時国会で審議される。経済対策に計上した31.5兆円超の約6割弱は新型コロナウイルスの感染拡大防止に充てる。病床確保の支援金に2兆円を盛り込んだ。成長戦略向けの支出の比率は約2割で、半導体の国内生産拠点の確保に6170億円、経済安全保障の一環で先端技術を支援する基金に2500億円などを積んだ。低所得世帯向けの10万円給付には1.4兆円、18歳以下への10万円相当の給付は21年度予備費からの拠出を含め1.9兆円を充てる。このほか最大250万円の中堅・中小事業者向けの支援金2.8兆円、資金繰り支援の1400億円などを盛り込んだ。看護師・介護士・保育士らの処遇改善には2600億円を投じる。本来、補正予算の編成は財政法で「(当初)予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費」に限って認められている。それが近年は補正を抜け穴に予算を膨らませるのが当たり前のようになっている。社会保障や公共事業など恒常的に必要な経費を積み上げる当初予算の規模は、翌年度以降の目安となりやすい。このため財務省はできるだけ厳しく査定する。補正予算の査定は比較的甘いとされる。一時的な措置であることが建前上の理由だ。一橋大の佐藤主光教授は「財務省が当初予算をむりやり絞るため、穴の空いたバケツとなり、補正予算が要求の主戦場となっている。構造的に必要な支出であれば、本来は税を確保して当初予算で対処すべきだ」と指摘する。「中小企業の構造転換を進める補助金を打ち出す一方で、転換を阻害しかねない減収企業への支援金も盛り込んでいる。本当に成長につながる投資になるのかも精査する必要がある」とも話す。今回の補正でまかなう経済対策は、成長と分配の両立に向けた産業構造や社会構造の変革が「喫緊の課題」とうたう。実際の中身は必ずしも「緊要」「喫緊」と言えないような事業も目立つ。例えば防災・減災対策として国土強靱(きょうじん)化計画の関連事業に1.2兆円を割いた。この計画は20年末に閣議決定し、5年間で15兆円を投じてダムや堤防などを集中的に整備する目標を掲げた。このタイミングの補正で改めて扱う理由は明確ではない。国土交通省は22年度予算案の概算要求にも関連事業を盛り込んだ。治水や高速道路網の整備などの内容はほぼ同じで、補正予算に前倒しする趣旨は曖昧だ。国交省内でさえ「本来は経済対策ではなくて当初予算で措置すべきものだ」とささやかれる。総務省は高齢者らのオンライン行政手続き利用を支援する事業に3億3000万円を計上した。内閣府も「デジタル田園都市国家構想推進交付金」の事業費として200億円を計上する。使途の一部は高齢者らにスマートフォンの使い方を指南する「デジタル推進委員」の全国展開などで、重複感は否めない。コロナが広がった20年度は3度にわたる補正で一般会計の歳出総額が175兆円を超え、過去最大となった。危機対応の財政出動や柔軟な予算編成はもちろん必要だ。問題は実態だ。補正が無駄なバラマキを招いていないか、検証が欠かせない。 *1-2:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20211127&c=DM1&d=0&nbm=・・ (日経新聞 2021.11.27) 国債残高1000兆円突破へ 10年で1.5倍、財政悪化の底見えず 政府は2021年度補正予算案の財源として国債を22兆円追加発行する。21年度末の残高は初めて1000兆円を突破する見通しとなった。規模ありきで成長の芽に乏しい予算づくりを見直さなければ、経済が停滞したまま債務だけが膨らむ状況に陥りかねない。21年度の国債発行額は当初予算から5割増の65兆円超に膨らむ。3度にわたる補正予算編成で112兆円を超えた20年度に次ぐ規模となる。リーマン・ショック直後の09年度の52兆円を2年続けて上回る。税収で返済しなければならない赤字国債や建設国債など「普通国債」の残高は今回の補正予算案による上積みで、21年度末時点で1004.5兆円となる見通し。21年度当初予算の段階では990兆円と見込んでいた。10年度の636兆円から10年あまりで1.5倍以上に膨らんだ。財政の悪化は底が見えない。国際通貨基金(IMF)によると、日本の国内総生産(GDP)比の政府債務残高は21年は米国のほぼ2倍の257%に達する。主要7カ国(G7)で最悪の水準が続く。日本は12年末に発足した第2次安倍政権以降、経済成長によって財政健全化をめざす姿勢を鮮明にしてきた。実際は目標の実質2%成長が実現したのは13年度だけ。大規模な財政出動や異例の金融緩和で景気をなんとか下支えしてきたのが現実だ。結果として、低成長のまま債務が増大する流れが続いている。財政頼みの構図は簡単に変わりそうにない。「追加的な対応なくしては、来年度にかけて公的支出が相当程度減少することが見込まれる」。政府は19日に決めた経済対策で、財政出動の息切れによる「財政の崖」が景気を下押しすることに懸念を示した。家計や企業の目先の支援に追われるコロナ対応の危機モードがなお続き、中長期の成長力を底上げする「賢い支出」の視点は乏しい。これから編成作業が本格化する22年度当初予算案では、経済対策に盛り込んだコロナ対応予備費5兆円も計上する方向だ。予備費は政府が国会の議決を経ずに使い道を決める。本来は安易な予備費の計上は避けるべきだ。巨額の枠が縮小できずに残り続ければ財政のさらなる重荷となる。 *1-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/771250 (佐賀新聞 2021/11/19) 「分配」柱に78・9兆円、子育て支援、GoTo再開も 政府は19日、新型コロナウイルス禍を受けた経済対策を臨時閣議で決定した。岸田文雄首相が掲げる「分配政策」を柱に据え、子育て世帯や所得が低い家庭などを幅広く支援する。地方の活性化につながる観光支援事業「Go To トラベル」の再開も明記した。国と自治体の財政支出は過去最大の55兆7千億円、民間の支出額などを加えた事業規模は78兆9千億円に上った。財源の不足分は新たな借金に頼る。裏付けとなる2021年度補正予算案を26日に決め、12月中旬の成立を目指す。首相は臨時閣議前の経済財政諮問会議で「経済を立て直し、一日も早く成長軌道に乗せていく」と述べた。対策は4分野で構成した。「新型コロナ感染拡大防止」では、3回目のワクチン接種も無料にすることを打ち出した。売り上げが急減した中小事業者に最大250万円の「事業復活支援金」を配り、住民税が非課税の家庭に1世帯10万円を給付。企業の休業手当を国が補う「雇用調整助成金」の特例措置の延長や、ガソリン価格を抑える原油高対策も盛り込んだ。「社会経済活動の再開と危機への備え」としてGoTo事業を再開し、国産ワクチンの研究開発・生産体制を強化する。「『新しい資本主義』の起動」には、18歳以下の子どもを対象とした10万円相当の給付、マイナンバーカードの新規取得者や保有者に対する最大2万円分のポイント付与、保育士、介護職、看護師の賃上げを明記した。経済安全保障の一環で先端半導体工場の国内立地を後押しし、国内の温室効果ガス排出を実質ゼロにする50年の脱炭素社会実現に向け「政策を総動員する」とした。最後の「安全・安心の確保」では、大規模災害に備えるために防災・減災を強化し、防衛力を増強する方針を示した。21年度補正予算案には幅広い政策に使うお金を管理する一般会計と、使い道を限定した特別会計の合計で31兆9千億円を計上する。来年夏の参院選をにらみ「30兆円超」の補正を求める与党の声に配慮した。22年度当初予算案では、前年度と同じ5兆円の新型コロナ対策予備費を手当てし、23年3月までの「16カ月予算」として切れ目なく景気をてこ入れする。経済対策の財政支出は、安倍政権が20年4月に策定した48兆4千億円がこれまでの最大だった。 *1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211120&ng=DGKKZO77759050Q1A121C2MM8000 (日経新聞 2021.11.20) 経済対策、見えぬ「賢い支出」 最大の55兆円、分配重視、首相「赤字国債など総動員」 政府は19日の臨時閣議で、財政支出が過去最大の55.7兆円となる経済対策を決めた。岸田文雄首相は日本経済新聞などのインタビューで、赤字国債発行も含めて財源を確保すると説明した。未来の成長を呼び込む「賢い支出」とは言いがたい項目が目立ち、目標とする「成長と分配の好循環」につなげられるかは見通せない。民間資金も入れた事業規模は78.9兆円と経済対策としては過去2番目に膨らんだ。内訳をみると、分配を重視する岸田政権の方針が色濃い。18歳以下の子どもへの1人10万円相当の給付や、低所得の住民税非課税世帯への10万円の支給はその代表例だ。一時的な消費拡大にしかつながらないこれらの個人向けの給付はざっと5兆円に及ぶ。新型コロナウイルスで減収に陥った事業者には最大250万円を支援する。規模ばかりが先行し、財源の裏付けは万全とは言えない。今回は2021年度補正予算案に一般会計で31.6兆円を計上する。首相は「赤字国債はじめあらゆるものを動員する」と言明した。消費税に関しては「触ることを考えていない」と述べ、増税には慎重な姿勢を示した。大型の財政支出は財源と一体で議論するのが世界の潮流だ。米国で15日に成立したインフラ投資法では道路・橋の修復など5500億ドルの歳出を既存のコロナ関連予算の振り替えなどでまかなう。雇用計画や教育支援などの家族計画には、法人税の引き上げや所得税の最高税率上げを盛り込んでいる。首相はインタビューで「経済の再生を行い、そして財政についても考えていく。これが順番だ」と語り、当面は経済の立て直しを優先する姿勢を鮮明にした。肝心なのは経済対策をどう中長期的な成長に結びつけるかだ。首相は成長戦略として、科学技術立国、地方からのデジタル化、重要な物資確保や技術開発といった経済安全保障の3本柱を挙げた。「国の予算が呼び水になり、民間の投資や参加につなげていく方向性が重要だ」と訴えた。具体例として米国の半導体メーカーの誘致にふれた。人工知能(AI)や量子分野といった先端技術支援の基金などに5000億円規模を盛り込んだが、力不足は否めない。首相は規制改革についても「成長戦略を進める上で必要なものはしっかり考えていく」と強調した。ただ、コロナ感染を調べる「抗原検査キット」のインターネット販売の解禁は今回の対策から外れた。業界の反対論を打破できなかった。コロナ対策では、病床確保のための補助金を積む。今夏の第5波では病床確保料を受け取りながら、すぐに患者を受け入れない「幽霊病床」が問題になった。首相は「ポイントは見える化だ」と指摘し、病院別の病床使用率や地域のオンライン診療の実績公表に取り組む考えを示した。 *1-5:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20211120&c=DM1&d=0&nbm=・・・ (日経新聞 2021.11.20) これで日本は変わるのか 未来を切り開くのか、過去に戻るのか。どちらを向いているのか分からない経済対策だ。岸田文雄首相が「数十兆円規模」といっていた対策は、ふたを開ければ財政支出だけで55兆円に膨らんだ。「過去最大」という見かけにこだわり、使い道をよく考えないまま額を積み上げたとしか思えない。かつて何度も見てきた光景のような気がする。バブル崩壊後、歴代政権は繰り返し巨額の経済対策を打ち出してきた。どれもうまくいったとは言えない。日本が歩んだのは「失われた20年」という停滞の時代だ。デフレ下では、借金を重ねてでも財政を通じて需要を底上げする必要がある。問題は使い道だ。過去の経済対策は無駄な公共事業や一時的な消費喚起策に偏っていた。将来の成長につながる「賢い支出」に知恵を絞ってきたとは言いがたい。今回も同じ轍(てつ)を踏んでしまったのか。対策の柱として目立つのは、家計や企業への給付金ばかりだ。一部が消費に回ったとしても、一時的な需要をつくり出すにすぎず、持続的な成長にはつながらない。本来やるべきは、生産性を高めるデジタル化や世界が競う脱炭素の後押しだ。人への投資や規制緩和を通じ、成長分野に人材が移動しやすくする改革も急がなければならない。今回の対策で、そうした分野に十分なお金が回るとは思えない。世界はすでに新型コロナウイルス後を見据えた成長競争に入っている。米中対立が収まる気配を見せないなか、日本はそのはざまで独自の強みを持たなければ生き残っていけない。日本はやはり変わらないのか。成長せずに借金だけが膨らむ。先祖返りしたかのような規模ありきの対策は、次の世代にそんな日本を引き継ぎかねない。 *1-6:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/834990/ (西日本新聞社説 2021/11/21) 新たな経済対策 規模を追わず質を高めよ 来夏の参院選を意識するあまり、大盤振る舞いが過ぎるのではないか。岸田文雄政権が19日に閣議決定した経済対策のことである。国と地方が支出する財政支出が55兆7千億円に膨らみ、過去最大となった。民間支出分などを加えた事業規模は78兆9千億円に達している。安倍政権時代に新型コロナウイルス感染症が急拡大し、国民に一律10万円の支給を決めた昨年4月の経済対策の財政支出が48兆円超だった。この際も議論を呼ぶ規模だったが、今回はそれをさらに大きく上回る。当時に比べ国内の感染状況はかなり落ち着いてきた。国民が期待する経済対策とはいえ規模を追うのではなく、質を高めることにもっと注力すべきだ。与野党ともに「ばらまき合戦」の様相を呈した衆院選で勝利した与党の要請は無視できず、規模優先になったとみられる。「成長と分配の好循環」の議論が影を潜め、既視感の強いメニューが並んだのは残念だ。対策の4本柱は、新型コロナ対策、次の危機への備え、新しい資本主義起動、安全・安心の確保だという。医療提供体制の拡充が最優先なのは論をまたない。感染者が自宅待機を強いられ、そのまま亡くなるような悲劇を繰り返してはならない。欧州などでは感染が再び拡大している。医療機関の受け入れ体制強化など第6波への備えは不可欠だ。コロナ禍に苦しむ生活困窮世帯などに必要な支援を急がねばならず、日本経済の立て直しや潜在成長率を引き上げる取り組みも重要である。製造業などの業績が急回復する一方、コロナ禍で厳しい状況の中小事業者は多い。事業継続のための支援を早急に届ける必要があろう。公明党が衆院選公約に掲げた18歳以下への10万円相当の給付も盛り込まれた。子育て支援策としても経済対策としても効果は限定的との見方が大勢だ。所得制限が設けられたとはいえ、その基準は緩い。選挙目当てのばらまきとの批判は根強い。対策の財源は、2020年度の決算剰余金と21年度の補正予算、22年度予算で手当てされるが、結局は赤字国債である。日本経済の回復は欧米や中国などより遅れている。今年7~9月期の実質国内総生産(GDP)は年率3・0%減のマイナス成長だった。民間調査機関によれば、21年度の成長率は政府年央試算の3・7%を下回る見通しだ。昨年来のコロナ禍で繰り返された巨額の経済対策には、政府が想定した効果があったのか。その点をしっかりと見極める国会での審議を求めたい。 <具体的には> *2-1-1:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20211127&c=DM1&d=0&nbm=・・ (日経新聞 2021.11.27) 防衛費、最大の7700億円 当初と合わせ6.1兆円、GDP比1%超 政府は26日に決定した2021年度補正予算案で防衛関係費に7738億円を充てた。補正予算で計上する額としては過去最大となった。当初予算とあわせると6.1兆円で、当初と補正をあわせた防衛費は国内総生産(GDP)比で1%を超して1.09%となる。当初予算と補正予算を単純合算した額がGDP比1%を超えたのは2012年度以降の10年間で8回あった。21年度のGDP比の水準は10年間で最も高い。哨戒機や輸送機といった装備の取得計画を前倒しし、自衛隊の警戒監視や機動展開の能力向上を急ぐ。日本周辺で活発な軍事活動を続ける中国への対応を念頭に置き、防衛力を強化する。不審な船舶や潜水艦の監視に使うP1哨戒機の3機の取得に658億円を計上した。自衛隊員や物資の大規模輸送に使うC2輸送機も243億円で1機導入する。ともに22年度予算の概算要求に盛り込んでいた。前年度の補正予算で発注することで納期を3カ月から半年程度前倒しし、早期に部隊に配備する。北朝鮮による相次ぐミサイル発射の対策も推進する。地上から迎撃する地対空誘導弾パトリオットミサイル(PAC3)について、これまでより防御範囲が広い能力向上型の取得を進める。441億円を措置する。沖縄県の米軍普天間基地(宜野湾市)の名護市辺野古への移設に801億円を充てる。戦闘機に搭載する空対空ミサイルや魚雷など、弾薬の確保にも予算を投じる。 *2-1-2:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/869702 (沖縄タイムス 2021.12.2) 沖縄県が不承認した新基地建設 国は工事継続 変更承認申請の対象外で 801億円補正予算 松野博一官房長官は26日の記者会見で、名護市辺野古の新基地建設を巡り、県が不承認とした変更承認申請の対象外の工事について継続する方針を示した。不承認に対する政府の対抗措置は「不承認処分の理由の精査を進める」と述べるにとどめた。岸信夫防衛相も「辺野古移設が唯一の解決策」と現行の工事を進める考えを示した。防衛省は2021年度補正予算案に、辺野古の埋め立てに801億円を計上。辺野古側海域のかさ上げ工事が予定より早く進んでいるとして、作業ペースを加速させる。 岸氏は同日の会見で、日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険性除去を考え合わせた場合、「辺野古移設が唯一の解決策」と述べ、着実に工事を進めるとした。現行計画を再検証する考えについては「今の計画が唯一」と述べた。同省は行政不服審査法に基づく審査請求などの対抗措置を検討している。補正予算案について同省は「補正の活用は辺野古移設を前に進めたいという意識の表れ」と説明。少しでも建設を早めることで、普天間飛行場の固定化につながらないよう基地負担軽減を図るとした。埋め立てている辺野古側の区域「(2)」と「(2)-1」は陸地化が完了し、高さ4~7メートルまでのかさ上げ工事に入っている。同省によると、4メートルまでの埋め立ては予定よりも約6カ月早く終えた。4~7メートルまでの埋め立ての進捗(しんちょく)(10月末現在)は「(2)」が2割、「(2)-1」が5割で、年度内の完了を目指す。最終的には最も高い地点で10メートルまでかさ上げする計画。松野氏は会見で、現在進めている工事は「すでに承認されている事案で進めていく」と説明。政府としては「地元の理解を得る努力を続けながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現するため全力で取り組んでいく」と述べた。政府として対抗措置を取るかどうかは「沖縄防衛局において不承認処分の理由の精査を進めていく」と述べ、慎重な姿勢を示した。 *2-1-3:https://news.yahoo.co.jp/articles/5f6744ddce1e1f4cafbe531903e61fa81143f639 (Yahoo、八重山日報 2021/11/9) 石垣島駐屯地22年度開設 作業員宿舎建設に着手 プレハブ11棟、最大500人宿泊 石垣島平得大俣地区の陸上自衛隊駐屯地建設に向け、防衛省は8日、宮良地区で仮設作業員宿舎の建設に着手した。島外から来島する作業員が宿泊する施設となる。駐屯地は2022年度の開設を予定しており、今後、隊庁舎などの建設作業が急ピッチで進む。防衛省は19年3月から駐屯地の用地造成工事に着手し、順次、隊庁舎などの建物の建設工事に着手している。沖縄防衛局は8日の八重山日報の取材に対し、駐屯地開設時期について「2022年度に開設する計画」と明示した。関係者によると、仮設作業員宿舎は宮良地区で民間企業が所有する旧パチンコ店敷地内に設置する。2階建てのプレハブ11棟を設置し、最大500人の宿泊が可能。旧店舗は改修し、食堂として利用する。8日には建設業者らが現場を訪れ、今後の作業工程などを協議する姿が見られた。沖縄防衛局は「施設が完成し次第、新型コロナウイルス防止対策と作業員に対する交通安全教育を行った上で、利用を開始する予定」としている。市幹部は「コロナも落ち着きつつある。500人が来島すれば一定の経済効果が期待できる」と話した。近年、八重山での大型公共工事は島内だけで作業員を確保するのが困難で、建設業者に渡航費や宿泊費を支払って島外から作業員を来島させるケースが増えている。防衛省が駐屯地外に設置する隊員宿舎の建設も本格化する。建設場所は市有地2カ所と旧民有地3カ所を予定しており、旧民有地の隊員宿舎建設に向け既に建設業者と工事請負契約を締結。このうち2カ所は工事に着手した。残る1カ所も「準備が整い次第着手する」としている。沖縄周辺で中国の脅威が増大する中、防衛省は南西諸島防衛強化の一環として石垣島への自衛隊配備計画を進める。警備部隊、地対艦ミサイル部隊、地対空ミサイル部隊を配備し、総勢500~600人規模を想定している。奄美大島、宮古島、与那国島でも陸自駐屯地が開設されており、南西諸島での駐屯地新設は現時点で石垣島が最後となる。 *2-1-4:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1203719.html (琉球新報 2020年10月7日) 宮古、石垣の自衛隊基地建設「工事止め丁寧に説明を」 玉城沖縄知事が防衛相へ要請 玉城デニー知事は7日午前、岸信夫防衛相と大臣就任後初めて面会し、宮古島市や石垣市で進む自衛隊基地の建設工事について、地域の理解を得るため「折々に工事を止めて、住民の皆さんに丁寧に説明をして頂きたい」と述べ、説明のため工事を一時停止するよう求めた。岸氏は先島への自衛隊配備計画について「いろいろ地元のご意見があることはよく承知している。宮古島市、石垣市ともしっかり調整し、今後も必要があれば住民の皆さんに説明していけるよう努力する」と述べるにとどめたという。米軍普天間飛行場の移設問題で玉城知事は「辺野古移設によることなく、普天間飛行場の1日も早い危険性の除去と閉鎖・返還」を訴えるとともに、県と国による対話の場を設けるよう求めた。岸氏は「これからも対話の場を作っていけるよう努力する」と話した。辺野古移設への言及はなかったという。会談は非公開で行われた。 *2-2:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20211127&c=DM1&d=0&nbm=・・ (日経新聞 2021.11.27) 省エネ住宅購入に最大100万円補助 国交省、子育て世帯向け 国土交通省は省エネルギー住宅の購入を支援する制度をつくる。子育て世帯を主な対象とし、断熱性能に優れた戸建てやマンションを買う際、最大100万円を補助する。住宅取得にかかる費用負担を和らげながら、省エネ住宅の普及を促す。2021年度補正予算案に関連費用で542億円を盛り込んだ。18歳未満の子どもを持つ世帯か、夫婦いずれかが39歳以下の世帯が新制度の対象になる。新築住宅の省エネ性能に応じて60万円、80万円、100万円の3区分に分けて補助。ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)の基準を満たせば100万円となる。新規購入の契約をした住宅について22年以降、工務店やハウスメーカーから補助の申請を受け付ける。着工して一定の工事が進んでいることが条件となり、22年10月末までが期限となる。同じ世帯を対象に省エネ性能を高める改修工事に対しても最大45万円を補助する。国交省は22年度当初予算にも一般向けの省エネ改修補助金を要求しており、対象要件など詳細を調整する。 *2-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/141877 (東京新聞 2021年11月10日) 18歳未満に一律10万円「基本的には必要ない」 専門家ら効果に疑問 与党のコロナ対策 与党が検討する新型コロナウイルス経済対策として、18歳以下の子どもに一律で10万円相当を配る必要はあるのか―。景気浮揚だけでなく困窮者支援の点でも、経済の専門家から効果を疑問視する声が出ている。「困窮者支援が目的なら、コロナで収入が減少した世帯に絞るべきだ。子どもを基準にするのはコロナ対策としては意味がわからない」。野村総研の木内登英氏は、18歳以下を対象とした一律給付をこう批判する。子育て世代の富裕層が対象となる一方、生活が苦しい子どもがいない世帯が外れてしまうからだ。経済対策としても、効果は高くなさそうだ。コロナ禍にもかかわらず、家計の現預金は増加。日銀によると、6月末に1072兆円で過去最高を更新した。経済活動の制限で、お金を使う機会が失われたことが大きい。新たな現金給付も使われずにさらに貯蓄に回る可能性がある。実際、全ての国民に10万円を給付した昨年の特別定額給付金は7割が貯蓄に回ったという分析がある。一時的な所得の増加は貯蓄に回る傾向がはっきりしており、余裕のある世帯はなおさらだ。このため、木内氏は景気対策として「無駄金になりかねない」とみる。第一生命経済研究所の熊野英生氏も「基本的には必要ない政策。やるなら当然所得制限は設けるべきだ」と指摘する。その上で「コロナで最もダメージを負ったサービス業などへの支援を優先すべきだ」とする。財務省の調査によると、2020年度の企業の純利益は、飲食や宿泊、運輸などの一部を除き、前年並みを保つか、前年を上回った。感染者数の減少で経済環境は回復期にある。特に製造業が好調など一律に苦しいわけではない。給付政策を巡っては、公明党はマイナンバーカードの新規取得者や保有者への3万円分のポイント付与の実現も目指す。ただ、既に実施していた最大5000円分のポイント還元では、カード普及に想定した効果が見られず、財務省が衆院選前に、ポイント付与事業の見直しを求めていた経緯がある。衆院選では、与野党が現金給付や減税など大型の経済対策を競った。政府関係者は「各党はバラマキ合戦に終始し、社会保障や税制など国民の暮らしの安定につながる抜本的な政策はほとんど議論されなかった」と批判する。 *2-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/144976 (東京新聞 2021年11月27日) マイナカードの取得促進に1.8兆円 ポイント付与の「アメ」ちらつかせ 補正予算案 2021年度補正予算案には、マイナンバーカードの取得などで最大2万円分のポイントを付与する事業費として、1兆8134億円が計上された。政府の狙いは40%程度にとどまる普及率の向上だが、個人情報漏えいなどの懸念に向き合わず、「アメ」をちらつかせて取得を促す手法に、識者から「本末転倒だ」と疑問の声が出ている。この事業では、マイナンバーカードの取得で最大5000円分、健康保険証としての利用登録と、預金口座の事前登録でそれぞれ7500円分を付与する。政府がポイントを使った普及促進を図るのは「成功体験」があるからだ。19年度補正予算以降、約3000億円を投じ、今年4月までの申請者に最大5000円分を付与する事業を行ったところ、新たに約2500万人が申請。カード保有者は約5000万人に倍増した。政府は今回の補正予算でさらなる取得者の増加のほか、登録が伸び悩む保険証としての利用や、預金口座との連携を進めたい考えだ。 ◆乏しい利用機会 情報漏えいへの不安も根強く ただ、普及率が上がらない背景には、利用機会の乏しさがある。カードを保険証として使おうとしても、専用の読み取り機を設置して利用できる医療機関や薬局は全国で約7%にとどまっている。加えて、個人情報が適切に管理されるのかという不安や抵抗感も根強い。健康や資産といったプライバシーに関わる情報を把握されかねないと懸念する人は少なくない。SMBC日興証券の丸山義正氏は「予算はカードの利便性を高めたり、セキュリティーを向上させたりすることに使うべきで、ポイントに充てるのは本来のあり方ではない」と指摘する。 <アメリカの対策> *3:https://www.bbc.com/japanese/59300401 (BBC 2021年11月16日) バイデン米大統領、1兆2000億ドル規模のインフラ投資法案に署名・成立 アメリカのジョー・バイデン大統領は15日、総額1兆2000億ドル(約140兆円)規模のインフラ投資法案に署名した。この大規模法案の成立は、支持率が低下するバイデン政権にとって、重要な立法上の成果となる。「私たちは今日ついに、これを達成する」と、ホワイトハウスで開かれた法案署名式でバイデン氏は、与党・民主党と野党・共和党の双方の連邦議員に語った。バイデン氏はさらに、「アメリカの人たちに伝えたい。アメリカはまた動き出しました。そして皆さんの生活は、もっと良くなります」と国民に呼びかけた。「一世一代」の大型財政支出と位置づけられるこのインフラ投資法は、総額約1兆2000億ドルのうち約5500億ドルを今後8年間で、高速道路や道路、橋、都市の公共交通、旅客鉄道などの整備にあてる。加えて、清潔な飲料水の提供、高速インターネット回線、電気自動車充電スポットの全国的なネットワーク整備などにも連邦予算で取り組む。アメリカの国内インフラ投資として数十年来の規模となり、バイデン政権にとっては重要な内政上の成果と受け止められている。財源には、新型コロナウイルス対策で計上した緊急予算の使い残し分のほか、暗号資産(仮想通貨)に対する新規課税の税収など、様々な収入が充てられる。この法案については、財政規律を重視する民主党中道派と、より進歩的な施策の導入を求める党内急進派とが対立。結果的に、野党・共和党から一部議員が賛成に回ることで議会を通過した。民主党内のこの対立と混乱が、今月初めのヴァージニア州知事選での民主党敗北につながったとも言われている。連邦議会では現在、ほかに大規模な社会福祉法案が検討されている。「Build Back Better Act(より良く再建法案)」と呼ばれるこの社会福祉法案は、育児や介護、気候変動対策、医療保険、住宅支援などの充実を図るものだが、成立の見通しがまだ立っていない。民主党の進歩派は今回のインフラ投資法案との同時成立を強く求めていたが、民主党中道派はこれに反対した。財政規律を重視する中道派は、この社会福祉法案で財政赤字がどれだけ増えるのか、議会予算局(CBO)にまず予測を報告するよう要求した。CBOは近くその試算を発表する見通し。(英語記事 Biden signs 'once-in-a-generation' $1tn infrastructure bill into law) <年金制度と“高齢者”の軽視> *4-1:https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/finance/popup1.html (厚労省) マクロ経済スライドってなに? マクロ経済スライドとは、そのときの社会情勢(現役人口の減少や平均余命の伸び)に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みです。 ●マクロ経済スライド導入の経緯 平成16年に改正する前の制度では、将来の保険料の見通しを示した上で、給付水準と当面の保険料負担を見直し、それを法律で決めていました。しかし、少子高齢化が急速に進む中で、財政再計算を行う度に、最終的な保険料水準の見通しは上がり続け、将来の保険料負担がどこまで上昇するのかという懸念もありました。そこで、平成16年の制度改正では、将来の現役世代の保険料負担が重くなりすぎないように、保険料水準がどこまで上昇するのか、また、そこに到達するまでの毎年度の保険料水準を法律で決めました。また、国が負担する割合も引き上げるとともに、積立金を活用していくことになり、公的年金財政の収入を決めました。そして、この収入の範囲内で給付を行うため、「社会全体の公的年金制度を支える力(現役世代の人数)の変化」と「平均余命の伸びに伴う給付費の増加」というマクロでみた給付と負担の変動に応じて、給付水準を自動的に調整する仕組みを導入したのです。この仕組みを「マクロ経済スライド」と呼んでいます。 ●具体的な仕組み (1)基本的な考え方 年金額は、賃金や物価が上昇すると増えていきますが、一定期間、年金額の伸びを調整する(賃金や物価が上昇するほどは増やさない)ことで、保険料収入などの財源の範囲内で給付を行いつつ、長期的に公的年金の財政を運営していきます。5年に一度行う財政検証のときに、おおむね100年後に年金給付費1年分の積立金を持つことができるように、年金額の伸びの調整を行う期間(調整期間)を見通しています。その後の財政検証で、年金財政の均衡を図ることができると見込まれる(マクロ経済スライドによる調整がなくても収支のバランスが取れる)場合には、こうした年金額の調整を終了します。 (2)調整期間における年金額の調整の具体的な仕組み マクロ経済スライドによる調整期間の間は、賃金や物価による年金額の伸びから、「スライド調整率」を差し引いて、年金額を改定します。「スライド調整率」は、現役世代が減少していくことと平均余命が伸びていくことを考えて、「公的年金全体の被保険者の減少率の実績」と「平均余命の伸びを勘案した一定率(0.3%)」で計算されます。 (3)名目下限の設定 現在の制度では、マクロ経済スライドによる調整は「名目額」を下回らない範囲で行うことになっています。詳しい仕組みは、下の図を見てください。 ※平成30年度以降は、「名目額」が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価の範囲内で前年度までの未調整分の調整を行う仕組みとなります。 (4)調整期間中の所得代替率 マクロ経済スライドによる調整期間の間は、所得代替率は低下していきます(所得代替率について詳しくは、「所得代替率の見通し」をご覧ください)。調整期間が終わると、原則、所得代替率は一定となります。 *4-2:https://www.dir.co.jp/report/research/policy-analysis/social-securities/20210210_022084.html (大和総研 2021年2月10日) 2021年度の年金額はマイナス改定、将来の年金のために、マクロ経済スライドの名目下限措置は撤廃を ◆2021年度の公的年金の年金額は、2020年度比で0.1%の引き下げとなった。4年ぶりのマイナス改定である。 ◆マイナス改定となったのは、2021年度より改定ルールが見直され、賃金の変化率が物価の変化率を下回った場合(つまり実質賃金が下落した場合)には、賃金変動に合わせて年金額を改定することが徹底されたためだ。改正前のルールに従えば、0%改定(年金額は据え置き)だったから、ルールの変更により現在の受給者の給付水準が0.1%分抑えられた。その効果は将来の年金水準の確保に及ぶことになる。 ◆年金給付額を実質的に引き下げる仕組みであるマクロ経済スライドは、2021年度は発動されなかった。2004年の制度改革以降、それが実施されたのは3回で、本来求められる給付調整は思うように進んでいない。年金額が前年度の名目額を下回らないようにするというマクロ経済スライドの名目下限措置の撤廃を、改めて検討すべきである。 *4-3:https://news.yahoo.co.jp/byline/kubotahiroyuki/20211109-00267190 (Yahoo 2021/11/9) 物価が上昇に転じなかった背景は2007年も今も変わらず、それでも金融緩和を修正する理由は全くないのか 原油価格や輸入原材料が高騰しており、企業はコスト増に直面している。企業間取引の段階では、コスト高を販売価格へ転嫁する動きがみられる。一方、最終消費段階の財にまでは転嫁はされてこなかった。この記述は最近のものではない。2007年に内閣府が出したレポートから抜粋したものである。「日本「経済2007 第1節 物価が上昇に転じなかった背景( https://www5.cao.go.jp/keizai3/2007/1214nk/07-00301.html ) 企業物価指数をみると、素原材料、中間財は中期的に大幅な上昇傾向にある一方、最終財では上昇がみられない。原油高等のコスト増は、川上、川中の生産財(素原材料+中間財)の価格にまでは転嫁されているが、川下の最終財にまでは転嫁が進んでいない。最終財は、品質向上が著しく下落基調にある電気機器のウェイトが大きい面もあるが、それらを考慮しても生産財と最終財の間の物価上昇率の差は大きい(内閣府の日本経済2007より)。直近の企業物価指数は前年比でプラス6.3%となり、伸び率は2008年9月の6.9%上昇以来、13年ぶりの高さとなっていた。ちなみに2008年9月の消費者物価指数は前年比プラス2.3%となっていた。この際の物価上昇の背景には原油高があったことで、消費者物価指数も一時的に2%を超えていたが、企業物価との乖離は大きい。その背景の説明が上記であり、これは現在でも変わっていない。この内閣府のレポートでは、原油価格や素原材料価格が高騰する中、企業取引段階では転嫁がある程度進んでいる一方で最終消費段階への転嫁が進まないことは、国内で生み出す名目付加価値の縮小につながっているとの指摘もあった。そして物価が上昇に転じないことや、個人消費が弱いことの背景として、賃金が伸び悩んでいることが挙げられるとの指摘もあった。今月8日に発表された日銀の金融政策決定会合における主な意見(2021年10月27、28日開催分)では、次のようなコメントがあった。「日米インフレ率の差は主にサービス価格であり、その大部分は賃金である。賃金引き上げには労働市場が更に引き締まることが必要である。家計・企業の待機資金の支出を後押しするためにも、所得と賃金の引き上げを目指すことが望ましい。どうして賃金の引き上げが困難なのか。賃金を引き上げれば物価が上がるとすれば、大胆な金融緩和策によって能動的に賃金を引き上げることは可能なのか。すでに異次元緩和と呼ばれた日銀の量的質的金融緩和策を決定してから8年半が過ぎたが、物価を取り巻く環境は2007年時点となんら変わることはない。[「金融政策の正常化とは、他国の政策動向にかかわらず、わが国での物価安定の目標を安定的に達成することであり、目標に達していないもとでは金融緩和を修正する理由は全くない。この点は、対外的に丁寧に説明すべきである。」との意見が「主な意見」にあった]。そもそも2%という物価目標が適正なのか。どんな金融緩和策をとっても物価を取り巻く環境に変化はないのに、目標に達していないもとでは金融緩和を修正する必要はないと言い切ることに正当性があるとは思えない。異次元緩和の副作用、債券市場の機能不全、金融機関の収益性への問題、そして日本の財政悪化を見にくくさせるなどの副作用も考えれば、少なくとも極端な緩和策から柔軟な対応に戻す格好の金融政策の正常化はむしろ必要とされよう。 *4-4:https://www.somu-lier.jp/column/pensionsystem-amendment/(Somu-Lier 2021.2.20)【2022年4月以降施行】年金制度改正法によって変わるシニア層の働き方とは 女性や高齢者の就業が進んでいることに合わせて、年金制度を変更するため、2022年4月より年金制度改正法が施行されます。今回の改正ではパートなどの短時間労働者への年金適用拡大や繰り下げ受給の上限引き上げ、確定拠出年金の要件緩和などが含まれます。特にシニアや短時間労働者の働き方に影響を与えるため、正しく理解し、該当する労働者に説明しましょう。今回は、年金制度改正法の4つの変更点の詳細とそれぞれの施行時期、シニア層と企業への影響について解説していきます。 ●年金制度改正の4つの変更点と施行時期 ○厚生年金の適用範囲の拡大 今回の改正で厚生年金の適用範囲が拡大しました。具体的には、常勤者の所定労働時間または所定労働日数の4分の3未満の短時間労働者であっても、一定の要件を満たせば加入できるようになり ・1週間の労働時間が20時間以上であること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金が1ヶ月8.8万円以上であること ・学生でないこと 現行制度において、上記の要件を満たした短時間労働者を社会保険に加入させる義務があるのは、被保険者となる従業員が501人以上の事業所のみでした。しかし今回、段階的に適用範囲を広げていくという改正がなされました。具体的には、2022年10月からは101人以上の事業所、2024年10月からは51人以上の事業所までが適用になります。また、今回の改正では、上記のうち「雇用期間が1年以上見込まれること」という要件は撤廃され、フルタイムと同様に2ヶ月以上となります。なお、5人以上の個人事業所で強制適用とされている業種(製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業など)に、弁護士や税理士などの士業も追加されます。 ○受給開始時期の選択肢の拡大 現在、公的年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、希望により60歳から70歳の間で受給開始時期を自由に決めることができます。65歳より前に受給を繰上げた場合、一年繰り上げにつき0.5%減額された年金(最大30%減)が支給され、支給開始年齢を66~70歳に繰下げた場合は一年繰り下げにつき0.7%増額された年金(最大42%増)を、生涯受給することになります。しかし、近年では健康寿命が延びたことにより高齢者の就労期間も長くなっていることから、年金の受け取り方にも多様な選択肢を設ける改正が行われました。今回の改正では、繰り上げ受給の減額率は0.4%に引き下げられ、60歳で年金を受給開始した場合は24%の減額になります。繰下げ受給の場合の増額率は変わらず0.7%のままですが、受給開始年齢の上限を70歳から75歳に引き上げ、75歳まで受給を繰り下げると年金額は最大でプラス84%になります。この改正は、2022年4月に施行され、対象となるのは2022年4月1日以降に70歳になる方です。 ○在職中の年金受給についての見直し 現行制度では、年金の支給繰り上げをしながら働いている60~64歳までの方は、賃金などと年金受給額の合計が月額28万円を超えると、超過分の年金の支給が停止されてしまいます。改正後はこの制度が見直され、年金の支給停止の基準額が月額28万円から47万円に緩和されることになりました。65歳以上で働きながら年金を受給している方は、もともと基準額が47万円となっており、変更はありません。また、現行制度では65歳以上で在職中の場合、退職時に年金額が改定されるまでは年金受給額が変わりませんでした。しかし、今回の改正で、65歳を過ぎてからも働いている場合、毎年10月に保険料の納付額をもとに年金受給額を見直し、年金額の改定が行われることになりました。これを在職定時改定といいます。在職定時改定制度があることで、長く働くメリットを感じることができるでしょう。 なお、これらの制度改正は、2022年4月に施行されます。 ○個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件の緩和 確定拠出年金(DC)とは、基礎年金や厚生年金のほかに掛金を積み立てて運用し、その積立額と運用収益をもとに支給される年金のことです。企業型DCと個人型DCがあり、企業型DCは企業が掛金を支払うもの、個人型DC(iDeCo)は個人が掛金を支払うものです。毎月の掛金を所得控除することができる、運用中の利益が非課税になる、年金受給時の税負担も軽くなるなどの、税制上の優遇措置があります。これまで、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入したい場合、各企業の労使の合意が必要でしたが、2022年10月にはこの要件が緩和され、原則加入できるようになります。また、受給開始時期の選択範囲については、これまでは60~70歳の間だったところ、2022年4月からは60~75歳に拡大されます。 ○年金制度改正が与える影響 今回の年金制度改正は、女性や高齢者の労働者が増加していることを受けて、多様な働き方に対応できる年金制度を目指したものです。例えば、短時間労働者を厚生年金に加入させるべき企業の適用範囲を広げることにより、より多くの短時間労働者が社会保険制度を利用できるようになります。これにより、育児や介護でフルタイム勤務が難しい方やシニア世代の働き方にとって、短時間労働という選択肢が加わるでしょう。また、受給開始時期の選択範囲の拡大や、在職中の年金支給停止の基準額の緩和により、シニア世代が仕事を続けやすくなります。今後、健康寿命が延びることによって老後の経済的な不安を抱える人が増える可能性があります。これからは、従来の「定年」という言葉に縛られず、生きがいとして仕事を続けることで金銭的不安を解消し、生き生きとした老後を目指す姿勢が必要なのかもしれません。今回の改正は年金制度の面からこのような生き方を応援していく試みがされているのではないでしょうか。また、企業にとっても、働く意欲のある人材を雇用形態にとらわれずに得ることができたり、経験豊かなシニア世代を採用したりすることによって、生産性の向上を期待することができます。 <介護制度と介護負担> *5-1:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021111300099 (信濃毎日新聞社説 2021/11/13) 介護職ら賃上げ 負担増に国民の理解を 介護職や保育士の賃金が来年2月から月額3%程度引き上げられる方向になった。地域の救急医療を担う看護師らも同様の対応になる。19日に決定する政府の経済対策に盛り込まれる。少子高齢化で重要度が増す社会保障の担い手だ。ボーナスを含めた昨年の平均月収は、全産業平均の35万2千円に対し、介護職が5万9千円、保育士が4万9千円低い。看護師は4万2千円高いが、医師の4割にとどまる。仕事の大変さに比べ低賃金で離職者が多く、人材不足が深刻化している。賃上げによる処遇改善は待ったなしの課題だ。人件費には安定した財源が要る。政府は、2~9月分を交付金として支給し、10月以降は報酬改定などで対応する方針を示す。医療や福祉分野のサービスに伴う価格は、政府が定め、診療報酬や介護報酬などとして事業者に支払われている。原資は、税金や保険料、利用者負担だ。報酬の引き上げ改定は、それぞれの増額につながる。国民の負担増が避けられない。財源の確保策を明確にし、国民の理解を得るべきだ。政府は、新たに立ち上げた公的価格評価検討委員会で、賃上げに向けた協議を進め、公的価格のあり方も見直す意向だ。開かれた分かりやすい議論を求めたい。報酬改定などがただちに賃上げに結び付くかは不透明だ。報酬に加算する仕組みを導入しても、事務作業が煩わしく利用が進まない事例もある。収入をどう分配するかは経営者の裁量だ。実態を踏まえた議論にしなければならない。確実に個々の賃上げに充てる運用が大切になる。社会保障制度全体の中で考える必要もある。65歳以上が支払う介護保険料は今年、全国平均で月6千円を超えた。介護利用料の自己負担が増えたり、公的年金の受給額が減ったりした人も多い。75歳以上の医療費2割負担も来年度始まる。保険料を滞納し預貯金などを差し押さえられた高齢者は年2万人に上っている。さらなる負担増に耐えられない人が続出する恐れはないか。社会保障制度は近年、小手先の見直しを積み重ねてきた。年金収入だけで老後を過ごせる状況になく、十分な医療や介護も望めなくなりつつある。制度全体を見渡し、給付や負担のあり方を抜本的に見直すことが急務だ。賃上げもその中で位置づけなくてはならない。 *5-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15126050.html?iref=comtop_Opinion_03 (朝日新聞社説 2021年11月29日) 介護等の賃金 中長期見据えた議論を 政府の経済対策で、看護や介護、保育の現場で働く人たちの賃金を来年2月から引き上げることが決まった。「春闘に向けた賃上げの議論に先んじて実施を」という岸田首相の意向を受けた当面の措置で、さらなる取り組みも有識者会議で議論し、年内に方向性を示すという。新型コロナや少子高齢化への対応の最前線に立つ人たちに、政権として報いる姿勢を示すとともに、政府が介入しやすいこれらの分野をテコに、広く民間の賃上げにつなげたいという思惑があるのだろう。だが、本来目を向けるべきは、中長期を見据えたサービスの担い手確保と、そのために必要な財源の負担をどう分かち合うかの議論であることを、忘れてはならない。どこまでの賃上げを目指し、それを賄うためには税や保険料がどう変わるのか。国民に分かりやすく示し、理解を得ながらしっかりと進めてほしい。来年2月の賃上げは、介護職員や保育士などで収入の3%程度(月額約9千円)、コロナ医療などの役割を担う医療機関に勤務する看護職員で1%程度(月額約4千円)という。人手不足が深刻なのもこれらの分野で、高齢化でこれから需要が大きく膨らむと見込まれる介護では、40年度に65万人が不足すると推計されている。ただ、現在の賃金水準は看護師の月平均39・4万円に対し、介護職員は29・3万円、保育士は30・3万円で、今回の引き上げが実現しても全産業平均の35・2万円に及ばない。一方、これらのサービスを支えているのは税金や保険料、利用者負担だ。継続的な賃金引き上げのための財源を確保するには、既存の予算や保険財政の中で他の費目を削るか、負担増を考えねばならない。政府はこれまでも介護職員や保育士の賃上げに取り組んできたが、こうした事情のもと、成果は限定的だった。まずは、思い切って財源を投入する方針を明確にする必要がある。保育所や介護サービスのための予算の大幅な拡充や保険料の引き上げなど、「財布」を大きくする議論に向き合うべきだ。低所得の人にとって過度な負担とならないよう、税金による軽減措置も検討課題になるだろう。賃金の引き上げだけでなく、長く働いてもらえるように職場環境を整えることや、専門性を高めてキャリアアップできるよう後押しすることも重要だ。仕事は大変なのに待遇が悪いからと、資格を持ちながら他の分野で働く人も少なくない。職務に見合った処遇への改善は急務だ。看板倒れは許されない。 *5-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/142863 (東京新聞 2021年11月15日) 差し押さえ高齢者、初の2万人超 介護保険料滞納で過去最多 介護保険料を滞納し、市区町村から資産の差し押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者が、2019年度は過去最多の2万1578人に上ったことが15日、厚生労働省の調査で分かった。2万人を超えるのは初めて。厚労省の担当者は「自治体が徴収業務に力を入れている結果だ」と分析する。介護保険制度が始まった約20年前と比べ、保険料が倍以上となり、高齢世帯の家計への負担が増していることも要因とみられる。65歳以上が支払う介護保険料は原則、公的年金から天引きされる。一方、年金受給額が年18万円未満の場合は自治体に直接納める。 *5-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211201&ng=DGKKZO78038950R01C21A2EA2000 (日経新聞 2021.12.1) 1人暮らし世帯拡大、5年で14.8%増 高齢者では5人に1人 介護や安全網が課題に 総務省が30日に公表した2020年の国勢調査は、日本全体で世帯の単身化が一段と進む現状を浮き彫りにした。一人暮らしが世帯全体の38.0%を占め、単身高齢者は5年前の前回調査に比べ13.3%増の671万6806人に増えた。中年世代の未婚率も上昇傾向にある。家族の形の多様化を踏まえた介護のあり方やまちづくり、セーフティーネットの構築が急務となっている。日本の世帯数は5583万154となり、前回調査に比べて4.5%増えた。1世帯あたりの人員は2.21人で、前回調査から0.12人縮小。単身世帯は全年齢層で2115万1042となり、前回調査から14.8%増えた。3人以上の世帯は減少しており、特に5人以上の世帯は10%以上減った。65歳以上の一人暮らし世帯の拡大が続いており、高齢者5人のうち1人が一人暮らしとなっている。男女別にみると、男性は230万8171人、女性は440万8635人で、女性が圧倒的に多い。藤森克彦・みずほリサーチ&テクノロジーズ主席研究員は「一人暮らしの高齢者は同居家族がいないので、家族以外の支援が重要になる」と指摘する。「財源を確保しつつ介護保険制度を強化し、介護人材を増やす必要がある」と語る。単身世帯の増加の背景には「結婚して子供と暮らす」といった標準的な世帯像の変化もある。45~49歳と50~54歳の未婚率の単純平均を基に「50歳時点の未婚率」を計算すると、男性は28.3%、女性は17.9%となった。00年のときには男性が12.6%、女性は5.8%だった。この20年間で価値観や家族観の多様化から、中年世代になっても独身というライフスタイルは珍しくなくなった。単身者向けに小分けした商品の開発・販売など新たなビジネスの機会が生まれる面もある。ただ、複数人で暮らすよりも家賃や光熱費の負担比率が高まるほか、1人当たりのごみの排出量などが増え、環境負荷が高まることも考えられる。高齢者であれば孤独死などにつながる懸念もある。高齢化とともに単身世帯が増える中で、通院や買い物を近場でできるようコンパクトなまちづくりも課題となる。体調を崩したり、介護が必要だったりする高齢者が増えれば社会保障費の膨張にもつながる。単身世帯数の拡大にあわせた社会のあり方を追求していく必要がある。 *5-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211201&ng=DGKKZO78039040R01C21A2EA2000 (日経新聞 2021.12.1) 外国人43%増、最多274万人に 総務省が30日に公表した2020年の国勢調査では、外国人の人口が過去最多の274万7137人となり、5年前の前回調査に比べ43.6%増と大きく拡大した。日本人の人口は1億2339万8962人で1.4%減った。外国人の流入により、少子化による人口減少を一定程度緩和している。新型コロナウイルスの感染が拡大する中でも、日本に住む外国人は減少に転じなかった。日本の総人口に占める外国人の割合は2.2%で、5年前の前回調査(1.5%)から上昇。国連によると20年に世界各国に住む外国人は3.6%だ。日本でも外国人は増えているが、諸外国に比べるとまだ少ない。岡三証券グローバルリサーチセンターの高田創理事長は外国人を巡り「人口対策の現実的な選択肢」としたうえで「就労ビザなど対応を増やしてきた流れの継続が肝要だ」と話す。国籍別にみると中国が66万7475人と最も多く、外国人全体の27.8%を占めた。 *5-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211205&ng=DGKKZO78170820V01C21A2MM8000 (日経新聞 2021.12.5) 日本の設備、停滞の20年 総量1割増どまり、投資抑制、低成長招く 日本の設備投資の低迷が続いている。この20年間で設備の総量を示す資本ストック(総合2面きょうのことば)は1割たらずしか増えなかった。米国や英国が5~6割ほど伸びたのと差がついた。企業が利益を国内投資に振り向けていないためだ。設備の更新が進まなければ労働生産性は高まらず、人口減の制約も補えない。低成長の構造要因として直視する必要がある。2001年から新型コロナウイルス危機前の19年までの日本の経済成長率は年平均0.8%にとどまる。米国(2.1%)や英国(1.8%)に水をあけられた。成長の壁としてよく指摘されるのは人口減少や少子高齢化だ。目をこらせば別の問題が浮かぶ。一橋大学の深尾京司特任教授は「設備投資の停滞も大きい」と指摘する。新たな機械やソフトウエアの導入は生産性を高め、成長力を押し上げる。経済学の成長理論では成長率と資本増加率は一定の関係がある。深尾氏の試算によると、主要先進5カ国で日本だけが資本増加の実績が理論値に及ばない。経済協力開発機構(OECD)の「生産的資本ストック」のデータが実態を示す。日本はハードとソフトを合わせた資本ストックが00~20年に9%しか伸びなかった。米国は48%、英国は59%増えた。日本はフランス(44%)やドイツ(17%)も下回る。日本企業は稼ぎを減らしてきたわけではない。財務省の法人企業統計調査によると、経常利益の直近のピークは18年度の84兆円。アベノミクスが始まった12年度から73%増えた。この間、設備投資は42%しか増えていない。投資は減価償却で目減りした分こそ上回るが、キャッシュフローの範囲内で慎重にやりくりする姿勢がはっきりしている。日本は10年代、人口減にもかかわらず労働供給は拡大した。就業者は10年間で378万人増え、特に女性や65歳以上の働き手が多くなった。「企業は割安な労働力の投入を増やし、労働を節約するロボット投入などを遅らせた可能性がある」(深尾氏)。教育訓練など人的資本投資も伸び悩んだ。OECDによると、企業が生む付加価値額に対する人材投資の比率は英国が9%、米国が7%に達する。日本は3%にすぎない。ヒトとモノにお金をかけて成長を目指す発想が乏しい。底堅かった労働供給にしても、人口が総体として減り続ける以上、いずれ頭打ちになるのは避けられない。本来、どの国よりも自動化などの取り組みが必要なのに投資に動けずにいる。日本企業は1990年代のバブル崩壊後、過剰な設備・人員・負債に苦しみ、厳しいリストラに生き残りをかけてきた。過剰な設備への警戒感が今なお残る。日本企業も海外では積極的にお金を使う。対外直接投資はコロナ前の19年に28兆円と10年前の4倍に膨らんだ。コロナ後も流れは変わらない。日立製作所は米IT(情報技術)大手のグローバルロジックを1兆円で買収した。パナソニックも7000億円超でソフトウエア開発の米ブルーヨンダーの買収を決めた。20年度の設備投資は日立が連結ベースで3598億円、パナソニックが2310億円にとどまる。各社が成長の種を外に求める結果、投資が細る国内市場は成長しにくくなる。海外で稼いだお金を海外で再投資する傾向もある。もちろん企業も世界に投資を広げる一方で国内に抱える雇用の質を高める取り組みは怠れないはずだ。学び直しなどの支援と同時に仕事を効率化するデジタル化も加速する必要がある。企業を動かし、資本ストックが伸び悩む悪循環を断てるような賢い経済政策こそが求められている。 <合理性のある所得の家族合算と分割> *6-1:https://digital.asahi.com/articles/ASPCK6GC3PCKUCLV00Y.html?iref=comtop_list_02 (朝日新聞 2021年11月17日) 10万円給付家庭、なぜ共働き有利に 背景に半世紀変わらぬ児童手当 18歳以下の子どもを対象にした10万円相当の給付で、所得制限をめぐる政府方針に対して、与党内から異論が噴出している。なぜこうした状況になったのか。背景には、半世紀にもわたって変化していない「児童手当」の仕組みがあった。政府は、10万円相当の給付にかかる時間を短くするため、児童手当の仕組みを使う。児童手当は中学生までの子どもを育てる世帯に、基本的に1万~1万5千円を支給する。対象世帯から市区町村に振込先の口座が届けてあるため、申請の手間を省くことができる。コロナ禍だった2020年にも児童手当の受給世帯に1万円を上乗せ支給した成功体験もある。自治体が先行した児童手当は、国が制度化した1972(昭和47)年1月の支給当初から所得制限があった。夫婦なら二人の年収を比べ、高い方で支給対象かを判定する。所得制限を超えると、今の仕組みでは月額5千円になる。今回の10万円相当の所得制限として持ち出された「年収960万円」は子どもが2人で、一方の配偶者は収入がない、といったモデル家庭の所得制限だ。夫婦合わせた世帯全体の収入は考慮しないため、高収入の共稼ぎ夫婦にも支給されることが起こりうる。仮に夫婦2人とも800万円の年収があり、世帯年収で計1600万円あっても、今回の10万円相当の給付を受けられる。だが、夫婦どちらか一方しか収入がなく、世帯年収が960万円なら10万円相当の給付はもらえない。児童手当に当初、世帯の合計所得でみる「世帯合算」が取り入れられなかった理由は、時代背景にありそうだ。内閣府の担当者は「制度ができた当時は、世帯主の男性が世帯収入の大半を稼いでいた時代だったからでは」と話す。 ●共働き世帯数は専業主婦世帯の2倍超 71年2月。時の佐藤栄作首相は、児童手当法案の趣旨を説明する本会議で、児童手当を「我が国の社会保障の体系の中で欠けていた制度」と称した。「長年の懸案」(当時の内田常雄・厚生相)だっただけに、衆参の本会議や社会労働委員会(当時)の議事録には活発な国会審議の跡が残る。ただ、審議では支給対象から外れた第1子や第2子も含めるべきだといった論点や、月額3千円という金額の根拠を問う議論が中心だった。所得制限については修正もなく、男性の働き手を念頭に1人の収入で判断する考え方への異論は少なかったとみられる。社会の実情はその後、大きく変わる。独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の資料によると、80年に専業主婦世帯の半数程度だった共働き世帯は、90年代半ばには専業主婦世帯を上回った。2020年には専業主婦世帯の2倍を超えている。児童手当ができた当時と、現実とのギャップは、財務省をはじめ政府内で意識されてきた。昨年末の予算編成では、菅義偉首相(当時)のもと、児童手当への世帯合算の導入が、自民党と公明党の間での政策協議で話題となった。ただし、この時の議論は保育所整備に必要な財源を捻出するため、児童手当を支給する世帯を少なくする理屈として財務省などが持ち出したものだった。このため、児童手当の創設以来、拡充に力を入れてきた公明の強い反発に遭った。自公両党はこの時、収入の多い方が年収1200万円以上あれば、22年10月分から月額5千円の児童手当の特例給付を打ち切ることで合意した。一方で、世帯合算の導入は見送った。その課題は「引き続き検討する」(昨年12月の全世代型社会保障改革の方針)とされたまま、今回の議論を迎えていた。児童手当以外の国の仕組みで世帯合算を導入している制度もある。低所得世帯向けに、大学の授業料などの負担を減らしたり、返す必要のない奨学金を支給したりする「修学支援新制度」や、私立高校の授業料支援の仕組みがその例だ。0~2歳の保育料も、無償化の対象となる低所得世帯を除き、世帯合算で利用料負担が決まる。17日の自民党の会合で高市早苗政調会長は、児童手当の所得制限で世帯合算を取り入れることを視野に見直しの必要性に改めて言及。「世帯合算でやった方がいいんじゃないかという声もある。今後、同様の事態が起きた時に迅速かつ公平に給付できるように整備をしたい」と語った。具体的には衛藤晟一・元少子化担当相をトップに、党の少子化対策調査会で議論する考えを示した。 *6-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/143290 (東京新聞 2021年11月17日) 世帯年収1900万円でも子ども2人分…なのに働く低所得層に届かぬ懸念 政府の現金給付案 大筋了承 自民党は17日の党会合で、18歳以下の子どもや住民税非課税世帯、困窮学生への10万円給付を含む経済対策案を大筋了承した。党内手続きを経て19日に閣議決定する。与党協議開始から約10日間の議論で決まった給付金制度は、所得制限のかかる世帯より収入の多い共働き世帯にも支給される一方で、住民税を納めながらも生活が苦しい低所得層に給付金が渡らないなど、国民の間に不公平感が生じる懸念がぬぐえないまま。与野党からも疑問視する声が上がっている。 ◆子どもへの給付 子どもへの給付は、迅速な支給を理由に児童手当の仕組みを利用。夫婦でより高い収入(社会保険料や税金が引かれる前の金額)を得ている方が所得制限の対象になるが、与党は「対象の9割をカバーできる」(自民党の茂木敏充幹事長)としている。だが、18歳以下の子ども2人の夫婦の場合、片方が年収961万円でもう片方が無収入だと給付を受けられず、共働きで夫婦それぞれが年収950万円なら子ども2人分が給付される。児童手当の対象は15歳以下で、今回対象に含まれる16~18歳への給付手続きには結局、時間がかかりかねない。自民党の高市早苗政調会長は17日の会合で「世帯合算ではなく、主たる所得者の金額で判断すると、不公平な状況が起きる」と指摘。福田達夫総務会長も16日、「個人的には(世帯で)合算した方が当然だと思う」と異論を唱えた。日本政策金融公庫の調査によると、19歳以上の大学生がいる家庭は在学費用だけで年間1人100万円以上の負担がかかるのに、子ども向け給付の対象外。政府・与党は困窮学生にも10万円を給付するとしているが、基準は未定だ。政府が昨年実施した学生向け緊急給付金では、家庭から自立しアルバイトで学費を賄っていることや「修学支援制度」を利用していることなど厳しい要件が課された。対象者は大学生や短大生らの1割にも満たなかったとみられ、十分な支援だったとは言い難い。 ◆低所得者層への給付 住民税非課税世帯には10万円が給付される一方、住民税を課されていても年収100万~200万円程度にとどまり、全国で数100万世帯あるとされる「ワーキングプア」層には給付が行き渡らない懸念もある。立憲民主党の長妻昭氏は「コロナ禍で格差が急拡大して困難な状況に陥っている人には子どもでもそうでなくても、緊急に支援しないといけない」と指摘している。 *6-3:https://digital.asahi.com/articles/ASP5P5VF9P5PUTFL00D.html (朝日新聞 2021年5月21日) 年収1200万円以上の児童手当廃止 改正法が成立 中学生以下の子どもがいる世帯が対象の児童手当のうち、年収1200万円以上の世帯に支給している月5千円の「特例給付」を廃止する改正児童手当法などが21日の参院本会議で、賛成多数で可決、成立した。いまの制度では子ども2人の専業主婦家庭で夫の年収が960万円未満の場合、子どもの年齢に応じて1人当たり月1万~1万5千円の児童手当が支給され、夫の年収が960万円以上なら月5千円の特例給付がある。成立した改正法は特例給付の支給対象を狭め、夫の年収が1200万円以上の世帯は2022年10月分から支給を取りやめる。昨年末に自民、公明両党が合意した。対象となる世帯の子どもは児童手当をもらう全体の4%で、約61万人と見込まれる。見直しで生じる年約370億円の財源は、待機児童解消に向けた保育所などの整備費用に充てる。待機児童解消に向け、政府は24年度までに約14万人分の保育の受け皿整備をする目標を掲げている。野党からは子育て関連の予算の中での組み替えでしかなく、子育てにかける予算全体を増額するべきだといった反対論が出ていた。 *6-4:https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/687262 (京都新聞社説 2021年12月2日) こども庁方針案 「器」より中身が重要だ 子ども関連政策の司令塔を目指す「こども庁」の政府基本方針案が明らかになった。創設は2023年度のできる限り早い時期と明記した。一元的な取り組みの推進に向け、焦点だった所管分野については、保育所に関わる部署を厚生労働省から移す一方、幼稚園は文部科学省に残す見通しとなった。小中学校の義務教育の権限の移管も見送られる方向だ。新組織づくりで各省庁の足並みがそろっているとは言い難い。縦割り行政の弊害を取り除き、子ども最優先の施策運営ができるかどうかが問われよう。基本方針案では、こども庁は首相直属の内閣府の外局として、各省庁への勧告権を持つ専任閣僚を置く。政策立案と子どもの成育、支援の3部門を設け、子どもの意見を反映させるモニター制度の導入や、民間人材の積極登用を打ち出している。新型コロナウイルスの感染拡大で、経済的な困窮や家庭内暴力の増加など、子どもを取り巻く環境は厳しさを増している。これらの問題への総合的な対処を強化する必要がある。ただ、方針案でこども庁に統合されるのは、厚労省の保育のほか、虐待防止や障害児支援、内閣府の少子化や貧困対策の関連部署で、文科省からの移管は一部にとどまる。このままでは、就学年齢を境に貧困、虐待対策が分かれるなど新たな問題が生じかねない。いじめや非行の対応では、地域や学校の連携が課題となろう。こども庁は、菅義偉前首相の肝いりの政策として当初は22年度中の創設を目指していた。だが、関係省庁間の調整などに手間取り、目標が先送りされた形だ。言うまでもなく、子ども政策の推進に重要なのは、「器」よりその中身だ。こども庁が扱う分野に、どういった少子化対策を含めるのか、対象となる年齢をどこで区切るのかなど現時点ではあいまいだ。政府は来年の通常国会への関連法案の提出を目指すというが、こども庁の創設でどんな効果を目指すのか、その全体像をはっきりと示すべきだ。政府の有識者会議がまとめた報告書は、子ども施策の具体的な実施を担う自治体の役割を強調している。各家庭の状況を把握できるデータベースの構築などを提言しており、積極的な現場での支援に生かしてほしい。 *6-5:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD106XI0Q1A211C2000000/ (日経新聞社説 2021年12月11日) 子ども政策は幼保一元化と財源が肝心だ 政府はこのほど、子ども政策の充実に向けた基本方針の原案を示した。子ども政策の司令塔となる「子ども庁」を内閣府の外局として新設し、担当の閣僚を置く。縦割りを排し、子ども政策の立案や強力な総合調整機能を持たせるという。年内に閣議決定し、2023年度のできる限り早い時期の子ども庁設置を目指す。少子化、貧困、虐待など、子どもを巡る環境は厳しさを増している。子ども政策を充実させることの大切さは論をまたない。子どもの健やかな成長は、日本の明日を左右する大きなカギとなる。ただ課題は多い。ひとつは、幼保一元化が進まないことだ。就学前施設のうち、保育所(所管は厚生労働省)と認定こども園(内閣府)は子ども庁に移すが、幼稚園は文部科学省に残すという。この3つは根拠法などは違えど、カリキュラム内容の整合性は図られてきた。保育所も幼児教育の一翼を担う。一元化によって地域の人材や施設がより有効に活用でき、内容も充実するだろう。幼保一元化は長年、課題とされながら、幼稚園団体の反対などで見送られてきた。原案は、文科省と子ども庁が相互に内容に関与するとしながらも「教育は文科省」を強調している。かえって現場の分断を深める恐れがある。また、子どもの問題は組織をつくれば解決するものではない。大事なのは具体的な施策であり、裏付けとなる財源だ。日本の家族関係の社会支出は、国内総生産の1%台にとどまる。欧州では3%前後が多い。基本方針は財源確保について「幅広く検討を進め、確保に努める」という表現にとどまった。早急に具体策を示し、思い切って増やす必要がある。それには高齢者に偏る社会保障の財源を子どもに振り向けるなど、痛みをともなう改革も必要になろう。なぜいま、子ども政策の充実なのか。国民に十分納得できるメッセージを発し、合意を得る。それだけの覚悟とリーダーシップを岸田文雄首相に求めたい。政府の原案に先立ち、どんな政策が必要か、有識者会議が報告書をまとめている。子どもの視点に立った政策立案やプッシュ型の支援、データの活用など、多くの施策が並ぶ。財源の裏付けがなければ、実現はおぼつかない。子ども庁の創設議論にかかわらず、今すぐできるところから、実効性ある対策を急ぐべきだ。 *6-6:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15141080.html?iref=pc_shimenDigest_sougou2_01 (朝日新聞 2021年12月12日) 厚遇、人材引き込む中国 1億円超す報酬、学者人脈も活用 中国は世界中の研究者をどのように引き込もうとしているのか。朝日新聞が入手した浙江省政府系組織「浙江省中南科技創新合作中心」の求人書類から見えてくるのは、資金力と人脈を利用した手法だ。72歳以下の引退した教授らの場合、国籍や学科を問わない。A級のランクを受けた場合、給料は120万元(約2100万円)以上で上限はない。350万元(約6200万円)の住居購入費、110万元(約2千万円)の赴任手当、毎年200万~1千万元(約3600万~1億8千万円)の研究費など計780万~1580万元(約1億4千万~2億8千万円)以上がもらえる。医療保険や交通費も準備され、配偶者も同伴できる。勤務先は中国の大学や研究機構、大企業の研究所など。仕事の内容として第一に挙げるのは、中国と出身国の教育分野の協力強化と両国の大学間の協力強化だ。招致した学者の人脈をテコに、外国の研究機構との協力を強めようという意図がうかがえる。1年のうち6カ月間、中国にいればよいとしており、拘束は強くない。浙江省が日本の専門家に期待するのが、日本が競争力を持つ素材と自動車、産業機械の分野で、同省関係の108件の求人を一覧にまとめ、日本語で募集をかけている。中国政府は、改革開放を加速させた1990年代半ばから「百人計画」に着手。研究環境を厚遇し、主に外国に流出した優秀な中国人研究者の呼び戻しを始めた。2008年からは「千人計画」と呼ばれる「ハイレベル海外人材招致計画」に拡充。日本人など外国人研究者も招き入れた。日米などの警戒が強まり、最近は中国政府は「千人計画」という名称を使わなくなったが、地方都市は競い合うように人材誘致を進める。帰国する中国人留学生も過去10年で約5倍に膨らみ、年間58万人(19年)を数える。中国政府は資金と人材の投入を進め、技術力も米国を追い上げる。研究開発費は過去20年で約27倍(人民元建て)となり、米国に次ぐ。全米科学財団によると、米国の大学で理系博士号を取得した中国人は5700人(20年)。10年で7割近く増えた。今年8月に発表された、研究者による引用回数が上位10%に入る「注目度の高い論文」(17~19年平均)で、中国が米国を抜き、初めて世界首位に立った。8分野のうち、材料科学や化学、工学、計算機・数学、環境・地球科学の5分野で首位だった。 ■日本、情報管理の強化を大学に要請 国外への技術流出の懸念を受け、日本政府は大学への働きかけを強めてきた。経産省と文部科学省は共催で毎年、主に大学を対象に安全保障に関するセミナーを開いている。大学の国際化が進む中、機微技術やデータの流出を防ぐための知識を共有する狙いがある。留学生の受け入れの際に研究目的と経歴に矛盾はないか調べたり、学内でアクセスできる情報の範囲を管理したりするよう求めるほか、研究者の海外出張時の情報管理にも注意を呼びかける。文科省も今年から技術流出対策を担当する参事官を設けた。大学には、安全保障(輸出管理)担当部門の設置を求めてきた。同省によれば、国立大学は全校、公立・私立も6割以上が応じたという。ある国立大学の教授は言う。「大学がチェックできるのはあくまでも公表されている経歴。うそを重ねて悪意を持って入ろうとする人物を探し出して排除するには限界がある。米国が安全保障上の理由から受け入れを拒んだ学生周辺の情報を共有するなど、政府として対応してほしい」。政府・自民党は準備中の法案で、先端技術など機密情報を共有できる研究者らを保証する資格にあたる「セキュリティークリアランス(適性評価)」制度の導入を議論している。類似の制度が欧米にあるが、大学の独立や研究の自主性、民間人のプライバシーにもかかわる問題だけに、慎重な検討を求める意見が強い。一方で、中国人は日本の大学の研究や経営を支える存在でもある。国内で少子化が進む中、大学は留学生の受け入れや国外の大学との共同研究を増やすなど、国際化を進めざるを得ない。文科省によると、中国人留学生は約12万人(2020年5月現在)で、日本が受け入れた留学生の約4割を占める。中国の有名大学に移った中堅の日本人研究者はこう指摘する。「日本の政府や政治家は日本の情報が流出することばかり警戒しているようだが、中国の方が研究環境に優れ、水準も高い領域は少なくない。経済安保の重要性は理解しているが、日本政府が人材を引き留めたければ、自らの研究環境を整えるのが先決ではないか」 ■摘発は「人種差別」、米で反対の動き 中国との技術覇権争いが先鋭化する一方、米国では、人材を通じた情報漏洩(ろうえい)への警戒を強めてきた前政権からの反動も出始めている。米司法省はトランプ政権下の2018年から中国の技術盗用の摘発などを担う「チャイナイニシアチブ」を開始。司法省のサイトには、助成金の不正受給、技術盗用など中国系の研究者や企業関係者らの摘発事例が並ぶ。バイデン政権下も摘発は続き、中国による知的財産盗用に厳しい姿勢をとり続ける。一方で、揺り戻しも起き始めた。今年1月、マサチューセッツ工科大学(MIT)の中国系の教授が中国政府などからの資金提供を開示していなかったとして、虚偽の納税申告容疑などで司法省に逮捕された。これに対し、MITは学長名で「これは大学間の協定で、個人的な受給ではない」と容疑を否定し、中国人学生や研究者らへの全面支持を表明した。スタンフォード大やプリンストン大でも司法長官に「チャイナイニシアチブ」の中止などを求める署名運動が広がっている。指摘される問題の一つが、取り締まりの線引きの「あいまいさ」だ。11月下旬、米ニューヨーク・タイムズ紙(NYT)は、「チャイナイニシアチブ」の一環で中国のスパイと疑われ、18カ月間自宅軟禁された末に無罪となった研究者の話を報じた。その中で「中国との結びつき」を示す情報開示の明瞭なルールがないことを指摘。「無関係の標的を見つけて手軽に成果を上げようとしている」という元捜査当局者の見方も紹介した。この問題は、米国の人種問題に発展する危うさもはらむ。全米の研究者や研究機関などが、アジア系の人種に絞った捜査だとして「チャイナイニシアチブ」の停止を求めて署名活動を展開。今年7月には、連邦議員約90人が「人種で対象を絞るのは差別であり、違法だ」との書簡に署名した。この手法では優秀な中国系人材が米国から流出し、中国を利するだけではないか――。NYTはそんな大学関係者の声も伝えた。米国に留学する外国人留学生の数は09年度、中国が01年度以来、再びインドを抜いてトップになり、コロナ下になるまで毎年増加。19年度には留学生全体の35%(約37万人)を占めた。「留学生たちを米国に引きつけ、とどまらせることが中国に勝つ方策だ」。米政府諮問機関「人工知能(AI)に関する国家安全保障委員会」の委員長として、今春、最終報告を出したグーグルのエリック・シュミット元最高経営責任者(CEO)は、そう強調する。大手IT企業が集まる西海岸のシリコンバレーは人口の39%が外国生まれ(米国全体では14%。投資会社調べ)。世界からいかに優秀な人材を集められるかが、米国経済を牽引(けんいん)するこの地域の隆盛の鍵だ。AI研究の大家で、中国の李克強(リーコーチアン)首相に大学の評価基準などを助言してきた、米コーネル大のジョン・ホプクロフト教授(82)は「優秀な中国人学生が米国に留学し、とどまってくれれば、米国の成長につながる。世界最大の経済大国になる中国とのつながりをいかに維持するか、戦略的に考えなければならない」と話す。 <日本の原発・火力・ガソリンエンジンへの固執は非科学的・感情的であること> PS(2021年12月16日追加):経産省は、*7-1のように、太陽光・風力による発電の膨大な出力制御が2022年度には北海道・東北・四国・九州・沖縄の5地域で発生するという試算をまとめ、その理由として、①再エネは不安定なので火力発電のバックアップが必要 ②火力発電の出力を50%以下(来春以降の見直しで20~30%)に引き下げる検討を進めている そうだ。 しかし、①は、2000年頃から20年以上も同じ説明をしており、「工夫がない」を超えて愚かと言わざるを得ず、解決もせずに言い訳にできるのは3年が限度と認識すべきだ。また、②は、*7-2のように、EUは温暖化ガスの排出ゼロに向けて天然ガスの長期契約ですら2049年までに禁止することを打ち出し、公共施設や商業ビル(2027年以降に新築するもの)と一般住宅(2030年までに)は、原則「ゼロエミッション」にすることを義務づけようとしているのに、再エネ由来の電力を捨てて火力発電を続けようと考えるのは科学的思考が全く感じられない。 その上、*7-3は「次世代原子力『小型モジュール炉』は、既存の原発より工期が短く、炉が小さく、建設費も安く、理論上は安全性が高い」として、脱炭素時代の電源として期待すると記載している。しかし、“理論上は安全性が高い”というのは科学的説明のない神話にすぎず、火山国・地震国の日本で地熱を利用せずに原発に依存したがるのは、短所をカバーしながら長所を活かすことのできない愚策である。また、*7-4のように、四電の伊方原発3号機も再稼働したが、中央構造線の真上にあり、南海トラフ地震による大津波の影響も受けそうな場所にある原発を稼働させるのは危険であると同時に、再エネを優先的に導入する方針にも反している。 このような中、*7-5のように、「国内電源は7割以上が化石燃料由来の火力発電が占め、その電気を使って走るEVは間接的にCO₂を出すEVは脱炭素の切り札と言い切れない。そのため、再エネへの転換が進まなければCO₂を減らせない」と言い訳しながら、トヨタはHV・PHVに固執してきたが、グリーンピースが世界の自動車大手10社の気候変動対策の評価でトヨタを最下位にしたのを受けて、EV化を加速するそうだ。豊田社長は、「EVの2030年の世界販売目標を350万台でも消極的というのなら、どうしたら積極的と言われるのかアドバイスして欲しい」とも言われたので、アドバイスを列挙すると下のとおりである。 イ)日本は1995年頃からEV化を始めているので、自動車産業のリーダーであり続けたけれ ば、各国政府の脱炭素宣言前に、各国政府にEV化・FCV化をロビー活動すべきだった。 ロ)PHVはエンジン付きで部品が多く、生産コスト・販売単価が高くなるため不要だった。 ハ)「敵は炭素で、内燃機関ではない」などのEV化に対する批判をするより、EV・FCV化 に適した電池・モーター・充電器の開発、車体の軽量化等に資本を集中すべきだった。 二)水素エンジン・EV・HV・PHV・FCVという「全方位」ではなく、資金の余裕がある うちに競争上優位な製品の開発に資金を集中すべきだった。 ホ)「EVシフトが進めば部品の多さから多くの雇用を吸収してきたエンジン関連産業が 要らなくなる」と書かれているが、それは一般消費者が不必要に高い価格で自動車を 買わされ、それだけ販売数量も減り、不便を強いられているということである。 へ)そのため、水素エンジンは航空機・船舶・列車等に使うよう資金の余裕があるうちに それらの新分野に進出し、失業・倒産を最小限に抑えつつ、産業高度化すればよかった。 また、商用・製造・農業用等の機械をEV・FCV化させるのもよいと思う。 ト)そうすることによって、日本のエネルギー自給率を飛躍的に向上させ、国民経済や 経済安全保障に貢献することが可能だったし、国家財政にも寄与できた筈だ。 *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211216&ng=DGKKZO78476850V11C21A2EP0000 (日経新聞 2021.12.16) 再生エネ発電の出力抑制、来年度5地域に拡大 経産省が試算 経済産業省は15日、太陽光と風力による発電を抑える出力制御が2022年度に北海道、東北、四国、九州、沖縄の5地域で発生するとの試算をまとめた。各地域の電力供給が需要を上回ると停電してしまうため、再生可能エネルギーによる発電を抑える。出力制御は太陽光発電の多い九州だけで起きていたが、広がる可能性がある。同省が電力会社の翌年度の出力制御の見通しをまとめたのは初めて。抑制する最大電力量は、九州は7億3000万キロワット時で地域の再生エネ発電量の5.2%に相当する。四国は5388万キロワット時で1.1%、東北は3137万キロワット時で0.33%、北海道は144万キロワット時で0.35%、沖縄は97.6万キロワット時で0.2%と試算した。経産省は再生エネの出力を抑える状況になった場合、火力発電所の出力を50%以下にするよう求めている。これを来春以降に見直し、20~30%に引き下げる検討を進めている。火力の出力を抑えればそのぶん再生エネの発電を増やせる。 *7-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211216&ng=DGKKZO78476750V11C21A2EP0000 (日経新聞 2021.12.16) EU、ガスの長期契約禁止、49年までに、CO2排出ゼロに向け 水素利用の拡大狙う 欧州連合(EU)の欧州委は15日、気候変動とエネルギー関連の法案を公表した。温暖化ガスの排出ゼロに向け、化石燃料を減らしてクリーンなエネルギー源を拡大する。柱の一つとして2049年までに原則として天然ガスの長期契約を禁止することを打ち出した。水素の利用拡大やビルの脱炭素に向けたルールも提案した。EUは50年に域内の温暖化ガスの排出を実質ゼロにする目標を掲げる。中間点として30年には90年比55%減らす計画だ。11月に英グラスゴーで開かれた第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)では各国が一段の排出減に取り組むことで合意した。EUは先陣を切って具体化に動き出す。天然ガスは石炭よりはクリーンなものの、二酸化炭素(CO2)は排出する。欧州委は49年までに長期契約を原則として終えるよう提案。安定供給などを目的とした1年未満の短期契約は認める。CO2の回収装置をつけている発電所なども例外になるようだ。法案の成立には曲折もありそうだ。足元ではガス不足でエネルギー価格が高騰している。ドイツはロシアと結ぶパイプライン「ノルドストリーム2」が完成したばかりだ。加盟国から反対の声が出る可能性がある。16日のEU首脳会議でも議論される見通しだ。欧州委は目標達成にはほとんどの化石燃料の利用をやめる必要があると主張する。ロシアへのエネルギー依存を減らせばEUが自立できるとみる。天然ガスに代わるエネルギーの主力になるとみるのが水素だ。いまはコストや規制がネックとなっている。普及拡大に向けて国境を越えるガス配送管に5%を上限に水素を混ぜることも認める方向だ。足元のエネルギー価格の高騰に対応した短期の対応策も示した。緊急時には有志国がガスを共同で備蓄したり、調達したりできるように制度を整える。EUでは一部の大国はガスを貯蔵しているものの、小国は関連施設を持っていない。各国が協力してガスを購入し、指定した場所に貯蔵できるような仕組みを設ける。欧州委は建物部門の脱炭素化に関する改革案も公表した。住宅や商業ビルなどから出る温暖化ガスは全体の4割弱を占める。公共施設や商業ビルを27年以降に新築する場合は原則として「ゼロエミッションビル」にすることを義務づける。ゼロエミッションビルはエネルギー消費が少なく、そのエネルギーも再生可能エネルギーなどでまかなえる建物だ。一般の住宅は30年までに義務づける方針だ。既存の建物の脱炭素化にも取り組む。EU域内で最もエネルギー効率が悪い分類は15%ある。公共施設や商用の建物は27年まで、住宅は30年までに最も悪い分類からの改善を求める。14日には輸送部門のグリーン化を進める対策を発表した。温暖化ガスの排出が少ない鉄道網の充実に力を入れる。欧州委によると、域内の国境を越えた旅客輸送で鉄道を使うのは7%にすぎない。30年には長距離鉄道の交通量を2倍にし、50年には3倍にする目標を掲げた。欧州委は22年にまとめる法案で、加盟国ごとにばらばらの長距離鉄道の予約方法の改善策を盛り込む。国境を越えた鉄道旅行に課す付加価値税の免除も検討する。主要都市を結ぶ路線は40年までに時速160キロ以上で走行できるようにする。 *7-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC032VF0T01C21A2000000/?n_cid=BMSR3P001_202112031238 (日経新聞 2021年12月3日) 日立が小型原子炉を受注 日本勢で初、カナダ企業から 日立製作所と米ゼネラル・エレクトリック(GE)の原子力合弁会社、GE日立ニュークリア・エナジーは2日、次世代原子力の「小型モジュール炉(SMR)」をカナダで受注したと発表した。日本勢の小型の商用炉の受注は初めて。既存の原発よりも工期が短く、炉が小さく理論上は安全性が高いとされる。世界が脱炭素にカジを切るなか、温暖化ガスを排出しない電源として期待されている。電力大手のカナダ・オンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)から受注した。受注額は非公表。2022年内に建設許可を申請し、最大4基を建設する。早ければ28年に第1号機が完成する。日立が強みを持つ軽水炉の技術を活用した出力30万キロワット級の「BWRX-300」と呼ばれる小型原子炉を納入する。小型原子炉は現在商用化している出力100万キロワット級の原子炉に比べて出力が小さい。工場で部品を組み立てて現場で設置する方式で品質管理や工期の短縮ができるため、建設費が通常の原発より安くすむとされる。各国で研究開発が進むが、日本国内での導入には原子力発電所への信頼回復や耐震性など課題も多い。 *7-4:https://www.kochinews.co.jp/article/detail/526079 (高知新聞 2021.12.3) 【伊方原発再稼働】安全を重く受け止めよ 四国電力の伊方原発3号機(愛媛県)がきのう、約2年ぶりに再稼働した。東京電力福島第1原発事故以来、原発への不信感は根強い。運転に前のめりになっては管理機能を低下させかねない。万全の安全対策と説明責任を求めたい。3号機は定期検査のため、2019年12月に停止した。この間、20年1月には広島高裁が運転差し止めの仮処分を決定した。これを不服とした四電の異議申し立てで、ことし3月に運転が容認されている。運転を禁じた決定は、地震や火山リスクに対する四電の評価や調査を不十分とした。異議審では、安全性の評価は不合理ではないと四電の主張をほぼ認める結果となった。一連の判断の前にも、3号機では運転差し止めの仮処分決定と異議審での取り消しが行われている。大規模自然災害の予測や備えを巡り、司法の見解さえ分かれる状況にあることを十分に認識する必要がある。福島第1原発事故は、原発でひとたび過酷事故が起きれば長期にわたり重大な被害をもたらすことを強く認識させた。専門家の見方さえ定まらない問題ならばなおさら、住民の不安と丁寧に向き合わなければ理解は得られはしない。安全性を揺るがせるのは災害ばかりではない。四電はことし7月、宿直者が原発敷地外へ無断外出を繰り返し、保安基準上必要な待機人数を満たさない時間帯があったことを発表している。10月の運転再開予定の延期につながるほどの事案を長く見逃してきたことにも驚く。再発防止策として、宿直者全員に衛星利用測位システム(GPS)付きスマートフォンを持たせるという。そうしたことが役立つにしても、決定打とはならないだろう。緊張感が乏しいのはなぜなのか。労務管理の在り方はもとより、安全意識の徹底が求められる。定期検査中には、制御棒を誤って引き抜き、また一時的にほぼ全ての電源が喪失されるなどのトラブルが相次いだ。原子力を扱う事業者としての適格性が問われたことを肝に銘じなければならない。3年ぶりに政府が改定した「エネルギー基本計画」は、30年度の電源構成に占める原発の割合を従来目標で据え置いた。近年の実績を大きく上回る数値で、今ある原発のほぼ全てを再稼働しないと達成は難しいとされる。新増設や建て替えの見通しは立たない。福島第1原発事故後、原発の運転期間は「原則40年、最長で延長20年」となり、それにのっとった動きも出ている。基本計画は、脱炭素化の達成へ再生可能エネルギーを優先的に導入する方針を示す。しかし、電力の安定供給や巨額投資に困難が伴う。原子力は可能な限り依存度を低減させる意向は維持し ているが、それへ向けた強い姿勢はうかがえない。脱炭素を原発の長期的な運転につなげたい思いもあるようだ。それを住民がどう受け止めるのかに関心を向ける必要がある。 *7-5:https://digital.asahi.com/articles/ASPDG5R69PDCOIPE00J.html (朝日新聞 2021年12月14日) EV化加速を迫られたトヨタ 市場拡大、慎重派イメージ転換狙い トヨタ自動車が電気自動車(EV)の2030年の世界販売目標を350万台に引き上げた。これまで、「脱炭素」の切り札としてEV一辺倒に偏りがちな政策の潮流と距離を置いてきた。それが、積極的な普及をアピールする方向に転じた。本格的なEV競争に入る。東京・お台場のショールームにはスポーツ用多目的車やスポーツカーなど、トヨタが今後投入するEVの開発車両が16車種並んだ。豊田章男社長は車両を披露しながら「私たちは長い年月をかけて、様々な領域で取り組みを進めてきた」と強調。「EVならではの個性的で美しいスタイリング、走る楽しさのある暮らしを届けたい」と力を込めた。トヨタは30年までに30車種のEVを販売する方針も明らかにした。トヨタは今回、EVへの積極姿勢をアピールしたが、これまではEVの急速な普及に慎重な見方を示してきた。政府が昨年10月、50年までの脱炭素を宣言し、今年1月には35年までに乗用車の新車販売で純粋なガソリン車をゼロにする目標を掲げた。トヨタにとって、早期のEV化を強く迫るものと映り、警戒心を抱かせた。トヨタが描く脱炭素時代の戦略は、水素エンジンの開発も進め、EVやハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド(PHV)、燃料電池車(FCV)と「全方位」でエコカーをとりそろえ、国や地域の事情に応じて柔軟に車種を投入する考え方だ。5月には、30年の世界販売1千万台のうち800万台を、車載電池の電気エネルギーを動力に使う「電動車」にする目標を公表。電動車800万台のうち、EVは、水素を使う燃料電池車(FCV)を含めて200万台。HVが電動車の主力で、PHVとあわせて600万台とした。これらの数字は、世界の実情にあわせて緻密(ちみつ)に積み上げた目標だ。そして豊田社長みずから記者会見の場などで、「敵は炭素で、内燃機関(エンジン)ではない。技術の選択肢を狭めないでほしい」などと、EVに偏りがちな政策の潮流をたびたび牽制(けんせい)してきた。会長を務める日本自動車工業会の記者会見でも今年9月、「一部の政治家からは、すべてEVにすればよいんだとか、製造業は時代遅れだという声を聞くことがあるが、違うと思う」と批判した。実際、EVは脱炭素の「切り札」と言い切れない。国内の電源は7割以上が化石燃料由来の火力発電が占める。その電気を使って走るEVは間接的に二酸化炭素(CO2)を出す。再生可能エネルギーへの転換が進まなければ、CO2を減らせない。レアメタルが必要な車載電池の生産には大量のエネルギーを使う。製造から走行、廃棄といった「車の生涯」で見ると、EVでもCO2を簡単には減らせない。一方、EVシフトが進めば、部品の多さからたくさんの雇用を吸収してきたエンジン関連産業が要らなくなる。失業や倒産も増える心配がある。豊田社長が「脱炭素は雇用問題だ」と主張する背景だ。ただ、こうしたトヨタの「正論」は、気候変動対策に後ろ向きだとみられるようになっていった。米紙ニューヨーク・タイムズは今夏、「クリーンカーを主導したトヨタが、クリーンカーを遅らせている」と、批判的に論評。環境保護団体のグリーンピースは11月、世界の自動車大手10社の気候変動対策の評価で、トヨタを最下位にした。「EVの全面移行に対する業界最大の障壁」と酷評した。一方、市場では「EV銘柄」が急成長だ。販売規模でトヨタの10分の1ほどのEV専業の米テスラは、株式の時価総額が1兆ドル(113兆円)を超えている。トヨタの3倍超の水準だ。自動車部品のデンソーは、EVに不可欠な技術が評価され、株価は2年で2倍に上昇。トヨタ株もこの2年で3割余り上昇したが、デンソーの勢いははるかに上回る。東海東京調査センターの杉浦誠司シニアアナリストは、「トヨタはEVについてのメッセージが少なく、市場では戦略が劣っているとみられかねない」と分析する。11月にあった9月中間決算の記者会見で、長田准執行役員は、「トヨタはハイブリッドの擁護派、EVの反対派ではないかといわれるが、思ったことが伝わらない。EVをどう伝えるか悩んでいる」と話していた。そして今回、トヨタはEV化を加速させる方向に転じた。「全方位」の手堅い電動化戦略は、資金に余裕のあるトヨタだからこそできる手立てだ。主力市場でHVの販売は好調で、FCVの技術でも世界をリード。EV開発も進めてきたが、「全方位」を主張すればするほど、EV戦略が評価されにくくなっていた。そして何よりも、世界や日本勢もEV化に向けてかじを切り始めた。豊田社長は説明会で「各国のいかなる状況や、いかなるニーズにも対応し、カーボンニュートラルの多様な選択肢を提供したい」と強調した。トヨタはいよいよEV専用車を来年から世界で販売する。車載電池への巨額投資も決めている。「EVにも強いメーカー」へと脱皮できるか。巻き返しを本格化させた。 <日本は、既にオリ・パラ・万博で国威発揚しなければならない開発途上国ではない> PS(2021年12月18日追加):*8-1のように、2030年の冬季オリ・パラ招致を目指す札幌市が、競技会場を2カ所減らして既存施設の改修・建替を進め、経費を最大900億円圧縮する開催概要計画の修正案を公表したそうだが、2,800~3,000億円もの巨費を投じる大会を気候変動で積雪すら危惧される札幌で再度開催することに、私は疑問を感じる。 もちろん、私は、東京大会についても、「同じ場所で二度も開催する必要はないだろう」と思っていたが、やはり経費が増大し、収支には国の大きな補助金を必要とすることになった。さらに、東京大会は、(IOCが独善的だったのではなく)日本政府が非科学的で失敗の多かった新型コロナ政策を、メディアが「コロナ禍」と呼んで中止・無観客開催を大合唱し、誘致しない方がよほどよかったような大会になってしまったのである。そもそも、イベントでもしなければ世界から顧みられないような発展途上国ならオリ・パラ・万博を開催し、新しい施設を造って国威発揚するのは有効な経済政策になろうが、世界第3位の経済大国ともなれば世界の競争市場で勝ち続けなければならないのであり、イベント頼みで国威発揚をする段階ではない。 そのような中、*8-2のように、「北京五輪の『外交的ボイコット』を表明する国が相次ぐ」そうだが、IOCは、*8-3のように、「五輪の政治化に断固反対」と宣言した。五輪はもともと政治の場ではないため、「外交的ボイコット」を表明すること自体が五輪を政治利用しているということであり、褒められる行為ではないため、政府関係者や閣僚を派遣しない国は静かに自国の選手を送り出した方がよいと思われる。 なお、アメリカ・オーストラリア・イギリス・カナダ等が、北京五輪を外交的ボイコットする理由を、「中国による新疆ウイグル自治区での大量虐殺や人権侵害」としているが、中国は「大量虐殺は世紀の嘘で事実ではない」としている。「どちらの主張が本当か?」については、*9-1のように、国際人権団体アムネスティは、ウイグル族などのイスラム教徒が多く暮らす中国北西部新疆地区で、中国政府が①人道に対する罪を犯している ②ものすごい人数が収容所で洗脳・拷問などの人格を破壊する扱いを受けている ③何百万人もが強大な監視機関におびえながら暮らしている ④人間の良心が問われている とする報告書を公表した。 しかし、*9-2のように、BBCは、⑤中国の人口政策でウイグル族の出生数が数百万減少し ⑥少数民族が暮らす南部4地区で出産年齢の女性の8割以上に避妊リングや不妊手術による出産防止措置を実施する計画を立てた とも指摘しており、欧米各国は中国の出産制限措置をジェノサイド(集団殺害)と批判しているのだ。これに対し中国は、⑦まったくのナンセンス、出生率の低下は出産数の割り当てが実施されたこと・収入増加・避妊具が入手しやすくなったこと等が原因 としている。私は、中国の人口政策は、イスラム教徒の多い新疆ウイグル自治区の女性を解放する変化の過程で起こることで、欧米や日本の主張は(意図的か否かは不明だが)誤解ではないかと思う。ユニクロの柳井会長兼社長も、*9-3のように、⑧人権問題というより政治的問題だ ⑨すべての取引先工場について第三者による監査を実施し、ウイグル人を含むいかなる強制労働も発生していないことを確認した と言っておられ、そちらの方が本当だと思われるので、人権侵害を指摘する人は、具体的に何が強制労働や人権侵害に当たるのかについて証拠に基づいて指摘すべきだ。さらに、*9-4のように、グンゼも強制労働の疑いをかけられ、新疆ウイグル自治区産の綿花使用を中止せざるを得なくなったそうだが、⑩生産工程で人権侵害は確認されていない としている。従って、新疆ウイグル自治区産の綿花使用を中止させる行為は、かえって新疆ウイグル自治区の女性から彼女たちにできる仕事を奪って自立を阻害する結果になっている可能性があると思うのである。 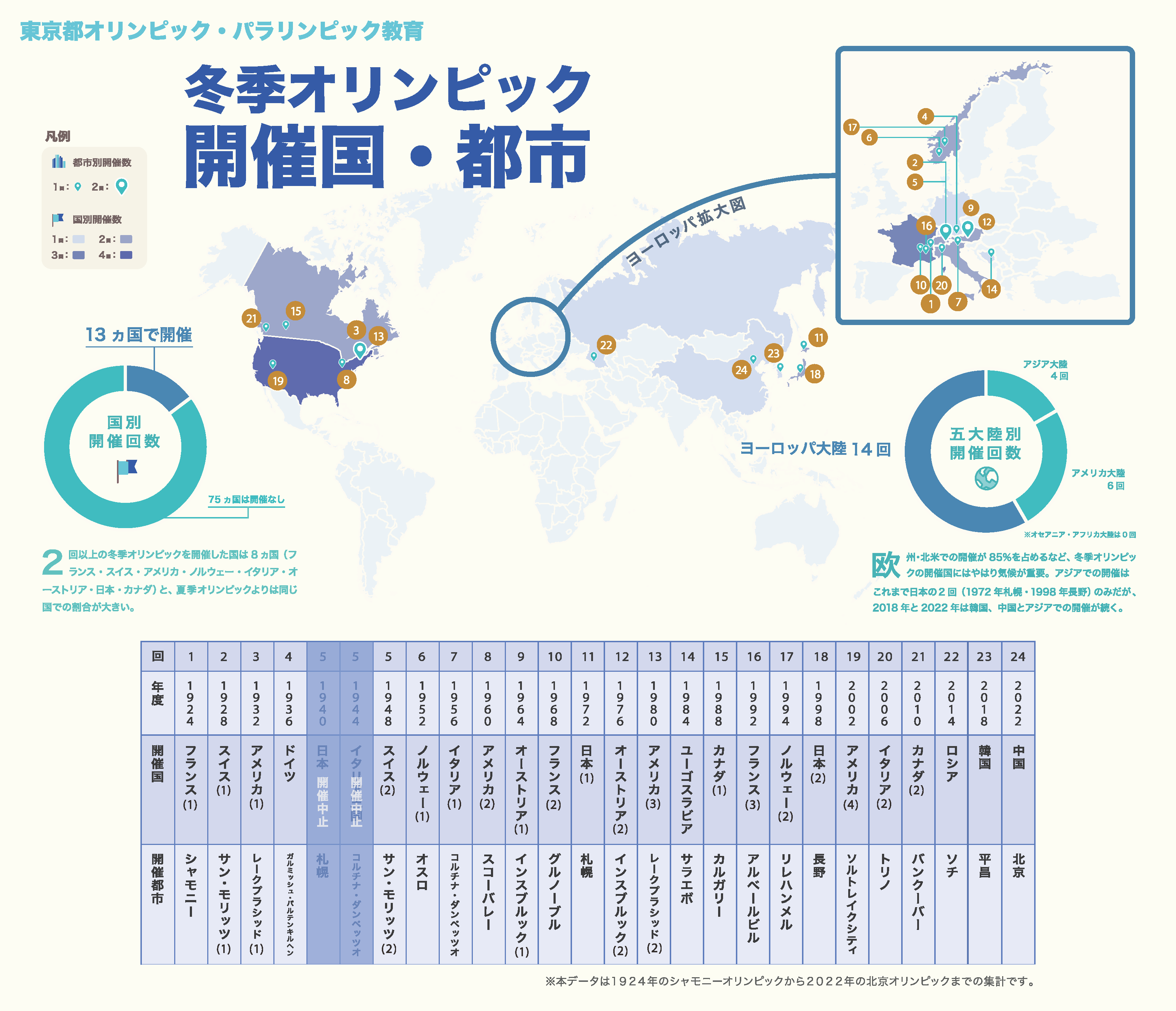  (図の説明:左図のように、冬季オリンピックの開催国は13カ国に集中しているが、現在は開催可能な国が増えている筈である。右図のように、北京冬季五輪は「冬」という文字をデザインに入れているが、冬という文字が共通なのは当然ではあるものの面白い) *8-1:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021120200872 (信濃毎日新聞社説 2021/12/3) 札幌五輪招致 東京の総括がなされねば 2030年の冬季五輪・パラリンピック招致を目指す札幌市が、開催概要計画の修正案を公表した。一昨年に示した経費を最大で900億円圧縮する。競技会場を2カ所減らすほか、既存施設の改修や建て替えを進めるという。東京五輪・パラは運営経費が当初計画から大幅に膨らんだ。自治体の財政が厳しい中で、経費を極力抑えるのは当然だ。ただ、それで市民の不安が和らぐとみるのは早計だろう。まず示されねばならないのは、2800億~3千億円もの巨費を投じる大会を地元で開くことの意義と課題だ。東京大会組織委員会の橋本聖子会長は、パラ閉幕時の会見で早くも札幌の招致実現に強い期待を語っていた。招致に向けて国会議員連盟を発足させる動きもある。東京大会の収支決算も済んでいない。経費増大の要因、大会が残したさまざまな教訓を総括する前に、次の招致に傾斜している。東京大会では国際オリンピック委員会(IOC)の独善的とも言える姿勢があらわとなった。五輪憲章は原則としてIOCが開催に財政的責任を負わないと明記する。開催都市契約では、不測の事態で組織委が変更を求めても対応する義務を負わない。コロナ禍で開催を危ぶむ声が高まっても顧みられることはなかった。巨額負担を嫌う各国の「五輪離れ」を受けて、IOCは従来の選定方式を変更。興味を示す都市と個別に交渉を重ね、開催地を早めに確保しようとしている。30年には複数の都市が名乗りを上げている。国際大会の実績などから札幌は本命視される。地元住民の支持は得られるのだろうか。市は来年3月をめどに道民の意向調査を予定する。市長は結果に縛られず、市議会や他都市の意向も踏まえて招致の可否を判断する考えを示している。「開催ありき」で走りだせば将来に禍根を残す。地域振興どころか、財政負担ばかり次世代に押しつけることになりかねない。経費の積算も透明性が欠かせない。納得し、大会を迎える機運を高められるか。それとも再考すべきか。住民が冷静に是非を判断できる材料がなくてはならない。2千億円余の運営費はチケットやスポンサー収入で賄う。東京大会で宣伝効果が得られなかった企業の五輪離れも懸念される。製氷を止めた長野市のスパイラルが、そり競技会場として大会概要案に盛り込まれた。長野県民も行方を注視していきたい。 *8-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/6176f97f8dd654ebd435427b86840d3820f60ef5 (日テレNEWS 2021/12/9) 北京五輪“外交的ボイコット”相次ぐ 日本の方針は?“ある人物”を派遣する案も 北京オリンピック開幕まで2か月を切る中、“外交的ボイコット”を表明する国が相次ぎ、中国と各国の対立が浮き彫りになっています。何が問題なのか、日本はどうするのか、詳しくみていきます。 ■4か国が北京五輪“外交的ボイコット” 東京大会に続く、コロナ禍2度目のオリンピックとなる冬の北京オリンピックは来年2月4日に開会式、20日に閉会式が行われます。来年は日中国交正常化50周年の節目になりますが、日本政府は今、難しい対応を迫られています。それがオリンピックに政府関係者や閣僚を派遣しない“外交的ボイコット”です。選手が出場できなくなるのではなく、政府関係者などを派遣しないということです。外交的ボイコットを表明したのは、アメリカ、オーストラリアと続き、新たにイギリス、カナダもボイコットを表明しました。これに対して中国側はすぐに反発し、それぞれの国の中国大使館の報道官は「中国政府はイギリス政府関係者を招待していない」、「国際社会と多くの選手の反対にあうだろう」、「カナダはスポーツを政治化せず、北京オリンピックを妨害する誤った言動をただちにやめなければならない。さもなければ、自ら恥をかくだけだ」と声明を出しています。これら4つの国がボイコットする理由は、中国の人権侵害です。アメリカ・ホワイトハウスのサキ報道官は「中国による新疆ウイグル自治区での大量虐殺や人権侵害」を理由にあげ「人権のために立ち上がるのはアメリカのDNAだ」と話しています。一方の中国側は、大量虐殺について「世紀の嘘で事実ではない」、「嘘とデマに基づいて北京冬季五輪を妨害しようとすることは、アメリカの道義と信頼を喪失させる」と主張しています。さらに、「断固とした対抗措置をとる」と猛反発しています。中国側の思惑について、北京で取材を続けるNNN富田徹総局長は「北京オリンピックは習近平政権の威信をかけた国家イベント。本音ではバイデン大統領を招待するなどして、華々しく盛り上げたかったはず。そのため、先月の米中首脳会談の後にアメリカが外交的ボイコットを発表したことは本当に痛手で、このままボイコットドミノが広がることを強く警戒しているとみられる」と話しています。 ■日本の方針は? 日本の方針についてですが、7日、岸田総理は「オリンピックの意義とか、我が国の外交にとっての意義等を総合的に勘案し、国益の観点から自ら判断していきたい」としています。同盟国のアメリカがボイコットするけれども、日本は日本で判断するということです。現時点でどうするかは、まだ決まっていません。一方、中国は先月、日本を「中国は東京五輪を全面支持した。日本は信義を守るべきだ」とけん制しています。この夏の東京大会は、コロナで開催が危ぶまれていた時も「中国は全面的に支援した。その義理を返しなさいよ」ということです。安倍元総理は9日、自身の派閥の会合で次のように発言しました。「ウイグルで起こっている人権状況については、政治的な制度、メッセージを出すことが我が国には求められているんだろう。日本の意思を示すときは近づいているのではないかと考えている」。日本の意思を示す時、つまり、日本も“外交的ボイコット”をするよう政府側に促したとみられます。また8日、自民党の高市政調会長も日本政府は“外交的ボイコット”を行うべきとの認識を示しました。政府関係者は「アメリカから同調圧力がないわけではない。日本が動かなかったら、西側諸国からの目が厳しくなる」との声もあります。アメリカがボイコットを表明して2日ほど経ちますが、日本がどのような決断をするか、世界も注目しています。 ■政府内ではある作戦が 政府内では、良さそうな作戦があるということです。それが、室伏スポーツ庁長官を派遣する案が持ち上がっているということです。政府関係者は「東京五輪に中国から来てくれた返礼は必要。中国から来た人と同じような立場の室伏長官の派遣でも問題ない」と話しています。東京大会には、中国の体育総局の責任者が来ました。スポーツ庁の様なところの責任者の方です。室伏長官はスポーツ庁のトップで金メダリスト。政府関係者ではあるけど、閣僚でも政治家でもありません。そうすれば、中国には「東京大会を応援してくれてありがとう。代表として長官を派遣します」、アメリカには「閣僚などの政治家は派遣していない」とどちらにも顔が立ちます。中国で起きている様々な人権問題は、うやむやにされることがあってはならない問題です。日本時間の9日夜、アメリカ主催で日本を含む110か国が参加する民主主義サミットが開かれ、中国を念頭にした人権問題が話し合われます。オリンピックを舞台とした政治の駆け引きは、ますます激しくなるといえます。 *8-3:https://digital.asahi.com/articles/ASPDD65XBPDDULZU001.html?iref=comtop_Sports_01 (朝日新聞 2021年12月12日) IOC「五輪の政治化に断固反対」 相次ぐ外交ボイコット受けて宣言 国際オリンピック委員会(IOC)は11日、五輪に関わるスポーツ界の代表を集めた「五輪サミット」をオンライン形式で開き、「五輪とスポーツの政治化に断固として反対する」との共同宣言を発表した。会議はトーマス・バッハIOC会長を座長を務め、米国、中国、ロシアの国内オリンピック委員会の会長や、IOC委員でもある渡辺守成・国際体操連盟会長はじめ主要競技の国際連盟会長、世界反ドーピング機関のウィトルド・バンカ委員長らが出席した。米国、英国、豪州などは来年2月の北京冬季五輪をめぐり、中国の人権問題への懸念を理由に、大会に政府首脳を派遣しない「外交ボイコット」を表明している。会議ではこの動きを受けて、「IOC、五輪、そしてオリンピックムーブメントの政治的中立の必要性を強く強調する」と訴え、スポーツ界の団結をアピールした。宣言ではこのほか、国連総会で北京冬季五輪・パラリンピック期間中の休戦決議案が採択されたことを歓迎し、173カ国が共同提案国になったことにも触れた。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で開かれた今夏の東京五輪については「世界的な大成功であることに感謝する」とし、「アスリートたちは前例のない挑戦にもかかわらず大会が開かれたことに強い満足感を示した」と称賛した。テレビとインターネットを通じたデジタル配信の視聴者はあわせて30億人を超し、五輪史上で最も多くの人に届いた大会になったと総括した。 *9-1:https://www.bbc.com/japanese/57437638 (BBC 2021年6月11日) 中国のウイグル族弾圧は「地獄のような光景」=アムネスティ報告書 国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは10日、ウイグル族などイスラム教徒の少数民族が多く暮らす中国北西部の新疆地区で、中国政府が人道に対する罪を犯しているとする報告書を公表した。 報告書でアムネスティは、中国政府がウイグル族やカザフ族などイスラム教徒の少数民族に対し、集団拘束や監視、拷問をしていたと主張。国連に調査を要求した。アムネスティ・インターナショナルのアニエス・カラマール事務局長は、中国当局が「地獄のような恐ろしい光景を圧倒的な規模で」作り出していると非難した。「ものすごい人数が収容所で洗脳、拷問などの人格を破壊するような扱いを受け、何百万人もが強大な監視機関におびえながら暮らしており、人間の良心が問われている」。カラマール氏はまた、BBCの取材に対し、国連のアントニオ・グテーレス事務総長が「責任を果たしていない」と批判した。「(グテーレス氏は新疆の)状況を非難せず、国際調査も指示していない」。「国連がよって立つ価値を守り、人道に対する罪に対して声を上げる責務が彼にはある」 ●報告書の中身 報告書は160ページからなり、かつて拘束されていた55人への聞き取り調査を基にしている。中国政府について、「少なくとも以下の人道に対する罪」を犯していたとし、「国際法の基本ルールに違反する、収監など厳格な身体的自由の剥奪」、「拷問」、「迫害」を挙げている。国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチも、4月に同様の報告書を発表。中国政府は、人道に対する罪に対する責任があるとした。欧米の一部の国や人権団体も、中国が新疆地区で、チュルク系民族に対するジェノサイド(集団殺害)を進めていると非難している。ただ、中国の行為をジェノサイドとしていることについては、反論も出ている。今回のアムネスティの報告書をまとめたジョナサン・ロウブ氏は10日の記者発表で、報告書について、「ジェノサイドの犯罪が行われたすべての証拠を明らかにはしたものではない」、「表面をなぞっただけだ」と説明した。中国は新疆地区で人権侵害はないと、一貫して主張している。 ●拘束や拷問の疑い 専門家らは、中国が新疆地区で少数民族への弾圧を始めた2017年以降、約100万人のウイグル族などのイスラム教徒が拘束され、さらに数十万人が収監されているとの見方でほぼ一致している。報道では、刑務所や収容所で身体的、心理的拷問が行われているとされている。人口管理のため、中国当局は強制不妊手術や中絶、強制移住を実施しているとも言われている。宗教や文化に基づく伝統の破壊を目的に、宗教指導者を迫害しているとの批判も出ている。中国はそうした指摘を否定。新疆地区の収容所は、住民らが自発的に職業訓練を受けたり、テロ対策として過激思想を解いたりするためのものだと主張している。アムネスティは、テロ対策は集団拘束の理由にならないと報告書で反論。中国政府の行動は、「新疆の人口の一部を宗教と民族に基づいてまとめて標的にし、イスラム教の信仰とチュルク系民族のイスラム教文化の風習を根絶するため厳しい暴力と脅しを使うという明らかな意図」を示しているとした。アムネスティは、新疆地区で収容所に入れられた人が「止まることのない洗脳と、身体的かつ心理的拷問を受けている」とみられるとした。拷問の方法としては、「殴打、電気ショック、負荷が強い姿勢を取らせる、違法な身体拘束(「タイガーチェア」と呼ばれる鉄製のいすに座らせ手足をロックして動けなくするなど)、睡眠妨害、身体を壁のフックにかける、極めて低温の環境に置く、独房に入れる」などがあるとした。タイガーチェアを使った拷問は、数時間~数日にわたることもあり、その様子を強制的に見せられたと証言した人もいたという。アムネスティはまた、新疆地区の収容制度について、「中国の司法制度や国内の法律の管轄外で運営されている」とみられると説明。収容所で拘束されていた人々が刑務所に移されたことを示す証拠があるとした。 ●中国へのさらなる圧力 今回の報告書の内容の多くはこれまで報道されてきたものだが、新疆地区での行動をめぐって、中国に国際的な圧力をかけるものになるとみられる。米国務省はこれまでに、ジェノサイドが行われていると表現。イギリス、カナダ、オランダ、リトアニアの議会も、同様の表現を含んだ決議を採択している。欧州連合(EU)、アメリカ、イギリス、カナダは3月、中国当局者に制裁を課した。これに対し中国は、それらの国の議員や研究者、研究施設などを対象に報復的な制裁を実施した。中国は国際刑事裁判所(ICC)の署名国になっておらず、同裁判所の権限が及ばないため、国際機関が中国を調査する可能性は高くない。一方、国連の国際司法裁判所(ICJ)が事件として取り上げても、中国は拒否権を発動できる。ICCは昨年12月、事件として取り上げないと発表した。ロンドンでは先週、一連の独立した聞き取り調査が実施された。イギリスの著名法律家サー・ジェフリー・ナイスが中心となり、ジェノサイドの訴えについて調べるものだった。 *9-2:https://www.bbc.com/japanese/57395457 (BBC 2021年6月8日) 中国の人口政策で、ウイグル族の出生数が数百万減少も=研究 中国政府の産児制限の影響で、南部・新疆地区で暮らすウイグル族などの少数民族の20年後の人口が、当初の予測より最大3分の1ほど少なくなる可能性があると、ドイツ人研究者が指摘している。中国の新疆政策に関する世界的な専門家で、共産主義犠牲者記念財団(米ワシントン)の研究員であるエイドリアン・ゼンズ氏は、現地の状況を新たに分析。その結果、20年後の少数民族の出生数は、当初の予測より260万~450万人少なくなる見込みであることがわかったという。中国政府の少数民族に対する弾圧が、新疆の人口に及ぼす長期的な影響について、査読を受けた学術研究が出されるのはこれが初めて。ゼンズ氏によると、中国政府が弾圧を強める以前は、新疆地区の少数民族の人口は、2040年に1310万人に達すると予測されていた。しかし現在では、860万~1050万人になるとみられるという。ゼンズ氏は、「ウイグル族の人口に対する中国政府の長期計画の意図が今回(の調査と分析で)はっきりした」と、この分析を最初に報じたロイター通信に話した。同氏は分析報告書で、新疆当局が2019年までに「少数民族が暮らす南部の4地区で、出産年齢の女性の8割以上に、避妊リング(IUD)や不妊手術による出産防止の措置を実施する計画を立てていた」とも指摘した。欧米各国は、中国が出産制限の措置を強制することで、ジェノサイド(集団殺害)を実行していると批判している。中国はそうした訴えを「まったくのナンセンス」だと否定。出生率の低下は、出産数の割り当てが実施されたことや、収入の増加、避妊具が入手しやすくなったことなどが原因だとしている。 ●漢族の比率が大幅増か ゼンズ氏の研究によると、中国政府は新疆地区に主要民族の漢族を移住させ、ウイグル族などを転出させる施策も進めている。新疆地区の漢族の人口比率は現在8.4%だが、2040年までには約25%に増える見通しだという。中国の公式統計では、新疆地区の少数民族が暮らすエリアの出生率が、2017~2019年に48.7%下落した。中国は先週、夫婦に3人まで子どもをもうけることを認める方針を発表した。しかし、新疆地区では反対の方針が取られている様子が、流出文書や証言などからうかがえる。出産数の割り当てに違反した女性は、拘束や処罰されているとみられる。今回のゼンズ氏の研究とその手法は、ロイター通信が人口統計や人口抑制政策、国際人権法などの専門家十数人に示し、妥当だとの反応を得たという。ただ、専門家の一部は、数十年先の人口予測について、予測不可能な事態の影響を受ける場合があると指摘している。 *9-3:https://digital.asahi.com/articles/ASP4S730RP4RULFA02M.html?iref=pc_rellink_03 (朝日新聞 2021年4月25日) ユニクロも無印も…新疆綿で板挟み「何言っても批判が」 ●経済安保 米中のはざまで 中国・新疆ウイグル自治区は、世界でも良質な「新疆綿」の産地として知られる。世界のアパレル企業が供給網として依存する一方、中国によるウイグル族などの強制労働があるとして欧米が問題視。「人権」をめぐる米中対立の先鋭化に、日本企業も揺さぶられている。8日、衣料品チェーン大手「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの記者会見。柳井正会長兼社長は「出店のペースを上げ、アジアで圧倒的ナンバーワンになる」と力強く宣言した。中国に展開するユニクロの店舗数は2月末時点で800店で、日本国内の807店を近く抜く見通しだ。コロナ禍からいち早く抜けた中国は21年1~3月期、前年同期比で18・3%の経済成長を遂げた。同社にとって中国は衣類の主要な生産拠点であり、最重点市場でもある。だが、海外メディアを含む3人の記者が立て続けにウイグルに関する強制労働と綿花使用の質問をすると、表情を曇らせてこう語った。「政治的な質問にはノーコメント」「人権問題というより政治的問題だ」「我々は政治的に中立だ」。豪シンクタンク「豪戦略政策研究所(ASPI)」が昨年3月に発表した報告書は、グローバル企業82社が、ウイグル族を強制労働させた中国の工場と取引していると指摘。報告書にはユニクロなど日本企業14社の名前があった。ファーストリテイリングは朝日新聞の取材に「すべての取引先工場について第三者による監査を実施し、ウイグル人を含むいかなる強制労働も発生していないことを確認した」と内容を否定した。報告書では「無印良品」を展開する良品計画も名指しされた。同社はウイグルの農場で綿を調達しているとしながらも、朝日新聞の取材に「(取引先の第三者による監査で)法令または弊社の行動規範に対する重大な違反は確認していない」と回答した。ウイグル問題で企業に対応などを求めてきた国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」の佐藤暁子弁護士は、柳井氏の発言を「『政治的に中立だからコメントしない』というのは全く的外れだ。特定民族に対して課す強制労働の問題は、国際的な人権上の問題であって、『内政干渉』になるから何も言わないという話ではない」と批判する。また、強制労働そのものを否定する中国にある企業に、強制労働の有無を問い合わせても、正直に答えるはずもなく、どれほど実態を把握できるのかといった、「監査」の実効性を疑問視する指摘もある。報告書で指摘された日本企業には、アパレルだけでなく玩具や電化製品の企業も含まれる。企業が関与を否定しても、株価の下落などの影響が広がる。12日にはフランスのNGOなどが「供給網を通じてウイグル族の強制労働に関与している疑いがある」としてユニクロなどのアパレル企業を告訴した。「中国と米国でビジネスを行っている以上、どちらかにだけ良い顔をするわけにはいかない」。ファーストリテイリングなどと共に、ASPIの報告書で名前を挙げられた別の企業の関係者はそう話す。「法令に沿ってビジネスをしているはずなのに、今は何を言っても批判されてしまう」として、米中、そして世論とビジネスの板挟みとなっている苦悩を吐露する。バイデン米政権は中国の行為を「ジェノサイド(集団殺害)」と断じ、欧州連合(EU)などと連携して対中制裁を発動。対中強硬姿勢を強めている。中国も防戦一方ではない。人権侵害を懸念するとともに、新疆綿を調達しないと発表したスウェーデンの衣料品大手「H&M」を、中国の共産党系団体が批判し、不買運動が起きた。経済的な報復措置で米欧の人権外交に反撃する構えを見せる。主要7カ国(G7)で唯一、対中制裁に踏み切っていない日本だが、16日の日米共同声明では、香港やウイグルの人権状況について「深刻な懸念を共有する」と明記した。政府関係者はこう語る。「対応を誤れば、企業は中国の巨大市場を失う。かといって米国の呼びかけは無視できない。政府や日本企業には厳しい踏み絵だ」 *9-4:https://digital.asahi.com/articles/ASP6J6G18P6JPLFA00F.html (朝日新聞 2021年6月16日) グンゼ、新疆綿の使用中止へ 人権侵害への懸念で 下着大手のグンゼ(大阪市)は16日、中国・新疆ウイグル自治区産の綿花の使用を中止することを明らかにした。新疆綿をめぐっては、中国側がウイグル族に強制労働をさせた疑いがあるとして、特に欧米が問題視している。同社は生産工程で人権侵害は確認されていないとするが、国際的に懸念が広がっている状況を考慮したという。同社によると、靴下の「ハクケア」シリーズの一部に新疆綿が使われていることがわかり、使用の中止を決めた。今後は別の産地の原料に切り替える方針という。在庫分は販売を続ける。新疆綿を使った衣料品をめぐっては、ファーストリテイリングが展開する「ユニクロ」のシャツが米国で輸入を差し止められるなど、各国からの視線が厳しくなっている。一方、中国政府は強制労働の事実を否定。新疆綿の使用中止を発表したスウェーデンの衣料品大手「H&M」は、中国で不買運動を受けた。衣料業界のサプライチェーン(供給網)は複雑で、最終的な商品を販売する会社が全てを把握するのは困難との声もあり、各社が難しい判断を迫られている。 <日本における再エネとEVの停滞は何故起こったのか> PS(2021年12月30日):*10-1のように、ドイツはフクイチ事故後「脱原発」を着々と進めているのに、日本のメディアは、*10-2のように、「電力の安定供給と気候変動対策を両立するため、フランスや英国が主導して欧州で再び原子力発電所を活用する動きが活発になっている」などとして、原発活用に向けた議論が停滞していることがよくないような書き方をしている。しかし、フクイチの事故処理も汚染水の処理もまともにできず、放射性廃棄物の最終処分場も決まっていないのに、脱炭素に原発が必要であるかのように言うのには原発を推進したい意図がある。しかし、このようにして、再エネやEVを不当に過小評価した結果、進んでいた日本の再エネやEVは周回遅れとなり、再エネ関連の新興中小企業はつぶされ、EVも育たず、日本の国益が害されたのである。そのため、矛盾したことばかり書かないようにすべきだ。 このような中、*10-3のように、独ヘルティ・スクール・オブ・ガバナンス教授のデニス・スノーワー氏が、①温暖化防止はグローバルな目標 ②COP26では国益を対立させる交渉がみられた ③一部企業のグリーンビジネスなどが実施されても、他企業の脱炭素化に反する行動を許してしまう ④報酬と制裁で全企業が環境に責任を持つよう政府が介入しなければならない ⑤専門家は効率的な脱炭素化実現にパリ協定の目標に沿った世界的な炭素価格が必要だとしている ⑥CO₂はどこで排出されても環境に及ぼす被害は同じで、すべての人が同じ炭素価格を負担するのが望ましい 等と記載している。私は、①~⑤に賛成だ。また、⑥については、近い将来に放射性物質の放出を含む公害のすべてに環境税をかけるのが経済の環境中立性を護るのに必要だと思うが、まずCO₂排出量に応じて環境税をかけ、森林・田園・藻場の育成によるCO₂吸収に応じて世界ベースで同じ金額の補助金を出すのがよいと思う。 *10-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15155646.html (朝日新聞 2021年12月27日) ドイツ、「脱原発」一本道 来年末、全基停止へ 地球温暖化対策として、欧州で原子力発電を再評価する動きが出るなか、ドイツが「脱原発」を着々と進めている。10年前、日本の原発事故をきっかけにかじを切った。原発の負の側面を直視し、再生可能エネルギーの普及に注力している。 ■福島の事故後、一転/欧州に延命論でも 今月末、1基の原発が営業を終える。「笛吹き男」の伝説で有名な西部ニーダーザクセン州ハーメルンから南に約8キロ。人口1万人弱の町エンマータールにある「グローンデ原発」だ。高さ約150メートルの冷却塔2塔から、白い蒸気が上る。加圧水型炉で、出力は1360メガワット。1984年に稼働後、何度も年間発電量で世界一になったという。1日の記者会見でリース州環境エネルギー相は「地域で一つの時代が終わる。脱原発は政治的な正しい決断だった」と述べた。ドイツでは、メルケル前首相が前任のシュレーダー政権の脱原発の方針を覆し、原発の「延命」を決めた。ところが約半年後の2011年3月、東京電力福島第一原発事故が起きた。メルケル氏は方針を百八十度転換し、17基あった原発を段階的に止めることにした。現在、稼働するのは6基。発電量の約14%を原発が占める。今月中に3基が停止し、22年末までにすべて止まる予定だ。今月発足したショルツ政権も、脱原発の方針を引き継ぐ。さらに脱石炭火力のペースも前政権より速め、電源に占める再生可能エネルギーの比率を現状の40~50%から30年までに80%に上げる方針だ。一方、脱原発を支持する市民は少しずつ減っている。アレンスバッハ世論調査研究所によると、「脱原発は正しい」との回答は12年には73%あったが、21年は56%。中高年ほど原発を支持する傾向が強かった。気候変動問題への対応で、各国が温室効果ガスの排出が少ない原発を再評価し始めている影響もあるとみられる。電源の約7割を原発に頼るフランスは温暖化対策や資源高への対応として最新型の原発を新たに導入する方針だ。今は原発のないポーランドも、40年代をめどに導入をめざす。こうしたなか、欧州連合(EU)の行政機関・欧州委員会は、原発を持続可能で温暖化対策に資する当面のエネルギー源とみなす方向だ。EUが掲げる「50年に温室効果ガスの実質排出ゼロ」を実現するには、避けられないとの判断だ。 ■おひざ元、再エネの街に変化 ドイツでも、同様の理由で原発の延命を訴える声が根強くある。これに対し、グローンデ原発のおひざ元、エンマータールのドミニク・ペタース町長(32)は「電力会社も行政も誰も再開は考えていない」と言う。行政も企業も廃炉に向け着々と準備を進めており、いまさらすべてをひっくり返すのは「非現実的」との考えだ。町は長年、原発によって潤い、町民の多くが原発関連の仕事を得た。電力会社からの豊富な税収で学校や消防署、道路などのインフラが整備された。当面は廃炉作業のための雇用が期待されるが、町は原発以外の生き残り策を探ってきた。約20年前に太陽光発電の研究所を誘致し、太陽光関係の製品開発などを続けている。原発のすぐそばには複数の風車も回る。ペタース町長は「私たちはエネルギーの町として、旧来型から新型へ変化を遂げている」と胸を張る。グローンデ原発のある地区選出の与党・社会民主党のヨハネス・シュラプス連邦議会議員(38)は「原発が気候に中立とは全く言えない」と話す。燃料調達時の環境汚染や、超長期的に影響が残る放射性廃棄物の最終処理のめどがたっていないからだ。「原発と石炭火力を同時にやめていくのは野心的だが、できる。ドイツは他国の手本になるだろう」 *10-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211228&ng=DGKKZO78829810Y1A221C2MM8000 (日経新聞 2021.12.28) 欧州、原発回帰の流れ、仏英主導、脱炭素・エネ安保対応 日本は議論避け停滞 欧州で再び原子力発電所を活用する動きが活発になっている。フランスや英国が主導する。電力の安定供給を保ちつつ気候変動対策を進める。欧州連合(EU)域外からの天然資源に依存しない、エネルギー安全保障の観点からも重視している。東日本大震災から10年を迎えた日本では原発に関する真正面の議論を避け、原発の位置づけは定まらないままだ。EUのフォンデアライエン委員長は10月に「我々には安定的なエネルギー源である原子力が必要だ」と述べた。EUは経済活動が環境に配慮しているか判断する基準「EUタクソノミー」で原発を「グリーン電源」に位置づけるか、加盟国間で激しい議論が続く。マクロン仏大統領は11月、国内で原発の建設を再開すると表明し、英国も大型炉の建設を進める。両国は次世代の小型炉の開発にも力を入れる。オランダは12月半ば、総額50億ユーロ(約6500億円)を投じる、原発2基の新設計画をまとめた。原発回帰の最大の理由は気候変動対策だ。EUは2030年の排出削減目標を1990年比40%減から55%減に積み増した。原発は稼働中の二酸化炭素(CO2)の排出がほとんどない。風力や太陽光と異なり、天候に左右されない。EUは19年時点で総発電量の26%を原発が占める。11年の日本の原発事故を受け、EUは原発の安全規制を強化してきた。17年には原発を安全に運用するには50年までに最大7700億ユーロの投資が必要との文書を作成。認可基準の擦り合わせや、原子炉の設計標準化などの対応を求めている。ドイツは他の加盟国と一線を画し、メルケル前政権が22年末までの「脱原発」を掲げる。新政権もこの方針を堅持するものの、ロシアへの天然ガス依存やガス価格高騰で脱原発方針を延期するよう求める声もある。日本は原発活用に向けた議論が停滞している。エネルギー基本計画では、30年度に電源に占める原発比率は20~22%を目標とする。ただ、達成には再稼働済みの10基に加えて再稼働をめざす17基を動かす必要がある。日本は長期の戦略を欠く。9月の自民党総裁選では次世代原発の小型炉などの新増設を進めるべきだとの意見も出たが、政策の変更も含めて活用の是非の議論すら封じる流れは変わっていない。日本では事故を受けて国民の反発も根強く、政府はより丁寧な説明が求められる。事故処理や放射性廃棄物の最終処分場も決まっていない。日本は再生可能エネルギー導入でも周回遅れだ。政治が責任を持って議論を主導せず先送りを続ければ、脱炭素の取り組みは遅れるばかりだ。 *10-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211230&ng=DGKKZO78845690Y1A221C2TCR000 (日経新聞 2021.12.30) 気候変動対策、報酬と制裁で 独ヘルティ・スクール・オブ・ガバナンス教授 デニス・スノーワー氏 11月に閉幕した第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)では、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」を実行するうえで必要な規則が確定した。産業革命前に比べた気温上昇を1.5度以下に抑えるという目標の達成を目指している。だが実際の拘束力に乏しいことなどから、達成には疑問符がつく。現在の経済体制では、企業は株主価値の最大化を探り、政治家は有権者の支持を最大限に得ようとしている。社会は、表層的な環境重視を含むポピュリズム(大衆迎合主義)などに翻弄される。経済的な繁栄や政治的な成功は、社会の安定や環境の健全性と切り離されてしまった。こうした状況をみる限り、グリーンビジネスや脱炭素に向けた投資活動に簡単に勇気づけられるべきではないだろう。すべての企業が環境に責任を持つように政府が介入しなければ、一部の企業のグリーンビジネスなどが実施されたとしても、他の企業による脱炭素化に反する行動を許してしまう。気候変動との戦いには、政府と企業の意図的な協力が求められるということになる。共有資産の管理については、2009年にノーベル経済学賞を受賞したエリノア・オストロム氏の研究がある。共有資産の関係者がルールづくりに参加し、執行することで、管理できている例を示した。まず、問題の認識と目的を共有することが不可欠だ。温暖化の防止は、本質的にグローバルな目標といえる。温暖化ガスはどこで排出されても、あらゆる人々に影響を与える。従って、目標に対する共通の認識を持つことが必要になる。だがCOP26では、国益を対立させるような交渉がみられた。次に、気候変動対策のコストと見返りを、すべての当事者にとってよりよい状態になるよう分配することだ。専門家は、効率的な脱炭素化の実現には、パリ協定の目標に沿った世界的な炭素価格が必要だとしている。二酸化炭素(CO2)はどこで排出されても環境に及ぼす被害は同じなので、理論上はすべての人が同じ炭素価格を負担するのが望ましい。企業が生産拠点を規制の緩い海外に移してしまう「カーボンリーケージ」の問題を防げる。もっとも貧困層や中間層は、炭素集約型の商品やサービスの価格が上昇し、購入できなくなってしまう可能性がある。炭素集約型の産業の雇用が減少すれば、失業者が増え、地域社会が経済基盤を失ってしまうかもしれない。気候変動対策を成功させるには、意思決定を公正で包括的にする必要がある。意思決定には、すべての当事者が参加できるようにすべきだ。COP26の交渉では、差し迫った気候変動の壊滅的な影響を最も受ける人々が除外されたと、多くの人が主張する。権力を持つ人々は、既得権を維持したいと考える傾向がある。明確な成果を測定することで、有益な行動に報酬を、不利益をもたらす行動には制裁を段階的に与える必要がある。信頼できる調停者が関与した、迅速で公正な紛争解決の仕組みは欠かせない。最後に、多極的な統治が必要だ。国際機関や国、地域、地方が相互に影響し合う。首尾一貫した合意を結び、実施する。COP26の提言には法的な拘束力がないうえ、気候変動対策で各国の主権は認められているものの、多極の統治システムは不在といえる。あらゆるレベルで気候変動政策は無視され、一貫性に欠ける。こうした要件を満たすのは難題で、一夜にして実現するものではない。だが次の世代には、気候変動対策を成功させるための社会や経済、政治的な条件を整える努力を、我々に期待する権利がある。
| 経済・雇用::2021.4~2023.2 | 10:10 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2021,11,09, Tuesday
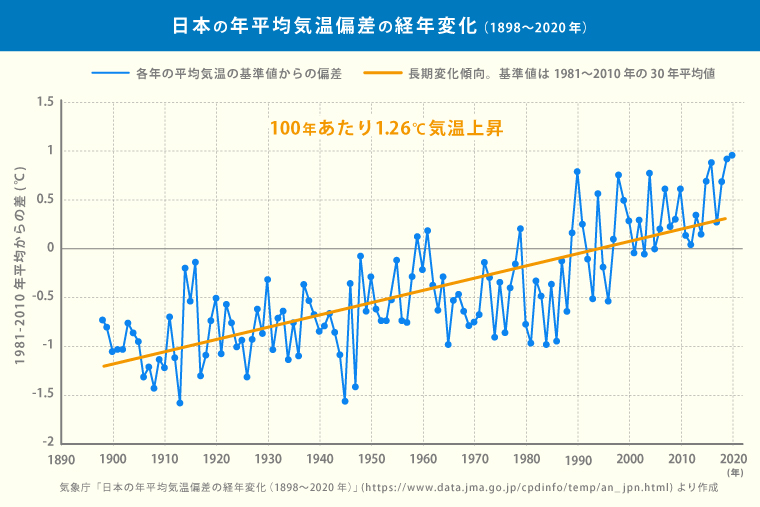 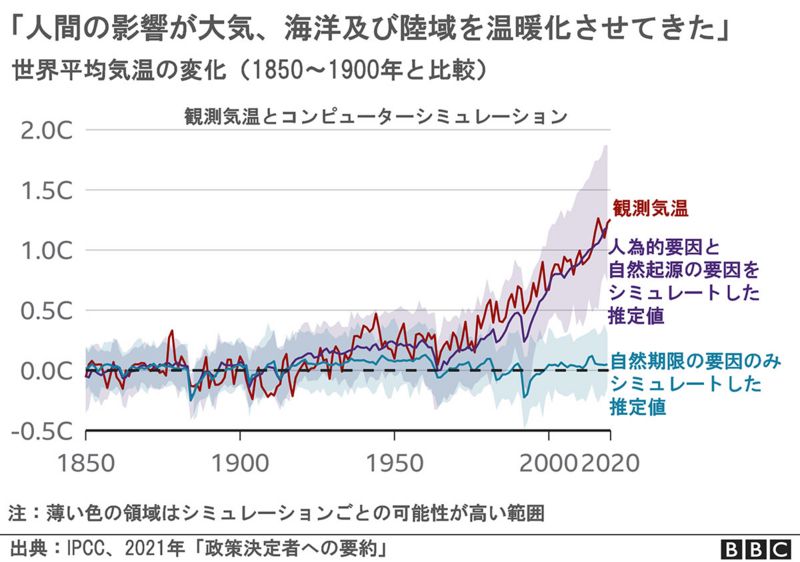 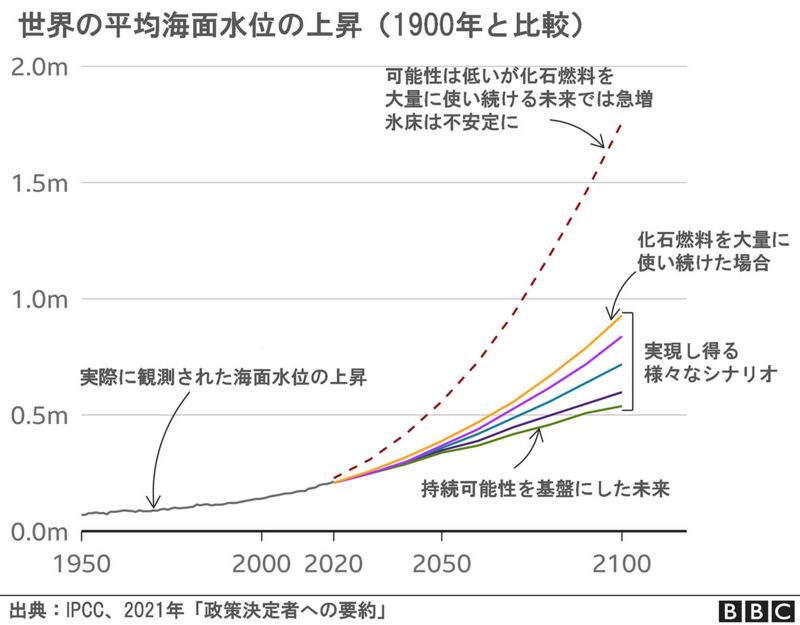 Hiromori 2021.8.9BBC 2021.8.9BBC (図の説明:左図は日本の1900~2020年までの気温上昇で、100年で1.26°C上昇している。中央の図は、世界の1850~2020年の気温上昇で、やはり1.26°Cくらい上昇しており、このうち自然要因の上昇は殆どなく、すべて人為的要因によるものであることが示されている。これに伴って、氷が解け、水の体積が増すことによって海面上昇するが、現在、既に25cmくらい上昇していることは、日本での体感と一致している) (1)COP26について 1)グテレス国連事務総長 グテレス国連事務総長は、*1-1のように、COP26首脳級会合にける演説で、「①最近発表されている気候変動対策は、状況を好転させない」「②各国提出の温室効果ガスの削減目標では、今世紀末の平均気温は産業革命前より2.7度上昇する」「③会議が失敗に終わったら、各国は気候変動対策計画を、毎年、常に見直さなければならない」と警告されたそうだ。 これに先立ち、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、2021年8月9日、*1-4のように、「④人間の影響が大気・海洋・陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がなく、大気・海洋・雪氷圏・生物圏において広範囲で急速な変化が現れている」「⑤海面水位が今世紀末までに2メートル上昇する可能性も排除できない」「⑥数十年中にCO₂その他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に地球温暖化は摂氏1.5度・2度を超える」「⑦対応を遅らせる余裕も、言い訳をしている余裕もない」としていたが、こちらは根拠が事実に基づいているので明快だ。 BBCだけでなく外国メディアは、このように情報量が多くて科学的・理論的な情報発信が多いが、日本のメディアは、殺傷事件・人格否定論・感情論が多く、政策に関しては定食もどきの「妥協のミクス」しか報道できないため、日本人の意識を低めて民主政治に悪影響を与えているのである。 2)岸田首相 岸田首相は、*1-2のように、COP26の首脳級会合における演説で、2050年までの温室効果ガス排出を実質0にする目標を改めて明言し、「①新たに5年間で途上国の気候変動対策に最大100億ドル(約1兆1350億円)の追加支援を行う用意がある」「②アジアでの再エネ導入は既存の火力発電を排出0化して活用することも必要だ」等と述べ、議長国である英国が求めていた2030年までの廃止に応じなかった。 そのため、環境NGOは、CO₂排出量の多い石炭火力発電の廃止には触れず、アンモニアやグレイ水素を活用して火力発電の継続を宣言したことにより、*1-3のように、日本を地球温暖化対策に後ろ向きな国に贈る「化石賞」に選んだ。 アンモニア(NH₃)は炭素(C)は含まず窒素(N)を含むため、燃焼した時にCO₂は出さないがNOxを出す。そのため、地球温暖化ではないが、有害な窒素酸化物を発生する。にもかかわらず、経産省は、2030年までに石炭火力燃料の20%をアンモニアにして混ぜて発電する技術の実用化を目指し、2050年にはアンモニアだけの発電も始めることを目指すそうだ。しかし、アンモニアは、化石燃料から水素を取り出して窒素と反応させて作るため、輸入エネルギーであって日本のエネルギー自給率向上に貢献せず、その水素を作るにも大量のエネルギーを使って温室効果ガスを出す馬鹿な選択なのである。 つまり、「③日本は資源のない国」「④エネルギーは熱からしかできないもの」という先入観をいつまでも捨てず、エネルギー自給率向上に役立たず公害を出し安価でもない輸入化石燃料に固執するのは、世界1の借金大国がさらに国富を海外に流出させるだけなのである。 そのため、再エネも進歩しており、さらに進歩させなくてはならない現在では、「電力の安定供給」「産業の国際競争力維持」などの言い訳は、石炭火力・アンモニア・原子力の必要性を合理的に説明する根拠とはならず、むしろ技術進歩を阻害して産業の国際競争力を弱める結果となっているのである。 3)産油国の脱石油政策と日本がやるべきこと 世界が脱炭素にかじを切ると、産油国は原油の輸出が減る。しかし、*1-5のように、サウジアラビアは、実力者のムハンマド皇太子が「脱石油」改革を掲げ、サウジアラムコがビジネスの転換を進めている。その改革の二大柱は、下流部門への進出とアジアシフトで、アミン・ナセル氏はアラムコを「エネルギーと化学の会社」に変貌させて鉱業の付加価値を高め、将来は欧米などの外国市場での株式上場もめざすようで、賢くて有望な計画になっている。 そのような中、日本は、10年1日の如く「燃料費の高騰で困ったから、原油を増産して欲しい」などとアメリカに言ってもらっているが、とっくの昔にエネルギーを再エネに転換しておくべきだったし、最初はトップランナーで、できたのである。 しかし、現在でも、*1-6のように、①再エネに限らず原発も選択肢とした“クリーンエネルギー戦略”を策定すると明記した ②コストばかり高くて環境を汚すリスクの大きな原発への投資をやめない ③そのため再エネ向け送電線の整備を徹底しない ④投資効率が悪い(=賢い支出でない) ⑤成長力の底上げに繋がらない など、政府支出を大きくすることの無駄遣いによるディメリットが目に余るのである。 また、新型コロナ対策には非科学的な対応が多すぎ、マスクや医療用ガウンすら作れず、ワクチンや治療薬の速やかな開発も行わずに利益の機会を逸し、緊急事態宣言による行動制限に頼って国民経済を疲弊させた罪は、金額に換算できないほど大きい。さらに、国民経済の疲弊を口実として、無計画で非科学的な新型コロナ対策の埋め合わせに何兆円もの投資効果0の予算を使うというのも全く賢くなく、成長戦略に欠け、その原資は(今は詳しく書かないが)誰が払うと考えているのだろうか。 なお、岸田政権は、賃上げに取り組む企業への優遇税制を強化し、看護師・介護士・保育士らの給与を引き上げるそうである。また、経済安全保障の観点から半導体の国内生産拠点も支援するそうだが、企業が激しい世界競争をしている現在、企業は(一時的に補助金をもらったとしても)生産性以上に製造コスト(土地代・人件費・水光熱費等々)の高い国に生産拠点を置くことは選択できない。そのため、日本は1990年代から次第に空洞化して、今では製造業も危ういという情けない状態であることを自覚すべきだ。 そのような中、会計検査院は、コロナ対策事業として計上された65兆円程の予算の3割超にあたる22兆円余りが未執行だったと指摘したそうだ。しかし、未執行の責任を問うだけなのが会計検査院の限界なのである。本当は、もっと安上がりで投資効果の高い予算の使い方はなかったのか(実際にはあった)、予算配布の仕組みが無駄遣いの温床ではなかったか(既存の仕組みを使わなかったため無駄が多かった)、いらなかったのなら繰り越すのはよいことではないのか(実際はよいことだ)なども、検討すべきなのである。 また、政治が需給ギャップを理由として大規模な経済対策の必要性を訴えることについては、個人消費を抑えながら需給ギャップを理由として国が支出を増やすのは、国の支出先は企業や個人のニーズに合うしっかり練られたものではないため、国民生活を豊かにしない。そのため、「新しい資本主義」の定義を早急に明らかにし、どの国民も犠牲にせずに豊かにして、本物の成長に繋げる予算づくりをすべきだ。 (2)日本がエネルギーの変換にも出遅れたのは何故か   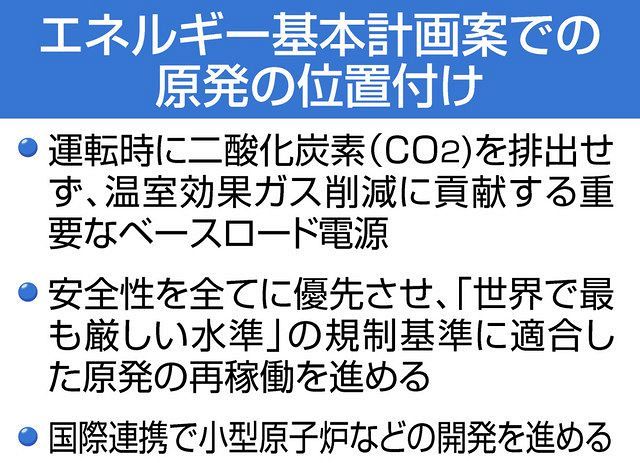 ローソン 2021.10.20東京新聞 2021.10.20東京新聞 (図の説明:左図のように、日本の2018年の1人当たりCO₂排出量は、発電からが50%近く、ガソリンからが25%近くを占めている。そのため、まず、発電を自然再生可能エネルギー《以下「再エネ」と記載する》にすれば、CO₂排出量を50%近く削減できる。また、移動手段を再エネ由来の電力を使ったEV等に変換すれば、CO₂排出量の25%近くを削減できる。従って、そのためのインフラ整備を行うのが最も安価でエネルギー自給率の向上にも資する予算配分になる。しかし、経産省は、右図のように、CO₂を排出しないベースロード電源であるとして既存原発の再稼働や小型原子炉の開発を進め、2030年には原発による発電割合を20~22%にまで増やそうとしており、これは日本にとっては何のメリットもない血税の無駄遣いになる) 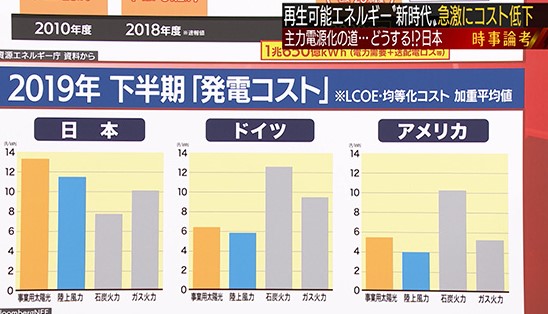 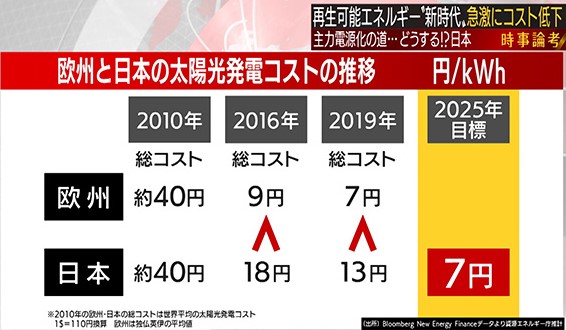 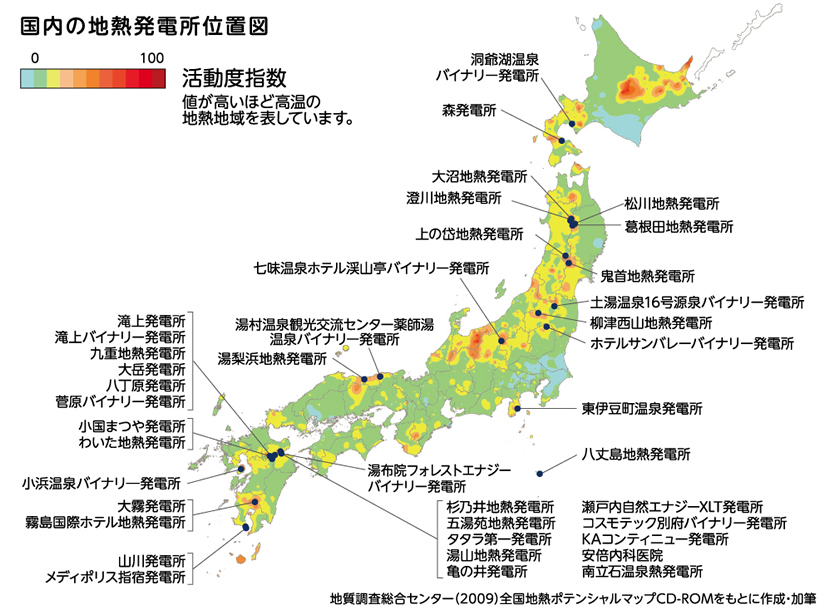 2020.2.23BS朝日 2020.2.23BS朝日 2016.6日本地熱協会 (図の説明:左と中央の図のように、2019年下半期に、太陽光発電のコストは日本13円・ドイツ6.5円・アメリカ5.7円であり、洋上風力も日本11.7円・ドイツ5.9円・アメリカ4円である。日本で再エネのコストが高止まりしている理由は、できない理由を並べて再エネの普及を阻んだからであり、これにより産業も含め全国民に迷惑をかけている。また、石炭火力・ガス火力より再エネの方が高いのも日本だけだが、再エネは変動費が0に近いため、これは当たり前だ。また、太陽光や風力も安定電源化することは可能だが、日本は地震・火山国で地熱が豊富であるため、その気になれば変動費無料の安定電源を確保することも容易なのである) 1)電源の再エネ化へ 政府は、*2-1のように、「第6次エネルギー基本計画」を改定し、再エネや省エネを推進する「地球温暖化対策計画」も定めた。今回は、再生エネを最優先で導入する方針を明記したそうだが、上の段の中央と右の図のように、2030年度電源構成で再生エネ比率は36~38%、LNG・石炭・石油などの化石燃料由来の火力発電が41%と目標は低い。 その上、過酷事故のリスクは0でなく、廃炉や核燃料の最終処分でもコストが著しく高い原発を、2030年度でも20~22%使用し、アンモニア(NH₃)発電まで始めるというのは、環境問題を温室効果ガス(CO₂)だけに限って矮小化しすぎている。仮に「環境問題はCO₂だけを考えればよい」と思っているとすれば、それは勉強不足である。 私は、2030年度なら再エネ比率80%も可能なので、できない理由を並べるのではなく、実現するために最善の努力すべきだと思う。そのためには、農林漁業地帯で本来の生産の邪魔にならない再エネを選んで発電し、農林漁業の副収入にできるよう、21世紀型の送電線を整備すればよいし、建物のガラスや施設園芸用ハウスの資材でも発電できるよう、規制を作ったり補助をつけたりすればよい。そして、その財源には、脱公害化に向けて環境税(or炭素税)を創設し、CO₂はじめNOxやSOxなどの有害物質の排出に課税するのが合理的である。 また、全国の地熱発電所数は、*2-6のように、2011年のフクイチ事故後の10年間で4倍に増えたそうだが、地震・火山国である日本が持つ豊富な地下資源である地熱は、変動費無料の安定電源であるため、発電量を増やすべきである。化石燃料は、CO₂の回収・貯蔵や再利用が完全にできたとしても、NOxやSOxを無視されては困るし、その技術はさらに発電コストを上げるものである。そのため、エネルギーに関しては、既に勝敗が見えており、現在は無駄な投資はやめて選択と集中をすべき時なのだ。 なお、自民党は、原発について、「必要な規模を持続的に活用」とし、「小型モジュール炉」「核融合発電」などの新たな技術開発も進める姿勢を打ち出したそうだが、どの地域に「小型モジュール炉」や「核融合発電炉」を作るのか? 玄海原発のケースでは、過酷事故のリスクが0ではない危険な原発を末永く続けて人口をさらに減らしたいとは思っておらず、安全で付加価値が高く、雇用吸収力の大きい産業を誘致したいため、それを後押しして欲しいのだ。 2)省エネについて 上の段の中央の図の「第6次エネルギー基本計画」では、省エネで総発電量の1割を削減するとされている。これについては、一般住宅や施設園芸用ハウスで地熱(1年を通して16°C)やヒートポンプを利用したり、建物の断熱性を高めたりすればかなりの省エネができ、屋根やガラスで自家発電すれば購入する電力が減る。そうすると、地域の資金が半ば強制的に外部に流出することがなくなり、エネルギー自給率の向上に資し、災害にも強くなって1石3鳥であるため、意欲を持って達成できそうだ。必要なのは、やる気と政府の後押しである。 また、建物の断熱性についても、さまざまな工夫があり得るが、ここで私が書きたいのは、*2-8・*2-9の小笠原諸島の海底火山噴火で生じた軽石の利用だ。現在、「沖縄、鹿児島両県に大量の軽石が漂着しているのは問題だ」「漁業や観光などに大きな被害が出ているので、国による手厚い支援が必要だ」とされ、国土交通省が漂流物の回収作業船を派遣しているそうだが、軽石は海に浮いているため、回収は比較的容易ではないのか? 例えば、「①漁に出られない漁船や地域の人が工夫しながら回収する」「②回収した軽石を買う人がいて利用する」などが考えられる。その後、「③買った軽石をよく洗って高い断熱性を要するコンクリート壁に使う」と、石に空気を含むので断熱性が高くて軽いコンクリート壁ができそうだ。火山から噴出した物質の耐熱性が高いことは、言うまでもない。 なお、日本の排他的経済水域には海底火山が多く、噴火している海底火山も少なくない。そのため、海底熱水鉱床に存在するとされる金属も、比較的浅い場所に大量に存在するかもしれず、海底の探査は欠かせないのである。 3)原発は筋が悪いこと ア)原発は過酷事故の被害が甚大である上、再エネよりもコストが高いこと 日本政府(経産省)は、*2-2のように、2030年には再エネの中の太陽光が原子力を抜いて費用が最も安いエネルギー源になるというの見通しを発表し、原発のコスト神話も崩壊した。太陽光発電は、太陽の核融合によるエネルギーを受けて発電しているもので、燃料を輸入する必要がないため、日本だから不利といった点はないが、それでも、2030年時点で太陽光発電(事業用)が1kw時あたり8円台前半~11円台後半というのでは、2019年後半のドイツ6.5円、アメリカ5.7円よりも高く、産油国であるにもかかわらず世界最安値のサウジアラビアの2.57円に遠く及ばない。そして、このエネルギー代金の差も、日本企業が日本で生産する選択肢を遠ざけているのである。 日本で再エネ発電を積極的に進めなかった理由として、「太陽光は夜間に発電できず、風力は天候の影響を受ける」ということを何度も聞かされたが、これは再エネを普及させず原発を推進するための口実にすぎず、地球上どこでも同じ条件なのに日本は工夫が足りなかったのだ。 原子力規制委は、*2-3のように、中電島根原発2号機が「新たな規制基準に適合している」とする審査書を決定したが、そもそも原発から30km圏内(緊急防護措置区域)の市町村に策定が義務付けられた避難計画の適否は規制委の審査対象になっておらず、事故時に計画通り無事避難できるのか否かは考慮されていないそうだ。 その上、半径30km圏内の人以外は安全かと言えば安全ではなく、“避難期間”が無限の長期に及ぶ地域もあり、島根原発の30km圏内には約46万人が暮らしているのである。それでは、人口が少なければよいのかと言えば、*2-4のように、フクイチ事故後、除染していない山中で生きる渓流魚やキノコの汚染は10年以上が過ぎた2021年秋でも続いており、食品基準(100ベクレル/kg)以下の食品であっても食べ続ければ胃癌・大腸癌・膵臓癌・肺癌が増えたのは予想通りなのだ。そのため、食品を生産する地域は、オーストラリアのように徹底して原発を持たない見識というものが必要だ。 イ)新型小型炉なら事故リスクは0なのか 自民党には、*2-5のように、「運転開始から原則40年の耐用年数が近づく原発について、開発中の小型モジュール炉を実用化して建て替えるべきだ」と提唱する人が少なくないが、小型モジュール炉だから既存の原発より安全性が高いとは、どういう意味か? どんな原発でも事故リスクは0ではあり得ず、ア)で書いたとおり、原発事故が起これば人口が少なくても無期限に故郷や資産を失う人が出る。その上、食料生産にも支障をきたすため、仮に「事故リスクは0だ」「安全性が高い」と言う人がいれば、その人の地元に小型原発を建設してエネルギーの地産・地消をすればよいと思う。「自分が嫌なことは、他人も嫌なのだ」ということを知るために、である。 ウ)総選挙における国民の選択はどうだったか 立憲民主党は「原発ゼロ社会の早期実現」を訴え、共産党は「2030年までに石炭火力と原発による発電を0にする」としていたが、私はこれには賛成だった。今回の総選挙で立憲民主党が自民党に競り負けて数を減らしたのは、立憲民主党の新しい候補者の多くが長く地元で活動して地元に根付いた人ではなく、立憲民主党のこれまでの国会質問も重箱の隅をつつくような人格攻撃が多すぎたからである。また、総選挙における政策には、その場限りのバラマキが多く、「それを誰が払うのか?」という当たり前の疑問を感じた人は多かったと思う。 なお、メディアが指摘するように、共産党との選挙協力が悪くて立憲民主党が数を減らしたのではない。異なる党であれば主義主張が異なるのは当然で、自民党と公明党も主義主張は異なるが、一致する点で協力してプラスの効果を出しているのである。また、自民党と公明党の主義主張が異なるからこそ、要望の出し先を工夫することによって、使い勝手がよくなる場合も多い。 さらに、遺伝情報が完全に同じ一卵性双生児でも、兄として育てられた人と弟として育てられた人は性格が異なるように、人の性格や思想信条は異なるのが当たり前である。そのため、メディアが異なることを悪いことででもあるかのような報道をするのは、メディアのスタッフのレベルが低いというだけではなく、民主国家の国民に悪い影響を与えているのだ。 4)日本のEVでの出遅れは、どうして起こったのか COP26の議長国である英国は、*2-7のように、ガソリン車など内燃機関を用いる自動車の新車販売を主要市場で2035年、世界では40年までに停止するという宣言に24カ国が参加し、「ゼロエミッション車」であるEVへの移行を目指すことを明らかにした。 米ゼネラル・モーターズやフォード、独メルセデス・ベンツなどの自動車大手6社が賛同しているが、日本政府はEVだけでなくHVも含めているため、この24カ国には含まれない。日本では、「ゼロエミッション車」のEVに、メディアも含めてくだらない欠点ばかり言い立てて後押しせず、世界のトップランナーだった日産までがEVによる自動車革命の功労者を犯罪者に仕立てあげてHVを作り始め、資金の無駄遣いをするに至った。日本は、化石燃料を購入して、国富を海外に流出させ、エネルギー自給率を下げ、地球温暖化を促進するのが、よほど好きな国なのか? (3)農業について   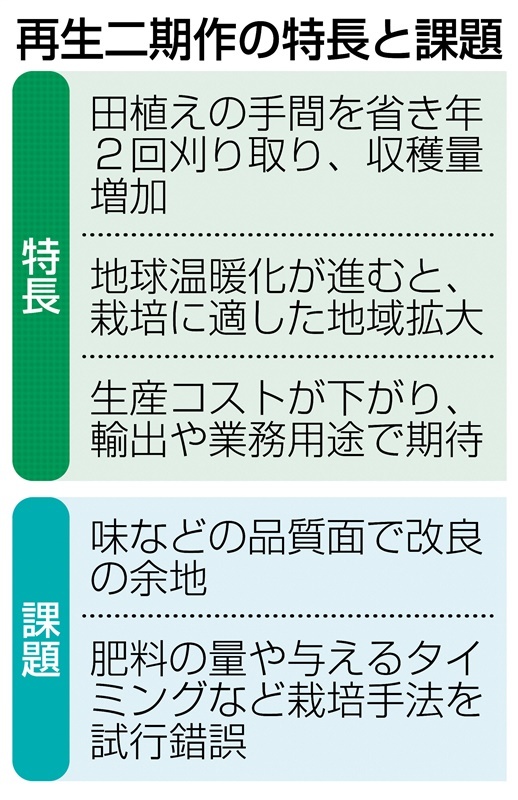 2020.9.18佐賀新聞(*3-1より) (図の説明:上の図のように、温暖な九州の気候を利用し、1回目の収穫時期や刈り取る高さを工夫すれば、収穫後のひこばえから「再生2期作」が可能で、2回の収穫の合計は一般的な収量の約3倍になるそうだ。私は、同種類の稲であれば、追肥をすることによって同じ味の米がとれると思うが、農業は温暖化の影響をプラスに利用できる場合もあることがわかる) 1)稲の再生2期作に成功 地球温暖化による気温上昇は感覚的にもわかるが、九州沖縄農業研究センターが、*3-1のように、稲の収穫後のひこばえを育てる「再生2期作」に取り組み、稲が十分に成熟した8月下旬に地面から50cmと高い位置で刈り取れば、2回目(11月上中旬に収穫)も加えた収穫が、2回の収穫で一般収量の約3倍の収穫が得られることを確認したそうだ。 今回の2期作は、2回目の田植えをしない“植えっぱなし”方式で大幅な省力化が期待されるそうだが、どうして今まで思いつかなかったのか、不思議なくらいだ。同センターは、稲の超低コストな栽培技術として加工米や業務用米での導入を目指すとしているが、品種が同じなら追肥などのケアをすれば、味も同じになると思われる。 ここから得られる教訓は、先入観を取り払えば、地球温暖化による気温上昇を利用して、これまで栽培できなかったものを栽培できるようになるということだ。 2)「アクアポニックス」による水産農法の始まり  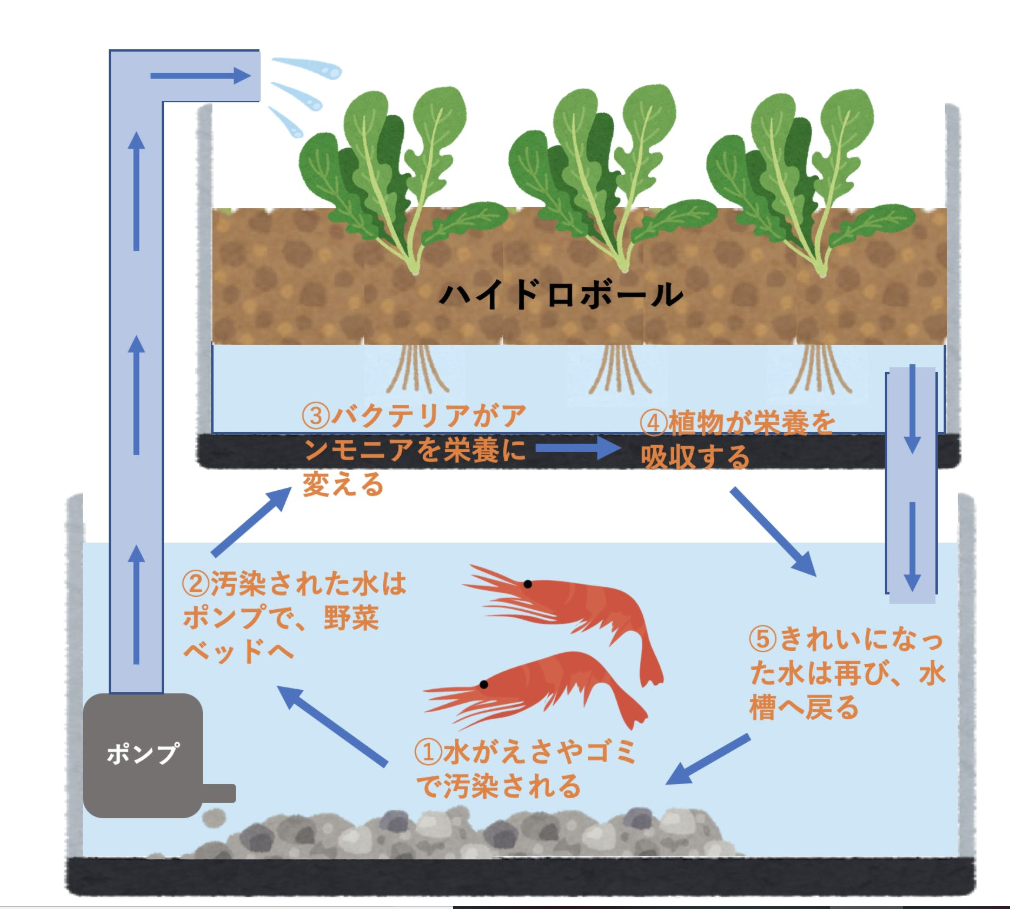   2021.9.1JAcom アクアポニックスの原理 アクアポニックスの使用風景 アクアポニックスとは、*3-2のように、チョウザメなどの淡水魚と野菜を同時に育てる自然界の循環を模した水産農法としてドイツで開発されたもので、(株)アクアポニックス・ジャパンと有限会社S.R.K.が、2021年8月31日に北海道で竣工した専用設備は、農薬や化学液肥を全く使用せず、水耕栽培と水産養殖を併用して太陽の自然光を使って育成する設計になっているそうだ。 この施設は、太陽光パネルなどの再エネ機器も導入し、全天候・通年型の設備で、豪雪や豪雨などの天候に左右されることなく稼働でき、極寒の地である北海道でテスト運用を兼ねて第1号プラントを建設し、米国農務省(USDA)はアクアポニックスで栽培される野菜作物を有機農産物として認定した。 確かに、このシステムなら、農薬がいらず、化学液肥よりも多種の豊富な栄養素を含んだ水で水耕栽培でき、同時に水産養殖もできるため、農業の付加価値や生産性が高くなる。また、チョウザメ(完全養殖でき、卵はキャビア)は、*3-3のように、宮崎県内の大淀川水系で捕獲されており、暖かい地域でも生息可能で、宮崎県では5万匹を養殖して米国・中国などに輸出しているそうだ。 そのため、佐賀県の武雄市や大町町、福岡県の久留米市など、豪雨で水害が頻発して米作もやりにくくなった地域は、アクアポニックスの設備を作り、プールの壁は水害に合わないくらいの高さにして、そこでチョウザメはじめ養殖したい魚を飼い、その上で野菜などの水耕栽培をすると問題解決できるだろう。また、長野県等の清流はあるが冬に寒くなる地域でも、季節に関係なく魚と野菜を収穫できる優れたシステムである。 (4)林業について 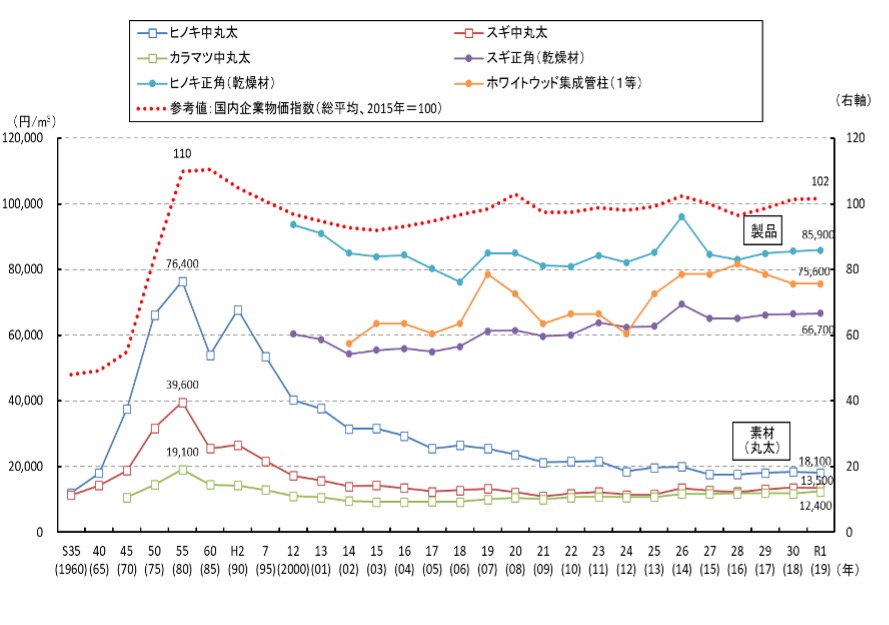    2021.9.7論座 2021.9.7論座 2021.9.7論座 2021.1.21BLOGOS (図の説明:1番左の図のように、現在は日本産丸太の価格が安く外材に負けなくなったが、それには都道府県の森林環境税等で補助しているという理由もある。木材製品の価格が高止まりしているのは、販売可能な上限価格を設定しているからだろうが、地域全体としては丸太のまま出荷するより付加価値の高い製品にして出荷した方がよいわけだ。左から2番目の図は、伐採した丸太を積み上げているところで、林業は軌道に乗せれば地方の有力な産業にできるものである。また、右から2番目の図は、太い木に育てるための間伐が十分に行われていない森のようだが、木材の使用目的にもよるが、密集して植林された木は間伐が必要になる。なお、1番右の図のように、皆伐して再度密集して植林するのは、皆伐時に土砂崩れなどを起こす上、密集して植えられた木の間伐がまた必要になるため、環境保全と省力化の両方のために工夫を要する) 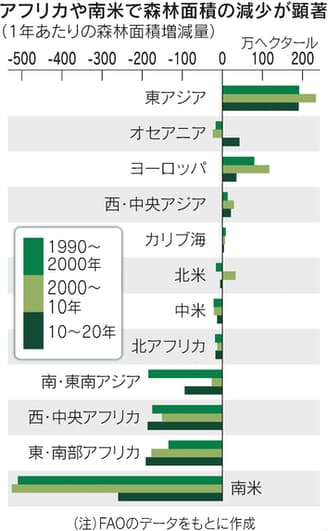    2021.11.6 GeasoneCashmere 2018.6.7朝日新聞 林業機械協会 日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、南米・アフリカ・東南アジアで森林面積が著しく減少し、東アジアでは増加している。また、下草狩りの大変さがよく言われるが、人間が草を刈って捨てていては単なる重労働にしかならないが、左から2番目のカシミヤ山羊や右から2番目の牛の放牧のように、森林に放して家畜に草を食べさせれば家畜の運動になり、自然に近くて健康にもよい飼育方法になるし、雑草より強い牧草やナギナタガヤ等を植える方法もある。なお、1番右の図は、電動のこぎりを使って木を伐採している様子だが、このほかにもスマート林業の便利なツールは多くなってきたし、今後も増やして欲しいものだ) COP26では、日本を含む130カ国超が、*4-1のように、食糧確保のための農地開発などで減少が続いている森林の破壊を、2030年までにやめて回復に向かわせる目標で一致したそうだ。森林の減少は南米・アフリカ・東南アジアで顕著で、FAOのデータでは、1990年~2020年に、南米で年400万ha、南アフリカで年200万ha弱、東南アジアで年100万ha減少し、世界全体の減少率は年0.1~0.2%で、30年間の合計は4%だったそうである。 森林減少の大きな要因は生活の糧を得るための農業開発(大豆やカカオなどの農産物、牛などの家畜のための伐採)であり、熱帯林アマゾンのあるブラジルでは牛肉の輸出が増えており、こうした農畜産物は先進国が輸入しているのだ。 また、「欧州や日本は国内法で森林保護を定めているが、規制は他国に及ばない」と書かれているが、森林保護のために規制するだけでは開発途上国の経済発展ニーズに合わないため、原生林として残すべき場所は保全・管理して観光地とし、それ以外は技術を駆使して稼げる林業にすることが必要だろう。 日本では、*4-2のように、先進技術を活用して林業の効率化を図る「スマート林業」が進められている。例えば、人力で行われていた植栽地の地ごしらえや下草刈りに機械を導入したり、伐採作業を機械化したり、植栽作業も苗木運搬にドローンを活用したりなどである。 しかし、「戦後に植栽した人工林が伐採期を迎えたから、皆伐する」というのは自然破壊であり、土砂災害のリスクが高まるため、私は間伐すべきだと思う。また、間伐しなければならないほど植林時に密に苗木を植えるのは、無駄が多くて生産性が低い。さらに、間伐するにも、新芽を鹿に食べられないくらい(1m以上?)の高さを残しておけば、また植林しなくても新芽が出て大きくなるので植林の手間を省くことができ、新しい木が根を張る時間も節約できるだろう。 さらに、下草刈りは人間が夏場に斜面で行うと大変だが、草の多い季節は牛・山羊・羊などの家畜を放牧して飼育すれば、双方にとってプラスになる。つまり、機械化されたスマート林業も大切だが、人間以外の生物に働いてもらう方法を先入観なく考えることも重要だ。 なお、2021年9月7日、*4-3に「①丸太の価格が長期的に低下した」「②1980年のピーク時からの40年間でスギ価格は1/3、ヒノキ価格は1/4分まで下がった」「③安い外材に勝てないと言われてきた国産材は、今では外材より安くなっている」「④丸太価格が低下しても国産の製品価格は横ばいで、消費者は価格低下の恩恵を受けなかった」「⑤その結果、製品生産者の利益は増加したが、山林経営者の所得は大きく落ち込み、山林の再生産ができなくなっている」などが記載された。 しかし、①②③④については、それを解決するために、2003年(平成15年)の高知県での導入を初めとして、現在は34都道府県で森林環境税が導入されており、民有林を含む山林の維持・管理費用(間伐・植林を含む)に充てることになっている(https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/36727.pdf 参照)。 国も、「パリ協定」を踏まえ、2024年度から個人住民税に上乗せして1人当たり1000円の森林環境税を徴収し、私有林の面積や林業就業者数などに応じて市町村に配るとのことである。また、間伐による林道整備や放置された森林の整備費用にも充当するそうだ。 そのため、①~⑤については、先人が植えてせっかく育った現在の木材資源を無駄にせず、山林の再生産をしながら賢く利用するために、導入された森林環境税の使い方が目的に適合しているか否か、もっと効率的な林業経営ができないかなどを、常に検証し続けなければならない。 (5)漁業について ← 海水温の上昇とCOP26 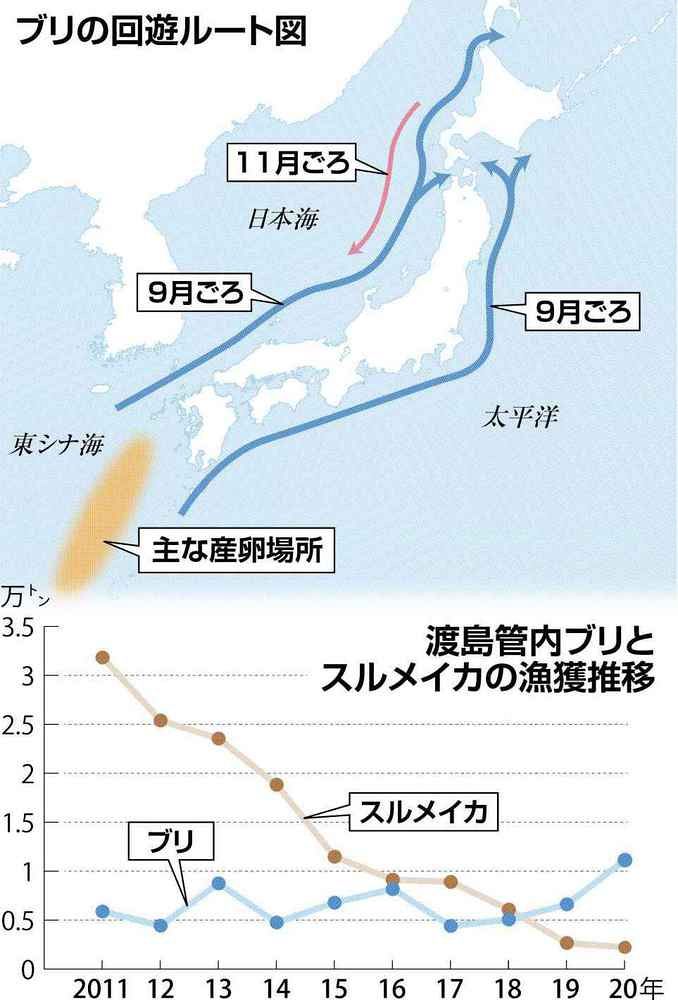 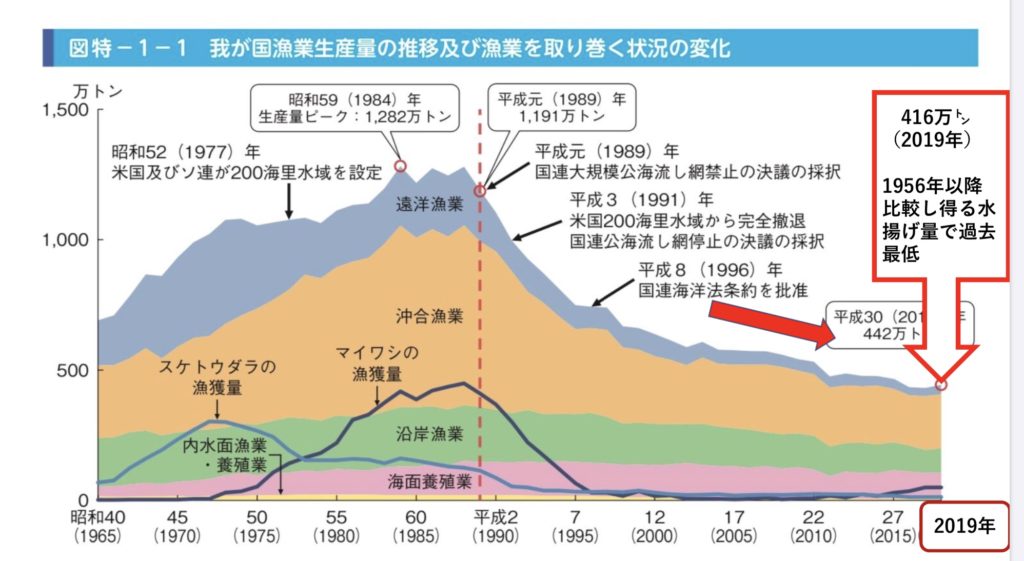 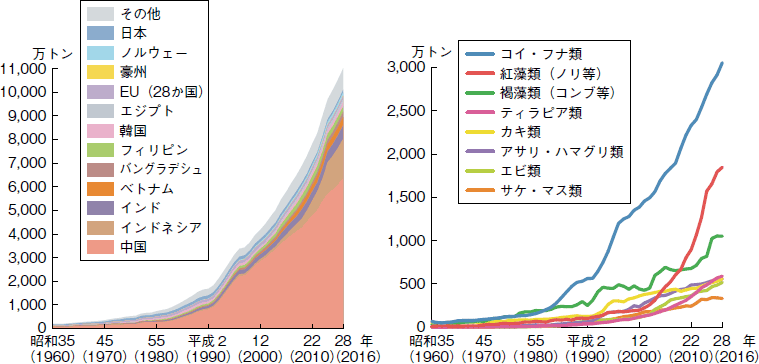 2021.11.2北海道新聞 水産庁 水産庁 (図の説明:獲れる魚の魚種の変化は海水温の上昇を示し、漁獲高は海の豊かさと水産業に対する政府の熱意を反映しているが、左図のように、北海道ではスルメイカやサケの漁獲高が減少し、ブリの漁獲高が増えたそうだ。しかし、中央の図のように、日本の漁獲高は、全体としては1984年の1282万tをピークに2019年は416万tと1/3以下に減少し続けており、その理由にはオイルショック後の燃油の高騰と水産業の軽視がある。しかし、右図のように、世界の漁獲高は等比級数的に伸びており、中でも中国・インドネシアの増加が著しい。魚種別では、コイ・フナなどの淡水魚の増加が著しく、次に養殖している海苔や昆布の増加が大きい。天然の海産物を獲りすぎると次世代が少なくなって次第に減少してしまうが、マイワシなど天然魚の餌になる魚の減少も気になる) 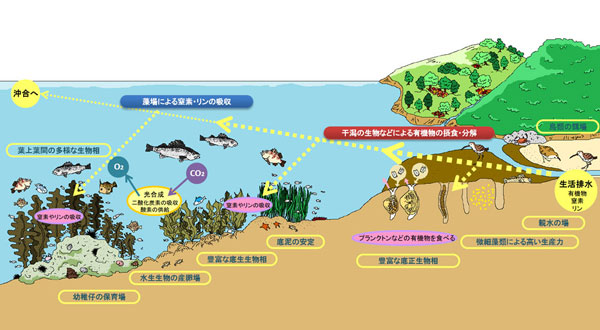  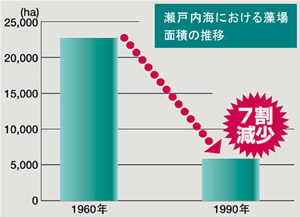 環境省(*5-2-1より) 水産庁 (図の説明:左図のように、藻場は窒素・リンを養分として吸収することによって富栄養化を防ぎ、水生生物の幼生の保育器となり、水生生物の餌ともなり、光合成をすることによりCO₂を吸収してO₂を発生させる重要な存在だ。また、干潟の生物もプランクトンを食べて海水の浄化に貢献している。しかし、中央の図のように、近年、埋め立て、工場排水・汚染水の流入、海水温の上昇などで藻場や干潟が減少し、海水が富栄養化して海の環境が悪化し、漁獲高の減った地域が少なくない。なお、右図のように、瀬戸内海の藻場は、1990年代には1960年代と比較して7割も減っていたそうだが、日本全体や世界レベルで藻場の面積を継続的に調査した記録はなく、その実態さえ把めていないことは大きな問題である) 1)COP26における日本の対応 沖縄タイムスが社説で、*5-1-1に、「①COP26は成果文書で産業革命前からの気温上昇を1.5°以下に抑える努力を追求する決意を示した」「②2015年に採択されたパリ協定と比較すると一歩踏み込んだ表現」「③200近い国と地域が決意を示した」「④焦点となった石炭火力は草案では『石炭火力の段階的廃止へ努力』だったが、『温室効果ガス排出削減対策が講じられていない石炭火力は段階的削減』に弱められた」「⑤世界で脱石炭の動きが加速する中、日本は2021年10月に決まったエネルギー基本計画でも石炭を現状では安定供給性・経済性に優れた重要なエネルギー源」と位置付けている」「⑥島しょ県沖縄では送電網が本土とつながっておらず、困難な事情もある」と記載している。 ①②③は、1.5°以下に抑える努力を追求するとした点で、2°以下としたパリ協定より厳しくなったが、原発を容認した点で甘くなっている。④の石炭火力については、日本は「CO₂を地下貯留する石炭火力ならよいだろう」というスタンスだが、発生したCO₂を全て地下貯留する保証はなく、その工程のために石炭火力発電の単価が上がるのは明らかだ。さらに、⑤のように、政府が「現状では安定供給性・経済性に優れている」などとして再エネの技術革新を阻害するから、日本では、いつまでも再エネが普及せず、安定供給の技術も進まず、再エネの単価が高止まりして、再エネが経済性で劣ることになってしまっているのである。 また、将来のないエネルギーにいつまでも資本投下していれば、資本生産性が上がらない。さらに、燃料費や電力料金を高止まりさせていれば、燃料費や光熱費が他のコストを食って、賃金を上げられず、労働生産性も下がる。つまり、政府(特に経産省)の判断の誤りは、民間企業の経営や国民の豊かさに著しいマイナスの影響を与えているのである。 なお、⑥について、離島は、送電網は本土と繋がっていないが、風が強く、狭い海峡になっていて海流の強い場所も少なくないため、風力発電の適地で潮流発電も有望だ。そのため、島内で完結したスマートグリッドを作れば、余るくらいの電力を得られるだろう。 2)海水温の上昇と漁業の現状 地球温暖化による海水温の上昇で、北海道では、*5-1-2のように、サケの漁獲が少なく(2002年の23万1,480tをピークに減り続けて5万1,000tまで減少)ブリが豊漁となり、道東では赤潮の発生で定置網に入っていたサケ等の大量死が相次いだそうだ。 サケ不漁・ブリ豊漁と北の海で異変が続き、ブリは単価が安いので北海道の漁師や漁業関係者の表情は冴えないそうだが、九州出身の私にとっては、サケは辛いばかりで御馳走とは言えず弁当のおかず程度の魚で、ブリの照り焼きは年末・年始の御馳走というイメージだった。そのため、下処置したブリに衣をつけて揚げるよりは、獲れたてのブリを鮮度のよいうちに照り焼きや塩焼きにして出荷した方が(6次産業化)、全国で需要が高まると思う。そのため、料理番組で、美味しいブリの調理法をやればよい。 それにしても、サケ不漁の原因は、①沿岸部の海水温の変化 ②漁獲期の海水温の上昇 ③母川回帰率低下 ④サバなどとの競合によるエサ不足による稚魚の生存率低下 などの4つの原因が重なっており、海水温の上昇が大きな影響を与えているようだ。 3)藻場について 藻場とは、沿岸域の海底でさまざまな海草・海藻が群落を形成している場所を指し、*5-2-1のように、種子植物のアマモなどで形成されるアマモ場と、 藻類のホンダワラ・コンブ・アラメなどの海藻で形成されるガラモ場・コンブ場・アラメ・カジメ場などがある。 そして、藻場は、①海中の様々な生物に隠れる場所や産卵する場所を提供し ②窒素やリンなどの栄養塩を吸収して光合成を行い ③水を浄化して酸素を供給し ④浅海域の生態系を支えている。また、藻場はそこでの食物連鎖によって生物多様性や生産力が高く、日本では古くから漁場として利用したり、アマモを農業用肥料として利用したりしてきた。 また、藻場は、草原や森林に匹敵する高い一次生産力があって沿岸の生態系に重要な役割を果たしており、例えば、大型の海藻は生長時に窒素・リンなどの栄養塩を吸収して富栄養化による赤潮等の発生を防ぎ、海草類は砂泥場に根を張って生活し海底の底質を安定化させて砂や泥が巻上るのを防ぐ。 しかし、地球の温暖化による海水温の上昇や湧昇流の減少による栄養塩類の濃度低下、農薬・除草剤などの化学物質や有害物質の影響、海藻を食べる動物(特にウニ類)の増加が原因で、岩礁域の藻場が消失する「磯焼け」と呼ばれる現象が起きており、いろいろな要因で藻場の減少が起こると海藻が消失する。 ただし、海藻を食べるウニ等を放置すると海藻の幼体が食べ尽くされて磯焼けが起こると書かれていることについては、ウニも美味しくて重要な海産物であるため、ウニの食べ物である海藻が少なくて身が入らないようなウニは捕獲し、売れない野菜を餌にして養殖すると身の入った立派なウニになるそうだ。 なお、海草や藻類は、*5-2-2のように、光合成でCO₂を吸収すると同時に、生態系を豊かにする。この「ブルーカーボン」は、森林がCO₂を取り込む「グリーンカーボン」より多くのCO₂を吸収しているとの研究報告があり、地球温暖化対策になる。そして、藻場がCO₂をためる量は、面積当たりで森林の約25倍にも上り、藻場はCO₂削減の非常に優秀な場といえるそうだ。 世界では米国・オーストラリアなどがCO₂削減にブルーカーボンの活用を探る動きをしており、日本は四方を海に囲まれ湾が入り組んでいるため海岸線の総延長が世界6位の約3万5千kmに上るので、ブルーカーボンによるCO₂削減に期待が持てる。 そのため、国が2024年度から徴収しようとしている“森林環境税”は、都道府県の森林環境税と重複しないよう環境税に変更し、森林の整備だけでなく藻場の育成にも使うようにすればよいし、日本は、次のCOP27で、世界で協調しての環境税による森林や藻場の整備を提案すればよいと思う。 4)海産物の価値と資源の減少 *5-3は、「①消費者のライフスタイルの変化で、国民1人当たりの魚介類の消費量は2020年度は23.4kgと2001年度と比較して4割減った」「②漁業者は『捕ったものを売る』から『売れるものを創る』へと姿勢を転換して活性化に繋げるしかない」「③1次産業と2次産業の食品加工・3次産業の流通・販売までを一手に担うので、掛け合わせて6次化という」と記載している。 まず、海産資源の減少については、海や河川を大切にし、海産物の住処を壊して繁殖できないようにしないことが重要だ。しかし、公害は、環境を壊した人が代金を支払うのではなく、関係のない人が代償を払わされる「外部経済(経済学で『市場に織り込まれないもの』を意味する)」になることが多いため、環境に悪いことをする人に環境税を課して環境回復に使うのは、Fairであると同時に合理的なのである。 また、①については、都会で共働きをしながら集合住宅や狭い分譲住宅に住んでいると、魚を丸ごと買ってきてさばいたり、煙を出して調理したりするのは、後の掃除まで考えると大変で、獲れたての新鮮な魚介類を手に入れるのも困難であるため、調理法にかかわらずできあがりの味には限界がある。そのため、②③のように、獲れた魚を新鮮なうちに適切に調理して、味が落ちないようにしながら運送して販売すれば、魚介類はもともと栄養的に優れた食品であるため、消費は回復するだろう。 それによって、生産地では、雇用が生まれ、より多くの付加価値を付けることができ、いらない部分は養殖魚の餌や肥料にでき、運賃も節約できて、消費が回復するため、1石5鳥になる。 ・・参考資料・・ *1-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/91a2a97bd8ba1049f1c164fda338beb47a6118f6 (毎日新聞 2021/11/2) COP26の失敗は「死刑宣告だ」とグテレス事務総長 首脳級会合で グテレス国連事務総長は1日、国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)の首脳級会合で演説し、各国が提出した現在の温室効果ガスの削減目標では、今世紀末の平均気温は産業革命前から2・7度上昇すると訴えた。会議が失敗に終わった場合、各国は「(気候変動対策の)計画を見直さなければならない。5年ごとではない。毎年、常にだ」と警告した。グテレス氏は「私たちは厳しい選択を迫られている。私たちが化石燃料への依存を止めるのか、それとも化石燃料への依存が私たちを止めるかだ」と強調。「最近の発表されている気候変動対策は、私たちが状況を好転させるための軌道に乗っているような印象を与えるかもしれないが、それは幻想だ」と述べた。そのうえで「(小さな島国や開発途上国にとって、COP26の)失敗は選択肢ではない。死刑宣告だ」と指摘。「未来を守り、人類を救うことを選択してほしい」と訴え、小さな島国や開発途上国向けの気候変動対策への支援資金などを増額するよう求めた。 *1-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/140763 (東京新聞 2021年11月3日) 途上国へ1.1兆円追加支援を表明 岸田首相がCOP26首脳級会合で 岸田文雄首相は2日、英北部グラスゴーで開催中の国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)の首脳級会合で演説した。途上国の気候変動対策への資金支援について「新たに5年間で、最大100億ドル(約1兆1350億円)の追加支援を行う用意がある」と表明。アジアなどの脱炭素化に貢献する姿勢を示したが、議長国・英国が求める石炭火力発電の早期廃止に関しては言及を避けた。 ◆石炭火力発電の早期廃止は言及せず 日本はこれまでに途上国への約600億ドルの支援を表明していたが、支援規模の拡大を打ち出した。石炭火力発電については、英国が先進国による2030年までの廃止を求めているが、岸田首相は「アジアでの再生可能エネルギー導入は既存の火力発電を、(温室効果ガスの)排出ゼロ化し、活用することも必要だ」と述べるにとどめ、応じる姿勢は示さなかった。首相は演説で、50年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする目標を改めて明言。また30年度に13年度比46%削減の目標を紹介し、「さらに50%の高みに向け挑戦」を約束した。途上国への資金支援などでは、「世界の経済成長のエンジンであるアジア全体の排出ゼロ化を力強く推進する」と述べ、電気自動車普及に関する技術革新の成果などもアジアに広めると訴えた。岸田首相にとって今首脳級会合への出席は、首相就任後初めての外遊となった。 *1-3:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021110700068 (信濃毎日新聞社説 2021/11/7) 日本に「化石賞」 信頼得られぬ首相演説 世界が落胆したのではないか。英グラスゴーで開かれている国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)での岸田文雄首相の演説である。二酸化炭素(CO2)の排出量が多い石炭火力発電について一言も触れなかった。それどころかアンモニアや水素を活用し、火力発電の継続を宣言している。この演説で、環境NGOが、地球温暖化対策に後ろ向きな国に贈る「化石賞」に日本を選んだ。演説後、岸田首相は「高い評価をいただき、日本の存在感を示すことができた」と記者団に述べている。むしろ日本への批判が高まるのではないか。COP26では、議長国の英国が「脱石炭」を最重要課題に位置づけた。温室効果ガスの排出対策を取っていない石炭火力の段階的な廃止を盛り込んだ声明に、46カ国・地域が署名している。新たに廃止を表明したのは23カ国だ。日本などの支援で石炭火力の建設計画が進むベトナムやインドネシアのほか韓国も加わった。企業組織も含めれば、賛同する団体は190に及ぶ。日本は、米国や中国とともに署名を見送っている。電力の安定供給や産業の国際競争力維持のため、石炭火力は必要との立場を崩していないのが実情だ。せめて首相演説では、石炭火力への考え方や国内事情を丁寧に説明するべきではなかったか。これでは各国の信頼は得られない。アンモニアや水素を使った火力発電の実現も不透明だ。アンモニアや水素は燃やしてもCO2が出ない。特にアンモニアは肥料用や工業用としても生産され、輸送も容易で、燃料として有望視されている。経済産業省は2030年までに、石炭火力の燃料の20%をアンモニアにして混ぜ、発電する技術の実用化を目指す。50年にはアンモニアだけの発電も始める。ただ、国内の全ての火力発電で20%をアンモニアにした場合、消費量は年2千万トンに上り、世界の貿易量に匹敵する。どう調達するか見通しが立っていない。アンモニアの生産にも課題がある。化石燃料から水素を取り出し、窒素と反応させるのが一般的だ。水素を作る際、大量のエネルギーを使うため、温室効果ガスを出す可能性が大きい。アンモニアの燃焼で有害な窒素酸化物が生じる恐れもある。すぐに使えない技術なのは明らかだ。国際公約として持ち出すには無責任と言わざるを得ない。 *1-4:https://www.bbc.com/japanese/58142213 (BBC 2021年8月9日) 温暖化は人間が原因=IPCC報告 「人類への赤信号」と国連事務総長 国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は9日、人間が地球の気候を温暖化させてきたことに「疑う余地がない」とする報告を公表した。IPCCは、地球温暖化の科学的根拠をまとめた作業部会の最新報告書(第6次評価報告書)を公表。「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れている」と強い調子で、従来より踏み込んで断定した。さらに、「気候システム全般にわたる最近の変化の規模と、気候システムの側面の現在の状態は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったものである」と指摘した。「政策決定者への要約」と題された42ページの報告書でIPCCは、国際社会がこれまで設定してきた気温上昇抑制の目標が2040年までに、早ければ2030年代半ばまでに、突破されてしまうと指摘。海面水位が今世紀末までに2メートル上昇する可能性も「排除できない」とした。「向こう数十年の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に、地球温暖化は摂氏1.5度及び2度を超える」とも警告した。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、「本日のIPCC第1作業部会報告書は、人類への赤信号」だと発言。「私たちが今、力を結集すれば、気候変動による破局を回避できる。しかし今日の報告がはっきり示したように、対応を遅らせる余裕も、言い訳をしている余裕もない。各国政府のリーダーとすべての当事者(ステークホールダー)が、COP26の成功を確実にしてくれるものと頼りにしている」と述べた。国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)は今年11月、英スコットランドのグラスゴーで開催される。今回のIPCC報告を含め、近年の気候変動の状況を検討した複数の報告書が、COP26に向けてこれから次々と公表される予定となっている。この報告書は今までになく、温暖化のもたらす壊滅的な打撃を明確に断定している。しかし科学者の間には、2030年までに温室効果ガス排出量を半減できれば、事態は改善できるという期待も出ている。報告の執筆者たちも、悲観して諦めてはならないとしている。 ●IPCC報告の要旨:現状について ・地球の2011~2020年の地表温度は、1850~1900年に比べて摂氏1.09度、高かった ・過去5年間の気温は1850年以降、最も高かった ・近年の海面水位の上昇率は1901~1971年に比べて3倍近く増えた ・1990年代以降に世界各地で起きた氷河の後退および北極海の海氷減少は、90%の確率で 人間の影響が原因 ・熱波など暑さの異常気象が1950年代から頻度と激しさを増しているのは「ほぼ確実」。 一方で寒波など寒さの異常気象は頻度も厳しさも減っている ●IPCC報告:将来への影響について ・温室効果ガス排出量がどう変化するかによる複数のシナリオを検討した結果、どのシナリオ でも、地球の気温は2040年までに、1850~1900年水準から1.5度上昇する ・全てのシナリオで北極海は2050年までに少なくとも1回は、ほとんどまったく海氷がない 状態になる ・1850~1900年水準からの気温上昇を1.5度に抑えたとしても、「過去の記録上、前例の ない」猛威をふるう異常気象現象が頻度を増して発生する ・2100年までに、これまで100年に1回起きる程度だった極端な海面水位の変化が、検潮器が 設置されている位置の半数以上で、少なくとも1年に1度は起きるようになる ・多くの地域で森林火災が増える ●「厳然とした事実」 報告書の執筆に参加した、英レディング大学のエド・ホーキンス教授は、「これは厳然とした事実の表明だ。これ以上はないというくらい確かなことだ。人間がこの惑星を温暖化させている。これは明確で、議論の余地がない」と述べた。国連の専門機関、世界気象機関(WMO)のペテリ・ターラス事務局長は、「スポーツ用語を使うなら、地球の大気はドーピングされてしまったと言える。その結果、極端な気象現象が前より頻繁に観測され始めている」と指摘した。報告書の執筆者たちによると、1970年以降の地表温度の上昇は、過去2000年間における50年期間で最も急速なペースだった。こうした温暖化は「すでに地球上のあらゆる地域で、様々な気象や気候の極端な現象に影響している」という。 ●世界平均気温の変化 今年7月以降、北米西部やギリシャなどは極端な熱波に襲われている。あるいはドイツや中国は深刻な水害に見舞われた。過去10年の相次ぐ異常気象が「人間の影響によるものだという結びつきは、強化された」と報告書は指摘している。IPCCはさらに、「過去及び将来の温室効果ガスの排出に起因する多くの変化、特に海洋、氷床及び世界海面水位における変化は、100年から1000年の時間スケールで不可逆的である」と明確に断定している。海水温度の上昇と酸化は続き、山岳部や極点の氷は今後、数十年もしくは数百年にわたり解け続けるという。「ありとあらゆる温暖化の現象について、その影響は悪化し続ける。そして多くの場合、悪影響は引き返しようのないものだ」とホーキンス教授は言う。海面水位の上昇については、さまざまなシナリオによるシミュレーションが行われた。それによると、今世紀末までに2メートル上昇する可能性も、2150年までに5メートル上昇する可能性も排除できないとされた。実現の可能性は少ないながら、万が一そのような事態になれば、2100年までにほとんどの沿岸部は浸水し、数百万人の生活が脅かされることになる。 ●「1.5度上昇」目標は 地球上のほとんどすべての国は現在、2015年12月に採択された気候変動対策のためのパリ協定に参加している。パリ協定で各国は、産業革命以前の気温からの気温上昇分を、今世紀中は摂氏2度より「かなり低く」抑え、1.5度未満に抑えるための取り組みを推進すると合意した。この「1.5度」目標について、IPCC報告書は、専門家たちが様々なシナリオを検討した結果、二酸化炭素の排出量が大幅に減らなければ、今世紀中に気温上昇は1.5度はおろか2度も突破してしまうと判断を示した。IPCCは2018年の特別報告書ですでにこの見通しを予測していたが、今回の報告書でそれを確認した。「1.5度上昇」について、報告書執筆者の1人、豪メルボルン大学のマルテ・マインシャウゼン教授は、「個別の年にはそれよりもっと早く、1.5度上昇に到達する。すでに2016年にはエルニーニョの最中に2カ月間、到達していた」と説明する。「最新報告は2034年半ばだろうと推測しているが、ひどく不確実だ。今すぐ起きるかもしれないし、起きないかもしれない」現在の地球の温度はすでに産業革命以前のレベルから1.1度、上昇している。そして近年、異常気象現象が頻発している。それが今後、何年もかけて1.5度上昇まで到達するとなると、「ますます激しい熱波が、ますます頻繁に起きる」と、報告書執筆者の1人、英オックスフォード大学のフリーデリケ・オットー博士は言う。「地球全体で、集中豪雨がさらに増えるだろうし、一部の地域ではなんらかの干魃(かんばつ)も増えるだろう」 ●何ができるのか 報告書を作成したIPCC1作業部会のカロリーナ・ベラ副議長は、「私たちはすでにあちこちで気候変動の影響を経験していると、報告書は明示している。しかし今後も、温暖化が進むごとに、変化も同時に起こり、私たちはそれをさらに経験することになる」と述べた。では、何ができるのか。気候変動がもたらす悪影響について、この報告書は今までになく明確に断定している。しかし多くの科学者は、2030年までに地球全体の温室効果ガス排出量を半減できれば、気温上昇を食い止め、あるいは反転させることができるかもしれないと、以前より期待を高めている。温室効果化ガス実質ゼロ(ネットゼロ)を実現するには、まずクリーンエネルギー技術の利用で可能な限り温室効果ガスを減らした後、残る排出を炭素隔離貯留技術によって回収する、もしくは植林によって吸収するなどの取り組みが必要となる。英リーズ大学のピアス・フォースター教授は、「かつては、たとえネットゼロを実現しても、気温上昇は続くと考えられていた。しかし今では、自然界が人間に優しくしてくれると期待している。もしネットゼロを実現できれば、それ以上の気温上昇はおそらくないだろうと。温室効果ガスのネットゼロが実現できれば、いずれは気温上昇を反転させて、地球を少し冷やせるようになるはずだ」と言う。今回の報告によって、地球温暖化の今後の展望が前より明確に示された。その影響は、避けようがないものが多い。しかし報告書の執筆者たちは、これが運命だと諦めてはいけないと警告する。「温暖化のレベルを下げれば、事態が一気に悪化する転換点に達してしまう可能性がかなり減らせる。破滅すると決まったわけではない」と、オットー博士は言う。気候変動における転換点とは、温暖化が続くことで地球の気候システムが急変する時点を意味する。各国政府の首脳陣にとって、今回のIPCC報告は長年何度も繰り返されてきた警鐘のひとつに過ぎないかもしれない。しかし、11月のCOP26は目前だ。それだけに、今までより大きく政治家たちの耳に響くかもれない。 *1-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210921&ng=DGKKZO75903340Z10C21A9M11000 (日経新聞 2021.9.21) 「脱石油」改革を主導 サウジアラムコ社長兼CEO アミン・ナセル氏 2019年、世界史上最大となる新規株式公開(IPO)を実現した。サウジアラビアの実力者ムハンマド皇太子が掲げる「脱石油」改革の柱となる事業に取り組む。生産コストや最大生産能力の大きさなどからみて、市場で比肩するプレーヤーのいない巨大企業のかじ取りをになう。世界は脱炭素へと急速にかじを切り、サウジアラムコもビジネスの転換を進めている。改革の二大柱は下流部門への進出とアジアシフトだ。アミン・ナセル氏はアラムコを「エネルギーと化学の会社」だと説明する。19年のIPOは国内市場で実施したが、将来は欧米など外国市場での株式上場もめざす。外貨建ての債券やイスラム債の発行にも踏み切り、これに伴い、秘密のベールに包まれていた経営情報の開示を進めている。石油の地盤固めも並行して進めている。欧米メジャーが投資を抑制する中、生産能力増強の手を緩めない。ライバル企業が市場から振り落とされた後、最後に残るプレーヤーとして残存者利益を総取りする戦略だ。国際特許の取得では多くのメジャーを上回り、技術面での優位を固めている。アラムコでは上流開発部門を率いる上級副社長として石油・天然ガス生産施設の拡充を推進。気候変動問題を念頭にクリーンエネルギー事業進出の旗振り役ともなった。キングファハド石油鉱物資源大学を卒業後、アラムコに入社。2015年から現職。 *1-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211109&ng=DGKKZO77381470Z01C21A1MM8000 (日経新聞 2021.11.9) 政府、30兆円超対策ありき 「新しい資本主義会議」提言、成長戦略乏しく 政府は歳出規模30兆円超を見込む経済対策の月内策定に向け、本格的な議論を始めた。「新しい資本主義実現会議」(議長・岸田文雄首相)は8日、経済対策や税制改正に向けた緊急提言をまとめた。規模が膨らみやすい基金や補助金が多く、成長力の底上げにつながるか見えにくい。これまでの新型コロナウイルス対策事業は予算の未執行が目立つ。本当に対策が必要な「賢い支出」を意識する必要がある。会議は首相の肝煎りで、来春にも中長期ビジョンをまとめる方針だ。ただ、政権の看板政策の具体的な成果を早期に出す狙いがあり、2回目の会合で緊急提言を出して経済対策への反映を目指すことにした。デジタルや環境、テレワーク推進など菅義偉政権が6月にまとめた成長戦略に似た内容が目立つ。路線は継承しつつ、再生可能エネルギーに限らず原子力も選択肢にしたクリーンエネルギー戦略を策定すると明記した。岸田政権で打ち出したのは、賃上げに取り組む企業への優遇税制の強化や、看護師や介護士、保育士らの給与引き上げといった分配戦略だ。経済安全保障の観点から半導体の国内生産拠点を支援することも盛り込んだ。首相は9月の自民党総裁選や先の衆院選で「数十兆円規模の経済対策が必要だ」と訴えた経緯がある。政府・与党内では30兆円超との規模感が浮上するが、懸念を指摘する声もある。会計検査院は5日、コロナ対策事業として計上された65兆円程度の予算のうち3割超の22兆円余りが未執行だったと指摘した。コロナ対策を盛り込んだ2020年度予算は「規模ありき」で編成した結果、使い切れずに21年度へ繰り越した予算が30兆円余りに達した。日本経済研究センターはこのうち16兆円程度が未消化だと試算する。野村総合研究所の木内登英氏は「20年度から繰り越された30兆円には必要無かったものもあるはずだ。経済対策は数十兆円という規模にこだわらず、必要な支援が届くように絞り込む必要がある」と話す。繰越金は経済対策の原資に回る見通しだが、本当に必要な項目への予算措置が課題となる。与党が大規模な経済対策が必要だと訴える根拠の一つが需給ギャップだが、冷静な分析が必要な状況になっている。内閣府は4~6月期の実質国内総生産(GDP)改定値を基に年換算で22兆円の需要不足だと試算した。足元はコロナ感染者数が減少して緊急事態宣言も解除され、個人消費は回復傾向にある。国際通貨基金(IMF)の経済見通しを前提にした民間試算によると、22年の需要不足は7兆円程度まで縮小するという。経済対策は19日にも決め、12月に開く臨時国会で裏付けとなる21年度補正予算案の成立を目指す。短期で策定するだけに規模ありきでは、実際に企業や個人のニーズにあわない予算を過大な金額で見積もる懸念がある。日本はコロナ前の経済への回復が米欧に比べて遅れている。これまでのコロナ下の経済対策の教訓を生かしながら必要な予算を厳選し、本当に成長につながる対策が求められる。 <エネルギー> *2-1:https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/978344.html (静岡新聞社説 2021年10月28日) 原発・エネルギー 脱炭素への経路明確に 政府は中長期の政策指針となる「エネルギー基本計画」を約3年ぶりに改定した。併せて再生可能エネルギーや省エネルギーを推進する「地球温暖化対策計画」も定めた。第6次となる今回の基本計画では、再生エネを最優先で導入する方針を明記し、2030年度の電源構成で現状の約2倍に当たる36~38%まで拡大する目標を掲げた。LNG、石炭、石油など現状で76%ある火力発電は41%まで低下させる。原発の構成比率目標は20~22%で据え置いた。温室効果ガスの中心となる二酸化炭素(CO2)の排出量が多いエネルギー部門での化石燃料依存からの脱却が鍵だ。再生エネ利用が軸となる社会構造に変革する必要がある。その経路を明確化する議論を深めなくてはならない。衆院選で各党間で議論が大きく分かれるのが、発電時にCO2を排出しない原発の扱いだ。温暖化対策には有効であっても、過酷事故への不安と恐れはつきまとう。中部電力浜岡原発が立地する静岡県にとっても、原発の再稼働は重要な論点となる。温暖化防止への国際枠組み「パリ協定」に基づき、政府は昨年、50年の「カーボンニュートラル」(温室効果ガスの排出量実質ゼロ)を宣言した。その前提となる30年度の温室効果ガス排出量を、13年度比で46%削減する目標も表明している。CO2排出量が世界で5番目に多く、欧米先進国に比べて温暖化対策の遅れが目立つ日本は、前倒しで計画目標を達成するぐらいの意気込みが求められる。基本計画で火力発電の依存度は下がっているが、国際的にはまだ不十分だ。欧州先進国は早ければ20年代、遅くても30年代の石炭火力全廃をうたう。石炭火力建設に対する投資や融資が厳しくなる中、石炭全廃への国際圧力は一層高まるとみるべきだ。東京電力福島第1原発事故では、10年を経ても事故処理と廃炉に向けた道のりは見通せないままだ。原子力規制委員会が基準に適合していると認めた原発は再稼働しているが、国民に受け入れられているとは言い難い。仮に可能な原発を全て再稼働させても構成比率目標には達しない上、新増設や建て替え(リプレース)は容易ではない。自民党は公約で「可能な限り原発依存度を低減する」としながらも、基準に適合していると認めた原発の再稼働を進めると明記した。「必要な規模を持続的に活用」とし、「小型モジュール炉」や「核融合発電」など、新たな技術開発も進める姿勢を打ち出した。公明党も原発依存度の低減を訴える一方、新設は認めず将来的に“原発ゼロ”社会を目指すとし、同じ与党でも自民と違いを見せている。「原発ゼロ社会」の早期実現を訴える立憲民主党は、実効性のある避難計画の策定や地元合意のないままの再稼働は認めないとした。原発の新増設はせず、全原発の速やかな廃止と廃炉決定を目指すとうたった。共産党は「30年までに石炭火力・原発の発電をゼロにする」としている。基本計画の電源構成を見る限り、主力電源としての再生エネの位置付けは、はっきりしてきた。しかし、その実態は未熟なままだ。現状で火発や原発を減らしたり停めたりした時、すぐにその穴を埋めることはできそうもない。再生エネを、安価に安定的に得るためには何が必要なのかも詰めていく必要がある。主力となる太陽光発電は立地できる場所が限られる。場所によっては自然破壊などの恐れがあり、地元住民とのトラブルも増えている。送電網が足りないとされ、発電コストも検討する必要がある。脱炭素化に向けては、炭素税などの議論も避けられないだろう。CO2の回収・貯蔵や再利用には新技術やイノベーションが欠かせない。投資を惜しまずに研究開発を推進し、成長戦略として育てていく必要がある。 *2-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/6217b8efb355ad651a679eb5aade9ace002593d7 (Yahoo 2021/7/14) 日本、原発「コスト神話」も崩壊…「2030年には太陽光の方が低価格」初めて認定 ●経済産業省が発表 政府予測値として初めて原発・安全性に続きコストの優位性さえも揺らぐ 2030年には再生可能エネルギーである太陽光が、原子力を抜いて費用が最も安いエネルギー源になるという日本政府の見通しが発表された。政府次元の予測としては初めて、再生エネルギーは高く原子力は相対的に安いというエネルギー政策の前提が崩れたと評価されている。朝日新聞は13日付けの紙面で、2030年時点で太陽光発電(事業用)が1キロワット時あたり8円台前半~11円台後半とし、原子力(11円台後半以上)より安くなるとの推算値を経済産業省が12日に発表したことを報じた。原子力発電は、政府の試算のたびに費用が高くなっていることが明らかになった。2011年の試算では30年時点の費用が1キロワット時当たり8.9円以上だったが、2015年には10.3円となり、今回は11円台後半まで増加した。原子力はこれまで最も安いエネルギー源と認識されてきたが、少なくとも推定値基準として太陽光、陸上風力(9~17円)、液化天然ガス(LNG)火力(10~14円)に続く4位に下がる展望だ。原子力の費用上昇には、安全対策と廃棄物処理が影響を及ぼした。2011年の福島原発事故後に規制が強化され、放射性物質の拡散防止などの工事が必要になり、事故時の賠償や廃炉費用なども増えた。また、使用済み核燃料の再処理や放射性廃棄物(核のごみ)問題も費用上昇の原因と指摘された。一方、太陽光は技術革新と大量導入などによりコストが少しずつ下がると見通した。2020年の1キロワット時当たり12円台後半から、10年後の2030年には8円台前半~11円台後半に費用が下がると集計された。今回算出された費用は、発電所を作り十分に稼動させた後の廃棄までにかかる金額を総発電量で割った値だ。同紙は「政府や電力会社は福島第一原発事故後も原発のコスト面の優位性を強調してきたが、前提が揺らぐ」として「政府が改定をめざすエネルギー基本計画にも影響しそうだ」と指摘した。日本は太陽光や風力などの再生エネルギーを「主力電源」として現状より大幅に拡大させる計画を持ってはいる。だが、太陽光は夜間に発電できず、風力などは天候の影響を受けるとし、相変らず原発への依存度を拡大している。特に、日本政府は2011年の福島事故後に原発をすべて閉鎖することにした政策を覆し、再び稼動させている。現在は電力生産全体のうち約6%を占める原発を、2030年には20~22%まで引き上げる予定だ。龍谷大学の大島堅一教授(環境経済学)は、同紙とのインタビューで「(政府発表で)原発が経済性に優れているという根拠はなくなった」と話した。毎日新聞も「政府や電力業界が原発推進のよりどころにしてきた『安さ』の根拠が揺らいでいる。」として「安全性に続き、また一つ『原発神話』が崩れた」と評価した。 *2-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/132585 (東京新聞社説 2021年9月23日) 島根原発「適合」 無事避難できるのか 原子力規制委員会は、中国電力島根原発2号機が、3・11後に定められた新たな規制基準に「適合」しているとする審査書を正式に決定した。しかしそもそも、原発から三十キロ圏内(緊急防護措置区域)の市町村に策定が義務付けられた避難計画の適否は規制委の審査対象になってはいない。もしもの場合、計画通り無事避難できるのかは、考慮されていない。住民は不安を募らせている。福島原発事故のあと、国は原発防災の対象区域を原発十キロ圏から三十キロ圏に一応は拡大した。事故の被害が広範囲に及んだからだが、とても十分とは言い難い。島根原発は全国で唯一県庁所在地に立地する原発だ。三十キロ圏は、島根、鳥取両県の六市にまたがり、約四十六万人が暮らしている。日本原子力発電東海第二原発の約九十四万人、中部電力浜岡原発の約八十三万人に次ぐ規模だ。寝たきりの高齢者や障害のある人など、避難時に支援の必要な人々は約五万二千人にのぼり、東海第二の約三万八千人を上回る。福島のように地震、津波、原発事故の複合災害が発生した場合、寸断された道路に多数の車両が殺到し、計画通り県外へスムーズに逃れうるという保証はない。島根県庁は原発から南東にわずか八・五キロ。広域避難の“司令塔”になるべき県庁が機能不全に陥る恐れも強い。中国電力は、三十キロ圏内の自治体と安全協定を結んではいる。しかし、再稼働に関する「事前了解権」を認めているのは、島根県と原発が立地する松江市のみ。島根県出雲市や鳥取県米子市など周辺五市は、「報告」だけで済まされる。避難計画が必要とされるのは、それだけの危険があるからだ。義務はあるのに権利はない−。鳥取県の平井伸治知事らが、立地自治体と同等の同意権を要求するのは当然だが、中国電がそれに応じる気配はない。島根原発に限らず、原発事故の被害は三十キロ圏内にもとどまらない。福島原発事故による放射線が大量に降り注ぎ、全村避難を強いられた福島県飯舘村は、村域のほとんどが三十キロ圏外だった。チェルノブイリ原発事故による放射能汚染は、欧州全土に及んでいる。原発を動かすことにこのようなリスクがある以上、再稼働の可否を立地地域だけで決めていいわけがない。これもフクシマの教訓だ。 *2-4:https://genpatsu.tokyo-np.co.jp/page/detail/1826 (東京新聞 2021年11月8日) 山の恵みへの汚染は今 福島浜通りの渓流魚とキノコ(2021年秋) 東京電力福島第一原発事故から10年が過ぎたものの、福島県浜通りの山中は除染も難しく、ほぼ手つかずのまま。そんな環境で育つ渓流魚や野生キノコへの放射性セシウム汚染はどんな状況なのか。地元住民の協力を得て採取を重ねた。海水魚は仮にセシウムを取り込んでも、周りが塩水のためどんどん排出するため、現在は汚染されている危険性はほとんどない。一方の淡水魚は排出スピードはゆっくりで、特に手つかずの山中に生きる渓流魚への影響は大きいことが知られてきた。今回、福島県南相馬市在住で測定活動を続ける白髭幸雄さん(71)の協力で、許可を取って帰還困難区域にも入った。その結果、食品基準(100ベクレル/キログラム)を満たす魚はゼロで、基準の数倍から100倍超という水準だった。大きい個体ほど高濃度になる傾向があった。唯一、ほっとしたのは、釣りが解禁されている楢葉町の木戸川。3回にわたり、地元住民から魚の提供を受けたが、内臓以外ではセシウムは検出されなかった。一方の野生キノコの採取は飯舘村で伊藤延由さん(77)と継続。今年はシーズンにもかかわらず、キノコの出が非常に悪く、マツタケやサクラシメジなどは掲載に間に合わなかった。採取できた4種は、これまでと同水準の濃度だった。 *2-5:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA117JX0R11C21A0000000/ (日経新聞 2021年10月12日) 自民・甘利幹事長「原発、小型炉で建て替えを」 自民党の甘利明幹事長は12日、党本部で日本経済新聞のインタビューに答えた。運転開始から原則40年の耐用年数が近づく原子力発電所について、開発中の小型モジュール炉(SMR)を実用化して建て替えるべきだと提唱した。SMRは既存の原発に比べて工期が短く、安全性が高いとされる。甘利氏は「温暖化対策のために原発に一定割合頼るとしたら、より技術の進んだもので置き換える発想がなければいけない」と主張した。菅義偉前政権がまとめた次期エネルギー基本計画案に関しては「変える必要性は当面ない」と述べた。再生可能エネルギーを最優先する原則など現行案の内容を支持する考えを示した。2030年度に温暖化ガスの排出量を13年度比で46%削減する政府目標を巡っては「原発を何基動かしてこの数字になるかを明示しなければならない」と指摘した。計画案は目標達成へ発電量に占める原発の比率を19年度の6%から20~22%に高めるとしているが、必要な稼働基数は示していない。甘利氏は経済産業相や党政調会長を歴任し、政府・与党でエネルギー分野の政策立案に関わってきた。 *2-6:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021110600108 (信濃毎日新聞 2021/11/6) 地熱発電所、原発事故前の4倍に 豊富な資源、「再エネ」で注目 全国の地熱発電所の数が、11年の福島第1原発事故後のおよそ10年間で、4倍に増えたことが6日、火力原子力発電技術協会の統計から分かった。豊富な地下資源を抱えながら開発が停滞していたが、再生可能エネルギーとして再び注目され、建設が進んだ。ただ小規模発電所が多く、全体の発電量は伸び悩んでいる。英国でCOP26が開かれ、脱炭素社会実現を迫られる中、日本も再エネ導入の加速化が急務だ。火力や原発に比べ総発電量に占める地熱の割合は極めて小さく、30年までに発電所数を倍増する目標を掲げた。統計によると、10年度は20基だった発電所は、19年度に92基に急増した。 *2-7:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211110&ng=DGKKZO77425610Q1A111C2EAF000 (日経新聞 2021.11.10) ガソリン車「40年ゼロ」、COP26、新車販売で24カ国宣言 第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)の議長国である英国は10日、ガソリン車など内燃機関を用いる自動車の新車販売を主要市場で2035年、世界で40年までに停止するとの宣言に24カ国が参加したと明らかにした。国は英国のほか、カナダ、オーストリア、イスラエル、オランダ、スウェーデンなども加わった。米ゼネラル・モーターズやフォード、独メルセデス・ベンツなど自動車大手6社が賛同した。24カ国は段階的に走行中に二酸化炭素(CO2)を排出しない「ゼロエミッション車」と呼ばれる電気自動車(EV)などへの移行を目指す。日本政府も乗用車の新車を35年までに全て電動車にする目標を設定しているが、EVなどだけでなく、ガソリンを使うハイブリッド車(HV)も含める方針だ。萩生田光一経済産業相は10日の記者会見で「脱炭素に向け多様な技術の選択肢を追求する。『完全EV』という約束には参加しないが、後ろ向きではない」と述べた。宣言には米カリフォルニア州やニューヨーク州など、38の地方政府や都市も加わった。 *2-8:https://www.tokyo-np.co.jp/article/141446?rct=national (東京新聞 2021年11月7日) 軽石漂着で与論島に回収船派遣 国交省、効果的な方法検討 沖縄、鹿児島両県に大量の軽石が漂着している問題で、国土交通省は7日、漂流物の回収作業が可能な海洋環境整備船「海煌」を鹿児島県・与論島に向けて派遣していることを明らかにした。悪天候のため7日時点で同県指宿市に待機しており、現地到着日時は未定。国交省によると、海煌は八代港(熊本県)を基地とし、普段は八代海や有明海で漂流ごみの回収に従事している。与論島では港に軽石が滞留し、発電用の重油を供給するタンカーが接岸できない状況が続いているが、今後1カ月程度は電力供給できる備蓄があるという。同船の作業などを通じて、各地で活用できる効果的な回収方法を検討する。 *2-9:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/766687 (佐賀新聞論説 2021.11.10) 軽石漂着 備え充実の契機に 小笠原諸島の海底火山噴火で生じた軽石が約2カ月後、千キロ以上離れた鹿児島県や沖縄県の島々に漂着し、漁業や観光などに大きな被害が出ている。火山による自然災害であり、大雨や地震の災害と同様に、国による手厚い支援は当然だ。漁業被害では、軽石が流入して漁港が使えず漁に出られないことがある。エンジン冷却のため船が海水と一緒に軽石を吸い上げ故障する恐れがあるからだ。ショベルカーを使ってすくい上げるなど地道な撤去作業が続いている。国はこの費用や必要な資機材の支援を加速させたい。さらに、ポンプを使うなど軽石を効率的に回収する方法について、専門家の意見を聞きながら早急に対応策をまとめるよう提案する。モズク養殖も種付けした網を海に設定する作業ができないままだ。港内のいけすに入れて蓄養していた魚が軽石をのんで死ぬ被害も報告されている。これら被害についても生産者の意欲を保てるよう支援が求められる。また鹿児島県の与論島では、タンカーが接岸できないため発電用重油の供給が滞っている。重要な港湾については、離島の生活に影響が出ないようにするためにも優先的に撤去すべきだ。港湾が長期間使えなくなった際の備蓄や対応策もあらかじめ考えておきたい。白い砂浜が軽石に覆われ一つの観光の魅力が失われている。全てを取り除くことは難しいが、撤去した軽石を集め捨てる場所の確保や有効活用策も合わせて、何らかの措置ができないか検討も必要だろう。軽石は黒潮に乗って漂流しており、高知沖などでも確認されている。今後、四国、本州の太平洋岸を中心に漂着する恐れがある。船舶の故障につながるだけに、港湾に軽石が流入しないようにフェンス(汚濁防止膜)を準備するなど関係機関による警戒と準備の加速も待たれる。原子力発電所では、原子炉の冷却に使う海水の取水設備に影響が出る恐れがある。原子力規制委員会が電力会社に対し注意喚起しているが、今の準備で万全なのかも含め確認が不可欠と言える。浮き彫りになった課題もある。沖縄に漂着する前に軽石の流れを監視、把握していれば、フェンスを張るなど港湾に入れない対応ができたのではないか。過去にも量が少ないとはいえ軽石が漂着したことがある。国は海底火山の噴火後、最悪のケースを想定しながら警戒しておくべきだった。また、軽石がサンゴ礁など沿岸の環境に与える影響をモニタリングできる重要な機会である。学者らと協力し、データ収集にも力を入れたい。大きな自然災害が起きると、想定外として思考停止する傾向がある。だが、不測の事態への対応ができる知識、仕組みを整えることによって、災害に強い強靱(きょうじん)な社会を実現できる。国内には多くの火山があっていつ噴火しても不思議はない。富士山など他の火山噴火への備えを点検、充実させる契機にすべきである。海には日常生活から排出されたポリ袋などのプラスチックごみが漂っている。多くの魚や海鳥がこれを誤って食べて死んでおり、生態系に悪影響があるとされる。軽石の漂流を一つのきっかけとして、こういったプラスチックの漂流についても思い起こし、対策を前に進めてほしい。 <農業> *3-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/576364 (佐賀新聞 2020/9/18) “植えっぱなし”2期作 収量3倍 農研機構が調査、栽培確認 国の研究機関・農研機構九州沖縄農業研究センター(福岡県筑後市)は、稲の収穫後のひこばえを育てる「再生2期作」に取り組み、2回の収穫で一般的な収量の約3倍が得られることを確認した。温暖な九州の特性を生かそうという取り組み。同センターは、稲の超低コストな栽培技術として、今後、加工米や業務用米での導入を目指すとしている。暖かい九州では、水稲を早い時期に植えて遅くに収穫することが可能。今後、地球温暖化による気温の上昇も予想される。このため、同センターでは、多年生の稲が収穫後に出すひこばえに注目。そのまま育てると収量がどうなるか、実際に調べた。センターの圃場で、研究用に開発された多収系統の水稲を用い、4月に田植えし、1回目の収穫時期や稲を刈り取る高さを変えて2年にわたり調べた。その結果、稲が十分に成熟した8月下旬、地面から50センチと高い位置で刈り取れば、2回目(11月上中旬に刈り取り)も加えた収穫が、自然条件に恵まれると、10アール当たり1・47トンと、平均的な収量の約3倍となることが分かった。今回の2期作は、2回目の田植えをしていた従来と違う、“植えっぱなし”方式で、大幅な省力化が期待される。同センターは今後、栽培の実用化に向けて、最適な水稲の品種の選定や施肥技術の開発などに取り組む予定。世界的には急激な人口増で今後、課題となる米不足に対応できるほか、国内的には自然災害などの状況に応じて2期作目の適否を判断できるメリットがあるとしている。 *3-2:https://www.jacom.or.jp/saibai/news/2021/09/210901-53613.php (JACom 2021年9月1日) 次世代型水耕栽培プラント農業「アクアポニックス」専用設備北海道に竣工 ●株式会社アクアポニックス・ジャパンと有限会社S.R.K.は、ドイツで開発されたアクアポニックス専用設備を北海道で初めて建設し、8月31日に竣工した。 アクアポニックスは、チョウザメなどの淡水魚と野菜を同時に育てる自然界の循環を模した水産農法。SRKが経営するホテル「ナチュラルリゾート・ハイジア」敷地内に「アクアポニックス・ハウス」として建設された。同設備は、農薬や化学液肥を一切使用しない自然循環型アクアポニックスプラント(水耕栽培と水産養殖を併用)システムで、屋内栽培で多く用いられるLEDではなく、太陽の自然光を活用して育成できるように設計されている。再生自然エネルギーの先進国で、SDGs推進国のドイツebf社代表のフランツ博士が設計。太陽光パネルなどの再生自然エネルギー機器も導入し、全天候・通年型の設備で、豪雪や豪雨などの天候に左右されることなく稼働でき、極寒の地である北海道でテスト運用を兼ねて第一号プラント設備を建設した。アクアポニックス農業は、食糧危機に対応する手段の一つとして国連がレポートで公表。安心・安全な次世代の食料調達手段として欧米諸国などで広く実施され、すでに米国農務省(USDA)はアクアポニックスで栽培される野菜作物を有機農産物として認定している。「アクアポニックス(Aquaponics)」の語源は、水産養殖の「Aquaculture」と水耕栽培の「Hydroponics」からなる造語で、魚と植物を同じシステムで同時に育てる全く新しい農法。自然界の循環を模した次世代の安心・安全な水産農法で、養殖する淡水魚が排出する老廃物を微生物が分解し、栄養豊富な水を作って循環させ、その水を植物が栄養として吸収し、生育する。吸収後の水は植物の浄化作用によって浄化され、淡水魚の水槽へ戻される。このように自然界を模したシステムにより、水耕栽培と養殖を同時に行うことができる。一般的な水耕栽培に用いられる液肥と違い、自然で安全な有機の液肥による水耕栽培が可能になる。 *3-3:https://www.yomiuri.co.jp/national/20201124-OYT1T50125/ (読売新聞 2020/11/24) 養殖以外は国内にいないはずのチョウザメ100匹超捕獲、養殖業者「逃げ出していない」 宮崎県内の大淀川水系で今年、国内には分布していないはずのチョウザメが、ウナギ漁などの際に100匹以上捕獲された。養殖場から逃げ出したとの見方もあるが原因は不明だ。10月以降は急減しており、餌を捕れずに死滅した可能性もあるが、ウナギの漁期が終わったため、捕獲が減ったとの見方もある。定着すれば生態系への影響も懸念されるだけに、関係者は注視している。大淀川は鹿児島県曽於そお市から都城市、宮崎市などを経て日向灘に流れ込む全長約100キロの1級河川。宮崎県水産政策課によると、チョウザメは7月頃から宮崎市や都城市などで、ウナギ漁の釣り針などにかかるようになった。県が、ウナギ漁師らが所属する県内水面漁連から聞き取ったところ、7月中旬から9月上旬にかけて、偶然針にかかるなどして約90匹が捕獲された。その後、9月末にかけ、さらに約20匹が捕れた。大きな個体は1メートルに達していた。宮崎市役所近くの大淀川で何度も釣り上げた同市のウナギ漁師山元隆之さん(48)は「これだけの数が確認されるのはおかしい。豪雨などで養殖場から逃げ出したのではないか」と推測する。県内では1983年、県水産試験場がチョウザメの養殖試験を開始し、2004年に完全養殖に成功した。卵は高級食材「キャビア」として需要が見込まれ、現在は小林市や椎葉村など県内8市村の18業者が計5万匹を養殖している。県は「日本一の産地」とPRしており、県内産キャビアは米国や中国などに輸出されている。県が大淀川水系で捕獲されたチョウザメを調べたところ、ロシアに生息するシベリアチョウザメという種類だったことがわかった。養殖されているチョウザメの半数はこの種という。県は、大淀川沿いの養殖場から逃げ出した可能性があるとみて調査したが、県内の全業者が「逃げ出していない」と答えた。チョウザメがいた理由は特定できていない。一方、10月の捕獲数は1匹で、ペースは急減している。県がチョウザメの胃の内容物を調べたところ、カゲロウなどの水生昆虫を食べていたことがわかった。チョウザメは素早く動く魚を捕るのは苦手といい、県水産政策課の谷口基もとき主幹は「水生昆虫やカニなどは大淀川に多くは生息していない。餌が捕れずに死滅する可能性が高く、繁殖の恐れは低い」と言う。ただ、県によると、ウナギ漁が10月1日から禁漁期間に入ったため、チョウザメが捕獲される機会が減ったことが原因との見方も残る。シベリアチョウザメは寒さに強く、餌さえ捕れれば冬を越せる可能性もある。大淀川の生態系に詳しい生物学習施設「大淀川学習館」(宮崎市)の日高謙次・主幹兼業務係長(41)によると、チョウザメの餌は、絶滅危惧種の魚アリアケギバチと重なるといい、「このまま宮崎の川に居着いてしまえば、生態系への影響も懸念される」と語る。県は漁協にチョウザメに関する情報提供などを要請している。 ◆チョウザメ=尾びれがサメに似ているため、その名が付いたといわれ、主に淡水域に生息する。体長1メートルを超えることも珍しくなく、ヨーロッパやロシア、中国などに分布するが、日本の川に野生のチョウザメはいないとされる。 <林業> *4-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA05AZE0V01C21A1000000/ (日経新聞 2021年11月6日) 30年までに森林破壊防止 130カ国目標、ハードルは高く 英北部グラスゴーで開催中の第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)で、日本を含む130カ国超が2030年までに森林の破壊をやめて回復に向かわせる目標で一致した。温暖化ガスの吸収源である森林は、食糧確保のための農地開発などで減少が続く。森林保全は途上国の経済構造に大きな変化を迫る面もあり、目標のハードルは高い。6日の会合では環境を破壊しない農業や貿易のあり方を議論した。議長国・英国は森林回復に5億ポンド(約760億円)拠出する計画を公表した。地球の気温上昇を産業革命前から1.5度以内に抑える「パリ協定」の目標達成に向けた声明は「森林破壊を食い止め、持続可能な貿易に投資する必要がある」と明記し、ハンズ英国務大臣が各国に対応を求めた。ノルウェーのエイド気候・環境相は「時間は限られている。森林の経済価値を測れないのが課題だ」と問題提起した。樹木は光合成によって大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収し、幹や根などに大量の炭素を蓄える。世界全体の森林の炭素量はCO2換算で2.4兆トンに上る。工業化してから人類が大気中に排出した総量に相当する。森林が減れば吸収源が失われる。切った木を燃やすと蓄えたCO2を放出する問題もある。減少は南米やアフリカ、東南アジアで顕著だ。国連食糧農業機関(FAO)のデータでは1990年から2020年にかけて南米で年400万ヘクタール、南アフリカなどで年200万ヘクタール弱が減少した。東南アジアは年100万ヘクタール減った。世界全体での減少率は年0.1~0.2%。30年間で計4%減った。減少の大きな要因は、生活の糧を得るための農業開発だ。大豆やカカオといった農産物、牛などの家畜のために木を切り倒している。世界最大の熱帯林アマゾンのあるブラジルは近年、牛肉の輸出が増えている。切った木を発電用の燃料として輸出する地域もある。こうした農畜産物を先進国が輸入する構図もある。欧州や日本は国内法で森林保護を定めているが、規制は他国には及ばない。森林開発は途上国の経済発展と表裏一体の面もあり、対策は一筋縄ではいかない。英国は6日、「生産国と消費国が協力して持続的な貿易をめざす」との方針を打ち出した。環境負荷が低い生産方法を認証制度、狭い土地で収量を増やす技術開発、低所得の小規模農家の支援といった実務レベルの検討を始めた。森林保全は農畜産物の消費国も含む世界共通の課題だ。温暖化対策と生物多様性の維持の両面で各国の協調が試される。 *4-2:http://www.hokuroku.co.jp/publics/index/51/detail=1/b_id=900/r_id=4914/ (北鹿新聞 2021.10.21) スマート林業 下草刈りの最新技術は 大館北秋田の 協議会 省力化へ作業車実演 先進技術を活用して施業の効率化を図る「スマート林業」の実現に向けて、大館北秋田地域林業成長産業化協議会(会長・福原淳嗣大館市長)は20日、花岡町字繋沢の市有林で下刈作業車の実演会を開いた。人力で行われている植栽地を整備する地ごしらえや下草刈り作業への機械導入を支援し、省力化を目指す狙い。林業事業者らが最新の作業車を実際に操作するなどし、性能を確かめた。戦後に植栽した人工林が伐期を迎える中、皆伐後の再造林に向けて作業の省力化が課題となっている。協議会事務局の大館市林政課によると、伐採作業は機械化が進んでおり、植栽作業でも苗木運搬にドローンを活用する実証試験が昨年、同市で行われた。苗木を植えた後の下刈り作業に大きな労力を要していることから、今後の機械化を支援するため実演会を企画。林業事業者や行政の担当者ら約30人が参加した。農業、林業用などの動力運搬車製造メーカー、筑水キャニコム(本社・福岡県)の担当者が訪れ、2年前に販売を開始した林内下刈作業車を紹介。四つのアタッチメントで、地ごしらえや下刈り、苗木の運搬作業ができる。斜面を上りながら生い茂ったやぶや草を刈り取り、伐採後に残された切り株を粉砕する様子を見学した。東北では5台導入され、本県では藤里町のみで使われている最新機械で、操作を体験した参加者は「下刈りは草が伸びる夏場に、日差しを遮るものがない現場で行うため労力がかかっている。すぐに導入するのは難しいが、省力化につながると期待を持った」と話した。来月は大館市が丸太の材積を計測するスマートフォンアプリの活用をテーマに研修会を開く。市林政課は「現場の人材不足を補うためにも、研修会を重ねてスマート林業の実践的取り組みを支援していきたい」としている。 *4-3:https://webronza.asahi.com/business/articles/2021090300002.html (論座 2021年9月7日) 国産材生産増加が山を裸にする〜日本林業の深刻な課題、山林経営者の収益を低下させ続ける林野庁の支援 ●問題の多い林野庁の政策 アメリカを起源とするウッドショックと言われる木材価格の高騰によって、日本で木材の国内生産を拡大すべきであるという主張が行われています。穀物の価格が上昇するときに、食料自給率を高めるべきだという主張が行われるのと同じです。しかし、木材についての主張は、食料以上に深刻な問題を抱えています。まず、現状を見ると、輸入は対前年同期比で、2020年は14%、2021年前半は16%、それぞれ減少しています。しかし、激減しているという状況ではありません。製材の価格については、直近の7月、通常材では10~20%程度、輸入材と品質的に近い乾燥材では2倍の上昇となっています。ただし、ウッドショックと言われる状況は、アメリカの低金利政策がもたらした住宅需要の増加などによるものであって、長期的に継続するとは考えられません。価格が上昇すると、市場は供給量を増やそうとします。国産材の生産増加という主張は、それを超えて人為的、または政策的に、市場の反応以上のことを実現しようというものでしょう。しかし、市場メカニズムに介入する行動を行うと、経済に歪みが生じます。特に、木材供給については、短期的に供給を増やすと、森林資源が減少し、将来の供給に問題を生じかねません。実は、林野庁は、問題の多い政策を実施してきました。最近の論調は、この歪んだ政策をさらに拡大しかねないという問題をはらんでいます。 ●再生産が極めて困難となっている日本の林業 木材(山元立木)は伐採されてから、丸太、製材品と形を変えて流通し、最終的に住宅メーカーの建材等として利用されます。ところが、川下の製材などの製品価格は安定的に推移しているのに、原料である丸太の価格は長期的に低下しています。1980年のピーク時から40年間でスギの価格は3分の1まで、ヒノキの価格は4分の1に下がりました。特に、かつては総ヒノキの家が最高級の住宅とされ、高級材と評価されてきたヒノキの価格は著しく低下しました。今では、ヒノキとスギはほとんど同じ価格となっています。また、かつて高い国産材は安い外材に勝てないと言われてきましたが、今では外材よりも安くなっています。輸入材価格は安定しているのに、国産材の価格はこれを下回り、かつ下がっています。農産物の場合と異なり、内外価格差は逆転し、それが拡大しています。これには、国産材の多くは乾燥していないという品質面での問題も反映しています。しかし、丸太価格が低下しても、国産の製品価格は横ばいでした。消費者は丸太の価格低下の恩恵を受けませんでした。製品価格については、国産も輸入も同水準です。製品の価格が安定して原料の丸太価格が低下していることは、製品の生産者の利益が増加していることを意味します。 ●大きく落ち込む山林経営者の所得 林業については、木材の生産に50年以上の超長期を要するという、他の産業と異なる特殊な事情があります。山林経営者(森林所有者)は、現在適期を迎えた木を伐採した後、将来の伐期時点の価格や収益等を予想して、その跡地に植林して育林すべきかどうかについて意思決定を行います。将来の収益を予想する際、林業経営者がベースとして参考とする指標は、現在の山元立木価格です。ところが、山元立木価格は、丸太以上に低下しています。これは製品価格の1割程度であり、丸太価格に占める山元立木価格の割合は1980年代の6割から2割程度へ低下しています。山林経営者の平均所得は11万円に過ぎません。(以下略) <漁業> *5-1-1::https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/863430 (沖縄タイムス社説 2021年11月15日) [COP26文書採択]削減目標 一層踏み込め 英国で開かれていた国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)は、成果文書を採択して閉幕した。文書は、産業革命前からの気温上昇について「1・5度に抑えるための努力を追求すると決意する」と示し「この重要な10年間」に行動する必要性を強調した。2015年に採択された「パリ協定」と比べると一歩踏み込んだ表現になったと言える。200近い国と地域がその決意を示せたことは評価したい。会議の焦点となった石炭火力の扱いは、議長国の英国が強い姿勢を示したものの最後まで協議が難航した。草案では「石炭火力」の段階的廃止へ努力するとしていたが、更新された案では「温室効果ガス排出削減対策が講じられていない石炭火力」の段階的廃止へと変わった。しかも最終盤で排出量3位のインドなどが反対し、廃止ではなく「段階的に減らす」と表現がさらに弱まった。国連の文書で特定のエネルギー源の扱いに言及するのは異例で一致をみるのが困難なのは分かる。だが、温暖化による海面上昇に危機感を持つ島しょ国などにとっては十分納得できる表現とは言えまい。各国が提出した温室効果ガス排出削減目標全てが実行されたとしても、30年の排出量は10年に比べて13・7%増えると分析されている。ジョンソン英首相が期待する通り、COP26が後に「気候変動の終わりの始まり」として位置付けられるかは、各国が目標を強化し、具体的に行動できるかに懸かっている。 ■ ■ 会議では、少なくとも20カ国余りが石炭火力を段階的に廃止していくと新たに表明した。その中には日本などの支援で石炭火力の建設計画が進むベトナムやインドネシアなども含まれる。脱石炭の動きが加速する中で、その道筋を示し得ていないのが日本だ。10月に決まったエネルギー基本計画でも、30年度の電源構成で石炭火力の割合は約2割と定めている。「現状において安定供給性や経済性に優れた重要なエネルギー源」との位置付けだ。岸田文雄首相はCOP26の首脳級会合に出席し「対策に全力で取り組み、人類の未来に貢献していく」と決意表明した。日本は50年に温室効果ガス排出実質ゼロとする方針だ。会議を機に具体的な体制整備を急ぐ必要がある。 ■ ■ 脱炭素の問題は私たちの足元の問題でもある。沖縄電力は昨年12月、50年までに二酸化炭素を実質ゼロとするためのロードマップ(工程表)を発表した。太陽光や風力由来の再生可能エネルギーを30年までに現在の約3・4倍に増やす。水素やアンモニアなどの「CO2フリー燃料」の導入を検討する方針も示した。ただ、島しょ県沖縄では送電網が本土とつながっておらず、困難な事情もある。地球温暖化は私たちの住んでいる地球の未来に関わる問題だ。困難ではあってもロードマップの着実な実施を求めたい。 *5-1-2:https://toyokeizai.net/articles/-/460458 (東洋経済 2021/10/7 ) 北海道「サケ獲れずブリ豊漁」で漁師が落胆する訳、北の「海の幸」の構図に異変、背景に温暖化も 10月に入り、秋の味覚が本格化するシーズンになってきた。北海道では秋サケの定置網漁が最盛期を迎えている。残念なことにここ数年、サケは不漁が続いている。その一方で、サケの定置網にはなじみのなかった大量のブリが入っている。北の海にいったいどんな異変が起きているのだろうか。 ●不漁続きのうえに大量死のアクシデント サケの漁獲量は2002年23万1480トンをピークにほぼ減り続け、2020年(速報値)は5万1000トンまで落ち込んでしまった。2015年までは年間10万トンを維持していたのだが、2016年に8万2000トン強と大台を割り込み、2020年は最盛期の22%の水準にまで激減した。深刻なのは漁獲量の減少だけではない。9月下旬以降、道東の海域で定置網に入っていたサケなどの大量死が相次いでいる。10月5日までの累計でサケ約1万2000匹、サクラマス約2000匹、コンブ85トン、そして大量のウニなどの漁業被害が確認されているのだ。周辺の海域では過去に経験のない赤潮の発生が確認され、道は海水の分析などの調査を進めている。気になる今年の漁だが、9月20日現在の「秋さけ沿岸漁獲速報」(北海道水産林務部)によると、オホーツクの353万尾、根室の43万尾など道全体で492万5064尾となっている。前年比では123.7%と回復しているかのように見えるが、関係者の見方は慎重だ。「確かに、走り(出始め)の数字は昨年を上回っていますが、昨年はかつてない不漁でしたから、その数字を上回っているといっても、それ以前と比べると少ないですからね。今年も、これからどうなるか。全期を見ないことにはなんとも言えませんよ」(水産林務部の担当者)。実際、5年前の2016年の同時期(609万7316尾)と比べると、今年の漁獲量は8割の水準でしかない。かつてに比べれば不漁に変わりはないということだ。ここ数年のサケ不漁と対照的に水揚げが急増しているのがブリである。かつて北海道ではあまり縁のない魚だった。半世紀前、1970年代の漁獲量は年間数百トン。1985年はわずか37トンだった。それが2000年代から増え始め、2013年に初めて1万トンの大台を記録すると、2020年は過去最高の1万5500トンに達した。サケの3割にまで存在感を高めているのだ。ちなみに、昨年は不漁だったサンマ(1万1700トン)を初めて上回った。サケ不漁、ブリ豊漁といった北の海での異変の構図が見えてくるのだが、漁師や漁業関係者たちの表情はさえない。サケを獲るための定置網にかかっているのはブリばかり。道東の漁港でのある日の水揚げは、サケはわずか550㎏、ブリはその3倍の1.5トンだったという。 ●圧倒的に単価が安いブリ ブリが豊漁でも、なぜ漁業関係者は喜べないのか。それは価値が圧倒的に違うからだ。2020年の北海道での卸値はサケの829円/kg(北海道太平洋北区計=農水省の水産物流通調査)に対し、ブリは179円/kg(同)でしかない。ほぼ2割の水準である。実際、10月初旬に都内のスーパーを訪れ、鮮魚コーナーを覗いてみたところ、北海道産の秋サケの切り身100グラム198円に対し、ブリの切り身は100グラム98円と半値だった。「一部の大型のブリは豊洲市場など本州で人気になっているようですが、秋に獲れるブリの大半は小型ですから、いくら天然でもそんなに需要はない。ましてや道内ではほとんど需要がないですね」(水産関係者)。しかも、同じ定置網にかかってもサケと同じ施設で保存、処理、加工できるわけではない。「サケとブリでは大きさが違うから冷凍庫にしても同じものは使えない。加工法、加工技術も違い、道内にはブリの加工技術に習熟している業者は少ないから、どうしても値がつかない」(前出の水産関係者)という。一方、サケの水揚げが少なければ、貴重な筋子やイクラも当然少量となるから、水産加工業者への影響も大きい。当然、消費者にもしわ寄せが来る。9月、札幌市内の鮮魚店では、秋サケの切り身が昨年に比べ1切れ100円から150円も高く、イクラにする前の生筋子にいたっては、昨年は100グラムあたり600円程度だったのが、今年は2倍の1200円だという。サケへの依存度が高かっただけに、ブリが豊漁といってもすぐに代用品として転換できるわけではないのである。毎年、精力的な孵化放流を行っているのに、なぜ漁獲量が低迷しているのか。サケは生まれ故郷の川に帰って産卵する。自然産卵の稚魚や放流された稚魚は春から初夏にかけて海に入り、オホーツク海で夏から秋を過ごして成長。北太平洋で越冬し、翌年ベーリング海に入る。秋になるとアラスカ湾で冬を過ごし、春になるとベーリング海に。これを繰り返し、成熟した親魚となって故郷の川に戻ってくる。このサイクルの中に大きな異変が起きているということは間違いなさそうだ。 ●サケ不漁の背景に「4つの説」 水産関係者や漁業関係者の間で指摘されている原因をまとめてみると、次のような仮説が浮かび上がってきた。 ①沿岸部の海水温の異変 放流時期である春先の沿岸部の冷たい海水温と、初夏の急激な 海水温上昇に対応できずに稚魚が大量に死んでしまう。稚魚にとっての好適水温帯(5度 から13度)の期間が短くなっている。 ②漁獲期の海水温上昇 沿岸の海水温が秋になっても高く、サケが沖合や深いところに 避難してしまうため、定置網にかからない(逆に温かい水温を好むブリが定置網に かかっている)。 ③母川回帰率の低下 1996年には5.7%だった生まれた川へ帰ってくる母川回帰率(北海道) が2016年は2.6%、2019年は1.6%にまで低下している。 ④エサ不足 海水温の上昇で分布域がサバなどと重なり、サバなどに負けてサケの稚魚の 生存率が悪化。 海水温をはじめとする海洋環境が変化する中で、複数の要因が絡んでいるのだろう。ここでひとつ注目したいレポートがある。国立研究開発法人「水産研究・教育機構」の水産資源研究所がまとめた「北太平洋におけるさけます資源状況と令和2年(2020年)夏季ベーリング海調査結果」である。この調査結果によると、北太平洋全体のさけます類漁獲量は、ロシアおよび、アラスカで減少傾向となった。これまで同地域はそれぞれ増加・横ばい傾向であったが、潮目が変わったのだ。特に2020年はロシアではサケとカラフトマス、アラスカではサケの漁獲量が大きく減少した。カナダやアメリカ南部3州(ワシントン、オレゴン、カリフォルニア)、日本、韓国では引き続き漁獲量の減少、あるいは低水準が続いている。その結果、2020年の漁獲量全体は対前年比で6割程度に減少したという。また、同調査によると、2014年ごろからベーリング海の水深200mまでの海水温が高い傾向が続いている。こうした北太平洋における資源や海洋環境の変化が、「日本に回帰するサケ資源の動向とも関連していると考えられる」としている。水産資源研究所の担当者は「稚魚がオホーツク海にたどり着けるかどうかが最大のポイント。そのためには、環境変化にも生き残れる活きのいい稚魚をつくるなど資源回復に向けた取り組みを行っています」と語る。サケ資源の回復は長い目で見守っていくしかないのだろう。 ●存在感増す「ブリ」新メニュー続々 話題をブリに移そう。かつては道民にとって馴染みのなかったブリが、この数年で一気に認知度を上げ、食材としての存在感を高めている。北海道の一大観光地・函館は、2018年にブリの水揚げが全国3位に、2019年には名物のイカの供給量を上回った。そうした状況を受け、函館では「はこだて海の教室実行委員会」が日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として、新たなブリ食文化を定着させようと昨年からさまざまなメニューを考案、開発している。昨年は下処置したブリに衣をつけて揚げた「函館ブリたれカツ」を、今年5月にはその進化系として「函館ブリたれカツバーガー」を、そして今度はうまみ成分イノシン酸に着目して製造した「ブリ節」でだしを取った「函館ブリ塩ラーメン」を開発した。「はこだて海の教室実行委員会」事務局の国分晋吾さんに活動の狙いと反響を聞いた。「函館では5年ぐらい前からブリの水揚げが増えています。そうした中、海洋環境の変化を伝えるためには、地産地消も兼ねた食文化を通じて情報発信していくことが重要だと考え、2020年にプロジェクトを立ち上げました。昨年は、子どもが食べやすく学校給食にも提供できるということでブリたれカツに挑みました。今年は、やや脂が少ない小型のブリは節に向いているということで、羅臼の加工業者さんにブリ節をつくってもらいました。そしてブリのアラや豚肉・鶏肉のひき肉などで取ったスープにブリ節を加えた函館ブリ塩ラーメンを開発し、試食会でも好評でした」。10月1日から函館市内の飲食店やスーパーでさまざまなブリ料理を提供する「函館ブリフェス」を昨年に続き開催。多くの市民が新たな地元の味・函館のブリを堪能した。「名物のイカとともにブリが新たな函館の魅力として定着していってほしいですね」(国分さん) ●ブランド「ブリ」で差別化も 一方、日高のひだか漁協では、地元でとれたブリを「三石ぶり」「はるたちぶり」というブランド名で出荷。船上での血抜き処理、脂肪率の計測などを行い、高脂肪率の大型サイズを厳選するなど、ブランディング戦略の強化で差別化を図っている。このほか、道内では北海道ならではの「ブリザンギ」も人気だという。函館の水産会社がオンラインで発売しているので取り寄せも可能だ。スーパーでサケ、ブリともに購入し、それぞれ牛乳に浸した後でフライにしてみた。どちらも衣はサクサク、中はふっくらとジューシーに仕上がった(写真:筆者撮影)。サケ、サンマ、イカといった北海道を代表する魚の水揚げが落ち続ける中、日増しに存在感を増している北海道のブリ。サケに代わって北海道を代表する魚となる日がくるのだろうか。サケはかつてのニシンのような運命をたどってしまうのだろうか。海洋環境の激変による生態系への影響を「地域の問題」として捉えていてはできることに限界がある。例えばサケの孵化事業についてみると、サケの不漁が続く中で、地元漁業者による孵化事業への拠出金が減少している。孵化事業関連への国の予算を大幅に増額するなどの措置も必要だろう。資源保護とともに次世代に貴重な食文化、水産文化を残すためにも知恵を絞っていきたいものである。これは地域の活性化にもつながる重要なテーマである。 *5-2-1:https://ocean.nowpap3.go.jp/?page_id=540 (環日本海海洋環境ウォッチ ―環境省・NPEC/CEARAC ― Marine Environmental Protection of Northwest Pacific Region) 藻場の生態系における役割について 藻場とは、沿岸域の海底でさまざまな海草・海藻が群落を形成している場所を指します。 主として種子植物であるアマモなどの海草により形成されるアマモ場と、 主として藻類に分類されるホンダワラ、コンブ、アラメといった海藻により形成される ガラモ場、コンブ場、アラメ・カジメ場等があります。藻場は、海中の様々な生物に隠れ場所・産卵場所などを提供し、窒素やリンなどの栄養塩を吸収して光合成を行い、 水の浄化や海中に酸素を供給することで浅海域の生態系を支えています。 藻場の植物体自体がアワビ等の貝類を始めとする色々な生物の餌になるだけでなく、 海藻に付着した微細な藻類や微生物が小型甲殻類や巻貝の餌になっています。 それらの小型の生物がいることにより、それらを食べる魚類も集まってくるため、 藻場は、生物多様性と生産力が高く、日本では古くから漁場として利用されてきました。 また、アマモなどは農業の肥料として利用されていたこともありました。これらの藻場は、いずれも陸上の草原や森林に匹敵する高い一次生産力を持つだけでなく、 沿岸の生態系にとってきわめて重要な役割を果たしています。例えば、大型海藻類が存在していると、大型海藻が生長時に窒素やリンなどの栄養塩を吸収し、蓄えて、 急激な増加を抑えるバッファー(緩衝装置)の働きをします。 これらの存在なしでは、河川から窒素やリンの栄養塩が豊富な水が流入すると、 植物プランクトンが急激に繁殖して赤潮等の原因になります。また、海草類は、砂泥場に根を張り生活しているので、海底の底質を安定化させることにより、 波浪等で砂や泥が巻上るのを防いでいます。埋め立て・浚渫によって浅場が減り、海藻・海草の生育する場が失われると、 富栄養化により植物プランクトンが増殖して赤潮が発生しやすくなります。 また、陸上の開発に伴って赤土が海に流入すると、海水の透明度が低下し光合成に必要な光量が得られなくなり、 藻場が消滅してしまいます。地球の温暖化による海水温度上昇、湧昇流の減少による栄養塩類濃度の低下、 農薬・除草剤などの化学物質・有害物質の影響(水質汚染)、 海藻を食べる動物(特にウニ類)の増加などが原因で、岩礁域の藻場が消失する「磯焼け」と呼ばれる現象が起きています。いろいろな要因が引き金となり、藻場の減少が起こると、 海藻を食べる生物の食圧が相対的に高まり、海藻の消失へとつながります。 海藻を食べるウニ等を放置した場合、新たに岩等に付着した海藻の幼体が食べ尽くされてしまうことから、 磯焼け現象が固定化されてしまいます。 *5-2-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/488314/ (西日本新聞 2019/2/20) 「ブルーカーボン」で温暖化防止 生態系も豊かに 海草や藻場の価値を見直す 福岡市で博多湾シンポ 海草や藻類などの海の生物が、光合成で吸収する二酸化炭素(CO2)「ブルーカーボン」が注目されている。森林が取り込むCO2「グリーンカーボン」の海洋版で、森林より多くのCO2を吸収するとの研究報告があり、地球温暖化対策として活用を探る国も出てきた。福岡市で11日開かれた「博多湾シンポジウム」(博多湾NEXT会議主催)では、湾が持つブルーカーボンなどの働きに注目し、沿岸域の価値を高める方策を考えた。ブルーカーボンは2009年、国連環境計画(UNEP)が提唱した。海は大気からCO2を吸収しており、アマモやコンブといった海草や藻類は海中でCO2を取り込む。森林から河川を通して海に流れ出たグリーンカーボンを、アマモやコンブの藻場が吸収する働きもあり、CO2削減と気候変動の緩和に役立つとされる。シンポジウムでは、国土交通省国土技術政策総合研究所の岡田知也・海洋環境研究室長が、このブルーカーボンに代表される沿岸域の多様な働きを、価値として見直そうと提言した。沿岸域に生息するアマモなどの藻場や、熱帯・亜熱帯で生息するマングローブ林は、CO2を吸収した後に地中の枝や葉、根で長期間貯留する機能があるという。岡田室長は、藻場がCO2をため込む量は、面積当たりで森林の約25倍にも上るとし、「藻場は(CO2削減に)非常に優秀な場といえる」と説明。魚の産卵や稚魚が成長する場となるアマモ場などを増やせば、CO2削減の効果が高まるとの考えを示した。国交省によると、世界では米国やオーストラリアなどがCO2削減にブルーカーボンが有効として、活用を探る動きが出ている。日本でも研究機関や学識者などが「ブルーカーボン研究会」を17年に設立し、同省などの協力で活用方法を探る。日本は四方を海に囲まれている上に湾が入り組んでいるため、海岸線の総延長が世界6位の約3万5千キロに上り、CO2削減に期待が持てるためだ。福岡市内でも、博多湾NEXT会議などがアマモ場を増やす取り組みを始めている。岡田室長はさらに、博多湾は赤潮の原因となる栄養塩「リン」の数値が下落傾向にあり、水質が浄化されて生物がすみつきやすくなっていると報告。「今やるべきことは、生物の生息場となる藻場や干潟などを再生すること」と強調した。藻場や干潟にはブルーカーボンだけでなく、魚介類を育てる食料供給、海岸浸食の防止、観光に代表される親水など多様な価値があるという。岡田室長は「人が沿岸域の多様な価値を知り、利用する機会が増えれば、護岸に藻場をつくる事業なども進めやすくなる。そうなれば、住民が知らないうちに温暖化緩和に貢献することになる。そんな正のスパイラルを進めたい」と呼び掛けた。シンポジウムではこれに先立ち、前環境省地球環境審議官の梶原成元氏が講演。地球温暖化で気温上昇や豪雨、台風の大型化が起きているとし、食料生産の不振や金融業界の損害補填(ほてん)の増加、冷房に使うエネルギー需要増などにつながっていると説明した。 ●藻場づくり粘り強く 「ペットボトルやポリ袋のごみ増加」 シンポジウムでは、博多湾周辺の漁業や水族館の関係者、海中調査を続ける団体などによる意見交換もあった。湾に多くの種類の魚介類がすみ、藻場も豊富にある一方、大量のごみの投棄がある現状や藻場づくりの難しさを話し合った。博多湾の水中調査を手掛ける一般社団法人「ふくおかFUN」(福岡市)の大神弘太朗代表理事は湾の特徴を「海草が豊富で、魚が多く集まる。岩場の生物も種類が多い」。福岡工業大付属城東高(同)の生徒たちは、湾北東部の和白干潟の観察を通して魅力を紹介した。同市港湾計画部環境対策課の小林登茂子課長は、携帯電話で表示できるアマモ場の分布マップ作成に、福岡工業大が取り組んでいることを報告した。一方で課題も挙がった。同市漁業協同組合伊崎支所の半田孝之運営委員会会長は、約40年前から湾のごみの量が増えていると報告。近年はペットボトルやポリ袋が目立つといい、漁協の回収活動では年間30~40トンが集まるという。マリンワールド海の中道(同)の中村雅之館長は、近隣の志賀島沿岸からアマモの苗を館近くに移植し、藻場を増やす活動をしている。「アマモは芽が出ても根が弱く、波風が強いと流される恐れがある。粘り強く続けることが大切になる」。住民の参加を募り、アマモ場を一緒に広げることを提案した。 *5-3: https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211106&ng=DGKKZO77335530W1A101C2MM8000 (日経新聞 2021.11.6) 漁業「6次化」で価値創造、産出額低迷も加工・販売が寄与 徳島、市場2割拡大 消費者の「魚離れ」や資源減少などを背景に各地で漁業産出額の減少傾向が続く中、1次産業の漁業者が「捕ったものを売る」から「売れるものを創る」へと姿勢を転換し、活性化につなげている地域がある。2次産業の食品加工や3次産業の流通・販売までを一手に担うことから、すべての数字を掛け合わせて「6次化(総合2面きょうのことば)」といわれる取り組みの先進地を探った。農水省が3月に発表した2019年の漁業産出額は1兆4676億円。1982年の2兆9577億円をピークに、ほぼ一貫して右肩下がりの状況が続く。ライフスタイルの変化に合わせ、食卓に魚介類が上る回数も減っており、国民1人当たりの魚介類の消費量(20年度、概算値)は23.4キログラムと、01年度比4割減の水準にまで落ち込む。再活性化には資源そのものが持つ価値を創意工夫で高めるほかない。加工、直売、宿泊、レストランなどといった漁業生産関連事業はなお成長余地があり、19年度の年間総販売金額は2301億円と、14年度比で1割超増加。1次の低迷(同0.9%減)を補い、全体で0.7%の成長を達成した。2次3次の割合を高めた筆頭は和歌山県。19年度の「6次化率」(海面漁業・養殖業産出額などとの合算値に占める漁業生産関連事業の割合)は、37.1%に達する。漁業産出額は14年比5.5%減少したが、漁業体験などの観光関連事業に市町村が主体的に取り組んだことなどにより2次3次の成長を促し、全体でも7%増を達成した。古式捕鯨発祥の地として知られ、反捕鯨団体からやり玉に挙げられたことで国際的に注目された同県太地町では、漁師自らがクジラやイルカを「食資源」としてだけでなく、観光資源にも変えようと取り組む。20年7月から網で湾内を仕切り、シーカヤックでクジラやイルカを見学できるようにした。20年度の来訪者は2300人。21年度も9月までで1600人が訪れた。29.5%で2位となった徳島県も、1次の低迷を2次3次で補い、全体の市場規模を2割成長させた。生産・加工に乗り出したくてもノウハウがない漁業者への支援を手厚くし、県水産研究所に商品開発テストができる加工機器を配備。未利用魚のレトルト食品加工や防災食品作りなど、付加価値を高める商品づくりを後押しする。業種の垣根を越えて取り組むのは三重県(28.7%)。1次が12.8%減と大きく落ち込む中、全体の縮小を5.6%減にとどめた。鳥羽市では14年、地元農水産物の販売場と郷土食を中心としたレストランを併設した産直市場「鳥羽マルシェ」が開業。漁協と農協が共同出資する全国的にも珍しい取り組みで、年間約30万人が訪れる。マルシェは県外からの観光客だけでなく、地場産を求める地域の需要をも掘り起こし、市の担当者は「農林水産ともに活性化につながった」と指摘する。新たな価値を創造し利益につなげようとする動きは各地で相次ぐ。鳥羽市の「くざき鰒(あわび)おべん企業組合」は船のスクリューに巻き付くため、漁師に嫌われていた海藻のアカモクに着目。健康食品として生まれ変わらせた。高知県黒潮町では捕った魚を食い荒らすため害魚として駆除したサメを活用する。犬向けのペットフードとしたところ好評で、9月からパッケージから販売までの一貫した取り組みを開始。駆除と収入増を両立させる新たなビジネスモデルとなっている。 <地方の人口と産業> PS(2021年11月18日追加):岸田総理は、*6-1のように、総理大臣官邸で第1回デジタル田園都市国家構想実現会議を開催し、「①デジタル田園都市国家構想は、成長戦略の最も重要な柱」「②デジタル技術の活用で、地域の個性を活かしつつ、地方を活性化し、持続可能な経済社会を実現」「③デジタル田園都市国家構想実現のため、自治体クラウド・5G・データセンターなどのデジタル基盤の整備し、デジタル基盤を使った遠隔医療・教育・防災・リモートワークの支援し、地方創生の各種交付金とデジタル田園都市国家構想推進交付金のフル活用し、デジタル臨調・GIGAスクール・スーパーシティ構想・スマート農業等の成果も活用し、誰一人取り残さないようデジタル推進委員を全国に展開する」と述べられたそうだ。 が、私は、①については、理由の説明がないため、何故、成長戦略になるのかわからなかった。後まで読むと、②③のように、5Gが整備されれば、デジタルインフラを使って遠隔医療・教育・防災・リモートワーク等々を行うことができるため、地方に住んでも不便でなくなり、生産性も上がるということのようだが、仕事にはリモートや腰掛ですむものの方が少ないので、これだけで魅力的な田園都市ができるのか疑問だった。 しかし、*6-2のように、在留資格を何度でも更新可能にし、農業を含む全分野で無期限に外国人の就労やその家族の帯同を認めて永住への道を開けば、地方でも必要な若い労働力を比較的安価に得ることができ、産業振興が容易になるだろう。ただ、税法上は5年以上日本に住むと永住者とされるのに在留10年でやっと永住権取得が可能になるというのは、外国人にとって不利益が大きいと思われる。また、介護従事者は、日本の介護福祉士の資格を取れなければ母国に帰国しなければならないが、介護福祉士の資格を持っていなくても慣れた人がやった方がよい仕事は介護施設に多いため、帰国を強制する必要はないと思う。なお、自民党のみならず国民にも外国人の長期就労・永住・移民を嫌う人が少なくないが、外国人労働者を排除することにより、日本企業でさえ国内で必要な労働力を得られず、生産拠点を海外に移したため、日本の産業が衰退する羽目になったことは忘れるべきでない。 外国人労働者の受け入れを拡大した場合には、*6-3のように、(日本人が外国勤務した時に必要なことを考えれば容易にわかるが)本人だけでなく家族にも日本語が必要になる。さらに、長期就労・永住・移民をする場合は、家族も含めて日本の一般教養が必要になるため、私は、日本語教師が常備している子ども用の小中高校や大人も通える夜間中学・高校などを、政府の支援の下で自治体が準備するのがよいと思う。 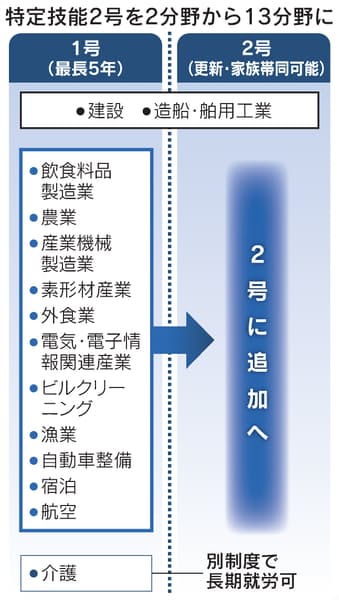  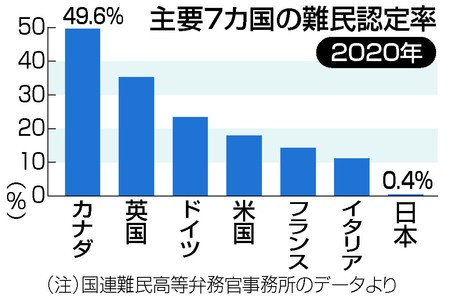 2021.11.18日経新聞 2021.5.28日経新聞 2021.6.19時事 (図の説明:左図のように、外国人の在留資格2号の対象に11分野を追加して13分野にする方向になっているそうだ。これに先立ち、中央の図のように、スリランカ人女性の殺害をはじめ、入管制度の問題によって犠牲になる外国人が後を絶たなかった。また、主要7ヶ国の2020年の難民認定率は、右図のように、0.4%と日本が著しく低いが、これは日本国憲法違反である) *6-1:https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202111/11digitaldenen.html (首相官邸 令和3年11月11日) デジタル田園都市国家構想実現会議 令和3年11月11日、岸田総理は、総理大臣官邸で第1回デジタル田園都市国家構想実現会議を開催しました。会議では、デジタル田園都市国家構想の実現に向けてについて議論が行われました。総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。「本日は、デジタル田園都市国家構想の実現に向けて、有識者の皆様方に、第1回目の議論をしていただきました。御協力に心から感謝を申し上げます。デジタル田園都市国家構想は、「新しい資本主義」実現に向けた成長戦略の最も重要な柱です。デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方を活性化し、持続可能な経済社会を実現してまいります。同構想実現のため、時代を先取るデジタル基盤を公共インフラとして整備するとともに、これを活用した地方のデジタル実装を、政策を総動員して支援してまいりたいと考えています。具体的には、5点申し上げます。まず1点目は、デジタル庁が主導して、自治体クラウドや5G、データセンターなどのデジタル基盤の整備を進めてまいります。2点目として、デジタル基盤を活用した、遠隔の医療、教育、防災、リモートワーク、こうしたものを地方における先導的なデジタル化の取組としてしっかり支援をしていきたいと思います。3点目として、地方創生のための各種交付金のほか、今回の経済対策で新しく創設をいたしますデジタル田園都市国家構想推進交付金をフルに活用いたします。そして4点目として、同時に、デジタル臨調やGIGAスクール、スーパーシティ構想、スマート農業等の成果も活用してまいります。そして5点目として、誰一人取り残さないよう、デジタル推進委員を全国に展開してまいります。当面の具体的施策及び中長期的に取り組んでいくべき施策の全体像については、年内を目途に取りまとめを行います。その上で、速やかに実行に移していくことで、早期に、地方の方々が実感できる成果をあげていきたいと考えています。本日の議論を踏まえ、若宮大臣が、牧島大臣と連携し、本構想の具体化に向け、政府全体として取り組んでいただくよう、よろしくお願いを申し上げます。」 *6-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE019ZY0R00C21A9000000/?n_cid=NMAIL006_20211117_Y (日経新聞 2021年11月17日) 外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野 出入国在留管理庁が人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格「特定技能」について、2022年度にも事実上、在留期限をなくす方向で調整していることが17日、入管関係者への取材で分かった。熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新可能で、家族の帯同も認める。これまでの対象は建設など2分野だけだったが、農業・製造・サービスなど様々な業種に広げる。別の長期就労制度を設けている「介護」を含め、特定技能の対象業種14分野すべてで「無期限」の労働環境が整う。専門職や技術者らに限ってきた永住への道を労働者に幅広く開く外国人受け入れの転換点となる。現在、資格認定の前提となる技能試験のあり方などを同庁や関係省庁が検討している。今後、首相官邸や与党と調整し、22年3月に正式決定して省令や告示を改定する流れを想定している。特定技能は人材確保が困難な業種で即戦力となる外国人を対象に19年4月に設けられた。実務経験を持ち特別な教育・訓練が不要な人は最長5年の「1号」を、現場の統括役となれるような練度を技能試験で確認できれば「2号」を取得できる。更新可能で家族も滞在資格が得られ、在留10年で永住権取得が可能になる。入管庁などは、2号の対象に11分野を追加し、計13分野にする方向で調整している。介護は追加しないが、既に日本の介護福祉士の資格を取れば在留延長などが可能となっている。ただ、自民党の保守派などの間では、外国人の長期就労や永住の拡大は「事実上の移民受け入れにつながりかねない」として慎重論が根強い。結論まで曲折を経る可能性もある。特定技能の制度導入時、入管庁は23年度までに34万5千人の労働者が不足するとみていた。足元では特定技能の取得者は月3千人程度で推移している。就労期限がなくなれば計算上、20年代後半に30万人規模になる。かねて国は外国人の長期就労や永住に慎重な姿勢を取ってきた。厚生労働省によると、20年10月末時点で国内の外国人労働者は172万人。在留期間が最長5年の技能実習(約40万人)や留学生(約30万人)など期限付きの在留資格が多く、長期就労は主に大学卒業以上が対象の「技術・人文知識・国際業務」(約28万人)などに限っている。「農業」「産業機械製造業」「外食業」など14分野で認められている特定技能も、長期就労できるのは人手不足が慢性化している「建設」「造船・舶用工業」の2分野にとどまる。新型コロナウイルスの水際対策の影響もあり、特定技能の資格で働くのは8月末時点で約3万5千人。日本商工会議所は20年12月、「外国人材への期待と関心は高い」と対象分野追加などを要望していた。外国人受け入れ政策に詳しい日本国際交流センターの毛受敏浩執行理事は「現業の外国人に広く永住への道を開くのは入管政策の大きな転換だ」と指摘する。 *特定技能:国内で生活する外国人は6月末時点で約282万人。活動内容などによって「永住者」(約81万人)、「技能実習」(約35万人)といった在留資格がある。出入国管理法改正で2019年に設けられた「特定技能」は技能試験や日本語試験の合格などを条件に、人手不足が深刻な業種14分野での就労を認めている。出入国在留管理庁によると、8月末時点で約3万5千人のうち、飲食料品製造業(約1万2千人)と農業(約4600人)の2分野で半数近くを占める。3年間の技能実習を終えた人が特定技能の資格取得を望む場合、日本語試験は免除され、実習時と同じ分野なら技能試験の合格も不要になる。新型コロナウイルスの感染拡大による入国制限で、新たな人材の確保が困難になった。実習終了後に帰国できない人が、在留資格を特定技能に切り替えて日本に残るケースが相次いでいる。 *6-3:https://mainichi.jp/articles/20181119/ddm/005/070/049000c (毎日新聞社説 2018/11/19) 就労外国人 日本語教育 政府の態勢は心もとない 外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、最も重視しなければならないのが日本語教育だ。日常会話など基本的な日本語能力を身につけなければ、日本社会で生活するのは難しい。ところが、入管法改正案は、日本語教育を法律事項として規定していない。今後その取り組みについて法務省令で定めようとしているが、政府の態勢は心もとない。一定の技能があれば業務に就ける「特定技能1号」は、日常会話以上の日本語能力が求められる。ただし、3年以上の経験を経た技能実習生は無試験で移行できる。政府は、1号には多くの技能実習生が移行すると見込んでいる。技能実習の過程で日本語を習得させればいい。そうすれば日本語教育にかけるコストも最小限に抑えられる--。そんな本音がのぞくような政府の対応だ。技術移転を名目としながら、実際には低賃金、長時間の労働を強いる技能実習制度の問題は大きい。その技能実習制度の下での日本語講習が充実しているとはとても言えない。日本語学校から教師を派遣してもらう都合がつかなければ、受け入れに当たる業界の監理団体の職員が教えることがあるという。国土交通省が建設分野の実習生に聞き取りした調査では、日本語のコミュニケーション能力が問題視され、現場に入れなかった例もあった。1号の資格を得れば、5年間という長期の在留が認められる。やはり専門的な教育機関の活用が欠かせない。その中核になるのが、全国に700校近くある日本語学校だろう。技能実習生や留学生が増えるのと軌を一にして、日本語学校は急増中だ。ただし、日本語教師は総じて給料が安く離職率が高い。全体として不足していると言われている。政府は、日本語教師の資格を公的に認定することで、教師の質の向上や定着を図る方針だ。だが、それだけでは十分ではない。外国人に対する日本語教育は、これまで地方自治体や、地域で日本語教室を開くNPO任せで、こうしたところへの支援は乏しかった。政府は必要な財政措置を取り、日本語教育を下支えする体制を構築すべきだ。受け入れの拡大は、それとセットで行う必要がある。 <COP26における化石燃料の位置づけと補助金> PS(2021年11月21、25日追加):COP26は、*7-1-1・*7-1-2のように、産業革命前からの気温上昇を1.5°に抑えることを目標とするため、土壇場での中印(背後に日本がいる)の修正要求ということで、「石炭火力発電は段階的に廃止する」から「排出削減対策が取られていない石炭火力発電の段階的な削減努力を加速する」にかなり弱められた形で合意された。しかし、このように目標を甘くしてきたことが、再エネの普及と単価の低減を妨げ、「EVはHVよりもかえってCO₂を排出する」などという弁解を許しているのだ。また、*7-1-1は「先進国や島国と新興国の立場の違い」などと悠長なことも言っているが、日本は島国なのに、言い訳ばかりしている間に先進国から借金過多の後進国に落ちようとしている稀な国なのである。さらに、日本政府は、燃料をアンモニアに代える技術でアジアを支援することを打ち出したそうだが、これは(多くの理由で)不合理な上、日本国民のために全くならない。なお、文書が強調した「重要な10年間」に各国がどのように行動するかが問われるが、それには日本を含む地球に住む1人1人の科学的合理性のある努力が必要である。 そのような中、*7-2-1のように、政府が閣議決定した55兆7千億円の財政支出による経済対策は、①18歳以下の子どもを対象とした1人10万円の給付金 ②科学技術立国のための10兆円の大学ファンド ③経済安全保障の確立 ④技術革新への投資拡大 ⑤地方のデジタル化 ⑥「Go To」補助金 ⑦看護師・介護職の賃上げ推進 などだそうだが、②③④⑤⑦の中には必要なものもあるかもしれないが、①は、配布時期から見て1兆円ずつかけた衆議院議員選挙支持の御礼と参議院議員選挙支持のお願いになっている。そして、これは候補者が必要なビラ配りをしたり、アルバイト代を支払ったりするどころではない権力を使った桁違いに大きな選挙違反だ。また、⑥は既に経済政策として1兆円も使う時期ではないため無駄遣いにすぎず、コロナ対策予算は日頃から医療制度の充実を疎かにして小さくケチり、経済を止める羽目になって数兆円もの大きな保証を払いながら誰も幸福にしなかった馬鹿な事例である。その上、原油価格が上昇したからといって、*7-2-2のように、25年以上もの準備期間があったのに対策を講じなかった石油関連業者に「補助金」を出すのは何のメリットもない。「新しい資本主義」が借金で大盤振る舞いをする大きな政府であるのなら、その借金を誰にどうやって返済させるつもりかを直ちに議論すべきだ。何故なら、内需(国内消費+国内投資)について、民間は国内消費が伸びて投資を回収できる国にしか投資しないため、金融緩和と消費税増税で物価を上げれば内需は減るばかりで増えないからだ。そのため、*7-4のような老朽化した水道管・橋を交換したり、適格にメンテナンスしたりしつつ、同時に電線を埋設・敷設して再エネ時代のインフラ整備に支援するのなら未来への投資になるが、選挙対策やその場限りのバラマキは止めて欲しいのである。 なお、*7-3のように、国内846社の国連SDGsへの取り組みをまとめたところ、2030年代までの実質ゼロ達成が43社、将来的に実質ゼロ以下にする宣言をした企業が267社(回答企業の31.6%)にのぼり、経産省傘下の経団連よりも意識の高いことがわかる。 米バイデン政権が日本・中国・インド等の主な消費国は協調して石油備蓄を放出すべきだと表明し、*7-5は、日本政府は石油国家備蓄を初めて放出するにあたって、①国家備蓄は145日分と90日分以上という目標を大きく上回り、貯蔵量は1990年代後半から変わらないこと ②国内石油消費量は省エネで減少して日数換算では増えているので、政府はこの余剰分を放出するとみられること ③政府は、アジアの石油市場で売却できないか詰めていること ④これまでの放出は紛争・災害で供給不足が心配される時だったこと ⑤多額の税金を投入して備蓄基地を作り、空きタンクができかねないため、これまで国家備蓄量を増やすことはあっても減らすことはなかったこと などを記載している。 しかし、あまりにも論理がおかしいため、石油ショック後の昭和50年に制定された「石油の備蓄の確保等に関する法律(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350AC0000000096)」を確認したところ、「第1条:我が国への石油の供給が不足する事態か災害の発生により国内の特定地域への石油供給が不足する事態が生じた場合、石油の安定的供給を確保して国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする」という石油の備蓄目的が書かれていた。今回の価格上昇は供給不足に起因するものであり、備蓄放出は国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資するので備蓄目的そのものの筈で、④は融通が効かなすぎ、⑤は論外である。また、③のアジア市場での売却では国内よりも単価が安く、備蓄放出が国民生活の安定や国民経済の円滑な運営にも資さない。その上、①②については、有事の際には145日分の備蓄があったとしても145日しか持たないため、エネルギーや食料は備蓄で安堵するのではなく自給率を高める必要があるのだが、日本政府はこれを完全に無視してきたのだ。 そのような中、*7-6のように、旭化成が2025年に再エネ由来の電力で水素を作ることができる世界最大級の装置を商用化し、水素の価格を2030年に330円/kg(現在の約1/3)に引き下げることを目指すそうだ。これまで、世界一高い価格で化石燃料を輸入してきた(無能な)商社は、人材を再教育して水が豊富な日本の水素を世界に販売するよう事業転換すべきだ。  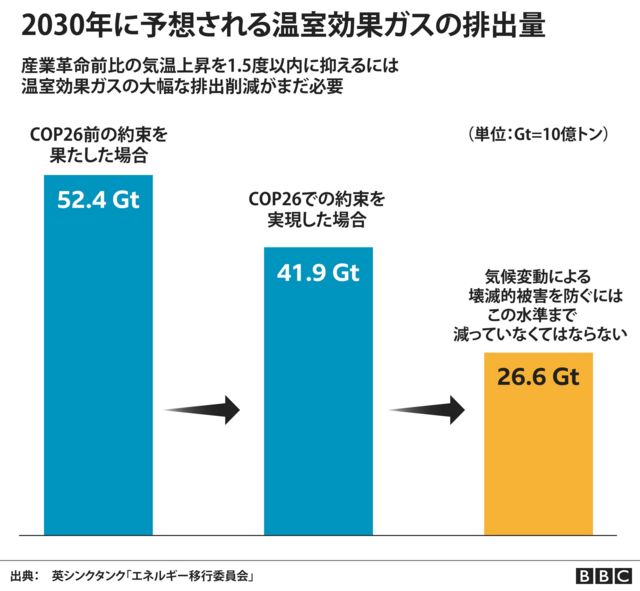 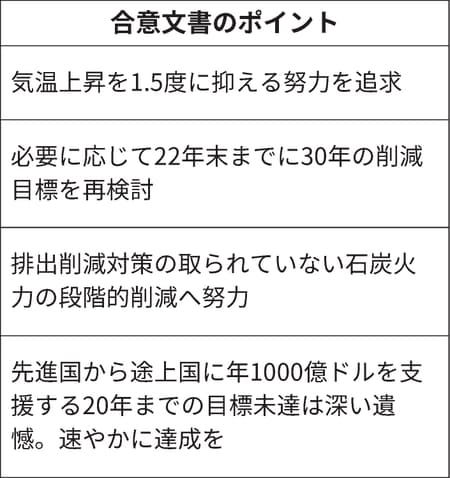  2021.11.10日経新聞 2021.11.14BBC 2021.11.14TBS (図の説明:1番左の図のように、地球の気候変動危機を緩和するために行われてきたCOP26だが、左から2番目の図のように、COP26の約束を守っても気温上昇を1.5°に抑えることはできない。それにもかかわらず、右から2番目の図のように、『石炭火力発電の廃止』は『段階的削減への努力』に弱められた。さらに、1番右の図のように、化石燃料への補助金削減を呼びかける表現が含められたのに、日本は、石炭だけでなく石油にまで補助金を出そうとしている点で、京都議定書から25年以上も準備期間があったとは思えない遅れようなのである。そのため、何故、こうなったのかを猛烈に反省して改善すべきだ) *7-1-1:https://digital.asahi.com/articles/ASPCH6H5RPCHULBJ002.html?iref=comtop_7_01 (朝日新聞 2021年11月15日)「失望は理解、しかし…」声詰まらせた議長 密室の40分で何が? 13日閉幕した国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)では、産業革命前からの気温上昇を1・5度に抑えることを新たな目標とするなど各国が歩み寄りを見せた。一方、石炭火力発電の廃止では、土壇場で中印の修正要求で表現が後退するなど、国情の違いによる対立も露呈した。13日、COP26の最後の公式会合でシャルマ議長は声を詰まらせた。「みなさんの深い失望は理解する。しかし、全体の合意を守ることも必要だ」。会場からの拍手に押されるようにして、木づちを打ち下ろし、合意文書を採択した。2週間にわたるCOPの後味を悪くしたのは、石炭火力発電をめぐる合意文書案の記載が、段階的な「廃止」から「削減」に弱められたからだ。採択直前に、先進国・島国と新興国の間の立場の違いが露呈した。石炭火力は世界の電力部門の二酸化炭素排出の7割を占め、「温暖化の最大原因」(国際エネルギー機関)だ。議長国・英国は自らが石炭火力の電源比率を2015年の23%から2%に減らしており、合意文書に「脱石炭」のメッセージを盛り込みたかった。欧州連合(EU)や、温暖化による海面上昇や災害の危機に直面する島国も強く支持し、合意の流れはできつつあった。13日午後の非公式会合。中国代表団は「まだいくつかの問題で相違点があることに気付いた」。インドのヤーダブ環境・森林・気候変動相は「途上国が石炭火力発電や化石燃料への補助金を段階的に廃止すると約束できるとは思えない」と主張し、文書案の修正を求めた。両国の排出量は世界1位と3位。両国ともエネルギー需要は伸びており、石炭火力は重要な電源だ。ヤーダブ氏は「世界の一部の地域は、化石燃料とその使用によって高いレベルの富と幸福を手に入れることができた。途上国は(累積の排出量を)公平に使う権利がある」と強調した。先進国が年間1千億ドルの資金支援をする約束が果たされていない途上国の不満も味方につけた。会合は中断し、シャルマ議長とケリー米気候変動担当大統領特使や中国の気候変動担当の解振華・事務特使が、EUやインドの代表団らと別室にこもり調整に走った。約40分の密室の会談で、「廃止」から「削減」に弱める流れが決まった。表現が弱まったことについて、シャルマ氏は記者団の取材に「私たちが目指していたものとは違っていたが、最終的に合意された」と無念さをにじませた。国際NGOグリーンピースのジェニファー・モーガン事務局長は石炭火力を削減していく合意について、「弱くて妥協もしているが、画期的だ」「石炭の時代が終わるというシグナルが発信された」などとコメントした。 ●「1.5度目標」にこだわった英国 「世界が必要としていたゲームを変えるような合意に達した」。COP26が閉幕した翌14日、議長国・英国のジョンソン首相は演説で胸を張った。COP26は英国にとって、欧州連合(EU)離脱後の外交で存在感を示すチャンスだった。新型コロナの影響で2年ぶりの開催だったが、参加が難しい途上国やNGOから再延期論が出る中でも、約130カ国の首脳を含む、約4万人を集めた。合意文書では、「世界の気温上昇を1・5度に抑える努力を追求する」と明記。「この決定的に重要な10年」という言葉を繰り返し、各国に来年までに削減目標の見直しを求めるとともに、毎年閣僚級の会合を開くことも決めた。石炭火力の段階的削減と非効率な化石燃料補助金の段階的廃止も、初めて明記した。後押ししたのは、洪水や山火事、干ばつなど、気候危機が現実になる中、世界で対策の加速を求める声の高まりだ。欧州では国政選挙の争点にもなり、ビジネスも脱炭素社会に向けて走り始めていた。COP期間中にも、「気候正義」を求める市民らのデモ行進がグラスゴーの街を埋めた。英政府は、パリ協定の実施ルールの完成という本来の交渉議題よりも、「1・5度目標の希望を残し、道筋をつける」ことを最大のテーマにした。シャルマ議長が33カ国を訪問するなど各国に働きかけた。主要排出国を含む150カ国以上が削減目標を更新し、1・5度目標の達成の条件とされる今世紀中ごろの「実質排出ゼロ」を宣言する国も140カ国以上に増えた。1・5度目標の達成が危ぶまれる状況に変わりはないが、脱炭素に向けたリーダーとしての存在感を示したといえる。バイデン政権でパリ協定に復帰した米国も、温暖化外交で主導権を取り戻そうと、英国を後押しした。ケリー大統領特使が各国を回り、最大の排出国の中国とはオンラインを含めて30回以上会談。COP26期間中に共同宣言を発表し、外交や経済で対立する両国が、そろって温暖化対策に臨む姿勢をアピールした。ケリー氏は閉幕後の会見で「パリがアリーナを建設し、グラスゴーで(脱炭素社会への)競争が始まった。そして今夜、号砲が鳴った」と話した。 ●石炭火力使い続ける日本に重い課題 今回の合意には課題も残されている。一つは途上国への資金支援だ。合意文書は、温暖化に備えるための対策への支援を25年までに少なくとも倍増させるよう促した。成果の一つだが、20年までに総額で年間1千億ドルの資金支援をするというパリ協定の約束が果たせていない。途上国は演説で「信頼は損なわれた」と失望をあらわにし、早期の実現を繰り返し求めた。日本を含む先進国が増額を発表したが、実際に資金を届けられるかが問われている。国際的な温室効果ガスの削減量取引の仕組みが合意に至った。過去2回のCOPで決裂してきたが、パリ協定のルールがようやく完成した。先進国が排出削減の事業を途上国で進めた場合、途上国で減った分を先進国の削減量とみなせるというもので、双方が国の削減量に算入する「二重計上」は認めないことや、京都議定書のもとで発行された過去の削減量(クレジット)は、13年以降の分に限って認めることにした。うまく使えれば削減にかかるコストを半減でき、30年に日本の年間排出量の4倍近い50億トンを減らせるとの試算もある。山口壮環境相は閉幕会合で「長年の宿題が解決した。日本の提案が合意の一助になったことを誇りに思う」とアピールした。途上国での削減を加速していくには、国の支援だけでなく、民間の資金を呼び込めるかが課題となる。合意文書に「削減する」と明記された石炭火力は、日本にも突きつけられた問題だ。政府は、将来も使い続ける計画で、燃料を石炭から二酸化炭素(CO2)を出さないアンモニアに代えていくことで排出をゼロにしていく方針だが、技術的にもコスト面でもハードルは高く、実現は見通せていない。岸田文雄首相は2日の演説で、これらの技術でアジア支援することを打ち出し、国際NGOから強い批判を浴びた。日本政府が15日に公表した交渉結果の概要には「石炭火力の削減」にかかわる記載はなかった。会議に参加した環境NGO気候ネットワークの伊与田昌慶さんは「COP26を通じて世界は脱石炭に踏み出した。日本は脱石炭をはっきりさせる必要がある。そうしなければ来年のCOP27でも再び国際的な批判にさらされることになる」と指摘する。 *7-1-2:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1423623.html (琉球新報社説 2021年11月15日) COP26文書採択 「重要な10年」へ行動を 英国で開催された国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)は成果文書を採択して閉幕した。文書は焦点となった石炭火力の扱いについて「排出削減対策が取られていない石炭火力発電の段階的な削減の努力を加速する」とした。採択前の案にあった「段階的廃止」から後退した感は否めない。だが世界の気温上昇を抑える共通目標に変わりはない。文書が強調した「重要な10年間」に、各国がどのように行動できるかが問われる。石炭火力の「段階的廃止」は温暖化対策にとって最重要課題といえる。COP26事務局の最新分析では、各国が提出した温室効果ガス排出削減目標全てが実行されても、2030年の排出量は10年比で13.7%増える。二酸化炭素(CO2)の排出量が非常に大きい石炭火力発電にメスを入れなければ、対策の実効性が薄まる。しかしいまだ十分な電力供給施設を持たない途上国には「廃止」は受け入れられない内容だった。会議では欧州などを中心に異論もあったが、文書採択を優先した形だ。その中で日本政府の態度には不満が残る。CO2を排出しないアンモニアとの混合燃焼など新技術を使うとして石炭火力の継続を表明した。確立していない新技術を掲げて化石燃料からの脱却を渋る日本の姿勢に対し、環境団体が「化石賞」に選んだのは当然だ。菅義偉前首相が掲げた温室効果ガスの「30年(14年比)46%削減、50年実質排出ゼロ」の国際公約は現在も有効である。実効性ある枠組み構築へ岸田文雄首相の指導力も問われる。周囲を海に囲まれ、危機に直面するのは沖縄を含め多くの島嶼(とうしょ)国・地域だ。水没の危機を訴えるマーシャル諸島代表が「落胆とともに変更を受け入れる。成果文書は私たちの命に関わる要素を含んでいる」と合意を優先した。その重みを受け止めねばならない。一方で参加国が「世界の平均気温上昇を1.5度に抑える努力を追求する」点で一致できたのは前進だ。パリ協定の努力目標だった1.5度抑制が新たに実現すべき目標となったからだ。まず当面の目標は30年の削減目標をどれだけ上積みできるかだ。経済産業省の資源エネルギー調査会の試算で、30年時点では太陽光の発電コストが原子力発電のコストを下回る結果が出ている。太陽光パネルを設置するための立地などに課題があるとはいえ、再生可能エネルギーの推進は最優先で取り組むべき項目だ。安全保障や経済で対立する米中2大国がパリ協定達成へ共同宣言を発したことも世界には追い風となっている。米中両国が先導役となり、対策が遅れる途上国への支援を活発化させる必要がある。COP26で得た共通目標を実現するために努力するのは地球に住む一人一人の責務だ。 *7-2-1:https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=810393&comment_sub_id=0&category_id=142 (中国新聞 2021/11/20) 経済対策 「規模ありき」では困る 政府がきのう、新たな経済対策を閣議で決めた。財政支出額は55兆7千億円と、過去最大の規模に膨れ上がった。今こそ政府の役割が問われるという認識の表れかもしれない。岸田文雄首相も言う通り、「持てる者と持たざる者の格差・分断」が新型コロナウイルス禍で浮き彫りになっている。ただ、対策の中身をみれば、子どもへの10万円給付から科学技術立国のための10兆円大学ファンドまで、目的がふぞろいな政策の寄せ集めとの印象も拭えない。焦点が定まっていない。緊急事態宣言が解除となった今は本来なら、コロナ禍からの「出口」戦略を指し示すべき時期ではないのだろうか。対策の4本柱として掲げるうたい文句も、「『新しい資本主義』の起動」以外は「国土強靱(きょうじん)化の推進」など見飽きたものにほかならない。分配重視の「新しい資本主義」にしても、関連政策として挙がっているのは、経済安全保障の確立に技術革新への投資拡大、地方のデジタル化といったものにすぎない。目指す社会の道筋が読み取れない。肝心の国内総生産(GDP)押し上げ効果は限られる、といった厳しい見方もある。規模の大きさにとらわれるあまり、一律の給付金や巨額基金などが目立つからだろう。忘れてはならないのは、2020年度政府予算のコロナ対策事業である。持続化給付金などを巡る不正受給や過払いが20億円近くに上ると会計検査院が指摘した。3度にわたる補正予算編成で計73兆円に積み上がったものの、約3割を使い残したいきさつもある。異例の経済対策も、それらの検証を踏まえていなければ「規模ありき」と受け取られよう。支援を必要とする人々に、十分なお金が届くのだろうか。今回も、生活困窮層への現金給付▽旅行や飲食への「Go To」補助金▽看護師や介護職などの賃上げ推進―といった施策が盛り込まれている。実効性や公平性について、丁寧に見極める必要があろう。既に議論が分かれているものもある。石油元売り業者に対する「ガソリン補助金」である。流通経路などが複雑で、加えて給油所の経営はただでさえ苦しい。小売価格まで恩恵が及ぶ保証はどこにもない。そもそも、価格上昇はガソリンに限るまい。引っ掛かる声があるのは当然だろう。財源の議論が聞こえてこないのも気掛かりである。所得再分配の一環で、岸田首相が訴えていた金融所得課税の強化は来年以降に先送りした。企業の内部留保への課税や英国などで進んだ法人税率引き上げといった手も検討すべきではないか。先の衆院選で、各党は大盤振る舞いの公約を並べた。来年夏の参院選を意識し、公約違反との批判を恐れているのかもしれない。だが財源の裏付けなしに事を進めるなら、「ばらまき」批判は免れまい。もはや国際公約になった「脱炭素社会」の実現も待ったなしである。内外の宿題に立ち向かいつつ、どうやって内需を掘り起こし、賃上げをもたらす好循環につなぐのだろう。「新しい資本主義」を目指す岸田首相には、もっと骨太の具体策を打ち出してほしい。 *7-2-2:https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/680217 (京都新聞社説 2021年11月19日) ガソリン補助金 効果と公平性に疑問符 政府は、ガソリン価格高騰を抑えるため、石油元売り各社に資金支援する緊急対策を打ち出した。価格が一定水準を超えた場合、卸売価格の上昇を抑える分の補助金を出し、店頭での値上がりに歯止めをかけるという。小売価格を抑制するために元売り側へ国費を投じるのは異例の取り組みだ。新型コロナウイルス禍からの経済回復の重荷を減らす狙いといえよう。政府は、実施のスピード感を重視し、本年度予算の予備費を使って年内開始を掲げる。ただ、対策の中身は生煮え感が拭えない。確実に小売価格を抑えられるかどうかの実効性や、業界支援の公平性にも疑問符が付く。ガソリン小売価格は、世界的な需給逼迫(ひっぱく)による原油高を背景に9月から上昇傾向が続き、今週初めの全国平均はレギュラー1リットル当たり168円90銭と約7年3カ月ぶりの高値水準となっている。新たな対策は、平均小売価格が170円を超えた場合に発動し、最大5円を抑制する案などが想定されている。軽油などを対象とするかも検討中という。問題は、補助金の分だけ卸売価格を下げても、全て小売段階に反映されるとは限らないことだ。店頭価格は、人件費や競合店対策も加味して小売店ごとに決められ、元売り業者が指示できない。小売店からは、コロナ禍での苦しい経営事情と、消費者からの厳しい価格監視の板挟みになりかねないと困惑する声も聞かれる。原油高の影響はガソリンにとどまらない。電気、ガス料金も1年前から10%以上の値上がりだ。円安の進行も重なってエネルギー全般や原材料が値上がりしており、ガソリンだけを特別扱いする根拠は明確でない。新対策の予算総額は数千億円規模ともみられている。政府は経済が回復するまでの時限的措置と説明したが、いつ、どういう状況まで続けるか分かりにくい。そもそも価格高騰を抑える方法には、ガソリンにかかる揮発油税などの税率を一定条件で時限的に引き下げる「トリガー条項」がある。発動には関連法改正が必要な上、急激な価格変動による混乱を避けるため見送られたという。補助金には、国民に身近で分かりやすい対策成果を示したい政府の思惑も透けるが、市場の価格形成をゆがめる国の介入は自制的であるべきだ。ガソリン価格抑制策の必要性と妥当性を詳しく説明し、どう機能したのか透明性のある検証が国会にも求められる。 *7-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2928D0Z21C21A0000000/?n_cid=NMAIL006_20211117_A (日経新聞 2021年11月16日) 温暖化ガス排出ゼロ、267社が宣言 本社SDGs経営調査 本経済新聞社は国内846社について、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」への取り組みを格付けする「SDGs経営調査」をまとめた。温暖化ガスの排出量を将来的に実質ゼロ以下にする宣言をした企業は267社(回答企業の31.6%)にのぼり、宣言企業のうち43社は2030年代までの達成を目標とし、産業界での脱炭素の取り組みが加速している。13日まで英グラスゴーで開かれた国連の第26回気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)では、温暖化ガスの排出削減などが話し合われた。目標達成に欠かせないのが企業の積極的な貢献だ。SDGs経営調査で温暖化ガスの排出削減について聞いたところ、回答企業の29.1%(246社)が排出量を実質ゼロにする「カーボンゼロ」を宣言していた。排出量を上回る削減効果を期待する「カーボンマイナス」も、コニカミノルタなど21社が宣言していた。宣言を実施した時期について聞いたところ、「21年」(56.9%)が最も多く、「20年」(24.3%)が続き、「19年以前」の18.4%を上回った。企業の脱炭素に向けた意識が高まっていることが浮き彫りとなった。宣言企業のうち78.7%は50年以降を達成の目標時期としている。一方で資生堂が自社の排出分について26年までに実質ゼロとする方針を掲げるなど、政府目標に先んじた達成を目指す企業も2割近くに上った。取引先の温暖化ガスの排出まで把握している企業(377社)は20年度に排出量を19年度比11.9%削減するなど、脱炭素の取り組みも進む。背景にあるのが投資家のESG(環境・社会・企業統治)重視の姿勢だ。企業は主要国の金融当局でつくる「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の指針に基づく気候リスク情報の開示などへの対応も求められている。企業別の総合格付けでは、アサヒグループホールディングスが全項目で高評価を獲得し、初めて最上位の格付けを得た。工場で再生可能エネルギーの活用を推進していることなどが評価された。「SDGs経営調査」は毎年実施しており、今年が3回目。事業を通じてSDGsに貢献し、企業価値の向上につなげる取り組みを「SDGs経営」と定義している。「SDGs戦略・経済価値」「環境価値」「社会価値」「ガバナンス」の4つの視点で評価した。国内の上場企業と従業員100人以上の非上場企業を対象とし、846社(うち上場企業784社)から回答を得た。 *7-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211121&ng=DGKKZO77764210Q1A121C2CM0000 (日経新聞 2021.11.21) 老いる水道管、進まぬ対策、耐用年数超え、全国13万キロメートル 人口減で更新の壁 全国で水道関連の事故が相次いでいる。10月には和歌山市で水道管が通る橋が崩落して広範囲で断水が発生。首都圏を襲った地震でも漏水事故が起きた。人口減少による水道事業の財政難で老朽化する施設の更新が滞っていることなどが背景にある。耐用年数を超えた水道管は全国に約13万キロある。頻発する事故は対策が進まぬ水道行政に警鐘を鳴らしている。10月3日、和歌山市の紀の川に架かる「水管橋」が崩落した。市内の約6万戸が断水し、復旧工事を経て断水が解消されるのに1週間ほどかかった。11月下旬になっても水管橋は崩落したまま。近くの道路橋に仮設の水道管が設けられたため通行止めとなり、周辺の別の道路橋では車の混雑が続いた。「普段、何気なく使う水道のありがたさを痛感した」。市内の女性(79)は振り返る。親戚らに自宅まで車で水を運んでもらったが、トイレや洗濯のたびに重い容器を持ち上げる必要があり「体にこたえたし、心理的にもストレスだった」。100人以上の透析患者がいるクリニックは透析に必要な水を給水車で提供してもらったが、入院患者の入浴や洗濯を制限せざるを得なかった。市によると、崩落事故は橋のアーチ部分から水道管をつっている鋼管製のつり材が腐食して切れたことが原因とみられる。橋は地方公営企業法施行規則に基づく耐用年数の48年を2023年3月に迎える予定だった。目視による点検の甘さも指摘され、市は調査委員会を設けて原因究明を進める。10月7日に首都圏で震度5強を観測した地震でも千葉県市原市の川に架かる水管橋の水道管から水が噴き出した。水道管の接続部分を固定するボルトが経年劣化で腐食していたとみられる。厚生労働省によると、水道管の事故は19年度、全国で約2万件報告された。水道管の法定耐用年数は40年。水道は高度経済成長期の1960~70年代に急速に普及し、多くが更新時期を迎えている。2018年度の総延長約72万キロのうち17.6%にあたる約13万キロが耐用年数を超えている。一方で、01年度は1.54%だった水道管の年間の更新率は18年度は0.68%に低下した。人口減少や節水の影響で使用水量が減り、料金収入による独立採算制である水道事業の経営が苦しくなったことが要因の一つだ。行政のスリム化や団塊世代の大量退職で工事に必要な人材も不足している。更新時期を迎える水道の工事計画や管理に遅れが生じている自治体もある。大阪市では水道管の総延長約5200キロのうち、法定耐用年数を超えた割合が21年3月末時点で51%に達した。20年度の水道事業収益は559億円でピーク時(1998年度)から約4割減り、関わる職員数もピーク時(75年度)の半分以下。市は18~27年度に1000キロの水道管を交換する計画だが「更新できる水道管は年間60~70キロが限界」(担当者)という。同市は20年10月、PFI(民間資金を活用した社会資本整備)形式の活用を目指し、約1800キロの水道管を16年間で交換する民間事業者を公募したが、応募した2者が辞退し頓挫した。採算が取れないと判断したもようで先行きの厳しさが透ける。対策に乗り出す自治体もある。香川県は18年、県内16市町の事業を統合し、県広域水道企業団による全国初の「1県1水道体制」を導入。特に老朽化が進む施設の改修を優先するなど効率的な事業につなげている。福岡県飯塚市は22年1月、水道料金の平均35%値上げに踏み切る。水道事業は料金収入の低迷で3年連続で赤字。水道管の老朽化が進んでおり、更新や耐震化のために値上げを決めた。近畿大の浦上拓也教授(公益事業論)は水道事業の広域連携について「各自治体で異なる水道料金の統一などがハードルとなり順調に進んでいない。都道府県がリーダーシップを発揮する必要がある」と指摘。値上げには「住民に十分に説明し理解を得るべきだ」と話す。 *7-5:https://news.yahoo.co.jp/articles/1b793a9cfecd746795b151a13928833cdeda18ad (朝日新聞 2021.11.24) 「最後のとりで」に異例の対応 石油の国家備蓄放出、政府の言い分は 米バイデン政権が23日、日本や中国、インドなど主な消費国と協調して石油備蓄を放出することを表明した。日本政府も石油の国家備蓄を初めて放出する方針だ。具体的な放出量や時期などを示していない国もあり、原油価格を下げる効果は見通せない。日本の石油備蓄は国が所有する国家備蓄と、石油会社に法律で義務づけている民間備蓄などがある。国家備蓄は全国10カ所の基地などで国内需要の約90日分以上を貯蔵することとし、民間備蓄は70日分以上と定めている。国家備蓄は9月末時点で145日分と目標を大きく上回っている。貯蔵している絶対量は1990年代後半からほぼ変わっていない。国内の石油消費量は省エネなどで減少傾向にあり、日数換算でみると増えている。政府はこの「余剰分」を放出するとみられる。政府は国内の需要動向などをみながら、国家備蓄の原油の種類を少しずつ入れ替えている。そのたびに一部をアジアの石油市場で売却しているという。今回放出する場合は、同じように市場に売却できないか詰めている。売却の収入は、ガソリン価格抑制のために石油元売り各社へ出す補助金の財源にする案もある。ただ、これまで備蓄を放出したのは、紛争や災害時で供給不足が心配されるときだ。レギュラーガソリンの平均価格が1リットルあたり185・1円と史上最高値を記録した2008年にも放出しなかった。放出する場合でも、まずは民間備蓄で対応し、国家備蓄には手をつけなかった。なにかあれば民間分を先に出し、国家備蓄は「最後のとりで」として温存しておくためだ。民間備蓄は国内の石油元売り会社のタンクに貯蔵されており、放出分を国内のガソリンスタンドなどに届けやすいこともある。政府は、余剰分の放出は目標量は満たしたままなので問題ないとしている。放出量も国内需要の数日分と限定的だ。米国との協調を演出するため、異例の対応に踏み出す。だが、これまで国家備蓄量を増やすことはあっても、大きく減らすことはまずなかった。多額の税金を投入し備蓄基地をつくったのに、空きタンクができかねない。10月に閣議決定されたエネルギー基本計画も「引き続き石油備蓄水準を維持する」と明記している。国家備蓄に初めて手をつけるなら、政府には十分な説明が求められる。 *7-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211125&ng=DGKKZO77853740V21C21A1EA2000 (日経新聞 2021.11.25) 水素製造量が世界最大級の装置 旭化成、25年商用化 旭化成は2025年に再生可能エネルギー由来の電気で水素を作ることができる装置を商用化する。水素製造量で世界最大級の装置で、製造する水素価格を30年に1キログラム330円と現在の流通価格の約3分の1へ引き下げを目指す。水素を活用した事業の採算が見込みやすくなり、脱炭素のカギを握るとされる水素供給網の整備が進む可能性がある。脱炭素の流れを受けて水素需要は拡大が見込まれており、その供給網の中核を水素製造装置が担う。旭化成は福島県で、水素の製造量を決める最大出力で10メガワットの装置の実証実験を実施しており、これを基に25年から受注を始める。欧州や中東などに売り込む。大型装置の量産を進めることで、現在1キロワットあたり20万円とされる装置価格を30年に5万円に下げる。水素価格を流通価格の3分の1程度に抑えられ、政府が水素普及に向けて掲げる30年目標と同程度になる。旭化成は複数の装置をつなぐ技術開発も進め、20年代後半には100メガワット規模に大規模化する計画だ。 <農林漁業の再エネによる副収入> PS(2021年11月22日追加):農林漁業は再エネによって副収入を得られる広い敷地を持っているため、①再エネによる副収入で農林漁業の収入を増加させることができ ②これにより国の補助金を減らすこともでき ③燃料費を地域外に吸い取られることなく地域内での消費に回すことができ ④分散発電によって停電のリスクも軽減できる。しかし、国が原発と化石燃料を安価で安定的なベースロード電源としたため、日本で芽生えていた再エネ機器の開発は、*8-2のように途絶えてしまった。本当に、先の見えない情けない国である。その上、*8-1は、「原発の使用済核燃料から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分方法は、原発の恩恵を享受してきた国民全体で解決すべき問題」としているが、私は「発電方法は原発や化石燃料でなければならない」と言ったことは一度もなく、電力小売全面自由化(2016年4月1日)まで電源選択の自由が国民に与えられていたわけではないため、「原発は安全・安心・安価で安定的な電源だ」と主張してきた人が全責任を負うべきだと思う。さらに、私自身は、京都議定書前後から国会議員時代も含めて、(馬鹿にされながら)一貫して再エネを増やすことを主張してきており、現在の結果は見えていたので、集団で悪乗りして誤った政策を進めた人たちが責任を負うのが当然である。 また、原発や化石燃料による集中発電が電力の安定供給に繋がるわけでないことは、*8-3の北海道地震で発生した大規模停電からも明らかだ。その後、酪農家や乳業メーカーに非常用自家発電機の導入を支援する地方自治体が出てきたのはよいが、その非常用自家発電機も風力・太陽光などの再エネ発電・蓄電設備・EV機器等を組み合わせたものではなく、化石燃料で動くため脱炭素に貢献しない。つまり、リスク管理は分散が原則で、災害がある度に先を見据えた一段上の装備をしながら復興するのが無駄のない復興予算の使い方なのである。 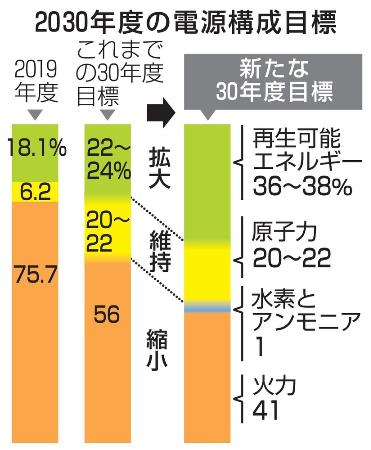 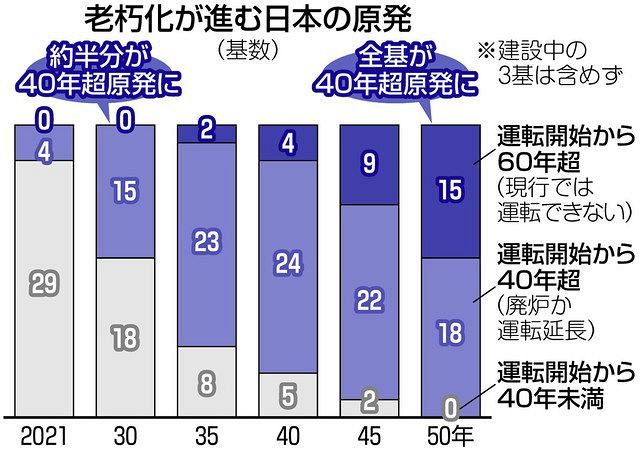 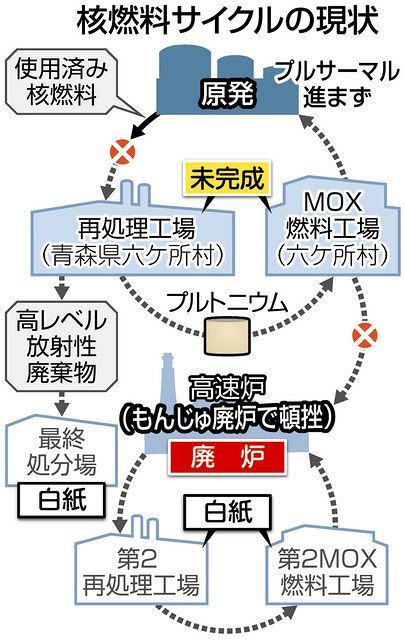 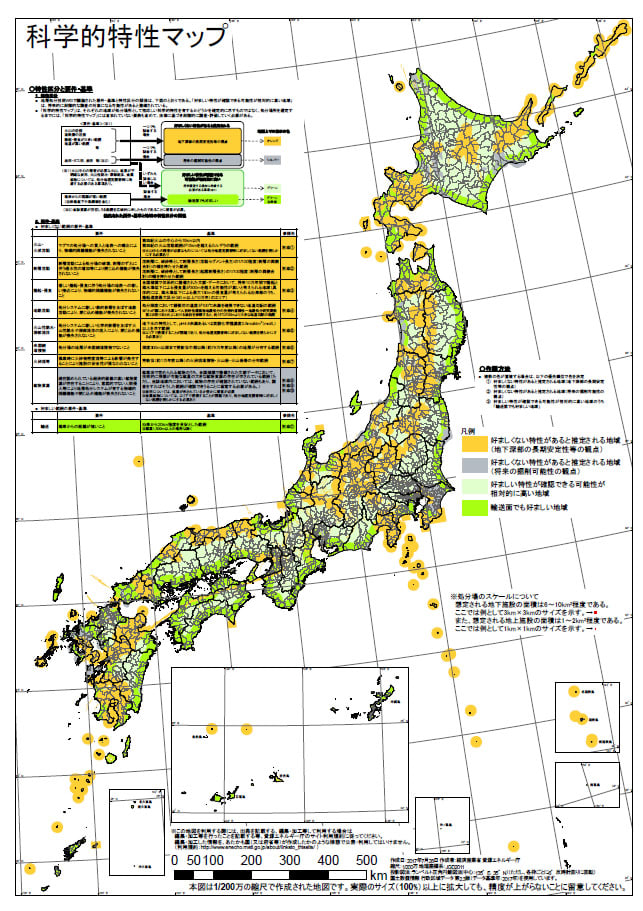 2021.10.22佐賀新聞 2021.10.20東京新聞 2017.11.14Goo (図の説明:1番左の図のように、日本は2030年でも火力発電を41%、原子力発電を20~22%も使う予定であり、その理由について「安価な安定電源だから」と嘘八百の説明をしている。そして、左から2番目の図のように、老朽原発の耐用年数を20年延長するなど原発建設当初よりも安全性に対して甘くしているのだ。さらに、右から2番目の図のように、核燃料サイクルは頓挫している上、1番右の図のように、最終処分場に適した地域も少ない) *8-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15118312.html?iref=comtop_Opinion_04 (朝日新聞社説 2021年11月21日) 核ごみ調査1年 計画への不信感直視を 原発の使用済み燃料から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分地をめぐる文献調査が北海道の寿都(すっつ)町と神恵内(かもえない)村で始まって1年がたった。国の計画では、文献調査は2年間の予定で、次には概要調査が控える。ただし、事業を進める経済産業省と原子力発電環境整備機構(NUMO)は、知事や町村長が反対すれば次の段階には進まないとしている。両自治体には、調査の進捗(しんちょく)や事業に関する情報を共有する「対話の場」がつくられたが、議論はまだ緒に就いたばかりだ。しかしながら、現地から早くも聞こえてくるのは調査をめぐる対立や分断である。たとえば寿都町では先月、調査への応募を決めた現職の町長と、反対を訴える新顔との間で、町を二分する選挙戦が繰り広げられた。両自治体に隣接する複数の自治体では、放射性物質を持ち込ませない「核抜き条例」が成立し、調査に伴う交付金も、道と周辺の多くの自治体が受け取りを辞退している。調査を容認すれば、計画は止まらないのではないかという不信感が根強くある。候補になりうる地域を示した「科学的特性マップ」を4年前に公表後、NUMOと経産省が全国各地で開く説明会は100回を超え、いまも続くが、両自治体に続くところはない。調査を含めた現行の計画が、地域で理解され、検討されるにはほど遠い状況にあることを、謙虚に受け止めなければならない。さらには破綻(はたん)した核燃料サイクルを前提とした計画そのものへの不信もあると見るべきだ。自民党総裁選では、河野太郎氏が核燃サイクルの見直しを掲げ、使用済み燃料を再処理せずに埋める「直接処分」に踏み込んだ。処分地建設で先行する北欧をはじめ海外でも直接処分が主流である。プルトニウムやウランを取り出す再処理をしなければ廃棄物の体積や有害度も変わるため、いまの計画は変更を迫られる。そもそもNUMOは原発の「環境整備」が目的の組織であり、最終処分地決定は原発運転継続の口実にもなりえ、際限なく廃棄物が持ち込まれるのではないかとの疑念もぬぐえない。岸田首相はコロナ対策で「最悪の事態を想定した危機管理」を唱える。そうであるなら、使い道のない大量のプルトニウムを抱え込むことになりかねない再処理や核燃サイクルの非現実性を直視したうえで、最終処分地について考える必要がある。 すでにある使用済み燃料をどう管理し、処分するのか――これは特定の地域ではなく、原発の恩恵を享受してきた国民全体で解決すべき問題である。 *8-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190512&ng=DGKKZO44689180R10C19A5EA5000 (日経新聞 2019年5月12日) 再生エネ機器 生産急減、風力9割縮小、太陽光は半分 中国勢、低価格で攻勢 再生可能エネルギー関連機器の国内生産が急減している。風力関連の生産額は2018年度に100億円台に落ち込み、9年間で9割減ったもようだ。太陽光も同年度の生産額がピークから半減した。日本企業は生産規模の拡大で出遅れ、欧米・中国勢の価格攻勢を受けている。政府は再生エネを成長産業と位置づけて国民負担も膨らんでいるが、国内生産の空洞化が止まらない状況になっている。日本産業機械工業会がまとめた17年度の風力発電関連機器の生産額は265億円と、16年度の3分の1となった。18年度は統計がある09年度と比べて9割超の落ち込みとなったもようだ。陸上に設置する風車では15年に三菱重工業が新規の製造をやめ、17年3月末には日本製鋼所が風力発電機の最終出荷を終了した。部品を手掛けるナブテスコや曙ブレーキ工業なども関連部品の生産を取りやめている。日本の風力市場はデンマークのヴェスタスや米ゼネラル・エレクトリック、独シーメンス系が席巻。三菱重工はヴェスタスと洋上風力の合弁会社を持つが、生産はデンマークなどで手掛ける。小型の風車では中国勢が攻勢をかけている。生産額が減少しているのは風力だけでない。光産業技術振興協会によると、太陽光パネルやパワーコンディショナー(電力変換装置)などの国内生産額は18年度に1兆7322億円となり、ピークだった14年度から半減した。特に太陽光パネル関連の生産額は13年度からの5年で約4分の1に減った。京セラは17年に伊勢工場(三重県伊勢市)で太陽光パネルの生産を中止。三菱電機は太陽光パネルの中核部材であるセルの生産を18年3月でやめた。パナソニックも18年に滋賀工場(大津市)を閉鎖し、マレーシア工場に移管した。だが今月9日にはそのマレーシア工場を中国企業に売却すると発表した。太陽光パネルではシャープが06年まで世界シェア首位で、風力発電機でも日立製作所や三菱重工が世界の大手に名を連ねていた。ただ市場拡大を見越して生産規模の拡大に走る欧米や中国勢に対し、日本勢は設備投資に二の足を踏み価格競争力が低下した。誤算だったのが12年に導入された再生エネの買い取り制度(FIT)だ。太陽光からつくる電力に高い価格がついたため、太陽光に投資が集中。環境影響評価に5年ほどかかる風力への投資は敬遠され、日本勢の撤退が相次いだ。投資が集中した太陽光も、国内製パネルでは国内需要をまかなえず、海外製パネルの流入を招いた。17年に京セラが国内シェア首位から転落し、中国や韓国企業が低価格で攻勢を掛けている。FIT費用の一部を電気代に上乗せする賦課金は18年度に2.4兆円に膨らみ、消費税1%分に相当する。家計などの国民負担によって発電事業者は利益をあげる一方、機器メーカーは生産を縮小し続けている。今後も国内生産の縮小傾向は続く見込みだ。制御機器大手のIDECは18年9月末で太陽光発電向けのパワコンから撤退。日立は19年1月に風力設備の自社生産から撤退すると発表し、国内の風力発電機メーカーは事実上なくなる。日立は6月には家庭向け太陽光のパワコン生産をやめる。英国や台湾には洋上風力の入札時に機器の自国・地域からの調達を重視して落札者を決めるなど、FITを産業振興に結びつける枠組みがある。米国やインドでは、割安な中国製太陽光パネルを念頭に18年から輸入品に対するセーフガード(緊急輸入制限)を発動し、25~30%の関税を課した。米国では米ファーストソーラーが18年12月期に最終黒字に転換し一定の成果があった。だがインドでは中国企業が東南アジアで生産したパネルの流入を招き、国内産業を育成できていない。産業振興で決定的な対策があるわけではない。日本では風力の発電能力が30年度までに現状の10倍程度に膨らむ見込み。外資に国内市場のハードを席巻されたなか日本勢には「エネルギー管理などシステムに力を入れ、海外勢と違いを出す」との声もある。国のエネルギー政策をにらみながら新たな収益分野を確保できるかが課題となる。 *8-3:https://www.agrinews.co.jp/p47585.html (日本農業新聞 2019年4月9日) 停電から生乳守れ 自家発電助成 各地で進む 昨年9月の北海道地震で発生した大規模停電を教訓に、酪農家や生乳を受け入れる乳業メーカー工場に対し、非常用自家発電機の導入を支援する地方自治体が出てきた。大規模停電時も生乳出荷が安定的にできるようにし、酪農家の経営安定につなげる。 ●関連装置費も 鳥取県 鳥取県は、2019年度予算で「酪農用非常電源緊急整備事業」として約3910万円を計上した。自家発電機導入には国が最大2分の1を補助するが、電気の安定供給に必要な配電盤などの装置は補助対象外。駆動にトラクターの動力取り出し軸(PTO)機能を活用する発電機は、トラクターとつなぐジョイントも必要だが、国の補助に含まれない。こうした関連装置について、4月1日以降に購入した場合、4分の1を助成する。県内の生乳生産、処理販売を担う大山乳業農協が4分の1を負担するため、酪農家の負担は実質半額になる。大山乳業農協の冷蔵貯乳タンク用非常電源整備についても、費用の12分の1を補助する。県は「災害はいつ起きるか分からない。早急に対策を進めてほしい」と助成の活用を呼び掛ける。 ●JAと一体で 北海道標茶町 北海道標茶町も19年度予算で、酪農家らの自家発電機導入を支援する。2400万円を計上し、1戸当たり最大20万円を助成する。これとは別に地元・JAしべちゃも昨年から独自支援を展開中で、JA、町が一体となって全農家約300戸での導入を目指す。JAの支援は自家発電機の導入に際し、1経営体当たり最大30万円を助成するというもの。希望者にはリースでも対応する。リース期間は5年と7年で、既に20経営体から受け付けた。JAの鈴木重充専務は「牛の健康を第一に国や町と一体で対応した。速やかな停電対策を進めたい」と意気込む。同町のコネクト牧場の坂井三智代表は「生産者も可能な限り災害に備えるが、生乳を受け入れる企業にも的確な対応をお願いしたい」と要望する。 <養殖の可能性> PS(2021年11月26日):*9-1のように、鮮度が高く環境負荷の低いサーモンを国内消費者に供給するため、静岡県に年間生産量5300tという国内最大級の陸上養殖施設を建設しているProximarに、JA三井リースが工場建設資金として25億円を融資したそうだ。また、海のない埼玉県でも、*9-2のように、魚を養殖する取り組みが広がっており、サバやウニの養殖に挑戦中とのことである。 なお、*9-3のように、ウニが海藻類を食べ尽くす磯焼けが深刻化しているという三陸沿岸で、夏の漁期に餌が減り実入りの悪いウニが多くなるので蓄養試験をしており、常に光を当てて人工的に育てた蓄養ウニが通年出荷に向けて期待を高めているそうだ。私は、餌の食べ残しがあって海水が富栄養化する養殖魚の生け簀の下に海藻を植え、そこでウニなどの海藻を食べる動物を飼えば、環境と経済が両立すると考える。  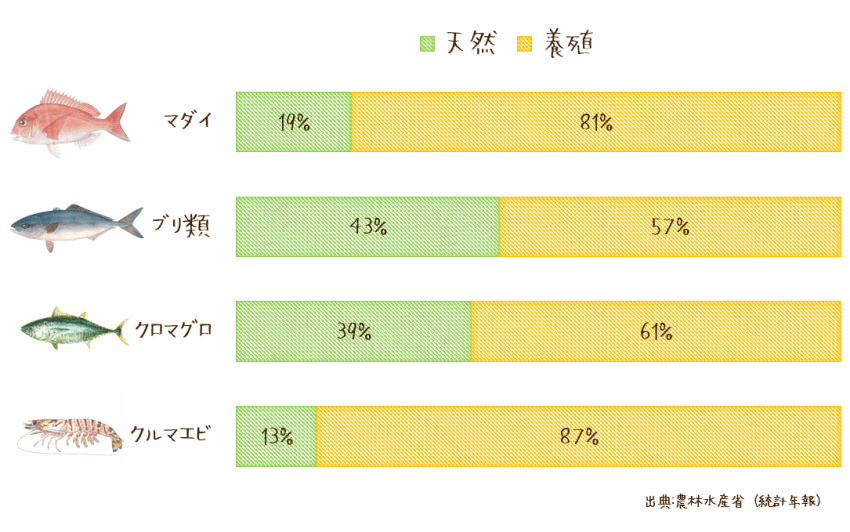 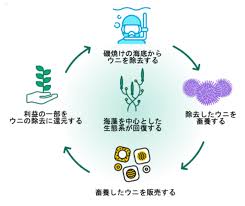 2015.1.5Daiamond 農林水産省 2021.3.30 PRTimes (図の説明:左図のように、完全養殖できる魚種が増え、全国各地で養殖され始めた。また、中央の図のように、50%以上が養殖魚という魚も増えている。なお、ウニが海藻を食べつくして磯焼けの原因になると書いている記事が多いが、右図のように、増えすぎたウニを蓄養しながら海藻を増やす方法もある) *9-1:https://www.jacom.or.jp/kinyu/news/2021/11/211117-55137.php (JAcom 2021年11月17日) 国内初アトランティックサーモン大規模陸上養殖事業者へ融資 JA三井リース [JA三井リースは11月17日、ノルウェー法人Proximar Seafood ASの100%子会社であるProximarに、工場建設資金として25億円を融資したことを発表した] Proximar Seafood ASは、世界有数のアトランティックサーモン養殖事業者Grieg Seafood ASAを傘下に持つノルウェーの企業グループGriegとの強固な関係を背景に、閉鎖循環型養殖システム「Recirculating Aquaculture System」(RAS)を活用したサーモンの陸上養殖事業を展開するため2015年に設立された。現在、同社の日本法人Proximarが静岡県小山町に年間生産量5300トンという国内最大級の陸上養殖施設を建設している。従来、日本で流通する生鮮アトランティックサーモンは主にノルウェーからの空輸に頼っているが、Proximarの陸上養殖で、より鮮度の高いアトランティックサーモンを国内消費者へ供給。さらにノルウェー・日本間の空輸により生じるCO2削減やRAS技術の活用による海洋環境への負荷ゼロなど環境課題にも貢献できる。JA三井リースグループは、農林水産業の持続的成長への貢献をサステナビリティ経営における重要な取組課題として位置付け、最適なフードバリューチェーンの構築に向けて国内外でソリューションを提供。このほど、Proximarが立ち上げた陸上養殖事業の将来性と社会的意義に着目し、工場建設資金の一部として25億円を融資した。 *9-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC250W50V21C21A1000000/ (日経新聞 2021年11月25日) 海なし県でサバやウニ 埼玉県内で養殖広がる 海なし県の埼玉県で魚を養殖する取り組みが広がっている。温浴施設を運営する温泉道場(埼玉県ときがわ町)が10月に神川町でサバの室内養殖場を開設したほか、久喜市の温泉施設は温泉を使ったウニの養殖に挑戦中だ。新鮮な水産物を施設で楽しんでもらい、新型コロナウイルス禍で落ち込んだ集客力の回復や、新たな特産品を目指す。温泉道場の温浴施設「おふろcafe白寿の湯」(神川町)に県内初となるサバの陸上養殖場が誕生した。養殖場の広さは約200平方メートルで、3基の水槽やろ過設備を設置した。サバ養殖を手掛けるフィッシュ・バイオテック(大阪府豊中市)から生育方法などの助言を受けながら1年半ほどかけて稚魚から育てる見込み。今後成長したサバは温浴施設にあるレストランで提供したい考えだ。海で育ったサバは生食することが難しいとされるが、施設内で養殖されたサバは生で食べられるのが特徴だ。建物内で水をろ過して循環させる完全閉鎖型の施設のため、寄生虫のアニサキスの心配がないという。養殖場の見学会なども実施して、地域の盛り上げ役の一翼を担う。温泉道場の山崎寿樹社長は「ここからがスタート。海なし県埼玉で新鮮な魚を食べてもらいたい」と話す。神川町の山崎正弘町長も「将来にわたって希望のある取り組み。地域産業の活性化につながると期待している」と歓迎する。温泉を使ってウニの養殖を目指すのは久喜市で「森のせせらぎ なごみ」を運営する山竹(同市)だ。地下約1500メートルからくみ上げた塩分濃度6%の温泉を使用し、研究を重ねる。ウニは雑食性のため、沿岸部でウニが周辺漁場で海藻類を食べ尽くす「磯焼け」が課題となり、駆除に取り組む地域もある。同社はそうした地域で駆除されたウニを利活用し、5月から飼育を始めた。現在はエサとしてワカメを与えているが、今後は地元で生産され余った野菜をエサとして与えることで「フードロスの削減にもつなげられたら」(山中大吾専務)と話す。コロナ禍で来店客数が減り、施設内のレストランの需要も大きく落ち込んだ。養殖したウニを使った料理を提供して、集客力の回復に役立てたい考えだ。ただ、屋内施設での養殖は一筋縄では行かない。行田市内の温泉施設は、駐車場の一部スペースを活用してふぐの屋内養殖を手掛けていたが、採算面や養殖の難しさから昨年養殖をやめたという。海なし県の新たな特産品として地元住民らに親しんでもらえるようになるか。各事業者の挑戦はこれからが正念場だ。 *9-3:https://kahoku.news/articles/20210910khn000018.html (河北新報 2021年9月10日) 実がたっぷり「蓄養ウニ」初水揚げ 通年出荷への期待高まる 岩手県大船渡市三陸町綾里地区で、常に光を当てて人工的に育てた蓄養ウニが9日、初水揚げされた。天然ウニならば既に漁期が過ぎているが、蓄養は実入りが良く、関係者は「上々の成果」と顔をほころばせた。出荷時季が限定されてきたウニの通年出荷に向け、期待を高めた。ダイバー2人が蓄養池に入り、約1000個、100キロのキタムラサキウニを拾い集めた。蓄養試験を手掛ける岩手県の担当者によると、可食部の生殖腺の重さは16・2グラムで、盛漁期の天然ウニと同程度の量となった。蓄養を始めた6月時点は6・8グラムだった。通常、ウニの漁期は8月初めまでで、お盆を過ぎると産卵期を迎えて品質が悪くなる。蓄養池では夜間、発光ダイオード(LED)照明を点灯。ウニに季節の変化を感じさせず、産卵期前の状態を保つことができたという。餌はコンブやワカメを与えた。県大船渡水産振興センターの山野目健上席水産業普及指導員(56)は「光の効果を屋外で実証できたのは画期的。天然物が出回らない端境期にも出荷できるようになる」と成果を強調した。10月以降も条件を変えて試験を続ける。三陸沿岸では近年、海水温の上昇で冬場にウニが海藻類を食べ尽くす磯焼けが深刻化。夏の漁期には餌が減り、実入りの悪いウニばかりになるという悪循環が続く。蓄養試験は磯焼け対策や生産者の所得向上を目指し、県が県内4カ所で行っている。大船渡では綾里漁協の協力を得た。残りのウニは17日に取る予定。今回の水揚げ分を含め全ては市内の「道の駅さんりく」の運営会社に出荷され、同駅で販売される。[蓄養]価格の安定や出荷調整を目的に、天然の魚類や甲殻類、貝類などをいけすなどで育て、短期間で大きくしたり太らせたりする飼育方法。
| 経済・雇用::2021.4~2023.2 | 12:17 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2021,09,02, Thursday
(1)アフガニスタンについて
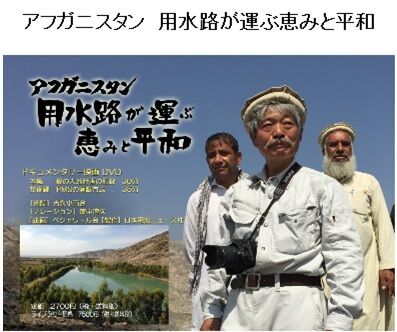    (図の説明:1番左の図のように、中村医師はアフガニスタンに2003年から用水路を建設し、用水路が完成した地域には、左から2番目の図のように緑地が広がっている。現在は、右から2番目の図のように、太陽光発電所と羊牧場を併設したり、1番右の図のように、砂漠に風力発電機を設置して動力を得たりすることもできる) 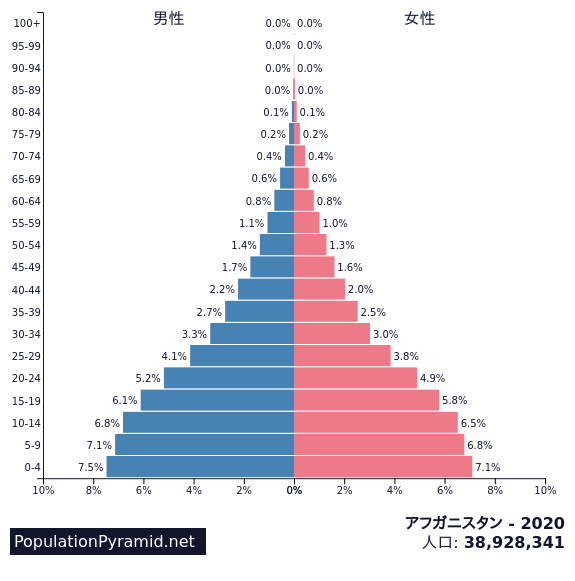 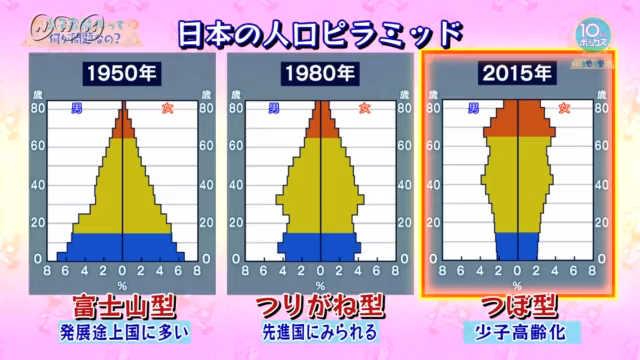 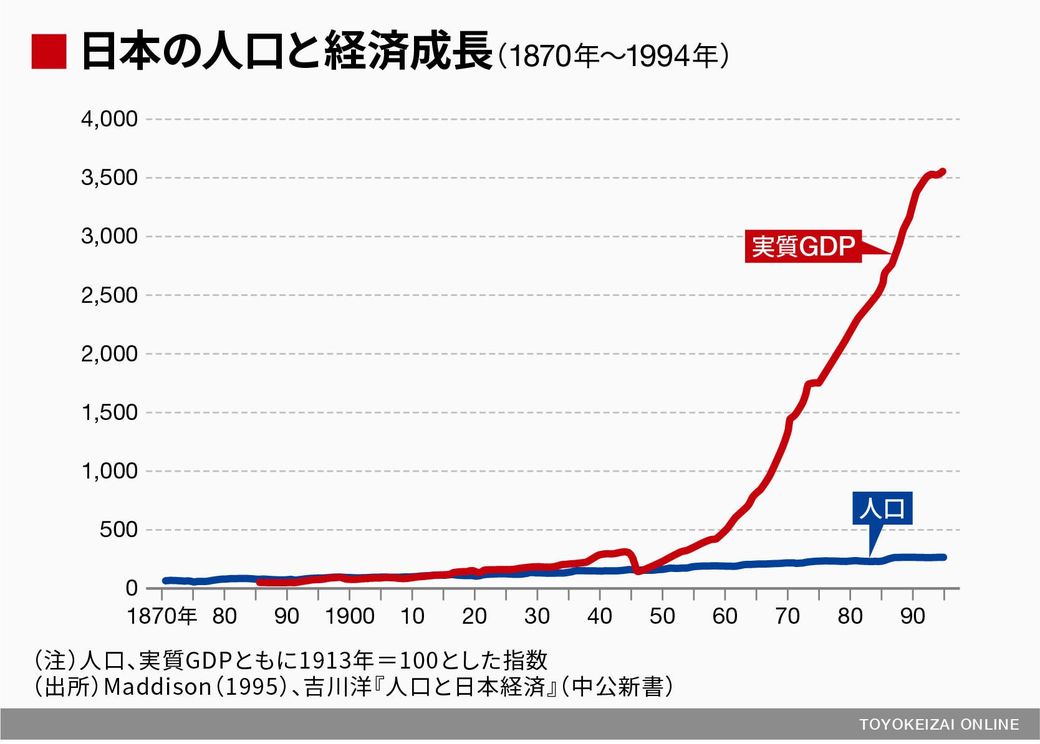 アフガンの人口ピラミッド 日本の人口ピラミッド 2018.6.4東洋経済 (図の説明:左図のように、アフガニスタンの人口ピラミッドは富士山型に近く、栄養状態が悪くて医療も普及していないため乳児死亡率が高いことを示す。これは、中央の図の日本の1950年以前《主に戦前》の状態に近いが、日本では、右図のように、戦後、急速に実質GDPが伸び、それにつれて栄養状態が改善し、教育や医療が普及して、一人一人の生産性が前より上がって豊かになり、人口ピラミッドがつりがね型からつぼ型へと変化した。つまり、多産と経済成長は正の相関関係がないだけでなく、教育を通して負の相関関係がありそうなのである) 1)米軍のアフガニスタン駐留終了が人権に与える影響 バイデン米大統領は、*1-1-1のように、「20年間にわたる米軍のアフガニスタン駐留が終了した」と明らかにし、12万3000人の米国人及び米国に協力したアフガン人の国外退避をだいたい終えた後、掃討をめざしていたイスラム主義組織タリバンが復権した。 が、未だ100~200人の米国人が出国できずに残っており、タリバンが求める経済支援と引き換えに自由かつ安全な移動に関する合意を履行するよう求めており、タリバンの報道官の方は米軍撤収について「私たちの国は完全な独立を手に入れた」とツイッターに投稿したそうだ。 *1-1-2は、①タリバンの統治を恐れて空港周辺に出国を望む市民数千人が殺到して死者が出た ②アフガン在住の各国国民や協力したアフガン人の国外退避は緊急を要する最優先事項 ③タリバンは国外退避を望むアフガン人に対し、新たな国造りに必要な人材として空港到着を阻んでいる ④在アフガニスタン米大使館員らは7月13日付の極秘公電で駐留米軍が8月31日に撤退すれば、直後にガニ政権や政府軍は崩壊する恐れがあると警告していた ⑤警告にもかかわらず、米政府はガニ政権とタリバンとの戦闘見通しを誤った と記載している。 また、*1-1-2は、⑥日米欧のG7は8月24日に緊急首脳会議を開いて、退避支援に全力を挙げること・人道危機回避への貢献・女性の権利擁護・テロ対策での緊密な連携を確認 ⑦日本政府は出国を求める人に各自で空港までの移動手段を確保するよう求めたが、市民に自己責任で移動を求めるのは無責任 ⑧日本政府はタリバンと交渉し安全地帯を確保して迎えに行くなどの安全で確実な方法を示すべき ⑨米軍撤退の教訓は、中央アジアの覇権争いを繰り返さず、故中村哲医師が実践したような取り組みで国を再生させること とも記載している。 さらに、*1-1-3は、⑩タリバンは、8月17日に首都カブールで開いた記者会見でザビフラ・ムジャヒド報道官が初めて姿を見せて国際テロ組織を国内から排除する方針を明らかにし ⑪報道官は「外国組織が他国に危害を与えるために国土を使うことを許さない」とも強調し ⑫資金源であるケシ栽培は「金輪際関わらない。そのためにも国際社会の援助が必要」と訴え ⑬ジェイク・サリバン米国家安全保障担当大統領補佐官は、8月17日の記者会見で「タリバンがどのような行動を世界に示すか次第。(政権承認の是非を)判断するのは時期尚早だ」と答え、女性の権利を守らせるために同盟国と連携してタリバンに圧力をかける と記載している。 このうち①は悲惨で、酷い刑がしばしば行われる国では②が不可欠だ。また、③は、タリバンの支配層が新たな国造り要員としてアフガン人の出国をの望まなかったとしても、その意味するところを文字の読めない末端まで理解できるとは限らず、自由な思想を持つリーダーの方がいつ殺されて失脚するかわからないため、残された人はやはり危険である。これは、日本の明治維新から第二次世界大戦以前と同じような状況だ。 従って、④⑤⑥については、⑤の警告に基づいて必要なことを終わらせた後で撤退すれば、①②は起こらず、何とか合格点だったただろう。しかし、日本の⑦も、市民に無理を強いている。⑧は、日本大使館を再開して安全地帯とし、ビザを発行して国外退避したい人をアフガニスタン国外に移送し、その後、日本に空輸するしかないと思われる。 それを可能にするには、⑨や*1-3に書かれている中村医師の実績と今後の日本の援助方針が効くだろう。中村医師は、アフガンを干ばつが襲って農地が砂漠化するのを見て、病気の背景には食料不足と栄養失調があると考え、「100の診療所より、1本の用水路を」と2003年からアフガン東部で用水路建設に着手した。 この用水路は、これまで約27kmが開通し、1万6,500haを潤して砂漠に緑地を回復させ、農民65万人の暮らしを支えている。中村哲医師の灌漑は、現地の人が維持・管理できるように江戸時代に築かれ今も使われている福岡県朝倉市の山田堰をモデルとし、護岸はコンクリートではなく鉄線で編んだ「蛇籠」に石を詰めて積み、そこに根を張る柳を植えて補強したもので、その防風・防砂林の植樹総数は100万本を超えて、工事に携わった人たちは現場で技術を習得して熟練工となり、中村さんは近年、国連機関やJICAとも連携してノウハウをアフガン全土に広めようとしていたのだそうだ。 農林業の技術移転によってアフガン全土に実りの豊かさをもたらすことは、戦争に割く人員を減らして穏やかに暮らすために不可欠な条件だと思われるため、適切な作物を選んで必要な工事を行い、今後の技術支援の軸にすべきだろう。 2)イスラム圏で女性の人権と自由をどう守るか タリバン執行部は、*1-2-1のように、「イスラム法の範囲内で女性の権利を尊重する」と主張しているが、旧タリバン政権下で女性を抑圧した過去があるため、国際社会は女性の人権が守られるのか強い懸念を抱いている。 そもそも、「『イスラム法の範囲内』で尊重される女性の権利」は、女性を1人の人間として男性と差別なく人権・自由を保障するものではなく、アフガン国内の女性が変えることはできない性格のものである。その例として、カブールで美容院の女性の肖像がスプレーで汚されていたり、女性が夫以外の男性の前で着飾ることや目以外の部位を露出することを認めなかったり、女性を拉致したり、女性を職場から追い出したりする事例は枚挙に暇がない。 アフガンで低迷する女性の識字率や社会進出の課題を告発し続けてきた女性記者エストライ・カリミさんは、「西部ヘラート州で、夫が運転する車で取材先に向かっていたところ、銃声が響き、戦闘員に取り囲まれて夫婦で拉致され、モスクの脇にあるタリバンの施設で『運転席の男は誰だ。女が夫や兄弟の同伴なしで出歩けると思っているのか』と尋問され、憤激するタリバン幹部に夫だと説明すると、勤務先や住所も確認され、約1時間後にモスクの宗教指導者がタリバン幹部をなだめて解放された」のだそうだ。 また、タリバン傘下に入った国営テレビ局「RTA」では、画面から女性キャスターの姿が消え、その一人のシャブナム・ダウランさんがSNSに投稿したビデオ声明で「タリバンから『帰れ』『政権が変わったんだ』と追い返された」と訴えた。 さらに、ロイター通信によると、南部カンダハルでは7月にタリバンが銀行を訪れ、女性職員9人に出勤停止を命じ、カンダハルの女子校に勤める女性教員は「学校は閉鎖したままで生徒が心配。たとえ授業が再開しても、科目は宗教に偏るでしょう。進学を志す女子がまた減ってしまう」と憤っているそうだ。 タリバンは政権に就いていた1996~2001年、極端なイスラム教解釈で女性の通学や就労を妨げ、服装を強要して国際的な批判を浴び、今後も女性の行動に一定の縛りをかける恐れが強いため、カブールではタリバンの権力掌握を受け、全身をすっぽり覆う衣装「ブルカ」を買い求める女性が店に殺到したのだそうだ。 アフガンでタリバンが猛攻を続けていた頃から、*1-2-2のように、海外留学中のアフガン人学生からは「また教育が奪われる」と懸念の声が上がっていた。アフガンで裁判官になるのが目標で、3年前に激しい競争の中でアズハル大の奨学金を勝ち取って単身でカイロに来た7人兄妹の長女は、教育を禁じるタリバンが国を支配すれば、「女性で単身留学している私は標的になる。帰国すれば命を狙われる」と話し、医者を目指していた妹は「もう諦めた。ここから逃げたい」と毎日泣いているそうだ。 タリバンが制圧した州都では、教育機関や政府施設が破壊され、一部では女性に体や顔を覆う衣装「ブルカ」の強要も始まったそうで、これらからわかるように、イスラムの女性が「ブルカ」を着たり、教育を受けなかったり、識字率が低かったりするのは、その文化を自ら望んでいるからではなく、支配者に強要されるからなのである。 3)今後の対応について アフガンの状況は、日本の第二次世界大戦前後の状況や女性の地位に似ている。これらを同時に解決するには、日本国憲法に近い徹底した民主主義憲法を導入し、男女平等の民法を制定し、女子差別撤廃条約に調印させ、男女雇用機会均等法や男女共同参画基本法を成立させなければならない。 外圧でそれらを行わなければ、アフガン内部のリーダーは、自由で人権を尊重する人ほど殺されて早く失脚するのである。そのため、私は、*1-3のような経済支援や日本企業の進出を、民主主義に基づく新憲法の導入等を条件として行うべきだと思う。そして、女性を教育して男女共同参画させることは、実は、産業や経済の発展にも大きく寄与するのだ。 (2)日本では、豪雨で繰り返す内水氾濫・外水氾濫 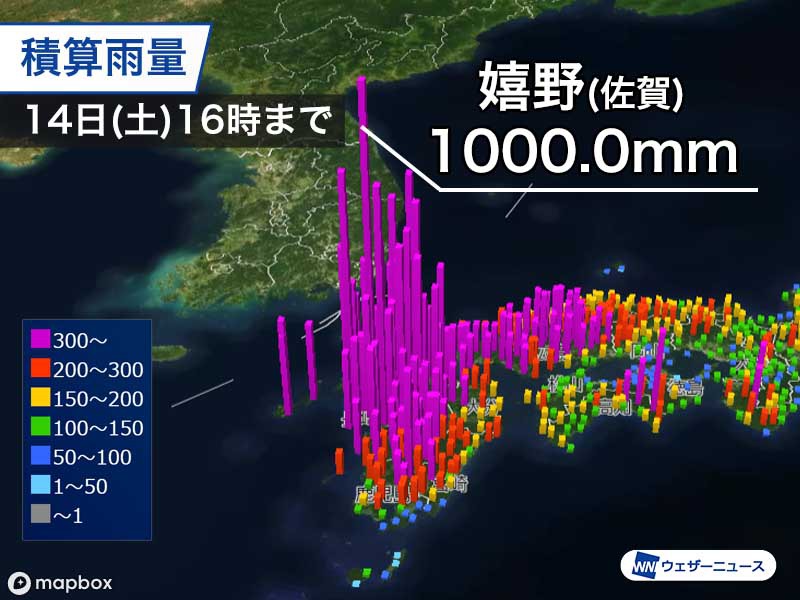 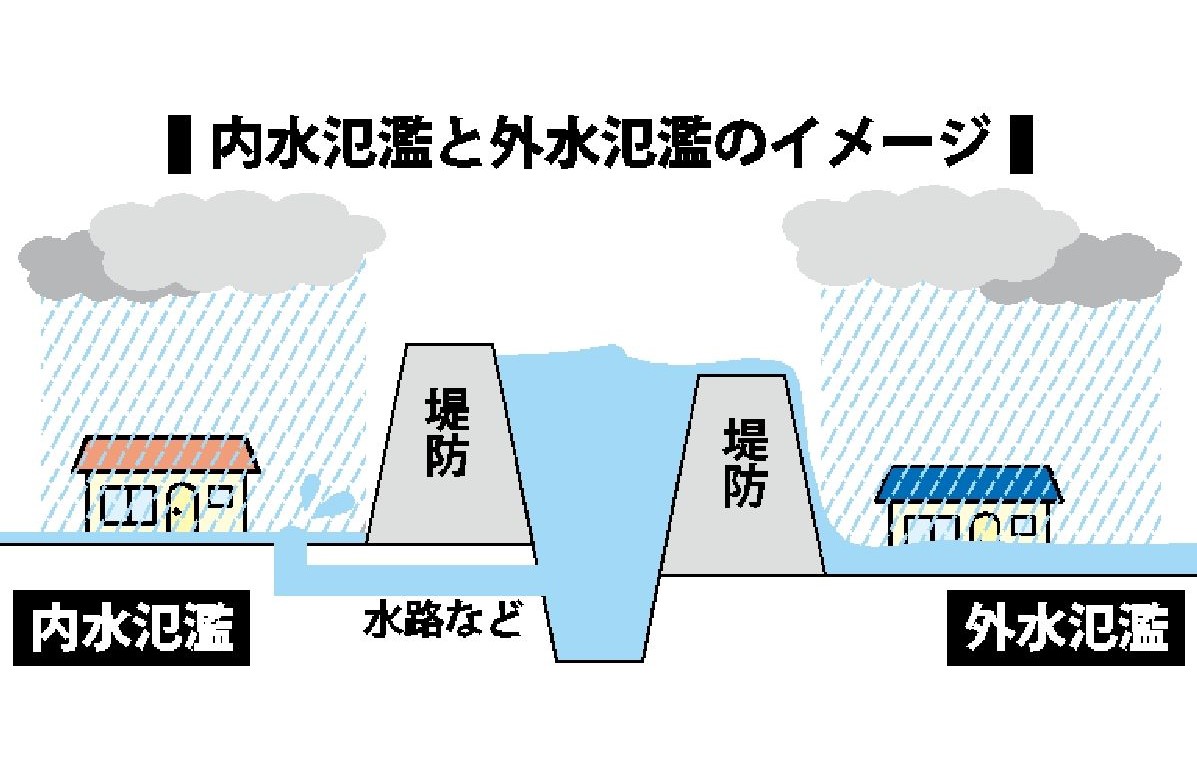 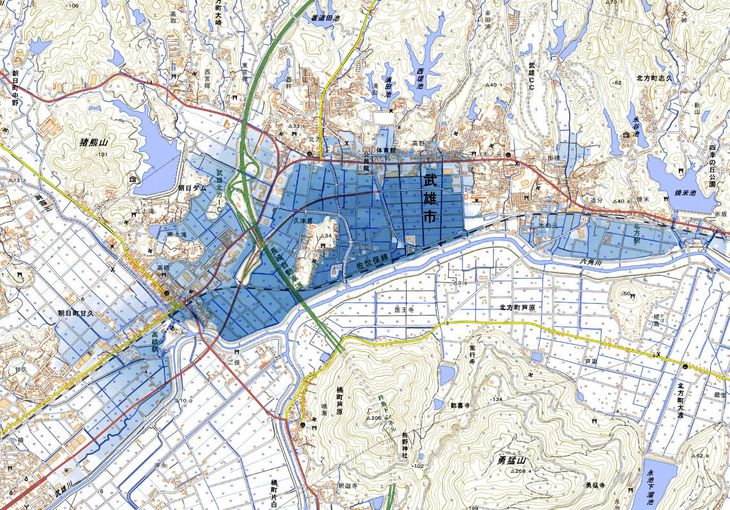 Weathe News 2019.8.29佐賀新聞 2021.8.14産経新聞 (図の説明:今夏は、左図のように、佐賀県《特に嬉野市》で1,000mmを超える雨が降り、低い土地にある市や町で、中央の図のような内水氾濫が起こった。そのうち武雄市や大町町は、2019年にも同じ場所で内水氾濫が起こっており、右図のように、洪水が予想される地域である)     2021.8.14日本TV 2021.8.16佐賀TV 2021.8.14朝日新聞 2021.9.1 順天堂病院 佐賀新聞 (図の説明:1番左の図のように、豪雨時の六角川本流の水面は住宅地の屋根より高く、一部で外水氾濫を起こしたと同時に広い範囲で内水氾濫を起こした。その結果、左から2番目の図のように、武雄市では住宅地が一時は3mも水に浸かった。また、右から2番目の図のように、大町町の順天堂病院も1年おきに1階が水没しており、せっかく病院を誘致できたのに残念なことだ。さらに、1番右の図のように、激甚災害の指定を受けて国庫補助率が上がったのはよかったが、かさ上げしなければならないのは補助率だけではなく住宅地そのものであるため、復旧にしか使えないのは使い勝手が悪い) 1)2021年8月の浸水被害 8月11日から降り続いた豪雨で九州北部の佐賀県武雄市・福岡県久留米市は、*2-1のように、水路や下水道の排水が追い付かず、雨水が地表にあふれる「内水氾濫」が起きて住宅浸水や道路の冠水が相次いだ。武雄市内では支流の内水氾濫に加えて六角川本流も一部で外水氾濫し、東部を中心に住宅地などが濁った水で覆われた。また、武雄市と隣接する大町町の順天堂病院も周囲を泥水で囲まれ、2019年と同様に孤立状態となった。 久留米市では、8月14日午前までの24時間降水量が観測史上最大の387mmとなり、筑後川支流で内水氾濫が起きて4年連続で市街地と田園地帯が水に漬かった。久留米市によると、支流は本流からの逆流を防ぐため合流点の水門を閉鎖し、水は本流にポンプで送るが、処理できなくなった雨水が広域であふれ、ポンプを増やしたり、堤防のかさ上げに取り組んだりしたが、圧倒的な雨量に及ばなかったそうだ。 佐賀県武雄市の被害概要について、*2-2のように、浸水の深さ・内水氾濫の面積・家屋被害数等が、2019年8月に県を襲った記録的大雨より深刻で、2年前の8月は降雨期間が3日間だったが、今夏は7日間(11~17日)続き、総雨量も最大約1,300mm(2年前は最大約500mm)で、六角川の排水ポンプが3回合計8時間50分(前回は1回合計3時間10分)停止し、家屋への浸水被害は2021年8月25日現在で床上1,273棟・床下390棟の計1,663棟(前回は1,536棟)、通行止めは約90カ所(前回は63カ所)、浸水の深さや内水氾濫の面積は2年前より大きく、地滑りの兆候も今回は3カ所で確認されたそうだ。 武雄市は、2年前と比べて内水氾濫が広がった理由を長時間の降雨と六角川の水位上昇に伴って排水ポンプの停止時間が長引いたことなどが影響したとみており、市長は「国交省には内水氾濫対策に目を向けてほしい」とし、ポンプ機能を維持する方策を専門家や国交省の河川事務所と早急に協議する意向を示しているそうだ。 2)国からの支援としての激甚災害の指定とこれから行うべきことについて 佐賀県武雄市や大町町で「内水氾濫」がよく起こる理由は、海抜0m地帯で、有明海に注ぐ六角川の勾配が緩く、満潮時は有明海の海水が上流約29kmまで遡り、広範囲で住宅地が川面より低くなり、雨水が下水道等から溢れることによるそうだ。つまり、標高が低いため自然排水が難しく、もともと浸水リスクの高いこの地域は、上の段の右図のように、洪水予想地域として地図上に記載されているのである。 これに対し、国交省は、六角川と牛津川流域の60カ所以上にポンプを設置し、住宅地に降った雨水を河川に排水しているが、大雨で河川の水位が上昇するとポンプの運転を停止せざるを得なくなり、ポンプによる排水が追いつかなくなる。これは、気候変動によって海面の高さが上昇し、豪雨も激しくなれば、ますます被害を大きくするものである。 確かに、下の段の1番左の図のように、豪雨時の六角川本流の水面は住宅地の屋根より高く、一部で外水氾濫を起こしたと同時に広い範囲で内水氾濫を起こしている。そのため、下の段の左から2番目の図のように、武雄市では住宅地が3mも水に浸かり、大町町の順天堂病院も、右から2番目の図のように、1年おきに1階が水没しているのだ。 これらの被害について、*2-3のように、今回も激甚災害の指定を受けることができ、国庫補助率が上がったのは不幸中の幸いだったが、広範囲に降る自然の豪雨を人工のポンプで排水すること自体に無理があるため、住宅地は土地を交換して高台に移転し、低地でもいつも川の水面上になるようかさ上げして田畑にするのが、今後の被害を免れる唯一の方法だと考える。 私が衆議院議員をしていた2005~2009年の間にも浸水被害があったため、地元の人に「土地のかさ上げか、高台への移転ができないのか」を聞いたところ、「①かさ上げする土がない」「②浚渫していないため、ダムや川の底に土が溜まって浅くなっている」「③それをする人手がない」「④個人の住宅に補助を出すことはできない」などのできない理由ばかりが返ってきた。 しかし、②の浚渫を行えば①の土も出るため、③は外国人労働者を雇用してでもやった方がよいだろう。また、このように頻繁に浸水するのなら、④の個人住宅や病院もかさ上げするか、高台に移転する方法を考えた方が、費用と時間をかけて行う復旧を「賽の河原の石積み」にせずに済むと思うわけである。 ・・参考資料・・ <アフガニスタン> *1-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210831&ng=DGKKZO75292470R30C21A8MM0000 (日経新聞 2021.8.31) 米軍、アフガン撤収完了、米最長の20年戦争終結、米国人ら12万人退避 バイデン米大統領は30日の声明で「20年間にわたる米軍のアフガニスタン駐留が終了した」と明らかにした。掃討をめざしたイスラム主義組織タリバンが復権し、米史上最長の戦争は敗走に近い形で幕を閉じた。国際テロ組織がアフガンを拠点に米国本土を再び攻撃するリスクは消えていない。バイデン氏は声明で、アフガンの首都カブールの空港で米国人やアフガン人の国外退避を支援した米兵に対し「米史上最大の空輸任務を実行した」と謝意を示した。米東部時間31日午後1時30分(日本時間9月1日午前2時30分)にアフガン戦争の終結について国民向け演説を行う。米軍がアフガンの国外に退避させたり退避を支援したりした米国人やアフガン人などの数は12万3000人に上る。ブリンケン国務長官は30日の演説で「米国の軍事面での戦いは終わった。米国のアフガンに対する新しい関与のチャプターが始まる」と強調した。米国の在アフガン大使館を閉鎖し、カタールの首都ドーハでタリバンとの対話を進めていく。アフガンでは100~200人の米国人が出国できずに残っていると明らかにした。アフガン戦争で米国に協力したアフガン人について「期限を設けずに彼らとの約束を守る」と断言。退避を望む米国人と並んで退避支援を続けるとした。タリバンに対して自由かつ安全な移動に関する合意を履行するよう改めて求めた。タリバンが求める経済支援などを念頭に「我々の対応は言葉ではなく行動に基づいて決まる」と指摘し、米国との協力を促した。一方、タリバン報道官は米軍撤収について「私たちの国は完全な独立を手に入れた」とツイッターに投稿。タリバンがカブールを制圧して以降、「恐怖政治」が復活するリスクが浮上している。バイデン氏は4月、約2500人のアフガン駐留部隊を撤収させると表明した。部隊を5800人規模に増やし、米国人に加えてアフガン戦争で米国に協力したアフガン人の国外退避を8月末まで進めると説明してきた。欧州や日本も自国民らを退避させた。泥沼の戦争を批判的にみる世論に配慮し、バイデン氏はアフガン撤収を貫いた。2001年の開戦直後はテロとの戦いを米国民の大半が支持したが、巨額の戦費や米兵の犠牲を伴う戦争に一般国民は恩恵を感じず熱気は冷めていった。バイデン氏が副大統領を務めたオバマ政権は16年末までの撤収を目指したが、治安悪化を受けて断念していた。タリバン復権でアフガン民主化の取り組みは失敗に終わった。アフガン戦争を通じて根付きつつあった女性の権利や報道の自由が後退する可能性が高まる。バイデン氏は軍事力を通じて「国家建設に関与しない」と繰り返し主張しているが、民主主義や人権を重視する外交方針に逆行する。 *1-1-2:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1381635.html (琉球新報社説 2021年8月26日) タリバン復権と混乱 国外退避に全力尽くせ アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンが首都カブールを制圧し、ガニ政権の崩壊から10日が過ぎた。空港周辺にはタリバンの統治を恐れ出国を望む市民数千人が連日殺到し、死者が出るなど混乱が続いている。ベトナム戦争末期に、米大使館からヘリコプターによる脱出を迫られたサイゴンの混乱を彷彿(ほうふつ)とさせる事態だ。アフガン在住の各国の国民や通訳などで協力したアフガン人の安全な国外退避は緊急を要する最優先事項である。各国は結束して退避支援に全力を挙げてもらいたい。バイデン大統領は8月に設定した米軍の撤退期限を維持する考えを強調したが、見通しが甘いのではないか。米メディアによると、タリバンは国外退避を望むアフガン人に対し、新たな国造りに必要な人材だとして空港到着を阻んでいるという。撤退期限の順守ではなく、人命を守ることを最優先させるべきだ。混乱の原因は米国にある。米史上最長の戦争の最終段階で「出口戦略」を誤った。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、在アフガニスタン米大使館員らが7月13日付の極秘公電で、駐留米軍が8月31日に撤退すれば直後にガニ政権や政府軍が崩壊する恐れがあると警告していたと報じた。米軍に協力したアフガン人らの退避手続きを急ぐようブリンケン国務長官らに求めていたという。警告されたにもかかわらず米政府は、ガニ政権とタリバンとの戦闘の見通しを誤った。タリバンによる侵攻が想定外の早さで進み、政府崩壊は予期できなかったというのは言い訳にすぎない。日米欧の先進7カ国(G7)は24日、アフガニスタン情勢を巡る緊急首脳会議を開き、退避支援に全力を挙げ、人道危機回避への貢献や女性の権利擁護、テロ対策で緊密に連携することを確認した。ここは国際社会の結束が求められる局面だ。一方、邦人と日本の協力者を退避させるため日本政府は自衛隊機を現地に派遣した。政府は出国を求める人に対し各自で空港までの移動手段を確保するよう求めている。だがタリバン戦闘員が空港に続く道路に検問所を設け、外国人を一時的に拘束する事態も出ている。丸腰の市民に自己責任で移動を求めるのは無責任である。日本政府はタリバンと交渉して安全地帯を確保して迎えに行くなど、安全で確実な方法を示すべきだ。タリバン政権は2001年、米中枢同時テロを起こしたアルカイダ指導者ビンラディン容疑者の引き渡しを拒んだため、米英軍の攻撃によって崩壊した。米軍はその後20年間、アフガニスタンに駐留したが、国家建設に失敗した。米軍撤退の教訓は何か。中央アジアの覇権争いを繰り返すのではなく、凶弾に倒れた故中村哲医師が実践した持続可能な取り組みによって国を再生させることではないか。 *1-1-3:https://www.yomiuri.co.jp/world/20210818-OYT1T50258/ (読売新聞 2021/8/19) アフガン制圧したタリバン、「国際テロ組織の排除」強調…政府承認取り付ける狙いか アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバンは17日に首都カブールで開いた記者会見で、国際テロ組織を国内から排除する方針を明らかにした。テロの温床になりかねないとする国際社会の懸念を 払拭ふっしょく し、「政府承認」を取り付ける狙いがある。会見には、正体不明だったザビフラ・ムジャヒド報道官が初めて姿を見せた。タリバンは2001年、米同時テロを起こした国際テロ組織「アル・カーイダ」の指導者をかくまい、政権崩壊を招いた。報道官は「外国組織が他国に危害を与えるために国土を使うことを許さない」と強調した。資金源である麻薬原料のケシ栽培についても「金輪際関わらない。そのためにも、国際社会の援助が必要だ」と訴えた。17日には、ナンバー2のアブドル・ガニ・バラダル師がカタールから帰国した。米国とのパイプを持つ穏健派として知られ、「バラダル師を大統領に据え、国際社会との関係構築を進めるのでは」(地元記者)との観測も出ている。ただ、18日にはタリバンの一派で、パキスタンとの国境付近を拠点とする「ハッカニ・ネットワーク」幹部もカブール入りし、タリバン幹部らと協議を行った。ハッカニ一派は各国でテロを引き起こし、米国がテロ組織に指定している。「アル・カーイダ」系のイスラム過激派組織「アル・シャバブ」など各国の武装勢力もタリバンに「祝意」を送っており、タリバンがテロ組織と関係を断絶できるかは不透明だ。一方、米ホワイトハウスは17日、アフガニスタン情勢に関する先進7か国(G7)首脳会議が、来週中にオンライン形式で開催されると発表した。バイデン大統領が、G7議長国を務めるジョンソン英首相との電話会談で合意した。タリバンが主導する新政権の承認などが議題となる見通しだ。ジェイク・サリバン米国家安全保障担当大統領補佐官は17日の記者会見で、タリバンの融和姿勢について、「タリバンがどのような行動を世界に示すか次第だ。(政権承認の是非を)判断するのは時期尚早だ」と答えた。女性の権利を守らせるため、同盟国と連携してタリバンに圧力をかける考えも明らかにした。 *1-2-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15017957.html (朝日新聞 2021年8月22日) アフガン、息潜める女性 政権崩壊1週間 カブールで18日、美容院の女性の肖像がスプレーで汚されていた。その前を歩くタリバンの戦闘員=AFP時事。タリバン強硬派は、女性が夫以外の男性の前で着飾ることや、目以外の部位を露出することを認めていない。アフガニスタンでイスラム主義勢力タリバンが権力を掌握し、ガニ政権が崩壊してから22日で1週間となる。タリバン執行部は「イスラム法の範囲内で女性の権利を尊重する」と主張しているが、旧タリバン政権下で女性を抑圧した過去があり、国際社会は女性の人権が守られるのか強い懸念を抱いている。女性が拉致されたり、職場から追い出されたりする事例は後を絶たない。社会は圧制の時代に逆戻りしてしまうのか。 ■タリバン、取材に向かう記者拉致 キャスターや銀行員、職場追われ 「州都を包囲するタリバンの戦闘部隊に見つかり、銃撃された。記者人生で最も死に近づいた瞬間でした」。地元メディア「パジュワク・アフガン通信」の女性記者エストライ・カリミさん(38)は、朝日新聞の取材に応じ、証言した。西部ヘラート州で今月2日、夫が運転する車で取材先に向かっていた。銃声が響き、とっさに顔をうずめた。耳元でサイドミラーが「カン! カン!」と弾をはじいた。戦闘員に取り囲まれ、夫婦は拉致された。カリミさんはモスクの脇にあるタリバンの施設で尋問された。「運転席の男は誰だ。女が夫や兄弟の同伴なしで出歩けると思っているのか」と憤激するタリバン幹部に、夫だと説明した。勤務先や住所も確認された。尋問が約1時間続いた後、モスクの宗教指導者がタリバン幹部をなだめ、解放された。夫婦はパソコンやカメラをバッグに詰め、翌朝の飛行機で首都カブールへと脱出した。同国で低迷する女性の識字率や社会進出の課題を、カリミさんは告発し続けてきた。「駆け出しの15年前、女性記者はほとんどいなかった。女性の尊厳を守りたい一心で書き続けた」。記事への反響が支えだった。ヘラートからカブールに退避して12日後の15日、カブールも陥落した。現在は夫婦で、保護団体のシェルターに隠れて暮らす。タリバンの一部戦闘員が「記者狩り」をしており、外出できない。カリミさんは「15年積み上げたものが政権崩壊と同時に崩れた。やっと女性たちが怒りの声を政治にぶつけられる時代になったのに」と声を落とした。タリバン傘下に入った国営テレビ局「RTA」では政権崩壊後、画面から女性キャスターの姿が消えた。その一人、シャブナム・カーン・ダウランさんはSNSに投稿したビデオ声明で「タリバンから『帰れ』『政権が変わったんだ』と追い返された」と訴えた。ロイター通信によると、南部カンダハルでは7月にタリバンが銀行を訪れ、女性職員9人に出勤停止を命じたという。タリバンは政権に就いていた1996~2001年、極端なイスラム教の解釈で女性の通学や就労を妨げ、服装を強要して国際的な批判を浴びた。今後、女性の行動に一定の縛りをかける恐れが強い。カブールではタリバンの権力掌握を受け、全身をすっぽり覆う衣装「ブルカ」を買い求める女性が店に殺到し、政権崩壊前に1着1千アフガニ(約1400円)ほどだったものが約5倍に値上がりした。カンダハルの女子校に勤める女性教員(29)は「学校は閉鎖したままで生徒が心配。たとえ授業が再開しても、科目は宗教に偏るでしょう。進学を志す女子がまた減ってしまう」と憤った。 *1-2-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/123786 (東京新聞 2021年8月13日) 「留学女性は命狙われる」「もう帰国できない」 教育禁じるタリバン支配地拡大でアフガン留学生ら悲鳴 アフガニスタンで反政府武装勢力・タリバンが猛攻を続ける中、海外留学中のアフガン人学生が危機感を募らせている。教育を禁じたタリバン政権が2001年末に崩壊して以降、アフガンでは教育が再開し、エジプトの首都カイロにあるイスラム教スンニ派権威機関アズハルの付属大学には若者約300人が留学している。タリバンが支配地域を広げる現状に、学生からは「また教育が奪われる」と懸念の声が上がっている。「なぜアフガンだけ何度もひどいことが起きるのか。私は何でアフガンに生まれたの?」。アズハル大で法律を学ぶララ・アブドラさん(22)が「戦争の日記」と呼ぶ小さな手帳には、1ページ目にこう書いてある。駐留米軍の8月末撤退を見据え、タリバンが侵攻を激化させた3週間前から日記を付け、友人や家族から聞いた現地の状況をつづっている。3年前、激しい競争の中でアズハル大の奨学金を勝ち取り、単身でカイロに来た。女6人、男1人の7人きょうだいの長女。アフガンで裁判官になるのが目標で、父(50)の夢でもある。父は女性が教育を受けることを重視し、母と共にカイロに送り出してくれた。妹たちも姉が目標だ。しかし、教育を禁じるタリバンが国を支配すれば、「女性で単身留学している私は標的になる。帰国すれば命を狙われる」と話す。家族が暮らす西部ヘラート州は、イラン国境付近がタリバン支配下に落ち、州都は陥落目前となっている。「お姉ちゃんの後に続く」と医者を目指していた妹(17)は「もう諦めた。ただ、ここから逃げたい」と毎日泣いているという。タリバンが制圧した州都では、教育機関や政府施設が破壊され、一部では女性に体や顔を覆う衣装「ブルカ」の強要も始まったという。20年前を思わせる状況に、アズハル大の学生らは「もう帰れない」「昔に逆戻りだ」と懸念する。教育が再開したアフガンからは、アズハル大への留学生が大幅に増えた。前学生会長のオスマン・ヌーリスタニさん(26)は「私の世代は教育を受けることができ、みんな必死に勉強してきた。それがまた奪われるのか」と憤る。攻防が続くアフガンでは、国軍約30万人に対してタリバンは約7万人。数では国軍が勝るものの、タリバンに攻め込まれた地域では、国軍が戦闘を放棄して逃げたとの情報もある。在エジプト大使館のアミヌラーク・アフマディ領事は「米軍に頼らずわれわれの手で国を守る必要があるが、国際社会からの財政支援も必要だ」と話す。 *1-3:https://digital.asahi.com/articles/ASMDB5QJTMDBTIPE01X.html?iref=pc_photo_gallery_bottom (朝日新聞 2019年12月11日) 「100の診療所より用水路」 中村さんが変えた暮らし アフガニスタンで銃撃されて亡くなったペシャワール会(福岡市)の現地代表、中村哲さん(73)が医療から灌漑(かんがい)・農業支援へと活動を広げたのは、アフガンを大干ばつが襲い、農地が砂漠化するのを目の当たりにしたからだ。病気の背景には食料不足と栄養失調があると考えて「100の診療所より、1本の用水路を」と、2003年からアフガン東部で用水路の建設に着手した。これまで約27キロが開通。用水路は福岡市の面積のほぼ半分に当たる1万6500ヘクタールを潤し、砂漠に緑地を回復させた。今、農民65万人の暮らしを支えている。高価な資機材がなくても現地の人が維持・管理できるようにと、現代的な施設ではなく、伝統的な技法を採り入れた。取水堰(ぜき)は、江戸時代に築かれて今も使われている山田堰(福岡県朝倉市)がモデル。護岸はコンクリートを使わず、鉄線で編んだ「蛇籠(じゃかご)」に石を詰めて積み、そこに根を張る柳を植えて、護岸を補強した。防風・防砂林の植樹総数は100万本を超えた。工事に携わった人たちは現場で技術を習得し、熟練工が育った。中村さんは近年、国連機関や国際協力機構(JICA)とも連携して、ノウハウをアフガン全土に広めようと考えていた。ペシャワール会の村上優会長は9日の記者会見で「全ての事業を継続していきたい」と決意を述べた。 <日本 ← 繰り返す豪雨による内水氾濫・外水氾濫> *2-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/785375/ (西日本新聞 2021/8/15) 「同じことの繰り返し」内水氾濫に住民疲弊 久留米、武雄で浸水被害 激しい雨音で眠れずに朝を迎えると、自宅は茶色い泥水に囲まれていた-。14日も豪雨に見舞われた九州北部。佐賀県武雄市や福岡県久留米市では住宅浸水や道路の冠水が相次いだ。水路や下水道の排水が追い付かず、雨水が地表にあふれる「内水氾濫」が起きたという。両市周辺では近年同じ被害が繰り返されており、住民たちは疲れ切った表情を見せた。「大雨が怖く、昨夜から2階で過ごした」。同日午前、武雄市朝日町の自宅から消防のボートで助け出された福田タケ子さん(85)は振り返った。市内では支流の内水氾濫に加え、近くを流れる本流の六角川が一部で氾濫。東部を中心に住宅地などが濁った水で覆われた。市や近隣自治体では2019年にも冠水被害が起きている。自宅が浸水した同市朝日町の樋口勝則さん(56)は、13日夕から避難所に身を寄せる。前回浸水時は避難所で1カ月を過ごし、泥水に漬かった家具の片付けに加え、職場も被災した。「元の生活に戻るのに半年かかった。たった2年で同じことの繰り返し。これからを考えると力が抜けてしまう」と頭を抱えた。市と隣接する大町町の順天堂病院は周囲を泥水で囲まれ、前回に続き孤立状態となった。町によると、雨水が建物内部に入り、入院患者を上階に避難させたという。周辺でも消防への救助要請が相次いだ。筑後川が流れる久留米市。14日午前までの24時間降水量は、観測史上最大の387ミリとなった。支流では内水氾濫が起き、4年連続で市街地や田園地帯が水に漬かった。市によると、支流では本流からの逆流を防ぐため合流点の水門を閉鎖。本流にポンプで水を送るものの、処理できなくなった雨水が広域であふれた。ポンプを増やし、堤防のかさ上げにも取り組んでいるが、圧倒的な雨量に及ばなかった。一部で道路が冠水した市中心部では、消防のボートで助け出される住民がいた。水をかき分けながら各戸を回り、取り残された人がいないかを見回っていた消防隊員は「水位が首の高さまである場所があった」と話した。膝まで水に漬かりながら自力で避難していた女性は「これほどの浸水は初めて。アパートの2階に住んでいるが、1階が浸水したので知人宅に避難する」と声を震わせた。 *2-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/12a76f5f1a8d5cbf30e81fd6caefc619ca5c692c (Yahoo 2021.8.26) 大雨 家屋1663棟浸水 「2年前より深刻」 佐賀・武雄市 8月11日から降り続いた大雨で甚大な被害が出た佐賀県武雄市で被害概要がまとまり、小松政市長が25日、記者会見で発表した。浸水の深さや内水氾濫の面積、家屋被害数などが2019年8月に県を襲った記録的大雨より深刻との認識を示し、「被災者の苦しみ、痛みに寄り添いながら一日も早い復旧と生活再建に全力で取り組む」と語った。小松市長はまた被災した市民、事業者らに市独自の生活支援策を検討する考えも示した。武雄市によると、2年前の8月は降雨期間が3日間だったのに対し、今夏の大雨は7日間(11~17日)続き、総雨量も最大約1300ミリ(2年前は同約500ミリ)に達した。武雄市を流れる六角川の排水ポンプが3回計8時間50分(同1回計3時間10分)停止した。家屋への浸水被害は25日現在、床上1273棟、床下390棟の計1663棟(同1536棟)で通行止めは約90カ所(同63カ所)。浸水の深さや内水氾濫の面積は「2年前より大」としている。地滑りの兆候も今回は3カ所で確認された。2年前と比べ、内水氾濫が広がった理由について市は、長時間の降雨と六角川の水位上昇に伴い、排水ポンプの停止時間が長引いたことなどが影響したとみている。この結果、朝日町、北方町、橘町で浸水の被害が大きかったと指摘した。小松市長は内水氾濫による被害が続いていることに「(管轄の)国土交通省には内水氾濫対策に目を向けてほしい。国、県、市町が可及的速やかに対策を打ち出す必要がある」と注文をつけた。今後、ポンプ機能を維持する方策を専門家や国交省の河川事務所と早急に協議する意向も示した。復旧・復興に向けては、新型コロナウイルスの急拡大に伴い、2年前と比べてボランティアが集まりにくい状況にあると報告。小松市長は「被災者支援を2年前より強化する」と語り、2年前に被災しながら再建した事業者らに「もう1回頑張っていただける再建費用の補助検討を現在、進めている」とした。市は災害復旧に関する支援策を9月議会に追加提案する予定。 ◇商工業被害額、店舗など84億円 記録的大雨で多大な被害を受けた武雄市で商工業被害額が25日時点で約84億円(速報値)にのぼることが、同日の県産業振興課への取材で判明した。県によると、同市の中小企業や個人事業主計230店舗が被災。最も多かったのが浸水被害という。さらに被害額は膨らむ可能性もあるという。2019年8月に県内を襲った大雨で武雄市は今回とほぼ同数の約230店舗が被災、被害額は約80億円だった。 *2-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/733382 (佐賀新聞 2021.9.1) 大雨被害、激甚災害指定へ 農業分野復旧は佐賀県全域、中小企業支援は武雄、大町 佐賀県内で11日から降り続いた記録的な大雨の被害に関し、棚橋泰文防災担当相は31日の閣議後会見で、激甚災害に指定する見通しになったと発表した。農業分野では地域を限定せず県内全域が対象になる「本激」となり、国庫補助率をかさ上げする。融資による中小企業の再建支援は武雄市、杵島郡大町町に限定する「局激」となる見込み。内閣府によると、農地や農道、水路などの農業用施設や林道の災害復旧事業は、通常の国庫補助率をかさ上げする。過去5年間の実績の平均では、農地は補助率を84%から96%にかさ上げしている。国庫補助の対象とならない小規模な農地でも、交付税措置などで自治体負担を軽減する。被災した市町や農家の財政負担を軽減し、早期復旧を後押しする。これらの措置は地域を限定しない。さらに武雄市、大町町には、中小企業の事業再建のための特例措置を適用する。保証限度額を増額することで、中小企業は民間金融機関から再建資金を借りやすくなる。激甚災害は経済的被害を基準に指定する。県市町が被害額を調査し、各省庁が査定。局激の場合、市町の財政規模ごとに基準額が設定され、基準額を超えた時点で指定の見込みが示される。閣議決定による正式指定には、1カ月ほどかかる見通し。棚橋氏は「被災した自治体は、財政面に不安なく、迅速な災害復旧に取り組んでいただきたい」と述べた。内閣府によると、公共土木分野での被害状況も査定を続けている。早期指定を要望していた佐賀県は「農地などの復旧が本激指定になることはありがたい。適用される措置を活用し、この2年間で再び被災された多くの方の支援に取り組んでいきたい」とした。一方、中小企業への特例措置が、武雄市と大町町に限る局激となることについては「具体的にどういった支援ができるのか中身を精査していく」としつつ、「本激でなければ実施されない『なりわい再建補助金』(復旧費の最大4分の3を公費補助)に関し、局激でも実施してほしいと要望していた。今後の国の対応を注視したい」と述べた。 <アフガンの攻防と女性デモ> PS(2021年9月6、7日追加):*3-1のように、アフガンのタリバン指導部は、制圧した都市で住民財産保護や生活維持に気を配るように戦闘員に指示したが、タリバン戦闘員は、①民家で「50人分の食事を作れ」と要求したり ②民家や学校に放火したり ③降伏した政府軍兵士を処刑したり ④12歳の少女に自分と結婚するよう強要したり など蛮行が目立ち、国連のグテレス事務総長は、8月13日、タリバンを非難した。 アフガン女性は、*3-2のように、9月2~4日、国の発展には女性の力が不可欠だと訴えて女性の教育機会保障・働く権利保障・政治参加保障をするよう求めるデモを行ったが、これに対して、タリバンは催涙ガスを使ったり、小銃の弾倉で女性の頭を殴ったりしたそうだ。タリバンは、8月中旬にカブールを制圧した直後の記者会見で「女性は働けるし、教育も受けられる。女性の権利はイスラム法の枠内で認められる」としたが、BBCのインタビューでタリバン幹部は、「女性が高い地位につくことはない」などと世界の女性を敵に廻すような発言をしている。 そのような中、*3-3のように、9月4日、タリバンは唯一制圧していない北東部パンジシール州を支配下におさめようと抵抗勢力(旧政府軍)と衝突し、米軍制服組トップは、タリバンが権力基盤を固めることができなければ「内戦」に陥る恐れがあると警告したそうだが、国民的英雄マスード司令官の息子で同地域を率いるアフマド・マスード氏は、パンジシール州は「強い抵抗を続けている」と強調している。 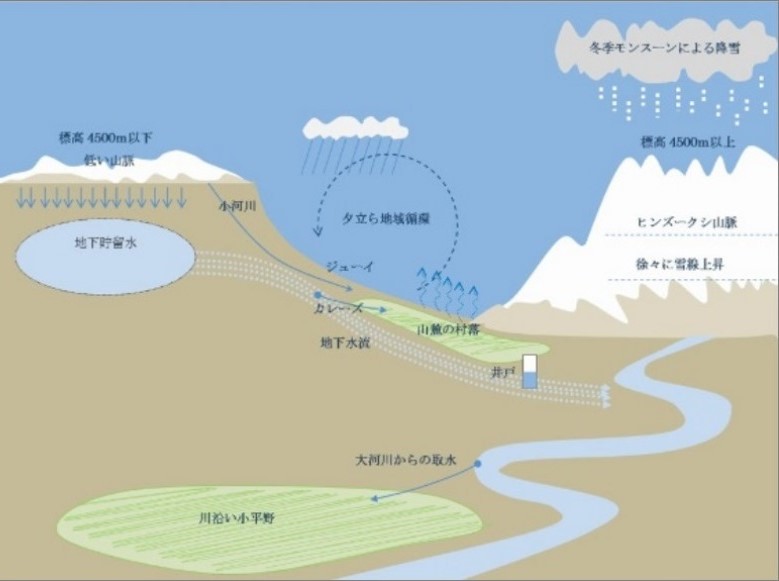   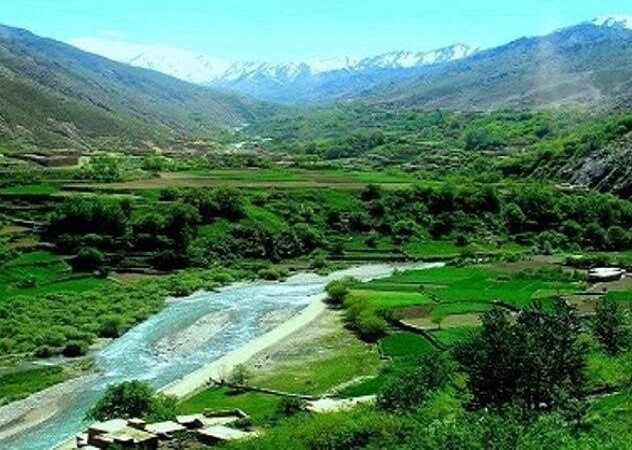 アフガンの地形 パミール高原 パンジシール州の位置 パンジシール州の風景 ペシャワール会より Ameba Parstoday (図の悦明:1番左の図のように、アフガニスタンは高い山や高原に囲まれており、水がないわけではなく水利施設が整っていないようで、左から2番目の図のパミール高原も手入れをした場所には緑がある。また、強い抵抗を続けているパンジシール州は、右から2番目の図のように北東部にあり、1番右の図のように、緑豊かな渓谷があって農業の潜在力も大きそうだ)    2016.11.1Ameba Smartagri Smartagri Perfectstone (図の説明:1番左はアフガニスタンの主食である小麦、左から2番目はアフガニスタンの葡萄、右から2番目は同サフランで、戦争前のアフガニスタンは食料自給率100%の農業国だったそうだ。また、1番右の図のように、パンジシール州ではエメラルドも採れる) *3-1:https://www.yomiuri.co.jp/world/20210814-OYT1T50221/ (読売新聞 2021/8/15) 民家や学校に放火、12歳少女に結婚強要…タリバン支配地で蛮行目立つ アフガニスタンの旧支配勢力タリバン指導部は13日の声明で、制圧した都市では住民財産の保護や生活の維持に気を配るよう、戦闘員に指示した。住民を懐柔し、支持を広げる狙いだが、支配地では蛮行が目立ち、国際社会からも批判が高まっている。タリバンは声明で、支配地の拡大は「我々に対する支持があってこそだ」と強調し、タリバンを恐れる住民に「心配する必要はない」と呼びかけた。だが、実態は違うようだ。タリバンが10日に制圧した北部プレフムリの主婦(22)によると、タリバン戦闘員は主婦の自宅に押しかけ、「50人分の食事を作れ」と要求したという。夫はスリッパ商人で、一家は裕福ではないが、肉や野菜、ヨーグルトなどを大量に提供させられたという。プレフムリからカブールに避難してきたリロマさん(43)は本紙通信員に、タリバンが民家や学校などに放火していると語った。リロマさんは、「タリバンの暴虐ぶりは昔と変わっていない」と非難した。カブールの米大使館によると、降伏した政府軍兵士の処刑も確認されている。タリバンは米国と和平合意を交わした昨年2月以降、住民の取り扱いに注意するよう、指導部が戦闘員に指示してきたが、浸透していないようだ。英紙デイリー・メール(電子版)によると、あるタリバン戦闘員は支配地域で、12歳の少女に自分と結婚するよう強要した。戦闘で夫を失った女性も、タリバン戦闘員の妻にされる場合が多い。国連のアントニオ・グテレス事務総長は13日、ニューヨークで記者団に、「アフガンの少女や女性が苦労して得た権利を奪われている。胸が張り裂けそうだ」と語り、タリバンを非難した。 *3-2:https://www.msn.com/ja-jp/news/world/ (毎日新聞 2021/9/5) アフガンで女性デモ 就業や政治参加求め タリバン、催涙ガスで応酬 イスラム主義組織タリバンが実権を掌握したアフガニスタンで2日から4日にかけ、女性の就業や政治参加の権利を保障するよう求めるデモがあった。首都カブールではタリバンが催涙ガスを使うなどし、負傷者が出たという。タリバンは2001年までの旧政権でイスラム教の厳格な教義に基づき女性の権利を制限した。デモ参加者は、国の発展には女性の力が不可欠だと訴えている。アフガンの民間放送局「トロニュース」(電子版)などによると、4日にカブール中心部で行われたデモでは、活動家やジャーナリストらが女性の働く権利や教育の機会の保障を求めるスローガンを掲げて行進した。大統領府に向かおうとしたデモ参加者に対し、タリバンの戦闘員らは催涙ガスを使ったという。ロイター通信は、女性が戦闘員によって小銃の弾倉などで頭を殴られ、血を流していたとの参加者の証言を報じた。参加者の一人はトロニュースに対し「私はタリバン政権崩壊後の20年間で学校で学ぶことができ、よりよい将来のために努力してきた。この成果を失いたくない」と訴えた。同様のデモはカブールで3日にあったほか、2日に西部ヘラートでも起きた。01年にタリバンの旧政権が崩壊するまでの約5年間、アフガニスタンの女性は教育が禁止されるなど厳しい制約下に置かれた。タリバンは8月中旬にカブールを制圧した直後の記者会見で「女性は働けるし、教育も受けられる。社会に必要な存在だ」とする一方、女性の権利はイスラム法の枠内で認められるとも強調した。タリバン幹部は英BBC放送のインタビューで、新政府の省庁で女性職員が元の職場に戻ることを希望すると述べる一方で「高い地位につくことはないだろう」と要職への女性登用を否定した。最終調整が続くタリバン政権の組閣でも、女性は起用されない見通し。 *3-3:https://news.yahoo.co.jp/articles/bc9b9a7323934577f5db64c0f7b950c62d5ce6d0 (RUETERS 2021/9/5) タリバン、北東部で抵抗勢力と戦闘 米軍幹部は「内戦」警告 アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンは4日、唯一制圧していない北東部パンジシール州を支配下におさめようと抵抗勢力と衝突した。米軍制服組トップは、タリバンが権力基盤を固めることができなければ「内戦」に陥る恐れがあると警告した。タリバンと抵抗勢力はともにパンジシール州を掌握したと主張しているが、いずれも確かな証拠は示していない。タリバンは1996─2001年にアフガンを統治した際、首都カブールの北にあるパンジシール渓谷を支配できなかった。タリバンの報道官は、パンジシール州の7地域のうち4地域を制圧したと主張。ツイッターで、タリバン兵士が州中心部に向けて進軍していると述べた。だが、国民的英雄マスード司令官の息子で同地域を率いるアフマド・マスード氏に忠実なアフガニスタン民族抵抗戦線(NRFA)は、「数千人のテロリスト」を包囲し、タリバンが車両や機材を放棄したと主張。マスード氏はフェイスブックへの投稿で、パンジシール州は「強い抵抗を続けている」と強調した。米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長はFOXニュースで「内戦に発展する可能性が高い状況というのが私の軍事的な見立てだ。タリバンが権力基盤を固め、統治を確立できるか分からない」と述べた。その上で、タリバンが統治を確立できなければ、今後3年で「アルカイダの復活やイスラム国(IS)もしくは他のさまざまなテロ集団の拡大につながる」との見方を示した。こうした中、パキスタンの軍情報機関、3軍統合情報局(ISI)のハミード長官が4日、カブール入りした。目的は明らかになっていないが、パキスタン政府高官は数日前に、タリバンによるアフガン軍再編成をハミード氏が支援する可能性があると述べていた。 <女性が権利尊重求めデモ> 現地メディアのトロ・ニュースによると、首都カブールでは、十数人の女性がタリバンに女性の権利尊重を求める抗議デモを行ったが、タリバンはこれを排除した。女性らが口を覆い、咳をしながら武装した兵士と衝突するのが映像で確認できる。デモ参加者の1人は、タリバンが催涙ガスやテーザー銃を使用したと語った。タリバンが女性らの頭を弾倉で殴り、出血したと話す参加者もいた。 <新政権は「あらゆる勢力」で構成> タリバン関係筋は、新政権の発表が5日からの週に先送りされるとの見方を示した。タリバン共同創設者のバラダル師は中東のテレビ局アルジャジーラで、新政権はアフガンのあらゆる勢力によって構成されると述べた。複数のタリバン関係者はこれまでに、バラダル師が新政権を率いるとの見方を示している。アルジャジーラによると、カタールの駐アフガン大使は、技術チームによりカブールの空港が再開され、支援物資などの受け取りが可能になったと明らかにした。アルジャジーラの記者は、アフガンの国内線運航も再開されたとしている。国連は、人道危機の回避に向けてアフガン支援拡大を呼び掛ける国際会合を13日に開く。 <自民党総裁選と政策論争> PS(2021年9月8、9日追加):日本のメディアは、アフガン情勢を事前に報道せず、オリ・パラの開催を批判することに専念し、新型コロナ危機は必要以上に言い立て、首相を変えさえすれば物事がうまくいくかのような報道をしていた。その結果、日本は、人を貶めるための不正確な人格攻撃情報であふれ、首相は短期で交代して民主主義政治の貧困を招いている。 そして、河野太郎氏の総裁選立候補の話が出ると、*4-1のように、原子力利権の守護神である経産省は、週刊文春を使って河野氏を人格攻撃する最終戦争に打って出た。私も週刊文春を使った人格攻撃をされた経験があるので知っているのだが、政策でかなわない時、論点をずらし、変なところを誇張して人格攻撃を行い、対象となった人を貶める卑怯な方法がよく使われる。河野氏の場合は、資源エネルギー庁幹部との会議で近く閣議決定される「エネルギー基本計画」に繰り返しダメ出しをしてパワハラを行ったように書かれているが、本当は世界に例を見ない出鱈目な「容量市場制度(大手電力の石炭火力に多額の補助金を与え、再エネ電力供給業者に多額の資金拠出を強制する制度)」の即時廃止又は抜本的改革を主張し、経産省がこれを無視したのだそうだ。また、原発と再エネの電源比率も、経産省は再エネ比率が想定以上に上がるのを妨げて原発の維持拡大に有利な抜け穴を作ろうとしているが、河野氏が「理不尽な内容のままなら閣議で反対する」と言い、経産省が論戦で完敗して、河野氏の「脅し」として一部週刊誌に漏洩し、「個人攻撃」で河野氏を叩こうとしたのだそうである。しかし、次の衆議院議員選挙は表紙を変えればいいのではなく、「脱原発して再エネ移行」を掲げるくらいの政策を掲げるのでなければ、(理由を長くは書かないが)自民党は落選者が続出すると思う。 本来は産業振興のために頭を使うべき経産省だが、このようにやるべきことの逆を繰り返した結果、*4-3のように、日本は労働生産性がOECD加盟36カ国中21位・主要先進7カ国最下位、賃金は唯一下がっている国になった。労働生産性は「付加価値(≒売上高-売上原価《人件費を除く》-経費《人件費を除く》)/総労働時間」であるため、水光熱費や土地代などの人件費以外の経費が高ければ労働生産性は下がり、賃金を労働生産性より高くはできないからである。 なお、付加価値を上げるには、人件費以外の経費を下げる以外に販売単価を上げて売上高を増やす方法もあるが、その基となる技術力も、*4-2のように、中国が注目度の高い科学論文の数で米国を抜いて初めて首位に立ち、年間の論文総数でも2年連続で1位になっているのに、日本は研究者数と研究開発費は世界3位、論文総数は4位であるにもかかわらず、「トップ10%論文数」の順位はインドにも抜かれてG7最下位の世界10位まで転落した。私も、その最大の原因は、「何をやっても日本の技術力は優れたままである」と根拠もなく思い込み、政治・行政がやるべき努力をしなかったことだと考えている。 日本で光熱費を下げて付加価値を上げるには、*4-4のように、変動費0の再エネで100%のエネルギーを賄い、外国に支払っていたエネルギー代金を国内で廻して、エネルギー自給率を100%にするのがよいし、それは可能である。一方、原子炉は、新型で小型でも、冷却時に海水を温め、外国に高い燃料代を支払う必要があり、暴走のリスクが0ではなく、使用済核燃料の処分に多額の費用がかかり、エネルギー安全保障でも劣るため、賢い選択肢とは言えない。そのため、それが見えることは、日本の首相には特に重要だ。なお、脱原発については、2011年のフクイチ事故以降は本気で議論してきており、既に10年も経過しているため、「明日や来年やめろ」というような性急な話ではないだろう。 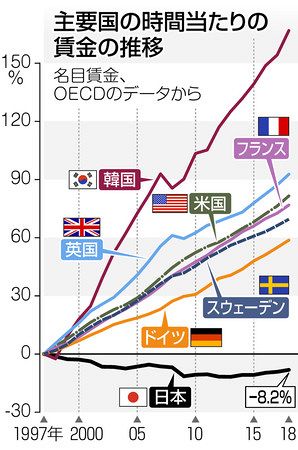 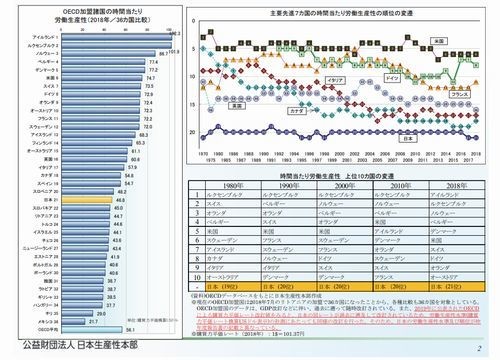 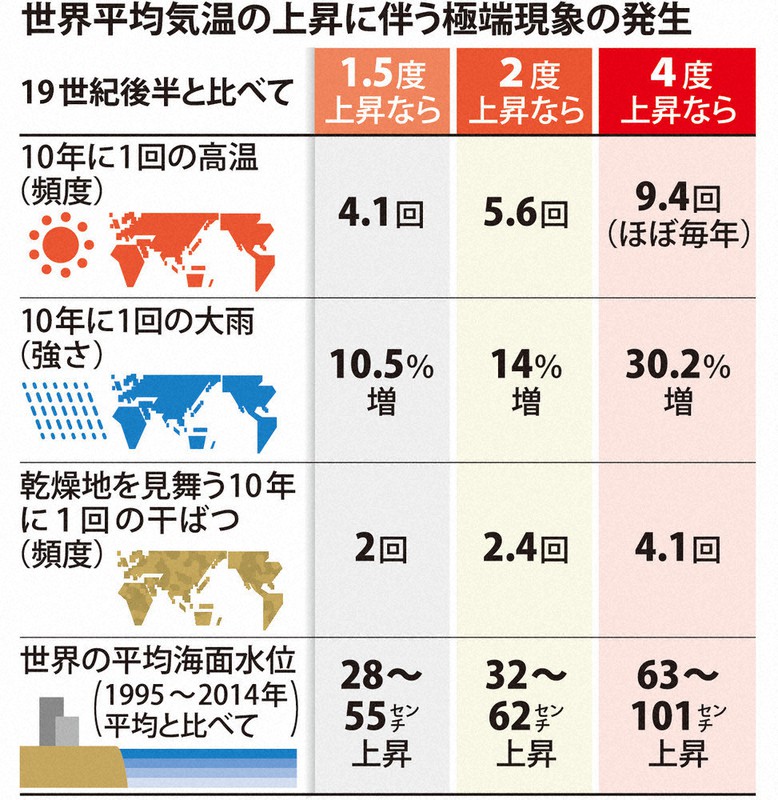  2019.8.29東京新聞 News.Mynavi 2021.8.10毎日新聞 2021.8.10西日本新聞 (図の説明:1番左の図のように、1997年を基準とした主要国の時間当たり賃金は、日本のみがマイナスになっている。また、左から2番目の図のように、労働生産性は日本がOECD加盟36カ国中21位・主要先進7カ国で最下位だ。また、右から2番目及び1番右の図のように、世界の平均気温上昇による極端現象は明らかに増えており、エネルギーの変換や技術開発はできるかぎり速やかに行わなければならない状況なのだ) 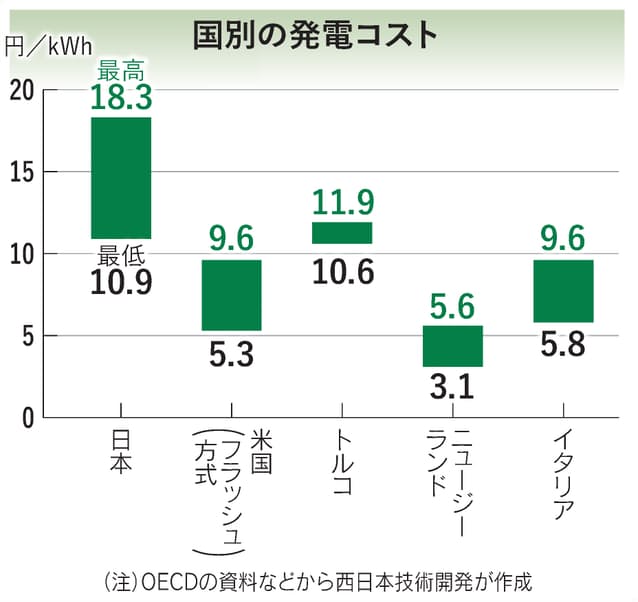  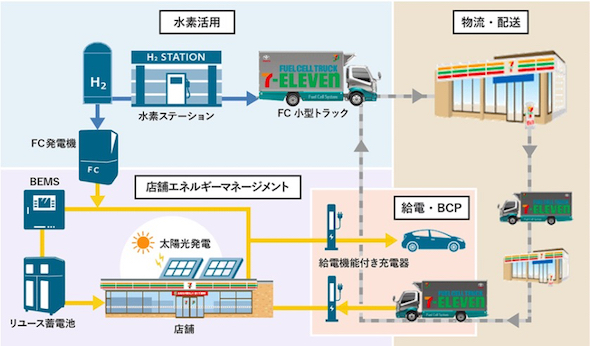 2021.6.10日経新聞 2021.8.26日経新聞 (図の説明:左図のように、日本の国別発電コストは著しく高く、日本の産業は足に重りをつけて競争させられているようなものである。しかし、日本には、中央の図の地熱発電はじめ未利用の再エネがふんだんにあり、これらを使えば安価な電力を実現できる。また、右図のように、今では自家発電しながらエネルギーを使う方法も多くできているため、決断が遅いくらいなのだ) *4-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/e3cdefcb9a0801e0983015441b3fc90dc28995ed (Yahoo 2021/9/7) 経産省による「河野太郎叩き」が意味すること〈週刊朝日〉 自民党総裁選の裏で大戦争が起きている。主役は、原子力利権の守護神・経済産業省の官僚と河野太郎規制改革担当相だ。連戦連勝の河野氏に対して、経産省は「文春砲」で最終戦争に打って出た。先週の週刊文春は、近く閣議決定される「エネルギー基本計画(エネ基)」について、経産省資源エネルギー庁幹部との会議で、河野氏が繰り返しダメ出しする様子を伝えた。普通に読めば、河野氏が理由なくパワハラ発言をしたと読める内容だ。文春は、菅義偉政権の目玉閣僚である河野氏を叩こうと考えた。その姿勢は、忖度報道ばかりの大手マスコミにはないもので貴重ではあるが、この記事はあることを報じていない。実は、この会議に至るまで、経産省と河野大臣、そして、河野大臣直轄の有識者会議「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(TF)」の間では、1年近く議論が行われてきたということだ。TFは電力会社から完全に独立した国内最高の専門家4人からなる。そのため、私が見る限り、経産省は論戦で完敗した。経産官僚はネット生配信で毎回恥をさらしたのだ。例えば、文春の記事にあった「容量市場」制度(将来の電力需要に備えるため、電力会社が準備する安定供給電源設備に対して、供給が不安定になりがちな再エネ電力などの供給業者が一定の資金をあらかじめ支払って、設備を維持してもらう制度)は、世界に例を見ないでたらめな制度だ。驚いたことに、大手電力会社の石炭火力に多大な補助金を与え、逆に再エネ電力供給業者に事実上の死刑宣告になるような多額の資金拠出を強制する制度になっている。河野氏は、即時廃止または抜本的改革を主張したが、経産省はこれを無視。エネ基最終案にも即時抜本改革さえ盛り込まなかった。河野氏が怒るはずだ。原発と再エネの電源比率の書き方についての争いも、文春の記事からわかるのは、経産省が、再エネの比率を想定以上に引き上げるのを妨げ、原発維持拡大に有利になるような抜け穴を作ろうとしているということ。30年以上官僚をやっていた私には彼らの魂胆がよくわかる。経産官僚は、電力利権と安倍晋三前総理や甘利明税調会長などの利権政治家の側に立ち、国民の利益を全く無視している。こうした真実を知れば、国民の多くは、経産官僚に対して罵声を浴びせたくなるだろう。やむなく河野氏が、理不尽な内容のままなら閣議で反対すると言ったのは当然のことだろう。それがどうして「脅し」になるのか、意味不明だ。経産省が、内部調整中のエネ基の文言を一部週刊誌だけに漏洩して、「個人攻撃」で河野氏を叩こうとしたのは、彼らの「政策論」が世の中で通用しないと悟ったからだ。つまり、彼らは負けを認めたのだ。官僚と族議員の利権に容赦なく切り込む河野氏の敵は、利権擁護派の官僚と自民党族議員全体に及ぶ。彼らは、週刊文春を味方につけた経産省とともに、かさにかかって河野叩きに出るはずだ。河野総裁や要職での起用の可能性もあるとなればなおさらだろう。マスコミによる河野氏への人格攻撃は、その報道の意図とは関係なく、原発維持拡大などの利権擁護派に利用されていることを国民はよく理解しておかなければならない。 ※「週刊朝日」9月17日号より ■古賀茂明(こが・しげあき)/古賀茂明政策ラボ代表、「改革はするが戦争はしない」フォーラム4提唱者。1955年、長崎県生まれ。東大法学部卒。元経済産業省の改革派官僚。産業再生機構執行役員、内閣審議官などを経て2011年退官。近著は『官邸の暴走』(角川新書)など *4-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15036209.html?iref=comtop_Opinion_01 (朝日新聞 2021年9月7日) 論文引用数、中国躍進の一方で日本10位 科学技術力の岐路、おごり捨てて 桜井林太郎 科学技術政策について考えさせられるリポートが先月、公表された。注目度が高い科学論文の数で、中国が米国を抜き、初めて首位に立ったという。文部科学省の科学技術・学術政策研究所が、引用された回数が上位10%に入る「トップ10%論文数」を調べた結果で、その国の科学技術力を示す一つの指標となっている。中国は、年間の論文総数でも2年連続で1位となり、「質、量ともに世界一になった」と報じたメディアもあった。知り合いの材料研究者は「10年前、中国の研究者は独創性が高い日本の論文を追いかけていたが、今では中国の論文を日本の研究者が追試していることも多い」と嘆く。ただ、中国が質でも世界一になったと言い切るのは時期尚早という意見もある。理工系のある大学教授によると「中国は自国の科学雑誌への投稿を促し、格が高い雑誌に育てた上で、論文を引用し合う場合も多い」からだ。文科省の研究所の分析でも、英ネイチャーや米サイエンスといった世界屈指の科学誌のシェアでは今なお、米国が圧倒的に強かった。中国は、米国に次ぐ英独の2位争いに加わろうと猛追している段階だ。一方、日本の凋落(ちょうらく)ぶりは目を覆うばかりだ。日本は、研究者数と研究開発費は世界3位で、論文総数は4位。なのに、「トップ10%論文数」の順位は2000年代半ばから下がり続けている。今回はインドにも抜かれ、G7最下位の世界10位に転落した。研究時間の減少や博士課程進学者の減少など、さまざまな要因が原因として挙げられている。しかし、最大の原因は「慢心」にあったのではないか。この10年余り、皮肉にも日本はノーベル賞の受賞ラッシュに沸いた。「中国のノーベル賞はごくわずか。科学技術力は日本が上だ」。そんな話を何度も耳にした。現状の認識がこの有り様では、中国だけでなく、世界から取り残されてしまうだろう。日本政府も危機感を強め、テコ入れを始めた。日本の科学技術力は今まさに分岐点にある。「失われた10年」を「失われた20年」にしてはいけない。 *4-3:https://news.mynavi.jp/article/20191218-941815/ (マイナビニュース 2019/12/18) 「労働生産性の国際比較 2019」公開 - 日本は主要先進7カ国中最下位 日本生産性本部は12月18日、「労働生産性の国際比較 2019」を公表した。これは、同本部がOECDデータベースなどをもとに毎年分析・検証し、公表しているもの。OECDデータに基づく2018年の日本の時間当たり労働生産性は46.8ドル(4,744円)で、OECD加盟36カ国中21位だった。名目ベースで見ると、前年から1.5%上昇したが、順位は変わっていない。日本の労働生産性は、米国(74.7ドル/7,571円)の6割強で、イタリア(57.9ドル)やカナダ(54.8ドル)をやや下回る程度の水準。主要先進7カ国では、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いているという。就業者1人当たりの労働生産性は81,258ドル(824万円)で、同じくOECD加盟36カ国中21位だった。日本の1人当たり労働生産性は、英国(93,482ドル/948万円)やカナダ(95,553ドル/969万円)といった国をやや下回る水準。米国(132,127ドル/1,339万円)と比較すると、6割強の水準となっている。1990年代初頭は米国の4分の3近い水準だったが、2010年代に入ってから3分の2前後で推移しているという。 *4-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA07CK60X00C21A9000000/ (日経新聞 2021年9月9日) 脱炭素が問う自民総裁選 原発と再生エネが主戦場 自民党総裁選は17日に告示され、29日投開票する。新総裁が首相になるため、誰が勝つかが関心事だが、そのまま政権公約となる各候補の政策についても国内外の熱い視線が注がれる。政府が掲げた2050年までに国内の温暖化ガス排出実質ゼロ、30年度に13年度比で46%削減する目標に向けた原子力発電と再生可能エネルギーのあり方が論戦の主戦場になる。総裁選は岸田文雄前政調会長、高市早苗前総務相が立候補を表明し、河野太郎規制改革相は10日にも明らかにする。今回の総裁選がこれまでとは異なり、エネルギー政策が注目されるのは、河野氏の脱原発を巡る過去の発言がある。河野氏は東日本大震災直後の11年7月の自民党の総合エネルギー政策特命委員会で原発政策について「放射性廃棄物を出すのに、なぜクリーンエネルギーと言ってきたのか」と批判。12年には超党派議連「原発ゼロの会」の発起人となった。河野氏は8日、内閣府で記者団に「再生エネを最優先に広く取り入れていくのが基本だ」と力説。「いずれ原子力はなくなっていくだろうが、明日や来年やめろというつもりはない」と述べた。「安全が確認された原発を再稼働するのはカーボンニュートラルを目指すうえである程度必要だ」と容認した。脱原発の考え方が変わったのかの質問には「変わっていない」と説明した。一連の発言には総裁選で脱原発に関して過度に焦点が当たるのを回避する狙いもあるとみられる。河野氏は新著「日本を前に進める」(PHP新書)で「与党議員ではできないことも、閣僚として権限を持てれば実現できる。権限があるということは、やる気になれば、実現できる」と記している。岸田氏は8日に発表した経済政策で「再生エネの最大限の導入は当然」とするとともに蓄電池、新型の小型原子炉などへの投資を提唱した。記者会見で原発を巡り「新増設の前に既存の原発の再稼働を進めていくのが大事だ」と話した。2日の日本経済新聞とのインタビューでは「脱炭素目標を掲げる以上は、より丁寧に日本の産業に目配りをし、責任を持って考えていかなければならない」と語った。7月に原案を示したエネルギー基本計画は30年度の電源比率で再生エネの割合を36~38%にした。高市氏は8日の記者会見で環境政策とエネルギー政策を一元的に担う「環境エネルギー省」の創設を主張。天候で変わる太陽光の発電量を補う電源として火力を挙げ、再生エネのさらなる導入と原子力の平和利用を唱えた。新著「美しく、強く、成長する国へ。私の『日本経済強靱(きょうじん)化計画』」(WAC BUNKO)で太陽光のリスクの最小化を提言。「太陽光パネルの傾斜が雨天時に地面を削り取る原因となっている」と指摘した。エネルギー政策の主な論点は電源構成だ。脱炭素へ原子力や再生エネ、火力の構成が適正で、実現可能かどうか。再生エネが季節や時間帯で発電量が変動する可変動電源ならそれを補強する電源とそのコストの議論も国民負担にかかわるだけに避けて通れない。地球温暖化は異常気象を生み、死者が出るほどの高気温や山火事、台風を含めた暴風雨など世界を恐怖に陥れる。生態系の破壊がもたらす異常気象の際限は想像がつかない。地球温暖化が国民の生命と財産を危険にさらす以上、国家指導者は最優先課題として防止策に取り組まなければならない。そのための国際連携も急務だ。総裁選は各候補の脱炭素への決意を確認すると同時にその政策の根拠が精緻で、実現できるのかを見極める場にもしたい。 <計画性なき日本の安全保障政策> PS(2021年9月10、11、15、23日追加):自民党保守派と称する人は、軍備を増強するのに予算を使うことには熱心だが、国民の生命・財産・領土・領海・資源を守る本当の国防計画はないようだ。何故なら、*5-1-1のように、食料自給率は2020年度に37%、エネルギー自給率は2018年に11.8%なのに、それを改善する努力はせず、国民の生殺与奪の権を食料やエネルギーを依存する国に委ねているからだ。 それどころか、*5-1-2のように、日本一の海苔産地である有明海沿岸の佐賀空港にオスプレイを配備することを自己目的化し、九州防衛局(=政府?)は、漁民と地権者は異なるため地権者にアンケート調査をしても意味がないのに、オスプレイ配備計画について地権者にアンケート調査し、土地売却の意向は「条件次第で売却」が最も多かったなどとしているのだ。しかし、重要なのは漁業権を持ち、安心・安全な食料を作っている漁業者であり、オスプレイ配備で隊員や家族ら2千人以上が移住してくることよりも、宝の海で食料生産を続けて食料自給率を上げることの方が、防衛にも協力することになり、地域活性化の上でも重要なのである。 一方で、*5-2-1のように、沖縄・尖閣諸島周辺の領海の外側にある接続水域では、112日間連続で中国海警局の公船「海警」4隻が航行し、領海への侵入も今年は18件起き、日本漁船への接近もたびたび発生し、海上保安庁は巡視船12隻を専従させて警戒を続けているが、中国は尖閣諸島を自国領土と主張し、中国公船の活動は“パトロール”として「釣魚島と付属島嶼は中国固有の領土で海警船が巡航することは法に基づく正当な措置だ」としている。また、中国海警局の元幹部は「365日の活動を可能にする『常態化』は10年以上前から計画されてきたもので、日本側にもその意思を伝えてきた」とし、中国外交筋は「日本側はいつも『領土問題は存在しない』としか言わず、まともに議論する意思がない。日本の漁船が挑発的に尖閣領海に入っている状況からも合意を破っているのは明らかに日本だ」と批判している。 これに対し、加藤官房長官は「極めて深刻な事態。我が国として冷静かつ毅然と対応していく考えだ」と述べ、赤羽国交相も「極めて深刻に受け止めている。海上保安庁では常に相手の勢力を上回る巡視船の隻数で対応し、万全の領海警備体制を確保している。事態をエスカレートさせず、冷静かつ毅然と対応を続けて領海警備には万全を期していく」と述べながら、*5-2-2のように、石垣市が尖閣諸島に行政標柱の設置を目指すと、*5-2-3のように、加藤官房長官は「政府は尖閣諸島および周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として政府関係者を除き、何人も上陸を認めない」と語り、肝心なところでは「毅然とした姿勢」どころか「及び腰」なのである。つまり、中国が10年以上前から計画してきた尖閣諸島領有については「領土問題は存在しない」と言ってまともな議論もせず、「冷静かつ毅然と対応する」としながら何もせず、「安定」の名の下に領土を放棄しようとしている。これは、どういうわけか。 *5-3のように、河野氏も「安全が確認された原発を当面は再稼働させるのが現実的」と言われたが、これは新たな安全神話だ。何故なら、原子力規制委員会は「①安全を考える場合、リスク0にならないことを前提に確率論的リスク評価が必要で、不完全性・不確実性はある」「②安全性目標は、他の死亡リスクとの比較や土地汚染に関する根拠(100TBq の根拠等)などある程度の価値判断を含む定性的な上位概念を示すことを考えて良い」としており、この安全性目標から外れていれば何が起こっても“想定外”とし、ある程度の汚染は甘んじるべきという価値判断をしているからである(https://www.nsr.go.jp/data/000227853.pdf 参照)。 また、本当に安全なら、i)電源三法による交付金 ii)原発関連施設の固定資産税 iii)電力会社からの寄付金 などの原発マネー(これまでに支払われた金額は総額2兆5,353億233万円と言われる)は不要な筈だが、原発立地自治体は原発が安全だと思っているからではなく、原発マネーが財政を潤すから原発の立地を受け入れているのである。しかし、1966年に日本で最初の原発が商業発電を始めてから既に55年が経過しているのに、未だに補助金を出さなければ運用できないような発電方法は既に破綻しているため、原発の処理と再エネ100%の実現こそが、汗をかき少し手を伸ばして可能にしなければならない課題なのだ。 なお、「デジタルの力で日本を前に進める」とも言われたが、デジタル化や自動化は民間では1980年代からやっているため、今頃、これを言わなければならないのは行政だけだ。さらに、デジタル化を当然としても個人情報保護や犯罪防止は必要不可欠であるのに、「デジタル化さえ進めば、後はどうでもよい」と考えている点で日本は著しく遅れている。なお、「自民党は保守政党だ」としながら「自民党を変え、政治を変える」と言うのは日本語の意味を間違えている。何故なら、「保守」とは、読んで字の如く「保ち守る」という意味で、「続けられてきた状態を維持し続けること、維持するための取り組み、維持するための主張」を指すからだ。 このような中、*5-4のように、①原子力規制委は中国電力島根原発2号機の安全対策が新規制基準に適合しているとする審査書を決定したが ②県庁所在地にある原発で事故時には46万人の住民避難が課題で ③中国電力は敷地近くの宍道断層による地震は基準地震動が最大加速度820ガルと想定 ④津波は最大11.9mと想定 ⑤三瓶山噴火の火山灰は最大56cm積ると想定 ⑥安全対策費は原発全体で6千億円程度の見積もっている そうだ。しかし、②は、事故時に46万人もの住民がどこに、どれだけの期間避難するつもりか問題であり、③の基準地震動は最大ではなく平均地震動であるため、最大地震動でも使用済核燃料プールの水がこぼれることはなく、管を含む原発のすべての部品が正常であるという前提に無理がある。④⑤については、その前提でよい理由は不明だが、事故が起これば歴史的に重要な地域で取り返しのつかない状況になることを考えれば、①は甘い審査だと私は思う。 なお、*5-5のように、台湾がTPP加盟の正式申請手続きを行うと、日本のメディアは、「⑥中国は中国大陸と台湾は1つの国に属するという『1つの中国』を唱えているため、中国の強い反発が予想される」「⑦対立する中台のTPP加盟を日本などの加盟国がどう判断するか外交的な駆け引きも含めて交渉が激しくなる」などと報道している。これに対し、台湾通商交渉トップの鄧政務委員は、「⑧中国はいつも台湾の国際社会との連携を阻もうとしてきた。もし中国が先にTPPに加盟すれば台湾のTPP参加は不利になる」「⑨台湾のTPP参加は台湾の利益と経済発展のために行うもので、中国の反対があっても彼らの問題だ」などと切り捨てて強い不満を表明されたそうだ。私は、独立国の意思決定に対する⑥⑦の質問や考察は失礼なので、⑧⑨の反発の方が尤もだと思う。また、尖閣諸島と同様、肝心なところで敵対する相手の顔色を見て首尾一貫性がなくなる国は、誰からも信用されなくなるだろう。   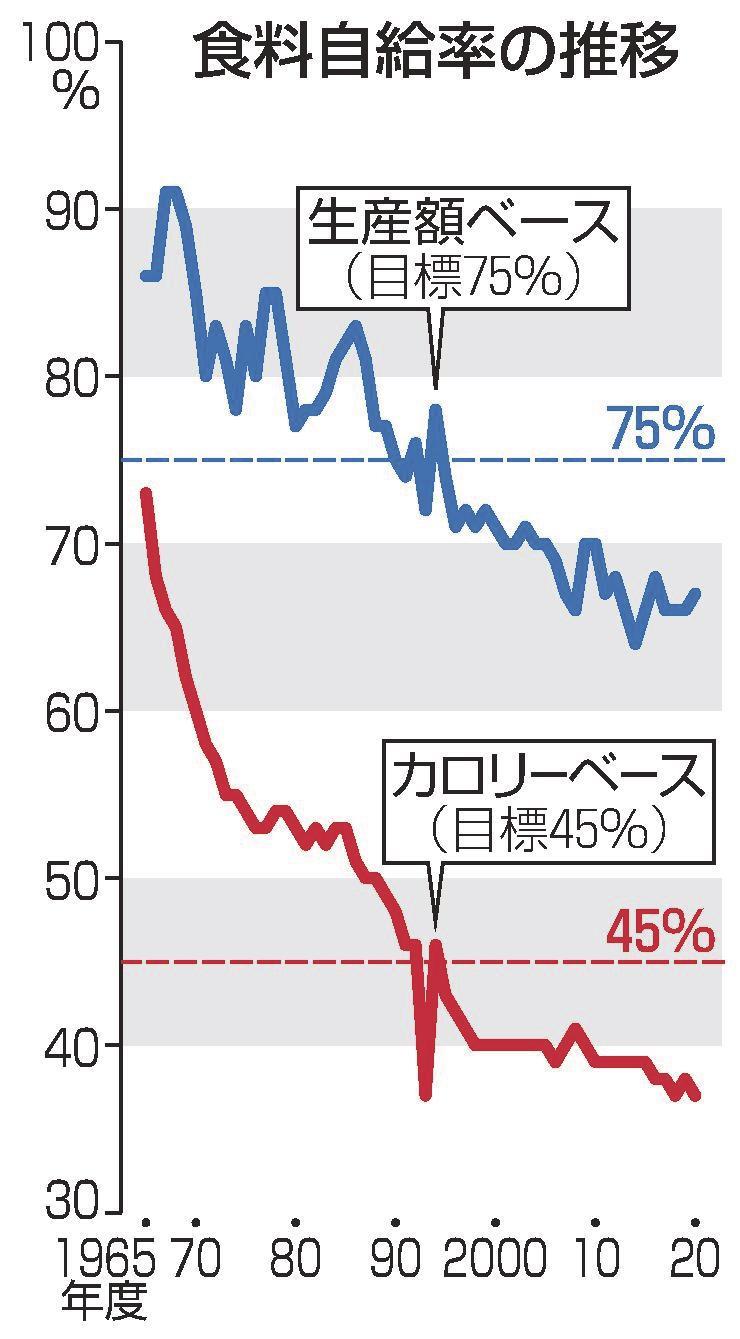 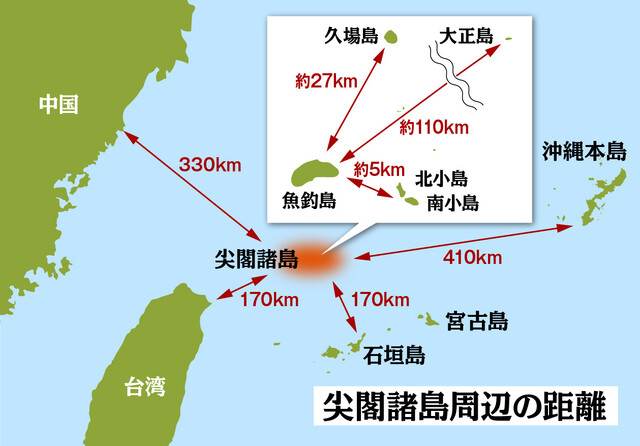 MotorFan Quara 2021.8.26山陰中央 2021.4.15Yahoo エネルギー自給率国際比較 食料自給率国際比較 食料自給率推移 尖閣諸島の位置 (図の説明:1番左の図のように、エネルギー自給率は先進国の中でも著しく低く、左から2番目の図のように、食料自給率も先進国の中でかなり低い。また、右から2番目の図のように、食料自給率は一貫して下がっており、政策が悪かったとしか言いようがない。さらに、1番右は尖閣諸島の位置関係を示す図で、沖縄県石垣島と中華民国《台湾》が170kmで等距離であるものの、中華人民共和国《中国》は330kmも離れており、全く関係ないと言える) 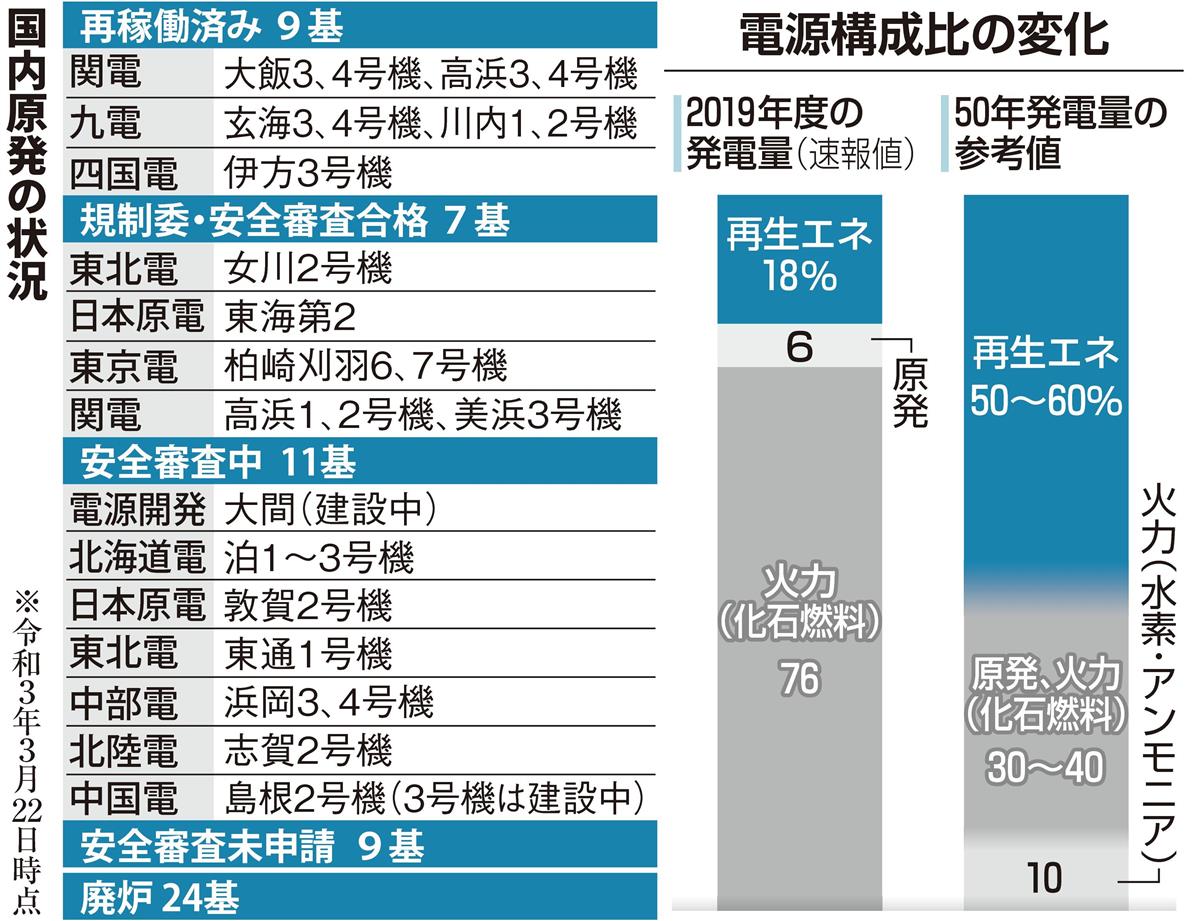 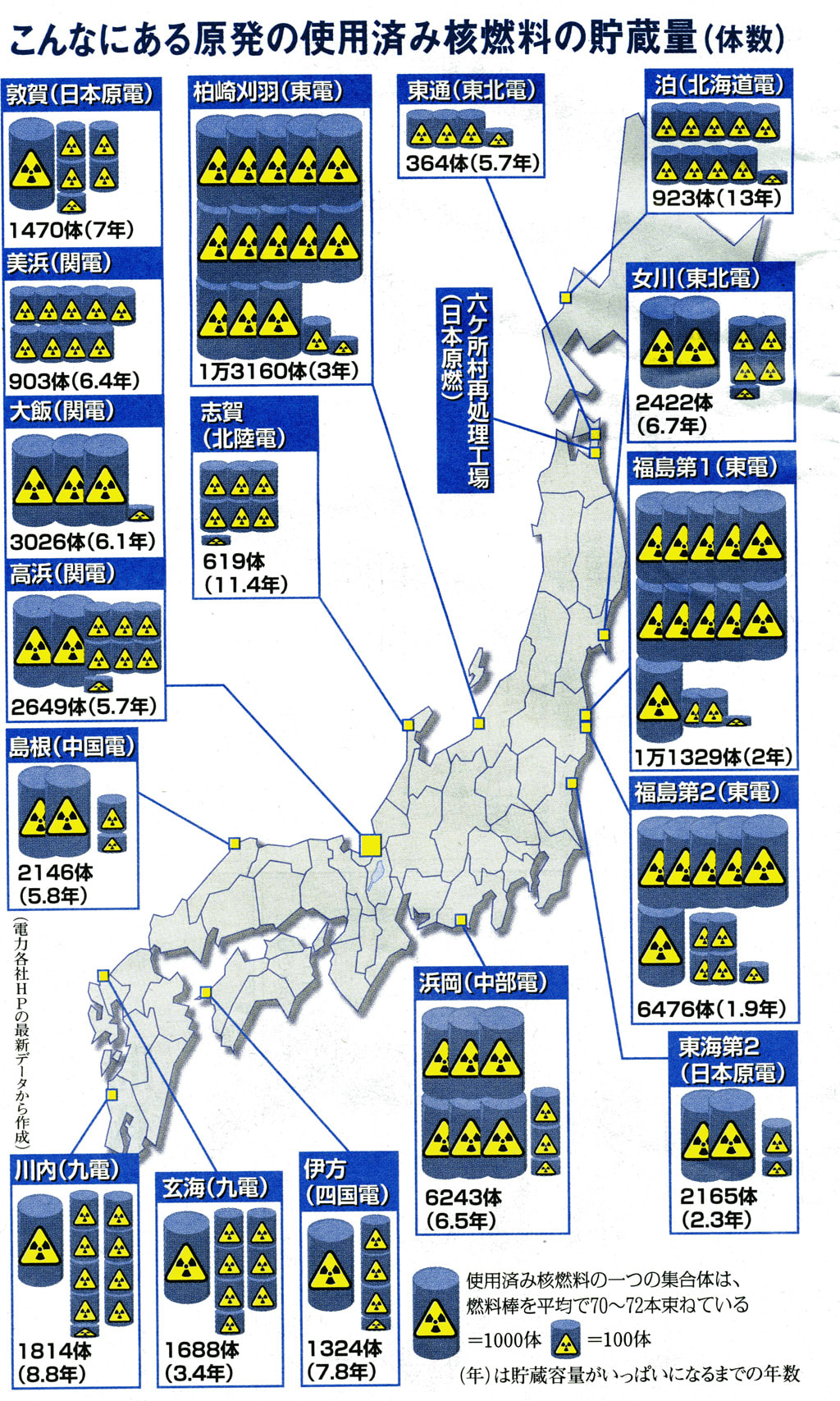 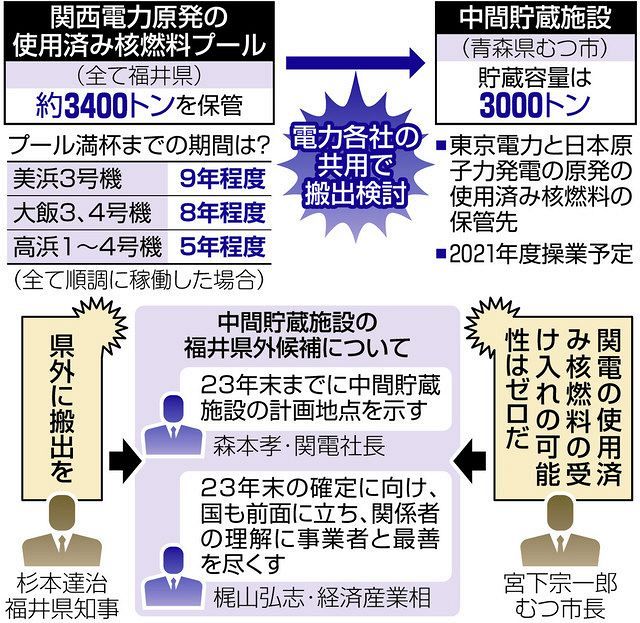  2021.4.9産経新聞 Goo 2021.4.29東京新聞 (図の説明:1番左の図のように、2019年時点で原発の発電量は6%しかなく、2050年までに原発と火力を30~40%にするということこそ、世界の流れに反しており、非現実的である上、理念が見えない。また、左から2番目と右から2番目の図のように、膨大な量の使用済核燃料が満杯に近く貯蔵されており、残りの貯蔵空間は少ないが、最終処分の方法もまだ決まっていない。そして、1番右の図のように、仮に玄海原発が自然災害や戦争による爆撃で爆発すると、歴史的に重要な場所を含む食料生産地域が汚染され、食料自給率は現在の1/4程度減ると思うが、日本政府は食料・エネルギーの自給率や食料の汚染にとりわけ疎いのだ) 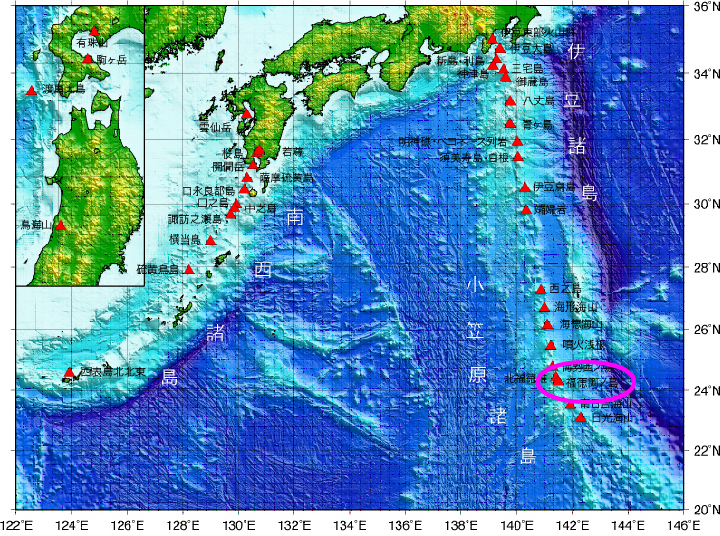 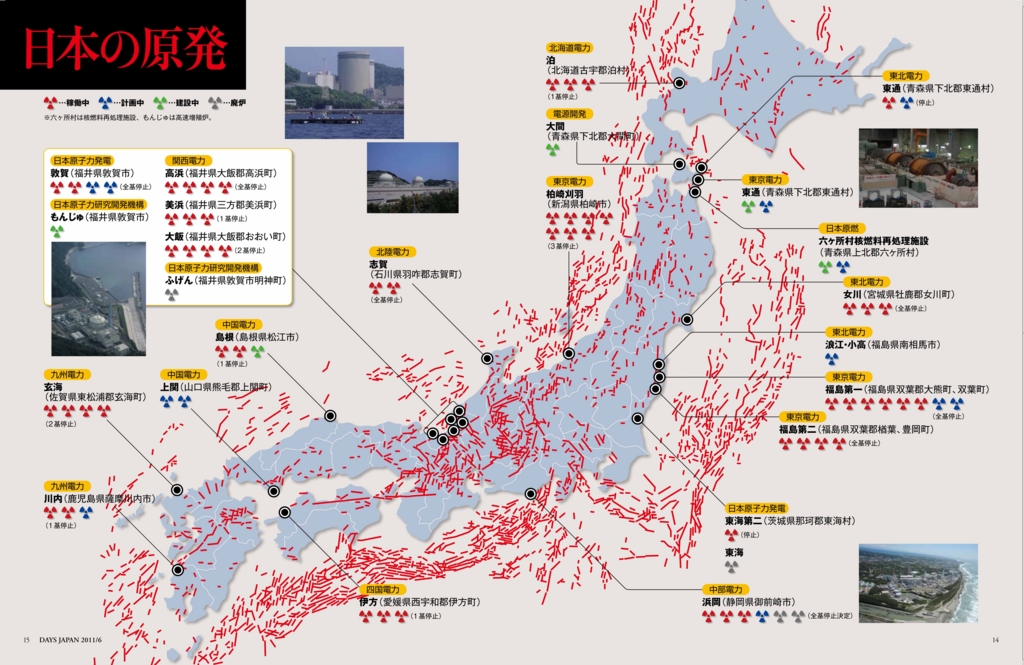 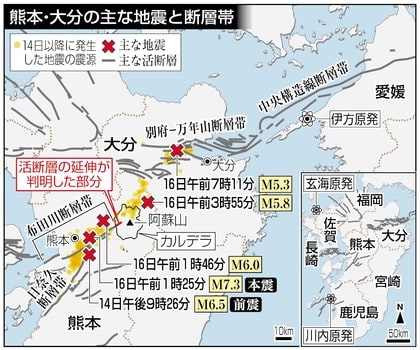 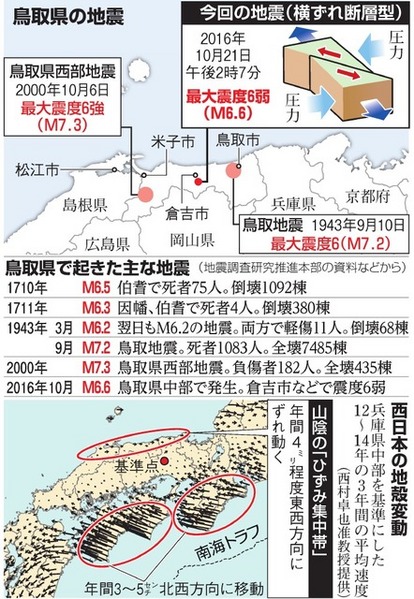 iMart 2016.6.19Goo 2016.10.21 朝日新聞 (図の説明:1番左の図のように、日本は北米プレートとユーラシアプレートの上にあり、ここに太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込んで、その内側に火山帯がある。そのため、左から2番目の図のように、押されてできた割れ目が多数の活断層になっており、知られている活断層が全てではない上、新しい活断層ができない保証もない。そして、右から2番目の図の熊本・大分の地震は中央構造線から連なる活断層の上で起こったが、特に伊方原発と川内原発は中央構造線に極めて近い場所にあり、図に活断層は描かれていないものの、近くには活断層が多いと考えるのが自然だ。また、1番右の図のように、2016年の鳥取地震では地殻変動によるひずみの集中で地震の起こるメカニズムが初めて明らかにされ、これもノーベル賞級の研究だと思う) *5-1-1:https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/84726 (山陰中央新報 2021/8/26) 食料自給率37% 過去最低 20年度、コメや小麦減少 農林水産省は25日、2020年度のカロリーベースの食料自給率が前年度から1ポイント低下し37%だったと発表した。1993年度と2018年度に並ぶ過去最低の水準。自給できているコメの需要減少や、ただでさえ輸入頼みの小麦の生産量が落ち込んだことが響いた。新型コロナウイルス禍で外食需要減少に伴う消費の落ち込みも押し下げた。新型コロナの影響では、家庭食の増加など自給率向上に寄与する要因もあったが、マイナス面が上回った。 1993年度は記録的なコメの凶作の年で、2018年度は長期的な自給率低下が続く中で天候不順となり、小麦などの生産量が減少し、いずれも37%だった。一方、生産額ベースの自給率は前年度から1ポイント上昇の67%だった。単価の高い豚肉や鶏肉、野菜、果実の生産額が増加した一方、魚介類などの輸入額が減少したため4年ぶりに上昇した。農水省の担当者は「外出自粛で清涼飲料水や土産物の菓子の需要が落ち込んだ」と説明。これらの原料として使用する砂糖類や植物油脂の輸入額が減ったことも上昇要因となった。品目別(重量ベース)の自給率では、コメが前年度と同じ97%、小麦は1ポイント下落し15%となった。野菜は1ポイント上がり80%、魚介類は2ポイント上昇の55%だった。農水省は19年度の都道府県別の食料自給率も発表した。カロリーベースでは北海道が216%で3年連続の1位となり、2位は205%の秋田県。東京都は都道府県別の統計として初めて0%を記録した。島根、鳥取はともに61%だった。 *5-1-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/735211 (佐賀新聞 2021/9/4) <オスプレイ配備>割れた意見、漁業者ら受け止めさまざま、配備候補地 地権者アンケート結果 オスプレイ配備計画の地権者アンケートで、計画への理解を尋ねた設問の結果は、賛否と「どちらとも言えない」の三つに割れた。土地売却の意向も、賛否に直接的にくくれない「条件次第で売却」が最も多く、地権者や漁業者の受け止め方はさまざまだった。漁協支所の運営委員の一人は、計画への理解について「どちらとも言えない」が3分の1を超えた点を「多くの人が判断しようがなかったのだろう」と推し量る。「説明不足」との指摘が相次いだ九州防衛局の地権者説明会を引き合いに「ずっと判断材料が不足したまま。アンケート結果をもってしても、どっちにも進めようがないだろう」。駐屯地予定地の直接の地権者が所属する漁協南川副支所では、「売却する」が「売却しない」をやや上回り「条件次第」が半数近くだった。微妙な数字で、田中浩人運営委員長は「正式な数字を見たばかりで、コメントする立場でもない。皆さんの考えが表れたものとしか言えない」と口数は少なかった。ただ、「条件次第」が多かった点には「どういう条件なのか精査し、今後、漁協内で協議すべきものと思う」とした。南川副支所の50代のノリ漁師は計画に賛成の立場で、土地を売却すると回答した。結果は「条件付きを含めると売却に賛成が多く、思った通り」と受け止める。配備で隊員や家族ら2千人以上が住み、地域活性化につながると期待する。「今回の結果を機に計画が前進してほしい」と話した。地権者でつくる有志の会の古賀初次さんは、質問が誘導的として疑問を呈しつつ「お金が欲しくない人はいないのだから、条件次第で土地を売ってもいいという人が多いのは当たり前」と指摘した。ノリ漁の準備が始まっており「この多忙な時期に、こんな大事なことを話すなんておかしい」と、漁協が防衛省のペースに乗って議論を進めていると批判した。 *5-2-1:https://digital.asahi.com/articles/ASP646HKSP62UTIL041.html (朝日新聞 2021年6月4日) 尖閣周辺の中国公船確認、112日連続 最長記録を更新 沖縄・尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で4日、中国海警局の公船「海警」4隻が航行しているのが確認された。接続水域での航行は2月13日から112日連続。2012年の尖閣国有化後、最長だった111日連続(昨年4~8月)を更新した。領海への侵入も今年は3日までに18件起き、漁船への接近もたびたび発生。海上保安庁は巡視船12隻を専従させて警戒を続けている。4日は午後3時現在、大正島沖で2隻、久場島沖で別の2隻が確認された。うち1隻は機関砲のようなものを搭載していた。通常、中国公船は4隻で航行していることが多いという。領海は、通常は潮が最も引いている大潮の干潮時の海岸線を基線とし、そこから12カイリ(約22キロ)までの海域をいう。沿岸国の主権が及ぶが、その国の平和や秩序を乱さなければ「無害通航権」といって他国船は事前通告なく通ることが認められる。この領海外側にある24カイリ(約44キロ)までが接続水域だ。沿岸国は犯罪が領海で起きるのを防いだり、違反した船を取り締まったりすることができる。日本は2012年9月に尖閣諸島にある五つの島のうち、魚釣島、北小島、南小島の3島を国有化した。それ以降、中国当局の船が周辺海域に近づく事案が頻繁に発生するようになり、領海侵入も増えた。1年間に接続水域内で確認された日数は12年は91日で、13年には232日に増加。一時期は減少していたが、19年に282日と再び増えると、昨年は333日と過去最多を記録した。頻度とともに懸念されるのは、船舶の大型化や武装化だ。海上保安庁が公開情報をもとに推定したところ、大型船(1千トン級以上)は12年に40隻だったが、昨年は131隻と8年間に3倍以上に増加した。海上保安庁の同水準の巡視船69隻を上回る勢力になっている。また、15年12月に機関砲を搭載した海警船も初めて確認され、以降は機関砲を搭載した船の接近が頻繁に発生している。海警局は18年7月に人民武装警察部隊に編入され、今年2月には武器使用を認める中国海警法も施行された。海上保安庁の奥島高弘長官は5月の定例会見で、尖閣周辺の情勢を「依然として予断を許さない厳しい状況」との見解を示し、「関係機関と緊密に連携して冷静にかつ毅然(きぜん)として対応を続け領海警備に万全を期す」と述べた。加藤勝信官房長官は4日の会見で「極めて深刻な事態と認識している。我が国として冷静かつ毅然(きぜん)と対応していく考えだ」と述べた。赤羽一嘉・国土交通相も4日の閣議後会見で「極めて深刻に受け止めている。海上保安庁では常に相手の勢力を上回る巡視船の隻数で対応し、万全の領海警備体制を確保している。事態をエスカレートさせず、冷静かつ毅然と対応を続けて領海警備には万全を期していく」と述べた。これに対し、尖閣諸島を自国領土と主張する中国は、中国公船の活動を「パトロール」と強調。日本政府が「国際法違反」と指摘している点について、中国外務省の汪文斌副報道局長は4日の定例会見で「釣魚島(尖閣諸島の中国名)と付属島嶼(とうしょ)は中国固有の領土であり、海警船が巡航することは、法に基づく正当な措置だ」と主張した。中国公船は12年の日本の尖閣国有化直後から定期的に航行するようになり、段階的に回数と態勢を引き上げてきた。自身も尖閣周辺のパトロール経験がある海警局元幹部は「365日の活動を可能にする『常態化』は10年以上前から計画されてきたものであり、日本側にもその意思を伝えてきた。当たり前のことができるようになっただけなのに、日本があおり立てて問題を大きくしている」と語る。日中両政府は14年、尖閣問題について「対話と協議を通じて、情勢の悪化を防ぐ」などとする4カ条の合意を交わした。だが、中国外交筋は「日本側はいつも『領土問題は存在しない』としか言わず、まともに議論する意思がない。日本の漁船が挑発的に尖閣領海に入っている状況からも、合意を破っているのは明らかに日本だ」と批判する。 *5-2-2:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1380399.html (琉球新報 2021年8月24日) 石垣市、国に尖閣上陸申請へ 行政標柱が完成、設置目指す 石垣市は23日、尖閣諸島への設置を目指している行政標柱が完成したと発表した。市が昨年10月に、市の行政区域に含まれる尖閣諸島の住所地の字名を「登野城」から「登野城尖閣」に変更したことに伴う取り組みの一環。市は今後、標柱設置のために国に尖閣諸島への上陸申請をしていくが、具体的な時期は未定という。23日に市内であった完成発表会で、中山義隆市長は「尖閣諸島とその周辺を取り巻く環境は大変厳しい状況が続いている。市はこれまで国に対し必要な措置を要請してきたが、いまだ状況に変化がない。尖閣諸島を市民、国民の皆さんに広く正しく知ってもらうことが重要だと考えている」と語った。標柱には石垣島産の御影石が使われ、「八重山尖閣諸島魚釣島」や「沖縄県石垣市字登野城尖閣二三九二番地」などと記されている。製作費は総額約200万円で、ふるさと納税による寄付でまかなった。国から上陸許可が出るまでの間は、この冬のオープンに向けて計画中の「市尖閣諸島情報発信センター」(仮称)で展示を予定している。 *5-2-3:https://news.yahoo.co.jp/articles/34ca6f79116d9ef11551a757e36c497cba10781c (Yahoo 2021年8月30日) 石垣市の尖閣標柱に日本政府「弱腰」 上陸申請めぐり“中国に屈した発言”も 石平氏「中国の反応など考慮する必要はない」 中国当局が東シナ海での休漁期間を解禁して以降、沖縄県・尖閣諸島周辺には連日、数十隻もの中国漁船が大挙して押し寄せている。日本の領土・領海を守り、先祖から受け継いだ海洋資源を守るためにも、尖閣諸島を行政区域とする石垣市は近く、「行政標柱設置のための上陸申請」を行う方針だが、日本政府は「及び腰」「弱腰」だという。これで、国民の生命や財産を守り抜けるのか。菅義偉政権の胆力が試される展開となっている。 ◇ 第11管区海上保安本部(那覇)によると、尖閣周辺の接続水域外側で25日、約60隻の中国漁船が操業しているのが確認された。中国当局が漁を解禁した16日以降、漁船を確認しない日はなく、19日には最多の約100隻が押し寄せた。海上保安庁の担当者は「接続水域や領海に接近する様子があれば、警告するとともに、違法操業があれば退去させる」と説明した。中国海警局船も要警戒だ。尖閣周辺の接続水域では26日、海警局船2隻の航行が確認された。18日連続で、1隻は機関砲のようなものを搭載していた。巡視船が領海に近づかないよう警告した。こうしたなか、石垣市は、昨年10月に尖閣諸島の字名を「石垣市字登野城」から「石垣市字登野城尖閣」に変更したことを受け、島名などを刻んだ行政標柱を製作し、23日公開した。魚釣島と南小島、北小島、久場島、大正島に設置する方針で、今後、国に上陸申請を行うという。中山義隆市長は同日の記者会見で、「尖閣周辺に中国船が連日出没し、大変厳しい状況が続いている」「これまでも国に対し、尖閣周辺海域の適正な管理や漁業者の安全操業の確保など、必要な措置を要請してきたが、状況に変化がない」「尖閣について国民に広く正しく知ってもらうことが大切だ」などと語った。行政標柱の設置は、日本の毅然(きぜん)とした姿勢を示すことになる。ところが、菅首相の女房役である加藤勝信官房長官は24日の記者会見で、「政府は尖閣諸島および周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として政府関係者をのぞき、何人も上陸を認めない」と語った。まだ、上陸申請が出ていない段階で、これを拒否する考えを示したのだ。日本沖縄政策研究フォーラム理事長の仲村覚氏は「菅政権の考えは、まったく理解できない。尖閣諸島は日本領土ではないのか?現在の状況では、『安定的な維持管理』ができているとは言えない。『中国に屈した発言』としか思えない。これでは、尖閣諸島だけでなく、他の領土も危ない」と懸念を示した。石垣市は淡々としている。企画部の担当者は、上陸申請を提出する時期を「検討中」としたうえで、「今回の標柱設置は、市の行政手続きの1つとして理解していただきたい。今後、申請にあたって政府に説明したい」といい、一切譲歩しない姿勢を示した。菅政権による新型コロナウイルス対策への不満などから、一部の世論調査では内閣支持率が30%を下回る「危険水域」に突入している。菅首相の地元・横浜市の市長選(22日投開票)では、首相が全面支援した候補が惨敗した。尖閣諸島に関する「及び腰」「弱腰」といえる姿勢は、習近平国家主席の中国にナメられ、さらに菅内閣の支持率を下落させかねない。中国事情に詳しい評論家の石平氏は「日本の領土である尖閣諸島について、(中国の反応などを)考慮する必要はない。ここまで中国を増長させた責任は、今回の加藤長官の発言をはじめとする、愚かな姿勢を示してきた日本政府にある。日本の領土であることをハッキリと主張して、行動すべきだ」と指摘した。 *5-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210911&ng=DGKKZO75676950R10C21A9MM8000 (日経新聞 2021.9.11) 河野氏「安全な原発は再稼働」 総裁選出馬を表明 河野太郎規制改革相は10日、国会内で記者会見し、自民党総裁選への出馬を表明した。原子力発電所について「安全が確認された原発を当面は再稼働させるのが現実的だ」と強調した。「デジタルの力で日本を前に進める」とも語った。新型コロナウイルス禍を踏まえ「皆さんと一緒に直面する危機を乗り越えていかなければならない」と訴えた。「人が人に寄り添う、ぬくもりのある社会をつくっていきたい」と述べた。総裁選への立候補を表明したのは岸田文雄、高市早苗両氏に続き3人目となった。出馬表明した3人で唯一の現職閣僚になる。規制改革、ワクチン担当の職務は続ける。河野氏は総裁選向けの政策パンフレットで「産業界も安心できる現実的なエネルギー政策を進める」と明記した。持論の「脱原発」政策を推進するとの見方があったため、現実的な路線をとると強調した。冊子は「日本を前に進める」と題し「自民党を変え、政治を変える」と掲げた。会見の冒頭で「自民党は保守政党だ」と指摘し「日本の一番の礎は伝統と歴史、文化に裏付けられた皇室と日本語だ」と力説した。保守層からの支持が念頭にある。記者会見では政府と日銀が掲げる2%のインフレ目標の達成に慎重な考えを示した。「かなり厳しいものがあるのではないか」と説いた。河野氏は10日夜のテレビ東京番組で、原発で燃え残った核燃料を再利用する「核燃料サイクル政策」に言及した。「方向転換することもテーブルの上に載せる必要がある。我々の責任で解決策を見いだし、実行していく必要がある」と話した。過去にも核燃料サイクルに異論を唱えていた。総裁選は17日告示―29日投開票で実施する。3人以上で争う構図になった。河野氏は世論調査で「次の総裁にふさわしい人」の上位に挙がる。日本経済新聞社の8月の調査は16%で首位だった。派閥横断的に若手を中心に衆院選の「選挙の顔」に期待する声がある。 *5-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/740315 (佐賀新聞 2021.9.15) 島根原発2号機が審査合格、全国唯一、県庁所在地立地 原子力規制委員会は15日の定例会合で、中国電力島根原発2号機(松江市)の安全対策が、新規制基準に適合しているとする「審査書」を決定した。これで正式に審査に合格した。合格は10原発17基目。事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉としては4原発5基目となる。全国で唯一、県庁所在地にある原発で、事故時の住民避難が課題だ。中国電は再稼働に向け、本年度内の安全対策工事完了を目指す。再稼働には、原発が立地する島根県と松江市の同意を得る必要があり、時期は未定。原発の30キロ圏に入る鳥取県などの動向も焦点となる。会合では、6月に取りまとめた審査書案に対する一般からの意見公募で、中国電が規制委から借り受けたテロ対策施設に関する機密文書を誤廃棄した問題に関し、「中国電に原発を運転する資格があるのか疑問」などの意見が寄せられたことを規制委事務局の担当者が説明。規制委側は、施設の運用ルールを定めた保安規定の審査の中で、引き続き中国電の改善姿勢を確認していくとした。審査書の決定には5人の委員全員が賛成した。中国電は、敷地近くの宍道断層による地震などを検討し、耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)を最大加速度820ガルと設定。最大で海抜11・9メートルの津波が敷地に到達すると想定し、海抜15メートルの防波壁を建設した。三瓶山(島根県)の噴火で敷地に最大56センチの火山灰が降り積もるとして対策を取る。中国電は2013年12月に審査を申請。18年には、新規稼働を目指して建設中の3号機の審査も申請した。1号機は17年から廃炉作業中。原発全体での安全対策費は6千億円程度と見積もる。 *5-5:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM230B00T20C21A9000000/?n_cid=BMSR3P001_202109231017 (日経新聞 2021年9月23日) 台湾、TPP加盟申請を発表 中国反発でも加入に強い意欲 台湾当局は23日、環太平洋経済連携協定(TPP)への加盟に向け、正式に申請手続きを行ったと発表した。同日午前、記者会見を開き、行政院(内閣)の報道官が明らかにした。加盟申請は22日午後に行った。中国の強い反発が予想されるなか、TPP加盟に強い意欲をみせた。TPPを巡っては、中国が16日に加盟申請を行ったことを公表したばかりだ。台湾として中国に加盟申請で大きく遅れれば、加盟が困難になるとみて申請手続きを急いだ。台湾の通商交渉トップである鄧振中・政務委員(無任所大臣に相当)は会見で、「中国はいつも、台湾の国際社会との連携を阻もうとしてきた。もし中国が先にTPPに加盟してしまえば、台湾のTPP参加は不利になることが予想された」と述べた。そのうえで、鄧氏は「台湾のTPP参加は、台湾の利益と経済発展のために行うものだ。中国の反対があっても、それは彼らの問題だ」などと切り捨て、強い不満を表明した。さらに「TPP加盟国は、台湾の貿易総額の24%以上を占める。今年、(閣僚級会合のTPP委員会の)議長国である日本とは非常に緊密な関係にあり、今こそ加盟すべき時が来た」と語った。蔡英文(ツァイ・インウェン)総統は、2016年の就任時からTPP加盟を悲願としてきた。台湾経済は中国に大きく依存している。台湾からの輸出は4割強を中国が占める。統一圧力を強める中国からの脱却を急ぐには、TPPに加盟し、中国への経済依存度を引き下げる必要があると判断した。ただ中国は、中国大陸と台湾は1つの国に属するという「一つの中国」を唱えている。台湾のTPP加盟には強硬に反対する姿勢だ。TPPには現在、日本やオーストラリアなど11カ国が加盟している。参加するには、加盟国すべての同意が必要となる。今後、対立する中台のTPP加盟を、日本などの加盟国がどう判断するか、外交的な駆け引きも含めて交渉が激しくなりそうだ。米国の今後の動きも大きな焦点となる。トランプ前大統領は17年1月、TPPから「永久に離脱する」とした大統領令に署名し、TPPから離脱した。バイデン政権が復帰を決定することは容易ではないが、中台の加盟申請でTPPを取り巻く状況は大きく変化しており、米国としても何らかの対応が必要になる可能性がある。 <アフガンへの支援と今後> PS(2021年9月17、18、24日追加):*6-1のように、タリバンが権力を掌握したアフガンで食料不足や物価高騰が深刻で、「①国民の93%が食事を十分にとれない事態で人道危機が迫っている」として、国連は、*6-2のように、9月13日、96カ国が参加する緊急会合で計12億㌦(約1300億円)超の拠出を表明した。グテレス事務総長は、ジュネーブの国連欧州本部で開かれた会合で「②事実上の政府であるタリバンとの関わりなしに人道支援を行うのは不可能」「③経済が崩壊すれば人道支援だけで問題は解決しない」「④国外資産凍結・IMF・世界銀行の支援停止などでアフガン経済はさらなる苦境に陥っている」と訴えたが、ドイツのマース外相や米国のトーマスグリーンフィールド国連大使は「⑤国際社会の支援を受けたいタリバンは政権発足にあたって女性の人権や旧政権に参加した人の安全などを守るとしていたが、既に多くの市民への暴力が報告された」と、タリバンの実行動に懸念を示されたそうだ。 また、*6-1には、2年前に戦闘に巻き込まれて夫を失い、自身も右足をけがして不自由になり、3歳から14歳までの7人の子どもと逃れてきた避難民女性が首都カブールの公園などにテントを張って暮らしている様子も書かれている。アフガンは食事も十分にとれない国民が93%に上るそうだが、男性は戦闘という破壊活動(生産とは反対の活動)を行い、女性は勉強も就業もできずに次々と7人も子どもを作っていれば、貧しかったり飢えたりするのは当然のようにも思うが、放っておくわけにもいかない。そのため、日本で消費期限が近づく災害用非常食や1年以上備蓄されている備蓄米・脱脂粉乳等々を、団体を通じて援助物資として送ったらどうか。その際、梱包する箱や袋に日本の国名・(男女を含む)作っている人の写真・農村の生産風景・再エネ発電等を映した印刷物を添付し、女性が働かなければ付加価値を高めることは困難で、豊かさは戦争をしても作れないことを示すメッセージにすればよいと思う。 なお、*6-3のように、イスラム主義勢力タリバンが首都カブールを制圧してから、自分たちの権利を守るために声を上げる女性も出てきているが、タリバンのメンバーが抗議デモの女性をムチで打つなど暴力を振るったり、女子学生への教育は認めたが学校で男女の間に仕切りを置いたり、女性は働くことができないと言ったり、女性に頭髪を覆うスカーフやブルカの着用を義務づけたりなど、女性差別が多すぎる。そのため、*6-1のドイツのマース外相や米国のトーマスグリーンフィール国連大使の懸念は的を得ているのである。 こちらが先だが、アフガンに平和・民主主義・人権・平等・信教の自由などを重視する憲法ができ、それに沿った民法・商法・税法等の法律ができれば、その後は、*6-4の中国主導の広域経済圏構想「一帯一路」やその他の鉄道・道路によって、アフガンで見込まれる非鉄金属・レアアース(希土類)等の資源開発や輸出が期待でき、バーミヤンの石仏などを復元すれば観光の要所にもなれるだろう。 *6-5のように、「⑥G20外相会議は、女性の権利尊重をタリバンに求めることで一致し」「⑦タリバンへの経済制裁については、維持を訴える米国と解除を求める中国で違いが明らかになり」「⑧G7は、タリバンに対し人権尊重・テロ対策・少数派を含む包括的な政権作りを求め」「⑨中国の王毅外相は、人道支援・難民問題に取り組むよう求め」「⑩中国は、タリバンとの意思疎通を続けて包括的な政権作りを促す方針でロシア等と協調して情勢の安定化を図る」とのことだ。⑦については、制裁をちらつかせながら「基本的人権の尊重」「男女平等」「信教の自由」等を定める憲法その他の法律を整備しなければ、⑥の女性の権利尊重はできないし、⑧⑩の人権尊重や包括的な政権作りもできない。そのため、よりよい形で安定をもたらすためには北風と太陽の両方が必要であり、男女平等に関しては、下の1番右の図のように、ドイツ11位・フィリピン17位・米国30位・韓国102位・中国107位・ミャンマー109位・日本120位と儒教・仏教・イスラム教を基盤とする国はキリスト教を基盤とする国より遅れているため、自由・平等・博愛を重視するキリスト教国に先導してもらった方がよいと思う。   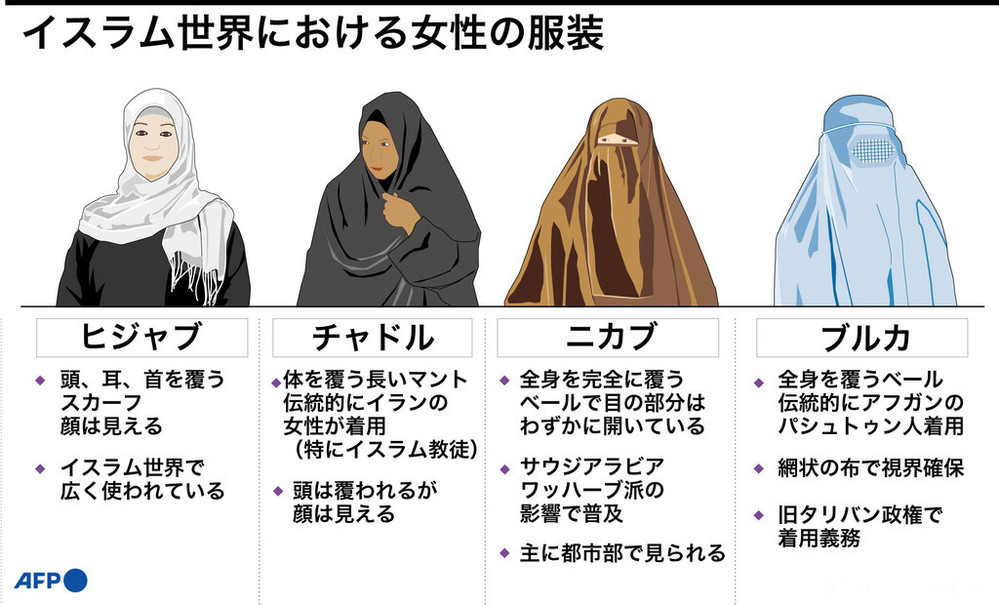   2021.9.10 2021.9.8CNN 2021.9.9afpbb 2021.9.17 2021.4.1 TokyoHeadline 日経新聞 毎日新聞 (図の説明:1番左の図は、アフガン女性が命がけで女性差別に抗議している様子で、左から2番目の図は、学校で男女間に仕切りを付けられた様子だ。また、中央の図は、イスラム世界において女性に許された服装で、男性目線のSEX中心でしかない。さらに、右から2番目の図は、鉱山開発のためにアフガンが期待する中国の「一帯一路」だ。そして、1番右の図は、男女格差の小さい順に並べた国名で、アフガニスタンは156ヶ国中156位で全体最下位である) *6-1:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210912/k10013255411000.html (NHK 2021年9月12日) アフガニスタン 国民の93%が「十分に食事をとれない事態」に 武装勢力タリバンが権力を掌握したアフガニスタンでは、食料不足や物価の高騰が深刻になっていて、国連は、国民の93%が食事を十分にとれない事態に陥っているとして、国際社会の支援が急務だと訴えています。アフガニスタンでは、仕事ができなくなったり銀行が閉鎖されたりして、多くの人が現金収入を絶たれ、食料不足や物価の高騰が深刻化しています。首都カブールには、国内各地で家を追われた避難民が公園などにテントを張って暮らしていますが、多くの人は近くの住民などが善意で運んでくれる食料を頼りにして飢えをしのいでいるということです。2か月半前に戦闘で家が破壊され、北部の州から子ども7人と避難してきたという女性は「子どもたちは飢えていて、ひと切れの小さなパンをめぐって奪い合いになっています。このひどい状況から抜け出すためにも支援が必要です」と話していました。WFP=世界食糧計画は、地域事務所の担当者がオンライン会見を開き、タリバンが権力を掌握した8月中旬以降、食事を十分にとれない人は、国民の93%にのぼるとして、支援のための食料の備蓄もなくなるおそれがあると説明しました。担当者は「冬を迎える前に助けを必要としている人たちを救えるかは、時間との戦いになっている」と話し、国際社会の支援が急務だと訴えました。 ●「誰も助けてくれず、取り残されている」 アフガニスタンで、各地での混乱を逃れ、首都カブールに避難してきた人たちは、多くが支援を受けられず、食事が確保できない深刻な状況に陥っています。このうちカブール中心部の公園には2000人余りの避難民がテントを張って生活しています。2か月半前に北部バグラン州での戦闘で家が破壊されたというザル・ベグムさん(42)は3歳から14歳までの子ども7人と逃れてきました。ザルさんは2年前、戦闘に巻き込まれて夫を失ったほか、自身も右足がけがで不自由となりました。着の身着のままで逃れてきたため食料を買う金もなく、近くの住民などが善意で運んでくれる食料だけが頼りですが、子どもたちの飢えをしのぐには十分ではないといいます。ザルさんは「政権の崩壊以降、誰も助けてくれず、取り残されています。私は足が不自由で、子どもたちもまだ幼いので食料の分け前をほかの人たちに取られてしまいます。子どもたちは飢えていて、ひと切れの小さなパンをめぐって奪い合いになっています。このひどい状況から抜け出すためにも支援が必要です」と窮状を訴えていました。 *6-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR13CXG0T10C21A9000000/ (日経新聞 2021年9月14日) アフガン支援でジレンマ 「タリバン政権」に米欧慎重、国連が緊急会合、1300億円超の拠出表明 アフガニスタンへの支援を協議する国連の緊急会合で各国は13日、計12億㌦(約1300億円)超の拠出を表明した。イスラム主義組織タリバンによる制圧後、食料不足や経済のまひ状態が続くアフガンに人道危機が迫る。「タリバン政権」の承認に慎重な国際社会は、暫定政権との協力をめぐりジレンマを抱えている。「事実上の政府であるタリバンとの関わりなしに人道支援を行うのは不可能だ」。国連のグテレス事務総長は13日スイス西部ジュネーブの国連欧州本部で開いた会合で、タリバンとの協力は不可欠だと繰り返し訴えた。会合には96カ国が参加した。国連が9~12月を乗り切るために必要としていた目標の6億ドルは達成できる見込みとなったが、グテレス氏は「経済が崩壊すれば、人道支援だけで問題は解決しない」とも述べ、アフガンが直面する現金不足の問題を指摘した。名指しこそしなかったものの、念頭にあるのは米国などが凍結した、アフガン中央銀行の約100億ドルもの国外資産だ。資産凍結や国際通貨基金(IMF)、世界銀行による支援の停止などで、最貧国の一つであるアフガン経済はさらなる苦境に陥っている。現金の不足で銀行は営業停止や引き出しの制限をしている。物価は高騰し、経済はまひ状態にある。国連開発計画(UNDP)によると、既に7割程度だった貧困率は22年半ばまでに97%に上昇する恐れがある。国民の3人に1人は次の食事もままならない状況だという。国際社会の支援を受けたいタリバンは政権の発足にあたり、女性の人権や旧政権に参加した人の安全などを守るとしているが、既に多くの市民への暴力が報告されている。7日に発表した暫定政権の顔ぶれには、国連制裁や米連邦捜査局(FBI)の指名手配対象が含まれた。女性や少数派の姿は見られない。ドイツのマース外相は「良いシグナルではない」と指摘。米国のトーマスグリーンフィールド国連大使も「言葉だけでは不十分だ。実際の行動を見なければいけない」とくぎを刺した。タリバン側との対話や調整を通じた大規模な支援や資産凍結の解除は「タリバン政権」の承認につながりかねないだけに、米欧は消極姿勢を崩さない。人道支援に約6400万ドルを拠出すると発表した米国では、13日の議会下院外交委員会の公聴会で懸念の声が出た。共和党のスコット・ペリー下院議員は「(米国民の)税金をテロ組織へ支払うことは米国の政策なのか」とブリンケン国務長官を問い詰めた。ブリンケン氏は「国連などを通じて支援する」と応じたが、議会の監視は厳しい。一方、隣国パキスタンはいち早く援助物資の空輸に動いた。パキスタンとともにタリバンと密接な関係を持つカタールも「無条件の支援」を国際社会に呼びかけている。12日にはムハンマド副首相兼外相がカブールを訪れた。中国は医療支援などでタリバンと接近している。王毅(ワン・イー)国務委員兼外相は8日、オンラインで開いたアフガン隣国の外相協議に参加し、「新型コロナウイルスワクチンを第1回分として300万回分寄贈する」と表明した。総額2億元(約34億円)分の食料や越冬物資なども提供すると述べた。ロシア、中央アジア諸国などとともに加盟する上海協力機構(SCO)の枠組みも活用してアフガンへの関与を強める。16日から2日間の日程で、タジキスタンの首都ドゥシャンベで首脳会議を開く。習近平(シー・ジンピン)国家主席がオンラインで出席する見通しだ。中国はアフガンからのイスラム過激派流入を警戒しており、人民解放軍は11日からロシア南部オレンブルク州で実施する対テロ合同軍事演習に参加している。タリバンとの関係を築き、復興を支援することでアフガンを安定させたい考えだ。 *6-3:https://news.yahoo.co.jp/articles/bdd36bb3e32f4f012c9261580af02629210e2879 (Yahoo、日テレ 2021/9/15) カブール制圧から1か月 タリバン支配下のアフガン女性たちの現状は? アフガニスタンでイスラム主義勢力タリバンが首都カブールを制圧してから1か月たち、注目されているのが「女性の権利」だ。旧タリバン政権下でその権利を大きく制限されてきた女性たちの間では、手に入れた自由がまた制限されてしまうのではないかと不安が広がっている。アフガン女性たちに現状を聞いた。 ●自分たちの権利を守るため 声を上げる女性たち 9月、首都カブールで行われた抗議デモ。自分たちの権利を守るために声を上げる女性も出てきている。デモに参加した女性たちは――「仕事に行けない女性、学校に行けない女性の助けになるために外に出ている。私は彼女たちの声になりたい」「アフガン女性は常に女性の権利を訴えてきた。アフガン女性も他の女性と変わりない。なぜ私たちは権利が無いのか。私たちもすべての権利を持つべきだ」。そして、9月8日、ロイター通信によると、タリバンのメンバーが抗議デモに参加した女性らをムチで打つなど暴力をふるったという話も出てきた。 ●旧タリバン政権下で権利を制限されてきた女性たち 1996年から2001年まで続いた旧タリバン政権下では、女性の権利は大きく制限されていた。例えば… ・頭の先からつま先まで全身を覆うブルカの着用義務 ・学校教育、就労の禁止 ・外出は男性親族の同伴が必要 などの制約があった。それが2001年、アメリカ同時多発テロをきっかけに、アメリカがアフガンを攻撃。旧タリバン政権が崩壊したことで、女性たちはそれまでの抑圧から解放された。女性YouTuberたちが登場し、日常生活の様子を動画で配信。おしゃれをして街を歩き、その様子を積極的に発信するなど、タリバン政権下とは打って変わって女性たちが輝いているように見えた。しかし、今回タリバンの支配が復活したことで、せっかく手に入れた自由がまた制限されてしまうのではないかという不安が女性たちの間で広がっている。 ●男女で仕切られた教室 タリバンは、「女性の権利を尊重する」として、12日には女子学生への教育を認めると発表したが、学校では男女の間に仕切りを置いたり、女性は頭髪を覆うスカーフの着用が義務づけられるなどさまざまな条件が課されている。タリバンの復権以降、女性たちはどんな思いで過ごしているのか、アフガン女性2人に話を聞いた。以前NGOで働いていて現在はパキスタンに避難している30代の女性――「タリバンから女性は働くことができないと言われ、新しい方針が決まるまでは家にいるよう言われた」「以前は、人と集まることも仕事もピクニックなども自由にできていたのに、今はそのすべてが奪われた」。日本に留学経験があり、現地の国際機関に勤めていた20代の女性――「出勤しても、オフィスは閉鎖され、タリバンの戦闘員に追い返され、いまだ出社できない状態」「外国人と仕事をしていたことが分かると危害を加えられる恐れがあることから、自宅の書類をすべて燃やした」「銀行にお金をおろしに行ったときには銃で武装したタリバン兵がいて、彼らの意に沿わない行動をしたら死につながってしまうだろう」と不安の中で生活している。20年ぶりに復権したタリバンは国際社会の目を意識して、表向きは女性の権利を保障すると主張している。しかし、女性たちの話や今実際に起きていることを見ていると、女性の権利がどこまで守られるのかは不透明で、今後、国際社会が注視していく必要がある。 *6-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210917&ng=DGKKZO75832810W1A910C2FF1000 (日経新聞 2021.9.17) タリバン、「一帯一路」意欲 パキスタンと道路接続も 鉱山開発、進展に期待 アフガニスタンを制圧したイスラム主義組織タリバンが大規模インフラ整備事業「中国・パキスタン経済回廊(CPEC)」への参加に意欲を見せ始めた。中国主導の広域経済圏構想「一帯一路」の関連で、アフガンの鉱山開発で利点がある。だが、アフガン情勢はなお安定せず、専門家は「中国はアフガンの加入に慎重だ」と指摘する。タリバンの報道担当は16日までに、CPECに加わりたいと述べた。中国とパキスタンを鉄道や道路で結び、同国南西部のグワダルの港を軸に発電所なども整備する計画で500億ドル(約5兆5000億円)前後の投資が見込まれる。鉄道や道路をアフガンに延伸すれば、同国で見込まれる非鉄金属やレアアース(希土類)などの開発を促せるとタリバンは期待しているようだ。アフガンは内陸国だが、パキスタンの港を使えば鉱物の輸出先を広げられる。中国は経済成長に欠かせない資源を大量に確保できる。タリバンを支えてきたパキスタンはアフガンへの影響力を強め、対立するインドをけん制できる。13日にはタリバンのメンバーがカブール近郊のアイナック鉱山を視察した。ロイター通信が報じた。中国企業は2008年、世界有数の銅鉱床があるこの鉱山の開発権を30億ドルで獲得したが、アフガン情勢が不安定だとの理由で、実質的な工事に着手していない。アフガンには未開発の鉱物資源が大量に埋蔵されているといわれる。中国は18年からタリバンにインフラでの協力を持ちかけてきたとされる。タリバンに近い関係者は「口頭では合意した。(タリバンの)暫定政権が国際社会に承認されれば、中国はアフガンで整備を進めるはずだ」と明かした。8日に開かれたアフガン周辺国の外相会議で中国は、アフガン側に穀物、防寒具、医薬品など3100万ドルの緊急支援を約束した。タリバンの報道担当は9月上旬の記者会見で「中国とよい関係を築きたい」と主張した。その前に中国の呉江浩外務次官補はタリバン幹部と電話で協議した。呉氏は「アフガンへの友好政策を励行する」という構えだった。だが、情勢に詳しいチェコの大学の専門家は「中国は焦らない。アフガンへの関与を深めるかどうか慎重に判断するだろう」と指摘する。パキスタンの内相は先週の記者会見で同国とアフガンの発展は相互に影響すると述べ、アフガンのCPEC参加を歓迎する姿勢をみせたが、この専門家は「パキスタンはテロの脅威にさらされており、CPECを広げれば同国のリスクも高まる」と説明した。 *6-5:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15053909.html (朝日新聞 2021年9月24日) 女性の権利尊重、G20要求 経済制裁、米中に相違 対タリバン イスラム主義勢力タリバンが政権を掌握したアフガニスタン情勢を協議する主要20カ国・地域(G20)外相会議が22日、オンラインで開かれた。米国務省によると、女性の権利尊重をタリバンに求めることで一致した。一方、タリバンへの経済制裁については、維持を訴える米国と解除を求める中国の姿勢の違いが浮き彫りとなった。米国務省によると、ブリンケン国務長官は外相会議で「制裁がアフガン市民に与える影響を抑えつつ、タリバンに対する制裁は維持する」との意向を示した。米政府は主要7カ国(G7)メンバーと足並みをそろえ、タリバンに対して人権尊重やテロ対策、少数派を含む包括的な政権づくりなどを求めている。タリバンは「人権を守る」などと表明しているものの、実際に行動で示すまでは制裁を維持したい考えだ。一方、中国外務省によると、中国の王毅(ワンイー)国務委員兼外相は「制裁を政治圧力のカードとすべきではない」と訴えた。米国や北大西洋条約機構(NATO)の拙速な撤退が混乱を招いたと非難し、人道支援や難民問題に取り組むよう求めた。中国はタリバンとの意思疎通を続けて包括的な政権づくりを促す方針。ロシアなどと協調して情勢の安定化をはかる姿勢を示している。日本外務省によると、茂木敏充外相は「タリバンに対し、多様な民族や宗派を含む包摂的な政治プロセスや、女性らの権利尊重を統一したメッセージで求めていくべきだ」と訴えた。 <無駄遣い・高齢者いじめ・消費税増税は何故起こるのか?> PS(2021年9月20日、10月2日追加):日本記者クラブ主催の公開討論会で、*7-1のように、自民党総裁に立候補した4氏が論戦し、河野氏はエネルギー政策のやりとりで「①私の脱原発は耐用年数が来たものは速やかに廃炉にして、緩やかに原子力から離脱していくことだけ」「②野田さんは将来も原子力に頼った方がいいと思っているのか」「③再エネを増やせなかったのは原発に重きを置こうという力が働いていたから」「④原発のコストが見直されて再エネの方が安いことが明確になった」「⑤核のごみの現実的な処分方法をどうするのかを議論をした方がいい」と言われた。私は、①②③④については、耐用年数が来ていなくても廃炉にすべきものやできるものはできるだけ早く廃炉にすべきだと思う。その代替は再エネ以外になく、日本の場合は再エネ化を進めることによって国や地方自治体に税外収入が入るため、呪縛のように言われている消費税増税を行わず、消費税を廃止することすらできる。また、最悪の事態に備えるのなら、⑤の核のごみも早急に処分すべきだ。 上の⑤を受けてか、*7-2のように、経産省が「⑥廃炉が相次ぎ、低レベル廃棄物の『蒸気発生器』と『給水加熱器』の処分を有用資源として安全に再利用されるなど一定基準を満たす場合に限り例外的輸出を可能にすることを新エネルギー基本計画改定案に盛り込んだ」「⑦電力会社から海外業者への支払いでコストが膨らむ可能性もある」そうだ。しかし、⑥について、私は、国内処分の原則は不要だと思うが、除染する人に被曝の可能性があり、除染の程度も疑問であるため、「放射性廃棄物を有用資源として安全に再利用する」とするのはよほどの放射能好きだ。また、⑦は、これ以上の負担を電力使用者にかけないためにも、安価に処分してくれるのでなければ、密閉した容器に入れて排他的経済水域内の3,000m以上深くて流れのない窪地に沈めるのが最も安価だと思う。しかし、その分量にも限界があるので、これ以上核廃棄物を増やさないことが最も重要だ。 また、*7-3のように、「⑧新型コロナ対策として人流抑制を考え」「⑨個人への給付金を検討し」「⑩緊急事態宣言より強制力の強いロックダウンに向けた法整備をする」と言った人もいたが、⑧⑩は感染症が蔓延しやすく、ワクチンや治療薬を作れない国のすることで、(もう長くは書かないが)日本はこれとは異なる。そして、今回の蔓延と個人の経済破綻は政治による人災であり、経済を止められて破綻した生産年齢人口の人が30万円の給付金をもらっても焼石に水だが、数が多ければ国民負担は大きい。つまり、生産年齢人口の人に補助しなければならないような政策を作ること自体が誤りなのである。 なお、*7-1では、「⑥全額消費税で支える基礎年金への制度変更」の話も出ていたが、これまで年金保険料を支払っていた人への基礎年金の支払いを停止するのは契約違反だ。そのため、最低保証年金を作るのなら、これまでの1~3階はそのままにして、最低生活に満たない人に保障する0階を設けるべきであり、その原資が消費税でなければならない理由もない。例えば、生産年齢人口にあたる人に景気対策として補助する政策をなくし、原発は早期にやめて再エネに変え、国内にある資源を有効に使って国や地方自治体が税外収入を獲得すればよいのである。 その1例は、*7-4のように、排他的経済水域内にコバルトリッチクラストが広く分布しており、コバルト・ニッケル・白金などのレアメタルやレアアース等を含む海底金属資源があるため、(国立公園内の地熱とともに海も国有なので)採取すれば国が税外収入を得られるのだ。 *7-5には、⑪バイク・自動車・航空機等を作ってきたホンダが宇宙事業に参入を表明 ⑫小型の人工衛星を載せるロケットを開発し、2020年代に打ち上げる目標 ⑬月面での作業ロボットも検討 ⑭火星探査の中継地と想定される月面での居住空間作りにも参画 ⑮地球から月面での作業ができる遠隔操作の分身ロボットにも取り組む ⑯地球と月の間の通信には遅延が生じるので、アシモの技術などを活用してスムーズに動かす機能を採用 などが記載されている。他の惑星における住居や作業ロボットは面白く、⑪~⑯は、既に必要な技術を持つ企業が多いので、それらとベンチャー企業を作れば比較的容易にできると思う。しかし、下の図のような海底金属資源を採取する海底作業にも、深海の圧力に耐える強靭な海底作業ロボットと運搬手段が必要で通信の遅延は生じないため、可能な会社は造船会社とベンチャー企業を作って、必要な機械を作ったらどうかと思う。そして、この装置の需要も国内だけではないだろう。 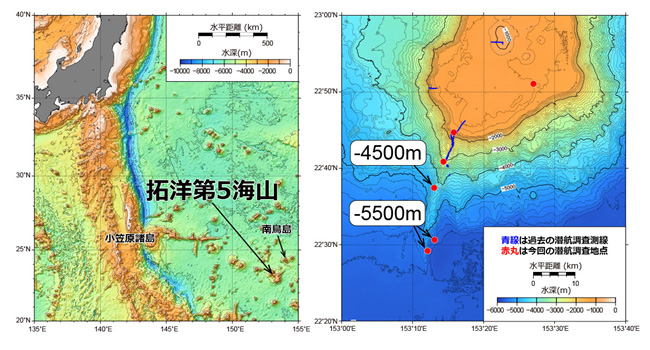   *7-4より (図の説明:左図は*7-4の図1、中央は図5、右図は図6で、日本の南東約1,800km沖にある巨大平頂海山の南斜面に、多量のコバルトリッチクラストが存在することがわかった) *7-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/803028/ (西日本新聞 2021/9/19) 「狙い撃ち」された河野氏のカウンター「原発に頼った方がいいんでしょうか」 「ポスト菅」を決める自民党総裁選(29日投開票)は18日、日本記者クラブ主催の公開討論会で立候補4氏による論戦が本格化。主役を張ったのは、報道各社の世論調査などで「次の首相にふさわしい人」の首位を走る河野太郎行政改革担当相だった。脱原発をはじめ数々のとがった改革志向の持論に対し、他の3氏が質問を集中。河野氏は「守り」の回答を崩さず、時には逆質問して「攻め」に転じる柔軟さも見せた。 ●改革志向の持論に定められた照準 相手を指名して見解をただせる討論会第1部の見せ場は、エネルギー政策のやりとりだった。自民内では少数派である河野氏の脱原発に照準を定め、野田聖子幹事長代行が「総理になったら、速やかに過去の発言を実行してしまうのか」と切り込んだ。河野氏は表情を動かさず、「私が言っている脱原発は、耐用年数が来たものは速やかに廃炉になる。緩やかに原子力から離脱していくことになる、というだけだ」。返す刀で、「野田さんは将来も、原子力に頼っていった方がいいと思っているんでしょうか」と切り返した。手元に準備した資料にはほぼ目を落とさない。「再生可能エネルギーを増やすことができなかったのは、原子力発電に重きを置こうという力が働いていたからだ」「原子力発電のコストが見直されて、再生可能エネルギーの方が安いということが明確になった」。こう畳み掛けた河野氏は、「原子力産業は、あまり先が見通せない」と言い切ってみせた。第2部で、原発の「核のごみ」を埋める最終処分場の場所が決まっていない問題を問われた際は、「もう、現実的な処分方法をどうするのかをテーブルに載せて議論をした方がいい」と一歩踏み込んだ。今回の総裁選。河野氏は支持の裾野を広げたいがためか原発再稼働の容認を明言し、脱原発の姿勢は玉虫色となった。だが、使用済み核燃料を再利用する「核燃料サイクル」の見直しは掲げ続けており、自民政権の伝統的な原子力政策路線との違いが際立っている。岸田文雄前政調会長は、そのアキレス腱(けん)を突き「(核燃料サイクルの停止は)原発再稼働と両立できるのか」「核燃料サイクルを止めればプルトニウムが積み上がり、外交問題にも発展しかねない」と整合性に疑問を投げ掛けた。 ●「一対一」の討論、最多の5回指名 河野氏の持論の一つである「税金で支える方式への公的年金制度改革」もまた、俎上(そじょう)に載せられた。 高市早苗前総務相は「基礎年金を税金で、となるとかなりの増税になる。年金制度の仕組みそのものに、大きなひずみが出てしまう」、岸田氏も「(消費税は)何%上がるのか」などと追及。これに対し、河野氏は「どれぐらいの年金を、どういう人を対象に支払うかによって税金の必要な額が違ってくる」と慎重な言い回しで言質を取らせない一方、「高齢者でも所得1億円の方に最低保障年金を出す必要はない」とアピールも忘れなかった。この日、候補者同士の「一対一」のやりとりは計12回あり、うち最多の5回で河野氏が質問相手に指名された。力をそいでおくべき標的に位置付けられたことは、自民の同僚議員間における人気は別として、国民的な知名度では頭一つ抜けている現実を裏付けた。 *7-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15048847.html (朝日新聞 2021年9月20日) 放射性廃棄物、海外委託も 国内処分の方針、転換 低レベルの原発主要機器 経産省 原発の放射性廃棄物は国内ですべて処分するという原則に関わる規制が、変わろうとしている。廃炉が相次ぐなか、低レベル廃棄物である一部の大型機器について、処分を海外業者に委託できるように輸出規制を緩和する。新たなエネルギー基本計画の改定案に方針が盛り込まれた。経済産業省が見直し案を検討するが、実施に向けては不透明な部分もある。海外での処分を検討しているのは「蒸気発生器」と「給水加熱器」、「核燃料の輸送・貯蔵用キャスク」の3種類の大型機器だ。いずれも原発の重要機器で、主なものだと長さは5~20メートル前後、重さは100~300トン前後もある。使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)ほど放射能レベルは高くはないが、低レベルの廃棄物として埋設処分などが必要だ。エネルギー基本計画の改定案に「有用資源として安全に再利用されるなどの一定の基準を満たす場合に限り例外的に輸出することが可能となるよう、必要な輸出規制の見直しを進める」と明記された。改定案には、今月3日から10月4日まで意見を公募している。国内ではこれまで原発24基の廃炉が決まり、2020年代半ば以降に原子炉の解体などが本格化する。国内に専用の処理施設がなく、発電所の敷地内で保管したままだと作業スペースが圧迫され、廃炉の妨げになると経産省は説明する。米国やスウェーデンでは放射性廃棄物を国外から受け入れ、除染や溶融をしたうえで、金属素材などとして再利用するビジネスが確立しているという。国際条約では、放射性廃棄物は発生国での処分が原則だ。相手国の同意があれば例外的に輸出できるが、日本は外国為替及び外国貿易法(外為法)の通達で禁じている。経産省は大手電力会社の要望などをもとに、専門家らを交えて検討してきた。国内処分を基本としつつ、対象を3種類の大型機器に絞り、再利用されることなどを条件に例外的に輸出を認める方向だ。法改正をしなくても通達の見直しなどで対応できるという。原発敷地内で保管している大型機器も対象になるとしており、稼働中の原発の廃棄物が輸出される可能性もある。電力会社から海外業者への支払額ははっきりしておらず、コストがふくらむ恐れもある。安全な輸送方法など課題は多い。規制が緩和されても、実施まで時間がかかりそうだ。低レベルの廃棄物は電力会社が責任を持って処分することになっている。原発の稼働や廃炉にともなって増えているが、処分先が決まらないことが大きな問題だ。たまり続ける廃棄物への地元住民らの不安感もあり、海外での処分に期待する見方もある。ただ、国内処分の原則を揺るがしかねないだけに、国や電力会社には十分な説明が求められる。 *7-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210920&ng=DGKKZO75906870Z10C21A9NN1000 (日経新聞 2021.9.20) 個人に給付金検討 一律の現金支給は否定 自民党総裁選の各候補は新型コロナウイルスの感染が再び拡大局面に入った場合の対策として、人流抑制を引き続き視野に入れる。個人への給付金を検討する考えを示し、一律の現金支給は否定する。規模や範囲、時期などが焦点になる。河野太郎規制改革相は19日のNHK番組で「次の緊急事態宣言に備えて給付金を一律ではなく、必要性や規模に応じて出せるようにする」と述べた。岸田文雄氏はかねて「非正規労働者や女性、困っている方々には直接給付金を用意しないといけない」と言明する。高市早苗氏は「本当にお困りの低所得者に手厚くする」と語る。野田聖子幹事長代行はクーポンでの配布を主張する。2020年4月に決めた経済対策で1人あたり一律10万円が特別定額給付金として支給された。所得が一定水準を下回った世帯に30万円を配る内容だったのを公平性や支給スピードを重視して転換した経緯がある。河野、高市両氏は緊急事態宣言よりも飲食店の営業制限などへの強制力が強い「ロックダウン(都市封鎖)」に向けた法整備の必要性に言及している。経済的な影響もより大きくなり、個人へのさらなる生活支援の議論が必要になる。 *7-4:http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20160209_2/ (国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立大学法人高知大学 2016年2月9日)5,500mを超える大水深に広がるコバルトリッチクラストを確認~コバルトリッチクラストの成因解明に大きな前進~ 1.概要 国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という)は、国立大学法人高知大学(学長 脇口 宏、以下「高知大学」)と共同で、戦略的イノベーション創造プログラム(※1以下「SIP」)の課題「次世代海洋資源調査技術(海のジパング計画)」における「海洋資源の成因に関する科学的研究」(研究代表者:鈴木 勝彦、JAMSTEC次世代海洋資源調査技術研究開発プロジェクトチーム成因研究ユニットリーダー)の一環として、日本の南東約1,800km沖に存在する巨大平頂海山 拓洋第5海山(図1左図)の南斜面において、無人探査機「かいこうMk-IV」(図2)を用いたコバルトリッチクラストの調査を実施しました(※2)。コバルトリッチクラストは、コバルト、ニッケル、白金などのレアメタルやレアアースの資源として期待されている海底の岩石です。今回の調査により、世界で初めて5,500mを超える大水深の海山の斜面においてコバルトリッチクラストの存在を確認し、研究用試料の採取に成功しました。今後、採取したコバルトリッチクラスト試料を詳細に分析・解析することによって、日本周辺におけるコバルトリッチクラストの成因解明に関する研究を進め、海洋資源調査技術の開発につなげていく予定です。 2.研究の背景・目的 形成後時間が経過した古い海山の斜面には、海山を形成する玄武岩や水深の浅い石灰岩等の基盤岩を覆うように鉄・マンガン酸化物を主体とした数mmから10cmあまりの厚さのコバルトリッチクラストが広く分布しており、コバルト、ニッケル、白金などのレアメタルやレアアース等を含む海底金属資源として注目されています(※3)。SIP「次世代海洋資源調査技術(海のジパング計画)」の「海洋資源の成因に関する科学的研究」課題においても、コバルトリッチクラストが対象となっており、科学的な研究を基にその調査技術の研究開発を進めています。過去にもJAMSTECの船舶・無人探査機を用いた拓洋第5海山の調査が行われており、水深3,000mより浅い海域において、系統的、かつ、連続的なコバルトリッチクラストのサンプリングや厚み計測などの調査が行われてきました。平成21年に海洋調査船「なつしま」航海(NT09-02 leg2、首席研究者:浦辺 徹郎、国立大学法人東京大学教授(当時))において、無人探査機「ハイパードルフィン」を用いて最初のコバルトリッチクラストの現場産状観察と系統的な試料採取が水深1,200mから3,000mまでの連続的な水深で実施されました(図1右図青線)。平成27年には、深海調査研究船「かいれい」航海(KR15-E01、首席研究者:飯島 耕一、JAMSTEC海底資源研究開発センター調査研究推進グループ技術主任)において「かいこうMk-IV」が拓洋第5海山の南方尾根にて潜航し、水深3,491mから3,360mの調査によってコバルトリッチクラストの産状観察と試料採取を行いました(図1右図青点)。JAMSTECにおけるこれまでのコバルトリッチクラストの研究で、採取された試料などから、同位体を用いた年代測定によって、コバルトリッチクラストの成長速度が数mm/百万年であることを明らかにするとともに(Usui et al., 2007; Goto et al., 2014)、モリブデン,タングステン、テルルなどのレアメタルがコバルトリッチクラストに濃集するメカニズムを解明し(Kashiwabara et al., 2011; 2013; 2014)、さらにコバルトリッチクラストの遺伝子解析(Nitahara et al., 2011)などを行って、多様な微生物が生息していることを明らかにしてきました。本調査では、コバルトリッチクラストの成因研究をさらに進めるため、無人探査機「かいこうMk-IV」を用いて、これまでの調査で成し得なかった拓洋第5海山の5,500m以深のコバルトリッチクラストの産状観察や試料採取を行って、拓洋第5海山のような巨大海山の大水深部にコバルトリッチクラストが広がっているかどうかを明らかにすることを計画しました。さらに、コバルトリッチクラストの現場環境と生成メカニズムの理解に向けて、電磁流速計、微生物現場培養・化学吸着実験装置の設置を計画しました。 3.成果 本調査では、無人探査機「かいこうMk-IV」を用いて、世界で初めて拓洋第5海山南方尾根の水深5,500mに広がるコバルトリッチクラストの現場観察に成功し、研究用のコバルトリッチクラスト試料を採取しました。これまでは、詳細なコバルトリッチクラストの調査のために、拓洋第5海山にて水深3,500mまでの現場観察と試料採取が連続的に行われていましたが、そこから2,000mも水深方向に延伸するものです。さらに、水深1,150m、3,000m、5,500mという異なる3つの水深での電磁流速計の設置、現場培養・化学吸着装置を設置しました。これによって、コバルトリッチクラストが形成される環境での有用なメタルを効率的に集めるメカニズムを観察し、さらには、コバルトリッチクラストの成長や有用メタル濃集に関わる微生物の観察が可能になり、コバルトリッチクラストの成因研究に大きな前進が期待されます。今回の調査で、南方尾根水深4,500m付近にコバルトリッチクラストが広がっていることを確認し(図3)、約2cmから約7cmの厚みのコバルトリッチクラストを採取しました(図4)。さらに南方へ進んだ5,500m付近では、崩れた崖が続く海底の所々に板状のクラストや庇状のクラストがあることを確認し(図5)、マニピュレータを使って幅30~40cm、厚さ約3cm~約8cmの板状の多数のクラスト試料を採取しました(図6)。これまで、大水深のコバルトリッチクラストのほとんどが船上からドレッジ(ケーブルで降ろしたバケツ状の採取器具を底引き網のように引っ張ること)によって試料が採取されているために、その試料は転石と呼ばれる現地性を確証できない試料でした。また、有人潜水調査船による火山岩の調査で同時にコバルトリッチクラストが採取された例はありますが、コバルトリッチクラストの調査を目的としていないため、散点的に発見されたものでその広がりは明確ではなく、試料採取も系統的なものではありませんでした。さらに、無人探査機を用いたコバルトリッチクラストの現場観察を系統的に行ったのは、拓洋第5海山の一連の調査のみで、水深も3,500mが最深でした。今回の調査により、拓洋第5海山の深さが5,500mを超える斜面にコバルトリッチクラストの広がりが確認され、さらに試料採取も行えたことから、コバルトリッチクラストの形成メカニズムを解明するための微生物学的・地球化学的機能の分析が行えるようになります。 4.今後の展望 採取したコバルトリッチクラスト試料の化学組成、同位体組成を分析し、水深によるレアメタル濃度(品位)の違いを調べます。そのデータと、海水の溶存酸素濃度や海水の元素組成とを比べることで、コバルトリッチクラストのレアメタル濃度を決めている要素を明らかにすることが期待されます。また、微生物の解析を行うことによって、コバルトリッチクラストに存在する微生物の種類等を把握します。現場培養装置と化学吸着装置は、いわゆる天然での実験装置であり、次年度に予定されている調査航海にて回収を行い、その分析・解析を行うことによって、深海におけるコバルトリッチクラストと海水との相互作用を把握し、コバルトリッチクラストに元素が濃集するメカニズムの全容を把握するとともに、微生物とコバルトリッチクラストの形成開始,成長との関わりを明らかにできることが期待されます。我々は拓洋第5海山をコバルトリッチクラストの成因研究を行うためのモデル地域と位置づけており、これまでの研究の蓄積と今回の成果、および、今後得られるデータにより、コバルトリッチクラストの成因の解明に迫ります。これを基にSIP「次世代海洋資源調査技術(海のジパング計画)」における「海洋資源の成因に関する科学的研究」の目的である高品位のコバルトリッチクラストの存在地域の予測と、調査手法の開発につなげます。これらの成果は、コバルトリッチクラストの鉱量評価にも貢献します。 ※1 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が自らの司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野の枠を超えたマネジメントに主導的な役割を果たすことを通じて、科学技術イノベーションを実現するために平成26年度より5カ年の計画で新たに創設したプログラム。CSTIにより選定された11課題のうち、「次世代海洋資源調査技術(海のジパング計画)」(プログラムディレクター 浦辺 徹郎、東京大学名誉教授、国際資源開発研修センター顧問)はJAMSTECが管理法人を務めており、海洋資源の成因に関する科学的研究、海洋資源調査技術の開発、生態系の実態調査と長期監視技術の開発を実施し、民間企業へ技術移転する計画となっている。 ※2 深海調査研究船「かいれい」KR16-01 leg1航海(首席研究者:飯島 耕一、JAMSTEC海底資源研究開発センター調査研究推進グループ技術主任、調査期間:平成28年1月9日~1月30日) ※3 コバルトリッチクラストの経済価値 一般社団法人日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)の見積もりでは、日本周辺のコバルトリッチクラストの経済価値は、回収率45%を仮定し、約100兆円とされている。現時点で商業的に採掘されている例は無く、深海から環境への影響を適切に評価しながら採鉱する技術を確立する必要がある。環境影響評価についてはSIP「次世代海洋資源調査技術(海のジパング計画)」の「海洋生態系観測と変動予測手法の開発」課題(研究代表者:山本啓之、JAMSTEC次世代海洋資源調査技術研究開発プロジェクトチーム生態系観測手法開発ユニットリーダー)において評価手法の国際標準確立を目指している。 *7-5:https://news.yahoo.co.jp/articles/314d36df22c554dc5246e96dffdbef0248786750 (Yahoo 2021/9/30) ホンダ、宇宙事業に参入 2020年代にロケットの打ち上げ目指す ホンダは30日、宇宙事業への参入を表明した。小型の人工衛星を載せるロケットを開発し、2020年代のうちに打ち上げることをめざす。国内の大手自動車メーカーが、打ち上げロケットを本格的に手がけるのは初めてという。月面で作業できるロボットなども、検討していく。ホンダはバイクや自動車、航空機など様々なものをつくってきた。宇宙事業は利益を出しにくいが、新領域に挑戦し、将来の成長の芽を育てたい考えだ。小形の人工衛星は、通信や地球観測などでの利用拡大が見込まれる。まずは高度100キロ程度の地球を周回しない「準軌道」に打ち上げ、距離を伸ばしていく方針だ。若手技術者を中心に19年末から開発をスタートした。エンジン開発で培った燃焼技術を応用する。火星探査の中継地として想定されている月面での居住空間づくりにも参画する。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で、生活に必要な水や酸素のシステム開発を進める。 ■月面開発に意欲 分身ロボットの実用化も 遠隔操作の「アバター(分身)ロボット」の実用化にも取り組む。月面開発が進む30年代以降に、地球にいながら月面での作業ができるようにする。アバターロボットは、VR(仮想現実)ゴーグルや手の動きを伝えるグローブをつけて操作する。開発中のものでは、コインをつまんだり、缶のプルタブをつかんだりできるようになったという。地球と月の間の通信は遅延が生じるため、人工知能(AI)を使って視線や手の動きなどから操作者の行動を予測し、スムーズに動かす機能を取り入れる。二足歩行ロボット「アシモ」の技術なども活用する。NTTデータ経営研究所によると、40年の世界の宇宙産業の市場は約120兆円で、20年の約40兆円から3倍になる見込みだ。小型衛星からのデータを、災害の予測や農業支援などへ活用することが期待される。民間の宇宙開発は広がっている。電気自動車メーカー、テスラを率いるイーロン・マスク氏の「スペースX」などが、大型ロケットを打ち上げている。国内では三菱重工業が大型の「H2A」を運用している。小型ロケットはコストが下がったこともあり、複数のベンチャー企業が事業化をねらう。ホンダは宇宙事業を大きく育てたい考えだが、競争は激しく開発費もかさむため、利益を出すのは簡単ではない。また、宇宙事業と並ぶ新領域として、4人乗りの垂直離着陸機「eVTOL(イーブイトール)」も開発する。試作機の実験を23年に北米で始め、30年以降の実用化をめざす。
| 男女平等::2019.3~ | 05:31 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2021,08,14, Saturday
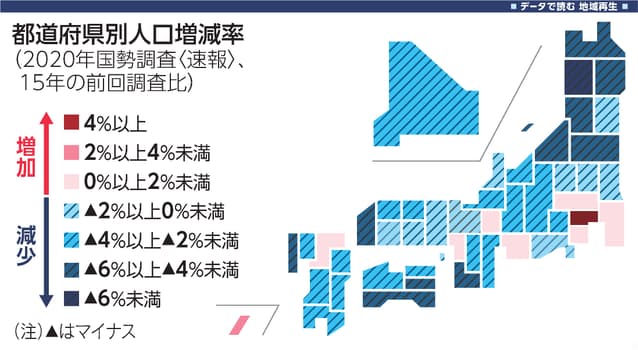  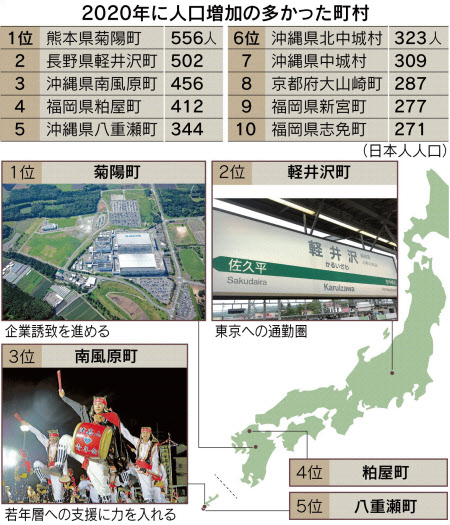 2021.7.16日経新聞 2021.7.16日経新聞 2021.8.13日経新聞 (図の説明:左と中央の図は都道府県別人口増減率で、今でも関東圏と福岡県・愛知県に集中し続けており、例外は沖縄県だ。その理由は、国策として関東・東海に集中投資して工業地帯を作ったこと、関東圏に若者を吸収する大学が多いことなどが理由であり、地方がさぼっていたからではない。沖縄県は、近年、地の利を生かして観光に力を入れ、出生率も低くないため、人口が増えている。右図は、最近、移住等に力を入れて人口を増やした市町村で、企業誘致を進めて働く場所を増やしたり、東京への通勤圏になったり、若者の支援に力を入れたりしているのだ) 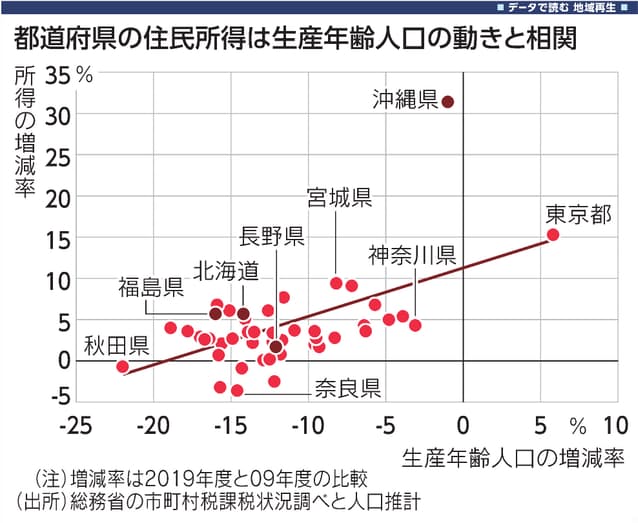 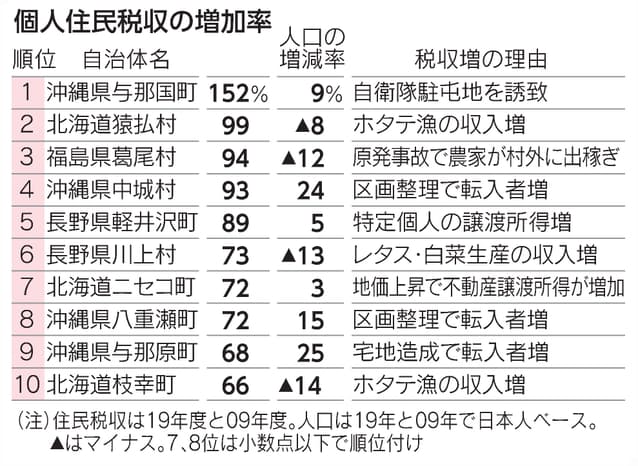  2021.7.2日経新聞 2021.7.2日経新聞 2021.8.13日経新聞 (図の説明:左図は、都道府県の住民所得は生産年齢人口の数と正の相関関係があるというグラフで、主たる稼ぎ手が生産年齢人口であることを考えれば当然だ。しかし、中央の図のように、農林漁業で個人所得を増やして個人住民税を増やした町村、区画整理・宅地造成で転入者を増やして個人住民税を増やした町村もある。ただ、沖縄県与那国島の自衛隊駐屯地誘致による個人住民税の増加は、新しく稼ぎだした所得というより所得移転によるものと言える。なお、右図のように、政府は「地域おこし協力隊」「地域活性化起業人」「テレワークの推進」などで移住促進計画を打ち出しているが、主たる産業の地方移転や筋の通った地方産業の活性化がなければ、ボランティアと腰掛に終わると思う) (1)農業の高付加価値化による地方の産業高度化へ 1)カイコから新型コロナワクチン 新型コロナについて、政府(特に厚労省)及び厚労省専門家会議は、2021年8月になっても「人流を減らす」しか言えていないが、*1-1-1は、①九大は世界的なカイコの研究機関で、2020年6月26日、カイコで新型コロナウイルスのスパイク蛋白質を生成できることを確認してワクチン候補となる蛋白質を開発することに成功したと発表し ②このスパイク蛋白質を注射したマウスに抗体ができるか否かの実験を2020年内に終わらせる方針で ③昆虫工場による大量生産により数千円で接種できるワクチンの臨床研究開始を来年度にめざす としている。 その後、この研究は、どうなったのだろうか。結果を出すのが遅すぎると他のワクチンが世界中に出回り、それよりよほど品質がよくて安価であることを証明できない限り、販売するに至らずもったいないことになる。そして、この技術を実用化しなければ、農業を高度化・高付加価値化する1つのよい機会が失われてもったいないのである。 なお、*1-1-2のように、遺伝子組換えカイコを使って新しい絹や医薬品の原料を作る研究が進んでおり、ヒト型コラーゲンを生成する遺伝子組換えカイコを作り、既に化粧品などに製品化しており、将来的には安全で安価な医薬品の製造も視野に入れているそうだ。私は、遺伝子組換えカイコが作る蛋白質で安全・安価な診断薬の原料となる抗体だけでなく、新型コロナの抗体も作ることができると考える。 2)米からコレラワクチン作成 東大の清野特任教授と幸特任研究員らは、*1-2のように、コレラの毒素を構成する部品からワクチンに使える無害な部分の遺伝子を組み込んだコメからできたワクチンの安全性をヒトで確かめたそうだ。米粒の中にワクチンの成分が入っており、すりつぶしてコメの粉末を飲むとワクチンの成分が腸に届いて免疫をつくるのだそうだ。また、コメに成分を封じ込めたため冷やさなくても長期間保存でき、冷蔵管理が難しくコレラが蔓延しやすい発展途上国で利用しやすいとのことである。ノーベル賞もののすごい発明だし、米の付加価値も上がるだろう。 なお、今後、遺伝子を組み換えたイネを大規模に栽培するためには、他にイネ科の植物がなく花粉が混じらない離島などの場所を選ぶか、ハウスで徹底管理するかする必要があるが、確かに、これなら理論上はあらゆる感染症のワクチンを同じ方法で開発でき、常温で保存できて、飲むだけで済むため利点が大きい。さらに、ワクチンだけでなく、抗体も作れると思う。 3)新型コロナの“治療”について 新型コロナの「抗体カクテル療法」が、*1-4-1のように、入院患者にしか認められていなかったが宿泊療養者にも使えるようになったそうだ。しかし、ウイルスが細胞に感染するのを防ぐ二つの中和抗体を組み合わせた薬であれば、軽症であればあるほど治癒しやすいので早期発見・早期治療が望ましいものの、中等症や重傷になっても根本的治療を何も行わずに「酸素吸入」「エクモ」を使った対症療法だけを行うよりは「抗体カクテル」を点滴した方が治癒しやすいので、厚労省が一律の単純な基準で制限を設けるよりも医師の判断に任せた方がよい。 そうすると、「抗体カクテル」の量が足りなかったり、高価過ぎたりするのなら、世界で使っている安価なイベルメクチンやアビガンなど他の武器も承認すればよい。このような中、いつまでも「病床が足りない」「自宅で亡くなる人もいる」など、不作為による人災を災害であるかのように言うのはいい加減にしてもらいたい。 なお、*1-4-2に、菅首相が、①自宅療養患者への連絡態勢を強化する ②患者が酸素投与を必要とした場合に対応する『酸素ステーション』を設ける ③軽症者の重症化を抑える抗体カクテル療法を集中的に使える拠点を整備する ④政府の新型コロナ感染症対策分科会提言を受けて、商業施設等の人流の抑制に取り組む と言われたそうだが、②③は別々の拠点ではなく、医師の判断で連続的に治療できるようにしなければ金ばかり使ってややこしくなるだけだ。 また、①については、新型コロナにかこつけてデジタル診療を推し進めようとしている人がいるが、感染症のように他人に感染する急性疾患に「自宅療養+デジタル診療」は向かず、成人病の手術後のように長期の療養を要するが他人には感染しない慢性期の療養に自宅療養が向くのである。そのため、この違いの分からない人が政策を決めているのが敗因であり、政府の新型コロナ感染症対策分科会も、相変わらず④のように人流抑制しか提言できていないが、その理由は説明されず、理由を説明するためのエビデンスも示されていないのだ。 4)住宅への木材活用と3Dプリンター 不動産各社が、*1-3-1のように、住宅に木材を活用する動きがあり、①住友不動産は戸建てリフォームで木材を再利用する取り組みを始め ②ケイアイスター不動産は注文住宅の国産材比率を100%に引き上げて環境配慮の姿勢を示し ③三井ホームは、強度や防音性などを高めてマンションを木造化できる新しい技術を開発して5階建て程度の中層マンションの木造化を進め ④三菱地所など建設・不動産7社も国産材の需要を掘り起こす取り組みを始めた そうだ。 近年は、湾曲した木材や間伐材などから製材した板や角材を乾燥して、節や割れなどの欠点部を取り除き、接着剤で接着してつくる集成材もあり、天然材と比較してかえって強度・寸法安定性・耐久性に優れていたりする。 また、*1-3-2のように、3Dプリンターを使って工場で住宅を製造して大型トレーラーで運んで施工するマイティ・ビルディングズのような会社もあり、⑤3Dプリンターに事前に図面データを入力し ⑥データ通りにノズルを動かし、紫外線を当てればすぐ硬くなる建築素材を噴射して積み重ね ⑦(例えば)天井部分の工程は、柱やパネルを設置した後で上から覆うように建築素材を噴出して形成し、固まった層は外壁や床材などになって現場工事が要らず ⑧小型住宅なら10日で完成し ⑨従来の建築工法と比べて費用を30%削減できる そうである。 大林組も3Dプリンターで大型ベンチを試作し、竹中工務店は2023年以降にイベント施設などの建築向けに3Dプリンターを導入する考えで、3Dプリンターは自由にデザイン設計しやすく、製造に携わる人手を減らせることも利点なので、三菱重工業は国産ロケット「H3」でエンジン噴出口部品の加工に3Dプリンターを採用したそうだ。 日本は災害が多いため建築法規制が厳しいのが課題だそうだが、集成材で骨組みを作り、3Dプリンターで作った小型の部屋を積み重ねれば、強度があり、軽くて断熱効果の高い住宅を、人手を省いて安価に作れそうだ。 5)再生医療と3Dプリンター 再生医療でも、*1-3-2のように、医療スタートアップのサイフューズが開発した3Dプリンターは、臓器疾患のある患者から採取した細胞を培養し、細胞を剣山に刺していって次第に細胞同士がくっついて固まることにより数週間で患者専用の臓器を製造する。この臓器は、患者自身の細胞で作るため移植後に感染症や拒絶反応が生じにくく、まず血管や骨軟骨などで臨床試験に入るそうで、2025年度にも移植手術で利用できるようにしたいそうだ。 3Dプリンターで作って欲しい患者専用臓器(歯も含む)には、ほかにどんなものがあるかを意見募集すると意外性があって有意義だろう。 6)代替肉と3Dプリンター 食品業界では、*1-3-2のように、イスラエルのリディファイン・ミートが3Dプリンターで代替肉によるステーキなどを製造する技術を開発し、アジア市場ではハンバーガーなどの製品群を2022年に提供する方針だそうだ。3Dプリンターが得意な分野を見いだして使いこなすことで、かなりのイノベーションが期待できる。 (2)農林漁業の販売力向上による地方産業の高度化 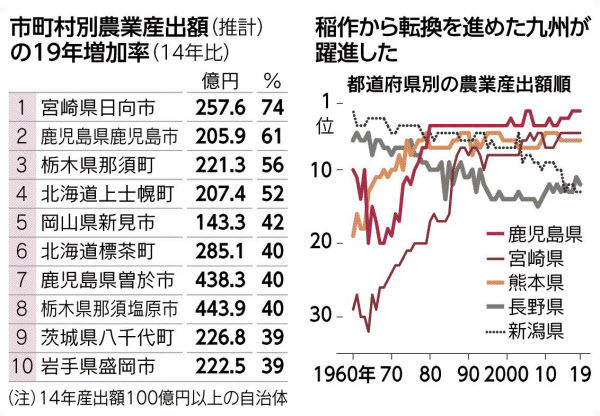 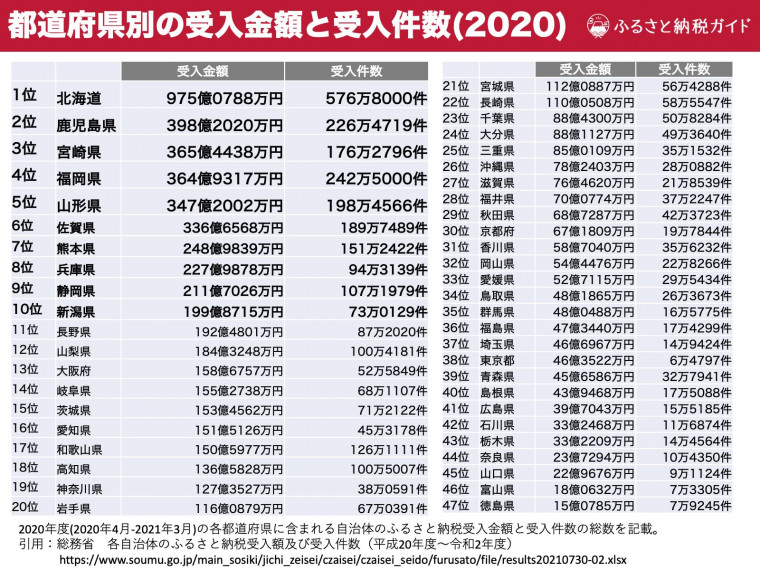 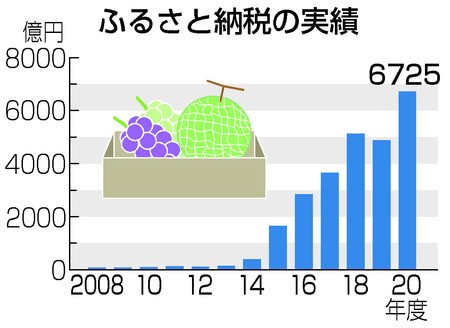 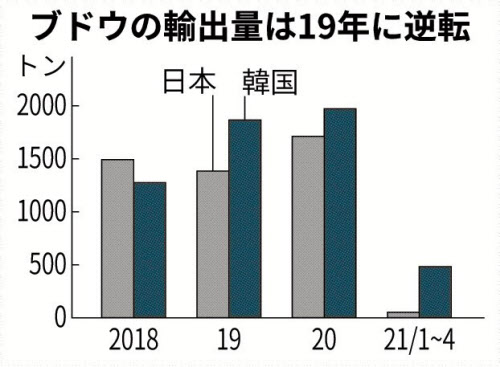 2021.8.14日経新聞 2021.8.12ふるさと納税ガイド 2021.7.29時事 2021.8.15日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、農業産出額は北海道・宮崎県・鹿児島県の市町で多く、ふるさと納税受入額の大きい地域と一致しているが、そこには努力があるのである。また、左から2番目の図のように、九州7県のうち5県までがふるさと納税受入額上位10県に入っている。ふるさと納税受入総額は、右から2番目の図のように著しく増えたが、これは皆で育てた結果だ。なお、1番右の図のように、日本の品種であるシャインマスカットの生産量・輸出量は韓国の方が大きくなっており、これは情けない限りだ) 1)農業の販売力向上と関連産業育成による地域での付加価値増加ついて *2-1は、「①2019年の農業総産出額は8兆8938億円で、北海道が1位で1兆2558億円、2位以下は鹿児島県・茨城県・千葉県・宮崎県・熊本県の順」「②農業競争力に大きな差が生じ、過去5年間で全国1741市区町村のうち6割が産出額増加、4割が減少」「③1960年時点は米どころが上位だったが、米の需要低下で稼げる農業の内訳が一変」「④躍進する九州勢の取り組みは地域ブランドを活用した『売れる農業』」「⑤稲作から施設を使った畜産・園芸への転換を進めた宮崎県などの九州勢が躍り出た」「⑥稼ぐ力を確立した地域が強みを発揮する」「⑦宮崎県では関係者が一丸となった競争力向上の取り組みが進み、県は1994年に『みやざきブランド確立戦略構想』を策定して『作ったものを売る』から『売れるものを作る』を目標にした」等を記載している。 このうち、⑥については、宮崎県や鹿児島県は1994年頃からやっていたのかもしれないが、私が衆議院議員になった2005年の段階で佐賀県の地元農協や農家を廻った時には、まだ「ブランド戦略」「『作ったものを売る』から『売れるものを作る』発想」はあまりなく、「米が安すぎる」「補助金が欲しい」という話が多かった。そのため、「食料自給率は低いのに・・」と思って自民党の農林部会で問題提議したところ、農水省は「国民が米より小麦製品を多く食べるようになって不得意分野の比重が高くなったから」と答えた。つまり、「国民が米を食べればいいのに」という発想だったし、意思決定権者が男性中心で栄養学の知識に乏しいためか、その発想は今でも残っている。 私は唖然としながら、製造業の監査・原価計算・経済学で得た知識・経験をフル活用し、i)大規模化による生産性の向上 ii)転作補助金の作成 iii)副産物の活用 iv)農地・水・環境維持のための補助金作成 などを行った。そのうちに、経産省が農業の6次産業化案を出して、第一次産業として原料を作るだけでなく、第二次産業の加工や第三次産業のサービスも組み合わせて地域で付加価値を高めることになり、現在に至っているわけである。 2)ふるさと納税の意義は、地方自治体の財源だけではないこと 地方公務員も税金で養われているため、「新しいことをして摩擦が生じるよりも現状維持のまま問題を起こさない方がよい」という現状維持型・やる気なしの人が多い。そのため、ふるさと納税で地方の努力を誘発しなければ、都会に集中する税収から地方交付税という形で多くの金を地方に配分し、少ない機関車で多くの客車を引っ張らなければならなくなって大変なのである。 そのような中、私が提案してできた「ふるさと納税」は、生産年齢人口の多くが都会に出るため税収が増えにくい地方の財源を少し取り戻しただけでなく、地方公務員をやる気にさせて地域ぐるみで優良な産品を作り出すのにも役立った。その理由は、i)地方公務員が頑張れば頑張るほど、目に見えて地方税収が増え ii)都会の消費者が価値あると感じる物を、地方公務員と農林漁業者が直接知ることができ iii)地方に多い農林水産物の価値を知るため、地域ぐるみでそれを高める工夫に繋がり iv)一村一品どころではない地方の製品の発掘・開発が進んだ からである。 そのふるさと納税は、*2-2-1のように、2020年度の寄付総額が約6,725億円で過去最高になり、嬉しいことだ。「巣ごもり需要」を背景に各地の返礼品を探して楽しむ寄付者が増えたためとのことだが、寄付総額は2019年度の1.4倍に増加し、自治体別の受け入れ額は、1位が宮崎県都城市の135億2,500万円で、2位が北海道紋別市の133億9,300万円であり、これは農業の高付加価値化の努力をしている県と重なっている。 また、ふるさと納税による2021年度の住民税控除額は約4,311億円で、東京都が参加していないため、最多は横浜市の176億9,500万円で、次は名古屋市の106億4,900万円、大阪市の91億7,600万円の順だった。 なお、*2-2-2のように、今後は太陽光発電や風力発電などの再エネの普及が進み、電気の約半分は市内産という長崎県五島市のように「原料の安全・安心は当たり前」「島の風と太陽から生まれた電気で製造」という取り組みや福島県楢葉町・愛知県豊田市・大阪府泉佐野市などが提供していた電気の返礼品なども増えると面白い。 3)それでは、見直すべきは何なのか このような中、*2-2-3は、「①ふるさと納税による寄付の膨張が止まらない」「②コロナ対策で農水省が始めた農林水産品の販売促進の補助金を使えば返礼率を大幅に高めることができる」「③高所得者ほど返礼品を多く受け取れ税優遇も大きい」「④昨年度の寄付額から換算すると全体で約3千億円の税収が失われたことになる」「⑤コロナ感染が特に広がっている東京などの都市部は、財源の流出で感染対策の費用を賄えない事態になっては困る」「⑥自治体間の財政力格差を是正するなら、今の地方税や地方交付税のあり方が妥当か否かを正面から論じるべき」「⑦ふるさと納税を続けるなら、返礼品をなくすなど抜本的に制度をつくり変えるべき」「⑧見直しの議論は進んでいない」と記載している。 しかし、①は、努力の賜物であって喜ばしいことであり、②は、東京で大流行している新型コロナによる東京での飲食店閉鎖で行き場を失った原材料の農水産物の販促を農水省が手伝い、これに市民が協力しているということで、高所得者は累進課税で多額の税を支払っており、ふるさと納税の限度額はそのごく一部にすぎないため、③はひがみ・妬みを利用した誹謗中傷である。また、④はどうやって計算するのかわからないが、⑤を含めて、もともと東京には投資が集中しているのに、東京五輪でさらに東京に集中投資した金額と比較すれば小さなものである。 そして、⑥は、消費税の全額地方税化など考えられる変更はありうるが、だからといって、このままでは都市部に生産年齢人口が集中するのは避けられないため、地方分散の名案を提案して見せるべきである。さらに、⑦⑧は、全貌の見えていない人が、「高所得者への妬み」と「返礼品憎し」で述べた主張であるため、実現すれば改悪になる。 4)特許権・商標権登録の重要性 高級ブドウ「シャインマスカット」など日本で開発されたブランド品種が、*2-3のように海外流出し、流出先の韓国で輸出の主力となって日本の5倍超の輸出額になったそうだ。また、栽培規模は日本1,200ha、韓国1,800ha、中国5万3,000haと桁違いだそうで、これでは日本のブランド農産物輸出額が減少する。 日本が開発費を支払って開発した品種は日本の財産であるため護るのが当然だが、法規制がされていなかったり、法規制しても実効性のない形で行われていたりすることが多い。ただ、葡萄やイチゴなど、果実を輸出すれば種も同時に輸出され、その種から栽培することが可能なものは流出防止できないため、世界ベースで特許権・商標権を登録しておくことが重要なのである。 (3)再エネによる地方産業の育成 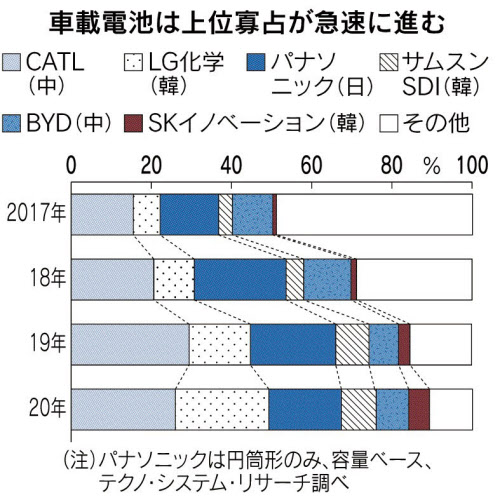 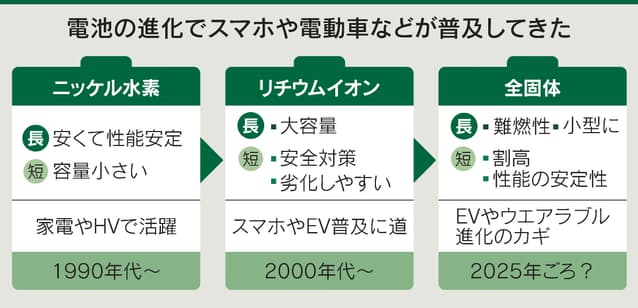 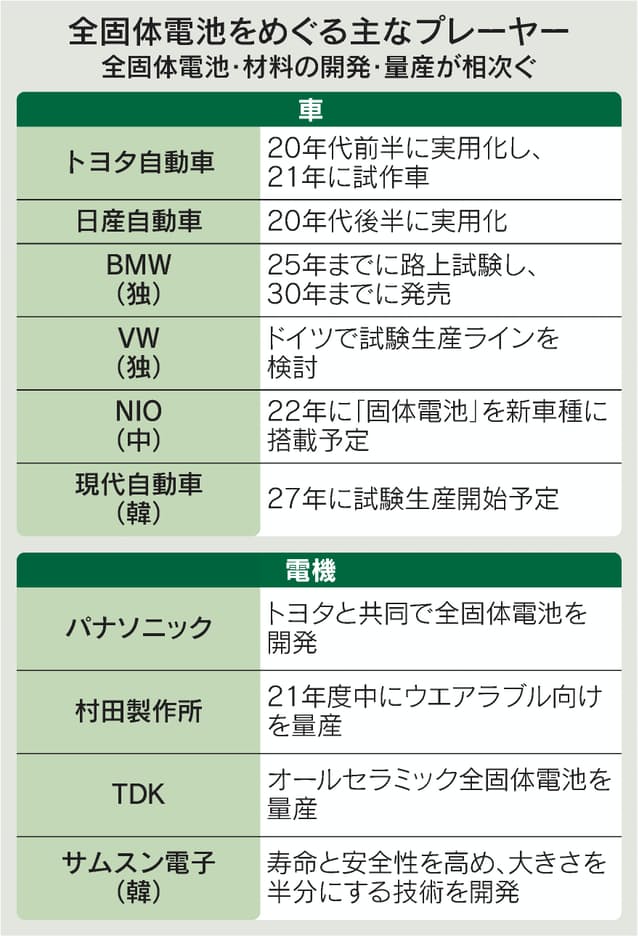 2021.5.22日経新聞 2021.6.3日経新聞 2021.6.3日経新聞 (図の説明:左図のように、日本でEVにくだらないケチを付けている間に、世界では車載電池の寡占が進み、中国・韓国の企業が善戦している。そして、中央の図のように、確かに電池も進歩しており、リチウムイオン電池の容量も大きくなったが、さらに安心して使えるためには、安価な全固体電池の市場投入が必要だ。また、右図のように、全固体電池をめぐる主なプレーヤーは、自動車会社と電機メーカーである) 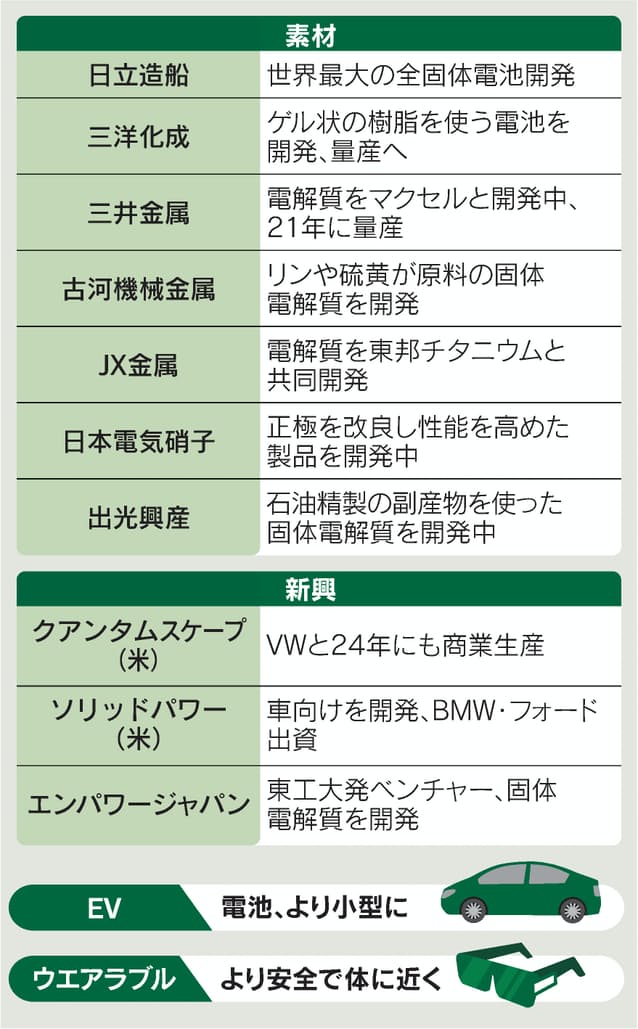 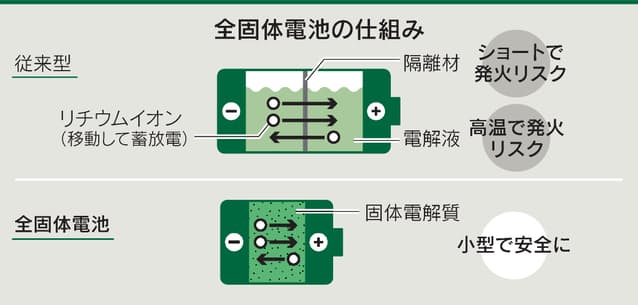  2021.6.3日経新聞 2021.6.3日経新聞 2021.8.19日経新聞 (図の説明:左図のように、EV電池はより小型に、その他はウェラブルなほど小さく軽くなるそうで楽しみだ。中央の図は、全固体電池の仕組みをリチウムイオン電池と比較したものである。ただし、右図のように、自動車は、EV化だけでなく自動運転化も進んでおり、これらは新しい技術であるため、その気になれば地方への工場誘致や地方企業の育成も可能だろう) 1)気候変動と再エネ 国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が、2021年8月9日、*3-1-1のように、①産業革命前と比べて世界の気温は2021~2040年に1.5度上昇し ②人間活動の影響は疑う余地がなく ③自然災害を増やす温暖化を抑えるには二酸化炭素排出を実質ゼロにする必要がある と指摘しており、そのとおりだと思う。 これについて、*3-1-2は、④報告書は2011~2020年で1.09度上昇し ⑤極地やシベリアで氷床や永久凍土の融解が報告され ⑥日本では巨大台風・豪雨、世界では異常熱波・大規模山火事が繰り返され ⑦当面続く気温上昇に備えて避難計画の見直し・食料確保等の対応が欠かせなくなり ⑧日本政府は、再エネ活用を模索すしつつ石炭火力の温存や家庭の取り組みに頼る姿勢を見せているが ⑨石炭火力の全廃・ガソリン車の販売禁止といった思い切った政策を早期に打ち出さなければ・・ と記載している。 このうち、①②③④⑤⑥⑦は、実体験に近いが、⑧のように、日本政府が石炭火力に頼れば、「EVはCO₂削減に貢献しない」などという屁理屈を許してしまうため、⑨は重要なことである。さらに、石炭は輸入しなければならないが、再エネなら国産にすることができ、地方で再エネ発電を行えば地方の所得を増やすことができるのである。 また、*3-2-1は、⑩日本最大の課題は脱炭素で ⑪環境問題対応が欧州を中心にスタンダード化した中で、日本も外圧で取り組まざるを得なくなったのは主体性がみえない ⑫米国もバイデン政権になって脱炭素に舵を切ったため、日本は外堀を埋められ ⑬2020年10月の菅義偉首相の決断がせめてもの救いだが ⑭約150年前の明治維新から日本は外圧による転換を繰り返し ⑮戦後の政治経済レジームも日本国憲法はじめ殆どが外圧によるもので ⑯日本は自律的に変わらず、外圧がなければ改革できない ⑰今回の脱炭素を中心とした外圧も日本にとってチャンスとの見方もできる 等と記載している。 環境問題の国際的認識は、(私の提案で)京都議定書から始まった。にもかかわらず、⑩⑰のとおり、再エネへの変換は日本にとってはプラスなのに、日本が主体性を持って世界をリードすることはできず、まさに⑪⑫⑭⑮⑯のように、欧米の外圧があってはじめて変わるわけである。⑬は、せめてもの救いだが、やはり遅い。つまり、変革は個人の意識と行動から始まるものであるため世代交代すればできるわけではないが、先見の明を持ち早く始めてトップランナーになった国・企業が大きな利益を得、慌ててついていく国・企業には座礁資産が多くなるのである。 2)再エネ由来の電源へ 経産省は、*3-2-2のように、2030年度の電源構成で再エネの主力化を進める新たなエネルギー基本計画素案を有識者会議に提出したそうだが、未だにCO₂排出量の多い石炭火力や問題の多い原子力への依存を続ける姿勢だそうだ。 政府が計画を抜本的に見直して脱炭素実現に不可欠な社会・経済の変革を促すことは重要で、それには、エネルギー基本計画に2030年までの石炭火力0、原発0を銘記すべきだ。そうすれば、2030年に向けてやるべきことは明確になり、それは送電網の整備・蓄電池の普及・発電場所の確保・場所にあった発電機の開発・再エネ関連機器の低コス化である。そして、“ベースロード電源”などという概念は廃止し、原発の新増設や建て替えはしないことにするのである。 日本で「再エネは天候によって発電量が変動するから、“ベースロード電源”が必要だ」などと言ってぐずぐずしている間に、*3-2-3のように、米テスラは日本で送電向け蓄電池を国内相場の約5分の1の価格で販売し、その電池の調達元はEV向けも調達する世界大手の中国寧徳時代新能源科技だそうだ。寧徳時代新能源科技は、テスラと25年末までの新たな電池の供給契約を結び、新電力のグローバルエンジニアリングが北海道電力の送電網にテスラの蓄電池システムを接続して電力の調整弁として機能させるそうである。 日本でも水素による蓄電方法や電池ができているが、方向が定まらずに右往左往して価格が高止まりしている間に、再エネ由来の利益も海外企業に持っていかれそうになっているわけだ。 3)再エネ由来の燃料へ イ)水素燃料航空機について 政府(経産省・国交省・文科省)と関連する民間企業(日航・全日空・川崎重工・三菱重工・IHI・燃料供給会社)が、欧州航空機大手エアバスが2035年までに水素燃料航空機を市場投入すると公表した外圧を受けて、*3-3-1のように、初めて水素を燃料とする航空機の実用化に向けて水素の貯蔵や機体へ注入するための空港施設の整備に向けた検討を始めるそうだが、これも追随型で遅い。 何故なら、水素はロケットや自動車を動かせる燃料であり、CO₂を排出しないため、水素燃料電池車が出た時に思いついて当たり前だからだ。現在、日本製の航空機は飛んでいないため、水素燃料航空機はゲームチェンジャーになれるところでもあった。 そして、新しいことをやろうとすると必ず「コストが高い」と言うが、コスト高で競争力がなく生産・販売できなければ、技術も進歩せずに消えていく。また、何であれ最初はコストが高く、大量に生産すれば安くなる筈なのである。 ロ)軽EVについて 軽EVの開発競争が、*3-3-2のように加速しており、日産・三菱は共同開発車を2022年度前半、ホンダは2024年、スズキは2020年代半ばに市場投入を目指し、ダイハツは開発を検討中だそうだ。「地方の足」である軽に脱炭素・EV化の流れが進むのは当然のことで、その理由は、EVなら近くで発電した安い電力で走ることができ、環境を害することがないからだ。 ガソリンエンジンを搭載しなくてよいため、軽EVが安くなるのは当然だと私は思うが、日本では国や自治体の補助金を含めた価格が200万円を切ると、走行距離が短くなるそうだ。しかし、中国では、上汽通用五菱汽車が2020年7月に発売した50万円を切る小型EVが爆発的に売れているのである。 EV先進国となった中国は、*3-3-3のように、百度が「ロボットカー」を発表し、中国自動車大手と共同出資してEVの製造・販売に今後5年間で500億元(約8500億円)を投じるそうで、百度のCEOは「未来の自動車はロボットEVの方向に進化する」と言っている。 ハ)ホンダについて 企業誘致すると、その企業が支払う住民税・事業税のほかに、その企業に勤める社員の年収に応じて住民税が徴収され、誘致した自治体の財源が増える。しかし、企業誘致には、①生産に有利(土地建物・人件費・水光熱費等のコストが安い) ②販売市場に近い ③質の良い労働力を集めやすい ④その他のインフラが整っている 等の企業にとって有利な条件があるだけでなく、⑤従業員の生活に便利(生活・教育・文化・交通面)である などの条件も比較されることを考慮しなければならない。 ホンダは、東京本社のほか埼玉県・三重県・熊本県などに製作所があり、埼玉県にある我が家の車はホンダのグレース(HV)だが、ホンダのトルネオ(ガソリン車)から乗り換えようとしていた時、EVが出るのを待っていたのにEVが出ないので、HVを買った経緯がある。 そのホンダが、*3-3-4のように、2021年度中に狭山完成車工場の四輪車生産を新鋭の寄居完成車工場に集約するそうだが、寄居工場の稼働開始は2013年であるのに、寄居町にホンダ関連で大きな受注を獲得した企業や工場の新増設の話はなく、商業にも目立った経済効果が出ていないそうだ。寄居工場は国内での増産投資が目的だったが、その後、ホンダが国際分業を一段と加速したのは、上の①②③が揃っているためではないのか? また、従業員の殆どは工場内の食堂や売店を利用し、狭山工場で勤務していたため狭山市周辺から通勤する人が多く、寄居町で消費する機会はかなり限られるのだそうで、この状況を打開するため、寄居町は今年秋にも狭山市周辺から通う従業員向けに移住・定住を促すツアーを開催したいと考えているそうだ。が、ホンダの工場進出で、従業員の住民税はさほど増えなかったが、法人関係の税が寄居町の財政を潤したのは確かである。 そのホンダが、*3-3-5のように、中国でEVなどの新エネルギー車を生産増強し、合弁会社を通じて約30億元(約500億円)投資し、広東省広州市の工場を増設して生産能力を年12万台上積みするそうだ。EV・PHVなどの新エネ車専用の新設備の建設面積は約18万6,000m²で、新しい生産設備が稼働すればホンダの中国での自動車生産能力は年161万台となり、現在と比べて約1割増える見通しだそうだが、これは、中国の方が上の①②③が揃っており、④の中のEV推進も積極的に行っているからだろう。 (4)医療・介護による地方産業の育成 1)日本の新型コロナ対応 *4-1-1は、①政府は新型コロナの入院対象者を重症化リスクの高い中等症・重症者に限り、それ以外は自宅療養を原則とした ②これまでは軽症・無症状の人も原則として宿泊療養させた ③目の届きにくい自宅療養は容体急変への対応が限られる ④中等症でも呼吸不全を起こして酸素投与が必要になる場合もある ⑤自宅療養を基本とするなら患者が安心して療養できる環境が必要 ⑥現状は往診等の在宅医療体制が整っている地域は少ない ⑦入院対象の仕分けは自治体の保健所が担う ⑧宿泊療養施設の拡充や在宅患者を見守る医師・看護師の確保など地域住民の不安を拭う策を講じるのが先 ⑨選択肢を広げるのが政府の務めであり、自粛要請に頼って病床確保を怠ってきた責任は重い と記載している。 ②については、感染者にとっては行き過ぎた強制の面もあったが、他者に感染させないために必要な措置だった。そのため、退院基準をPCR検査で2度陰性が続いた人として、療養中に軽症者向けの薬を投与し、回復を早めて速やかに退院させればよかったのだが、軽症者向けの薬をいつまでも承認しないという厚労省の不作為があった。また、⑦については、保健所職員が単純な基準で判断するのではなく、医師が患者の全体像を見て判断しなければ医療ミスの起こる可能性が高くなるが、既に起こった医療ミスの責任は保健所がとるつもりなのか? また、①③④⑤⑥で、患者が亡くなった場合の医療ミスの責任は、これまで医療制度を軽視し続けてきた厚労省がとるのか、患者を仕分けした保健所がとるのか、それとも政府全体でとるのか? 私は、不作為も含め、政策を作って意思決定してきた人(厚労省及び同専門家会議)が故意または重過失の責任をとるべきだと考える。 なお、⑧の宿泊療養施設の拡充は昨年の新型コロナ感染の当初から言っており、既にホテル等の既存建物が多い日本で新しい施設を造るのは無駄だが、ホテルを抑えても実際には使われない場合が多く感染防止の本気度が疑われた。また、宿泊療養施設の患者を見守る医師・看護師の確保も最初から言っていたのに未だできておらず、在宅患者を見守る医師・看護師・介護士の確保は慢性疾患の患者を見守るためには必要だが、急性感染症の患者を自宅療養させるのはリスクが高い上に感染拡大に繋がるため常識外れだ。 従って、⑨の選択肢を広げるのが政府の務めというのは正しいが、それは慢性疾患の場合であり、新型コロナのような感染症は入院やホテル療養などによる隔離を基本とすべきだ。また、自粛要請に頼るのも、最初の3カ月なら仕方がないものの、日本なら国民が自粛している間にすべての準備をすませておくべきであり、できた筈である。 18世紀末にジェンナーが天然痘ワクチンを開発して世界で天然痘が根絶され、1960年代に日本がポリオの生ワクチンをソビエトから緊急輸入して世界に先駆け1000万人を超える子どもたちに一斉接種してポリオの流行を止めたように、ウイルス性の感染症にはワクチン接種が決定打であることは100年以上も前からわかっていた。 にもかかわらず、2020年の日本で、*4-1-2のように、⑩ワクチン接種が円滑に進む地域は準備に早く着手した ⑪きめ細かな診療体制も敷かれ医療機関同士や行政との連携が密だった ⑫接種率が高い地域の多くは大病院が少なく、かかりつけ医が患者に目配りしている ⑬地元医師会・大学・行政が連携して役割分担している ⑭こうした連携は一部で全国的には道半ば ⑮患者は軽い病気やケガで大病院を利用するケースが多く、効率的・機動的な医療が妨げられている ⑯接種をきっかけに地方で芽生えた取り組みはコロナ後の医療改革のヒント 等が書かれており、ここでいちいち反論を書くことはしないが、愚かぶりが著しい。 何故なら、ワクチンの接種は当然のこととして、ワクチンを、i)どう早く作るか ii)どう早く接種するか iii)二重接種等にならないようにどう整理するか を最初から考えておくのが当たり前であり、これを実行したのが欧米・ロシア・中国等で、日本の厚労省及び同専門家会議は多額の税金を使ってワクチンを外国から買いあさることしかできなかったからである。 2)日本における分析と政策立案の欠陥 ← 新型コロナの対応から *4-1-2には、⑩ワクチン接種が円滑に進む地域は準備に早く着手した ⑪きめ細かな診療体制も敷かれ、医療機関同士や行政との連携が密だった ⑫接種率が高い地域の多くは大病院が少なく、かかりつけ医が患者に目配りしている ⑬地元医師会・大学・行政が連携し役割分担している ⑭こうした連携は一部で全国的には医療機関の規模に応じた役割分担と連携は道半ば ⑮患者は軽い病気やケガで大病院を利用するケースが多く、効率的・機動的な医療が妨げられている ⑯接種をきっかけに地方で芽生えた取り組みはコロナ後の医療改革のヒント 等が記載されていた。 このうち、⑩⑪⑬⑭は事実だとしても、⑫については、「接種率が高い地域は、大病院が少ない」のではなく、大病院が少ない地域は地方で、高齢化率が高いため接種率が高いのである。また、高齢者はワクチンの力を知っているためワクチン接種に積極的で、頼れる大病院が少ないことを自覚しているので自助にも熱心なのだ。 また、⑮については、「軽い病気やケガで大病院を利用してはいけない」と言いたそうだが、「軽い病気やケガ」の定義はどこまでで、それは誰が決めるのか? 私は、患者自身で病気の軽重を決めるのは危険だし、重篤化したりこじらせたりしてから大病院に行っても、治癒するのに時間がかかったり、治癒できなかったりするため、最初が肝心だと考えている。 さらに、⑯は、新型コロナやワクチン接種という急性感染症を例として、成人病や慢性疾患における医療ネットワークの必要性を論じている点で無理がある。何故なら、急性疾患の場合は、1分でも1秒でも早く対応するのが病気やケガを悪化させず、回復の確率を上げるコツだからだ。 また、*4-2-1は、政府は⑰感染が急拡大している地域は自宅療養を基本とする新方針を発表し ⑱入院は重症者や重症化のおそれが強い人を対象とし ⑲自宅宿泊療養の新型コロナ患者への往診の診療報酬を大きく拡充して新型コロナ感染者への医療提供体制を強化するよう協力を要請し ⑳地域の診療所が往診やオンライン診療で患者の状況を把握して適切な医療を提供するようお願いし ㉑血液中の酸素飽和度を測定するパルスオキシメーターを配布 としている。 しかし、⑰~㉑は、診断と治療が終わって急性期を脱し、慢性期に入っている人には有効だが、急性疾患の初診で重症化の恐れがあるか否かは、患者に対面し、検査をし、患者の全体像を把握した上で初めて判断できるもので、保健所が時間をかけて中等症にした人を、(いくら診療報酬を拡充されたとしても)オンライン診療による初診だけで医師が引き受けるのはリスクが高すぎて元が取れないと思う。何故なら、診断ミスによる医療過誤で信用を失えば病院経営に深刻な打撃を与えるからで、それはもちろん、患者のためにもならない。 3)医療ネットワークに組み込むべき往診・訪問看護・訪問介護 医療ネットワークの要素には、大病院・かかりつけ医・往診・訪問看護ステーション・介護ステーションがあり、1人の患者を例にとれば、病気やケガの発生・治療・療養・リハビリなどの各段階において有機的に連携されていることが望ましい。しかし、現在は、そうなっていないのが課題なのである。 そのような中、大阪府は、*4-2-2のように、新型コロナ感染者のうち自宅療養者の健康観察を強化するため、訪問看護を府内全域で実施すると発表したそうだ。新型コロナのような感染しやすい急性感染症を自宅で療養するのはいかがなものかと思うが、他の病気で自宅療養する時に往診や訪問看護が必要不可欠なのは間違いない。しかし、訪問看護も、保健所が必要だと判断した患者ではなく、医師が必要だと判断した患者に対して、医療行為の一環として連携して行うべきである。そのため、大病院でもかかりつけ医でも、訪問診療科・訪問看護科・訪問介護科を常設し、検査・治療・療養・リハビリ・栄養指導・生活支援などを各段階で一貫して行うようにすると患者が便利だ。が、この場合は、病院の中にケア・マネージャーが必要だろう。 4)介護保険制度について 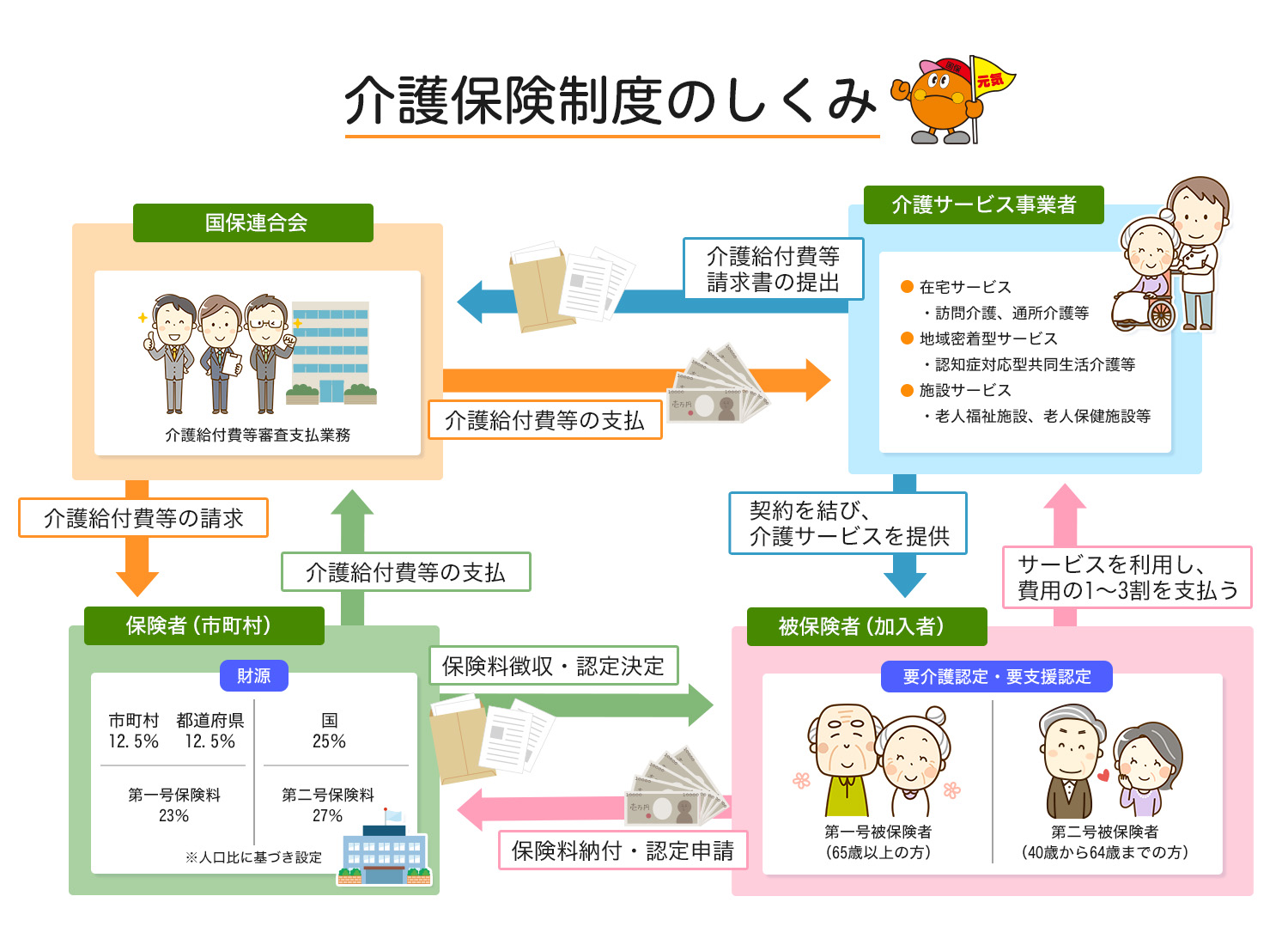 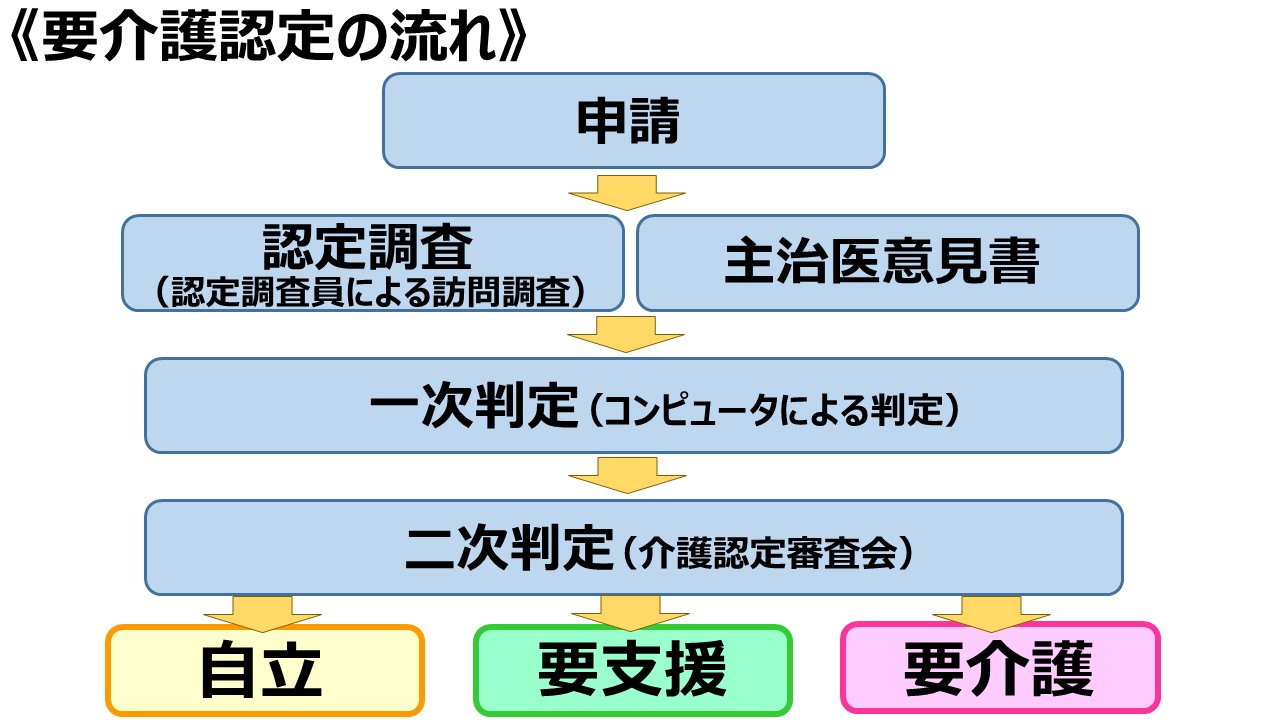  国保連 介護求人 2021.8.21日経新聞 (図の説明:介護保険制度の仕組みは左図のとおりで、所得によって介護保険料の負担額が異なるだけでなく介護費用の負担割合も異なり、これは保険の枠組みから逸脱している。また、40~65歳の第二号被保険者は介護サービスを受けられる病気も限定されているため、サービスの提供における差別があると同時に、介護保険料の徴収年齢にも合理性のない差別がある。また、要介護・要支援・自立の判定は本人の申請に基づいて行われ、中央の図のように、判定を経て決定されるので、自治体の判定に依拠するところが大きい。このような中、右図のように、日経新聞が介護給付費を大きく減らした上位10市町村を掲載しているが、工夫して賢く減らしたのか、単に介護費用を削っただけなのかは要検討だ) イ)介護給付費の削減について 日経新聞は省庁の広報機関のような見解を述べることが多いが、*4-3-3も、①介護給付費は2020年度に10兆円に達し、介護保険制度が始まった2000年度の3倍以上に膨らんだ ②持続可能性を高めるには圧縮が急務 ③全国では既に59市町村が削減に成功した ④高齢者1人当たり給付費は保険者2018年度で26万円と制度開始時から11万円強増えた としている。 しかし、①④は、介護保険制度がスタートした2000年度は、i)介護サービスが充実しておらず ii)介護の担い手も不足しており iii)介護を受ける世代の人に「本来なら家族が介護するべきところ、人様の世話になるなんて」と思う人が少なくなかったため、比較すること自体が無意味なのである。そして、2020年になっても、介護保険料が高い割には、不必要な介護用品に補助を付けている例もあるのに必要なサービスを受けられない人も多く、年齢による介護保険料負担の不公平感もあるため、介護制度は未だ不完全な制度と言える。 また、②は、自分は介護を担わないと思っている人の発言であり、③は、もともと不十分なサービスを減らすことが適切だったか否かについて、事例毎の検討を要する。 さらに、*4-3-3は、⑤高知県南国市は保健師・栄養士・理学療法士等が協力して介護予防に取り組み ⑥1人当たり給付費を2001年度の28万円弱から24万円(2018年度)まで減らし ⑦「地域ケア会議」で身体的負担の少ない公営住宅紹介等の個別支援プランを策定し、食事や運動も精緻に計画・検証し ⑧多くの事例で自立生活が維持できるようになった ⑨沖縄県名護市は給付増の要因になりやすい施設入所を生活に支障なく抑制しようと配食サービスの普及に力を注ぎ ⑩北海道鶴居村・天塩町はクラブを作って運動を促し、糖尿病や肥満の人に個別指導をして機能低下を防ぎ、高齢者1人当たりの給付費を各36.7%、25.3%減らした としている。 しかし、⑤⑩は、健康寿命が延びるのでよいと思うが、⑥のように一時的に給付費が減っても最後は介護を受けて亡くなるため、1人当たり給付費は数年~十数年後には元に戻るか増えると思われ、科学的な継続調査と結果の公表が望まれる。また、⑦の身体的負担の少ない公営住宅紹介もGoodだと思うが、今後は国として身体的負担をかけないバリアフリー住宅の建築基準を作ればさらに効果的だ。また、⑨の配食サービスや⑩の栄養指導もよいが、スーパーなどで美味しくて栄養バランスのよい薄味の惣菜や弁当を売っていれば、自立した自宅生活がしやすい。 このほか、セコム等が見守りサービスを実施しているが、生活支援の便利屋機能を加えると、介護保険の生活支援サービスを受けずに自宅生活のできる人が増えると思う。 ロ)市民が見た介護保険の20年とこれから 介護保険制度創設は、私が、1995年頃、さつき会(東大女子卒業生の同窓会)が発行したエッセイ集に載っていた共働き先輩女性の介護での苦労話を読み、「明日は我が身」と身につまされて「現役時代によい制度を作っておかなければ、退職後にひどい目に合う」と実感し、メーリングリストでさつき会の会員に呼びかけつつ、通産省(当時)の人に言って始まったものだ。 その介護保険制度について、2020年4月29日、西日本新聞は社説で、*4-3-2のように、①2000年4月に「介護の社会化」を掲げて始まった介護保険制度で家族頼りだった介護は民間サービスが担うようになり ②社会的入院の解消を促し、「老親の世話は同居する女性の役割」という社会通念を拭い去るのに貢献 ③この20年で高齢化がさらに進み要介護・要支援認定者と必要な費用が3倍に増えた ④介護サービス需要が急速に伸び、制度の維持が困難に ⑤大変な仕事の割に介護職員の平均給与が全産業平均を大きく下回って現場の人手不足が深刻 ⑥外国人材への期待も高いが新在留資格「特定技能」による受け入れは進んでいない ⑦団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年には約34万人の介護人材不足が見込まれる としている。 また、⑧国は財政逼迫を受けて負担増と給付減を行い ⑨介護の必要性が低いとされる利用者サービスを全国一律の介護保険から切り離す動きが始まって要支援者の訪問介護と通所介護は既に市町村に移管され ⑩要介護1、2の一部サービス移管案も浮上しており ⑪急な負担増は利用抑制を招いて生活の質や健康への悪影響があり ⑫市町村への事業移管は居住地によるサービス格差の懸念が大きく ⑬介護保険の財源は保険料と公費(税金)で構成されるので、公費負担アップや介護保険加入年齢の40歳以下への引き下げも要検討 としている。 このうち、①②はそのとおりだが、③の高齢化の進展は創設当時からわかっていた。また、介護を受ける人が増えて介護を外部化することに対する違和感が減ったため、実際の要介護・要支援者のうち認定される人の割合も増えたと思う。そして、④の介護サービス需要が急速に伸びたのは本当に必要な実需だったからにほかならず、工夫もせずに「制度の維持が困難になった」と言うのはお役所仕事そのものである。また、同じサービスの給付に対して負担率が異なるのは、保険の枠組みから外れてもいる。 ⑤も何度も聞いたが、全員を同じ給与にする必要はなく、看護師や介護士の資格があれば相応の資格手当や技術加算分を支払い、管理職には管理職手当を支払い、日本語がよくわかる人には日本語手当を支払うなどして、⑥の外国人も十分活用しながら、サービスを削ることなく、介護の能力に応じた給料を支払えば、⑦の介護人材不足は解消するだろう。また、そもそも介護保険制度は、⑬の介護保険制度への加入を働く人全員(40歳以下も)にすべきである。 さらに、国(特に厚労省)が、(新型コロナ対策を見てもわかるように不要なことをして膨大な無駄遣いをしながら)⑧のように“財政逼迫”として介護制度の負担増・給付減を行ったのは、⑪のように、介護を受ける人のことを全く考えず、介護サービスという今後は世界で膨大な産業となるサービスの芽を摘んでいる。また、⑨⑩⑫のように、要支援や要介護1、2を介護の必要性が低いとして全国一律の介護保険制度から切り離すと、各地方自治体はこれまでの国策の結果として生産年齢人口と高齢者人口の比率が異なるため、格差が生じて不公平になるのだ。 「市民が見た介護保険の20年」と題し、*4-3-1は、⑭2005年の改正で要介護者への給付とは別に要支援者への予防給付ができた ⑮2014年の改正では、要支援者のホームヘルプとデイサービスが予防給付から地域支援事業に移され、特別養護老人ホームの利用は要介護3以上となった ⑯利用者に選択権があるとして始まり、介護が必要と認定されれば給付が保障されていたのに、いつの間にか予防重視型になった ⑰2020年の要支援・要介護認定者669万人のうちサービス利用者は515万人で約4分の1は介護制度を利用していない ⑱厚労省は家族で対応していると説明するが、自己負担を払えず利用できない人が一定数いる ⑲ホームヘルプが抑制され、同居家族がいると生活援助を利用できないという解釈が市町村で広がった ⑳ホームヘルプは高齢者の自立支援に資することがないと批判を浴びてヘルパーが減った ㉑厚労省は地域包括ケアを掲げるが、ヘルパーが減ってどうやって地域での暮らしを支えるのか疑問 ㉒要支援者が要介護認定を受けても地域支援事業のデイサービス等を引き続き利用できるよう見直され、要介護認定を受けても給付の対象にしなくて良い仕組みになった ㉓予防給付や地域支援事業を拡大する方向性で制度を維持しようとするのはおかしい としている。 私も、⑮のように、要支援者のホームヘルプとデイサービスを地域支援事業に移して特別養護老人ホームの利用は要介護3以上に限定し、㉒のように、要介護認定を受けても地域支援事業を利用できるようにすれば、国は介護費用を節約できるが、介護の必要な人が介護を受けられない事態が発生していると思う。また、⑰のように、高い介護保険料を支払いながら介護費用を支払えずに介護を受けていない人もいるだろう。これに対し、⑱のように、厚労省が「家族で対応している」と説明するのは、昔返りで介護保険制度の意図を理解していない。 また、⑭⑯のように、介護と支援のどちらを選択するかを高齢者が選択できるのではなく、要支援者のホームヘルプとデイサービスを地域支援事業に移し、⑲のように、介護費用を節約したい地方自治体が「同居家族がいると生活援助を利用できない」と解釈すれば、同居する女性に介護を強いることとなり、介護保険制度の意味を失わせる。そうなると、⑳のように、ヘルパーが減るのも当然で、㉑の厚労省の言う地域包括ケアは、「女性を中心とする地域ボランティアがやれ」ということになり、介護を無償労働化している点で介護を担当する人に極めて失礼だ。 従って、㉓は、予防給付や地域支援事業の一部は本来の介護ではないため、その費用は介護保険制度から拠出するのではなく、税金から別に予算を出すべきであろう。 5)診療は、ITやオンラインを使いさえすれば進んでいるわけではないこと 厚労省は、*4-4のように、新型コロナで自宅やホテルで療養する人に対し、電話やオンラインで診療した場合の診療報酬を2倍超に引き上げると自治体に通知したそうだが、自宅にいる患者に電話やオンラインで初診すれば、検査はできず、患者の様子も本人の報告を聞くだけであるため、何もしないよりはいいという程度に終わる。 その報酬が2,140円だったのを4,640円にしたとしても、初診の診断ミスのリスクには見合わないため、急性感染症に遠隔診療を促すのは賛成しない。重要なのは、時と場合に応じてどういう内容の検査・診察をして判断したかであるため、「この際、オンラインを使った遠隔診療を進めよう」という考えで遠隔診療を進めるのは慎むべきである。 (5)国と地方自治体の財源 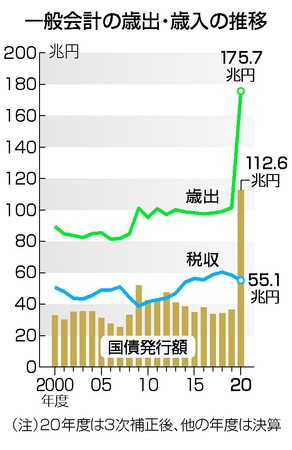 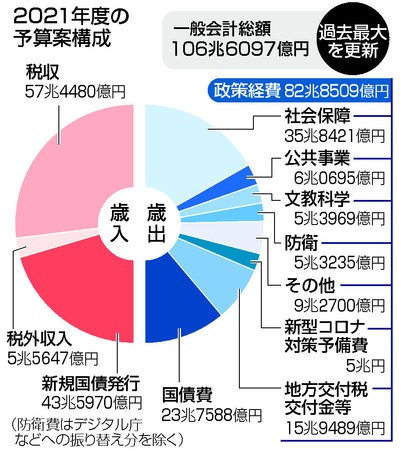 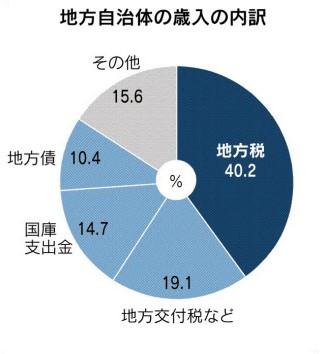 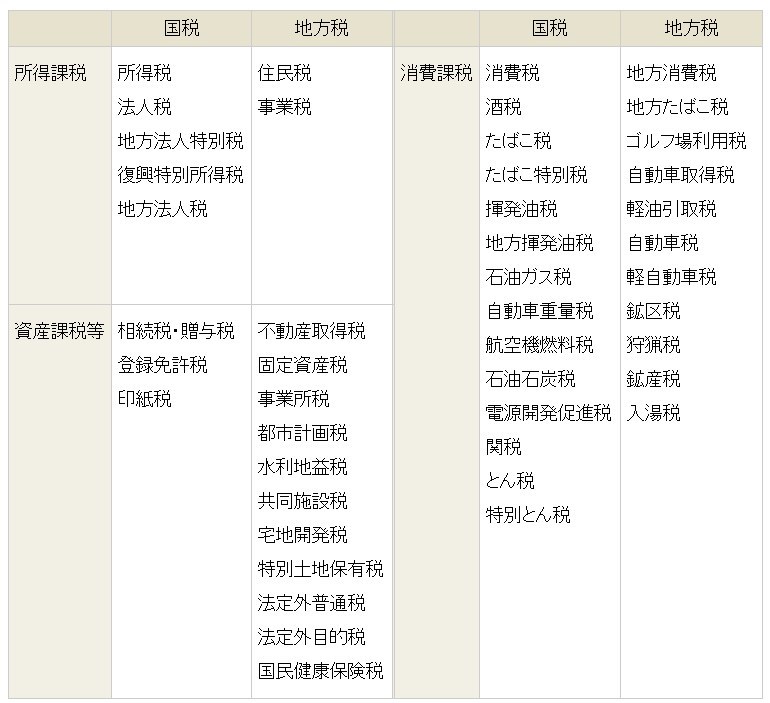 2020.12.15時事 2020.12.21時事 2020.6.10日経新聞 栗原税理士事務所 *5-1より (図の説明:1番左の図のように、2000~2020年度の日本全体の歳入は40~60兆円の間であり、2000~2019年度の歳出は80~100兆円程度だったが、2020年度は新型コロナ対策として約176兆円もの効率の悪い予算を組んだため、国債発行額が40兆円から約113兆円に跳ね上がった。そして、左から2番目の図のように、2021年度当初予算における歳出も過去最高の約107兆円で、このうち税収で賄われるのは約57兆円、税外収入で賄われるのは約6兆円にすぎず、残りの約44兆円は新規国債発行によるものだ。なお、地方自治体の歳入の一部となる地方交付税交付金は、国の2021年度歳出予算のうち約16兆円だ。右から2番目の図は、地方自治体の2018年度決算で、歳入は地方税40%、地方交付税19%、その他16%などである。1番右の図は、税目別の国税と地方税の振り分けだ) 1)国の財源のうち税外収入 上の左から2番目の図の歳入構造には、①税収 ②税外収入 ③新規国債発行がある。このうち、①の税収を増やすためには、i)国民や法人の稼ぎを増やす ii)既存の税の税率を上げる iii)新しい税目を作る などの方法があるが、ii)は何の工夫もいらないものの景気を押し下げる。また、i)は、付加価値を上げたり、販売力を伸ばしたり、生産性を上げたりする根本的な解決法もあるが、金融緩和による通貨量増加だけでは景気のカンフル剤にしかならず、物価が上がって購買力平価が落ちれば国民生活は貧しくなる。さらに、iii)は、環境に悪い行動に環境税を課し、環境によい行動の補助金財源にすれば、財政中立で環境改善への二重のインセンティブとなる。 ③の新規国債発行については、国の責任で生じた過去の年金積立金不足を新規国債発行で賄うのは公平・公正の観点から必要だが、景気対策として行われる無駄遣いを国債で賄えば、その国債を返還する世代に不当な負担を押し付けることになる。ただし、地域間送電線・道路の建設等のように次世代への負債と資産がセットで残るものならば、負債だけが引き継がれるわけではないため世代間の公平・公正を害しない。しかし、その金額を正確に把握するためには、国への複式簿記による公会計制度の導入、迅速な会計処理、その年度の決算に基づく次年度の予算審議が必要で、これは民間企業なら必ず行っているもので、多くの国で採用しているものでもある。 なお、仕方なく発行された国債であったとしても、令和2年度末に906兆円と見込まれる公債発行額は令和2年度税収64兆円の14年分にあたるため、とても税収から返済できるものではない(https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/04.pdf 参照)。そのため、国民に負担をかけずに国債を賢く返済するには、②の税外収入が必要不可欠で、税外収入は、これまで開発してこなかっただけに潜在的資源が多いのである。 例えば、*5-1-1のように、日本は陸地及び排他的経済水域ともに地熱資源が豊富だ。しかし、経産省が地熱発電所を増やすため国立公園内などに適地を見つける調査を本格化するといっても、2030年度に地熱発電を1%に引き上げるという小さな目標だ。環境省が自然環境や景観を損なうという理由で開発に慎重だったとのことだが、原発や化石燃料の方が自然への悪影響や景観悪化はずっと大きいため言い訳にすぎず、次期エネルギー基本計画には「地熱資源の活用による国の税外収入の増加」を明確に記載すべきである。 2)国から地方自治体への国庫支出金、地方自治体の税外収入 イ)地方自治体の再エネ発電 *5-1-1の地熱発電をはじめとする再エネを使った売電収入は、地方自治体の資産を使って行えばその地方自治体の税外収入になる。そのため、地方自治体も、これまで活用してこなかった再エネ発電で安価な電力を作り出し、その自治体における光熱費を下げて、農業や製造業を有利にする方法がある。この時、頑張って黒字化した地方自治体には、右から2番目の図の地方交付税が減らされるのがマイナスのインセンティブにはなるが、もらえる地方交付税の金額を大きく上回る稼ぎがあれば地方自治体にとっても国にとっても役立つことは言うまでもない。 ロ)地方自治体のごみ発電 地方自治体は、“邪魔者”であるゴミを集めて処分しているつもりだと思うが、ゴミの収集がこれだけ整然と行われる組織はそれ自体が財産である。その理由は、ゴミは、分別とリサイクルで利用可能な資産になるからだ。 その1例は、*5-3-1のごみを燃やした熱を利用してタービンを回して発電する「ごみ発電」で、日立造船など上位3社の累計受注件数が5年で倍増したそうだ。世界には日本以外にもごみ活用の先進国があり、再エネ比率が6割を超えるスウェーデンは、国内で発生するごみの約半分を焼却して発電に利用し、余熱も暖房用などで家庭に供給し、肥料にも使うため自国のごみだけでは足らずに近隣諸国からごみを輸入しているそうだ。そして、今後は経済発展に伴って、アジアが市場を牽引する見通しとのことである。 そのような中、*5-3-2は、①全国のごみ処理費は年間2兆円を超え、10年前と比べて1割増えた ②人口減に伴う担い手不足の懸念も強まる ③財政も厳しさを増す中、持続可能な地域を築くためには排出削減への戦略的施策が欠かせない などとしている。 しかし、ゴミ処理は必要不可欠なサービスであるため無料である必要はなく、ゴミ袋を有料化することによってゴミ収集費を回収することが可能で、そうすると必然的に不要なゴミは減る。しかし、ゴミの分別がややこしすぎるのは生活に不便を強いるため、簡単な分別で処理できる包装資材の開発などの川上改革を行い、異なる色の有料ゴミ袋を使うなどして分別も簡便にできるようにした方がよい。 こうすれば、①は、年間2兆円のごみ処理費は有料化で回収した上、地方自治体はごみ発電や温水供給による税外収入を得ることができる。また、②は、自動化や移民の受け入れを考えることなく言うべきではない。さらに、③は、工夫もなく、「環境保護=国民に我慢を強いること」というイメージを作っている点で愚かな発想だ。 そのような中、川上村は可燃ごみの4割を占める生ごみの回収を一切せず、各家庭で堆肥化することによって全国の自治体で一番排出量を少なくしたそうだが、これは庭や畑が広くない地域では不潔になるため無理なことである。 3)地方自治体の歳出削減 大阪市は、*5-4のように、市役所本庁舎で使用する電力を2021年12月から太陽光やバイオマス発電など再生エネ由来100%の再エネに切り替えるそうだ。また、大阪府では2021年4月から既に本庁舎などで使用する電力を再エネ由来100%の調達に切り替えており、日立造船がバイオマス発電による電力を供給しているとのことである。 が、使用する電力を地方自治体自身で作れれば、光熱費が0になってSDGsにも役立ち、発電できる場所は考えれば少なくない筈だ。 4)地方自治体の歳入増加 上の右から2番目の図及び*5-2-1のように、2018年度決算における地方自治体の歳入は、①地方税40.2% ②地方交付税19.1% ③国庫支出金14.7% ④地方債10.4% ⑤その他15.6%で、自前の財源だけで財政運営ができている自治体は少ない。 しかし、地方自治体もIT化を進めれば人件費削減が可能な筈だし、新型コロナ対策も国と同様に人流抑制を繰り返して経済を止めるのではない方法もあった。そして、その場合は、家計や企業の緊急支援額を低く抑えることができ、財源不足が大きくなることはなかったのである。 なお、*5-2-2のように、⑥新型コロナ感染拡大は人口の流れに影響を与え ⑦2020年の1年間で大都市から地方への移動が鮮明になって ⑧東京、関西、名古屋の三大都市圏の人口の合計は2013年の調査開始以来初めて減少し ⑨大都市から地方に人口が流れる傾向があり ⑩人口増の多い町村は子ども医療費無償化・幼小中一貫校設置・待機児童0・住宅地整備・企業誘致などの環境整備が注目される そうだ。 住民税・事業税・固定資産税などの地方自治体の歳入を増やすためには、企業や生産年齢人口の増加が必要であるため、移住してもらうのがBestで、そのための努力は、上の⑩に代表されるだろう。しかし、人口が分散すれば、著しく狭くて高い住居や過度に節水した不潔な水道や長い行列に悩まされることもなく、自然に近い場所で居住することが可能なのである。 ・・参考資料・・ <地方産業の高度化―その1:農林漁業の高付加価値化> *1-1-1:https://digital.asahi.com/articles/ASN6V721GN6VTIPE00P.html (朝日新聞 2020年6月26日) カイコからコロナワクチン? 九大が候補物質の開発成功 九州大学は26日、昆虫のカイコを使い、新型コロナウイルスワクチンの候補となるたんぱく質を開発することに成功したと発表した。「昆虫工場」による大量生産で、数千円で接種できるワクチンの臨床研究開始を来年度にもめざす。九大は世界的なカイコの研究機関として知られる。カイコは遺伝子操作したウイルスを注射すれば狙ったたんぱく質を体内で生産できることから、このたんぱく質を使って、新興の感染症を想定したワクチン開発技術を研究してきた。九大は1月に公開された新型コロナウイルスの遺伝情報をもとに、ウイルスが人間の細胞に感染するための突起状の「スパイクたんぱく質」に着目。大学で飼育するカイコで、このたんぱく質が生成できることを確認したという。別のコロナウイルスの研究では、スパイクたんぱく質を注射したマウスの免疫反応で体内にできた「抗体」で、ウイルスの感染を予防できる結果がすでに得られている。九大は新型コロナでもマウスを使った実験を年内にも終わらせる方針。製薬企業と連携し、早ければ来年度にも人間での研究を始める意向だ。26日の記者会見で日下部宜宏教授(昆虫ゲノム科学)は「ワクチン開発は世界中で進むが、スピードよりも、途上国も含めて接種できる安価なワクチンを、安定して生産することをめざしたい」と話した。また、九大の西田基宏教授(薬理学)らは26日、すでに使われている約1200種類の薬の中から、新型コロナの重症化防止も期待できる薬を3種類、発見できたと発表した。新型コロナの患者にも見られる呼吸不全や血管の炎症などの治療薬のため、早期の投与開始が見込めるとして「年内にも実用化につなげたい」と説明している。 *1-1-2:https://www.nippon.com/ja/features/c00508/ (Nippon.com 2012.7.9) [農業生物資源研究所]遺伝子組換えカイコで医薬開発に挑戦 紀元前から続く養蚕の歴史に新しい一ページが刻まれそうだ。遺伝子組換えカイコを使って新しい絹や医薬品の原料を作る研究が進んでいる。その先端を行く農業生物資源研究所(茨城県つくば市)を訪ねてみた。 ●カイコが持つタンパク質生成の高い能力に注目 独立行政法人農業生物資源研究所(生物研)は、農業分野におけるバイオテクノロジーの中核機関として2001年に設立された。カイコが持つタンパク質生成の高度な能力に着目し、カイコが従来作る種類以外のタンパク質を作らせる研究を続けている。すでに、遺伝子組換えカイコ由来のタンパク質を使った化粧品が市販されているほか、将来的には安全で安価な医薬品の製造も視野に入れている。研究の詳細を紹介する前に、まずはカイコについて解説しておきたい。養蚕は紀元前15世紀ごろが起源とされる。日本では1~2世紀ごろに始まり、1909年には生糸生産高が世界一になったが、化学繊維の普及や後継者不足などによって徐々に衰退。現在は中国やインド、タイが主な産地である。日本国内には遺伝資源も含めて約600種類のカイコが存在するが、いずれも成虫(カイコガ)になっても飛ぶことができない。長い歴史のなかで養蚕に適するように品種改良、つまり“家畜化”されたためだが、これが遺伝子組換えカイコを産業化する際のメリットになる。遺伝子組換え生物はカルタヘナ法(※1)の対象で、厳密に管理しなければならない。カイコの場合、飛んで逃げる心配がないため管理しやすいのである。カイコは孵化(ふか)からおよそ1カ月後に繭(まゆ)を作る。その繭の原料となるのがタンパク質。タンパク質は体内の絹糸腺という器官で作られるが、絹糸腺内の部位によって、作られる種類は異なる。後部絹糸腺ではフィブロインというタンパク質が、中部絹糸腺ではセリシンというタンパク質がそれぞれ作られる。カイコが作り出す糸は、糊状のセリシンが繊維状のフィブロインを包み込んだ格好となっている。おおよそ、セリシン25%、フィブロイン75%の割合だ。糊状のセシリンは水溶性なので、繭をぐらぐらと湯で煮立たせると溶出し、繊維状のフィブロインだけを絹糸(シルク)として取り出すことができる。 ●何世代も機能を受け継げる遺伝子組換え技術 さて、遺伝子組換えカイコの研究だが、遺伝子組換えカイコを作り出す際には、2つのDNAをカイコの卵に注射する。1つ目は、トランスポゾンというDNA上を移動できる遺伝子に、特定のタンパク質をつくるための外来遺伝子を組み込んだベクターDNA(※2)。もう1つは転移を促す酵素を組み込んだヘルパーDNA。これらを注射した卵を孵化させて、得られた次世代の個体群をスクリーニングすれば、利用可能な遺伝子組換えカイコだけを得ることができる。「卵の中でも生殖細胞に分化する部分を狙ってDNAを導入することで、特定の能力を何世代にもわたって引き継ぐことができます。この技術によって遺伝子組換えカイコの量産が可能になりました」と生物研主任研究員の内野恵郎氏は話す。生物研は9年前、外来遺伝子の性質が現れる場所をコントロールする技術も確立した。繊維状のフィブロインを作る後部絹糸腺で発現させると、シルクの改質が可能となり、生物研では蛍光色のシルクの開発に成功している。一方、糊状のセリシンを作る中部絹糸腺で発現させると、糊の中に狙ったタンパク質を作ることができる。セリシンは水に溶けるので、タンパク質の抽出もたやすい。生物研遺伝子組換えセンター長の町井博明氏は、「当研究所では生成するタンパク質の98%以上がセリシンという品種も開発。それと組み合わせればより多くのタンパク質が得られる」と技術の有効性を強調する。生物研は、群馬県蚕糸技術センター、前橋遺伝子組換えカイコ飼育組合、民間企業などと連携しながら研究を進めている。町井氏は「日本の養蚕業は厳しい状況にあるが、遺伝子組換えカイコが養蚕業の再活性化につながるかもしれない」と期待を寄せる。 ●化粧品から将来は医薬品開発へ 群馬県藤岡市にある株式会社免疫生物研究所では、生物研から技術提供を受けて、ヒト型コラーゲン(※3)を生成する遺伝子組換えカイコを作り出した。すでにそのコラーゲンを化粧品などに製品化している。特に苦労したのはコラーゲンの抽出だった。1つの繭から生成されるコラーゲンは約10mg。これを抽出するためには繭の成分を水に溶かし、こして繊維質を除去しなければならない。しかし、糊状のセリシンがフィルターの目に詰まってしまい、思うようにこすことができないという問題が残った。免疫生物研究所製造・商品開発部蛋白工学室長の冨田正浩氏はさまざまな工夫を重ね、最終的に10mgのコラーゲンから6~7mgを回収する手法を編み出した。免疫生物研究所はすでにヒト型コラーゲンを化粧品などに使用している。一般に化粧品には魚由来のコラーゲンを使ったものが多く、なかにはアレルギー反応を示す人がいるが、ヒト型コラーゲンなら問題ない。しかも、シルクや繭のイメージは化粧品のイメージアップにつながり、商業的にもメリットがありそうだ。「ゆくゆくは医薬品や医薬部外品を開発したいと考えています。たとえば、抗体を使った診断薬を開発する場合、細胞培養やマウスの体内で抗体を生産させるプロセスがあります。でも、動物愛護の観点からマウスの使用は減らしたいところですし、細胞培養にコストがかかって製品価格が上がるのも問題です。抗体はタンパク質の一種ですから、遺伝子組換えカイコで診断薬の原料となる抗体を作ることができれば、こうした問題はすべて解決できます。安全で安価な医薬品を作れる可能性があるのです」(冨田氏)。カイコが作る絹糸は、絹織物の美しさと滑らかな手触りで人々を魅了してきた。今後は、遺伝子組換えカイコが作るタンパク質が安全で安価な医薬品を生み出し、人々の健康に貢献するのかもしれない。 *1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210808&ng=DGKKZO74574720W1A800C2MY1000 (日経新聞 2021.8.8) 米粒にコレラワクチン成分 東大など、遺伝子操作のイネ栽培 東京大学の清野宏特任教授と幸義和特任研究員らはコメからできたワクチンの安全性をヒトで確かめた。米粒の中にワクチンの成分が入っており、すりつぶして飲むだけでコレラの毒素による下痢症状を防ぐ。コメに成分を封じ込めた結果、温度や湿気の影響を抑え、冷やさなくても長期間の保存ができる。コレラがまん延する発展途上国などでは冷蔵管理が難しく、利用しやすいワクチンの開発が待たれていた。ワクチンは千葉大学などと共同で開発した。コレラは東南アジアやアフリカなどの発展途上国で多く発生し、発症すると下痢の症状が出る。これまでのワクチンは冷蔵保存が必要だった。研究チームはコレラの毒素を構成する「部品」から、ワクチンの成分に使える無害な部分の遺伝子をイネに組み込んだ。この部品はコメがもつ天然のカプセルにたまる。コメの粉末を飲むと、ワクチンの成分が腸に届いて免疫をつくる。これまでにマウスやブタ、サルなどで免疫ができるのを確認した。コメであってもワクチン候補にあたるため、今回は健康な大人の男性60人を対象に医師主導治験を実施した。ワクチンを飲んだ人の健康に問題はなく、血清を調べると40~75%の人でコレラの毒素に立ち向かう抗体ができていた。飲む量が増えるにつれて抗体の量も増えていた。今後は有効性を慎重に確かめるほか、遺伝子を組み換えたイネを大規模に栽培できる体制づくりなどの課題を乗り越えたいという。研究チームによると、理論上はあらゆる感染症のワクチンが同じ方法で開発できるという。常温で保存でき、飲むだけで済めば利点は大きい。 *1-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210802&ng=DGKKZO74401590S1A800C2MM0000 (日経新聞 2021.8.2) 住宅、木材活用に知恵 環境にも配慮、住友不動産やケイアイスター 不動産各社が住宅で木材を一段と活用する動きが目立ってきた。住友不動産は戸建てのリフォーム事業で従来は廃棄していた木材を再利用する取り組みを始めた。戸建て分譲住宅を手がけるケイアイスター不動産は注文住宅の国産材比率を100%に引き上げ、輸入材を使う場合に比べて環境負荷を減らす。改築や新築時の二酸化炭素(CO2)排出量の削減などにつながる環境配慮の姿勢を消費者にアピールして、需要取り込みを狙う。住友不はこのほどリフォームサービス「新築そっくりさん」で木材の再利用を始めた。従来、柱などの主要な構造材以外に使用している木材はリフォーム時に廃棄処分していたが、品質を確認のうえ顧客の同意を得られれば壁の内側の下地材などとして再利用する。同社のリフォームは建て替えるよりも廃棄物の排出量が半分で済む特徴がある。木材の再利用を進めることで改築時の廃棄物をさらに減らせる。新たな資材の調達も減らせるため、資材輸送時のCO2排出量も削減できると見込む。同社は年1万棟の大規模リフォームを手掛けており、環境配慮のサービスとしても顧客にアピールしていく考えだ。ケイアイスター不動産は平屋建ての注文住宅「IKI」について、4月以降の契約分から使用する木材を全て国産材に切り替えた。これまでも全体の約8割を国産材としていたが、新たに構造材の梁(はり)もすべて国産木材で建てられるようにした。同社によると、木造の戸建て住宅は鉄筋コンクリート(RC)造と比べ建築時に排出するCO2を約29トン削減できる。1世帯が排出する約7年間分のCO2に相当する。輸入材を使用するよりも輸送時の環境負荷も減らせる。全て欧州産の木材を使って建てた場合は国産材を使った場合に比べて約8.5倍のCO2が発生するとの試算もある。建屋の価格は17坪(約56平方メートル)で599万円から。今後3年間で500棟の受注を目指す考えだ。三井ホームは5階建て程度の中層マンションの木造化を進める。第1号物件となる賃貸マンションを東京都稲城市で建設している。強度や防音性などを高めてマンションを木造化できる新しい技術を開発した。建設時のCO2排出量もRC造の半分程度に減らせる見込みだ。政府は4月、2030年度の温暖化ガス排出量を13年度比で46%以上減らす目標を決めた。住宅部門でも省エネルギー性能の向上や太陽光発電など再生可能エネルギーの導入などを加速する必要があり、コンクリートに比べて断熱性の高い木材の利用が住宅で一段と進む可能性がある。ウッドショックが懸念されていることもあり、輸入材よりも環境負荷を低減できる国産材への注目も高まる。三菱地所など建設・不動産7社も国産材の需要を掘り起こす取り組みを始めている。環境に配慮した住宅は消費者からの支持も得やすいとみられ、今後も不動産各社で木材活用が進みそうだ。 *1-3-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC27B9W0X20C21A5000000/?n_cid=NMAIL006_20210812_H (日経新聞 2021年8月12日) 3Dプリンター、10日で住宅建築 臓器も代替肉も製造 戸建て住宅がわずか10日で完成――。米スタートアップが昨年から住宅の建築に活用しているのは3Dプリンターだ。従来は樹脂や金属加工に使われてきた3Dプリンターは技術開発が進み、移植用臓器や代替肉にも活用分野が拡大。短期間で人手がかからないものづくりを実現し、イノベーションも生み出すとの期待が膨らむ。米カリフォルニア州の砂漠地帯に位置するランチョミラージュ。この地域の一角に、2021年中に計15戸の「印刷」された戸建て住宅が建つ計画が動き出す。手がけるのは米建築スタートアップ、マイティ・ビルディングズだ。同社は自社工場で3Dプリンターで住宅を製造、そのまま大型トレーラーで運んで施工するビジネスモデルだ。3Dプリンターには事前に図面データを入力する。データ通りにノズルを動かし、紫外線を当てるとすぐに硬くなる特殊な建築素材を噴射して積み重ねる。例えば、天井部分の工程では柱やパネルを設置した後、上から覆うように建築素材を噴出して形成していく。固まった層は外壁や床材などになるため、大がかりな現場工事は要らない。一人暮らしなどに向く小型住宅なら、10日程度で製造から施工までできるという。国内大手住宅メーカーによると、戸建て住宅の建築は2カ月ほどかかる場合が一般的。同社のスラバ・ソロニーツィン最高経営責任者(CEO)は「従来の建築工法と比べて費用は30%削減できる」と自信を見せる。同社は昨年から同州で住宅を供給しており、日本市場への参入に向けた検討も始めた。3Dプリンターを使った建築は世界で広がっている。オランダの3Dプリンターメーカー、サイビ・コンストラクションは世界で10台以上の納入実績を持つ。同社は数分で固まる素材も開発。これらを使ってアラブ首長国連邦やオランダなどで住宅が建てられている。国内大手も動く。大林組は3Dプリンターで高さ2.5メートル、幅7メートルの大型ベンチを試作。早ければ22年にも3Dプリンターの商業化を目指す。竹中工務店もオランダのスタートアップと共同で3Dプリンター技術の検証を進め、23年以降にイベント施設などの建築向けに導入する考えだ。企業による3Dプリンターの活用はこれまで、樹脂や金属の成型が中心だった。金型成型などの既存技術と比べて短期間で製造でき、少量多品種生産にも対応できることから試作品づくりなどに使われている。自由なデザイン設計がしやすく、製造に携わる人手を減らせることも利点だ。三菱重工業は国産ロケット「H3」でエンジン噴出口部品の加工に3Dプリンターを採用。100億円程度とされる打ち上げコストの半減をめざす。調査会社の富士経済(東京・中央)によると、樹脂や金属を素材とする世界の3Dプリンター市場は19年の1186億円から25年は1833億円と5割以上伸びる。デロイトトーマツグループの入江洋輔氏は「最近では技術開発が進んで3Dプリンターで加工できる素材などが増え、印刷速度も上がってきた」と指摘する。単なるものづくりの代替手段にとどまらず、イノベーションを生み出す役割も3Dプリンターが担う。その一例が再生医療だ。医療スタートアップのサイフューズ(東京・文京)が独自に開発した3Dプリンターは、臓器に疾患がある患者から採取した細胞を培養し、患者専用の臓器を製造する。3Dプリンターで細胞を剣山に刺していき、次第に細胞同士がくっついて固まることで数週間で臓器が完成する。25年度にも移植手術で利用できるようにしたい考えだ。臓器は患者の細胞からつくるため、人工臓器と比べ移植後に感染症や拒絶反応リスクが生じにくい。まず血管や骨軟骨などで臨床試験に入った。同社の三條真弘氏は「移植可能な臓器をつくるためには3Dプリンター技術が不可欠だ」と話す。食品業界ではイスラエルのリディファイン・ミートが3Dプリンターで代替肉によるステーキなどを製造する技術を開発した。植物由来の素材をプリンターのノズルで噴射して積み重ねて製造。アジア市場ではハンバーガーなどの製品群を22年に提供する方針だ。3Dプリンターはデザインが複雑な構造物や、細胞を培養した臓器など特殊な用途で強みを発揮する。一方、大量生産には金型成型の方が適する場合もある。3Dプリンターが得意な分野をいかに見いだして使いこなすか、巧拙が問われる。 ●人手不足緩和へ導入 人手がかからず短期間でものづくりができる3Dプリンターの活用が広がれば、日本の産業界が陥っている慢性的な人手不足の緩和につながる。特に建設業界は人材の高齢化が進む一方、3K(きつい、汚い、危険)のイメージから若者は就業を避けがちだ。労働政策研究・研修機構が2019年に公表した推計では、鉱業・建設業の就業者が17年の493万人から40年に300万人未満に落ち込む。人手不足に苦慮する建設業界では近年、部材加工や施工の一部でロボット導入が相次ぐ。そんな中、住宅をまるごと自動で造ってしまう3Dプリンターの活用はさらに先を行く取り組みだ。みずほリサーチ&テクノロジーズの岩崎拓也氏は「競争力維持のため、国内産業は3Dプリンターの活用領域を見極めて構造転換する必要がある」と指摘する。課題もある。日本の建設業界は災害が多いことなどを背景に法規制が厳しく、3Dプリンターによる大規模な住宅の建築は事実上難しい。柱など住宅の主要な構造部材は日本産業規格(JIS)などの規格・基準に沿わないと使えず、個別に認定を受ける必要がある。デロイトトーマツグループの入江氏は「日本企業は品質へのこだわりが高く、量産への活用には抵抗もある」とみる。欧州では3Dプリンターの製造受託サービスが普及する一方、「自前主義」が強い日本では同様のサービスが少ないことも普及の壁となる。人手不足や規制、過剰品質など3Dプリンター導入の利点や普及に向けた課題は、日本の産業界が直面する問題そのものだ。3Dプリンターを今後どう活用していくかは、こうした問題にどう向き合うかの試金石にもなる。 *多様な観点からニュースを考える:深尾三四郎 伊藤忠総研上席主任研究員 新時代に合った日本発祥の技術。コロナ禍のイタリアでは、ロックダウン下の工場停止で在庫不足に陥った人工呼吸器の弁をミラノのファブラボ(市民共有型の工場)が3Dプリンターで即時生産し、病院に供給したことで数多くの命が救われた。印刷機に送信される製品設計図等のIPをデータの耐改ざん性と機密性を担保するブロックチェーンで管理し、IP使用量に見合う利用料を徴収するシステム構築もイタリアの中小企業の間で試行されている。製造時CO2排出が多い金型を省き、樹脂素材はリユース・リサイクルできるので脱炭素化にも貢献する。1980年に名古屋で光硬化樹脂を積層する光造形法を発明した小玉秀男氏が3D印刷の生みの親。 *1-4-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15011223.html (朝日新聞 2021年8月15日) 抗体カクテル、宿泊療養者にも 重症化防止へ厚労省 新型コロナ 入院患者にしか認められていなかった新型コロナウイルスの「抗体カクテル療法」が、宿泊療養者にも使えるようになった。首都圏を中心に病床が逼迫(ひっぱく)するなか、この治療で症状が軽い人たちの重症化を防げれば、医療提供体制への負担軽減にもつながりそうだ。抗体カクテル療法は、ウイルスが細胞に感染するのを防ぐ二つの中和抗体を組み合わせた点滴薬。軽症や中等症の患者向けで、肥満や基礎疾患などがある高リスクの人の重症化を抑える効果が見込まれる。国内では初の軽症者向けの薬として7月に特例承認された。感染初期の治療の選択肢を広げると期待されている。厚生労働省が13日付で都道府県などに出した通知によると、宿泊施設を臨時の医療施設とみなすことで、ホテルなどで療養している患者も治療対象とする。自治体や専門家からは、自宅療養者への使用を求める声も上がるが、高齢者施設や自宅で療養している患者への使用は現時点では認めない、とした。宿泊施設では、投与後に少なくとも1時間は経過をみる。また、投与して24時間以内の副作用として重いアレルギー反応「アナフィラキシー」が報告されていることなどを踏まえ、十分な観察ができるようにすることも求めた。宿泊療養施設での抗体カクテル療法の実施は、東京都の小池百合子知事が13日の記者会見で、態勢を整備したことを表明。「コロナとの闘いに新たな武器が加わった。攻めの戦略で、いかにして重症化を防いでいくかになる」と語った。厚労省によると、11日時点でホテルなどの宿泊施設に滞在する療養者は、全国に1万4871人で、4週間前の約3倍となった。自宅療養者は約13倍の7万4135人にのぼっている。 *1-4-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15010172.html?iref=shukatsu_mainbox_top (朝日新聞 2021年8月14日) 「酸素ステーション」整備 商業施設「人流を抑制」 首相表明 菅義偉首相は13日、自宅療養患者への連絡態勢を強化する考えを示した。患者が酸素の投与が必要になった場合に対応する「酸素ステーション」を設けて対処するといい、こうした方針を関係閣僚に指示したという。首相官邸で記者団の取材に応じた。首相は自宅療養の患者について「必ず連絡が取れるようにする」と述べた。また、軽症者の重症化を抑える抗体カクテル療法を集中的に使える拠点を整備する考えも示した。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は12日、感染拡大が深刻な東京都で、人出を緊急事態宣言が始まる直前の5割まで減らす必要があるとの緊急提言を公表した。首相は「提言を受け、関係団体と連携し、商業施設などの人流の抑制に取り組んでいきたい」と説明。また、コロナのワクチン接種で「10月初旬までに、希望する国民の8割に2回打てる態勢を作っている」とも述べた。 <地方産業の高度化―その2:農林漁業の販売力向上> *2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210814&ng=DGKKZO74783390T10C21A8EA1000 (日経新聞 2021.8.14) 「売れる農業」県内一丸 稲作からの転換奏功、宮崎や鹿児島、ブランド確立 基幹産業として地域を支えてきた農業の競争力に大きな差が生じている。過去5年間で全国1741市区町村のうち6割の974が産出額を伸ばした一方、4割は減少した。躍進が目立つ九州勢の取り組みを探ると、地域ブランドを活用した「売れる農業」の姿が見えてくる。農林水産省が3月に公表した2019年の農業総産出額は8兆8938億円。都道府県別の産出額では北海道が統計の残る1960年以来首位を守り、1兆2558億円だった。2位以下は鹿児島県、茨城県、千葉県、宮崎県、熊本県が順に並ぶ。60年時点では新潟県など米どころが上位の常連だったが、需要低下もあり稼げる農業の内訳が一変。台風被害を防ぐため稲作から施設を使った畜産や園芸への転換を進めた宮崎県などの九州勢が躍り出た。2014年から集計が始まった自治体別の産出額(推計)でみても、九州が目立つ。19年のトップは宮崎県都城市で877億円。14年比増加率(産出額100億円以上の226自治体を集計)でも首位は74%増の宮崎県日向市だった。2位は61%増で鹿児島市、都城市も25%増で33位に入った。稼ぐ力を確立した地域が、より強みを発揮する。マンゴーの産地、宮崎県日向市は県やJAなどと取り組んだ高級マンゴーのブランド「太陽のタマゴ」のほか畜産などで生産力を高めた。主力の養鶏では事業者が鶏舎の清掃などの分業化を進めて作業効率を向上。鶏肉の年間出荷回数を従来の4.5回から5~6回程度まで引き上げた。日向市だけでなく、宮崎県内では関係者が一丸となった競争力向上の取り組みが進む。県は1994年に「みやざきブランド確立戦略構想」を策定し「『作ったものを売る』から『売れるものを作る』」を目標に据えた。おいしさや鮮度といった商品そのものの「質」を高めるだけでなく、安心・安全を前面に畜産物と花卉(かき)を除くすべてのブランドに月2検体以上の残留農薬検査を義務付け、基準値を超えた場合には迅速な出荷停止措置をとれる体制を整えた。都城市は60年以降、稲作から畜産への転換を進めてきたことが功を奏し、2019年、初の首位となった。主力産品のひとつ「宮崎牛」は1986年、県内関連団体が共同で「より良き宮崎牛づくり対策協議会」を発足させ、品質向上への動きを加速。「日本一の努力と準備」を合言葉に全国大会で史上初の3連覇を果たしたことなどで、首都圏をはじめとした大消費地からの評価を高めた。増加率2位の鹿児島市も「鹿児島黒牛」や「かごしま黒豚」の産地の一つとして、県や周辺自治体と連携して知名度向上に力を入れる。県は全国に先駆けて1989年から販売力の強化を目的とした農産物の認証制度をスタートした。2010年代半ばからは輸出も強化。牛肉は東南アジアでの人気が高く、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、県全体の輸出額が前年度比5%減少の214億円だった20年度も、畜産物は21%増の106億円と過去最高額を更新した。鹿児島黒牛と宮崎牛は17年末、国が保護する地域ブランドに登録された。鹿児島黒牛は遺伝子解析などの先端技術を使い、改良に長く取り組んできたと認められた。宮崎牛は種牛の一元管理を全国で初めて構築したと評価された。地域ブランドには「神戸ビーフ」「特産松阪牛」も名を連ねており、世界に知られる和牛産地と南九州が肩を並べている。 *2-2-1:https://www.jiji.com/jc/article?k=2021072801196&g=eco (時事 2021年7月29日) ふるさと納税、過去最高6725億円 「巣ごもり需要」背景か-20年度 ふるさと納税の2020年度の寄付総額が約6725億円で、過去最高になったことが28日、分かった。寄付件数も過去最多だった。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「巣ごもり需要」を背景に、各地の返礼品を楽しむ寄付者が増えたためとみられる。総務省が近く公表する。寄付総額は19年度の約4875億円から1.4倍に増加。寄付件数は約3489万件で、制度開始以来12年連続で最多を更新した。自治体別の受け入れ額は、1位が宮崎県都城市で135億2500万円。2位が北海道紋別市の133億9300万円で、同根室市125億4600万円が続いた。一方、ふるさと納税による21年度の住民税控除額は、前年度比1.2倍の約4311億円だった。最も多いのが横浜市の176億9500万円で、名古屋市106億4900万円、大阪市91億7600万円の順となった。ふるさと納税は、寄付額から2000円を引いた額が現在住んでいる自治体の住民税などから控除される仕組み。豪華な返礼品を提供する競争の過熱が問題となり、19年6月から返礼品は「寄付額の3割以下の地場産品」などの基準を守る自治体のみ参加できる制度に移行した。 *2-2-2:https://digital.asahi.com/articles/ASP867HHFP7ZTIPE01P.html (朝日新聞 2021年8月10日) 「電力まで五島産」広がる再エネ ふるさと納税でも復活 再生可能エネルギーの「産地」を売りにする動きが広がっている。地域の太陽光や風力などでつくった電気をブランド化して地域振興につなげる狙いだ。ふるさと納税の返礼品としてPRする自治体もある。 ●「電力まで五島産」 レシピカードには、こんな言葉が記されていた。東京や大阪の百貨店で開かれた物産展で、長崎県五島市の水産加工会社「しまおう」が魚のすり身に昨年から添えた工夫だ。 ●原料の安全・安心は当たり前 しまおうは地元でとれるアジやアゴ(トビウオ)ですり身やかまぼこを作る。昨春、地元の新電力会社と契約し、工場の電気はすべて地元の再エネでまかなっている。カードには「島の風と太陽から生まれた電気で製造しています」と記し、風車のイラストも描いた。山本善英社長(51)は「原料の安全や安心は当たり前。地元の電気が注目されるようになれば」と話す。五島市では太陽光や風力発電など再エネの普及が進み、使う電気の約半分は市内でつくっている計算だ。沖合に巨大な風車を新たに8基浮かべて発電する計画も進んでおり、2023年ごろには8割まで上げる予定だ。電気は、大手電力会社には売らず、できるだけ「地産地消」に生かす。今夏には、使う電気をすべて地元の再エネでまかなう企業を独自に認定する「五島版RE(アールイー)100」という取り組みを始める。五島と政府の景気刺激策をもじった「GOTO RE100」というロゴマークも作り、認定された企業はロゴを使って取り組みをアピールできる。地元の福江商工会議所の清瀧誠司会頭(81)は「人口減少の著しい離島は、他ではできないことをしなければ生き残れない。島の電気を活用して生産段階から差別化を進め、地元企業の価値を高めたい」と話す。 ●スタバも関心「お店で知って」 電気の産地には、企業も関心を示す。スターバックスコーヒージャパンは10月までに、約350店舗ある直営路面店すべてで、使う電気を地域の再エネに切り替える。富山や鹿児島の店では地元の水力発電所の電気を使う。徳島では地元の木質バイオマス発電所から調達し、近くの森林の維持・管理にも役立てる。広報担当者は「ビジネスを続けるには、地域活性化への貢献は欠かせない。お店を通じて、地元の再エネも知ってもらいたい」と話す。アウトドア用品大手、スノーピークも7月、新潟県三条市の本社などで使う電気を市内の木質バイオマス発電所に切り替えた。電気代は少し高くなる見込みだが、「地元に根ざした事業をしており、地産地消に貢献したい」(広報)としている。ふるさと納税の返礼品として地元の再エネを提供する動きもある。阿蘇山のふもとにある熊本県小国町は8月初旬、地元の電気を返礼品に加えた。町には地熱発電所が立地し、太陽光や水力を含む発電出力は約3万7千キロワット。町内で使う電気の約2・6倍に及ぶ。特産のあか牛や馬刺しなどの肉類には知名度で劣るが、「町の新電力会社の経営安定にもつながる。町外からの問い合わせも多い」(町の担当者)。 ●ふるさと納税もお墨付き 地元の電気を返礼品として提供して寄付者の電気代を割り引く自治体は数年前からあった。しかし、総務省が今年4月、「電気は地場産品に当たらない」との見解を出した。一般の送配電網で供給される電気は様々な地域で発電されたものが混ざってしまうためだ。再エネの普及をめざす政府の方針を受けて、総務省は一転して6月に一定の条件下でこれを容認した。政府のお墨付きを得たことで、返礼品をきっかけに再エネ普及が進む、との期待も出ている。電気の返礼品は今春まで福島県楢葉町や愛知県豊田市、大阪府泉佐野市など全国9市町が提供していた。地元の太陽光や水力で発電した電気をもとに17年から返礼品を提供している群馬県中之条町は10月再開をめざす。担当者は「またぜひ使ってもらいたい」。ただ、寄付者が返礼品としての電気を受け取るには、自治体の指定する新電力会社と契約を結ぶ必要がある。手続きの煩雑さが寄付額の伸び悩みにつながっているとの見方もある。 *2-2-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15008803.html (朝日新聞社説 2021年8月13日) ふるさと納税 「官製通販」見直しを ふるさと納税による寄付の膨張が止まらない。昨年度に全国の自治体が受け入れた寄付額は前年度を4割も上回り、過去最高の6724億円にのぼった。自治体間の過剰な競争を抑えるため、返礼品を「寄付額の3割以下」にするルールが導入され、19年度は7年ぶりに減少に転じた。だが、ルールは早くも骨抜きになっている。例えば、コロナ対策で農水省が始めた農林水産品の販売促進の補助金を使えば、返礼率を大幅に高めることができる。20年度に寄付額が急増したのはコロナ禍での「巣ごもり消費」に加え、ルールの形骸化も影響しているだろう。ふるさと納税は、寄付額の多寡にかかわらず、自己負担は実質2千円だ。高所得者ほど返礼品を多く受け取れるうえ、税の優遇も大きい。コロナ禍による格差の是正が政策課題になるなか、不平等な仕組みをこれ以上放置することは許されない。総務省によると、寄付額の45%が返礼品の購入費や、返礼品を選ぶ民間のポータルサイトへの手数料などに費やされている。昨年度の寄付額から換算すると、全体で約3千億円の税収が失われることになる。コロナ感染が特に広がっている東京などの都市部は、ふるさと納税で寄付する人が多い。財源の流出が続き、感染対策の費用をまかなえないような事態になっては困る。ふるさと納税の当初の趣旨は、寄付を通じて故郷に貢献してもらうことだった。しかし現状では「官製通信販売」になってしまっている。NTTグループの昨年の調査では、「出身地への貢献」のために制度を利用した人は12%しかいなかった。自治体間の財政力の格差を是正するのであれば、いまの地方税や地方交付税のあり方が妥当かを、正面から論じるべきだ。そもそも寄付とは、見返りを求めないものである。返礼品を受け取らずに、災害の被災地に寄付をする人もいる。ふるさと納税を続けるのであれば、返礼品をなくすなど抜本的に制度をつくり変える必要がある。しかし見直しの議論は進んでいない。ふるさと納税は菅首相が総務相時代に創設を決めた。反対した幹部が「左遷」されたこともあり、制度の欠陥を指摘されても、総務官僚らは見て見ぬふりを決め込んでいる。地方自治は「民主主義の学校」と言われる。返礼品を目当てに、自分が暮らす自治体から受けた行政サービスに対する負担を回避する制度は、地方自治の精神を揺るがす危うさがある。制度の生みの親である菅首相には、政策の誤りを認め、欠陥をただす責任がある。 *2-3:ttps://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210815&ng=DGKKZO74788420U1A810C2EA1000 (日経新聞 2021.8.15) 「シャインマスカット」 中韓の生産、日本上回る 日本発ブランド、流出先で輸出の主力に 高級ブドウ「シャインマスカット」をはじめ、日本発のブランド品種の海外流出が深刻さを増している。流出先の韓国では、もともとのシャインマスカットが今や輸出の主力となり、輸出額は日本の5倍超に膨らんだ。中国国内での栽培面積は日本の40倍超に及ぶ。海外への持ち出しを禁止する改正法が4月に施行したが、実効性には課題を残したままだ。農林水産省によると、シャインマスカットは2016年ごろから海外流出を確認。法規制が追いついていなかった経緯もあり、韓国などへの持ち出しと現地栽培、輸出が膨らんでいった。19年には日韓のブドウの輸出数量が逆転した。21年1~4月の韓国産ブドウの輸出額は約8億円と前年同期比で1.5倍に増えた。このうちシャインマスカットが約9割を占めた。日本の輸出額は1億4700万円にとどまり、量では7倍の差がついた。農林水産・食品産業技術振興協会によれば、ブランド果実の流出先は中国、韓国が中心だ。シャインマスカットのケースで、栽培面積は日本が1200ヘクタールなのに対し、韓国は1800ヘクタール、中国では5万3000ヘクタールと規模は桁違いだ。ブドウ以外でも同協会の20年の調査で、30以上の品種の海外流通が確認された。静岡県のイチゴ「紅ほっぺ」や高級かんきつ「紅まどんな」などが標的になっている。政府は登録品種の海外持ち出しを禁じる改正種苗法を4月に施行した。違法持ち出しに罰金や懲役を設けたが、違反事案は絶えない。意図的かどうかにかかわらず、一度流出すると種苗や苗木の追跡は難しくなる。日本政府はブランド品種を中核にし農林水産物輸出額について25年に2兆円、30年に5兆円に増やす目標を掲げる。20年の輸出額は9217億円。当初目標の「19年に1兆円」には届かなかった。海外流出に歯止めをかけられず、さらに流出先で輸出まで膨らむ状況が続けば、一連の目標に黄信号がともる。 <地方産業の育成―その1:再エネ> *3-1-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA074ZX0X00C21A8000000/ (日経新聞 2021年8月9日) 気温1.5度上昇、10年早まり21~40年に IPCC報告書 国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は9日、産業革命前と比べた世界の気温上昇が2021~40年に1.5度に達するとの予測を公表した。18年の想定より10年ほど早くなる。人間活動の温暖化への影響は「疑う余地がない」と断定した。自然災害を増やす温暖化を抑えるには二酸化炭素(CO2)排出を実質ゼロにする必要があると指摘した。温暖化対策の国際的枠組みのパリ協定は気温上昇2度未満を目標とし、1.5度以内を努力目標とする。達成に向け先進各国は4月の米国主催の首脳会議(サミット)で相次ぎ温暖化ガスの新たな削減目標を表明した。今回の報告書は気温上昇を抑える難しさを改めて浮き彫りにした。10月末からの第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)での議論が次の焦点になる。IPCCは5つのシナリオを示した。21~40年平均の気温上昇は、50~60年に実質排出ゼロが実現する最善の場合でも1.5度になる。化石燃料への依存が続く最悪の場合は1.6度に達する。18年の報告書は1.5度になるのは30~52年とみていた。予測モデルを改良し、新たに北極圏のデータも活用したところ10年ほど早まった。上昇幅は最善の場合でも41~60年に1.6度になる。化石燃料への依存が続く最悪の場合は41~60年に2.4度、81~2100年に4.4度と見込む。過去の気温上昇も想定以上に進んでいたとみられる。今回、11~20年平均で1.09度と分析した。18年の報告書は06~15年平均で0.87度だった。1850~2019年の二酸化炭素排出量は累計2390ギガトン。気温上昇を1.5度以内に抑えられる20年以降の排出余地は400ギガトンとみる。今の排出量は年30~40ギガトンで増加傾向。10年ほどで1.5度に達する。産業革命前は半世紀に1回だった極端な猛暑は1.5度の上昇で9倍、2度で14倍に増えると予測する。強烈な熱帯低気圧の発生率も上がり、干ばつも深刻になる。平均海面水位は直近120年で0.2メートル上がった。今のペースは1971年までの年1.3ミリの約3倍と見積もる。気温上昇を1.5度以内に抑えても、2100年までに今より0.28~0.55メートル上がると予測する。気候変動のリスクを正面から受け止め、対策を急ぐ必要がある。IPCCは気候変動に関する報告書を1990年以来5~7年ごとにまとめている。最新の研究成果を広く踏まえた内容で信頼度が高く、各国・地域が温暖化対策や国際交渉の前提として活用する。第6次となる今回は22年にかけて計4件の報告書を公表する予定だ。 *3-1-2:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021081100128 (信濃毎日新聞社説 2021/8/11) 温暖化報告書 深刻さを共有しなければ 深刻さはより深まっている。人類への警鐘と受け止め、二酸化炭素(CO2)排出量の実質ゼロを確実に果たさねばならない。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が、最新データに基づく地球温暖化の予測を報告書にまとめた。温暖化は人間の影響とすることに「疑う余地がない」と初めて断言。世界の平均気温は、対策を進めても2021~40年に、産業革命前と比べて1・5度上昇する可能性が高いとした。13年の報告書では、温暖化と人間の影響について「可能性が極めて高い」と指摘。18年の特別報告書で、上昇幅が1・5度に達するのは30~52年としていた。踏み込んだ表現や、約10年早まった分析は、スーパーコンピューターを駆使し、より精度を高めた結果だ。科学に裏付けられた知見として共有する必要がある。温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」は、気温上昇を2度未満、できれば1・5度に抑える目標を掲げる。2度を超えると、極端な高温や豪雨などが頻発し、海面が上昇すると考えられるからだ。報告書によると、11~20年で1・09度上昇した。既に極地やシベリアで氷床や永久凍土の融解が報告されている。日本では巨大台風の襲来や豪雨、世界では異常熱波や大規模な山火事が繰り返されるようになった。当面続く気温上昇に備え、避難計画見直しや食料確保といった対応が欠かせなくなりつつある。報告書は、50年にCO2排出量を実質ゼロに抑えられた場合、温度は今世紀後半に下降し、1・5度未満に収まる予測も示している。解決のための目標は明確だ。日本政府は、30年度に13年度比で46%削減、50年に実質ゼロを表明している。ただ、再生可能エネルギーの活用を模索する一方で、石炭火力を温存し、家庭での取り組みに頼る姿勢を見せる。石炭火力の全廃やガソリン車の販売禁止といった思い切った政策を早期に打ち出さなければ、実現は困難ではないか。生物多様性の保全や海洋プラスチックごみ対策も温暖化抑止につながる。森を守り、化学肥料を減らして農作物を育て、プラスチックをできるだけ使わない暮らしを、地域や個人でも進めたい。10月末には英国で国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議が開かれる。各国の足並みはそろっていない。報告書の知見を最大限に生かし、世界が一体となれる合意を目指さねばならない。 *3-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210729&ng=DGKKZO74269830Y1A720C2EN8000 (日経新聞 2021.7.29) 脱炭素の外圧、変革に生かせ 今日、日本の最大の課題は脱炭素だ。一連の環境問題への対応は、欧州を中心にスタンダード化するなかで日本も取り組まざるを得なかったものだ。そもそも「日本は環境先進国」と思っていたなかで生じた「外圧」による対応に、必要性を感じながらも釈然としない思いを抱く日本人も多いのではないか。米国もバイデン政権になって脱炭素に向けて大きく舵(かじ)を切っただけに、日本は外堀を埋められた。2020年10月の菅義偉首相の決断がせめてもの救いだ。外圧が主導し、日本の主体性がみえない対応はいかがなものかという見方は当然だ。だが、約150年前の明治維新以来、日本は50年周期の外圧による転換の繰り返しだった。幕末の欧米列強の外圧がなければ、明治維新の近代化、統一国家実現は不可能だった。その後、1920年代の世界大恐慌後の重化学工業化も同様で、戦後の政治経済のレジームは日本国憲法をはじめほとんど外圧だった。70年代以降の環境問題による転換も同様だろう。公害問題の深刻化に伴う自主的な側面はあったが、大きなドライバーになったのが、石油危機でのエネルギー価格高騰のほか、米国のマスキー法などを中心とした自動車の排ガス規制だった。以上、日本は常に外圧に対し、やらされているという被害者意識を持ちつつも、その潮流に乗って大きく社会構造や経済システムを転換させてきた。日本がなかなか自律的に変わりにくいなか、外部環境の転換がなければ改革はできなかった。第2次世界大戦が終わって3四半世紀が過ぎ、バブル崩壊という第2の敗戦を経て、新型コロナウイルス危機は第3の敗戦との見方もある。ただし、脱炭素も含めた環境問題はそもそも日本が先進的な分野である。日本ほど自然災害への遭遇も含め、自然と向き合う生活を文化としてきた国民も珍しい。今回の脱炭素を中心とした外圧も、日本にとって大きなチャンスとの見方ができる。70年代の一時的な成功体験に安住し、その後バブルに陥ったことによる停滞を一気に挽回する発想転換が必要だ。そこでは世代交代も含め、保有資産が座礁資産化するのも覚悟しつつ、過去を捨て去る決断も必要になるだろう。 *3-2-2:https://373news.com/_column/syasetu.php?storyid=141076 (南日本新聞 2021/7/30) [エネルギー計画] 脱炭素へ抜本的改定を 経済産業省は、2030年度の電源構成で再生可能エネルギーの主力化を進める新たなエネルギー基本計画の素案を有識者会議に提出した。菅義偉首相が打ち出した50年の温室効果ガス排出量実質ゼロや、30年度に排出量を13年度比で46%削減するといった国際公約の実現に向けた重要な一歩ではある。だが、再生エネ拡大には課題が山積し、二酸化炭素(CO2)排出量が多い石炭火力や、諸問題を抱える原子力への依存を続ける姿勢は変わらない。政府は脱炭素の実現に不可欠な社会や経済の変革を促すため、計画を抜本的に見直していかなければならない。基本計画は中長期的なエネルギー政策の指針で、将来の電源構成や原発の運営の方向性などを示し、おおむね3年に1度改定してきた。今後、意見公募などを経て10月までに閣議決定する見通しだ。素案では、現行目標が22~24%の再生エネを36~38%と大幅に拡大する方針を示した。19年度実績の約2倍に相当し、政府は建設期間が比較的短い太陽光に期待している。ただ、太陽光は急速に導入を進めてきた結果、新たな適地の確保が難しくなっている。悪天候で発電が減った時に備え、他の電源を用意するコストがネックになる恐れもあり、順調に進むかは不透明だ。再生エネ拡大は国際的潮流だが、素案の目標はドイツの65%、米カリフォルニア州の60%などに比べて見劣りする。政府は電力を消費地に届けるための送電網の整備や蓄電池の普及を急ぎ、大幅な拡大を目指す必要がある。一方、現在主力の火力は現行の56%から41%へと大きく減らす。このうち、近年は総電力の3割前後を占めるまでに拡大した石炭火力は19%に削減するが、安定供給性や経済性に優れているとして活用する道を残す。米国が35年の電力脱炭素化を掲げ、各国が石炭火力の全廃を打ち出す中、日本の温暖化対策の遅れが際立っていると言わざるを得ない。原子力については、東京電力福島第1原発事故後に再稼働した原発は33基中10基で、19年度実績は6%程度にとどまる。しかし、目標は現行の20~22%に据え置かれ、低コストで安定供給が可能な「重要なベースロード電源」という位置付けも維持した。目標達成には30基程度を稼働させる必要がある。安全対策でコストがかさむ中、政策の見直しは避けられないのではないか。さらに焦点だった原発の新増設や建て替えの方針は盛り込まれず、問題を先送りした感は否めない。原発に対する国民の不信感は根強い。政府は原発の是非を含めた議論を深め、将来像を示すべきである。 *3-2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210819&ng=DGKKZO74903140Y1A810C2TB2000 (日経新聞 2021.8.19) テスラ、日本で送電向け蓄電池 価格5分の1に 米電気自動車(EV)大手のテスラが日本で電力ビジネスに参入する。電力需給の調整弁となる大型蓄電池と制御システムを電力事業者に供給し、天候によって発電量が変動する再生可能エネルギーの有効活用を後押しする。国内相場の約5分の1の価格で販売する予定で、再生エネの導入コストが下がる効果も期待できる。再生エネ発電所は安定して発電しにくい。必要以上に発電すると需給バランスが崩れ、送電網がパンクして停電を起こしかねない。電力インフラに組み込む蓄電池に余剰電気を蓄えさせ、需要が増えたときに放電させれば再生エネを無駄なく使える。テスラ日本法人のテスラモーターズジャパン(東京・港)は第1弾として、新電力のグローバルエンジニアリング(福岡市)が2022年に北海道千歳市で稼働させる拠点に大型蓄電池を納入する。容量は6000キロワット時で、一般家庭約500世帯分の1日の電力使用量に相当する。グローバルエンジニアリングは北海道電力の送電網にテスラの蓄電池システムを接続し、電力の調整弁として機能させる。1キロワット時当たりの納入価格は5万円弱と従来の推計価格(24万円強、19年)を大きく下回る。電池の調達元は中国の寧徳時代新能源科技(CATL)。EV向けも調達する電池の世界大手で、このほどテスラと25年末までの新たな供給契約を結んだ。提携関係からテスラは有利な条件で取引できるとみられる。経済産業省は7月、新しいエネルギー基本計画の原案をまとめ、30年度の電源全体に占める再生エネ比率を現行の22~24%から36~38%に引き上げるとした。これに伴い、計2400万キロワット時分の蓄電池が必要になる見通しだ。テスラは米国やオーストラリアで需給に応じて自ら電力を売買する事業を展開している。日本でもほかの新電力や商社などと組み、電力ビジネスを拡大するとみられる。 *3-3-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0121X0R00C21A8000000/ (日経新聞 2021年8月1日) 水素航空機の空港施設整備、官民で検討 燃料貯蔵など 政府は水素を燃料とする航空機の実用化に向け、水素の貯蔵や機体へ注入するための空港施設の整備に向けた検討を始める。二酸化炭素(CO2)を排出しない水素を燃料とする航空機は次世代技術として期待される。今秋をめどに、具体化に向けた課題を整理してまとめる。経済産業省は3日午後にも、国土交通省や文部科学省のほか、関連民間企業による検討会の初会合を開く。水素燃料航空機の空港インフラ整備について日本政府が検討するのは初めて。民間からは日本航空や全日本空輸、川崎重工業、三菱重工業、IHI、燃料供給会社が参加する。水素燃料航空機を運航させるには、液化水素燃料の貯蔵タンクや、送配管といった施設を設置する必要がある。現状の制度面での課題や、費用試算も含めて検討し、早期実現を後押しする。欧州航空機大手のエアバスは、2035年までに水素燃料航空機を市場投入すると公表した。他メーカーの動向も踏まえ、経産省は30年までに要素技術を確立する必要があるとみている。 *3-3-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/123525 (東京新聞 2021年8月11日) 軽電気自動車の開発加速、発売へ 価格200万円切りが焦点 軽自動車の電気自動車(EV)の開発競争が加速している。日産自動車と三菱自動車は共同開発車を2022年度前半に発売し、スズキは20年代半ばの投入を目指す。「地方の足」である軽にも、脱炭素の流れが波及している。安さが魅力の軽でEVが広まるには、国や自治体の補助金を含めた価格が200万円を切り、どこまで下げられるかが焦点になりそうだ。ホンダは24年の発売を計画。ダイハツ工業は開発を検討中。日産と三菱自は他社に先駆けて発売し「軽EVの開拓者」(関係者)を狙う。スズキは今年「EV事業本部」を新設した。走行距離と価格のバランスを見極めることが重要になりそうだ。 *3-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210819&ng=DGKKZO74903370Y1A810C2FFJ000 (日経新聞 2021/8/19) 百度、自動運転EVに本腰、吉利と提携、8500億円投じ生産 ロボタクシー事業拡大 中国インターネット検索最大手の百度(バイドゥ)は18日、未来のクルマのあり方を示した自動運転のコンセプト車「ロボットカー」を発表した。中国自動車大手との共同出資会社で参入する電気自動車(EV)の製造・販売には今後5年間で500億元(約8500億円)を投じる。8年前に開発に着手した自動運転技術の進歩を訴えた。「未来の自動車はロボットカーの方向に進化する」。18日、オンラインで開いた発表会で、李彦宏(ロビン・リー)董事長兼最高経営責任者(CEO)はこう強調した。ロボットカーは2人乗り。ハンドルやアクセル、ブレーキなどの運転席がなく、前面には大きなパネルがある。人工知能(AI)が学習することも特徴で、乗客の好みに応じた運転やサービスを提供するとしている。発表会で実際に走行する場面を披露したものの、ロボットカーの発売時期については触れなかった。現段階では未来のクルマとの認識だが、ネット大手の百度は近く、EVメーカーの仲間入りを果たそうとしている。今年初めに発表した中国民営自動車大手、浙江吉利控股集団との提携が戦略の柱になる。3月に立ち上げたEV製造・販売の共同出資会社、集度汽車は百度が55%を出資して主導権を握った。集度汽車は今後5年間で約8500億円を投じることを決め、自動運転技術を搭載したEVを製造・販売する。2022年4月に開かれる北京国際自動車ショーでコンセプト車を公開し、同年中にも受注を始める計画だ。具体的には、吉利が開発したEV専用のプラットホーム(車台)を活用し、吉利の工場を活用するとみられる。百度が自動運転技術の開発に着手したのは13年と競合より早く、17年には自動運転技術の開発連合「アポロ」を立ち上げた。トヨタ自動車や独フォルクスワーゲン(VW)、米インテル、米エヌビディアといった世界の大手が参画し、中国政府の支援を受けている一大連合だ。パソコンやスマートフォンの基本ソフト(OS)のように「自動運転車のOSといえる基幹システムを生み出すこと」を目標に掲げた。これまで百度は自動車大手にシステムを提供して「稼ぐ」モデルを描いてきた。実際、国有自動車大手の中国第一汽車集団や新興EVメーカーである威馬汽車がアポロを搭載したEVを投入した。ただ、中国国内での利用は進みつつあるものの、パソコンの「ウィンドウズ」やスマホの「アンドロイド」のように、市場を牛耳るにはほど遠い状況だった。次なる一手が、自ら車両の製造・販売を手掛けることだった。自動車大手とタッグを組み、収益化を急ぐ方針に転じた。百度など中国勢の自動運転技術の実力について、日系自動車メーカーの幹部は「成長が著しい」と評価する。自動運転で先行してきた米国勢に迫っている。20年の公道での自動走行試験の距離は米ゼネラル・モーターズ(GM)子会社と、米アルファベット傘下のウェイモに並び、百度も100万キロメートルを越えた。自動運転タクシーにも本格的に乗り出し、自動運転分野における「百度経済圏」の構築も急ぐ。現在は北京、広東省広州、湖南省長沙、河北省滄州の限定した公道で展開し、3年以内に30都市まで拡大する。これまでは実験段階で地図アプリで予約する仕組みだったが、本格的な事業展開に備えて専用アプリを立ち上げることも表明した。百度が自動運転分野で成果を急ぐのは、主力の検索事業の成長が鈍化しているためだ。売上高の約6割は検索を中心とするネット広告収入だ。中国政府が米グーグルなどの利用を制限し、検索サービスでは圧倒的なシェアを誇るが、20年12月期の売上高は1070億元と前の期を下回った。百度は長く、アリババ集団、騰訊控股(テンセント)と並ぶ中国のネット3強、いわゆる「BAT」と評されてきたが、収益面や時価総額では差が開いた。2強の背中は、はるかかなたにある。自動運転技術を搭載したEVはスマホ大手の小米(シャオミ)が参入し、自動運転タクシーも滴滴出行(ディディ)などが力を入れている。これまで中国勢の先頭を走ってきたと自負する百度の実力が今こそ問われる。 *3-3-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC166RR0W1A710C2000000/ (日経新聞 2021年8月11日) ホンダ寄居工場の進出効果、地元では実感乏しく ホンダは2021年度中に狭山完成車工場(埼玉県狭山市)の四輪車生産を新鋭の寄居完成車工場(同県寄居町)に集約する。狭山市の地域経済への懸念はこれまでも話題になってきたが、一方で寄居町の商工業は盛り上がっているのか。地元の商工団体や商店を訪ねると、民間ではまだ大きな経済効果が感じられない状況が浮き彫りになった。寄居工場の稼働開始は13年。06年の建設計画発表当初は、10年に稼働開始予定だったが、08年のリーマン・ショックで3年遅れた。「当初は町内の製造業にもっと大きな波及効果があると思っていた」。寄居町商工会の担当者は話す。しかしホンダ関連で大きな受注を獲得した企業や、工場の新増設の話も聞かないという。計画当初、寄居工場は国内での増産投資が目的だったが、その後、ホンダが国際分業を一段と加速。協力部品メーカーを含めて増産の意義は薄れ、町内の中小製造業が食い込む機会も広がらなかったとみられる。例えばホンダ系の大手部品メーカー、エイチワンは07年、増産に向けた工場用地を近隣の熊谷市に確保したが、21年3月に売却を発表した。商業にも目立った経済効果は出ていない。町内の中心部にある寄居駅南口の一等地で20年間続いた大型スーパー「ライフ寄居店」は13年に閉店し、今も空き店舗のままだ。寄居駅周辺の約40店で構成するふるさと寄居商店会会長で新島薬品を経営する新島清綱氏は「期待はしているが、ホンダの工場ができてから新しい客が増えた印象はまだない」と言う。要因の1つは、工場の立地も影響しているようだ。寄居工場は寄居駅から東武東上線で南東方向に4駅目のみなみ寄居駅前にある。同駅はホンダが東武鉄道に整備を要請し、事業費を全額負担した。駅舎と工場を結ぶ渡り廊下があり、従業員は駅から工場敷地内に直接入れる。駅前に商店はなく、従業員のほとんどは昼間、工場内の食堂や売店を利用するようだ。また「もともと狭山工場で勤務し、いまも狭山市周辺から通勤する従業員が多い」(寄居町役場)。車で通勤する場合、最終的には国道254号を北上して寄居工場に通うのが一般的で、寄居駅前は通勤ルートに入らない。従業員が町内で消費する機会はかなり限られる。こうした状況を打開しようと、寄居町は今年秋にも狭山市周辺から通う従業員ら向けに「移住・定住を促すツアーを開催したいと考えている」(担当者)。ただ寄居町と隣接する深谷市の花園地区には、22年秋に約120店舗を集めたアウトレットモールが開業予定で、町内の消費が流出する可能性もある。民間にはまだ目に見える経済効果が出ていないかもしれないが、ホンダの工場進出が寄居町の財政を潤したのは確かだ。寄居町の21年度の一般会計当初予算は約112億円、町税は約45億円。ホンダ進出で町税が5億円ほど増えたこともあったという。税収増の効果をもとに、地元企業の技術力向上をどう支援してホンダ関連の受注獲得に結びつけるか。ホンダ関連の従業員の移住促進や商業の活性化にどうつなげるか。寄居町にとってこれからが正念場となる。 *3-3-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210819&ng=DGKKZO74903030Y1A810C2TB2000 (日経新聞 2021.8.19) ホンダ、中国で新エネ車増産 EVなど、年12万台上積み ホンダが中国で電気自動車(EV)など新エネルギー車の生産増強に乗り出すことが18日までに分かった。合弁会社を通じた総投資額は約30億元(約500億円)で、南部広東省広州市の工場を増設し生産能力を年12万台分上積みする。2024年2月以降の稼働を目指す。ホンダは中国で新車販売を伸ばしてきたが、新エネ車を巡っては中国ブランドなどとの競争が激化しており巻き返しを急ぐ。ホンダの中国での合弁会社、広汽ホンダが広州市当局に提出した工場増強に関する入札申請書で投資計画が明らかになった。新設備の建設面積は約18万6000平方メートルで、10月の着工を予定する。EVやプラグインハイブリッド車(PHV)といった新エネ車専用の生産設備となる見込みだが、車種などは明らかになっていない。広汽ホンダは広州市に4工場を持ち年77万台の生産能力を持つ。一方、ホンダの別の合弁会社、東風ホンダも湖北省武漢市で3工場を運営し、生産能力は年72万台。広州市の新しい生産設備が稼働すれば、ホンダの中国での自動車生産能力は年161万台となり現在に比べ約1割増える見通し。ホンダの中国での新車販売台数は20年に19年比5%増の約163万台で2年連続で最高を更新した。21年も1~7月累計で前年同期比20%増の約89万台と伸びているが、足元では7月まで3カ月連続で前年実績を割り込むなど減速している。 <地方産業の育成―その2:医療・介護> *4-1-1:https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=781600&comment_sub_id=0&category_id=142 (中國新聞 2021/8/8) コロナ入院制限 制度設計、甘すぎないか 新型コロナウイルス感染症の入院対象者を、政府が絞り込む方針だという。重症化リスクの高い中等症や重症の感染者に限り、それ以外は自宅療養を原則とする。呼吸困難や肺炎などでも重症化リスクが低いと判断されると、自宅療養になる。これまでは、軽症や無症状の人も宿泊施設で療養させるのが基本だった。目の届きにくい自宅療養では容体急変への対応などが限られ、心もとない。感染者の激増を受けた苦肉の策だろうが、国民の命を左右しかねない方針転換である。必要な医療を受けられず、置き去りにされるようなことがあってはなるまい。入院制限の対象は「爆発的感染拡大が生じている地域であり、全国一律ではない」と菅義偉首相は説明する。念頭にあるのは首都圏だろう。だが感染力の強い変異株「デルタ株」は全国に広がっており、新規感染者は連日1万人を超す。地方にとっても人ごとではない。中等症でも、肺炎など症状によっては呼吸不全を起こし、酸素投与が必要になる場合もある。実際、5月がピークだった「第4波」では、自宅療養者が適切な医療を受けられずに重篤化したり死亡したりする事例が大阪で相次いだ。その教訓から今回、国民や医療関係者の間で懸念が高まり、与野党から異論が噴出したのは当然だろう。自宅療養を基本とするなら、何よりもまず、患者が安心して療養できる環境が必要である。現状では、往診などの在宅医療体制が整っている地域は少ない。宿泊療養施設の拡充や在宅患者を見守ることのできる医師や看護師の確保といった、地域住民の不安を拭い去る策を講じるのが先のはずだ。政府の方針では、入院対象の仕分けについては、自治体の保健所がまず担うという。ただ、各地の保健所はすでに業務がパンク状態とされる。対応する余力はあるのだろうか。また、自宅療養から入院への切り替えは地域の医師の判断に委ねられるものの、明確な基準は示されていない。制度設計が甘すぎるのではないか。緊急事態宣言下の6都府県では、自宅療養者が4日時点で約3万7千人に増えている。その4割近くは東京で、入院や療養先を調整中の人は1万人近くに上るという。入院の制限でさらなる増加は目に見えている。自宅療養者の急変に適切に対処できるとはとても思えない。見過ごせないのは、これほどの方針転換を専門家や自治体に相談せず、生煮えで政府が打ち出したことだ。首相は「国民の安全安心、命と健康を守る」と繰り返してきたが、今回の方針は感染拡大防止策の手詰まりをさらけ出していよう。ワクチン接種が進み、重症化リスクの高い高齢者の感染が減少傾向にあるのは確かである。にもかかわらず、入院制限を打ち出したのは、接種が済んでいない40~50代の感染者や重症者が急増したためだろう。楽観が過ぎ、あまりにも見通しが甘かったと言わざるを得ない。本来、選択肢を広げるのが政府の務めではないか。自粛要請に頼るばかりで、コロナ専用病棟をはじめとする病床確保を怠ってきた責任は重い。手を尽くして感染者を抑え、医療崩壊を食い止めねばならない。 *4-1-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC223NE0S1A720C2000000/?n_cid=NMAIL006_20210807_A (日経新聞 2021年8月6日) 接種進捗が示す医療効率 かかりつけ医、大病院と密に 新型コロナウイルスの感染拡大や医療崩壊を防ぐには高齢者だけでなく、重症者が急増している40~50代へのワクチン接種が欠かせない。接種が円滑に進む地域は準備にいち早く着手したことに加え、きめ細やかな診療体制が敷かれ、医療機関同士、行政との連携も密だ。接種率の地域差から高齢化時代のあるべき地域医療の姿が見えてくる。都道府県別にみた全世代の1回目の接種率(8月3日時点)は山口県が45.6%でトップ。和歌山、山形、高知、熊本、群馬、佐賀の各県と続く。最下位は沖縄県の29.3%でトップから16.3ポイントの開きがあった。接種率が高い地域の多くは高度医療を提供する大病院(500病床以上)が少ない傾向があり、かかりつけ医(一般診療所、20病床未満)が患者に目配りする。地元医師会や大学、行政との関係も良好で連携・役割分担が進むほか、大規模災害を見据えた体制づくりなどを検討しており、医師の有事対応力が高い地域も多かった。和歌山県は2019年10月時点で約1000カ所の一般診療所があり人口10万人あたりでは110.8と都道府県で最多。県人口の4割近くの35万人が集まる和歌山市には4割の一般診療所が集中する。一方、500病床以上の大病院は県内に2カ所だけ。患者は一般診療所の受診が中心。個別接種が進み接種率を押し上げる一因となった。南海トラフ地震などに備えた即応体制への意識の高さも対応力を底上げした。県福祉保健部の野尻孝子技監は「コロナの感染拡大防止に向けた仕組みではない」とするものの、県は大規模災害が休日や夜間に起きた際、地域の開業医が「地域災害支援医師」として緊急医療にあたる仕組みを検討している。仁坂吉伸知事は接種率の高さについて「準備をしっかりやったから」と胸を張る。佐賀県ではかかりつけ医を地域第一線の医療機関と定義する。大町町は4カ所ある町内の病院の医師や看護師らが診察に訪れた高齢者に直接予定を聞き、接種日を設定した。通院歴がある人に医療機関側から連絡もしたという。同町職員は「日ごろ診ている患者をコロナから守ろうと医療スタッフが熱心に働いた」と振り返る。行政と大学の連携協定が奏功しているのは山形県。県内人口の4分の1が集まる山形市が設けた大規模会場に、山形大学医学部が医師や看護師を派遣。吉村美栄子知事は大学、医師会、看護協会、薬剤師会が協力する「オール山形」の成果を強調する。山口県も県内の市町や医師会などが参加する対策会議を発足させ、早い段階から情報共有を進めた。個別接種や集団接種の体制を整え「高齢者接種の立ち上がりから順調に接種できた」(県新型コロナウイルス感染症対策室)。福島県相馬市では、コロナの感染拡大前から市と地元医師会が密に連携してきた。救急医療の主な担い手である公立相馬総合病院の夜間急患体制を維持するため、開業医が当番で勤務する制度を導入。11年の東日本大震災の発生後は、市職員と開業医が連携し、避難所で被災者の健康管理にあたった。とはいえ、こうした連携はなお一部で、全国的にみると医療機関の規模に応じた役割分担と連携は道半ば。患者も軽い病気やケガで大病院を利用するケースが多く、効率的で機動的な医療が妨げられている。接種をきっかけに地方で芽生えた取り組みは、コロナ後の医療改革のヒントを投げかけている。 *4-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE039AP0T00C21A8000000/ (日経新聞 2021年8月3日) 首相「往診・遠隔医療で協力を」 在宅療養で医師会長に 菅義偉首相は3日、首相官邸で日本医師会の中川俊男会長らと面会し、新型コロナウイルス感染者への医療提供体制を強化するよう協力を要請した。「地域の診療所が往診やオンライン診療で患者の状況を把握し、適切な医療を提供するようお願いする」と述べた。政府は2日に示した新方針で感染が急拡大している地域は自宅療養を基本とし、入院は重症者や重症化のおそれが強い人を対象とすることにした。自宅療養を円滑に進める環境を整えるには医療機関の協力が不可欠と判断し、医師会による後押しを促した。中川氏は「特に自宅療養への対応に重点を置いた体制整備を進めている」と答えた。首相は血液中の酸素飽和度を測定するパルスオキシメーターの配布に加え「自宅宿泊療養の新型コロナ患者への往診の診療報酬を大きく拡充している」と指摘した。中川氏は「全国的な緊急事態宣言の発令で強力な感染防止対策が必要だ」と訴えた。医師の負担が過重にならないように人流抑制などの対策を講じるよう求めた。 *4-2-2:https://digital.asahi.com/articles/ASP856V0BP85PTIL024.html (朝日新聞 2021年8月5日) 自宅療養者向け訪問看護、大阪全域で 健康観察を強化 大阪府は5日、新型コロナウイルス感染者のうち自宅療養者に対する訪問看護を府内全域で実施すると発表した。感染の急拡大に伴い自宅療養者も増加しており、健康観察を強化するのが狙いだ。府内の新規感染者は3~5日、3日続けて1千人を超えた。5日の府発表で、自宅で療養する無症状や軽症の人は4633人。「第4波」のピーク時には約1万5千人にのぼった。保健所は自宅療養者への健康観察を電話などで行い、血中酸素飽和度を測るパルスオキシメーターも配布する。しかし、感染者の増加が続けば保健所業務は逼迫(ひっぱく)し、対応しきれなくなる可能性もある。そこで府は7月から、和泉保健所管内などの訪問看護ステーションと連携し、保健所が必要だと判断した人について、本人の同意を得たうえで訪問看護を行う仕組みを広げてきた。府は医療用マスクやガウンなどを提供するほか、初期費用5万円、1回の訪問あたり2万円を支給する。7月は保健所で対応できる状況だったため、この仕組みの利用実績はないが、6日から府内108の訪問看護ステーションと協力し、実施範囲を府内全域に広げる。吉村洋文知事は5日、「感染者が増えてきたら保健所だけで健康観察を十分にやりきるのは難しい。自宅療養者の症状が急に悪くなることもある。早く治療し、早く治すことが、結果として病床確保にもつながる」と記者団に語った。 *4-3-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/5fda340edb774d1ecd0f30f642ca3094497ad5fa (福祉新聞 2021/7/28) 市民が見た介護保険の20年 福祉フォーラム・ジャパンセミナー 福祉フォーラム・ジャパン(渡邉芳樹会長)は7月10日、オンラインセミナー「市民がみた介護保険の20年」を開催した。講演した小竹雅子・市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰は、20年以上介護保険の電話相談を行い、厚生労働省の審議会を傍聴し続けてきた中で、「市民の声と専門家の意識にギャップを感じてきた。介護保険で高齢者の主体性がどこまで保障されるのかに関心を持ち続けてきた」と言う。講演では電話相談に寄せられた内容を交え、制度改正の動向を解説しながら市民目線で問題点を挙げた。2005年の改正では要介護者への給付と分けて要支援者への予防給付ができた。14年の改正では要支援者のホームヘルプとデイサービスが予防給付から地域支援事業(総合事業)に移され、特別養護老人ホームの利用は要介護3以上となった。こうした流れに対し、小竹氏は「利用者に選択権があるとして始まり、介護が必要と認定されれば給付が保障されていたはずなのに、いつの間にか予防重視型になってしまった」と指摘した。20年の要支援・要介護認定者669万人(4月)のうちサービス利用者は515万人(5月)。約4分の1は利用していないことを挙げ、「厚労省は家族で対応していると説明するが、自己負担を払えず利用できない人が一定数いるのではないか。そうだとすると、ゆとりのある高齢者しか給付を受けられないことになる」とし、実態を調査すべきと提起した。小竹氏は、ホームヘルプが抑制されていることも危惧した。同居家族がいる場合、生活援助を利用できないという解釈が市町村で広がったとし、「ホームヘルプは高齢者の自立支援に資することがないと批判を浴び、ヘルパーも減っている。厚労省は地域包括ケアを掲げているが、ヘルパーが減る中でどうやって地域での暮らしを支えることができるのか疑問だ」と述べた。そのほか、今年4月に要支援者が要介護認定を受けても、これまでの地域支援事業のデイサービスなどを引き続き利用できるよう見直されたことに対し、「要介護認定を受けても給付の対象にしなくても良いという仕組みであり、認定者に給付をするという介護保険の原則に穴が開いた」と心配した。講演後は参加者で意見交換も行われ、「予防給付や地域支援事業を拡大する方向性で制度を維持しようとするのはおかしい」と発言があり、セミナーで座長を務めた宮武剛副会長は「その点は大議論が必要だ」と応じた。 *4-3-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/604539/ (西日本新聞社説 2020/4/29) 介護保険20年 抜本改革の議論始めよう これからの高齢者の介護を社会全体で担い続けることができるのか-。創設20年の節目を迎えた介護保険制度が大きな曲がり角にさしかかっている。2000年4月に「介護の社会化」を掲げ始まった制度だ。それまでは家族頼りだった介護を多様な民間サービスが担うようになった。家庭の事情などで余儀なくされる社会的入院の解消を促し、「老いた親の世話は同居する女性の役割」という社会通念を拭い去るのにも貢献した。社会保障の歴史に画期をなす挑戦だったと言える。この20年で、高齢化はさらに進んだ。要介護・要支援認定者は3倍に増え、必要な費用も3倍に膨らんだ。介護サービスの需要は急速に伸び、制度の維持が年々、困難になっている。何より深刻なのは現場の人手不足だろう。大変な仕事の割に収入が少ないイメージが人材確保の壁になっている。実際、介護職員の平均給与は全産業平均を大きく下回る。外国人材への期待も高いが、新たな在留資格「特定技能」による受け入れは進んでいない。団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる25年には、約34万人の介護人材不足が見込まれる。国はロボットや情報通信技術の活用などで現場の負担を緩和するとともに、処遇改善にも本腰を入れるべきである。財源も心配だ。国は財政逼迫(ひっぱく)を受け、所得に応じて利用者負担を引き上げ、特別養護老人ホームの新規入所要件の厳格化などを進めてきた。「負担増」と「サービスの制限・縮小」だ。介護の必要性が低い利用者のサービスを全国一律の介護保険から切り離す動きも始まった。既に要支援者向けの訪問介護と通所介護は市町村に移管されている。要介護1、2の一部サービスの移管案も浮上している。急激な負担増は利用抑制を招き、生活の質や健康への悪影響も否定できない。市町村への事業移管には居住地によるサービス格差の懸念が多い。ともに慎重な検討が欠かせない。介護保険の財源は、自己負担を除けば保険料と公費(税金)で構成される。利用者増をにらんだ公費負担のアップや、保険料を払う年齢を現行40歳から引き下げることも検討せざるを得ないだろう。いずれにしろ国民的な合意形成が必要だ。急速な高齢化で「介護の社会化」が危うくなり、介護離職や老老介護も深刻な問題になってきた。それだけに所得や家族構成にかかわらず、必要とする人に適切なサービスを提供する介護保険の理念は今後も輝きを増すだろう。今後20年の社会を支えるため、制度の抜本的改革の議論を始めるべきである。 *4-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210821&ng=DGKKZO75008650R20C21A8MM8000 (日経新聞 2021.8.21) 介護給付 抑制に「秘策」、59市町村が開始時から圧縮 高知・南国、個別支援で自立促す 介護給付費(総合2面きょうのことば)の膨張が止まらない。2020年度は10兆円に達したもようで、介護保険制度が始まった00年度の3兆2400億円から3倍以上に膨らんだ。持続可能性を高めるには圧縮が急務となるが、全国をみると、すでに59市町村が削減に成功している。高齢者の自立生活の維持に向けた支援策など、取り組みからヒントを探った。高齢者1人当たりの給付費は保険者(市区町村を中心に、広域連合など全国1571団体)ごとに比較可能な18年度で26万円(利用者負担軽減の払い戻しなどを除く)と、制度開始時から11万円強増えた。そうした中、給付を減らしたのは18市41町村。市では高知県南国市の13.2%減を筆頭に、徳島県小松島市、北海道石狩市、沖縄県浦添市などが上位となった。町村では東京都小笠原村が46.9%減でトップ。北海道鶴居村、沖縄県与那国町が続く。高知県南国市はケアマネジャーだけでなく保健師や栄養士、理学療法士などが協力して介護予防に取り組み1人当たり給付費を01年度の28万円弱から24万円(18年度)まで減少させた。各分野の専門家を集めた「地域ケア会議」で身体的負担の少ない公営住宅を紹介したり、水分摂取の不足などを警告したりと個別の支援プランを策定。食事や運動なども精緻に計画・検証し、多くの検討事例で自立生活が維持できるようになった。高知県は1人当たりの医療費(市町村国保)が高水準にあり、同市も全国平均を2割(18年度、年齢調整前)上回っている。ただ、01年度比では4.4%減少させており、担当者は「介護にも医療にもかからない健康な高齢者を増やしていくことで、結果的に給付費・医療費双方の抑制につなげていきたい」と話す。沖縄県宜野湾市は介護に頼らず最小限の支援だけで自立した生活を続けられるよう、安価に利用できるサービス拡充に力を入れる。本来2万3400円のデイサービスを、市の助成で週1回まで最安2340円(1割負担になる所得層の場合)で利用できるようにしたほか、今秋には手すりをつけるなどの住宅改修も安価にできるようにする。給付増の要因になりやすい施設入所を生活に支障がない範囲で可能な限り抑制しようと取り組むのは沖縄県名護市。配食サービス普及に力を注ぎ「食事の心配をしなくてよければ在宅で過ごしたい」という高齢者を後押しする。新型コロナウイルス禍の外出自粛の影響もあり、20年度は前年度比1.5倍の延べ3万1000食近くを提供した。東京都小笠原村は名護市とは逆に村営有料老人ホームを新設したことが奏功した。以前は高齢者の多くが比較的高価な都区部の施設に入所、負担義務のある同村の給付が膨張する要因となっていた。給付費を抑制した自治体は相対的に農業などの1次産業が強く、現役で働き続ける高齢者が多い傾向がある。さらに削減した市町村内でも地域差は顕著で、10.9%減少の北海道石狩市では札幌市に隣接する市街地エリアに比べ市町村合併で編入された漁村部で介護認定が重度化するタイミングが遅かった。日々の暮らしが予防の下地になる。こうしたことを受け積極的に身体を動かすことに取り組む自治体も増えている。北海道鶴居村や天塩町は、クラブを作って運動を促すことで体力を落とさないようにしたり、糖尿病や肥満の人に個別指導をしたりして機能低下を防ぐ。両自治体は高齢者1人当たりの給付費をそれぞれ36.7%、25.3%減少させた。 *4-4:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO74827960X10C21A8MM8000/ (日経新聞 2021年8月17日) コロナ遠隔診療 報酬2倍、厚労省、自宅療養急増に対応 厚生労働省は16日、新型コロナウイルスの自宅療養者らを電話やオンラインで診療した場合の診療報酬を2倍超に引き上げると自治体に通知した。自宅やホテルなどで療養する人が急増していることに対応する。菅義偉首相は同日、記者団に「医療体制の構築が極めて大事だ。自宅にいる患者への電話による診療報酬を引き上げる」と述べた。電話やオンラインでの初診の報酬は従来の2140円に2500円を上乗せし、倍以上にする。再診は730円に2500円を加算し、4倍超に引き上げる。感染拡大が続く東京都内では自宅療養者が2万人を超えた。入院・療養先が未定の人も1万人を上回る。診療報酬の手当てによって医療機関による遠隔の支援を促す。対面診療では感染防護対策などを理由に既に診療報酬を加算している。厚労省はコロナ対応の臨時施設に医師らを派遣する際の補助金も引き上げる。健康管理を強化した宿泊療養施設、入院待機ステーションなども念頭に置く。医師は1人1時間あたり今の倍の1万5100円となる。 <国・地方自治体の財源> *5-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210826&ng=DGKKZO75127550V20C21A8EP0000 (日経新聞 2021.8.26) 地熱の本格調査、国立公園内で、発電量、30年度に1%目標 安定供給に寄与 経済産業省は地熱発電所を増やすため、国立公園内などに適地を見つける調査を本格化する。環境省と連携し、北海道や九州など30カ所を現地調査する。国の調査はこれまで公園外を中心に5カ所だけだった。太陽光発電や風力発電よりも出力の変動が小さく、温暖化ガスの排出削減と電力供給の安定に役立つと期待される。2022年度予算の概算要求に資源量の調査費など地熱発電の開発支援として183億円を盛り込む。110億円を確保した21年度予算から6割増やす。温暖化ガス排出量を30年度までに13年度比で46%減らす目標の達成に向け、地熱発電で30年度に総発電量の1%を賄う計画だ。地熱発電の適地の8割は国立公園などの自然公園内とされる。環境省はこれまで自然環境や景観を損なうといった理由で開発に慎重だった。今年度に入って小泉進次郎環境相が自然公園内の開発を急ぐと表明した。開発許可の要件を明確にするなどして、事業化を支援する。経産省の予算額の過半は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が担う国の調査に充てる。地表で人工的に地震波を発生させ地下の構造を把握する。地震波が跳ね返ってくる速さなどをもとに地熱発電に使える熱水や水蒸気がたまる場所がわかる。地表調査と簡単な掘削調査に2年ほどかける。有望な場所と判断すれば、開発したい民間事業者を募って引き継ぐ。すでに地熱発電を手がける九州電力などの大手電力や資源開発会社が候補となる。経産省は調査地の半分が事業化につながるとみる。JOGMECは20年度に調査を始め、北海道の大雪山や岩手の八幡平などの5地点を調べた。新たに北海道の支笏洞爺国立公園や新潟と長野の妙高戸隠連山国立公園、熊本と大分にまたがる阿蘇くじゅう国立公園などの30カ所ほどを調査する。1つの公園内の複数の地点を調べる場合もある。21、22年度にそれぞれ15カ所程度調べる。21年度は数カ所の予定だったが、予算の付け替えで拡大する。経産省は公園を管理する環境省などと調整に入った。経産省によると、日本の地熱の資源量は米国とインドネシアに次ぐ世界3位の2347万キロワットにのぼるが、発電の設備容量は60万キロワットにとどまる。資源量が半分未満のフィリピンやニュージーランド、メキシコ、イタリアなどよりも設備が少なく、伸ばせる余地は大きい。7月に示した次期エネルギー基本計画の原案で「安定的に発電できるベースロード電源」と位置づけた。総発電量に占める再生可能エネルギーの比率を19年度の18%から30年度に36~38%に高め、このうち地熱は0.3%から1%に引き上げる。設備容量を150万キロワット程度に増やす必要がある。すでに開発のめどが立った場所などの発電開始で現行の60万キロワットから100万キロワットに引き上げ、国の調査地の事業化でさらに50万キロワット上積みする。調査開始から発電までの期間は急いでも8年程度。30年度に間に合わせるには適地探しはギリギリのタイミングとなっている。 *5-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210823&ng=DGKKZO75023210T20C21A8MM8000 (日経新聞 2021.8.23) 再生エネ導入に最大75%補助 環境省、自治体の脱炭素支援 環境省は再生可能エネルギー導入などで地域単位で先行して電力消費に伴う温暖化ガス排出実質ゼロを目指す自治体を支援する。事業費の最大75%を補助する交付金を設ける。2030年度までに少なくとも100カ所で電力の脱炭素を実現し、成功モデルをつくる。22年度予算の概算要求に「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を盛り込む。初年度は200億円を想定し、20~40自治体を対象に30年度まで継続支援する。交付金で設備費の2分の1から4分の3をまかなう。温暖化ガス排出量を30年度までに13年度比で46%減らす目標の実現につなげる。市街地や団地、離島など地域単位で家庭や商業施設といった民生部門の実質ゼロを目指す。事業の進捗に合わせて翌年度への繰り越しや設備導入の順番変更をできるようにし自由度を高める。民間事業者にも使える。自治体は9年間の計画を作る。太陽光など再生エネ設備の導入のほか、蓄電池や水素設備による再生エネの活用、建物の断熱改修などに一体的に取り組むことが条件だ。交付金制度の法制化も検討している。 *5-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXKZO60178610Z00C20A6EA2000/ (日経新聞 2020年6月10日) 地方財政とは 自前の税収は4割 ▼地方財政 総務省は毎年末、都道府県と市区町村を合わせた地方自治体全体の翌年度の収支などの見通しを地方財政計画としてまとめる。財源不足はバブル崩壊後の1994年度以降、急激に拡大。リーマン・ショック後の2010年度には過去最大の18兆円に達した。近年はアベノミクスによる景気拡大で大幅に縮小してきた。直近の18年度決算によると、歳入は地方税が4割を占める。地方財源として国が配分する地方交付税は2割弱。借金である地方債は1割強だ。自前の財源だけで財政運営できる自治体は少ない。歳出は地方債を償還(返済)する公債費や人件費など必ず支払わなければいけない義務的経費が9割を超える。コロナ禍の前から財政は硬直的で余裕がないと言える。地方債などの借入金残高は14年度ごろから緩やかに減少し、20年度は前年度から約3兆円少ない189兆円を見込んでいた。足元では新型コロナウイルス対策で各自治体が家計や企業の緊急支援に動く。歳出の急増を政府からの地方創生臨時交付金などで賄いきれなければ財源不足が大きくなる。借入金残高も再び増勢に転じる見通しだ。 *5-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210813&ng=DGKKZO74745310T10C21A8EAC000 (日経新聞 2021.8.13) 脱・大都市 町村も受け皿に、23区若者、移住に関心48% 新型コロナウイルスの感染拡大は人口の流れに大きな影響を与えた。総務省が公表した住民基本台帳に基づく人口動態調査をみると、2020年の1年間で大都市から地方への移動が鮮明になった。都会を避け移住を決断した人が選んだのはどのような地域だったのか。東京、関西、名古屋の三大都市圏の人口の合計は13年の調査開始以来初めて減少した。東京都は20年の転入者数から転出者数を引いた転入超過(帰化など含む)が6万人ほどで、19年に比べておよそ2万7千人減った。日本人の人口の増減率は46道府県で改善し、東京だけ伸びが鈍った。新型コロナで東京など大都市から地方を受け皿に人口が流れた傾向がデータから読み取れる。人口増の多い町村を見ると、熊本県菊陽町が556人で1位となり、長野県軽井沢町が502人と続いた。地方創生の取り組みとして、子育て世代への支援の手厚さが共通する。菊陽町は子どもの医療費の無償化や企業誘致に取り組み、人口が増え続ける。住宅地を整備し、指定の区域に転入した人に最大100万円の補助金を出す。子どもが生まれたら10万円を支給する。別荘地として有名な軽井沢町は東京駅まで新幹線で1時間程度で、通勤圏となっている。総務省は「テレワークの普及で移住者が増えた」と分析する。幼小中の一貫校の設置といった教育環境の整備も注目される。沖縄県南風原町は那覇市に近く交通の利便性がよい。住宅地を開発し、中学生までの子どもの通院費無料など子育てをする若年層への支援に力を入れる。8位の京都府大山崎町も「待機児童ゼロ」など育児環境の良さをアピールする。「新型コロナを機に地方への関心が高まっている。東京一極集中の是正につなげる」。秋田県出身の菅義偉首相は地方創生への思いを強調する。内閣府の調査によると、東京23区の20歳代で地方移住に関心のある人は19年末時点で39%だった。新型コロナの感染拡大後の21年4~5月は48%と、10ポイント近く上昇した。意識は変わった。移住希望者は既存の政府の支援策を活用できる。総務省は09年度から「地域おこし協力隊」を各地へ派遣する。1~3年程度、地方に移り住んで地域振興の担い手になってもらい、定住につなげる。13年度に1000人ほどの隊員は増加し、20年度にはおよそ5400人になった。24年度は8000人を目指す。縁のない土地での生活に慣れるまでは大変だ。21年度から隊員の経験者による移住生活のサポートを始めた。協力隊の任期終了後に定住した人は多くが就業・起業する。自治体職員などの行政関係が最も多く、観光業、農林水産業が続いた。最近はデジタル分野の素養や接客のノウハウがある人も歓迎されるという。新型コロナの感染拡大をきっかけにテレワークが普及すれば、仕事を続けたままの移住という選択肢も出てくる。政府は「転職なき移住」の実現に向けた環境整備も進める。仕事を辞め新たな土地に定住するのは覚悟がいる。内閣官房の高原剛地方創生総括官は「若い人の職の不安が移住の障壁だった。転職なき移住はその心配が不要」と説く。移住先が気に入らなければ、元の生活に戻れるという利点もある。個人に加え、企業にも行動を促す。内閣府は総額100億円の「地方創生テレワーク交付金」を創設した。大都市部の企業が地方でテレワークの拠点を開けるように「サテライトオフィス」の設置の支援も始めた。仕事ばかりではなく、日常生活の全般を支える仕組みも不可欠になる。武田良太総務相は「遠隔教育、遠隔診療など住みたい地域に住みながら、必要なサービスが受けられる取り組みが広がっている」と話す。 *5-3-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61880510S0A720C2TJ2000/ (日経新聞 2020年7月27日) ごみ発電、海外で受注倍増 日立造船がAIで安定焼却 日本のごみ焼却発電プラントメーカーが、海外での受注を伸ばしている。日立造船など上位3社の累計受注件数は5年で倍増した。各社は人工知能(AI)で燃焼を安定させる最新技術を投入し、ごみの埋め立てを規制する欧州や、インフラ需要が拡大する新興国市場をさらに切り開く。ごみ焼却発電プラントは、ごみを燃やした際の廃熱を利用してタービンを回し発電する。日本企業が技術力で先行する分野だ。日立造船は2月、子会社の日立造船イノバ(スイス)を通じ、英国レスターシャー州のプラントを受注した。発電出力は4万2000キロワットで、総送電量は一般家庭8万世帯分の年間消費量に相当する。英国でのプラント受注は12件目となった。 ●EU埋め立て規制が追い風 欧州で受注が伸びる背景には、欧州連合(EU)が2015年に定めた「埋め立て規制に関する指令」がある。埋め立てで処理するごみの比率を30年までに10%以下に抑えるという内容だ。経済協力開発機構(OECD)によると、ごみ発電の技術で先行する日本は、埋め立て比率が1%未満。対して英国は14%、フランスは20%、イタリアは23%と高い。世界エネルギー会議は欧州のごみ発電プラント市場が21年に51億ドル(5500億円)と、10年前の2倍に膨らむと予測する。日本勢は広がる商機を狙う。10年には日立造船がスイス、14年には日鉄エンジニアリングとJFEエンジニアリングがそれぞれドイツの同業を買収し、海外進出の足がかりをつくった。3社の海外での累計受注件数は19年度末で84件で、14年度末の37件から倍増している。スイスのコンサルティング大手の調査では、19年に欧州・中東・アフリカを合わせた市場のシェアで、日本勢が過半を占めた。各社はさらに受注を伸ばすべく、技術開発に取り組んでいる。力を入れるのが無人化だ。日立造船は日本IBMと組み、焼却炉内の温度を自動で安定させる技術を今年度中に開発する。蒸気の発生量などの情報をもとに、数分~数十分後の温度をAIで予測する。発電に最適な温度を下回る場合には、燃えやすいごみを投入するなどして温度を一定に保つ。焼却炉にはプラスチックや生ごみなど様々なごみが投入され、それぞれの性質で燃焼状態が変わる。現在は温度が安定しない場合、作業員が経験に基づき投入するごみを選んでいる。人材頼みだった作業を自動化し、安定した発電を実現する。JFEエンジもAIを使った自動運転プログラムを開発した。焼却炉内の様子を1分ごとに撮影し、温度や燃え方を把握。供給する空気の量や、投入するごみの量を調節して温度を一定に保つ。国内プラントで実証実験を進めており、発生する蒸気量が安定する効果も確認できたという。大下元社長は「日本の環境技術は競争力も高く、今後も欧州など海外で積極的に受注獲得に動いていく」と語る。 ●天候の影響なし 世界には日本以外にもごみ活用の先進国がある。再生可能エネルギーの比率が6割を超えるスウェーデンは、国内で発生するごみの約半分を焼却して発電に利用し、余熱も暖房用などに家庭に供給している。肥料などにも使うため自国のごみでは足らず、近隣諸国からごみを輸入している。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の電力消費量に占めるバイオマス発電の量は約1割で、ごみ発電はさらにその一部になる。規模は小さいが、ごみが排出される限り安定的に発電できる。再生エネでも太陽光や風力は天候や時間帯で発電量がぶれるデメリットがある。ごみ発電は足元では欧州で需要が拡大しているが、今後は経済発展に伴ってインフラ需要が広がるアジアが市場をけん引するとみられる。アジアのごみ焼却発電プラント市場は21年に64億ドル(約6900億円)と、10年前と比べ3.7倍になる見通しだ。日鉄エンジはNTTデータなどとマレーシアでごみ発電を導入するための調査に取り組む。中国のプラントメーカーも台頭するなか、日本勢は効率性の高い技術で優位を保とうとしている。 *国内ごみ発電の余剰電力、新電力が9割落札 日本国内では新電力がごみ発電による電力供給の主役になっている。エネルギー調査会社のリム情報開発(東京・中央)によると、2020年に実施されたごみ焼却施設の余剰電力入札50件のうち、94%にあたる47件が新電力に落札された。比率は4年前の86%からさらに上昇した。事業に必要な電力を100%再生可能エネルギーでまかなうことを目指す国際的な企業連合「RE100」に加盟する日本企業は30社を超える。NTTグループの新電力大手、エネット(東京・港)の池田ひなた経営企画部部長は「環境負荷の低い電力を要望するお客さんは年々増えている」と話す。新電力は19年度の国内の電力販売量の15.4%を占めるが、ほとんどの企業が太陽光や風力発電など再生エネの自前設備を持たない。そこで目を付けたのが、ごみ焼却施設が生み出す電力だ。19年2月の神戸市東部環境センター(神戸市)の入札では、大手の関西電力と新電力の計8社が競り合い、丸紅新電力(東京・中央)が落札した。人口減少が続く日本では、ごみ焼却発電プラントの増加は見込めない。限られた再生エネの安定電源の争奪戦は激化しそうだ。 *5-3-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC194EP0Z10C21A6000000/ (日経新聞 2021年7月10日) 「脱ごみ社会」自治体挑む 長野・川上村、生ごみゼロ 全国のごみ処理費は年間2兆円を超える。増加傾向にあり10年前に比べ1割増えた。人口減の進展に伴う担い手不足の懸念も強まっている。財政も厳しさを増す中、持続可能な地域を築くためには排出削減への戦略的な施策が欠かせない。企業が環境意識を高める中、先進的に取り組む自治体では新たな産業を呼び込むなど、活性化にも寄与し始めた。環境省が3月にまとめた一般廃棄物処理の実態調査(2019年度)によると、1人1日あたりの排出量は918グラム。都道府県で最少は長野県で816グラムだった。京都府(836グラム)、滋賀県(837グラム)が続く。長野県は800グラム以下に減少させる目標「チャレンジ800」を策定。啓発を進め、14年度以降、日本一を維持する。全77市町村のうち60がごみ袋を有料化。記名式に踏み込んだ自治体も同じく60あった。自治体のごみ問題に詳しい山谷修作東洋大名誉教授は「有料化や記名式はコストの可視化や排出責任の明確化につながり減量への動機づけになる」と指摘する。全国自治体で一番排出量が少ない川上村(有料・記名、294グラム)は、可燃ごみの4割を占める生ごみの回収を一切せず各家庭で堆肥化する。生ごみは水分含有量でも自治体を悩ませる。そのままでは焼却炉の温度を下げてしまい、ダイオキシン発生を誘発。一方で温度を維持しようとすると、燃料費がかさむ。財政難から3基の焼却炉すべてを耐用年数を超えて運用する上田市(有料・記名、770グラム)は、16年から自己処理を促す「生ごみ出しません袋」の無料配布を始めた。畑がない家にもメリットを直接感じてもらおうと、乾燥生ごみ1キログラムにつき1ポイントとする事業も開始。5ポイント集めれば市内のJA直売所で500円分の野菜などに交換できる。2位の京都府では、京都大と連携して発生抑制に取り組む京都市(836グラム)がけん引する。1980年から発生場所を特定する「細組成調査」を開始。市はピーク時の年間排出量82万トン(00年度、1人あたり排出量は1608グラム)を半減する目標も策定した。18年度に目標を達成し、処理費は4割減の224億円(20年度)にまで減った。減量のメリットは処理に費用がかかるケースが多い事業者にとっても大きい。東京都多摩市は15年「利益率5%の事業者が50万円のもうけを出すには1000万円の売り上げ増が必要。処理(持ち込みの場合10キログラム350円)に年500万円を費やすなら、ごみ1割減でも50万円の経費削減となり同等の効果を生む」と具体例を挙げて可視化。事業所1人あたり排出量の2割減につなげた。環境負荷低減が世界的な要請となる中、取り組みは活性化にも直結する。全国に先駆け、焼却・埋め立てごみをゼロにする宣言を行った徳島県上勝町には、町の人口(1500人)を超える約2000人が例年視察などに訪れる。調査時点でもなお539グラム(市町村で30位)を排出しているが、住民自ら45品目に分別し、資源化を進めることで年間処理費を6割減程度まで抑制した。焼却炉は00年、ダイオキシン類対策特別措置法の基準を満たさなかったことを機に廃止。環境都市としてブランド力が高まり、15年に町外事業者がビール製造場を新設した。キャンプ場などレジャー施設も増えている。 *5-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF1628X016072021000000/ (日経新聞 2021年7月16日) 大阪市、本庁舎の電力すべて再生エネに 12月から 大阪市は16日、市役所本庁舎で使用する電力について12月から再生可能エネルギーに切り替えると発表した。入札で9月下旬まで事業者を募り、太陽光やバイオマス発電など再生エネ由来100%の電力による供給を求める。年間の使用電力量は約656万キロワット時を予定する。現在、市の本庁舎は中部電力と電力契約をしており、再生エネに限定した調達はしていない。府・市が3月に発表した「おおさかスマートエネルギープラン」では、府や市の庁舎で再生エネ電力の調達を推進すると表明しており、それに沿った取り組みだ。松井一郎大阪市長は同日、記者団に対して「SDGs(持続可能な開発目標)は25年の国際博覧会(大阪・関西万博)のテーマでもある。我々ができるところから持続可能な社会をつくっていきたい」と話した。府でも4月から本庁舎などで使用する電力を再生エネ由来100%の調達に切り替えた。日立造船がバイオマス発電により電力を供給している。 <人材不足と外国人労働者及び難民の受け入れについて> PS(2021/8/29追加):*6-1-1のように、アフガニスタンで反政府勢力タリバンが首都カブールを勢力下に置いた事態を受け、「タリバンの司令官の1人が公開処刑・手足の切断・投石による処罰等の実施を公言した」とBBCが報じているため、難民支援の弁護士団体が、2021年8月16日、アフガニスタン出身者への緊急措置による迅速な保護を求める声明を公表した。 その内容は、①我が国に庇護を求めるアフガニスタン出身者に対し、難民認定手続の審査を待たずに、アフガニスタン出身者であることが確認できれば、緊急措置として迅速に安定的な在留資格を付与すること ②難民認定手続外で在留資格の変更を求めるアフガニスタン出身者に対しても、緊急措置として迅速に安定的な在留資格への変更を認めること ③前記1と2で付与又は許可する在留資格は最低でも在留期間1年とし、更新を可能とすること ④在留するアフガニスタン人が日本への家族呼び寄せを希望する場合、在留資格認定証明書の許可要件の緩和や大使館での迅速な査証の発給など、最大限の配慮をすること などである。 しかし、*6-1-2のように、アフガニスタンにいる日本人と日本大使館の外国人スタッフらを退避させる目的で派遣していた航空自衛隊の輸送機は、8月26日現在、米国の要請を受けて迫害の恐れがあるアフガニスタン人14人を首都カブールの空港から隣国パキスタンに退避させただけだ。そして、日本政府は、カブール空港内で活動していた外務・防衛両省の支援要員を撤収させ、輸送機を安全なパキスタンのイスラマバードに待機させているとのことである。つまり、日本は一刻を争う大使館スタッフ等のアフガニスタン人の移動も行わず、退避を希望する日本大使館やJICAのアフガニスタン人等の現地スタッフとその家族ら約500人を残したまま、外務省が「現地に残る日本人は、ごく少数」と説明しているわけだ。本当に人命を第一に考える国であれば、このような場合は、日本の関係施設で働いていたアフガニスタン人を一刻も早く出国させるためにあらうる手を尽くす筈で、そのために外務・防衛両省の支援要員を派遣しているため、応急のビザを出して日本に退避させ、その後で難民認定を行うことも容易である。そして、それもできないようなら外務・防衛両省から派遣した意味がない。 ただ、日本におけるテロリズムの定義は、特定秘密保護法第12条第2項で、「政治その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動を言う」とされているため、どんな国家であっても国を作ってしまえばその権力に逆らう者がテロリストとされる。そのため、アフガニスタンの事態は、日本における「テロリズム」の定義のおかしさをあぶり出し、この考え方が政治亡命せざるを得ない人への冷たい仕打ちに繋がっていると思われる。 なお、日本という国が今でも人命を大切に考えていないことは、*6-2の名古屋入管で死亡したスリランカ人女性ウィシュマさんの事件からも明らかで、ウィシュマさんの死亡後、入管庁が公開した最終報告書は「死因の特定は困難」とし、行政文書の開示請求で名古屋入管が送ってきたのはほぼ黒塗りの約1万5千枚の文書という不誠実なものだった。そのため、私も、国連も問題視している非人道的な入管制度が抜本から変わらない限り、日本が外国人労働者と共存し、難民を受け入れて成長できる国になることはないと考える。 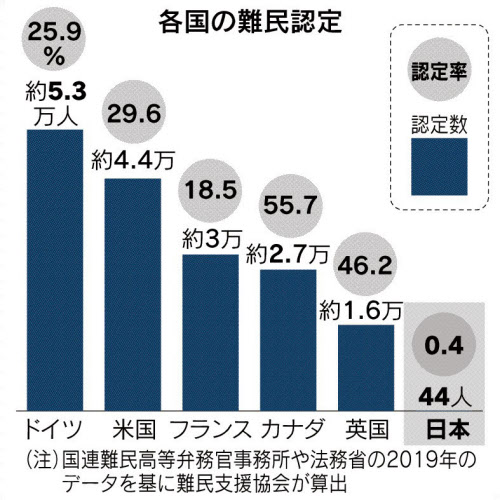  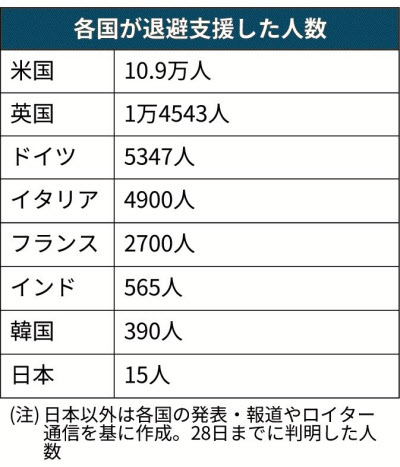 2021.6.3日経新聞 2021.6.17Goo 2021.8.29日経新聞 (図の説明:左図は、先進国の難民認定数・認定率だが、日本は2019年に44人、0.4%と著しく低く、中央の図のように、近くのミャンマー出身者の難民認定数・認定率でさえ0人、0%だ。また、右図は、アフガニスタンから各国が退避支援した人数だが、日本は全部で15人とやる気のなさが際立っている) *6-1-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/cefcca8b5d95b8c7e1a0859e2372961d5baf66f2 (Yahoo 2021/8/17) 「在日アフガニスタン人の迅速な保護を」難民支援の弁護士らが声明 アフガニスタンで反政府勢力タリバンが首都カブールを勢力下に置くなどの事態を受け、難民を支援する弁護士の団体「全国難民弁護団連絡会議」は8月16日、アフガニスタン出身者への緊急措置による迅速な保護を求める声明を公表した。声明は、法務省や外務省に宛て送付されている。全国難民弁護団連絡会議では、現在のアフガニスタンの状況について、タリバン司令官の1人が、公開処刑、手足の切断、投石による処罰などの実施を公言したとBBCが報じていることを指摘。「タリバンの理念に反する者、女性やマイノリティへの人権侵害が更に広範 化し悪化することが懸念されます」としている。そのため、在日アフガニスタン人から、本国の家族を日本に呼び寄せることはできないかという訴えが弁護士や支援関係者に寄せられているという。全国難民弁護団連絡会議は、現在、比較的多くのアフガニスタン出身の庇護希望者が日本で在留資格を得ているものの、難民として認定されず、人道配慮による在留が認められないケースもあると指摘。アフガニスタンで迫害や重大な危害を受けるおそれがあるアフガニスタン出身の在留者らを本国に送還しないよう求めている。 ●「迅速な在留資格付与」求める 声明では、次のことを求めている。 1、我が国に庇護を求めるアフガニスタン出身者に対し、難民認定手続の審査を待たず に、アフガニスタン出身者であることが確認でき次第、緊急措置として迅速に安定的 な在留資格を付与すること 2、難民認定手続外で在留資格の変更を求めるアフガニスタン出身者に対しても、緊急 措置として迅速に安定的な在留資格への変更を認めること 3、前記1と2で付与又は許可する在留資格は最低でも在留期間1年とし、更新を可能と すること 4、在留するアフガニスタン人が日本への家族呼び寄せを希望する場合、在留資格認定 証明書の許可要件の緩和や大使館での迅速な査証の発給など、最大限の配慮を すること *6-1-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S15025646.html (朝日新聞 2021年8月29日) 自衛隊機、アフガン人輸送 14人、米の要請受け隣国へ アフガニスタンにいる日本人や日本大使館の外国人スタッフらを退避させるために派遣されていた航空自衛隊の輸送機が26日、アフガニスタン人14人を首都カブールの空港から隣国パキスタンに退避させていたことがわかった。米国の要請を受けて運んだ。今回の派遣の根拠となった自衛隊法84条の4「在外邦人等の輸送」に基づき、外国人を輸送したのは初めて。複数の政府関係者が明らかにした。14人は旧政権の政府関係者らで、「国内にとどまれば、迫害される恐れがあった」という。輸送機は25日以降、カブールの空港に複数回降り立った。だが、治安悪化などの影響で、日本が退避対象としていた大使館スタッフなどのアフガニスタン人を、空港に移動させることはできなかった。27日には、退避を望んだ日本人1人をC130輸送機でパキスタンの首都イスラマバードに運んだ。外務省は現地に残る日本人は「ごく少数」と説明。今回は退避を希望していなかった、としている。一方、退避を希望する日本大使館や国際協力機構(JICA)のアフガニスタン人などの現地スタッフとその家族らは残されたまま。政府関係者によると、そうした人は約500人規模になるとみられる。自衛隊法84条の4は「外国における災害、騒乱その他の緊急事態」に際し、防衛相が外相からの依頼に基づいて、輸送を行う。日本人だけでなく、外国人も運べると規定する。過去4件実施したが、運んだのはいずれも日本人だった。政府は、カブールの空港内で活動していた外務、防衛両省の支援要員をいったん撤収させた。だが、輸送機をイスラマバードに待機させており、「退避に向けた努力を継続する」としている。 *6-2:https://www.fnn.jp/articles/-/227546 (FNN 2021年8月21日) 「“鼻から牛乳”は日本のジョークです」ウィシュマさん映像の全容判明 名古屋入管に収容中死亡したスリランカ人女性のウィシュマさんの問題について、遺族にのみ開示された監視カメラの映像の全容がわかった。そこに映し出されていたのは、日々衰弱しながらも生きようとしたウィシュマさんの姿と入管職員の人権を蹂躙する非人道的な行為だった。ともに映像を見た従姉妹マンジャリさんに映像の詳細を時系列で聞いた。 ●「“鼻から牛乳”は日本のジョークです」と職員が説明 ▽3月1日午後9時32分から37分の5分間。 職員2人が部屋にいてベッドに座っているウィシュマさんに薬を渡す。「喉の奥まで薬を入れてね」と職員が言うが、ウィシュマさんは水を飲んだら嘔吐してしまう。そのあとウィシュマさんが「コーヒー」と言って、職員が紙パックのカフェオレを渡す。職員がウィシュマさんの嘔吐のあとを拭こうとすると、ウィシュマさんがカフェオレを吹き出し、それを見た職員が「鼻から牛乳や」と言って笑った。ウィシュマさんは「コーヒーだけ飲める」と語って映像は終わった。 この映像を見ながら入管庁の職員は「これは日本のジョークです。ウィシュマさんと仲良くするための」と遺族らに説明した。これに対してポールニマさんが怒り「こういう状況で冗談を言うのか」と言うと職員は黙り込んだ。この頃になるとワヨミさんはずっと泣いていた。 ●「痛い」と訴えても「しょうがない」と嘲る職員 ▽3月2日午後6時45分から47分の2分間。 ベッドに寝ているウィシュマさんを職員が動かそうとして、服や手を引っ張るとウィシュマさんは大声で「痛い」と訴える。職員は「自分で身体を動かさないから、痛いのはしょうがない」「食べて寝るだけだから身体が重くなる」と嘲るように言う。なぜ身体を動かそうとしたのか説明はない。 ▽3月3日午後4時58分から5時10分の12分間。 部屋には職員1人と白衣を着た看護師がいる。ウィシュマさんはベッドに寝ていて、「まるで遺体のように動かない」(マンジャリさん)。看護師は体温と血圧を測り、いろいろ話しながらウィシュマさんの手のマッサージをする。 看護師はウィシュマさんに手を握ったり広げたりするように言うが、ウィシュマさんは出来ない。さらに看護師はウィシュマさんの腕を上げ下げするが、大きな声で痛がる。ウィシュマさんは大きな声で痛がったが看護師は腕の上げ下げを続けた ●「本当に看護師なのか」と遺族は訝しがった 看護師は「明日先生に会うから症状を全部言うように。ご飯を食べられない、歩けない、耳鳴りがする、頭の中が工場みたい(幻覚をみる)」と言うと、ウィシュマさんは「死にたい」と言う。看護師は「日本人の金持ちの恋人を探して結婚して幸せになるんじゃないの」と言う。そのあとも看護師は4、5回「明日先生に症状を言うように」と繰り返した。ウィシュマさんが「目も見えない」というと「それも言ってね」というだけだった。この映像を見ながらワヨミさんの夫が「この人は本当に看護師なのか。こんなに衰弱している人になぜ腕を上げ下げさせるのか」と訝しがった。これに対して佐々木聖子入管庁長官は「この人は週5回入管に来る看護師だ」と答えた。この後「時間もかかったので休憩しましょう」となり、遺族は休憩室に移ったがワヨミさんが大声で泣きだし嘔吐した。そこで「これ以上映像を見るのはやめよう」と、代理人の指宿昭一弁護士と相談して、映像を続けてみることを中止した。これが12日遺族に開示された映像の全容とその日の遺族の姿だ。映像を見た後ワヨミさんは記者団の前で「お姉さんは犬のような扱いを受けた」と泣きながら訴えた ●黒塗りの1万5千枚の文書が意味するものは 最後の映像から3日後、ウィシュマさんは死亡した。入管庁の公開した最終報告書には、死因の特定は困難だとしている。遺族の代理人の弁護士団は、収容中の状況をさらに詳しく調べるため名古屋入管に対して行政文書の開示請求を行った。しかし名古屋入管から送られてきたのはほぼ黒塗りの約1万5千枚の文書だった。筆者はこれまでの取材を振り返りながら、入管庁や名古屋入管の職員はなぜ人命を蔑ろにし、人の尊厳を踏みにじる行為を平気で行えるようになったのだろうと考えた。遺族の代理人の1人である駒井知会弁護士はこう語る。「東京入管に朝行くと、割とお洒落な服を着た沢山の若者たちが奥の入口に吸い込まれていくのを見ます。若者たちは建物の職員控え室で入管の紺の制服に着替えるのでしょう。若い彼ら、彼女らが誇りを持って職場に向かえる日が来るためにも私たちは戦いたいです」 ●すべての映像を公開し入管制度の国民的議論を いまの入管制度と組織が変わらない限り、ウィシュマさんのような悲劇は必ず繰り返されるだろう。そしてこの人権を無視し、非人道的な行為に加担させられるのは日本の前途ある若者なのだ。国連も問題視する非人道的な入管制度が抜本から変わらぬ限り、日本という国に未来はこない。まずはウィシュマさんのすべての映像を公開し、国民1人1人が入管施設の現実を直視したうえで議論を始めるべきだ。映像の公開が無い限り、政府は人権を軽視し国民から真実を隠そうとしていると言わざるを得ない。 <産業の付加価値向上と教育・研究> PS(2021年8月30日):産業を高度化して付加価値を高めるには科学技術・教育・研究が重要だが、*7-1-1のように、この面でも日本の研究力は低落の一途を辿り、注目論文数が世界10位に転落した。高コスト構造により、国内の製造業が比較優位性を持てず産業が海外流出すれば、それに関わる科学技術や研究も低調になるのは必然で、科学技術や研究が低調になれば国内の製造業の比較優位性がさらに低くなるという悪循環が生じる。 その結果、日本の国際的な存在感が低下して世界10位に落ちたことについて、*7-1-1は、①2019年の研究開発費は18兆円(名目額、購買力平価換算)でなお世界3位 ②大学関係者の中では、低迷のきっかけとして2004年の国立大学法人化を挙げる声が多い ③注目論文の国別の世界シェアは、中国24.8%、米国22.9%、英国5.4%、ドイツ4.5%で、日本は2.3%に留まる ④全体の論文数も現在は4位で2000年代半ばから急落 ⑤博士号取得者が日本だけ減少 ⑥博士人材が企業内でうまく活用されていない ⑦日本が低迷する要因は、大学教員の研究時間が減っていること ⑧『選択と集中』ではなく、個々の研究レベルを上げる政策の中で取り組むべき としている。 しかし、研究開発費は世界3位で少ない方ではなく、人口もドイツ(約84百万人)・英国(約68百万人)より多いため、①②⑦は主たる原因ではなく、③④は⑧のように「選択と集中」で世界が注目するようなイノベーションを含む研究がやりにくく、注目される論文を書くと細かいケチをつけて足を引っ張るメディアの多いことが原因だ。⑤は、⑥のように、時間とカネをかけて博士になっても企業で活用されず、大学や研究所でも短期の任期雇用しかなければ、博士号の取得は本人にとって費用対効果が合わないのである。 なお、突然、注目論文を書けるようになるわけではなく、初等・中等教育による基礎があって高等教育を理解でき、博士にもなれる。しかし、*7-1-2のように、日本では、政府が「一斉休校は要請しない」と言っても、「子どもを通じて、新型コロナが家庭に感染が広がる懸念がある」として、「一斉休校を要請すべき」とする論調が多く教育の優先順位が低い。が、教育に真面目に取り組んでいる国は、早くから大学生に毎週PCR検査を行い、新学期が始まる前にワクチン接種を済ませて、対面教育を継続するための最大限の努力をしているのである。 中国については、*7-2-1が、⑨自然科学分野の論文の注目度の高さを示す指標で世界1になった ⑩中国は材料科学(48.4%)・化学(39.1%)・工学(37.3%)などの5分野で首位、米国は臨床医学(34.5%)・基礎生命科学(26.9%)で首位 ⑪産業競争力の逆転も現実味 ⑫注目論文数は、中国は2018年(17~19年の平均)に4万219本となって米国の3万7124本を抜き首位 ⑬注目論文のうち上位1%に当たる「トップ論文」も、中国(25%)・米国(27.2%)で質の面でも実力をつけている姿が鮮明 ⑭中国が量と質をともに高めている背景には圧倒的な研究人材の厚さと伸びがある ⑮科学論文の量や質を左右するのは資金力だけではない ⑯研究人材の育成で日本は中国以外の国にも大きく出遅れている と記載している。 また、*7-2-2は、⑰米中が威信を懸けて科学力を競う主戦場の一つが宇宙開発 ⑱中国が送り込んだ無人探査機が2021年5月に火星に着陸 ⑲中国は2019年に世界で初めて月の裏側へ無人探査機を着陸させた ⑳中国の研究力向上を支えるのは積極投資と豊富な人材 ㉑胡錦濤前国家主席時代の2006年に「国家中長期科学技術発展計画綱要」で2020年までに世界トップレベルの科学技術力を獲得する目標を掲げ ㉒人材の獲得・育成に中長期的に取り組んで米欧の大学に若者を留学させた ㉓2008年に開始した「千人計画」では海外在住の優れた研究者らを積極的に呼び込んだ としている。 このうち、⑨⑩⑪は、産業に使う研究で中国がトップに立っている姿だ。⑫⑬⑭は、⑳㉑㉒㉓のように、中国政府によって長期の政策として行われてきたことで、産業の付加価値を高めるためにも正攻法である。そして、日本では、何かというと予算さえつければよいかのような議論が横行するが、⑮⑯がまさに事実であり、初等教育から研究人材の育成までやるべきことの逆を行ってきたと言える。なお、⑰⑱⑲は、日本の宇宙研究と違って重要な本質をずばっと突いた地球人が注目する焦点であり、志の高さが感じられる。  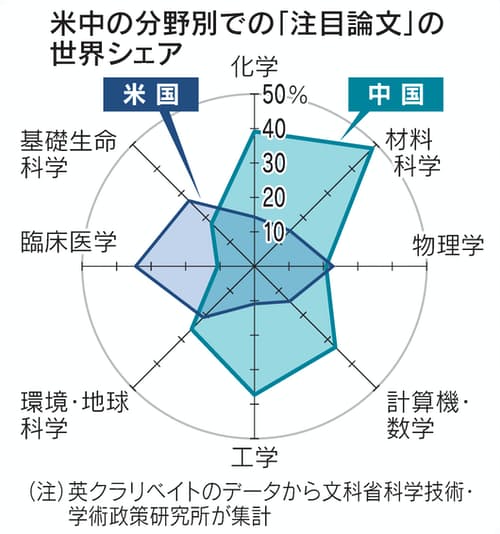 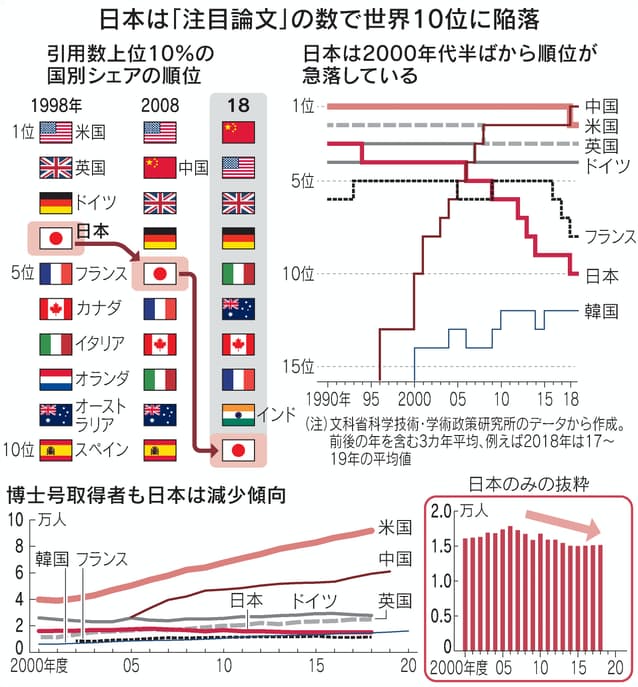 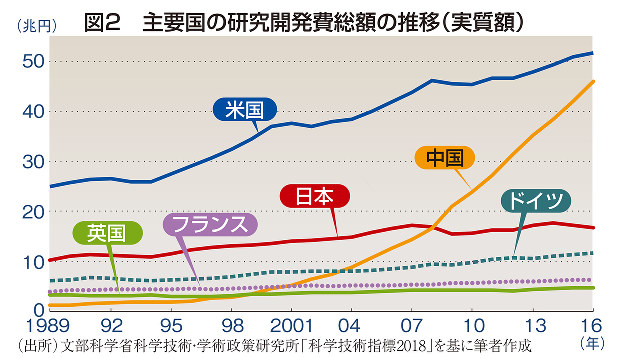 2021.8.8日経新聞 2021.8.29日経新聞 WeeklyEconomist (図の説明:1番左の図のように、引用上位10%の論文シェアで中国は米国を抜いた。左から2番目の図は、分野別の注目論文数の世界シェアだ。また、右から2番目の図のように、注目論文数で日本は10位に落ち、博士数も日本だけ減少傾向だ。しかし、1番右の図のように、日本の研究開発費総額は世界3位を維持しており、米国や中国のように増えてはいないが、ドイツ・フランス・英国以上であるため、何がネックになっているのか正確に調べるべきである) *7-1-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC209AC0Q1A820C2000000/ (日経新聞 2021年8月29日) 日本の研究力、低落の一途 注目論文数10位に 「科学技術立国」を掲げる日本の国際的な存在感が低下している。文部科学省の研究所が8月上旬にまとめた報告書では、科学論文の影響力や評価を示す指標でインドに抜かれて世界10位に落ちた。世界3位の研究開発費や研究者数も伸び悩んでおり、長期化する研究開発の低迷に歯止めがかからない。世界の科学論文の動向は文科省の「科学技術・学術政策研究所」が毎年まとめている。今回発表した最新のデータは、2018年(17~19年の3年間の平均)のものだ。1年では特殊な要因によるぶれが出かねないため、3カ年の平均値で指標を出している。10位になったのは、研究分野ごとに引用数がトップ10%に入る「注目論文」の数だ。研究者は研究成果を論文にまとめる際、関連する論文を参考として引用する。引用された数は社会やその研究分野へのインパクト、評価や注目度を示す指標になるわけだ。注目論文の国別の世界シェアをみると、中国が24.8%で米国を初めて逆転して世界一に立った。米国は22.9%で、米中で世界の50%近くを占めた。大きく離れて英国(5.4%)、ドイツ(4.5%)などが続き、日本は2.3%にとどまった。日本の低迷は最近始まったことではない。国際ランキングの推移を見ると、特に2000年代半ばからの急落が目立つ。1980~90年代前半は米国、英国に次ぐ3位を維持していた。だが94年にドイツに抜かれ、2005年までは4位になり、その後順位を落とし続け、ついに2ケタ台になってしまった。注目論文のうち引用数が上位1%の「トップ論文」もほぼ同じ推移だ。00年代前半まで長く4位だったが、今は9位に落ちた。研究開発の活発さを示す全体の論文数もかつては米国に次ぐ2位だったが、現在は4位だ。低迷のきっかけに04年の国立大学の法人化を挙げる声は大学関係者の中で多い。その後、国から配られる大学の運営費に関する交付金は年々削減されていき、大学は人件費や管理費の抑制を進めたという指摘がある。00年代半ばから低下したのは資金だけではない。他国に比べても目立つのが、将来の国の研究開発を下支えする博士号取得者の減少だ。米中は年々その数を伸ばしており、英国や韓国も00年度に比べて2倍超となった。ドイツやフランスも横ばい水準を維持している。一方の日本では、06年度の約1.8万人をピークに減少傾向が続いており、近年は約1.5万人で推移している。影響は大学だけではなく、企業の研究力にも及ぶ。米国では企業の研究者のうち博士号所有者の割合が、ほぼ全ての業種で5%を超える。日本は医薬品製造や化学工業などを除いた多くの産業で5%未満にとどまる。専門的な知識を持って入社する博士人材が、企業内でうまく活用されていない状況だといえる。民間なども加えた日本の研究者の総数は20年で68.2万人、19年の研究開発費は18兆円(名目額、購買力平価換算)で米中に大きく離れてもなお世界3位を保っている。ただ、前年からの増加率は1%以下とほぼ横ばいの水準だ。増加率2ケタ台で研究者数がトップの中国や、研究開発費で首位をキープする米国との差は開く一方だ。日本が低迷する要因について、調査担当者は「大学教員の研究時間が減っている」ことをあげる。改善するにはどうしたらいいか。政府の科学技術政策の司令塔である「総合科学技術・イノベーション会議」の議員を務める橋本和仁さん(物質・材料研究機構理事長)は「『選択と集中』ではなく、個々の研究レベルを上げる政策の中で取り組むべきだ。例えば、短期的な成果を求めないようにするため、若手の雇用を増やすべきだという議論になるだろう」と指摘する。政府は3月に閣議決定した「第6期科学技術・イノベーション基本計画」で、博士課程人材への財政支援の拡充、大学の経営基盤強化や若手研究者の支援などに向けて10兆円規模のファンドを立ち上げる方針を掲げた。実効性が問われる。 *日本の科学技術計画 政府が5年に1度策定するもので、日本の科学技術政策の中長期的な方針を示す。科学技術基本法(1995年制定)が2020年に改正されたのに伴い、従来は「科学技術基本計画」との名前だったが現在は「科学技術・イノベーション基本計画」と呼ぶ。3月に閣議決定した21~25年度の第6期計画では「今後5~10年間が、我が国が世界を主導するフロントランナーの一角を占め続けられるか否かの分水嶺」との危機感を示した。5年間で政府の研究開発投資を総額30兆円にするといった目標を掲げた。 *7-1-2:https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082400648&g=soc(時事 2021年8月25日)夏休み延長、分散登校も コロナ拡大で不安広がる―政府「一斉休校要請せず」 新型コロナウイルスの感染急拡大が収まらない中、夏休み明けの学校再開に向け、全国の自治体が対応に苦慮している。政府は全国一斉の休校は要請せず、自治体に対応を委ねる意向。一方で子どもを通じて家庭に感染が広がる懸念もあり、夏休みの延長や分散登校を決める自治体も出ている。新学期の対応について、萩生田光一文部科学相は20日、「地域の事情に合わせて判断を変えていくということで、国としての一斉休校は行わない」と説明。そのため自治体の判断が分かれている。札幌市では予定通り、23日から中学校の2学期が始まった。一方、東京都は現時点で一斉休校は求めず、状況に応じて時差登校や短縮授業の検討を要請する通知を出した。大阪府も一斉休校はしないが、修学旅行を原則延期したほか、部活動の一部を中止に。愛知県も修学旅行の休止を検討するなど、行事を見直す動きは広がっている。一方、横浜市は市内の小中学校など約500校を対象に、26日までの夏休みを延長し31日まで臨時休校にした。市教委の担当者は「感染状況が厳しく、保護者から再開を不安視する声も寄せられた」と明かす。神奈川県内では川崎、相模原両市も小中学校の8月末までの休校を決定。東京都調布市は小中学校を9月5日まで休校にした。分散登校に踏み切るケースも多い。群馬県の県立学校では2学期の始業式から9月12日まで、生徒らを分けて交代で登校。熊本市では小中学校について、オンライン授業と登校日を学年ごとに分ける方式を1日から10日まで導入する。岐阜県では、県立高校の2学期の授業を当面オンラインで実施。県教委の担当者は「高校は通学エリアが広く、感染リスクが小中学校より高い」と説明している。大阪府寝屋川市も夏休み明けの登校を見合わせ、小中学校は8月27日までオンライン授業としている。政府は学校での感染防止対策として小中学校に抗原検査の簡易キットを配布する方針。教職員のワクチン接種も促すが、10代以下の子どもの感染も急増する中、自治体からは「看過できない状況になれば一斉休校も判断としてあり得る」(吉村洋文大阪府知事)との声が出ている。 *7-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05A1O0V00C21A8000000/?n_cid=BMSR3P001_202108101701 (日経新聞 2021年8月10日) 中国論文、質でも米抜き首位 自然科学8分野中の5分野 自然科学分野の論文の注目度の高さを示す指標で中国が初めて世界一になった。文部科学省の研究所が10日、最新の報告書を公表した。研究者による引用回数が上位10%に入る「注目論文」の数で初めて米国を抜いた。分野別でも8分野中、材料科学や化学、工学など5分野で首位に立った。学術研究競争で中国が米国に肩を並べつつあり、産業競争力の逆転も現実味を帯びてきた。科学論文の数は国の研究開発の活発さを測る基本的な指標だ。文科省科学技術・学術政策研究所が英調査会社クラリベイトのデータを基に主要国の論文数などを3年平均で算出・分析した。中国が学術研究の量だけでなく、質の面でも実力をつけている姿が鮮明だ。注目論文の本数を調べたところ、中国は2018年(17~19年の平均)に4万219本となり、米国の3万7124本を抜き首位になった。米国も08年に比べて3%増えたが、中国は約5.1倍と急増。シェアは中国が24.8%、米国が22.9%と、3位の英国(5.4%)を引き離した。注目論文のうち上位1%に当たる「トップ論文」でも、中国のシェアは25%と米国の27.2%に肉薄した。文科省科学技術・学術政策研究所の担当者は今後について「中国のいまの勢いは米国を追い抜く様相を見せている」と指摘する。注目論文の世界シェアを分野ごとにみると、材料科学で中国は48.4%と米国(14.6%)を大きく引き離した。化学が39.1%(同14.3%)、工学は37.3%(同10.9%)などと計5分野で首位となった。米国は臨床医学(34.5%)や基礎生命科学(26.9%)で首位となった。バイオ分野で強さが目立つものの、産業競争力に直結する分野で中国が強さを示した。全体の論文数では昨年の集計に引き続き中国が首位になり、米国を上回った。中国は35万3174本、米国が28万5717本で、その差を20年調査時の約2万本から約7万本に広げた。一方、日本は論文の質・量ともに順位が低下し、科学技術力の足腰の弱さが浮き彫りになった。注目論文のシェアではインドに抜かれ、前年の9位から10位と初めて2ケタ台に後退した。トップ論文のシェアも9位と前年から横ばいだった。10年前と比べた減少率はともに10~15%と大きく、論文の質が相対的に下がっている。日本の全体の論文数は6万5742本と米中の20%前後の水準にとどまった。米中のほか韓国、ドイツ、フランス、英国などは10年前と比べ増えているが、日本は横ばいにとどまる。長期化する研究力低下に歯止めをかけるのに「特効薬」はなく、衰退を食い止めるのは難しい。科学論文の量や質を左右するのは資金力だけではない。中国が量と質をともに高めている背景には、圧倒的な研究人材の厚さと伸びがある。世界一を誇る研究者数を年々増やしている。一方、中国・米国に続いて3位の日本は横ばい水準で伸び悩む。中国の19年時点の研究者数は210万9000人と世界首位だ。前年から13%増と高水準で伸びた。日本は68万2000人(20年時点)と中国・米国に続く3位だが、増加率は0.5%にとどまる。研究人材の育成で日本は中国以外の国にも大きく出遅れている。文科省科学技術・学術政策研究所によると、日本で大学院の博士号を取得した人数は06年度をピークに減少傾向だ。米中や韓国、英国では15~20年前に比べて2倍超の水準で伸びている。ドイツやフランスは横ばい水準だ。 *ひとこと解説 青山瑠妙:早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 自然科学分野の論文の注目度の高さを示す指標で中国が初めて世界一になった。世界一になった理由として、一般には研究開発費の増加が指摘されている。なかでも大学に配分される科研費は文系、理系を問わず、潤沢である。研究者の人数が多いことも一因であるが、その多くは欧米で教育を受けた研究者であることは忘れてはならない。さらに、中国の論文を網羅した学術データベースの存在も中国の論文の引用回数の底上げに貢献した。国際競争力を目指すには、科研費の充実をはじめとした日本政府の政策支援が求められる。 *7-2-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC103PJ0Q1A810C2000000/ (日経新聞 2021年8月10日) 中国、科学大国世界一を視野 米国の競争力基盤揺るがす 中国が「科学大国世界一」の座を米国から奪おうとしている。文部科学省の研究所が10日発表した報告書では注目度の高い論文の数で初めて首位となり、研究の量だけでなく質の面でも急速に台頭していることを印象づけた。戦後の科学研究をリードしてきた米国の優位が失われつつあり、産業競争力にも影響する可能性がある。米中が威信を懸けて科学力を競う主戦場の一つが宇宙開発だ。5月には中国が送り込んだ無人探査機「天問1号」が火星に着陸し、習近平(シー・ジンピン)国家主席は「中国は惑星探査の分野で世界の先頭集団に入った」と胸を張った。2019年には月の裏側へ世界で初めて無人探査機を着陸させている。「中国の技術力は米国に負けないレベルに達している」と京都大学の山敷庸亮・有人宇宙学研究センター長は指摘する。米国は1950年代以降、科学技術の分野で世界を先導してきた。産業競争力の源泉であり軍事上の優位を支える土台でもあったが、その基盤を中国が揺るがしている。中国の研究力向上を支えるのが積極投資と豊富な人材だ。中国の19年の研究開発費(名目額、購買力平価換算)は54.5兆円と10年間で2倍以上に増えた。首位の米国(68兆円)にはなお及ばないが、増加ペースは上回る。研究者の数も210万人と世界最多で、18年に155万人だった米国を大きく引き離す。現在の中国の姿は戦略的な計画に基づく。胡錦濤(フー・ジンタオ)前国家主席時代の06年に始動した「国家中長期科学技術発展計画綱要」で、20年までに世界トップレベルの科学技術力を獲得する目標を掲げた。研究開発投資を拡充し、対外技術依存度の引き下げを進めてきた。人材の獲得や育成にも中長期的に取り組み、米欧の大学などに若者を積極的に留学させた。08年に開始した「千人計画」では海外在住の優れた研究者らを積極的に呼び込んだ。国内でハイレベル人材を育てる計画も推進してきた。当面、中国の勢いは続きそうで、ノーベル賞の受賞なども増える公算が大きい。3月には今後5年間、官民合わせた研究開発費を年平均7%以上増やす方針を示した。米スタンフォード大学の報告によると、学術誌に載る人工知能(AI)関連の論文の引用実績で中国のシェアは20年に20.7%と米国(19.8%)を初めて逆転した。近年、米国は技術流出に警戒を強め、中国から研究者や学生を送り込むのが難しくなっている。中国は最先端の半導体などをつくる技術はまだ備えておらず、研究を産業競争力の強化につなげる段階でも壁は残る。日本の衰退は一段と進んでいる。注目度の高い論文の数ではインドに抜かれ10位に陥落した。世界が高度人材の育成を競うなか、大学院での博士号の取得者は06年度をピークに減少傾向が続き、次世代の研究を支える人材が不足している。米国では民主主義などの価値を共有する日本との協力を重視すべきだとの声もあるが、このままではそんな声さえ聞かれなくなる恐れがある。 *多様な観点からニュースを考える 山崎俊彦:東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授 2021年8月11日 貴重な体験談「人材の獲得や育成にも中長期的に取り組み、米欧の大学などに若者を積極的に留学させた。08年に開始した「千人計画」では海外在住の優れた研究者らを積極的に呼び込んだ。これが全てを物語っている気がします。米国で名を挙げた企業や大学の研究者が中国に戻ったり中国の組織で兼任したりしているのを実際にたくさん目にします。 <中国の塾規制とオンラインゲーム規制> PS(2021年9月1日追加):*8-1のように、中国政府が教育費負担を抑えて少子化対策を行うために学習塾の規制強化に乗り出し、①習国家主席が「児童生徒の勉強は基本的に学校内で教師が責任を負うべきだ」とされ ②週末や長期休暇中の授業時間を制限し ③受験競争の激しい山東省が学校に児童生徒に塾通いを勧めないよう要求した そうだ。しかし、①は正論でも、先に学校で教師が責任を負えるような授業をするのでなければ親子は別の方法を考えなければならず、④家庭教師への依頼が増えコストが上がって かえって困りそうだ。ただし、放課後児童クラブ等に家庭教師を招いて複数で授業を受け、コストを抑える方法もあるかもしれない。 なお、*8-2のように、中国政府が18歳未満の未成年のオンラインゲーム利用を週3時間に制限する新規則を公表したのはよいことだと思う。何故なら、オンラインゲームにふけると勉強や読書の時間を少なくし、心身の健康に悪影響があることは疑いない上、「eスポーツ」は実際に身体を鍛えるわけではなく、ゲームより有意義な時間の使い方はいくらでもあるからである。 *8-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM229HK0S1A620C2000000/ (日経新聞 2021年7月11日) 中国が教育費高騰で塾規制 受講料、平均年収の2倍も 中国政府が学習塾の規制強化に乗り出す。政府内に監督部門を新設し、週末授業や学費の制限を検討する。家計の教育費負担を抑えて少子化対策につなげる狙いだが、政府の思惑通りになるかどうかは見通せない。 ●少子化対策へ習氏「学校が責任もて」 「児童生徒の勉強は基本的に学校内で教師が責任を負うべきだ」。習近平(シー・ジンピン)国家主席は6月、唐突に教育問題を取り上げた。背景には少子化対策がある。中国政府は夫婦1組に3人目の出産を認める法改正に着手した。長年の産児制限で1人っ子が圧倒的に多い中国では、親が子どもの教育に巨額のお金を投じる。一人娘が6月に全国統一大学入試「高考」を受けた北京市の呉さんは「同級生で高校3年生の塾代に年30万元(約510万円)かけた家もある」と明かす。北京市の会社員の平均年収は260万円程度とされ、2倍近い計算だ。教育費は若い夫婦が出産をためらう大きな原因だ。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は2020年に1.3まで下がった。政府は教育費の軽減が出生率の反転に欠かせないとみて、教育行政で「双減(2つの軽減)」を掲げた。高騰する家庭の教育費と宿題など児童の負担の2つを軽くする意味だ。矛先は塾業界に向かった。中国教育省は6月、「校外教育機関監督局」を新設した。塾への規制をつくり、監督する。週末や長期休暇中の授業時間を制限したり、学費の標準モデルを策定したりするのが検討課題という。全国に先立って動き出した地域もある。受験競争が激しいことで有名な山東省は6月、省内の学校に夏休み中の対応に関する通知を出した。児童生徒に塾通いを勧めたりしないよう要求した。シンクタンクの前瞻産業研究院によると、中国の教育産業の市場規模は20年までの5年で4割増えた。新型コロナウイルス禍でもオンライン授業が広がり、需要は底堅かった。 ●講師の経歴詐称や「秘密特訓」で高額徴収 親の教育熱を逆手に取った塾の不法行為も社会問題になった。独占禁止法などを管轄する国家市場監督管理総局は6月、15社の学習塾に総額3650万元の罰金を支払うよう命じた。講師の経歴詐称や、わざと高い学費を設定して値引きで割安感を演出する行為があった。教育省も6月、親への注意喚起という形で学習塾をけん制した。「秘密の特訓コース」などと銘打って高額の授業料を追加徴収する例などを挙げた。もっとも、新型コロナの爪痕で若者の職探しは厳しさを増す。「高考の数点の差が人生を左右する」との考えも根強く、我が子を少しでも良い大学に進学させようと必死になる親は多い。中国では塾講師や家庭教師のアルバイトをする学校教師が少なくない。給料が安く、大都市では給料だけで暮らせないからだ。評判のよい学校教師が塾で教えれば、塾の人気も高まる。北京市内の大手塾で教壇に立つ趙さんは「公立学校を辞めて塾に転職する教師もいる」と明かす。 ●「家庭教師への依頼増えるだけ」 中国共産党は加速する少子高齢化が経済成長を鈍化させると危機感を抱く。所得の伸びはすでに鈍り、習指導部は家計の大きな負担である教育費に目をつけ、塾規制という「奇手」を繰り出した。ただ、学校教師の待遇改善など本質的な対策を怠ったままでは、政策効果にも限界がある。趙さんは「塾の授業を規制しても家庭教師への依頼が増えるだけで、コストはかえって高くなる。そうなれば親の反発が強まるだけではないか」と話している。 *8-2:https://jp.reuters.com/article/china-regulation-gaming-tencent-holdings-idJPKBN2FW0E7 (ロイター 2021年8月31日) 中国の未成年オンラインゲーム規制、関連株が下落 愛好家は怒り 中国政府が18歳未満の未成年によるオンラインゲーム利用を週3時間に制限する新規則を公表したのを受け、騰訊控股(テンセント・ホールディングス)といったゲーム企業の株価が下落した。また、ソーシャルメディア上ではゲームを楽しむ若者が怒りを表明している。オンラインゲームを「精神的アヘン」と表現したこともある中国当局は新規則について、依存の高まりを食い止めるのに必要だと説明。共産党機関紙の人民日報は、政府は「非情に」ならざるを得ないとする記事を出した。同紙は、オンラインゲームにふけることは10代の若者の日常の勉強、心身の健康に影響があることは「疑いの余地がない」と指摘。「ティーンエージャーが荒廃すれば家庭が荒廃する」とした。一方、中国の若いゲーム愛好家は怒りを表明した。中国版ツイッター「微博(ウェイボ)」のあるコメントは「こうした規則と規制をつくるおじいさんとおじさんのこの集団はゲームをプレイしたことがあるのだろうか?『eスポーツ』プレイヤーにとって最良の年齢が10代にあることを理解しているのだろうか?」と投稿。「性的同意は14歳。16歳で働きに出られる。しかし、ゲームをプレイするには18歳にならなければならない。これは全くの冗談だ」とした。31日のテンセントの株価は3.6%安。米上場の網易(ネットイーズ)はオーバーナイトで3.4%安。31日の香港上場株も同程度値を下げている。韓国のクラフトンは3.4%安。東京市場ではともに中国市場へのエクスポージャーを持つネクソンとコーエーテクモがそれぞれ4.8%安、3.7%安。
| 経済・雇用::2021.4~2023.2 | 12:02 AM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2021,07,22, Thursday
(1)地球温暖化の影響で増える自然災害
1)洪水の多発とダム決壊の恐れ イ)欧州の「100年ぶり」の豪雨 ← これから頻繁に起こるのでは?    2021.7.16Yahoo 2021.7.17News Week 2021.7.17NHK (図の説明:2021年7月16日、欧州西部を襲った記録的豪雨で河川が氾濫して発生した洪水) 欧州西部を襲った記録的豪雨で、*1-1-1のように、水位の上昇が続いて河川が氾濫し、洪水が発生して住宅が押し流されるなどの大規模な被害が発生し、7月16日時点で、ドイツ・ベルギー・オランダで約1,300人の安否が確認されず、死者が120人を超えたそうだ。 また、ケルン当局の報道官は「ネットワークが完全に遮断され、インフラは完全に破壊された。病院は患者を受け入れられなくなっている」とし、ドイツ政府は700人を超える軍隊を動員して救援にあたっているが、ダムが決壊すれば下流地域が一段の洪水に見舞われる恐れがあるとして放流も試みているとのことである。 気象学者は、「気候変動の影響でジェットストリームの流れが変わったため、今回の豪雨が引き起こされた」と指摘し、欧州委員会のフォンデアライエン委員長も、「今回の洪水の規模を踏まえると気候変動が影響していることは明らかなので、迅速に対応する必要がある」という考えを示しているそうだ。 ロ)中国河南省は「1000年に1度」の暴雨 ← これから頻繁に起こると思うが・・    2021.7.22Ameblo 2021.7.21BBC 2021.7.21Yahoo (図の説明:中国河南省の記録的大雨で、左図は、地下鉄が浸水した様子、中央の図は、街中の様子、右図は、亀裂が生じて決壊する恐れがあるとされる満タンのダムの様子) 中国河南省でも、7月17日以降に記録的な大雨が続き、*1-1-2のように、鄭州市で地下鉄が浸水するなどして7月21日までに少なくとも計16人が死亡して10万人が避難し、鄭州の気象局は「1000年に1度の暴雨」だとして警戒を呼びかけているそうだ。 鄭州市では、7月17日以降の3日間で年間雨量に匹敵する617ミリの雨量を計測し、20日午後6時頃に、雨水が地下鉄構内への浸水を防ぐ遮水壁を越えて線路まで流れ込み、市内の地下鉄全線が運行停止となって、500人余りが避難したが逃げ遅れた12人が死亡した。このほか、家屋の倒壊等によっても4人が死亡したそうだ。 また、*1-1-3のように、駅や道路が冠水し、住民1万人以上が避難を余儀なくされ、人口約9400万人の河南省に最高レベルの気象警報が発令されている。さらに、洛陽市のダムに20メートルほどの亀裂が生じて決壊する恐れも出ており、同地域には兵士が配備されいるが、軍は「いつ決壊してもおかしくない」と警告したそうだ。 同地域では少なくとも今後24時間は土砂降りの雨が続くと予想されており、洪水発生の原因は複合的であるものの気候変動による気温上昇は激しい降雨のきっかけになる。 2)気温の上昇に伴う海面の上昇 イ)氷河の融解 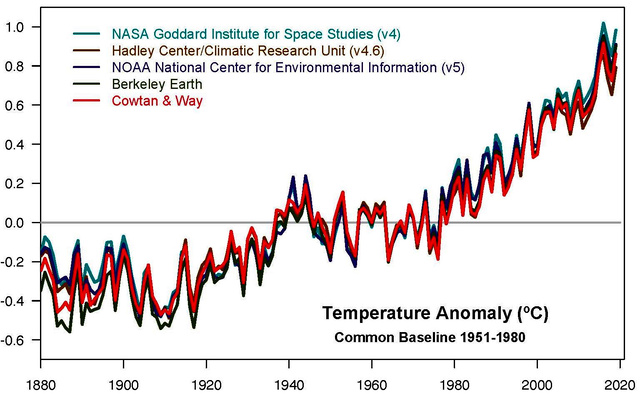 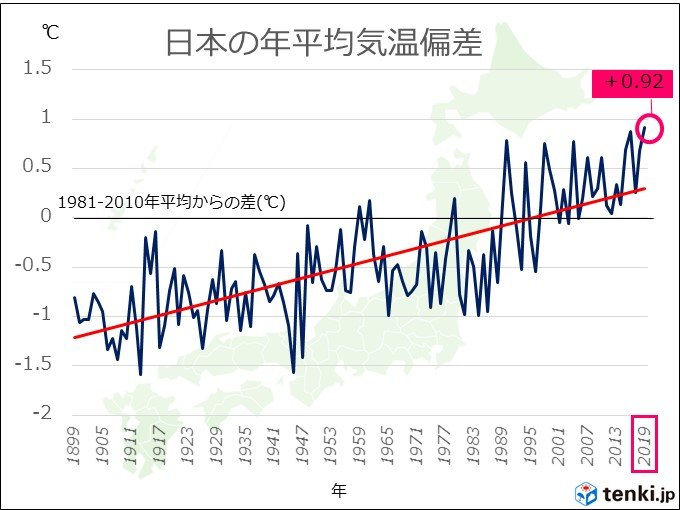 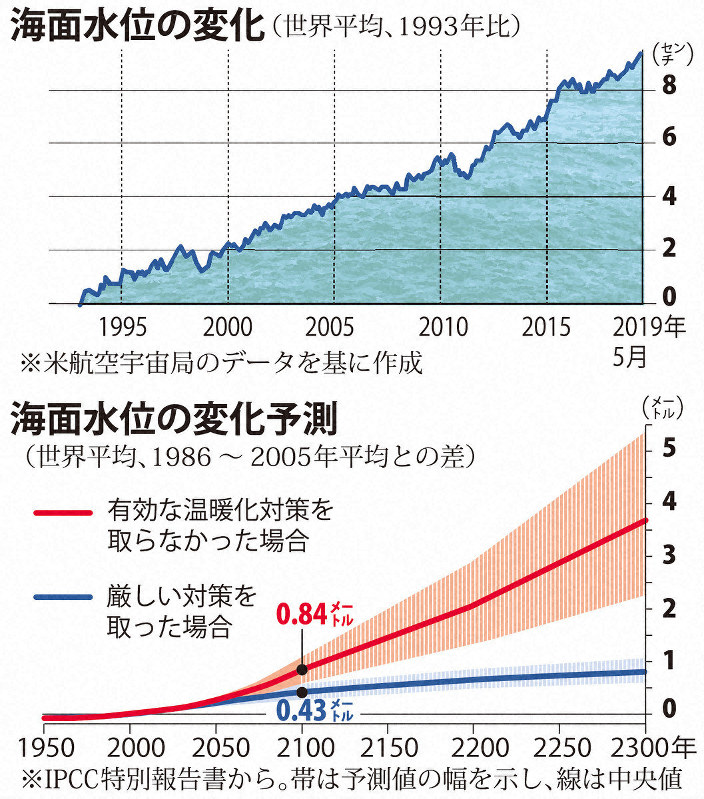 2020.1.16朝日新聞 2019.12.24日本気象協会 2019.9.25毎日新聞 (図の説明:左図は、世界の気温の推移を、1951~1980年の平均気温を基準として1880~2020年の年間平均気温についてグラフにしたもので、初めは低かった気温が近年になって急速に上がり、全体で約1°C上がっているが、上昇幅は新興国が市場参入して多くの化石燃料を使い始めた時期に大きくなっている。中央の図は、日本の気温が1981~2010年の平均を基準として年間平均でどれだけ高かったか低かったかを1899~2019年についてグラフにしたもので、マイナス部分が多いように見えるが、実際には1889年と比較して2019年は2°C近く上昇している。世界の気温上昇に伴って海水温も上がり、右図のように、1950年と比較すると2020年には既に30~40cmは海面上昇しており、これは見た目の実感と一致している)   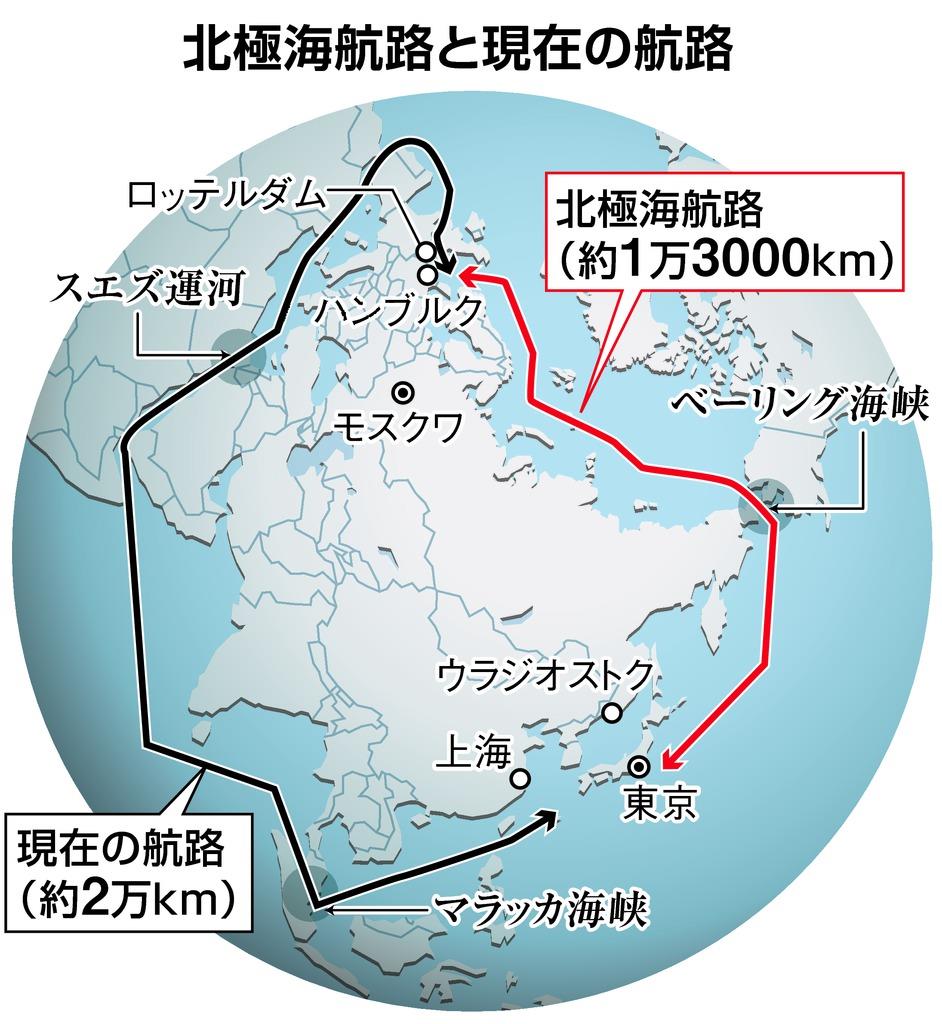 2021.7.22Gooddo 2021.7.21AmericanView 2018.11.15産経新聞 氷河の後退 (図の説明:気温が上がると海面が上昇する理由は、左図のように、極地の氷が解けたり、中央の図のように、山間部の氷河が解けて後退したりするからだ。右図は、北極海の氷が解け、北極海を通行しやすくなった場合の航路短縮のメリットを記載しているが、海面上昇で国土が狭くなったり、インフラが使えなくなったりするディメリットは考慮されていないようだ) *1-2-1のように、カナダ・フランス・スイス・ノルウェーの研究者が、NASAの衛星「Terra(テラ)」に搭載したカメラで世界各地21万カ所以上の氷河の写真を撮影し、20年分の衛星写真をまとめて、2000年から2004年にかけては年間2,270億メートルトンの氷河が失われ、2015~2019年には年間2,980億トンが解けて、このままのペースで融解が続けば、今世紀半ばには多くの氷河が完全に失われる可能性があると、『Nature』に掲載したそうだ。 論文は、この変化の原因に温暖化や降水量の増加を挙げており、溶けて河川や海に注ぎ込んだ水の量は、過去20年間に観測された海面上昇分の約5分の1に相当するとしているが、過去20年間に観測された海面上昇分の約1/5にすぎないのなら、残りの4/5はどこから来たのか? 日本でも、海面上昇は重大問題で、これまで標高の低かった地域は海抜以下になって下水の排水が困難となり、洪水も起こり易くなる。中国で地下鉄に水が流れ込んだ例は、東京・大阪でも他人事ではなく、これ以上、海抜の低い地域に人口を密集させて、そこに地下鉄をはじめとするインフラを集中投資することは意味が問われるようになった。 氷河が減ると、氷河をバッファとして比較的低く保たれてきた海水温はさらに上がりやすくなり、急速に溶ける氷河の水は北インドでは狭い渓谷を下ってふたつのダムに到達し、200人が亡くなる事故という環境災害を引き起こした。そして、国連の気候変動に関する政府間パネルが2018年に発表した報告書は、その凄まじい洪水や地滑りが高山で起きやすくなっている原因を温暖な気候にあると指摘している。 ロ)2020年は日本も世界も平均気温が史上最高で、豪雨・異常高温が相次いだ 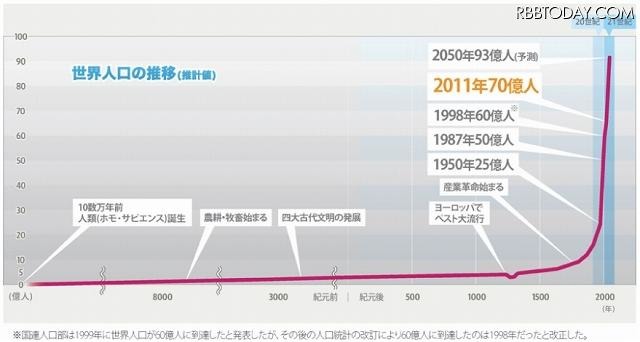 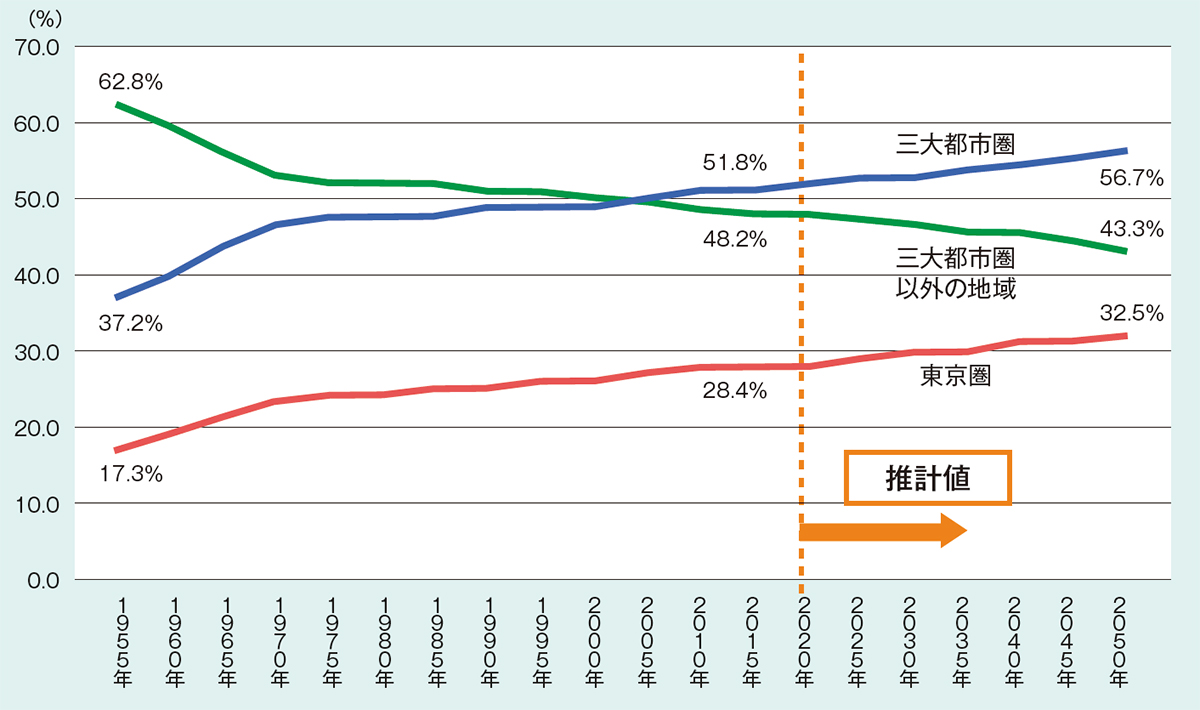 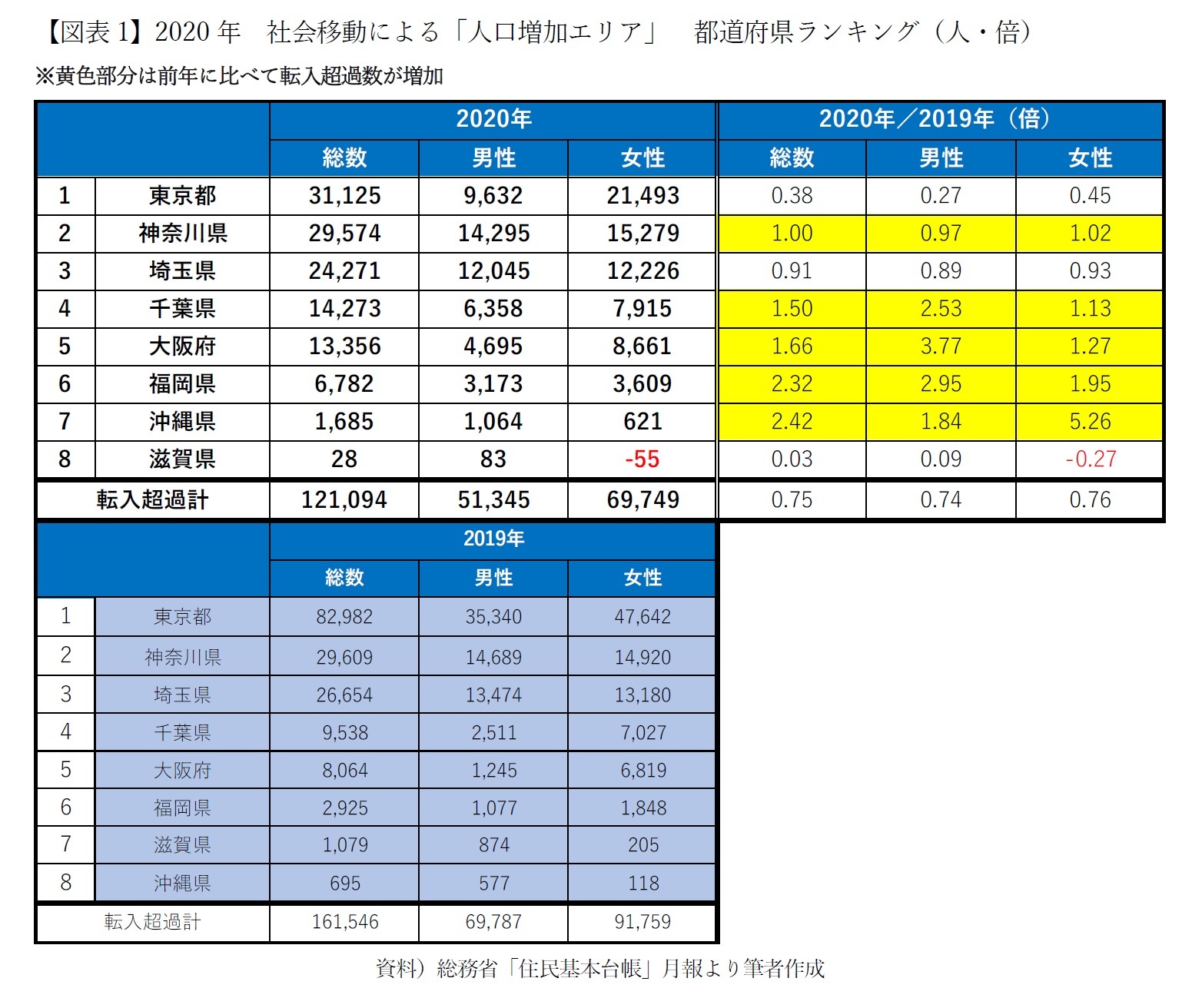 RBBTODAY COM 日生基礎研究所 日生基礎研究所 (図の説明:左図のように、世界人口は産業革命後に急速に伸びはじめ、現在は70億人程度だ。また、中央の図のように、日本の人口は太平洋戦争後の経済成長期に都市に集中し始め、三大都市圏それも東京圏に住む人口が著しく増えて、今では都市しか知らない人の割合も多くなった。右図は、2019~2020年の社会的移動による人口増加の割合で、これらの複合的要因が都市におけるヒートアイランド現象の原因となっている) 2020年夏以降は太平洋の中部・東部の海面水温が平年より低くなるラニーニャ現象が発生して2020年末から2021年にかけては寒い冬になったが、英国気象庁によると、2021年の世界の気温は2015年以降の数年間よりはラニーニャ現象の影響で少し涼しくなるものの、1850~1900年の平均よりは約1度高く、長期的な温暖化傾向に変わりはないとのことである。 また、*1-2-3によると、都市部ではヒートアイランド現象による気温上昇が別途加味されるが、日本全体の気温の推移を確認する場合は都市部を除いた地点の全国をまんべんなく抽出して調べたところ、日本の平均気温は昭和元年から令和元年(1926~2019年)の94年間で1.4度上昇し、猛暑日も平成以降急激に増えて2010年代の10年間は1980年代と比較すると日数が4.6倍になるそうだ。 その上、都市部は建築物・舗装道路・人工排熱等の影響で気温が上がりやすく、ヒートアイランド現象が起こるため、全国平均よりも気温の上昇が大きく、年間猛暑日も明確に多いそうだが、これも体感と一致している。 (2)それではどうすればよいのか 1)都市の構造を変える    東京(日本) 大阪(日本) 福岡(日本) (図の説明:左図は、東京の空中写真だ。スカイツリーの近くを流れる空を映して青く見えているのは隅田川で、下水道で処理しきれなくなった場合は汚水も流すため、近くで見ると濁っていてきれいでない。また、東京の地面は、殆どがコンクリートとアスファルトで覆われており、コンクリート製の建物が密集して緑が少ないため、ヒートアイランド現象を起こし易い。つまり、都市計画が乏しい。中央の図は、大阪の空中写真で、大阪城近くを撮影しているため緑が多く見えるが、街中は東京と同じかそれ以下だ。大阪城近くを流れている大川(旧淀川)や寝屋川も、空を映して青く見えてはいるが、近くで見るときれいな川ではない。なお、右図は、福岡の空中写真で、空港にJR直通の地下鉄が乗り入れていたり、空港が街に近かったりするのはよいが、都市は東京と同じくコンクリートとアスファルトで覆われ、コンクリートの建物が密集して緑は東京より少ない《福岡の人は「自然が近いからいい」と言っていたが》。そして、どの都市も飛行機から見ると家並が時代を経るに従って無秩序に広がっていき、都市計画はないようだ)    ロンドン(英国) パリ(フランス) 上海(中国) (図の説明:左図は、ロンドンの空中写真で、東京よりは高さの揃った建物が並んでいるが、コンクリート・アスファルト・石造りの建物が多く、街中を流れるテムズ川はきれいでない。しかし、東京より緯度が高いため、年間平均気温は低い。中央の図は、凱旋門を中心として放射状に広がったパリの街で、建物の高さ・設計がかなり統一されているため、街の景観が良く絵になる。緑は道路からは多く見えないが、建物の中庭にもあるようだ。また、右図は上海で、競って近代的な建物を建てているので一つ一つはおしゃれな建物も多いが、街全体としての整合性・統一性がなく、少し路地に入ると昔ながらの汚ない建物も多い。緑は東京と同じか少し多いくらいで、道は広くなったが近くを流れる蘇州河・黄浦江の水はきれいでない。そのため、ここも、環境に配慮した都市計画が必要だろう) イ)日本の都市構造について 日本の都市は、奈良・京都を除いて、道路は建物の隙間を利用して作ったかのように狭くてわかりにくく、碁盤の目になっていない。そのため、番地で住所を探しにくいが、スマホの地図を見ながら歩くと危ない上、逆に居場所を探知されて悪用されるケースもあるため、私自身はスマホを使っていない。 そのため、これからの都市造りは、あらかじめ安全性で土地にランクを付け、水やエネルギーの供給計画を立て、必要な交通システム・上下水道・電気・ガス・病院・学校・保育所・介護施設・緑地などのインフラ整備を行う必要がある。何故なら、そういうことを考えずに建物を増やしていくと、災害のリスクが上がり、結局は住環境が悪くなるからで、既にできている都市も、今後10~100年の街づくり計画を立て、それに合わせていく必要があろう。 ロ)「空飛ぶクルマ」を使った交通システム JALは、*3-3のように、2025年度に、三重県等で空港と観光地を結ぶ「空飛ぶクルマ」を使ったサービスを始めるそうだ。空港を起点に目的地に行く「空飛ぶクルマ」が実用化されれば、道路の渋滞緩和や過疎地の交通に役立ちそうだ。 しかし、「クルマ」が空から落ちてきては人も建物もたまったものではないため、事故時も安全が保たれるクルマ・道・ルールを作って欲しい。例えば、道路を3階建てにして、1階は歩行者・自転車・自動二輪車・緑地専用、2階は自動車専用、3階は「空飛ぶクルマ」専用にしておけば、「空飛ぶクルマ」は最悪でも3階に落ちるだけですみ、3階の道路に不時着することも可能だ。そして、目的地となる場所は、建物の屋上か3階以上にポートを作る必要があるだろう。 なお、この交通システムは、これまで道路の整備が遅れていた場所で作った方が早くできそうで、もしアフリカで作れば、サバンナを道路で分断せずに自動車専用道路を作ることができる。 2)せめて「30年の計」がある予算を作るべき 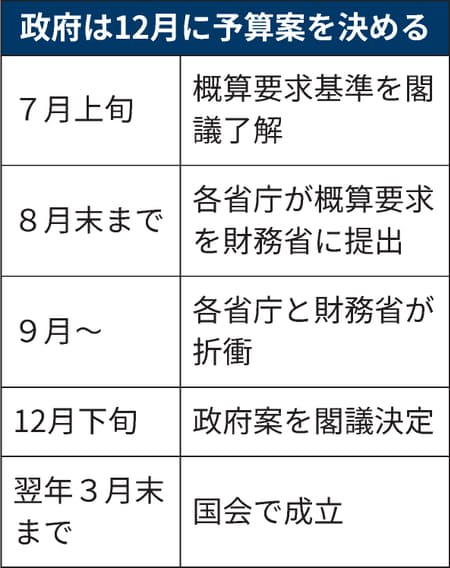 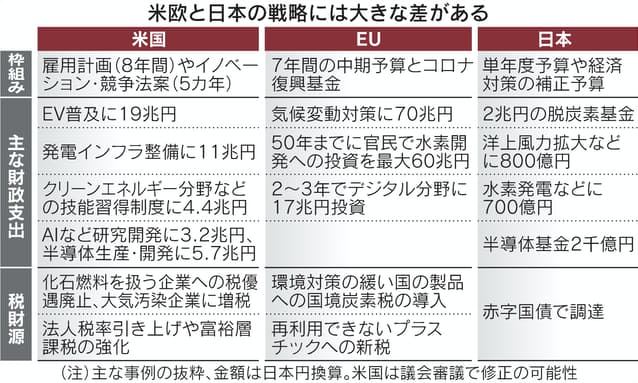 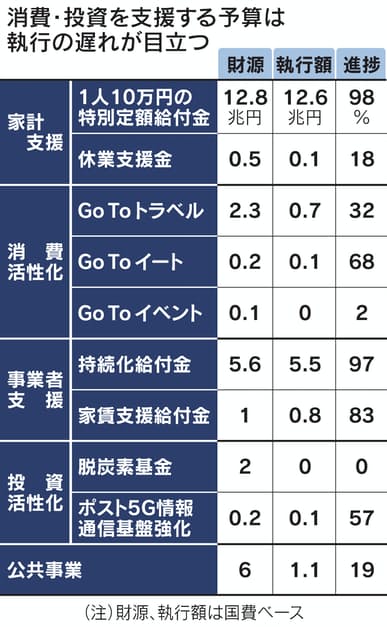 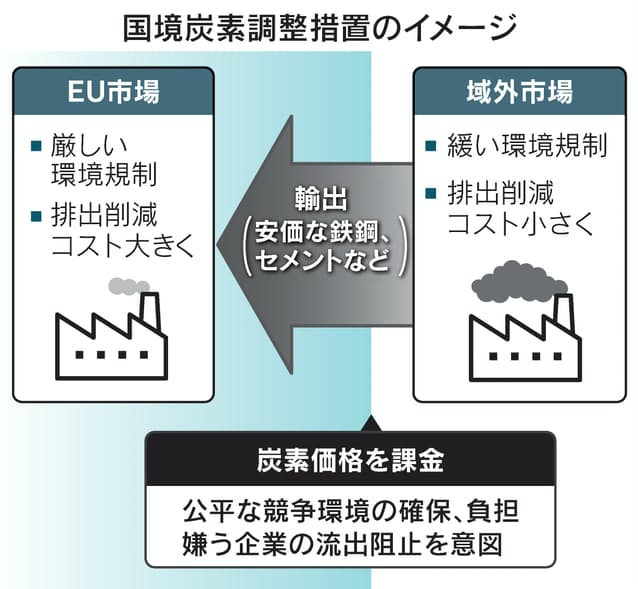 2021.7.3日経新聞 2021.7.15日経新聞 2021.6.24日経新聞 2021.7.14日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、政府は2021年12月下旬に来年度予算を閣議決定するが、そのためには7月から各省庁が財務省に概算要求を提出して折衝しており、2022年1~3月に国会の予算委員会で行われる議論は殆ど反映されない。そして、予算委員会は、予算審議の場ではなく、首相・大臣を小さな政治とカネ問題で誹謗中傷する場と化している。また、左から2番目の図のように、米国や欧州は、複数年かけてグリーンイノベーションを行うため徹底的な投資をするが、日本は、グリーンイノベーションには単年度で思いつき程度の予算しか割かず、役に立たない景気対策ばかり行って無駄遣いしており、財源は赤字国債なのだ。さらに、さっさとワクチンや治療薬を承認して先に進めば、人流ばかり止めなくても新型コロナの流行は止まるのに、それはやらずに人流を止め、その保証として右から2番目の図のように大きな無駄遣いをしている。なお、1番右の図のように、EUが環境対策の緩い国の製品に対し国境炭素税を導入するのは正しく、これに反対している環境保護に消極的な日本のメディアは見識が疑われるのだ) イ)日本の財政支出 政府が6月に閣議決定した骨太の方針では、*2-2-1のように ①グリーン社会の実現 ②デジタル化の加速 ③少子化の克服 ④地方の活性化の4分野を今後の重点課題とし、2022年度予算で重点分野の予算を増やすために、財務省は各省庁の裁量的経費を前年度から10%減らし、削減額の3倍を特別枠で要求できるようにして成長分野に優先的に予算配分できる特別枠を設けるよう調整するとのことである。 そして、予算規模の大きい社会保障関係費は高齢化による自然増に抑え、医師の技術料等の診療報酬見直しなどでどれくらい伸びを圧縮できるかを今後の焦点にし(このように医療及び医療人材を粗末にしたのが今回の情けない結果を招いたのだが)、新型コロナに関連する予算は影響が現時点で見通しにくいため、金額を示さない(無限の)事項要求を認めるそうだ。 しかし、財務省のこのような硬直したやり方では、無駄な支出(長くは書かないが、本当は社会保障費ではない)を省いて効率的な財政運営を行うことはできない。そのため、国の財政状態及び収支の状況を一目瞭然に把握することができ、事業別の費用対効果を計測することが可能な複式簿記による公会計制度を導入して、支出の費用対効果やその財源(国民に賦課する税収だけでなく資産から得られる収入を含む)について、毎年度、見直しを行うべきなのだ。 なお、私は、日本も環境税(or炭素税)をかけ、そこから環境によい製品への投資を促す補助金を出して、民間の力をフル活用し、できるだけ早い時期に気候変動問題を片づけるべきで、それは可能である上に、日本にとってメリットが大きいと考えている。 ロ)欧米の財政支出と財源 米国や欧州は、*2-2-2のように、新型コロナ危機の出口を見据えて環境・デジタル分野で数十兆円規模の財政支出に動き始め、その財源として、米国は法人税率の引き上げや富裕層への課税強化策を表明し、EUは国境炭素税案を公表している。 なお、*2-2-3のように、EUの国境炭素調整措置案は、第三国にEU並みの気候変動政策を要求するもので、当然、中国・ロシアはじめ日米も対象になる。これを貿易摩擦に繋がるなどとと捉える思慮の浅い国は、国際基準作りでリーダーになる資格がない。 (3)エネルギーを変える  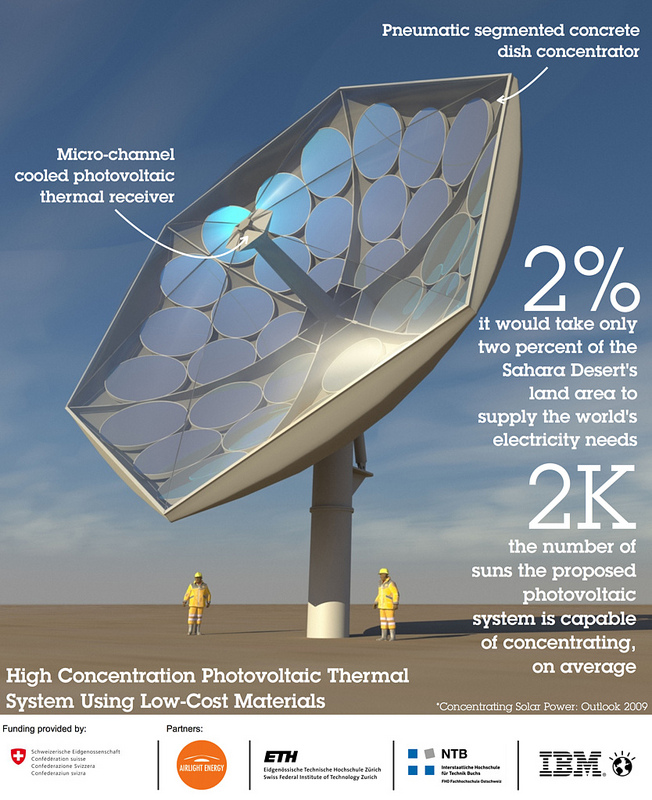   2017.6.27日経BP 2013.4.24IBM研究所等 2019.5.21日板 2021.3.23exite news (図の説明:1番左は、バスの駐車場屋根にとりつけた従来型の太陽光発電機で、左から2番目は、鏡を使って2000倍の面積から太陽光を集める太陽光発電機だ。また、右から2番目は、ビルの窓に取り付けた透明ガラスの太陽光発電機、1番右は、温室に使った透明膜の太陽光発電機で、いろいろな進化形があるので場所を選んで使えばよい。そして、これらの技術は、都会にとっても、農業地帯にとっても、また砂漠にとっても福音となるだろう) イ)2030年度の日本の電源構成は再エネのみにすべき 朝日新聞は社説で、*2-1-1のように、経産省が政府の次期エネルギー基本計画素案で新しい目標を示し、①2030年度の再エネ比率を36~38%とし ②再エネ最優先と明記したが ③原発比率は昨年の発電実績で4.3%に過ぎないのに20~22%に据え置いた と記載している。 高知新聞も、*2-1-2のように、④最安値とされた原子力のコストが上がり、太陽光が原子力を下回った ⑤改正地球温暖化対策推進法は2050年までの脱炭素社会の実現を明記し ⑥それには大規模な省エネとCO₂排出量の4割を占める電力部門の対応がKeyで ⑦太陽光など再エネの導入量を増加して主力電源にすべきで、火力は縮小へ国際的な圧力がある ⑧再エネ拡大には送電網の整備が必要だ と記載している。 また、愛媛新聞も社説で、*2-1-3のように、「太陽光『最安電力』 再生エネを促進し、原発は全廃を」と題して、⑨「最も安い電力」が原子力から太陽光に交代した ⑩原子力は発電コストの安さを強みとしてきたが、安全性への懸念・高レベル放射性廃棄物の最終処分・経済的な優位性も揺らいでいる ⑪国は太陽光など再エネの主力電源化を推し進め、原発の速やかな全廃に道筋を付けるべき と記載しており、全くそのとおりだ。 しかし、そもそも①④⑨⑩の「原発が最安コストの電源だった」というのも嘘だったことは確実で、使用済核燃料の最終処分費用や事故時の対策費、平時の公害対策費などのすべてを加えたコスト計算はしていなかったのだ。そのため、これらをすべて含めれば、1kwh当たり11 円台後半という試算も安く見積もりすぎであろう。 一方、太陽光は日本では30年時点で8円台前半~11円台後半と言われているが、現在は日射量の少ないドイツ・デンマークでも7~8円、日射量の多いチリ・メキシコは3~5円、アラブ首長国連邦は3円であるため、日本も次世代太陽光発電機器を住宅・ビルなどに地道に取り付けていけば相当の発電効果・節電効果が得られ、5円程度にはなるだろう。そして、水力・地熱・風力なども無駄にせず発電すれば、変動費0の低コストエネルギーを国内で自給できるのである。 そのため、⑦⑧⑪のように、再エネの主力電源化を進め、送電網を整備して、原発は速やかに全廃するのが無駄遣いをなくす前向きの投資となる。もちろん、火力は⑥⑦のように、CO₂を排出し、縮小へ国際的な圧力がある上、変動費が0ではなく高価な輸入燃料を使わなければならないため、2030年度の電源構成で41%も残す必要はないと思う。 なお、「原発はCO₂を排出しないから地球温暖化防止に資する電源だ」という主張もあるが、原発は平時でも温排水を排出して海を温めており、外国の分まで含めて数が多ければ、これも見過ごすことはできない。また、*2-3のように、中国広東省の台山原発で燃料棒が破損し、冷却材中の放射性物質の濃度が上昇したそうだが、放射性物質は平時でも取り除くことができないという理由でトリチウムを海に流しており、公害は地球温暖化だけでないことを考慮すれば、一日も早い廃止が必要なのである。 ロ)「現役世代からの医療費召し上げ」とはどういうことか (2)2)イ)の新型コロナで無差別に休業させた企業への助成金、景気対策のバラマキ、(3)の原発補助金のように、もっと賢い方法があるのに血税を無駄遣いしてきた例は多い。しかし、日経新聞はじめいくつかのメディアは、それらを批判するどころか推奨してきた。 その上で、*2-1-4のように、「現役世代からの医療費召し上げは限界だ」と題して、①75歳以上の後期高齢者が入る医療制度に対して現役世代の加入者を中心とする企業の健康保険組合などが負担する支援金が一段と膨張した ②全世代型社会保障を看板に掲げるなら医療費膨張を制御し ③不足する財源は現役世代からの召し上げだけに頼らず安定した税財源の確保に力を尽くす必要がある などと記載している。 しかし、①③の問題は、現役サラリーマンは協会けんぽ・組合健保・共済組合に加入し、退職すると国民健康保険に入り、75歳以上になると後期高齢者医療制度に入るという年齢で区切ったため医療需要が増える時には別の保険に入ることになる誤った区切り方が原因で発生している。 保険理論に沿った保険制度は、サラリーマンが加入する協会けんぽ・組合健保・共済組合に退職者も加入し続け、75歳以上になっても同じ保険に加入し続けるものである。そうすれば、応能負担で保険料を支払い、リスクの低い人がリスクの高い人を支え、生涯を通じて見れば損得なしの本来の保険制度となる。そして、その結果は、現役サラリーマンの負担はもっと増え、企業は定年年齢を延長して健康な支え手である期間を伸ばすようにするだろう。介護保険も同様で、これらを徹底したときに、②の全世代型社会保障になるのだ。 にもかかわらず、「高齢者と同じ保険に入り続けるのは嫌だ」「現役世代が高齢者の保険に支援金を払うのも嫌だ」「医療費に消費税投入を増やせ」「高齢者は世代内互助せよ」と言うのなら、それはわがままにすぎない。「後期高齢者人口が増加する」のは前からわかっていたことで、医薬品・医療機器などのイノベーションは早く治す方向に起こるため、医療費削減に資する筈だ。また、新薬の値段が高いのは、普及が遅いため単価が高いか、厚労省が言い値で機材や薬品を買っているか が理由で、いずれにしても改善すべき点は高齢者ではなく厚労省側にある。 なお、2006年6月に老人保健法が改正され、2008年4月から後期高齢者医療制度が創設されたが、その原案を厚労省の担当者が自民党内の厚労部会に持ってきた時、私は「保険の原理に反する」と言って反対したが、その時の担当者の答えは、「そのかわり、患者負担以外は医療保険者からの拠出金と公費(税金)で賄うから」というものだった。私は、「そういう意図的な割合では、不公平になる」と言ったのだが、現在、後期高齢者医療制度の財源は、患者の自己負担分を除いて現役世代からの支援金(国保や被用者保険者からの負担)4割・公費(国・都道府県・区市町村の負担)5割・被保険者からの保険料1割で構成されているのである。 また、「医療現場で検査の重複を減らせ」というのも、単純すぎる。その理由は、独立した病院で「Second Opinion」を取りたい場合もあるからで、デジタル化した検査結果記録を患者自身が簡単に持ち運びできるようにするのはよいものの、別の病院で二重に検査することも当然あってしかるべきだからである。 このように、社会保障を疎かにしてきたことが、実需であり成長分野でもある産業の伸びを抑えてきた。そして、これにより、本来なら上昇する潜在力のあったGDP成長率も上昇せず、国民は豊かになるどころか貧しくなっているのだ。 (4)機械を変える ← 先端技術の使用 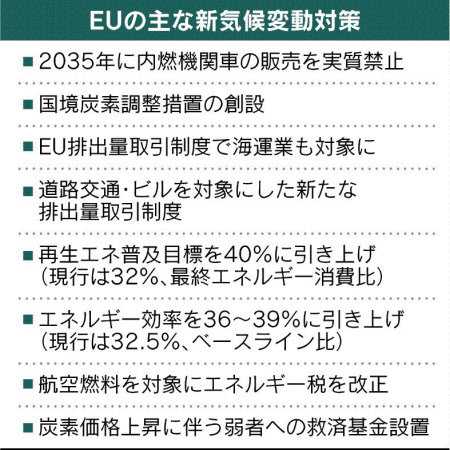 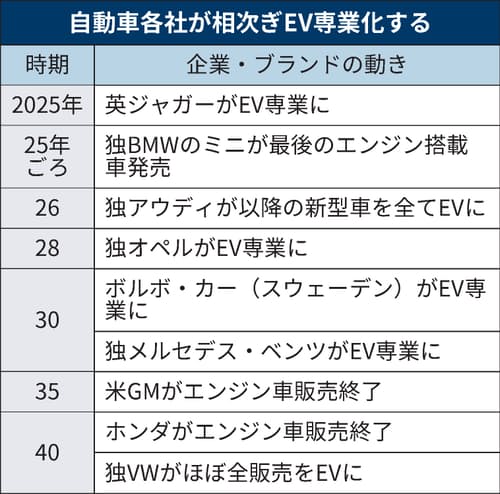   2021.7.15日経新聞 2021.7.22日経新聞 2021.1.26朝日新聞 2021.4.16 Business Insider Deutschland (図の説明:1番左の図は、EUの主な気候変動対策で、左から2番目の図は、自動車各社のEV専業化スケジュールだ。また、右から2番目の図は、ボルボのEVで、1番右の図は、メルセデス・ベンツのEVだ) 1)EVへの移行 イ)欧米のケース 欧州委員会は、*3-1のように、7月14日、温暖化ガス排出大幅削減に向け、①2050年の温暖化ガス排出実質0という目標の中間になる2030年までに、1990年比で55%減らす目標を実現するため ②ガソリン・ディーゼル・ハイブリッド等の内燃機関車の販売を2035年に事実上禁止し ③自動車からのCO₂排出を2035年までに100%減らすよう定め ④環境規制の緩い国からの輸入品に国境炭素調整措置を2023年にも暫定導入し ⑤自動車及びビルの暖房用燃料に新しい排出量取引制度を設けてCO₂排出の炭素価格を上乗せするそうで、Perfectな案である。 これを受けて、*3-2-2のように、ボルボは製品ラインナップの完全な電気自動車(EV)化へ向けた技術ロードマップを発表し、⑥実走行距離1000kmのEVを目指し ⑦バッテリーパックをクルマのフロアに統合しセル構造を利用して車両全体の剛性(安全性)を高め ⑧充電時間もバッテリー技術の向上とソフトウエア・急速充電技術の継続的改善によって2020年代半ばまでに現在の半分にし ⑨バッテリーセルを100%再エネで生産することを目指し ⑩使用済バッテリーのリユースやリサイクルも計画し ⑪EVのエネルギーインフラでの活用も計画している とのことである。 さらに、独自動車大手ダイムラーのメルセデス・ベンツは、2021年7月22日、*3-2-3のように、⑫販売する新車を2030年にもすべてEVにすると発表し ⑬8つの電池セル工場を新設するなど、2030年までに400億ユーロ(約5兆2000億円)をEVに投資し ⑭EVに不可欠な車載電池では専業メーカーと共同で世界に8つの大型工場を設け ⑮2022年に満充電で航続距離1000km以上の新型車を発表し ⑯EVファーストからEVオンリーに踏み込む こととし、このほか独アウディや英ジャガー等の高級車ブランドもEV専業への転身を発表しているそうだ。 このように、政府が政策の方向性を明確にすると、民間企業も戦略を立てやすく、そのための技術開発や投資を行えるのだが、さすがボルボは徹底していてスマートであり、ベンツは世界展開が早く、日本だけ置いてきぼりになった感がある。日本は屁理屈が多すぎ、競争もなさすぎるため、ボルボやベンツの工場を誘致してはどうか? ロ)中韓のケース これまで日本車が圧倒的なシェアを占めていた東南アジアの自動車市場でも、*3-2-1のように、現地政府のEV振興策に呼応して中国・韓国のメーカーがEVで先手を取ろうとしており、タイでは中国の長城汽車が、インドネシアでは韓国の現代自動車が現地生産に乗り出そうとしているそうだ。 タイは、現在は日本車の生産・販売シェアが約9割に達するが、大半をガソリン車が占め、長城汽車は2020年にタイから撤退した米GMの工場を取得して参入し、3年間でEVを含む9車種の電動車を投入するとのことである。 タイ、インドネシア両政府に共通するのは、動きの鈍い日本車へのいらだちで、タイではEV普及目標の引き上げを検討する政府に対し、バンコク日本人商工会議所自動車部会が「全体でのゼロエミッションを考えて段階的に進めるべきだ」として慎重な議論を求め、インドネシアも同様だということだが、日本国内でもよく言われるこの屁理屈は、どちらから先でもよいが解決すべき問題を先送りするために使われている見識の低いものである。 ハ)日本のケース 日本車は、*3-2-1のように、東南アジアで1960年代から現地組み立てを始め、主要国の新車販売に占めるシェアが約8割に達しているが、いつまでもガソリン・エンジンに執着した結果、EVでゲームチェンジが起こって中国勢が小型車・商用車で攻勢をかけているそうだ。 そのため、*3-2-4に、2021年7月21日、スズキ・ダイハツがトヨタ・日野・いすゞの商用車連合に合流すると発表し、トヨタにとって電動化など脱炭素における商用車分野協業の総仕上げになると記載されているが、商用車の技術開発会社に軽自動車を得意とする2社が加わって大型から小型まで商用車を全方位で開発する体制が整うのはよいものの、すべてがトヨタ頼みでは多様性がなくなりそうである。 地方では、狭い道でも通りやすくて自転車代わりに乗りこなせるため、軽自動車が初心者用や主婦用として購入されるケースが多い。ただし、安い価格で脱炭素を実現してもらいたいのは当然だが、ダサくてもよいわけではないため、VWやフィアットを選ぶ人もいる。つまり、日本車は、企画が洗練されておらず、(馬鹿の一つ覚えで)工夫が足りない感があるのだ。 2)有望な新技術を選ぶ脱炭素ファンドができた このような中、*3-4のように、企業の脱炭素化に向けた世界最大規模の枠組みとして、米投資ファンドTPGキャピタルが気候変動対策に特化したファンドを組成し、アップル・グーグル・ボーイングなどの米国を代表する企業20社以上と日本の三井住友銀行が出資して、当初の運用規模が約54億ドル(約6000億円)になるそうだ。 そして、このファンドは、①脱炭素化に向けた技術を有するベンチャー企業に資金を投じ ②新技術開発を促進し ③2021年中に出資額を70億ドル程度まで引き上げ、④三井住友銀行は出資先への融資や新規株式公開の支援などで連携し、また、⑤気候変動対策を巡っては米アップルが2億ドル規模の森林再生ファンドを既に立ち上げており ⑥アルファベットは環境関連に使途を絞った社債「サステナビリティボンド」の発行を決めている とのことである。 このほか、脱炭素化を巡っては米ブラックロックが新興国向けインフラファンドを立ち上げ、国際協力銀行・第一生命・三菱UFJ銀行などが出資を決めて、ファンド総額5億ドル規模を目指しており、このように、金融の視点から気候変動問題に対応し、脱炭素化の技術を保有する企業を探して育てるのはよい考えだと思う。 3)日本に国際ルール作成能力があるのか 日経新聞は、*3-2-5のように、EUが2021年4月に公表した「タクソノミー(事業が持続可能と判定される基準)」について、「①『閻魔大王』のように企業が選別される」「②環境に優しいとされるプラグインハイブリッド車はEVへの移行期に伸びると見込まれていたが、2026年以降は新車で売りにくくなる」「③天然ガスは石炭よりCO2排出量が4割少なく、石炭から再生エネへの移行期の繋ぎ役になるとされてきたが、欧州投資銀行のホイヤー総裁は2021年末までにガスへの投融資から手を引く方針を表明した」等と記載している。 しかし、②③は繋ぎ役でしかなく、繋ぎ役が出演できるのは主役が出てくるまでの時間でしかないため、もともと予想されていたことで、繋ぎ役で凌いでいる間に主役を作らなければならなかったのだ。また、天然ガスについては、燃料として使わなくても化学工業原料として使える上、燃料としてのガスならオリンピックの聖火と同じく再エネ由来のH₂を使えばよいだろう。 つまり、「完全にはできないから妥協する」という地点から出発すると何も解決できないため、「日本は欧米主導のルールを受け入れることが多かったが、ルールをつくる側に回れるかどうかは国益を左右する」と言いたいのなら、我田引水によって歪んでいない合理的なルールを作って見せる必要がある。何故なら、これまでは、日本人の私が見ても、先進的かつ合理的で世界のリーダーになってもらいたいのは、欧州のルールの方だったからだ。 ・・参考資料・・ <洪水の多発と地球温暖化の関係> *1-1-1:https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/07/1201300.php (Newsweek、Reuters 2021年7月17日) ドイツ・ベルギー洪水の死者120人超に、行方不明約1300人 欧州西部を襲った記録的な豪雨で河川の氾濫により洪水が発生し、16日時点でドイツ西部などで約1300人の安否が確認されていない。水位の上昇が続き、一部地域で通信が途絶える中、ドイツとベルギー両国の死者は120人を超えた。ドイツのラインラント・プファルツ州とノルトライン・ウェストファーレン州に加え、ベルギーとオランダで、河川の氾濫で住宅が押し流されるなど大規模な被害が発生。これまでにドイツだけでも103人の死亡が確認された。このうち12人は、夜間に鉄砲水に襲われたケルン南方のジンツィッヒにある障がい者施設の入所者だった。地元メディアは、洪水による家屋倒壊が増えているため、犠牲者数が増加する恐れがあると報道。ベルギーではこれまでに少なくとも20人の死亡が確認され、安否不明は20人となっている。ドイツでは16日時点で約11万4000世帯が停電。洪水に見舞われている一部の地域では携帯電話網が機能停止に陥り、被災者と連絡が取れない状態になっている。ラインラント・プファルツ州では、ケルン南方のアールワイラー地区で約1300人の安否が未確認。ケルン当局の報道官は「ネットワークが完全に遮断され、インフラは完全に破壊された。病院は患者を受け入れられなくなっている」と述べた。ドイツ政府は700人を超える軍隊を動員し、救援にあたっている。独政府報道官によると、メルケル首相は次期首相候補であるキリスト教民主同盟(CDU)のラシェット党首から捜索や救助活動を巡る状況報告を受け、近く被災地を訪問する予定という。ARD(ドイツ公共放送連盟)は、メルケル首相が18日にシュルトを訪れると報じた。当局は、ダムが決壊すれば下流地域が一段の洪水に見舞われる恐れがあるとして、放流を試みている。ドイツ西部シュタインバッハタール・ダムは昨晩にかけて決壊の恐れが高まったため、下流地域で約4500人が避難した。気象学者は、気候変動の影響でジェットストリームの流れが変わったために今回の豪雨が引き起こされたと指摘。欧州委員会のフォンデアライエン委員長も、今回の洪水の規模を踏まえると気候変動が影響していることは明らかだとし、迅速に対応する必要があるとの考えを示した。 *1-1-2:https://digital.asahi.com/articles/ASP7P4142P7PUHBI00V.html (朝日新聞 2021年7月21日) 地下鉄浸水12人死亡 中国・河南「千年に1度の暴雨」 中国・河南省で17日以降、記録的な大雨が続き、省都の鄭州市で地下鉄が浸水するなどして21日までに少なくとも計16人が死亡、10万人が避難した。鄭州の気象局は「1千年に1度の暴雨」だとして、警戒を呼びかけている。習近平(シーチンピン)国家主席は同日、被災者の救済に取り組むよう関係部門に対して重要指示を出した。中国メディアによると、鄭州市では、20日午後4~5時の1時間で201・9ミリの雨が降り、中国全土での観測史上最大を記録した。17日以降の3日間では、鄭州市の年間雨量にほぼ匹敵する617ミリの雨量を計測したという。地元メディアによると、鄭州市では20日午後6時ごろ、地下鉄構内への浸水を防ぐ遮水壁を越えて雨水が線路にまで流れ込んだ。市内の地下鉄は全線が運行停止となり500人余りが避難したが、逃げ遅れた12人が死亡したという。ほかに5人がけがを追った。中国のSNSには、鄭州市内の地下鉄車内で乗客が胸のあたりまで水につかったまま取り残されている様子を映した動画も投稿されている。このほか、鄭州市内では家屋の倒壊などによって4人が死亡した。 *1-1-3:https://www.bbc.com/japanese/57911006 (BBC 2021年7月21日) 中国・河南省で記録的豪雨 12人死亡、1万人以上が避難 中国中部・河南省は、今月16日から続く記録的豪雨で、深刻な洪水被害に見舞われている。駅や道路が冠水し、住民1万人以上が避難を余儀なくされている。当局によると、鄭州市でこれまでに少なくとも12人が死亡した。また、主要道路が閉鎖され、空の便が欠航するなど、10都市以上に被害の影響が出ている。人口約9400万人の河南省には最高レベルの気象警報が発令されている。洪水発生の原因は複合的だが、気候変動による気温上昇は激しい降雨のきっかけになる。 ●ダム決壊の恐れも ソーシャルメディアでは、道路全体が水没している様子が画像から確認できる。水の流れは速く、車やがれきが漂流しているのがわかる。こうした中、河南省のダムが決壊する恐れが出ている。当局によると、洛陽市のダムに20メートルほどの亀裂が生じている。同地域には兵士が配備され、軍は声明で「いつ決壊してもおかしくない」と警告した。ツイッターには、鄭州市で浸水した地下鉄の車両に乗っていた乗客が、肩のあたりまで水に浸かっている映像が投稿されている。現実の状況を撮影したものなのかは不明。救助隊がロープを使って人々を安全な場所に引き上げる様子や、列車の座席に立って水に浸からないようにする人の姿などが確認できる。車両内に何人が閉じ込められているのかは不明だが、これまでに数百人が救助されたとの報告がある。シャオペイと名乗る人物は、中国のソーシャルメディア「微博(ウェイボ)」に助けを求めるメッセージを投稿した。「車両内の水が自分の胸にまで達している。もう声も出ません」。消防局はその後、この人物が救助されたと明らかにした。 ●3日間で1年分の雨量 「生まれてからずっと鄭州市で暮らしているが、こんな大雨は経験したことがない」と、56歳のレストラン経営者はAP通信に語った。鄭州市ではこの3日間で、通常の1年分の雨量に匹敵する雨が降ったと報じられている。同地域では少なくとも今後24時間は土砂降りの雨が続くと予想されている。 *1-2-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/794b549b846d24273ef57f58173d01c107872ca7 (Yahoo 2021/5/1) 世界の山間部の氷河が、2050年までに“完全消失”する:衝撃の研究結果が意味すること これまでに氷河を散策した経験がないなら、近いうちに行きたくなるかもしれない。標高の高い場所にある世界の氷河が、科学者が想定していたよりも速く溶けていることが判明したのだ。すでに2015年以降だけで年間3,000億トン近くの氷が失われている。4月28日に発表された包括的な研究によると、このままのペースで融解が続けば、今世紀半ばには多くの氷河が完全に失われる可能性があるという。このほどカナダとフランス、スイス、ノルウェーの研究者たちが、米航空宇宙局(NASA)の衛星「Terra(テラ)」に搭載された特殊なカメラで撮影された20年分の衛星写真をまとめた。このカメラは「ASTER(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer=アスター)」と呼ばれる機器で、世界各地の21万カ所以上の氷河の写真を撮影している。氷河の表面の特徴を立体的に捉えるために、撮影にはふたつのレンズが使用された。今回の研究にはグリーンランドと南極の大規模な氷床は含まれていないが、こちらは別の科学者のチームが調査している。今回の研究は『Nature』に掲載されたもので、2000年から04年にかけて年間2,270億メートルトンの氷河が失われたことが判明した。ところが15~19年には、溶ける量が年間2,980億トンまで増えていたことも明らかになっている。こうした変化の原因として論文では、温暖化や降水量の増加を挙げている。すべてを合わせると、溶けて河川や海に注ぎ込んだ水の量は、過去20年間に観測された海面上昇分の約5分の1に相当するという。 ●人々の生活を脅かす現象 問題は海面上昇にとどまらないが、重大な問題であることには変わりない。インドネシアやバングラデシュ、パナマ、オランダといった沿岸国や米国の一部の住民の生活が脅かされているからだ。また内陸地域の一部では、何百万人もの人が雪解け水からきれいな水を得ている。降雪量が少ないときは、長年にわたって氷河が予備の水源になっているのだ。そうした状況はアンデス山脈やヒマラヤ山脈、アラスカ州の一部に特に見られている。「氷河は地球全体の多くの場所に冷涼で豊富な水を提供しています」と、ノーザンブリティッシュコロンビア大学の地球科学教授で今回の論文執筆者のひとりであるブライアン・メヌーノスは言う。「これらの氷河がなくなると、そうしたバッファとしての機能が失われてしまいます」。これまでの氷河溶解に関する研究では、空間的にも時間的にもほとんど計測が実施されていなかった。このため氷河が実際にどれほど後退しているのかについては、不明瞭な点があったという。それが詳細な衛星写真を使うことで、「わたしたちの推計では不明確な部分を大幅に減らすことができました」と、メヌーノスは言う。21万1,000カ所すべての氷河のデータを処理するために、ノーザンブリティッシュコロンビア大学のスーパーコンピューター1台を1年間にわたってほぼフル稼働させる必要があった。 ●厳しい未来への警鐘 今回の研究結果は厳しい未来に警鐘を鳴らしているのだと、ブリストル大学の地理学教授のジョナサン・バンバー(今回の研究には参加していない)は言う。「これは21世紀の世界の氷河の質量損失に関する最も包括的、徹底的かつ詳細な評価です。かなり詳細な研究結果のおかげで、世界全体の個々の氷河の変化を初めて知ることができました」と、バンバーは説明する。現在の傾向が続けば、標高の低い山地の一部では2050年までに氷河が完全に失われることが分析で示されていると、バンバーは言う。「研究自体やその成果は素晴らしいものですが、最上段に掲げられたメッセージはとても悲観的です。氷河は消えゆく運命にあり、水源や自然災害、海面上昇、観光、そして地域の生活に深刻な影響を与えているのです」。論文の筆者たちも、この評価と同じ考えだ。ノーザンブリティッシュコロンビア大学のメヌーノスは、今世紀半ばまでにカスケード山脈やモンタナ州のグレイシャー国立公園などの場所から氷が完全になくなるだろうと指摘している。「見られるうちに見ておいたほうがいいでしょうね」と、メヌーノスは促す。急速に溶ける氷河が生み出す水は、環境災害を引き起こすことがある。例えば今年2月には、融解が進んでいたヒマラヤの氷河が北インドで崩れ、水の壁が狭い渓谷を下ってふたつのダムに到達して200人が亡くなる事故が起きた。国連の気候変動に関する政府間パネルが18年に発表した報告書は、そうした凄まじい洪水や地滑りが高山で起きやすくなっている原因は、温暖な気候にあると指摘している。「氷河の後退や永久凍土の融解によって山の斜面の安定が崩れ、氷河湖の数や面積が増えると予測される」と、報告書では結論づけている。「その結果、地滑りや洪水、水が滝状に流れる現象が、かつてそうした現象がなかった場所でも起きるだろう」 ●氷河の損失の半数が北米に カナダと欧州の研究者たちが執筆した今回の論文は、アラスカやカナダ西部、米国で溶けつつある氷河が、世界全体で加速する氷河の質量損失の半分近くを占めていることも突き止めている。「アラスカ州の南東部は心配な場所です。ここ10年間で途方もない変化が起きています」と、メヌーノスは指摘する。アラスカ州では融解する氷が原因で地震の規模が大きくなっている。3月に『Geophysical Research』に掲載されたアラスカ大学フェアバンクス校の研究者たちの論文によると、氷河の下にある地面が隆起して圧力が解放され、付近の断層にかかる力に影響を及ぼしているのだという。全体としては悪いニュースではあるが、研究チームが20年間の衛星写真からまとめたデータの量に専門家は感銘を受けている。「本当に素晴らしい成果だと思いました」と、NASAゴダード宇宙飛行センターの雪氷圏科学研究所所長のトム・ノイマンは言う。「時系列の威力がはっきりと示されています。多くの場合、こうした調査には5~7年単位の年月がかかります。研究チームがいまでも優れたデータを集めているという事実は驚きに値します。そうしたデータは史上初の成果を得る上で大きな力になったのです」。ノイマンは、NASAの地球観測衛星「ICESat-2」のミッションのプロジェクトサイエンティストを務めている。ICESat-2は、地球の極地にレーザーを反射させて氷河や極地の氷床の損失を計測し、世界の海面上昇への影響を監視する。「20年は続けたいと思います。そしていつの日か、今回の論文のようなものを執筆できればいいですね」と、ノイマンは語る。 *1-2-2:https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/210104/cpd2101040638001-n1.htm (産経BZ 2021.1.4) 2020年は日本も世界も平均気温が史上最高 豪雨、異常高温相次ぐ 2020年の世界と日本の平均気温が、観測が始まった19世紀末以降、最高となる見込みであることが気象庁の調査で分かった。気温上昇に伴い、各地で30年に一度の規模の高温や大雨などが頻発。国内も九州で豪雨災害が発生するなどした。地球温暖化も寄与したとみられ、2020年は新型コロナウイルスだけでなく、気象も人類に牙を向いた年として記憶されそうだ。一方、今年はこうした傾向がやや緩和されるとの見方もある。気象庁によると、世界の1~11月の平均気温は平年(1981~2020年の平均)から0・47度上がり、16年1~11月の0・45度を抜いて1891年以降、歴代1位となった。100年で0・75度上昇したことになる。太平洋南東側やアフリカ大陸の南東側の海を除くほとんどの地域で、平年より平均気温が高くなった。日本の平均気温も1898年の観測開始以来、過去最高となり、平年より1・07度高かった。100年あたりでは1・27度上昇した。各地で異常高温もみられ、気象庁がまとめた主な現象だけでも世界の11地域で発生。シベリアの一部地域では気温が平年より14・2度高くなり、永久凍土まで解ける地域もあった。気象庁のまとめでは、8~9月に米国西部で森林火災が発生するなど、2020年は8件の気象災害が発生。うち6件が大雨、1件がハリケーンによる被害だった。6~10月にインドなどを含む南アジアで発生した大雨で、周辺では2700人以上が亡くなった。国内では7月に九州で長期にわたる豪雨災害が発生したが、この雨をもたらした暖かく湿った空気と長く停滞した梅雨前線は、九州を襲う前の6月中旬以降、中国の長江の中・下流域でも活動を活発化させ、270人以上が死亡・行方不明となる豪雨を発生させた。気象庁異常気象情報センターの担当者は「20年が暑かった原因は、温室効果ガスによる地球温暖化に加えて複数ある」と分析する。20年初頭は北極にある寒気が南に降りてきにくい大気の状態だったことから、暖冬が進行。さらに19年ごろからインド洋の海面水温が平年より高まったことが地球全体に広がり、年間を通してさらなる温暖化に寄与した可能性があるという。一方、20年夏以降は太平洋の中部・東部の海面水温が平年より低くなるラニーニャ現象が発生。ラニーニャ現象が発生した年は日本列島は寒くなる傾向にあるといい、20年末から21年にかけては一転して寒い冬となるという。気象庁と同様に地球温暖化を監視している英国気象庁によると、21年の世界の気温は15年以降の数年間よりはラニーニャ現象の影響で少し涼しくなるものの、1850~1900年の平均よりは約1度高く、長期的な温暖化傾向に変わりはないとみられる。 *1-2-3:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000044799.html(パシフィック・コミュニケーションズより抜粋 2020年3月23日)昭和から令和で気温1.4度上昇! ■平成の31年間は1989年の観測史上、もっとも日本の気温が上昇した期間。 昭和元年から令和元年(1926~2019年)の94年間で、日本の平均気温は1.4度上昇。 ■世界全体で見ても平均気温は上昇傾向。2019年の世界の年平均気温は史上2番目の高さで、15~19年の5年間、10~19年の10年間の平均気温はいずれも過去最高。 ■気象庁発表によると、2020年3月~5月の気温は全国的に高く、夏(6月~8月)の気温も全国的に平年並みか、高め。昨年より早い時期から真夏の太陽が照り付けると想定される。 ■日本全体で進む高気温化 都市化による影響が小さい全国15地点(※)の年平均気温偏差(濃い折れ線)および全国13地点*1の猛暑日*2の平均年間日数(薄い折れ線)の推移。 *1:全国15地点:網走*,根室,寿都,山形,石巻,伏木,飯田*,銚子,境,浜田,彦根,宮崎*,多度津,名瀬,石垣島(全国13地点:全国15地点のうち、*以外の地点) ※都市部ではヒートアイランド現象による気温上昇が別途加味されるため、日本全体の気温推移を確認する場合は、都市部を除いた地点を全国まんべんなく抽出している。 *2:日最高気温が35度以上の日 日本気象協会によると、昭和元年から令和元年(1926~2019年)の94年間で、日本の平均気温が1.4度上昇したことがわかりました。2015年7月に発表された研究によると、大気中の二酸化炭素レベルが現在とほぼ同じだった300万年前の気温は、現在よりも2℃から3℃高く、海抜は最低でも6メートル高かったことがわかっています(※)。この内容から単純に計算すると、気温が1度上昇するごとに海面は2mほど高くなることから、気温1.4度の上昇がどれほど大きな変化かわかるでしょう。中でも、平成以降の約30年は気温が一段と高くなっており、統計的にも平成の30年は1898年の統計開始以降、最も暑い30年間だったと言うことができます。また、猛暑日の出現日数についても1920年から10年刻みで日数を確認したところ、平成以降急激に猛暑日が増えていることがわかりました。特に2010年代の10年間は1980年代と比較すると猛暑日の日数が4.6倍にも及ぶほか、1926年以降で猛暑日の出現日数が多かった年をランキングにしてみると、上位5カ年のうち4カ年が平成元年以降に集中するなど、直近30年の気温の高さが伺えます。 ※Dutton et al. 2015 https://science.sciencemag.org/content/349/6244/aaa4019 ■都市部でも大きな変化が 横浜・京都・福岡など都市部では全国平均よりも大きく気温が上昇。年間の猛暑日数に関しても明確な増加傾向にあることが分かりました。一般的に、都市域では建築物や人工排熱などで気温が下がりにくいヒートアイランド現象の影響を受けやすいため、その効果が全国平均よりも顕著な気温上昇傾向として表れた可能性があります。 ■令和を迎えた昨年、日本全体の年平均気温の最高を更新。2020も高気温の見通し 2020年1月、気象庁は、2019年の日本の年平均気温(基準値との差:+0.92℃)が、1898年の統計開始以来で最も高い値であると発表。加えて、世界気象機関(WMO)は、2019年の世界の年平均気温(基準値との差)が史上2番目の高さであり、15~19年の5年間、10~19年の10年間の平均気温はいずれも過去最高であると発表するなど、日本だけでなく世界全体で見ても多くの研究で高気温化が認められています。日本全体の気温上昇は、地球温暖化の影響と自然変動の影響を受けていると考えられ、今後ますます注意が必要です。また、気象庁が20 年2月25日に発表した、向こう3ヶ月(3月~5月)と今年夏(6月~8月)の天候見通しによると、今年の夏の気温も全国的に平年並みか高めになるとのことです。また、梅雨時期の降水量はほぼ平年並みで、その後は高気圧に覆われて晴れる日が多くなると予想。昨年は7月下旬まで雨が続き、気温が上がらなかったことを考えると、今年は昨年より早い時期から真夏の太陽が照り付けるでしょう。この結果を受けて、日本気象協会は、今年は本格的な夏を待たずに、いち早く猛暑対策を行う必要があるとしています。(以下、略) <政策の方針と予算> *2-1-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14983912.html (朝日新聞社説 2021年7月22日) 30年電源構成 原発維持は理解できぬ 2050年に脱炭素社会を実現するために、30年度にどんな電源構成をめざすべきか。経済産業省がきのう、政府の次期エネルギー基本計画の素案で新しい目標を示した。再生可能エネルギーを「最優先」と明記し、30年度の再エネ比率を36~38%と現行目標より14ポイント高くした。再エネを主力電源と明確に位置づけたことは評価できる。一方、理解できないのが、原子力の比率を20~22%に据え置いたことだ。国際エネルギー機関(IEA)が集計した昨年の国内の発電実績の速報では、原発の割合は4・3%に過ぎない。素案が示す原発比率の達成には、新規制基準で審査中の11基を含む国内の原発27基を、8割の高稼働率で運転させる必要がある。しかし現実には、福島の事故以来、国民の不信感が根強く、再稼働は進んでいない。コストが安い電源だとの主張も根拠が揺らいでいる。経産省が今月まとめた電源別の発電コスト試算の最新結果では、30年に新設する原発は1キロワット時当たり11円台後半以上。04年には5・9円とされていたが、安全対策費用が増え続けて上昇傾向が止まらない。30年時点で8円台前半~11円台後半と最も安くなる見通しの事業用太陽光など、コスト低下が進む再エネとは対照的だ。素案が「可能な限り原発依存度を低減」としながら、非現実的な目標を掲げざるを得ないのは、30年度の温室効果ガス排出を13年度より46%減らす新しい政府目標との整合性を取る必要があるからだろう。それだけ無理をしても、30年度の電源構成の目標で最も大きいのは火力だ。昨年実績の7割からは下がる見通しだが、依然、41%もある。そもそも、8年半後の電源構成を現状から大きく組み替えることには限界がある。発電施設の建設や送電システムの改革には時間がかかるからだ。まずやるべきは、脱炭素社会実現をめざす50年のあるべき電源構成の姿を示すことではないか。主役は現時点では、再エネしか考えられない。昨年の発電実績で21・7%と、現行の30年目標(22~24%)に匹敵する水準に育った再エネの潜在力を、できる限り生かすのが得策だ。30年度の数字は、50年の目標に向けての足取りを検証するための中間指標との位置づけで考え直すのが望ましい。太陽光や風力など電源ごとに具体的な施策を挙げた長期の実行計画をまとめ、検証と修正を重ねながら柔軟に進めていく。そんな態勢を整えることこそ、脱炭素社会への早道になるだろう。 *2-1-2:https://www.kochinews.co.jp/article/471271/ (高知新聞 2021.7.14) 再生エネの優位性を磨け 2030年時点の各電源の発電コストについて経済産業省が示した新たな試算は、太陽光が最安になった。これまで最も安いとされた原子力のコストが上昇し、太陽光は初めて原子力を下回った。原子力は東京電力福島第1原発事故を受けた規制強化に伴い、安全対策費が膨らんだ。このため前回15年の試算より1割程度上がった。改正地球温暖化対策推進法は、50年までの脱炭素社会の実現を明記している。そのためには、大規模な省エネルギーとともに、二酸化炭素(CO2)排出量の4割を占める電力部門の対応が鍵を握る。中期目標では、30年度の排出量を13年度比で46%削減する。取り組みの加速が求められている。太陽光など再生可能エネルギーは導入量の増加で主力電源になると見込まれる。今夏をめどに改定する「エネルギー基本計画」に合わせた電源構成の新目標は、現行より引き上げる方向で検討されている。火力は縮小へ国際的な圧力がある。そこで、原子力は目標を維持するとの見方が出ている。CO2を排出しない再生エネと原発の電源割合を引き上げることで補うことをもくろむ。発電コストを巡っても、経産省は原子力の安さを強みと位置付けてきた。だが、その見方も安全性とともに揺らいでしまった。災害などを想定した事故防止対策のコスト増加が見込まれる。第1原発の廃炉で最難関とされる溶融核燃料(デブリ)の取り出し費用などは含んでおらず、コストはさらに上昇することは間違いない。この試算は発電設備を新たに更地に建設して運転した場合を前提としている。土地取得の費用などは含まず、利用状況などで数値は変動するとはいえ、運転開始から40年を過ぎた原発が再稼働する中、新増設は厳しい状況だ。石炭火力はCO2排出抑制の対策費がかさむため、上昇を見込む。一方、太陽光の発電コストは、事業用、住宅向けとも下がるとした。世界的に普及が進むことでパネルなどの価格が低下するとみる。陸上風力や液化天然ガス(LNG)火力なども、発電コストを最も安く見込んだ場合の試算値では、原子力の発電コストを下回った。ただし、再生エネへの期待を膨らませても、導入は簡単に拡大するものではない。送電網の整備費などは今回の試算に含まれていない。天候に左右される発電条件など、乗り越えなければならない課題も多い。来年4月施行予定の改正温対法は、太陽光や風力発電などの促進区域を市町村が設定する制度を創設する。手続きの簡素化や資金面での優遇を想定している。だが、生態系や景観の悪化を懸念する住民らの反対運動も目立つようになった。国は土砂災害などが想定される地域は指定対象から除外する方針のようだが、地域の混乱を誘発するようでは本末転倒だ。再生エネの優位性を生かすように、きめ細やかな対応が求められる。 *2-1-3:https://www.ehime-np.co.jp/article/news202107150013 (愛媛新聞社説 2021年7月15日) 太陽光「最安電力」 再生エネを促進し原発は全廃を 経済産業省が2030年時点での発電コストの試算を示し、「最も安い電力」が原子力から太陽光に交代した。太陽光の発電コストが原子力を下回るのは初めてとなる。原子力は発電コストの安さを強みとしてきた。だが、安全性への懸念や、高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分などの問題に加え、経済的な優位性も揺らぎ、存在意義は薄れる一方となっている。国は太陽光など再生可能エネルギーの主力電源化を推し進めるとともに、原発の速やかな全廃に道筋を付けるべきだ。試算は、発電設備を更地に新設して運転するのが前提となっている。原子力の発電コストは04年試算で1キロワット時当たり5・9円だったが、11年の東京電力福島第1原発事故を機に上昇。前回15年は10・3円以上、今回は11円台後半以上だった。前回試算と比べると、1基当たり平均1千億円と見積もった安全対策費が今回は2千億円になった。福島の事故を巡る廃炉や賠償、除染などの見積額も12兆2千億円からほぼ倍増。これらが発電コストを押し上げている。廃炉で最難関の溶融核燃料取り出しや、除染土壌の最終処分の費用は試算に含まれておらず、原発のコストが上振れするのは避けられないだろう。二酸化炭素(CO2)排出量が多い石炭火力も排出抑制対策に費用がかかり、発電コストの上昇が見込まれる。地球温暖化の元凶でもあり、原発と同様に一刻も早く廃止すべきだ。一方、太陽光は世界的な普及拡大でパネルなどの価格が低下し、発電コストが下がる。最安の計算値は、事業用が1キロワット時当たり8円台前半、住宅用が9円台後半。陸上風力も原子力を下回る見通しという。今年5月、「50年までの脱炭素社会実現」を明記した改正地球温暖化対策推進法が成立。政府は30年度の温室効果ガス排出量を13年度比で46%減らす目標を掲げる。達成に向け、省エネと合わせ、より安全で安価な再生エネの普及拡大に注力するのが合理的といえる。ただ、課題も残る。太陽光や風力発電の適地は全国に分散しており、大消費地への送電網拡張が欠かせない。天候の変化に備えた蓄電池の整備なども必要になる。こうした費用は試算に入っておらず、コストを抑える取り組みが重要だ。大規模施設を設置するための森林伐採が土砂災害リスクを高めるとの懸念もある。水質や景観への悪影響を理由とした反対運動も各地で起きている。国は地元に対応を丸投げしてはならない。行政と住民、事業者の利害を調整し、丁寧に合意形成を図る制度が必要ではないか。経産省は今月21日にもエネルギー基本計画の改定案を提示する。計画の土台となる30年度の電源構成目標で、再生エネを大きく伸ばす姿勢を明確に打ち出し、民間企業による投資拡大や技術革新につなげたい。 *2-1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210726&ng=DGKKZO74163590V20C21A7PE8000 (日経新聞社説 2021.7.26) 現役世代からの医療費召し上げは限界だ 75歳以上の後期高齢者が入る医療制度(後期制度)に対し、現役世代の加入者を中心とする企業の健康保険組合などが負担する支援金が一段と膨張した。今後、団塊世代の後期高齢化で消費する医療サービスはますます増える。菅政権が全世代型社会保障を看板に掲げるなら、医療費膨張を制御するとともに、不足する財源は現役世代からの召し上げだけに頼らず、安定した税財源の確保に力を尽くす必要がある。厚生労働省によると、2019年度に健保組合などが後期制度に払った支援金総額は前年度より3.7%増え、6兆5220億円となった。後期制度を導入した08年度以降で最高だ。主因は(1)後期高齢者人口の増加(2)医薬品・医療機器などのイノベーションがもたらした診療報酬の増額――の2点だ。イノベーションの恩恵は全世代の患者が広く享受する。新型コロナの例を出すまでもなく病の脅威に診療報酬政策を適切に用いるのは当然である。一方、後期高齢者人口の増大は22年から拍車がかかる。すべての団塊世代が後期高齢者になる25年に向け、医療費膨張に歯止めが利かなくなる事態を憂慮する。国会は先の通常国会で、一定以上の年金所得などがある後期高齢者の窓口負担を1割から2割に高める法改正をした。しかし対象者が限られ、医療費膨張を制御する効果は乏しい。根本からの対策を視野に入れるときだ。医療現場では検査の重複を減らすのが課題である。マイナンバーを生かし、デジタル化した検査結果の記録を患者自身が簡単に持ち運びできるようにすべきだ。また、最も有効かつ安全で経済的な薬の使用方針を決める「フォーミュラリー」も医療費の制御効果が高い。厚労省は来年度の診療報酬改定で、病院への導入を後押しする仕組みを工夫してほしい。もっとも、これらの対策をとっても現役世代の支援金増加をくい止めるのは難しい。骨折や慢性疾患のリスクがほかの世代よりも格段に高く、保険原理が働きにくい後期高齢者の特質を考えれば、その医療費に消費税の投入を増やすのが理にかなっていよう。今後10年程度は、消費税増税は不要というのが首相の立場だが、超高齢国のリーダーとして責任ある考えとは言えまい。税率10%後のあり方について政治的な議論の場を設定するときである。 *2-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0311G0T00C21A7000000/ (日経新聞 2021年7月3日) 概算要求に特別枠 22年度予算、成長分野の投資促す 財務省は2022年度予算の概算要求基準で、成長分野に優先的に予算配分できる特別枠を設けるよう調整する。各省庁で使い道を決められる裁量的経費を前年度からまず10%減らすよう求め、削減額の3倍を特別枠で要求できるようにする。デジタル化の加速や脱炭素など菅義偉政権が力を入れる分野で政策を集め、投資を促す狙いがある。概算要求基準は各省庁による予算要求のルールとして位置づけられる。政府が近く与党と調整し、正式に決める。各省庁は8月末までに財務省に概算要求を出す。財務省は金額と政策を査定し、年末までに政府の予算案をつくる。政府は6月に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)で①グリーン社会の実現②デジタル化の加速③少子化の克服④地方の活性化――の4分野を今後の重点課題にした。22年度予算編成に向けて、既存の事業の見直しを求めてメリハリを利かせたうえで、重点分野の予算を増やす。公共事業や教育など一般会計の裁量的経費は、21年度当初予算で約15兆円だった。前提として各省庁には既存経費の10%削減を求める。特別枠は削った額の3倍を上乗せして要求できる。人件費など義務的経費を減らした分についても特別枠に入れることを認める。歳出に上限は設定しない。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、昨年の予算編成では概算要求の締め切りを1カ月遅らせて9月末にするなどの対応を取った。特別枠も設けなかったため、22年度は例年のかたちに戻る。予算規模の大きい社会保障関係費の扱いについては、骨太方針に従い、過度に膨張しないよう高齢化に伴う伸び(自然増)に抑える方針を示す。21年度予算では社会保障費の伸びを4800億円と見込んでいたが、薬価改定などで実質的な伸びを3500億円にとどめた。22年度は団塊の世代が75歳以上になり始める影響もあって、自然増はこれまでより増える見通し。医師の技術料など診療報酬の見直しなどでどれくらい伸びを圧縮できるかが今後の焦点になる。新型コロナに関連する予算などでは、影響が現時点で見通しにくいことを考慮し、金額を示さない事項要求を認める。21年度の当初予算は一般会計で106.6兆円と9年連続で過去最大を更新した。22年度も膨張が予想される。 *2-2-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA13AP70T10C21A7000000/ (日経新聞 2021年7月15日) 米欧の財政支出、脱炭素・ITに集中 日本は配分課題 米国や欧州が新型コロナウイルス危機の出口を見据え、環境やデジタルの分野で数十兆円規模の巨額の財政支出に動き始めた。税財源の計画も打ち出し、数年単位の持続的な成長戦略と位置づける。明らかになっているメニューの比較で日本は支出が実質的に10分の1に及ばず、メリハリも効いていない。長期構想に基づいて予算を無駄なく戦略的に配分する仕組みを整えなければ国際競争で劣後する恐れがある。米欧はもともと産業振興に巨額の補助金などを投じることには慎重だった。ただ脱炭素などの新技術の開発では政府がインフラ開発などで旗を振らなければ、民間の投資が伸びにくい。国家を挙げて技術覇権の確立を狙う中国に後れを取りかねないとの危機感も米欧政府の背中を押す。米バイデン政権が掲げた「雇用計画」は8年間で2兆ドル(約220兆円)をインフラ整備や気候変動対策に投じる。電気自動車(EV)を購入する消費者への補助金などに総額約19兆円、電力網の刷新に約11兆円など巨額のメニューが並ぶ。中国との覇権争いも絡むデジタル経済のカギを握る半導体支援も重点テーマだ。2022会計年度(21年10月~22年9月)から5年間で、米国内に工場や開発拠点を設ける企業への補助金など計5.7兆円を出す法案を米議会上院が可決した。政策を実現する財源確保の一環で法人税率の引き上げや富裕層への課税強化策も表明している。欧州連合(EU)は気候変動分野に集中投資する。21年から7年間の中期予算と「コロナ復興基金」の計約1兆8千億ユーロ(230兆円)のうち3割を気候変動対策にあてる。目玉は水素戦略だ。30年までに日本の目標の3倍超にあたる年1千万トンの生産体制を整える。EUは14日、国境炭素税の案を公表した。環境対策が不十分な国・地域からの輸入品に欧州の排出枠価格と同程度の税を課す。事実上の関税として年100億ユーロ近くの収入を想定し、環境投資の新たなサイクルを回す。中国は2014年から基金を作り、半導体関連技術に5兆円超の大規模投資を進めている。上海に二酸化炭素排出枠の取引所を設け、気候変動対策にも本腰を入れる。成長分野への支出で日本は質量ともに見劣りする。脱炭素に10年間で2兆円を投じる基金は20年度第3次補正予算に急きょ盛り込んだ。EVなど向けの経産省の補助金は21年度に155億円で、19兆円の米補助金に比べ桁違いに少ない。第一生命経済研究所の永浜利広氏は「経済規模の違いを考えても日本の支出は米国の10分の1以下。成長力で差が広がりかねない」という。単年度主義の硬直的な予算で赤字国債の発行に頼る財政運営も限界がある。大和総研の神田慶司氏は「コロナ後にどういう経済社会をつくるのか、財政健全化に目配りしつつ、いつまでにどれだけの政策・予算が必要なのか大きな青写真が見えない」と指摘する。日本もコロナによる経済への打撃を和らげるため、予算は大幅に増やしている。国際通貨基金(IMF)の集計によると20年以降の財政対応は計88兆円、国内総生産(GDP)比にして15.9%に上る。米国の25.5%ほどではないが、先進国で中程度の水準だ。しかし規模ありきの編成の結果、約30兆円を使い残した。無駄な部分を大胆に見直しつつ、民間の投資を促すような戦略的配分が求められる。政府は22年度予算編成ではデジタルや脱炭素などに充てる特別枠を2年ぶりに設けた。実際は各省庁のばらばらの要求の受け皿という面がある。経済成長がないまま政府債務ばかり膨らむ危うい状態に陥る恐れがある。経済協力開発機構(OECD)の見通しによると日本の21年と22年の実質成長率は主要7カ国(G7)で最も低い。長期展望や柔軟性に乏しい予算や政策の仕組みのままでは米欧の背中がますます遠のきかねない。 *2-2-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR13BNE0T10C21A7000000/ (日経新聞 2021年7月14日) EU並み気候変動対策、第三国に要求 国境炭素税 欧州連合(EU)の欧州委員会が14日公表する国境炭素調整措置(CBAM)案は、第三国にEU並みの気候変動政策を要求するものだ。中国やロシアをはじめ、日米なども対象になる可能性がある。EUは緩やかに導入を進めることで他国との対立を避けたい考えだが、貿易摩擦につながるリスクがある。「第三国の生産者が排出を減らすインセンティブになる」。欧州委の担当者はこう強調する。EU域外の事業者がEUに製品を輸出するために排出減に向けて努力するというわけだ。実際、EU並みの気候変動対策をとっていれば制度の対象にはならない。CBAMは国境炭素税とも呼ばれる。影響が大きそうなのがロシアや中国、トルコの企業だ。EUの輸入に占める割合を見ると、セメントではトルコが37%を占めるほか、肥料では36%をロシアが、鉄鋼ではトップ3に中国、ロシア、トルコが名前を連ねる。厳しい環境規制で競争力の低下を懸念する欧州の鉄鋼やセメント業界などは制度の導入を支持する一方、中ロや日米などの域外国は懸念を示してきた。保護主義的な措置で、世界貿易機関(WTO)の無差別原則などのルールに違反しているのではないかといった理由だ。EU高官は6月、日本経済新聞の取材に「2050年に温暖化ガス排出の実質ゼロを宣言した先進国を念頭に置いた制度ではない」と述べた。だが日米などの企業のすべての製品が対象外になるかは不透明な面が残る。日米などは全国的な排出量取引制度を持たないため、EUと同等の環境対策をしているとデータで示すことが難しい可能性がある。EUでは排出量取引に基づいて、二酸化炭素(CO2)を出す権利の価格が日々公開される。データで示せなければ、制度の対象になるリスクが高まる。EU内にも貿易摩擦につながりかねないと不安視する声はある。とりわけ米国とはトランプ前政権時代には通商問題を巡って関係が冷え込んだ。フォンデアライエン欧州委員長は6月のバイデン大統領との首脳会談でCBAMを巡って意見交換することに同意するなど、一定の配慮を見せた。23年から3年間の移行期間を設けたのも、各国の理解を得るためだ。制度が成立するには、加盟国の承認と欧州議会の同意を得る必要がある。成立までに1~2年かかるとの見方もあり、制度設計を巡って曲折がありそうだ。日本経済研究センターは欧米が国境炭素調整を導入した場合の日本の製造業への影響について、CO2・1トンあたり50ドル(約5500円)の場合、EU向けに年2.5億ドル、米英に年5.67億ドルを支払う可能性があると試算する。業種別の負担額は機械産業で290億円、輸出額の大きい自動車産業も215億円になる。関税の上乗せで輸出額も減少する見通しだ。試算ではCO2排出量の多い鉄鋼業は欧米への輸出額が5・7%、窯業・土石業で4・7%、それぞれ減少する見通し。日本も炭素税などを導入すれば越境課税は回避できる。ただCO2・1トンあたり50ドルの炭素税を導入すると、日本経済研究センターは製造業の納税額が約1兆2010億円になると試算する。19年度に企業が納めた法人税(10.8兆円)の1割強に相当する。 *2-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/118798 (東京新聞 2021年7月23日) 中国・台山原発、仏なら一時停止 燃料棒破損、合弁の電力会社見解 中国広東省の台山原発の燃料棒が破損し冷却材中の放射性物質の濃度が上昇した問題で、合弁で同原発を建設したフランス電力(EDF)は23日までに「フランスであれば、状況を正確に把握し(濃度上昇の)進行を止めるため、原子炉を一時停止する」との見解を発表した。23日付のフランス紙レゼコーは「事故ではないが、進行性の状態で深刻だ。フランスであれば、できるだけ早く原子炉を止める必要がある」とのEDF関係者のコメントを伝えた。EDFは22日の声明で、原子炉を止めるかどうかの決定は、中国側が主導権を握る運営企業にあると指摘した。 <先端技術の応用> *3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210715&ng=DGKKZO73887760V10C21A7MM8000 (日経新聞 2021.7.15) EU、ガソリン車販売を35年に禁止、排出ゼロへ包括案、国境炭素税は23年にも 欧州連合(EU)の欧州委員会は14日、温暖化ガスの大幅削減に向けた包括案を公表した。ハイブリッド車を含むガソリン車など内燃機関車の新車販売について2035年に事実上禁止する方針を打ち出した。環境規制の緩い国からの輸入品に事実上の関税をかける国境炭素調整措置(CBAM)を23年にも暫定導入する計画だ。欧州委案が成立するには、原則として加盟国との調整や欧州議会の審議を経る必要がある。企業や域外国の反発も避けられそうにない。欧州委の政策パッケージは、30年までに域内の温暖化ガスの排出量を1990年比55%減らす目標を実現するための対策だ。2030年目標は50年に排出実質ゼロにする目標の中間点となる。欧州委はガソリンやディーゼルといった内燃機関車について、35年に事実上禁止する方針を初めて提案した。自動車のCO2排出規制を同年までに100%減らすよう定める。フォンデアライエン欧州委員長は14日の記者会見で「化石燃料に依存する経済は限界に達した」と述べ、速やかに脱炭素社会を実現すると表明した。対応を迫られる自動車業界は反発を強める。ドイツ自動車工業会のヒルデガルト・ミュラー会長は7日、「35年にCO2をゼロとすることはハイブリッド車を含むエンジン車の事実上の禁止だ。技術革新の可能性を閉ざし、消費者の選ぶ自由を制限する。多くの雇用にも響く」と訴えた。トヨタ自動車幹部は「戦略練り直しは避けられない」と話す。欧州委は燃料面からも運輸部門の排出減を促す。自動車とビルの暖房用の燃料を対象にした新しい排出量取引制度を設け、CO2排出にかかる炭素価格を上乗せする。EUには産業や電力など大規模施設を対象にした排出量取引制度がある。だが炭素価格の上昇による燃料費の高騰が低所得層の家計を圧迫しかねないとの批判もあり、当面は別建ての制度とする。従来の排出量取引制度では海運を新たに対象とする。欧州委が導入を目指すCBAMは国境炭素税とも呼ばれる。当初は鉄鋼、アルミニウム、セメント、電力、肥料の5製品を対象とする方針。23年からの3年間を移行期間として暫定的に始め、事業者に報告義務などを課す。26年から本格導入され、支払いが発生する見通しだ。欧州委は30年時点でCBAMに関連する収入を年91億ユーロ(約1.2兆円)と見込む。制度案では、EU域外の事業者が環境規制が十分でない手法でつくった対象製品をEUに輸出する場合、EUの排出量取引制度に基づく炭素価格を支払う必要がある。製品の製造過程における排出量に応じた金額を算出し、事業者に負担させる。EU域内外の負担が等しくなるという考え方だ。 *3-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGS155WI0V10C21A7000000/ (日経新聞 2021年7月21日) 中韓勢、東南アジア市場でEV先手 長城汽車や現代自 日本車が圧倒的なシェアを占める東南アジアの自動車市場に、中国・韓国メーカーが電気自動車(EV)で先手を取ろうとしている。タイでは中国・長城汽車、インドネシアで韓国・現代自動車が現地生産に乗り出す。両社とも現地政府のEV振興策に呼応した。日本勢は、21日に発表したトヨタ自動車やスズキなどの商用車連合で、こうした動きに対抗する構えだ。「変化する時が来た」。長城汽車は6月末、バンコクで開いた新車発表会で日本車への宣戦布告ともとれるスローガンを打ち出した。タイは日本車の生産・販売シェアが約9割に達するものの、大半をガソリン車が占める。長城汽車は3年間でEVを含む9車種の電動車を投入して市場の切り崩しを狙う。同社は2020年にタイから撤退した米ゼネラル・モーターズ(GM)の工場を取得して参入した。800億円弱を投じて人工知能(AI)技術やロボットを導入し、年産能力約8万台の「スマート工場」に改修。手始めに6月からハイブリッド車(HV)の生産を始めた。23年までにEV生産を開始する計画だ。工場改修はタイ政府のEV振興策を利用し、最長8年間の法人税免除の恩典を受けた。タイは30年までに国産車の3割をEVにする目標を掲げる。長城汽車タイ法人の張佳明社長は「タイで電動車のリーダーとなり、産業高度化に協力する」と強調する。タイは東南アジア最大級の自動車市場だが、EVシフトは遅れている。自動車大手はEVを現地生産しておらず、20年の販売台数は約1400台にすぎない。このうち約6割を中国・上海汽車集団の輸入車が占める。同社はタイ財閥チャロン・ポカパン(CP)グループとの合弁工場でEVを現地生産する予定という。日本車は日産自動車の「リーフ」やトヨタ自動車の高級車「レクサス」の一部車種の輸入販売にとどまる。現地生産は三菱自動車が23年から開始する計画を持つものの、全体的にはHVを優先する傾向が強い。充電インフラが整っておらず、所得水準もまだ低いためだ。長城汽車もまず、中国で補助金分を引いた実売価格が約120万円の小型EV「欧拉」を、中国から輸出してタイ市場に投入する。市場開拓を進めながら時期をみて現地生産に切り替えるとみられる。野村総合研究所タイの山本肇シニアマネジャーは「中国勢が間隙を突いて、低価格EVでシェアを伸ばしてくるのは確実だ」と指摘する。タイと並ぶ域内2大市場の一角であるインドネシアには現代自動車が攻め入る。首都ジャカルタ近郊で総事業費約1700億円の工場建設が進む。当初の年産能力は15万台で、年内にガソリン車の生産を開始する。現地報道によると22年にもEV生産に乗り出す。同国は日本車の販売シェアが9割台後半と、ほぼ市場を独占してきた。現代自の工場建設にはインドネシア政府の働きかけがあった。進出が決定した19年11月はインドネシアと韓国が経済連携協定(EPA)を妥結した時期と重なる。韓国から輸入する自動車部品の大半が無関税となり、韓国メーカーは日本車と同等な条件での競争が可能になった。インドネシア政府は19年の大統領令で、国産車の20%をEVとする目標を打ち出した。だが、同国が13年に出した小型エコカーの振興策を受けて、日本車は設備増強を実施済みで追加投資に慎重だ。そこで白羽の矢が立ったのが現代自動車だった。タイ、インドネシア両政府に共通するのは、動きが鈍い日本車へのいらだちだ。タイではEV普及目標の引き上げを検討する政府に対し、日本車の業界団体に当たるバンコク日本人商工会議所自動車部会が「全体でのゼロエミッションを考えて段階的に進めるべきだ」として慎重な議論を求めた。タイは火力発電が中心のため、EVだけ増やしても温暖化ガスの排出は減らせないという理屈だ。インドネシアも同様の課題を抱える。日本車の主張は一理あるものの、中韓勢との投資競争に後れをとれば、かつて家電や携帯電話でシェアを失ったように自動車市場も奪われかねない。 ●商用車も日本強く 5社連合で守り固める 日本車は東南アジアで1960年代から現地組み立てを始め、主要6カ国の新車販売に占めるシェアは約8割に達した。ただ、足元で中国勢がEVで小型車のみならず商用車でも攻勢をかける。21日にスズキやダイハツ工業が、トヨタ自動車、日野自動車、いすゞ自動車の商用車連合に合流すると発表したのも、中国勢の攻勢に対抗する守り固めの意味がある。東南アジア最大級の市場のタイは小型商用車「ピックアップトラック」が市場の半分以上を占める。20年の国内販売全体でもいすゞのシェアは23%に達し、トヨタ(31%)に次ぐ2位を占める。インドネシアでも日野、三菱ふそうトラック・バス、いすゞが商用車で寡占状態だ。だが、日本勢のすきを狙い、中国勢が商用車でも攻勢をかける。タイでは商用車大手、北汽福田汽車がEVトラックを21年中にも発売する予定だ。現状、スズキは軽商用車の海外展開をしていない。5社連合で技術力を結集した小型EVなどを出せれば、日本勢の存在感が維持できる可能性がある。 *3-2-2:https://www.webcg.net/articles/-/44769 (Webcg 2021.7.1) ボルボが全車EV化へ向けたロードマップを発表 ボルボ・カーズは2021年6月30日(スウェーデン現地時間)、製品ラインナップの完全な電気自動車(EV)化へ向けた、技術ロードマップを発表した。 ●目指すは実走行距離1000kmのEV ボルボは現在、自社製品の急速な電動化と、より長い一充電走行可能距離や短い充電時間を可能とするバッテリーセル技術の開発を推し進めている。特にプロダクトについては、近い将来、SUVタイプの新型EVを投入し、2020年代半ばにはその次の世代となる第3世代のEVも導入するとしている。このモデルでは、航続距離をさらに伸ばすとともに、バッテリーパックをクルマのフロアに統合し、セル構造を利用して車両全体の剛性を高める、より高効率な車両パッケージも実現するという。一方、バッテリーの開発・生産に関しては、スウェーデンの大手バッテリーメーカーであるノースボルトと提携。現在のものより最大で50%エネルギー密度の高いバッテリーセルの開発を計画している。さらに2020年代の後半には、1000Wh/リッターというエネルギー密度の達成と、実走行距離1000kmのEVの実現を目指しているという。また充電に要する時間については、バッテリー技術の向上、ソフトウエアや急速充電技術の継続的な改善により、2020年代の半ばまでに現在のほぼ半分になると予想している。 ●生産や廃棄の段階における環境負荷低減にも腐心 ボルボはプロダクトの電動化以外の点でも二酸化炭素排出量の削減を推進。ノースボルトと共同開発するバッテリーセルについては100%再生可能エネルギーを使用して生産することを目指しており、他のサプライヤーとも2025年までに100%再生可能エネルギーでバッテリーを生産できるよう、取り組みを進めているという。加えて、使用済みバッテリーのリユースやリサイクルについても計画。エネルギー貯蔵などの二次利用の可能性も調査を進めている。EVのエネルギーインフラでの活用についても計画しており、SUVタイプの次世代EVでは、双方向充電により車載バッテリーの電気を電力網に流すことができるようになるという。これにより、EVのドライバーは電力の生産時に排出されるCO2量がピークとなる時間には、電力網にエネルギーを供給してCO2の排出抑制に貢献。そしてCO2排出量が減少する時間にクルマを充電することができるようになると説明している。(webCG) *3-2-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR223I60S1A720C2000000/ (日経新聞 2021年7月22日) 独メルセデス、30年にもEV専業に 5.2兆円投資 独自動車大手ダイムラーの高級車事業会社、メルセデス・ベンツは22日、販売する新車を2030年にもすべて電気自動車(EV)にすると発表した。8つの電池セル工場を新設するなど、30年までに400億ユーロ(約5兆2000億円)をEVに投資する。オンラインで開いた記者会見で、オラ・ケレニウス社長は「高級車のEVシフトは加速している。転換点は近づいており、30年までにメルセデスは準備できているようにする。EVファーストからEVオンリーに踏み込む」と述べた。22年に満充電で航続距離1000キロメートル以上の新型車を発表する。25年にEV専用の車台(基本設計)を3種類導入。それ以降に出す車台はすべてEV専用とする。代表車種の「Sクラス」や「Cクラス」の次期モデルはEVだけになる見通しだ。ガソリン車などの販売終了時期は市場によって前後するとしている。ハラルト・ウィルヘルム最高財務責任者(CFO)は30年までにEVの生産コストを同じ車格のガソリン車と同等水準に引き下げるとしたうえで、売上高に占める調整後EBIT(利払い・税引き前損益)比率を10%以上で維持するとの見通しを示した。EVに不可欠な車載電池では専業メーカーと共同で世界に8つの大型工場を設ける。4つは欧州で、米国と中国にも建設する。年間生産能力は高級EV200万台分前後に相当する計200ギガワット時(2億キロワット時)を計画する。メルセデスはこれまで30年に新車販売の半分をEVかプラグインハイブリッド車(PHV)にし、39年にガソリン車の販売終了などで二酸化炭素(CO2)排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を目指す計画を掲げていた。半分をEV・PHVにする期限は25年に前倒しする。EV専業化に向け、PHVを含むエンジン搭載車への投資を26年までに19年比で8割減らす。欧州連合(EU)の欧州委員会は14日、35年にエンジン搭載車の販売を事実上禁止する規制案を発表した。すでに独フォルクスワーゲン(VW)傘下の独アウディや、ボルボ・カー(スウェーデン)、英ジャガーなどの高級車ブランドが相次いでEV専業への転身を発表している。 *3-2-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD21AF30R20C21A7000000/?n_cid=SPTMG002 (日経新聞 2021年7月21日) トヨタ、商用車連合を拡大 大型から軽まで電動化 トヨタ自動車が中心の商用車連合にスズキとダイハツ工業が加わる。トヨタにとって電動化など脱炭素における商用車分野の協業の総仕上げとなる。4月に日野自動車といすゞ自動車と立ち上げた商用車の技術開発会社に軽自動車を得意とする2社が加わり、大型から小型まで商用車を全方位で開発する体制が整う。「国内の自動車保有台数7800万台のうち軽は(4割の)3100万台を占める。地方では半数を超える」。トヨタの豊田章男社長は21日の記者会見でこう切り出し、「商用軽は収益だけを考えると非常に厳しいが日本では欠かせないものだ」と軽の重要性を強調した。スズキの鈴木俊宏社長は「求めやすい価格で脱炭素を実現するには単独では非常に難しい」と参加の理由を説明した。「企業としても脱炭素をアピールできる軽の商用電気自動車(EV)へのニーズはこれまでも高かった」と別のスズキ幹部は背景をこう解説する。今回の協業で改めて強調したのが、商用車分野を電動化や脱炭素の技術開発の起点とする考えだ。物流を担う商用車はあらかじめ決められたルートを通ることが多い。「(充電設備など)インフラとセットで考えることが不可欠」(豊田社長)なEVや燃料電池車(FCV)などの開発には向いている。トヨタが日野・いすゞとの商用車連合を発表した際、念頭にあったのが、福島県での再生エネルギーから作った水素を活用したFCVのトラックによる物流網の構築だった。今回の参画で、FCVの軽商用車も視野に入り取り組みが広がる可能性がある。3月の商用車提携発表後に、自治体・インフラ事業者、運送事業者など、多くの関係者から一緒にやりたいとの声がトヨタに寄せられた。荷物の集配所から受け取る人までの「ラストワンマイル」の物流を担う軽自動車は電動化やコネクテッドなど新技術の開発には欠かせないと判断した。トヨタからスズキとダイハツに声をかけた。軽の商用車が加わることで、中長距離物流を支える大中型トラックを含めて物流に関わる技術開発が加速できるとみる。鈴木社長は「大型と軽がつながることで非常に効率がいい物流ができる。大きな成果に結びつくのではないか」と期待を示す。トヨタにとっては、大きさの制約がある中で、いかに安く作るかを突き詰めてきた軽メーカーのノウハウを取り込む狙いもある。電動化やつながる車などは今後いかに安く作れるかがカギとなる。商用車を軸とした5社連合で、新たなプロジェクトを始める起点にもなり得る。 *3-2-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210724&ng=DGKKZO74149360U1A720C2MM8000 (日経新聞 2021.7.24) GXの衝撃(5)取捨選択、欧州が主導 ルールが決する競争力 欧州委員会が4月に公表した、分類を意味する「タクソノミー」と呼ぶ数百ページの資料。企業が手がける事業がどういう基準を満たせば「持続可能」と判別されるかを示す。「まるで『閻魔(えんま)大王』みたいに企業が選別される」。こんな受け止め方が広がる。電池製造や発電などが対象で、欧州連合(EU)の温暖化ガス排出の8割をカバーする。企業は基準外の製品を作れなくなるわけではないが、ESG(環境・社会・企業統治)が広がる中、投資を集めにくくなる。 ●PHVにも逆風 環境に優しいとされる製品もやり玉に挙がる。例えば日本の自動車メーカーが強みを持つプラグインハイブリッド車(PHV)。2026年以降は「持続可能」などの分類から外れ、新車で売りにくくなる恐れがある。PHVは、ガソリン車と電気自動車(EV)の間に位置する。EVへの移行期に伸びると見込まれているが「タクソノミーでPHVの普及期の寿命は5年ほど短くなった」と専門家は分析する。石炭火力発電がタクソノミーで外される一方、天然ガスは欧州でも意見が割れる。ポーランドなど東欧諸国は「脱石炭を進めるうえで当面は認めるべきだ」と訴える。逆風の予兆はあった。「控えめに言ってガスは終わった」。欧州投資銀行(EIB)のホイヤー総裁の1月の発言。21年末までにガスへの投融資から原則、手を引く方針を表明し波紋を呼んだ。 ●ガスも縮小懸念 天然ガスは石炭より二酸化炭素(CO2)排出量が4割少ない。天候によって変わる太陽光や風力の発電量を補う役割から、石炭から再生エネへの移行期の「つなぎ役」になるとされてきた。「天然ガスの黄金時代」が到来するとのリポートを国際エネルギー機関(IEA)が公表したのは10年前。クリーンとされる液化天然ガス(LNG)の消費はこの間に6割増えた。ただ、IEAは21年5月、50年のカーボンゼロ達成には、ガスを含む化石燃料の開発投資の即時停止が必要とのシナリオを公表した。日本エネルギー経済研究所の二宮康司氏は「今のままでは30年代以降、ガスも石炭のように悪者扱いされる」とみる。国内最大手の東京ガスが関東で張り巡らすガスのパイプラインは地球1.5周分。輸入のため港湾に設けたLNG基地は1カ所で1000億円規模だ。ガスが石炭のように縮小の道をたどればこうした設備が「座礁資産」となり使い道を失う。タクソノミーのような欧州発のルールが世界の潮流となってきたケースは多い。欧州各国によるガソリン車の販売規制の表明を伊藤忠総研の深尾三四郎氏は「欧州自動車メーカーのディーゼル不正を機に欧州が有利になるようなルールに変えてしまった」と指摘する。車が製造されてから廃棄されるまでの10年間の「ライフサイクル」でみたCO2の排出量は、IEAの20年のまとめによるとガソリン車で1台あたり平均34トン程度だった。EVが24~28トンで、PHVは約25トンと、PHVは環境性能に優れるケースもあるのにEU基準ではアウトになる。欧州がEV導入の高い目標を掲げる中、ESGの圧力により、石油開発は足元で急減。ただ実際に選ぶのは消費者で、EVの普及が遅れれば需給バランスが大きく崩れ、ガソリン価格は高騰しかねない。多角的なリスクを抱えながら企業は難しい選択を迫られている。日本は通貨や通商などで欧米主導のルールを受け入れることが多かった。グリーントランスフォーメーション(GX=緑転)でルールをつくる側に回れるかどうかは、産業競争力にとどまらず、国益をも左右する。 *3-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC071580X00C21A7000000/?n_cid=NMAIL006_20210709_Y (日経新聞 2021年7月9日) JAL「空飛ぶクルマ」で旅客輸送 25年度に事業化 日本航空(JAL)は2025年度に「空飛ぶクルマ」を使った事業に乗り出す。三重県などで空港と観光地を結ぶ旅客輸送サービスを始める。ANAホールディングス(HD)も25年度に同様のサービスへの参入を検討している。空の移動が身近になれば道路渋滞の緩和や過疎地の交通対策にも役立つ。海外でも実用化競争が進んでおり、新ビジネスに見合うルール整備が課題となる。空飛ぶクルマは空を飛び近中距離を手軽に移動する次世代の乗り物。JALが使うのはeVTOL(電動垂直離着陸機)と呼ぶ2人乗りのドローン型の機体で、航続距離は35キロメートル。最高時速は110キロ。三重県とこのほど実証実験や事業化に向けた連携協定を結んだ。機体を開発したのはJALが20年に出資したドイツのスタートアップ、ボロコプター。リチウムイオン電池に蓄えた電気で複数のプロペラを回して飛ぶ。まず20キロの近距離圏内を飛ぶ実験を進め、さらに地方の都市間を結ぶような50~150キロの中距離圏のサービスを検証する。事業化の際は発着ポートを設けやすい空港を起点に観光地をつなぐ見通し。料金は今後詰める。最終的には中距離圏内であらゆる場所に行き来するタクシーのようなサービスにする構想だ。輸送事業者としてだけでなく、操縦者の訓練や安全管理などのオペレーターサービスを他の輸送事業者に提供して稼ぐ仕組みも想定する。空飛ぶクルマは滑走路が不要で機動性が強み。都市内を簡単に移動できるため、交通渋滞の解消につながると期待されている。交通手段に乏しい過疎地の移動問題の克服にもつながる。一方で社会で広く受け入れられるサービスとするにはルール整備が不可欠だ。三重県は特区として空飛ぶサービスを認めているが、他県との行き来はできない。政府は電動かつ自動操縦で飛ぶ機体を空飛ぶクルマと見なし、ルールづくりを急いでいる。機体は航空機とみなされるため航空法に基づく制度の見直しが必要で、25年までに詰める。航空機燃料を使わないため安全基準も新たな考え方が必要となる。操縦ライセンス、運航の決まりなど整理すべき点は多い。実用化では海外が先行する。トヨタ自動車が出資する米新興企業のジョビー・アビエーションは24年に輸送サービスの商用化を計画。欧州エアバスも24年のパリ五輪での有人サービスの実現を目指している。将来はスマートフォンから予約可能なタクシーサービスの提供をめざす。国内航空大手は空飛ぶクルマなど次世代モビリティー事業を成長の柱の一つと期待する。米モルガン・スタンレーは40年までに世界の空飛ぶクルマの市場規模が1兆5千億ドル(約165兆円)に成長すると予測する。 *3-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB273460X20C21A7000000/ (日経新聞 2021年7月27日) 脱炭素ファンド、Appleなど参画 三井住友銀行も出資 企業の脱炭素化に向けた世界最大規模の枠組みが立ち上がる。米投資ファンド、TPGキャピタルは気候変動対策に特化したファンドを組成する。当初の運用規模は約54億ドル(約6000億円)で、脱炭素ファンドでは過去最大規模となる。アップルやグーグル、ボーイングなど米国を代表する企業に加え、日本からは三井住友銀行が出資する。脱炭素化に向けた技術を有する世界のベンチャー企業に資金を投じることで、新技術の開発を促進する。TPGが27日に発表した。米国の大企業や大手年金基金などから約54億ドルを集めた。2021年中に出資額を70億ドル程度まで引き上げる方針だ。ファンド出資者にはグーグルの持ち株会社であるアルファベットやアップルなど米IT(情報技術)大手に加え、ボーイングやゼネラル・モーターズ(GM)なども名を連ねる。20社以上が加わるとみられ、日本からは三井住友銀行が5000万ドルを投じて参画する。ファンドを通じて、再生可能エネルギーや二酸化炭素を排出しない輸送手段など、脱炭素化に貢献する技術を有するベンチャー企業などに出資する。投資額は1件当たり数百億円規模を想定している。ポールソン元米財務長官がファンドの取締役会長を務める。ポールソン氏は自身のシンクタンクで気候変動対策に向けた分析を手掛けており、出資先の選定などで手腕を振るう。気候変動対策を巡っては、米アップルが2億ドル規模の森林再生ファンドを立ち上げたほか、アルファベットが環境関連などに資金使途を絞った社債「サステナビリティボンド」の発行を決めるなど米IT大手の取り組みが加速している。だが、気候変動対応に関する技術を有したベンチャー企業に出資するファンドにこうしたIT大手が参画するのは異例だ。背景には投資先が有する技術にいち早くアクセスしたいIT大手側の思惑がある。ファンドは出資者や投資先が参加する企業連合を立ち上げる方針。こうした場を通じて、脱炭素化に向けた有望な技術を有するベンチャーとの協業や出資につなげていく。日本から参画する三井住友銀行は、出資先への融資や新規株式公開(IPO)の支援などで連携していく考えだ。TPGは1992年創業のプライベートエクイティ(PE=未公開企業投資)。直近の運用資産残高は960億ドル(約10兆円)で、未公開株や不動産投資などに強みをもつ。脱炭素化を巡っては、米ブラックロックが新興国向けのインフラファンドを立ち上げた。国際協力銀行や第一生命、三菱UFJ銀行などが出資を決めており、ファンドは総額5億ドル規模を目指している。 <新型コロナと五輪に関する世論から見た教育の問題点> PS(2021年7月30日、8月2日《図》追加):*4-1のように、衆院内閣委員会で、政府の新型コロナ分科会の尾身会長が「①医療の逼迫が既に起き始めている」「②一般の人々に危機感が十分に伝わっていない」「③緊急事態宣言が出て人流は徐々に減っているが、期待されるレベルには至っていない」「④日本社会みんな危機感を共有することが今非常に重要だ」「⑤入院や重症者の数が増え、入院調整・宿泊療養・自宅療養の人も急増している」「⑥今の状況で求められることは、人々に危機感を共有してもらえるようなメッセージを出し、効果的な対策を打つことに尽きる」等と言われたそうだ。 しかし、2020年1月に始まった新型コロナ騒動から既に1年半経過し、②の一般の人々の危機感は2020年2月から高まって協力したのに、厚労省だけが危機感を持たず、蔓延や①⑤を防ぐための検査による潜在患者の洗い出し、水際対策の徹底、ワクチン・治療薬の開発・承認、医療機関の広域連携、療養先の確保などの全てを行わず、③の“緊急”事態宣言による人流減少だけを主張して現在に至っているのだ。そのため、④は、これまでの経緯を忘れて、どの口で言えたものかと思う。また、⑥の「人々が危機感を共有するメッセージ」として「国民に自粛を求めながら、オリンピックを行うのは矛盾だ」などと関係のない2つの事象を結びつけるのも“専門家”からかけ離れており、そんなことは根拠を示してきちんと説明すれば理解されることである。さらに、「⑦デルタ株の感染力を前提としていない」というのも、デルタ株は何故感染力が高いのか、それに対してどういう対応方法が適切なのかに関するしっかりした調査もなく、ワクチンや治療薬が効かないというデータもない時に、言うべきではない。 また、*4-2のように、日本医師会、日本病院会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、東京都医師会も、「⑧感染爆発を避けるため危機感共有を」という緊急声明を7月29日に出し、その内容は「⑨40~50代の中等症患者の増加で医療の逼迫が懸念されると指摘し、政府に十分で安定したワクチンの供給を要請する」だそうだ。しかし、ワクチン接種を進めるのは当然のことで、今回の五輪はお祭り騒ぎどころか練習試合ででもあるかのように観客もいないため、間接的影響ででもこの2つを結び付けるのはおかしい。さらに、医療関係者が国民にテレワークの実施を求めるのも越境で変であり、国民は運動をせず、目が悪くなったり、ロコモになったり、孤独で心を病んだりした方がよいとでも言うのだろうか。 なお、IOCのアダムス広報部長は、*4-3のように、東京五輪のメインプレスセンターで記者会見し、「⑩五輪関係者は最も頻繁に検査されており、別世界みたいで、われわれから感染を広げていることはない」と強調し、バジェット医事部長も五輪が「⑪医療崩壊に影響することはない」と訴えられたそうだ。組織委がまとめた大会関連の陽性者は7月1日以降で累計198人となり、陽性となった海外からの大会関係者2人が入院したそうだが、母国なら入院の必要があるのか、その後に中等症や重症になったかについても、報告された方が役に立つ。 このように外国の対処方法と比較した方がよい理由は、*4-4のように、日本政府が「⑫新型コロナワクチン接種証明書の国内利用を特別な事情で接種できない人への差別を理由として認めなかったり(本当は、差別にならないようにすることもできる)」「⑬接種証明書を持つ入国者に72時間以内の陰性証明の提出と14日間の待機措置を求めたり(本当は、いずれか1つでよい)」「⑭外国が発行した接種証明書の利用を認めず、日本の証明書は受け入れるよう交渉したり(相互主義の常識に反する)」など、非科学的かつ非常識な対応が多いのに「何様のつもりか」と思うような不公平な取り扱いを求めているからである。 なお、上昌広氏が、*4-5に、「⑮新型コロナ対策で日本は1回以上ワクチン接種を受けた人がG7最下位で一人負け」「⑯ワクチン接種が進む国は感染者が急速に減少」「⑰G7で感染者数が増加しているのは日本だけ」「⑱米疾病対策センターはワクチン接種を済ませた人はマスク着用義務を解除し、ドイツもワクチン接種を終えた人への制限を緩和」「⑲日本の最初の躓きは無症状感染対策なのにPCR検査を抑制したこと」「⑳感染の抑制と最も相関したのは、感染者数当たりの検査数だったが、厚労省や専門家たちはこの研究成果を無視し続け、政府のコロナ対策分科会会長の尾身氏は、2021年10月の講演で『無症状者にPCR検査しても感染は抑えられない』と公言している」「㉑これは厚労省で医療政策を仕切る医系技官の意向を代弁したもので、医系技官は、『PCRは1%程度の偽陽性があり、PCR数を増やせば医療が崩壊する』と主張して検査数を抑制した」「㉒『米国医師会誌(JAMA)』5月6日号は『殆どのPCRの特異度は100%』と記しており、2020年5月の段階でPCR検査の精度が高いことは世界の常識となって世界各国が大規模スクリーニング検査体制の構築を進めていた」と書かれており、全くその通りだ。 また、「㉓日本の人口千人あたり検査数は、インドの半分以下で後進国レベル」「㉔厚労省は、変異株の大部分を見落とした」「㉕世界は『マルチプレックスPCR』を用いて1回の検査で変異株の感染を判断しているが、日本は検体を国立感染症研究所などの専門施設に運ぶ2段階検査に固執している」「㉖厚労省がここまでPCRを抑制する理由は、感染症ムラ(厚労省医系技官、感染研、専門家で構築される利益共同体で健康局結核感染症課が中心)の利権に関わるからである」「㉗コロナ対策で、感染症ムラにとっての『公共事業』となったのは積極的疫学調査で、法定感染症が発生した時、厚労省が指示して感染研と保健所が連携して実施することと定められている」「㉘コロナ感染症対策分科会委員の押谷東北大学教授が、2020年3月22日のNHKスペシャルで、『全ての感染者を見つけなければいけないというウイルスではなく、クラスターさえ見つけていればある程度の制御ができる』」と述べたが、この指摘が間違いだったのは明白で、感染が蔓延すればクラスター対策では対応できないことは素人でもわかる」と書かれているが、私も㉓~㉘は、あまりにも不自然でおかしいと思っていたのである。 さらに、「㉙彼らがクラスター対策に固執している理由は研究費(2019年度の約3億4千万円から、2020年度には36億5400万円に増額)で、2020年度に採択された41人中20人が感染研、27人が感染症ムラの関係者」「㉚研究成果は東京大54報、感染研19報、横浜市大16報であり、感染症ムラの情報独占や過剰な資源投入は、日本の研究力を削いでいる」「㉛4月8日現在、PubMedには6万2905報のコロナ論文が収載されており、米国1万1251報、中国(8881報)、イタリア(6945報)、イギリス(6448報)、日本(1333報)でG7最下位だ」「㉛ワクチン開発に成功した独ビオンテックと米モデルナは、元はがん治療ワクチンを開発していたバイオベンチャーで、ゲノム情報を分析してワクチン候補となるmRNAの配列を決定するノウハウを有しており、2020年1月に中国の研究チームがコロナのゲノム配列を公開すると、その情報を分析してワクチン開発に取りかかったが、彼らの成功は感染症・免疫学・情報工学の専門家の有機的な連携によるものだ」等も書かれており、なるほどそうだったのかと思われた。 最後に、「㉜PCR検査もできず、37.5度4日間の自宅待機を強要し、ワクチン・治療薬の開発もできず、緊急事態宣言を繰り返す日本で、多くの人命と財産が失われた」「㉝クラスター対策に固執して非科学的な対応を取り続けてきた感染症ムラと、彼らの暴走に目をつぶった政治家による人災だ」「㉞これまでの経緯を検証し、ゼロベースで体制を見直さねばならない」と書かれているのは全くそのとおりだ。しかし、「感染症ムラの暴走をコントロールするのは、本来、政治の役割だ」というのは、それをやるためには厚労省の医系技官をリードできるようなその分野に詳しく能力ある人材を担当に選ばなければならないが、「国民から選ばれて選挙で勝つ人」は必ずしもそうではなく、仮にそういう人がいたとしてもやはり厚労省の医系技官から煙たがられて担当になれないという日本特有の人事の根本的問題があるのである。 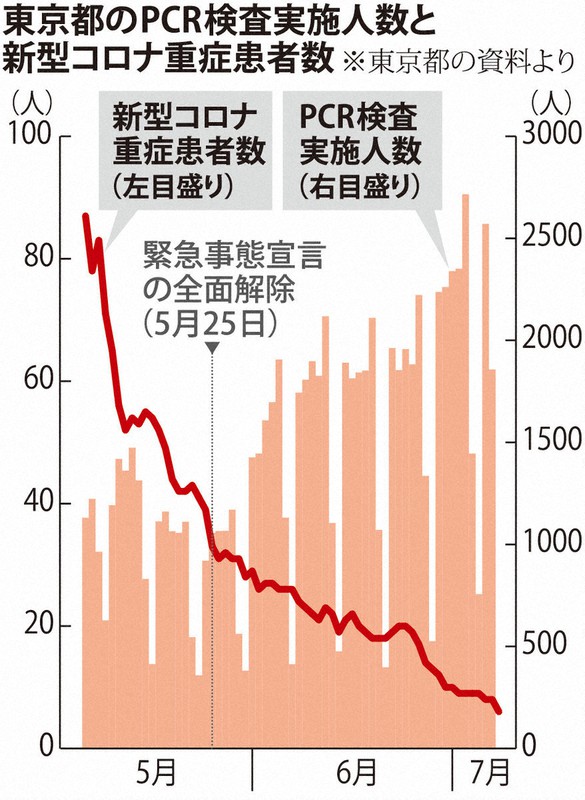 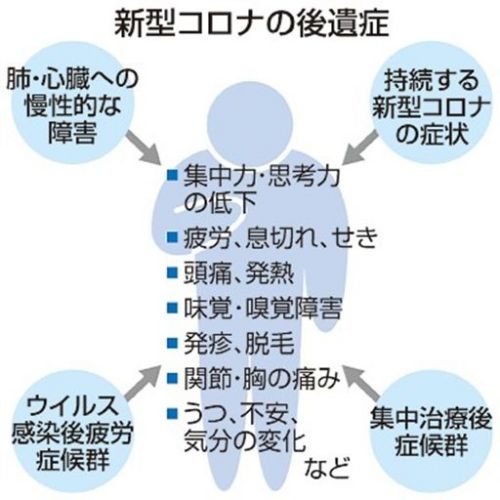 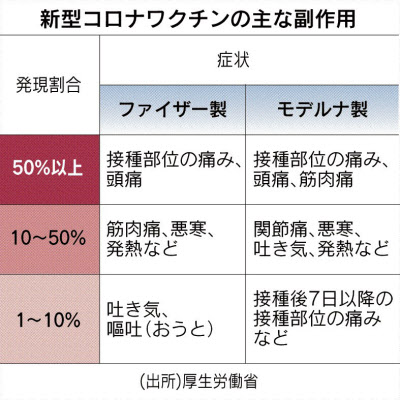 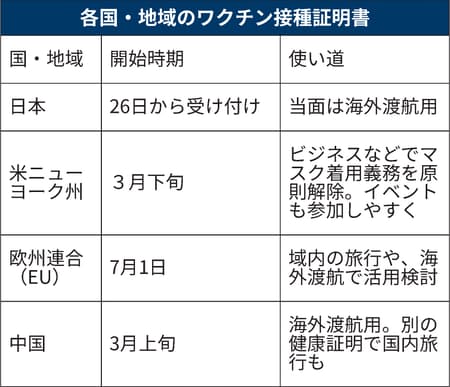 2021.7.9毎日新聞 2021.8.2琉球新報 2021.6.17日経新聞 2021.7.12日経新聞 (図の説明:東京圏の患者数が増えていると言われるが、1番左の図のように、東京都のPCR検査数は少し増えたが、ワクチン効果で重症者数は漸減している。また、左から2番目の図のように、新型コロナウイルスも中等症以上になると後遺症を残すケースが多発しており、これは日本脳炎やポリオ《小児麻痺》ウイルスも重症化すると神経系に後遺症を残すことを考えれば常識的に考えられることだが、日本では、最初、『軽症者は病院に行くな』と呼びかけられていた。なお、日本脳炎やポリオはワクチンによって撲滅されたのだが、現在は、右から2番目の図のように、ワクチンの副作用ばかりを強調し、1番右の図のように、感染リスクの低減したワクチンの既接種者にワクチンパスポートを出すことをためらうという世界でも珍しい対応をしている) *4-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14991935.html (朝日新聞 2021年7月29日) 尾身氏「危機感伝わらず」 迫る医療逼迫指摘 閉会中審査 衆院内閣委員会の閉会中審査が28日開かれ、東京都の新型コロナウイルスの感染者が急増している点について、政府の新型コロナ分科会の尾身茂会長は「医療の逼迫(ひっぱく)がもうすでに起き始めている」との認識を示した。その上で「人々に危機感が十分に伝わっていない」などと懸念を語った。菅義偉首相は27日に記者団に対し、感染の急拡大による五輪への影響について「人流は減少している。心配はない」と述べた。28日の内閣委では、立憲民主党の柚木道義氏が人流の減り方は十分なのか尋ねた。尾身氏は「緊急事態宣言が出て徐々に減っているが、期待されるレベルには残念ながら至っていない」と指摘。続けて「入院や重症者の数が増えている。入院調整や宿泊療養、さらに自宅で療養している人も急増している」と述べ、医療逼迫の懸念を示した。その上で、尾身氏は「一般の人々に十分に危機感が伝わっていないということが、大きい一つの原因だ。日本の社会みんな危機感を共有することが今非常に重要だ」と語った。柚木氏から、首相による発信の仕方など政府の対応について問われ、尾身氏は「今の状況で求められることは二つだ。人々にしっかりと危機感を共有してもらえるようなメッセージの出し方。効果的な対策をしっかり打つ。この2点に尽きる」と述べた。感染拡大と五輪開催との関係を指摘する意見も出た。共産党の塩川鉄也氏は「政府は国民に自粛を求めながら、世界最大の式典を行う。大きな矛盾だ」と指摘した。西村康稔経済再生相は「都内の人流は一定の減少をみている」と強調した上で、「医療提供体制を確保していく上でも、自宅で家族か、いつもいる仲間と少人数で観戦応援をお願いできれば」と述べた。また、ワクチン接種に関し、首相が会見で、野村総合研究所のリポートをもとに「人口の4割がワクチンを1回接種したあたりから、感染者の減少傾向が明確」と発言した点について、立憲の玄葉光一郎氏が「デルタ株の感染力を前提としていない」と問題視した。これに対し、西村経済再生相は「野村総研以外のデータも首相は理解している。政府全体で正確な情報を伝えたい」と語った。 ■都の説明、都庁内からも批判 「医療逼迫、第3波ほどではない」 「大丈夫との発信、意味あるのか」 新型コロナウイルスの新規感染者数が2日連続で過去最多を更新した東京都が強調するのが、病床が逼迫(ひっぱく)して医療危機に陥った冬の第3波との違いだ。都は重症化しやすい高齢者の感染が激減し、医療への負荷が当時とは異なると説明する。だが、入院者数は急増し、病床逼迫へ警鐘を鳴らしてきた都の専門家の説明とも食い違い、政府内、都庁内から批判の声が出ている。「第3波のピーク時と比べるとワクチン接種が加速した。重症化しやすい60代以上も減っている。第3波の時とは状況が異なると認識している」。小池百合子知事は28日午後、国内外のメディア向けのオンライン講演で、そう強調した。27日の2848人の感染者を年代別にみると、60代以上は全体の5%。一方、第3波でピークとなった1月7日(2520人)では、60代以上が14%に達した。1月7日に121人を数えた重症患者数も、27日は82人にとどまる。27日夜、都のコロナ対策を担当する吉村憲彦・福祉保健局長は記者団に異例の説明の場を設け、「第3波のピークとは感染状況の質が違う。医療に与える圧迫は変わっていることをご理解いただければ」と説明した。吉村局長は、第3波で9割弱に達した病床使用率が今は半分弱になっているとも強調。「医療提供体制がにっちもさっちもいかなくなって、死者がばたばた出ることは現状ない」とした上で、「いたずらに不安をあおるようなことはしていただきたくない」と述べた。だが、こうした吉村局長の説明は、都が毎週開いてきたコロナ対応のモニタリング会議での、感染症対策の専門家や医師たちの説明とは食い違う。21日の同会議では、「新規陽性者数が急速に増加すれば、医療提供体制が逼迫の危機に直面する」との専門家のコメントを公表。指摘の通り、病床は徐々に埋まり、27日時点の入院患者数は2864人と1カ月前と比べて倍増している。厚生労働省の幹部は「不安をあおらないでほしい」との吉村局長の訴えについて、「東京の感染状況は不安になる状態。逆のメッセージを出した方がよかったんじゃないか」と指摘する。病床に余裕があるとの説明に対しても、「いまはそうかもしれないが、来週、再来週は絶対に逼迫する」と警鐘を鳴らす。東京五輪が開かれる中、あえて第3波との違いを強調した吉村局長の説明に対し、都の福祉保健局内からも批判の声が上がる。ある幹部は「病床にまだ余裕があることは事実だとしても、その点を強調して『まだ大丈夫だ』と発信することにどれだけの意味があるのか」と疑問を呈する。 *4-2:https://mainichi.jp/articles/20210729/k00/00m/040/401000c (毎日新聞 2021/7/29) 日医など9団体が緊急声明「感染爆発避けるため、危機感共有を」 新型コロナウイルスの感染者急増によって医療提供体制の逼迫(ひっぱく)は間近だとして、日本医師会(日医)や日本病院会など9団体が29日、緊急声明を出した。声明は全国の感染者数が過去最多を更新したことに触れ、「今後の爆発的感染拡大を避けるための危機感の共有と対策が必須」と指摘。全国を対象に緊急事態宣言を出すことを検討し、40~64歳のワクチン接種を推進するよう政府に求めている。記者会見した日医の中川俊男会長は「(緊急事態宣言は)要請がないから発令しないというスタンスでは間に合わない。政府には早め早めに手を打ってほしい」と訴えた。開催中の東京オリンピックの影響について問われた東京都医師会の尾崎治夫会長は「(五輪の開催で)お祭り騒ぎをしているのに自粛してと言うのは難しく、間接的な影響はあったかもしれない」と語った。声明は、40~50代の中等症患者の増加で医療の逼迫が懸念されると指摘し、政府に十分で安定したワクチンの供給を要請。国民には徹底的にテレワークを実施することなどを求めている。声明は日医、日本病院会のほか、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、東京都医師会の連名で出された。 *4-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/120263 (東京新聞 2021年7月29日) IOC広報部長「五輪はパラレルワールド。われわれから広げていない」新型コロナ感染者数過去最多に 国際オリンピック委員会(IOC)のアダムス広報部長は29日、東京五輪のメインプレスセンター(東京都江東区)で記者会見し、国内で感染者数が過去最多を更新していることに関連し「五輪関係者は最も頻繁に検査されており、パラレルワールド(別の世界)みたいなものだ。われわれから感染を広げていることはない」と強調した。バジェット医事部長も五輪が「医療崩壊に影響することはない」と訴えた。大会開催でお祭りムードが広がり、間接的に感染拡大につながっているのではないかとの質問に対し、東京五輪・パラリンピック組織委員会の高谷正哲スポークスパーソンは「専門家の評価に耳を傾けながら安全安心な大会運営に努めたい」と述べるにとどめた。組織委は29日、大会関連で選手3人を含む24人が新たに新型コロナウイルス検査で陽性になったと発表した。組織委が取りまとめた大会関連の陽性者数としては1日当たりで最多。陽性者は今月1日以降で累計198人となった。陽性となった海外からの大会関係者2人が入院していると明らかにした。 *4-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210725&ng=DGKKZO74155890U1A720C2EA3000 (日経新聞 2021.7.25) 接種証明、入国活用も検討 五輪後の感染状況見極め、」渡航向け申請あすから、まず5カ国 政府は26日、新型コロナウイルスワクチンの接種証明書の申請受け付けを始める。海外渡航向けの発行が目的で、全国の市区町村で対応する。まずイタリアなど5カ国が対象になる。東京五輪後の感染状況を見ながら、証明書を持つ人が日本への入国時に利用できる措置の導入も検討する。接種証明書を査証(ビザ)の発行時や入国審査の際に示すと、入国後の待機措置やPCR検査が免除される。手続きが省略されるため、新型コロナ禍での出入国の負担が減る。ビジネス往来の活性化にもつながる。政府は21日、日本で発行する接種証明書が海外の5カ国に入国する際に利用可能になると発表した。イタリア、オーストリア、トルコ、ブルガリア、ポーランドが対象になる。5カ国のほか、韓国でも入国時に隔離されないようにする手続きが簡素になる。隔離免除の申請に必要な書類の一つに認められた。証明書の申請は26日から市区町村で受け付ける。ワクチンを接種した時点で住民票があった市区町村が窓口になる。申請書と接種済み証、パスポートなどを提示する。当面、証明書の交付は書面になる。接種した日時やワクチンの種類、パスポート番号、氏名、生年月日などを日本語と英語で表記する。費用は無料で、スマートフォンのアプリを使う電子証明書の発行も視野に入れる。日本の外務省は外国が発行した証明書の利用を認めず、日本の証明書は受け入れてほしいと交渉してきた。フランスなど一部の国は日本の要請を容認しなかった。出入国の制限は両国が同じ条件を課す「相互主義」を原則にしていることも一因になったとみられる。現時点で5カ国のみとなった日本の証明書の受け入れ国を広げるには「相互主義」への対応が避けられないとの声があがる。外国で発行された証明書を持つ人が日本への入国時に利用できる基準などが課題になる。そのひとつが中国製やロシア製など日本で承認されていないワクチンの扱いだ。中国製を巡っては米欧製に比べて効力が低いとの見方がある。日本の場合、海外からの入国者に原則として72時間以内の陰性証明の提出や、14日間の待機措置を求める。渡航先で活用できても日本への再入国時に証明書が使えない点も議題になる。出入国在留管理庁によると、6月に帰国した邦人は4万3千人、外国人の入国者は1万7千人にのぼる。宿泊施設での待機措置は大きな負担になっている。足元ではコロナの感染状況が再び拡大傾向にあり、政府は導入時期を慎重に探る構えだ。新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂会長は20日の日本テレビ番組で、東京都の1日当たりの新規感染者数が「8月第1週に3千人近くまで増加する」との見通しを示した。政府は入国時の接種証明書を活用するのは感染者数が減少局面に入った段階を想定しており、8月8日の東京五輪の閉幕後になる公算が大きい。経団連は移動自粛の緩和など証明書の国内での活用を提言したが、政府は現状では及び腰だ。ワクチン接種は任意でアレルギーなど特別な事情で接種できない人への差別につながりかねないと懸念する。当面は海外渡航での利用を念頭に置く。 *4-5:https://facta.co.jp/article/202106024.html (POLITICS 2021年6月号[罷り通る出鱈目])「ワクチン敗戦」のA級戦犯、「感染症ムラ」の暴走を止めるのは、本来、政治の役割。加藤官房長官と田村厚労大臣は、その責任を放棄してきた。 新型コロナウイルス(以下、コロナ)対策で、日本は一人負けを続けている。1回でもワクチン接種を受けた人の割合は、2.0%以下(4月29日現在)で、主要先進国(G7)で最下位だ。英国(50.4%)、米国(43.0%)は勿論、G7で日本に次いで接種が少ないフランス(22.4%)にもはるかに及ばない。ワクチン接種が進む国では、感染者が急速に減少している。英国の人口百万人あたりの感染者数は1月10日のピークの881人から32.5人(5月1日現在)に減少し、日本(40.0人)よりも少ない。G7で感染者数が増加しているのは日本だけだ。この状況は国民生活にも影響する。英国では、5月17日に屋内での飲食、映画館などの娯楽施設、ホテルの営業が再開し、6月21日にはマスクの着用を緩和し、ナイトクラブの営業を再開する予定だ。米国も状況は変わらない。カリフォルニア州のユニバーサル・スタジオは4月16日に営業を再開し、27日には、米疾病対策センター(CDC)が、ワクチン接種を済ませた人には、マスク着用義務を解除する方針を出した。5月4日、ドイツでもワクチン接種を終えた人への制限を緩和する方針が発表された。この状況は、緊急事態宣言下の日本とは対照的だ。なぜ、日本だけ上手くいかないのだろうか。実は、このことは今に始まった話ではない。日本のコロナ対策は、昨年から一貫して「劣等生」だった。政府は「日本型モデルの成功」と自画自賛してきたが、実態は違う。本稿では、日本のコロナ対策の失敗の本質をご紹介しよう。 ●医系技官の意向を代弁した出鱈目 コロナ対策の目的は国民の生命と生活を守ることだ。これは、人口当たりの死者数と国内総生産(GDP)の変化を用いれば国際比較が可能となる。日本の2020年の人口10万人あたりのコロナによる死者は2.6人、GDPは対前年比で4.8%減だ。19年のGDPは前年より0.3%増だったから、実質5.1%減となる。本稿では、この値を「GDP変化率」と定義する。では、G7ではどうだろうか。10万人あたりの死者数は日本とは桁違いだ。最も多いのはイタリアで122.7人、日本の47.2倍だ。最も少ないドイツ(40.3人)でも日本の15.5倍となる。一方、経済ダメージは、死者数ほどの差はない。最もダメージが軽微なドイツの「GDP変化率」は5.5%減で、日本(5.1%減)と大差ない。欧米と比較した場合、日本は経済ダメージは大きいものの、死者数の抑制に成功したという見方も可能だ。東アジアと比較すれば、この評価は一変する。主要4カ国・地域の死者数は日本2.6人、韓国1.8人、中国0.3人、台湾0.03人で、「GDP変化率」は、日本5.1%減、中国3.7%減、韓国3.0%減、台湾0.3%増だ。死者数、「GDP変化率」の何れにおいても、日本は最低だ。日本はどこで間違えたのだろう。最初の躓きはPCRを抑制したことだ。コロナ対策が難しいのは、感染者の多くが無症状であることだ。それゆえ周囲にうつしてしまう。コロナ対策の本丸は無症状感染対策で、世界中の研究者がこの問題に取り組んだ。最初の報告は、昨年1月24日、香港大学の研究者たちが英『ランセット』誌に無症状感染の存在を報告したものだ。その後、「無症状コロナ感染」をタイトルに含む約800の英文論文が発表されている。この中で特記すべきは、11月11日、米海軍医学研究センターの医師たちが、米『ニューイングランド医学誌』に発表したものだ。1848人の海兵隊の新兵を隔離して感染状態を調べたところ、51人(3.4%)で感染が確認され、46人は診断時に無症状だった。若年者においては、感染者の大半が無症状ということになる。その後、12月2日にスリランカの研究者が、PCR体制の強化がもっとも有効な対策という論文を、医療政策研究の最高峰『ヘルス・アフェアー』誌で発表した。この報告で、感染の抑制と最も相関したのは、感染者数当たりの検査数だった。ところが、厚労省や専門家たちは、このような研究成果を無視し続けた。政府のコロナ感染症対策分科会会長を務める尾身茂氏は、10月14日の横浜市での講演で「無症状者にPCR検査しても感染は抑えられない」と公言している。もちろん、これは厚労省で医療政策を仕切る医系技官の意向を代弁したものだろう。尾身氏自身、医系技官OBだ。医系技官は、流行当初から「PCRは1%程度の偽陽性があり、PCR数を増やせば、医療が崩壊する」と主張し、検査数を抑制してきた。昨年8月まで医系技官トップで事務次官級の医務技監を務めた鈴木康裕氏は、10月24日の毎日新聞で「陽性と結果が出たからといって、本当に感染しているかを意味しない」とコメントしている。この発言も出鱈目だ。『米国医師会誌(JAMA)』5月6日号には「コロナの診断テストの解釈」という論文が掲載され、「ほとんどのPCRの特異度*注は100%である」と記されている。昨年5月の段階で、PCRの精度が高いことは世界の常識となっており、中国をはじめ世界各国が大規模スクリーニング検査体制の構築を進めていた。この手の出鱈目は枚挙に暇がない。11月25日の衆議院予算委員会で田村憲久厚労大臣は「アメリカは1億8千万回検査しているが、毎日十数万人が感染拡大している」と答弁しているが、これも不適切だ。前述したように、感染抑制と相関するのは、検査の絶対数ではなく、感染者数あたりの検査数だ。田村大臣発言当時の米国の感染者あたりの検査数は12.3回で、日本の18.9回以下だ。その後、米国は検査体制強化に努め、4月29日現在の感染者あたり検査数は20.0件で、日本(14.5件)を追い越した。 * 特異度(とくいど)=臨床検査の性格を決める指標の1つで、ある検査について「陰性のものを正しく陰性と判定する確率」として定義される値である。 ●変異株6割見落とす「二段階検査」 感染症対策の根幹は検査だ。菅義偉総理は繰り返し「検査体制の強化」を主張するが、日本の検査能力はいまだに後進国レベルだ。4月29日現在の人口千人あたりの検査数は0.58件で、英国(15.8件)、米国(3.1件)はもちろん、インド(1.22件)の半分以下である。PCR抑制は様々な影響を与えた。変異株のまん延もその一つだ。厚労省はPCR陽性例の4割を変異株の検査に回したが、そもそもの検査数が少なく、かつ6割はノーチェックなのだから、変異株の大部分を見落としてしまった。4月19日~25日の間に東京都では5090人のPCR陽性が確認され、このうち41%に変異株検査を実施したが、56%が陽性だった。大阪・兵庫・京都では、変異株の割合は80%を超える。実は、世界の変異株検査のやり方は、日本とは全く違った。二段階検査のような手間のかかる方法ではなく、複数の遺伝子配列を同時に増幅することができる「マルチプレックスPCR」を用い、一回の検査で変異株の感染を判断している。この方法を用いれば、検体を国立感染症研究所(感染研)などの専門施設に運ぶ必要はなく、医療機関や民間検査センターでも検査が可能で、結果はその日中にわかる。1月8日、米食品医薬品局(FDA)は、「マルチプレックスPCR」の使用を推奨したが、感染研は執拗に従来の方法にこだわり、いまだに導入されていない。 ●「公共事業」と化した積極的疫学調査 なぜ、厚労省は、ここまでPCRを抑制するのか。それは感染症ムラの利権に関わるからだ。感染症ムラとは、厚労省医系技官、感染研、専門家で構築される利益共同体だ。その中心は健康局結核感染症課だ。コロナ対策の法的根拠となる感染症法と検疫法を所管し、後述する感染症関係の研究予算を差配する。課長は医系技官の指定席だ。コロナ対策で、感染症ムラにとっての「公共事業」と化したのは積極的疫学調査だ。この調査は、感染症法で規定される法定感染症が発生したとき、厚労省が指示し、感染研と保健所が連携して実施することと規定されている。この調査では、感染者を発見したら、保健所が濃厚接触者を探しだし、PCRを実施する。もし、感染していれば、さらに濃厚接触者を探し、芋づる式に感染者を見つける。この芋づるをクラスターと呼ぶ。クラスター調査は、世界のどこでも実施している標準的な感染対策である。日本があえて「積極的」と称するのは、感染者の過去14日間の行動を調べ、接触者を探しだし、彼らを検査するからだ。この際、保健所職員を動員しての人海戦術による聞き取りを実施する。海外では感染者が見つかると、その後に接触した人を洗い出し、発症するか調査するだけだ。この際、接触アプリを活用する。厚労省や「感染症ムラ」の研究者は、積極的疫学調査を自画自賛する。コロナ感染症対策分科会の委員を務める押谷仁・東北大学教授は、昨年3月22日のNHKスペシャルに出演し、「全ての感染者を見つけなければいけないというウイルスではないんですね。クラスターさえ見つけていれば、ある程度の制御ができる」と述べている。この指摘が間違いであったのは、いまや明白だ。感染がまん延すれば、クラスター対策では対応できないことは素人でもわかる。感染研も積極的疫学調査の実施要領に「(大流行下では)感染経路を大きく絶つ対策が行われているため、個々の芽を摘むクラスター対策は意味をなさない場合がある」と記していた。ところが、彼らは未だにクラスター対策に固執する。1月8日には、実施要領の記載を「効果的かつ効率的に積極的疫学調査を行うことが重要になる場合がある」と変更し、2月25日に分科会が提出した提言には現行の調査を強化した「深掘積極的疫学調査」を盛り込む始末だ。なぜ、ここまでしてクラスター対策に拘り、PCRを抑制するのか。それは「クラスターさえ見つけていれば、ある程度の制御ができる(押谷教授)」というフィクションが通用している限り、彼らがカネとポストを独占できるからだ。研究者にとってのカネとは研究費だ。結核感染症課は「新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業」を所管する。この予算は19年度の約3億4千万円から、20年度には36億5400万円に増額された。公募形式だが、採択されるのは感染症ムラの面々ばかりだ。20年度に採択された41人中、20人が感染研で、27人が感染症ムラ関係者だ。彼らが受け取った研究費の総額は約31億1800万円で、全体の85%を占める。もちろん、感染症ムラの研究者がしっかり成果を出してくれれば問題はない。ところが、研究成果が乏しい。米国立医学図書館データベース(PubMed)によれば、4月14日現在、日本人研究者が筆頭著者の856報の論文が発表されている。施設別で最も多いのは東京大で54報だ。感染研は19報で7位、横浜市大(16報)と同レベルだ。感染症ムラの情報独占や過剰な資源投入は、日本の研究力を削ぐ。4月8日現在、PubMedには6万2905報のコロナ論文が収載されている。国別でトップは米国の1万1251報で、中国(8881報)、イタリア(6945報)、イギリス(6448報)と続き、日本(1333報)はG7で最下位だ。人口10万人あたりで比較すると、日本は1.1報。OECD加盟国37カ国中32位で、ハンガリーやコロンビアと同レベルである。コロナ研究は熾烈な競争の世界だ。様々な分野の専門家が参入する。例えば、ワクチン開発に成功した独ビオンテックと米モデルナは、元はがん治療ワクチンを開発していたバイオベンチャーだ。ゲノム情報を分析し、ワクチン候補となるmRNAの配列を決定するノウハウを有していた。昨年1月、中国の研究チームがコロナのゲノム配列を公開すると、その情報を分析し、ワクチン開発に取りかかった。彼らの成功は感染症に加え、免疫学や情報工学の専門家の有機的な連携によるものだ。感染症ムラの「お医者さん」がカネと情報を独占する日本とは違う。 ●「感染症ムラ」の暴走に目をつむる 余談だが、ゲノム研究の世界的リーダーは中村祐輔・がん研がんプレシジョン医療研究センター所長だ。昨年、米メディアがノーベル生理学・医学賞候補に挙げた。残念なことに、中村氏が「感染症ムラ」から招聘されることはない。中村氏は大阪大学を卒業した外科医だが、あまりにも高名な中村氏は「感染症ムラ」にとって煙たい存在なのだろう。話を戻そう。では、どうすればいいか。感染症ムラの暴走をコントロールするのは、本来、政治の役割だ。その役割を担うべきは、加藤勝信官房長官と田村厚労大臣だ。前職は、それぞれ厚労大臣と自民党コロナ対策本部本部長で、政府・与党の責任者を務めた。ところが、彼らは、その責任を放棄してきた。PCRについての田村厚労大臣の不適切な発言は前述の通りだ。加藤官房長官の姿勢を象徴するのは、37.5度4日間の自宅待機への対応だ。検査を希望する国民に理解を示すことなく、昨年5月8日には「我々から見れば誤解」と国民に責任を押し付けた。PCRもできず、ワクチンも開発できず、緊急事態宣言を繰り返す日本で、多くの人命と財産が失われた。クラスター対策に固執し、非科学的な対応を取り続けてきた感染症ムラと、彼らの暴走に目をつむった政治家による人災だ。これまでの経緯を検証し、ゼロベースで体制を見直さねばならない。 *著者プロフィール:上昌広(かみまさひろ);特定非営利活動法人「医療ガバナンス研究所」理事長、1968年生まれ。兵庫県出身。東大医学部卒。国立がんセンター中央病院薬物療法部医員として造血器悪性腫瘍の臨床研究に従事し、2016年まで東大医科学研究所特任教授を務める。2005年より東大医科学研究所先端医療社会コミュニケーションシステムを主宰し、医療ガバナンスを研究。医療関係者など約5万人が購読するメールマガジン「MRIC(医療ガバナンス学会)」の編集長を兼ねる。 <五輪開会式から見た教育の問題点> PS(2021年7月31日追加):五輪選手は世界の一流であるため、さすがに質が高くて気持ちの良い競技をするが、それぞれ地域の代表なので東京五輪のような無観客の会場で競技をするのは久しぶりだろう。その五輪で開催地の見識と実力が最も現れるのは開会式と閉会式だが、*5-1のように、開会式は新型コロナのパンデミックを理由に無観客・選手のマスク着用が義務付けられていた。しかし、ワクチン接種が済み、毎日PCR検査をして陰性を証明している選手にマスク着用は不要であるし、観客にワクチン証明か陰性証明があれば無観客である必要もないのだが、その判別もつかないのが、日本の厚労省・同専門家会議・政治家・メディアなのである。 私も東京五輪の開会式は見たが、①選手の入場行進に「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」などのゲームの楽曲が多く使われ ②歌舞伎俳優市川海老蔵さんの演技は少しで ③各種競技のピクトグラム(絵文字)をパントマイムのパフォーマーが演出し ④聖火リレーの最終ランナーに大坂なおみ選手が起用されていた。 私の感想は、①②は、日本の芸術の貧困であり、③は面白くはあったが笑う以上の何ものでもなく、歌も上手ではなくて、この開会式にはリオ五輪のようなメッセージ性も本当の芸術もないと思った。唯一存在したメッセージは、最後に④で日本の多様性を示したことだが、これは先進国では当たり前のことで、それと同時に、声がスタジアムに届くよう五輪開会式の会場近くで五輪中止の抗議デモが行われていたのは、外国人差別が現れている上に、外国からのお客さまに対して失礼で、航空自衛隊が描いた空の五輪も風で吹き飛ばされて形にならなかった。 五輪の開会式は、企業にとっても技術や製品を世界に発信する好機だった筈だが、*5-2のように、⑤夜空に立体的な地球を描いたドローンショーは米インテル ⑥水素で聖火をともしたのはENEOS ⑦国立競技場にプロジェクター・音響設備・照明器具を納入して開会式の演出を支えたのはパナソニック ⑧聖火のトーチに使ったアルミニウムの3割は東日本大震災の仮設住宅の窓サッシを再利用してLIXILが製造 ⑨日本代表選手が着る「式典服」と「開会式服」をAOKIHD が用意 ⑩スウェーデン選手団の公式ウエアはサステナビリティーを重視して回収したペットボトル由来の再生ポリエステルなどを採用してユニクロが提供 だそうだ。 しかし、⑤は、素晴らしかったが、米企業インテル製で平昌冬季五輪でも同じショーを披露していたので目新しくはなかった。また、⑥⑧⑨⑩は、開会式の放送時に解説や地球環境配慮のメッセージがなかったため、気付いた人が少ない。⑦は、今や日本の家電はパナソニックしか生き残っていないというお寒い状況を告げるメッセージなのである。さらに、だらだらと入ってきた選手団のプラカードは、国名が漫画の吹き出しに書いてあってアホかと思った。 なお、この開会式を演出したのは、*5-3のように、元お笑い芸人の小林氏だったそうで、小林氏は過去にユダヤ人のホロコーストをコントで茶化した人権意識と見識の低い人だった。組織委の武藤事務総長は小林氏の役割を「全体を統一的で一貫性あるものにするもの」と説明されているが、確かに一貫性を持って教養の香りのない開会式だった。また、7月19日には、開会式の冒頭の楽曲を制作した小山田氏が学生時代の暴行で辞任し、その前には式典を統括するクリエーティブディレクターの佐々木氏が女性タレント容姿侮辱問題で辞任しているため、今回の開会式の軽薄さは、大会を組織した人の首尾一貫した軽薄で教養に欠ける価値観に基づく人選の結果だと言える。なお、*5-4のように、東京五輪の開会式で演出を担当した小林氏の解任について、海外の主要メディアは一斉に報じ、ベンアリ駐日イスラエル大使もツイッターで「ホロコーストの生存者の娘として、小林氏の過去の反ユダヤ主義的な言動に衝撃を受けた」と投稿されたのは当然のことだが、軽薄の仲間である日本メディアは大して問題にしなかった。 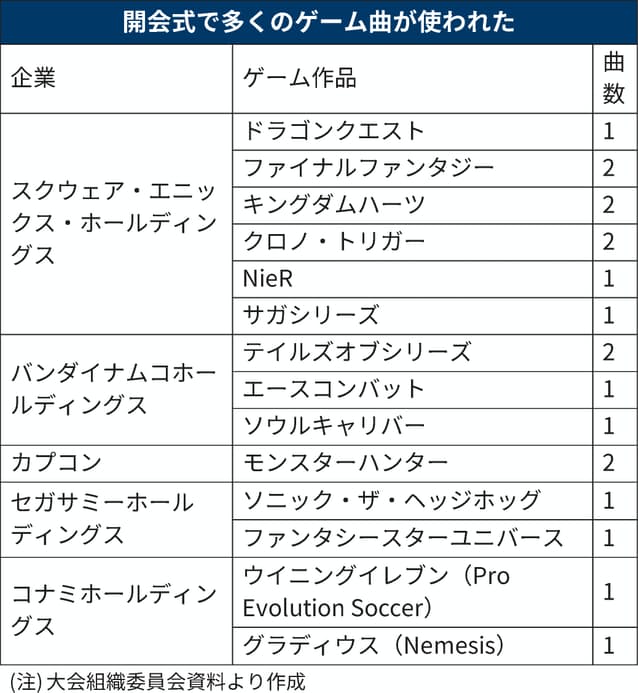   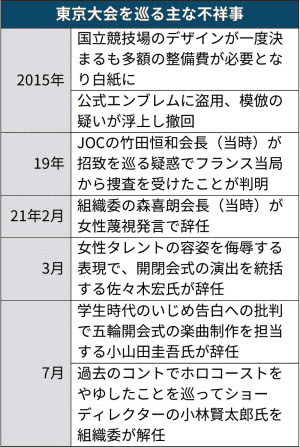 2021.7.23、2021.7.24日経新聞 (図の説明:1番左の表は、開会式で使われたゲーム曲のリストで、左から2番目の図は、日本選手団の入場の様子だ。また、右から2番目の図は、聖火の点火の様子で、1番右の表は、東京五輪をめぐる不祥事のリストだ) *5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210724&ng=DGKKZO74152200U1A720C2NNE000 (日経新聞 2021.7.24) 異例の開会式、各国で詳報 無観客や選手マスク姿、東京五輪、大坂選手の点火速報 東京五輪の開会式が23日、国立競技場(東京・新宿)で行われた。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)下で開かれた今回の開会式について海外メディアは、初めて無観客となったことや選手がマスクを着用して参加したことなど異例ずくめである様子を報じた。米メディアのCNNやニューヨーク・タイムズ(NYT)などは開会式をライブで中継した。選手の入場行進には「ドラゴンクエスト」など日本の有名ゲームの楽曲が使われたと紹介し、各種競技のピクトグラム(絵文字)をパントマイムのパフォーマーが演出したなどと伝えた。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんによる演技も開会式のハイライトとして注目を集めた。聖火リレーの最終ランナーにはテニス女子の大坂なおみ選手が登場、聖火を点火したときには主要メディアが相次いで速報を流した。AP通信は「空っぽのスタジアムで控えめなセレモニーが開かれるなか、東京五輪は始まった」と伝えた。「想像していたものと大きく異なったが、ようやく集まれたのでこの時間を大切にしよう」と呼びかけた国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長による開会式の演説も紹介した。英BBCは「リオ五輪のようなカーニバルも、ロンドン五輪のようにスカイダイビングする女王もいなく、世界が最大の試練に立ち向かうなかで開かれる大会だと思い知らされた」と報じた。「この大会はマスク着用やコロナの陽性検査、そして無観客などこれまでとは異なるが、オリンピックが世界最大のショーであることに変わりはない」と指摘した。五輪の中止を呼びかける抗議デモについても報道が相次いだ。米公共ラジオ放送NPRは五輪開催について日本人の大半が「必要ではなく、危険な状況を作って国民に健康リスクをもたらすと感じている」と報じた。NYTは東京都が現在、コロナの感染拡大に伴い緊急事態宣言を発令中だと指摘。開会式のプログラムの合間に静けさが戻ると、会場の外に集まった抗議デモ参加者の声がスタジアムにも届いたと伝えた。 *5-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC242IB0U1A720C2000000/ (日経新聞 2021年7月24日) 幻想ドローンショー 五輪開会式、企業の技術が支える、環境配慮を世界に発信 23日の東京五輪開会式は、企業にとっても技術や製品を世界に発信する好機となった。夜空に立体的な「地球」を描いたドローン(小型無人機)ショーを手がけたのは米半導体大手のインテル。エネルギー大手のENEOSホールディングス(HD)は五輪史上初めて、環境負荷が小さい水素で聖火をともした。スポーツと平和の祭典を企業が培った技術が支える。夜空を彩ったドローンショー。1824台のドローンが五輪のエンブレムを形作り、平和を象徴する青い地球へと姿を変えた。インテルは2018年の平昌冬季五輪でも1200台超のドローンでショーを披露した。今回、使ったのは4つの羽根を備える「シューティング・スター」という同社のドローンだ。数は平昌の約1.5倍。1台340グラムと軽く、最大秒速11メートルまでの風にも耐える。高精細LEDを4つ搭載。「鮮明で境界のない明るさを実現し、より細かいグラフィックス表現が可能になった」(インテル日本法人の鈴木国正社長)。平昌では各機1つだった。ドローンの動き、光の色や点滅はアニメーションのソフトウエアなどで設計した。インテルは今回の東京五輪で、高性能CPU(中央演算処理装置)を駆使したデータの生成・処理などの技術を提供する。アスリートの動作を複数のカメラで即座に分析したり、立体データから自由に視点を移動したりといったもので、テレビ放送にも活用される。パナソニックは国立競技場にプロジェクションマッピングに使うプロジェクターや音響設備、照明器具を納入し、開会式の演出を支えた。音響設備はスピーカーから離れていても明瞭な音が聞こえる。照明器具は瞬時にオン・オフでき、高精細な4Kや8K放送で色を鮮やかに再現できるように設計した。地球環境への配慮は今大会の大きなテーマだ。国立競技場と夢の大橋(東京・江東)に設置された聖火台にはENEOSHDが水素を供給する。再生可能エネルギー由来の水素だ。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などが福島県に設立した「福島水素エネルギー研究フィールド」(福島県浪江町)で製造し、東京まで運ぶ。再生エネ電力を使い、水を電気分解して発生させた「グリーン水素」だ。製造時にも二酸化炭素(CO2)は出ない。聖火のトーチに使うアルミニウムの製造はLIXILが担った。アルミをリサイクルして窓サッシなどをつくる技術が評価された。素材の約3割は東日本大震災の被災者が暮らした仮設住宅の窓サッシを再利用した。トーチ本体を作ったのは金属加工・販売のUACJ押出加工(東京・中央)。軽量化しつつ、桜をイメージした複雑なデザインを実現する必要があった。金型の設計を繰り返し、約3年がかりで完成させた。トーチは全長71センチ、重さ1.2キロ。約1万本が全国で聖火をつないだ。紳士服大手のAOKIホールディングス(HD)は日本代表選手が記者会見の場などで着る「式典服」と「開会式服」を1600人分用意。日本オリンピック委員会(JOC)などが19年に実施したコンペで数十社の中から選ばれた。開会式服は白いジャケットと赤のパンツ。ジャケットの生地には日本の職人の特殊技術で小さな穴をあけ、通気性と伸縮性を高めた。シャツやブラウスには吸水・速乾機能を持たせた。AOKIHDの青木彰宏社長は「国内で60年間スーツを作ってきた技術を発信できる」と期待する。ファーストリテイリング傘下のユニクロは、スウェーデン選手団に公式ウエアを提供した。環境先進国とされる同国のためサステナビリティー(持続可能性)の観点を重視。回収したペットボトル由来の再生ポリエステルなどを採用した。選手入場時には、国内外で人気の高い家庭用ゲームのテーマ曲などが使われた。「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」などスクウェア・エニックス・ホールディングスの6作品から9曲が採用された。ネット上では「ドラクエの曲で鳥肌が立った」などと大きな反響があった。カプコンの「モンスターハンター」やバンダイナムコホールディングスの3作品、セガサミーホールディングスやコナミホールディングスから各2作品が使われた。 *5-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210723&ng=DGKKZO74137290S1A720C2NN1000 (日経新聞 2021.7.23) 五輪組織委、止まらぬ迷走、開会式演出の小林氏解任、低い人権意識が根底に 東京五輪の運営を担う大会組織委員会の混乱が収まらない。開会式を翌日に控えた22日、ショーディレクターを務める元お笑い芸人の小林賢太郎氏を過去のコント内容を巡って解任した。かねて不祥事は相次ぎ、19日には開会式の楽曲担当者が辞任したばかり。根底にある人権意識の希薄さや「密室体質」を払拭できず、東京五輪そのもののイメージを損なった。開閉会式の制作・演出チームの一員だった小林氏は過去にユダヤ人の大量虐殺(ホロコースト)をコントで扱い、SNS(交流サイト)上で批判が集まっていた。組織委の橋本聖子会長は22日の記者会見で「次々と多くの問題が発覚し、後手に回っている印象があり反省している」と述べた。組織委の武藤敏郎事務総長は小林氏の役割を「全体を統一的、一貫性あるものにするもの」と説明。組織委は演出内容を見直すかどうかを検討したが、22日夜に変更しないと発表した。精査した結果、小林氏1人で演出を手掛けた部分はなかったとし、「予定通り実施する方向で準備を進めている」とコメントした。橋本氏が問題を把握したのは22日未明。外交上の問題にもなりかねないとして同日午前に解任した。米ユダヤ系団体が小林氏を非難する声明を出していた。菅義偉首相も首相公邸で記者団の質問に答えて「言語道断だ。全く受け入れることはできない」と批判した。組織委を巡っては、3月に式典を統括するクリエーティブディレクターの佐々木宏氏が演出関係者に女性タレントの容姿を侮辱するメッセージを送った問題で辞任した。組織委はこれを受け、式典の制作や演出を担うチームを再編成。詳細なメンバーを開会式の9日前となる7月14日になって発表した。選定過程などの説明はなかった。19日にはメンバーの一人、ミュージシャンの小山田圭吾氏が雑誌で告白した学生時代のいじめが問題となり、辞任に追い込まれた。小山田氏は開会式の冒頭の楽曲を制作しており、当該部分の変更を迫られた。小山田氏の場合、いったん組織委は続投させる意向を示していた。今年2月には前会長の森喜朗氏が女性蔑視発言で辞任。組織委の人権意識の低さが相次ぐ不祥事の根底にはある。小山田氏辞任の際、武藤氏は「佐々木氏の辞任後、時間がない中で必要な人たちを仲間内で集める形になった」と説明。小山田、小林両氏について過去の問題の把握や精査はできていなかった。かねて不透明な体質が批判されてきた組織委。2015年には大会エンブレムで盗作疑惑が浮上し、アートディレクターを限られた幹部で決めた経緯が批判された。森氏辞任の際も後任人事を巡り、森氏が元日本サッカー協会会長の川淵三郎氏へ直接就任を打診したことが「密室人事」と非難された。教訓が生かされず、不祥事が収まらない。組織委は都や日本オリンピック委員会(JOC)、政府や民間など出身母体が異なる職員が集まり14年に発足した。専門家が集まった混成組織で職員は約8千人に及び、統治機能が働きにくい。エンブレム見直しでは選考方法を公募に切り替えた。当時の幹部は「国民的事業なので、オールジャパンで策定すべきものだった」と反省の弁を述べたが、不透明な構図は再び繰り返された。五輪の開会式目前になって制作・演出の主要メンバー2人が去った。開会式の演出はほぼ完成し、国立競技場ではリハーサルが連日行われていた。「このタイミングで演出を変更するのはかなり難しい」(組織委の担当者)のが実情だった。開会式は10億人以上がテレビで視聴するとされる。「マイナスのイメージがどうしてもぬぐえない状態で開幕を迎えようとしている」(橋本氏)。「多様性と調和」をテーマに、日本を世界に発信する場は揺らぐ。 *5-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210723&ng=DGKKZO74137320S1A720C2NN1000 (日経新聞 2021.7.23) イスラエル大使「衝撃受けた」 海外から批判相次ぐ 23日に開かれる東京五輪の開会式で演出を担当する元お笑い芸人の小林賢太郎氏の解任について主要な海外メディアも一斉に報じた。スキャンダルが立て続けに起きていることから厳しい批判が相次ぐ。ロイター通信は小林氏がユダヤ人の大量虐殺(ホロコースト)をコントのネタにしていたとみられる動画が拡散したことについて「組織委員会の頭を悩ませる最新のスキャンダルとなった」と報じた。小林氏の解任は開会式の楽曲を制作したミュージシャンの小山田圭吾氏の辞任に続くもので「さらに恥をさらす事態となった」と断じた。AP通信は「感染再拡大の懸念が高まっているにもかかわらず開催を優先させる政府への批判が土壇場の不祥事につながっている」と分析した。外国政府からも批判の声が上がる。ベンアリ駐日イスラエル大使はツイッターで「ホロコーストの生存者の娘として、小林氏の過去の反ユダヤ主義的な言動に衝撃を受けた」と投稿。その上で、小林氏を解任した組織委員会に対して「迅速な対応に感謝する」と述べた。 <先端技術の応用から見た教育の問題点> PS(2021年8月1日追加):*6-1のように、全ゲノム健診で欧米が先行しており、ゲノム解析装置の進化で1人あたりの解析コストは20年前の10万分の1の1,000$(約11万円=109.7¥/$X1,000$)に下がって、世界のゲノム関連市場は2028年までに20年比3倍超の約630億$(約7兆円=109.7¥/$X630億$)に拡大するそうだ。日本では、「①ビッグデータだ」「②マイナンバーだ」「③位置情報だ」と言って勝手に他人の個人情報を集めて使っておきながら、このような時だけ「個人情報保護」「医療倫理」などとして進歩を妨げる声が強くなる。しかし、それなら通常の健診も同じだ。さらに、医療は守秘義務を護るため、①②③よりはずっと安全で、遺伝情報は病気になる可能性が他の人より高いことを示すだけで、現時点で病気でなければ仕事に影響ないため職場で降格や解雇をする理由はない。さらに、遺伝情報は、生命保険会社がそれだけを見てリスク判定できるほど高い確率で一定の病気にかかることを現すわけではないため、守秘義務を護り、データ管理をしっかりしておけば問題ない筈だ。 このように、新型コロナ・ゲノム・地球環境・五輪等の問題を考えるにあたって、驚くほど非科学的で基礎的教養に欠ける思考が続いているのは呆れるほかないが、その根源は多くの国民に行われている教育にあるだろう。 例えば、*6-2-1のケースのように、「①東京都立高校が70年以上も普通科110校で男女別の募集定員を設定して入試の合格ラインで男子に下駄をはかせ」「②都教委が『急に変えると中学の進路指導などが混乱する』と言い」「③副校長だった教員が『理系難関大学への進学実績は保護者の関心事であり、理数系に苦手意識を抱きがちな女子より男子が増えるほうが喜ばしい』と言ったり(これは『ふざけるな』と言いたい)」「④都教委と私立高が全体の定員が都立約6割、私立約4割になるよう調整したり(私立は男女別学で高いのに)」「⑤複数の大学医学部入試で女性差別をして男子に下駄を履かせたり」など、憲法26条1項の「能力に応じて、等しく教育を受ける権利を保障する」に反すると同時に女性に対する人格権の侵害を行い、能力ある人から安価でよい教育を受けさせ社会の発展に資するという教育のもう1つの目的も果たしていない。にもかかわらず、教育者が憲法や教育基本法に反する①~⑤の考え方を持ち、それを疑問にすら思わずに70年以上も継けてきたことは、教育者の質に疑問を感じざるを得ないのだ。 さらに、*6-2-2は、「⑥文科省は小中高校や幼稚園等の教員に10年毎の講習を義務付ける『教員免許更新制』を廃止する方針を固め」「⑦最新の知識や技能を習得する狙いだったが」「⑧多忙な現場の負担が一層増すなど数々の問題が当初から指摘されていた」「⑨現役教員の調査では、8割超が負担を感じ、6割弱が講習内容に不満を持っていた」「⑩講習の頻度が10年に1度では技能向上に結びつかない」「⑪各教育委員会の研修内容とも重複する」としているが、⑥⑩は、確かに10年に1度では技能向上に結びつかないものの、⑪は、教育委員会によって研修レベルが異なるため全国統一された底上げが必要だ。また、⑧⑨のように、多忙を理由として負担を感じるのなら、長期休暇のない職種も研修が義務付けられているのだから工夫が足りないし、⑦の意欲に欠ける不適格な教員と言わざるを得ない。なお、「⑫教え子の未来を左右する教員の責任は極めて重く、教育者としての力や質を高める努力が常に求められる」と言っても、(私はその時に議論の中心にいたので知っているのだが)政治主導がなければ教員が研鑽を積み技能を高める仕組みは入らなかったし、愚痴のように実態を言っているだけでは改善しない。 そのため、政治を批判する前に、教育者自らが常日頃から問題点を把握・検証・改善し続けるべきであり、また、それができる人材を公立校の教員として採用すべきだ。そうでなければ、親の負担が重すぎて、子育てはできないのである。 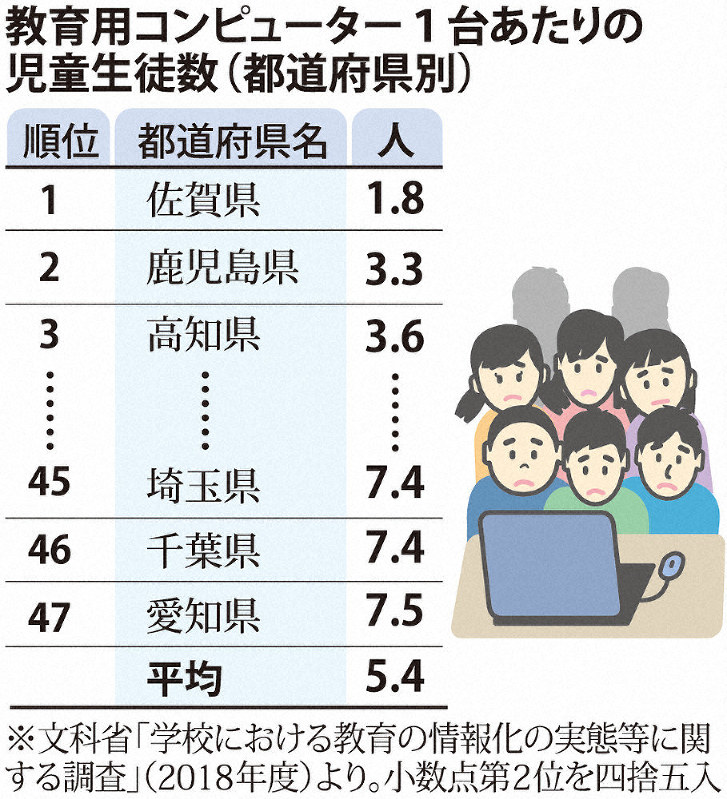 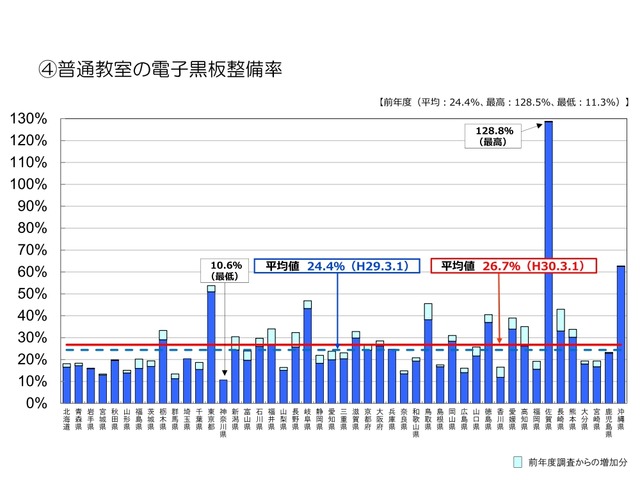 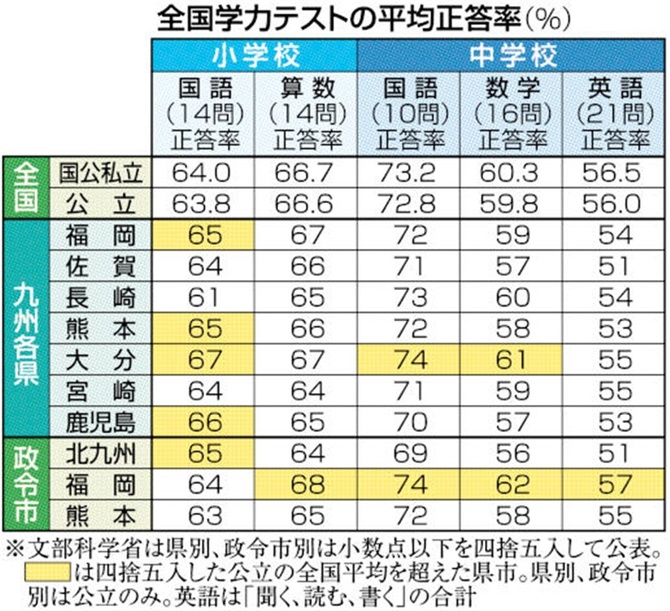 2019.11.28毎日新聞 resemon 2019.8.1西日本新聞 (図の説明:左図のように、教育用PCは九州・四国で普及しており、大都市圏の方が普及していない。また、中央の図のように、普通教室の電子黒板は佐賀県が飛びぬけて普及しており、これらは教育に対する優先順位のつけ方に違いがあるからだろう。右図は、九州地区と全国を比較した学力テストの正答率で、これは地方より大都市、公立より国公私立全体の方が高いが、全国と比較して理由を分析し、教え方を改善していくのも教育者の仕事だと思う) *6-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210725&ng=DGKKZO74155430U1A720C2EA4000 (日経新聞 2021.7.25) 倫理や個人情報課題に 全ゲノム健診、欧米先行 筑波大学などが始める全ゲノム健診では欧米が先行する。一例は米新興企業バリアンティクス(マサチューセッツ州)で1回5600ドル(約62万円)。米国立ヒトゲノム研究所によると、解析装置の進化で1人あたりの解析コストは1000ドルと、20年前の10万分の1に下がったという。米調査会社グランドビューリサーチによると、世界のゲノム関連市場は2028年までに20年比3倍超の約630億ドルに拡大する。予防意識の高まりから健康診断サービスが市場の成長をけん引するとみられている。ただ個人情報保護や医療倫理などの面で課題は多い。ゲノム情報に関する倫理制度に詳しい早稲田大学の横野恵准教授は「ルール整備を通じて差別や不利益に対する利用者の懸念を軽減することが必要だ」と話す。米国では検査の結果に基づいて生命保険や医療保険などの加入を拒否されるといった問題が起きた。08年に遺伝情報に基づく差別を禁止する法制度が整ったが、なお職場での降格や解雇といった事例が相次ぐ。日本では17年、複数の生命保険会社の約款に遺伝情報を用いるかのように読める記載があったことから、金融庁が削除を要請した経緯がある。筑波大でも検査により不利益を被る可能性を事前に説明することや、厳格なデータ管理を求める意見が出たという。今回のサービスでは検査前に対面でリスクを説明し、データは専用サーバーで物理的に隔離する。森・浜田松本法律事務所の吉田和央弁護士は「十分なインフォームド・コンセント(説明と同意)が必要だ」と話す。 *6-2-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14987293.html (朝日新聞 2021年7月25日より抜粋) 男女別定員は必要か 東京都立高校は、募集定員が男女別に設定されています。70年以上にわたって続く制度で、性別によって入試の合格ラインが異なるため、問題視する声があがっています。2018年には大学の医学部入試で、女性や浪人生が差別を受ける不正も明らかになりました。中学の学校現場の声や法律の専門家の話から、入試にまつわるジェンダーの問題について考えました。 ■公立高では都立入試だけ 本社アンケート 都立高校の男女別定員は、全国でみると異例の制度だ。朝日新聞が今年6月、47都道府県にアンケートしたところ、都道府県立高校で定員を男女別にしているのは東京都だけだった。過去に男女別にしていた7府県は「男女の比率にあらかじめ一定の範囲を定めることは合格ラインが異なることになり、男女平等の理念にそぐわない」(兵庫県)などとして、いずれも廃止。一部の学校で残っていた群馬県でも昨年春の入試を最後に廃止した。アンケートでは、男女の生徒数が同程度であるメリットも聞き、「混声合唱や部活動での団体活動が実施しやすい」といった回答があった。一方、「入学時に男女の数字に差が生じることがあるが、課題は生じていない」と答えた自治体もあった。都立高校の男女別定員制度は1950年度に導入された。現在は普通科110校で定員が男女別になっている。一方、定員の9割までを男女別の成績順で決め、残り1割を男女合同の成績順で決める「緩和措置」も98年度から導入。今春の入試では42校がこの措置をとった。男女別定員制度については、これまでも撤廃を求める声が上がっていた。男女別定員を話し合う東京都の検討委員会は90年に撤廃を提言。「小中学校での『男女平等』が高校で一転し、全日制普通科のみ男女を区別して選抜するのは疑問」とした。また、外部の有識者や学校の関係者でつくる都の入試検討委員会も見直すよう指摘している。制度が続いているのはなぜか。都教育委員会は「急激に変えると中学の進路指導などが混乱する。影響が大きいので慎重に検討する必要がある。緩和措置を導入するなど、議論は進めている」としている。私立高校との関係も影響している。都教委と私立高校は、全体の定員が都立約6割、私立約4割になるよう調整。朝日新聞のアンケートでは、東京都以外の17県も私立高との定員調整をしていると回答した。東京都以外の道府県では、性別に基づく定員の調整はいずれも「ない」と答えた。一方、男子生徒の比率が高い東日本の公立難関高で昨年まで副校長だった教員は「数学と理科が難しいと(結果として)女子の合格者が減る」と打ち明ける。理系の難関大学への進学実績は保護者の関心事でもあったといい、「理数系に苦手意識を抱きがちな女子より、男子が増えるほうが、喜ばしい。女子のほうが元気なので、女子がちょっと少ないほうが学校としてはバランスがいいと感じていた」という。 (中略) ■「違憲、医学部入試と根は同じ」 ジェンダー平等を求める弁護士の会 都立高校入試の男女別定員制は、憲法や教育基本法に違反する許されない性差別だ――。「都立高校入試のジェンダー平等を求める弁護士の会」が6月末、制度の廃止と、合否判定における男女格差の是正を求める意見書を公表した。同会のメンバーは2018年に発覚した複数の大学医学部入試での女性差別問題で、訴訟などに関わってきた。意見書では、男女別定員制について「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保障する憲法26条1項に反すると指摘。性別などによる教育上の差別を禁じた教育基本法にも反すると訴えている。また、日本も批准している女子差別撤廃条約は男女に「同一の試験」を保障することを求めているとしたうえで、男女別定員は、受験生個人に保障されている「自ら選んだ学校の入試で公正に評価される権利」の侵害にあたると指摘している。都立高入試は、男女別の定員を明示している点では医学部入試問題と異なるが、同会メンバーの山崎新弁護士(48)は「男女の合格最低点の差を明示せず、正確な情報を隠してきたという点で、東京都は入試の公正性についての説明義務を果たしているとは言えない。性別のみに着目した入試を長年行ってきたという意味で、医学部入試問題と根は同じ」と指摘する。私立校でも男女別定員があり、男女で倍率が異なる学校はあるが、山崎弁護士は「公立校は、憲法に適合し、男女の機会平等を担保しなければならないため、例えば『男女の人数は半々が良い』などの目的で現状のような男女格差を正当化することができない」と訴える。自身も都立高出身といい、「塾が出す偏差値分布では、当時から明らかに男女で差がある高校もあった。にもかかわらず制度が長年維持されてきたのは、多くの場合、不利益を受けるのが女子だったからだ」と指摘する。「根底には性差別への感度の鈍さがある。公正に評価され、能力に応じた教育を受ける個人の権利をないがしろにしてまで、『私立校との定員調整』といったシステムを維持する合理性はない」 ◇フォーラムアンケートに寄せられた声の一部を紹介します。 ●その後の人生にも影響 共学と言っても大学は成績順で合否が決まるし、高校でも理系文系でクラスが分かれれば男女比が極端に異なるクラスもたくさんある。男女比を半々にしたいがために有能な子が不合格になり、希望する教育を受けられないのはおかしいと思う。その後の人生にも影響してしまうのでは。(東京都 30代女性) ●ステレオタイプ、目の当たりに 数年前に大学受験をしました。知人の女性が国立の大学に不合格になり、その母親が「女の子だし私立で十分だ」と慰めるように言ったのを見て衝撃を受けました。また先日、中学生の女の子の親から勉強について相談を受けていたところ「女の子だから数学は苦手で」と言われました。どちらも言った当人に悪気のない慰めや擁護ですが、そのような言葉で子供の首を絞めている側面があるように思います。適当に作られたステレオタイプが実際に成績に影響する(ステレオタイプ脅威)という事実もあるそうです。大人によるこうした刷り込みをどうにか減らせれば、と願います。(東京都 20代男性) ■不利益の当事者、見えぬまま 取材の過程で1990年の朝日新聞朝刊1面の記事を見て驚きました。30年以上前に、都の検討委員会が都立高校の男女別定員制度を撤廃するよう求める記事が載っていたからです。当時からこの制度が「男女平等」に反するという指摘があったにもかかわらず、議論が進まないのはなぜなのでしょうか。山崎新弁護士が「この議論が深まらないのは、当事者が見えないから」と指摘していました。合格最低点が明示されない今の制度では、性別で合否が分かれても受験生自身が知ることができません。合格最低点は東京都だけでなく、すべての都道府県で公表しておらず「ブラックボックス」となっています。公平な入試のために何ができるか、受験生目線で知恵を絞るべきではないでしょうか。 *6-2-2:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/573482 (北海道新聞 2021/8/1) 教員免許更新制 廃止に併せ検証必要だ 文部科学省は小中高校や幼稚園などの教員に10年ごとの講習を義務付ける「教員免許更新制」を廃止する方針を固めた。最新の知識や技能を習得する狙いだったが、多忙な現場の負担が一層増すなど数々の問題が当初から指摘されていた。講習の効果自体にも疑問符が付き、マイナス面ばかりが目立つ。廃止は当然である。2009年度に導入されたこの制度は、「教育再生」を掲げた第1次安倍政権の看板政策だった。現場の実態を十分に反映していない制度設計や運用は、政治主導が過ぎた面がなかったか。教員が研さんを積み技能を高める大切さは言うまでもない。文科省は廃止で済ませず、問題点を検証し今後に生かす責務がある。更新制は教員免許に10年の期限を設け、更新時に大学などで30時間以上の講習を受ける仕組みだ。教員は約3万円かかる講習費を自己負担し、受講するために長期休暇などのまとまった時間を割く必要があった。面積が広大な道内では移動や宿泊も重荷だった。文科省による現役教員の調査では、8割超が負担を感じ、6割弱が講習内容に不満を持っていた。講習の頻度が10年に1度では技能向上に結びつかない、各教育委員会による研修内容と重複する―といった現場の指摘も当初から上がっていた。もっと早く対応する必要があったのではないか。教員はいじめや不登校、さらにコロナ禍への対応に追われ、長時間労働を強いられている。免許更新の負担が加われば、教員志望者が減るのも無理はなかろう。導入前の論議では、指導力を欠く「不適格教員」の排除が強調され、現場の管理を強める安倍政権の意向が色濃く反映した。教育の実態に詳しい専門家の知見を軽んじる姿勢も顕著だった。それが今回の方針転換につながったことを忘れてはならない。文科省は来年の通常国会で廃止に必要な法改正を目指す。国会の論議を通じ、教訓を探るべきだ。教え子の未来を左右する教員の責任は極めて重い。教育者としての力や質を高める努力が常に求められる。ただ今回の経緯を踏まえれば、いたずらに制度を変えても実効性に乏しいのは明白だ。子どもの思いや悩みにじっくりと向き合い、学ぶ喜びが感じられるよう授業で創意工夫を重ねる。そんな人材を育てるため、文科省や各教委には働き方改革や研修の改善を進めてもらいたい。 <新型コロナへの対応から見た厚労省はじめ政府の問題点> PS(2021年8月7日追加):*7-1のように、「①新型コロナ第5波の勢いが止まらず、染み出すように地方へと広がっている」「②『五輪を開催しながら外出自粛を求めるのは矛盾したメッセージになる』と専門家が指摘してきた」などとして五輪と結び付ける論調が多いが、①については、7月20日前後は夏休みが始まって学生が帰省する影響であり、②については、国民は五輪と外出自粛が矛盾したメッセージになるから戸惑うほど馬鹿ではなく、変異株を口実にしていつまでも人流を抑えることしかしない厚労省に愛層をつかしているのである。 また、*7-2-1の「③首相は第5波による患者急増を受けて重症者以外は基本的に自宅療養の方針を8月2日に出し、病床逼迫の緩和を狙った」「④入院制限を巡って、急変を見逃すリスクが増すとして、知事や与野党から批判が続出した」「⑤政府は8月5日、新型コロナ患者の入院制限に関して、肺炎などの中等症で酸素吸入が不要でも、高リスクなら入院できると明確にした」については、③⑤は、医師が患者の状況から臨機応変に入院や治療の判断をするのが合理的で、入院・治療に医師以外の人が基準を設け、保健所が重症度の判断をするのは、そもそも医師法違反である。また、入院制限があると、④のように急変を見逃すリスクがあったり、必要な治療を行えなくなったりするので、医師も治療に責任を持てなくなる。そのため、病床逼迫していない地方自治体が同じにする必要はないし、1年半も“病床逼迫”と言い続けている厚労省と同専門家会議は国民に対して無責任極まりなく、これが国民が怒っている理由なのだ。 さらに、*7-2-3のように、さっさとワクチンを接種してリスクの低くなった人から経済活動を始めればよいし、そのためには、感染リスクの高い職域の人には企業がワクチン接種を求めてよい。また、*7-2-2のように、抗体カクテル療法等の治療薬も早く承認し、ワクチン接種ができない人も安心できるようにすればよかったのに、これまで厚労省がやってきたことは、検査を十分に行わず、水際も不合理で、ワクチンや治療薬も承認せずに、まるで国民の身体で新型コロナウイルスを大切に培養しているかのように逆の対応が多かったのである。 なお、*7-3のように、「⑥全国知事会が国への緊急提言をまとめて、ロックダウン(都市封鎖・強制的外出禁止・生活必需品以外店舗閉鎖措置)のような手法の検討を求めた」とのことだが、私は日本の感染状況なら水際対策を合理的にし、さっさとワクチンを接種し、治療薬を素早く承認して治療すれば、私権の制限は不要なくらいだったと考える。むしろ、故意にそれをやらず、国民の身体で新型コロナウイルスを培養してきたのは、私権の制限やロックダウンの可否を口実に憲法に緊急事態条項を入れたり、(詳しくは書かないが、そのうち表に出るのでわかる)特定の事柄を推し進めたりするのが目的だったようで、とても許せるものではないのだ。 また、*7-4のように、米国の企業や州政府では「⑦職員に新型コロナワクチンの接種を義務づける動きが広がり、違反すれば解雇される場合もある」「⑧未接種者には週1~2回の検査やマスク着用を求める」とのことだが、取引相手・客・同僚などに迷惑をかけないため当然だ。日本で接種を急がせるとすれば、接種可能な希望者には接種できる体制が整ってからのことだが、例えば「11月以降の接種は、無料ではなく有料」にすればよいと思う。 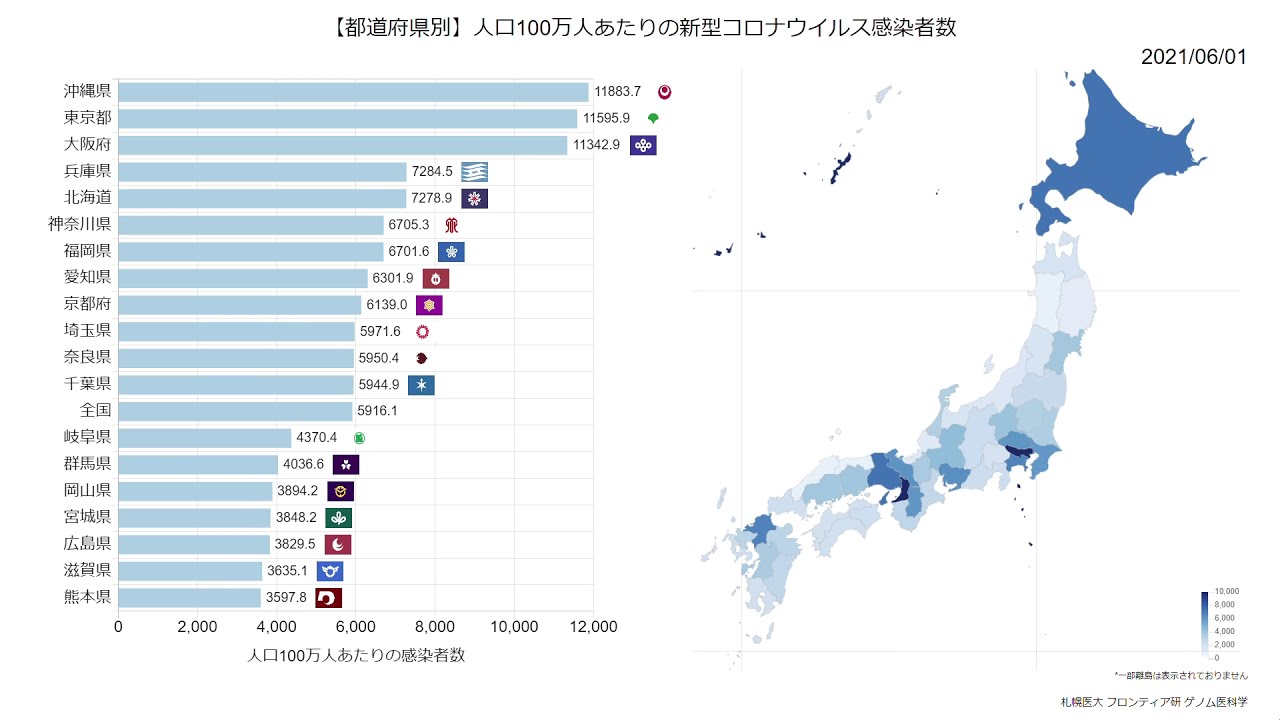 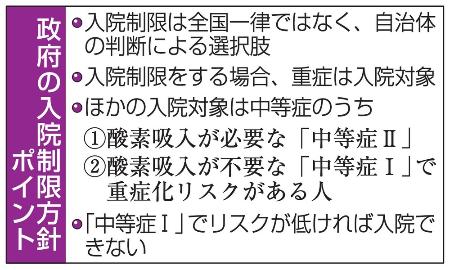 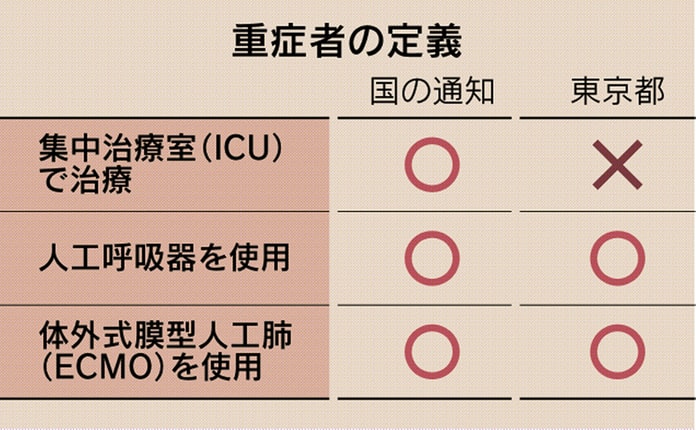 2021.7.7NHK 2021.8.5琉球新報 2020.8.19日経新聞 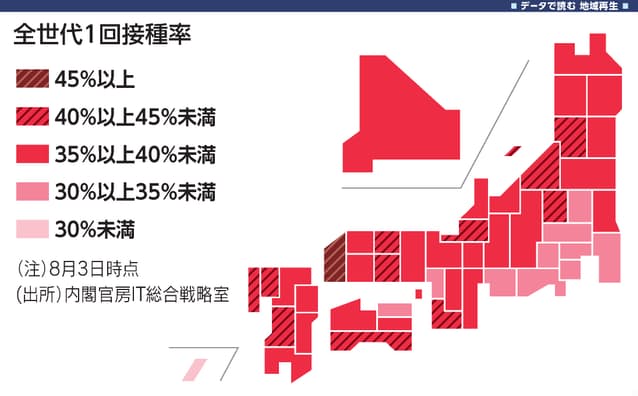  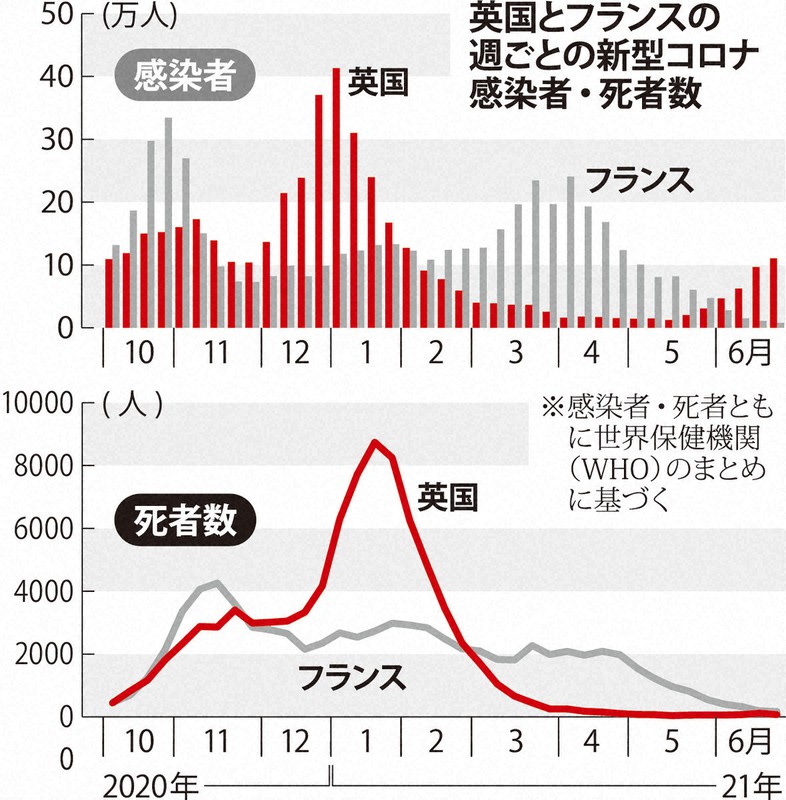 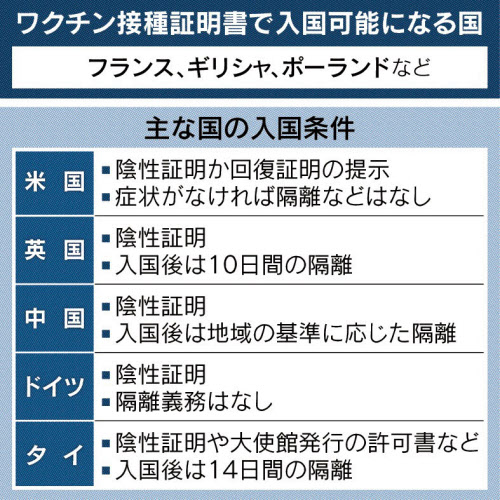 2021.8.6日経新聞 2021.7.6毎日新聞 2021.6.26日経新聞 (図の説明:上の段の左図のように、人口100万人あたりの新型コロナ感染者数は沖縄県が最高だが、下の段の1番左と左から2番目の図のように、全世代のワクチン1回接種率も沖縄県が47都道府県中最下位で、ワクチンの効果は明らかである。また、下の段の右から2番目の図のように、英国とフランスは感染者数が一時的に増加したが、死者数は一貫して減っており、ここでもワクチンの効果が明らかで、1番右の図のように、ワクチン接種によって入国条件を緩和する国が増えたが、これは科学的合理性がある。しかし、日本政府は、必要なことは行わずに入院制限や私権制限を行おうとするばかりで、先進国とは言えない。そして、上の段の中央の図のように、重症か中等症かで入院制限をしているが、医師でもない人がわけもわからず勝手な基準を作って医療行為の可否を決めるのは医師法違反である上に国民皆保険に反する。また、上の段の右図のように、重傷者の定義も常識からかけ離れており、1年半も何をやっていたのかと思う) *7-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/e741ddbcf183aafe6bd5f889864b3b3ba17e6f33 (朝日新聞 2021/8/4) 勢い止まらぬ「第5波」 お盆を待たず地方にも急拡大 新型コロナウイルスの「第5波」の勢いが止まらない。五輪が開催される中、感染が東京など都市部だけでなく、染み出すように地方へと広がる――。専門家が懸念していた状況が現実になっている。人の移動が活発になるお盆の時期を前に、さらなる全国的な感染拡大への懸念が高まっている。朝日新聞の集計では、人口10万人あたりの1週間の感染者数をみると、4連休直前の7月19日には、最も深刻なステージ4(25人以上)は東京、神奈川、千葉、沖縄の4都県。ステージ3(15人以上)も埼玉、石川、鳥取、大阪の4府県だった。それが連休明け直後の25日には、埼玉や大阪はステージ4に。茨城や京都も新たにステージ3になった。今月3日時点でみると、ステージ4に茨城、栃木、群馬などの北関東の各県や、京都、兵庫などの関西圏、福岡などが加わって計23都道府県に拡大。ステージ3はこれらの隣接県を中心に8県となり、全国的に感染者数は増え続けている。昨年末には東京で感染者が増え、帰省の影響もあって年明けから全国に拡大した。第5波でも、お盆で感染が全国に拡大することが心配されていたが、それよりも前にすでに拡大している形だ。五輪を開催する一方で、外出自粛を求めることが「矛盾したメッセージ」になると専門家は指摘してきた。実際、繁華街の人出はこれまでの宣言時に比べても減り方が鈍い。 *7-2-1:https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-1369431.html (琉球新報 2021年8月5日) 中等症、高リスクなら入院 政府、説明内容を修正 政府は5日、新型コロナウイルス患者の入院制限に関し、自治体に示した説明内容を修正した。肺炎などの中等症で酸素吸入が不要でも、高リスクなら入院できると明確にした。菅義偉首相は、入院制限を行うかどうかは自治体の判断とした。首相は感染「第5波」による患者急増を受け、重症者以外は基本的に自宅療養との方針を2日に打ち出し、病床逼迫の緩和を狙ったが、与党からも反発。わずか3日で説明の見直しに追い込まれた。入院制限を巡っては、重症手前の中等症で自宅療養する人が増え、急変を見逃すリスクが増すとして、知事や与野党から批判が続出。与党が撤回を求めたが、首相は拒否した。 *7-2-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/120971 (東京新聞 2021年8月1日) <新型コロナ>抗体カクテル療法 墨田区がスタート 墨田区内四カ所の医療機関で、新型コロナウイルスの新たな治療「抗体カクテル療法」が始まった。基礎疾患のある軽症者や中等症の患者向けで、重症化を防ぐ効果があるとされている。区は独自に、この療法を受けられる区民向けの入院枠計二十床を確保した。政府が特例承認した抗体カクテル療法は、二種類の抗体を組み合わせて点滴投与する。海外の臨床試験では、入院や死亡のリスクを七割減らす効果があるとされた。区内では、都立墨東病院(江東橋四)などで七月二十七日から順次、治療をスタートした。 ◇ 墨田区によると、六月以降、区内高齢者施設でクラスターは起きていない。七月からは六十五歳以上の高齢者の重症者はゼロだ。西塚所長は「命を守るワクチンの効果は出ている」と手応えを語る。区は集団接種会場として、仕事帰りに利用できる駅近くのホテルなどを平日夜間や週末に活用。金曜日の七月三十日夜、錦糸町駅に近い「東武ホテルレバント東京」(錦糸一)では、シャンデリアのきらめく宴会場で約四百人が接種を受けた。会社員の渋江みのりさん(23)は「夜までやってくれて助かる。快適な会場でスムーズに受けられて驚いた」と話した。 *7-2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210804&ng=DGKKZO74484910U1A800C2MM0000 (日経新聞 2021.8.4) NY市、接種証明義務付け 飲食やジム利用で米国初、接種率向上目指す 二ューヨーク市のデブラシオ市長は3日、同市内のレストランやバー、スポーツジムなどの屋内施設を利用する顧客や従業員に新型コロナウイルスのワクチン接種証明の提示を義務付けると発表した。全米の都市で初めて。ワクチンの接種拒否層に対する圧力が広がっている。接種証明の義務付けは8月16日から段階的に導入し、9月13日には全面実施する。デブラシオ市長は3日の記者会見で「ワクチン接種は健康で充実した生活を送るためには必要だ」と述べた。新たに接種証明パスを発行する計画を示した。同市長はすでに警察官や教員を含む市職員にワクチン接種を義務付ける方針を示した。市の成人の66%はワクチン接種を完了したが、接種率は伸び悩む。接種を加速するため、接種者に100ドル(約1万1000円)支払う取り組みも始めた。民間も独自に接種証明書を求める。ニューヨークを拠点に高級レストランやバーを展開するユニオン・スクエア・ホスピタリティー・グループは、9月7日から店内の飲食客にワクチン接種証明書の提示を求める。提示がない場合は「屋外の座席で飲食はできるが店内には通さない」という。 ●社員に接種要求 大手企業ではグーグルやフェイスブックなどが従業員にワクチン接種を求める。米メディアは3日、マイクロソフトが9月から米国内のオフィスで従業員にワクチン接種を求めると報じた。米食肉大手タイソンフーズも3日、全従業員のワクチン接種を義務付けると発表。従業員の半分以上が未接種といい、現場で働く接種者には200ドルを出す。アワー・ワールド・イン・データによると、米国の新規感染者数(7日移動平均)は2日に8万5千人を超え、およそ5カ月半ぶりの高水準となった。感染力の強いインド型(デルタ型)が全体の8割超を占めるなか、ワクチン接種率の低い南部州などで感染拡大が顕著となっている。デルタ型の感染リスクが懸念され、接種ペースはじわりと回復する。1日あたりの接種回数(7日移動平均)は2日時点で67万回となり、50万回まで落ち込んだ7月上旬から増えた。それでもピークだった4月の338万回に比べると5分の1程度にとどまる。(以下略) *7-3:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021080300105 (信濃毎日新聞社説 2021/8/3) 知事会緊急提言 ロックダウンは危うい 新型コロナの流行第5波を受け、全国知事会が国への緊急提言をまとめた。感染対策、検査・医療体制、事業者支援と雇用対策、ワクチン接種などについて計91項目に及ぶ。国民に対しても、夏の帰省や旅行の中止や延期を求めた。第5波は、緊急事態宣言下で五輪を開く東京から一気に地方へ波及し、各地で急拡大が続く。政府は、宣言対象地域の拡大で対応している。効果は乏しく、危機感を共有できる国民への強いメッセージも打ち出せていない。緊急提言は、政府へのいら立ちや不信、悪化する足元の感染状況への焦りが、形になったと言える。政府は知事たちの危機感をきちんと受け止めるべきだ。一方、知事会が提言の中で「ロックダウンのような手法」の検討を求めた点は、人権や自由との兼ね合いから問題がある。ロックダウンは、都市を封鎖したり、強制的に外出禁止や生活必需品以外の店舗の閉鎖をしたりする措置だ。人出を抑えるには有効だが、経済への影響は大きい。欧米を中心に多くの国や地域が踏み切ったものの、感染封じ込めに成功したとは言い難い。昨年3月から断続的にロックダウンを行いワクチン接種も進めた英国では、ほぼ規制が解除された先月27日時点でも1日の新規感染者が2万人を超えている。他の国でも、感染力が強いデルタ株がまん延する中、減少につながらなかったり、解除するとすぐに増加に転じたりしている。ロックダウンを強いられたために家庭内で女性や子どもへの暴力が増え、被害者支援が受けられない事態も起きている。外出禁止を理由に、集会やデモを取り締まる国もある。日本には、強制的な外出禁止を定めた法規定がない。営業や移動の自由を保障する憲法に抵触する恐れがあるからだ。ロックダウンの法整備を求めることは、改憲への誘い水になりかねない。新型コロナに対応する特別措置法も「権利制限は必要最小限でなければならない」と定める。措置を強める前に、やるべきことがあるのではないか。いつでも誰でも何回でも受けられる検査体制は構築できたか。陽性者を一般の生活から離し確実に医療につなげているか。国も地方も不断の検証と見直しが要る。住民と行政に信頼関係がなければ、どんな対策も効果は期待できない。不信が飛び交う中でロックダウンを口にするのは危うい。 *7-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210807&ng=DGKKZO74611080X00C21A8MM0000 (日経新聞 2021.8.7) 米、接種義務相次ぐ 企業・州政府、違反なら解雇も 米国の企業や州政府で職員に新型コロナウイルスのワクチン接種を義務づける動きが広がってきた。違反すれば解雇される場合もある。インド型(デルタ型)の感染が止まらないためだ。米ユナイテッド航空は6日、全米の拠点に所属するすべての従業員に接種を義務づけると通知した。全米の大手航空会社で初めての試み。「全員が接種すれば全員がより安全になる」。スコット・カービー最高経営責任者(CEO)は従業員への手紙で利点を強調した。米食肉大手タイソンフーズは3日、全従業員に完全な接種を義務づける方針を発表した。マイクロソフトも9月から、従業員や取引先などが職場に入る際に接種証明の提示を求める。グーグルやフェイスブックなども出社する従業員に義務づける方針だ。米CNNは6日までに、未接種のまま出社した従業員3人を解雇した。州政府でも接種の義務づけが相次ぐ。ハワイ州や南部バージニア州などは5日、州の職員に接種証明を求めると発表した。未接種者には毎週のコロナ検査を課す。ハワイ州の場合、接種を受けない場合の解雇も辞さない。バイデン大統領も7月末、連邦政府職員に接種状況の開示を義務づけると発表した。未接種者には週1~2回の検査やマスク着用を求める。連邦政府の取引企業にも同様の措置を求めている。 <五輪を見て思ったこと> PS(2021年8月10、13日):*8-1のように、菅首相が、東京五輪について「開催国としての責任を果たし、無事に終えることができた」と言われたのはそのとおりで、五輪を誘致しておいて途中で投げ出すのは無責任すぎるので、無観客開催で高揚感や経済効果が落ちたのは残念だったが、中止するよりはずっとよかったと思う。 私は、*8-3のうち、開会式・閉会式・男女体操決勝・新体操決勝・アーティスティックスウィミング・100m決勝・男子マラソン後半・マラソンスウィミングなどを見たが、100m決勝や男子マラソンでは国籍が違ってもアフリカにルーツを持つ選手が細くて長い足で快走するのに感心し、女子体操・新体操・アーティスティックスウィミングは、旧ソ連系と中国選手の技術の高さと美しさに感心した。日本選手も頑張っていたが。 また、マラソンスウィミングも見たのだが、*8-2のように、水質汚染で薄いカレー汁のような色をして、私なら足もつけたくないくらい汚かった。この場所は、前から、i)悪臭が報告され ii)大腸菌の濃度を懸念する場所で iii)大雨が降ると大量の未処理下水道排水が流れこんでトイレ臭を放っていたため、東京都は、iv)水質改善のために神津島の砂を海中投入し v)大腸菌を防ぐためのポリエステル製のスクリーンを設置し vi)降雨時の流出水を貯める新しい貯水タンクを設置して湾内に放出する前に処理できるようにした のだそうだが、あれは汚染水の色だった。そのため、フォックススポーツ・オーストラリアが「排泄物の中で泳ぐ。オリンピック会場で下水漏れの恐れ」という見出しで水質汚染と悪臭問題を報じたり、ブルームバーグ誌が東京湾の水質問題を「it stinks」と報じたりしたのも理解でき、これを「人工ビーチがあり、レインボーブリッジを眺める景観が最高」と表現する人は、自然の美しい海岸を見たことのない人だと思う。なお、iv) v) vi)の東京都の水質改善対策は大した効果のなさそうな弥縫策であるため、このような場所で2時間前後も泳がせることは、新型コロナが流行している今はなおさら不潔で、選手に失礼である上に人権侵害も心配された。そのため、東京都の下水処理システムを最新のものに変更して東京湾を清潔な海にすることは、東京湾の環境や漁業に不可欠である。 なお、*8-4にも書かれているとおり、東京五輪は開会式だけでなく閉会式も芸術性が乏しくお粗末だった。大竹しのぶは灰色のセンスの悪いスタイルで昭和の格好の子供たちと何かをしていたが、私も「ここで、大竹しのぶ?」と思ったので、芝生でイベントを見ていた外国人選手たちが続々と引き揚げたのも理解できる。一方、*8-5のように、次の開催地パリからのライブ中継は、マクロン大統領も登場し、仏空軍のアクロバットチームがスモークで空にフランス国旗を描き、BMXに乗った若者が競技施設の屋根や名所を走る映像が流れて見応えがあった。また、ワクチン接種証明書か陰性証明書の提出を義務付け、イベルメクチン等の治療薬を承認していれば“密”になってもかまわないため、日本国民が中止や無観客五輪ばかりを主張し、バッハ会長の“銀ブラ”にまでケチをつけるような非科学的“空気”を作っていることには呆れるほかない。 *8-6も、「①バッハ会長の銀座散歩は、IOCファーストに映った」「②新型コロナ感染対策規則集『プレーブック』によって柔道ジョージア代表の2人が東京タワー等を観光した際は参加資格剥奪された」「③政府は『大会関係者は入国後14日間は行動範囲が限定されるが、その後は制約がない』として、バッハ会長の行動を問題視しなかった」「④大会序盤の7月26日に、バッハ会長が笑顔で話しかけた視線の先には阿部兄妹がいて、マスクはつけていたものの、距離は1メートル以内と近かった」と記載している。 しかし、②③は、ワクチン接種済なら選手やIOC関係者は入国後14日間の自粛も不要であるのに、14日間行動範囲を限定したり、ワクチン接種済選手家族の観戦を認めなかったりする規制の方が過剰なのである。ただ、ジョージア代表の2人の選手が東京に関心を持ってくれ、被感染リスクを犯しても街に出たいと思ってくれたことは有難いものの、街に出ると重症にならないまでも感染する可能性はあるため、ワクチン接種をしていない人もいると思われる他の選手に競技中に感染させて迷惑をかける可能性はある。従って、ワクチン接種済で入国後14日経過後のバッハ会長が、①のように、大会終了後に“銀ブラ”をしたり、④のように、ワクチン接種済の選手にマスクなしで話しかけたりしても何の問題もない。それどころか、このようなことに対して、“IOCファースト”とか変な“公平性”を持ちだして他人に不自由を強いたり、足をひっぱったりしたいと考える心を持つことこそ重症の心の病で、外国人差別でもあり、教育の問題である。     日刊スポーツ 2021.8.8daily (図の説明:1番左の図は、大竹しのぶと子どもたち、左から2番目の図が男声ソプラノ《!?》によるオリンピック賛歌だが、いずれもミスキャストでレベルの低い出し物だった。右から2番目の図は、東京音頭による盆踊りで少しは明るくなったものの豪華さはない。さらに1番右は、途中で退場する外国人選手たちだ) *8-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA091130Z00C21A8000000/ (日経新聞 2021年8月9日) 五輪閉幕、首相「開催国の責任果たした」 国民に謝意 菅義偉首相は9日、長崎市内で記者会見し、8日に閉幕した東京五輪について「開催国としての責任を果たし、無事に終えることができた」と評価した。「国民の理解と協力のたまものだ。心から感謝申し上げたい」と謝意を示した。新型コロナウイルスの感染拡大による1年の延期で「様々な制約の下での大会となった」と振り返った。感染対策は「海外から『厳し過ぎる』という声もあったが、『日本だからできた』と評価する声も聞かれた」と説明した。「選手のみなさんは大活躍だった。素晴らしい大会になった」と強調した。大会関係者や医療従事者、ボランティアにも賛辞を送った。首相は9日、首相官邸のツイッターにビデオメッセージを投稿した。すべての選手に「大きな拍手を送りたい」とたたえた。「夢や希望、感動を子ども、若者、世界の人々に届けてくれたことは何ものにも代えがたい未来への財産になった」と訴えた。 *8-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/42e2b7d0eccbf2bb31db3c3673ee4cf3f8620f16 (Yahoo 2021/7/20) 東京五輪のお台場会場の水質汚染と“トイレ臭”問題も海外に波紋…「排泄物の中を泳ぐ」「大腸菌濃度レベルが上昇」 「選手村」での新型コロナウイルス感染や猛暑問題など3日後に開会式を控えた東京五輪に次から次へと懸念すべき問題が浮上しているが、今度はトライアスロンやオープンウォータースイミングなどの会場となっている、お台場海浜公園の水質汚染問題が海外に波紋を広げている。フォックススポーツ・オーストラリアのホームページは「排泄物のなかで泳ぐ。オリンピック会場で下水漏れの恐れ」という強烈な見出しで水質汚染と悪臭問題について報じている。「暑さもさることながら、オリンピックのオープンウォータースイミングやトライアスロンの選手たちが最も心配しているのは、東京湾の水質に懸念がある“臭い湾”だ。トライアスロンやオープンウォータースイミングの会場では、悪臭が報告されており、大腸菌の濃度レベルが上昇していることが懸念されている」としている。お台場海浜公園は、綺麗な砂浜の人工ビーチがあり、レインボーブリッジを眺める景観は最高だが、大雨が降ると、大量の未処理の下水道排水がここに流れこみ、強烈なトイレ臭を放つ。2019年にトライアスロンと、パラトライアスロン、オープンウォータースイミングのプレ大会が開催されたが、選手からは「臭い」とのクレームが続出。パラトライアスロンのスイムは基準以上の大腸菌が検出され中止になっていた。東京都は水質を改善するために伊豆諸島の神津島の大量の砂を海中に投入し、大腸菌を防ぐためにポリエステル製のスクリーンを設置。降雨時の流出水を貯めるための新しい貯水タンクを設置して湾内に放出する前に処理できるようにした。様々な対策は講じてきたが大雨が降ると未処理水を放水せざるを得ないようで、根本的な解決にはなっていない。記事では、それも踏まえて「東京では7月27日から大雨が予想されており、東京湾へ下水が流入する危険性が高まっている」と不安視している。ちなみにトライアスロンは26、27、31日に開催され、マラソンスイミングは8月4、5日に行われる。オーストラリアのトライアスロンチームは1日に2回、自ら水質検査をし、対策を練っており「チームは独自の戦略を準備している」という。ブルームバーグ誌もトライアスロンやオープンウォータースイミングの会場である東京湾の水質問題を報じており、ブルームバーグのレポートは、「it stinks (臭い)」というたった2つの言葉に、今回の問題を集約した。同誌は「問題は単に湾内の水が臭うということではない。これは、東京都が合流式下水道を採用していることが原因だ。合流式下水道とは、雨水と汚水の排水を分離せずに合流させる方式である。ほとんどの場合、このシステムはうまく機能するが、しかし、東京は台風や洪水の影響を受けやすい地域であり、排水システムはすぐに負荷がかかる」と原因を分析。東京都の水質改善の対策を紹介した上で「数週間前から不快な匂いを放っている」と、大会直前になっても改善されていない悪臭と、大会期間中の雨によってさらに状況が悪化することを懸念している。 *8-3:https://digital.asahi.com/articles/ASP8B5W9QP8BUCVL010.html?iref=com_tokyo2020_news_list_n (朝日新聞 2021年8月10日) 五輪閉会式、推計4700万人見た 視聴率最高の競技は ビデオリサーチは10日、NHK総合が8日に中継した東京オリンピック(五輪)閉会式の前半(午後7時58分開始)の平均世帯視聴率(速報値、以下同)が関東地区で46・7%だったと公表した。他地区は関西41・3%、名古屋40・7%、北部九州で41・5%だった。関東地区の個人視聴率は31・5%だった。全国32地区分のデータをもとにした同社の推計では、全国で4699万7千人がこの中継をリアルタイムで視聴したという。ニュースを挟んだ閉会式後半(午後9時23分開始)の世帯視聴率は関東地区で39・8%だった。競技を中継した番組で世帯視聴率(関東地区)が高かったのは▽日本が米国に勝って金メダルを獲得した野球男子決勝の後半部分(7日、NHK総合)=37・0%▽大迫傑(すぐる)選手が6位入賞した男子マラソンの後半部分(8日、同)=31・4%▽日本が延長の末スペインに敗れたサッカー男子準決勝(3日、日本テレビ)=30・8%。 東京五輪で番組平均視聴率が高かったのは ※左から内容(放送日・放送局)、世帯視聴率、個人視聴率 ①開会式(7月23日・NHK) 56.4% 40.0% ②閉会式(8月8日・NHK) 46.7% 31.5% ③野球男子決勝 日本×米国の後半部分(8月7日・NHK) 37.0% 23.5% ④男子マラソンの後半部分(8月8日・NHK) 31.4% 17.7% ⑤サッカー男子準決勝 日本×スペイン(8月3日・日本テレビ) 30.8% 19.6% ⑥サッカー男子準々決勝 日本×ニュージーランドの後半~PK戦 (7月31日・NHK) 26.9% 17.0% ⑦卓球女子団体決勝 日本×中国の前半部分(8月5日・NHK) 26.3% 16.4% ⑧野球男子準決勝 日本×韓国の後半部分(8月4日・NHK) 26.2% 15.9% ⑨サッカー男子1次ラウンド 日本×南アフリカの後半(7月22日・NHK) 25.1% 15.9% ⑩卓球混合ダブルス決勝~表彰式(7月26日・フジテレビ) 24.6% 15.7% (ビデオリサーチの関東地区の速報値をもとに作成。世帯視聴率はチャンネルを合わせた世帯の、個人視聴率は見た人の割合。競技が連続した複数番組にわたる場合は視聴率の高い方のみを記載) *8-4:https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12136-1191509/ (日刊ゲンダイ 2021年8月10日) 大竹しのぶは“貧乏クジ”を引かされた…五輪閉会式で大トリも演出ドッチラケで評価散々 「まるで葬式」と海外メディアに報じられた東京五輪開会式よりも、評価が低いともっぱらなのが閉会式だった。とりわけ大竹しのぶ(64)が合唱団の子供たちと宮沢賢治の「星めぐりの歌」を歌い、聖火台の火が消えるのを見守る大トリのフィナーレはドッチラケで、「なぜ大竹しのぶだったのか」「大女優に恥をかかせた」などとSNSでの評価は散々である。「会場は暗くシーンとして、芝生でイベントを見ていた外国人選手たちも続々と引き揚げていった。彼らも楽しもうとしていたはずですが、出演者も演出も意図も、何が何だか分からなかったのだと思います」(スポーツ紙デスク)。それはお茶の間で式典を見ていた視聴者も全く同じ。組織委によると閉会式のコンセプトは「Worlds we share」。エグゼクティブプロデューサーでスポーツマネジメント会社経営の日置貴之氏(46)は日刊スポーツに対しこう語っていた。「大会の基本コンセプトに『ダイバーシティー&インクルージョン(多様性と調和)』とある。それを考え開閉会式をつくってきた。僕が大事にすべきは、みんながそれを言える、理解する開閉会式」。東京五輪招致の際のコンセプトだった「復興五輪」については「省いたつもりはない。演出には復興の観点もあり、1ミリも忘れていない」とし、東北・復興へのメッセージは「見てもらえば分かる」と胸を張ったそうだ。で、なぜ大竹しのぶだったのか。某ベテラン広告プロデューサーはこう言う。「芸能界の大御所で、選考で名前を挙げれば誰からもケチがつかなかったでしょうし、次の五輪のパリは芸術の都ですから、大竹さんのアートな雰囲気もぴったり。閉会式でmilet(ミレイ)の歌ったエディット・ピアフの『愛の讃歌』は大竹さんも舞台などで歌われているし、何より反戦護憲派で、容姿侮辱や凄惨ないじめ喧伝、ホロコーストをネタにするような過去もありませんからね。また、夜10時すぎに子供を登場させるのは本当はアウトなのですが、その母親、理解ある保護者役のイメージも大竹さんに託したかったのかもしれません」。だが、五輪担当記者はこう言って、首をかしげた。「事実、いわゆる『身体検査』は念入りだったと思います。とはいえ、大竹さんの出演は唐突だったし、復興五輪を印象付けるためでしょうが岩手生まれの宮沢賢治の合唱は安直だったのではという意見が現場ではほとんどでした」。いずれにしても、こうした後ろ向きな基準で閉会式の演出プランが練られていたとすれば残念な限りである。前出のプロデューサーはこうも言う。「今回の東京大会も仕切った電通の担当者たちは電通の中でも特権階級でIOCのバッハ会長が接待されれば、自分たちも同じように優遇されて当然てなものです。世論などどこ吹く風どころか、完全に見下していますから。今回の閉会式も素晴らしい出来だったと自画自賛していて不思議じゃない。だからバッハ会長は大会が終わるやコロナ禍の中、堂々と“銀ブラ”なんかしてるんですよ」。大竹は9日、自身のインスタグラムを更新。「私自身、今この時の開催に、全く疑問が無かったわけではありません」と複雑な心境を打ち明けながらも「制作側のお話を聞いた上で考え、選手の皆さんの5年間を想い、明日に繋がる力になればと舞台に立ちました」と閉会式を振り返った。誰が何をやっても批判されるのは承知の上とはいえ、貧乏クジを引かされた気分だろう。 *8-5:https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2021/08/08/kiji/20210808s00041000661000c.html (スポニチ 2021年8月8日) 東京五輪閉会式 中継のパリ会場は“めっちゃ密”…ネット驚き「過去の動画かと」「同じ世界なのか」 東京五輪は8日、17日間の全日程を終え、無観客の東京・国立競技場で閉会式が行われた。式の終盤では小池百合子東京都知事からパリのアンヌ・イダルゴ市長へ五輪旗渡されるなど、次の開催地への「引き継ぎ式」が行われた。式では東京とパリを一部ライブ中継でつなぐ演出が行われ、エマニュエル・マクロン大統領らが登場。仏空軍のアクロバットチーム「パトルイユ・ド・フランス」が大空を飛び、セーヌ川、エッフェル塔など美しい街並みをバックにトリコロールのスモークを空に描いた。BMXに乗った若者が競技施設や名所から魅力をアピールする映像も流れた。パリのエッフェル塔近くの特設会場にはフランス国旗を手にした大勢の人々が詰めかけて「密」の状態。無観客の東京とは正反対の映像にネット上では驚きの声が続出し、「人多すぎて過去の動画かと思った」「もはや突き抜けてて凄い」「同じコロナ禍の世界とは思えない」「パリってこれ生中継なの?」「パリ、めっちゃ密だけど大丈夫?」「めっちゃマスク無しで密」「めっちゃ密で盛り上がってるパリの映像見ると、なんともいえん気持ちになる」などの声が上がっていた。 *8-6:https://mainichi.jp/articles/20210812/k00/00m/050/181000c?cx_fm=mailasa&cx_ml=article&cx_mdate=20210813 (毎日新聞 2021.8.12) IOC、選手家族の観戦認めず バッハ会長は視察ざんまい 東京オリンピックは主催者の国際オリンピック委員会(IOC)のためにあるのか。そう言いたくなるトーマス・バッハ会長の行動だった。大会期間中、IOCファーストに映る場面はいくつもあった。極めつきは閉幕翌日の9日、東京・銀座の散歩だろう。ポロシャツ姿のバッハ会長は午後4時過ぎ、警護がつく中で銀座を散策した。政府はこの行動を問題視しなかった。新型コロナウイルスの感染対策をまとめた規則集「プレーブック」で選手は厳しい制限下にあった。柔道ジョージア代表の2人が東京タワーなどを観光した際は、参加資格証を剥奪されている。一方、大会関係者は入国後14日間、行動範囲が限定され公共交通機関の不使用などが求められるが、それを経過すれば行動に制約はない。7月8日に入国したバッハ会長は行動制限の対象に該当しないというのだ。大会序盤の7月26日、柔道の競技会場となった日本武道館で、バッハ会長は上機嫌だった。笑顔で話しかけた視線の先には、前日に金メダルを獲得した男子66キロ級の阿部一二三、妹で女子52キロ級の阿部詩のきょうだい。関係者席で大野将平が2連覇を果たした男子73キロ級を一緒に観戦した。マスクはつけていたものの、距離は1メートル以内と近かった。(以下略)
| 環境::2015.5~ | 01:08 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2021,07,08, Thursday
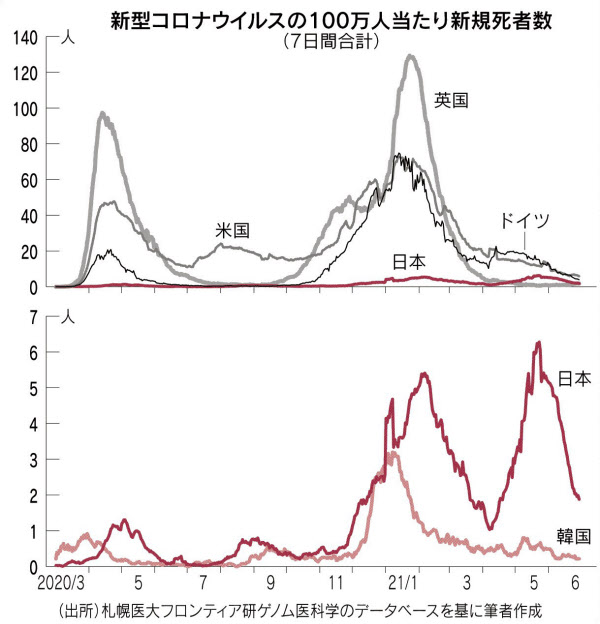 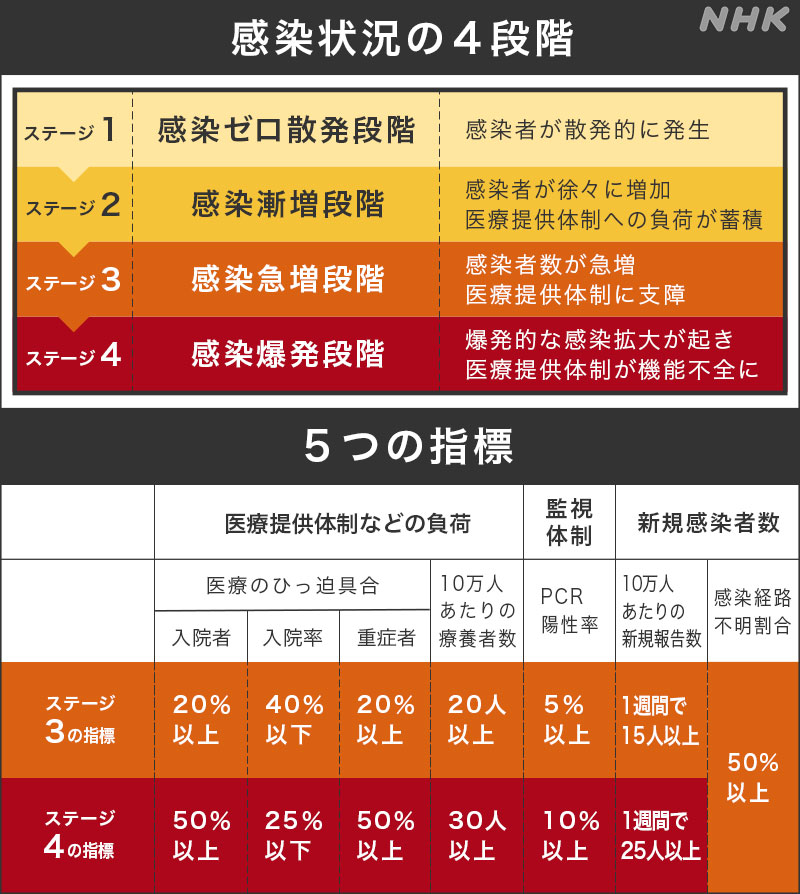 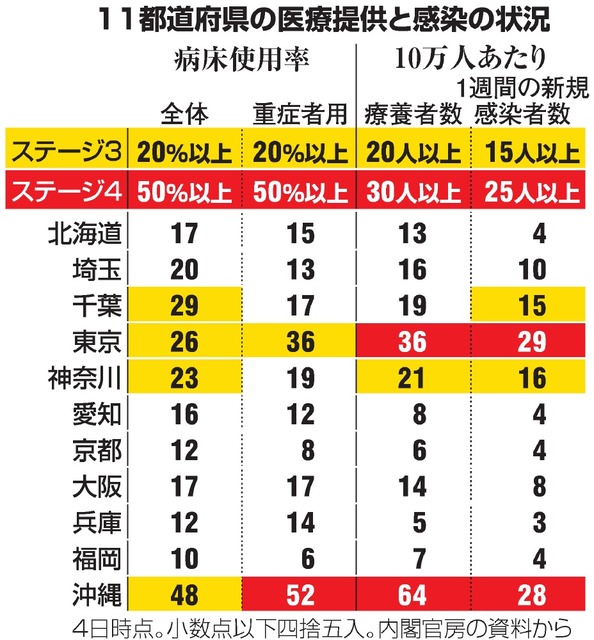 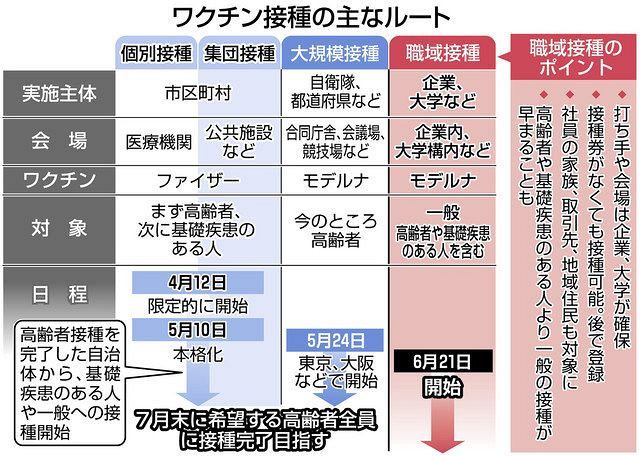 2021.7.2日経新聞 2021.7.7NHK 2021.7.8朝日新聞 2021.6.2東京新聞 *4-1-2より (図の説明:1番左の図は「人口100万人当たり新型コロナ死者数の推移」で、日本は欧米に比べて著しく低いが、近くの韓国より高い。また、欧米・韓国は治療薬とワクチンで感染を抑え込み、日本はこれをやらなかったので、また山ができている。さらに、左から2番目の図のように、人口10万人当たり療養者数が30人以上になると医療が逼迫すると言ったり、機能不全になると言ったりするのも異常で、右から2番目の図のように、病床使用率20%代をステージ3として五輪を無観客にしているのだから、何を考えているのかと思う。なお、1番右の図のように、職域接種が進み始めるとワクチンが足りないと言って接種を停止しており、政府の過失《もしくは故意》にも程があるのだ) (1)国家100年の計 1)中国、習近平総書記の演説にはあった国家100年の計 中国共産党の習近平総書記が、7月1日、*1-1のように、北京市天安門広場で党創立100年記念式典の演説を行われた。私は、中国が改革開放を始めた1990年代に公認会計士・税理士として中国進出企業の監査・国際税務・ODA等で関わっていたため、中国が1990年代に生産で遅れていた理由と、それを克服した経緯を一部ではあるが知っている。そのため、習近平総書記の演説について気がついたことを指摘する。 イ) 国家100年の計について 国家100年の計について、習総書記は、「①中国は、後進的な状態から世界第2位の経済大国へと歴史的な躍進を達成し、それは共産党主導で実現させた」「②全党と全国各民族人民による持続的な奮闘で、党創立最初の100年に掲げた目標を実現し、この地に『小康社会』を築き上げ、絶対的な貧困問題を歴史的に解決し、社会主義現代化強国の全面的な実現という次の100年の奮闘目標に向けて邁進している」とされている。 しかし、中国を名目GDP世界第2位の経済大国にしたのは、鄧小平(1920~1926年にパリ留学)が1978年12月に改革開放路線に転換したからで、鄧小平路線の特徴は、i)経済優先 ii)不均等発展の容認 iii)社会主義体制外の改革先行方式 iv)市場経済の積極的導入 等であり、これら社会主義市場経済体制が中国の経済発展を作った。また、鄧小平氏は1980年代には政治体制改革の必要性も説いていたが、1989年の天安門事件後に政治体制改革を放棄したそうだ。 なお、習総書記は、「③中国共産党は誕生当初から、中国人民に幸福をもたらし、中華民族の復興をもたらすことを使命と決めており、この100年、中国共産党が中国人民を束ね率いた全ての奮闘、全ての犠牲、全ての創造は中華民族の偉大な復興を実現するという一つのテーマに帰結する」とされており、使命に関する理念は立派だと思うが、共産主義の必要性があったかどうかは疑問である。 何故なら、日本は自由主義でも太平洋戦争後の廃墟から約20年で立ち直り、復興期の私の両親の働く姿と1980~1990年代の中国の若者の働く姿がよく似ていたため、中国は大国であるため広くてまとめにくくはあるだろうが、むしろ共産主義体制をとったことで経済発展が30年遅れたように思うからである。 ロ)中華民族の歴史 中華民族の歴史については、「④中国共産党と中国人民の勇敢で強固な奮闘で、中華民族が搾取され、辱めを受けた時代は過ぎ去ったことを世界に宣言する」「⑤私たちは社会主義革命を進め、中国で数千年にわたって続いていた封建的な搾取と圧迫の制度を消滅させ、中華民族の有史以来、最も広く深い社会変革を実現した」とされている。 確かに④⑤のように、中国共産党が列国の支配から中華民族を解放し、深い社会変革を実現したのかもしれないが、私は(他国の実情はよくわからないものの)、蒋介石が中国に自由主義経済を作っていれば、停滞の30年もなかったかもしれないと思う。 ハ)社会主義について 習総書記は、社会主義について、「⑥中国を救い発展させられるのは中国の特色ある社会主義だけだ」「⑦揺るぎなく改革開放を推進し、計画経済体制から活力に満ちた社会主義市場経済体制への歴史的転換を実現した」「⑧改革開放こそが現代中国の前途と運命を決める鍵となる一手であり、中国が大股で時代に追いついた」「⑨100年前、中国共産党の先駆者たちは、真理を堅持し、理想を守り、初心を実行し、使命を担い、犠牲を恐れず、勇敢に戦い、党に忠誠心を持ち、人民に背かない、偉大な建党精神をつくり上げ、これが中国共産党の精神の源」とされているが、⑧の改革開放や社会主義市場経済体制は、本当は社会主義でも共産主義でもない。そして、中国は市場主義経済に移行して後、大股で時代に追いついたのである。 東西冷戦後、社会主義体制だった国に関与して私がつくづく思ったことは、自由主義市場経済体制における自由競争こそが工夫と発展を産み、国の経済発展の原動力になるということだった。そのため、私は、経済で儲けさえすればよいという近視眼的な自由ではなく、理念とセーフティネットを持った進化した自由競争が必要だと考えている。 二)中国の今後について 習総書記は、「⑩2012年の第18回党大会以降、我々は経済一辺倒ではなく政治・文化・社会・環境保護の一体的な発展を重視する『五位一体』体制を見据えて推進した」「⑪中国の革命、建設、改革、中国共産党の創立と強化、発展のために大いに貢献した毛沢東・周恩来・劉少奇・朱徳・鄧小平・陳雲といった同志ら上の世代の革命家を深く忍ぶ」「⑫中国共産党の100年の奮闘から過去に私たちが成功できた理由を見て、未来にどうやって成功を続けられるか明らかにし、それによって新しい道で揺るぎなく、初心の使命を心に刻み、美しい未来を切り開かねばならない」「⑬中国のことをうまくやるために、カギとなるのは党だ」「⑭中国の特色のある社会主義はなぜ良いのか、それはマルクス主義によるものだ」としておられる。 ⑩については、尤もだ。また、習総書記が共産党の党大会でされた演説なので、⑪⑫⑬⑭を言うのも当然だが、ロ)に書いたように、マルクス主義は競争を廃して人々の工夫をやめさせるため、技術が進歩・発展することは少なかった。これが、人間の欲求を動機づけとして活用しないマルクス主義の国すべてに起こった停滞という歴史的事実である。 それでは、何故、中国は改革開放後、名目GDPが世界第2位の経済大国まで発展できたのかといえば、第1に、欧米や日本など外国に見本があったため、それを目標にして一丸となって進むには共産主義体制下での強力な管理体制が有効だったからだ。また、第2に、(科挙のように)海外も含む有能な研究者を厚遇で集めて付加価値を上げる努力をし、世界の研究者を集めて学会を開き、世界の優良企業を誘致して、世界の知を積極的に受け入れたことが大きい。 ただ、第3に、購買力平価によるGDP総額は、2020年に中国が世界第1位、米国が第2位になっているが、同じ購買力平価による1人当たりGDP(分配の仕方にもよるが、国民1人1人の豊かさの指標)は、2020年に中国は世界73位(同米国7位、日本28位)であり、これは中国は人口が多く物価が安いために起こったことである(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%84%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%80%E4%BA%BA%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8A%E5%AE%9F%E8%B3%AAGDP%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88 、 http://www.iti.or.jp/column031.htm 参照)。 そして、このようなことは、日本でも、明治維新後の中央集権と官僚制の開始や太平洋戦争後の復興期に同様に起こったが、世界1の分野が増えて外国に見本がなくなった時、多様性がなく自由な発想のできない制度は工夫がなされにくいので、次の方向性を見失うのだ。 ホ)外交について 外交の歴史については、「⑮中華民族は平和、和睦、調和を5000年以上にわたって追求し、継承してきた」「⑯中華民族の血には、他人を侵略し、覇権を追求する遺伝子はない」と言われているが、三国志などを見る限り国内での酷い戦争も多かったように私は思うが、漢民族は比較的温和だったと聞いてはいる。 また、今後の外交理念として、「⑰人類の将来の運命に心を配り、世界のすべての先進的な力と協力して前進する」「⑱中国は常に世界平和の建設者であり、世界の発展の貢献者であり、国際秩序の擁護者だ」「⑲新たな道のりでは、平和、開発、協力、互恵の旗印を高く掲げ、独立した外交政策を追求し、平和的発展の道を守り、新しい形の国際関係の構築を促進しなければならない」「⑳人類の運命共同体の道を守り、『一帯一路』の質の高い発展を促し、世界に新たな機会を提供しなければならない」「㉑平和、開発、公正、正義、民主、自由という全人類共通の価値観を守る」と言われているのは、総論賛成だ。 しかし、⑱⑲㉑については、国際秩序は「国際法が国内法に優先する」という人類共通の約束事があるため、国内法を優先させて他国の領土を侵害するのは許されないし、「内政干渉しない」という原則もあるため、既に独立国である中華民国(台湾)を無理に併合したり、同国の外交を妨害したりすることも許されない。そして、中国の民主主義や人権に関しては、強力な一党独裁で遅れていることが事実であるため、そろそろ本気で民主化すべき時だろう。 なお、日本では悪口を言う人も多いが、⑳の「一帯一路」は中国国内での経験を基にして、それを他の開発途上国にも敷衍しているものであるため、善意で行う限り、良いことだと思う。 へ)防衛について 防衛については、「㉒中国人民はこれまで他国の人民をいじめ、抑圧し、奴隷のようにしたことはない」「㉓中国の人民は、いかなる外部勢力が私たちをいじめ、抑圧し、奴隷のようにすることも決して許さず、故意に(圧力を)かけようとすれば、14億人を超える中国人民の血肉で築かれた『鋼鉄の長城』の前に打ちのめされるだろう」等と述べられた。 このうち㉒については、TV放送で聞いた時すぐに、「そうかな?」と疑問に思った。他国の人民を積極的に奴隷にしたことはないかもしれないが、自分のことを「中華民族」と呼んでいる反面、周辺の民族のことは東夷(とうい)・南蛮(なんばん)・西戎(せいじゅう)・北狄(ほくてき)という蔑んだ呼び方をしていた歴史的事実がある。 また、日本に倭国(わこく)・奴国(なこく)などという失礼な文字をあて、朝貢してきた国の女王に卑弥呼(ひみこ)という卑しさを現す文字をあてている。文字のなかった日本について記載してあるのは有難いものの、発音にあてられた文字には敬意が感じられない。 なお、㉓は自衛権としては尤もであるものの、領土については、武力ではなく国際法にのっとって主張してもらいたい。 2)それでは、日本の「骨太の方針」に国家何年の計があるか ← 対応が遅すぎる上、タイムスケジュールも不明 「骨太の方針」が、*1-2のように、①新型コロナ対策の強化に加え ②デジタル化 ③脱炭素化 ④地方創生 ⑤少子化対策の4分野を成長の原動力と位置づけて決まったそうだ。 このうち、①については、かなり述べたので簡略に書くと、ワクチン接種完了を「10~11月にかけて」としているのは、「解散」「解散」と騒ぎ立てるメディアや野党を、新型コロナ禍を建前として黙らせるのが目的のように見える。 しかし、何回衆議院が解散されようと、政権が変わろうと、背後の官僚機構が政策を決めている限り、政策は変わらない。さらに、議員が官僚機構よりよい政策を作れなければ、政権は官僚機構に頼らざるを得ないということを、与野党・メディアともに認識すべきだ。そして、それを認識すれば、やるべきことはわかる筈である。 ②③④⑤については、1990~2000年代から始めたものなので、今後のスケジュールを示さなければ意味がない。総花的かと言えば、日本では人口の中で割合が増えている高齢者のニーズを無視しており、高齢者の人権を軽く見ていると同時に、今後は世界で同じことが起こるので、経済における深慮遠謀にも欠ける。 「どの政策を、(財源を含めて)どうやって実現していくか」については、これまで何度も述べてきたように、単にきりつめるだけでなく、正攻法で財源を増やすことや無駄遣いをなくして効率の良い使い方をすることを考えるべきだ。しかし、役所や官僚機構は、税外収入を増やすことは苦手で、古い仕事を既得権として維持しながら、ポジション増加のために新しい省庁を作ることには熱心だ。そのため、「デジタル庁」「こども庁」は、これまでの担当部署を廃して作るのでなければ、無駄遣いと調整すべき相手が増えるだけであろう。 「最低賃金の引き上げ」については、*1-5はじめ、多くの人が言っているが、「賃金を上げれば、生産性が上がる」のではなく、「生産性を上げれば、賃金を上げることができる」のである。そうでなければ、経営が成り立たないので、日本企業は雇用を減らすか、工場を人件費コストの安い海外に移転するかして、日本では雇用が失われる。 にもかかわらず、東大の渡辺教授が、「⑥日銀の異次元緩和で円安が進み、政策目的は円安だけでなく物価と賃金も上げることだったが、円安なのに物価も賃金も上がらなかった」と書いておられる。しかし、金融緩和は円の価値を下げるだけで、金融資産を持ち人口に占める割合の高い高齢者の実質所得や実質年金は減ったため、高いものは買えなくなり、日本製ではなく海外製の安いものに需要が向いたのであり、それは当然の結果だった。 つまり、現在は鎖国をしている時代ではないため、中国・東南アジアなどの海外で安くてよいものができれば、高いだけで値段ほどには品質の違いがない日本製は売れなくなる。従って、「⑦日本は安い国になった」ということ自体は、国民を批判することではなく、政策によって起こった経済現象にすぎないのである。 また、「⑧海外で物価上昇が進めば、現地の競合製品が値上がりするので日本企業も値上げできるが、日本では値上げできないという二極化が既に起きている」というのは、現在の日本は中国・東南アジア等と比較してむしろ共産主義化が進み、顧客ニーズに合ったものを作っていないという面も大きい。そのため競争に負けているのであり、これも自然な経済現象であるため、本質を改めない限り改善しない。 *1-2は、そのほか「⑨持続可能な財政の姿が見えない」「⑩コロナ禍に伴う経済対策で2020年度の一般会計歳出総額は175兆円超、国債は112兆円が新規発行された」「⑪2021年度予算もコロナ対策予備費に5兆円積み、過去最大規模の106兆円に膨らみ、追加支出の恐れもある」「⑫内閣府は、日本経済が高成長したとしてもPBは2025年度に7兆3千億円程度の赤字」「⑬EUは復興財源として国境炭素税などを検討」なども記載している。 ⑩⑪⑫は、コロナ禍というより、五輪の無観客開催も含めてコロナ政策禍であるため、このような政策しかできなかった根本的な問題を解決すべきである。また、コロナ政策禍によって生じた膨大な歳出増・財政赤字と失業は、*1-4のように、無駄遣いの景気対策をするのではなく、今後を見通して炭素税か環境税を導入して再エネ投資を進めることによって解決すべきだ。 なお、五輪の無観客開催については、*1-7のように、政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身会長ら“専門家有志”が「無観客が望ましい」との提言を公表し、これが多くのメディアで主張されて国民の不安を煽っていたが、その根拠は「i)競技場内での感染はないと思うが、人流を抑制したい」「ii)市中と矛盾したメッセージを発しない」「iii)一般市民との公平性」などだそうで、科学とは全く関係のないものだった。 しかし、その影響で五輪が無観客化されたことによって五輪の経済効果がなくなったマイナスは大きく、五輪のために投資した企業は損失を出し、無観客なら五輪の魅力も半減如何になる。さらに、「自国の検査で陰性だったのに、日本で感染が判明した選手団員が出た」「デルタ株の感染力が強い」などを大きく報道しているが、その根拠や解決法について“専門家”の理路整然とした説明はなかったし、「日本のPCR検査のカットオフが厳しいのだ」という説もある。その上、「デルタ株だからワクチンが効かない」とか「デルタ株だから中等症・重傷になる人の割合が増える」ということはない。なお、無観客なら国立競技場を建て替える必要もなかったため、五輪が終わったら民間に売却し、それで五輪開催にまつわる損失を穴埋めすればよい。何故なら、国民は、国民を幸福にしない誤った政策の尻拭いのために税金を負担したくはないからだ。 このような中、*1-3には、「⑭新型コロナ禍で2020年春から積み増した予算73兆円のうち、約30兆円が使い残し」「⑮家計・企業への支払いを確認できたのは約35兆円とGDPの7%程度で、13%を支出した米国と比べて財政出動の効果が限られる」「⑯財政ニーズが強い時に予算枠の4割を使い残す事態は、日本のコロナ対応の機能不全を映し出している」「⑰翌年度への予算繰り越しが30兆円程度出る2020年度は極めて異例」「⑱ワクチン接種の遅れが消費や投資を制約させた影響が大きい」「⑲欧米や中国はコロナ後の成長基盤づくりをにらんでグリーン関連政策やデジタル化など戦略分野へ中長期的財政出動を競う」と書かれている。 このうち、⑱は深刻である上、ワクチンを接種しても「差別」などと言ってワクチンパスポートを出さず、リスクの低い人の経済活動まで止め、⑭⑮の国に補助されなければならない人を増やした。さらに、ワクチンや薬剤の開発・承認も進めず、⑲にも不熱心で、産業の付加価値を上げたり、コストを下げて利益を得たりする機会を逸している。 その上、⑯⑰のように、予算枠を使い残して翌年度に繰り越すこと自体が悪いかのように言うため、ゆとりを持って予算を設定し、不必要になったら使わないという当然のことができない。そして、これは、国に複式簿記による公会計制度を導入して財産管理を徹底しつつ、考え方を変えなければ解決できないものである。 さらに、⑮で「家計・企業への支払いが日本はGDPの7%程度、米国は13%なので、日本の財政出動の効果が限られる」としていることについては、新型コロナ感染者の状況が異なる他国と同じ政策をとる必要はなく、日本の財政には無駄遣いするゆとりはない。 なお、*1-6にも、「⑯後発薬原材料調達は6割が海外で、供給リスクが指摘される」「⑰塩野義は抗菌剤の原料生産設備を今年末までに岩手県に設ける」「⑱日本での原材料製造コストは中国の5倍以上との試算」「⑲国内回帰は薬のコスト上昇に繋がりかねない」などが記載されているが、同じ製品を日本で作ると製造コストが5倍以上になるのが問題なのである。そのため、理由を分析して問題解決すべきであり、そうしなければ他産業も日本には戻って来ず、それと同時に技術も日本から失われるのだ。 (2)客観的根拠に基づく軌道修正が不得意な国、日本 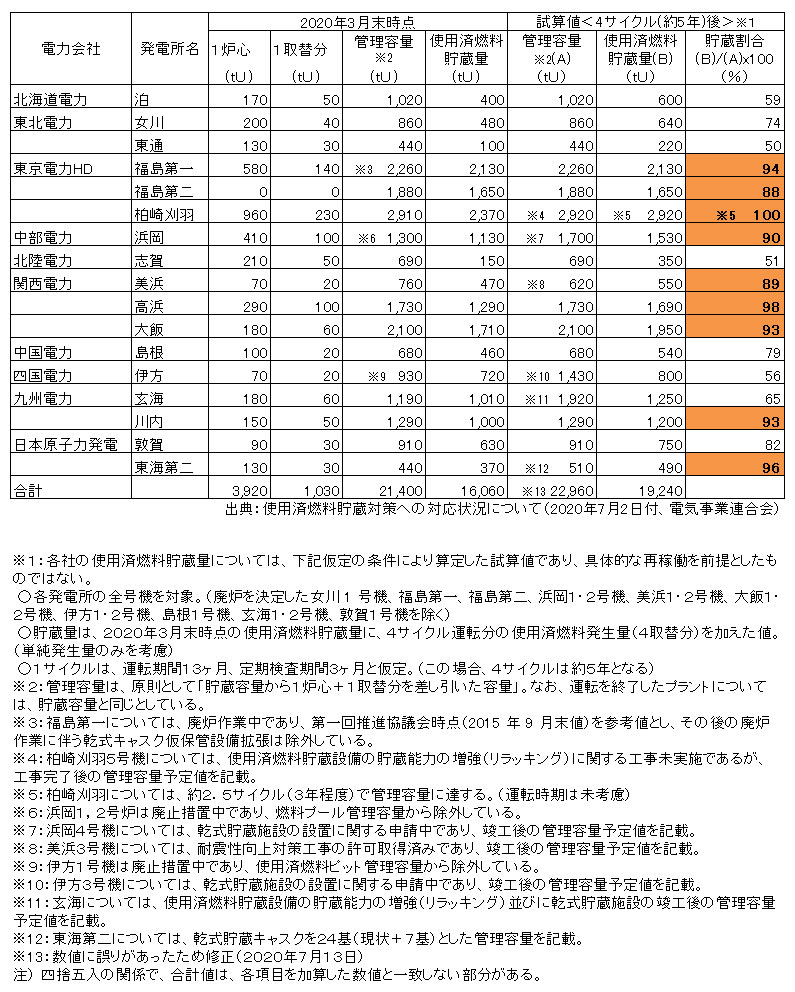  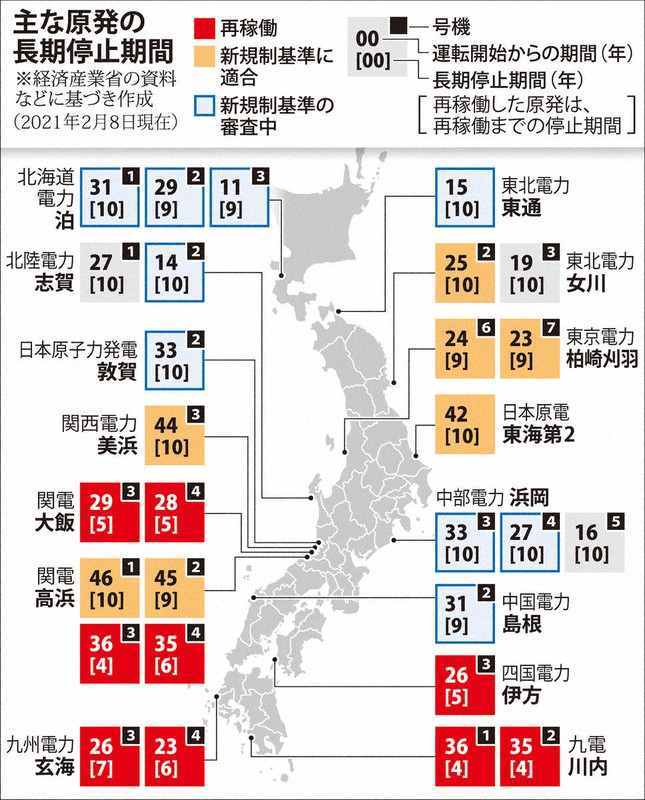 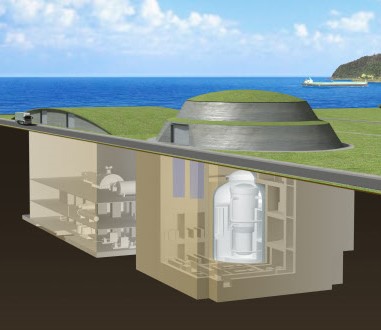 2020.12.21 2021.6.24 2021.2.20 2021.6.26 Net IB News 東京新聞 毎日新聞 日経新聞 (図の説明:1番左の図のように、使用済核燃料の貯蔵割合が100%に近い原発は多く、それは稼働すれば増えるものである。また、左から2番目の図のように、40年を超える関電美浜原発3号機が再稼働したが、その30キロ圏内には28万人弱が暮らしている。さらに、右から2番目の図のように、長期停止の後に再稼働した原発も多い。なお、1番右の図の地下に埋める形式の小型原発が問題解決できるかのような記述があるが、結局のところ何も解決してはいない) 1)それでもまだ、原発の建て替えをしたい人がいるのは何故か? 日経新聞は、*2-1-1のように、「①60年に達する原発が今後出てくるのに、経産省はエネルギー基本計画に原発の建て替えを盛り込まない方向」「②政府は2030年度までに、温暖化ガス排出量を2013年度比で46%以上削減し、2050年には実質ゼロをめざすと決めた」「③原発はCO2を排出しない電源で、これにより2050年の脱炭素社会実現に向けた道筋が描きにくくなった」「④地球環境産業技術研究機構によると、原発活用は電力コストの上昇を和らげる効果もある」「⑤2050年に再生エネで電力すべてを賄うと、送電網の整備などに大きな費用がかかると見込まれるため、電力コストは今の4倍程度に増える」などと、記載している。 ②については、よいと思うが、遅すぎるくらいだ。また、①③については、脱炭素は地球温暖化や公害をなくす一手段にすぎず、それ自体が目的ではないため、普段から温排水や放射性物質を排出し、事故が起こると手が付けられなくなる原発は既に失格であり、早く卒業すべきだ。 具体的には、*2-1-2のように、フクイチ事故を起こした原発処理水を海洋放出して漁業に迷惑をかけようとしており、フクイチ事故自体も広い範囲の農林漁業と地域住民に多大な迷惑をかけた。その上、難しい原状回復のために支払う電気代や税金は莫大で、それがコストに上乗せされている。さらに、*2-4のように、原発建設当時からわかっていた筈の放射性物質を含む使用済核燃料の廃棄場所は未だになく、これにも税金と電気代を使うことになりそうなのだ。 それにもかかわらず、④の「原発活用は電力コストの上昇を和らげる効果もある」などと言っている地球環境産業技術研究機構は、いかにも地球環境を護るような名前の組織だが、理事長の山地憲治氏は原子力の専門家で(https://www.rite.or.jp/about/outline/pdf/yamaji_cv.pdf 参照)、経産省の有識者会合と同様、原発推進派の下請機関である。さらに、⑤については、高度化した送電網の整備は喫緊の課題であるため、この際、送電に参入する組織がインフラ投資を行い、装置が簡単で燃料代0の再エネ電力を普及させた方が賢いに決まっている。 2)耐用年数を過ぎた原発を再稼働させる無神経 イ)仮に避難できれば、原発を再稼働してもよいのか 運転開始から40年を超える関西電力美浜原発3号機が、*2-2-1のように、2021年6月23日、10年ぶりに再稼働したが、重大事故の際に避難対象となる30キロ圏内には28万人弱が暮らしており、避難の実効性には疑問符が付いている。 しかし、原発事故で土地や住居を捨てて避難し、何年~何十年もどこで暮らすつもりか?「国策だったから」として、また国が除染したり公営住宅を建設したりすることを期待しているのなら、既に国策として原発を使う必要はなく、むしろ地域が補助金目当てに原発を再稼働したのだから、復興費用を全国民に負担させる理屈は通らなくなっている。つまり、避難する用意があったとしても、原発を再稼働してよいという理屈は既に破綻しているのだ。 なお、水戸地裁は、30キロ圏に国内最多の94万人を抱える日本原子力発電東海第二原発の運転を禁じる判決を出したが、その根拠も、「市町村で避難計画の策定が遅れており、実現可能な避難計画がなければ運転を認めない」と言うに留まっており、避難した後、どうするかについての考察はない。 ロ)40年超の老朽原発を再稼働する非常識 そのような中、*2-2-2には、「①関西電力が44年を経た福井県の老朽原発を再稼働させ、40年ルールから外れたケースが初めて現実となった」「②関西電力は、同様に老朽化した高浜1、2号機の再稼働も進める方針」「③福井県の再稼働同意は、それを条件とする巨額の交付金を経産省が県に提示したから」「④経産省と大手電力は今回の再稼働を原発復権に向けた足掛かりの一つと捉えている」「⑤例外として最長20年の延長を認める規定がある」「⑥40年の寿命を迎えた原発から順次廃炉して脱原発を着実に進める予定だった」と記載している。 国税庁が示している耐用年数は、単なる建物・建物付属設備でも鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の場合は、工場・倉庫用:38年、公衆浴場用:31年で、金属造の場合は、工場・倉庫用:最長31年、公衆浴場用:最長27年である。また、電気設備・給排水・衛生設備、ガス設備は15年しかなく、機械・装置の耐用年数は、6~13年だ。(https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html 、https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensutatemono.html 、https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukikai.html 参照)。 つまり、放射性物質が飛び交うような過酷な環境でない普通の建物や建物付属設備の耐用年数でも、工場・倉庫用38年で、使用済核燃料プールのように常に水を貯めている建物付属設備なら、公衆浴場用31年である。さらに、電気設備・給排水・衛生設備、ガス設備の耐用年数は古典的で単純なものでも15年しかなく、機械・装置は6~13年で精密になるほど短いのである。 そのため、日頃から周辺機器の点検や交換を行っていたとしても、40年の耐用年数は長い方で、⑤のように、40年ルールから外れる例外を作ることこそ緩くて甘いのだ。そして、それを存分に利用しようと、③のように、国が巨額の交付金を提示し、それにつられて①②④のように、なし崩し的に40年ルールを無視し、⑥の脱原発を闇に葬るやり方は、水際対策をザルにして先端技術も使わず、新型コロナを何度も蔓延させて国民に大損害を与えたのと同じ構図である。 3)日本における想定の甘さ イ)地震の想定と活断層 原子力規制委員会は、*2-3-1のように、九電が玄海原発で想定する地震の最大の揺れを引き上げる必要があるとの見解を示したそうだ。基準地震動とは、原発の耐震設計で基準とする地震動で、周辺の地質・地震学・地震工学等の見地から極めてまれでも発生する可能性があり、大きな影響を及ぼす恐れもあると想定されて、原発の地震対策の前提になるものだそうだ。 規制委は、原発周辺の活断層などによる地震に加えて、過去に国内で発生した地震データを使って揺れを想定する方法を導入し、電力各社に最大の揺れの想定を見直す必要があるかどうか回答するよう要請したそうだが、電力会社が想定を作り直せばお手盛りになるし、耐震補強の追加工事費用も電力料金に加算される。 さらに、活断層も、*2-3-2の「未知の活断層」だけでなく、プレートが強い力で押しあえば新しい活断層ができる可能性もあるため、過去にできた活断層だけを問題にしていることの方がむしろ不思議なくらいである。 そのため、再エネの豊富な九州は、早々に原発を卒業し、大手電力も装置が簡単で燃料費0の再エネ発電に転換した方がよいと考える。その方が、玄海原発周辺の安全性が増し、他産業の誘致がしやすくなるメリットがある。 ロ)使用済核燃料の処分 原発稼働で発生する使用済核燃料は、*2-4のように、再処理工場を経て最終処分場やMOX燃料加工施設に運ばれることになっている。そして、現在、日本国内で貯蔵されている使用済核燃料は約1万8,000tに上り、約5年後には、福島第二で88%、柏崎刈羽で100%、浜岡原発で90%、美浜原発で89%、高浜原発で98%、大飯原発で93%、川内原発で93%、東海第二原発で96%と、一時保管場所の9割が埋まると試算されている。 また、九電玄海原発ではトラッキングで290t、乾式貯蔵施設の設置で440t、四電伊方原発では乾式貯蔵施設の設置で500t、中電浜岡原発では乾式貯蔵施設の設置で400tの追加保管が見込まれるが、これらは原発敷地内に放射性廃棄物が増えることにかわりない。また、東電と日本原電が出資した青森県むつ市の中間貯蔵施設は3,000tの保管を最長50年予定しているが、再処理後の高レベル放射性廃棄物最終処分場の選定はできていない。 なお、使用済核燃料も恐ろしく危険なもので、フクイチのような自然災害による自爆もあり得るが、戦争なら原爆を運んで落とすよりも、原発を攻撃すれば原爆の何十倍もの威力でその国を自爆させることができるものである。そのため、使用済核燃料の処分は、これらのリスクも考慮したものでなければならないのだ。 ハ)小型原発の開発 原発の是非を巡る議論が続いているのに、*2-5は、「①出力30万kwの小型原発を開発する動きがある」「②小型化して建設費を抑え、安全性も高めた」「③脱炭素に繋がる電源として実用化への取り組みは欧米が先行」「④三菱重工は国内の電力大手と小型炉の初期的設計の協議に入った」「⑤建設費は1基2,000億円台で5,000億円規模の大型炉の半分以下」「⑥小型炉は蒸気発生器を原子炉内に内蔵し、ポンプなしで冷却水が循環」「⑦小型炉は地下に設置できるので、航空機等による衝突事故への備えが高まる」「⑧密閉性が高まり放射性物質の飛散も防げる」「⑨米国ではプールにまるごと沈め、非常用電源なしでも冷却でき事故が起きにくい小型炉を開発」などと記載している。 このうち③は、(2)1)に記載したとおり、脱炭素は地球温暖化や公害をなくす一手段にすぎず、それ自体が目的ではないのに、原発を推進するために目的を矮小化して記載している点で悪意であるし、パリ協定も原発は推進しないことを明らかにしている。また、①②⑤については、小型化したから安全になったというのは新たな安全神話にすぎず、出力30万kwが2,000億円台なら出力100万kwが5,000億円台よりも割高なので建設費を抑えたとは言えない。そして、その2000億円には地元懐柔費・事故時の現状復旧費・最終処分場建設費等は入っているのか? さらに、⑥⑨は、ポンプなしで冷却水が循環したとしても、冷却して回収した熱はどこかに逃がさなければならないため、それが海か空気を温めることは避けられず、温暖化防止に貢献することはない。その上、⑧のように、放射性物質の飛散は防げても発生は防げないし、使用済核燃料をどこかに処分しなければならないことに変わりはない。 なお、⑦のように、地下に置いて航空機が突っ込む事故への備えが高まったとしても、サイバー攻撃やミサイル攻撃に対抗できない点は同じであるため、このような危険を犯し、地域住民の犠牲と大金を払って、④のように、国内電力大手が燃料費無料の再エネ(水力・地熱も含む)より原発を選択するには、また何かのからくりがありそうだ。 (3)外交・防衛にも計画性のない国、日本 ← それで勝てるわけはない 1)日本の外交について ← 台湾有事と尖閣諸島問題から 日本は、1972年9月29日に北京で締結した「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html 参照)」の2条で、「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」としているため、中華民国(台湾)の独立性について曖昧で消極的な態度をとっている。 しかし、中華民国(台湾)は独立国であり、中華人民共和国との合併を望んではいないため、7条の「日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない」に該当し、日本政府と中華人民共和国政府の共同声明に基づいて、中華民国(台湾)の独立性が左右されるのはおかしい。 このような中、*3-1のように、麻生氏は「①中国が台湾に侵攻した場合、安保関連法が定める『存立危機事態』に認定し、限定的な集団的自衛権を行使することもあり得る」「②台湾有事は、日本の存立危機事態に関係してもおかしくない」「そのため、日米で一緒に台湾を防衛しなければいけない」との認識を示された。 ①②③の繋がりについては、もう少し詳しい説明を要するが、尖閣諸島問題を見ると中華人民共和国政府の国内法優先による横暴は目に余り、それは国際法にのっとった話し合いでは長期間解決することができていないのである。これは、日本の外交が情けないことも理由の1つだろうが、それだけが理由ではないと思われる。 2)日本の防衛について ← 今さら原子力潜水艦が必要か このような中、*3-2は、「①自由で開かれたインド太平洋を海洋安全保障戦略の基本としている4カ国の専門家が原子力潜水艦の必要性を指摘した」「②今後米中関係がさらに悪化して行く中で、台湾有事も想定せざるを得ない」「③燃料の補充が長期にわたって不要なので、潜水艦、砕氷船、発電バージに小型軽水炉は最適」「④長期間潜ったまま航行できる原潜が中国海軍の動きを抑えるのに役に立つ」等を記載している。 また、*3-3は、「⑤ディーゼルエンジンと蓄電池で駆動する潜水艦と違い、原潜は半永久的に潜水可能」「⑥高濃度の核燃料は数十年にわたって原子炉を稼働させることができる」「⑦燃料を気にすることなく原子炉からエネルギーを得て海水を蒸発させて真水を生み出し、それを電気分解して酸素供給も可能」「⑧船員の酸素確保のために浮上する必要もないため、連続潜航距離を伸ばせる」「⑨米国が、1958年に原潜で北極点の下を潜航通過し、当時、原子力は人間が制御でき、平和利用すれば人々の生活を豊かにするという考えが大勢だった」「⑩その後、原子力潜水艦や原発がいくつも大事故を起こした」等を記載している。 ⑤⑥⑦⑧は事実だろうが、狭い原潜の中に原子炉を積んでいれば、原潜内で放射能が上がることは確実で、放射性廃棄物は海中に捨てており、撃沈された時は燃料もろとも海中投機されるため、原潜の数が増えて実戦で使われれば海洋汚染が進む。そのため、⑨のように、1950年代に原潜を作ったのはわかるが、⑩のように、原発事故や放射能による被害が明らかになった後に、原潜を作ろうというのは時代錯誤も甚だしい。 にもかかわらず、②④を論拠として、日本が原潜を作ろうすれば台湾も迷惑だろう。何故なら、台湾付近で原潜が戦闘を行い、そこで何隻も撃沈されれば、付近の環境や漁業に悪影響を与えるからで、①もまた、時代錯誤の日本主導でこのような指摘になったのではないかと思う。さらに、③に「燃料の補充が長期にわたって不要」と書かれている原潜のメリットは、再エネでも潮流発電を使えば海中でひっそり充電して水素と酸素を作ることが可能だ。 また、④の「長期間潜ったまま航行できる原潜が中国海軍の動きを抑えるのに役立つ」という主張については、そんなことはないだろうし、人間が乗って運転する時代も既に去り、戦争は無人で行う時代になりつつあって、海中や空中はそれに適しているように見える。 (4)人を大切にしない国、日本 ← 医療・介護はじめ社会保障と人権を粗末にしすぎ 1)医療・福祉について イ)過疎地の医療について 日経新聞は、*4-1-1で、「①2050年の人口が2015年比で半数未満となる市町村が3割に上り」「②829市町村(66%)で病院存続が困難になる」「③公共交通サービス維持も難しくなり、銀行・コンビニが撤退するなど生活に不可欠なサービスの提供もできなくなる」「④地域で医療・福祉・買い物・教育機能を維持するには、一定の人口規模と公共交通ネットワークが欠かせない」と記載している。 交通ネットワークが整っていれば、少し広い範囲を医療・教育・福祉・買い物圏にすることができるため、必ずしも1市町村に1つ以上の基幹病院が必要ではないが、病院なら何があっても車で30分以内で専門医にアクセスできるネットワークが必要だし、小中学校はスクールバスで15分以内、保育所・介護事業所は車で5~10分以内にアクセスできる必要があるだろう。 従って、「⑤医療圏内で20人以上の入院患者に対応した病院を維持できる境目となる人口規模は1万7500人で、これを下回ると存続確率が50%以下」というのはかなり大雑把な言い方で、病気によって専門医は異なるため、もう少し広い範囲を視野に入れ、それぞれの病気や事故時には専門医に30分以内でアクセスできる必要がある。そのため、新型コロナ禍でバス事業者が経営難に拍車をかけられたのであれば、小中学校を合併してスクールバスを走らせたり、診療・健診バスや送迎バスを走らせたりなど、これまでなかったバスの使い方を考えるのも一案だ。 また、「⑥基準を満たせない市町村の割合は2015年の53%から2050年には66%まで増える」というのも、病院をネットワーク化してそれぞれに専門の重点を変え、距離が遠くなる地域は診療・健診バスを走らせてカバーするなど、サービスを向上させながら効率化する方法もある。そのため、固定観念ではなく、問題解決重視で改善を重ねることが重要だ。 なお、「⑦2050年に銀行の本支店・営業所は42%、コンビニは20%の市町村で0になるリスクがある」というのは、集落が消滅する前にそういうものがなくなって不便になり、集落の消滅に拍車をかけるので、集落が消滅しないよう、仕事を作り、移住者を増やす必要がある。現在は、農林業・再エネ・製造業の国産化や地方分散が進められている時期であるため、その気になれば仕事や移住者を増やせる筈である。 ロ)全体としての医療の課題 公共経済学の専門家が、*4-1-2のように、「①新型コロナの感染拡大を巡っては、変異株の脅威のほか、五輪開催という重大なリスク要因が存在する」と記載しておられるが、ワクチンは変異株にも有効で、かつ五輪関係者はワクチンパスポートか陰性証明を持ってくる人であるため、検査もワクチン接種もしていない日本人よりよほど安全なのである。 そして、*4-1-2は「②ワクチン接種の大幅加速という好材料も出てきた」とも書いているが、*4-3-1のように、せっかく民間企業が職場接種を始めたら「接種に使われる米モデルナ製ワクチンの供給が追いつかなくなった」として、政府が職場接種の申請受け付けを急遽停止することにした。しかし、職場接種はモデルナ製でなければならないと決まっているわけではなく、「打ち手」が足りないわけでもないため、現役世代の接種を加速させて全体を感染から守るためには、政府は必要な場所に速やかにワクチンを供給することを考えるべきだ。 *4-1-2には、「③ポストコロナの医療供給体制にとっても重要な課題が浮き彫りになった」とも書かれているが、日本の医療供給体制の不合理は新型コロナで初めてわかったのではなく、時代の先端を行く科学の導入や地域医療計画に合わせた医療圏の設定・病院間の分業などの継続的改善を行うことが必要だったのにやっていなかったのだ。そして、厚労省・財務省の著しく単純化された合理化案で改悪されてきたというのが実情である。 また、このほか、*4-1-2には、「④ワクチン接種が加速している欧米諸国は死者数が大幅に減少した」「⑤欧米は死者数で第3波は到来していないが、日本には過去のピークを上回る第4波が到来している」「⑥欧米は景気もV字型の回復軌道に乗ったが、日本は経済効果があり景気回復のチャンスでもある五輪さえ無観客にして逃している」「⑦本格的な市中感染の到来を予期せず、全国レベルのワクチン接種に大きく出遅れたのが、その違いを生んだ主因である」等も書かれており、これは事実だ。 ただ、日本の場合は、地方自治体や国民にある程度の衛生意識があるため、政府による全国一律の強制的ロックダウン等は不要だったのだが、おかしな論調のメディアに引きずられた政府のコロナ対策や医療政策が悪すぎたのである。 また、「⑧急性期医療へのシフトなど構造改革急げ」「⑨利用者の受診抑制の要因や影響探る必要」とも書かれているが、日本の人口当たりベッド数は世界トップクラス、コロナ感染の規模は諸外国より限定的だったにもかかわらず、「医療現場が逼迫する」と言われ続けてまともな医療も受けられない人が続出した。何故か? その原因を一つ一つ解決し、患者のQOL(Quality of Life)を高めながら医療システムを良い意味で合理化することが、医療制度の改善に繋がるし、それはできるのである。 2)教育について イ)教員の質と教員免許更新制 *4-2-1は、「①文科省が、2009年度に導入された教員免許更新制廃止の方向で検討しているが、遅きに失した」「②免許期限を10年とし、30時間以上の講習を自費で受けると更新が認められる」「③数万円の講習費用と交通費を負担して夏休み等に講習に通うことに、教員の大多数が負担感を示し、役に立っていると答えたのは1/3だった」「④更新制は教員不足の一因にもなった」「⑤文科省は、教員の資質確保が目的で、不適格教員を排除する趣旨ではないとする」「⑥教員の多忙さが増し、学校現場の疲弊が深いのに、なぜ免許更新が必要か」「⑦いじめはじめ、子どもたちが抱える問題への対応が追いついていない」「⑧教員が子どもとじっくり向き合って力量を高め、それぞれが直面する課題を持ち寄って自主的に学び合う時間と余裕を生むことが肝心だ」と記載している。 このうち②③については、資格を維持して業務を続けるには、公認会計士(年間40単位)・税理士(年間36単位)も、毎年度に一定以上の研修を受けることが必要で、長い夏休みなどない勤務体系でも時間を作って研修を受けている。その効果は、i)刻々と更新される実務の標準をキャッチアップし ii)知識を深く整理し iii)自分が担当していない業務にも視野を広げる などであり、大学教授の講義の中に実務から離れた役立たないものもあるが、全体としては役立つものが多い。費用は、有料・無料の両方があり、昨年からはリモートでの無料の講義が増えている。 つまり、研修を受けることを負担に感じる人は、もともと勉強好きでないのだと思うが、勉強嫌いな教員に習った子どもが勉強の面白さを教えてもらって勉強好きになるわけがない上、⑥⑦⑧のように、何十年も「忙しさ」を勉強しない口実にして根本的な問題解決をしない人たちに習った子どもに問題解決能力が身につくわけもなく、お粗末な教育の結果は既に出ている。そのため、そういう人が教員を続けていること自体が子どもや国家にとってマイナスであるため、⑤も必要であり、研修内容は毎年改善してよいが、①の教員免許更新制は残した方がよいと思う。 なお、④の免許更新制が教員不足の一因になったという点は、これからの日本を背負う子どもを教育する教員の給料を銀行員・会社員よりも高くし、博士など専門性があり優秀な人が教員になりやすい環境を整えるべきである。 ロ)「才能を持つ子ども」の定義と誤った評価 *4-2-2は、「①芸術・数学などで抜きんでているが、学年毎のカリキュラムや周囲にうまく適合できず、不登校になるケースもある」「②文科省によると、米国では同年齢より特に高い知能や創造性・芸術的才能などを発揮する子どもを「ギフテッド」と呼び、早期入学や飛び級といった特別な教育プログラムが用意されている」「③中にはこだわりが強すぎたり、集団行動が苦手だったりする子もいるとされ、どう支援するかも課題」「④日本では、単純な課題は苦手だが複雑で高度な活動は得意など多様な児童生徒が一定割合存在する」「⑤同質性の高い学校文化そのものを見直すべきとの意見」「⑥松村教授は「『トップ人材を輩出する目標でなく、困っている才能児のニーズに対応する視点で議論すべき』と指摘」「⑦発達障害を抱える子もいるとして特別支援教育や生徒指導との連携も必要とした」などと記載している。 日本では、①の文脈で語られる時、「抜きんでている」という言葉の意味が低いレベルであることが多い。②の米国における「ギフテッド(神から才能を与えられた者という意味)」呼ばれる子どもは、音楽ならモーツァルト、体操ならコマネチ、男子100mならカール・ルイス、科学ならアインシュタインのような本物の「ギフテッド」であり、そういう人やその卵を探して特別な教育プログラムで育てているのである。従って、本人の自然な欲求としてこだわりが強く、努力もしており、だからこそ他人ができない何かを成し遂げることができるのだ。 そのため、③のように、こだわりが強いことを悪いことであるかのように言ったり、集団行動をしないから性格がおかしいかのように言ったりするのは、凡人の歪んだ劣等感の裏返しにすぎない。もし、⑥⑦のように、才能児が困っている点があるとすれば、凡人の誤った評価で発達障害扱いされたり、成長を妨げられたりすることだろう。つまり、⑤のように、いつも集団行動や同質性を強制し、それを疑問にすら思わない大人の方が問題なのである。 なお、④のように、「複雑で高度な活動が得意など多様な児童生徒が一定割合存在する」というのは、よいことでこそあれ悪いことではない。そして、通常は、複雑で高度な活動ができる人は単純な課題はすぐできるが、単純なことを繰り返すのが嫌いなだけである。いずれにしても、これからは、単純作業や体力勝負の仕事はコンピューターやロボットにとられ、人間は複雑で高度な作業で出番が多くなるため、教員の考え方も変える必要がある。 3)間違いだらけの新型コロナ対策 イ)新型コロナと五輪 新型コロナが拡大している中、「五輪を開催しても国民は安全なのか」という論は、*4-3-5をはじめ多い。しかし、「菅首相が何より優先しなくてはならないのは、五輪を予定通り終わらせることではなく、国民の命を守るためコロナ感染を一日も早く収束に向かわせることだ」とし、五輪を開催すると国民の命が守れないかのように記載しているのは変だ。 これは、「子どもの安全のため、放課後は子どもを学校に残さない」と言いつつ、かぎっ子を街に放り出してきたのと同様、安全を建前として使ったより悪い選択への強制である。さらに、五輪の開催を政争の具に使うのは、今後の日本外交に悪影響を及ぼすため許すべきではない。 具体的には、*4-3-5は「①五輪開催都市である東京で新型コロナ感染者が急増している」「②1,000人/日超の新規感染者数の報告が続き、5月の第4波ピーク時を上回っている」「③専門家は現在の増加ペースで推移すれば五輪閉会後には2,400人程度に上るとの試算を公表した」としているが、私も英国と同様、今後は新型コロナによる死者数だけを開示すればよいと考える。理由は、ワクチン接種が進むにつれて重症化する人が減るからで、治療薬やワクチンの準備もできずに天気予報のようなことしか言わない日本の“専門家”会議は既に失格なのである。 また、「④東京など首都圏の感染者数は全国のおよそ2/3を占めている」「⑤感染力の強いデルタ株への置き換わりが進み、感染再拡大が首都圏から全国に波及する可能性もある」のであれば、ワクチンはデルタ株にも有効であるため、感染者数の多い首都圏にワクチンを先に配布すれば、感染者数が減って他地域への波及も減る。ここで、誤った「公平」を持ち出すのは科学的ではなく、おかしな平等教育の結果である。 さらに、「⑥選手約1万人、大会関係者約4万1千人の来日が見込まれる」「⑦五輪は選手らと外部の接触を遮断する“バブル方式”で運営される」「⑧種目の大半は無観客で行われる」「⑨選手らの多くがワクチン接種を済ませ、厳格な検査と行動制限でウイルスの国内流入を防ぐとする」「⑩事前合宿先で感染が判明した例もあり、水際対策は万全ではあるまい」「⑪管理の緩さが露呈した関係者の行動も問題視されている」「⑫『バブル方式により、日本国民がコロナ感染を恐れる必要はない』『感染状況が改善した場合、有観客を検討してほしい』としたバッハ会長の現状認識にも疑問が湧く」とも書かれている。 しかし、⑨のようなワクチン接種済の人が、⑥のように4万1千人来ても伝染するリスクは低いため、⑦⑧⑪は、外国人に対するヒステリックな対応で差別的でもある。また、⑩については、PCR検査のカットオフの問題で、日本のPCR検査は長時間増幅させているという報告もあり、水際対策はビジネス目的で入国している内外の人に対する方が甘いため、私は、⑫のバッハ会長の見解に賛成だ。 なお、「⑬選手村には、2回目の接種を終えていない日本人スタッフらが出入りする」というのは、出入りする関係者は五輪関連者として早くワクチンを接種すればよい。そのため、「⑭五輪を発生源としたクラスターを認知した場合、大会を続行するかどうかを検討しておく必要がある」のように、ワクチン接種済の軽症者ばかりのクラスターが発生したからといって大会を中止するようなことがあれば、五輪は世界中で報道されるため、世界の笑い者になるだろう。 「⑮生活や事業がコロナ前に戻るのはいつかを国民は一番知りたい」については、*4-3-3のように、東京五輪の原則無観客開催で多くの企業が肩すかしを食らい、スポンサー企業も製品や技術を売り込む好機の筈が人々の目に触れる機会が大幅に減っている状況なので、必要な場所に早期にワクチン接種を済ませ、この1年間で経営状況が悪くなった日本企業に五輪でさらに追い打ちをかけるのをやめた時、生活や事業は少しずつコロナ前に戻ると言える。 ロ)誤った新型コロナ対策とそれによる破綻 政府は、*4-3-4のように、7月12日、東京都に4度目の新型コロナ緊急事態宣言を出し、蔓延防止重点措置を含む6都府県の住民に県境をまたぐ不要不急の外出自粛を要請した。そして、「接種の有無による不当な差別は適切でない」として、ワクチン接種証明書は海外渡航用に限り、ワクチン接種済者も同じく移動を止めて経済を停滞させている。しかし、感染リスクが低くなり、移動を止める理由のなくなった特定地域のワクチン接種済者の移動の自由を侵害するのは憲法違反であると同時に、それこそ差別である。 国内の観光地も政府から僅かな補助金をもらうより、感染リスクの低いワクチン接種済者からでも営業を始めた方が助かり、納税者も同じだ。また、「都道府県間の移動は控えよ」というのは理由不明で、知事の権限範囲が異なることくらいしか理由を思いつかない。そのため、私は経団連の「接種証明書を早く活用し、国内旅行などの要件を緩和すべき」という提言に賛成だ。 さらに、「学校は、新型コロナで運動会も中止になった」と聞くが、延期すればよく、中止にまでする必要はない。そのため、「何故、ここまで融通が効かないのか」と不思議に思う。 なお、*4-3-2のように、東京商工リサーチによると、負債1,000万円未満を含めた新型コロナ関連破綻が累計で1,661件になったそうだ。ここでおかしいのは、夜に飲食店を利用することや酒を飲むこと自体が悪いかのように、飲食店の酒類提供や営業時間制限を設備の状況に関わらず一律に行っていることである。破綻すれば、事業主は負債を負って失業し、従業員も失業するが、これを助けるのに、生活保護や「Go To Eat」による血税のバラマキばかりしている体質なら、日本も破綻寸前でお先真っ暗なのだ。 4)難民と留学生 サッカー・ワールドカップ予選のため来日していたミャンマー代表選手のピエ・リヤン・アウンさんが、*4-4-1のように、クーデターを起こした国軍に抗議の意志を示して帰国を拒否し、日本に難民認定を申請されたそうだ。 日本政府は、日本への在留継続を望むミャンマー人に対し、緊急避難措置として在留延長や就労を認める方針を示したそうだが、ピエ・リヤン・アウンさんが母国の家族やチームメートの身を案じながら下した苦渋の決断にも応える必要がある。 難民条約は、人種・宗教・政治的意見などを理由に母国で迫害される恐れがある人を難民と定義して各国に保護するよう求めているが、日本は他の先進国と比較して難民認定数が極端に少ない。そのため、本来、保護されるべき人が保護されずに送還されている可能性が高く、外国人の人権保護という視点から、難民認定制度については見直すべきである。 また、*4-4-2のように、合宿期間中に世界ランキングが下がって五輪に出場できなくなり、コーチとともに近く成田空港から帰国する予定だったウガンダの重量挙げ男子選手が、「日本で仕事がしたい。生活が厳しい国には戻らない」という趣旨の書き置きを残して名古屋行き新幹線の切符を購入したそうだ。こういう人は、希望があればスポンサー企業がついて中京大学に留学させ、次のオリンピックを目指せるようにするか、何かいい方法がありそうだ。 なお、ウガンダは、英語が通じ、キリスト教が6割を占める国で、現在の主要産業は農林水産業・製造・建設業・サービス業で、自動車・医療機器・医薬品などは輸入しており、日本企業のアフリカ進出の拠点になれそうな国である(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uganda/data.html 参照)。 (5)先端科学で証明する日本人のルーツと古代史 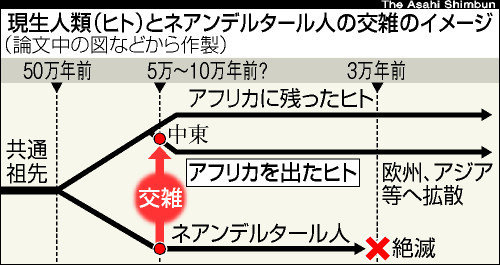 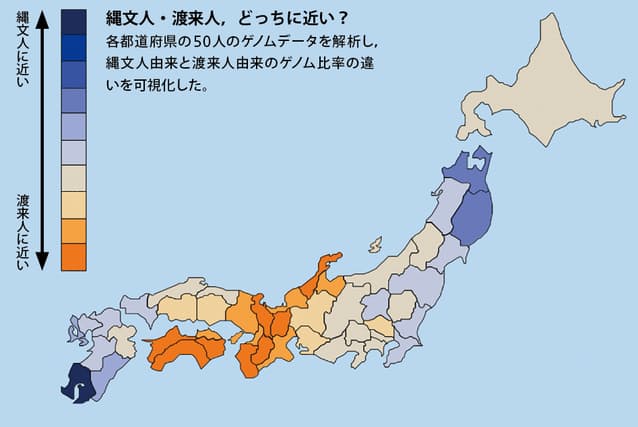 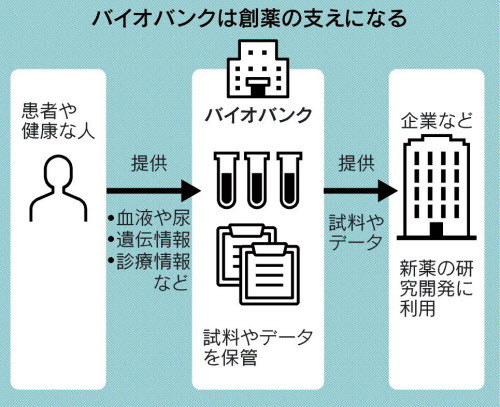 2010.5.7朝日新聞 2021.6.23日経新聞 2021.7.8日経新聞 *5-1より *5-2より (図の説明:左図は、ホモサピエンス《現生人類》がアフリカで発祥し、ネアンデルタール人などと交雑しながら世界に広がり、それぞれの地域に適した姿に進化してきたことを示す図だ。中央の図は、日本における都道府県毎の50人のゲノム情報をもとに違いを可視化し、縄文人由来のゲノムが多い県は青色、渡来人由来のゲノムが多い府県はオレンジ色で表示したもので、沖縄県は縄文人由来のゲノム比率が他県と比べて極めて高いが地図に含まれていない。右図は、東北大学と製薬大手5社が創薬目的で作るバイオバンク構想だ) 東北大学と製薬大手5社が、*5-2のように、10万人分のゲノムを解析するためのコンソーシアムを設立し、本格的にゲノムデータを創薬や診断技術開発等に利用できるようにし、日本も、ようやくゲノムをもとに新薬を探す「ゲノム創薬」の基盤整備が進むのだそうだ。 年齢・性別・生活習慣・病歴などのデータも合わせて蓄積するそうだが、正しいデータ分析のできない人はゲノム・年齢・性別などによる固定観念で人を差別するようにもなりがちであるため、注意してもらいたい。しかし、人間のDNAを短時間で読むことができ、ゲノムを解析することが可能になったのは、著しい進歩だ。 新型コロナウイルスを通して誰もが容易に理解できるようになったことは、DNAが分裂する時にはコピーミスも発生し、これによって変異が起こり、より有利な変異をした個体が生き残って、次の進化をしていくということだ。有性生殖をする生物は、次世代を残すのに少し時間を要するが、DNAのコピーミスだけでなく、交配によって両親から両方のDNAを受け継ぐことによっても、より生き残りやすい個体がより多くの子孫を残す形で進化できる。 人間も有性生殖をする生物の一つであるため、上の左図のように、ホモサピエンスがアフリカで発祥し、ネアンデルタール人などと交配しながら世界に広がり、それぞれの地域に適した形に進化してきたが、これは各地域に住む人のDNA分析をするという先端科学を使って証明されたことだ。診療や健診の際に、それぞれの国で人口の10%程度のDNA分析ができれば、どの地域が強い繋がりを持ち、どういう経路を辿ってホモサピエンスが現在の分布になったのかを、より正確に知ることができるだろう。 また、上の中央の図は、*5-1のように、日本における都道府県毎の50人のゲノム情報をもとに違いを可視化し、縄文人由来のゲノムが多い県は青色、渡来人由来のゲノムが多い府県はオレンジ色で表示したもので、沖縄県は縄文人由来のゲノム比率が他県と比べて極めて高いが、地図には含まれていないそうだ。 この研究の結果、日本人は、縄文人の子孫が大陸から来た渡来人と混血することで生まれ、47都道府県で縄文人由来と渡来人由来のゲノム比率は異なることがわかり、渡来人由来のゲノム比率が高かったのは滋賀県・近畿・北陸・四国で、沖縄県はじめ九州・東北(多分、北海道も)で縄文人由来のゲノム比率が高かったとのことである。 この結果は、渡来人が朝鮮半島経由で九州北部に上陸したとする考え方とは一見食い違うが、私は、渡来人は環日本海を自由に航海できたため、九州北部や日本海沿岸だけでなく、海路で繋がる瀬戸内海沿岸にも上陸し、縄文人の子孫と1000年以上かけて混血したのだと思う。どのような過程で混血が進んだかについては、沖縄などのように、さほど混血しなかった地域もあり、一様ではないだろう。 ただし、使った器で進化や文化の程度を図れるものではない。例えば、有田焼を使っている人が唐津焼を使っている人よりも進んでいるわけではなく、それぞれの場所にある材料を使い、その時代にあった技術を使って、必要なものを作ったにすぎないだろう。そのため、考古学は、生物学的・科学的知見も合わせて、首尾一貫性のある納得いく歴史を示してもらいたい。 ・・参考資料・・ <中華民族と東夷・南蛮・西戎・北狄、倭国・奴国・卑弥呼> *1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210702&ng=DGKKZO73480930R00C21A7M11500 (日経新聞 2021.7.2) 共産党100年 習氏演説要旨、中国が大股で時代に追いついた 中国共産党の習近平(シー・ジンピン)総書記(国家主席)は1日、北京市の天安門広場で党創立100年記念式典の演説に臨んだ。「(中国は)後進的な状態から世界第2位の経済大国へと歴史的な躍進を達成した」と述べ、党主導で経済成長などを実現させたと強調した。演説の要旨は次の通り。 ◇ 同志と友人のみなさん。今日は中国共産党の歴史と、中華民族の歴史において、非常に重大で荘厳な日である。私たちはここに盛大に集まり、全党、全国各民族とともに中国共産党創立100周年を祝い、中国共産党の100年にわたる奮闘の輝かしい経過を振り返り、中華民族の偉大な復興の明るい未来を展望する。まずはじめに、党中央を代表し、全ての中国共産党員に、熱烈な祝意を表す。ここで党と人民を代表し、全党と全国各民族の人民による持続的な奮闘を経て、私たちは最初の(党創立)100年で掲げた目標を実現し、この地に(大衆の生活にややゆとりのある)「小康社会」を全面的に築き上げ、絶対的な貧困問題を歴史的に解決し、社会主義現代化強国の全面的な実現という次の(中華人民共和国成立から)100年の奮闘目標に向けて意気盛んにまい進していることを厳かに宣言する。これこそが中華民族の偉大な栄光である。これこそが中国人の偉大な栄光である。これこそが中国共産党の偉大な栄光である。中国共産党は誕生当初から、中国人民に幸福をもたらし、中華民族の復興をもたらすことを初心と使命と決めている。この100年来、中国共産党が中国人民を束ね率いて行った全ての奮闘、全ての犠牲、全ての創造はひとつのテーマに帰結する。それは中華民族の偉大な復興を実現するということだ。中国共産党と中国人民の勇敢で強固な奮闘をもって中国人民は立ち上がり、中華民族が搾取され、辱めを受けていた時代は過ぎ去ったことを世界に厳かに宣言する。中華民族の偉大な復興を実現するため、中国共産党は中国人民を束ねて率い、自力更生し、発奮し、社会主義革命と(社会主義現代化)建設という偉大な成果を生んだ。私たちは社会主義革命を進め、中国で数千年にわたり続いていた封建的な搾取と圧迫の制度を消滅させ、社会主義の基本制度を確立し、社会主義の建設を推進し、帝国主義や覇権主義による転覆と破壊、武装挑発に打ち勝ち、中華民族の有史以来、最も広く深い社会変革を実現した。経済的文化的に遅れた人口の多い東方の大国(だった中国)が社会主義の社会に大きく進んだという偉大な飛躍を実現し、中華民族の偉大な復興の実現に向けた根本的な政治前提と制度の基礎を築き上げた。中国共産党と中国人民は勇敢で強固な奮闘をもって世界に厳かに宣言する。中国人民は古い世界を打ち破ることに優れているだけでなく、新しい世界を建設することにも優れている。中国を救えるのは社会主義だけであり、中国を発展させられるのは中国の特色ある社会主義だけである。揺るぎなく改革開放を推進し、各方面からのリスクや挑戦に打ち勝ち、中国の特色ある社会主義を創り、堅持し、守り、発展させ、高度に集中した計画経済体制から活力に満ちた社会主義市場経済体制への歴史的転換を実現した。閉鎖や半閉鎖から全方位開放への歴史的転換を、生産力が相対的に遅れていた状況から経済の総量で世界第2位に躍り出る歴史的突破を、人民の生活で衣食が不足していた状況から総体としてはややゆとりがある社会を、さらに全面的にややゆとりがある社会に向かう歴史的な飛躍をそれぞれ実現した。中華民族の偉大な復興の実現のため、新しい活力にあふれた体制上の保障と急速発展の物質的条件を提供した。中国共産党と中国人民は勇敢で強固な奮闘をもって世界に厳かに宣言する。改革開放こそが現代中国の前途と運命を決める鍵となる一手であり、中国が大股で時代に追いついたのだ。(2012年の)第18回党大会以降、中国の特色ある社会主義は新しい時代に入り、我々は党の全面的指導を堅持・強化し、(経済一辺倒でなく政治や文化、社会、環境保護の一体的な発展を重視する)「五位一体」の体制を全体を見据えて推進し、(小康社会の建設や厳格な党統治など4項目を推進する)「四つの全面」の戦略的体制を協調して推進し、中国の特色ある社会主義制度を堅持し改善した。国家のガバナンス体制とガバナンス能力における現代化を推進し、規範に基づいた党の運営を堅持し、比較的整った党内の法規体系を形成し、一連の重大なリスクと挑戦に打ち勝った。第1の100年における奮闘の目標を実現し、第2の100年では奮闘の目標の戦略的計画を明確に実現し、党と国家の事業は歴史的成果をあげ、歴史的変革を起こし、中華民族の偉大な復興を実現するため、より整った制度保障と、より堅実な物質的基礎と、より自発的な精神力を与えた。同志と友人のみなさん。100年前、中国共産党の先駆者たちが中国共産党をつくり、真理を堅持し、理想を守り、初心を実行し、使命を担い、犠牲を恐れず、勇敢に戦い、党に忠誠心を持ち、人民に背かない、偉大な建党精神をつくり上げた。これが中国共産党の精神の源である。同志と友人のみなさん。この100年、我々が得た全ての成果は中国共産党人、中国人民、中華民族が団結し奮闘した結果である。毛沢東同志、鄧小平同志、江沢民(ジアン・ズォーミン)同志、胡錦濤(フー・ジンタオ)同志を主要な代表とする中国共産党人は、中華民族の偉大な復興のために、歴史書を光り輝かせる偉大な功績をあげた。私たちは彼らに崇高なる敬意を表する。今このとき、私たちは中国の革命、建設、改革、中国共産党の創立と強化、発展のために大いに貢献した毛沢東、周恩来、劉少奇、朱徳、鄧小平、陳雲といった同志ら上の世代の革命家を深くしのぶ。新中国を創立し、守り、建設するにあたって勇敢に犠牲となった革命烈士を深くしのぶ。香港特別行政区の同胞、マカオ特別行政区の同胞、台湾の同胞と多くの華僑に心からあいさつする。中国人民と友好に付き合い、中国の革命と建設、改革事業に関心と支持を寄せる各国の人民と友人に心から謝意を表する。同志と友人のみなさん。初心を得るのは易しく、終始守るのは難しい。歴史を鑑(かがみ)として、盛衰を知ることができる。私たちは歴史で現実を映し、未来を長い目で見通す。中国共産党の100年の奮闘の中から過去に私たちがなぜ成功できたかをはっきりと見て、未来に私たちがどうやって成功を続けられるか明らかにし、それによって新しい道のりで揺るぎなく、自覚的に初心の使命を心に刻み、美しい未来を切り開いていかねばならない。 ●党は国に不可欠 歴史を鑑として、未来を切り開くには、中国共産党の強固な指導を堅持しなければならない。中国のことをうまくやるために、カギとなるのは党だ。中華民族の近代以来180年余りの歴史、中国共産党の成立以来100年の歴史、中華人民共和国の成立以来70年余りの歴史が、すべて十分に証明している。中国共産党がなければ、新中国はなく、中華民族の偉大な復興もない。歴史と人民は中国共産党を選んだ。中国共産党の指導は、中国の特色ある社会主義の最も本質的な特長であり、中国の特色のある社会主義制度の最大の優位性であり、党と国家の根本的な所在、命脈の所在、全国の各民族の人民の利益と運命にかかわっている。新しい道のりでは、私たちは党の全面的な指導を堅持し、党の指導を絶えず充実させ、「四つの意識」を強め、「四つの自信」を固め、「二つの擁護」を徹底し、「国の大者」を銘記し、党の科学的な執政、民主的な執政、法に基づく執政の水準を絶えず向上させ、大局をまとめ、各方面を調整する核心となる党の役割を十分に発揮しなければならない。中国共産党は常に最も広範な人民の根本的な利益を代表し、人民と苦楽をともにして一致団結し、生死を共にし、自らのいかなる特殊な利益もなく、いかなる利害集団、いかなる利権団体、いかなる特権階級の利益も代表しない。中国共産党と国民を分割して対立させようとするいかなる企ても、絶対に思いのままにならない。9500万人以上の中国共産党員も、14億人余りの中国人民も許さない。歴史を鑑として、未来を切り開くには、マルクス主義の中国化を引き続き推進しなければならない。マルクス主義は私たちの立党と立国の根本的な指導思想であり、私たちの党の魂と旗印である。中国共産党はマルクス主義の基本原理を堅持し、事実に基づいて真実を求めることを堅持し、中国の実際から出発し、時代の大勢を洞察し、歴史の主導権を握り、苦難の探究を行う。絶えずマルクス主義の中国化と時代化を推し進め、中国人民が絶えず偉大な社会革命を推し進めるよう指導する。中国共産党はなぜできるのか、中国の特色のある社会主義はなぜ良いのか、それはマルクス主義によるものだ。新たな道のりでは、私たちはマルクス主義、レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、(2代前の総書記である江沢民氏の)「『3つの代表』の重要思想」、(前総書記である胡錦濤氏の)「科学的発展観」を堅持する。新時代の中国の特色ある社会主義思想を全面的に支持し、マルクス主義の基本原理と実際の中国の現状、中国の優れた伝統文化を組み合わせ、マルクス主義を用いて時代を見つめ、把握し、先導し、現代中国のマルクス主義と、21世紀のマルクス主義の発展を継続していく。歴史を教訓とし、未来を切り開くには中国の特色ある社会主義を堅持し、発展させる必要がある。独自の道を歩むのは、党の全ての理論と実践の足がかりであり、さらにこれは党の100年の闘争により得た歴史的結論だ。中国の特色ある社会主義は、党と人民が多大な苦しみと大きな代償を払ったことによる成果であり、これは中華民族が偉大な復興を実現する正しい道のりである。私たちは中国の特色ある社会主義を堅持し、発展させ、物質文明、政治文明、精神文明、社会文明、生態文明を一体的に発展し、促進する。中国式の近代化への新たな道を創造し、人類文明の新たな形態を作り出した。新たな道のりでは、党の基本理論、基本路線、基本戦略を堅持し、「五位一体」と「四つの全面」を一体的に推進する。改革開放を全面的に深化させる。新たな発展段階を足がかりとし、新しい発展理念を完全で正確かつ包括的に実行する。新しい発展パターンを構築し、高品質な発展を促進し、科学技術の自立を進める。人民自らが主であることを保障し、法の支配に従って国を統治し、社会主義の核心的価値体系を堅持する。発展中の人々の生活を保障し改善し、人と自然の調和と共生を堅持し、人民の繁栄、国家の強盛、美しい中国を共に推し進めていく。中華民族は、5000年以上の歴史の中で形成された輝かしい文明を持ち、中国共産党は100年の闘争と70年以上の統治経験があり、我々は積極的に人類文明の全ての有益な成果から学び、すべての有益な提案と善意の批判を歓迎する。ただ、私たちは決して「教師」のような偉そうな説教を受け入れることはできない。中国共産党と中国人民は、中国の発展していく運命を自らの手中に収め、自らの選択した道を歩む。歴史を教訓とし、未来を切り開くには、国防と軍隊の近代化を加速しなければならない。強国には強軍が必要で、軍は国を安定させなければならない。党が銃(軍)を指揮し、自ら人民の軍隊を建設することは血と火の闘争のなかで党が作り出し、破られない真理だ。人民解放軍は、党と人民のために不滅の功績を築き、(共産党によって守られた世の中である)「紅色江山」を守り、民族の尊厳を守る強力な柱であり、地域と世界平和を守る強力な力である。新しい道のりでは、新時代の党の強大な軍隊の思想を全面的に貫く。新時代の軍事戦略の指針を堅持し、人民解放軍に対する党の絶対的な指導力を維持し、中国の特色ある強大な軍隊の道を歩み続ける。政治建軍、改革強軍、科技(科学技術)強軍、人材強軍、法に基づき統治された軍隊を全面的に推進、人民解放軍を世界一流の軍隊へと建設する。より強力な能力と防御するための信頼性の高い手段で人民解放軍を建設すれば、国家主権、安全、発展の利益を守ることができる。 ●「一帯一路」発展促す 歴史を教訓とし、未来を切り開くには、人類運命共同体の構築を絶えず推進しなければならない。中華民族は平和、和睦、調和を5000年以上にわたって追求し、継承してきた。中華民族の血には、他人を侵略し、覇権を追求する遺伝子はない。中国共産党は人類の将来の運命に心を配り、世界のすべての先進的な力と協力して前進する。中国は常に世界平和の建設者であり、世界の発展の貢献者であり、国際秩序の擁護者である。新たな道のりでは、平和、開発、協力、互恵の旗印を高く掲げ、独立した外交政策を追求し、平和的発展の道を守り、新しい形の国際関係の構築を促進しなければならない。人類の運命共同体の道を守り、(中国の広域経済圏構想)「一帯一路」の質の高い発展を促し、世界に新たな機会を提供しなければならない。中国共産党は平和、開発、公正、正義、民主、自由という全人類共通の価値観を守る。協力を堅持し、対立をやめ、開放を守る。封鎖をやめ、互恵を守り、ゼロサムゲームをやめ、覇権主義と強権政治に反対する。歴史の車輪を明るい目標に向かって前進させる。中国人民は正義を重んじ、暴力を恐れない人々である。中華民族は強く、誇りと自信を持つ民族である。中国人民はこれまで他国の人民をいじめ、抑圧し、奴隷のようにしたことはない。過去にも現在にも、将来においてもありえない。同時に、中国の人民は、いかなる外部勢力が私たちをいじめ、抑圧し、奴隷のようにすることも決して許さない。故意に(圧力を)かけようとすれば、14億人を超える中国人民の血肉で築かれた「鋼鉄の長城」の前に打ちのめされることになるだろう。歴史を教訓とし、未来を切り開くには、多くの新しい歴史的特徴を持つ偉大な闘争が必要となる。戦い、勝利することは、中国共産党の無敵で強力な精神力である。偉大な夢を実現するには、粘り強く、たえまない戦闘が必要だ。今日、私たちは、歴史上のどの時代よりも中華民族の偉大な復興という目標に近づいている。これを実現するための自信と能力があり、同時にさらに大変な努力をする必要がある。新しい道のりでは、私たちは、危機意識を高め、常に安全な時も危険な状況を考え、総体国家安全観を貫き、開発と安全を統一的に計画する。中華民族の偉大な復興戦略と世界でこの100年なかった大変革の両方を統一的に計画する。我が国の社会の主要な矛盾の変化によってもたらされた新しい特徴と新しい要求を深く理解する。複雑な国際情勢がもたらす新たな矛盾と新たな課題を深く理解し、あえて戦い、闘争を得意とし、山があれば切り開き、水があれば橋をかけ、あらゆるリスクと挑戦を克服する。歴史を教訓とし、未来を切り開くには、中国人民がより大きな団結を強化しなければならない。100年の闘争の道のりで、中国共産党は統一戦線を重要な位置づけとし、常に最も広範な統一戦線を統合し発展させ、団結できるすべての力を結集し、動員できるすべての肯定的な要因を動員し、闘争の力を最大化する。愛国統一戦線は、中国共産党が中華民族の偉大な復興を達成するために、国内外のすべての中国人民を結集するための重要な武器である。新しい道のりでは、私たちは政治思想の誘導を強化し、共通認識を広く結集し、世界の英雄と人材を結集し、最大の公約数を探し続け、最大同心円を描き、国内外のすべての中国人民の力と心を一つの場所に集約する。民族の復興を達成するために力を結集しなければならない。歴史を教訓とし、未来を切り開くには、党が建設する新たな偉大な工程を継続的に推進しなければならない。自己革命への勇気は、中国共産党が他の政党と区別する顕著な兆候である。私たちの党は試練と苦難があったが、今も活発だ。その一つの重要な理由は、私たちは常に党が党を管理し、厳重に統治し、あらゆる歴史のなかで自らのリスクに絶えず対処し、世界情勢の深い変化の歴史的過程において、私たちの党が時代の先頭を走ってきた。歴史的過程において、国内外の様々なリスクと課題に直面するとき、常に国民のよりどころとなることを保証する。クリーンな政府を構築し腐敗との戦いを揺るぎなく促進し、党の高度な性質と純粋さを損なう全ての要因を断固排除する。健全な党を侵食するすべての病毒を除去し、党の質、色、味が変わることを防ぐ。新しい時代の中国の特色ある社会主義の歴史的過程において、党が常に強い指導的核心となるよう努力する。同志と友人のみなさん。私たちは「一国二制度」「香港人による香港の統治」「マカオ人によるマカオの統治」、高度な自治の方針を全面的かつ正確に徹底し、香港、マカオ特別行政区に対する中央の全面的な管轄権を実行する。特別行政区が国家の安全を守る法律制度と執行体制を実施し、国家主権と安全、発展の利益を守り、特別行政区の社会の大局的な安定を維持し、香港とマカオの長期的な繁栄と安定を保たねばならない。台湾問題を解決し、祖国の完全な統一を実現することは、中国共産党の変わらぬ歴史的任務であり、中華の人々全体の共通の願いだ。「一つの中国」の原則と(それを認め合ったとする)「92年コンセンサス」を堅持し、祖国の平和統一プロセスを推進する。両岸の同胞を含むすべての中華の人々は、心と心を一つにし、団結して前進し、いかなる「台湾独立」のたくらみも断固として粉砕し、民族復興の美しい未来を創造しなければならない。いかなる人も中国人民が国家主権と領土を完全に守るという強い決心、意志、強大な能力を見くびってはならない。同志と友人のみなさん。100年前、中国共産党が成立した時は50人強の党員しかいなかったが、今では9500万人以上の党員を擁し、14億人余りの人口大国を指導し、世界的で重大な影響力を持つ世界最大の政権政党になった。100年前、中華民族が世界の前に示したのは一種の落ちぶれた姿だった。今日、中華民族は世界に向けて活気に満ちた姿を見せ、偉大な復興に向けて阻むことのできない歩みを進めている。同志と友人のみなさん。中国共産党は中華民族の不滅の偉業を志し、100年はまさに風采も文才も盛りだ。過去を振り返り、未来を展望し、中国共産党の強い指導があり、全国の各民族の人民の緊密な団結があれば、社会主義現代化強国を全面的に建設する目標は必ず実現でき、中華民族の偉大な復興という中国の夢は必ず実現できる。偉大で、光栄で、正しい中国共産党万歳!偉大で、光栄で、英雄である中国人民万歳! *1-2:https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=770962&comment_sub_id=0&category_id=142 (中国新聞 2021/7/8) 骨太の方針 財政の裏付け見通せず 菅義偉政権初となる「骨太の方針」が決まった。政府の経済財政運営の基本的な方向性を示す指針で、新型コロナウイルス対策の強化に加え、デジタル化、脱炭素化、地方創生、少子化対策の4分野をコロナ後の成長の原動力と位置づけた。いずれも日本が以前から直面している課題であるが、政権が当然取り組むべき政策を寄せ集めたように映る。総花的で新鮮味に欠ける。テーマや目標を並べても、確実に実行できなければ意味がない。にもかかわらず、どの政策を優先し、財源を含めてどうやって実現していくのかも判然としない。踏み込み不足と言わざるを得ない。コロナ対策では、ワクチン接種の見通しを「10月から11月にかけて終える」と明記した。ワクチン接種の加速で、感染収束の機運を高め、支持率回復につなげたい狙いがあるのだろう。さらに、首相が肩入れする「こども庁」の創設検討や最低賃金の引き上げなども盛り込んでいる。秋までに行われる衆院選に向けて、国民の関心を引きたい思惑も透ける。骨太の方針が政権・与党のアピールの場になりつつあるのではないか。存在感を失い、今のような形骸化が進めば、もはや役割を終えたと言われても仕方あるまい。とりわけ看過できないのは、一連の政策を裏付ける持続可能な財政の姿が見えてこない点である。国と地方の政策経費を税収などで賄えているかを示す基礎的財政収支(プライマリーバランス=PB)について、政府は2025年度に黒字化する財政健全化の目標を掲げている。コロナ禍を受けて昨年は明記しなかったが、今回は黒字化目標を「堅持する」との言葉が復活した。同時に新型コロナが経済と財政に及ぼす影響などを21年度中に検証し、「目標年度を再確認する」とした。目標の見直しや先延ばしに含みを持たせた形だ。財政健全化への道筋を曖昧にしては、骨太の方針の意義自体が問われる。コロナ禍に伴う経済対策で、国の20年度の一般会計の歳出総額は175兆円を超え、借金に当たる国債は112兆円を新規に発行した。21年度予算もコロナ対策の予備費に5兆円を積むなど、過去最大規模の106兆円に膨らんだ。感染の収束はまだ見通せず、追加の支出が必要になる恐れもある。内閣府が今年1月にまとめた中長期の経済財政の試算では、日本経済がたとえ高成長を果たしたとしても、PBは25年度には7兆3千億円程度の赤字となる見通しだ。目標達成は絶望的なことは明らかである。それでも目標の「堅持」を修正しなかったのは、こちらも衆院選を意識し、財政健全化の議論を先送りにしたのではないか。欧米の政府は、財政出動とともに財源確保策も打ち出している。米国は経済対策の財源を企業や富裕者層の増税などで調達する方針で、欧州連合(EU)も復興基金の財源として国境炭素税などを検討している。年度内に行われる検証作業では、安易な目標の先送りに終わらせず、歳出・歳入両面で具体的な財政健全化策の検討を急ぐ必要がある。 *1-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA11A0I011062021000000/ (日経新聞 2021年6月24日) コロナ予算、30兆円使い残し 消化はGDP比7%、米13%に見劣り 成長へ財政回らず 新型コロナウイルス禍を受けて2020年春から積み増してきた国の予算73兆円のうち、約30兆円を使い残していることが判明した。家計や企業への支払いを確認できたのは約35兆円と名目国内総生産(GDP)の7%程度にとどまった。GDPの13%を支出した米国と比べ財政出動の効果が限られる展開となっている。危機脱却へ財政ニーズが強い時にもかかわらず予算枠の4割を使い残す異例の事態は、日本のコロナ対応の機能不全ぶりを映し出している。脱炭素関連の投資やデジタル化の推進、人材教育など戦略分野のコロナ禍後の成長を押し上げる財政資金ニーズは大きい。にもかかわらず予算の規模を大きくみせるために枠の確保ありきで政策の中身が置き去りになっており、成長分野へ予算が行き届いていない。脱炭素へ2兆円を投じた基金は、支援の中身が詰まっていないなかで枠の大きさの議論が先行して3次補正に盛り込まれた。経済産業省が基金の支援対象となる分野を公表したのは4月に入ってからで、ようやく企業の公募が始まった段階だ。使い残しが多いのは約21兆円の追加歳出を盛り込んだ20年度3次補正が21年1月に成立したことに加え、コロナ禍の長期化が原因だ。翌年度への予算の繰り越しが「30兆円程度」(菅義偉首相)出る20年度は極めて異例だ。東日本大震災後に多額の予算を積んだ11~12年度でも繰越額と不用額を合わせても年10兆円を超えた程度だった。コロナ対策では20年6月に当時の安倍晋三首相が記者会見で「GDPの4割に上る世界最大」規模の「230兆円」の経済対策で「日本経済を守り抜く」と打ち出した。約1年を経て実際に家計や企業に出回った国費は資金繰り支援策を除くベースでGDP比7%程度。4月末までに同13%の2.8兆ドル(約307兆円)を消化した米国と比べて遅れが目立つ。4割と安倍前首相が打ち出したのは財政支出に民間資金も加えた事業規模ベースの経済対策の金額だった。財政投融資を活用した100兆円規模の資金繰り支援策が大きい。資金繰り支援の比率がコロナ対策の9%にとどまる米国と対照的だ。予算の執行状況は20年4月以降に打ち出した経済対策などについて、内閣府が21年5月にまとめた調査を基に日本経済新聞が資金繰り支援策を除いて集計。100億円以上の事業が対象で、国費ベースで9割以上をカバーしている。1人10万円の給付金など緊急を要した家計支援策は予算の9割強がすでに支払われるなど執行が進む。一方、GoToトラベルなど消費活性化の予算は進捗率が35%にとどまった。ワクチン接種の遅れが消費や投資を制約させた影響が大きい。米欧や中国はコロナ後の成長基盤づくりをにらんでグリーン関連政策やデジタル化などの戦略分野へ中長期的な財政出動を競う。日本では政府・与党内で21年度補正予算を求める声が強まりつつあるが、規模を大きくみせる枠の確保競争に終始せずに、成長につなげる政策の中身を詰める作業が欠かせない。 *1-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK0794K0X00C21A7000000/ (日経新聞社説 2021年7月7日) 成長促進と財政規律を両立できる予算に 政府は7日の閣議で、2022年度予算の概算要求基準を了解した。これに沿った各省庁の概算要求を8月末に締め切り、年末に予算案を編成する運びだ。財政の規律を保ちつつ、新型コロナウイルス対策や成長基盤の強化に国費を重点配分する必要がある。不要不急の支出で予算をいたずらに膨らませてはならない。21年度予算の編成は、コロナ禍で異例の対応を迫られた。感染症の収束を予見できないという理由で明確な概算要求基準の設定を見送り、各省庁の概算要求の締め切りも1カ月延ばした。コロナ対策については、金額を明記しない「事項要求」を今回も認める。ただ成長戦略を推進するための「特別枠」を設け、高齢化の進展に伴う社会保障費の「自然増」を抑える目安を示すなど、例年の手法に近い形に戻した。コロナ禍の克服はいまも最優先の課題だ。とはいえワクチンの接種率が上がり、経済社会活動の正常化が進むにつれて、この先の成長基盤の強化や財政の健全化をより強く意識せざるを得ない。緊急時でも投入できる国費には限りがある。政府が「青天井」の概算要求を見直し、一定の基準を復活させたのは妥当だろう。重要なのは無駄やばらまきを排し「賢い支出」に徹する姿勢だ。20~21年度の国の一般会計総額は当初予算と補正予算の合計で280兆円を超えたが、使い残しや繰り越しも目立つという。その検証を怠ったまま、むやみに予算を積み上げていいはずがない。コロナ対応の名目で経済対策を繰り返しても、困窮者の救済や病床の確保といった問題はなかなか解消しない。背景には様々な要因があろうが、予算配分の優先順位も正しいとは言い難い。成長戦略にも同じことが言える。デジタル化やグリーン化などの推進に予算を重点配分するのは当然だが、緊急性や必要性の高い事業を選別しなければ、絵に描いた餅になりかねない。各省庁は節度とメリハリのある概算要求を心がけるべきだ。景気の回復で税収が堅調なのを幸いに、コロナ対策の不透明な事項要求を連発したり、成長戦略の名目で不要な公共事業や施設整備を強要したりするのは許されない。コロナ対策はもちろん、成長の促進や財源の確保に心を砕くのは米欧も同じだ。日本も責任ある予算編成を心がけたい。 *1-5:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA24DN70U1A620C2000000/ (日経新聞 2021年6月25日) 渡辺努・東大教授「賃金上がらぬ問題、まず認識を」、安いニッポン・ガラパゴスの転機 経営者・識者に聞く 国内では安定した生活を送っているのに、海外から見れば安く、貧しくなる日本。気づかないうちに深刻度を増すこの病理から、どうしたら抜け出せるのか。渡辺努・東大教授に聞いた。 ――なぜ日本は安い国になったのでしょうか。 「2012年末からの安倍晋三政権下では黒田東彦総裁が就任した日銀の異次元緩和もあって円安が進んだ。政策の目的は円安だけでなく物価も賃金も上げることだったが、読みが違った。円安なのに物価も賃金も上がらなかった。海外からみれば日本のサービスは安くなる」 ――日本人からみると海外では高くて買えないものが増えます。日本のモノやサービスの質は国際的に見て相対的に低下していくのでしょうか。 「たとえばパスタやラーメンをつくるときに材料になる小麦は輸入価格が高くなる。企業は最終製品を値上げできていないので、消費者は痛くもかゆくもない。企業はどうしているか。コスト削減をして、値段を据え置いて頑張る。あるいは商品のサイズが小さくなる。この場合は質が落ちている。消費者の満足度が落ちている。そして賃金は上がらない」 ――訪日外国人(インバウンド)向けのホテルでは外国人用の高級価格が設定されています。こうした価格の二極化は広がっていくのでしょうか。 「不動産ではそういうことが起きている。ある規格のマンションが、シドニーと日本で比較され、まるで貿易ができるかのように裁定が働いている。海外の人が投機的に家を持つと、日本人の給料では買えなくなってくる」。「同じ商品やサービスなのに2つの価格があるという意味での二重価格は国内では発生しにくいと思う。だが日本企業の製品価格は国内向けと海外向けで違ってくる。海外で物価上昇が進めば、現地の競合製品が値上がりするので日本企業も値上げできる。だが日本ではできない。こうした二極化は既に起きている」 ――この状況を打開する政策はあるのでしょうか。 「もともとは企業が賃金や価格を上げられないことに原因がある。これは企業行動にインプットされてしまっている。これまでも製品やサービスの値段を上げようとした企業はあるが、値上げすると客が逃げていく。そういうことから企業は学習していく。悪循環だ。日本の消費者が特別だということだ。海外の消費者は理由のある値上げについては仕方ないと受け入れる。日本人は一円たりとも値上げはだめだと反応する。アベノミクスが本格化した13年は一部の企業が値上げしたが、結局売り上げが落ちてしまった」。「この問題が解決していない理由は、みんな気がついていないからだ。値段が上がらないのはいいことだとポジティブに考える人がいる。賃金は上がらないので、値段は低い方が良いという。まず賃金が上がっていない問題を認識することが大事だ」 *1-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210702&ng=DGKKZO73481460R00C21A7TB2000 (日経新聞 2021.7.2) 医薬原料調達で「脱中国」 塩野義など生産国内回帰へ、依存度下げ安定確保、コスト5倍の試算も 医薬品原材料の生産を巡り、国内製薬業界で海外依存を見直す動きが出てきた。抗菌剤など欠品すると医療に大きな支障が出る品目で、各社が国内回帰に乗り出す。塩野義製薬は2022年にも手術用抗菌剤の原料の生産を岩手県で始める。医薬品原料は中国の生産シェアが高く供給リスクが指摘されてきた。安定調達へ「脱中国」が進むが、国内回帰にはコスト面で課題が残る。医薬品原材料とは医薬品の有効成分が含まれる原薬やそのもとになる化学物質。国内回帰の動きがあるのは主に後発薬の原材料だ。後発薬は公定価格が安く抑えられており、製造原価を下げる目的で原材料生産の海外移転が進んできた。塩野義は医薬品製造子会社のシオノギファーマ(大阪府摂津市)を通じ、「セファゾリン」など「セフェム系」と呼ぶ抗菌剤の原料を生産する設備を21年末までに金ケ崎工場(岩手県金ケ崎町)に設ける。年産能力37トンで稼働し、5年後に50トンに引き上げる。生産した原料は抗菌剤を手がける国内後発薬メーカーに売る見込み。塩野義は初期投資としてまず20億円強を投じる。後発薬メーカーは従来、セフェム系原料のほぼ全てを輸入に頼ってきた。特に中国依存度が約3割と高い。抗菌剤は手術後の感染症などを防ぐために投与する。欠品すると手術が難しくなり医療体制の維持に影響が出かねない、重要な薬だ。厚生労働省は医療現場に重要な医薬品として抗菌剤や血栓予防剤など約500品目を定め、安定確保を製薬会社に呼びかけている。最重要と指定するセフェム系原料は19年に国内で50トン使われ、塩野義の拠点がフル稼働すれば全量をまかなえる計算だ。抗菌剤市場全体でみても約1割をカバーできる見通しだ。抗菌剤では19年、中国当局が環境規制を理由に現地メーカーにセファゾリン原料の生産を停止するよう命令。調達難によってセファゾリンで国内シェア6割の日医工が供給停止に追い込まれ、医療現場に影響が出た。国内調達できればこうしたリスクを低減できる。明治ホールディングス傘下のMeiji Seikaファルマも22年3月期中に岐阜工場(岐阜県北方町)で「ペニシリン系」と呼ぶ抗菌剤の原料の試験生産を始める。現在は海外調達しており中国などへの依存度が高い。同社は「試験生産を経て、生産ノウハウを再度蓄積する」とする。ニプロも滋賀県内にペニシリン系の原材料の生産施設を設ける予定。投資額は数十億円になるとみられる。厚労省によると後発薬原材料を調達する製造所の6割が海外で、中国が約14%、インドが約12%と高い。一方で、各国の保護主義政策に供給が左右されかねない状況だ。政府がまとめた21年版の通商白書では、4月時点で50強の国が医療品を輸出制限している。インド政府は4月、国内メーカーがライセンス生産している新型コロナウイルス治療薬の輸出を当面禁止とし、国内使用を優先した。米国では政府主導で生産の国内回帰の動きが進む。バイデン米大統領は2月、サプライチェーン(供給網)の見直しに関する大統領令を出した。半導体が注目されたが、医薬品も対象とする。米食品医薬品局(FDA)は同月、新型コロナ禍により中国から原薬調達が難しくなり、一部の医薬品が供給不足に陥ったと明らかにした。ただ、原薬生産の国内回帰には課題が残る。製薬会社によると日本での原材料製造コストは中国の5倍以上との試算もある。日本製薬工業協会の中山譲治前会長(第一三共常勤顧問)は「国内回帰は薬のコスト上昇につながりかねない」と話す。薬価が定まっているなか、メーカーがコスト上昇分を転嫁し、流通業者への納入価格を上げるのは容易ではない。厚労省の中では「安定確保が必要な医薬品の薬価算定で『例外』を設けるべきか否かの議論も必要」(幹部)との声もある。 *1-7:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/704218 (佐賀新聞 2021年7月10日) 無観客五輪、開催意義を実感させよ 政府が東京都に4度目の新型コロナウイルス緊急事態宣言を発令し、埼玉、千葉、神奈川3県に対するまん延防止等重点措置を延長することを決定した。これを受け、政府と大会組織委員会、東京都、国際オリンピック委員会(IOC)など5者が協議し、東京五輪は首都圏全ての会場を無観客とすることを決めた。近代五輪が無観客で開催されるのは初めてのことだ。パンデミック(世界的大流行)の中、異例の大会となる。首都圏での感染はさらに拡大を続けるとの予測もある。組織委は選手村を中心に、感染対策の手を緩めることなく万全を期すとともに、無観客であっても五輪の開催意義を市民が実感できるよう「舞台」を整えなければならない。既に多くの選手団が事前合宿のため入国し、各自治体で練習に励んでいる。自国の検査で陰性証明を受けていたにもかかわらず、感染力の強いデルタ株による感染が判明した選手団員が出たのは組織委にとって驚きだった。入念な検査が入国時も大会中も欠かせないことを思い知ることになった。海外に目を向ければ、大規模広域大会の欧州サッカー選手権で英国やフィンランドのファンから多くの感染者が出た。競技場や街の広場、あるいはパブでマスクをせずに肩を組み、歓声を上げるなどしたのが原因とされる。注目度の高いスポーツ大会、とりわけ国の代表選手が出場する大会では、喜びを爆発させるファンが多数出る傾向がある。世界保健機関(WHO)はこれに教訓にして、IOCと組織委に助言を続けていくとした。だが、国内では、政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂会長ら専門家有志が「無観客が望ましい」との提言を公表していた。政府はすぐには耳を傾けず、会場定員の50%以内で、最大1万人とする観客基準で突き進もうとした。独善的な姿勢を真摯に反省すべきである。6月下旬の共同通信の電話世論調査では、五輪とパラリンピックの開催による感染再拡大の可能性について「不安を感じている」と回答した人が86・7%に達していた。今回の無観客決断はいかにも遅かった。首都圏の会場が無観客と決まったことで、ボランティアと警備担当要員の規模は大規模な見直しが必要になった。主に観客が熱中症になった場合の対応に当たる予定だった医療従事者も規模が見直され、大幅な人員縮小が見込まれる。医療現場の負担が軽減され、最優先で取り組まなければならないコロナ感染対応で、人的な余裕が生まれるメリットも期待できそうだ。しかし、安倍晋三前首相が大会の1年延期を決定したときに語った「完全な形での開催」は実現しなかった。菅義偉首相が何度となく強調してきた「ウイルスに打ち勝った証し」としての五輪の実現も難しくなった。バッハIOC会長が言う「誰もが犠牲を強いられる大会」になるのは明らかだ。観客と喜びを共にしたいと望んでいた選手、会場で観戦できるはずだった市民はさぞかし残念だろう。それでも開催に懐疑的な人、開催を持ちわびている人が共に意義深く感じる大会にしなくてはならない。菅首相らにはその責務がある。 <客観的根拠に基づく軌道修正が不得意な国、日本> *2-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210630&ng=DGKKZO73407630Q1A630C2MM8000 (日経新聞 2021.6.30) エネ基本計画、「原発建て替え」盛らず 脱炭素の道筋、不透明に 経済産業省は今夏をメドに策定するエネルギー基本計画に、将来的な原子力発電所の建て替えを盛り込まない方向で調整に入った。東京電力柏崎刈羽原発で不祥事が相次ぐなど原発への信頼回復ができていないと判断した。原発建て替えの明記を見送ることで、2050年の脱炭素社会の実現に向けた道筋が描きにくくなる。国の中長期のエネルギー政策の方向性を示すエネルギー基本計画はおおむね3年に1度見直しており、作業が大詰めを迎えている。二酸化炭素(CO2)の排出抑制につながる原発の建て替えを明記するかどうかは、エネ基本計画見直しの最大の焦点となっていた。法律上の稼働期間の上限である60年に達する原発が今後出てくることから、政府として建て替えを進めていく方針を明記し、将来にわたって原発を活用する姿勢を示せるかに注目が集まっていた。東電福島第1原発の事故後の14年に策定したエネ基本計画で、原発建て替えの表現を削除して以来、建て替えの記載は消えたままだった。7月にも原案を示す新たな計画では建て替えを明記しない方向だ。判断を先送りし、3年後に計画を見直す際にあらためて判断する。国内の原発は建設中の3基を含め36基ある。東電福島第1原発の事故後、再稼働できたのはこのうち10基にとどまる。直近では東電柏崎刈羽原発でテロ対策の不備など不祥事が相次ぎ、信頼回復が遠のいている。原発はCO2を排出しない脱炭素電源だ。政府は30年度までに温暖化ガスの排出量を13年度比で46%以上削減し、50年には実質ゼロをめざすと決めた。エネ計画について議論する経産省の有識者会合でも「最大限活用すべきだ」との指摘が出ていた。地球環境産業技術研究機構(京都府木津川市)が5月にまとめた脱炭素のシナリオ分析によると、原発の活用は電力コストの上昇を和らげる効果もある。50年に再生エネで電力すべてを賄うと電力コストは今の4倍程度に増える。送電網の整備などに大きな費用がかかると見込まれるためだ。一方、再生エネで5割、原発で1割を賄うケースでは2倍程度に上昇を抑えられると試算する。 *2-1-2:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1212256.html (琉球新報社説 2020年10月23日) 原発処理水海洋放出 地元の不安を押し切るな 東京電力福島第1原発で増え続ける処理水の問題で、政府は海洋放出の方針を月内に決定する。地元は漁業者を中心に反対の声を上げており、影響を受ける人々と向き合わないまま方針決定に突き進むことになってしまう。処理水には放射性物質トリチウムが含まれる。環境や人体に与える影響を巡る検証は十分ではなく、復興に取り組む地場産業に及ぶ風評被害にも懸念が尽きない。放射性物質の除去技術や安全性が確立するまでの間の新たな保管場所の確保など、海洋放出を回避する方策を探るべきだ。第1原発では溶融核燃料(デブリ)を冷やすための注水などで、現在も1日に170トン程度の汚染水が増え続けている。東電は多核種除去設備(ALPS)を使って汚染水から放射性物質を取り除く処理をしているが、水に似た性質があるトリチウムは除去することができない。東電は処理水を保管する原発敷地内のタンク容量が、2022年夏に限界に達するとしている。政府も処分方法の決定を急ぐ姿勢を強めており、菅義偉首相は21日に「いつまでも先送りできない」と語った。背景には、海洋への放出を始めるには設備工事や原子力規制委員会の審査などで2年程度の準備を要するため、現状が決定のタイムリミットだとする判断がある。だが、時間切れを理由に地元の反対を押し切ることなど許されるはずがない。炉心溶融(メルトダウン)した原発から出る処理水を海に流し続けることによる環境影響は簡単に予見できるものではなく、問題視するのは当然だ。処理水の保管を東電の敷地内に限定せず、政府としても別の保管先の確保を検討する対応などがとれるのではないか。トリチウムの除去技術開発に注力することも、原発事故を起こした東電や国の責任であるはずだ。また、震災の津波でさらわれた漂着物が沖縄で見つかることがあるように、海洋放出の影響は原発沿岸だけにとどまらない。周辺諸国からの非難は避けられないだろう。19年には、韓国による水産物の輸入規制を巡って世界貿易機関(WTO)の紛争処理手続きで日本が敗訴した。国際社会は福島の原発事故を終わったと見なしていないことを自覚する必要がある。処理水の扱いに関する議論は13年に始まった。この間には、17年に東電の川村隆会長(当時)が海洋放出について「判断はもうしている」と発言し、地元の反発を招いた。18年には、国民の意見を聞く公聴会の直前に、本来除去されているべきトリチウム以外の放射性物質が処理水に残留しているのが発覚した。東電、政府の結論ありきの姿勢やデータに対する不信も、処理水の処分方法が長年決まらない要因の一つにとなってきた。地元や国民の不安の払拭を第一とした、誠実で慎重な対応が必要だ。 *2-2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/112551 (東京新聞 2021年6月24日) 「混乱するのが見えている」30キロ圏に28万人 広域避難不安拭えず 老朽・美浜原発3号機再稼働 運転開始から40年を超える関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)が6月23日、10年ぶりに再稼働した。重大事故が起きた場合、避難対象となる30キロ圏内には再稼働した原発では最多の28万人弱が暮らす。県内外へ避難が計画されているが、避難先の確保など実効性に疑問符が付いたままだ。中心市街地が30キロ圏内にある福井県越前市は人口約8万人。2019年8月に初の広域避難訓練が行われ、今年1月には国の避難計画がまとまった。美浜3号機で重大事故が発生すれば、北に位置する同県坂井市やあわら市、石川県小松市や能美市へ避難する。県や市の計画では、地区ごとに避難先の小中学校や公民館が細かく設定され、病院の入院患者や高齢者福祉施設の入所者などの搬送先も決められた。しかし、福祉施設からは懸念の声が上がる。障害者施設で入所者の避難を担当する40代女性は「施設で毎年訓練をしているが、実際の避難では手伝う人も車両も足りず混乱するのが目に見えている。着の身着のまま逃げたとしても、布団などの物資はどうなるのか」と表情を曇らせた。 ◆実効性ない計画なら…水戸地裁は運転禁じる判決 広域避難を巡っては、30キロ圏に国内最多の94万人を抱える日本原子力発電東海第二原発(茨城県東海村)について、水戸地裁は3月、運転を禁じる判決を出した。市町村で避難計画の策定が遅れており、実現可能な避難計画がなければ運転を認めないという基準が示された形だ。福井県の担当者は美浜原発について「東海第二とは状況が違う。避難に使用するバスや避難先などをしっかり確保できる計画になっている」と強調する。ただ、美浜原発周辺の避難人口は、既に再稼働した福井県内にある2原発よりも多い。住民を避難させる場合に県内にあるバスの3分の1にあたる278台が必要となるなど、一段とハードルが高い。新型コロナウイルスの感染拡大で避難の難しさはさらに増した。人が密になるのを避けるためにバスの台数を増やし、避難所で避難者が間隔を空けることを避難計画に盛り込んだ。だが、昨年8月に関電大飯原発(福井県おおい町)などで行った訓練では、避難所の収容人数が減り、新たな避難場所の確保が必要になるという課題も浮かんだ。今年1月には福井県内の記録的大雪で、避難で使う国道8号や北陸自動車道で車の立ち往生が発生し、長時間通行できなくなった。福祉施設の責任者を務める50代男性は「計画で避難先が決まっていても実際に役に立つのか分からない。いざとなったら入所者は計画とは別の県外施設へ避難させる」と話した。 *2-2-2:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021062700079 (信濃毎日新聞社説 2021/6/27) 40年超原発稼働 例外が常態化する懸念 関西電力が、福井県にある美浜原発3号機を再稼働させた。運転開始から44年を経た老朽原発だ。原発の運転には、2011年の東京電力福島第1原発事故を踏まえ「原則40年」とするルールが導入されている。原則から外れたケースが、初めて現実となった。「例外中の例外」として、最長20年の延長を認める規定もある。40年の寿命を迎えた原発から順次廃炉にし、脱原発を着実に進める―。事故を機に多くの国民が原発の危険性に気付くなか、そう考え導入されたルールだった。関西電力は、同様に老朽化した高浜1、2号機の再稼働も進める方針だ。他の電力会社にも再稼働を目指す40年超原発がある。今後、例外が常態化していく恐れがある。老朽原発は建材の劣化など安全性に課題があり、地域住民には不安が募っている。国民の理解を得ずに原発推進の既成事実を積み重ねるような対応は、看過できない。事故の教訓に立ち戻り、40年ルールの重要性を再確認する必要がある。安倍晋三前政権以降、政府は、脱原発を求める世論をよそに実質的な原発回帰を進めてきた。経済産業省と大手電力は、今回の再稼働を原発復権に向けた足掛かりの一つと捉えているようだ。美浜3号機は、設置が義務付けられたテロ対策の施設が未完成のため、今年10月の設置期限までに再び停止となる。わずかな期間の再稼働にこだわったのも、40年超原発の再稼働に道を開くことを重視したからではないか。福井県が再稼働に同意したのは今年4月。同意を条件とする巨額の交付金を経産省が県に提示するなど、国が積極的な役割を果たしたことが分かっている。菅義偉政権は、世界的な脱炭素化の加速を受け温室効果ガスの大幅削減を打ち出した。最近は、温室ガスを排出しないことを名目に原発推進を求める議員連盟が自民党にできるなど、政府・与党に表だった動きも目立つ。原発政策がこれまで、ごまかしの連続だったことを忘れてはならない。典型は使用済み核燃料の問題だろう。今回も、再稼働で増えていくのは分かっているのに、一時保管する関電の原発の燃料プールは約8割が埋まったままだ。行き場は決まっていない。原発にいつまで頼るのか、使用済み核燃料はどうするのか。数々の問題を放置して目先の経営や業界の利益を優先する姿勢は、到底認めることができない。 *2-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210707&ng=DGKKZO73642330X00C21A7MM0000 (日経新聞 2021.7.7) 玄海原発 地震想定見直し 規制委、九電に求める 原子力規制委員会は7日、九州電力が玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)で想定する地震の最大の揺れを引き上げる必要があるとの見解を示した。4月に厳しくした地震の揺れの想定方法に基づき電力会社に見直しを求めるのは初めて。九電は3年以内に想定を見直して規制委の再審査に合格する必要がある。想定する揺れの大きさは基準地震動と呼ばれ地震対策の前提になる。規制委は4月、原発周辺の活断層などによる地震に加え、過去に国内で発生した90件ほどの地震データを使って揺れを想定する方法を導入した。電力各社に対し、最大の揺れの想定を見直す必要があるかどうか9カ月以内に回答するよう要請した。九電は4月、新たな方法でも玄海原発の揺れの想定は変わらないと規制委に伝えたが、規制委は7日、この主張を却下した。九電は想定を作り直し、規制委の再審査を受けることになる。耐震補強の追加工事が必要になれば費用が膨らむ可能性がある。玄海原発3、4号機は2018年に再稼働している。九電の川内原発(鹿児島県薩摩川内市)と日本原子力発電の東海第2原発(茨城県東海村)は従来の揺れの想定を変える方針を規制委にすでに報告済みだ。 *2-3-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGG201GK0Q1A120C2000000/?n_cid=SPTMG002 (日経新聞 2021年1月20日) 原発「未知の活断層」対策強化 規制委が規則改正案了承 原子力規制委員会は20日の定例会で、原子力発電所などで「未知の活断層」への備えを強化するため、新しい評価手法を盛り込んだ関連規則の改正案を了承した。電力会社は原発を襲う揺れを再評価し、現行想定を上回った場合、追加工事などの対策を迫られる可能性がある。一般からの意見公募を経て、3月をメドに決定、施行する。従来より多くの地震データを反映した評価手法を用いて、原発ごとに未知の活断層による揺れの再評価を電力会社に求める。再評価の結果が現在想定している揺れ(基準地震動)を上回る場合、改正規則の施行後9カ月以内に原子炉設置変更許可を申請し、施行後3年以内に審査に合格して許可を得る必要がある。影響を受けるのは原発周辺に目立った活断層がなく、未知の活断層の影響を重視している原発で、九州電力の玄海原発(佐賀県玄海町)や川内原発(鹿児島県薩摩川内市)などだ。再評価結果が今の想定を上回り、現在の施設では耐震性が不十分だと判断されれば、追加工事などが必要になる可能性もある。追加工事の猶予期間については工事規模などを踏まえて、規制委があらためて設定する。 *2-4:https://www.data-max.co.jp/article/39260 (Net IB News 2020年12月21日) 行き場を失う原発の使用済み核燃料~5年後に9原発で容量9割が埋まると試算 原発を稼働していると毎年発生する、放射能を含む使用済み核燃料が行き場を失っている。原子力発電所で発生した使用済みの核燃料は、再処理工場を経て最終処分場やMOX燃料加工施設に運ばれるが、再処理を行うまでの間は、原子力発電所内の「燃料プール(貯蔵施設)」や中間貯蔵施設などで一時保管される。現在、日本国内で貯蔵されている使用済み核燃料は約1万8,000t。使用済み核燃料は原発を稼働すると増え続けるため、その一時保管場所が課題になってきた。そのため、九州電力の玄海原子力発電所の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強(290t)、同敷地内の乾式貯蔵施設(440t)の設置、四国電力の伊方発電所敷地内の乾式貯蔵施設(500t)の設置、中部電力の浜岡原発敷地内の乾式貯蔵施設(400t)の設置などが見込まれている。また、東京電力ホールディングス(株)と日本原子力発電(株)が出資し、リサイクル燃料貯蔵(株)が運営する青森県むつ市の中間貯蔵施設が2021年度に操業開始を目指すとされ、ここでは最長で50年、3,000tの保管が予定されている。このように約4,600t相当の使用済み燃料貯蔵施設の拡大に向けて取り組みがなされている一方で、表のように電気事業(連)の試算値では、約5年後に東京電力の福島第二で88%、柏崎刈羽で100%、中部電力の浜岡原発で90%、関西電力の美浜原発で89%、高浜原発で98%、大飯原発で93%、九州電力の川内原発で93%、日本原子力発電の東海第二原発で96%などと9つの原発で一時保管場所(管理容量)のおよそ9割が埋まってしまうと試算されている。さらに、使用済み核燃料を再処理工場で処理した後の高レベル放射性廃棄物を地層に埋める最終処分場の選定問題も難航している。原発はCO2排出量の削減に役立つとされるものの、発電後の放射性廃棄物の問題を含めて真摯に見つめたうえで、今後の方針を再度見直すべきではないか。 *2-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210626&ng=DGKKZO73297070V20C21A6TB0000 (日経新聞 2021.6.26) 小型原発の開発、日本勢動く 脱炭素へ実用化探る、三菱重、建設費半額に/日立、カナダで商談 原子力発電所の是非を巡る議論が続く日本でも小型原発を開発する動きが出てきた。三菱重工業は出力が従来の3分の1の原子炉を開発する。小型化して建設費を抑え、安全性も高めた。小型原発にはIHIなども米新興企業に出資して参画する。脱炭素につながる電源としての実用化への取り組みは欧米が先行していた。三菱重工は国内の電力大手と小型炉の初期的な設計の協議に入った。出力は30万キロワットと、従来の100万~130万キロワットの3分の1以下だ。工場で複数の部品で構成するモジュールをつくり、現地で据え付ける。設備も簡素化し、現地での作業量を減らせる。電力需要にあわせ設置数を変えられ、将来は海外での受注も視野に入れる。建設費は1基2000億円台と、東日本大震災前に5000億円規模とされた大型炉の半分以下にする。同社の小型炉は蒸気発生器を原子炉内に内蔵し、ポンプなしで冷却水が循環する。非常用電源が災害などで失われた際の安全性を高めたという。東日本大震災では東京電力福島第1原子力発電所で非常用電源が機能しなくなり、冷却できなくなった。小型炉は地下に設置でき、航空機などによる衝突事故への備えが高まる。密閉性が高まり放射性物質の飛散も防げる。商用運転の事例は欧米でもないが、複数の建設計画が進んでいる。米国では新興企業のニュースケール・パワーが小型炉を開発し、米規制当局の技術審査を終えた。出力は約7万7000キロワットで、複数を組み合わせて使う。プールにまるごと沈め、非常用電源なしでも冷却でき事故が起きにくいという。これまで5年から7年かかっていた工期も約3年に短くできる。「2040年代までに400~1000基の受注をめざす」(チーフ・コマーシャル・オフィサーのトム・ムンディ氏)としており、世界各国で11の新設計画についてそれぞれ電力会社などと覚書を交わした。ニュースケールには日揮ホールディングスとIHIも出資した。日立製作所と米ゼネラル・エレクトリック(GE)は海外市場を開拓する。受注を重ねて作業の習熟度を高めれば、建設費を700億~800億円台に下げられるとみる。カナダのオンタリオ電力と出力30万キロワットの小型炉の納入を巡り商談しているほか、エストニアやチェコなどでも営業している。小型炉への注目が高まっているのは、先進国で従来型の大型炉の建設が停滞しているからだ。大型炉は安全対策費が膨らみ、投資回収が難しくなっている。日立・GE連合は英国で大型炉を使う電力事業を計画したが、1基1兆円規模の投資に見合う経済性がないとみて撤退した。三菱重工もフランスの旧アレバ(現フラマトム)と開発していた100万キロワット級の「アトメア」の開発を凍結した。国際エネルギー機関(IEA)は、50年にカーボンゼロを達成するには化石燃料への投資を止め、30年までに毎年1700万キロワット分、31年以降は毎年2400万キロワット分の原発稼働が必要と試算する。関西電力と九州電力も小型炉などの活用を長期計画に明記した。国内の主要企業では約1万人が原発事業に従事し、三菱重工で約4000人、日立でも約1600人が働く。メーカーには小型炉の開発・建設を通じ、関連する雇用や技術を維持したいとの思惑もある。課題も多い。ひとつは発電コストだ。三菱重工の場合、1キロワット時あたり10円強のいまの大型炉より高くなる見込み。国内では原発管理の不備も続き、地元住民の反発もある。いま策定中のエネルギー基本計画でも、原発の建て替え・新増設を明記するのか議論が割れている。国内での新設の原発は09年に稼働したのを最後に、青森県や島根県で着工済みの工事は進んでいない。 <防衛にも計画性のない国、日本←それでは勝てるわけがない> *3-1:https://www.jiji.com/jc/article?k=2021070500799&g=pol (時事 2021年7月5日) 台湾有事で集団的自衛権行使も 麻生氏 麻生太郎副総理兼財務相は5日、東京都内で講演し、中国が台湾に侵攻した場合、安全保障関連法が定める「存立危機事態」に認定し、限定的な集団的自衛権を行使することもあり得るとの認識を示した。存立危機事態は、日本と密接な関係にある他国が攻撃され日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態で、集団的自衛権を行使する際の要件の一つ。麻生氏は「(台湾で)大きな問題が起きると、存立危機事態に関係してきても全くおかしくない。そうなると、日米で一緒に台湾を防衛しなければいけない」と述べた。 *3-2:https://newswitch.jp/p/23594 (ニュースイッチ 2020年8月29日) 「むつ」以来のタブーを破り、日本が原子力潜水艦を造るべき深い理由、元IEA事務局長・田中伸男氏「まずは米国から1隻購入し技術移転を」 現在、世界で使われている商業用原子炉はそのほとんどが大型軽水炉である。この炉型は大型かつベースロードで運用し、電力線網で広範囲に送電するという集中型電力システムで低コストを実現してきた。しかし東京電力福島第一原子力発電所事故でリスクの高さを露呈し、安全対策の強化で建設コストが上昇、新設では太陽光風力発電に対して競争力を喪失しつつある。今後は既存原発の運転期間を延長することでコスト上昇を抑えるしかない。大型軽水炉は将来的には小型モジュラー炉にとって代わられるだろう。軽水炉の弱みは、冷却水の供給が何らかの理由で途絶えることで燃料のメルトダウンを招く点にある。逆に船舶用の動力として使えば、万が一の場合、海中投棄でメルトダウンは防げる。燃料の補充が長期にわたって不要な点で潜水艦、砕氷船、発電バージなどで小型軽水炉は最適である。日本も原子力船「むつ」を建造し、自前の舶用小型軽水炉を実証したが、放射線漏れを起こし、残念ながら建造路線は放棄された。まずは、むつの失敗を総括するところから始めなければならない。笹川平和財団では北極海航路用砕氷船を前提として勉強会を始めたところである。関係者の話を伺ったが、むつ建造に関わった複数企業の設計インターフェースの悪さ、海外専門家から放射線漏れの可能性を指摘されながらも十分に検討しなかった建造体制の不備などが問題だったようだ。笹川平和財団では2017年から18年にかけて、インド洋地域における海洋安全保障に関する日米豪印4カ国専門家会議を開き、政策提言を取りまとめた。記者会見で配られた提言は報道されなかったが、その中に「日本政府はシーレーン防衛のため原子力推進の潜水艦保有を検討すべきではないか」という項目があった。自由で開かれたインド太平洋を海洋安全保障戦略の基本としている4カ国の専門家が一致して原子力潜水艦の必要性を指摘したのは重い。ポストコロナの中国が南シナ海や東シナ海での軍事活動強化に走り、香港の一国二制度を否定したのは、狙いが台湾併合にあることは明らかだ。今後米中関係がさらに悪化して行く中で、台湾有事も想定せざるを得ない。長期間潜ったまま航行できる原潜が中国海軍の動きを抑えるのに役に立つ。日本の持つディーゼルとリチウムイオン電池の潜水艦は静音性などに大変優れるが、毎日浮上する必要があり、秘匿性能と航続距離に課題がある。最近、北朝鮮のミサイルを撃ち落とす新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」計画が放棄された。敵国領内での基地攻撃の可否が議論されているが、そもそも攻撃を受けた場合、通常型巡航ミサイルでの反撃は攻撃ではなく防御だ。非核巡航ミサイルを装備した原潜による敵の核攻撃抑止も、米国の核の拡大抑止の補完として検討されるべきであろう。まずは1隻、米国から購入し技術移転、乗員の訓練などのための日米原子力安全保障協力が必要だ。日本に核装備は不要で核兵器禁止条約にも加盟すべきだが、緊張の高まる北東アジアの状況を考えれば、むつ以来のタブーを破り原子力推進の潜水艦建造を検討する必要があると考える。 【略歴】田中伸男(たなか・のぶお)東大経卒、通商産業省(現経済産業省)入省。通商政策局総務課長、経済協力開発機構(OECD)科学技術産業局長などを経て07年に欧州出身者以外で国際エネルギー機関(IEA)事務局長に就任。16年笹川平和財団会長、20年顧問。70歳。 *3-3:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77734 (現代 2021.1.21) なぜ原子力潜水艦は長い潜航が可能なのか? 推進力、水、酸素すべてを賄う原子の力 ●原子力潜水艦が長く潜水を続けられる理由とは? 1954年の今日、世界初の原子力潜水艦であるアメリカの潜水艦「ノーチラス号」の進水式が執り行われました。原子力潜水艦は、その名前の通り原子力を動力として駆動する潜水艦のことをいいます。ディーゼルエンジンと蓄電池によって駆動する通常の潜水艦と違い、原子力潜水艦は半永久的に潜水可能というメリットがあります。なぜなら、高濃度の核燃料は数十年にわたって原子炉を稼働させることが可能であり、燃料補給がほぼ不要だからです。燃料を気にすることなく原子炉からエネルギーを得られるため、海水を蒸発させて真水を生み出すこともでき、それを電気分解することによって酸素を供給することもできます。これにより、船員の酸素確保のために浮上する必要もなく、連続潜航距離をさらに伸ばすことができるのです。そういった理由から、原子力潜水艦の実現を強く望んだのが、アメリカの海軍大佐ハイマン・リッコーヴァー(Hyman George Rickover、1900-1986)です。第二次世界大戦で潜水艦の重要性を実感した彼は、戦後上官から新しい任務を受け取りました。それが、核エネルギーによる潜水艦の現実性についての研究だったのです。リッコーヴァーが赴いたのは、テネシー州のオークリッジにある国立研究所でした。そこでは、アルヴィン・ワインバーグ(Alvin M. Weinberg、1915-2006)などの研究者が核エネルギーの平和的利用について模索していました。リッコーヴァーは彼ら研究者たちを、ついで軍の上層部を説得し、原子力潜水艦の実現に動き出します。そして、時間と競争しているかのような凄まじいペースで工事を完了させ、戦後10年も立っていない1954年に進水式に至ったのです。ワインバーグによって水の蒸気を利用するコンパクトな原子炉が提案されたことがターニングポイントだったようです。翌年には本格的に稼働し、1958年には北極点の下を潜航通過しています。当時は、原子力は人間が制御でき、平和に利用すれば人々の生活を豊かにするという考えが大勢を占めていた時代です。それに基づき、原子力の商用が強く推進されました。元アメリカ大統領・アイゼンハワー(Dwight David Eisenhower、1890-1969)による1953年の「平和のためのアトム」演説などが代表例です。しかしその後、原子力潜水艦や原子力発電所がいくつもの大事故を起こすことになるのは皆さんもご存じのとおりです。ワインバーグも、当時は安全性より経済面を重視するきらいがあったことを認めています。 <人を大切にしない国、日本 ←社会保障と人権を粗末にしすぎ> *4-1-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2390A0T20C21A6000000/ (日経新聞 2021年6月25日) 市町村66%、病院存続困難に 人口減少巡り国交白書 政府は25日、2021年の国土交通白書を閣議決定した。人口減少により2050年に829市町村(全市町村の66%)で病院の存続が困難になる可能性があるとの試算を示した。公共交通サービスの維持が難しくなり、銀行やコンビニエンスストアが撤退するなど、生活に不可欠なサービスを提供できなくなる懸念が高まる。地域で医療・福祉や買い物、教育などの機能を維持するには一定の人口規模と公共交通ネットワークが欠かせない。人口推計では50年人口が15年比で半数未満となる市町村が中山間地域を中心に約3割に上る。試算によると、地域内で20人以上の入院患者に対応した病院を維持できる境目となる人口規模は1万7500人で、これを下回ると存続確率が50%以下となる。基準を満たせない市町村の割合は15年の53%から50年には66%まで増える。同様に50年時点で銀行の本支店・営業所は42%、コンビニは20%の市町村でゼロになるリスクがある。新型コロナウイルス禍は公共交通の核となるバス事業者の経営難に拍車をかけた。20年5月の乗り合いバス利用者はコロナ前の19年同月比で50%減少し、足元でも低迷が続く。白書は交通基盤を支えられないと「地域の存続自体も危うくなる」と警鐘を鳴らす。 *4-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210702&ng=DGKKZO73459090R00C21A7KE8000 (日経新聞 2021.7.2) コロナが示した医療の課題(上) 逼迫時の役割分担 明確に 小塩隆士・一橋大学教授(1960年生まれ。東京大教養卒、大阪大博士(国際公共政策)。専門は公共経済学) <ポイント> ○政策の微調整での対応は信認弱める恐れ ○急性期医療へのシフトなど構造改革急げ ○利用者の受診抑制の要因や影響探る必要 新型コロナウイルスの感染拡大を巡っては、変異株の脅威のほか、五輪開催という重大なリスク要因が存在する。一方で、ワクチン接種の大幅加速という好材料も出てきた。感染拡大の発生から1年半近くが経過し、ポストコロナの医療供給体制にとっても重要な課題が浮き彫りになった。まず新型コロナが日本人の健康に及ぼした影響を大まかにみてみよう。感染者数・死者数ともに、日本はほかの先進国と比べ著しく少なく、影響はかなり限定的だというのが一般的な受け止め方だろう。果たしてその理解でよいか。コロナ対策の評価にも影響する。図は、新型コロナを原因とする100万人当たり新規死者数(7日間合計)の推移を国際比較したものだ。図の上段は英米独日の比較、下段は日韓の比較だ(上段の目盛りは下段の20倍)。日本での影響はこれまで欧米諸国に比べ極めて軽微だった。しかし2つの点に注意が必要だ。まず図の上段の右端、つまり直近の数字をみると日本と英米独との差はほとんどなくなっている。ワクチン接種が加速している欧米諸国で死者数が大幅に減少してきたからだ。その結果、コロナの影響は「瞬間風速」としては、今では欧米とほぼ同じレベルになっている。変異株の影響もあり先行きは不透明だが、足元のこの状況は押さえておいたほうがよい。さらに重要なのは、図の上下を比較すれば明らかなように、死者数が形成してきた「波」の違いだ。欧米の死者数は2つの大きな波を形成してきたが、第2波が2021年1月ごろにピークを越えた後は、何とか収束に向かいつつある。日本では20年春に第1波が発生し、現在の波は通常、第4波と呼ばれる。欧米の第2波、日本の第3波には規制の解除・緩和を受けたリバウンド(感染再拡大)という共通点がある。だが欧米には死者数でみる限り第3波は明確な形では到来していない。景気もV字型の回復軌道に乗った。一方、日本には過去のピークを上回る第4波が到来し、対応に苦慮している。韓国でも、日本の第4波のような大きな波は発生していない。こうした波の違いは、日本政府によるコロナ対応の問題点を示唆している。本格的な市中感染の到来を予期せず、全国レベルのワクチン接種に大きく出遅れたのが、違いを生んだ主因だというのが筆者の判断だ。欧米諸国はワクチン接種と厳格な移動規制の合わせ技で、コロナ感染を力ずくでねじ伏せつつある。これに対し、日本がとってきたアプローチは経済活動に目配りをしつつ、感染者数などの動きをみながら、緊急事態宣言の発令と解除を繰り返し、さらに地域別に規制の濃淡をつけるなど、微調整で対処するものだ。本格的なロックダウン(都市封鎖)を許容する法制度がなく、ワクチン接種を急がなかったという制約条件、しかも五輪開催も予定される状況の下では、この方針は最適解だったかもしれない。だがそれはあくまでも制約条件を所与とした場合の机上の話だ。ロックダウンは難しいとしても、ワクチン接種なしで移動抑制だけで感染を抑え込もうとしても無理が出てくる。政策の微調整はそれだけを取り出してみれば合理的だとしても、方針を分かりにくくし、政策への信認を弱めてきた可能性がある。規制とリバウンドのいたちごっこを生み、政策の調整が感染の波を増幅させ、収束をむしろ遅らせてこなかったか。また入国管理や検疫に漏れはなかったか。経済への影響も含め、詳細な検証が必要になる。そうした対応の問題点を考慮に入れても、日本のコロナ感染の健康面へのショックは国際的にみれば軽微だったとの見方はできる。だが医療システムが余裕を持って感染拡大に対処できたかと問われると、答えは残念ながら「ノー」だ。日本の人口当たりベッド数は世界でトップクラスだ。しかも感染拡大の規模は諸外国より限定的だった。にもかかわらず、コロナ対応の最前線に立つ医療現場は逼迫し、崩壊寸前、あるいは事実上の崩壊に至ったところも少なくない。日本のベッド数は確かに多いが、精神病床や療養病床の比重も大きい。コロナ対応が可能な一般病床は全体の6割弱だが、すべてが急性期医療に特化しているわけではない。厚生労働省の「地域医療構想に関するワーキンググループ」の会合(20年10月21日)に提出された資料によると、全医療機関のうち、新型コロナ患者の受け入れ可能な機関は23%、受け入れ実績がある機関は19%にとどまる。しかも受け入れ実績のある機関でも、人工呼吸器、体外式膜型人工肺(ECMO=エクモ)またはその両方を使用した患者を受け入れていた機関に限ると全体の4%どまりだ。民間医療機関に患者の受け入れを要請する法制度も未整備だ。現場レベルでの調整は徐々に進んでいるが、感染再拡大をみてからの対応であり、後手に回ったといわざるを得ない。医療システムにかかる負荷は全体としてみれば小さくても、局所的には耐え難いほど高くなる。それを認識せず、その仕組みも改めずに経済活動を優先すると大変なことになる。日本の医療供給体制はもともと新型コロナのようなパンデミック(世界的流行)を想定した仕組みにはなっていない。公的介護保険の導入後も、日本の医療供給は平均在院日数の長い患者の療養を念頭に置いた面が色濃く残っている。社会全体の医療資源の使い方として非効率な面はないか。この問題がコロナ禍で改めて浮き彫りになった。医療供給体制にとって最低限必要なのは、医療逼迫時における地域医療機関の役割分担を明確にしておくことだ。長期的には、医療資源を急性期医療に一層シフトさせるとともに、地域医療機関間のネットワーク化を推進するなど、構造的な改革が求められる。最後に、日本の医療供給体制にとっての潜在的な問題点を指摘しておきたい。コロナ禍の下で利用者の受診抑制の動きがみられることだ。厚労省の研究でも明らかなように、コロナ禍の下で健康診断や各種のがん検診、人間ドック受診を抑制する傾向もみられる。問題は利用者の抑制行動が何を意味するかだ。抑制した人とそうでない人を比較して、コロナ発生前からの健康状態の変化に差がなければ、医療サービスの供給に過剰な部分があったことになる。逆に抑制した結果、健康状態が悪化していれば、必要な医療サービスがコロナ禍で受けられなかったことになる。この判定は極めて難しい。感染収束後も長期の追跡調査が必要だ。所得や就業状態など他の要因にも左右される。だがコロナ禍は医療を巡る利用者の行動変容をもたらしている可能性が高い。だとすれば、医療給付費の長期予測にも大きな影響が出てくる。まさしく統計的なエビデンス(証拠)に基づく政策評価・立案が必要となるテーマだ。コロナ禍は日本の医療供給体制の効率性や持続可能性にもかなりの影響を及ぼしている。 *4-2-1:https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021071400125 (信濃毎日新聞社説 2021/7/14) 教員免許更新制 廃止の判断遅きに失した 遅きに失したと言うべきだろう。文部科学省が、教員免許の更新制を廃止する方向で検討を進めている。更新には30時間以上の講習を自費で受ける必要があり、負担を訴える現場の声は導入当初から強かった。10年以上にわたって半ば漫然と存続させてきたことが問われなければならない。廃止で事を済まさず、文科省は経過を検証すべきだ。萩生田光一文科相が、制度の抜本的な見直しを中央教育審議会に諮問している。廃止の結論を得て、来年の国会への教員免許法の改定案提出を目指す。免許の期限を10年とし、大学などで講習を期限内に修了すると更新が認められる。お金と時間を負担するのは教員だ。数万円の講習費用と交通費を出し、夏休みの期間などに通わざるを得ない。教員を対象にした文科省の調査で、大多数が負担感を示す一方、講習が役に立っていると答えたのは3分の1にとどまった。自由記述では、制度を廃止すべきだとの回答が最も多かったという。更新制は教員不足の一因にもなってきた。定年前に期限を迎える教員が早期退職する動機になるほか、産休・育休取得者の代替教員の確保を難しくしている。更新を忘れて免許が失効していることが分かり、引き続き教壇に立てなくなった事例もある。2000年代初めころ、自民党の議員らから上がった「不適格教員の排除」の掛け声が制度化の発端だ。管理の強化があらわな主張に現場の反発は強く、いったんは見送られたが、第1次安倍政権下、政治主導で免許法が改定され、09年度から導入された。文科省は、教員の資質確保が目的で、不適格教員を排除する趣旨ではないと説明している。そもそもなぜ免許の更新は必要なのか。制度化の根拠は曖昧だ。その後、民主党政権が廃止の方針を打ち出したものの、参院で過半数を失って法改定を断念。自民党の政権復帰で立ち消えになっていた。教員の多忙さは増し、学校現場の疲弊は深い。いじめをはじめ子どもたちが抱える問題への対応が追いついていない現状がある。そこへ官製の研修が詰め込まれ、現場をさらに追い立てている。その状況をどう改めるか。教員が日々、子どもとじっくり向き合って力量を高める。それぞれが直面する課題を持ち寄って自主的に学び合う。そのための時間や余裕を生むことが肝心だ。文科省は現場を下支えすることにこそ力を傾けなくてはならない。 *4-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210715&ng=DGKKZO73895020V10C21A7CE0000 (日経新聞 2021.7.15) 芸術や数学で突出でも不登校 「ギフテッド」の子に支援策 文科省会議、指導法など議論 特定分野で突出した才能を持つ子どもへの支援について話し合う文部科学省の有識者会議は15日までに、初会合を開き、具体策の検討を始めた。芸術性や数学力などの面で抜きんでているものの、学年ごとのカリキュラムや周囲にうまく適合できず、不登校になるケースも。こうした子どもの状況に応じた指導の在り方、大学、民間団体との連携などを議論し、年内にも論点をまとめる。文科省などによると、米国では、同年齢よりも特に高い知能や創造性、芸術的才能などを発揮する子どもを「ギフテッド」と呼び、早期入学や飛び級といった特別な教育プログラムが用意されている。中にはこだわりが強すぎたり、集団行動が苦手だったりする子もいるとされ、どう支援するかも課題となっている。一方、日本では「単純な課題は苦手だが複雑で高度な活動は得意など、多様な特徴の児童生徒が一定割合存在する」(1月の中教審答申)とされるものの、十分に議論されてこなかった。このため、教育関係者や保護者らの間でも認識や対応にばらつきがあるのが現状だ。会合では、実際にこうした子どもが不登校となっている事例が報告されたほか、「同質性の高い学校文化そのものを見直すべきだ」との意見が出た。委員の松村暢隆関西大名誉教授は「『トップ人材を輩出する』といった目標から出発するのではなく、困っている才能児のニーズに対応するとの視点で議論していくべきだ」と指摘。発達障害を抱える子どももいるとして、特別支援教育や生徒指導との連携も必要とした。 *4-3-1:https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/202107/0014461592.shtml (神戸新聞 2021/7/1) 職場接種停止/国は態勢立て直しを急げ 政府は、新型コロナウイルスワクチンの企業や大学などでの職場接種の申請受け付けを急きょ停止した。想定を超える申請が殺到し、接種に使われる米モデルナ製ワクチンの供給が追いつかなくなったためだ。与党からは、国と自治体による大規模接種分を回すなどして早期再開を求める声が出ているが、見通しは立っていない。このまま打ち切られる可能性もあるという。開始から間もない方針転換で、準備を進めていた企業などの混乱は計り知れない。政府は見通しの甘さを猛省し、停止の経緯と再開の可否についてきちんと説明するべきだ。混乱は自治体の現場でも起きている。7月後半以降のワクチン配分量が政府から示されないなどで、兵庫県内の複数市町で64歳以下の接種予約が滞っていることが分かった。米ファイザー製を含めたワクチン供給量は全国民分を確保していると政府は強調するが、実際に大きな混乱が生じているのはなぜか。菅義偉首相は「1日100万回」「11月末までに希望者全員に」などの数値目標を掲げた。これを達成するため、準備不足にもかかわらず、スピード重視で進めようとした無理がたたったのは明らかだろう。政府は態勢を早急に立て直し、今後のワクチン供給量と配分計画を明確に示すべきだ。職場接種は、現役世代の接種を加速させ、社会全体を感染から守る効果への期待が大きい。だが課題も多い。1カ所で最低千人程度に接種するのが要件とされ、医師や会場は自前で確保しなければならない。すぐ対応できる大企業が先行する一方、国内企業の大半を占める中小企業にはハードルが高く、不公平感は否めない。温泉地や業界団体が同業各社を集めて共同実施にこぎつけた例もあるが、医師や会場が確保できず断念した企業もある。政府は小規模でも接種が可能な仕組みや、負担軽減に向けた支援拡充を検討するべきだ。一方、「打ち手」の争奪戦が起きれば、軌道に乗りつつある自治体の接種に影響しかねない。国と自治体、医師会などが連携して接種体制の再点検に努めねばならない。接種の本格化に伴う同調圧力にも注意が必要となる。持病や医学的な理由で接種を受けられない人や、副反応への不安などから接種を望まない人もいる。接種の強要や、打たない人が不利益を被るような対応があってはならない。今後、接種対象となる若い世代には高齢者と比べて副反応が出やすいとの報告もある。政府や自治体は、丁寧な情報開示と相談窓口の充実に取り組んでもらいたい。 *4-3-2:https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20210622_03.html (東京商工リサーチ 2021.6.22) 「新型コロナウイルス」関連破たん 1,661件 6月22日は16時時点で「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1,000万円以上)が7件判明、全国で累計1,580件(倒産1,482件、弁護士一任・準備中98件)となった。月別では2月(122件)、3月(139件)、4月(154件)と、3カ月連続で最多件数を更新した。5月は124件と、2021年1月以来4カ月ぶりに前月を下回ったが、過去3番目の件数と高水準だった。6月は22日までに105件が判明し5カ月連続で100件を超え、前月を上回るペースで推移している。なお、倒産集計の対象外となる負債1,000万円未満の小規模倒産は累計81件判明。この結果、負債1,000万円未満を含めた新型コロナウイルス関連破たんは累計で1,661件となった。3度目の緊急事態宣言は沖縄県を除き6月20日をもって解除された。ただし、一部地域はまん延防止等重点措置に移行し、飲食店の酒類提供や営業時間の制限は継続する。当面は流動的な状況で、消費関連企業にとって厳しい環境が続きそうだ。ダメージを受けた企業への金融支援策は継続するが、事業環境が回復しないままコロナ融資の返済がスタートする過剰債務の問題も浮上している。息切れや事業継続をあきらめて破たんに至るケースも目立ち始め、コロナ関連破たんは引き続き高水準で推移する可能性が高い。 【都道府県別】(負債1,000万円以上) ~ 30件以上は12都道府県 ~ 都道府県別では、東京都が372件(倒産351件、準備中21件)に達し、全体の約4分の1(構成比23.5%)を占め、突出している。以下、大阪府159件(倒産151件、準備中8件)、神奈川県80件(倒産73件、準備中7件)、愛知県74件(倒産74件、準備中0件)、北海道64件(倒産63件、準備中1件)と続く。22日は北海道、山形県、茨城県、東京都、石川県、大阪府、兵庫県でそれぞれ1件判明した。10~20件未満が17県、20~30件未満が8府県、30件以上は12都道府県に広がっている。 【業種別】(負債1,000万円以上)~飲食が最多284件、建設153件、アパレル135件、宿泊83件 ~ 業種別では、来店客の減少、休業要請などで打撃を受けた飲食業が最多の284件。一部地域では休業や時短の要請が継続し、営業制限が続く飲食業の新型コロナ破たんがさらに増加する可能性が強まっている。次いで、工事計画の見直しなどの影響を受けた建設業が153件、小売店の休業が影響したアパレル関連(製造、販売)の135件。このほか、インバウンドの需要消失や旅行・出張の自粛が影響したホテル,旅館の宿泊業が83件と続く。 また、飲食業などの不振に引きずられている飲食料品卸売業が75件、食品製造業も49件と目立 ち、飲食業界の不振が関連業種に波及している。 【負債額別】(負債1,000万円以上) 負債額が判明した1,551件の負債額別では、1千万円以上5千万円未満が最多の557件(構成比35.9%)、次いで1億円以上5億円未満が527件(同33.9%)、5千万円以上1億円未満が272件(同17.5%)、5億円以上10億円未満が98件(同6.3%)、 10億円以上が97件(同6.2%)の順。負債1億円未満が829件(同53.4%)と半数を占める。一方、100億円以上の大型倒産も6件発生しており、小・零細企業から大企業まで経営破たんが広がっている。 【形態別】(負債1,000万円以上) 「新型コロナ」関連破たんのうち、倒産した1,482件の形態別では、破産が1,309件(構成比88.3%)で最多。次いで民事再生法が80件(同5.3%)、取引停止処分が73件(同4.9%)、特別清算が12件、内整理が7件、会社更生法が1件と続く。「新型コロナ」関連倒産の約9割を消滅型の破産が占め、再建型の会社更生法と民事再生法の合計は1割未満にとどまる。業績不振が続いていたところに新型コロナのダメージがとどめを刺すかたちで脱落するケースが大半。 先行きのめどが立たず、再建型の選択が難しいことが浮き彫りとなっている。 【従業員数別】(負債1,000万円以上) 「新型コロナ」関連破たんのうち、従業員数(正社員)が判明した1,466件の従業員数の合計は1万8,143人にのぼった。1,466件の内訳では従業員5人未満が783件(構成比53.4%)と、半数を占めた。次いで、5人以上10人未満が294件(同20.0%)、10人以上20人未満が206件(同14.0%)と続き、従業員数が少ない小規模事業者に、新型コロナ破たんが集中している。また、従業員50名以上の破たんは2021年1-3月で11件発生し、4月は1件発生した。 ※ 企業倒産は、負債1,000万円以上の法的整理、私的整理を対象に集計している。 ※ 原則として、「新型コロナ」関連の経営破たんは、担当弁護士、当事者から要因の言質が取れたものなどを集計している。 ※ 東京商工リサーチの取材で、経営破たんが判明した日を基準に集計、分析した。 *4-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210710&ng=DGKKZO73760110Q1A710C2EA2000 (日経新聞 2021年7月9日) 企業落胆、商機失う 観光業など、打撃大きく 東京五輪の原則無観客開催で多くの企業が肩すかしを食らっている。宿泊を見込んでいた観光業界は収益への打撃が避けられない。スポンサー企業も製品や技術を売り込む好機のはずが、人々の目に触れる機会が大幅に減る。「朝からキャンセルが止まらない」。東武ホテルレバント東京(東京・墨田)では、9日午前だけで十数件の予約キャンセルが入った。期間中は稼働率約7割を見込んでいたが下がることは必至。大会期間中は通常より数割高い価格で設定していたが、緊急事態宣言の影響もあり「値下げは避けられない」と話す。京王プラザホテルも予約キャンセルが入り始めている。都内の高級ホテルでは大会関係者らの予約が多く入り、無観客でも一定の需要が見込まれる一方で、中堅・中小のホテルのダメージは大手より大きい。JTBなど旅行3社は9日、1都3県での観戦チケット付きの全ツアーを払い戻すと発表した。3社はスポンサーでもあり、このうち1社の幹部は「数十億円のスポンサー料や人件費などをかけてきたが、全て水の泡だ」とため息をつく。グッズ販売も苦戦が避けられない。アシックスは当初、約200億円の売り上げを見込んでいた。同社は9日「無観客シナリオは業績予想に織り込み済み」と発表し、業績下振れ懸念の払拭を図った。大会を「技術のショーケース」と期待していたスポンサーも思惑が外れた。NTTは高速通信規格「5G」を活用。セーリングでは観客席から沖合の船を間近で観戦できるように映像を映し出し、ゴルフでは専用端末を観客に配る計画だった。だが楽しめるのは大会関係者のみになる。セコムは警備ロボット、NECは入退場を管理する顔認証システムを導入するが、PR効果は薄れる。トヨタ自動車は燃料電池車(FCV)や電気自動車(EV)など1000台以上を提供する計画だったが、修正を検討する。大和総研は無観客の場合、大会期間中の経済効果が3500億円程度と、通常開催より4500億円縮小すると予測する。五輪は世界中で視聴される。映像演出など画面を通じて技術をアピールする機会はなお残る。 *4-3-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA124F40S1A710C2000000/ (日経新聞 2021年7月12日) 県境またぐ移動自粛、接種者も対象 戸惑う観光地 政府は12日、東京都に4度目となる新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を適用した。まん延防止の重点措置を含む6都府県の住民には県境をまたぐ不要不急の外出自粛を要請する。ワクチン接種者も一律に対象とする。26日から申請を受け付ける接種証明書も海外渡航用だ。夏のかき入れ時に期待していた国内観光地には戸惑いが広がる。東京の宣言は8月22日まで。宣言を延長する沖縄県、宣言に準じる重点措置を延長する埼玉・千葉・神奈川・大阪の4府県も期限は同じだ。夏休みやお盆に人の移動が活発になるのをにらんだ。政府が8日に改定した基本的対処方針は特に東京や沖縄について「帰省や旅行など都道府県間の移動は極力控えるよう促す」と明記した。国内でも高齢者を中心に増えつつある接種済みの人も扱いに差をつけなかった。首相官邸によると11日時点で65歳以上の76%、2700万人がワクチンを少なくとも1回打っている。ほとんどがファイザー製で3週間後に2回目を打つため、7月中に多くが接種を完了する。ワクチンの普及に期待していた観光地は今回、冷や水を浴びせられた。首都圏からの観光客が多い京都市。八坂神社近くの旅館「ギオン福住」の山田周蔵社長は「東京が動かないと話にならない」と肩を落とす。「予約は4月以降、修学旅行以外はほとんど入っていない。8月中旬までも期待できなくなった」。温泉地の群馬県草津町の旅館「ホテル一井」の市川薫女将も「(8月以降の)予約の入り方が鈍ってきた」と話す。クラブツーリズムは12日以降、東京や沖縄が発着地となる添乗員付きツアーを中止とする。日本旅行の小谷野悦光社長は「夏休みの旅行需要も見込めず、去年より厳しい状況。この夏をどう乗り越えるか、正念場だ」と話す。日本旅行業協会(JATA)の菊間潤吾副会長は「我々にいつまで我慢しろというのか」と憤りを隠さない。政府は感染力の強いインド型(デルタ型)の拡大を警戒している。内閣府幹部は「(接種者であっても)ウイルスを運ぶリスクがある。特にインド型は侮れない」と語る。海外では接種証明書を経済再生に生かす取り組みが進む。欧州連合(EU)は夏のバカンスシーズンを前に、1日から本格運用を始めた。加盟国やスイスなど約30カ国で使える。QRコードを示せば出入国時の検査や自主隔離が免除される。発行数は2億件を超えた。シンガポールは人口の半数が2回目を接種する見込みの7月末以降、制限緩和を進める方針だ。現在は5人までの飲食店の利用を接種者グループは8人まで認めることなどを検討している。日本も26日、証明書の申請受け付けを始める。加藤勝信官房長官は12日の記者会見で「海外に渡航する際に防疫措置の緩和を受けるのを目的とする」と述べた。イタリアなど十数カ国に要請している。国内での活用は現時点で想定していない。「接種の有無による不当な差別は適切ではない」と説明した。チグハグにも映る対応に経済界は異を唱える。経団連は接種証明書を早期に活用し、国内旅行などの要件を緩和すべきだと提言している。病床確保などの対策を進めつつ、経済をいかに回すかはコロナの感染拡大当初からの課題だ。ワクチンの普及など状況の変化を踏まえた柔軟な対応も求められる。 *4-3-5:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/707944 (佐賀新聞 2021.7.17) コロナ拡大と五輪、国民は「安全」なのか 国民の「安全」を守り、暮らしに「安心」をもたらす。一国のリーダーにとって最大の責務であることは言うまでもない。世界が注目する東京五輪・パラリンピックの開幕が迫った日本で、菅義偉首相はその使命を果たしているのか。五輪開催都市である東京で新型コロナウイルスの感染者が急増している。1日当たり千人を超す新規感染者数の報告が続き、5月の「第4波」ピーク時を上回っている。4度目になる緊急事態宣言が発令中だが、その効果は表れていない。専門家は現在の増加ペースで推移すれば、五輪閉会後には2400人程度に上るとの試算を公表した。年末年始の「第3波」さえ超える水準だ。東京など首都圏の感染者数は全国のおよそ3分の2を占めている。今後、インドに由来する感染力が強いデルタ株への置き換わりが進み、感染再拡大が首都圏から全国に波及する可能性もある。感染を収束させられないのは、政府対策の不備や迷走が第1の要因だろう。それでも五輪は23日に開幕する。21日には一部競技が先行して始まる。菅首相が「安全、安心な大会を実現する」と主張し、開催に突き進んできたためだ。1964年以来、日本では2度目となる夏の五輪には選手約1万人、大会関係者約4万1千人の来日が見込まれ、入国は本格化している。五輪は選手らと外部の接触を遮断する「バブル」方式で運営され、10都道県での広域実施となる33競技・339種目の大半は無観客の会場で行われる。菅首相は選手らの多くがワクチン接種を済ませている上、厳格な検査と行動制限を課すことで、ウイルスの国内流入を防ぐと強調する。だが事前合宿先で感染が判明した例もあり、水際対策は万全ではあるまい。選手村には、2回目の接種を終えていない日本人スタッフらが出入りする。管理の緩さが露呈した関係者の行動も問題視されている。バブルに穴がないか常時点検するとともに、五輪を発生源としたクラスター(感染者集団)を認知した場合、大会を続行するかどうかを検討しておく必要がある。菅首相はコロナ禍で行われる東京五輪の開催意義を巡って「世界が一つになり、難局を乗り越えていけることを発信したい」と繰り返している。さすがに「コロナに打ち勝った証し」との言い回しは封印したようだ。だが、生活や事業がコロナ前に戻るのはいつかという国民が一番知りたいことに答えていないのに、無責任な意義付けだと指摘せざるを得ない。主催者である国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長の現状認識にも疑問が湧く。バブル方式によりコロナ感染を「日本国民が恐れる必要はない」と断言。首相と会談した際には、感染状況が改善した場合「有観客」を検討してほしいと伝えたという。首相と同じく「五輪ありき」の姿勢がうかがえ、国民感情を軽視していると批判されても仕方あるまい。菅首相が何より優先しなくてはならないのは、五輪を予定通り終わらせることではない。国民の命を守るためコロナ感染を一日も早く収束に向かわせることだ。憲法に基づく野党の臨時国会召集要求に応え、コロナ対策を充実させる論議に臨むべきだ。首相に値するか問われている。 *4-4-1:https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/929053.html (静岡新聞社説 2021年7月14日) 来日選手難民申請 認定制度見直す機会に サッカー・ワールドカップ予選のため来日していたミャンマー代表選手のピエ・リヤン・アウンさんが、クーデターを起こした国軍に抗議の意志を示して帰国を拒否し、日本に難民認定を申請した。本国の家族や帰国したチームメートの身を案じながら、自らが帰国した場合、生命の危機にさらされると考えて下した苦渋の決断だった。クーデター後のミャンマー情勢には世界の目が注がれている。日本政府は5月、日本在留の継続を望むミャンマー人に対して緊急避難措置として在留延長や就労を認める方針を示した。ピエ・リヤン・アウンさんは在留延長が認められ、難民認定も出入国在留管理庁は迅速に手続きを進めるという。日本は他の先進国と比べて難民認定の判断基準が厳しく、認定数が極端に少ないと指摘されている。ここ数年、ミャンマー人は一人も認定されていなかった。人道上の見地から安心して帰国できる治安情勢になるまで保護するのは当然で、国際社会の視線を気にした例外的な対応であってはならない。認定のハードルが高いため、これまで本来、保護されるべき人が保護されていないまま本国へ送り返されるようなことはなかったのか。難民認定の在り方について見直す機会にしたい。難民条約は人種、宗教や政治的意見を理由に母国で迫害される恐れがある人を難民と定義し、各国が保護するよう求めている。日本は条約に加入した1981年以降、計約840人を難民として認定してきた。だが、他国と比べると、難民の受け入れに消極的なのは一目瞭然で、条約加入国の義務を十分果たしているとはいえない。2019年の1年間だけでも、難民認定はドイツ約5万3千人、米国約4万4千人、フランス約3万人に上る。認定率も18~30%と高い。日本の認定者は44人で、認定率は0・4%だった。他国なら難民と認められても当然な状況ながら日本で認定されなかったため、本国に帰ることもできず難民申請を繰り返さざるを得ない外国人も多いのではないか。先の国会で難民申請の回数を制限する入管難民法の改正案が提出されたが、入管施設収容中のスリランカ女性の死を巡って野党の強い反発もあり、与党は成立を断念した。難民認定は人命に関わる重要な手続きだ。申請者の出身国の情勢をしっかり見極めた上で認定の是非を判断しなければならない。国会での政治的駆け引きではなく、外国人の人権保護という原点に立ち戻って認定制度について真剣に議論する必要がある。 *4-4-2:https://www.jiji.com/jc/article?k=2021071601004&g=spo (時事 2021年7月16日) ウガンダ選手が所在不明 事前合宿地の大阪府泉佐野市〔五輪〕 大阪府泉佐野市は16日、東京五輪の事前合宿で受け入れているウガンダ選手団の男子選手の所在が分からなくなっていると発表した。この選手は重量挙げのジュリアス・セチトレコさん(20)で、市は警察に届け出た上で行方を捜している。16日正午すぎに、セチトレコ選手の新型コロナウイルスのPCR検査が行われていないことに気付いた市職員が、ホテルの部屋を確認したところ不在だった。部屋には「日本で仕事がしたい。生活が厳しい国には戻らない」という趣旨の書き置きが残されていた。市はJR西日本に問い合わせ、同選手が名古屋行き新幹線の切符を購入したことも確認したという。市によると、セチトレコ選手は合宿期間中に世界ランキングが下がって五輪に出場できなくなり、コーチとともに近く成田空港から帰国する予定だった。選手団9人は6月19日、成田空港に到着。入国時の検査で1人が陽性判定を受けた。一行が泉佐野市に移ってから残りの8人全員が濃厚接触者と特定され、さらに別の1人の感染が判明。その後、基準を満たしたため練習を再開していた。 <先端科学で証明しよう、日本人のルーツと古代史> *5-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC18CCA0Y1A610C2000000/ (日経新聞 2021年6月23日) 渡来人は四国に多かった? ゲノムが明かす日本人ルーツ 私たち日本人は、縄文人の子孫が大陸から来た渡来人と混血することで生まれた。現代人のゲノム(全遺伝情報)を解析したところ、47都道府県で縄文人由来と渡来人由来のゲノム比率が異なることがわかった。弥生時代に起こった混血の痕跡は今も残っているようだ。東京大学の大橋順教授らは、ヤフーが2020年まで実施していた遺伝子検査サービスに集まったデータのうち、許諾の得られたものを解析した。1都道府県あたり50人のデータを解析したところ、沖縄県で縄文人由来のゲノム成分比率が非常に高く、逆に渡来人由来のゲノム成分が最も高かったのは滋賀県だった。沖縄県の次に縄文人由来のゲノム成分が高かったのは九州や東北だ。一方、渡来人由来のゲノム成分が高かったのは近畿と北陸、四国だった。特に四国は島全体で渡来人由来の比率が高い。なお、北海道は今回のデータにアイヌの人々が含まれておらず、関東の各県と近い比率だった。以上の結果は、渡来人が朝鮮半島経由で九州北部に上陸したとする一般的な考え方とは一見食い違うように思える。上陸地点である九州北部よりも、列島中央部の近畿などの方が渡来人由来の成分が高いからだ。大橋教授は「九州北部では上陸後も渡来人の人口があまり増えず、むしろ四国や近畿などの地域で人口が拡大したのではないか」と話す。近年の遺伝学や考古学の成果から、縄文人の子孫と渡来人の混血は数百~1000年ほどかけてゆっくりと進んだとみられている。弥生時代を通じて縄文人と渡来人が長い期間共存していたことが愛知県の遺跡の調査などで判明している。どのような過程で混血が進んだのかはまだ不明で、弥生時代の謎は深まる一方だ。今回の解析で見えた現代の日本列島に残る都道府県ごとの違いは、弥生時代の混血の過程で起こったまだ誰も知らない出来事を反映している可能性がある。書物にも残されていない日本人の歴史の序章は、ほかならぬ私たち自身のゲノムに刻まれているのだ。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210708&ng=DGKKZO73668690X00C21A7TB2000 (日経新聞 2021.7.8) 10万人のゲノム解析 東北大・武田など5社連携 創薬に利用、欧米を追う 東北大学は7日、武田薬品工業やエーザイなど製薬大手5社と、10万人分のゲノムを解析するためのコンソーシアムを設立したと発表した。製薬会社が従来の10倍以上のゲノムデータを創薬や診断技術の開発などに利用できるようにする。欧米には数十万人規模のバイオバンクがすでにあり、ようやく日本もゲノムをもとに新薬を探す「ゲノム創薬」の基盤整備が進む。バイオバンクは健康な人や患者から、血液や尿などの試料、そのゲノムを解析したデータを収集する。年齢・性別、生活習慣や病気の履歴などのデータも合わせて蓄積し、これらを創薬研究する企業や大学などに提供する。データを活用すれば、新薬の開発やそれぞれの患者に適した治療をする「個別化医療」の実現に役立つ。東北大が運営する東北メディカル・メガバンク機構は2012年に設置。宮城県、岩手県の15.7万人超のデータや試料をもつが、ゲノム解析に時間や費用がかかり、企業が利用できるデータは約8300人分にとどまっていた。コンソーシアムは文部科学省の予算約40億円と企業の資金をもとに、24年までに10万人分のゲノム解析を目指す。21年度中に6万人分の初期的な解析を終える予定だ。参加するのはエーザイ、小野薬品工業、武田、第一三共、米ジョンソン・エンド・ジョンソン傘下のヤンセンファーマ。5社は10万人分のゲノムデータを優先的に利用できる。記者会見した東北メディカル・メガバンク機構の山本雅之機構長は「10万人のゲノムデータがあれば、日本人で見つかる遺伝子変異を網羅的に探せるだろう」と話した。製薬会社は治療薬や診断法の開発につなげる狙いだ。武田は国内でも先駆けてゲノム創薬に取り組んできた。19年には英国の「UKバイオバンク」に参加。一定の使用料を支払い、50万人規模のゲノムデータを活用している。20年には東北メディカル・メガバンク機構と共同研究を開始。認知機能の低下など精神・神経疾患を引き起こす要因を中心に調べ、新薬や治療法の確立を目指している。エーザイも21年5月に国立がん研究センターが持つがん組織のゲノムデータをもとに、希少がんの治療薬の開発に乗り出している。もっとも、ゲノムデータ収集で先行するのは欧米だ。武田が参画する英国の「UKバイオバンク」は06年から健康な50万人を追跡。米ファイザーや英アストラゼネカなど世界のメガファーマも参画する。ゲノムデータをはじめとして、生活習慣や既往歴などの情報が利用でき、創薬に利用しやすいという。英国にはがんや希少疾患の患者を対象とした政府系機関によるバイオバンクもあり、18年12月に10万人のゲノム解析を終えた。米国では100万人分を目標に約49万人分を集めた取り組みなどがある。ゲノム解析などに詳しいアーサー・ディ・リトル・ジャパンの小林美保シニアコンサルタントは「UKバイオバンクは英政府が支援しており、データが集まってくる仕組みがある」と指摘する。日本も国の支援のもとデータを集める仕組み作りが必要だ。 <感染者・濃厚接触者も検査で陰性になれば出場させるのが適切> PS(2021年7月20、21日追加):*6-1のように、「①東京五輪に出場する選手が新型コロナ感染者の濃厚接触者でも、試合開始6時間前に実施するPCR検査で陰性なら出場を認める」「②国内の濃厚接触者は14日間の自宅待機等が求められ、五輪選手への特例的対応」「③プレーブックでは、濃厚接触者は個室に移動し、1人での食事などが求められ、試合出場に国際競技団体の同意が必要とされていた」「④南アフリカのラグビーチームで選手ら18人が大会での濃厚接触者の取り扱いが課題となっていた」と書かれている。 しかし、濃厚接触者は感染を疑われる者でしかなく、PCR検査で陰性ならその疑いは晴れている。また、PCR検査を数回やって陰性ならなおさら安心で、14日間の自宅待機・個室への移動・1人での食事も不要であり、プレーブックの方が間違いだ。もちろん、国民も同じである。そのため、南アフリカの選手が1人であれ複数であれ、不要な出場禁止や幽閉は、権利の侵害にあたる。また、*6-2の米女子体操選手と濃厚接触者になった選手も、PCR検査で陰性なら何の問題もなく出場を認めてよい筈だ。 さらに、*6-3のように、「①私立米子松蔭高は、7月16日に学校関係者に新型コロナ感染が判明し、第103回全国高校野球選手権鳥取大会への出場を一度は辞退した」「②ベンチ入りした全野球部員の陰性を確認したが、7月17日の試合直前に辞退を決めた」とのことだが、選手本人が陰性なら辞退する必要はない。にもかかわらず、学校関係者に新型コロナ感染が判明したことを罰するかのように、出場を辞退させるのは非科学的すぎる。また、学校関係者に感染者がいたことが全体の責任ででもあるかのような対応をとれば、悪くもない感染者を窮地に追い詰め、差別やいじめに繋がって教育上も悪影響がある。そのため、「鳥取県高野連が世論の高まりを受けて出場を容認したからよい」のではなく、こういう理不尽な判断が教育現場でまかり通った理由を追及すべきである。 *6-1:ttps://digital.asahi.com/articles/ASP7J3V8MP7JUTQP005.html (朝日新聞 2021年7月16日) 五輪選手、濃厚接触者でも検査陰性なら出場へ 特例対応 東京オリンピック(五輪)・パラリンピックに出場する選手が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と判定されても、試合前のPCR検査で陰性となれば出場を認める方向で、政府と大会組織委員会が調整していることがわかった。通常、国内の濃厚接触者は14日間の自宅待機などが求められており、五輪、パラリンピック選手への特例的な対応となる。政府と組織委の対応方針では、濃厚接触者と判定されても、試合開始の6時間前をめどに実施するPCR検査で陰性となれば、出場を認めるという。コロナ対策のルールをまとめた「プレーブック(行動規範)」では、濃厚接触者と認定されると、個室への移動や1人での食事などが求められており、試合出場については国際競技団体の同意などが必要とされていた。今月13日に来日した南アフリカのラグビーチームで選手ら18人が濃厚接触の調査対象者と判定され、事前キャンプ地入りを一時的に見送るなどしており、大会での濃厚接触者の取り扱いが課題となっていた。テニスの4大大会、ウィンブルドン選手権では、濃厚接触者となった選手は自動的に10日間の隔離を強いられ、棄権扱いになっていた。 *6-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/117784 (東京新聞 2021年7月19日) 米女子体操選手が陽性 事前合宿中、1人濃厚接触 千葉県印西市は19日、同市で事前キャンプをしていた東京五輪の米女子体操選手団のうち、10代選手1人が新型コロナウイルス検査で陽性になったと発表した。別の選手1人が濃厚接触者として宿泊先のホテルで待機している。市によると、選手団は15日の入国後、毎朝スクリーニング検査を実施。10代選手は18日に陽性疑いが出て、19日未明に病院の検査で確定した。選手団はトレーニング以外での外出はしておらず、移動は貸し切りのバスを利用していた。感染した選手と濃厚接触者を除く選手団は19日午後、東京五輪の選手村に移動した。 *6-3:https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-1359293.html (琉球新報 2021年7月21日) 米子松蔭高、鳥取大会初戦を制す コロナで辞退から一転 学校関係者に新型コロナウイルスの感染者が出たため、第103回全国高校野球選手権鳥取大会への出場を一度は辞退しながら、一転して出場が決まった私立米子松蔭高の再試合が21日、米子市内で開かれた。17日に行われるはずだった境高との初戦(2回戦)で、米子松蔭高は0対2でリードされていた九回裏に3点を入れ、逆転サヨナラ勝ちした。米子松蔭高は春季鳥取大会を制した強豪校。16日に学校関係者の陽性が判明。ベンチ入りした全野球部員の陰性を確認したが、17日の試合直前に辞退を決めた。世論の高まりを受け、県高野連は19日に不戦敗の記録を取り消し、出場を容認した。
| 経済・雇用::2021.4~2023.2 | 11:46 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
PAGE TOP ↑
