左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。
|
2020,01,23, Thursday
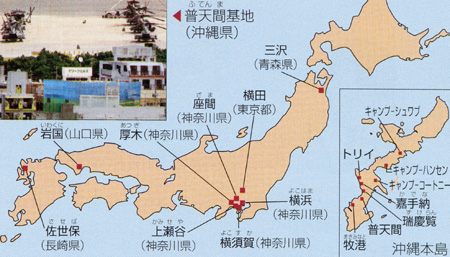  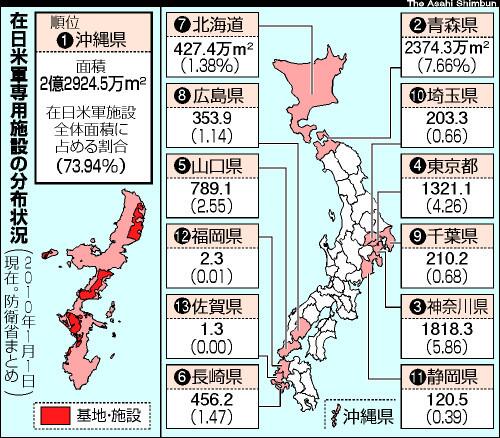 (図の説明:左図のように、米軍基地は関東と沖縄に集中しており、中央と右図のように、沖縄は約2億3千万m₂と日本全体の約74%を占める。これは、太平洋戦争後の状況に応じて設置されたもので、現在の自衛ニーズに合わせた配置ではない。また、首都圏に6箇所もの広大な基地があるのは土地の無駄使いである上、合目的的でもなく、沖縄は全体が基地の島になっているのに尖閣諸島の領海に中国船が頻繁に入っているのは、自衛のニーズに合っていない証拠である) (1)日米同盟の必要性 1)日米リーダーの認識 2020年1月19日で日米安全保障条約改定から60年となるのに合わせ、米国のトランプ大統領は、*1-3のように、「①60年間の強固な同盟関係は、米国、日本、インド太平洋地域、そして世界平和、安全、繁栄に不可欠だった」「②安全保障環境が変わって新たな課題が出てくる中、同盟をさらに強化・深化させることが不可欠で、日本の貢献が増すことを求める」という声明を発表し、米国国務省のオータガス報道官も、2020年1月17日、「③負担は公平でなければならない」とした。 日本の安倍首相は、2020年1月19日、日米安全保障条約署名60周年を記念する式典で、*1-4のように、「④日米安保条約は、アジアとインド太平洋、世界の平和を守り、繁栄を保証する不動の柱だ」「⑤60年・100年先まで日米同盟を守って強くしていこう」と呼びかけた。 私は、日本のみでは自衛することも不可能で、人権や世界情勢に疎い日本政府のみの判断で猛進されるとむしろ危険であるため、日米同盟は必要だが、それには、以下に述べる多くの問題点を解決することが必要だと考える。 2)問題点 信濃毎日新聞は、*1-1のように、「①日米安全保障条約は、朝鮮戦争中の1951年に締結され、米軍の日本駐留がサンフランシスコ講和条約を結ぶ上での条件だった」「②1960年1月19日に改定され、米国の日本防衛義務が5条に盛られると同時に、日本に防衛力の維持・発展を義務付け、在日米軍を守る義務も課した」「③60年経過したので、そろそろ外交の基軸を築き直せ」と記載している。 1991年にイラクがクウェート侵攻した時は、日本は、平和憲法のおかげでExcuseできて自衛隊を派遣せずにすんだが、130億ドル(約1兆3千億円)の資金拠出をしても、今一つ感謝されなかった。その後、日本は、海賊から自国の船を護るためと言いつつ自衛隊を海外派遣するようになったが、集団的自衛権は認めていないというExcuseにより、米国と一緒に戦争に参加することはなかった。 しかし、2000年代になって米中枢同時テロ後、日本は、テロとの戦いを宣言した米国を支持してテロ対策特別措置法を成立させ、海上自衛隊をインド洋での給油活動に従事させた。また、国連決議のないイラク戦争でも、日本はイラク復興支援特措法を設けて、サマワに陸上自衛隊を駐屯させた。集団的自衛権も自衛権のうちだが、それを認めた現在では、米軍の活動に対する自衛隊支援の地理的制約が機能しにくくなった。 このような中、日本は、米国から兵器を大量購入し、米軍との連携領域を宇宙やサイバーへと広げ、唯一の被爆国でありながら核兵器禁止条約に参加できず、防衛費や在日米軍経費を膨らませ、日米地位協定の改定もせずに、内政面でも不利な日米貿易協定を呑んだ。 また、北海道新聞が、*1-2に記載しているように、戦後の日本は、冷戦の中で米国と経済・安保の両面で協調することによって発展を遂げたが、国際情勢は冷戦期から大きく変わり、米国はトランプ政権の下で「世界の警察官」の立場から降りようとしている。また、米軍との連携を目的にした自衛隊の中東派遣は、海外での武力行使を禁じた日本国憲法に違反しており、行き過ぎた対米追従は平和憲法という宝を失う行為となる。 そのため、「外交・防衛は、親分の米国を頼って日米安保のみ」という構図は考え直し、米国とは密に連携しながらも多国間協調や平和を大切にする独立した大人の外交が、今後の日本には求められる。 (2)日米同盟の具体的なコストと効果 1)膨張する防衛費は、専守防衛に適合したものか? 政府は、北朝鮮の核・ミサイル開発や中国の軍拡など安全保障環境の厳しさを強調し、防衛費を拡大させ、*2-2・*2-3のように、トランプ米大統領の求めに応じて対外有償軍事援助(FMS)として米国製の高額な最新鋭兵器を買っているが、日本の厳しい財政事情の下、その目的と費用対効果は厳しく吟味すべきだ。 つまり、2020年度の当初予算案で、防衛費は5兆3133億円で、文教・科学振興費の5兆5055億円に匹敵し、公共事業費の6兆8571億円に近づく規模だからで、「防衛費のために社会保障費を削る」というのは、国民生活を直撃することによって個人の命をないがしろにしており、それこそ「国民の命を護る」という理念から外れる。 私は、外交や防衛の専門家ではないが、会計・税務・財務の専門家として、31億円もかけて護衛艦を空母に改修するのは、艦の安全性を害さないのか、ミサイル時代に意味があるのか、について疑問に思う。また、そこで運用される米国製の最新鋭ステルス戦闘機F35Bも6機で793億円もし、陸上配備型迎撃ミサイルシステムは、(配備先がまだ決まっていないのに)米国からの発射装置の取得等に129億円を投じ、最終的には東西2基で5千億円を超える巨額だそうで、他にもあるだろうから、これこそ合計額とその明細を明らかにすべきである。 そして、昨年末に改定された「防衛計画の大綱」「中期防衛力整備計画」は、「陸海空のみならず宇宙・サイバー空間などの新たな領域への対応」を掲げており、これらは日本の専守防衛の方針に合致しているのか疑問であるため、国会の予算審議では導入の必要性や是非から議論してもらいたく、これらの議論は、刑事事件にならない「桜を見る会」やちゃちな公選法違反の追及よりも、文字通り桁違いに重要なのである。 ただ、トランプ米大統領の強い要請から、安倍首相が米国への政治的配慮をせざるを得ない事情はわかる。それは、親分である米国を頼って好き勝手なことをしながら、日本国内のメディアがトランプ大統領をコケにする報道をしたり、交渉の担い手である安倍首相の続投を危うくさせたりしているからで、これではトランプ大統領には、とりわけ高い報酬をもらわなければ、安倍首相と交渉して日米同盟を続けるメリットはないわけである。 つまり、日本メディアの問題点は、官僚が政策のKeyを握っており、(それを知っているにもかかわらず)責任だけを政治家にかぶせ、本当はあまり力のない政治家を批判して権力と闘っているポーズをとっていることで、この形だけの民主主義は本物の民主主義国では通用しないということなのである。 2)辺野古新基地と馬毛島・グアム移転の並立は不要な筈である 沖縄県名護市辺野古の新基地建設は、日本を護るための費用対効果が低すぎるため、日米同盟の維持に不可欠というよりも、公共事業者への利益誘導に変質してしまったようだ。 具体的には、*2-4-1・*2-4-2のように、米軍普天間飛行場の移設は、辺野古に軟弱地盤が存在するため、地盤改良5年、埋め立て5年、施設整備3年を要し、合計13年以上かかり、総工費は最大2兆6500億円まで膨らむそうだ。政府の試算は確かに杜撰であるため、費用対効果からみた辺野古新基地建設の必要性を早急に再検討すべきだ。 また、埋め立て予定海域への外部の土砂の投入も生態系を破壊しており、*2-4-3のように、鹿児島県の馬毛島に基地のうち日本の防衛に必要な部分を移転すれば、埋め立てや自然破壊は不要である。にもかかわらず、政府が前のめりに突き進んでいるのは、米政権の意向より、政府の対面や公共事業の既得権益の影響の方が大きいのではないだろうか。 さらに、日本の防衛に不必要な部分は、*2-4-4のように、グアムに移転すればよく、米軍は2024年10月から約5千人の海兵隊員が移転を始め、約一年半かけて完了させる方針だそうで、米国もまた安全保障環境の変化に応じて柔軟に対応すればよいのである。 そして、2012年に日米両政府が修正合意した米軍再編計画では、在沖縄海兵隊約1万9千人のうち約9千人をグアムやハワイなどへ移転させることや、米軍普天間飛行場の辺野古移設が盛り込まれたそうだが、石垣島や宮古島に自衛隊基地ができ、自衛隊と米軍の運用の一体化がいっそう進む以上、もっと多くの海兵隊員をグアムやハワイ、場合によっては台湾やその他の地域に移転させることが可能であろう。 3)「思いやり予算」について 第二次世界大戦終結から75年、冷戦終結から30年が経過して、安全保障環境が変化した結果、米国は、*2-5のように、在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)を約20億ドルから約80億ドル(80億ドルX109円/ドル=8720億円)に増額することを要求している。 これは、米国にとって日本に置く基地の必要性が下がったということであるため、米軍は世界規模でやるべきことが他に山ほどあることにも鑑み、トランプ大統領に米軍駐留経費負担を現在の4倍以上に増額することを求められたのをよい機会として、日本の自衛のために役立っている米軍基地だけを残して日本にある米軍基地を1/4以下に減らし、駐留経費を現状維持するか、それ以下に下げるのが日本にとっても都合がよいと考える。 4)日米安保条約60年の平和主義を前提とした効果的な再構築は? 熊本日日新聞も、*2-1のように、「①日米安全保障条約は2020年1月19日で60年を迎えた」「②戦後の復興と繁栄を支える土台となった安保体制の重要性は今後も変わらない」「③日本では、米国の戦争に巻き込まれるリスクへの懸念が根強く、過度な一体化を危ぶむ声もある」「④日本は憲法が掲げる平和主義を前提に、米国との関係をどうつくるのかを再検討する時期に来ている」「⑤在日米軍人らの特権を認めた日米地位協定も抜本的な見直しが急務だ」としており、そのとおりだと思う。 (3)中東への自衛隊派遣について 政府は、*3-1・*3-4のように、トランプ大統領の要請に応じ、自衛隊を中東に独自派遣する方針となったが、徳島新聞が記載しているとおり、この局面での日本のトランプ大統領への追従は高リスクだと私も思う。 このように、民主主義国である米国の行動に問題がある中で、中国との関係修復を進めているが、中国は国内の民主化が課題の国であり、日本は、日本国憲法に基づいた独立的な距離感を持つことが求められる。 なお、*3-2・*3-3のように、ホルムズ海峡周辺への自衛隊派遣は、自衛隊法に基づいておらず、自衛隊の海外派遣を日常化させたい日本政府が米国からの有志連合への参加呼びかけを「渡りに船」で選択したものだと言われており、安保法制の下で日本が紛争に巻き込まれたり、日本が武力行使を行うことになる恐れがある。そのため、外国での武力による威嚇や武力行使を禁止する日本国憲法9条に反すると思う。 ・・参考資料・・ <日米同盟の必要性> *1-1:https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200119/KT200118ETI090005000.php (信濃毎日新聞 2020.1.19) 日米安保60年 「外交の基軸」を築き直せ 1991年秋、米国の大学に留学中の筆者は、教室で学生からの“総口撃”にさらされた。イラクのクウェート侵攻を受けた湾岸戦争から半年余り。「なぜ日本は自衛隊を派遣しなかったのか」「カネでは協力にならない」「そんな同盟国は要らない」。日本が対米傾斜を深め、自衛隊の海外派遣に道を開いた戦争だったことは後で知った。いまなら米国の学生たちに、どんな意見を返すだろう。 <湾岸戦争を契機に> 日米安全保障条約は朝鮮戦争さなかの1951年に結ばれた。日本が防衛手段を持つまでの「暫定措置」とされたものの、米軍の日本駐留は、サンフランシスコ講和条約を結ぶ上での条件だった。米国がこの権益を手放すことはなく、60年前のきょう、新日米安保条約に改定されている。旧条約で曖昧だった米国の日本防衛義務が5条に盛られた。日本に防衛力の維持・発展を義務付け、在日米軍を守る義務も課した点は見落とせない。米国が防衛力増強と負担分担を、日本に繰り返し迫る根拠となった。条文は在日米軍の活動範囲を日本と極東に限っている。が、ベトナム戦争や70年代からの中東危機で、この制約は当初からないがしろにされてきた。安保体制が大きく変容し始めたのは冷戦が終わってからだ。湾岸戦争を前に、米国は日本に人的貢献を求めた。海部俊樹政権は「平和憲法がある」とし、130億ドル(約1兆3千億円)の資金拠出で応えている。この対応は「小切手外交だ」との猛烈な批判を招く。米国に見限られる―。日本の外務・防衛当局に不安が広がったという。海部政権は結局、初の自衛隊海外派遣に踏み切り、戦後のペルシャ湾で機雷掃海に当たらせた。冷戦終結で薄れつつあった安保の意義は、極東条項を離れ「アジア太平洋地域の安定と繁栄の基礎」に再定義される。「湾岸のトラウマ」と呼ばれた政府の経験は、世紀が変わって間もなく起きた米中枢同時テロ後の反応となって表れる。テロとの戦いを宣言した米大統領を小泉純一郎首相はいち早く支持し、おざなりな国会審議でテロ対策特別措置法を成立させる。海上自衛隊はインド洋での給油活動に従事した。国連決議のないイラク戦争も日本は認めた。イラク復興支援特措法を設け、陸上自衛隊は安全とは言えないサマワに駐屯する。安保の定義は「世界課題への対処」へとさらに範囲を広げている。 <際限なき軍拡より> 違憲性も安保条約の枠も顧みず、米国の世界戦略に追随する路線を安倍晋三政権も踏襲する。憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認。在日米軍の活動範囲と自衛隊による後方支援の地理的制約を取り払った。台頭する中国へのけん制を意図し、専守防衛から懸け離れた兵器を大量に購入、米軍との連携領域を宇宙やサイバーへと広げつつある。安倍政権は日米同盟を「外交の基軸」に据える。国際社会への協力と対米協力が同義となった日本の外交と政策は主体性を失っている。トランプ米政権がパリ協定から離脱しても意見できない。唯一の被爆国でありながら、イラン核合意や中距離核戦力(INF)廃棄条約の破棄も止められず、米国の反発を恐れて核兵器禁止条約への参加に二の足を踏む。内政面でも、不利な日米貿易協定をのまざるを得なかった。防衛費や在日米軍経費は膨らみ、基地を抱える地域の危険除去に欠かせない日米地位協定の抜本的な改定すら言い出せずにいる。あのころの米国の学生たちに、こう伝えてみたい。「小切手外交」も無意味ではなかった。東日本大震災の際、クウェートでは「私たちが支援する番だ」との声が上がり、多額の義援金が寄せられた。たくさんの原油を無償提供してくれた。戦後の経済支援は東南アジアで日本への信頼を培った。日本が本気になって多国間協調による地域の平和構築を提唱すれば、戦禍を被ったアジアの国々が背を向けるとは思えない、と。そのためには、凝り固まった外交=安保の構図を解きほぐす必要がある。アジアや国際社会の安定に向けた日本の役割を整理する。安保の適用範囲を極東に戻して米国の世界戦略と一線を画し、自律した外交構想に組み入れたい。不安定な世界情勢で安保体制の見直しは現実的でない―。そんな声が聞かれる。際限のない軍拡競争は対立の大本を正しはしない。条約を逸脱した日米安保の現状こそが、北東アジアの秩序を揺さぶっている現実に、もっと目を向けなくてはならない。 *1-2:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/384535 (北海道新聞 2020.1.19) 日米安保60年 追従ばかりでは危うい 現行の日米安全保障条約の署名から、きょうで60年を迎えた。戦後日本は米国と経済、安保両面で協調することによって発展を遂げてきた。だがいま、安保協力の中身と、取り巻く国際情勢は、冷戦期から大きく変質している。その一つは、安倍晋三政権が自衛隊と米軍の一体化を加速させていることだ。今月には米軍との連携を事実上の目的にした自衛隊の中東派遣に、国会の熟議もなく踏み切った。憲法は海外での武力行使を禁じている。専守防衛を逸脱しかねない行き過ぎた対米追従は危うい。米国はトランプ政権の下で自国第一主義に走っている。「世界の警察官」の立場から降りようとし、同盟国には見返りを求めている。安保条約の趣旨は、日本が米国の言いなりになることではない。中国が軍事面でも台頭し、テロも多極化する中、日本が平和国家の道をどう歩み続けるのか。対米連携とともに、多国間の協調に軸足を置いた外交・安保に力を注ぐのが取るべき道だろう。今年直面するのが米軍駐留経費を巡る特別協定の改定交渉だ。トランプ政権が11月の大統領選を見据え、日本に一層の負担増を求めてくることは間違いない。本来は米側が支払うべき人件費などについて、日本側が負担する「思いやり予算」は本年度、1974億円に上る。日本の負担割合は同盟国の中で突出して高く、すでに8割を超えているとされる。にもかかわらず、米側は昨年夏、瀬踏みをするかのように現行の5倍の負担を求めてきたという。論外である。米軍は中国や北朝鮮、ロシアなどの脅威を見据え、在日米軍基地をアジア・太平洋地域の戦略拠点としている。こうした米側の利益を踏まえ、一方的な主張に対しては明確に反論すべきだ。日米安保によって、沖縄には国内の米軍専用施設の7割が集中する。戦後はまだ終わっていない。県民が反対する中、安倍政権が工事を強行する、米軍普天間飛行場の辺野古移設がその象徴だ。米海兵隊の輸送機オスプレイの訓練が今週から道内で実施される。沖縄の負担軽減を名目に、日本全体にその負担がじわじわ広がっていることも見過ごせない。米軍の特権的な法的地位を定めた日米地位協定は一度も改定されていない。米国に追従する前に安倍政権がなすべき懸案は山積している。 *1-3:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200119/k10012250921000.html (NHK 2020年1月19日) 日米安保60年 トランプ大統領が同盟の意義を強調 日米安全保障条約の改定から19日で60年となるのに合わせ、アメリカのトランプ大統領は「60年にわたり両国の強固な同盟関係は世界の平和、安全、繁栄に不可欠なものだった」などとする声明を発表しました。1960年に改定された今の日米安全保障条約は、19日で署名から60年となります。これに合わせ、アメリカのトランプ大統領は18日、声明を発表しました。この中でトランプ大統領は、「過去60年にわたり、両国の強固な同盟関係はアメリカ、日本、インド太平洋地域、そして世界の平和、安全、繁栄に不可欠なものだった」と同盟の意義を強調しています。そのうえで、「安全保障をめぐる環境の変化が続き、新たな課題が生じる中で、日米同盟を一層強化し深めることが不可欠だ。今後、相互の安全保障への日本の貢献がさらに増し、同盟関係が引き続き発展していくと確信している」として、日本のさらなる貢献に期待を示しました。日米同盟をめぐっては、アメリカ国務省のオータガス報道官が17日、NHKとの単独インタビューで、「負担は公平でなければならない」と述べるなど、トランプ政権はことし夏にも本格化する見通しの日本とのアメリカ軍の駐留経費をめぐる交渉で、日本に対しさらなる負担を求めていく姿勢を示しています。 *1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200120&ng=DGKKZO54579580Z10C20A1MM8000 (日経新聞 2020.1.20) 首相、日米安保条約は「不動の柱」 署名60年記念式典で 安倍晋三首相は19日、現行の日米安全保障条約署名60周年を記念する式典に出席した。日米安保条約に関し「今やいつの時代にもまして不滅の柱。アジアとインド太平洋、世界の平和を守り、繁栄を保証する不動の柱だ」と述べた。「60年、100年先まで日米同盟を堅牢(けんろう)に守り、強くしていこう」とも呼びかけた。首相は「宇宙、サイバースペースの安全や平和を守る柱として、同盟を充実させる責任がある」と強調し、新たな課題に対処するため同盟関係の拡充をめざす考えを示した。日米同盟を「希望の同盟」と表現し「歩むべき道はただ一筋。その希望の光をもっと輝かせることだ」と語った。トランプ米大統領は記念式典に先立ち、18日に声明を発表し「安全保障環境が変わり新たな課題が出てくるのに伴い、同盟をさらに強化し深化させることが不可欠だ」と訴えた。「日本の貢献の拡大と同盟の発展が続くことを確信している」との期待感も示した。19日に都内で開いた記念式典には日本側から麻生太郎副総理・財務相や茂木敏充外相、河野太郎防衛相らが出席した。米側からはヤング駐日臨時代理大使やシュナイダー在日米軍司令官らのほか、条約署名時に大統領だったアイゼンハワー氏の孫らも参加した。現行の安保条約は1960年1月19日に、首相の祖父である当時の岸信介首相とアイゼンハワー氏のもとで結んだ。岸氏とハーター国務長官らが署名し、51年に結ばれた旧条約を全面改定した。首相は記念式典で「岸は日本の首相として米大統領とゴルフをした最初の人物だった。2番目は私だ。アイゼンハワーと岸が培った友情は新しい安保条約となって実を結んだ」と振り返った。 <日米同盟の費用対効果> *2-1:https://kumanichi.com/column/syasetsu/1329075/ (熊本日日新聞 2020年1月21日) 日米安保条約60年 平和主義前提に再構築を 日本と米国の相互協力をうたった現行の日米安全保障条約は、19日で署名から60年を迎えた。米国に日本防衛の義務を課す一方、米軍に基地を提供する条約は、日本の外交・安全保障政策の基軸と位置付けられてきた。戦後の復興と繁栄を支える土台となった安保体制の重要性は、新しい時代においても変わらないだろう。しかし「米国第一主義」を掲げるトランプ米大統領は、批判の矛先を日米安保にも向ける。さらに中国の台頭や北朝鮮の核危機など国際情勢は不安定さを増している。こうした中で日本は、憲法が掲げる平和主義を前提に米国との関係をどうつくるのか、再検討する時期に来ている。冷戦後の日米安保体制は、1996年の安保共同宣言が転機となった。湾岸戦争や朝鮮半島危機を経て、同盟の目的を「アジア太平洋地域の安定的繁栄」と再定義。翌97年に自衛隊と米軍の役割を定めた日米防衛協力指針(ガイドライン)を改定し、自衛隊と米軍の運用の一体化がいっそう進んだ。さらに、2015年に安倍晋三政権下で成立した安全保障関連法は、集団的自衛権の行使を解禁し、地理的な制約なく米軍の後方支援を可能とした。日本では、米国の戦争に巻き込まれるリスクへの懸念は根強く、過度な一体化を危ぶむ声もある。こうした対米追随の進行にもかかわらず、日米同盟は盤石とは言えない。トランプ氏は、防衛義務と基地提供という「非対称」の負担を、「不公平だ」と主張する。改定交渉が本格化する在日米軍駐留経費は、負担増が求められるに違いない。米政権が迫る巨額の米国製の防衛装備品の調達により、防衛予算は膨らみ続けている。安保条約と同時に署名され、在日米軍人らの特権を認めた日米地位協定も、抜本的な見直しが急務だ。沖縄をはじめ各地で住民の暮らしが脅かされる状況が続く限り、国民の信頼は得られない。内向き志向を強める米国は、国際社会での影響力低下は避けられないだろう。日本は日米安保体制を基軸としながら、中国との互恵関係や、対北朝鮮での韓国との連携など多角的な外交を展開し、これからの時代に合った安全保障の枠組みを築いていく必要がある。 *2-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14303890.html (朝日新聞社説 2019年12月23日) 膨らむ防衛費 ゆがみを生む対米配慮 トランプ米大統領の求めに呼応するかのように、米国製の高額な最新鋭兵器を買いまくることが、防衛予算のあり方をゆがめはしないか。厳しい財政事情の下、その費用対効果が厳しく吟味されなければならない。 安倍政権が決めた2020年度の当初予算案で、防衛費が今年度当初に比べ、1・1%増の5兆3133億円となり、6年連続で過去最大を更新した。文教・科学振興費(5兆5055億円)に匹敵し、公共事業費(6兆8571億円)に近づく規模である。社会保障費の自然増などで財政の硬直化が進むなか、防衛予算を聖域化することなく、国民生活全体に目配りした配分が必要だ。専守防衛からの逸脱だとして、朝日新聞の社説が一貫して反対してきた護衛艦の空母への改修に31億円が計上された。そこで運用される米国製の最新鋭ステルス戦闘機F35Bは、まず6機を793億円で購入する。陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」には、配備先がまだ決まっていないというのに、米国からの発射装置の取得などに129億円を投じる。最終的には東西2基で5千億円を超える巨額の事業である。国会の予算審議では、導入の是非から議論するよう、改めて強く求める。安倍首相は1月の施政方針演説で、安全保障環境の激変に対応した防衛力の構築に向け、「従来とは抜本的に異なる速度で変革を推し進める」と語った。その帰結が米国製兵器の大量購入だとすれば、トランプ氏への政治的配慮が優先され、妥当性の分析がおろそかになっていると言わざるを得ない。安倍政権下ではすでに、米政府から直接兵器を買う有償軍事援助(FMS)が急増している。11年度の432億円が、19年度は7013億円に。20年度も4713億円と高い水準だ。高額な兵器は複数年の分割払いとなるため、「後年度負担」が将来の予算を圧迫する。20年度の契約に基づき、21年度以降に支払われる額は2兆5633億円にのぼり、訓練など本来必要な予算にしわ寄せが及ぶことが懸念される。昨年末に改定された「防衛計画の大綱」「中期防衛力整備計画」は、陸海空にとどまらず、宇宙やサイバー空間といった新たな領域への対応を掲げた。ただ、今回の予算案全体を見渡しても、さまざまな課題への優先順位は明確でない。徹底した取捨選択を進め、効率的な防衛力のあり方を主体的に考え抜かねばならない。近隣外交による緊張緩和を地道に進めながら、日本の安全保障を確かなものとすべきだ。 *2-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/570817/ (西日本新聞社説 2019/12/24) 膨張する防衛費 「専守」から逸脱しないか その規模の膨張だけでなく、中身の変質にも重大な懸念を抱かされる。2020年度政府予算案の防衛関係費のことだ。過去最高の5兆3133億円が計上された。第2次安倍晋三政権発足後、8年連続の増額となる。政府は、北朝鮮の核・ミサイル開発や中国の軍拡など安全保障環境の厳しさを強調し、防衛費を拡大させる一方だ。総額を押し上げた要因に、米政府から直接、兵器を購入する対外有償軍事援助(FMS)がある。20年度も4713億円と安倍政権下で実に4倍に増えた。トランプ米大統領からの強い要請に応じたのではないか。地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」関連費も計上したが、まだ配備先も確定していない状況である。その必要性について十分に吟味したのか甚だ疑問だ。ここでも米国への政治的配慮が目立つ。さらに政策の変質もうかがえる。戦後日本が安全保障の基本原則としてきた「専守防衛」から、自衛隊が逸脱してしまうのではないかと疑念を生じさせる内容が含まれている。専守防衛とは、他国から攻撃されて初めて、自衛のため最小限度の防衛力を行使する-憲法9条に基づく考え方である。自衛隊は「盾」の役割に徹するため、攻撃型空母や戦略爆撃機は保有できないというのが、長年の政府見解だった。そこから変質した象徴が「いずも」型護衛艦の「空母化」改修費だ。米国から初めて取得する最新鋭ステルス戦闘機F35Bの搭載を想定し、離着陸できる甲板に改修する。遠洋でも運用可能にする計画である。今年の防衛白書では、戦闘機搭載は「必要な場合」に限り「多機能な護衛艦に変わりない」と記した。だが実態は専守防衛とは相いれない「敵基地攻撃能力」に該当するのではないか。政府は、戦闘機に搭載し、敵の射程圏外から反撃できる長距離巡航ミサイル「JSM」も導入する方針だ。護衛艦の空母化とともに、従来の政府見解との整合性を国内外に分かりやすく説明すべきだろう。自衛隊と米軍の一体化が進む中、自衛隊の運用面で専守防衛が有名無実化する恐れは否定できない。安倍政権は集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法制定をはじめ、専守防衛を空洞化させる動きを進めてきた。国民の理解を得ないまま既成事実を積み重ね、安保政策の基本をゆがめることは許されない。予算案には宇宙やサイバー、電磁波など新領域に備える組織の関連費用も盛られた。専守防衛を課された自衛隊がどこまで対応するのか。年明けの国会審議で徹底した議論を求めたい。 *2-4-1:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1047123.html (琉球新報社説 2019年12月24日) 辺野古埋め立て 血税の浪費直ちにやめよ 米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、埋め立てに10年程度を要すると政府が見積もっていることが分かった。軟弱地盤が存在するためだ。順調に進んだとしても、普天間飛行場の返還は2030年代になる。辺野古移設が普天間の早期の危険性除去につながらないことは明らかだ。沖縄の民意に反するばかりか、貴重な自然を破壊し、血税の浪費につながる新基地建設は即刻中止すべきだ。県は昨年の時点で、地盤改良に5年、埋め立てに5年、施設整備に3年を要し、合わせて13年以上かかると指摘していた。大幅に長期化するという見通しの正しさが裏付けられた格好だ。県の試算によると、総工費は最大2兆6500億円まで膨らむ。投入される国費が莫大(ばくだい)な金額になるのは間違いない。だが政府は、埋め立て工事に要する総事業費を「少なくとも3500億円以上」としか説明していない。いつ完成するのか、費用はいくらかかるのか、といった肝心の部分を置き去りにしたまま、見切り発車で工事を始めたからだ。政府のやり方は泥縄式であり、ずさんの極みと言うほかない。日米両政府が13年に合意した現行の基地返還計画は、埋め立てに5年、施設整備に3年を見込み、普天間飛行場の返還は「22年度またはその後」とされた。工事は当初計画よりも大幅に遅れ、埋め立て工事の進捗(しんちょく)率は県の推計で全体の1%にとどまっている。埋め立てに「10年程度」かかるというが、実際はさらに長引く可能性もある。大浦湾側に軟弱地盤が存在することは昨年3月、市民が情報開示請求で入手した沖縄防衛局の地質調査報告書によって公になった。防衛省は把握していたが、認めたのは今年1月だ。都合の悪い情報を隠してきたのである。地盤の改良が必要な海域は73ヘクタールにも及ぶ。深いところでは海面から約90メートルに達している。砂を締め固めたくいを約7万7千本打ち込む工法が示されている。国内で前例のない難工事である。そもそも実現性さえ疑わしい。防衛省は地盤改良工事に入るための計画変更を年明け以降に県に申請するという。県は承認しない構えだ。新基地建設反対は玉城デニー知事の公約なのだから当然である。今後、新たな法廷闘争につながる可能性もある。埋め立ての賛否が問われた2月の県民投票で投票者の7割超が反対した。民意の重みをないがしろにし、問答無用で新基地建設を強行するさまは、およそ民主主義国家の振る舞いとは思えない。政府は新基地の建設を断念し、県内移設を伴わない普天間飛行場の速やかな全面返還を米国に提起すべきだ。この先10年以上も普天間飛行場の脅威が続く事態は断じて容認できない。 *2-4-2:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1049092.html (琉球新報社説 2019年12月27日) 辺野古9300億円 埋め立てを即時中止せよ 防衛省は25日、名護市辺野古の新基地建設の総工費を9300億円、完成までの期間を約12年とする試算を示した。大浦湾側に広がる軟弱地盤への対応で、総工費は2014年に明示した3500億円の約2・7倍になり、22年度以降とした普天間飛行場の返還時期は30年代以降にずれ込むことが確実になった。県が指摘してきた通り、国の新基地建設計画は大幅な見直しを余儀なくされた。県内の公共事業としては空前の規模だが、国民の反発を避けるため数字を過小に見積もったと見た方が妥当だ。国内に前例のない難工事であり、工費も期間もさらに膨れ上がる可能性が大きい。沖縄防衛局によると、移設事業に投じた予算は既に約1471億円に上っている。現時点で投入された土砂は埋め立て区域全体の1%程度にすぎないにもかかわらず、当初示した3500億円の3分の1以上を使っている。さらにこれから大規模な地盤改良工事が始まるというのに、9300億円でとどまるとは到底考えにくい。どのような工法でどれほどの費用を見込むのか、積算の根拠をまず説明すべきだ。そもそも政府は、大浦湾側に軟弱地盤が広がることを把握しながら、その存在を国民にひた隠しにしてきた。16年3月にまとめられた沖縄防衛局のボーリング調査報告書には、地盤の強さを示すN値がゼロという「マヨネーズ」並みの軟弱さを示す結果が示されていた。18年3月に市民の情報開示請求で報告書が明らかになった後も、政府は軟弱地盤の存在を明確にしなかった。同年9月の県知事選で、政権が支援する候補者に不利になると考えたからではないか。新基地建設に反対する玉城デニー知事が当選すると、政府は知事選までの間は止めていた海上工事を再開。昨年12月に、埋め立て予定海域への土砂の投入を強行した。費用や期間が大幅に膨れ上がると知りながら、土砂投入に突き進んだ。埋め立ては止められないという既成事実をつくるためとみられる。沖縄の民意の無視はもちろん、税金で基地建設費を負担する国民を欺く行為だ。国の借金は国内総生産(GDP)と比べた比率で、主要国最悪の水準だ。富を生み出さない米軍基地の建設に、天文学的な額の税金を費やすなどばかげている。玉城知事は総工費が最大2兆6500億円、完成までの年数は13年以上という独自の試算を示し、普天間の危険性除去について新たな道を探る対話を政府に訴えた。軟弱地盤をはじめ基地建設に適さない条件を抱える辺野古は、もはや唯一の解決策ではない。 現計画に固執すれば、国の財政規律をゆがめ、普天間の危険性除去が一層遠のく。政府は埋め立て工事を即刻中止し、県との協議に臨むべきだ。 *2-4-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/569722/ (西日本新聞 2019/12/20) 馬毛島買収、評価額の3倍超に疑問も 米艦載機の訓練移転用地 米軍艦載機の訓練移転候補地として、政府が進める鹿児島県・馬毛島(西之表市)の買収に疑問の声が上がっている。地権者と再合意した買収金額約160億円は、政府が2016年度に算定した評価額の3倍超に。国の公害等調整委員会が「森林法への抵触」を認定した、地権者による独自工事の費用を上乗せしたためとみられる。なりふり構わぬ買収劇の背景には、安全保障に「応分の負担」を迫る米トランプ政権の圧力がある。政府は11月29日、馬毛島(約8平方キロ)の99%を所有する開発会社「タストン・エアポート」(東京)と売買の再合意にこぎ着けたが、それまでには紆余(うよ)曲折があった。関係者によると、タストン社には土地売却後も島に拠点を残し、資材の供給などで訓練場建設に参画したい意向があり、交渉過程で「4万坪(0・13平方キロ)は訓練場の完成まで売らない」と主張。防衛省は島全体の国有化を目指しており、一時期は決裂寸前になった。だが、菅義偉官房長官、和泉洋人首相補佐官を中心とする首相官邸が「全面譲歩」を防衛省に指示。政府はこの4万坪を買収する際、タストン社の要求に応じ、さらに5億円程度を追加して支払うことも検討しているという。「国の用地買収としては異例の譲歩」(官邸幹部)を重ねたプロセスだった。 ■ 政府が前のめりに突き進んだのは、米政権の意向が大きい。馬毛島で計画されているのは、陸地を空母に見立てて離着陸を繰り返すFCLPと呼ばれる訓練で、「空母の能力を維持する上で最も重要」(防衛省幹部)。現在は硫黄島(東京)で行われているが、艦載機部隊の置かれる米軍岩国基地(山口県)から約1400キロと遠く、米国は航続距離の短い機種には危険が伴うと懸念していた。平たんな無人島の馬毛島は岩国から約400キロの位置にあり、日米両政府は11年6月に訓練移転候補地として合意したが、年月が経過していた。政府関係者によると、トランプ大統領は安倍晋三首相に対し、「マゲシマ」の名前を挙げてFCLPの早期移転を重ねて要求。トランプ氏が在日米軍駐留経費(思いやり予算)の大幅な増額を求める構えを崩していないこともあり、日本政府はこれをなだめる「ディール(取引)」の材料として馬毛島を位置付け、買収交渉を加速させた。タストン社は、当初の日米合意を見越して独自に島に滑走路を造成し、その建設費用も含め400億円台での売却を主張していた。一方、防衛省は16年度に行った不動産鑑定で島の評価額を45億円と積算。両者の隔たりは大きかったが、官邸はタストン社に歩み寄る形で買収金額を約160億円まで引き上げた。タストン社も、親会社の経営悪化などから資金繰りに窮して態度を軟化させ、今年1月の仮契約を経て再合意となった。「今回の買収合意は、最近の日米関係で最大のヒットだ」。菅氏は周囲にこう誇る。政府は、中国軍が海洋進出を活発化させていることをにらみ、馬毛島を南西諸島の防衛拠点として整備し、日米による“不沈空母化”も検討している。 ■ ただ、タストン社が実施した滑走路造成については国の公害等調整委員会が16年、「森林法の許可申請、届け出の範囲を超える開発、伐採が推認される」と認定している。滑走路も織り込んだ買収は、政府が違法造成を容認したと受け取られかねない。この点をただした共産党の田村貴昭衆院議員の質問主意書に対し、政府は今月17日、「森林法違反で何らかの処分が行われたとは承知していない」とする答弁書を閣議決定。約160億円の積算根拠も「購入手続きに支障を及ぼす」と説明を拒んだ。日米安保緊密化の名の下に急展開した馬毛島買収に対し、「強引すぎる」との声は与党幹部からも漏れている。 *2-4-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201905/CK2019050402000125.html (東京新聞 2019年5月4日) グアム移転 24年10月にも 沖縄海兵隊 米軍が現地に伝達 日米両政府が合意している在沖縄海兵隊の米領グアムへの移転計画で、米軍が二〇二五米会計年度の前半(二四年十月~二五年三月)に移転を始め、約一年半かけて完了させる方針を地元議会に伝えていたことが分かった。建設中の新たな海兵隊基地の名称は「キャンプ・ブラズ」となる予定。米軍筋が共同通信の取材に明らかにした。米軍筋によると、移転する海兵隊員は約五千人と見込まれ、このうち約千七百人がグアムに常駐し、残りは半年ごとに入れ替わる部隊となる。沖縄から移転する隊員数はこれまで約四千人と公表されていた。米軍は今年二月四日、移転計画の最新案をグアム議会のティナ・ムニャバーンズ議長に説明した。米軍筋は、トランプ政権の方針や来年の米大統領選の結果などによって、移転計画の遅延や変更もあり得るとしている。海兵隊の新基地はグアム北部のアンダーセン空軍基地近くに建設中で、二六年までに完成予定。名称は海兵隊准将やグアム選出の米下院準議員を歴任した地元出身の故ベン・ブラズ氏に由来する。アンダーセン空軍基地近くのフィネガヤン地区では、日本政府からの資金提供も活用し、下士官用宿舎などの整備も進んでいる。隊員の家族を帯同することから、島内では人口増加に対応しようと道路や医療施設なども建設されているが、労働者不足のため整備の遅れが指摘されている。一二年に日米両政府が修正合意した米軍再編計画には、在沖縄海兵隊約一万九千人のうち約九千人をグアムやハワイなどへ移転させることや、米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古(へのこ)への移設が盛り込まれた。沖縄では昨年十二月、辺野古沿岸部への土砂投入が始まり、今年二月二十四日実施の県民投票では、埋め立て反対が多数となっていた。日米はグアム移転を、普天間飛行場移設の進展とは切り離し二〇年代前半に始めることを確認している。 <在沖縄海兵隊のグアム移転> 日米両政府は2012年4月、在沖縄米海兵隊約9000人を国外へ移転し、米領グアムなどに分散するとの内容を盛り込んだ在日米軍再編見直しの共同文書を発表した。グアム移転は米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の進展状況とは切り離して進めることでも合意しているが、菅義偉官房長官は昨年10月の記者会見で「結果的にリンクしている」と発言し、移設が実現しなければグアム移転も進まないとの認識を示した。 *2-5:https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13400.php (NewsweekJapan 2019年11月16日) トランプが日本に突き付けた「思いやり予算」4倍の請求書、21年3月末の日米特別協定更新の期限を前に、日本が負担している約20億ドルを約80億ドルに増やすことを日本政府に求めた トランプ米大統領が日本政府に対し、在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)を大幅に増やすよう要求していることが分かった。事情を知る米政府関係者および元米政府関係者がフォーリン・ポリシー誌に語った話によれば、トランプ政権は日本政府に米軍駐留経費負担を現在の4倍以上に増額することを求めているという。7月に日本を訪問したジョン・ボルトン国家安全保障担当大統領補佐官とマット・ポティンジャーNSCアジア上級部長(いずれも当時)が要求を伝えたとのことだ。米政府が米軍駐留経費の負担増を要求しているアジアの同盟国は、日本だけではない。ボルトンとポティンジャーは韓国にも、経費負担を現在の約5倍に増やすよう求めたと、同じ消息筋は語っている。日本には約5万4000人、韓国には約2万8500人の米兵が駐留している。「このように法外な要求を一方的に突き付けるやり方は、反米感情に火を付けかねない」と、元CIA分析官でもあるヘリテージ財団のブルース・クリングナー北東アジア担当上級研究員は懸念する。「同盟が揺らぎ、米軍のプレゼンスが縮小して抑止力が弱まるようなことがあれば、恩恵に浴するのは北朝鮮や中国、ロシアだ」 ●基地整備や兵器購入も トランプ政権の日韓両国政府への要求は、世界規模で同盟国に国防支出を増やさせようとする動きの一環と位置付けられる。トランプは以前から、ヨーロッパの同盟国の国防予算が少な過ぎると批判していた。そうした圧力は効果を発揮したらしい。NATO諸国は来年末までに、国防予算を2016年の水準に比べて1000億ドル以上積み増すことにした。トランプがNATOの次に目を向けたのがアジアの同盟国だったようだ。アジアでは、中国が軍事力を増強している上に、北朝鮮の軍事的脅威も再び高まっている。日本は、アメリカとの特別協定の下、米軍駐留経費として約20億ドルを拠出している。現在の特別協定は、21年3月末に更新期限を迎える。3人の元米国防総省当局者によれば、米政府は協定更新に向けた交渉が本格化するのを前に、この予算を約80億ドルに増やすことを日本政府に求めた。韓国も年内に同様の協定の更新期限を迎える。ある元米国防総省当局者によれば、米政府は韓国政府に対し、駐留経費負担を約50億ドルに引き上げるよう要求している。しかし、日本と韓国は既に米軍の活動のために莫大な費用を負担している。米議会調査局によると、日本は、第二次大戦後の米軍外国基地建設プロジェクトの中でもとりわけ大規模な3つに関して費用のかなりの部分を負担する。具体的には、沖縄県の普天間飛行場代替施設建設に121億ドル(費用の全額)、山口県岩国の海兵隊航空基地建設に45億ドル(費用の94%)、そして、海兵隊員4800人が沖縄から移転することになるグアムの施設に31億ドル(費用の36%)である。日本の経済的負担は、米軍駐留経費だけではない。日本は防衛装備品の90%以上をアメリカ企業から購入している。ロッキード・マーティン社の最新鋭ステルス戦闘機F35やボーイング社のKC46空中給油機などだ。膨張し続けるトランプの要求に対して、日本政府は頭を悩ませることになりそうだ。 <中東への自衛隊派遣> *3-1:https://www.sankei.com/politics/news/191027/plt1910270009-n1.html (産経新聞 2019.10.27) 自衛隊中東派遣、ホルムズ海峡排除せず どうなる武器使用 政府は、緊張が高まっている中東海域での情報収集態勢を強化するため、早ければ年明けに自衛隊を独自派遣する方針だ。ただ、派遣の方法や法的整合性の検討、部隊への教育訓練の実施期間を踏まえると来春にずれ込む可能性がある。国家安全保障局を中心に外務省、防衛省などで活動場所や時期の調整を進めている。政府内には「与野党から反対や慎重な意見が相次いでいる。3カ月後(年明け)というのは難しいのではないか」(防衛省幹部)との声もある。自衛隊派遣の検討を具体化したのは、サウジアラビアの石油施設への攻撃、イラン国営会社所有のタンカーの爆発など情勢が緊迫化する中、石油輸入を中東に依存する日本が主体的に情報収集に関わらざるを得なくなったからだ。得た情報は米国主導の有志連合構想に加わる国などに提供する方向で調整している。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は18日の記者会見で、派遣先として「オマーン湾」「アラビア海北部」「バべルマンデブ海峡東側」を中心に検討すると発表。事態が最も緊迫し、情報収集の必要性が高いホルムズ海峡には言及しなかった。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「中東地域のどこかを特筆して排除していない」と述べ、ホルムズ海峡で活動する可能性も排除せずに検討する考えを示した。 ◇ 政府は自衛隊の中東派遣の具体的な方法について、海上自衛隊の護衛艦1隻を新たに派遣する案を軸に検討している。すでに中東近隣で海賊対処の任務についている海自のP3C哨戒機2機のうち1機の任務を今回の情報収集に変更することも選択肢に入る。防衛省の統合幕僚監部の検討チームでは、さまざまな事態を想定しながら必要な装備などについてケーススタディーを進めている。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「新規の船(護衛艦)の派遣と、ジブチを拠点とするP3C哨戒機や護衛艦の活用も検討対象にしている」と説明した。すでにソマリア沖アデン湾での海賊対処のため、護衛艦1隻とP3C哨戒機2機がアフリカ東部のジブチを拠点に他国と連携して活動している。ジブチは情報収集を目的とする今回の派遣候補地に近い。このため、日本から護衛艦1隻を追加派遣して計2隻態勢とすれば、「1隻は既存の海賊対処を継続し、もう1隻は新たな情報収集」という2つの任務の両立が可能となる。海上自衛隊が保有する護衛艦は48隻で、能力や装備が今回の任務に適しているのは20隻余り。中国の海洋進出が強まる中、「東シナ海などに展開する護衛艦を減らして警戒監視を弱めるわけにいかない。現場のやりくりに余裕はない」(自衛隊幹部)と不安視する向きもある。ただ、海賊対処部隊は平成28年、海賊事案の減少に伴い2隻態勢だったのを1隻に減らした。防衛省関係者は「『もともと2隻だろう』といわれれば、その通りだ」と語る。一方、派遣済みのP3C哨戒機2機のうち1機を海賊対処から情報収集に転用する場合、活動場所はバべルマンデブ海峡東側の公海の上空になる公算が大きい。オマーン湾はジブチから2千キロ余り離れており、所要時間や航続距離を考えると往復するだけでほぼ終わってしまうからだ。今回の派遣は、防衛省設置法で定められる省の担当業務「調査・研究」を法的根拠としている。常日頃の日本周辺海域での警戒・監視の根拠規定にもなっている。つまり、中東派遣は通常の任務の延長線上に位置づけられる。正当防衛以外での武器使用はできず、日本関係船舶を武器を使用して護衛することは法的に難しい。 *3-2:https://2019constitution.fc2.net/blog-entry-1.html (憲法研究者 2019/11/1) ホルムズ海峡周辺へ自衛隊を派遣することについての憲法研究者声明 1、2019年10月18日の国家安全保障会議で、首相は、ホルムズ海峡周辺のオマーン湾などに自衛隊を派遣することを検討するよう指示したと報じられている。わたしたち憲法研究者は、以下の理由から、この自衛隊派遣は認めることができないと考える。 2、2019年春以来、周辺海域では、民間船舶に対する襲撃や、イラン・アメリカ両国軍の衝突が生じている。それは、イランの核兵器開発を制限するために、イラン・アメリカ等との間で結ばれた核合意から、アメリカ政府が一方的に離脱し、イランに対する経済制裁を強化したことと無関係ではないだろう。中東の非核化と緊張緩和のために、イラン・アメリカ両国は相互に軍事力の使用を控え、またただちに核合意に立ち戻るべきである。 3、日本政府は、西アジアにおける中立外交の実績によって、周辺地域・周辺国・周辺民衆から強い信頼を得てきた。今回の問題でもその立場を堅持し、イラン・アメリカの仲介役に徹することは十分可能なことである。またそのような立場の外交こそ、日本国憲法の定めた国際協調主義に沿ったものである。 4、今回の自衛隊派遣は、自衛隊の海外派遣を日常化させたい日本政府が、アメリカからの有志連合への参加呼びかけを「渡りに船」で選択したものである。 自衛隊を派遣すれば、有志連合の一員という形式をとらなくとも、実質的には、近隣に展開するアメリカ軍など他国軍と事実上の共同した活動は避けられない。しかも菅官房長官は記者会見で「米国とは緊密に連携していく」と述べているのである。ほとんどの国が、この有志連合への参加を見送っており、現在までのところ、イギリスやサウジアラビアなどの5カ国程度にとどまっている。このことはアメリカの呼びかけた有志連合の組織と活動に対する国際的合意はまったく得られていないことを如実に示している。そこに自衛隊が参加する合理性も必要性もない。 5、日本政府は、今回の自衛隊派遣について、防衛省設置法に基づく「調査・研究」であると説明する。 しかし防衛省設置法4条が規定する防衛省所掌事務のうち、第18号「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」とは、どのような状況において、自衛隊が調査・研究を行うのか、一切の定めがない。それどころか調査・研究活動の期間、地理的制約、方法、装備のいずれも白紙である。さらに国会の関与も一切定められていない。このように法的にまったく野放し状態のままで自衛隊の海外派遣をすることは、平和主義にとってもまた民主主義にとってもきわめて危険なことである。 6、わたしたちは安保法制のもとで、日本が紛争に巻き込まれたり、日本が武力を行使するおそれを指摘してきた。今回の自衛隊派遣は、それを現実化させかねない。 第一に、周辺海域に展開するアメリカ軍に対する攻撃があった場合には、集団的自衛権の行使について要件を満たすものとして、日本の集団的自衛権の行使につながるであろう。第二に、「現に戦闘行為が行われている現場」以外であれば、自衛隊はアメリカ軍の武器等防護をおこなうことができる。このことは、自衛隊がアメリカの戦争と一体化することにつながるであろう。第三に、日本政府は、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合について、存立危機事態として集団的自衛権の行使ができるという理解をとっている。しかし機雷掃海自体、極めて危険な行為である。また戦闘中の機雷掃海は、国際法では戦闘行為とみなされるため、この点でも攻撃を誘発するおそれがある。このように、この自衛隊派遣によって、自衛隊が紛争にまきこまれたり、武力を行使する危険をまねく点で、憲法9条の平和主義に反する。またそのことは、自衛隊員の生命・身体を徒に危険にさらすことも意味する。したがって日本政府は、自衛隊を派遣するべきではない。 *3-3:https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2019/191227.html (2019年(令和元年)12月27日 日本弁護士連合会会長 菊地裕太郎 ) 中東海域への自衛隊派遣に反対する会長声明 2019年12月27日、日本政府は日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動を目的として、護衛艦1隻及び海賊対策のためにソマリア沖に派遣中の固定翼哨戒機P-3C1機を、中東アデン湾等へ派遣することを閣議決定した。2018年5月に米国がイラン核合意を離脱後、ホルムズ海峡を通過するタンカーへの攻撃等が発生していることから、米国はホルムズ海峡の航行安全のため、日本を含む同盟国に対して有志連合方式による艦隊派遣を求めてきた。これに対し日本は、イランとの伝統的な友好関係に配慮し、米国の有志連合には参加せずに上記派遣を決定するに至った。今般の自衛隊の中東海域への派遣は、防衛省設置法第4条第1項第18号の「調査及び研究」を根拠としている。しかし、同条は防衛省のつかさどる事務として定めている。そもそも、自衛隊の任務、行動及び権限等は「自衛隊法の定めるところによる」とされている(防衛省設置法第5条)。自衛隊の調査研究に関しても、自衛隊法は個別規定により対象となる分野を限定的に定めている(第25条、第26条、第27条及び第27条の2など)。ところが、今般の自衛隊の中東海域への派遣は、自衛隊法に基づかずに実施されるものであり、防衛省設置法第5条に違反する疑いがある。日本国憲法は、平和的生存権保障(前文)、戦争放棄(第9条第1項)、戦力不保持・交戦権否認(第9条第2項)という徹底した恒久平和主義の下、自衛隊に認められる任務・権限を自衛隊法で定められているものに限定し、自衛隊法に定められていない任務・権限は認めないとすることで、自衛隊の活動を規制している。自衛隊法ではなく、防衛省設置法第4条第1項第18号の「調査及び研究」を自衛隊の活動の法的根拠とすることが許されるならば、自衛隊の活動に対する歯止めがなくなり、憲法で国家機関を縛るという立憲主義の趣旨に反する危険性がある。しかも、今般の自衛隊の中東海域への派遣に関しては、「諸外国等と必要な意思疎通や連携を行う」としていることから米国等有志連合諸国の軍隊との間で情報共有が行われる可能性は否定できず、武力行使を許容されている有志連合諸国の軍隊に対して自衛隊が情報提供を行った場合には、日本国憲法第9条が禁じている「武力の行使」と一体化するおそれがある。また、今般の閣議決定では、日本関係船舶の安全確保に必要な情報の収集について、中東海域で不測の事態の発生など状況が変化する場合における日本関係船舶防護のための海上警備行動(自衛隊法第82条及び第93条)に関し、その要否に係る判断や発令時の円滑な実施に必要であるとしているが、海上警備行動や武器等防護(自衛隊法第95条及び第95条の2)での武器使用が国又は国に準ずる組織に対して行われた場合には、日本国憲法第9条の「武力の行使」の禁止に抵触し、更に戦闘行為に発展するおそれもある。このようなおそれのある活動を自衛隊法に基づかずに自衛隊員に行わせることには、重大な問題があると言わざるを得ない。政府は、今回の措置について、活動期間を1年間とし、延長時には再び閣議決定を行い、閣議決定と活動終了時には国会報告を行うこととしている。しかし、今般の自衛隊の中東海域への派遣には憲法上重大な問題が含まれており、国会への事後報告等によりその問題が解消されるわけではない。中東海域における日本関係船舶の安全確保が日本政府として対処すべき課題であると認識するのであれば、政府は国会においてその対処の必要性や法的根拠について説明責任を果たし、十分に審議を行った上で、憲法上許容される対処措置が決められるべきである。よって、当連合会は、今般の自衛隊の中東海域への派遣について、防衛省設置法第5条や、恒久平和主義、立憲主義の趣旨に反するおそれがあるにもかかわらず、国会における審議すら十分になされずに閣議決定のみで自衛隊の海外派遣が決められたことに対して反対する。 *3-4:https://www.topics.or.jp/articles/-/305910 (徳島新聞社説 2020年1月6日) 国際展望 トランプ追従は高リスク トランプ米大統領の決断が、幕が開いた2020年の世界を震わせている。イランのソレイマニ司令官爆殺は「宣戦布告」に等しい。イランは引くに引けず、報復に出る可能性が高まっている。トランプ氏は作戦実行後、「強い米国」をアピールするように、写真投稿アプリに星条旗の画像だけを掲げた。大統領選挙に勝つためなら何でもやりかねない。そんなトランプリスクが、今年の世界を覆っている。少なくとも、北朝鮮の非核化は、実現が遠のいたと言えるだろう。11月の米大統領選は、一層の関心事となった。焦点はトランプ政治の継続か否か。民主党の候補が誰になろうが変わらない。敗れるなら、米国の政策は一変する。温暖化抑制、移民対策、銃規制など、多くの分野で逆方向に動き出すだろう。鍵を握るのは、対抗馬が持つ「勢い」だ。トランプ氏は白人の農家や労働者に底堅い支持基盤を持つが、広がりはない。支持者が喜ぶ政策を実行し、相手をおとしめて勢いをそぐ。戦術はそれしかない。共和、民主両党が拮抗する「スイングステート(揺れる州)」が勝負を決める。前回の勝利に直結した中西部「ラストベルト」の諸州は、今回も注目の的だ。楽勝が見通せない中で、トランプ氏は米国第一主義を強める。激戦州の有権者に受ける成果を求め、国際関係に及ぼす長期的な悪影響など省みない。その典型が、米軍撤収で混迷を深めたシリア情勢だ。昨年10月、「イスラム国」(IS)掃討で共に戦ったクルド人勢力を見捨て、トルコ軍のシリア侵攻を誘発した。同盟への「裏切り」がアジアで再現されない保証はない。民主党の候補者を絞り込む予備選は2月上旬のアイオワ州で始まり、13州が集中する3月3日で流れが固まる。現在の主要論点は、医療保険制度や移民問題など日常に関わるテーマだ。外交は隅に置かれている。だからこそ、現役候補にとって独占的なアピール手段となりやすい。一方、民主党が政権を奪還しても、中国への強硬姿勢には大きな変化がない、との見方が有力だ。安全保障を理由とした「技術冷戦」は、既に超党派の動きとなり、目先の妥協を許さない状況だ。昨年始まった米中貿易戦争は、人工知能(AI)や宇宙空間を巡る長期的な覇権争いの幕開けにすぎない。習近平国家主席は昨年末、共産党政治局から「人民の領袖」とたたえられ、かつての毛沢東に匹敵する権威を確立しつつある。絶対的な権力の下で、ウイグル自治区で起きているような人民管理体制は強固になっていく。米国との対立と反比例するように、日本への接近姿勢は強まっている。春には習主席の国賓来日が予定される。わが国の立ち位置が問われる局面が増えるだろう。トランプ追従一辺倒では通用しない。 <「軍事力による現状変更を認めない」の意味は何?> PS(2020.1.24追加): 尖閣諸島を領有していると主張する中国は、*4-3のように、国防白書に「①南シナ海の諸島や沖縄県の尖閣諸島(中国名・釣魚島)は、中国固有の領土と強調し」「②武器使用も放棄せず、一切譲歩しない」等としている。これに対し、安倍首相はじめ日本の関係者は、*4-1のように、「③中国が軍事力などを使って現状を変更する試みは、受け入れられない」と繰り返し述べるに留まり、日本の外務省は、*4-2のように、「④尖閣諸島が日本固有の領土であることは、歴史的・国際法上明らか」「⑤日本が実効支配している」「⑥従って尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題は存在しない」「⑦日本は領土を保全するために毅然かつ冷静に対応する」とする。 しかし、③の言い方では、「軍事力を使わない(中国の国内法による)変更ならよい」と思われても仕方なく、④の尖閣諸島が日本固有の領土であることも主張していない。また、本当に固有の領土であれば、現状変更をせずに永遠に放置する必要はない。さらに、⑤は事実だが、①②を前提として中国船が領海内に頻繁に侵入しても、⑥のように「領有権の問題は存在しない」として、⑦の領土・領海の保全もしておらず、自衛権の行使もしていないのが現状なのである。それでも、米軍基地や自衛軍は必要か? *4-1:https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK27001_X20C14A1000000/ (日経新聞 2014/1/27) 首相「軍事力による現状変更認めず」 中国けん制、米CNNインタビューで 米CNNテレビは26日、安倍晋三首相とのインタビューを報じた。CNNによると、安倍氏は「中国が軍事力などを使って現状を変更する試みは、いかなるものも受け入れられないと理解することが重要だ」と述べ、中国をけん制した。沖縄県・尖閣諸島をめぐる問題を念頭に置いた発言。CNNの英語通訳によると、安倍氏は中国が過去20年間、軍事費を毎年約10%も増加させてきたと指摘し「アジア各国と同様に日本の懸念材料だ」と批判。軍備拡張は中国の経済成長や繁栄に貢献しないとし、中国側がこれを確実に理解するよう取り組んでいきたいと述べた。また、中国と軍事的に対抗する意図はないと強調。一方で、首相として日本の領海や領土を守る責任を果たしていくと訴えた。安倍氏は政権の経済政策、アベノミクスの「三本の矢」にも言及。成長戦略のための構造改革について「抵抗する人たちにも、私が行ってきたことを正しいと納得させ、取り組むようにさせることが重要だ」と語った。インタビューは、安倍氏が世界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)出席のため、スイスを訪れた際に行われた。 *4-2:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html (外務省 平成28年10月18日) 日本の領土をめぐる情勢、尖閣諸島について 尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり, 現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決し なければならない領有権の問題はそもそも存在しません。日本は領土を保全するために毅然としてかつ冷静に対応していきます。日本は国際法の遵守を通じた地域の平和と安定の確立を求めています。 *4-3:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47712610U9A720C1000000/ (日経新聞 2019/7/24) 尖閣諸島は「固有の領土」 中国が4年ぶり国防白書、台湾統一に「武力放棄せず」 中国政府は24日、「新時代の中国の国防」と題した国防白書を発表した。国防白書の発表は2015年5月以来、4年ぶり。南シナ海の諸島や沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)は「中国固有の領土だ」と強調した。台湾を巡っても統一のため「武器使用は放棄しない。あらゆる措置をとる」と主張し、領土・領海問題を巡り周辺国に一切譲歩しない考えを強調した。米国など関係国とのあつれきが高まるのは必至だ。白書は世界情勢について「覇権主義や強権政治が台頭し、国際的な秩序は衝撃を受けている」と指摘した。米国を名指しして「単独主義に走り大国間の競争を引き起こし、軍事費を大幅に増やしている」と批判。日本についても「戦後体制を突破し、軍事の外向性を強めている」と主張した。 <沖縄の地の利と気候、さくらを見る会> PS(2020年1月25日、2月14日追加):*5-1のように、名護市の名護城公園周辺を約1万本のヒカンザクラが彩り、「第58回名護さくら祭り」が始まり、気温が25度を超える陽気となった那覇市では、*5-2のように、かりゆしウエアを着た会社員の姿が目立ち、かりゆしウエアの制服や通年着用を認める会社も多いそうだ。私自身は模様の多すぎる「かりゆしウエア」は好きでないが、「沖縄は冬服がいらないので経済的だ(=冬服を着る機会はない)」と言う人もおり、沖縄は地の利と気候を生かして基地よりも生産性の高い産業を作ることができる筈である。 このように予算に関する重要案件が多い中、*5-3のように、「『桜を見る会』懇親会の契約主体が個々人だというのは不自然で首相の説明通りだったとしても脱法行為だ」などと予算委員会で野党の国会議員が桜の会ばかりを追及しているのは、白でもグレイか黒だと印象付けて議員の価値を貶める自殺行為だ。何故なら、私は地元が九州で旅行代金が高くなる上、秘書の手も廻らなかったのでそういう企画はしなかったが、野田聖子さん(岐阜が地元)はじめ地元からバスで東京に来れる範囲の国会議員は、旅行会社を通して後援会の中の希望者を東京にバス旅行させ、そこに国会見学を組み込んで議員が国会案内等をする人が多かったからだ。その際の旅行代金はもちろん個々の後援会員の負担だと思われるが、そうでなければ旅行に参加した後援会員と参加しなかった後援会員の間に不公平が起こる。安倍首相のケースでも、ホテルと会費支払いの契約を結んだ主体は個々の参加者であり、首相の事務所が会費を受け取ってホテルに渡したのは、煩雑な仕事を手伝ったにすぎないと思われる。さらに、そのホテルの得意先だったり、このように煩雑な事務を手伝ったり、立食パーティーに参加者全員分ではなく40~50%分の食事を出したりすることによって、1人5千円の会費支払いで済ませることは経済合理性もある。そのため、政策に関する議論をさしおいて、政治資金規正法違反等の刑事事件もどきに仕立てあげ、辞めさせたい政治家の根拠なき人格攻撃を行うのは、民主主義の議論の仕方ではないと思う。なお、私は、会計・監査・税務の専門家で、衆議院議員だった時に現在の政治資金規正法改正に加わり、これは単式簿記に基づいて作成されるため網羅性・検証可能性に乏しく、監査証明も限定されているため完全とは言えないものの、一昔前のような大きな不正・買収は起こらなくなっているので、メディアはじめ皆が頭を切り替えるべき時だと考える。   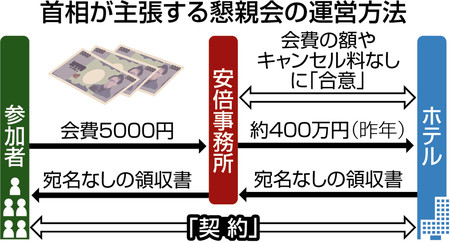 *5-1より *5-3より (図の説明:左図のように、沖縄は、地球の海水面が低かった時代には、九州から台湾まで続く陸地だったようだ。現在は、中央の図のように、既に桜が咲き始めている常夏の島である。また、右図は、「さくらを見る会」の話だが、宛名なしの領収書は(推奨はしないが)一般によく見られるものであるため、推論に人格攻撃を目的とした強引さがある) *5-1:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1063110.html (琉球新報 2020年1月25日) 名護さくら祭りが開幕 ピンク色の彩り、観光客たちが楽しむ 26日まで、オレンジレンジのライブも 沖縄本島北部に位置する名護市の名護城公園周辺を約1万本のヒカンザクラが彩る「第58回名護さくら祭り」(同実行委員会主催)が25日、同公園などで始まった。26日まで仮装パレードやオレンジレンジのライブなどでさまざまなイベントが開かれる。実行委員会によると現在の開花状況は二~三分咲き。晴天となった名護城公園ではピンクや白に色づき始めた桜が名護市民や観光客を楽しませていた。25日、名護城入口でオープニングセレモニーが開かれ、渡具知武豊名護市長が「たくさんの花と樹木がお待ちしている。各種イベントも時間が許す限り楽しんでほしい」と呼びかけた。 *5-2:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1062912.html (琉球新報 2020年1月25日) 冬だけど「かりゆし」 暑い沖縄、通年着用の人増えてます 「暑いし、かりゆし」。一年で一番寒い時期にもかかわらず、連日夏日を記録し“常夏”の雰囲気も漂う沖縄では、一年中かりゆしウエアを着る人がじわじわ増えている。県内企業では一年を通してかりゆしウエアでの出勤を認めている会社もあり、通年着用を後押ししている。気温が25度を超え汗ばむ陽気となった24日の那覇市。県庁北口交差点ではセーターを着込んだ観光客の姿を尻目に、かりゆしウエアを着た会社員の姿が目立った。ランチタイムを終えた昼すぎ、明るい緑のかりゆしウエアを着た医療事務の高江洲達さん(31)=那覇市=は「今日からかりゆし」と笑顔で語る。3年ほど前まで福岡で生活していたこともあり「沖縄はずっとかりゆしでいける。楽だし、私服っぽいのが好き」と仕事に戻っていった。国際通りにある店舗で勤務する40代男性は「制服がかりゆしなので一年中かりゆしを着ている。寒い時は上から羽織る」と語る。実際、かりゆしウエアを制服にしたり、通年での着用を認めたりする会社は多い。「元祖紅いもタルト」でおなじみの御菓子御殿は「紅芋カラー」のかりゆしウエアが制服。日本トランスオーシャン航空(JTA)は乗客と接触しない本社勤務などの「間接部門」で通年着用を許可している。同社担当者によると、夏日の24日は「かりゆしが多かった」と語った。この動きに縫製業者も機敏に反応している。メーカー関係者は「観光客の需要もあるが、1月の売り上げは伸びている。いつでも新作を投入できるように急ピッチで準備を進めている」と明かした。沖縄が冬でも暖かくなったのは地球温暖化の影響で、もろ手を挙げて喜べないが、“常夏”が進めばかりゆしウエアの需要はさらに伸びるかもしれない。 *5-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202002/CK2020021402000135.html (東京新聞 2020年2月14日) <点検「桜を見る会」>懇親会 「契約主体は個々」不自然 安倍晋三首相の後援会が「桜を見る会」前夜に東京都内のホテルで毎年開いてきた懇親会。首相は後援会の主催としながらも、ホテルと会費の支払い契約を結んだ「主体」は、あくまで個々の参加者だったと主張している。後援会の指示に従って会費を払っただけの参加者が「ホテルと契約した」との解釈は不自然だが、首相は国会答弁でこの説明を繰り返している。後援会がホテルと契約していないとの見解を変えない理由は、政治資金収支報告書に、懇親会の収支が記載されていないことを正当化するためとみられる。政治団体の収支があったにもかかわらず不記載だった場合は、政治資金規正法に違反するからだ。首相は、一人五千円の会費の支払いについて「集金した全ての現金を、その場でホテル側に手渡す形で、参加者から支払いがなされた」と話す。首相の事務所は、会費を受け取ってホテルに渡しただけなので、後援会に入金や出金はなかったという理屈だ。さらに首相は「(ホテルとの)段取りを行ったにすぎない事務所職員は、契約上の主体にはならない」とする。だが一方で、会場を予約したのは事務所の職員で、昨年の懇親会の準備経費は自身の選挙区支部から支出したと認めている。これに対し野党は、ホテルと主体的に契約したのは後援会だと指摘。首相の説明通りであったとしても脱法行為に当たると批判している。 <外交に役立つ国際貢献> PS(2020年1月27、29、30日、2月2日追加):*6-1のように、中国では、春節時・流通の要所である武漢市という最大の間の悪さで新型コロナウイルスによる肺炎が発生し、国内での死者数が80人に達したそうだ。このため、武漢市では、①病院に診療待ちの人があふれ ②医療従事者用の白い防護服などの物資が不足し ③上海市などの大都市から医師団が続々と武漢市へ派遣され ④武漢市は市内の交通を遮断する封鎖措置に踏み切るなどして感染の拡大防止策を採り ⑤中国政府は、海外への感染拡大を防止するため海外団体旅行中止を通達したそうだ。日本は、「イ.空路で来日したバスツアーの旅行客に新型肺炎の感染者を確認した」「ロ.客のキャンセルが相次いで困った」などと騒いでいるだけでなく、日本政府や日頃から中国と関係のある日本企業は、電子レンジか湯煎で温めれば食べられるような餃子・シュウマイなどの中華料理やみかん(ビタミンCが豊富)・マスク等を武漢市民に寄付したらどうか? 東日本大震災の時と同様、人は困った時に助けられるのが最も有り難いため、これが今後の外交や食品輸出に寄与することは間違いなく、日本は、*6-2のように、「i)恒久の平和を念願し」「ii)偏狭を地上から永遠に除去しようと努め」「iii)全世界の国民が恐怖と欠乏から免がれて平和に生存する権利を有することを確認し」「iv)いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないと信じ」「v)日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」とする立派な日本国憲法を持っており、国民は、「こんなのは理想に過ぎないから、現実に合わせてレベルを落としたい」とは思っていないのである。 しかし、*6-3のように、「①自民党女性局は平易な文章にイラストを織り交ぜ、『女性に読んでほしい』と憲法冊子を作成し」「②憲法は幸せのカタチを守る基本的なルールで、幸せのカタチは時代によって変わっていく」「③三原じゅん子局長は『憲法の話は苦手と思っている女性にこそ読んでほしい』と話した」「④『青年に音楽を演奏する機会を与える』と書かれたスイス憲法や「⑤同性婚を認める」アイルランド憲法などの例を紹介している」とのことだ。 このうち①③については、日本国憲法は義務教育である中学校社会科(現在は、公民)の教科書に添付されて勉強したため、男女とも「読んだことがない」と言うのは不可能で、「女性は平易な文章でなければ理解できない」「女性は憲法の話は苦手」などと決めつけるのは女性蔑視である。また、憲法(原文:The Constitution of Japan)は国の骨格と方針を定めたもので、その13条に「すべて国民は、個人として尊重される(原文:All of the people shall be respected as individuals.)」と書かれているとおり、個人は自由な生き方を尊重され、②のように「国や憲法が(個人の)幸せのカタチを決める」わけではない。 さらに、④は、第26条で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めているため、音楽のみを取りださなくても政府の意思決定次第で教育できる。また、⑤については、24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」としているが、この両性は異性でなければならないとは書かれていないため同性婚を排除しておらず、14条で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」としているため、敢えて憲法で同性婚を認めると取り上げて書く必要はないと考える。それよりも、もともと人間は多様なのに「多様性≒同性婚、障害者」というような誤った議論が多いのが問題だ。つまり、「現行憲法は時代に合っていない」などと言っている人の話をよく聞くと、その人こそ現行憲法を理解していなかったり、読んですらいなかったりするのである。 このような中、*6-4・*6-5のように、大分市はじめ東京都・他の地方自治体・日本政府などが、武漢市(湖北省)への民間チャーター機の往路等で中国政府にマスクや防護服などの緊急援助物資を運び、「雪中送炭」と中国のネット上で感謝の声が広がったそうだ。なお、メディアでは武漢市にあるユニクロがクローズしているところが報道されたが、伸縮性のある布で顔にフィットするマスクを急いで作り、店先で販売したらよいだろうと思った。 *6-6のように、台湾でもマスクが不足して「1人3枚まで」にしているそうだが、台湾と関係の深い自治体や民間企業は寄付したらいかがか? *6-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54875690X20C20A1AM1000/ (日経新聞 2020/1/27) 新型肺炎、拡大加速 「患者1000人増加も」武漢市長、春節連休を3日間延長 中国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の猛威が止まらない。武漢市の周先旺市長は26日夜、記者会見し、今後患者数は「1000人近く増加する可能性がある」と話した。中国国内の死者数が27日時点で80人に達するなど感染拡大を受け、中国政府は同日、春節(旧正月)の連休を2月2日まで延長すると発表した。武漢市を中心に医療機関の受け入れ体制や物資の不足なども深刻化している。「新型肺炎の疑いがある患者が2209人、発熱外来が643人。このうち45%前後に新型肺炎の診断が下る可能性がある」。周市長は26日夜、武漢市内の診療状況について説明した。武漢市のある湖北省では既に約700人が新型肺炎にかかり76人が死亡している。市民がSNS(交流サイト)に投稿した動画などによると、武漢市では病院内に診療待ちの人があふれかえっており、医療従事者用の白い防護服などの物資が不足しているという。武漢市は急増する患者の診察・治療体制の整備を急ピッチで進めている。国営新華社通信によると、同市内で少なくとも2つの新型肺炎に特化した病院を建設する予定で、ベッド数は計2千床を超えるとみられる。また上海市などの大都市から医師団も続々と武漢市へ派遣されている。中国では武漢市が23日から市内の交通を遮断する封鎖措置に踏み切るなど感染の拡大防止策を採っているが、食い止められていない。中国の保健当局は27日、国内の患者数は累計で2744人となり、死者は80人にのぼると発表した。直近半日で患者は約700人増えた。さらなる感染防止措置として国務院(政府)は27日、春節休暇を従来の1月30日までから2月2日まで3日間延長すると発表した。新型肺炎は発熱など患者の自覚症状がないケースもあるという情報があり、こうした人からオフィスや学校などでウイルスが広まるのを防ぐ狙いだ。国内の対応とともに海外への感染拡大防止にも動いている。中国政府は27日から海外団体旅行を中止するよう国内の旅行会社に対して通達した。ただ春節休暇を利用した中国人による海外への渡航ピークは既に過ぎている。日本の厚生労働省は26日、国内で4例目の新型肺炎の感染者を確認したと発表した。武漢市から観光で来日した40代の男性で愛知県の医療機関に入院している。男性はバスツアーの旅行客で、22日に空路で来日したという。陸路で中国本土とつながる香港とマカオは独自の入境制限に踏み切った。香港政府は26日夜、27日から中国湖北省の居住者と過去14日間に同省を訪れた人の入境を禁止すると発表した。マカオ政府も湖北省の居住者が入境する際に感染していないとする医師の証明書を提示するよう求める。一方、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は26日、新型肺炎への対応を協議するため北京へ向かっていると、SNS上で明かした。WHOはこれまでの会合で、加盟国の検疫体制の強化などが求められる「緊急事態宣言」を見送った。しかし、その後も日本など中国国外でも患者数が増加しているため、事務局長自らの中国入りを判断したとみられる。 *6-2:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 (昭和二十一年十一月三日公布の日本国憲法より抜粋) 日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果とわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 *6-3:https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-1064852.html (琉球新報 2020年1月28日) 自民、世論喚起へ憲法冊子を作成 「女性に読んでほしい」 自民党女性局は28日、憲法改正を目指す党の考え方をまとめた小冊子を作成した。平易な文章にイラストを織り交ぜた仕上げで、改憲への世論喚起が狙い。「憲法は幸せのカタチを守る基本的なルール」などとしている。三原じゅん子局長は取材に「憲法の話は苦手と思っている女性にこそ読んでほしい」と話す。「青年に音楽を演奏する機会を与える」と書かれたスイス憲法、同性婚を認めるアイルランド憲法などの例を紹介。「幸せのカタチは時代によって変わっていく」と改正の意義を説いた。小冊子は見開きA5判10ページ。党の各都道府県連に2千部ずつ配布する。 *6-4:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/579783/ (西日本新聞 2020/1/30) 「武漢頑張れ」激励込めマスク3万枚を大分市が寄贈 中国から感謝も 新型コロナウイルスによる肺炎が拡大する中国で、日本の支援に称賛の声が広がっている。大分市が27日、友好都市の湖北省武漢市に「武漢加油(頑張れ)」のメッセージを添えてマスク3万枚を送ったところ、短文投稿サイト微博(ウェイボ)に「感動した」などの投稿が続出。閲覧数は3億7千万回を超えた。邦人を帰国させるため武漢入りした日本政府のチャーター機が物資を届けたことにも感謝の投稿が相次いだ。大分市のマスク寄贈は、中国共産党機関紙の人民日報が28日に報じた。マスクの入った段ボール箱に「武漢加油!」の紙が貼られていたことや、大分市が財政的に余裕がない中で支援に乗り出したことを伝えた記事は微博で瞬く間に拡散。「中国語の“頑張れ”には本当に心がこもっている」「裕福でないのに、こんなにたくさん寄付してくれるなんて」「大分市に行ってお礼を言いたい」といった書き込みが相次いだ。政府チャーター機が28日にマスクなど支援物資を運んだニュースも、微博の閲覧数が7千万回を超えた。2008年の四川大地震で日本の救援隊がいち早く現地入りしたことに触れ「あの時も助けに来てくれた」と感謝する投稿や、中国人客の減少で苦境に陥っている日本の観光地を励ます書き込みも見られた。大分市は29日にも防護服200着を武漢市に送った。マスクを送った際、他に不足している物資を尋ねる手紙を添えたところ、武漢市側から要望があったという。防護服は地元医師会の協力を得て集めた。大分市には市民などから物資の支援や寄付金の申し出が相次いでおり、市は今週にも受け入れ態勢を整える予定。担当者は「反響の大きさに驚いている。武漢は長く交流してきた友人のような存在で、早く平穏な生活に戻ってほしい」と話した。 *6-5:https://digital.asahi.com/articles/ASN1Z3VHBN1YUHBI04J.html?iref=comtop_8_01 (朝日新聞 2020年1月30日) 日本の援助、「いいね」中国で15万超 新型肺炎めぐり 日本政府は、新型コロナウイルスによる肺炎が発生した中国・武漢市(湖北省)への民間チャーター機の往路で、中国政府への緊急援助物資を運んだ。中国のネット上では感謝の声が広がっている。328日深夜に武漢に到着した第1便には、中国向けに日本政府が手配したマスク約1万5千枚や手袋5万組、防護眼鏡や防護服などが積み込まれた。30日に到着した第2便も、地方自治体からの支援物資を運んだ。東京都は二つの便の合計で約2万着の防護服を提供しているという。外務省によると、茂木敏充外相が26日にあった中国の王毅(ワンイー)外相との電話協議で協力を申し出て、中国側から求めがあった物資を送った。昨年はエボラ出血熱が流行するコンゴ民主共和国へ防護服を支援するなど、政府は感染症の流行に見舞われた地域への緊急援助を続けている。日本政府からの支援が届いたというニュースは、中国版ツイッターの「微博(ウェイボー)」で広く拡散されており、15万を超える「いいね」がつけられた投稿もある。全国的に交通機関の停止や商業施設の閉鎖などが相次ぐ苦境の中の明るい話題として称賛を集めている。28日午後には、武漢市と友好都市の関係にある大分市が医療用マスクを送り、その箱に「武漢加油(がんばれ)」と記されているというニュースが投稿された。「中国語で書いてくれるなんて」「心の底からありがとう」などと感動を伝える書き込みがあふれ、関連する投稿の閲覧総数は、29日までに3億8千万回にも上っている。ほかにも、日本国内の店などが中国人向けに掲げた「同舟共済(ともに乗り越えよう)」「最重要的朋友(一番大切な友だち)」などといったメッセージの画像も、SNSで広く拡散されている。2008年の四川大地震の被災地での日本の救援隊の活動を記憶している人も多く、つらいときに本当に必要な物を送ってくれることを意味する「雪中送炭」という四字熟語とともに、感謝を伝える人もいる。「日本に行ってみたくなった」と記す人もいるが、中国では感染拡大を防ぐために、27日から海外への団体旅行は禁止されている。ただ、中国客の激減で日本の観光地が打撃を受けていることも広く知られており、こんな書き込みもあった。「ウイルスが去ったら絶対日本に応援に行く」「微力でも、今度は私があなたたち日本の経済に貢献します」 *6-6:https://digital.asahi.com/articles/ASN21645BN21UHBI02T.html?iref=pc_rellink_01 (朝日新聞 2020年2月1日) 台湾、マスク販売を統制「1人3枚まで、1枚は20円」 新型コロナウイルスによる肺炎でマスク需要が高まるなか、台湾当局はマスクを販売する際、1人3枚までに制限し、価格も一律1枚6台湾ドル(約20円)と定める措置を始めた。2月中旬まで続く見通しで、中国など海外へのマスクの輸出も禁じている。台湾で初の感染者が確認された1月21日以降、台北市内の雑貨店では「マスク売り切れ」の貼り紙が掲げられ、入荷してもすぐに無くなる状況が続く。春節の休みも影響し、マスクの生産量は1日に約400万枚にとどまる。約2300万人の市場の需要には追い付かない状況だ。 <日米安保条約の見直しについて> PS(2020年1月28日追加):これに先立ち、G20サミット後の記者会見で米国のトランプ大統領は、*7-1に佐賀新聞が記載しているとおり、「①日本が攻撃されたら米国は日本のために戦わなくてはならないが、米国が攻撃されても日本は戦わなくてよいため、日米安全保障条約は米国にとって不公平だ」「②条約破棄は全く考えていないが、以前から安倍首相にも問題提起している」としていた。現在の日米安全保障条約は、*7-3のように、どちらからでも条約終了の意思を通告することができ、その場合、通告後1年で終了することになっているが、日本は、*7-4のように、日本国憲法で戦争を放棄し、陸海空軍その他の戦力は保持しないことになっているため、国際連合憲章に定める自衛のためにも日米安全保障条約は必要なのである。 また、新潟日報は、2020年1月27日、*7-2のように、「③日米安全保障条約が1960年1月に改定署名されてから60年経過した」「④宇宙やサイバーの新たな領域で日米同盟を強化することも必要になった」「⑤日米同盟の下で、日本は軽武装政策を取って戦後の驚異的経済成長を成し遂げることができた」「⑥米国の戦争に巻き込まれるリスクが高まらないか」「⑦条約改定60年の節目に同盟関係のゆがみを正すのは、戦後外交の総決算を掲げる安倍首相にふさわしい仕事」等と記載しており、何とか軽武装で自衛する方法を考える必要があるわけだ。 *7-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/395893 (佐賀新聞 2019年7月4日) 日米安保見直し発言、認識を正し、本質の議論を 米国のトランプ大統領が日米安全保障条約について「米国にとって不公平な合意だ」と主張し、見直しに言及した。20カ国・地域首脳会議(G20サミット)後の記者会見での発言で、「条約破棄は全く考えていない」としたものの、以前から安倍晋三首相にも問題提起していると述べた。戦後日本の安保政策の基軸となってきた日米安保条約に関わる、極めて重大な発言である。だが、トランプ氏の主張は正確な認識に基づかず、一方的過ぎる。日本政府は日米間で条約見直しの議論は一切ないと否定するが、まず大統領に認識を正すよう求めていく必要があろう。発言の背景には、日米貿易交渉に安保政策を絡めて取引材料とする狙いもあるだろう。その真意を見極めたい。日米の同盟関係は近年、自衛隊と米軍の一体化が進んでいる。今回の発言も日本の役割拡大を求める圧力の一環ともみられる。その現状でいいのか。あるべき同盟関係の姿や、今後の日本の安保政策について本質的な議論に取り組むべきだ。トランプ氏は記者会見で「日本が攻撃されたら米国は日本のために戦わなくてはならないが、米国が攻撃されても日本は戦わなくてもいい。不公平だ」と述べた。2016年の大統領選中にも同様の主張をしているが、現職大統領としての発言であり、看過できない。まず、その認識を正すべきだ。1960年に全面改定された日米安保条約は、第5条で日本有事の際に米国が日本を守ると義務付ける一方、第6条で日本が極東の安定確保のため米軍に基地を提供すると定めている。それぞれのリスクとコストが非対称的なため、以前から米国に不満があったのも事実だ。トランプ氏の発言には来年の大統領選をにらんだ国内向けの側面もあるだろう。だが在日米軍基地は、世界に展開する米軍の戦略的拠点として米国のメリットになっている。一方、日本は年約2千億円の在日米軍駐留経費のほか騒音対策費など応分の負担をしている。「双方の義務はバランスが取れている」というのが日本政府の見解だ。この認識を改めて確認すべきだ。トランプ氏の発言には、この夏から本格化する貿易交渉で日本に譲歩を迫る戦略や、対日貿易赤字削減のための巨額の防衛装備品購入を求める狙いもあるだろう。駐留経費負担の増額を要求してくる可能性もある。だが、圧力の下で交渉の主導権を握られる事態は避けなければならない。公正な交渉を進めるべきだ。解せないのは、G20の際に行われた首脳会談での安倍首相の対応だ。安保条約に対するトランプ氏の不満は来日直前に米メディアが報じていた。にもかかわらず首相は真意をたださなかったという。トランプ氏の会見後、首相は「自衛隊と憲法の関係で何ができるかは説明してきた」と述べたが、日米間でどういう協議があったのかを国民にきちんと説明すべきだ。安倍政権の下、安保政策は対米偏重が進んできた。集団的自衛権の行使を解禁する安保関連法を制定、日米防衛協力指針(ガイドライン)を改定し、日米連携の一層の緊密化を掲げる。だが、米国の戦略に巻き込まれる懸念も膨らむ。近隣諸国との関係構築に努め、安保環境を整備していく構想に日本が主体的に取り組むべきではないか。 *7-2:https://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/20200127521024.html (新潟日報 2020年1月27日) 安保改定60年 同盟の在り方が問われる 日本を取り巻く安全保障環境が大きく変容する中で、条約に基づく日米同盟はどうあるべきか。その在り方が問われる。現行の日米安全保障条約が、1960年1月に改定署名されてから60年が過ぎた。米軍による日本駐留や内乱鎮圧を認めた旧条約を全面改定した現行の安保条約は、米国の対日防衛義務や日本による米国への基地提供義務を定めている。安倍晋三首相は署名60年の日本政府主催の記念式典で、「今や日米安保条約は、いつの時代にも増して不滅の柱。世界の平和を守り、繁栄を保証する不動の柱だ」と表明した。同時に、宇宙やサイバーの新たな領域で日米同盟を強化する意向も強調した。日米安保条約とそれに基づく日米同盟は日本外交の基軸である。同盟の下で、日本は軽武装政策を取り、戦後の驚異的な経済成長を成し遂げたといえる。冷戦終了後、北朝鮮の核の脅威や中国の軍事力増強など北東アジアに緊張が解けない中でも、大きな役割を担ってきた。一方で、米国第一主義を唱え国際社会の分断を増幅するような政策を打ち出しているトランプ米政権の存在は同盟を巡る不安要因となっている。懸念するのは、日本の対米傾斜が加速すれば米国の戦争に巻き込まれるリスクが高まらないか、ということだ。日米安保体制は冷戦終結や湾岸戦争などを機に、たびたび変質してきた。91年のソ連崩壊後には、安保体制の目的を「アジア太平洋地域の安定的な繁栄」へ再定義し、安保条約の「日本と極東」の範囲を踏み越えた。こうした米国の世界戦略に引っ張られる形で進んだ自衛隊と米軍の一体運用が、安倍政権になって加速している。安倍政権は歴代政権が憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認し、安全保障関連法を成立させた。対日赤字の是正を求めるトランプ氏に対しては、最新鋭戦闘機F35といった米国製武器を大量購入している。それでもトランプ氏は「米国第一」優先、同盟関係軽視の姿勢を改めない。日米安保条約は「不公平」と批判し、日本側にさらなる負担を迫っている。「豊かな国が十分な負担をしないで、米軍の抑止力の恩恵を受けるのは米国を食い物にする行為だ」とし、在日米軍の駐留経費負担(思いやり予算)の5倍増を求めているという。だが日本は米軍駐留経費のうち7割以上を負担している。沖縄をはじめ、米軍機の騒音や事故リスクなど基地周辺の市民生活に与える負の影響は大きい。さらに、米兵の法的地位や基地の運用を定めた日米地位協定の抜本的な見直しは実現していない。これでは対等な同盟とは言えまい。条約改定60年の節目を機に、同盟関係のゆがみを正す。それは、「戦後外交の総決算」を掲げる安倍首相にふさわしい仕事のはずだ。 *7-3:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html (外務省) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のとおり協定する。 第一条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。 第二条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。 第三条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。 第四条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。 第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。 第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。 第七条 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。 第八条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。 第九条 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。 第十条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。 日本国のために アメリカ合衆国のために 岸信介 クリスチャン・A・ハーター 藤山愛一郎 ダグラス・マックアーサー二世 石井光次郎 J・グレイアム・パースンズ 足立正 朝海浩一郎 *7-4:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 日本国憲法 昭和二十一年十一月三日憲法より抜粋 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 <日本のみで防衛することが危険な理由> PS(2020.1.28追加):厚労省をはじめとする日本政府は、*8-1のように、「マクロ経済スライドによって年金給付額の上げ幅を賃金水準や消費者物価上昇率よりも低くすることによって、年金保険料支払時よりも年金給付額を目減りさせる」という契約違反(≒詐欺)を行った。そして、日経新聞はさらに、「①年金財政が行き詰まるのを防ぐため、高齢世代に痛みを求めるのは当然」「②現役世代が不利益を被ることがないように年金のマイナス改定を可能にする制度改革が不可欠」「③マクロ経済スライドの制度化以降、日本経済は長期デフレに直面したため、実質年金額は上がる傾向にある」等と記載している。しかし、①は、私がこのブログに何度も記載したとおり、本質的原因のないところに原因を押し付けて35%にも達する65歳以上の高齢者の生活を困窮させ、③の状況を導いているものだ。また、上記のように無駄遣いが多い中、②のように、国民を現役世代と高齢者とに分断し、高齢者のせいにして年金のマイナス改定を要求するような人権侵害体質であるため、日本だけで物事を決めると人権を護れず危険なのである。 なお、*8-2に「④三菱電機に大規模なサイバー攻撃があり」「⑤個人情報や企業機密が外部に流出した可能性がある」「⑥防衛・電力・鉄道などの情報や取引先との製品の受注・開発に関する情報、幹部会議の資料などが流出した情報に含まれている」等が書かれているが、このような情報は専用線を使うなどして外部からアクセスできない状態にしておくことが1980年代から専門家の中では常識であったため、中国系のハッカー集団が関与していたとしても、防衛以前の緩さで運用している日本側に問題がある。このように、超時代遅れで、国民負担により費用だけ莫大に使う体質であるため、日本のみで防衛を行うことは不可能なのだ。 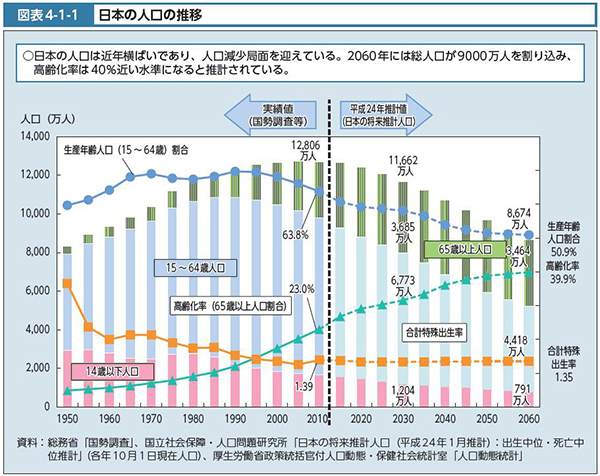 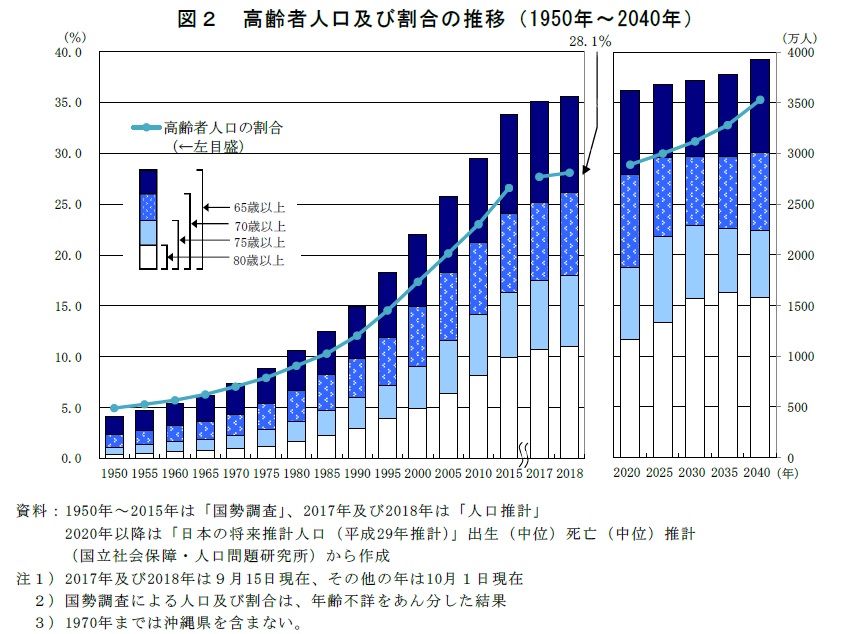  (図の説明:左図のように、人口構成が変わるのは1970~80年代には既にわかっていた。それにもかかわらず、対応をとらずに年金積立金を無駄遣いしてきたのが日本の厚労省なのであり、その結果、中央の図のように高齢化率が30%を超え、現在は「年金給付額を下げればよい」などとと言っているのだ。また、右図のように、「日本の人口が0になりそうだ」などと少子化自体を問題視して煽る論調もよく見かけるが、人間も生物であるため減り方はこのようなカーブにはならない上、少子化を人口減少と結び付けて「産めよ、増やせよ」論にしてしまう態度も、女子差別撤廃条約に反する人権侵害なのである) *8-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200128&ng=DGKKZO54893990X20C20A1EA1000 (日経新聞社説 2020.1.28) 年金のマイナス改定を可能に 厚生労働省は2020年度の年金支給額を0.2%引き上げる。04年の年金改革法に定めたマクロ経済スライドによって、現役世代の賃金水準や消費者物価の上昇幅より年金の上げ幅を低くする。賃金・物価情勢との比較で年金の増額幅を抑えるのは2年連続になる。将来、年金財政が行き詰まるのを防ぐために高齢世代に一定の痛みを求めるのは当然である。だがマクロスライドには欠陥がある。原則、名目年金額を前年度より減らさない仕組みだ。現役世代が大きな不利益を被ることがないよう、年金のマイナス改定を可能にする制度改革が不可欠だ。マクロスライドをひと言で表すと、年金の実質価値を毎年度小刻みに目減りさせる仕組みになる。もっとも制度化以降、日本経済は長期のデフレに直面してきた。このため名目年金額を減らさない仕組みに阻まれ、年金の実質価値は逆に上がる傾向にある。当初、厚労省は19年間で年金の減額調整を終える計画だった。しかし先送りを繰り返した結果、今後さらに30年近く調整を続ける必要があるという見通しを、19年の財政検証に際して出している。これは、高齢者が年金をもらいすぎていることにほかならない。会計検査院は国の17年度決算の検査報告にあわせ、この欠陥がなければ04年度以降に3兆3千億円の税財源が節約できたと推計した。年金マイナス改定によって経済情勢の影響を受けないようにすれば現役世代の不利益は和らぐ。無年金・低年金に陥る可能性がある現役世代への対策も必要だ。就職氷河期世代に代表されるように、無職だったり望まないのに非正規社員として働き続けたりしている人は、保険料を払う余裕に乏しく、満足な年金をもらえない将来を感じとっている。年金の最低保障機能を強めるために、基礎年金に限ってマクロスライドの適用を外すのが一案だ。確定拠出年金を充実させるのも、厚生年金などの実質価値目減りを補うのに有効である。 *8-2:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54586740Q0A120C2MM0000/ (日経新聞 2020/1/20) 三菱電機にサイバー攻撃 中国系か、防衛情報流出恐れ 三菱電機は20日、大規模なサイバー攻撃を受け、個人情報や企業機密が外部に流出した可能性があると発表した。流出した情報には防衛や電力、鉄道などの社会インフラに関する情報や、取引先との製品の受注・開発に関する情報、幹部会議の資料などが含まれているもようだ。三菱電機は「社会インフラに関する機微な情報や機密性の高い技術情報、取引先に関わる重要な情報は流出していないことを確認した」としている。関係者によると、中国系のハッカー集団「Tick(ティック)」が関与した可能性がある。三菱電機は「(流出を確認するための)ログが消去されており実際に流出したかどうかの確認はできない」とし、一部が流出した恐れがあるという。同社によると、国内外のパソコン、サーバーの少なくとも数十台以上で不正に侵入された形跡が見つかった。不正アクセスされたデータ量は文書を中心に約200メガバイト。防衛省や原子力規制委員会、資源エネルギー庁などの官公庁に加え、電力や通信、JR・私鉄、自動車大手など国内外の企業に関する複数の情報が不正アクセスを受けた。同社が不正アクセスに気づいたのは2019年6月28日で、国内拠点のサーバーで不審なファイルの動作を検知した。同様のファイルが中国など複数国の拠点で見つかったため、大規模なサイバー攻撃を受けた可能性があるとし、対象端末について外部からのアクセスを制限した。同社は社内調査を理由に公表していなかった。同社は企業など向けにセキュリティー対策を講じる事業を手掛けており、今回の不正アクセスが影響する可能性もある。公共施設やオフィスビル、データセンターなどの制御システム向けサイバーセキュリティーサービスを19年7月から提供。あらゆるモノがネットにつながる「IoT」を導入した工場がサイバー攻撃を受けた箇所を特定する技術も開発している。 <新型肺炎患者や中国人に対して差別をするのは無知すぎること> PS(2020年1月30、31日、2月1、5、7、8、11、12、13、16、19、23日追加): 中国の武漢市で新型コロナウイルスによる肺炎が発症し、世界に感染が広がったが、*9-1・*9-2のように、一般的なインフルエンザと同様、せきエチケット・こまめな手洗い・人混みを避けることなどで予防でき、症状も軽そうだ。にもかかわらず、ハンセン病の強制隔離を彷彿とさせるような感染者に対する差別や強制隔離の要請が多いのは気にかかる。なお、手洗いは、いつでもこまめで丁寧に行うのが原則で、最近、アルコールを手にすり込めば消毒が終わったと考える人が多いのは、その手でいろいろなものを触るので問題である。また、せきやくしゃみが出る人がマスクを着けるのは当然のマナーであるのに、電車の中などで大きな口を開けて平気でせきをする人がいるのは、新型コロナウイルスに限らず迷惑だ。そのため、私はいつでも電車に乗る時はマスクをして予防しているが、本当は、感染している人にマスクをしたり、せきエチケットを守ったりして欲しいのである。 また、新型コロナウイルスは、最初は動物から人に感染したかもしれないが、ウイルスもDNAを変化(進化)させながら代を重ね、一代の時間は短く、そのうち人から人に感染する性質を得たものだけが次の人に感染するため、人から人にも感染する性質に変わる。従って、ウイルスの特徴は最初から最後まで一定ではなく、ウイルスに抗生物質は効かず、抗ウイルス薬なら効くとされている(https://weathernews.jp/s/topics/201811/080175/)。しかし、ウイルスに効くものには、このほか身体が備えている免疫があるため、日頃から栄養を十分取って免疫を強くしておくことが重要だ。しかし、抗生物質を使って他の細菌を排除し、自分の免疫(兵力)をウイルスに集中させる方法もあるというのが、私の経験だ。なお、最も感染しやすい場所は、マスクを買うための行列や混み合った医療機関の待合室だろう。 なお、武漢からチャーター便で帰国した人をどう扱うかについては、*9-3・*9-4のように、中国の衛生当局が新型ウイルスは発症していない人からも感染する可能性があるとしているため、①フランスは1カ所に集めて14日間経過観察 ②オーストラリアは2週間の離島隔離 ③米国は適切な証拠に基づく公衆衛生対策を講じ、3日~2週間の隔離が必要になるかもしれない としているが、私は、オーストラリアの2週間の離島隔離がBestだと思う。日本の場合なら、例えば沖縄空港に着陸して琉球大学で検査し、暖かい場所で14日間過ごして、症状のない人や回復した人は開放するというイメージだ。 このような中、*9-5のように、厚労省は、チャーター機の第1便で帰国した日本人のうち3人が感染していたと発表し、このうち2人は国立国際医療研究センターで検査を受けた後、発熱やせきなどの症状がないため千葉県内のホテルに相部屋で滞在させられ、陽性の結果を受けて県内の医療機関に入院したそうだが、中国では、感染しても症状が出なかったり、症状が出ないまま他の人に感染することが報告されていたため、厚労省の担当者が「想定外だった」としているのは、とても専門家の判断とは思えない。 そのため、*9-6のように、経産省がフクイチ汚染処理水の処分方法について、①前例ある海洋と大気への放出が現実的選択肢 ②放射性物質監視の面から海洋放出の方が確実に実施可能 ③(危険と言うのは風評被害にすぎないため)風評被害対策の徹底が必要 としていることに、想定外はないと言えるのか? 実際には、想定外ばかりであるため、その後に起こることについて誰がどういう形で責任を持つのか明確にすべきだ。誰かが辞めても何の意味もない。 2020年2月1日、*9-7のように、日本農業新聞が、「①低所得者ほど栄養バランスの取れた食生活ができず、子どもや高齢者が十分な栄養を取れずに健康が脅かされている」「②低所得層の子どもは、成長に欠かせないタンパク質、カルシウム、鉄の摂取量が少ない」「③所得の低いお年寄りほど健康な体を維持するために必要な栄養素が足りない『低栄養』に陥っている」「④多くの人が依然、主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスの取れた食生活をしていない」「⑤注目したいのは子どもに無料か低額で食事を提供する『子ども食堂』だが、国の支援が欠かせない」「⑥食育も忘れてはならない」「⑦所得200万円未満の人に主食・主菜・副菜を組み合わせられない理由を聞くと、『時間がない』という回答が多かった」などを記載している。 農業界が栄養バランスに問題意識を持ってくれたのはよいことで、その結果は、「主食の米さえ作ればよい」という発想を変えることに繋がると思うが、①③は、高齢者の負担増・給付減など高齢者に関する施策が貧しすぎることが原因で、②④⑥のために給食を充実させようとしているのだが、その意味を理解していない学校も少なくない。さらに、女性は必要な栄養学を中学・高校で学んでいるが男性は学んでいないため、食事作りや政策・経営に関する意思決定に栄養学の知識がいかされず、この問題の本質は教育なのである。また、⑤を実践している人には敬意を表するが、夫婦2馬力で子育てすれば食品くらいは不自由しない世の中になっているため、よく考えて結婚相手を選び離婚せずに育児を行うようにして、国に甘えすぎるのはやめて欲しい。⑦についても、野菜ジュース・牛乳・卵・総菜など、共働きや単身者を前提とした比較的安価で時間のなさを補う製品も多く出たため、現在は栄養の知識があるか否かが分かれ目になっている。 なお、佐賀新聞が、*9-8に、「小泉環境相の『育休』どう考える?」という記事を掲載しているが、「父親が取得する育児休暇のアピールにはなったが、育児のために早退や欠席をすると職場での不利益に繋がるのは男女とも同じで、8日間くらいなら有給休暇をとればよいだろう」と、私は思った。実際、このくらいの期間なら、お手伝いのお手伝いくらいしかできないため、この程度なら休みであって「育休をとった」「子育てをした」などと胸を張るのはおこがましい。また、男女にかかわらず、出産や子育ては夫婦2人の労働だけではできない大変さがあるため、「(同じ職業の人の)男女間格差を放っておきながら、(職業の違う人の)女性間格差が問題だというようなくだらないことを言わずに、家事労働への外国人労働者の導入を行えばよい」と、私は30年近く前から言ったり書いたりしていたわけである。 2020年2月5日、*9-9のように、さだまさしさんが「存在理由」と名付けたオリジナルアルバムを制作しており、アルバムの軸に「中村医師に捧げる歌を据えたい」とされているそうで楽しみだが、職業の違う人と生きざまが違うからといって落胆する必要はなく、自分の存在理由(私にもある)を存分に発揮すればよい。中村医師が医療をさておき農業・食料増産に努められたのは、下の図のように栄養失調・不潔・過労などの状態にありながら薬で病気の治療だけを行っても、焼石に水だからである。 日本政府が、*9-10のように、米ホーランド・アメリカ・ラインの「ウエステルダム」に石垣港に入港しないよう求めたのは、観光立国を標榜する日本としては逆の行動だ。「ウエステルダム」が石垣港の後に那覇に行く予定だったのなら、まっすぐ那覇港に入港させて12.5日間船内に隔離し、「ダイヤモンド・プリンセス」と同様に検査して陽性の患者は琉球大学病院で適切にケアし、同時に船に医薬品や食料品等を補給させるのが筋である。台湾・韓国・フィリピン・ベトナム等が事実上拒否しているからといって医療観光も視野に入れている日本が拒否すべきではなく、むしろ他国でケアできないクルーズ船も入港させて同じようにケアするのが今後のためだ。いざという時に入港を拒否して景気の心配をしているのは、誤りだ。 なお、日本政府の対応は、*9-11のように、福岡市の高島市長がクルーズ船の入港や外国人観光客の入国を制限できる基準とルールを定めるよう求める意見書を法務省に提出し、宮崎政務官が出入国在留管理庁に対してその対応を指示されたのだそうだが、福岡なら対処できる病院も多い筈で、検査が済みリスクがなくなるまで乗客をクルーズ船から降ろさなければ問題はないため、両人そろって不合理で非人道的な行動を戸惑いもなく行った点が怖いのである。 また、*9-12のように、クルーズ船の寄港にむけて一生懸命に商談しており、クルーズ船会社や自治体の関係者を集めた商談会が2月6日に福岡県で予定されていたのに、外国の船会社関係者が出席できずに商談会が中止となり、営業活動に影響が出ているそうだ。唐津市には5月14日に中国の上海を出発した客船が寄港する予定になっており、担当者が「その頃までに感染が終息していればいいが」とこぼすのも無理はない。 2020年2月11日には、*9-13をはじめ、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で新たに検査結果が判明した103人のうち65人の感染が確認され、全体で135人の感染が判明したので拡大が止まらない事態だと報道しているメディアが多いが、①乗客乗員約3700人のうちの135人は3.6%にすぎないこと ②潜伏期間(感染したけれども症状が出ていない期間)に発症する人がいるのは当然であること から、船内で隔離された後に感染したのでなければ、隔離に成功したと言える。そのため、必要なものを補給しながら潜伏期間が過ぎるのを待つ方が、乗客にとって快適だろう。また下船する際の全員のウイルス検査は実施した方が安心だろうが、潜伏期間が過ぎても発症していない人は感染していなかったと言えるため、検査キットや人材が足りない中で優先順位をつけるのは仕方がない。それより、*9-14のように、新型肺炎に対応するため急にマスクを買うというのは、インフルエンザの時期で、放射性物質も飛んでいる関東では、あまりに無防備だ。また、その不備に乗じて、マスクの買い占めをするなど論外である。 2020年2月12日には、「『ダイヤモンド・プリンセス』の船内では医療行為が行われないため、乗客を全員降ろしたらどうか」と主張するメディアがあるが、医療行為が必要な人のみを降ろし、必要なものを補給しながら潜伏期を過ぎるのを待つべきだと考える。何故なら、「可哀想だから、乗客全員を降ろす」ということになれば、国内で新型コロナウイルスによる肺炎の感染が拡大するため、クルーズ船の寄港自体に反対運動が起きるからだ。例えば、*9-15の日本への入国を断られたクルーズ船「ウエステルダム号」は、入港させる国がなく、こちらの方が深刻で人道に反する行為である。また、「人権があるから、何も強制できない」と主張する人もいるが、日本国憲法は「12条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」「13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めており、公共の福祉に反しても自由にする権利があるとはしていないのである。 また、*9-16に、「新型肺炎で寄港を拒否され、海をさまようクルーズ船はどこが助けるのか」という問いに対し、国交省が「①明確な決まりはなく、船籍や自国民の割合で国が対応するかどうか考える」「②人命の危機が迫っていれば人道的な面から近隣国ということもある」「③船には入港しないよう要請し、港湾を管理する自治体には入港を認めないよう頼んでいる」「④条約の想定外なので、国際ルールが必要」等と答えているが、③については、あらかじめ入港を許可していたクルーズ船に入港しないよう要請すれば、契約違反による損害賠償が発生しそうだ。さらに、①②④については、病人が出たため海難救助に準じて予定していなかった港にでも寄港させるというのならありうるが、病人が出たので予定していた港にも寄港させず、医療を受ける機会を逃させるというのは、自国民でなくても人道に反すると考える。 2020年2月13日、日本農業新聞が、*9-17のように、新型コロナウイルスのため中国で人の移動が制限された結果、収穫や流通が停滞して中国産野菜の日本への輸入が滞り始めたと記載している。日本で使われているマスクの80%が中国製というのにも驚いたが、2月の財務省貿易統計では、タマネギ・ニンジン・ネギ・キャベツなどの8割以上が中国産とのことで、日本では耕作放棄地を増やしながら農業を粗末にし、外国人労働者の入国制限も厳しくして柔軟な対応をせず、中国で割安に加工まで行う業務用野菜の輸入に頼って中国が風邪を引いたら日本で品不足が起こる状態になっている。他にも多くの仕事が中国に流れたため、(作っている場所で磨かれる)技術も日本からなくなるのは時間の問題で、優越感だけではやっていけないのである。 *9-18のように、新型コロナウイルスの感染が起きている大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号に米国人やその家族が約380人乗っており、米国民を退避させるために在日米国大使館がチャーター機を手配しているのはよいことで、船内感染が起こっていたのなら米国内でもう2週間隔離するという米国の判断は正しいし、他国も速やかにそうすればよいだろう。私はクルーズ船を病院船に使って徹底的にケアするのが、乗客が最も快適に過ごせる隔離方法だと考えていたが、感染症の検疫官とは思えないような無防備な検疫官が船内感染していたり、感染した乗員に乗客のケアをさせていたり、船内が不潔であったりしたのなら、日本国内でもさらに2週間隔離したいくらいであり、「既に国内で散発的に流行し始めたから、水際での阻止は不要だ」という議論にはならない。そのため、*9-19のように、ダイヤモンド・プリンセス号の全乗客をウイルス検査して、陰性の場合は14日間の経過観察期間が終わる19日から健康状態に問題がなければ順次下船させるというのは、船内感染させたのはクルーズ船の船主と日本政府の失敗だから仕方がないとしか言えない。なお、*9-20のように、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて各国・地域の政府が相次いでクルーズ船の入港を拒否したが、これが最も人道に反する行為であり、クルーズ船を入港させた上でクルーズ船を病院船として使って乗客を隔離したり、陽性の人を陸上の病院や自衛隊の病院船で治療したりするのがあるべき姿だったと思う。 *9-21のように、感染症対策に詳しい神戸大医学部の岩田教授が、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」に乗船し、「①船内の2次感染リスクの管理が不十分だった」「②クリーンゾーンとレッドゾーンが区分けされていなかった」「③熱のある方が部屋から出て歩いて医務室に行っていた」「④感染症のプロなら、あの環境では怖い」と指摘された。私も、乗員の検査は最初に行い、外部の人を含めたクリーンな人のみが乗客へのサービスを行うべきで、食事もクリーンで栄養バランスのとれたものを外部から運んだ方がよかったと思う。しかし、クルーズ船内では香港で下船した乗客が新型コロナウイルスに感染していたことがわかった後も、2月5日までビュッフェスタイルで食事が出され、乗員・乗客は近距離で接していたため、高齢者を多く乗船させている割には衛生管理に疎いと思われ、衛生意識が今後のクルーズ船の改善点だ。なお、自民党にも医師の議員はいるため、そういう人を厚労省の大臣・副大臣・政務官のいずれかに任命しておかなければ、専門知識のない素人ばかりでは状況に応じた判断ができないのである。 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客を14日間も船に止めおきながら、その期間中に必要な検査をしなかったという*9-22のミスがあったのは、厚労省の仕事のレベルの低さを露呈するものだ。そのため、米国・カナダ・英国・韓国・香港などの14日間の施設隔離は妥当で、日本は厚労省や保健所でトリアージなどしているより、早急に検査と治療の体制を整えるべきだ。そもそも、今の時代に病院が複数の患者を同室に入院させるのは、感染症でなくても治療環境が悪すぎるし、感染症は新型肺炎だけではないのである。  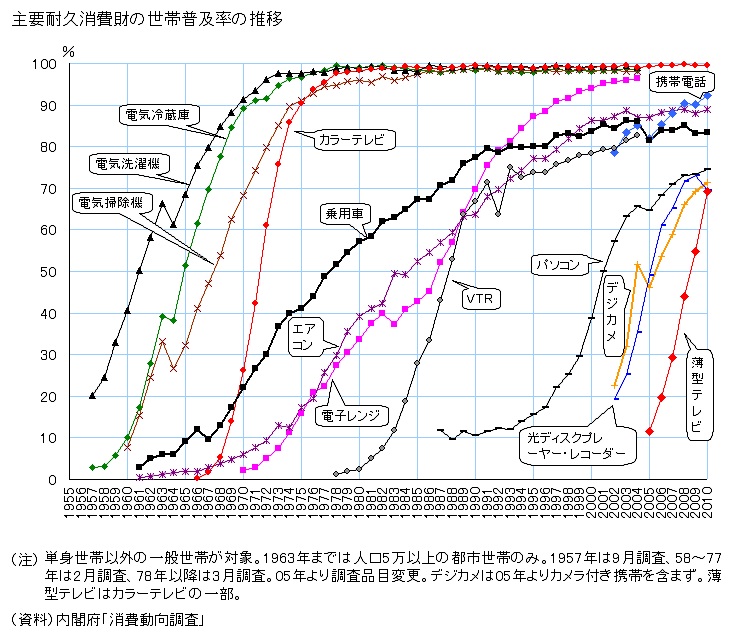 インフルエンザによる死亡率 耐久消費財の世帯普及率推移 (図の説明:左図の1900年以降の日本におけるインフルエンザ死亡率を見ると、1955年頃からみるみる減少し、1990年以降は人口10万人当たり3人以下になっている。これは、医療の進歩の影響よりも、右図の耐久消費財の普及で現わされる日本における栄養状態・清潔に関する意識・正しい情報の共有・文化度の向上による影響の方が大きいと言われている) *9-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/579261/ (西日本新聞 2020年1月27日) コロナウイルス感染 どう防ぐ? 新型肺炎対策を専門医に聞いた ●手洗い、せきエチケット…「正しい方法」で 中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の発症者が急増し、米国やタイなど世界的に感染が広がっている。中国政府は「人から人への感染が認められる」としており、日本国内で発症者が増える可能性も否定できない。専門家は「現段階では、一般的な風邪やインフルエンザの予防策の徹底」を呼び掛ける。あらためて感染予防に必要なことを聞いた。コロナウイルスは、人や動物に感染するウイルスの一種。国立感染症研究所(東京)によると、コロナウイルスが原因となる風邪は10~15%(流行期35%)で、軽い症状にとどまるものが多い。ただ、中には2003年に中国で流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)や、中東地域で発生している中東呼吸器症候群(MERS)のように重症化しやすいものもある。輸入感染症に詳しい国立国際医療研究センター国際感染症センター(東京)の忽那賢志(くつなさとし)医師は「新型ウイルスの感染力はまだ比較が難しいが、重症化するリスクや致死率はSARSやMERSに比べて低い」とみる。ただ、高齢者や持病がある人など抵抗力が低下している人は注意が必要という。国内での感染拡大については「感染から発症まで時間があるため、感染者が知らずに入国し、ウイルスが侵入するリスクはある」。その上で「発症者が受診した医療機関で迅速に診断し、的確に対応する備えが重要だ」と強調する。市民生活では「外出を控えるなどの過剰な反応は必要なく、手洗いやせきエチケットなどを正しい方法で行えば十分」と話す。飯塚病院(福岡県飯塚市)感染症科の的野多加志(たかし)部長も「風邪やインフルエンザの一般的な予防法を徹底することが大切」と言う。手洗いは、指の間や手首などもせっけんを使って念入りに洗うなど、正しい方法でこまめに行う。水やせっけんがない場合はアルコール消毒も有効だ。せきやくしゃみが出る人はマスクを着ける。手のひらで口や鼻を押さえると、付着したウイルスを周囲に広げてしまうため、マスクがない場合は、ハンカチやティッシュペーパーか、二の腕で押さえると良い。「意外と正しい方法を知らない人も多いので、この機会に確認してみてほしい」と的野部長。また、インターネットなどで過度に不安をあおる誤った情報が拡散していることを懸念。「厚生労働省や国立感染症研究所などの信頼できる情報源から正しい情報を収集し、冷静に対応して」とも呼び掛けている。 *9-2:https://digital.asahi.com/articles/ASN1Y74S9N1YULBJ00Y.html (朝日新聞 2020年1月29日) 新型肺炎、SARSより強い感染力か 致死率は低く推移 中国国内の新型コロナウイルスによる肺炎の感染者は、中国政府の29日の発表で5974人。同じコロナウイルスによって起き、2002~03年に流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)の中国国内の感染者数5327人(世界保健機関=WHO調べ)を上回った。SARSと比べて、新型ウイルスはどんな特徴があるのか。WHOなどによると、SARSでは患者のおよそ20%が呼吸不全などで重症化し、中国国内では7%、世界全体では9・6%が亡くなった。一方、新型ウイルスではこれまでに約20%が重症化し、2・3%が死亡している。SARSの流行時にWHOで封じ込めに当たった東北大の押谷仁教授(ウイルス学)は、新型ウイルスによる致死率がSARSよりも低いことに着目。「重症な肺炎に進行せず、発熱やせき、くしゃみといった症状で収まる人が今回は多いのでは」とみる。一方、患者数は最近急増している。WHOは23日、新型ウイルスが1人の患者から1・4~2・5人に感染していると発表したが、「実際にはもっと多く、感染はさらに広がるのではないか」。その理由として押谷さんは、新型ウイルスはより軽症の患者でも、感染力を持っているためではないか、と推測する。SARSは、重症の患者を見つけて隔離して感染の広がりを防げたから封じ込めに成功した。今回は、軽症の患者が感染に気付かないまま、ほかの人に広げている可能性があるという。いまのところ、今回の患者の8割ほどは軽症とみられている。ただ、東京医科大の濱田篤郎教授(渡航医学)は、軽症にみえても、高齢者では発熱しないまま呼吸不全に陥ることがあり、注意が必要だという。感染者や死亡者についての情報は日々、変わっている。国立感染症研究所の鈴木基感染症疫学センター長は、「最初の感染者が発表されてまだ1カ月余りで、現地での調査もまだ十分できているとはいえないようだ。病原性などについても正確な数値はまだ分からない」としている。 ●こまめな手洗いが有効 新型肺炎の感染はどうやったら防げるのか。東北医科薬科大の賀来満夫特任教授(感染制御学)によると、ウイルスは鼻や口、目などの粘膜から入ることで感染すると考えられるという。様々な物を触る中で手に付着しやすいため、予防には「手についたウイルスをこまめな手洗いで洗い落とすことが有効」と話す。日常生活で目や口、鼻など顔を触るくせのある人は注意してほしいという。こうした点は、かぜやインフルエンザの予防と同じだ。患者がマスクを着けると感染を広げない効果があることは分かっている。健康な人のマスク着用は「立証は難しいが、一定の効果があると考えていい」という。ただ、手洗いもマスクも感染を完全には防げない。組み合わせてリスクを下げてほしいという。厚生労働省は28日、国民からの相談を受け付ける電話相談窓口(03・3595・2285)を設置した。医学的知識を持った職員が相談に答える。今後は外国語にも対応する予定という。受付時間は土日祝日を含む午前9時~午後9時。 ●医師「新型インフルの教訓も生かして」 国内でも新型コロナウイルスのヒトからヒトへの二次感染が初めて確認され、国内流行の懸念が高まっている。この先どんなことが起き、何に気をつければいいのか。2009年に海外から持ち込まれ、国内で推計2千万人がかかった「新型インフルエンザ」の教訓について、元厚生労働省技官の沖縄県立中部病院、高山義浩医師(49)に聞いた。ヒトからヒトに感染する新型の豚インフルは09年、4月にメキシコや米国で確認され、世界的に拡大した。日本では5月に神戸市で国内感染が判明し、8月に初の死者が沖縄県で出るなど全国に広がった。09年度の推計国内患者は2061万人で、約200人が死亡した。厚労省の感染症専門医として奔走した高山さんは「今回と同様、専門医も病原性や感染力が十分わからない中で初期対応を迫られ、混乱が起きた」と振り返る。市民に大きな影響が出たのが「新型インフルにかかったかどうか、検査が受けられなくなった」ことだ。厚労省や都道府県の方針では、発生当初は封じ込めのため軽症でも感染が疑われる人はウイルス検査をし、隔離のために入院するなど手厚い対応をとる。一方、一度流行が確認された後は、死亡や重症患者を減らすために健康リスクの高い人が手厚い対応を受けられるよう方針が変わる。このため軽症の人が医療機関にかかってもウイルス検査が受けられずに帰宅を求められ、「そんな話は聞いていない」と押し問答になったこともあった。高山さんは「医療機関の検査体制にも限界がある。国内での流行とともに検査対象が絞り込まれていくことを知っておいてほしい」。新型コロナウイルスも流行後は医療機関のパンクを避けるため、軽症者に受診を控えるよう呼びかける可能性があるという。受診できる医療機関も制限がかかる可能性がある。新型インフルは当初、感染が疑われる人に専門で対応する「発熱外来」が地域の中核病院などに設置された(現在は名称が「帰国者・接触者外来」に変更)。受診前には電話をする必要がある。一方で、若い患者が多かった新型インフルと異なり、新型コロナウイルスの死者は高齢者や持病のある人が多いとされる。高山さんは「高齢者施設ではマスクやグローブなどの感染対策の資材が、病院に比べてそろっていない恐れがある。入居者の通院を一時的に訪問診療で集約するなど、病院に行かなくても済む方法を検討すべきだ」。肺炎リスクを下げるため、肺炎球菌やインフルワクチンの接種も勧める。「現時点では(02~03年にアジアで流行した)重症急性呼吸器症候群(SARS)ほどの致死率はなく、感染力もインフルほどはないと考えられる。適切な感染対策でリスクの高い人も守れる可能性はある」と高山さん。「新型インフルが流行した10年前と比べて国外からの観光客が増え、新興感染症は常に持ち込まれる恐れがある。手洗いやせきエチケットなどインフルと同様の対策を取り、感染が不安な人は人ごみを避けてほしい」と話している。 *9-3:https://www.cnn.co.jp/world/35148651.html (CNN 2020.1.29) 武漢からの帰国者は隔離すべきか、当局が迫られる難しい判断 中国湖北省武漢市から退避する米国人を乗せたチャーター便が、現地時間の29日に米カリフォルニア州オンタリオに到着する。同便に搭乗している約240人の中には、新型コロナウイルスの感染者がいる可能性もある。同便が到着した時点で、衛生当局は難しい選択を迫られる。たとえ症状が出ていなくても、人との接触を避けるためにオンタリオで隔離すべきなのか。隔離する場合、どの程度の期間が必要なのか。中国の衛生当局は、新型ウイルスは発症していない人からも感染する可能性があるとの見解を示した。しかし米衛生当局は、それが事実かどうかの確証はないとしている。そうした事情が、武漢市から帰国する米国人にどう対応すべきかをめぐる判断を一層難しくしている。乗客の中には、30人あまりの外交官やその家族が含まれる。28日に記者会見した米保健福祉省のアレックス・アザー長官も、乗客に対する具体的な対応については言葉を濁し、「適切な証拠に基づく公衆衛生対策を講じる」と話すにとどめた。カリフォルニア州サンバーナーディノ郡の当局者は同日、チャーター便で到着する人は、3日~2週間の隔離が必要になるかもしれないと説明。感染の兆候が出ている人はいないとしながらも、隔離された場所にベッドや携帯電話の充電器、テレビを用意していることを明らかにした。空港でも公共エリアには立ち入らせず、米疾病対策センター(CDC)が許可を出すまでは一般の人と接触させないとしている。一方、フランスの衛生相は26日、武漢から帰国させるフランス人は1カ所に集めて経過を観察し、14日間拘束すると説明していた。 *9-4:https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3892022.html (TBS 2020.1.29) オーストラリア政府、帰国者を2週間 離島隔離へ オーストラリアのモリソン首相は29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中国・武漢市などに滞在しているオーストラリア人を退避させ、2週間、離島で隔離する方針を明らかにしました。「私たちはけさ、武漢で孤立しているオーストラリア人の出国支援に取りかかることを決断しました」(オーストラリア モリソン首相)。モリソン首相は29日、チャーター便などで移送される帰国者を離島で2週間隔離し、新型コロナウイルスの感染検査を行う予定だと明らかにしました。オーストラリア政府によりますと、現在、武漢市のある湖北省には、600人以上のオーストラリア人が滞在登録をしています。帰国者が隔離されるのはオーストラリアの北西に浮かぶクリスマス島で、密航者の収容施設などがある離島です。退避計画の詳細は現在検討中だということですが、子どもや高齢者、短期旅行者が優先的に移送されるとみられています。 *9-5:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14347707.html (朝日新聞 2020年1月31日 より抜粋) 症状ない帰国者2人感染 新型肺炎、厚労省「想定外」 中国の湖北省武漢市を中心に新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、厚生労働省は30日、チャーター機の第1便で帰国した日本人のうち3人が感染していたと発表した。このうち2人は、発熱やせきなどの症状がない国内初の感染例だった。また、東京都と三重県、京都府でも新たに感染が確認された。国内の感染者は14人となった。厚労省によると、チャーター機で帰国後、症状がないのに検査で陽性反応が出たのは40代男性と50代女性の2人。国立国際医療研究センター(東京都新宿区)で検査を受け、千葉県内のホテルに滞在していた。陽性の結果を受け県内の医療機関に入院した。2人はそれぞれ別の帰国者と相部屋だったが、ほかに症状を訴えている人はいないという。感染しても症状が出ない「不顕性感染」か、症状が出る前だった可能性がある。自覚のないまま感染を広げる恐れがあり、中国では報告されていたが、厚労省の担当者は「想定外だった」と話した。これを受け、安倍晋三首相は30日、「新型コロナウイルス感染症対策本部」の会合で「水際対策などのフェーズをもう一段引き上げていく必要がある」と語った。武漢市など感染者の多い地域に滞在したことがあるすべての入国者の健康状態と日本国内での連絡先を確認する方針だ。第1便の帰国者は、検査で陰性反応が出ればホテルから自宅に戻れる予定だったが、2週間は待機してもらうことにした。相部屋もやめる。第2便の帰国者も、症状がなくても基本的に警察大学校(東京都府中市)と西ケ原研修合同庁舎(同北区)に滞在してもらう。厚労省によると、3人のうちもう1人は50代男性。羽田空港に到着した時は症状がなかったが、その後、鼻水やのどの痛みが出て都内の病院に入院していた。容体は安定しているという。また、検査に同意せずに帰宅していた2人も、30日になって検査を受けたいと申し出てきたという。ほかに感染が確認されたのは、中国湖南省から東京に来ていた30代女性と三重県在住の50代男性、京都府在住の20代女性。いずれも武漢市に一時滞在していたという。世界保健機関(WHO、スイス・ジュネーブ)は30日、専門家委員会による緊急会合を始めた。 ■第2便、入院26人 武漢市から帰国を希望する日本人を乗せた日本政府の民間チャーター機の第2便が30日、羽田空港に到着し、210人が帰国した。13人が体調不良を訴え、空港から東京都内の医療機関に搬送。このほか症状のなかった13人も帰国後の検査の後に医師の判断で入院し、入院者は計26人になった。第3便も30日夜、羽田空港を出発。帰国者を乗せ、31日午前に日本に到着する予定。外務省によると、約200人を乗せるとしている。第4便は来週の派遣になる見込みという。第2便では、搭乗前の中国当局の検査で熱やせきの症状があった2人の出国が認められなかった。政府によると、30日時点の帰国希望者は約300人だが、人数が増える可能性もある。 ◇ 中国国家衛生健康委員会は30日、感染者は前日より1737人増の7711人、死者は38人増の170人に達したと発表した。チベット自治区でも初の感染者が確認され、感染は中国本土の全ての省・自治区・直轄市に広がった。 ■新型肺炎の感染者数(日本時間30日午後11時現在。各国・地域の政府発表・報道から累計) 中国 7711(死亡170) 日本 14 香港 10 タイ 14 シンガポール 13 注)10人未満の国・地域は省略したが、数字からは新型肺炎を中国国内に封じ込めることに、だいたい成功していると言える。 *9-6:https://www.nishinippon.co.jp/item/o/580192/ (西日本新聞 2020/1/31) 処理水、海洋放出の利点強調 東京電力福島第1原発で増え続ける処理水の処分方法などを議論する政府小委員会で、経済産業省は31日、前例のある海洋と大気への放出を「現実的な選択肢」とし、うち放射性物質監視などの面から「海洋放出の方が確実に実施できる」と強調する提言案を新たに示した。地元など幅広い関係者の意見を丁寧に聴きながら方針決定するよう政府に要請。放出に際しては風評被害対策の徹底を求めた。小委は地層注入、水素放出、地下埋設も含めた五つの処分方法を検討し、経産省は前回会合で、国内外で処分実績のある海洋と大気の放出を軸にした具体的な3案を示したが今回、こうした書きぶりは修正した。 *9-7:https://www.agrinews.co.jp/p49889.html (日本農業新聞 2020年2月1日) 低所得者の食生活 栄養格差の解消を急げ 低所得者ほど栄養バランスの取れた食生活ができていない──。そんな結果が厚生労働省の2018年国民健康・栄養調査で出た。所得の違いで、子どもや高齢者が十分な栄養が取れず、健康が脅かされる事態は見過ごせない。栄養格差の解消に国は一層力を入れるべきだ。調査は生活習慣病対策の参考にするため、健康増進法に基づき毎年実施。今回は18年11月、5032世帯を対象に行い、1月中旬に公表した。浮かび上がったのは、多くの人が依然、主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスの取れた食生活から遠ざかっているという厳しい現実だ。栄養バランスの取れた食事を、どのくらいの頻度で取っているか聞いたところ、1日2回以上が「ほとんど毎日」という人は男性45・4%、女性49%で半数に満たない。「ほとんどない」も男性、女性いずれも1割前後いた。「ほとんどない」の割合を年間世帯所得別に見ると、より深刻な問題が見えてきた。所得が最も低い「200万円未満」の割合は男性20・8%、女性13・4%。所得が最も高い「600万円以上」と比べ、男女ともに2倍近く高かった。低所得者ほど栄養バランスの取れた食生活が送れていない栄養格差が浮き彫りになった格好だ。「低所得層の子どもは、成長に欠かせないタンパク質や鉄の摂取量が少ない」「所得の低いお年寄りほど健康な体を維持するために必要な栄養が足りない『低栄養』に陥っている」。こうした栄養格差は研究者のこれまでの調査でも明らかになっている。厚労省が定める国民健康づくり運動「健康日本21」(13~22年度)では、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を重点に掲げ、低栄養や生活習慣病などの予防・改善活動を展開しているが、解消には至っていない。栄養格差の解消に何が必要か。低所得者への経済的支援の充実はもちろんだが、注目したいのは子どもに無料か低額で食事を提供する「子ども食堂」だ。設置数は19年が3718カ所。各地で広がりをみせる一方、運営資金が課題となっており、国の支援が欠かせない。子ども食堂に食材を無償提供するJAも増えており、こうした動きを広めることも有効だろう。食育も忘れてはならない。今回の調査では、所得200万円未満の人に主食・主菜・副菜を組み合わせられない理由を聞くと、「食費の余裕がない」よりも「手間がかかる」「時間がない」という回答が多かった。栄養バランスの取れた食事の重要性を地道に訴え、理解を深めてもらう必要がある。農水省は新しい食育推進基本計画を来年3月に策定する予定で、近く議論を本格化させる。栄養格差の解消へ、どのような処方箋を描けるか。知恵を絞り、意欲的な目標と効果的な方針・施策を打ち出してほしい。 *9-8:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/483693 (佐賀新聞 2020年2月1日) 小泉環境相の「育休」どう考える? 佐賀県内男性の取得鈍く トップ、上司次第で意識変化も 第1子が誕生した小泉進次郎環境相が「育児休業」を取得する意向を表明した。「大臣という要職にありながら大丈夫か」と懸念する意見がある一方、「率先して範を示し、今後につなげてほしい」と歓迎する声も上がる。佐賀の男性の育児休業取得事情を調べてみた。佐賀県選出の山下雄平参院議員も4歳の娘がいて、小泉環境相の育休取得を歓迎している一人だ。山下議員も政治活動で地域の会合に出席する機会が多いが、「育児のために早退したり、欠席したりするのは言いづらい雰囲気がある」と語る。子どもに熱が出て病院に連れて行く時さえも「なかなか言い出しづらい」といい、小泉環境相の育休取得が、議員に限らず男性も子育てをするという雰囲気につながればと期待する。総務省から鳥取県庁に出向中、3人目の子どもが生まれ、2週間の育児休業を取得した山口祥義知事も小泉環境相の育休宣言を「英断」と評価する。佐賀県庁では、出産後の「出産補助休暇」(3日間)と出産前後の「配偶者出産時育児休暇」(5日間)を合わせた「8日間の育児休暇」の取得を促す。2016年度は知事部局の対象職員82人中21人(25%)、17年度は70人中36人(51%)、18年度は86人中51人(59%)が取得し、年々増加している。だが、「育児休業」の取得率となるとめっきり減る。育児休業は子が2歳までに1度、1日から長期まで選んで取れるが、18年度の男性職員の取得率は対象81人中わずか4人(4・9%)。県人事課は「育児休暇の取得率を高めつつ、利用促進を図りたい」と話す。民間事業所内でも男性の育休取得の動きは鈍い。県労働条件等実態調査をみると、調査事業所では2006~09年度は0%で、以降も1割にも届いていない。そのような状況の中、先進例と言えるのが半導体や液晶パネル向け精密化学品製造の「JSRマイクロ九州」(佐賀市、約110人)。1週間から約3カ月といった期間で、これまでに7人の男性社員が育児休業を取得した。最初の一人は、上司や同僚が取得を強く促して実現したという。その後は「子どもが誕生したら取るもの」という認識が広がった。父親の育児参加を支援するNPO法人ファザーリング・ジャパン九州の森島孝理事(40)は、男性の育休取得が広がらない大きな要因を「会社の雰囲気」や「周りに迷惑がかかる」などの思いがあると指摘する。一方で、業務の見える化や効率化ができていなければ育休取得を促すのは難しく、そうした環境の改善は「会社の考え方や体制を見直し、働きやすく、強い会社をつくるチャンスでもある」と強調する。JSRマイクロ九州もワークライフバランスの充実を図り、会社の付加価値を高める視点で取り組んでいるという。男性、女性社員に関わらず長期育休で欠員が出れば一時的に派遣社員を雇用してバックアップするなど環境を整えている。「『育休の対象者は限られていて、独身者や子育てが終わった世代は関係ない』と思われているのが現状では」と森島さん。「育休は会社のトップや上司が取ると取りやすくなる。『大臣が取ったから』と言えばもっと取りやすくなる。小泉環境相の発言は、意義が大きい」と話す。 ●記者の目 「当たり前」変える契機に 5年ほど前、会合で沖縄の新聞社を訪れた。「うちの職場は2人が育休中で」。そう話す社員に、そういえば私は取らなかったと明かすと、「なぜ取らないんですか?」と奇異な目で見られた。当時、私には男性社員が育休を取るという考え自体がなかった。意識の違いで、これほどまでに「当たり前」が違ってくる。取材中、育児休業は本来、仕事を継続していくための準備期間という位置づけなのだと聞いた。実際、ある取得者は「育休を取っていなかったら仕事を理由に子育てに参加しなかったかもしれない。夫婦で互いにサポートする体制を手に入れたことが何より」と話していて、準備期間だという話に深く納得がいった。一言に「育児休業」と言っても、本来の狙い、目的や取得による効果や影響など、知っているようで知らないこと、誤解したままのことは多いのではないかと感じた。小泉環境相の取得宣言をきっかけに、多くの「当たり前」を変えていくために必要なことを考えていきたい。 *9-9:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/581518/ (西日本新聞 2020/2/5) 「中村哲医師にささげる歌を」 さだまさしさんがアルバム制作へ 長崎市出身のシンガー・ソングライターさだまさしさん(67)が、「存在理由」と名付けたオリジナルアルバムを制作している。デビューから46年、あえて自らの立ち位置を問い直すテーマに取り組むきっかけとなったのは、アフガニスタンを支援する非政府組織(NGO)「ペシャワール会」現地代表、中村哲医師=享年73=の非業の死だったという。「中村医師のことが胸から離れない」と語るさださん。アルバムの軸には「中村医師にささげる歌を据えたい」とも話している。さださんは、自ら提唱して建設したナガサキピースミュージアム(長崎市)の主催で2004年に中村さんの講演会、10年にはペシャワール会の活動報告展を開いたが、直接の面識はない。ただ、「お互い侠客(きょうかく)の血を引く者として常に意識してきた」存在だという。中村さんの祖父は、北九州・若松港の石炭荷役請負業「玉井組」を率いた玉井金五郎。金五郎の長男、火野葦平の自伝的小説「花と龍」のモデルとして知られ、中村さんも生前、金五郎の生きざまに大きな影響を受けたと語っている。さださんの母方の曽祖父、岡本安太郎も明治時代、長崎港で港湾荷役を取り仕切った「岡本組」の元締。最盛期には気性の荒い沖仲仕(おきなかし)500人を束ね、任侠(にんきょう)の大親分として地元で語り継がれている。中村さんの行動は「無私の精神」で知られるが、東日本大震災や豪雨などの被災地で支援ライブを続けるさださんの行動理念にも義と情の部分で共通するものがある。一方で、ルーツは似ていても実際の生きざまの違いに落胆しているとも言う。「玉井金五郎の孫と岡本安太郎のひ孫があまりにも差がありすぎて、正直めげている」「俺は今まで何をやってきたんだと、自分のアイデンティティーに疑問を持っているところ。のうのうと生きてきたなあとね」。中村さんが銃弾に倒れた時、さださんはすでにアルバム制作に取り掛かっていたが、その死が頭から離れず「花と龍」を再読。わが身と照らし合わせながらたどり着いた答えが、自らの「存在理由」をテーマに据えることだったという。「とりあえず自分に問いかけてみる。『いったい歌作りの矜持(きょうじ)とは何ぞや』と。大したものはできないかもしれないが、やらずにはいられない」。中村さんにささげる歌は「まだ格闘中」(さださん)だが、アルバムと同じく「存在理由」と銘打ったコンサートツアーは4月中旬にスタート。アルバムは5月ごろ発売の予定だ。 *9-10:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55373830X00C20A2EA2000/ (日経新聞 2020.2.7) 新型肺炎、さまようクルーズ船 入港拒否相次ぐ 新型コロナウイルスによる肺炎を巡り、日本や中国周辺を回る大型クルーズ船の運航に支障を来す例が相次いでいる。横浜に到着した船の乗客多数が感染していたことを受け、日本やアジアの国や地域で入港を拒否する動きが広がっているためだ。1月以降に中国を訪れた大型船21隻は全てアジア・オセアニア地域にとどまり、うち複数の船が次の寄港地が決まっていない。向かう先で入港できず、次でも断られ、行き場を失う船が出てきた。日本経済新聞は情報会社リフィニティブとIHIジェットサービス(東京都昭島市)がそれぞれ展開する船舶の位置情報配信サービスを活用し、過去の航跡と現在位置を地理情報システムなどを使って分析した。日本時間7日午後5時までの航跡をみると、日本が石垣入港を拒否した米ホーランド・アメリカ・ラインの「ウエステルダム」(定員約1960人、乗組員約800人)は、1日に香港を出航した。台湾の高雄経由で、6日午後に石垣港の南西約100キロメートルまで近づいたが、入港しなかった。当初はその後那覇に行く予定だったが、太平洋を南下する針路を取っている。イタリアのコスタクルーズ社が運航する「コスタ・セレーナ」と「コスタ・ベネチア」は、韓国周辺の東シナ海上にとどまっている。米シーボーンクルーズラインの「シーボーン・オベーション」は2日ごろ香港を出港、フィリピン方面に向かったものの、途中でベトナムに向けてほぼ直角に針路を変えて同国中部沖まで航行した。しかし港に寄らずに南下し、7日朝タイ中部の港にようやく入った。日本政府は7日、ウエステルダムが石垣港に入港しないよう求めたことを明らかにした。乗員乗客の大多数が外国人だった。赤羽一嘉国土交通相は同日「8日の那覇寄港を取りやめ、当面のスケジュールを白紙とし、次の寄港地を検討すると連絡が入った」と述べた。台湾や韓国、フィリピン、ベトナム当局も事実上拒否している。1月以降に中国に寄港したクルーズ船は合計21隻ある。許可がおりる港を探して移動を続けている船のほか、次の寄港地がみつからず、港にとどまっている船も多数あるとみられることがデータから読み取れる。中には横浜の「ダイヤモンド・プリンセス」のように、乗客乗員が船から出られないケースも出ている。クルーズ船は数百~数千人の乗客とその半数程度の乗務員を乗せている。一般的に寄港地に半日~1日程度停泊し、一部の乗客を入れ替えながら現地ツアーを開く。東アジアでは日本や中国、東南アジア諸国などを回ることが多い。海上移動は数日かかることもあり、その間、乗客乗員は同じ空間で過ごす。日本には日本郵船系の「飛鳥2」や商船三井系の「にっぽん丸」など外航クルーズ船が3隻あり、ほとんどのツアーは乗客の9割以上が日本人だという。外国籍の船では日本発着でも外国人が半数程度を占めているとみられ、アジアでは中国人客が最も多い。データ分析では、1月以降に中国に寄港した21隻のうち11隻が日本に入港したことも分かった。運べる旅客数は最大計3万5000人に上り、乗務員も含めると5万人程度に及ぶとみられる。福岡や長崎、那覇に複数回入港した船もあった。新型肺炎の影響拡大で、世界の主要クルーズ企業が加盟するクルーズライン・インターナショナル・アソシエーションの加盟各社は、過去14日間に中国本土に出入りした乗客乗員の乗船を拒否する対応をとっている。中国への寄港はできず中国ツアーは中止や目的地変更が相次ぐ。米プリンセス・クルーズは「ダイヤモンド・プリンセス」の沖縄・台湾行き2本を中止した。MSCクルーズ(スイス)や米ロイヤル・カリビアン・インターナショナルも上海発着をやめた。日本クルーズ客船の「ぱしふぃっくびいなす」は9日の三亜(中国海南省)と11~12日のアモイ(福建省)から台湾の台南と高雄、花蓮に寄港地を変えた。同社によると「例年に比べキャンセルが増えてきている」という。旅行各社はキャンセル対応に追われ、日本旅行は「事態が長期化すると困る」とこぼす。国交省によると、外国籍クルーズ船は2月に123回来る予定だったが、75回に減った。クルーズ旅行は世界的に人気が高まっており、寄港地経済への恩恵が大きい。各地で打撃が出る可能性もある。外資系クルーズ大手の日本代理店は「クルーズ自体にネガティブなイメージが付かなければいいが」と心配する。運航会社の株価にも影響が出ている。グループ会社がダイヤモンド・プリンセスを運航する米カーニバルの株価は、6日の終値が19年末から13.9%下落した。 *9-11:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/582424/ (西日本新聞 2020/2/7) 「有事の際の入国基準を」 福岡市長が新型肺炎拡大で国に意見書 福岡市の高島宗一郎市長は7日、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、クルーズ船の入港や外国人観光客の入国を制限できる基準とルールを定めるよう求める意見書を、法務省に提出した。高島市長は1月30日、自身のブログで「当面は中国本土からのクルーズ船の寄港を拒否すべきだと思っている」と主張していた。7日、宮崎政久法務政務官と面会した高島市長は「例えば、下船する際に解熱剤を飲んで検疫をすり抜けるようなケースもあると聞いている。国には有事の際の入国基準をしっかり策定してほしい」と要望。宮崎政務官は、出入国在留管理庁に対し遺漏のない対応をするよう指示を出したとした上で、「市民の不安を拭い去るため、現場の皆さんと緊密に連携していく」と応じた。面会後、高島市長は「われわれの考えに共感してもらえた。国には経済対策も併せて対応をお願いしたい」と話した。 *9-12:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/486420 (佐賀新聞 2020.2.8) 唐津市「寄港キャンセルなし」 新型肺炎でクルーズ船 小型の高級客船の誘致に成功し、寄港数を伸ばしている佐賀県唐津市。昨年の唐津港への寄港数は過去最多の11回で計3827人が上陸、今年は9回の寄港予約が入っているが、新型コロナウイルス感染拡大の影響について唐津市は「現在のところはキャンセルは出ていない」と話す。ただ、営業活動に影響が出ている。クルーズ船会社や自治体の関係者を集めた商談会が6日、福岡県で予定されていたが、外国の船会社関係者が出席できず中止になった。市みなと振興課の担当者は「新型コロナウイルスへの対応で商談どころではなくなったようだ。販路拡大に向けた貴重な営業の場がなくなってしまった」と肩を落とす。市には5月14日、中国・上海を出発した客船が寄港する予定になっている。担当者は「そのころまでに感染が終息していればいいが」とこぼした。 *9-13:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020021102000171.html (東京新聞 2020年2月11日) 新型肺炎感染 クルーズ船 新たに65人 全員検査 判断揺れる クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で起きた新型コロナウイルスの集団感染で、厚生労働省は十日、新たに検査結果が判明した百三人のうち六十五人の感染が確認されたと発表した。クルーズ船では検査した延べ四百三十九人のうち百三十五人の感染が判明し、拡大が止まらない事態になっている。中国湖北省武漢市から帰国した邦人らを合わせると、国内の検査で陽性となった感染者は百六十一人となった。厚労省は、船内に待機する約三千六百人の乗客乗員全員に対し、下船する際のウイルス検査の実施を検討していると明らかにした。全員検査を実施する場合、結果を待ってからの下船になるとした。加藤勝信厚労相は検討理由について「国民の不安や懸念にしっかり対応する必要がある」と述べた。一方、菅義偉官房長官は会見で、全員検査は難しいとの認識を示した。船内の感染者数が百三十人を超えたことについて、厚労省の幹部は「乗船者に客室待機してもらう対策を講じた後に増えているのかどうかは分からない。疫学調査や専門家の意見を踏まえて判断したい」と述べた。日本環境感染学会は拡大を防ぐために感染制御に詳しい医師や看護師の専門チームを十一日にクルーズ船に派遣する。厚労省は九日も、検査結果が判明した五十七人のうち六人の感染を確認したと発表した。うち五人は乗員で陽性の結果が出るまで業務に従事していた。不足する医薬品については、九日までに乗客延べ約千八百五十人分の要望があり、同日までに同約七百五十人分を船内に搬入。残りも手配を急ぐ。 ◆「一般病院も受け入れ可」 厚労省転換に自治体困惑 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客らに新型コロナウイルスの感染者が相次いでいる問題で厚生労働省が「感染症の指定医療機関でなくても、患者を受け入れて良い」と全国の都道府県などに通知していたことが十日、分かった。厚労省は「感染症法に沿った対応」と説明、個室など一定の設備がある病院を前提とするが、一般の病院での感染者受け入れにつながる突然の方針変更に、自治体は困惑している。厚労省の通知は九日付。感染症法は「緊急その他やむを得ない理由があるとき」は、指定医療機関以外の病院で指定感染症の患者を入院させられると定めている。感染者が増えていることから、規定に沿って通知を出したという。現在、感染者を受け入れている神奈川、東京、埼玉、千葉、静岡にある指定医療機関は四十九病院計三百四十五床。室内の空気や細菌が流出しないよう気圧を低くする陰圧制御や、他室とは独立させた換気設備などを備えている。通知を受け、関東地方のある自治体は十日、管轄病院に感染者を受け入れられるかの確認に追われた。ただ、この自治体の幹部は一般の病院で受け入れが決まったわけでないとしながら「地域がパニックになるのではないか」と不安を隠さない。 ◆態勢整う病院あるか <岡山大の津田敏秀教授(環境疫学)の話> 病院には体の弱っている人や高齢者がいる。一般の病院で受け入れるとき注意しないといけないのは院内感染だ。だが、例えば感染した人を受け入れるために急に一フロアを空けるなどということができる病院が、どれだけあるのだろう。これまで国の対応は後手後手に回ってきた。仕方のない面もあるが、これからは先を見て対応することが大事だ。中国での湖北省以外の感染者がどのように推移するか。日本での広がりを考えるうえで参考になるのではないか。 *9-14:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020021002100042.html (東京新聞 2020年2月10日) 新型肺炎で「マスク狂騒曲」止まらず 欠品、高値転売、詐欺まで 新型コロナウイルスによる肺炎が広がる中、感染への不安心理による「マスク騒動」が収まらない。買い占めによって店頭から消え、売り上げは例年の9倍近くまで跳ね上がる。インターネット上では高額転売が横行し、騒ぎに便乗したサイバー攻撃まで登場。一体、どこまで広がるのか。(中沢佳子) ◆どこにもない…定価の数倍で転売 「購入はお一人さま二点まで」。七日に東京・銀座のドラッグストアを訪れると、そんな張り紙が掲げられていた。しかし、そこにあるのは商品名と値段が書かれた札のみ。「売り切れなんです。次回の入荷も全く分からなくて」と店員の女性。周辺の五店回るも、どこも「メーカー在庫希薄のため欠品」「入荷は未定」と断り書きが出ていた。高額転売も横行。フリーマーケットアプリ「メルカリ」では、公式ブログが「適切な範囲での出品・購入にご協力を」と呼びかけていながら、この日も箱入りマスクなどが定価の数倍以上で出品されていた。 ◆マスク売上、例年同期比の8.9倍 市場調査会社「インテージ」によると、一月二十七日~二月二日の全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストア計四千店のマスクの売り上げは約百八十七億一千六百万円。同時期の例年平均の約八・九倍に上る。二〇〇九年の新型インフルエンザ拡大のピーク(約六十五億四千万円)をはるかに超え、手指消毒剤やマスク用除菌スプレーの売り上げも例年の十倍以上だった。「過去にない異常な事態。メーカーはどこもフル稼働で増産し、毎日出荷している」と明かすのは、マスクやおむつなどのメーカーでつくる「日本衛生材料工業連合会」の高橋紳哉専務理事。この時期は花粉症やインフルエンザへの備えで出荷が増えるとはいえ、例年の比ではないという。「購入量が多すぎて生産が追い付かない。節度ある買い方をしてほしいのだが」 ◆詐欺サイトにつながるサイバー攻撃も サイバー攻撃も現れた。ネットセキュリティー専門会社「トレンドマイクロ」によると、「マスクを無料送付、確認をお願いします」というメッセージが拡散。URLをクリックすると詐欺サイトに誘導され、クレジットカード情報が盗まれる恐れがある。保健所からの注意喚起を装い、ウイルスに感染するファイルを添付したメールも登場している。物が消える不安から買い占めに走る群集心理は今も昔も変わらない。一九七三年のオイルショック時は、トイレットペーパーがなくなるといううわさに、人々が血眼になって店に殺到した。記録的な冷害でコメ不足に陥った九三年は、外米の輸入でしのごうとした政府の思惑をよそに国産米を求める行列が絶えず、「平成のコメ騒動」といわれた。 ◆「正しい情報がパニックを防ぐ」 「買い占めは不安を解消するための獲得競争であり、自衛行動」と東京女子大の広瀬弘忠名誉教授(災害・リスク心理学)は指摘する。無駄になるかもしれないと思っても、あれば買ってしまう。今回のように感染症の被害状況や先行きが見通せない時に目立つといい、冷静な行動を促すには不安の増幅に歯止めをかける必要があると説く。「客船での足止めやマスクの買いだめなどがショッキングに報道され、不安があおられている面もある。感染の広がりやマスクの供給状況など、正しい情報やデータを出すことがパニックを防ぐ方策だ」 *9-15:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200212&ng=DGKKZO55498990R10C20A2TJC000 (日経新聞 2020.2.12) 日本が拒否したクルーズ船 タイも国内反発で拒否 タイ政府は11日、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大防止で日本に入国を断られたクルーズ船「ウエステルダム号」について、タイも入港を拒否すると発表した。当初は受け入れる予定だったが、国内で反発があり、方針転換した。同号はタイに向かっていたが、今後、どのような針路を取るかは不透明だ。同号の運航会社は10日、「13日にタイに入国し、乗客は空路で帰国する」と明らかにしていた。タイ政府はこの情報がインターネット上に広がり、パニックになったことを入港拒否の理由の一つに挙げた。今後、他のクルーズ船の受け入れも拒むかは不明だ。フィリピンやベトナムに入国を断られた別のクルーズ船「シーボーン・オベーション号」はタイに入港を認められ、7日に着岸した。他のクルーズ船にもタイへ向かう動きがみられていた。 *9-16:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020021202100021.html (東京新聞 2020年2月12日) 新型肺炎で海をさまようクルーズ船 どこが助けるの? 新型コロナウイルスによる肺炎の影響で、港に入れないクルーズ船が日本近海をさまよっている。クルーズ船は寄港先で食料や燃料を補給していく。どこにも受け入れてもらえなければ、いずれ乗客乗員の人命にかかわる事態になる。そんな状況になったらどの国が責任を負うのか。専門家に聞くと、どうやら国際的な取り決めは、ない。 ◆あちこちで寄港を拒否され… 台湾・高雄から横浜へ向かっていたクルーズ船「ウエステルダム」。寄港予定だった沖縄県・石垣島や那覇で入港を「拒否」された。乗客乗員計二千人余りの一部に新型肺炎の発症者がいたためだ。十日現在も寄港先が決まっていない。六日に那覇を出発したクルーズ船「スーパースター・アクエリアス」は、行き先の台湾、出港した那覇から寄港を拒否される事態に陥った。結局、台湾が受け入れることになり、予定より遅れて八日に到着した。東南アジアを巡っている日本船籍のクルーズ船「ぱしふぃっくびいなす」は台湾での寄港を拒否され、長崎港へ向かっている。横浜・大黒ふ頭に着岸している「ダイヤモンド・プリンセス」も、乗客乗員は中に留め置かれている。つらい状況だろうが、海の上をさまよっている船があることを考えると、まだましなのかもしれない。 ◆食料は10日ほどで尽きる 入港させてくれる港がなければ、船はどうなるのか。あり得なさそうな事態が、日本近海で起こりそうになっている。「豪華客船は数千人乗客乗員がいる。食料は一週間か十日間でなくなり、燃料も補給しないといけない。通常は寄港先で調達するのだが…」と、神戸大の若林伸和教授(航海システム学)は語る。つまり、客船が洋上にさまよっていられる日数は、この程度。これより長くなると、人道上の問題になりかねない。どの国が救いの手を差し伸べる決まりになっているのか。 ◆船籍や自国民の割合を考慮 外国からの船の入港には、検疫、出入国、港湾の管理で三つの役所がかかわる。入港拒否は港湾を所管する国土交通省の担当だ。問い合わせてみると…。「明確な決まりはない。事案に応じて適切に対処するとしか言えない」。海事局外航課の長井総和課長はこう説明し、「頭の体操になってしまうが、船籍や自国民の割合で、国が対応するかどうかを考える。人命の危機が迫っていれば人道的な面から近隣国ということもあるだろう」と続けた。ちなみに、国交省に制度上、入港拒否権はなく、「船に入港しないよう要請するとともに、実際に港湾を管理している自治体に入港を認めないよう頼んでいる」(長井課長)という。 ◆条約の想定外 国際ルールが必要 今回の事態をみると、日本政府は、日本人の比率を重視して対応を変えているようだ。ダイヤモンド・プリンセス号は乗客の半分が日本人だったのに対し、寄港拒否された二つの船では、乗客が外国人中心だったからだ。若林氏は「ダイヤモンド・プリンセス号は、邦人保護の観点から入港が許されたのだろう」と語る。現在の扱いは「検疫法に基づく検疫が続いているという整理で乗客を留め置いている」(厚生労働省結核感染症課の加藤拓馬課長補佐)という状態だ。若林氏は「海上のさまざまな権益を取り決める国連海洋法条約では、今回のような寄港先が決まらないという事態は想定されていなかった。どの国が船に対して責任を持つのか、早急に議論して国際ルールを作るべきだ」と警鐘を鳴らす。 *9-17:https://www.agrinews.co.jp/p50006.html (日本農業新聞 2020年2月13日) 新型肺炎の混乱 野菜にも 中国産輸入が停滞 移動制限で収穫できず 国産切り替えも 猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、中国産野菜の日本への輸入が滞り始めた。例年2月はタマネギやニンジンなどの輸入野菜が多くなり中国産が主力だ。現地で人の移動が制限され、収穫や流通が停滞し、解消の見通しは立たない状況だ。混乱が長期化する様相の中、一部の流通業者には国産に切り替えようとする動きが出ている。生鮮野菜の輸入量は、年間で2、3月が特に多い。昨年2月の財務省の貿易統計では、タマネギやニンジン、ネギ、キャベツなどの8割以上が中国産だ。中国政府は、ウイルスまん延を防ぐため、人の移動を厳しく規制している。地域によっては「3人以上集まってはいけない」などと制限。人員確保が難しく野菜を収穫できず、出荷適期を過ぎても畑に放置されている模様だ。今の時期、日本に輸入される中国産タマネギは、前年10月に内陸部の甘粛省で収穫、貯蔵後、山東省の加工場で皮をむき、袋詰めしたものが多い。日本の輸入業者によると「山東省政府は1月末、省内の各企業に2月9日まで加工場などを稼働しないよう通達を出した」という。10日から一部で稼働は再開したが、「出荷量は限定的。野菜を梱包(こんぽう)する段ボールやビニール工場などの稼働遅れも問題になっている」(同)。青ネギやニンジンは、主産地が山東省から福建省に移っている。「産地移行に合わせ、山東省の労働者が福建省に出稼ぎに行き、加工を担うことが多い」(同)が、移動制限で作業が停滞している。輸出する港でも混乱が生じている。港で働く従業員の多くが春節期間中に帰省したが、移動規制で職場に戻れず、人員不足による作業遅れで積み下ろしや積み替えを待つコンテナが増えている。主要な輸出港の天津港(天津市)。90人の従業員が働くコンテナ運営会社によると、同社は通常、毎日150~200個のコンテナをさばく。だが、従業員の6割が現場復帰できず、6000個のコンテナが港で滞留。同社は「港に処理待ちのコンテナがあふれている」と指摘。冷蔵・冷凍コンテナで運ぶが、電力不足で野菜などは品質低下が発生している。影響の程度や期間が見通せない状況を受け、国産需要が高まりそうだ。日本の輸入業者は「中国産タマネギの仕入れ値は2倍近くに上がっている。現時点は各業者が輸入在庫を抱え、国産へのシフトは限定的。ただ、3月以降も長期化すれば状況は変わってくる」とみる。業務用カット野菜の製造業者も「今後の調達が大変」と漏らす。国内主力のタマネギ産地、ホクレンは「2月に入って、大手外食チェーンなどから問い合わせがある」(玉ねぎ馬鈴しょ課)と説明する。北海道産タマネギは潤沢で量はそろうが、「国内の皮むき加工業者は人手不足」(同)で、需要が増えた場合にどれだけ対応できるかは不透明という。 *9-18:https://digital.asahi.com/articles/ASN2J0FFJN2HUTIL025.html?iref=comtop_8_04 (朝日新聞 2020年2月16日) 米から救出機「遅すぎ。乗らない」 拒むクルーズ船客も 新型コロナウイルスの集団感染が起きている大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号。横浜港に停泊中の船から米国民を退避させるため、在日米国大使館はチャーター機を手配していると15日に公表した。米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、船には米国人やその家族が約380人乗っている。船室内からも出られない状況が続き、ツイッターやフェイスブックなどで窮状を訴えたり、情報発信や交流をはかったりする人もいる。その中に「チャーター機には乗らない」と話す人がいた。カリフォルニア州から妻と乗船しているマシュー・スミスさん(57)だ。スミスさんは船内のアナウンスや食事などの様子とともに、「船内が危険だというネット上のデマにだまされないで」といった趣旨のツイートをした。15日、米政府がチャーター便を手配すると発表すると、「船内で検疫を終えた方がいい」とも発信した。朝日新聞の電話取材に応じたスミスさんの説明は次のような内容だった。予定された14日間の検疫期間が終わるまではあと数日。そのタイミングでの米政府のチャーター機派遣という決定は、「遅すぎた」。また、「検疫期間中でウイルスの検査結果も出ていない人々をまとめてバスに乗せ、飛行機で帰国させるという対応は、ここまで船室内で我慢してきた努力を無駄にするようなものだ」とも話した。その上で「しかも米国内でさらにもう2週間検疫するという。シンプルにばかげている」。感染の有無を調べる検査を受けていなかったり、検査の結果がまだ出ていなかったりする多くの人とともにバスや飛行機に乗る方がリスクが高い――。スミスさん夫妻はそう考え、船にとどまることを選んだという。また、チャーター機に持ち込める荷物は1人1個で70ポンド(約30キロ)までとされていることも問題だと話す。船に残した荷物がどうなるのかについても米大使館から説明がないため、戸惑っている米国人の乗客もいるという。大使館は、チャーター機で帰国しない米国人は一定期間、米国への入国は認められないと説明している。だが、その期間がいつまでなのかも明らかにされていないという。スミスさんは言った。「船で検疫を終え、検査結果が陰性となった時点で日本政府が上陸を許可してくれればいい。帰国できるようになるまでの間、東京に滞在するかもしれない」 *9-19:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200216&ng=DGKKZO55697760V10C20A2CC1000 (日経新聞 2020.2.16) クルーズ船、全乗客検査へ 新型コロナウイルスの集団感染が発生し、横浜港で検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」を巡り、加藤勝信厚生労働相は15日、全乗客をウイルス検査する方針を明らかにした。同船では新たに67人の感染が確認されたことも発表し、同船の感染者は計285人となった。同船には当初、乗客乗員約3700人が乗船。検査能力の限界から全員一斉の検査は見送っていた。厚生労働省は民間検査機関などに協力を要請。年齢などで区切って順次検査を進めることで、乗客全員を検査できるメドが立ったという。感染者と同室だった人を除く70歳以上の高齢者には検査を実施しており、70歳未満の乗客についても16日をめどに順次、検査を実施。陰性と判明した場合は、14日間の経過観察期間が終わる19日から健康状態に問題がなければ順次下船する。東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授(感染症学)は「より早い段階で全員のウイルス検査に踏み切るべきだったが、受け入れ施設や検査体制の確保でやむを得なかった面もある」と話す。「下船した乗客の感染を確認した香港や、船籍国の英国、運航会社のある米国との情報共有を徹底していれば、横浜到着前に検査や感染防止の体制を整えることができた可能性がある」と指摘している。 *9-20:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200216&ng=DGKKZO55697800V10C20A2CC1000 (日経新聞 2020.2.16) 入港拒否、各地で相次ぐ 国際ルールに穴 新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、各国・地域の政府によるクルーズ船の入港拒否が相次いだ。根拠が不明確なケースもあるが、感染症を想定した国際的な取り決めはなく、ルールの穴が浮かんでいる。日本人5人を含む約2200人を乗せたオランダ籍のクルーズ船「ウエステルダム」が13日、カンボジア南部の港に到着し、14日から一部乗客の下船が始まった。同国のフン・セン首相は「私たちは責任をもって乗客を助けなければならない」と表明した。米国企業が運航する同船は2月1日に香港、5日に台湾・高雄を出て沖縄・石垣港に向かっていたが、日本政府から「新型肺炎を発症した恐れのある人が確認された」として外国人の乗客乗員の入国を拒否された。11日にはタイ政府からも入港を拒否されていた。香港の企業が運航するバハマ籍の「スーパースターアクエリアス」も台湾で寄港を断られて那覇に向かっていたところ、7日に日本政府から入港辞退を求められた。その後、台湾は受け入れに転じ、台湾当局の検疫では乗客乗員に感染者は確認されなかったとされる。国土交通省の外航課は「乗客らに感染の可能性がある場合、受け入れは個別判断になる。運航会社の拠点、船籍国、乗客の多い国が判断要素となる」と説明している。香港や韓国、フィリピンなどもクルーズ船の入港を事実上拒否しているが、個別の船について感染者の有無は必ずしも明らかではない。世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は12日に「科学的な証拠に基づいたリスク評価をしていないことが多い」と苦言を呈した。 *9-21:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200219-00000029-mai-pol (毎日新聞 2020/2/19) クルーズ船「乗船」の神戸大教授が対応批判 菅氏は「感染拡大防止を徹底」と反論 感染症対策に詳しい神戸大医学部の岩田健太郎教授が18日、政府の許可を得て、横浜港で検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」に乗船した経験として、船内の2次感染リスクの管理が不十分だったと指摘する動画を公開した。菅義偉官房長官は19日の記者会見で「感染拡大防止に徹底して取り組んできている」と反論したが、政府高官は「いろいろな指摘には謙虚に耳を傾けたい」と述べた。岩田氏の説明によると、厚生労働省の協力を得て、災害派遣医療チーム(DMAT)の一員として18日に乗船した。18日夕方に下船後、動画投稿サイトで「ウイルスが全くない安全なグリーンゾーンと、ウイルスがいるかもしれない危ないレッドゾーンが、ぐちゃぐちゃになっていて、どこが危なくて、どこが危なくないのか全く区別がつかない」「熱のある方が自分の部屋から出て、歩いて医務室に行っている」「感染症のプロだったら、あんな環境に行ったら、ものすごく怖くてしょうがない」などと訴えた。菅氏は19日の会見で、「レッドゾーンとグリーンゾーンがぐちゃぐちゃ」との指摘に対して、「イエスかノーで答えることはできない」と回答。また感染対策の例として「乗員はマスクの着用、手洗い、アルコール消毒などの感染防御策を徹底するとともに、乗員の感染が確認された場合には同室の乗員も自室待機にするなど感染拡大防止を徹底している」と述べた。しかし、岩田氏の指摘は、こうした「感染確認後の対応」ではなく、それ以前の「検疫の初期段階にとるべき対応」に関するものだ。菅氏自身、18日の会見でクルーズ船への対応について「良かった点も、悪かった点もある」と認めている。クルーズ船は19日から下船が始まったが、政府は今後、一連の対応について検証する方針を示しており、岩田氏の指摘についても議論になるとみられる。 *9-22:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/491777 (佐賀新聞 2020.2.23) 下船の1人、新型肺炎発症、栃木の女性、感染確認 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の新型コロナウイルスによる肺炎(COVID19)集団感染で、栃木県は22日、検査で陰性となり19日に下船した60代の日本人女性1人の感染が確認されたと発表した。クルーズ船を下船して帰宅した人の陽性確認は初めて。厚生労働省は22日、下船した乗客23人について、2月5日以降の健康観察期間中にウイルス検査をしなかったミスがあったと発表。加藤勝信厚労相は「深く反省する。こうしたミスが起きないよう徹底したい」と謝罪した。政府が乗客乗員約3千人超に2週間にわたって船内待機を求め、実施した大規模検疫と下船の判断は大きな課題を残した。栃木県によると、女性は21日に発熱があり、22日のウイルス検査で陽性と確認された。下船後は公共交通機関で栃木県内に戻り、最寄り駅から自宅までは友人が車で送った。移動中はマスクをしていた。厚労省によると、検査漏れのあった23人の内訳は日本人19人と外国人4人。下船後の精査で判明した。23人には再検査を要請し、3人は陰性だった。残る20人とは検査時期を調整する。感染拡大防止策を取った5日以前に一度検査していずれも陰性だったが、下船前に改めて検体を取る際に部屋に不在だったり、検査時期を確認しなかったりしたのがミスの原因という。症状が出れば地元で対応する。政府は新型肺炎対応策をまとめた基本的対処方針を25日にも公表する見通し。厚労省は、船内で作業をした同省職員は医療関係者らを除き、検査をすることも22日公表した。対象は41人。下船後2週間は自宅勤務する。22日は感染者と同室だった濃厚接触者89人が下船した。健康観察のため、埼玉県和光市の税務大学校に滞在する。日本人乗客らの下船はほぼ終了した。下船者の感染確認は、外国政府のチャーター機で帰国した人にも相次いでいる。厚労省によると計25人の感染が判明。米国籍の18人、イスラエル国籍の1人、オーストラリア国籍の6人だった。下船者への対応は日本と海外で異なる。米国やカナダ、英国、韓国、香港は14日間、施設で隔離。日本では日常生活に戻り、健康状態を2週間チェックし、不要不急の外出自粛を求めている。 <個性から新品種へ> PS(2020年2月2日追加):冬枯れになる冬は、花が少なく閑散とした街並みが多いが、*10のように、JA庄内みどりが冬に咲く桜「啓翁桜」を栽培したそうだ。今後は、広大な敷地での栽培や管理にドローン・自動草刈機等での省力化を必要としているそうだが、輸出だけでなく国内にも植えて欲しい。国内の桜は、4月前後に一斉に咲いて短い期間で散り、華やかな期間が短すぎるため、季節をずらして咲く桜があれば、一年にわたって寂しくないからだ。このように、最初は「狂い咲き」と呼ばれながら個性の違いで生じた桜を繁殖させて新品種にすると、その希少さが価値を高くする。他の花にも、季節のずれた品種があればよいと思う。      椿 蝋梅 水仙 白とピンクの梅 (図の説明:1番左は12月・1月に咲いていた椿、左から2番目は今咲き始めた蝋梅《ろうばい》、中央の水仙と右2つの梅はこれから咲く花だが、これに桜その他の花が加わると、冬も明るいだろう) *10:https://www.agrinews.co.jp/p49902.html (日本農業新聞 2020年2月2日) 輸出拡大へ省力化を 北村地方創生相 山形県を視察 北村誠吾地方創生担当相は1日、地域のニーズを把握するために山形県を訪れ、JA庄内みどりを視察した。同JAが輸出に取り組む、冬に咲く桜「啓翁桜」の栽培を見学した。意見交換したJAや生産者は輸出やスマート農業への支援を求めた。JAは啓翁桜を県内でも先駆けて香港やベトナムに輸出し、年々栽培規模を拡大させている。田村久義組合長は「新規の輸出先としてロシアと商談中」と説明。北村担当相は「ロシア大使館に魅力を伝え、売り込みたい。関係省庁で連携し、産地を支援していく」と応えた。JA花木専門部長の高橋正幸さん(53)は、啓翁桜の栽培法や広大な敷地を管理する苦労を説明。北村担当相は「ドローン(小型無人飛行機)や自動草刈り機の導入など、迅速な省力化の必要性が分かった」と述べた他、「啓翁桜の栽培体験など、教育機関と連携して子どもたちに特産物について教えてほしい」と地域での魅力発信にエールを送った。JAの視察後は、水田に囲まれ「庄内のウユニ塩湖」と呼ばれる宿泊施設「ショウナイホテル スイデンテラス」や、木を基調にした児童遊戯施設「キッズドーム ソライ」などを巡った。 続き▽
| 外交・防衛::2019.9~ | 02:54 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2020,01,15, Wednesday
  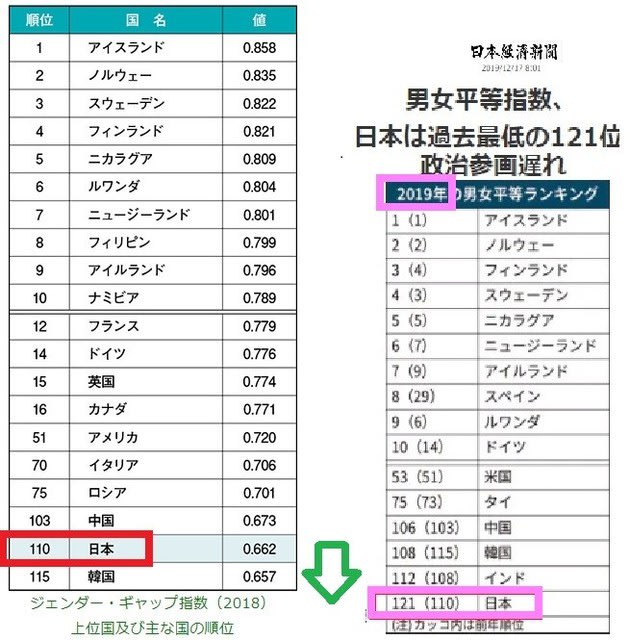 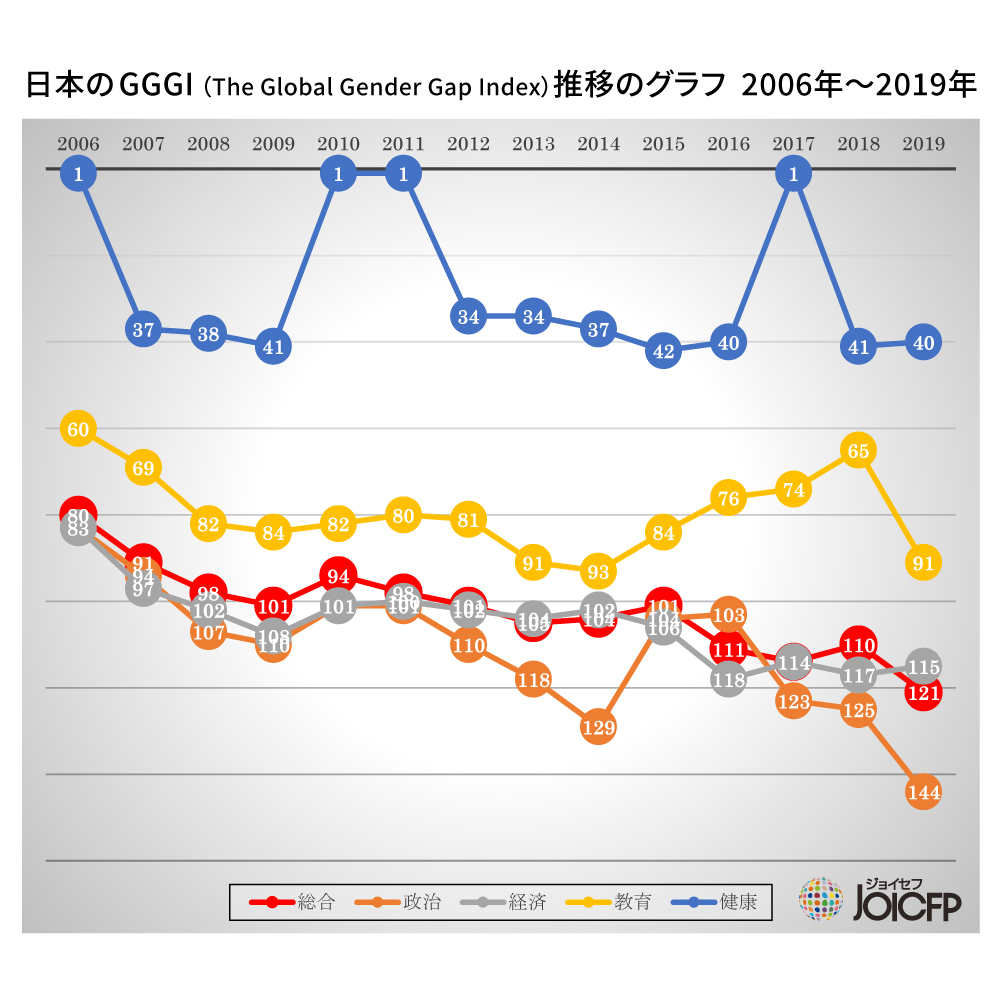 2020年1月11日の総統選で勝利した蔡英文氏 日本のジェンダー・ギャップ指数 (図の説明:中国と向き合うにはかなりの覚悟が必要だが、左の2つの図のように、2020年1月11日の総統選では、中国と向き合う台湾の女性総統である蔡英文氏が圧勝した。日本は、右の2つの図のように、世界経済フォーラムの2019年ジェンダー・ギャップ指数で、総合121位《中国、韓国、インド以下》となり、特に政治分野における順位が144位と低い) (1)台湾の民意と関係諸外国の対応 1)台湾総統選での蔡英文氏の圧勝を祝福する 台湾の総統選(2020年1月11日投開票)で、*1-1のように、蔡英文候補が圧勝されたことを心から祝福する。高い投票率と蔡氏の過去最多得票により、台湾の民意は「中国との距離を保って自由で民主的な社会であり続けることだ」と明確に示された。 これには、香港の状況を目の当たりにした台湾の有権者の切実な危機感と昨年1月の習近平中国国家主席の「一国二制度」による統一を迫る演説が影響し、総統選前に中国が台湾海峡を航行させた国産空母も台湾住民の反発を招いたそうだ。その理由は、自由や人権の有り難みを知っている人は、それが踏みにじられようとすれば必死でそれを護ろうとする上、台湾の人口構成は中国系ばかりではないからだろう。 2)米国の対応 このような中、*1-2のように、トランプ米政権は、軍事・経済の両面で台湾を支援しており、今後は米国が世界における自国の「抑止力の源泉」と位置づける軍事と経済の両分野で中国の覇権的な攻勢の最前線に立つ台湾を積極支援していく考えだそうで、これには私も賛成だ。 米国は、2018年に米高官の台湾訪問や定期的な武器売却を求める「アジア再保証イニシアチブ法」をトランプ大統領の署名で成立させ、「自由で開かれたインド太平洋地域」の推進に向けた台湾支援を着実に進めてきた。トランプ政権は、台湾経済が中国への依存度を急速に強めていることにも危機感を募らせ、現在、議会や政府内部で米国と台湾との経済関係の緊密化に向けた自由貿易協定(FTA)の締結を提唱する声が広がりつつあるそうだ。 ここが、*1-1に書かれている「①台湾独立志向の蔡政権に対して中国は牽制を強め、台湾と国交を持つ国は中国の圧力で15ヶ国まで減った」「②蔡氏は中国が主張する『一つの中国』を受け入れないが、民進党が綱領で定める『独立』も封印してきており、そのバランス感覚を持ち続けてほしい」などと言うような強い側について、前例どおりに、いつまでも現状維持すればよいとする日本人の態度とは異なる。私自身は、台湾(中華民国)が中国から独立したままでいてよいと考える。 3)中国の対応 2016年、トランプ米次期大統領が1979年以来の前例を破って正式な外交関係のない台湾の蔡英文総統と電話会談した時には、*1-3のように、中国は米政府に「米中関係の大局が不要な妨害を受けることがないよう、『1つの中国』政策を守って台湾問題を扱うよう促した」とのことである。 また、2020年の台湾総統選における蔡総統の再選について、日米英の高官らが歓迎の談話を出したことについて、*1-4のように、中国外務省報道局長は「一つの中国の原則に反するやり方で、強烈な不満と断固とした反対を表明する」とのコメントを発表して各国に抗議した。 4)日本の対応 日本は、*1-5のように、日経新聞も「台湾の中国離れ加速が米中対立の火種になる」などと記載しているが、台湾は親日的な国であり、火種になっても弱者を犠牲にすればよいのではなく、やらなければならないことはある。 さらに、「台湾(中華民国)が独立したままでは、中国とよい経済関係を持てない」ということはあってはならない筈で、日本はじめ他の独立国は中国と経済関係を持ち貿易をしている。そのため、台湾は中華民国として国連に加入し、台湾の「経済的利益」をWTOを通して、または米国・ヨーロッパなどとのFTAで保ちながら、「国家の安全」と「経済的利益」を両立させればよいと考える。その方が、近くの日本も安心して付き合いやすい。 (2)女性に「控えめであること」を要求する日本文化 台湾総統選では、台湾人の人権や一国二制度への賛否が重要なテーマになったため、今回は蔡英文氏への女性差別どころではなかったと思うが、*2-1のように、男女は発信についても機会均等ではない。 私自身は、ディスカッション時には積極的に挙手して堂々と発言する方だが、そうすると、女性の場合は「声が大きい」「でしゃばり」「人の意見を聞かない」「独善的」等々の男性ならありえない批判に晒されることが多い。しかし、発言も発信もしなければ認められないため、女性の場合は矛盾した要求の下に置かれるわけだ。 また、黙っていても周りが実績を理解し評価して昇進させてくれるほど世の中は甘くないため、上を目指せば自分の経歴や実績をアピールせざるを得ないが、女性がそれを行うと「謙虚でない」「目立ちたがり」「性格が悪い」等々のマイナス評価もついてくる。つまり、女性が発言や発信に控えめになるのは、生まれつきの「男女の違い」や「女性の不得意部分」などではなく、女性に「控えめであること」を要求する文化によるものであり、女性への矛盾した要求が女性の活躍を妨害しているわけである。 そのため、*2-3のように、女性リーダーの育成において、まるで女性に覚悟が足りないかのように女性に覚悟の大切さを学ばせるというのは、本当の理由を理解しておらず、女性に対して失礼である。 (3)女性の実績と評価 「ウィキペディア」の記事も、*2-2のように、男性の記事が8割を占めるそうだが、リーダーに占める女性の割合が低ければ、実績があっても「ウィキペディア」に載らないため、「ウィキペディア」だけが是正を目指しても限界があるだろう。 さらに、「ウィキペディア」はじめメディアやネットに掲載されている記事は、その多くが本人ではなく他人が書いたものであるため、社会の一般常識と同様、女性を過小評価したり、頑張る女性をちゃかしたり、馬鹿にしたりする女性蔑視を含んだものが多い。そして、これが長く露出し続けるため、その評判が定着するというのが、私の経験である。 (4)農業における女性の参画とリーダーシップ 農業は食品を扱う業種であるため、消費者の心をつかむには、*3-1のように、マーケティングが重要であると同時に、食品に関する知識が多くマーケットで商品選択の主体になっている女性を活躍させることがKeyである。そもそも「道の駅」の原点は、自分で作った農産物をリヤカーに積んで道端で売っていた農家の主婦で、彼女たちが持ってきた新鮮で安価な農産物や行き届いたサービス・料理に関するアドバイスなどが消費者の人気を集めていたのだった。 そのため、*3-2のように、農漁業の経営が6次産業化を進める中、生産者であると同時に、生活者・消費者の視点を併せ持つ女性の役割が重要であることは明らかである。それにもかかわらず、農山漁村の女性の地位が低く、女性の社会参画促進や地位向上への啓発を今頃やっているのは、(何もしないよりはずっとよいが)遅すぎる。 そして、2017年3月5日の記事によると、JA女性役員、女性農業委員の割合は10%には届かず、①役員になり外出が増えると夫が嫌な顔をし ②男性役員ばかりの中で意見が通らず ③組織化されていない農業女子の集まりでさえ出掛けるのに家族の許可がいる のだそうだ。 日本農業新聞の2020年1月13日の記事では、*3-3のように、国連がジェンダー平等を含む持続可能な開発目標(SDGs)達成の担い手に協同組合を位置付け、JAグループが女性参画の数値目標を決めて女性参画を進展させた結果、2019年7月末時点で正組合員や役員比率の全てが前年を超し、女性正組合員比率が22.36%、女性総代が9.4%、全役員に占める女性割合は8.4%と増えたそうだ。しかし、役員どころか、女性正組合員比率も22.36%しかないのでは、日本の農村地帯におけるジェンダー平等はまだまだだと言わざるを得ない。 ・・参考資料・・ <台湾の民意と関係諸外国の対応> *1-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/575782/ (西日本新聞社説 2020/1/15) 台湾総統選 中国は危機感受け止めよ 中国とは距離を保ち、現在の自由で民主的な社会を守るという民意が明確に示された。台湾総統選(11日投開票)は中国との統一を拒否する与党民進党の現職蔡英文氏が過去最多得票で圧勝し、再選された。高い投票率も考え合わせると、半年以上に及ぶ香港の混乱を自国の将来と重ねた有権者の切実な危機感の表れと言えるだろう。蔡氏勝利の流れをつくったのは昨年1月の台湾政策に関する習近平中国国家主席の演説である。高度な自治を認める「一国二制度」による統一を迫った。当時、蔡氏は窮地に立たされていた。前年の統一地方選で年金制度改革など内政の混乱が響いて民進党が大敗し、党主席辞任に追い込まれ、総統再選も容易ではないとみられていた。習氏の演説以降、風向きは変わり、台湾で中国への警戒感が高まった。6月以降、香港で起こった大規模な反政府デモは「一国二制度」が形骸化している現実を国際社会に示し、それを目の当たりにした台湾では総統選の流れを決定的にした。「今日の香港は明日の台湾」と訴えた蔡氏の言葉が有権者の心をつかみ、総統選と同時に行われた立法委員(国会議員)選も民進党が過半数を維持した。中国にとっては民主派が圧勝した昨年の香港区議選に続く受け入れ難い結果だろう。だが、強権政治への拒否感が香港や台湾で広がっている現実を真剣に受け止めなければならない。台湾独立志向である民進党の蔡政権に対し、中国はけん制を強めてきた。台湾と国交を持つ国は中国の圧力で7カ国が断交し、今や15まで減った。総統選前には初の国産空母を台湾海峡で航行させた。こうした行為は台湾住民の反発を招くだけで、逆効果だったことは選挙結果から一目瞭然である。今後さらに台湾へ圧力をかけ続ければ、蔡政権を積極的に支援するトランプ米政権との対立も一段と深まりかねない。米国は昨年、インド太平洋戦略で「強力なパートナーシップ」を結ぶ相手と台湾を位置付け、戦闘機などの兵器売却を決めた。大国となった中国には、武力統一もちらつかせる強権的態度を慎み、香港や台湾の声に耳を傾ける懐の深さを示す-そうした振る舞いが求められる。蔡氏は、中国が主張する「一つの中国」を受け入れない一方で民進党が綱領で定める「独立」を封印してきた。中台間の緊張を不必要に高めない現実的な判断だろう。中台関係は東アジア情勢にも悪影響を及ぼしかねない。米中の覇権争いの最前線でもあり、難しいかじ取りを迫られるが、そうしたバランス感覚は持ち続けてほしい。 *1-2:https://www.sankei.com/world/news/200112/wor2001120024-n1.html (産経新聞 2020.1.12) トランプ政権 軍事・経済の両面で台湾支援へ トランプ米政権は台湾総統選での蔡英文氏の再選に関し、中国の脅威をにらんだ米台連携を円滑に継続できるとして歓迎する立場を明確に打ち出した。今後は、米国が世界における自国の「抑止力の源泉」と位置づける軍事と経済の両分野で、中国の覇権的な攻勢の最前線に立つ台湾を積極支援していく考えだ。ポンペオ国務長官は11日に発表した声明で、蔡氏について「(中国からの)容赦ない圧力にさらされる中、中台関係の安定維持に取り組んできたことを称賛する」と強調。さらに「台湾が蔡氏の下、自由、繁栄、国民のためのより良き道を希求する国々の輝かしい手本となり続けることを期待する」と表明した。米国では2018年、米高官の台湾訪問や定期的な武器売却を求める「アジア再保証イニシアチブ法」がトランプ大統領の署名で成立し、「自由で開かれたインド太平洋地域」の推進に向けた台湾支援が着実に進められてきた。中国問題に詳しい政策研究機関「戦略国際問題研究所」(CSIS)のボニー・グレイザー研究員は今後の中国の出方について「当面は米台の動向を見極め、台湾に圧力をかける機会を模索するだろう」と分析。近い将来に中台が武力衝突する可能性は否定しつつも、「米国は台湾の抑止力強化に向け一層の協力を図るべきだ」と訴えた。トランプ政権は一方で、台湾経済が中国への依存度を急速に強めていることに危機感を募らせている。議会や政府内部では、米国と台湾との経済関係の緊密化に向けた自由貿易協定(FTA)の締結を提唱する声が広がりつつある。政策研究機関「ヘリテージ財団」のライリー・ウォルターズ研究員は、米台がFTA交渉に向けた「高官級の経済対話」の枠組みを構築すべきだと指摘する。同財団のウォルター・ローマン氏も「トランプ政権が中国や日本などと貿易合意に達し、蔡氏が再選した今こそが米台FTAに向けた好機だ」と強調した。 *1-3:https://www.bbc.com/japanese/38204570 (BBC 2016年12月5日) 中国、トランプ氏と台湾総統の電話会談に抗議 ドナルド・トランプ米次期大統領が1979年以来の前例を破り、正式な外交関係のない台湾の蔡英文総統と電話会談したことについて、中国外交部は3日、「米国の関係各方面に厳正な申し入れをした」と明らかにした。中国国営メディアによると、外交部は米政府に「米中関係の大局が不要な妨害を受けることがないよう」、「1つの中国」政策を守り、台湾問題を「慎重に、適切に扱うよう」促したという。またこれに先立ち王毅外相は3日朝、台湾側による「つまらない策略だ」と台湾を批判した。トランプ氏と蔡総統は2日に電話会談。トランプ陣営側が台湾総統に電話をしたという情報もあるが、トランプ氏は2日、「大統領に当選しておめでとうと、台湾総統から電話してきた」とツイートした(強調原文ママ)。トランプ陣営によると、トランプ氏は蔡総統に今年1月の総統就任への祝辞を述べたと言う。米国は1979年に中国と国交を樹立し、台湾とは断交した。それ以来、大統領や次期大統領が台湾首脳と直接会話したことはないとされている。中国の反発を呼ぶ可能性についてメディアが報道すると、トランプ氏は「米国は台湾に何十億ドルもの兵器を売ってるのに、おめでとうの電話を受けちゃいけないって、興味深いな」とツイートした。ホワイトハウスは、トランプ氏と台湾総統との電話会談は、米外交政策の転換を意味するものではないと強調。米メディア報道によると、ホワイトハウスも電話会談の後に知らされたという。トランプ氏の報道担当は、次期大統領は米国の台湾政策について「よく承知している」と述べた。 ●何が問題なのか 国共内戦で毛沢東率いる中国共和党軍に敗れた中華民国と国民党は1949年、台湾に移動。中華民国は国連代表権を維持し、欧米諸国には唯一の中国政府と承認されていたが、1971年に国連総会が中華人民共和国を唯一の中国の正統な政府と承認。中華民国は国連を脱退した。米政府は1979年に台湾と断交し、中華人民共和国の「一国二制度」を支持した。しかし断交してもなお、台湾にとって米国は唯一の同盟相手で最大の友好国だ。米国の台湾関係法ではは、台湾防衛用のみに限り米国製兵器を提供すると約束し、台湾の安全などを脅かす武力行使などに対抗し得る防衛力を米政府が維持すると約束している。中国は台湾に向けて多数のミサイルを配備しており、もし台湾が公式に独立を宣言すれば武力行使も辞さないと言明している。今年1月に圧勝した蔡総統率いる民進党は、伝統的に台湾独立を綱領としており、蔡政権は「一国二制度」政策を受け入れていない。 <解説1> 懸念から危機感と怒りへ キャリー・グレイシーBBC中国編集長 台湾に関する米政府の40年近くにおよぶ慣例をトランプ氏が破り、台湾総統と直接会談したことは、中国政府関係者を驚嘆させた。11月8日の当選以来、中国政府はトランプ氏のアジア政策顧問が誰で、対中政策がどうなるのか理解しようと、躍起になっている。台湾総統との電話会談は、これまで懸念だったものを怒りに変質させるだろう。中国政府は台湾を一地方自治体とみなしている。独立主権国家としての形式を一切否定することが、中国外交政策の主要優先事項なのだ。 <解説2> 穏やかな反応 シンディ・スイBBC記者、台北 中国の反応は比較的穏やかだった。最初からいきなりトランプ氏とぎくしゃくしたくないからだ。加えて中国は、トランプ氏は政治家として経験不足だとみているので、今のところはとりたてて騒がず、見逃すつもりだ。米政府が、中国と台湾に関する政策に変化はないと表明したことも、中国にとってはある程度の安心材料だろう。しかし舞台裏では中国はほぼ間違いなく、このような外交失態を二度と起こさないよう、トランプ陣営を懸命に「教育」しているに違いない。蔡総統のこの動きを受けて、中国政府はいっそう蔡氏に対して怒り、不信感を抱き、中国からの正式独立を目指しているものとみなすだろう。 *1-4:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54333200S0A110C2FF8000/?n_cid=TRPN0017 (日経新聞 2020.1.12) 中国が日米英に不満表明 蔡氏への祝意に反発 中国外務省の耿爽副報道局長は12日、台湾の蔡英文(ツァイ・インウェン)総統の再選に日米英の高官らが歓迎の談話を出したことに「(中国大陸と台湾は一つの国に属するという)一つの中国の原則に反するやり方で、強烈な不満と断固とした反対を表明する」とのコメントを発表した。すでに各国へ抗議したという。耿氏は「台湾地区の選挙は中国の一地方のことだ」と指摘。「台湾問題は中国の核心的利益だ。中国と国交を結ぶ国と台湾とのいかなる形の政府間往来にも反対する」と強調した。 *1-5:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54327820R10C20A1EA2000/ (日経新聞 2020/1/11) 台湾、「中国離れ」加速 米中対立の火種に 統一を遠ざけるため距離を置くか、経済交流の果実を求めて接近するか――。中国との距離を巡る「自立と繁栄のジレンマ」と呼ばれる問題を巡り、台湾の民意は揺れ動いてきた。鴻海(ホンハイ)精密工業など台湾企業は1990年代から中国に進出し、連携を深めた。2001年の世界貿易機関(WTO)加盟で中国の経済成長に弾みがつくと、中台経済の一体化を求める声が強まり、08年には対中融和を掲げる国民党の馬英九政権が発足した。だが情勢は一変した。台湾の中央研究院による19年3月の世論調査では、対中関係で「国家安全を重視する」との回答が58%に上り、「経済利益を優先する」を27ポイントも上回った。呉介民・副研究員は「統一への危機感の高まりに加え、米中摩擦で対中接近が必ずしも利益に結びつかなくなった面もある」と分析する。対中強硬路線を鮮明にする蔡氏の再選で、台湾を巡る米中対立が激化するのも確実だ。米国は1979年に台湾と断交して中国と国交を樹立。その後は「台湾関係法」に基づき台湾の安全保障を支える一方、対中協調を重視して台湾独立を綱領に掲げる民進党と距離を置いてきた。だがトランプ米大統領は就任直前の16年12月に蔡氏と電話で直接やりとりし、19年にはF16戦闘機の台湾への売却を決めるなど、中国への配慮で封印されてきた「タブー」は次々と破られた。蔡政権は中国大陸と台湾が1つの国に属するという「一つの中国」原則を認めない一方、党が持つ独立志向を封印する立場をとる。「現実路線で米の信頼を得る戦略」(民進党幹部)だ。米国防総省は19年のインド太平洋戦略の報告書で、台湾をシンガポールなどと並ぶ「有能なパートナー」とした。蔡氏は「米国との関係は過去最高にある」と誇り、2期目では同戦略への協力や米との軍事接近を鮮明にする公算が大きい。中国にとって台湾は海洋進出の出入り口に位置し、東アジアへの米国の介入を防ぐ安保体制を築くうえでも譲れない「核心的利益」だ。米台の接近は中国の激しい反発を引き起こすのが必至だ。半導体受託生産最大手、台湾積体電路製造(TSMC)など次世代通信規格「5G」の核心技術を握る企業が存在する台湾は米中ハイテク摩擦の最前線にもなる。米国がハイテク分野で中国とのデカップリング(切り離し)を本格化すれば台湾を避けて通れず、供給網で深く関わる日本にも影響が及びかねない。 <女性に「控えめであること」を要求する文化> *2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191202&ng=DGKKZO52770090Z21C19A1TY5000 (日経新聞 2019.12.2) 男女の発信スタイルの違い 機会平等を担保しよう OECD東京センター所長 村上由美子 米ハーバード・ビジネススクールでは、成績上位5%の学生にベイカー・スカラーという最優秀賞を与える。MBA(経営学修士)を取得する女子学生は4割を超えたが、ベイカー・スカラーの女性比率は2割程度にとどまっていた。学力や潜在的能力など男性と同じ条件を満たして入学した女性達。入学後に苦戦したのは、クラスでのディスカッションだった。ハーバードでは成績の50%がディスカッションへの参加で決まる。積極的に高々と挙手し、ものおじせず発言する男性に比べ、女性の参加は控えめだった。この問題に気がついた大学側は、意識的に発言機会を男女平等にするよう教授陣を促した。その結果、ベイカー・スカラーの男女比率は改善。ついに昨年は男女間の成績の差異は完全に消滅した。男女のコミュニケーションや発信スタイルの違いに配慮することで、機会平等を担保するという興味深い例だ。私自身にも経験がある。ニューヨークの投資銀行で管理職に昇進した時だ。ボーナスシーズン前に自分の功績をアピールしにくる部下は全員男性だった。女性の部下が昇進やボーナスの交渉に来る事はめったになかった。私自身も新入社員時代「主張せずとも上司は私の成果を認めてくれている」と勝手に思い込んでいた。部下を評価する立場になって初めて、男性がいかに積極的に自己アピールしていたかに気づいたのだ。公平な評価・判断には、男女の違いを意識し、自らにインプットされる情報の偏りを精査する必要があると学んだ。日本でも女性を積極的に採用し、昇進を促進する企業は増えた。しかし彼女達の声は経営に生かされているだろうか。男女の違いを理解した上で、女性の持つ能力を開花させる取り組みが必要だ。効果的に会議に参加するためのコーチングを提供したり、司会役が女性に積極的に発言機会を与えたり、意識的に女性の背中を押し議論への参加を促すことが効果的だ。経済協力開発機構(OECD)の調査では、宿題にかける時間は女子学生の方が男子学生よりも長いという結果が出ている。女性は準備を周到に整える傾向があるが、自己肯定力は男性の方が往々にして高い。このような特性を理解した上で、女性の不得意部分を補う工夫を施せば、自らの能力を発揮し活躍する女性がさらに増えるはずだ。 *2-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/570293/ (西日本新聞 2019/12/22) 「ウィキペディア」にも男女格差 ネット事典、男性記事が8割占める ●是正目指す「ウィキギャップ」 インターネット上の百科事典「ウィキペディア」。何かを検索したら上位に出てくるおなじみのサイトだ。ただ、人物を紹介する記事の約8割は男性で、女性は実績があって著名でも記事が存在しないケースも多いという。そこで、ウィキペディアに女性の記事を増やし、ネット上の男女格差をなくそうというイベント「ウィキギャップ」が世界各地で開かれている。新たな試みが目指すゴールは、ネット上だけでなく、実社会における格差解消だ。2001年に登場したウィキペディアは、誰もが無料で自由に編集に参加できるのが特徴で、世界約300言語で展開されている。11月末、福岡市内のビルの一室で、女性を中心に15人ほどがパソコンに向き合い、作業に没頭していた。それぞれが詩人や経済学者など「載せるにふさわしい」と思う女性の業績や経歴を調べ、3時間ほどかけて執筆した。参加した司書の古島信子さん(50)はネットサーフィンという言葉を普及させたとされる司書「ジーン・アーマー・ポリー」について翻訳。「興味を持った人が彼女を知るツールの一つになればうれしい」。なぜ男性の記事が多いのか。「執筆者に男性が多いので、女性著名人や女性の関心が高い事柄は軽視されやすい」と指摘するのはウィキペディアに詳しい武蔵大の北村紗衣准教授(フェミニズム批評)。英王室キャサリン妃のウエディングドレスに関する記事やブラックホールの撮影に携わった女性科学者に関する記事が「百科事典として取り上げるに足らない話題」として“削除依頼”が出されたこともあるそうだ。運営するウィキメディア財団によると執筆者の9割が男性と推測される。北村准教授は「書く人の多様性がないと内容にも偏りが生じる。女性執筆者が増えることが女性記事の増加、百科事典の質の向上につながる」と力を込める。そもそも、現在「活躍する立場」の多くを男性が占めているのが現状で、男性の人物記事が多いのは当然という指摘も。特に日本は、先日発表された男女格差を指数化した報告書でも世界153カ国中、121位と低迷。女性議員(衆議院)や女性管理職の割合は1割程度にすぎない。政治分野の男女共同参画推進法や女性活躍推進法など法整備が進んでも、実態の改善には時間がかかりそうだ。一方で、ウィキペディアに女性の記事を増やす取り組みは、さまざまな立場の人が参加しやすい。北村准教授は「ネット上の男女格差解消の動きが、実社会に波及することも期待できる」と話す。 【ウィキギャップ】スウェーデン外務省などの呼びかけで「ネットの男女格差を埋めよう」と2017年に始まり、約60カ国で開催。30の言語で約3万2000本の記事が編集された。国内では東京や大阪でも開催され、今後も横浜などである予定。福岡のイベントは丸 *2-3:http://qbiz.jp/article/103068/1/ (西日本新聞 2017年2月5日) 女性リーダー育成 覚悟の大切さ学ぶ 福岡市で研修 企業など組織の担い手となる女性を育成する「女性トップリーダー育成研修」が2〜4日、福岡市で開かれた。福岡県内の企業役員や管理職などの女性20人が参加し、さらに飛躍するために必要なことを学んだ。研修は福岡女子大(同市東区)が初めて企画。2泊3日を共にして交流を深め、将来につながる人脈を築く狙いがあるという。国際基督教大の北城恪太郎理事長や地元経済界トップらがリーダーに欠かせない心構えや教養を伝授した。4日のグループワークでは、参加者が目指すリーダー像を議論。「周囲の意見を聞きすぎて、自分らしさを出せていない」「リスクを避けようとすると部下が育たずさじ加減が難しい」などと悩みを語り合い、自分の克服すべき弱点や強みをあぶり出した。参加した福岡空港ビルディング営業部次長の鰺坂裕子さん(49)は「意識して上を目指す覚悟が必要だと感じた。ここでできたネットワークは財産になると思う」と手応えを語った。参加者は3月の最終研修までに目指すリーダー像を固め、それを実現する行動計画を発表する。 <農業における女性の参画とリーダーシップ> *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p39945.html (日本農業新聞 2017年1月19日) 販売革新へ戦略を 人材育成で初講習会 全中・全農 JA全中とJA全農は18日、農畜産物のブランド化など販売戦略の企画・実践力を向上させるための講習会を東京都町田市で初開催した。JAや連合会の販売事業戦略担当職員らが、「販売革新」をテーマに少人数のグループ討議を展開。どんな戦略をとれば販売力アップが見込めるかを参加者が提案し合うスタイルで、消費者の心をつかむ方策について議論を掘り下げた。20日まで開く。担当者と経営側との間に立つ職員を対象とし、11人が参加した。2、3人のグループでの討議で、参加者のJAが抱える販売戦略の課題克服や、JA内の意識改革をどう進めるかなど販売革新の方向性を話し合った。JA高知市が展開する、野菜「芥藍菜(かいらんさい)」の認知度向上策に関して、試食や貯金・共済の粗品とすることで消費者の認知度を高めていくとの提案があった。新潟県JA新潟みらいのカレー専用米の販路拡大に向けては、他産地との差別化のため「米どころ新潟が本気で作った専用米」とPRしたり、既存の有名カレー商品とタイアップ販売したりしてみてはどうか、といった意見が参加者から示された。これに先立ち、農産物流通に詳しい流通経済研究所の南部哲宏特任研究員が講義。マーケティングの意義について、卸売市場だけでなく「実際に食べてくれる人たちの情報を集めて意味を見つけ、どういうことが求められるのかを発見することが大事」と強調した。JAグループは自己改革でマーケットイン(需要に応じた生産・販売)に基づく事業方式への転換を目指している。講習会は、抜本的な改革が求められる中、実需・消費者の潜在的なニーズを掘り起こし、新たな販売戦略を中心となって担う人材の育成を狙って企画した。2日目は課題解決に向けた販売事業戦略の提案書を作成するためグループ討議を実施し、最終日に発表する。 *3-2:https://www.agrinews.co.jp/p40297.html (日本農業新聞 2017年3月5日) 農山漁村女性の日 発展の鍵握る活躍期待 3月10日は「農山漁村女性の日」。この日を前後して、農山漁村女性の社会参画促進や地位向上へ、さまざまな啓発行事が行われる。女性は農業従事者の約半数を占め、農村社会と農業の発展に欠かせない存在だ。農業経営が6次産業化を進める中、生産者であり、かつ生活者と消費者の視点も併せ持つ女性の役割は、ますます重要さを増していくはずだ。その役割の価値を見つめ直すきっかけにしよう。農業経営やJAなどの方針決定の場へ、女性の参画が増えている。農水省の調査によると、女性の認定農業者は2016年3月で1万1241人と前年より429人増えた。12年から毎年400人以上増え続けている。JA女性役員は1305人(16年7月)で、全役員に占める割合は7.5%と前年比0.3ポイント増。女性農業委員も2636人(15年9月)で、全委員に占める割合は7.4%と同0.1ポイント増となった。農水省の「農業女子プロジェクト」も4年目を迎え、農業女子メンバーは、今では500人を超える。企業と提携して商品を開発したり、教育機関と組んで学生に就農を促したりと活動が盛んだ。ことし初めて、農業女子の取り組みを表彰するイベントを開いてPRを強める。ただ、社会参画への進み方は遅い。女性認定農業者が増えているとはいえ、全体の4.6%だ。JA女性役員、女性農業委員も、第4次男女共同参画基本計画で共に早期目標に掲げる10%には届かない。「役員になり外出が増えると、夫が嫌な顔をする」「男性役員ばかりの中で意見が通らない」。JA女性役員からは、そういった不満の声が上がる。一方、組織化せず活動の自由度が高く見える農業女子の集まりの中でさえ「出掛けるには家族の許可がいる」と悩む声を聞く。家族経営が主流で、かつ男性が中心となっている農村社会の閉鎖的な構図が、依然としてうかがえる。女性農業者が真に活躍し、能力を発揮するにはまだ厚い壁があるのだ。家族の後押しはもちろん、活動を受け止める男性らがさらに理解を深める必要がある。日本政策金融公庫が16年に発表した調査では、女性が経営に関与している経営体は、関与していない経営体よりも経常利益の増加率が2倍以上高かった。特に、女性が6次産業化や営業・販売を担当している経営体で、経常利益の増加率が高い傾向にあった。買い物好きでコミュニケーション能力が高い女性だからこそ、的確に消費者ニーズを把握できていることの表れだ。農業収益を増やし、経営発展の鍵を握るのは女性農業者だ。「農山漁村女性の日」が3月10日とされたのは、女性の三つの能力である知恵、技、経験をトータル(10)に発揮してほしい――との願いが込められている。もっと活躍できる社会へ、家族、地域挙げて環境整備を急ぐべきだ。 *3-3:https://www.agrinews.co.jp/p49717.html (日本農業新聞 2020年1月13日) 女性参画が進展 JA新目標着実に JAの運営で女性の参画が進んでいることが、JA全中の調査で分かった。正組合員と総代、役員(理事など)全ての女性参画割合が前年を上回った。国連は、ジェンダー平等を含む持続可能な開発目標(SDGs)の達成の担い手に協同組合を位置付けており、識者は「けん引する勢いで取り組んでほしい」とJAグループに期待する。 ●正組や役員率全て前年超す 19年7月末 JAグループは、2019年3月の第28回JA全国大会で、従来を上回る女性参画の数値目標を決めた。①正組合員30%以上②総代15%以上③理事など15%以上──を掲げた。第4次男女共同参画基本計画やJA全国女性組織協議会の独自目標を踏まえた。19年7月末現在の女性正組合員比率は、22・36%と前年から0・49ポイント上昇。総代は9・4%と同0・4ポイント増えた。全役員に占める女性の割合は8・4%で同0・4ポイント増だった。女性役員総数は同9人減の1366人。JAの大規模合併で、役員総数が847人減の1万6260人と大幅に減った影響とみられる。一方、100JAで女性役員がゼロだった。全中は「女性参画の推進には、JA経営トップ層の理解が欠かせない。トップ層が集まる会議で必要性や意義を伝え、理解を求めていきたい」としている。 ●SDGsけん引を △協同組合や農村女性の活躍に詳しい奈良女子大学の青木美紗講師の話 SDGsの視点で見ると、数値を引き上げ、高い目標を持つことは大切だ。協同組合は、SDGsの推進で大切な事業や活動をしている。JAが、けん引する勢いで取り組んでほしい。一方、数値目標が独り歩きしないようにすべきだ。女性参画のメリットは、女性目線の事業提案ができること。女性組合員や生活者の視点に立った提案の実行でJA事業の拡大も期待できる。女性の意見に耳を傾け、否定しないことが重要だ。家事や育児などを行うことの多い女性が、参加しやすい環境を整えることも大事。女性参画が進めば、性別や立場を問わずさまざまな人がJAの経営や事業に参画しやすくなるはずだ。 <EU委員長の意思決定と日本の政治・行政> PS(2020年1月17日追加):*4-1のように、EUは、域内での温室効果ガスの排出を2050年に実質0にする目標達成に向けて、経済・社会構造を転換していくために、低炭素社会への移行を支える技術革新への投資を今後10年間で少なくとも約122兆円行い、これによって再エネへの転換を図って経済成長に繋げるそうだ。これは覚悟のいる大胆な判断で、かつ科学的・合理的な判断でもあり、フォンデアライエン欧州委員長も女性だ。 一方、私が提案して(私がこう言うと、必ず嘘だと決めつける人がいるが)太陽光発電・EV・自動運転車を世界で最初に市場投入した日本は、*4-3のように、原発と石炭を“ベースロード電源”に指定したり、送電網のコストを太陽光企業にツケ回したりするなど、再エネやEVの普及を妨害するための経産省の後ろ向きの対応にことかかない。そして、こういうことが続けば、日本に豊富な再エネの利用が阻害され、日本国民を豊かにすることはできない。 このような中、*4-2のように、農業では無人田植え機の電動版もできたそうで、これなら日本だけでなく世界でニーズがあると思われるが、メーカー希望小売価格が1468万1700円では高すぎて国内でもなかなか普及できず、世界で普及するのは中国製をはじめとする他国製になるだろう。これが、名目インフレ(名目物価上昇)の悪弊の一つなのである。 このように、日本では殆ど男性の“(同じ仕事を続けてきた国内志向で視野の狭い)ベテラン”と言われる政治家・行政官が政治・行政を担当してきた結果、*4-4のように、税収が伸び悩んで2025年の「基礎的財政収支」は国・地方あわせて3兆6千億円の赤字になるのだそうだ。そして、その原因に必ず世界経済の減速というような外的要因を挙げるが、景気対策と呼ぶ無駄遣いが多く、根本的解決になる投資をしないのが本当の原因であるため、これまでどおりではいけないということだ。 *4-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202001/CK2020011502000274.html (東京新聞 2020年1月15日) 温室ガスゼロへ122兆円投資 EU、技術革新へ今後10年で 欧州連合(EU)欧州委員会は十四日、EU域内で温室効果ガス排出を二〇五〇年に実質ゼロにする目標の達成に向けて経済・社会構造を転換していくため、今後十年で少なくとも一兆ユーロ(約百二十二兆円)を投資する計画を発表した。低炭素社会移行を支える技術革新への投資を通じて経済成長を図る一方、石炭発電の比率が高い東欧などに対し、再生可能エネルギーへの転換を支援する構え。投資計画は、フォンデアライエン欧州委員長の総合環境政策「欧州グリーンディール」の資金面の裏付けとなる。一兆ユーロの約半分はEU予算で賄い、残りは加盟国や公的機関、民間などが拠出する。投資計画はEU欧州議会と加盟国の承認が必要。フォンデアライエン氏は十四日、フランス・ストラスブールで開かれた欧州議会本会議で「行動し損ねた場合のコストは巨大なものになる。今、投資するしか選択肢がないのだ」と訴え、巨額の出資に理解を求めた。「欧州グリーンディール」は先月就任したフォンデアライエン氏の看板政策。欧州委は現在策定中の二一~二七年のEU中期予算の25%を気候変動対策に充てる方針を既に示すなど、気候変動対策を急いでいる。フォンデアライエン氏は「われわれを待ち受ける(経済・社会の)転換は前例がない」と強調。構造転換の波に激しく揺さぶられる「人々や地域を支援」しつつ、「グリーン経済の投資の波を起こす」と訴えた。石炭への依存度が特に高いポーランドは、低炭素社会移行に莫大(ばくだい)な費用がかかるとして、昨年十二月のEU首脳会議で「五〇年に排出ゼロ」のEU目標への合意を留保するなど、資金調達が重要な問題となっている。 *4-2:https://www.agrinews.co.jp/p49749.html (日本農業新聞 2020年1月16日) 業界初 無人田植え機 電動コンセプトも クボタ展示会 農機メーカーのクボタは15日、京都市内で製品展示見学会を開き、基地局の設置が必要ない自動運転トラクターや、業界で初となる無人運転田植え機を発表した。同社は、トラクターと田植え機、コンバインで自動運転農機をそろえることになる。無人運転の電動トラクターなどコンセプト農機、創立130周年記念の特別モデルも展示。スマート農業の普及につながる製品を充実させた形だ。新しく発表した「アグリロボトラクタMR1000A」は、単独で自動運転ができる機種だ。従来の無人トラクターは自動運転の際、近くに移動基地局の設置が必要で、農家にとって負担になっていた。新製品は、国の電子基準点情報を利用することで、基地局を設けなくてもよい初めての機種となった。今月中に発売。メーカー希望小売価格は1468万1700円とした。会場ではトラクターと田植え機、コンバインで、自動運転のラインアップをそろえたことをアピールした。10月に発売する「アグリロボ田植機NW8SA」は、業界初の無人運転田植え機だ。有人自動運転ができる自脱型コンバイン「アグリロボDR6130A」は昨年12月に発売した。新型機械「X(クロス)トラクター」のコンセプト機も披露した。完全無人運転の電動トラクターで、4輪クローラーで動く。車高を変える機能を備え、水田でも畑でも使えるのが特徴だ。有人運転の電動機は2023年の発売を目指す。同社は20年に創立130周年を迎えることから、会場には記念特別モデルも展示した。オレンジメタリックの特装色で、田植え機や耕運機などを用意した。この他、衛星利用測位システム(GPS)直進アシスト機能付きトラクターなどの試乗も行った。展示見学会は16日まで。2日間で代理店の担当者ら5000人の来場を見込む。 *4-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200117&ng=DGKKZO54478640W0A110C2EA1000 (日経新聞 2020.1.17) 送電網コスト、誰が負担? 太陽光企業にツケ回し案、国「後出し」非難受け修正も 再生可能エネルギーの普及に向け、費用負担のルールを決める議論が紛糾している。焦点は送配電網の維持費用を誰が負担するか。普及させるには国民負担をできるだけ減らす必要があるが、新たなコスト負担を強いられる見込みが濃厚な再エネ事業者側からは、海外勢を含めて「後出しじゃんけん」との非難が噴出。今年度内の着地に向け、大詰めを迎えている。もめているのは、政府が2023年度に導入見込みの「発電側基本料金」制度の詳細だ。これまで電力の小売事業者が託送料金で負担していた送配電設備費用を発電事業者にも分担させる。負担の公平性の確保や電力システム全体のコスト低減につなげるのが狙いだ。23年度の制度導入を目指すことは19年9月の経済産業相直属の専門会合で決まっていた。ただFIT(再生可能エネルギー固定価格買い取り制度)の発電事業者については、追加コストと同水準を補填して調整する措置(調整措置)を置くことを検討することになっていた。FIT事業者が販売価格への転嫁ができないことに配慮した。ところが、前後して「利潤配慮期間」と呼ばれる12年7月~15年6月に認定された電源については、買い取り価格自体が高額に設定されていることを理由に、調整措置の対象外という案が19年夏に浮上した。これに驚いたのが、この期間に高額な買い取り価格を当て込んで日本の太陽光発電事業に参入した発電事業者らだ。 ●10年間で6000億円 太陽光発電を手掛けるオリックスの関係者は「こんなひどい後出しじゃんけんは見たことがない。当社の株主は外国人投資家も多い。日本の再エネ制度への信頼を損なう制度変更だ」と憤る。発電事業者らの試算によると、該当する期間の電源で稼働済みの全案件を対象にすると、23年度以降の10年間で計約6千億円の課金につながるという。カナディアン・ソーラー・アセットマネジメントの中村哲也社長は「予定していた利益を遡及的に奪う制度変更で納得できない。将来の投資も難しくなる」と話す。事業者からは、このまま利潤配慮期間に何の調整措置も講じられない場合、日本も加盟するエネルギー憲章条約に基づき「投資家に対する公正待遇義務に違反する」として、国との仲裁を求める訴えを起こすとの発言も飛び出す。再エネ制度の変更をめぐるトラブルが起きているのは日本だけではない。スペイン政府は10年に制度変更を行い、海外の発電事業者らから30件以上の仲裁を申し立てられた。資源エネルギー庁は「スペインの例は買い取り価格自体を引き下げるなど、より直接的な制度の不利益変更だった。日本のようにコストが上昇して間接的に利益が減ることまで条約違反といえるかは疑問」と反論する。国は高まる事業者らの不満を収めるため、19年12月17日の専門会合で新たな制度案を示した。発電側の課金によって負担が減る小売事業者と、FITの発電事業者が交渉して新たな取引価格を決める内容だ。小売り側が取引価格に一定程度を補填することを見越した案だ。 ●普及へ透明性を 結局、負担をグルグル付け替えているだけで、誰が何を負担しているのか理解しにくい構図になっている。新提案への発電事業者の反応は「少しでも補填してもらえるならありがたい」というものから「交渉力が劣る事業者が損をするのでは解決にならない」など温度差がある。1月以降も制度設計を巡る議論が続く見通しだが、結論が出るかどうかは微妙だ。再エネを普及させるために政府が当初高い収益モデルを示し、国内外から投資を呼び込む手法は欧州など海外政府も活用している。ただその後、持続可能性の観点から参入事業者に不利な制度に変え、事業者が不信感を抱く事態が繰り返されれば、再生エネの普及自体が遠のく。必要な負担をどう配分するのか。丁寧な説明も含めて、透明性の高い制度設計が欠かせない。 *4-4:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020011701001236.html (東京新聞 2020年1月17日) 25年度の赤字額は3・6兆円に 基礎的財政収支、税収伸び悩み 政府は17日、経済財政諮問会議を開き、中長期財政試算を示した。重要指標の「基礎的財政収支」は、高い成長率が続く楽観的な想定でも、黒字化を目指す2025年度に国・地方の合計で3兆6千億円の赤字になる。世界経済の減速で税収が伸び悩み、赤字額は昨年7月試算の2兆3千億円から拡大。目標達成に向け、一段の歳出抑制と歳入増加策が必要となる。GDP成長率は、昨年12月に決定した経済対策の効果などで、23年度に実質で2%、名目で3%台の高成長を実現すると想定した。この場合、基礎的収支は前回試算と同じ27年度に黒字化するが、黒字額は1兆6千億円から3千億円に縮小した。 <農林中金は職員を地方に多く置くべき> PS(2020年1月18日追加):農林中金は、*5-1のように、①2022年にも本店を有楽町から大手町に移転する ②都内の複数の事務所を集約して効率化に繋げる ③賃料等で年間約20億円のコスト削減をする ④ペーパーレス化等で職員1人当たりのスペースを半減させる ⑤JAグループ一体となって効率的で働きがいのある職場づくりを目指す としているが、農林中金の役割は、農協が地方の農業者から集めた預金を農業の発展のために使うことであり、都市銀行と同様に外国で散財することではない。そのため、地方の農協に支店を置いて優秀な人材を配置し、農業地帯を歩いて実情を知った上で、農業の発展のためにできることを企画すべきだ。 従って、①②はよいと思うが、農林中金本社に約1200人もの職員を置いておく必要はなく、本社は300人くらいにして残りは地方に配置し、農村地帯で経験を積ませるのがよいだろう。何故なら、そうすれば農業現場のニーズを知ってスキームを作ることができ、③の賃料も格段に安くなる上、地方に人材が供給されるからである。ただし、人の能力が結果を左右するため、優秀な人材を採用する必要があり、そのためには④のように職員1人当たりのスペースを半減させるのではなく、外資系並みのゆとりある快適なオフィスを作って、⑤を達成させるべきである。 なお、現在は、*5-2のように、政府が技術革新でCO2を削減するために、今後10年間で官民あわせて30兆円を研究開発に投資し、2050年までに世界で予想される排出量以上の年600億トン以上を削減する目標を掲げているが、ここで重要な役割を果たすのは、地方にある再エネ資源と農林漁業なのだ。 さらに、*5-3のように、台湾の鴻海がFCAと中国でのEVの合弁会社設立に向けて交渉する時代となり、再エネ・EV・自動運転は農林漁業や地方で大きな役割を果たすのである。 *5-1:https://www.agrinews.co.jp/p49765.html (日本農業新聞 2020年1月18日) 農林中金本店移転へ 東京・大手町に 事務所集約し効率化 農林中央金庫が本店を東京・有楽町から大手町に移転する方向で検討していることが17日、分かった。都内にある複数の事務所を集約し、効率化につなげる。賃料などで、年間約20億円のコスト減を見込む。年度内をめどに移転を巡る方針を正式決定。2022年にも移転する。農林中金は1923年に創立し、当初は日本橋に本店があった。1933年に現在の場所にあった「農林中央金庫有楽町ビル」に移った。93年に第一生命ビルと一体化し、現在の「DNタワー21」となった。農林中金は土地の約4分の1、建物の3分の1強を所有している。現在のビルには農林中金の職員約1200人が勤めており、同ビル近くや豊洲、大手町のJAビルにも本店機能を持つ事務所がある。どこまで集約するかは調整中だが、これらを集約し移転することで、賃料をはじめとした運営コストの削減につなげる。移転先は、JA全中やJA全農が入るJAビル近隣のビルで調整。複数フロアを購入する方向だ。22年から1年程度で段階的に移転をしていく。厳しい事業環境を受けて、JAが経営基盤強化に取り組む中で、農林中金としても効率化を進める。ペーパーレス化などを通じて、新たなビルではこれまでに比べて、職員1人当たりのスペースを半減させることを目指す。JAビルの近くとすることで、JAグループ内の連携強化にもつなげる。農林中金は「関係者と調整中だが、本店機能集約は検討している。創立100周年に向けて、JAグループ一体となり、効率的で働きやすく、働きがいのある職場づくりを目指したい」として、移転を働き方改革にもつなげる考えだ。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200118&ng=DGKKZO54509560X10C20A1EA3000 (日経新聞 2020.1.18) 技術革新でCO2削減 政府新戦略、10年で官民30兆円投資 政府は技術革新で世界の二酸化炭素(CO2)排出削減をめざす新戦略をまとめた。CO2吸収素材を活用したセメントの普及など日本が得意とする先端技術の研究を加速し、今後10年間で官民あわせて30兆円を研究開発に投資する。2050年までに世界で予想される排出量を上回る年600億トン以上を削減する目標を掲げた。政府が21日に開く統合イノベーション戦略推進会議で、革新的環境イノベーション戦略として決定する。政府は地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」実現のため19年6月に長期戦略を閣議決定した。今回の戦略はこれを補完し、日本が強みを持つエネルギー・環境分野の施策を打ち出し、世界のCO2削減を先導する役割を強調する。各国の研究機関をつなぐ拠点となるゼロエミッション国際共同研究センターを立ち上げる。ノーベル化学賞を受賞した旭化成の吉野彰名誉フェローが研究センター長に就く。吉野氏は17日、安倍晋三首相と面会し「地球環境問題は人類共通の課題。高い目標があるほど研究者は一生懸命頑張る」と述べた。内閣府などによると、世界全体では毎年500億トン規模のCO2が排出され、30年には570億トンになる見込みだ。600億トン以上削減できる技術の達成をめざす。 *5-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200118&ng=DGKKZO54539960X10C20A1FFN000 (日経新聞 2020.1.18) FCA、EVで巻き返し、鴻海と「空白地」中国攻略へ 欧米自動車大手フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)は17日、台湾の電子機器の受託製造サービス(EMS)世界最大手、鴻海(ホンハイ)精密工業と中国での電気自動車(EV)の合弁会社設立に向け交渉していると発表した。FCAにとって中国とEVはほぼ「空白地」。自動車生産のノウハウが薄い鴻海と組む異例の戦略で巻き返しを図る。鴻海側は16日に合弁を設立する方針だと発表。FCAの17日の声明では、「最終的な合意に至るとは限らない」との注記をつけたうえで、2~3カ月以内に拘束力のある合意を目指すとした。FCAによると折半出資で次世代のEVと「つながるクルマ」を開発・生産する新会社も設立を目指す。鴻海は同社からの直接出資は4割を超えないとし、残りは関連会社などを通じた出資になる見通しだ。FCAの自動車生産のノウハウと、鴻海のスマートフォンなどデジタル機器製造のノウハウを融合し、つながるEVの生産を目指す。EVなどの次世代車の生産を巡り、自動運転技術開発の米ウェイモと自動車部品大手のマグナ・インターナショナル(カナダ)が組んだり、中国新興EV大手の上海蔚来汽車(NIO)が中堅自動車メーカーの安徽江淮汽車集団(JAC)に生産委託をするなどの動きが出ている。ソフトに強みを持つ新興企業と伝統的な自動車産業のプレーヤーが組む動きが多く、大手自動車メーカーとEMSという今回の組み合わせは異例だ。鴻海は中国の配車サービス最大手、滴滴出行に出資、FCAはウェイモと協業しており、今後こうした新興企業が合弁に合流する可能性も注目される。FCAは2019年12月に仏グループPSAと対等合併で合意、規模を生かしてEVを強化する方針を示していた。ただ両社にとって中国を含むアジアは空白地だ。調査会社のLMCオートモーティブによると、両社を合わせてもアジア全体の販売台数は約50万台(18年)でシェアは約1%にとどまる。中国のEV市場は足元では停滞しているが、長期的には成長が見込まれる。FCAは中国では広州汽車集団と自動車合弁を組んでいるが、広州汽車はトヨタ自動車やホンダとも広くEVを生産している。FCAとPSAの統合が完了すれば、鴻海との合弁を軸に、PSAが欧州で培ったEVのノウハウもつぎ込みながら、巨大市場を開拓する考えとみられる。 <女性議員や閣僚も標的になりやすいこと> PS(2020.1.20追加):「選挙が汚れて国会議員の質は悪い」というイメージ操作が頻繁に行われ、今回は女性である河井案里氏が、昨夏の参院選で違法な報酬を支払ったと運動員が証言したと話題になっている。しかし、*6-1に書かれている「①2019年夏の参院選でウグイス嬢に法定金額を上回る、3万円の日当を支払った」「②ビラ配り、のぼりを持ったり、手を振ったりなど、選挙事務所や現場で選挙運動に直接かかわったAさんに11日で15万5千円の報酬を支払った」「③時給1000円くらいで上限は日当15000円までになると言われた」「④最初から報酬を約束されていた」「⑤数十万円の報酬を受け取った運動員が地元紙で報じられている」「⑥公職選挙法で認められていない運動員に報酬を支払った容疑」を、*6-2の現在の公職選挙法に照らして見ると、選挙運動員には報酬を支給することはできないが、うぐいす嬢には1日 1 人につき15,000円以内(超過勤務手当は支給できない)を支給することができ、労務者(人数制限はない)にも1日 1 人につき15,000円以内(10,000円+超過勤務手当はの上限5,000 円を支給することができる。そのため、①については、ウグイス嬢が手振りやビラ配りなどの単純労働も行っていれば(ウグイス嬢は、ふつう雑用も行い、地元の人とは限らないため買収しても仕方なく、こういう少額では買収されないだろう)市場価格と言われる3万円の日当を払っても法令違反とは言えないだろう。また、Aさんは単純労働しかしていないため、②③④は公職選挙法違反ではない。さらに、⑤⑥は、事実なら違法だが、検察はこの点は指摘していない。 つまり、女性である河井案里氏を標的にして「国会議員は金で汚れている」というイメージを作っているが、現在は収支報告書で収支を報告し、監査も受けているため、昔のようなビッグな金の動きはないのである。 *6-1:https://dot.asahi.com/wa/2020011500092.html?page=1 (週刊朝日 2020.1.15) 河井案里参院議員が違法報酬も 昨夏の参院選で運動員が証言 2019年夏の参院選で、車上運動員(ウグイス嬢)に法定金額を上回る、3万円の日当を支払ったとして刑事告発されている、河井案里参院議員。広島地検は15日、河井議員と夫で前法相の克行衆院議員の事務所を強制捜索した。さらに案里議員にはウグイス嬢への「日当疑惑」だけではなく、選挙運動した男性、Aさんにも15万5千円の報酬を支払っていたことが本誌の調べでわかった。公職選挙法では、ウグイス嬢や、選挙運動に直接関わらない事務スタッフに限り報酬の支払いが認められる。Aさんは選挙運動に直接かかわり、報酬をもらっていた。ウグイス嬢と同様に、その支払いは買収になる可能性がある。Aさんによれば、参院選の少し前に、案里議員の知り合いから選挙を手伝ってくれないかと話があったという。「4月の統一地方選で広島の地方議員さんの事務所に出入りしていたことがあった。その関係で声がかかりました」。予定が空いていたAさんは承諾。当時をこう証言する。「時給1000円くらいで、上限は日当で15000円までになるけど、いいかと聞かれました。週刊文春でも名前が出ていた、Tという秘書からでした」。ビラ配り、のぼりを持ったり、手を振ったり、選挙事務所や現場で直接、選挙運動に加わった。7月6日から選挙が終わるまで合計11日間、手伝ったという。その後、T秘書から「時間がある時に、寄ってほしい」と言われて、指定された広島市安佐南区にある案里議員の夫、克行衆院議員の政治資金管理団体「河井克行を育てる会」の事務所(広島市安佐南区安東)を訪れたのは、7月31日だった。「T秘書から封筒に入った現金112500円を渡されました。そして『残りは振り込みます』と言われました。スマートフォンで銀行口座をチェックしたところ、同じ日に43000円が案里議員の自民党広島県参議院選挙区第7支部から振り込まれていた。合計で155000円をもらったことになります」。Aさんは本誌にこう証言し、スマートフォンで銀行の取引履歴を見せてくれた。そこには<20190731 43000円 ジユウミンシュトウヒロシマケンサンギインセンキョクダイナナシブ>と記されていた。自民党広島県参議院選挙区第7支部は案里議員が支部長を務めている。「口座番号は選挙期間中に聞かれたのでメモして渡したように記憶しています。最初から報酬を約束されていましたから」(Aさん)。また、案里議員の選挙を手伝っていたBさんも報酬を打診されたという。「案里議員の選対責任者から、30万円でと言われた。断ると50万円でどうかと言われた。内容からして、公選法に引っかかるかもと辞退した。私以外にも、複数の人が報酬をもらっていると聞いた」(Bさん)。すでに、数十万円の報酬を受け取った運動員が地元紙で報じられている。「ウグイス嬢への法定で決められた金額以上の日当を払っていたという疑いや、公職選挙法で認められていない運動員に報酬を支払った容疑も浮上している。運動員への報酬は支払いがあるだけでアウトだ。そちらも捜査を進めている」(捜査関係者)。Aさんはこう言う。「公選法で受け取ることができない金とは知らなかった。取材を受けて認識しました。何か対応を考えたいと思っています」。案里議員の事務所は取材に対し、こう回答した。「刑事事件の進捗や捜査への支障の有無などを勘案し、適切な時期に皆様に説明致したい」 *6-2:https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/senkyo/senkyokanriiinkai/oshirase/20181106.files/senkyoundouhiyou.pdf#search=%27%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%AE%E5%A0%B1%E9%85%AC%E4%B8%8A%E9%99%90%27 (「選挙運動費用の制限と届出」より抜粋) 報酬及び実費弁償の支給 <選挙運動従事者、労務者に支給することができる報酬> ①選挙運動員 支給できない ②選挙運動のために使用する車上運動員 1日 1 人につき15,000円以内 (いわゆるうぐいす嬢 等) (超過勤務手当は支給できない) ③専ら手話通訳のために使用する者 1日 1 人につき15,000円以内 (超過勤務手当は支給できない) ④専ら要約筆記のために使用する者 1日 1 人につき15,000円以内 (超過勤務手当は支給できない) ⑤労務者(人数制限はない) 1日 1 人につき10,000円以内 (超過勤務手当は10,000 円の 5 割以内) <女性がリードした環境政策とエネルギー変換> PS(2020.1.21追加):太陽光発電・分散発電・電気自動車は、1995年前後に私がインドに行った時、人口の多いインドで自動車が普及し始めたのを見て「化石燃料では必ず行き詰る」と考え、日本の経産省に提案したものだ。しかし、これを「私が最初に提唱した」と言うと、必ず「嘘だ。謙虚でない。そんなことは誰でもできるのに傲慢な思い込みだ」などと言われた。その後、誰でもできるのならさっさと他の人がやればよいのに、日本は大したこともせずにくだらない妨害行為を行い、ドイツのメルケル首相やヨーロッパ諸国、中国などが先に採用して、日本はまたまた外国に追随するという情けない結果となった。 世界では、*7-1のように、ドイツで再エネによる分散発電が進みつつあり、日本では、*7-2・*7-3のように、広島高裁が伊方原発3号機の運転を認めない仮処分決定をしたところだ。原発に絶対安全はなく、事故が起これば広い地域を壊滅させる猛烈な公害を引き起こし、伊方原発は中央構造線の上にあるのに災害想定が甘すぎる上、原発を海水で冷却することによって海に大量の熱を捨てて海水温度を上げているのだが、四国電力は、まだ「極めて遺憾で、到底承服できない」として不服申し立てをしようとしている。さらに、経産省は依然として原発を重要なベースロード電源と位置付け、2030年度の電源構成に占める割合を20~22%に引き上げる計画で、脱原発を求める国民世論と大きな乖離があるのだ。そのため、安全対策の拡充で発電コストが上がり、核燃サイクル計画も破綻し、日本が世界有数の火山国で地震も極めて多いことを考えれば、今国会で速やかにエネルギー政策を考え直すべきである。 そして、後輩の皆さん、*7-4のように、佐賀県立唐津東高校の校歌は下村湖人作詞で、大きな志や開拓者精神、希望を歌に込めた素晴らしいものだが、私はこれを歌っていた生徒の頃には、「われらの理想は祖国の理想、 祖国の理想は世界の理想」というのはどうやって実現するのか、全くわからなかった。しかし、本物の理想を追求すれば、祖国がついてきたり、祖国がすぐについてこなくても世界で採用されて祖国が後から追随してきたりすることもあり、こういうことも可能だったのだ。そして、ここに表現されている自然も護らないと・・。    2020.1.18毎日新聞 2020.1.17 2017.12.14朝日新聞 2019.9.12東京新聞 中日新聞 (図の説明:左から1番目と2番目の図のように、広島高裁が伊方原発3号機の運転を認めない仮処分決定をした。右から2番目の図のように、阿蘇山から160km以内にある原発は、このほかに玄海原発と川内原発がある。また、1番右の図のように、福島第一原発事故では、広い範囲が放射性物質で汚染され、成長中で細胞分裂の激しい若い人が特に帰還できない状況だ) *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200121&ng=DGKKZO54622930Q0A120C2MM8000 (日経新聞 2020.1.21) エネルギーバトル 電力、代わる主役(上) 技術が変える供給網、大手介さず個人で融通 電力の主役が電力会社から個人や新興企業に移ろうとしている。自然エネルギーを使った発電技術とIT(情報技術)が急速に発展し、個人間や地域内で電力を自在にやりとりできるようになったためだ。電力会社が大型発電所でつくった電気を自社の送電網で送るという当たり前だった景色が変わりつつある。「不便を感じずに環境に貢献できてうれしい」。独南部に住むエンジニアのトーマス・フリューガーさんは、独ゾネンの蓄電池を使った電力サービスをこう評価する。2010年創業の同社は契約者間で電力を融通し合う仕組みを実用化。顧客は欧州で5万人いる。 ●月額料金はゼロ 蓄電池とソーラーパネルを家庭に取り付ける初期費用に平均200万円かかるが、月に約20ユーロ(2400円)支払うフリューガーさんは年間の電気代が6分の1程度になった。今は月額料金ゼロが標準プランだ。電気は需要と供給が一致しないと停電が起きる。日本の電力会社は多くの発電所を抱え、その稼働率の変化で供給量を調整して対応する役割を担ってきたが、ゾネンはそれを崩す。強みは人工知能(AI)に基づくアルゴリズムによる調整だ。電気が余分なところから足りないところへ、安くつくれる場所から市場で高く売れる場所へと自動で判断する。利用者は自ら気づかない間に電気を融通し合い、家庭で必要な分をまかなう。クリストフ・オスターマン最高経営責任者(CEO)は「旧来の電力会社のモデルは時代遅れだ。巨大な発電所が国全体に電力を供給するモデルは機能しなくなる」と話す。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は蓄電池の価格が30年までに16年の約4割に下がるとみる。中国企業の増産を背景に、さらに下がると指摘する関係者もおり、ゾネンのような活用は広がりそうだ。 ●巨額投資不要に 国際エネルギー機関(IEA)によると、新興国の経済成長を背景に電力需要は40年に17年の1.5倍に増える。その4割を太陽光などの再生エネが占める見込みで、発電の主役も石炭から交代する。大型の石炭火力や原子力発電所の発電能力は約100万キロワット。国内の家庭の電力消費量は1カ月250~260キロワット時で、家庭用太陽光の月間発電量は300キロワット時超が多いとされる。蓄電池でためたり、地域で融通できたりすればマネジメントは可能だ。大型発電所や、それをつなぐ長い送電網を巨額の投資で作らなくても、電力ビジネスを展開できるようになる。国内で地域ごとに独占権を持つ電力会社が「発電・送配電・小売り」の事業をまとめて手掛けるようになったのは1951年。再生エネやテクノロジーの進化が、70年の慣行を変える。電力自由化で先行した欧州では電気をつくる会社、送る会社、売る会社など、機能ごとの再編が進んだ。既に英独では石炭などの化石燃料よりも再生エネの発電量が上回る月もある。電力大手は石炭やガス、原子力などの大型発電所の効率をどう高めるかにばかり力を入れてきた。ただ、競争のルールそのものが大きくかわり、エネルギー産業は転換期を迎えている。 *7-2:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1059877.html (琉球新報社説 2020年1月20日) 伊方差し止め 原発ゼロへ転換すべきだ 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁が運転を認めない仮処分決定をした。伊方3号機の運転を禁じる司法判断は、2017年の広島高裁仮処分決定以来2回目だ。再び出た差し止め決定を業界や政府は重く受け止めるべきである。今回主な争点となったのは、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)や、約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクに関する四国電や原子力規制委員会の評価の妥当性だった。地震に対する安全性について四国電は、伊方原発がある佐田岬半島北岸部に活断層は存在せず、活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価は必要ないと主張していた。だが高裁は「敷地2キロ以内にある中央構造線自体が横ずれ断層である可能性は否定できない」ことを根拠に挙げ、「四国電は十分な調査をしないまま安全性審査を申請し、規制委も問題ないと判断したが、その過程は過誤ないし欠落があった」と指摘した。火山の危険性を巡っては、最初の禁止判断となった17年の仮処分決定は阿蘇カルデラの破局的噴火による火砕流到達の可能性に言及したが、その後の原発訴訟などでリスクを否定する判断が続いた。だが今回は「破局的噴火に至らない程度の噴火も考慮すべきだ」として、その場合でも噴出量は四国電想定の3~5倍に上り、降下火砕物などの想定が過小だと指摘した。それを前提とした規制委の判断も不合理だと結論付けた。東京電力福島第1原発事故で得られた教訓は「安全に絶対はない」という大原則だ。最優先されるべきは住民の安全であり、災害想定の甘さを批判した今回の決定は当然である。四国電は「極めて遺憾で、到底承服できない」と反発し、不服申し立てをする方針を示した。政府も原発の再稼働方針は変わらないとしている。だがむしろ原発ありきの姿勢を改める契機とすべきだ。共同通信の集計によると原発の再稼働や維持、廃炉に関わる費用の総額は全国で約13兆5千億円に上る。費用はさらに膨らみ、最終的には国民負担となる見通しだ。原発の価格競争力は既に失われている。電力会社には訴訟などの経営リスクも小さくない。一方、関西電力役員らの金品受領問題では原発立地地域に不明瞭な資金が流れ込んでいる実態が浮かび上がった。原発マネーの流れにも疑念の目が向けられている。政府は依然、原発を重要なベースロード電源と位置付け、2030年度に電源構成に占める割合を20~22%に引き上げる計画だ。脱原発を求める国民世論とは大きな乖離(かいり)があり、再生可能エネルギーを拡大させている世界の潮流からも取り残されつつある。政府や電力業界は原発神話の呪縛からいい加減抜け出し、現実的な政策として原発ゼロを追求すべきである。 *7-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/576849/ (西日本新聞社説 2020/1/19) 伊方差し止め 甘い災害想定に重い警鐘 原発再稼働を進める電力各社の安全対策と、それを容認している原子力規制委員会の判断は妥当なのか。その根幹に疑問を投げ掛ける司法判断である。四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転禁止を求めて、50キロ圏内である山口県の住民3人が申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁が運転を差し止める決定をした。伊方原発は細く延びる佐田岬半島の根元にある。深刻な事故が起きれば半島住民の避難は困難を極める。対岸約40キロの大分県を含む九州や中国地方にも甚大な被害が広がりかねない。伊方原発のそばを国内最大規模の中央構造線断層帯が走り、約130キロ離れた熊本県・阿蘇山も活発に活動を続けている。地震と噴火による災害リスクが適切に調査、判断された結果として、再稼働が認められたのか-。これが争点だった。決定は調査、判断ともに「甘い」との結論になった。地震については、原発周辺の活断層の調査が不十分と指摘した。阿蘇カルデラの噴火によるリスク評価も過小と判断した。加えて、安全性に問題がないとした原子力規制委の判断も誤りで不合理と断定している。福島第1原発の事故後、政府は「世界最高レベルの新たな規制基準」に適合した原発の再稼働を進めてきた。伊方3号もその一つだ。今回の決定は、規制基準へ適合させてきた電力会社の調査と、規制委の判断がともに不十分と指弾しており、「基準適合」に対する国民の信頼が揺らぐことは間違いない。規制委は最新の知見を踏まえながら、不断に基準を見直す努力を重ねる必要がある。電力各社も災害リスク調査のあり方などを改めて検証すべきだ。原発に関する司法判断はかつて、行政や専門家の判断を追認するものが大半だった。福島の事故後は裁判官によって従来より厳しい判断も出るようになった。運転差し止めを認めたのは今回で5例目であり、伊方3号機の運転を認めない仮処分決定は2017年に続き2回目だ。政府は福島事故後も原発をベースロード電源と位置付け、30年度に電源構成に占める割合を20~22%に引き上げる計画だ。ただ再稼働できたのは5原発9基にとどまる。再稼働しても、司法判断で止まる可能性があることが今回改めて示された。安全対策の拡充で、発電コストにおける原発の優位性は後退している。核燃サイクル計画も事実上、破綻したと言えよう。日本は世界有数の火山国で地震も極めて多い。ここで将来にわたり原発と共存していけるのか。今回の決定はエネルギー政策を考え直す契機ともしたい。 *7-4:http://www.people-i.ne.jp/~kakujyo/kooka.htm (佐賀県立唐津東高等学校校歌 下村湖人作詞、諸井三郎作曲) 天日輝き 1.天日かがやき大地は匂い 潮風平和を奏づる郷に 息づくわれらは松浦の浜の 光の学徒 光、光、光の学徒 2.はてなく広ごる真理の海に 抜手をきりつつ浪また浪を こえゆくわれらは松浦の浜の 力の学徒 力、力、力の学徒 3. 平和と真理に生命をうけて 久遠の花咲く文化の園を 耕すわれらは松浦の浜の 希望の学徒 希望、希望、希望の学徒 4.われらの理想は祖国の理想 祖国の理想は世界の理想 理想を見つめて日毎に進む われらは学徒 光、力、希望の学徒
| 男女平等::2019.3~ | 02:58 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2020,01,11, Saturday
(1)日米貿易協定発効
   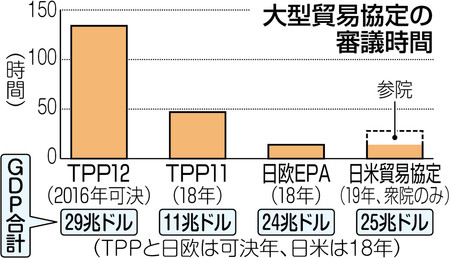 2019.9.26 2019.10.19 2019.11.19 2019.11.16 日本農業新聞 日本農業新聞 Yahoo 東京新聞 (図の説明:さくら国会であまり話題に上らなかったが、日米貿易協定では、左の2つの図のように、農業への影響が大きいにもかかわらず、右の2つの図のように、本質を突いた議論があまりなされなかった。これは、日本では、感覚の遅れた行政が調整して政策を決め、国会はそれに追随しているだけで、民主主義がうまく機能していないことを意味する) 2020年1月1日に、*1-1のように、日米貿易協定が発効したが、TPPは2018年末に、EUとのEPA2019年2月に発効しているため、これによって日本の農業生産額は減少すると思われる。国会議決の際に与党が賛成、野党が反対だったのは、実際には貿易自由化を進めたのが経産省だからだ。 一方、日本は自動車及びその部品をの攻めの分野として“カード”として使おうとしたが、関税撤廃は継続協議となり、得たものはなかった。 そして、農業に関しては、いつも生産基盤強化や農業者の支援のためとして予算がつけられるが、これまでも同様の政策がなされてきたのに離農者が多いため、その費用対効果は検証する必要があり、効果が低いのなら「桜を見る会」どころではない額の選挙目的のバラマキであるため、政策を根本的に考え直す必要がある。従って、費用対効果を正確に把握できる国の会計処理と正確な統計が必要なのである。 なお、*1-2のように、政府は、「①日米貿易協定が発効しても日本の農家の所得や生産量は一切減らない」「②万全の国内対策を打つ」と述べているそうだが、①はあり得ないので「③日本農業が受ける影響はどの程度か」を正確に見積もらなければ、②の万全の対策は打てない筈だ。このように、日本の立法・行政は理論的で建設的な議論を行わず、感情的な言葉だけが飛び跳ねているわけである。 (2)日本の自動車産業は本当に強いのか? 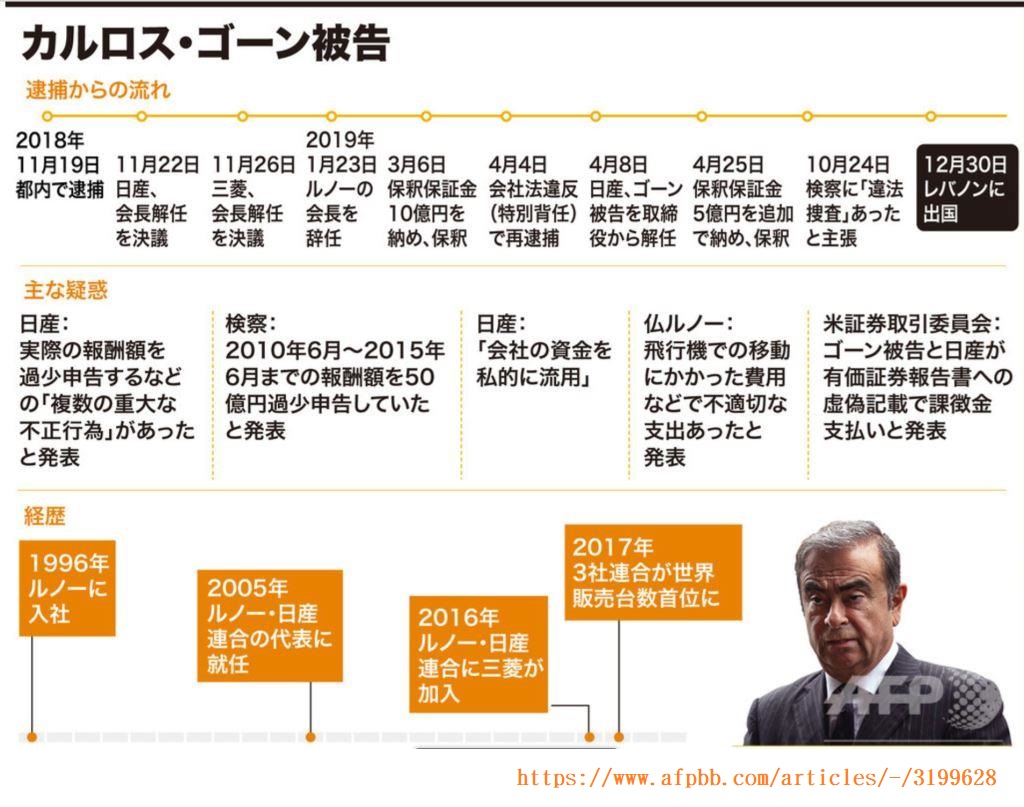  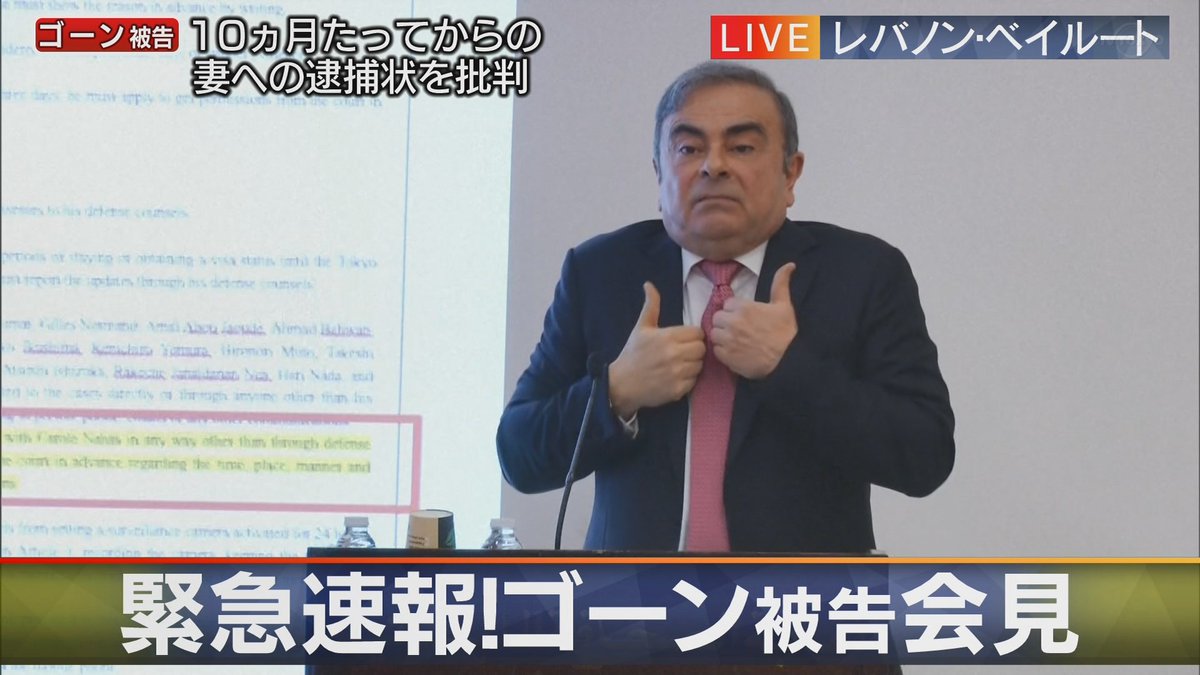 (図の説明:左図のように、2018年11月逮捕時のゴーン氏の容疑は、役員報酬の過少記載による金融取引法違反だったが、「これだけでは罪にならない」と見て、検察は2019年4月に会社資金の私的流用による会社法違反を罪状に加えた。しかし、日産と司法取引して逮捕したのなら、最初から容疑はすべてわかって書面によるバクアップもあった筈なので、こういうところからもゴーン氏を有罪に陥れるためにない頭を絞って罪を探していることがわかり、これが人権侵害なのである。さらに、中央の図のように、日産と司法取引しながら、たったこれだけの容疑を整理するのに2年もかかっているのはのろく、これでは最高裁まで闘ったら高齢になっても結論が出ておらず、人権侵害も甚だしいわけである。この際、一人の人間が築き上げた人生を台無しにするのに、「忙しいから時間がかかった」などというのは言い訳にもならない) 1)ゴーン氏逮捕事件の本質 私は、このブログの2018年12月4日・2019年4月6日などに記載したとおり、「ゴーン事件の本質は、経営上の争いに司法取引を用い、“私利私欲にまみれた独裁者”というレッテルを張って実績あるリーダーを追い出したことだ」と最初から見ていた。 そのため、先見の明を持ってリーダーシップを発揮していた(こうすると日本では“独裁者”と言われることが多いのだが)ゴーン氏をなくした日産が、経済産業省出身で社外取締役の豊田氏が薦めるガバナンス改革を行えば、漂流し始めることは予測できたので、*2-2のように、日産の業績が悪化し、*2-1のように、西川氏が辞任することになったのは想定内だった。 また、2010年にオランダに設立された子会社「ジーア社」は、法務部門を所管する外国人の専務執行役員の告発によると、リオデジャネイロやベイルートでゴーンが使う住宅の購入費・改修費を支払っていたそうだが、「イ.その告発は正確なのか」「ロ.刑事事件に相当する違法行為なのか」についても検討する必要があった筈だ。 東京地検特捜部はゴーン氏に、「①役員報酬の未払い分を隠した金融商品取引法違反」「②日産の資金を不正送金した会社法違反」という容疑を示したが、①は本来ゴーン氏が受け取れる筈の役員報酬をメディアが多すぎると叩いてできた法律で、株主が納得していれば問題ない性格のものである。そして、このような経営者叩きを続けていれば、外国人のみならず日本人でも有能な人は日本で会社を作らず上場もしなくなる。また、②は、日本人にはなじみのないやり方でも、販促であって不正でない場合もあるため、短絡的な解釈は禁物だ。 そして、ゴーン氏は、2019年6月24日に東京地裁で行われた公判前整理手続きにケリー氏とともに主席し、保釈中、弘中弁護士の事務所に通って弁護団と議論を重ね、弁護団はゴーン氏の認識や記憶を前提に公判での主張を組み立てて公判で予定する主張内容を、2019年10月17日、既に裁判所に提出しているので、日本の検察や裁判所はいつでもそれを参照できる。しかし、それ以上の証明や反論は、日本の司法の支配下にいてはできない事情があるのである。 2)ゴーン氏の出国 検察が容疑者としてメディアに発表した途端、日本のメディアは、*3-1のように、「ゴーン被告」と呼んで犯罪人扱いをし、殺人犯かレイプ犯ででもあるかのような保釈条件を求めた。つまり、ここでは「無罪の推定」は働いておらず、日本のメディアは「有罪の推定」を働かせ、「言論の自由」「表現の自由」と称して無節操なイメージ操作をしてきたのである。 そのため、無断ででも出国しなければ、日本メディアのしつこい情報操作に負ける上、検察が書類を押収して都合の悪い証拠は出さず、このままでは本人が無罪の証拠を出すこともできないため、ゴーン氏は出国を選んだのだろう。私は、出国に成功してよかったと思う。 日本の検察は、有罪が確定する前からまるで有罪が確定しているかのようにメディアに知らせ、メディアは疑問も持たずに裁判抜きで人を貶める報道をいっせいにしたのだから、ここでゴーン氏が日本のメディアを外して他国を中心としたメディアと自由にコミュニケーションを取ったのは当然である。 また、ゴーン氏は、*3-5のように、プロの力を借り、プライベートジェットを使って、出国に際しては楽器箱に隠れて関西空港からトルコ経由でレバノンに入り、*3-2のように、「有罪が前提の政治的な迫害を逃れた」という声明を発表し、*3-4・*3-6のように、「事件は自らを引きずり下ろすクーデターだ」等々と記者会見で述べているが、これを批判するのは当たらないと思う。 3)今度は「違法出国」が罪とは・・ このように、ゴーン氏の容疑内容は、2019年6月24日の公判前整理手続きで既に行われており、出国するにはそれだけの理由があったため、*3-3のように「違法出国が法秩序を踏みにじる行為だ」などという主張をする前に、ゴーン氏の刑事事件としての逮捕と長期の拘束が日本国憲法に定められた人権侵害にあたらないのかを反省すべきだ。 森雅子法相は、*3-3のように、「刑事裁判そのものから逃避し、許されない」と批判し、東京地検の斎藤次席検事は「日本の刑事司法制度を不当におとしめる主張で到底受け入れられない」とコメントしているが、刑事裁判に当たる事案か否かも含め、日本の司法の公正性が信頼できないので避けたのだから、この根本を忘れずに日本国憲法に沿った司法に改めるべきだ。 上記が、*3-7の琉球新報社説への私の説明でもあり、さらにゴーン氏の場合は、大切な人を人質にとられたのではなく自分が不当に長く拘束され、権利を大きく制限されたのだから、「人質司法」というよりは「拷問」「人権侵害」と言う方が正しい。 また、日本では検察が起訴した途端に「推定有罪となり、検察のメンツのために無罪の人が刑務所に入れられ、有罪率が99.4%で、反証は殆ど取り上げられない」ため、その本質を改革すべき森雅子法相が、「(逃亡は)どの国の制度でも許されない」と批判したのは本質を理解しておらず、*3-8のように、ゴーン氏が「法相の発言は愚か」と言うのは理解できる。 なお、法務省は、森雅子法相が「潔白だと言うのなら、(日本の)司法の場で正々堂々と無罪を証明すべきだ」と発言したことを3カ国語でHPに掲載したそうだが、刑事裁判では「推定無罪」の原則が働き、逮捕するにあたっては逮捕時に逮捕理由を説明し、検察官が有罪を立証しなければならないのであるため、森雅子法相は弁護士の割には知らなすぎる。 (3)単なる情報戦ではなく、人権を求める戦いである ゴーン氏の出国については、*4-1・*4-2のように、海外メディアは好意的だそうだが、私は中国でもとっくの昔に卒業した“文化大革命”のようなことを言っている日本のメディアの方がおかしいと思っていたため、ゴーン氏の出国が成功してよかったと思う。また、レバノンと日本の間に“犯罪人”引渡条約がないのは幸いしたが、今後は、レバノン政府が日本の圧力に屈しないことが必要だ。 また、ゴーン氏は、これだけ負のイメージを擦りつけられたのだから、*4-3のように、ハリウッド映画化して、ビジネス界・自動車革命の時代背景・各国の世論・日産社内の経営権争いに司法が介入した日本の事情などをリアルに表現すれば、これまでにないものすごいビジネス映画になると考える。ただし、命に気を付けて行動して欲しいくらいの真剣勝負になる。 このような中、日経新聞は社説で、*4-4のように、「日本の法廷の場なら議論が深まったかもしれない」などとありもしない嘘を書いているが、司法制度が違っても人権が大切なことは普遍であるのに、それがない日本の司法を改革しなければ、そうはならない。ゴーン氏がSECとは争わずに100万ドルの課徴金を支払ったのは、同時に多くの敵を作らないためだろう。 なお、日本は特殊な国であるという日本の立場の説明は、言い訳としていろいろな分野でよく聞かれるが、グローバルな世界でそれは通用しない。また、プライベートジェットには不特定多数の人は乗らないため、手荷物チェックが緩いのは当然である。 (4)日本はこうして遅れていく 「日本の自動車産業は今後も強いか」については、結論から言って「危うい」というのが私の見方だ。その理由は、ゴーン氏が率いていた日産・三菱・ルノー組を、将を捕えることによって漂流させて護ったのは、*5-1のトヨタだからである。トヨタは、EVではなくハイブリッド車に妥協した会社で、国を挙げてEVを推進していた中国の環境規制も緩めさせるように働いた。 そのため、*5-2のように、欧州の自動車大手が事業活動に伴うCO2の純排出量もゼロにする「カーボンニュートラル」を相次いで宣言し、2019年11月4日には、独フォルクスワーゲン(VW)がEVを量産し始め、メルケル首相が「独自動車産業の未来の礎石となる」と述べ、VWのディース社長が「VWの新しい歴史が始まる」としているのは希望が持てる。私は、次に自動車を買うなら、高すぎなければポルシェかベンツのEVにしたいと思っているくらいなので、外国人労働者と組み合わせて九州のどこかで工場誘致したらどうかと考える。 そのような中、*5-3のように、日経新聞は社説で「①2018年度に国内で消費した1次エネルギーの約9割は化石燃料に支えられている」「②化石燃料から水素を取り出して使う」「③千代田化工建設などのグループは、天然ガスから取り出した水素を別の化学物質に変えて日本に持ち込む計画」「④資源国にとっても保有資源を有効に使い続ける道になるはずだ」「⑤水素利用技術の確立に向けて、資源国と連携した取り組みを加速していかねばならない」などと、馬鹿なことを書いている。 何故なら、①は、先見の明のなさによるものであり、②③④については、化石燃料から水素を作るなど愚の骨頂で、⑤については、「日本には資源がないから、資源は輸入しなければならない」という先入観から抜けられない頭だからだ。こうして日本はどんどん遅れて行き、国民は貧しくなっていくが、私は、このようにして作られた水素は使わないつもりだ。 なお、*5-4のように、地球温暖化対策のパリ協定に関する目標や政策の評価で、日本は、六段階評価で下から二番目の「極めて不十分」と判定されたそうだが、全体として尤もである。 ・・参考資料・・ <日米貿易協定> *1-1:https://www.agrinews.co.jp/p49413.html (日本農業新聞 2019年12月5日) 日米協定“拙速”承認 来年1月1日発効へ 参院 日米貿易協定は4日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、承認された。来年1月1日に発効する見通し。牛肉、豚肉などは環太平洋連携協定(TPP)と同様に関税を削減。生産額の減少は過去の大型協定に匹敵する。昨年末に発効したTPP、今年2月に発効した欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)に続き大型協定の発効が迫り、日本農業はかつてない自由化に足を踏み入れる。同協定を巡る交渉は4月に開始。9月に最終合意し、10月に署名した。合意内容の公表から協定の国会審議までは1カ月足らず。TPPなど過去の大型協定と比べても異例の短さで、情報開示や国民的な議論の不十分さが目立った。同日の採決では、自民、公明両党と日本維新の会などが賛成。立憲民主党、国民民主党などの共同会派や共産党は反対した。政府は今後、関連する政令改正などの国内手続きを終え、米国に通知する。米国側は国内法の特例に基づき議会審議を省く方針。両国の合意で発効日を決められ、米国の要望に応じて1月1日の発効となる見通しだ。発効後、日米は追加交渉に向けた予備協議に入り、4カ月以内に交渉分野を決める。政府は関税交渉について「自動車・自動車部品を想定しており、農産品を含めてそれ以外は想定していない」(茂木敏充外相)としているが、具体的な交渉範囲は協議次第だ。協定では、牛肉は関税率を最終的に9%まで削減する。セーフガード(緊急輸入制限措置=SG)を設定した一方、発動した場合、発動基準をさらに高くする協議に入る。TPPのSGと併存し、低関税で輸入できる量がTPPを超えるため、政府は加盟国との修正協議に乗り出す。今後、追加交渉での農産品の扱いやSGの発動基準数量の引き上げの動向などが焦点になる。日本の攻めの分野の自動車・同部品の関税撤廃は継続協議となった。政府の影響試算では、農林水産物の生産額は、米国抜きのTPP11の影響も踏まえると最大2000億円減る。国会審議で野党は、日欧EPAなど発効済みの他の貿易協定も含めたより精緻な試算を求めたが、政府・与党は応じなかった。政府・与党は現在、中長期的な農政の指針となる食料・農業・農村基本計画の見直しの議論を進めている。一連の大型協定による農産品の自由化にどう対応するか具体策が問われている。 ●国内対策 農家規模問わず 政府は4日、日米貿易協定に伴い、国内対策の指針となる「TPP等関連政策大綱」改定案を自民、公明両党に示し、了承された。農業分野では、中山間地を含めた生産基盤強化の必要性を強調し、「規模の大小を問わず、意欲的な農林漁業者」を支援する方針を明記。新たに肉用牛や酪農の増頭・増産対策などを盛り込んだ。政府は5日に正式決定し、2019年度補正予算に農林水産業の対策費として3250億円程度を計上する。改定案では、国内外の需要に応え、国内生産を拡充するため農林水産業の生産基盤を強化する必要性を指摘。畜産クラスター事業による中小・家族経営支援の拡充や、条件不利地域も含めたスマート農業の活用も盛り込んだ。規模要件の緩和や優先採択枠の設置で対応する。自民党TPP・日EU・日米TAG等経済協定対策本部(本部長=森山裕国対委員長)などの会合で、西村康稔経済再生担当相は「(農業の)国内生産を確実に拡大するため、中山間地域も含めた生産基盤を強化していく」と述べた。森山本部長は会合後、「(家族経営を)政策の横に置くのではなく、中心に据えてやっていくことが大事だ」と記者団に語った。改定案には輸出向けの施設整備、堆肥活用による全国的な土づくりの展開、家畜排せつ物の処理円滑化対策、日本で開発した農産物の新品種や和牛遺伝資源の海外流出対策なども盛り込んだ。農林水産分野の対策の財源について、既存の農林水産予算に支障のないよう「政府全体で責任を持って」確保する方針は改定案でも維持した。TPPの牛肉SGの発動基準見直しを巡っては、「日米貿易協定の発効後の実際の輸入状況などを見極めつつ、適切なタイミングで関係国と相談を行っていく」との記述にとどめた。 ●日米協定国会承認 期限ありき審議不足 再協議規定 農業扱い不透明 日米貿易協定は、踏み込んだ議論には至らないまま、国会審議が終結した。来年1月1日発効を目指す政府・与党は、野党側の資料請求にも応じず、議論がかみ合わないまま審議が進展。野党も最終的には4日の参院本会議での採決に応じたため、農産品の再協議の可能性をはじめとした懸念を掘り下げることなく、協定は承認された。衆参両院の委員会審議は22時間余り。過去の経済連携協定を大きく下回る。参院本会議では、これまでの委員会審議と同様に、農産品について、米国が「特恵的な待遇を追求する」と明記した再協議規定への懸念が続出。採決の最終盤となっても不明瞭な部分が残っている実態が改めて浮き彫りになった。国民民主党の羽田雄一郎氏が再協議規定について「米国の強い意志を感じる」と指摘。大統領再選を目指すトランプ氏の強硬姿勢を警戒した。協定に賛成した日本維新の会の浅田均氏も「米国がさらに強気の姿勢で交渉に臨んでくるのは不可避。積み残しになった自動車・同部品の関税撤廃の確定も含め、交渉は一筋縄ではいかない」と警鐘を鳴らした。ただ、野党側は採決を容認。会議場内では「反対」などの声が出たが、賛否の投票作業は淡々と進んだ。衆参両院を通じて、審議不足は否めない結果となった。衆院では、自動車の追加関税の回避の根拠となる議事録など示さない政府・与党に対し、主要野党が反発して退席。与党側が審議時間の消化を優先。質問者不在のまま割当時間を消化する「空回し」を含めても、審議時間は22時間余りにとどまる。一方、環太平洋連携協定(TPP)は2016年、衆参両院に特別委員会を設けて計130時間以上審議。日米協定の審議時間は短さが際立つ。さらに衆院では、協定の審議が「桜を見る会」の説明責任を巡る与野党の駆け引き材料になった部分も多い。野党内からも「政争の具にせず、審議の充実を追求していくべきだった」(幹部)と審議運営を批判する声が出ている。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p49059.html (日本農業新聞 2019年10月24日) 日米影響試算 審議の材料たり得ない 日米貿易協定が発効しても、万全の国内対策を打つので日本の農家の所得や生産量は一切減らない──。政府がそんな影響試算を発表した。現実離れしていると言わざるを得ない。これでは国会審議の材料になるはずもない。政府は納得感の得られる試算を出し直すべきだ。日米協定の承認案は24日から衆院本会議で審議が始まる。審議を進める上で重要な材料の一つとなるのが、日米協定によって日本農業が受ける影響試算だろう。日米協定発効に伴い、日本農業が受ける打撃はどの程度か。影響をしっかり試算した上で必要な国内対策を考える。これこそが本来あるべき姿のはずだ。だが、政府が先週発表した影響試算は、そうした期待に沿う内容とは言い難い。試算によると、日米協定発効に伴い、安い米国産農林水産物が日本に押し寄せた結果、国産の価格も低下。国内の農林水産物の生産額は600億~1100億円減る。減少額がとりわけ大きいのが牛肉で、最大約474億円に達するという。不思議なのはここからだ。生産額が減るにもかかわらず、国内の農家の所得、生産量は一切減らないという。コスト低減や経営安定につながる万全な国内対策を措置するからで、食料自給率も変わらないという。そもそも国内対策の検討が始まるのはこれからで、まだ決まっていない。にもかかわらず、なぜ日本の農家所得や生産量に影響なしと言い切れるのか。首をかしげたくなる農家も少なくないだろう。環太平洋連携協定(TPP)や欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)に合意した際も政府は影響試算を発表。今回同様に国内対策の効果で、日本の農家所得や生産量に影響なしという内容だった。政府には、農家の不安を大きくしたくない気持ちがあるのかもしれない。だが、貿易自由化に伴う打撃に目を背けたままでは、十分な国内対策が出来上がるとは思えない。今回の影響試算には、国内対策を考える以外にも、もう一つ重要な意味合いがある。来年3月の策定に向けて議論が本格化している新しい食料・農業・農村基本計画だ。同計画は今後10年間の農政の指針となる。10年後と言えば、日米協定やTPP、日欧EPA発効に伴う関税削減が、今よりずっと進んでいる時期。その時に日本農業が受ける打撃はどの程度か。それをきちんと踏まえて新たな基本計画を策定する必要がある。「農家の不安にもしっかり向き合い、生産基盤の強化など十分な対策を講じる」。安倍晋三首相は臨時国会冒頭の所信表明演説で力強く宣言した。ならば、まずは現実離れした一連の影響試算を見直すべきだ。このまま国会審議に突き進んでも議論は深まらず、生産基盤強化という首相の決意にも疑問符が付きかねない。 <日本の自動車産業は強いか> *2-1:https://digital.asahi.com/articles/ASMCK71NCMCKULFA00L.html?iref=comtop_favorite_01 (朝日新聞 2019年11月18日) ゴーン氏追放、西川氏の大誤算 主導した改革は己の身に 日産自動車前会長のカルロス・ゴーンを東京地検特捜部が電撃的に逮捕してから19日で1年になる。世界に衝撃を与えた事件の裁判は来春にも始まる。ゴーンはすべての事件で無罪を主張している。弁護側は捜査の手続きそのものが違法だとして争点化する方針で、検察側と弁護側の全面対決となる。ゴーンに代わって経営トップにのぼりつめた社長の西川(さいかわ)広人も、自らの報酬不正の責任を問われて今年9月に辞任に追い込まれた。極秘に進めた社内調査をもとに特捜部の捜査に全面協力し、ゴーンを「追放」した日産にとっても、この1年は想定外の連続だった。 ◇ 「おかしな会社があるぞ」。日産自動車が「ベンチャー投資」目的で2010年にオランダに設立した子会社「ジーア」に対し、社内では疑問の声がたびたびあがっていた。「投資活動を全然していない」「休眠法人ではないか」。設立の数年後にはこうした指摘が上層部に寄せられ、役員が「すぐ調査を」と指示していた。だが実態がつかめない。「その下にまた会社があって、仕組みが複雑すぎるんです」(当時の役員)。調査に関わった監査役(当時)も「手を尽くして調べても、よくわからなかった」と振り返る。暗礁に乗り上げた調査の突破口は「有力な内部告発だった」と複数の日産関係者は明かす。前会長カルロス・ゴーンの部下で法務部門を所管する外国人の専務執行役員が「これ以上、不正につきあわされるのはごめんだ」とジーア社の実態を監査役に打ち明けたというのだ。ベンチャー投資をするはずのジーア社は、リオデジャネイロやベイルートでゴーンが使う住宅の購入費や改修費を支払っていた。この専務執行役員はその後、司法取引に応じ、東京地検特捜部の捜査に全面協力することになる。監査役らは昨年春から、米法律事務所レイサム&ワトキンスと組んでゴーンの不正の調査に本格的に着手した。ゴーンはもちろん、社長の西川(さいかわ)広人にも知らせずに動き出した。それは、ゴーン側近の西川に知らせたら「どう反応するかわからない」(幹部)と警戒していたからに他ならない。監査役が証拠を示してゴーンの不正を西川に初めて説明したのは昨年秋。ゴーンが電撃的に逮捕された11月19日の1カ月前だった。すでに特捜部との間で司法取引の協議が進んでいた。幹部らは「全てが整った段階で説明した」と明かす。西川はこのころ、仏政府の要求を受け、連合を組む仏ルノーと日産の経営統合に意欲を示すようになったゴーンと対立。ゴーンに疎まれ、社長の座を追われそうになっていた。「窮鼠(きゅうそ)猫をかむ」のたとえ通り、「西川はゴーン降ろしに最後に乗っかった」(幹部)。11月19日午後10時。横浜市の日産本社で緊急記者会見に1人で臨んだ西川は「当然、解任に値する」と強調し、ゴーンとの決別を宣言した。それから1年足らず。自らも報酬不正で社長の座を追われることになろうとは、西川は思いもしなかった。この1年は多くの日産関係者にとっても誤算続きだった。 ●旗振った改革、辞任迫られる誤算 「会社の仕組みが形骸化し、透明性が低い。ガバナンス(企業統治)の問題が大きい」。ゴーンが逮捕された昨年11月19日夜の記者会見で、日産自動車社長(当時)の西川(さいかわ)広人はゴーンの不正を長年見抜けなかった理由をそう説明した。その後の日産の動きは素早かった。3日後に臨時取締役会を開いてゴーンの会長職を解任。12月17日の取締役会で「ガバナンス改善特別委員会」を設置し、外部有識者から改善策の提言を受けることを決めた。逮捕直後から、ゴーンの不正を止められなかった西川の責任を問う声が社内外でくすぶっていた。カリスマのゴーンを「追放」して経営トップに就いた西川にとって、自らの求心力を高めるにはガバナンス改革という旗が必要だった。特別委は今年3月にまとめた報告書で、人事・報酬の決定権のゴーンへの集中が不正を招いた原因だと指摘。社外取締役の権限を強める「指名委員会等設置会社」への移行を提言し、日産は6月の株主総会で移行に必要な議案を提案した。仏ルノーが一時、この議案への投票を棄権する意向を示すと、西川は強く反発。改革の頓挫を避けたい日産はルノー出身者のポストを増やして人事面で譲歩し、なんとかルノーの賛成をとりつけた。経済産業省も、同省OBで社外取締役の豊田正和を通じて改革の実現を促した。だが、会社の形を大きく変える改革には「副作用」も伴う。「自分たちの思い通りの人事をすることができなくなりますよ」。日産から水面下で相談を受けた法務アドバイザーは「移行は危険だ」と伝えていた。懸念は現実のものとなる。ゴーンの不正を追及する急先鋒(きゅうせんぽう)だった西川自身の報酬不正が社内調査で判明。9月9日の取締役会では、取締役11人のうち7人を占める社外取締役の多くが西川に辞任を迫った。この時点での辞任を否定していた西川の外堀は一気に埋まった。旗を振って進めたガバナンス改革が機能した結果、自らが辞任に追い込まれたとは皮肉だ。社外取締役は「ポスト西川」選びも主導した。首脳人事の決定権を握る指名委員会が次期社長に指名したのは専務執行役員の内田誠。社内では西川の辞任後に暫定的に社長代行を務める山内康裕の昇格を期待する声が多く、取締役でもない内田の起用に驚く声もあった。指名委も6人中5人を社外取締役が占め、残る1人はルノー会長のジャンドミニク・スナール。スナールは他の社外取締役と水面下で人選を調整し、トップ人事に積極的に関わった。経営トップを自らの手で決められないもどかしさに、「結局、日産への影響力を強めたのはスナールではないか」と幹部は嘆く。来月1日に発足する内田新体制の前途は多難だ。今月12日に2020年3月期の業績予想を下方修正。ゴーンが進めた拡大路線の修正は難しく、純利益は前年比65・5%の大幅減益になる見込みだ。日産三菱・ルノーの3社連合に安定をもたらしていた「ゴーン1強」体制が崩れたいま、ルノーが経営統合を求めて再び圧力を強める可能性もある。「将来の展望や野心的な戦略がない。3社の関係がゆがんで成長が滞っている」。ゴーンは最近、知人にこう漏らし、日産の行く末を案じたという。=敬称略 ●来春にも公判、全面対決の構図鮮明 ビジネスジェット機で羽田に到着した日産自動車のカルロス・ゴーン前会長を東京地検特捜部が電撃的に逮捕してから19日で1年。世界に衝撃を与えた事件は、来春にも始まるとみられる公判に向けた手続きが進む。検察、弁護側双方の大まかな主張が出そろい、全面対決の構図が鮮明となっている。ゴーン前会長は今年4月までに計4回逮捕され、役員報酬の未払い分を隠したとする金融商品取引法違反事件と、日産の資金を不正送金したなどとする会社法違反事件で起訴された。今月11日に記者会見した弁護団の弘中惇一郎弁護士によると、保釈中のゴーン前会長は弘中氏の事務所に通って裁判の記録を読むなどし、週に何回も弁護団と議論を重ねている。弁護団は前会長の認識や記憶を前提に、公判での主張を組み立てているという。弁護側は公判で予定する主張内容を10月17日に裁判所に提出した。すべての事件で無罪を主張するだけでなく、捜査の手続きそのものが違法だと争点化し、公訴(起訴)棄却を申し立てる方針を示した。裁判で公訴棄却が認められて確定した例はまれだが、主任弁護人の河津博史弁護士は「過去に例のないほど違法な捜査が行われた。単なる戦術ではない」と強調する。焦点の一つが、特捜部が日産幹部2人と交わした司法取引の違法性だ。本来は部下がトップの不正を明らかにする代わりに罪を減免されるようなケースが主に想定されている。弁護側は、日産の経営陣がゴーン前会長を失脚させる目的だったとし、「実質的な当事者は日産だ」と指摘。「2人は業務命令で司法取引したにすぎず、法の趣旨に反する」と主張する。これに対し、検察幹部は「弁護団の筋書きは根拠がなく妄想だ」と一蹴。「裁判所が違法性を認めるとは思えない」と自信を見せる。今後も公判に向けて証拠や争点を絞り込む公判前整理手続きが進められるが、弁護側は検察側が提出する供述調書の大半について、証拠採用に同意しないとみられる。このため、検察側は司法取引に応じた2人を含め多くの日産幹部を証人申請することが予想される。弁護側は西川前社長も一連の行為に関与したとして証人申請するとみられ、状況によっては公判が長期化する可能性もある。地裁は、金商法違反事件について初公判を来年4月にも開きたいとの意向を示している。審理は来年いっぱいは週3日のペースで隔週行う案も示しているという。ただ、会社法違反事件の審理については未定になっており、公判のスケジュールはなお流動的だ。 *2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191203&ng=DGKKZO52882830S9A201C1MM8000 (日経新聞 2019.12.3) 日産、ルノー連携で事業再建 新社長、中計見直し 日産自動車の内田誠社長兼最高経営責任者(CEO)は2日、就任後初めて記者会見し、仏ルノー、三菱自動車との関係について「アライアンスの活動を通して利益を上げていくことに注力する」と語った。日産は値引き頼みの販売が重荷となり業績悪化が深刻だ。世界主要市場の縮小や次世代技術対応など事業環境が厳しさを増すなか、日仏連合をテコに業績回復を目指す考えだ。内田氏は「私が指揮を執って新たな事業計画を策定する」と述べ、中期計画を見直す方針も示した。日産に43%出資する筆頭株主の仏ルノーは仏政府の意向を受ける形で19年春、日産に経営統合を打診。内田社長は経営統合の協議について「ルノー会長とも今は全くしていない」と述べ、少なくとも当面は進めない考えを示した。ただ、将来の関係については言及しなかった。西川広人前社長は「ネガティブなインパクトが大きく、否定的だ」と明確に反対していた。日産の業績は大きく悪化している。20年3月期の連結純利益は1100億円と前期比66%減る見通しだ。立て直しに向けて日仏連合での協力を拡大する。拡大路線を進めるために過大な目標を設定して無理を重ねた反省から、企業風土の改革も進めると表明した。内田氏は1日付で就任した。元会長カルロス・ゴーン被告の後を継いだ西川前社長が報酬問題で辞任したのを受けたものだ。 <ゴーン氏の出国> *3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200101&ng=DGKKZO54007910R00C20A1MM8000 (日経新聞 2020.1.1) ゴーン元会長、レバノンへ無断出国 保釈条件違反 日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(65)が日本を出国し、中東レバノンに入ったことが31日、分かった。元会長は保釈条件で海外渡航が禁じられており、無断出国とみられる。日本とレバノンの間に犯罪人引き渡し条約はなく、4月にも始まる見込みだった元会長の刑事裁判は事実上、困難になった。元会長はレバノン国籍を持っており、「私は今、レバノンにいる。有罪が予想される日本の偏った司法制度の下でのとらわれの身ではなくなった」などと声明を出した。同国外務省は元会長が30日に合法的に入国したとの声明を出した。東京地裁は31日、東京地検の請求を受けて元会長の保釈を取り消す決定をした。保釈保証金計15億円は没収される。現地メディアなどによると、元会長はプライベートジェットを使い、トルコ経由でレバノンに入った。出国に際して元会長が楽器箱に隠れたとし、レバノン入国後、同国大統領と面会したとの報道もある。日本の出入国在留管理庁関係者によると、元会長名での出国記録はなく、日本で正規の出国手続きを経ていない可能性がある。外務省関係者は事実関係や出国の経緯について「現地の日本大使館などを通じて確認中」と語った。元会長の弁護人を務める弘中惇一郎弁護士は31日、東京都内で報道陣の取材に「事実とすれば保釈条件に違反している」と話した。 *3-2:https://digital.asahi.com/articles/ASMD04H87MD0UHBI00J.html (朝日新聞 2019年12月31日) ゴーン被告「有罪が前提、政治的な迫害逃れた」声明全文 日産自動車のカルロス・ゴーン前会長の広報担当者は米東部時間30日夜(日本時間31日昼)、取材に対してゴーン前会長の英文の声明を発表した。全文の訳は以下の通り。 ◇ 私は現在レバノンにいます。もうこれ以上、不正な日本の司法制度にとらわれることはなくなります。日本の司法制度は、国際法・条約下における自国の法的義務を著しく無視しており、有罪が前提で、差別が横行し、基本的人権が否定されています。私は正義から逃げたわけではありません。不正と政治的な迫害から逃れたのです。やっと、メディアのみなさんと自由にコミュニケーションを取ることができます。来週から始められることを、楽しみにしております。(原文は英語) ●レバノン大使館の関係者?は無言 東京都港区の駐日レバノン大使館が入るビルの前には、31日午前から報道陣が集まった。ビル入り口のインターホンはスイッチが切られているのか呼び出し音は鳴らず、レバノン大使館の関係者とみられる男性が出入りしたが、記者の問いかけには一切応じなかった。 *3-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14317743.html (朝日新聞社説 2020年1月7日) ゴーン被告逃亡 身柄引き渡しに全力を 世界を驚かせた逃走劇から1週間が過ぎた。情報が交錯し、経緯にはいまだ不明な点が多いが、保釈中の日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告が、国籍をもつレバノンに違法に出国したことは間違いない。法秩序を踏みにじる行為であり、断じて許されるものではない。森雅子法相はきのう記者会見し、国際機関などと連携して、日本での刑事手続きが適正に行われるよう、できる限りの措置を講じる考えを示した。会社法違反などの罪に問われたゴーン被告は無罪を主張し、東京地検が日産関係者と交わした司法取引についても違法だと訴えていた。被告が不在のままでは裁判は開かれず、事件は宙に浮くことになりかねない。レバノン政府とねばり強く交渉するのはもちろん、日本の司法制度について丁寧に情報を発信するなど、あらゆる外交努力を尽くし、ゴーン被告の身柄の引き渡しを実現させる。それが政府の責務だ。あわせて、前代未聞の逃走を許してしまった原因は何か、究明を急ぐ必要がある。ゴーン被告はプライベートジェット機を使って関西空港から出国した可能性が高いとみられる。一連の審査手続きに不備や緩みはなかったか。国民に対する説明と適切な改革が求められるのは言うまでもない。ゴーン被告は起訴・保釈・再逮捕などの曲折を経て、昨年4月末から身体拘束を解かれていた。住居玄関への監視カメラ設置、パソコンや携帯電話の利用制限など、弁護側が示した条件を裁判所が認めた。にもかかわらず、結果として今回の事態を防げなかったことを、関係者は重く受け止めねばならない。15億円という保釈保証金は、富豪であるゴーン被告に対するものとして適切だったか。弁護士にすべて預けるはずだった複数の旅券を、途中から1冊に限ってとはいえ、被告が携帯することを認めたことに問題はなかったか――。他にも点検すべき事項はあるはずだ。日本では容疑を認めない人を長く拘束する悪弊が続き、国内外の批判を招いていた。それが裁判員制度の導入などを機に見直しが進み、保釈が認められるケースが増えてきている。ゴーン被告の処遇は象徴的な事例の一つであり、運用をさらに良い方向に変えていくステップになるべきものだった。その意味でも衝撃は大きいが、だからといって時計の針を戻すことはあってはならない。捜査・公判の遂行と人権の保障。両者のバランスがとれた保釈のあり方を模索する営みを続けるためにも、今回の逃走の徹底した検証を求める。 *3-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200109&ng=DGKKZO54192030Z00C20A1MM8000 (日経新聞 2020.1.9) ゴーン元会長「無実」強調 レバノンで会見 逃亡経緯語らず 保釈条件に違反して逃亡した日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告は日本時間の8日午後10時から、レバノンで記者会見した。一連の事件について「日本の検察や日産の経営陣が画策したもの」と無実だという従来の主張を繰り返した。事件は自らを引きずり下ろすクーデターだとしたが、検察など日本の関係者は事実と異なると反論した。ゴーン元会長が会見するのは、2018年11月に逮捕されて以来、初めて。元会長は会見で「日本の司法は非人道的。公正な裁判を受けられないと判断した」などと述べ、自らの逃亡を正当化。勾留の長さを強調するなど日本の刑事司法制度の批判を展開したが、逃亡方法などについては一切話すつもりはないとした。ゴーン元会長は起訴された一連の事件について「検察や日産の経営陣によるもの」とし、西川広人前社長兼最高経営責任者(CEO)ら日産の元幹部ら6人の名前を挙げた。元会長は逃亡後、米メディアの取材に対し日本政府の関係者の名前を会見で挙げる意向も示していたがレバノン政府への配慮を理由に見送った。森雅子法相は9日未明に会見し「刑事裁判そのものから逃避し、許されない」と批判。東京地検の斎藤隆博次席検事は「日本の刑事司法制度を不当におとしめる主張で到底受け入れられない」とのコメントを出した。日産の広報担当者は「当社はすでに(反論の)声明を出しており、新たなコメントは必要ない」と述べた。ある日産幹部は「茶番劇だ」などと反論。別の幹部も「不正の証拠もたくさんあり、ゴーン元会長の主張は議論のすり替えにすぎない」と厳しく指摘した。 *3-5:https://digital.asahi.com/articles/ASN142T3QN14UHBI00F.html?iref=comtop_8_05 (朝日新聞 2020年1月4日) ゴーン被告、プロが逃がす?元グリーンベレーの名前浮上 日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)がレバノンに逃亡した問題で、米紙ウォールストリート・ジャーナルは3日、ゴーン前会長が米陸軍特殊部隊出身とみられる男性ら2人の助けを借り、音響機器を入れる箱に隠れて日本を出国したと報じた。同紙によると、ゴーン前会長は12月29日、プライベートジェットで関西空港を発ち、30日にトルコ・イスタンブールに到着。大雨の降る中、車で約90メートル移動してより小型のジェット機に乗り換え、レバノンにたどり着いた。いずれも機内にはゴーン前会長ら乗客の他にパイロット2人、乗務員1人が乗っていたという。トルコの航空会社は、ゴーン前会長の逃亡に際して記録を改ざんしたとして、従業員を刑事告訴。同紙はトルコ当局の捜査に詳しい関係者らの話として、この従業員が、ゴーン前会長が関空で飛行機に乗り込むまでに箱がどのように使われたかを捜査員に証言したと伝えている。同紙が写真で確認したこの箱は、角が金属で強化されており、機体後部近くの通路に押し込まれていた。もう一つの箱にはスピーカーが入っていたという。同紙はまた、関空からイスタンブールへの飛行計画書には、米国のパスポートを持つ男性2人だけが乗客として書かれていたと指摘。2人はその後、ゴーン前会長が乗った小型機ではなく民間機でレバノンまで向かったという。この米国人のうち1人は陸軍特殊部隊グリーンベレーの出身者で、2009年にアフガニスタンで武装グループに拉致された米紙ニューヨーク・タイムズの記者を救出したことで知られる人物と同姓同名。民間警備業界では著名だという。もう1人は、この男性と関係のある会社の従業員として働いたことがある人物だという。ゴーン前会長の米国の広報担当者は、朝日新聞の取材に「ゴーン氏の日本出国をめぐるいかなる報道についても、現時点ではコメントはしない」と回答した。 *3-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200109&ng=DGKKZO54192800Z00C20A1EA2000 (日経新聞 2020.1.9) ゴーン元会長、司法・日産批判に終始 日本メディア大半排除 日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告は8日のレバノンでの記者会見で改めて無実を主張した。事件は当時の日産経営陣の「策略」とし、日本の司法は「非人道的」だと非難。会見では日本メディアの大半を排除し、一方的に主張を展開した。国際手配を受けるなど不安定な立場が続くなか、国際世論を味方に付けたいとの思惑が透けた。ゴーン元会長は会見で、自身が日本で罪に問われた内容について「中傷のキャンペーンに過ぎず、想像の産物」「検察が日産の幹部と画策したものだ」などと批判した。元会長は、中東の知人側に資金を流出させるなどして日産に損害を与えた会社法違反(特別背任)の罪と、役員報酬の「未払い分」約91億円を有価証券報告書に記載しなかった金融商品取引法違反の罪で起訴された。元会長は特別背任罪に問われた資金の支出について、社内の適正な手続きを経ていたなどと主張。報酬の過少記載については「支払われていない報酬が容疑とは理解に苦しむ」と述べた。元会長が日本に戻らなければ裁判は始まらず、事件の真相解明は宙に浮く。元会長は「公正さが確保されればいかなる所でも裁判に臨む」としたが、「(日本は)有罪率が99%を超え、公正な裁判は受けられない」などと話した。この日の会見は元会長側の意向により「過去に関係を築いたメディア」だけを招待する形で行われた。フランスや中東のメディアが大半を占め、日本メディアの参加は数人にとどまった。元会長は会見で事件に関する日本メディアの報道も批判し、日本メディアの多くを排除した理由を問われると「客観的な見方ができると判断した人を選んだ」と答えた。日本の捜査当局は国際刑事警察機構(ICPO)を通じて元会長を国際手配し、7日に駐レバノン大使がアウン大統領と面会して協力を求めた。だが、元会長はレバノンの政財界に太いパイプを持ち、同国政府はこれまで一貫して元会長を擁護する立場を取ってきた。捜査関係者は「レバノン政府が元会長を日本に引き渡すとは思えない」と悲観的な見方を示す。元会長はレバノンに長期間滞在する考えを示し、「数週間以内に全ての証拠を開示し、嫌疑を晴らしたい。真実を明らかにしたい」とした。安倍晋三首相は8日夜、都内で自民党の河村建夫元官房長官らと会食した。河村氏によると、首相はゴーン元会長を巡る問題について「本来、日産の中で片付けてもらいたかった」と述べたという。 *3-7:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1052965.html (琉球新報社説 2020年1月7日) ゴーン被告国外逃亡 裁判で無罪主張すべきだ まるでスパイ映画を見ているような衝撃的な事件だからこそ、冷静に問題を見極める必要がある。会社法違反罪などで起訴され保釈中の前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告が日本を出国し、国籍があるレバノンに逃亡した。保釈の条件として海外渡航は禁止されていた。東京地裁は保釈を取り消し、保証金15億円を没収する。ゴーン氏は逃亡後、次のような声明を出した。「私はもはや有罪が前提で、差別がはびこり、基本的人権が否定されている不正な日本の司法制度の人質ではなくなる。日本の司法制度は、国際法や条約に基づく法的義務を著しく無視している。私は裁きから逃れたのではなく、不正と政治的迫害から逃れた」。否認すれば勾留が長引く「人質司法」は日本の司法制度の問題点として、かねて批判されてきた。早く解放されたいがために、やってもいない罪を認めてしまうなど冤罪の温床ともいわれる。裁判で有罪が確定するまで罪を犯していないものとして扱う「無罪の推定」原則にもとる人権上の問題も指摘されている。その意味でゴーン氏が指摘する「人質司法」の問題は、日本の司法制度の欠陥として改善すべき点が多い。その点は指摘を真摯(しんし)に受け止めるべきである。しかしその問題と、今回ゴーン氏が違法と知りつつ企てて実行した国外逃亡の責任は別の問題だ。ゴーン氏は日本の制度下で保障された権利でもって経済活動をし、多大な報酬と高い地位を得ていた。その中で日本の刑事法により罪に問われた以上、法の手続きにのっとって裁判で主張すべきだ。それが義務である。そうせずに国外に逃亡した責任は厳しく問われるべきだ。法的責任だけではない。金さえあれば違法行為もまかり通るという悪印象を世界に与えた責任も重い。逃亡の過程では、米国の警備会社やトルコの航空会社職員を含め組織的に違法行為を重ねた疑いがある。日本では入管難民法違反の疑いがあるだけでなく、出入国を巡る国際的な司法への挑戦とも受け取れる。ただ、今回の事件を保釈条件の厳格化につなげてはならない。国際的に批判を浴びている身柄拘束の在り方を是認する意見が強まることを危惧する。日本の保釈率は最近10年、わずかに上がる傾向にある。人権に配慮する流れを止めてはならない。重要なのは、ゴーン氏がなぜ国外へ逃亡できたかを詳細に検証することだ。関係当局にとっては、映画のような逃亡劇を現実に許した大失態である。重大に受け止め、再発防止を徹底する必要がある。ゴーン氏は、自身が「無罪だ」と主張するのなら、日本の裁判の場で身の潔白を証明すべきだ。そうしてこそ、日本の司法制度の欠陥に対する自身の指摘に説得力を持たせることもできる。国外逃亡は道理から外れた道だ。 *3-8:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202001/CK2020011002000256.html (東京新聞 2020年1月10日) 森法相「誤った喧伝看過できない」 ゴーン被告「法相の発言は愚か」 レバノンに逃亡した前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告は九日、森雅子法相が被告の記者会見を受けて「わが国の法制度や運用について誤った事実を殊更に喧伝(けんでん)し、到底看過できない」などと批判したことに対し「非常に愚かだ」と反発した。レバノンのテレビインタビューに答えた。ゴーン被告は八日の記者会見で、日本の司法制度について「『推定有罪』の原則がはびこっている」と非難。森氏も九日に二回にわたって記者会見し「適正な手続きを定め、適正に運用されている」と反論するなど、非難の応酬となっている。被告は森氏の記者会見を受けた九日のテレビインタビューで「日本の司法制度は時代遅れだ」と主張。「有罪率は99・4%で、司法制度が腐敗している。(罪のない)多くの人が刑務所に入れられている」と述べた。法相が個別事件に関して会見すること自体が極めて珍しい。保釈がなかなか認められないとするゴーン被告の主張に欧米やレバノンの一部メディアが同調。日本政府は国際社会に被告への賛同が広がるのを打ち消そうと躍起になっている。 ◆3カ国語でHP掲載 法務省 法務省は九日、ゴーン被告のレバノン逃亡をめぐる森雅子法相の記者会見でのコメントを、日本語のほか、英語、フランス語でもホームページに掲載した。ゴーン被告が八日に開いた記者会見を受け、森氏は九日に会見を二回開催。「(逃亡は)どの国の制度でも許されない」などと批判した。 ◆被告が「無罪証明すべき」 法相、発言を訂正 森雅子法相は九日、日本の司法制度に対するゴーン被告の批判に反論するため、同日未明に開いた記者会見での発言内容の一部を訂正したとツイッターで明らかにした。「無罪を主張」と言うべきところを「無罪を証明」と言い間違えたとしている。森氏は会見で「潔白だと言うのなら、(日本の)司法の場で正々堂々と無罪を証明するべきだ」と発言。刑事裁判では、あくまで「推定無罪」の原則があり、その中で検察官が有罪を立証する仕組みになっているため、インターネット上で批判が出ていた。 <単なる情報戦ではなく、人権を求める戦いである> *4-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202001/CK2020010102000104.html (東京新聞 2020年1月1日) ゴーン被告逃亡 海外報道は好意的 レバノンや仏メディア 日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告の国外逃亡について、逃亡先のレバノンや国籍を持つフランスのメディアはおおむね好意的に伝えた。レバノン紙によると、ゴーン被告は三十日に首都ベイルートの国際空港に到着。大手紙アンナハル記者は「レバノン市民として合法的に入国した。アウン大統領と面会した」としているが、真偽は不明。レバノン政府は今のところ正式なコメントを出していない。両親の出身地で被告が少年時代を過ごしたレバノンでは、立身出世の「英雄」として被告を擁護する声が多い。友人の一人は「新年に訪れた奇跡だ」と歓迎し、「彼はいま、適切な保護下にある」と明かした。別の友人は本紙取材に「彼はレバノンだけではなく、日仏にとって偉大な経営者。母国で無実を証明すればいい」と話した。「ゴーン氏の華々しい新展開」と伝えた仏経済紙レゼコーは、未確認情報ながら「警戒が厳しい大きな空港を避け、人目につく機会が少ない小さな空港からプライベートジェット機で飛んだようだ」と解説。仏高級紙ルモンドは、再保釈された四月から監視下に置かれ「妻と会い、話す権利すらなかった」と一定の理解を示した。一方、仏左派紙リベラシオンは「裁判所による禁止に違反して出国した」「脱獄」などと表現するなど批判的な論調で伝えた。 ◆レバノンと引渡条約なし 外務省幹部「逃げ得の可能性」 外務省幹部は三十一日、前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告が日本から逃亡し、国籍があるレバノンに入国したと表明したことに関し「事実関係を確認中だ」と取材に答えた。政府関係者は身柄引き渡しについて「さまざまな方策を考える必要がある」と述べ、レバノン政府への要請も視野に検討する考えを示した。外務省幹部は、日本とレバノンは犯罪人引渡条約を結んでいないとして「基本的には相手国の理解を得ないと被告人は引き渡されない」と説明。「現段階で、レバノン政府が協力的かどうかは不明だ」と語った。別の外務省幹部は一般論と断った上で「法務省と協議し、外交ルートを通じて引き渡しを求めることになるだろう。ただ、レバノン政府が応じず、『逃げ得』になる可能性がある」と述べた。自民党の葉梨康弘元法務副大臣は取材に対し「公的機関は被告人を監視できるわけではなく、信義則が破られた。想定外で、結果は言語道断だ」と強調した。 ◆楽器箱に隠れ日本脱出? レバノンの主要テレビMTV(電子版)は三十一日、カルロス・ゴーン被告が楽器箱に隠れ、日本の地方空港から出国したと報じた。出国に際し、民間警備会社のようなグループの支援を受けたとしている。情報源は明らかにしておらず、信ぴょう性は不明。レバノン紙アフバルアルヨウムも「警備会社を使い、箱に隠れて密出国した」と報じた。MTVによると、このグループはクリスマスディナーの音楽隊を装ってゴーン被告の滞在先に入り、楽器箱に隠して連れ出した。映画のような脱出劇で、日本の当局者は気付かなかったとした。その後に出国し、トルコ経由でレバノンに入国したが、その際はフランスのパスポートを所持していたと伝えた。 *4-2:https://digital.asahi.com/articles/ASN142HVZN14UHBI007.html?iref=comtop_8_06 (朝日新聞 2020年1月4日) ゴーン被告逃亡「正しかった」8割 仏紙読者アンケート 仏紙ルモンドは3日、日産自動車と仏自動車大手ルノーの会長だったカルロス・ゴーン被告(65)のレバノン逃亡についての論評を掲載し、「本当に汚名をすすぎたかったのなら、裁きから逃れた理由がわからない」として、日本で裁判を受けるべきだったと主張した。ゴーン前会長が声明で、逃亡の理由を「不正な日本の司法制度」から逃れるためとした説明に反論した形だ。同紙は「民主主義国家での裁きを拒み、裁かれる場所をもっとも自分の都合のいいように選ぶ可能性を不当に手に入れた」と前会長の逃亡を批判。「西欧人はゴーン氏の事件を通じて、日本の司法の特殊性、ある意味においてはその厳しさに気づくことになった」と伝えつつ、「彼が逃げ出せたのは、批判されていたほどは(保釈条件が)厳しくなかったからだ」とも指摘した。日本の犯罪率の低さといった要素を踏まえずに「中世のような(遅れた)司法システム」と非難するのは、「日本の文化の正しい理解にもとづかない」ものだと論じた。ただ、日本の司法システムを批判する論調が支配的なフランスでは、ゴーン前会長の逃亡容認論が根強い。仏紙フィガロが2日、「ゴーン氏が日本から逃げ出したのは正しかったか」と読者に尋ねたところ、そうだと応じた人が77%に上った。同紙は毎日、主要ニュースについてのアンケートを実施している。紙面にその日の質問を載せて同紙のサイトで投票してもらい、翌日の紙面で結果を伝える仕組みだ。ゴーン前会長の逃亡問題には、8万6798人が投票した。投票ページに寄せられたコメントには「有罪がまったく証明されていないのに非人間的な扱いをする日本人の爪から抜け出した。見事だ」「ゴーン氏は何年間もフランスの最も主要な企業の一つ(ルノー)に奉仕した偉大な人物だ」「日本の司法は全く偏っている。逃げ出せてようやくゴーン氏は説明の場を持てる」など、逃亡を肯定する書き込みが並ぶ。「この逃亡は、フランスのイメージを悪くするだろう。日本人は、どこかフランスを体現しているこの男(ゴーン前会長)の恥ずべき逃避を忘れないだろう」といった声も寄せられている。 *4-3:https://digital.asahi.com/articles/ASN132TS1N13UHBI009.html?iref=comtop_8_04 (朝日新聞 2020年1月3日) ゴーン被告、ハリウッド映画プロデューサーと面会 米紙 米紙ニューヨーク・タイムズは2日、レバノンに逃亡した日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)が昨年12月、東京都内の住居で、ハリウッドの映画プロデューサーと面会していたと報じた。ゴーン前会長は日本の司法制度への不満を語っていたといい、同紙は「2人の会話が、ゴーン前会長の当時の思考の一端を知るヒントになるかもしれない」としている。同紙によると、ゴーン前会長が面会したのは、米アカデミー賞作品賞などを受賞した「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」(2014年)のプロデューサーを務めたジョン・レッシャー氏。ゴーン前会長はレッシャー氏に対して日本の司法制度を批判し、無実の証明に苦心していることを説明。映画をつくれば、人びとがより自らに同情的になってくれるかどうかを気にしていたという。ゴーン前会長を知る複数の人物の話として同紙が報じたところでは、ゴーン前会長は日本での初公判に向けた手続きが進む中、著名人の裁判について調べていた。極めて高い確率で有罪になる日本では、公正な裁判が受けられないと確信するようになったという。楽器を入れる箱に隠れ、プライベートジェットを使ったなどといわれるゴーン前会長の逃亡をめぐっては、欧米メディアが「スパイ映画のよう」などと報道。同紙も「ハリウッドらしい要素は全てそろっている」と伝えている。ただ、レッシャー氏との面会が、ゴーン前会長の逃亡方法に影響を与えたかは定かではない。レッシャー氏は、日本の新聞社に在籍していた米国人記者の体験記をもとにしたドラマの制作陣に名を連ねている。朝日新聞は、レッシャー氏が代表を務める米カリフォルニア州のプロダクションに連絡したが、2日夜時点でコメントは得られていない。 *4-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200110&ng=DGKKZO54227140Z00C20A1EA1000 (日経新聞社説 2020.1.10) ゴーン元会長の「情報戦」に有効な反論を 特別背任などの罪で起訴され、保釈中に密出国した日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告が逃亡先のレバノンで記者会見した。日本の刑事司法を批判し、逮捕は検察と日産の共謀によるもので自分は無実などと、これまでとほぼ同じ主張を繰り返した。これが日本の法廷の場であれば議論が深まったかもしれない。そう思うと残念だ。世界を驚かせた日産をめぐる事件の裁判は開かれず、真相は分からないままになってしまう可能性が高い。歴史、文化や国内の治安情勢が違うのだから、日本とレバノン、フランスなどとでは司法制度もそれぞれ異なる。異なる制度のもとで刑事訴追されたことへの驚きや失意は理解できなくもない。だが元会長が繰り返す日本異質論には誤解や一方的な思い込みが多い。自身の報酬に関する虚偽記載についても無実であれば、なぜ米証券取引委員会(SEC)からの同様の指摘には、争わず100万ドルの課徴金を支払ったのか。納得できるような説明はなく、一方的主張との印象が強い。保釈中に妻と会えなかった点も繰り返し批判している。だが捜査関係者によれば、妻は日産の資金が元会長側に流れたとされる企業の代表を務めていた。通常は「事件関係者」ということになり、接触の禁止は十分ありうる措置だ。東京地検は妻に対しても偽証の疑いで逮捕状を取っている。ゴーン元会長はこの先も、同じような批判をいろいろな場面で繰り返すだろう。元会長に共感する海外メディアも多く、「情報戦」に敗れれば誤ったイメージが定着し、日本の信頼を大きく傷つける。ひいては海外の人たちが、日本で生活することをためらうような事態さえ招きかねない。ゴーン元会長が会見した直後、森雅子法相が未明に会見を開いてすぐに反論したことは評価したい。だが国内だけでなく、あらゆる手段を使って海外に向け、日本の立場や考え方を正しく伝えていく必要がある。今回の問題では、日本の空港でのチェック体制に穴があることが明らかになった。出入国在留管理庁や税関、国土交通省などは深刻に受け止めるべきだ。今年は夏に東京五輪・パラリンピックの開催を控え、テロや不法行為の危険性が高まる。事件を受けて対策を講じたというが、本当に大丈夫なのか。一から見直すべきである。 <日本はこうして遅れていく> *5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191123&ng=DGKKZO52522790S9A121C1EA1000 (日経新聞 2019.11.23) トヨタ、中国2位に、1~9月新車販売、GM抜く 中国の1~9月の新車販売台数(乗用車)でトヨタ自動車が米ゼネラル・モーターズ(GM)などを抜き、前年同期の5位から2位に浮上した。中国政府との関係を強化し、環境技術の協力や販売店の整備などで攻勢をかけるなど中国を重視してきた戦略が実を結びつつある。「中国は国を挙げて電気自動車(EV)を推進している。需要にこたえる重要なモデルだ」。22日に開幕した広州国際汽車展覧会(広州モーターショー)で、トヨタのレクサス部門トップの沢良宏執行役員は力を込めた。レクサス初のEVを世界に先駆けて公開し、中国を重視している姿勢を印象づけた。トヨタと中国の合弁会社は多目的スポーツ車(SUV)の中国専用車も発表した。SUVは中国の乗用車市場の4割を占め、メーカーの勢力図を左右する。戦略車で現地の若者らを取り込む。トヨタの中国での勢いは著しい。英調査会社のLMCオートモーティブによると、1~9月の新車販売台数(乗用車)シェアは前年同期の5位(6.4%)から2位(7.8%)に浮上した。中国全体の新車販売台数は1~9月に1837万台と10.3%減った。好調だったEVを中心とする新エネルギー車も7月から前年同月比マイナスに転じ、10月は5割近く減った。政府が6月下旬から補助金を減らした影響が大きい。主要メーカーは規制対応で新エネ車の投入を増やしており、競争は激しさを増す。GMや同社と組む上海汽車集団の独自ブランド、民営最大手の浙江吉利控股集団などが販売台数を落とすなか「シビック」が若者をつかんだホンダは13%増、「カローラ」が人気のトヨタも8%増だった。LMCオートモーティブの康軍アナリストはトヨタは「現地の若者向けのデザインが成功し、販売価格や豊富な品ぞろえが顧客獲得につながった」という。足元では年間約50店のペースで販売店を増やし、販売店網も「レクサス」を含め約1300店舗(2019年1月時点)に広がった。また、中国系メーカーが7月に都市部などで施行された新排ガス規制「国6」対応で出遅れたのに対し、日本車の燃費の良さなどが評価されてきたことも大きい。米中貿易摩擦で米国車のイメージが悪化したという敵失もあった。 *5-2: https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191203&ng=DGKKZO52875480S9A201C1EA1000 (日経新聞 2019.12.3) 欧州車、生産も「CO2ゼロ」、VW、EV部品会社に義務付け 排出枠取得、新たな負担に 欧州の自動車大手が事業活動に伴う二酸化炭素(CO2)の純排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」を相次いで宣言している。欧州連合(EU)が義務付けを目指し、消費者の環境意識も高まる中での各社の危機感が背景にある。自動車大手は部品や物流も含む排出ゼロをめざすが、部品などのサプライヤーには波紋が広がる。11月4日、独フォルクスワーゲン(VW)の電気自動車(EV)「ID.3」の量産が独東部ツウィッカウ工場で始まった。式典でメルケル首相が「独自動車産業の未来の礎石となる」と述べ、VWのヘルベルト・ディース社長は「VWの新しい歴史が始まる」と応えた。VWが自賛する理由は欧州最大のEV工場というだけではない。生産する車種はVW初のカーボンニュートラルだ。VWは使用電力に再生可能エネルギーを購入、車両輸送などで減らせないCO2分はインドネシアの熱帯雨林保存プロジェクトに投じ相殺する。走行時にCO2を出さないEVには「不都合な真実」がある。火力発電が多い地域では、走行のための電気や電池をつくる際にCO2を出す。生産やエネルギー生成、リサイクルまでを評価するライフサイクル評価(LCA)で見ると、ガソリン車より多くCO2を排出することもある。 ●「悪玉論」広がる そこで企業は行動に移した。VWは全体で2050年にカーボンニュートラル達成を目指して工場投資を決め、独ダイムラーも39年の実現を打ち出した。欧州以外の企業に先んじ、動いたのは2つ理由がある。一つはEUの欧州委員会が50年にEU全体でのカーボンニュートラル義務付けに向け動いていることだ。石炭火力発電に頼る東欧の加盟国は反発するが、西欧でコンセンサスになりつつあり企業は今から対応が必要だ。もう一つは「自動車悪玉論」の広がりだ。9月のフランクフルト国際自動車ショーでは環境団体「ザンド・イン・ゲトリーベ」が「自動車は悪」と訴え、会場の入り口のひとつを封鎖する過激な行動に出た。別の団体は自転車で1万2500人が会場に乗り付けるデモを実施した。自動車大手の中には将来の販売減につながるとの危機感も出始める。VWのディース社長は「ザンド」との対話にも乗り出し、負のイメージ払拭に躍起だ。もっとも自社だけでニュートラル達成は難しい。VWはID.3に部品を供給する企業から初めてカーボンニュートラルを義務付ける契約を結んだ。車載電池は韓国LG化学が再生エネを使い生産しているという。だがほとんどの部品メーカーが排出枠の購入などで辻つまを合わせているとみられる。環境の名の下の新たな負担だ。VWは手綱を緩めない。調達担当のシュテファン・ゾンマー取締役は「持続可能性は(サプライヤーとの)取引を決める要素となる」と述べ、義務化の対象を他の車種、工場に広げる計画だ。 ●素材産業厳しく 5月に車部品世界首位の独ボッシュが唐突に20年のニュートラル達成を宣言したのも、こうした背景があるもよう。同社はまず排出枠を購入し、30年までに2400億円超を省エネや再生エネに投資して実現する考えだ。独部品大手コンチネンタルも9月、40年に実現するとの目標を掲げた。苦しいのがCO2を多く排出する素材産業だ。樹脂大手の独コベストロは25年に09年比50%削減の目標を掲げるが、マルクス・シュタイレマン社長は「今はここまでしか宣言できない」と努力の限界を指摘する。電源構成や電力料金など外部要因に依存する部分が大きいからだ。鉄鋼もCO2を排出しない生産は基礎研究段階だ。EUでは車業界に対し、LCAで規制する議論が進む。世界で最も厳しい環境規制を導入し、他地域より企業の競争力を高めるのがEUの施策だった。日本では「夢物語」とも思われる話が現実のビジネスに影響を与え始めている。日本企業も無視できない。 *5-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200112&ng=DGKKZO54325530R10C20A1EA1000 (日経新聞社説 2020.1.12) 化石燃料を使い続けるなら 地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の本格運用が2020年から始まった。温暖化ガスの排出削減に向けた取り組みの強化が求められる中で、排出量が多い石炭火力発電所を使い続ける日本に向けられる視線は厳しい。国が掲げる中長期のエネルギー目標は脱炭素の要請に応えられているか、改めて点検が必要だ。ただし、18年度に国内で消費した1次エネルギーの約9割は、石炭を含む化石燃料だった。私たちの暮らしや経済活動はこれに支えられている現実がある。太陽光や風力など再生可能エネルギーは最大限伸ばしたい。だが再生エネだけでは需要を賄いきれないとすれば、温暖化対策を講じながら、化石燃料を効率的に使い続ける方法を考える必要がある。手掛かりの一つが、化石燃料から水素を取り出して使う技術だ。石炭や石油を、水素と二酸化炭素(CO2)に分離し、温暖化の原因となるCO2は地中に埋め戻したうえで水素を発電燃料などに使う。こうした活用法の実用化に向けた活動が始まっている。川崎重工業などの企業グループは、オーストラリアの低品位炭から水素を取り出し、これを液化して日本に運ぶサプライチェーンの構築に向けた実証事業を進めている。世界初となる液化水素の運搬船も19年12月に進水した。千代田化工建設などのグループは、天然ガスから取り出した水素を別の化学物質に変えて日本に持ち込む計画だ。国際石油開発帝石や日立造船は、CO2と水素を合成して都市ガスの主成分のメタンをつくる実証試験を開始した。実用化には水素の製造費用を大幅に下げるなど、高いハードルがある。燃料電池車の普及やCO2を出さない発電への転換に弾みをつけるためにコスト低減を急がなければならない。資源国にとっても保有資源を有効に使い続ける道になるはずだ。水素利用技術の確立に向けて、資源国と連携した取り組みを加速していかねばならない。 *5-4:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019121290135411.html (東京新聞 2019年12月12日) 温暖化対策 日本に厳しい目 パリ協定目標「極めて不十分」 海外の研究機関でつくる「クライメート・アクション・トラッカー」は、開催中の気候変動枠組み条約第二十五回締約国会議(COP25)の会場で、地球温暖化対策のパリ協定で三十余りの国や地域が掲げる目標や政策の評価を公表。日本については、国内外で石炭火力発電所を推進していることなどを理由に六段階評価で下から二番目の「極めて不十分」と判定した。パリ協定は産業革命前からの気温上昇を二度未満、できれば一・五度に抑えることを目指しているが、各国の目標の水準では今世紀末に約三度上昇すると予測。目標の引き上げを求めた。世界全体では、再生可能エネルギーが順調に普及しているものの、天然ガスの利用が拡大。二〇一七~一八年に化石燃料の燃焼で増加した二酸化炭素排出量の三分の二近くが天然ガスによるとして、歯止めをかけるよう警鐘を鳴らした。最高評価の「見本になる」に当たる国はなかった。それに次ぐ「一・五度に整合」がガンビアとモロッコ、「二度に整合」にインドやコスタリカなど六カ国が入った。天然ガスの利用が増えている欧州連合(EU)やオーストラリアなど十一カ国・地域は「不十分」と評価。それより低い評価の「極めて不十分」は日本や中国、韓国、ドイツなど十カ国だった。担当者は「日本は石炭や天然ガスへの依存から早急に脱却し、海外援助も中止するべきだ」とコメントした。パリ協定離脱を国連に正式通告した米国は、ロシアやサウジアラビアなど五カ国とともに最低の「決定的に不十分」とされた。 <意思決定と教育> PS(2020/1/13追加):*6-1のように、国連環境計画(UNEP)が、2008年から2017年までの10年間を「失われた10年だった」と厳しく総括する報告書をまとめたが、日本は国内で石炭火力発電所の新設を進め、海外でも石炭火力発電所の建設支援を続けている。日本には再エネ資源が豊富なのに、日本の意思決定権者が一昔前の化石燃料や原発から脱却できないのは何故かと考えると、科学的・論理的に思考して実行するための勉強(≒教育)ができていないからだ。そして、これはEVを世界最初に実用化したゴーン氏と、それにケチをつけることしかできなかった日本のメディア・行政との違いでもある。 日本は、1980年代に「ゆとり教育」と称する勉強しない方向への教育改革を進めたので、社会を構成する人々の知的判断力が低くなった。*6-2に書かれている思考力・判断力はもちろん重要だが、それには知識や論理的思考訓練が必要なのである。また、論理的思考には理数系科目の理解が不可欠であるため、「ゆとり教育」で理数系の内容を削減したのも間違いだった。 なお、何かしようとすると、*6-2・*6-3のように、「教員に時間的余裕がない」「長時間労働を是正すべき」「働き方改革が必要」という声が必ず聞かれるが、合理的に自分たちの問題を解決して必要な教育を遂行することのできない学校や教員が、生徒に思考力・判断力・問題解決力などを教えられる筈がなく、教員の質の低下は既に起こっているのではないかと思う。もし、教員の質が高く、教科に興味をわかせる教育ができたら、モンスターになる生徒や保護者はもっと減ると思われる。 世界は、*6-4のように、新たな「学歴社会」に突入しており、高度な知識や技能を要する仕事が多くなった。そのため、教員にも修士号・博士号を要求してよいのかもしれないが、日本は、“専門性より人間性”を重視する雇用慣行を維持したままである。しかし、実際には、専門性と人間性は二者択一の性格ではないため、これらを二者択一であるかのように言う文化が問題なのであり、専門性や技術力がなければ競争以前なのである。 *6-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/475644 (佐賀新聞 2020/1/12) 温室ガス排出量、増加続く、「失われた10年」と国連総括 2008年から17年までの10年間に世界の温室効果ガス排出量がほぼ一貫して増え続け、国連環境計画(UNEP)が「失われた10年だった」とこの間の地球温暖化政策を厳しく総括する報告書をまとめていたことが12日分かった。各国の削減対策は不十分としており、18年も排出量は増加。パリ協定の温暖化抑制目標を達成するには石炭火力発電所の新設中止など思い切った対策が急務だと指摘している。国内で石炭火力発電所の新設を進め、海外の建設支援も続ける日本に方針転換を求める圧力がさらに強まりそうだ。報告書によると、UNEPが世界の排出量の分析を始めた08年から17年までに世界の温室効果ガス排出量は平均で年1・6%増加し、17年には過去最高の535億トンに達した。約10年前に「目立った削減対策が取られず、成り行きのまま排出量が増える」とのシナリオで予測された排出の伸びとほぼ等しかった。18年はさらに増えて553億トンに上ったとみられている。それでも各国政府が再生可能エネルギーや省エネの大幅拡大、森林破壊の防止や植林などの対策を大幅に強化すれば「産業革命以来の気温上昇を2度より十分低くし、1・5度になるよう努力する」とのパリ協定の目標達成はまだ不可能ではないと分析した。一方で現在、建設中の石炭火力発電所が全て稼働すると気温上昇を1・5度に抑えることは不可能で「新設をやめ、既存の発電所も徐々に減らすことが目標達成に欠かせない」と指摘した。UNEPは08年から毎年、温暖化の被害防止に必要な温室効果ガスの削減量と実際の排出状況に関する調査報告をまとめている。今回、10年間の変化を改めて分析した。 *6-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/573435/ (西日本新聞社説 2020/1/6) 教育再生元年 学ぶ喜びを知ってほしい 新学習指導要領がこの4月から、小中高で順次実施され、戦後教育の転換点ともいわれる大改革がいよいよ本格化する。学年を問わず「主体的・対話的で深い学び」という新たな指導理念が導入される。知識を蓄えるだけでなく、それを活用する思考力や判断力、表現力などを育むことが主眼である。小学高学年では外国語(英語)が教科となる。論理的思考を学ぶプログラミング教育も始まる。グローバリズムやIT社会に対応するためとされる。高校ではいずれ、大規模な教科・科目再編も行われる予定だ。負担が確実に増えるだけに、子どもが「学ぶ喜び」と「考える楽しみ」を体得できるよう、教員は指導に知恵を絞ってほしい。学習の原動力は、何よりも知的好奇心である。 ■読解力向上が課題だ 戦後、日本の教育行政は「詰め込み」と「ゆとり」の間を振り子のように揺れてきた。米国流の自由で余裕のある教育から始まり、1960年代以降は学習量が増え、カリキュラムも過密化した。これが詰め込み教育と批判され、国は80年代に学習量を減らすゆとり教育を進めた。しかし、2000年代に入ると潮目が変わる。15歳の応用力や読解力を問うため、経済協力開発機構(OECD)が実施する学習到達度調査(PISA)で03年、日本は大きく順位を下げた。いわゆる「PISAショック」だ。この結果を受け、文部科学省は前回の指導要領改定で「脱ゆとり」にかじを切った。今回の改定はその流れを踏襲し、さらに深い思考力などの育成を目指している。昨年末発表されたPISA18年調査では、科学と数学の応用力は上位に踏みとどまったものの読解力は15位と低迷した。この順位に一喜一憂する必要はないが、読解力は学力の土台だ。読解力が伸び悩む要因に、若者に広がる会員制交流サイト(SNS)が短文中心である影響を指摘する識者もいる。授業で長文に親しむ機会を増やす工夫を求めたい。授業で新聞を活用するNIE(教育に新聞を)の推進も後押しになるだろう。家庭でも、SNSのルールをつくり、読書習慣を生活に定着させてほしい。 ■現場の声に耳を傾け 「主体的・対話的で深い学び」の実現には、教員にも授業を練る余裕が欠かせない。公立小学校の18年度教員採用試験の倍率は2・8倍で過去最低だった。九州では福岡県の1・3倍を筆頭に2倍未満が4県もある。定年による大量退職時代の到来と相まって、教育の質の低下を招きかねない深刻な事態と言えよう。民間への就職の堅調さが背景にあるようだが、教員という仕事を敬遠する風潮も広がってはいないか。深刻な長時間労働を是正するため、働き方改革を急ぐべきだ。まずは、各学校で教員が担う膨大な業務の削減に本気で取り組んでほしい。一連の改革は政府の教育再生実行会議が起点となってきた。大改革だけに、政治主導による強いリーダーシップが必要な場面もあろう。ただ議論が生煮えのまま「改革ありき」で強行しては、教育の現場に混乱を広げてしまう。大学入試改革を巡る騒動に、それは明らかだ。英語民間検定試験と国語・数学への記述式問題を導入する方針を検討した二つの会議の内容が昨年末公開された。16年の時点で、昨年問題となった地域格差や採点ミスの可能性は指摘されていた。文科省は仕切り直しの議論の中で、現場や識者の声に誠実に耳を傾けるべきだ。今年は「教育再生元年」とも呼ばれる。主体的に行動し、よく考えて判断する。異なる意見を持つ人と話し合い、問題を解決する-そんな力を養える教育環境を着実に整えたい。 *6-3:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1055817.html (琉球新報社説 2020年1月12日) 教員の長時間労働 働き方改革の道筋付けよ 長時間労働などで学校現場が疲弊し、教員にゆとりや将来への希望が見えなくなっている現状が改めて浮き彫りになった。県教職員組合(沖教組)が40歳未満の若手教職員に行ったアンケートで、定年まで現在のような働き方を続けられないとする人が55%に上った。月平均の時間外労働は平均55・7時間となり、持ち帰りの仕事も10・6時間あった。働き方改革関連法の施行によって、民間企業では時間外労働は原則月45時間と定められたが、それを大きく超える実態だ。教育現場はいじめや不登校などの課題が山積している。「モンスターペアレント」の対応に神経をすり減らす例があるのも事実だ。教員が多忙故に疲れ切っていては適切な対処ができない恐れがある。教員の残業を減らし、ゆとりある教育現場にするための具体的な対策が求められる。本紙が昨年12月に市町村の教育委員会へ聞いたアンケートでも、公立小中学校で月100時間を超える残業をした教員が延べ810人、「過労死ライン」とされる80時間超は少なくとも延べ2329人だった。学校現場の長時間労働は常態化している。文部科学省は昨年1月、働き方関連法に沿う形で公立校の教員の残業が月45時間を超えないようにする指針を出した。しかし、指針に罰則規定はなく、「臨時的な特別の事情」の場合は月100時間を超えない範囲で延長できるとしている。そもそも県内の公立小中学校でタイムカードやICカードなどで客観的に勤務時間を把握していたのはおよそ半数の21市町村だった。その他は教員自身がエクセルデータに記入したり、出勤簿に押印したりする方法で勤怠を管理していた。労働時間が正確に管理されず、月45時間の指針を守らなくても罰則もない状況では、指針が形骸化しているのも無理はない。沖教組のアンケートによれば、教員が本来時間をかけたいのは教材研究や補習指導、学年学級運営など子どもたちを指導する業務だが、時間外勤務が発生する理由は報告書作成や校務分掌などが上位となり、生徒と向き合う時間が取れていない実態も見えた。経済協力開発機構(OECD)の国際教員指導環境調査で日本の中学校教員の週当たりの仕事時間は56時間と世界最長だ。にもかかわらず、生徒が自ら考える力を育む授業を実践する教員は各国平均に比べて低い水準にある。多忙さが子どもの指導に向けられていないのだ。いま、学習指導は暗記中心の授業から表現力や深い思考を養う方向へ転換している。教員の指導法がより高度になるよう、授業の準備を充実させる時間が必要だ。教員の仕事の在り方を抜本的に見直し、働き方改革の道筋を付けたい。 *6-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191208&ng=DGKKZO53006550V01C19A2MM8000 (日経新聞 2019.12.8) 「博士」生かせぬ日本企業、取得者10年で16%減 世界競争、出遅れも 世界は新たな「学歴社会」に突入している。経営の第一線やデジタル分野では高度な知識や技能の証明が求められ、修士・博士号の取得が加速する。主な国では過去10年で博士号の取得者が急増したのと対照的に、日本は1割以上減った。専門性よりも人柄を重視する雇用慣行を維持したままでは、世界の人材獲得競争に取り残されかねない。「日本人だけでは定員を埋められない。経済学の修士課程は6割が留学生だ」。データ分析を駆使したミクロ経済学を研究する、東京大学の渡辺安虎教授は危機感を募らせる。今夏まで米アマゾン・ドット・コム日本法人で経済学部門長を務めた経験から「社会的なニーズは必ずある」と断言するが、日本人の大学院への進学意欲は乏しい。科学技術・学術政策研究所によると、米国や中国では2016年度までの10年間に博士号取得者が2割超増えた。修士号でも傾向は同じ。企業などで上級ポストを射止めるには高い学位が必要になる。グーグルなど米IT大手に先端分野の技術者として入社するには、修士・博士号が求められる。トランプ政権がビザ発給を厳格化するまで、中国からは年数千人が渡米して博士号を取得。民間企業の成長のけん引役になっていた。一方、日本の博士号取得者は16年度に1万5000人と10年間で16%減った。少子化は関係ない。この間に4年制大学の入学者は一貫して増えている。学生が専門課程への進学をためらい、日本は世界の中で相対的な「低学歴化」に沈んでいるのが実情だ。大学などの研究者の収入が不安定な面は否めないが、企業の機能不全も深刻だ。博士課程で人工知能(AI)を専攻した大山純さん(仮名)は今、国内電機大手でインフラ分野の営業と開発に従事する。採用面接では専門知識はほぼ問われず、逆にこう求められた。「学位取得より入社を優先してほしい」。結局、博士号は取らなかった。経団連は毎年、加盟各社が「選考時に重視した点」を調べている。上位を占めるのは「専門性」ではなく、「コミュニケーション能力」など人柄に関する項目ばかりだ。入社後も専門性は評価されにくい。30歳前後の平均年収を比べると、日本の学部卒人材が418万円なのに対し、修士・博士の大学院卒は524万円。その差は1.25倍だ。米国の修士の平均年収は763万円で、学部卒の1.4倍を稼ぐ。博士では915万円と1.68倍まで開く。高学歴者に高収入で報いるのは、世界の常識だ。社会学者の小熊英二・慶応義塾大学教授は「グローバルの人材評価基準から日本市場は隔絶されている」と指摘する。倍以上の年収で外資に転じる博士が後を絶たないのは、国内企業の待遇の悪さの裏返しだ。「社会」に出ても稼げないため、日本では博士号を保持する研究者の75%が大学などに所属する。日本では1990年代に政府主導で博士を増やしたが、雇用が不安定なポスドク問題を生み出した。科学技術振興機構の永野博研究主幹は「企業に採用される人材を、大学側が育ててこなかった面もある」と話す。米国では博士の4割が企業で働き、イノベーションの原動力になっている。高度人材の育成と確保は、国家の競争力も左右する。雇用慣行と教育現場。2つのアプローチで改革を急ぐ必要がある。 <警察の呆れた優先順位> PS(2020年1月14日追加):ゴーン氏の場合は刑事事件になるか否かもわからないようなことで長期間拘束したが、40代の女性を人質にとって立てこもった20代の日本人男性に対しては、*7のように、10時間経っても警察官が事務所内で男の説得を続けているのに呆れた。単独の現行犯なのだから、その男を拘束すると同時にさっさと女性を解放しなければ、その女性はたまったものではないだろう。つまり、警察は、日産のような組織は護るが、40代の女性のような個人はどうでもよいという価値観を持っているらしく、この価値観がおかしいのである。これなら、被害者になった場合でも、日本の警察に頼むより元グリーンベレーの人に頼んだ方が早そうだ。 *7:https://digital.asahi.com/articles/ASN1G571VN1GPTIB00D.html?iref=comtop_latestnews_02 (朝日新聞 2020年1月14日) 立てこもりの男が軽いけが 女性が人質、説得続く 出雲 14日午後2時半ごろ、島根県出雲市神西沖町(じんざいおきちょう)の運送会社「上田コールド」の従業員から「立てこもりたいという男が来て部屋の外に出された」と110番通報があった。島根県警によると、男は刃物のようなものを持っており、同日午後10時現在、事務所2階で40代の女性従業員を人質にとって立てこもっている。女性にけがはないが、男は軽いけがをしているという。県警によると、男は「社長に会わせろ」という趣旨の話をしており、警察官が事務所内で男の説得を続けている。男は階段に通じる廊下にいて、比較的落ち着いた状態だが、ブラインドをおろす時にけがをしたと話しているという。女性従業員は廊下の奥の部屋に入れられているという。県警によると、男は午後2時20分ごろ、事務所を訪れ、「今から立てこもる」と言って女性従業員を人質にとった。当時、7人ほどの従業員がいたが、ほかの従業員は外に出されたという。県警は、男は20代で、同社との雇用や取引の関係はないとみている。現場は、JR山陰線の出雲神西駅から北西約1・5キロで、周囲には住宅や田畑が広がる。40代の男性従業員は「配送から戻ってきたら事件が起きていた。会社ともめて辞めたような人は聞いていない。女性が心配だ」と話した。同社のホームページによると、同社は生鮮品の冷凍・冷蔵輸送に特化した運送会社。1973年の創業で出雲市や鳥取市に物流センターがある。上田コールド出雲物流センター(出雲市長浜町)の従業員によると、本社では普段、10人前後が働いているという。 <ゴーン氏の主張は正当である> PS(2020年1月17日追加):*8のように、日産は、ゴーン氏の不正を許してきたガバナンスの改善などに関する報告書を東京証券取引所に提出して、CEOリザーブ(CEOの交際費の筈)を利用した支出、仏ルノーとの統括会社を使った会社資金の私的流用等の不正に関する社内調査結果を新たに盛り込み、「ゴーン氏が事実を隠したため、取締役は不自然さを探知できず、監査役も是正できなかった」とし、ゴーン氏の方は、「CEOリザーブは多くの役員がチェックするもので、私のサインだけで支払われたCEOリザーブは1ドルもない」と主張しているそうだ。 しかし、①CEOリザーブを設けること自体 ②その金額 ③使い方 などについては、役員が了承し監査役もチェックしている筈で、チェックする立場の人は疑問があれば質問して妥当性を調べるのも仕事のうちであるため、「不自然さを探知できなかった」「ゴーン氏のすることに反対できなかった」と言うのは「仕事をしていなかった」と言うのと同義である。一方、ゴーン氏だけのサインで支払われたCEOリザーブが1ドルもないのであれば、思いついたように後付けでゴーン氏のみを批判するのは妥当ではない。 *8:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14329752.html (朝日新聞 2020年1月17日) 日産、東証に不正調査を報告 「ゴーン前会長への反論」 日産自動車は16日、カルロス・ゴーン前会長による不正を許してきたガバナンス(企業統治)の改善などに関する報告書を東京証券取引所に提出した。CEO(最高経営責任者)の裁量で使える予算「CEOリザーブ(予備費)」を利用した支出や、仏自動車大手ルノーとの統括会社を舞台にした会社資金の私的流用など、前会長の不正に関する社内調査結果を新たに盛り込んだ。逃亡先のレバノンで開いた会見で「無実」を主張した前会長と真っ向から対立する内容だ。報告書では、前会長がCEOリザーブを使って、海外の知人が経営する企業や、販売代理店に計4670万ドル(約51億円)の不正な支出をしたと認定。前会長をめぐる特別背任事件で、東京地検特捜部が起訴した内容に重なる。ルノーとの統括会社「ルノー・日産BV(RNBV)」を通じて、パリ郊外のベルサイユ宮殿でのパーティー費用やカンヌ映画祭への知人の招待費用などの私的な支出を含め、少なくとも計1137万ユーロ(約14億円)の不正支出があったとも認定した。これらの調査結果は、昨年6月に東証に提出した「改善報告書」の内容に付け加える形で盛り込んだ。日産幹部は「会見への反論にもなっている」と話す。ゴーン前会長はベイルートで8日に開いた会見で、CEOリザーブについて「多くの役員がチェックするものだ。私のサインだけで支払われたCEOリザーブは1ドルもない」と主張。日産は報告書でこうした支出の背景について、前会長が「事実を隠したため、取締役は不自然さを探知できず、監査役も是正できなかった」と指摘した。
| 司法の問題点::2014.3~ | 09:01 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,12,16, Monday
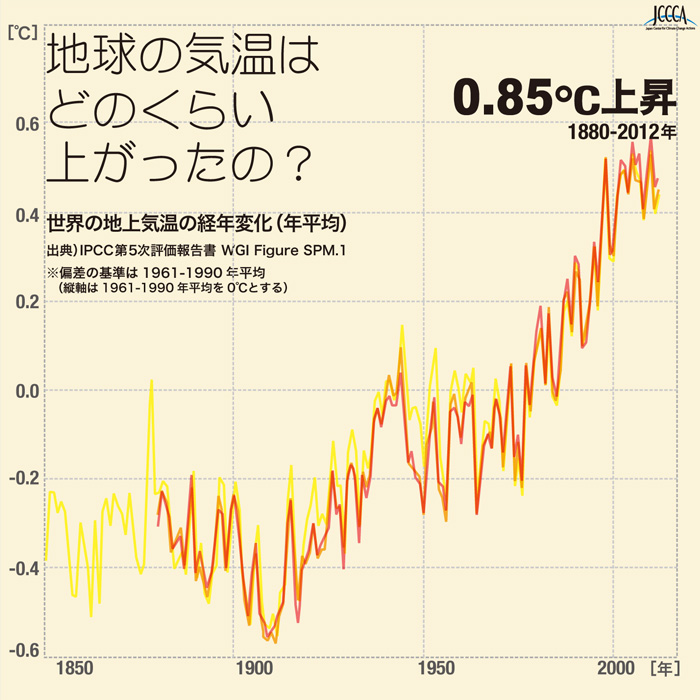 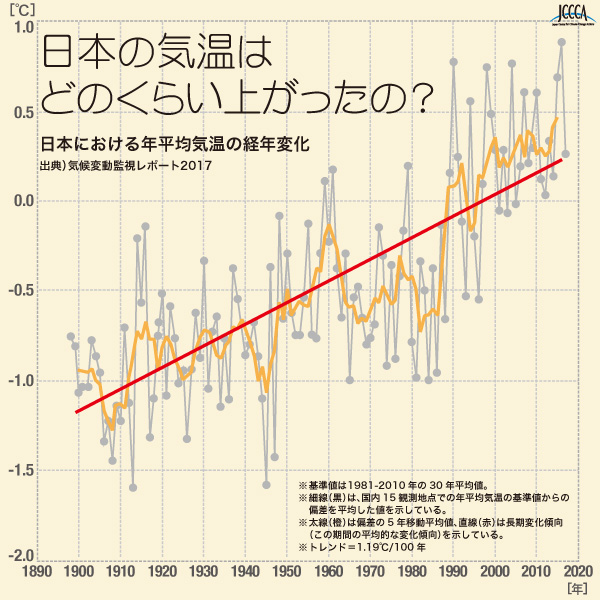 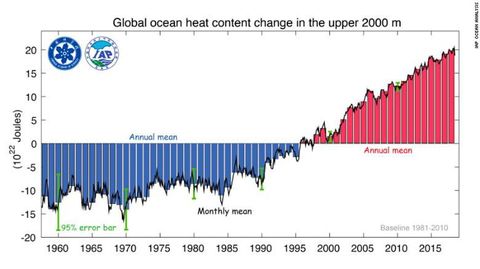 気温の上昇 海水温の上昇 (図の説明:左図のように、地球の気温は1880年~2012年に0.85°C上昇し、中央の図のように、日本の気温は1900年~2017年に1.19°C上昇している。また、右図のように、海水温も上昇しており、これらは農業・漁業に影響を与えている) (1)米国とのFTA交渉における日本の敗北 1)農業は、自動車と引き換えにはできない 経済官庁が農業を差し出して確保しようとしてきた自動車の利益は確保されず、*1-1のように、日米貿易協定における米国の自動車関連の関税撤廃の約束はあることにされているが実際はなく、これは「ある」ことにしないと米国貿易額の92%をカバーしたとしているのが50%台に落ち込んで国際法違反の協定となり、国会批准ができないからだそうだ。 この日米貿易協定は、自動車・部品の関税撤廃が実現しないと800億円程度、農産物は9500億円程度の生産減少が生じる可能性があり、日本のGDPはマイナスになるそうだ。トランプ氏は強力なネゴシエーターで農産物も自動車も「勝ち」、日本は農産物も自動車も「完敗」であり、その上、日本は米国から大量の武器購入や基地負担の増大を要請されて、一部は既に行っているわけである。 こうなった理由は、日本の政治・行政には長期計画やそれに伴う戦略がなく、成り行き任せで国民のために必死の交渉を行わないことや、メディアが外国との交渉中に首相や政治家を批判して貶め、首相をレイムダックのようにさせることが大きいと、私は考える。 2)食料自給率低下と隙だらけの安全保障 TPPや日米貿易協定締結のために、経済官庁が農業を差し出して自動車の利益を確保しようとしたことを受け、日本政府が甘い想定に基づいて農業に厳しい条件を突きつけたため、農業を放棄したり、農業を承継しない人が増えた。 その結果、*1-2のように、耕作放棄や農地転用による農地面積の減少が農水省の想定を大きく上回り、2015~19年(5年間)に、荒廃農地は7万7000ha、農地転用は7万5000ha、合計15万2000haの農地が減少し、再生された農地は3万2000haに留まる。 しかし、*1-3のように、農業の生産基盤や担い手が減れば、1億人の人口を擁する我が国の食料自給率はますます下がり、いくら防衛費を増強しても兵糧攻めだけで結果が出て戦争は終わり、エネルギー自給率も7.4%なので、日本を責めるのに武器はいらないのである。その上、ミサイルに核弾頭など積まなくても、原発を狙えば勝手に自爆する状態だ。 なお、農林水産業は地方の重要な産業であるため、これを大切にせず、たたいて担い手をいためつければ、「地方創生」にも大きなマイナスなのである。 (2)農業の解決例 1)環境税を使う スペインのマドリードで開かれたCOP25は、*2-1のように、徹夜で協議したが対立が解けず、積み残されていたパリ協定の実施ルール作りの合意を断念して次回会合に先送りしたそうだ。私は、化石燃料に世界ベースで環境税をかけて資金を集め、CO₂を吸収する藻場や緑の面積(CO₂吸収力)に応じて公正にそれを配分するのが、どの国からも文句が出ず、エネルギーの転換が進むと考える。 この時は、日本国内の農地・山林・藻場も、その面積(CO₂吸収力)に応じて資金を受け取ることができるので、受け取った資金をその手入れに活かすことができる。 2)温暖化を活かす 地球温暖化が現在のペースで進むと、海面が上昇して陸地が減ったり、野生動植物の生息適地がなくなったりするのだが、日本では、*2-2のように、現在も暖かい地域はさらに暖かくなり、緯度の高い北海道でも米作が容易になり、標高の高い所まで何らかの作物ができるようになるため、自治体毎の影響を環境省のHPで確認できるよう準備を進めているそうだ。 農業分野は、将来のその地域の気候が現在のどの地域と同じになるかをそのHPで判断でき、転換する品目・品種や転換スケジュールの検討で参考になるため、果樹などの栽培や転換に時間がかかるものは、苗木の準備計画に役立ててもらいたいそうだ。 3)生産性を向上させる 農林水産業の全自動化につながる技術開発が進んでいるが、*2-3は、全自動化の技術開発と併せて、農村での雇用創出から定住化につながるような研究をしてもらいたいとしている。 高望みしたり、不可能に挑戦したり、解決の難しい社会の課題に挑んだりすることを「ムーンショット(月を撃つ)」と言うそうだが、そのような人たちのおかげで、現在は、ロケットで月の軌道まで行って実際に月を撃つことができるようになったのである。従って、ムーンショットは実現可能であり、他の技術も同様に進歩しているのだ。 もちろん、全自動化しても、機器を作ったり、使いこなしたり、維持管理したりすることができる人材が必要になるので新しい仕事が生まれるが、若い人が農村に定住したいと思う社会制度にしなければ、国として成り立たなくなることは明らかである。 4)付加価値を上げる ①米粉の例 米粉市場は伸びており、その理由は、*2-4のように、圧倒的な品質力(微細粉にする高い製粉技術、加工技術)の進展でパン・菓子・麺など多彩な商品化が実現し、和菓子やせんべいの原料だった従来の米粉の世界を一新して米粉新時代を開いたからだそうで、消費増で工場の稼働率も向上し、一部メーカーは小麦粉並みの製粉コストを実現して、伸びる需要に生産が追い付いていないとのことである。 実需側の在庫も少なく、このままでは3万トンを超す需要を満たせず、地域によっては原料確保に苦心する企業も出そうで、海外市場も「グルテンフリー市場」が急成長しているとのことだ。私は米粉で作るなら、ラーメンよりフォーだと思うが、今のところ、フォーの即席麺はないため、先入観のない加工品開発や販促活動に期待したい。 ②ゲノム食品の例 消費者庁は、*2-5のように、ゲノム編集技術で品種改良した農水産物の大半について生産者や販売者らにゲノム編集食品であると表示することを義務付けないと発表したが、表示がなければゲノム編集食品かどうか分からないため、消費者が選択できずに悪貨が良貨を駆逐する状況になる。さらに、このような規制は厳しくして対応した方が、付加価値が上がるのである。 (3)その他の地方産業 ①林業 林野庁は、*3-1のように、森林空間を活用した「森林サービス産業」の創出に乗り出し、森林空間そのものを活用して、木材生産・供給だけでなく、健康需要などを見据えて森林体験や商品開発で新たなビジネスを生み出し、山村地域に新たな雇用と収入を生み出すそうだ。 しかし、最も効果があるのは、子育て世代の多くが地方に住み、森林・田畑・海などを見ながら育つ子どもを増やして、自然に対する美意識を育てることだと、私は考える。 ②観光業(クルーズ船の寄港) 2019年の沖縄へのクルーズ船の寄港予定回数は、*3-2のように、過去最多を更新する719回に達するそうだ。経済成長著しいアジアでのクルーズ市場拡大がこの背景にあり、今後も寄港増や船舶の大型化が見込まれるとのことである。 沖縄へのクルーズ船寄港予定回数が過去最多の719回に達する背景には、クルーズ市場が拡大するアジア市場に近接しているという地理的な優位性があり、クルーズ旅行は比較的安価な「カジュアルクルーズ」の増加に伴って市場が拡大しており、沖縄以外の国内でクルーズ船が多く寄港するのはいずれも九州の博多、長崎で、地理的な近さが強みなのは明らかだそうだ。 ③漁業 農水省が、*3-3のように、水産資源保護のために新たな取引規制を作り、魚介類の水揚げ場所や出荷日を示す公的な証明書を作って、国が指定した魚や一部の輸入品を国内で取引するときに添付を求め、違法操業で証明書のない魚介類は事実上、市場で売買できなくするそうだ。 ただ、私は、水産庁の漁業対策は資源管理に偏っており、漁業資源が減少した本当の理由を科学的に追及していない点で不足だと考える。 このような中、*3-4のように、海水温が50年間で表層水温1.23度上昇した結果、朝鮮半島では食卓の魚が変遷し、「イシモチ→スケソウダラ→サバ」と国民魚が変わり、温暖化や乱獲の影響でスケソウダラの「国籍」も変わって、近年はカタクチイワシとサバが豊漁となり、この2~3年の1位はサバだそうだ。 日本でも似たようなことが起こっているため、地球温暖化や海水温上昇の影響は漁業にも大きな影響を与えているわけである。 ・・参考資料・・ <日本の農業と食料自給率> *1-1:https://www.agrinews.co.jp/p49324.html (日本農業新聞 2019年11月26日) 「完敗」 協定の深刻さ 国際法違反 責任重く 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏 このところ、「ある」ものを「ない」と言うのが話題になっているが、「ない」ものを「ある」と言うのもある。日米貿易協定における米国の自動車関連の関税撤廃の約束は、合意文書が示す通り「ない」が、その約束が「ある」ことになっている。それは、「ある」ことにしないと米国側の貿易額の92%をカバーしたとしているのが50%台に落ち込み、前代未聞の国際法違反協定となり、国会批准ができないからである。米国は大統領選対策として成果を急いだので、協定を大統領権限で発効できる(関税が5%以下の品目しか撤廃しない)「つまみ食い」協定と位置付けたから議会承認なしに発効できるが、国会で正式に承認する日本側は国際社会に対する顔向けとしても責任は重い。筆者も役所時代はもちろん、大学に出てから多くの自由貿易協定(FTA)の事前交渉(産官学共同研究会)に参加してきた中で、経済産業省や外務省、財務省が世界貿易機関(WTO)ルールとの整合性を世界的にも最も重視してきたと言っても過言ではない。しかも、経済官庁が農業を差し出して確保しようとしてきた「生命線」たる自動車の利益が確保されなかったのだから、心中は察して余りある。試算例でも明白だ。政府が使用したのと同じモデル(GTAPと呼ばれる)で、自動車関税の撤廃の有無を分けて日米協定の影響の直接効果を改めて試算し直した。「直接効果」とは、政府が用いた「生産性向上効果」(価格下落と同率以上に生産性が向上)、「資本蓄積効果」(国内総生産=GDP=増加と同率で貯蓄・投資が増加)などの、いわゆる「ドーピング剤」を注入する前の効果のことである。表が示す通り、自動車と部品の関税撤廃は日本の生産額を3400億円程度増加させる可能性があるが、関税撤廃が実現しないと800億円程度の生産減少に陥る可能性がある。一方、農産物は9500億円程度の生産減少が生じる可能性も示唆される。全体のGDPで見ても、自動車を含めても0・07%(政府試算の10分の1程度)、自動車が除外された現状ではほぼゼロという状況である。GTAPモデルにおける「労働者は完全流動的に瞬時に職業を変えられる」といった非現実的な仮定を修正すれば、日本のGDPはマイナスになる。日本にとっては農産物も自動車も「負け」、トランプ氏は農産物も自動車も「勝ち」という、日本の完敗の実態が数字からも読み取れる。国際法違反を犯してまで完敗の協定を批准する事態の深刻さを再認識したい。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p49488.html (日本農業新聞 2019年12月14日) 農地減少 政府想定上回る 荒廃、転用2倍ペース 対策見直し必須 耕作放棄や農地の転用による農地面積の減少が農水省の想定を上回って進んでいる。2015~19年の5年間に発生した荒廃農地は7万7000ヘクタール、農地転用は7万5000ヘクタールに上った。それぞれ同省が想定した2・5倍、1・5倍のペースで増えた。農地の再生が一定程度進んだものの、新たな荒廃農地の発生や転用に追い付かない状況だ。農地は1961年をピークに一貫して減少し、2019年は439万7000ヘクタールまで落ち込んだ。政府が15年に策定した食料・農業・農村基本計画に掲げる25年の確保目標440万ヘクタールを既に下回った。19年までの5年間の減少面積は12万1000ヘクタールに及ぶ。同省が変動要因を分析したところ、5年間で新たに発生した荒廃農地と農地以外に転用された面積は、合計で15万2000ヘクタールに上る。一方、再生された農地面積は3万2000ヘクタールにとどまり、減少要因が増加要因を大きく上回った。基本計画では、荒廃農地と農地転用を合計で8万1000ヘクタールにとどめつつ、2万7000ヘクタールの農地を再生することで、農地の減少を5万4000ヘクタールに抑える想定だった。同省は、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度を使って農地保全に取り組んだ地域は耕作放棄が抑制され、農地の再生も想定以上に進み、政策が効果を発揮したとみる。一方、「高齢化の進展や担い手不足などで新たな荒廃農地の発生が大きく見通しを上回った」(農村振興局)と認める。現行の対策だけでは、農地減少が十分に食い止められていないことが明らかになった格好。将来にわたり農地を確保するため、より踏み込んだ対応が求められそうだ。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p48934.html (日本農業新聞 2019年10月8日) 国会論戦に望む 弱る生産基盤「解」導け 安倍晋三首相の所信表明演説に対する各党の代表質問を皮切りに国会論戦が始まった。現憲法下200回目の国会で、令和初の本格的な論戦となる。構造改革路線に偏った農政では農業・農村の未来を切り開けない。生産現場の声に耳を傾け、農家に寄り添う農政に軌道修正する節目の国会とすべきだ。謙虚な政権運営も求められる。首相は所信表明でこれまであまり使わなかった言葉を盛り込んだ。その一つが農業の「生産基盤の強化」だ。日米貿易協定について触れた部分で「それでもなお残る農家の皆さんの不安にもしっかり向き合い、引き続き、生産基盤の強化など十分な対策を講じる」と語った。ところが生産基盤の強化をどう進めるのか、何も語らなかった。一方で「地方創生」の項目で農産物輸出には字数を費やし、「それぞれの地方が誇る農林水産物の輸出をさらに加速」することや「農産品輸出拡大法の制定」を強調した。国内で需要が減る米を海外に輸出できれば、水田を守る手法の一つとはなる。だが、輸出拡大に向けた競争力強化だけでは従来の構造改革路線と何ら変わらない。農家の高齢化や担い手不足は深刻で、中山間地域を中心に集落消滅が起き始めている。規模拡大や競争力強化は必要だが、大規模農家だけでは農村や集落を守れない。中小規模の家族経営を含めて多様な担い手が共存できる農業・農村をどう実現するのか。国会で議論を深め、具体策を示すべきだ。安倍政権が中央集権的な官邸主導の政策決定を進める中で、地方自治体の農業部門は人員、財源とも縮小が進んだ。生産現場と密着した農政は、地方自治体やJAグループなどの農業団体の協力や連携なくして軌道に乗せられない。生産基盤の立て直しに向けは、こうした連携の強化も不可欠だ。首相は所信表明の「一億総活躍社会」の項目で、「多様性」の言葉も使った。農業や農村こそ多様性が重要となる。若い新規就農者から田舎暮らしで移住する定年退職者まで、さまざまな人を呼び込まない限り、生産基盤の強化は絵に描いた餅に終わりかねない。国会は、国民への説明責任を果たす重要な場である。首相は日米貿易協定について「ウィンウィン」と語ったが、それでは納得を得られない。情報開示の在り方も異様だった。日本政府は最終合意するまで公式な情報提供をしなかった。秘密交渉とされた環太平洋連携協定(TPP)でも節目で情報を一定に開示した。「安倍1強」で通商交渉の情報さえ開示されないのであれば、国会は空洞化する。新たな食料・農業・農村基本計画策定や正念場を迎えた米政策2年目、豚コレラ対策など農政を巡る課題は山積みだ。国会で熟議を尽くし、農家に寄り添う施策で国民の財産である農業の生産基盤を後世に引き継ぐのが農政の眼目だろう。 <農業の解決例> *2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019121501001866.html (東京新聞 2019.12.15) COP25、合意断念し先送り パリ協定ルール、対立解けず閉幕 スペイン・マドリードで開かれた国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議(COP25)は15日、一部積み残されていたパリ協定の実施ルール作りの合意を断念し、来年の次回会合に先送りする決議を採択し、閉幕した。会期を2日延長して徹夜で協議したが対立が解けなかった。来年に本格始動するパリ協定では、深刻な地球温暖化を踏まえて史上初めて、全ての参加国が自主的な目標を掲げて温室効果ガス排出削減を進める。ルールの大枠は過去の交渉で決まっており、完成しなくても協定は始動するが、出だしから課題を抱えることになった。来年の会議は11月に英国で開かれる。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p49450.html (日本農業新聞 2019年12月10日) 温暖化で植物適地移動 VoCCで分析 果樹転換参考に 長野県など研究 地球温暖化が現在のペースで進むと、国内の高山帯に生息する野生動植物は、21世紀末に生息適地がなくなる可能性がある──。長野県環境保全研究所などでつくる研究グループが発表した。全国1キロ四方ごとに温暖化の影響を推計したのは初めて。影響は市町村ごとに閲覧できるようにし、農業分野では作物転換の検討に使ってもらう。推計には、気候変動速度(VoCC)という指標を用いた。現在のペースで温暖化が進むと、VoCCの全国平均は1年当たり249メートルとなる。樹木の移動は、最大で同40メートルといわれており、気候変動に追い付けない。これは、身近な自然が将来、緯度の高い所や標高の高い所でしか見られなくなるということを示唆する。都道府県ごとに影響を見ると、沖縄が同2174・3メートルで、最も速度が速かった。次いで千葉、長崎となった。自治体ごとの影響は、環境省のホームページ内で確認できるよう準備を進めている。農業分野では、将来の地域の気候がどの地域と同じになるのか判断でき、転換する品目・品種や転換のスケジュールの検討で参考になる。同研究所の高野宏平研究員は「果樹などの永年作物は栽培や転換に時間がかかる。苗木の準備計画に役立ててもらいたい」と話す。 <ことば> VoCC ある地点で気候が変化した場合、将来同じ気温になる場所の最短距離を、変化した時間で割った速度のこと。例えば、年平均気温15度の場所が100年間で100キロ北上したら、VoCCは1年当たり1キロとなる。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p49317.html (日本農業新聞 2019年11月25日) 農業の完全自動化 農村への定住策視野に 農林水産業の全自動化につながる技術開発が進んでいる。過疎・高齢化で人手不足に悩む農村にとってありがたいが、農村への定住促進や雇用機会の創出など農村人口を増やす策を忘れてもらっては困る。全自動化の技術開発と併せ、農村での雇用創出から定住化につながるような研究が必要だ。 内閣府は昨年度から、解決が難しい社会の課題に挑むような研究開発を促すため「ムーンショット型研究開発」という制度を創設した。従来技術の延長にはない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究を進めるという。研究領域として少子高齢化対策や地球環境問題などを示し、目標例として「2040年までに農林水産業の完全自動化を実現」することを挙げる。ムーンショットとは「月を撃つ」ということ。米国のジャズシンガー、ノラ・ジョーンズさんの歌に、月を撃つという意味の歌詞がある。高望みをする、不可能に挑戦する、というような意味合いで使われた。内閣府では既存技術の組み合わせではない独創的なアイデアを取り入れた技術開発を進めるために、この表現を使ったようだ。「農林水産業の完全自動化」は「35年までに高齢者のQoL(生活の質)を劇的改善」「40年までに建設工事の完全無人化を実現」などとともに、野心的な目標例として掲げた。農業の現場では、ロボットトラクターのような自動化技術、圃場(ほじょう)の作業状況や作物の生育状態を遠隔地から確認できる情報通信技術(ICT)など、最先端の技術が瞬く間に広がっている。内閣府が目指す農業の完全自動化は、月を撃つような荒唐無稽な夢物語では既になくなりつつある。過疎化、高齢化で労働年齢人口が急速に減っている農業にあって自動化技術は魅力的だ。だが、果たしてそれだけでいいのか、あえて疑問を挟みたい。農村が美しいのは、棚田にしろ牧草地にしろ、人が手を入れいているからだ。ロボットが農業をすれば、農地の見た目の美しさは維持されるかもしれないが、生活の匂いは伝わらない。全自動化が求められているのは働き手がいなくなったからだ。しかし、この研究は対症療法でその場しのぎのように見える。完全自動化しても人手は要る。機器を使いこなす人材の教育や故障時の修理要員など、全自動化の普及に伴う新しい仕事が生まれるはずだ。人手不足の根本原因への対処が必要だ。月を撃つような斬新な発想で研究開発に取り組むなら、工学的な機械開発だけではなく、労働や人口などの社会科学と組み合わせ、農村への定住化対策も視野に入れた広い分野の研究として進めてはどうか。若い人が居つく農村像を描いてほしい。ノラ・ジョーンズさんの歌では「あなたは月を撃とうとして、完全に失敗した」と続く。国民の期待を見定め、的を外さない研究を求めたい。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p49361.html (日本農業新聞 2019年11月30日) 伸びる米粉市場 実需と結び付き強化を 米粉の消費が伸びている。品質の向上で品ぞろえが増えたことが大きい。国の後押しで輸出機運も高まる。課題は生産の安定、実需との結び付き、製粉コストの低減、魅力的な商品開発だ。有望な米粉市場を安定軌道に乗せるため、官民一体で取り組みを加速させよう。米粉新時代を開いたのは、圧倒的な品質力だ。微細粉にする高い製粉技術、加工技術の進展で、パンや菓子、麺など多彩な商品化が実現。和菓子やせんべいの原料だった従来の米粉の世界を一新した。2018年からは、日本米粉協会が、健康食材の特性を生かす「ノングルテン米粉認証制度」、消費者が選びやすいよう菓子・パン・麺用の表示をする「米粉の用途別基準」の運用を始め、普及に一役買った。アレルギー対応食材として認知度も高まり、需要量は近年、堅調に推移。農水省などによると17年度2万5000トン、18年度3万1000トン、19年度は3万6000トンを見込む。消費増で工場の稼働率が向上し、一部メーカーは小麦粉並みの製粉コストを実現している。問題は、伸びる需要に生産が追い付いていないことだ。米粉用米は、水田活用の直接支払交付金による転作支援もあり、一定に定着した。過去2年は2万8000トンで推移。19年度も同水準になる見込みだ。主食用価格が堅調で、米粉用米の生産が足踏みしている状況だ。実需側の在庫も少なく、このままでは3万トンを超す需要を満たせず、地域によっては原料確保に苦心する企業も出そうだ。有望な米粉市場に生産現場が対応できないのはもったいない。専用品種や多収品種の導入で、主食用に近い収益性を上げている産地もある。米粉用米生産の政策目標は25年度までに10万トンにすること。伸びしろはある。官民挙げ、水田フル活用による転作誘導、生産と実需の結び付きを強めるべきだ。もう一つの活路は海外市場だ。欧米では、麦に含まれるグルテン由来の疾病が社会問題となっており、「グルテンフリー市場」が急成長している。日本の米粉・関連食品の輸出は過去2年間は、約50トン、約200トン。今年は約700トンを見込む。着実に増加しているが、まだ緒に就いたばかりだ。日本の強みは、グルテン含有量「1ppm以下」という世界最高水準の「ノングルテン表示」で日本産米粉をアピールできること。だがこの表示は民間認証で、これを早急に日本農林規格(JAS)に格上げして、農水省による「お墨付き」として海外市場での有利販売につなげてほしい。併せて、混載による流通コストの低減、米粉ラーメンなど付加価値の高い加工品の開発、現地での地道な販促活動を継続すべきだ。米粉の市場性、可能性を追求することは、日本の水田を生かし、世界の健康に貢献することにつながる。 *2-5:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019091901002102.html (東京新聞 2019年9月19日) ゲノム食品、表示義務なし ルール決定、年内にも流通 消費者庁は19日、ゲノム編集技術で品種改良した農水産物の大半について、生産者や販売者らにゲノム編集食品であると表示することを義務付けないと発表した。ゲノム編集食品は特定の遺伝子を切断してつくられるが、外部から遺伝子を挿入する場合と挿入しない場合があり、現在開発が進む食品の大半は挿入しないタイプという。厚生労働省は同日、同タイプの販売について安全性審査を経ずに届け出制にすると通知。今回の消費者庁の発表で流通ルールの大枠が決まった。早ければ年内にも市場に出回る見通しだが、表示がなければゲノム編集食品かどうか分からず、消費者から不満が出るのは必至だ。 <他の地方産業> *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p49495.html (日本農業新聞 2019年12月15日) 「森林サービス」創出 健康需要で産業化へ 林野庁 林野庁は、森林空間を活用した「森林サービス産業」の創出に乗り出した。森林空間そのものを活用し、これまでの木材生産・供給だけでなく、健康需要などを見据えて森林体験や商品開発で新たなビジネスを生み出し、山村地域に新たな雇用と収入を生み出すのが狙い。どれだけ多くの民間団体・企業の参入を促し、定着させることができるかが鍵となりそうだ。同庁は、健康志向の高まりに加えて、企業が従業員の健康管理を考える「健康経営」の考え方が広まっていることや、インバウンド(訪日外国人)需要が伸びていることに着目。「健康」「観光」「教育」の観点で森林を活用して、新たな需要を取り込むのが「森林サービス産業」の狙いだ。子育て層を対象にした森林体験、企業の研修・保養利用などを想定する。具体策を検討するため、同庁は有識者らでつくる森林サービス産業検討委員会(委員長=宮林茂幸東京農業大学教授)を設置。①エビデンス(効果)②情報共有③香イノベーション──の専門部会で議論に着手。19年度中に報告書を取りまとめ、20年度以降、モデル育成を本格化させる。香イノベーション部会では、スギやヒノキなどを精油の原料として有望視。新たな市場形成を見据え、精油の効用やアロマテラピーでの使用状況などを調査する。エビデンス部会は、森林浴などが健康に与える効果のデータを集積し、事業化を後押しする。今年度は研究成果などの情報を集める。情報共有部会では、森林サービス産業に関心を持つ企業や団体、自治体などを引き合わせるプラットフォームの創設を構想。同庁は「Forest Styleネットワーク」を発足した。12月3日時点で63の企業や団体、地方公共団体などが加入。今後、新たな事業が生まれるきっかけを生み出す交流の場としたい考えだ。同庁は「民間や自治体と協力し、モデル地域の育成を進めていく」(森林利用課)としている。 *3-2:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-851348.html (琉球新報 2019年12月1日) 沖縄へのクルーズ船の寄港、過去最多の719回予定 2019年 アジアのクルーズ市場拡大が背景 2019年の沖縄へのクルーズ船の寄港予定回数が19日現在で、過去最多を更新する719回に達することが主要5港の港湾管理者への取材で分かった。18年は529回の見込みで、来年は1年で190回の大幅増となる。那覇港が67回増、平良港が63回増、石垣港が51回増でけん引している。719回寄港すれば130万人が訪れると試算でき、入域観光客数増加に寄与しそうだ。18年は12月31日までにクルーズ船の寄港数が2回以上あるのは5港で那覇243回、中城28回、本部2回、平良144回、石垣107回。その他が計5回で過去最多の合計529回となる見込み。19年の寄港予定は那覇310回(18年比67回増)、中城43回(同15回増)、本部1回(同1回減)、平良207回(同63回増)、石垣158回(同51回増)となっている。本部を除く4港で軒並み増える予定で、記録を塗り替えることになる。県がまとめたクルーズ船の寄港回数と海路入域観光客数をみると、17年は515回の寄港で94万1900人が訪れている。1回当たり1828人が訪れた計算となる。この数値と19年のクルーズ船寄港回数を単純に掛けた場合、19年の海路入域観光客数は131万5千人になると試算される。沖縄へのクルーズ船寄港数の増加は経済成長著しいアジアでのクルーズ市場拡大が背景にあり、今後も寄港増や船舶の大型化が見込まれる。県内の主要5港では岸壁の新設、整備、改良などが実施、計画されており、受け入れ態勢整備が進んでいる。そのためクルーズ船の寄港回数は今後さらに増加すると予想される。一方、クルーズ船は台風や寄港地変更などによってキャンセルされることもあり、実際の寄港数は予定数から減少することもある。 <解説>巨大市場近接で優位/交通渋滞解消など課題 2019年の沖縄へのクルーズ船寄港予定回数が過去最多の719回に達する背景には、クルーズ市場が拡大するアジア市場に近接しているという地理的な優位性がある。クルーズ旅行は比較的安価な「カジュアルクルーズ」の増加に伴い市場が拡大しており、1週間前後の短期間の旅行商品も増えている。特に中国は市場が伸びており、30年には1千万人市場になると見込まれている。巨大市場の上海、厦門、香港などから近い沖縄への寄港が多くなっているという。実際、沖縄以外の国内でクルーズ船が多く寄港するのはいずれも九州の博多、長崎。地理的な近さが強みなのは明らかだ。県内への寄港数を見ても09年は95回だったが、この10年で7倍に急増する見込みだ。そこで国も受け入れ態勢を強化しようと、民間資金を活用した「官民連携による国際クルーズ拠点」を指定している。現在、県内では本部港と平良港が指定されており岸壁が整備されている。那覇港も同制度への応募を準備。石垣港は国の方針で岸壁を延長している。市場取り込みの準備は着々と進む。一方、大型のクルーズ船寄港は一気に数千人が港から押し寄せることになる。那覇港では3隻が同時に寄港することもある。近隣の商業施設の混雑や交通渋滞などが引き起こされ、オーバーツーリズムだと指摘する声もある。観光客、地元住民の不満も低減し、持続可能な旅行形態として定着できるか。市場拡大に向けた受け入れ態勢整備が急務となっている。 *3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191126&ng=DGKKZO52596760V21C19A1MM8000 (日経新聞 2019年11月26日) 水産資源保護へ新規制 農水省、取引に産地証明、各国と協調、乱獲抑制 水産資源の枯渇を防ぐための新たな取引規制ができる見通しになった。魚介類の水揚げ場所や出荷日を示す公的な証明書を作り、国が指定した魚や一部の輸入品を国内で取引するときに添付を求める。違法操業で証明書のない魚介類は事実上、市場で売買できなくなる。米欧が先行する流通の規制を日本も取り入れ、国際的な水産物の資源管理(総合2面きょうのことば)の実効性を高める。魚介類は新興国を中心に消費が拡大し、乱獲による資源の枯渇が懸念されている。農林水産省によると2015年時点で世界の水産資源のうち約3分の1は、このままでは減少が止められない水準まで数が減った。とれる魚が減り、日本の漁業・養殖業の生産量は18年に439万トンと、ピークだった1984年の3分の1になっている。資源の管理に向け、海を回遊するマグロやサンマなどは各国で漁獲枠の設定が進む。沿岸漁業は地域ごとに禁漁期間がある。ただ、管理をすりぬける違法操業は後を絶たない。日本でも2017年の密漁の検挙数は20年前より3割増えた。違法操業を防がなければ、資源管理の実効性は保てない。このため農水省は漁獲段階だけでなく、流通でも乱獲の防止につながる対策をとる方針だ。具体的には魚介類に採取者や水揚げ港、出荷日を記した証明書をつける。漁業協同組合の組合員や国・地方から許可を受けた事業者による適法な漁による水揚げだけが証明書を得られる。証明書がない魚介類は市場で扱えないようにする。不正を防ぐため、証明書は国の登録を受けた漁協などが出す。ICタグなどデジタル化した形式も認める。証明書を義務化する対象は、密漁のリスクが高いナマコやアワビから始める見通しだ。輸入する水産物でも、一部では相手国の証明書を添付することを義務づける方針だ。対象は今後決めるが、輸入額が大きく密漁のリスクが高いイカやサンマなどが候補となる。日本は水産物では世界3位の輸入国。密漁でとった魚介類は受け入れず、海域全体で資源を守る。農水省は関連法案を早ければ20年の通常国会に提出する。法案の成立後、2年程度かけて対象とする魚介類を定め、制度の運用を始める。先進国では輸入する魚介類に証明書を求める動きが広がっている。農水省によると、09年に始めた欧州連合(EU)は養殖を除くすべての水産品が対象で、米国と韓国も乱獲が懸念される一部の魚で採用した。各国が証明書のある魚介類しか輸出入しなくなれば、乱獲された魚介類の流通を世界的に抑えることができる。日本は米欧と連携して、国際的な資源管理の議論を主導する考えだ。漁獲制限による資源管理はルールを守らない漁が後を絶たず、守る漁業者との間で不公平感が出る。岩手県漁業協同組合連合会の担当者は「流通面での対策が講じられなければ、密漁をなくすことはできない」と話す。 *3-4:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191103-00034824-hankyoreh-kr (Yahoo 2019/11/3) イシモチ→スケソウダラ→サバ…熱い海が「国民魚」変える ●朝鮮半島「食卓の魚」変遷史 50年間で表層水温1.23度上昇 全世界の水温変化の2.5倍超え 1人当たり年間水産物消費量59キロ 7年間で60%以上増加…世界1位 温暖化・乱獲でスケソウダラの「国籍」変わる 最近2~3年間の1位はサバ 「飲み水とおかずが切れて兵士たちが動揺した。林慶業(イム・ギョンオプ)将軍がいばらの木を持ってきて水に刺しておくと、イシモチの群れがかかったのでおかずにして食べた」。西海地域では朝鮮の仁祖(インジョ)の時代の林慶業将軍をイシモチ漁の始祖とする伝説が伝えられている。西海を渡る途中、飢えた兵士たちのために釣りをしたところ、木の枝と枝の間に挟まるほどイシモチが豊富に採れたという話だ。茶山チョン・ヤギョンの兄、チョン・ヤクチョンが全羅南道新安郡黒山島(シナングン・フクサンド)に島流しになっていた時に書いた魚類学書『チャ山魚譜』(1814)を改題した詩人のソン・テクス氏の本『海を抱いた本 チャ山魚譜』(2006)にも「イシモチの鳴き声が漢陽(ハニャン、現在のソウル)まで聞こえた」とある。こうした話は文字通り「伝説」としてのみ残った。1970年代には年間3万~4万トンに達していたイシモチの漁獲量は、40年後には半分に落ちた。イシモチを塩漬けにして干して作る干物「クルビ」も、秋夕(中秋節)のギフトセットでしか見られない状況だ。流通業界では2~3年前からニベやイシモチより大きさが3倍ほどある中国産フウセイでクルビ不足を補っている。かつては「国民魚」として東海を泳ぎ回っていたスケソウダラは国籍を変えた。1970年代には年間漁獲量が最大5万トンに達していたが、2010年代に入ってからは1~9トン程度だ。最近は市場に出回るスケソウダラは90%以上がロシア産だ。学界と業界では定着性魚種ではスケソウダラの幼魚の乱獲が、回遊性魚種では水温の変化が影響しているとみている。5年間にわたりスケソウダラの幼魚の放流などの「スケソウダラ再生プロジェクト」を推進してきた海洋水産部は、今年からスケソウダラの漁獲を年間を通じて禁止した。 ●スケソウダラ沈み、サバ浮上 韓国は年間1人当たりの水産物消費量が2017年現在59.3キロで世界第1位だ。「水産大国」ノルウェー(53.3キロ)や日本(50.2キロ)も抜いた。スピードも速い。2000年には36.8キロに過ぎなかったが、60%以上も増えたことになる。その間に「国民魚」も替わった。1990年の国民1当たり1日平均消費量が最も多い水産物はスケソウダラだったが、スルメイカに交替した。最近2~3年のアンケート調査ではサバが名実共に「好きな魚」第1位だ。韓国人の食卓の魚が替わったのには、何よりも朝鮮半島周辺海域の水揚げ推移が変わった影響が大きい。スケソウダラやイシモチだけでなく、東海岸の「常連」だったサンマやハタハタも滅多に見なくなった。一方、カタクチイワシとサバは豊漁だ。1970年には5万トン程度だったカタクチイワシの漁獲量は2017年には21万トンに、サバは3万トンから21万トンに大幅に増えた。1970~80年代には年間3万~4万トンだったスルメイカも2010年代には15万トンにまで跳ね上がった。まず、地球温暖化などによる水温の変化が原因の一つに挙げられる。国立水産科学院の集計によると、朝鮮半島海域の表層水温は1968年~2018年の間に1.23度高くなった。同期間の全世界の水温変化(0.49度上昇)を上回る数値だ。同院のハン・インソン研究士は、「水温上昇時は栄養塩類の量が減り、水産生物の成長が制限され得る。繁殖と生息地の移動も影響を受ける。ただし生息地と魚種によって影響に違いが出る可能性はある」と指摘する。最近、朝鮮半島海域に暖流性魚種のサバやカタクチイワシが大量に入ってきた一方、寒流性魚種のスケソウダラやハタハタは北上した。イカは南海から東海や西海に生息地を広げており、南海岸では亜熱帯魚種が多く見られるよるになっている。クロマグロが2010年に初めて漁獲量統計の対象になったのに続き、去年の統計によれば済州沿岸に現れた魚類の42%がキンチャクダイ、タカノハダイなどの亜熱帯種であった。 ●「幼魚の乱獲を規制すべき」 急激な魚種変化を異常気象だけで説明することは難しい。中国漁船中心の攻撃的な操業や無分別な乱獲などの方が影響が大きいという指摘もある。産卵もしていない幼魚を安値で売ったり生餌に使ったりして水産資源の枯渇を引き寄せているというのだ。スケソウダラ激減のきっかけも1970年の幼魚漁獲禁止令解除だという見方が支配的だ。1976年には、スケソウダラの漁獲量の実に94%が幼魚だった。イカの漁獲量が2016年の約12万トンから昨年の4万トンあまりに急減したことをめぐっても、同院のカン・スギョン研究士は「産卵場所の低水温現象で産卵資源が減少した上、多くの漁船による乱獲まで重なったため」と分析する。昨年発行された海洋水産開発院の報告書『幼魚乱獲の実態および保護政策の研究』によると、2016年の漁獲量のうち、幼魚の割合はタチウオが69~74%、イシモチが55%、サバが41%に達した。産地価格が1万ウォン(1キロ当たり)以上にもなるほど収益性の良いイシモチなどが未成魚(幼魚)のうちに捕獲され、飼料に使われていると報告書は指摘する。さらに「ノルウェーは1971年に30センチ未満のサバの捕獲を禁止した結果、2014年には北東大西洋のサバのうち成魚の割合は89%となった。タチウオ、イシモチなどの幼魚は販売場所や違法漁獲物の取引を規制すべき」と指摘する。 ●おまえ、どこの海から来たの 所得水準が上がり西欧の水産物に対する需要が拡大することにより、輸入品目が多様になった効果もある。サケ、ズワイガニ、ロブスターなど、かつては高級飲食店でしか扱われなかった輸入水産物は、いまや大手スーパーやコンビニでも簡単に買えるようになった。韓国農水産食品流通公社の統計によると、ズワイガニの輸入額は昨年1億2675万ドルで2年前と比べ3倍ほど増加した。サケの輸入の20%を占めるトンウォン産業の関係者は「2000年代に『ウェルビーイング』の流れに乗って大衆的需要が形成された。原価負担が分散し、価格も下がった」と語る。イーマートの関係者は「エビの産地を2015年の3カ所から昨年は10カ国に増やすなど、価格の合理化を図っている」という。水産物の消費の仕方や購買経路が多様化していることも関心が集まる部分だ。大型スーパーなどからからコンビニエンスストアやオンラインに目を向ける消費者が増えている。コンビニ「GS25」の資料によれば、去年1~9月の水産物の売上げは前年同期比で26.1%増え、ロブスターやサバなどの魚介類の売上比率も2017年の8.0%から今年上半期には10.2%に増加した。同社の関係者は「手軽に料理できる食品を求める流れが続いていているとともに良質の食事を求める20~30代が増えたことで、水産物の需要も増加傾向にある」と語った。 <エネルギーの国産化と地方創成> PS(2019.12.18追加):*4-1のように、「環境保護≒不便を我慢すること」と解している人は多いが、飛行機に乗らずに長時間かけて移動する方法を選べる人は限られている。そのため、航空機燃料を水素に変更したり、航空機を電動化したりするのが合理的で、そうすると「環境保護→進歩→経済発展」にできる。その理由は、①便利さを犠牲にしない ②CO₂はじめ排気ガスを出さない ③国産化可能な燃料であるため輸入する必要がなく、エネルギー自給率も上がる ④水素を作るための電力に再生可能エネルギーを使えば、地方振興に役立つ などが挙げられる。そのため、これまで作っていなかった航空機を日本企業が作る場合に、原油由来のジェット燃料を使う航空機を作る必要はないだろう。既に、IHIとIHIエアロスペースは、*4-2のように、2012年に米ボーイング社と共同で世界初の再生型燃料電池システムを民間航空機に搭載して飛行実証することに成功しており、経産省も電動飛行機を作ろうとしている。    *4-2より 2019.1.24News24 2019.2.17朝日新聞 (図の説明:左図のように、燃料電池航空機が既にできており、中央と右の図のように電動航空機の開発も始まっているので、早く実用化すべきだ) *4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191218&ng=DGKKZO53492300Y9A211C1MM0000 (日経新聞 2019.12.18) 先進国「飛び恥」じわり、環境意識、飛行機手控え 航空会社が陸路提供 欧州など先進国を中心に飛行機の利用を手控える動きが広がり始めた。温暖化ガスの排出増加による環境負荷への関心が高まっているためで、16歳の環境活動家、グレタ・トゥンベリ氏が交通手段として飛行機を回避していることでも注目を集める。短距離の移動に鉄道の利用を勧める航空会社や温暖化ガスの排出量の少ない燃料の使用を促す例も出てきた。グレタ氏は米誌タイムの2019年の「今年の人」に選ばれた。9月にニューヨークで開催された国連気候行動サミット、12月のマドリードでの第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)にそれぞれ参加するため、ヨットや鉄道で移動した。環境負荷が比較的小さいとの判断だ。海をまたぐような長距離の移動にも飛行機の利用を避けた。「気候変動の危機が実際に起きている問題であることを示したい」との考えからだ。グレタ氏の出身国のスウェーデンには、飛行機の利用が恥だと考える「フライトシェイム(飛び恥)」という造語がある。スウェーデンの国営空港運営会社によると、1~9月の国内線の利用者数は前年同期より約8%減少した。同社は景気減速に加え、気候変動を巡る議論を要因にあげた。スイス金融大手UBSが9日発表した欧米やアジアなど8カ国の消費者を対象とした調査によると、回答者の37%が環境への影響を懸念し、過去1年間に飛行機の利用回数を減らした。ほかに25%が「利用減を検討している」と回答した。回答者を欧米4カ国に限れば、利用回数を減らした割合は42%で、5月調査(21%)の2倍になった。国際航空運送協会(IATA)によると、18年の航空業界の二酸化炭素(CO2)排出量は約9億トンで、世界全体の約2%に相当した。米国の非営利団体、国際クリーン交通委員会(ICCT)によると、民間の飛行機のCO2排出量は過去5年で32%増えた。年平均では5.7%増で、国際民間航空機関(ICAO)の予測(約3.3%)よりもペースは速い。先進国発の飛行機のCO2排出量が全体の約6割を占める。一部の航空会社は対策を始めた。KLMオランダ航空は鉄道会社と連携し、20年3月からアムステルダムとブリュッセル間の便数を減らし、代わりに鉄道での移動を提供する。米ユナイテッド航空は10月末、CO2削減技術やバイオ燃料開発に4000万ドル(約43億円)投資すると発表した。フランスは20年、同国発の航空券を対象に環境保全のためのエコ課税を導入する方針だ。新たに得られる税収は鉄道などほかの輸送手段の強化にあてる。ドイツも20年、航空券への課税率を引き上げる。米西部カリフォルニア州は19年、輸送用燃料に適用する排出量取引制度を航空燃料にも広げた。UBSは、飛行機の利用を恥と思う動きが「勢いを増している」と指摘する。気候への影響に対する意識が高まれば、欧州における20年の飛行機の利用者の伸び率は19年の前年比約4.8%から3.4%に低下すると推測する。「飛び恥」の意識が急速に高まった場合は、飛行機の利用者の伸び率が前年より3.5%減る可能性があるとも試算している。英ビジネス・エネルギー・産業戦略省によると、英国における国内便の乗客1人当たりのCO2排出量は1キロメートル当たり133グラムと、長距離便(102グラム)や国内鉄道(41グラム)に比べて多い。 *4-2:https://response.jp/article/2012/10/05/182565.html (Response 2012年10月5日) IHI、世界初となる再生型燃料電池システムの民間航空機飛行実証に成功 IHIとIHIエアロスペースは、米ボーイング社と共同で再生型燃料電池システムを民間航空機に搭載し、飛行実証することに成功した。再生型燃料電池システムの飛行実証は、世界初の試み。再生型燃料電池は、充電可能な燃料電池で、エンジンからは独立して電力を供給することができる。また副産物は水のみであるため、省エネルギー化、二酸化炭素排出削減を可能とし、航空機の環境負荷を低減する。今回の飛行実証は、ボーイング社の環境対応技術実証を目的としたecoDemonstrator計画の一環として、米シアトル近郊においてアメリカン・エアラインのボーイング737型機を用いて実施。フライト試験では、航空機の離陸前から高度上昇中において、燃料電池からの発電による電力供給を行い、巡航飛行時に航空機の電源を用いて充電を実施。その後、再度、発電、充電、発電のサイクルを行うことに成功している。IHIは、今回得られた経験をもとに、再生型燃料電池の小型化、大出力化の改良を進め、航空機の低燃費及び環境負荷低減に寄与する民間航空機用補助電源の製品化に向けた検討を実施していく。 <大学入試共通テストでの国語・数学の記述式問題について> PS(2019.12.19追加):*5-1のように、50万人の受験生の採点をしなければならない大学入試共通テストへの国語・数学の記述式導入はしない方がよいと私も思うが、その理由は、①一人の採点者が採点してもブレが生じる記述式を50万人規模で多様な採点者が行えば、入試の質や公平性が確保できず ②そもそも思考力の育成には、学校だけでなく家庭やメディアなど一般社会の大人が論理的な議論を見せておくことが必要であり ③知識や科学に基づかない議論は無意味であるため、高卒段階では知識や理解力を測る方が重要であること などである。 しかし、国語・数学の記述式問題がないとなると、入試改革が漂流状態に陥ったとする論調も多く、*5-2のように、「情報をつなぎ合わせただけの文章を書く」「他の学生と同じような論点を書く」「検索で集めた情報の中から自分の意見を探す」などとも書かれてもいる。しかし、「ジョークを2つ示して、共通する笑いどころを考えて書かせる」よりも、インターネットで情報を集めて自分の意見をまとめた方がずっと高尚なものができそうであり、思考力・表現力・批評力は内容があって初めて意味があるものだ。従って、知識の活用力は大学入試で測るよりも、大学卒業後に持っておくべきものだと、私は考える。 なお、私がこのブログで記載している文章について、「新聞等の情報をつなぎ合わせただけの文章を書いた」と思う人がいたとすれば、それは甘すぎるし、女性を過小評価している。何故なら、これらの文章は、大学までに学んだ知識、公認会計士・税理士として持っている知識・経験・監査手法、国会議員として社会調査を兼ねて地元を廻りながら集めた問題点などを総合的に考慮して書いたもので、添付した新聞記事等は、情報の比較やup-date・証拠資料などとして使っているにすぎないからだ。このように、記述式の評価は採点者によって異なり、採点者は自分の知識・経験・想像力の範囲内でしか採点できず、最高でも7~8割しかとれないのである。 *5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191208&ng=DGKKZO53091800X01C19A2EA1000 (日経新聞社説 2019.12.8) 記述式入試は抜本的に見直せ 何のための入試改革だったのか。原点に立ち返り、ゼロベースから仕切り直す時だ。政府・与党は、来年度の大学入試共通テストで導入予定の国語と数学の記述式問題を延期する方向で検討を始めた。受験生の混乱を招いた行政の責任は重い。記述式では、50万人規模の採点を民間事業者が担う。採点者には学生バイトも加わる。今国会の審議で文部科学省は、採点の信頼性をいかに確保するかについて説得力ある解決策を示せなかった。実施にこだわる同省は国立大に対し、国語の記述式を2次試験の受験者数を絞る「二段階選抜」に利用しないよう促す。これは、公平な採点が難しいことを認めたに等しい。不信感は募る一方で、政権への批判を恐れる与党が試合中断のタオルを投げ込んだ格好だ。一方、記述式を合否判定に使う予定の国公私立大は全体の半数にとどまった。こうした状況で来年度からの実施を急ぐ意味は実質的に失われた。導入を見送り、各大学が個別試験で受験生の思考力・表現力を測る独自の記述問題を充実するほうが合理的である。新テストでは、英語民間試験でも制度の不備で導入を見送った。入試改革は破綻しつつある。なぜこのような事態に至ったのか。真摯な検証が欠かせない。当初の構想は、一発勝負をやめて、複数回受験が可能な「到達度試験」への転換を目指した。急速な少子化により、大量の受験生を1点刻みでふるい落とす従来型試験の意味が薄れたからだ。共通テストはスリム化する一方、各大学が記述式を含む個別試験を拡充し、学力を丁寧に判定する改革を志向した。しかし、複数回実施は困難と判断。民間の協力で、英語力や思考力を問う方向にカジを切った経緯がある。記述式のみ大まかな到達度で評価し、残りはマーク式の1点刻みで選抜する。矛盾を抱えた新テストの構造自体を抜本的に見直す必要がある。その場しのぎの延期はさらなる混迷と不信を招く。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191219&ng=DGKKZO53509930Y9A211C1CR8000 (日経新聞 2019.12.19) 思考力底上げ 重い課題 共通テスト、記述式見送り、漂流 大学入試改革(上) 2020年度に始まる大学入学共通テストの二本柱だった英語民間試験と国語、数学の記述式問題が消え、足かけ6年にわたった入試改革は先が見えない漂流状態に陥った。混乱の過程で浮かんだ日本の入試制度の課題とその解を探る。情報をつなぎ合わせただけの文章、ほかの多くの学生と同じような論点――。学生にリポートや論文の書き方を教える早稲田大ライティング・センターの佐渡島紗織教授(国語教育)は、学生の文章のそんな箇所に気づくことが少なくない。インターネットで情報が簡単に入手できる現代。「検索で集めた情報の中から自分の意見を探すような傾向もみられる」。このため指導の場面では、ネット上に答えがなさそうな課題を出す。例えばジョークを2つ示して「共通する笑いどころ」を考えて書かせる、といった具合だ。「考える学生を育てることに意識的に取り組む必要がある」と佐渡島教授。ベテランの高校教員からも「この10年間で生徒の思考力が急激に落ちた」「調べて発表するのは得意だが、自分の考えを聞くと答えられない」といった声が上がる。日本の10代の思考力に、黄信号がともっている。文部科学省は共通テストへの記述式問題の導入を、こうした現状を打開する切り札に位置づけた。答えを選択肢から選ぶのではなく、自分の力で書くことで思考力や表現力を測る――。「小中学校は学習指導要領の改訂を経て表現力などを重視する授業に変わっているのに、高校は大学入試に縛られて指導を改善できていない」という同省などの不満もあった。その理念は現実の壁に阻まれた。当初「最大300字程度」だった記述の上限は検討が進むにつれ、「80~120字程度」にしぼんだ。50万人規模の答案を約20日間で採点できるようにするためだが、それでも公平性への疑念を払拭できず、実施まで1年の土壇場で見送りに追い込まれた。「小中学校は指導改善の成果が出ている」という改革の前提も揺らぐ。経済協力開発機構(OECD)の18年の学習到達度調査(PISA)で、日本の15歳の読解力は参加国・地域中15位と過去最低の順位に沈んだ。特に記述式問題の正答率が落ち込み、批評的に考える力の弱さなどが指摘された。思考力の底上げは待ったなしだ。現場は模索する。大分県教育委員会は15年度から「深い学び研究会」と呼ぶ事業を始めた。大きな課題を共同作業で考え、答えを導く「知識構成型ジグソー法」という対話型学習を広め、学びの深化を目指す。6月、同県立大分鶴崎高で開かれた現代文の研究授業では3年生の生徒が哲学者の西谷修さんの評論を題材に「他者との関係があることで、人間が一つの存在として成り立つ理由は何か」をジグソー法で考えた。指導した佐藤秀信教諭は「これからの社会を生きていく力を育むには、本質的な問いに向き合う学習が欠かせない」と強調する。情報化やグローバル化が急速に進み、高校教育も変わる中で、大学入試が旧態依然の暗記中心型であってよいわけがない。知識の活用力や、自分の考えを伝える力を測るうえで記述式問題は有力な手段だが、私立大は実施が難しい大学も多い。次代に必要な学力をどう問うか。今後の制度設計の重い課題だ。 <地方で作れるエネルギー> PS(2019年12月20、23、25、27日、2020年1月5日追加):*6-1のように、COP25は「パリ協定」の実施ルール合意を見送って閉幕したそうだが、国を先進国と途上国に分けて「他国(“途上国”)への“技術支援”で削減できた温室効果ガスの排出量を自国の削減分として計算する」などという小賢しいルールは、“先進国”自体のCO₂排出量を減らすわけではないため、合意しなくてよかったと思う。それより、どの国も実際にCO₂排出量を減らす必要があり、それは可能で、そうした方が日本の地域振興にも役立つ。 例えば、*6-2の福岡県八女市の地域新電力会社「やめエネルギー」のように、地域の再エネを使って発電し、大手電力会社に支払っていた年間約53億円の電気料金の一部を地元で廻したり、もっと積極的にやるとすれば発電した電力を他の地域に売ったり、豊富な水資源を使って水素と酸素を作ったりなど、エネルギーを電力と水素に変えさえすれば、環境と両立させながら地域を潤すことが可能なのだ。 なお、*6-3のように、茨城大学、茨城県農業総合センターなどの研究グループによると、地球温暖化の影響で2040年代には「コシヒカリ」の白未熟粒が全国で2010年代の2倍に増え、その経済損失が351~442億円と見積もられるそうだが、これは佐賀県では既に起こって解決済のことで、高温耐性品種で特A評価のヒノヒカリやサガビヨリなどが開発済である。 「少子高齢化で支え手が不足するから、消費税増税と痛みの分配という難題と向き合うことが社会保障改革である」とする記載は、*6-4はじめ、財務省主導でメディアによってしばしば行われる。しかし、この議論に欠けているのは、①高齢者の生活に対する配慮 ②少子化した理由の正確な分析 ③公会計の導入による国の無駄遣いの排除 ④財源確保の手段に関する工夫 だ。このうち、①については、今回の消費税増税は反対が少なかったが、高齢者は何も言わずに(他に方法がないため)節約するだけであり、それによって財・サービスが売れなくなるのは当然で、実際に生活に困っている人は多いのだ。また、②のように、少子化したことがいけないかのような批判も多いが、日本国憲法で男女平等になった戦後も女性が仕事と子育てを両立できる社会を作らず、憲法施行から65年以上経過した今でも保育所や学童保育が足りず、教育に金がかかるシステムにしておきながら、何でも国民(特に女性)の責任であるかのように言って国民負担を増やそうとするのは不誠実で安易だ。そして、③については、日本は景気対策と称する無駄遣いが多いが、そもそも無駄遣いとそうでないものを区別して、国有財産をしっかり管理できる会計すら採用していないのが大きな問題なのである。さらに、④については、外国に高額の資源代金を払うことが目的のようなエネルギー政策をとって国民を貧しくさせながら、工夫もなくあちこちで金をばら撒いているのを改めればよいのだ。 なお、*6-5のように、唐津市馬渡島と平戸市的山あづち大島周辺の海に、東京都の民間企業が大規模な洋上風力発電を設置する計画があり、最大65基の風力発電機を設置して発電出力61万7500kwを見込むそうだ。私は、遮るものがないので安定した風が吹き、漁業以外の産業がないため地元の人も積極的であることから、離島が風力発電基地になるのはよいが、地元の会社がそれを行えば電力料金が地元で廻るので、さらによいと思う。また、景観や漁業との両立のためには、よくある風力発電機を立てるのではなく、環境影響評価の段階で鳥などの野生動物を巻き込まず、むしろ漁礁となったり養殖と併用させたりできる風力発電機を指定した方がよいため、漁協も出資してお互いに工夫しあう事業主体にしたらどうかと考える。 このような中、*6-6、*6-7のように、政府は、中東海域での情報収集態勢を強化するためとして海上自衛隊を中東に派遣することを閣議決定し、不測の事態(??)に日本船舶の護衛に当たり、武器使用も排除しないそうだ。しかし、エネルギーをいつまでも中東から輸入する高い石油に依存していることも化石の名にふさわしく、「調査・研究」名目なら国会の承認なく自衛隊を海外に派遣できるというのは都合よく拡大解釈しすぎである。さらに、日本の船舶を海賊等から護衛すべきは、日本の自衛隊ではなく、その海域を領有する国の海上保安庁であるため、日本はそのような無駄遣いで負の投資をする金があるのなら、速やかに必要な送電線を敷いたり、レアメタルを採掘したりした方が未来のためにプラスの投資になるのである。 ドイツでは、*6-8のように、太陽光・風力などの再エネ発電シェアが、2019年には前年から5.4ポイント上昇して46%となり、発電量に占める再エネ比率が化石燃料を上回ったそうだ。原子力発電所は海を温める上、事故時は化石燃料よりも深刻な公害をもたらすためお薦めでないが、自動車等の電動化とあいまって、再エネ発電によるクリーンなエネルギー社会を早く作ってもらいたいものである。  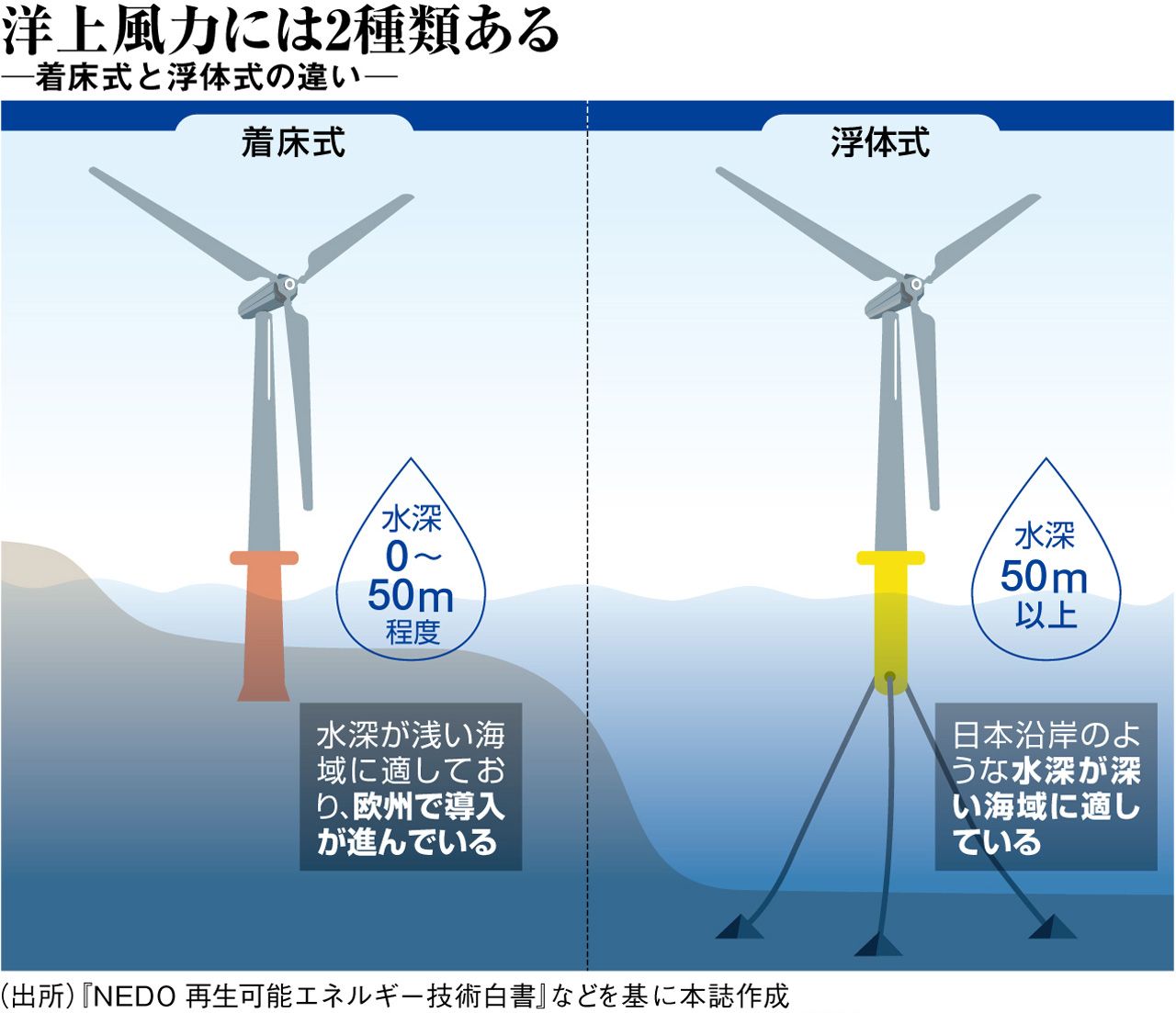 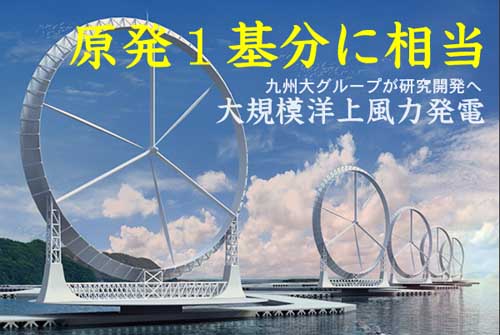  (図の説明:左の2つは、よくある風力発電機。右から2番目は大型の風レンズ風車、1番右は、カーボンファイバーを使った風レンズ風車が養殖施設に併設されている様子だ。右の2つがお薦めで、さらに発電量が増したり、鳥が飛びこまない工夫があったりすればよいと思う) *6-1:https://www.agrinews.co.jp/p49506.html (日本農業新聞 2019年12月17日) 温室ガス削減強化 世界が協調し踏み出せ 地球温暖化の対策を話し合う国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議「COP25」は、「パリ協定」の実施ルールの合意を見送って閉幕した。異常気象による災害が日本を含め世界で頻発している。各国は早期に合意し、二酸化炭素(CO2)をはじめ温室効果ガスの削減強化に協調して踏み出すべきだ。世界の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す「パリ協定」は2015年に採択され、20年に始まる。運用ルールは昨年のCOP24でほとんど決まっており、今回の合意の見送りが与える影響は少ないとの楽観的な見方もある。しかし、完全な形で合意できなかったことは国際協調のきしみをうかがわせた。今回合意を目指したのは、途上国などへの技術支援で削減できた温室効果ガスの排出量を自国の削減分として計算するルール。実効力を高めるものとして期待された。ところが両方の国で二重計上しないルールを巡って難航。自国の実績が減らされることを懸念するブラジルやインドなどが反対し、合意は来年以降に先送りされた。世界最先端水準の削減技術を持つ日本は、東南アジアなどへの技術支援で温室効果ガスの削減に貢献できるはずだ。政府は、早期の合意に向けた合意形成に全力を挙げるべきだ。世界の環境団体でつくる「気候行動ネットワーク」は、地球温暖化対策に後ろ向きな国に贈る「化石賞」に日本を選んだ。石炭火力発電の利用にこだわる政府の方針を批判したものだ。不名誉で遺憾である。政府は、環境に優しいエネルギーに転換する姿勢を示すべきだ。世界の科学者などでつくる、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の特別報告書は、世界の平均気温は17年時点で産業革命前に比べおよそ1度上昇しており、「早ければ2030年には1・5度上昇し、異常気象がさらに増加する」とした。国連環境計画(UNEP)の報告書でも、世界の温室効果ガスの排出が今のペースで進めば、「破壊的な影響」が出ると警告した。削減のスピードを上げなければならない。国連のグテレス事務総長は、9月の温暖化対策サミットでこれまで以上の対策を取るように各国を促した。しかし、来年再提出することになっている削減目標の引き上げを表明した国は、80カ国ほどにとどまる。排出量が多い中国やインド、日本などの主要国の新たな削減への取り組みが鈍い。米国は、「パリ協定」からの離脱を通告したままだ。地球温暖化は世界の食料生産にも甚大な被害を与える。危機感を強めなければならない。今回の会議では、温室効果ガス削減目標の引き上げを各国に促す文言が成果文書に盛り込まれた。義務付けは見送ったとはいえ、各国は足並みをそろえて取り組むべきだ。日本は率先して目標を引き上げ、削減強化の世界的機運を高める必要がある。 *6-2:http://qbiz.jp/article/135441/1/ (西日本新聞 2018年6月10日) 電力料金地元で循環 事業開始から1年 「やめエネルギー」社長 本村勇一郎さん(40) 子育て支援メニュー構想も 福岡県八女市の地域新電力会社「やめエネルギー」が昨年5月に事業を開始してから1年。「電気料金として地域外に流れていた資金を地元で循環させる」ことを目的に、広川町を含む八女地域の73社の出資で設立された。本村勇一郎社長(40)に経営の現状、今後の事業展開について聞いた。 −この1年を振り返って。 「事業所を中心に既存の電力会社から切り替えをお願いして回りましたが、最初は私たちの取り組みを知ってもらう啓発活動のようなものでした。その中で理解をいただいて契約数も少しずつ増えていきました」 −小売り契約数は250件に達した。 「『やめのでんき』のブランド名で販売していますが、茶業、林業、ちょうちんや仏壇といった伝統工芸、酒蔵など八女ならではの事業者の方も契約を結んでくれました。契約容量も約5メガワットまで伸び、近く採算のめどが立ちそうです。当初、みやま市の新電力会社『みやまスマートエネルギー』に担ってもらっていた電力供給も、今年5月からは自社でしています」 −あらためて会社設立の目的は。 「八女市全体で年間約53億円の電気料金を大手電力会社などに支払っていますが、これまでそのお金は地元には残らなかった。電力自由化をきっかけに一部でも地域に残せないか、それを循環させ、八女を潤すことができないかという思いが私たちの原点です」。(以下略) *6-3:https://www.agrinews.co.jp/p49536.html (日本農業新聞 2019年12月20日)温暖化続けば― コシ白未熟粒倍増 年間損失442億円 茨城大学など2040年代予測 茨城大学、茨城県農業総合センターなどの研究グループは19日、地球温暖化の影響で2040年代には、米「コシヒカリ」の白未熟粒が全国で10年代の2倍に増える予測を発表した。これまでのペースで温室効果ガスの排出が増え続けた場合、21世紀末に気温が4度上昇し、40年代に全国の平均白未熟粒発生率は12・6%(10年代は6・2%)。経済損失は1年間で442億円で、10年代の5・15倍と推計した。高温耐性品種の開発など、長期的な戦略が求められる。白未熟粒は登熟期の高温で多発し、米の検査等級が下がるため農家収入が減る。研究グループは、これまで明らかになっていなかった発生率の増え方や経済損失を、主要品種である「コシヒカリ」で日本全国を1キロ四方ごとに区切って予測した。温室効果ガスの排出量は、パリ協定の目標量に抑えられた場合と、これまでのペースで増え続けた場合の二つの想定に基づいて行った。全国の白未熟粒発生率の平均は、パリ協定の目標量に抑えた場合(10年代は7・1%)でも、40年代に10・9%に増えることが分かった。これは10年代の約1・5倍に相当する。発生率が高い地域は、沿岸の平野部から広がり、偏りが予想される。さらに2等米以下の水田面積の割合は、40年代には低くて26・2%、高ければ32・9%と推定した。2等米の発生が増え年間の経済損失は低くて351億円、高ければ442億円と見積もった。同大学農学部の増冨祐司准教授は「温暖化へ長期的な戦略を立てるとともに、高温耐性品種の開発・導入が重要。同時に各地域で実行可能な対策を検討・確立・実施する必要がある」と警鐘を鳴らす。 *6-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019122002000138.html (東京新聞社説 2019年12月20日) 社会保障改革 難題と向き合わぬのか 政府の全世代型社会保障検討会議が中間報告をまとめた。政権主導の改革を担うはずだが、その推進力は心もとない。何より財源確保をはじめ負担の分かち合いという難題に向き合っていない。将来を見据え全世代が安心を得られる制度へのつくり直しができるのか、甚だ疑問だ。「人生百年時代の到来を見据えながら」「社会保障全般にわたる持続可能な改革を検討してきた」。報告書はそううたっている。だが、持続する制度の実現には、必要な財源をどう手当てするのか、その議論が欠かせない。なぜなら、今後直面する大きな課題が、高齢者数がピークを迎え、財源不足と介護などの人材不足が深刻化する二〇四〇年ごろに向けた制度の再構築だからだ。人口減の中で、これまでのように現役世代が保険料で支える力は弱まっている。だから、税財源の根本的な見直しという難題に今から取り組まねば間に合わないのではないか。政権が政治主導で検討会議を設置したのなら、四〇年を見据えた増税など「痛みの分配」こそ果敢に議論すべきだった。安倍晋三首相は消費税率の10%超への引き上げ議論を現政権では封印した。ならば、「将来の安心」を次世代に渡すための財源確保策を具体的に示すべきだろう。今回の改革案は雇用、年金、医療、介護の四分野だが、対策の射程は団塊世代が七十五歳を超え医療や介護ニーズが高まる二五年までだ。しかも、年金では厚生年金の適用拡大の対象となる企業規模の撤廃は盛り込まれなかった。医療の七十五歳以上の自己負担の引き上げもどこまで対象を広げるのか不明だ。業界や与党の反発から踏み込み不足の感は否めない。首相の言う「全世代型」とは、高齢者に偏っている給付を現役世代にも振り向けることのはずだ。だが、肝心の子育て支援策が見当たらない。一九年の出生数は想定より早く九十万人を下回りそうだ。実効性ある支援がなければ少子化を止められまい。気になる点がまだある。制度は「大きなリスク」に備える役割だという。小さいリスクは自己責任でという意味か。リスクの大小を誰が判断するのかも含め丁寧な説明が要る。どれだけの負担を引き受ければ納得できる給付を得られるのか、それを知りたい。政府は、その将来像を早く示すべきだ。 *6-5:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/470024 (佐賀新聞 2019/12/25) 唐津の馬渡島周辺に洋上風力発電計画 東京の企業が県に説明、最大65基設置 佐賀県唐津市の馬渡まだら島と長崎県平戸市の的山あづち大島周辺の海に、大規模な洋上風力発電を設置する計画があることが分かった。東京都の民間企業が計画し、最大65基の風力発電機を設け、総発電出力は61万7500キロワットを見込む。国内では実用例が少ない、海底に固定しない「浮体式」の発電機も導入する見通し。今後は2028年の運転開始を目標に、工事に必要な環境影響評価(アセスメント)への対応を進める。24日に県庁であった県環境影響評価審査会で、実質的な事業主体である再生可能エネルギーの発電事業会社「INFLUX」(インフラックス、東京都)が計画の概要を説明した。洋上風力発電機を設置する想定区域は、馬渡島と的山大島の周辺と中間の海域約1万9546ヘクタール。平均風速が毎秒7・63メートルと状況がよく、水深80メートル以内の比較的浅い区域を抽出した。東松浦郡玄海町の絶景ポイント「浜野浦の棚田」からの景観にも配慮するという。1基当たり9500~1万2千キロワットの風力発電機を最大65基設置する計画で、水深50メートル以内は海底に固定する「着床式」、50メートル以上は「浮体式」を採用する予定。アセスを経て、25年の着工、28年の運転開始を目指す。総事業費は4200~4500億円。今後は地元との調整を進め、渡り鳥など生態系への影響も詳しく調べる。インフラックスの担当者は「事業による環境への影響はあると思われるが、風車の配置などを考慮し、できる限り低減する。地元にも丁寧に説明したい」と話す。県内では同じ会社が唐津市の神集かしわ島近海に、大規模な洋上風力発電設備を設置する計画があり、別の事業者も唐津市肥前町の向島むくしま沿岸に数基の洋上風力発電を設置する計画がある。 *6-6:https://www.sankei.com/politics/news/191027/plt1910270009-n1.html (産経新聞 2019.10.27) 自衛隊中東派遣、ホルムズ海峡排除せず どうなる武器使用 政府は、緊張が高まっている中東海域での情報収集態勢を強化するため、早ければ年明けに自衛隊を独自派遣する方針だ。ただ、派遣の方法や法的整合性の検討、部隊への教育訓練の実施期間を踏まえると来春にずれ込む可能性がある。国家安全保障局を中心に外務省、防衛省などで活動場所や時期の調整を進めている。政府内には「与野党から反対や慎重な意見が相次いでいる。3カ月後(年明け)というのは難しいのではないか」(防衛省幹部)との声もある。自衛隊派遣の検討を具体化したのは、サウジアラビアの石油施設への攻撃、イラン国営会社所有のタンカーの爆発など情勢が緊迫化する中、石油輸入を中東に依存する日本が主体的に情報収集に関わらざるを得なくなったからだ。得た情報は米国主導の有志連合構想に加わる国などに提供する方向で調整している。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は18日の記者会見で、派遣先として「オマーン湾」「アラビア海北部」「バべルマンデブ海峡東側」を中心に検討すると発表。事態が最も緊迫し、情報収集の必要性が高いホルムズ海峡には言及しなかった。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「中東地域のどこかを特筆して排除していない」と述べ、ホルムズ海峡で活動する可能性も排除せずに検討する考えを示した。 ◇ 政府は自衛隊の中東派遣の具体的な方法について、海上自衛隊の護衛艦1隻を新たに派遣する案を軸に検討している。すでに中東近隣で海賊対処の任務についている海自のP3C哨戒機2機のうち1機の任務を今回の情報収集に変更することも選択肢に入る。防衛省の統合幕僚監部の検討チームでは、さまざまな事態を想定しながら必要な装備などについてケーススタディーを進めている。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「新規の船(護衛艦)の派遣と、ジブチを拠点とするP3C哨戒機や護衛艦の活用も検討対象にしている」と説明した。すでにソマリア沖アデン湾での海賊対処のため、護衛艦1隻とP3C哨戒機2機がアフリカ東部のジブチを拠点に他国と連携して活動している。ジブチは情報収集を目的とする今回の派遣候補地に近い。このため、日本から護衛艦1隻を追加派遣して計2隻態勢とすれば、「1隻は既存の海賊対処を継続し、もう1隻は新たな情報収集」という2つの任務の両立が可能となる。海上自衛隊が保有する護衛艦は48隻で、能力や装備が今回の任務に適しているのは20隻余り。中国の海洋進出が強まる中、「東シナ海などに展開する護衛艦を減らして警戒監視を弱めるわけにいかない。現場のやりくりに余裕はない」(自衛隊幹部)と不安視する向きもある。ただ、海賊対処部隊は平成28年、海賊事案の減少に伴い2隻態勢だったのを1隻に減らした。防衛省関係者は「『もともと2隻だろう』といわれれば、その通りだ」と語る。一方、派遣済みのP3C哨戒機2機のうち1機を海賊対処から情報収集に転用する場合、活動場所はバべルマンデブ海峡東側の公海の上空になる公算が大きい。オマーン湾はジブチから2千キロ余り離れており、所要時間や航続距離を考えると往復するだけでほぼ終わってしまうからだ。今回の派遣は、防衛省設置法で定められる省の担当業務「調査・研究」を法的根拠としている。常日頃の日本周辺海域での警戒・監視の根拠規定にもなっている。つまり、中東派遣は通常の任務の延長線上に位置づけられる。正当防衛以外での武器使用はできず、日本関係船舶を武器を使用して護衛することは法的に難しい。 *6-7:https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122700270&g=soc (時事 2019年12月27日) 官邸主導の自衛隊派遣、拡大する恐れ 中東シーレーン安全確保 中東に派遣される海上自衛隊は、不測の事態には日本船舶の護衛に当たり、武器使用も排除されない。本来なら立法措置を講じるべきだが、国会承認の必要がない防衛省設置法の「調査・研究」が派遣根拠になっている。国会のチェック機能が働かず、首相官邸が主導する形の海外派遣が今後、なし崩しに広がっていく恐れがある。調査・研究は学術的なイメージもあるが、「情報収集」と読み替えた方が分かりやすい。防衛相の命令で自衛隊を運用でき、日本近海での日常的な警戒監視活動の根拠になっている。地理的な制約がないとはいえ、中東の緊迫した海域で長期間、実任務に就く活動の根拠に調査・研究を用いるのは、拡大解釈と言わざるを得ない。調査・研究に基づく海外派遣の先例には、2001年の米同時テロ後、米艦などへの後方支援活動に先立ち、インド洋で護衛艦が情報収集に当たったケースがある。ただ、当時の派遣は旧テロ対策特別措置法の成立後で、準備を目的にしたものだった。今回、特措法は制定されず、テロ対策特措法に明記されたような国会承認の手続きは踏まれない。日本船舶を護衛する場合の海上警備行動への任務の切り替えも閣議決定で完結し、国民を代表する国会には結果を報告するにすぎない。首相官邸の裁量で実力部隊の自衛隊を海外で運用することが可能で、シビリアンコントロール(文民統制)や情報開示の面で大きな問題をはらんでいる。 *6-8:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200104&ng=DGKKZO54032220U0A100C2NNE000 (佐賀新聞 2020.1.4) 独、再生エネ発電が逆転、昨年46% 化石燃料上回る ドイツの発電量に占める再生可能エネルギーの比率が2019年に初めて化石燃料を逆転した。太陽光や風力などの再生エネの発電シェアは18年から5.4ポイント上昇し、46%に達した。石炭などの化石燃料は約40%だった。英国でも原子力を含めた二酸化炭素(CO2)排出ゼロの電源が初めて化石燃料を上回り、欧州の脱炭素を裏付ける結果となった。独フラウンホーファー研究機構太陽エネルギー研究所(ISE)が2日、ドイツの19年の純発電量をまとめた。企業の自家発電は含まない。1年間の発電量5155億6千万キロワット時(515.56テラワット時)のうち24.6%を風力が占め、最大の電源となった。発電量は18年比16%増え、シェアは4.2ポイント上昇した。太陽光のシェアは0.6ポイント上がり9.0%だった。バイオマスと水力もそれぞれシェアを伸ばし、再生エネ全体で237テラワット時となり、化石燃料の207テラワット時を上回った。化石燃料では品質の悪い褐炭が4.4ポイント減、石炭が4.5ポイント減とそれぞれ大きくシェアを落とした。発電量でもそれぞれ22.3%、32.8%減った。天然ガスはシェアが3.1ポイント上昇し、10.5%、22年までに運転をすべて停止する原子力は0.5ポイント増の13.8%だった。フラウンホーファーISEは、再生エネの逆転の理由について「発電費用の安い再生エネの拡大で、欧州排出量取引制度(EU-ETS)の排出枠価格が上昇し、CO2排出の多い褐炭などの発電では利益が出なくなっている」と指摘する。英米ナショナル・グリッドによると、英国では19年に風力・太陽光・水力・原子力を合わせたCO2排出ゼロの発電量シェアが48.5%となり、化石燃料の43.0%を初めて上回った。欧州連合(EU)は19年12月、2050年に域内のCO2の純排出をゼロにする目標で合意した。自動車などの電動化が柱のひとつで、動力となる電気を生み出す発電の脱炭素が実現のカギを握っている。 <多様な人が考えれば、地方創生も可能> PS(2019.12.22追加):*7-1に、2018年に関東・関西にある主要6空港以外の地方空港から入国した訪日客は、前年比11.7%増の758万人と入国者数全体の25.2%に達し、客数は2008年の5.5倍になったと書かれている。しかし、福岡の人が欧州に行くには関東・関西の空港まで来て出国するのではなく、福岡空港で出国してソウル空港に行った方が飛距離が短く、乗り換えも便利なのである。つまり、福岡空港・仙台空港・千歳空港などは既にその地域の主要空港であるため、成田、羽田、中部、大阪、関西、神戸の主要6空港を除く57空港を地方空港と位置付けるのは東京目線だと思う。また、佐賀空港は九州佐賀国際空港と名前を変更して海外路線を開拓し、10年間で入国訪日客が70倍以上になったのである。そして、乗客にとっては各地の空港が網の目のように結ばれている方が便利だ。 政府は、*7-2のように、「まち・ひと・しごと創生会議」を開き、2020年度から5年間の第2期地方創生総合戦略を了承したそうだが、その内容は、①地方への移住・定着の促進 ②関係人口の創出 ③2024年度までの東京圏への一極集中是正 ④多様な人材の活躍を目標に据えてJAの参画も強調 などだそうだ。しかし、①には、都市と賃金格差のあまりない仕事の存在が不可欠で、地方の製造業・農林漁業の生産性向上が必要になる。また、③の東京圏への一極集中是正は、過密で狭すぎない住居で暮らせるKeyだが、実行には地方のインフラ・産業・教育・文化の向上が必要で、②④や第1期で行った事業の効果に関する検証が重要だ。 *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191222&ng=DGKKZO53672170R21C19A2MM8000 (日経新聞 2019.12.22) 空からの地方創生(上) 訪日客は地方直行、25%が主要6空港以外へ 西日本の伸び顕著 インバウンド(訪日外国人)の玄関口として地方空港(総合2面きょうのことば)が存在感を増している。2018年に成田や関西など主要6空港以外の地方空港から入国した訪日客は前年比11.7%増の758万人と入国者数全体の25.2%に達した。客数は08年の5.5倍となった。自治体の誘致などで直行便が増え、西日本の空港で伸びが目立つ。韓国や中国など東アジアからが中心だが、欧州便が就航する動きも出ている。16日午前9時すぎ、フィンランド航空の定期便の初便がヘルシンキから新千歳空港に着いた。同国の男性プログラマー(35)は来日17回目だが北海道は初めて。「友人が留学したことがあり来てみたかった」と話す。新千歳には同日、オーストラリアのカンタス航空も就航。タイからは18年に道内の空港を通じ10年前の約220倍の14万人が入国し、観光地は国際色を増す。全国の空港で入国した訪日客は2932万人と10年で3.5倍。地方空港の伸びはそれを上回る。国土交通省「空港管理状況」や法務省「出入国管理統計」などから空港ごとの利用者や入国者を集計。08年以降に訪日客が入国した63空港から成田、羽田、中部、大阪、関西、神戸の主要6空港を除く57空港を「地方空港」として独自に分析した。入国訪日客が最も伸びたのは山形空港。08年の2人が18年に6550人に膨らんだ。台湾からのチャーター便が18年度に123便と4年間で9倍以上増えた。山形県が航空会社の着陸料減免や旅行会社への助成などで支援し、山形を起点に東北の食や温泉を楽しむツアーが人気という。18年の入国訪日客は福岡の241万人を筆頭に17空港が5万人を上回り、うち11空港が西日本だ。東京や京都など「ゴールデンルート」以外を見たいという訪日リピーターを集める。政府も点から線へ訪日客の周遊を誘おうと自治体の広域連携を支援する。佐賀空港は10年間で入国訪日客が70倍以上。18年度のチャーター便は177便と地方空港では4位だった。佐賀県も着陸料などの優遇で訪日客の観光を促し、年間100億円規模の経済効果を見込む。足元での韓国便運休は痛手だが、中国の西安から新路線を招くなど手を打つ。地方発着の国際定期便は19年夏に週1132便と14年冬の1.8倍に増えた。ただ、訪日客は18年に韓国からが全体の4割強で台湾、中国、香港を加えた4カ国・地域が9割を占める。中国などが増え19年1~9月は前年同期を上回ったが、日韓対立の影響で9月にはほぼ全空港で韓国からが前年を下回った。空港経営に詳しい慶応義塾大学商学部の加藤一誠教授は地方空港の東アジア依存について「運航コストや効率面から距離の近い西日本への路線が多くなる」と指摘。「幅広い地域からの路線を誘致するとともに、地元から海外へのアウトバウンド需要の創出にも取り組むべきだ」と語る。19年に日本の12会場で開かれたラグビーワールドカップ(W杯)は訪日客の多様化で可能性を示した。出場17カ国(イングランドなど3チームは英国)からの入国は9月に地方空港で前年比40.6%増と全体の伸びを上回った。20年の東京五輪・パラリンピックでも地方にどう波及効果を呼び込むかが課題となる。 *7-2:https://www.agrinews.co.jp/p49535.html (日本農業新聞 2019年12月20日) 地方創生 第2期総合戦略 人材活用 JA参画を 政府は19日、まち・ひと・しごと創生会議(議長=安倍晋三首相)を開き、2020年度から5年間の第2期地方創生の総合戦略を了承した。関係人口の創出を柱の一つにし、24年度までに東京圏への一極集中の是正を目指す。多様な人材の活躍を目標に据え、JAの参画も強調した。20日に閣議決定する。第2期総合戦略では、最重要課題に東京一極集中の是正を掲げた。18年時点で13万6000人の地方から東京圏への転入超過数を24年度までに解消する。一極集中是正に向けて、地方への移住と定着の促進に加え関係人口創出に力を入れる。兼業や副業で、農山村で働いたり、祭りや草刈りを手伝ったりするなど、多様な形で農山村と関わる関係人口を広げ、地方と都市のつながりを強化する。政府は関係人口の拡大に取り組む自治体数で1000を目安にするが、数値目標(KPI)とはしない。数字ではなく関係づくりを重視したい考えだ。第2期総合戦略の共通目標として、「多様な人材の活躍推進」の他、持続可能な開発目標(SDGs)で持続可能な地域づくりを進める「新しい時代の流れを力にする」を提示した。JAの参画も強調した。具体的には、住民を中心に地域の課題解決に取り組む「地域運営組織」や住民の暮らしを支えるサービス、機能などを集約し、周辺集落と交通網で結ぶ「小さな拠点」の形成などでJAを明記した。国の地方創生総合戦略の決定を踏まえて、各自治体は今年度中にも第1期(15~19年度)の検証と併せ、第2期の地方版総合戦略策定を決定する。 <1カ月ではあてにできないこと> PS(2019年12月28、29日追加):*8-1のように、政府は少子化対策として男性国家公務員に1カ月以上の育児休暇を取得させる取り組みを2020年度から実施するそうだ。男性の育休取得が進まない理由は、①業務面の懸念 ②育休を取得しにくい雰囲気 ③育休中は無給扱いで標準報酬日額の50~67%にあたる手当金が出るが収入減になること などの背景があったからとのことだが、これは女性も全く同じで、男性なら問題にするが女性なら問題にしないという風潮は根強い性別役割分担意識に基づく女性差別だ。また、これを個人の福利を増すためではなく少子化対策としてやろうとしている点は個人を大切にしない全体主義の発想であるし、1カ月休んだくらいでは(何もしないよりはよいが)家事・育児を理解することすらできないと思う。 このような中、*8-2は、スーパーで肉や魚を買った客が、商品のラップを外して中身を包み、トレーは店内のごみ箱にポイとすてることが問題にされており、不便やコストアップを受け入れる意識改革が進んでいるのをよいことのように記載しているが、家事労働を効率化しなければ仕事と家事を両立することはできない。そして、このようなことを、主体として家事労働をした人でなければ想像もつかないのかと不思議に思う。この事例で(1995年頃にリサイクルを提唱した)私が気付くのは、④それから四半世紀経っても不便なままのゴミ収集やリサイクル方法を改善しない自治体や企業の怠慢 ⑤客のニーズに合わせない店舗 である。④については、(指定のごみ袋を買わせるなどして)ごみ収集に手数料をとってもよい時代になったため、分別しやすく、いつでも出せるゴミ収集に改めるべきだ。また、⑤については、私も、トレイに入っている肉が脂身が見えないようにトレイ側に折りたたまれて入っていて「まいったな」と思うことがあるし、確かにトレイはかさばりもするため、トレイに入れたものとビニール袋に入れたものの両方を準備して購入者が選択できるようにした方がよいと思う。 なお、家事の効率化には、*8-3のような加工野菜や調理済惣菜が便利で需要が増えるのは当然だが、これまで加工すると原産地表示が不要になった。そのため、(かなり遅いが)食品表示法改正によって2022年4月から全ての加工食品に原産地表示が義務化されるようになったのは、需要者の手を伸びやすくするだろう。 *8-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191228&ng=DGKKZO53963870X21C19A2EA3000 (日経新聞 2019.12.28) 男性公務員の育休「1カ月超」原則に 少子化対策男女共に手厚く 政府は27日、少子化対策として男性の国家公務員に1カ月以上、育児休暇・休業を取得させる取り組みを発表した。2020年度から実施する。部下の育休は上司の責任と位置づけ、全員取得を目指す。「月100時間残業」といった長時間労働の是正とセットで取り組む必要もあり、職場の意識や働き方を変えられるかが焦点となる。新制度では、既存の育児休業のほか、特別休暇「男の産休」(最長7日間)や年次休暇を活用し、1カ月以上休めるようにする。育休中は無給扱いだが、標準報酬日額の50~67%にあたる手当金が出る。有給の休暇とセットにすることで収入減の懸念を和らげる。このほか男性の育休取得が進まない背景に、業務面の懸念や取得しづらい職場の雰囲気もある。このため、上司が対象職員と相談しながら取得計画を作成し、育休中の職場の体制を事前に整えるとした。部下の取得状況を直属の上司や幹部の人事評価にも直結させて、職場が一丸となって取り組む姿勢を明確にする。今回、対象となる男性国家公務員は約44万人で、長時間労働を抱えるケースの多いキャリア官僚も含む。職場ごとに計画策定や取得状況を公表し、フォローアップすることも検討している。菅義偉官房長官は同日の女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会で、各省庁の幹部に「男性の育児参加、女性活躍、少子化対策の観点から極めて重要だ」と強調した。菅氏の下で8月末から検討を始め、わずか4カ月で制度の発表にこぎつけたのは、少子化への危機感の表れだ。政府は15年に「希望出生率1.8」を目標に掲げたが、18年の合計特殊出生率は1.42と3年連続で下がった。厚生労働省が24日発表した19年の出生数(年間推計)は、予想よりも2年早く86万人まで落ち込んだ。国立社会保障・人口問題研究所によると、夫婦に聞いた「理想」の子どもの数は2.32人。都内の30歳代の女性会社員は「平日の夜は(家事や育児を1人でこなす)ワンオペ。2人目はためらってしまう」と語る。男性が子育てや家事に費やす時間は先進国中、最低の水準だ。一方で、夫の家事・育児時間が長いほど第2子以降の出生割合が高いという調査結果もある。共働き世帯が当たり前になった今、男女ともに仕事と子育てを両立できる職場環境づくりが欠かせない。もちろん育休の取得だけがゴールではない。男性が前向きに取り組めるように、出産前の「両親学級」といったスキルアップの機会を増やすことなども課題だ。政府は民間企業などへの波及も狙う。男性も保育所の送り迎えができるように、子どもと夕食を取れるように、政府と民間が一体となった継続的な取り組みを期待したい。 *8-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/571540/ (西日本新聞 2019/12/27) 食品トレーは必要?“くるりポイ”巡り議論広がる 消費者、店側の声 スーパーで肉や魚を買った客が、商品のラップをくるりと外して中身を包み、トレーは店内のごみ箱にポイ。この「くるりポイ」行為を報じた「あなたの特命取材班」の記事を受け、インターネット上で容器包装のあり方が議論になっている。プラスチックごみ削減が国際的な課題となる中、消費者は何を求めているのか。意見の一部を紹介する。記事をヤフーニュースで公開した11月、コメント欄には約4700件の意見が寄せられた。「私も見た」との目撃情報、マナー面や衛生面で問題視する声に加え、議論は「なぜ『くるりポイ』をする人がいるのか」にも及んだ。理由の一つに挙がったのが、トレーの分別収集の分かりにくさだ。容器包装リサイクル法は市町村に分別収集の「努力義務」を課しており、対応はさまざまだ。福岡市では燃えるごみだが、北九州市では資源ごみ。白色トレーを分別する自治体もあり、「洗浄や乾燥に手間がかかりすぎて、店に捨てる人もいるのだろう」と推測する意見も。来年7月からはレジ袋の有料化が義務付けられる予定だが、「トレーがかさばって持参した買い物袋に入りきらない」との不満も噴出していた。家庭ごみを減らしたい高齢者の事情も垣間見えた。「買った物をカートに積み、バスで家まで運ぶ。少しでも荷物を減らしたい」「有料のごみ袋がすぐ満杯になる。ごみ出しも大変」。商品の見栄えを良くする「上げ底トレー」、野菜や果物を保護する「念のためトレー」、個包装の菓子をさらに包む「おもてなしトレー」などの丁寧すぎる包装についても、店側に簡素化を求める意見が相次いだ。一方で、店側にも言い分があるようだ。「無駄な経費になるトレーなど、本来なら自分たちも使いたくない」。「レジを素早く通して客の待ち時間を短縮し、クレームを最小限にするための店側の気遣いでもある」。「消費者のニーズである衛生的で均一化された品質、安定価格を実現するために、中間センターで食材処理や包装をする仕組みができあがってきた。変えるには、不便やコストアップを容認する消費者の意識の変化も必要」。確かに「野菜が少しでも傷んでいると苦情が出るので、トレーに入れる」というコメントもあり、多様なニーズの板挟みとなっている様子だ。しかし、消費者からは「トレーか袋かを選べるといいのに」「簡易包装でトレーに載せて売り、トレーは店が回収を」などのアイデアも。容器持参で買いたいという声や、トレー価格の上乗せを容認する声も少なくなかった。不便やコストアップを受け入れる意識改革は、少しずつ進んでいる。 *8-3:https://www.agrinews.co.jp/p49580.html (日本農業新聞 2019年12月26日) 加工・業務野菜 需要捉え好機逃がすな 国内で消費する野菜の6割を加工・業務用が占める。高齢・単独世帯や共働き世帯の増加、個食化の進展、消費者の求める利便性・簡便性を背景に需要が伸びる。国内産地は、消費動向を分析し、きめ細かい対応で好機をつかむべきだ。2018年度のカット野菜・冷凍野菜・野菜総菜の小売販売動向調査(農畜産業振興機構)によると、09年から18年までの10年間の全国のスーパー約1000店舗の販売額は、いずれも10年前より増加した。1000人当たりの販売金額は冷凍野菜は5545円と10年前比22%増、野菜菜総菜は7215円と同50%増。カット野菜は7236円と3・3倍になった。伸びが大きいカット野菜を「サラダ」「キット」「カット」「総菜サラダ」に4分類したところ、サラダは同4倍、キットは同3・5倍、カットは同2・6倍、総菜サラダは同3倍だった。品目で見ると、消費動向の変化が分かる。多くの品目が増加する中、ゴボウはカットは減り、総菜サラダが増加。簡便性の高まりで、調理済みの総菜サラダの活用が多い。加工・業務用といったひとくくりの用途ではなく、末端の消費動向を詳しく分析した産地づくりが必要といえる。日本農業新聞は企画「ゆらぐ基~広がる危機」で、人手不足に悩む外食企業が、カット野菜の使用を増やしている事例を紹介。その需要に対し輸入野菜が浸透し、国産が需要を取りこぼしている点を指摘した。国内産地は今まで以上に加工・業務用に目を向けるべきだ。JAグループでは、JA全農が加工・業務用のブロッコリー産地づくりに乗り出した。東北から九州の10県の生産者に、加工時の歩留まりが良い通常の2倍の重さのブロッコリーを生産してもらい、コンビニのセブン―イレブンと取引。11月から国産サラダとして販売が始まった。全農によると、契約取引で農家は安定収益が見込め、調製作業の省力化といった利点もあるという。食品表示法の改正で、22年4月には全ての加工食品に原料原産地の表示が義務化される。国産ニーズが高まることは必至で追い風が吹く。この好機を商機に結び付けたい。農水省も来年度の概算要求で、加工・業務需要に対応した新事業を要求。安定的な生産・供給に向けて、生産事業モデルの育成を支援する計画だ。事業者にとって使い勝手のよい支援策となるよう求める。加工・業務用野菜の取引は「定時・定量・定品質・定価格」の「4定」が重要といわれる。青果物は天候不順に合いやすく「4定」を履行するには、需給調整が大きな鍵を握る。産地だけでなく、卸売会社などの流通業者の協力も不可欠だ。業界一丸で「4定」に挑戦し、加工・業務需要を取り込み、産地の活性化につなげよう。 <「日本産は安全」とも言えないこと> PS(2019年12月31日、2020年1月9日追加):*9-1のように、TPP発効から1年経過した現在、日本産を優遇してきた関税の削減・撤廃で食肉・果実を中心に輸入が増え、今後は日欧EPAや日米貿易協定も発効するので日本の農業は自由化の波に晒されている。しかし、日本産の肉は確かに美味しいが蛋白質を摂りたいのに同時に多量の脂肪を摂らされ、(米国産は安いが品質がイマイチというのと異なり)カナダ産の豚肉は美味しくて脂肪が少ない上に安く、ニュージーランド・オーストラリア産の牛肉は脂肪が少なく価格も安いため、私も普段使いはこちらに変更した。しかし、これらは、飼育方法を変えれば日本でもできることなのだ。また、ニュージーランド産のリンゴは手頃な大きさで一人暮らしや少人数の家族に適している上、価格も安い。一方、日本産は価格が高い上に大きすぎて少人数の家族には向かず、冷蔵庫にも入りにくい。つまり、日本産は、マーケットリサーチしてニーズに合わせた生産をすることが苦手で、その理由は、農業が国に頼りすぎているからなのである。そのため、農協始め農業関係の皆さまは、農業で勝っている国を訪ねて農業の「Best Practice」を実地に調査されるのがよいと考える。 それでは、日本産は安全なのかといえば、牛肉は米国に合わせてBSEの検査基準を引き下げたため米国並みになり、それなら安い方がよいことになった。また、*9-2・*9-3のように、経産省と(疫学の専門家ではない)原発の専門家が「基準値以下に薄めればよい」などという非科学的な理屈で、フクイチの汚染水を海洋放出か大気放出すると決めたような感覚だ。そのため、「日本産」の表示は安全性を保障しないことになり、安全性は地域の取り組みによって変わるものの、地域別の産地表示がなされていなければ選択することができないため、日本産全体を避けた方がよいことになるわけである。 このような状況の下、*9-4のように、立憲民主党と国民民主党が合流協議で焦点の一つとなっている原発政策で、「再稼働を認める条件を厳格化して原発ゼロを目指す方向」という玉虫色の決着をするそうだ。しかし、電力自由化が進んだ今、大手電力会社もグリーンエネルギー・全国展開・海外展開などの新しい選択肢ができたのだから、電力総連の組織内議員を抱える国民民主党がこのような対応をするのは、野党の弱さの原因の一つになるだろう。 *9-1:https://www.agrinews.co.jp/p49626.html (日本農業新聞 2019年12月31日) TPP発効1年 食肉、果実で輸入攻勢 日米控え警戒強まる 環太平洋連携協定(TPP)の発効から30日で1年。関税の削減・撤廃を機に、食肉や果実を中心に輸入攻勢が強まり、国内農業はかつてない自由化の波にさらされている。各国が対日輸出を強化する中、参加国と非参加国でのシェア争いも激化。日欧経済連携協定(EPA)に続き、年明けには日米貿易協定の発効も控える。国内では警戒感が広がっている。 ●豚肉・牛肉 カナダ産対日強化 「カナダにとって日本は最大の輸出相手国に成長した。TPPによってさらに新しいチャンスがきた」。カナダ産豚肉の輸出団体、カナダポーク・インターナショナルは11月、対日輸出増の手応えをこう表現した。財務省の貿易統計によると、1~11月期の豚肉の輸入量は、前年同期比4%増の88万6671トン。同5%増のカナダ産は、4月に単月の輸入量で初めてトップの米国を上回るなど勢いを増す。「品質には定評がある。関税削減で価格面でも優位性が高まった」(大手輸入業者)など、品質・価格の両面で攻勢をかける。国内での人手不足が深刻化する中、カットなど1次加工品を中心としたメキシコ産も同16%増と大幅に増えた。牛肉は、輸入量全体では前年同期並みだが、カナダ産が同95%増の3万9730トン、ニュージーランド産が同32%増の1万7368トンと、参加国からの輸入量は大きく伸びた。「関税削減で高価格帯の価格が下がり、米国産からシフトした」(食肉業者)という。主力のオーストラリア産は現地価格の高騰が影響したため、同5%減となった。輸入と競合するとされる乳用種の小売価格は、年明け以降、下落傾向が続いている。農畜産業振興機構の調べによると、2019年度の11月までの乳用種など「その他」の牛肉の小売価格は、ばら肉が100グラム当たり386円と前年度比9%安となっている。 ●ブドウ・リンゴ 店頭でも存在感大 スーパーなどの店頭で急速に存在感を高める輸入果実も、TPP参加国からの攻勢が鮮明になっている。発効国で関税が撤廃されたブドウは同27%増の4万3556トン。オーストラリア(25%増)やメキシコ(122%増)などからの増加が目立つ。卸売業者は「種なし皮ごとの手軽さが消費者に受けている。関税撤廃で価格が下がったことも大きい」と指摘する。リンゴも、同30%増えた。ニュージーランド産が同35%増と大きく伸ばした。異常気象や高齢化で国内産地が課題を抱える中、「国産リンゴの不足分を補う」(卸売業者)との声もあり、シェアを奪われる可能性がある。 ●ワイン・乳製品 低価格の競争激化 ワインは、同7%増の26万1359キロリットル。日欧EPAで関税が即時撤廃された欧州からの増加が中心だが、メキシコ(15%増)、ニュージーランド(7%増)などからの輸入も増えた。山梨県で「日本ワイン」の醸造に力を入れるワイナリーは「国内では、低価格帯のワインを選ぶ消費者の比率が高い」と、輸入増加による競争の激化を懸念する。乳製品は、ナチュラルチーズが同6%増の27万900トンとなった。もともと関税が低い野菜は、大幅な増加は見られなかった。 ●影響監視継続的に 農畜産物の貿易に詳しい北海道大学農学部の東山寛准教授の話 食肉やブドウといった果実など影響が懸念されていた品目では、確実に輸入量が増えている。国は、品目ごとの輸入量の動向や国内価格への影響を継続的に注視して、必要な国内対策に結び付けることが重要だ。今後、懸念されるのが、国内対策の財源確保になる。これまで安定的な財源となっていた関税やマークアップ(輸入差益)が年々減っていく中で、将来的にどう財源を捻出するのか。国は明確な枠組みを示すべきだ。4月以降、関税の削減率は3年目水準に下がり、輸入攻勢はさらに強まるだろう。産地には、価格ではなく、付加価値を高めるなどの対抗策が求められる。 *9-2:https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=600592&comment_sub_id=0&category_id=142 (中国新聞 2019/12/29) 福島原発の処理水 地元に我慢強いるのか 東京電力福島第1原発の汚染水は、いくら処理しても放射性物質が残る。タンクに保管され、増え続ける「処理水」をどうするか。政府の小委員会の議論が大詰めを迎えている。海洋放出と大気放出を軸にした取りまとめ案を先ごろ、経済産業省が示した。風評被害の懸念は根強く、タンクでの長期保管を望む声もある。技術面や時間的制約から選択肢を絞り込んだのは理解に苦しむ。未曽有の原発事故によって、深手を負った地域経済は今もなお復興の途上にある。追い打ちを掛けるような提案ではないのだろうか。小委員会では、他にも地層注入、放射性物質トリチウムの分離、地下埋設の3案を検討課題としていた。いずれも新たな技術や規制が必要だとして、「現実的な選択肢として課題が多い」と除外。前例が国内外にある、海洋と大気に放出する案だけを残した。廃炉作業では、溶融核燃料(デブリ)の取り出しという未知の技術開発に挑もうとしている政府の姿勢とは、落差があまりに大きい。処理水でも、地元が風評被害に遭わずに済む手だてを見いだすべきである。結論を急ぐのは、2022年夏ごろまでに保管タンクに収めきれなくなることと無関係でないだろう。背に腹は代えられないからと、手っ取り早い策を選んだように映る。取りまとめ案では、保管中の処理水全てを1年間で海洋や大気に捨てたとしても、一般の人が年間に被曝(ひばく)している線量の約1600分の1~約4万分の1にとどまるとしている。だからといって風評被害が起きないとは限るまい。地元にとって死活問題であるのに、風評被害の深刻さや規模は比べられないとして、経産省は各案での被害想定を示さなかった。福島県民からすれば、誠実さを欠く態度に受け取れよう。原発事故によって、県産米は今も、放射性物質濃度について全量全袋検査を続けている。農業や水産業にとどまらず、観光にも影響が及ぶ恐れもある。小委員会の委員から「社会的影響は極めて大きい、とはっきり書くべきだ」といった意見が相次いだのは当然だろう。最終的に処理方法を決めるのは政府である。小委員会からの提言書が、重要な判断材料になる。だからこそ、各案が及ぼす風評被害の程度も明記する必要があるのではないか。原子炉から抜け落ちたデブリは水で冷やし続けている。それに伴って生じる汚染水の量は、事故直後に比べて3分の1ほどに減ったとはいえ、1日当たり170トンに上る。おととい公表された最新の廃炉工程では、25年までに汚染水を100トン以下にするとした。それで目いっぱいというのが、安倍晋三首相の言う「アンダーコントロール(制御できている)」の実態に他ならない。福島県内の漁業は、魚種や海域を限定した試験操業がほそぼそと続き、先行きは見通せていない。畜産業でも、避難指示が解除された地域でさえ牛農家の95%が立ち直れていない。地元から上がっている不安や懸念に丁寧に耳を傾け、支援してこそ「復興」は近づく。これまでの苦境を思えば、新たな我慢を強いるべきではない。 *9-3:https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201912/0012996958.shtml (神戸新聞社説 2019/12/29) 原発処理水処分/「安全神話」に頼りすぎだ 東京電力福島第1原発の敷地内で保管する処理水の処分について、経済産業省が政府小委員会に海洋と大気への放出を軸とする3案を示した。いずれも放射性物質による健康不安や風評被害への懸念が大きい。社会的影響を無視した強引な絞り込み方には地元で反発の声が高まっている。ゼロベースで再考すべきだ。第1原発では、事故で溶け落ちた核燃料を冷やす際に生じる汚染水が増え続けている。多核種除去設備(ALPS)で浄化した後の処理水を、敷地内にタンクを増設して保管している。東電は2022年夏ごろに満杯になるとしており、小委員会で検討を続けてきた。ALPSでは放射性物質のトリチウムを除去できない。しかし海水や空気で基準値以下まで薄めれば健康上の問題はないというのが東電や政府の見解だ。国内外の原子力施設で海洋放出されていることも今回の経産省案の根拠になっている。しかし公聴会などでは人体の内部被ばくや、食物連鎖によって濃縮される問題を研究者らが指摘した。トリチウムの「安全神話」が生まれているとの科学的な批判を受け止め、議論を丁寧にやり直す必要がある。そもそも第1原発内だけで保管するのもおかしな話だ。人が住めなくなった原発の周辺地など、候補はある。それなのに、不明確な根拠で保管継続を選択肢から外したのは乱暴と言わざるを得ない。近畿大学などのチームは、トリチウムの除去技術を開発している。こうした研究の実用化を支援することが、事故を起こした東電や国の責任ではないか。処理水にトリチウム以外の放射性物質が残っていたことを東電は公表しなかった。隠蔽(いんぺい)体質への反省も十分でないまま、放出に地元の理解が得られると考えているなら甘過ぎる。自然界に放出した場合の漁業などへの風評被害についても、経産省案は十分に検討していない。住民の実害への不安にも寄り添う態度が見られない。政府案は、コストが低い海洋放出の優位性を強調する文言が並ぶ。リスクを軽んじれば最大の被害を招くという警鐘を真摯(しんし)に受け止めるべきだ。 *9-4:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/381853?rct=n_politics (北海道新聞 2020/1/9) 立憲と国民、原発再稼働厳格化で調整 立憲民主党と国民民主党が合流協議で焦点の一つとなっている原発政策を巡り、再稼働を認める条件を厳格化し、原発ゼロを目指す方向で最終調整していることが分かった。昨夏の参院選を前に両党など4野党が合意した事実上の共通政策に基づき、避難計画や地元合意を条件付け、再稼働が困難な内容とする。立民の枝野幸男、国民の玉木雄一郎両代表が7日夜の会談で一致。関係者が9日、明らかにした。立民が「一日も早い原発ゼロ実現」を掲げ、再稼働を認めないのに対し、国民は「2030年代」を目指し、再稼働を容認する電力総連などの組織内議員を抱える。このため政策は原発が主な論点となっている。 <風と流れをとらえるグリーン&ブルーインフラ> PS(2020年1月3日追加):*10のように、ノーベル化学賞を受賞された吉野彰さんが言われるまでもなく、今後は環境を護る経済でなければ持続可能ではない。しかし、それを実現する技術革新・地域資源の利用などの脱炭素の要請は、実は日本にも地方にも追い風なのである。そのため、国が無駄遣いをする余裕などない人口減時代の新たな国土計画には、いつまでも直接支払いをあてにする農業ではなく、農林水産業を生業とする場所で同時にエネルギーを創出できるような投資をしてもらいたいわけだ。 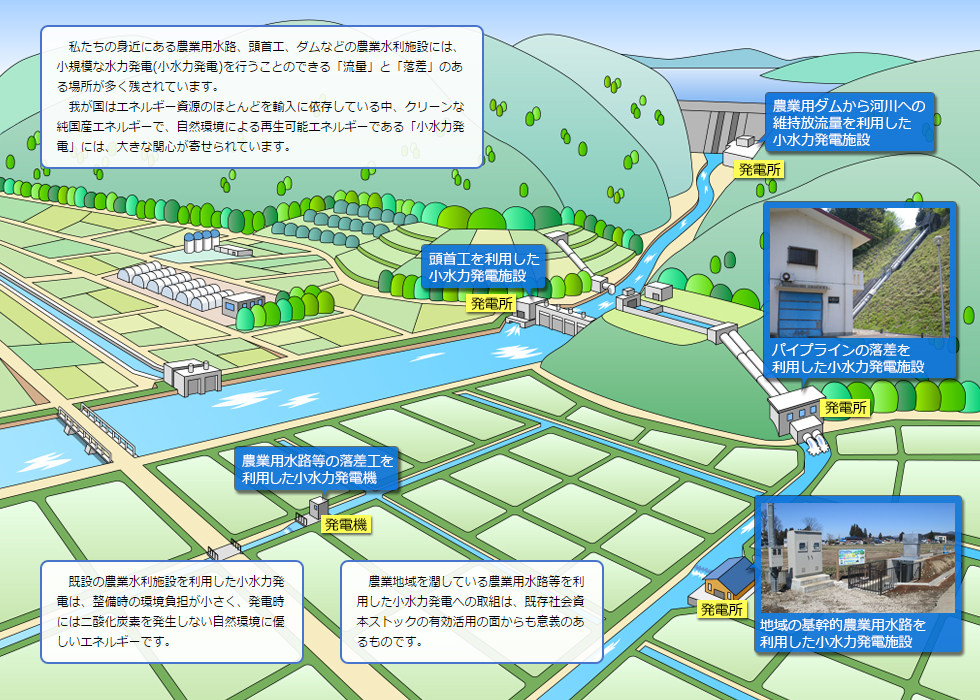     (図の説明:1番左は、農業施設に設置できる発電機例、左から2番目は農業用水路に設置した小水力発電機、右の3つは農業地帯に建てられた風力発電機だが、風力発電機は進歩が望まれる。なお、中央の図のように、田畑が小さく区切られているのをよく見かけるが、もっと大きな区割りにしないと大型機械が入らず、生産性が上がらないだろう) *10:https://www.agrinews.co.jp/p49627.html (日本農業新聞論説 2020年1月3日) [風をとらえる] 緑の資本論 農と自然の力で世直し グリーンパワーが日本を再生へと導く。今年は、農業や自然環境が持つ豊かな恵みを国土や地域づくりに生かす「グリーンインフラ(緑の社会資本)」推進の年。人口減、地方衰退、気象災害などの課題を克服し、持続可能な社会へ踏み出す時だ。成長から成熟へ、競争から共創へ。大転換期を生き抜く「緑の資本論」を提唱する。「グリーン公共事業」「グリーン経済」「グリーン資本主義」。より良い経済や社会のためのキーワードは「グリーン」。総称して「緑の資本論」と名付け、社会課題の「解」を探る。まずグリーンインフラの実例から──。 ●大地潤す命の水 その人は人生を懸けて「命の水」を求めた。昨年12月、アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師。享年73。中村さんは「百の診療所より1本の用水路」を信条に、内戦と干ばつに苦しむ不毛の地で「緑の大地計画」を進めた。生きるための水は、大地を緑の沃野(よくや)に変えた。17年かけて27キロに及ぶ農業用水路を通し、1万6500ヘクタールの土地を潤した。その水は今、65万農民の営農と暮らしを支える。平たんな道ではなかった。資金、機材、技術、労力、どれも乏しい。生態系もこれ以上壊したくない。答えは中村さんの足元、郷里の福岡県にあった。筑後川の中流、朝倉市に江戸時代から伝わる「山田堰(ぜき)」。大小の石を斜めに敷くことで暴れ川の流れを和らげ、用水路に導くせきである。今も現役で、一帯を有数な水田地帯に変えた。この技術を中村さんに橋渡ししたのが「山田堰土地改良区」の前理事長・徳永哲也さん(72)。昨春、中村さんから「ぜひ現地を見てほしい」と誘われ、アフガンに赴いた。「目にしたのは山田堰そのものでした」。胸が詰まった。中村さんも満面の笑み。その笑顔が最後になるとは思いもよらなかった。「山田堰は世界に誇れる技術」と言ってくれた中村さんの思いが今は分かる。「先生の遺志を継ぐのが私たちの務めです」。江戸の知恵が時空と国境を越え、人々の暮らしとなりわいを支える。 ●共生・循環経済を ダムや橋をハードインフラとするなら、今求められているのは「緑の社会資本」。1次産業や自然の持つ多様な力を地域づくりや国土計画、防災・減災に生かすこと。「緑の大地計画」は、その生きたお手本である。国交省は昨年を「グリーンインフラ元年」と位置付け、今年から官民連携のプラットフォームを始動させる。引き金は、深刻化する気候変動と環境破壊、1次産業や地方の衰退だ。食、農、環境など17分野で、2030年までに国連が各国に問題解決を求めた「持続可能な開発目標」(SDGs)。今年から運用が始まる温暖化防止のパリ協定。「持続可能社会」が世界の共通語になった。その有効な解決策となったのがグリーンインフラ。欧米では1990年代後半から、都市緑化による雨水管理、自然環境を利用した減災・防災対策が始まった。特に欧州は生物多様性の保全を重視。水質や大気の浄化で気候変動を和らげる「生態系サービス」の考えを取り入れる。造園家で東京都市大学特別教授の涌井雅之さんは「日本こそが、自然共生と再生循環の歴史を持つ」と指摘。里山などの知恵を引き、日本人は自然を「手入れ」することで、その恩恵を最大化し、災害を最小化してきたという(総合情報誌『地域人』)。 ●農山村は先進地 グリーンインフラは、農業の多面的機能そのものだ。だが生産基盤の弱体化は、災害への抵抗力を弱め、集落機能の喪失は環境破壊の悪循環を招いている。国土管理と防災の視点で、森林・河川、水田、里山・里海、農業水利、都市農地などの役割を再評価し、先端技術と組み合わせ、維持・修復のために直接支払いや公共投資を大胆に行うべきだ。いわば日本版「グリーン・ニューディール」政策である。自然環境の「保全」と併せ、農山村の資源を宝に変える「攻め」でも投資、雇用、人材を呼び込みたい。営農型大型太陽光発電、バイオマス(生物由来資源)や小水力発電によるエネルギーの地産地消、小型電動車の「グリーンスローモビリティ」、人工知能(AI)を活用した「スマートため池」など、農山村は課題解決の先進実験場だ。そこで大事なのは住民の参加。地域内外の多様な人材が、それぞれの持ち場で、課題に関わりを持つことだ。棚田の復活、生き物が集うビオトープや水辺の再生、市民農園参加など、身近なところから一歩踏み出してみよう。ノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんは言う。「環境と経済を調和させる技術革新が持続可能な社会を開く」。地域資源や先端技術を活用し、社会や経済の仕組みを変えるのは脱炭素時代の要請だ。各省庁も発信を強める。国交省のグリーンインフラ戦略のほかに、環境省の「地域循環共生圏」、農水省の「農林水産業×環境・技術×SDGs」構想などがある。新たな国土のグランドデザインに向け、関係省庁を横断的につなぐ国家戦略と体制が必要だ。経済界も変わり始めた。環境や社会課題に配慮した「ESG」投資が広がる。社会貢献が企業価値となる時代だ。「グリーン・キャピタリズム」(緑の資本主義)が企業活動の新潮流になるだろう。国連環境計画(UNEP)は、環境リスクや生態系への影響を減らし、人々の生活の質を向上させて不平等を解消するための「グリーン経済」を提唱する。「緑の資本論」で、環境と調和した持続可能な社会をどうつくるか。国連が求めた「大胆な変革」へ。残された時間は多くない。国家も個人も問われている。 <次の農業基本計画は・・> PS(2020年1月4、9日追加):私は、①食料自給率の向上 ②農業の多面的機能の発揮 ③農業の持続的発展 ④農村の振興 という農業基本計画には賛成だが、「若者が田園回帰し始めても農業者や農地の減少が止まらない」背景には、農業を始めるには「自然や農業が好きであること」以外のさまざまなハードルが存在することがあると思う。そのハードルとは、i)世襲でなければ用地を確保しにくい ii)個人企業なので、資金を要しリスクを伴う iii)機械の値段が高い iv)家族労働を強いるので配偶者に仕事の選択の余地がなく、1人当たりの年収が少ない v)家制度を前提としたムラ社会に溶け込まざるをえない vi)ただ働きが多い などであるため、求められる農業のスタイルは、世襲制度・家制度・家族労働・ムラ社会・共同作業という価値観を共有しなくても安心して農業を選択できる方法を準備すること、農業機械や農業資材の高額すぎる価格付けをやめること、融資やリスク回避の方法を充実することなどだと考える。 上のi) ii)iii)iv)については、*11-2のように、よい承継相手を見つけることができれば世襲でない方法もあるが、譲渡(もしくは賃貸)の範囲や公正な価値について書面で契約しなければ不満が残る。日本では不動産評価に売却価値を用いて収益還元価値を使わないため、立派な果樹等が評価されないことになり易いが、これらは事業承継や企業価値評価に慣れた公認会計士・税理士等に任せればよいと思う。また、引退者が園地を現物出資して承継者と農業生産法人を作り、貢献分の利益を配分してもらえば、引退者は園地と縁が切れる寂しさもなく、承継者にスムーズに技術移転することが可能だ。なお、*11-3のように、若者が推進力となって「田園回帰」が起こっているそうだが、*11-4のように、多様な移住者が活躍できる地域づくり、交通網・病院・学校などのインフラの確保は必要で、全国町村会の食料・農業・農村基本計画の改定に向けての政策提言に期待される。ただし、「交付金」は、既得権益化するのではなく、離陸するための滑走期間の投資として使って欲しい。 *11-1:https://www.agrinews.co.jp/p49633.html (日本農業新聞 2020年1月4日) [風をとらえる] 転換期の基本計画 後世意識し使命果たせ 農家の営農と生活、農村の風景は10年後の2030年にはどうなっているか。国民の食料はしっかり守られているか。目指すべき姿を描く新たな食料・農業・農村基本計画の検討が詰めに入る。時代状況が激変、価値観が多様化しつつある転換期にふさわしい、後世に恥じない基本計画を打ち立てるべきだ。農業者や農地の減少が止まらず、追い打ちを掛けるように国際化を受け入れた。一方で、若者の田園回帰に見られる農業への新たな期待も広がる。その中で迎えた今回の基本計画の改定は、政府の段取りでは3月。審議日程は残りわずかしかない。議論が尽くされているかというと、疑問だ。正式な審議開始は昨年9月で、駆け足の印象を拭えない。だが、基本計画の使命は大きい。原点にさかのぼりたい。初の基本計画は2000年。前年に制定された食料・農業・農村基本法の①食料の安定供給の確保②多面的機能の発揮③農業の持続的な発展④農村の振興──という基本理念に沿った政策を具体化し着実に進めるためだ。当時は、世界貿易機関(WTO)農業交渉が始まるという時期。国際化の荒波から、国民合意の下に農業をどう守るかという切迫した状況認識があった。国民の食料安全保障として食料自給率目標を基本計画で定め、洪水防止をはじめとする多面的機能の維持へ中山間地域等直接支払制度を導入するなど、新たな局面に対応した農政転換を果たしたのもこの時である。今の状況はどうか。環太平洋連携協定(TPP)、日欧経済連携協定(EPA)と日米貿易協定が相次ぎ発効。WTO交渉で想定していた水準をはるかに超える自由化を受け入れた。本来なら経営・所得安定の在り方を抜本的に検討すべきところだったが、基本計画の審議では全く踏み込んでいない。ただ、生産基盤の維持・強化が欠かせないという共通理解は深まった。特に家族経営や中小規模農家に目配りすることを、政府が方向性として示したことは大いに歓迎したい。どう具体化するかが今後の焦点だ。事業の補助要件を緩和するだけで終わらせてはならない。一人一人の力を集め、地域として大きな力を発揮してもらうことが重要だ。その手だてを考えることが、今後の審議に欠かせない。地域の姿が変わりつつあることにも目を向けたい。若者らが農村に移住する動きがある。地域の外から農業を応援する都市住民も増えている。どのようなビジネススタイルや生活のにぎわいが生まれるか、農業・農村の新しいイメージを描く作業も手付かずで残っている。時代の転換期に直面する今回の基本計画は、背負う課題があまりに多い。過去の審議に当たった委員は本紙取材に「いま振り返り、使命を果たしたと言える」(森本一仁氏=農業)と語った。今回も胸を張れるように論議を尽くしてほしい。 *11-2:https://www.agrinews.co.jp/p49678.html (日本農業新聞 2020年1月9日) [新たなバトン 世襲ではない継承へ](2) 果樹園に新規就農 契約巡り食い違い 壁乗り越え信頼感 (山口県周南市) 山口県周南市須金集落。細い1車線の道路を進むと急傾斜のブドウ園が見えてくる。見谷勇さん(86)、朝子さん(83)夫妻が45年前から育ててきた1・2ヘクタールの観光果樹園だ。2年前、見ず知らずの田中友和さん(43)、和歌子さん(42)夫妻が受け継いだ。他人への継承はいくつもの壁があったが、田中夫妻は独立して2年、ほぼ営農計画通りで売り上げも順調だ。友和さんは「消費者に喜んでもらえるブドウを作り、農家の仲間を増やしたい」と見据える。朝子さんは「以前のお客さんが今も喜んで買っている。丁寧な仕事だから、これからも大丈夫」と園を託す。2人とも県外出身の公務員だった田中夫妻。友和さんは働きながら農家への夢を温めてきた。40歳を間近に控えた頃、行楽で見谷夫妻のブドウ園を訪れ、観光農業と果樹に興味を感じた。一方、見谷夫妻の子どもたちは農業を継ぐ気はなく、夫妻も自宅から30分離れた園地に続く細い山道の運転が高齢で難しくなってきたことなどから、離農を考えていた。「あんなに美しい園地は他にない」(県農業会議所)といわれるまでにした園地の荒廃は辛い──。そこで、知人の勧めで県農業会議所の後継者を募集する農家のリストに登録した。2015年、就農先を探していた田中夫妻はリストで三谷夫妻の果樹園を見つけ、会議所に問い合わせた。その後、勇さんと田中夫妻、市など関係機関が集まり、継承に向けた会議を何度も開いた。16年に田中夫妻は退職し、子どもを連れて同集落に移住。2年後の継承に向けて見谷夫妻の元で研修を始め、草刈りや配達などに励んだ。しかし、研修半ばに契約問題が浮上。友和さんは資産の売買額を園地全体のものとして、合意できたと思っていたという。見谷夫妻は金額は農地とブドウの木230本分と捉え、農機や作業所、トイレなどは別途契約すると考えていたため、齟齬(そご)が生じてしまった。当事者同士での話し合いが続いた。ブドウの木が育つまで7年間ほぼ無収入という苦難を乗り越えてきた勇さんは、当初の金額では「納得できなかった」という。他にも、研修内容など意思疎通が難しい局面が何度かあった。勇さんは人に教えた経験がなく、親子以上の年齢差での研修は手探り。特に繁忙期は教える余裕もなかった。肝心の売買金額が合意できず、田中夫妻は研修をやめることも考えたが、未収益期間の長い果樹の新規就農は難しく、最終的には当初の金額から上乗せして契約した。勇さんから過去2回分の青色申告を見せてもらい、経営内容が良好だったことも決断を後押しした。県農業会議所は「契約問題は大きな反省点」とし、教訓とする考えだ。朝子さんは「田中さんたちが折れてくれた」と感じる。見谷夫妻も田中夫妻も「金額面は最初に書面で残すべきだった」と後悔する。だが、継承を果たした今は、互いに感謝する。「懸命に働く姿を間近で学べた」と和歌子さん。友和さんも、棚や農地だけでなく販路も継承できたことは「見谷さんのおかげ」と感じる。勇さんは「山間部で土地は最高。高品質のブドウを作り続けてほしい」と願う。見谷夫妻は継承後、果樹園は見に行かないと決めている。朝子さんは「私たちが行ったら気を使わせてしまう。人柄が優しい2人だから、お客さんとの関係もうまくいく」と見守る。見谷夫妻は心の中で応援し続ける。 *11-3:https://www.agrinews.co.jp/49644?page=2 (日本農業新聞 2020年1月5日) 「田園回帰」着々と 本紙独自調査 28府県移住最多 若者が推進力 都道府県の移住施策担当者に移住者の数や傾向、施策などを聞いた。移住者数の全国調査は政府統計になく、17年度実績から本紙が調べている。17年度は26府県で移住者数が過去最多だった。ただ、各県で移住者の定義が大きく異なり、単純比較はできない。そのため都道府県ごとの過去の調査と比べた。岩手など、調査手法を変えたなどで17年度以前と比較できない県もあった。東京や大阪など都市の都府県は調査しておらず、新潟や熊本は公表していない。長崎県は、移住者を「県と市町村の相談窓口を通じて県外から移住した人」として調べ、06年度からの調査で18年度は初めて1000人を突破した。県によると、16年度に「ながさき移住サポートセンター」を発足させたことなどが奏功し、飛躍的に伸びている。高知県は、「転勤や進学は除き、定住する意志を持って県外から県内に生活拠点を移す」と定義する。県と市町村の相談窓口で把握した数は18年度が934組1325人で、12年度から8倍に増えた。新規就農を希望して移住する若者も目立つ。07年度から調査し、移住者を順調に増やす福井県は、就農相談を定期的に行い、農家希望者向けのバスツアーなど移住と農業部門が連携して進める。専業農家だけでなく、直売所や兼業農家、週末農業など、多様に農との関わりを求める移住者が多いとした県の回答が多かった。一方、移住者数が減り「頭打ち」とする県もあった。島根県は、県外からの転入者に5年以上居住する意志を持っているかを市町村の窓口で調べ、全市町村からの報告から把握する。18年度は3900人で、17年度に比べ200人以上減った。同県は「移住者が減ったことは重く受け止めているが、関係人口の拡大なども力を入れていく」とする。移住者数が減少した他の県も「県の認知度を高めることが重要で、移住者の増減だけで一喜一憂していない」「移住者数の正確な把握は難しく、定住を重視する」などと答えた。 *11-4:https://www.agrinews.co.jp/p49640.html (日本農業新聞 2020年1月5日) [風をとらえる] 農村価値創生 格差解消と両輪で築け 農村に可能性や価値を見いだす移住者らが増えている。この機運を生かし、多様な主体が活躍できる地域づくりを進めたい。それは生産面だけでなく交通網や病院、学校など生活基盤の確保が前提だ。田園回帰を広げ都市との格差解消と向き合い農村価値創生の時代を開こう。移住者に関する日本農業新聞の調査では、以前と比較可能な28府県で2018年度の移住者数が過去最高を記録した。住んでいなくても地域や住民と継続的に関わる「関係人口」や、農村を訪れる訪日外国人(インバウンド)も増えている。人々のつながりや里山の暮らし、食文化、山や田畑といった農村の価値に魅了されている。地元の農家や地域住民だけでなく、世代や仕事、立場などの垣根を越えて連携、融合していくことが農村価値創生の鍵となるだろう。そして価値の土台をつくるには、都市と農村の格差と真剣に向き合わなければならない。農村の価値創生は、効率性や目先の財政にとらわれては実現できない。政府は学校統廃合や病院の再編を進めるなど、地方創生を進めるとしながら矛盾した政策を続けている。また、選果場の閉鎖や、農業施設や水利施設の老朽化、人手不足など生産基盤の弱体化も深刻だ。新しい考えや仲間を受け止める包容力の向上や、多世代が集う場の仕組みづくりなどのソフト面と共に、学校や病院、通信網、農業施設など生活・生産基盤の充実は両輪で考える必要がある。学校や病院がない農村をあえて目指す移住者はいないだろう。全国町村会は食料・農業・農村基本計画の改定に向けて、「新たな価値を創造する舞台としての農村」をつくることを柱とした政策提言を行った。農村の価値を持続的、安定的に高めるための「農村価値創生交付金」の必要性を主張している。地域独自の多様な取り組みが展開できるよう、国が使途の大枠を決め自治体に客観的な基準で配分する仕組みだ。財源は既存の補助金の移行などで確保するとしており現実的な提案だ。交付金は、移住者らの呼び込みや道路や学校、通信など都市と農村の格差解消でも期待される。産業政策や各府省の地域政策と連動させ、政府は総力を挙げて具体化すべきだ。今年は、3月の策定に向けて基本計画の改定論議が大詰めとなる。21年度の施行を目指す新たな過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)も、策定への論議が本格化する。また、20年度から5年間の地方創生の基本方向を示した第2期総合戦略が昨年末に閣議決定され、これを受けて各自治体は地方版総合戦略を策定する。こうした農業・農村振興の中長期的なビジョンづくりとその取り組みに向け、田園回帰を後押しする政策と基盤の格差解消を両輪として考え、農村価値創生を実現させたい。 <ごみ処理と給電・給湯> PS(2020.1.6追加):*12の鳥栖市真木町の広域ごみ処理施設建設予定地は、災害リスクのみならず人口密度から考えても適地ではないだろう。ゴミ処理施設建設は周辺住民に嫌がられるわけだが、少し離れた高い場所にある山林を拓いて作り、ゴミ処理で発生する熱で発電したり湯を作ったりして、迷惑をかける地域の住民に低価格で販売すれば、マイナスとプラスが相殺されるのではないだろうか。発生するCO₂は、それだけなら山林の成長にプラスだ。 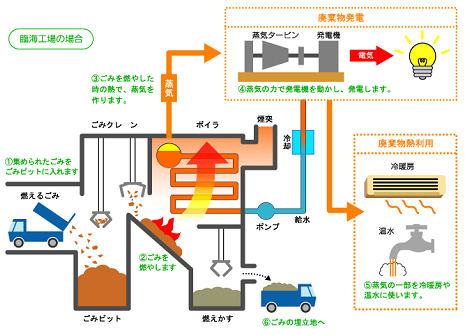 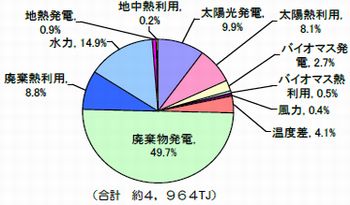 (図の説明:左図のように、ゴミの焼却熱で発電するのは普通になりつつあり、右図のように、再エネ発電に占める割合も高い。また、ゴミ処理時に発生する熱で給湯するシステムもある) *12:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/473078 (佐賀新聞 2019年1月6日) 鳥栖ごみ処理施設予定地「災害の危険」 島谷・九大大学院教授が講演 鳥栖市真木町の次期広域ごみ処理施設建設予定地の災害リスクについて考える講演会が5日、同市内で開かれた。河川工学の専門家で土木学会九州北部豪雨災害調査団長などを務めた島谷幸宏・九州大学大学院教授は「筑後川流域で最も災害の危険性がある地域」と語り、適地ではないとの見解を示した。島谷教授は、国土交通省が2016年に公表したハザードマップで予定地の浸水想定が最大5メートル未満に見直され、地形的にも河川が集中している点に注目。国交省が昨年10月、気候変動で気温が4度上昇した場合、九州北西部は短時間雨量が1・5倍、洪水発生頻度は4倍になると発表したことに触れ、「毎年氾濫が起きる可能性がある。常識的には選ばない場所」と指摘した。福岡県朝倉市などを襲った17年7月の豪雨後に現地調査をした経験などを踏まえ、「仮に大きな水害が発生すれば、1軒当たり2トンの水害ごみが出る。施設をかさ上げして造っても周辺道路が水没し、土砂などが流れてきたら簡単に復旧できないのではないか。ごみが運べず大混乱する恐れがある」などと語った。講演会は予定地周辺の住民らでつくる「ハザードを考える会」(代表=馬場祐次郎・鳥栖市あさひ新町区長)が主催し、同市や久留米市、みやき町などから約100人が参加した。 <これが日本の林野庁のレベルだ> PS(2020/1/10追加):森林の間伐が行われない等の問題点を指摘したら、*13のように、山肌をまるごと伐採する皆伐をしはじめたのが日本の林野庁である。このやり方が、大規模な土砂崩れを発生させると同時に、山の保水力をなくし、流れ出した土で川やダムが浅くなって、水害が起こりやすくなるのは誰でもわかることである。それらを総合的に考えることもできず、単に現在の木材生産量を増やすことだけを目的として、戦後せっかく植えたスギ・ヒノキなどの森林資源を数十ヘクタールにもわたって皆伐するのに補助金を出すなど、専門家のすることとはとても思えず、呆れるわけである。 *13:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/574555/ (西日本新聞 2020/1/10) 「皆伐」から「自伐」減災林業 九州の業者が連絡会結成へ ●小規模作業、土砂崩れ拡大防止に 小規模な林道や作業機械を使って、スギやヒノキなどの人工林を伐採する「自伐型林業」を推進するため九州の自伐型林業者が今月、連絡会を結成してネットワーク化を図る。国は木材生産量を増やすために、山肌まるごと伐採する「皆伐」を推進している。林業研究者は、このやり方が「土砂崩れなどの災害を拡大させる」と問題視しており、山への負荷の小さい自伐型林業の推進により減災を進める狙いだ。自伐型林業は、山林所有者や中山間地の住民が、山の斜面や水の流れを考慮した上で、自らパワーショベルを使って山の中に軽-小型トラックが1台通れる幅2メートル程度の道を高密度に整備し、木材を搬出するやり方。小規模だが、伐採作業を森林組合などに委託する委託料がかからないため利益を出しやすい。一部の木は伐採せずに残して100年超えの優良材に育て、持続可能な林業へつなげる。国内の山林では、戦後の造林政策で植えられたスギやヒノキが利用に適した時期を迎えている。そうした木を数十ヘクタールにわたり高性能林業機械を使って切り出す皆伐が主流となっている。林野庁は2018年度から初めて皆伐(再造林も含む)作業にも補助金を適用する補助事業を始めた。木材生産量を増やし「成長産業化」する狙いだ。自伐型林業を推進するNPO法人、自伐型林業推進協会の中嶋健造代表理事は、17年の九州豪雨で33人が死亡した福岡県朝倉市を調査。その結果、「調査した皆伐地域のすべてで崩落を確認した。地形を考慮せずに林道が築かれ、そこから崩れた場所も目立った」と指摘する。林野庁は九州豪雨の原因調査で「雨量が原因」としたが、中嶋氏は「林業にも大規模災害となった一因がある」と訴える。九州大の佐藤宣子教授(森林政策学)は「皆伐後しばらくたつと広く根を張った木がなくなり、山が最ももろくなる。地形などを踏まえて伐採をしないと災害につながる恐れがある」と話す。連絡会には現段階で、宮崎県、熊本県などで活動する自伐型林業者のグループなど6団体が加入予定。26日に福岡市早良区の九大西新プラザで設立記念講演会を開く。
| 農林漁業::2019.8~ | 04:43 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,11,25, Monday
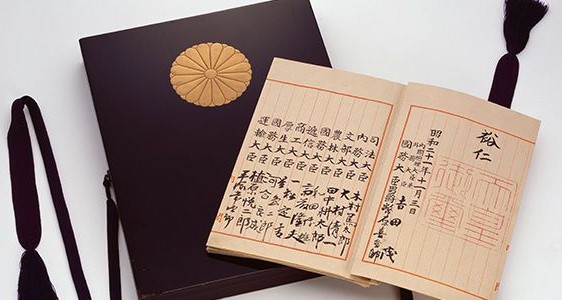    大日本帝国憲法との比較 2018.3.22朝日新聞 (図の説明:1番左は、日本国憲法成立時の原本で、左から2番目は、大日本帝国憲法との要点の比較である。また、右から2番目は、2018年の自民党改憲案で、1番右は、日本国憲法が成立から72年間改憲していないとする図だが、「長く改憲していないから」というのは「連合国から押し付けられた憲法だから」というのと同様、改憲する理由にはならない) 私が表題に、「護憲が保守で憲法変更勢力が革新の筈だが・・」というコメントをつけたのは、現在、「保守」を標榜する人々が改憲を主張し、現行憲法を護ろうとする人々を「革新」と呼ぶ逆の事態になっているからで、これは、現在では、「保守」「革新」という言葉で国民を色分けすることが無意味になっていることを意味すると同時に、現行憲法が少なからず無視されてきたことを意味している。 (1)自民党改憲案について 1)憲法9条(戦争放棄)に、9条の2を創設する案 *1-1の自民党改憲案は、9条全体を維持した上で、次に9条の2を追加して、「①1項:前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」「②2項:自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」としている。 しかし、①は9条と比較して冗長で、目的と行動に論理的整合性があるとは言えない。また、②は、内閣総理大臣が戦争を始めてしまった後では、戦争反対や自衛隊の行動制限は国益に反するため国会も言い出しにくくなり、追認せざるを得ないだろう。 太平洋戦争の時は、戦争に反対する内閣総理大臣は殺されたり、失脚させられたりして、戦争に反対しない人が内閣総理大臣になるまで交替させられた。外務省の重要ポストも、戦争推進派が占めるまで人事異動が続いたそうだ。つまり、それらの反省の上に立っている現行憲法の方が、より平和を担保している上に、文章としてもずっとスマートなのである。 そのため、「時代とともに状況が変わったから」「現行憲法は外国の押し付けだから」などとして改憲を主張するだけでなく、*1-2-1・*1-2-2・*1-2-3・*1-2-4・*1-2-5等の根源的な問いに論理的に答えた上に、現行憲法よりも改憲案の方が優れている理由を明快に説明できなければ、改憲の提案はできないと考える。 2)73条(内閣の職権)に、73条の2・第64条の2の緊急事態条項を新設する案 *1-1の自民党改憲案は、内閣の事務を定める第73条の次に第73条の2「①1項:大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる」「②2項:内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない」を追加している。 しかし、①は、「特別の事情がある時は、内閣は国会による法律の制定によらずに、政令を制定することができる」としているのであり、自然災害によるものだけに限定される保証はない。これは、*1-3-1のように、緊急事態条項が、大規模災害や戦争など国家そのものの存立が脅かされる可能性がある場合に、全体の利益のために個人の権利を抑制する考え方である「国家緊急権」の思想に基づいていることから明らかだ。 緊急時とは、2012年の自民党改憲案では「外部からの武力攻撃」「内乱」なども入っていたため、次第に拡大解釈されたり、強制になったりすることが想定内だ。これは、*1-3-2のマイナンバーカードが、最初は個人情報保護の観点から「取得は自由だ」と言って導入されながら、今では国民監視の目的を現し始めて次第に取得を強要しだしており、同じような流れであるため要注意なのである。 さらに、*1-1の自民党改憲案は、国会の章の末尾に、特例規定として64条の2「③大地震その他の異常かつ大規模な災害に議員より、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる」を追加している。 しかし、*1-3-1のように、2011年の東日本大震災では被災地の地方選を延期した経緯があり、改憲しなくても災害時には臨機応変に対応できる。それよりもむしろ、国会の審議を経ない緊急の政令により、国民の権利が堂々と損なわれる状況を作る方が危いのである。 3)参院選「合区」解消のために、47条を変更する案 *1-1の自民党改憲案は、「参院選における合区を解消するため」として、47条を「①1項:両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる」「②2項:前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と変更しようとしている。 しかしながら、現行憲法の47条は、「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」としか書かれておらず、詳細は公職選挙法で定められているため、改憲ではなく公職選挙法を変更すれば済む上、憲法としては現行憲法の方が簡潔で読みやすく、スマートでもある。また、選挙制度の変更なら、民主主義を実効あるものにするために、参議院議員の合区解消だけでなく、衆参両議院の選び方を総合的に考慮する必要があると考える。 4)地方自治の基本原理である第92条を変更する案 *1-1の自民党改憲案では、92条を「地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と変更することになっているが、この文章にも憲法にそぐわない稚拙さがある。 現行憲法の92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」とだけ書いてあり、その法律が地方自治法であるため、変更した方がよい点があるのなら地方自治法を変更すればよい。そして、現在では、重要なことは、既に定められている憲法や地方自治法を護っているかどうかになっているのだ。 5)教育の充実のためとして、26条3項、89条を変更する案 *1-1の自民党改憲案は、教育の充実のため、26条1、2項は現行のまま、3項を加えて「①3項:国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない」と変更し、さらに89条を「②公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」となっている。 しかし、①は、憲法には書かれていないが、教育基本法には既に書かれていることであり、それでも足りない部分があれば教育基本法を変更すればよいため、改憲する必要はない。さらに、②は、現行憲法では「公の支配に属しない」とされている文言を「公の監督が及ばない」としてむしろ支出の制限を甘くしており、これは私立学校や私立の幼稚園・保育所に補助するための変更だろうが、その意図とそれによって生じる結果をしっかり議論して明確にすべきだ。 (2)主権在民を徹底するために、やるべき改憲はこれである *2の日本国憲法の第7章の財政を見ればわかるとおり、予算に関しては、第83条~第89条まであるが、決算に関しては、90条の「①国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める」と91条の「②内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない」しかない。 そして、①によれば、毎年会計検査院が検査し、内閣が次年度に検査報告とともに国会に提出しなければならないのは国の収支だけで、国の財政状況については提出する必要がなく、国民への報告も義務付けられていない。また、②によれば、内閣は、国会や国民に対して少なくとも年に1回、国の財政状況について報告しなければならないが、会計検査院の検査は義務付けられておらず、収支の報告はしなくてよい。つまり、これは、条文数の問題ではなく、内容の不十分さの問題であり、政府の非効率な支出(無駄遣い)と国民負担増の温床となっているものだ。 そのため、90条は「1項:国の財政状態及び収支の状況は、複式簿記で記帳した上で、毎年決算を行って財務諸表を作成し、会計検査院が検査するとともに、監査法人がこれを監査しなければならない。」「2項:会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。」と変更し、91条は「内閣は、国の財政状態及び収支の状況を示す財務諸表を、その検査報告書、監査報告書とともに、次年度には国会及び国民に提出しなければならない。」と変更すべきだ。これに伴って、*2-2の財政法も、当然、現金主義・単年度主義から発生主義に変更しなければならない。 これを一般企業に例えれば、会計検査院は内閣総理大臣の支配下にあるため内部監査人の位置づけで、監査法人が外部監査人の役割を果たすことになり、国の会計情報に本物のチェックが働いた後に、毎年、納税者である国民に開示されることになる。そして、予算は、前年度の決算書を見ながら議論すべきであり、それは可能だ。 ・・参考資料・・ <自民党改憲案> *1-1:http://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250054-n1.html (産経新聞 2018.3.25) 【自民党大会】「改憲4項目」条文素案全文 【9条改正】 第9条の2 (第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。 (第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 (※第9条全体を維持した上で、その次に追加) 【緊急事態条項】 第73条の2 (第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。 (第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。 (※内閣の事務を定める第73条の次に追加) 第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。 (※国会の章の末尾に特例規定として追加) 【参院選「合区」解消】 第47条 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第92条 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。 【教育の充実】 第26条 (第1、2項は現行のまま) (第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 *1-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115360S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日) 自衛隊明記、与野党で対立、自民改憲案、衆参憲法審へ 与野党による今後の憲法改正論議は、自民党が3月にまとめた改憲案がたたき台になる。柱は(1)自衛隊の明記(2)緊急事態条項(3)参院選の「合区」解消(4)教育充実――の4項目。自民党は衆参両院の憲法審査会で説明し、各党と議論する。自衛隊の明記などで与野党が対立する構図だ。自民党案のポイントを読み解いた。自民党憲法改正推進本部がまとめた9条の改正条文案は、現在の9条を維持して、「9条の2」を新設する内容だ。新たな条文を追加する「加憲」とすることで、公明党の理解を得たい考えだ。自民党にとっての最大のポイントは「自衛隊」の保持を明記することだ。憲法に「自衛隊」を明確に位置付けて、自衛隊違憲論を解消する狙いがある。政府はこれまで、自衛隊は国の自衛に必要な必要最小限度の実力組織であり、2項で保持を禁じる「戦力」には当たらないと解釈してきた。しかし、一部の憲法学者はこの解釈を疑問視し、安倍晋三首相は「ほとんどの教科書に自衛隊は違憲の疑いがあるという記述がある」と指摘する。自衛隊については「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」と定義した。首相が自衛隊の「最高の指揮監督者」と明記。自衛隊の行動は「国会の承認その他の統制に服する」とも記し、自衛隊の任務や予算が国会の管理の下にあることも盛り込んだ。自衛隊法の規定を引用する形で、文民統制(シビリアンコントロール)の考え方を明示した。今後の与野党協議では、自衛隊の任務と活動範囲が論点になりそうだ。首相は自衛隊を明記しても、これまでの自衛隊活動に関する憲法解釈を変える考えはないと説明する。野党は自民案にある「自衛の措置」との表現が曖昧であり「集団的自衛権の行使拡大につながる」と懸念する。「後法は前法に優越する」という法解釈の基本原則を念頭に、戦争放棄や戦力不保持の今の規定が「空文化する可能性は排除できない」(立憲民主党の福山哲郎幹事長)との批判もある。そもそも自民党改憲推進本部が当初示した条文案は「必要最小限度の実力組織」として「自衛隊を保持する」と表現していた。党内から「誰が『必要最小限度』を判断するのか」などと異論が相次ぎ、最終案では「必要最小限度」の文言を削った経緯がある。これまでの政府解釈を踏襲した表現を削除したことで「公明党が乗りづらい案になった」(党幹部)との見方も出ている。 *1-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115480S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日)9条の扱い焦点 問われる専守防衛 自民党がまとめた4項目の憲法改正案のうち焦点となるのが9条だ。条文の書きぶり次第で、自衛隊に認められる武力行使の範囲や保有できる防衛装備品が際限なく広がりかねないからだ。日本が掲げる「専守防衛」との整合性が問われる。政府は現行の9条に基づく専守防衛のもと、防衛力を自衛のための必要最小限度に限っていた。自衛権は、日本が直接攻撃を受ける「個別的自衛権」だけを認めてきた。2015年成立の安全保障関連法で、日本が直接攻撃を受けていない場合の「集団的自衛権」も使えるようにした。年末に改定する防衛大綱の議論も絡む。自民党案は「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と明記する。これまで保有していなかった空母や爆撃機といった攻撃型兵器も「必要な自衛の措置」とみなして解禁する可能性を野党は警戒する。政府は護衛艦を事実上の空母として使えるよう改修する案を検討する。防衛省幹部は「防御目的の空母なら専守防衛の範囲内。現行の9条のままでも保有は認められる」と語る。 *1-2-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/561422/ (西日本新聞 2019/11/21) 憲法と安保法 司法は逃げずに判断示せ 安全保障法制の大転換、それも違憲性を帯びた政策の是非を問う訴訟である。裁判所が内閣や国会の立場を忖度(そんたく)して及び腰になる必要はなかろう。正面から憲法判断に踏み込み、司法の独立性を示してこそ、国民の信頼が得られるのではないか。集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は違憲として、市民約1500人が国家賠償を求めた訴訟で東京地裁は請求を全面的に棄却した。原告側はきのう、これを不服として東京高裁に控訴した。九州を含め全国22地裁・支部で提起された同種訴訟では、今春に札幌地裁で初の判決(原告敗訴)が示され、原告側が同じく控訴している。残念なのは東京、札幌両地裁が肝心の憲法判断を避けたことだ。原告側は3年前に施行された安保関連法により(1)憲法の前文や9条に基づく平和的生存権が侵害された(2)自衛隊の活動領域の拡大でテロや戦争に巻き込まれる危険も増した‐ことで精神的苦痛を受けたとして、1人10万円の賠償を求めていた。判決は、平和について「抽象的概念で個人の思想や信条で多様な捉え方が可能」「手段も国際情勢に応じて多岐多様にわたる」とし、平和的生存権は国民に保障された法的権利とは言えないと断じた。また「戦争やテロの切迫した危険は認め難い」「原告の苦痛は受忍限度内で義憤ないし公憤とみるほかない」と述べ、安保関連法の違憲性に関する判断は示さなかった。日本の司法は違憲審査について消極的といわれる。一般に具体的な権利の侵害がない場合や外交・防衛などの統治行為に関しては判断を避ける例が多い。国民の代表で構成する立法府の決定は民意の反映でもあり、極力介入しないという立場だ。しかし、今回の訴えをこの論理で退けるのは疑問だ。安保関連法は一内閣の独断による憲法解釈の変更に端を発し、国会では与党が憲法学者らの違憲の指摘を半ば無視するように成立させた。その結果、専守防衛の理念は揺らぎ、国の行く末に不安を抱く人は原告だけにとどまらない。であれば、司法がここで厳しいチェック機能を果たしてこそ、三権分立は成り立つ。判決は、戦争やテロの恐れを否定したが、仮に危険が切迫した段階で司法が機能しても、もはや手遅れになりかねない。全国の訴訟原告7千人余りの中には多くの戦争体験者や自衛官を家族に持つ人も含まれている。憲法前文は「政府の行為で再び戦争の惨禍が起こることがないよう決意し、主権が国民に存することを宣言する」としている。司法はこの重みを踏まえ、今後も続く審理や判決で、真摯(しんし)に役割を果たしてほしい。 *1-2-4:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/562371/ (西日本新聞 2019/11/25) ローマ教皇、長崎で核廃絶訴え 「核なき世界は実現可能」 ローマ・カトリック教会の頂点に立つ教皇(法王)フランシスコが24日、被爆地・長崎市を訪れた。教皇として初めて爆心地に立ったフランシスコは原爆落下中心地碑を背に演説し「核兵器のない世界は実現可能であり、必要不可欠であると確信している」と発言。各国の指導者に対し「核は安全保障への脅威から守ってくれるものではないと心に刻んでください」と訴え、長崎を最後の被爆地にするため、核廃絶に向けて動くよう求めた。教皇の長崎訪問は38年前の故ヨハネ・パウロ2世以来2度目。24日午前、教皇は爆心地公園に到着し、被爆者から受け取った花輪を碑にささげた。演説では長崎を「核が破滅的な結末をもたらすことの証人である町」と表現。核兵器の製造や改良を「テロ行為」と非難し、大量破壊兵器によって実現させようとする平和や安全を「恐怖と相互不信を土台とした偽り」と言い表した。元首を務めるバチカンが批准した核兵器禁止条約を挙げて「国際法の原則にのっとって迅速に行動し、訴えていく」と宣言、米国の「核の傘」に依存し条約に参加しない日本などをけん制した。歴代教皇と同様に、フランシスコも核について繰り返し発言してきた。これまでにも広島と長崎の被爆の歴史から「人類は何も学んでいない」と述べ、2017年末には被爆後の長崎での撮影とされる写真「焼き場に立つ少年」を広めるよう教会関係者に指示。この日も教皇のそばにはこの写真のパネルが置かれた。激しく雨が降る中、参列者約千人は雨がっぱ姿で教皇の声に耳を傾けた。爆心地に続き、国内でキリスト教信仰が禁じられた時期に宣教師や信者が処刑された日本二十六聖人殉教地に足を運び、午後は長崎県営野球場で3万人規模のミサを執り行った。夕方からは、もう一つの被爆地・広島市に移動し、平和記念公園で集いに出席。原爆ドームの前で、戦争を目的とした原子力の利用を「犯罪以外の何ものでもない」と指弾した。教皇は26日までの滞在中、東京都内で東日本大震災被災者との交流を行い、天皇陛下との会見や安倍晋三首相との会談を予定している。 *1-2-5:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14269133.html?iref=comtop_shasetsu_01 (朝日新聞社説 2019年11月25日) ローマ教皇 被爆地からの重い訴え 平和の実現にはすべての人の参加が必要。核兵器の脅威に対し一致団結を――。核軍縮の国際的な枠組みが危機にある中、被爆地から発せられた呼びかけをしっかりと受け止めたい。13億人の信者を抱えるローマ・カトリック教会のトップ、フランシスコ教皇が長崎と広島を訪れ、核兵器廃絶を訴えた。教皇は2年前、原爆投下後の長崎で撮られたとされる写真「焼き場に立つ少年」をカードにして教会関係者に配った。今回、長崎の爆心地に立って「核兵器が人道的にも環境にも悲劇的な結末をもたらすと証言している町だ」と語り、「記憶にとどめるこの場所はわたしたちをハッとさせ、無関心でいることを許さない」と力を込めた。ローマ教皇の来日は1981年以来、38年ぶり2度目だ。前回来日したヨハネ・パウロ2世が平和外交を展開して東西冷戦の終結に影響を与えるなど、教会は核廃絶を含む平和への取り組みを重ねてきた。フランシスコ教皇も米国とキューバの国交回復で仲介役を務める一方、自らが国家元首であるバチカンは、核兵器の製造や実験、使用を禁じる核兵器禁止条約が2年前に国連で採択された後、いち早く条約に署名・批准した。ただ、国際協調より自国第一主義が優先される現実のなかで、核軍縮への取り組みは後退している。米ロの中距離核戦力(INF)全廃条約は8月に失効。2021年に期限を迎える両国間の新戦略兵器削減条約(新START)も存続が危ぶまれる。来年には核不拡散条約(NPT)再検討会議が開かれるが、核保有国と非保有国の溝は深まる一方だ。「わたしたちの世界は、手に負えない分裂の中にある」「相互不信の流れを壊さなければ」。そう危機感を訴え、世界の指導者に向かって「核兵器は安全保障への脅威から私たちを守ってくれるものではない」と説いた教皇の思いにどう応えるか。唯一の戦争被爆国である日本の責任と役割は大きい。安倍政権は、日本が米国の「核の傘」に守られていることを理由に核禁条約に背を向け続けているが、それでよいのか。核保有国と非保有国の橋渡し役を掲げるが、成果は見えない。政府の有識者会議は10月、日本がとりうる行動を記した議長レポートをまとめたが、非保有国が多数賛同した核禁条約を拒否するだけでは実践は望めまい。教皇は広島でのスピーチで「戦争のために原子力を使用することは犯罪」「核戦争の脅威で威嚇することに頼りながら、どうして平和を提案できようか」と述べた。この根源的な指摘を無駄にしてはならない。 *1-3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115540S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日)緊急事態条項 災害時、内閣が政令 緊急事態条項は「国家緊急権」の思想に基づく。大規模災害や戦争など国家そのものの存立が脅かされる可能性がある場合に、全体の利益のために個人の権利を抑制できるとする考え方だ。緊急時とは「大地震その他の異常かつ大規模な災害」を想定する。2012年の自民党改憲案に盛った「外部からの武力攻撃」「内乱」などは外し、対象を絞った。64条の2で国会議員の任期延長、73条の2で政府の緊急政令を規定する。国会議員の任期延長は、選挙の「適正な実施が困難であると認めるとき」が対象。11年の東日本大震災では被災地の地方選を延期した経緯があり、国政選挙でも同様の事態を想定したものだ。緊急政令の制定は供給が不足する生活物資の買い占めを禁じて配給制にしたり、災害復旧に必要な物資の価格を統制したりすることを想定する。野党からは憲法改正をしなくても緊急時に対応できるとの指摘が出ている。緊急政令で国民の権利が損なわれる可能性を懸念する。 *1-3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14269201.html (朝日新聞 2019年11月25日) マイナンバーカード「取得強要だ」 省庁全職員の家族まで調査 国家公務員らによるマイナンバーカードの取得を進めるため、各省庁が全職員に対し、取得の有無や申請しない理由を家族(被扶養者)も含めて尋ねる調査をしている。内閣官房と財務省の依頼を受け、氏名を記入して上司に提出するよう求めている。職員からは、法律上の義務でないカード取得を事実上強要されたと感じるとの声が出ている。政府はカードを2021年3月から健康保険証として使えるようにする計画で、6月に閣議決定した「骨太の方針」に、公務員らによる今年度中のカード取得の推進を盛り込んだ。22年度末までに国内のほとんどの住民が保有するとも想定し、「普及を強力に推進する」としている。朝日新聞は各省庁などに送られた7月30日付の依頼文を入手した。内閣官房内閣参事官と国家公務員共済組合(健康保険証の発行者)を所管する財務省給与共済課長の役職名で、各省庁などの部局長から全職員に、家族も含めてカード取得を勧めるよう依頼。10月末時点の取得状況の調査と集計・報告、12月末と来年3月末時点の集計・報告を求めている。調査用紙には個人名の記入欄、家族を含む取得の有無や交付申請の状況、申請しない場合は理由を記す欄があり、「部局長に提出してください」ともある。財務省給与共済課によると、調査対象は国家公務員ら共済組合員約80万人と被扶養者約80万人。同課は「回答に理由を記載するかは自由で、決して強制ではない。人事の査定に影響はない」と話している。調査は取得に向けた課題を洗い出すためで、今後は各省庁などを通じて取得率の低い部局に取得を促すという。マイナンバー法で、カードを取得するかは任意だ。経済産業省の関係者は「公務員は政府の方針に従い、カードを持つべきだというのは分かるが、記名式で家族の取得しない理由まで聞かれ、強要と感じた」。財務省の関係者は「取得を迫るようなやり方に違和感を覚える。ほぼ全住民が保有すると閣議で風呂敷を広げたせいで、普及に必死になっている」と漏らす。マイナンバーカードは16年1月に交付が始まった。利便性の低さや個人情報の漏洩(ろうえい)への懸念などから、交付枚数は約1823万枚、取得率は14・3%にとどまる。総務省所管の団体は7月、普及が進むとの政府の想定に基づいて5500万枚分の製造を発注している。 *1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115600S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日) 「合区」解消 参院、都道府県単位で 参院選の「合区」は、隣接県を1つの選挙区にすることだ。「1票の格差」を是正するため、2016年から「鳥取・島根」と「徳島・高知」で導入した。地元出身者を送り出せない県ができ地方の声が国政に届きにくくなったとして改憲による解消をめざす。衆参両院議員の選挙の選挙区や投票の方法の根拠となっている47条に新たな規定を追加した。参院の選挙区は改選ごとに各都道府県から少なくとも1人を選出できるように改める。参院議員を「都道府県代表」と位置づければ国会議員を「全国民の代表」と定めた43条と矛盾しかねないという指摘もある。公明党は「参院の大幅な権限見直しにつながる」と慎重だ。 *1-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180503&ng=DGKKZO30115660S8A500C1M10900 (日経新聞 2018年5月3日) 教育充実 環境整備に努力義務 自民党の改憲案は「教育充実」について、教育を受ける権利を定めた憲法26条に3項を設け「国は教育環境の整備に努めなければならない」とする努力義務を明記した。「各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保する」と書き込み、家計負担の軽減を打ち出した。かねて憲法への「教育無償化」明記を目指してきた日本維新の会への配慮がにじむ。同党の改憲原案の一部を取り込むことで改憲に賛同を得たい考えがある。ただ、財源確保が難しいことなどから自民党案は「無償化」の明記は見送った。幼児教育から大学までの教育無償化を訴える維新の協力が得られるかは不透明な状況だ。私立学校に補助金を出す「私学助成」が合憲であることも明確にする。憲法89条が公の財産の支出を禁じる「慈善、教育、博愛の事業」の対象について「公の監督が及ばない」事業とする。 <財政> *2-1:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 (日本国憲法 昭和21年11月3日 抜粋) 第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければ ならない。 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の 定める条件によることを必要とする。 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを 必要とする。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け 議決を経なければならない。 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、 内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、 内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して 国会の議決を経なければならない。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益 若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の 事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、 次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政 状況について報告しなければならない。 *2-2:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000034 (財政法 昭和二十二年法律第三十四号) 第一章 財政総則 第一条 国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。 第二条 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、 支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。 ○2 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも 含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。 ○3 なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換による ものを含む。 ○4 歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の 支出をいう。 第三条 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に 属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に 基いて定めなければならない。 第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。 但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内 で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。 ○2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を 国会に提出しなければならない。 ○3 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければ ならない。 第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入に ついては、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合に おいて、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。 第六条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金の うち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた 年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。 ○2 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。 第七条 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時 借入金をなすことができる。 ○2 前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しな ければならない。 ○3 財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を 経なければならない。 第八条 国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基く ことを要する。 第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、 又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。 ○2 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も 効率的に、これを運用しなければならない。 第二章 会計区分 第十一条 国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。 第十二条 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければ ならない。 第十三条 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。 ○2 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の 歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に 限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。 第三章 予算 第一節 総則 第十四条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。 第十四条の二 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、 特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、 その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。 ○2 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内と する。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。 ○3 前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。 ○4 前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続 費につき重ねて審議することを妨げるものではない。 第十四条の三 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内に その支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り 越して使用することができる。 ○2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費 という。 第十五条 法律に基くもの又は歳出予算の金額(第四十三条の三に規定する承認があつた金額を 含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為を なすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。 ○2 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計 年度、国会の議決を経た金額の範囲内において債務を負担する行為をなすことができる。 ○3 前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降 五箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人 に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補 給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるもの は、この限りでない。 ○4 第二項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告 しなければならない。 ○5 第一項又は第二項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為 という。 第二節 予算の作成 第十六条 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為 とする。 第十七条 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その 所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を 作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければなら ない。 ○2 内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越 明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しな ければならない。 第十八条 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越 明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。 ○2 内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の 概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に 対しその決定に関し意見を求めなければならない。 第十九条 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国 会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算 に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合 における必要な財源についても明記しなければならない。 第二十条 財務大臣は、毎会計年度、第十八条の閣議決定に基いて、歳入予算明細書を作製 しなければならない。 ○2 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び 各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、毎会計年度、第十八条の閣議決定のあつた 概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務 負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しな ければならない。 第二十一条 財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに 内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費 要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。 第二十二条 予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に 関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。 一 第四条第一項但書の規定による公債又は借入金の限度額 二 第四条第三項の規定による公共事業費の範囲 三 第五条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額 四 第七条第三項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額 五 第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為の限度額 六 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項 七 その他政令で定める事項 第二十三条 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、 その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、 各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に 区分しなければならない。 第二十四条 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、 歳入歳出予算に計上することができる。 第二十五条 継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内に おいては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の 理由を明らかにしなければならない。 第二十六条 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為を なす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出を なすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。 第二十七条 内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例 とする。 第二十八条 国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。 一 歳入予算明細書 二 各省各庁の予定経費要求書等 三 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び 純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表 四 国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における 見込に関する調書 五 国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度 末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書 六 国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高 の見込に関する調書 七 国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度 及び当該年度の状況に関する調書 八 国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出 額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについ てはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書 九 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、 当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書 十 その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類 第二十九条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、 これを国会に提出することができる。 一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に 基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを 含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合 二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合 第三十条 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、 これを国会に提出することができる。 ○2 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く 支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなした ものとみなす。 第三節 予算の執行 第三十一条 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に 対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。 ○2 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分 しなければならない。 ○3 財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければ ならない。 第三十二条 各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外に これを使用することができない。 第三十三条 各省各庁の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は 部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此 移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて 国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。 ○2 各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の 間において、彼此流用することができない。 ○3 財務大臣は、第一項但書又は前項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、 その旨を当該各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。 ○4 第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入 歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければ ならない。 第三十四条 各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された予算に基いて、 政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に 関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。 ○2 財務大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、 支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。 ○3 財務大臣は、第一項の支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長に通知する とともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。 第三十四条の二 各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、 継続費及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費その他財務大臣の指定する経費に 係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費又は国庫債務 負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。 以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を 経なければならない。 ○2 財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長 及び会計検査院に通知しなければならない。 第三十五条 予備費は、財務大臣が、これを管理する。 ○2 各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を 明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。 ○3 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、 閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する 経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定すること ができる。 ○4 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第三十一条 第一項の規定により、予算の配賦があつたものとみなす。 ○5 第一項の規定は、第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為に、第二項、第三項 本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第十五条第二項の規定により国庫債務負担 行為をなす場合に、これを準用する。 第三十六条 予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、 次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。 ○2 財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなけれ ばならない。 ○3 内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に 提出して、その承諾を求めなければならない。 ○4 財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。 第四章 決算 第三十七条 各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る 歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に 送付しなければならない。 ○2 財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、 歳入決算明細書を作製しなければならない。 ○3 各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣 の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければ ならない。 第三十八条 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の 決算を作成しなければならない。 ○2 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに 左の事項を明らかにしなければならない。 (一) 歳入 一 歳入予算額 二 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額) 三 収納済歳入額 四 不納欠損額 五 収納未済歳入額 (二) 歳出 一 歳出予算額 二 前年度繰越額 三 予備費使用額 四 流用等増減額 五 支出済歳出額 六 翌年度繰越額 七 不用額 第三十九条 内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び 継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月 三十日までに会計検査院に送付しなければならない。 第四十条 内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において 国会に提出するのを常例とする。 ○2 前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、各省各庁 の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。 第四十一条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年 度の歳入に繰り入れるものとする。 第五章 雑則 第四十二条 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを 翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に 支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの(当該支出 負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する 経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 第四十三条 各省各庁の長は、第十四条の三第一項又は前条但書の規定による繰越を必要 とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、 財務大臣の承認を経なければならない。 ○2 前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の 範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 ○3 各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らか にして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。 ○4 第二項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第三十一条第一項の規定 による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定に よる通知は、これを必要としない。 第四十三条の二 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その 年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る 事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。 ○2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。 第四十三条の三 各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない 事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の 承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき 債務を負担することができる。 第四十四条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。 第四十五条 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めを なすことができる。 第四十六条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに 公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、 講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。 ○2 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の 状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。 第四十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政 手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) 第三条及び第四条の規定は、適用しない。 第四十六条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている 書類等(書類、調書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が 記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に 記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に よつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報 処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において 同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、 当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。 第四十六条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、 当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を 使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものを いう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。 ○2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の 提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に 当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。 第四十七条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。 附 則 抄 第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第十七条第一項、 第十八条第二項、第十九条、第三十条、第三十一条、第三十五条並びに第三十六条の 規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第三条、第十条及び第三十四条の 規定の施行の日は、政令でこれを定める。 ○2 第四条及び第五条の規定は、昭和二十三年度以後の会計年度の予算に計上される 公債又は借入金について、第七条、第三章の規定(第十七条第一項、第十八条第二項、 第十九条、第二十八条、第三十条、第三十一条並びに第三十四条乃至第三十六条の 規定を除く。)及び第四章の規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算 について、これを適用する。 第一条の二 内閣は、当分の間、第三十一条第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する 場合において、当該配賦の際、目に区分し難い項があるときは、同条第二項の規定に かかわらず、当該項に限り、目の区分をしないで配賦することができる。 ○2 前項の規定により目の区分をしないで配賦した場合においては、各省各庁の長は、 当該項に係る歳出予算の執行の時までに、財務大臣の承認を経て、目の区分をしな ければならない。 ○3 財務大臣は、前項の規定により目の区分について承認をしたときは、その旨を会計 検査院に通知しなければならない。 第三条 この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十一年度の 決算に関しては、なお従前の例による。 第四条 従来予算外国庫の負担となるべき契約に関する件として帝国議会の協賛を経た 事項は、日本国憲法施行後においては、国庫債務負担行為となるものとする。 但し、この場合においては、改正後の第十五条第三項の規定は、これを適用しない。 第五条 左に掲げる法令は、これを廃止する。 明治四十四年法律第二号(公共団体に対する工事補助費繰越使用に関する法律) 明治五年太政官布告第十七号(政府に対する寄附に関する件) 附 則 (昭和二四年四月一日法律第二三号) 抄 1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。但し、第二十三条及び附則第一条の 二の改正規定は、昭和二十四年度の予算から適用する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第六〇号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。 附 則 (昭和二五年五月四日法律第一四一号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七三号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年三月五日法律第四号) 抄 1 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日 から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、 会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の 実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和二九年五月八日法律第九〇号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 改正後の財政法の規定は、昭和二十九年度分の予算から適用する。 附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇八号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年四月一二日法律第四六号) この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の規定は、昭和四十年度分の 予算から適用する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年九月一九日法律第八六号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月五日法律第一〇九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに 第三十条の規定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の 会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、 委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に 満了する。 一から十三まで 略 十四 財政制度審議会 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる 経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を 改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成 十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で 定める。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 <主権在民を侵害する報道とその理由> PS(2019年11月27、28、29日、12月1日追加):これだけ多くの政治的事象が起こっているのに、TVは全局で、*3-1の「桜を見る会」を政治家のスキャンダルに仕立てあげ、*3-2の沢尻エリカさんの「大麻中毒」もまた、全局でしつこく報道している。しかし、「桜を見る会」の予算は、過去5年間は約1766万円、来年度予算の概算要求も約5700万円と、他の無駄遣いに比べると重箱の隅をつついたような数字で重要性が低い。野党は、国会議員70人余りからなる追及本部を立ち上げ、不法行為にはならないことについて「安倍首相や昭恵夫の推薦だった」と追求しようとしているが、「お友達だけを大切にしている」と言うのは、生徒が「先生がえこひいきする」と言っているのと同じレベルで情けない。それとも、政策に関する議論もしているのだが、TVがスキャンダルしか取り上げないのだろうか?さらに、沢尻エリカさんたちの薬物中毒のしつこい報道も「国民がいかにくだらないか」を国民に印象付けている。 しかし、それらは、「国民が選挙で選んだ政治家はろくなことをせず、国民も愚かなので、民主主義(主権在民)はやめて天皇を元首とし、官が主導するのがよい」という結論を導き出す前哨戦となるため、メディアが真に民主主義の媒体として機能しなかった代償は大きい。だから、メディアは真実かつ倫理的でまともな報道をすることが求められるのである。 また、*3-3のように、週刊文春が「安倍首相の事務所スタッフが『桜を見る会』のツアーに参加する地元支援者らに同行して上京する旅費を政治資金で支払った疑いがあり、事実なら事務所や後援会に『収支が発生していない』と説明した首相の説明と矛盾する可能性がある」などと報じているが、事務所スタッフが後援会の人に付き添って同行するのは仕事による出張であるため、これらのスタッフに政治資金から出張旅費を支払うのは何の問題もなく、むしろ必要なことで、いちゃもんが過ぎるのである。なお、事務所スタッフが後援会の人に付き添っても、後援会の人は旅行会社やホテルに旅費等の支払いをしているため、何ら問題はない。 このような中、*3-4のように、佐賀新聞が「10兆円規模の経済対策は過剰だ」と指摘しているが、私は、これらの中身を精査して災害対策や景気対策名目のその場限りの支出を排除したり、より低コストで将来性の高いものに変更したりする必要があると考える。何故なら、これらは、結局は、さまざまな形で国民負担に繋がるからである。 さらに、東京新聞はじめメディアが、*3-5のように、内閣府が共産党の宮本衆議院議員による関連資料要求の後に安倍首相主催の「桜を見る会」の招待者名簿を廃棄したと書いているが、①どこに行ったか ②選挙で誰を応援したか については個人情報であるため、名簿を廃棄していなかったとしても本人の同意なく開示すれば個人情報保護法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057)違反になる。にもかかわらず、しつこく廃棄の時間を調べたり、「デジタルデータを復元せよ」「情報開示は・・」などと言っているのは、与野党・メディアとも個人情報保護の意味がわかっていない。さらに、招待者の中に“反社会的勢力(定義が疑問)”が入っていたそうだが、首相が招待者の1人1人をチェックするわけもなく、首相はもっと大きな仕事をするものだ。 なお、*3-6に、佐賀新聞が既に私が上記で答えたこと以外に、「①後ろめたいことがないのなら、なおさら国会に出て可能な限り関係書類を示して野党の質問に答えるべき」「②安倍首相が、各界において功績・功労のあった方々という招待基準を無視し、後援会関係者というだけで招いていたとすれば公費を使って後援会関係者をもてなしたことになる」「③できるはずの潔白の証明をしようとしないのは、自ら潔白ではないと認めたことになる」などを記載しているが、このうち①③については、安倍首相を辞めさせるために野党が追及しているため、いろいろ説明して合理的であったとしても、別の事案を探して汚いかのように言うと思われる。また、②についても、叙勲(これにはおかしな基準が多いと思うが)ではあるまいし、「(どこにでも咲いている)桜を見る会」に、それほど厳格な招待基準が必要とは思われず、招待客に会を主催するホストの好みが入るのは自然だろう。また、価格はホテル側と合意していれば問題なく、立食パーティーなら人数分の食事を準備しているケースの方がむしろ少ない上、価格交渉するのも普通だ。つまり、国の正確な財務諸表やその明細書がないため、金額や性格の重要性に応じて予算委員会・決算委員会で質問時間を割り当てることができず、重箱の隅をつついて政権闘争するのが野党ということになっているのが国民にとって最大の不幸なのである。 *3-1:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191125/k10012190551000.html (NHK 2019年11月25日) 「桜を見る会」野党側が追及本部立ち上げ 山口県訪問し調査へ 総理大臣主催の「桜を見る会」をめぐり、野党側が追及本部を立ち上げ、ことしの招待者のうち1000人程度が安倍総理大臣からの推薦だったことなどについて、地元の山口県下関市を訪れるなどして調査を進めることになりました。立憲民主党、国民民主党、共産党など野党側は25日、「桜を見る会」の追及チームの体制を強化して国会議員70人余りからなる「追及本部」を立ち上げ、初会合を開きました。本部長に就任した立憲民主党の福山幹事長は、「真相究明を進め、倒閣に向けた運動を進めていく。安倍政権は、自分たちのお友達だけを大切にして、国民生活はほったらかしだ。追及の手を緩めず一致結束して頑張りたい」と述べました。 そして、ことしの招待者のうち1000人程度が安倍総理大臣からの推薦だったことや、昭恵夫人からの推薦もあったこと、それに招待者名簿が野党議員が資料請求したのと同じ日に廃棄されたことなどについて、8つの班に分かれて調査を進めることを決めました。今後は、安倍総理大臣の地元の山口県下関市などを訪れて関係者から話を聞きたいとしているほか、引き続き安倍総理大臣に国会で説明責任を果たすよう求めていくことにしています。 *3-2:https://www.chunichi.co.jp/chuspo/article/entertainment/news/CK2019111602100052.html (中日新聞 2019年11月16日) 過去に「大麻中毒」など薬物使用疑惑報道 逮捕された“エリカ様“沢尻エリカ容疑者の横顔 東京都内の自宅で合成麻薬MDMAを所持したとして、警視庁は16日、麻薬取締法違反容疑で女優の沢尻エリカ容疑者(33)を逮捕した。沢尻容疑者は、2005年に出演した映画「パッチギ!」で日本アカデミー新人賞をはじめ、映画賞に多数輝き、フジテレビ系ドラマ「1リットルの涙」での演技も高く評価され、一躍人気女優の座に上り詰めた。だが、07年9月、自身が主演した映画「クローズド・ノート」の舞台あいさつで、「別に…」と答え、自由奔放な振る舞いが批判されるなど話題になり、“エリカさま”と呼ばれた時期もあった。小学6年でモデルとして芸能界デビュー、少女ファッション誌「ニコラ」のモデルも務めた。03年、TBS系「ホットマン」で連続ドラマに初出演し、04年に「問題のない私たち」で映画初出演を果たした。演技力が買われ、以降映画出演が続き、「シュガー&スパイス 風味絶佳」(06年)「手紙」(同)、「新宿スワン」(15年)、「不能犯」(18年)などで主演した。12年の主演作「ヘルタースケルター」ではヌードを披露。転落していく女優を演じ話題になった。「億男」(18年)、「人間失格 太宰治と3人の女たち」(19年)でも存在感のある役を演じたばかりだった。プライベートでは、09年にはクリエイター高城剛さんと結婚したが、その後、夫婦関係をめぐり、迷走の末、13年に離婚した。女優としてのキャリアを重ねていく一方、薬物との接点もこれまで指摘され、「大麻中毒」など薬物使用疑惑が週刊誌などで報じられていた。 *3-3:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/369062 (北海道新聞 2019/11/27) 首相事務所、桜見る会旅費を政治資金から支出か 週刊文春報道 2015年の「桜を見る会」を巡り、安倍晋三首相の事務所スタッフがツアーに参加する地元支援者らに同行して上京する旅費を、政治資金で支払った疑いがあると、週刊文春が27日、ウェブサイトで報じた。事実なら事務所や後援会に「収支が発生していない」とする首相の説明と矛盾する可能性があり、野党が追及を強めそうだ。ウェブサイトなどによると、ツアーには地元事務所のスタッフが多数同行しており、約89万円はスタッフの旅費だった疑いがあるとしている。首相はこれまで、旅費や宿泊費などは参加者が直接旅行代理店に支払ったと説明。違法ではないとの考えを示している。 *3-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/458775 (佐賀新聞 2019年11月27日) 経済対策:10兆円規模は過剰だ 政府は来週にも経済対策を取りまとめ、2019年度補正予算、20年度当初予算にその経費を計上する。20年早々から切れ目なく執行する「15カ月予算」として、自然災害からの復旧・復興を加速させ、海外経済の下振れリスクへ備える方針だ。与党幹部らの要請も背景に、総額は10兆円規模に膨らむ見通しとなっている。堤防の強化や被災者の生活再建に向けたケアなど台風などによって大規模な被害を受けた地域への迅速な支援は必要だ。日米貿易協定による米国産牛肉の輸入増に直面する畜産農家への補助なども、一定程度は考えなければならないだろう。米中貿易摩擦による企業業績への圧力も高まってきた。英国の欧州連合(EU)離脱問題も企業活動を萎縮させている。こうした情勢に対する警戒は強めなければならない。しかし、広範囲に景気を喚起する大型対策が急務となっている局面ではない。実際、政府の景気認識も「緩やかに回復している」との判断を維持している。そんな中で、経済対策に10兆円を費やすのは過剰と言うしかない。むしろ、景気の安定を利用して、後退を続けてきた財政再建に向けた取り組みを立て直す方が、政策の方向性としては合理性があるだろう。消費税増税の負担軽減に向けた追加対策は既定路線だが、そのほかの対策は、対策名目の「間口」の広さに乗じて、詰め込んでいる感さえある。自動ブレーキなどの先端的な安全機能を備えた「安全運転サポート車(サポカー)」普及に向けた助成、小学5年生から中学3年生がパソコンを1人1台使える環境の整備、ドローンなど先端技術を使ったスマート農業の促進など、政府が盛り込もうとしている対策は、政策自体としては今の経済社会情勢に合致したものだろう。反対する理由はない。しかし、経済対策として直ちに予算計上して迅速に実施していく必要性については首をかしげざるを得ない。この間、幹事長ら自民党幹部らが相次いで補正予算を巡り10兆円規模を求めて発言、不要不急と思える事業が次々と対策に紛れ込んでいった。2閣僚辞任や「桜を見る会」問題で政権に対する逆風が強まっていることが背景にあると見るのは、うがちすぎだろうか。政府は対策に盛り込む予定の全ての政策について、早急な予算計上が必要かどうか改めて点検し、必要性が薄ければ採用を見送り、規模を絞り込むべきだろう。経済対策を盛り込む19年度補正、20年度当初予算は国会で審議に付される。政府が説明責任を果たすのは当然だが、政府を追及する野党の責任も重いことは指摘しておきたい。今回の対策では、財政投融資も活用される。成田空港の新滑走路や新名神高速道路の6車線化などに少なくとも3兆円を投じるという。財投は一般会計予算と違い、政府が財投債を発行して市場から資金を調達、それを長期間、低利で貸し付ける制度だ。国債のように税収で償還する仕組みではなく、国の借金には含めないため、対策規模を拡大する手段としては使い勝手がいいのかもしれない。だが、資金が計画通りに返済されなければ、国民負担につながることは言うまでもない。 *3-5:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201911/CK2019112702000148.html (東京新聞 2019年11月27日) 桜を見る会 名簿廃棄、資料要求後 「別の担当課、知らず」 安倍晋三首相が主催した「桜を見る会」の今年の招待者名簿を巡り、内閣府は二十六日、野党の追及本部が国会内で開いた会合で、五月九日に名簿を廃棄した時間帯が、共産党の宮本徹衆院議員による関連資料要求よりも後だったことを明らかにした。廃棄と資料要求を担当した課が別だったため「廃棄の時点で、資料要求は知らなかった」と説明した。野党は「証拠隠滅だ」と改めて批判した。内閣府によると、名簿の廃棄は大臣官房人事課が担当し、五月九日午後の早い時間帯に行った。一方、宮本氏の資料要求は同日正午すぎに大臣官房総務課が把握した。総務課は資料要求について速やかに人事課に伝えず、人事課の担当者が要求を知らないまま名簿を廃棄したという。今年の招待者名簿については、内閣府が宮本氏から資料要求があった五月九日に廃棄したことを明らかにしていたが、廃棄の時間帯が資料要求よりも前か後かには言及していなかった。自民党の二階俊博幹事長は二十六日の記者会見で招待者名簿について「後々の記録、来年の参考にもなるから、いちいち廃棄する必要はない」と苦言を呈した。菅義偉(すがよしひで)官房長官は記者会見で、桜を見る会の招待客を巡り、首相や官房長官らの推薦が二〇一四年の約三千四百人から今年は約二千人に減っているのは過少説明との野党の指摘に対し「招待者名簿を既に廃棄しており、確認できていない」と釈明した。菅氏は、首相や官房長官らの推薦について「自民党関係者からの推薦も多く入っていたのではないか」との見方も示した。 *3-6:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/460110 (佐賀新聞 2019年11月30日) 桜を見る会、首相は国会で説明を 安倍晋三首相主催の「桜を見る会」を巡る問題がなかなか収束しない。新たな疑問点が次々と指摘される一方、政府側の説明は納得できるものではなく、公的行事を私物化していたのではないかという疑いは深まる一方だ。特に、真相解明に必要な招待者名簿が、共産党議員から提出を求められると、開催から1カ月もたっていないのにもかかわらず、大型シュレッダーで細断、破棄された事実は、公的行事私物化の事実を隠そうとしたのではないかとの深刻な疑念を生んでいる。招待者推薦の内訳から後援会が「桜を見る会」の前日に開いた前夜祭の収支、そして名簿破棄に至るまでの詳細を把握でき、また説明する責任があるのは当事者でもある安倍首相以外にいない。後ろめたいことがないのであれば、なおさら国会に出て、可能な限り、関係書類を示して野党の質問に答えるべきだ。次から次に疑わしい新事実が出てきて、「桜を見る会」を巡る問題は拡散気味だが、大きく三つに分類することができる。まず焦点になったのは安倍首相が「各界において功績、功労のあった方々」という招待基準を無視して、後援会関係者を招いていたのではないかという問題だ。桜を見る会は公費で賄われ、酒食も振る舞われる。仮に後援会関係者というだけで招いていたのだとすれば公費を使って後援会関係者をおもてなししていたことになり、まさに私物化に当たる。次が、桜を見る会前日に後援会関係者向けに開いた「前夜祭」の夕食会とその会費の金額だ。会場が東京都内の高級ホテルだったにもかかわらず会費が相場より安い5千円だったことから、安倍首相の議員事務所が実費不足分を補った公選法違反の可能性や政治資金収支報告書への不記載の疑いが指摘されている。桜を見る会を私物化したとの批判に対して安倍首相は11月20日の参院本会議での答弁で、「招待者の基準が曖昧で、結果として招待者の数が膨れあがった」と主張したが、厳格に解釈すべき基準を曖昧に解釈していたのが実態で、答弁は論点をすり替えている。また、前夜祭については「夕食会を含め、旅費、宿泊費など全ての費用は参加者の自己負担で支払われている。安倍事務所や後援会としての収入、支出は一切ないことを確認した」と強調。金額に関しては「(参加者の)大多数がホテルの宿泊者という事情を踏まえ、ホテル側が設定した価格との報告を受けている。毎年使っているとか、規模であるとか、宿泊をしているかをホテル側が総合的に勘案して決めることだ」と述べたが、根拠となる資料は示されなかった。さらに深刻で、説明に説得力がないのは招待者名簿を破棄してしまったことだ。共産党議員の提出要求の1時間後に大型シュレッダーで細断されており、名簿に安倍首相にとって都合の悪い部分があり、国会に提出されないよう「証拠隠滅」したのではないかとみられている。通常は可能なはずの電子データの復元についても菅義偉官房長官は「事務方からできないと聞いている」と説明にならない答弁を繰り返すだけだ。できるはずの潔白の証明をしようとしないのでは自ら潔白ではないと認めていることになる。 <憲法が守られていない事例(その1)-健康で文化的な生活> PS(2019年11月28日追加): *4-1・*4-2のように、パートなど非正規で働く人たちの厚生年金の加入要件は、現在は「従業員501人以上の企業に勤務し、週20時間以上働いて、月給8万8千円以上」に限られているが、2022年10月に「101人以上の企業」、2024年10月に「51人以上の企業」に順次引き下げる案が有力だそうだ。対象拡大を目指す背景には、国民年金だけの人が低年金に陥らないようすることと、現在の年金保険料収入を増やす狙いがあるが、労働時間や賃金要件は現状を維持し、50人以下の企業も対象から外れ、政府は「中小企業の負担感や生産性向上に配慮し、助成金等の支援策も検討する」としている。 しかし、*4-3のように、日本国憲法では「25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」「27条:すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されており、要件に満たない労働者は不十分な社会保障でよいとしてきたのが誤りである上、いつまでも専業主婦世帯をモデルとするのも、憲法27条及び男女雇用機会均等法違反だ。 さらに、中小企業(定義不明)の生産性が低いとは限らず、むしろ厚労省始め役所の生産性の方が低そうで、社会保険料くらいは負担できるシステムにするのが筋であるし、その方が誰にとっても福利が増すわけである。 *4-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/458871 (佐賀新聞 2019年11月27日) 厚生年金加入要件、2段階で拡大、22年に101人以上の企業 パートなど非正規で働く人たちの厚生年金で、政府、与党が加入対象となる企業要件を2段階で拡大する検討を始めたことが27日、分かった。現在、加入が義務付けられている企業の規模は「従業員501人以上」。これを2022年10月に「101人以上」、24年10月に「51人以上」に順次引き下げる案が有力だ。厚生年金の保険料は労使折半。51人以上に引き下げれば新たに65万人が加入対象となる一方、企業の保険料負担は1590億円増える見通し。政府は将来的な企業要件の撤廃を目指しているが、中小企業の経営面への配慮などから、今回の制度改正では撤廃の時期は明記しない方向。これまで一度に51人以上に引き下げる方向で検討してきたが、経営への打撃を最小限に抑えたい中小企業が慎重な対応を求めていた。来年の通常国会に関連法案を提出する。対象拡大を目指す背景には、国民年金だけの人が将来、低年金に陥らないよう年金額を手厚くする狙いがある。パートやアルバイトで働く人は現在、(1)従業員501人以上の企業に勤務(2)労働が週20時間以上(3)月給8万8千円以上―などの要件を満たせば、厚生年金の加入対象となる。今回の制度改正では企業要件を引き下げる一方、労働時間や賃金の要件は現状を維持する。26日に開かれた政府の全世代型社会保障検討会議では、議長を務める安倍晋三首相が「中小企業の負担感や生産性向上に配慮しつつ、厚生年金の適用範囲を考える」と述べていた。 *4-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14274047.html (朝日新聞 2019年11月28日) パート厚生年金、2段階拡大 従業員51人以上に 厚労省調整 厚生労働省は、厚生年金が適用されるパートらの範囲を2段階で広げる方向で調整に入った。今は勤め先の企業規模が「従業員501人以上」であることが条件だが、2022年10月に「101人以上」、24年10月から「51人以上」に引き下げる。新たな保険料負担が生じる中小企業に配慮し、一定の準備期間を設けて理解を得たい考えだ。厚生年金には、正社員などフルタイムで働く人のほか、「501人以上の企業で週20時間以上働き、月収8万8千円以上」などの条件を満たすパートらも加入できる。今は約40万人だが、厚労省の試算では、適用対象の企業規模を51人以上にすると約65万人増える。政府は、厚生年金の方が国民年金よりも年金額が高いため、適用拡大によって低年金・無年金になる人を減らせるとしている。保険料収入が増え、年金財政が改善する効果も見込む。厚労省によると、企業規模を51人以上にした場合、モデル世帯の将来の年金水準は0・3ポイント上がる。一方、厚生年金の保険料は労使折半で払う。パートの加入者が1人増えると、一緒に生じる健康保険料とあわせて、年約25万円の負担増になるとの厚労省の試算もある。中小企業側は、最低賃金の引き上げなども課題になる中、保険料負担まで増えれば「経営に大きなインパクトを及ぼしかねない」などと慎重論を展開。また、パート自身が保険料負担を避けようと働き方を調整すれば、人手不足が加速する恐れもあると指摘している。ただ、政府は来年の通常国会に適用拡大の法案を提出する方針。中小企業側の理解を得るため、助成金などの支援策も検討している。 *4-3:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 (日本国憲法より抜粋) 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上 及び増進に努めなければならない。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 <憲法が守られていない事例(その2)-違憲立法審査権> PS(2019年11月29日、12月5日追加):日本国憲法は、「81条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定めており、これは最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所であることを規定したものであるため、違憲立法か否かを判断するには、(よく必要と言われる)憲法裁判所は不要だ。 さらに、民事訴訟・行政訴訟など下部の法律で要求される当事者適格(特に原告適格)や訴えの利益などの訴訟要件を満たした訴訟でなければ違憲立法を提訴する資格がないとし、訴えの利益を狭く解釈しているのも、実質的に国民が違憲立法審査権を行使するのを困難にしている。 そのような中、*5-1のように、戦後の憲法裁判記録が多数廃棄され、自衛隊や基地問題に関する当初の議論が検証不可能になったのは、大きな問題だ。 また、日本政府は、*5-2のように、米国主導の「有志連合」には参加しないが、国会承認がいらず防衛大臣の判断のみで派遣可能な「調査・研究」という名目で、もともとは日本と友好関係を持っていた中東イランに自衛隊を派遣するそうだ。しかし、危機の迫った日本の船舶を護衛するわけでもないのに、単なる情報収集態勢強化のために自衛隊を遠方に派遣するのは、違憲の可能性が高い安全保障関係法令からもはみ出している。そのため、敵を増やす結果しか招かなそうなこの自衛隊派遣について、国会はその理由・目的・結果をよく検討すべきだが、この件に関しては「桜を見る会」ほどにも議論できないのが、我が国の深刻な問題なのである。 *5-1:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019080401001662.html (東京新聞 2019年8月4日) 戦後憲法裁判の記録を多数廃棄 自衛隊や基地問題、検証不能に 自衛隊に一審札幌地裁で違憲判決が出た長沼ナイキ訴訟や、沖縄の米軍用地の強制使用を巡る代理署名訴訟をはじめ、戦後の重要な民事憲法裁判の記録多数を全国の裁判所が既に廃棄処分していたことが4日分かった。代表的な憲法判例集に掲載された137件について共同通信が調査した結果、廃棄は118件(86%)、保存は18件(13%)、不明1件だった。判決文など結論文書はおおむね残されていたが、歴史的裁判の審理過程の文書が失われ検証が不可能になった。裁判所の規定は重要裁判記録の保存を義務づけ、専門家は違反の疑いを指摘する。著名裁判記録の廃棄は東京地裁で一部判明していた。 *5-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14281400.html (朝日新聞社説 2019年12月4日) 中東へ自衛隊 国会素通りは許されぬ 緊張が高まり、不測の事態も想定される中東に自衛隊を派遣することの重みを、安倍政権はどう考えているのか。政府・与党だけの手続きで拙速に決めることは許されない。国会の場で、派遣の是非から徹底的に議論すべきだ。中東海域への自衛隊派遣について、政府が年内の閣議決定をめざしている。早ければ年明けにも、護衛艦1隻を向かわせるほか、海賊対処のためソマリア沖で活動中のP3C哨戒機1機の任務を切り替える。米国のトランプ政権が核合意から一方的に離脱し、米国とイランの対立は深まるばかりだ。政府は米国が主導する「有志連合」への参加を見送り、独自派遣を強調することで、イランを刺激しまいとしている。だが、有志連合とは緊密に情報共有を進める方針であり、状況次第で、米国に加担したと見られても仕方あるまい。朝日新聞の社説は、関係国の対話と外交努力によって緊張緩和を図るべきだと、繰り返し主張してきた。米国の同盟国であり、イランとも友好関係を保つ日本が、積極的に仲介役を果たすことも求めてきた。こうした取り組みに逆行しかねない自衛隊派遣には賛同できない。法的根拠にも重大な疑義がある。日本関係の船舶を護衛するわけではなく、情報収集態勢の強化が目的として、防衛省設置法の「調査・研究」に基づく派遣だという。国会承認がいらないだけでなく、防衛相の判断のみで実施可能だ。自衛隊の活動へのチェックを骨抜きにする拡大解釈というほかない。政府が今回、閣議決定という手続きをとることにしたのは、公明党などにある懸念に応え、政府・与党全体の意思統一を図る狙いがあるのだろう。しかし、先に派遣ありきの議論で、数々の問題が解消されるとは思えない。政府は現地の情勢について、船舶の護衛がただちに必要な状況ではないと説明している。それなのに、派遣の決定を急ぐのはなぜか。活動を始めた有志連合と足並みをそろえ、米国への協力姿勢をアピールする狙いがあると見ざるをえない。だが、いったん派遣すれば、撤収の判断は難しくなる。立ち止まる機会は、今しかない。この節目に、国会論議を素通りすることは許されない。9日に会期末を迎える今国会では、いまだ中東派遣を巡る突っ込んだ質疑が行われていない。だとすれば、国会の会期を延長し、日本が採るべき選択肢を議論すべきではないか。そのことこそ、政治に課せられた国民への責任である。 <無駄のない安価で本質的な公共事業をすべき> PS(2019年12月1、2、3日追加):*6-1のように、気候変動による海面上昇で、ガンジス川下流のインド・バングラデシュ国境地帯にある汽水域のマングローブが浸食され、この地域の鹿が減ってベンガルトラも姿を消す恐れがあるそうだ。また、人間も海面上昇で海辺の自宅に海水が入ってくるようになり、人間を含む生態系全体が内陸に移動せざるを得なくなった。しかし、*6-2のように、日本の標高は東京湾の平均海面が基準となっており、日本水準原点の高さは明治6年6月(1931年)から明治12年12月(1937年) までの東京湾の平均海面を見て決められたままだそうで、標高は海面上昇とともに一律に下がった筈なので、“歴史”“伝統”“前例”と称して惰性で同じことをやり続けるのは、日本の非科学的な点である。 なお、近年は、*6-3のように、気候変動によって豪雨が増加し、水位超過が年を追うごとに増えて「氾濫危険水位」を超える事例が、2018年に日本全国で474件に達するそうだ。この原因には、海面上昇・気温の上昇による頻繁で強い豪雨・長期にわたる河川管理の不適切・住宅適地選定の誤りなどが考えられ、さんざん無駄遣いをしてきた上げ挙句の予算不足は言い訳にならない。そのような中、日頃からの治水対策はもちろん重要だが、人口減にもかかわらず海に面した大都市に人口を密集させ、土地価格の高騰から地下鉄・地下街さらには地下貯水池などの地下施設を作り、浸水すれば莫大な被害が生ずるという都市計画自体を考え直す必要がある。 では、どういう土地の使い方をするのが合理的かと言えば、*6-4及び東日本大震災の津波被害を参考にすれば、「①人は高台に住む」「②工場もゆとりを持つ高台に移動する」「③農地を低い土地に作って遊水地の働きを持たせ、遊水地部分には水害にあっても1年で回復できる作物を植え、水害復旧には国から補助をする。トラクター・コンバイン・大型乾燥機などの農機具は十分な高さのある場所に保管する」などが考えられる。そのため、以前どおりに復旧したり、むやみに仮設住宅を立てたりするのは、無駄遣いの中に入るわけだ。 ただ、*6-4に書かれている大町町の灰塚さんの場合は、順天堂病院周辺の農地約6haであるため、県・町・順天堂病院・その他の適切な会社が買い取って介護等のサービスを受けやすいマンションや公営住宅を建て、高齢者や病院のスタッフはじめそのような住宅に住みたい人を住まわせるのが便利だと思う。そのため、灰塚さんは、この土地を耕作者のいなくなった他のよい土地と交換すればよいのではないか? 佐賀県には、*6-5のように、九州新幹線長崎ルートが開業すると並行在来線が不便になるという問題があるが、これはJR九州に依存しすぎているからかもしれない。何故なら、埼玉県ふじみ野市(私の自宅)は、東武東上線・有楽町線(地下鉄)・東急東横線・みなとみらい線が相互乗り入れして直通運転になったため、池袋・永田町・有楽町がもともと直通だったのに加えて新宿・渋谷・横浜・元町中華街などが直通で繋がり、便利になった。*6-5のケースなら、並行在来線の運行を他の鉄道会社に移管してJR九州と相互乗り入れさせたり、ディーゼル車両ではなく蓄電池電車や燃料電池電車にしたりなど、もっと希望が持てる前向きな案が考えられる筈で、私鉄は九州にこだわらず東急など沿線の街づくりが得意な会社の方がよいかもしれない。 *6-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14274014.html (朝日新聞 2019年11月28日) (世界発2019)気候変動、ベンガルトラ窮地 200頭生息のガンジス川下流、海面上昇 絶滅が心配されるベンガルトラの最大の生息地の一つで、インドとバングラデシュの国境地帯にあるマングローブが、気候変動による海面上昇の打撃を受けている。50年後にはベンガルトラが姿を消してしまう恐れがあるという。 ■飲み水・えさピンチ、絶滅危惧に追い打ち 野生生物の宝庫と言われ、ベンガル語で「美しい森」を意味するシュンドルボン。青森県とほぼ同じ総面積、約1万平方キロメートルのマングローブは世界最大級で、ガンジス川下流のデルタ地帯にある。数千の川や入り江が複雑に入り組む。海水の混じった汽水がマングローブの生育に適し、ベンガルトラのほか、ワニや鹿、カワイルカなど様々な生物が生息する。主要部分は国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界自然遺産に登録されている。だが、約100の島からなる現地を小型船でめぐると、豊かだったはずの自然環境は変わり果てていた。岸辺の木々は消え、泥が積み上がっている。高さ2メートルほどの急ごしらえの堤防も、少しずつ浸食されている。海面上昇が進んでいるのだ。「年間約550ヘクタールの土地が失われている。海面上昇で土中に海水が混じり降雨量の減少も加わって、土中の塩分の濃度が上がっている。ベンガルトラの飲む淡水が少なくなってしまう」。ベンガルトラの保護活動に取り組んでいる地元NGOのアニル・ミストリ代表はそう心配する。すでに二つの島が沈んだ。えさとなる鹿にも影響が出ている。世界自然保護基金(WWF)によると、世界で生存するトラは1900年からの100年間で密猟の影響などで95%減り、4千頭を切った。インドやバングラデシュ、中国などに生息するベンガルトラは、昨年時点でシュンドルボンに202頭いることが確認されている。バングラデシュ・インディペンデント大学のシャリフ・ムクル氏は、環境変化で「2070年までにベンガルトラはシュンドルボンから完全に姿を消してしまう可能性がある」と予測している。 ■家・田畑に海水、1万人移住/トラ襲撃被害 シュンドルボンには人が住む集落が50カ所ほどあるが、海面上昇で生活も脅かされている。農家のブロゲン・マンダルさん(44)は「米の収量は昨年の600キロから180キロも減った」と嘆いた。海水が森林や田畑に入り込み、土壌を変えてしまったためだ。一帯の水も海水が混じる量が増え、取れる魚の量が減っている。モハン・マンダルさん(56)一家は、海辺の自宅に海水が入ってくるようになったため、地元政府がつくった堤防の内側に移住した。「5年後には堤防が壊れてしまうかもしれない。そうなったらどこに住めばいいのか」。この数年、暑い夏が長くなり、冬が来るのが遅く短くなったと感じる。「夏は暑すぎて、太陽が地上にあるようだ」。地元報道によると、一帯では海面上昇などですでに約1万人が移住を余儀なくされている。シュンドルボン一帯は雨期になるとベンガル湾の方角からサイクロンが直撃する。島の一つで、約4万人が暮らすバリ島にはサイクロンによって大量の海水が流入することもしばしばで、土壌の塩分が多くなってしまった。住民は生活や農業のため地下30メートルほどから水をくみ上げ続け、すでに枯渇してしまった地域が相次いでいる。シュンドルボンの巨大マングローブは、04年のインド洋大津波で大きな被害を防いだこともあり、自然災害から人間を守る天然のフェンスだった。マングローブが失われれば、植物や野生動物だけでなく、人間の生活も危うい。地元NGOのミストリ氏は「人間もこの自然の一部だという認識で生態系を守らなければならない」と話す。トラが人間を襲う事故も頻発する。生息域が狭まり、えさが減っているのが原因とみられている。インド・西ベンガル州政府はトラの生息地にネットを張り巡らせ、トラの封じ込めに努めている。それでも事故は起きてしまう。蜂蜜を採集していた夫をベンガルトラに殺されたというコイシャラさん(60)は「トラは私たちにとって恐ろしい存在だったが、安全を願って共に生きてきた。その調和が壊れてしまった」と話す。 *6-2:https://www.jk-tokyo.tv/zatsugaku/107/ (東京さんぽ) 日本の標高を決める水準原点 日本の標高は東京湾の平均海面が基準となり、それが標高ゼロメートルと決まっているそうです。その正確な高さを定めた水準原点は東京湾にあるのではなく、湾岸より地盤のよい国会議事堂前の憲政記念館(東京都千代田区永田町1-1)の庭にあります。この日本水準原点の高さは、明治6年6月(1931年)から明治12年12月(1937年) までの東京湾霊岸島で測定した東京湾の平均海面を見て決められました。水準原点は小豆島産の花崗岩でつくられた原点標石に水晶板が埋め込んであり 、この水晶板の目盛ゼロの線(法令では零分画線の中点)が基準となります。 ○標高は24.4140m。 明治24年(1891年)この場所に日本水準原点が初めて設置されたときの標高は 24.5mでしが、1923年の関東大震災によって日本水準原点の地盤が86.0mm沈下したため、その標高が24.4140mと改められました。水準原点を保存している建物は工部大学校(東京大学工学部前身)。第1期生佐立七次郎(さたち・1856~1922)さんの設計で、建物は石造りで平屋建になります。建築面積は14.93㎡で軒高4.3mローマ風神殿建築にならい、トスカーナ式 オーダー(古典建築の構成原理)をもつ本格的な模範建築で、明治期の数少ない近代洋風建築として貴重なものだそうです。また、建物正面には「大日本帝国」「水準原点」の凝った文字が右から横書きで書かれてあり、「大日本帝国」の文字が残っている建物としても貴重であり 、現在は東京都指定有形文化財(建造物)に指定されています。 *6-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/563324/ (西日本新聞 2019/11/28) 「氾濫危険水位」超過河川4年で5.7倍 18年474事例、28%が九州 河川の水位がいつ氾濫してもおかしくない「氾濫危険水位」を超える事例が2018年に全国で474件に達し、うち3割近い136件を九州7県が占めたことが、国土交通省への取材で分かった。水位超過はこの数年で顕著に増加しており、都道府県が管理する河川での発生が大半を占めた。台風の強大化や豪雨の頻発が背景にあるとみられ、国交省は気候変動を見据えた治水対策の検討に乗り出した。国交省によると、水位超過は年を追うごとに増えており、全国の件数は14年(83件=うち九州8件)の5・7倍に増え、九州7県が28%を占めた。国交省は「気候変動による豪雨の増加で、河川の安全度が相対的に低下している恐れがある」と分析。九州は他地域より豪雨が多かったため、全国に占める割合が高まった可能性が高い。河川の管理主体別では、都道府県が全国で86%(412件)、九州7県で82%(112件)を占めた。九州の県別の内訳は、福岡29件▽佐賀14件▽長崎4件▽熊本16件▽大分25件▽宮崎18件▽鹿児島6件。都道府県管理は、洪水時などに甚大な被害が想定されている国管理と比べ、氾濫対策が遅れているとみられる。関東や東北で甚大な被害が出た今秋の台風19号でも、堤防が決壊した71河川140カ所のうち64河川128カ所が都道府県管理だった。群馬大大学院の清水義彦教授(土木工学)は「都道府県管理河川は予算不足などで対策が遅れがちで、(降雨時間や範囲の)規模が小さい豪雨であふれる河川もある」と指摘。水位低下につながる遊水池の設置や河道の掘削といった対策について「早急に進める必要がある」と訴える。気象庁によると、1時間に50ミリ以上80ミリ未満の降雨量を示す「非常に激しい雨」の回数は、約30年前の約1・4倍に増えた。気候変動が豪雨増加の要因と指摘され、国交省の有識者検討会は気温が2度上昇すれば洪水頻度が2倍になるとの試算をまとめ、7月末に対策強化を提言した。国交省は、社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)の小委員会で気候変動を踏まえた治水対策の見直しの検討に入っており、国管理河川の治水計画を改定する方針。自治体にも温暖化の影響を考慮するよう促しており、都道府県管理河川の計画見直しにつながる可能性がある。 *6-4:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/563318/ (西日本新聞 2019/11/28) 「つらい」臭う田畑、油に奪われた実り…農家の無念 九州大雨3カ月 九州北部を襲った8月の記録的大雨から28日で3カ月。鉄工所から流れ出た油混じりの水に田畑が漬かった佐賀県大町町の農家灰塚晃幸さん(64)は今季、収穫と作付けを断念した。県は土壌調査を終えて来春の営農再開を目指す方針を打ち出したが、灰塚さんの田畑には油の臭いが残り、農機具修復の見通しも立たない。「精魂込めて長年向き合った農業を奪われた」と無念さを募らせる。「今ごろは田んぼを耕して、麦をまく時期やったのに」。灰塚さんは、稲の切り株が残る田んぼを見つめた。近くのブロッコリー畑には雑草が生い茂る。4トンの収量を見込んでいた大豆は立ち枯れしたままだ。会社勤めから専業農家になって約35年。亡くなった父、安清さんが広げた順天堂病院周辺の農地約6ヘクタールを耕してきた。この夏、病院周辺の田畑の大半が大雨で冠水し、油が作物と土に付着した。自宅も床上1・3メートルまで浸水。大雨から1カ月間、避難所に暮らしながら、いても立ってもいられずに田畑を回った。10月、茶色に変色した稲穂を廃棄するために刈り取った。トラクターとコンバイン、大型乾燥機など農機具は全て修復不能に。「米に触れる部分は油が付着したらだめ。使ったら風評被害を生む」と諦めた。今月25日、大町町役場で開かれた被災農家の説明会。県と町の土壌調査では、農地153カ所のうち4カ所で水稲の生育に影響を及ぼすレベルの油を検出したと報告を受けた。灰塚さんの農地15カ所は、自然分解や石灰散布で営農再開できるレベルだった。それでも不安は消えない。「油はゼロではなく今も臭いがする。来年6月に田植えができるかどうか」。農機具の損失は4千万円相当に上る。国などの補償を受けても4割程度は自己負担になる。自宅の再建も見通しは立っていない。「全壊」判定の母屋には住めず、隣の農業小屋2階に家族3人で寝泊まりしている。いつもなら年末が近づくと自家栽培のもち米を蒸して、餅をつき、親戚に配っていた。今年のもち米は、捨てるしかなかった。正月には親戚一同が自宅に集まってカラオケ大会でにぎやかに過ごしてきたが、すでに断りを入れた。「3カ月たっても、状況は何も変わらん。何の作業もできんのがつらい」。農家の営みを失った重さが日々のしかかる。 ◇ ◇ ●罹災証明受け付け2300件 8月の記録的大雨で被災した佐賀県。全20市町にあった避難所は10月20日までに全て閉鎖されたものの、自宅の浸水被害で戻れない人々が公営住宅67戸で仮住まいを続け、民間物件を借り上げて公費負担する「みなし仮設住宅」14戸の入居も決まっている。罹災(りさい)証明書の申請受け付けは13市町で2302件に上る。県によると、県内6市町に設置された災害廃棄物の仮置き場のうち、大町町と白石町は廃棄物を全て搬出。福岡、長崎両県の施設などと連携して広域処理が進んでいる。今月26日時点で住宅被害は全壊87棟、大規模半壊106棟など。農林水産関係や商工業など被害総額は約355億円に上る。 *6-5:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/461153 (佐賀新聞 2019年12月3日) 並行在来線ディーゼル化、速度遅く長崎線に乗り入れできず? <新幹線長崎ルート>肥前山口で乗り換えか 九州新幹線長崎ルートの2022年度暫定開業に伴い、並行在来線となる肥前山口-諫早間を走る普通列車が、佐賀方面の長崎線に乗り入れできない可能性があることが分かった。並行在来線の一部区間は経費削減で非電化となり、速度が遅いディーゼル車両で運行するため、肥前山口駅での乗り換えが必要になる見通し。佐賀県は利便性が損なわれるとして、JR九州との協議で現行の乗り入れ本数の維持を求めている。肥前山口-諫早間は、佐賀、長崎両県が鉄道施設を維持管理し、JR九州が運行を担う「上下分離」方式を採用する。2016年の6者合意で、長崎ルートの暫定開業から23年間は普通列車を「現行水準維持」することが決まった。ただ、特急が走る肥前鹿島までは電車で運行できるが、肥前鹿島-諫早は経費を抑えるため、非電化区間となる。普通列車はディーゼル車両になり、肥前山口-諫早間で運行する。県によると、JR九州は速度が遅いディーゼル車両の長崎線への乗り入れはダイヤ編成上、困難との見方を示しているという。現行で1日に上下約30本程度の普通列車が運行し、半数以上が乗り換えを必要とせずに佐賀駅や鳥栖駅まで走っている。沿線住民の通勤通学の足として重要な役割を果たしているが、暫定開業後は一切乗り入れできなくなる可能性が出てきた。佐賀県は、JR九州や長崎県と進めている並行在来線の協議の中で、普通列車の在り方について問題提起している。JR九州が試験走行しているスピードが出る新型ディーゼル車両の導入を提案するなどしている。県交通政策課は「6者合意の『現行水準維持』は本数だけでなく、利便性も含まれる。通勤通学の時間帯の乗り入れを実現できるよう申し入れていきたい」と話す。JR九州は取材に対し、「ダイヤは需要や経営資源を考慮し、可能な限り利便性を確保するよう開業直前に決めるもので、現時点のコメントは差し控える」と回答した。 <発生主義会計採用の必要性を示す重大な事例(その1)-年金> PS(2019/12/6追加): 政府は、公的年金制度に関し、消費税を引き上げ、金利を下げてマネーサプライを増やすというインフレ政策をとりつつ、物価スライド制を導入して、公的年金の実質受給額を減らすことに熱心だった。長寿命化により、*7-1のような中小企業で働く非正規労働者の厚生年金加入や高齢者の就業促進のための改革は必要だが、メディアや日本総研の西沢氏が、「①将来世代に目配りする改革が不十分」「②高齢者から反発が出るような制度改革がなければ、若年層からの信任は得られない」「③マクロ経済スライドの強化策を見送ったので、世代間の格差縮小という点で課題が多い」などとしているのは不適切だ。 何故なら、③は、年金や介護保険制度が不十分だった時代に親の生活の世話や介護を行った現在の高齢者とそれを社会に任せることのできる若者との世代間格差の方がずっと大きいことを無視しており、①②は、現在の日本を造ってきた高齢者に感謝するどころか高齢者を馬鹿にする発言で、このような良識のない発言が「オレオレ詐欺」のような高齢者にたかる若者を作る温床となっているからだ。そして、現在の高齢者に対するこのような扱いが続けば、将来の年金制度は、制度が持続しても価値の小さなものになるだろう。なお、介護保険制度も介護保険料の支払者・受給者とも、全世代の働く人にすべきだ。 それでは、「年金については、どうすればよかったのか」と言えば、厚生省(当時)が積立方式だった年金制度を1985年に賦課課税方式とし、単年度主義にしてその年の収支しか気にしなくなったため、*7-2のように、公的年金の給付水準が現役世代の負担に依存することとなり、散々、無駄遣いした上で「積み立てられた厚生年金の運用資産総額が200兆円に達している」などと呑気なことを言うようになったのが問題なのである。従って、積立方式を変更する必要はなかったのだが、今からなら発生主義に基づいた積立金を準備する必要があり、その金額の計算方法は民間企業が使っている退職給付会計と同じだ。現在の積立金と発生主義に基づいて計算された積立金の差額については、国民には全く責任がないため痛み分けする必要はなく、国債を発行して長期間で返済するしかない。 *7-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52982720V01C19A2EA1000/ (日経新聞 2019/12/5) 75歳から受給も可能 政府の改革案まとまる 政府が検討を進めてきた公的年金制度の改革案が5日、固まった。中小企業で働くパート労働者も厚生年金への加入を義務づけるほか、75歳から受け取り始めると月あたりの年金額を最大で84%増やせる仕組みに変える。制度の支え手拡大や高齢者の就業促進に重点を置く。ただ現在の高齢者への給付を抑え、将来世代に目配りする改革はなお不十分だ。自民党が5日開いた社会保障制度調査会を受け、まとめた。2020年1月から始まる通常国会への改正法案の提出をめざす。公的年金改革は5年に1度実施する将来見通し(財政検証)を受け、19年夏から本格的な議論が始まった。議論の土台になる財政検証で示されたのは経済が順調に推移しても、将来の給付水準は今より2割弱下がるという先細りの将来像だ。政府は厚生年金の支え手拡大で、年金制度の持続性を高めることを重視した。高齢になるとパートや嘱託など短時間勤務に切り替える人も多く、働き方が変わっても厚生年金に加入できるようにする。現状は(1)従業員501人以上の企業に勤務(2)週20時間以上働く(3)賃金が月8.8万円以上――などの条件を満たす短時間労働者が対象。政府案では企業規模の要件を見直し、まず22年10月に従業員101人以上の企業に対象を拡大。24年10月には51人以上まで基準を下げる。厚生年金には18年度末で4440万人が加入するが、厚生労働省の試算では新たに65万人が加入する見通しだ。企業規模の要件を101人以上に見直すと、将来世代の所得代替率(現役会社員の手取りに対する高齢夫婦世帯の年金額の割合)は約0.2%改善する。対象を51人まで拡大すると改善幅は約0.3%まで広がる。将来不安に備えるには65歳を過ぎても健康な間はできるだけ長く働いて、公的年金はいざという時まで取っておけるようにもする。その中核になるのが年金の受け取り開始年齢の引き上げだ。今は原則65歳が受給開始年齢で、60~70歳の間で時期を選べる。これを75歳まで延ばす。受取時期を1カ月遅らせるごとに月あたりの年金額は65歳で受け取るより0.7%増える。75歳まで遅らせると84%増だ。19年度の厚生年金は夫婦2人のモデル世帯で月22万円。賃金や物価などの変動を考慮しなければ、75歳まで繰り下げた際の年金額は40万円強に増える。海外では平均寿命の延びに合わせて支給開始年齢を遅らせる国もあるが、選択肢の拡大で対応する。働く高齢者の年金を減らす「在職老齢年金」も見直す。今は60~64歳の場合、厚生年金と賃金の合計が月28万円を超えると年金の一部が支給停止になる。働いても収入が変わらず、就労意欲をそぐとの批判があった。この基準額を47万円に上げる。19年度末の試算では、新たに46万人に対して約3000億円の財源が必要だ。公的年金の支給額を抑えて制度の持続性を高める「マクロ経済スライド」の強化策は見送った。物価や賃金が低迷している時は機能せず、04年の導入から発動したのは2回のみ。調整が機能しなければ、高齢者の年金は維持されるが将来世代の給付水準は下がる。日本総合研究所の西沢和彦氏は「高齢者から反発が出るような制度改革をしなければ、若年層からの信任は得られない」と指摘する。世代間の格差縮小という面でみると課題は多い。 *7-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191204&ng=DGKKZO52929710T01C19A2EN2000 (日経新聞 2019.12.4) 厚生年金のあるべき資産構成 公的年金について、5年に1度の財政検証が行われた。これに伴い、厚生年金の運用資産構成の見直し、すなわちモデルポートフォリオの新たな検討が進んでいる。現在、厚生年金の運用資産総額は200兆円に達しつつある。公的年金の給付水準維持が現役世代の負担に依存するとはいえ、現時点で積み立てられた膨大な資産とその運用収益がクッションとなる。この意味で、資産運用の枠組みとしてのモデルポートフォリオは重要である。それにもかかわらず、モデルポートフォリオに関する議論が密室で行われているようだ。専門家にしか理解できない議論なのか。そうだとしても、素人からも意見がある。第1に、各資産の収益率に関して。今後の国内債の利率がほぼゼロであり、当面その上昇は期待薄だ。だとすれば、ポートフォリオでの国内債割合を低くし、その分を他の資産に移すべきだろう。第2に、資産を移管する先としての株式について。ひとつに、株式を国内と海外に分ける意味である。国内で元気な企業は、海外でも元気であり、利益の相当部分を外で稼いでいる。これは国内企業の海外化であり、株式を内外に分ける合理性を消滅させている。さらに、海外株の投資パフォーマンスが国内株を上回って久しい。海外経済の成長率が日本を上回っているためである。以上からすれば、内外の株式の区分をなくし、株式全体としての資産配分を考えるのが正しい。第3に、株式投資のベンチマークとしてのインデックスの再考である。国内株式について、上場区分とともに、インデックスの構成企業を見直そうとの議論が本格化する。これまで公的年金が信奉してきた東証株価指数(TOPIX)が絶対ではなくなった。第4に、50年、100年に一度のリスクへの対応である。公的年金のそもそもの目的は国民の安定的な老後生活にある。このことから、経済的な変動だけではなく、自然災害への目配りが必須となる。とくに、間近に迫っていると政府が注意喚起している南海トラフ大地震である。ポートフォリオの基本は分散投資である。大地震のリスクにさらされた日本に置くべき資産を調整するのは当然だろう。密室であってもいいが、以上に留意した議論を期待したいものだ。 <発生主義会計採用の必要性を示す重大な事例(その2)-固定資産> PS(2019/12/9追加):*8-1・*8-2のように、国や地方公共団体のインフラ老朽化が進んだとして、事故が起きてからあわてて維持・管理を議論し、予算の獲得合戦をし、原因を専門スタッフの不足・無駄な公共事業の削減・人口減などに結び付けて誤った“解決策”に導かないためには、固定資産台帳を整備して存在する固定資産は網羅的に取得価額・耐用年数・減価償却・修繕等の状況を把握し、物理的・金額的に管理しておく必要があった。しかし、地方公会計の統一基準が採用された地方公共団体の固定資産台帳でさえ、現在は整備済17.9%、整備中35.9%、未整備46.2%であり(新地方公会計統一基準の完全解説P51~93など参照)、国はもちろん未整備である。そして、漏れなく重複なく金額の重要性に応じて必要な維持管理を行うには、複式簿記による会計を行って資産・負債・引当金などを正確に把握していることが必要であり、民間企業は、皆そうしているのだ。そして、それらの正確な資料を基に、例えば上下水道・ごみ処理・道路・橋などのインフラの維持管理をどう効率化するか、広域化して地方公共団体が所有するか、民営化するか、どのくらい国の助成を求めるかなどを議論する必要があるわけだ。 なお、中央自動車道笹子トンネルで、ずさんな点検により老朽化を見落とし、天井板が崩落して9人が死亡した事故は、目視や音で老朽化の診断をしていたというので驚いた。医療に例えれば、年齢も考えず、顔色を見て聴診器で音を聞いただけで、検査はしなかったのと同じで、21世紀の維持管理や検査からはほど遠い。つまり、固定資産のメンテナンスは、鉄道会社や工場と同様、それを獲得した瞬間から効率的に行っておくべきものなのである。 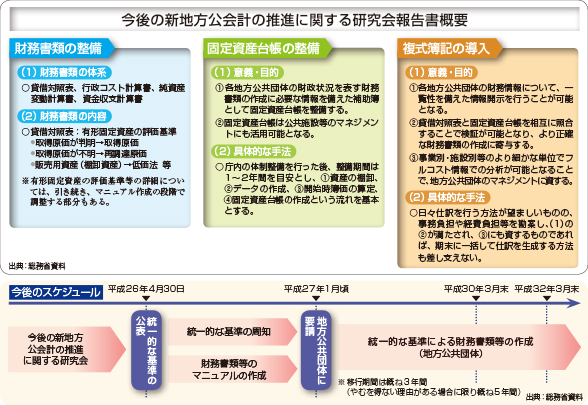 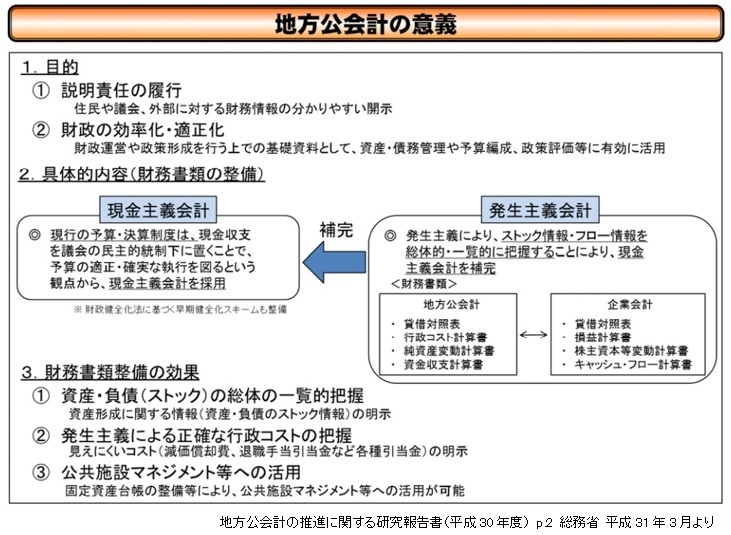 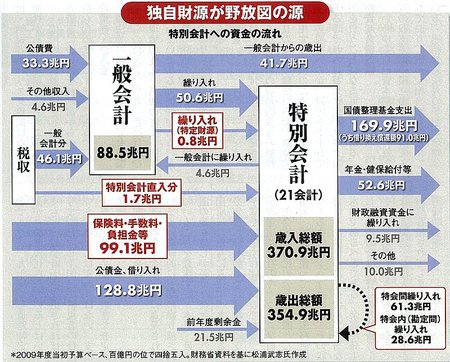 地方公会計の導入経緯 地方公会計の完成度 国の会計 (図の説明:左図のように、2020年3月末までに、統一基準による地方公会計が全国の地方公共団体で適用されるが、中央の図のように、複式簿記による発生主義会計は、単式簿記による現金主義会計の補完という位置づけだ。その理由は、日本国憲法及び財政法が、単式簿記による現金主義会計を前提としているからだそうで、これが計画性のない無駄遣いの原因になっている。しかし、膨大な資産・負債や収支を伴う国の会計基準は、右図のように、未だ単式簿記による現金主義会計のみであり、税金と保険料や収入と借入金などをごっちゃにしている状況だ) *8-1:https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190718-OYT1T50341/ (読売新聞 2019/7/19) 地方のインフラ 進む老朽化への対策急ぎたい 老朽化が進む地方のインフラ(社会基盤)をどのように維持・管理していくか。重い課題の克服へ有効策を探りたい。全国の道路や橋、トンネル、水道管などは高度成長期に集中的に整備された。このため、多くが一斉に耐用年数を迎えつつある。地方自治体は人口減などで財政が厳しく、更新や補修に十分対応できていない。自民党は参院選の公約で、防災や減災のための「国土強靱きょうじん化」を掲げる。ただ、老朽化への対応策は具体性を欠く。立憲民主党や国民民主党は、地方インフラの維持に言及していない。喫緊の問題で論戦が低調なのは残念だ。2012年に起きた中央自動車道・笹子トンネルの天井板崩落事故を受け、国と自治体はインフラの点検を強化している。読売新聞が今年、国と自治体に行った調査では、点検で損傷度合いが最も深刻だと判定された580か所のうち、4割近くで修繕や撤去の見通しが立っていない。大きな事故が起きてからでは遅い。優先順位を付け、効率的に改修したい。損傷前にこまめに補修する「予防保全」が有効となる。ドローンなどの先端技術による点検の省力化も進めるべきだ。水道管は、総延長の約15%が40年の耐用年数を過ぎている。多額の更新費用が重荷となる。現状でも、水道事業の経営は危機的だ。全国の公営上水道事業は、約3割が赤字である。さらに人口が減れば収益は先細りとなる。水道法改正で、今秋から運営権を民間に売却する「コンセッション方式」が導入しやすくなる。民間ノウハウを活用して効率化を図る狙いだが、安全面の不安などを理由に自治体は消極的だ。利用者の理解なしには実施できまい。事態を打開する方策として、公営事業の広域連携がある。給水人口の少ない公営事業者が、施設の共有や工事の一括発注などを進めれば、経費を削減できる。積極的に取り組んでもらいたい。すでにゴミ処理や消防、公立病院の再編などで広域化の動きが広がっている。利害を調整しつつ、共助の動きを広げるには、都道府県の役割が重要になる。人口減少への対策では、中心部に都市機能を集約する「コンパクトシティー」の推進も有力な選択肢といえる。住居や商業施設などに加え、公共施設などのインフラも集中させることで、行政のコストを抑えることができる。各地方の実情に合わせ、具体策を練り上げる必要がある。 *8-2:https://www.sankei.com/west/news/170710/wst1707100006-n1.html (産経新聞 2017.7.10) 迫りくる崩壊(1)老朽化「いずれ橋は落ちる」20年後、7割が建設50年超 高度経済成長期に整備が進んだインフラが老朽化している。人命に関わるこの危機に国や自治体などがどう立ち向かおうとしているのか、その現状を探る。1967(昭和42)年12月、米国のウェストバージニア州とオハイオ州を結ぶ吊り橋「シルバー橋」が突然崩壊し、46人が犠牲となった。約40年前に建設されたこの橋は補修や点検が十分に行われず、老朽化に伴う金属疲労が進んだことが原因だった。日本より30年早く1920~30年代に急速に道路や橋の整備が進んだ米国。しかし、十分な維持管理費が投入されなかった結果、耐用年数の目安とされる50年が経過した80年代には道路や橋の老朽化によって事故が相次ぐようになる。「荒廃するアメリカ」といわれ、社会問題になった。「米国再興のためインフラ整備に1兆ドル(約113兆円)を投じる」。昨年の大統領選では、そんな公約を掲げたドナルド・トランプ氏が当選を果たした。 ■ ■ ■ 日本でも平成24(2012)年12月、恐れていた事故が起きた。山梨県の中央自動車道笹子(ささご)トンネルで、ずさんな点検によって老朽化を見落とした結果、約140メートルにわたって天井板が崩落。車3台が下敷きとなり、9人が死亡した。米国での事故と日本での惨事。国土交通省の徳山日出男・道路局長(26年当時)は部下にこう檄を飛ばした。「いずれ必ず橋も落ちる。住民が巻き込まれて自分が刑事被告人になったつもりで書け」。26年4月、国交省の社会資本整備審議会道路分科会で「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」がとりまとめられた。「最後の警告-今すぐ本格的なメンテナンスに舵(かじ)を切れ」との副題がついたこの提言の前文にはこうある。「今や、危機のレベルは高進し、危険水域に達している。ある日突然、橋が落ち、犠牲者が発生し、経済社会が大きな打撃を受ける…そのような事態はいつ起こっても不思議ではない」。戦後から高度成長期にかけて多くの整備が進んだ道路や橋、トンネル、上下水道。それらのインフラが耐用年数の目安である50年を経過しつつある今、かつて米国で起きた落橋事故も現実味を帯びる。もし、同様の重大事故が発生すれば一体誰が責任を負うのか。 ■ ■ ■ 笹子トンネルの事故では、責任追及の矛先は道路を管理する中日本高速道路と子会社に向けられた。犠牲者9人のうち20代の男女5人の遺族らが原告となった訴訟では、横浜地裁が「目視だけの点検を選択した過失があった」として会社側の過失を認め、総額4億4千万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した。この事故では高速道路会社が責任を負ったが、国道や都道府県道、市町村道などの道路や、それらにかかる橋の場合、管理者の国や自治体が責任を負うことになる。 ■ ■ ■ 危機感を募らせた国交省は、26年から自治体などに対し5年に1度の定期点検を義務づけた。その結果、28年3月までに点検を終えたもののうちトンネルの46%、橋の12%で修繕が必要と判断された。建設50年を超える割合は、今から20年後にはトンネルが57%、橋が71%にまで達する。昭和45年の大阪万博前後にインフラ整備が進んだ近畿地方でも今から20年後には橋の約7割(約4万4千橋)が建設50年を超えるが、全国の橋の7割以上を管理する市町村では慢性的な財政難に陥っている。同省が平成28年、全国の自治体に現在の予算規模で修繕が可能か尋ねたところ、約6割の市町村が「不可能」と答えた。さらに、人口減に伴う技術者不足が追い打ちをかける。同省の調査では、市町村の土木部門の職員数は8年度から25年度までに約3割減少。特に道路の維持・管理業務を担当する職員が「5人以下」の市は全体の約2割、村では9割以上にも及んでいる。「このままでは対応しきれない」。衝撃的な数字に同省幹部らは頭を抱えた。 <発生主義会計採用の必要性を示す重大な事例(その3)-原発> PS(2019/12/10、12追加):*9-1のように、原発の本当のコストは、電力会社が支払う建設費のほかに、フクイチ事故後の損害賠償・廃炉・除染等の費用を国が支えて国民負担になっているが、一般企業の場合は、汚染物質は外に出さず、外に出したらその企業が回収するのが原則だ。さらに、汚染土の放射能濃度が8千ベクレル/kg以下なら公共事業の盛り土などに使えるようにするというのも、該当する地域の住民を犠牲にする行為だ。また、原発立地地域には、電源三法交付金制度(1974年制定:電源開発促進税法・電源開発促進対策特別会計法・発電用施設周辺地域整備法、https://www.fepc.or.jp/nuclear/chiiki/nuclear/seido/index.html)により、国民から集められた資金が政府から約3500億円(2015年のケース)配賦されており、使用済核燃料の保管場所も未だ決まっていないが、いずれも国民負担になるものだ。なお、これらは、本来は発生主義で費用を認識し、負債性引当金を積んでおかなければならないものである。 一方、*9-2のように、2020年に「パリ協定」の本格始動を控える中、日本はCO₂を排出する石炭火力発電所の建設計画が10基以上あり、開発途上国に石炭火力発電所の輸出も行っているため、「化石賞」を贈られる事態となっている。しかし、「化石燃料を燃やす代わりに原発にする」というのは、海水温の上昇を促進させる上、原発事故による深刻な環境汚染とも隣り合わせであるため、薦められないわけだ。 そのため、環境問題解決のためのエネルギー革命期を迎えている現在、*9-4のノーベル化学賞受賞者の吉野さんが記念講演で述べられたとおり、再生可能エネルギーと電池がエネルギー革命の中心になることは明らかだ。日本は、化石燃料もウランも乏しい国だが、再生可能エネルギーは豊富で、これに電気自動車を組み合わせれば、環境・経済・利便性・エネルギー自給率の向上という要件をすべて満たして発展することが可能で、いずれも日本発の技術なのである。 なお、水素はロケット燃料として使われているエネルギーで、再生可能エネルギー由来の電力で水を電気分解すればCO₂を出さずにいくらでもできるので、*9-3のように、「①川崎重工が世界初の液化水素運搬船の進水式を実施し」「②オーストラリアで採った安価な石炭から水素をつくって日本に輸入する予定で」「③JXTGホールディングスはLPGを原料に水素を生産してFCV向けに水素を供給している」「④水素で発電するよりLNGや石炭で発電した方がコストが安い」などと言っているのには呆れる。何故なら、日本は水と再生可能エネルギーは豊富な国で、海の水を電気分解すれば水素・酸素・塩が同時にでき、その時にCO₂その他の排気ガスは全く出さず、液化水素運搬船は水素の輸出用に使った方がよいくらいだからだ。なお、水素による燃料電池も、自動車だけでなく航空機・船舶・列車等々に応用可能な日本発の技術である。 .jpg) 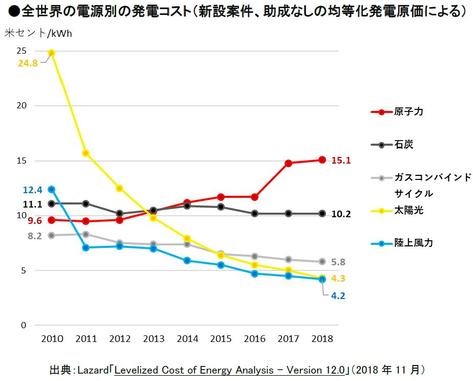  (図の説明:左図のように、2017年の日本のエネルギー自給率は7.4%で、他の先進国と比較して著しく低い。また、中央の図のように、世界の発電コストは、2018年には原子力が最も高く、風力・太陽光が安くなっている。このほか、日本は、右図のような地熱も豊富だ) *9-1:https://digital.asahi.com/articles/ASM1L4W0PM1LULFA013.html (朝日新聞 2019年1月23日) 原発の本当のコストは? 経産省の「安い」試算に異論 ●エネルギーを語ろう 日立製作所が英国での原発計画を凍結したことは、原発がもはや安い電源と言えなくなった現実を私たちに突きつけました。原発や事故処理のコストをどう考えたらいいのでしょうか。電力のコスト分析に詳しい大島堅一・龍谷大教授に聞きました。 ●経産省のコスト試算「甘すぎ」 ―経済産業省が2015年に示した2030年時点の発電コスト(1キロワット時)で、原発は10・3円となっていて、天然ガス火力(13・4円)や石炭火力(12・9円)より安く試算されていました。 「原発の建設費の想定が甘すぎます。福島の事故以前に建設されたような原発を建てるという想定で建設費を1基4400億円とし、そこに600億円の追加的安全対策を加算するというものです。設計段階で安全性の高い原発を想定しないという非常に奇妙な試算です」 ―試算に使われた事故の発生確率にも疑問を呈していますね。 「経産省の試算では、追加的な安全対策を施すので、(福島第一原発のような)『過酷事故』が起きる発生確率は半分になるとしています。素朴な疑問ですが、なぜ、半分になるのでしょうか?」 ●原発建設費 2基で3・5兆円も ―原発の建設費は世界的にみても高騰しています。 「英国で計画中の『ヒンクリーポイントC原発』(160万キロワット級×2基)の建設費245億ポンド(欧州委員会の14年の想定。直近の為替レートで日本円に換算すると約3・5兆円)です。それが大事なファクトです。メルトダウンした核燃料を受け止めるための『コアキャッチャー』や、大型航空機の衝突に耐える二重構造の格納容器など、安全性能を高めたためです。経産省の試算のように安くできるはずがありません」 ―こうした状況を踏まえた場合、原発の発電コストはいくらになるのですか? 「私は、原発の1キロワット時あたりの発電コストは17・6円になると試算しています。米電力大手エクセロンの経営幹部は昨年4月、『新しい原発は米国内では高くてもう建てられない』と発言しています。日立製作所も想定した収益が見込めないとして、英原発輸出計画を凍結しました。そんな現実からしても17・6円は外れていないと思います。もはや原発にコスト競争力はありません。斜陽産業として、いかに『たたむか』を考える時です」 ●重い国民負担 東電の責任は ―福島第一原発事故後、当時の民主党政権は東京電力を潰さずに国有化し、損害賠償の支払いなどを国が支える枠組みをつくりました。この枠組みをどうみますか? 「残念なのは、東電の責任について議論を尽くさず、あいまいにしてしまったことです。それで国がずるずると事故費用を出す形になり、結果的に国民負担を大きくしています。環境汚染の費用は汚染者が負担する『汚染者負担原則』がありますが、それから逸脱しており、大問題だと思います」 ―損害賠償に加え、廃炉や除染などの費用が膨らんだ結果、事故費用の総額が21・5兆円に倍増したとして、経産省は16年に新たな負担の割り振り策をまとめました。 「これも大問題です。経産省は賠償費用の新たな増大分についても電気料金から払うことにしました。福島の事故以前に電気料金の中にその費用を組み込んでいなかったので、国民にはそのツケがある、という理屈ですが、それは違います。東電のツケですよ。もしJRが事故を起こしたら、国民にツケがあるといって運賃から事故費用を徴収しますか?」 ―廃炉費用は東電の送電部門の合理化益を充てる、除染費用は東電株の将来の売却益を充てる、ということになりました。 「これもおかしな仕組みです。(電力会社がコストを電気料金に上乗せする)『総括原価方式』の理念からすれば、仮に送電部門で合理化益が出たら、料金を下げるべきです。除染費用でアテにする東電株の売却益も、元々は国費を使っているので、売却益が出たら国庫に戻すべきです」 ―では、どのように事故費用を捻出すればいいのでしょうか。 「『汚染者負担』が原則ですが、もしそれでは対応できないということなら、国会で東電の責任問題をしっかり議論し、『国にも責任があった』と見える形にして、税金でまかなうという判断はあってもいいと私は考えます。しかし今の負担の割り振り策では、事故費用を電気料金から、『こっそり』取るようなやり方だと言わざるを得ません」 ●実態に合ってない「復興」 ―一方、政府は放射能濃度が1キロあたり8千ベクレル以下となった汚染土を公共事業の盛り土などに使えるようにしました。 「汚染土の最終処分の量を減らしたいからでしょう。それは、ひいては東電の費用負担を減らすことになります。さらに新たな除染を国の公共事業とみなす措置もできました。これも東電が支払うべき費用を軽くしているのです」 ―政府が進めている避難者の帰還政策をどう見ていますか。 「避難指示の解除を受けて避難者が帰ったかというと、実際には様々な理由で帰れない方が多いのです。でも解除したので賠償は打ち切ります、と。実態に合っていないのです。復興の実態が伴っていないのに『問題はもうなくなりました』とされてしまうことを私は恐れています」 ◇ 大島 堅一(おおしま・けんいち)龍谷大学教授(環境経済学)。1967年福井県生まれ。一橋大大学院経済学研究科博士課程単位取得。著書に「原発のコスト」(岩波新書)、共著に『原発事故の被害と補償』(大月書店)など。脱原発社会に向けた政策提案を続けるシンクタンク「原子力市民委員会」の座長も務める。 *9-2:https://www.fnn.jp/posts/00049284HDK/202001311454_reporter_HDK (FNN PRIME 2019年12月6日) 「地球は大幅に温暖化」の衝撃報告書!日本は“批判の的”…小泉大臣は何を語る?COP25開幕 ・「パリ協定」の本格始動を2020年に控える中、「COP25」開幕 ・各国の削減目標では大幅な気温上昇は不可避 ・石炭火力推進の日本は批判の的…積極的な発信ができるか ●「大幅な気温上昇不可避」報告書 国連事務総長は危機感あらわ 地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」が12月2日からスペイン・マドリードで開幕した。 △国連 グテーレス事務総長;今のままの努力では不十分なのは明らかだ 国連の事務総長は、開幕を前にした記者会見で各国に対し、温室効果ガスの削減目標を引き上げるなど対策の強化を表明するよう求めた。この発言のもととなったのは、COP25開幕前に公表された、国連環境計画(UNEP)の衝撃的な報告書。各国が、パリ協定で目標として現在提出している温室効果ガスの排出削減量を達成したとしても、『世界の気温は産業革命前から3.2度上昇する』というのだ。つまり現在の各国の削減目標では、大幅な気温上昇は避けられない危機的な事態だという。仮に、気温を1.5度上昇に抑えるためには、現在年1.5%ほど増えている排出量を、毎年7.6%減らす必要があると分析している。パリ協定では各国に対し、2020年2月までに、現在提出している削減目標を引き上げたうえでの再提出、もしくは更新することを求めている。一方で、数値目標の引き上げも再提出も義務ではなく、求められているだけという状況がある。そのためグテーレス事務総長は、COP25の会合のなかで、各国が温室効果ガスの削減目標の引き上げを表明することで、気候変動問題の機運を世界全体で高めていくことを求めているのである。 ●”日本は温暖化対策に消極的”国際的な批判も・・・ では、日本はどうなのか。国連環境計画の報告書では、各国の取り組みに対しても言及していて、日本についての記述もある。「石炭火力発電所の建設を中止するほか、再生可能エネルギーを利用することで石油の利用を段階的にやめていくこと」。日本では、二酸化炭素を排出する石炭火力発電所の建設計画が現在も10基以上ある。そのうえ、途上国へ石炭火力発電所の輸出を行っていることで、国際的な批判を受けている。しかし、梶山経済産業大臣はCOP25が開幕した後の12月3日の会見でこう述べた。 △梶山経済産業大臣;石炭火力発電など、化石燃料の発電所は選択肢として残していきたい 国際的な環境NGOのグループは、温暖化対策に消極的だと判断した国や地域に、皮肉をこめて「化石賞」を贈っている。梶山大臣の発言を受けて、早速 日本は12月3日、COPの会場内で「化石賞」を贈られる事態となってしまった。 ●日本の発信に世界が注目 ギリギリの調整続く 日本は、国際的な批判をどのように巻き返せるのか。「気候変動問題は、クールでセクシーに取り組むべきだ」と発言して、国内外から注目された小泉進次郎環境大臣もCOP25に出席する。そして、11日には閣僚級会合でスピーチを行う予定だ。ここで日本の石炭火力発電所に対する姿勢、そして数値を引き上げたうえでの削減目標の再提出について言及があるのか、世界は注目している。小泉大臣はこれまで、会見で「数値目標の引き上げは検討していきたい」としながらも、「関係機関の調整があるので、数値の引き上げ以外の方法も考えたい」とも話している。11日のスピーチについても、石炭火力発電についても言及する方向で調整しているが、どこまで発言できるのか。政府内の調整がギリギリまで行われているのが現状だ。2020年からパリ協定が本格的に始まるのを前に、アメリカは正式に離脱を通告。世界的な機運に水を差しかねない状況の中、気候変動問題で日本が孤立しないためにも、今回のCOP25で積極的な発信・行動力を求めたい。 *9-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191212&ng=DGKKZO53243570R11C19A2TJ2000 (日経新聞 2019.12.12) 川重、世界初の水素運搬船 進水 来秋に完成 豪で液化し日本に 川崎重工業は11日、世界初となる液化水素運搬船の進水式を実施した。2020年秋に完成させる。同社は丸紅やJパワー、英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルなどと組み、オーストラリアで採った安価な石炭から水素をつくり、日本に輸出するプロジェクトに取り組んでいる。今回の運搬船を使い、オーストラリアで生産した水素を日本に運ぶ実証を20年度に始める。11日、川重の神戸工場(神戸市)で行われた進水式にはリチャード・コート駐日オーストラリア大使や、トヨタの内山田竹志会長らの関係者を含め計4千人程度が出席。「すいそ ふろんてぃあ」号と名付けられた全長116メートルの運搬船は今後、水素を格納するタンクなどをつける。水素はセ氏マイナス253度まで冷して液化すれば体積を800分の1に圧縮でき、大量に輸送できる。水素はこれまでロケットの推進燃料などとして使われてきたが、用途は広がっている。トヨタ自動車は10月に水素を使う燃料電池車(FCV)「ミライ」の新モデルを公開。国内石油元売り最大手のJXTGホールディングスは横浜市の拠点で液化石油ガス(LPG)を原料に水素を生産。全国41カ所のステーションでFCV向けに水素を供給している。調査会社の富士経済は、30年度の水素関連市場は18年度比50倍以上の4085億円に膨らむと試算。燃焼時に二酸化炭素(CO2)を排出しない水素は、低炭素社会を実現する切り札として期待が高まっている。中東情勢が緊迫化する中、化石燃料に依存するリスクが浮き彫りになっていることも背景にある。課題はコストだ。現状では水素で発電するよりも、液化天然ガス(LNG)や石炭で発電した方が大幅に安い。LNGと同じくらいのコスト競争力を実現するには、国際的な供給網(サプライチェーン)の確立と大量輸送の実現がカギを握る。川重は30年ごろの商用化を目指し、大型船の開発も進める方針だ。 *9-4:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53100260Y9A201C1I00000/ (日経新聞 2019/12/8) ノーベル賞吉野彰さん講演 「電池がエネ革命の中心に」 ノーベル化学賞を受賞する吉野彰・旭化成名誉フェローは8日午前(日本時間8日夜)、ストックホルム大学で記念講演した。授賞理由となったリチウムイオン電池の開発経緯や展望を紹介。環境問題解決のためのエネルギー革命の時代を迎えていると説明し、「リチウムイオン電池がその中心になる」と話した。記念講演は「ノーベルレクチャー」と呼び、10日夕に開く授賞式の関連行事になっている。吉野氏は「リチウムイオン電池の開発経緯とこれから」というタイトルで、化学賞を同時に受賞する3氏の中で最後に講演した。吉野氏は、過去の発火の危険を調べる実験の映像などを映し出しながら、「電極に炭素を使う実験がうまくいき、安全な電池として市場に出せると確信した」と語った。リチウムイオン電池は環境問題の解決に重要な役割を果たすとし「特に電気自動車が世界の市場を大きく変えていく」と力を込めた。「環境、経済、利便性が同じように発展していくことが重要だ」と訴え、電気自動車や人工知能(AI)が人々の生活を支える未来社会の映像を流した。「これからのエネルギー革命にリチウムイオン電池が中心的な役割を果たす」という言葉で講演を締めくくると、会場からは大きな拍手が起こった。終了後にはノーベル化学賞を受賞する3氏が壇上に並び、会場からの祝福に応えた。
| 日本国憲法::2019.3~ | 09:45 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,11,04, Monday
    2019.10.31TBS 札幌のマラソンコース 大通り公園 (図の説明:1番左の番組を始め、全国版のメディアでもマラソン・競歩の札幌移転を批判する声が多かったが、それは東京人の目線にすぎない。左から2番目は札幌のマラソンコースで、右の2つは大通り公園だが、大通り公園は美しい道路だ。2020年のYOSAKOIソーラン祭りのチーム等が、街にくり出てオリンピックの閉会式に花を添えると、翌年からその地域への観光客や祭りへの海外チーム参加が増えそうだ)     時計台 北海道大学 北海道庁 (単調と言われている)新川通 (図の説明:それぞれの場所で塗り替えしたり、植栽を充実したりして手を入れれば、東京とは違った美しさが見られるだろう)          (図の説明:上の段の左の3つは、YOSAKOIソーラン祭りチーム、下の段の左の4つは、徳島の阿波踊りチーム、一番右の上下は沖縄エイサー祭りチームだが、他地域の祭りの友情出演があればさらに華やかになり、日本の民族衣装と踊りが外国人に喜ばれると思う) (1)マラソン、競歩の開催地移転への批判について 2020年東京オリンピックのマラソン、競歩を東京から札幌に移して開催することを国際オリンピック委員会(IOC)が決定した時、私は意外な気がしたが、尤もだと思った。 その後、メディアは、*1のように、「出発時刻を早めたり、ミストを出すベンチを備えたり、遮熱性舗装をしたりして努力したのに・・」「IOCは強権だ」「不平等条約だ」等の批判をしていたが、弥縫策の「対策したふり」では間に合わないような猛暑になる可能性も大きかったため、この批判は当たらない。それよりも、「オリンピックの開催都市になるためのプレゼンテーションで『日本は温暖な気候だ』と言っていたのは虚偽だった」と言われそうである。 (2)遮熱性舗装について 表面に遮熱財を塗布して赤外線を反射させ路面温度の上昇を抑える遮熱性舗装は、*2のように、人が立つ高さでは逆にアスファルト舗装より気温や紫外線が高くなるという研究結果がまとまったそうだ。しかし、“遮熱性舗装”の仕組みについて考えればわかることだが、遮熱性舗装をしたからといって熱エネルギーがなくなるわけではなく、アスファルトに吸収されずに反射されるだけなので、この結果は当然なのである。 このことについて、樫村東京農業大教授(運動生理学・環境生理学)の研究チームは、「路面温度はアスファルトより約10度低かったが、高さ50センチ、150センチ、200センチではいずれもアスファルトより遮熱性舗装の方が高く、遮熱性舗装は熱中症のリスクを高める」と日本スポーツ健康科学学会で2019年8月30日に発表されたそうだ。 国土交通省や東京都の担当者は、東京でのマラソンや競歩を可能にするため結果を矮小に評価し、日本独特の根性論で切り抜けようとしていないだろうか? それよりも、アスファルトやコンクリートで覆われた地面を減らし、緑地を増やして、本当に過ごしやすくて豪雨に強い街を作るべきである。 (3)札幌のオリンピック、マラソンコースについて 札幌のマラソンコースについては、新川通(北区、手稲区)が日陰が少なく単調だというクレームが多かったため、*3のように、新川通を他の地区に変更する方向で検討しているそうだが、私は、北海道の大自然が放映されるのもよいと考える。 日陰の少なさは中央分離帯や両側に大きな並木(白樺・イチョウ・桜など)を植樹し、単調さは低層に3kmづつ異なる花(この時期に咲く花)を植えれば、市街地にはない北海道らしい自然の美しさが見られる。大自然に比べればおもちゃのようなビルやテレビ塔のある景色が一番よいと感じるのは、都会のコンクリートの中で育った人の感受性にすぎない。 なお、オリンピックのマラソンで大きな高低差を許されるのなら、大通り公園から40km以内に支笏湖や中山峠が入るので、中山峠付近を出発点として下りながら札幌市内の大通り公園を目指すのも美しいコースになるだろう。 ・・参考資料・・ *1:https://digital.asahi.com/articles/ASMB00GWXMBZUTQP01S.html (朝日新聞 2019年11月1日) マラソン騒動で見えたIOCの強権ぶり「不平等条約だ」 2020年東京五輪のマラソン、競歩の開催地を東京から札幌に移す国際オリンピック委員会(IOC)の案について話し合うIOC、東京都、大会組織委員会、国の4者によるトップ会談が1日正午、都内で始まった。 ●マラソン札幌開催が正式決定 小池知事「合意なき決定」 開催都市・東京の小池百合子知事は移転に反対してきたが、この会議の冒頭で「IOCの下した決定を妨げることはしない。合意なき決定だ」と述べた。なぜ「合意なき決定」ができたのか。組織委幹部はささやく。「都や組織委は、不平等条約を結ばされているようなものだから」。日本側が嘆くのは、東京都や組織委などがIOCと結ぶ「開催都市契約」だ。いったいどのような内容なのだろうか。「IOCは、オリンピック・ムーブメントの最高の権威で、五輪はIOCの独占的な財産である」。序文で、IOCの立場が明確に宣言されている。別の大会関係者は、こう解説する。「東京都は自らの意思で立候補して大会の開催場所をIOCに提供した立場。組織委はIOCの意向で動く手足で、いわばイベント屋だ」。組織委自体も、開催都市契約に基づいて設立された。1日に最終日を迎えた調整委員会は準備状況を確認し、話し合う場だが、意見が対立した場合の最終決定権は日本側にない。それを示す条文がある。「調整委が解決できない問題がある場合、あるいは、調整委の勧告に従って行動することをいずれかの当事者が拒否した場合、IOCが最終的な決定を行う」。さらに、こんな記述もある。「IOCは指針およびその他の指示を修正し、かつ新たに出す権利を留保する。開催都市(東京都)、NOC(日本オリンピック委員会=JOC)、及びOCOG(組織委)は、これらの修正、および新しい指針および指示の全てに対応するものとする」。今回の例に当てはめると、契約上、東京都も組織委も「マラソン、競歩の札幌開催」というIOCの「指示」に逆らえない。IOCが「決定事項」と強気だったのは、こうした裏付けがあるからこそだ。組織委や都も、IOCの要求を無条件にのんできたわけではない。経費を抑えるために、立候補ファイルにあった競技会場の新設を一部取りやめ、既存会場を利用することにした。それでも、IOCや国際競技団体を説得するのに、1年以上の時間を要した。マラソンの暑さ対策も、昨夏から深夜の開催などを模索していたが、IOCから「テレビ映りが悪い」などの理由で、却下された経緯がある。組織委幹部は「五輪開催に興味のある都市は、どう思うだろうか。開催都市とIOCの関係は、考え直すべき時が来ているのでは」と言う。契約の内容は過去大会を踏襲し、今回が特別というわけではない。IOCに強い権限を定める「五輪憲章」に沿い、その順守を求める内容になっている。五輪憲章には「IOCは五輪開催都市契約が定める拠出金のほかは、それと異なる内容の合意が書面でなされていない限り、大会の組織運営と財政、開催について財政的な責任を負うことはない」との文言もある。契約はIOC総会で開催都市に決まった直後に結ぶことになっており、東京の場合、13年9月に東京都、JOC、IOCの3者の間で結ばれた。組織委も14年に契約を結んでいる。契約内容は当初は非公開だったが、17年5月に公表された。組織委の公式サイト(https://tokyo2020.org/jp/news/notice/20170509-01.html別ウインドウで開きます)などから確認できる。 ●IOCの権限が強い開催都市契約 五輪憲章に基づき、IOCは、オリンピック・ムーブメントの最高の権威であって、これを主導し、また、オリンピック競技大会は、IOCの独占的な財産であって、IOCはこれに関するすべての権利とデータ(特に、組織、運営、利用、放送、記録、表現、複製、アクセス、流布に関する、あらゆる形態、手法またはメカニズムのすべての権利であるが、これらには限定されるわけではない)を、既存のものか将来開発されるものかを問わず、全世界を通して永続的にこれを所有する(序文)。遅くともIOCが選手村の開村を求める公式日から本大会終了までの間、開催都市および本大会におけるイベントを開催する他の都市全体におけるすべての会場の出入り口と大通りを、オリンピックシンボルおよびその他のオリンピック関係の言葉とイメージで装飾する(第22条)。IOCは、オリンピック憲章に基づき、また、IOCがその単独の裁量にて本大会にとって最も利益になると考えた場合、いかなる時でも、競技、種別および種目に変更を加える権利を留保する。上記第6条(略)の規定に基づき、組織委は、本大会プログラムに関する競技、種別および種目の追加および/または削除を含め、これらの変更についての全費用を負担するものとする(第33条)。メダルおよび記念メダルを含めたすべてのメダルと賞状は、厳格な監督の下、またIOCの書面による事前承認を得た上で、制作し、配布されるものとする(第40条) *2:https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201908260000658.html (日刊スポーツ 2019年8月27日) 五輪マラソン、猛暑対策の「遮熱性舗装」は逆効果 路面温度の上昇を抑える効果があるとして、東京オリンピック(五輪)の猛暑対策に国や都が導入を進めている「遮熱性舗装」が、人が立つ高さでは逆にアスファルト舗装より気温や紫外線が高くなるという研究結果がまとまった。樫村修生東京農業大教授(運動生理学・環境生理学)の研究チームが30日の日本スポーツ健康科学学会で発表する。樫村教授は「遮熱性舗装は熱中症のリスクを高める」としている。 ◇ ◇ ◇ 16年8月31日、東京・青山通りの実験コースを試走した瀬古利彦さんが「明らかに涼しい」と太鼓判を押し、導入が決まった遮熱性舗装が、猛暑対策としては逆効果になるという研究がまとまった。樫村教授らは五輪開催期間(7月24日~8月9日)に重なる今年7月26日、路面、50センチ、150センチ、200センチの高さで気温、紫外線強度などを計測した。路面温度はアスファルトより約10度低かったが、高さ50センチ、150センチ、200センチではいずれもアスファルトより遮熱性舗装の方が高かった。7月26日は暑さ指数28~31度だった。暑さ指数31度以上と条件が厳しかった8月8日の計測では、遮熱性舗装はアスファルトより最大で4度高かった。「日射が強くなればなるほど遮熱性舗装の方が高くなります」(樫村教授)。五輪の暑さ対策として遮熱性舗装の研究を進めていた国は15年7月15日~9月27日に検証実験をしている。75日間の平均で、高さ50センチでは遮熱性舗装の方が0・2度低く、150センチでは0・1度高かったが、「有意差はない」としていた。樫村教授は「五輪期間中は暑さ指数が30度を超えます。平均値ではなく、暑さ指数が高いときはどうなるのかを計測しないといけない」と指摘する。樫村教授らの計測では、高さ50センチが最もアスファルトとの差が大きかった。「小さな子ども、ベビーカーに乗った赤ちゃん、車いすの人が特に影響を受けるということです。もうひとつのリスクは紫外線で、遮熱性舗装ははね返りが大きく、アスファルトの4倍以上です。傘をさしても紫外線は防げない。熱中症のリスクを高めるだけではなく、目や肌への障害も高めます」。樫村教授は<1>遮熱性舗装は路面温度を下げる<2>夜間の放射熱を軽減し、熱帯夜を少なくすることは認める。しかし、問題は晴れた日の強い日射だ。7月24日~8月9日の気象データでは、晴れが75%。「4日に3日は晴れるんです」。マラソンコースは道路延長20・2キロ(都道・区道14・6キロ、国道5・6キロ)。都道・区道は75%、国道は52%、遮熱性舗装工事が終了している。 ◆遮熱性舗装 表面に遮熱財を塗布し、赤外線を反射させて路面温度の上昇を抑える舗装。もともと屋根など建築に用いられていたが、ヒートアイランド対策として02年、道路舗装に使われるようになった。東京五輪の猛暑対策として「アスリート・観客にやさしい道の検討会」が16年、導入を提言した。 ◆暑さ指数 <1>気温<2>湿度<3>日射・地面や建物からの放射熱から算出する。25~28度が「警戒」、28~31度が「厳重警戒」、31度以上が「危険」で、日本スポーツ協会は31度以上では「運動は原則禁止」、28~31度では「激しい運動は中止」と定めている。気温に単純換算できないが、日本スポーツ協会では気温31度以上が「厳重警戒」、気温35度以上が「危険」。 〇…国土交通省と東京都の担当者は今月20日、樫村教授を訪ねた。「おうかがいし、データを見せていただきました」(国交省道路局・武藤聡沿道環境専門官)。武藤氏は「ひとつの研究成果だと思います」と話しながらも「我々もさまざまな実験、シミュレーションをしています。これまで遮熱性舗装の方が特別高くなるという結果は出ていません」として、暑さ指数31度以上など悪条件下での計測は「今のところ特に考えていない」としている。 *3:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/361315 (北海道新聞 2019/11/4) 五輪マラソンコース、新川通の変更検討 日陰少なく単調 札幌での移転開催が正式に決まった2020年東京五輪のマラソンを巡り、大会組織委員会がベースとしている北海道マラソンのコースから、新川通(北区、手稲区)について他の地区に変更する方向で検討していることが3日、関係者の話で分かった。新川通は日陰が少なく、選手らの暑さ対策に課題が残ることなどが主な理由。組織委は詳細について今後詰めの作業を急ぐ方針。東京五輪マラソンのベースとされる北海道マラソンのコースのうち、新川通は高低差が少ない直線で、18・5~31・5キロ地点の往復13キロある。ただ、日陰や目標となる建物が少なく、選手らが直射日光を長く浴びるリスクがあり、直線で景色の変化に乏しい。ランナーの間では「精神力が問われる」と言われ、北海道マラソンの難所になっている。関係者によると1日のマラソンの札幌移転決定を受け、組織委の担当者らが3日道内入り、札幌市内を訪れてコースの検討のために現地視察を行ったという。 猛勉強しているため、ブログの記載をしばらく休みます。 資料持ち込み可だったため、何とか90点以上とれました(2019年11月9日)。 <日本は長所を活かして頑張らないと> PS(2019/11/11追加):*4-1のように、大会組織委の武藤事務総長が、男女マラソンコースの発着点候補になっている大通公園は、「重要な夏のイベントが同時期にあり、調整が課題」とされたそうだが、オリンピックも世界に向けて発信できる重要なイベントであるため、これまでのイベントをオリンピック終了後に行えば、オリンピック関係者も続きに楽しめてよいだろう。 また、*4-2のように、道議会全会派のうち自民会派のみが新庁舎での喫煙所の設置を決めており、北海道医師会の長瀬会長が、来年1月に完成予定の新しい道議会庁舎を完全禁煙とするよう自民党道連の吉川会長に要望されたそうだが、自民党は、男性中心でかつ煙草栽培農家やたばこ販売組合の応援を受けているため、煙草に甘いのである。 なお、日本はインフレ政策(→賃金上昇)・貿易黒字による円高・頑張らない方向への改革により、加工貿易の比較優位性が新興国より低くなっているため、*4-3のように、貿易収支が赤字に転じ、この傾向は今後も続くだろう。そのため、国内消費や旅行収支は重要なのであり、これまでの蓄積を生かし発展させて、アジアの奥座敷としての地位を獲得する必要がある。 *4-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363115?rct=s_tokyo2020_marathon (北海道新聞 2019/11/9) 発着点3案「それぞれ課題」 組織委が視察 五輪マラソン 東京五輪マラソン・競歩の札幌開催に向け、大会組織委の武藤敏郎事務総長は8日、札幌市を訪れ、男女マラソンコースの発着点として組織委が検討する市内3カ所を視察した。武藤氏は「発着点は早期に決めなくてはならない。12月初旬の国際オリンピック委員会(IOC)理事会に向け実務者会議で協議したい」「施設整備や運営は簡素化、効率化を図る」と述べた。会場(発着点)は北海道マラソンの発着点である大通公園(中央区)が最有力とされる。同日に市と道、組織委で発足した実務者会議は、この大通案に、札幌ドーム(豊平区)、円山公園(中央区)を加えた3案で検討を始めた。武藤氏は視察後に市役所で記者会見し、「それぞれ素晴らしい施設だがデメリットもある」と指摘。札幌ドームではアリーナ出入り口の改修の必要性やコースの高低差を問題視し、円山公園は「丘陵地帯のため競歩コースには難しい」などとした。有力視される大通公園については「重要な夏のイベントが同時期にあり、調整が課題」とした。 *4-2:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363470(北海道新聞 2019/11/11) 道議会新庁舎の完全禁煙を 道医師会長、自民党道連会長に要望 北海道医師会の長瀬清会長は10日、来年1月完成予定の新しい道議会庁舎を完全禁煙とするよう、自民党道連の吉川貴盛会長に要望した。吉川氏は「道連として真摯(しん し)に受け止める」と述べ、新庁舎の会派控室に喫煙所を設置することを決めている自民党・道民会議に対し、要望内容を伝える考えを示した。長瀬氏は、札幌市内で吉川氏に要望書を手渡し「公共(施設)の道議会には市民も子どもも入る。他の県に及ぼす影響も大きい」と喫煙所設置を撤回するよう求めた。吉川氏は「最終的には道議会自民党が決めることになるが、今の話を(自民会派に)しっかり伝える」と応じた。要望後、長瀬氏は記者団に対し「(問題が)1歩も2歩も進んだ。道連会長として手腕を発揮してほしい」と話した。道議会全5会派のうち、自民会派のみが新庁舎での喫煙所の設置を決めており、他会派から全会派での協議を求める声が上がっている。 *4-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/452341 (佐賀新聞 2019年11月11日) 経常黒字10兆3382億円、19年度上半期、3・3%減 財務省が11日発表した2019年度上半期(4~9月)の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は、前年同期比3・3%減の10兆3382億円だった。半期ベースでの黒字は11期連続。中国向け自動車関連部品や半導体製造装置の輸出が減少したことが影響し、経常収支の黒字幅は縮小した。経常収支のうち、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は、前年同期の1兆1245億円の黒字から241億円の赤字に転じた。輸出は6・1%減の37兆5796億円、輸入は3・3%減の37兆6038億円だった。旅行や貨物輸送を含むサービス収支は2711億円の赤字となった。旅行者のお金の出入りを示す「旅行収支」の黒字は1兆3451億円だった。韓国からの旅行者は減った一方、外国人旅行客全体は増加した。海外投資で生じた利子や配当の動向を表す第1次所得収支の黒字は、ほぼ前年同期並みの11兆3079億円だった。同時に発表した9月の経常収支の黒字額は前年同月比12・5%減の1兆6129億円だった。黒字は63カ月連続。中国向け自動車関連部品などの輸出が落ち込み、黒字幅が縮小した。ラグビー・ワールドカップ(W杯)の開催により訪日客が増え、旅行収支は拡大した。 <再エネの利用と送電について> PS(2019年11月13、15日):私は、北海道の自然や雄大さが好きで、札幌・定山渓、支笏湖・洞爺湖、昭和新山、摩周湖、函館、知床・釧路・根室などのいろいろな場所に何回か行った。そのため、*5-1のように、JR北海道がJR札幌駅南口に高さ約230mの新幹線と各交通機関との結節点となる新ビルを建設して、バスターミナルも整備するのは良いと思うが、空港と鉄道の便利な連結も必要だ。 また、北海道は観光や農林漁業だけでなく再エネ発電にも向いているため、*5-2のような太陽光・風力・地熱発電による電力を集め、鉄道に最新の電線を敷設することによって本州に送電することも可能だ。それらの工夫により、*5-3のように、何でも高コストのため、要するに何もできない我が国のインフラが少しは更新しやすくなると思われる。 赤羽国土交通相は、*5-4のように、九州新幹線長崎ルートを佐賀空港経由のルートでフル規格整備することについて、「地盤の問題などもあり難しいのではないか」と述べられたそうだが、他の新幹線が建設されている地盤と比較すれば根拠がなく、佐賀駅経由の結論を導くための言い逃れにすぎない。しかし、新大阪駅と同様、新佐賀駅を作ることも可能である上、大きな荷物を持って移動するのに国交省の航空(国際・国内も!)・港湾・鉄道の非連結政策が不便で仕方ないのは事実であり、どういう人の移動を前提としているのかと思うことが多いのである。     (図の説明:1番左は、釧路湿原のタンチョウ《冬》、左から2番目は釧路湿原のハマナス《夏》、右の2つは羅臼のシャチで、自然がすごいわけである) *5-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/363806 (北海道新聞 2019年11月12日) 札幌駅新ビル 道内一230メートル 創成川東に新幹線改札 JR計画 JR北海道の島田修社長は11日の記者会見で、JR札幌駅南口の札幌市中央区北5西1、西2の両街区に一体的に整備する新ビルのうち、西1街区の高層棟は地上47階建てを目指すことを明らかにした。JRによると、高さ約230メートルで、現時点で道内で最も高いJRタワー(38階建て、173メートル)を超え、道内一の高層ビルとなる。両街区を一体的に開発する札幌市とJRなどは同日、準備組合を設立し、島田社長と秋元克広市長が札幌市内で記者会見した。島田社長は、高層棟について「JRタワーより高層のビルを目指したい」と述べ、今月1日に東京・渋谷に開業した渋谷駅直結の高層ビル「渋谷スクランブルスクエア」をモデルに、新ビルを新幹線と各交通機関との結節点としたい考えを示した。市によると、新ビルは2030年度末の北海道新幹線札幌延伸に向けて、29年秋の完成を目指す。高層棟には、世界展開する高級ホテルやオフィス、商業施設を併設。西2街区の低層棟には商業施設をつくる。両街区1階部分にはいずれもバスターミナルを整備。2階には両街区をつなぐ歩行者用デッキをつくり、バスの待合所などを配置し、災害時には帰宅困難者を受け入れるスペースとする。また、北海道新幹線札幌延伸を踏まえ、創成川東地区に新幹線用の東改札を開設することも検討。その際、創成川を横断し、西1街区の新幹線駅舎と結ぶ歩行者用デッキの設置についても調整する。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191113&ng=DGKKZO52098720S9A111C1TJ1000 (日経新聞 2019年11月13日) 道路舗装で太陽光発電、ミライラボ、EV給電も 中日本高速など、CASE対応 「眠れる資産」とされた道路に、最新テクノロジーを実装する動きが広がっている。新興企業のMIRAI-LABO(ミライラボ、東京都八王子市)は太陽光パネルを装備した道路舗装を開発した。中日本高速道路は道路に埋め込んだセンサーを使い、自動運転で必要なデータを発信するシステムを開発している。車の電動化など「CASE」の普及をにらみ、総延長約128万キロメートルに及ぶ道路の価値の掘り起こしが本格化する。2006年設立のミライラボは非常用電源など省エネ機器を手がけ、全国の警察や自治体に販売する新興企業。今回、太陽光で発電する道路舗装「ソーラーモビウェイ」を開発した。太陽光パネルを特殊な樹脂で覆い道路の舗装材の代わりに使う。現在、道路舗装大手NIPPOと性能試験を進めており、2022年の実用化を目指す。通常の太陽光パネルは衝撃に弱く割れやすい。今回、ミライラボは柔軟性のある素材を使い衝撃に強いパネルを採用した。舗装面にパネルが露出していると車がスリップしたり路面が摩耗したりする。これを防ぐためセラミック片を混ぜた透明な樹脂でパネルを覆う。ビル屋上などの太陽光パネルは光の角度が浅いと発電効率が落ちる。開発した舗装材はセラミックが太陽光の角度を変え、1日を通した発電量を高める効果が期待できるという。電気は地中の電線を通じ蓄電池にためる。電気自動車(EV)などで使ったバッテリーの再利用も想定する。国内には総延長約128万キロメートルの道路が走っているが、車や人の移動用途が中心の「眠れる資産」だ。ミライラボの平塚利男社長は「高速道路と国道の半分を発電型の舗装にすれば日本の消費電力の16.5%を賄える」と試算する。ミライラボがにらむのは、車の電動化や自動運転など「CASE」の本格到来だ。発電した電力は街灯や道路表示板に加え、将来は走行中のEVへの無線給電や、自動運転に必要な道路状況に関するデータ通信の電力源としての活用を想定している。停電で自動運転車に情報が送れなくなると事故につながる恐れもあり、電源を道路で賄えるメリットは大きい。道路を発電基地にする利点はほかにもある。平地の少ない日本では森林を伐採してパネルを設置するケースが多く、道路を活用すれば環境破壊を防げる。災害で停電が起きてもパネルで発電すれば信号や街灯を維持できる。再生エネルギーの送電網不足が問題となるなか、道路での発電は「地産地消」につながる。国内の道路は老朽化が進み、今後大規模な改修時期を迎える。国土交通省の試算では今後30年間、高速道路や一般道で年2兆円超の工事が必要になる。老朽化対策の時期がCASEの大波と重なることから、道路に最新テックを埋め込む技術開発が広がる。中日本高速道路(NEXCO中日本)は高速道路にセンサーやカメラを整備する。すでに東名高速など主要道に地磁気センサーを埋め込み、渋滞情報などのデータを集めている。今後、高精度カメラを短い間隔で設置し、道路の運行状況を絶え間なく監視できるようにする。同社は管轄する道路の約6割が建設から30年たち、「来年度から首都圏の主要道路が改修時期を迎える」(担当者)。次世代通信規格「5G」が実用化すれば大容量の映像データをスムーズに送受信でき、自動運転車へのデータ送信など道路の付加価値を高める。大成建設は豊橋技術科学大学と共同でEVのワイヤレス給電システムを開発している。地面に電極を敷設し、受電装置を備えたEVが上を走ると電気が送られる。ブリヂストンも東京大学などと共同でタイヤを通じて道路から充電する技術開発を進めている。道路から給電できれば搭載するバッテリー量を減らし車体の軽量化にもつながる。普及に向けた課題はコストだ。ミライラボとNIPPOが試験を進める発電型の舗装材は「まだ価格を設定する段階ではない」(NIPPO)というが、大幅なコスト増は避けられない。生産規模の拡大によるコスト低減や、道路の付加価値向上による新しい収益モデルの構築が必要になる。海外でも政府や企業がCASE対応を急いでおり、今後は国際競争も激しくなる。例えば道路での太陽光発電は米国やフランスなどで開発が進むが、現時点で明確な成功例は出ていないという。 *5-3:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20191113&c=DM1&d=0&nbm=・・・ (日経新聞 2019年11月13日) 最新技術、課題はコスト インフラ老朽化契機に改修 国土交通省によると、建設後50年以上の道路や橋の割合は2018年の25%から33年に6割に高まる。最新技術はコスト低減が課題になるが、低コスト化やノウハウ蓄積で海外に先行できれば、新たなインフラ輸出の商材になる可能性もある。国交省は2月、インフラの定期点検要領を改正した。従来は橋やトンネルの状態を人の目で確認する必要があったが、同等の情報が得られればカメラやドローン(小型無人機)などの活用も認めた。これを受け、ゼネコン以外の異業種が最新技術を応用する動きが活発になっている。リコーは複数台のステレオカメラを搭載した一般車両を走らせ路面の状態を調査する技術を開発。デジタルカメラで培った画像処理技術を応用する。カシオ計算機は時計「G-SHOCK」の技術を応用しセンサーを搭載したネジを開発。構造物のゆがみなど経年変化の情報をリアルタイムで解析できる。国交省は今後30年で必要になるインフラの更新費用が最大で194兆円に上ると推計する。単にインフラを更新するのではなく、CASE対応のような付加価値向上や新技術の育成に結びつける工夫が不可欠になる。 *5-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/450863 (佐賀新聞 2019/11/7) 「佐賀空港ルート難しい」九州新幹線の整備で国交相 赤羽一嘉国土交通相は5日の参院国交委員会で、九州新幹線長崎ルートの整備方式見直しに関し、佐賀空港を経由するルートでフル規格で整備する考え方について「地盤の問題などもあり難しいのではないか」と述べ、実現性は低いとの認識を示した。立憲民主党の野田国義議員(福岡県)の質問に答えた。赤羽氏は佐賀空港の立地状況を念頭に、空港経由に難色を示した上で「関係者の皆さんが意見を腹蔵なく言いながら結論に導かなければならない」と話した。10月28日の山口祥義知事との面談内容も問われ「高規格ネットワークを張ることが国益に沿う。知事は若いから長期に県知事を行うと思うので、中長期的な視野で結論を出していただきたいという話をした」と説明した。水嶋智鉄道局長は佐賀新聞社のインタビューで、フル規格は佐賀駅経由が合理的との見解を示している。 <問題だらけの大学入学共通テスト> PS(2019年11月13、14、16、21、22日):*6-1の国語記述式問題は、誰が採点するかで結果が変わり、標準回答を作るため問題と正答例をテスト実施前にベネッセ子会社の「学力評価研究機構」の数人が閲覧するのも問題であるため、国語の記述式テストをやるとすれば大学毎の二次試験に限った方がよいと、私も思っていた。そのため、国語の記述式問題の成績を判断材料から外すより、大学入学共通テストから記述式問題を無くすのが無駄な費用を省けてよい。 また、*6-2のように、英語も複数の民間試験を利用すれば受験生の成績を比較できないため、「2020年度実施の入試で民間試験を出願資格として使うことは難しい」という東大の判断に賛成だ。さらに、「複数の民間試験のどれを使ってもよい」などとという入試はあり得ないため、この方式は中止すべきだ。なお、これまで勉強した人は、勉強したことに損はないと思う。 このような中、*6-3のように、首都圏の高校生グループが、「記述式の是非を巡る議論をするには客観的データが必要だ」と感じ、中高生や教師らにインターネットで呼び掛けて大学入学共通テストに導入される国語の記述式問題の自己採点の再現実験を実施し、正誤の判断が大きく分かれることを証明して出題中止を訴えたそうで、Over Expectation(期待以上)の思考力を持つ生徒たちだ。また、「誰が判断してもばらつきが出る」「思考力を測る目的なのに型にはまった答えを導き出そうとしている」等の指摘も、全くそのとおりで感心した。 2019年11月16日、*6-4・*6-5のように、「①大学入学共通テストの国語・数学の記述式問題は、50万人規模の試験で採点にバラツキが出る」「②記述式の採点はベネッセのグループ会社が約61億円で受託している」「③入試改革の背景に官民癒着がある」「④英語の民間試験の実施団体であるベネッセの関連法人には、旧文部省や文科省の幹部らが再就職していた」「⑤文科省も共通テストで記述式を出題する意義を否定している」等の理由により、共通テストの記述式問題の導入は断念するのが妥当な選択だという声が多い。ただでさえ団塊の世代の1/2の人数になっている若い世代が論理的思考力・科学的創造力などを身に付けるには、各段階での教育内容の充実や入試の正確性・公平性・公正性が不可欠であるため、私は、50万人規模の大学入学共通テストは広い知識をマークシート方式で問い、コンピューターで短時間に採点するのが合理的だと思う。そして、その結果を受けて進む各大学の二次試験で、受け入れ大学が要求する受験生の科学的思考力、論理性・判断力などを記述式の出題も含めて問うのが合理的だろう。 私は、英語で仕事をすることが多く、読み書きだけでなく聞く話すも必要だったのでよくわかるが、Broken Englishでも話せないよりましではあるものの、知識人が話す場合にはBrokenでは尊敬されない。そのため、日本でしか通用しない検定試験を受けてもあまり意味がなく、英語を母国語とする国の検定試験のうち(大学入試なら留学を意識して)TOEFLEなら意味があると思っていた。そのような中、*6-6のように、ベネッセのGTECが主流になりつつあったというのは驚きで、民間企業に利益を上げさせるための入試制度に見えるが、教育は真面目に考えないと対象世代を不幸にする。従って、唐津東高がGTECの「模擬試験」を取りやめたのはよいと思うが、だからといって「部活があるから受けたくない」というのは英語の勉強をさぼることになるため、しっかり勉強はさせておくべきだ。また、日本は、数学・物理・化学・生物・世界史・日本史・地理等の英語以外の科目をすべて日本語で学ぶため、外国人とコミュニケーションするには英語で覚えなおすことが必要で、日本人の総合的英語力は同じアジアのインド・香港・シンガポールなどに大きく劣る。従って、他の科目の教科書で使う単語や熟語にも英語を併記しておき、試験の一部を英語で行うのがよいと思う。 *6-7のように、メディアは2019年10月に始まった幼児教育・保育の無償化に関する財源が足りなくなり、中高所得層や単価の高い保育所の利用者が想定を上回ったため「金持ち優遇策」だとしているが、私は、児童手当と幼児教育・保育の無償化が実現した現在、むしろ所得税における子どもの扶養控除を廃止してよいのではないかと考える。何故なら、これこそ高額の所得税を支払う人(高所得者)ほど有利で、非課税世帯にはメリットのない制度だからだ。さらに、幼児教育・保育はサービスであるため、所得によって値段を変えると二重課税になる上、学ぶことが多い現在の子どもは3歳から義務教育として語学・音感・ダンス等のできることを前倒しして教えるとともに、既に保険料を支払い収入はなくなっている高齢者への社会保障給付を減らすのではなく、生産年齢人口の期間に景気対策や補助金を要する人を減らすのがよいと思う。 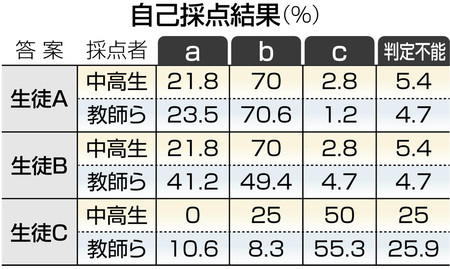 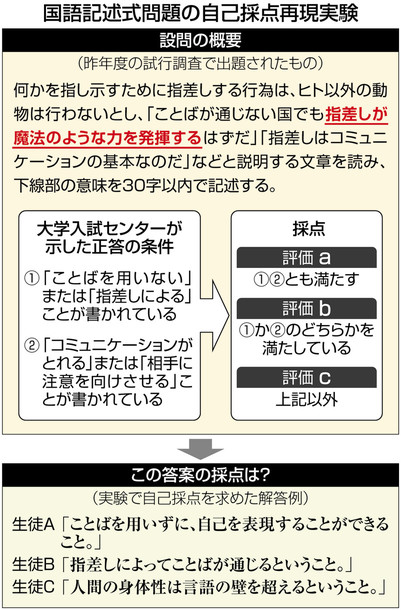 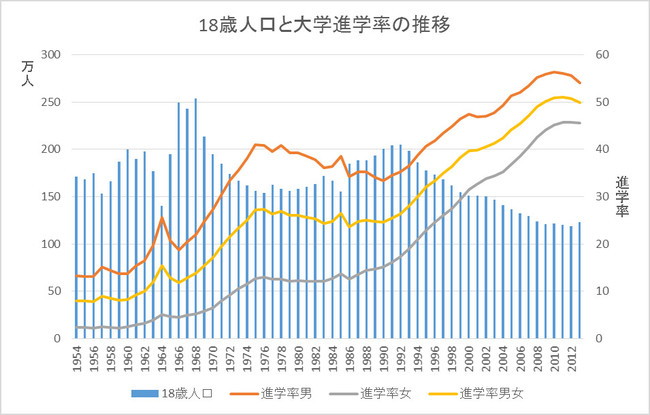 *6-3より 18歳人口の推移 (図の説明:インターネットでアンケートをとってあっと言う間に統計処理した結果を出せるのは今だからこそできることだが、これをやった高校生は偉いと思う。そして、左図のように、正誤判断にバラツキがでている。また、多様性のある民主主義社会では、言語で明確に内容を伝えることが大切であり、どこの国でも人を指さすのは失礼とされる場合が多いため、中央の図の問題もよくない。さらに、現在の18歳人口は団塊の世代の約半数であり、一人一人が充実した教育を受ける必要性が増しているのだ) *6-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/364439?rct=n_topic (北海道新聞 2019年11月13日) 二段階選抜で国語の記述式除外を 国公立大に要請へ、文科省 2021年1月が初回となる大学入学共通テストを巡り、文部科学省が全国の国公立大に対し、合格可能性が低い受験生を門前払いする二段階選抜で、国語に導入される記述式問題の成績を判断材料から外すように要請する検討に入ったことが13日、文科省への取材で分かった。記述式問題は国語と数学で出題されるが、国語は自己採点が難しく、採点ミスも起きやすい懸念がある。文科省は、二段階選抜後に何らかの問題が判明すると救済が難しいことや、自己採点と実際の成績のずれによる混乱を防ぐ観点から、マークシート式の結果のみを判断材料とするよう配慮を求めたい考えだ。 *6-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/education/edu_national/CK2019111202000206.html (東京新聞 2019年11月12日) 東大20年度入試 副学長見解「民間試験利用 難しい」 文部科学省が大学入学共通テストへの英語民間検定試験の導入を延期したことを受け、東京大の入試担当の福田裕穂(ひろお)副学長は十一日の記者会見で、二〇二〇年度実施の入試で民間試験を出願資格として使うことは難しいとの見解を示した。英語民間試験は、共通テストへの導入は見送られても各大学が独自の判断で利用することは可能。各大学の対応が注目されている。東京大は昨年、共通テストへ民間試験を導入することについて学内で検討し、公平性への不安や責任の所在の不明確さなど、さまざまな問題点を文科省へ指摘。林芳正文科相(当時)は東京大の五神真(ごのかみまこと)学長と会談し、関係者の意見交換の場を設置して意見を聞くことなどを約束していた。福田副学長は「文科省の延期の発表は、受験生の安心を得るに至っていないという判断だと理解する。われわれがそのまま民間試験を出願資格とすることは難しいと私自身は考える」と語った。正式な対応は学内の入試監理委員会で決め、ホームページで公表する。英語民間検定試験については、四年制大学の約七割が大学入試センターのシステムを通じて利用する予定だった。システムは延期になったが、独自に民間試験の結果を受験者に提出してもらうことは可能なため、予定通り利用するのか、取りやめるのか、方針を明確にする必要がある。国立大学協会(国大協)は二十九日に各大学がホームページなどで公表することを決めている。福田副学長は「国大協の日程に合わせるかは決めていないが、できるだけ早く公表したい」と話した。 *6-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/education/edu_national/CK2019111402000185.html (東京新聞 2019年11月14日) 国語記述式 採点ばらつき「公平性欠く」 高校生ら再現実験 二〇二〇年度実施の大学入学共通テストに導入される国語の記述式問題について、首都圏の高校生グループが中高生や教師らにインターネット上で呼び掛けて自己採点の再現実験を実施した。十三日に開いた会見で、同じ解答を巡り正誤の判断が大きく分かれる結果を公表。「現行のシステムでは公平な判定や自己採点が難しいことが裏付けられた」とし、出題中止を訴えた。自己採点は、受験生にとって二次試験で出願する大学を最終的に決める材料。実際の得点と乖離(かいり)すると、適切に出願先を選べなくなる。そのため高校生らは、記述式の是非を巡る議論をするには客観的なデータが必要だと感じ、アンケート形式による再現実験を思い立った。今月九~十一日の三日間にインターネットで呼び掛け、高校生八百十五人、中学生二十人、大人六百十人の計千四百四十五人が参加。大人のうち八十六人は現職の教員、予備校講師やその経験者だった。実験では、昨年度大学入試センターが行った共通テストの試行調査の出題を利用した。参加者にセンターが示した正答の条件、満点解答例を提示した上で、生徒A、B、Cの三つの答案例を採点してもらった。その結果、どの答案でも判断がばらついた。中高生八百三十五人のグループと教員ら八十六人のグループに分けて分析すると、生徒Aの答案では、両グループとも約二割が満点正解の評価a、約七割が部分正解のbとなった。一方、答案Bでは、aが中高生は二割なのに対し、教員らは四割に上った。さらに、センターが条件とする語句を直接含まない答案Cについては、両グループとも四分の一が、正答か誤答か判断がつかない「判定不能」とした。代表の高校生(16)は「誰が判断してもばらつきが出る。現状の採点システムに問題があるということだ」と指摘、中止を訴えた。別の生徒(17)は「よりよい試験へ改革するのはいいことだが、十分準備して実施するべきだ。いったん立ち止まり、当事者の声を聞き入れて」と思いを語った。再現実験に参加したうち約九百人が寄せた感想も一部紹介。「人によって表現が異なり、解答の解釈も一通りではない。公平性、確実性に欠ける」「思考力を測る目的なのに型にはまった答えを導き出そうとしている」「五十万人規模の採点は不可能。民間業者への委託は論外」など、すべて否定的な意見だったという。 <国語記述式問題> 思考力などを問うとして共通テストに導入。3問出題、各解答を正答の条件を全て満たしているかなどによりa、b、cで採点。さらに3問の結果を掛け合わせて5段階で総合評価する。マークシートと違い、採点者によって判断がぶれることや、受験生が正確に自己採点できないことが心配されている。自己採点は出願する大学を選ぶ最後の材料で、実際より高く自己採点すると難易度の高い大学に出願し2次に進めなかったり、低く自己採点して志望先をあきらめることが起きる可能性がある。 *6-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019111602000177.html (東京新聞社説 2019年11月16日) 記述式試験 腰を据えて仕切り直せ 二〇二〇年度開始の大学入学共通テストで、国語や数学の記述式問題でも、採点のばらつきなどの不安が膨らんでいる。もう一つの柱の英語民間試験導入は延期された。見切り発車で良いのか。東京大学は記述式の利用方法の公表を留保している。「政治的な動きがあり、見極めたうえで判断せざるを得ない」(福田裕穂副学長)というのがその理由だ。新テスト導入が一年余後に迫る中、国会の争点と化す異常事態に教育現場には戸惑いも広がる。五十万人規模の試験で採点にばらつきが出る懸念は一八年に行われた試行調査では拭えなかった。採点ミスは0・3%あった。採点結果と受験生の自己採点が一致しない割合も約三割に上っている。本番の採点者は一万人以上になるとみられ、学生アルバイトが含まれる可能性もある。政治主導の入試改革の背景に官民癒着があるのではないかという疑念が、記述式への批判を増幅している側面もある。英語の民間試験を巡る国会での議論の中で、試験の実施団体の一つであるベネッセの関連法人に旧文部省や文部科学省の幹部らが再就職していたことも明らかになった。記述式の採点はベネッセのグループ会社が約六十一億円で受託している。大学入試センターは今月、二万人の高校生の答案などを使い、複数の採点者でミスを防ぐなど、採点の精度を上げるための検証作業を始めた。ただ、どこまで改善できるかは不透明なうえ、自己採点との食い違いは検証の対象外だ。問題を容易にすれば、採点のばらつきなどは少なくなるだろう。だが思考力や表現力を測るという本来の目的からは遠ざかり、かかる費用と得られる効果は見合うものになるのかという別の課題が生じる。記述式の導入自体に無理があるのではないか。文科省は、一定水準に満たない志願者を二次試験の対象から外す二段階選抜の判断材料に、国語の記述式の成績を使わないよう国公立大学に要請する検討に入っているという。必要なのは表面的な取り繕いで批判をかわそうとすることではなく抜本的な見直しだろう。人口減少など困難な社会の課題に取り組む若い世代に、未来を切り開いていく力を身に付けてほしい。それが思考力などに重きを置く入試改革の原点のはずだ。高校や大学がその理念を共有し、二次試験のありようを含め、腰を据えて仕切り直しをするべきだ。 *6-5:https://www.kahoku.co.jp/editorial/20191116_01.html (河北新報 2019年11月16日) 大学入学共通テスト/記述式導入は中止の決断を 2021年からの大学入学共通テストでの記述式問題の導入を巡って、文部科学省が迷走している。全国の国公立大に対し、受験生を門前払いする二段階選抜では、国語の記述式の成績を判断材料にしないように要請する検討を始めたという。これでは、共通テストで記述式を出題する意義を文科省が自ら否定しているのと同じだ。懸念されるさまざまな混乱の回避のためだというが、共通テストの記述式問題の導入は、きっぱりと断念するのが妥当な選択だ。制度的欠陥が幾つも指摘され、公平な採点への疑念も持たれながら、膨大な費用をかけてまで、導入する意味に乏しい。野党4党は既に中止法案を衆院に提出しており、原点に戻ってあるべき制度を議論し直してもらいたい。記述式の出題に関して強い違和感が残るのは、採点業務に受験産業を担う企業グループが携わる点だ。受験教材の販売から大学入試の採点まで、一私企業のグループが関与するのは好ましくない。批判と懸念が寄せられるのは当然だろう。問題や解答の漏洩(ろうえい)の危惧ばかりではなく、採点の公平性と正確性にも疑問が残る。業者側は「公平でぶれない採点を行う」としているが、採点者は学生アルバイトが中心となる。客観的な採点マニュアルを整備したとしても、やはり不安は募る。文科省は採点基準を明確化し、機械的に採点ができるような記述式問題を出題するとしている。しかし、機械的に採点可能な問題を出題するのであれば、マークシート方式がふさわしい。この点でも文科省の説明は矛盾している。記述式の出題は、受験生の思考力、判断力、表現力を問う重要性が入試改革の議論の中で指摘され、導入が決まった経緯がある。各大学が実施する2次試験で記述式の問題があまり出題されていないという現状批判もあった。大学入試センター試験の過去の問題を見れば、そうした指摘は事実誤認に基づくのは明らかだ。長い実績を積んできたセンター試験の問題は練り上げられた良問が多く、受験生の学力を適切に測れないことは決してない。また、各大学が実施する2次試験では、各教科で記述式の問題が出題されてきた。センター試験で基礎的な学力、記述式や小論文を含む2次試験で応用的な学力を見るという効果的な役割分担がなされてきたと言える。数学の記述式問題は、国語に比べれば、採点の客観性は一応は担保できよう。しかし、採点の期間がわずかに約20日と短く、約50万人の答案を全くミスなく果たして採点できるのか心もとない。幾つもの制度的欠陥と運営の不安を抱える記述式問題の導入である。受験生の心情を考えれば、中止の決断は一刻も早い方がよい。 *6-6:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/456411 (佐賀新聞 2019年11月21日) 県立高「模試」対応分かれる 英語民間検定試験導入見送りで 2020年度の大学入学共通テストへの英語民間検定試験の導入見送りを受け、佐賀県内の県立高校で、本番に備えたトレーニングと位置付けて12月に受ける予定だった民間検定試験をそのまま実施するかどうか対応が分かれている。唐津市の唐津東高は12月7日のGTEC(ジーテック)検定版の受験を保護者の負担軽減などを理由に取りやめた。別の10校では大学が個別試験(2次試験)で採用する可能性や学力向上を考え、予定通り実施する準備を進めている。英語の民間検定試験については、20年度に実施される検定試験が共通テストで活用される予定になっていた。県内の高校は今年12月のジーテックの検定を本番に向けた「模擬試験」のように位置付けていた。学校関係者によると、ベネッセコーポレーション(本社・岡山県)が実施するジーテックの受験料は1人1回6380円で、3千円程度の同社の模試と比べて倍近くの金額という。共通テストへの導入見送りが決まり、唐津東高は「保護者に負担をかけてまで受けさせる必要性はない」と考え、12月の検定を取りやめ、保護者にも13日に通知した。対象になる2年生は既に昨年1回、今年1回受けており「大学での活用が正式に決定した時点でさらに検定を受けるかどうかを決める。仮に必要になったとしても、来年以降の検定で対応できる」と話す。一方、予定通りに検定を受ける佐賀北高や小城高は「英語の学力や『読む・聞く・書く・話す』の4技能を測る上では意味がある」と説明している。ジーテックなどの英語民間検定試験は、20年度の共通テストには導入されないが、国立大は同年度の個別試験に採用するかどうかを29日に公表する予定。別の県立高校の担当者は、ジーテックの点数に応じて個別試験に加点してきた大学がある経緯を踏まえ「従来のように個別試験に生かされるなら、12月も受けた方がいい」という考えを示す。県西部の高校では、保護者や生徒から「本番が見送られたのなら12月の試験も取りやめ、返金してほしい」「部活があるから受けなくていいなら受けたくない」などの声も出ているというが、試験をキャンセルするには至っていない。ベネッセコーポレーション広報部は12月の検定のキャンセル状況について「日々、状況が変わっている。不確定な情報を公表することは誤解につながる」とし、件数などは明らかにしていない。受験を取りやめた学校への対応については「(受験料を)既に振り込んでいる場合は全額を返金する」と話している。 *6-7:https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20191122/KP191121ETI090006000.php (信濃毎日新聞 2019年11月22日) 幼保無償化 抜本的改定をためらうな 早速ほころびが生じている。10月に始まった幼児教育・保育の無償化の財源が足りなくなっている。数百億円を借金もして賄うという。財政の安定化と引き換えに消費税増税分の一部を財源に充てていながら、費用を子どもたちに付け回すのでは意味がない。真に必要な保育政策は何か、保護者や現場の意見を基に練り直すべきだ。政府は制度の抜本的な改定をためらってはならない。無償化は3〜5歳児が原則全世帯、0〜2歳児は住民税非課税世帯を対象とする。認可外保育の利用者には上限を設け、一定額を補助している。国は本年度予算に3882億円を計上した。ふたを開けてみれば、中高所得層の利用者と単価の高い保育所の利用者が想定を上回った。本年度の税収は法人税の下振れで大幅な減額が見込まれる。赤字国債などで穴埋めせざるを得ない。通年となる来年度の予算7800億円にも、1千億円ほどの上乗せが避けられないという。予算の半分が年収640万円超の世帯に回ることから「金持ち優遇策だ」との批判が出ていた。無償化の予算をむしろ、保育士の待遇改善や研修費に充て「保育の安全性を高めてほしい」との保護者の訴えも強かった。安倍晋三政権はまともに取り合わず、ずさんな制度設計のまま実施を半年前倒しした。対象から漏れた世帯、給食費の負担が生じた世帯を自治体が独自に支援し、住む市町村によって受けられる恩恵が異なる状況を招いている。全国の待機児童数は4月時点で1万6700人余と減少に転じている。半面、希望先の保育園に入れないといった「潜在的な待機児童」は7万4千人と、昨年を6千人も上回っている。働きながら育児をする女性は増加傾向にある。無償化によって来春からの需要が高まり、待機児童が再び増え、保育士の不足が深刻化する懸念が拭えない。認可保育所の利用料には元々、低所得世帯の減免措置があり、所得が多いほど高額になる応能負担が取り入れられていた。無償化の所得制限をきめ細かくし、残る予算を保護者の要望に沿った施策に振り向ける方法もあろう。子育て支援が急務とはいえ、体系立てた少子化対策に位置付けなければ効果は期待できない。受けのいい“大盤振る舞い”を仕掛けた結果、社会保障の借金がさらに膨らむのでは、何のための消費税増税なのか分からなくなる。 <スポーツ教育について> PS(2019年11月15、17、21日追加):私が衆議院議員をしていた時に、アトランタ五輪のセーリング女子で銀メダルを獲得した*7-2の重由美子さんが唐津市のヨットハーバーで後進の指導に当たっておられ、そこに招かれて「トップアスリートを目指して日本全国から集まった選手の就職が厳しく、選手が経済的に苦しい」という話を聞いたことがある。 そのため、*7-1のように、九経連佐賀地域委員会(委員長・陣内佐賀銀行会長)で、SAGAスポーツピラミッド推進グループ推進監の日野氏が佐賀ゆかりのトップアスリート育成を目指すSSP構想について講演され、現在でも佐賀県が働きながら練習し競技が続けられる就職支援を行っているのは極めて重要なことだ。しかし、新人選手の育成のためには引退したトップアスリートを指導者として招いたり、アスリート候補者を就職で支援したりすることが不可欠であるため、中学・高校のクラブ活動指導者や放課後児童クラブの指導員としての職を与えれば、双方にとってメリットが大きいのではないかと考える。 なお、*7-3のように、教員には長時間労働の問題があると言われながら長く改善されていないが、その理由は、①部活動指導 ②授業準備 ③事務・報告書の作成 ④学校行事 ⑤学習指導 ⑥成績処理などだそうだ。このうち、②④⑤⑥はプロの教育者しかできない仕事だろうが、③の事務の多くは雑用係がやればよく、報告書の作成もITを使えば効率化が容易だ。さらに、①については、スポーツクラブなら教員よりもアスリート引退者、文化クラブなら大学教授・研究所・報道関係の引退者などの専門家が加わった方がうまく教えられると思う。また、*7-4のように、佐賀県の場合はサッカー・J1サガン鳥栖があるため、このチームの引退選手にクラブ活動の指導をしてもらうのも名案だ。コーチが外国人だとユニバーサルな意識も養われそうである。 *7-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/453655 (佐賀新聞 2019年11月14日) アスリート支援に協力を 九経連委員会 県SSP推進監が講演 九州経済連合会佐賀地域委員会(委員長・陣内芳博佐賀銀行会長)がこのほど、佐賀市で開かれた。県文化・スポーツ交流局SAGAスポーツピラミッド推進グループ推進監の日野稔邦氏が佐賀ゆかりのトップアスリート育成を目指すスポーツピラミッド構想(SSP構想)の取り組みについて講演した。会員ら約60人が参加した。日野氏は「2024年のパリ五輪・パラリンピックでは佐賀ゆかりのアスリートを10人出したい」と述べ、高校レスリングや柔道などで成果を上げている現状を示した。「継続的に佐賀ゆかりのトップアスリートを育て、効果を広げていきたい」と話し、アスリートの就職やビジネス創出などで企業関係者の協力を呼び掛けた。県は、トップアスリートが働きながら練習し、競技が続けられるよう就職の個別支援を行っており、雇用アスリートの練習時間に応じて企業に支援金を用意している。23年に佐賀で開かれる国民スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会に向けて整備するSAGAサンライズパークは、スポーツと他産業の融合によるビジネス創出などに活用する構想も説明した。 *7-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/312596 (佐賀新聞 2018/12/9) セーリング銀の重由美子さん死去、アトランタ五輪で日本初メダル 1996年アトランタ五輪セーリング女子470級で銀メダルを獲得し、同競技の日本勢初のメダリストとなった重由美子(しげ・ゆみこ)さんが9日午前3時15分、佐賀県唐津市の病院で死去した。53歳。唐津市出身。日本連盟関係者らが明らかにした。親族によると、死因は乳がんという。葬儀・告別式は13日午後1時から唐津市鏡3528の1、パインフィールド・ホールで。喪主は父五十男(いそお)さん。佐賀・唐津東高出身。2人乗りヨットのかじを取るスキッパーとして活躍し、アトランタ五輪では木下アリーシアさんと組んで快挙を果たした。五輪は3大会連続出場で、92年バルセロナ大会は5位、2000年シドニー大会は8位だった。近年は唐津市の佐賀県ヨットハーバーで後進の指導などに当たっていた。 *7-3:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1026841.html (琉球新報社説 2019年11月17日) 教員の長時間労働 業務内容の抜本見直しを 県立の中学、高校、特別支援学校の教職員を対象にした2018年度の勤務実態調査で、厚生労働省が過労死の目安とする月80時間の残業時間を上回った教員が、延べ3078人にも上った。このうち月100時間を超えたのは延べ1314人を占める。教員の生命や心身の健康を脅かす長時間労働は、直ちに解消しなければならない。小学校を含めた県内教職員の17年度の病気休職者数は前年度比11人増の424人で、在職者に占める割合は2・8%と全国の0・85%より約2ポイントも高い。業務負担と疾患発生との関連が考えられる。教員は、児童生徒と直接向き合い、必要な知識を身に付けさせ、豊かな人間性を育成する立場にある。日々の業務をこなすだけで疲労困憊(こんぱい)していく職場環境では、子どもたちのためにもならない。働き方改革関連法の4月施行によって、民間企業では時間外労働は原則月45時間、年間360時間以内を守らなければならなくなった。現在は大企業だけだが、来年4月から中小企業にも適用される。文部科学省は今年1月、働き方関連法に沿う形で、公立校の教員の残業時間を1カ月45時間を超えないようにするという指針を出した。民間企業で月45時間が上限となる中で、教員の働き方にも同じ条件が求められるのは当然だ。ただ、文科省の残業上限の指針に罰則はない。「臨時的な特別の事情」の場合は月100時間を超えない範囲で延長できるともしており、実効性に疑問がある。そもそも公立校の教員に時間外手当は支給されていない。教職員給与特別措置法(給特法)によって基本給に一律4%の手当が上乗せされているだけだ。まずはサービス残業の温床となる給特法を改め、労働基準法の働き方のルールを教員にも適用することの検討が必要だ。県教育庁の勤務実態調査の残業理由を見ると、最も多いのが部活動指導で、授業準備、事務・報告書作成、学校行事、学習指導、成績処理が続く。早朝や放課後、土日に行われる講座の残業は調査の対象外となっており、現場から「実態はもっと深刻」と指摘されている。子どもたちの学習や育成に関わる広範な業務は、簡単に削減や合理化をするわけにはいかない重責だ。個人情報保護の関係で、家に持ち帰れない業務もある。現状の半分以下に残業を削るといっても、簡単なことではない。教師の負担軽減を図り、ゆとりある働きやすい職場環境を実現するには、教員定数の増員が根本的な対策だ。ただし、そのためには財源の裏付けが必要になる。増員が無理なら、教員の業務内容を抜本的に見直すしかない。最も負担が重い部活動指導などの在り方にメスを入れるべきだ。業務の見直しに向けては保護者や地域の理解と協力が不可欠となる。 *7-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/456588 (佐賀新聞 2019年11月21日) (動画)元サガン鳥栖のF・トーレス氏が豪雨被災地の小中一貫校を訪問、「大好きな佐賀が被災して胸が痛んだ」 8月にサッカー・J1サガン鳥栖で現役を引退した元スペイン代表のフェルナンド・トーレス氏(35)が21日、佐賀県大町町の小中一貫校・大町ひじり学園を訪問した。同町は8月の佐賀豪雨で大きな被害を受けており、児童生徒約350人に励ましの言葉を送った。トーレス氏は佐賀県が災害に見舞われたことをニュースで知り、被災地の様子を映像や写真で見て、「大好きな佐賀が被災して胸が痛んだ。自分に何ができるかずっと考えていた」とこの間の心境を打ち明け、「みんなの元気な顔を見て少し安心したが、見えないところで疲労や苦労もあると思う」と慰めた。さらに佐賀県のSAGAスポーツピラミッド(SSP)構想のアンバサダー(大使)としての立場から、「スポーツを通して佐賀を元気にしたい」と語った。学校には、トーレス氏のサインが入ったユニホームやサガン鳥栖の試合観戦チケットなどが贈られた。児童代表で6年生の堤大虎(たいが)君が「憧れのトーレスさんに会えるとは思っていなかった。励みになります。グラシアス(スペイン語でありがとう)」とお礼を述べた。 <食育について> PS(2019/11/16、18追加): *8-1のように、広島市の市立小の7割で、「『いただきます』から約10分間おしゃべりしてはいけない」という時間帯があるそうだ。そして、この間は、①昼食を残さず食べて栄養を十分取らせる ②食べ物を大事にする気持ちを育む ③食事マナーを定着させる ④そしゃくの推進 を目的として、クラシック音楽を流し、児童に黙って食べさせ、これを食育と呼んでいるのだそうだ。 2008年の「食育の推進」は、当時衆議院議員だった私も関わっていたので説明すると、食育に黙って食べさせることを推進する目的はなく、*8-2のように、⑤家庭の経済力格差に拘わらず、子どもが成長するのに必要な栄養を与え ⑥なるべく地域の食材を使って ⑦本当に美味しい給食を食べさせることにより、(家庭では乏しくなった)日本の味や調理の技を次代に引き継ぐ という意図がある。 そのため、「口から食べ物を飛ばしながら食べる」「おしゃべりに夢中になると箸が動かない」「立ち歩いて人にちょっかいを出す」ということが起こるのなら、全員に黙って食べさせるのではなく、そういう行動そのものをきちんと理由を説明してやめさせるのが食育なのだ。テレビ番組でも「食事中にしゃべるな」と親が怒るセリフが聞かれることがあるが、食事は家族団欒や家族間のコミュニケーション・情報交換の貴重な時間であるため、「食事中にしゃべるな」というのは逆の躾である。なお、子どもの教育は歯磨きから始まって強制が多く、美味しい給食を出しているのに食べない子がいるのなら、「空腹になる」という経験をさせることも必要だ。 また、焼き物の盛んな佐賀県では、子どもの感性を育てる機会である食育には、食事の栄養バランスや味だけでなく食器も含まれるとして、給食用食器に強化磁器を使用しており、ペットの餌入れのような金属製食器からは10年以上前に卒業している。 さらに、学校給食のために開発した軽くて強い磁器は、*8-3の公民館や病院・高齢者施設・社員食堂などでも求められるものであるため、需要に合った絵柄や値段をつければ営業次第で大量に売れる可能性がある。      *8-2より 有田の強化磁器製 室蘭のプラスチック製 金属製 (図の説明:左の2つは、優勝《埼玉県越生町立越生小学校》、準優勝《奈良県宇陀市立学校給食センター》の献立、中央は、壊れにくいように強化磁器で作った有田の給食用食器、右から2番目は、室蘭市のプラスチック製給食用食器、1番右は、よくある金属製の給食用食器だ。私は、強化磁器の給食用食器に軍配を挙げたいが、子どもの食器としてかわいい絵柄は室蘭市のプラスチック製給食用食器だ。さらに、室蘭市の食器の中央のものには海産物の絵とその名前が日本語で書かれているが、これには野菜・果物・花・樹木・動物などのいろいろなシリーズやデザインが考えられ、日本語と英語の両方で名前を記載しておけば覚えやすいだろう) *8-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/o/559528/ (西日本新聞 2019/11/14)給食、おしゃべり禁止の10分 広島市、市立小の7割 「楽しくない」「息苦しい」児童も 「もぐもぐタイムって知っていますか」。広島県内の小学校に子どもを通わせる40代の女性から、中国新聞の「こちら編集局です あなたの声から」にこんなメールがあった。カーリングで話題になったおやつの時間のことではない。この学校では「給食中におしゃべりしてはいけない時間帯」を指すらしい。「給食は会話しながら楽しんでほしいのに」と女性は言う。黙って食べるのはどうしてなのだろう。まずはこの学校を訪ねた。ちょうど昼時。子どもたちが元気いっぱいランチルームに集まってきた。もぐもぐタイムは「いただきます」から約10分間で、クラシック音楽が流れる。教室は静まり、みんなひたすら食べている。音楽がやんだ途端、またにぎやかになった。「ごちそうさま」までの残り分はおしゃべりを楽しんでいいそうだ。「食育は大切。きちんと味わい、嫌いな食材も成長に必要な量は頑張って食べてほしい。マナーも学ばせたい」と、校長は説明する。「だから落ち着いて食べる時間が要るんです」。他の学校はどうなのか。広島市立の全142小学校にアンケートした。回答した106校のうち、給食中に私語をしない時間を「設けている」「一部の学年、学級で設けている」としたのは71・7%の76校。浸透ぶりに正直、驚いた。低学年を中心に5~10分間とする学校が目立つ。呼び名は他に「かみかみタイム」「ぱくぱくタイム」など。狙いを問うと、残さず食べきり、栄養を十分取らせる▽食べ物を大事にする気持ちを育む▽食事マナーを定着させる▽そしゃくの推進-など、盛りだくさんの答えが返ってきた。確かに、文部科学省の「食に関する指導の手引」を見ると、これらを身に付けさせるよう求めている。1954年施行の学校給食法では「栄養改善」だった給食の主目的が、2008年の大幅改正で「食育の推進」に転換したことが背景にある。 ◆ ただ、給食指導はそう一筋縄ではいかないらしい。教員に個別に尋ねてみると、こんな本音も。「口から食べ物を飛ばしながら食べる」「おしゃべりに夢中になると一切、箸が動かない」「立ち歩いて人にちょっかいを出す」…。悪戦苦闘する姿が見えてきた。しかも、給食に充てる時間として市教委が示す目安は50分。準備と片付け時間を含むから、食べる時間はせいぜい20~25分だ。おしゃべりを楽しむ時間を担保しながら、集中して食べる時間も設ける-。もぐもぐタイムは、こうした課題に立ち向かうための工夫と言えそうだ。振り返れば昭和の教室では、掃除の時間になっても泣きながら給食を食べさせられていた子どもがいた。心の傷になりそうな光景に比べれば時間内に集中して食べる実践の方が子どもも受け入れやすいだろう。ただ、もぐもぐタイムも押し付けになっていないか、現場も見直す必要がありそうだ。実際にこの取材中、市内の40代男性から「娘は『給食が楽しくなくなった』と不満ばかり言う」との声が寄せられた。もぐもぐタイムは前の学年でもあったが苦ではなかった。それが今の担任は食べる間中、ただただ私語を厳しく禁じて息苦しいと。子どもが強制と感じ、負担になれば逆効果。これも教員の腕次第と言えるだろう。家庭も、学校に任せきりではいられない。文科省の手引には前置きがあった。「食に関する問題は言うまでもなく家庭が中心となって担うもの」。学校は、共働きなどで忙しい家庭を支えるという立ち位置だ。学校が培う食育のノウハウを家庭も共有できたら-。もぐもぐタイムを1分でも短くできるかもしれない。 *8-2:https://cookbiz.jp/soken/news/kyusyoku_koushien2017/ (クックビズ総研 2018年1月5日) おいしい給食日本一を決める「全国学校給食甲子園®」 2017年12月2、3日の2日間、「第12回全国学校給食甲子園®」の決勝大会が、東京の女子栄養大学(駒込キャンパス)で開催されました。これは、実際にこどもたちが食べている学校給食の中から日本一を決める大会です。大会ルールには、実際に学校給食として提供したことのある献立でなければならないこと(複数日分の単品を組み合わせた献立は不可)、文部科学省学校給食摂取基準に基づいていることなどが定められています。また、大会名に「地場産物を活かした我が校の自慢料理」というサブタイトルがついているように、応募する給食の献立は地場産物を使用し、その特色を活かしたものでなくてはなりません。つまり、学校給食の献立内容、調理技術、衛生管理、チームワークなど、トータルで評価される大会なのです。決勝大会には、第4次審査までで選ばれた全国6ブロックの代表12校・施設が参加。応募献立をその場で作り、食味審査が行われます。また、今回初めての試みとして、審査委員をこどもたちに見立てて食育授業を行う「応募献立食育コンテスト」も実施されました。今年は全国から2025校の応募があり、学校給食現場からの意気込みを感じることができました。 ●決勝スタート!制限時間1時間で6食分の給食を調理 「こどもたちのおいしい笑顔のためにベストを尽くすことを誓います」という選手宣誓で大会の火ぶたが切られ、熱い戦いがはじまりました。制限時間は1時間。各出場校・施設から栄養教論(または学校栄養職員)と調理員の計2名が協力して給食6食分を作りあげ、片付けまで終わらせなくてはなりません。(中略) ●甲乙つけがたい!審査委員一同がうなった食味審査 完成した給食は、こども特別審査委員2名を含む、計16名が「食味審査」をします。決勝に残った全12校・施設の給食が審査会場に並べられ、仕上がりと味がチェックされました。主菜・副菜・デザートと献立のバランスも考えられた彩りのよい給食を前に、「一生懸命作ってくれたのだから全校のを食べなくちゃ」「実際にこんなに工夫された献立を食べられるこどもたちはきっと給食が好きでしょうね!」と、審査委員たちからも審査への意気込みが感じられます。おいしそうに試食をしていた審査委員たちに話を聞きました。「今年は地場産物をアピールした献立が多い傾向にありました。とくに野菜をたくさん使っていたのが印象的でしたね。生産者さんの思いまでも伝わるような気がしました」(審査委員長・東京国立博物館長 銭谷眞美さん)。「1996年にO157による集団食中毒が発生して、学校給食がさみしくなり、どうすればいいかわからない時期がありました。それからこの20余年でずいぶん華やかになり、味も質もレベルアップしましたね。非常にうれしく、すばらしいことだと思います」(審査委員・東京医科大学微生物学分野兼任教授 甲斐明美さん)。「地域のものが盛りだくさんで、おいしく食べてほしいという愛情がひしひしと伝わってきます。色もカラフルですし、苦手な食材はこどもたちの好きな味つけにするなど、工夫がされているなと感じました。兵庫県の給食にはもち麦麺を使っていましたが、これは麺を切りそろえるときに出る切れ端だそうですね。フードロス問題の解決にもつながって非常にいいなと思いました」(審査委員・農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長 西経子さん)。「嫌いな大根があったけど、おいしく作ってくれていたから食べられました」(こども特別審査委員) ●いよいよ「日本一の給食」が決定!受賞者は…… 「第12回全国学校給食甲子園®」では、優勝と準優勝以外にも、味のバランスがよい、地場産物をうまく使っているといったさまざまな角度から見た優秀賞が4校に、特別賞が3校に授与されます。また、もっとも優秀な食育授業をした栄養教諭1名に授与される、応募献立食育部門賞も今回初めて設けられました。審査結果の発表時間が近づくと、会場は人で埋め尽くされ、熱気を帯びてきました。選手たちが入場し、審査委員長の講評に続き、いよいよ審査結果の発表です。まずは、決勝に出場した12校・施設すべてに入賞が授与されます。続いて優秀賞、特別賞が発表。呼ばれた学校・施設の選手は喜びいっぱいで壇上し、中には涙ぐむ選手も。審査委員から賞状とトロフィー、メダル、記念品が授与されました(全受賞一覧は、記事末尾を参照ください)。各賞の授与が終わると、いよいよ残すは準優勝と優勝のみとなり、会場にも緊張が走りました。準優勝と優勝は写真・コメントとともにご紹介します。 ◎準優勝 奈良県宇陀市立学校給食センター(学校栄養職員・辰己明子さん、調理員・宇良章子さん) <準優勝校の献立> 宇陀の黒豆ごはん、大和肉鶏のグリル 宇陀産自家製ブルーベリーソース、大和まなのかみかみ酢の物 ゆずの香り、かぶの雪見汁、黒豆を使ったずんだもち風あんもち、牛乳。 地産地消を積極的に推進する宇陀らしい、地域食材がふんだんに使われた献立です。 <準優勝者>辰己明子さん(左)と宇良章子さん 名前が呼ばれたときは、ふたりとも「やったー!」という気持ちでいっぱいだったそう。「食材を届けてくれる農家のみなさん、市民のみなさんのおかげです。こどもたちが『がんばって!』と送り出してくれたので、喜んでくれると思います。」(辰己さん)。「給食センターのみんなといっしょに勝ち取った賞です」(宇良さん)。実は、調理員の宇良さんは、第8回と11回にも参加し、入賞、特別賞を経ての今回の準優勝でした。来年には定年を迎えるため、チャンスはあと1回。「もちろん来年もトライします。目指すのは優勝です!」と意気込んでいました。準優勝校の給食は、食味審査でも大変よい評価を受けていました。「地鶏にブルーベリーソースを合わせるなんて、もはやフランス料理ですね。味も非常にレベルが高かった」と審査委員の中野博さん(元ハイランドリゾートホテル&スパ名誉総料理長)が大絶賛するほどの味だったようです。 ◎優勝 2025校・施設の頂点に輝いたのは、埼玉県越生町立越生小学校(栄養教諭・小林洋介さん、調理員・三好景一さん)。唯一の男性ペアでしたが、栄養教諭、調理員ともに男性のペアで出場し、優勝したのは史上初めてとのこと。 <優勝校の献立> 山吹の花ごはん、越生うめりんつくね、五大尊つつじあえ、上谷の大クス汁、ゆずの里ゼリー、牛乳。 地場産物の米や野菜、特産品の梅やゆずを使うだけなく、観光名所の山吹を表現したごはんや、つつじをイメージさせるあえものなど、食欲をそそる楽しいひと工夫が光る献立です。 <優勝者>小林洋介さん(中央左)、三好景一さん 応援に来ていた同僚調理員の方々も輪に加わって、喜びを分かち合っている姿が印象的。小林さんの熱い思いにまわりが刺激されて食の意識が高まり、いい関係を築いていることが、見てとれる一場面でした。「地元の特産物を活かしたことが評価されたのだと思います。食育は、保護者が関心をもてば、こどもたちも自然と興味を抱くので、保護者も巻き込むようにしています。この優勝によって町の食の意識が高まると思うので、町全体の食育を盛り上げていくのが今後の目標です」(小林さん)。「小林先生の、こどもたちと越生町への愛の大きさでいただいた賞です。先生は給食のことだけでなく町の発展まで考えていて、いつも刺激をもらっています。実は、同い年で同じ血液型。会ったときから、うまくやれると思っていました(笑)。明日からもがんばります!」(三好さん) 。決勝に出場した12校・施設の計24名から各賞が選出されています。各賞の受賞者は次の通りです。 •応募献立食育部門賞(食育コンテストでもっとも優秀な食育授業) 福井県春江坂井学校給食センター(坂井市立東十郷小学校) 栄養教諭・越桐由紀子さん •21世紀構想研究会特別賞 群馬県川場村学校給食センタ- 学校栄養職員・阿部春香さん、調理員・桑原敦志さん •女子栄養大学特別賞 岡山県新見市立新見学校給食センター 栄養教諭・西村香苗さん、調理員・徳永日登美さん •こども審査員特別賞(こどもたちがもっとも食べたい給食) 佐賀県神埼市学校給食共同調理場 栄養教諭・阿部香理さん、調理員・岡健一さん •優秀賞(藤江賞=とくに優れた調理技術を発揮) 愛媛県西条市立神拝小学校 栄養教諭・武方美由紀さん、調理員・川名良子さん •優秀賞(船昌賞=とくに地場産物をうまく活用) 新潟県新潟市立女池小学校 栄養教諭・金永雅美さん、調理員・石塚恵海さん •優秀賞(三井製糖賞=とくに味のバランスに優れていた) 福島県立相馬支援学校 学校栄養職員・服部恵未子さん、調理員・横山千秋さん •優秀賞(武蔵エンジニアリング賞=とくに有効に調理器具を活用) 兵庫県芦屋市立精道小学校 栄養教諭・奥瑞恵さん、調理員・浦口正義さん •準優勝(家族の笑顔 株式会社日本一賞) 奈良県宇陀市立学校給食センター 学校栄養職員・辰己明子さん、調理員・宇良章子さん •優勝(久原本家グループ本社賞) 埼玉県越生町立越生小学校チーム 栄養教諭・小林洋介さん、調理員・三好景一さん <まとめ> 学校給食への意欲ある取り組みと、創意工夫が見られる献立がそろった第12回大会でした。きっと、この大会が現場の栄養教諭や調理員の士気を上げ、ひいては学校や保護者の食育への関心も高めるきっかけになっているのでしょう。また、12回を通してみても、年を追うごとに学校給食の献立内容が進化しており、この大会が現場の技術レベルを押し上げる一助となっているとも言えるのではないでしょうか。海外からも注目される日本の学校給食と「全国学校給食甲子園®」から今後も目が離せません。 *8-3:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1027771.html (琉球新報 2019年11月19日) 心もお腹も満たされる! 地元食材で安くおいしい料理提供 沖縄本島北部で広がる地域食堂 ゆんたくで住民同士につながり 住民が主体となった「地域食堂」の取り組みが本島北部で広がりつつある。いずれも住民同士の交流などを目的に、地域の女性たちが地場産食材を活用して手料理を安価で集落民に提供しており、高齢者を中心に「安くておいしい」「みんなと話すのが楽しい」と好評を得ている。11日、本部町豊川公民館では、住民がおしゃべりを楽しみながら鶏肉の照り焼き、かき揚げ、五目ご飯などに舌鼓を打っていた。地域食堂「キッチンとうばる」は2016年3月から月3回、公民館で月曜正午から1時間開店している。午後に高齢者の体操教室が開かれるのに合わせて日程を決めた。運営スタッフは10人。住民から提供される野菜などを活用し1食200円で40人分用意する。調理と配膳、車のない利用者の送迎を分担している。開設当初から携わる阿波根明子さん(78)は「ご飯食べてゆんたくして体操。これが流れよ」と笑う。喜納曙さん(69)は「1人暮らしの高齢者や独身男性も多い。何か役に立つことを、と那覇市の真地団地の百金食堂を参考に始めた」と振り返り「最初は客が集まらなかったが、今では毎週やってほしいとの声もある。喜ぶ声が励み。今後はスタッフを増やせれば」と語った。よく利用するという60代男性は「1人暮らしで調理が面倒。インスタントで済ませることもあるから、安くで作ってくれると助かる」と話した。兼城昌一区長は「ゆんたく目的の人も多く、交流の場にもなっている」と目を細めた。今帰仁村玉城の「キッチンたも~し」は、メンバー約10人で17年5月から月1回、夕食を大人300円、子ども200円で提供している。スタッフの榎本広枝さん(47)は「昔と比べると『あの子どこの子?』というような顔が見えない状況が生まれていて、地域の横のつながりをつくろうと始めた。子どもを連れて家族で来店する人もいる」と話す。メニューは皆で話し合い、時期ごとにおせちやおでん、クリスマスチキンを出したりもする。10月21日、夫婦で訪れた高良道子さん(87)は「料理は栄養満点。話したことがない人と知り合う機会になっていて、毎回楽しみ」と話し、笑みがこぼれた。地域食堂はこのほか本部町伊野波、今帰仁村の今泊と崎山、国頭村桃原、大宜味村の津波、喜如嘉などの集落で開かれている。 <練習場所や監督・コーチのポストが少ないのが原因なのでは?> PS(2019年11月18日追加):*9-1・*9-2のように、フィギュアスケーターの織田信成氏(32)が関西大アイススケート部監督を辞任し、部員の学力向上などを目指して練習時間の変更に取り組むとコーチの浜田美栄氏(60)から無視されたり、「監督に就任してから偉そうになった」等の陰口を言われたりして、大阪地裁にモラハラの損害賠償請求を提訴されたそうだ。 私は状況を知らないので明確には言えないが、女性フィギュアの経験がなく、女性フィギュアのコーチとしての経験や実績の少ない織田氏が、男性フィギュアで五輪7位に入賞しただけで浜田コーチの上司にあたる女性フィギュアの監督に就任したのは変であるし、練習のさせ方について意見の相違があったのだろうと推測はできる。しかし、女性コーチをモラハラとして提訴するのは、上に立つ女性に対する東アジア独特のよくある批判のようにも見える。 それではどうするのかについては、日本のフィギュアスケート選手はカナダで練習する人が多いが、既に豊かな国になっている日本なら、フィギュアはじめさまざまなスポーツをきちんと習って練習できる大学や施設がもっと多くてよい筈で、それらの競争によって練習方法も切磋琢磨して進歩すると思う。また、大学の方は、ロシア・中国・カナダ・アメリカ・韓国などのフィギュアに強い国が、どのように選手を育てているのかについて研究する必要があるだろう。 *9-1:https://digital.asahi.com/articles/ASMCL4W6LMCLPTIL00Z.html (朝日新聞 2019年11月18日) 織田信成さん、関大コーチを提訴「モラハラあった」 プロフィギュアスケーターの織田信成さん(32)が18日、関西大アイススケート部監督を辞任したのは無視や陰口などのモラルハラスメント(モラハラ)があったからだとして、同部コーチの浜田美栄さん(60)に慰謝料など1100万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。訴状によると、同部出身の織田さんは現役引退後、2017年4月に監督に就任した。就任前の同年2月ごろに浜田さんのレッスン方法を注意した後、無視されるなどのモラハラを受け始めたと主張。今年になって部員の学習時間確保のために練習時間を変更したり、部則に学業成績を考慮する規定を設けようとしたりした後、モラハラが激しくなったとしている。織田さんは体調を崩して入院するなどして5月末から指導が難しくなり、9月に退任せざるを得なかったとして、慰謝料などを求めている。提訴後に会見した織田さんは「学生や選手がよりよい健全な環境で練習できるように、との思いで提訴した」と話した。関西大は「アイススケート競技がシーズンに入り、多くの選手が練習に懸命に取り組んでいる時期に提訴がなされたことは大変残念」とするコメントを発表した。浜田さんは18日夜、朝日新聞の取材に「まだ訴状が届いていないので詳細は分かりかねます。シーズン中であり、生徒の大事な大会も控えておりますので、現時点でのコメントは差し控えさせていただきます」と答えた。 *9-2:https://www.nikkansports.com/sports/news/201911180000317.html (日刊スポーツ 2019年11月18日) 織田信成氏「監督で偉そうに」浜田Cのモラハラ提訴 プロスケーターで9月まで関大(大阪・吹田市)のアイススケート部監督を務めた織田信成氏(32)が18日、同大学の施設(高槻市)で指導する浜田美栄コーチ(60)からモラルハラスメントを受けたとして、1100万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。大阪市内で行われた記者会見に臨んだ織田氏の思いを、担当の弁護士は「フィギュアスケート界の悪弊に一石を投じたい」と代弁。織田氏自身は時折声を詰まらせながら「(浜田コーチと)30歳近く離れていて、僕から何かを言うのは難しい環境だった」と語った。現役時代に10年バンクーバー五輪7位入賞を果たした織田氏は、17年4月に母校である関大のアイススケート部監督に就任。訴状などによるとコーチが「(織田氏が)監督に就任してから、偉そうになった」などと陰口をたたき、今年に入って部員の学力向上などを目指して練習時間の変更に取り組むと、無視などの対応をされたと主張。その結果、40度を超える発熱や筋肉の震えなどで3月26日~4月2日にかけて大阪・高槻市内の病院に入院。以降も恐怖や不安から変調が続いたという。
| 教育・研究開発::2016.12~2020.10 | 09:34 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,10,03, Thursday
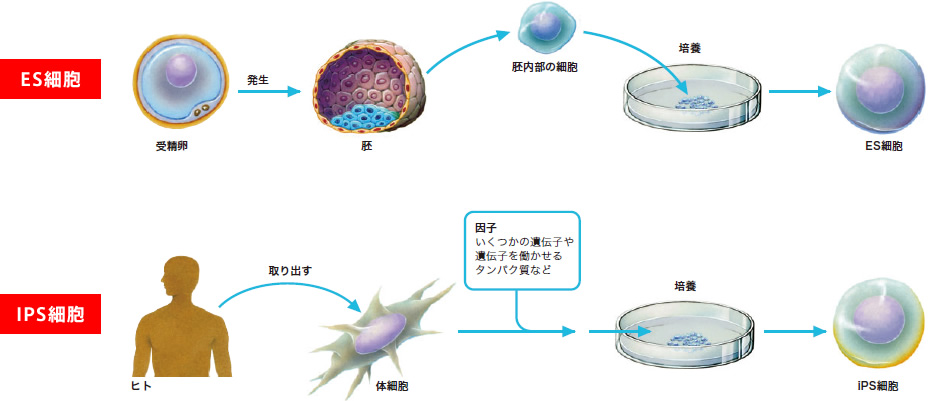 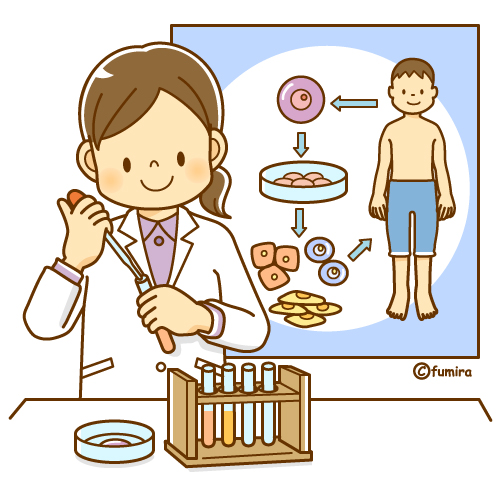 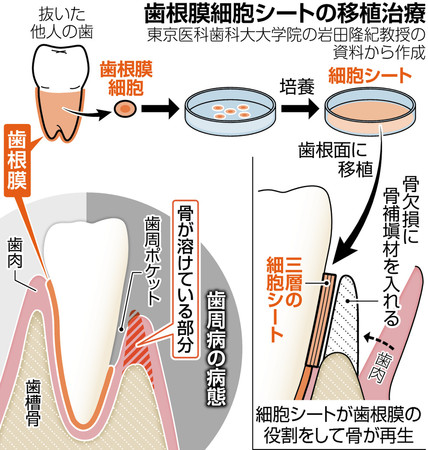 2019.7.19東京新聞 (図の説明:左図のように、初期化されて何にでも分化できる細胞は、卵細胞《ES細胞or胚性幹細胞》とiPS細胞が有名だが、このほかにも成人の体内に幹細胞は多い。これを、中央の図のように、成人から採取して臓器等に成長させ、移植するのが再生医療だ。また、右図のように、既に分化した細胞を増やして、似た組織に移植する方法もある) (1)公立病院の赤字拡大と病院再編 1)公立病院はどうして赤字拡大したのか 日経新聞は、*1-1-1で、「①地方自治体が運営する公立病院の赤字拡大が止まらず、本業の赤字総額が2017年度に4782億円となり2012年度比で5割増えた」「②公立病院は民間病院が手がけたがらない救急・小児科などの不採算医療を提供したり、過疎地の医療水準を維持したりする役割がある」「③赤字を公費で埋め続けると自治体財政が悪化し、保育や介護などの公的サービスにしわ寄せがいく」「④非効率な医療が温存され入院や治療を増やそうとしてムダに医療費が膨らむ」としている。 このうち②は正しく、黒字化だけを考えれば民間病院のように不採算部門は切り捨てて採算がとれる診療科だけを残せばよいのだが、そうすると救急や小児科だけでなく産婦人科のない地域もでき、誰もが速やかに先端医療にアクセスできる状態が保てない。そのため、①になる理由を精査すべきなのであり、④のように非効率な医療が温存されていると単純に言うのは危険だ。さらに、③については、自治体は、医療・介護・保育費用だけを支出しているのではなく、他に節約すべき無駄遣いが多いため、血税を単なる景気対策に使っていないかをこそ確認すべきだ。 なお、*1-1-2のように、医療費は消費税が非課税になっているため、病院が支払った消費税は患者に転嫁できず、病院の自己負担になってしまう。これが公立病院に限らず病院の赤字拡大の大きな原因で、医療費を非課税にすることは消費税導入時から問題になっていた。そのため、非課税ではなく0税率にすれば、支払った消費税が還付され、消費税増税が病院経営に影響しない公正な条件が整うわけである。 さらに、*1-1-1は、公立病院の看護師は民間病院より賃金が高いので無駄遣いだと言わんばかりだが、看護師は労働量や責任と比較して労働条件が悪すぎるのが問題なのであるし、医師にも、*1-3-1のような無給医がおり、無給医でなくとも残業時間の多くは残業代を請求しておらず、労働基準法違反の状態で病院経営がやっと成り立っているのが現状だ。そのため、まず労働条件を一般労働者並みにしてから、病院の本当の赤字額を算出すべきである。 まさか、*1-3-2のように、いい加減で形だけの仕事をしているお役人や人の顔色を見て同調しているだけの人よりも、人の命を助けるために一刻を争う3Kで責任の重い仕事をしている医師・看護師・介護福祉士の賃金の方が安くてよいと言う人はいないと思うが、*1-3-3のように、相応の報酬を支払わなければ真面目で優秀な人がその分野に来ず、医療の場合は、それが私たちの命に直結するのである。 2)それでは、どうすればよいか 厚労省が発信しているのか、メディアの理解がその程度なのかはわからないが、*1-1-3のように、「①診療実績が少なく非効率な医療を招いている」として公立病院と公的病院の25%超にあたる全国424の病院について「②ベッド数や診療機能の縮小なども含む再編統合について議論が必要」として、厚労省が病院名を公表したそうだ。 しかし、①については、どこに住んでいても助かる時間内に治療できる病院にアクセスができるためには、診療実績が少ない病院も出るだろうし、それを非効率と決めつけることもできない。ただ、②のベッド数や入院日数が先進諸外国と比較して多いのなら、それは改善すべきだ。 そのため、その地方自治体の医療計画の下で、地域内の病院がネットワークを作って必要な医療を最小のコストで行うように再編することは必要だが、病院の統合・病床数の削減・診療機能の縮小などを自己目的化してしまうと、日本の医療水準を下げることになる。 そのような中、「団塊の世代の全員が75歳以上になる2025年度をターゲットに、病気が発症した直後の急性期患者向けの病院ベッドを減らす」というのは、「助けないから、早く死んでくれ」と言っているのと同じであり、良識が疑われる。急性期の患者に医療スタッフを手厚く配置するのは当然のことで、これに関して医療費がかさむから病床数を減らすというのは、算術しかできず医療を知らない人の主張であるため、そういう人は、即刻、医療政策の議論から退出してもらいたい。しかし、慢性期の患者を収容するベッド数を適正化して、訪問介護・訪問看護による自宅療養や介護施設での収容に移行するのは、そのインフラを整備してからならよいと思う。 これらについて、北海道新聞は社説で、*1-2-1のように、「病院再編リストは、地域の事情に配慮が足りない」としており、南日本新聞も社説で、*1-2-2のように、「公的病院の再編は、地域実態踏まえて議論せよ」として、日本の南北から反論が出ている。私は、同等以上の治療のできる病院が「助かる時間内のアクセス」で行ける場所にあればよいと思うが、離島・山間部ではドクターヘリを使っても助かる時間内に病院に辿りつくのが困難な場所もあるため、各地域が主導して判断すべきである。 (2)先進医療を使って完治させる方法もある 1)癌の免疫療法 これまでの癌治療は、副作用が激しい割には余命を伸ばす程度の効果しかなかったことを素直に認めるべきだ。その状況の下で、*2-1の癌の免疫療法のように、人間がもともと持っている自然治癒力を強化して癌細胞だけを殺す方法が出てきたのである。これは、癌細胞だけを狙って殺せるため、これまでの化学療法や手術よりも副作用が小さく、効き目も確かだ。 しかし、厚労省は癌の標準治療を今でも「手術」「化学療法(抗がん剤治療)」「放射線治療」としており、この方法では患者が幸福にならない上、要介護者が増えるばかりだ。にもかかわらず、これが科学的根拠に基づいているとして免疫療法を劣後させているのは、理屈がわかっていないため臨機応変に対応することができない人の判断である。私は、他の副作用の多い治療法よりも免疫療法を優先して速やかに保険適用し、癌を治癒させる同様の方法の開発を奨めるべきだと考える。 2)iPS細胞を使った再生医療 東京医科歯科大の武部教授らの研究で、*2-2のように、前腸組織から出るレチノイン酸という物質が、肝臓・胆管・膵臓のもとになる細胞ができるのを促し、ヒトのiPS細胞から肝臓・胆管・膵臓が同時にできたのは快挙だ。これまで、iPS細胞から神経細胞を作っていたが、これにiPS細胞ではなく自分の幹細胞を使えば、「いつまでも分裂し続けるかも知れない」「他人の細胞なら自分の免疫が排除する」というような副作用がなく、*2-4-1のような「どこまで部品交換したら、自分でなくなるか」という問題も起きない。 3)自分の細胞を使った再生医療 東京医科歯科大大学院の岩田教授らが始めた、*2-3の「抜いた親知らずの歯根膜細胞を培養して三層にした細胞シートを歯周ポケットのある歯根面に移植すると、歯根膜が歯根と歯槽骨をつないで歯を支えて細菌の侵入を防ぐとともに、シートから骨形成を促すサイトカイン(タンパク質)が出て骨を再生する」という親知らずを使った新しい再生医療も快挙だ。 このくらいなら、他人の抜いた歯を使った細胞シートを移植しても良いし、「全国の歯周外科にこの治療法が普及すれば、歯周病が引き起こす糖尿病・脳血管疾患・脳梗塞・心臓疾患・関節リウマチ・アルツハイマー病などが減り、医療費の削減効果も大きい」というのは福音だ。 さらに、本人の抜いた親知らずの歯髄を増やせば、脊髄損傷も治療できるのではないかと考えるため、医科と歯科の交流が望まれる。 4)再生医療による臓器移植 ア)3Dプリンターを使うケース 日本は、精密機械の製造技術が進んでいるため、(消毒できない)細胞から無菌で臓器を作るのに適していると言われている。 そのような中、*2-4-1のように、リコーが3DプリンターでiPS細胞から育てた神経細胞を敷いて20層ほど積み重ね、約1cm角のサイコロ形をした神経細胞の塊を作った。このプリンターの技術で様々な形をした細胞の塊を作ったり、異なる細胞を混ぜ合わせたりし、将来は大脳皮質の一部をつくって、脳の治療にも役立てるそうだ。「患者が必要としている機能を提供する」というコンセプトもよいし、応用範囲が広そうだ。 また、イスラエルのテルアビブ大学が3Dプリンターでヒトの細胞を積み上げて血管まで備えたミニ心臓をつくったというのも素晴らしい。この分野は、世界で研究競争が進んでおり、高い目標を掲げれば実現する時代が来ている。そして、これは、臓器移植が臓器不足に直面している中で、より優れた解を与えているのだ。 なお、ブタの身体を使って臓器を作る研究も進んでおり、「どこまで臓器を取り換えても自分でいられるか」については、自分の幹細胞を使えば全く問題はないだろう。しかし、他人のiPS細胞を使う場合は、少なくとも脳が置き換えられない限りは「自己」の意識は存在するものの、そのiPS細胞はドナーの性質を持つため、ドナーを厳選すべきということになる。 イ)ブタを使って腎臓と膵臓の再生を行うケース 慈恵医大と大日本住友製薬が、*2-4-2のように、iPS細胞とブタの胎児組織を使って人の体内で腎臓を作る再生医療の共同研究を始めたそうだ。腎臓は、尿管や糸球体などの複雑な構造を持つためiPS細胞から作るのは難しいとされてきたが、再生医療による人工腎臓を移植できるようになれば完治して透析せずにすむため、患者の福利と医療・介護費用の節約に大きく資するだろう。 また、東京大の中内特任教授は、*2-4-3のように、移植医療用として、人のiPS細胞を使ってブタの体内で人の膵臓をつくる研究を実施する方針を明らかにしたそうだ。 ウ)臓器の骨格だけを使うケース 京都大学の森本教授と国立循環器病研究センターの山岡部長らは、*2-4-4のように、再生医療では幹細胞を目的の細胞に育てて移植する研究が多いが、臓器まで作るのは難しいため、組織の細胞を薬などで除去する脱細胞化技術を使って残った骨格を移植することで早期の臨床応用につなげる治療を行って成功しているそうだ。 また、慶応義塾大学の北川教授らは、肝臓を界面活性剤などで脱細胞化して洗い流して臓器の立体構造を支える骨格だけにし、そこに人のiPS細胞から育てた肝細胞や血管内皮細胞などを入れて大型の立体臓器が作り血管をつなぐ方法を考えているそうだ。 しかし、脱細胞化するのなら、ブタではなく亡くなった方の臓器を使ってもよいため、厚労省は日本製品を作れるよう、速やかにガイドラインを見直すべきだと考える。 5)再生医療に関する倫理 日経新聞は、*2-4-5で、「①創造的破壊の陰には、端緒となる大発見や研究成果がある」「②人類が肉体を補い続ける新たな手段を獲得し、さらに高みに上らんとできるのは、あらゆる細胞に育つiPS細胞が登場したからだ」「③iPS細胞は、京都大学の山中伸弥教授が2007年にヒトの細胞での作製に成功し、12年にノーベル生理学・医学賞を受賞した」と記載している。 しかし、①は正しいものの、最初に発見されたあらゆる細胞に育つ細胞は受精卵(ES細胞)であって、iPS細胞ではない。「受精卵はあらゆる細胞に育つことができるのに、成長すると決まった組織にしかならないのは何故か」という命題を研究して発見されたのが所定の場所では所定の組織にしかならないという法則で、その原理は、*2-2の前腸組織から出るレチノイン酸が、肝臓・胆管・膵臓のもとになる細胞ができるのを促すような、調和を保ちながら合目的的に分化させる遺伝子(DNA)による制御である。そして、そのDNAに傷ついた箇所があると、調和を保ちながら細胞分裂することができずに癌細胞になるわけだ。 そして、他人の卵細胞を使うのは倫理に反するため、既に分化した細胞を初期化する方法を研究している中でiPS細胞が発見され、③のノーベル生理学・医学賞に結び付いたと記憶しているが、その後の研究で、成人の体内にも初期化された細胞は多く存在することがわかった。 そのため、③のみに焦点を当てるのは、既に評価され権威を与えられたものしか評価できない文系のドアホだ。さらに、「人の臓器を量産する試みには、期待や畏怖の念などさまざまな反応が寄せられる」「異次元のイノベーションで、それまでの時代との軋轢がある」という感情論も無駄な悩みだ。その理由は、レントゲンで人の体を透視できるようになったり、抗生物質の出現で治らなかった病気が治るようになったりして人類の寿命が延びたことも異次元のイノベーションだったが、これらがそれまでの時代と軋轢があったかどうかを考えればわかるだろう。 <厚労省の病院再編> *1-1-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43736670V10C19A4SHA000/?n_cid=DSREA001 (日経新聞 2019/4/25) 公立病院、膨らむ「隠れ赤字」 税で穴埋め増える懸念 地方自治体が運営する公立病院の赤字拡大が止まらない。自治体の補填を除いた本業の赤字総額は2017年度に4782億円となり、12年度比で5割増えたことが日本経済新聞の調べでわかった。最終的な損失も膨らんでおり、公的負担が急増する恐れがある。公費投入が増えると、過剰病床の縮小・集約など医療の効率化が遅れる懸念が強まる。 ■本業の赤字は5年で5割増 公立病院は都道府県や市町村がつくり、国立や大学の病院と異なる。民間病院が手がけたがらない救急や小児など不採算の医療を提供したり、過疎地の医療水準を維持したりする役割があり、公費投入に意義はある。ただ赤字を公費で埋め続けると自治体財政は悪化し、保育や介護などの公的サービスにしわ寄せがいく。さらに非効率な医療が温存され、入院や治療を増やそうとしてムダに医療費が膨らむ恐れがある。総務省が集計する公立病院決算は医業収入にも自治体の補助を含み、本業の実態が見えにくい。日経新聞は本業の力を見るため、公費を除く「純医業収支」を独自に算出した。対象は都道府県や市町村が持つ783病院のうち、12~17年度に比較できる671病院。その結果、損益悪化が止まらない状況が判明した。純医業収支が黒字の病院数は12年度の45から17年度は19に減り、全体に占める割合は7%から3%に下がった。合計赤字額は5割増えたのに対し、公費投入額は5%増にとどまり、15年度以降は借入金に頼っている。 ■経営のプロ育たず 環境が厳しいのは民間病院も同じだが、公立病院は非効率な業務構造が温存されている。全国公私病院連盟によると、民間は医業の費用が収入と均衡するが、公立は費用が1割多い。公務員の看護師は人員配置や給与体系を柔軟に変えられない。事務職は短期で異動するため経営のプロが育たず、無駄遣いが生まれやすい。建設費単価は公的な日赤病院などよりも1割ほど高い。厚生労働省の調べでも、17年度の一般病院の経常利益率は民間が2.3%、公立はマイナス1.5%との結果が出た。埼玉県立がんセンター(伊奈町)は典型例だ。13年に建て替えて病床を増やしたものの、患者数は想定を下回り赤字が急増。18年度予算は同センターを含む県立4病院への一般会計からの繰入額が建て替え前の1.8倍に膨らんだ。県病院局は「見通しが甘かった」と認める。 ■首都圏で目立つ公費投入 過大な公費投入は民間との競合が激しい首都圏で目立つ。17年度の1ベッドあたり公費投入額の首位は東京都の617万円で、全国平均の約2倍。総額で見ると都立8病院だけで400億円と、全国の1割近い公費を使った。都病院経営本部は「都立しかできない機能がある」と訴えるが、広尾病院(渋谷区)と大塚病院(豊島区)は空きベッドが増え、外来患者数は全国平均を下回る。日本総合研究所の河村小百合上席主任研究員は「都は財政規模が大きいため、巨額の公費投入が見過ごされている」と指摘する。千葉県も病院に過大投資し、損失の穴埋め額が膨らんだ。国内の病床は過剰感が強く、公立は全国の病床の15%弱に達する。病床を埋めるために入院患者を増やそうとすれば、ムダに医療費が膨らむ。総務省は07年に公立病院改革の指針を作り、全国の公立病院に施設・診療機能の再編を促した。すでに60を超す再編例があるが、多くの地域では再編の取り組みが様々な壁に阻まれている。 ■病院再編、年収減に強い抵抗感 4月1日、兵庫県川西市の市立川西病院の運営者が医療法人・協和会に変わった。赤字脱却を目指すための民間委託だ。3年後に別の場所に新病院を建て、協和会の別病院と統合する。2病院の医師を新病院に集めて救急体制を充実させる。現在の病院跡地には診療所と介護施設を整える。ハードルは市立病院の看護師らの処遇だった。民間運営になると年収が平均153万円、率で3割近く下がる。当初4年は市が差額を補うが、半数の職員は退職か市役所事務職に異動した。「公務員でなくなることに抵抗感は強い」(同病院経営企画部)。川西市はなんとか乗り越えたが、往々にして労務問題は公立病院改革にブレーキをかける。「都立病院は独立行政法人化すべきだ」。2018年1月、東京都は有識者委員会から提言された。実現すれば人事や予算を柔軟に決められる。7千人超が非公務員になるが、都立病院労働組合は「労働条件を悪化させる」と反対を表明。都は「23年度までに検討を進める」(病院経営本部)と、結論を出すかどうかも不透明だ。 ■自治体間の責任分担、調整が難航 複数の自治体が絡むと、運営責任や資金分担を巡り綱引きが生じる。千葉県香取市にある県立病院と国保小見川総合病院(市と東庄町で開設)。数年前に2病院の建て替えとセットの再編案が浮上した。県は市主導で赤字額が大きい県立病院を小見川病院に統合する案を推した。市は責任を押しつけられると警戒し、逆に県主導の建て替えを求め、小見川病院を市単独で建て替えた。これで再編案は消え、県立病院の赤字は膨らんだ。公立病院再編は縦割り意識を脱した発想が要る。08年に地方独立行政法人として発足した日本海総合病院(山形県酒田市)の前身は近接する市立と県立の2病院。県立の赤字が膨らみ、建て替えを控えていた市立病院が統合を提案した。原動力は「このままでは共倒れになる」との危機感だった。県と市、病院間で厳しい調整を重ね、県立は規模を拡大し重症者向け拠点病院、市立は縮小してリハビリ病院とする役割分担を決定。職員には業績手当てを入れた。中小病院との連携も進め、開業以来、黒字を続ける。栗谷義樹理事長は「個々の病院ではなく地域全体の医療を効率的に提供する経営が必要だ」と説く。サービス水準を落とさずに効率化するには、自治体や職員が既得権益にしがみつくのをやめる必要がある。 ■民間との連携がカギ そのためには民間病院をまじえた医療体制の見直しもカギを握る。神奈川県は16年度に、総合病院の汐見台病院(横浜市)を医療法人に譲渡した。知事が「県立は小児科などに特化すべきだ」と判断した。従来の医療を続けることを条件に譲渡先を公募し、毎年7億円超あった公費繰入額はゼロになった。医療情報を分析するケアレビューの加藤良平代表は「都市部は公立病院が民間との役割分担を徹底し、規模を縮小すれば公費に依存する問題は改善する」と指摘する。 【集計方法】総務省がまとめる地方公営企業法が適用される公立病院の「病院事業決算状況」の項目に基づく。医業収益から医業費用を差し引いた医業収支から、さらに自治体の補助金のうち医業収益に含まれる「他会計繰入金」(救急医療と保健衛生行政費)を除いて「純医業収支」を独自に算出した。自治体の公費負担は医業内と医業外の合計額。期間中に再編統合した病院や独立行政法人化した病院は除外した。 *1-1-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/547177/ (西日本新聞 2019/9/30) 増税、負担じわり 非課税の医療費も値上げ 「軽減税率」導入 混乱は必至 消費税率が10月1日から10%に引き上げられる。増税は2014年4月に現在の8%になって以来、5年半ぶり。低所得者の負担軽減や増税に伴う消費の落ち込みを防ぐため、政府は飲食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率制度を初めて導入するのに加え、キャッシュレス決済へのポイント還元など手厚い対策を用意している。ただ、制度が複雑化しており、混乱は必至だ。私たちの暮らしはどう変わるのか。改めてまとめた。電気やガス料金は経過措置で11月分から増税分が上乗せされる。九州電力と西部ガスによると、原燃料価格の変動も加味したモデル家庭の11月料金は、九電の電気料金が10月より93円高い6508円、西部ガスのガス料金が110円高い5827円になる。公共交通の料金も上がる。JR九州は1円単位を四捨五入し、10円単位で値上げ。在来線の初乗り運賃は10円高い170円となる。値上げの割合を示す平均改定率は1・850%。西日本鉄道の路線バスは、区間に応じて10~30円値上げ。100円の区間など、値上げしない区間もある。高速バスは、子会社を含む6社で運行する全34路線のうち31路線で10~400円を値上げする。銀行の手数料は10月1日に引き上げられる。主な銀行の現金自動預払機(ATM)の時間外手数料は108円から110円に。ATMを使って他行に3万円未満を現金で振り込んだ場合の手数料は、540円から550円になる。郵便や宅配の料金も増税の対象だ。通常はがきは1円値上がりして63円に、手紙(25グラム以内の定形郵便物)は2円高い84円になる。8月から新料金に対応したはがきや切手を販売しており、現行のものは今月30日で販売を終了する。ヤマト運輸は10月1日から、宅急便の料金を現金払いは1円単位を切り上げた価格にする。電子マネーやスマートフォンによるキャッシュレス決済の場合は切り上げをしない。一方、消費税が非課税で値上げにならないものもある。住宅の家賃や土地の売買、商品券やプリペイドカードの売買などだ。学校の授業料や火葬料も非課税取引に当たるため今回の増税の影響は受けない。ただ、公的医療保険でカバーされる医療費は消費税の課税対象外だが、医療機関が業者から仕入れる物品などは消費税がかかるため、国は10月から診療報酬を増税分引き上げる。初診料は60円、再診料は10円高くなる。 *1-1-3:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50232120W9A920C1MM8000/ (日経新聞 2019/9/26) 424病院は「再編検討を」 厚労省、全国のリスト公表 厚生労働省は26日、市町村などが運営する公立病院と日本赤十字社などが運営する公的病院の25%超にあたる全国424の病院について「再編統合について特に議論が必要」とする分析をまとめ、病院名を公表した。診療実績が少なく、非効率な医療を招いているためだ。ベッド数や診療機能の縮小なども含む再編を地域で検討し、2020年9月までに対応策を決めるよう求めた。全国1652の公立・公的病院(2017年度時点)のうち、人口100万人以上の区域に位置する病院などを除いた1455病院の診療実績をもとに分析した。がんや救急など高度な医療の診療実績が少ない病院や近隣に機能を代替できる民間病院がある病院について「再編統合について特に議論が必要」と位置づけた。424病院の内訳は公立が257、公的が167だった。今後、厚労省は地域の医療計画をつくる各都道府県に対し、地域内の他の病院などと協議しながら20年9月末までに対応方針を決めるよう求める。他の病院への統合や病床数の削減、診療機能の縮小などを25年までに終えるよう要請する。ただ罰則規定や強制力はなく、権限は各地域に委ねられている。特に公立病院の再編や縮小には住民の反発も予想される。改革が進むかは不透明で、実効性を高める施策が必要になりそうだ。政府は団塊の世代の全員が75歳以上になる25年度をターゲットに、病気が発症した直後の「急性期」の患者向けの病院ベッドを減らす「地域医療構想」を進めている。看護師などを手厚く配置するため医療費もかさむのに、病床数は過剰となっているためだ。ただ各地域が医療計画で示した急性期病床の削減率は公立病院全体で5%にとどまっている。このため厚労省は縮小する余地のある過剰な医療の実態を明らかにするため、この春から分析を進めていた。 厚労省が再編の検討を求めた公立・公的病院 【北海道】北海道社会事業協会函館、木古内町国保、国立病院機構函館、市立函館南芽部、函館赤十字、函館市医師会、森町国保、松前町立松前、厚沢部町国保、奥尻町国保、長万部町立、八雲町熊石国保、せたな町立国保、今金町国保、北海道社会事業協会岩内、国保由仁町立、市立三笠総合、国保町立南幌、国保月形町立、栗山赤十字、市立芦別、北海道社会事業協会洞爺、地域医療機能推進機構登別、白老町立国保、日高町立門別国保、新ひだか町立三石国保、新ひだか町立静内、市立旭川、国保町立和寒、JA北海道厚生連美深厚生、町立下川、上富良野町立、猿払村国保、豊富町国保、利尻島国保中央、中頓別町国保、斜里町国保、小清水赤十字、JA北海道厚生連常呂厚生、滝上町国保、雄武町国保、興部町国保、広尾町国保、鹿追町国保、公立芽室、本別町国保、十勝いけだ地域医療センター、清水赤十字、町立厚岸、JA北海道厚生連摩周厚生、標茶町立、標津町国保標津、町立別海、市立美唄 【青森】国保板柳中央、町立大鰐、国保おいらせ、国保南部町医療センター、国保五戸総合、三戸町国保三戸中央、青森市立浪岡、平内町国保平内中央、つがる西北五広域連合かなぎ、黒石市国保黒石 【秋田】大館市立扇田、湖東厚生、市立大森、地域医療機能推進機構秋田、羽後町立羽後 【岩手】国立病院機構盛岡、岩手県立東和、岩手県立江刺、奥州市国保まごころ、一関市国保藤沢、洋野町国保種市、岩手県立一戸、岩手県立軽米、盛岡市立、奥州市総合水沢 【宮城】蔵王町国保蔵王、丸森町国保丸森、地域医療機能推進機構仙台南、国立病院機構仙台西多賀、国立病院機構宮城、塩竈市立、宮城県立循環器・呼吸器病センター、栗原市立若柳、大崎市民病院岩出山分院、公立加美、栗原市立栗駒、大崎市民病院鳴子温泉分院、美里町立南郷、湧谷町国保、石巻市立牡鹿、登米市立米谷、登米市立豊里、石巻市立、南三陸 【山形】天童市民、朝日町立、山形県立河北、寒河江市立、町立真室川、公立高畠、酒田市立八幡 【福島】済生会川俣、地域医療機能推進機構二本松、三春町立三春、公立岩瀬、福島県厚生連鹿島厚生、福島県厚生連高田厚生、福島県厚生連坂下厚生総合、済生会福島総合 【栃木】地域医療機能推進機構うつのみや、国立病院機構宇都宮 【群馬】群馬県済生会前橋、伊勢崎佐波医師会、公立碓氷、下仁田厚生 【茨城】笠間市立、小美玉市医療センター、国家公務員共済組合連合会水府、村立東海、国立病院機構霞ケ浦医療センター、筑西市民 【千葉】千葉県千葉リハビリテーションセンター、国立病院機構千葉東、地域医療機能推進機構千葉、千葉市立青葉、銚子市立、国保多古中央、東陽、南房総市立富山国保、鴨川市立国保、国保直営君津中央病院大佐和分院 【埼玉】蕨市立、地域医療機能推進機構埼玉北部医療センター、北里大学メディカルセンター、東松山医師会、所沢市市民医療センター、国立病院機構東埼玉、東松山市立市民 【東京】国家公務員共済連九段坂、東京都台東区立台東、済生会支部東京都済生会中央、東京大学医科学研究所付属、東京都済生会向島、地域医療機能推進機構東京城東、奥多摩町国保奥多摩、国立病院機構村山医療センター、東京都立神経、国民健康保険町立八丈 【神奈川】川崎市立井田、三浦市立、済生会平塚、秦野赤十字、国立病院機構神奈川、相模原赤十字、東芝林間、済生会神奈川県、済生会若草、横須賀市立市民 【新潟】新潟県立坂町、新潟県立リウマチセンター、新潟県厚生連新潟医療センター、国立病院機構西新潟中央、豊栄、あがの市民、新潟県立吉田、三条総合、新潟県立加茂、見附市立、国立病院機構新潟、厚生連小千谷総合、新潟県立松代、新潟県立妙高、上越地域医療センター、新潟県立柿崎、新潟県厚生連けいなん総合、魚沼市立小出、南魚沼市立ゆきぐに大和、町立湯沢、労働者健康福祉機構新潟労災、佐渡市立両津 【富山】あさひ総合、富山県厚生連滑川、富山県リハビリテーション・こども支援センター、かみいち総合、地域医療機能推進機構高岡ふしき 【石川】国保能美市立、国家公務員共済組合連合会北陸、津幡町国保直営河北中央、町立富来病院、町立宝達志水、公立つるぎ、地域医療機能推進機構金沢 【福井】国立病院機構あわら、坂井市立三国、越前町国保織田、地域医療機能推進機構若狭高浜 【山梨】地域医療機能推進機構山梨、北杜市立塩川、韮崎市国保韮崎市立、北杜市立甲陽、山梨市立牧丘、甲州市立勝沼、身延町早川町国保病院一部事務組合立飯富 【静岡】JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉、伊豆赤十字、国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター、JA静岡厚生連清水厚生、JA静岡厚生連静岡厚生、地域医療機能推進機構桜ケ丘、菊川市立総合、市立御前崎総合、公立森町、浜松赤十字、市立湖西、JA静岡厚生連遠州、労働者健康福祉機構浜松労災、共立蒲原総合 【長野】川西赤十字、佐久穂町立千曲、長野県厚生連佐久総合病院小海分院、東御市民、国保依田窪、長野県厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯、長野県厚生連下伊那厚生、下伊那赤十字、国立病院機構まつもと医療センター松本、国立病院機構まつもと医療センター中信松本、安曇野赤十字、飯綱町立飯綱、長野県立総合リハビリテーションセンター、信越、飯山赤十字 【岐阜】岐阜県厚生連岐北厚生、羽鳥市民、岐阜県厚生連西美濃厚生、県北西部地域医療センター国保白鳥、国保坂下、市立恵那、岐阜県厚生連東濃厚生、国保飛騨市民、厚生会多治見市民 【愛知】津島市民、あま市民、一宮市立木曽川市民、愛知県心身障害者コロニー中央、みよし市民、碧南市民、中日、国立病院機構東名古屋、ブラザー記念 【三重】三重県厚生連三重北医療センター菰野厚生、三重県厚生連大台厚生、済生会明和、町立南伊勢、市立伊勢総合、桑名南医療センター、亀山市立医療センター 【滋賀】地域医療機能推進機構滋賀、大津赤十字志賀、守山市民、東近江市立能登川、長浜市立湖北 【奈良】済生会中和、奈良県総合リハビリテーションセンター、済生会御所、南和広域医療企業団吉野、済生会奈良 【京都】国立病院機構宇多野、市立福知山市民病院大江分院、舞鶴赤十字、国保京丹波町 【大阪】大阪市立弘済院附属、仙養会北摂総合、市立藤井寺市民、冨田林、済生会支部大阪府済生会新泉南、和泉市立、生長会阪南市民、健保連大阪中央、高槻赤十字、市立柏原 【和歌山】海南医療センター、国保野上厚生総合、済生会和歌山、国保すさみ、那智勝浦町立温泉 【兵庫】兵庫県立リハビリテーション中央、国家公務員共済連六甲、高砂市民、明石市立市民、多可赤十字、公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター、公立香住、公立豊岡組合立豊岡病院日高医療センター、公立村岡、国立病院機構兵庫中央、兵庫県立姫路循環器病センター、相生市民、たつの市民、加東市民、柏原赤十字 【鳥取】岩美町国保岩美、日南町国保日南、南部町国保西伯、鳥取県済生会境港総合 【島根】国立病院機構松江医療センター、地域医療機能推進機構玉造、出雲市立総合医療センター、津和野共存 【岡山】備前市国保市立備前、岡山市久米南町組合立国保福渡、総合病院玉野市立玉野市民、せのお、備前市国保市立吉永、労働者健康安全機構吉備高原医療リハビリテーションセンター、瀬戸内市立瀬戸内市民、赤磐医師会、笠岡市立市民、矢掛町国保、国立病院機構南岡山医療センター、井原市立井原市民、鏡野町国保 【広島】北広島町豊平、国家公務員共済連吉島、広島市医師会運営・安芸市民、広島県済生会呉病院、呉市医師会、国家公務員共済連呉共済病院忠海分院、日立造船健保組合因島総合、三原市医師会、府中北市民、国立病院機構広島西医療センター、総合病院三原赤十字、府中市民、総合病院庄原赤十字 【山口】岩国市立錦中央、岩国市立美和、光市立大和総合、周南市立新南陽市民、地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会、光市立光総合、美祢市立美東、美祢市立、小野田赤十字、下関市立豊田中央、岩国市医療センター医師会、厚生連小郡第一総合、国立病院機構山口宇部医療センター、山陽小野田市民 【徳島】国立病院機構東徳島医療センター、徳島県鳴門、阿波、海陽町国保海南、国保勝浦、阿南医師会中央 【香川】国立病院機構高松医療センター、香川県厚生連滝宮総合、さぬき市民、済生会支部香川県済生会 【愛媛】国立病院機構愛媛医療センター、宇和島市立吉田、宇和島市立津島、西条市立周桑、鬼北町立北宇和、愛媛県立南宇和 【高知】JA高知、佐川町立高北国保、地域医療機能推進機構高知西、いの町立国保仁淀、土佐市立土佐市民 【福岡】福岡県立粕屋新光園、嶋田、嘉麻赤十字、飯塚嘉穂、労働者健康安全機構総合せき損センター、川崎町立、中間市立、遠賀中間医師会おんが、北九州市立総合療育センター、芦屋中央、宗像医師会、国立病院機構大牟田、飯塚市立 【佐賀】小城市民、国立病院機構東佐賀、地域医療機能推進機構伊万里松浦、町立太良、多久市立 【長崎】日本赤十字社長崎原爆、国保平戸市民、平戸市立生月、市立大村市民、日本赤十字社長崎原爆諫早、長崎県富江、北松中央 【大分】杵築市立山香、臼杵市医師会立コスモス、竹田医師会 【宮崎】地域医療機能推進機構宮崎江南、国立病院機構宮崎東、五ケ瀬町国保、日南市立中部、えびの市立、都農町国保、国立病院機構宮崎 【熊本】国保宇城市民、国立病院機構熊本南、小国公立、天草市立牛深市民、熊本市医師会熊本地域医療センター、熊本市立植木、熊本市立熊本市民 【鹿児島】済生会鹿児島、鹿児島市医師会、鹿児島厚生連、鹿児島赤十字、枕崎市立、南さつま市立坊津、肝付町立、公立種子島 【沖縄】なし *1-2-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/349451 (北海道新聞社説 2019.9.29) 病院再編リスト 地域事情に配慮足りぬ 厚生労働省は、全国1455の公立病院や日赤などの公的病院のうち、診療実績が乏しく、再編・統合の議論が必要とする424の病院名を初めて公表した。高齢化により膨張する医療費を抑制する狙いがあるという。そのうち道内は111病院中54病院と全都道府県で最も多く、道民生活に与える影響が大きい。道内は面積が広大で、公共交通機関に恵まれず、通院に時間がかかる人も多い。とりわけ冬季はままならなくなる。大都市と過疎地に一律の基準を当てはめ、再編・統合を促すのは無理があろう。対象となった病院や自治体などから反発や戸惑いの声が挙がるのも当然だ。無年金や低年金で暮らす高齢者もいる。弱者の切り捨てにつながる再編・統合は許されない。厚労省は、来年9月までに結論を出すよう都道府県を通じて対象病院に求める方針だ。道は各地の実情を十二分に考慮し、住民一人一人に寄り添い、丁寧に議論を進めてもらいたい。今回、厚労省は2017年度のデータを基に、がんや脳卒中、救急など9項目の診療実績と、競合する病院が車で20分以内の場所にあるかで分析し、判断した。機械的にリストを作成し、一方的に名指しするのは、乱暴だと言わざるを得ない。18年度の医療費は42兆6千億円と過去最高を記録し、団塊の世代が全員75歳以上になる25年度にはさらに大きく膨らむ。医療費削減のため、政府は25年時点の望ましい病床数が全国で約119万床になると推計し、都道府県に計画を策定させた。この通り進めるには、現状より5万床以上減らす必要がある。手術や救急に対応し医療費のかかる「急性期」の病床数を減らし、在宅医療やリハビリ向け病床への転換を促すという。広い道内で急性期病床を減らせば、道民の命に関わりかねない。公立・公的病院は地域コミュニティーの核となる存在だ。強引に再編・統合を進めれば、過疎地の人口減に拍車がかかり、地域崩壊を招く懸念が拭えない。道は、21の医療圏ごとに協議会を設け、再編・統合など地域医療のあり方を検討中だ。医師不足は深刻で、公立・公的病院の多くが赤字経営になるなど課題は山積している。住民の声に耳を傾け、安心できる医療体制の将来像を示してほしい。 *1-2-2:https://373news.com/_column/syasetu.php?storyid=110686 (南日本新聞社説 2019.9.28) [公的病院の再編] 地域実態踏まえ議論を 厚生労働省は、診療実績が乏しく再編・統合の議論が必要と判断した全国424の公立・公的病院名を公表した。鹿児島県内では鹿児島市医師会病院など8病院が対象となった。年々増加の一途をたどる医療費の抑制は待ったなしの課題である。団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になる2025年が目前に迫り、医療提供体制の見直しは避けられない状況だ。だが、再編されれば適切な医療サービスを受けられなくなるという住民の不安は大きい。政府、都道府県は数字によって機械的に進めるのではなく、地域の実態に十分配慮すべきだ。今回、17年度のデータを基に重症患者向けの「高度急性期」、一般的な手術をする「急性期」に対応できる1455病院を調査。がんや救急医療といった9項目の診療実績と、競合する病院が「車で20分以内」の場所にあるかを分析した。再編・統合検討が必要とされたのは全体の約3割だった。厚労省によると、対象の病院には、廃止や病床(ベッド)削減、機能転換、他の病院への診療科移転などを検討してもらう。来年9月までに結論を出すよう、都道府県を通じて対象病院に要請するとしている。政府は自宅など住み慣れた地域で暮らせるよう「地域包括ケアシステム」の構築を目指している。一方、医療提供体制の見直しでは、民間を含めて全国で124万6000床(18年)ある病院のベッド数を25年に119万1000床まで減らす方針だ。病院のベッドに関しては、少子高齢化などに伴う人口構成の変化に合わせた機能転換が求められている。現状では「高度急性期」「急性期」のベッド数が多く、高齢者にニーズの高いリハビリ向けは不足しており、ミスマッチ是正が課題となってきた。今回、病院名公表に踏み切ったのは、特に停滞している公立・公的病院の再編・統合の議論を加速させる狙いがある。ただ、懸念される問題点は多い。そもそも、へき地や離島にある病院の役割を考えれば、経済合理性重視で評価を下せるものではない。長年頼みにしてきた地域の病院が遠隔地に統合されるとなると住民の不利益は計り知れない。県内で対象となった病院の地元からは反発の声が出ている。公立種子島病院(南種子町)は島中南部の医療拠点だが、再編されれば車で1時間以上かかる西之表市に行かなければならなくなる。交通手段のない高齢者にとっては深刻な問題だ。国の借金や将来世代の負担を考えれば、再編に切り込むのは理解できる。だが、数字を挙げて指摘するだけでは地元は納得しまい。行政と共に住民も加わり、地域医療のあるべき姿について真摯(しんし)に議論することが重要である。 *1-3-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019062802000276.html (東京新聞 2019年6月28日) 無給医、50病院に2100人 大半雇用契約なし 大学病院、研究名目で診療 文部科学省は二十八日、労働として診療を行っているのに給与が支払われない「無給医」が、五十の大学病院に計二千百九十一人いたと発表した。調査対象とした医師約三万二千人の7%に上るが、まだ各大学が精査中の医師が千三百四人いて、人数がさらに増える可能性がある。無給医の多くは雇用契約を結ばず、労災保険も未加入だった。各大学は文科省の指導に基づき、給与の支払いや雇用契約の締結を進める。大学病院には、大学院生らのほか、自己研さんや研究目的の医師が在籍し、その一環で診療に携わる場合には給与を支払わない慣習が広く存在する。今回の調査では、診療のローテーションに組み込まれていた場合などを実質的な労働だったとし、給与の支払いがない医師を無給医とした。判断は各大学が専門家らに相談して行った。調査は一~五月、国公私立九十九大学の百八付属病院に在籍する医師と歯科医師を対象に実施。昨年九月に診療に従事した計三万一千八百一人(教員や初期研修医を除く)について、同月の給与の支給状況などをまとめた。無給医と確認された二千百九十一人のうち、合理的な理由なく給与を支払っていなかったのは五十病院のうち二十七病院の七百五十一人。契約上は週二日なのに実際は週四日診療しているような例も含まれ、最大二年間さかのぼって支払う。残る千四百四十人は五十病院のうち三十五病院に所属し、無給の合理的な理由はあるが、診療の頻度や内容を踏まえて今後は給与を支給する。これらとは別に、六十六病院の三千五百九十四人が、ほかの所属先から大学病院で働いた分も含めて給与を受け取っているなど、合理的な理由があり給与を支給しない現状を維持するとした。病院別では、無給医が最も多かったのは順天堂大順天堂医院の百九十七人(対象者の46%)で、北海道大病院百四十六人(同24%)、東京歯科大水道橋病院百三十二人(同62%)が続いた。昭和大歯科病院は百十九人、愛知学院大歯学部病院百十八人で、それぞれ対象者全員が無給医だった。無給医かどうか精査中の千三百四人の内訳は、日本大板橋病院三百二十一人、東大病院二百三十九人、日大歯科病院二百十一人、慶応大病院二百人など。全対象者のうち、合理的な理由なく雇用契約を結んでいなかった医師は千六百三十人、労災保険の対象外だったのは千七百五人だった。多くの無給医は深夜や休日に、別の医療機関でアルバイトなどをして生活費を得ており、過重労働による診療への悪影響などが懸念されている。 ◆医療事故の責任あいまいに <全国医師ユニオンの植山直人代表の話> 文部科学省の調査は大学病院に報告を求める形で実施され、病院によって調査手法や無給医かどうかの判断に違いがある。今回明らかになった結果は氷山の一角で、実際はもっと多いだろう。いくら研修や研究のために病院にいるといっても、免許を持つ医師が診療をし、病院が報酬を得ている以上は賃金が払われるのが当然だ。加えて、雇用契約がなければ、労働時間の管理もなされず、医療事故が起きた際に責任の所在があいまいになることで患者の不利益にもなりかねない。早急な改善が必要で、国もフォローアップしていくべきだ。 <無給医> 大学病院などで実質的に労働の実態があるのに、給料が支払われていないと判断された医師。病院の人件費が限られているため、便宜的に無給とされたり、一部しか支払われなかったりするケースがある。(1)大学院生らが教育や研修名目で働かされる(2)契約した以上に勤務に入れられる-など、形態はさまざま。病院で診察や病棟管理を担う一方、生活費を稼ぐために深夜や休日にアルバイトをして、過労死した医師もいる。 *1-3-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201909/CK2019093002000231.html (東京新聞 2019年9月30日) 調査手法を情報公開 統計不正 総務省が再発防止策 政府の統計不正の再発防止策を話し合う総務省の統計委員会は三十日、会合を開き、毎月勤労統計の重点的な検証結果を盛り込んだ報告書を正式決定した。統計の調査手法などを積極的に情報公開し、透明性の高い作業環境づくりを促すことが柱。外部の目を光らせることによって再発防止につなげる。報告書では、毎月勤労統計を所管する厚生労働省に対して詳細な調査手法の公開に加え、業務マニュアルを整備して全ての職員が作業内容を把握できるようにすることを求めた。特定の職員が長期に業務を担い、不正が見過ごされてきた反省を踏まえた。外部の研究者にとって調査データを利用しやすくする環境整備も促している。不正が発覚した後、過去のデータが一部で保存されておらず再集計が困難になった。このため、必要な情報を電子化して永久保存することを要請。八月に大阪府の調査員による虚偽報告が発覚したことを受け、調査員が業務上の困り事を相談できる窓口も設ける。報告書を受け取った高市早苗総務相は記者団に「統計の品質の向上と信頼性の確保に取り組みたい。厚労省が二度と同じ過ちを繰り返さないのはもちろんだが、統計は国民が合理的な判断をするための重要な情報で全ての府省が対策を進めてほしい」と述べた。 <勤労統計不正> 企業の賃金や労働時間を把握する「毎月勤労統計」で、厚生労働省が不正な調査手法を取っていた問題。2004年から東京都の500人以上の事業所で、本来の全数調査でなく抽出した3分の1程度しか調べていなかった。統計を基に算出する雇用保険や労災保険、船員保険の給付額が本来より低くなり、延べ約2000万人が過少支給になった。雇用形態や学歴など労働者の属性別に賃金を把握する「賃金構造基本統計」でも計画と異なる郵送調査をしていた。 *1-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190929&ng=DGKKZO50303850X20C19A9MM8000 (日経新聞 2019.9.29) 米IT人材獲得戦 異状あり、インド系半減 囲い込むGAFA 米国のIT(情報技術)人材の争奪戦に異変が起きている。世界から人材を引き寄せるのが米IT産業の強みだったが、トランプ政権がビザ(査証)発給を厳格にして相対的に賃金が低い案件の承認を一気に絞った。インド系のIT大手での承認が急減した一方、グーグルなど「GAFA」は高報酬をテコに承認を増やし、むしろ人材の囲い込みに拍車をかけている。米国は「H1B」ビザでIT人材などを受け入れてきた。受給者はインド出身が7割に及ぶ。米国での起業を夢見る若者。世界の優秀な人材を選べる企業。米国発のイノベーションの「舞台装置」だ。「オバマ政権なら3週間でとれるといわれていたのに」。インターネットを使った教育事業をシリコンバレーで始めようとした日本人起業家、真田諒さん(35)は頭を抱えた。インド出身の技術者を採用しようとしたが、H1Bの申請がいっこうに受理されない。当局と4カ月にわたるやり取りの末、技術者の年収を当初の8万ドル(約860万円)から13万ドル弱に引き上げ、やっと承認にこぎつけた。トランプ政権は2017年の大統領令でH1Bビザの審査を厳しくした。移民局によると、18年度(17年10月~18年9月)の承認件数は新規と更新の合計で約33万5000件と前年度から1割減った。雇用主企業別では、システム構築や保守を請け負うITサービス企業の急減が目立つ。インドに本社を持つインフォシスとタタ・コンサルタンシー・サービシズ、同国を開発の主力拠点とするコグニザント・テクノロジー・ソリューションズのいわゆる「インド系」大手3社は承認上位の常連だったが、18年度の承認は3社合計で59%減った。かねて「高度人材の名のもとに割安な賃金で労働者を呼び、米国人の職を奪う」との批判もあった。「高学歴の申請を優先する仕組み」(米法律事務所)に変え、米国人と競合しそうな「中技能・中所得」に狙いを定めて発給を絞り込んだ可能性が高い。「成果」は出ているようだ。インフォシスは19年半ばまでの2年間に米国内で新たに1万人を雇用した。インドから大勢のIT人材を連れてくることが難しくなり、代わりに米国に拠点をつくって地元の大学で採用を増やした。対照的に、グーグルなどのGAFAはH1BでのIT人材の獲得を加速させている。4社合計の承認件数は18年度に28%増え、インド系との差が急縮小している。GAFAがビザの申請対象者に示した年収(中央値)は12万~15万ドルとインド系の8万ドル前後を上回り、「賃上げ」も続く。動画配信のネットフリックスも報酬を引き上げて人材獲得を急ぐ。「高技能・高収入」なら審査が通りやすい状況を活用し、したたかに動く姿が浮かぶ。ビザ申請の年収をみると、日本勢はインド系に近い位置にとどまる。世界で人事・報酬制度を見直している日立製作所。カリフォルニア州のデジタル子会社では高報酬の用意を整えつつあるが「日本の本社への配慮もあって制度全体としては踏み込めていない」と人事担当者は漏らす。米国の異変は他の国々にはIT人材を得る好機にもなる。カナダや英国はすぐに人材の囲い込みに動いた。日本も柔軟な給与体系づくりや待遇の改善を急がないと、せっかくの機会を逃しかねない。 <先進医療> *2-1:https://mainichi.jp/articles/20190227/ddm/005/070/039000c (毎日新聞 2019年2月27日) がん新免疫療法 公的保険でどう支えるか 新たながん免疫療法として期待される「CAR-T細胞療法」に使われる製剤の製造・販売が、厚生労働省の専門部会で承認された。今夏にも公的医療保険が適用される。効果は高いが、治療費も超高額なことでも注目されていた新薬だ。こうした薬を医療保険制度にどう組み込んでいくのか。国民皆保険の日本が直面する大きな課題と言える。承認されたのは製薬大手ノバルティスファーマの「キムリア」だ。患者から取り出した免疫細胞に遺伝子操作を加え、がん細胞への攻撃力を高めた製剤で、点滴で体内に戻す。これがCAR-T細胞療法で、キムリアは特定の白血病とリンパ腫の患者の一部が対象となる。 患者数は年間約250人と予測されている。臨床試験では白血病患者の8割で症状が大幅に改善した。 他の病気でも同種の技術を使う治療法の開発が進んでおり、がん治療の新たな柱になる可能性を秘める。ただ、キムリアの臨床試験では重い副作用が出るケースも報告されている。体制が整った医療施設で、慎重に効果を見極める必要がある。キムリアの日本の薬価はこれから決まるが、米国では1回の治療に約5200万円かかる。巨額の開発費に加え、製造工程も複雑だからだ。日本には高額療養費制度があるため、超高額な新薬でも、患者の自己負担には上限がある。一方で、高額な薬の保険適用が拡大すれば、医療財政の圧迫は避けられない。超高額な薬価で話題になったがん免疫治療薬「オプジーボ」の価格引き下げ騒動を教訓に、厚労省は、市場規模が拡大した薬については、薬価の改定時期を2年に1回から年4回に見直した。適切に運用していく必要がある。米国では、キムリアの投与から1カ月後に治療効果が上がった場合に限り、製薬企業に費用が支払われる。企業の新薬開発意欲を保ちつつ、薬剤費の膨張を抑える方策として、日本でも検討の余地がある。貧富の差を問わず、一定の医療が受けられることが皆保険の利点だ。高額だが有効性の高い薬に保険を適用するため、症状の軽い病気に使う薬は患者負担を増やして財政のバランスをとる。そんな観点での国民的な議論も深めるべきだ。 *2-2:https://digital.asahi.com/articles/ASM9M567MM9MULBJ00H.html?iref=comtop_list_sci_f02 (朝日新聞 2019年9月26日) iPS細胞から「ミニ多臓器」初成功 東京医科歯科大 ヒトのiPS細胞から、肝臓と胆管、膵臓(すいぞう)を同時につくることができたと、東京医科歯科大の武部貴則教授らの研究チームが発表した。iPS細胞から、それぞれの臓器がつながった「ミニ多臓器」をつくったのは初めてという。論文は25日付の英科学誌ネイチャーに掲載される。iPS細胞を使ったこれまでの研究は、神経や心臓の細胞といった特定の細胞をつくるものが多かった。武部さんらは2013年、iPS細胞から初めての臓器となる「ミニ肝臓」をつくった。しかし、一つの臓器をつくって移植したとしても、機能が十分に発揮されなかったり長く働かなかったりするという課題があった。研究チームは、iPS細胞から複数の臓器を同時につくれないかと考えた。まず、iPS細胞から前腸組織と中腸組織という消化器系の臓器のもとになる二つの組織をつくった。これをくっつけたところ、境界部分に肝臓、胆管、膵臓のもとになる細胞が出現した。この細胞を培養すると、肝臓と胆管と膵臓がつながったミニ多臓器ができた。受精から1~2カ月の胎児の臓器ほどの大きさという。チームは前腸組織から出るレチノイン酸という物質が、肝臓、胆管、膵臓のもとになる細胞ができるのを促したとみている。実際にヒトに移植するには臓器とともに血管なども同時につくらなければならない。武部さんは「まだ基礎研究の段階だが、10年以内に今回開発した技術を実用化させて患者に届くようにしたい」と話している。 *2-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201907/CK2019071902000182.html (東京新聞 2019年7月19日) 細胞シートで歯周病治療 抜いた親知らず捨てずに活用 親知らずが歯周病患者を救う-。抜いた親知らずなどから採取した細胞を培養して細胞シートを作り、患部に貼り付けて歯周病を治療する治験(臨床試験)を、東京医科歯科大大学院の岩田隆紀教授(46)らが始めた。医療廃棄物として捨てられていた親知らずなどを使った新しい再生医療。高齢になっても多くの歯が残れば、生活の質の向上が期待できそうだ。歯周病は歯と歯肉の間に細菌が増え、歯こうが蓄積することで歯茎に腫れや出血を起こす。進行すると歯と歯肉の境目(歯周ポケット)が深くなり、歯を支える歯槽骨を毒素が溶かす。新しい再生医療は、抜いた歯の歯根膜細胞を培養して三層にした細胞シートを、歯周ポケットのある歯根面に移植する。歯根膜は、歯根と歯槽骨をつないで歯を支え、細菌の侵入を防ぐ。シートからは骨形成を促すサイトカイン(タンパク質)が出る。つまりシートが歯根膜の役割をして骨を再生する。移植手術では、歯槽骨が欠けた部分に顆粒(かりゅう)状の骨補填(ほてん)材を入れて歯肉を縫合する。手術は一時間程度。外来で済む。岩田さんらは二〇一一年から、患者自身の抜いた歯で細胞シートを培養して移植する臨床研究に着手した。重症七人を含む十人(三十三~六十三歳の男女各五人)に行った移植では、現在も拒絶反応や痛みなどは起きていない。歯周ポケットの深さは術前の平均五・六ミリから正常範囲の同二・四ミリに。歯槽骨の再生も維持できているという。これを受け、岩田さんらは東京女子医科大歯科口腔(こうくう)外科の安藤智博教授のグループと昨年末から、他人の抜いた歯を使った細胞シートを移植する治験を始めた。既に六十四歳女性など三人に実施。本年度中にさらに三例の移植を行い、二〇年度中に安全性と有効性を検証する。岩田さんによると、抜いた歯一本から一万シートの生産が可能で、一シートで二、三本の移植ができる。現在は七本の歯から培養した約七万製品分の細胞を凍結保存中。岩田さんは「全国の歯周外科にこの治療法が普及すれば、歯周病が引き起こす糖尿病や脳血管疾患が減り、医療費の削減効果も大きい」と話す。 ◆歯磨き、食生活…予防も大切 歯を失う原因として最も多い四割を占めるとされる歯周病。厚生労働省の患者調査では二〇一七年に約三百九十八万人に達する。日本歯周病学会理事の専門医で、東京都内で開業している若林健史さん(62)に、どう防ぐかを聞いた。予防の決め手はフロスや歯間ブラシなども使った歯磨きの励行。菓子や炭酸飲料など糖分の多い食生活を見直すことも重要で、三、四カ月に一回は歯科で歯石の除去をするとよい。喫煙は歯周病のリスクを五~八倍高めるという。「女性には歯周病リスクが三回ある」と若林さん。まず、思春期はホルモンバランスが変化し、口中の細菌が増えやすい。女性ホルモンが増える妊娠・出産期も注意が必要。唾液が減って乾燥しやすい更年期も歯周組織が劣化するという。糖尿病と肥満は歯周病の危険因子であり、逆に歯周病は糖尿病や肥満を悪化させる。歯周病菌は血液を通じて脳梗塞や心臓疾患、誤嚥(ごえん)性肺炎、早産や低体重出産、関節リウマチを招くことが知られている。最近ではアルツハイマー病との関連も指摘される。 *2-4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191002&ng=DGKKZO50376970Q9A930C1TL1000 (日経新聞 2019年10月2日) 心臓が量産品に変わる日、第7部 医ノベーション(1) 自らの肉体を自在につくる技術を人類がひとたび手にしたら、どんな未来が待っているのだろうか。そんな想像を膨らませ、取材は始まった。羽田空港の駐機場を望む川崎市の研究開発拠点。リコーの研究室で、両手で持てそうな小型プリンターがせわしなく動く。左右に走るヘッド部分から、ぽたぽたとしずくが落ちる。漏れ出たインクではない。1滴ずつが神経細胞を含む液体だ。ヘッドが小刻みに行き来し、絵や文字を印刷する代わりに神経細胞を丁寧に敷き詰める。1~2時間で最大20層ほど積み重なり、約1センチメートル角のサイコロ形をした塊になる。神経細胞は、再生医療の切り札とされるiPS細胞から育てた。この3Dプリンターの技術を使えば、細胞の塊を様々な形に変えたり、異なる細胞を混ぜ合わせたりできる。将来は大脳皮質の一部をつくり、病気やケガで傷んだ脳の治療に役立てる。事務機器のインクジェットプリンターを担当した開発員も加わり、研究は熱を帯びている。 ■1万人の患者が移植を待つ リコーは、必ずしも完全な臓器をつくろうとはしていない。「患者が必要としている機能を提供する」(バイオメディカル研究室の細谷俊彦室長)方針だ。だが「交換可能な臓器」の開発が焦点になっているのは明らかだ。2019年春、イスラエルのテルアビブ大学が3Dプリンターでヒトの細胞を積み上げ、血管まで備えたミニ心臓をつくったとのニュースが伝わった。佐賀大学も、ヒトの細胞から血管を組み立て、人への移植を目指している。本物そっくりの臓器をいかに実現するかは大きな課題だ。3Dプリンターの活用は有力な手立てで、すでに先陣争いが始まっている。3Dプリンターはまず、ものづくりの現場で脚光を浴びた。樹脂などを熱や光で加工し、いとも簡単に立体部品に仕立てる。臓器すらもつくれる時代が間近に迫り、遠くない未来に臓器は「量産品」に変わる。衰えたり傷んだりした臓器は、スペア(予備)の臓器と取り換え、命あるかぎり補える。そうなれば、私たちの肉体は朽ちるだけのものではなくなる。フランス生まれの外科医アレクシス・カレルが血管をつなぎ合わせる技術を究め、臓器移植への道を開いてノーベル生理学・医学賞を受賞したのが1912年。60年代から始まったとされる移植医療は、深刻な臓器不足に直面する。腎不全患者などが望む腎臓移植は、国内では年間1500件前後。約8割が健康な人からの提供で、1万人以上の患者が移植を待つ。量産臓器が既存の移植医療を一変させるのは確かだ。ディスラプション(創造的破壊)のインパクトはそれだけにとどまらない。研究者の一人はいう。「私は歯を器具(インプラント)に置き換えたが、臓器だって同じ。どこか壊れたら取り換えるだけだ。おかしなことではない」。国内外で、肝臓や心臓など内臓の8割以上が臓器再生の研究対象になっている。最先端技術は、肉体をどこまでも入れ替えるだけの潜在力を秘めている。人類は幾多の技術進歩を目の当たりにしてきた。いつの時代も、生まれ落ちた本来の体を取り戻すことが医療の最大の使命だった。今の臓器移植も自らの体の一部を補うだけだ。ところが、これからは自分の肉体が新たな肉体に次々と置き換わる。自分の肉体の大半が新しい臓器で満たされたら、私自身でありえるのか。生まれながらの私ではないのだから、私と名乗ってはいけないのだろうか。人類史上、ほとんど意識したことのなかった問いにさいなまれる。新たな肉体が私でないとしたら、私が私でなくなる日は近づいている。東京大学の中内啓光特任教授は「今から30年もすると、長生きしている人の多くは新たな技術で体を補い、生まれた時のままの体でいる人は少数派になっているだろう」とみる。そして、量産した臓器は、治療の選択肢として珍しくはなくなる。 ■どこまで「自分」でいられるか 中内特任教授は、驚くような方法で自然な臓器をつくろうとしている。ブタの受精卵にヒトのiPS細胞を仕込み、本来はブタの胎児が持つ膵臓(すいぞう)や腎臓をヒトのものに置き換える計画を温める。生まれたブタからヒトの臓器を取り出し、移植を待ちわびる患者を救うのだという。19年秋からはマウスの受精卵にヒトのiPS細胞を入れ、きちんと育つかどうかを調べる実験に取りかかった。私が少しでも私であり続けるため、本人のiPS細胞でできた臓器の作製が最終目標だ。あなたはどこまであなたでいられるのだろうか。哲学に詳しい京都大学の沢井努特定助教は、臓器移植が思うがままにできるようになったとき「外から取り込んだ組織が一定割合を超えたころから、自然(な自分)かそうじゃないかの議論が起こりうるのではないか」と推測する。ただ「心臓の働きを補うペースメーカーを埋め込むと、機械であるにもかかわらず自分の肉体の一部のように愛着をもつ人もいる」とし、臓器を交換しながらも私は私のままと感じる人はいると考えている。東大の中内特任教授の答えはこうだ。「体の大部分が他人から提供された臓器や機械に取り換えられても、脳が置き換えられない限り『自己』の意識は存在する」。防衛医科大学のチームは最近、血小板や赤血球の働きをする人工血液を開発した。大量出血で死にそうな10匹のウサギに「輸血」したところ、6匹の命が永らえたという。人工なので血液型とは無縁だ。研究成果が公になると「血液型占いはどうなっちゃうの?」「輸血したら自分じゃなくなっちゃう?」と多くの反響を呼んだ。技術の進歩によって現代人が自問自答しなければならないテーマがまた1つ増えた。 *2-4-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/o/500209/ (西日本新聞 2019/4/5) ブタを使って人の腎臓再生 慈恵医大、iPS細胞で 東京慈恵医大と大日本住友製薬は5日、人工多能性幹細胞(iPS細胞)とブタの胎児組織を使って、人の体内で腎臓を作る再生医療の共同研究を始めたと発表した。サルで安全性や効果を確認した後、3年後に人での臨床研究に進み、2020年代に実用化を目指す。慈恵医大の横尾隆教授は「将来的に臓器移植に代わる治療法にしたい」と話している。ただブタの細胞を体内に入れることから予期せぬ問題が起こる懸念があり、慎重な実施を求める声もある。腎臓は、尿管や糸球体など複雑な構造を持つため、iPS細胞から作るのは難しいと考えられてきた。 *2-4-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/o/506443/ (西日本新聞 2019/4/28) ブタ体内で人の膵臓、iPS利用 東大が年度内にも実施、国内初 東京大の中内啓光特任教授は28日までに、人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使って、ブタの体内で人の膵臓をつくる研究を実施する方針を明らかにした。将来、移植医療用として使うのが目的。学内の倫理委員会と国の専門委員会による2段階審査で認められれば、2019年度中にも国内で初めて人の臓器を持つ動物をつくる実験に着手する。臓器移植を希望する人に対して、提供者が少ない状態は慢性的に続いており、中内氏は「まずは品質を確かめる。10年以内に治療に役立てたい」と話している。 *2-4-4:https://www.nikkei.com/paper/related-article/tc/?b=20191002&bu=・・・ (日経新聞 2019/9/16) 再生医療 細胞除去し「骨格」だけ活用 京大は皮膚/慶大が肝臓 再生医療などによる病気治療に、組織や臓器の骨組みだけを活用する研究開発が進んでいる。再生医療では幹細胞を目的の細胞に育てて移植する研究が多いが、臓器まで作るのは難しい。このため組織の細胞を薬などで除去する脱細胞化技術を使い、残った骨格を移植することで早期の臨床応用につなげる狙いだ。京都大学の森本尚樹教授と国立循環器病研究センターの山岡哲二部長らは生まれつき大きなほくろを持つ「先天性巨大色素性母斑」患者の皮膚を再生する臨床研究を実施中だ。放置すると悪性黒色腫になる恐れがある母斑は皮膚の真皮部分にあるが、細胞培養技術でも真皮の再生は難しい。新手法は患部を切り取り2000気圧で10分間処理する。母斑も含め細胞は死ぬが真皮組織の骨格は残る。これを患部に戻す。後日、患者の培養した表皮を移植する。「真皮がないと表皮は定着しないため、母斑組織を殺した上で真皮を再利用する」(森本教授)。現在までに10例実施。真皮に血流が復活し皮膚全体も機能しているのを確認した。1年の経過観察を終え、治療効果を評価中だ。慶応義塾大学の八木洋専任講師、北川雄光教授らは肝臓の新しい再生医療の実現を目指す。肝臓を界面活性剤などで脱細胞化して洗い流すと、臓器の立体構造を支える骨格だけが残る。肝臓内の血管や管の構造も維持されている。そこに人のiPS細胞から育てた肝細胞や血管内皮細胞などを入れれば大型の立体臓器が作れ、血管をつなぐことができると考えた。日本人の肝臓と大きさや構造が似ているブタの肝臓から骨格を作る想定で10~15年後の実用化が目標だ。現在は日本医療研究開発機構の支援を受け実験を重ねている。iPS細胞から肝臓細胞を作る技術を持つ大阪大学の水口裕之教授の協力も得て進めている。八木講師は「重症の肝硬変患者向けに、生体肝移植とは異なる新たな移植治療を普及させたい」と話す。阪大の澤芳樹教授らは心臓移植を受けた患者などから不要になった元の心臓弁を提供してもらい、脱細胞化し弁の構造だけを残して別の患者に再利用する手術を臨床研究として実施している。動物の弁などを利用する人工心臓弁に比べて耐久性が高いと考えられる。移植した患者自身の細胞が脱細胞化弁に入り込んで自己組織化されるため拒絶反応も起きにくい。医師主導臨床試験(治験)を計画中だ。脱細胞化技術は死亡した人から提供された臓器や骨、皮膚などを治療に用いる移植医療が盛んな米国で進んでいる。東京医科歯科大学の岸田晶夫教授は「約20年前から製品化され始めた」と話す。日本でも厚生労働省が2019年5月に製品評価のためのガイドラインを公表した。作成に携わった岸田教授は「海外製品が数多く入ってきたときに評価しやすいような枠組みを作った」と話す。そのうえで「自国製品を作らないと海外に後れを取る」と危機感を募らせる。iPS細胞や免疫研究など日本が強みを持つ分野と組み合わせた研究開発が競争力につながると訴える。 *2-4-5:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20191002&c=DM1&d=0&nbm=・・ (日経新聞 2019年10月2日) 可能性と倫理のはざまで 創造的破壊の陰には、端緒となる大発見や研究成果がある。人類が肉体を補い続ける新たな手段を獲得し、さらに高みに上らんとできるのは、あらゆる細胞に育つiPS細胞が登場したからだ。iPS細胞は、京都大学の山中伸弥教授が2007年にヒトの細胞での作製に成功し、12年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。全国約1800人を対象とした内閣府の調査(17年)では、iPS細胞など再生医療に関するイノベーションによって病気やケガなどの治療技術が進歩すると考える人が9割を超えた。14年には、日本の理化学研究所などが目の難病「加齢黄斑変性」の患者にiPS細胞から育てた細胞を初めて移植した。一般の人々の目に映る医療の姿は、iPS細胞の誕生前後でがらりと変わった。異次元のイノベーションは破壊や急速な変化を伴うだけに、それまでの時代とのあつれきは避けられない。人の臓器を「量産」する試みには、期待や畏怖の念などさまざまな反応が寄せられる。東京大学の中内啓光特任教授の研究は今でこそ国も認めるが、10年に構想を発表したときは世界で議論が巻き起こった。京都大学iPS細胞研究所上広倫理研究部門の藤田みさお特定教授は「動物を使ってヒトの臓器の作製を目指す研究は新しく、議論すべき対象になっている」と指摘する。地殻変動を引き起こしたiPS細胞の「生みの親」である山中教授はどんな思いなのだろうか。山中教授が監修した書籍「科学知と人文知の接点」(弘文堂)に、複雑な心境が垣間見える。ヒトのiPS細胞をつくった後の苦悩を明かし、「大きな倫理的課題を生み出したことに気づき茫然(ぼうぜん)としたことを覚えている。(中略)どのような研究にも、光と影がある。うまく使えば人類の福音となるが、使い方を誤ると人類の脅威となる」と吐露した。イノベーションは、その後の新しい時代を生きる人類に相応の責任と覚悟を迫っている。 <精神医療における過剰診断と人権・教育> PS(2019年10月4日追加):*3-1の発達障害という言葉を近年よく聞くようになったが、これらが“病気”として統計に現れるようになったのは、下の図の上の段の左図のように平成18年以降であり、それまではなかった。さらに、*3-1は、診断レベルとされていないが本来は診断レベルの「グレーゾーン」があるとしており、その障害の中には外見上は健常者にみえるタイプがあり、「彼らは他者との違いが理解できるため最もつらい思いをしている」などとしているが、外見上、健常者に見えるのなら何ら問題はない上、DNAが違うのだから他者と違うのは当然だ。さらに、上の段の中央の図のように小学生の数が減っているのに、上の段の右図のように、“障害者”を増やして特別支援教育をすることの方が大きな問題である。 なお、*3-1は、ASDの特性を①物事や手順へのこだわりが強い ②コミュニケーションが苦手 ③予想外のことが起こるとパニックを起こす ③ADHDには、落とし物・忘れ物が多い ④じっとしているのが苦痛 ⑤感情を抑えられない ⑥全てにバランスのとれた人はいないので、誰もがグレー としているが、この特性の捉え方自体が躾や習慣の悪さを正当化しながら、“普通(バランスよく不完全?)”が最善だという信仰のような考え方をしている。しかし、このようにして特別支援教育を受ける子どもを増やせば、“普通”の人には理解できない突き抜けた才能を活かすことはできないし、その子の機会を奪うことにもなる。 このように何でも精神障害に仕立てた結果、日本は精神病患者の在院日数が下の段の左図のように先進諸外国と比較して飛びぬけて長く、さらに、*3-2のように身体拘束もしており、これは人権侵害である。また、下の段の右図のように、日本は人口当たりの精神科ベッド数が先進国最多であり、問われるべきは日本人の良識・精神障害者に対する差別意識・日本の精神医療の在り方・精神科ベッド数の多さなのだ。 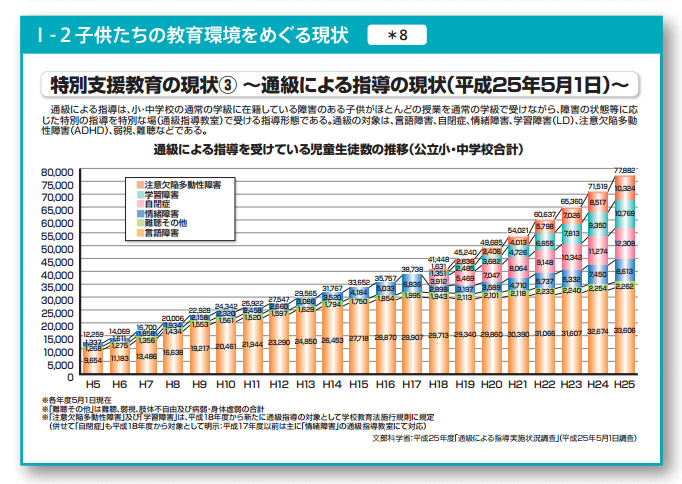 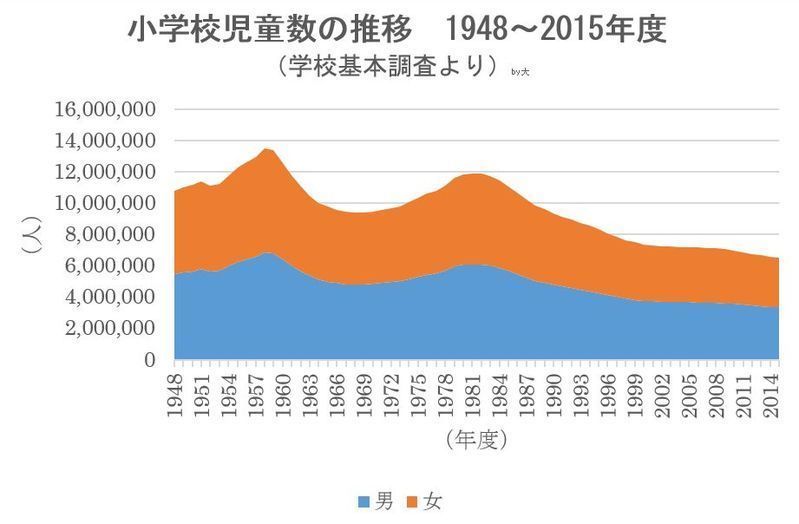 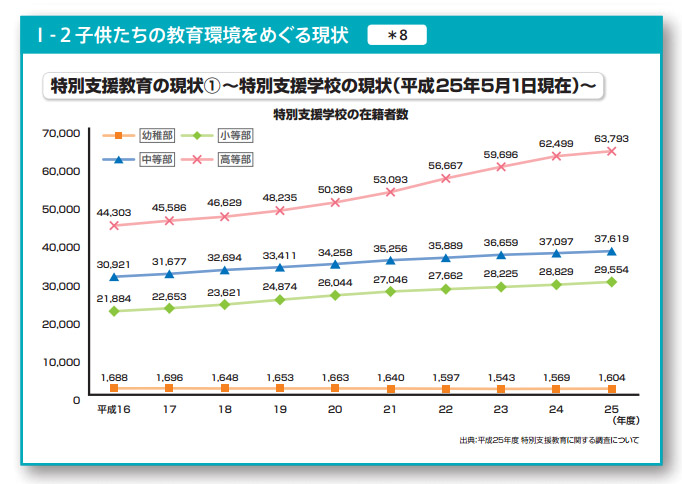 障害別通級指導の児童生徒数 小学校児童数の推移 段階別特別支援学校在籍者数 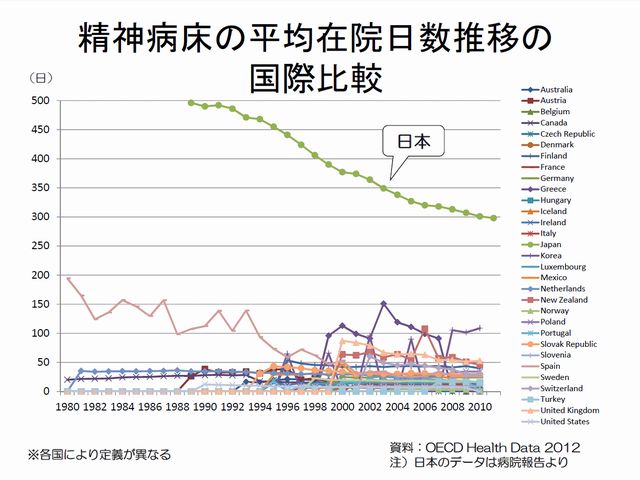 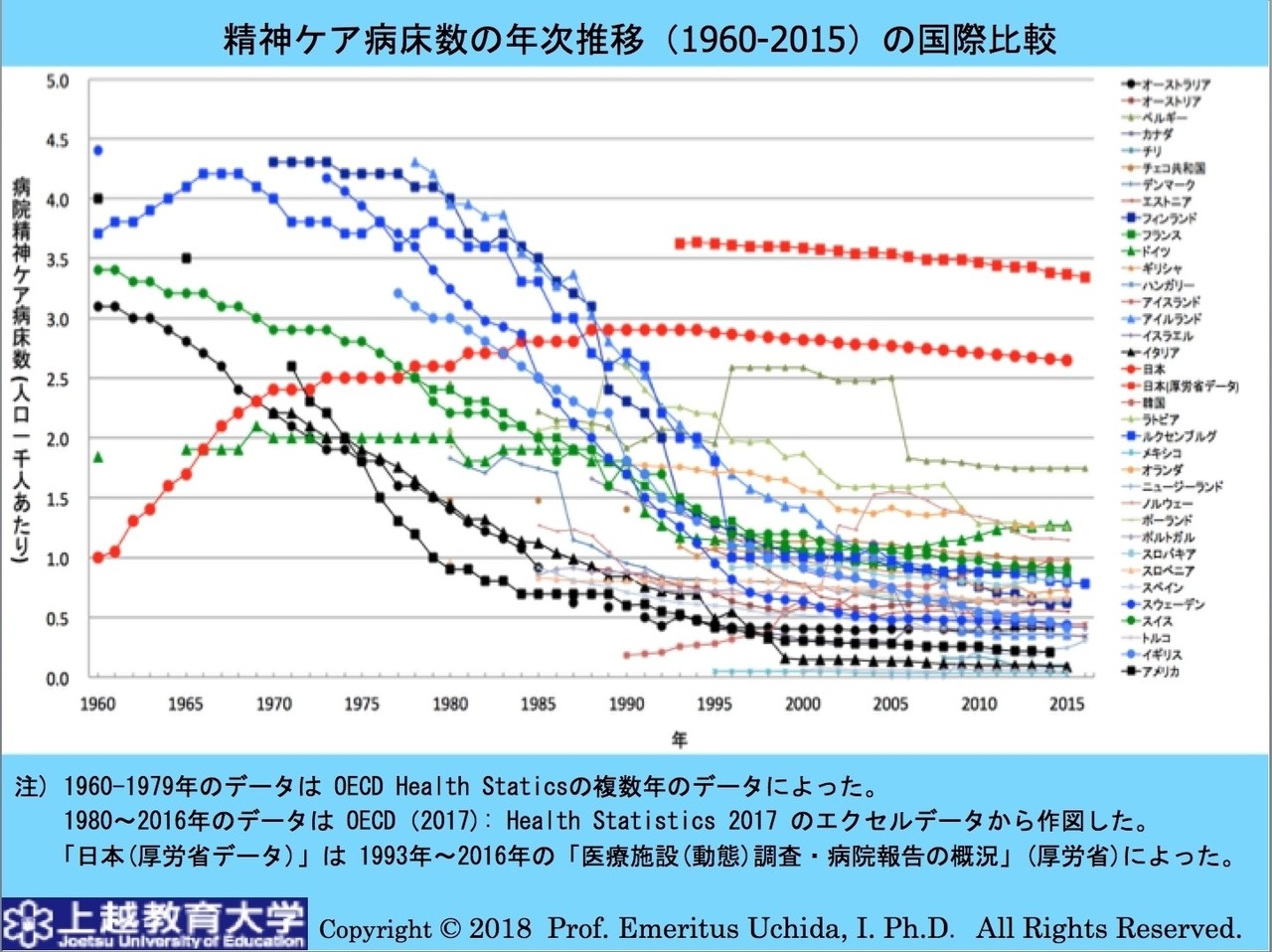 精神病床の平均在院日数推移国際比較 精神ケア病床数推移国際比較 *3-1:https://www.sankei.com/west/news/190824/wst1908240003-n1.html (産経新聞 2019.8.24) 発達障害の「グレーゾーン」 実際には診断レベルも 見落とされやすいタイプのASD 発達障害をめぐり、近年、「グレーゾーン」という言葉がよく使われるようになった。一般的に、発達障害の傾向はあるが診断レベルではないことを意味する。だが専門家からは、本来であれば診断レベルにありながら見落とされているケースもあると指摘する声も。特に発達障害の一つ、自閉症スペクトラム障害(ASD)の中には、外見上は健常者にみえるタイプがあり、「彼らは他者との違いが理解できるために、最もつらい思いをしている」と訴える。 ■ある意味、誰もがグレー 発達障害は、ASDや注意欠陥・多動性障害(ADHD)などの総称。主な特性として、ASDには、物事や手順へのこだわりが強い▽コミュニケーションが苦手▽予想外のことが起こるとパニックを起こす。ADHDには、落とし物・忘れ物が多い▽じっとしているのが苦痛▽感情を抑えられない-などがあるが、人によってさまざまだ。「人はだいたい、ASDかADHDのどちらかだ」と話すのは、発達障害を専門とする「どんぐり発達クリニック」(東京)の宮尾益知(ますとも)院長。誰もがASDやADHDの素質を部分的に持ち、それが特技や仕事の向き不向きにつながるもので、「全てにバランスのとれた人はいない。そういう意味では、誰もがグレーといえる」。ただし、その素質のために社会生活に支障をきたしている場合は「障害」と診断され、必要な支援を受けることができるようになるとする。 ■ASDの中の3タイプ だが、実際に医師らからグレーゾーンとされている人について、発達障害に詳しい京都大の十一元三教授は「専門医が診れば発達障害、特にASDの診断がつく人が多い」と指摘する。 *3-2:https://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20190218_4.html (京都新聞 2019年2月18日) 精神科の拘束 医療の在り方見直しを 精神科病院で手足をベッドにくくりつけるなどの身体拘束を受けた入院患者が、10年間で2倍近くに急増していることが厚生労働省の調査で分かった。2017年度の年次調査によると、全国で1万2千人強にのぼる。調査方法が変わったため単純比較はできないものの、03年度の5千人強から増加の一途だ。施錠された保護室に隔離された患者も1万3千人近くに増えている。本来は極めて限定的な場合だけに認められる身体拘束が、安易に行われている可能性がある。拘束は、患者がさらに精神的に不安定になる悪循環を招く。人権侵害の恐れにとどまらず、長期間の拘束によるエコノミークラス症候群などで死亡し、訴訟になるケースも起きている。問われているのは、日本の精神医療の在り方である。日本は人口当たりの精神科ベッド数が先進国で最多であり、必要がないのに長期入院を続ける「社会的入院」が生じやすいとされる。平均入院日数も、身体拘束の期間も突出して長い。諸外国では施設を脱して地域で暮らしながら治療する流れが一般的だ。イタリアのように精神科病院をなくした国もある。身体拘束が増えるのは逆行している。厚労省は「増加の原因は分析できていない。不要な拘束などをしないよう引き続き求めていく」としている。だが、実態を詳しく調査し、状況の改善に本腰を入れるべきではないか。拘束が適切かどうかを第三者が検証できる仕組みが求められる。「閉鎖的」と言われがちな日本の精神医療を見直し、透明化するきっかけとしてほしい。現場の人手不足が身体拘束の一因との声もある。一般病床と比べて少ない医師や看護師の配置を増やす必要がある。さらに気になるのは、患者に対する意識の問題だ。「(患者への対応のため)精神科医に拳銃を持たせてくれ」。昨年6月、日本精神科病院協会の会長が機関誌に、部下の医師のそんな発言を引用して載せていたことが問題となった。精神疾患はいつ、だれが発症してもおかしくない。認知症による入院も増えている。それなのに、日本では患者に対する差別意識が残り、精神医療の問題をタブー視して遠ざける感覚も根強いとされる。身体を拘束される人が増える社会は健全とはいえない。一人一人が関心を持ちたい。 PS(2019年10月5、6、7日追加):*4-1のように、佐賀県基山町に対馬藩の藩校名をとった東明館中高一貫校があり、佐賀県が教育に力を入れているのはよいことだ。その生徒数が中高で370人しかおらず定員(900人)を大きく割り込んだのは、近くに佐賀西高校・弘学館高校などの進学校が多く、生徒や保護者がより進学実績の高い高校を選択するのが原因であって、つめ込み教育をするのが原因ではない。早稲田佐賀中高一貫校は、一定割合の生徒が早稲田大学に入試なしで進学できるのが人気を博している大きな理由だ。しかし、知識も理論も、初等中等教育で学ぶことはしっかり身に着けておかなければ大学に行っても授業内容を吸収できない。つまり、知識をつめ込むのがいけないのではなく、知識を背後にある理屈も考えずに丸暗記するのが理解も応用的展開もできないためいけないのであり、これでは優れた研究開発など望むべくもない。従って、先生の要件は、知識を背後にある理屈とともにわかりやすく解説でき、生徒にも自ら考えることを促せる人で、そのための実力と識見を有していること になるのである。 このような中、*4-2のように、目黒虐待死事件で、父親が「①理想を押しつけた」などと弁解しているが、「②勉強してなかった」「③食事をいっぱい食べてた」と聞いて、5歳の子どもに食事制限を始め、死ぬほどの暴力を振るったのがこの事件である。このうちの②については、まだ5歳であることを考えれば文字を書けるだけでも上出来で、③については、幼児や成長期の児童・生徒に栄養バランスを考えて食事を多く食べさせるのが基本中の基本であるため、食事制限をするのは母親も含めて無知すぎる。そのため、①のように、「理想を押しつけた」とするのは、「理想」の内容が疑問である上、「理想」という言葉に失礼だ。つまり、このような栄養学の基礎知識は中学・高校の家庭科で教えているため、きちんと勉強して理解し覚えておくことが、判断を間違わないため誰にとっても必要なことなのだ。 しかし、児童相談所も「忙しかった」「引っ越して前の児童相談所から情報が来なかった」等の弁解が多く役に立っていなかったが、*4-3のように、改正児童福祉法で2022年4月(先の話)から全ての児童相談所に医師の配置が義務付けられて医療と連携することになり、法医学者が関わって虐待を早期発見できるようになったのは進歩だ。今後は、親に育てる力がなく危うい目にあっている子を親から引き離した場合に、きちんと育てられるシステムの整備が必要だ。 この子育てシステムには、現在は乳児院・児童養護施設(86.6%利用)と里親制度(13.3%利用)があり(https://npojcsa.com/foster_parents/index.html 参照)、「里親制度」とは、育てることができない親に代わって一時的に家庭内で子を養育する制度で里親と子の間に法的な親子関係はなく、実親が親権を持ったまま里親に里親手当てや養育費が自治体から支給されるものだ。一方、「養子縁組」は民法に基づいて法的な親子関係を成立させる制度で、養親が子の親権を持ち養育費等は支給されない(https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/happy_yurikago/infographics 参照)。私は、親に子を育てる能力や判断力がない場合には、「養子縁組」の方が子のためになると思うし、自分の子は既に家を離れて部屋も空いているのでもう1~2人養子を育ててもよいと思う夫婦は少なからずいると思うが、そのためには幼保無償化・義務教育の無償化をはじめ高等教育の低コスト化が必要なのである。そのため、*4-4のように、たいした所得でもないのに「所得が高い」とターゲットにして小さな“不公平”を言い立てるのではなく、子を育てるのに多額の金がかからない社会にすべきだと考える。 なお、*4-5には、「①これまで保育料に含まれていた副食費が無償化対象外になった」「②自治体が担ってきた徴収業務を直接保育園が行うことになった」「③これまでも絵本代など保護者から月千円前後を徴収してきた」「④副食費の徴収に口座振替を活用する園がある」「⑤副食費を巡っては『子育て支援の充実』『施設側の負担軽減』を理由に自治体が独自に助成するケースもある」等が書かれているが、食事は栄養バランスが大切なのに、食費を主食費と副食費に分けたり、主食を家から持参させたりするというのには呆れた。何故なら、子の成長にはむしろ“副食”の蛋白質・カルシウム・ビタミン類の方が重要であるし、“主食”を家から持参させれば保護者は手を省けないからである。さらに、③がこれまで保育料に含まれていなかったというのにも驚いたが、保育園も③のように集金していたのなら集金はできるので、②は問題なく、④のように口座振替を使う方法もある。また、ふるさと寄付金を活用して、⑤のように子育て支援を充実させるのも地域色が出てよいだろう。 さらに、*4-6のように、北海道新聞が社説で、「質の悪い保育の悪影響は成人後にも及び、国の基準は3~5歳では先進国の水準に及ばないため、子どもの健全な発達を保障する幼児教育や質の確保も緩みなく」としており、今後は質の高い幼児教育という視点も重要である。 *4-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14206205.html (朝日新聞 2019年10月5日) (けいざい+)続・奇跡の高校:4 学校再建、佐賀でも託され 「お願いがあるのですが……」。札幌新陽高校(札幌市)校長の荒井優(44)に5月、旧知の立命館慶祥高校(北海道江別市)の校長から連絡が入った。佐賀県基山町にある私立東明館中学、高校の理事長になってくれないかという。新陽高校を再建した手腕を買われてのオファーだった。札幌から佐賀まで1700キロ、片道6時間。新陽はようやく黒字化が見えたばかり。相談すると新陽の全員が反対だった。だが荒井は「むげにできない」と7月、東明館の理事長を兼務した。福岡県境にある基山町は旧対馬藩の飛び地で、東明館は対馬藩の藩校名をとって1988年に開学。中高6年制の進学校で、卒業生の1割は医師だ。しかし、この10年余は生徒数が減り、進学実績も振るわない。周辺の久留米大附設(福岡県久留米市)や弘学館(佐賀市)が男子校から共学になって人気を集め、早稲田佐賀(佐賀県唐津市)や上智福岡(福岡市)など有名大の系列校もできた。東明館の生徒数は中高合わせ370人で、定員(900人)を大きく割り込む。2015年から立命館の支援を受けてきたものの、危機的な状況は、荒井が新陽の校長に就任したときと似ている。荒井にとって縁がある土地だ。基山町の隣の鳥栖市は、かつて仕えた孫正義の故郷。ソフトバンク時代には、福島第一原発事故の被災者を九州に避難させる計画作りにもかかわった。孫は子どものころ、ほかの子に解き方を教えるのが得意で、先生になるのが夢だった。荒井は偶然にも、かつてのボスの夢を追う。東明館理事長に就いたことを孫にメールで伝えると、「すごいね! 頑張って」と返信がきた。まず生徒を増やさなければならない。荒井は9月21日、東明館のオープンスクールで「21世紀型進学校をめざします」と来場者に語りかけた。九州の進学校では、朝からの補習や1日7コマの授業など「つめ込み教育」をするところが珍しくない。そこで来年度に新設するのが、新陽でも採用した「探究コース」。暗記重視の座学ではなく、生徒が自主的にテーマ設定し、課題解決を目指す学習だ。従来の教育熱心な保護者だけでなく、今までの教育に飽き足らない層を取り込むことも狙っている。見学に来た小5の父は「つめ込み式じゃないのが魅力」と荒井にひかれた。小6の孫の進学先として検討する祖父母も「Tシャツ姿の理事長さんが面白そう」。知名度も実績もこれからだが、荒井に助言する京都造形芸大副学長の本間正人は「いろんな人を巻き込む魅力と引力が桁外れ。今後の教育界を背負う五指に入る」と彼を買う。「折り入ってお話が……」。荒井のもとに学校再建を託したいという依頼がその後も舞い込んでいる。 *4-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14206334.html (朝日新聞 2019年10月5日) 父「理想、押しつけた」 目黒虐待死、法廷で謝罪 東京都目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5)が虐待死したとされる事件の裁判員裁判が4日、東京地裁であった。保護責任者遺棄致死などの罪に問われた父親の雄大被告(34)は、亡くなる直前の結愛ちゃんの気持ちを検察官に問われ、「言い表せない深い悲しみ、怒りの中にいたんじゃないか」と陳述。「親になろうとしてごめんなさい」と泣きながら謝罪した。雄大被告は「思い描いた理想を結愛に押しつけてきた。エゴ(自分勝手)が強すぎた」と事件の原因を分析。結愛ちゃんが「ゆるしてください」などと書いたノートを見た感想を問われると、「私の機嫌をとるためだけに書かされたという印象」と答えた。雄大被告によると、2016年4月、公園でシーソーの乗り方も知らず、さびしそうな表情を見せた結愛ちゃんに「父親が必要だ」と思い、母親の優里(ゆり)被告(27)と結婚。「笑顔の多い明るい家庭に」と理想を描いたが、血のつながりがないことを負い目に感じ、それをはね返そうと必要以上にしつけを厳しくした。歯磨きや「食事への執着」について結愛ちゃんを直接しかるようになり、改まらないと「焦りやいらだちが暴力に向かった」。雄大被告は仕事を求めて香川県から東京都に転居。18年1月に東京で母子と合流した後、結愛ちゃんから「勉強してなかった」「食事をいっぱい食べてた」などと聞いて怒りが爆発し、食事制限を始めたという。2月下旬には、勉強を命じたのに無視して寝ようとしたことに激怒。馬乗りになって騒がないように口をふさぎ、「謝れ」と怒鳴ってシャワーで水を浴びせ、顔を複数回殴ったと説明した。死亡直前、嘔吐(おうと)を繰り返した結愛ちゃんを病院に連れて行かなかったことについては、「虐待の発覚を恐れる保身の気持ちが強かった。ありえない判断だった」と反省の弁を述べた。一方で、香川の児童相談所の職員から面会時に「血がつながってないから(実子の弟と)差別しているのでは」と言われたと不満をあらわに。児相を信頼できず、転居先の東京の住所を教えなかったと明かした。 *4-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/548492/ (西日本新聞 2019/10/4) 法医学の目 虐待見逃さない 傷の原因を見極め/人手不足が課題 児童虐待が深刻化する中、遺体解剖のイメージが強い法医学者が関わり子どもの命を救おうとする取り組みが始まっている。傷やあざから原因を特定する専門性を生かし、虐待が疑われる子どもの早期保護や支援につなげる。6月に成立した改正児童福祉法では、2022年4月から全ての児童相談所に医師の配置を義務付けるなど、医療との連携は欠かせなくなっている。児相関係者は「虐待の見逃しを防ぐため、科学的視点で助言をくれる心強い存在」と期待を寄せる。 * 「園児の顔にあざがある」。長崎県内の保育施設から、長崎市の県長崎こども・女性・障害者支援センター(児相)に通告があった。幼児は「パンチしたの」と話すばかりで要領を得ない。児相は虐待を疑い、幼児を一時保護した。父親は「寝ぼけて家具にぶつけたのだろう」と説明したが、児相は不審に思い長崎大法医学教室に連絡した。幼児のあざを確認した法医学者の意見は「歩いている時に打ってできるものではない。押されたり蹴られたりした反動で何かにぶつかるなどしてできた可能性がある」。大人の力が加わっている疑いが強まった。児相は身体的虐待があったと判断して支援を継続。定期的に面会する中で、父親は暴力を認めたという。近所の住民から「泣き声が激しい」と通告を受けた別のケースでは、児相職員が保育施設で幼児の体を確認すると、あざのような皮膚の変色が複数あった。写真を撮り、同教室にメール送信。法医学者が写真を見た上で、施設に駆け付け目視すると、あざではなく悪化した湿疹と分かった。 ** 今年6月に札幌市で2歳女児が衰弱死、8月には鹿児島県出水市で4歳女児が溺死した事件があった。児相などの行政機関が傷やあざを把握しながら一時保護につながらず、幼い命が失われるケースは後を絶たない。幼児は自ら説明できず、学齢期でも親から口止めされたりかばったりして虐待の痕跡を隠そうとしがちだ。大人が正しく見極める必要があるが、児相職員も含め経験が十分ではない。見逃しを防ごうと、長崎県では約10年前から長崎大法医学教室と2カ所の児相が連携し始めた。病院や保育施設などから通告を受けた児童相談所が判断に迷ったら、法医学者に傷の写真を見てもらったり、目視で確認してもらったりする。昨年は22人、今年は8月末までに17人の子どもが対象になった。「軽傷で『自分でぶつけた』などと保護者に流ちょうに説明されると、職員は納得してしまいがちだ。法医学者の科学的な見解があると、確信を持って支援や保護を始められる」と柿田多佳子・同センター所長(60)は意義を強調する。同教室の池松和哉教授(48)は「子どもは傷の治りが早く、悠長に様子を見ていては虐待の兆候を見落とし、支援のタイミングを逃してしまう。親子を支えるきっかけになれば」と話す。福岡市こども総合相談センター(児相)も、九州大と福岡大の法医学者に診察を委嘱する形で同様の取り組みを行い、昨年は26人の子どもについて意見を聞いた。福岡県久留米児相(久留米市)や同県大牟田児相(大牟田市)なども年に数件、法医学者の力を借りることがあるという。千葉大病院(千葉市)は昨年7月、児相や警察が虐待の疑いで保護した子どもを法医学専門の医師が診察する「臨床法医外来」を、全国で初めて開設した。 *** 今年3月に閣議決定された新たな虐待防止策には、児相と法医学者などとの連携強化も盛り込まれた。ただこうした取り組みを全国に広げるには課題がある。日本法医学会によると、司法解剖などの実務に携わる法医学者は約200人。警察が、18年に事件事故や自殺で死亡し「異状死」として取り扱った遺体約17万体のうち、死因究明のために解剖されたのは約2万体で約12%(警察庁調べ)。“本業”も十分カバーできていない中で、「虐待予防に人手を割く余裕はない」との声が現場から上がることもあるという。児相に協力している同学会前理事長の池田典昭九州大教授(63)によると、親が「風呂場で熱いお湯がかかった」と説明しても、服の上から熱湯をかけなければできないやけどの特徴が見られたりする。傷痕から受傷の経緯を分析するのは、小児科医や外科医では難しい。池田教授は「まず人手不足を解消する必要があるが、命を救うために法医学ができることはたくさんある」と話している。 *4-4:https://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20191006_3.html (京都新聞 2019年10月6日) 幼保無償化 不公平をなくす見直しを 幼児教育・保育の無償化が始まった。消費税率10%への引き上げに合わせ、増収分の一部を活用した少子化対策だ。安倍晋三政権が掲げる「全世代型」社会保障の看板政策といえる。認可保育所や幼稚園、認定こども園に通う全ての3~5歳児と、住民税非課税世帯の0~2歳児の保育料が原則無料になった。子育て費用が軽くなるのは保護者にとって助かるだろう。ただ、政権主導で急ごしらえした制度と保育現場にずれが多く、不安を残したままのスタートとなったのは否めない。象徴的な問題の一つが、給食の副食(おかず)費の扱いだろう。副食費はこれまで保育料に含まれていたが、国は無償化の対象外として非課税世帯などを除いて実費負担を求めたからだ。保育料は、収入に応じて段階的に設定されてきた。低所得者は以前から減免されており、無償化の恩恵は小さいのに定額の実費が増えると負担感は重い。かえって出費超となる「逆転現象」の恐れもある。こうした事態を防ぐため、京都府は9月議会で新たに市町村による副食費支援への助成費を設けた。どこまで負担軽減をするかは市町村の判断で、地域格差が広がる可能性もある。無償化される幼保施設の線引きにも不満が根強い。インターナショナル校や民族学校は「各種学校」だとして対象外にされたが、保護者らは「同じ権利を認めて」と訴えている。希望しても認可施設に入れない待機児童は恩恵がないばかりか、状況の悪化が危惧される。全国の待機児童は4月時点で約1万6千人、「潜在的」な待機も約7万4千人いる。さらに無償化が新たな保育需要を掘り起こし、自治体による受け皿拡大が追いつかない恐れが高い。このため国は無償化から当初は外していた無認可保育施設を5年期限で補助対象に加えた。独自財源で補助上限額を引き上げるなどする自治体も多い。だが、保育士の数や設置面積などが不十分な無認可に広げることで、子どもの安全や保育の質の低下が懸念されている。京都市は補助期間を1年半に短縮し、無認可施設が早期に国基準を満たすよう促す方針だ。保育士不足は全国的に深刻さを増している。資格を持つ「潜在保育士」の掘り起こしなど官民挙げた確保策が必要だろう。一部の保育所や幼稚園では無償化に合わせ、「便乗」が疑われる値上げも見られた。理由に挙げられる保育士の待遇改善や環境整備に使われているか、行政はしっかり監視してほしい。不安が拭えないのは、どんな保育の受け皿や「質」が必要かの検討がなおざりのまま進められた結果といわざるをえない。幼保無償化には年間約7760億円が充てられる。財源となる消費増税は全ての人が負担するのに、一律の無償化は所得の高い人ほど受益が大きいという根本的な矛盾に不公平感が渦巻いている。本当に必要とする子育て世帯に恩恵が行き渡るよう不断の見直しが必要だろう。 *4-5:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/549108/ (西日本新聞 2019/10/7) 無償化対象外、おかず代不安 保育園、新たに徴収業務 「未納でも食べさせないと」 消費税率10%への引き上げを財源として1日から始まった幼児教育・保育の無償化では、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代など)は無償化の対象から外れ、自治体が担ってきた徴収業務を直接保育園が行うことになった。新たに滞納への対処が必要になるほか、事務負担増も見込まれており、現場からは不安の声が上がっている。「滞納した子の給食を出さないわけにはいかない。これまでも絵本代などで保護者から月千円前後を徴収してきたが、集める金額も大きくなる。問題なくできるだろうか」。約160人の児童を預かる福岡市城南区の信明保育園の高山英樹園長は頭を悩ませる。昼食の主食(ごはんなど)は各園児が持参し、副食を給食として提供する。今月からは副食費として同園が月4500円を実費徴収することになった。最大の懸念は「滞納への対応」。これまでは副食費は保育料に含まれて市が徴収していた。滞納があった場合でも市から園に渡される委託費は減額されず、保育や給食の質は確保されてきた。 ▼「自腹」負担も だが、今後は副食費の滞納分がそのまま園の負担となる。「督促することによって保護者との関係が悪くなる恐れもあり、なかなか言いにくい。1年間滞納すると1人5万円ほど。決して小さな金額ではない」。市によると保育料の未納は年間1億円ほどに上る。国は、無償化から副食費を外した理由について「食費を保護者が負担してきた幼稚園や義務教育の学校給食との公平性確保」「在宅で子育てする場合でも必要な費用だ」などと説明する。従来通り自治体が徴収を代行することは「制度上できない」という。福岡市内では、副食費の徴収に口座振替を活用する園があるなど、各園が模索する。福岡市保育協会の篠原敬一理事長は「大規模な制度改革で国の対応は遅れた面もあるが、無償化自体はとても良いこと。試行錯誤しながらやっていくしかない」と話す。 ■自治体の独自助成じわり 副食費を巡っては、「子育て支援の充実」や「施設側の負担軽減」を理由に自治体が独自に助成するケースもある。福岡県内では田川市や大任町などが幼稚園、保育園問わず副食費として1人月4500円を上限に施設側に助成している。九州各県によると、長崎県で21市町中6市町、宮崎県で26市町村中3町村が無償化にする方向という。秋田県内では半数以上の15市町村が県との共同事業に自治体独自の助成を上乗せして全面的に無償化する。県の担当者は「秋田は全国一の人口減少県。歯止めをかけるための経済的支援になればと力を入れている」と話す。一方、人口規模の大きな自治体では今のところ助成の動きは広がっていない。福岡市は第3子以降の副食費は免除しているものの、全児童を対象とした財政支援は行わない方針。市によると、幼稚園、保育園の副食費を全て無償化した場合の費用は年間10億円ほどで「負担が重い」としている。 *4-6:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/352065 (北海道新聞社説 2019.10.7) 幼保無償化 「質」の確保も緩みなく 消費税率引き上げに伴い、幼稚園や保育所などが無償化された。増収分から年間約8千億円を投じ、全ての3~5歳児と低所得世帯の0~2歳児について、利用料の全額または上限まで補助する。一昨年の衆院選の看板政策で「無償化ありき」で実施に至った。待機児童解消は道半ばで、保育士の待遇改善も進んでいない。無償化で需要の掘り起こしが見込まれる上、保育士不足の中で「量」の確保を急いだため、保育の「質」への不安が拭えない。子育て世帯の負担軽減に異論はないが、誰もが安心して公平に享受できることが大前提だろう。既に便乗値上げとみられる動きもある。国と自治体は、待機児童解消を緩みなく進めながら、制度の穴を確実にふさぐ必要がある。無償化の緊急性には、当初から疑問が出ていた。低所得世帯には既に減免制度があり、高所得世帯ほど恩恵が大きくなるからだ。そもそも保育所に入れない待機児童数は4月時点で1万6千人、入所を諦めた潜在的待機児童数は7万人を超え、不公平感は強い。無償化は本来、認可施設が対象だが、反発を受けて国の指導監督基準を満たさない認可外にも広げ、是正に5年間の猶予を認めた。認可外施設は体制が手薄なところも少なくなく、死亡事故の発生率は認可を大きく上回る。このため国は、自治体が条例で無償化対象を制限できるとしたが、認可外が待機児童の受け皿になっている現状では難しかろう。ましてベビーシッターなどは、行政の立ち入り検査もない。やみくもに無償化を急ぎ、安全に疑問のある保育サービスが増える余地を生んだといえる。せめて札幌市のように、認可外施設への指導内容の公表など、情報発信を進めてもらいたい。待機児童対策で、国は次々に基準緩和を進めてきた。だが、切り札とした企業主導型保育所は、手厚い補助を当て込んだ新規参入が相次ぎ、甘い審査で助成金詐取や破綻を許した。一方で、給食費を巡り国の負担が増したとして、肝心の保育士の人件費加算を直前で見送った。ずさんな制度設計のしわ寄せを受けるのは子どもたちだ。質の低い保育の悪影響は成人後にも及ぶとの海外の研究もある。ただでさえ、国の基準は3~5歳では先進国の水準に及ばない。幼児教育をうたう以上、子どもの健全な発達を保障するだけの余裕を現場につくらねばならない。 <介護保険とその財源、エネルギーの再エネ化など> PS(2019年10月13日追加):*5-1のように、「①高齢化で増加する医療費を抑えるため、医療提供体制の見直しが避けられない」「②地域住民の安心を確保できるよう見直す際は地域事情に十分配慮すべき」「③病院ベッド数は人口減少と少子高齢化に伴う人口構成の変化に合わせた機能転換が必要」「④若い世代に多いとされる急病・大けがの手術の際に入院する『高度急性期』『急性期』のベッド数の必要性は低くなる」「⑤脳血管障害・骨折の手術後のリハビリに対応する『回復期』のベッド需要が高まる」「⑥急性期ベッドは看護師配置が手厚く診療報酬が高いが、現状では回復期ベッドが足りずリハビリ中の高齢者が入院している例も多い」「⑦地域医療の将来像は住民本位で」と書いたメディアは多い。しかし、(私が大学で習って衆議院議員時代に始めた)病院ネットワークの充実は、①の高齢化による医療費の増加を抑えるためではなく、最小のコストで充実した医療を提供するために行うものだ。そのため、②③は当然であるものの、高齢者が増えれば脳血管疾患・心疾患・骨折などが増えて急性期患者の絶対数が増えるため、④は事実でない。また、⑤は事実だが、現在は理学療法士を配備したリハビリ病棟が少ない上、回復期には縦割りの病院間の引っ越しをしなければならないというのも患者にとっては負担であるため、そのまま急性期病棟にいることが多いわけである。また、診療報酬は診療内容によって決まり、急性期の方が高いため、病院は急性期の患者を多く入れた方が利益が多いので、⑥も誤りである。つまり、高齢化に対応するための給付抑制と病院の悪徳性を先入観として持った上で考えると事実と異なる認識で誤った結論を導くのであり、⑦の住民のニーズに合った治療を最低コストで行うためにこそ、病院の再編やネットワーク化は行うべきなのである。 このような中、*5-2のように、つしま医療福祉グループ・江別市・北海道が北海道のモデル事業として「生涯活躍のまち」を整備したり、*5-3のように、JAが主体となって介護保険事業の種類ごとにWGを設置し、現場の情報やノウハウを共有したり、課題解決策を探って事業改善に生かし介護を底上げしたりして地域の声を反映した介護保険制度の充実に繋げようとしたりしているのは、正攻法で期待が持てる。そのため、介護の対象者を組合員だけではなく、一般市民にも開放して欲しいくらいだ。 しかし、厚労省は、*6-1のように、「⑧65歳以上の高所得世帯の介護保険サービスの自己負担月額上限を2~3倍に引き上げる」「⑨介護サービスを利用する時の自己負担は年収に応じて1~3割」「⑩これは介護保険制度の維持が目的」としている。しかし、年収に応じて保険料の支払額を変え、⑧⑨のように、年収に応じて利用料まで変えるのは、食料品の値段を年収に応じて変えるのと同じくらい馬鹿の一つ覚えの応能負担思考だ。また、介護が保険制度である以上、不公正に制度を複雑化させる。さらに、介護状態になり、これから高い年収が入るわけのない人の利用料を上げるという発想は、⑩の介護保険制度の維持どころか介護保険制度の意味を失わせるものである。つまり、*6-2のように、今でも不足している介護保険制度の利用をさらに控えさせることになるため、全世代型社会保障と言うからには、何歳であっても必要な介護を受けられ、介護保険料の支払者は所得のある人全員にすべきなのだ。 この介護サービスは20世紀から必要性が指摘され、21世紀始めの2000年4月1日に、日本で最初に施行されたもので、現在は韓国で2008年から、台湾で2019年からなど公的介護保険制度の運用を開始している国が多い。それにもかかわらず、このような新しいサービスは邪魔者扱いにしてまともに育てることすらできないのが、(特定の首相ではなく)我が国の政府なのである(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf 参照)。そして、主権者は国民自身だ。 なお、介護はじめ社会保障サービスの原資は、(これも馬鹿の一つ覚えのように)消費税だと唱えて決して疑問を持たないメディアが多いが、*7-1・*7-2のようなリチウムイオン電池・太陽光発電・EV(どれも日本発の技術)を組み合わせれば、日本は外国に多額の燃料費を支払うことなく、CO₂を排出しないクリーンなエネルギー体系を作って国民を豊かにすることができた。にもかかわらず、経産省・経団連・原発推進派などの既得権者が逆風を吹かせて予算を無駄遣いしつつ、先駆的企業の経営を危うくし、先駆的企業の技術が日本ではいかされずに海外に先を越されたのである。そのため、そういう状況を変えることなくノーベル賞受賞だけをいくら騒いでも、科学技術創造立国になったり、先進技術を使ったベンチャー企業の育成ができたりするわけはないのだ。ただ、世界の中ではかなり遅れたが、*7-3のように、「再エネ100%のネットワーク」が始動したのは、日本政府の愚かさと比較すれば少しは希望が持てる。 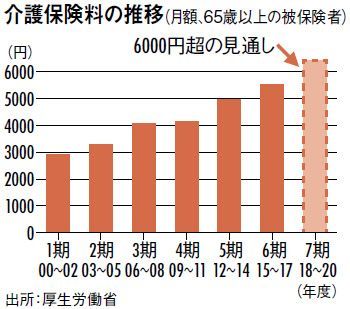  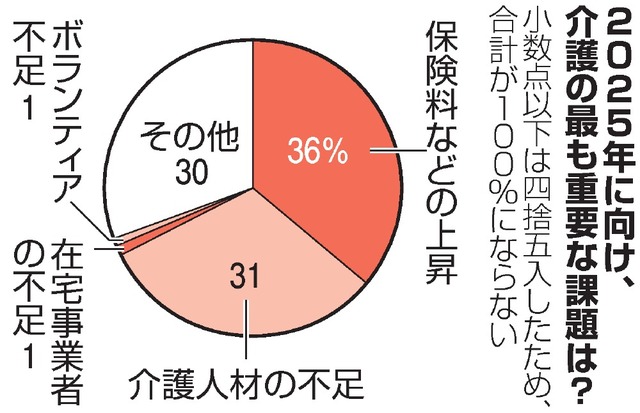 2018.4.4朝日新聞 (図の説明:左図のように、65歳以上の被保険者から集める介護保険料は増加の一途を辿り、提供される介護サービスは減少している。また、中央の図のように、介護サービスには、半額の公費が投入されているが、介護保険料を支払っているのは65歳以上と40~64歳のみであり、意味なく複雑である。また、右図のように、団塊の世代が75歳を超える2025年には介護保険料の上昇と介護人材の不足が懸念されているとのことだが、まず所得のある人全員が介護保険料を負担し、全世代が介護を受けられる単純な全世代型社会保障にし、外国人労働者を活用すれば多くの問題が解決しているだろう) 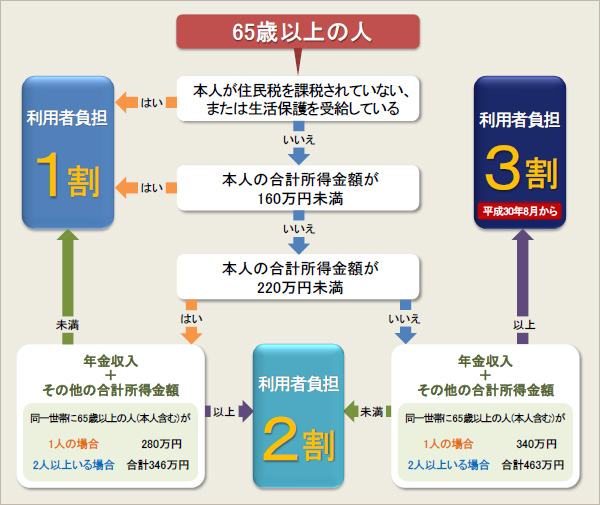 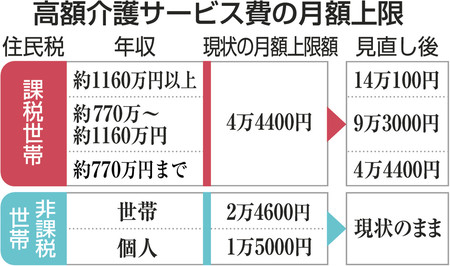 2019.10.6東京新聞 (図の説明:左図のように、介護を受けた時に支払う介護保険料の割合は、物価高の中ではたいして多くもない所得で2割・3割と増加する。また、右図のように、毎月の上限支払額も所得によって段階的に増えるが、介護と医療は同時に受ける場合が多いため、合わせて一定以下に抑えなければ生活できなくなるのである) *5-1:http://www.the-miyanichi.co.jp/shasetsu/_41417.html (宮崎日日新聞社説 2019年10月9日) 公的病院再編 ◆地域事情に十分配慮せよ◆ 厚生労働省による再編・統合の検討が必要な全国の公立・公的病院の公表が波紋を呼んでいる。全国1455病院のうち、対象になったのは本県7病院を含む計424病院。高齢化に伴い増加の一途をたどる医療費を抑えるには医療提供体制見直しが避けては通れない。地域住民の安心を確保できるよう、地域事情に十分配慮すべきだろう。病院のベッドに関しては、人口減少と少子高齢化に伴う人口構成の変化に合わせた機能転換が必要だと指摘されてきた。つまり、比較的若い世代に多いとされる急病、大けがの手術の際に入院する「高度急性期」「急性期」ベッドの必要性は低くなる。一方で、脳血管障害や骨折の手術後のリハビリに対応する「回復期」ベッドの需要が高まるとされている。急性期ベッドは看護師配置が手厚く診療報酬が高く支払われる。だが現状では、回復期ベッドが足りず、リハビリ中の高齢者が入院している例も多いとされ、ミスマッチ是正が課題になってきた。この方向に沿って医療提供体制を見直すため、国が各都道府県に策定を求めたのが地域医療構想だ。全国の病院のベッド数は2018年で約125万床だが、同構想では25年に必要なのは約119万床で、削減が可能と思われた。ところが厚労省が全国の病院に報告を求めたところ消極姿勢が目立ち、公立・公的病院はほぼ削減が進まない見通しであることが分かった。このため今回、病院側や都道府県に対し再検討を促すため、病院名の公表に踏み切った。しかし、全国知事会など地方3団体が「地域の不安が増す」などとして反発を強めている。確かに懸念される問題点は多い。第一に、山間へき地、離島への立地や、がんの先進治療など民間病院では限界がある医療を提供するという公立・公的病院ならではの役割は、経済合理性重視で評価を下せるものではない。そもそも患者一人一人の立場になれば、長年頼みの綱にしてきた地域の病院が遠隔地に統合されるなどすれば、不安、不利益は計り知れないだろう。さらには、公立・公的病院の再編・統合により、現状でも深刻な地方の医師不足に拍車が掛かりかねない。それが引き金になって人口減少、過疎化がさらに進む可能性も否定できない。地域医療構想は都道府県が複数の自治体単位で策定し、それを受けて各病院側が具体的なベッド数削減を決めていく。その過程では、地元の医療関係者のほか住民代表らも加わった会議で協議することになっている。地域医療の将来像は住民本位で探っていくべきだ。地域の不安解消に丁寧な議論が必要だ。 *5-2:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/351158?rct=n_hokkaido (北海道新聞 2019年10月3日) 共生のまちづくりへ つしまグループ、江別市、道が協定締結 道は3日、つしま医療福祉グループ(札幌、対馬徳昭代表)と江別市が同市大麻地区で進める「生涯活躍のまち」整備について、全道のモデル事業としての成功に向け、同グループと同市とで3者協定を締結した。事業は、同市が構想を策定。同グループが約3万平方メートルの敷地に、サービス付き高齢者向け住宅や保育所、住民の交流拠点など9種類の施設を建設する。予算は40億円超の見通しで、2021年4月完成予定。道は運営手法などを全道に波及させ、人口減少対策につなげたい考えだ。道庁での締結式で、対馬代表、三好昇市長、鈴木直道知事が協定書に調印。道と同グループは人事交流などを行う。鈴木知事は「全国に誇る先駆的なプロジェクト。成果を全道に広げたい」と述べた。 *5-3:https://www.agrinews.co.jp/p48848.html (日本農業新聞 2019年9月29日) JA主体 介護底上げ 高齢者福祉ネット体制強化 情報やノウハウ6WGで共有へ 介護事業に取り組むJAなどで構成し、高齢者福祉対策を担ってきた「JA高齢者福祉ネットワーク」が、10月から運営方式をJA主体に見直し、活動を強化する。居宅介護支援など介護保険事業の種類ごとに六つのワーキンググループ(WG)を設置。各JAはWGに参加し、情報やノウハウの共有、課題解決策を探り、事業改善に生かす。WGで出た意見や要望は政策提言し、地域の声を反映した介護保険制度の充実につなげていく。ネットワークは、介護事業を展開する全国の約260JA、約50の県中央会と厚生連、12の全国機関で構成し、JAの介護保険事業の中心的な役割を果たしてきた。JA全中が事務局を務め、研修会などを開いてきたが、ネットワーク非会員JAへの全中のアプローチが難しいことや、介護保険事業の収支が厳しさを増していることなどが課題だった。課題解決も含めて、ネットワークの役割などを再検討。従来の参加型の協議会方式から、JAが結集する方式へ転換し、全体で介護保険事業の底上げを目指す。全中は、情報提供や研修会の開催などでJAを後方支援する体制に変更する。介護事業に取り組む全JAに参画を促していく。WGは①経営管理②居宅介護支援③訪問・定期巡回④通所介護⑤小規模多機能⑥介護・医療連携──で構成する。各JAは、それぞれが展開する事業内容と課題に応じてWGに所属する。より濃密で鮮度の高い情報を入手でき、県域を超えたつながりによる新たな事業展開のヒントを得ることに期待がかかる。WGで出た現場の声は、JAグループの政策提言にもつなげる。全中営農・くらし支援部は「WGでは現場からの意見を最優先に吸い上げ、政策提言に生かしたい」と話す。JAグループ全体の介護保険事業の収益は年間で約300億円。業界でも上位規模になる。 *6-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201910/CK2019100602000119.html (東京新聞 2019年10月6日) 高所得者 介護負担増へ 65歳以上、月額上限2~3倍 厚生労働省は五日、膨張する社会保障費抑制のため、主に六十五歳以上の高所得世帯を対象に、介護保険サービスを受ける際の自己負担の月額上限を引き上げる方針を固めた。現在の月額上限は低収入の世帯を除くと四万四千四百円だが、年収約七百七十万円以上の世帯は九万三千円、約千百六十万円以上は十四万百円に増やす。政令改正し二〇二一年度にも導入する。介護保険制度の維持が目的で、比較的余裕がある高齢者に相応の負担を求める。介護サービスを利用した人の自己負担は一~三割。利用者の負担が過重にならないよう「高額介護サービス費」という仕組みがあり、月ごとの自己負担額に上限を設け、超えた分は払い戻してもらえる。現在、上限は住民税課税世帯であれば収入額に関係なく四万四千四百円。今回、これを見直す。具体的には(1)年収約七百七十万円までの世帯の月額上限は四万四千四百円(2)年収約七百七十万~千百六十万円の世帯は九万三千円(3)年収約千百六十万円以上は十四万百円-とする。対象となる六十五歳以上の世帯は数%の見込み。住民税非課税の場合の上限は、現行の世帯二万四千六百円、個人一万五千円を維持する。 *6-2:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/480560 (沖縄タイムス社説 2019年10月7日) [介護保険見直し]「利用控え」広げないか 果たして、これまでのように支援を受けることができるのか。来年の通常国会での法案改正を目指し、政府内で介護保険見直しに向けた議論が進んでいる。並ぶのは利用者の負担を引き上げるいくつもの項目だ。3年に1度実施している制度改正で、厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会の部会は、自己負担2割の対象者拡大▽ケアプラン作成の有料化▽自己負担の月額上限引き上げ-などを論点に挙げている。社会保障費を抑制するため、年末までに結論を出すという。65歳以上の全ての高齢者を対象に2000年にスタートした介護保険は、年収に関係なく1割負担でサービスが受けられ、「介護の社会化」に貢献してきた。だが15年に年収280万円以上の人を対象に2割負担が導入され、18年に340万円以上の人は3割に引き上げられた。財務省などは2割負担を原則とするよう求めており、今度の改正で年収要件を引き下げ、2割負担の対象が広がる可能性がある。ただ既に2割に引き上げられた人のうち、3・8%がサービス利用を減らしたり、中止したりしたことが同省の調査で分かっている。「利用控え」の割合は、1割に据え置かれた人の3倍に上った。例えば月2万円の負担が4万円に跳ね上がれば、サービスをためらう人が間違いなく増えるだろう。支援が受けられず重症化しないか心配だ。 ■ ■ ケアプラン作成の有料化も焦点の一つである。ケアプランはサービスに詳しいケアマネジャーに依頼するのが一般的で、誰もが公平にサービスを受けられるよう現在は全て保険からの給付で賄われている。仮に1割負担となった場合、高い人で月に1400円ほど支払うことになる。毎月のことであり決して小さくない額だ。月ごとの自己負担額に上限を設ける「高額介護サービス費」の引き上げも検討されている。住民税課税世帯なら収入に関係なく4万4400円の現行から、年収約770万円以上の世帯は9万3千円、約1160万円以上は14万100円に増やす方針だ。比較的余裕がある層とはいえ、税金などを引かれた後、月5万円から10万円近い支出増は家計へ影響を及ぼす。十分な調査と説明を求めたい。 ■ ■ 18年度の介護保険給付費は10・7兆円で制度開始時の3倍に増加した。団塊世代全員が75歳以上となる25年度は15兆円を超える見込みだ。高齢化の進展に伴う社会保障費の伸びを抑える狙いがあることは理解するものの、利用者の負担が限界に近づいているのも事実である。老後資金2千万円問題などで公的年金制度への不安が高まっている。消費税も10%にアップされたばかりだ。今は健康でも介護を必要とする時期は、多くの人にやってくる。制度が維持されても、生活が成り立たなければ本末転倒である。 *7-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14212779.html (朝日新聞 2019年10月10日)電池ビジネス、急拡大 日本メーカーが牽引、競争激化 吉野さんノーベル化学賞 今年のノーベル化学賞に決まった吉野彰・旭化成名誉フェローらが開発したリチウムイオン電池は、用途を広げながら市場拡大を続けている。牽引(けんいん)してきたのは、日本の素材や電機メーカーだ。ただ近年は中国勢が台頭し、競争は激しさを増している。リチウムイオン電池は、電気自動車(EV)やスマートフォンなど向けの需要が伸び、市場規模の拡大が見込まれる。調査会社の富士経済の予測では、2022年の世界市場は7・4兆円で、17年の2・3倍に伸びるという。旭化成は、電池の正極と負極を隔てる膜の「セパレーター」の生産能力が世界一で、市場シェアの約2割を握る。吉野氏の研究成果と同社独自の技術を組み合わせ、1990年代に量産化に着手。20年度までに生産能力を16年度比で8割増やす方針で、工場の増強を計画する。小堀秀毅社長は「リチウムイオン電池が、今後ますます世界の人々の暮らしに役立つものになっていくと期待している」との談話を出した。ほかの主要部材でも日本勢は強い。日立化成は、EV用電池の負極材で世界有数のシェアを誇る。宇部興産は、電気の通り道になる電解液で、耐久性を高める独自の技術を持ち、こちらも世界有数のシェアだ。電池そのものの生産にも、電機メーカーなどが力を入れてきた。東芝は自社のリチウムイオン電池を、スズキの簡易ハイブリッド車や東京メトロの車両の非常用電源向けに納入している。パナソニックは自動車向けに注力し、いまや電池事業の年間売上高は数千億円規模と、冷蔵庫や洗濯機を上回るまでに成長。EV大手の米テスラと組み、米国に電池工場も構えている。ただ、日本勢の地位は揺らいでいる。中国の新興メーカー、寧徳時代新能源科技が、中国政府の支援を受けて急成長し、EV向けの出荷量ではパナソニックを抜いたとされる。17年には日本法人を設立し、営業攻勢をかけている。電気の通り道に液体を使わず、発火のリスクを抑える次世代技術「全固体電池」の開発競争も始まっている。トヨタ自動車はパナソニックと提携し、20年代前半の実用化をめざす。一方、激しい競争の中で撤退に追い込まれる動きも相次ぐ。日産自動車とNECは昨年、共同出資する電池メーカーを中国企業に売ると決めた。世界に先駆けてリチウムイオン電池を実用化したソニーも17年に電池事業を村田製作所に売却した。関連技術や市場環境は大きく変化しており、この先も再編含みの競争が続きそうだ。 *7-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191010&ng=DGKKZO50809460Z01C19A0EA1000 (日経新聞社説2019年10月10日)電池の革命がノーベル賞を手にした 今年もまたうれしいニュースが飛び込んできた。ノーベル化学賞が旭化成の吉野彰名誉フェローに贈られることが決まった。授賞の理由はリチウムイオン電池の開発。97歳と過去最高齢となるジョン・グッドイナフ博士らとの共同受賞だ。パソコンから携帯電話、スマートフォン、それに電気自動車。現代の暮らしは、これらに使われる電池の革命なしには考えられない。文句なしの受賞といえる。充電すれば繰り返し使える電池の性能は電極にどんな材料を選ぶかで決まる。1980年代半ば、吉野氏はグッドイナフ氏が開発した正極にあう負極を探した。最初は電気を通すプラスチックに着目したが、実用に見合う性能が引き出せない。試行錯誤の末、たどり着いたのが旭化成が得意としてきた炭素材料。85年にリチウムイオン電池の基本構造を確立した。リチウムイオン電池は従来の電池より小さく軽くて電圧も高い。ソニーが91年に初めて製品化し、当初は安全性に課題もあったが、携帯機器で普及した。2010年ごろまでは日本メーカーがリードしたが、その後、韓国勢などが台頭し市場での立場は逆転した。産業での日本の優位性が長続きしなかったことを悔やむ声があるが、それだけ世界が求めていた革新的テクノロジーだった。日本企業に所属する研究者の受賞は2002年に化学賞をとった田中耕一島津製作所シニアフェローに次ぐ2人目だ。吉野氏も田中氏も1980年代の業績で、大手メーカーが中央研究所を設け、将来の応用を見据えて基礎研究にも力を入れていた時代だった。科学研究の実力は国力を映し出す鏡ともいわれる。成果から受賞までに20年、30年かかることを考えると、2000年以降、今回で19人を数える日本の科学者の受賞ラッシュは、80年代の日本の豊かさと余裕のたまものだろう。喜んでばかりはいられない。足元で日本の研究力は元気がない。優れた論文の数からみる実力は各分野で低下。知の拠点となる大学のランキングもじり貧だ。1901年に始まったノーベル賞は1世紀以上たった今も「科学界の最高の賞」とされる。人類への貢献にこだわり息の長い基礎研究を顕彰してきたからだ。吉野氏が今後何を語るのか注目しよう。そこから科学技術創造立国への復活のヒントを得たい。 *7-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14212804.html (朝日新聞 2019年10月10日) 再エネ100%のネットワーク 再生可能エネルギーの利用を100%にすることを宣言する、日本の企業や教育機関、病院などのネットワーク「再エネ100宣言 RE Action(アールイーアクション)」が9日、設立された。遅くとも2050年までに消費電力の100%を再エネ化する目標を設けて、毎年、比率を公表する。再エネ100%を宣言する国際的な企業連合「RE100」には現在、日本企業25社が加盟しているが、参加できるのは消費電力の規模が大きな企業に限定されている。規模の小さな国内企業・団体からも同様のネットワーク設立を求める声が上がっていた。RE Actionは日本気候リーダーズ・パートナーシップなど4団体によって発足、まず28企業・団体が参加した。 <生物の進化をつかさどるDNAの変異> PS(2019年10月16日追加):同じ厳しい気候や感染症に晒されても生き残る個体とそうでない個体があり、*8には、有性生殖が多様性を生んだと書かれているが、有性生殖によるDNAの組み替えだけではそれまでになかった全く新しい性質は獲得できない。しかし、無性生殖する細菌やウイルスもDNAが変異して環境に適した性質を持つ個体が生き残り、進化は無数に起こるDNA変異の中から、より環境に適した個体がより多くの子孫を残す形で起こると言われている。 そして、最近、日本でもカムイサウルスが発見され下のように展示されているが、この恐竜の骨格は飛べない鳥エミューの骨格と類似しているため、骨格の並べ方が違うのではないかと、私は思う。歩く時は下のエミュー型、走る時は下のロードランナー型になったのではないだろうか。つまり、“恐竜”の多くは、飛べない鳥に進化していたのだろう。     カムイサウルスの骨格 エミューの骨格と生体 走るロードランナー (図の説明:1番左のカムイサウルス《むかわ竜》の骨格は、左から2番目のエミューの骨格に似ているため、生きていた時の姿は右から2番目のエミューに似ており、走る姿は1番右のロードランナーのようだっただろう。それを明らかにするには、カムイサウルスが立ったり走ったりする時の重心の位置と、その大きな骨格を動かす筋肉の大きさを現生動物から推定する必要がある)      anchiornisの化石と想像図 ガチョウ ペンギン シラサギ (図の説明:1番左のanchiornisは翼のある恐竜の化石で、左から2番目はその想像図だ。そして、中央のガチョウの嘴にも歯のようなギザギザがあり、顔も似ている。さらに、右から2番目のペンギンの口の中は恐ろしい歯並びで、泳ぐ魚を捕獲して丸呑みしながら切り裂くのに適していそうだ。また、1番右のシラサギは美しい鳥だが、首の曲がり方が蛇を思わせる) *8:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/549199/ (西日本新聞 2019/10/7) <33>多様性を生む有性生殖 性教育といっても月経や精通、妊娠や出産、性感染症や望まない妊娠の話ばかりではありません。理科や生物の授業で習った「有性生殖」も大切な性の話です。有性生殖は雄と雌、男と女という性別があり、それぞれの精子と卵子を授精させて命をつなぐこと。子どもは、両親から半分ずつ受け継いだ新しい遺伝子を持つので、性格や体質は両親とは異なります。このように有性生殖は遺伝子を混ぜ合わせて、人が多様になるように命をつなぐ方法です。今年も猛暑の夏でした。もし気温が40度になって、みんなが熱中症になってしまうと大変です。けれども高温にも強い体質の人が必ずいます。その人は熱中症で倒れている人に「大丈夫?」と声を掛け、水を与えることができます。エイズは比較的新しい病気ですが、感染の機会があってもエイズを発症しない人たちがいます。その体質は、エイズの登場以前に獲得した遺伝子の働きによるものだと分かってきました。この人たちの体質から、新しい薬や予防法が開発されようとしています。地球の大きな寿命に比べれば、人間の寿命は約100年。私たちは自分の特徴に気付くことはないかもしれません。しかし気候が大きく変化したり、未知の病気が流行したりしたときに多様な人がいれば、それに対処し乗り越えられる誰かがいるはずです。こんなことを話した性教育の出前授業の後でいただいた、とっておきの感想文を紹介します。 <僕が一番心に残ったことは、人が有性生殖をするのは、命を多様にしてさまざまな人が生まれてくるからということです。いろいろな長所や短所を持った人がいることで、その人の長所が別の人の短所を助けることができるという点がすごく良いなと思いました。自分にないものを持っている人をうらやましがったり、ねたんだりするのではなく、その人がいつか自分を助けてくれるかもしれないんだという気持ちを持ちたいと思いました。また、自分の長所が他の人をどのように助けることができるのか考えようと思いました> 有性生殖で命をつなぐ意味は「誰かが誰かを助けるために」。このように考えてくれる高校生がいると、未来も安心だと思えます。 <外国籍の人の教育に関する取り扱い> PS(2019年10月20日追加): *9-1・*9-2のように、学齢期でも小中学校に通えない外国籍の子どもが日本国内に約2万人おり、外国人労働者の受け入れを拡大すれば数が増える。国際人権規約では、小中学校教育を「義務的なもの」として「すべての者」に「無償とする」と規定しているが、日本国憲法が定める義務教育の対象は「国民」となっており、外国人は対象外で法律上は就学させる義務がないことが問題の背景にあるそうだ。 確かに、*9-3の日本国憲法26条は2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めており、日本国民以外には義務を課していないが、外国籍の子も教育を受ける権利があり、国際人権規約では小中学校教育を「すべての者に義務」としている上、外国籍の子にも教育を受けさせた方が質の良い労働力が増えて生活保護受給者を増やさず日本にとってもプラスだ。そのため、これまで外国籍の子を軽視していたのは国・地方自治体の配慮不足が過ぎる。 また、*9-4の教育基本法も、日本国憲法を受けて日本国民しか対象にしていないが、第4条に教育の機会均等を掲げ、「人種・信条・性別・社会的身分・経済的地位又は門地によって教育上差別されない」とし、国・地方自治体に義務教育の機会保障・その水準確保・適切な役割分担と相互協力による責任ある実施を要請しているため、外国籍の子にもこれを準用すればよかったのだ。そのため、教育基本法の前文に、「国内に在住する外国人には、この法律を準用する」という一文を付け加え、教育基本法の理念をしっかり実現すればよいだろう。 *9-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/443320 (佐賀新聞 2019年10月19日) 外国人の不就学 学ぶ権利は平等だ 学齢期なのに、小中学校に通えない外国籍の子どもが国内に2万人近くいる可能性がある。文部科学省の初の調査で分かった。少子高齢化対策で政府が外国人労働者の受け入れを拡大し、外国籍の子は確実に増える。子どもが学ぶ権利は国籍に関係なく平等だ。国が主導し、自治体と共に早急に対策を講じるべきだ。文科省が「不就学」の可能性があるとした外国籍の子は1万9654人。この年代は住民基本台帳には約12万人登録されており、16%を占める。このうち、就学していないことが明らかなのは千人で、残りは状況の把握すらできていないといい、その事実が事態の深刻さをうかがわせる。実際には住民登録していない子どももいるだろう。日本も批准した国際人権規約は小中学校の教育を「義務的なもの」とし、「すべての者」に無償とするとしている。ただ、憲法が定める義務教育の対象は「国民」。外国人は対象外で、法律上は就学させる義務がないことが問題の背景にある。調査から浮かぶのは、外国人への就学案内が不親切という実情だ。多くの市区町村が、保護者の希望があれば入学させるという待ちの姿勢で、積極的に働き掛けていない。住民登録時に全員に就学案内をする自治体は半数。義務教育年齢の子どもを登録する「学齢簿」に準じる書類を外国人全員に作る所も半数に満たない。小学校新入学の年齢の子がいる家庭に案内を送るのは63%、中学校は48%にとどまる。多くが日本語で記しており、理解が危ぶまれる。驚くのは、就学状況が不明な場合の対応について、65%もの自治体が「特に実施していない」と答えたことだ。国は「通知などで対応を促してきた」というが、責任を押し付け合って済む問題ではない。文科省は今年に入ってようやく実態把握や対策を検討し始めたが、遅きに失した感がある。外国人が住むのは東京都、大阪府、神奈川県、愛知県など都市部が多い。人数が多い自治体は把握が不十分な一方、国際結婚などで外国人が散在する地域は受け入れの経験が少なく、人手や予算もないという課題がある。国がこの問題を自治体任せにしてきたために地域ごとの差が大きい。外国人労働者の多い浜松市は積極的に家庭への訪問を繰り返してきた。文科省はこうした先進事例を一刻も早く全国に紹介し、きめ細かな対応を促すべきだ。さらには制度を整え、自治体の財政支援に力を入れる必要がある。文科省の別の調査では、日本語指導が必要な高校生の中退率は平均の7倍以上。卒業しても就職者の40%が非正規労働で、進学も就職もしない比率も高い。日本語が不自由なまま働いたり、きょうだいの世話をしたりする子どもの将来が心配だ。制度からこぼれ落ちた子どもたちが犠牲になっていいわけがない。読み書きもままならずに大人になれば、貧困状態に陥る恐れが大きい。教育を受けて就職し、生活が安定すれば、結局は日本社会全体が利益を得る。4月の改正入管難民法施行による新たな在留資格創設で、外国人労働者とその子どもは一層の増加が見込まれる。門戸を開いた以上、国として責任を持つべきだ。こんな恥ずかしい状況を放置したままでは安倍政権は国際社会に顔向けできまい。直ちに対策を実行する必要がある。 *9-2:https://www.sakigake.jp/news/article/20191020AK0015/ (秋田魁新報社説 2019年10月20日) 外国人不就学問題 国主導の対策が急務だ 日本で暮らす外国籍の子どものうち、約16%に当たる1万9654人が小中学校に通っていない不就学の可能性があることが、文部科学省による初の調査で分かった。外国人労働者の受け入れが拡大する中、外国籍の子どもは確実に増える。不就学の子どもをなくすためにも、国は早急に就学環境を整える対策を講じる必要がある。調査は5~6月に全1741市区町村の教育委員会を通じて実施した。調査対象としたのは住民基本台帳に住民登録する外国籍の子ども12万4049人。このうち実際に不就学を確認したのは千人で、残りは調査時に自宅に不在だったり、学籍簿に名前が無かったりして、状況の把握すらできていないという。文科省はこれら全てを合計した人数について、不就学の可能性があると判断した。まずは実態把握を急がなくてはならない。日本は、外国籍の子どもが公立小中学校への就学を希望すれば、国際人権規約などを踏まえて無償で受け入れている。ただ日本人と違い就学義務はない。加えて働いたり、家できょうだいの面倒を見たりしている不就学の子どももいる。こうした子どもたちを孤立させてはならない。学ぶ権利は国籍に関係なく平等にある。調査からは自治体の対応や支援態勢にばらつきがあることも浮き彫りとなった。就学を促す取り組みを特に行っていない自治体は65%に上り、4割が就学案内を送っていなかった。送付したとしても日本語のみの記載といった案内も多くある。日本語指導が必要な子どもに特段の対策をしていない自治体は半数余りで、「人員や予算が不足」「どのような支援を行うべきか分からない」などを理由に挙げていた。せっかく就学しても日本語が分からなければ、学校に居づらくなり、退学となるケースも少なくない。将来の進学や就職などにも影響する。国は「通知などで対応を促してきた」としている。しかし自治体任せにするのではなく、自ら主導して、外国籍の子どもたちが安心して学校に通えるようにするべきである。積極的に家庭への訪問を繰り返している自治体や、民間と連携して日本語教育を推進している自治体もある。文科省はこうした先進事例を広く紹介することで、きめ細かな対応を促してほしい。外国人の不就学問題の解消は日本の子どもたちにとってもメリットがある。同じ教室で多様な言語や文化に触れながら学ぶことはコミュニケーション力を高め、寛容性や柔軟性を育むことにつながる。本県で不就学の可能性がある子どもは2人とされたが、県による再調査ではゼロだった。ただ本県でも在留外国人の増加に伴い、外国籍の子どもは増えている。今後を見据えて、今から準備を進めておくことが重要である。 *9-3:http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/a002.htm (日本国憲法 教育関係の条文抜粋 昭和二十一年十一月三日) 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 *9-4:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=01&id=2442) (教育基本法 平成十八年十二月二十二日法律第百二十号 我々日本国民は、①たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、②世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 第一章 教育の目的及び理念 (教育の目的) 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 (教育の目標) 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 ①幅広い知識と教養を身に付け、②真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 (生涯学習の理念) 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 (教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 第二章 教育の実施に関する基本 (義務教育) 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 (学校教育) 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 (大学) 第七条 ①大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、②深く真理を探究して新たな知見を創造し、③これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。 (私立学校) 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。 (教員) 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 (家庭教育) 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 (幼児期の教育) 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 (社会教育) 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 (政治教育) 第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 (宗教教育) 第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 第三章 教育行政 (教育行政) 第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。 (教育振興基本計画) 第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 第四章 法令の制定 第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。 附 則 〔抄〕 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 <教員の質と労働条件など> PS(2019年10月21、24、28、29日追加):*9-4の教育基本法第9条に、「①教員は崇高な使命を深く自覚して絶えず研究と修養に励み、職責の遂行に努めなければならない」「②教員は使命と職責の重要性に鑑み、身分が尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない」と記載されている。一般社会でもいじめやハラスメントは多発しているが、*10-1のように、教員自身がいじめを行っているようでは、児童生徒にいじめを行わないよう指導することはできず、首謀者か追随者かは問わず、いじめを止めるのではなく加担する側に立つのは勇気や公正な態度の見本を示すどころか逆を行っていて、①からほど遠い。 また、*10-2は、「③忙しい時期は勤務時間を延長して夏休み中に休暇を取るような『変形労働時間制』を公立校の教員にも適用できる法改正案を政府が閣議決定した」「④夏休み中も部活動や研修があり、必ず休みが取れるとは限らない」「⑤過労死労災認定の基準となる月80時間を超えて残業をしている教員は、文科省の16年度の調査で小学校で3割余・中学校で6割近くに上り、日本の教員の勤務時間は欧米各国に比べると突出して長い」「⑥順次導入される次期学習指導要領では、思考力や表現力を引き出す授業の工夫が一層求められる」等が書かれているが、企業と比較して教員は休みが多いので、私は③は妥当だと思う。そして、いつまでも④⑤を主張しているようでは思考力がなく、⑥を行うことができる教員が何割いるのか考えさせられる上、自分が上手くない人から教わっても上手くはなれないため、部活や外国語指導を従来の教員に担当させるのが効果的かどうかも疑問だ。さらに、学校も組織であるため教員が雑用に翻弄されずに本当の教育を行える体制を作ることはできるし、とっくの昔に作っていなければならない。つまり、②は、質の高い教育を行うために定めたもので、教員の数のみを問題にするのではなく待遇の適正化によって質の高い人材を確保しようとしているのである。 なお、*10-3のように、関東では2019年度当初時点で公立小中学校に配置すべき教員が少なくとも503人不足しており、産休・育休取得者や病気休職などが出た場合に代わりの教員を確保できない現状が覗えたそうだ。しかし、そのリストの人材が枯渇した理由は、少なくなった新卒者を多くの企業が奪い合っているからで、それでも定年を60~65歳に保たなければならない理由はない上、待遇が悪ければ教員免許を持っていても教員という職業を選択する人は少なくなることを忘れてはならない。 インドネシアでは、*10-4のように、ジョコ大統領が米ハーバード大経営大学院を修了してゴジェックを創業したマカリム氏を教育・文化相に任命し、先進国入りを目指して高度産業を担える人材育成を最重要課題の一つに掲げて教育改革をするそうだ。日本は、最終学歴こそインドネシアより高いが、頑張らない方向への改革を続ければ、2045年には先進国に入っていないかもしれない。 2019年10月28日、*10-5のように、日本私立大学連盟の鎌田会長が、「⑦高等教育の無償化は『国私格差』拡大の恐れがある」「⑧私大の増収に寄与しない」「⑨新制度は受給対象者を2浪、20歳までに限っている」「⑩国立大学と私立大学の卒業生が国や社会全体にもたらす便益にこれほど大きな差があるとは考えられない」と批判されているが、日本の高等教育の問題は国私格差を無くすために国公立大学の授業料を上げて学生の高等教育負担を増やし、志のある学生に高等教育を受けにくくさせたことに由来する。また、私大は入試科目が少なく(=学生の知識や理解度はそれだけ狭くて浅い)、建学の精神に基づいて学生の選抜方針や教育方針を自由に決めることができ、巨大マスプロ教育(=議論したり、考えたりする教育が僅少)によって⑩も十分でないため、⑦のように、授業料の国私格差だけを問題にするのは、志ある学生を育てようとしている高等教育無償化の趣旨とは異なる。また、教育は人材育成のためにあり、大学の増収のためにあるのではないため、高等教育無償化に関する⑧の批判には驚いた。さらに、⑨の受給対象者を2浪に限っているのは、就職もせず大学受験で何浪もできる人はそれだけ裕福な家庭の子であることから当然で、年齢制限については、社会に出た後で再び大学で学ぶ意欲のある人は、働いている期間にそのくらいの貯金はしておけということだ。 また、*10-6のテレビ番組(プライムニュース)は私も見ていたが、キャスターが「受験生の経済状況や居住地で不利が生じて不公平ではないか」と言ったので、萩生田氏が「『あいつ予備校に通ってずるい』と言うのと同じだ(≒不公平に当たらない)」と答えたのであり、私は同意だ。だが、大学入学共通テストで導入される民間検定試験がいくつもあると比較できないため、留学に影響するTOEFL一本にするのがよいと考える。中学・高校でTOEFL試験を何度も行えば、不公平はなくなり、受験生も慣れる。そして、それだけでは受験生間に差がつかないとか、大学教育に不十分だと考える大学は、東大のように二次試験を行えばよいだろう。 なお、2019年10月29日、*10-7のように、朝日新聞が、大学入試改革として2020年4月から英検やGTECなど7種類の英語民間試験を活用することについて、「⑪塾に通わずに受験勉強をしている母子家庭の子や離島の生徒を例に出して教育機会均等と全く逆としている」「⑫教育基本法は『すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならない』とする」「⑬大臣が地域・経済格差が教育格差に繋がるのを容認したことが問題」「⑭都会の裕福な家の子が何回も受験の練習をするのを妨げられない」等を記載しているが、7種類の英語民間試験を活用することこそ比較可能性をなくして公正な評価を不可能にするため問題なのである。そのため、大学入試なら、各大学が入試として認定する民間試験を指定し、例えば留学に役立つTOFLEの結果のみを採用することとして、中学・高校から学校でTOFLEの試験を繰り返せば、すべての問題を前向きに解決できるが、そのためには延期が必要だろう。 また、教育は、“身の丈”を伸ばすために行うものだが、⑪は、公立の初等・中等教育の教育内容が不十分で、塾に通わせなければ高等教育の受験もおぼつかない現状が問題なのであり、それは英語だけの問題でもないため、なったばかりの文科大臣の発言の問題に帰するのは小さすぎる。さらに、⑫や*9-4の教育基本法4条に定められた教育の機会均等は、入試の機会均等や奨学金などで一応は達せられており、結果平等を求めるものではない。⑬⑭については、地域間格差や経済格差が教育格差に繋がっているのは事実だが、これは地域間の産業格差や教育に対する意識格差が密接に関係しており、首都圏や都会だから有利とも限らないため、教育基本法13条、17条のように、国と地域で総合的な基本計画を立てて進めなければならないのである。 *10-1:https://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/20191020502333.html (新潟日報社説 2019年10月20日) 教員のいじめ 本分忘れた許し難い暴走 子どもの教育という自らの職責を忘れた、信じられない暴走である。あまりの荒廃ぶりにあぜんとする。これでは、子どもも保護者も学校に不信と不安を抱く。再発を防ぐためにも、なぜ問題が起きたのか、歯止めを掛けられなかったのかを徹底的に解明しなければならない。神戸市立小学校の教諭4人が同僚に対して、度重なるいじめ行為をしていた。加害者は30代の男性教諭3人と40代の女性教諭1人である。集中的に被害に遭っていた20代の男性教諭は精神的に不安定になり、9月から欠勤した。羽交い締めにして激辛カレーを食べさせる。無料通信アプリLINE(ライン)で別の女性教員に性的なメッセージを送るよう強要する。訴えられたいじめの内容は極めて悪質だ。男性教諭は50種類以上のいじめがあったと申告している。熱湯の入ったやかんを顔に押し付けられる暴行、灰皿に入れた水を車内でまき散らされる嫌がらせなどもあったという。ほかに20代の教員3人が暴言やセクハラを受けていた。「反抗しまくって学級つぶしたれ」。加害教員が児童にこう言っていたとの訴えも明らかになっている。事実であれば、子どもたちをいじめに加担させようとしたとも受け取れる。常軌を逸しているというほかない。問題が発覚し、ショックを受けた児童が学校を休んだケースもあった。子どもへの心理的影響もとても心配だ。学校でのいじめは増加し続けている。文部科学省の最新の発表によると、全国の小中学校や高校、特別支援学校での2018年度のいじめ認知件数は54万3933件、心身に深刻な被害が生じる「重大事態」は602件。ともに過去最多だった。いじめ防止は今や学校や教員にとって最大の課題だろう。にもかかわらず、教員同士の間でもいじめがあったことにやりきれない思いに駆られる。神戸市教委によると、欠勤している男性教諭は昨年以降いじめを受けていた。それを市教委が確認したのは今年9月。男性教諭の家族が訴えたからだ。この間、校内で問題はどう扱われていたのか。今春異動した前校長と現校長はいじめの相談を受けても、市教委に詳細を伝えなかった。それが、問題を深刻化させた面もあろう。市教委が設置した調査委員会による調べはこれから本格化する。管理職の対応の問題点も掘り下げ、理由や背景を明らかにしなければならない。このところ本県でも、教員の不祥事が相次いでいる。9月には長岡市の小学校校長が買春の疑いで逮捕され、十日町市内の中学校教諭が児童買春で書類送検された。モラルの低下は目を覆うばかりである。子どもたちや地域を裏切ることのないよう、教育界は自らに課せられた責任の重さを改めて肝に銘じてもらいたい。 *10-2:https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20191021/KT191018ETI090016000.php ( 信濃毎日新聞 2019年10月21日) 教員変形労働制 根本的な是正にならない 年度初めや学校行事が立て込む忙しい時期は勤務時間を延長し、代わりに、夏休みの期間中に休暇を取る―。働く時間を年単位で調整する「変形労働時間制」を公立校の教員にも適用できるようにする法改正案を政府が閣議決定した。長時間労働が常態化した教員の働き方改革の一環と位置づけている。ただ、休暇をまとめて取れるようにしても、労働時間が全体として減るわけではない。むしろ、学期中の長時間労働を追認することになりかねない。定時が延びると会議などが入り、家に持ち帰る仕事がかえって増えないか…。心配する声が現場から出ている。夏休み中も部活動や研修があり、必ず休みが取れるとは限らない。表向き残業時間は減っても、どこまで過重労働の是正につながるのか疑問だ。文部科学省は、教員の残業時間の上限を月45時間とする指針を1月に定めている。この指針の位置づけも条文で明確にするが、変形労働制は月ごとの上限をなし崩しにする恐れがある。日本の教員の勤務時間は欧米各国に比べると突出して長い。経済開発協力機構(OECD)の2018年の調査では、5年前よりさらに増えた。過労死の労災認定の基準となる月80時間を超えて残業をしている教員は、文科省の16年度の調査で、小学校で3割余、中学校では6割近くに上る。順次導入される次期学習指導要領では、思考力や表現力を引き出す授業の工夫が一層求められる。小学校では英語が教科になり、授業時間も増える。教員の負担が増すのは目に見えている。一方で、子どもを取り巻く問題は深刻化している。18年度に全国の学校で確認されたいじめは54万件を超え、心身に重大な被害が及ぶ事態も600件に達した。自殺した小中高校生は330人余に上り、ここ30年で最も多い。親から虐待される子も増えている。教員に時間と気持ちの余裕がなければ、子どもと丁寧に向き合うことはできない。発しているサインや異変を見過ごすことにもなる。過重な負担を減らすには、十分な教員数を確保するとともに、学校や教員が担ってきた仕事を見直し、分担する仕組みや補う態勢を整えていく必要がある。法改正により一律に変形労働制が取られるわけではなく、導入するかどうかは自治体が判断する。国会での法案審議に加え、地方議会や地域で、学校現場の実情を踏まえた議論が欠かせない。 *10-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201910/CK2019102002000144.html (東京新聞 2019年10月20日) 教員不足 公立小中500人 本紙1都6県アンケート 本紙が関東1都6県の計39の自治体の教育委員会に行ったアンケートで、2019年度当初時点で、公立小中学校に配置すべき教員が、少なくとも503人不足していたことが分かった。教員不足の自治体は16で4割に上った。回答からは、産休・育休取得者や病気休職などが出た場合に、代わりの教員を確保できない現状がうかがえ、児童生徒への影響も懸念される。教員の採用や配置は都道府県と政令市の各教委が行う。本紙は今年六~七月、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬の各県と横浜、川崎、相模原、さいたま、千葉の五つの政令市の教委にアンケートした。東京都内は二十三区と人口二十万人以上の五市の教委に調査した。調査結果によると、小学校では十三自治体で常勤三百四十四人、非常勤三十九人が不足。中学校も十三自治体で、常勤八十三人、非常勤三十七人が不足していた。小学校では学級担任十三人が、中学校は教科担任二十三人が不足していた。教員が配置できない理由で多かったのは、産育休などの教員の代役となる非正規教員の不足だ。教員の欠員が出た場合、学校などはまず都道府県教委などが持つ登録リストに載っている人の中から後任を探す。しかし近年、このリストの人材は枯渇気味。登録しているのは「教員採用試験の不合格者」が多く、二〇一〇年ごろからは、かつて大量採用されたベテランが退職期を迎え、正規採用が増えたことで登録者が減った。教員志望者自体も減少傾向にあり、新たな登録も減っている。一方で欠員を埋めるための需要は増加している。「大量退職、新規採用増」の影響で、公立学校では教員の年齢が若返っており、ここ数年はその世代が産休や育休を取ることが多い。教員確保が難しい理由として「若手教員が増えて産休・育休取得者が増加しているため」(千葉県)という回答も目立った。「病気休職が日々発生している」(東京都八王子市)との回答もあるように、過密労働による精神疾患などで休んだり、辞めたりするケースも少なくない。 *10-4:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51299530T21C19A0FF1000/ (日経新聞 2019/10/23) インドネシア、教育相にゴジェック創業者、競争力強化へ人材育成急ぐ インドネシアで23日、配車サービス大手、ゴジェック創業者のナディム・マカリム氏(35)が教育・文化相に就任した。2045年の先進国入りを目指すジョコ大統領は高度な産業を誘致するために人材育成を2期目の最重要課題のひとつに掲げている。ゴジェックで200万人の運転手を教育して職を生み出したナディム氏の経験を生かし、産業界に必要な人材育成を急ぐ。ジョコ大統領が23日発表した新内閣の目玉はナディム氏の教育・文化相就任だった。ナディム氏は早速、5千万人の児童・生徒を対象に、IT(情報技術)教育などを充実させる考えを示した。ジョコ氏は「産業界で役立つ人材育成の突破口を作ってほしい」として、教育機関と産業界の懸け橋としての役割も期待するとした。ナディム氏は1984年生まれで、米ハーバード大経営大学院を修了した。ゴジェックを起業し、15年にスマホを使った配車や宅配、金融などのサービスを本格的に始め、わずか3~4年でインドネシア人の生活に不可欠なサービスに育てた。ゴジェックは世界に20社ほどしかない巨大未上場企業「デカコーン」(企業評価額100億ドル=1.1兆円=以上の未上場企業)となった。ナディム氏は21日、入閣要請を受諾し、ゴジェックの最高経営責任者(CEO)を退任した。ナディム氏は23日、従業員に宛てた電子メールで、ゴジェックが配車などで人々の生活を改善してきたことに触れ、「インドネシアが(ゴジェックにいるような)高度な人材をもっと生み出すためには教育システムを変える必要がある」と入閣の理由を述べた。もともとは得意分野のデジタル担当相やイノベーション担当相などとして登用する案も出ていたが、最終的に教育・文化相という重要閣僚で起用することが決まったのは、ナディム氏がゴジェックで運転手を教育して職を与えたことを高く評価したためだ。就職につながる国の教育システム作りを託した。ジョコ氏は早い段階からナディム氏の事業に注目して支援してきた。15年12月に配車サービスを禁止する通達が出た際には「誰のための規制だ」と運輸相を叱責し、事実上撤回させた。19年4月にはゴジェックの運転手向けのイベントにジョコ氏が参加するなど、ジョコ政権とナディム氏の関係は深かった。ジョコ氏は組閣にあたって、ミレニアル世代(1980年から2000年ごろ生まれの若者)の代表として、有力スタートアップ経営者や大手財閥の若手経営者らの入閣を検討していた。なかでもナディム氏には4月の大統領選で再選を決めた直後から接触しており、意中の人物として早くから決めていたようだ。ただ、ナディム氏の前には大きな壁が立ちはだかる。インドネシアの労働人口のうち、最終学歴が小学校卒以下の人が約4割で、中学校卒以下も合わせれば約6割に達する。産業界からは「即戦力として使える人材が少ない」(日系企業)といった不満が出ていて、海外からの投資が周辺国に流れる一因となっている。ジョコ氏は23日、閣僚に対して「具体的な成果を意識して仕事をするように」と訓示し、早期に結果を出すことを求めた。教育は一朝一夕で改善するものではないが、ナディム氏は短期間で教育の抜本的な改善と、産業界への人材の送り出しという困難な課題に答えを出さなくてはならない。 *10-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191028&ng=DGKKZO51395670V21C19A0CK8000 (日経新聞 2019年10月28日) 高等教育の無償化、「国私格差」拡大の恐れ、前日本私立大学連盟会長 鎌田薫氏 私大の増収寄与せず/現行補助廃止なら改悪 2020年4月から低所得世帯の学生が対象の高等教育の無償化が始まるが、日本私立大学連盟の鎌田薫前会長(早稲田大学前総長)は私立大学には問題が多い制度だと批判する。来年4月から、大学、短大、高専、専門学校に在学する住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を対象として、新たな授業料減免制度が始まり、給付型奨学金も拡充されることになった(高等教育の就学支援新制度)。初年度の予算は7600億円が予定されている。600校を超える4年制私立大学全体に対する助成金総額が3000億円弱だから、この金額は画期的に大きなものといえる。ただし、この授業料減免制度は学生の授業料を国が代わって大学に支払うものであるから大学の収入増にはつながらず、国の負担分は消費税引き上げによる財源を用いた内閣府の社会保障関連予算に位置づけられる。グローバル化、情報化と少子高齢化が急速に進む現代日本社会においては、国民一人ひとりが高度の知識・技能を身につけ、新たな価値を創造していくことが強く求められている。一方で、教育費負担が子どもを持つことに対する最大の抑制要因となっている。実際にも、低所得者層の大学進学率は漸減傾向にあり、経済格差と教育格差の悪循環が懸念されている。これらのことを考えれば、市民生活の安定と国の繁栄を維持発展させるためには、高等教育費負担の軽減を図ることが必要であり、新制度がその第一歩を踏み出したこと自体は高く評価しなければならない。しかし、その制度設計には私立大学として看過できない問題点があり、私学団体も一貫して批判的な意見を述べてきた。ここでは、特に国私間の格差を拡大させる恐れについて私見を述べたい。 □ □ □ 国の高等教育費支出は、学生1人あたり、国立大学202万円、私立大学15万円であって、13倍を超える格差がある。これらはいずれも平均額であり、国立大学生の3割は授業料減免の恩恵を受けているし、私学助成の交付額は大学によって様々であるから、一人ひとりについて見れば、より多様な比率になる。その意味では精密さに欠ける比較ではあるが、国立大学と私立大学の卒業生が国や社会全体にもたらす便益にこれほど大きな差があるとは考えられず、国費の投資効率や納税者間の平等という観点からは正当化が難しい格差といえよう。本来なら、こうした異常な格差を解消した上で、個々の学生の能力と経済状況に応じて幅広く柔軟な支援策を講ずるべきであって、大学の設置形態によって支援内容に差を設けることは合理的でなく、不当な格差を拡大させる恐れもある。例えば、ある受験生が強く進学を希望する私立大学の特定学部の授業料が160万円であるとすると、新制度による支援は70万円を上限としているから、90万円の自己負担を覚悟しなければならない。この受験生が第一希望を断念して国公立大学に進学すれば、学費全額を国が負担するという今回の制度が本人と国の将来にとって果たして有益なのだろうか。現状でも国立大学生の世帯収入が私大生のそれを上回っており、受験準備に十分な投資ができなければ難関大学に進学できない傾向が顕著になっている。新制度が国は国公立大学への進学を強く奨励しているというメッセージと受け止められれば、この傾向はさらに強まり、制度目的とは逆に受験準備のために十分な投資をする余裕のない受験生はますます進学が困難になる恐れがある。学部学生の約8割に対する教育を担っている私立大学には、低所得者層を含む多様な学生が在籍している。そのため、各私立大学は独自の支援措置をとっており、その総額は毎年900億円規模に上っている。現在は、年収841万円以下の世帯の学生に対する各私大独自の授業料減免額の2分の1について国庫補助を受けられるものとされている。実際の交付額は90億円程度に留まっているが、就学支援新制度の導入に伴って、従来の補助は廃止されるといわれる。最も多くの学生が属する年収400万~900万円の世帯に対する授業料減免への公的支援がなくなったとしても、各大学は従来の減免措置を取りやめることはできないだろうし、新制度の影響で支援策の拡充を迫られるかもしれず、私立大学にとっては改悪としかいいようがない。しかも、その原資には学生からの授業料も含まれるため、実際上は学生相互間の所得移転による社会保障の肩代わりを拡大させるものであり、本来あるべき方向性とは逆行している。 □ □ □ 新制度は受給対象者を2浪、20歳までに限っている。さらに、現行制度では補助対象としていた大学院生の授業料減免が廃止されるとすると、教育再生実行会議や人生100年時代構想会議などが、生涯を通じて何時でも必要なときに必要なことを学べる体制を整えることや、博士学位取得の促進などを提言してきたが、そうした政策と矛盾することになる。新法付則の定める施行後4年の見直しに向けて、国私間格差の抜本的解消、諸外国で行われているような国公立大学に低所得者層の学生を一定数入学させる制度の導入、中間所得層を含む幅広い学生に対する支援措置の拡充などについて深く真剣に検討されることを切に期待する。 *10-6:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/358826?rct=n_society (北海道新聞 2019年10月28日) 萩生田文科相、「身の丈に合わせて」発言謝罪 萩生田光一文部科学相は28日、大学入学共通テストの英語で導入される民間検定試験に関して「自分の身の丈に合わせて頑張ってもらえれば」とテレビ番組で述べたことについて、報道陣の取材に応じ「国民、特に受験生に不安を与えかねない説明だった。おわびしたい」と謝罪した。民間試験導入を巡っては、受験生の経済状況や居住地によって不利が生じるのではないかと懸念の声が高まっており、全国高等学校長協会は2020年4月開始の延期を求めている。番組は24日に放映され、萩生田氏は不公平への懸念について「『あいつ予備校に通ってずるい』というのと同じだと思う」との見方も示していた。 *10-7:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14235380.html (朝日新聞 2019年10月29日) (時時刻刻)「格差を容認」批判噴出 英語民間試験、文科相「身の丈に合わせがんばって」 2020年度から始まる大学入学共通テストで活用される英語の民間試験について、萩生田光一文部科学相が「身の丈に合わせてがんばって」と発言し、28日、謝罪に追い込まれた。教育格差を容認するような教育行政トップの発言に、受験生や教育関係者から憤りの声が上がった。野党は大臣の辞任を求め、追及を強める考えだ。 ■謝罪、発言は撤回せず 「国民の皆様、特に受験生の皆さんに不安や不快な思いを与える説明不足な発言であった」。28日、萩生田氏は文科省内で謝罪した。問題の発言は、24日の報道番組で、大学入試改革の目玉として来年4月から活用が始まる英語民間試験に言及した際に飛び出した。現在の高2が主に受ける共通テストでは、英検やGTECなど7種類の民間試験を使って、英語の「読む・聞く・話す・書く」の4技能を測る。国のシステムで各人の成績を集約し、出願先の大学に提供する。練習のために何度受けてもいいが、大学に提供されるのは高3で受けた2回までの試験の成績だ。住む場所や家庭の経済状況によって不公平が生じないか――。こんな質問に、「『あいつ予備校通っててずるい』というのと同じ」などと反論。生徒の境遇により本番までの受験回数に差が出るのを認めた上で、「身の丈に合わせて、2回をきちんと選んで勝負してがんばってもらえば」と述べた。ただ、萩生田氏は28日の取材では不公平を容認しているとの指摘に対して、「どんなに裕福でも2回しか結果は提出できないので、条件は平等」と強調。発言は撤回せず、「民間試験なので、全ての人が(本番の)2回しか受けてはいけないというルールにはできない」などと釈明した。受験料が2万5千円を超える試験や、会場が都市部の10カ所に限られる試験もあり、地域格差や経済格差の問題は、導入が決まった当初から指摘されてきた。文科省は、低所得世帯の受験料減免を業者に求めたり、離島の受験生に交通費や宿泊費の一部を補助する支援策を来年度予算の概算要求に盛り込んだりした。一方で、萩生田氏は1日の会見で、新制度について「初年度は精密さを高めるための期間」などと発言。「生徒を実験台にするのか」などと批判を浴びた。今回の発言で、さらに批判が強まりそうだ。文科省幹部は「『なぜあんな発言を』と考える職員はいるだろう。高校などに説明する際に悪影響が出るのが心配だが、立ち止まる余裕はない」と語った。 ■教育機会均等と「全く逆」 萩生田氏の発言はSNSなどを通じて広がり、「地方の貧乏人は身の程を知れという姿勢?」などと反発が相次いだ。都内の高校2年の男子生徒(17)は母子家庭で、塾に通わずに受験勉強をしている。「与えられている条件が人によって違うのに、『身の丈に合った』と言われると、自分の可能性を抑え込まれた感じがする」と言う。「そもそも身の丈に左右されてしまうような制度。それを止めるどころか推進するような発言だと腹が立ちました」。都立高校の50代教諭は「教育を担当する大臣として、あり得ない発言」と憤る。離島の都立高校に赴任したことがある。受験料や船代、宿泊代をこつこつためていた生徒の家族をいくつも知っている。「格差を追認するような発言を大臣がしていいのか」。識者からも批判の声が上がる。小林雅之・桜美林大教授(教育社会学)は「国がすべきことと全く逆の発言であり、問題だ」と言う。教育基本法には「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず」とある。小林教授は「国はもっと支援策を講じるべきだ。全国高校長協会が延期を求めるなど、試験への批判も強い。再検討した方がよい」と言う。萩生田氏の発言に対し、野党は強く反発する。大臣の辞任を求め、厳しく追及する構えだ。英語民間試験を巡っては、野党統一会派と共産党が24日、「経済的な状況や居住地域に左右される」などとして、導入を延期する議員立法を衆院に提出した。その後、飛び出した萩生田氏の発言に、野党国対幹部は「憲法で保障された教育の機会均等なのに大臣自らが不平等を容認している。国会でも取り上げざるを得ない」。一方、菅義偉官房長官は28日午前の記者会見で萩生田氏の文科相としての資質について問われると、「適材適所だと思っている」と述べた。 ■<視点>制度自体に問題、浮き彫り 英語民間試験の活用について「身の丈に合わせてがんばってもらえば」と発言した萩生田光一文科相が「説明不足だった」と謝罪した。だが問題は「説明不足」だったことではない。まず、大臣が「身の丈に合わせて」と格差を容認する言葉を口にしたことだ。地域・経済格差が教育格差につながるのを防ぐのが大臣の責務だ。課題を受験生に押しつけ、開き直ったとも受け取れる。こんな姿勢では、教育政策を預かる資格はない。さらに深刻なのは、制度自体が「身の丈入試」であることを拭えない点だ。民間試験を使う以上、都会の裕福な家の子が何回も受験の練習をするのを妨げられない。萩生田氏の発言は、この問題を改めてあぶり出した。11月1日から受験用の「共通ID」の申し込みが始まる。受験生の不安はすでに限界を超えている。 <一般社会であった有名ないじめ> PS(2019年10月23、24日追加): *11-1は、「①メーガン妃の『個人的な手紙』を報じたのは著作権侵害・データ保護法違反などにあたるとして、ハリー王子夫妻が英大衆紙と親会社を提訴した」「②王子は『こうした攻撃的な報道は他人の人生を台無しにするいじめだ』と強く非難している」としている。しかし、“血統書付きの家庭”の出身でないのはメーガン妃の責任ではなく、それでも公爵夫人になれたのはメーガン妃の実力であるため、これらの報道は「人種差別」「いじめ」に入るだろう。また、「③服装やふるまいが伝統破りだと頻繁に指摘され」「④側近の退職が相次ぎ、『気難しい公爵夫人』とあだ名を付けられ」「⑤一部メディアで激しい批判にさらされた」のも、肌の色や経歴が異なれば似合う服や行動が異なるのは当然であるため、(頭の固い)側近が退職したからといってメーガン妃のせいと決めつけるわけにはいかない。つまり、この種の報道は「言論の自由」「表現の自由」よりも「名誉棄損」や「人権侵害」に当たるのだ。そして、イギリス国民は、メーガン妃の肌の色や経歴をメリットとして活かした方が賢いし、私はデザイナーの実力でメーガン妃の容姿をぱっと輝かせる服装を見たいと思っている。 また、*11-2は、日本の現皇后雅子妃の話で、2003年に「⑥適応障害(そういう精神病はない)」という変な病名で“療養”に入られて後、皇后になってから輝きを増したと言われている。しかし、私は結婚1年目に中東を訪れた時と比較して現在のファッションは顔立ちを活かせないぼーっとしたもので、これが日本の皇室に“適応”した姿とは情けなく思う。さらに、日本のマスコミは「笑顔」「笑顔」と繰り返し、意味もなく笑うことを強要しているが、(女優じゃあるまいし)外国人から見ると本物の喜びからくるのではない意味のない笑いはむしろ気味が悪いのだ。また、「⑦エリート中のエリートで美しい女性は相当に鼻持ちならない人格」「⑧ミーミーミーでは無く、自己主張が少なく、人に合わせる」等は、日本で女性に対してよく使われる評論だが、⑦は女性蔑視に由来し、⑧のように自己主張が少なく他人に合わせるだけの人は存在感や魅力がない上、こういう仕草を強要するのは女性差別であることがわかっているだろうか。 私も、Fairでなく女性蔑視を含む過小評価や意図的に歪められた批判をメディアやネットで吹聴されて大きな損害を受け、「こういう社会の雰囲気を変えることが唯一の解決策だ」と思って提訴したが、勝訴しても意図的に歪められネットに掲載された誹謗中傷は消されなかった。そのため、息子がネットで中傷被害を受けて加害者を特定するために法廷で闘うことを決めた*11-3のような母親がいるのに、違法行為になるネット上の匿名の誹謗中傷の犯人を明らかにしなかったり、それらの記載を削除しなかったりするプロバイダーは、犯罪幇助者か犯罪者本人だと考える。しかし、子の方は、サッカーを辞めて他のことをしたり、不登校や自傷行為などで自分が学べない状況を作るよりは、もっとよい学校に転校して自分の道を開いた方がよさそうだ。  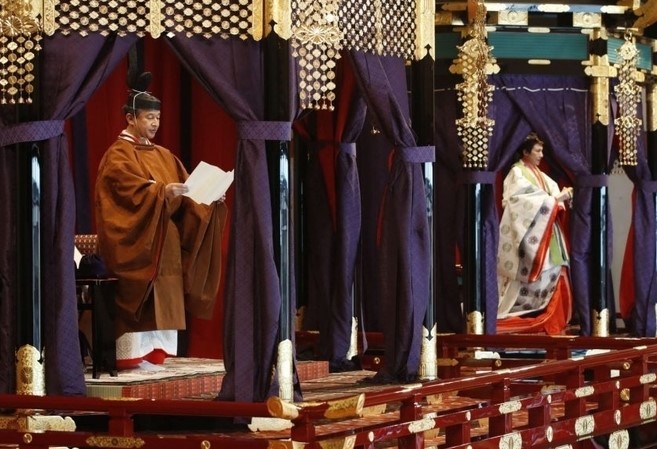   (図の説明:上の写真は、2019年10月22日に行われた即位礼正殿の儀で、左から雅子皇后、天皇・皇后両陛下、秋篠宮ご一家、ご親戚の順に並べた。十二単衣は平安時代の装束だが、制服のように全員同じ色ではなく、人ごとに異なる色にしたり、比翼仕立てにしたりして工夫すると、色合いやシルエットがもっと美しくなると思う)     (図の説明:1番左の写真は、即位礼正殿の儀を見つめる国賓の夫人たちで、凛としながらすっきりしておしゃれだ。左から2番目の写真は、即位礼饗宴の儀の様子だが、雅子皇后の服のフリルが大きすぎるのは、かえっておしゃれでない。さらに、右の2つは皇居に到着する国賓たちで、このような中、通訳を介さずにおもてなしできるのは誰にでも真似できるわけではない長所だが、誰にとって鼻持ちならないと言うのだろうか?) *11-1:https://digital.asahi.com/articles/ASMB22HJGMB2UHBI00C.html?iref=pc_extlink (朝日新聞 2019年10月3日) ハリー王子夫妻、大衆紙を提訴 「今度は妻が犠牲に…」 英王室のハリー王子とメーガン妃は1日、メーガン妃が書いた「個人的な手紙」の内容を報じたのは著作権侵害やデータ保護法違反などにあたるとして、英大衆紙と親会社を提訴したと発表した。王子は声明で、こうした報道は「他人の人生を台無しにするいじめだ」と強く非難した。英メディアによると、「個人的な手紙」は、メーガン妃が実父トーマス・マークルさんに宛てた手書きのものだとみられる。英大衆紙メール・オン・サンデーが今年2月に写真付きで報じていた。同紙によると、手紙は昨年8月に書かれた。手紙の中でメーガン妃は、トーマスさんが娘に金銭的な支援を求めたことも受けたこともないとメディアに語ったのはウソだと断じ、「どんな金銭的支援も申し出てきた。愛し、味方してきた」とつづっている。トーマスさんの作り話が自分たち夫婦を傷つけたとし、「私の心はばらばらに砕かれた」と書いていたという。トーマスさんは昨年5月の夫妻の結婚式直前、心臓手術を受けたとされる。健康上の理由で式を欠席すると英王室が発表していた。だがその前に、式に着る礼服を採寸する様子を金銭と引き換えに芸能カメラマンに撮影させた「やらせ」が発覚。物議を醸していた。ハリー王子は長文の声明で、メーガン妃に対する攻撃的な報道がエスカレートしていると指摘。今年5月に長男アーチー君を出産し、育休に入って姿を見せないのをいいことに、タブロイドがウソを書き立てていると非難している。「一番恐れているのは歴史が繰り返されることだ。愛する人が商品化され、実在する人間として扱われなくなった時に何が起きるか知っている」と、パパラッチに追われた末に事故死した母のダイアナ元妃にも触れた。「私は母を亡くし、今度は妻が、同じ強力な力の犠牲になるのを見ている」と怒りをにじませた。メーガン妃は英王室入りにあたり、米国出身の元女優で、男女平等や人権問題に積極的に発信し、母親がアフリカ系であることなどが注目された。その後は服装やふるまいが「伝統破り」だと頻繁に指摘され、側近の退職が相次いだことから「気難しい公爵夫人」とあだ名を付けられるなど、一部メディアで激しい批判にさらされている。 *11-2:https://news.yahoo.co.jp/byline/saitokaoru/20190628-00131842/ (Yahoo 2019/6/28) 雅子さまが突然輝きを増した理由 16年ぶりの「衣装映え」が物語る変化 (齋藤薫:美容ジャーナリスト・エッセイスト) ●あまり知られていない、雅子皇后の意外な人柄 使命感なのだろうか、それとも解放感なのだろうか、きっと誰もが気づいたはず。雅子妃が、皇后になられるやいなや、見事に輝きを増したこと。マスコミは「輝くばかりの笑顔!」を連発した。存在感が増すのは当然としても、まるで別人のように生き生きとした表情を見せてくれたのは一体なぜなのか?単純に考えれば、輝きを増した理由はやはり劇的なまでの環境変化。いわゆる適応障害の原因は、一般的に“環境の変化”にあると言われるが、じつはその解決策もまた、基本的には環境の変化が決めてになるというのが、大方の見方。言うまでもなく、一般女性が皇室に入るほどのドラスティックな環境変化は他にない。でも、皇太子妃が皇后になることもまた、ひょっとすると同じ規模の激変なのかもしれない。つまり今、私たちの想像が全く及ばないほどの圧倒的な変化が、雅子妃に訪れているということなのだ。ちなみに、“適応障害”になりやすいのは、心の弱い人でもなければ、ストレスを溜めやすい人でもないという説がある。むしろ完璧主義で、有能かつ、真面目、負の要素が少ない人ほど、そのリスクが高いと言われるのだ。何よりも、気配りがあって、人の心が読める人に意外にも多く見受けられると言うのが特徴だ。そういう人に突如大きな環境変化が訪れると、360度へ必死で対応してしまうから、知らぬ間にストレスが限界を超える。どうもそういうことらしい。かつて、雅子妃の「人となり」について、皇室に近い人の話に基づくこんな記事を見たことがある。あまりに立派なキャリアから、どうしても“強い女性”をイメージしてしまいがちだが、その記事はむしろ逆であると指摘していた。雅子妃は自我を通すタイプでは決してない。どちらかと言うと周囲に合わせ、協調しようとするタイプだと言うのである。皇室を孤軍奮闘、開かれたものにしようとしてきた美智子妃の方が、よほど自分の意見を明確に語り、きちんと通そうとする人であると。また数々の報道によれば、紀子妃も比較的モノを言う人であり、そういう意味では雅子妃がいちばん軋轢を避けようとするメンタリティーの持ち主と言うことになる。でも逆を言うならそれは、対応の難しさが限界を超えなければ、非常にスムーズに新しい環境に順応できる人であることを示している。だから皇后という立場には見事に順応し、一気に長いトンネルから抜け出られたとも言えるのだ。おそらくは、くすぶっていた使命感の蛇口を目一杯開けることができたことと、ある種の解放感が相まってのことなのだろう。もちろん想像に過ぎない。しかし人間の心の内は意外なほど明快に姿形に現れるもの。即位の儀前後から、雅子妃の顔が明らかに変わった。こんなに自然な笑顔を目にしたのは久しぶり。単純に輝きの量が増えている。瞳からも皮膚からも。その発光こそ、一気に回復に向かった証。今の自分の環境をそのままに受け入れたことの証ではないのか? またそのオーラの正体、光の内訳は、“生命力”であることもはっきり見てとれた。それぐらい強い煌めきが体内から発せられているのが感じられたのだ。 ●16年ぶりに戻ってきた「ファッションセンスと衣装映え」 さらに「衣装映え」が認められるのも、それこそ体調を崩された2003年以来。いや、実際にはご成婚数年目から、「衣装映え」は影を潜めていた気がする。着る服がよく映えているさまを「化粧映え」ならぬ「衣装映え」と呼ぶなら、そもそもが雅子妃ほど「衣装映え」する人は珍しいほどなのに、体調を崩されてからは、着る意欲をも失われたかに見えていたから、久しぶりの「衣装映え」、それがこの上なく印象的だ。服を着るのにも、生命力が必要。生きるエネルギーが減退していると、人間は不思議にどんな服を着ても、単にハンガーにかけたように、体に馴染んでは見えないのだ。以前このコラムでも書いたように、雅子妃はもともと大変にお洒落で、天性センスの良い人である。外務省時代のファッションをほんの数種類見るだけで、知的で上品だけれど華やかな、絶妙なバランスのお洒落ができる人であることがよくわかる。比較するのもなんだが、当時バブルに沸いた時代の徒花“ボディコン・ワンレン”にも全く引けを取らない程の力強い存在感を放っていた。またその品格ある美しさと華やかなセンスは、ご成婚後も、そのままロイヤル・ファッションに生かされたかに見えた。それこそ結婚1年目、中東を訪れたときのファッションは未だ鮮烈な記憶として映像ごと残っている。グリーンと黒のストライプをあしらったつば広帽、同じグリーンと黒のコントラストも艶やかなロングジャケットとパンツのスーツ。そう簡単には着こなせない、ハイファッションだ。これを見た時、あまりのクール・ゴージャスに息を飲むと同時に、ついに新しい日本の女性像を世界にアピールしていく存在が現れたとちょっと興奮したもの。この女性こそが日本に新しい時代をもたらすキーパーソンになるのだと、無性にワクワクしたものだった。ふと脳裏をよぎったのが、ケネディ大統領が新しいアメリカを築く時、実は揺るがぬキーパーソンとなっていたジャクリーン・ケネディという存在。まさしく何ヶ国語をも操り、「ジャッキー・スタイル」と言う言葉を生むほどそのファッションセンスが絶賛を浴びた人である。いやひょっとすると、世界的に注目を集めたダイアナ妃的な存在感を生むことになるかもしれないとまで思ったもの。しかしその後、雅子妃流の華やかなスタイルはいきなり影を潜め、もう二度と見られなくなる。あるいは中東諸国ご訪問の直後から、そのファッションについて、皇后様よりも目立ってしまわれないか? 少々華やか過ぎるのでは? などという、皇室的な忖度が周囲からなされたのではないか。皇太子による、のちの“人格否定”発言の時も、その一部は“ファッションセンスも一緒に否定されたこと”を指しているのではないかと思ったほど。以前も書いたように、本来センスのある人がセンスを否定され、お洒落を奪われるのは、それこそ人格を否定されたような格別の苦痛を伴うもの。その後のファッションの弱々しさは体調のせいもあるかもしれないが、どう考えても意図的に地味な、物静かな服が選ばれていた。あれほど美しく華やかで、誰より「衣装映え」した人が……と、なんだか胸が締め付けられるような思いがしたのである。ところが不思議なことに、即位の儀から、突然その「衣装映え」が戻ってきたのである。体調はまだ回復されたわけではないと言われるが、そういう意味ではこれまでにないレベルの回復が見られたことを確信した。それこそ“誰か”より目立ってはいけないという足かせも完全になくなり、長いブランクを経て、名実ともに心置きなく“持ち前のセンス”を生かせるようになったのではないか?ロイヤル・ファッションは、単に“皇室の人々の装い”に留まらない。ある意味“国民の誇り”となり、理屈を超えた国家的エネルギーになるもの。ファッションの意味を超え、服の役割を超えて、人々を動かし活力を与える不思議なパワーを宿すのだ。でなければ、キャサリン妃やメーガン妃のファッションの詳細や是非が、英国で連日ニュースになるわけがない。そういう意味でも、雅子妃にセンスと「衣装映え」が同時に戻ってきた事は、日本にとって特別なニュースとなるのだろう。そして、本人が外交の場で通訳だったのだから当然のことなのに、「通訳のいらない外交」に喜びを感じるのは、私たち日本国民は語学に対して苦手意識が強いからだろうけれど、ともかくファッションと語学は外交の鍵。我慢の時を経てもう一度、「何につけてもこの人を見ていたい」と言う“雅子皇后ブーム”が来るのかもしれない。正直、量的にも質的にも、今の小室圭氏の比ではないほどネガティブな報道が続く中にあっても、心静かに回復を願ってきた“潜在的な雅子妃支持者”は、おそらく驚くほど多いはずだ。公務でもほとんど姿を見られなかった中で、なぜ支持者の心が変わらなかったのか? 考えてみれば不思議だが、潜在的な雅子妃ファンが少なくない理由は、それだけじゃない、もう一つ別のところにある気がする。 ●あの逆風の中での支持は、「アンバランスなまでの有能さと人間性への共感」 言うまでもなく、この人ほど見事な経歴を持つ日本女性はそうはいないのだろう。ハーバード大学卒、東大大学院編入、外務省入省後オックスフォード大学にも留学と言う、エリート中のエリート。そういう女性がどんな人格を持つのか、まぁ想像もつかないなりに決めつけもでき、おまけにここまで美しいとなれば、普通に考えると相当に鼻持ちならないタイプとなる。そういう風になることを世間も許容せざるを得ないレベルの女性である。にもかかわらず、前述したように、ミーミーミー(私が私が)なタイプでは全く無い。むしろ自己主張が少ない、人に合わせるタイプ。日本の高校時代は自らソフトボール部を作り、ハーバード大学在学中は自ら日本の文化を伝える財団などを作って積極的に活動していたと言うから、単に控えめとは違う。しかし時と場合で控えめにさえなれるって、このキャリアから考えると何か奇跡的である。ともかく、そういうアンバランスなまでの有能さと人間性を持ち合わせた女性。とてつもない経歴に反して、謙虚で奥ゆかしくもある、精神的にはどこかとても古風な女性であると言われるのだ。そのアンバランスこそまさに日本女性の理想。改めてこの人を新しい規範として、日本女性のイメージを再構築したいと思う人が多いのではないか。“お言葉”の多くもリアルに報道されない日本では、皇族一人ひとりの人柄までを伺い知ることはできないのに、それでも伝わってくる人間性、その質の高さを感じ取る人が少なくなかったということだろう。現在の天皇陛下が、結婚前「雅子さんでないと結婚は考えにくい」と語ったことが、今更ながらに思い出され、そして深く納得させられる。やはり特別な女性なのだ。皇后であることを差し引いても。とりわけ笑顔の美しい人であるという最初のインパクト、そこから読み取れる人間性に、人々は本能的に惹きつけられ、表面的ではない共感が生まれた。皇族であるかどうかを超えて、何があろうと変わらない“人間の本質”を見つめつつ、だから適応障害に見舞われたことも納得の上で、密かに応援し続ける支持者が多かったのかもしれない。人への支持は、本来そうあるべきだ。言い換えれば、雅子妃への穏やかな人気は、従来の皇族女性へのものとは少し違う。あくまで1人の女性としての才能と、皇室に生きること自体に戸惑いを見せた“普通の人の感性”に対してのもの。つまり体調を崩されたことにより、逆にシンパシーが揺るがぬものとなり、だから長い沈黙も耐えられたのかもしれない。もちろんその間、もどかしくもあった。でも体調の回復により、より強固になったシンパシーが今まさに息を吹き返し、ある意味内向的でありながらも、同時にグローバルな才能に溢れた、“新皇后”の真の覚醒を、ワクワクしながら待っている。ついに輝きを取り戻した笑顔に、もう一度、日本女性の未来像を託し、“日本の誇り”にしたいから。 *11-3:https://digital.asahi.com/articles/ASMBS5Q4TMBSUTFL00F.html?iref=comtop_8_03 (朝日新聞 2019年10月25日) 息子がネット中傷被害、加害者特定へ裁判「命が危ない」 「根っからのうそつき体質」「自作自演」――。中学に入学後、いじめにあった埼玉県の男子生徒や家族を苦しめたのは、学校での無視や暴力にとどまらない、ネット上での中傷だった。子どもの命の危機を感じた母親は、加害者特定のため、法廷で闘うことを決めた。「根っからのうそつき体質」「一生いじめられっ子」……。2017年10月、埼玉県川口市の市立中学校に通っていた当時3年の男子生徒は、ネットの掲示板に実名がさらされ誹謗(ひぼう)中傷を受けた。母親によると、生徒は15年の中学入学直後から入部したサッカー部内で無視されたり殴られたりするようになった。母親は学校側に対応を求めていたが、有効な対策がないまま、16年秋から不登校に。自傷行為もあり、断続的に学校に行けない状況が続いたという。実名をあげられるほどにネットでの中傷が激化したのは、こうした中で学校側が全校を対象に初めて開いた保護者会がきっかけだった。学校側は対応の遅れを認め、保護者や生徒に反省の弁を述べたものの、事実関係を簡略化したり、事実と異なる説明をしたりした。そのため、「そのくらいでいじめって言われるのか」「学校の謝罪があっても黙らない被害者側は何が目的なの」「自作自演だ」など、むしろ生徒側に批判的な書き込みが目立つようになった。中には「自転車に乗っている○○を××(場所)で見た」など居場所を事細かに載せたものもあり、生徒は恐怖で外に出られなくなってしまったという。母親は「ネット上で悪口やデマがさらされると24時間心の休まる時がなく、避難場所がないのと同じ。特に相手が誰だか分からないのは恐怖しかなかった」と振り返る。 ●加害者3人を特定 どうすれば事実無根の書き込みを止められるのか――。母親は18年1月、弁護士に相談。書き込んだ相手を特定するために裁判を起こすことにした。12月には東京地裁がプロバイダーに開示を命じ、加害者側の氏名が明らかになった。ただし、個人の特定に結びついたのは、多くの書き込みの中の3人による4件のみ。担当した荒生(あらお)祐樹弁護士によると、発信者(加害者)を特定する場合は通常、①掲示板のサイト管理者などに、書き込んだ人物のIPアドレス(ネット上の「住所」)の開示を求める裁判手続きをする②IPアドレスから経由したプロバイダーを割り出し、氏名などの開示を求めてプロバイダーを提訴する、という大きく2段階を踏む。しかし、利用者すべてのIPアドレスの接続記録は膨大なので、プロバイダーが保存しているのは3~6カ月間が一般的だ。それ以前の書き込みについては接続記録自体が残らないため、加害者側にたどり着くのは困難。しかも、接続記録の保存はプロバイダーが任意で行っている。荒生弁護士は「プロバイダー責任制限法に発信者情報の開示請求権はあるのに、接続記録が消去されてしまうと権利行使ができない」と指摘する。また、発信者情報の開示を命じる判決を得るには、原告側が「プライバシー侵害」や「名誉毀損(きそん)」などの権利侵害が明らかだと主張・立証しなければならない。そのため、今回も実名が記載されていた書き込み4件に絞って裁判を起こした。さらに、弁護士をたててサイト管理者に連絡したり、プロバイダーと裁判したりするのは、費用も時間もかかる。海外に本社があるサイトの場合だとなおさらだ。母親は「放置すれば子どもが命を絶ってしまうという危機感があり、自分で闘うしかなかった」と話す。荒生弁護士は「ここまで闘える人は少なく、途中であきらめてしまう人も多い。しかし、ネットでの中傷は、加害者特定の手段もあるし、名誉毀損罪や侮辱罪などの刑法上の罪にもなり得る。抑止のためにも、このことが社会に広く認識されることが大事だ」と話す。生徒側はその後、訴訟前に和解が成立した1人を除く2人の加害者に対し、損害賠償を求め提訴。30万円の支払いなどで和解が成立した。 ●誰もが被害者に ネットのトラブルは子ども同士のいじめに限らず、誰もが被害者になり得る。ネット中傷の被害回復や風評対策に詳しい河瀬季(とき)弁護士によると、①リアルな世界でのいざこざ②暴走族に入っていた過去や「バイトテロ」など自らの軽はずみな行為が残り続ける③勝手に盗撮された画像がアップされるなど自分と無関係に巻き込まれる、などがパターンとしてあるという。①は、いじめのほか、特定の企業・人物をおとしめようとしてライバルが悪評を書き込む例も目立つ。被害回復の手段としては、ハードルの高い加害者特定よりも書き込みの削除が一般的だという。ただ、ネットは転載・拡散が容易なため、膨大な量の中傷ページが残ってしまいやすい。削除には問題のページを探し、それぞれのサイト管理者に削除依頼を出す必要があり、法律面だけでなくIT知識も求められる。河瀬弁護士は「行政の人権窓口などに、こうした分野に強い人材を置くなど、対策が必要な時期に来ている」と指摘する。被害者支援に乗り出す市民団体も出てきた。17年に発足した「ネット被害を考える協議会」(前川恵会長)。被害者家族やボランティアが中心となり、ネットで中傷された被害者からの相談を受け、書き込みを監視したり、被害者に代わって加害者のアカウントに書き込みをやめるようメッセージを送ったりするなどの活動をしている。会では今後、ネットのルール作りについて提言活動を行う予定で、10月末まで広く一般から被害対策案を募集している。前川会長は「『投稿者の身元を確認しやすくする』『加害サイトの広告主に注意を呼びかける』なども考え得るのでは。広く意見を募りたい」と話している。送付先はファクス(03・6434・5539)またはメール(info@net-higai.org)へ。 ●最近の被害例 2009年 お笑い芸人・スマイリーキクチさんのブログに、スマイリーさんが殺人事件に 関与したかのような事実無根の書き込みをしたとして、容疑者6人を書類送検 12年 大津市立中学校で前年に起きたいじめ自殺にからみ、「加害者の祖父が県警 OB。病院に天下り」などの誤情報が広まる 17年 SNSに事実と異なる書き込みをして男子高校生を中傷したとして19歳の少年 を名誉毀損容疑で逮捕 17年 神奈川県の東名高速でワゴン車があおり運転を受けた末に停車させられ、 トラックに追突されて夫婦が死亡した事故で、無関係の建設会社が「容疑者 の勤務先」などと名指しされて中傷 19年 茨城県の常磐自動車道で男性会社員があおり運転を受けた後に殴られた 事件で、無関係の女性が「同乗していたガラケー女」と名指し <柿くへば 鐘がなるなり 法隆寺> PS(2019/10/24追加): *12に「柿の収穫が終わった木に一つ実を残しているのは、来年はもっと実ってほしいというおまじないか、自然に対する礼節か」と書かれているが、柿の木のある農家の方に尋ねたところ、柿の実を食べる野鳥のために残してやっており、「来年はもっと実ってほしい」という人間の利己心からではないそうで感心した。私も、柿・桃・ビワなどは大好きだが、皮をむかなければならないというよりは、遠慮なく食べられる手頃な値段でないのが問題なのだと思う。さらに、干し柿が一つ一つ袋に入っていたり、高価すぎたりしているのは、その出世ぶりに呆れるくらいだ。 *12:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14229306.html (朝日新聞 2019年10月24日) (天声人語)柿くへば…… 柿の収穫が終わった木に、ぽつんと一つ実が残っているのをご覧になったことはないだろうか。それは「木まもり」というのだと白洲(しらす)正子の随筆に教わった。来年はもっと実ってほしいというおまじないかも……と書きつつ、思いを巡らせている▼「それは、自然に対する一種の礼節ともみられるし……実も葉もふるい落としたあとはさぞかし淋(さび)しかろうと、想像した人間のやさしい思いやりのようにも見える」。秋の青い空にある小さな朱色に、正子は心引かれた▼夏が長く、秋が短くなった気がしてならないこの国だが、季節を彩ってくれる恵みの数々がある。なかでも柿は、奈良時代にはすでに食べていたというから、ずいぶん長いお付き合いである▼数年前に九州の柿の産地で農協の人と話したとき、消費の伸び悩みを嘆いておられた。今や皮をむく果物は、それだけで敬遠されがちだと。少しの手間を惜しんであの甘さを味わえないとすれば、もったいない話である▼正岡子規は食いしん坊で柿も好物だったがゆえに〈柿くへば……〉の名句を生んだ。奈良の宿で山盛りの柿を食べていたら、鐘が鳴る音が聞こえたと随筆にある。「柿などというものは従来詩人にも歌よみにも見放されておるもので……」と得意そうに書いている▼あの句なかりせば、後の人々が柿にこれほど趣を感じることもなかったか。最近はその色ゆえにハロウィーンにちなんだ果物として並べるお店もあるという。それもまた新たな趣だと考えてみる。 <他の惑星の水・空気・気温> PS(2019年10月26、31日追加):*13-1のように、「①火星には、かつて温暖で地球の表面のような液体の水(=海)に覆われていた時代があった」「②大量に火星表面にあった液体の水は、今は火星の地下に蓄えられている可能性が高い」ということが火星探査で明確になり、火星の表面は酸化鉄を含む砂で覆われ、気温は20℃~-130℃、大気は殆どCO2、気圧は地球の0.6%、南極冠の近くの地下では液体の水からなる湖も見つかり、オリンポス山は高さ約25km、マリネリス峡谷は深さ5~10kmだそうで、これはコロンブスのアメリカ大陸発見に匹敵する大発見だ。また、*13-2には、35億年前の火星には生命の誕生や生存に向いた環境の塩湖があったとする研究結果を、金沢大の福士准教授(環境化学)らのチームが英科学誌ネイチャーコミュニケーションズに発表し、生物のパーツになる有機物も見つかったが、火星の直径は地球の半分程度で重力が小さいため、水蒸気を含む大気を留めておくことができずに水が蒸発して失われたらしいとしている。さらに、*14のように、月の南極にも氷が存在し、月では太陽光が届かないクレーター内などに水が氷の状態で存在するとみられており、水は、飲み水だけでなく、水素と酸素に分解すれば呼吸ができロケットの燃料としても使えるため、NASAはどれくらいの水が利用できるか調べるそうだ。しかし、日本のメディアはラグビーワールドカップやくだらない事件ほどにもこれらを取り上げず、これが日本における教育の大きな問題点である。 そのような中、日本では、*15-1・*15-2のように、台風19号による千曲川の堤防決壊で、最新鋭の北陸新幹線全編成の3分の1にあたる120両が長野新幹線車両センターで水没し、車両の床下にモーター制御等の電気設備を集中させているため、乾かしても通電すればショートする危険があり、被害額は300億円超だそうだ。しかし、ハザードマップで最大10~20mの浸水が予想されていた場所を用地買収し、たった2mの盛土をして、車両を高い場所に移動させることもなかった上、復旧(??)すればよいと考えるのは、事前・事後の両方に甘さがある。また、ルールやマニュアルへの記載がなかったから災害時に臨機応変な対応をしなかったというのも、日本における教育の緩さの結果だろう。 なお、*15-3のように、河川の氾濫等で浸水する恐れがある場所に設置されながら浸水対策がされていない浄水場が全国で578カ所にのぼり、福島県いわき市の平浄水場が水没して最大約4万5千戸が断水したそうだが、これも復旧すればよいのか? この浄水場は2000年に市のハザードマップで浸水想定区域に入ると判断されたが、現実的にこのような被害が起きるとは想定していなかったため(??)、対策が取られなかったのだそうだ。しかし、無駄遣いも多い目先だけしか見ていない予算の編成替えを行い、根本的解決をすべきだ。 2019年10月31日、*15-4のように、日経新聞が「③全国の1/4、580カ所の工業団地に浸水の恐れがある」「④堀江パーツ工業は台風19号襲来で膝上まで浸水し、社員は『浸水経験がなく、雨風が吹き込まないように工場の窓に目張りをする程度だった』と述べた」「⑤最大想定2m以上5m未満が220カ所、5m以上が35カ所あった」「⑥計測器のアンリツは生産設備を2階に移していたため、被害が殆どなかった」などが記載されている。このうち③⑤は、昔は沼地だった田を埋め立てたり、川の中州や扇状地に工業団地や高齢者施設を造ったりなどの安全性を無視した土地利用が原因なので、早急に土地利用規制を見直すべきである。何故なら、企業の不注意に発する被害にいちいち国の予算を費やしていては、いくら税金を上げても教育・科学・福祉などに予算が廻らないからで、中でも④は、台風や豪雨災害が続いている中で、あまりに呑気だ。⑥は既に建設している建物を何とか安全に使っているようだが、今後も継続していく企業は、もっと安全な場所に立地すべきだ。 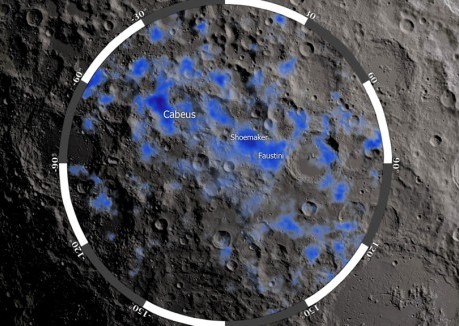 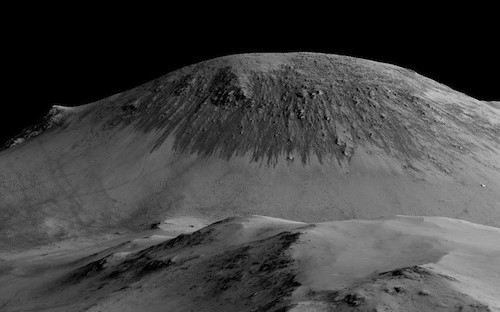  (図の説明:一番左は「http://karapaia.com/archives/52243174.html」に掲載されている月の表面にある水、中央は「https://newspicks.com/news/1195435/body/」に掲載されている火星の表面を流れる水、右は火星のクレーターの中にある氷で、素晴らしい発見だ) 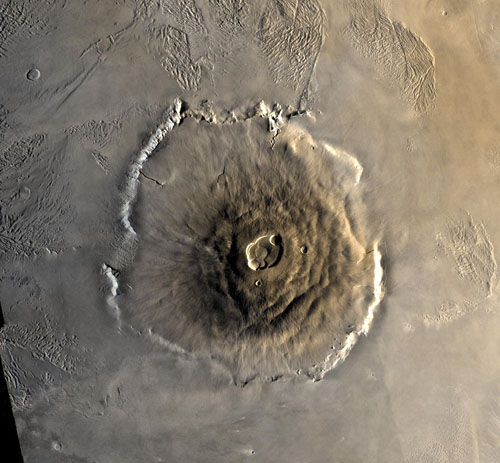 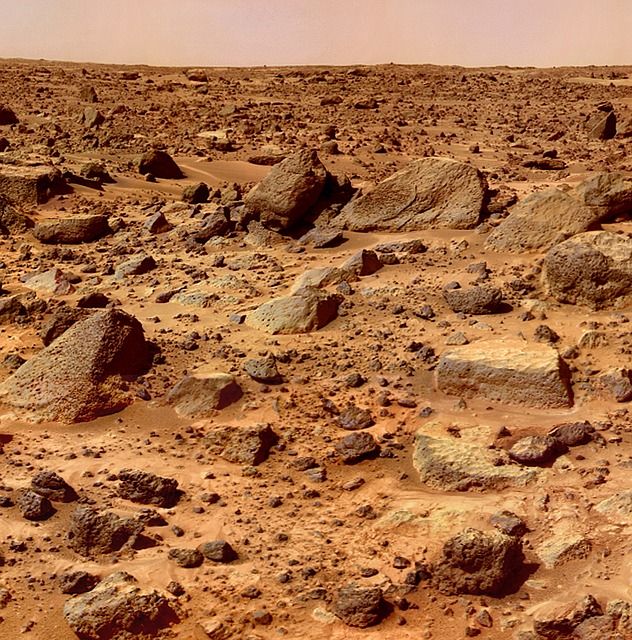 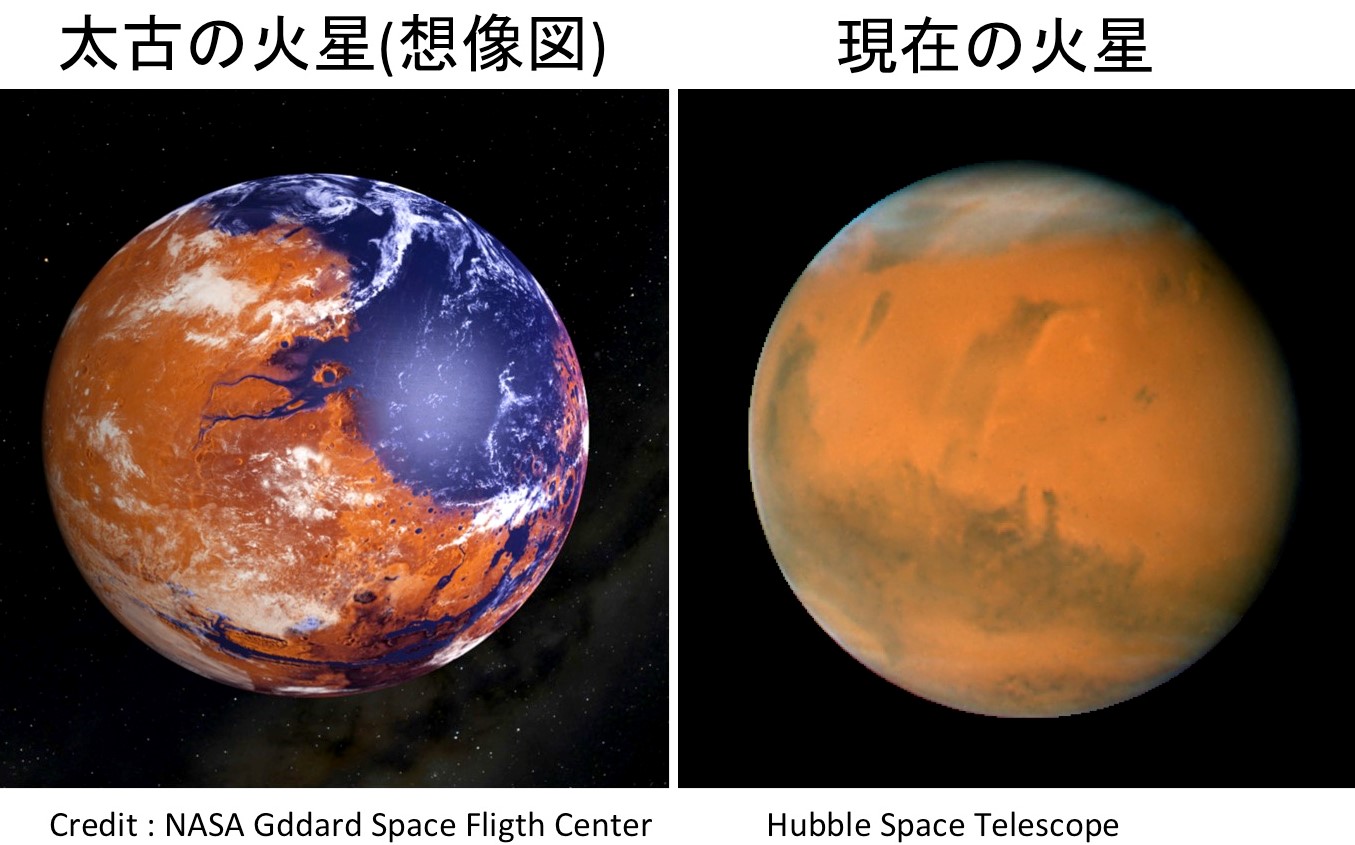 (図の説明:左は火星最大の火山であるオリンポス山で、中央は水が流れたような跡がある火星の地表、右は太古と現在の火星の様子だ。太古は水が豊富だったのに、火星の水が表面から消えた理由とその水がどこへ行ったのかが現在の最大の謎だが、地球では水が戻ってくるだけ有難いと思って、土地の割り振りを考え直すなどの対策を採る必要があろう) *13-1:https://news.yahoo.co.jp/byline/hidehikoagata/20180730-00091150/ (Yahoo 2018/7/30 抜粋) 火星大接近 -火星に生命は存在するのか? 2018年7月末現在、火星に限らず地球以外の天体から生命、または確実な生命の痕跡は何一つ見つかっていません。火星においても、20世紀前半まで人々が想像していたような火星人(=知的生命体)が存在しないことは今では明らかです。火星について分かっていることは、火星にはかつて温暖な時代があり、地球の表面のように液体の水(=海)に覆われていた時代があったことと、かつて大量に火星表面にあった液体の水は、今日では火星の地下に蓄えられている可能性が高いことが、今日までの火星探査で明確になったことでしょう。これらのことから、表面近くの火星地下に微生物程度なら存在するのではないか?または、表面や地下に、かつて生命が存在していた痕跡(=化石)があるのではないかと期待が膨らみます。火星は地球のすぐ外側を公転している太陽系第4番惑星で、地球から観察すると、2.2年毎に地球に接近します。夜空に赤く不気味に輝く火星。火星が赤く見えるのは、その表面が鉄さび、すなわち酸化鉄を含む砂で覆われているからです。火星では、地軸が約25度傾いているため、地球のように四季の変化が起こります。気温は、時期と場所により20℃~-130℃と幅があり、大気の成分はほとんどが二酸化炭素ですが、気圧は地球のおよそ0.6%しかありません。火星の表面は起伏に富んでおり、太陽系でもっとも高い火山、オリンポス山は高さ約25km、また、マリネリス峡谷は長さ約4000km、深さ5~10kmにもおよぶ巨大な峡谷です。表面を覆い尽くすような、大規模な砂嵐が周期的に発生するのも火星の特徴です。今年も運悪く、5月以降、火星全体を覆う砂嵐が発生しており、火星の表面の様子が詳しく分からない状況が続いています。火星の北極と南極には、ドライアイスと氷からできた極冠があり、その地下には永久凍土の形で多量の水が存在するのではと考えられています。南極冠の近くの地下に液体の水からなる湖が見つかったという最新の研究成果も発表になっています。火星は質量が地球の1/10と小型の地球型惑星です。その分、地球より早く進化した惑星と考えられ、かつては大量の水がその表面を覆っていました。果たして火星の地下には生命が存在しているのでしょうか。 *13-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/445937 (佐賀新聞 2019年10月25日) 太古の火星に塩湖存在、生命に好適、土壌分析 35億年前の火星に塩湖があったとする研究結果を、金沢大の福士圭介准教授(環境化学)らのチームが25日、英科学誌ネイチャーコミュニケーションズに発表した。水はほぼ中性、塩分は地球の海の3割程度でミネラルも豊富。生命の痕跡は確認されていないが、誕生や生存に向いた“ほどよい”環境だったという。火星の表面に液体の水があったことは確実とされているが、水質が分かったのは初。チームは「生命の存在可能性を議論するには、水に何が含まれていたかも明らかにする必要がある」と話す。場所は赤道付近にあるゲールクレーター。米航空宇宙局(NASA)の火星探査車キュリオシティーが得た土壌の組成データを分析した。層状の結晶が積み重なったスメクタイトという鉱物に注目すると、層の間に水から移ったとみられるカルシウムやマグネシウム、カリウムなどが残っており、かつて水中にあった量が推定できた。同じクレーターからは生物のパーツにもなる有機物が見つかっている。火星の直径は地球の半分ほど。重力が小さいため水蒸気を含む大気をとどめておきにくく、水が早々に蒸発し、失われたとみられている。 *14:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191026&ng=DGKKZO51447530W9A021C1CR0000 (日経新聞 2019年10月26日) 月の南極の氷を探れ NASA、22年に探査車 米航空宇宙局(NASA)は25日、月の南極に存在する氷の分布を調べる無人探査車「バイパー」を2022年に月面に送ると発表した。24年に飛行士の月面着陸を目指す「アルテミス計画」に先立ち、将来の有人探査で飲み水などに利用できる可能性を探る。バイパーはゴルフカートほどの大きさ。民間企業が開発する輸送手段で22年12月に月の南極に着陸させる。約100日かけて数キロ走行し、センサーで地下に氷がありそうな場所を探す。太陽光の当たり方や温度の異なる数カ所で地中1メートルまでドリルで掘り、土壌を採取して搭載装置で成分を調べる。月では太陽光が届かないクレーター内などに水が氷の状態で存在するとみられる。飲み水だけでなく、水素と酸素に分解すればロケットの燃料として使える。NASAはどれくらいの水が利用できるか調べる狙いだ。 *15-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201910/CK2019101802100028.html (東京新聞 2019年10月18日) 水没した北陸新幹線 どうなるの? 全損なら被害300億円超 ◆ 水没新幹線・再利用困難か 台風19号による千曲川の堤防決壊で水浸しになった北陸新幹線の長野新幹線車両センター(長野市)。最新鋭の車両が並んで水没した光景に、衝撃が広がった。残った車両で一~二週間後には全線運転再開となる見通しだが、水に漬かった車両は再び走ることができるのか。 ◆全編成の3分の1、120両が水没 「何でこんなことが起きるのか」。東海道新幹線の運転士を長年務めた中村信雄さん(81)は、今回の事態に驚く。車両センターで水に漬かったのは、北陸新幹線全編成の三分の一に当たる十編成。JRの東日本と西日本が所有し、七編成は屋外、三編成は車庫の中にあった。一編成は十二両で、被害車両は計百二十両に上る。JR東日本によると、一車両の製造費は約三億円。十編成で計約三百二十八億円とされる。同社は水が引いた十五日から被害状況の調査を始めたが、全貌はまだ分かっていない。 ◆床下電気設備に泥水 今後どうなるのか。鉄道アナリストの川島令三氏は「全損で廃車ということにはならないのでは」とみる。 車両の床下には、モーター制御などの電気設備が集中している。「機器類はそれぞれ箱に入っている。一つ一つ開けて水が入ってないか確認し、使えないなら箱ごと交換する。座席も汚れてしまったのならきれいにするか、交換する。車体そのものは使えそうだ」 ◆ 乾かしても通電でショートの危険 一方、再利用に悲観的なのは工学院大の高木亮教授(電気鉄道システム)だ。「床下の機械類のうち、電気で動いているものが一番泥水に弱い。泥水には電気を通す成分が入っていて、付着してしまうときれいにするのは難しい。乾いても絶縁が効かなくなっているから、電気を通すとショートし、場合によっては火災が起きる」と話す。さらに、「車両の外壁と内側の壁の間に配線を埋め込んでおり、端子類に泥水がかかっていても拭き取ることはできない。水に浮き、他の車両にぶつかってできたであろう車両のへこみの写真も見たが、アルミ製車両の修理は極めて難しい」とし、新品に買い直すしかないとみる。 ◆120両を陸路で運ぶのは非現実的 鉄道ジャーナリストの梅原淳氏は、修理自体が事実上不可能との見方だ。「浸水した車両センターでは修理できる設備がなく、JR東日本新幹線総合車両センター(宮城県利府町)や、JR西日本白山総合車両所(石川県白山市)に運ぶ必要がある。どちらに向かっても、急勾配のある線路にブレーキも利かない車両を移動させるのをJRは嫌がるだろうし、百二十もの車両を陸路で運ぶことも現実的ではない」 ◆ハザードマップで浸水予想 「移動しておけば…」 長野新幹線車両センターは独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」が建設し、JRの東日本と西日本に貸し付けている。長野市のハザードマップでは最大で十メートル以上二十メートル未満の浸水が予想されていた場所だが、なぜここに造ったのか。同機構の担当者は「一九九七年の供用開始時には、ハザードマップはできていなかった」と説明。「長野駅から近く、広い平たん地があり、用地買収に支障が少ないことを考慮して建設地を選定。長野県が作製した洪水浸水被害実績図を参考に、約二メートルの盛り土をした」とする。前出の中村さんは、六七年、大阪府摂津市の東海道新幹線鳥飼車両基地に大雨で近くの川の水が流れ込んだ際、車両を本線に移動させ、浸水から守った事例を指摘。「北陸新幹線も何とか助けることはできなかったのか。浸水しないように移動させるべきだったのでは」と話している。 *15-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191024&ng=DGKKZO51301000T21C19A0EA1000 (日経新聞社説 2019年10月24日) 新幹線の水没が残した課題 台風19号による打撃は新幹線にも及んだ。千曲川の堤防決壊でJR東日本の長野車両センターが浸水し、北陸新幹線の全車両の3分の1にあたる10編成120両が水没した。新幹線は地域経済を支える大動脈だ。復旧作業を急ぐとともに、事前の対策に甘さはなかったか、検証作業と再発防止策の導入をJR東には求めたい。ズラリと並んだ新幹線が泥水につかる映像を見て、言葉を失った人は多いだろう。だが、被害はそれだけではない。同センターにある変電所や車両の検査庫にも水が押し寄せ、検査の途中で建物の中にあった車両も浸水した。台風当日に同センターにいた36人の社員らは水かさの上昇で退避できず、翌日、ボートで救出されたという。まずJR東が全力を挙げるべきは速やかな復旧だ。台風以降運行を見合わせていた長野―上越妙高間の安全確保にメドが立ち、北陸新幹線全線の運行を25日から再開する。水没した車両は当面使えないが、他の車両をやりくりして列車本数は通常の約8割、東京―金沢の直通列車は同9割の本数を走らせるという。運行停止や大幅な減便が長期化すれば北陸の地域経済はじめ影響が広範に及ぶ可能性があっただけに、復旧の取り組みが進み始めたことは歓迎したい。一方で事前の備えが十分だったかについては厳しいチェックが必要だ。長野市の洪水ハザードマップによると、同センターのある一帯は最大10メートル以上の洪水被害が予想されている地域だ。まさかの事態に備え、車両を高架線上や浸水の恐れのない他の基地に移しておく対応はとれなかったのか。同じJR東でも東北新幹線の那須塩原の基地のように、今回、事前に車両を避難させておいた例もある。長野の教訓を踏まえ、今後同様の事態にどう備えるかのルールづくりや設備の強化が欠かせない。他のJR各社も自分たちの体制を点検する契機にしたい。 *15-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14229300.html (朝日新聞 2019年10月24日) 浸水想定578浄水場、対策せず 台風19号、福島では被害も 河川の氾濫(はんらん)などで浸水する恐れがある場所に設置されながら、浸水対策がされていない浄水場は全国で578カ所にのぼっている。台風19号の大雨では、福島県いわき市の平(たいら)浄水場が水没し、最大で約4万5千戸が断水した。災害からの復旧を支えるインフラの備えが遅れている。厚生労働省は、2018年9月に公共施設や病院などにつながる全国の主要な浄水場3521カ所を調査。その結果、22%に当たる758カ所が浸水想定区域にあり、そのうち76%の578カ所は入り口のかさ上げや防水扉の設置などの対策がされていなかった。土砂災害警戒区域にも542カ所あるが、うち496カ所が未対策だという。厚労省は各自治体の承諾が得られていないとして、個別の施設名を公表していない。いわき市では13日午前1時半ごろ、市内を流れる夏井川が氾濫して平浄水場の1階に水が流れ込み、電気を各設備に流す心臓部が約80センチ浸水。段階的な通水が22日に始まり、27日ごろに断水は解消する見通しだが、浸水家屋の掃除や洗濯が出来ず、深刻な影響を与えている。市内で最大の同浄水場は00年、市のハザードマップで浸水想定区域に入ると判断された。しかし、防水扉設置などの対策は取られなかった。市水道局の加藤弘司局長は「現実的にこのような被害が起きるとは想定していなかった。財源も限られるなか、具体的な対策を検討できていなかった」と話す。豪雨で水道施設が被災し、断水する例は近年、全国で相次ぐ。11年7月の新潟・福島豪雨では約5万戸で最長68日間、18年7月に広島県などを襲った西日本豪雨では約26万3千戸で最長38日間の断水が続いた。名古屋大の中村晋一郎准教授(土木工学)は「浸水対策などハード面の対策も必要だが、限られた予算の中で、すぐに実施することは難しい。断水のリスクに備え、住民側の事前の対策も合わせて必要だ」と話す。 *15-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191031&ng=DGKKZO51614510R31C19A0MM8000 (日経新聞 2019年10月31日) 工業団地580カ所浸水恐れ 全国の4分の1、本社調査、供給網寸断リスク 全国各地に甚大な浸水被害を与えている大型台風。福島県や栃木県で一部の工業団地が冠水し、水害に対するモノづくりの現場のもろさが浮き彫りになった。官民挙げて全国各地でつくった工業団地にどれほど浸水リスクが潜んでいるのか。日本経済新聞が調べたところ、4分の1の工業団地に浸水の恐れがあることがわかった。栃木県足利市の毛野東部工業団地。金属部品加工の堀江パーツ工業では、12日の台風19号襲来で膝上まで浸水し、プレス機や完成部品が水につかった。ラインの一部が動いたのは17日。ある社員は「浸水経験がなく、雨風が吹き込まないように工場の窓に目張りをする程度だった」と明かす。工場が被災すれば深刻な供給網の寸断が起きかねない。自然災害が頻発する中、足元に潜む水害リスクを把握し、対策を講じる必要性が増す。日経新聞は国土交通省が公表している地理データベースを活用。全国の洪水浸水想定区域(総合2面きょうのことば)と、2181カ所の工業団地(10万平方メートル以上)を照合したところ、27%にあたる580カ所が浸水想定区域と重なっていた。浸水レベルも調べた。最大想定が「2メートル以上5メートル未満」は220カ所と1割に達し、「5メートル以上」は35カ所あった。一戸建ての場合、2メートル以上は1階、5メートル以上は2階が水没する。冒頭の工業団地は2メートル以上5メートル未満の想定だった。日本の製造業が伸び盛りだった1960~80年代。全国の自治体や土地開発公社が工業団地整備にまい進した。災害リスクを今ほど意識せず、平たんでまとまった用地が多い河川流域が選ばれることが少なくなかった。法律で浸水想定区域を定めるようになったのは2001年からだ。それ以前の工業団地は河川氾濫を十分想定せず、リスクが高いところが多い。千曲川の氾濫で水没した長野市の北部工業団地も2メートル以上の浸水リスクがあった。市の主導で造成したのは90年。一角にある調整池は排水路や下水管があふれる内水氾濫に備えたもので、今回は貯留上限を軽く超えた。対策次第では同じ場所でも明暗が分かれる。福島県郡山市の郡山中央工業団地では多くの企業が浸水被害に遭ったが、計測器のアンリツは過去の浸水被害を教訓に生産設備を2階に移していたことで、被害はほとんどなかった。国内外の工業団地に詳しい東大の新宅純二郎教授は「進出企業は事業継続計画(BCP)の見直しが重要だ」と説く。11年の東日本大震災のときは、半導体大手ルネサスエレクトロニクスの工場が被災し、自動車向けなど世界のサプライチェーンに打撃を与えた。中小の部品企業でも高いシェアを持っていれば、取引先は世界に広がる。日本企業は世界への影響を念頭に置き、水害の多発という新たな難問に対処していく必要がある。 <農業こそ再エネと蓄電池だ> PS(2019年11月1、2日追加):*16-1のように、台風15号の被害を受けた千葉県は、北海道地震を教訓に発電機導入の動きが広がり、酪農家の6割が燃料系の自家発電機を保有しており、停電時も搾乳できたのはよかった。しかし、燃料供給が途絶えて苦労した農家もいたそうで、農家は太陽光や風力などの再エネ発電による潜在力が高いため、日頃から蓄電池を備えて電力販売を副収入にしていれば電力を供給する側に回れた筈だ。従って、農業に対するエネルギー補助は、国富を外国に移転する軽油・ガソリンではなく、再エネ発電と蓄電池にすべきだ。 しかし、分散型発電を行って電力を供給するには、大手電力会社から独立した送電網がなければならない。そのため、私は、*16-2のように、水道を民営化するのではなく、地方自治体が上下水道部門を分社化して外に出し、新インフラを利用したい発電会社・送電会社・ガス会社・通信会社などにも出資してもらって、最新技術を使った上下水道管の更新と電線の地中化を(共同溝として)速やかに行い、送電線や通信線を道路並みに公共化するのがよいと思う。 *16-1:https://www.agrinews.co.jp/p49113.html (日本農業新聞 2019年10月30日) 自家発電機導入広がる 燃料の備蓄不可欠 千葉県酪連調査 9月の台風15号によって大きな被害を受けた千葉県で、酪農家の6割が燃料系の自家発電機を保有していることが千葉県酪農協連合会の調べで分かった。北海道地震などを教訓に発電機導入の動きが広がり、多くの農家が停電時も搾乳できた。一方、発電機を動かす燃料の調達に苦労した酪農家もおり、一定の燃料を備蓄する必要性も浮かび上がった。県酪連では台風の直撃を受けた後、生乳を出荷する県内の酪農家496戸を対象に、自家発電機の導入状況を調査した。その結果、279戸が発電機を所有していると回答。レンタルやリースしているケースも合わせると304戸に上った。県酪連は「東日本大震災や北海道地震以降、県や国の補助事業などを活用して発電機を導入する農家は増えている」とみる。農家の減災対策への意識が高まっているためだという。ただ、発電機を保有していても、倒木などの影響で燃料供給が途絶え、搾乳の合間に燃料を探し回るなど、苦労した農家もいた。乳牛100頭を飼育する鴨川市横尾地区の「カスヤファーム」では停電が1週間以上続いた。同ファームでは計5台の発電機を活用し、台風が上陸した2日後の9月11日には出荷を再開した。生乳約4・2トンを廃棄するなど被害はあったが、発電機の備えで被害を軽減できた。同社代表の糟谷英文さん(52)は、給油所の停電が続き通常通り機能しない中、空いている給油所を探して市外まで車を走らせた。高齢者や遠出できない周辺の酪農家に燃料を分けることもあった。鴨川市酪農会の会長も務める糟谷さんは「発電機の備えだけでなく、事前にある程度(軽油やガソリンを自己保有できる上限分)の燃料を買っておく必要性を痛感した。周辺農家にもその重要性を伝えていきたい」と話している。 *16-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/553072/ (西日本新聞 2019/10/22) 水道民営化検討せず 九州10市 災害対応、高騰懸念 市町村を基本単位とする水道事業の運営権を民間企業に委託する「コンセッション方式」の促進を盛り込んだ改正水道法が今月、施行された。水道事業の基盤強化が目的だが、西日本新聞が九州の政令市、県庁所在市、中核市の計10市に同方式の導入について尋ねたところ、全ての市が「導入予定はない」と回答した。最も身近なインフラで命に直結する水の「民営化」への懸念の大きさを裏付けている。10市の水道事業担当部局によると、導入しない理由として、長崎市は「コンセッションは官と民の役割やリスク分担の整理がいる。海外では再度公営化した事例もあり、安全安心な水を民間に委ねることには、市民の理解を見極める必要がある」と強調。佐賀市も「水道事業にまったく知識がない事業者が災害が起きたときに責任を果たせるのか」と懐疑的な見方だ。北九州市は「選択肢は広がったが、検討もしていない。現時点では広域連携を重視している」と回答。熊本市も「地下水で全ての水源を賄っており、効果的に運用する独自のノウハウが求められる」とした。給水人口約156万人(2017年度)を抱える福岡市は「市民に無理な負担を求めることなく安定的に黒字を確保できる」と説明。大分市も現行の直営での安定経営を理由に挙げた。一方で、鹿児島市は「当面検討もしないが、老朽化施設が増えるなどして経営状況が悪化するとなると、検討することもあり得る」と述べた。厚生労働省によると、上水道でコンセッションの導入例はこれまでなく、宮城県などが導入を検討中。ただ民営化による水道料金の高騰や水の安全性の確保、災害時の対応を民間企業ができるかといった点で市民にも不安の声は根強い。浜松市は導入の可能性を検討し、市民向け出前講座などで説明を重ねてきたが「市民、国民全体としても理解が進んでおらず、導入を進めるのは困難と判断した」として今年1月に検討も含めて導入を当面延期した。水道事業の民間委託の是非は、あくまで自治体の判断だ。民営化の動きが広がっていないことについて、厚労省水道課は「コンセッションは(官民連携の)選択肢の一つ。地域の状況に合わせて検討されるものと考えている」と話した。 【ワードBOX】改正水道法 人口減に伴う水需要減少や水道施設の老朽化、深刻化する人手不足で経営が厳しい水道事業の基盤強化が目的。昨年12月の臨時国会で成立し、今月1日施行された。自治体が浄水施設など資産を保有したまま運営権を民間企業に売却できる「コンセッション方式」の促進を盛り込み、民営化しやすくした。自治体間の広域連携や官民連携の推進も掲げる。
| 科学・医療 | 01:04 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,09,26, Thursday
 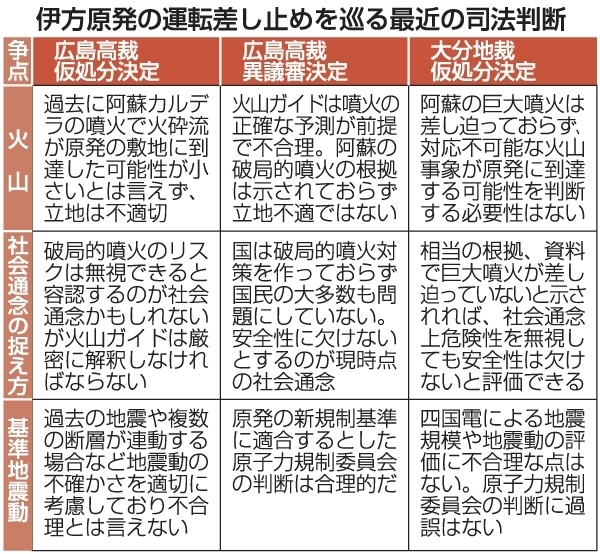 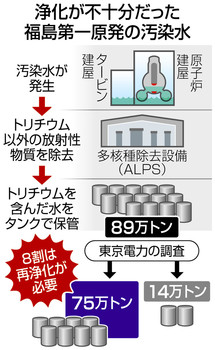 2018.9.29西日本新聞 2018.9.29東京新聞 (図の説明:左図のように、阿蘇山から130km圏内に3つ原発があり、中央の図のように、裁判所は社会通念を基に火山の危険性を無視することを容認している。しかし、原発は、万が一にも事故を起こしては困るという方向に社会通念も変化してきている。また、右図のように、フクイチの汚染水は(何をやっていたのか)再浄化の必要なものが8割に上り、まだ増えている) (1)裁判所も含めて低い日本の環境意識 1)東日本大震災前後の東電経営陣への無罪判決は正しいか 2011年のフクイチ事故について、検察審査会が強制起訴した裁判で、*1-1のように、東電の旧経営陣が「無罪」になった。しかし、国の地震予測の「長期評価」で津波高は最大15.7mにのぼるという報告が事故の3年前になされていたため、大津波は想定内だったと言える。 また、担当の東電社員がそれを元副社長に報告したところ、「(津波想定の)水位を下げられないか」と言われ、「津波対策を検討して報告すること」を指示され、「防潮堤を造る場合は完成までに4年を要して数百億円かかる」と報告したところ、元副社長は「外部機関に長期評価の信頼性を検討してもらう」と言ったと、担当の東電社員が証言しており、その外部機関は東電の言いなりになる機関だったため、対策の先送りは過失ではなく故意である。 しかし、東電旧経営陣の業務上過失致死傷罪の責任を問うには、①原発事故との因果関係 ②大津波の予見可能性 ③安全対策での回避可能性 がポイントになるそうで、このうち①②については、東日本大震災で大事に至らなかった東北電力女川原発は869年の貞観地震を踏まえて海抜15mの高台に建てられ、実際に高さ14~15mの津波が来たのであるため、(事故時の経営陣だけではないが)東京電力の予見の甘さと原発事故には強い因果関係がある。さらに、③については、「防潮堤を造るには4年を要する」とされているが、防潮堤を造るのに4年もかかるのは長すぎる上、防潮堤を造る以外にも予備電源を高い場所に移動したり、使用済核燃料を内陸の安全な場所に移動したりなどの他の対策も考えられることから、この判決は東電の経営陣に甘い。 さらに、*1-2には、緊急時に使う設備が事前の準備不足で機能しなかった疑いがあるので、原子力規制委員会の更田委員長が事故前の安全対策の検証をすると書かれているが、津波の危険性がある地域で非常用電源まで浸水するような低い場所に置く原発の設計自体、安全については全く考えていなかったことの証である。 2)原発の廃炉廃棄物をリサイクルするとは!? その上、*1-3の「④原発の廃炉に伴い発生する金属やコンクリートの廃棄物のうち汚染の程度が比較的低いものをリサイクルする」「⑤原子力規制委員会が放射能の測定方法を見直している」というのには驚いた。 何故なら、放射能汚染の程度が比較的低ければ安全ということはなく、放射性廃棄物は人間が住む環境から隔離した場所に集めて長期間管理するのが原則だからだ。それができないほど多くの廃棄物が出たのなら、それこそ誰の責任で、どうして原発稼働を今でも続けているのかを明確にすべきだ。 3)玄海原発の差し止め訴訟 おかしな地裁判決でもそのまま通すという上と下のご機嫌を伺うだけの情けない組織のようだが、*1-4-1・*1-4-2のように、福岡高裁が、「原発なくそう!九州玄海訴訟(長谷川照原告団長:素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理の専門家)」が玄海原発の運転差し止めを求めた住民側の即時抗告退けた。 しかし、阿蘇の破局的噴火リスクは低いとはいえず、日本のような地震・火山の多い国で、原発近くの高い場所に使用済核燃料プールを置き、設計当初よりも安全を無視して使用済核燃料を詰め込みながら原発を運転するのは危険である上、事故時の“避難計画”も実効性がないため、安全なエネルギーへの速やかな転換が求められるのである。 (2)フクイチ事故の汚染水による海洋汚染 1)処理水放出は正しいか 原田前環境相が、*2-1のように、「フクイチ原発事故で増え続ける汚染水の処理水は、海洋放出しかない」と述べたことに対して、全漁連の岸宏会長が「絶対容認できない。発言撤回を強く求める」と述べたそうで、当然のことである。 海洋放出してよいとする理由を、原子力規制委員会は、*2-2のように、「放射性物質で汚染された地下水は除去設備で浄化され、トリチウム(三重水素)だけ取り除くことができない」「批判に科学的根拠はなく、風評被害にすぎない」などとしているが、実際には、*2-6のように、汚染水にはトリチウム(半減期12年)だけでなく、ストロンチウム90(同299年)、ヨウ素129(同1570万年)なども国の基準値を超えて含まれていた。 また、*2-4のように、「処理水は薄めて海洋放出するのが妥当」と原子力規制委が韓国に伝えたというのは、間違ったことを言っているのに上から目線で呆れるのである。何故なら、「科学的、技術的な判断を行う規制委員会としては、基準以下に薄めて海洋に放出する方法が妥当」としているが、ここには「基準以下なら安全」と「薄めて基準以下にすれば総量が多くても海洋は処理できる」という誤った2つのセオリーが含まれているからだ。 放射性物質を含んでいても無味無臭で味も変わらないため、食べても無害だと勘違いしている“専門家(何の??)”が多い。そのため、わかりやすい例を挙げれば、*3-1の東京湾の水質悪化は、処理しきれなかった汚水が東京湾に流れ込んで起こる問題だ。しかし、東京の人口が10人だったら、全く処理せずに汚水を流しても川も海もそれを包含して浄化することができるだろう。しかし、1000万人以上の汚水を川や海が浄化することはできないのであり、その違いは汚物の総量であって濃度ではない。さらに、“基準”は、人間が勝手に定めた法的限界値であり、自然に関する不変の真理ではないのだ。 そのため、*2-3のように、韓国が「原発汚染水は国際問題だ」として、IAEA総会で日韓が応酬することになったが、日本政府代表が非科学的で反論にならない反論をすればするほど、環境意識の低さで世界に呆れられる。何故なら、皆、騙されるほど馬鹿ではないからだ。 2)トリチウムの害について トリチウムは、*2-5のように、水素の同位体で、最大エネルギー18.6keV、平均エネルギー5.7keVという非常に低いエネルギーのβ線を放出し、物理的半減期は12年だ。環境には、トリチウム水(HTO)の形で放出され、飲料水や食物から摂取されたトリチウム水は胃腸管から完全に吸収され、トリチウム水蒸気を含む空気を呼吸することによっても肺に取り込まれて殆どが血液中に入るのだそうだ。 そして、血中のトリチウムは細胞に移行して24時間以内に体液中にほぼ均等に分布し、有機結合型のトリチウムは、排泄が遅く体内に長く留まる。トリチウムのβ線による外部被ばくの影響は無視できる程度だが、ヒトに障害が起きるのはトリチウムを体内に取り込んだ場合の内部被曝で、ヒトが長期間摂取した被曝事故例では、症状としては全身倦怠、悪心、その後白血球減少、血小板減少が起こり、汎血球減少症で死亡する。 そのため、岩手日報は、*2-2のように、「福島原発処理水は、長期保管の可能性を探れ」と記載している。東電はタンクでの保管は2022年夏ごろ満杯になるとの試算をまとめ、保管容量を増やすのは困難だとしているが、初めから薄めて海洋放出するつもりではなかったのか。それなら、これまでに使ったタンク費用の妥当性や東電・政府の不誠実さも問われ、被害は実害であって風評被害ではないため、漁業関係者だけでなく消費者も反対なのである。 (3)後退した環境・衛生に関する意識 1)東京の下水道の不潔さ 東京の下水道は、コレラの流行をきっかけとして明治17年(1885年)から始まったため、現在は大量のストックがあり、老朽化している上、人口増加に追いついていない。そのため、*3-1のような事態になったのだが、東京は人口増加で地方税が十分に入ってきたのだから、無駄遣いばかりせずに、下水道を維持修繕する過程で計画的に完全浄化システムに変更していくべきだったのに、何故か、これをやっていないのである。 2)ゲノム食品に対する表示義務の緩さ 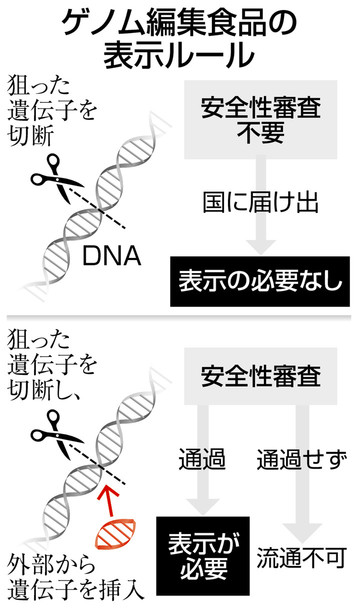 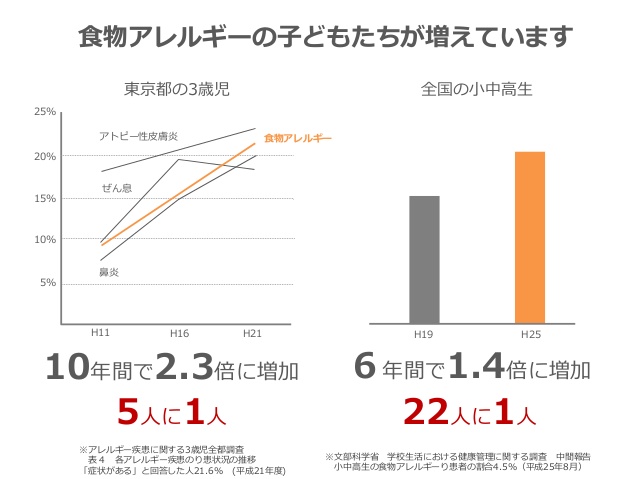  2019.9.20東京新聞 子どもの食物アレルギーの増加 食物アレルギーの原因食物 (図の説明:左図のように、ゲノム食品の表示義務は、消費者が選択できないくらい緩くなってしまった。一方で、中央の図のように、食物アレルギーが増加しており、右図のように、鶏卵・甲殻類・乳製品・小麦などが原因物質として多いが、これは何故か?甲殻類は、外骨格まで食べてしまうと、そこに毒があるせいか、私も腹の調子が悪くなる。鶏卵・乳製品は、日本人の消化器が慣れていないのかもしれない。小麦の場合は、これまで米国産が多かったため、害虫防除の遺伝子を挿入した小麦を食べた時に、体が小麦全体を防御するようになるのかも知れない) 消費者庁は、2019年9月19日、*3-2-1・*3-2-2のように、「①外部遺伝子を組み込まない食品は、遺伝子改変がゲノム編集によるのか、従来の育種技術によるのかを科学的に判別できず、表示義務に違反する商品があっても見抜けないため表示を義務化しない」「②外部遺伝子を組み込み、安全性審査が必要となる食品は表示を義務付ける」と決めたそうだ。 しかし、①は、その食品の作り方を尋ねて検証すれば科学的に判別できるし、そもそも違反を見抜けないから表示を義務化しないなどというのは、アメリカに過度に忖度してか始めから腰が引けていておかしい。また、②も「安全性審査が必要となる食品」と限定することによって、「安全性審査が必要になると思わなかったから」という言い訳ができ、どちらにしても消費者が選択できる環境にならないのだ。そのため、消費者が購入時に簡単に比較して選択できるよう、表示の義務化を行って真実と異なる場合は虚偽表示とすべきだ。 そして、このように自分の判断で食品を選べる環境を整えることが、コストがかかっても安全で美味しい作物を作る動機付けになり、そういう食品のブランド化もできる。逆に、そういう環境がなければ、安いが安全とは言えない作物が市場を席巻し、これまであった日本の食品産業の優位性も失われるだろう。 3)地球温暖化対応への消極性 国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が、*3-3のように、「世界全体で有効な対策が取られないまま地球温暖化が進むと、今世紀末に世界平均の海面水位は最大で1.1m上昇すると予測した特別報告書を9月25日に公表したそうだ。 世界平均の海面水位は1902年から2015年までの間に16cm上昇し、2006~2015年は年3.6mmのペースで上昇し、1901~90年の平均ペースの約2.5倍と先例がないスピードで水位が上がっているそうで、満潮時の海面と岸壁との差が既に小さくなっていることに気づいている人の実感が数字で裏付けられた形だ。 そして、温室効果ガス削減が進まず、今世紀末の世界の平均気温が産業革命前より最大5.4°C上がった場合、世界平均の海面水位は1986~2005年の平均に比べて、61cm~1.1m(中央値84cm)上昇するそうだ。確かに、海面上昇に伴い、低地にある都市は海抜0m付近になって、ポンプを使わなければ水が海に流れず、高潮災害が頻発する等の事態になると思われる。 ただ、最近の台風や豪雨災害を見ていると、この地球温暖化は温室効果ガスのみではなく、海底火山の噴火も影響しているように見える。 (4)フクイチ原発事故と癌の増加 1)フクイチ関係の福島県民を対象にした甲状腺検査について 2011年のフクイチ原発事故時に18歳以下だった福島県民を対象にした2014~2015年度分の甲状腺検査について、福島県の評価部会は2019年6月3日に、「現時点で、発見された癌と被曝の関連は認められない」とする見解をまとめたそうだ。 しかし、厚労省の人口動態統計はすべて暦年で出されているため(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/index.html 参照)、他の地域や日本全体と正確な比較をするには暦年単位で結果を出す必要がある。 また、福島県民を対象にした2014~2015年度分の甲状腺検査の規模なら、対象年が終わって6カ月後には調査報告書がまとまっていてもよく、4年以上もかかるのは遅すぎる。 さらに、真実を求めることが目的なら、調査結果を他の地域と比較することが必要なのであって主観的な“評価”は不要だ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/dl/h7.pdf、https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/dl/h10.pdf 等参照)。 そのため、*4-1の福島の小児甲状腺癌と被曝との関連調査は、まじめにやれば貴重な調査結果が出たのに、「線量と癌の発見率には関係がない」と結論づけるために、迅速で正確な調査をしなかったように見える。なお、日本全体では、フクイチ事故以前は死因の1/3と言われていた癌が、事故後直ちに死因の1/2と静かに修正されたのは呆れるほかない。 2)内部被曝・外部被曝について *4-2のように、内部被曝については、チェルノブイリや福島の経験からデータを出すことはできるし、実際に隠されていたデータや論文も多く出てきているが、ICRP・IAEA・WTOのような世界機関にはデータがないとされ、日本の食品安全委員会は「自然放射線や医療被曝を除く放射線で、生涯100ミリシーベルト以下の被曝なら健康に影響は出ない」としている。しかし、この安全基準には、科学的根拠が全くないのだ。 さらに、外部被曝では、日本の法律上の一般公衆線量限度は1mSV/年以下だが、政府は警戒区域や計画的避難区域の人は、20 mSV/年まで許容できるとした。しかし、20 mSV/年は頑強な原発労働者の基準であり、成長期の子どもや妊婦、免疫力の低下している人にまで当てはめるのは危険で人命軽視である。そして、*4-3のように、チェルノブイリ原発事故の場合は、5mSV/年で強制移住だったが、福島では20 mSV/年以下なら帰ることを強制しているのだ。 3)メディアの報道 メディアの中では比較的よく原発被害を報道していたテレ朝だったが、2014年8月30日、フクイチの取材や冤罪事件に心血を注いでいた報道ステーションのディレクター岩路真樹さんの遺体が自宅で発見され、「なんらかの権力による他殺ではないか」という説が流れた。 そして、*4-4のように、「関東の子どもの健康被害」は隠されているのだそうだ。しかし、体力の弱い子どもだけでなく、大人も多かれ少なかれ同じような健康被害が出ることは間違いないのである。 <低い環境意識> *1-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019092002000193.html (東京新聞社説 2019年9月20日) 東電旧経営陣に無罪 「人災」の疑問は残る 東京電力の旧経営陣は「無罪」-二〇一一年の福島第一原発事故で検察審査会が強制起訴した裁判だった。本当に予想外の事故だったのか疑問は残る。事故の三年前まで時計の針を戻してみよう。国の地震予測である「長期評価」に基づく津波の試算が最大一五・七メートルにのぼるとの報告がなされた。東電社内の会合で元副社長に「『(津波想定の)水位を下げられないか』と言われた」-担当していた社員は法廷で驚くべき証言をした。元副社長は否定し、「そもそも長期評価は信頼できない」と反論した。 ◆「力が抜けた」と証言 社員は「津波対策を検討して報告するよう指示された」とも述べた。だから、その後、防潮堤を造る場合は完成までに四年を要し、建設に数百億円かかるとの報告をしている。元副社長は「外部機関に長期評価の信頼性を検討してもらおう。『研究しよう』と言った」と法廷で応じている。てっきり対策を進める方向と思っていた社員は「想定外の結論に力が抜けた」とまで証言した。外部機関への依頼は、対策の先送りだと感じたのだろう。実際に巨大津波の予測に何の対策も講じないまま、東電は原発事故を引き起こしたのである。この社員は「時間稼ぎだったかもしれないと思う」「対策工事をしない方向になるとは思わなかった」とも証言している。社員が認識した危険性がなぜ経営陣に伝わらなかったのか。あるいは対策の先送りだったのか。これはぬぐえぬ疑問である。旧経営陣の業務上過失致死傷罪の責任を問うには(1)原発事故との因果関係(2)大津波などが予見できたかどうか(3)安全対策など結果回避義務を果たせたか-この三点がポイントになる。 ◆電源喪失予測もあった 東京地裁は争点の(2)は「敷地高さを超える津波来襲の予見可能性が必要」とした。(3)は「結果回避は原発の運転停止に尽きるが、原発は社会的有用性があり、運転停止だと社会に影響を与える」ため、当時の知見、社会通念などを考慮しての判断だとする。原発ありきの発想に立った判決ではないか。「あらゆる自然現象の想定は不可能を強いる」とも述べたが、それなら災害列島に原発など無理なはずである。宮城県に立地する東北電力女川原発との違いも指摘したい。女川原発が海抜一五メートルの高台に建てられたのは、八六九年の貞観地震を踏まえている。だから東日本大震災でも大事には至らなかった。〇八年の地震予測「長期評価」が出たときも、東北電力は津波想定の見直しを進めていた。ところが、この動きに対し、東電は東北電力に電子メールを送り、津波対策を見直す報告書を書き換えるように圧力をかけた。両社のやりとりは公判で明らかにされた。「危険の芽からは目をそらすな」-それは原発の事業者にとって常識であるはずだ。旧ソ連のチェルノブイリ事故が示すように、原発でいったん事故が起きれば被害は極めて甚大であり、その影響も長期に及んでしまう。それゆえ原発の事業者は安全性の確保に極めて高度な注意義務を負う。最高裁の四国電力伊方原発訴訟判決でも「(原発の)災害が万が一にも起きないように」と確認されていることだ。「最大一五・七メートルの大津波」という重要なサインが活(い)かされなかったことが悔やまれる。〇四年にはスマトラ沖地震の津波があり、インドの原発で非常用海水ポンプが水没し運転不能になった。〇五年の宮城県沖地震では女川原発で基準を超える地震動が発生した。これを踏まえ、〇六年には旧経済産業省原子力安全・保安院と電力会社による勉強会があった。そのとき福島第一原発に敷地高一メートルを超える津波が来襲した場合、全電源喪失から炉心損傷に至る危険性が示されている。勉強会が活かされたらとも悔やむ。防潮堤が間に合わなくとも電源車を高台に配備するなど過酷事故対策が考えられるからだ。福島第一原発の非常用電源は地下にあり、水没は容易に発想できた。国会事故調査委員会では「明らかな人災」と厳しく非難している。今回の刑事裁判は検察が東電に家宅捜索さえ行わず、不起訴としたため、市民の検察審査会が二度にわたり「起訴すべきだ」と議決したことによる。三十七回の公判でさまざまな事実関係が浮かんだ意義は大きい。 ◆地震の歴史は繰り返す 安全神話が崩れた今、国の原発政策に対する国民の目は厳しい。歴史は繰り返す。地震の歴史も繰り返す。重大なサイン見落としによる過酷事故は、やはり「人災」にも等しい。繰り返してならぬ。苦い教訓である。 *1-2:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50074040Q9A920C1TJM000/ (日経新聞 2019/9/22) 規制委、福島第1事故の調査再開、事故前の安全対策を検証 原子力規制委員会が東京電力福島第1原子力発電所事故の調査を約5年ぶりに再開する。更田豊志委員長が重視するのは、事故前の安全対策の検証だ。緊急時に使う設備が事前の準備不足で機能しなかった疑いがある。事故現場の痕跡を分析し、今後の安全規制に生かす。事故に伴う放射線量の高さから、原因の詳しい調査は2014年から休止していた。放射線量が下がり、ようやく原子炉建屋に入れるようになった。近く事故分析に関する検討会を再開する。メンバーには原発の構造に詳しい外部有識者や、原子力規制庁の職員に加えて、更田委員長も名を連ねる。検討会に委員長が入るのは異例だ。更田委員長には事故時の安全対策を検証することが「今後の安全対策を考えるうえで重要な教訓を与える」との強い思いがある。福島第1原発は11年の東日本大震災に伴う津波の影響で原子炉を十分に冷却できなくなり、1~3号機が炉心溶融(メルトダウン)を起こした。14年10月にまとめた報告書では、事故の拡大につながった電源喪失について「津波による浸水が原因」との見解を示した。電源喪失と津波による浸水の時刻は一致するなどと指摘し、地震の揺れが関与していたとする一部の見方を否定した。ただ、当時は放射線量が高くて建屋内の調査ができなかった。なお残る疑問の1つが、2号機で原子炉内部の圧力を下げるベントがなぜうまく働かなかったのかだ。2号機は1~3号機のなかで、最も多くの放射性物質が外部に漏れ出たとされる。格納容器内の水を通って、放射性物質が減った気体を放出するベントができなかったためだと東電は推定する。ベントができなかったのは、一定の圧力で自然に破れる配管内の板が破れなかったとの見方がある。設定圧力が高すぎた疑いがあるが、更田委員長は「ベントを減圧、冷却手段として期待していたのだったら、そんなに設定圧力を高くするはずがない」との疑問を持っている。ベント設備は1992年に国が過酷事故対策をまとめたことから電力会社側が自主的に設置した。調査の焦点となるのは「本当に狙ったような意図の施工がされていたかどうか疑問がいくつもある」(更田委員長)。最初に炉心溶融と水素爆発を起こした1号機では、非常時に原子炉を冷却する装置「非常用復水器(IC)」が停止していることに気づかなかったことが問題となった。発電所員らが復水器の仕組みや使い方を十分に理解していなかった可能性がある。福島第1原発所長だった吉田昌郎氏(故人)も政府のヒアリングに対し、理解不足との認識を示している。規制委は現場に残る復水器の状態を確認しつつ、同じ設備を持つ日本原電敦賀原発1号機(福井県)とも比較しながら、東電が所員にどのような教育をしていたのかなどソフト面の対策が十分だったかも調べる。規制委は検討会での議論を踏まえて20年に報告書をまとめる予定だ。今後の規制に反映すべき点があれば対応する。ただ、今回はまだ原子炉格納容器内は立ち入ることはできず、炉心溶融の詳細な経緯など真相究明は21年以降も続く見通しだ。 *1-3:https://genpatsu.tokyo-np.co.jp/page/detail/1101 (東京新聞 2019年7月24日) 廃炉金属のリサイクルの現状は-進む原発老朽化で大量発生へ- 原発の廃炉に伴い発生する金属やコンクリートの廃棄物を少しでも減らすために、汚染の程度が比較的低いものをリサイクルする「クリアランス」制度。老朽原発の廃炉が相次ぐのを見込む電力業界は審査の効率化を求め、原子力規制委員会が放射能の測定方法を見直している。国の実証事業で金属廃棄物を加工した工場周辺では、市民団体が「うやむやのまま全国の原発から持ち込まれるのでは」と警戒し、情報公開の徹底を要望。リサイクル製品が社会的に受け入れられるかも未知数だ。 *1-4-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/545988/ (西日本新聞 2019/9/25) 玄海原発の差し止め認めず 住民側の即時抗告退ける 福岡高裁 九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)を巡り、周辺住民らが九電に運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、福岡高裁(山之内紀行裁判長)は25日、差し止めを認めなかった昨年3月の佐賀地裁決定を支持、住民側の即時抗告を退けた。即時抗告したのは、「原発なくそう!九州玄海訴訟」のメンバー約70人。阿蘇カルデラ(熊本県)の破局的噴火の発生リスクは低いといえず、重大事故が起きる可能性があると主張。避難計画やテロ対策にも不備があると訴え、九電側は「破局的噴火の可能性は低く、避難計画も合理的」としていた。昨年3月の佐賀地裁決定は「阿蘇カルデラが破局的噴火直前の状態ではないとした九電の判断は不合理とはいえない」と判断。避難計画も適切として申し立てを却下した。 *1-4-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/432088 (佐賀新聞) 【速報】福岡高裁も運転差し止め認めず 玄海原発即時抗告審 九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県東松浦郡玄海町)を巡り、運転差し止めを認めなかった佐賀地裁の仮処分決定を不服として佐賀など九州・山口の住民らが申し立てた即時抗告審で、福岡高裁(山之内紀行裁判長)は25日、棄却する決定をした。申し立てたのは、玄海原発の操業停止を求める訴訟を起こしている「原発なくそう!九州玄海訴訟」(長谷川照原告団長)に加わる住民ら71人。別の住民らが同原発の運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審は、福岡高裁が今年7月に棄却していた。 <汚染水による環境汚染> *2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019091101001726.html (東京新聞 2019年9月11日) 全漁連「処理水放出」発言に抗議 原田前環境相に 東京電力福島第1原発で増え続ける汚染水浄化後の処理水について、原田義昭前環境相が海洋放出しかないと述べたことに対し、全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長は11日、東京都内で記者会見し「絶対容認できない。発言撤回を強く求める」と述べた。岸氏らは同日午前、環境省を訪れ原田氏の秘書官に抗議文を提出した。岸氏は記者会見で、福島県内の漁業者から「怒り心頭に発している」などの憤りや不安の声が寄せられたことを明らかにし、「漁業の将来に大きな影響を与える。政治不信にもつながる。風評被害の増長を心配している」と話した。 *2-2:https://www.iwate-np.co.jp/article/2019/9/15/64534 (岩手日報 2019.9.15) 福島原発処理水 長期保管の可能性探れ 東京電力福島第1原発にたまり続ける処理済みの汚染水をどうするのか、判断が迫られている。敷地にはタンクが林立し、保管中の水は7月末時点で約110万トン。東電は2020年末までに137万トン分のタンク容量を確保する計画だが、それ以降は未定だ。東電は先ごろ、タンクでの保管は22年夏ごろ満杯になるとの試算をまとめた。大型化などで保管容量を増やすのは困難だという。原子力規制委員会は薄めての海洋放出が合理的との考えだ。試算には、放出決定を国に促す姿勢がにじむ。処理水が増え続けているのは、溶融核燃料を冷却する注水や、流入する地下水が次々と汚染されていくからだ。処理水の処分方法は政府の小委員会で検討し、地元など関係者との調整を踏まえて国が基本方針を決める。試算だと3年後に限界が来る。規制委の更田豊志委員長は「処分方法が決まったとしても準備に少なくとも2年はかかる。意思決定の期限が近づいていると認識してほしい」と希釈しての海洋放出を改めて求めた。しかし、漁業関係者は反対姿勢を強める。当然だろう。事故によって甚大な被害を受け、抑制的な操業を余儀なくされている。政府小委員会は8月の会合で、漁業関係者からの求めが多かった長期保管を初めて正式議題に取り上げた。放射性物質で汚染された地下水は除去設備で浄化される。ただ、トリチウム(三重水素)だけは取り除くことができない。この物質は運転中の原発でも生じ、放射線の影響が少ないとして世界で放出が認められている。しかし、たとえ生物への影響がないとしても、風評被害の懸念がある。耐え続けてきた漁業者の苦労が水泡に帰しかねない。処理水には韓国も目を向ける。日本に対して海洋放出計画の有無など事実関係の確認を要求。政府は、現時点では具体的な結論が出ていないと回答した。韓国は原発事故に関し、本県産を含め8県産の水産物の輸入を禁止。世界貿易機関(WTO)がその措置を容認しているだけに、処理水の行方は気になるところだ。可能な限り長期保管の道を探るべきだ。その場合、自然に放射線量が減るのを待つことになろう。原発敷地外での場所確保は本当に難しいのか政府は精査すべきだ。仮に海洋放出すると判断するなら、漁業者に対する国の全面的なバックアップの約束が不可欠だ。これまでの汚染水漏れや公表の遅れで信頼感を欠いている東電と漁業者の関係構築も大前提になる。 *2-3:https://digital.asahi.com/articles/ASM9K10C1M9JUHBI03N.html (朝日新聞 2019年9月17日) 韓国「原発汚染水は国際問題」 IAEA総会で日韓応酬 国際原子力機関(IAEA)の総会が16日、本部のあるウィーンで始まった。韓国政府の代表は、東京電力福島第一原発にたまり続ける、放射性物質を含んだ汚染水の処理方法について「今も解決されていないままで、世界中に恐怖や不安を増大させている」などと述べ、国際的な問題であると強調した。これに対し、日本政府の代表が反論し、IAEAでも日韓が応酬することになった。総会には韓国政府の代表として文美玉(ムンミオク)・科学技術情報通信省次官が出席。日本の原田義昭前環境相が処理済みの汚染水について「海洋放出しかない」と発言したことに触れ、「もし海洋放出するなら、もはや日本の国内問題ではない。生態系に影響を与えかねない深刻な国際問題だ」と訴えた。IAEAの積極的な関与を求め、「日本は十分かつ透明な措置をとるべきだ」とした。これに先立ち、日本の竹本直一・科学技術担当相は福島第一原発事故後の情報提供について、「国際社会に対して透明性をもって丁寧に説明してきている」と述べ、汚染水についても「議論の共有を含め、取り組みを継続していく」としていた。日本側は韓国代表の発言後に再び発言し、福島原発事故に関して昨年までIAEAの調査団を4次にわたって受け入れ、取り組みの評価を受けていると強調。「韓国代表の発言は海洋放水を前提としており、受け入れられない」とした。また、原田氏の発言は「個人的」なものだとして、処理方法は経済産業省の小委員会で協議中であると説明した。日本の主張に対しては韓国も反論し、日韓は計3回ずつ発言。韓国代表の厳在植(オムジェシク)・原子力安全委員長が「(日本が)言葉を明確で十分な行動に移すことが重要だ」と締めくくり、応酬を終えた。 *2-4:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190925/k10012098841000.html (NHK 2019年9月25日) 「処理水は薄めて海洋放出が妥当」原子力規制委が韓国に伝える 福島第一原子力発電所にたまり続けるトリチウムなどを含む水の扱いについて、原子力規制委員会の更田委員長は韓国の規制当局トップに対し、「科学的、技術的には基準以下に薄めて海洋放出するのが妥当だ」との見解を伝えたことを明らかにしました。福島第一原発で出る汚染水を処理したあとの水には、取り除くのが難しいトリチウムなどの放射性物質が含まれ、これまで構内のタンクにおよそ115万トンが保管されていて、毎日170トン前後増え続けています。この水の扱いについて、今月20日までウィーンで開かれていたIAEA=国際原子力機関の総会で韓国の代表が懸念を示し、日本側は「丁寧に情報を出すなどIAEAも評価している」などと反論し、両国の間で応酬となりました。これについて原子力規制委員会の更田豊志委員長は25日の会見で、IAEA総会の期間中、韓国の規制当局トップと意見交換する場があったことを明らかにし、この中で水の扱いで懸念を伝えられたということです。これに対して更田委員長は、最終的には政府が決定する案件だと前置きしたうえで、「科学的、技術的な判断を行う規制委員会としては基準以下に薄めて海洋に放出する方法が妥当と判断している」と従来の見解を伝えたということです。トリチウムなどを含んだ水について、国はこれまで濃度を基準以下にして海や大気中などに放出する5つの案と、タンクに長期保管する案を示していて、現在、有識者でつくる国の会議で議論が行われています。 *2-5:https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-02-02-20.html (抜粋) <タイトル> トリチウムの生物影響 (09-02-02-20) 将来のエネルギー源として計画が進められている核融合(炉)にかかわる環境・生物影響、とくにトリチウムの人体への影響が注目される。トリチウムはトリチウム水(HTO)の形で環境に放出され人体にはきわめて吸収されやすい。また、有機結合型トリチウム(OBT)はトリチウムとは異なった挙動をとることが知られている。動物実験で造血組織を中心に障害を生ずることが明らかにされ、ヒトが長期間摂取した重大事故も発生している。 <更新年月> 2000年03月 (本データは原則として更新対象外とします。) <本文> トリチウムは水素の同位体で、最大エネルギー18.6keVで平均エネルギー5.7keVという非常に低いエネルギーのβ線を放出し物理的半減期は12年である。大気上層中で宇宙線中の中性子と窒素原子核との衝突によって生成する天然トリチウムが自然界の水循環系に取り組まれているとともに、核実験や原子力施設などから主としてトリチウム水(HTO)の形で環境に放出され、生物体へは比較的簡単に取り込まれる。ヒトの体重の60〜70%は水分で、個人差はあるが、女性よりも男性、老人よりも若者、太った人よりも痩せた人の方が含水量が多い傾向にある。表1は国際放射線防護委員会(ICRP)がトリチウムの被ばく線量計算のために水分含有量を推定したもので、“体重70kgのヒトの60%(42kg)が水分である”と仮定している。このうちの56%は細胞内液、20%は間質リンパ球、7%が血しょう中に、残りは細胞外液として存在するものとしている。飲料水や食物から摂取されたトリチウム水は胃腸管からほぼ完全に吸収される。トリチウム水蒸気を含む空気を呼吸することによって肺に取り込まれ、そのほとんどは血液中に入る。血中のトリチウムは細胞に移行し、24時間以内に体液中にほぼ均等に分布する。また、トリチウムは皮膚からも吸収される。最近問題になっているのは有機成分として取り込まれた場合の有機結合型のトリチウム(OBT:Organically Bound Tritium)で、一般に排泄が遅く、体内に長く留まる傾向がある。トリチウムは水素と同じ化学的性質を持つため生物体内での主要な化合物である蛋白質、糖、脂肪などの有機物にも結合する。経口摂取したトリチウム水の生物学的半減期が約10日であるのに対し、有機結合型トリチウムのそれは約30日〜45日滞留するとされている。トリチウムのβ線による外部被ばくの影響は無視できるが、ヒトに障害が起きるのはトリチウムを体内に取り込んだ場合である。ヒトの場合にはこのような事故例は少ないので、主として動物実験から被ばく量と障害の関係が推定されている。放射線の生物学的効果を表す指標をRBE(Relative Biological Effectiveness,生物学的効果比)というが、いろいろな生物学的指標についてのトリチウムβ線のRBEは表2のように示される。基準放射線をγ線とした場合のRBEは1を超える報告が多い。血球には赤血球、白血球(好中球、単球、マクロファージ、好酸球、リンパ球など)、血小板がある。これらはすべて骨髄の造血細胞から作られ、それぞれ機能が異なる。ヒトの末梢血液をin vitro(生体外)で照射してTリンパの急性障害をしらべた結果、トリチウムの細胞致死効果はγ線より高く、また放射線感受性はいずれの血液細胞もマウスよりヒトの方が高いことが明らかにされている。トリチウム被ばくの場合、幹細胞レベルでは変化があっても通常の血液像の変化は小さい。したがって急性障害のモニタリングには幹細胞チェックが重要である。トリチウム水を一時に多量摂取することは現実的にはあり得ないが、低濃度のトリチウム水による長期間被ばくの場合を考えねばならない。実際に、トリチウムをヒトが長期間摂取した被ばく事故例が1960年代にヨーロッパで起きている。トリチウムは夜光剤として夜光時計の文字盤に使用されているが、これを製造する二つの施設で事故が発生している。一つは、トリチウムを7.4年にわたって被ばくした例で280テラベクレル(TBq)のトリチウムと接触し、相当量のトリチウムを体内に取り込んだ事例である。尿中のトリチウム量から被ばく線量は3〜6Svと推定されている。症状としては全身倦怠、悪心、その後白血球減少、血小板減少が起こり、汎血球減少症が原因で死亡している(表3)。もう一つの例も似たような症状の経過をたどり汎血球減少症が原因で死亡している。臓器中のトリチウム量が体液中よりも6〜12倍も高く、体内でトリチウムが有機結合型として存在しているものと推定されている。発電所および核燃料再処理施設の稼働によりトリチウムも放出されるが、ブルックヘブン・トリチウム毒性プログラムは低濃度トリチウム水に長期間被ばくする場合の健康影響について示唆を与えてくれる(表4)。夜光剤を扱う施設ではラジウムペインターの骨肉腫がよく知られているが、トリチウムの場合はラジウムの場合と明らかに異なることは注目される。トリチウムによる発がんに関する報告は多くはないが、X線やγ線との比較によるRBEが求められている(表5)。これらは動物での発がん実験や培養細胞がん化実験の結果で、トリチウムRBEは1〜2の範囲である。このほか、遺伝的影響を調べるために染色体異常の誘発、DNA損傷と修復などの細胞生物学的研究や、発生時期、すなわち胞子発生期、器官形成期、胎児期あるいは器官形成期における放射線感受性の研究も行われている。 *2-6:https://digital.asahi.com/articles/ASL8N4CR7L8NUGTB004.html (朝日新聞 2018年8月21日) 福島)第一原発の汚染水、トリチウム以外にも放射性物質 東京電力は20日、福島第一原発で増え続ける放射性物質トリチウムを含んだ低濃度の汚染水について、保管する大型タンクに入れる前の放射性物質の検査で、トリチウム以外に、ストロンチウム90、ヨウ素129が国の基準値を超えていたことを明らかにした。東電はこれまで「トリチウム以外の放射性物質は除去されている」として、十分な説明をしていなかった。構内で発生した汚染水は、セシウムを吸着する装置と、62核種を除去する装置「アルプス」を通り、取り除けないトリチウムを含む汚染水がタンクに保管されていると説明されていた。だが、「アルプス」の出口で汚染水を定期的に調べている分析検査で、トリチウム(半減期12年)のほか、ストロンチウム90(同29年)とヨウ素129(同1570万年)が国の基準値を上回っていた。最大値はトリチウムは1リットルあたり138万ベクレル(基準値の約23倍)、ストロンチウム90は141ベクレル(同約5倍)、ヨウ素129は62ベクレル(同約7倍)だった。東電は「吸着するフィルターの性能が落ちていたことも考えられる」としている。数値はホームページで公表しており、国が定める敷地境界の放射線量(年間1ミリシーベルト)も超えておらず、「保管上は問題はない」としているが、「今後はわかりやすくお知らせしていきたい」とコメントした。現在、タンクには約109万トンの汚染水がためられている。処理を巡っては、海洋や大気での放出といった方法が国で議論されている。東電によると、仮に放出となれば、事前に検査が行われる。放射性物質が検出されれば、アルプスに再び送って除去できるという。東電は「現在の汚染水がそのまま放出されるわけではなく、今回のこととは別問題」としている。 <後退した環境・衛生に関する意識> *3-1:https://www.excite.co.jp/news/article/Buzzap_58298/ (Excite news 2019年8月20日) 【コラム】「東京湾うんこまみれ問題」はどれだけ根深く深刻なのか、13年前から指摘も【東京オリンピック】 東京オリンピックに関して先日から話題になっている、トライアスロンなどの競技の会場ともなる東京湾が「トイレ臭い」という問題。実はあらゆる意味で極めて根の深い、深刻な話でした。 ◆東京湾のオリンピック本番会場「トイレ臭い」問題とは 産経新聞と朝日新聞が報じたところに寄ると、お盆前の8月11日に行われた本番会場と同じお台場海浜公園で行われた水泳オープンウオーターの東京五輪テスト大会。猛暑の真っ只中であったこともあり、参加選手からは水温や気温、陽射しの強さなどが過酷だと懸念の声が漏れました。これに加えて物議を醸したのが水質です。東京都や大会組織委員会が大腸菌類の流入を抑制するためにポリエステル製の水中スクリーンをコースの外周約400mに設置したものの、「正直くさい。トイレみたいな臭い」などと異臭を指摘する声が続出しました。来年には東京オリンピックの本番で、世界中から集まったトップアスリートたちが東京湾のこの会場で泳ぐわけですが、トイレ臭いとはいったいどういうことなのでしょうか。原因と現在に至る経緯を振り返って見ると、小手先ではどうにもならない極めて深刻な問題が浮かび上がってきました。しかもこれ、人災です。 ◆東京23区の大部分で採用されている「合流式下水道」の問題 この問題を知るために、まずは戦後日本のし尿の歴史を見直してみましょう。厚生省が(恐らくは昭和34年前後に)監修した「し尿のゆくえ」という極めて貴重で優秀なドキュメンタリー映画が作られています。当時は川や海へのし尿の投棄が日常的に行われており、寄生虫に加えてチフスや赤痢といった伝染病の蔓延など、衛生に関する非常に深刻な問題であった事がわかります。とはいえ出来が良すぎるため食事中は「絶対閲覧禁止」です。この作品がモノクロであることを天に感謝するレベルですので、心してご覧ください。現在は、日本のほとんどの場所でこのドキュメンタリー中盤で理想として語られる「水洗トイレから下水に流す」という方式が採用されています。もちろん東京でもこの方式が採用されているものの、東京都下水道局によると、東京都の区部の約8割では、汚水と雨水をひとつの下水道管で集める古いタイプの「合流式下水道」という仕組みが採用されています。この合流式下水道では、家の屋根や道路などに降った雨水を流す雨水管とトイレの水を含む生活排水を流す汚水管が別れておらず、いずれも同じ合流管に流れ込みます。晴天時や一定量までの雨の日は、この合流管からの下水を水再生センターで沈殿処理と生物処理によって処理した後、消毒・放流します。ですが一定以上の雨が降った際は、街を洪水から守るために汚水と雨水の混合した下水は簡易処理のみで河川や海に放流されてしまいます。上記映画でも言及されていた衛生や健康の問題、また洪水の起こりやすい関東平野での治水という観点から、東京では下水道の整備が急務となり、コストの安い合流式下水道が採用されてきました。現在は雨水と汚水を分ける分流式下水道の採用、切り替えなども行われているようですが、残念ながら2020年までに切り替えることは不可能です。なお水再生センターでは、塩素剤等の薬剤で大腸菌等を消毒して放流しているとされていますが、公益財団法人東京都環境公社の「東京湾の水質汚濁 -雨天時負荷が水質へ及ぼす影響-」という研究では、大雨後に多数の糞便性大腸菌が検出されたことが報告されています。つまり誇張でもなんでもなく、ゲリラ豪雨や台風のような大雨が降った後に東京湾は文字通りの「うんこまみれ」状態になってしまうのです。なんでそんな大切なことが分からなかったの?という疑問も出てきそうですが、実は以前から分かっていました。 ◆「東京湾うんこまみれ問題」はずっと前から指摘されていた 大雨が降ると東京湾に糞便性大腸菌が流れ出すという問題は、決して今回の東京五輪テスト大会で判明したものではありません。上記の「東京湾の水質汚濁 -雨天時負荷が水質へ及ぼす影響-」は2006年の研究発表資料ですし、国立環境研究所の2006年の公開シンポジウムでも「雨が降ると東京湾はどうなるか? -降雨後の水質変化-」の中で糞便性大腸菌が降雨時に「平水時の100~1万倍くらいまで高く」なることが指摘されています。そしてこの問題は、2013年の東京オリンピック開催決定直後に主催の東京都にもしっかり認識されていることが報じられています。スポニチは2013年9月27日の記事で、当時の猪瀬直樹東京都知事が定例記者会見で、東京オリンピックのトライアスロン会場となるお台場海浜公園周辺の海水が「大雨の時に大腸菌が多いことがある」と述べていることを伝えています。猪瀬知事(当時)はオリンピック開催までに下水道施設を改善して対処する考えを表明、「東京都はほぼ完璧に対策を取る。上流の県の水もきちんとやっていただきたい」として水質改善に向けて政府に申し入れる意向を示していました。またこの問題は、2017年7月に小池都知事も出席した都の幹部会議でも「雨が降った時が課題。対策を考えないと」と議題に上がりました。この問題を報じた朝日新聞の記事ではお台場海浜公園では「大腸菌が増えて、泳げる水質を定める国の「水浴基準」を満たさないことがあるため、ふだんは遊泳禁止。14年の都環境科学研究所の調査では、雨が3日間降らなかった後は基準をクリアしたが、大雨の直後は大腸菌がその時の約100倍に増え、基準を超えた」と指摘しています。この問題について長く取り組んでいる港区の榎本茂区議会議員によると、「平成24年(編集部注:2012年)度だけでも187万7200平方メートル、実に東京ドーム1.5杯分の未浄化下水が運河に放水されました」とのこと。日刊ゲンダイの記事によると、榎本議員は2014年9月の港区議会定例会では「私もNPOの代表をしていた平成19年(編集部注:2007年)に、このお台場でカキを使った大規模な水質浄化実験を提案し、お手伝いをしたことがあります。宮城からいただいてきたカキは、残念ながら1年を待たずして死滅してしまいました。理由の一つに挙げられたのが、毎月何度となく流れ込んでくる未浄化の生活排水によるものです」と指摘しています。また2017年5月13日に榎本議員が「ほぼ山手線の内側エリアのトイレ台所の汚水が雨水と共に、レインボーブリッジの袂から、塩素を混ぜただけの状態で放流されている」としてFacebookアカウント上にアップした動画での茶色く汚濁した水はかなり衝撃的です。榎本議員はここで「東京都下水道局は塩素で大腸菌は死んでいると言うが、港区の雨天時の水質調査をみても、大腸菌は死んでいないし、この放流されている水質が「水質汚濁防止法」の排水基準や、より厳しい上積み条例である「東京都環境確保条例」の基準を満たしているとは到底思えない」と指摘しています。つまり、少なくとも2006年の段階では問題が明らかにされており、東京オリンピック開催決定時点の2013年にも当時の都知事が問題を認識し、現在の小池都知事になった2017年にも問題として把握されていたということ。ですが開催まで1年を切った現時点でも東京都の対策が「ほぼ完璧」の域に至っていないことは8月11日に証明されたとおりです。 ◆本当にここでオリンピックやって大丈夫なの? さてこんな状態の東京湾で、本当に東京オリンピックのトライアスロン競技を開催することはできるのでしょうか。上述したように、東京都や大会組織委員会は大腸菌類の流入を抑制するためのポリエステル製の水中スクリーンをコースの外周約400mに設置しています。東京オリンピック本番ではこのスクリーンを3重にするとのこと。東京都が2018年夏にコースそばに膜を設置して水質を調べたところ、3重の膜の内側で大腸菌類は基準値を下回っていたものの、膜の外は調査した22日間のうち5日間で基準値を超えていたとされています。大雨の後に糞便性大腸菌が大量に検出されても、1日程度で急減することは「東京湾の水質汚濁 -雨天時負荷が水質へ及ぼす影響-」でも示されているとおり。朝日新聞は大会組織委担当者の組織委の担当者は「膜の設置で水質の安全は担保できる。あとは大腸菌が流れ込む原因となる大雨や台風が、本番で来ないことを祈るのみ」という言葉を紹介しており、運頼みという状況であることが分かります。うんこだけに。実際に8月17日に開催されたパラトライアスロン・ワールドカップでは大腸菌による水質悪化でスイム抜きのデュアスロンとなりましたが、翌18日には国際トライアスロン連合基準で最悪の「レベル4」が「レベル1」まで改善されたため、トライアスロン・世界混合リレーシリーズ大会は予定通り実施されています。なお、会場となるお台場海浜公園では毎年夏にお台場海水浴「お台場プラージュ」が10日ほどの期間限定で開催されています。台風10号の襲来を前にした8月14日の水質の動画が撮影されていますが、前日からの降雨がほとんどない状態です。話が戻りますが、雨が降らなければそれで解決という話ではありません。水質は基準をクリアしていたとしても、例えば貴田裕美選手はテスト大会時に「水温も気温も高いし、日差しも強くて過酷だった。泳ぎながら熱中症になるんじゃないかという不安が拭えなかった」と述べています。また野中大暉も「他の会場と比べても暑い。脱水の心配もあるので、水分補給とかを工夫をしていかないと」と話すなど、晴れた場合は水温、気温、陽射しなどで熱中症の危険が発生するという、まさに前門の虎後門の狼状態となっています。国際水連のマルクレスク事務総長が水温の問題について「最も大切なのは選手の健康。水温の状況を見ながら5時、5時半、6時、6時半と開始時間を変更する可能性もある」と述べていますが、こうなるとまた別の問題が発生します。それは先日BUZZAP!が報じて大きな反響を得た、東京五輪ボランティアが「終電で現場に行かされ、徹夜の交流で士気を高めさせられる」という問題です。海辺の炎天下での徹夜明けのボランティア作業が過酷なことは、改めて指摘するまでもありません。この会場でトライアスロンを開催する以上、どうやっても誰かが過重な負荷や負担を強いられるという、いわゆる無理ゲー状態となっていることがよく分かります。そもそもうんこまみれの東京湾で海外のトップアスリートを泳がせることが日本の「オモテナシ」なのかという疑問もありますが、トイレを素手で掃除する事を美徳とする日本人にとっては、これも滝行のような「精神修練の場」ということになるのでしょうか。 *3-2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019092002000179.html (東京新聞 2019年9月20日) ゲノム食品 表示義務なし 年内にも流通 消費者庁「判別できず」 消費者庁は十九日、ゲノム編集技術で品種改良した農水産物の大半について、生産者や販売者らにゲノム編集食品であると表示することを義務付けないと発表した。ゲノム編集食品は特定の遺伝子を切断してつくられるが、外部から遺伝子を挿入する場合と挿入しない場合があり、現在開発が進む食品の大半は挿入しないタイプという。厚生労働省は同日、同タイプの販売について安全性審査を経ずに届け出制にすると通知。今回の消費者庁の発表で流通ルールの大枠が決まった。早ければ年内にも市場に出回る見通しだが、表示がなければゲノム編集食品かどうか分からず、安全性に疑問を持つ消費者から不満が出るのは必至だ。消費者庁は、表示を求める声が消費者団体などから上がっていることを踏まえ、義務付けない食品についても、生産者や販売者らが自主的に包装やウェブ上などで表示するよう働き掛ける方針。消費者庁は義務化しない理由について「(外部遺伝子を組み込まない食品は)遺伝子の改変がゲノム編集によるものか、従来の育種技術で起きたのか科学的に判別できず、表示義務に違反する商品があっても見抜けないため」と説明。製造から流通までのトレーサビリティー(生産流通履歴)の仕組みも不十分で、追跡が不可能だとした。一方、外部遺伝子を組み込み、安全性審査が必要となる食品は表示を義務付ける。 *3-2-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14192008.html (朝日新聞社説 2019年9月25日) ゲノム食品表示 これで理解得られるか 役所の名称とは裏腹に、消費者・市民に寄り添っているとは言いがたい決定だ。ゲノム編集技術を使った食品について、消費者庁は先週、遺伝子の配列をわずかに変えただけなら、編集した旨の表示を事業者に義務づけることはしないと発表した。既存の品種改良との区別が難しく、たとえ義務化しても違反者を特定することができないため、としている。消費者団体などが批判の声を上げたのは当然だ。朝日新聞の社説は、科学的に安全か否かの議論とは別に、自分の判断で食品を選べる環境を整えることが大切で、その視点に立って表示のあり方も考えるべきだと主張してきた。今回の措置は、消費者の権利を尊重し、適切に行使できるようにするという、消費者行政の目的と相いれない。見直しを求める。消費者庁も、どんな食品かを知りたい消費者がいることを、当然認識している。そこで、厚生労働省に届け出があったゲノム編集食品については、事業者に対し、消費者への積極的な情報提供を呼びかけている。何とも中途半端な対応だが、そういうことであれば当面は食品を開発・販売する側に期待するしかない。ゲノム編集を施したことを明示し、問い合わせがあれば丁寧に答える。情報の公開と説明に前向きに取り組む姿勢を見せることが、信頼を生み、今後のビジネスにも役立つと考えてもらいたい。そのためにも、表示・公開の方法に一定の基準を設けることを検討すべきだ。どんな遺伝子に手を加えたのか、成分はどのように変化したのかなどについて、企業秘密を守りつつ、どこまで公にするか。ホームページに載せるだけでいいのか、購入時に認識できるようにするにはどうしたらよいか。事業者任せにせず、消費者庁も入って、工夫や研究を重ねてもらいたい。厚労省の責任も重い。業者が届け出るべき情報の中には、アレルギーの原因物質が新たにつくられていないことを確認する項目などもある。開発段階で十分な試験がなされているか、データは信頼できるか、入念なチェックが求められる。ゲノム編集は発展途上の技術だ。最新の動向を幅広く収集するとともに、懸念材料が出てきたときには、事業者にすみやかに対応をとらせ、安全性を検証できる仕組みをあらかじめ整えておくことが欠かせない。効率のいい品種改良を可能にするゲノム編集技術は、国内はもちろん世界の農林水産業を大きく変える可能性を秘める。それだけに、幅広い理解を得られるよう慎重に歩みを進めたい。 *3-3:https://mainichi.jp/articles/20190925/k00/00m/040/160000c (毎日新聞 2019年9月25日) 海面水位、世界平均1・1メートル上昇と予測 地球温暖化で IPCC特別報告書 世界全体で有効な対策が取られないまま地球温暖化が進むと、今世紀末に世界平均の海面水位は最大で1・1メートル上昇すると予測した特別報告書を25日、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表した。台風など熱帯低気圧の強さも増して、高潮などによる沿岸部の被害が増加すると指摘しており、島国の日本をはじめ各地の防災対策に影響を与えそうだ。報告書によると、世界平均の海面水位は1902年から2015年までの間に16センチ上昇した。特に2006~15年は年3・6ミリのペースで上昇し、1901~90年の平均ペースの約2・5倍と先例がないスピードで水位が上がっている。さらに温室効果ガス削減が進まず、今世紀末の世界の平均気温が産業革命前より最大5・4度上がった場合、世界平均の海面水位は1986~2005年の平均に比べ、61センチ~1・1メートル(中央値84センチ)上昇すると予測した。南極の氷がどんどん解けていることなどから、IPCCが2014年に公表した報告書の予測より上昇幅は1割程度拡大した。海面上昇に伴って低地にある大都市では、これまで100年に1回程度の頻度で発生していた高潮災害などが、2050年には毎年のように起こるという。IPCCは温暖化に関する知見を各国に提供する政府間組織で、195カ国が参加している。今回の報告書は海と極地・高山地域の氷への影響に焦点を当て、公表済みの約7000の論文を基にして、日本の研究者4人を含む36カ国計104人の専門家が執筆に関わった。 <癌の増加> *4-1:https://digital.asahi.com/articles/ASM634WF5M63UGTB009.html (朝日新聞 2019年6月4日) 福島の小児甲状腺がん、被曝との関連否定 県の専門部会 2011年の東京電力福島第一原発事故時に、18歳以下だった福島県民を対象にした14~15年度分の甲状腺検査について、福島県の評価部会は3日、「現時点で、発見されたがんと被曝(ひばく)の関連は認められない」とする見解を取りまとめた。今回検討した検査は、11~13年度に続く2巡目。約27万人が受診し、このうち71人で、がんまたはがんの疑いが発見された。部会では、国連科学委員会による被曝線量の推計を使って、受診者の推計線量と、がんやがんの疑い発見の比率を、性別や年齢、検査年度などの影響が残らないよう調整して分析。線量とがんの発見率に関係がないと結論づけた。出席者からは、被曝線量の推計が個人別ではなく、地域で区分していることなどが指摘されたが、鈴木元(げん)部会長は現時点でできうる範囲のものと説明。「今回の結果をもって、(今後も)事故の影響が出ないとは言えない」とも述べた。 *4-2:https://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/7b914e413119f15ca27d5b158f258b2d (Goo 2015.2.18) 内部被ばくの影響は10年後、必ずでてくる、西尾正道北海道がんセンター院長、インタビュー/ 財界さっぽろ 放射線による健康被害は外部被ばくばかりが問題視される。しかし、深刻なのは体内に放射性物質を取り込んでしまった内部被ばく。長年、臨床医として放射線治療をしてきた第一人者に人体に及ぼす内部被ばくの影響を聞いた。世界機関に内部被ばくのデータなし ――食品安全委員会は7月26日、自然放射線や医療被ばくを除く放射線で、健康に影響が出るのは内部被ばく・外部被ばくを合わせて、生涯で100ミリシーベルト以上との答申案をまとめました。 西尾 日本の法律上では、一般公衆の線量限度は1ミリシーベルト/年ですが、政府はICRP(国際放射線防護委員会)の基準をもとに警戒区域や計画的避難区域を設け、校庭の活動制限の基準を3.8マイクロシーベルト/時間、住民には屋外で8時間、屋内で16時間の生活パターンを考えて、年間20ミリシーベルトとしました。この線量基準は年齢も考慮せず、放射線の影響を受けやすい成長期の小児や妊婦にまで当てはめるのは危険です。では、なぜこんな基準が示されたのか。移住を回避させる目的としか考えられません。しかし、原発事故の収拾のめどが立っていない状況で、住民に20ミリシーベルト/年を強いるのは人命軽視の対応です。そうした中で、今度は食品安全委員会から生涯で100ミリシーベルト以下なら安全だという答申が出された。しかも内部被ばくも含むという。しかし、内部被ばくについては、これまでICRPもIAEA(国際原子力機関)もまったく取り上げていません。むしろ原子力政策を推進する上で不問にしていた。だから内部被ばくに関するデータはまったく持ち合わせていないというのが現状です。 ――にもかかわらず、100ミリシーベルトという数字を出したと。 西尾 結局、内部被ばくと外部被ばくの人体影響の差はまったくわかっていないので、とりあえず線量が同じなら同等と考えましょうというのが今の世界のコンセンサス。何の根拠もなく、わからないから1対1にしようということです。 ――ものすごく乱暴な結論ですね。 西尾 ですから、内部被ばくの1ミリシーベルトと外部被ばくの1ミリシーベルトが同等の健康被害かどうかということすらわかっていない。内部被ばくは近くにある細胞にしか影響を与えません。局所的にアルファ線やベータ線の影響は強いわけですが、それを体全体の線量に合わせてしまうと60兆個の細胞のうちの局所的な個数ですから、見かけ上ものすごく少ない線量しか出てこない。そういうトリックがあります。そもそも国は、国民の被ばく線量もはかっていないのに、新たな規制値をつくるのは何の目的なんだということですよ。自分がどれだけ被ばくしているかもわからないのに、ただ数字だけが踊っている。 ――考えられることは。 西尾 今後、予想される食品汚染ということになると内部被ばくの問題です。政府にはそういうデータはまったくないと思います。このタイミングで出てくるというのは、たとえばセシウムだったら年間5ミリシーベルトに抑えようと、肉だったらキロ当たり500ベクレルにしようとなっていて、そういうものを食べていれば年間5ミリシーベルトくらいになるということなんだけど、いまの規制値だとそれで収まりきらない可能性がある。だからもっとぼかした形で「一生涯にこれだけいいですよ」と。国民をだます手法の1つとして考え出されたものだと思います。ごまかしです。いままでの基準値だって、水は100ベクレルでした。それが東京・金町浄水場の水道水から210ベクレルの放射性ヨウ素が出たといったら、一気に300ベクレルに上げた。原発作業員も年間被ばく量は100ミリシーベルトといっていたら、それじゃ作業させられないから一気に250ミリシーベルトに上げた。その場でクリアできなくなったら、基準値を上げているだけ。一貫してそう。こんなことをやっていたら10年後は大変な問題が起こりますよ。「人ひとり死んでいない」とバカなことを言う人もいるけれど、それは目先の利益を追いかける人の発想です。問題は今後、奇形児が生まれたり、がんが増えたり、そういうことは確実に起こります。 ――これまでに起こった原発事故で、内部被ばくによる人体への影響は明らかだと思うのですが。 西尾 いま世界中で内部被ばくを含め、隠されていたデータがどんどん出てきています。2000年以降、10ミリシーベルト以下の低線量でも健康被害があるという論文もいくつかあります。とくに子ども。放射線の影響は大人の3倍から4倍ありますよ。乳幼児の場合だったら、同じ甲状腺への取り込みは8倍から9倍になる。英国の使用済み核燃料棒の再処理工場があるセラフィールドでは、子どもの白血病が通常より10倍の罹患率です。チェルノブイリもそうです。IAEAの予想では4000人くらいの過剰がん患者というけれど、実際には100万人近く出ている。今回の福島だって、欧州のグループは今後50年間で42万人が、がんになると予想。ところがIAEAは6000人。ケタが2つも違うようなことを言っている。現在も、極めて原子力推進派の意見が世界を支配しているのです。避難住民は疎開ではなく移住すべき ――いまも福島原発からは放射性物質は出ているんでしょうね。 西尾 専門家は水素爆発時の100万分の1くらいになっていると言っていますが、いずれにせよ微量は出ていると思います。 ――一連の爆発時にどんな放射性物質が放出されたのでしょう。 西尾 9割方はヨウ素131。あとの1割弱はセシウム134と137が半々くらいといわれています。 そのほかにコバルト、ストロンチウム、プルトニウムなど、もろもろ30核種50種類くらいの放射性物質が出た。 ただ、ヨウ素は半減期が8日だから、いまはほとんどなく、セシウムだけが残っている状況です。セシウム137の半減期は30年、134は2年です。 ――一番毒性の強いのは。 西尾 プルトニウムです。アメリカの西海岸やハワイでも検出されています。 ――そういうものを吸い込んだ人も、たくさんいるんでしょうね。 西尾 たとえば体内にセシウム137を取り込んだとします。物理的半減期が30年といっても、生物的には代謝する過程で体外に出ていきますから、実際には100日くらいしかない。4カ月もたっていたら4割くらいになっている。放射性物質を100取り込んだとして9割はヨウ素だから検出されない。1割のセシウムも3分の1くらいになっている。ですから理論的には100あったとしても3しか残っていない。 ――国民はすでに汚染された肉などを食べた可能性もあります。 西尾 いまくらいの量だと実際にはそれほど問題はないと思います。ただ、食べ続けると健康へのリスクは高くなるでしょう。 ――やはり食物が気になります。 西尾 政府は飲食物に関する規制値も緩和しました。年間線量限度をヨウ素では50ミリシーベルト、セシウムでは5ミリシーベルト、しかも従来の出荷時の測定値ではなく、食する状態での規制値です。これではますます内部被ばくは増加します。ちなみにホウレンソウの暫定規制値はヨウ素でキロ当たり2000ベクレル、セシウムは同500ベクレルとなりました。放射性物質は、よく水洗いすれば2割削減され、茹でて4割削減され、口に入るときは出荷時の約4割になります。確かに調理によって人体への取り込みは少なくなりますが、汚染水や人体からの排泄物は下水に流れていく。それは最終的に川や海に達します。環境汚染が進むことは避けられません。今後、日本人は土壌汚染と海洋汚染により、内部被ばく線量の増加を覚悟する必要があります。 ――高い放射線量が計測される町にも人はいます。 西尾 20マイクロシーベルトになっているところは、さしあたって住めません。疎開でなく移住です。 疎開は少したったら帰ってくるという発想ですが、それは無理です。汚染地域では産業が成り立たない。 生活の基盤がつくれないのだから移住すべきだと思います。 21世紀は放射性物質との戦いの時代 ――いまそういうところに住んでいる人は被ばくし続けているわけですよね。 西尾 いまくらいの数値だったら問題はないでしょう。世界中には自然放射線を年間10ミリシーベルト浴びているところもある。世界平均で2.4ミリシーベルト。それほど深刻になるほどではありませんが、地域経済は成り立たない。日本は最も原発に適さない国です。世界で発生する震度6以上の地震の半分は日本です。海に囲まれ、津波のリスクもある。国土が狭いから何かあっても逃げられない。静岡県の浜岡原発でチェルノブイリと同じことが起こったら、東京がすっぽり汚染地域に入ってしまう。そのくらい狭い国土なんです。中国はこれから原発を400基つくるといっています。日本にだって54基ある。何らかの事故でまた放射性物質がばらまかれる事態は想定しておかなければなりません。そんな時代に内部被ばくを不問にして健康被害を語るのは、まったくの片手落ち。21世紀は放射性物質との戦いの時代です。1980年以降、がんの罹患者数は増えています。昨年は心臓病を抜いてがんが、全世界で死因のトップになりました。これは単純な高齢化の問題だけでは説明がつかない。人工放射線が何らかの形で関与している可能性がある。そのくらいの思い切った発想で、放射線の健康被害を慎重に検討することが求められていると思います。 *4-3:https://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/7b914e413119f15ca27d5b158f258b2d (Goo 2013.8.21) 被曝【10ミリでガン増加、政府データ】チェルノブイリなら「5ミリで強制移住」福島では20ミリで帰れ! ●MSN産経ニュースより 2013.11.8 【追加被ばく「年間20ミリ以下」で影響なし 規制委、住民帰還で提言へ】 東京電力福島第1原発事故で避難している住民の帰還に向け、放射線防護対策の提言を検討している原子力規制委員会が、年間の追加被ばく線量が20ミリシーベルト以下であれば健康に大きな影響はないという見解を提言に盛り込む方針を固めたことが8日、分かった。放射線防護対策を議論する11日の検討チームで提言案を示し月内にもまとめる。提言を受け、政府は住民帰還に向けた具体的な放射線対策を年内にとりまとめる方針。国際放射線防護委員会(ICRP)は原発事故のような緊急事態後の段階では、住民の被ばく線量を年1~20ミリシーベルトにする目安を示している。田中俊一委員長も住民が不慣れな避難先でストレスを抱えて病気になるリスクもあるとし、「年20ミリシーベルト以下であれば全体のリスクとして受け入れられるというのが世界の一般的考え方だ」と述べていた。政府は事故後、年20ミリシーベルトを基準に避難区域を設定。ただ、除染の長期目標は年1ミリシーベルトとし論議を呼んでいた。規制委は国際基準を再確認し提言案に盛り込む。 ●MSN産経ニュースより 2013.11.8 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131108/dst13110814110005-n1.htm 原子力規制委員長 「年間20ミリシーベルトまで許容」した方がいい。チェルノブイリなら5ミリで強制移住。 自民党の鬼木議員は「基準値は厳しすぎる。500ベクレルに戻せ」と言い、安倍政権は福島原発付近の出荷規制を次々に解除。【原子力規制委員長「年間20ミリシーベルトまで許容した方がいい」】 民主党政権時に定められた放射能基準値も酷かったですが、自民党はその基準値を更に緩めようとしている動きを見せています。自民党の鬼木議員は「基準値は厳しすぎる。500ベクレルに戻せ」と言い、安倍政権は福島原発付近の出荷規制を次々に解除。そして、先日に福島原発と除染状況を調査するため来日した国際原子力機関(IAEA)の専門家チームのフアン・カルロス・レンティッホ団長は「必ずしも(国が追加被ばく線量の長期目標に掲げる)年間1ミリシーベルトでなくてもいい」と述べました。日本の原子力規制委員長もこれに合わせる形で「年間20ミリシーベルトまで許容した方がいい」と発言をしており、原子力を規制する側の組織が、体制側の連中を容認しているのが分かります。おそらく、政府や権力者の間では基準値を緩める前提で話が進んでいるのでしょう。だから、国民の反発を抑えるために、IAEAの団長や原子力規制委員会の連中にこのような言葉を言わせているのだと思います。山本議員らは何とか1ミリシーベルト以下の基準値にしようと努力をしていますが、政府が基準値を緩める方向で動いているため、多勢に無勢という感じの状況です。本当は基準値を厳格化するべきなのに、基準値を緩めるとか私には出来ません。政府の連中は本気で、「お金さえ手に入れば後はどうでも良い」と考えています。でなければ、今の状況で「基準値を緩める」なんて言葉は言わないはずです。 ●読売新聞 2013年10月25日(金) http://s.news.nifty.com/headline/detail/yomiuri-20131024-01364_1.htm 【IAEA報告書 「1ミリ・シーベルト」はあくまで長期目標】 東京電力福島第一原子力発電所の事故による除染は当面、どのレベルまで実施すべきなのか。国際原子力機関(IAEA)の調査団は、徹底除染により年間被曝(ひばく)線量を「1ミリ・シーベルト以下」にすることについて、「必ずしもこだわらなくてもよい」との見解を示した。適切な指摘である。環境省にはIAEAの見解に沿い、除染を加速させることが求められる。調査団は今月、第一原発周辺の現地調査を実施して除染状況をチェックし、報告書をまとめた。注目すべきは、報告書が、国際的基準に照らし、「年間1~20ミリ・シーベルトの範囲内のいかなるレベルの個人放射線量も許容し得る」と明記した点である。避難住民の帰還に向け、政府が設けている「20ミリ・シーベルト以下」という目安を補強するものだ。早期の帰還実現への弾みとしたい。政府は、除染の長期目標として「1ミリ・シーベルト以下」も掲げる。だが、1ミリ・シーベルト以下にならなければ帰還できないと思い込んでいる住民が少なくない。民主党政権が、徹底除染を求める地元の要望を受け、1ミリ・シーベルトを当座の目標としたことが尾を引いている。ゼロリスクにとらわれると、除染完了のめどが立たなくなる。住民の帰還は遅れるばかりだ。IAEA報告書も、1ミリ・シーベルトについて、「除染のみで短期間に達成できるものではない」と結論付けた。政府には、その事実関係を丁寧に説明するよう注文した。政府は、1ミリ・シーベルトが安全と危険の境目ではないことを住民に周知する必要がある。環境省は、第一原発周辺の11市町村で除染を実施しているが、汚染土を保管する仮置き場の確保などが難航し、作業は大幅に遅れている。現在、7市町村の除染計画を見直している。汚染レベルが比較的低い地域で重要なのは、除染と併せ、住民の生活再建に必要なインフラ整備を進めていくことだ。1ミリ・シーベルトを一気に目指さず、段階的に取り組めば、除染からインフラ復旧に、より多くの費用を振り向けられる。報告書のこの提言は、除染計画の参考になろう。政府は除染費用として、今年度までに約1兆3000億円を計上した。要した費用は東電に請求する仕組みになっているが、経営が悪化している東電に支払う余力はない。電気料金の値上げなどで国民の負担となる可能性が高い。いかに効率よく的確に除染を進めるか。喫緊の課題である。 *4-4:https://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/746becae201fb092dd7a03cda57b1291 (goo 2014.4.16) 報道ステーション せっかく取材したのに、東京の汚染は全面カットだった! ●「無いこと」にされている関東の子どもの健康被害 川根…「放射能防護プロジェクト」に参加している三田茂さんという医師がいます。この3月に小平市の病院を閉院して、東京から岡山へ移住することを決断されています。今年3月11日に、『報道ステーション』で古舘伊知郎さんが甲状腺がんの特集をやりました。古舘さんは三田先生にも取材に行っています。三田医師は、東京・関東の子どもたちの血液、特に白血球の数値が低くなっている、と明らかにしました。それは柏市や三郷市のようなホットスポットだけでなく、埼玉市や川崎、横浜、相模原の子どもたちの数値も悪くなっている、と指摘しました。話を聞いた古舘さんたちは驚いて、「先生の名前と顔が出るが、話していいのか」と聞きました。三田先生は「大事なことだから、きちんとした良い番組を作ってくれるなら出して構わない」と、OKを出しました。ところが、数日後に連絡が来て、「実は東京が危ないということは報道できない」と、全面カットになったそうです。福島だけの問題になってしまいました。三田先生は、他の医師にも「甲状腺エコー検査機器を共同で買って、治療し直しましょう」と呼びかけているのですが、反応がない。多くのテレビ局や新聞社からも、「東京の子どもの健康問題はどうなっているんだ」と取材を受けていますが、一本の記事にも番組にもなっていません。今のマスメディアは、「東京は安全だ、危険なのは福島だ」という情報操作がなされているのです。 <ゲノム編集食品表示の緩さ> PS(2019年9月29日追加):*5に書かれているとおり、今回のゲノム編集食品の表示については「遺伝子を切り取って機能を失わせるだけなら、(安全性に問題がないので《??》)表示規制の対象外にする」としているが、本当に安全かどうかは、薬と同様、多くの人が長期間摂取した後でなければわからない。そのため、消費者の選択権をなくしてそういう食品を食べたくない人にまで無理矢理食べさせるような表示規制は問題だ。また、消費者の立場を護るために作られた消費者庁の存在も、消費者の立場を護らないのであれば無駄になる。今、この緩い表示規制に対して民間ができることは、ゲノム編集していない食品には「ゲノム編集した食品は入っていない」という文言を大きく書くことしかないが、EUではゲノム編集食品も規制の対象にすべきだとの司法判断が出たそうだ。(本当はそれが当たり前だが)司法が正常に働く国は羨ましい。 *5:https://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20190929_3.html (京都新聞社説 2019年9月29日) ゲノム食品 許されない「見切り発車」 消費者の不安や懸念を置き去りにし、これでは「見切り発車」といわざるを得ない。狙った遺伝子を破壊して特定の機能を失わせたゲノム編集食品の流通や販売が、あさって10月1日から解禁される。血圧を抑える成分が多いトマトや芽に毒のないジャガイモ、肉厚なマダイなどの開発が進んでおり、早ければ年内にも食卓に並びそうだ。政府はゲノム編集技術で品種改良した食品の販売に向け、届け出制度を導入するが、特定の遺伝子を壊す手法なら安全性審査は不要だ。ゲノム編集食品であるとの表示も義務付けない。ゲノム編集は生物の遺伝子を改変する技術の一種だ。簡便な手法の開発に伴い、従来の遺伝子組み換え技術より効率よく高い精度で遺伝子を書き換えることができ、医療や農林水産分野での応用が期待されている。その技術を使った食品開発は昨年6月に政府が決定した「統合イノベーション戦略」に盛り込まれ、議論が加速。厚生労働省や消費者庁などが安全性や流通ルールの検討を急いでいた。厚労省によると、遺伝子組み換え食品と同様、遺伝子を外から組み込む場合は厳格な安全性審査を求める一方、遺伝子を切り取って機能を失わせるだけなら規制の対象外とする。ゲノム編集食品の大半が届け出だけで販売が認められるという。精度が高いゲノム編集ならば想定外の変化や異常は起きにくく、安全面は従来の品種改良と同程度のリスクというのが、その理由だ。だが新技術ゆえに未知の部分も多い。予期せぬ変異は生じないと断言できまい。ゲノム編集の方法や新たなアレルギー原因物質の有無などを届け出る必要があるものの、違反しても罰則はなく実効性に疑問符が付く。ゲノム編集食品の開発・流通を促進させるためとはいえ、拙速過ぎないか。消費者はどう受け止めているのか。厚労省の意見公募に約700件が寄せられ、大半が「長期的な検証をしてから導入すべきだ」といった懸念だった。消費者庁の姿勢も疑問だ。流通・販売の解禁に際し、検査が難しいことなどを理由にゲノム編集食品であるとの表示を義務付けない方針を決めた。表示がなければゲノム編集食品かどうか分からず、消費者は知らないうちに口にする恐れがある。不満が出るのは必至だろう。消費者目線で対応すべき官庁として存在意義が問われる。ゲノム編集によって有用な品種改良が短期間で可能になる。消費者にも利点は多い。しかし食の安全・安心へのこだわりは根強い。欧州連合(EU)でも昨年、ゲノム編集食品も規制の対象にすべきとの司法判断が下された。不安を解消しないまま、ゲノム編集食品の流通が既成事実となる事態は避けたい。少なくともゲノム編集を施したとの明示は欠かせない。情報を正しく消費者に知らせ、安全で安心な食品を「選ぶ権利」を確保することが重要である。拙速に解禁しても消費者に受け入れられない。遠回りであっても法整備やルール作りを通じ、新しい技術への理解を深めることこそ早道といえよう。 <原子力規制委員会は人体に関する専門家ではない> PS(2019年9月29日追加):上のように、人体の専門家である医師が内部被曝の危険性を説明しているのに、原子力の専門家である原子力規制委員会が「科学的に安全だ」と言ったから安全で、それを信じない人は「非科学的であり、風評被害の根源だ」などと*6が記載しているのは、“専門家”の区別もつかない文系のドアホと言うしかない。原子力の専門家である原子力規制委員会が言っている安全性は、「人体への安全性」ではなく「原子力産業と経産省継続の安全性」なのに、よくもここまで主観的・感情的なこじつけが書けるものだ。もちろん、何だって食べたい人が食べるのは自由だが、国全体では医療費・介護費が増えて年金支給額は減るだろう。 *6:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/546973/ (西日本新聞 2019/9/29) 処理水放出、遠い「安心」 原田・前環境相発言を読み解く 「思い切って(海洋に)放出するほかに選択はない」。東京電力福島第1原発で増え続ける処理水について、原田義昭前環境相=衆院福岡5区=がこう問題提起し、論議を呼んでいる。科学的根拠に基づくとされる「安全」と、それでもなお多くの人々が素直には胸に抱けない「安心」-。今回、あらためて浮き彫りになったのは、このギャップを埋めるのが簡単ではないという現実だ。原田氏の発言は、環境相退任前日の9月10日に飛び出した。放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出を主張し、「それによって残るであろう風評被害や漁業者の苦労は、国を挙げて補完することが極めて大切だ」と強調した。処理水は今も毎日170トンずつ増え、現在計116万トンがタンク約千基に保管されている。東京電力は2022年夏ごろには満杯になり、原発の廃炉作業にも支障が出る恐れがあるとしている。国は有識者でつくる小委員会を設置し、気体にして大気中に放つ「水蒸気放出」や「地層への注入」なども選択肢に処分方法を話し合っているが、答えは出ていない。 ■ 専門家である原子力規制委員会の見解は、トリチウムの人体への影響は極めて小さいので心配なく、海洋放出が「処理水処分の現実的、唯一の選択肢」(更田豊志委員長)というものだ。原田氏は、この「科学性」に依拠して声を上げた。誰もが触れたがらないことを、勇気を出して世に問うたと受け止めたのは、復興相経験者の自民党議員。「フクシマの復興を真に加速させる意味で、(原田氏の発言が)放出を決断するきっかけになればいい」。松井一郎大阪市長と吉村洋文大阪府知事も、「環境被害がないものは国全体で処理すべきだ」と同調。大阪湾で、一部の処理水放出を受け入れても構わないと踏み込んだ。これに対し、福島で日々生きる住民からは、海洋放出は水産物などへの風評被害を招くとして「容認できない」との反発が出ている。相馬双葉漁協(福島県)の立谷寛治組合長は「『安全』を訴えても、どうしても信じてもらえない消費者が一定数はいる。原発事故後に試験操業でこつこつやってきて、風評被害がやっと徐々に減っているのに、漁師の努力に水を差すつもりか」と憤る。昨夏には、処理水中にトリチウム以外の放射性物質が残留していることも判明。漠とした不安の影を濃くした。 ■ 国の小委員会メンバーでもある東京大大学院の関谷直也准教授(災害情報論)は「科学的に安全だからといって、社会的な課題が解決していないのに放出を急ぐとすれば早計だ」と指摘。小委員会は、風評被害との向き合い方もテーマに検討を深めている。原田氏の後任の小泉進次郎環境相も福島を訪れ漁業関係者に陳謝し、こう述べた。「世の中に一石を投じる必要性は分かるが、簡単に石は投げられない」。では、どうすれば人々の「安心」を獲得して「安全」に近づけていけるのか-。処理水はたまり続ける。解決策はまだ見えない。 <東京オリンピックのトライアスロンは、美しい自然と歴史ある街を舞台に> PS(2019年10月1日追加):東京オリンピックのトライアスロン競技会場がお台場海浜公園のままであれば、トライアスロン選手に酷であるだけでなく、見る方も楽しくないし、日本開催のオリンピックなのに日本の醜さばかりが世界に報道され、日本の歴史や自然の美しさが報道されない。そのため、*7のトライアスロンは、神奈川県江の島からスイムを開始し、バイクで鎌倉の名所や横浜港・元町中華街・東海道などを通って、最後に東京都内の名所をランしてゴールするように変更すれば、面白い競技を通して周囲の美しい自然と歴史(日本の鎌倉時代、江戸時代、明治維新、現代)をパノラマで世界に発信することができる。この時、日本の報道機関が、江の島付近の自然や海中、鎌倉時代、江戸時代、明治以降の歴史や付近の自然を外国の報道機関も的確に報道できるよう、あらかじめ映像や解説を渡しておけば効果的だと思う。 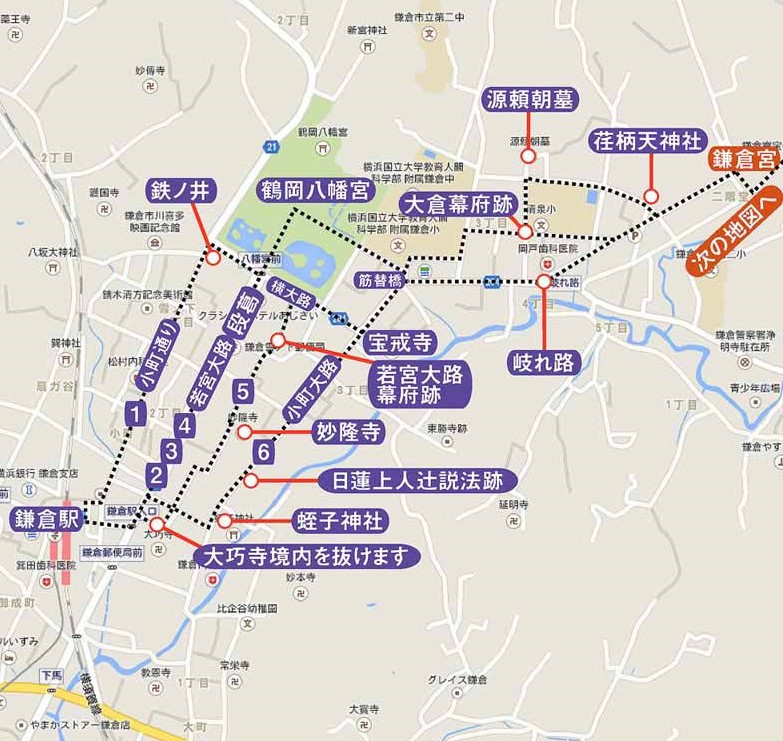 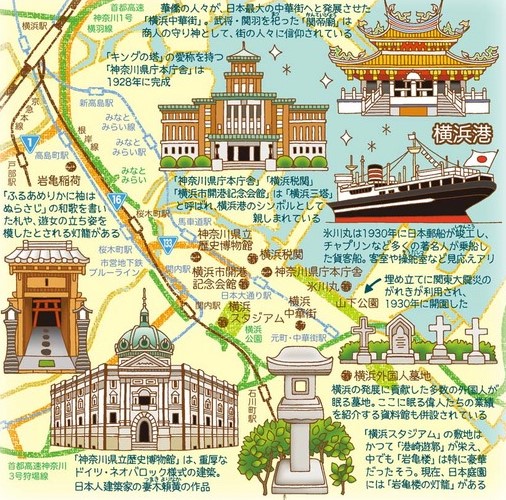    (図の説明:一番左の図は、鎌倉の名所旧跡を示した地図で、中央の3つは横浜の名所だ。また、一番右が東京の名所を示した地図だが、いずれも錚錚《そうそう》たるものである) *7:https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/games-olympics/triathlon/index.html (概要のみ抜粋) トライアスロン 距離:オリンピックディスタンス(スイム1.5㎞、バイク40㎞、ラン10㎞) スイム(水泳)、バイク(自転車)、ラン(長距離走)の順で、1人で連続して行う競技で、屋外で行われます。着順を競う競技です。
| 原発::2015.11~ | 04:33 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,09,09, Monday
 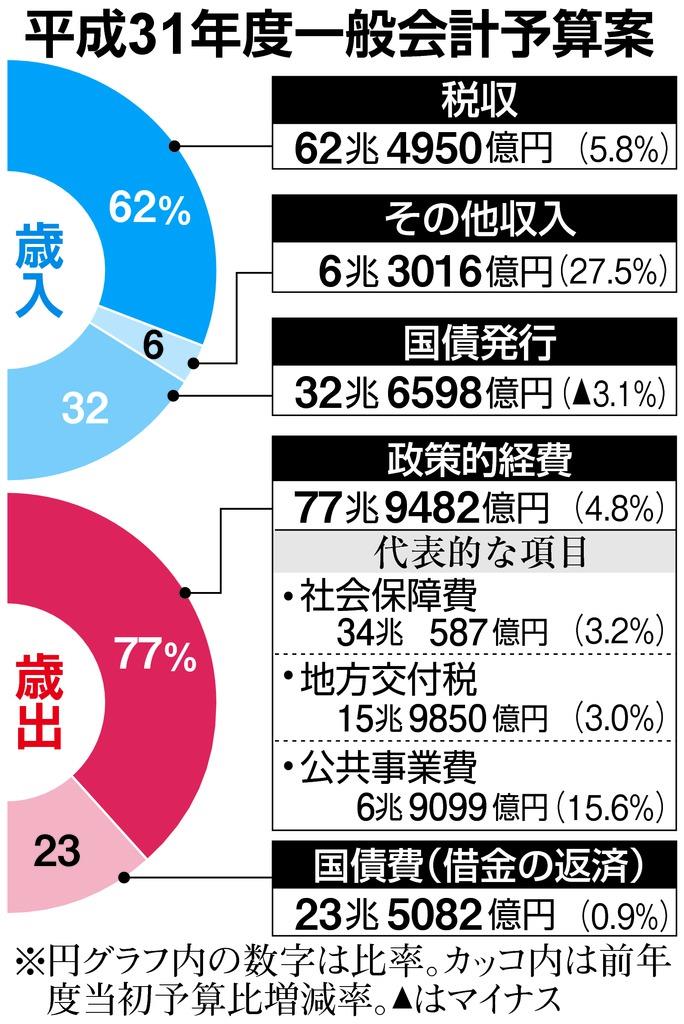 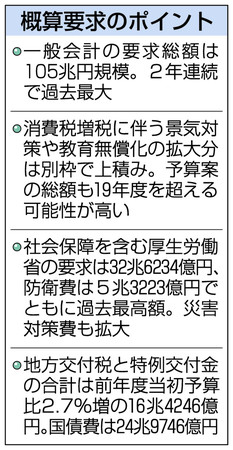 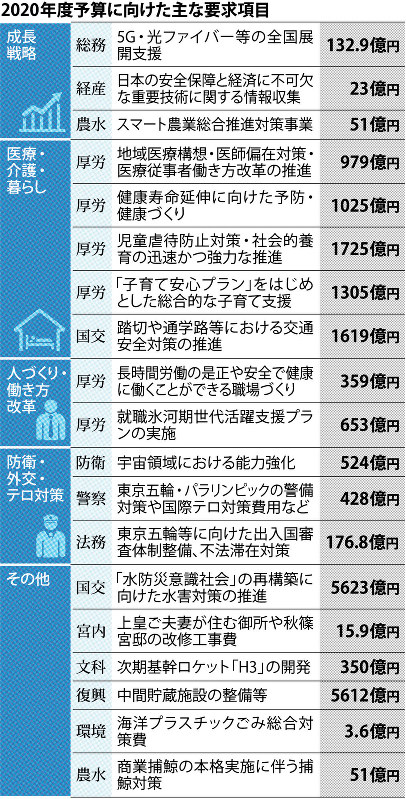 2018.11.17・2018.12.21産経新聞 2019.8.31東京新聞・毎日新聞 (図の説明:1番左の図のように、日本の国家予算は増加の一途を辿り、左から2番目の図のように、2019年度予算は100兆円を超えて2/3は税収だが残り1/3は国債で賄われている。従って、国の財政状態と収支の状況を正確に知って合理的な管理をするため、国際会計基準に従った公会計制度を導入することが急務だ。さらに、2020年度については、右の2つの図のように、日本の国家予算は105兆円を超えそうだ) (1)日本の国家予算と公会計制度 1)国家予算総額とその決め方について *1-1・*1-2のように、2020年度の政府予算概算要求が出そろい、総額105兆円規模になるそうだ。多くのメディアや経済評論家は、総額30兆5千億円と支出額が最大の年金・医療を無駄遣い扱いしているが、本当は支出の内訳を見なければ、そのうちのどれが無駄で本当に必要なのかを判断することはできない。そして、これは民間では当然やっていることなのである。 また、国債費の支払いも借金を返済している部分と利子を支払っている部分がごっちゃになっているため、これによっては財政状態がよくなったのか悪くなったのかさえ判断できない。しかし、現在なら、借り換えして利子の支払を限りなく0に近づけることができる筈で、これも民間企業なら当然やっていることだ。 このように国の財政状態も歳出の効果も不明になる理由は、国が現金主義に基づく単式簿記を使っており(小使い帳方式)、発生主義に基づいた複式簿記によるコストセンター毎の会計(民間はすべてこちら)を行っていないからだ。そして、予算と言えば集団毎の分捕り合戦になるが、単に総額が大きいだけで「社会保障費が無駄遣いの根源だ」などと言うのは間違っており、私は単なる景気対策の支出こそが効果の薄い無駄遣いだと思う。 さらに、国の歳入も消費税を別枠にする国は他に無いし、消費税を上げて生産性の低い景気対策目的の支出を行っていては、いつまでたっても国全体の生産性が上がらない上、国の収支や財政状態も改善しない。私は、既に先進国となり、世界に先駆けて高齢化しつつある日本で最も効果的な成長戦略は、消費税を廃止又は低減させ、年金も減らさずに民間の可処分所得を増やし、市場で本当に必要とされ選ばれる製品やサービスに力を入れることだと考える。何故なら、これらは、後に他国でも必要とされ喜ばれるものだからだ。 そのため、消費税を増税して景気対策に支出するのは、①消費税増税が自己目的化している ②景気対策と称して選挙に有利な支出を増やしている ように見える。 2)農林水産業の補助金について 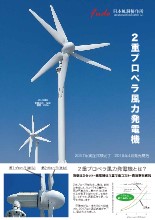  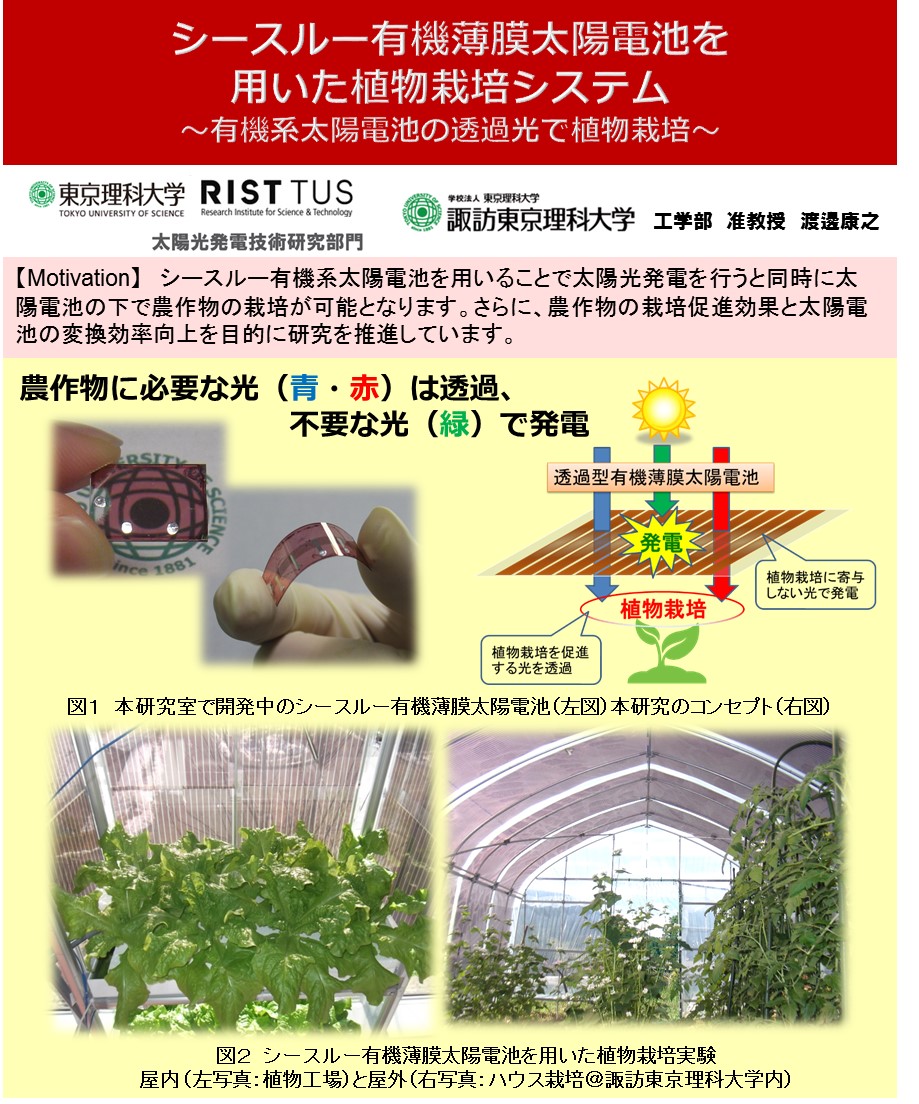  (図の説明:1番左の図は改良型風力発電機で、2番目の図はハウスに設置した太陽光発電機だ。また、右から2番目の図のように、植物の生育に必要な青と赤の光を通し、不要な緑の光で発電するシースルー型太陽光発電機もできた。一番右の図のように、薄膜型太陽光発電機の応用分野は農業を含めて広い) 私も、*1-3に書かれているとおり、食料・農業・農村基本計画は、食料自給率向上を重視するとともに、農林水産業は地域の重要な産業であるため地域政策もあわせて考えるべきだと思う。そして、今までそうなっていなかった理由は、農水省等の中央省庁で政策を考えている官僚の多くが都会育ちで、地方の事情に無関心だからだろう。 そして、前に書いたとおり、人口減少と高齢化によって日本の食料自給率は向上するのが当然であり、世界の人口増加を考えれば日本の食料自給率を向上させておくことは必須で、それと同時に、高齢化・共働き化が加工食品のニーズを高めると考える。 また、生産基盤の再建や担い手不足等も課題だが、これらは、農林水産業が儲かる魅力的な職業になれば解決する。しかし、国は真っ赤な赤字であるため、再エネを農林水産業の副収入として所得を得つつ地域の金が外部流出しないようにしたり、農林水産業をスマート化したり、外国人労働者を入れたりなど、生産性向上に資する方向で補助金をつけるのがよいと思う。 なお、中山間地域等は、穀類生産には条件が不利でも他の作物でも不利とは限らない。そのため、TPPやEUとのEPAに対抗するには、徹底した適地適作と経営合理化の追及が必要だ。 3)本当に必要な防衛費はどこまでか ← 予算委員会でチェックすべき *1-2に、防衛省の要求も過去最高額を塗り替えたと書かれており、*1-4には、来年度予算の防衛省概算要求額は過去最大の5兆3223億円で、米国からの高額な兵器の購入が総額を押し上げたと書かれている。私も、TPPレベルのFTA妥結の見返りや日米同盟の見返りに不要な物まで高い価格で買わされているのではないかと思う。 そのため、国会の予算委員会では、防衛省の概算要求額の内訳をチェックし、憲法で定める自衛のための必要最小限度の実力を保持するのに必要十分かどうかを確認する必要があり、それまでに正確な前年度実績と次年度の予算案ができていなければならない。そして、これは会計期間・会計制度・国会の審議日程を少し変更すれば可能であり、民間企業は(海外に多くの子会社や支店があっても)期末から2カ月後に開催される株主総会で、これをやっているのである。 (2)鉄道の高架化と駅ビルの建設は、新しい街づくりを進めやすくするとともに、生産性向上に資する投資である *2-1・*2-2のように、神奈川県で京急の電車とトラックの衝突事故が起きたが、事故現場は「開かずの踏切」で、このような踏切は都市部に多く、踏み切りを渡るために長時間待たなければならない。また、道路も狭いため、渋滞を招き、大型車の運転には神業を要する。 そして、日本の都市には海外と比較してこのような踏切が多く、ストレスが多い上、生産性を低くしている。そのため、根本的な解決は、踏切を高架化して道路を拡幅し、駅ビルや駅近の踏切下に店舗や駐車場を作って時代にあった街づくりをすることだと思う。さらに、地方にも危険な踏切が多く、高架化して1階を道路の拡張に使ったらどうかと思う。 しかし、これらを行うには国や地方自治体は予算を要するが、日本の問題は、工事費が高いだけでなく工事に時間がかかりすぎ、他国なら3年ですむ重要な街づくりが30年かかってもできないという深刻な状況になっていることである。 (3)災害復興と防災投資 1)佐賀豪雨について 佐賀県をはじめとする北部九州地域で、*3-1-1・*3-1-2のように、記録的な大雨による浸水が起こった。近年は、1時間に100ミリを超す大雨が多く、それを聞いても驚かなくなったが、大町町で佐賀鉄工所大町工場から約5万リットルの油が流出したのは、周辺住民にも農業にも痛手だった。 佐賀鉄工所大町工場からの油の流出は約30年前にも発生し、油をためる油槽がある建物を数十センチかさ上げしたり、建物に高さ3.5メートルの重量シャッター3台を設置したりして対策はとっていたそうだが、その「想定」を超えるレベルの浸水だったとしている。しかし、想定にはゆとりを持ち、厳重な防護をしなければ意味がない。 農地への油の流出被害は推計で約82万5千平方メートルに及び、農作物被害は収穫間近の水稲25.8ヘクタール・大豆15.3ヘクタールと、天災と人災が重なり大変なことになってしまった。 なお、*3-1-2のように、農業用水路から六角川に排水するポンプを稼働させていたが、流出した油が川から有明海に広がることを恐れた町の指示を受けてポンプを停止したため、水は行き場を失って地域をのみ込み、家屋も油まみれになった。私は、確かに六角川や有明海に油が広がるとさらに被害が大きくなるため、川に排水しなかったのはまずは正解だと思う。 「どげんしたら地域を守れたのか」については、海上保安庁に海上流出油事故や有害液体物質・危険物の流出事故の対応を専門に行う海上流出油事故対応チーム(https://www.jstage.jst.go.jp/article/safety/45/6/45_445/_pdf/-char/ja 参照)があり、ナホトカ号やダイヤモンドグレース号の油流出事故などの油流出事故への対応・処理にあたった部署であるため、ポンプの停止や水門の閉門と同時に、ここに油の除去を依頼すればよかったと思う。 このような場合、海上保安庁が「私たちならできる」と手を挙げず、国土交通省・農水省・総務省もすぐに気付いて救援依頼をしなかったのは、セクショナリズムが原因だろう。 なお、*3-1-3のように、佐賀県の豪雨被害で、武雄市・多久市・杵島郡大町町が「局地激甚災害」に指定され、復旧事業の国庫補助率が引き上げられることになったのはよかったが、市民の生活再建への直接的な助成ではなく、市町の復旧事業を支える意味合いが強いそうだ。 しかし、「前に向かって進める基盤ができた」のはよかったが、何度も同じことを起こさず、災害を事前に予防できる街を造るには、復旧ではなく新しい区割りによる復興が不可欠である。 2)胆振東部地震について 胆振東部地震をきっかけとして、*3-2-1のように、北海道内全域の停電が発生し、これは、電力需要の約半分を担っていた北電苫東厚真火力発電所の発電機3基が相次ぎ損壊して電力の需給バランスが崩れて全電源が停止したからだった。 私も、広大な地域で使われる電力を少数の大型電源に依存する態勢はもろく、エネルギー代金を海外に吸い取られるため、再エネによる分散発電で停電リスクを減らし、同時に送電ロスも減らすのが最終的な解だと思う。そうするためには、「マイクログリッド」を進め、太陽光、風力、バイオガスなど地域の特性に合った再エネを活用して地域経済を活性化しつつ、余った電力は他の地域に販売するための送電線を鉄道や道路に付随して設置するのがよいと考える。   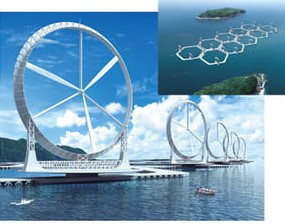  (図の説明:1番左の図は、牧場に設置された風力発電機、左から2番目の図は、山林に設置された風力発電機だ。また、右から2番目の図は、海の養殖施設に設置された風力発電機で、1番右の図が潮流発電機だ。どれも、野生生物を傷つけずに最大の出力を出す工夫が求められる) 3)宮古島台風について 台風13号が通過した宮古島市では、*3-2-2のように、市内の約8割を超える2万590戸が停電した。島も「マイクログリッド」の適地であるため、太陽光、風力、海流などの地域特性に合った再エネを利用して「マイクログリッド」を進め、経済を活性化するのがよいと思う。 4)東日本大震災について 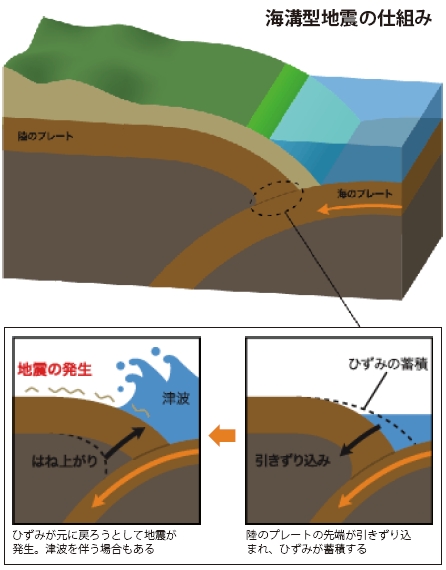 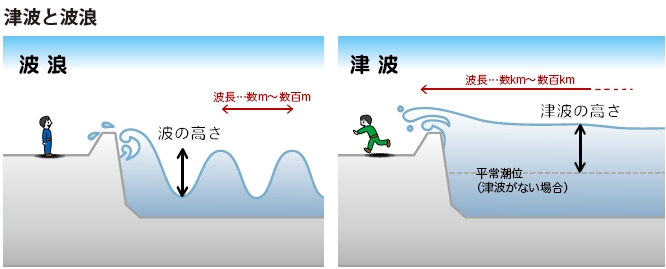   (図の説明:1番左と左から2番目の図は、津波が起こるメカニズムだ。津波は、普通の波と異なり、大きな水塊が迫ってくるので薄い防潮堤なら圧力で壊れる。右から2番目の図が、実際に堤防を乗り越えて岩手県田老町の漁協付近を襲った津波で、1番右の図は、岩手県宮古市の津波後の光景だ《http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/63/special_01.html》。この写真から、どういう構造の建物が地震・津波に堪えるかわかる) *1-2に、2020年度の特別会計で扱う東日本大震災復興予算の要求は2兆242億円だったと書かれている。もちろん、東日本大震災は、原発事故という人災がなくても未曾有の自然災害だったが、その対策としてとられた措置は、復興税を払って復興に協力してきた国民が納得できるものだったかどうかについて、今後のためにも事実を開示してもらいたい。 i) かさ上げ地は本当に安全か? 東日本大震災では、過去の津波記録が残る神社は津波が到達しない高台に作られていたため被害を免れることができた。そのため、一定周期で訪れる大震災や大津波に対応するためには、高台に宅地を作らなければ同じ被害に遭うことがわかっている。 従って、*3-3-1のうち、高台に新しく街を造って移転する防災集団移転が最も安全な防災方法であり、高台に移転した住民を孤立させてはいけない。何故なら、土地をかさ上げして整備する土地区画整理は、かさ上げ高が十分でなければ同じ被害にあうことになるが、かさ上げされた高さは2011年に襲った津波高よりも低く、予算の関係からか十分な高さのかさ上げができていないからである。 しかし、漁業者や水産関係の食品加工会社が、海の近くのかさ上げした土地で営業したいのはわかるし、合理的でもある。その場合は、前回と同じ津波が来ても退避できる高さの階を持つビルを建設することが必要条件になる。最もやってはならないことは、元どおりに復旧することだ。そして、十分に整備された安全な宅地に住民が少なければ、人口過多の都会や海外からの移住を促す政策を考えればよいだろう。 ii) 巨大防潮堤は有益か、有害か? *3-3-2の巨大防潮堤は、白砂の浜と松林の風景を遮る醜いコンクリートの壁で、かつ高さ5メートルでは役立たない。私は、海から遠ざかる選択肢がなければ、海の近くで低層階は舟形にして津波をかわし、大津波から退避するに十分な高層階のある建物を作ればよいと思う。 しかし、395kmの高さが最大15.5mの防潮堤では、東日本大震災級の大津波を防げない上、景観を損ね、陸と海が遮断される結果、陸からの栄養塩が海に流れなくなる。そのため、このような公共事業ありきの防潮堤を作ってはならない。 私も、人工の構造物は自然の猛威の前にはひとたまりもないため、人間は自然に対して謙虚であるべきだと思うし、津波を一時的にせき止めて進行を遅らせる程度の構築物に莫大な予算を使うのは止めてもらいたい。巨大防潮堤は三陸海岸の景色や生態系という資産をなくし、無用の長物に膨大な金をかけたという意味で次世代の人にとってもマイナスだと私は思うし、巨大防潮堤を作るという判断の正否を、のんびりと歴史に任せて、あの世で審判を受けられても困るのだ。 5)熊本地震について *3-4のように、来春の熊本県知事選に、現職の蒲島氏が「熊本地震からの復興の流れを、今ここで止めるわけにはいかない」として、4選を目指して立候補する意向を固めたそうだ。 知事としての適否は勤めた期数で決まるわけではなく、これまでの実績と次への期待で決まるものだ。そこで、私は「創造的復興」に賛成であるため、蒲島現知事を応援したい。震災で街づくりをやり直さなければならない状態になったことは、見方を変えれば新しい街づくりの推進力ともなるため、一皮むけた便利な空港・港湾・道路と心地よい住宅・田園造りを進めて欲しい。 (4)社会保障給付削減と消費税増税への圧力 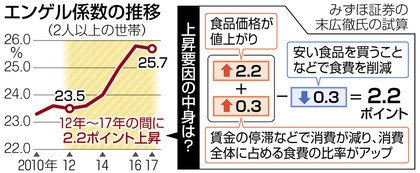   2018.3.19東京新聞 2018.11.15共同通信 (図の説明:左図のように、インフレ政策と消費税増税で物価が上がって実質年金額が減ったためエンゲル係数が上がり(=国民が貧乏になり)、悪影響を受けた人の多くは高齢者だ。また、中央の図のように、世界の中で日本は女性の活躍も進んでいない。そして、右図のように、支え手の増加には高齢者や女性のほか外国人労働者も考えられている) 1)3号被保険者制度は何のために作ったか? ← 1985年に初代男女雇用機会均等法ができたため、女性の社会進出を防ぐために専業主婦を優遇したのである 政府は、2015年に、*4-1のように、使い道が約30年間決まっていなかった専業主婦が国民年金に任意加入だった時代(1985年改正以前)に納めた保険料収入による年金積立金約1兆5500億円を、2015〜2024年度の公的年金給付に充てる政令を決定し、これを10年間にわたって給付財源として活用するとのことだった。 1985年の年金制度改正では、*4-1・*4-2のように、サラリーマンの夫を持つ専業主婦が「第3号被保険者」として保険料負担なしで国民年金に加入することになったのだが、それ以前は約7割の主婦が任意加入して保険料を納めており、積立金が7246億円、その後の約30年間の運用収益が8282億円あり、2014年3月末時点で総額1兆5528億円になっていたそうだ。 *4-2に、1985年改正で、「サラリーマンの専業主婦を国民年金制度に強制適用するため3号被保険者制度を創設し、これによって女性の年金権が確立した」と書かれているが、それまでは7割の主婦が任意加入して保険料を納め、働く女性は働く男性と同じく厚生年金・共済年金に強制加入して保険料を支払っていたので、専業主婦も強制加入にして保険料を納めさせるのがむしろ公平だった。また、全ての年金積立金を発生主義できちんと運用していれば、現在のような著しい年金積立金不足は起きなかった筈なのだ。 2)年金制度の「不都合な真実」は誰の責任(ここが重要)で起こったのか? 有権者の誰にとっても生活に直結する最も重要な政策は社会保障だが、*4-3は、年金について、「①年収500万~750万円未満の層は65歳までに3200万円必要」「②年収が1000万~1200万円未満の世帯の不足額は6550万円に上る」「③非正規雇用の比率が高い団塊ジュニア世代は、貧困高齢者になりそうな人が他世代より多い」 「④夫が働き、妻がずっと専業主婦の世帯を『標準』として将来の年金水準を見通すが、今の日本の世帯は共働きが主流」「⑤急務なのは現在の高齢者の年金給付を抑える『マクロ経済スライド』が発動しにくい仕組みを改めることだ」としている。 そのうち、①②は、年収が多い人ほど年金保険料の支払いも多いのに、年金支給額は働く世代全体の平均年収の50~60%に設定されるので、年収が多かった人は年金でカバーされる生活費の割合が低くなり、残りを貯蓄でカバーしなければならないために起こる現象だ。 また、パートやアルバイトなどの非正規雇用は戦前からあったものの、1990年代以降は新入社員にも非正規雇用が増え、これは労働基準法・男女雇用機会均等法等で護られない雇用形態であるため、③の問題が起きた。さらに、④のように、今でも、夫が働き妻はずっと専業主婦であり続ける世帯を「標準」と考えているのは、時代錯誤と言わざるを得ない。 そして、日経新聞はじめ多くのメディアや論客と言われる人々が、「高齢者の年金給付を抑えることが重要で、それに反対するのはポピュリズムだ」などと説いているが、これまで述べてきた通り、高齢者を犠牲にするよりも先に改善すべきことが山ほどあるのである。 3)社会保障の給付減と消費税増税しか思いつかないのは何故か? ← 国民をより豊かで幸福にしたいという発想がないからである *4-3は、「①団塊の世代が75歳以上になり始める2022年から高齢者医療費の伸びが加速し、会社員らの保険料負担はどんどん重くなる」「②超高額医薬品の使用は医療保険制度そのものを揺さぶる」「③介護の担い手不足は、2025年に55万人に上る」「④給付と負担のあり方に知恵を絞ることになる社会保障改革に『聖域』はないほうがいい」などと記載している。 そのうち①③④については、なるべく長く支え手の側において保険料収入と健康を維持し、②については、高額医薬品といっても医療保険での負担を加味して価格を高くしているものも少くないため、外国での販売価格と比較したり、新しい製品は自己負担での混合医療を認めて効くようなら速やかに同価格で医療保険からも負担するようにしたりし、④については、外国人労働者も活用する などの合理的な課題解決をすべきだ。 また、*4-4は、「⑤政府税調が中期的な税制の在り方をまとめる答申の骨子が判明し、現役世代を支え手とした社会保障制度や財政は少子高齢化で『深刻な課題』に直面している」「⑥制度維持には十分で安定的な税収基盤の確保が不可欠だ」「⑦10月の消費税率引き上げ後も何らかの増税策が必要」と記載している。 しかし、⑤については、少子高齢化するのは1980年代にはわかっていたのに対策も行わず、歳入に対してはきちんとした管理もせずに放漫経営をしてきたことに問題があるため、国に公会計制度を導入して歳出とその効果を正確に検証できるようにし、保険料は発生主義で積み立てるなどの改革をしなければ、負担増をしても放漫経営の規模が拡大するだけなのである。 さらに、⑥⑦については、「消費税は安定財源だからよい」という主張が多いが、景気が悪くても安定して入ってくるのでよいと言われる消費税は、景気調整のためのビルトインスタビライザー効果がないため、むしろ悪いのである。 4)支え手の拡大はすべき 厚労省は、*4-5のように、省内の全部局に「非正規」や「非正規労働者」という表現を国会答弁などで使わないよう求め、東京新聞がこのことを情報公開請求した後に撤回したそうだ。 本当は、労働基準法・男女雇用機会均等法等で護られない雇用形態である「非正規雇用労働」自体をなくさなければならないのであり、言葉を「有期雇用労働者」「派遣労働者」に変えれば問題が解決するわけではない。そして、労働基準法・男女雇用機会均等法等で護られない不利な雇用形態で働く人があってはならず、働き方の多様化は、年齢や性別にかかわらず正規労働の範囲内として、必要な条件を設定して行うべきなのである。 <国家予算と公会計制度> *1-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14159061.html?iref=comtop_shasetsu_02 (朝日新聞社説 2019年8月31日) 来年度の予算 ばらまき封じの徹底を 総額105兆円規模となる2020年度の政府予算の概算要求が出そろい、編成作業が本格的に始まる。年末に向けて削り込んでいくが、19年度に続き、100兆円規模の超大型予算が組まれる可能性が高い。年金や医療などの経費が30兆5千億円、借金の返済にあてる国債費が25兆円と、この二つで要求総額の半分を占める。税収を60兆円台と見込んでも、社会保障費だけで半分は使ってしまう。その他の政策経費をまかなう分だけでも、10兆円以上は新たな借金をしなければならない。厳しい懐事情をよそに、防衛費など、のきなみ増額の要求が並ぶ。消費税率が10%になって税収が増えるから、2年限りの消費税対策が別枠で認められるからと、絞り込みが甘くなっては困る。いまの暮らしに欠かせない政策や真の成長戦略に手厚く配分するのはもちろんだが、同時に将来世代も見据え、予算づくりに臨まねばならない。予算編成のルールとなる概算要求基準には、本格的な歳出改革に取り組み、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除すると書いている。19年度も同じ表現があったが、実行できたとは言い難い。今回こそ本気で取り組むべきだ。ところが各省の要求を見ると、不安が募る。防災事業や水産業の交付金、企業や文化事業を支援する補助金では、政策効果が不十分、経費がかかりすぎている、といった問題点がこれまでに政府内で指摘されていながら、今回も盛り込まれた事業がある。一つひとつの施策について、見直しの徹底が求められる。高齢化で増え続ける社会保障費も、聖域ではない。景気対策も、予算をふくらませる要因だ。確かに、米中の追加関税のかけあいや、英国の欧州連合(EU)からの離脱など、先行きには不透明感が漂う。10月の消費税増税後の消費の動きも、見極めなければならない。安倍首相は増税の影響について、19年度の予算で「十二分の対策を取っている」と強調する。世界経済の行方も踏まえた目配りは必要だが、増税対策や景気対策の名を借りたばらまきは、封じなければならない。どんな対策なら、より少ない費用で最大限の効果を引き出せるか、精査するべきだ。政権が掲げる25年度の財政健全化の目標は、新たな借金をできるだけ抑えなければ達成できない。次世代の負担を増やさぬよう、政策の費用対効果を見極め、ばらまき封じを徹底する。それが予算編成の課題だ。 *1-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201908/CK2019083102000157.html (東京新聞 2019年8月31日) 一般会計、105兆円規模 二〇二〇年度予算編成で財務省は三十日、各省庁からの概算要求を事実上締め切った。一般会計の要求総額は百五兆円規模に膨らみ、二年連続で過去最大を更新。年金・医療など社会保障を担う厚生労働省や防衛省の要求が最高額を塗り替え、災害対策費も全体を押し上げた。今年十月の消費税増税に伴う景気対策などは別枠で上積みするため要求には含んでおらず、査定で抑えても、十二月に組む予算案は一九年度の百一兆四千億円を超える可能性が高まった。安倍政権は景気後退を防ぐために歳出拡大を辞さない考えで、増税に踏み切っても財政健全化の進展は多難な情勢だ。要求総額の百兆円超えは六年連続。重点施策で上積みできる「特別枠」を各省庁が活用した結果、一九年度要求から約二兆円増えた。省庁別の最大は厚労省の三十二兆六千二百三十四億円。看板政策の就職氷河期世代支援に六百五十三億円を割いた。医療など社会保障の中核的な経費は、高齢化に連動した「自然増」を五千三百億円計上し、他省庁分を含む合計では三十三兆円程度に達した。防衛省は、高額装備品の取得により五兆三千二百二十三億円を計上。豪雨など災害対策を拡充する国土交通省は一九年度当初予算比18%増の七兆百一億円を求めた。他には子供が巻き込まれる事件・事故の防止、選手強化や警備といった東京五輪対策が目立った。自治体に配る地方交付税と特例交付金の合計は2・7%増の十六兆四千二百四十六億円。また借金返済に充てる国債費が全体の四分の一近くの二十四兆九千七百四十六億円に伸びている。特別会計で扱う東日本大震災復興予算の要求は二兆二百四十二億円だった。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p48667.html (日本農業新聞 2019年9月7日) 基本計画見直し着手 食料自給率向上が焦点 地域政策も鍵 農水省は6日、農政の中長期的な羅針盤となる食料・農業・農村基本計画の見直しに着手した。吉川貴盛農相が食料・農業・農村政策審議会(会長=高野克己・東京農業大学学長)に計画変更を諮問。来年3月に新たな食料自給率目標などを示した計画を閣議決定する。生産基盤を再建し、自給率向上の道筋をどう描くかが焦点。担い手不足にあえぐ中山間地域を維持させる地域政策を打ち出せるかも課題だ。同計画は食料・農業・農村基本法に基づき、5年ごとに見直す。同審議会の企画部会は今後、「食料の安定供給確保」「農業の持続的な発展」「農村の振興」などのテーマで年内に計6回の会合を開き、議論する。11月には現地調査や地方での意見交換会も開く予定だ。現行計画は、カロリーベース自給率を2025年に45%に引き上げる目標を掲げた。だが、18年は37%と前年比1ポイント低下し過去最低となった。新たな計画では、どのような水準の自給率目標を設定するかがポイント。自給率下落に歯止めをかけ、上向きに転じさせる施策の検討が求められる。吉川農相は諮問に当たり、農業生産所得の増加や輸出拡大などについて、農政改革によって「成果が着実に現れ始めている」と強調。一方、人口減少や高齢化などを課題に挙げた。地域政策については「地域資源を活用して仕事を作り、人を呼び込むことで活力を向上させる必要がある」と強調した。審議会と企画部会の委員を務めるJA全中の中家徹会長は、近年は農業産出額や生産農業所得が増加しているものの「生産基盤が強化されたかといえば決してそうではないのでないか」と提起。現行計画の徹底した検証が必要だと訴えた。会合では、自給率向上への具体策や次世代への経営継承などの人材確保の必要性を指摘する意見が相次いだ。農村政策の充実、先端技術を活用した「スマート農業」の普及も課題に挙げた。 [解説] 難局打開へ徹底議論を 国内農業は今、生産基盤の縮小が加速する中、大型通商協定が相次ぎ発効するという、かつてない難局にある。食料安全保障が大きく揺らぐ事態も招きかねない。これまで以上に実効性のある対策が求められる。政府が設定した見直し期限は来年3月。検討に費やすことができる期間は6カ月程度しかない。打開策を導き出すための徹底した議論ができるかどうかが問われている。生産基盤の弱体化に歯止めがかからず、自給率向上には、その再建が欠かせない。18年度の基幹的農業従事者は145万人。10年間で2割以上減った。耕地面積442万ヘクタールも減少が続く。特に、中山間地域を含む条件不利地にはてこ入れが必要だ。規模拡大など、産業政策に偏る安倍政権の農政を見直し、地域政策を充実させる時期に来ている。日本にとって過去最大の農産物の市場開放を受け入れた環太平洋連携協定(TPP)、欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)は、4月から2年目に突入した。日米貿易協定交渉も9月末に署名が見込まれる。現在講じている対策が足りているか検証が必要だ。2018年度のカロリーベース食料自給率は37%に落ち込み、目標との差はさらに開いた。目標未達成だった検証の徹底が必要だ。一層の下落を食い止めるためにも、新たな自給率目標の設定に当たっては、必要な施策をより踏み込んで示すべきだ。 *1-4:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-982455.html (琉球新報 2019年9月3日) <社説>防衛費要求過去最大 専守防衛逸脱チェックを 底が抜けたように歯止めがかからない。来年度予算に向けた防衛省の概算要求のことである。 要求額は過去最大の5兆3223億円。本年度当初予算比1・2%増で、2012年の第2次安倍政権発足以降7年連続の増額となった。米国からの高額な兵器の購入が総額を押し上げた。トランプ米大統領の要求に応え、不要な物まで買わされていないか。大いに疑問だ。政府は昨年策定した中期防衛力整備計画(中期防)で、19年度から5年間の防衛予算総額の目安を27兆4700億円と設定した。伸び率は従来の年平均0・8%から1%超に拡大し、中期防単位では14~18年度の約24兆7千億円から2兆円超の大幅増となった。一般会計全体の概算要求総額は過去最大を2年連続で更新する105兆円規模となった。高齢化に伴う社会保障費の増加に加え、この防衛費の膨張が要因となっている。国会で十分にチェックし、議論が尽くされた結果かどうか疑問だ。社会保障費を抑制し、消費税増税を10月に控える中、防衛費だけ特別扱いは許されない。青天井で増え続けている防衛予算に国民は注意を払うべきである。危惧するのは内容である。憲法で定める自衛のための必要最小限度の実力、いわゆる専守防衛を事実上、逸脱する様相を帯びているからだ。それを許してはいけない。新たな防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」や中期防で位置付けた護衛艦「いずも」の空母への改修費に31億円を計上した。同艦で運用する米国製の最新鋭ステルス戦闘機F35Bの取得費に846億円を要求する。政府は「多機能・多用途の護衛艦」と説明しているが、運用によっては攻撃型空母になりかねない。今回、宇宙分野の能力向上策として「宇宙作戦隊」の新設も明記した。米宇宙軍から指導教官を招き、自衛隊員を同軍に派遣するという。米中ロが加速させている宇宙分野の軍事利用に参画する構えだ。強い疑問を覚えるのは、米国から購入される高額な兵器だ。F35Bのほか、陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の発射装置取得費に103億円を盛り込んだ。秋田、山口県への配備計画を巡り、防衛省の調査にミスが相次いだことを踏まえて設置に伴う土地造成費や津波対策費の計上は見送った。しかし設置場所さえ決まっていないのに発射装置を購入するのは、地元合意よりも米国支援を優先したい姿勢の表れと言えよう。専門家からはミサイルの効果に疑問の声もある。南西諸島への陸自配備経費には237億円を計上した。尖閣有事などを想定した配備強化だが、中国を刺激し、お互いの軍拡につながる恐れがある。大切なのは、軍備に巨額の血税を投じることではなく、外交努力で紛争の火種を除去することだ。 <鉄道の高架化は、生産性向上策で街づくり投資である> *2-1:https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/keikyu-railway-accident/ (日経新聞 2019.9.5) 京急事故、踏切の危険性を探る 5日午前、京浜急行電鉄の神奈川新町ー仲木戸駅間(横浜市)で電車とトラックの衝突事故が起きました。事故現場になったのは、国土交通省が安全対策を主導してきた「開かずの踏切」の一つでした。通常の踏切に比べ、約4倍もの事故が起きるという首都圏鉄道網の鬼門です。衝突時、トラックは遮断機の間にいたとみられ、神奈川県警などが詳しい事故原因を調べています。事故現場は横浜市神奈川区の京浜急行電鉄「神奈川新町第1踏切道」です。踏切は神奈川新町駅と仲木戸駅の間にあり、神奈川新町駅のすぐ近く。周辺には商店や企業の事務所、工場、住宅などがあります。京急の線路には、並行してJRの線路や国道が走っています。 ●開かずの踏切の定義 国土交通省は40分以上の待ち時間がある踏切を開かずの踏切とみなし、2016年に全国532カ所を指定しています。事故が起きた「神奈川新町第1踏切道」もそのひとつ。ピークで48分もの待ち時間がある「緊急に対策の検討が必要な踏切」でした。カラー舗装で車道と歩道を分けて事故防止に配慮はしていましたが、立体交差などの対策は打てていませんでした。「交通量が少ない踏切のため優先度は低かった」(京急)としています。 ●開かずの踏切データ(開かずの踏切は全国532カ所のうち、7割の371カ所が首都圏に集中) 国土交通省は2016年6月に「緊急に対策の検討が必要な踏切」として全国の1479カ所を指定しました。このうち、長時間遮断機の降りた状態が続く「開かずの踏切」は全国で532あり、7割にあたる371カ所は首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に集中しています。最多は東京都の245で、今回事故の起きた神奈川県が73で続きます。一方、関西圏は130カ所とそれほど多くありません。 全国的にみて、交通の集中する首都圏は踏切事故のリスクにさらされやすいといえます。 ●踏切の安全対策 踏切の安全対策には莫大な費用がかかります。線路と道路を分離する立体交差化には1カ所だけでも億単位の工事費が必要で、鉄道会社には負担が重くのし掛かります。そこで国土交通省などが「当面の対策」と位置づけるのが、自動車道と歩道を見分けやすくするカラー舗装です。100万円程度で済むため、多くの踏切で採用されています。ただ、開かずの踏切などで起こる事故防止の観点からは、抜本的解決になっていないのは言うまでもありません。 ●全国の踏切事故件数 ●これまでの主な踏切事故 ①1989/1/29 秩父鉄道 秩父線 西羽生駅〜新郷駅間、踏切道に進入してきた自動車に列車が衝突して脱線 ②1990/1/7 JR北海道 室蘭線 白老駅〜社台駅間、踏切道に進入してきた自動車に列車が衝突 ③1991/6/25 JR西日本 福知山線 丹後竹田駅〜福知山駅間、踏切道の高さ制限用固定ビームに荷台のパワーショベルが接触して踏切道内に停止していたトラックに列車が衝突 ④1991/10/11 阪急電鉄 京都線 正雀駅〜南茨木駅間、踏切道に進入してきた自動車に列車が衝突して脱線 ⑤1992/9/14 JR東日本 成田線 久住駅〜滑河駅間、踏切道に進入してきた自動車に列車が衝突して脱線 ⑥2007/3/1 JR北海道 石北線 美幌駅〜緋牛内駅間、踏切道に進入した大型トレーラーに列車が衝突し脱線 内閣府の交通安全白書によると、踏切事故の件数はこの20年で半減しました。2018年の事故件数は247件と、500件近かった2000年前後からは大きく減りました。国土交通省が鉄道各社に対して踏切の安全対策を求めてきた成果が出ているといえます。踏切に関連する重大事故は51人が負傷した2007年のJR北海道の事故以来、起こっていませんでした。今回の事故は比較的乗客の少ないお昼の時間帯で起こりましたが、通勤や帰宅の時間帯などに重なっていた場合にはより大きな影響が出ていた可能性があります。これまでの踏切の安全対策だけでは十分だったとは言えず、対策の見直しが必要になりそうです。 ●主な鉄道各社の開かずの踏切数 2016年6月時点で鉄道各社の開かずの踏切の数を調べると、京浜急行電鉄は7カ所と多くはありません。上位を見ると、西武鉄道が81で最多で、東日本旅客鉄道(JR東日本)が76で続きます。各社とも安全対策を施していますが、踏切がある限りは事故のリスクは残ります。 ●海外と比べて日本の都市部は踏切が多い(東京23区はパリの90倍) 海外と比較すると、日本の都市部は踏切の多さが目立ちます。例えば、フランスのパリは周辺3県を含めて踏切は7カ所しかありません。東京都は23区だけでパリの90倍の踏切があります。その他の主要都市と比べても多く、日本の鉄道に特有の問題と言えそうです。 *2-2:https://digital.asahi.com/articles/ASM967WK4M96UTIL064.html?iref=comtop_8_01 (朝日新聞 2019年9月7日) 京急事故、列車なぜ衝突 異常時に踏切前で止まれる設計 大型トラックとの衝突・脱線事故から2日ぶりに、京急本線が7日午後、全線で運転を再開した。踏切内で車が立ち往生するトラブルは、各地でしばしば起きている。今回の現場でも、立ち往生を想定した安全システムは整備されていた。それなのになぜ、ぶつかるまで列車は止まれなかったのか。5日昼前、横浜市神奈川区の神奈川新町駅に隣り合う踏切で、事故は起きた。京急の説明によると、トラックは警報機が鳴り始める前に踏切内に入り、立ち往生していた。現場の踏切には人や車などの障害物を検知する装置がある。装置は、警報機が鳴り出した時点で地上30センチ以上にある障害物をレーザーで検知。踏切から10メートル、130メートル、340メートルの地点に設けた3カ所の専用信号機が一斉に赤色に点滅して、運転士に異常を知らせる仕組みになっている。運転士は、踏切から少なくとも600メートル離れた地点でこの信号の点滅を確認できる。ここで非常ブレーキをかければ、最高速度の時速120キロで走っている快特列車でも、踏切の手前で止まれる設計だ。点滅を確認した場合、運転士は状況に応じて通常ブレーキか非常ブレーキをかける。途中で障害物を検知しなくなれば信号が消えるため、そのときは状況を確認しながら減速をやめて通常の運転に戻すという。事故当時、検知装置や信号は正常に作動したと京急は説明している。今回の運転士は京急の聞き取りに対し、「信号に気付いてブレーキをかけたが、間に合わなかった」と話しているという。運転士はどの時点でブレーキをかけたのか。京急は取材に「調査中」としており、国の運輸安全委員会や神奈川県警などが走行データを分析する。別の大手鉄道会社の元運転士によると、障害物検知装置が作動することは「しばしばある」という。「もともと運転中は赤信号に敏感になるが、検知装置の信号は複数の赤色灯が激しく点滅するため、かなり目立つ」と話す。事故を防ぐ仕組みは多様だ。障害物を検知した場合、自動でブレーキをかけるシステムを導入している鉄道会社もある。信号に応じて列車の速度を自動制御する「自動列車制御装置(ATC)」などの信号保安装置と、検知装置を連動させる仕組みだ。東急電鉄は、東横線や目黒線、大井町線などにこのシステムを導入。検知装置が作動した場合、踏切に接近してくる列車は自動的にブレーキがかかる。京王電鉄や小田急電鉄のほか、近鉄、東武東上線、JR京浜東北線も同様のシステムだ。西武鉄道は池袋線と新宿線の踏切のうち、見通しの悪い4カ所で、検知装置と自動ブレーキを連動させているという。ただ京急など、運転士が手動でブレーキをかける鉄道も多い。京急はその理由を「自動ブレーキで止まるようにすると、トンネル内や橋の上など、かえって乗客に危険が及ぶ場所に止まってしまうことも考えられる」と説明する。2017年9月には、小田急線の沿線であった火災現場に近い踏切で、消火活動のために非常ボタンが押され、自動ブレーキで現場の目の前に止まってしまった列車の屋根に火が燃え移った例もあった。今回の事故について、工学院大の高木亮教授(交通システム工学)は「システムの想定通りに障害物を検知できた事例だ」とし、「鉄道会社としては防がなければいけない事故だったと考えられる」と指摘する。「衝突事故を防ぐには、障害物を検知した時点で自動的にブレーキがかかるシステムの導入が必要だ。手動に任せて信号を見落とすのと比べれば、事故のリスクは小さくなる」 <災害復興と防災投資> *3-1-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/422825 (佐賀新聞 2019.9.5) <佐賀豪雨>鉄工所の油「想定超え」で流出 住民は「30年前と同じ」と憤り 記録的な大雨による浸水で、杵島郡大町町の佐賀鉄工所大町工場から約5万リットルの油が流出して1週間が過ぎた。県によると、工場や順天堂病院周辺では回収が進んでいるが、農地や宅地などでは油除去の見通しが立っていない。油流出は約30年前にも発生し、同社では建物のかさ上げなどの対策をとっていたが、今回はその「想定」を超えるレベルの浸水となり、被害が拡大した格好だ。「畳やタンスなど油が染みて処分せざるを得ない。思い出の写真もほとんど処分してしまうかも。言葉にならない」。周辺道路の冠水で一時孤立した順天堂病院の近くに住む岸川マサノさん(73)は肩を落とした。「油さえ来ていなければこんな状態になっていない。健康被害も心配」と今後への不安を吐露した。回収作業は、自衛隊や九州地方整備局、鉄工所社員らがオイルフェンスを六角川に5カ所設置したり、吸着マットを使って実施。油膜は六角川の六角橋から下流では確認されず、県は「有明海への油流出はない」「ノリ漁への影響はない」との見方を示している。県によると、油の流出範囲は大町工場から東と南東方向に約1キロに及んだ。農作物への被害は水稲25・8ヘクタール、大豆15・3ヘクタール。流出面積は推計で約82万5千平方メートルに及び、「国内でも類を見ない最大規模」と指摘する専門家もいる。大町工場では1990年7月の水害時に同様の油流出が発生。事故の反省から同社が講じた主な対策は、油をためる油槽がある建物の数十センチのかさ上げと建物への高さ3・5メートルの重量シャッター3台の設置だった。今回は、かさ上げした建物で最大60センチの浸水が発生するなど「想像を超える雨」(同社)だった。同社によると、油槽は八つで約10万リットルを保管。建物内で管理し、床下約3メートルに設置している。冷却し強度を高めるため、ベルトコンベヤーを使ってボルトを油槽に移動する。24時間稼働していて、油槽にふたはない。設備の構造上、密閉することは難しいという。浸水当時の8月28日は、午前4時半ごろに油槽がある建物の稼働を停止させたが、その30分後には油の流出を確認。浸水の勢いが激しく、午前5時半ごろには従業員は避難した。同社によると、三つの重量シャッターのうち、北東側と南西側のシャッターから水が入り込んだ。油槽に水が流れ、油が浮き上がる形であふれ出したという。今回の油流出を受け、杵藤地区広域市町村圏組合は、佐賀鉄工所大町工場の熱処理工場に対し、8月30日付で消防法に基づく使用停止命令を出した。「小学6年だった30年前も同じ被害にあった。反省を踏まえ打つ手があったのではないか。天災と人災が重なったと思う」。工場近くにある自宅に油が流れ込んだ野口必勝さん(42)は憤りが収まらない。同社では「新しい対策をとっていく必要がある」との考えを示す。同様の事業所にも今回のような事案が考えられることから、県工業連合会の吉村正会長は「近年は、いつ大きな災害が起きるかわからない。これを教訓に業界全体で対策を考えていきたい」と話した。 *3-1-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/540982/ (西日本新聞 2019/9/6) 排水ポンプ 苦悩の停止 佐賀・大町町の操作員 「油拡散防げ」町から指示 記録的な大雨に見舞われた佐賀県大町町に、水害から地域を守ろうともがいた町民がいた。町から排水機場の操作を委託されている牛島忠幸さん(62)は8月28日、農業用水路から六角川に排水するポンプを稼働させていたが、流出した油が川から有明海に広がることを恐れた町の指示を受けて停止。水は行き場を失い、地域をのみ込み、牛島さんの家屋も油にまみれた。「どげんしたら地域を守れたのか」。自問を続けている。牛島さんは周囲の冠水で孤立状態になった順天堂病院近くの下潟排水機場の向かいに暮らす。油混じりの水に漬かった自宅と会社事務所の片付けに追われる。「油でめちゃくちゃ。でも、大変そうな地域の人の姿を見るのがもっとつらい」。祖父の代から水門管理を担い、住民から「係さん」と呼ばれる。2000年に排水機場が開所し、父から「係さん」を継いだ。大雨が降れば、何時でも雨具を着て排水機場に向かう。あの日も、そうだった。しとしと雨が落ちる27日昼からポンプを動かした。夜通し排水機場の水位計に気を配った。強まる雨脚。28日午前6時、水位が4メートル近くに。2時間で2メートルも上がった。「排水が追い付かん。これまでと違う」。午前11時23分、携帯電話が鳴り、町の担当者が言った。「鉄工所の油が流れているのでストップしてくれ」。ポンプを止めれば住宅が水に漬かる。頭に浮かんだものの「町には逆らえん」。指示に従った。ただ、水位に応じて用水路から川に自然排水する水門は開けたままにした。既に水位は門の下部に達しており、水面に浮いた油は滞留すると考えた。わずかな望みを胸に家に戻った。ぐんぐん水位が上昇。黒い油水にのまれる一帯を、2階からただ見つめるしかなかった。ポンプは停止後に冠水し、故障。水門も国土交通省九州地方整備局職員の手で閉められていた。町は「油の拡散を防ぐには、この選択しかなかった」、九地整も「ポンプ車などで水位を下げる努力を続けた」と説明。ポンプ停止と閉門がどこまで増水に影響したか分からない。ただ、家が漬かった住民たちは「油拡散を防ぐために私たちが犠牲になったのか」と憤る。地域の暮らしを守るのか、油による広域被害を防ぐのか-。「係さん」として今も川と向き合う牛島さんの思いは晴れない。「国と町の判断が間違っていたとは思わん。でも、水門だけでも開けていれば、助かった家や畑もあったんじゃなかか」 *3-1-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/423970 (佐賀新聞 2019年9月7日) <佐賀豪雨>3市町局地激甚災害指定へ 武雄、多久、大町、局地激甚災害(局激) 山本順三防災担当相は6日の閣議後会見で、佐賀県の豪雨被害について激甚災害に指定する方針を明らかにした。地域を限定する「局地激甚災害(局激)」で、武雄、多久の2市と杵島郡大町町を指定する。国庫補助率を引き上げるなど市町への財政支援を手厚くし、復旧事業を加速させる。今後の被害額の調査によっては、別の市町も追加で指定される可能性がある。指定によって国庫補助率は1、2割かさ上げされる。農地などの災害復旧は3市町が対象で、公共土木関連では多久市と大町町、中小企業支援では武雄市と大町町が対象になる。市民の生活再建への直接的な助成ではなく、市町の復旧事業を支える意味合いが強い。過去5年間の自然災害で公共土木の復旧事業の補助率を平均すると、通常70%が指定後に83%に引き上げられている。農地は83・1%から96・0%になっている。激甚災害は、人的被害でなく経済的被害を基準に指定する。県市町が被害額を調査し、各省庁が査定する。地域を限定する「局激」の場合、市町の財政規模ごとに基準額が設定され、基準額を超えた時点で激甚災害指定の見込みが示される。内閣府は今回、被害額と市町ごとの基準額について「さまざまな数字が出て混乱する恐れがある」として明らかにしなかった。山本氏は会見で「被災地の復旧、復興を加速化させるため激甚災害に指定する見込みとなった」とした上で、「被害状況はまだ調査中のため、基準を満たす地域があれば追加して指定し、公表する」と述べた。指定される3市町以外が追加される可能性がある。菅義偉官房長官らに被災地支援を要望した後、都内で取材に応じた山口祥義知事は激甚指定の方針について「前に向かって進める基盤ができた」と話した。県によると、過去5年は西日本豪雨(2018年)や九州北部豪雨(17年)、熊本地震(16年)などで県内は毎年、激甚災害の指定を受けている。いずれも市町単位で指定する「局激」ではなく、地域を特定せずに災害そのものを指定する激甚災害(本激)だった。 *3-2-1:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/342364 (北海道新聞 2019/9/7) 全域停電1年 供給網の在り方再考を 胆振東部地震をきっかけとする道内の全域停電(ブラックアウト)が発生してから、きのうで1年がたった。地震発生時、道内の電力需要の約半分を担っていた北海道電力苫東厚真火力発電所の発電機3基が相次ぎ損壊。需給バランスがたちまち崩れ、全電源が停止する未曽有の事態となった。この1年間、北電による設備増強でブラックアウトが再発するリスクはかなり低減した。それでも、広大な北海道で使われる電力を少数の大型電源に依存する態勢のもろさが完全に解消されたとは言えまい。道民生活がまひした1年前の経験を教訓に、より強靱(きょうじん)で安定した電力供給の在り方を考えたい。北電は2月、液化天然ガス(LNG)を使用する石狩湾新港火発1号機の営業運転を始めた。発電容量57万キロワットは、稼働している北電の発電所としては苫東厚真4号機(70万キロワット)と2号機(60万キロワット)に次ぐ規模だ。3月には、北海道―本州間の送電線「北本連系線」の容量も1・5倍の90万キロワットに増強された。さらに今後、全国の電力会社が経費を分担して120万キロワットまで増やす計画となっている。新たな大型電源の稼働と本州からの緊急送電機能の強化によって、災害時に大規模停電が発生する可能性は1年前に比べて相当小さくなったことは間違いない。とはいえ、胆振東部地震をはじめとする過去の大規模災害は、電力会社にとって「想定外」の被害をもたらしてきたことも事実だ。もうブラックアウトは起きないと楽観視せず、官民が協力し、より進化した電力供給の仕組みを目指すべきであろう。その意味で、災害時に再生可能エネルギーを使って地域の電力を賄う「マイクログリッド」(小規模送電網)構築の試みが、道内各地で始まっていることを大いに評価したい。経済産業省資源エネルギー庁の支援事業の1次公募で採択された全国5件のうち3件を道内(釧路市、十勝管内上士幌町、石狩市)の取り組みが占めた。マイクログリッドは、大規模停電が発生した際、北電の電力系統から特定地域の配電網を切り離し、その中で地元の再生エネ電力を供給する仕組みを基本とする。太陽光、風力、バイオガスなど地域特性に合った再生エネを有効活用し、地方経済を活性化する一助にもなるのではないか。 *3-2-2:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-985282.html (琉球新報 2019年9月7日) 宮古島、停電なお1万1000戸 台風13号 今夜復旧見込み 非常に強い台風13号は6日、久米島、宮古島を暴風域に巻き込みながら北上し沖縄地方を通過した。市内の約8割を超える2万590戸が停電した宮古島市では、6日午後11時現在、1万1140戸が引き続き停電している。宮古島市は7日朝から城辺、上野、下地の各支所と池間島公民館に携帯電話などの充電ができるように発電機を設置する。行政サービスを求める市民に対して上野支所を除く各支所で対応する。沖縄気象台によると、台風は久米島と宮古島を暴風域に巻き込みながら北上し6日朝までに暴風域を抜けたが、台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気が不安定になっている。沖縄本島地方と先島諸島では7日にかけて雷雨や竜巻が発生しやすい状況が続いており、警戒が必要だ。沖縄電力によると、沖縄本島や八重山支店からの応援作業要員も停電の復旧作業に当たっており、7日夜に復旧見込みとしている。台風は6日午後9時45分現在、東シナ海にあり、時速35キロで北上している。8日午後9時には温帯低気圧に変わる見込み。宮古空港では5日午後0時22分に観測史上最大となる最大瞬間風速61・2メートルを記録。住宅の床下浸水が1件確認されたほか、宮古島市で30~70代の男女5人が、宜野湾市で80代女性が、それぞれ強風にあおられて転倒するなどして負傷した。 *3-3-1:https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0907/mai_190907_3527897284.html (毎日新聞 2019年9月7日) かさ上げ、高台移転1400ヘクタール 8%が空き地、利用未定 東日本大震災8年半 東日本大震災の被災者向けに自治体が復興予算を投じ整備した宅地約1291ヘクタールのうち、東京ドーム約23個分にあたる約107ヘクタールが空き地や利用未定地となっている。毎日新聞が被災自治体に実施したアンケートで明らかになった。全体の約8%に過ぎないが、これ以外にも宅地に自宅を再建できないまま断念する可能性がある住民も一定数いるとみられる。かさ上げした市街地の広範な利用未定地で住民がわずかだったり、高台移転先では住民が孤立したりして、復興に向けた課題となっている。アンケートは7〜8月、宮城、岩手、福島の被災3県の30市町村に実施し、全自治体から回答を得た。対象は、内陸や土地をかさ上げして整備する土地区画整理(区画整理)▽高台に移転先を整備する防災集団移転(防集)▽漁業者が多く暮らす地区でかさ上げを図る漁業集落防災機能強化(漁集)——の3事業。防集と漁集は空き区画を、区画整理は利用予定が未定の区画を尋ねた。面積では陸前高田市は一部農地を含む37・3ヘクタールで最大。区画ベースでは、回答があった宅地約1万7700区画のうち、空き区画や利用未定なのは約12%の約2160区画。一方で地区全体のうち、半数以上の空きが生じているのは12地区、5区画以上は39地区あった。宮城県石巻市や南三陸町、福島県いわき市、岩手県釜石市や山田町で目立った。 *3-3-2:https://www.sankei.com/photo/story/news/171120/sty1711200002-n1.html (産経新聞 2017.11.20) 東日本大震災:賛否分かつ巨大な壁 海岸に横たわる防潮堤 海辺に立つ宿の窓からおかみの岩崎昭子さん(61)が海をのぞく。岩手県釜石市の根浜海岸。白砂の浜と松林で知られる。視界の一部をコンクリートの壁が遮る。東日本大震災の復興工事で高さ5メートルの防潮堤が築かれた。震災で津波を受け、1階が水没した。地区住民が高台移転に踏み切る中、現地再建の道を選んだ。海の幸と水平線から昇る日の出を売りにした宿だ。海から遠ざかる選択はなかった。海の近くに残るということは防潮堤を受け入れることを意味する。震災から7年に迫る今も巨大防潮堤を巡る議論がくすぶる。395キロ。岩手、宮城、福島の被災3県の防潮堤の総延長だ。高さは最大15.5メートル。ビルの4階に匹敵する。数十年から百数十年に1度の津波に耐える規格で建造された。「圧迫感がある」。「景観を損ねる」。「海と遮断される」。賛否の応酬は否定的な声が優勢に見える。被災地を離れるほど反対意見が台頭する印象を抱く。行政が住民合意を取るのに丁寧さを欠いて賛成派と反対派の対立を招いたり、公共事業の利権構造がむき出しになったりし、負のイメージが増幅された。 ●良かったのか悪かったのか 「奥尻と同じ轍(てつ)を踏むな」。反対派が合言葉にする。平成5年の北海道南西沖地震で津波に遭い、198人が命を落とした。町は復興事業で全長14キロ、高さ10メートル級の防潮堤で島を取り囲んだ。そのせいで景観が台無しになって観光客の足が遠のき、海の生態系も乱れて主力産業の漁業が衰退したとささやかれている。28年度の観光客は2万7千人。地震前年の半分に落ち込んだ。環境変化の影響を受けやすいといわれるアワビの漁獲高も8分の1に低落している。人口も4700から2750に減少。地域の陰りを示す数字には事欠かない。だが、防潮堤が島の弱体化を招いたかどうかの因果関係ははっきりしない。「観光客の減少も漁業不振も人口減も地震前から顕在化していた」。島民の多くは、島が細ったのは複合的な理由で防潮堤だけをスケープゴートにするのは見誤っていると語る。北海道の同じ離島で人口規模も近い礼文島も似た傾向で人口と観光客を減らしている。島の衰えは防潮堤の有無にかかわらず、地域の共通課題である実態を裏付ける。. ●判断の正否は歴史が裁く 岩手県の旧田老町(宮古市)に「万里の長城」の異名を持つ防潮堤がある。全長2.4キロ。高さ10メートル。X字の二重構造を持つ。昭和8年の昭和三陸津波で911人の死者を出し、44年かけて建設された。東日本大震災の津波は堤体を乗り越え、全体の5分の1が破壊された。人工の構造物は自然の猛威の前にひとたまりもなく、人間は自然に対してもっと謙虚であるべきだ。巨大防潮堤は自然を征服したと思い上がった人間をたしなめる文脈で語られる。しかし、防潮堤が役立たずだったかと言えばそうではない。津波を一時的にせき止め、進行を遅らせた。避難の時間稼ぎができて難を逃れた人は少なくない。町の犠牲者は181人。隣接市町村より少ない。昭和三陸津波の時と比べても5分の1に減っている。人を死なせないこと。防災の最大の目的だ。景観も被災地の活性化も大事。生き延びた人を立ち直らせることも。ただ、これらは最優先ではない。防潮堤の適否は次世代の人を犠牲にしないことに有益かどうかで判断されるべきだ。防潮堤は人命を守ることに一定の効果がある。景観や地域活性化を理由にした反対論も傾聴に値するけれども、1番手ではない。命には命で対抗しないと釣り合わない。巨大防潮堤を造ることによって住民に依存心が芽生え、危機意識が薄まってかえって死の危険性が高まるというのなら、対等の議論として成立する。岩崎さんは防潮堤に目をやる。災害対策基本法は「行政は災害から国民の生命、身体、財産を保護しなければならない」と定める。5千人を超す死者を生んだ昭和34年の伊勢湾台風の惨劇が行政の責務を明確にした。目の前のコンクリートの塊が住民意思を置き去りにした役所の独断専行の産物だとは思いたくない。曲がりなりにも住民との合作なのだ。東日本大震災の被災地は巨大防潮堤と共に歩む運命を選んだ。その判断の正否は歴史に裁かれる。千年に1度の天災が再び起き、将来世代の命を守れなかったら。「われわれの先祖は愚かだった」と言われるのだろう。あの世で批判を受ける覚悟はできている。 *3-4:https://digital.asahi.com/articles/ASM973603M97TLVB003.html (朝日新聞 2019年9月7日) 蒲島・熊本県知事が4選出馬へ「地震からの復興進める」 来春の熊本県知事選に、現職の蒲島郁夫氏(72)が4選を目指して立候補する意向を固めた。7日、朝日新聞の取材に「熊本地震からの復興の流れを今ここで止めるわけにはいかない」と語った。9日の県議会代表質問で正式に表明する。蒲島氏の任期満了は来年4月。3選を決めた直後の2016年4月に熊本地震が発生。被災者の住まい再建に優先的に取り組む一方、「創造的復興」を掲げ、空港や港湾、道路の整備を推し進めてきた。熊本県ではこれまで、4期以上を務めた知事はおらず、蒲島氏も16年の立候補の際には「3期目で実を結ぶ」として、仕上げの任期と定めてきた。ただ、今年8月28日の定例会見で「熊本地震の被災者の住まいの再建を最優先に、取り組まなければならない復興の課題がまだ多くある」と語っていた。7日は取材に対し「地震からの復興をスピード感を持って進める必要がある」と述べ、知事として引き続き復興に取り組んでいく姿勢を示した。知事選には、前熊本市長の幸山政史氏(54)が立候補の意向を表明している。 <社会保障について> *4-1:http://qbiz.jp/article/73996/1/ (西日本新聞 2015年11月2日) 年金積立金1.5兆円配分 保険料塩漬け30年 給付財源 一元化受け割合決定 政府は1日までに、使い道が約30年間決まらなかった年金積立金約1兆5500億円について、2015〜24年度の公的年金給付に充てるとの政令を決定した。積立金は、専業主婦が国民年金に任意加入だった時代に納めた保険料の収入。分立する各年金制度への配分方法が決められず塩漬け状態だった。会社員が加入する厚生年金に公務員らの共済年金を10月に一元化したのをきっかけに、配分割合が決まった。政令では、積立金の半分を厚生年金(統合後の共済年金を含む)に振り向け、残り半分を自営業者などの国民年金と厚生年金(同)の加入者数に応じて分けると規定。今後10年間、給付財源として活用する。給付額に影響はないが、年50兆円規模の年金財政に少しだけゆとりが生まれそうだ。1986年4月の法改正で、サラリーマンの夫を持つ専業主婦は「第3号被保険者」として保険料負担なしで国民年金に加入することになった。それ以前は国民皆年金が整った61年度から、約7割の主婦が任意で加入し保険料を納めていた。85年度末までに積み上がった保険料は7246億円。その後、約30年間に運用収益8282億円も加わり、2014年3月末時点で総額1兆5528億円と倍以上に膨らんでいた。政府はこれを24年度まで、毎年約1500億円ずつ給付費に回す。15年度は運用収益見込みを含め1590億円を計上した。各制度への配分は厚生年金に1480億円、国民年金に110億円。問題の積立金をめぐっては、任意で保険料を納めた主婦の夫の何割が会社員で何割が公務員なのか確定できず、制度間の配分ルールが政府内で長年まとまらなかった。だが、厚生年金と共済年金の一元化を機に所管各省の調整が進み、給付費への投入が実現した。厚生年金と共済年金の一元化 国家公務員と地方公務員、私立学校教職員向けの共済年金を廃止し、会社員の厚生年金に統合する「被用者年金一元化法」が2012年に成立し、ことし10月1日に施行された。官民格差の是正と規模拡大による財政安定化が目的。共済独自の上乗せ給付「職域加算」を廃止し、両年金で異なる保険料率を段階的にそろえる。公務員ら約440万人の加入で厚生年金の加入者は4000万人弱に増えた。 *4-2:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/04/s0419-3d.html (社会保障審議会年金部会 平成14年4月19日 抜粋) 公的年金制度の歩みとこれまでの主な制度改正 《制度の充実》 昭和40(1965)年 : 給付水準の改善、「1万円年金」の実現、厚生年金基金制度の創設 昭和41(1966)年 : 国民年金においても夫婦「1万円年金」の実現) 昭和44(1969)年 : 「2万円年金」の実現(標準的な厚生年金額2万円、国民年金も 夫婦2万円) 昭和48(1973)年 : 物価スライド制、賃金再評価の導入(「5万円年金」の実現) 《本格的な高齢社会の到来をにらんだ対応》 【昭和60(1985)年改正】 ○全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設 ○給付水準の適正化(成熟時に加入期間が40年に伸びることを想定して給付単価、 支給乗率を段階的に逓減) ○サラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦)の国民年金制度への強制適用(第3号 被保険者制度の創設)、これによる女性の年金権の確立 ○障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障) ○5人未満の法人事業所に対する厚生年金の適用拡大 ○女性に係る老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(昭和75(2000)年までに55歳 →60歳) 【平成元(1989)年改正】 ○完全自動物価スライド制の導入 ○学生の国民年金制度への強制加入 ○国民年金基金制度の創設(地域型国民年金基金の創設、職域型国民年金基金の 設立要件の緩和) ○被用者年金制度間の費用負担調整事業の創設(平成9年度に廃止) 【平成6年(1994)年改正】 ○60歳台前半の老齢厚生年金の見直し(定額部分の支給開始年齢を平成25(2013)年 までに段階的に60歳から65歳まで引上げ) ○在職老齢年金制度の改善(賃金の増加に応じて賃金と年金額の合計が増加する仕 組みへの変更)、失業給付との調整 ○賃金再評価の方式の変更(税・社会保険料の増加を除いた可処分所得の上昇率に 応じた再評価) ○遺族年金の改善(共働き世帯の増加に対応し妻の保険料拠出も年金額に反映できるよう、 夫婦それぞれの老齢厚生年金の2分の1に相当する額を併給する選択を認める) ○育児休業期間中の厚生年金の保険料(本人分)の免除 ○厚生年金に係る賞与等からの特別保険料(1%)の創設 【平成8(1996)年改正】 ○旧公共企業体3共済(JR、JT、NTT)の厚生年金への統合 【平成12年(2000)年改正】 ○老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢引上げ(平成37(2025)年までに段階的 に60歳から65歳まで引上げ) ○年金額の改定方式の変更(既裁定者の年金(65歳以降)は物価スライドのみで改定) ○厚生年金給付の適正化(報酬比例部分の5%適正化、ただし従前額は保障) ○60歳台後半の厚生年金の適用拡大(70歳未満まで拡大。65~69歳の在職者に対する 在職老齢年金制度の創設) ○総報酬制の導入(賞与等にも同率の保険料を賦課し、給付に反映。特別保険料は廃止) ○育児休業期間中の厚生年金の保険料(事業主負担分)の免除 ○国民年金の保険料に係る免除等の拡充(半額免除制度の創設、学生納付特例制度の創設) *4-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190724&ng=DGKKZO47676130T20C19A7MM8000 (日経新聞 2019.7.24) 日本の針路(2)年金だけでは描けぬ安心 不都合な真実 直視の時 有権者が参院選で最も重視する政策にあげたのは社会保障だった。参院選での与党の勝利は社会保障のために消費税率を10%に上げる公約が信任を得たことを意味する。しかし「人生100年時代」にどう備えるかという国民の不安に、与党が選挙戦できちんと向き合ったとはいえない。「鋭意作業している」。根本匠厚生労働相は公的年金の将来像を示す「財政検証」の公表時期を聞かれるとこうかわし続けた。老後資金が2000万円不足するとの金融庁の報告書で国会が紛糾するのを見た政府は検証を選挙後に延期し、与党も早期公表を求めなかった。だが「不都合な真実」を隠したところで老後の安心は確保できない。「50代で最も多い年収500万~750万円未満の層は65歳までに3200万円必要になる」。ニッセイ基礎研究所は65歳以降も生活を変えないことを前提に、こんな試算を出した。年収が1000万~1200万円未満の世帯の不足額は6550万円に上るという。他の民間調査機関も老後資金の独自試算を次々と公表した。「公的年金のほかに必要な金額は月額4万円」「非正規雇用の比率が高い団塊ジュニアの世代は、貧困高齢者になりかねない人が他の世代よりも多い」。最もデータを持つ国が実態を示し、与党がこれを直視して人生100年時代の安心を描く作業に力を注がなければ、国民の不安は払拭できない。5年に1度の公的年金の定期健診にあたる財政検証のあり方にも課題がある。財政検証は100年先まで人口と経済を見通して年金の水準や財政の状況を確認するものだが、過去の検証では、年金制度の課題をとらえきれていない懸念がある。14年の前回検証では夫が働き、妻がずっと専業主婦という世帯を「標準」として将来の年金水準を見通した。こうした世帯では、現役世代の平均手取り年収と比べた年金の給付水準(所得代替率)が約30年後に50%超になることを示し、04年の年金改革で約束した水準を確保できるとした。しかし、今の日本の世帯は共働きが主流だ。国民年金のみで年金額が少ない単身世帯も増えている。いまの年金制度がこうした世帯の生活をどこまで支えられるのか。今回の検証では世帯の多様化を踏まえ、実態を評価することが欠かせない。その上で急務なのは、現在の高齢者の年金給付を抑え、将来の年金の目減りを抑える「マクロ経済スライド」が発動しにくい仕組みを改めることだ。そして、私的年金など自助努力と一体で老後に備える国民を支援する制度を整えていくことが、国民の不安を払拭する第一歩になる。年金よりも遅れた医療・介護の改革も課題だ。団塊の世代が75歳以上になり始める22年から高齢者医療費の伸びは加速し、会社員らの保険料負担はどんどん重くなる。投薬1回で数千万円になるような超高額の医薬品の登場は医療保険制度そのものを揺さぶる。人材急募――。都内の介護施設には決まって求人の貼り紙がある。部屋が空いていても人手不足で入居できない特別養護老人ホームは珍しくない。25年に55万人に上る介護の担い手不足を解決する知恵が要る。安倍晋三首相は10%後の消費税について「10年くらいは上げる必要はない」と述べた。だが給付と負担のあり方にぎりぎりの知恵を絞ることになる社会保障の改革を前に「聖域」はないほうがいい。 *4-4:https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-982929.html (琉球新報 2019年9月3日) 社会保障維持へ安定税収を、税調 少子高齢化で「課題深刻」 政府税制調査会(首相の諮問機関)が中期的な税制の在り方について月内にまとめる答申の骨子が3日、判明した。現役世代を支え手とした社会保障制度や財政は少子高齢化で「深刻な課題」に直面しており、制度維持には「十分かつ安定的な税収基盤の確保が不可欠」だと指摘。10月の消費税率引き上げ後も何らかの増税策が必要との考えをにじませる。公的年金の受給水準の先細りを念頭に置き、老後の資産形成を後押しする環境整備なども促す。政府税調が中期答申を作るのは2012年の第2次安倍政権発足後、有識者主導で再始動してからは初めて。4日の総会で本格討議に入り、9月下旬に決定する方針。 *4-5:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019090190070550.html (東京新聞 2019年9月1日) 「非正規と言うな」通知撤回 本紙の情報公開請求後に 厚生労働省が省内の全部局に、根本匠厚労相の指示として「非正規」や「非正規労働者」という表現を国会答弁などで使わないよう求める趣旨の文書やメールを通知し、本紙が情報公開請求した後に撤回したことが分かった。同省担当者は撤回の理由を「不正確な内容が散見された」と説明。根本氏の関与はなかったとしている。厚労省雇用環境・均等局によると、文書は「『非正規雇用労働者』の呼称について(周知)」という件名で四月十五~十六日に省内に通知。当面の国会答弁などの対応では、原則として「有期雇用労働者」「派遣労働者」などの呼称を用いるとした。「非正規雇用労働者」の呼称も認めるが、「非正規」のみや「非正規労働者」という表現は「用いないよう留意すること」と注意を促している。各部局に送信したメールには、同じ文書を添付した上で「『非正規雇用』のネーミングについては、(中略)ネガティブなイメージがあるとの大臣(根本氏)の御指摘があったことも踏まえ、当局で検討した」と記載され、今回の対応が根本氏の意向であることがうかがえる。「大臣了」と、根本氏の了承を意味する表現も明記されていた。「非正規」の用語に関しては、六月十九日の野党の会合で、厚労省年金局課長が、根本氏から使わないよう求められていると説明。根本氏は同月二十一日の記者会見で「指示した事実はない」と課長の発言を否定した。その上で、働き方の多様化に関し「単に正規、非正規という切り分け方だけでいいのか、それぞれの課題に応じた施策を講じるべきではないかという議論をした記憶がある」と話していた。本紙は七月十二日付で文書やメールを情報公開請求した。雇用環境・均等局は同月下旬に文書やメールの撤回を決めたとしている。撤回決定後の八月九日付で開示を決定した。堀井奈津子同局総務課長は撤回の理由について、文書に単純な表記ミスがあったことを指摘。根本氏の意向に触れたメールについては本紙の情報公開請求後に送信の事実や内容を知ったとして「チェックが行き届かなかった」と釈明した。文書については「大臣に見せていないし、省内に周知するとも伝えていない。文書作成に関して大臣の指示も了承もなかった」と説明。メールにある「大臣の御指摘」や「大臣了」についても、メールを作成した職員の勘違いとしている。 ◆格差象徴に政府ピリピリ 正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の解消は、安倍政権の重要政策になっている。安倍晋三首相自身も「非正規という言葉をこの国から一掃する」と強調してきた。厚生労働省が「非正規」との表現を使わないことを文書やメールで省内に通知したのは、それだけ表現に神経質になっていたためとみられる。総務省の労働力調査(詳細集計)によると、役員を除く雇用者に占める非正規労働者は、第二次安倍政権発足当初の二〇一三年で年平均約千九百十万人(36・7%)だったが、一八年には約二千百二十万人(37・9%)に増加した。非正規労働者は、正社員に比べて賃金や社会保障などの面で待遇が悪く、格差拡大や貧困の問題と結び付いている。企業には都合の良い「雇用の調整弁」とされ、否定的な意味合いで受け止められることが多い。労働問題に詳しい法政大の上西充子教授は、厚労省の文書について「非正規という言葉だけをなくしてしまえ、という取り組みに映る。正社員になれず社会的に不遇な立場にある非正規労働者を巡る問題の矮小(わいしょう)化につながりかねない」と指摘。「問題と向き合うなら、逆に非正規をちゃんと社会的に位置付けないといけない」と訴える。 <台風15号による停電と送電に関するセキュリティー> PS(2019年9月12、13日追加):*5-1・*5-2に、2019年9月8日に関東を直撃した台風15号の影響で、「①千葉県は9月12日午前零時現在でも、約39万2千戸が停電」「②停電で浄水施設も稼働できず、2万戸が断水」「③交差点の信号機も殆ど作動せず」「④携帯電話も不通」「⑤停電で給油にも時間がかかる」「⑥クリニックも停電」「⑦復旧に1週間はかからないが、全面復旧は13日以降」「⑧気温が30度を超え、熱中症とみられる症状で午後4時までに48人が搬送された」「⑨倒れた鉄塔の送電網が断たれただけで約10万戸が停電した」「⑩東電は他電力の支援も含め1万人以上を投入して復旧作業に当たっているが、鉄塔や電柱が倒れ電線の切断箇所が多い」「⑪南房総地域では現場に行き着けない場所もある」などが書かれている。 このうちの①②③④⑤⑥⑧⑨は、生命に関わるインフラを、たった1系統の脆弱な電力ネットワークに頼って予備電源を準備していなかったセキュリティーの甘さにも問題がある。つまり、ここは地震・津波などの大災害も予想される地域なので、送電網を二重にしたり、自家発電装置を持って分散発電したりしておく必要があるのだ。また、⑦⑩⑪は、壊れた個所を自動的に知らせる装置がついていない電力会社の機器の古さにも問題があり、作業している人数が多い割には進捗が遅いように見える。 酷暑の中で停電・断水にあっておられる方々には心からお見舞い申し上げるが、風力も太陽光も豊富な房総半島なら、今後は再エネ等の地域資源を使った分散発電を進めたらどうかと思う。そして、*5-5のように、政府は地熱発電の普及に向けて開発段階の支援制度を拡充するそうだが、房総半島は温泉が多く地熱資源も豊富であることが既にわかっている。 また、*5-3のように、大規模農業団地計画が埼玉県羽生市で動き出し、全体計画24haのうち9.5haに進出する3社が決定したそうだ。転作による適地適作や農業用ハウスへの薄膜型太陽光発電設備の設置、農地への風力発電設備の設置などで高収益を上げられれば、進出したい企業はさらに増えるだろう。 なお、2019年9月13日、朝日新聞が、*5-4のように、「⑫東電は復旧を急がねばならない」「⑬房総半島の山間部などで倒木の多さに手間取った」「⑭福島第一原発の事故で経営が苦しい東電は、送配電部門の投資を抑えてきた」「⑮長期的には電線の地中化が有効な対策で、国も電力会社も無電柱化に力を入れる時だ」と記載しているが、⑫は当然のこととして、⑬については、倒木や停電の存在は昼と夜に上空(宇宙も含む)から写真をとればすぐわかるため、自衛隊か米軍に頼めば早かったのにと思う。さらに、⑮については、地方自治体が国の支援を受けて、電気、電話、水道、ガス、光ファイバー等のライフラインを一緒に道路や鉄道などの地下に埋設する共同溝を作り、電力会社も共同溝を利用するのが電力自由化・発送電分離の時代にふさわしい。ここで、「共同溝は、1kmあたり○億円かかるから電柱にしよう」などと言うのは、(理由を長くは書かないが)日本独特の欠点だ。そうなると、発送電分離を徹底しやすく、⑭の問題は比較的安価に解決することができ、無駄な景気対策をせずに生産性を上げながら必要な事業を行うことが可能である。 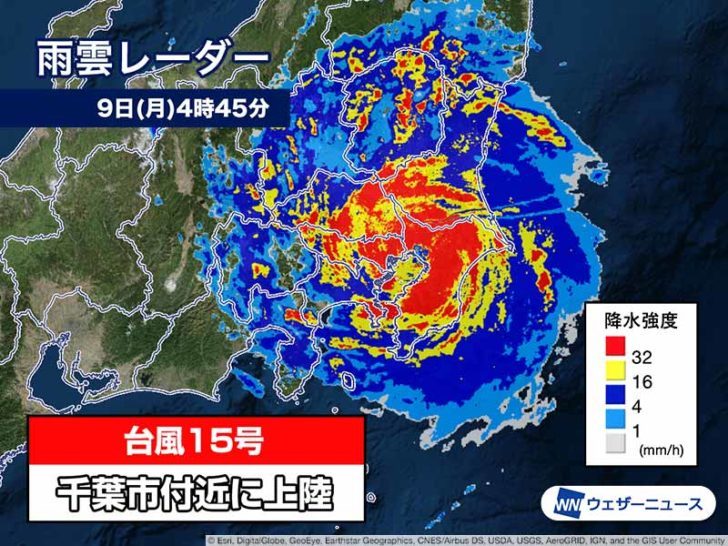 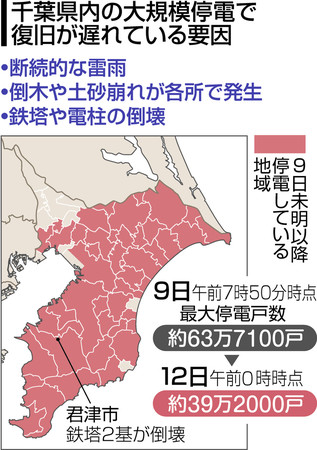    2019.9.9WN 2019.9.12東京新聞 2019.9.10朝日新聞 2019.9.10Abema (図の説明:比較的狭い範囲に強風を吹かせた1番左の台風15号の影響で、中央の2つの図のように、送電線の鉄塔や電柱が倒れ、左から2番目の図のように、千葉県内で大規模な停電が広がった。また、右図のように、農業用ハウスも倒壊している) *5-1:https://digital.asahi.com/articles/ASM9C5QL3M9CUTIL06F.html (朝日新聞 2019年9月11日) 動かぬ信号、イオンに殺到、給油制限…停電続く千葉の今 台風15号の影響で、千葉県内では停電や通信障害が続く。停電で街の機能が失われた房総半島南部。開店した店やガソリンスタンドには長蛇の列ができていた。房総半島南端の千葉県館山市では11日も、交差点の信号機がほとんど作動していない。夜は暗闇のなか、車がライトの有無を確認して最徐行で通る。一方で昼は連日、30度を超える猛暑。冷蔵庫に閉じ込めていた冷気も消え、食品は異臭を放ち始めている。市内の飲食店やコンビニも大半が休業中で、開店した店に客が殺到。この日朝開店した同市八幡のイオン館山店では、カップ麺や電池を求める買い物客の列ができた。数十キロ離れた同県鴨川市の丸谷成三さん(76)は「停電で冷蔵庫が動かないのが痛い。一日も早く復旧してほしい」と訴えた。車への依存度が高い地域。館山市八幡の丸高石油は1台2千円を限度に、9、10日は約1千台ずつ、11日は早朝から約500台に給油した。だが、給油待ちの車列が数百メートルに伸びて交通を妨げたため、警察からの要請で販売を中止した。高橋浩二・取締役部長(46)は「ガソリンは用意できるが、人力で給油するのでスタッフが足りない」と声を落とす。隣の南房総市では携帯電話の不通が続く。携帯各社によると、停電で基地局が機能していないのが原因だ。携帯大手3社が急きょ、移動基地局車を南房総市役所に配備。11日、市役所の半径約100メートルの範囲で電波が入り、多くの市民がスマホを手に駆けつけた。農業の男性(44)は「取引先との連絡が取れず困っている。ネットもつながらないので、どこに何があるのかも分からない」と嘆いた。同市富浦町の「生方内科クリニック」は強風で看板が飛ばされ、手書きの紙で「診療中」と張り出していた。停電が続く中、生方英一院長(61)が懐中電灯を片手に診療している。11日午後、熱中症の症状で訪れた市内の男性を診察した。自宅の屋根を修復していた際、体調が悪くなり、足がけいれんし動けなくなったという。男性は生理食塩水の点滴を受けると「だいぶ良くなった。診療をやっていて本当によかった」と喜んだ。このほか、糖尿病の薬が切れた人など1日約10人が来院する。生方院長は「停電でまともな診療はできないけど、困っている人たちを見捨てて休むことなんてできない」と語った。今後も通常通りの時間で診療を続けるという。 *5-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019091202000162.html (東京新聞 2019年9月12日) 千葉の停電 全面復旧あす以降 台風15号による千葉県を中心とした大規模停電で、東京電力は十一日、全面復旧は十三日以降になると明らかにした。一週間はかからない見通し。千葉県では十二日午前零時現在、約三十九万二千戸が停電。船橋市などで新たに停電が発生した。断水も二万戸あり、市民生活への影響が長期化している。茨城、神奈川、静岡三県の停電は解消された。東電によると、今回の停電は台風によるものとしては戸数、期間とも同社で過去最大級。千葉市などを含む地域の復旧は十二日以降、成田市や木更津市などの地域が十三日以降になるという。千葉県では、十日に続き県内全域で気温が三〇度を超え、十一日は熱中症とみられる症状で午後四時までに四十八人が搬送された。断水が続いているのは君津市や南房総市など。県によると、停電により浄水施設などが稼働できなくなったのが原因とみられる。 ◇ 東電は当初、11日朝までに停電を約12万戸に減らす計画だった。他電力の支援も得て復旧作業に当たっているが、送電線をつなぐ鉄塔や電柱が倒れ、電線の切断箇所も多く、被害は東電の想定を大きく超えている。倒木や断続的な雷雨も復旧を長引かせている。房総半島南部の君津市の緑茂る丘の上で、鉄塔二基が根元から折れて横倒しになっている。高さは四十五メートルと五十七メートル。この鉄塔の送電網が断たれただけでも、約十万戸が停電した。電柱も南房総地域を中心に多数倒壊。東電パワーグリッドの金子禎則(よしのり)社長は十一日朝の会見で「過去に例のない風速、気圧で非常に多くの設備が被害を受けた。一つの現場で直す量が見込みより増えてしまった」と、硬い表情を見せた。作業には他電力も含め一万人以上を投入するが、南房総地域では現場に行き着けない場所も。君津市内では倒木や土砂崩れが二百五十カ所以上に及ぶ。断続的な雷雨も作業中断を余儀なくさせた。現場によっては一部設備の交換で済むという想定が外れ、損傷が確認された電線や電柱の交換が必要となったという。昨年九月の台風21号でも、関西全域で最大百六十八万戸が停電し、全面復旧には十六日を要した。十一日夕の東電の会見で、全面復旧の見通しを問われた技術部門の担当者は「一週間かかるとは思っていない」と歯切れが悪かった。復旧計画の見通しの甘さを報道陣から指摘され、「反省している」と述べた。停電復旧時には漏電が起き火災につながることもある。東電はアイロンやドライヤーなど電熱器具をコンセントから抜いておくことや、外出時はブレーカーを切るよう呼び掛けている。 *5-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190912&ng=DGKKZO49625090Q9A910C1L83000 (日経新聞 2019年9月12日) 「農業団地」企業が選ぶ理由 全国でも珍しい大規模農業団地計画が埼玉県羽生市で動き出した。全体計画24ヘクタールのうち先行する約9.5ヘクタールに進出する3社が決定。全都道府県に設けられた農地中間管理機構(農地バンク)を活用して農地を集積して企業に貸し出す。同様の取り組みは各地であるが行き詰まる例も多い。羽生ではなぜ順調なのか。群馬県との県境にある羽生市は東京から約60キロメートルでコメ作りが盛んだ。だが「後継者不足や耕作放棄地の増加が課題」(同市農政課)。そこで高収益農業を掲げ、農家の転作や市内外から農業への進出を促そうと、2018年3月に農業団地の構想を作成し、11月に公募を始めた。市が面積など企業の要望を聞いたうえで地権者と調整し、農地バンクが借り上げて貸し出す。農業団地は東北自動車道の羽生インターチェンジから車で5分と出荷や観光農園に有利だ。9.5ヘクタールに対して5件の応募があり、市への問い合わせは約40件あった。審査を経て進出が決まったのは、市内のスーパーと東京都内の農業資材メーカー、埼玉県内のハーブ農園の3社。いずれも20年の土地賃借契約を結ぶ。「これだけまとまった土地はめったにない」(進出企業の担当者)。羽生市役所には全国から視察も相次ぐ。農業問題に詳しいみずほ総合研究所の堀千珠主任研究員は「農業集積地の開発で最も重要なのは地権者との調整。知らない人や企業に貸すことに抵抗を感じる人は多い」と話す。また農地を相続した地権者が県外在住で連絡がつかないか、地権者が多すぎて調整がつかないことも多い。今回、農業団地全体の地権者は約80人。先行する9.5ヘクタールでは約35人で市内在住者が多いことが幸いした。しかも多くがすでに農地を貸した経験があり、貸すことに抵抗が少ないのもスムーズに運んだ理由だ。それでも「土地の利用方法を市が勝手に決めるな」と反発する人もおり、市の職員2人が説得に当たった。こういった農業団地開発では、企業などから進出の打診があってから農地を探し始める自治体もあるという。工業団地への誘致では考えにくい。「他地域では自治体の担当者と一緒に地権者まわりをしたこともある」(羽生に進出する企業)。こうした手間を企業に求めないことも企業が羽生を選んだ理由の一つだった。行政が求められることを的確に理解、遂行することが成功への第一歩のようだ。 *5-4:https://www.asahi.com/articles/DA3S14175820.html (朝日新聞社説 2019年9月13日) 停電の長期化 「想定外」ではすまない 命にかかわる事態である。政府は全力をあげて被災者を支援すべきだ。9日に上陸した台風15号による大規模停電で、千葉県を中心に深刻な影響が広がっている。当初、東京電力は11日中の復旧を目指すと発表したが、13日以降にずれ込んだ。厳しい暑さのなかで不便な生活が続き、熱中症の疑いによる死者も出た。停電にともなう断水なども起きている。東電は復旧を急がねばならない。停電は最大時で90万戸を超えた。東電管内で起きた台風によるものでは規模、期間とも過去最大級という。12日午後8時時点でも約29万戸が電気のない生活を余儀なくされている。台風が去った後も天候が不安定で、断続的な作業にならざるを得なかったうえ、房総半島の山間部などで倒木の多さに手間取ったというが、見通しが甘かったと批判されても仕方がない。きめ細かで、確実な情報発信の徹底が求められる。復旧後には、大規模停電の原因や、なぜ復旧作業に時間がかかったのかを、厳しく検証する必要がある。他の電力会社を含め、停電を起こさぬ努力だけでなく、よりスムーズに復旧できる態勢をつくるためだ。10万戸相当の停電につながった鉄塔2基の倒壊では、強度の想定を超える風が吹いた可能性がある。倒壊の状況を精査し、必要ならば「耐風性」の想定を見直さねばならない。福島第一原発の事故で経営が苦しい東電は、需要の伸び悩みもあり、送配電部門の投資を抑えてきた。電柱の交換や補強といった安全確保策に甘さがなかったかも、検証すべきだ。安倍首相は「復旧に全力を挙げる」と述べた。自治体からは電源車の継続的な手配や、さらなる給水支援を望む声が出ている。各省庁ができることを考え速やかに対応してほしい。心配なのはお年寄りや病人ら災害弱者だ。病院は非常用発電機で機能を維持しているが、燃料補給が欠かせない。介護施設の中には水洗トイレが使えず、職員が手動で流しているところもある。最優先でニーズをくみとり、支える必要がある。停電が解消しても、日常が戻るには時間がかかるだろう。強風で多くの屋根が損傷し、ブルーシートも相当いる。他の自治体や企業も支援の手をさしのべたい。昨年は北海道地震でブラックアウトが起き、台風21号でも関西でのべ約220万戸が停電した。長期的には電線の地中化が有効な対策である。コストはかかるが大規模停電の影響と復旧費用を考えれば、国も電力会社も無電柱化に力を入れる時だ。 *5-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190913&ng=DGKKZO49737160S9A910C1EE8000 (日経新聞 2019.9.13) 地熱開発 国が掘削調査 再エネ普及へ企業負担減 経済産業省は地熱発電の普及に向け、開発段階の支援制度を拡充する。これまで企業に任せていた有望地点を探す初期の掘削調査を、2020年度から国が石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)を通じて代行し、企業の負担を大幅に軽くする。リスクが大きい開発初期の調査を国が主導することで民間が積極的に参画できる環境をつくりたい考えだ。地熱開発は長期の官民の関与が必要だ。掘削して地下構造などをはかる「初期調査」に約5年、発電に必要な蒸気の噴出量をはかる「探査事業」などに約2年かかる。その後、事業化する判断をした後も、環境アセスメントや発電所の建設などに7年程度かかる。中でもリスクが大きいのが初期調査だ。地面に穴を開け、発電に適した地層の構造になっているか、企業が1回あたり数億円かけて入念に調べる必要がある。ただその結果、地層が発電に適していなければ失敗に終わる。調査はこれまでも国が費用の一部を補助していたが、企業側からは国がより関与すべきだとの声が多かった。JOGMECは初期調査のうち、地中に発電に不可欠な熱水や蒸気が十分に含まれているかの調査を代行する。期間は20年度から6年程度としたい考えで、企業が将来計画をたてやすくする。企業が掘削に慎重なのは、多方面との調整作業が難航しがちという事情もある。地熱に適しているとされる地域の多くは、国立公園や国定公園のなかにある。そこで掘削をしようとすると、近くの温泉などへの影響を懸念する地元自治体や、環境省、林野庁などとの難しい調整が必要になる。こうした調整を経産省やJOGMECが担うことで、開発に向けた調整がスムーズになる可能性がある。 <首都圏における災害とインフラ、人口密度など> PS(2019.9.14、15、16追加):*6-1のように、台風15号は千葉県で大規模停電を引き起こし、今後の対策として老朽インフラを新しいインフラに更新していくことに私も賛成だが、台風・豪雨だけでなく地震・津波が起こることも前提として街づくりは行う必要がある。 このような中、*6-2のように、日本の首都である東京は、大雨・台風の際には処理能力を超えるため下水処理されずに直接川に流された汚水が、お台場に到達して“トイレ臭”を発し、大腸菌の数も基準を超えるという不潔な状態であることが、先日の五輪テスト大会で明白になった。このように、古くて処理能力が不十分な下水道を使っているため東京の川はいつも汚いが、その汚水を入り江に張った膜で防御するという改善策を聞いた時にはさらに呆れて、オリンピックのお祭り騒ぎよりも、きちんとしたインフラ整備が先ではないかと思った。 今では東京に1300万人、東京・神奈川・埼玉・千葉の東京圏に3600万人(日本全体の人口の1/3)が住むようになり、下水道だけでなく上水道も質が悪かったり量が少なかったりして節水を強い、不潔な状態になっている。そして、地震・津波に襲われる危険がある東京で、さらにインフラを拡大をするのは金がかかりすぎる上、無駄遣いになるリスクもある。 そのため、私は、*6-3のように、国会議事堂やその関連施設などの主要な首都機能を安全な場所に移転(もしくは疎開)してはどうかと考える。移転する場所は、栃木県・福島県南部は原発事故の影響で適切でなくなり、岐阜・愛知地域や三重・畿央地域は既に人口が多いため、涼しくて地震・津波の心配がない長野県松本市付近にし、新しい国会議事堂は英国のように議論しやすい民主主義向きの設計にしてはどうかと思う次第だ。 一方で、*6-4の佐賀県三瀬地区のように、よい農産物を生産する重要な地域であるにもかかわらず、人口が少ないためバスの運行も採算が合いにくい地域もある。私は、将来、マイクロバスやジャンボタクシーも自動運転の電動車にすれば、さらにコストを減らして運行数を増やすことができると考える。 なお、敬老の日の2019年9月16日、徳島新聞が社説で、*6-5のように、「運転免許の返納が高齢者の生活の質の低下に繋がらないよう、『高齢者の足』の確保を」という記事を書いており、全くそのとおりだと思う。ただ、運転免許を返納しなければならないほど衰えてくると、自宅で家事(火や薬品を使う)をするのも心もとなくなるため、選択肢の1つとして、朝に迎えに来て、食事・風呂・運動・娯楽・文化活動を提供し、夕方に家に送り届ける宅老所を中心部に作ればよいと思う。ただし、8Kテレビで高齢者が若い頃に感動した映画を見ることができたり、多種の新聞・雑誌・本などが置いてあったり、書道・手芸・カラオケができたり、歩いて買い物や病院に行ったりなど、家にいるより便利で居心地が良い場所にしなければならない。 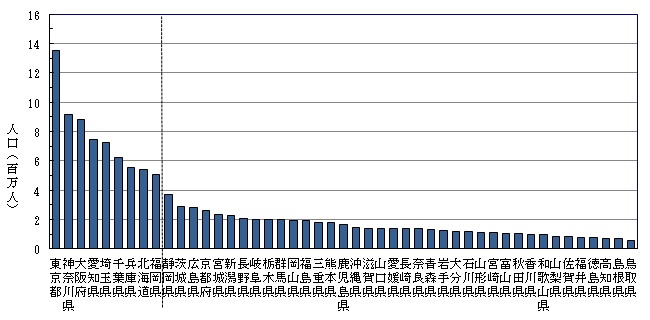  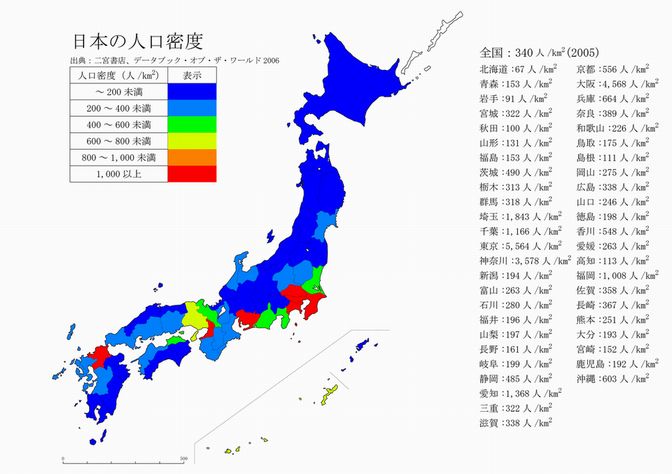 (図の説明:左の図は、人口の多い順に都道府県を並べたもので、中央の図は、上位と下位それぞれ10都道府県の人口・面積・人口密度を示したものだ。また、右の図は、日本地図に都道府県別の人口密度を示したもので、赤色の地域は人口密度が高い) *6-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190914&ng=DGKKZO49820850T10C19A9MM8000 (日経新聞 ) 老朽インフラ、日本の岐路に 、台風で停電、復旧あと2週間 送電網や道路橋、更新コスト重く 大規模停電を引き起こした台風15号は生活インフラが抱える災害リスクを浮き彫りにした。なお17万戸が停電し影響はライフラインに広がる。1970年代に整備が進んだ送電施設は更新時期が迫り老いるインフラは道路などにも共通する課題だ。国と地方を合わせた借金が1千兆円と財政が厳しく社会保障費も膨らむなか、巨額投資によりインフラをどこまで維持していくか、重い判断が迫られる。台風15号が首都圏を直撃した9日以降、千葉県南部を中心に停電が続く。東京電力パワーグリッドは13日夜、東京都内で記者会見し、「今後、2週間以内におおむね復旧見込み」と発表した。同社は当初、11日に全面復旧するとの見通しを発表していたが、会見で「過去の被害規模から過小な想定をしてしまった。複雑な難工事に直面している」と釈明した。房総半島の送電網は山林に張り巡らされており、倒木によって大規模に損傷しているという。台風による被害は広範囲に及び、停電の全面復旧は時間がかかる傾向にある。2018年に関西を襲った台風21号の被害は、全面復旧まで17日間を要した。停電はライフライン全体に影響を及ぼした。携帯電話の電波を飛ばす基地局が多くの場所で機能せず、スマートフォンの電源も確保できなくなったため、11年の東日本大震災の際には避難所や支援物資の情報共有で力を発揮したSNS(交流サイト)の効果も限定的なものになった。市役所などに設置された充電設備には電源を求める人で長蛇の列ができた。被害が広がった背景として、想定外の強風に加え、送電設備の老朽化も指摘されている。送電線の鉄塔は70年代に建てられたものが大部分を占める。倒壊し、10万戸の大規模停電につながった千葉県君津市の鉄塔は72年に完成したものだった。電力各社などでつくる電力広域的運営推進機関によると、15年度末の時点で約25万基ある送電鉄塔のうち、製造年が00年代のものは年約千基ペースなのに対し、70年代は年6千~8千基にのぼる。東京電力管内の鉄塔の平均使用年数は42年。設置場所や塗装などによって違いはあるが、老朽化は着実に進行している。広域機関は既存の設備を現在のペースで全て更新した場合、鉄塔で250年程度かかる計算としている。台風に有効とされるのが、電柱の地中化だ。だが、電柱は1キロメートル当たりの復旧費が2千万~3千万円で済むのに対し、地中化は同4億~5億円に上る。東京電力ホールディングスは東日本大震災の原発事故で経営危機に陥り、送電関連の設備投資を抑えることで収益を確保してきた。91年に送電や配電設備などに約9千億円を投じたが、15年に8割減の約2千億円まで減少。発送電分離など電力が自由化に進むなか、耐久性があると判断した設備は更新を先延ばしするなどして、できる限り投資を抑えているのが実情だ。インフラの老朽化は電力以外でも深刻だ。建設から50年以上が経過する施設の割合は18年3月時点で73万ある道路橋の25%、1万超のトンネルの20%、5千の港湾岸壁の17%に及ぶ。時間が経過すれば割合はさらに増える。33年には道路橋の6割超、トンネルでも4割が建設から50年を超える。国土交通相に就任した赤羽一嘉氏は、大規模自然災害について「発生のたびに100年に1度の規模だといわれるが、今後は毎年起きると思って対策を進める必要がある」と指摘する。国交省の推計では今後30年間で必要となる費用は最大で約195兆円に及ぶ。ただ、日本の財政状況は先進国で最悪だ。人口減少に備えて既存インフラの廃止や、住宅や商業施設を集約する「コンパクトシティー」も重要な選択肢だ。しかし名古屋大学の中村光教授は「住民の反発を恐れて自治体での議論はほとんど進んでいない」と警鐘を鳴らす。維持すべき施設を選別する方法論は専門家の間でも議論は深まっていないという。 *6-2:https://news.livedoor.com/article/detail/16921713/ (日刊ゲンダイ 2019年8月13日) 五輪テスト大会で選手から悲鳴 お台場の海“トイレ臭”を専門家が解説 1年後の東京五輪に向けて、水泳競技「オープンウオーター」のテスト大会が11日、東京・お台場海浜公園で開催されたが、参加選手から高水温や悪臭に対する不満の声が相次ぐ散々な結果だった。国際水連は競技実施の条件として会場の水温を16度以上31度以下と定めている。この日の水温は午前5時の時点で29・9度(競技中の水温はなぜか非公開)。そのため午前10時だった男子の開始時間を、女子とほぼ同じ午前7時に前倒しした。ロンドンとリオ五輪の日本女子代表の貴田裕美(コナミスポーツ)は「水温も気温も高く、日差しも強くて過酷だった。泳ぎながら熱中症になるんじゃないかという不安が拭えなかった」と悲鳴を上げた。ロンドン五輪金メダルのウサマ・メルーリ(チュニジア)も「今まで経験した中で最も水温が高く感じた」とヘトヘトだった。 ■「すぐに競技場所を変更すべき」 さらに、選手に酷だったのがニオイだ。約1時間泳いだ男性選手は「正直、くさいです。トイレみたいな臭いがする」と衝撃の証言をした。だが、お台場の海が“くさい”のは必然だという。元東京都衛生局職員で、環境・医事ジャーナリストの志村岳氏がこう言う。「お台場はゴミで埋め立てられた場所。海底のゴミが、海水を汚染しています。ただでさえ、隅田川などが運ぶ汚水が流れ込むうえ、大雨や台風の際は、下水の処理能力を超えた汚水が川に放出され、お台場に到達する。しかも、地形が入り組んでいるため、これらの汚水が外海に出て行かず、よどんでしまう。お台場は東京でもっとも泳いではいけない海なのです」。お台場はかつて、海水浴禁止だったが、2014年から港区が期間限定で海水浴場として開放。期間中、汚水の流入を防ぐ膜を設置して“泳げる海”にしている。今回のテスト大会でも、入り江口に約400メートルの膜を張った。苦情を受けて、本番では膜を3重に厚くするという。「焼け石に水です。例えば、いくら3重にしたところで、膜では、トイレ臭の原因と考えられるアンモニアの流入は防げません。都の職員も分かっているはずです。五輪開催1年前に問題が表面化したのに、小手先の対策でごまかせば、各国は黙っていないでしょう。すぐに、競技場所を変更すべきです」(志村岳氏)。東京五輪の暑さ対策で整備された「遮熱性舗装」は、空間気温がかえって上昇することが指摘されているが、今度は海水のトイレ臭。「くさいものにフタ」は許されない。 *6-3:https://www.excite.co.jp/news/article/B_chive_economics-politics-japanese-politics-capitaltransfer-candidate/ (エキサイト 2019年2月21日) 首都移転議論の候補地は? 首都移転は常に議論の俎上に載せられるテーマです。現在の首都である東京への一極集中が問題視されているためです。この首都はどこへ移転すべきと議論されているのでしょうか。 ●3つある 首都移転の候補地は大きくわけて3つあります。ひとつは栃木県や福島県南部のあたりです。東京から新幹線で1時間ほどでアクセスできることに加えて、夏場は比較的涼しい場所のため、候補地のひとつとされてきました。 ●岐阜、愛知地域 もうひとつが岐阜、愛知地域です。日本の3大都市と言える東京、名古屋、大坂において、中間点である名古屋の周辺に首都移転計画がありました。確かに日本のほぼ中央といえる場所にありますから、交通などにおいては便利かもしれません。さらに、東京と大阪の中間点といった位置づけにもなりますし、北陸方面からのアクセス回路も作ることができます。 ●三重、畿央地域 もうひとつの候補地が三重県や畿央と呼ばれる場所です。奈良県などを含むものでしょう。もともと平城京があり、史実の上でも日本の首都であったわけですから、原点回帰とも言えるかもしれません。さらに、リニア中央新幹線が名古屋から先の大坂まで通った場合には、名古屋と大坂の中間点くらいの場所に新たな首都が作られるといった可能性も考えられるでしょう。しかしながら、首都移転には莫大な費用がかかるため、実現に向けてはさまざまな問題点が山積みになっているというのが現状となっています。 *6-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/427543 (佐賀新聞 2019年9月15日) <昭和バス再編>代替にマイクロバス購入を 三瀬地区、運行案固まる 昭和自動車(唐津市)の路線バス再編に伴い代替交通手段を考える三瀬地区公共交通検討会議(会長・井上文昭三瀬自治会長)が13日夜、佐賀市三瀬支所で会合を開き、運行本数や料金体系などの案を取りまとめた。同一路線を利用する神埼市と協議していく。これまでの会合で、三瀬支所から横武(神埼清明高校前)まで中型バスかマイクロバスを定時定路線で運行する方針を決めていた。今回の案では、29人乗りのマイクロバスを購入し、乗客が少ない場合や点検時は神埼市脊振で使用するジャンボタクシーを併用する。平日が神埼行き7便、三瀬行き8便で、土曜が各5便、日曜・祝日が各4便と、現在の三瀬発着便とほぼ同じ規模にする。三瀬支所~横武の運賃を抑えるなど、神埼経由でJRを使い佐賀市街地の高校に通う生徒の負担が変わらないようにする。委員は「学生が安心して通学できる」と今回の案を評価しつつ「バス停は今まで通りでいいが、どこでも降車できるようにしてはどうか」と注文もしていた。 *6-5:https://www.topics.or.jp/articles/-/257805 (徳島新聞社説 2019年9月16日) 敬老の日 「高齢者の足」の確保を きょうは「敬老の日」である。本県の100歳以上は533人を数える。医療の進歩、食生活や公衆衛生の向上などにより、超長寿社会が実現したことは喜ばしい。一方で高齢化に絡む痛ましいニュースが少なくない。その一つが、自動車のアクセルとブレーキの踏み間違えが原因とみられる交通事故だ。誰しも年をとると、体力や視力が衰える。健康に不安を感じたら、運転免許証を自主返納することが望ましい。問題は、その後の「生活の足」をどう確保するかだ。県警によると、2018年の自主返納者は3082人で過去最高だった。今年は6月までで1791人と、昨年を上回るペースで返納されている。4月、母子が犠牲になった東京・池袋の事故が心理的に影響しているという。とはいえ、県内の公共交通機関は脆弱である。返納が高齢者の生活の質低下につながってはならない。近年、健康寿命を平均寿命に近づけることへの意識が高まってきた。介護に頼らず、いつまでも元気で生き生きしていたいと思うのは当然のことである。そのためには、生活習慣病の予防など健康に留意することはもちろん、積極的に社会参加し、日々、生きがいや喜びを感じながら暮らすことが大事だろう。だが遠出できず、買い物に行くこともままならないとなれば、食の偏りや低栄養を招きかねない。1人暮らしだと、孤独に陥ってしまうこともあろう。運転免許返納後の不自由をなくすため、過疎地の自治体などは、自主返納者らを対象に、さまざまな優遇措置を打ち出している。主なものは、運行するバスの運賃半額や割引、タクシー料金の一部助成などだ。バス会社も路線バスの運賃半額を実施している。料金を1割引きとするタクシー会社(個人を含む)も増えてきた。ただ、バスは本数が限られている。割引の区間やサービスの利用回数が限定されているケースも多い。求められるのは利便性の向上だ。そのためには鉄道、路線バス、貸し切りバス、コミュニティーバス、スクールバス、タクシー、福祉車両といった、あらゆる交通手段を柔軟に組み合わせることが欠かせない。国や県、市町村などは今、そうした方法を模索している。交通網の最適化が図られ、乗り継ぎや長距離移動が楽になれば、全体の利用者増も期待できよう。運行形態の抜本的な見直しによる交通機関の維持なくして、自主返納者を含む高齢者の足確保やサービス拡充はありえない。本県の高齢化率は33・1%に達している。3人に1人が高齢者である現実を直視し、地域の足を全員で支える意識を共有したい。 <全世代型社会保障とは> PS(2019年9月16、21、22日追加):*7-2のように、総務省が9月16日の敬老の日にあわせてまとめた9月15日の人口推計では、65歳以上の“高齢者”人口が総人口の28.4%で、後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上は14.7%(7人に1人)になった。また、労働力調査によると、65歳以上の“高齢者”の就業率は非正規雇用が多いものの、2018年時点で24.3%であり、政府は70歳までの就労機会を拡大する法改正を準備しているそうだが、私は75歳を視野に入れた法改正をしてもよいと思う。ちなみに、埼玉県内の企業は、*7-3のように、65歳以降の雇用に87%が肯定的で、「熟練の技術や知見を持つ高齢者への期待が高まっている」とのことだ。 そのような中、日経新聞が社説で、*7-1のように、「①介護費用は2019年度予算で11.7兆円に達し」「②65歳以上の高齢者が支払う保険料は全国平均で月5869円、40~64歳の保険料も上昇して現役世代の大きな負担だ」「③高齢化が進む中で制度を維持するために介護保険の給付と負担の見直しが必須」「④厳しい現実を直視し、痛みを伴う改革に踏み込むべきだが、痛みはみなで分かちあいたい」「⑤給付を効率化することが欠かせず、掃除や料理を手伝う生活援助サービスは大きな課題」「⑥介護サービスを利用する際の自己負担は原則1割だが、原則2割にすべき」「⑦介護サービスのケアプランづくりも一定の負担が必要」などと記載している。 このうち、①については、2000年から始まった介護保険制度であり、始まった当初は足りないものだらけだったため増えるのが当然であり、増えたのは単なる景気対策と違ってニーズが高かったということである。また、②については、40歳未満の人は介護保険料を支払っていないため、働いている人すべてが介護保険料を支払うように制度改革し、合わせて介護制度は病児の介護も担うようにすべきだ。さらに、⑤は、男性には定年制を言いながら、家事・介護の労働負担を考慮しないドアホさであり、⑦は、家のリフォームの仕方を相談しただけで金をとるのと同じくらいあくどい。さらに、⑥は、以上のすべてを改善し、何事も無料はよくないため子どもの医療費負担も1割にしてから考えるべきである。そして、③④のように、事実を無視して痛み分けばかり述べるのは、高校まではゆとり教育、大学時代は麻雀づけ、就職してからは家事・育児・介護には関係ないと思っている人が記事を書いているからだろう。そのため、労働市場で高齢者が担う役割は大きいし、新聞社や役所などの幅広い視野を要する組織は、1年以上の長期育児休暇や介護休暇取得を義務付け、従業員に家事・育児・介護等を経験させるのがよいと思う。 これが、全世代型社会保障の輪郭で、*7-4の幼保無償化もよいし、地方自治体が独自財源で不足部分を補うのもよいとは思うが、正しい理念を持った政策にして欲しい。 なお、*7-5に、八田達夫氏が「⑦無償化で需要が増えて待機児童問題は悪化した」「⑧認可保育所の0歳児枠は基本的に廃止せよ」「⑨全員が保育士との要件を6割まで緩めよ」と書いておられる。そして、⑦の理由について、「⑩無償化は高所得世帯ほど恩恵が大きく、子の貧困を救うために使えた財源を中高所得者が奪う結果をもたらす」「⑪保育サービスの供給量は保育士の数がネック」としておられるが、これだけ無駄遣いをしている日本政府が幼保無償化と待機児童対策の二者択一を行う必要はなく、単なる景気対策を削減すべきだ。さらに、3~5歳児の全世帯無償化は義務教育の3歳開始を視野にしており、貧困対策ではないため、⑩は反論になっていない。従って、⑨⑪の保育士不足は、幼稚園・小学校の教員免許取得者・栄養士・外部講師・雑用係などでチームを組んで教育・保育を提供しながら埋めるのが適切だ。さらに、⑧については、「⑫0歳児保育を不必要に多く生み出しているから」と書かれているが、育児休業を取れるのは実際には職場である程度の実績を積んだ正規雇用の女性だけであるため、認可保育所の0歳児枠を廃止すれば子を持てない夫婦が増える。また、「⑬都会では認可保育所が足りない」と書かれているのは事実だが、地方には比較的広い教室や園庭を持つ認可保育所に空きがあるため、これが首都圏に過度に人口を集中させ地価をはじめ物価を上昇させた弊害なのである。 さらに、*7-6のように、国公私立大学・短期大学の97%にあたる1043校が住民税非課税世帯向けに開始される大学・短大の無償化対象となり、該当する学生には授業料の最大年70万円減免と給付型奨学金の最大91万円支給が行われるそうだ。住民税非課税世帯とは、独身者・単身者なら年収100万円以下、障害者・未成年者・寡婦(寡夫)なら年収約204万円以下の人で、対象はかなり絞られたがないよりはよくなった(https://www.amazon.co.jp/ref=dra_a_ms_hp_ho_xx_P1700_1000?tag=dradisplay0jp-22&ascsubtag=7e93be7451ad705a3c98e4f9e11c2625_CT# 参照)。しかし、子を大学まで出した上で2000万円以上の老後生活費を準備するのは、住民税非課税世帯でなくとも困難だ。教育は、(集団に埋没するのではなく)革新や生産性向上のために考えながら働くことのできる人材を創るために必要な国家的投資でもあるため、今後は、国立大学授業料の低減や対象者の要件緩和が必要だ。 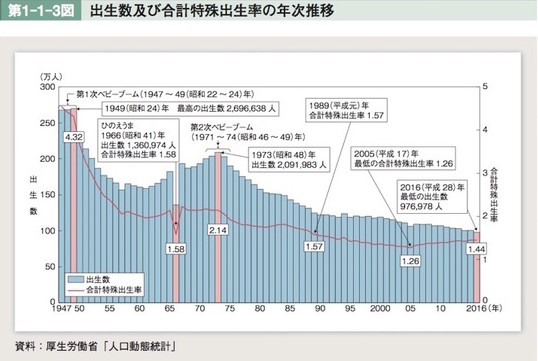 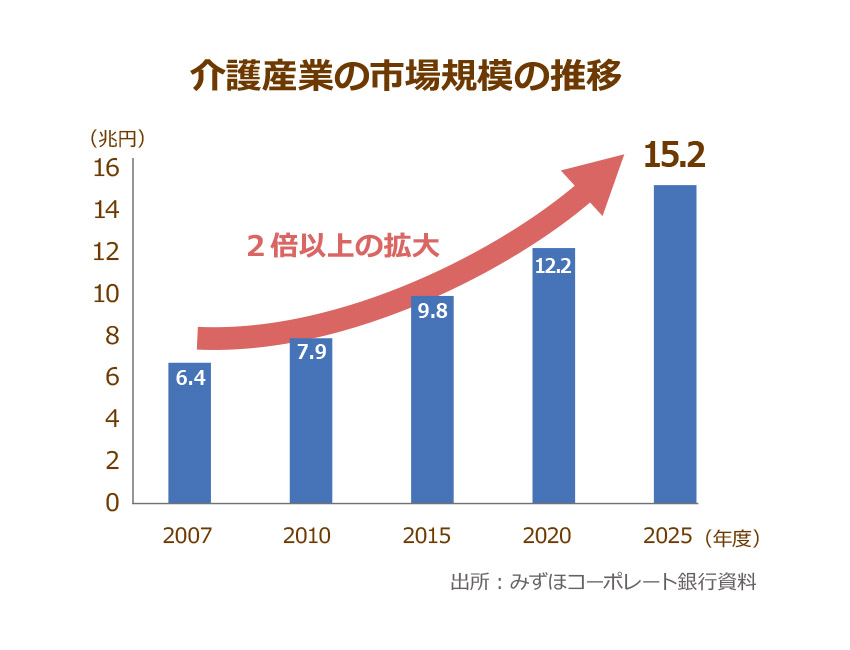 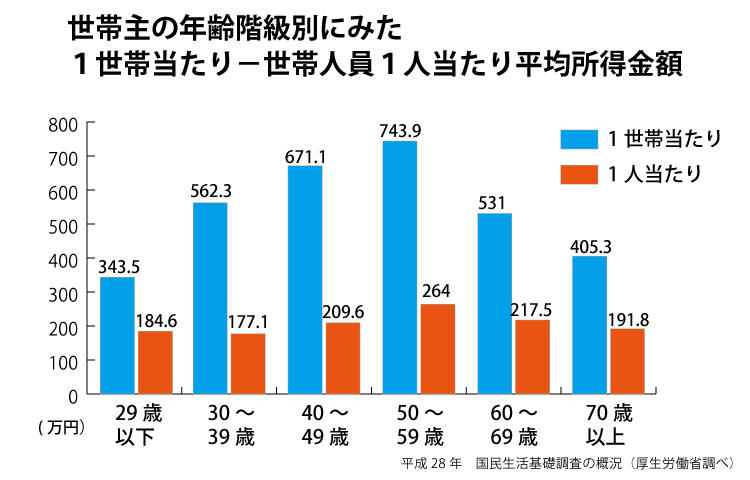 日本の出生数・合計特殊出生率推移 介護産業の市場規模 年齢階級別平均所得 (図の説明:左図のように、戦後の1947~1949年に第一次ベビーブームが起こり、出生率が高くなって団塊の世代が生じ、その子が1973年前後に生まれて第二次ベビーブームとなった。そのため、団塊の世代が後期高齢者になる頃の社会保障が心配されているが、生産性向上と支え手の拡大で乗り切るべきだ。中央の図の介護保険制度は、女性の社会進出と核家族化の要請により日本で生まれた制度だ。しかし、2000年に始まったばかりの制度で実需でもあるため、増加するのは当然だ。その介護保険料は、日本では40歳以上しか納付していないが、右図のように所得の少ない高齢者に多く負担させるよりも、働く人すべてで負担するのが公正・公平である) *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190916&ng=DGKKZO49842270U9A910C1PE8000 (日経新聞社説 2019年9月16日) 介護保険は給付と負担の双方に切り込め 介護保険制度の見直しに向けた本格的な議論が、社会保障審議会の部会で始まった。高齢化がさらに進むなかで制度を維持するためには、給付と負担の見直しが必須だ。厳しい現実を直視し、痛みを伴う改革に踏み込むべきだ。介護保険は3年に1度、制度を見直している。今回の議論は2021年度からの実施に生かすためのものだ。介護保険の現状は厳しい。介護費用は19年度の予算ベースで11.7兆円に達した。制度創設時の00年度の3倍以上にあたる。65歳以上の高齢者が払う保険料も全国平均で月5869円で、00年度の約2倍に増えた。40~64歳の保険料も同様に上昇しており、現役世代の大きな負担だ。介護費用には税も投入されるが、過度に膨らめば、制度の持続が難しくなる。団塊の世代が全員75歳以上になる25年は、もう目前だ。介護予防の取り組みで健康寿命を延ばし、できるだけ介護が必要にならないようにするのは一つの手だが、今の給付を効率化することが欠かせない。なかでも掃除や料理などを手伝う生活援助サービスは、大きな課題だ。訪問介護の一種だが、介護の必要性が比較的低い軽度者については、自治体の事業に移すことを検討すべきだ。一方、一人暮らしの高齢者や老々介護の人は多く、現役世代の介護離職も防がねばならない。給付抑制だけでは限界がある。負担増をどう分かちあうか、正面から議論する必要がある。高齢者が介護サービスを利用するさいの自己負担は「原則1割」だ。収入の多い一部の人のみ、2、3割となっている。経済的に苦しい人には配慮しつつ、原則を2割にすることが望ましいだろう。介護サービスの利用計画(ケアプラン)づくりは現在は自己負担がないが、これも一定の負担が必要ではないか。そもそも介護は、人手不足が深刻だ。処遇改善を着実に進めることはもちろん、介護ロボットの活用などで働きやすい環境づくりを急がねばならない。高齢者、とりわけ75歳以上が増える一方、現役世代の人口は減少していく。改革の遅れは、将来への付け回しを増やすばかりだ。介護だけでなく、医療でも高齢者に一定の負担を求める改革を進める必要があろう。痛みはみなで分かちあいたい。 *7-2:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49851150V10C19A9MM8000/ (日経新聞 2019/9/15) 65歳以上人口が最高28.4% 7人に1人が75歳以上 総務省が16日の敬老の日にあわせてまとめた15日時点の人口推計によると、65歳以上の高齢者人口は前年比32万人増の3588万人だった。過去最多を更新し、総人口の28.4%を占めた。後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上は53万人増え1848万人となった。総人口の14.7%とおよそ7人に1人に上り、超高齢化社会を支える制度づくりが急務だ。70歳以上の人口は98万人増の2715万人で、総人口に占める割合は21.5%に上った。ほかの年齢層に比べて増加数が多いのは1947~49年生まれの「団塊の世代」が含まれるためだ。同省によると65歳以上の割合は世界201の国・地域のうち最も高い。2位のイタリア(23.0%)を大幅に上回っている。国立社会保障・人口問題研究所の推計では今後も上昇し、2025年に30.0%、40年には35.3%に上る見込みだ。働く高齢者数も増加している。労働力調査によると、65歳以上の就業者数は18年、862万人と過去最多を更新した。15年連続で前年より増えた。約半数の469万人が企業などに雇用され、このうち76.3%にあたる358万人がパートなど非正規雇用だった。非正規職に就く理由は男女ともに「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最多となった。日本の高齢者の就業率は18年時点で24.3%。男女別では男性が33.2%、女性が17.4%だった。主要国の中でも高い水準にあり、米国は18.9%、カナダは13.4%だった。政府は人手不足などの問題を解決するために、70歳までの就労機会を拡大する法改正を準備している。企業が深刻な人手不足に直面し、労働市場で高齢者が担う役割が拡大している。 *7-3:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38911390T11C18A2L72000/?n_cid=SPTMG002 (日経新聞 2018/12/13)埼玉県内企業、65歳以降の雇用 87%が肯定的 埼玉りそな産業経済振興財団(さいたま市)が実施した埼玉県内企業の高齢者雇用に関する調査で、65歳以降の雇用に肯定的な回答は9割近くに上った。同財団は「企業の人手不足感が強まり、熟練の技術や知見を持つ高齢者への期待が高まっている」と分析している。65歳以上の高齢者を「積極的に雇用したい」「環境、条件などが整備されれば雇用したい」が合わせて87%だった。65歳以降の雇用が「ある」との回答は70%。政府は70歳までの就労機会の確保を目指しているが、多くの県内企業ですでに65歳以上の高齢者が働いている現状が浮き彫りになった。高齢者に期待することを複数回答で聞いたところ「熟練した技術や知見の活用、伝承」が88%で最多。次いで「人手不足への対応」(71%)、「若手の育成」(64%)の順だった。高齢者雇用の課題は「健康管理」(78%)が最も多かった。調査は10月中旬に実施し、236社から回答を得た。 *7-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201909/CK2019091502000122.html (東京新聞 2019年9月15日) 幼保無償化「国以上」6割 さいたまや千葉 独自財源で拡大 幼児教育・保育の無償化に関し共同通信が県庁所在地など計百三自治体に行った調査で、国の基準では無償化とならない世帯に、独自財源で何らかの経済的支援を実施または検討している自治体が六十二市区と約六割に上ったことが十四日、分かった。国の制度以外に取り組む予定がないと答えたのは四十一市町だった。安倍政権は「三~五歳の全ての子どもを無償化する」と看板政策をアピールしてきた。しかし、実際には恩恵を受けられない家庭もある。待機児童問題も解消されない中、自治体が国の制度設計の不備を補う形で独自策を講じている実態が浮き彫りになった。調査は八~九月、県庁所在地と政令市、東京二十三区、昨年四月時点で待機児童が百人以上の計百三自治体を対象に実施。九月十三日時点の結果をまとめた。国の制度では、認可保育所や認定こども園などに通う三~五歳児の場合、保育料は無料となる。一方、認可外保育所などを利用する場合は全額無料とはならず、上限付きで利用料が補助される。ゼロ~二歳児は年収が低い住民税非課税世帯に対象が限られる。国を上回る取り組みとして最も多かったのは「利用料補助の上限額引き上げ」で、さいたま、千葉など二十市区。さいたま市では、市が一定の保育の質があると判断した認可外施設に限り、国より二万円上乗せし、実質的に月五万七千円まで補助できるようにした。鳥取や高知など十五市区は「対象外の世帯を一部無償化する」と回答。例えば大阪市や鳥取市は、母親が働いていないなど国基準では「保育の必要性が認められない世帯」も対象とする。山形、宇都宮など八市区は、住民税非課税世帯以外のゼロ~二歳児について保育料を値下げするなどとした。 *7-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190920&ng=DGKKZO49983690Z10C19A9KE8000 (日経新聞 2019.9.20) 経済教室幼保無償化の論点(上)待機児童の解消 最優先で、八田達夫・アジア成長研究所所長(1943年生まれ。ジョンズ・ホプキンス大博士(経済学)。専門は公共経済学) <ポイント> ○無償化で需要増え待機児童問題は悪化へ ○認可保育所の0歳児枠は基本的に廃止を ○全員が保育士との要件を6割まで緩めよ 政府は2019年10月から、幼児教育・保育の認可保育所の無償化を全面的に実施する。認可保育所に子どもを預ける場合、0~2歳児については住民税非課税の低所得世帯、3~5歳児については全世帯がそれぞれ無償化の対象となる。本稿では、この改革を政策目的の観点から評価する。 保育政策の重要な目的は、子どもを欲しい親が子どもを持てるようにすることだ。それができていない主因は以下の2つである。第1に低所得者の多くが子どもを健全に養っていくには貧困すぎる。結婚をためらう若者は多い。第2に都会の中所得者の場合は、子どもが待機児童になる可能性が子どもを産みにくくしている。待機児童になると、無認可保育所に入れるか、労働参画を諦めねばならない。入所の可否が極端に大きな差をもたらす仕組みは、若い夫婦が将来保育コストを予測することを不可能にしている。これらの問題は無償化では解消しない。まず生活保護世帯は現在も保育料が無償だし、低所得者に対する保育料軽減策は既にある。子どもの貧困対策には保育所だけを無償にしても役立たない。少なくとも所得税の給付付き税額控除(低所得者への所得水準に応じた補助金)を別途用意する必要がある。加えて今回の無償化は高所得世帯ほど恩恵が大きい。子どもの貧困を救うために使えた財源を中高所得者が奪う結果をもたらす。しかも中産階級にとっての障害である待機児童数は増えてしまう。認可保育所を無償にすれば認可保育サービスへの需要量は大幅に増えるが、供給量は保育士の数により制限されているからだ。その状況での無償化は入所選考で落とされた親に何の恩恵も与えない。待機児童をなくすことこそ、保育政策の喫緊の課題だ。最小の財政支出で実現し余裕の資金を低所得者の生活一般に使えるようにすることを基本とすべきだ。待機児童とは、認可保育所あるいは認証保育所などに入れない児童のことをいう。認可保育所とは、児童福祉法に基づき施設の広さや保育士数などの設置基準を満たし都道府県知事により認可された施設である。設置基準が厳しいため、児童1人あたり費用は高い。情報公開されている東京都板橋区では、1人あたり費用が0歳で月42万円、1歳で21万円、4歳以上で11万円だ。一方で多額の国費負担により保育料は極めて低く抑えられている。保護者の年収が500万円の場合、月額保育料は3万円未満(0歳と1歳)から2万円未満(4歳)の範囲だ。認可保育所に申し込んだ児童の入所選考は、自治体がその地域の児童福祉を必要とする人の数に合う保育サービス供給量を算定し、一定の入所基準に基づき提供する「配給制度」だ。従って認可保育所と保護者が直接に入所の契約をするのではなく、保護者は自治体が指定する認可保育所に子どもを預けねばならない。都会では認可保育所が足りないので、すぐに入所できないケースが多い。入所基準は、両親ともフルタイムで働いている場合は優先順位が高く、一方がパートタイムで働いている場合は低い。そのため例えば両親ともフルタイムで外資系企業で働く高所得世帯の子が認可保育所に入れる一方、パートタイムの職にしか就けない比較的低所得の親の子が入れない。仮に中高所得者の保育料を引き上げられれば、需給調整がなされ供給不足は解消するはずだ。経済学的には、待機児童とは「多額の国費がつぎ込まれている認可保育所の保育料を行政が需給均衡水準より過度に低く決めているために発生している認可および認証保育所サービスの供給不足のこと」だ。今回の無償化はもともと低く設定されている保育料をさらにゼロまで引き下げるのだから、待機児童問題を悪化させる。このダメージを和らげるには、無償化とは関係なく待機児童問題対策の王道を実施することだ。都会の中産階級が最も必要とする待機児童問題に有効な対策を提案したい。追加的な費用をかけずに実行できる。第1は現制度が生み出している0歳児保育への過剰な需要を減らすことだ。現在は0歳児を持つ母親の多くは、子どもが1歳に達するまで育児休業をとれる。しかし1歳になってから保育所に入れようとしても、保育所は0歳から入る子どもで埋まっている。そこで1歳からの枠を確保するために、0歳時点では育休を諦めて保育所に預け、出産後まもなく職場に復帰するという現象が起きている。0歳児保育を不必要に多く生み出している。国の0歳児に対する保育士配置基準は1歳児の2倍だ。0歳児保育の増加は1歳児以上の保育所収容数を減らし、待機児童全体を不必要に増やしている。この問題の解決策は認可保育所の0歳児枠を基本的に廃止することである。そうすれば保育士が0歳児保育から解放され、1歳からの入所に十分な枠を確保でき、親は0歳の時は家庭保育、1歳になったら復職という選択が可能となる。その一方で、育児休業をとれない母親については、保育ママやベビーシッターに対する費用を行政が支援すれば、月額40万円前後の0歳児認可保育費用に比べてコストを大幅に節約できる。この方策は基本的に東京都江戸川区で取り入れられ成功してきた。国の改革としても導入すべきだ。第2は認可保育所の全員が保育士でなければならないという現行要件を6割まで引き下げることだ。「東京都の認証保育所」は保育サービス提供者の総数では認可保育所と同等で、6割が保育士であることが要件だが、問題は生じていない。認可保育所の保育士要件をこの水準まで引き下げて、減少分を保育士以外の人で補えば、保育士が認可保育所から解放される。それにより認証保育所の増設が可能となり、差し引きで待機児童数を減らせる。1997年創設の横浜保育室や、01年創設の東京都認証保育所など認証保育所への国費投入はほぼないため、認可保育所より高い保育料と自治体からの補助で大半の財政を賄っている。東京都の場合、平均保育料は約6.5万円である。認証保育所は、認可保育所に劣らない高い評価を得ている。表で示したように、東京都江東区での保護者の評判が高い保育園ランキングでも明らかである。東京都全域での平均でみても、認証保育所の方が認可保育所より評価が高い。教育内容などで利用者の要望に応えているからだろう。認証保育所の緩やかな保育士要件が特段の質の低下をもたらしているわけではない。認可保育所の保育士要件をこの水準まで引き下げれば保育の質を下げることなく、待機児童数を減らせる。まずこれらの王道対策を実施しダメージを和らげた後で、低所得者以外の無償化を廃止し、認可保育所の保育料を認証保育所の水準以上に引き上げ、生み出された財源を保育士の待遇改善と給付付き税額控除の創設に投入すべきだ。 *7-6:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190921&ng=DGKKZO50021120Q9A920C1CR8000 (日経新聞 2019.9.21) 無償化、大学・短大97%の1043校が対象、低所得世帯向け、4月開始 31校は申請見送り 2020年4月に始まる低所得世帯を対象とした高等教育の無償化制度を巡り、文部科学省は20日、募集停止などを除いた国公私立の大学・短期大学1043校(全体の97%)が制度の利用を申請し、全校が要件を満たして対象になったと発表した。一方、私立の大学・短大31校と国公私立の専門学校1024校は自ら申請を見送るなどして対象外となった。無償化制度は住民税非課税世帯やそれに準じる世帯が対象。授業料を最大で年70万円減免するほか、生活費として返済不要の給付型奨学金を最大で同91万円支給する。大学などが制度の対象となるには、教育体制や経営・財務について一定の要件を満たす必要がある。文科省によると、国公立の大学・短大186校と、国公私立の高等専門学校57校はいずれも利用を申請し、全てが要件を満たした。私立の大学・短大は888校のうち857校が申請し、全校が要件を満たした。この中には留学生が行方不明になり不適切管理が指摘された東京福祉大も含まれる。31校は各校の判断で申請を見送った。文科省によると、このうち10校弱が経営上の要件を満たせないとみられる。ほかは「規模が小さく対象者が見込まれない」「独自の奨学金制度がある」などが理由で、医学部などは授業料が高く、支援額では大幅に不足するため利用を見送ったようだ。国公私立の専門学校は2713校中1696校が申請。1017校が見送った。申請したうちの7校は要件を満たさず、1校は審査継続中で、無償化対象となったのは全体の62%にとどまる。申請見送りは「社会人が多い」「準備が整わない」などが理由という。私大は今春で3割が定員割れに陥っているが、ほとんどが無償化対象になったことについて、文科省は「制度は低所得者に高等教育への道を開くことを第一にしている。一定程度(経営に)しっかり取り組んでいれば要件は満たせる仕組みだ」と説明する。無償化の対象校は同省のサイトで確認できる。一方、文科省は低所得世帯を対象とした今回の制度開始により、国立大の学部生のうち、中所得世帯などの1万9千人は授業料負担が増えると推計している。各大学独自の中所得世帯向けの支援制度がなくなる見通しであることなどが理由だ。同省は家計への影響を抑えるため、経過措置を検討する。無償化制度の財源は10月の消費増税で賄う。無償化で低所得世帯の高等教育進学率が将来的に8割まで上がった場合、年約7600億円が必要になると試算されている。桜美林大の小林雅之教授(教育社会学)は「学生が教育を受ける機会が広がったことは評価できる。低所得世帯の学生がより多く通う専門学校は、対象を増やしていく必要がある。制度を知らずに支援を受けられない学生が出ないよう、制度の周知も大きな課題になる」と話している。 <幼保無償化について> PS(2019年9月23日追加):1990年代に、仕事との両立が不可能なので子を作らないと決めた時から、私は「少子化の原因は、職住接近していないことと保育所の不備にある」と考えて、保育所の整備を主張してきた。また、私の東大の後輩は、学童保育がなかったため子を他人の家に預けて研究を続けながら、学童保育の必要性を主張してきた。それから、四半世紀後の現在でも保育や学童保育が不足しているが、その人の子は既に結婚し、これらは行政のアクションのトロさを示すものだ。そして、そういう私に「シニア民主主義」などと言った人は、権力(?)に対する建設的な批判をしたのではなく、高齢者差別を奨める罵詈雑言を言ったにすぎない。 そのような中、*8-1のように、日経新聞が、2019年9月23日、幼保無償化の論点として、①地方で虐待予防や女性活躍推進など意義 ②待機児童増で保育所受け入れ拡大圧力も ③保育の質低下回避へ無償化の制度修正を という記事を書いている。①のように、虐待予防や女性活躍推進などの意義を掘り下げて書いているのは「現在だからこそ」と評価できるが、②のように、いまだに「無償化によって保育所利用が増え保育所への受け入れ圧力が拡大する」「待機児童が増える」というのを無償化の欠点としているのは問題だ。何故なら、これらの潜在的ニーズは女性の犠牲によって潜在化しているだけなのであり、子育てにおける女性のストレスを増加させているからだ。さらに、保育所を利用するのに共働きが求められるというおかしさも、家庭生活に対する行政のいらぬ介入により子育てに関する女性のストレスを増やしている。しかし、これらの論点は、幼保無償化によって再度リスト化されたので、③のように幼保無償化を後退させるのではなく、前進させながら解決すべきだ。 また、*8-2も、④子どもの安全や保育の質の確保という課題が残されたまま ⑤幼稚園が無償化に必要な申請をしていない ⑥保護者は幼稚園に文句を言いづらい ⑦自治体の「保育の必要性」認定が一大作業 ⑧給食費をめぐって混乱 などと記載しているが、④⑧はこれまでもやってきたことを正確に行えばよいだけである。また、⑤⑥は、保護者の立場に立った運営をしていないため、地方自治体や幼稚園の方に問題がある。さらに、⑦は、ニーズのある人は誰でも利用できるようにすべきで、行政が勝手に「保育の必要性がない」と決めつけること自体に問題があるのだ。従って、政府の混乱というよりは、これまでの地方自治体や厚労省の不作為・不効率のツケが廻ってきたのだと思われる。 さらに、*8-3は、⑨制度を支える保育士の待遇が悪い ⑩潜在保育士が多い ⑪保育士の平均就業年数に対して支給される処遇改善費は平均10年以上に対する12%で頭打ちで、経験の長い保育士がいても昇給させにくい ⑫保育士不足は待機児童問題に直結している と書いている。⑨⑪の給与の決め方は、女性が多い保育士は10年程度働いた後は結婚して辞めることを前提としているようだ。さらに、女性が主体となる職業は、(女性差別のため)看護師・介護師なども平均給与が低く設定されているが、それが⑩⑫の結果を招いているため、経験や実力のある保育士はそれ相応の高給にすべきなのである。 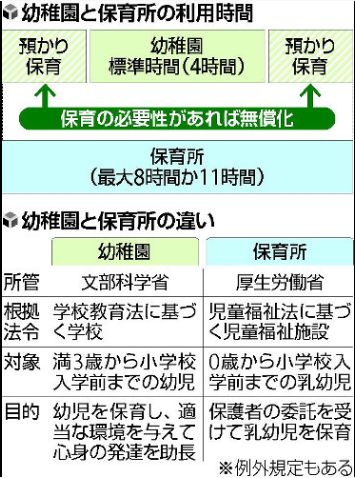 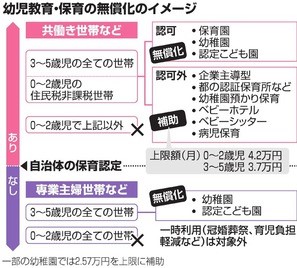 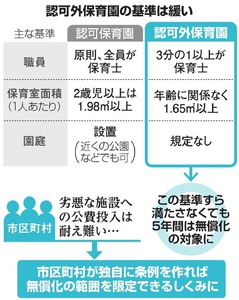 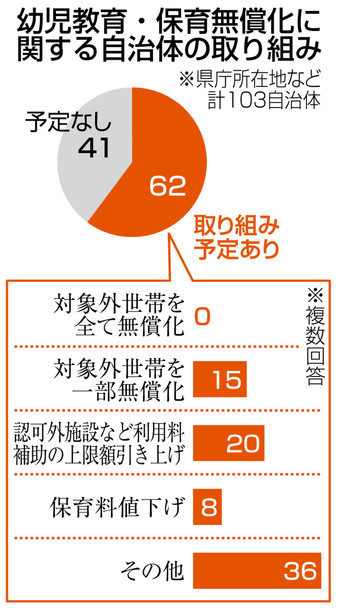 2018.5.15帆足Blog 2018.6.1朝日新聞 2019.7.7朝日新聞 2019.9.15東京新聞 (図の説明:1番左の図のように、幼稚園は文科省の管轄、保育所は厚労省の管轄であるため、小学校の入学年齢を満3才として教育し始め、0~2歳と学童保育を保育とするのがよいと、私は考える。左から2番目の図のように、専業主婦の0~2歳児は「保育の必要性がない」として今回は無償化されていないが、専業主婦も求職活動・介護・第2子の出産などのさまざまな理由で保育の必要性が生じることはあるため、専業主婦を差別するのはよくない。また、右から2番目の図のように、認可外保育所の設置基準は緩いため、質の向上は重要だ。さらに、国の基準は最低を確保するものであるため、右図のように、自治体独自の基準や補助もあってよいが、どうしても国の基準にすべきと考えられるものは、現場からの要請で次第に改善していけばよいだろう) *8-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190923&ng=DGKKZO50033540Q9A920C1KE8000 (日経新聞 2019年9月23日) 幼保無償化の論点(中)上限額設定・所得制限検討を、柴田悠・京都大学准教授(1978年生まれ。京都大卒、同大博士(人間・環境学)。専門は社会学、社会保障論) <ポイント> ○地方で虐待予防や女性活躍推進など意義 ○待機児童増で保育所受け入れ拡大圧力も ○保育の質低下回避へ無償化の制度修正を 10月から幼児教育・保育無償化により、3~5歳は全員無償、0~2歳は住民税非課税世帯のみ無償となる(幼稚園と認可外保育施設は上限額まで無償化)。無償化には一定の意義があるが、課題も多い。第1の意義は地方で虐待予防が進むことだ。虐待などの不適切な養育は、幼児の脳を物理的に変形させ、その後の社会生活を困難にする。山口慎太郎・東大准教授らが全国調査データを分析した研究によれば、母親が高卒未満の家庭では不適切な養育が生じやすく、子どもの社会的発達が遅れやすいが、子どもが2歳半時に保育所に通っていると、不適切な養育が予防されやすく社会的発達が健全になりやすい。従って保育所定員に余裕のある地方では無償化により、社会経済的に不利な家庭の保育利用が増え、虐待予防が進むと期待できる。第2の意義は地方での人手不足緩和と女性活躍だ。無償化により認可保育所(認定こども園を含む)への申し込みが増えると見込まれる。岡山市が2018年に実施した保護者対象のアンケート調査によれば、無償化により認可保育所の利用希望者数が3歳児でも4歳児でも2割増える見込みだ。特に4歳児では幼稚園から保育所への需要の移動が見込まれる。5歳児は調査されていないが、おそらく4歳児と同様だろう。日経新聞と日経DUALが18年に実施した主要143自治体へのアンケート調査でも、約8割が「無償化により保育所への利用申し込みが増える」と回答した。保育所を利用するには、基本的に共働きが求められる。そのため保育所定員に余裕のある地方では無償化により母親の就業が増え、人手不足緩和や女性活躍が進むと期待できる。第3の意義として育児費用の減少により、産みたい人が産みやすくなるという少子化対策効果が挙げられるが、効果は限定的だろう。確かに全国の50歳未満有配偶女性を対象としたアンケート調査(15年国立社会保障・人口問題研究所実施)では「理想の子ども数を持たない理由」の第1位は「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」(56%)だ。しかし全国20~59歳男女対象のアンケート調査(12年内閣府実施)では「子育て全体にかかる経済的な負担として大きいと思われること」の第1位は「大学・専門学校などの高等教育費」(69%)、第2位は「塾などの学校外教育費」(49%)、第3位は「小・中・高の学校教育費」(47%)で、「保育所・幼稚園・認定こども園の費用」は第4位(45%)だった。つまり幼保無償化により「子育ての経済的負担感が減る」と感じる人は子育て世代の半分弱にすぎない。むしろ専門学校や大学などの高等教育費を軽減するほうが、子育て世代の約7割の負担感軽減につながる。多くの人々にとって産みやすい環境を整えるという意味では、幼保無償化よりも高等教育費軽減のほうが効果が大きそうだ。またより根本的な対策としては働き方の柔軟化こそが必要だ。一方、最大の課題は主に都市部で待機児童が増えることだ。野村総合研究所による18年実施の全国アンケート調査に基づく試算をみてみよう。女性の就業率が今後国の目標通りに上昇すれば、保育の定員は、18年度から20年度末にかけて32万人分増やす政府の計画が実現してもなお、23年には28万人分不足するという。政府の計画では「保育の申し込みをしたがかなわなかった数」(顕在的待機児童数)を基に32万人という将来需要を想定する。一方、野村総研の試算は「保育(幼稚園の預かり保育を除く)を希望していたが諦めて申し込みをしなかった数」(潜在的待機児童数)も含めて将来需要を想定しており、「待機児童の完全解消に必要な定員数」により近い。岡山市の調査でみたように、無償化により保育所の利用希望者はさらに増えると見込まれる。待機児童がいる都市部では待機児童が一層増える公算が大きい。待機児童が増えると何が問題なのか。第1に保育の質が低下し子どもの発達に悪影響が生じかねない。第2に職場復帰がかなわなかった母親は、孤立育児によるストレスが高まり、虐待リスクが高まりかねない。第3に職場復帰できなかった母親の持つスキルが職場で生かされず、人手不足にも拍車がかかり、企業経営や経済成長に悪影響が生じる。第4にそれらが総じて育児環境の悪化につながり少子化が一層進行する。以下では、第1の問題について詳しくみていこう。待機児童が増えると、厚生労働省から自治体に対して「国の基準ギリギリにまで児童を保育所に受け入れてほしい」という要請が、これまで以上に強まる可能性がある。厚労省は16年、待機児童の多い114市区町村などに対し「人員配置や面積基準について、国の基準を上回る基準を設定している市区町村では、国の基準を上回る部分を活用して1人でも多くの児童を受け入れる」よう要請した。いずれの自治体も「保育の質が下がる」との懸念から要請を退けたが、今後無償化により待機児童が増えた場合、同様の要請が強まり「国の基準ギリギリにまで児童を受け入れる」自治体が増える可能性がある。1人の保育士・幼稚園教諭が何人まで児童をみてよいかを示す日本の保育士・幼稚園教諭配置基準は、0~2歳については先進16カ国平均(0~3歳で7人)よりも手厚い(0歳で3人、1~2歳で6人)。しかし3~5歳については先進19カ国平均(3歳以上で18人)よりもはるかに悪く、先進19カ国で最悪だ(3歳で20人/保育士、4~5歳で30人/保育士、3~5歳で35人/幼稚園教諭)(12年経済協力開発機構報告)。また保育士の学歴は先進諸国の中で中程度だが、仮に保育所が3~5歳児童を国の基準ギリギリにまで受け入れれば、そこでの保育士の労働環境と保育の質は先進諸国の中ではかなり悪いレベルになるだろう。「幼児教育・保育の質が園児の発達に与える影響」に関する最新の国際比較研究によれば、質の低下した保育所に通った場合、子どもの発達(認知能力および非認知能力の短期的・長期的発達)は、通わない場合よりも悪くなる可能性が高い(図参照)。主に都市部では無償化により待機児童が増えることで、保育の質が低下し子どもの発達に悪影響が生じかねない。ではどうすればよいか。待機児童を減らすとともに保育士の給与・労働環境を改善し、保育の質を守る必要がある。そのための財源は無償化の制度を一部修正すれば捻出できる。幼稚園と同様に月2万5700円までを3~5歳保育無償化の上限額とすれば、約2千億円の財源が浮く。3~5歳幼保無償化を、0~2歳保育無償化と同様に住民税非課税世帯に限定すれば、約7千億円の財源が浮く。上限額設定や所得制限は虐待予防などの意義を大きく損なうことなく、待機児童の増加や子どもの発達の悪化も防止できる。政府にはぜひ検討してほしい。 *8-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14188766.html (朝日新聞 2019年9月23日) 準備、大丈夫? 幼保無償化 預かり保育「無償化辞退」各地で 幼児教育・保育の無償化が10月から始まる。すべての3~5歳児と、低所得世帯の0~2歳児が対象だ。安倍晋三首相が2年前の衆院選で打ち出した少子化対策だが、制度の検討や周知は十分ではなく、現場では混乱も起きている。子どもの安全や保育の質の確保といった課題も残されたままだ。関西のある自治体にこの夏、問い合わせの電話が入った。「近所の幼稚園の預かり保育が、無償化の対象にならないと聞いたが、どういうことか」。自治体職員が確認すると、幼稚園は無償化に必要な申請をしておらず、こう説明した。「預かり保育は希望者が多く、利用できない人もいる。利用者だけ無料では不公平になる」。保護者の一人は「仕事を続けるには、預かり保育を利用するしかないので、幼稚園に文句は言いづらい」と思い悩む。幼稚園が夕方まで行う「預かり保育」は無償化の対象だが、園側の申請が必要で、無償化するかどうかは各園の判断次第だ。内閣府や文部科学省によると、「申請手続きが手間」「無償化で利用者が増えれば職員増が必要になり、人件費がかさむ」などの理由で、こうした「無償化辞退」が各地で起きているという。また子どもを認可外施設などに預ける場合、利用者が無償化の対象になるには、自治体から「保育の必要性の認定」を受ける必要がある。この認定も自治体にとっては一大作業だ。子育て世代の転入が増えているさいたま市では、6月末から認定申請の受け付けを始めたところ、2週間近く、無償化の上限額などに関する問い合わせの電話が殺到。7月末の締め切りまでに2万件超の認定申請があり、結果の通知作業は委託業者の力を借りても9月後半までかかった。無償化の対象になれば、保育料は必要なくなったり減額されたりするため、施設側も混乱する。さいたま市内の複数の幼稚園では、金融機関への手続きが遅れ、10月分として従来と同額の保育料などを引き落とすという通知が保護者に届いた。市は全幼稚園に書面で注意を呼びかけた。岡山市は8月から庁舎内の会議室に専用の相談・対応窓口を置き、スタッフ3人が約370件の相談を受けた。専用コールセンターには「自分は対象か」「待機児童対策が先」などの問い合わせや意見が約820件も寄せられた。市は無償化を歓迎しつつ保育ニーズの増加に気をもむ。2020年度の認可保育所などの入所申し込み数を1万9424人と試算していたが、最大4千人増える可能性もあるとする。4月時点の待機児童数は全国で4番目に多い353人。19年度末の待機児童解消を掲げ、施設整備や保育士の処遇改善に取り組むが「達成は厳しくなっている」。 ■おかず代、実費化めぐりドタバタ 給食費をめぐっても混乱が起きている。これまで3~5歳児が認可保育所などに通う場合、主食代の月約3千円は実費で保育所に、おかず代約4500円は保育料の一部として自治体に払ってきた。10月分からは、保育料と一緒におかず代も無償になるのを避けるため、おかず代は実費で払うようになる。施設側などは支払い方法の変更について保護者に説明を進めたが、内閣府は8月22日付の自治体への通知で、これまで国と自治体が実際におかず代として施設側に渡してきたのは、物価調整分の約680円を足した約5180円だったと説明した。約4500円を実費でもらうだけでは、施設側の収入は差し引き約680円減ることになる。直前になって保護者に負担増を求めるのは難しく、保育所などの経営者は、施設側が約680円を負担せざるを得なくなると強く反発。自治体からも「680円は国が負担するべきだ」と批判の声が上がった。結局、内閣府は9月18日付で約680円は国と自治体で負担し、おかず代は約4500円のままにすると通知した。滋賀県内の認定こども園は「経営に直結する問題だった。政府の混乱ぶりが露呈した」とあきれる。 ■安全・保育の質、課題残したまま 無償化が動き始めたのは17年9月。安倍首相が衆院解散・総選挙に踏み切る際、消費税率10%への引き上げによる増収分の使い道を変え、無償化に充てると表明した。具体的な制度設計は後回しだった。政府は当初、無償化の対象は認可施設の利用者を想定していたが、認可外施設の利用者や与党から「不公平だ」と批判されると認可外も対象に。認可外は保育士の配置などの基準が緩いが、5年間は基準を満たさなくても対象にすることにした。今度は子どもの安全や保育の質が担保されないとの懸念が強まったが、自治体が条例で対象施設を限ることを認めるにとどめた。東京都杉並区は条例を定め、埼玉県朝霞市は検討中だが、こうした動きは一部にとどまる見通しだ。内閣府によると、保育施設で昨年起きた死亡事故は、認可保育所(約2万3500カ所)で2件、認可外施設(約7700カ所)で6件。04年からの累計では認可61件、認可外137件だ。都道府県などによる認可外への立ち入り調査は、17年度は対象施設の7割にとどまり、このうち4割超が国の基準に違反していた。ベビーシッターは立ち入り調査の対象外だ。全国保育団体連絡会の実方伸子副会長は「本当に心配。国が責任をもって、子どもの安全と保育の質の確保に向けた対応を早急に講じるべきだ」と訴える。無償化よりも、保育所整備や保育士の処遇改善で、待機児童の解消を優先すべきだとの声はやまない。企業主導型保育所では定員割れや休園などが相次ぎ、審査や指導監査の甘さが問題となっている。課題を残したまま、国と地方を合わせて年8千億円を投じる無償化がスタートする。 *8-3:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/474227 (沖縄タイムス社説 2019年9月22日) [保育士の低賃金]待遇改善待ったなしだ 10月1日の幼児教育・保育無償化まで10日を切った。日本の保育制度の大きな変革だが、制度を支える保育士の待遇の問題が残されたままのスタートとなることに、危機感を覚える。〈沖縄の保育士のリアルな給料 自分は保育経験トータル7年目で(手取り)12万6千354円。生活できません〉県内の認可保育園で働く女性保育士は、総支給額17万1500円の給与明細とともにツイッターでそう発信した。保育士の賃金の低さはかねて問題視されてきた。2018年度の賃金構造基本統計調査によると、県内の保育士の月給は20万8千円。全国平均月給より3万1300円低く、県内全産業の平均を5万7300円下回る。手取りとなるとさらに減り、保育士がツイッターで訴えた「生活できない」はリアルな叫びといっていい。保育士の有効求人倍率は県平均の3倍を超え、仕事はあるが、なり手がいないのが現状だ。県内には保育士の資格を持つ人が2万人以上いるが、およそ半分が、保育士として働いていない「潜在保育士」となっている。子どもの命を預かり、成長を促す保育士。責任が重く、専門性が高い仕事に、賃金が見合っていないと感じる人が多いということだろう。保育士自身が日々の生活に不安を抱えていては、丁寧に子どもたちと関わることもままならない。 ■ ■ なぜ保育士の賃金は低いのか。認可保育園のほとんどを占める私立保育園は、地域や施設規模などを基に国が定め、支給する「公定価格」が運営費の原資になる。国はこれまで増額してきたがまだ低い。各園は公定価格に基づいた委託費を人件費や管理費、事業費に充てるが配分はその園の裁量に任されており、園の状況によって給料が異なる。保育士の平均就業年数に対して処遇改善費が支給されるが、平均10年以上に対する12%で頭打ちのため、経験の長い保育士がいても、園側は昇給させにくい。国は、例えば0歳児3人につき保育士1人などの配置基準を定める。より丁寧な保育をしようと基準以上の保育士を配置すると、1人当たりの人件費が少なくなる。公定価格は、公務員の給与水準を基に八つに地域区分されるが、沖縄は最低水準地域で、最高水準地域に比べ20%も公定価格が低く設定されている。しかも、沖縄の保育士の給与は、同じ地域区分の青森より3万円ほど低いという。沖縄の賃金が際立って低い原因は何か。県はしっかり調査し対策を取る必要がある。 ■ ■ ことし4月時点で、県内の認可保育園142園で314人の保育士が不足している。待機児童数は全国で2番目に多い1702人。保育士がいなければ、ハコがあっても子どもを預かれない。保育士不足は待機児童問題に直結している。無償化で保育ニーズはさらに高まる。子どもたちのため保育士の待遇改善が急務だ。
| 経済・雇用::2018.12~2021.3 | 04:47 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
|
2019,08,30, Friday
 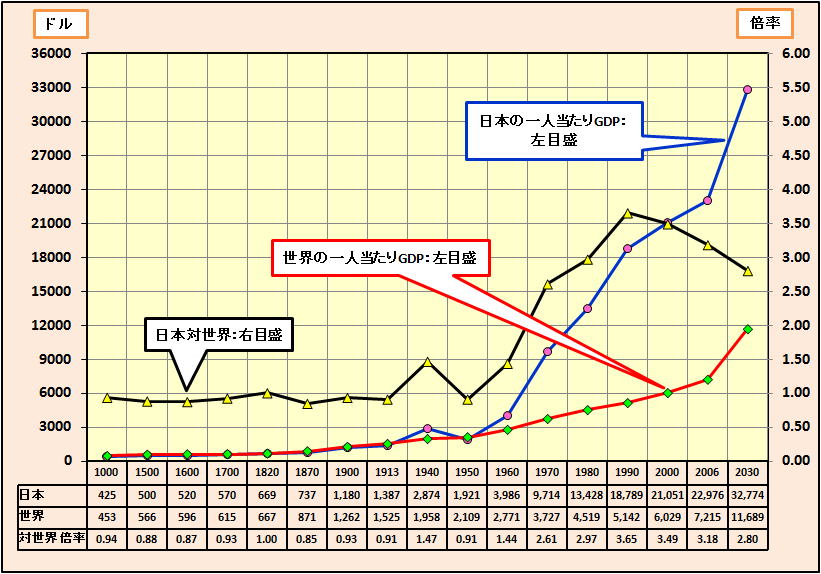 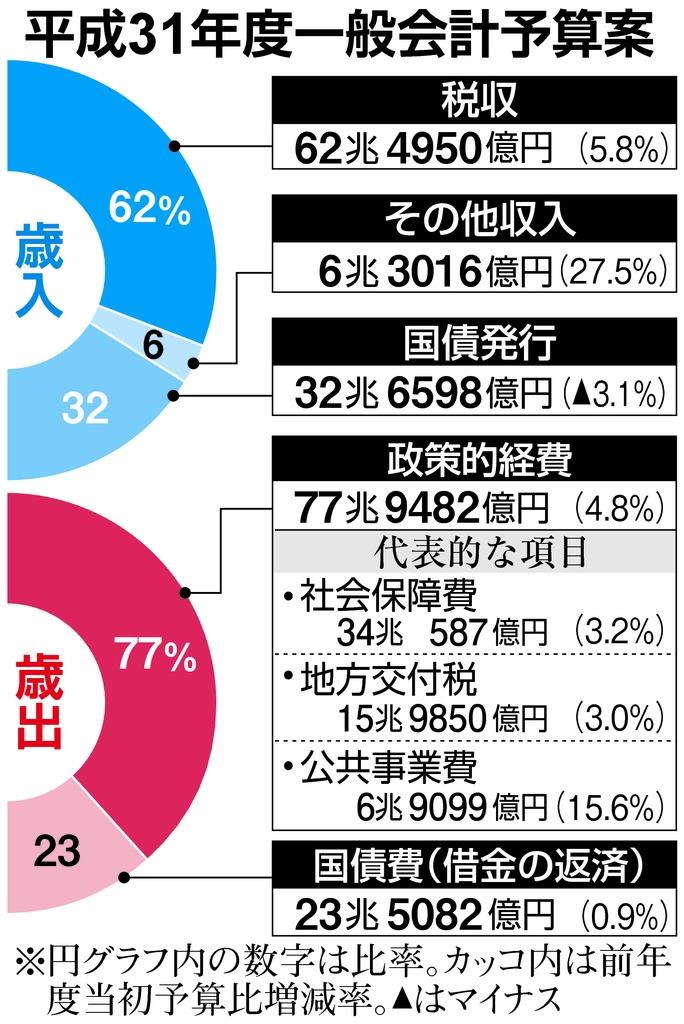  日本の出生数推移 一人当たりGDP比較 2019年度政府予算 2018.12.21産経新聞 (図の説明:左図のように、日本の出生数・出生率は戦後の1947~1949年を最高として漸減しているが、中央の図のように、一人当たりGDPは著しく増加している。個人の豊かさは、一人当たりGDPの方がよく表すが、近年は世界の一人当たりGDPも上がり、世界と比較した場合の日本の一人当たりGDP倍率は下がっている。また、右の2つの図のように、政府支出は過去最高に達しているが、社会保障についてはその充実や高齢者の増加で仕方がない面があるものの、投資に当たらない景気対策と称する生産性の低い支出は国全体の生産性向上の足を引っ張っている) (1)高齢ドライバーに対する運転免許返納の大合唱は正しくないこと 1)高齢者の免許証返納を奨める高齢者いじめ *1-1のように、高齢ドライバーの同一の事故が繰り返し報道され、家族に高齢の親に免許返納を提案させたり、強引に免許証を取り上げさせたりして、高齢者に免許返納させようという動きがある。 報道を信じた家族は、「よかれ」と思って善意で老親に免許返納を奨めるわけだが、同世代の高齢ドライバーによる事故が報じられたからといって、運転の必要性や老化の程度は人によって異なるため、他の高齢ドライバーが起こした事故を個人に敷衍するのは妥当ではない。 さらに、まだ運転できる人に無理に免許を返納させれば、仕事や買い物に支障をきたしたり、高齢者を引きこもりにしたりして、健康寿命を縮める。そのため、「運転の自信を失った」「必要でなくなった」と本当に自分で感じる人以外は、家族の勧めがあっても免許を返納する必要はないと、私は考える。 このような中、*1-5のように、警察庁が、①高齢ドライバーに実技試験を課し ②技能に課題があれば安全機能を備えた車のみに限って運転を認める「限定免許」の対象とする 方針を出した。しかし、教習は、高齢者だけを対象とするのではなく、長くペーパードライバーだった人が再度運転を始める時や自動車の仕組みが大きく変わった時もやる必要があると、私は思う。 なお、高齢ドライバーによる事故には、ハンドルやブレーキ操作ミスが多いそうだが、個人を犠牲にして免許を返納させるよりも、安全装置を導入する方が理にかなっている上、それによって新時代のニーズにあった自動車ができるのである。 2)生産年齢人口にあたる人が起こした事故 しかし、*1-2のような生産年齢人口にあたる人の「あおり運転」もたびたび起こっており、これは、1)とは異なり、意図的であって許し難い。そのため、何故、すぐに対策を講じなかったのかが疑問だ。そして、一般の人が気を付けるべきことは、必ずドライブレコーダーを装備して運転時の証拠を残し、事故時に冤罪を押し付けられないようにすることとなる。 また、*1-3のケースは、ワゴン車とバイクの追突死亡事故が発生し、ワゴン車の運転手はスマホの画面でミステリーやホラー系の漫画を読みながら運転を続け、夜間だったことからその様子がフロントガラスに反射して写り、それが本人の車のドライブレコーダーにはっきりと記録されていたのだそうで、このようにたるんだ人が運転しているのは恐ろしいことである。 3)根本的な解決 自動車は既に贅沢品ではなく生活必需品となっており、とりわけ足の悪い人には便利な移動ツールだ。そのため、私が10年以上前から言っているように、*1-4のような手放し運転できる運転支援システムや安全装置の搭載は、EV・燃料電池車・ガソリン車などのエネルギー源や大型・中型・小型車といった車種を問わず、どの車種でも速やかに行うべきである。 (2)個人情報の無断使用と個人情報保護について 1)就職情報サイト「リクナビ」の「内定辞退率」予測データ販売 日経新聞は、*2-1のように、①就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリアが、学生の同意を得ずに「内定辞退率」の予測データを売っていたこと ②リクナビが就職活動の代表的な情報プラットフォームになっていること ③学生の信頼を裏切ったこと について、「個人情報を扱う自覚はあるか」と厳しく糾弾している。 しかし、*2-2のように、日経新聞は経産省の「信頼ある自由なデータ流通政策」に協力してきた。上の③のように「信頼したから」と言ってそれに応える人ばかりではないし、②のように情報プラットフォームになって多数の情報を扱うからより正確な結果が出せるのであり、購入価値のあるデータを作るには多量のデータを分析することが必要だろう。そのため、「プラットフォーマー」だったことが問題なのではなく、個人情報を他の用途で勝手に使用してよいことにしたのが問題なのである。さらに、①の予測は、AIが統計的に推測できるような“普通”の行動をする人にしか当てはまらないことにも留意すべきだ。 また、2013年にJR東日本が「Suica」の乗降データを匿名化して社外に販売し、個人情報保護に反すると批判が相次いだことについて、*2-3のように、匿名化されたビッグデータでもいくつかのデータを組み合わせれば、高確率で個人を特定できることが指摘されている。つまり、「匿名加工すれば個人情報の扱いではなくなり、本人の同意がなくても第三者に提供できる」という指針が間違っているのだ。 2)医療ビッグデータの活用!? 日経新聞は2019年8月21日の社説で、*2-4のように、「①医療ビッグデータを使いこなせ」「②高齢化が進む中、効率的で質のよい医療の提供は重要な課題だが、それを支える検査や治療の記録などの膨大な医療ビッグデータの活用が進まない」「③デジタル技術が生かされておらず、宝の持ち腐れで、医療産業の国際競争力も低下しかねない」などと記載している。 しかし、①は個人情報の悪用に繋がる可能性が高く、②③はデータ提供者の同意の上で治験を行ったり、医療保険会社が使用された薬と治療効果を比較したりすれば、ビッグデータでなくても検証できる。さらに、「新薬開発のためなら個人の権利を無視してもよい」と考える製薬会社があるとすれば、その会社の薬が患者の側に立って開発されたとは思えない。 そのため、厚労省の有識者会議で「用途に公益性があると認められた場合」といってもそれがどういう場合かを吟味する必要があるくらいで、私は、EUのやり方の方が見識があると思う。日本もルールづくりに関与したいのなら、まず「人権」「個人情報」「個性」「差別」などの正しい意味を理解してからにすべきだ。 3)ゲノムデータの収集 東芝は、*2-5のように、従業員のゲノムデータを収集して数万人規模のデータベースを構築するそうだ。断りにくいという社内のプレッシャーはあるものの、これは希望者を対象にしている点で許せる。しかし、個人の生活や遺伝的要因を会社に調べられるのは、(どうにでも使えるという)リスクがある。 なお、東芝は、これによって多くのデータを分析し、特徴別に複数のパターンに分けることで、最適な予防法・治療法の開発に繋げることが可能になるとしているそうだ。 4)マイナンバーカードによる強引なデータ収集 政府は、*2-6のように、個人番号が記載されたマイナンバーカードの普及率を高めるため、年度末までに国・地方の全ての公務員にマイナンバーカードを取得させるそうだ。 国がそうまでするのは、国民一人一人に割り当てられた12桁のマイナンバーで年金・税金・社会保障などを照合し、国民を効率的に監視下に置くのが目的だ。そのため、マイナンバーカードの取得が進まないのであり、その国民の判断は、国が率先してビッグデータを活用して個人情報を使うことを奨めている人権無視の政策を進めていることから見ても正しい。 (3)論調に見る「個人の権利」「社会保障」の軽視 1)年金制度は効率的に運用されているか 日経新聞はじめ多くのメディアは、*3-1のように、①日本の社会保障は「中福祉・低負担」で ②その差を財政赤字が埋めているため ③負担を中レベルに引き上げるべきだ とする。しかし、ここには年金保険料を支払ってきた割に年金をもらえているか、つまり、i)年金資産運用の適格性 ii)年金保険料集金の網羅性 iii)年金管理事務の効率性 iv)年金関係法令の妥当性 に関して検討がなく、足りなくなれば負担増・給付減して国民にしわ寄せすればよいという省庁の発想の受け売りがあるにすぎない。 私から見ると、i) ii)とも不十分で、iv)の年金関係法令が“きめ細やか”と表現される無意味な複雑さも手伝って、iii)の効率性は著しく低い。また、*3-3のように、未納者が多い上に未納者データを紛失したりなど、年金保険料をきちんと集めて管理する風土があるのか否かが疑問という民間企業ではありえないようなことが続いているわけである。 2)支え手の拡大 上記、1)のiv)の年金関係法令に関しては、*3-4のように、支え手を拡大するために、会社員らの入る厚生年金の適用を拡大し、高齢者やパートらの加入を増やす改革に乗り出すとのことだが、パートだから厚生年金の適用がなかったというのは、パート労働者(多くは女性)の生活を全く考えていない法体系だったということだ。 そのため、*3-2の「支え手」を増やす改革を急ぐのは賛成であるものの、「支払われた年金保険料を誠意をもって大切に管理し、できるだけ多くの年金支払いをする」というコンセプトが共有されないまま、負担増・給付減をいくらやっても無駄遣いが増えるだけだと考える。 「少子高齢化の進行で『支える側』の現役世代が減り、『支えられる側』の高齢者の割合が増えた」というフレーズも何度も聞いたが、それは人口構成を見れば1980年代からわかっていたことで、1985年に積立方式を賦課課税方式に変更してばら撒くのではなく、積立方式のまま年金支払いに十分なだけの積立金を備えておくべきだったのだ。 また、「現役世代の手取り収入に対して厚生年金の給付水準『所得代替率』は50%以上あればよい」というのも理由が不明であり、政府の言う「モデル世帯」に国民の何%が当たるのか、さらに国民の一部に関する試算だけをやればよいのか についても疑問である。 平均寿命や健康寿命が延びたので、私は、高齢者も*3-5のように68歳と言わず、75歳であっても「支える側」に入れることにやぶさかではないが、そのためには、就業における高齢者差別がなく、気持ちよく働ける仕事のあることが大前提になるわけだ。 <高齢者いじめ> *1-1:https://www.sankei.com/west/news/190603/wst1906030013-n1.html (産経新聞 2019.6.3) 高齢者の免許返納、説得のポイントは 相次ぐ高齢ドライバーによる事故で、免許証の自主返納を呼びかける動きが広まっている。高齢の親に返納を提案する家族も増えているが、応じないケースが少なくない現状も。半ば強引に免許証を取り上げるなどの強行な手段も考えられるが、家庭内でのトラブルにもつながりかねず、高齢者自身が納得した上で返納することが重要な課題になる。どうすれば説得を受け入れてもらえるのか。「免許を返納した方がいい」。大阪府内に住む80代男性は昨年、同居する50代の息子から免許の返納を持ちかけられた。同世代の高齢ドライバーによる事故が相次いで報じられていたが、それでも返納には抵抗があった。しかし息子も譲らず、妻や孫も加勢。説得は最終的に男性が返納に応じるまで続いたという。「説得に悩む家族の話はよく聞くが、頭ごなしに返納を求めるだけでは、かえってかたくなになってしまう」。高齢社会の問題に詳しいNPO法人「老いの工学研究所」の川口雅裕理事長(55)は指摘する。警察庁が平成27年に75歳以上のドライバーと免許返納者約1500人ずつを対象とした調査では、「家族らの勧め」を返納理由とした人が33%で最も多く、「運転への自信を失った」や「必要性を感じなくなった」を上回った。一方、運転を継続しているドライバーは67・3%が「返納しようと思ったことはない」と回答。「家族の勧めで返納について考えたことがある」は4・7%にとどまっている。高齢者の車の運転に対するスタンスはさまざまで、単なる移動手段としてではなく、運転そのものを楽しみに感じていたり、苦労して手にした免許や車そのものに特別な思い入れを抱いていたりするケースもある。川口さんは「まずは免許や車が親にとってどういう存在なのかを理解することが大切」と話す。車を使う頻度や目的によって、効果的な説得方法は変わってくる。例えば、免許返納者への公共交通機関やタクシーの割引などのサービスは、移動手段として車を利用してきた人には有効だ。一方で、運転自体を趣味にしている場合はメリットとは感じず、車に思い入れがある場合、その“喪失感”を埋めることにはならない。重要なのは、返納後の生活に対して「ポジティブな提案」をすること。車の維持費に充てていた資金で旅行に行くことや、日常生活での新たな趣味や地域活動への参加を提案することが挙げられる。川口さんは「親と同居している人もいれば、疎遠になっている人もいる。返納が必要だと感じたら、まずはコミュニケーションを取ることから始めてみてほしい」と話している。 ■年間40万人超返納も後絶たぬ事故 運転免許の自主返納制度は平成10年に始まった。スタート初年は年間2596人だったが、30年には42万1190人が返納。このうち、75歳以上が半数以上を占める。返納が進む一方、高齢者による事故は後を絶たない。警察庁の調査では、29年の免許保有者10万人当たりの死亡事故件数は85歳以上が年間14・6件。運転免許を取得したばかりの16~19歳の11・4件を大きく上回った。また、75歳以上と75歳未満で比較すると、75歳未満が3・7件なのに対し、75歳以上は7・7件と2倍以上になり、高齢になるほど事故が多くなることが明らかになった。高齢者の免許保有者も増えており、75歳以上の免許保有者は19年に283万人だったのが、30年には564万人に。このうち、80歳以上は98万人だったのが、227万人となっている。 *1-2:https://digital.asahi.com/articles/ASM8N55NSM8NUJHB017.html (朝日新聞 2019年8月20日) 「車遅く頭にきた」容疑者供述 あおり運転自体も捜査へ 茨城県守谷市の常磐自動車道であおり運転を受けた後、男性会社員(24)が殴られ負傷した事件で、傷害容疑で逮捕された会社役員宮崎文夫容疑者(43)=大阪市東住吉区=が「男性の車が遅く、進行を妨害されたと感じて頭にきた」と話していることが、捜査関係者への取材でわかった。男性のドライブレコーダーには、宮崎容疑者が数キロにわたってあおり運転をする様子が映っていたという。県警は20日、宮崎容疑者と、あおり運転の際に同乗し同容疑者をかくまったとして犯人蔵匿・隠避容疑で逮捕された喜本(きもと)奈津子容疑者(51)を送検した。捜査関係者によると、宮崎容疑者は「車をぶつけられたので殴った」と傷害容疑について認める一方、「危険な運転をしたつもりはない」と供述。しかし県警は、ドライブレコーダーの映像などから危険な運転があったのは明らかとみている。そのため、傷害容疑とともに、あおり運転そのものについても、道交法違反(車間距離保持義務違反など)や、あおり運転で被害者に恐怖心を与えたとして暴行容疑などを視野に調べる方針だ。一方、より刑罰の重い自動車運転死傷処罰法の危険運転致傷の適用について、捜査幹部は「現時点で法律の要件を満たす上で困難な部分がある」との見方を示している。同幹部は「今回はあおり運転後に、手で殴りけがをさせた事案で、危険な運転行為で直接的に衝突などの事故により負傷したものでない」と話す。自室で宮崎容疑者をかくまったとして逮捕された交際相手の喜本容疑者は、高速道路上で宮崎容疑者が殴る様子を携帯電話で撮影していたことを認めている。県警は、宮崎容疑者の暴行を止めなかったなどとして、傷害幇助(ほうじょ)容疑も視野に調べを進めている。 *1-3:https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagiharamika/20190630-00132169/ (Yahoo 2019/6/30) スマホ漫画で追突死亡事故 真実を明らかにしたのはドラレコだった ■楽しかった夫婦ツーリングが、一瞬の追突事故で暗転 まずは、この写真をご覧ください。高速道路の事故現場から引きあげられた250ccのオートバイが、レッカー車の荷台に横倒しの状態で積まれています。ハンドル周りは原形をとどめず、車体も大破しています。つい数時間前まで、このバイクには39歳の女性が乗っていました。夫婦で2台のバイクを連ね、ヘルメットに装着された無線機で楽しい会話を交わしながら、泊りがけのツーリング……。しかしその楽しい旅は、自宅まであと少しというところで断ち切られてしまったのです。2018年9月10日、午後9時11分、事故は関越自動車道下り線、大和PAから小出ICの間の見通しのよい片側2車線の直線道路で発生しました。夫の井口貴之さんは左車線を、妻の百合子さん(当時39)はその後ろを走っていました。制限時速80キロの区間でしたが、百合子さんは時速約70キロで走行していたところ、後ろから運送会社のワゴン車が時速100キロのスピードで追突。百合子さんは避ける間もなく、そのままワゴン車の前後輪に轢かれたのです。 ■高速道路上に横たわる妻の変わり果てた姿 無線での会話が、突然の百合子さんの悲鳴とともに途切れたことに異変を感じた貴之さんは、すぐに自分のバイクを路肩に止め、百合子さんの姿を確認しに後方へと戻りました。しかし、目に入ったのは無残な光景でした。百合子さんは40~50秒後に走行してきた後続車にも轢かれ、脳挫傷等の致命傷を負い、命を奪われたのです。現場はその後、7時間にわたって通行止めになったほどの大事故でした。事故の翌朝、ワゴン車の運転手は、「なぜこんなことになったんだ」と詰め寄った貴之さんにこう説明したそうです。「対向車に気を取られて、わき見してしまった」 。結局、運転手は逮捕されることはなく、事故処理されました。 ■ドライブレコーダーに写っていた「スマホ漫画」の動かぬ証拠 ところが、事故から1週間後、思わぬ展開を見せます。新潟県警は、ワゴン車を運転していた男性(当時50)を、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)の疑いで逮捕したのです。夫の貴之さんは語ります。「逮捕後、警察からその理由を聞いて驚きました。わき見という当初の説明は全くの嘘で、加害者は、高速道路に入ってからもスマホの小さな画面で、ミステリーやホラー系の漫画を読みながら、十分に前を見ず運転を続けていたそうです。そして、前方の妻のオートバイに気づかずに追突したのです」 。実は、加害者がスマホで漫画を読み続けていたことは、本人の車のドライブレコーダーにはっきりと記録されていました。夜間だったことから、その様子はフロントガラスに反射して写っており、約4時間にわたってその映像が残されていたというのです。この映像をもとに警察が加害者から事情を聞いたところ、本人が「わき見」ではなく「ながらスマホ(漫画読み)」をしていたことを認めました。また、加害者の車には、運転手の目の動きを感知し、居眠りや脇見を3秒以上検知すると警報ブザーが鳴る装置も取り付けられていましたが、それすらも無視し、マンガを読みふけっていたといいます。時速100キロの車は、10秒間に約280メートル進みます。高速道路で10秒以上前方から視線をそらすことが、どれほど危険な行為なのか……。検察官は、「これは目隠しをして走っているのと同じだ」と述べたそうです。夫の貴之さんは、今回、私に直接連絡をくださった理由について、こう話してくださいました。「加害者の言い分だけで処理をされた交通事故のことを『Yahoo!ニュース』の柳原さんの記事で知り、妻の事故と全く同じだと思いました。もし、ドライブレコーダーに映像が写っていなければ、この事故は単純なわき見運転で処理されていた可能性が大だったでしょう。なぜこんなことで妻は殺され、私たちの人生が壊されなければならなかったのか……。私は、ながらスマホの危険性、そして加害者が嘘をつくことの悪質性を広く世間に知っていただきたいと思うのです」 ■マンガを読みながらの運転は悪質な「危険運転」 この事故は現在、新潟地裁長岡支部で刑事裁判が進行中です。夫の貴之さんは、事故後、心身に大きなダメージを受け、仕事復帰にも長い時間がかかったそうですが、被害者参加制度を利用してご自身も検察官と共に法廷に立ち、6月24日には被告に対して直接尋問を行いました。被告が運送業務に携わるプロドライバーであるにもかかわらず、スマホで漫画を読みながら高速走行をしていたこと、そして、事故直後にそのときの閲覧履歴を消去するなどして事実を隠し、「対向車線のほうをわき見していた」と嘘の供述をしていたことの悪質性に言及し、危険運転致死など重い罪を課してほしいと述べたそうです。「ながらスマホ」による事故のニュースをたびたび耳にする昨今ですが、実際に車を運転していると、信号待ちなどで明らかにスマホに夢中になっているようなドライバーをたびたび見かけます。ドライバーはこの行為の危険性を改めて認識すべきでしょう。ましてや、スマホの小さな画面でコマ割りされた漫画を読みながら、クルマを運転するなど論外です。次の裁判は、7月16日。被告人に対しての論告求刑が行われる予定です。 *1-4:https://news.livedoor.com/article/detail/16991243/ (読売新聞 2019年8月28日) 高速「手放し運転可能」、BMWが国内初実用化 独BMWの日本法人は27日、渋滞した高速道路で手放し運転ができる運転支援システムの搭載を今月から始めたと発表した。同社によると、手放し運転ができる自動車の実用化は国内で初めてという。支援システムはドライバーの疲労軽減が目的で、安全確認は運転手が行う。ドライバーが前方を注視しているかどうかを車内カメラで監視し、よそ見や居眠りの状態が続いたと判断されると警告音などで注意を促す。時速60キロを超えた場合も、ハンドルに手を添える必要がある。報道陣向けの試乗会では、高速道路で前の車に追従して走行し、暗いトンネル内でも車線をはみ出すことはなく、加速や減速もスムーズにこなした。7月生産分以降の最新型「3シリーズ」や「8シリーズ」などに標準装備している。すでに購入した人も、販売店で制御ソフトの更新を有償で行えばシステムが使える。日産自動車も高速道で手放し運転が可能な新型「スカイライン」を9月に発売する。高精度な3次元の地図データなどを駆使して実用にこぎ着けた。 *1-5:https://r.nikkei.com/article/DGXMZO49134150Z20C19A8MM0000?s=1 (日経新聞 2019年8月29日) 高齢ドライバーに実技試験 警察庁、事故対策へ検討 高齢ドライバーによる交通事故対策として、警察庁は運転技能を調べる実車試験を導入する検討を始めた。高齢者を対象にブレーキやアクセルの操作を試験し、技能に課題があれば、安全機能を備えた車のみに限って運転を認める「限定免許」の対象とする。高齢者による事故の原因は操作ミスが多く、事故のリスクを軽減する狙いがある。2020年度予算の概算要求に調査費2700万円を計上する。高齢者向けの限定免許は早ければ21年度に創設される見通しで、実車試験も同時期の導入を念頭に制度設計を進める。現在は75歳以上のドライバーを対象に免許更新時に認知機能検査を義務付け、検査を経て医師に認知症と診断されれば免許取り消しか停止になる。ただ認知機能に問題がなくても運転技能が衰えているケースがあり、専門家から実車試験の導入を求める声が上がっていた。実車試験の対象者は認知機能検査を受ける高齢ドライバーを想定。アクセルとブレーキの踏み間違いや、対向車線へのはみ出しといった危険な運転の兆候がないかどうかなどを調べる。20年度の調査ではこうした危険な運転について、車の安全機能でどの程度制御できるかを実証する。限定免許の創設は、相次ぐ事故を受けて政府が6月に決めた緊急対策に盛り込まれた。ドイツやスイス、オランダといった先行して限定免許を導入している国では、医師による診断や実車試験の結果などに基づき対象者を決めている。警察庁はこうした各国の事例を基に、新たに導入する限定免許の対象者を判断する基準として、実車試験の結果を活用する方針だ。具体的な試験の項目などについては、対象となる高齢者の負担が重くなりすぎないように配慮する。75歳以上の運転免許保有者は2018年末時点で563万人で、社会の高齢化とともに20年に600万人に増えると推計される。75歳以上による死亡事故は18年に460件発生し、全体に占める割合(14.8%)は過去最高だった。東京・池袋で4月に80代のドライバーの車が暴走し母子2人が死亡するなど、重大事故も後を絶たない。19年上半期(1~6月)に発生した高齢ドライバーによる事故を警察庁が分析したところ、34%はハンドルやブレーキの操作ミスが原因だった。自動車各社は操作ミスの影響を軽減する安全装置の導入を急いでおり、新車の17年の搭載率は加速抑制機能が65.2%、自動ブレーキが77.8%だった。後付けの装置の商品化も広がっている。実車試験の導入を巡っては警察庁が17年に設置した有識者会議の分科会でも議論されたが、「どのような運転が事故のリスクが高いと言えるかという判断基準が明確でない」などの課題が示され、結論は出なかった。 <個人情報の無断使用と個人の特定> *2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190829&ng=DGKKZO49110140Y9A820C1EA1000 (日経新聞社説 2019.8.29) 個人情報を扱う自覚はあるか 個人データを扱う企業としての自覚を問われている。就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア(東京・千代田)が学生の同意を得ずに「内定辞退率」の予測データを売っていた問題で、政府の個人情報保護委員会が是正を求める勧告を出した。人材サービスへの信頼が損なわれれば、人的資源を効率的に配分する柔軟な労働市場づくりにもマイナスだ。同社は影響の大きさを認識し、再発防止に向けた具体策を早急に示すべきだ。リクナビに登録した学生がどの企業の情報を閲覧したかを、同社は人工知能(AI)で分析。それをもとに内定を辞退する確率を推計するサービスを始め、計38社と契約した。これまでに約8千人分の個人データを本人の同意を得ないまま提供していた。個人情報保護法違反と判断されたのは当然だ。十分に説明しないまま分析に使ったデータも約7万5千人分にのぼり、個人情報保護委は改善を指導した。見過ごせないのはリクナビが就職活動の代表的な情報プラットフォームになっている点だ。学生の間では、これを使わずに就活を進めるのは難しいとの声が多い。他のサイトに比べた優位性を利用して個人データを集めていたのだとしたら、まさに学生の信頼を裏切る行為である。面接でAIが応募者と対話して適性を探るなど、採用選考や人事管理にIT(情報技術)を活用する動きが広がり始めている。業務効率化につながるが、個人データの扱いが公正なことが前提だ。リクルートキャリアには徹底した再発防止策を講じる責任がある。学生にとっては、自分のデータがどの企業に提供されていたのかなどが不明なままだ。同社は説明を尽くさなければならない。個人データの購入企業にも説明責任がある。合否判定に使っていた例は出てきていないが、データの購入目的について、学生の納得のゆく情報開示が求められる。 *2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190820&ng=DGKKZO48719040Z10C19A8MM8000 (日経新聞 2019年8月20日) ワタシという商品(上) リクナビのつまずき 革新の波、使う知恵試す データエコノミーの落とし穴があらわになった。人工知能(AI)が個人の心理を読む時代が現実となり、日本では学生データの利用を巡る「リクナビ問題」が起きた。個人情報を扱う責任を負いながら、便利なデータ社会を実現できるか。課題に直面している。8月上旬、経済産業省にいら立ちが広がった。「最悪のタイミングだ」。職員の一人は唇をかんだ。政府が20カ国・地域首脳会議(G20サミット)で「信頼ある自由なデータ流通」を提唱。リクナビ問題が発覚したのは、経産省がこの構想を後押しするデータ活用事例集の公表準備を進めているさなかだった。 ●年80万人が利用 就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア(東京・千代田)は2018年以降、学生の十分な同意を得ずに内定辞退率の予測データを38社に販売するなどしていた。年80万人が使うなくてはならない就活の「プラットフォーマー」が震源地だったことで問題は深刻になった。トヨタ自動車やNTTグループ、三菱電機などデータを購入した企業も説明に追われる。日本企業はデータ利用で米国勢などに出遅れ、その経験不足は個人情報の保護意識も鈍らせた。環境や人権に配慮した経営で知られる英蘭ユニリーバは、2年前からAIを採用に使う。「欧州本社も加わり、情報の用途や対象を何重にも確認する」。日本法人でデータ保護を統括する北島敬之さんは話す。データエコノミーの進展は、新たな技術を次々と生んでいる。個人の信用や将来性まで点数化されるようになったが、問われるのは使い手である人の知恵だ。米カリフォルニア州は20年の新規制で、AIで趣味や思想を割り出す手法を制限する。欧州もAIの決定に異議を唱える権利を定めた。慶応大学の山本龍彦教授は「日本は企業倫理も法制度もAI時代に追いついていない」と指摘する。 ●「スイカ」の教訓 マッキンゼー・アンド・カンパニーの推定では、30年までにAIは世界で1400兆円の経済活動を生む。日本も立ちすくんでいては巨大な情報鉱脈にたどり着けない。教訓は13年の「スイカ・ショック」だ。JR東日本がIC乗車券「Suica」の乗降データ活用に動いた直後だった。匿名化して社外に販売したが、説明が足りず個人情報保護に反すると批判が相次いだ。多くの企業が個人データを使う新事業の立ち上げに慎重になった。「国が白黒の判断を下さず、グレーのままにしたのが問題だった」。国立情報学研究所の佐藤一郎教授は振り返る。ルールが曖昧なままでは前に進めない。リクナビも丁寧な説明が欠かせなかった。適切な手続きを踏めば、学生を特定しない企業単位の辞退数予測などの形で、人材難の各社が機動的な採用に使えた可能性がある。個人も意識を高める必要がある。「後輩には他のサイトと使い分けるよう伝える」。早稲田大学4年の女子学生は憤る一方、内定を得たのもリクナビのおかげと割り切り、最適解を探す。個人情報はデータの世紀の資源だ。使いこなせば、豊かさをもたらす。「ワタシという商品」を巡るトラブルは問題解決の好機だ。企業も政府も個人も、やるべきことは見えている。 *2-3:https://digital.asahi.com/articles/ASM8B2394M8BULBJ002.html?iref=pc_extlink (朝日新聞2019年8月11日)進む匿名データの第三者提供に警鐘 日本でも特定の恐れ 客の購入動向やニーズに応じた商品やサービスを薦めたり、企業の業務の効率化につながったり。ビッグデータは幅広い分野で利活用が広がっているが、前提となるデータの匿名性は保たれているのか――。今回の論文は警鐘を鳴らす。 ●ビッグデータ、匿名化でも高確率で個人特定 海外で指摘 欧米では、先月発表されたこの研究内容は関心を集めた。米紙ニューヨーク・タイムズは「あなたのデータは匿名化されている? だが科学者はあなたを特定できている」、英紙ガーディアンは「データは指紋 ネットの世界ではあなたはあなたが思っているほど匿名ではない」との見出しでそれぞれ報じた。匿名データからの個人の特定をめぐっては、過去に別の研究者が、公開情報に含まれる生年月日、性別、郵便番号から米州知事の病歴記録を特定した。また、有料動画配信サービス・ネットフリックスが提供した匿名化された閲覧履歴情報を使い、研究者が公開の映画レビューサイトの内容と照合して、個人を特定したケースなどもある。米国ではデータがオンライン公開されることが多く、属性にまつわるさまざまなデータが日本より入手しやすい事情はある。ただ、日本でも匿名化して、まとめられたビッグデータの提供が進みつつあり、対岸の火事とはいえない。個人情報保護法が改正され「匿名加工情報」の考えが導入された。2013年、JR東日本が外部に販売していたICカード「Suica(スイカ)」の乗降履歴から、個人が特定される恐れがあると批判を浴びたことがきっかけだった。匿名加工には基準があり、特定の個人の識別につながる氏名や生年月日、住所などの全部または一部を削除したり、住所を県や市までにあいまいにしたりといった要件を満たせば個人情報の扱いではなくなり、本人同意がなくても第三者に提供できる。ただ、匿名加工に関する政府の指針は、あらゆる手法によって特定できないということまでは求めず、現在の一般的な技術レベルで特定できなければよいとしている。また、匿名化の方法の細かいところは必ずしも明確ではないとされる。産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員は、個人が識別されない適切な匿名加工の必要性を強調。そのうえで「論文が指摘している問題は匿名加工情報の制度設計でも議論された。一人しかいないようなデータがあれば、どうしてもリスクが高くなる」と話す。個人を特定するために、例えば交通系ICカードの乗降履歴と、別会社のポイントカードの購買履歴などを突き合わせる行為は「照合」と呼ばれ、個人情報保護法で禁じている。政府の「パーソナルデータに関する検討会」の技術担当会合で主査を務めた国立情報学研究所の佐藤一郎教授は、「購買履歴や治療履歴などは人によって大きく異なるので、(特定につながる)リスクがあると知っておいてほしい」と語る。ただ、データの削除や、あいまいにする加工を進めすぎると、ビッグデータ活用の芽を摘むことになる。国の個人情報保護委員会の担当者は「個人情報保護と利活用のバランスを取り、最新の技術動向も注視していきたい」と話す。 *2-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190821&ng=DGKKZO48773980Q9A820C1EA1000 (日経新聞社説 2019年8月21日) デジタル社会を創る 「医療ビッグデータ」を使いこなせ 高齢化が進むなか効率的で質のよい医療の提供は重要な課題だ。しかし、それを支える検査や治療の記録など膨大な「医療ビッグデータ」の活用が進まず、デジタル技術が生かされていない。宝の持ち腐れでは、医療産業の国際競争力も低下しかねない。 ●新薬開発に使いにくく 医療ビッグデータは問診記録や検査結果、投薬情報など多岐にわたる。個人情報として慎重な取り扱いが必要だが、新薬開発や病気予防、健康管理に役立ち医療費抑制にもつながると期待される。国は2018年、個人を特定できないよう医療情報を匿名化して使う仕組みを定めた「次世代医療基盤法」を施行した。医療ビッグデータの利用推進が目的だ。だが製薬企業などにとって使い勝手が悪いという。匿名化したデータでは病気ごとの患者数や薬の処方実績などの統計は出せても、一人ひとりの薬の効き目や症状の推移を把握できないからだ。医療情報は従来、活用よりも保護を重視する考え方が強かった。発想を変えて、十分な情報漏洩対策は施しつつも、創薬などのニーズに即した活用をもっと重視した制度設計にすべきだろう。日本には世界有数の規模を誇る診療報酬明細書(レセプト)の情報を集めた「ナショナル・データベース」がある。ことし5月の法改正で介護データと照らし合わせて解析できるようになった。一歩前進だが、制約はなお大きい。厚生労働省の有識者会議で用途に公益性があると認められた場合にしか、企業は利用できない。自社製品の開発や販売に生かせなければデータの魅力は薄れる。大学や研究機関でも、認められた人が専用の部屋でネットに接続できない端末でのみ使える。クラウドを上手に活用し利便性を高めるなど改善の余地は大きい。電子カルテの情報を使いこなすのも大きな課題だ。記載の仕方が病院や担当科ごとに異なり、国の標準化計画は進展が遅い。医療現場は診療業務に追われシステム改修の余裕がないというが、それだけではない。縦割り組織やメーカーの顧客囲い込み、研究者によるデータ独占など、あしき慣習を絶つ必要がある。医薬品医療機器総合機構(PMDA)は18年から、全国23の病院の協力を得てレセプトと電子カルテの情報の統合データベースを運用し始めた。副作用の把握を目的としているが、用途や対象病院の拡大を検討してはどうか。利用価値は高いのに基盤整備が途上の分野もある。コンピューター断層撮影装置(CT)や磁気共鳴画像装置(MRI)による診断画像のデータベース構築だ。画像をAIに学習させ、がんや脳疾患の診断を支援するサービスが大きく伸びると予想される。信頼できるデータが豊富なほど診断精度は上がる。ところが、多くの大学や病院がもつ画像は紙焼き写真のみで、もとになるがん組織の保存状態も悪い。関係学会による画像のデジタル化を国が継続的に支援すべきだ。 ●国際ルール積極関与を 今後は遺伝子データの収集も進む。19年から全国の拠点病院で、がん患者の遺伝子を解析して最適な治療薬を探す「がんゲノム(全遺伝情報)医療」が始まった。一定の条件を満たせば公的保険の対象となり、年間数万人分の解析が実施される見通しだ。国立がん研究センターは集約したデータを製薬企業などに最大限開放し、がんの新薬開発などに生かしてほしい。米国のように、データの提供サービスに民間の参入を認めるのも検討に値する。身近なところでは、スマートフォンや腕時計型センサーによる心拍数や血圧、体温、血糖値などの測定が広がり、データが集まりだしている。病気の発症や進行を遅らせ、健康寿命を延ばす研究などに生かせる。こうした遠隔の測定や投薬管理サービスでは米欧のIT企業や製薬企業が先行する。日本人のデータが知らぬ間に海外に流出する可能性もある。データ利用に関する同意項目などに、一人ひとりが注意する習慣をつけたい。個人情報に配慮しながら国境を越えて医療データをやりとりする、データシェアリングの方式を標準化する動きも米欧を中心に活発になってきた。日本も率先してルールづくりに加わるべきだ。 *2-5:https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/04940/ (日経BP 2019/5/15) 東芝が従業員のゲノムデータを収集へ、数万人規模のデータベース構築 東芝は、「東芝Nextプラン」で新規成長事業の1つに位置付けた精密医療の取り組みの一環として、日本人に特徴的な遺伝子を効率的に解析する「ジャポニカアレイ」によるゲノムデータの収集開始を決定した。また、医療分野のスタートアップ投資に実績のあるBeyond Next Venturesと業務提携契約を締結した。東芝グループは、2018年11月8日に全社変革計画「東芝Nextプラン」を発表し、「超早期発見」「個別化治療」を特徴とした精密医療を中核とする医療事業への本格的な再参入を表明した。また、東芝のDNAであるベンチャースピリットを呼び覚まして新規事業を創出する新たな仕組みとして、100億円規模のコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)機能を導入している。疾病は個人の生活パターンや遺伝的要因(体質)によって異なるため、より多くのデータを分析し、特徴別に複数のパターンに分けることで、最適な予防法・治療法の開発につなげることが可能となる。「ジャポニカアレイ」によるゲノムデータの収集開始はその第一歩で、国内グループ従業員の希望者を対象に、ゲノムデータや複数年の健康診断結果などを含む数万人規模のデータベースを構築する。これにより東芝は、「予防医療」の実現に向けた研究開発を、医療研究者をはじめとする医療・ライフサイエンスに携わる機関や企業と共同で推進する。また、精密医療事業の事業化や収益化には社外の力を積極的に活用することも重要となることから、Beyond Next Venturesとの連携を通じ、優良な医療系ベンチャー企業の探索や協業の検討を推進していく。このほか東芝は、精密医療事業を本格的に推進するため「一人ひとりのクオリティ・オブ・ライフ(QOL)の向上を応援します」「積み重ねた技術力と、新たなパートナーシップでこれからの先進医療・ライフサイエンスを支えます」「次の世代も見据えた予防医療にデジタルの力を活かします」の3つを目標とする「精密医療ビジョン」を新たに作成した。東芝グループは、このビジョンのもとに予防から治療にわたる複数のテーマで要素技術などの技術開発に着手しており、研究から実用化に向けたさまざまなパートナーシップを組みながら事業の成長を目指す。 *2-6:https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20190821/KT190820ETI090002000.php (信濃毎日新聞 2019年8月21日) マイナンバー 強引なカード普及促進策 個人番号が記載されたマイナンバーカードの普及率を高めるため政府は年度末までに国と地方の全ての公務員に取得させる考えだ。そうまでする必要があるのか。カードの普及が自己目的化しているかの強引なやり方には疑問が拭えない。国、地方それぞれの共済組合から職場を通じて交付申請書を配布し、手続きを促す。申請書には家族分を含め、あらかじめ名前などを印字する。霞が関の中央省庁で始めている身分証との一体化も出先機関や自治体に順次広げる。実質的な取得の義務化だ。マイナンバーは、国民一人一人に割り当てられた12桁の番号である。年金や税金などの個人情報を番号で照会し、事務を効率化するとして2016年1月に導入された。預金口座にも適用し、国民の所得や資産を正確につかむことで脱税などを防ぐことも狙う。希望者には、顔写真付きのICカードが交付される。番号のほか氏名、住所、生年月日が載り、身分証明書になる。政府は、22年度にほとんどの住民がカードを持つことを想定するものの、現状は程遠い。交付は今月8日時点で1755万枚、人口比で13・8%にとどまる。申請書を受け取った公務員は提出を拒みにくいだろう。公務員だからといって、本人の希望が前提であるカード取得を強いていいのか。まして扶養家族まで対象に含めるのは普及促進の度が過ぎる。内閣府の世論調査では、カードを「取得していないし、今後も取得する予定はない」との回答が半数を超えている。理由は「必要性が感じられない」が最多で「身分証になるものは他にある」「情報漏えいが心配」と続いた。利点が乏しい一方で不安が残る制度―。国民のそんな受け止めが見て取れる。公務員への働き掛けのほかにも政府は普及策をあれこれ打ち出している。消費税増税に伴う景気対策ではカードを活用した「自治体ポイント」を計画する。21年には過去の投薬履歴を見られる「お薬手帳」の機能も持たせる。カードの利点をアピールしようと活用範囲を拡大していけば、その分、情報漏れや不正利用の心配が膨らむ。脱税防止といった本来の目的がかすんでもいく。普及を図りたいなら、強引な促進策ではなく、制度への国民の理解を広げる努力が先決だ。何のための個人番号か、なぜカード取得を促すのか。出発点に立ち返って丁寧に説明するべきである。 <個人の権利や社会保障の軽視> *3-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190820&ng=DGKKZO48739010Z10C19A8EN2000 (日経新聞 2019年8月20日) 社会保障を巡る認識ギャップ 日本の社会保障は「中福祉・低負担」であり、その差を財政赤字が埋めている。これに対して専門家は負担を中レベルに引き上げるべきだと考えている。一方で、多くの国民は福祉水準の方を高レベルに引き上げてほしいと願っている。そして政治は票を意識して国民意識に寄り添おうとするから、認識ギャップは放置され、財政赤字だけが拡大していくことになる。この放置された巨大な認識ギャップこそが社会保障問題の解決を難しくしている最大の原因だ。このギャップを少しでも小さくしていくためには、まずは政治が短期的な人気取りではなく、長期的な国民福祉の安定を考えた議論を展開すべきだ。国民の側も次のような点で社会保障への理解(社会保障リテラシー)を高めていくことが必要だ。第1は、社会保障の給付と負担は一体だという認識を持つことだ。これは当然のようにみえて結構難しい。例えば消費税率を引き上げようとすると「それにより社会保障がどう改善されるのかを示すべきだ」という意見が出る。しかし、現在の低すぎる負担レベルを正そうと消費税率を引き上げるのだから、税率を上げても社会保障のレベルが高まるわけではない。第2は、適切な期待を持つことだ。例えば年金について「百歳までも安心して暮らしていける年金水準にすべきだ」というのは過度な期待である。年金制度があっても自ら老後に備えるのは当然だ。一方、若者たちの中には「自分たちが老人になる頃には年金はもらえない(文字通り受け取る年金がゼロ)」と悲観する向きも多いが、これはあまりにも期待レベルが低い。現行の年金制度は長生きリスクに備えて自己努力を補う有力な手段となっている。第3は、自分自身がどんな形で負担しているかを知ることだ。近年、消費税率の引き上げが遅々として進まなかったこともあって、社会保険料の引き上げが続いてきた。このため勤労者と企業が相対的に重い負担をすることになってしまっている。これは、勤労者が負担する社会保険料は給料から天引きされているため、本人も負担の高まりを認識していないからだ。政治の側と国民の側の双方が社会保障を巡る巨大な認識ギャップを埋める努力をしてほしいものだ。 *3-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/538855/ (西日本新聞社説 2019/8/29) 年金の将来 「支え手」増やす改革急げ 5年ぶりの健康診断は厳しい結果だった。放置すれば命を縮めかねない。すぐに大手術をするわけにはいかないが、体力の増強などやるべきことに早急に取り組む必要がある-。厚生労働省が公表した公的年金の財政検証結果から読み取るべきは、こんな結論だろう。少子高齢化の進行で「支える側」の現役世代が減り、「支えられる側」の高齢者が受け取る年金給付水準の低下は避けられない。老後に対する国民の不安は募るばかりだ。厚生年金の加入対象者を拡大するなど、支え手を増やす制度改革で国民の不安解消に努めるべきだ。財政検証では、現役世代の手取り収入に対する厚生年金の給付水準「所得代替率」を試算した。政府にとっては、モデル世帯で所得代替率50%以上を維持という約束が、将来も守られるかが焦点の一つだった。経済成長の度合いによって6通りで試算し、高成長3ケースでは約30年後も約束は守られるとした。5年前の試算結果とほぼ同じで、根本匠厚労相は「経済成長と労働参加が進めば、一定の給付水準が確保されながら約100年間の負担と給付が均衡し、持続可能となる」と強調した。年金制度の「100年安心」をアピールする狙いだ。ただ、それでも現在の所得代替率61・7%からは大幅に低下する。しかも、この3ケースは経済成長と高齢者の就労が順調に進むという甘い条件設定での見積もりだ。それらが低迷するケースでは40%台に落ち込む。楽観を排して見通せば、年金制度も受給者の生活も「100年安心」とは言い難い。不安解消には、年金給付水準の低下抑制が欠かせない。厚生年金の加入対象者を中小企業のパートにまで広げたり、賃金要件を緩和したりすれば、給付水準は改善する。厚生年金の保険料は労使で折半するため企業側の反発が予想されるが、支え手の層を厚くするためにも腰を据えた議論が必要だ。現在は20歳から60歳まで40年間となっている基礎年金加入期間を45年に延ばす案や、厚生年金の加入上限年齢を75歳に引き上げる案などについても、給付水準の改善につながるという試算が出た。これらについても検討してほしい。「就職氷河期世代」の非正規労働者など、老後への備えが十分ではない人は少なくない。無年金や低年金への対策は待ったなしだ。政府は検証結果を踏まえて制度改革案をまとめ、関連法案を来年の通常国会に提出するという。与野党とも政治の責任として、より望ましい年金の将来像づくりに合意できるよう議論を尽くすべきだ。 *3-3:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/403840 (佐賀新聞 2019年7月22日) 年金機構が個人情報紛失、未納者データのDVD 日本年金機構の東京広域事務センター(東京都江東区)が、国民年金の未納者の個人情報が入ったDVDを紛失したことが22日、機構への取材で分かった。未納者の氏名や住所、電話番号が含まれている可能性があるが、情報の流出や悪用は確認されていないという。機構によると、機構は国民年金の保険料未納者に支払いを訪問や電話で催促する業務を外部業者に委託。業者が状況を報告するための情報を記録したDVDを同センターに送付し、届いた後に行方不明になった。機構の担当者は「具体的な個人情報の内容や人数、行方不明になった時期は調査中」としている。 *3-4:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49083190X20C19A8SHA000/?n_cid=NMAIL006(日経新聞2019/8/27)年金、支え手拡大急ぐ パート加入増で給付水準上げへ 厚生労働省が27日公表した公的年金の財政検証では、少子高齢化で先細りする公的年金の未来像が改めて示された。日本経済のマイナス成長が続き、労働参加も進まなければ2052年度には国民年金(基礎年金)の積立金が枯渇する。厚生労働省は一定の年金水準を確保できるよう、会社員らの入る厚生年金の適用を拡大し、高齢者やパートらの加入を増やす改革に乗り出す。 *3-5:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49054290X20C19A8SHA000/?n_cid=NMAIL006 (日経新聞 2019/8/27) 年金、現状水準には68歳就労 財政検証 制度改革が急務 厚生労働省は27日、公的年金制度の財政検証結果を公表した。経済成長率が最も高いシナリオでも将来の給付水準(所得代替率)は今より16%下がり、成長率の横ばいが続くケースでは3割弱も低下する。60歳まで働いて65歳で年金を受給する今の高齢者と同水準の年金を現在20歳の人がもらうには68歳まで働く必要があるとの試算も示した。年金制度の改革が急務であることが改めて浮き彫りになった。 <インフラ整備は最初の都市計画が重要であること> PS(2019年8月31日、9月3日追加):*4-1のように、熊本地震からの復興と将来の都市づくりのため、「中心市街地を『歩いて暮らせる上質な生活都市』に転換する新たな街づくりが必要」として、熊本市の大西市長・市の幹部・市の職員・市議など28名の視察団がフランスに派遣されることになり、これに対して、「①市長や議員が飛行機でビジネスクラスを利用する」「②生活再建できない熊本地震の被災者が残される中で、議員が物見遊山のように海外視察に行くことは納税者の理解を得られない」との批判があるそうだ。しかし、①については、一般企業の常識から考えると、市長・議員・市の幹部などが出張時にビジネスクラスを利用するのは当たり前であり、②についても、街づくりが進む前に都市計画をしておくことが重要だ。ただ、本当に都市計画のための見聞であることは大切で、そのためには議員は少人数づつに分かれてあちこちの街を視察し、必要な質問を行い、正確な報告書を提出して、その後の議論に資するのでなければならない。その時は、共産党の議員も分担して、中国・ロシア・東ヨーロッパなどの開発の進みつつあるモデルにしたい都市を視察して報告すると役に立つと思う。 なお、*4-2のように、横浜市で第7回アフリカ開発会議(TICAD)が開かれ、「横浜宣言」に「自由で開かれたインド太平洋」「海洋安全保障」などが入れられたそうだが、それはアフリカの開発とはあまり関係ないだろう。また、尖閣諸島に関しては抗議が甘いのに、何に関しても中国の悪口を言ったり、投資額だけでなく中国独自の取り組みとの違いも際立たせたいなどと中国と競争するためにアフリカ開発援助をしているような発言をしているのは日本の意識が低いと言わざるを得ない。私は、*4-5のように、アフリカ開発銀行のアデシナ総裁が、中国の経済圏構想『一帯一路』について、「アフリカの経済成長に寄与する」「中国が『債務のワナ』の意図を持っているとは思わない」とされているとおり、現在のアフリカは、1950年代の日本と同様に、今から経済成長する地域で、そのためにインフラ整備を必要としており、人口増加しつつある平均年齢の低い国が多いため、借金は経済発展すれば返せると思う。 そして、日本が援助するのなら、アフリカの貴重な自然を破壊せずに開発を進めるため、都市計画を先にたて、民間企業を中心として上下水道・再エネによる分散電源・EV・FCV・携帯電話・パソコン使用などを前提とする「質の高いインフラ投資」をすべきだ。 さらに、*4-3のように、G7首脳会議で日米欧が素早く一致したとおり、2050年までにアフリカ大陸は人口が倍増して25億人になると予想されるため、治安の悪化を防ぐには雇用創出しなければならないが、日本はこの状態を1940~1950年代に経験済であり、これらを解決する方法は、女性も含めた教育・人材づくり・家族計画・経済成長であることがわかっている。そのため、中国と同様、一時的な格差拡大を恐れずに、できる所からやっていくことが必要だろう。 2019年9月1日、日本農業新聞が、*4-6のように、「①人口が倍増するアフリカは、今後の有望成長地域で食料輸入国が多い」「②農業振興で成長を後押ししたい」「③アフリカの食料安全保障も大問題」と記載している。私は、エネルギーは全く排気ガスを出さない再エネ由来の電動にすべきだと思うので、わざわざ食料を作れる田畑でバイオ燃料を作ることには反対で、さらにスマート農業にしすぎると人口増のアフリカで雇用吸収力が低くなるのではないかとも思うが、①であるからこそ②③は非常に重要で、JAグループ等の農業関係団体は技術協力や人材育成が可能だと思う。また、アフリカで技術協力した日本人の方にも貴重な経験になるし、アフリカの家族農業をまとめた農業協同組合との連携や6次産業化もできるだろう。 なお、JA全農が、*4-7のように、組合員の家庭や営農施設向けの電力の販売に乗り出すそうだが、各地域の電力会社から電力を調達するのでなく、ハウス・畜舎・田畑などで再エネ発電を行えば、完全なグリーン電力にでき、営農の大きなコストダウンや農家の副収入確保が可能になる。また、この方式は、アフリカなど電力インフラの遅れている地域でも活用できる。 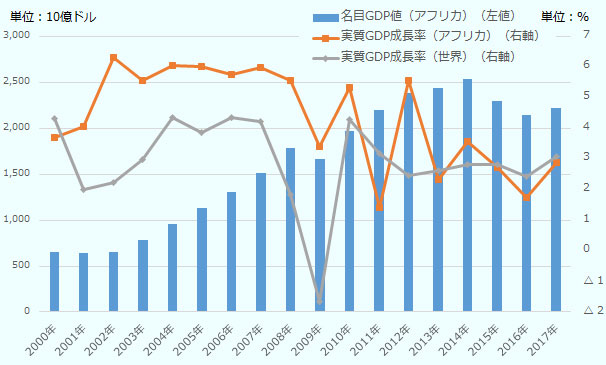 .jpg) .jpg) アフリカのGDPと経済成長率 アフリカの人口ピラミッド 日本の人口ピラミッドの変化 (図の説明:左図のように、アフリカ諸国は変動はあるものの世界平均より経済成長率が高く、これから成長する国々である。中央の図のケニア・ナイジェリア・エチオピアの人口構成は、右図の日本の1940年代、南アフリカの人口構成は1955年くらいに当たり、先進国の援助でスピードが速まりつつ、インフラ・経済・医療・教育の充実は似たような道を辿ると思われる) 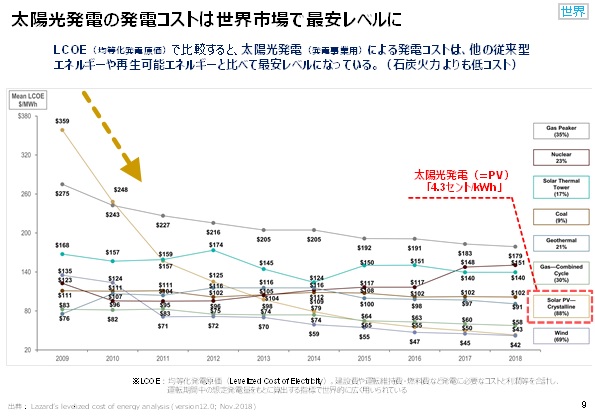    世界では最安値の太陽光発電 改良型風力発電機 地熱発電 *4-1:https://digital.asahi.com/articles/ASM8V5392M8VTLVB00B.html?iref=comtop_8_05 (朝日新聞 2019年8月30日) 熊本市、海外視察に1850万円 市長はビジネスクラス 熊本市が今秋、大西一史市長をはじめ、市幹部や市職員、市議ら28人からなる視察団をフランスに派遣することになった。6泊8日で、市負担の予算は計約1850万円。市は視察の理由を、熊本地震からの復興と将来の都市づくりには中心市街地を「歩いて暮らせる上質な生活都市」へと転換する新たなまちづくりが必要で、フランスが欧州の先進事例と説明している。今年6月、熊本市と交流都市の関係にあるエクサンプロバンス市から「日仏自治体交流会議」の準備会議への招待状が大西市長に届き、倉重徹議長にも議員との交流を求める招待状が届いた。これに合わせる形でフランスの3都市を巡る視察団の派遣を企画した。市都市政策課によると、一行は10月30日に熊本を出発。同日夕にストラスブール市に到着。31日に同市の市長を表敬後、公共交通を優先したまちづくりを視察。11月2日にオルレアン市を回り、3日に交流都市のエクサンプロバンス市に移動。翌4日に同市の市長を表敬し、5日まで市内を視察して6日に帰国する。大西市長は県産農産物品の売り込みのため視察の途中でイタリア・ミラノ市を訪問し、エクサンプロバンス市で合流する予定だ。市議会からは倉重議長のほか、自民の寺本義勝議員、小佐井賀瑞宜議員、光永邦保議員、公明の井本正広議員、市民連合の福永洋一議員が参加する予定。参加議員は各会派の代表として選ばれた。視察の準備は昨年から始め、市幹部と職員の費用は今年度当初予算で議決済み。市議会分については、9月定例会に770万円の補正予算案を提出する。経済界から参加する4人の旅費は自己負担という。市長や議員は飛行機でビジネスクラスを利用する予定。市議会事務局によると、交通費や滞在費を含む議員1人あたりの旅費約106万円は全額公費から支出する。議員は視察後の報告書提出の義務が無く、議会事務局が感想を聞き取って報告書を作成する。海外視察の事例については「近年は無く、少なくとも改選前の前期の4年間は無かった」としている。市議6人が同行する海外視察ついて、大西市長は27日の記者会見で「派遣する議員数については議会がお決めになること。熊本市の市電延伸にも色んなご意見があり、多様な方が実際に現地を見て違う角度から将来の熊本について検討する機会。視察の目的も明確でまちづくりの知見を深められる」と説明。倉重議長も取材に対し、「路面電車をいかしたまちづくりやコンパクトシティーを実現した先進国で、なるべくたくさんの議員に一緒に交通体系を体験してもらい、その意見を将来の熊本のまちづくりにいかす」と話す。一方、これまで市議会の海外視察に加わってこなかった共産の上野美恵子議員は「市民の代表として市長と議長の表敬訪問は理解できる。しかし、まだ生活を再建できない熊本地震の被災者が残されるなかで、議員が物見遊山や大名行列のようにゾロゾロと海外視察に行くことは納税者の理解を得られると思えない」と批判している。 *4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190830&ng=DGKKZO49193050Q9A830C1MM0000 (日経新聞 2019年8月31日) TICAD横浜宣言、インド太平洋構想を明記、中国念頭に 民間重視を強調 横浜市で開いた第7回アフリカ開発会議(TICAD)は30日午後、「横浜宣言」を採択して閉幕した。安倍晋三首相が提唱する「自由で開かれたインド太平洋」構想にTICADの成果文書として初めて触れ、重要性について認識を共有した。今後のアフリカ開発では民間ビジネスを重視していく姿勢も前面に出した。インド太平洋構想はアジアとアフリカを結ぶインド洋や太平洋地域で、法の支配や航行の自由、経済連携を推し進めるものだ。首相が2016年8月にケニアで開いた前回TICADの基調演説で打ち出した。横浜宣言では同構想に「好意的に留意する」と言及した。中国が主導する広域経済圏構想「一帯一路」を意識し、アフリカ諸国が中国に傾斜しすぎないよう促すものだ。アフリカでのインフラ開発では中国の融資に頼り、巨額の債務を負った事例が指摘される。6月の20カ国・地域首脳会議(G20大阪サミット)でまとめた首脳宣言や「質の高いインフラ投資原則」を共通認識として歓迎することも盛り込んだ。相手国に返済が難しいほど過剰な債務を負わせないよう、透明性と持続可能性を重視する内容だ。優先事項の一つでも海洋安全保障を挙げ、中国の海洋進出を念頭に「国際法の諸原則に基づくルールを基礎とした海洋秩序の維持」を訴えた。経済連携では「アフリカ開発における民間部門の役割を認識」と盛り込んだ。民間ビジネスを活性化してアフリカ経済の自律性を高める狙いで、政府間が主導する中国の対アフリカ支援との違いを訴えた。首相は閉会式で「民間企業のアフリカにおけるさらなる活動を後押しするため支援を惜しまない」と強調した。アジアでの開発で日本が取り組んだ経験がアフリカでも役立つことを確認し、日本がアフリカ諸国での人材育成を支援する「ABEイニシアチブ3.0」を評価した。日本への留学やインターンを促進し、今後6年間で3000人の産業人材の育成を目指す仕組みだ。女性起業家への支援も歓迎する考えを明記した。アフリカ開発を巡っては中国も00年から中国アフリカ協力フォーラムを計7回開き、18年の会合では3年間で約600億ドルの拠出を表明した。首相も28日の基調演説で今後3年間で200億ドルを上回る民間投資の実現を後押しする考えを示した。ただ投資額だけで対抗するのではなく、中国独自の取り組みとの違いも際立たせたい考えだ。横浜宣言ではTICADの基本理念として日本とアフリカだけでなく国際機関や第三国にも開かれた枠組みだと強調した。同宣言では日本が目指す国連安全保障理事会の常任理事国の拡大を念頭に「安保理を含む国連諸組織を早急に改革する決意を再確認」することも明記した。次回の第8回TICADは22年にアフリカで開く。TICADは前回初めてアフリカで開いており、3年ごとに日本とアフリカで交互に開催する方向性を明確にした。日本が1993年に立ち上げたTICADでは参加する日本やアフリカ諸国で共通する問題意識を盛り込んだ宣言を出すのが通例だ。28日に開幕した今回はアフリカ54カ国のうち過去最高の42カ国の首脳級が参加した。 *4-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190831&ng=DGKKZO49225340Q9A830C1EA3000 (日経新聞 2019年8月31日) 人口増リスク、欧米が注視 対立が目立った26日までのフランスでの主要7カ国(G7)首脳会議で日米欧が素早く一致した分野がある。西アフリカのサハラ砂漠南部「サヘル地域」での雇用創出などを通じた開発支援だ。マリやチャドなどサヘル地域5カ国は世界のアフリカへの成長期待をよそに治安が悪化し、統治が機能していない。背景には人口が増えるなかで貧困や若年層の失業が膨らみ、過激派勢力が不満を募らす若者を引き込む負の構図が浮かぶ。2050年までに人口が倍増して25億人になるアフリカ大陸。欧米は「最後の市場」としての潜在性よりも、リスクへの意識を強めているように見える。西アフリカのある高成長国の閣僚も「雇用創出できなければ、人口は文字通りに爆発し、世界の問題になる」と話す。特に地理的に近い欧州は大量の難民流入やテロのリスクに直面する。アフリカの安定成長を促して人口増に伴う雇用を確保し、インフラや衛生整備を進めなければ、食料不足や疫病の流行といった危機も招きかねない。今回のアフリカ開発会議(TICAD)で安倍晋三首相が平和構築への協力を打ち出し、教育や医療支援も強調したのは欧米の懸念に呼応した動きといえる。「スクランブル(先を競った奪い合い)」と形容される最後の市場を巡る各国の競争は思わぬ結果を生む可能性もある。改革を進め、外資を呼び込んで成長する国と、負のサイクルから抜け出せない国との格差が広がる兆しがある。人口予測通りにいけば、50年には世界の4人に1人はアフリカ人となる。世界銀行総裁候補だったナイジェリアのオコンジョイウェアラ元財務相は訴える。「アフリカを育むことは世界の未来に直結する」 *4-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190831&ng=DGKKZO49216720Q9A830C1EA3000 (日経新聞 2019年8月31日) アフリカ投資拡大へ「人づくり」前面 TICAD閉幕 、膨らむ債務 対処後押し 支援先行の中国を意識 第7回アフリカ開発会議(TICAD)は30日、アフリカの経済成長の進展をめざす「横浜宣言」を採択して閉幕した。日本は会議を通じて民間主導の投資を訴え、政府としては投資拡大の環境を整える人材育成を前面に掲げた。中国の融資で過剰債務を抱える国などの実態を踏まえ、投資や支援で先行する中国に傾斜しすぎないよう促す狙いもある。安倍晋三首相は30日のTICAD閉幕後の記者会見で「日本とアフリカの懸け橋となる人材の育成に力を入れていく」と強調した。治安から公的債務、保健、産業まで投資拡大の前提となる能力向上をはかる。具体策のひとつが今後3年間でのべ30カ国に公的債務のリスク管理研修を実施することだ。ガーナやザンビアへの債務管理やマクロ経済政策を助言する専門家の派遣を決めた。ケニアの鉄道など中国の融資で重い債務を抱えた例が指摘される。財政が悪化すれば円借款などを用いたインフラ支援などが難しくなる。横浜宣言には6月の20カ国・地域首脳会議(G20大阪サミット)でまとめた首脳宣言や「質の高いインフラ投資原則」の歓迎を盛り込んだ。過剰な債務を負わせないよう透明性と持続可能性を重視する内容だ。首相は記者会見で「支援は対象国の債務負担が過剰にならないようにしなければならない」と述べた。宣言で「自由で開かれたインド太平洋構想」の評価に初めて触れたのは、中国の「一帯一路」構想を意識した。アフリカ側にも「投資や援助を受ける国を多様化したい」(ジブチのユスフ外相)との声がある。30日の「平和と安定」に関する会合では、河野太郎外相がアフリカ諸国の国連平和維持活動(PKO)の能力向上支援に触れた。ケニアなどのPKO訓練センターで日本の自衛官らによるPKO部隊の研修を充実させる。アフリカでは治安が悪化している地域が多く、地域格差拡大の要因にもなる。アフリカ市場が発展し民間投資が増えるためには情勢の安定が重要だ。 *4-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190831&ng=DGKKZO49221200Q9A830C1FF8000 (日経新聞 2019年8月31日) アフリカ開銀総裁「一帯一路は成長寄与」 債務のワナ否定 アフリカ開発銀行(AfDB)のアデシナ総裁は30日、日本経済新聞のインタビューに対し、中国の経済圏構想「一帯一路」について「アフリカの経済成長に寄与する」と評価した。中国が過剰債務の代償としてインフラ権益を奪う「債務のワナ」について「中国がそうした意図を持っているとは思わない」と述べ、中国のインフラ投資を歓迎する姿勢を見せた。アデシナ氏はアフリカの持続的な経済成長にはインフラ整備が欠かせないと述べた。不足している資金を最大で1080億ドル(約11兆円)と予測し、海外から投資を呼び込むことが重要との考えを示した。「一帯一路」については「アフリカの発展に寄与する」と評価した。また、アフリカの一部の国で対外債務が増えていると指摘し、各国が「債務についての透明性を確保し、処理の道筋を示すことが非常に重要だ」と述べた。一方で「アフリカで債務危機に陥っている国はない」と述べ、現時点でのアフリカ諸国の債務水準は問題視しない考えを示した。足元のアフリカ経済については良好との認識を示した。「2019年の平均成長率は4.1%を確保できる」と述べた。今後のリスクに米中貿易戦争と英国の欧州連合(EU)離脱、インドとパキスタンの緊張の3つを挙げた。アデシナ氏は8月28~30日に横浜市で開いたTICADに出席するため来日した。 *4-6:https://www.agrinews.co.jp/p48606.html (日本農業新聞論説 2019年9月1日) 日・アフリカ会議 農業支援で関係強化を 日本政府が主導する第7回アフリカ開発会議(TICAD7)は、民間企業の投資強化など「横浜宣言」を採択して閉幕した。人口が倍増するアフリカは、今後の有望な経済成長地域だ。一方で食料輸入国が多い。日本の先進技術を含め、農業振興で成長を後押ししたい。「後進地域がゆえの先進性」──潜在的な成長力を秘めるアフリカ大陸の可能性はこう表現できる。「横浜宣言」で、民間投資の大幅拡充やデジタル革命へ対応を明記した理由だ。農業面でも同じ。JAグループが6月開設した戦略拠点「イノベーションラボ」。ベンチャー企業と連携し、幅広い分野でITを活用した新規事業の創出を目指す。その一つ、日本植物燃料(神奈川)は、アフリカのモザンビークで新たな挑戦を進める。現地農家にバイオ燃料作物栽培を推進。それを契機に農家に電子マネーを広げ、少額融資などを行う。鍵は普及している携帯電話の活用だ。合田真代表は、情報通信技術(ICT)を駆使し、農林中金やJA全農など総合事業を行うJAグループと連携すれば、「さらに現地の農村を発展できる」と強調する。吉川貴盛農相はTICAD期間中、「農業」部門に参加し、アフリカの食料安全保障確立に関連し、専門家派遣の拡充や、先端技術を駆使したスマート農業の振興などを強調した。TICADでは、二つの視点が欠かせない。地球規模の食料安保と中国の存在感だ。アフリカ諸国はかつて農産物の輸出大国でもあった。だが度重なる紛争や気象災害で国土は荒廃した。豊富な鉱物資源は多国籍企業の収奪に遭う。土地収奪も重なり、アフリカ農業は衰退の一途をたどる。基礎的食料さえも不足し食料輸入大国に転落した。人口増と食料輸入の同時進行は、世界の食料安全保障上も大問題となりかねない。アフリカ大陸の経済成長の潜在力は大きい。今年5月には域内の関税撤廃などを目指す自由貿易協定も発効し、巨大な統一市場への期待も膨らむ。中国やインドに匹敵する13億人の人口で、2050年には25億人と倍増し世界の4分の1を占める見通しだ。巨大な胃袋をどうやって満たすのか。いま一つの視点は中国の動き。2000年からアフリカ協力フォーラムを7回開催。昨年は、3年間で600億ドルを拠出する巨額支援を表明した。米中貿易紛争の激化は、安全保障問題も絡む。こうした中で、今回のTICADでは中国に対抗し日本の存在感を強める戦略的な意味合いも一段と強めた。一方、食料自給率の向上は喫緊の課題だ。農業分野支援は、日本の高い技術力を生かせる。既に干ばつに強い多収性の「ネリカ米」振興は高い評価を受けている。JAグループなど農業団体はアジアの途上国を中心に人材育成に力を入れてきた。今後はアフリカを含め日本の“農協力”発揮の時でもある。 *4-7:https://www.agrinews.co.jp/p48629.html (日本農業新聞 2019年9月3日) 全農 電力販売を本格化 割安提供 家計、営農後押し JA全農は、JA組合員の家庭や営農施設向けの電力の販売に本格的に乗り出す。各地域の電力会社より安価に供給し、家計の負担や営農コストの削減を後押しする。地方では電力小売りへの参入業者が少ないが、「JAでんき」の愛称で北海道と沖縄県、一部の離島を除く全国で展開。2021年度までに累計35万戸の契約を目指す。子会社の全農エネルギーが各地域の電力会社などから電力を調達し、正・准組合員やJAグループ役職員の家庭、営農施設に届ける。電力会社の送電網を使うため、電力の安定性は従来と変わらない。JAを通じて申し込むが、地域のJAが同社や全農と代理事業契約を結ぶ必要がある。家庭用電力の料金は、各地域の電力会社より割安に設定する。自前の発電所などを持たないため料金を抑えられる。全農によると、標準的な4人家族の使用量で、電気料金は5%前後安くなる。使用量が多いほど割安な料金体系で、世帯人数が多い農家は、さらに電気料金の引き下げメリットが受けられるという。ハウスや畜舎などの営農施設向けには、使用実態の調査や料金の試算を個別に行った上で、値下げが見込める場合に切り替えを提案する。営農施設には、地域の電力会社も規模や使用量に応じて割安な料金を設定している場合があるためだ。16年の電力小売り全面自由化で、家庭や小規模事業者も電力会社を選べるようになった。だが、JAの組合員が多い地方では、大都市圏に比べ参入業者が少なく、切り替えが進んでいない。全農はその受け皿となり、組合員の電力コスト削減を目指す。16年に電力事業に参入後、電力の使用規模が大きい精米や食肉などの加工工場、物流センターといったJAグループの施設向けに先行して取り組み、全国的に供給できる態勢を整えてきた。全農は現在、電力事業に取り組んでもらうJAへの説明や提案を進めている。19年度は50JA程度でモデル的に供給を開始。20年度以降、対象となる全てのJAに広げたい考えだ。19年度からの3カ年計画では、契約件数の目標を21年度までの累計で35万戸と掲げた。全農は「安価な電力の供給で家計負担の抑制や営農コストの削減に貢献したい」(総合エネルギー部)とする。従来のLPガスや灯油と組み合わせたエネルギー利用の提案や、営農用エネルギーの総合診断なども展開していく方針だ。 <“普通”信奉(≒同質主義)は、病根の一つである> PS(2019年9月2日追加):持って生まれたDNAと周囲の環境の違いのために発現する多様な個性を、*5のように、“普通”でないから脳機能障害による発達障害だとし、“グレーゾーン”まで含めて医療機関の受診を奨める報道は少なくないが、これは間違った知識を一般の人に与えるのでよくない。何故なら、医師が「経過をみましょう」と言っても、母親が「ママ友」の繋がりで発達障害と診断してくれるクリニックを捜して「むしろ安心した」と言うような状況になるからだ。人の性格や生育スピードにはばらつきがあるので、周囲の大人が「普通でない」と感じたからといって脳機能障害と考えるのは間違いであり、その子に対する人権侵害でもある。 学校や社会に適応できない理由には、くだらないことで仲間外れにしたり、いじめたりする影響があるからで、発達障害というよりは“文化”の方を変えなければならない側面が大きい。そして、社会に出てまで支援を受ける人の割合が多いのは困るため、それぞれの個性を活かした教育や能力開発が必要だ。さらに、普通に働いている大人まで「見過ごされた人」として、その症状を「①空気が読めない」「②ミスを繰り返す」などとしているが、①は、空気を読んで周囲に合わせることしかできない深刻な無思考(他人依存)症候群であり、②は、慣れないことは誰にとっても難しいため仕事ができるためには熟練しなければならないということだ。 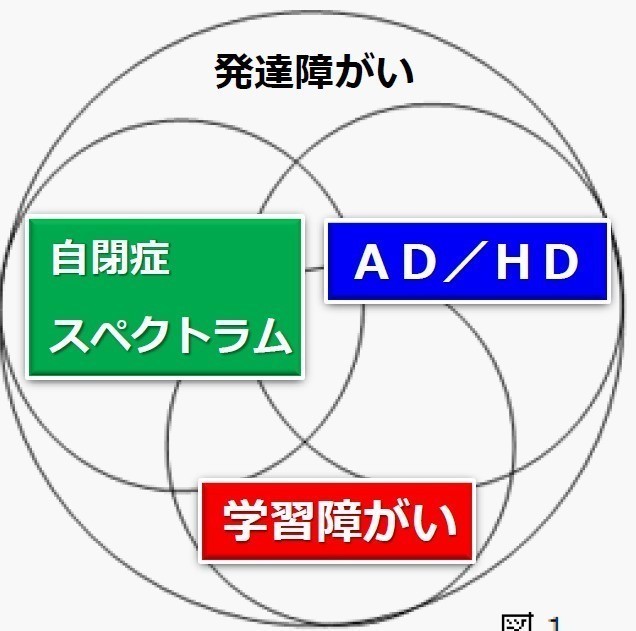 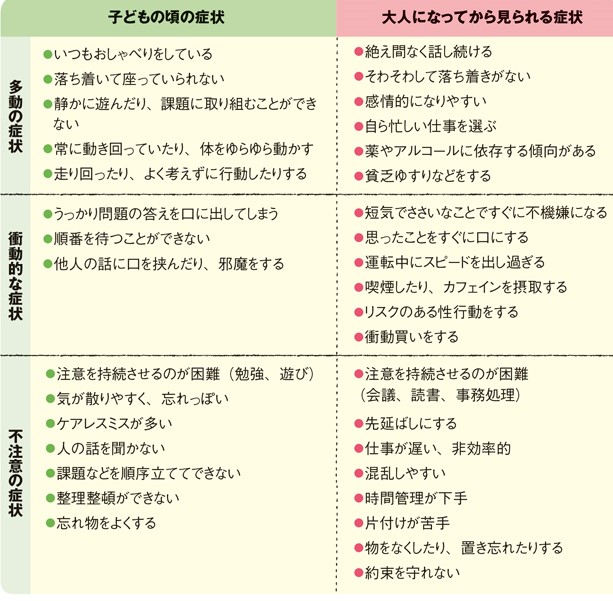 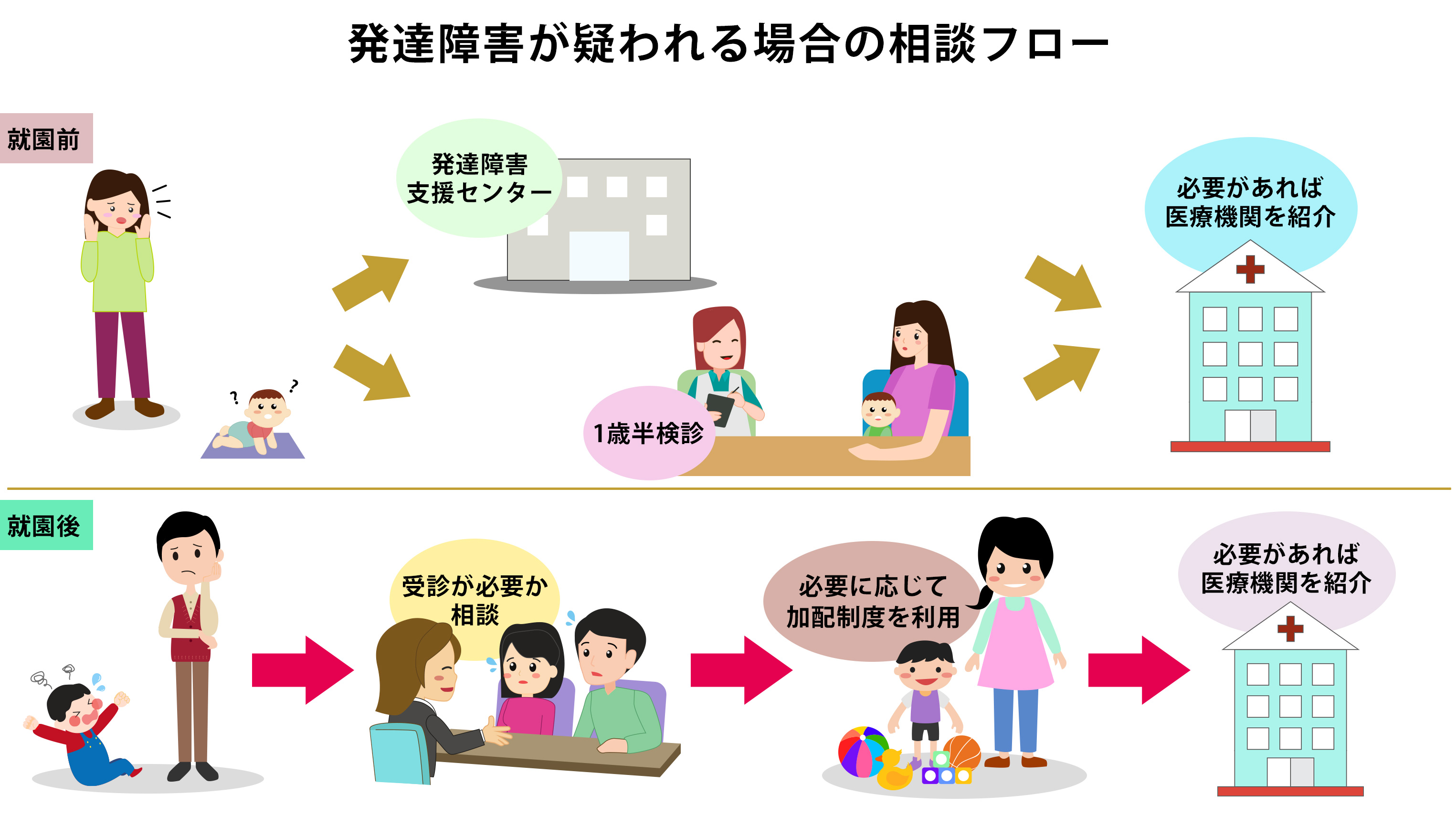 (図の説明:最近、左及び中央の図のように、程度の差こそあれ誰にでもある多様性の範囲に入るものまで発達障害として精神障害に入れ、右図のように、相談してケアされることを奨めているが、これはむしろ教育や躾の妨げとなって子どもの機会を奪う) 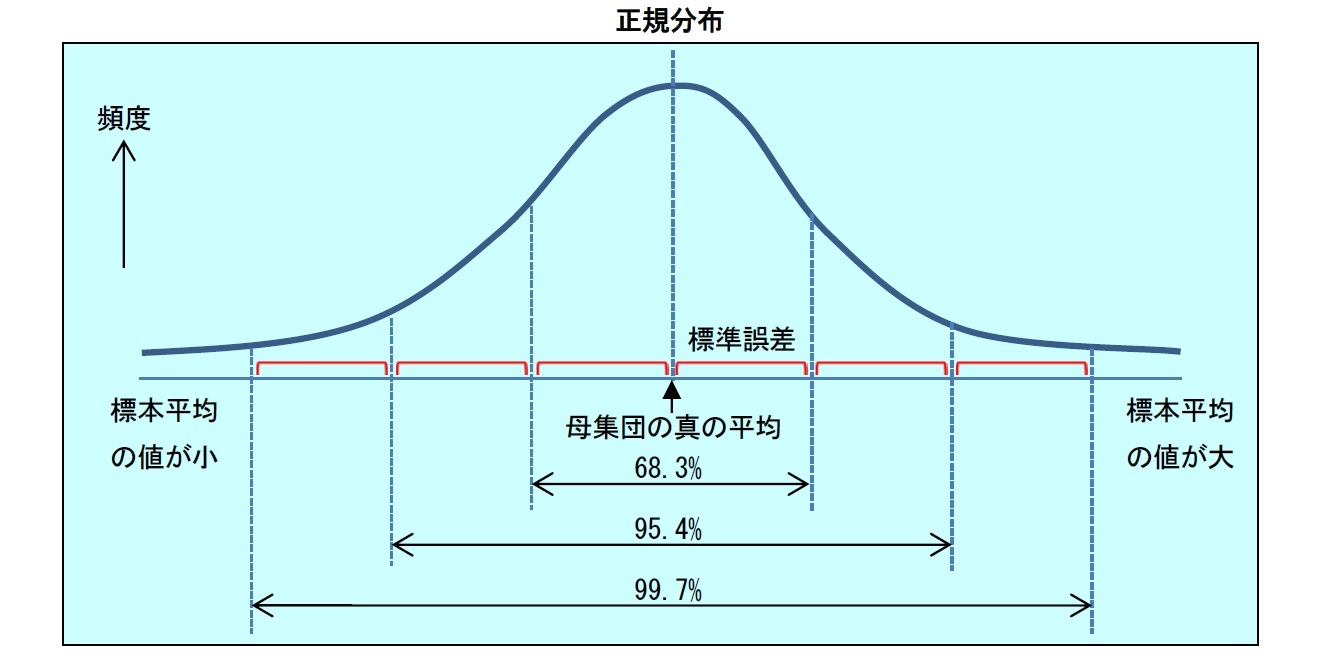 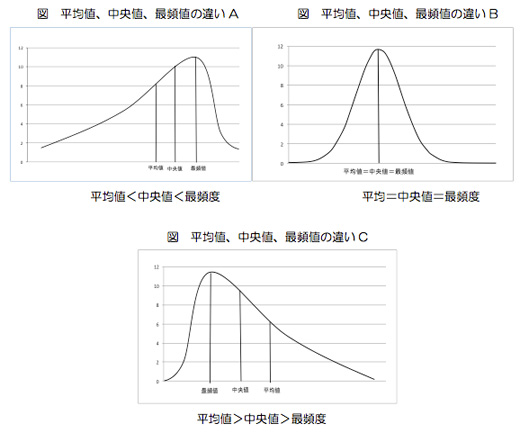 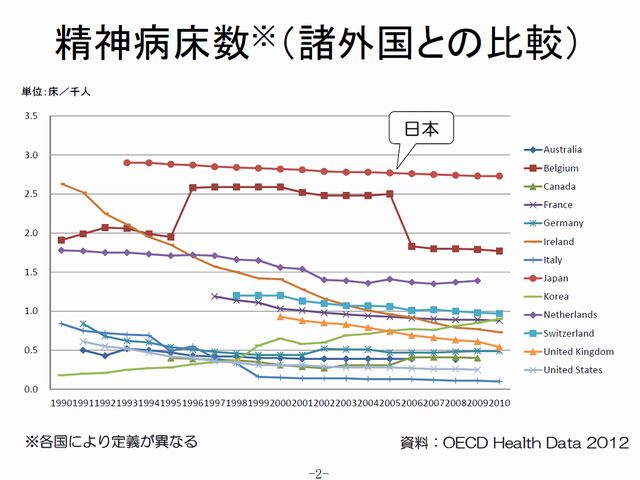 (図の説明:左図のように、人は成績・身体能力・所得・貯蓄高等と同様、性格にも多様性があり、普通と言うのは中央から2σ《95.4%が入る》か3σ《99.7%が入る》内の人だ。そして、3σより向こうの両端にも0.3%《1000人に3人》の人がおり、右端《0.15%、1000人に1.5人》には優秀な人がおり、左端《0.15%、1000人に1.5人》には駄目な人がいて、普通が最もよいわけではない。また、中央の図のように、ばらつきが左右対称に分布している場合は平均値・中央値・最頻値は一致するが、歪んだ分布をしている場合には平均値・中央値・最頻値は異なる。そして、日本は何でも精神障害ということにする結果、世界でも突出して精神病床の多い人権侵害国になっている。ただ、既製服や既成靴を買う場合は「普通」の範疇に入る人の方が品物が豊富でよいのだが、この「普通」も国によって大きく異なることは誰もが知っているとおりだ) *5:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14160488.html (朝日新聞 2019年9月2日) (記者解説)発達障害、寄り添うため 特性は多様、早めに専門機関へ 生活文化部・土井恵里奈 ・脳の機能障害が原因とされ、手術や投薬では解決しない。障害特性は一人ひとり違う ・専門家や専門機関と早めにつながり、社会生活上の困難を小さくすることが大切 ・障害を見過ごされた大人、診断されない「グレーゾーン」の人たちの支援も課題 ■診察のため予約殺到 東京都江戸川区の児童精神科クリニック「まめの木クリニック」には、発達障害かどうか診察を求める電話が後を絶たない。「健康診断や学校で(発達の凸凹を)指摘されて来る人、自分で調べて来る人が多い」。上林靖子院長はそう話す。初診予約は年内すでにいっぱい。2年待ちの時もあった。東京都内の女性の長男(中2)は発語が遅く、あちこちにふらふら行くなど落ち着きがなかった。1歳半の健診では「経過をみましょう」と言われ、病院を受診しても「発達障害の疑いはありますが……」とあいまいだった。「ママ友」のつながりで同クリニックを知った。約10カ月待ち、長男が2歳のころ受診。発達障害と診断された。女性はこう振り返る。「むしろ安心した。それまでは情報が得られなくて先が見えなかったから」。今も定期的に長男と通院し、医師や臨床心理士らに相談する。女性は「最初は長男がなぜこんな行動をするのか共感してあげられなかった。子どもへの接し方を学び、子どもが穏やかに生活できるようになった」と話す。発達障害の特性による育てにくさに直面し、周囲に言えなかったり理解されなかったりして悩んでいる人は多い。発達障害かどうかは、成育歴を聞き取る問診や知能検査などを経て医師らが診断する。厚生労働省によると、特性を適切に把握できる児童精神科医は少ない。発達障害の原因は脳の機能障害とされる。手術や投薬で治ることはなく、当事者は特性と生涯向き合う必要がある。だから、医師や臨床心理士といった専門家と早くからつながることが大切だ。上林院長は「発達障害の特性ゆえのやりにくさをうまく乗り越えていけるようにして、社会に送り出してあげることが大切」と指摘する。発達障害は一様ではない。読み書きや計算など特定の課題の学習につまずく「学習障害」(LD)、こだわりが強く、他人の気持ちを想像したり共感したりするのが苦手な「自閉スペクトラム症」(ASD)、衝動性が強かったり、忘れ物や遅刻などの不注意が多かったり落ち着きがなかったりする「注意欠陥・多動性障害」(ADHD)がある。複数の特性が重複していることもよくある。特性から光や音、接触に過敏だったり、暑さや寒さ、痛みに鈍感だったりする人もいる。 ■高校でも支援の動き 政府も後押ししている。2005年に発達障害者支援法が施行され、早期の発達支援が重要と条文にうたわれた。学校や社会に適応できずに不登校やうつ、引きこもりといった「二次障害」を防ぐためで、「障害の早期発見のため必要な措置を講じること」が国と地方公共団体の責務となった。だからこそ発達障害の疑いのある子どもがいれば、いち早く地元の市役所や町村役場を頼りたい。行政機関は求めに応じて医療機関を紹介してくれる。ただ地域格差があり、都道府県と政令指定市に設置されている「発達障害者支援センター」も支援の窓口だ。発達段階に応じた児童発達支援(未就学児対象)や放課後等デイサービス(小学生から原則高校生まで)も制度化されている。専門性を持った職員から社会的スキルなどを学ぶが、こうした情報も行政とつながることで得られやすくなる。幼稚園や保育所、小中学校には教員や支援員が増やされることがある。高校でも、通常学級に在籍しながら発達の程度に応じた特別な指導(通級指導)を受けることができる。一方、義務教育が終わると支援が行き届かない場面が増える。孤立しないよう、積極的に向き合う高校もある。和歌山県立和歌山東高校では、発達に課題がある生徒の保護者とは入学前の早い時期に面談している。読み書きを苦手にしている生徒に対しては、在籍する通常学級で黒板を書き写しやすくするため、重要なことを黄色の線で囲むなど工夫している。こうした配慮は他の生徒にも好評で、退学者が減るなど全体に好影響をもたらしている。石田晋司校長(58)は「社会に出ると多様な人と関わっていく。得手不得手を助けたり助けられたりすることを学ぶことは、どの子にとってもプラス。人を理解する力をつけることにつながる」と話す。 ■「見過ごされた」大人 困難を抱えていたのに、子どもの時に「見過ごされた」人たちがいる。大人の発達障害だ。昭和大付属烏山病院(東京都世田谷区)には大人の発達障害専門の外来があり、来院者が絶えない。臨床心理士らに付き添われ、怒りや不安の感情との向き合い方や時間を管理するスキルなどを学ぶ。仕事や生活での具体的な困り事を当事者同士が話し合うプログラムもある。「家に食材をため込む」「体調が悪い時は特に片付けが苦手」。当事者たちは日頃の悩みを互いに打ち明ける中で自己理解を深め、解決のアイデアを共有する。障害の傾向はあっても発達障害と診断されない、「グレーゾーン」に置かれる人たちもいる。困難や生きづらさはあるのに、支援の手が届きにくい。神奈川県の男性会社員(31)は子どもの時から忘れ物や遅刻、不注意が多かった。周囲から孤立し、22歳でうつに。発達障害を疑って受診したが、医師からは「ADHDの傾向はあるが断定できない」と言われた。就職活動時はリーマン・ショック。特性を職場に伝えるのはマイナスと考え、言えなかった。職場では複数の業務を同時にこなすのに苦労。転職を繰り返した。2年前、グレーゾーン当事者の支援団体「OMgray事務局」をつくった。定期的に東京に集まり、就労や生活の困り事の解決策などを情報交換する。男性は「社会に普通にいる存在として受け止めてほしい」と話す。女性の当事者会「Decojo」には、診断を受けた人もグレーゾーンの人も参加し、困り事をブログに書き込んでいる。代表の沢口千寛さん(27)は「当事者だけでなく、私たちの行動を理解できず振り回されている人や社会にも見てほしい。理解し合い、歩み寄れるようになれば」と話す。 ■「普通」に見える、でも困っている 学校で職場で手をさしのべて 23万人。発達障害の診断などを受けるために医療機関を受診した人の推計(17年度)だ。受診者といっても、学校に通ったり働いたり子育てしたりと「普通」に見える。でも壮絶に困っている。生きづらさを抱えたまま社会に紛れている。「空気が読めない」「ミスを繰り返す」。当事者の困りごとは切実だが、外からは見えにくい。「怠けている」「だらしない」と責められやすい。「グレーゾーン」だと、相談先も十分でない。病気のように重いほどつらいとは限らないことも、この障害の特徴だ。子どもは自分で苦しさを伝えづらく、いじめにつながりやすい。無理を重ね不登校になった子もいる。大人になると、周囲が助けてくれる場面は少なくなる。特性を抱えながらも、発達障害という言葉さえ知られていない時代に子どもだった人は今、30代、40代を過ぎている。就職氷河期のロストジェネレーション世代とも重なり、非正規雇用など不安定な生活を強いられている人は多い。ひきこもりに陥るなど社会からの孤立が心配だ。当事者の言葉は重い。「人生で普通の人の100倍怒られてきた」「パターンをたたき込んで普通になろうともがく。努力して努力して、でもなれなくて。自分はダメと思い、殻に閉じこもっていく」「社会に出たら迷惑をかける。出ないことが社会貢献」。当事者を縛る「普通」とは何だろう。常識? 標準? ものさしは一つ? いろんな国や言語があるように、一人ひとりの普通は違う。学校にも職場にも地域にも、「苦手ならちょっと代わりに」とさしのべる手がたくさんあるといい。発達障害の痛みを和らげるには、医療より社会にできることが大きい。特効薬がない障害の鎖をほどいてゆく力になるのは、医師や専門家だけじゃない。どこにでも普通にいる私たちだ。 <日本は、本当に法治国家か?> PS(2019年9月3日追加): 総務省が、ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した件を審査した「国地方係争処理委員会」が、*6-1・*6-2のように、除外決定の再検討を石田総務相に勧告することを決めて総務省は敗訴したが、これは新制度への参加が認められなかった静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町も同じであるため、提訴すれば速やかに結論が出るだろう。何故なら、日本国憲法に「第84条:あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定められており(租税法律主義)、新たに定められた法律が施行前に遡って効力を持つこと(遡及効)はないからだ。さらに、総務省の通知は、国税庁の通達と同様に一つの考え方であって法律ではないため、総務省が「メチャクチャだ」と感じたとしても通知の順守を強要すれば憲法違反になる。そのため、大阪府知事が、*6-3のように、「総務省のおごり」「国は真摯に受け止めて見直すべき」としているのは妥当であり、メディアや行政は、もっと法律を勉強しておく必要がある(笑)。 なお、佐賀県は、(私の提案で)日本の中でも病院のネットワーク化が進んでいるので、*6-4の東多久町に建設する新病院は、①どのような先進医療を ②どういう新しい施設で市民に提供するか についてのコンセプトを決め、新病院の建設を使い道として県人会や同窓会などで「ふるさと納税」を集めればよいと思う。 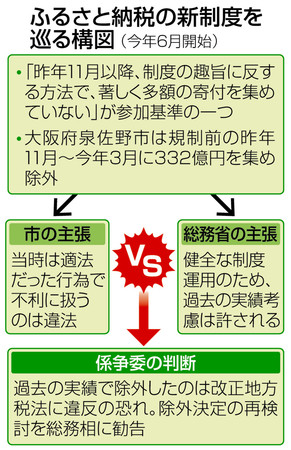 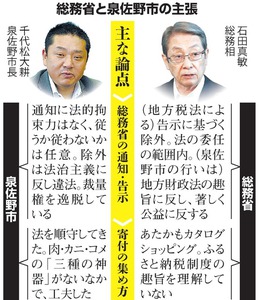 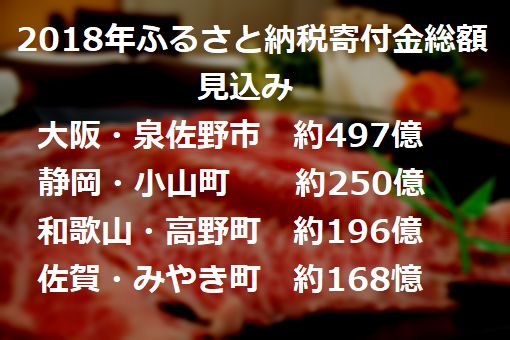 2019.9.3東京新聞 2019.8.27朝日新聞 (図の説明:左図には、泉佐野市の勝因は地方税法違反と書かれているが、そもそも租税法律主義を定めた憲法違反である。また、中央の図には、泉佐野市は肉・カニ・米の三種の神器がないと書かれているが、私は農産物でなくても地域を振興する何かであればよいと思う。確かに、右図のように、大阪府泉佐野市・静岡県小山町・和歌山県高野町・佐賀県みやき町は頑張ったわけだが、これは上記の法的根拠で除外される理由にはならないわけだ) *6-1:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201909/CK2019090302000146.html (東京新聞 2019年9月3日) ふるさと納税 泉佐野市除外、違法か 係争委、再検討勧告へ ふるさと納税の新制度から、大阪府泉佐野市が除外された問題を審査した第三者機関「国地方係争処理委員会」は二日、除外決定の再検討を石田真敏総務相に勧告することを決めた。過去に不適切な寄付集めをしたとして除外した総務省の対応は、新制度を定めた改正地方税法に違反する恐れがあると指摘した。同省が事実上の「敗訴」となる極めて異例の判断を下した。総務省には、勧告の文書を受け取ってから三十日以内に、再検討の結果を泉佐野市へ通知するよう求める。同省は再検討を義務付けられるが、別の理由で改めて除外するのは可能。審査を申し出た市は「主張がおおむね理解された」とコメントした。同様に新制度への参加が認められなかった静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の三町は勧告の対象外。委員長の富越和厚元東京高裁長官は記者会見で、泉佐野市による寄付集めを「制度の存続が危ぶまれる状況を招き、是正が求められるものだった」と述べ、問題があったとの認識を示した。ただ、それを除外の根拠にすることは認められないと指摘。理由として「改正地方税法に基づく新制度の目的は過去の行為を罰することではない」と説明した。六月開始の新制度は、改正法に基づく総務相の告示で「昨年十一月以降、制度の趣旨に反する方法で、著しく多額の寄付を集めていない」ことが参加基準の一つになった。市はインターネット通販「アマゾン」のギフト券などを贈り、昨年十一月~今年三月に三百三十二億円を獲得。総務省は基準を満たしていないとして五月に除外を決めた。 *6-2:https://digital.asahi.com/articles/ASM9263JXM92ULFA03B.html?iref=pc_rellink (朝日新聞 2019年9月2日) 総務省、泉佐野市に完敗 「メチャクチャだったのに…」 ふるさと納税制度からの除外をめぐる総務省と大阪府泉佐野市の対立で、同省の第三者機関・国地方係争処理委員会が2日、石田真敏総務相に除外の内容を見直すよう求めた。係争委は、法的拘束力のない通知への違反を除外理由にしたことを「法に違反する恐れがある」と認定しており、事実上、総務省の「完敗」となった。係争委の富越和厚委員長は委員会後の会見で、6月の地方税法の改正前の泉佐野市の行為は「世間にやり過ぎと見られるかもしれないが、強制力がない通知に従わなくても違法ではない」と説明した。係争委は今回、改正法の施行後に守るべきものとして総務省がつくった基準を、法改正前の行為にあてはめて除外を判断したとして、違法の疑いがあると認定。同省に直接、除外の判断の撤回までは求めなかったが、総務省が除外の根幹として掲げていた理由は「少なくとも本件で使うべきではない」と退けた。富越委員長は、総務省が泉佐野市を除外する判断を続ける場合は、新たな法的根拠を提示する必要があるとの見解を示した。係争委の勧告に、総務省内では戸惑いの声が上がった。同省幹部の一人は朝日新聞の取材に「泉佐野市の集め方はメチャクチャだったのに。係争委の厳しい判断は受け入れがたい」と話す。一方、政権幹部の一人は「今後訴訟になった時に対応できるよう整理するということ。根本的な問題ではないのでは」との見方を示した。 *6-3:https://digital.asahi.com/articles/ASM933HCLM93PTIL005.html?iref=comtop_list_nat_n05 (朝日新聞 2019年9月3日) 大阪府知事「総務省のおごり」 ふるさと納税の勧告受け ふるさと納税制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の判断に対し、同省の第三者機関・国地方係争処理委員会が「法に違反する恐れがある」と見直しを求めたことについて、大阪府の吉村洋文知事は3日、記者団に「妥当な判断。国は真摯(しんし)に受け止めて見直すべきだ」と述べた。吉村知事は、国が元々通知として出し、6月施行の改正地方税法に盛り込んだ「返礼品は寄付額の3割以下の地場産品に限る」とのルールを、法改正前の泉佐野市の行為にあてはめて除外したと指摘。「法律を遡及(そきゅう)適用しないのは大原則。新しい制度から外すのは総務省のおごりだ」と批判した。 菅義偉官房長官は記者会見で「総務省において対応について検討が行われる。各自治体で使途や返礼品について知恵を絞り、健全な競争が行われ、地域の活性化につなげていくことが大事だ」と述べた。 *6-4:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/421806 (佐賀新聞 2019年9月3日) 新病院は東多久町に 建設地を選定多久、小城検討委 多久市立病院(多久市多久町)と小城市民病院(小城市小城町)の統合計画で、多久、小城の両市は2日、新しい統合病院の建設予定地が多久市東多久町に選定されたと発表した。選定の理由は「両市民の利便性や経営の安定性に加え、医療機関が特定の地域に偏らないことなどを総合的に判断した」としている。今後は地権者との協議を進め、新病院の建設費に関する負担割合や診療科目などを両市で議論する。両市長や医師会、両病院の代表者らで構成する建設地の検討委員会が8月30日、佐賀市で3回目の会議を非公開で開き、候補地5カ所の中から適地を選んだ。両市の事務局によると、多久、小城市はそれぞれ、自らの市域への建設を会議で要望した。民間の病院が少ない多久市は「公立病院がなくなれば医療過疎地になる」とし、財政支援などで経営の安定に努力すると訴えた。建設予定地は東多久町別府の約2・6ヘクタールの範囲。現在は水田などが広がり、北東に佐賀LIXIL(リクシル)製作所の佐賀工場がある。両市長が2日、両市議会に選定の概要を説明した。今後は両市で新病院の準備室を立ち上げ、具体的な協議に入る。2020年に診療科目や病床数を定めた基本計画の策定を目指す。検討委の委員長を務める池田秀夫佐賀県医師会長は「両病院ともに老朽化が進んでおり、必要な医療を継続して両市民に提供するためにも、早期の病院建設を望む」とのコメントを出した。 PS(2019年9月5日追加):*7-1のように、「情報社会でデータを使ってなら人権侵害をしてもよい」という感覚は早急に正すべきだが、そういうことをする人の心の底には、他を貶めたり差別したりすることによって自分の優位を保とうとする誤った意識がある。そのため、私は、「表現の自由」「日本文化」の名の下にあらゆる角度から女性差別された嫌な経験から、「他人を差別した人が有利になることはない」ということを徹底しなければならないと考えている。 そして、*7-1には、被差別部落の事例が掲載されているが、*7-2の外国人のケースも、「包丁購入=殺人犯」とするのは飛躍しすぎているため重傷を負った裕子さんが話せるようになってから犯人について聞くことが不可欠なのに、警察もまた孤立無援に近い外国人を差別を利用して犯人に仕立て上げることが多いわけだ。例えば、*7-3のゴビンダさんの冤罪事件は有名だが、その他にも人権侵害にあたる事件は多い。 *7-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/422734 (佐賀新聞 2019年9月5日) 情報社会と権利侵害、感覚が鈍っていないか 個人情報やプライバシーをめぐってインターネットの負の側面を象徴するような出来事が続く。就職情報サイト「リクナビ」の運営会社は学生の閲覧履歴を基に内定辞退率を予測し、個人を特定する形で企業に販売していた。常磐自動車道でのあおり運転事件で無関係の女性が「同乗者」と名指しされ、実名と写真がさらされた。就職活動に関わる情報は学生の人生を左右しうる。それが本人も知らない間に採用側に提供される。事件のたび虚実ない交ぜの情報がネット上で飛び交い、平穏な日常を送っていたら突然、デマ情報で「犯罪者」扱いされる。企業しかり、個人しかり。個人データや情報、名誉権に対する意識の希薄さを浮き彫りにする。身近なところで気になっていることがある。今年3月、被差別部落(同和地区)の地名や戸数、人口などを掲載した『全国部落調査』の復刻版が、ネットのフリーマーケット「メルカリ」に佐賀県内から出品されていた件だ。『全国部落調査』は1936年、政府の外郭団体が融和事業を進めるため作成した報告書で、70年代、企業や調査会社が就職や結婚の際の身元調査のために購入し、社会問題となった『部落地名総鑑』の原本とされる。それが2016年、神奈川県の出版社が復刻版発行をネットで予告し、出版は差し止め処分が出たが、ネット上でダウンロードできた。出品物はデータを個人で印刷したとみられ、約200ページ、売価3500円で、行政関係者が気づいた時は既に3冊が売れていた。出自をめぐる差別は普段は見えないが、就職や結婚など人生の節目に出現する。そして人を排除し、引き裂く。購入者は一体何のために買ったのか。出品者はコトの重大性を認識しているのか。そんな資料が公然と出回っている現実は、長きにわたる部落差別撤廃の取り組みの内実を問う。同様に、差別をあおる行為は特定の国の人々やマイノリティーに対して顕著だ。国際社会での日本の経済力が低下し、格差が拡大する中、雇用や社会保障への不安と不満が募っていることが関係するのか。いら立ちが社会的弱者に向かい、それがネットという匿名性の空間に噴出している。インターネットの普及でさまざまな情報が瞬時に手に入るようになり、個人が自由に情報発信できる時代になった。ただ、利便性ゆえ、社会規範を逸脱した行為や権利侵害を誘発しやすい。一度ネット上で広がれば長期間残り、不特定多数の目に触れるという点で、影響は大きく、深刻だ。デマ情報問題では女性が投稿者の法的責任を追及する方針だが、情報の洪水の中で、こうした権利侵害行為への感覚が鈍っていないか。自戒したい。 *7-2:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190903-00000061-asahi-soci (朝日新聞 2019/9/3) 逮捕のベトナム人実習生、容疑を否認 包丁購入は認める 茨城県八千代町の住宅で8月24日、大里功さん(76)が殺害され、妻の裕子さん(73)が刺されて重傷を負った事件で、裕子さんに対する殺人未遂容疑で逮捕されたベトナム国籍の農業実習生グエン・ディン・ハイ容疑者(21)が「現場に行っておらず、刺してもいない」と容疑を否認していることが3日、捜査関係者への取材でわかった。茨城県警は同日、ハイ容疑者を水戸地検に送検した。捜査関係者によると、ハイ容疑者は容疑を否認する一方で、事件前日の午後5時ごろ、近くのホームセンターで包丁を購入したことは認めている。購入したのは、現場に落ちていた凶器とみられる包丁と同じ型のものだったという。県警は、同店の防犯カメラの映像などからハイ容疑者を特定したという。県警によると、ハイ容疑者は農業実習生として昨年11月から1年間の期限で在留しており、大里さん宅から約2キロの宿舎に他の実習生らと住んでいた。大里さん宅近くの畑で野菜を栽培するなどしていたという。ただ大里さんは元会社員で、実習生の受け入れなどは確認されていないという。県警は、事前に凶器を準備した計画的犯行とみるとともに、室内が物色された形跡がないことなどから、夫婦との間に何らかのトラブルがあった可能性があるとみて調べている。 *7-3:http://www.jca.apc.org/~grillo/ (ウイズダムアイズ 2019.9.5) 外国人冤罪事件から日本が見える ウイズダムアイズは真実を見通す眼です。私たちが裁判官に期待したい眼です。 ●ゴビンダさん冤罪事件 1997年3月、東京都渋谷区で一人の日本人女性が殺される事件が発生しました。 間もなく、近くに住んでいたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんが逮捕されました。一審無罪、それにも関わらず勾留が続き、新しい証拠調べもないままに2000年12月高裁での逆転有罪・・・と異様な経過をたどる事となりました。 ●ロザールさん冤罪事件 1997年11月、フィリピン人女性マナリリ・ビリヤヌエバ・ロザールさんは、恋人と同居していたアパートのベッドで恋人が刺されているのを発見しました。ロザールさんはすぐにY病院に駆け込み、助けを呼びました。救急隊員は、硬直の状況等を多少確認しただけで警察に通報しました。その直後、ロザールさんは松戸署に連行され、その後逮捕状もないまま拘束され、二度と釈放されませんでした。 ●トクナガさん冤罪事件 2000年6月27日長野県警豊科署は、3歳の長女に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の疑いで、同県穂高町穂高に住む日系ブラジル人の工員トクナガ・ロベルト・ヒデオ・デ・フレイタス容疑者(23)を逮捕しました。トクナガさんの逮捕容疑は同年6月25日ごろ、長女のマユミちゃんが自分になつかないことに腹を立て、全身を殴るけるなどの暴行を加え死に至らしめたというもの。 公判では一貫して「暴行したのは当時の妻」と無罪を主張。一審長野地裁では無罪判決を受けました。しかしその後も「無罪勾留」が続き、東京高裁は2002年6月8日、1審無罪判決を破棄し、懲役5年を言い渡した。弁護人は閉廷後、「控訴審は、当時を知る元妻らを証人として出廷させず、事件について真摯(しんし)な検討を加えたとは言い難い」としています。 ●姫路冤罪事件(ジャスティスさん冤罪事件) 兵庫県姫路市2001年6月19日、市内の花田郵便局に、目出し帽をかぶった2人組の強盗が入り、約2200万円が奪取されました。その犯人とされたのが、ナイジェリア人のジャスティスさん。この事件については担当の池田弁護士のサイトがくわしいです。 ●ニック・ベイカーさん冤罪事件 2002年にサッカーワールドカップを見に日本にやってきたイギリス人のベイカーさんが成田空港で麻薬の不法所持で逮捕された事件。ベイカーさんはプルーニエという男にだまされて鞄を持たされたと主張しましたが、日本の警察はこのプルーニエを調べもしないで出国させました。ところがその後、このプルーニエがベルギーで、他人をだまして麻薬を運ばせようとした容疑で逮捕されました。このことを証拠として申請した弁護側の要求を蹴って、東京地裁は2003年6月にベイカー氏に懲役14年の判決をくだしました。2005年10月、控訴審でも有罪となり、上告はせずに服役した。 ●モラガさん無罪勾留事件 チリ国籍のモラガさんは2001年8月、知人と共謀し東京都内と諏訪市で窃盗を働いた容疑で逮捕された。2003年5月29日、諏訪簡裁で無罪判決。検察控訴の後、8月29日、東京高裁の決定により再勾留されました。2004年年8月17日逆転有罪。最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は2004年12月14日付けで上告を棄却する決定をし、懲役二年が確定した。11月上旬に上告趣意書を提出し、わずか一カ月余りで最高裁は十分な審理をしたとは思えない。一審の無罪判決が軽んじられている決定である。 <高齢者差別による活動制限は人権侵害である> PS(2019/9/7追加):すべてのメディアで長時間に渡って繰り返し繰り返し高齢ドライバーによる交通事故が報道された後、*8-1のように、九州の240自治体にアンケートで尋ねた結果、18自治体が「①免許更新を厳格化すべき」とし、「②65歳以上のサポカー購入に1人1台に3万円補助している」「③後付け装置の購入を支援している」とする自治体もあり、「④交付税措置を検討してほしい」とする自治体もあったそうだ。政府は「⑤75歳以上を対象にサポカーだけを運転できる限定免許を導入する方針」としているが、①は、“高齢者”だけを一律に厳格化すれば、老化に程度の差がある高齢者に対して差別になり、②も65歳以上の全員を運動機能の衰えた高齢者とすることには無理がある。そのため、私は高齢か否か、故意か過失かを問わず、自動車運転が事故に繋がらないように運転支援車の普及を義務化しつつ、既に所有されている自動車にも国の補助をつけて車検時に運転支援プログラムを導入するのがよいと考える。 なお、*8-2のように、「車の運転をやめて移動手段を失った高齢者は、要介護状態になるリスクが2.2倍になる」という研究結果が日本疫学会誌に発表されたが、これは当たり前のことで、要介護状態になれば支える側から支えられる側になるのである。当たり前である理由は、筋力と同様に頭脳も使わなければ衰えるため、頭脳がつかさどる言語能力・思考力・健康維持力なども落ちるからで、事故のリスクだけが人体への悪影響ではないことを考慮すべきだ。 *8-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/539398/ (西日本新聞 2019/8/31) 高齢事故防止 広がる助成 九州5市町導入、26自治体検討 高齢ドライバーによる交通事故が相次ぐ中、事故防止につながる「安全運転サポート車」(サポカー)や後付け安全装置への関心が高まっている。西日本新聞は九州7県の全自治体にアンケートを行い、5市町がサポカーや後付け装置購入に助成していることが分かった。26自治体は検討中とした。公共交通が乏しい地域を抱える自治体は、助成の必要性は感じているものの「財源がない」と国の財政支援を求めた。18自治体が「免許更新を厳格化するべきだ」と回答した。アンケートは九州の7県と市町村の計240自治体に送付、今月までに218自治体(回収率90・8%)が回答した。助成制度の有無や検討状況、国への要望などを聞いた。助成制度がある5市町のうち、福岡県苅田町は65歳以上がペダルの踏み間違い加速抑制装置などを備えたサポカー購入時、1人1台に限り3万円を補助する。同県うきは市、熊本県玉名市、大分県日出町は、後付け装置の購入を支援。玉名市は地元企業が開発した踏み間違い防止ペダルの取り付けに5万円まで出す。宮崎県新富町はサポカーと後付け装置の購入両方に3万~5万円を補助する。サポカーと後付け装置の両方の助成を検討するのは13自治体。ほかに13自治体が後付け装置の補助を検討している。制度のない自治体のうち、少なくとも50自治体が「交付税措置を検討してほしい」(熊本県八代市)などと回答した。政府は75歳以上を対象にサポカーだけ運転できる「限定免許」を導入する方針で、福岡県須恵町など8自治体が支持した。10自治体は高齢者を中心に免許更新の厳格化に言及した。同県柳川市は「急発進防止機能装置の義務化や更新時の技能指導が必要」、熊本県甲佐町は「実技試験の導入」を提案した。独自の取り組みをしている自治体もある。宮崎県都城市は4月から65歳以上を対象に自動車学校での実技訓練やサポカーの試乗を始めた。同県美郷町は10月、ドライバーが自ら運転する時間や場所の条件を申告する「補償運転」を始める。免許返納者らの「足」確保を手助けする自治体も多かった。長崎県西海市は4月から事前予約制の乗合ワゴンを運行。高齢者へタクシー券を配布する自治体も多い。 *8-2:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190905-00000137-kyodonews-soci (KYODO 2019/9/5) 高齢者運転中止、要介護リスク倍 外出減、健康に悪影響か 車の運転をやめて自由に移動する手段を失った高齢者は、運転を続けている人と比べ、要介護状態になるリスクが2.2倍になるとの研究結果を、筑波大の市川政雄教授(社会医学)らのチームが5日までに日本疫学会誌に発表した。運転をやめたが公共交通機関や自転車を使って外出している人は、リスクが1.7倍だった。高齢者の事故が問題になり、免許返納を勧めるなど運転をやめるよう促す機運が高まっている。だが市川教授は「運転をやめると閉じこもりがちになり、健康に悪いのではないか。事故の危険だけを考えるのではなくバス路線を維持・充実させるなど活動的な生活を送る支援も必要だ」と話す。
| 年金・社会保障::2019.7~ | 11:03 PM | comments (x) | trackback (x) |
|
PAGE TOP ↑
